2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年10月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
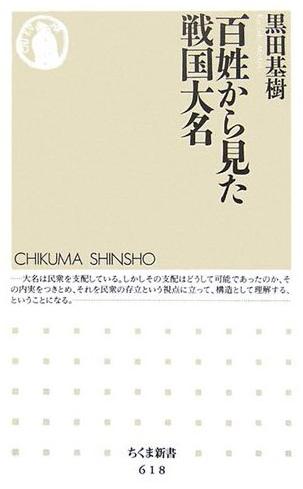
★ 黒田 基樹 『百姓から見た戦国大名』 ちくま新書 (新刊)
▼ こんな刺激的な書物が、新書という体裁をとって、700円強で手に入る時代になったとは、ホント、幸せな世の中になったもんだ、というしかない。 皆の衆。 ひとまず、本屋に走れ。▼ 大河ドラマでは、今放映されている「巧妙が辻」を初めとして、一般に人気が高い、戦国時代。 そんな時代、民衆と戦国大名とは、どのような関係にあったのか。 この本は、赤裸々に解明して余すところがない。▼ とかく、戦国大名は、社会、とりわけ「ムラ」に依存していた。 北条氏康の隠居、武田晴信(信玄)のクーデターは、飢饉時の「世直し」とした行われたものらしい。 飢饉に深く彩られ、政治に陰を落としていた戦国時代は、江戸時代後半の大飢饉の時代と同様、端境期に死亡率が急騰するのが恒常化していた時代だった。 他国に侵攻しての「刈田狼藉」による略奪は、生存のための、国内飢饉対策として必要だったという。 その戦争には、大名と家臣団のみならず、食いつめた村人が、略奪目当てで、足軽として参加していた。▼ そんな社会のベースになったものこそ、畿内では13世紀後半、全国的には15世紀までに形成された、「惣村」「惣庄」にほかならない。 メンバーシップ(構成員)を認定して、「政治団体」として「法人格」をもち、「警察権」「徴税権」「立法権」まで掌握し、独自の武力を保有しては公権力を振るう「ムラ」の創成。 それは、階級差・身分差を持ちながらも、飢饉を背景として生存のため、鎮守や村寺を結集の核として、用役確保のため結成された、構成員の「寄り合い」で運営される組織であるという。 ムラ同士、用役をめぐって「合戦」「訴訟」を展開。それがムラの領主同士の戦争にまで発展していく。 否、ムラこそ領主を作り出していく存在なのだ、という指摘には驚くほかはない。▼ ムラを維持しなければ、戦国大名・国衆は存立できない。 戦国大名・国衆は、守護大名と違い、排他的・領域的・一円的支配をもつ。 その戦国大名領国は、「惣」「領」をブロックとして形成され、その「領」には「城」がおかれていたという。 大名・国衆は、「領」内のムラに課税して、ムラも「城」を避難場所としていた。 避難場所の整備ため、ムラの提供していた「城普請役」が、やがて土木工事、特に「治水工事」に転用されていく。 大名・国衆は、ムラを維持するために年貢減免を行わなければならない。 またムラは、領主による平和・安穏の対価として、年貢・公事を「ムラ請」でにない、減免をエサに百姓を招聘して農業をおこなう。▼ また、戦国大名・国衆の家中(家臣団)は、個別領主層が自力救済を放棄して、裁定権を唯一の主家に委ねていくことによって誕生してゆく。 そこでは、ムラ同士の対決が、領主同士の対決に発展していくことを断固禁止された。大名・国衆は、小代官の任免などを通して、年貢・公事徴収権にまで容喙、ムラとのルートを開く。 このとき、領主・小代官でもない、ムラの徴税担当者が、役人であると同時にムラ代表者という、「村役人」制度が形成されていく。 減税・「徳政」を通して、大名権力を確立していく。 ▼ 「ムラ」同士の紛争も、北条氏統治下の「目安(訴状)制」の全面展開によって、「家人(中)」を飛び越した直接訴訟権が認められ、「万人に開かれた裁判制度」の創出されてゆく。 中世までの裁判とは、大名や御家人、公家や寺社といった、権力関係者間の利害調停にすぎず、ムラが訴訟しようとすれば、自分の領主を通じて、莫大な礼物を関係機関に渡さなければならない。 戦国大名下では、領主との伝統的な相論方法で、実力行使の一つであった「逃散」も、「自力救済」ということで禁止。 「首謀者一人を斬首」は、百姓一揆の処罰法にも転用されていったという。 また宿場町においても、「実力行使」が禁止され、相論が起きた際にも、大名が裁判権を行使する、「楽市」―――大名自らが平和(楽)を保障―――の制度が始まるのだという。この頂点において、大名間の「実力行使」を禁止して裁判を待つよう求めるものこそ、羽柴秀吉の「惣無事令」のほかならない。 ▼ 実は、信長・秀吉の領国の年貢収取体系は、まったく分かっていないという。 むしろ、北条家研究によって、戦国大名こそ、近代国民国家の出発点になっていることが、様々な方面から、明らかにされて面白い。 村高は、イコール耕地面積ではない。 領主とのギリギリの政治交渉によって決まるらしい。 また、永禄3年頃の大飢饉をきっかけに、税金は「銅銭」から「米」―――現物給付に一大転換をとげる。 その反面、ムラ同士の「実力行使」は近世でも続く。 なによりも驚かされるのは、北条統治下では、税金増額の論理として、「御国のため」が使われた―――「御国概念」の出現―――ことにあるかもしれない。 近代国民国家の時代、国民を戦争に動員するため、日本で使われた単語「御国」は、北条統治下で出現した、家臣団・奉公人以外の村人に対して、貢献を呼びかけるものだったのだ。▼ ただ行論上、惜しまれるのは、「惣村」の成立は、15世紀までであって、戦国時代と重なっていないことの説明が、尽くされていないことであろうか。 「惣村」を基盤として、戦国大名が析出されたのは、あらかた理解できる。 しかしそうして成立した戦国大名は、「惣村」をどのように変容させていったのか。 当然の疑念であるだろうに、あまり触れられていない 。ただ、「惣村」が無批判に、現代の「ムラ社会」の原型として、超歴史的に説明するだけで終わってしまっていないか。 歴史でありながら、「惣村」と大名権力が―――他にもいろいろあるけれど―――ノッペラボウな同質なものとして扱われ、非歴史的な説明になっている嫌いが見え隠れする。▼ とはいえ新書としては素晴らしい。ぜひ、お勧めしておきたい一冊であろう。評価 ★★★★価格: ¥ 735 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Oct 28, 2006
コメント(2)
-

★ 中日が日本シリーズに負けた理由: 日本シリーズ戦略史メモ
▼ どうも、中日は、日本シリーズでは勝てないねえ。 思うんだけど、戦略がないんじゃないか。▼ だいたい、日本シリーズの歴史は、3期に分割されると思うのよ。 第1期は、1950年~1977年。 第2期は、1978年~1994年。 第3期は、1995年~。▼ 第1期は、戦略なしの時代。 とにかくエースが、先発にも、リリーフにもまわる時代だった。 監督はエースと心中するのが当然の時代。 1958年の日本シリーズ。 第3戦から5連投して、西鉄奇蹟の「3連敗の後、4連勝」を達成させた稲尾和久は、シリーズ成績は「4勝2敗」だった。 翌年の南海の杉浦忠は、4連投「4連勝」。 なにも、稲尾・杉浦クラスでなくても、南海のスタンカは、1964年の御堂筋シリーズで、第6戦・第7戦を連続登板、連続完封して日本一に導いている。 スタンカは、最後の日本シリーズ3勝ピッチャーである。 以後、日本シリーズでは、3敗ピッチャーは現れても、3勝ピッチャーは、現れていない。▼ むろん、投手に分業制が導入されていなかったせいだ。 稲尾は1961年、42勝をあげた年、半数はリリーフで稼いでいる。 晩年の国鉄の金田正一は、同点で勝てそうだなと思うと、登板志願して、勝ち数をずいぶんと稼いだため、オールドプロ野球ファンには、たいへん評判が悪い。 そんなファンが神のようにあがめ奉るのは、「サイちゃん」こと、稲尾和久である。 「8時半の男」、板東英二、星野仙一だって、完全なリリーフピッチャーとはいえなかった。 連投、先発・抑え兼任は、とくに日本シリーズでは常識だった。1975年の日本シリーズでは、山口高志が阿修羅のごとき快刀をみせつける。▼ 第2期の画期は、1978年の広岡達朗の登場である。 ここで初めて、日本シリーズにおいて、短期決戦を戦略でのりきろうという考え方があらわれてくる。 「第7戦で勝つこと」から入って、そこから逆算する形で、戦略を編み出していく。 第5戦で3勝2敗と勝ち越しても、第6戦で「3-12」と一方的に負けても、慌てない。 第7戦で、満を持してエース松岡を投入。 途中大杉の疑惑の本塁打で中断したものの、日本シリーズを制覇する。▼ 以後、西武ライオンズの全盛時代の到来とともに、この方式は洗練される。 日本シリーズは第3戦を重視。 エースは3戦と7戦に登板させる。そして経験があって安定感のあるベテランピッチャーは、2戦と6戦に登板させる。 なぜなら中5日で投げられるから回復が期待できるから…こんなことが真顔で言われていた時代があったのだ。 7戦で4勝をあげるために周到な計画を! 第2期の日本シリーズは、総力戦にほかならない。▼ これを吹き飛ばしたのが、第三期の野村克也の登場ではないか。 オリックスを叩きつぶした1995年の日本シリーズは、最初に外国人ブロスの剛球でねじ伏せて、そのままの勢いであっさりと勝ってしまった。 「短期決戦は勢い」という今の流れができたのは、明らかに野村ヤクルトの鮮やかな勝利が原因だろう。▼ しかし、この副作用が効き過ぎていないか。 たしかに野村ヤクルトは、勢いで4勝1敗で制した。 しかし、このときの野村ヤクルトは、ヤクルト史上最強チームだった。 イチローのオリックスとは総合力で歴然とした差があった。 たとえ「勢い」を外されたとしても、2の矢、3の矢をつぐことができた。 15勝ピッチャーが、山部と石井一久、2名も残っていたのである。 1995年日本シリーズ第五戦は、豊田泰光が解説をしていたが、オリックスのレベルの低さを酷評する異様な解説ぶりは、忘れられない。 野村は決して勢いで野球をしたのではない。▼ どうも今回の日本シリーズというか、ここ10年ほどの日本シリーズをみて不思議に思うのは、「勢い」のかけ声は良いとしても、「総力戦」という感じがしないことだ。 力が出せないまま、一方的に終わってしまうシリーズが急増している。 日本シリーズをデザインしようとする強靱な意志が感じられない。 ▼ だいたい、第1戦に川上、第2戦に山本昌を投げさせたとして、第7戦までもつれた場合、誰に投げさせるつもりだったのだろう。 朝倉に、最後を託すのか? その辺、武田勝が残っている日本ハムとは違う。 外されると、ケアできていない。 山本・朝倉・中田が倒されると、川上でも支えきれなかったという所だろう。 「7戦で4勝」といいながらも、どのように勝ちを取っていくかについて詰められていない感じ。 プレーオフを勝ち上がってきたパ・リーグのチームと漫然と戦い、「勢い」で負けてしまう。それの繰り返しという感じがしてならない。▼ 今となっては、「森西武VS野村ヤクルト」の、秘術を出し尽くした老監督対決が、懐かしく思い出されてならない。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Oct 26, 2006
コメント(2)
-
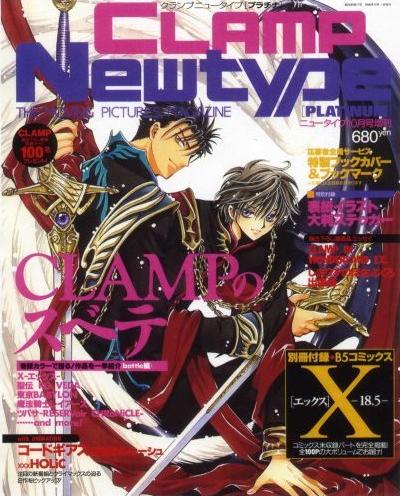
★ 甦る過去の亡霊 『CLAMP Newtype PLATINUM 』角川書店 2006年 10月号 (新刊)
▼ 人は、しばしば、過去の自分と対決しなければならないらしい。 とりわけ近年、その頻度がずいぶん増しているように思えるんだけど、 私が年をとったからだろうか。 私の気のせいだろうか。▼ 『Zガンダム 劇場版』3部作 辛かったなあ。 富野作品とすごした青春が、走馬燈のように思い出されて。 セリフの一つ一つを克明に覚えているし、 そのシーンまで思いだせるものだから、 榊原良子と、島津冴子のいないZガンダムは、殺意さえ覚えました。 僕は、とうとう、最終作を見に行かないことにしたんだけど、 ホンッと、行かなくて正解だったと思う。▼ 『時をかける少女』 ゆうきまさみや、とり・みきたちの、下北沢ブルースじゃないけど、 思い出ある作品なんで、パスした。知世主義者としては許せない。▼ 『日本沈没』 映画版「日本以外全部沈没」の方が面白そうというのならまだしも、 『日本ふるさと沈没』(注)の方が面白そうというのは、反則だろう。▼ 『セーラー服と機関銃』 薬師丸ひろ美……じゃなかった、薬師丸ひろ子の物悲しい歌声。 僕にとって思い入れのある、とっても好きな歌なんだけど、 昭和歌謡曲の傑作でもあるらしい。 それを、長澤まさみが歌うのは、どうよ。 演じるのは許すが(許すのかよ!)▼ おまけに、『エヴァンゲリオン』まで、劇場で復活するという。 「魂のルフラン」の旋律で、僕にとっては終わっていたというのに… これで『うる星やつら』まで復活したら、身が持たないゾ、と思ってたら 『クランプ ニュータイプ』のお出ましである。▼ 過去の亡霊との対話はつらい。▼ 『東京BABYLON』は面白かったなあ、 説教くさいと批判されたけど… 実はすんごく、こった設定で、最初から最後まで大川七瀬が、 コントロールしていたものだったらしい。へー。▼ 『レイアース』は、つまらなかったなあ… 獅堂ひかるは、キャラが最後まで不鮮明すぎたとおもう。 可愛くて元気なキャラは難しい。▼ 『カードキャプターさくら』かあ…過去の病気が、ぶりかえしそうだ。 「大道寺知世×木之本さくら」本だしてる同人誌ないかなあ…▼ 『X』かあ…劇場版は悶絶したなあ。血が飛びまくったし… おや、18巻の続編まで収録されているぞ、どれどれ… 線が入りすぎて良く分からないや。 そもそも、どんな話で終わっていたんだっけ。▼ 『つばさ』 絵が汚いので見てないや。▼ まあ、CLAMPファンにとっては、素晴らしい、 そしてCLAMPを卒業したものにとっては、忘れたい。 そんなすてきな作品に仕上がっているのではないでしょうか。▼ そんな、卒業した僕でも許せないのは、 『わたしの好きな人』に言及されていなかったこと。 素晴らしい佳品が集められていて、 CLAMPの最高傑作だと思うのになー。評価 ★★★価格: ¥ 680 (税込) 名古屋を沈没させる話と、鶴田謙二の作品が、なかなか楽しめて良い。評価 ★★★☆価格: ¥ 680 (税込)たいへん乙女チックかつメルヘンな童話。絵がすき。評価 ★★★☆価格: ¥ 483 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 追伸 (10月27日付)こんなのが出てた。むー、どうしよう… ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Oct 23, 2006
コメント(1)
-
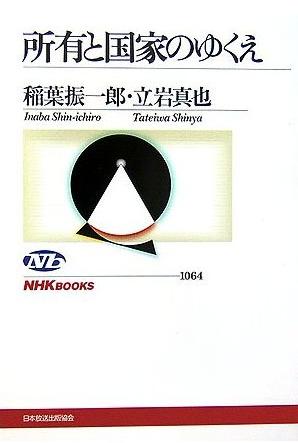
★ 稲葉振一郎・立岩真也 『所有と国家のゆくえ』 NHKブックス (新刊)
▼ 悪いのは僕だ、ということは分かってる。 でも、しばしば、「これはあんまりではないか」と言いたくなるような事態に、人は遭遇することがあるもんだ。 さぞかし、この書物との出会いは、そんな不条理さに満ち満ちたものであった。 時間と金を返して欲しい。▼ そうなんだ。 もとはといえば、「立岩真也って、どんなことを言ってるんだろう」「手際よくまとめられた本があれば、とても便利なのにな」と、下心丸出しで、本書に飛びついたのが悪かったにちがいない。 稲葉振一郎氏と立岩真也の対談とくれば、立岩真也が理解できる上に、稲葉氏と立岩氏の、スリリングな対談になるんじゃないか。 「一粒で2度おいしい」。 ええ、胸を躍らせて、飛びつきましたよ、わたしは。 その結果は、言うまでもない。 立岩真也って、結局、何を言っている人なのか、最後まで分からなかったのだ。▼ とりあえず、気を取り直してまとめてみよう。▼ 稲葉振一郎氏によれば、立岩真也氏とは、「分配する最小国家」「冷たい福祉国家」―――加害の防止と、分配だけをおこなう国家―――を提唱されている方らしい。 稲葉さんは、ケインズ主義的福祉国家の自明性を解体して、干渉国家・管理国家という批判を封じるため、「ケインズ主義的最小国家」=古典的最小国家に金融政策をプラスしただけの国家像を提起する。 一般的に現代では、外部経済を内部化することで、環境問題などに対応していく方向性に対して、「外部」の存在、市場の限界を強調する議論が多かった。 ところが立岩氏は、「所有する能動的な主体」から議論を始めない。 所有の主体は、理論の主人公にとっての他者として現れ、「他者にとっての他者」としてしか形成されない。 私の身体は、自分にとってどうにもならないが故に、私のものだろう。 逆に、私の身体によって得られたものは、「切り離し」「譲渡」可能であるが故に、誰の者であってもいいのではないか。▼ 人は何かを所有(そして取引)する主体でありながら、同時に、取引されたり所有されたりする手段でもある。 所有を確定して市場を議論する、という方法が採られるものの、そもそも市場が、資産の商品化に見られるように、所有自体を変形させてゆく。 立岩氏の「他者にとっての他者」議論は、所有に止まれば面白いが、ダイナミックな市場に敷衍できないのではないか、「譲渡できるもの」「譲渡できないもの」の区分は、苦しい時は絵に描いたモチにすぎないものではないのか。 その稲葉氏の批判に対して、立岩氏は後者に対して、「譲渡できないもの」を譲渡しなくて済むような基本財が一人一人確保した上で、譲渡したくないものの譲渡を人に求めてはならないという原則でどうしていけないのかと反論するものの、前者には応えていない。 両者は、厚生経済学の基本定理の初期条件が、人は市場で取引に参加する前に「生きている」、取引に参加しなくても生きていける、極めておめでたいものであることに同意する。▼ しかし、稲葉氏が「市場は所有にフィードバックするため、自給自足に戻れない」を敷衍し、市場が絶対的な生活水準低下を招く可能性がある、すなわち「底上げしていない」「パレート最適に社会を導いてくれない」(スミス以来、経済学者の前提)ことをシステマティックに言おうとするという議論に、なかなか立岩氏が食らいついてくれない。 格差拡大は、稲葉氏にとっては、市場の前提であるコミュニケーションの透明性を損なうから是認できない。 「分配は平等か、不平等か」ではなく「パレートの意味で良い方向なのか、悪い方向なのか」を問題視する。 タガが必要であるが、どのようなタガをはめるべきかについて、なかなか見えてこない。▼ 「分配のために国家がいる」ということから始まる国家論は、なかなか面白い。 リベラリズムは、個人間の効用・価値観は比較不能であるので共存を大事にしようというと、保守主義者はそのためにも国家の役割は抑制されるべきだという。 しかし「最小国家」では、比較不能な価値の共存が掘り崩されるので、リベラリストたちは、ロールズを始めとして、「何かを予感しつつ」も折衷主義に走り「ケイパビリティ」「フェアネス」を語らざるをえない。 分配ついてどのような基準でいくべきか。 あまり具体的に考えられていないし、変更可能性・実行可能性な「合意」について語ろうとするものの、なかなか前に進まない。最後、その理論的意義を評価する「基準的な他者(として将来世代)」を持ちこむ場合、搾取論的ではなく、「他者がこの世に存在できる環境を整えておくことが現役世代の義務」という論法を採るべきである、という提案に合意する。しかし、そんな「環境」とは何だろう。▼ ノージックは、ホッブスなどとは違い、他人の承認の必要がない権利を構想し、権利は歴史的背景によって決まるとして、「歴史原理VS状態原理」の中では、仮想論敵を状態原理に入れていた。 しかし、「局所VS全域」という軸を設定すると、むしろ論敵のほうが「社会の承認」が必要なだけ「局所」的ではないのか。 ノージックの議論は、ロールズの「無知のベール」同様の、圧倒的な普遍主義を前提としなければならないのではないか。 立岩の議論も、ロールズ・ノージック同様の、否、むしろ彼等よりも「他者との関係性」が入っている分だけ、さらに複雑な操作による基礎付けが要求されるような、権利が合意を超越する議論なのではないのか。 その稲葉氏の誘いに、権利には合意が必要だが合意に回収されない権利がある、と回答。 綜合されているとはいえ、これでは議論が発展しないだろう。▼ 第4章「国家論の禁じ手を破る」では、流行らなくなった「批判理論」「規範理論」について語られるが、どうにもカタルシスが感じられない。 ブルジョア国家論も、マルクス主義的国家論も、共有してきた「道具的国家」像。 それに対して、グラムシのヘゲモニー論が一歩踏み出し、アルチュセール以降、「主体的国家」像がみられ、あまつさえヘーゲル的(?)な「主体的国家」(国家有機体説)像に本家帰りするような傾向さえみられたという。 フーコーの権力論の衝撃は、「めくらましを解除したら真実が現れる」ことの否定、まっさらなものはなにもなく、2次的な産物にすぎないことを明らかにしたことにある。 フーコーについては、人々の性格・規範でさえ権力に先立たれていて、権力批判の身振りさえ権力に与えられたもの、と、「隘路」として理解した人が多かったが、「権力者がいない」「力の流れで、主体が生み出される」「権力とは事実性にすぎない」「国家と権力は同一ではない」ことを理解していない。 格差・不平等について、自己に責任がなくて不利益を被っている場合、搾取論ではない基礎付けとしては、国家を保険会社として捉え補償するという考えかたになるしかない。 しかし、これでは「責任主体」があいまいになってしまいかねない。そこで本書は唐突に終わる。▼ 嫉妬で分配をもとめて何が悪い。 嫉妬がなければ競争が起きないだろうが!は、鮮烈であった。 アソシエーショニズムは、所詮、企業よりもパフォーマンスが落ちてしまわざるをえない。 ローマーは、遺産相続の禁止以外は資本主義と変わらない社会主義を構想しただけでなく、「搾取」論的不平等論の無効を宣告―――搾取されるほどのものも持たない人のことを考えると余計なものでしかない―――した人物であるという。▼ この本のレビューを書くため、読み直してみた。 少し理解できたので、怒りが少しはおさまったものの、初めに読んでいる時は、むかついて仕方がなかった。 とにかく、この本の立岩真也の語り口は、紆余曲折を繰り返していて、分かりにくい。 ほとんど、対談で喋ったことが、そのまま原稿化されてしまい、まったく手が入れられていないようなのだ。 そんなバカなことをする奴が、いったいどこにいる!!!!。 いくらなんでも、こんな手抜きを許すわけにはいかない。▼ たとえば、「譲渡し得ない資産」である「人的資本」などの議論は、いったい、結局、どう引き継がれ、どう合意ができて、どう差異が埋まらないのか。 こんな肝心なことがさっぱり分からない。 稲葉氏と立岩氏の議論が、すれ違いまくって、ちっとも対談の感じがしない。 これに比べれば『動物化する世界の中で』(集英社新書)の方が、破綻していることが示されている分だけ、遙かにマシといえるだろう。 どうやら立岩氏は、喋っているうちに、混濁していた思考が整理されてきて、終わりにはそれなりにシャープな議論にまとまる方の様だ。 それはいい。 ただ、いちいち、その全過程が収録されるなんて、ウザイことこの上ない。 読んでいて殺意さえ覚える。 稲葉振一郎氏が立岩真也の議論まで、読者のために丁寧にまとめている努力には、たとえまったく報われなかったにせよ、頭が下がる。 おそらく、この対談。 適切にまとめれば、1/3で済むような、シロモノではないか。 はっきりいって、その方が10倍くらい面白かったにちがいない。▼ あと、立憲主義の民主主義に対する優越について、ルーマンを持ちだして語ることに、何か意味があったのか……。 そりゃ、人(そして人権)は「社会(行為)システムの外側」=環境にすぎないんだから、当然の前提なんじゃないの?。 その後をあからさまに、「立憲主義を限界づけるのは、民主主義なのか?」……という問題提起をするんだけど、なんか知ってるくせに黙ってるというか、マッチポンプというか、嫌みな感じがしてしまうゾ。▼ 要は、なにごとにも、学問に近道はない、ということか。 稲葉氏部分は、星3つ。立岩氏部分は星1つ半、平均星2つとした。ご寛恕願いたい。評価 ★★価格:¥ 1,176 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 『動物化する世界の中で』↓評価 ★★★価格: ¥ 693 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Oct 18, 2006
コメント(0)
-
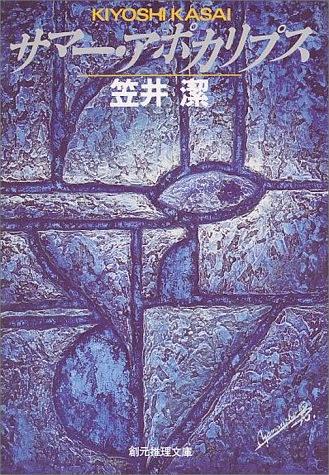
★ 北朝鮮核開発と世界革命 笠井潔 『バイバイ、エンジェル』 創元推理文庫 1995年 (初出は角川書店 1979年)
▼ 諸君 私は革命が好きだ 諸君 私は革命が大好きだ 産業革命が好きだ 国民革命が好きだ フランス革命が好きだ フェルキッシュ革命が好きだ 農業革命が好きだ 勤勉革命が好きだ 8月15日革命が好きだ 太閤検地封建革命が好きだ 少女革命が好きだ▼ なんか違うものまで、交じっているような気がするが……… というわけで、このブログを愛読している方には、まったく意外に思われないかも知れないが、内容がなんであれ「革命」と名前がつくものが大好きな私は、いつだって火の出るように熱い小説を好む。そんな人にお勧めしたい小説は、笠井潔『バイバイ、エンジェル』である。▼ 死んだはずの人物から届いた手紙。パリのアパルトマンに転がった、首なし死体。ラルース家をめぐる連続殺人事件。これを解決するために立ち上がる、日本人留学生、矢吹駆。かれはいう。 集められた諸事実は真実にたいして権利上同等である無数の論理的解釈を同時に許すそう嘯いて、「本質直観」による「現象学的推理」を駆使して、有機的全体から、全体の支点にあたるものを見出して、解決に導いていく………本書における支点は、首無し死体。首は、なぜ切り落とさなければならないのか? ▼ とにかく意味不明に格好いい。「認識論的還元を超えて、私の生そのものの還元を企て」る矢吹の生活は、「あらゆる剰余を剥ぎ取って、もっとも単純な生の形を露呈」させるため、家には暖房も友人も恋人も所有物もない。そして、近代精神のグランメール、観察と推論と実験の操作が真理への唯一の道、という考えを批判する。反ナチ・レジスタンス、フランス共産党員の父(警視)をもつ、女子大生ナディア・モガールを道化師(ピエロ)として、本書は怒濤のクライマックスを迎える。未読の方は、以下、ネタバレもあるので、ブログを読むのをやめて、本書を読んで確認して欲しい。応援してくれれば言うことはない。▼ なによりもこの書の熱さは、かつて新左翼の革命運動に従事していた著者・笠井潔が、「ヘーゲル=マルクス主義」と呼ぶものを打倒・清算するために書いたことに起因しているだろう。最後、矢吹駆は、このラルース家殺人事件の真の黒幕、世界革命組織「ラ・モール・ルージュ(赤い死)」の幹部と対決するのだ。その詳細を転載しておこう。 お喋りは終わりにしましょう。わたしたちは必要な話をしなければなりませんわ。あなたは組織の統括者になるべき人間です。組織の中央委員になるべきなのです。……… わたしの組織は…究極の革命組織です。人類史が生み落とした最後の革命組織なのです。その綱領は?私たちはあらゆる革命の敗北の、その究極の根拠を発見したのです。なぜ、一切の革命は常に絶対に敗北するのでしょうか。歴史は、破れた革命の残骸に埋め尽くされているではありませんか。なぜ、革命はいつだってまるで悪い運命に呪われているかのように絞殺され続けてきたのでしょうかなぜです?理由は、そう、わかってしまえば実に簡単なことなのです。それは、革命の中にいつも解きがたい矛盾と背理が含まれていたからです。革命は、胎内に、敵対者の罠をはらんでいたのです。その罠とは、<革命は人民による人民のための事業である>という愚昧な命題です。この命題こそが、革命の敗北の根拠なのです。革命そのものとこの命題のあいだにあるものは、決して解くことのできない矛盾と撞着だけです。そうです。革命と人民とは本質的に無関係です。いいえ、あらゆる歴史の現実が露骨に示しているのは、革命の最悪の敵が人民そのものであったという事実なのではありませんか。革命の真の敵は、刑務所や軍隊や政治警察や武装した反革命ではなく、…人民という存在だったのです。……………<人民>とは、人間が虫けらのように生物的にのみ存在することの別名です。日々、その薄汚い口いっぱいに押しこむための食物、食物を得るためのいやいやながらの労働、いやな労働を相互の監視と強制によって保障するための共同体、共同体の自己目的であるその存続に不可欠な生殖、生殖に男たちと女たちとを誘い込む愚鈍で卑しげな薄笑いに似た欲情 …。この円環の閉じこめられ、いやむしろこの円環のぬくぬくした生温かい暗がりから一歩も出ようとしないような生存のかたちこそ<人民>と呼ばれるものなのです。つまり人民とは、人間の自然状態です。……………だから人民は、本質的に国家を超えることができないのです。国家とは、自然状態にある個々の人間が、絶対的に自己を意識しえない、したがって自己を統御しえないほどに無能であることの結果、蛆が腐肉に湧き出すように生み出された共同の意志だからです。制度化され、固着し、醜く肥大化した観念、生物的存在と密通し堕落した観念、これが国家だからです。あなたの理論によれば…人民と国家は永遠の共犯者なのですね。人民とは、国家の足元で、窮極のところ生物学的な殺人に還元される利害抗争に明け暮れ、ある時は飽食して眠り、ある時は飢えて暴徒化し、この両極を無意味に機械的に往還するだけの自然状態にあるような人間たちの別名なのですね。……… 政治こそが革命の本質を露わに体現する場所です。組織は革命が棲まう身体です。私たちは、最後の、決定的な放棄を準備するための武装した秘密政治結社なのです。社会を全的な破滅へと駆りたてる武装蜂起こそ、観念の激烈な輝きが世界を灼きつくす黙示録の瞬間の実現なのです。けれども、蜂起はいつも、あなたの憎悪する人民の反乱の頂点で、なんらかの政治スローガンを掲げて組織されたものです。平和、土地、パン、自由ですか。いいえ、スローガンになど本当の問題はないのです。それは、季節に合わせて適当に着け替える衣服にすぎません。どんなスローガンでもいいのです。問題はただ蜂起が体現する観念の激烈さと純粋さだけにあるのです。………しかし、蜂起の現実的目標は、権力です。権力……。あなたは、わたしたちがあの愚かな髭面のユダヤ人やその使徒たちのように国家に身を売るとでも考えているのですか。あらゆる革命は、人民に拝跪することによって国家に粉砕されるか、国家に拝跪することによって人民を奴隷化するか、つまり敗北か堕落かのいずれかに逢着したのでした。しかし、これはただ、人民と国家とが革命にとって二重の敵であることを理解しなかったために惹き起こされた結果にすぎません。わたしたちは、違います。すると、あなたたちの窮極の目標はなんなのでしょう。<赤い死>の最大限綱領は…わたしたちが介在しなければ、どのように激しい反乱であろうといずれ沈静するものです。国家と人民は二本の脚のように互いを必要としているのですから。諍いは一時のもの、暗黙のうちに将来の和解を計算しながら、国家と人民は争うのです。しかし、わたしたちは、この予定調和の円環を噛み破ってしまう。あらゆる詐術と陰謀によって、後戻り不能の場所にまで人民を駆りたて、暗黒と腐敗と<赤い死>の、混乱と暴力と破局の一時代を現出するのです。………そして革命は、内に向かっては社会の永続的な破壊を推し進め、外に向かっては、国際社会の秩序をずたずたに切り裂くための策謀を絶え間なく実践しなければなりません。その最大の武器が、そう核兵器です。あなたは、わたしたちが核戦争だけは避けねばならないといった迷妄に毒されていると思いますか。いいえ、全面核戦争こそが、世界革命の本当の中身です。核の炎となかで世界が焼け落ちることによってのみ、社会と文明は決定的に破壊されるのです。私たちの最大限綱領は、国家と人民の廃止です。それはまた、文明と社会の窮極の、最終的な破壊でもあります。文明そして社会とは、国家と人民の永遠の共犯体制の別名なのですから。………全面核戦争を頂点とする世界革命戦争は、世界人口を少なくとも現在の4分の1以下、うまくいけば10分の1以下まで引き下げることでしょう。そして、1世紀にわたる混乱の時代から新しい集団が成長してくるのです。 ………破局を生き延びた一握りの人々は、性によっても、労働によっても強制されることのない、ただ観念と意志にのみ依存した自由な集団を築くことになるでしょう。必然の罠はついに永遠に追放されるのです。………そのとき、全人類は単一の結社の成員になるのです。全人類はただ厳格な論理と理性によってのみ結合される。▼ 凄い。 あまりの熱さに火傷しかねない。 これほどまで、ヘーゲル=マルクス主義のもつ醜悪な側面を徹底的に戯画化した作品を、私は知りません。 なぜ推理小説という形態をとって、こんなやりとりを描くのか。 議論を巻きおこしたことは、ある意味当然。 本格推理小説としての体裁があまりにもキチンと整えられているだけに、かえって不気味なまでに革命というテーマがうきあがってしまう。本格推理小説として完成されたものが読みたい方は、『サマーアポカリプス』の方がお勧めです。▼ とはいえ、カリカチュアにすぎないはずの、「国家と人民の廃絶」という政治綱領に、正直、かなり萌え萌えになったことは、告白しておかねばなるまい。 世界全面核戦争っすよ、旦那。 その結果、理性と論理にもとづくアソシエーションができるんでっせ。 なんか、「うる星 2」みたいに感じられていいじゃん、という訳で、これで何とか北朝鮮の話題に持っていける(笑)。 ▼ そんな私だから、北朝鮮が核武装しても、なんか面白そうなことが、待ちかまえていそうに感じられてしまう。 アメリカ相手に、良くやるよなーというのは、無論のこと、世界が終わるんなら文句言わない、って優香、核で焼け落ちて国家にかわってアソシエーションになるっつーのが萌えを刺激して止まないのですね。▼ いったい、なに騒いでるんですか、皆さん。 とくに、北朝鮮は核実験できない、とかバカにしていながら、いざ核実験に成功するとあわてたのか、ならば日本も核保有だと、騒いでる皆さんは醜悪ですよ。 日本が核武装してもしなくても、北朝鮮が打ってくればどーせ死ぬんだし、核武装しても喜ぶのは、相互確証破壊を口実に核シェルターに待避できる、安倍ちゃんとそのお仲間たちだけじゃん。あなたは、どーやったって、死ぬんです。ジタバタしたり、チマチョゴリ切っても、チキンに見られるだけでっせ。 ▼ 制裁、大いに結構。戦争、大いに結構。むろん米朝妥協で、日本右翼がハシゴ外され大困惑するのも大いに結構。小泉首相じゃないけれど、「勝って良し、負けて良し」。そんな気分で、核実験騒動を楽しんで見てはいかがだろう。どうせ、かわんないんだし。▼ 退屈しないからいい、と思うのは、ライトスタッフだと思うんだが。評価 ★★★☆価格: ¥ 672 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Oct 12, 2006
コメント(2)
-

★ 宮田律 『中東イスラーム民族史』 中公新書 (新刊) 2
(この日記は1からの続きですので、こちらからお読みください)▼ 古代ペルシャ帝国の栄光とペルシャ語に誇りをもつペルシャ人は、アラブに同化しなかった最初の民族だという。アッバース朝時、公的世界で閉め出されていたペルシャ語は、詩文(叙事詩・文学)で復活した。フィルドゥーシー『王の書』が標準ペルシャ語を提供したのだという。イラン人居住地域には、ペルシャ王権がつぎつぎと復活。シーア派がイランで国教的地位を占めたのは、イラン人の民族意識を背景に、サファヴィー朝が衰退しつつあった「十二イマーム派」を採用したからにすぎない。18世紀後半、カージャール朝成立以降、ロシアとイギリスのグレートゲームに巻きこまれ、傀儡国家となったイラン。二十世紀パフラヴィー朝成立以降、レザー・シャーは、「イラン民族の栄光」を訴え、古代ペルシャ帝国やゾロアスターのシンボルを復活して、民族意識を高揚させるとともに、宗教教育廃止・鉄道建設・女性教育・軍事増強など、「脱イスラム」が推し進められてゆく。しかし、聖職者・教徒は反発。これに、自由主義・左翼勢力たちも合流。この反王制の動きだったはずのものが、1979年のイラン民族主義よりもイスラム普遍主義を強調するイラン・イスラム革命に発展してしまうのは、60年代から王制打倒をかかげ、社会正義の実現を説いて貧困層の熱烈な支持を受けた、ホメイニのカリスマによるものらしい。アフマディネジャド政権は、イスラム世界に対してメッセージを発する原理主義、というよりも、国内向「反米・反イスラエル」、すなわちイラン・ナショナリズムを鼓舞する政権であるという。▼ 脱亜入欧を実践したというナショナリズムを持っていることが日本と似ているトルコ。アム・ダリア川南側の通り徘徊する遊牧系トルコ民族「セルジューク」が、やがてイラン高原を支配、11世紀にはアナトリア高原に入っていくことで、イラン高原をこえたペルシャ語の高尚言語としての広まりを化をもたらしい。セルジュークは、あつかいにくい遊牧系トゥルクマーン族をアナトリア高原に移しピザンツ帝国との戦闘にあたらせた。支配が開始されると、トルコ人が大挙移住。これがアナトリアのトルコ化の開始となって、13-14世紀までに完了するという。一方、トルコ語文学が完成するのは、トルコ人がイラン文化を愛したこともあって、オスマン朝まで待たねばならない。そのオスマン朝では、各宗派ごとに「棲み分け」とミッレト制による自治がおこなわれ、それが欧州の自国宗派保護を名目にした介入をまねいていく。パレスチナ問題も、ギリシャ正教とカトリックの聖地管轄問題に端を発するという。19世紀、民族自立の名の下、次々と独立していくことで、多民族国家オスマン朝は、「トルコ・イスラム国家」の性格を次第に強めていくことになり、独立をめぐって暴力の応酬がひきおこされる。それが、広範な自治を与えられてオスマン朝に誇りを抱いており、元々は独立よりも帝国内でトルコ人と同等の権利と自由を求めていたにすぎない、アラブ人の離反を招いてしまう。アブデュルハミト2世の専制政治を打倒した「青年トルコ党」は、オスマン人のオスマンを説き平等を公約したものの、実態はトルコ人のためのトルコ人にほかならなかった。「パン・トルコ主義」は「パン・アラブ主義」をまねき、アラブとトルコの連携が寸断。「アラビアのローレンス」によるアラブの反乱につながっていく。▼ 雑学も楽しい。「岩のドーム」は、元は、ジュピター神を祭る神殿なんだとか。トルコ語は、ペルシャ語と同様、以前はアラビア文字を使っていたが、チベット・モンゴル語・日本語と語順が同じであるアルタイ語系だという。盛時のバグダードには、商品ごとに区画分けされたスーク(市場)をもち、厳しい品質監視が政府の手でなされていて、6万の公衆浴場があったそうだ。レザー・シャーは、イラン人をアーリア人種にカウントするよう、ナチスに要請していたり、トルコ人はイスラム神秘主義の影響を強く受けていた事実があるという。委任統治領というのは、国際連盟憲章が戦勝国による敗戦国の領土併合を認めていないことによって誕生したこと。イランの圧力によってイラクはバスラの玄関口「シャトル・アラブ川」のかつての全域領有から全域放棄に次々と譲歩を余儀なくされていったこと。イランは石油精製設備が乏しいのでガソリンの4割を輸入に依存していること。とくに、中央アジアをめぐり、トルコ・イランが対立している様子は、なかなか日本の新聞で伝えられることが少なく、本書を読むことは、中央アジアをめぐる政治を理解する上で、裨益することたいへんなものがあろう。▼ 欲をいえば、アラブ人がのっぺりとした印象がぬぐえないことか。とくにウマイヤ朝以降、アラブ人の民族性について、「自らを統治するもの、他者を奉仕するもの」と位置づける意識をもつとしているが、ならばトルコ人とアラブ人の400年に及ぶ共闘関係は、どのように説明するつもりなのか。アッバース朝の次が、トルコ人からのアラブ人の離反、すなわち1000年も時代が飛んでしまうのでは、著しく説得力がかける。西アフリカから湾岸まで広がる、アラブ人に通用するような議論とも思えない。また、アフマディネジャド政権がナショナリズムである、とされ、イスラムとナショナリズムが敵対するものとして描かれがちなのも気がかりだ。シーア派がイラン・ナショナリズムとして受容されたように、両者は対立するものではない、という所論とどう整合しているのか。読んでいて、よく理解できなかった。▼ しかし、この書からえる情報は素晴らしい。秋の夜長に是非お勧めしたい一冊である。評価 ★★★★価格: ¥ 924 (税込)追伸 更新が遅くなってしまい申し訳ありません。←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Oct 8, 2006
コメント(1)
-

★ 宮田律 『中東イスラーム民族史』 中公新書 (新刊) 1
▼ 中東情勢は複雑怪奇 ……… 平沼騏一郎ならそう口走りたくなるような、イラン核開発に、ハマス・ヒズボラに、アザガデン油田利権の危機。昨今くらい、歴史に由来した、中東の政治情勢を丁寧に解説してくれる本が、求められていることはありません。そんな人のための本、といっても良いでしょう。▼ 目次はこんな感じ 序章 中東三民族の特徴 第1章 イスラームを誕生させたアラブ 第2章 イスラーム世界に多大な影響を与えたイラン文明 第3章 欧米支配とイラン民族主義の台頭 第4章 トルコ民族の興亡 第5章 共存していたトルコ人とアラブ人 第6章 近現代におけるアラブ・ナショナリズム 第7章 トルコをめぐる現代中東の国際関係 第8章 突出するイラン・ナショナリズムと米欧・イスラエル▼ 全般的に重なりあう記述が多い点が難点かもしれない。 そのためトピックごとにまとめてみましょうか。▼ 近年、中東史は、アラブ、トルコ、イラン3民族競合史に、ユダヤ人が入りこんで「四国志」ならぬ「四民族史」になっている。イラン・イラク戦争でも、スンニー派シリアは、シーア派イランと結びついていて、イラクとはお互いに「アラブ世界の統一と発展、植民地支配からの解放、社会主義」であるバース主義を唱えながら、国家同士は競合下にあったという。とはいえ、そのためシリアもイラクも、世俗主義が強い。一方でヨルダンは、アラブ・ベドウィンが多数派パレスチナ人を支配する、イラクと同じような少数派支配国家。どこまでも中東の政体というのは、ゴチャゴチャしていて難しい。▼ 本書によれば、イスラム原理主義は、アラブ民族主義の失墜、イスラエルの勝利、アラブ諸国の西欧型経済発展計画の失敗によって、世俗主義へのアンチテーゼとして社会に広まっているらしい。トルコでも、「貧困層の受け皿」として、原理主義が台頭している。しかし、古代ペルシャ文化とペルシア語への強い誇りをもち、アラブに同化することがなかったイランでは、貧富の差の拡大、若者失業者の改善、政治腐敗、民主主義の欠如といった、イスラム原理主義の原因となった状況がまったく改善されていない。アラブとイランには、文化障壁があるので伝わらないのだ、とか。▼ そんな現代中東事情を押さえつつも、その歴史を明らかにしていく。▼ 今も、強力な部族社会であるアラブ。多神教を堕落としたムハンマドは、教徒の代表だけではなく、軍司令官でもあった。このことからみてもイスラムは、教徒共同体が必要なため、宗教だけではなく、政治・社会制度にほかならない。隊商組織化・軍事遠征に手馴れていたアラブ人たちは、有能な征服者・支配者として、つぎつぎと支配を広げていく。アラビア語は行政用語、多様な非アラブ系住人が流入する都市での共通語として、民族の違いを越えて、ゆっくりと「アラブ化」が浸透していった。軍人による貴族政治ウマイヤ朝に対して、アッバース朝は、イラン人の登用をおこなうとともに、カリフが「ペルシャ化」して「絶対的権威」になっていったという指摘には唸らされる。そんな違いがあったんだ。▼ 近現代アラブのナショナリズムとイスラムは、トルコからアラブが独立した後に、英仏などの委任統治勢力に敵対することになった。とはいえアラブ・ナショナリズムの本格的勃興は、イスラエル建国まで待たなければならない。1967年中東戦争の敗北、70年ナセルの死、79年エジプト単独講和で、アラブ・ナショナリズムは退潮してしまう。▼ トルコ、ペルシャ(イラン)と違い、アラブは統一されていないので、われわれには3者が絡まる外交関係が良くわからない。本書のアラブ編の白眉は、この国家間関係の整理にあるのではないか。仲が良かったの国家同士は、「パフラヴィー朝イラン-イスラエル」「湾岸保守王国-アメリカ」「かつてのエジプト-シリア-ソ連」「建国当初のイスラエル-ソ連」「トルコ-イスラエル」。仲が悪いのは「イラン-アラブ」以外には「シリア-イラク」「イラク-イラン」「シリア-トルコ」といった隣接諸国なんだとか。トルコは、伝統的にアメリカ・西側陣営につき、アラブと仲が悪かったものの、キプロス領有問題とイスラエルの対アラブ勝利によって、1970年代には、「アラブ-トルコ関係」は蜜月関係になったという。またトルコは、エジプト・イランとは、競合関係にあるという。その一方、近年イランでは、保守穏健派(聖職者・バザール商人:ラフサンジャニ元大統領)・保守強硬派(中下層:アフマディネジャド現大統領)・改革派(ハタミ前大統領)の対立関係があるようだ。イランの影響力はイラクにも浸透していて、アメリカも心配しているが、イラク人の多くは心良く思っていない。現在のイラク・イラン接近が見られるが、それはイラク・シーア派とクルド人独立派主導の政権を快く思わず、支援しようとしないアラブ諸国に対する、イラクの怒りでもある、という観点はたいへん示唆に富む。(続きはこちら応援お願いします 長すぎて1日分では終わらなかった…)評価 ★★★★価格: ¥ 924 (税込)追伸 更新が遅くなってしまい申し訳ありません。←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Oct 6, 2006
コメント(1)
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-

- ジャンプの感想
- 週刊少年ジャンプ2025年51号感想その…
- (2025-11-18 13:00:34)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 今年も神田古本まつりに行きました。
- (2025-11-10 15:52:16)
-
-
-

- この秋読んだイチオシ本・漫画
- 禁忌の子/山口 未桜
- (2025-11-16 18:00:05)
-







