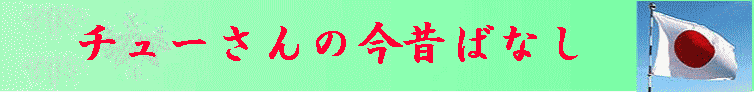2012年07月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-

エピローグ
・平成4年(1992年)3月 に 定年退職 してから、20年以上が過ぎました。平成11年(1999年) に 京都 へ行ってからも10数年が経ちました。年齢も 85歳 間近 になりました。その間、私 にも 日本 にも良いことはあまりなかった、と思います。私の場合は、平成11年(1999年) の京都旅行の年の秋に 腹腔内腫瘍 が見つかり、入院して 開腹手術、またその3年後に、別の箇所の 良性腫瘍 で入院手術、その間に 膝痛 も起こって、旅行も出来なくなりました。それで、パソコン の扱いを習得して、楽しむことを始めました。私は 老年者 ですから、これらの身体の障害の起こるのは仕方のないことですが、先進国 日本 も良くない事が続きました。天災や事件としては、 香川県大渇水、松本サリン事件、阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件、新潟県地震、そして 東日本大震災 と、大津波による 原子力発電所損壊・放射能汚染、などなど。政治については、自民党 の長期政権が平成5年(1993年)の選挙に敗れ、日本新党 の 細川内閣 にとって代わられましたが、細川政権 も1年とは持たず、再び 自民党政権 に戻り、10年ほど続きました。それがまた、民主党 に政権を奪われて、今にいたっています。 その間、どの政権も 国家財政 を建て直しできず、政権維持のためにバラマキを続け、今や 日本国 の 財政累積赤字、つまり 「国の借金」 は 千兆円 を超えています。この先、日本経済と国民の暮らし は、いったいどうなるのでしょうか ・・・・・。さて、2年あまり続けてきた、私の ブログ 「チューさんの今昔ばなし」 も、昭和3年 のころのことから書き始めて、今の時代 に来てしまいました。現在のことは、若い方々もよくご存知のことばかり。、私の 想い出日記 もそろそろ終わりにしたいと思います。ブログは、 「始めのころに書いた箇所が見にくい、面倒だ」 と、よく言われます。それで、この ブログ を、私の ホームページ に組み込んで、見ていただくことにしました。このブログを、書き初めの 昭和3年 から 最終ページまで、ホームページ 用 に改訂し、内容も書き加えて、公開しています。 目次 から、どのページでも見られます。 新ホームページアドレスは ・・・・・ http://chusan.info/ 題 名 は 「チューさんの今昔ばなしと野菜ワールド」なお、このエピローグ以後のことは、 ホームページ の方に書いていますので、そちらでご覧ください。 永い間、私のブログをご覧いただき、コメントも数々頂戴して、ありがとうございました。この ブログ は、このまま置いておきます。私の寿命があって体力が続くようでしたら、また テーマ を替えて、新しい ブログ を書き始めたいと思っています。では、最後に、皆々様のご健勝をお祈りいたします。
2012年07月30日
コメント(7)
-

退職後の京都旅行(2)・・・故郷の町よさらば!
・平成11年(1999年)3月、若いときから引き立てていただいた先輩・TM先生 の 米寿祝賀会 に出席のため 京都 へ出かけました。この年の2年前、顔に異物ができて、診断の結果、皮膚がん と分かりました。すぐに手術を受けて、患部を切除してもらいました。入院はせず、通院で事後の処置と追加観察を続けましたが、自分ももうこんなものができる年代に入ったかと感しました。兄姉も、みな世を去り、私の体にも異物ができるようになったことから、京都 に来るのも終わりかもしれない、との思いがしました。京都 も、繁華なところは以前よりも美しくなったなと思っていましたが、昔を知る者としては、ずいぶん派手なけばけばしい街になったな、とも感じていました。以前から、京都 へ来て帰る日には、円山公園 のなかの料理店で、昼食をとるようにしていました。この店は公園内の奥の南端にあって、その南側には長い白い土塀が続いています。土塀には狭い入口があって、一歩南へ入れば、東大谷本廟 の 墓地。東山 の中腹に見渡すかぎり 墓石また墓石。私の姉二人 もここに眠っています。この1枚の土塀を隔てて、こちら側 は、桜が咲き観光客のざわめきがにぎやかな、この世の世界。そして、あちら側 は、この世のつとめを終えた人たちの眠る、静寂安楽 の世界。私はここへ来るとき、いつもその思いがしました。年とってからはなおさらです。 長楽寺門前この境界の公園側を奥へ登っていくと、お寺があります。名は 長楽寺。小さいお寺ですが、歴史は古く、源平合戦 で敗れて都へ連れ戻された、平清盛 の娘・中宮・徳子 (建礼門院) は、ここで落飾したと伝えられています。 安徳天皇遺品 崇徳上皇念持仏お寺には、安徳天皇・崇徳上皇 の遺品が今も残されています。最奥には 鐘楼 があって、遺品を拝観したものは、鐘を突いてもよいということでした。この釣鐘は、まさに “祇園精舎の鐘” 。突き鳴らす鐘の音は “諸行無常” と響いているように聞こえました。 長楽寺の鐘を突く妻
2012年07月25日
コメント(1)
-

退職後の京都旅行(1)
・停年退職後、京都へは毎年行っていました。私も妻も永く京都に住んでいましたから、たいていのところは見ていますが、その後公開するようになったところを見たり、まだ訪れていない店で食事をしたりしました。まずは墓参。私の両親兄姉の墓は東山の西大谷の最奧、清水寺に近いところにあります。以前は静かな場所でしたが、近くの道路が、近ごろは “ちゃわん坂” と言うようになり、観光客の声が聞こえるようになりました。 東山・大谷本廟(西大谷)入口東山の高台寺も観覧できるようになって、豊臣秀吉の妻・高台院の遺品や高台寺蒔絵などを見ました。 高台寺有名料理店のうち、七条大和大路近くの「わらじや」で、名物の “うぞうすい” を食べました。この店は、私が通学した小学校の学区内にあり、創業4百年といわれています。すぐ東の 国立博物館 一帯が、昔、方広寺大仏 の境内だったことから、店の名は、この場所で 豊臣秀吉 がわらじを脱いで休息した、との故事からというそうです。店先には、大きなわらじが吊るしてあります。この店は戦前、私の店の得意先で、私も小学生のころ何回か配達に行ったことがありますが、客になって料理を食べたことはまだありませんでした。この店の名物は “うぞうすい” です。“うぞうすい”というのは、鰻の骨を抜き、ほかの具も加えて雑炊仕立てにしたものです。 うぞうすいを食べる妻「わらじや」 の帰りに、通学した小学校やその付近一帯を歩いて見ました。60年昔と大きくは変わっていないな、という印象でした。自分の年齢も70歳に近くなり、将来よりも過ぎた昔を振り返ることが多くなっていました。
2012年07月18日
コメント(1)
-

著書出版
・停年後の楽しみに、旅行とともに、日本の古典文学書朗読を始めたことを、6月18日のブログに書きました。古事記から読み始めて萬葉集に進みましたが、こんな古典の中にも野菜が時々出てくる、それも食べ物としてだけでなく、物語や歌での情景表現の材料としても使われていることに興味を持ちました。それで一旦初めに戻って、野菜についての記載のある箇所に、ラベルを付けていくことにしました。4年ほどかかった古典文学書朗読を終えてから、もう一度、野菜の登場する箇所を読み返しました。そのころ購読していて、ときどき投稿もしていた新聞社にこの話をしたら、取材に行くと言って記者がやって来ました。それからしばらくして、この新聞の文化欄に 「古典文学に野菜いっぱい」 との題で写真のような記事を掲載してくれました。 古典文学に野菜いっぱい」の新聞記事これが掲載されると、 「記事を読んだ」 といって古い友人から手紙が来たり、他の 新聞社 からの取材を受けたりしました。また、これをまとめて本にしろと、いくつかの 出版社 から誘いがありました。今までも同じ専門の先輩たちが大昔の野菜を調べて著書を出していますが、どれも野菜の渡来・来歴・昔の食生活を記録的に調べたものばかりでした。私は、それよりも、野菜がそれぞれの古典文学作品での、季節の表現や情景描写や比喩などの材料としての使われ方に重きを置いて、著書を書いてみようと考えました。ただ、今まで、論文調や教科書式の固い文章ばかり書いてきた癖が付いているので、それを直して、小説風の砕けた文体で書くのに苦労しました。それにモノクロながら野菜の挿絵も描いたので、原稿の出來上がりまで1年近くかかってしまいました。単行本にしてくれるという大阪の出版社を選び、数回の校正を経て、平成10年(1998年)8月、 「古典文学と野菜」 の書名で刊行。この種の本は珍しいと思われたのか、この年の日本図書館協会選定図書に選ばれました。おもに各地の図書館が買ってくれたようです。 著書「古典文学と野菜」停年退職後、何か仕事らしいことができたらと思っていましたが、あとに残るものができたのは、ほんとに嬉しいことでした。気がつくと、私の60歳代も終わりになっていました。
2012年07月13日
コメント(1)
-

停年旅行(3)・・・先祖の地へ
・平成6年(1994年)5月、金沢観光旅行に続いて、隣の福井県に入り、父の出身地を10年余ぶりに訪れました。峠を越せば石川県という山間地です。昔はひとつの村でしたが、今は合併して、坂井市の一地区になっています。夏は涼しいのですが、冬は豪雪の地です。田畑は少なく、林業が主体の山村。以前は交通機関がなく、電車の終点から2時間ほども歩かねばなりませんでした。私どもは芦原温泉駅からタクシーに乗り、川沿いの道を通って地区に入りました。私は10回目、妻は2回目の訪問です。着いて驚いたことには、地区の中央を貫通して幅8メートルほどの道路ができていました。国道364号線だそうで、いずれは石川県の山中温泉へ延伸するとの話でした。旧村道と交わるところが交差点になって、信号機が付いているのを見て、時代も変わったなと思いました。 父の郷里の家人一倍元気だった当主の従兄弟も、70歳になって年老いた感じでしたが、従兄弟の孫3人が中学生、小学生となってにぎやかでした。先祖代々の墓に参り、無事に停年まで勤め終えられたことを報告しました。地区に住んでいた伯父や伯母たちもすでに亡く、これらの親類の墓にも詣で、各家へも訪れて仏壇を拝みました。自分たちも高年者となり、再びこの地を訪れることが難しいだろうと思い、地区の中をあらためてよく見て回りました。父の実家のすぐそばを流れる川をまたいで、国道に新しく橋が架けられていました。名付けて “ひろせばし” 。 ひろせばし地区を流れる川は、このあたりで浅く広がっているので、昔から この付近一帯を 広瀬 と呼んでいたようです。父の実家で一泊した翌日、別れを惜しみながら、タクシーで新しい国道364号を南へトンネルを抜け、坂道を降り,九頭竜川を渡って永平寺へ。 永平寺永平寺は、開祖・道元(どうげん)禅師が、京都の宗派争いを避けて、北陸のこの僻地を選び、ここに禪の修行道場を開いて800年、今も、京都の観光地化した寺院と違って、曹洞宗(そうとうしゅう)のきびしい禪の修行場としての気風が感じられる寺でした。この年の北陸行きは、金沢から始めて、父祖の地を訪れて先祖の霊を拝み、永平寺で真の仏道の修行場を見る良い旅でした。
2012年07月07日
コメント(1)
全5件 (5件中 1-5件目)
1