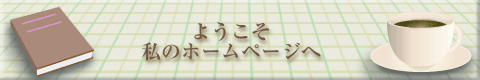全662件 (662件中 1-50件目)
-
バラ色の薔薇が咲いた
ノースポールを背景に薔薇が咲いた。いわゆるバラ色薔薇には色々の色があるが最初はこの色次に赤。近頃はブルーの薔薇があるらしい。薔薇はバラ色がよい。夢がある。突然ですがモネの家は暫らく旅に出ます。長い間ありがとうございました。
2007年05月30日
コメント(1)
-
アルペンブルーが咲いた
アルペンブルーは花びらが5枚のブルーの花である。アルペンブルーは初夏の花でこれが咲くといよいよ夏に入る。アルペンブルーはよく増える花である。放っておくとあっという間にアルペンブルーで覆いつくされる。モネの家の庭のアルペンブルーはまだ小勢力だが油断は禁物
2007年05月28日
コメント(0)
-

オリーブの花が咲いた
オリーブの花が咲いた白い小さな花である。モネの家の庭にもオリーブの実ができるか
2007年05月25日
コメント(2)
-
白地に赤、アマリリス開花
アマリリスの花が咲いた。白地に赤、直径15センチ以上の大きな花が咲いた。アマリリスは気温が暖かくなってから急に成長し一気に花を咲かせる。この成長の仕方はアマリリスが他の花々と違うところアマリリスは大きな球根に貯えた栄養で花を咲かせる。アマリリスの花を次の年にも咲かせるためには今年の花が終わってからの手入れが大切だ。近年は水耕栽培用のアマリリスの球根が千円前後で売られている。アマリリスの球根はクリスマスの頃から売られているが春になってからがお買い得のようだ。時々売れ残ったアマリリスの球根の中に掘り出し物があったりする。種苗店は処分価格で出しているところもある。但し、ほしい品種のアマリリスがあれば早めに買っておくに越したことはない。水耕栽培用のアマリリスの球根を花が終わった後、土に植えても来年咲くことがある。アマリリスは日の光が強いところよりも少し日陰になるところが良いのかもしれない。木陰に植えられたアマリリスは気の付かないうちに咲いていることがある。アマリリスの花が満開になってから見つけると宝物を見つけた感じである。アマリリスの花は大きい、アルペンブルーの何百個分であろうか。今までに見たアマリリスの花は赤いのと白地に赤の筋が入ったもの、白いもの。モネの家の庭のアマリリスは白地に赤の筋が入ったもの。
2007年05月23日
コメント(0)
-

ブルースターが咲いた。
ブルースターが咲いた。数ヶ月ぶりである。花の色がやや淡いブルーなのであまり派手さはない。緑の木陰にそっと咲いているので時々気が付く。そのときには近寄ってしっかりと眺める。ブルーの花びらが五つあって星の形に見える。花の花びらの数は三、四、五、六、その他とあるようだ。四枚、五枚、六枚をよく見かける。菜の花は四枚、ブルースターは五枚。360度を割り切れる数になっているようだ。花びらが7枚の花や13枚の花ないだろうと思うがどうだろう。四葉のクローバーがあるからひょっとするとひょっとしているかもしれない。割り切れないものがあったとしても自然のすること。花センターのブルースターの花の色はしっかりしているがモネの家の庭のブルースターの花の色は淡い。品種によるものか栽培条件によるものか栽培条件で変わるものなら色々試してみるのも面白そうだ。家庭園芸栽培大百科花の品種改良入門
2007年05月21日
コメント(1)
-

藤の花は終わりにけり
藤の花が咲いたと騒いでいたのは何時のことだったか。花はもう散ってしまって小さな莢ができている。これが十センチほどの大きさに育つ。中には種がいくつか含まれている。品種改良するにはこの種が必要であろうが花を楽しむためだけであれば一株か二株の藤の木があれば良い。この藤の莢は花が終わった後の藤の余韻として冬まで眺めることができる。人類としては藤の莢はとりあえず眺めるだけの価値を見出しているが近年は流行のバイオマスなどに使えないかと思うが生産量は極めて少なそうだ。淑物としての種子の生産効率も稲や大豆などと比べるとかなり小さい。これではバイオマス燃料などの原料としても期待できない。乗用車1台で年間1万キロメートルをリッター当り16キロメートル走ると仮定すると使うガソリンは625リットルとなる。リッター130円なら81,250円比重を0.85としてガソリンの重量を求めると531.25kgとなる。豆などからその重量の半分の燃料が取れるならば1,062.5kgの豆があれば乗用車を1年間走らせることができると考えるの素人考えの極致だろうか。1, 062.5kgの豆を得るために大豆なら4反(4000平米)程度要ることになる。藤の莢からはとてもそれほど大量の種子を取ることはできない。藤の種からバイオ燃料はモネの家の庭の空想物語。日本における自動車バイオ燃料の普及に向けて菜の花エコ革命エネルギー作物の事典バイオマスで拓く循環型システム
2007年05月18日
コメント(0)
-

田のあぜに野蒜の種が
田植えから一月近くが経つ田んぼの稲はしっかりと根付いて大きくなり始めた。そんな田んぼを見ていると伸びるが目に入った。田という装置は米の生産に非常に強力に貢献しているが他の植物たちにとっても都合のいいこともあるらしい。この野蒜は大きい。丈は高いし茎も太い。できた種もしっかりと大きい。野蒜は畑地でよく見かける。それは痩せて痛々しいほどであるが、田のあぜに育つ野蒜は人間で言うと朝青龍のようなものといえるかとにかく大きい。田園地帯の人々にとって、野蒜は山菜ではなく単なる雑草。稲作に特に悪さをするわけでもなく役に立っているわけでもなさそうだ。イチゴにニラ、ナスに大麦、きゅうりに落花生を混色すると虫が来ないらしいが、野蒜があることによって何かの害虫が稲に寄ってこないということがあれば良いのだが。田のあぜは色々なことに有効利用されている。あぜの最大の理由は水漏れを防ぐことである。近年はトラクターに巨大な独楽を横倒しにしたようなものであぜを短時間で効率よくつけているところがある。しかし、これも使い方を熟知していないと全く役に立っていない。下地の草を刈ったり、枯れ草を除去して下地を整えた上にあぜをつけなければあぜの上面だけ残って肝心の漏水防止を担う部分が崩れ落ち、ざる状態になりかねない。昔のあぜは鋤簾というものを使って人力で丁寧に仕上げていた。時々モグラが直径5センチほどの穴を開け、水を漏らしたが、通常の状態では水を漏らすことはなかった。このあぜに農家は大豆、小豆、サトイモなどを植えて抑草、あぜの補強、生産性の向上などを図っていた。また、彼岸花が適当に自生していて飢饉時の荒蕪作物といわれていた。ひょっとすると野蒜も飢饉時の荒蕪作物としてあぜに導入されていたのかもしれない。地域が異なると農業の方法にも違いはある。モネの家の庭にはこんな大きな野蒜は育っていない。草木花歳時記(春の巻)母と子の野草料理
2007年05月16日
コメント(0)
-

桑の実はまだ若い
桑の実が大きくなってきた。桑の実は小さな実がいくつも集まって一つの実を作っているようだ。もう半月ほど経てば熟した実がができるであろう。赤色から濃い紫色に変わればよく熟している。桑の種類にも色々あるようで小さな実、大きな実が成る品種がある。大きな実は食べやすそうであるが以前食べた実は甘さが足りなかった。品種によるものか土地の肥沃さ加減によるものかはわからなかった。この桑の実は甘さを追及した桑の品種のようだ。今は実に棘のようなものがついているがよく熟すと目立たなくなる。実を作っている小さな一粒一粒が膨らんでその中に隠れてしまうか花が何時咲いていたのか気が付かなかった。あまり目立たない花を咲かせているようだ。気が付くとポッコリと実がついている。種子が十分成長するまでは目立たぬようひっそりとしている。野山でも実が赤く熟して緑色の葉っぱのスキマから見えるようになって桑があると気づく。このことは桑の生き方かもしれない。モネの家の庭の桑の実はまもなく自己主張をする。白実桑《果樹苗》☆超大実品種!☆桑の実食べて元気になろう! マルベリー“ポップベリー” 大苗
2007年05月14日
コメント(3)
-

楚々と庭石菖(ニワセキショウ)咲く
ニワセキショウの花が咲いた。庭中にポツポツと咲いている。アヤメ科の植物だそうだ。五弁の花びらがついている。色は薄紫から濃い紫まであるようだ。モネの家の庭では薄紫のが咲いている。花が終わるとぽつんと小さな実ができる。これからまた来年芽が出て花が咲くのであろう。ニワセキショウは回りと仲良く暮らしているらしく大きな花が終わった後であるとかまだ他の花が進出していない痩せ地などによく生えている。増え方もあまり強力ではなさそうだ。ぐい飲み程度の大きさの鉢に一株植えて机の片隅に置くと部屋が和む。小さな花は小さな花で楽しめる。楚々と咲く庭石菖(ニワセキショウ)はモネの家の庭の初夏の風物詩身近なときめき自然散歩田園風物詩
2007年05月11日
コメント(0)
-

シランが花盛り
立夏を過ぎた。夏に入った。昨日は真夏日を迎えた地域もあった。夏の到来が早くなったように思う。今度のサミットでは2050年までに温室効果ガスの排出を半減するという提案をするそうだ。2020年までに温室効果ガスの排出を減少傾向にする必要があるらしい。成功すると温暖化傾向は産業革命ごろの2度上昇程度に収まるそうだ。2050年はあと43年。長いようでもあっという間に来てしまう。シランが花盛りであるが花盛りの時期が少し早くなるだけで済むかもしれない。山野草 シラン■宿根草■ブルーシラン9cmポット苗2個セット
2007年05月09日
コメント(1)
-

コデマリが咲いた。
白い小さな花が無数集まってコデマリが咲いた。小さな白い花を一つよく見ると五枚の花びらがついている。めしべが五本、おしべが十数本付いている。これだけあれば大量の種子ができそうなものだがコデマリのこばえが大発生し他と頃を見たことはない。種子ができるのはまれなのかもしれない。コデマリは小さな花が集まって直径4から5センチくらいの半球上の花の塊を作っている。この花だけを飾ってもよいし他の花と組み合わせても良い。庭にある花をそのまま眺めるのも良い。大量の小さな花を一輪一輪眺めていくのも時のたつのを忘れて良い。花が咲いたときに良い形にするには前の年からの手入れが要りそうだがただ花を咲かせて楽しむには特別な手入れは要らない。コデマリはあまり手を掛けなくても花が咲いてくれる。
2007年05月07日
コメント(2)
-

レタスとテントウムシ
レタスにテントウムシがやってきた。テントウムシは星が七つあるテントウムシ。このテントウムシは害虫の天敵らしい。いつつ星は害虫らしい。ナナテントウムシがいるということはこのレタスに何か害虫がいるようだ。アブラムシだろうか。目で見てもよく分からない。このナナホシテントウムシはカメラを向けるとちょっとポーズを取ってからさっさと葉の裏側へ回ってしまった。ナナホシテントウムシにとって人間は脅威に見えるらしい。子供の頃はテントウムシとよく遊んだ。テントウムシを採ってきて掌に載せて動くさまをじっと見ている。それで何をするわけでもないがテントウムシが動いているのが不思議で見ていた。テントウムシにとっては迷惑だったかもしれない。空腹でえさを探して動き回っていたのかもしれない。あるいはちょうど退屈していたので人間の子供相手に気晴らしをしていたのか。掌を動き回って、そして不意に羽を広げてぱっとどこかへ飛び立ってしまう。テントウムシの綺麗なつるつるした羽の下側にやわらかい羽があってそれで飛んでいく。今の季節は大根や白菜などの花にアブラムシがびっしりついている。そのアブラムシをめがけてどこからともなくテントウムシが寄ってくる。このテントウムシはちょっと寄り道をしているのかもしれない。天敵戦争への誘い「ただの虫」を無視しない農業虫と草木のネットワーク天敵利用で農薬半減植物は考えるオオムギ天敵のはなし
2007年05月02日
コメント(0)
-

青いイチゴ、イチゴの季節
イチゴの蔓にイチゴが実った。まだ青い。白いというほうが正確だろうか。白い花が終わって緑色を帯びた実がつきだんだん大きくなって緑色から白みを帯びてくると実の先端の方から赤みが差してくる。全体が赤くなると出来上がり。お店には赤く熟したイチゴが並んでいる。イチゴの蔓には緑色から赤いのまで色々揃っている。全体が赤くなるまで待てなくて半分ぐらい赤くなったイチゴを食べたこともある。酸っぱいという言い方は適切ではない。お酢のような酸っぱさではない。草の味といったほうが的確だと思う。未熟な味である。やはりイチゴは赤く熟したものがおいしい。イチゴ栽培は儲かるのであろうか、近くの農家はイチゴハウスを増設していた。イチゴ農家にも様々あって、イチゴの苗を地面に直接植えている農家もあれば高設栽培といって腰よりちょっと高い棚に置いたポットやプランターに苗を植えたり、液肥を流す装置をつけた設備に苗を植えたりしている。増設していたイチゴハウスはどのタイプのものを作るつもりだろうか。加温したり、冷したりして今ではほぼ年中イチゴを食べられるようになった。でも、本来のイチゴは春のもの。だんだん赤くなってくるのじっと待つのもイチゴの楽しみ方イチゴの作業便利帳増補改訂イチゴ
2007年05月01日
コメント(0)
-

ピンクの渦流に想う。
ピンク色の椿の花が咲いた。このピンク色の椿の花は長々と咲き続ける。咲き始めが何時だったのか忘れてしまった。2月だったとすれば2ヶ月咲き続けている。まだ蕾はたくさんあるのでこれからもこのピンクの椿は咲き続けるだろう。昨年はこんなに長く咲いていただろうか。暖冬と春先の冷え込んだのが影響しているのかと考える。時々思い出したようにピンクの花を見せてくれるのはうれしい。全開したばかりという花はピンク色が透き通ったように見える。時間が起つと透明感が薄れ、実体感がましてくる。花が充実してくるというのか老いるというのか。花びらの先端から茶色実を帯びてくる。花は一つ終われば次の花が咲いて長い期間椿の花を楽しめるが個々の花一輪については花の命は短い。花一輪を観察してみると数十枚の花びらが重なり合って一つの花を形成している。並び方は外から中心へ向かってらせん状に並んでいるというべきか中心から外へ向かってらせん状に広がっているというべきか。花びらは数えた花では60枚。5枚が一組のなっているようだ。12組が少しずつ不規則に角度を変えて重なっている。真ん中には象牙色のとがったものがある。これも時間が経てば花びらになっていくのか、それともこれがおしべめしべなのか分からない。赤い椿であれば真ん中におしべめしべがあってその奥に甘い蜜がある。小鳥たちがやってきて蜜を吸う。時には残酷に人間が花を取って吸うこともある。ピンクの椿の花はどのような仕組みで種を作るのか花を見ただけでは分からない。話せば、稼ぐ
2007年04月27日
コメント(0)
-

カラスのエンドウ
カラスのエンドウの花があちらこちらで咲いている。紫色のカラスのエンドウの花が咲いている。もう花が終わって莢ができているカラスのエンドウもある。カラスのエンドウの花は一斉に咲くのではないようだ。カラスのエンドウの花は長い期間に少しずつ咲いていく。花が咲く時期をずらせることで一定の期間内にできる種は少ないが生き残りの確率を高めているといえる。いつでも種を生産し続けている。カラスのエンドウは弱い植物だと思う。まだ、他の植物が出てこない早春から花を咲かせて春中花を咲かせている。他の植物が出てくると枯れていなくなってしまう。カラスのエンドウは他の植物が進出してこない期間帯を狙って花を咲かせている。これはカラスのエンドウの見事な生存戦略かもしれない。場所を選ぶ、時間を選ぶなどして勝てるところで勝つ、あるいは適するところで生存する。中小零細企業にとっては生き残り戦略策定のヒントになる。新分野進出を考える場合も強い競合がいるところへ不用意に進出してはいけない。競合のないところ、あっても弱いところへ進出する。新しい市場では他の強豪が進出してくる前に成果を収めてさっさと退出する。一攫千金を目指すのではなく小さな成果を長い期間にわたって得られる仕組みを作る。などなど、カラスのエンドウを見て反省することは多い。カラスのエンドウはモネの家の庭で生存競争を繰り広げている。モネの家は日本経済、地方経済の中で立ち上がれなくて悪戦苦闘している。中小企業経営の生き残り戦略「負けるが勝ち」の生き残り戦略
2007年04月26日
コメント(0)
-

ハナミズキが咲き始めた。
ハナミズキの花がぽつぽつと咲き始めた。庭木のハナミズキの中の一本に花が咲いた。今年のハナミズキの魁である。街路樹として植えられているハナミズキの開花はもう少し先のようだ街路樹がのハナミズキが一斉に咲くと通りが明るくなる。例年四月末から五月初めに咲いているようだ。連休中に咲くのか楽しみである。庭にあるハナミズキは赤が入っているものと白とがある。ハナミズキは普通に水をやっておれば育てるのは簡単なようだ。乾燥しないところでは放任でも今のところは順調に育っている。街路樹として植えられたもので枯れているものを見ることがある。植樹されてから根が活着するまでの間に水分が不足したのかもしれない。新しく植樹された街路樹で一昨年、昨年と順調に花を咲かせていた。今のところは枯れることなく無事に育っているようだ。今年はどんな花を咲かせるのか楽しみである。商工会議所の方たちが音頭を取って市の花として定着してきた。モネの家の庭にハナミズキがあるのも街路樹のハナミズキの美しさに惹かれたため。町の木公園の木図鑑(春・夏)町の木公園の木図鑑(秋・冬)散歩が楽しくなる樹の蘊蓄葉形・花色でひける木の名前がわかる事典街路樹
2007年04月25日
コメント(0)
-

藤に囲まれたピンクのチューリップ
花を咲かせた藤の若木の根元からピンクのチューリップが一輪花を咲かせた。チューリップは赤と黄色が良いと思っているがピンクのチューリップ。薄紫の藤の花とピンクのチューリップの組合せでなんとなく穏やかな色彩になっている。まもなくゴールデンウィークだがこの花たちはそれまで持つだろうか。端午の節句の花は菖蒲なのでこの花たちの出番ではない。この花たちはみどりの日を飾ることができるかどうか。市中を歩いていると驚くほど大きなチューリップにであう。花びらが開いたとき20センチはあろうかと思う大きさである。品種のほか育て方によると思われるが実に立派なものだと思う。このピンクのチューリップは痩せ地に植えられているので球根自身が持つ養分のみで花を咲かせている。よく咲いたものだと拍手を送りたい。よく手入れしても来年は今年と同じぐらいの花を咲かせられるかどうか。このチューリップを楽しむとき、アジュガの青紫と組み合わせてみると色の対比が面白いかなと思う。ほかに赤や黄色のチューリップと一緒にするのも良いと思う。濃紫のチューリップとの組合せも考えられるがやめにしたい。バランの濃い緑とあわせてみたらどうかとも考える。チューリップが好きな人のうち赤、黄、ピンク、その他が好きな人の割合はどうなっているのだろうか。赤50%、黄色30%、ピンク10%、その他10%と独断で推定機会があればアンケート調査してみると面白い結果が出るかもしれない。やり方はフリーマーケットなどでそれぞれ100本のチューリップを無料で配布する。どれかの色が配り終えた時点でそれぞれ配った本数を勘定して割合を出してみる。あるいは素直にどの色のチューリップが好きか調査用紙に記入してもらう。只今モネの家の庭のピンクのチューリップは藤の花に囲まれて見ごろ?理念が独自性を生む感性と独創力
2007年04月24日
コメント(0)
-

濃紫色のチューリップを見ましたか
濃紫色のチューリップが咲いた。濃紫色のチューリップははじめて見る。濃紫色のチューリップができる世の中になったのか濃紫色のチューリップを作り出した人はすごい。このチューリップの色は濃い紫でつやがある。からすの羽の色と同じである。遠くで見れば黒く見えるが近づいて見ると紫色である。こんなチューリップが一輪ぽつんとあるのは異様である。華やかさがない。沸き立つものがない。という印象を受ける。珍しいものではある。これをここに持ち込んだ人の深層心理はどんなものなのか。この花を作り出した人はどのような気持ちで品種改良してきたのであろうか。花に集う虫たちはチューリップといえば赤、黄、ピンク、白ではなかったか。この濃紫色のチューリップに虫たちは集うのであろうか。虫たちが集まらなければこの濃紫色のチューリップはどうなるのだろうか。この濃紫色のチューリップは人の手によって作り出されて人の手によって増えていくことができる。自然に営みだけでこの濃紫色のチューリップができることはあるのだろうか。チューリップは赤と黄色に限るというかたくなな心の持ち主にとってはこの濃紫色のチューリップは異端である。衝撃である。そうはいうもののこれを作り出した人はこの色が自慢であり、生きる糧となっているのであろう。また、少なくとも一人、この濃紫色のチューリップに興味を示して、モネの家の庭に持ち込んだものがいる。社会全体ではかなりの数の人々がこの濃紫色のチューリップの周りに集まっていることと想像できる。この濃紫色のチューリップを排除はしないがやはりチューリップは赤と黄色に限る。四季に花を咲かせる
2007年04月23日
コメント(1)
-

アジュガが一株
アジュガの花が咲いた。アジュガは別名十二単とも言われているそうだ。アジュガよりも十二単と呼ぶ方が日本らしく奥ゆかしい感じがすると思うが種苗店の名札にはアジュガと書かれている。アジュガという名前には味がある(ない)とだじゃやれてみる。アジュガはたくさんの花の集まりでできている。これかたらたくさんの種子が飛び出してどんどん増えていくことだろう。近所では庭中に広がっているお宅がある。管理がたいへんだろうと思うが庭中がアジュガの青紫で覆われているところも壮観である。アジュガは育ちやすい花のようで栽培管理で特に気をつけることはなさそうだ。ほぼ放任でどんどん増えていく。思わぬところから生えてくるので育てることよりもむしろいかにして間引きをしていくかの方がたいへんだと思う。アジュガの花を楽しむには大量の株が並ぶ平面で楽しむか鉢植えにして一株だけをじっくり育て鑑賞するか。アジュガはどちらの楽しみ方も可能である。一株を机の片隅におけばアイデアのヒントになるか空想への入り口になる。昔の人は十二単と呼んでいた。花の種類が少ない時代には珍重されていたに違いない。庭で育てて楽しんだのか鉢植えで楽しんだのか。貴族の間で広まったのか庶民の間で広まったのか。アジュガは広く一般に広まってはいなかったようだ。小さい頃は回りにアジュガはなかったように思う。そして、モネの家の庭にも近年やっと入ってきた。季節の草花多年草・球根
2007年04月21日
コメント(0)
-

薄紫に藤の花が咲いた
藤の花が今年はたくさん咲いた。去年の藤の花は数えるほどの房しかできなかったが今年は多い。藤の花は咲き始めてからわずかの間に全開になった。藤の花は面白い咲き方をする。藤の花は咲いてから暫らくの間楽しめる。花の房についていいる一つ一つの花が上から順番に咲いて下りてくる。一番下の花が咲いて凋むまで花を楽しめる。花が終わると莢に入った種ができる。種の入った莢はかなり大きくて子供のちょうど良い遊び道具になる。昔の子供ははこれ使って遊んだものだ。遊び方は?藤の花は一房一房を楽しむのと枝全体、木全体を楽しむのとがある。木全体を眺めると花に奥行きができる。この奥行きが藤の花に奥ゆかしさを与えている。近くのお寺には数百年を経た藤の木がある。枝の長さも十メートルを超えていると思われる。花の房の長さも1メートル近くになるようだ。もうそろそろ花盛りを迎える頃である。車で行くと駐車場に苦労する。以前は列車で行って駅から徒歩でお寺まで行った。駅から同じ方向へ行く人で道は混雑していたがこの花見客を目当てに藤餅なども売られていた。藤色をした羽二重餅というというようなもの。花見のみやげ物としては結構珍重されていた。このお寺の藤を駐車場の算段をしながら見に行くべきかモネの家の庭の若木の藤の花を見て済ませるか。お寺とモネの家の庭とでは雰囲気が格段に異なるので思案する。万葉びとの四季を歩く薩摩焼ぐい呑み 藤文 直径6.2cm×高さ4.8cm
2007年04月20日
コメント(0)
-
赤いエンドウの花が咲いた
赤いエンドウの花が咲いた昨年種をまいておいたエンドウの花が咲いた。花が咲くまでにかなりの時間がかかるようだ。芽が出てから蔓が一気に成長するまでにはかなり時間がかかったが50センチぐらいからは一気に伸びた。どうもSの字を、上を右に下を左に引っ張ったような成長曲線そのままのような気がする。はじめは緩やかで途中は急速にそして後は緩やかになって最後には止まってしまう。今このエンドウは急激に立ち上がったところにいるようだ。この時期の花は生気に満ち溢れている。エンドウの花は何かの動物の形に似ているように思えて小さい頃はこの花を摘んで色々と想像をめぐらせたものだ。象さんに似ていると思ったのかウサギさんに似ていると思ったのかそれともネズミさんだったか。赤い豌豆の花を見ると他愛もないことで楽しんでたなと懐古する。今では赤い花は絹さやに違いない。早く莢ができないかな、柔らかい絹さやはどう食べるのが一番かなと考えている。ん、ちょうちょがいない。昔は、豌豆の花にはちょうちょがセットになっていたように思う。今年はちょうちょの出だしが遅いのか、それともこの付近では住めなくなったのか。豌豆の花の咲く時期が早かったのか。どうしたのだろう。モネの家の庭は昆虫にとっては住みやすいところと思っていたが勘違いだったか。もうしばらく赤いエンドウの花とちょうちょの関係を観察してみよう。
2007年04月19日
コメント(0)
-

防犯のしつけ
防犯のしつけは重要だと思う。防犯のしつけがなされているのではないかと思う出来事のあった。普段は行かない隣のご町内へ出かけたとき、ちょうど小学校の下校時間であった。ウィンドブレーカに眼鏡、花粉よけのマスクをしていたので服装はかなり怪しげであったと思う。新1年生ではないかと思われる女の子が「こんにちは」と声を掛けてくれた。山道などでは行き会ったとき見知らぬ同士でも「こんにちは」と声を掛け合うのがマナーらしいが街中で見知らぬ同士が声を掛け合うことはなかったのでびっくりした。考えてみれば人に合えば挨拶をするのが昔からの習慣である。大都会などで生活をして帰ってくると昔の習慣をどこかに置き忘れてきていた。人口が少ない地域ではほぼ校区内の生徒の顔は地域の人は大体覚えており、あれはどこそこの子、上には誰と誰、下には誰と誰と知られていたようだ。それがうっとうしいという人もいる。反面、見知らぬ人が来るとすぐ分かるものだ。この女の子は地域のものと見て挨拶をしてくれたのかそれとも学校なり家庭で防犯上のしつけとして、道で見知らぬ人と出会えば、とりあえず「こんにちは」と挨拶をして通り過ぎることと教えているのだろうか。モネの家の庭では特に考えていないが。自己プレゼンの文章術聞く技術人前でアガらない話し方のコツ
2007年04月18日
コメント(0)
-

宮崎県の東国原知事が
宮崎県の東国原知事が定例記者会見で記者の方々に「定例記者会見は必要ですか。」と質問されたとか、「あなた方の知りたいことと県民の知りたいこととは違うのではないか。」などと発言されたという報道があった。ブログのアクセスが少ないものにとっては知りたいと言って集まっていただける方たちがおられるのはのはほんとうにもったいないことだと思う。昔、佐藤栄作という方が内閣総理大臣を辞められる少し前の記者会見の席でテレビでの報道を要求されたという話を聞いたことがあった。そのときのテレビに映った記者会見だったのか、のちの報道番組を見たのか、特集記事を読んだのか忘れてしまったが。情報を発信する、伝える人、受け取る人の考え方がそれぞれに異なるので政治のリーダーが国民一人ひとりあるいは県民一人ひとりに真情を伝えるのはまことにたいへんなことだと思う。情報を受け取る側としては、「こんな報道があった。」、「それでほんとうのところはどうなんだろう。」と考える。モネの家の情報を伝える場合には、「これを伝えたいのだが受け取り手はどう受け取ってくれるのか。」と考える。しかし、モネの家の情報を伝える場合には、読んでもらう、見てもれう前にどうやって手にとってもらうかに多くの努力を要している。論理力を鍛えるトレーニングブック(意思伝達編)
2007年04月17日
コメント(0)
-

黄色い小花
黄色の小さな花が庭の至る所に顔を出している。直径1センチほどの花。年がら年中途切れることなく黄色い花を咲かせている。花が終わると綿毛のようなものができている。この花はちょっと前までは真冬には少し花を控えていたようだったが昨年あたりから夏と冬とを問わず咲いている。気が付けば庭中にネットワークを張り巡らしているようだ。最初は小さくて黄色い花という印象であったがいまでは黄色い花のじゅうたんで他の花を圧倒してしまうかもしれないという不安がある。目立たぬようそして着実に地歩を固めていき気が付いたときには不動の地位を築いているというのは一見弱者だが実は強者のひそかな戦略かも知れない。小さい花は一つの花を咲かせるのに必要なエネルギーは少なくて済む。花を大きく見せたいときには花の数を増やして大きく見せる。土地が痩せているところでは少ない数の花を咲かせ、肥沃な土地では多数の花を咲かせる。一つ一つの花には無数の種ができてそれが更に広がっていく。暑さにも寒さにも強く、少しぐらいの乾燥にも強そうだ。この花は日本の在来種ではなさそうだ。昔はこんな花を見たことはなかった。ところで今近くの堤防には菜の花らしきものが花盛りである。種類は分からないが十字花科植物の黄色い花が咲いている。猛烈な勢いで広がっている。黄色い花が堤防の斜面を覆っている様は綺麗だと思うが昔にはなかった光景のように思う。なたねの花なら種を取って油を様々に利用するとも考えられる。誰かが油を採る目的で空いている地面を有効活用しているのだろうか。モネの家の庭には黄色の小さな花はあるがまだ菜の花は押し寄せていない。ナタネの絵本菜の花エコ革命
2007年04月16日
コメント(0)
-
赤いサルビアが今
サルビアの花が咲いている。サルビアが自然に咲くのは夏から秋にかけてだったと思う今の時期に咲いているサルビアはふんだんに人の手が入っている。自然界のサルビアはまだ芽を出し始めた頃。温室で育ったサルビアにとってそのままの自然は少し寒かろうと思う。このサルビアは枯れることもなく元気に花をつけている。サルビアにとって育つために気温はたいした問題ではないようだサルビアにとっては花を咲かせるときに気温が必要なのではないかと思う。サルビアの花を一度咲かせてしまうと少々寒いときがあっても花を咲かせ続けるのではなかろうか。サルビアの花には色々の種類がある。同じ花の形で赤いのやら青いのやら色の違うものがある。赤いサルビアというものは聞くだけ、見るだけで心を弾ませる。赤いサルビアを大量に植えているところがある。今年もおそらく同じように植えられるであろう。赤いサルビアで覆われた土地はよく目立つ。どのサルビアの花も己を主張しているようで目移りする。どのサルビアの花も世界に一つしかない。時空を超えても一つしかない。このサルビアの花は花を咲かせたばかり。これからたくさんの花をつけていくことだろう。一株のサルビアからモネの家の庭にどんどん増えていくだろう。
2007年04月13日
コメント(0)
-

街には銀輪花盛
中学校の入学式が終わったらしい。新しい自転車にのった新中学一年生が颯爽と走っている。新しい自転車は不思議なことにブリジストンのベルトドライブばかり。この時期の少年少女は同じものを持ちたがる傾向にあるようだ。一年ぐらい経つと独自の方向へ歩みだす。自転車メーカーはブリジストンの外に宮田、ナショナルなどもあったと思う。でもなぜか新中学生はブリジストンに乗っている人が多い。値段が安いのか、車体が軽いのかデザインが優れているのか。以前は、てんとうむしなどというものもあったが今はどうなのだろうか。チェーンは時々外れることがあったがベルトドライブはどうなのだろうか。車体も鉄ではなくステンレススチールかアルミなのか銀色に光る車体が多い。前籠もステンレスなので丈夫で綺麗だ。街には新しい自転車に乗った新中学一年生が目立つ。リュックサックを背に負い、頭にヘルメットを着けている。新一年生は乗り方ですぐ分かる。運転中はこれを見かけたら要注意。まもなく交通安全週間が始まるとおもう。少しだれた乗り方をしているのは上級生なのでひとまず安心である。ふと思うことがある。幼稚園、小学校、中学校が同じ場所に同居している場合、幼稚園、小学校へは徒歩で通っていたのが中学生になったとたんに自転車通学になるのは不思議だ。自転車通学は中学生のステイタスシンボルなのだろうか。昔は通学の行き帰りに弟妹を乗せているのをよく見かけた。現在は二人乗り禁止になっているのでこのような光景は見なくなった。幼稚園、小学校の生徒にとっては中学生になって自転車通学するのは憧れの一つであった。この時期、街には銀輪の花が咲く。モネの家の庭の近所にも大輪が二つほど咲いていたようだ。【完全組立/防犯登録無料】2007ブリヂストン モンスターブーン 28インチ3段変速付【通勤・通学...
2007年04月12日
コメント(1)
-

黄色と紫の花びらを持つ花
パンジーだと思う。ビオラと書いてあったのかどうかあやふやだ。まとめて大き目のスミレということにしておこう。散歩していると昔ながらのスミレが群生しているところにであった。花は小さいが花は引き締まった感じ。動物で言うなら野生に満ち溢れているという言い方になろう。一株二株があちらこちらに点在しているのはよく見かけるが広い範囲に固まっているのははじめて見た。古くから続いていそうな農家の庭先であった。自然に種が飛んできたのか古の人が採種してきて蒔いたものか相当の年月を掛けて増えてきたものと思う。それに比べるとパンジーは気軽に楽しめる。春先に園芸店へ行けば必ず売っている。それを買ってきて鉢植えなり庭植えなりをして手入れすれば良い。数が欲しければ植える場所と財布と相談をすれば何とかなる。また、公園などへ行けばたいていのところは大量に植わっている。花を眺めて楽しむだけであればそれで十分。古来のスミレは鉢植えにして楽しむには花が小さすぎるのかもしれない。しかし、スミレの紫は昔から人の心をひきつけてきたようである。スミレの花は野に置いたほうが引き立つのかもしれない。そんなことを言った俳人が居られてようだ。スミレにとっても野の方が住み心地は良いのではなかろうか。パンジーやビオラは人とともに進化してきたようで野では育たないのではなかろうか。モネの家の庭のパンジーは放任で育っていくであろうか俳句鑑賞辞典欣一俳句鑑賞
2007年04月11日
コメント(0)
-

矢車草が咲いた。
矢羽に似た花びらを持つ矢車草が咲いた。咲いた矢車草は一輪だけである。青紫の矢車草が咲いた。近年の技術でを活用すれば他の色の矢車草もあるような気がする。花びらの形に変化のある矢車草もあるかもしれない。しかし、それはもう矢車草とは呼べないと思う。矢車草は矢羽に似た青紫の花びらを持つ花である。昔から矢車草とはこんなものだと思い込んできた。矢羽の形をした花びらの花は矢車草。春の青紫の花は矢車草。という風に刷り込んできた。矢車草の花全体は丸い形になっていて親しみやすい。青紫の花びらは赤や黄色の他の花に比べて未知への想像をかきたてやすい。サイダーのような爽快感がある。矢車草は増えやすくはなさそうだ。それとも土地の状況が矢車草に適していないのかもしれない。ガイラルディアなどは数年のうちに広がってしまったがモネの家の庭の矢車草はまだ一株だけである。数株は欲しいところである。草花栽培の基礎新版【農学基礎セミナー】草花栽培の基礎
2007年04月10日
コメント(0)
-

芍薬の若芽
芍薬の若芽が出てきた。春には色々な植物の若芽が出てくる。大概は若緑色をしているが芍薬は赤い。赤いので他の植物の違いがはっきりする。芍薬の花を咲かせるのは難しい。肥やしをうんとやらないと花を咲かせない。痩せ地では今年も花が咲かなかったで終わってしまう。芍薬の花が咲いているところの土は一目で違うことがわかる。腐葉土の集まりのような土である。いかにも肥えていそうな感じがする。小石があったり、茶色い土が見えていたりはしない。雑草の生え方もちがう。カヤの類が生えていることもない。柔らかそうな草が生えている。手入れが行き届いていて雑草など生えていないこともある。ぬくぬくとした感じの土に育っている芍薬はよく花を咲かせているようだ。有機栽培という農法が提唱されている。慣行栽培というやり方に対比する方法のようだ。無機肥料を多用する現在の農法への反省から昔の方法への回帰を促すような農法である。土地に有機物を戻して土の中の微生物の種類や数を増やして養分を植物が利用しやすいようにする農法らしい。良い土は触ってみるとふかふかした感じがある。いま芍薬が生えているところはそのような状態とは程遠い。ふかふかの土になるには毎年よく手入れをしても数年かかるのではないかと思う。芍薬の若芽は出てきたが今年はモネの家の庭で芍薬の花は見られないかもしれない。県知事選と県議選が終わった。それぞれ当選するべき人が当選したようである。地縁、血縁、組織、人物、政策などの要素によって支持を受け、県議選では6000票以上の支持を受けられると当選しているようだ。投票率が年々下がっているようだ。ただ、特定の郡市では群を抜いて投票率が高いところがある。その地域の選挙への関心の深さを見ることができる。その地域では選挙以外でも意外な活動を多数やっているようだ。地域の人々が様々な活動に積極であることが投票率という形で表示されたということか。仮説:新成人になってすぐ選挙に投票する機会を与えられた年代の投票率は、そうでなかった年代の投票率に比べて高い。今年、新成人になってすぐ選挙に投票する機会を与えられた年代の今後の投票率の推移をフォローしてみると面白いかもしれないとおもった。地力はよみがえる有機農法自然の実りがわかる本
2007年04月09日
コメント(0)
-
赤い方の三椏
三椏の花が満開である。庭には二株の三椏があり。一株は白、もう一株は赤である。赤の方が花としては華やかであるので今日は赤を公開。赤といってもオレンジ色に近い。ベージュに近い中に橙色があるのは華やかに思う。白いのがあって赤いのがあると赤が引き立つ。赤だけでは白と赤がある場合のようには引き立たない。以前、三椏の苗を売っているのを見かけたがかなり高かった。かんきつ類の苗に比べると2倍から3倍の感じだった。増やしたり育てたりするのが難しいのか供給に対して需要が多いのか。生け花にも使われるそうなので生産と供給ルートを作れば新しい事業になりうる可能性はある。山から市中へ山の花を直送することは可能だと思う。もし三椏の樹形を小型化できれば庭のないマンションの室内でも楽しめそうだ。庭のあるところでは三椏の自由を尊ぶこともできる。モネの家の庭ではかろうじて赤と白二株を確保している。東洋町の町長が辞任した。再度町長に立候補して事業の継続を目指すそうだ。ある人が大きな事業を進める際の一つの心得をこのように言っていたのを思い出す。「事業というのは水の入った風船をみんなが針で担いでいるようなものだ。一人だけで担ごうと力むと風船が破れてしまう。みんなが力を合わせて一斉に担いだときに事業は壊れないで成功する。」逆にたった一人の強力なリーダーシップで成功している事例もあるのでどちらか一方が正しいというわけではないが、多くの人と一緒に事業に携わる場合には参考にできる話。
2007年04月06日
コメント(1)
-

白いほうの三椏
三椏の花が満開である。庭には二株の三椏があり。一株は赤、もう一株は白である。赤の方が花としては華やかであるが今日は白を公開。県西部では三椏を栽培しているところがあるそうだ。今頃はさぞ花盛りだろうと思う。整然と直線的に植えられた三椏は壮観だろうと想像する。昔はおそらく山の中にランダムに生えていたではなかろうか。今の山の中にも時々見かける。生えている密度は昔と今でどう変わっているのだろうか。今と同じように疎らだったものを生産の能率を上げるために密植したのかも知れない。あるらしい三椏畑をアクティブには探していない。三椏畑の近所ではニュースになっているのかもしれないがココまでは届いていない。和紙を生産している組合に問い合わせるのも一つの方法かもしれないと思う。あるいは新聞社に問い合わせるという手はどうか。つつじの開花時期についてはよくニュースになっている。三椏の開花時期についてもニュースになっている可能性もある。一株の三椏と大群の三椏とまた、整列している三椏と自由に距離を取っている三椏とどれに興味をもてるだろうか。どれが一番美しいかということではなく。ただ、目に見える形にあるのはモネの家の庭にある二株の三椏のみ。出雲 民芸紙 三椏 萱漉き楮・三椏・雁皮が紙になる迄【特殊カボチャ】 タキイ アトランチック・ジャイアント [春まき野菜のタネ]【マクワ】 タキイ交配 金太郎 [春まき野菜のタネ]【世界の珍しい野菜】 花オクラ
2007年04月05日
コメント(0)
-

苔むしぬ
花を求めて庭の中を探索していると緑のじゅうたんのようなものを見つけた。様々な種類の苔を収集している人もいる。この苔にもちゃんとした名前がついているものと思うが調査していない。この苔は名前が美しいのではなくそのものが美しい。この美しい苔は何と聞かれた初めて名前が欲しくなる。とりあえずもうせんの様なので毛氈苔(仮)と付けておく。苔の成長速度はどのくらいであろうか。君が代の世界では数千年ということになっているようだ。現実世界では環境によって1年で○平方センチということではなかろうか苔の繁殖には水分が欠かせないらしい。常時水分があるようなところに苔は生えているようだ。この苔が生えているとところは特に湿った場所のようには見えない。この苔の下の土が水分を含んでいるのかもしれない。瓦礫状態の土が水分を豊かに含んだ土に変化するまでどのくらいの時間がかかったか。5~6年?、10年?、20年?理科で習った植生の変遷は、荒野からコケ類が生え、コケ類から草類、草類から低木、低木から高木の植生へ変化していくと習った。モネの家の庭での変化はどうだったのだろうか。この苔は草類を増やすの貢献し役目を終えてここにあるのか、それとも、草や木が倒れて腐葉土になったところに生えてきたのか。いまの苔の状態を見ると後者のような気がする。苔にも様々あるようだ。モネの家の庭は植物の種類が増える方向に進んでいる。農園直送 苔玉 キンメイ竹アトランティックジャイアントの種子/福種
2007年04月04日
コメント(0)
-
ほんとうの名は
見かけない花が咲いた。花の形は小さな鈴のようである。鈴といっても下がチューリップのように開いているもので鐘を小さくしたような鈴白い花びらが六枚あって、その花びらに緑色の大きな斑点が一つずつ入っている。白の部分は真っ白、雪のように真っ白である。葉っぱは水仙の葉っぱそのものである。緑色の葉っぱを背景に真っ白な花がある様子は白いライトをつけているようである。これを見つけたときには新しい花だと感じた。園芸店で似たような花の名前を見るとすずらん水仙という名前がついていた。ぴったり一致しているかどうか怪しいがとりあえずすずらん水仙としておこう。時々見かけない花が現れる。植えてすぐ花を咲かせるものもあれば数年経ってから花をさかせるものもある。花が咲いている苗を植えても翌年は花を咲かせないで忘れた頃に花を咲かせるものもある。忘れていた花が土になじんでようやく自分自身の力で花を咲かせるようになったらしい。モネの家の庭のすずらん水仙のほんとうの名前は何だろう。岩手県知事選に立候補しているサスケ氏が当選するとマスクを取るという新聞報道があった。ふと、マスクをとる取らないを論争して岩手県がよくなるのだろうかと思った。岩手県民のために何をやるかを掲げることが大切ではないかと思う。
2007年04月02日
コメント(3)
-
危機感募る気候変動
タンポポの綿毛があった。早すぎる気がする。以前は四月に入り入学式の前後にタンポポを見かけ、綿毛はその後であったように思う。半月ぐらい早いのだろうか。NHKラジオで四万十川の近くにあるトンボ博物館(?)の館長さんがトンボの羽化が例年より十日早い。だが桜の開花は例年通り。逆に春ゼミの鳴きだす時期が遅れている。生態系がめちゃくちゃになっている。といっておられた。我々のような一般のものは、今年は花が咲くのが早い程度の認識しかもっていなかったが深く自然とかかわっておられる方達はほんとうに危機感を抱いておられる。四万十川も四十年ぐらい前に比べると非常に汚れているそうだ。そういわれれば吉野の大河もうん十年に比べると別世界になっている。うん十年前は凍った池ですべることができたが現在は凍らなくなった。三月のタンポポの綿毛はまん丸でかわいいがその背景には気候変動が忍び寄っている。大丈夫なのかなあ。モネの家の庭が亜熱帯化するなどという想像はしたくない。ごめん、タンポポ君に罪はないのだ。まん丸な君はほんとうに美しい。神秘だ。自然はよくこんなものを作り出したものだ。棘のようなもの一つ一つが次の世代。この丸いものは次世代を新天地へ送り出すプラットフォーム。写真の綿毛はモネの家の庭の重要メンバー
2007年03月31日
コメント(0)
-
赤い桃の花が咲いた
赤い桃の花が咲いた桃の花であることはわかるが品種はもうわからなくなってしまった。自分ひとりで楽しむときには名前など適当に付けておけば良いのだが人と話をするときに品種がわからなくては困ることが多い。品種に関心がある人などと話すときには話題が品種に移らないように用心勝手な名前をつけて話をしても良いのだろうが新品種と思われても困る。わからなくなったものは仕方がないのでわからないといっておこう。ひょっとしたら詳しい人が識別してくれることを期待して。花はほぼ満開のが一輪、あと蕾が続々と続いている。満開の花が綺麗か、咲きかけが良いか、蕾が良いか。どの花をどの角度で撮ろうかと思案する。花一輪一輪に個性がある。太陽の光との関係で時々刻々と変化する。光の角度、その光で最も美しく見える花はどれか。その花をどちらから撮ろうか。写真を撮りながら様々に楽しめる。この赤い桃の花は赤とは言いながらやや紫がかっている。緋の赤ではない。緋の赤ではない赤も良い。モネの家の庭の赤い花々。
2007年03月30日
コメント(1)
-
ユキヤナギ、柳に見立てた想像力
ユキヤナギが咲いた。小さな花を細長い枝にそって無数につけたユキヤナギが咲いた。ユキヤナギ、漢字で書けば雪柳柳の木はつるっとした感じの幹がすっと立ち上がって斜め上方に張りだした太い枝から細長い枝が垂れ下がっている。ユキヤナギはこの細長いところが柳に似ている。ユキヤナギの枝は横もしくはやや上方に張りだしている。横に張り出して上方へ湾曲している枝もある。柳は上から下へほぼ垂直に垂れ下がっている。細長いところは共通点。枝の向きはまったく異質。異質な点をそぎ落とし、共通な点から想像を膨らませ雪柳としたのであろうか。この花、雪柳と聞かなければ白猫の尾などと勝手に付けたかもしれない。上方へ湾曲した枝が風に吹かれてゆらゆらゆれている様は昼寝の猫が尾っぽをゆらゆらさせている様に似ていないだろうか。昔の人はそのような直接目で見て感じられる喩えではなく、想像の世界での一致をユキヤナギと表現したに違いない。このような態度を奥ゆかしいと表現してよいであろうか。このユキヤナギこの時期だけ庭の花たちの主役になっている。生態系にとってはどうなのだろう。虫たちが来ているようには見えない。小鳥たちも来ていない。花が咲いているから実はできるのだと思うが関心を持って見ていなかった。ユキヤナギはこれだけ花を咲かせているがどんどん増えるということも無い。ユキヤナギはこの時期は花を咲かせるだけであとはひっそりとしている。今の一瞬、モネの家の庭の主役はユキヤナギ追加:モネの家の庭のユキヤナギは横や上方を向いている枝が多いが他の写真などを見ると柳のように垂れ下がっているものもある。昔の人も案外直接的なイメージで名前を決めたのかもしれないとも思う。若いユキヤナギの枝は横や上方を向くが古くなってくると柳のように垂れ下がるのかもしれないと推測する。ユキヤナギ 1m
2007年03月29日
コメント(1)
-

正統派桃の花咲く
桃の花が咲いた。ほんとうに桃色の花が咲いた。近年はやや白っぽいのや赤などを見ることが多かったのでこのような昔見た花の色を見ると懐かしい。旧ひな祭りは四月十九日なので花の時期は過ぎてしまう。NHKラジオ(だったと思う。)で、特派員の方が信州のひな祭りは四月三日だと報告されていた。理由は忘れてしまった。この時期信州ではりんごの花が咲いているのでしょうか。こちらではひな祭りは三月三日にする人も居れば旧のひな祭りにする人もいる。飾る花は三月なら草ボケを使い、四月なら桜、桜が無ければその時ある花を使っていたようだ。桃の節句に桃の花をちょうどいい具合に飾ることができるのはめったに無い。正統派桃の花が咲いたときに桃の節句を祝うということもできる。モネの家の庭の正統派桃の花は今が見ごろ。今朝のNHKラジオで高知県北川村のマルモッタン モネの庭の支配人の方がモネの庭のことを話されていた。北川村のモネの庭では今、ポピーが花盛りとのこと。睡蓮は四月半ばから咲き始め、五月には薔薇も咲きこの時期が最も見ごたえのある時期だと話されていた。北川村のモネの庭へは、高知市から室戸方面へ約60キロメートルだそうだ。徳島方面からだと国道55号線を室戸方面へ走って室戸から高知市方面へ向かう。徳島市から3時間半から4時間ほどで行くことができる。読んであげたいおはなし(上)
2007年03月28日
コメント(2)
-
チオドノグサ
チオドノグサの花が咲いた。ブルーの花と白の花球根で増やすものらしい。昨年秋の植えておいたもの花が咲いて暫らく経っている。花の名前がわからなかった。スミレのようでもあるがスミレではない。他に思い当たる花の名前を知らなかった。花のラベルが近くにあるが泥で汚れて読みづらい。ようやくチオドノグサかミヤマホタルカヅラのようだとわかった。葉っぱの形からチオドノグサであろうと決めてしまった。これでとりあえずはもやもやから開放される。園芸店に珍しい花があると衝動買いをする。そして、コンセプト無しで目に付いた土地に植えてしまう。はじめは覚えていたりラベルがあったりで花の名前を知っているが年が変わると思い出せなくなってしまっている。天然流といえば聞こえは良いが唯の放任である。昔、道のでき方の絵本があった。あらすじは、ある日、子牛が鼻歌交じりに草原をふらふらと散歩してい。子牛が歩いた後が草原に一筋の線として残っていた。草原には色々な事件が起こる。ウサギが野犬に追われて草原を逃げ回っているうちにこの線に出あった。ウサギは必死になってこの線を辿って逃げ、野犬はこの線を辿ってウサギを追った。そして、草原に残された線は少し太くなった。次に師がやってきてこの線を辿って獲物を探した。その次に開拓農民がこの道をたどってやってきて道になった。農場がこの道の両側に次々と開発された。やがて、工場が出来、多くの人がやってきて町ができた。道は更に広くなり道路になった。それでも形はその昔子牛が作ったくねくね曲がった線に沿って作られていた。というお話であった。庭に植物を植えるときもそのときの気分で植えたものが後々動かしがたい縛りになることがある。特に樹木は動かすことが困難である。モネの家の庭には植えたときの気分を思い出させる思い出の植物が多数ある。
2007年03月27日
コメント(0)
-

緑に赤が映えるポインセチア
ポインセチアが真っ赤な葉っぱと緑の葉っぱを広げている。モネの家の庭にこれまでとは異質の植物がやってきた。花ではなく葉っぱが美しい観賞植物。ポインセチアの美しさは赤い葉の美しさにある。この赤い葉をいかに元気よくするかが美しさを引き出す方法。活き活きした葉っぱでなければならない。つやのある葉っぱでなければならない。汚れていてはならない。皺くちゃではいけない。枯れた部分があってはいけない。赤が赤でなくてはならない。肥料を適時適切にやり、水をやり、葉っぱが汚れたら水で洗い流す。風雨に痛めつけられないように保護をする。暑さ寒さを適当に調節をする。日光の当たり具合を加減する。などの普通の手入れをこまめにやることが大切か。ポインセチアは地面に直接植えるよりも鉢植えのほうが世話はしやすい。ポインセチアはずいぶんたくさんの品種があるようだ。赤から赤紫、白、斑いりなど様々にある。ポインセチアの都合で多様化してきたのか人間の都合で多品種が出てきたのかポインセチアも人間に依存して生存領域を拡大しようとしているようだ。見てわかる観葉植物の育て方
2007年03月26日
コメント(0)
-

ムスカリはコバルトブルーに
ムスカリの花が咲いた。去年は一株だったのが今年は十数株になっている。驚異的な急成長である。一年でこんなに増えるのか、それともずっと前から準備されていたのが今年になって一挙に花開いたのか。コバルトブルーのムスカリがこんなにたくさん咲くと心が楽しくなる。近くでムスカリが群生しているところを2箇所見つけた。一つ目は県道の車道と歩道とに囲まれたわずかな花畑。近所の人が育てたのか県が植えたのか見事に群生している。もう一つは県立美術館の奥の山の斜面にある散歩道。県内各市町村の町の木と町の花が植えられ説明が添えてある。ムスカリはそれらを巡る道端に群生している。他の花々はまだ芽を出したばかりだったがムスカリは他の草々に先駆けてコバルトブルーの花を掲げていた。草の新芽にコバルトブルーの組合せが山の斜面に見えた。ムスカリはコンパクトな花で青紫が美しいので好む人が多いのかもしれない。旺盛な繁殖力からの栽培に特別の手間を必要としないのかもしれない。あちらこちらで一株、二株と見かけることが多い。ムスカリはコバルトブルーのものしか見ていないがヒヤシンスなどのように赤やピンク、白といったものがあるのだろうか。あるいはこれから出現してくるのだろうか。ムスカリにコバルトブルーだけでなく多彩な色が出てくるとまた楽しくなる。チューリップよりかなり小さいので少ない面積で色を組み合わせた楽しみ方ができる。モネの家の庭ではムスカリの基本色コバルトブルーの花が十数本咲いて楽しみの真っ最中ネムノキの園芸品種ネムノキ “レッドパウダー”(樹高 1.2m内外)
2007年03月23日
コメント(1)
-
草むらに白いヒヤシンスが咲いた
春の草が育ちつつある中に白い花を見つけた。白いヒヤシンスが咲いていた。若草色の草むらに白い花があるとよく目立つ。白い花は無垢という感じがする。赤やピンクやブルーに無いものを感じる。白いヒヤシンスだけがこの草むらにある。赤やピンクなどのヒヤシンスの前年にモネの家の庭に来ていたものちょっと花の時期がずれて咲いた一株だけ離れて咲いているのは孤高の証し。花の種類の増やし方としては毎年違った種類を植えていくというやり方。毎年の花を大事に育ていていけば十年で十種類を得ることができる。庭を花でいっぱいにしようとすれば少しずつ根気よく花を増やしていくのが良い。モネの家の庭に適する花適さない花がわかってくると思う。モネの家の庭に適さない花をうまく育てるのも園芸技術であるが無理をして育てないという選択ををすることも必要。モネの家の庭に適する花を見つけるには時間がかかる。こうして見つけた花は長くモネの家の庭に留まるであろう。白いヒヤシンスはこうして一年をモネの家の庭で過ごしてきた。来年またこんな白い花を咲かせてくれるとうれしい。痩せ地がだんだんと肥沃になり花や雑草などがよく育つようになるとこの庭に適する新しい植物の種類も増えてくる。逆にそのように植物の込み合った場所を嫌って消えてしまう植物も出てこよう。
2007年03月22日
コメント(0)
-

二羽のカラスが来た。
珍しいことにからすが二羽やってきた。二羽のカラスはつがいのようだ。手前がメスで奥のがオスではなかろうか。手前のメス、人家の近くで大胆不敵に広場の真ん中でえさを啄んでいる。それとも向うのオスが用心深くメスを警護しているので安心しているのであろうか。二羽はどちらかが動くともう一方も同調して動いている。阿吽の呼吸というのか絶妙のコミュニケーションというのかガラス越しにそっと見ているのだがこちらが少しでも怪しい動きをするとさっと飛び立つ。野生の動物には人間が忘れてしまった、あるいは無くした能力があるようだ。カラスのオス君は奥さんも気がかりだが左手奥のほうにあるものにも興味があるようだ。今日の新聞のマンガに「どこに行ってた?」と聞かれ「人間動物園!!」と答えている動物の親子が描かれていた。案外、このカラスのご夫婦は「今日はお天気がよく気持ちがいいから人間でも見に行こうか。」と来たのかもしれない。窓越しにカメラを構えている人間を見てなんと感じたであろうか。モネの家の庭にはたまにカラスがやってくる。昔からの町と新興住宅地を端から端まで歩いてみた。共通していることはどちらも空き家が目立つ。戸建の立派な住宅が住む人も無くひっそりとしているところがあった。その隣にはまだ若い世代の住民がいて活気のあるおうちがあった。違っているところは古い町には同じ苗字のお家が多いということ。親子、兄弟、孫、ひ孫とずっと同じ地域に住み、代を重ねる毎に世帯が増えていったのだろうと思う。郵便や宅配を届ける人はたいへんだろうと思う。新興住宅地には同じ苗字は少ない古い町も新しい町も住む人がいなくなった家の割合は同じぐらいに見えた。カラス狂騒曲
2007年03月20日
コメント(0)
-

庭の槙に野鳥が来た。
野鳥を見る趣味は無いが野鳥が近くに来ると落ち着かない。こんな状態を血が騒ぐというのだろうか。思わずカメラを向けてみた。窓ガラス越しにそっと近づく。距離は3メートルぐらいである。肉眼で見ると鳥の特徴がよくわかるが木陰なのでやや暗く写った。野鳥の趣味は無いのでこの鳥の名前は知らない。すずめやカラスではない。もずでもないと思う。もちろん鳩ぐらいは知っている。今年はやはり変だ。こんな野鳥がこんな近くに来ることは今までになかった。えさを探しているのだろうか。巣作りの場所を探しているのだろうか。それとも単にこのあたりの居住環境がよくなったためであろうかこの鳥、野鳥愛好家の方だとどんなコメントをしてくれるだろうか。今朝の新聞ではツバルが温暖化による海面上昇で海没の危機にさらされているという写真が出ていた。普段見かけない野鳥の出現と温暖化とは結び付けて考えたくない。我田引水ではあるが、モネの家の庭が林になりつつあって、野鳥の生息環境が整いつつあると考えたい。華麗なる一族が終わった。文芸春秋にも華麗なる一族の華麗なる鑑賞方法という記事が出ていた。今回で三回目になっているそうだ。時代の転換期にこの華麗なる一族はヒットするそうだ。このところキムタクが出演している映画がいくつかあった。ラジオなどでも最終回の話題を取り上げていた。総じていくつかのメディアを通じて華麗なる一族を華麗に盛り上げていたような感じをうけた。ふと、華麗なる一族のほんとうの意味は出演した俳優さんに華麗な人たちを集めたので華麗なる一族ではないかと本末転倒なことを思ったりもした。野鳥歳時記 春夏秋冬〈2枚組〉
2007年03月19日
コメント(0)
-

ピンクのヒヤシンスが咲いた
ヒヤシンスが三色並んで咲いた。赤、ブルー、そしてピンクピンクのヒヤシンスは柔らかい色。花びらがくるりと反対方向まで巻いている。たこの足のようである。ヒヤシンスの花はピンクのたこを頭からいくつもくっつけているような感じ。花びらは周縁部が白く中心部へいくほどピンクが濃くなっている。地面からすぐアロエに似た圧肉の葉っぱが6本伸びている。葉っぱの緑は濃い、周縁部は黄色味を帯びている。白とピンクと緑の組合せが花のピンクを際立たせている。土は鹿沼土と赤玉土、腐葉土を混ぜたものだ。配分はほぼ等量、目分量。一年目の球根は球根が持っている力で花が咲くのでこんなもので良い。次の年から花を咲かせようとするともう少し丁寧に面倒を見る必要がある。手間を掛けずに毎年花を見ようとすれば毎年新しい球根を植えること。球根を育てるところから楽しむか、花だけを楽しむか。予算と手間と心意気に相談する。目標は球根と自由自在に対話できること。花を咲かせたい時に咲かせたい花を花を咲かせる。まずは水遣り、肥えやり、土作りから始める。モネの家の庭の球根栽培が根付くの何時の日か12か月楽しむ花づくり
2007年03月17日
コメント(0)
-

ブルーのヒヤシンスが咲いた。
ヒヤシンスが咲いた。三種類あるヒヤシンスの二番目はブルーである。青紫にところどころ白味を帯びたところがある。赤を見てブルーを見るとブルーがいっそう強調される。赤を見るとエネルギーが満ち溢れる思いだが、ブルーを眺めていると色々なことを思い浮かべる。ブドウのブルーとは少し違う。アガパンサスのブルーに似ているようだ。桔梗のブルーにも似ているか。スミレのブルーはやや濃いようだ。アネモネのブルーも濃い。月曜日のブルーは意味が違うか。そういえば気分がブルーであったときもあった。あのときの気分はヒヤシンスのブルーでは表せないな。グラジオラスのブルーはやはり明るいブルーだ。陽光が降り注ぐ空からのスカイブルーに似ている。ブルーエンジェルスというアクロバット飛行のチームもあった。日本のはブルーインパルスという名前だったと思う。青い色は人を物思いの淵に引き込む効果があるようだ。名前をつけた人はブルーエンジェルスやブルーインパルスという言葉に何を託したのだろうか。モネの家の庭のブルーのヒヤシンスは何を想っているのだろうか。早稲田大学の清水選手が西武からお金をもらっていたことに関して謝罪の記者会見の模様が報道されていた。清水選手は問題が明らかになったとき真実を隠していたことを謝罪していた。清水選手は二つのルール違反をしていたことになる。一つは、アマチュア選手は球団からお金をもらってはいけないのにお金をもらったこと。二つ目は真実を語らなかったこと。昔からスポーツはルールに則って行うものだ、スポーツ選手はルールを守ることに堅いと教えられてきた。神話は神話として大事に取ってこう。ストラテジック・コミュニケーション(5)一流の気くばり12のルールインターネットと法第3版
2007年03月16日
コメント(0)
-

赤いヒヤシンスが咲いた。
ヒヤシンスが咲いた。赤いヒヤシンスである。赤い小さな花をいっぱいつけて一つの花を形作っている。小さい花はチューリップのような形でしかも花びらが長く反り返るような形になっている。百合の花に似ているといったほうが良いかもしれない。真ん中の軸から真横に花がついている。こんな形に似た公共放送用のスピーカーを見たこともある。グラジオラスはあらゆる方向に花の存在を示すと同時にあらゆる方向からの虫の接近を誘っているように思う。それとも全方向に花粉を飛ばすにはこの形が良いのかもしれない。ヒヤシンスには色々な色のものがある。原種はどんな色だったのかこのヒヤシンスは赤い色をしている。赤い色は人間の都合で出現した色ではあるがヒヤシンスにとっても何らかのメリットがあるに違いない。たとえば赤以外の光線が弱いところでも十分成長できるとか。赤に反応する人や動物をひきつけて、肥料を与えてもらったり、交配の手伝いをしてもらったりとか。今、ヒヤシンスはこの赤いヒヤシンスの外にピンクと青がある。しかもこれらはほとんど同時に開花している。見事な品種改良だと思う。これらの花は来年も三種同時に咲くであろうか。それは花が終わった後、モネの家の庭でどのような栽培管理を行うかによろう。ところでANAの航空機が胴体着陸した件で前脚扉のヒンジのボルトが外れていたそうだ。ボルトはヒンジから抜けないようにピンで留める仕組みらしい。ピンは残っていたがボルトは発見されなかったとか。2005年製造だから新しい機体である。趣味園芸などでは何かあったとしても花が咲かないだけですむが機械ものはちょっとしたことが原因で大きなトラブルを引き起こすことがある。航空機の整備や運行に携わっている人たちはほんとうのご苦労様です。造園がわかる本コーディネーターの仕事土木工事現場の上手な運営法建築設計実務のチェックシート第2版
2007年03月15日
コメント(3)
-

青紫をいっぱいに広げて
ブルーのアネモネが花びらをいっぱいに広げた。早朝はやや閉じてチューリップ上になっていたが太陽の光を浴びると花びらを開くようだ。見る時刻によって様々な形を見せてくれる。開ききった花を見るとかなり大きな花である。アネモネという種類はわかったが品種はわからない。自己流の名前をつけるとすると「ブルーエンゼル」「ブルーヘブン」「ブルースマイル」「ブルーサンシャイン」「紫焔」「紫苑」などを思いつく。固定した名前をつけて楽しむかその時その時に思いついた名前で楽しむか人に見せるときには固定した名前が必要だが、自分自身が楽しむときには花の色があれば良い。名前など気分に合わせていくつも用意すれば良い。とはいっても園芸店ではどんな名前で売っていたのだろうか気にかかる。花たちにはかわいそうだがモネの家の庭では時々花の名前が行方不明になる。花の品種改良入門
2007年03月14日
コメント(0)
-

アセビの花が咲いた
白いアセビの花が咲いた。アセビの花は1本の枝に沿って無数に咲いている。漢字では馬酔木と書いてアセビと読むらしい。名前の由来については馬が葉っぱを食べると足が痺れたようになることから来たらしい。もし、この葉っぱをイヌが噛むとどういうことになるのか。人には影響ないのかと思ったらやはり嘔吐、下痢などの症状を起こすらしい。幼児の居る庭には不向きな木かもしれない。薬用としては牛馬の寄生虫駆除や害虫駆除に用いるようだ。人間の体に役に立つ使い方はまだ無いようだ。花を見て楽しむことが良いのかもしれない。ここにあるのは白い花だがピンクの花もあるようだ。ツツジ科の花木に属するそうだ。それなら様々な花の色があっても不思議は無い。この花を粋と思うか野暮と思うかは個人の感じ方による。花は美しく罪は無いのだが、モネの家の庭にはなぜかこの木がある。なるべくなら毒木を植えないほうが安全安心である。びっしり咲き乱れるかわいらしいピンク 赤花アセビ 根巻き大苗
2007年03月13日
コメント(2)
-

赤紫が映えるほとけの座
ほとけの座が一気に咲き出した。暖冬からほんとうの春へ移っていく。ほとけの座は春の花である。この花が咲くと春だという気持ちになる。昔からの脳への刷り込みがそうさせる。この次に咲くレンゲとあわせて春にはこの花と思い込んでいる。早春に緑色の葉っぱに赤紫の葉が咲いているところは思い出に残りやすい。ほとけの座を見ると条件反射的に春だと認識してしまう。ほとけの座が咲くころは地面があまり湿っていなくて腰を下ろしても寝そべっても気持ちが良い。ほとけの座を見るのは幼児の目の高さが一番良い。ほとんどこの時期に思い込んでしまっているからおそらく幼児期の早春の暖かい日にこの花を見て遊んでいると思う。ほとけの座とは昔の人はよくよく面白い名前をつけたものだ。子供なら「小人のキセル花」などという名前をつけても良いか。この花が邪魔者扱いされないのには花が咲く時期が良い。花が美しいのみならず、麦作にもこれから始まる稲作にも邪魔をしない植物出るから人間としては厄介者扱いをしない。そんな気持ちもかすかにあってほとけの座という神妙な名前をつけたのかもしれない。モネの家の庭にも咲いたほとけの座は早春の気持ちを豊かにしてくれる野の花である。幼児は世界をどうみているか?
2007年03月12日
コメント(0)
-
風の中で撮ったクリスマスローズ
モネの家の庭にはクリスマスローズが咲き乱れている。ほんとうによく咲くものだと思うほどたくさんのクリスマスローズが咲いている。クリスマスローズの花がたくさんあるとどれを撮ろうかと迷う。クリスマスローズは素敵な葉であるが被写体としては難しい。クリスマスローズの花は下向きに咲いている花が多い。写真に撮るには上向きの花、せめて横向きの花が欲しい。やっと見つけた横向きの花。風に揺られて焦点を合わせづらい。風の周期を測って、一瞬止まるときを待つ。風に吹かれたクリスマスローズは丸みを帯びた花びらがやや凋んで見える。花も綺麗にとって欲しいと思っているだろうに。風に対抗する姿になっている。人間のちょっとした気まぐれでこんな写真になった。
2007年03月09日
コメント(0)
全662件 (662件中 1-50件目)