2016年04月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

クロアチア・スロベニア6カ国周遊旅行11(4/22 ザグレブ市内観光 その1)
昼食を終え、徒歩にて市内観光を開始。イリツァ通りをイェラチッチ広場方面に向かい左折すると目の前にケーブルカーの姿が。世界一短いと言われるザグレブのケーブルカー「ウスピニャチャ(Uspinjaca)」はザグレブのお年寄りのために1890年に作られ、移動距離は66mと。乗車時間は30秒ほどとのこと。乗るのかと思っていたら我々はその横の階段をひたすら登る事に。片道4クローネ(Kn)、60円程度とのこと。ケーブルカーの終点、ゴルニー・グラードの丘駅のそばにそびえ立つこの建物は、13世紀に建てられた見張り塔でロトルシチャック塔(Kula Lotrščak)。毎日正午に打ち鳴らされる大砲(空砲)の音は驚くほど大きく、ザグレブの名物になっていると。窓から大砲の砲口が覗いていた。ザグレブの街の眺めを楽しむ。10Knでロトルシチャック塔にも登れるとのことであったが。さらに狭い路地を進むと路地の左手に、屋根が印象的な建物が見えて来た。赤、白、青のタイル模様が美しい建築物。正面奥の建物は、『聖カタリーナ教会』。ザグレブで一番美しいバロック様式の教会がカタリーナ広場に。聖マルコ教会(Crkva sv. Marka)。クロアチアの首都・ザグレブにあるカトリック教会で、旧市街のグラデツ(Gradec)の中心にある。もともとロマネスク様式で建てられ、14世紀には礼拝堂とアーチがゴシック様式で建設され、19世紀末にヘルマン・ボレ(en:Hermann Bollé)によりネオ・ゴシック式に改築されたのだと。屋根に有名な美しいカラータイルが。正面左側にはクロアチア・スラヴォニア・ダルマチア王国(Triune Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia)の紋章右側はザグレブの紋章。教会のファサード。何故か最上部右側の像の頭がなかったが。この日のザグレブ現地ガイドの女性。聖マルコ教会の裏側の屋根は紋章はなくモザイクのみ。聖マルコ教会の右手には国会議事堂が。そして左側には首相官邸が。国会議事堂と共に外見は思いのほか簡素。さらに進むと石の門が。何百年にも渡りザグレブ市民の暮らしを見守り続けてきた「石の門」。現在の姿は18世紀に造られたもの。門は中世の時代にすでに存在していたという記録が残されていると。1731年の大火で城壁と東門(現在の石の門)周辺が焼け落ちた際、焼け跡には,そこに掲げられていたキリストを抱く聖母マリアの絵(イコン)が無傷の状態で見つかったと。これはカトリックでしばしば見られる「奇跡」に相当するそうで,現在その絵は鉄格子で守られた小さな祠に掲げられていた。この絵は鉄格子で守られており覗きにくいためか,新たに立体像が傍らに据えられていた。そして両者は,お祈りに現れた人の捧げた花や灯明に囲まれていた。そしてロウソクや花を捧げて祈る人々が絶える事なく。キリストを抱くマリア像の像。見晴台からの聖母被昇天大聖堂(Zagrebačka katedrala)。丘の上に建ったザグレブのシンボル「聖母被昇天大聖堂」。聖母マリアが人生を終える時、天国へ肉体と霊魂を伴って昇ったという信仰に基づいて建築された、高さ100メートルを超える大聖堂。10年以上前にこの地を仕事で訪れたが、その時も同じ場所の補修工事が行われていた事を想い出したのであった。展望台の後方には巨大なクジラが飛んでる絵を発見。中心がピンクのマロニエの花が美しかった。
2016.04.30
コメント(0)
-

クロアチア・スロベニア6カ国周遊旅行10(4/22 クロアチア・ザグレブ へ)
リュブリャーナ市内観光を終え、バスにて高速A2アウトバーンを利用してザグレブに向かう。 のんびりとした、そして新緑にあふれた車窓風景を楽しむ。グループの女性陣のうち何人かは爆睡中。 料金所を通過。この料金所は国境をまたがって長距離の移動をすることが多い観光バス等重量貨物車を対象に、インフラ利用に関する負担の公正の観点から、道路使用料金を支払う仕組みになっている模様。 ザグレブ(Zagreb)まで49kmの表示。車窓には黄金の景色が現れる。 菜の花畑が一面に拡がる。 再び高速料金所。 そしてクロアチア国境ゲート。 クロアチアは2013年に欧州連合に加盟しているが、ヨーロッパの国家間において国境検査なしで国境を越えることを許可するシェンゲン協定に入っていないため国境検査を受けなければならないのである。 バスを降り、パスポートを提示し入国許可の印をパスポートに押してもらい再びバスに戻ったのであった。そこにはクロアチア国旗がはためいていた。 再びザグレブに向かいバスは進む。クロアチアの有名スーパー『KONZUM』 の案内板。バスは順調にザグレブ市内に入ってきた。道路にはトラム(路面電車)が頻繁に通過していた。 街路樹のマロニエの花咲くザグレブの街。 ピンクのマロニエの花も所々に。マロニエの和名は西洋栃の木 (セイヨウトチノキ)。マロニエの名はフランス語名の Marronnier からきている。パリでも街路樹として植えられ、「マロニエの並木道」が有名。 クロアチア国立劇場前を通過。 イェラチッチ広場に近いイリツァ通りの路面電車(トラム)の線路横に停車しバスを降りろと。大胆なドライバーの決断。我々に、レストランまでの歩かせる距離を少なくするために親切心から街中心場所まで入ってきてくれたのであった。 慌てて添乗員が交通整理。なんと路面電車(トラム)の運転手は我々全員が下車するまでトラムを停車させ待っていてくれたのであった。そして私の目の前を通過する時に、私が感謝の手を振ると振り返してくれたのであった。 おかげでそのまま昼食用のレストランに入れたのであった。昼食はまずスープ。 黒ビールを注文。 そしてこの日は、ザグレブ風カツレツ(Zagrebacki odrezak)。。薄い肉でチーズやハムを巻きカリッと揚げたカツレツとのことであったが食べたのはハムカツ?
2016.04.29
コメント(0)
-

クロアチア・スロベニア6カ国周遊旅行9(4/22 リュブリャーナ市内観光)
この日は8:45にホテルを出発しリュブリャーナ市内観光へ。実は昨夕の自由散策、この日の早朝散歩でほぼ既に見た場所なのではあるが。バスでホテルを出発し、あっという間に龍の橋を渡り直ぐにバスを下車。前日撮影した龍の姿。龍の橋 (Zmajski most)はリュブリャーナがオーストリア=ハンガリー帝国の一部であった1900年 - 1901年に造られたと。街のシンボルである龍が橋の四隅に配置されていた。その昔、ある探検隊が伝説の龍と戦い、打ち勝った場所とされているとのこと。こちらもスロベニア人彫刻家ヤコヴ・ブルダルの作品。慟哭の表情は理解できたが。三本橋(Tromostovje、トロモストウイエ)。Wikipediaによると『三本橋は、リュブリャニツァ川に架かっている橋であり、スロベニアの首都リュブリャナのシンボルの1つである。リュブリャナ中心地に位置。1280年からこの位置に木製の橋が架けられていた。そして1657年の火災の後、再建。この橋は、1842年にイタリア人の建築家ジョバンニ・ピッコによって設計された新しい橋に取り替えられた。ジョバンニ・ピッコが設計した石のアーチ橋は中央部に設けられている。そして、1929年にスロベニア人の建築家ヨジェ・プレチュニック(1872 - 1957)が歩行者専用の橋を両側に付け加える設計をした。この設計では中央と両側、計3本の橋があるので三本橋と呼ばれるようになった。この仕事は1932年に完成された。』この日の現地ガイドの女性。 三本橋とフランシスコ会教会(ピンク色の建物)。広場の中心地には、非常に有名なスロベニア人の詩人フランツェ・プレシェーレンと彼のムーサ・ユリヤの銅像が建っていた。ムーサと言えば、ギリシア神話の女神。音楽や文学を司る神。その女神がプレシェーレンに何かを彼の頭の上に掲げているが何を持っているのであろうか?そしてプレシェーレン像の下にも。彼の詩の一場面を表しているのか?リュブリャーナという名前の由来には諸説あるが、一番有名なのがスロヴェニア語のljubljena(最愛の)から来ているというもの。スロヴェニアは英語表記でSloveniaであり、世界で唯一国名にloveが含まれている国で、首都の名前が最愛のという意味なのだとのネット情報。静かな流れのリュブリャニツァ川。リュブリャーナ大聖堂とリュブリャーナ城、 白壁を背景に咲く藤の花とその影も美しかった。 リュブリャーナ城へのケーブルカーも動き始めていた。 丘の上のリュブリャーナ城の塔にひるがえるリュブリャーナ城旗。リュブリャナ大聖堂の2本の尖塔。バロック様式の建物で1996年,ローマ教皇も訪れたという場所。大聖堂の入り口の扉。威厳と歴史を感じたのであったが。これ実は1996年のローマ法王来訪時の時に作られたものとのこと。しかし1250年間におよぶスロベニアのキリスト教の歴史を表していると。ドアは全面青さびがふいており、その中で、人の手が触るドアノブだけがピカピカとてかり、異様に輝いているのがとても印象的。遠足か?小学生の団体の姿も。 聖堂内部。 ステンドグラスも美しかった。 リュブリャーナ大聖堂の裏門。 市庁舎前の泉。尖塔の下部は白の大理石の彫刻で飾られていた。市庁舎。 内部を見学。 建物の壁面いっぱいに浮き彫りにされたリュブリャナの市街地図が。ナルシストの語源となった美少年ナルキッソスの像。ナルキッソスについては次のような神話があるのだと。ゼウスと親しくしていたエコーという妖精(美しい少女の姿)がいた。エコーは、森で見かけ自分を無視した美少年(ナルキッソス)を復讐の女神に懲らしめるよう頼んだ。ナルキッソスは、水に映る自らの姿に恋するように神から罰を与えられたが、決して報われることのない恋にやつれ、森の湖のそばで力尽きて死んでしまい、可憐な白い水仙(ナルシス)の花と化した。このことから自らを美しいと見とれてしまう状態をナルシズムというのだと。新市街に建つリュブリャーナ大學。 三位一体聖堂正面。 再びプレシェーレノフ広場に戻る。 ピンクのフランシスコ会教会の屋根の上に置かれた像。 自由時間に市庁舎前に行くと先ほどの小学生が歌を歌いながら小劇を披露中。 子どもの姿は心和ませてくれるのであった。 市場にはガラス細工も販売されていた。 市内観光を終え、朝市を見学しながらバスに向かって。
2016.04.28
コメント(0)
-

クロアチア・スロベニア6カ国周遊旅行8(4/22 リュブリャーナ早朝散歩 その2)
線路の先に瀟洒な建物が。 ティヴォリ公園。公園内にあるプレチニクの設計した散歩道を歩いていくとティヴォリ城に辿り着く。近代美術館(Moderna Galerija / Museum of Modern Art)前の銅像。 何を表現しているのであろうか?手を挙げて前に進む人間の集団のようでもあるが。 アメリカ大使館前。警備の女性の許可をもらい撮影。 スロベニア外務省。 国立博物館分館(Narodni muzej Slovenije)。緑地公園に面したクリーム色の建物。1885年に建設された国立博物館。 国立博物館の緑地に立つ17世紀のスロベニアの啓蒙運動のリーダー、『VALVADOR』 の像。スロベニア国会議事堂(Parliament of Slovenia)。 エントランスの彫刻は見事の一言。 三位一体聖堂(Ursuline Church of The Holy)リュブリャニツァ川まで戻り川沿いを歩き再び3本橋まで戻る。 朝市を楽しむ。海外で朝市を覗くと、その国の人々がどの様なものを食べているのかが解り興味深いのである。日本より種類の多くの野菜・果物が並んでいた。大きな真っ赤なイチゴが売られていたので一箱購入。 各種履き物も朝市で売られていた。 朝市の建物の壁には南国を思わせる白黒の絵画が描かれていた。 そして約1時間半の早朝散歩を終え7:30過ぎにホテルに戻る。 そして朝食はバイキングスタイル。
2016.04.27
コメント(0)
-

クロアチア・スロベニア6カ国周遊旅行7(4/22 リュブリャーナ早朝散歩 その1)
この日も5時過ぎに早朝起床しシャワーを浴びる。そして6時前にリュブリャーナ市街への早朝散歩に。ホテルから10分かからずにリュブリャニツァ川に架かる龍の橋に到着。 龍はスロベニアの首都リュブリャーナのシンボルである。1895年のリュブリャーナ大地震によって崩落した肉屋の橋の代わりに、リュブリャーナ初の鉄筋コンクリートの橋として建設。1901年に開橋された当時、フランツ・ヨーゼフ1世の即位40周年(1848-1888)を祝賀する意味を込めて、祝賀橋(ドイツ語でJubiläumsbrücke)と命名されたが、4頭の竜の彫刻によって装飾されていることから、竜の橋と呼ばれるようになったと。そして山の上にはリュブリャーナ城が。橋の上や欄干には変わった彫刻が。何を表現しているのであろうか? こちらも不気味な顔のない彫刻。体に穴があいていたり、溶岩のようなものがまとわりついて・・・。さらに尻尾も。スロベニア人彫刻家ヤコヴ・ブルダル(Jakov Brdar)の作品と。 リュブリャニツァ川に架かる肉屋の橋。恋人たちが鍵をつけていると。恋が破れた時、女性は鍵を外すが、男は未練たらしく残すのだと。遠くに3本橋が見えた。スロベニア人彫刻家ヤコヴ・ブルダルの作品。 広場の朝市は準備中。 リュブリャーナ大聖堂の扉。素晴らしい教会の扉。中央の光っているノブと幾つかの丸い壺は慈悲の壺(水?)であると。 リュブリャーナ大聖堂外壁のピエタ像大聖堂南の外壁面のニッチ(彫像などを安置するための壁面に掘り込んだ空間)にゴシック様式のピエタ像が。15世紀の製作とのことであるが色彩豊か。ピエタ(イタリア語:Pietà、哀れみ・慈悲などの意)とは、聖母子像のうち、死んで十字架から降ろされたキリストを抱く母マリア(聖母マリア)の彫刻や絵の事。リュブリャーナ観光の中心地であるプレシェーレノフ広場から3分程のところにある旧市庁舎。クラシカルな建物の雰囲気が素敵です。前庭にはオベリスクが。1584年に建てられ、その後1717年から1719年にかけて後期バロック様式と古典様式を組み合わせた建物に改装された。破風の上に突き出るように造られた時計塔が。奥の双塔はリュブリャーナ大聖堂(聖ニコラス大聖堂)。プレシェーレノフ広場に面した、17世紀に建てられたフランシスコ会教会。周りのほかの建物が殆ど白色のなかピンク色なので目立つ建築物。正面外壁には『プロビデンスの目』が描かれたフランシスコ会教会。旧・新市街地を見下ろせる丘の上に建つリュブリャナ城。城の見張り塔には1848年頃から見張り番が住み込んでおり、火事の警告を知らせる役割など現在も担っていると。ウェディングホールやカフェ、リュブリャナの歴史について詳しく知ることができるミュージアムもあるとのこと。城へのリフトは9時から運転開始。ビルの谷間からの朝の陽光が。 リュブリャニツァ川の川面に朝焼けが映る。 リュブリャーナの街並みのミニチュア。 真ん中に3本橋、そして小高い山の上にリュブリャーナ城が。スロベニア銀行。オペラ座 (Opera in Balet (SNG Opera in balet Ljubljana))スロベニア国立美術館。プラヴォスラヴナ教会 (Pravoslavna cerkev)
2016.04.26
コメント(0)
-

クロアチア・スロベニア6カ国周遊旅行6(4/21 ブレッド城)
「ブレッド城」は湖の北側に建っていました。バスで狭い坂道を上り約15分で、城の側にある駐車場に着いた。「ブレッド城」は、11世紀、ブリクソン司教によって造られた城で湖面から約100mの高さの断崖に建つ。城の最も古い部分は鐘楼で、ロマネスク様式で建てられており、他の部分はルネッサンス様式の建築。建物は2つの中庭を囲むように造られており、階段でつながっていた。2階には16世紀に造られた礼拝堂と邸宅があり、現在は博物館や、造幣所、レストランなどとして使われていた。城の展望台からは、ブレッド湖と周囲の山々を一望することが出来たのであった。駐車場でバスを降り登城すると、正面に城門が現れた。右上は登城道であると同時に、この登城道から登って来た敵を攻撃できるようになっていた。 跳ね橋を渡って急な坂道を上ると、城内への入り口へ。 城門は櫓門になっていた。 チケット売り場を通り城内へ入って行く道の両側は高くなっており、 正面には邸宅(現博物館)が現れた。この建物は博物館ショップであり、あまり城っぽくない建物。城の南面にはテラスがあり、1階部分はカフェテラスになっていた。時間さえ許せば、この場所で、湖をはじめとする絶景を楽しみながらゆっくりと時の流れを感じたいのであったが。 ここからはスロベニアそしてユリアンアルプスの最高峰、標高2,864mのトリグラフ山も見えた。(写真中央左)。トリグラフ山はスロベニア国旗に描かれている山。トリグラフは、スラブ語で3つの頭の意味。その名前のとおり、三連の山が印象的であった。添乗員によると、なかなか見えるチャンスは少なくラッキーであると。スロベニア国旗。旧ユーゴ時代は白、青、赤の三色旗に、中央に金で縁どった赤い星をおいた旧ユーゴ旗に似た図柄だったが、赤い星を取り除き、代わりに左肩に国章をはめ込んでいる。国章には、国内最高峰で3つの頂からなるトリグラフ山(2863m)をかたどったものに、アドリア沿岸部と河川を表す波形が描かれている。3つの星は、神聖ローマ帝国時代にこの地を治めたツェルイェ公領の紋章にちなんでいると。テラスからのブレッド湖の眺望。南西方向に見下ろすブレッド湖・聖母被昇天教会の建つ小島、その背後の山並みの景色は絶景。ブレッド湖のエメラルドグリーンの美しさ、周りの木々の新緑の美しさが余計に美しさを際立たせていた。先ほど船で行ったブレッド島と聖母被昇天教会。 アイアン細工のオブジェを売ってるショップ。 スロヴェニアの首都リュブリャナのトレードマークであるドラゴン像や白鳥、黒鳥が展示されていた。 城内にはワインセラーも。再び城の南面のテラスを上部より。 1階部分には井戸が残ってた。こんな岩山の上に井戸が掘られていたとは驚き、井土の深さは何m?。 「印刷工房」に入る。ここでは、グーテンベルク時代のような印刷を実演してくれていた。工房の2階には、この人物像の後ろにスロベニア初の印刷された本などが展示されていた。この人物の名前は忘れましたが。手すきの紙にブレッドの絵をプレス印刷し、それにシールする。なかなか面白い。ブレッド湖の湖畔の高台にある聖マルティヌス教会の姿も確認できた。 ドローンが城内を飛行していた。 ブレッド城の見学を終え、再びバスに乗りブレッド湖岸を散策。ブレッド市庁舎。秋篠宮ご夫妻がこの地を訪れた折り(2013.6.29)に植栽された桜の木であると。しばし湖畔からの絶景を楽しみながら自由時間を楽しむ。この「ブレッド湖」はボート競技には条件がいい場所で、何度か「世界ボート選手権」が開催されているのだと。 なるほど湖面には、コース用の浮きが幾筋も。土産物売り場のこの店にも各種蜂蜜が販売されていた。試食コーナーでしばし・・・・・。そして再びバスに乗り込み、この日の宿泊地のリュブリャーナへ向かう。湖畔には観光用の馬車の姿も。E61ターンバイク沿いの教会の赤い尖塔。料金所を通過。観光用バスは重量を確認している模様。この日のホテルは、ホテル パルク (Hotel Park Ljubljana)。旧市街の三本橋や龍の橋までは川をはさんで徒歩10分以内で行ける便利な場所。部屋も狭くはなくまあまあ。 チェックイン後、添乗員のNさんが希望者をリュブリアーナ新市街と旧市街の境にある人気スポットまでの散策に連れて行ってくれたのです。約1時間の散策を終えスーパーマーケットに立ち寄った後、ホテルに戻り夕食、そしてアルコールも入り爆睡したのであった。
2016.04.25
コメント(0)
-

クロアチア・スロベニア6カ国周遊旅行5(4/21 ブレッド湖 聖マリア教会)
満腹にならなかった昼食後は、再びバスにてブレッド湖畔に向かう。車窓から断崖絶壁の上のブレッド城がが姿を現した。湖畔でバスを降り船乗り場へ。ブレッド湖畔の案合板。 「ブレッド湖」はオーストリアとの国境に近い場所に。湖の遠くの方に見えているのがこのブレッド湖に浮かぶ小島「ブレッド島」。スロベニアは、アドリア海に面しているが海には「島」はなく、このブレッド島がスロベニアに唯一ある天然の島であると。この国では湖の中の島も島数に数えるらしい。日本では?湖畔から「プレトナ(pletana)」と呼ばれる小さな手こぎ船で渡るのであった。 このプレトナの船頭は、マリアテレジア(マリーアントワネット母)の時代からの世襲制で、ムリノ村出身の男性のみ漕ぎ手となることが出来るのだとガイドから。そしてモーターボートは環境保護のため禁止されていると。 二艘の手こぎ船でブレッド島を目指す。もう一つのグループが乗った船が先頭を進む。 中央の島の聖マリア 教会 は15世紀に建てられたと。 我が船の船頭。我々もライフジャケットの着用等は一切なし。 ブレッド城の後ろに見える山は、ヨーロッパ・アルプスの東南端「ユリアン・アルプス」 ブレッド島にに到着。 島への上陸前にブレッド島への現地ガイドが添乗員と打ち合わせ中。 シーズンには多くのカップルが、ひっきりなしにここで結婚式を挙げると。言い伝えによると、新郎が新婦を抱えて教会に通じる99段の階段を上りきったら、夫婦の願いが叶うのだと。失敗すれば、結婚式を挙げれない・・??ここで結婚式を挙げたい人たちは、男性は肉体作りに、女性はダイエットに励むのだと。ブレッド島にはかつてスラブ民族に伝わる愛の女神ジヴァの神殿があったことから、島にある聖マリア教会は愛の聖地となり、現在でも多くのカップルがここで結婚式を挙げていると。 聖マリア教会は聖母被昇天教会(Church of the Assumption of the Virgin)とも呼ばれていると。この教会の創建は8~9世紀頃で、今見る姿になったのは17世紀。ブレッド島と共にブレッド湖に影を落とす様子は、今でもスロベニアを代表する風景のひとつになっていると現地ガイドから。聖母被昇天教会の52mの塔。以前テレビのこの教会は冬場のブレッド湖が全面凍結した冬に石材を凍結湖面上を運搬し建設したと説明していたことを想い出したのであった。聖母被昇天とは、聖母マリアが人生の終わりに、天使たちと一緒に肉体と霊魂を天国に上がっていったという意味とのこと。 教会の入り口にはイエス様が。 ゴシック様式のメアリ女王の祭壇は補修工事中。 ゴシック様式のメアリ女王の祭壇。聖ドイツ皇帝 ヘンリー二世やその妻の像が。この教会は、明るく、あちこちに可愛らしい天使の姿も。教会の祭壇には「望みの鐘」と呼ばれる鐘がありました。鳴らすと願いがかなうと言われているのですが、もちろん私も鐘を鳴らす為に紐を引っ張ってみました。しかし、結構重かったのでした。聖母被昇天教会の52mの塔の木製階段を上る。階段の透かし彫りとこの透かしを通過する光の模様が美しかった。 塔頂からの ブレッド城とユリアン・アルプス。反対方向には、チトー元大統領別荘(現ホテル)も確認できた。丁度14時の鐘が二つ。鐘が鳴り出すと目の前の機械が動き出したのであった。 地上に降り、売店へ。多くの種類の蜂蜜が販売されていた。まるで巨大絵画の如し。 船着き場には鴨?が日向ぼっこ中。 帰路は別の船で。船のバランス上、座っている観光客の移動を指示。
2016.04.24
コメント(0)
-

クロアチア・スロベニア6カ国周遊旅行4(4/21 ブレッドへ)
旅行2日目、この旅行の最初の観光地のスロベニア・ブレッドへバスで向かう。ザルツブルグからブレッドまでは238km。A1アウトバーン入り口近くからの聖ANNA教会と工場の水蒸気白煙。この日は朝から快晴。A10アウトバーンをスロベニアぬ向かう。バスの車窓から白き山々の風景を楽しむ。山頂が平らな山も。 ザルツブルグから南へ50kmほど行ったところの人口3000人弱の町、Werfenの山の上に建つホーエンヴェルフェン城が車窓から。11世紀に建てられた中世のこの城は、映画「サウンド・オブ・ミュージック」にも登場していると。ホーホケーニヒ山周辺。 こちらは険しい頂の山が続いていた。 エベレストの如き形の山も。グロースグロックナー(Großglockner)であろうか?オーストリアにある山で、国内最高峰、標高は3,798メートル。ザルツブルク州、ケルンテン州、チロル州の東チロルにまたがる。この日は進行方向左の後方席に陣取る。青空に飛行機雲が。この旅行では多くの飛行機雲を見ることができたのであった。長いオーストリア→スロベニア国境に近くにあるKeravankeトンネルを通過すると聖Georgen教会が。 どの山も頂には雪が残っていた。 アイゼントラッテンのレストランでトイレ休憩。トイレは有料で、ここでは0.5ユーロ、コインを入れてゲートを通過し利用するのであった。オーストリア、アルプスの絶景ドライブ『グロースグロックナー山岳道路(Großglockner Hochalpenstraße)』案内板。 多くの土産物、チョコレートが並んでいた。 今回の我々のバス。スロベニア(SLO)ナンバーのかなり年季の入ったバス。今回訪問した国のナンバープレートの国識別文字は以下の通り。D:ドイツ (Deutschlandドイツ語 )A:オーストリア (Austria)SLO:スロベニア (Slovenia)HR:クロアチア (Hrvatska クロアチア語)MNE:モンテネグロ (Montenegro)BIH:ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosna I Hercegovina セルビア・クロアチア語)ランズクロン城(Burg Landskron)が山の上に。ケルンテン州の城で16世紀に14世紀の旧防塁の基礎壁の上に建築された城。A11アウトバーンのオーストリア出口国境を通過。 カラヴァンケン自動車トンネル通過の為の検査?で一時停止。 カラヴァンケン自動車トンネルを通過しスロベニア側入り口国境へ。 国境を無事通過しスロベニアに入国。 スロベニアに入りアウトバーンの名称もA1からE61に変わる。そしてアウトバーンを降りブレッド湖に向かう。 ブレッド湖畔近くのレストランでこの日の昼食。2階に案内される。屋根裏にはバイクが展示?保管?されていた。部屋のランプシェードは気に入った。鱒料理。味はこんなものでしょうか。 添乗員が日本からポン酢を持ってきてくれていました。そしてデザート。パンケーキ風のデザートが印象的。
2016.04.23
コメント(0)
-

クロアチア・スロベニア6カ国周遊旅行3(4/21 ザルツブルク早朝散歩)
長い時間の飛行機の疲れもなく、4時には2人とも早朝起床。 このホテルは、メッセツェントルム ザルツブルク エキシビション センターおよびザルツブルガリーナから徒歩 5 分の場所。3階建て、全 120 室の客室にはWiFi (無料)が装備。この日は9時の出発で時間があるため、早朝散歩を開始。 ホテル前の八重桜は満開。 陽光に山の岩肌が輝きだした。 白き山肌が時々刻々とオレンジの色を増していくのであった。 アウトバーン入り口料金所。 巨木には白い花が今が盛りと撓わに。 公園の中には卓球台が2台。ネットはアルミ製。屋外での卓球は風が邪魔をするのだが・・・。 ザルツァハ川(Salzach)に架かる巨大水門に出会う。この川はオーストリアとドイツを流れる河川。イン川の支流で、長さは225km。水源はザルツブルク州のKrimml近郊のキッツビュール・アルプス (Kitzbühler Alpen )。 白き山々を背景にゆったりと流れるザルツァハ川は絶景そのもの。オーストリアにいることを実感した時間であった。 水門を上流側から。日本にはない水門の形状。 陽光が増し川面に映る光景も時々刻々と変化。 水量は多いが静かに流れ、、川面も静かに鏡の如く風景を映していた。 空の青、建物の白、木々の花のピンク、土手の緑そして再び川面の青とBEST MIX。 いつまでも立ち止まっていたい時間と風景。岩山を背景に見える塔はミュルン寺。 遠く山の上にはザルツブルク旧市外の建築物が見えた。小川にも陽光が差し込み新緑が輝いていた。 自撮り。 そしてホテルに戻り朝食。再び青空を背景の八重桜。 このホテルは帰路の最終日の宿泊ホテル。ザルツブルク市内観光を楽しみ、再びこのホテルに宿泊するのであった。
2016.04.22
コメント(0)
-

クロアチア・スロベニア6カ国周遊旅行2(4/20 ミュンヘン経由ザルツブルクへ)
ロシア南東部のシベリア連邦管区のブリヤート共和国とイルクーツク州・チタ州に挟まれた三日月型の湖であるバイカル湖の北方を目指して飛行。 ロシア・シベリア東部を流れるアルダン川の蛇行が美しかった。レナ川の右支流で、長さは2,273km。西シベリア平原の西北部に位置し、北極海の一部であるカラ海上空を目指す。 眼下には北極圏の白き風景が一面に。 一年のうち夏の2ヶ月以外は氷に閉ざされるカラ海を目指す。 白く凍結した高原か?カラ海に面したオビ湾上空。湾の一番奥にはオビ川の河口がある。湾の周囲はロシアのヤマロ・ネネツ自治管区で、湾の西はヤマル半島、東はギダン半島、タゾフスキー半島でタズ川が注ぐタゾフスカヤ湾が。 夕食を楽しむ。クリーミーアルフレドソース のラヴィオリ。ポーランドのブワディスワボボ上空。砂嘴(さし)の先に臨む海はバルト海。 そしてミュンヘンに近づく。 機窓からはカラフルな田園風景が拡がっていた。ミュンヘン近郊の街並み。 ミュンヘン空港を横に見て飛行機は旋回。 高速道路が眼下に。 そしてミュウヘン空港に到着。時間は現地時間17:20。 ドイツ全土に展開している3大スーパーの一つのEDEKAが空港ロビーに。無事出国手続きを完了し、待っていた大型バスにてこの日の宿オーストリアザルツブルクに向かう。ミュンヘン中央駅など市内中心部へ移動する鉄道(Sバーン)が横を走っていた。ガイドのバス内の説明で総勢33名のツアーであることを認識。夫婦7組、女性2人4組、男性単独6名、女性単独3名そして我々2人。 平均年齢65歳以上??。高速を利用しオーストリア・ザルツブルク(Salzburg)に向かう。 車窓から広大な菜の花畑が。 イルシェンベルク付近からの岩山。 白いのは雪ではなく石灰岩の岩肌。ドイツのアウトバーンには速度無制限区間といわれる区間と速度制限区間があるのです。大型トラックは80km/h、バスは条件にもよるが多くの場合100km/hが制限速度とのこと。このアウトバーンは片側3車線道路。もちろん車両は右側通行。 このアウトバーンの普通車の制限速度は120km/hであった。右に行くとインスブルック。インスブルックは1964年と1976年に冬期オリンピックを開催した都市。 教会の塔も夕日を浴びていた。 西の空がオレンジ色に。 そして日没間近。 ドイツ・バイエルン州のローゼンハイムとザルツブルクの間にある淡水湖キーム湖が左手に。キーム湖に沈む夕日。時間は19時前。 そして19:40前にホテルに到着。ホテルはアリーナ シティ ホテル ザルツブルグ( Arena City Hotel Salzburg)。フロントでチェックイン手続き中の添乗員。歴史に詳しく、良く勉強している気配りに長けた40代始めのベテラン添乗員。
2016.04.21
コメント(0)
-

クロアチア・スロベニア6カ国周遊旅行1(4/20 羽田空港から)
【海外旅行 ブログリスト】👈リンクこの日4月20日から旅友のSさんとクロアチア、スロベニア6ヶ国周遊10日間の旅行に出発です。今回も10年間連続で旅友のSさんとでのツアー参加。出発地は羽田空港、以前の成田空港と比べて非常に便利なツアー。今年もトランクとリュックサックで参加。着替えは種類ごとに風呂敷に纏めセルフで詰め込みました。旅友のSさんが愛車のジューク(JUKE)で迎えに来てくれました。妻に見送られて8:30に出発。集合時間は羽田空港国際線旅客ターミナル3階の団体受付カウンターに10:35ですが早めに出発。戸塚から東海道を利用し横浜新道へ向かう。 首都高速湾岸線に車を進め羽田空港へ。前方に横浜ベイブリッジが見えて来た。 そして大黒ふ頭を通過し鶴見つばさ橋へ。 そしていつもの浮島町にある駐車場に約1時間で到着。ここで愛車は帰国までの10日間我々の帰国を待ってくれるのです。 係員が我々のトランクを送迎車に載せてくれました。 簡単な手続きを完了し、送迎車に乗り羽田空港国際線旅客ターミナルまで。 ターミナル3階には久月の特大鎧飾りが。そして多くの外国人が立ち止まりデジカメにて撮影していました。4F江戸舞台にも同様な装飾があり、早くも我々の帰国後のゴールデンウィークがやってきたような気分。団体カウンターに到着すると既に今回の旅行の添乗員が待ってくれており私の名前をいきなり呼んでくれました。やはり男2人での参加は珍しいのでしょうか?誰かが直ぐ解ったようです。近くにいた若い女性係員にも『男2人の参加は珍しいの?』と訪ねるとニコッと笑って小さく頷くのでした。搭乗までの手続きの説明を受け、チケットを受け取り今回の利用便のルフトハンザ航空カウンターへチェックインに向かう。もちろん今回もエコノミークラスでミュンヘンまで二人並んで仲良く。 搭乗口での集合時間まで時間があるので今年もロビー内を散策。そして今年は羽田国際線初めての「鯉のぼり」が登場。50匹ほどの鯉が、到着ロビーの高い天井に向かって盛大に泳いでいました。室内ですが空調用の風が流れている為か、気持ちよさそうに泳いでいたのです。今年もその下には「藤棚」の装飾が。藤(の造花)は去年と同じく精巧な造り。そして昨年より棚の数が充実していると感じたのです。何故か我が住む市の名前の為か、藤棚にはSENSITIVE(敏感)な私なのです。「江戸舞台」にも久月の鎧兜が。4階には、「和」と「江戸」をテーマにした飲食店とショップが並んでいます。メインストリートの江戸小路は江戸時代の街並みを再現。ショップには演芸場を模した店舗、中央にはイベントスペースの「江戸舞台」もあって、日本文化の発信にも一役買っているのです。 江戸時代、旅の始発点は日本橋。その1/2ミニサイズの日本橋が羽田空港に設置されているのです。まさに旅立ちは昔も今も日本橋。総檜(そうひのき)づくりの「はねだ日本橋」が羽田で旅行者の出発を待っているのです。我々もこの旅の出発点としてこの日本橋を渡ったのです。 はねだ日本橋を上った先にあるのが「お祭り広場」。 奥の壁には、いろいろな願い事が書かれた航空券型の多くの絵馬が展示されて(お供えされて?)いました。 その中にこんな絵馬も。海外旅行前に日本人が書いたのでしょうか?それともジョークなのでしょうか?楽に死ねる方法を探している時点で生にしがみついてるのではと感じたのですが・・・・・。出国手続きを完了し、搭乗口へ。12:35発のルフトハンザ・LH715+ANA・NH585の共同運航便。目的地はドイツ・ミュンヘン。慕尼黒は中国語? 利用便はエアバスA300。 座席は左側最後列の58A席。 ミュンヘンまでは11,518km、飛行時間11時間37分とのこと。定刻の12:35に出発。飛行機は新潟方面に向かう。 中央に見えたのは奥只見湖か? 40分ほどするとこのFLIGHTの機内食用メニューが配られた。 とりあえずビールを注文。ドイツビール・ヴァルシュタイナーを楽しむ。そして飛行機は日本海を横断しロシア・ウラジオストックの北方に向かう。 そしてこの日の最初の機内食を楽しむ。 ロシア上空に入り北極圏に含まれるサハ共和国方向に。時間は離陸後約3時間。
2016.04.20
コメント(0)
-

ミツバチの内検
明日20日かから旅友と10日間のクロアチア方面の旅行に行くので、ミツバチの内検を行いました。今年は3群が何とか越冬してくれ、女王蜂も産卵を進めています。既に継箱にて2階建てにしています。蜂の数も大夫増えてきました。真ん中には女王蜂の姿も。内検中には多くの働き蜂が乱舞。そして巣門に帰って行きます。こちらは別の群です。蓋を開け、麻布を取り除くと多くのミツバチ嬢が。産卵も進んでいます。比較的新しい綺麗な巣蓋が。ミツバチ嬢がそれぞれ自分の役割を一生懸命に。この群の内検を終わり元の状態に。女王蜂が逃げ出さないように、巣門にプラスチック製のゲートを設けましたが効果は如何に?働き蜂は通過でき、女王蜂は通過できないスリット幅にしたつもりですが・・・??。そして最後の群です。この群の群勢が一番強いのです。産卵も進んでいます。私が留守の間にこの巣蓋の中にいる働き蜂が誕生するのでしょうか?王台(女王蜂を育てるために、働き蜂が作る小部屋)の存在は3群とも確認できませんでした。内検が終わった後です。こちらの巣門にもトールゲート【tollgate】?を取り付けました。養蜂箱が並んでいますが、白の発泡スチロールが残っているものは残念ながら越冬できなかった群なのです。ボーイッシュなマネキンも女王蜂を監視中?ミツバチ用に栽培している菜の花の満開もあと数日でしょうか。留守中に分蜂せずに仲良く私の帰りを待っていて欲しいとお願いしてこの日の内検を終わったのです。
2016.04.19
コメント(1)
-

夏野菜の植え付け
我が趣味の菜園の夏野菜の植え付けもほぼ完了しました。苗は、種から育てたもの。通販やホームセンターで購入したものが混在しています。まずはトマト、ミニトマト。17日の強風対策の跡がまだ残っていますが。 今年も大玉の『桃太郎』とミニトマト『アイコ』の苗を定植しました。 キュウリ。 既に支柱も立て、海外旅行から帰国後にネットを敷設予定です。 こちらはナス。中長ナス、水ナスを植え付けました。 種から育てたもの、購入した苗が混在しています。 ピーマン、万願寺トウガラシ。 万願寺トウガラシは果肉は大きくて分厚く、柔らかく甘味があり、種が少なく食べやすいことが特徴。 スナップエンドウも順調に成長し、収穫を始めました。タマネギも大きくなってきました。イチゴも後1週間程度で収穫可能でしょうか。ジャガイモも芽を出し芽欠きの時期です。そしてアスパラガスは次々に芽を出し、毎日食卓に。我が家の横の菜園全体です。南側。北側。そして養蜂場のある菜園にも。トウモロコシ。 種から育てた2種類を定植しました。 枝豆。 早生苗。晩生用は未だビニトンで成育中です。帰国後には定植できるでしょう。 ブロッコリー。 スティックブロッコリーも植え付けました。 春蒔きのスナップエンドウです。 ミツバチ用の菜の花畑も開花し、ミツバチ嬢が花と戯れています。 19日の明日は、この菜園にカボチャ、スイカを定植し、旅行前の植え付けは完了です。旅行中にしっかりと根を張り、成長していてくれることを願っているのです。
2016.04.18
コメント(0)
-

イチゴの防鳥網掛け
我が趣味の菜園のイチゴも気温の上昇とともに順調に成長しています。 新たな葉も日に日に大きくなり、白い可愛い花、そしてイチゴのアカチャンも多数姿を見せてくれています。 ハウスイチゴ農家にとって、イチゴがきれいな大きな実をつけるためには大切な作業があります。それは花が咲いたら行う受粉作業。確実に受粉ができていないと実ができなかったりいびつな形のイチゴができたりします。基本的に植物の受粉は虫や鳥、風などによって自然受粉をしています。しかしハウスのなかで栽培しているイチゴには、その自然による受粉交配はほぼ不可能。そこで昔は、一花一花ごとに手作業で筆などを使って受粉作業をしていた様ですが、本当に骨の折れる作業だったようです。その受粉作業を人の代わりにより自然に近い形で行ってくれるのがミツバチなのです。 我がイチゴ畑は露地栽培ですが、この日も我がミツバチ嬢?が訪花してくれていました。既に赤くなり始めた実も所々に。 この実はミツバチ嬢が訪花し忘れたのでしょうか?形が凸凹。こうなるとプロのイチゴ農家の方は商品価値が落ち、出荷できなくなってしまうのです。周囲の実はきれいな形に成長してくれています。 実が赤くなり始めると、カラス等野鳥がこの赤い実を目敏く見つけ突っついてしまうのです。この日はこれを防ぐため、防鳥網を敷設しました。 網の目幅を小さくしすぎると、ミツバチ嬢が中に入れなくなってしまい受粉作業が出来なくなってしまいますので網の目幅も重要なのです。 こちらは自宅横の菜園のイチゴ畑です。 こちらは養蜂場のある菜園のイチゴ畑。 昨年は生育のイチゴ苗が順調に成長してくれましたので、多くの苗を植え付けたのです。血液型B型人間としては、苗を捨てるのは勿体ないのです。これでもやむなく苗を捨てたのですが・・・・。こちらのイチゴの畝はマネキンが野鳥をしっかり見張ってくれている?のです。 今年は多くのイチゴが収穫できそうです。孫達もイチゴ狩りを楽しみにしていてくれるはず。20日からクロアチア方面の海外観光ツアーに参加しますが、帰国時にはたくさんのイチゴが赤い実を付け、ミツバチ嬢とともに私の帰宅を大歓迎してくれるはずなのです。
2016.04.17
コメント(0)
-

フキ(蕗)の収穫
この日は実家の竹藪にフキ(蕗)の収穫に行ってきました。既に姉夫婦がタケノコを収穫中。 この時期、この竹藪にはタケノコと併せてフキ(蕗)が収穫時期を迎えているのです。 フキ(蕗)は古くから日本人に親しまれてきた野菜の1つで、特有の香りとほろ苦さが持ち味。また、フキの花茎である「フキノトウ」は、春の味覚として食卓を楽しませてくれるのです。 ハサミで15分ほど茎が太めのものを収穫しました。 フキの茎が緑色のものと赤っぽい紫色のものがあります。赤いのはアントシアニンでは?茎の根本が太陽光にさらされているかどうかでは?長女夫婦に電話連絡すると早速孫たちを連れて、タケノコ、蕗を採りに来ました。家に持ち帰ると妻が早速調理してくれました。フキはアクが強いので調理前にアク抜きをすると。茎を鍋に入る長さにカットし、まな板の上に並べて塩をかけ、両手で前後に押し転がすように板ずりをするのだと。そして塩分少なめの蕗の佃煮(キャラブキ)の完成です。たくさんのフキを収穫してきたつもりでしたが、キャラブキにすると思ったほど多くなかったのです。洒落た器で、これも旬の山の幸を楽しみました。そしてセリ(芹)のおひたしも。 豚バラと筍、百合根、ネギの炒め物も。 ここ数日は、ベジタリアンに近い生活を送っている我が家夫婦なのです。
2016.04.16
コメント(0)
-

天然の芹(セリ)
我が養蜂場のある菜園の下に農業用の水路があります。そこに多くの芹(セリ)が自生しています。子供の頃はこの小川にはタニシや小魚も住んでおり、アメリカザリガニを捕まえて遊んだ記憶があるのです。セリは有毒なドクゼリとの区別が必要ですが、毎年この時期に収穫していますので確認済みなのです。和名は、まるで競い合う(競り)ように群生していることに由来するのですが写真からも納得できるのです。収穫し家に持ち帰ったセリ。春先の旬のこの時期、若い茎や根をおひたしやイタメモノ等とする習慣があるのです。セリは春の七草の一つでも。正月7日にセリなど七草を入れて炊いた七草粥を食べると万病を防ぐと伝えられています。妻がこの日は炒め物に。旬の幸を追いかけている、『アクティブシニア』 なのです。
2016.04.15
コメント(0)
-

ミツバチの検査
一昨日、我が趣味の養蜂のミツバチの検査が行われました。 検査員の男女2名の方が我が家に車で来られ、保護具を纏い我が養蜂場へ。そして検査開始。 検査員は神奈川県湘南家畜保健衛生所の方々。この機関が「家畜伝染病予防法」に基づいて、家畜(牛、馬、豚、鶏、めん羊、山羊、みつばち等)の伝染病予防及びまん延防止のための検査、診断、指導を行っているのです。家畜とは、その生産物(乳、肉、卵、毛、皮、毛皮、労働力など)を人が利用するために馴致・飼育している動物を指すのです。類義語に益獣(えきじゅう)があり、また鳥類のみを指した場合は家禽(かきん)と呼ぶのです。すなわち、みつばちは家畜伝染病予防法でいう「家畜」なのです。ただし、「家畜」という言葉は一般的には、人間が利用する動物の中で、愛玩動物(金魚、セキセイインコなどのペット)を除く、動物が生み出す生産物を利用する事に特化した哺乳類や鳥類を指すのです。一部の魚介類(マダイ、カキ、アコヤガイなど)や爬虫類(スッポン、ヘビ、ワニ)など人が食用や薬用、皮革など工業用に利用するために養殖されている動物は家畜ではなくまた野生動物を捕獲したものは家畜には含めないとのことです。検査官からいただいた書類には、神奈川県公報が添付されていました。神奈川県告示第82号。家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項の規定により蜜蜂の腐そ病の検査を次のとおり実施する。 平成28年3月4日 神奈川県知事 黒岩祐治。腐そ病は、ミツバチが感染する病気の中で最も重い病気。腐そ病菌が孵化3日以内の幼虫に感染すると、幼虫やサナギの時期に死亡してしまうのです。趣味の養蜂を実施している私への検査実施に関する書類も頂きました。検査のため巣箱を開けました。 女王蜂も元気に活動していました。 産卵も順調のようで検査は合格。 別の群の検査も合格。 働き蜂の巣門への出入りも活発です。 3群全て腐そ病の症状はなく合格とのこと。検査員の女性から追加説明が。県内で『アカリンダニ症』の発生がニホンミツバチで確認されていると。感染しても多くは無症状であるが、重度に寄生すると呼吸困難や働きバチの寿命の短縮が起きるとのこと。【www.pref.shiga.lg.jp/g/kachiku/gyohatu/files/8_sugimoto.pdf】また外来種の新種の『ツマアカスズメバチ』が北九州で発見されていると。 これまで国内では長崎県対馬市のみにおいて確認されていましたが、対馬市以外では初めて確認されました。 ツマアカスズメバチの基本情報原産地 中国、台湾、東南アジア、南アジア形態的特徴 ・体は全体的に黒っぽい ・アゴの周りと腹部がオレンジ色 ・大きさは20~30mm程度ツマアカスズメバチの生態主に昆虫類(ミツバチを含む)を捕食します。樹木の高い位置に営巣することが多いです。在来スズメバチよりも大きな巣をつくるといわれています。 【http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tumaakasuzumebati.html】よりいずれも見つけた場合は連絡して欲しいとのこと。3群の検査費180円を支払いました。 そしてこの日の検査を無事終了したのです。
2016.04.14
コメント(0)
-

タケノコ掘り
実家の兄から、屋敷の中にある竹藪にタケノコが姿を現して収穫の時期だと。早速、タケノコ掘りに行ってきました。 私の子供の頃には、竹藪の広さは現在の4倍以上あったのでしょうか。少しずつ整理され、現在は4~50m2程度。 太い立派なタケノコを発見。地上へ10cm程度顔を現していました。 こちらはスラッとした形。 15分ほど鉄ノミで3本を収穫。2本は途中から切ることなくほぼ完璧。血液型B型としては上出来なのです。 こちらは私と同じメタボ。 私のあるべき姿なのです。 早速、妻が米糠で茹でてくれ、この日はタケノコご飯を楽しみました。 竹の子の煮物も。 そしてアサリの味噌汁。 我が農園のエシャレットをビールのつまみに。 春の旬の海の幸、山の幸そして自ら収穫したものを楽しんでいるアクティブ・シニアなのです。
2016.04.13
コメント(0)
-

俣野別邸庭園の木々や花々(その2)
更に庭園の花々を楽しむ。ヨコハマヒザクラ。ヨコハマヒザクラは横浜市在住の白井勲氏が、昭和47年にヤマ ザクラ系の兼六園熊谷桜と寒緋桜の交配により作り出したもので ソメイヨシノの開花に先立って鮮やかな紅色の,重なり合うような 花をつけると。 ウラシマソウ。苞の中に伸びた付属体の先端部が細く糸状に伸び、その姿を、浦島太郎が釣り糸を垂れている姿に見立てて、この和名があると。 私の保有する『野草の名前』の本には優しい絵までが。なるほど、昔の人の想像力に脱帽。冠の髻(もとどり)を収める高い部分・巾子の形、色までをも想像したのでしょうか。ジューンベリー。 5弁の白い花で、果実は直径7-10mm、6月頃に黒紫に熟すのです。果実が6月(June)に収穫できるところから、ジューンベリーという名称がついたと。 シャクナゲ。チューリップ。 綿の花。開花して果実ができ、はじけて白いワタがぶら下がっていました。 ヒュウガミズキ(日向水木)。「日向~」の名前の由来は、日向(宮崎県)に多く植栽されていた、という説と、明智日向守光秀(みつひで)の所領だった丹波地方(京都北部)に多く植栽されていた、という説があるとのこと。魚のうろこが重なったような形の花がぶら下がるようにして咲いている。 シャガ( 著莪)の群生地。シャガの名前はヒオウギの漢名「射干」を日本語読みしたものといわれ、葉がヒオウギに似ているところから間違って名付けられたと言われているのです。白っぽい紫のアヤメに似た花。花弁に濃い紫と黄色の模様が。 野イチゴの一種クサイチゴの花。桜も苺も、同じバラ科というのも以外。花が咲いて1ヶ月後もすれば赤い果実が。クロフネツツジ。安土桃山時代から日本に来航する外国船は黒船と呼ばれていた。その黒船で持ち込まれた躑躅というのが名の由来。別名をカラツツジ(唐躑躅)。アセビ(馬酔木)。馬酔木の名は、「馬」が葉を食べれば毒に当たり、「酔」うが如くにふらつくようになる「木」という所から付いた名前であると。スイセン。 淡い黄色が珍しい。 ハナモモの、テルテモモ(照手桃)。通常のハナモモは枝が横に広がりますが、テルテモモは、縦の箒状になるのが特徴。ピンクと白が仲良く並んでいました。ハナモモの、テルテモモ(照手桃)のピンク。 ハナモモの、テルテモモ(照手桃)の白。 タケノコ。 そして入口のオオシマサクラ。
2016.04.12
コメント(0)
-

俣野別邸庭園の木々や花々(その1)
俣野別邸庭園の花々を紹介します。まずは真っ黄色なヤマブキの花。一重のヤマブキ。八重のヤマブキ。ワラビ。タチツボスミレ。椿の赤い花が美しく命を終えていた。バナナではなくバショウ(芭蕉)。ウコン桜。黄色の花を咲かせる桜。八重桜(やえざくら)ネモフィラ。手前には濃い青紫色の5つの水玉模様がついているような白い花。帰宅して調べてみるとネモフィラ・マクラタと言う種類。姿の如く「ファイブ・スポット(Five Spot)」という英名があるらしい。カラフルなヒメキンギョソウ。美しい色彩美。オオシマザクラ。既に紅葉を始めた?モミジ。ミツバツツジ。アネモネ。タンポポ。綿毛も美しく。キバナカタクリが群生。キバナカタクリはアメリカやカナダの山地に自生するカタクリで、日本には園芸用として入ってきた品種で、セイヨウカタクリとかヨウシュカタクリとも呼ばれていると。上に向かって強く反り返り存在感を示していました
2016.04.11
コメント(0)
-

俣野別邸庭園へ
【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク自宅から車で10分ほどの場所にある俣野別邸庭園へ妻と行ってきました。もともとこの場所には旧住友家俣野別邸があった場所なのです。65年間この地に生きていますが、全くこのような住友家別邸が近くにあることを知りませんでした。住友の名のある会社で長年お世話になっていたのですが・・・。旧住友家俣野別邸(以下俣野別邸)は、1939(昭和14)年に住友財閥の第16代住友吉左衛門友成の別邸として戸塚区東俣野町に建設されたとのこと。当時の郊外邸宅の有り様を物語る歴史的価値の高さから、2004(平成16)年に国の重要文化財に指定されたと。管理団体の横浜市が一般公開を目指して一部の老朽化した箇所の復元工事を進めていたところ、2009(平成21)年に出火。母屋約659m2を全焼したと。その後約4haの外苑部分を『俣野別邸公園』として2013年3月に公開する運びとなったと。(http://hamarepo.com/story.php?story_id=1764)有料駐車場に車を停め散策開始。駐車場横の芝生の下には雨水調整池が。入り口の俣野別邸庭園案内板。入り口の坂を上る。カスミザクラ?それともオオシマザクラ?であろうか、ほのかに香る白い花の大木が。坂を上っていくと、左手に入り口が閉鎖された鉄骨階段が。そしてその上には建物の屋根が見えた。焼失を免れた旧住友家俣野別邸の一部であろうか。更に歩を進めていくと、大きな凧を持ったオジサンが。凧を上げに来ているのであろうか?最奥に園内の唯一の建物の公園管理棟が。管理棟の前には、花の終わったソメイヨシノとこれを囲むチューリップ、クリスマスローズが開花中。管理棟内には休憩用のテーブル、椅子が用意されていた。そして園内の『3ヶ月開花予報』がホワイトボードに示されていた。園内MAPと花の写真の説明板が丁寧に。 管理棟の前は広い芝生広場になっていました。園内には数匹の猫がのんびりと。野良猫であろうか?しかし綺麗な姿の猫。 約1時間ほど、園内の花々を楽しんだのであった。紅葉シーズンにもモミジ等が美しいのであろう。また秋に行ってみようと思っています。明日はこの園内で開花していた花々を紹介いたします。
2016.04.10
コメント(0)
-

潮干狩り
義兄に誘われて潮干狩りに行ってきました。場所は横浜市金沢区野島町にある野島公園沖。駐車場が混雑するとのことで7:30に車で出発。9時前に到着するも目的の第1&2駐車場は既に満車。Uターンして何とか室ノ木地区臨時駐車場にすべり込む。徒歩にて野島公園に向かう。夕照橋を渡る。橋の下では干潮前であったが既に潮干狩りを楽しむ家族が。 夕照橋を渡る義兄。左手には長い柄の熊手と網が。そしてクーラーボックスの上には胴付水中長靴が。準備万端の潮干狩りのプロ!! 夕照橋の下にある釣り舟・船宿『新修丸』や『カサゴ』。既に釣り舟は出港済み。 そして10分ほどで野島公園管理棟前へ。この管理棟では野球場の利用・予約受付を行っているとのこと。ここでトイレを済ませ更に公園奥へ向かう。 野島公園案内図。野島公園は、横浜市最南部平潟湾入口に浮かぶ小さな島の公園で、歌川広重に描かれた「野島夕照」で知られています。海抜57m の野島山を中心としてバーベキュー場、キャンプ場、野球場などの施設を備え、展望台からは横浜の海はもちろん、房総半島や富士山まで360 度の景色を見ることができるのです。野島貝塚など、市の歴史を感じる事のできるスポットも。 海岸に辿り着くと目の前に見慣れた造船所の巨大ゴライアスクレーンが。 あさり採りのルールを説明する表示板。『じょれん』の使用禁止、くまでの幅は15cm以下、あさりの殻の幅は2cm以下は採取禁止。 胴付水中長靴を履いていざ出陣。私のアサリ採りの道具。短い熊手と、プラスチック籠を改造した篩い。 海の砂の上にこの籠を置き、熊手で砂ごとこの籠に掻き込みこれを引き上げ海面上で揺らし、海水で洗いながら砂を落とすのである。そして小さい貝は海に戻し、2cm以上のあさりをバケツに。残念ながらカメラ持参で海に出るのは危険でしたので実況中継はここまで・・・・。義兄は長柄の熊手と網を持ち、海の深場へ。4月9日のこの日は中潮の絶好の潮干狩り日。 岸に水分補強で戻ると、干潮間近い11時頃には多くの潮干狩りの人々が。 子供たちは潮が引いて出来た砂浜で懸命に。 家族で楽しむ父子連れ。 目の前には八景島シーパラダイスのサーフコースター リヴァイアサン。しかし何故かこの日は動いているのが確認できなかったが・・・・?。 松林には家族連れのカラフルな多くのテントが並んでいた。 途中水分補強、腹ごしらえで2回ほど岸に戻ったのであったが約3時間の奮闘で中型バケツ一杯近くを採取。アサリ以外にもシオフキやカガミ貝?も。 そして12時半過ぎに引き上げ開始。途中ちびちゃん二人が真っ裸で着替え中。旧伊藤博文金沢別邸。旧伊藤博文金沢別邸は、この野島公園の中にあり、明治31年(1898年)に初代内閣総理大臣の伊藤博文公により建築され、その歴史的価値から平成18年11月1日に横浜市指定有形文化財に指定。第1駐車場の満車のランプは既に消えていた。 砂抜き用に海水を大型ペットボトルに入れて帰宅。 そして発泡スチロール箱で砂抜きを一夜。 時々噴水の如く一筋の糸が水面上のあちこちで。 そして早速アサリの炊き込みご飯を妻が作ってくれたのでした。 アサリのバター酒蒸しも美味。 アサリの味噌汁も楽しみたいと思っているのです。久しぶりの潮干狩りを子供に返り必死に!!楽しんでしまいました。
2016.04.09
コメント(0)
-

はなかいどう (花海棠)咲く
我が家の横の農園の入り口の、はなかいどう(花海棠)が開花しました。海棠という漢字は、棠が梨を意味し、「海を渡ってきた梨」という意味で名付けられたとのことです。桜(ソメイヨシノ)に引き続いて咲きだす春の代表花の一つ。いやソメイヨシノが散り始める頃に濃いピンクの可憐な花を枝いっぱいに咲かせると言った方が正確かもしれません。淡いそして濃いピンクの花の色がなんとも美しいのです。開花前の、濃いピンクの蕾が垂れ下がる姿も個性的。その姿は、さくらんぼに似ているのです。今日、4月8日の誕生花なのです。花びらは雄しべと雌しべを軽く包むような半開状態になり、完全に開かない花が多いようです。ハナカイドウ(花海棠)の花言葉は『艶麗』『美人の眠り』『温和』『友情』。「艶麗」「美人の眠り」という花言葉は、ほろ酔い加減で眠そうにしている楊貴妃の姿を見た唐の玄宗皇帝が「海棠の眠り未だ足らず」といったことに由来しているのだと。
2016.04.08
コメント(0)
-

3月の太陽光発電 実績
我が家の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の3月の実績です。発電積算は586KWと2月の553KWより33KWプラスとなりました。しかしながら2月は29日と3月に比べて2日少ないので同等と言うことでしょうか。また3月の東京電力さんへの売電量は367KWH、17,616円です。3月のスタートは好天に恵まれ発電量も順調でした。毎日の発電、売電、買電、消費電力のデータです。2週目は低調、売電0の日が3日間も。3週目はまあまあ。4週目は全体的に不調。5週目は後半に頑張りました。3月29日のこの日はこの月の最高の発電量31KWHを達成。緑が発電量、そして黄色が売電量。発電したものの殆どを売電していることが解るのです。逆に3月9日はこの月最低の発電量1KWH。売電量はもちろん0KWHでした。4月に入りましたが、発電量は伸びていません。月初はサクラの花の咲くころに急に気温が低くなる花冷えが続いていました。また花曇りで我が太陽光発電も発電量を一気に増やせない状況です。
2016.04.07
コメント(0)
-

君ヶ野ダムの桜
再び三重の津の事業所を訪ねました。ホテルからの早朝の街の眺め。 同僚のレンタカーで現場に向かう。現場はホテルから40km弱の距離。私の会社生活でも1,2位の不便な場所。途中、車窓からの桜を楽しみシャッターを押す。 前日の雨で水量を増した川は堰から水が大きな幅の滝の如く。 道路沿いの桜はここも満開状態。 君ヶ野ダムの横を走る。放流の白き曲線が美しかった。 君ヶ野ダムの堰堤を渡る。 対岸の山の斜面に咲く多くの桜が迎えてくれた。 対岸に車を停めつかの間の散策。ダム湖沿いの道路の桜並木が見えた。 早朝のダム湖の水面は静かに。 君ヶ野ダムは昭和47年竣工とのこと。雲出川水系八手俣川のダムで重力式コンクリート方式。堰堤高は73m、長さ323m。総貯水容量は23300千m3。 市営宿泊施設レークサイド君ケ野は君ケ野ダムの湖畔にあり、自然の中でゆったりとした一夜を津市美杉町ならではの地元食材をふんだんに使った魚ずくし、肉鍋料理等でくつろげると。春の桜・秋の紅葉は見事であると。 ダムを覗き込む。 再び車を走らせ車窓の桜を楽しむ。 ダム湖を囲む山々の上部にも桜の木々が。ミニ吉野の光景。 再び君ヶ野ダムが見えてきた。 先ほど渡ったダム堰堤とダム湖。 水面には桜が映って美しかった。4月3日(日)に行われた君ケ野ダム公園桜まつりの提灯がぶら下がっていた。 美杉地域の循環バスとすれ違うが乗客は二人。狭い道路、乗客数には大きすぎるバス。 遠くダム湖に架かる赤い花広大橋が。 対岸の道路にも桜並木が。 そして下之川の街並み いや 村並み。正に日本の山村風景。 八手俣川沿いの桜並木。 畑のネットは鹿、猪対策とのこと。新たに建設された「住民交流センター」と隣接する「美杉ホットテラス」。温泉施設もありローリーで下から温泉を運んでいるのだと。 仲山神社の桜。三重県三大奇祭の一つ数えられる下ノ川仲山神社のごんぼ祭りは男女根崇拝に拠る素朴な子孫繁栄・五穀豊穣を願う祭りとのこと。昨年は我が同僚も参加させていただいたのです。西迎寺の桜は見事な老木。 そして走ること1時間強で現場に到着。
2016.04.06
コメント(0)
-

三州ショウガの植え付け
今年もホームセンターで購入した三州ショウガの種の植え付けを行いました。冷えた生ビールには、最高に美味しい・・・正に夏の味覚。味噌をつけてガリガリとかじって食べるのです。そして収穫のタイミングによっては、茎ショウガ、葉ショウガ、新ショウガ、種ショウガと様々な風味を楽しむことができるのです。袋から取り出して見ました。三州ショウガは小ぶりのショウガ。体を温める成分「ショウガオール」が一般の生姜の3倍も含まれる品種。30cm間隔に種ショウガを置いていきました。その間に化成肥料と鶏糞を。そして丁寧に土をかけ、その上から黒マルチを敷いたのです。手前の2畝が三州ショウガなのです。発芽までには1か月ほどかかりますがじっと待つしか「ショウガナイ」ないのです。失礼いたしました。
2016.04.05
コメント(0)
-

校庭内の桜並木
我が家の近くの大学、高校、中学、小学校が開設されている私立大学の校庭の名物の桜並木の見物にも。昨年の竜巻でこの桜並木の老木が1本根こそぎ倒れた事もあり、この桜並木は大きく枝を落としたのであろう。この舗装部分が倒木の場所か。学校入り口にも巨木の桜が。右に曲がり大学方面への桜並木を歩く。大学の競技場の周囲も桜に囲まれている。桜並木の奥には高層校舎が。ピンクの桜の帯の手前には濃い緑の人工芝が雨に濡れて。折り返して、『上を向いて歩こう』。競技場橋からの高層校舎とその下の桜並木。
2016.04.04
コメント(0)
-

引地川の桜見物
この日の早朝に、車で10分ほどの引地川沿いの桜並木を見に行ってきました。車を川沿いの駐車場に停め散策開始。幸い雨はあがり、傘なしで。満開状態の桜を楽しむ。 上流に向かって川の流れを右側に見ながら進む。 青空が背景にあると桜が輝くのであるがこの日の朝は残念ながら。 テレビのニュースによると、全国の桜の名所のうち約8割がソメイヨシノを植えていると。ソメイヨシノは本州から北海道の南部(道南)まで広く分布。ただし、沖縄と、北海道の大部分の広い地域では育たないのだと。このソメイヨシノはオオシマザクラとエドヒガンの交配種。 白い桜も。これがオオシマザクラ? 老木の桜の主幹にも蕾が。 桜はバラ科サクラ属サクラ亜属サクラ節に分類されると。ヤマザクラやオオシマザクラ、エドヒガンなどの11種の野生種があり、これらの組み合わせで、現在400以上の品種があるのだと。 川面を覗き込むように桜の枝が。 川のカーブにピンクの帯が両側に。 既に花時雨(はなしぐれ)が。 濃いピンクの椿も負けじと存在感を。 ユキヤナギの白も負けじと。 Sカーブのピンクの曲線。 椿の花びらも雨に濡れて。 カーブミラーに写っていた桜並木。 川面も僅かにピンクに染まっていました。 老木には桜の管理番号?札が針で固定されていた。 樹齢30年以上であろうか?60年ほど経ったソメイヨシノに関しては、樹勢が衰える木が多いと。 橋の袂まで戻る。 再びカーブミラーに映る桜を。 橋からの上流川を望む。
2016.04.03
コメント(0)
-

我が家の横の菜園
我が家の横にある趣味の菜園の状況です。手前がイチゴ。日に日に新葉が出てきて盛り上がってきています。気温の上昇とともにイチゴの生育は盛んになり、開花を始めています。だいたいソメイヨシノの開花期と同じ時期に開花するのでは。我がミツバチ嬢?も訪花を始めています。スナップエンドウが二畝。奥が昨年秋から越冬したもの。手前は種を春蒔きし定植したものです。高さ2m程の支柱を立てて、つるもの用ネットを張りました。伸びたつるは、ひもでネットに誘引して這わせています。黄色の紙はハモグリバエの食害防止用の捕獲粘着シート。ハモグリバエの食害により、絵を描いたような葉が出て来てしまうのです。スナップエンドウの手前にはトマト定植用の2条(2列)植え用の苗床も準備が完了。植え付けの前に支柱を立てます。その方が根を傷つけることがないとご近所の農友から。そして手前にはまたまたイチゴ。今年は孫用に多くのイチゴをこの家の横の菜園に栽培しています。養蜂場のある菜園では、収穫時に孫がミツバチに刺される危険があるからこちらにと娘からの強いリクエストなのです。無事に大きな真っ赤な実をつけて、孫がイチゴ狩りが楽しめると良いのですが。黄色の菜の花は蕪が開花したもの。この花もミツバチ用なのですがやや過保護なのです。その手前にジャンボニンニクと普通のニンニクを栽培中。一番前はキュウリ定植用の苗床も準備が終わりました。右手はタマネギ栽培。左手のビニトンの中ではトウモロコシやナス、スイカ、カボチャ、ズッキーニ等の種を蒔き苗を育成中なのです。反対側からの菜園のほぼ全景です。空豆は越冬中にアブラムシにやられたのか元気がありません。そしてアスパラガスも元気に顔を出し始めました。サラリーマン生活を昨年末で卒業し、菜園を楽しむ時間が増えましたので菜園が大夫綺麗になり、『菜園らしくなった』と妻からもお褒めの言葉を。今月20日からは10日間ほど海外旅行に行きますので、その分も前倒しで農作業を進めているのです。
2016.04.02
コメント(0)
-

兜飾り
昨年の暮れに我々長女に長男が誕生しました。先日、妻が五月人形の『兜飾り』を購入し贈りました。男の赤ちゃんが生まれて、初めて迎えるお節句(五月五日の端午の節句)を、初節句といってお祝いするのです。生まれたばかりの赤ちゃんが、丈夫に、逞しい男性に成長するように、願いを込めてお祝いする行事で、江戸時代から続いている習わしのようです。ネット情報によると大昔からの長い武家政治の中で、鎧や兜は男子にとって非常に大切なもの。それが今日では、その「精神」を大事にするためと、戦いの身体防護として鎧、兜は「身を守る」という大切な役目をもっているため、五月人形として鎧や兜を飾る事が、男の子の誕生を祝い、無事に成長して、強く、立派な男となるようにとの家族の願いを意味するのだと。つまり、鎧、兜が身を防いでくれて、その子に交通事故や大きな病気がありませんように、受験、就職、結婚など、「人生の幸福に恵まれますように」という想いが鎧、兜にはこめられているのだと。内飾りの兜飾りと陣羽織のSETを贈りました。妻のお気に入りのデザインで鮮やかな彫金が気に入ったと。戦国武将の誰をモチーフにした兜飾りなのでしょうか?鍬形は竹雀の兜、源義経?中央に10菊紋章?陣羽織も紺地に龍柄の金襴織が美しい。孫が実際に着用できる陣羽織。2歳6ヶ月前のお姉ちゃんは付属のオルゴール付きの写真入れを持って。1週間ぶりのご対面でしたが、生後3ヶ月も過ぎ、順調に成長し表情も大変豊かになり、私に笑いかけるほどに。元気にすくすくと成長して欲しいと願っている『じいじ』なのです。
2016.04.01
コメント(1)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- フランスあれこれ・・・
- 【PARIS】【illuminations de Noëlク…
- (2025-11-19 04:20:29)
-
-
-

- 国内旅行どこに行く?
- 清水寺参道を歩く 徒歩20分で仁王門…
- (2025-11-19 11:30:04)
-
-
-
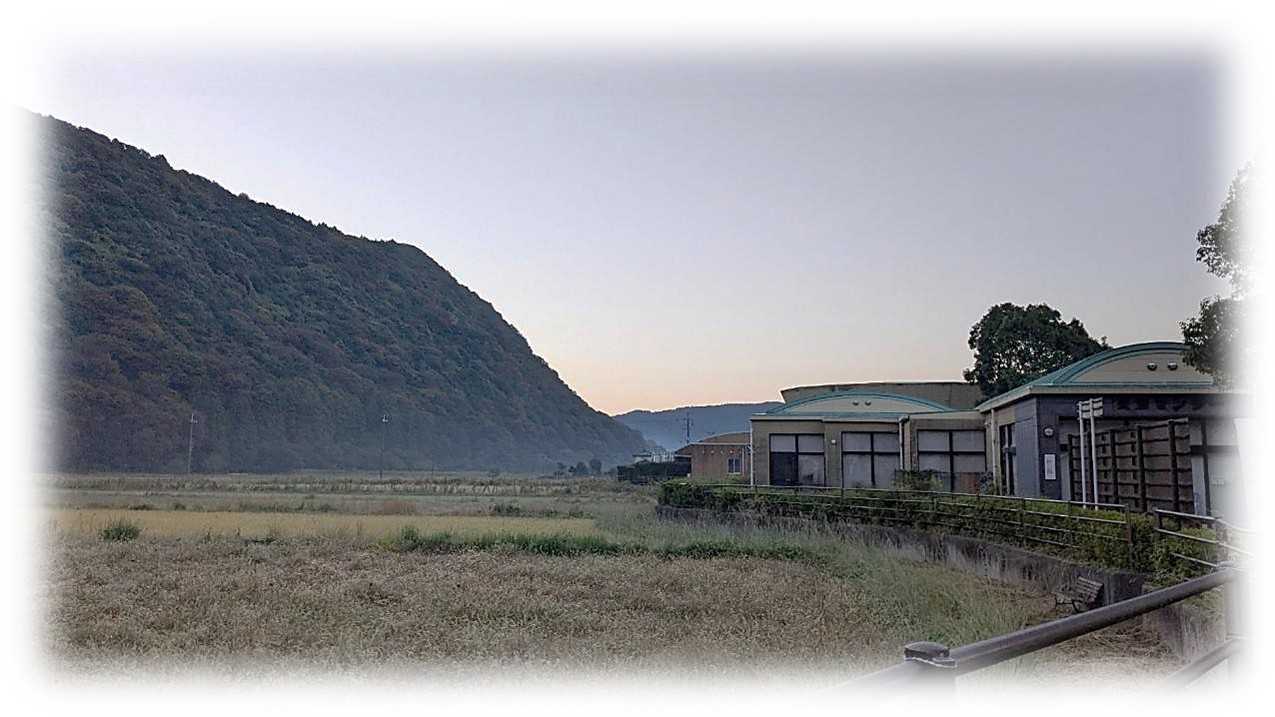
- 日本各地の神社仏閣の御朱印
- 周防國・長門國一ノ宮巡りday2(元乃…
- (2025-11-19 14:06:58)
-







