PR
Keyword Search
Comments
【甥のステント挿入…
 New!
Gママさん
New!
Gママさん2025年版・岡山大学…
 New!
隠居人はせじぃさん
New!
隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…
 noahnoahnoahさん
noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん
Calendar
足利学校の見学を終え、足利市内を通り次の目的地である金山城へ向かう。
途中、街路樹がピンクに染まっていた。 
桃の木か八重桜ではと思ったが、近づいてみるとピンク一面の花水木であることが
解ったのであった。
この様にピンク一面に染まった花水木は初めて見たのであった。

渡良瀬川に架かるバランスのよい3連アーチは、巨大な鉄骨の芸術そのものの魅力。

森高千里が歌った「渡良瀬橋」 を想い出したのであった。

そして目的地の史跡金山城跡ガイダンス施設に到着。
金山城は、群馬県太田市のほぼ中央にそびえる標高235.8メートルの独立峰、
全山赤松に覆われた金山に築かれた山城。別名「新田金山城」、「太田金山城」。
史跡金山城跡ガイダンス施設は、金山城跡の歴史を紹介する歴史学習の場、
金山来訪者の憩いの場として、平成21年5月30日に金山の麓に開館したとのこと。
こちらは太田市金山地域交流センター入り口。別の団体が管理していいる様子。

反対の道路側が史跡金山城跡ガイダンス施設。
外壁には金山城の石垣をイメージした石版が配置されたユニークな外壁の建物。

史跡金山城跡ガイダンス施設の玄関。

入場料は無料

館内には金山の歴史が詳しく書かれており、各ポイントでは城主であった横瀬氏が
軍議をしていたりというジオラマが展示されていた。

パンフレットによると
「金山城は、1469(文明元)年に岩松(新田)家純により築かれました。
その後、岩松氏の重臣横瀬(由良)氏に実権が移っています。
この時期、上野と呼ばれた群馬県地域は、越後の上杉氏、甲斐の武田氏、
相模の小田原北条氏など、有力な戦国大名に取り囲まれていました。
金山城主の横瀬氏は、上杉氏や小田原北条氏と関係を保ちながら生き残りを図っていました。
その間、十数回もの攻撃を受けましたが、金山城は一度も城の中枢部に攻め込まれず、
その守りの堅さを誇りました。しかし、1584(天正12)年小田原北条氏の謀略により
直接支配下に入りました。
そして、1590(天正18)年豊臣秀吉が小田原北条氏を攻め落としたことにより、
金山城も廃城となりました。」と。
施設中央にある"戦国シアター"という大スクリーンで金山城の歴史を学ぶ。
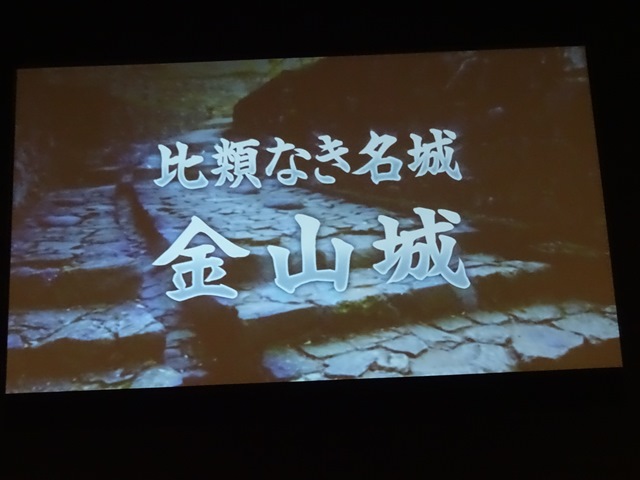
金山城模型も展示されていた。こちらは写真撮影可。

見張り櫓も復元されていた。

施設の見学後は、再び車で狭く曲がりくねった山道を登り、金山城趾に向かう。
駐車場横には太田市観光ガイドマップが。
日本百名城スタンプは南曲輪休憩所に置いてあることがきちんと説明してあった。

金山場周辺のハイキングコース案内。

城趾に向かい坂道を徒歩で登っていくといたる場所に山ツツジが満開状態。

石垣の先を隠す物見台下虎口に到着。
金山城の石垣は北条流の築城法とのこと。
畝掘や障子掘は水のない空掘の底に畝を残し、敵兵の行動を阻害するという、
北条流築城術の特徴
畝堀とは堀の底に畝をもうけることによって敵兵の堀の底での自由を奪う築城法。
障子堀とは畝堀と同様、底に畝をもうけた堀。畝が格子状になっているのが特徴。
以前訪ねた山中城にも同様な堀があったことを想い出したのであった。

最近更新したような木橋を渡る。

遠く太田市北部運動公園の芝桜がピンクに光っていた。満開も近そう。

太田市街並みが眼下に。

月ノ池と大手虎口。金魚がのんびりと泳いでいました。
高い山の上に大きな池があるということは非常に例がなく珍しいもの
麓から城道を上がって来た人は、城門の手前でまず月ノ池を目にすることに。
直径が7.5メートルほどの石垣で囲われていた。
古代より雨乞いの場でもあったことも解っていると。

難攻不落な城であったことが石垣の重厚感から。

井戸の脇には、礎石に基づいて復元された建物も。中には竈も復元されていた。
また内部には、発掘時の写真が展示されていた。

実城の脇にある日ノ池がきれいに復元されていた。
日ノ池の大きさは、月ノ池よりも倍以上あり直径が17.5m、深さは2mと。
この月ノ池、日ノ池は冬でも枯れることなく満々と水を湛えていると。

南曲輪休憩所でスタンプをGETするSさん(右)。

スタンプをGET、やれやれ。

新田神社の参道には樹齢800年といわれる金山の大ケヤキが。
新緑が眩しいくらいに輝いていた。

新田神社でお参りを済ます。
お札を購入し会社に持ち帰りたかったが社務所は閉鎖中。

石垣を楽しみながら金山城跡を下る。

金山は小鳥がさえずる森。

未だ発掘途中であろうかブルーシートで保護されている場所も。

竪堀と更新された丸太橋。

そして駐車場に戻り、ボランティアのオジサンから金山城跡の説明を受け
雑談も交わして、再び車に乗り込み次の目的地の鉢形城を目指したのであった。
-
牛久大仏へ(その3) 2025.11.19
-
牛久大仏へ(その2) 2025.11.18
-
牛久大仏へ(その1) 2025.11.17










