PR
Keyword Search
Comments
【甥のステント挿入…
 New!
Gママさん
New!
Gママさん2025年版・岡山大学…
 New!
隠居人はせじぃさん
New!
隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…
 noahnoahnoahさん
noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん
Calendar
松田・寄のロウバイ園を楽しんだ後は、南足柄市にある曹洞宗大雄山最乗寺を目指す。
道了尊仁王門を左手に見ながら更に坂を上っていく。
大雄山最乗寺は初夏のあじさい や秋の紅葉なども美しく四季を通じて楽しめる場所。
仁王門から境内へ続く参道は「あじさい参道」と言われるほどあじさいが続く絶景。
約3kmの道を10,000株のあじさいの花が埋め尽くすのだと。

そして奥の駐車場に車を駐め大雄山最乗寺巡りの開始。
参道の両側には苔むした歴史を感じさせる石碑が並んでいた。

本堂に向かって参道階段を上っていく。
参道沿いには多くの杉の巨木が。
この杉林は最乗寺境内を囲むように、約17万本もの大植林地となっており、境内の約26haが
県の天然記念物の杉林になっているのだと。
最大のものは幹周が7mほどあるとされており、樹高は45mとのこと。

寄進された巨大な石灯籠が並ぶ。

大木の幹の上の方から「トントン・・トントン・・」の音が。
アオゲラの雄ではないかと旅友のSさんから。頭頂部の赤い鮮やかなラインがズームで
確認出来た。アオゲラは日本固有種で、日本を代表する啄木鳥(きつつき)。

瑠璃門(るりもん)への階段を上る。
ここ瑠璃門手前の階段の紅葉が人気のフォトスポットとのこと。

石段を登った先には、「瑠璃門」(右)と「碧落門(へきらくもん)」(左)という名が
付いた二つの入口門があった。
下の写真は「瑠璃門」。

「瑠璃門」には白雲閣、衆寮、僧堂に続く回廊が巡らされており禅寺らしい景観を造っていた。

璃門を潜ると最乗寺本堂境内が拡がっていた。
 山号は大雄山。曹洞宗の寺院。
山号は大雄山。曹洞宗の寺院。
応永元年(1394年)了庵慧明により開山された600年以上の歴史をもつ古刹。
創建の際に貢献したといわれる妙覚道了が、寺を守護するため天狗となって山中に
身を隠したという伝説から道了尊ともよばれる。
曹洞宗では福井県の永平寺、横浜市の総持寺に次ぐ格式の寺院とされる。
正面に「書院」。

右には「白雲閣」。
寺の総受付で御朱印もここで頂けた。

大雄山最乗寺全景 案内板。

境内中央部に「光明亭」と名付けられた東屋が池の上に。

左側にあるのが「僧堂」。
その手前左に「光明軒」そして大香炉、巨大な時計台が並んでいた。

境内からの「碧落門(へきらくもん)」。

「本堂(護国堂)」。
昭和を代表する仏教建築家、伊東忠太設計で1954年(昭和29年)落成。
本堂前両側には見事な枝垂れ桜が。

間口15間、奥行き12間。
御本尊は釈迦牟尼仏、脇侍に文殊・普賢両菩薩を祀り、日夜国土安穏が祈念され、
朝晩の勤行や当山山主が修行僧に対しての説法の場。

本堂手前の巨大な灯籠。その後ろに枝垂れ桜。

最乗寺本堂、「護国殿(ごこくでん)」と書かれた扁額。

本堂内部。
本堂内部の広さはおよそ300畳あるのだと。美しい装飾に魅了されたのであった。

照明器具も本堂としてはやや違和感があるが、味のあるデザイン。

真下から。

御本尊の釈迦牟尼仏。
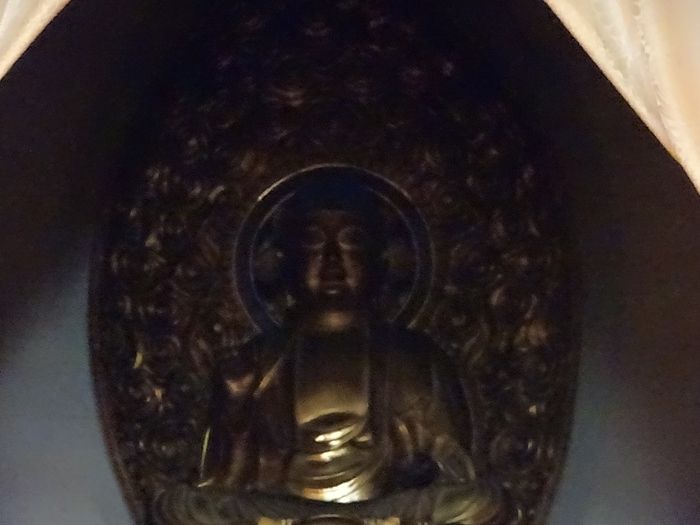
本堂隣の「開山堂」。

本堂前の「鐘鼓楼」。

「鐘鼓楼」をズームで。

「開山堂 (金剛壽院) 」を正面から。
昭和36年再建。開祖了庵慧明禅師尊像等、歴代住持霊牌を祀る。
本堂と共に昭和の総檜造りの名建築である。

「金剛水堂」。
当山開創の時、道了様が自ら井戸を掘り、土中から鉄印を得たが、これが当山重宝の
諸病を癒していると、伝えられていると。

「鐘楼」。
鐘楼は,銅版の瓦葺で上重は四手先組物,軒は扇垂木で竜の彫刻が。
下重は二手先組物,軒は二軒繁垂木。
柱の周囲の彫刻も見事。
多宝塔の下の斜面にも苔むした多くの石碑が。

不動堂の下に「洗心の滝」が。

「大天狗 小天狗 御大尊像」と刻まれた石碑。
最乗寺と天狗の関係は寺の建立の歴史に由来。1394年、了庵慧明(りょうあんえみょう)という
僧が最乗寺を開山した際に、了庵の弟子の道了が寺を守るために天狗に変身したという伝説が
あるのだと。境内の各門には天狗の像がそれぞれ祀られていた。

「多宝塔」手水舎。

「多宝塔」への階段を上がる。

「多宝塔」。南足柄市指定重要文化財。
多宝塔は、方形層上円形木造二重の塔で、江戸時代末の文久3年(1863年)に建立。
高欄のない縁をめぐらし、中央は間桟唐戸、脇は間連子窓。
曹洞宗の寺院としては珍しく、内部に多宝如来を祀った厨子が安置されていると。

離れてズームで多宝塔上部を。見事な高欄と四手先組物。

「不動堂」。
圓通橋から不動堂を望むと明神ヶ岳山麓から湧水を引いた「洗心之滝」を仰ぐことが出きると。

ここにも湧清水が流れていた。

「御真殿(
当山守護妙覚道了大薩をご本尊に大天狗・小天狗が両脇侍として祀られている。
朝晩の祈祷から日中の特別祈祷が、修行される道場。

御真殿脇に朱に彩られた「羽団扇(はうちわ)」と奉納された大小の高下駄が。
ここ最乗寺の祭神は、道了尊と言う天狗様なので、寺紋の「羽団扇」がいたるところに
見られたのであった。
天狗の履き物は、高下駄だが、下駄は左右一対そろって役割をなすところから、
夫婦和合の信仰がうまれ、奉納者が後を絶たないのだと。

天狗の下駄は普通は一本歯、ここでは何故か、二本歯。
一本歯の下駄は山道を歩くための下駄であり、山の中で修行する僧侶や山伏などの修験者が
主に用いたと。このことが由来となって天狗が履いていたとされ、「天狗下駄」とも
呼ばれるのであるが。

世界一大きい重さ1000貫 、3.8トンという巨大な鉄の下駄(
3.8トンの一本歯は安定性が悪くて危険であるから二本歯なのであろうか?
同様に小さな下駄も、一本歯は不安定で戻すのに手間がかかる?
何故か気になるのであった。

・・・ つづく ・・・
-
牛久大仏へ(その3) 2025.11.19
-
牛久大仏へ(その2) 2025.11.18
-
牛久大仏へ(その1) 2025.11.17










