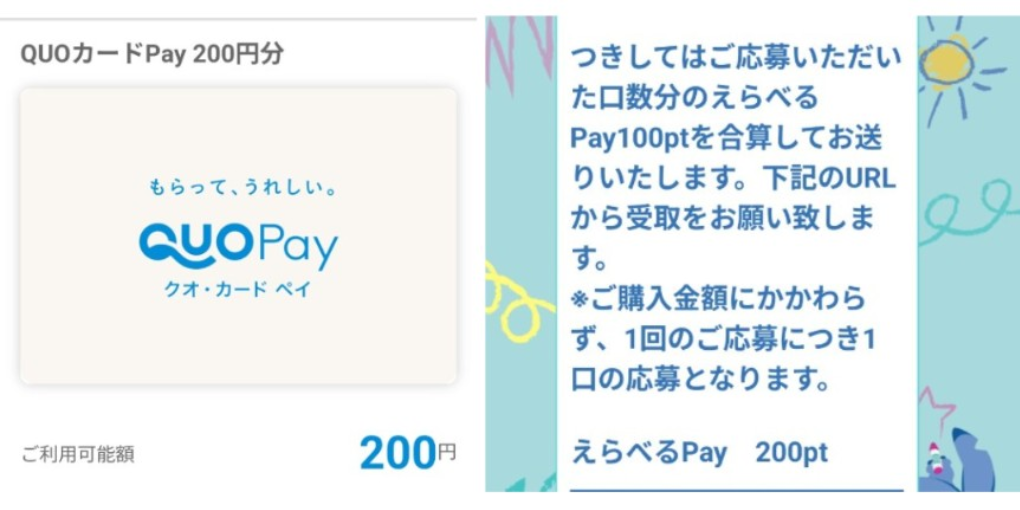2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年03月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
第二東京タワー
第二東京タワーの建設地が東京都墨田区に決定しました。高さは世界一の600m以上になるそうです。おりしも映画「オールディズ三丁目の夕日」で建設中の東京タワーのシーンがあったりして現東京タワーは観光スポットとしての人気が再燃しています。戦後の復興期を見つめてきた東京タワーがその使命の多くを第二東京タワーに引継ぎ、いわば隠居することになるのは昭和世代としてはちょっと寂しい気もしますが、現東京タワーは第二東京タワー完成後もFMラジオ用電波塔として運用を続けるそうです。 第二東京タワーの建設地の決定が今の時期になったのは何か運命的なものを感じます。現東京タワーが経済復興の象徴であったのと同様に第二東京タワーの建設には日本経済のバブル崩壊後の永く暗い時代からの脱出のシンボルになってくれるのではないかと。デフレ脱却がほぼ確実となり、株価も急上昇する中、末端の雇用条件は決して好転していない状況で、やっと本格的な景気回復への象徴となり、何十年後かには「オールディズ 2 墨田区の夕日」なんて映画になったりして。そのころには日本も福祉や教育で「大国」と呼ばれるような国民のための国として世界最高の成功例となるようであればいいなと夢を見ます。
2006年03月31日
コメント(0)
-
柴崎コウの新作
今度、柴崎コウが出演する映画で気になるものがあります。それは「北斗の拳」と「どろろ」です。どちらも元はコミックからアニメになったもので、だいぶ昔の作品です。似たような事例で「キャシャーン」と「キューティーハニー」も割合に記憶に新しいところですが、この2作品はお世辞にも成功作とは言えなかった様に思います。そもそもアニメを実写化するのは非常に難しいのです。過去に多くの作品が失敗しています。例えば「愛と誠」や「サーキットの狼」や「エイトマン」など。成功か失敗かは見る側の主観によるところが大きいとは思いますが、柴崎コウの代表作と胸を張って言えるような作品になりえるのか・・・。出演者や監督が良くても、なにしろ原作がが破天荒すぎるので陳腐な作品になりはしまいかと心配です。それに、「北斗の拳」のレイナ役はまあ許すとしても「どろろ」はちょっとイメージ違いすぎだと思います。手塚治の原作の「どろろ」のどろろは、背の低い丸顔の男の子(本当は女の子)なので、柴崎コウのようなスレンダーな八頭身の体や細面はあまりにもミスマッチのような気がするのですが・・・。しかし、今乗りに乗っている女優、柴崎コウがこの難しい挑戦をどうこなすのか? 楽しみでもありますね。
2006年03月30日
コメント(0)
-
恋のダウンロード♪
ちょっと今さらかも知れませんが、先日、テレビで仲間由紀恵のトークと歌を聞きました。歌はauのCMの「恋のダウンロード♪~」という例の歌なのですが、あのCMの前のバージョンで「え?本当に歌うんですか?」ってあわてるシーンがありましたよね。だから「ああ女優だから歌は苦手なのかな。」と思っていたのですが、仲間由紀恵ってそもそも歌手としてデビューしたらしいのです。ちょっと驚きました。さらに沖縄舞踊は師範代クラスの腕前なのだとか。やるなあ、仲間由紀恵。 さらにさらに、私は「恋のダウンロード♪~」の歌の歌詞は「恋のダウンロード♪二人はRAID(レイド:複数のハードディスクで互いに補間し、安全性と処理能力を高める技術)」と歌っているのだと思っていて、「なるほど、IT用語でラブソングってのも現代風でおもしろいな。」とマジに納得していました。ところがこれ、「恋のダウンロード♪二人パレード♪」という歌詞なのだそう。二人パレードっていったい何?よく解りません。 「ごくせん」や「トリック」ですっかりコミカルなキャラとして定着している感のある彼女ですが、あれだけの美貌ですから今後の幅広い活躍が楽しみです。
2006年03月29日
コメント(0)
-
三つ葉
今日は3、2、8で三つ葉の日です。三つ葉は日本では普通に使われる香味野菜なのですが、海外ではあまり一般的ではありません。それもそのはず、日本原産の野菜で、これを食する習慣は日本と中国くらいにしかないのだとか。今ではほぼ100%栽培されたものですが、本来は野草・山菜の部類に入る野趣豊かなものでした。 売られている三つ葉は大きく分けて3種類あります。「切り三つ葉」「糸三つ葉」「根三つ葉」の3種です。切り三つ葉は主として関東で好まれ、一度発芽させた芽を刈り取り、有る程度成長した根に改めて芽を出させ生育させるという手の込んだ栽培方法をとっています。こうすることで最初の芽を捨石とし、植物の命とも言える根が成長し栄養分を貯えてから新しい芽を吹かせることで良質な三つ葉を得る事ができます。糸三つ葉は主として関西で好まれ、水栽培したものです。香りも良く安価なので関東でもスーパーなどではこちらが普通かもしれません。根三つ葉はより自然に近い、畑で栽培されたもので、土をかけて軟化栽培したものです。生育に時間がかかり、手間もかかるので高価です。一部、天然物も出回っているようです。関東で好まれます。 さまざまな日本料理に使われていますが、代表的なものはやはり、かきあげ、吸い物、茶碗蒸し、お雑煮、親子丼と言ったところでしょうか。歯ざわりと香気は他のものに変えがたいものがあります。特に親子丼には絶対欠かしたくないと個人的に思います。最近は和食にもルッコラやズッキーニなどが多用されるようになりましたが、古くから食されている日本の野菜もやはりいいものだと思うのです。
2006年03月28日
コメント(0)
-
西遊記 今日は特番
フジテレビの西遊記が先週、最終回で、今日は特番をやるみたいですね。今回は珍しく天竺大雷音寺にたどり着き、お経を受け取るまでが描かれているのですが、どうも大雷音寺の僧たちには違和感がありました。原作では天竺=御仏のおわす場所=極楽浄土ということになっていましたから、頭の固い衛兵と木っ端役人みたいなのが偉そうにしている天竺なんて聞いたことがありませんし、お経をもらうのに三蔵の命を犠牲にしなければならないというのも原作にはなかったと思います。お釈迦様が堺正章というのもピンとこないキャスティングですし、お釈迦様が出てきたとたんあっさりお経がもらえてしまったのは拍子抜けです。 一方で深津絵里はなかなかいい演技をしてくれたと思います。三蔵法師の役となるとどうしてもあの伝説になりつつある女優、故 夏目雅子さんと比べられてしまい、可愛そうに思っていましたが、最終回の演技は人間としての三蔵法師の心を表現するような迫力がありました。個性派女優としてこれからの活躍に期待したいですね。
2006年03月27日
コメント(0)
-
おむすび
おむすびは稲作文化圏の日本らしいファーストフードと言っていいものですが、古くは弥生時代の遺跡から炭化したおむすびが発見されるなど、ずいぶん永い事すたれることなく伝えられてきた伝統的な料理です。シンプルなものですが人の心を捉える何かがあります。 形は三角や俵型などいろいろありますが、基本形は何か具中央の入れられて周囲を海苔で巻くスタイルです。基本形の範囲のなかでも、具の選択は融通無碍で、無限にバリエーションが考えられます。この応用の利くところも今でもおむすびが愛されている理由の一つでしょう。 コンビニで手軽に購入するのもおむすび、おむすびだけで商売をする専門店も存在します。専門店のおむすびは一味違います。米の産地と品種にもこだわり、塩にこだわり、そしてなにより握り方が絶妙なのです。しっかりと整形されていながら口に入れるとほろりと崩れる絶妙の握り加減です。これは握りずしに通じるものがあります。単純なように見えて高度な技術を要する立派な料理です。 子供の頃、母親が遠足の日に握ってくれたおむすびは、具は梅干だけ、米も安い標準米でしたが、年に何回かしか食べられない特別な食べ物でした。でも当時は庶民の食生活が大きく変わろうとする時期でもあり、アルミホイルやラップなどもその頃から家庭に普及し始めた頃で、我が家のおにぎりはラップで包んだ上から新聞紙でくるんだちょっとかっこ悪いもので、友達のアルミホイルやバスケットを美しく使ったしゃれたおむすび弁当がうらやましくもありました。 コンビニのおにぎりは、海苔を食べる直前に巻くことができる「パリパリタイプ」と海苔がすでに巻かれている「しっとりタイプ」が選べるようですが、私は昔からの習慣でしっとりタイプのほうがおにぎりらしく感じてしまいます。友人の言うには少数派らしいですが。 シンプルでありながら多様性と発展性も併せ持つおむすびは、これからも日本人の生活から消えることなく発展していく事でしょう。できるならばおむすびの達人の握り業を科学的に検証し、後世に伝えてもらいたいと思います。高級な料理ではないので、技術はすたれてしまいがちです。技術がすたれれば料理自体もすたれてしまいます。おむすびは稲作文化の象徴であり、和食の原点と思いますので、絶えることなく続いて欲しいと思います。
2006年03月26日
コメント(0)
-
電気記念日
今日は、電気記念日です。1878年(明治11年)のこの日、工部大学校(現:東京大学工学部)で日本で初めて50個の電灯が点灯した日だそうです。 家庭で電気が使えるようにするためには、発電所と送電線のネットワークが必要です。これらは個人で整備するようなものではないと思いがちですが、世界で最初の電気事業を始めたのは、あの有名な発明王エジソンです。すでに電球を発明していたエジソンは、それを一般家庭にも普及させるべく発電所と送電線ネットワークを作ってしまったのです。そのあまりの便利さに急速に電気は社会の重要なインフラとなっていきます。しかし、エジソンは電気事業においては後発の事業者に敗れてしまい、撤退することになってしまいます。それはエジソンが使っていたのは直流方式だったためです。後発組は交流方式を採用していました。直流とは一方向にだけ電流が流れる方式で、電池などはこれに当たります。交流は電流の流れる方向が一定のリズムで反転する方式で、今世界中で使われている家庭用の電気はすべてこの方式になっています。交流方式には変圧器を使って電圧を簡単に変えられるという利点があり、電気は高電圧であるほど送電ロスが少ないという特徴があります。発電所から街までは高電圧で送電し、使う場所のすぐそばで低い電圧に変圧した方が効率がいいのです。しかし、家庭用燃料電池など長い距離を送電する必要が無い場合には、直流も蓄電が可能であることなど良い点があり、現在では見直されつつあります。 普段当たり前のように使っている電気ですが、一部の人を除いてなんだかよく解らないものというイメージが強いと思います。電気とはどんなものなのでしょうか。電気の話をするとき、避けて通れないのが電流と電圧です。電流は、水の流れによく例えられます。水は高い所から低い所へ流れますが、電流は水の代わりの電子が電圧の高いところから低いところへ流れます。電圧というのは簡単にいうと電子の混み具合の差のようなもので、電子がたくさんある所と少ないところでは、たくさんあるところから少ないところへ移動しようとします。これが電圧です。日本では家庭用の電気は交流100Vですが、エアコン用に交流200Vを別に引いている場合も多いです。最近では単相三線式といって100Vも200Vも両方使える方式が主流になっています。ここまで書いたことはすべて単相交流についてなのですが、工場や大型ビルで使われる三相交流というのもあります。これは少し話しが難しくなってしまうので今日は止めておきます。 エジソンが電球を発明したときに、とても苦心したところがあります。フィラメントの材質です。明るさと耐久性を兼ね備えた材料を見つけるために6000種類もの材料を試したといいます。そして最終的に採用されたのは、なんと日本の京都府八幡市男山の竹だったのです。あの世紀の発明に日本の竹が一役かっていたなんてちょっと誇らしい気分になりますね。
2006年03月25日
コメント(0)
-
桜
今年も桜が咲く季節がやってきました。桜咲く季節は別れと出会い、旅立ちの季節でもあります。そのせいか日本人は桜の花に深い思い入れがあります。そして多くは希望や新しい挑戦などポジティブなイメージと心浮き立つような楽しい宴のイメージで、桜の花が嫌いな人はあまりいないのではないでしょうか。 古事記に桜の起源が書かれています。桜の霊である「木之花咲耶姫(このはなさくやひめ)」が最初の桜のタネを富士山からまいたといわれ、「さくやひめ」の名前から「さくら」になったということです。もちろん、伝説で史実ではありませんが、古事記の時代にすでに桜は日本人にとって大切な花だったことが見てとれます。 現在、私たちの目を楽しませてくれる桜は、8割くらいはソメイヨシノです。この品種は江戸時代の末期に開発され、急速に広まっていきました。しかし、寿命が木としては短く、50年くらいで弱って枯れてしまうことが多いそうです。立派な桜並木を維持するには定期的に植え替えをしなければなりませんし、幹の内部の腐食などで樹医の治療を受けなければならなくなる木もあるぐらいに弱い樹木です。 地方自治体などでは予算不足で桜並木のメンテナンスまで手が廻らないところもあるようですが、これだけ人の心にポジティブな思いと憩いの場を与えてくれる花もそうはないのでがんばって手入れしてもらいたいですね。 願はくは 花の下にて 春死なむ そのきさらぎの 望月のころ 西行 世の中に たえてさくらの なかりせば 春の心は のどけからまし 在原業平
2006年03月24日
コメント(0)
-
梅干
梅干は、日本と中国ではありふれた食品ですが、世界的にはとても変な食べ物と思われているきらいがあります。寿司や刺身や天ぷらは好きだけれど梅干は無理!という外国人は多いようです。 梅干は、漬物の一種ですが、「土用干し」といわれる天日で干す工程があるのが普通の漬物と違っています。梅の木は果樹であり、梅の実は果物であるはずなのですが、青酸という毒が含まれていて生で食べることはできません。梅の実は青いうちに収穫され、梅干にしたり、梅酒にしたりともっぱら加工用として栽培されています。加工すると特に解毒を意識しなくても不思議に毒は消えてしまいます。 昔は梅干は家庭で漬けるもので、家ごとに味が違って面白いものでした。小粒でさらっと乾いたタイプや大粒でしっとりしたタイプなどそれぞれの家庭の流儀で、家庭の数だけ梅干があったものです。万葉集や百人一種にも梅は頻繁に登場しますので、奈良・平安の時代には栽培されていたと思いますが、梅干は保存性の良い食品ですから、兵糧として戦国時代の必需品になりました。梅干の保存性は驚異的であり、最古のものでは400年以上前のものが今でも食べられる状態で現存しています。近世では戦後の食糧難の時代に、庶民のご飯やお弁当のおかずとしてずいぶんお世話になりました。料理の材料としてもピリッとした酸味が料理にアクセントを付けてくれるものとして大切です。某グルメコミックで紹介されていたものですが、日本酒で梅干を煮て、梅干の香りと味を移したお酒をしゃぶしゃぶのタレに加えるととても美味しいです。 梅干に含まれるクエン酸は殺菌効果や疲労回復効果があり、さらにカルシウムの吸収を助ける効果もあることも解っています。最近の人はそんなに梅干を食べることは無いようですが、伝統的な食品だし、健康にも良いとなればもっと食べてもらいたいですね。最後に梅を題材にした歌を2首ほど。 「春もやや けしきととのう 月と梅」 松尾芭蕉 「梅一輪 一輪ほどの あたたかさ」 服部嵐雪(はっとりらんせつ)
2006年03月23日
コメント(0)
-
茶
お茶は、日本人にとって単なる飲み物以上の大切なものです。世界広しといえども、日常的な飲料を飲むという行為を、茶道という精神世界の高みにまで広がる芸術に繋げているのは日本だけでしょう。茶の原産地は中国南部の雲南省からインドのアッサム地方にかかる山地と言われていますが、決定的な根拠はなくはっきりとしていません。また、日本に伝来したのもいつのことなのか良く解っていません。飲み物として広く普及する前は仏教の僧が薬として用いていたことから、仏教伝来と深く関わりがあると言われています。カテキン、ビタミンCなどを豊富に含むお茶が薬として用いられたのも当然ですし、仏教関係の文献にもお茶の記載は度々見られるそうです。 お茶の「チャ」という発音は、中国の広東語の発音がそのまま伝わったものらしいです。また、中国のお茶は烏龍茶のように発酵茶・半発酵茶が普通だろうと思っている方が多いと思いますが、そんなことはなくて緑茶も普通に飲まれているそうです。 甘さも旨みもごく淡いお茶という飲み物がなぜこれほど人々の心を捉えるのか不思議です。一つにはカフェインが含まれていることもあるとは思いますが、昔は飲み物がそもそもあまりなかったからでしょうか。 お茶は茶の木の若葉を摘んで蒸す、炒るなどの工程を経て作られますが、日本ではもっぱら発酵させない緑茶です。緑茶の緑は当然お茶の葉の葉緑素ですし、高級なお茶になればきゅうすの中で茶葉が開き、摘んできたばかりのような姿をみせます。日本人はどうやら過度に手を加えることを好まず、必要最低限の加工に抑え、自然の味わいを良しとするところがあるようです。(念入りに手を加えるものもありますが。)料理もしかり、木工製品や竹製品なども自然物の風合いをそのまま生かすことを常に主眼に置いているようです。副材料など何も使わず、シンプルに作られた日本茶もそういう日本文化ならではのものかも知れません。
2006年03月22日
コメント(0)
-
わさび
わさびは、和食の一つの花であるお作りには欠かせない香辛料です。珍しく日本原産の食用植物であり、アブラナ科ワサビ族の植物です。すがすがしい香りと独特の刺激的辛さが日本人に愛されています。古くは奈良時代の文献にわさびの記述が見られ、鎌倉時代頃になると食用とされたようです。本格的に栽培が始まったのは江戸時代ですが、わさびは大変環境に敏感な植物で、清流の中でないと育ちません。温度にも敏感で、ちょっとの違いでわさびは育たなくなってしまいます。ですから、わさびを栽培するための山葵田を作ることはとても難しい仕事です。また、成長が遅く、苗を植えつけてから収穫までは3年くらいはかかります。このため、本わさびはとても高価なものです。わさびの辛味はシニグリンと呼ばれる配糖体が酵素と反応してできるのですが、すりおろすなどして細胞が壊れたときにこの反応が起きて辛味が生まれます。そして、わずか5分程度でピークを迎え、その後は急速に香りは失われます。食べる直前にすりおろすのが良いのです。また、金気を嫌うため、鮫皮のおろしを使うのが良いと言われています。できるだけ細かく細胞を壊した方が良いので、鮫皮のおろしはこの点でも好都合です。 家庭では本わさびはなかなか使える物ではないので、チューブか粉のわさびが一般的に使われています。これらは、西洋わさび(ホースラディッシュ)が主な原料で、高級な物になると半分くらいは本わさびがブレンドされているものもあるようです。代用品とは言え、安価で手軽にわさびの風味を楽しめますのでこれはこれで有りと思います。特に粉わさびは馬鹿にできない鮮烈な辛味と香りがあり、あえて粉わさびを使った方が良い料理もあるようです。 私は、ビーフステーキのソースにわさびを使うのがお気に入りです。香りが飛ばないように食する直前にソースの材料に加えます。ローストビーフのソースにもホースラディッシュが使われますので、チューブのわさびとビーフステーキとの相性は悪くないようです。 わさびはデリケートで清らかな環境でしか育たず、そして原産地として日本にのみ自生していたということは、いかに昔の日本の自然環境が素晴らしかったを示しています。現代日本は、欧米と同じく飲み水さえお金で買わなければならない国になってしまいました。次にわさびを口にする機会にでも古の時代の美しい日本の風景に思いを馳せてみるのも一興です。
2006年03月21日
コメント(0)
-
だし
だしは料理の味の根幹を支える大切な要素です。日本では昔からカツオだしと昆布だしを併せてつかうのが最も標準的で、料理の本でも単にだしと書かれている場合はカツオと昆布のだしを指すくらいにスタンダードです。しかし、世界を見渡してみると、日本人にとっては当たり前のこのだしが、実はかなりの優れものであることが解ります。西洋料理ではフォンやブロードといっただしをとるのに大変な手間がかかります。牛の骨をオーブンで焼いたり、香味野菜と長時間煮込んだり、とても家庭ではできません。だから家庭では調理中に自然に出てくる肉やハムや野菜の旨みを利用し、特にだしをとるということはしていないようです。それに対して日本では、横着をしなければ家庭でもきちんとしただしを簡単にとることができます。和食の基本だしは究極のインスタント食品といえるかもしれません。しかし、それはカツオ節と昆布にすでにすごい手間と知恵と技術が詰め込まれているからであって、保存性を高め、味を高め、使う時は簡単に使えるという、永い食文化の歴史の中で育てられてきた素晴らしいものです。このだしのおかげで薄味なのに豊かな旨みを持つといった、他の国の料理ではなかなかできないようなことが可能となっています。また、カツオと昆布を併せるというやりかたも実に理にかなっています。カツオ節のイノシン酸と昆布のグルタミン酸が合わさると、単純な足し算の7.5倍相当の旨みが発揮されるそうです。初めて二つのだしを併せることを考えた人は、旨みの相乗効果なんて知るはずもなく偶然のことだったのでしょうが、和食界の革命的出来事といっていいかもしれません。 私個人的には、干し椎茸のだしを忘れるわけにはいきません。干し椎茸にはグアニル酸という旨み成分が含まれていますが、これが昆布などのグルタミン酸と合わさると旨みの相乗効果はなんと30倍にもなるそうです。我が家では豚汁やけんちん汁など具沢山の汁物には干し椎茸のだしが定番です。冷蔵庫の冷水ポットに干し椎茸を常に戻して常備しておくとすぐに使えて便利です。戻した椎茸も刻んで具にできますしね。その他にもアサリのコハク酸の味も捨てがたいですし、煮干のだしも他のだしでは肩代わりできない独特の旨みを持っています。料理の基本であるだし一つとってもこれだけの広がりを持っている日本の食文化って素晴らしいとつくづく思います。
2006年03月20日
コメント(0)
-
みりん
みりんは、今では日本独自の調味料として日本中に普及していますが、中国から伝来してきた戦国時代には、みりんは甘口のお酒として飲まれていました。それも高級な酒としてであり、特に高貴な女性に人気があったようです。みりんの製法は、簡単に言ってしまえば、日本酒の製造工程の麹菌による糖化発酵が終わったところで、日本酒なら酵母菌によるアルコール発酵に移行するところを、みりんでは行わず、焼酎などのアルコールを加えて熟成させます。このため、糖分を残しつつ、アルコールも適当に含んだみりんとなります。 みりんが調味料として使われるのは江戸時代からですが、調味料として以上に大変優れた特徴があり、日本料理になくてはならない物になりました。 上品な甘味:砂糖はショ糖が主成分ですが、みりんの甘味の主成分はブド ウ糖です。 ブドウ糖はショ糖に比べて甘味は控えめですがその分すっき りしています。 照り・艶 :料理に美味しそうな照り・艶を与えます。 浸透効果 :他の調味料が素材に浸透するのを助けます。煮物にはなくて はならぬ存在です。 煮崩れ防止:アルコール分が魚などの食材の表面を締め、煮崩れしにくく なります。江戸時代は、今回のみりんを含め、味噌、しょう油、砂糖などさまざまな和食の基礎が確立した時代です。しかし、江戸時代ということはまだ数百年前ですから、和食の文化は、日本の縄文・弥生の時代からの歴史に比べればまだ若い文化と言えるかもしれません。他国の食文化に埋没することなく、これからも和食の文化を育てていく必要があると感じます。
2006年03月19日
コメント(0)
-
しょう油
しょう油は、和食の最も普遍的な調味料です。ほとんどの料理にしょう油を使います。ここまで幅広く使用される調味料は世界でも珍しいです。例えばフランス料理ではバターと生クリームが料理に重要ですが、味付けは基本的には塩・コショウです。イタリア料理でもオリーブオイルやトマト、チーズを多用しますが、やはり味付けの基本は塩・コショウです。複雑な成分を持つ発酵調味料はアジア文化圏に多いのです。その中でも日本のしょう油は最も洗練された豊かな物です。 しょう油は、最初は味噌の副産物として生まれました。味噌を仕込んだ樽の底に残る液体がたまりしょう油のルーツです。やがて味噌の副産物としてでないしょう油の生産が始まります。現在のたまりしょう油も途中までは味噌と良く似た工程で作られています。 たまりしょう油は、生産性が低く、熟成に3年もかかり、高価なものだったので、一部の身分の高い人しか口にできませんでした。江戸時代中期に小麦と大豆を半々に使った濃口しょう油の製法が発明され、大量生産が可能となり、熟成期間も6ヶ月に短縮されて民衆の間に広まっていったのです。 しょう油は、麹菌の働きでできるグルタミン酸、乳酸菌の働きでできる乳酸、さらに濃口しょう油の場合には酵母菌の働きによるアルコール類(香り成分)等が含まれる複雑で高度な発酵食品です。しょう油が生まれる以前にも魚醤と呼ばれる魚の塩漬けを発酵させて作る調味料がありました。日本では秋田のしょっつる、海外でもベトナムではニョクマム、タイではナンプラーなど、漁業が盛んな地方では、比較的簡単に作れることもあって普及しましたが、日本では濃口醤油が普及すると、そのグルタミン酸などの旨み成分の豊富さから次第に魚醤は醤油に代わって行ったのです。今では、ソイソースとして世界中で使われるようになって、グローバルスタンダードな調味料となりました。野菜や果物をふんだんに使ったウスターソースなども素晴らしい調味料ではありますが、魚介類、特に生の魚介類に合う調味料はしょう油以外に考えられません。日本が世界に誇るべき食文化の一つです。
2006年03月18日
コメント(2)
-
味噌
味噌は日本人にとってなくてはならない物です。日本人のソールフードと言える味噌汁も、もちろん味噌なしではできません。味噌は中国で発明され、日本に伝わってきました。有力な説では昔、朝鮮半島にあった高句麗と言う国が他国に攻められ、一部の難民が日本に逃れてきた時に伝えたとされています。 味噌は大きく分けて豆味噌、米味噌、麦味噌に分類できます。豆味噌はもっとも基本的な味噌です。原始的といってもいいかも知れません。蒸した大豆に直接、麹菌を働かせて造ります。でも技術的にはむしろ米味噌や麦味噌の方が造りやすく、豆味噌は酒造りと同じで職人の高度な技術が必要なのです。豆味噌造りは繁殖力の強い納豆菌との戦いでも有ります。納豆菌から麹菌を守るため、熱に強い納豆菌をほぼ完全に死滅させるほどの高温で蒸してから麹を植え付けたり、味噌玉という、潰した豆を麹で包んだ団子を作ったり、大変な手間がかかります。 米味噌は、米に麹を繁殖させた米麹と大豆を使います。同じ米味噌でも西京味噌は米7:豆3、信州味噌は米5:豆5、仙台味噌は米4:豆6と多種多様なバリエーションがあります。豆味噌よりは造りやすいため、日本全国に広まって地方それぞれに根付いた味噌が作られています。 豆味噌は、加熱しても飛んでしまう香り成分が少なく、煮詰めると旨みも増すため煮込み料理には適しています。米味噌は香り成分として日本酒に近い揮発性の高い成分を多く含んでおり、そのため煮立たせる事は厳禁です。味噌と一言でいっても、米味噌である西京味噌と豆味噌である八丁味噌ではまったく別物と言っていいくらい味が違います。料理人は料理の材料に合わせて複数の味噌をブレンドして使います。そのブレンドは無限の広がりを持っています。日本の食文化の奥深さを垣間見せてくれます。気の利いた料理屋では、味噌汁でも夏と冬ではブレンドの比率を変えています。季節によって人が快いと思う塩分濃度が違うためらしいです。細やかな技です。 私が子供だったころに比べれば、世の中が豊かになり、コンソメでもブイヤベースでもトムヤムクンでも、なんでも美味しいスープが飲めるようになっても、やっぱりNo.1は味噌汁であることは絶対ゆずれません。ちなみに私的には、味噌汁の身は、豆腐、シジミ、ナスがベスト3ですね。
2006年03月17日
コメント(0)
-
春はあけぼの
厳しかった冬もようやく終わり、春がやってきました。スーパーの野菜売り場には、菜の花やタラノメ、新じゃがなど春の味覚が並びます。季節感をはっきり感じるひと時です。昔の人は里山や畑で自ら収穫した山菜や野菜を味わっていたのでしょうから季節感をより強く感じていたのでしょうね。ゆったりと明けて行く春の朝。萱ぶき屋根と畳の家、障子越しに聞こえる小鳥の鳴き声。味噌汁の香り。そしてほろ苦い菜の花のおひたし。失われつつある日本の原風景です。
2006年03月16日
コメント(0)
-
悩み
最近「音」に悩まされています。まず、自動車。といっても他人の車の騒音ではありません。自分の車の騒音です。古い車なので仕方ないのですが、ダッシュボードの奥の方からビビリ音がエンジン回転数に比例して聞こえてきます。車の中で聞こえる音は、発生源を突き止めるのが難しいのです。運転していてとても不快です。次に、マンションのどこかから聞こえてくる金属の缶を叩いたようなコーンという音。これもいったいどこから聞こえてくるのか解りません。それから、冷蔵庫の音。モーターが唸る音は仕方ないと思うのですがそれ以外にカチカチカチ、カチカチカチという規則的な音がします。それも決まって朝と夕方の1、2時間に限って聞こえるのです。他にも上階の子供の足音や内装材の伸縮で発生するバキっという音など、気にし始めたらたくさんの音の中で生活している事が解り、今まで気にもしていなかった小さな音さえ、集中力を奪いイライラを募らせます。本当に困っています。夜も良く眠れません。多少の音なんか気にしなくなる催眠術でもかけてもらいたい今日この頃です。
2006年03月15日
コメント(0)
-
ホワイトデー
今日は、ホワイトデーですね。ホワイトデーのホワイトは何を意味するのでしょうか。答えは砂糖の白です。何かウェディングドレスの白のイメージと重なって乙女の純白な心を意味するような先入観があるのですが、実際は、全国飴菓子工業協同組合が、飴の材料の砂糖の白から考えて決めたものです。当時の菓子業界は、バレンタインのチョコレートの大幅な売り上げ増を横目で見つつ、なんとか自分たちの会社の製品を贈る記念日を流行させようといろいろと手を打っていました。バレンタインのお返しというコンセプトも、マシュマロの日やクッキーの日がそれぞれの菓子メーカーの団体で定められ、飴菓子工業協同組合も参入したかったのですが、キャンディーの日や飴の日ではライバルたちとの差別化を図れず、インパクトが弱かったのです。そこで考えついたのが飴の原料の砂糖の色を記念日の名前にするということだったのです。みごとな作戦勝ちですね。また、商品名やキャンペーン名称など、名前というのが販売戦略上いかに重要かが解ります。でも、ちょっとだけ業界の作戦にまんまと乗せられて悔しい気もしますね。
2006年03月14日
コメント(0)
-
サンドイッチ
今日は313でサンドイッチの日です。トランプゲームのポーカーが三度の飯より好きだったサンドウイッチ伯爵が、ポーカーをしながら片手で食べられるように考案したと言われるこの料理ですが、けっこう奥が深いです。パンの種類、具の組み合わせ、焼いたり、揚げたりと融通無碍です。この辺は日本料理の海苔巻きに通じるところもありますね。定番的なものを考えただけでも、ポテト、卵、ハム、カツ、ベーコン・レタス・トマト、野菜などなど、きりが無いくらいにあります。他にも明太子や海苔の佃煮、ローストビーフなど変形技まで入れたらほとんど無限にあるといってもいいくらいでしょう。ソースもいろいろと変化を楽しめます。 でも具沢山のサンドイッチを形良く作るのはなかなか難しいものです。私はサブマリンサンドが好きです。これだとあまり形の崩れを気にしなくて済みますから。具はやっぱり卵が一番ですね。基本中の基本、サンドイッチは卵に始まり、卵に終わると思っています。
2006年03月13日
コメント(0)
-
母なる星地球
今日は地球の素顔について考えて見たいと思います。地球は直径12800kmの惑星で、太陽に近い方から水星、金星に次いで三番目を回っていて、太陽からの 距離は1億4000万キロほどです。太陽の大きさは地球の109倍ですから地球と太陽の位置と大きさを解り やすく例えてみると、太陽の直径が仮に1mだったとすれば、地球は、太陽から10m離れたところを回 っており、その大きさは9mmになります。大きすぎず小さすぎず、太陽からの距離もちょうど良く、奇 跡のバランスで生まれた水と生命の星です。一番高い陸地は約8000mくらい、一番深い海は約12000mく らいですから、もし、地球の大きさが直径10cmのリンゴほどの大きさだったとすれば、山の高さは 0.06mm、海の深さは0.09mmとなり、ほとんど凹凸は無いに等しいことが解ります。陸地が乗っている地 殻と呼ばれる岩石層の厚さは7km程度ですから、0.05mmに相当し、卵の殻の10分の1程度の薄膜一枚の上 で私たちは生活している事になります。見上げれば果てしなく続いているように見える大気の層は1万 mくらいの高さまでで、そこから上は成層圏です。リンゴ地球では0.075mmの極薄のヴェールのようで す。たったこれだけの厚みの大気圏で台風が発生したり、寒冷・温暖前線が生まれたりしてダイナミッ クな気候というものを作っています。考えてみればとても不思議なことです。そしてこれだけ薄いもの ですから本来とてもデリケートなものなのです。ちょっとした大気の成分の変化で気候は大きく変動し 、実際に地球は過去に全球灼熱地獄や全球凍結の時代を経験しています。腫れ物に触るように接しなけ ればいけないほどはかなく薄いヴェールを、私たち人類は今までずいぶん痛めつけてしまいました。よ うやく始まった地球を守る取り組みが間に合うかどうか、これからが正念場です。
2006年03月12日
コメント(0)
-
納豆
納豆はお好きですか。関西圏の方は食べられない人が多いようですね。かく言う私は、味や臭いは好きなのですが、あの糸引きが煩わしくていやなので納豆大好き!とは言えません。でも糸引きが気にならない食べ方で食べるようにしています。味噌汁に納豆を入れる「納豆汁」、「納豆オムレツ」、「納豆スパゲティ」などはほとんど糸を引きませんし、ちょっと反則技かもしれませんがマヨ納豆なども糸引きはずいぶん少なくなります。最近発見した技なのですが、調味料を入れる前に徹底的にかき回すと糸をあまり引かなくなります。そう、400回くらいはこねる必要があるのですが、300回を超えたくらいで急に手ごたえがなくなります。それが糸を引きにくくなった目安です。こうなると口の前で箸をくるくる回すあのしぐさをしなくて済むようになります。興味のある方は試してみてください。 納豆は縄文時代から食されていたようです。当時の人が納豆菌の存在を知っていたわけはないのですが、なにせ納豆はわりと簡単に出来てしまいます。納豆菌は自然界ではありふれた菌ですし、他の菌に比べて熱に強いので、熱を加えた枯れ草なり、藁なりを軽く煮沸して納豆菌以外の菌を殺菌し、茹でた大豆を包んでおけば納豆菌が繁殖して納豆になります。ですが、やはり意図的に納豆を作るようになるのは稲作が広まってからのことではないかと思います。やはり納豆はわらづとで包むのが一番造りやすかったろうと思いますので。 納豆に含まれる納豆キナーゼという物質は、血栓を溶かす性質があり、脳梗塞や心筋梗塞に極めて有効であると言う事が解っていますし、納豆菌は、腸内の悪玉菌の増殖を抑制する性質もあり、その働きはヨーグルトの乳酸菌以上であるという研究報告もあります。好き嫌いの分かれる納豆ですが、世界に誇るべき日本の食文化の一つであることは間違いなさそうです。
2006年03月11日
コメント(0)
-
砂糖
今日は、310で砂糖の日です。砂糖はサトウキビ(甘蔗)やサトウダイコン(てん菜)から作られます。サトウダイコンから作られるようになったのは比較的最近のことで、古くはサトウキビのみが砂糖の原料でした。サトウキビを煮詰めて砂糖を作る方法を発明したのはインドといわれ、紀元前500年ごろのインドの仏教典に砂糖やサトウキビの記述があることや、英語の「Sugar」の語源が古代インドのサンスクリット語の「Sarkara(サッカラ)=砂粒の意味」に由来すると言われています。当時、砂糖は調味料ではなく薬とされていたようです。日本へ伝来したのは奈良時代の754年にあの有名な中国の僧の鑑真が持ち込んだと言われています。当時は日本には砂糖を作る技術はなく、もっぱら輸入に頼っていたため、高級品であり、庶民が口にできる物ではありませんでした。江戸時代に入って鎖国政策をとると貿易は長崎の出島のみで行われましたが、砂糖を輸入するために銀や銅が大量に海外に流出し、その対策として幕府はサトウキビの栽培を奨励したため砂糖の精製技術が発達し、ようやく国産の砂糖の生産が行われるようになったのです。国産の砂糖で特に注目すべきは四国特産の和三盆糖です。独自の精製の工程は、人の手で徹底的にこね、不純物を押し出すという作業を中心とした大変に手間も力もいるものでしたが、こねていく工程で砂糖の結晶が細かくなり、口どけが良いという利点があって、いまでも高級和菓子にはなくてはならない物であり、伝統的な製法が今でも続けられています。こうして国産化に成功し、少しは庶民的な価格になった砂糖ですが、まだまだ高価で毎日の料理に使えるようなものではありませんでした。本格的に庶民の日常的調味料となるのは、明治に入って日清戦争に勝利し、台湾に精糖工場を建設したことによります。和風の味の代表格ともいえる砂糖と醤油の味付けはこれ以降に一般化していったのです。 砂糖の主成分はショ糖という物質です。ショ糖はブドウ糖と果糖の分子が一個づつ結合したもので、このうちブドウ糖が人体の全てのエネルギー源となります。もちろん砂糖でなくても、例えばご飯のデンプンもブドウ糖の分子がたくさん連なってできているものですから、消化吸収の過程でいずれはブドウ糖になります。でも砂糖の場合は即効性があり、口にすればすぐに吸収され、特に脳のエネルギー源としては大変優れているのです。昔からの習慣の「おめざ」も、栄養が欠乏している寝起きの脳にエネルギーを与えるのに有効であると経験的に解っていたからこその習慣なのでしょう。 最近では、サトウキビから作った糖をアルコール発酵させ、自動車の燃料に使う試みが始まっています。これだけ科学が進歩しても最後に人類を助けてくれるのは生き物であり、自然であると思います。恩を仇で返すような事だけはしないようにしたいものです。
2006年03月10日
コメント(0)
-
遊牧民
モンゴルの遊牧民がうらやましくなることが時々あります。広大な草原の中でゆったりと流れる時間の中で生きている遊牧民たち。ゲルと呼ばれる組み立て式の住居で、土地に縛られることなく大草原を移動しながら羊や山羊を飼って生活しています。財産と呼べるものはこまごまとした家財道具以外はゲルと家畜たちだけです。羊の乳を飲み、チーズを、酒を造り、ほぼ自給自足の生活ですが、貧しい感じはありません。むしろ豊かでおおらかな生活に見えます。彼らの生き方を見ていると、本当の人間らしい生き方とはこういうものなのではないかと思ってしまいます。子供のころからテストで優劣を付けられ、大人になれば仕事上の無理難題や住宅ローンに苦しめられる。多くの人が寿命を全うせずに自ら命を絶っていく。何かが間違っている…。 ここ十数年で日本の都会の空は青くなくなってしまいました。モンゴルの空は今でも青く高いです。
2006年03月09日
コメント(0)
-
ミツバチ
今日は、3(ミツ)、8(ハチ)でミツバチの日です。ミツバチは人類にとってとても大事な昆虫です。ハチミツは、砂糖の工業的生産が成功するまでは貴重な甘味料でしたし、ローヤルゼリーの圧倒的な栄養価は不老長寿の薬として時の権力者に好まれました。最近では天然の抗生物質と呼ばれるプロポリスが医薬品として注目を集めています。 ハチミツはミツバチが花の蜜を集めたものが原料ですが、単に花の蜜が濃縮されたものではありません。花の蜜は多糖類という分子の大きい糖が主成分なのですが、ハチミツは酵素などの働きで分解され果糖とブドウ糖に分解され、さらに水分が蒸発し、巣内で熟成されてあの濃厚なハチミツになるのです。 ローヤルゼリーは女王蜂の唯一の食べ物で、若い雌蜂が花粉や蜜を材料に体内で合成します。成分は各種アミノ酸、ビタミン、ミネラルなどがバランス良く豊富に含まれています。女王蜂はこのローヤルゼリーのみを食べる事で、毎日2000個くらいの卵を産みます。これは女王蜂自身の体重と同じくらいの重さですから驚異的なことです。 プロポリスは蜂の巣の材料である蜂ヤニのなかに含まれています。成分としては植物由来のフラボノイドが多種類含まれています。抗菌作用や抗酸化作用があり、ミツバチは巣の中を衛生的に保つためにこれを利用していると考えられます。 人類が天然のミツバチの巣からハチミツを採取した歴史は古く、紀元前15000年頃の洞窟壁画にミツバチの巣に手を伸ばす人類が描かれているのが見つかっていますし、エジプトでは紀元前1000年ころのお墓からハチミツの入ったツボが発見されています。しかし、現代のように蜂を飼いならし、巣箱の中に巣を作らせる近代養蜂が発明されたのは19世紀に入ってからです。日本では18世紀の文献でミツバチを人家で飼育した記録がありますが、巣箱方式でなく蜂に勝手に巣を作らせて、適当な時期に巣ごと採取して蜜を取る方法だったと思われます。なぜならこのころのミツバチは日本ミツバチで、山野に繁る大木の空洞の中に営巣する性質があり、巣箱には入らない蜂なのです。明治以降になって西洋ミツバチが輸入され、巣箱を使った近代養蜂が始まります。 ミツバチは生物学的にも非常に興味深い昆虫です。蟻と並んで「社会」を造る昆虫であり、王、女王、働き蜂など役割分担を行います。蜜の有る花畑の位置をダンスで仲間に知らせ、組織的に行動して効率よく蜜を集めます。だれに教わるでもなくこういう行動ができるのは生命の神秘と言えます。 ハチミツはとても素晴らしいものなのですが、実は私は少し苦手です。あの濃厚な甘味と独特の風味がしつこく感じられてしまうのです。一生懸命蜜を集めてくれたミツバチさんには申し訳ないですが。
2006年03月08日
コメント(0)
-
絹
今日は、日本人になじみが深い高級布地素材の絹について書いてみます。 絹の原料はカイコの繭の繊維をほぐした物です。絹は最新の化学繊維でもまねできない大変優れた特徴を持っています。 1.上品な光沢がある 独特の光沢があり、織物に仕立てたときには、あらゆる繊維素材の中 で抜きん出た美しさを持っています。 2.肌触りが良い 肌と同じくタンパク質でできていますから肌に優しい素材です。 化学繊維だとかぶれてしまうような肌の弱い人でも絹なら大丈夫と言 う人もいます。 3.通気性・吸湿性が良い シルクの繊維は断面が三角形になっており、布地にした時に適度な隙 間ができるため、湿気を吸収してくれますし、通気性に優れています。 4.静電気が起き難い 生体素材ですから、ナイロンやポリエステルのようなプラスチックに 近い素材に比べて帯電しにくいです。 5.繊維の引っ張り強度が高い。 羊毛や綿の繊維に比べて強度が高く、丈夫です。 6.紫外線を通しにくい 元が繭ですから内部のさなぎを守るため紫外線をブロックする性質を 持っています。このように非常に優れた特徴を多く持つ絹が世界で珍重されたのは当然で、シルクロードの大変な旅をしてまでも欲しがる人がたくさんいて、高価で取引されました。当然日本でもこんな素晴らしいものをほっておくはずがありません。養蚕が始まったのは4500年位前の中国と言われていますが、日本へは2000年位前に伝わったようです。なんと邪馬台国・卑弥呼の時代ですから永い歴史があることに驚かされます。平安の雅な十二単も絹があればこそですし、化学繊維のなかった昔は養蚕は農家の貴重な収入源ともなり、稲作のできない山間部では欠かせない産業となったのです。 カイコの原種は中国の野生の蛾である「クワコ」だと言われています。絹を作り始めたのは6000年位前の中国で、最初は自然に作られた繭を集めて絹を作っていたと考えられています。前述したように4500年くらい前から、効率を良くするため大量に飼育するようになったと思われます。永い飼育の歴史の中で、カイコは人間が世話をしてあげなければ生きていけなくなりました。きれいな糸をたくさん吐いて大きな繭を作るカイコを選択的に飼育することで品種改良されていったのです。その過程でカイコは飛ぶことを忘れ、人間の助けがなければ繁殖できなくなったのです。 カイコは桑の葉しか食べません。これはコアラがユーカリの葉しか食べないのと一緒で、桑の葉にある種の毒素があり、カイコはそれに対して解毒能力を持っているかららしいです。このことでカイコは桑の葉を独占できるわけです。まだ野生だったころの生き残り戦術の名残でしょう。最近では、遺伝子組み換え技術などを駆使し、桑以外のものを食べる蚕を開発する試みや、カイコが食べてくれる人工の餌なども研究されています。今まではカイコを飼うには桑畑が必要でしたからどこでも飼育できるというものではありませんでしたが、人工の餌が実用化されればどこでも飼育でき、桑の葉を収穫する手間もいらなくなります。素晴らしい素材である絹がますます世界中で使われるようになるといいですね。
2006年03月07日
コメント(0)
-
ジャンヌ・ダルク
今日は、ジャンヌ・ダルクの日です。1429年、イギリスとの百年戦争で苦戦するフランス皇太子シャルル7世のもとに、大天使ミカエルの啓示を受けたというジャンヌ・ダルクが現れました。ジャンヌ・ダルクはフランスの伝説的英雄です。百年戦争においてフランスが圧倒的劣勢を強いられる中、彼女は突然現れました。ジャンヌは辺境の地に住む何の変哲もない羊飼いの少女でした。その少女が大天使ミカエルの啓示を受け、甲冑を身に付け、剣と天使の図柄の軍旗を携えてイギリス軍に立ち向かったのです。そして、勝利の見込みのまったくないと言われたオルレアンの戦いにも奇跡的に勝利し、オルレアン城と町を開放する事に成功するのです。 ジャンヌ・ダルクはただの伝説は空想の世界の人ではありません。れっきとした歴史上の人物です。百年戦争、オルレアンの戦いという言葉が並ぶとなんだか中世もののアニメの話かと思ってしまいますが、間違いなく現実に起こった事なのです。 なぜ20歳にも満たない普通の羊飼いの娘がこんな偉業をやってのけることができたのか謎です。大天使ミカエルの啓示を受けたというのはさすがに作り話でしょうから、彼女自身がよほどの強烈な心を突き動かされる何かがあったのでしょう。彼女が身に付けた甲冑は、25kgもあったと言います。華奢な少女の体にあまりにも重過ぎる甲冑を身につけて最前線に立ったのです。もしジャンヌがいなければ現在のフランスはないといっても過言ではないでしょう。 伝説的英雄となったジャンヌですが、最後は悲壮なものでした。イギリス軍に捕らえられ、宗教裁判にかけられて魔女の濡れ衣を着せられ、なんと生きたまま火あぶりの刑に処されてしまうのです。わずか19歳の時のことです。 ジャンヌ・ダルクは、多くの勇猛な部下を率い、戦場を駆け抜けた軍人なのですが、私の中では女傑のイメージはまるでなく、神がかり的なカリスマ性で部下を率いながらも、悩み、戸惑う少女の一面も併せ持っている姿をイメージしています。彼女の業績や神秘性の割には日本では知名度はあってもどんなことを成し遂げた人なのかはあまり知られていないようです。アニメ化すれば味のある作品ができそうですが、どこかのアニメ会社でやってくれないかな。
2006年03月06日
コメント(0)
-
竹
最近、竹が見直されているようです。建築材料や工業製品の材料として注目されているのです。例えば高級外車の内装や、住宅の床や壁、パソコンのキーボードにまで広がっています。一時はプラスチックにその座を奪われ、少なくなっていた竹製品ですが、プラスチックにはない温かみがあり、日本人にとっては懐かしさもある竹が復権しているのは、日本文化への回帰のようで喜ばしいことです。 竹は、古くから日本人となじみが深く、古くは古事記の時代、日本最初の物語である竹取物語をみてもそれはよく解ります。昔はいたるところに竹林があり、人々は竹を刈ってざるやかごなど、さまざまな生活用具を作りました。竹の食器などは特有のさわやかな香りがして、瀬戸物などにない良さがあります。 竹は植物としてみた場合、かなり特異な特徴を持っています。あんなに高く成長する植物で、中空構造をもっているものは他にありません。また、非常に成長が速く、これは通常の植物が茎の先端部分のみに成長点を持つのに対し、竹は筍の時点ですでに全ての節に成長点を持ち、全ての節が同時に成長するため、ちょうどアンテナが伸びるように急激に成長できるのです。速いときには1日で120cmも成長するそうです。中空であることも成長が速いことの理由の一つです。かといって、スカスカではなく、非常に緻密な繊維構造を持っていて、同じ重さの鉄と比較すると倍の強度があるそうです。 緻密な組織は水漏れしないので旅人の水筒にも使われました。また、熱にも強いので昔の農家では囲炉裏の上に竹で棚を吊り、魚や野菜などをいぶしたりしました。この竹の棚は何十年も経つとすすで黒くなり、わびたいい味がでるので、茶道の茶室に飾る一輪挿しなどに喜ばれました。 竹を焼いて作る竹炭は、消臭効果が高く、その効果は木炭よりも優れています。また、人体に無害で食品に練りこんで黒い色を付けたりします。竹炭を焼くときに竹酢液という液体が副産物として採れます。この液は殺菌力が強く、農薬の代わりに使ったり、薄めて怪我をしたときの傷の殺菌などに利用できます。 筍は言うまでもなく和食に欠かせない材料で、ヨーロッパには竹は生育していませんので日本独自の食文化です。また、筍の皮は、筍を守るため抗菌作用があり、昔は握り飯をこれで包んでいました。 このようにあげればきりがないほど役に立つ竹ですが、繁殖力旺盛な割には環境の変化には弱いようで、大きな竹林はなかなか見られなくなりました。竹が見直されているこの機会に竹林を保全する動きが広まってくれるといいなと思います。竹林のえもいわれぬ風情は、どこか日本人の心に語りかけてくるものがあるように思うのです。
2006年03月05日
コメント(0)
-
沖縄
今日は、3(月)4(日)でさんしんの日です。さんしんとは沖縄の楽器の三線です。最近、沖縄の文化が本土でも紹介され好評です。独特の料理、芸能など、同じ日本という国なのにエキゾチックな魅力に溢れています。 三線は、よく三味線のような楽器と説明されると思いますが、本当は歴史としては三線の方が古く、本来、三味線の方が「三線のような楽器」と称されるべきなのかもしれません。工芸品としての美しさも三味線より三線のほうが優れているように思います。三線の胴には蛇の皮が張られています。これがブランド物のワニ革製品のような高級感をかもし出しています。本土には大きな蛇がいないため、三味線は猫や犬の皮が使われています。 三線が優れた工芸品となったのには理由があります。昔の武士社会の日本では、床の間に刀掛けを置き、武士の魂である大小の日本刀を飾っていました。沖縄では床の間には、三線を三線箱に入れて飾っていました。飾り三線と言われるものです。その家の主人が歌舞芸能に理解がある印であり、生活にゆとりがあることを示していたと言います。三線も高価なものから比較的安価なものまで有りますから、どんな三線が飾られているかでその家の格を示していたのです。沖縄では人が破産した時、まず最初に家を売り、ついで墓を売り、最後に家伝の三線を売ったといわれるぐらいに沖縄の人は三線を大切にしてきたのです。 刀を床の間に飾る文化は「武士道」を尊ぶ文化です。武士道とは死ぬ事と見つけたり。有る意味野蛮です。沖縄では三線を飾る事で「平和」、「協力」などを表わしているように思います。このように沖縄では他に類を見ない独特の文化が育ってきて、最近では個性的な沖縄出身のアーティストも多いですね。 沖縄の音楽にはとてもわかりやすい特徴があります。それは音階です。普通の音楽は、ドレミファソラシドですが、沖縄音楽ではドミファソシド、つまりレとラが使われないのです。お手元に何か適当な楽器があったら、ドミファソシドを適当に並べて鳴らしてみてください。あら不思議、それだけで沖縄音楽っぽくなりますよ。
2006年03月04日
コメント(0)
-
ひな祭り
今日は、ひな祭りですね。数ある日本の年中行事の中でも、ウキウキと心浮き立つような楽しい風習です。舞台装置の主役、雛人形は、世界でも珍しいほど高い芸術性を持った伝統工芸品です。ルーツは流し雛です。平安時代に中国から伝わったこの風習は、紙で作った人形(ひとがた)に穢れを移して川に流すというもので現在でも行われている地方も有ります。雛の語源は「ひいな」という官女の手作りの男女一対の人形で、子供たちはこの人形で「ひいな遊び」というおままごと遊びをしました。江戸時代になると、お雛さまを飾り、桃の花や白酒、菱餅やあられなどを供えて祝う現在の「ひな祭り」の形になりました。ひな祭りも端午の節句も男のお祭り、女の子のお祭りという区別はもともとなかったのですが、はっきりと分けるようになるのも江戸時代からです。雛人形は江戸時代の豪商など裕福な人達によって大変豪勢できらびやかなものが生まれました。 白酒についてですが、酒粕で作る甘酒とごっちゃにしている人が多いようです。白酒は、新嘗祭に供えられる、その年に収穫された新米で作った新酒「白酒(しろき)」と同じ御神酒であり、本来はもち米とうるち米、米麹、焼酎などで作ったお酒で、ろ過していないので白く濁っています。どぶろく、濁り酒のようなものですね。古代の酒造りが始まったころの姿を今に残しているのかも知れませんね。とは言え、一般家庭ではやはり、甘酒で代用するのが普通でした。私の家でも母親が大鍋いっぱいに作るのですが、酒粕が口に残るのがいやで、ガーゼで漉して飲んだりしました。今では、ノンアルコールの白酒が売られていますが、あのころは何でも家庭で作っていて、作る過程での香りや音なども子供の心の中で思い出になっていました。そういう思い出が根っこのある文化を創るのだと思います。
2006年03月03日
コメント(0)
-
ミニの日
今日は、3(月)2(日)でミニの日です。私は小さい物がとても好きです。ミニカーとか人形などのミニチュア物も好きですし、実用品でも小さいものが好きなのです。例えば、自動車などは多くの人が本音では大きくてりっぱな車に乗りたいと思っているようなのですが、私の場合は小さいけれども性能と質は良いという車が理想です。よく高級車は中が広くてゆったりしていて良いなんて言いますが、私はむしろ窮屈でない程度にタイトな空間が好みです。車は走るためのものですから必要以上に広い必要はないと思うんです。日本の道路では車は小さい方が何かと便利ですし、車体も軽くて燃費にも有利ですし、第一、大きな3列シートの車に1人か2人しか乗らないで走るというのは何か不合理で気持ちが悪いのです。車以外でもパソコンやその周辺機器なども性能が同じならコンパクトな物を選びます。さらにはキッチンの鍋ですらコンパクトに収納できるスタック式のものが好きです。幼いころから狭い家に住んできたので貧乏性なのかもしれません。 人間って巨大な物と微細なものに引かれる性質があると思います。お祭りなどでは競って巨大な山車を作ったり、ものすごく太いしめ縄を作ったり。時には巨大なオムレツやコロッケを作ってみたりもします。反面、昔から競って小さい物を作る風習もあって、米に文字を書いて見たり、小さな人形の顔を目の瞳まで細かく描きこんだりします。私の勝手な思いですが、それらは人間の精神の二面性を表わしていると思います。巨大なものは「開放」や「発散」を、微細なものは「凝縮」や「集中」を、という感じです。また、「衆」と「個」の対比とも言えるかも知れません。そう言えば、自分はワイワイガヤガヤ物事をするのは好きではなく、コツコツ一人でやるタイプだったなあと思い出しました。
2006年03月02日
コメント(0)
-
ビキニ・デー
今日は、ビキニ・デーです。といっても水着の話ではありません。1954年(昭和29年)、太平洋のビキニ環礁でアメリカが水爆実験を行った日なのです。ビキニは太平洋西部にある美しい珊瑚礁の楽園のような島でした。人も住んでいました。周囲の海では多数の漁船が操業していました。こともあろうに、アメリカはそこで水爆実験を行ったのです。広島・長崎の原爆のわずか1年後のことです。水爆「ブラボー」のエネルギーは広島型原爆の1000倍と言われています。現地住民は約230kmはなれたロンゲラップ島に強制移住させられていましたが、風下になったロンゲラップ島には大量の死の灰が降り、多くの人が被爆しました。周囲で操業していた漁船も数多く被爆し、日本の第五福竜丸もその一つです。 水爆は、原爆の爆発エネルギーを火種に、原爆の周囲に詰めた重水素に核融合反応を起こさせ、膨大なエネルギーを開放する兵器です。そんな物を爆発させればどんな事になるか科学的に推測すればわかりそうなものですが、当時ソ連が原爆の開発に成功したことからこの非道な実験に踏み切ったのです。しかも、現地の住民は安全とはいえない場所に強制移住させたものの、周囲の海域にいる船舶は何も知らされずいきなり死の灰を浴びせられたのです。ビキニ環礁は今でも放射能汚染が残っていて人が住める環境ではありません。当時のアメリカは太平洋戦争に勝利し、勝ったものは何をしてもいいと言う「選ばれし者の理論」に陥ってしまっていたのかも知れません。広島・長崎は戦争というやるかやられるかの殺し合いの中でのことであり、結局殺し合いにルールもモラルもないのだとあきらめるしかありませんが、ビキニの件はまったく違います。被爆したのは何の罪もない無関係な人なのです。たかだか60年程度前にこれだけの馬鹿げた行為を行ってしまったことは、アメリカのみならず人類の汚点として永遠に語り継がれることでしょう。 ところで、水着の方のビキニですが、このビキニというネーミングは今回の話題のビキニ環礁事件から採ったらしいです。なんでも発明者がインパクトのあるネーミングを考えていてニュースでビキニの水爆実験を知り、名づけたのだとか。脳天気なのもいい加減にしてくれと思っちゃいますね。今からでも名称変更して欲しいものです。
2006年03月01日
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1