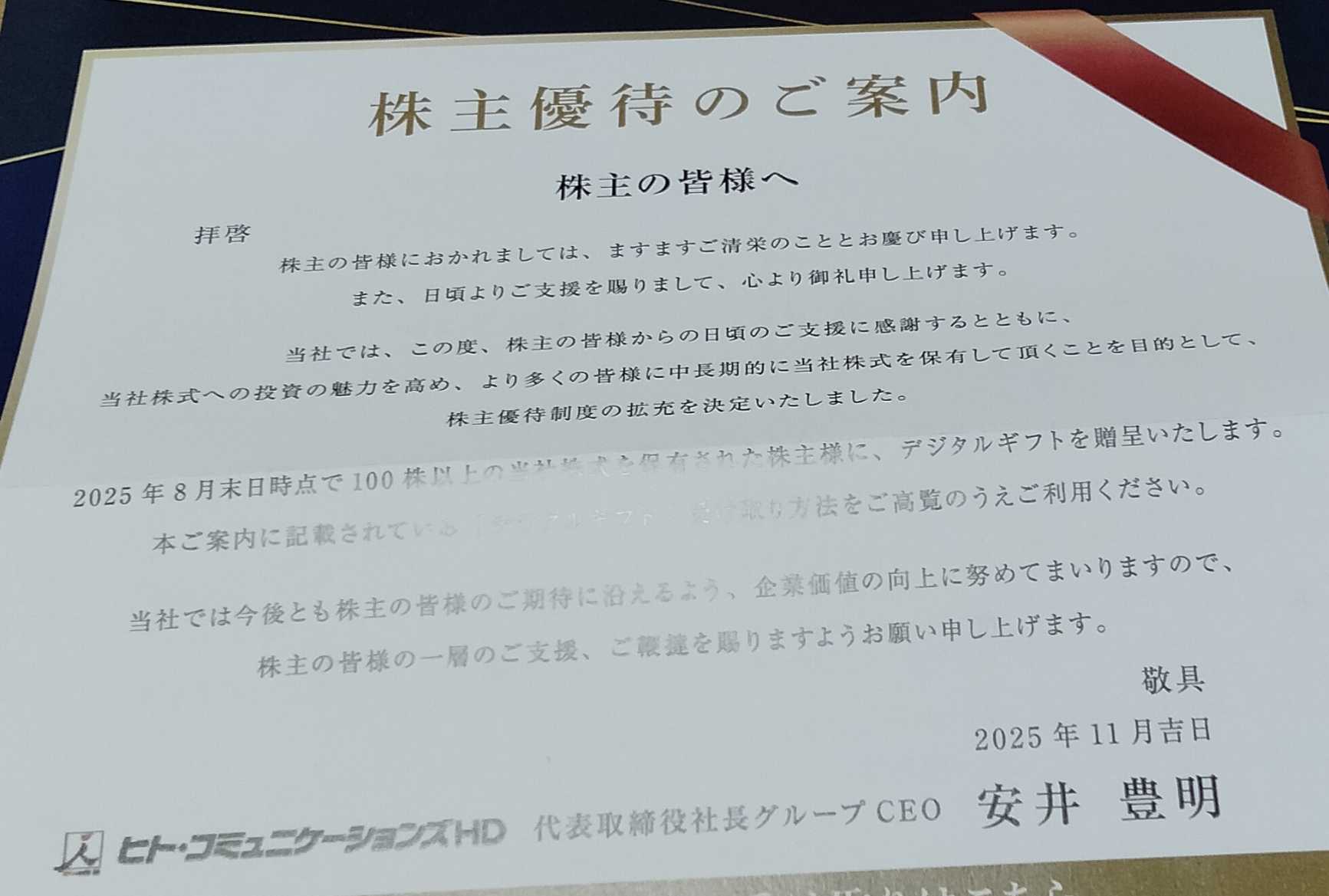2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年05月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
ヘルシーアイスクリーム
今日は良く晴れて、東京では28℃を超える暑さでした。いちおうまだ5月だと言うのにちょっと先が思いやられます。日照不足で肌寒いと思えば、晴れれば夏日なので体の調整機能がついていきません。 この暑さでアイスクリームが売れているそうです。なかでも注目はヘルシーアイスクリームと言われているもので今年のトレンドのようです。コエンザイムQ10やビタミンCが入っているもの、黒酢を使ったものなどさまざまなものがありますが、乳脂肪を抑え、豆腐や豆乳、ヨーグルトなどを使ったアイスクリームは今までのアイスクリームとは別物の新しいアイスクリームです。豆腐のアイスクリームなんてさっぱりしすぎて美味しくないんじゃないかと思いますが、しっかりとコクがあって美味しいらしいです。それでいてヘルシーなのですからありがたいですね。食品メーカーも他との差別化を図るため相当力を入れているようですから今後はヘルシーアイスが主力商品になっていくのでしょう。でも、私のような古い人間は、昔ながらの伝統的なアイスクリームもなくならないようにメーカーさんにはお願いしたいですね。
2006年05月31日
コメント(0)
-
掃除機
今日は、5、3、0でゴミゼロの日ですが、同時に掃除機の日でもあります。ゴミのお話は5月3日に書いてしまっているので、今日は、掃除機について書きます。 最近はサイクロン方式が流行りのようで、ほとんどのメーカーが出しています。空気の渦の遠心力を利用してゴミを捕らえるので、フィルターのつまりがなく吸入力が落ちにくい、紙パックが不要とのことなのですが、ある団体の調査では、ゴミが溜まるにつれ吸入力が落ちるのはサイクロン方式であり、むしろ紙パック式の方が吸入力の低下が少ないという結果が出ています。さすがにサイクロンの元祖、ダイソンのものはかなり高成績だったようですが、日本のメーカーの物は全滅状態でした。いったいメーカーは発売する前にテストしないのかと疑いたくなります。日本の物は一見してそんなに大きい遠心力が働きそうもない構造です。遠心力だけではゴミを分離しきれないため、たいていの機種はフィルターも付いていてこれがすぐに詰まってしまうようです。我が家にもサイクロン方式の掃除機が2台有りますが、やはりこまめにフィルターの掃除が必要です。とは言え、紙パック式は、紙パックを買いにいくのが面倒ですし、形が古くなると、合う紙パックが手に入らなくなりそうでいやです。掃除機なんて一度買ったら10年は使い倒したいですからね。次に買い換える時には、なんとかもうちょっとまともな紙パック不要の掃除機を開発してもらいたいです。 私は無精者なので、掃除機も使いたいときにひょいっと持ち出して使えないと嫌です。組み立てたり、コードを引き出してコンセントに差し込む、コンセントが遠い場所では延長コードを使って…。ダメです。その時点で掃除をする気力が萎えます。なので私はコードレスの掃除機を愛用しています。特にエレクトロラックスの縦型の掃除機は使いたいときにすぐに使え便利です。といってもこれもサイクロン方式なのでこまめなゴミ捨てとフィルター掃除は必要なのですが。でもコードレスの掃除機の最大の問題点は、吸入力が弱いことです。バッテリーの能力の限界がありますので、いたしかたないところです。これもメーカーさんにがんばってもらって、小型軽量の強力バッテリーとモーターを開発してもらうしかないですね。バッテリーの寿命は意外と長いみたいです。もう5年くらいは使っていますが平気です。家事用の家電製品はたくさんありますが、もっとも不便さが残っているのがこの掃除機だと思います。あまり高額にはできない商品だからかもしれませんが、各メーカーさんのいっそうの努力に期待します。
2006年05月30日
コメント(0)
-
コンニャク
今日は、「こん(5)にゃ(2)く(9)」で、コンニャクの日です。あなたはコンニャクはお好きですか。どちらかと言えば主役になれない万年脇役のコンニャクですが私は大好きです。煮物などでコンニャクが入っていないとがっかりしてしまいます。豚汁などでもコンニャクは絶対に欠かしたくありません。また味噌田楽なども美味しいですね。コンニャク自体にはさして味があるわけでもないのですがあの食感がたまりません。 コンニャクの原料は里芋の仲間であるコンニャクイモです。コンニャクイモは成長が遅く、さらに冬の寒さに弱く、種芋を植え付けてから3年間、毎年秋に掘り起こしては室(むろ)に保管し翌年の春に植え直すことを繰り返さなければなりません。しかもこのイモ、食用には適していません。煮ても焼いても、食べようものなら強力なアクで七転八倒すること請け合いです。すりおろし何度も水にさらして石灰などでアク抜きする工程が必要なのです。ここまで手間をかけても栄養分はほとんどゼロ。なんとも効率の悪い作物です。コンニャクは近年では逆にカロリーがほとんどないことが注目されて見直されていますが、いままでこんな食べ物が、なくなることもなく堂々と生き残ってきたのは、日本の食文化が、単に風味や栄養だけでなく、食感という重要な味の要素に気付いていたからに他なりません。相当な手間隙をかけながらも栄養はゼロという事実をものともせず、連綿と食文化の中に取り入れてきたのは一種こだわりのようなものを感じます。おそらく日本人は寒天や葛などグミ系の触感が好きなのでしょうね。 煮物などにするときには、アク抜きした時の石灰臭を除くため、下ゆでしなければならないのが一手間ですが、炒めたり、炒り煮したりの濃い味付けのときは下ゆでは必要ないそうです。最近、「おからコンニャク」というものが人気のようです。焼いたりすると肉そっくりの食感になり、ダイエットに良いのはもちろん単純に美味しいとのことで売れているそうです。一過性のブームに終わらず新しいコンニャクの一ジャンルとして定着するといいなとコンニャク好きとしては思います。
2006年05月29日
コメント(0)
-
野菜高騰
野菜の値段が高騰しています。冬の間も今年の厳しい寒さのため高価だったのですが、春になってようやく一息つけると思いきや、今度は日照不足でさらに厳しい収穫量の低下だそうです。生活に不可欠の野菜などがのきなみ3割から4割も値上がりしたのではたまりません。人間とは不便なもので、野や山で食べ物を探すのも山菜採り以外ではそうそうできません。農家の人など自分で畑を持っているのでなければ、商業的に売られているものを買うしかないのです。野菜といい、先日書いたイワシといい、これだけ科学文明の社会になっても本当の命を支える基盤は案外脆弱なのではないかと思う今日この頃です。
2006年05月28日
コメント(0)
-
百人一首
今日は、百人一首の日です。1235年のこの日、藤原定家が「小倉百人一首」を撰じました。同じく定家の撰となる「百人秀歌」が原形だと言われています。今では歌集としてより伝統的なかるたとして多くの人に愛され、競技としても全国的に定着しています。もっとも私はもっぱら坊主めくりでしたが。 かるたとして庶民に定着するのは江戸時代からで、やはりもともとは歌集として作られました。主に古今集や新古今集などの、天王の命令により編まれた勅撰和歌集から採られているものが多いようです。ただ、わざとなのか手違いなのか元の歌と少しだけ言い回しが変わっているものもあるようです。星の数ほどある歴代の名歌の中から絞りに絞った100首だけに、日本の四季おりおりの景観や恋愛の心など日本人の美意識が結集された珠玉の歌集となっています。クラシック音楽のように、時代のはやりすたりに影響されない一生涯愛読できるこの歌集は、私にとってはある意味、心のよりどころにすらなっています。 百人一首が作られるきっかけは、定家の日記「明月記」に、「京都の嵯峨にある宇都宮頼綱の山荘にの障子に貼るための色紙として、古来の歌人たちの歌を各一種選んだ」と記されていることから宇都宮頼綱の依頼で彼の家の装飾に使うのが目的だったようです。 百人一首と言えば普通「小倉百人一首」ですが、百人一首は一つだけではありません。「新百人一首」「後撰百人一首」「新々百人一首」「愛国百人一首」など「小倉百人一首」を手本とした歌集が作られています。それだけ後世に残した影響が大きかったのですね。 せっかくですから最後に何首か紹介して今日の日記とさせていただきます。 ○記念すべき一首目 秋の田の 仮庵の伊庵の 苫をあらみ わが衣出は 露に濡れつつ 天智天皇 (訳)秋の田のかたわらにある仮の小屋。その小屋の屋根を葺いた苫の目が粗いので、 わたしの衣の袖が露に濡れていくばかりです。 ○一番おなじみの僧侶の歌 これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関 蝉丸 (訳)これがあの、旅立つ人も帰る人も、知っている人も知らない人も、 別れてはまた逢うという、逢坂の関です。 ○平安の有名女流エッセイストの歌 夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ 清少納言 (訳)夜が明けないうちに、鶏の鳴きまねをしてだまそうとしても、この逢坂の関(=あなたと 逢うこと)を邪魔することを許さないだろう。 ○平安の有名女流作家の歌 清少納言とはライバル同士 めぐりあひて 見しやそれそれとも わまぬ間に 雲がくれにし 夜半の月かな 紫式部 (訳)久しぶりに会って、その人かどうか見分けがつかないうちに 雲に隠れてしまった夜更けの月のように、あの人は姿を隠してしまった。 ○ラスト百首目 ももしきや 古き軒端の しのぶにも なほあまりある 昔なりけり 順徳院 (訳)宮中の古びた皇居の軒の端を見るにつけ、しのんでもしのびきれない 昔の(皇室が栄えていた時代)ことであるなあ。
2006年05月27日
コメント(0)
-
洗濯乾燥機
最近、高額な洗濯乾燥機が売れているようですね。ドラム式、斜めドラム、ヒートポンプ、銀イオン洗浄などなど、いったいどれが良いのかさっぱり解りません。本やインターネットで調べると、ドラム式は、叩き洗いなので衣類に優しいけれど洗濯に時間がかかること、脱水時の振動を抑えるのが難しいことが解ります。また、トップオープンドラム式以外のドラム式はドラムを支える軸受けが1ヵ所しかないいわゆる「片持ち」になってしまいますので、よほどしっかりした造りにしないと強度的に持ちません。従来の全自動洗濯機も片持ちではあるけれど、垂直に立っているため重力の影響を受けなくてすみます。ドラム式が発売されたころは故障が多かったようですが、今では良くなったのでしょうか。価格もまだまだ高いですね。全自動洗濯機と乾燥機をセットで買うよりも遥かに高額です。私は結局価格の面で納得できず全自動洗濯機と乾燥機を買いました。でも頭上に重たい乾燥機を乗せてあるので地震の時に倒れやしないか心配です。あれだけの重量があるとやわな転倒防止の鎖くらいでは役に立ちません。この点だけでもドラム式洗濯乾燥機が欲しいのですが。 今、興味があるのは日立のビートウォッシュです。他のものとはまったく違う方式で脱水時の振動も少なそうだし、これで洗浄力があってと衣類の傷みが少なければ買いだと思うんですが、CMなどの動画でみると回転する底板で衣類が思いっきりこすられているように見えますので衣類の傷みは有りそうですね。日立以外のメーカーでも何か画期的な方式の洗濯機を開発してもらいたいです。出来ればシンプルで軽くてお安いのがいいのですけれど。
2006年05月26日
コメント(0)
-
イワシ絶滅?
イワシの水揚げ価格がとんでもないことになっているようです。一匹1,000を超える高騰。これは個体差もありますがグラムあたりの価格は鯛の倍以上の価格になります。イワシにもカタクチイワシやウルメイワシなどいろいろありますが、一番問題なのはマイワシで、もうすでに日本近海のマイワシは絶滅したと言う人もいるほどです。有史以前から日本人の大切な食料となり、節分の魔除けになるなど文化にも深く根付いてきたイワシと日本人の関わりも終焉を向かえようとしています。マイワシ以外のイワシもマイワシと同じ道をたどる可能性大です。そうなればチリメンジャコやニボシなどの伝統的な食品も輸入に頼ることになります。また、養殖魚の餌もイワシの稚魚が使われていますから食卓に昇る全ての魚に影響すると言っていいでしょう。 これが乱獲による漁獲量減少なら漁獲量の計画的調整で復活させることができる可能性があります。かっての秋田のハタハタのように。でも、どうやら乱獲が原因ではなく、長期的な気候変動が原因らしいのです。世界的にみると漁獲量は増えているのにイワシは減っていないところもあって、ここまでマイワシが減っているのは日本近海に限定されているようです。 これからはもう冷凍の輸入物か加工食品でしかイワシを楽しむことはできなくなるかも知れません。もともと傷みやすいイワシだからこそ、近海ものの新鮮なイワシの刺身は、こたえられない美味しさだったのですが、それも幻となってしまいそうです。気候変動も元はと言えば人類の二酸化炭素排出に起因しています。100年後の日本人はいったい何を食べているのか無意味に心配になったりします。
2006年05月25日
コメント(0)
-
春雷
今日は、変な天気の一日でしたね。午前中は日が差していたのに、午後からは急に崩れ雷雨となってしまいました。今年の五月は五月晴れの日がほとんどありません。前線が停滞し、このまま梅雨になだれ込んでしまいそうな勢いです。 春雷が多い年は日照になるという言い伝えがあります。今年の夏も暑くなりそうです。
2006年05月24日
コメント(0)
-
水質
私の住んでいる地区では、水道水がかなり硬水のようです。日本では普通軟水が多いのですが、我が家では、バスタブの底や鏡、洗面所のボールの底などにちょっと油断すると白く硬いスケールがびっしりと付いてしまいます。これが通常のカルシウム系のものなら酸性のクリーナーで落とせるのですが、我が家では酸でもアルカリでもビクともしません。どうやらシリカ(ケイ素)系のものではないかと思っているのですが、定かではありません。今度水道局にでも問い合わせてみようと思っています。もしシリカ系のスケールだとすれば酸でもアルカリでも溶けず、溶かすためにはフッ化水素などかなり危ない薬品が必要で素人の手には負えません。自治体の供給している水ですから飲料用に支障があるようなことはないと信じていますが、掃除の手間が大変ですし、できることならなんとかしてもらいたいものです。一戸建てなら水道メーターの直後に付ける高性能なフィルターなども売られていますから対処のしようもあるのですが、マンションではどうしようもありません。 水は生活のなかで最も大切なインフラです。水の質で住む所を選択するのも生物として自然なことだと思うのですが、現代ではそれもなかなか許されませんね。飲み水は既に買って飲むのが常識になってしまいましたが、風呂や選択など日常用水の水質改善はこれからの日本において充分ビジネスチャンスになると思うのですが、いかがでしょうか。関連企業の方。
2006年05月23日
コメント(0)
-
フライパン
先日、フライパンのことを書きましたが、土日も何かいいフライパンがないか探していました。レミパンも買って半年ですが、そろそろくっつきやすくなってきてフライパンとしてはもう退役願いたいところです。鍋や蒸し器としては問題なく使えるのですが、オムレツなどにはもう限界です。しかし、我が家はIHなので、なかなかIH対応で厚底のテフロン加工のフライパンはホームセンターには有りません。やっと見つけてもまた半年で買い換えるのでは財布にも地球にもやさしくありません。 調べてみるとテフロンがくっつきにくい性質は約300℃くらいで変質して失われてしまうのだそうです。てっきり表面が傷付いてくっつきやすくなるのだと思い、洗うときにも柔らかいスポンジで洗うようにしていたのにがっかりです。300℃くらいはガスでもIHでも調理中には簡単に超えてしまいます。しかもテフロンは熱伝導性が非常に悪く、このためなおさら、短時間でささっと調理したい炒め物や卵料理などは強火を使いたくなってしまいます。これではテフロン加工のフライパンは永持ちするわけがありません。 そこで、鉄のフライパンを買って永く使おうと思ったのですが、これまたIH200Vで使えるものは見つかりません。唯一リバーライトのものは大丈夫そうなのですが、IHだと鉄のフライパンに必要な最初の空焼きや汚れてきたときの焼き直し(リフレッシュ)が出来ないのでカセットコンロを使ってやるようになってしまいます。よく油の馴染んだ鉄のフライパンには憧れもあるのですが、ガスの炎あってこその鉄フライパンであって、やはりIHには似つかわしいものではないのかもしれません。 他にはステンレス、アルミ、鋳物、チタンなどもありますが、くっつきやすい、傷つきやすい、重いなどやはり古くから現場のプロに愛用されている鉄以上のものはなかなかないようです。どなたかIH200Vで使えるくっつかないフライパンをお使いの方はぜひ教えてください。
2006年05月22日
コメント(0)
-
ダヴィンチ・コード
昨日から映画「ダヴィンチ・コード」が封切られたようです。伝説的な天才ダヴィンチは類まれなる人物であった事は事実ですが、個人的に言わせてもらえば、冷静にみればどう考えても飛びそうもないヘリコプターだとか、鳥のようにはばたく飛行機だとか、駄作である以前にこの人ほんとに物理学の法則が解っているの?と思うデッサンも多いです。やはり、アイデアと探究心豊富なアーティストであって、科学者とは言いにくいと思います。 「ダヴィンチ・コード」の本来のテーマは多分キリスト教のダークゾーンにあると思います。博愛の精神が教義であるはずのキリスト教は、世界でもっとも迫害と殺戮の歴史に彩られたいみじき宗教でも有ります。そして、死海文書、聖杯、聖櫃など妖しげで伝説的なアイテムに事欠かない、どこか人類の過去と未来を内包するかのような近づきがたい謎の恐ろしさが有ります。宗教ってもっと明るく楽しい物であってもいいと思うのですが、日本で言えば、古事記の時代から神は人類の見方ではなく忌み恐れる物として描かれています。やはり人間は、古代でも現代でも、厳しい鞭と僅かの飴で生かされている弱く愚かな存在なのかもしれませんね。
2006年05月21日
コメント(0)
-
労働者の人権はどうなる?
今、恐ろしい法律が検討されているようです。それは労働者の残業手当がもらえなくなるというもの。今までもサービス残業が横行している日本だというのに、こんな法律が本当にできれば労働者は奴隷のようにこき使われるようになってしまいます。 今回の法案は年収400万円以上のホワイトカラーが対象ということですが、これはボーナスも入れれば月収25万円くらいの人から引っかかってきます。ということは概ね30代後半くらいであればほとんどのホワイトカラーの人は対象になってしまうのではないでしょうか。今までは労働基準法を横目で見ながら、労働者に訴えられないようにそこそこの待遇を外さないようにサービス残業させてきた会社もこの法律施行後はお上のお墨付きでタダ働きを強要できるようになってしまうのです。 日本は、先進国の中で労働者の人権が軽んじられている傾向があるのに、さらにそれを助長するような事を、こともあろうに法律で定めるというのはいったい何を考えているのでしょうか。本来なら残業は原則廃止し、その分雇用を増やし、失業者を減らすことが国民の生活の質の向上や税収のアップにも有効だと思うのですが。最近の政府は本当にどうしようもありません。自民党が政権を握っている限りこの特権階級優遇・庶民いじめスパイラルは止まる事はないように思います。
2006年05月20日
コメント(0)
-
新茶
新茶が出回る季節です。まさに新緑の色に澄んだ緑茶は、世界で最も美しい飲み物だと思います。世界で主流となっている紅茶や烏龍茶などの発酵茶でなくあえて緑茶を好んだのは日本人の美意識ゆえかもしれません。 ところで新茶はなぜ美味しいのでしょうか。新米と一緒で新しく新鮮だから?いいえ違います。確かにお茶は生鮮食品と言われ、買ってきたらなるべく早く飲みきるのが良いのですが、収穫地では基本的には新茶でなくとも摘んだその日に加工してすぐに出荷されます。お茶は普通年4回収穫期があります。産地によって違いますが、5月頃、6月頃、7、8月頃、9月頃というふうに春から秋にかけて摘まれ、冬はお茶の木は、お休みです。このお休みの間に春に備えてじっくりと養分を貯えたお茶の木は、春の訪れに一気に生命のエネルギーを開放し、新芽を芽吹くのです。これが新茶です。冬の間に貯えた養分をたっぷりと含んでいるから新茶は美味しいのです。年の初めに収穫されるお茶なので一番茶とも呼ばれます。 新茶のそれも一芯二葉の新芽から作られた高級茶葉を、作ってすぐに味わえるこの季節だけの贅沢はそうそう庶民にできるものでもないですが、年に一度くらいは奮発して日本人に生まれた喜びを満喫してみたいものですね。
2006年05月19日
コメント(0)
-
言葉
今日は、5、1、8で言葉の日です。言葉は言の葉とも呼ばれ、古来より不思議な魔力を持っていると言われてきました。例えばヨーロッパの黒魔法や白魔法などでは呪文(スペル)を用い、自然界のエネルギーを利用できると信じられていました。今でも魔女を名乗る人たちが実在します。 日本や中国では、お経が呪文の役目を果たしています。魔を封じる呪文、悪霊を退散させる呪文。梵字などが書かれたお札や、お墓の卒塔婆なども呪文に関連したマジックアイテムとみることもできます。日本でもヨーロッパの白魔法のように病気を治すのにも呪文を用いることも多く、例えば「オン、センダラ、ハラバヤ、ソワカ」と唱え、月光菩薩に病気の治癒をお願いすれば病巣が焼かれ治癒するとされていました。この「…ソワカ」というのは日本の呪文の典型的な形のようで、だれでも聞いた事があるのではないでしょうか。 仏教のアイテムである数珠は、呪文を唱えた回数を数える道具だったという説があります。また、神道でも、神社でお守りを売っています。これも中を開けてみた事はないですが、もともとは呪文を書いた紙を忍ばせてあったのかも知れません。身近なところでも呪文に関連するアイテムはあるもので、、日本人がいかに呪文としての言葉と文字に敬意や恐れなど特別な感情を持っていたかがわかります。ちょっと研究に値するテーマではありますね。
2006年05月18日
コメント(0)
-
省燃費グッズ
最近のガソリン価格の高騰には本当に困ってしまいますね。だからというわけでは無いのですが、最近、カー用品店などにガソリン節約をうたう怪しげな用品が驚くほど出ています。昔はオイル添加剤が多かったのですが、一時期のマグネットやイオン系を経て、最近の流行は電気モノのようです。バッテリーに接続するもの、シガーライターソケットに差し込むものなどいろいろです。中身はコンデンサーのようなものである場合がほとんどらしいのですが、所詮、電気モノですから正常に運転されているエンジンの点火系統は充分な性能を持っているので、それ以上に点火プラグに飛ぶ火花を強くしても効果はないと思います。旧車で、へたったプラグを新品に交換すると性能がはっきりと向上する事がありますが、それは故障が直って正常になっただけで、自動車メーカーは、エンジンごとに必要な点火の火花のエネルギーを計算して設計しているのですから追加の部品を付けたところでよくても無意味、悪くすれば故障の原因箇所を増やすだけだと思います。 しかし、私も昔はいろいろなものを試していた時期もあります。エンジン内をテフロン系樹脂でコーティングして摩擦を減らすというオイル添加剤、燃料パイプに強力な磁石を取り付けガソリンの微粒子化によりパワーアップ&省燃費化するというもの、吸気管内に旋風機の羽根のようなものを取り付けて空気に旋回流を与えガソリンの気化を良くしパワーアップするというものなど、まあ、だめもとで一種の趣味で付けていたのですけれど、やはりというか、当然というか、効果の有ったものなど一つもありませんでした。そんなお手軽グッズで簡単にパワーアップしたり、燃費が良くなったりするのであれば、たとえ特許料を払ってでも自動車メーカーが採用すると思います。自動車メーカーは0.1km/L単位で燃費を良くし、他メーカーに勝つために研究費をたくさん使っているのですから。 燃費を良くする一番の方法は「乗り方」です。昔、エコノメーターという省燃費走行を促すメーターが付いていた車がありましたが、これは急激にアクセルを開けると針が赤印のゾーンを指し、「ガソリンたくさん使ってるよ~」と注意を促すものでした。このメーターが付いていなくても、要は急加速はできるだけしないでスムースな運転を心がければいいのです。あとは、トランクに不必要な物を積んだままにしないことですね。夏だと言うのにトランクの床下にタイヤチェーンが積みっぱなしになっている人もけっこういるのではないでしょうか。 いっそのこと狭い日本、自動車は一部の例外を除き、軽自動車にしてしまうというのはどうでしょう。軽自動車だって馬鹿にしたものじゃない、富士山の5合目までだって上れます。もう20年以上も前に実践しましたから間違いありません。むしろ、昔の軽自動車はブレーキが弱く、下りではブレーキが焼けて怖かったです。今では軽自動車もずいぶん立派になって、屋根付きのスクーターのような感覚だった昔と違い、普通車のスモールカーと大差なくなってきていますから、みんながみんな軽自動車に乗れば京都議定書のCO2削減目標にも近づけると思うのですが。
2006年05月17日
コメント(1)
-
旅の日
今日は、旅の日です。松尾芭蕉が「奥の細道」へ出発した日なのだとか。「奥の細道」は、芭蕉が弟子の河合曾良を連れ、江戸から東北・北陸地方を巡り大垣に至る、歌枕を巡る旅です。150日間、2400kmに及ぶ雄大なものでした。「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也。舟の上に生涯をうかべ、馬の口とらえて老いをむかふるものは、日々旅にして旅を栖とす。」で始まる序章は有名な名文です。芭蕉の、人生は旅と同じという無常観をよく表わした序章となっています。 芭蕉は忍者だったのではないかという噂があります。その理由は、「奥の細道」の旅にあると言います。 (1)奥の細道では46歳の芭蕉が一日50kmも歩いており、しかもそうとう足が速かった。 かなりの訓練を受けた人間でないとこれだけの歩行を150日間も続けることはできないと 思われる。 (2)この旅には現代の金額にして600万円ほどの費用がかかっており、当時の芭蕉にそれほど の財産はなかったことから、幕府の命を受けての秘密の任務を遂行していたとしたら、 費用は幕府持ちとなり、つじつまが合う。 (3)この旅のあと、弟子の曾良が、諸国の実情を調査する今で言う諜報機関のような役につ いており、曾良ももともと忍者であった可能性がある。ということだそうです。ほんとうだったら面白いですね。そのネタで小説の一つも書けそうです。芭蕉の足跡をたどって、各地にある句碑などを巡る旅は人気があります。自分もできることならやってみたいですが、2400kmを歩くのはちょっと気が遠くなるので、いくつかの自分の好きな句のゆかりの地だけでも巡ってみようかなと思っています。
2006年05月16日
コメント(2)
-

鍋
昨日に続いて調理器具ネタです。今日はお鍋の話を書きます。私の鍋に対するこだわりは、収納性です。着脱式ハンドルとスタック収納が出来るものを必死に探していた時期があります。クリステルもあるし、ティファールもあるし、別に探さなくてもいくらでもあると思う人がいると思いますが、それらは私のこだわりには対応できませんでした。なぜかと言えば、ハンドルにガタが有りすぎるのです。安心して使うためには着脱式であることを忘れてしまうくらいしっかりしていないとだめだと思います。そして今使っているのは、これです。これはけっして高級品ではないのですが、ハンドルにガタがなく、クリステルのような「耳」も出ていないのですっきりスタック収納できます。シールカバーもついており、冷蔵庫にそのまま入れられます。 それから、重宝しているのはアルコフラムのガラス製の片手鍋です。これですね。私の持っているのとは少し違いますが。これも取っ手が着脱式になっています。ガタはまったくありません。ガラス製なのでそのまま電子レンジに入れられますし、冷蔵庫へ入れるときも取っ手が邪魔になりません。でも、オール電化のマンションに引越してしまったので電子レンジ専用鍋になってしまいました。それでも便利なので捨てる気になりません。我が家のはもう20年くらい前に買ったもので、蓋は透明のガラス、本体はオレンジ色の透明ガラスです。今はこのタイプはもうないみたいです。 そのほかに、IHで使える親子鍋も持っています。テフロンコートなので滑りが良く、丼物が作りやすいです。これです。あと、日常的に一番良く使うのは珍しくも有りませんがレミパンですね。一応、写真を。22cmの小さい方で炒め物でも煮物でもなんでもできるので愛用しています。ただ、消耗品のテフロンコートの鍋にしては価格が高すぎるという人が多いみたいですね。 次はIH用の土鍋を買おうかと思っているのですが、IHクッキングヒーターが壊れるという噂も聞くので悩み中です。 調理器具は毎日使うものですから使いやすいものをいつも探し求めています。その他の調理器具やキッチン小物なども気が向いたら紹介します。また、何か優れものをご存知の方がいらっしゃいましたら、書き込みよろしくお願いします。
2006年05月15日
コメント(0)
-
フライパン
今、調理器具についていろいろと考えています。鍋は、今使っているのが、取っ手が外せて4つのサイズの鍋が入れ子に収納できるもので、無名のメーカーですがこれが安いわりに使いやすく気に入っています。問題はフライパンで、もっとも使用頻度の高い器具なのにこれといったものになかなか出会えません。まず、うちはIHなのでIH対応でなくてはなりません。手入れのしやすさから言ってノンスティックコーティングのものの方がいい。できれば消耗品でなく長持ちするものが欲しいのですが、なかなかないですね。お安く売られているテフロンコーティングのものは、半年かそこらですぐこびりつきやすくなってしまいますし、底が変形して膨らんでしまいます。今はリバーライトのセラートのフライパンを使っていますが、ノンスティック性は今ひとつですね。次は同じくリバーライトのナノセラかシラルガンのガラスセラミックコーティングを試してみたいのですが、どちらもなかなか高価です。どなたかIH対応で、こびりつかず、長持ちして、手入れが楽なフライパンをご存知の方はぜひ教えてください。
2006年05月14日
コメント(1)
-
もののけ姫
先日、「もののけ姫」がテレビで放送されました。画質からみるとこれもデジタルリマスターなんでしょうね。こうして名作がデジタル化されて永久的に近いかたちで保存されると安心です。昔の名作でフィルムの劣化や保管の不注意で失われてしまった作品は数多く、私のような記憶の片隅にかろうじて残している人がいなくなれば、忘却のかなたに消えてしまう作品はたくさんあります。「怪獣ブースカ」とか、「キャプテンウルトラ」とか数えれば枚挙にいとまがないところですがぜひとも大切に保存してもらいたいです。数年に一度の特番でしか出番がなかったとしても多額の費用をかけて製作された作品なのですから大事にしたいものです。 さて、もののけ姫ですが、私にはどうもテーマが伝わってきません。宮崎アニメは「ナウシカ」が未来を舞台としたSFである以外、ファンタジーの部類の作品が多いですね。なにか昭和40年代の国籍不明の少女漫画みたいな。最初から現実的でないことをお約束に始まっている物語のような気がします。「ラピュタ」も「紅の豚」も。「もののけ姫」は古代の日本が舞台なのですが、科学的な考察はなく、やはりファンタジーですね。 実は私は、「ナウシカ」のファンではあるのですが、宮崎アニメファンではありません。むしろ本来ハードボイルドな大人のアニメだった「ルパン三世」を子供受けするものに堕落させてしまった張本人だと思っているくらいです。でも、日本、というより世界で一番優れたアニメ作品を作りえる集団なのですから、ぜひとも手塚治虫の「火の鳥」を超えるような作品を作ってもらいたいと思っています。
2006年05月13日
コメント(0)
-
日本株の行方 2
昨日、日本株の先行きの不安について書いたのですが、日経平均株価は今日はさらに強烈な下落です。はたして復活できるのでしょうか。 株の良くないところは適正価格がないところです。理論的な適正価格は、過去いろいろな計算方法が考え出されてきましたが、結局、現在は古くから有るPERに落ち着いています。所詮参考程度の数値です。普通の商品であれば材料費や手間賃などからなる原価があり、利益や経費を乗せて売られます。原価以下で売れば損をしてしまうのでそれ以下になることは在庫整理など特別な事情を除けばまずありません。でも株は、配当金等を受け取る権利にしか過ぎず、株券も現在では実物が動くことはほとんどありません。原価というものがないのです。根拠のないうたかたのような価格ですから、人気が出ると株価は急騰し、売られると我も我もと売りに走り、株価は急激に下がり、時に暴落します。ほとんど公認ギャンブルのようになってしまっているのが現在の株式市場です。 本来、株は、投資をし、配当を受け取るためのものでした。大航海時代に航海に必要な資金を集めるために始まった株は、今では世界の経済活動のかなりの部分を占めていますが、本来の意味からはずれ、売買差益を追求するマネーゲームになってしまっているのです。 本当の経済というものは、シルクロード貿易がそうであったように、商品を作る人、運ぶ人、売る人、買う人など一連の人々が文化を形成しつつ作り上げていくものだと思いたいのですが、現在ではどろどろとしたマネーゲームを無視して経済の話は出来ないようです。もう少し経済の勉強は続けようと思いますが、どうも私には向いていないようです。
2006年05月12日
コメント(2)
-
日本株の行方
最近、少しは経済のことも勉強しようと思い、株式関連のテレビ番組をよく見ています。しかし、最近の日経平均株価は去年の勢いがありませんね。ライブドアショック以来じわじわと上がってはガクンと落ちるのを繰り返していて、もう日本株も終わりかなと思えるほどです。が、しかしテレビに出てくる証券会社の人たちは、みなさんまだまだ上がる、18,000円は狙える、20,000円はいけると景気のいい強気の発言ばかりです。 最近、これらの発言はほんとに信用できるのか疑問を感じるようになりました。なぜなら、証券会社はより多くの個人投資家に株の売買をやってもらった方が手数料収入が入り儲かるわけです。個人投資家、それも多くはインターネットで株取引が出来るようになってから参入した素人投資家は、専門家がああ言うのならとりあえず安定した会社の株を買っておけば儲かるだろうと考えても無理はありません。もしかすると証券会社の人たちは一連托生で、無知な素人投資家を株式投資の世界に引き込むために、日本株はまだまだ上がると口裏を合わせて言っているのではないかとさえ思えてしまうのです。証券会社は個人投資家が儲かろうが損しようが知ったことではありません。大切なのは多くの人に取引をしてもらって手数料を稼ぐことです。それが彼らの仕事です。はたして本当のところはどうなのか。年末までには答えが出るでしょう。楽しみに見守ることにします。
2006年05月11日
コメント(0)
-
コットン
今日は、510でコットンの日です。コットンつまり綿は人類が利用した繊維のなかでも最も古い部類にもので、5000年の歴史があると言われています。原産地はインドで、紀元前2500-1500年頃の遺跡であるモヘンジョダロから綿布が発見されています。古代インドの宗教書「リグ・ヴェーダ」にも綿の記載があり、紀元前から綿が利用されていたことがわかります。インドからヨーロッパへはシルクロードを経てアラビア商人が伝えたともアレキサンダー大王の遠征で持ち帰られたとも言われています。現在でも例えば日本では全衣料品の約40%くらいはコットンが占めているそうです。 麻と並んで植物繊維の代表格である綿は、3大天然繊維(綿、絹、羊毛)の一つでもあります。綿はコットン、麻はリネン、絹はシルク、羊毛はウール。カタカナにするとどれも慣れ親しんだ繊維ですね。しかし木綿と言ったときはそれはコットンの繊維のワタ、あるいはコットンの繊維で織った布のことですが真綿と言ったときはシルクの繊維で作ったワタのことを指します。これ、意外に思う方が多いのではないでしょうか。 綿は、アオイ科ワタ族に属する植物で、有用な繊維は綿花ともコットンボールとも言われる花の部分にあります。通常、植物の繊維は茎や皮の部分を割いたり、潰したりして得ますが、綿の場合は大変利用しやすい形で収穫できるので古代から利用されてきたのでしょう。コットンの繊維は一本一本が4層構造になっており、さらに中央部にはマカロニのような中空層があります。そして繊維が最初から天然の撚りが入っていて絡み合っています。このため内部に空気を貯えていて、吸湿性と断熱性に優れ、冬暖かく夏涼しい性質を持っています。いいことづくめのようなコットンですが、近年ではネガティブな面も指摘されています。 綿は害虫に弱いため、大量の農薬を使用します。さらに、収穫する際には葉や茎の汁が付くと台無しになるため、枯葉剤を使って枯らしてから収穫します。古代の人が細々と栽培していたのと違い、効率を求めるとコットンも農薬漬けの農作物になってしまうのです。しかし、今ではオーガニックコットンと呼ばれる、無農薬有機栽培の綿花を、繊維に加工する工程にまで細心の注意を払って作ったコットンが作られるようになりました。価格は一般のコットンの2倍くらいはするらしいですが、充分にその価値はありそうですね。
2006年05月10日
コメント(0)
-
駐車場問題
道路交通法の改正で駐車違反の取締りが民間に委託され、厳しくなります。違法駐車をなくそうという考えはとても良いことなのですが、運送業者の荷物の積み下ろしなども違法とされてしまうものも多く、業者は頭を抱えています。本来は取り締まりの強化と駐車場の増設をSETで行うべきなのですが、政府は、取り締まりは行うが駐車場の整備は民間でやれということのようです。もっともどんなに駐車場を増やしても追従するように都市部へ侵入してくる車の台数は増えるでしょうからきりがないでしょうね。やはり都市部への車の乗り入れを抑えるしかないのではないでしょうか。日本は土地が狭いのでアメリカのようなモータリゼーションをまねしようとしても無理があります。車の台数を減らす、出来るだけコンパクトなシティコミューターを開発、普及させるなどアメリカよりはヨーロッパ的な方向性で努力するほうが可能性があるように思います。あとは在宅勤務を一般化させ、通勤で膨れ上がっている昼間の都市の人口を減らせばエネルギーの節約にもなり一石二鳥ではないでしょうか。 私はもう怖くて路上駐車はできません。違法ではない路上駐車の法律上はあるのですが、幅員が6m以上の道路で交差点から何m離れていなければいけないとかややこしいので実質的にどこが合法的に路上駐車できる場所なのか解りません。もうこれからは大きな駐車場のある郊外のホームセンターやスーパーマーケットにしか行かないことにします。免許の点数も反則金もまっぴらごめんですからね。いっそのこと車はもう乗らないというのも一つの方法です。前から思っているのですが、買い物などに車を使うときはいつも一人で乗っています。もったいないですね。ピザやさんのバイクみたいに屋根付きで雨が振っても濡れないスクーターがもしあれば積極的にそれを使うと思います。簡単に作れそうだけどないんですよね。やはり安全性などが難しいのでしょうか。ぜひ、各オートバイメーカーに開発してほしいと思います。
2006年05月09日
コメント(0)
-
自動車税
自動車税の通知書が届きました。なんでも新車登録から13年以上たっている車は税金が10%増額されるのだそうで、古い車を大切に乗っている人がなぜこんな目に合わなければならないのか疑問です。古い車は新しい車に比べると排ガスが環境に優しくないということらしいのですが、それなら単純にCO、CO2、NOXといった有害ガスの濃度でなく絶対量で課税するべきだと思います。排気量4000ccとか6000ccとかの外国製高級スポーツカーなどは明らかに過剰なエンジンを搭載しています。小さなエンジンの車でガソリンもできるだけ節約して、もう14年近くも大切に丁寧に乗ってきたのに、そんな古い車に乗りたいのなら環境税を加算しますと言われてしまう。片や湯水のようにガソリンをがぶ飲みし、制限速度100km/hの国で300km/hも出せる不必要に巨大なエンジンを積んだ車はお咎めなし。なんか納得いきません。 そりゃあ古い車には効率の悪い面もあるでしょう。私の車は1600ccですが、現代の車で言えば1400とか1300ccクラスくらいの性能でしかないですが、ガソリンは排気量なりに食いますので効率は確かに悪いです。しかし、今後恒久的に、13年経ったら新車に買い換えるという義務を国民に負わせるつもりなのでしょうか。車1台を作るために必要な資源やエネルギーを考えると、どう考えても古いものでも使えるうちは大切に使い続けるほうが環境にはやさしいと思います。むしろ、古い車を大切に乗っている人は減税されてもおかしくないくらいだと思うのですが。 街中で時々古い車をきれいに磨いて乗っているひとを見かけます。スバル360や初代のセリカや愛のスカイラインなど。とても素敵なことだと思います。部品もよほど努力しないと手に入らないでしょうに、よく維持されていると思います。並々ならぬ情熱の賜物です。 家電製品のPSE法もそうでしたが、政府は何か大きな勘違いをしています。大切に使えば軽く20年は使える車を、13年で間接的に強制廃棄させるような法律を平気で作ってしまう恐るべきコモンセンスが日本の政治家や官僚にまともな政治ができそうにない証拠になると思います。環境を考えるなら、もう一度冷静に本当にやるべきことは何なのか考え直していただきたいものです。
2006年05月08日
コメント(0)
-
海猿
昨夜、「海猿」がテレビ放送されました。録画はしたのですが、実は忙しくてまだみていないのですが(^_^;)。単なるラブロマンスでなく、命や使命といった骨太のテーマを持っていますから面白くないはずがありません。さらに、最新劇場版の「海猿 Limit of Love」はさらなる盛り上がりが予想され、涙腺の弱い人は要注意の予感。せこい私はレンタルが出てから鑑賞することにしましょう。 しかし、5月5日から6日にかけての加藤あいのマスコミ露出率ときたらすごかったですね。一日中どこかのチャンネルで出ていました。多分宣伝のためと割り切って、出演料は映画制作社持ちくらいの勢いであらゆる番組に片っ端からオファーをとるような状態なのでしょうが、加藤あい本人は大変ですね。最近メディア作品の寿命が短くなってきていて短期間に売れるだけ売りまくり、すぐに次の作品へと移行していくみたいな流れが多くなってきたように思います。新しい作品が次々と出てくる事事態はいい事なのですが、もう少しじっくりと時間をかけて売り出ししてもいいような気がします。ちょっとあまりにも矢継ぎ早すぎてついていけないいんです、最近。しかし、リバイバルに飽きた最近まれにみる大型作品、期待大ですね。
2006年05月07日
コメント(2)
-
水資源の枯渇
この日記では過去何回か書いているのですが、水資源の枯渇は加速するばかりで勢いの留まることを知りません。水の惑星と言われる地球にあって、その水の97.5%は海水など直接飲用や農業用には使えない水です。人類が生活用に使える淡水は僅か2.5%で、さらに河川や湖沼など比較的利用しやすい水は0.01%ほどでしかないのです。これは、例えば地球全体の水が20リットルのポリタンク1杯分だとすれば、人類が容易に使える淡水は2cc、小さじ半分以下になってしまいます。国連でも事の重大性に気付き、「水無くして未来なし」と危機を訴えています。水の枯渇は飲み水の心配だけに留まらず、農作物の栽培も出来なくなり、食糧危機へと直結しています。工業製品も水無しでは生産効率が極端に落ちるものが多く、人類のありとあらゆる活動が水に依存しているといっても過言ではありません。豊富にある海水を安価に淡水化できる技術が切望されていますが、それが実現されればおそらく人類は、今度は海が干からびるまで海水を汲み上げてしまうのでしょうね。 日本は水が豊かな国と言われ、局所的に渇水が起こる事も最近はありますが、世界的には恵まれていると言っていいでしょう。それゆえに水資源については危機感が薄い面がありますが、本当は地球レベルで水資源が枯渇したときに一番困るのはおそらく日本です。日本は食料の大部分を輸入に頼っています。農作物であれ、食肉であれ、収穫するまでには大量の水が使われています。例えば牛丼一人前作るために必要な水は2000リットル、ハンバーガー1個で1000リットル、白いご飯お茶碗一杯でも800リットルとなります。日本人の主食である米が、小麦などに比べて栽培に大量の水を必要とするところも痛いところです。 今、地球全体の人口は64億人くらいです。有識者の予測ではこのままいくと2050年には40億人が水不足に苦しむことになると試算しています。つまり3分の2の人類が飢えと乾きにさいなまれ存続の危機を迎えるというのです。実に恐ろしいことです。世紀末は大地震でも核戦争でもロボットの氾濫でもなく、水資源の枯渇によって訪れるということになりかねません。水の惑星が水の枯渇で滅びるのも一種運命的なものを感じてしまいますね。 日本は海水淡水化のほか、水の再処理・リサイクルの面でも世界のTOPを走っています。この技術が地球を救うことが果たしてできるのか。今後に期待したいところです。
2006年05月06日
コメント(0)
-
鯉のぼり
今日は、こどもの日、端午の節句ですね。端午の節句には兜や五月人形、ちまきや柏餅、菖蒲湯など話題に載せるアイテムは豊富ですが、今日は鯉のぼりについて書いてみたいと思います。 鯉のぼりの由来は中国の故事からきていると言われています。古代中国の霊山に「登竜門」という滝があり、そこを登りきった鯉は龍になって天に昇るというものです。「登竜門」という言葉は日本でも慣用句として使われていますね。龍に変身して天に昇ることをたくましい生命力と出世になぞらえて、こどもたちが元気に育ち、りっぱな人になるよう願いを込めているのです。鯉のぼりのポールの一番上でカラカラと回っているものは矢車といって魔除けの意味があります。その下の吹流しは古代中国の「五行説」、万物は、木・火・土・金・水の五つの要素で形成されているとする考え方に由来して五色に彩られています。魔除けの意味があると同時に、家のシンボル、旗印の意味を持っています。昔は家に鯉のぼり用のポールが立っているのはわりと普通のことでしたが、昨今の住宅事情ではなかなか難しいですね。 鯉のぼりの歌で「いらかの波と雲の波~♪」というのがありますが、けっこう「田舎の波と雲の波~♪」と思っている人が多いみたいです。正しくは「いらか」とは瓦のことですよね。家々の屋根瓦を波に見立てているのですね。蛇足ですけれど「いらかの波」というと昔、少女漫画で同名の作品がありました。これを読んでいた人は「いらかの波」の意味は良く解っているはずです。今でも古本屋などで入手可能ですかね?大人買いしてもう一度一機に読んでみたい作品です。
2006年05月05日
コメント(0)
-
ラムネ
今日は、ラムネの日です。1872年(明治5年)、東京の実業家・千葉勝五郎が、ラムネの製造販売の許可を取得したそうです。中国のレモン水を参考に考案したとされています。 ラムネはある年代以上の方にとっては思い入れの深い飲み物ではないでしょうか。昔はお祭りの縁日以外でも駄菓子屋などで売られていて、冷たく冷えたラムネは子供たちの定番のご馳走でした。ビー球で栓をするという他に類を見ないパッケージはいまでも健在です。というか、あれを止めたらもうラムネじゃないですよね。昔は瓶の口部分を整形する前にビー球を入れてから口の部分のガラスを加熱して形造り、中身を充填するときはシロップと炭酸ガスを瞬時に吹き込んで、さかさまにしてビー球が口の穴を塞ぐようにしていたそうです。子供のころはどうやってこのビー球を瓶の中に入れたのか悩んだこともあります。サイダーなどの場合だとあらかじめシロップと炭酸をよく混ぜて瓶に充填し、王冠で栓をするという作り方です。圧力はあまりかからない充填方法です。ラムネの瓶の独特のスタイルは中身のジュースの、他にはない製法あればこその形なのです。今では瓶の口部分だけプラスチックで別に作って瓶本体と合体させるように変っていますね。昔ながらのラムネは、今冷静に考えてみれば甘くてシュワシュワでレモンの香りがほんのりと付いた砂糖水だったと思います。が、あのパシュと栓を抜くときの快感や夏の暑い日に遊び疲れての一休みのときに喉に来る清涼感はかけがえのない贅沢な飲み物でした。果汁なんか一滴も入っていない有る意味ジャンクフードなわけですがいまだに消えてなくならないのは、やはりファンが多いんでしょうね。 ちなみにラムネはレモネード、サイダーはシードル(リンゴ酒)が語源だそうです。現在では中身の違いは余り無く、ビー球で栓をされたものがラムネ、王冠で栓をされたものがサイダー等と区別されているそうです。 ラムネは今でも存続をかけた厳しい戦いのさなかにあるそうで、個人的にはシンプルで風情のあるラムネにはぜひ生き残ってほしいと考えています。
2006年05月04日
コメント(4)
-
ゴミ
今日は5・3でゴミの日です。ゴールデンウィーク中にこんな暗い話題もどうかとは思いますが、お付き合い願いたいと思います。 各自治体によって多少の差はあれゴミ問題に苦しんでいない所はないと思います。もともと物理的に無理があるのです。処分に困るゴミの多くは石油から作られるプラスチック類です。今ではダイオキシンが発生しない焼却技術のおかげで燃やすことができるようになりましたが、それでも石油由来の燃えカスがゼロになるわけではありません。これらはもともとは地中深くで眠っていた物で、それをさらに化学的に安定な物質に加工していますから、自然界のサイクルから外れてしまっているものなのです。木製の物や金属の物を中心に使っていた時代では、物は遅かれ早かれ土に還り、次の再生の時を待つ事になります。際限なく供給される石油由来のリサイクル不可能な工業製品は、最終的には埋め立て処分するしかなく、埋め立てる土地がなくなるのは時間の問題なのです。なんとかして石油由来の製品を土に返す方法を考えないと、人類はそう遠くない未来にゴミの山のなかで命運尽きる事になりかねません。プラスチックを石油に戻す方法も開発されてはいるようですがエネルギー収支からみてとても有効とは言いかねるのが現状のようです。唯一生分解性プラスチックというものが自然に還る製品として期待されていますが、価格や耐久性の面で普及は今一つです。 こうしたゴミの究極的処分方法として、地中深くのマグマの中に捨てて強力な熱と圧力で原子レベルまで分解してしまうという方法もアイデアとしてはあるようです。しかし、地球の内部にまで手を出してそれこそ致命的な副作用があるかもしれないので実際にはそんなことはできないでしょう。やはり土に還らない物、リサイクルできないものは最初から使わないのが最良の策ではないでしょうか。元に戻せないことはやらない、生活の中で大切なものを守るときに基本の考え方です。現代においては、巨大なビルを建てるときでも、取り壊すときの事などはまったく考えていません。上屋は壊せても地中数十メートルまで打ち込まれた鉄筋コンクリートの杭を取り除くのは事実上不可能なのです。 今後は商品の製造にしろ、建物の建設にしろ、役目を終えた時にどうやって自然に還すのか関係官庁がチェックし、承認を得た上でなければ出来ないようにするのが当たり前だと思います。じわじわと破滅へ追い込まれている現状を国や地方自治体がどう考えているのか、経済学者やコラムニストなど社会的影響力がある人たちにぜひ問い正していただきたいものです。
2006年05月03日
コメント(0)
-
鉛筆
今日は、鉛筆記念日です。1886年、眞崎仁六という人が、東京の新宿(現在の新宿区内籐町)に眞崎鉛筆製造所という工場を創立した日なのだそうです。これが後に三菱鉛筆となります。鉛筆が普及するまでは日本では筆やロウ石を細く削った石筆が使われていました。ちなみに三菱鉛筆は旧財閥系の三菱グループとは何のかかわりもないそうです。 鉛筆は最近あまり見かけなくなりましたが、昔は小学生などはみんな鉛筆を使っていました。私の子供のころはシャープペンシルというのもまだなくて、一部の裕福な子は、芯ホルダーと製図用具を使っていました(ペン型の軸の中に太さ2mmくらいの芯を入れて、軸の先端にある開閉式の爪で芯を固定し、芯を削って尖らせて使う)。押し出し式のロケット鉛筆というのもありましたね。 鉛筆の芯の硬さの表示であるBやHですが、なぜこの文字が使われているかご存知ですか。「B」はブラック(Black)、「H」はハード(Hard)のかしら文字、「F」はファーム(Firm)のかしら文字で「ひきしまった」を意味しているそうです。「F」は「B]と「H」の中間の硬さということなのですが、じゃあ「HB」はどうなるんだとだれもが思いますよね。「HB」は「F」よりも柔らかいのだそうです。さらに、「H」は「9H」まで、「B」は「6B」までありますので、全部で17種類の硬さがあるということになります。つまり、硬い順に「9H」「8H」…「2H]「H」「F」「HB」「B」「2B」…「5B」「6B」ということですね。 鉛筆になぜ「鉛」の文字が使われているかと言うと、古代ギリシャやローマで細く形作った鉛の棒を筆記具にしていたことからきているそうです。一説によれば徳川家康や伊達政宗も外国から入ってきた鉛筆を使っていたのだとか。 最近ちょっと影の薄い鉛筆ですが、個人的には、カチッとしたシャープペンより3Bくらいの濃く柔らかい鉛筆でアイデアをメモしたり図を書いたりするのが好きです。気のせいでしょうがその方が柔軟な発想ができるように思います。プラスチックでなく木でできているのもいいですね。あまり売れないと鉛筆が絶滅してしまいそうで心配です。
2006年05月02日
コメント(2)
-
焚き火と料理
今日は、5月最初の日だと言うのに、まさに夏日で汗ばむような陽気でした。ゴールデンウイーク中ということもあり、多くの方が行楽に行かれているのでしょうね。お金も暇も無い私は、今日もパソコンと向き合って僅かな余暇を過ごしています。 行楽シーズンとなると私はキャンプに行きたくなります。日常を離れ、自然の中で束の間の時間を過ごすのは楽しいものです。一時期禁止されているところが多かった焚き火も、最近はできるキャンプ場が増えているようでうれしいことです。なぜなら私は焚き火が子供の頃からとても好きなのです。ゆらゆらと揺れる炎や木の焦げる臭い、目や鼻を刺激する煙、赤熱した炭からでる赤外線のエネルギー。たぶん、原始人が感じた炎に対する畏敬の念のDNAを引き継いでいるのだと勝手に解釈しています。太古の昔、炎という恐るべきものを自らの支配下に置くことに成功し、厳しい生存競争の中、圧倒的な力をつけ始めた私たちの祖先の希望が焚き火の炎の中にあったと思うのです。 焚き火を使って調理したキャンプ料理は、理屈でなく本能に語りかけてくる美味しさです。牛ばら肉の塊焼き、豚のスペアリブ、ジャガイモの丸焼き、焼きトウモロコシなど。個人的には合挽き肉と香辛料たっぷりで作ったシシカバブーや、意外なところで揚げシューマイなんていうのがお勧めですね。残念ながら今年はキャンプには行けないと思いますが、読者の皆さんで自慢のキャンプ料理などありましたらコメントにでも書き込んで教えてくださいね。よろしくお願いします。
2006年05月01日
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1