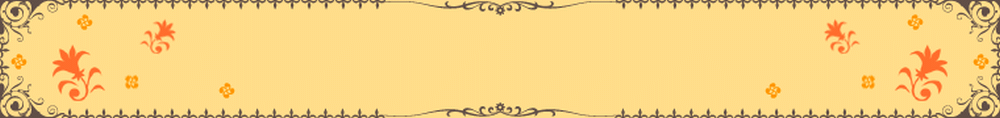全623件 (623件中 1-50件目)
-
六月も終わりました。六月にその後見た映画(続々々)。
6月も終りました。見放題になった桜坂劇場の6月のプログラムは全29本すべて制覇。その後見た映画です。評価はB:優、C:良、D:不可。Aは特別良かった作品にのみ例外的に付けた。 『ひぐらしのなく頃に 誓』:思わぬ儲けもの。(C) 『パイナップルツアーズ』:真喜屋力、中江裕司、當間早によるオムニバス沖縄映画。(ちなみに真喜屋氏は現在桜坂劇場のプログラムディレクター。)(C) 『バオバブの記憶』:明確な主張をしないこの手のドキュメンタリーは苦手。(D) 『クレアの純真』:凡作だがフランス映画はやはり好き。(B) 『REPO!』:これも思わぬ儲けもの。軽く楽しめた。(C) 『西の魔女が死んだ』:良い作品だが、やや思想不足。(C) 『長江に生きる』:ドキュメンタリー。三峡ダム建設のために国は貧農に不利な移住を強制する。大地に根ざして生き、ただ自分や家族(体の弱い夫)の生活を守るために抵抗し続ける主人公の女性ビンアイの姿が感動的。(A) 『美しい妹』:1997年クラウジック監督『プレイバック』(レビュー2007.3.17)の姉妹編のような作品。マリオン・コティヤールが二役。若い娘の魂の彷徨の物語。精神的土壌がフランス的で、佳作だが日本で劇場未公開なのもうなずける。(B) 『TOKYO JOE』:マフィアに裏切られた故にFBIに協力しシカゴマフィアを壊滅させた日系人・衛藤健の伝記ドキュメンタリー。(B) 『愛の嵐』:名作だが二度目を見る気はずっとなかったが、劇場にかかったので見にいった。(B) 『ソフィー・マルソーの愛人』:フランス映画に時々ある男2人と女1人の物語。(C) 『死刑執行人もまた死す』:ナチに抵抗したプラハ市民を題材にした秀作。フリッツ・ラング監督1943年作品。(A) 『ぐるりのこと。』:140分は冗漫。一見名作と騙されるが、少し時間がたって思い起こすと内容は浅い。(C) 『百万円と苦虫女』:蒼井優は好演だが、脚本と描き方に問題あり。(B) 『縛師』:緊縛SMが題材のドキュメンタリー。構成が極弱。(C) 『青い鳥』:意外と名作。中学校のイジメが題材だが、大人の世界も同じ。(B) 『川は流れる』:悪人の出てこないハッピーエンド作品。古い沖縄の風景も興味深い。(B) 『神々の深き欲望』:これも二度は見ないと思っていた名作。(A)
2009.07.08
コメント(178)
-
六月、その後見た映画(続々)
6月、その後見た映画(続々)。評価はB:優、C:良、D:不可。Aは特別良かった作品にのみ例外的に付けた。 ひめゆりの塔(1953今井正) 鉄男 雨が舞う 金爪石残照 ルートヴィヒ 受取人不明 悪い男 エクステ イノセント カミュなんて知らない イノセント 『ひめゆりの塔』:史実の悲劇はもっと悲惨であったという非難もあるが、終戦後8年のまだ知られざることが多かったであろう時期に、本土の日本人にひめゆり学徒のことを知らしめた意義は大きい。(B) 『鉄男』:塚本晋也作品。好きとは言えなが見て大変面白かった。(B) 『雨が舞う 金爪石残照』:敗戦まで日本企業が台湾で経営していた金山のドキュメンタリー。タイトルの残照という語が示しているように、ノスタルジックなだけで明確な主張を欠く。(C) 『ルートヴィヒ』:相当昔に3時間版を見て、何か総集編を見ているようでインパクトが薄かったが、この4時間版は別作品であるかのごとく良かった。(B) 『受取人不明』:キム・ギドク監督作品。1970年頃米軍基地が近くにある韓国の農村。帰国した黒人米兵を待ち、受取人不明で戻ってくる手紙を出し続ける女、その混血の子の青年、子供の頃の事故で片目の少女、二十年前の朝鮮戦争で夫を失ったその母、故国から離れての駐留に耐えられない若い米兵、その他互いに関係し合う人々の群像劇。単に批判ではなく、戦争や米軍の駐留が貧しい韓国農村に落とす影を描く秀作。(B) 『悪い男』:キム・ギドク監督作品。普通の女子大生がヤクザに惚れられ、はめられ、娼婦に身を堕としていく。出発点は彼女が男に示した蔑みの眼差し。二人の一種の純愛。(B) 『エクステ』:園子温監督のホラー作品。ホラーと言ってもコミカルでもある。毛髪の不思議さ、他人の毛髪をエクステンションとして身につけることの不気味さが発想の原点か?。ここでも親による子供の虐待がテーマの一つ。(B) 『イノセント』:ヴィスコンティ作品。ボクの特別に好きな映画作品50選に入る。ビデオは持っているが、今回劇場で2日間連続で見た。ラウラ・アントネッリが魅力的過ぎる!。(A) 『カミュなんて知らない』:高校生による無動機殺人を大学生が映画にする。準備・稽古・クランクイン。どれが現実か映画か曖昧になる。映画とは映画内のことだけがリアリティーを持つ。ゴダール的。(B)
2009.06.23
コメント(5)
-
嬉しい苦しみ(?!)
桜坂劇場の新しい会報7月号(6/27~7/31)を昨日入手。既にDVD等で見ている作品が何本もあるが、上映されるなら是非見ておきたいのが、 神々の深き欲望 アラキメンタリ メイプルソープとコレクター シリアの花嫁 子供の情景 四川のうた 沈黙を破る 懺悔 惑星ソラリス フィッツカラルド 死刑執行人もまた死す 恐怖省 の12本。沖縄関連作品として見ておきたいのが、 真夏の夜の夢 川は流れる カメジロー 沖縄の青春 えんどうの花 網走番外地 南国の対決 沖縄やくざ戦争 沖縄10年戦争 の7本。それ以外で関心のあるのが、 ぐるりのこと。 百万円と苦虫女 縛師 サスペリア*テルザ最後の魔女 青い鳥 食客 の7本。しかしこれら26本すべてをこなそうとすると、また昨年見て良かった『ONCE ダブリンの街角で』ももう一度見ようとすると、6/28(日)には、 10:20『青い鳥』 13:40『ぐるりのこと。』 16:40『ONCE ダブリンの街角で』 18:40『百万円と苦虫女』 21:20『縛師』 の5本連チャンの時間割。かつては名画座で3本立てというのもたまに見たし、パリに旅すると貪欲に1日3~4館をはしごしたこともあるが、理想は1日1本、せめても時間をあけて1日2本だ。 しかも今回は長い作品が多い。『神々の深き欲望』175分、『ぐるりのこと。』140分、『サスペリア*テルザ』175分、『沈黙を破る』130分、『懺悔』153分、『ソラリス』165分、『フィッツカラルド』157分等々…。 映画を見るのが楽しみなのか義務なのか解らなくなってきた。恐るべし、見放題システム!。
2009.06.20
コメント(3)
-
『ラブホテル』相米慎二監督(1985日活ロマンポルノ)- 続き -
ラブホテル その2 (つづき) 2年後、自殺を思いとどまった村木はタクシーの運転手をしていた。早朝勤務あけの村木がアパートに向かうと途中の公園で良子が待っていた。ヤクザの借金の取り立てが及ばないように彼女とは離婚し、別々に暮らしていた。朝からヤクザが来ることはないと、こうして彼女は朝会いに来るのだ。彼女が持ってきた弁当をたべ、彼女に促されて村木は良子を抱いた。 ある夜タクシーでの仕事中、村木は2年前のホテトルの女・名美を街で見かけ、後をつけた。そしてとあるマンションから出てきた名美を自分のタクシーに乗せることに成功する。あてどもないといった彼女は海に行くことを求めた。 名美は勤務するアパレル会社の既婚の上司・太田(益富信孝)の愛人だったが、太田は名美をお荷物に感じ始めていた。ある日会社に太田の妻が怒鳴りこんできて名美をなじり、名美は会社までクビになってしまう。彼女は家から太田に電話をするが、直ぐに切られてしまう。それでも彼女は思いねたけを延々と受話器に向かって話して続ける。これはジャン・コクトーの一人芝居『人間の声』がネタ元だろう。ボクはプーランクが作曲したモノローグオペラで知っているのだが、これも自分を捨てた愛人に、女が夜自分の部屋から電話で話す一人劇だ。 そんな名美が村木に求めたのは、2年前のラブホテルの続きだった。同じホテルの同じ部屋で二人は2年前を再現する。名美は同じ服装で現れる。ロマン「ポルノ」ではあるが、二人の行為は描かれない。ただことを終え、あるいはことの最中から、既に醒めていた。寝ている名美を置いて部屋を去って行く。2年前は、正に死に物狂いだったから村木は名美を抱くことに深く「生」を燃焼させた。だからこそ名美も燃えた。しかし今の村木にはそんな深い情念の発散はなかった。元妻や名美に謂わば付きまとわれ、求められても、そうした女の生命力には負けていた。名美の生命力に救われ生に踏み留まったけれど、また2年後その名美を街で見かけたときは「生」の情念に憧れた。しかし平時の彼にはそういう生きる情熱はなかった。名美が手料理の材料を持ってアパートを訪れると、村木は既に越していた。帰り道名美は村木の部屋に向かう良子とすれ違う。 村木と2人の女との物語だけれど、生きる情熱を欠いた村木の無気力は、真に生を燃焼させることのできない現代社会の人間のメタファーでもあるだろう。
2009.06.19
コメント(3)
-
『ラブホテル』相米慎二監督(1985日活ロマンポルノ)
ラブホテル (日活ロマンポルノ) 相米慎二監督 83min (桜坂劇場 ホールCにて) 「桜坂ロマン座セレクション」と題された桜坂劇場の日活ロマンポルノ特集、今回の4本のうち、先日の『ラスト・キャバレー』に続き2本目に見た。残り2本『蕾の眺め』(田中昇1986)と『天使のはらわた / 赤い眩暈』(石井隆1988)はパスするつもり。余談だが、この「赤い眩暈」の眩暈を「めまい」と読める人は今どれくらいいるのだろう。めまいは普通は目眩で、それでも読めない人も少なからずいそうだが、ボクも「めまいで良いんだよな~?」と辞書で調べてしまった。こういう難しい漢字を使うのも一つの作為だが、ポルノの題名の文化レベルも高かったものだ。 ところで『ラブホテル』の監督は『セーラー服と機関銃』の相米慎二。『セーラー服』が1981年の作だから、1985年にこの作品の監督は既に名をなしていた。低迷していたロマンポルノにてこ入れする意図もあったようだ。この作品を相米監督のベストとする人もいる。投票者数は少ないが IMDb での得点も 7.8 と高い。冒頭の組事務所でのレイプシーンの描写を除けば、その後もセックスシーンはあるものの、描こうとする人間ドラマに不可欠なシーンばかりであり、また自然な描写で、21世紀の今現在の目で見ればポルノ的要素は希薄だ。 村木(寺田農)は小さな出版社を経営していたが倒産した。3千万の借金取り立てのヤクザに妻・良子(志水季里子)は犯され、絶望した村木は死のうと思う。とあるラブホテルの301号室。村木は、あれは何と言うフーゾクだろう、ホテトルと言うのかな?、要するに売春婦を電話で呼ぶ。やって来たのは名美(速水典子)という女だった。 村木はいきなり女に手錠をかけるとナイフで脅し、今日死ぬ自分はお前を道連れにすると言い、女は恐れおののいているが、気弱で善良そうな村木の自殺前の最後の悪態であり、死ぬ前に(あるいは死ぬために)これまで抑制するだけで実践出来なかった欲求の爆発を無理にしようとしていることが観客にはわかる。 どれだけ時間がたち、二人の間にどんなことがあったかはわからない。股間にピンクローターを入れられた名美が一人身をのけぞらせしてイキまくり、喘いでいるのを村木は呆気にとられたように見つめていた。 (つづく)
2009.06.19
コメント(0)
-
『聴かれた女』山本政志監督(2006日本)-つづき-
聴かれた女 その2 (つづき) だからこそサツキの恋人のような普通の女には迷惑なヘンタイもいるわけだし、またサツキの会社の同僚のような問答無用に一方的に迫ってしまう男もいる。しかし建設的で、大切なのは、そういう男女の性差を互いに理解して付き合うこと。 その意味ではサツキは賢かった。リョウの盗聴を知り、恐らくは彼の色々な策略があったことも知りながらリョウを受け入れる。そして一度は彼に拒絶されながらも、再び彼との関係を構築していこうとする。「さあ、始めましょう。」という最後のセリフは、「セックスを始めましょう」というのではなく、「二人の関係を築いていきましょう」と解するべきだろう。 実写劇映画の大きな面白さが、役者の演技性、素の本人のむきだし性にあるということを何度かボクは書いている。それを映画監督のジャン・ユスターシュは「自分の映画は、自分の役者たちのドキュメンタリーだ」と表現した。蒼井そらのA・V女優としての作品は知らない。しかしポルノ映画ではなくA・Vでは、女優は絡みのシーンで単に演技としてアエギ声をあげるだけとは限らない。実際にピンクローターで執拗に局部を攻められ、場合によっては実際に感じ、イッたりもする。その辺の真偽は微妙だけれど、少なくも男優は実際にシャセイする。もし女優が実際にも感じて声をあげているとしたら、演技と実際の混交だ。A・Vというのはそういう世界だ。そういうA・V界の女優であるためか、カラミ以外のシーンでの蒼井そらは、普通の映画女優に比べて、素の彼女をさらけ出している。その非演技性がとても面白かった。 レンタルしたDVDには『聴かれた女の見られた夜』という姉妹作も特典映像として入っていた。本編が盗聴するリョウの視点から描かれているのに対して、この姉妹編はサツキの視点で撮られた別テイクだ。これは面白い試みではあるが、実際には不要であり、退屈した。映画というのはその両者を統合して仕上げるべきであり、1本で両方の観方を可能にするべきだ。そしてこの『聴かれた女』本編は十分にそれに達していた。イマジネーションの乏しい人のための蛇足テイクに感じらる。
2009.06.16
コメント(0)
-
『聴かれた女』山本政志監督(2006日本)
聴かれた女 山本政志監督 MAN, WOMAN AND THE WALL Masashi Yamamoto 84min (レンタルDVD) 一昨年7月に桜坂劇場で取り上げられたが、その時はまだ定休日なしで店をやっていたので、夜のみ上映だったこの作品は見逃した。今回レンタルを見つけたので早速借りて鑑賞。余談だけれど、先日見た『愛のむきだし』は237分でほぼ4時間。そういう作品と比べて84分なんてものは、劇場でも家でも気軽に見始める決心がつきます。 弱小雑誌の記者リョウは一人暮らし。あるマンションの一室に引っ越してきた。壁が薄く隣室の音が聞こえることに気づく。隣は一人暮らしの若い女だ。リョウは壁にコンクリートマイクを設置。女(サツキ)がシャワーを浴びる音や、恋人との愛の営みの音(声)を聞き、妄想にふける。いつしかリョウはサツキに恋するようになり、偶然を装って出会い、彼女に好感を持たれるようになる。 そうしてリアルに付き合い始めてももちろん彼は盗聴を続け、隣室の音を聞きながらジイ行為に耽る。こんなリョウをヘンタイと呼ぶ人もあろう。しかしコンクリートマイクを使うとか、親からと装った宅配便を小道具に使うとか、そこまで実際にするかしないかの差こそあれ、男の性や愛はこういうものだ。 上手く彼女の恋人を排除することにリョウは成功する。その際に取った手段は強引でややいかがわしくもあるが、その恋人というのは声を変えて脅迫エロ電話をして隠しカメラで彼女の映像を見ながら興奮してマス行為をするという本当のヘンタイ、と言うか彼女も迷惑しているのだから許されるよう。サツキはリョウに身を委ねようとするが、彼は戸惑いを感じ実現しない。しかしまた盗聴をしながらジイにふける。サツキはシャワーを出すと足音をたてないようにリョウの部屋に忍び込みマス中の彼の不意を襲った。二人は見つめ合い、サツキは言った。「さあ、始めましょう。」 この映画は男と女の性や愛の違いの本質を良く描いている。女が実際にそばに居てくれる相手を、直接に感じることを求めるのに対して、男はあくまで頭、イマジネーションの世界に生きる。肉体的交渉でも直接感じるよりも相手の女が感じていることを見て興奮する。その相手の女に自己を同化させているとも言える。だから盗聴によるイマジネーションではない現実のサツキには違和感、物足りなさを感じてしまった。 (つづく)
2009.06.16
コメント(0)
-
六月、その後見た映画(続)
6月、その後見た映画(続)。評価はB:優、C:良、D:不可。Aは特別良かった作品にのみ例外的に付けた。 デメキング PLASTIC CITY ダンサー・イン・ザ・ダーク いとしい人 ゼラチンシルバーLOVE 佐賀のがばいばあちゃん こねこ 『デメキング』:んんん、何と言うべきか?。映画として見るべき部分が皆無ではないが、全体としては駄目駄目。怪獣デメキングがダニエル・ジョンストンの The Frog of Innocence に酷似していて気になった。どっちが先か、あるいはパクったのか。(D) 『PLASTIC CITY』:個別に料金を払っては見なかったろう映画。予告編で想像したのとはかなり違った。オダギリ・ジョーは特訓したであろうポルトガル語と中国語を話していたが、KKDの『悲夢』のレビューに書いたのと同じセリフの下手さを露呈。(C) 『ダンサー・イン・ザ・ダーク』:久しぶりに再見。その間に同じフォン・トリアーの作品を数本見たが、『奇跡の海』に似ている。ここでは痛烈なアメリカ批判。(A or Bで迷う) 『いとしい人』:これも予告編とは違った印象。核心的ネタバレをしない上手な予告編だったかも。実際にはかなり迷走的展開、つまりは理屈ではなくオンナ心の心理的展開で、それが良かった。(C) 『ゼラチンシルバーLOVE』:(既に)老写真家・操上和美の初監督作。一種のますた-べ-しょん的作品。こんなことやめておけば良かったのに…。せめて20~30分の短編なら良かったかも。一見アート風なものを観て、アートした気分になりたい人、つまりは観る側が知的ますた-べ-しょんをしたい人にオススメ。永瀬、宮沢、天海の役者陣は好演。(D) 『佐賀のがばいばあちゃん』:島田洋七が自伝本を映画化。素朴なストーリーの素朴な手法の映画。主人公中学生時代役の役者の演技が光っていた。(C) 『こねこ』:猫というのは野生動物ではなく、何千年という歳月の中で人と共棲するようになった動物。猫社会での猫同志のかかわり合い方、猫と人とのかかわり合い方、それは人間社会の人同志の関係を反省するのにも示唆的。映画はまたソ連崩壊後のロシア社会の問題をも何気なく描いていた。それにしてもボクは「やっぱり猫が好き」。桜坂劇場周辺には猫が多い。今日も見終わって外に出たら沢山の猫たちがそれぞれ気ままにくつろいでいた。(B)
2009.06.14
コメント(4)
-
六月、その後見た映画
6月、その後見た映画。評価はB:優、C:良、D:不可。Aは特別良かった作品にのみ例外的に付けた。 詩人の血 ゼロの焦点 雪の下の炎 うつしみ 戦場のレクイエム 聴かれた女 聴かれた女の見られた夜 紀子の食卓 山桜 キャラメル 『詩人の血』:とにかもかくにもジャン・コクトー。コクトーを知るという以外で、たんに21世紀に見る映画作品としては感動はなし。(C) 『ゼロの焦点』:たぶんこの映画を見るのは初めて。意外とあっさりしていた。有馬稲子がいい、いい!。(C) 『雪の下の炎』:反政府活動ということで33年間牢につながれ激しい拷問も受け、現在インドに住むチベット僧のドキュメンタリー。このチベット問題について言うなら、中国政府は「人道に反する罪」を行なっている。(B) 『うつしみ』:園子温作品。ビデオによる非常にラフな作りで、表面的にはどうしようもない深夜テレビ番組レベルだが、内容的にはかなり面白い。(C) 『戦場のレクイエム』:前半の激しい戦闘シーンは、後半のために本当にあの形で必要だったろうか。祖国のために戦った兵士であるのは確かだが(ただし内戦)、『雪の下の炎』を見た後だとちょっとさめる部分も。(C) 『聴かれた女』:男と女の本質を面白く描いている。半ば本人剥き出し的な蒼井そらの演技が魅力的。(B) 『聴かれた女の見られた夜』:隣室の女を男が盗聴するのが『聴かれた女』だが、盗聴されている女の側の視点で描き直した別テイク。面白い試みだが、なくもがな。(C) 『紀子の食卓』:園子温作品だが、新作『愛のむきだし』とかなり似たテーマの作品。テーマの一つは役割主義的家族関係だが、黒沢清の『トウキョウソナタ』ともつながる。(B、ややオマケすればA) 『山桜』:篠原哲雄監督というと『地下鉄に乗って』が最悪・最低だった。予告編を見て懐疑的だったが、予想よりはるかに良かった(田中麗奈も)。時代劇とは言っても作るのも観るのも現代人なのだから、政治的側面、愛やしきたり等の側面に関して現代をもう少し考えさせる視点があればより良かった。(C) 『キャラメル』:たぶん初めてみるレバノン映画。美容エステサロンが舞台でトニー・マーシャル監督『エステサロン ヴーナス・ビューティー』を連想した。明るく自由に生きようとする女たちの姿は同じだが、背景にある因襲的社会という条件は重い。(B)
2009.06.12
コメント(0)
-
何故か日本映画が並んだ。
5月30日から桜坂劇場パートナーシップ「世果報」になり、映画見放題になったという「恐ろしい」(笑)出来事のことは書いたが、6月に入ってこれまでに見た映画は偶然日本映画ばかりになってしまった。備忘のために短評のみしておくことにした。 羅生門 ゆきゆきて神軍 張込み 9.11-8.15 日本心中 ヴィタール 愛のむきだし 愛のむきだし めざめ ボルベール <帰郷> (以上の内『ヴィタール』『めざめ』『ボルベール』はDVD、後の2本は洋画。でも何故かどちらもスペイン系。) 『羅生門』:何度か見ているがデジタル完全版というので見にいった。前に書いているように黒澤明は苦手なのだが、やはりこれは良かった。(評価:B優) 『ゆきゆきて神軍』:奥崎謙三を追ったドキュメンタリー。彼のように一途にはなれないが、彼の論点には共感出来る部分が多い。ドキュメンタリー作品としての作りは秀逸。(評価:A特優) 『張込み』:こちらも2度目。野村芳太郎ののろさに辟易するかと予感したが、劇場で見ると物凄く良かった(前回はテレビ)。松本清張の社会や人間洞察はやはり深い。ただし暗い、哀しい。(評価:B優) 『9.11-8.15 日本心中』:美術文芸評論家・針生一郎の思索を中心に据え、日本の思想の閉塞状況・不毛性を浮き彫りにするセミ・ドキュメンタリー。どなたかが「この映画は好きか嫌いかだ」と書かれていたが、そうではなく、ここで語られる思想的内容を理解できる知識や思想をどれだけ持っているかだ。(評価:B優) 『ヴィタール』(DVD):良かった、良かった。特にテンポ感、時間の流れがいい。(評価:A特優) 『愛のむきだし』:上に2回書いたのはミスではない。この4時間の映画を水曜と木曜と2日間続けて見た。本当は昨日金曜も3度目に行きたかった。実にエンターテイメント映画でありながら、観る人の知の深さに応じて深い内容が理解できる。(評価:A特優) 『めざめ』:不思議な映画。生と死と魂と肉体と愛の連鎖。これも時間感が好きだ。(評価:B優) 『ボルベール <帰郷>』:ありきたりなテーマとも言えるけれど、それをここまで魅力的に描いた発想力・脚本力・監督力は秀逸。(評価:B優) どの作品についても個別にレビューが書ければ、と思っています。
2009.06.06
コメント(3)
-
『ユッスー・ンドゥール 魂の帰郷』ピエール=イヴ・ボルジョー監督(2006スイス)
RETOUR A GOREE RETURN TO GOREE Jean-Yves Borgeaud フランス語・英語 112min(1:1.85) (桜坂劇場 ホールAにて) 以前なら見にいかなかった映画。見て良かった。「以前なら」と書いたが、この映画を見た5月30日から桜坂劇場に新しい会員制度が出来た。年会費3万円で映画が見放題。月額2千5百円。実に安い。有り難い。何本、何度見ても良いわけで、それでも出費はこれまでの1/3か1/4。何でも貪欲に見よう。 ユッスー・ンドゥール、ゴレ島のグリオ(語り部)の家系出身のミャージシャンは知らなかった。ゴレはセネガルの首都ダカールに属する小島。かつて新大陸への黒人奴隷貿易の送り出し港だった。何千万の黒人がアメリカ大陸に送られ、途中で多くが死んで捨てられた。 ユッスー・ンドゥールは現代の語り部として歴史を歌で語る。新大陸のブルース、ジャズ、ゴスペル、ラップに音楽的親近感を感じる。チュニジア出身で盲目のスイスのピアニストのモンセフ・ジュヌと共に、そんな音楽を求めてアメリカ大陸からヨーロッパを巡り、最後にゴレ島に戻るという音楽ロードムービー。 アトランタでは教会でゴスペルのグループと、ニューオリンズではジャズのグループと共演。黒人ドラマー・アイドリス・ムハンマド、ニューヨークでは黒人女性ヴォーカリストのピエン・スレッドギルなどと出会い、一緒に旅を続ける。ヨーロッパではリュクサンブール(ルクセンブルク)へ。地元のミャージシャンと共演、シンポジウムを開き、出会ったリュクサンブール人、ドイツ人のミャージシャンも従えてゴレ島へ。一緒に来た黒人ミャージシャンは彼らのルーツであるアフリカの地を踏むのは初めてだ。そんな彼らとこの象徴的ゴレ島で最後にコンサートが行われる。 ゴレ島からかつての黒人奴隷の行程に習いアメリカに渡り、そこで奴隷たちの子孫と共に再びゴレ島に戻る。またジャズ等の根を共有するアフリカ音楽との関係性を探る。これ自体は至って平凡な構成ではある。むしろ自分は、白人をも含めて一緒にジャズ等を演奏するという姿が良いと感じた。音楽の世界には相互理解や尊重はあるが、民族を分断しようという政治的アパルトヘイト・ウォールはない。アーリア人とユダヤ人とパレスチナ人が対立するような構図は存在しない。黒人と白人が一緒にジャズを演奏する。
2009.06.03
コメント(1)
-
5月に見た映画(つづき)
前回5月22日時点で4月、5月に見た映画を列挙したが、その後5月中に見た作品を挙げておきたい。これで5月には計33本を見たことになる(内映画館21本)。(カッコ)内のA~Dの評価は前回も書いたように、Bが良かった作品、Cがまずまず良かった作品で、Dのみが駄目だった作品だ。また特に良かった作品や大好きになった作品にのみ"A"をつけた。好きと言えるまでの恋愛猶予(DVD)(C)残菊物語(B)銀の鈴(B)アデルの恋の物語(VHS)(B)クローンは故郷をめざす(D)戦場のピアニスト(B)水の中のナイフ(VHS)(C)REPULSION 反撥(VHS)(B)島の色 静かな声(C)サマリア(DVD)(A)接吻(A)ユッスー・ンドゥール 魂の帰郷(B)今宵、フィッツジェラルド劇場で(D)猫が行方不明(VHS)(C orD)以上旧作にDVDの他VHSが多いのは、シネスコやビスタなどの左右がカットされず、ノートリミングのレターボックスであれば、レンタルは両方あればDVDではなくVHSを借りるからだ。なぜならDVDでは盤面に問題があると全然見られなかったり、問題箇所以降が見られないが、ビデオは仮に一部映像や音声に問題があっても、それ以外の部分はしっかり見られるからだ。旧メディアにも良い点はある。
2009.06.02
コメント(2)
-
4月、5月に見た映画
パソコン無し生活を続けています。だからこのブログも携帯からアップ。携帯だとやはりパソコンより膨大な時間を要します。一方桜坂劇場通いは2日に1本か3日に2本のペース。レビューを書いてない作品がどんどん増えていきます。そこで見た映画のリストアップだけでもしておきたいと思いました。A~Dの評価は、Bが良かった作品、Cがまずまずの作品、Dが駄目だった作品で、特別に良かった作品にのみ例外的にAをつけました。なので大雑把にはA~Cは良かった映画で、Dだけが良くなかった映画ということですので、BやCが悪い映画とは理解しないでください。 ――4月―― そして、私たちは愛に帰る(B) ロシュフォールの恋人たち(C) シェルブールの雨傘(B) PARIS(C) ザ・ローリング・ストーンズ シャイン・ア・ライト(C) シャッフル(C) その木戸を通って(C) 我が至上の愛 アストレとセラドン(B) メイド・イン・USA(DVD)(B) ロルナの祈り(C) マリア・カラスの真実(C) この自由な世界で(B) ラ・ボエーム(B) 英国王給仕人に乾杯!(C) ――5月―― 黒い十人の女(B) ハーヴェイ・ミルク(B) イングリッシュ・ペイシェント(VHS)(C) 狂ったバカンス(DVD)(B) ラスト・キャバレー(B) アニー・ホール(VHS)(B) 潜水服は蝶の夢を見る(B) いのちの戦場 アルジェリア1959(C) 春夏秋冬そして春(C) ホルテンさんのはじめての冒険(B) 悲夢(B) ブレス(B) 弓(DVD)(B) ラブホテル(B) 近松物語(B) 妖精たちの森(DVD)(C) 永遠のこどもたち(B) うつせみ(DVD)(A) THIS IS ENGLAND(A) 桜坂劇場に新しい会員制度が出来るので、来月からはもっと劇場通いが増えそうな予感。予感というより必至。なのでますますレビュー未アップ作品が増えていきそうです。そろそろパソコン買うか修理しないと…!。
2009.05.22
コメント(5)
-
『悲夢』キム・ギドク監督(2008韓国)その4
悲夢 (つづき)-4- そして最後はワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』をも思わせる純愛の世界でもあるのだが、二人は統合される、あるいは分析医の言った意味で互いに愛し合うラストだ。 人を愛することは互いに傷つけ合うことをも前提とする。人と人(男と女)は元々別々の自我を持った存在なのだから、全き自分を相手にぶつければ、必ず相手を傷つけるはずだ。表面的な優しさとか自重とか、相手を思いやっての行動とか、そうした一般的に「愛情」と呼ばれる愛、そんな現世的愛は、まだまだ低レベルの愛でしかない。自我を剥き出しにして相手に接し、結果として互いに傷つけ合い、それをも受け入れるのを喜びとするのが愛であり、それは人(個人)が、自分の中にある肯定的面と否定的面、好きな自分と嫌いな自分、それをも含めて自分を結局は肯定しようとする自己愛にも似ている。そしてこのジンとランのように、かつて離ればなれになった自分の半分であるベターハーフと出会ったとき、究極の愛が成立するのだ。しかしそんな愛は稀であり、必ずしも現世的幸せとは両立しえない。 とでもキム・ギドクは言いたいのだろうか。
2009.05.19
コメント(4)
-
『悲夢』キム・ギドク監督(2008韓国)その3
悲夢 (つづき)-3- ここから先のネタバレはしないでおく。前作『ブレス』では台湾のチャン・チェンを使ったが、一言のセリフもない役だから、韓国語が出来ないことに問題はなかった。ではオダギリの場合は?。監督はオダギリ一人だけに日本語を喋らせている。物語のジンの設定は日本人なのか韓国人なのかわからない。しかしその雰囲気はやはり韓国人であるより日本人だ。韓国人にも日本人にも色々な人はいるが、例えば男尊女卑的であったりすることも含めて、韓国人男性はより「男」なのだ。その点ある種の日本人男性は、女性に対して弱くもあり、また一種中性的でさえある。そういう意味でキム監督が日本人役者を使った理由が良くわかる。 そのオダギリに日本語を話させたのにはそこにも理由がある。韓国人によるアテレコにしてしまっては、結局セリフ(声)のキャラクターが韓国人男性になってしまう。もちろん撮影の際の演技は自国語の方がのびのびと出来るという利点もあるが、二人で一人というランとジンの、二人である方の側面、それが言語の違いということで明確に感じられる。 途中からの、夢と現が交錯する曖昧性・幻想性のことを書いた。映画後半、ネタバレになるのでストーリーを書いていない部分だが、ここでの印象はベルイマンの『仮面ペルソナ』(最近はただ「ペルソナ」とも〔1966〕)だ。最後の白い壁の部屋の場面は『ペルソナ』冒頭のリヴ・ウルマンとビビ・アンデルソンの病院のシーンを連想させる。ベルイマンの映画は2人の人格が重なり合い曖昧となる、言ってみれば精神分析の転移の世界だった。あるいはベルイマンの影響を強く受けた吉田喜重にも筆致が近いかも知れない。 単なる真似ではなく自分の表現世界として立派に消化しているが、キム・ギドク監督の作品を見ていると、何かしら大監督の作品を連想させられる。『ブレス』の刑務所の監視カメラがアップで写され、カメラが無気味に動く映像はキェシロフスキの『駅』そのものと言って良い。当たり前と言えばそうなのだが、この監督が如何に多くの芸術映画を見ていて、それを評価し、また影響を受けているか、あるいはそうした作品を見ることで自分の表現を創りあげているかがわかる。彼はヨーロッパ受けが良いが、根本にそういうものがあるのだ。 (つづく)
2009.05.19
コメント(0)
-
『悲夢』キム・ギドク監督(2008韓国)その2
悲夢 (つづき)-2- ランは別れた恋人を嫌悪していた。ジンの方は別れた恋人への執着を引きずっていた。ジンは元カノとのデートの夢を見る。するとランは夢遊病で元カレに会いに行ってしまう。嫌悪する男に抱かれるのだからランにとっては迷惑な話だ。ジンとランにとって二人が同時に眠ることが問題なのだが、二人とも夜は寝たいし眠くもなるので、睡眠シェアはなかなか上手くいかない。 元カノを忘れられないジンと元カレを忘れたいラン。ジンとランは二人で一人。表と裏、あるいは白と黒。なるほどジンが未練がましい夢を見るからランは嫌悪する元カレに夢遊病で会いに行く。しかしどうなのだろう。夢を見るのがジンで、実行するのはランだけれど、ランの方もニュートラルでなく「嫌悪」という形で元カレを精神的に整理できていないのでではないだろうか。元カノとの夢を見るジンをランは非難するけれど、彼女のその嫌悪の裏返しがジンの未練なのであり、ランが元カレとのことを消化出来れば、ジンも元カノを忘れられるはずだ。 そんな中で、段々に二人は惹かれ合っていく。映画中盤から、どこまでが夢で、どれが現実なのか、やや曖昧な、幻想的な描写となっていく。ジンはランとお寺で楽しげにデートをするが、ジンは車の中で目を覚まし夢だったことを知る。ジンは梵鐘を鳴らしたりしたお寺でのランとのデートの夢の過程を一人辿るが、そこにランはいない。でも夢で二人で積み上げた小石の塔は実際にあった。そして車に戻るとそこにランがやってくる。これは夢遊病のランなのか、目覚めた現のランなのか、それともこれもまた夢なのか。夢だとすればランは(もし眠っていれば)ジンの車にやってくるだろうが、それならそのときジンは車の中で眠っているはずだ。 こうしていわば夢と現が交錯し、境界が曖昧となってくる。それはまさしく分析医の言った「二人が愛し合えば」ということなのだろう。しかしそれでもジンは元カノを夢から完全に追い払うことはできなかった。しかしこの中途半端な状態は別の危険をも孕んでいた。それはランがジンが夢に見ないことまで行動してしまう危険だ。ランは半ばジンの夢に拘束され、また半ば自由でもある。 (つづく)
2009.05.19
コメント(0)
-
『悲夢』キム・ギドク監督(2008韓国)
悲夢 BI-MONG/SAD DREAM キム・ギドク(金基徳) Kim Ki-duk 93min(1:1.85) 韓国語/日本語 (桜坂劇場 ホールBにて) 前回初めてのキム・ギドク作品は同監督第9作『春夏秋冬そして春』だったが、2本目は第15作(最新作)の『悲夢』。主演は韓国人女優イ・ナヨンと日本人俳優オダギリ ジョー。 誰でもが感じるだろうこの映画の変わったところは、舞台は韓国・ソウルなのだけれど、オダギリは日本語、他のすべては韓国語を話すことだ。普通ならオダギリが韓国語のセリフを憶えて撮影し、後で韓国人役者のアテレコを入れるところだ。この不自然なやり方には色々な意味で監督の意図がありそうだ。そしてそれは成功していると思うが、その点は後で書くことにする。 そんな監督の意図とは別に、ボクはそれが残念でならない。オダギリという俳優、動作や表情はともかく、しゃべりはすこぶる下手だからだ。激しく心情を吐露するようなとき、この人のセリフは心情と言葉との間にフィルターのようなものが介在する。ここでは役者の演技だけれど、もし自分が実生活でこういう人のしゃべりを聞いたら、心で強く感じていることがそのまま言葉になっているのではなく、ワン・クッション反省・反芻してから言葉にしていると感じるだろう。あるいは実際には少ししか感じてないことを、まず心の中で増幅して重大事化し、それを言葉にしているといった感じを持つだろう。 ジン(オダギリ)は自動車事故を起こす。相手の運転者は怪我をしているが、彼は怖くなって逃げてしまう。気づくとそれは夢だった。ジンが気になって夢の事故現場に行くと、夢の通りの当て逃げ事故を警察が処理していた。監視カメラの映像から当て逃げ犯がわかり警察は向うが、ジンは後をつけた。家の前には事故車があり、寝ていたというランを警察は逮捕する。 こうして二人は関わり合うことになる。そしてわかったことは、ジンが夢を見、その夢の中のジンの行動を寝ているランが夢遊病の形で実行するということだった。精神分析医(?)は二人が実は一人であり、唯一の可能な解決は二人が愛し合うようになることだと言う。 (つづく)
2009.05.19
コメント(0)
-
『春夏秋冬そして春』キム・ギドク〔金基徳〕監督(2003韓国・ドイツ)その3
春夏秋冬 そして 春 (つづき)-3- この後の物語は書かないことにする。各季節の動物による象徴は猫、蛇、亀だった。春夏秋冬はもちろん人の一生に準えられていて、春に再び戻ることで同じ人の生が繰り返されることを円環構造で表現していることは書いた。冬に連れて来られた赤ん坊が春に、最初の少年僧と同じ位置にいることも書いた。 でも忘れてはならないのは逆行的に見た円環ではないだろうか。老僧は人というもの、具体的には若い僧を達観していて、人は煩悩を持ち、過ちも犯すものとして、若い僧が何をしでかそうが決して動じない。しかし師はなにも特別な聖人であるのではない。若い僧は色々な過ちを犯すが、最後にはかつての師の後を継ぐ。つまりそこに至るまでの若い僧の人生(映画の中心的ストーリー)は、老住職の過去でもあるのだ。若い僧は子役から最後のキム・ギドク監督自身まで4人の役者が演じる。それには異なった年齢の人生各時期に一人の役者のメイク(化粧)ではなくそれぞれの年齢に合ったキャラクターを使ったのだろうが、実は物語の抽象化でもある。最初の春の少年僧が成長して夏の青年僧になったと文字通り解釈しても良いけれど、その間に2世代、3世代が入っていると解釈しても良い。つまりは冬の赤ん坊が2つの春の少年になり、夏の青年、秋の青年となり、冬の壮年、そして春から秋に登場した師匠(住職)になる。それが人が変わらず繰り返す人の誕生から死だということだ。 ここに描かれる「人の誕生・成長・死」は寺の修行僧だが、監督も観客もほとんどすべては一生、こうした瞑想や修行とは無縁の現世的世界に生きる。そもそも性的煩悩がなければ人類は滅びて更新されない。殺生を含めた数々の深い過ちを犯した秋の修行僧に住職は生き続けなければならないと強くたしなめる。 そんなことから感じられるのは、人は過ちを犯しながらも生きていかねばならない。あるいは生きるべきだということであり、大切なのは罪意識をも持った(キリスト教的に考えるなら原罪を持った)上での、精神の充足による平安だということだ。そしてそれはこの映画の主人公のように俗世間から離れての隠遁した修行でも良いけれど、皆がそういうわけにはいかないだろうから、自分の中の信仰のようなもの、あるいは確固とした価値観・哲学を持つことと、それに従って生きることが重要なのだ。
2009.05.17
コメント(2)
-
『春夏秋冬そして春』キム・ギドク〔金基徳〕監督(2003韓国・ドイツ)その2
春夏秋冬 そして 春 (つづき)-2- 内的罪意識と書いたけれど、この映画が重きを置くのは内面の価値観や意識だ。それを象徴するような描写がある。湖に浮かぶこの寺は本当に小さいのだが、中央の扉を開けて中に入ると、正面にはささやかな祭壇があり仏像が祀られている。その中央スペースの左右は布団1枚敷ける程度の小部屋(?)になっていて、住職も弟子もそこに寝るのだが、扉だけあって壁がない。つまり一つの部屋の左右の空間にドアだけがつっ立っている(もしかしたらフォン・トリアーの『ドッグヴィル』がヒントになった?)。朝既に起きている住職がまだ寝ている子供修行僧を起こすとき、壁はないから直接に修行僧が見えているのに、わざわざドアを開けて声をかける。もちろん二人が二つの空間(部屋?)を行き来するのは必ずこのドアを通ってだ。幼稚に解釈すればそれは「ごっこ」の世界だけれど、これは実際にはない壁によって仕切られていると捉える観念的世界だ。 夏:象徴は鶏。精神的ことが原因の身体の病が治らない高校生ぐらいの娘を、母親が療養のためにこの寺に預けていく。もちろん二十歳前ぐらいになった若い修行僧は性の煩悩に悩まされる。ただ自然があるだけで、テレビもなければ雑誌もない。その中に置かれた若い男女。当然のごとく二人は愛し合うようになる。ちなみに娘の着ているセーラー服やワンピース、ジーンズから、物語の設定が現代であったことが初めて示される。 そんな日々の中で娘の病はいつしか癒えていた。若い僧が現世的愛や肉欲に溺れていることを知った師は、病気が治ったのだからと娘を家に帰すが、若い僧には別れが耐えられなかった。 ところで夜、師と弟子は見えない壁に仕切られた左の部屋で、娘は右の部屋に寝ていた。壁がないのだから若い二人は目と目を合わす。娘は修行者でないから当たり前として、若い僧には観念的に壁は存在するはずだから、本来2枚の壁に隔てられているから寝ている娘は見えないはず。ここに若い僧の内的世界、つまりは信仰あるいは解脱への過程の中断が象徴されている。若い僧は娘の寝所に夜這うのだけれど、内開きの扉は寝ている師が引っかかって開かない。彼はドアからでなく、壁のあるはずの場所を通って娘の布団の中に向う。信仰、修行からの完成な逸脱だ。 (つづく)
2009.05.17
コメント(0)
-
『春夏秋冬そして春』キム・ギドク〔金基徳〕監督(2003韓国・ドイツ)
春夏秋冬 そして 春 Fruhling, Sommer, Herbst, Winter... und Fruhling キム・ギドク(金基徳) Kim Ki-duk 102min(1:1.85) 韓国語 (桜坂劇場 ホールBにて) まともに韓国映画を見るのは昨年10月8日と9日にレビューを書いた『シークレット・サンシャイン』と『ユア・マイ・サンシャイン』、チョン・ドヨン主演の2本の「サンシャイン」に続き3本目。だから本国よりも欧米で評価の高いキム・ギドク作品を見るは初めて(この映画もドイツと共同製作)。この後同監督の『ブレス』と『悲夢』も見にいく予定だ。 韓国の山間にある小さな湖。元々は人造湖らしいが、湖中に樹が生えた緑の中の美しい自然。そこに浮かぶ小さな仏教(禅宗?)の僧院(映画のために作られたセットで、寺は実在しない)。外界とはボートで行き来するしかない孤立した世界。そこに老住職(?)と若い修行僧がいた。題名が示すように春、夏、秋、冬、春の5部からなり、修行僧はそれぞれおおよそ10才、20才、30才、40才、50才。「冬」に新しく連れてこられた赤ん坊が、最後の「春」には成長して最初の「春」の主人公と同じような少年となり、円環構造を成す。2つの「春」の少年は同じ子役が演じる。 春:このパートの象徴は犬らしい。少年は魚、蛙、蛇に小石を付けたひもを結びつける。小石の重さで思うように動けないのを見て面白がっている。その様子を住職は陰から見ていた。深夜少年が眠るのを待って、住職は少年の背中に大きな石を縛り付けた。朝起きた少年は背中の石をとってくれと言う。住職は前日の生き物の小石を取り除くことが先だと言い、1匹でも死んでいたら一生その石を心に抱えて生きるのだとたしなめる。少年が重い石を背負い、昨日の場所に行くと、魚は死んでいた。まだ生きていた蛙は小石を取り除いて解放することが出来たが、蛇は他の動物に襲われたらしく血を流して死んでいた。自分のしたことの重さに少年は泣き出してしまう。 この映画に監督が込めた仏教的思想は正直なところ良くは解らない。しかしこの最初のエピソードで重要なことは、人の罪深さの認識であり、心に石を抱えて生きていかねばならないという住職の言葉なのだが、赤ん坊から無邪気に育った少年が、ここで内的「罪意識」を持たされたということだ。 (つづく)
2009.05.17
コメント(0)
-
『ラスト・キャバレー』(日活ロマンポルノ)金子修介監督(1988)
ラスト・キャバレー (日活ロマンポルノ) 金子修介監督 78min (桜坂劇場 ホールCにて) 桜坂劇場では最近ご無沙汰だったけれど、夜に女性専用席も設けて、日活ロマンポルノを数本ずつ特集してます。店があったので夜はほとんど外出できず、この催しを見るのは今回が初めて。 日活ロマンポルノ最終期、ロマンポルノが終焉する1988年の作品で、ストーリー自体、また特に最後の閉店パーティーのシーンは、ロマンポルノのお別れパーティーの体があります。かつてのロマンポルノのスターたち(岡本麗、風祭ゆき、江崎和代)が、閉店するキャバレーのお別れパーティーに、このキャバレーのかつてのホステスとして登場してます。 そんなやや特殊な作品ではあるけれど、低予算・短期間撮影なのに(だから?)立派な映画作品になっている。派手なズーミングや長回しは、これは遠景を撮ってからカメラを移動して近景を撮るとか、ショットとリバースショットを繰り返すのに比べれば速く撮れるからだし、フィルムの(時間も)節約のためには何テイクも撮り直すのでなくワンテイク的になる。監督の厳格な意図を役者が完璧に演じるまでテイクを重ね、いわば役者が監督の人形となるのとは違い、役者の新鮮な演技という映画の醍醐味がある。裸や絡みさえ出していれば内容はあまり注文を(会社上層部から)つけられない自由度が監督にはあったという。そんなこんなで、あくまでポルノ系ではあるけれど映画としてはかなり面白い。比べればお金をかけ、人気役者を使った昨今の日本映画の多くが、なんと内容が薄いことか!!。 駅前再開発の立ち退きで閉店するキャバレー・ローズ。経営者の父と高校生のあい子が店の二階に暮らしていたが、父は娘にマンションを買い与え、自分は一人地方ででもまた店を開こうと考えていた。娘は父が誰か女と暮らすのでは?と探るけれど、そういうことはなかった。一方娘は大学生タツヤと恋仲になる。父のことが気になり気遣いながらもとやかく言わない娘。愛する男と体でも結ばれている娘を見守る父。この辺の親子の心の交流が良い。さながらフランス映画の良好な父娘関係を見ているかのようだ。人はそれぞれ孤独であり、自分の生を生きる。だからこそ愛を求める。パーティーが終わった無人のキャバレーには宴の後の寂しさが漂う。そこに静かに佇むあい子とタツヤが印象的。
2009.05.12
コメント(6)
-
『ラ・ボエーム』ロバート・ドーンヘルム監督(2008ドイツ・オーストリア)その5
LA BOHEME Robert Dornhelm (つづき)-5- 別れながらミミを忘れることが出来ないロドルフォだが、ある日ムゼッタが瀕死のミミを連れてくる。死を目の前にしたミミはせめても最後はロドルフォと過ごしたかったのだ。 ところで先にオペラの持つ祝祭的な魅力のことに触れた。なんとは言っても歌手(役者)や指揮者、楽団員、そして大道具などのスタッフ、一団となって上演を行うのは観客を楽しませるためだ。そして実際に劇場で観客の前で上演が行なわれる。観客は2千人ぐらいその劇場に集う。こうして観客と演者やスタッフがそれぞれの立場で時間を共有する。そこには祝祭的な意味がある。これが映画と演劇の根本的違いだ。映画は観客抜きに既に完成されており、演者や監督・スタッフはいない。そしてこれが明確に感じられる時間、祝祭を共に生き、その祝祭が終わろうとしていることを感じさせるのがカーテンコールなのである。上演が終わり幕が閉じる。観客が拍手をする中、今しがた終幕で死んだはずのミミ、正確にはミミを演じた歌手を含めて歌手たちや指揮者などが幕の前に現れ観客に挨拶をし、観客は拍手や掛け声・投げ花で演者を称賛し、労を労う。このカーテンコールがオペラには不可欠なのではないかと思う。祝祭を明確に祝祭たらしめる瞬間なのだ。欲を言えばこの瞬間を感じさせる何かが映画の最後に欲しかった。 これで思い出されるのがモーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』だ。ドン・ジョヴァンニの存在ゆえに貴族や農民など様々な6人がドン・ジョヴァンニの悪事を協力して暴くという形で関係を持つ。しかし彼が地獄落ちしていなくなったとき、元々無関係だった6人をつなぐものはない。ミュンヘン・オペラでのレンネルトの演出は巧みにも、この最後の場面の前に幕を下ろしてしまい、それぞれが自分の将来を語り別れていく最後を、幕の前で歌わせた。このオペラのメインドラマ自体が、そのドラマのために集まり、ドラマが終われば離散していくという枠に収められているわけで、この構造はオペラ上演に似ている。 とにもかくにも、ドルンヘルム監督によるこの『ラ・ボエーム』、オペラ映画としてはなかなかの佳作かも知れない。
2009.05.03
コメント(7)
-
『ラ・ボエーム』ロバート・ドーンヘルム監督(2008ドイツ・オーストリア)その4
LA BOHEME Robert Dornhelm (つづき)-4- この映画はオペラ・ファンを対象にしたのではなく、むしろオペラをあまり知らない人々をオペラに誘うことを目的としているらしいことをどこかで読んだ。そういう意味で、あくまで音楽が中心にあって、映画の写実とは違うというオペラの持つ性格と、映像が主である映画を上手く融合させているのではないかと思う。 ムゼッタ役はニコル・キャベル。この人は美声で素晴らしい歌手なのだが、ごく一般的観点で言うなら、決して美人とは言えないかも知れない。アフリカ系アメリカ人で、コリアンとコーカサスの血も混じった東洋系の顔立ち。どなたかのレビューに「何もあんな顔の歌手を使わなくても」というのがあった。しかしそれは映画的見方であって、オペラはまず歌(声)ありきなのだ。事実ボクの好みの顔ではないのだが、それでも彼女を見て・聴いているうちに、ムゼッタという軽薄だけれど心根の優しい女性が、歌声・音楽を通して、演じるキャベルの顔の中に見えてくる。これがオペラの見方なのであって、写実だけを求めてはならない。初心者をオペラに誘うためには、こういうオペラの見方を促すことも必要だ。映画的な写実や美男美女を期待してオペラを観に行ったら失望してしまうだろうから。 実はこの映画、第一幕のロドルフォ、ミミそれぞれのアリアや2人の二重唱から、観て(聴いて)いて涙が滲んでしまった。そして終幕のミミの歌ではもう涙ボロボロ。同じ物語を普通の映画で見ても、あるいはオペラ『ラ・ボエーム』を劇場で生で観てもボクが涙を流すことはまずないだろう。プッチーニの音楽は甘美で、人の声の持つ力は大きい。音だけをCDなどで聴いている時には涙もありだ。つまりこの映画が「音楽を聴く」ことを阻害していない。 ストーリーをネタバレ承知でちょっと(オペラというのはストーリーを知っていて観るものだ)。1930年代ルイ・フィリップの七月王政のパリ。売れない詩人・劇作家のロドルフォとお針子ミミの二人が恋に落ち一緒に暮らすようになるが、ミミは肺病を病んでおり、貧乏ゆえに何もしてやれないロドルフォは不甲斐なさからミミと上手く行かなくなる。別れれば金持ちに囲われることだってできる。そんな二人は愛しながらも別れる。 (つづく)
2009.05.03
コメント(2)
-
『ラ・ボエーム』ロバート・ドーンヘルム監督(2008ドイツ・オーストリア)その3
LA BOHEME Robert Dornhelm (つづき)-3- 「技術が発達して、映画やら、ビデオやら、いろーんな方法でオペラを再現しようとしてきたけど、結局のところそれには成功できてないねぇー。」と、音楽評論家の吉田秀和氏は以前ラジオで言っていたけれど、劇場で観る(聴く)オペラを知り、またそれを愛する者の共通の感想ではないだろうか。上演のテレビ録画は、画面を見ずに聴くだけならまだ良いが、映像も見ていしまうとオペラの抜け殻を見ているかのごとくなのだ。 さてそんなわけだから、ボクはオペラ映画というのをそれほど見ていないが、これまでの中で唯一高く評価しているのは、イングマール・ベルイマンの『魔笛』だ。さすがに巨匠、オペラや特にこの『魔笛』が好きな上に、映画というものの性格を良く知り、また舞台演出家でもあるから芝居をも良く知っているから出来たことだろう。決してオペラそのものの再現は出来ていないが、オペラ上演の祝祭的な面をも含めて、劇場でオペラを観る者の楽しみを、映画によってもたらしてくれる。ベルイマンが成功したのは、「オペラの再現」をしようとせず、「オペラを劇場で観る楽しみの再現」をしたからではないかと思う。残念なのは原語のドイツ語ではなくスウェーデン語で歌われていることだ。 長々とオペラ観やオペラ映画観を書いてきたが、いよいよ本題のローベルト・ドルンヘルム監督、アンナ・ネトレプコ&ローランド・ビリャソン主演の、オペラ映画『ラ・ボエーム』についてだ。結論から言うと、もちろんオペラ上演の再現ではないが、映画としてはなかなかの出来なのではないかと感じた。 その成功の理由は主演の二人のルックスに負うところが大きい。というより、ネトレプコとビリャソンというルックスの良い、しかも歌手としても一流の二人がいたからこそ、監督あるいは製作者はこの映画を作ることにしたのではないかと思う。正直に言って、美貌のアンナ・ネトレプコを見ているだけでボクは満足だ。5月8日まで1日1回だけやっているので、できればもう1回見に行きたい。DVDが出たら買ってしまいそうだ。 (つづく)
2009.05.03
コメント(0)
-
『ラ・ボエーム』ロバート・ドーンヘルム監督(2008ドイツ・オーストリア)その2
LA BOHEME Robert Dornhelm (つづき)-2- 宝塚の男役が低い声で歌う(つまりはより写実化に向う)のに対して、オペラのズボン役はソプラノの高い女声で歌われる。 写実に向う映画ではしばしば「嘘っぽい」とか「真実味に欠ける」と批判されるが、オペラの場合は筋が他愛なかっり、荒唐無稽なのは当たり前だ。思うにオペラの「音楽」というのは、抽象化、普遍化なのだ。ロドルフォとミミという男女の愛を描くと同時に、その具体を通して表現されるのは男女の愛という普遍でもある。 だからオペラは基本は音楽だけで「仮に」完成している。音楽というのは、基本的に理性にまず訴えかける言語とは違い、直接に人の情動に訴えかける。そして声の力もある。ある感情を表現しようと歌われる「人の声」は強く聴く者に訴える。ワーグナーの『ワルキューレ』第一幕の最後近くでジークムントが樹の幹に深く刺さった剣を見事引き抜いたときのジークリンデの叫びは、単なる「アーーッ!」というものだけれど、その(叫び)声は聴く者を深く感動させずにはおかない。 それではオペラにおける舞台上の歌手たちの演技とは何か。聴覚は音楽や人の声で充たされたとしても、人には視覚がある。CDで聴くオペラはこれを欠く。愛し合っている恋人が愛の二重唱を歌うとき、目は抱き合う二人の姿を欲する。しかしそれは聴覚にもたらされたものを阻害するものであっては不都合だ。だから写実に過ぎる映像であってはならない。それはせっかく音楽や声が聴衆にもたらした普遍化、感動を下世話に限定してしまうからだ。それ故、矛盾するようだが、巨漢のおばさん歌手の演じるうら若き乙女で良いのだ。つまり人はそこに巨漢のおばさんを見るのではなく、映画的写実では表現出来ないかも知れない、清純な乙女の理想像を見ることが可能だからだ。 以上のような意味で、多くのオペラ映画は、基本は音楽と声がもたらす感動を、写実の映像で限定し、結果壊してしまう。そしてオペラの公演をビデオ録画したものも、実際に生を観るのならよいが、一度劇場を離れてテレビ画面や映画スクリーンで見るとき、人はその映像をより写実として見てしまうのだ。そしてそれとは別に、もちろんオペラの舞台上演には祝祭的性格もあり、それも映画やDVDでは捨象されてしまう。 (つづく)
2009.05.03
コメント(0)
-
『ラ・ボエーム』ロバート・ドーンヘルム監督(2008ドイツ・オーストリア)
LA BOHEME Robert Dornhelm 114min(1:2.35) (桜坂劇場 ホールBにて) 他の映画のレビューでオペラのことに触れることがあるので、お気づきの方もおられるかも知れませんが、ボクは相当のオペラ好きです。とは言っても特に好きなのはモーツァルト、ワーグナー、リヒャルト・シュトラウスなど独墺系のもの。このプッチーニとかヴェルディに代表されるようなイタリアオペラを自分から聴く(観る)ことはあまりありません。もちろんチケットを貰えば喜んでいそいそと出掛けますが。でもそんなイタリアオペラの中で最も好きな演目はこの『ラ・ボエーム』かも知れません。そもそも小学生の時に(自分から積極的にではありませんが)初めて劇場で観たオペラはプッチーニのこの『ラ・ボエーム』でした。 ところでオペラというのは、まず理想的なのは劇場で生を聴く(観る)こと。しかしいつもいつもそうはいかないので、普段の楽しみはCDなどで音だけを聴く。しかしDVDなどで映像を見ながら音を聞くのは、ボクの場合かなり稀です。映像入りのDVDを持っていても、普段はたいてい音のみを聴いています。 そんなわけでボクはオペラ映画には基本的に懐疑的。この辺にオペラのオペラたる所以がありそうなのだけれど、このブログでオペラ映画を取り上げるのは初めてなので、少しそのことを考察しておきたいと思った。 最近見た映画を例にとると、ダルデンヌ兄弟監督の『ロルナの祈り』で薬中でボロボロの青年を演じた俳優ジェレミー・レニエは、2ヶ月で15キロ体重を減量して撮影にあたった。つまり映画というのは基本は写実に向う。ではオペラは?。この『ラ・ボエーム』のミミも『椿姫』のヴィオレッタも最後は肺病で死んでいくが、どちらも80キロ、90キロある巨漢のソプラノが歌う(演じる)ことだってある。あるいは清純なうら若き乙女の役を、とうに40歳を過ぎた、どう見てもおばさん顔の歌手が演じることだって珍しくはない。つまりオペラというのは基本、歌がメインであって、ルックスは二の次なのだ。だいたい舞台セットだって映画的写実からは程遠い。 ズボン役と言って、女性歌手が若い男性の役を演じるオペラもある。『フィガロの結婚』のケルビーノや『薔薇の騎士』のオクタヴィアンがそうだけれど、これは宝塚の世界とはちょっと違う。 (つづく)
2009.05.03
コメント(0)
-
『トウキョウソナタ』黒沢清監督(2008日本)その7 --蛇足--
トウキョウソナタ 黒沢清監督 (つづき)-7- /蛇足 映画を見ても、周囲のリアルの人々を見ても、日本人の家族のあり方でよく感じるのは、子供もできて、結婚10年とか15年ぐらいたった夫婦の男女の交わりの不在や想像困難性だ。そういうことを羞恥するとか秘めるという文化もあるだろう。しかし映画で言えば、結婚前の恋愛時のセックスや不倫関係のセックスが少なからず描かれるのに対して、年月を経た家族の中の夫と妻の性関係が描かれることや、直接描かないにしてもその存在を想起させることが極端に少ない気がする。 恋愛時の二人は男と女だ。不倫の二人も男と女だ。しかし結婚15年の夫と妻はお父さんとお母さんという役割を(だけを?)担う。最近はどうか知らないが、両親がセックスをしている姿など想像もしたくないという中学生ぐらいの子供が(大学生でも)少なくない(なかった)。逆に両親の間にセックスがあって、それを知って両親がまだ愛し合っていて離婚しそうにないと安心する子供が描かれる欧米映画は何本か見ている。 この映画の中の竜平と恵もそうだ。この二人のセックスは想像しにくい。したくもない。しかし恵と強盗のラブシーンはあった。長男は恵にいみじくも「離婚しちゃえば。」と言い、「まだイケテルよ。」とも言う。そして恵はお母さん役を離れたとき、一人の女に戻ることで強盗とのラブシーンも自然なこととして描かれる。 男であることや女であることをも含めて、夫も妻も「個性を持った一人の人間」であるはずが、そうした個性を切り捨てて父や母であるという役割に埋没しているのが、日本の家族に於ける夫や妻の姿ではないだろうか。男と女であるからこそセックスも自然なことなのであって、その個性を切り捨てて父や母の役割を担うだけになったとき、その二人のセックスは不自然なものとなり、だから秘める必要も生じる。そして日本人は最もセックスをしない国民だという事実の一端を構成する。セックスレスでなくとも、夫婦間のセックスは頻度が低いのだ。 今ボクは性という一面からこの物語が含むテーマをやや我田引水的に考察したけれど、役割に埋没することで個人を捨てるという日本的家族のあり方に、オーストラリア人脚本家や黒沢監督や自分が違和感を覚える(覚えているだろう)ことの一種の説明になったのではないかと思う。
2009.04.27
コメント(2)
-
『トウキョウソナタ』黒沢清監督(2008日本)その6
トウキョウソナタ 黒沢清監督 (つづき)-6- ネタバレになるのでこの後半からラストへの流れは詳しくは書かない。間抜けな強盗(役所広司)が家に押し入り、最初はその強盗に脅迫されて恵は人質になるが、途中からはむしろ恵が主導権を握って、強盗が盗んだプジョーのカブリオレで海への逃避行となる。プジョーのカブリオレは映画冒頭で免許を取った恵がショールームで見て憧れを感じた車だった。電動でオープンになるカブリオレだけれど、屋根のないオープンカーとは解放であり、また車はアナザーワールドに彼女を連れ出してくれる。もちろんハンドルを「握らされる」→「好んで握る」のは彼女だ。海辺の小屋では強盗とのラブシーンもあるが、こうして彼女は役割ではない自分を取り戻す。途中ショッピングモールで清掃員姿の夫・竜平と出くわすが、彼女は気にもとめない。 その竜平は自分が掃除をするトイレで札束の入った封筒を拾い、そのままくすねたいという誘惑と戦いながら走り回って一夜を過ごす。そしてそんな中で恐らく、やはり役割ではない自分にたち帰る。二男の健二はミニ家出をする。長男の貴はアメリカ軍としてイラクに行っていて姿は現さないし、その動静もわからないが、戦争の現実やアメリカだけが正義でないこと思い知って帰ってくるらしいことが、恵の夢という形で知らされる。 一夜明けて家の食卓には貴を除く3人が一人、また一人と帰ってくる。恵は朝食の用意をし、新生佐々木家家族のスタートだ。そして最後は数ヶ月後で、健二の弾くドビュッシーの『月の光』が流れる美しいラストが用意されている。 このラストには竜平、恵、健二の親子3名が姿を現すが、各人の個性の上に構成された新しい佐々木家の様子が描かれている。その新しい家族のあり方はまだぎこちなく、発展途上かも知れないが、天才ピアニストとしての健二への期待と重ねられ、希望に満ちたものだ。 ここで敢えてまた『歩いても 歩いても』と比較するなら、リアリティーという意味では実に写実的な是枝作品が、単なる現状の追認でしかなく、前向きな反省を結局のところ何も含まないのに対して、この黒沢作品には反省・改心・希望という建設的なメッセージがある。 (つづく)
2009.04.26
コメント(0)
-
『トウキョウソナタ』黒沢清監督(2008日本)その5
トウキョウソナタ 黒沢清監督 (つづき)-その5- 制限字数で途切れてしまったけれど、母・岸恵子と暮らしていた娘・デルフィーヌは一人暮らしを始める理由として、「お母さんといると自分が自分でいられない。」と言った。良くも悪くも、親と一緒にいると、子供はどこかで、多かれ少なかれ、親の目に写る子供を演じてしまう。それは良い子を演じるという場合だけではなく、親に反抗的な場合も同じことだ。もちろんこれは親でないルームメイトや恋人との同居の場合も似ているが、本質は違う。この場合は自ら選んでの人間関係であり、解消も可能だが、親の場合は与えられた、解消不能の関係であり、それは無言の心理的圧力をともなっている。特に子供の側に。 家族のあり方、人間関係や社会のあり方で、どちらが正しいといったことは簡単には言えない。オーストラリア人である原脚本家が日本人のあり方に自分との違いを感じたのは当然だとしても、明確に意識しているかどうかは別として、この日本人あり方に違和感を感じている日本人が少なからずいることも確かだ。自分はそうだし、黒沢監督もそうだろう。 この物語は、各人の個性化(個性実現)の上に新しい家族関係を再構築するという物語なのだ。映画には竜平と同じように会社をリストラされ、やはり家族には言えずにフェイクの生活を続ける黒須という人物が登場する。しかしこの家族は、黒須も妻も娘も、家族内の役割を演じることにしがみつき、それぞれの個性実現による新しい家族関係の構築ができなかった。それは不幸な結末を迎えることになるのだけれど、役割主義の破綻ということだ。映画前半を見ていて、それは(写実的あるいは自然主義的という意味で)リアリティーがあるようで、黒沢的非現実感の濃い世界でもあるのだけれど、いったい黒沢監督がどうこの物語を後半からラストに向けて展開するのかが興味津々だった。そうしたらやはりやってくれました。ただでは済まない黒沢監督の「映画」でした。これまでのホラー・サスペンス系の黒沢作品を裏切らない「黒沢映画」の世界。役所広司の登場と同時に正に黒沢清独特の映画世界に突き進んでいく。 (つづく)
2009.04.26
コメント(0)
-
『トウキョウソナタ』黒沢清監督(2008日本)その4
トウキョウソナタ 黒沢清監督 (つづき)-4- つまりここに描かれる竜平の失業や家で父親の権威をふるうことも、健二のピアノや貴の外人部隊志願も一つの契機であり、物語を進める素材であって、それを使って描かれるのは、家族内の役割に埋没した4人が、一人一人の個人を生き、その上で家族を構成するという、家族のあり方の変質なのだ。若い息子2人は自らそれを始めるが、竜平にとってはリストラ・失業というショック、恵には後半で描かれる事件が必要だった。「誰かここから引き上げて~!」と恵が悪夢に魘されるように、自分だけでは現状からなかなか脱出できない。 この映画の原脚本を書いたのは東京に居たことのあるマックス・マニックスというオーストラリア人。それを黒沢清監督と弟子の田中幸子が加筆・修正した。マニックスが日本の家族や夫婦・親子関係に見たもの。そしてそこに黒沢監督が興味を感じたもの。それは没個性を前提とした、役割主義ではないだろうか。健二は音楽あるいはピアノに類稀な才能を持ち、本人もその実現を欲した。しかしこの家族内で求められるのは、そんな自己実現ではなく、単に従順な子供という家族内での役なのだ。 健二はある経緯から学校で担任教師の実像を暴いてしまう。同級生たちは「革命だ!」と騒ぎたてるが、何が革命なのかと言えば、先生と生徒という役割主義の破壊なのではないだろうか。先生という役の担任と、生徒という役の健二が、先生と生徒という関係を演じるのではなく、生の人間としての担任の姿を剥き出しにしたのが健二の行為だった。そしてこの構造はメインの物語である佐々木家の物語と相似なのだ。 オーストラリア人が日本の社会に見て感じたこと。ボクとしてはもう連想するに事欠かない。それは例えばもう半世紀も前に丸山真男が『「である」ことと「する」こと』で指摘したことにもつながるのだけれど、ここではやや脱線気味だが岸恵子の書いていることをちょっと取り上げよう。岸恵子はフランス人映画監督イヴ・シャンピと離婚後、娘デルフィーヌと二人で暮らしていた。ある日デルフィーヌは一人暮らしを始めると言いだす。岸は一緒にいれば良いじゃないと言うが、娘は「お母さんといると自分が自分でいられない。」と言った。別に二人は親子として仲が悪かったのではない。 (つづく)
2009.04.26
コメント(0)
-
『トウキョウソナタ』黒沢清監督(2008日本)その3
トウキョウソナタ 黒沢清監督 (つづき)-3- さてそんな佐々木家だが、家族としては崩壊寸前、あるいは実質的に既に崩壊しているかも知れない。それをなんとか家族としてまだ成立させているのは、「お母さん」たる恵(小泉今日子)だろう。ここまで見てきたように、父と長男、父と二男の2つの親子関係はほぼ崩壊している。積極的悪意はないが、長男と二男の兄弟関係もないかのごとくだ。この2人が関わるシーンはたぶん1回もなかった。それに対して、恵は竜平の妻であり、貴の母でも健二の母でもある。 竜平の妻が恵で、その恵の息子が貴で、だから恵を仲介として竜平と貴は親子であり、また貴も健二も恵の息子だからやはり恵を仲介として2人は兄弟だという具合だ。「お母さん役も悪いときばかりじゃない」といったこの恵のセリフがあったが、正に恵はお母さん役を担うことで家族の軸となっている。 そんな恵ではあるけれど、彼女はアイデンティティー・クライシスにある。彼女は最近運転免許を取った。身分証明書として健康保険証ではなく自分一人のものが欲しかったと言う。健康保険証は竜平を筆頭人として家族4のものだ。つまりそれは彼女本人を証明するものではなく、佐々木家という家族の妻であり母であるという位置を示すだけだ。専業主婦だから家族と切り離された彼女だけの「佐々木さん」という顔を職場で持つこともない。しかもそのお母さんという役にしても「悪いときばかりじゃない」ということは「良いときは少ない」ということでもある。 竜平は総務部長としてそれなりに必要な仕事をしていたのだろう。しかしそれは研究・開発とか、宣伝とか、売り込みとか、そういう具体的に形をなす職種ではなかった。だから再就職の面接で何が出来るかと問われても、「人間関係を円滑に取り持つ」ことができるといった曖昧なことしか言えない。そして家でも、家父長的に権威をふるうという形で「一家の主人」「父親役」を演じてたに過ぎない。恵は恵で「母親役」を演じる。そんな母に貴は「離婚しちゃえば」と言う。貴は「まだイケテルよ」とも言う。これは一人の人として、あるいは女としてまだまだ十分に魅力があるという意味だろう。良き(?)息子という家族内の役割から脱して自分を生きようとしたのが貴のアメリカ外人部隊への志願であり、健二のピアノだ。 (つづく)
2009.04.26
コメント(0)
-
『トウキョウソナタ』黒沢清監督(2008日本)その2
トウキョウソナタ 黒沢清監督 (つづき)-2- 会社をクビになったなんて言えないし、竜平としては然るべき、つまり(彼の価値観から)家族に対して権威を落とさないような再就職ができてから偉そうに話をしたかったのだろうけれど、この不景気のご時世、ハローワークは長蛇の列で、そんな都合の良い再就職なんてできはしない。なんとか得られたのはショッピングモールの清掃員の仕事。竜平は毎朝背広を着て出勤し、今まで通りを装った日々を送る。 大学生の、でも未成年という設定だから18か19の長男・貴(小柳友)。こういった青年が今時どれぐらいいるのか?、なんて言ったら怒られるかも知れないが、若者らしく理想主義的で、世界・社会の現実に疑問を感じている。アメリカ的自由とか民主主義を正しいと信じていて、アメリカで新しく始まった外国人兵士部隊なる制度に志願して、アメリカ軍としてイラクに戦いに行こうと考えている。自分が世界のためにできることを求めている。他の方策もあるらしいが、未成年だから原則的には親の承諾が必要だ。もちろん竜平は頭ごなしに駄目と言うだけ。息子の話をしっかり聞いて説得するというような本当の意味での親(家父長)の権威ではない。子供の意見をちゃんと聞かずに、ただ反対して従わせるのが権威だと思っている。でもそんな「空権威」であることは息子・貴にも既にお見透し。話が通じるとすればそれは母・恵だということを知っている。母を説得して貴はイランへと旅だっていく。 健二(井之脇海)は小学校の6年生。こんな家庭に育っているからか、大人の欺瞞は知り過ぎている。やはり空権威の担任教師の欺瞞を暴くようなことをするから、その担任にとっては煙たい存在だ。そんな健二はピアノ教師(井川遥)が自宅でピアノのレッスンをしているのを通りから聞き・眺めるのだった。健二はピアノを習いたいと思うが、これまた父・竜平は頭ごなしに「ピアノは駄目だ」だった。健二は給食費として親から預かったお金を月謝として払い、密かに金子先生にピアノを習い始める。 (つづく)
2009.04.26
コメント(0)
-
『トウキョウソナタ』黒沢清監督(2008日本)
トウキョウソナタ 黒沢清 TOKYO SONATA Kiyoshi Kurosawa 119min(1:1.85) (桜坂劇場 ホールCにて) 1月に見て、まだレビュー書いていませんでした。なかなかの秀作。橋口亮輔の『ぐるりのこと。』、是枝裕和の『歩いても 歩いても』の2本と合わせて最近の家族物の日本映画として比較している人もいて、その大方は『歩いても 歩いても』をいちばん評価し、この『トウキョウソナタ』をいちばん下位に位置付けている。『ぐるりのこと。』は結局見に行かなかったけれど、予告編から想像するに軟弱過ぎる感じ。だいたいタイトル最後に「。」を付しているのが気に入らない。モーニング娘でもあるまいし…。とは言っても見ていない作品の評価はできないからこれは除くとして、自分としては黒沢作品は是枝作品より遥か遥かに良い映画でした。 家の中に風が吹きこんで新聞紙が飛ばされる。カメラがスーっと横にパンしていくと外は突然強い雨が降り出し、開いた窓から雨が入っている。急いで窓を閉め、濡れた床を拭く女。彼女はふと何を思ったか、窓を再び開くと雨に濡れるがままに身を任せるのだった。 こんな出だしだったと記憶しているけれど、いきなり見ている自分は「映画という世界」に引き込まれる。「映画の物語の世界」という意味ではなく、自分は映画を見ているのだという「映画という世界」にだ。 こうして始まった「映画」は前半で、この佐々木家の主人・妻・長男・二男の4人の現在や性格や互いの関係を丁寧に描いていく。家父長的権威をかざすお父さん・佐々木竜平(香川照之)。家族揃った夕飯の食卓で一人ビールを旨そうに飲むのだけれど、妻や息子たちはそのお父さんが食事に箸をつけるまでじっと待っている。まあ多分に戯画チックだけれど、このようにジョークとシリアスの混交したような描写は黒沢監督の世界だ。例えば暗そうなことをユーモラスに描くから表面的にはあまり暗くならない。でも実はしっかりとその暗さは描いてしまう、とかだ。 そんなお父さん・竜平なのだけれど、ある日突然会社(計測器メーカーのタニタということになっていた)をリストラされてしまう。総務部長(だったか課長?)だった彼、仕事の調整役、いわばなんでも屋で、具体的専門職ではないからハローワークでの再就職も難しい。 (つづく)
2009.04.26
コメント(0)
-
『シェルブールの雨傘』ジャック・ドゥミ監督(1964フランス)その4
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG (つづき)-4- ド・ゴールがアルジェリアの独立を承認したのは、いずれ民族自決が必至となるだろうという認識もあったが、膨らむ一方の戦費への懸念が背景にあった。フランスの物語に時々使われる展開ではあるが、恋人たちの不幸の要因となったもう一つは、多額の税金の請求が突然ジュヌヴィエーヴの母を襲ったことだ。戦費が膨らむから国は未納の税を1フランでも多く取ろうとしたのだし、そうして取った税金はアルジェリアで使われるということでもある。そういう意味でこの若い二人の悲恋物語を構成したのは、1から10までアルジェリア戦争という当時の社会的・政治的・歴史的な状況だったのだ。 もう一つこの物語で見落とすわけにはいかないのは社会階層の問題だ。映画冒頭から感じるのは、肉体労働者たるギイ、病気の叔母、その世話をするマドレーヌの生活と、ジュヌヴィエーヴや母のブルジョワ的生活の対比だ。日本ではお金持ちか貧乏人かという差でしかないが、ここには純然たる「階級」差がある。 この映画よりも後の時代だけれど、ボクがパリの小学校に通っていた頃、ブルジョワ階層の子供と労働者階層の子供の間にはほとんど交流はなかった。単に金があるかないかではなく、生活文化が全く違うから接点自体がない。だからもう何十年か前にこの映画を(恐らくテレビで)初めて見たとき、この身分差の恋に先はないだろうと冒頭から感じた。 「若すぎる」と言うだけで、母は階級のことなど言わないが、根本にあるのはそれだったはずだ。そしてそれは母だけの意識ではなく、ジュヌヴィエーヴにとっても実はそうなのだ。彼女に悪気はないが「あなたはいつもガソリンの臭いがするのね。」「これが僕の香水だ。」というセリフがあったと思う。こんなところに何気なくそれが表現されている。二人が愛し合ったことは事実だけれど、最後のガソリンスタンドのシーンは二人がそれぞれ収まるべきところに収まったことを示している。ギイにふさわしいのはマドレーヌであり、ジュヌヴィエーヴにはカサールなのだ。 いちばん最初にミュージカル映画が苦手だと書いたが、この作品はこうして深い背景の下に描かれているので抵抗が少ないのかも知れない。
2009.04.19
コメント(5)
-
『シェルブールの雨傘』ジャック・ドゥミ監督(1964フランス)その3
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG (つづき)-3- ブノワ・マジメルの映画が描くのは1959年のアルジェリア。事態がいちばん泥沼化していた頃だ。ゴダールが1960年に撮った『小さな兵隊』は1958年の話。フランスでは撮れず映画の舞台をスイスのジュネーブとした。この映画はフランスで1963年まで公開禁止だった。その間に何があったかと言えばド・ゴールが大統領に強権集中させた第五共和制の大統領となって、1960年にアルジェリア独立を承認、1962年にはエヴィアン協定の成立。映画『ジャッカルの日』に代表されるようなド・ゴール暗殺未遂事件は何度も起きている。 『シェルブールの雨傘』はセリフのすべてが歌われる、いわばオペラ形式(オペラにはジングシュピールなど歌わないセリフのあるのもある)。映画冒頭で自動車修理工達の「オペラを観にいく」「ボクは映画だ」という会話はこの作品に対する監督の思いの表現だろう。きっとオペラの第一幕、第二幕…というのにならって監督は旅立ち・不在・帰還という三部構成をとる。しかし各々は「1957年11月」「1958年1月」「1959年1月」と明確な日時が付されている。この日付は、単なる悲恋ストーリーとして映画を観るだけなら不必要だ。そんなに込み入った筋ではないから、日付など示されなくとも時間の経過はごく自然に理解できる。 きっと監督にはこの物語をアルジェリア戦争の推移の中に位置付けようという意図があるのだ。そして二人が再会するエピローグはアルジェリア問題の一応の解決の後の1963年クリスマス。この年にはゴダール作品の公開禁止も解かれている。 ギイがシェルブールに戻っとき、怒りやすいとか、彼が前とは変わったと周囲は言う。帰ってきてみれば、恋人が別の男と結婚してしまっていたのだから荒れるのも当然だろう。だがここに描かれるのは今ならPTSDと呼ばれるようなことかも知れない。1962年アラン・レネは『ミュリエル』にそういう帰還兵ベルナールを登場させた。 (つづく)
2009.04.19
コメント(0)
-
『シェルブールの雨傘』ジャック・ドゥミ監督(1964フランス)その2
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG (つづき)-2- 話は少しずれるけれど実は1964年のこの作品は、1961年ドゥミ監督の第一作『ローラ』、1968年の『モデル・ショップ』と合わせた三部作だった。『ローラ』はドゥミ監督の出身地ナントが舞台で、ローラ(アヌーク・エメ)はこの港町で歌い手でもあり船員相手の女でもある。そんなローラの幼なじみが『シェルブール』でドヌーヴと結婚する宝石商カサールで、ローラを愛するけれど失恋する。『シェルブール』の中でカサールの語る過去の恋の傷とはこのローラとの物語なのだ。この『ローラ』の中でも同じマルク・ミシェルが同じロラン・カサールという役を演じている。ちなみにアヌーク・エメ演じるローラは第三作『モデル・ショップ』ではヌードモデルのようなことをしている。また時間の整合性は欠くが、『ロッシュフォールの恋人たち』の中の女性バラバラ殺人事件の被害者はこのローラと思われる。 あまりにも有名で『シェルブールの雨傘』は独立した一話だけの物語と思われ勝ちだし、そうするとギイ不在の間に金の力を利用してジュヌヴィエーヴと結婚してしまうカサールを、この物語の中で若い二人の純愛を裂く役割を担っているだけの役のように感じる人もいるかも知れないが、実はカサールという人物は、少なくとも監督の意識の中では、血も肉もある生きた人物なのだ。 そしてこの映画の撮影は1963年夏で、物語は1957年11月から1963年クリスマスまでを描いている。ギイが不在となるのは兵役ゆえであり、アルジェリアに送られる。我々日本人にとって、さらに21世紀の大方の我々日本人にとっては、兵役だアルジェリア戦争だと言っても、それはジュヌヴィエーヴとギイの悲恋の原因となる単なる戦争という意味しか持たないだろう。しかし63年にこれを撮った監督にとっては、そして64年にこの映画を観たフランス人にとっても、それはかなりリアリティーを持ち、またまだ後を引いていた大事態だったはずだ。21世紀の今でも、1974年生まれで直接には全くこの戦争を知らない俳優ブノワ・マジメルに映画『いのちの戦場 -アルジェリア1959-』を作らせてしまう戦争なのだから。 (つづく)
2009.04.19
コメント(0)
-
『シェルブールの雨傘』ジャック・ドゥミ監督(1964フランス)
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG Jacques Demy (Michel Legrand) 91min(1:1.66) (桜坂劇場 ホールCにて) この名作映画を見るのは何回目だろうか。3度目ぐらいか。でも劇場で見るのは初めて。もしかしたら全くのノーカット版で見るのも初めてなのかも。見憶えのないシーンがあった。ミュージカルとオペラの違いについてはいずれ別稿で書きたいと思っているけれど、とにかく元来ボクは大のミュージカル嫌い(オペラは好きだけれど)。でもこの映画の場合はミュージカルであることにあまり抵抗がない。 さてさて、18か19の若きカトリーヌ・ドヌーヴの美しさとか、この悲恋物語のほろ苦さを今さら書いてもしょうがないし、と言うかそんなことを書くのも気恥ずかしいので、ちょっと別のことを書いてみようと思う。 映画っていうのには普通、表面的な物語があって、それには登場人物の心理とかも含まれるけれど、そして作品によってはかなり意図的に何かを比喩的に表現しようとしている場合もある。それとは別に、あるいは重なって、物語の背景などに対する監督とかの思想・心情が、時に意識的に、時に無意識的に表現されている。 そしてもう一つフランス人文化の特色。理屈っぽいとも言えるが、みんなが一角の「自分の意見」を持っている。関心の対象は政治であったり哲学であったり。映画監督なんていうのは表現者だし知識階層でもあるから尚更だ。だから単なるラブストーリーでも背景にはそうした監督の思想が強く反映されていることが多い。そして観客は観客で作品の持つそういう面に強い関心を持つ。だからもちろんこの映画は感動的な悲恋物語ではあるのだけれど、上っ面のそうしたストーリーだけではなく、社会の背景のようなことがしっかりと描かれている。 (つづく)
2009.04.19
コメント(0)
-
『シャッフル』メナン・ヤポ監督(2007米)その3
PREMONITION Mennan Yapo (つづき)-3- ここから先はほぼネタバレになります。 リンダとジムは幸せな結婚をした。愛らしい2人の娘にも恵まれ、幸せなはずの日常だった。しかしそれは何時しか惰性にもなり、二人は大切な何かを忘れかけていた。夫婦は何時の頃からかセックスレスで、夫は会社の女性アシスタントと不倫の一歩手前。水曜日の1泊出張では同じ部屋に泊まって不倫が実体化するはずだった。そんな折リンダは予感の1週間をシャッフルされて生きることになる。 夫の死を知らされた木曜日から映画、あるいは彼女の予感の生は始まるけれど、週がシャフルされているらしいことにやがて気付いたリンダは、まだやってきていない日曜日や水曜日に、生き方や運命を変えようと努力する。最初の日曜日には休みの夫を娘たちと久しぶりに十分な時間を過ごさせる。晩には娘たちへの愛を確認させる。 惰性の日々に忘れていた夫への愛を再認識し、夫もそのことに気付いて夜二人は何ヶ月ぶり?、何年ぶり?にベッドで結ばれる。出張の日家を後にした夫は生命保険額を3倍にし、アシスタントには電話で夜の逢瀬を断る。 この日リンダがしようとしたのはもちろん夫の事故を阻止することだ。リンダは車で夫を追った。そして携帯電話で愛を確認し合い、二人は幸せだ。しかし根本の運命を変えることはできなかった。追いついたリンダの見ている前で、エンストした夫の車にタンクローリーが衝突して2台とも激しく炎上してしまう。 再びベッドで目を覚ますリンダ。家具などがない。娘が引越しのトラックの到着を告げる。起き上がった彼女のお腹は大きかった。愛を再確認し合った夜の結晶だ。リンダは明るかった。恐らく幸せでさえあった。目には見えない何か、それは死んだ夫の自分や娘たちに対する愛、自分の夫や娘たちへの愛を信じることが出来たからだ。 ベルイマンなどの神の不在やら沈黙。それはこの映画でもリンダと神父の会話で語られるように、何かを信じるということの不在であり、現代西洋文明や物質文化に於ける人々の不幸だ。信仰の対象はキリスト教やイスラームの神である必要はない。しかし人は信じる何かがなければ幸せたり得ない。それを人の死と絡めて描いている点がファティ・アキンともつながり、アジア的なのかも知れない。
2009.04.14
コメント(4)
-
『シャッフル』メナン・ヤポ監督(2007米)その2
PREMONITION Mennan Yapo (つづき)-2- この映画の原題はPREMONITION。予知とか予感といった意味。見ていないのだけれど鶴田法男監督のJホラーに『予言』というのがあって、欧米では同じ「PREMONITION」という題だった。この『シャッフル』は『予言』のリメイクではないが、着想としてヒントになったらしい。電話ボックスでふと目にした新聞に娘の事故死の記事があり、娘一人を中に残してきた車を見るとトラックが衝突して炎上してしまう。なるほど『シャッフル』に似ている。 IMDbでこの映画の評価(観客の採点)を見ると大多数は5点~6点の低評価だが、それに10点~9点の少数の高評価が重なったような点数分布になっている。その差はこの映画に期待したもの、あるいはどういう映画として捉えたかの差ではないかと思う。スリラー、サスペンス、ホラーを期待したのではきっと物足りないのだろう。しかしこの作品はサスペンス性を物語の牽引力にしてはいるが、テーマは愛の更新・再建であり、あるいは愛といった目に見えない絆や信仰の意味を問うものなのだ。 しかし日本のチラシを見てもそのことには全く触れられていない。「並び替えられた1週間 ― その謎を解けば、運命は変わる」であり、「映画における "新たなストーリーテリングの可能性" に挑んだ、衝撃の未体験ストーリー!」とあるだけで、人間ドラマとしての内容ではなくサスペンス性、スリラー性が歌われているのみだ。 監督の名など無関心に見たこの作品。ちょっと変わったメナン・ヤポという名は知らなかった。アメリカ映画ではあるけれど、メナンというのはアラブやイスラーム系なのか?。調べたらトルコ人を両親に西ドイツのミュンヒェンに生まれたドイツの映画人。『そして、私たちは愛に帰る』のファティ・アキン監督と同種の境遇の人。戦後の経済成長時に労働力の不足を埋めるため大量に受け入れたトルコ移民は、その後ドイツにとって経済や文化や社会的に制約・拘束となるけれど、このアキンやヤポの映画を見ていると、異文化を持ちながらドイツ文化に同化することでドイツ文化に新たな豊かさをもたらしている感じだ。2人とも現代のドイツ映画界を担った存在らしいけれど、これまでのドイツ映画にはなかったものを持っている。 (つづく)
2009.04.14
コメント(0)
-
『シャッフル』メナン・ヤポ監督(2007米)
PREMONITION Mennan Yapo 96min(1:2.35) (桜坂劇場 ホールCにて) この映画、自分が見るような映画ではない、少なくとも予告編やチラシで配給会社が「売り」にしているような作品なら自分が見にいくような映画ではないと思ったのですが、その予告編を見て何かヒッカカりました。2~3のブログのレビューを見ても低評価だし、東京の映画館でも不人気で早々に上映を打ち切ったというし。サンドラ・ブロックのファンではないし、見に行こうか迷った日の那覇は土砂降りの雨。それでも見に行ったのは一種の勘。良い作品で儲けものでした。 予告編というのは映画の映像から作られているから、予告編製作者の意図とは別に、その作品の質のようなものを垣間見る、推定することが出来る。予告編というのはまあ一種の客引き誇大広告のようなものだから、その作品の実体を見抜こうとするのがボクの予告編の見方です。 映画は10年弱前の回想シーンに始まり、最後には半年後ぐらいを描いた短いエピローグがあるけれど、メインは2児の母親リンダの日曜から土曜の1週間が描かれる。最初は木曜日で、夫ジムは前日から1泊の出張で不在だけれど、2人の娘を小学校に送っていったり、家事とかの日常。ただ夫からの意味不明な留守電がちょっと気になる。すると玄関のチャイムが鳴って、ドアを開けると保安官がいた。保安官は彼女がリンダ・ハンソンだと確認すると、ご主人のジム・ハンソンは昨日交通事故で死んだと告げる。ところがその晩寝て翌朝目が覚めると階下には夫がいてテレビを観ている。そしてそのまた翌朝リンダが目を覚ますと夫は死んでいて、階下には親族・友人が喪服を着て集まっている。 実は日曜から土曜までの7日間がシャフルされ、リンダは順不同にそれを生きる。これは映画の話法ではなく、リンダの意識としての順だ。だから例えば2日目に階下に降りて行くとき彼女は夫は事故で死んだと思っているが、テレビを観ている夫というのは事故以前の日なのだ。 この謎解きサスペンス、あるいは一種の心理ホラーゆえに、曜日が順不同に混ぜこぜになっていることを捉えたのが、あるいはそれをこの映画の売りにしようとしたのが『シャッフル』という邦題だ。 (つづく)
2009.04.14
コメント(0)
-
『そして、私たちは愛に帰る』ファティ・アキン監督(2007ドイツ・トルコ)その5
AUF DER ANDEREN SEITE Fatih Akin (つづき)-5- この映画は、社会、それは政治であったり、宗教、体制、文化であったりするのだけれど、それがいかに個人を縛り、それ故に世界や人々が不幸であるか、それからの解放を人の愛、愛と言わないまでも相互理解に希望するかの物語であるように思う。3組の親子が登場するけれど、イェテルとアイテンは映画の描く時間の中では出会うことはない。この二人の間には最初から愛が存在しているからだ。しかし他の2組の親子は映画の最初と最後で変質する。 この映画の中では制度や社会はむしろ負の側面が描かれる。非民主的でクルド人や民主化運動を弾圧するトルコ政府。政治亡命という制度を持ちながら、帰国すれば不当に重い刑を課せられると知りながらアイテンの亡命申請を却下するドイツ。事情無視で宗教的にイェテルをなじる2人のトルコ人。過去を忘れてトルコ人移民の存在を迷惑がるドイツ社会に同調しているだけのズザンネ。 他方個人は正の側面が描かれる。困っているアイテンに手を差しのべるロッテを筆頭に、警察に追われるアイテンを屋上に逃す婦人、制度上は当然何も出来ないけれどロッテに協力的情報を与えてくれる領事館職員。 男たちが同じ方向に歩いて行くのを窓から見たズザンネがネジャットに「みんな何処に行くの?」と問う。「モスクです。今日は犠牲祭なので。」イブラーヒーム(アブラハム)は息子イスマイール(イシュマエル)を神に犠牲として捧げるお告げを夢に見る。信仰の証しとしてイブラーヒームがイスマイールに剣を振り下ろしたとき、剣の先が丸くなった。これを記念したのが犠牲祭(代わりに羊を捧げる)。「子供のころ、父は神を敵に回してもお前を守る」と言ったとネジャットは語る。ここに読み取れるのは、宗教(制度)に対する個人の愛の優位ではないだろうか。イェテルの死が人々をトルコに集めた。ロッテの行動、そして結果的にその死が、ロッテとズザンネ、アイテンとズザンネ(メタファーとしてはトルコとドイツ、更にはアジアとヨーロッパ)の愛や理解や和睦を再構築した。そして更にアリとネジャットの関係の再構築の希望を準備する。この映画は親子といったプライベートな愛を通して、実は異文化社会の相互理解や和合の期待を描いているのだと思う。
2009.04.08
コメント(2)
-
『そして、私たちは愛に帰る』ファティ・アキン監督(2007ドイツ・トルコ)その4
AUF DER ANDEREN SEITEFatih Akin(つづき)-4-〔以下ネタバレ含む〕最初に書いたように映画は3組6人の親子を描く。互いに知らずに深く関係しているとも書いたが、ボクの感想を書くためにネタバレしてしまおう。(以下完全ネタバレ)身勝手なアリに愛想を尽かしてイェテルは出て行こうとするが、カッとなったアリはイェテルを叩き、たまたま打ち所が悪く彼女は死んでしまう。出所後アリは本国送還になって故郷のトルコ・フィリオスに帰る。息子のネジャットはイェテルが娼婦までして仕送りをしていた娘アイテンのことが気にかかり、自分が援助しようとイスタンブールでアイテンを捜すが見つからない。彼はイスタンブールに来て自分のアイデンティティーに疑問を感じてドイツ語書籍の書店を買い取って住み着く。そのアイテンはトルコ警察を逃れてドイツにいたが、ロッテと親密になっていた。しかし不法入国者としてドイツ警察に捕まり、ロッテの援助で政治亡命を申請するが却下され本国送還となる。もちろんトルコに戻ると政治犯として逮捕され、刑期は15年とも20年とも分からない。ロッテはアイテンを愛していたから(これを単なる同性愛と捉えるのは単純に過ぎる)、母ズザンネの反対を押し切ってアイテンを救おうとイスタンブールに行く。何ヶ月もの時間を要するのでロッテは間借りをするが、貸すのはネジャットだった。しかしネジャットは、そのロッテが自分の父が殺してしまったイェテルの娘アイテンを出獄させるために来ているなど知る由もない。しかしひょんな偶然からロッテはアイテンが警官から奪い隠していたピストルで殺されてしまう。行き場のない悲しみを抱えて母ズザンネがイスタンブールにやってくる。娘の暮らしていた部屋が見たいと彼女は貸し手ネジャットと会う。ズザンネは娘を失ってその気持ちを理解し、娘の意思を継いでアイテンの出獄に尽力する。ドイツ人女性が射殺されたことはドイツとの外交問題にもなり兼ねず、転向を条件にアイテンはあっさり釈放され、かつては相容れなかった反欧米のアイテンとトルコ嫌いズザンネは抱き合って和解する。死んだ娘を思うズザンネと接したネジャットが海峡を渡って父アリに会いに行くところで映画は終わる。(つづく)
2009.04.08
コメント(0)
-
『そして、私たちは愛に帰る』ファティ・アキン監督(2007ドイツ・トルコ)その3
AUF DER ANDEREN SEITE Fatih Akin (つづき)-3- 前回奇妙な邦題と書いたけれど、ドイツ語原題 AUF DER ANDEREN SEITE は、拙いボクのドイツ語力で解釈すると、反対側(別の側、もう一方の側)に(では)ぐらいの意味ではないだろうか。映画は一種の枠のようなものを持つ構成だ。犠牲祭に車で何処かへ向かう男(実はネジャット)がトルコの何処かのガソリンスタンドで給油するシーンで映画は始まる。場面はガラッと変わって北ドイツはブレーメン。市庁舎広場のブロンズの音楽隊像がチラッと写るのでそれとわかる。それからブレーメン、イスタンブールと6人の物語が描かれ、最後にまた冒頭のシーンがそのまま戻ってくる。そしてその後のエピローグへと続く。この男(実はネジャット)はイスタンブールからダーダネルス海峡を渡って、今は父のいる小アジア・アナトリアのフィリオスに向かっていた。ドイツ語原題は、一つには海峡の反対側を意味しているのではないだろうか。つまり海峡を隔ててヨーロッパ側からアジア側へ向かう。ある理由でトルコにやってきたネジャットはイスタンブールに留まってドイツ語書籍の書店の経営を始めたわけだけれど、その彼が文字通りヨーロッパからアジアへ向かうのがこの映画の大枠にあるのである。 前回トルコのEU加盟是非論に触れた。そして冒頭には監督やネジャットがドイツ生まれのトルコ移民二世であると書いた。教養はゲーテを講義するドイツ人でありながら、別の文化的ルーツとしてトルコ人やムスリムであるという、バイリンガルなだけでなくバイカルチャーであるのが彼らだ。父アリのイェテルに対するあり方の背景にはイスラーム社会の男尊女卑性があるかも知れないし、息子ネジャットがこの父親と相容れない心情はここにも原因があるかも知れない。またイスラームでは売春は罪だから、トルコ女性イェテルが売春をしているのを知った2人のトルコ人男性は電車の中まで見知らぬ彼女をつけ回して非難・説教をする。あるいはこのどちらの背景にもイェテルがクルド系であるという差別意識があるのかも知れない。 これまで脈絡もなく羅列するように書いてきた様々なこと、それらは愛の再構築というこの物語の背景ではない。すべては物語の本旨と切り離すことはできず、互いに深く結びついている。 (つづく)
2009.04.08
コメント(0)
-
『そして、私たちは愛に帰る』ファティ・アキン監督(2007ドイツ・トルコ)その2
AUF DER ANDEREN SEITE Fatih Akin (つづき)-2- ズザンネはロッテの父親と離婚している(あるいは結婚に至らなかったシングルマザーだった?)が、娘が見知らぬトルコ女性を助け、家に住まわせて面倒を見、仲良くしていることを快くは思っていなかった。 映画はこの6の人生が、それと互いに知らず交錯していく様子を、時間がやや相前後しながら描いていく。そしてそれは奇妙な邦訳タイトルが示すように、親子の絆などの愛にたち帰る、あるいは再構築する流れなのだけれど、これ以上ストーリーを書くと完全ネタバレになってしまうので、もっと別のことを先に書いてみることにする。 この映画のことを調べていて、と言ってもボクはドイツ語をスラスラとは読めないので当のドイツではなくフランス語の批評やブログなどが主なのだけれど、そうしたレビューの基調は日本と同じでも、やはり日本人のレビューとは違ったことがたくさん書かれているのを目にした。それは異文化問題であり、トルコ問題であり、とりわけトルコのEU加盟の是非の議論と関わることだ。 ここ何年にも渡って、そして古くにさかのぼれば45年以上前の1963年頃からトルコの欧州加盟は燻り続けている。トルコという国はヨーロッパとアジアに跨がっている。ボスポラス海峡・マルマラ海・ダーダネルス海峡の西側のトラキア(面積としてはトルコ全土の3%)がヨーロッパ、残りのアナトリアはアジアに属する。宗教的には国民の99%がムスリム(主にスンナ派)。60年代に不足した労働力として西ドイツは多数のトルコ移民を受け入れた。やがて低成長になったけれど追い出すわけにもいかず、現在ドイツには300万近くのトルコ系住民がいる。 フランスやドイツにはトルコのEU加盟に反対する人も多い。軍事的にはNATO加盟国で、親米&親イスラエル。歴史的にはオスマン帝国侵攻の脅威の記憶もあるし、EU加盟の最大人口国となる国の国民がほぼイスラームだということにも抵抗があろう。具体的にはキプロス問題はあるし、クルド人の扱いに関する問題、そして西欧基準からは決して達しているとは考えられない人権や民主化。一方ではクルド人差別が問題にされ、他方ではトルコ内でもより保守的で男尊女卑的クルド系国民に対する非難もある。 (つづく)
2009.04.08
コメント(0)
-
『そして、私たちは愛に帰る』ファティ・アキン監督(2007ドイツ・トルコ)
AUF DER ANDEREN SEITE Fatih Akin 122min(1:1.85) ドイツ語・トルコ語・英語 (桜坂劇場 ホールCにて) 久しぶりに身を任せて見て、素直に感動を持った映画でした。もちろんボクがこう言うのは、単純な感動大作とは似てもつかないものです。そういう子供騙しは見ていてただシラケるだけのひねくれた自分です。チラシや予告編を見て当たりか外れのどちらかだと予測していたのですが、当たりの方でした。ファティ・アキン監督作品を見るのは初めてです。 このアキン監督、トルコ移民二世として(西)ドイツに生まれ育った、どう言えば良いのか、トルコ系ドイツ人(?)。同性の親一人・子一人の3組6人の物語だけれど、一応の主人公ネジャットの位置付けに監督自身の反映があるかも知れない。父親アリはトルコからの移民労働者で、今は引退して年金暮らし。息子ネジャットの方はドイツ生まれかごく幼い頃からドイツに暮らす。大学の講師でゲーテなどを講義しているから知的文化としてはドイツ人のインテリだ。父親アリはもっとトルコ人であり、学問などない平凡な男。特別に仲が悪いわけではないが、知的にも文化的にも接点がない。 ネジャットはハンブルク暮らし。アリは汽車で1時間弱のブレーメンに一人暮らし。妻(ネジャットの母)は息子がごく幼い頃に死んでいた。寄る年波に孤独や故国への思いも感じる日々。そして偶然見つけたトルコ出身の娼婦イェテルを囲って一緒に暮らし始める。 イェテルは一人娘アイテンをトルコに残してきていて、ブレーメンで靴店で働いていると偽り、学費などを仕送りしていたが、もう何年も会っていなかった。トルコでそのアイテンは反政府政治活動をしていた。この母娘はクルド人だ。 アイテンはイスタンブールでのデモで警察に追われる身となり、仲間の手引きで偽名を使ってドイツに逃れた。彼女はブレーメンの靴店をシラミ潰しに回って母イェテルを探すが見つかるはずもない。一番安いと教えられた大学の学食で食事する3ユーロの金ももうなかった。そこで彼女に出会い、事情を察して手をさしのべたのがドイツ人女子学生のロッテ。ロッテは母ズザンネとブレーメンに暮らしていた。 (つづく)
2009.04.08
コメント(0)
-
『画家と庭師とカンパーニュ』ジャン・ベッケル監督(2007フランス)その5
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER Jean Becker 105min(1:2.35) (桜坂劇場 ホールCにて) (つづき) さてタイトル考に戻って邦題『画家と庭師とカンパーニュ』。画家と庭師を列記することで、この映画が画家と庭師の二人の物語ではなく「うちの庭師」と言っている画家の物語であることを見えにくくしている。またカンパーニュ(田舎、カントリー)を付したことで、いたずらに田舎がテーマであるように感じさせてしまう。しかしこれも「パリ人が見た」田舎なのだ。 「ワインやボウルで飲む朝食のカフェオレ。正にフレンチ・カントリーの世界!」と感動を表現した日本人・女子のレビューを読んだ。しかし手のない大型の瀬戸のカップで飲むモーニング・カフェオレはパリでもそうだし、ワインにしてもフランス人にとって珍しいものではないし、カントリーチックでもない。そういう流行のオシャレチックなことを楽しむのは大いに結構だけれど、作品の持つ本質にはもっと気付いて欲しい。 しかしながらボクは最初の回で、物足りないとか、尖った部分が減ったとか言い、低い点しか与えなかった。それは一つには批判的部分をあまり明確にしなかったことによる。というか、ここまで書いて来たように批判を内包することは十分理解出来るのだが、そのやり方が稚拙過ぎたということだ。そしてこの稚拙さが第二の理由なのだが、色々な点でリアリティーがなさ過ぎる。自分の生活や妻との旅行について庭師が語る内容は、まるで安っぽいコントのごとくだ。かと言ってニヤっとさせられるような洗練された笑いを含むものでもない。 言いたいことや理解して欲しいことは、この手の映画では、まずリアリティーのある人物・行動・会話を描いておいて、その中から観客に伝わるようにするべきで、決してリアリティーを犠牲にしてまで、「こうすれば、これが理解される」というあまりに短絡的な表現はするべきではないということだ。
2009.03.28
コメント(0)
-
『画家と庭師とカンパーニュ』ジャン・ベッケル監督(2007フランス)その4
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER Jean Becker 105min(1:2.35) (桜坂劇場 ホールCにて) (つづき) 庭師に教わって知ったばかりの「ヅィー」(草刈りのための、死神グリム・リーパーが持っているような大鎌)のことを話題にして、展覧会でマグダに紹介された若いスノッブな批評家をやり込めるシーンにしても、都会人の知らないことを持ち出して、「自分のペース」で相手を煙に巻いているだけの自己満足だ。だいたいこの展覧会で知人の絵を理解しようと少しもしない主人公の態度自体、都会的なことの無意味を表すより、画家の自己本位性を表している。 なるほど最後には、庭師が希望したように、庭師の好きな物ものばかりを描いて個展を開き、そこで庭師に教わったナイフと紐を持ち歩くことの有用性を実践するシーンもあるが、それもこれも結局のところ画家にとって自己本位性の新しいアイテムでしかないのだ。詰まるところ、庭師との出会いによっても画家は一向に変わることはないという物語なのだ。 そしてこの対立、つまりこの映画では画家と庭師や妻や娘との対立は、都会(端的にはパリ)と地方の対立でもあり、主人と使用人との対立でもある。画家は呼び捨ての「マグダ」でいいと庭師に言うが、庭師は「マダム・マグダ」としか言おうとはしない。画家の優雅で気ままな生活が描かれる一方で、退職前の庭師の過酷な労働の様子が描かれる。定期的に医療検診を受けながら手遅れになるほど病気を悪化させる庭師に対して、画家は設備の整った病院の有能な医師を友人に持つ。都会の楽した金持ち、つまりは画家の同類として、娘の恋人は高級スポーツカーで登場させている。 庭師はと言えば旧式ののろいバイクで小さな犬にもバカにされている。バイクを新調すると犬もバカにはできず、庭師もご満悦。でもこれを可能にしたのは庭師の仕事での小遣い稼ぎであり、大して腹も痛ますに画家はその給金を払ったのだ。互いに異なっパリと田舎の存在はフランスという社会の構造なのだけれど、両者は誇りを持ちながらも、対立をも内包した共存だ。他のベッケル作品にも見られることだが、ある種プロレタリア映画的側面があるとも言える。そう考えるとヴェルディのオペラ『ナブッコ』を登場させたのも意味深だ。ナブッコ王の正統の娘フェネーナと奴隷の子アビガイルレの対立の物語だからだ。 (つづく)
2009.03.28
コメント(0)
-
『画家と庭師とカンパーニュ』ジャン・ベッケル監督(2007フランス)その3
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER Jean Becker 105min(1:2.35) (桜坂劇場 ホールCにて) (つづき) こんなことをくどくど書くのは、この映画は、多くの方が感想として書かれているような心暖まるだけの作品ではなく、もっと辛辣なものを持っていると感じたからだ。タイトル分析で書いた点が、この画家を理解する上で大きな助けとなる。 映画の最初の方で、画家がパリの妻と電話で話すシーンがある。写るのも聞こえるのも画家の姿や声だけだが、断る妻に一方的に「いいよ、お金は送る。」とかなんとか言っている。あるいは帰り際に「今度の時でいいよ」という庭師に対して意地でもその時に給金を渡そうとする。突然パリの妻を捕まえたとき、妻が友人との約束をキャンセルして画家と昼食をとることにしたので彼は大満足だ。娘が結婚相手として画家と大差ない年齢の男性を紹介したとき、頭ごなしに一方的に反対する。庭師の息子が失業したとき、知人に頼んで好きなサッカーの試合のセキュリティーの仕事を世話する。庭師が倒れるとパリまで連れていって知り合いの医師に診察を委ねる。 こうしたすべては一見表面的には親切とも見えるけれど、実はいわば自分のペースですべてを仕切ろうとする画家のあり方を示している。妻が画家と離婚すると言うのも、たんに画家が若いモデルや教え子との浮気を繰り返しているからだけではない。自分勝手に自分のペースですべてを進める夫にウンザリしているのだ。 だから若い愛人のマグダが、お姉さんだか叔母さんだったか忘れたけれど、会いに行くと言って、実は別の男に会いに行き画家の元を去り、頭ごなしの反対で娘に愛想をつかされたとき、深酒をして心理的に荒れる。それはどちらの場合も自分のペースから逃れていった2人であり、またそういう当たり前のことを受け入れられない自分がいるからなのだ。 都会のネズミが田舎に行って田舎のネズミととの友情を育む。そして田舎のネズミの単純で純朴な生活感を知るようになる。といった物語ではなさそうなのだ。そのように観るのは観客の希望的見方でしかない。画家はそう一時思い込むだけであって、実は何も変わりはしない。 (つづく)
2009.03.28
コメント(0)
-
『画家と庭師とカンパーニュ』ジャン・ベッケル監督(2007フランス)その2
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER Jean Becker 105min(1:2.35) (桜坂劇場 ホールCにて) (つづき) 成功した五十代の画家(オートゥイユ)。妻とはなんとなく上手く行ってない。二十歳ぐらいの娘も、嫌っているというほどではなくても「そういうお父さん」として当たらず障らず。画家はどちらも愛しているつもりだが、自分本位の一方通行。そんな画家はパリを離れて子供時代を過ごした田舎の生家(相続していた)に一人で住むことにした。 田舎の家だから庭も広い。かつては家庭菜園もあれば、死んだ母はバラを育てたりしていた。でも庭は荒れ放題で、それを管理・手入れするノウハウも力も画家にはない。彼は広告を出して庭師を募集した。 やって来たのは小学校の幼な友達。40年ぶりの再会。小学生のときは仲の良い悪ガキコンビだったが、40年の歳月は身分も階級も文化も全く異なった二人にしていた。画伯になってお金持ちになってパリに住む画家と、鉄道保線夫という3K仕事をしてきた庭師。 再会を喜び、画家には有能な庭師であり、庭師には好きな庭師ができる仕事だったが、二人の生き方や考え方には開きが大い。幼なじみというのがなければ、階級の違う雇い人と雇われ人としての関係のみで、互いに相手の生活や人生に関わることもなかったろう。 この映画の原題は「私の庭師との対話」ほどの意味だ。配給会社の思惑は放っておくとして、原題を少し分析してみたい。「私の庭師」というのはmon jardinierで、英語にすればmy gardenerってことになるけれど、あなたは自分の庭師をお抱えになってますか?。いないでしょ、たぶん。ボクも持ってません。つまりはこの2語だけで使用人を持てる金持ちであることがわかる。そしてhis gardenerでなくmy gardenerとあるから、このタイトルは画家の主観から見たタイトルということになる。そんな画家の主観は「我が友」とか「田舎の幼なじみ」とは言わずに、「うちの女中」っていうのと同じノリで「私の庭師」って呼んでいる。つまりここに既に画家の庭師に対する主人意識が見てとれる。更に「対話」という部分はdialogueという、妙にお堅いというか事務的な、要するに暖かさの感じられない語が使われている。もちろんこれも画家の主観として。 (つづく)
2009.03.28
コメント(0)
-
『画家と庭師とカンパーニュ』ジャン・ベッケル監督(2007フランス)
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER Jean Becker 105min(1:2.35) (桜坂劇場 ホールCにて) このジャン・ベッケル、それほど見ていませんがどちらかと言うと好きな監督さんで、『殺意の夏』や『エリザ』は大好きな作品です。それが『クリクリのいた夏』になるとちょっと物足りなくなり、この『画家と庭師…』では更にその感が強くなっている。歳をとったんだなぁと言ってしまっては失礼でしょうか。尖った部分が希薄になっています。 映画には、一般観客と批評家の評価が一致する作品もあれば、正反対になるものもあります。後者の場合、自分は観客側の評価と一致するケースもあれば、批評家に組するケースもあります。フランスのある映画サイトを見ていたら、この作品は後者、すなわち批評家と一般観客の評価が一致しない作品の好例ではないかとありました。『ル・モンド』紙などは酷評。批評家評は5つ星での採点にすれば平均一つ星★☆☆☆☆、一方観客評は星4つ以上★★★★☆だとありました。今回はボクは星2つ、オマケして3つでしょうか。ちなみに過去のベッケル作品のボクの採点は、『殺意の夏』と『エリザ』が星4つないし5つ。『クリクリのいた夏』が星3つといったところでしょう。 ダニエル・オートゥイユについて言うと、「完璧な演技」と書いている人が何人かいました。完璧と言えばそうなのかも知れないけれど、『八日目』『そして、デブノーの森へ』他、ここ10年15年のジローやハネケやルコントやソーテ等の作品の彼の演じるキャラクターは似かよっていて、パターン化された同じような役作り・演技の使い回しと感じられてしまう。新しさがないからつまらないのだけれど、それはまあそれでも良い。ただ映画作品としては、そのお決まりのオートゥイユを使っても、意味ある物語をしっかり見せてくれないといけない。ハネケの『隠された記憶』とかソーテの『愛を弾く女』のように。余談だけれど、こんなオートゥイユは女優ではシャーロット・ランプリンクに似ているかも知れない。 (つづく)
2009.03.27
コメント(0)
全623件 (623件中 1-50件目)
-
-

- おすすめ映画
- サマー・ウォーズを観ました
- (2025-11-24 00:18:47)
-
-
-

- 特撮について喋ろう♪
- (特撮キャラ)黒影豹馬・ブラックジ…
- (2025-11-29 19:00:06)
-
-
-

- SMAPが大好きな(興味が)ある人♪
- ハピバ☆ ・「カフネ」
- (2025-08-18 23:53:31)
-