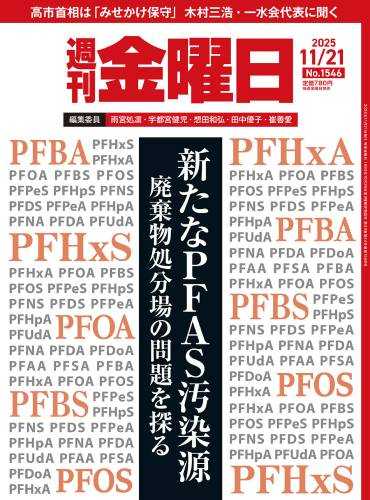2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2014年05月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

Jazz、その出会い。その2
Jazz、その出会い。その2前回は、新しいもの「菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール」のことでした。今回は、1967年のジョージ大塚トリオ「PAGE1」です。アルバムのリリースは1968年です。今から46~7年前のもの。このトリオの演奏は名古屋YAMAHAビルのホールで聞きました。「PAGE1」が出た時です。日本Jazzのレコードレーベルtactが出来、そこから多くのJazzの録音がリリースされました。この度、それら中から、ピアノトリオを選んでCDが出たようです。その中の1枚です。懐かしく、つい手が出てしまいました。実はレコードもあったのですが、レコードを聴く機械が手許には無くCDで聴くしかないのが実情です。もう半世紀近く前のものですが、活き活きした演奏を楽しみました。ページ1ジョージ大塚トリオジョージ大塚(ds)市川秀男(p)寺川正興(b)1967年10月14日録音
2014.05.29
コメント(0)
-
菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール
Jazz、その出会い。もうずいぶん前から活動していたらしいので、こちらが知らなかっただけ。2005年から活動している「菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール」のこと。タワーレコードで視聴して購入。それも2枚も。『夜の歴史』と『戦前と戦後』だ。久しぶりに新たなJazz(Jazzと言うよりラテンであるが)を知ったと思う。実に魅力的だ。You tubeで見て下さい。菊地成孔は『東京大学のアルバート・アイラー-東大ジャズ講義録・歴史編/大谷能生共著』で知っていたくらいで、演奏家としては全くノー・マークであった。こちらはJazzの好きな人には面白本いと思う。
2014.05.27
コメント(0)
-

『夢十夜 双面神ヤヌスの谷崎・三島変化(へんげ)(宇能鴻一郎)』
本屋の棚に宇能鴻一郎の名を見つけて、おやっ?あの人はまだ現役で書いていたのか?宇能鴻一郎は【純文学の世界は一発芸で稼ぐ以外は小さなパイの取り合いだ。新聞の求めに応じて自分の文学的立場を書いたら、[先輩作家を敵視する]と評された。(中略)一刻も早く純文学から逃げ出すことだ。】とポルノ小説のモーツァルトを目指した、という。その昔、川上宗薫、梶山季之と並び密かに読む作家であった。今でもそうかも知れない。この『夢十夜 双面神ヤヌスの谷崎・三島変化』もあだ花のようだ。そして、手に取り新作であることを確かめる。ぱらぱらとページをめくりタイトル,目次を読む。一瞬買うか買うまいか迷う。このたび、図書館(地元の図書館にはなくて、県の図書館で借りる)で借りて読む。それについても予約をして、であった。夢十夜とあるように、全部で十夜からなる・・・、第一夜 ヴィナス第二夜 殉教第三夜 少年第四夜 羅馬第五夜 聖牛第六夜 谷崎、三島第七夜 福岡第八夜 秘密第九夜 鮎子第十夜 愛人(かな)あとがき――気のむくままの謝辞と補注著者、宇能鴻一郎の少年時代からある時点までの事柄を交えながら亜礼知之君として著者が登場する。劇中劇的な扱いで、亜礼の小説が入ってくる。構成は複雑だが、それぞれのエピソードとして亜礼の小説は面白く読める。全体に貫かれているのは、亜礼(宇能鴻一郎)の芸術観だと思う。80年の人生、その豊富な経験と知識(絵画、彫刻、建築、音楽、文学、映画)が縦横無尽に繰り広げられている。実名で書かれる作家も、それらしい人を連想させる部分も、それぞれに僕ののぞき趣味的な興味をそそられる。下世話な読み方で、作者には申し訳ないが。でも、大変面白かった。週刊文春HP以下、版元のHPから、「十の夢」という形で展開される長編小説。著者自身の満州における幼年時代、殉教を志した長崎の花魁、 現代に蘇る谷崎と三島……様々なテーマが交錯し時空を超えた壮大な小説世界を構築する。三十年もの 間純文学から離れていた芥川賞作家・宇能鴻一郎復活! の書き下ろし小説。『夢十夜 双面神ヤヌスの谷崎・三島変化(へんげ)(宇能鴻一郎)』2014年3月10日 第一版第一刷井済堂出版
2014.05.25
コメント(0)
-

【明治屋 閉店】
【明治屋 閉店】名古屋市栄の明治屋が5月22日閉店。これは、ニュースになるのですね、TVニュースでも取り上げていました。お昼休みにのぞくと、レジは長蛇の列。先週まで沢山あったワインの棚もほとんど空、他の棚も完売状態でした。この跡地は駐車場になるそうです。写真は、裏から見た明治屋のあるビルです。このビルの手前(今は駐車場)が丸善でした。
2014.05.23
コメント(2)
-
『巨匠の目 川端康成と東山魁夷』
『巨匠の目 川端康成と東山魁夷』仕事の都合で数年前からこの時期に静岡に行きます。それはいつも月曜日に仕事があり一晩泊って翌日帰ります。その翌日の楽しみが<静岡市美術館>へ行くことです。今年は『巨匠の目 川端康成と東山魁夷』を見ました。美術展というより川端康成の書および収集物と本の装丁、他の作家から川端康成への手紙の展示。東山魁夷も同様に収集物と魁夷の絵。ボクには手紙と装丁が面白かった。しかし、その中で太宰治の芥川賞を下さいという手紙と菊池寛からの手紙。これは川端が菊池寛に金の無心(?)をしたものへの返事らしい。その二通は、興味は湧くが他人に見せるものだろうかと思った。すでに三人ともこの世にはいないが、歴史のかなたのものでもあるまいに…。http://www.shizubi.jp/exhibition/future_140412.php
2014.05.20
コメント(0)
-

不断菜(不断草)
冬がれわけてひとり唐苣(たうじき) 野水しらじらと砕けしは人の骨か何 杜国『冬の日』「狂句こがらしの巻」より。『第九折々のうた(大岡信)岩波新書』から引用。唐苣とは今の不断菜(不断草)のこと、と出ていた。その当時からあった。今ではスイスチャードと言われることが多い。写真は茎や葉脈が赤いが黄色、オレンジ色、白と様々である。そのままでも食べられるが、茎は炒めると甘みが出ておいしい。
2014.05.18
コメント(0)
-
『木野(村上春樹)文藝春秋2014.3』
ボクには分からないが、村上春樹読者には『木野』が一番の評判らしい。村上の不熱心な読者のボクにとっては、唯一主人公木野の聴くJazzが気になった。アート・テイタムのピアノソロや、コールマン・ホーキンスの「ジェリコの戦い」、そのベーシスト、メジャー・ホリーのことなど。古いJazzマンの名前も出てくる。特にコールマン・ホーキンスの「ジェリコの戦い」は、1962年のライブ録音。‘62はボクがjazzを聴き始めたころで、今は手許にはないが、LPがその後出て、買った思い出もある。此の度、村上春樹を読み、『ジェリコの戦い』を思い出し、そのことを考えると、実に興味深い。しかし、ボクのJazzの知識や経験の殆どが今から40年前のもので、それ以降は、それらの経験知識のヴァージョンアップ的焼き直しでしかないとつくづく思うのである。ボクの持論の一つに、ティーンエイジャーの頃、13歳から19歳までに何に凝っていたか、何が好きだったか、何に淫していたのか、寝食忘れて何をしたか、その何が人生の一部を大きく決めるということなのだが、ボクの場合それがJazzであった。結局自分はその頃から一歩も出ていないのだと、本質は何も変わらないのだと、三つ子の魂百までというが、その上にティーンエイジャーの魂も付け加えられるのだと言う事だ。少し付け加えれば、ボクのティーンエイジャーは、jazzと映画と小説とTVやラジオであった。繰り返すが、いまだにその中に居る。
2014.05.17
コメント(0)
-

『東京オリンピック 文学者の見た世紀の祭典(講談社編)』
昭和39年の東京オリンピックの文学者による記録『東京オリンピック 文学者の見た世紀の祭典(講談社編)』を読む。その大会を見ることなく死んだ佐藤春夫当時72歳から29歳の大江健三郎まで40人の作家が新聞や雑誌に寄せたものを、開会式、競技、閉会式、随想の4構成で91篇から成る。錚々たるメンバー、先にあげた二人以外三島由紀夫(当時39歳)石原慎太郎(32歳)阿川弘之(44歳)曽野綾子(33歳)瀬戸内晴美(42歳)他に小林秀雄、大岡昇平、武田泰淳、井上靖、松本清張、水上勉などなど・・・。その中で、「日本人の国際感覚(武田泰淳)」を一部引く、【しかし、いくら知りたがっても、全部知りつくすことはできません。そこで、めいめいが自分流に知ったつもりになり、(略)ところが、全部を知りつくすことが出来ないという絶対条件は変わらないのだから、それぞれの専門家の意見をうかがって安心しようとする。しかるに、専門家なるものがまた、全部を知りつくすことができない人間にすぎず、また、好ききらいの偏見からのがれることのできない生物なのですから、云々】小林秀雄「オリンピックのテレビ」、円盤投げの選手が【しきりに円盤に唾を付けている。(中略)解説者の声・・・口の中はカラカラなんですよ、唾なんか出てやしないんですよ――私は、突然、異様な感動を受けた。】【勝負するすべての選手達が、その肉体の動きによって、私の眼に、何も彼も、さらけ出している。(中略)孤独だとか、自分との闘いだとか、そんな文学的常套語を使うより、選手達の口の中はカラカラだと言う方がいいかも知れないのである。】菊村到「やってみてよかった」の一節【こんどのオリンピックは、筆のオリンピックなどともいわれた。ずいぶん、おおぜいの小説家や評論家が、オリンピックについて、なにかを書いてきた。/こんなにも多くの文士が、あるひとつの行事に対して、いっせいに勝手なことを書きちらした、ということは、おそらくほかに例がないだろう。】全部を読むつもりはなかったが、あれよあれよと言う間に396pを読み終えた。『東京オリンピック 文学者の見た世紀の祭典(講談社編)』講談社文芸文庫2014年1月10日第一刷発行2014年2月17日第二刷発行
2014.05.14
コメント(0)
-
白ゆき姫殺人事件(中村義洋)
中村義洋は『みなさん、さようなら(2012)『ちょんまげぷりん(2010)』『ゴールデンスランバー(2009)』を見ている。どれも面白かった。しかし、今回は首をかしげる。シニア料金1100円も返せとも思わない。でも、すっきりしない。あまりにも机上のお話し過ぎるからだ。いや、そうじゃない。今のTV局なんてあんなもんだ。裏も取らずに興味本位の垂れ流し状態だよと。それも含め今を照射しているのだよ。そうだとしてもご都合主義すぎないか。真犯人が誰であるかに視点はむいていない。一制作会社の男、赤星(綾野剛)のツイッターを支点に物語が展開してゆく、そのことに警鐘を鳴らすことやTVの無責任さも分かる。今の世の中の危うさだ。その点の葛藤がないのがご都合主義と言う理由だ。すべてに今更と思える。でも、時間余り遊ばせて頂いた。感謝。
2014.05.12
コメント(0)
-
『女のいない男たち(村上春樹)』
単行本ではなく文藝春秋を図書館で借りて読みました。それも3作。村上春樹を読むのは初めてです。遠い昔『風の歌を聴け(1979)』を読んだくらいで、すっかり忘れていますが。まずの感想は、とても読み易い、でした。純文学でこれほど売れるのも分かる気になりました。しかし、きっとその読み易さが陥穽では(?)と用心用心であります。2014年5月8日の中日新聞夕刊、コラム「大波小波」に(男のいない女)氏が【反知性主義】を持ち出し、警鐘を鳴らしています。それには同感ですと言いたいところですが、まだ村上春樹を3作、それも短編のみの読者としては早計だからです。さて、読み終えた3作は「ドライブ・マイ・カー」「イエスタデイ」「独立器官」です。丁度単行本の前から3作品にあたります。図書館で借りた順序に従い読んだだけですから、これは偶然です。村上春樹にはよく音楽が出てくるようだ。「ねじまき鳥クロニクル」の初めにクラウディオ・アバド云々があったし、(これは出たときに立ち読み)小沢征爾との対談集もあし、Jazzについてのものもある。これらの知識は、すべて立ち読みのつまみ読みからです。記憶違いもあるかも知れません。「ドライブ・マイ・カー」にベートーヴェンの弦楽四重奏が出てきたので、手許にあるそれのCDをかけています。その程度の理解です。この読み易さの後ろにあるものが何か、それを掴むには再三再度読むことだと、思っています。いずれ単行本でと、思っています。「イエスタデイ」の関西弁訳は面白い。それもミーハー的な興味だと自分自身のことは捉えています。なぜ、今になり村上春樹を読む気になったのか、それは分からないのですが、「イエスタデイ」の訳や「ドライブ・マイ・カー」でのタバコを窓の外に捨てるところなど、単行本では変わったことを新聞で読んだからだとも思う。ミーハー的好奇心、覗き見趣味的なものが動機であったと思うのです。しかし、これを機に単行本を読み、いろいろ考えてみようと今は思っています。
2014.05.10
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1