2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2011年01月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
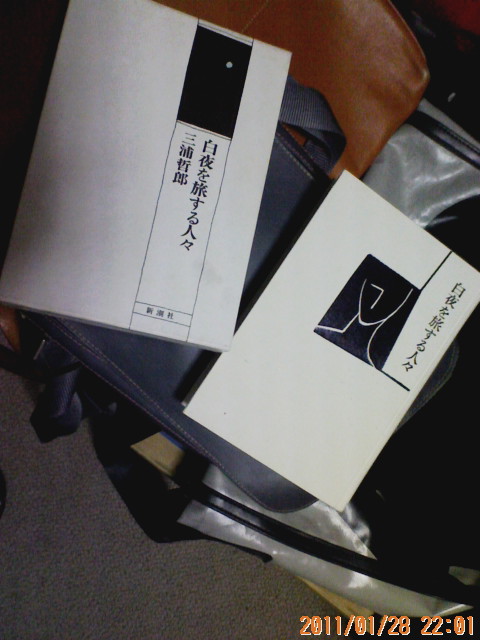
『白夜を旅する人々(三浦哲郎)』
今年(2011年)の読書は、マリオ・バルガス=リョサを中心にしたラテンアメリカ文学と三浦哲郎と決めた。その三浦哲郎の第一回目が、『白夜を旅する人々』。新潮2010年11月号に『白夜を旅する人々』の続篇『暁の鐘』(遺稿)の書き出しが掲載された。わずか2ページであったが。そのことが背中を押し、『白夜を旅する人々』を読んだ。これは、作者三浦哲郎の自伝的家族の話、その話の前半分。後半分は、『暁の鐘』になる予定であった、それを完成させることなく三浦哲郎は亡くなった。●三浦哲郎年譜『筑摩現代文学大系81 1978年11月25日初版 三浦朱門・三浦哲郎・立原正秋集』 より昭和6年(1931)3月16日、青森県八戸市三日町13番地に父荘介、母いとの三男として生まれる。兄に文蔵、益男、姉に縫、貞子、きみ子がいた。家は〈丸三〉という屋号で呉服屋をしていた。昭和12年(1937)6歳満六歳の誕生日に、次姉貞子が青函連絡船から津軽海峡へ入水した。これをきっかけに兄や姉たちがつぎつぎと自滅の道を辿ることになる。夏、長兄文蔵が失踪した。翌年秋、長姉縫が服毒自殺をした。昭和24年(1949)18歳四月、早稲田大学政経学部経済学科に入学。次兄益男の世話になったが、その兄が翌年春、突然行方不明となり、休学届を出して帰郷する。それからの数年間は、一家のいわば暗黒時代で、血というものについて思い悩むようになった。年譜のように、三浦哲郎は六人兄弟姉妹の末っ子。『白夜を旅する人々』では、長男清吾、長女るい、次男章次、次女ゆう、三女れん、それと三浦哲郎と思われる三男羊吉が登場人物。この前半で、次女れんが青函連絡船から投身自殺、長男清吾は失踪、長女るいは睡眠薬で自殺をする。るいの葬儀の場面でこの物語は幕を閉じる。そして、『暁の鐘』は、長女るいの喪が明けたところから始まる。その後の章次のこと、ゆうがどのようにし琴の師匠になってゆくのかが書かれたのだと思う。るいとゆうは白子と言われる生まれつき色素を持たない体質であった、そのことが家族兄弟姉妹を翻弄したことは想像に難くない。白子でもない次女れんがその遺伝的運命故投身自殺する。その遺書の部分は目頭が熱くなる。あくまで、『白夜を旅する人々』は小説であり物語であるが、つい作者の実際と重ねてしまう。買い置きをした三浦哲郎が手許に10冊ほどある。短編モザイク3冊以外は古本屋やBook Offで求めたもの。三浦哲郎の印税には寄与していない、申し訳ないが・・・。それを今年2011年は読もうと決めた。今、『忍ぶ川(新潮文庫)』を湯船につかりながら読んでいる。「忍ぶ川」は3~4度目だが、若いとき、ちょうどその映画があったとき読んだのが初め、そのときは然程いいとは思わなかった。今はしみじみと胸にせまる。奇しくも、今回の第144回芥川賞が私小説の極北と思われる西村賢太が受賞。三浦哲郎の芥川賞「忍ぶ川」も私小説といわれるものであった。『白夜を旅する人々(三浦哲郎)』装幀:司修昭和59年10月25日 発行昭和60年2月15日 10刷発表誌「新潮」昭和56年5月号~昭和59年10月号
2011.01.31
コメント(0)
-
古本屋をまわる
名古屋市内の古本屋は点在している。が、鶴舞公園から上前津にかけては古くからそこに古本屋が集まっている。40年以上前、中学から高校のころに学校帰りにその場所にはよく行った。当時は今の倍以上の古本屋があったと記憶している。今は10軒程である。さて、久々にその古本屋街に行った。目的は、岩波文庫の『産業革命』と同じく岩波文庫の『武玉川』、それとラテンアメリカ文学である。あったのは『武玉川』。これは今でも出版されているので、普通に手に入るが、全4冊が1200円。新刊で買えば2800円はするはず。『産業革命』は見つからず。ラテンアメリカ文学も駄目でした。その替わり『アメリカの心の歌(長田弘)』を見つける。おなじ所で『モーガンズ・クリークノ奇跡』のDVD(廉価版)も見つける。これはラッキー。約2時間ほどの古本屋巡りでした。
2011.01.25
コメント(0)
-
「宋襄の仁」
「宋襄の仁」無益のなさけ。時宜を得ていない憐れみ。のこと。新潮社のPR誌「波」に連載中の『長谷川伸と日本人/第十三回『坂の上の雲』と捕虜(山折哲雄)』で知った。山折哲雄は、司馬遼太郎の『坂の上の雲』に触れて、司馬遼太郎は長谷川伸の『日本捕虜志』を【ひそかに熟読していたのではないかと思ったのだ。】と書いている。そして、【明治37年(1904)日露戦争下、上村彦之丞がロシア艦隊の三隻内、一隻を轟沈し残る二隻の追撃をせず、沈めた巡洋艦リューリックの乗員の救助に当った。その数627名であった。そのことを後に知った参謀秋山真之は「あの二隻は遁がすべきではなかった」といった。戦略目的を犠牲にしてまで敵の漂流兵を救うのは「宋襄の仁」だ、とまでいって上村を批判しつづけた。】これを読んで知った。実は、【この後に山折哲雄は上村を批判した人物について、長谷川伸は『日本捕虜志』には秋山真之が出てこないのだが、何故司馬遼太郎が『坂の上の雲』で秋山真之の名が出たのかを、どうしてだったのだろうか】、と述べている。本稿は今回その疑問で終っている。その解釈は、次回になる模様。【】内は引用及び南包の書き換え部分。
2011.01.20
コメント(0)
-
芥川賞 西村賢太氏
芥川賞 西村賢太氏西村氏のコメント。【「自宅にいてそろそろ風俗(店)に行こうと思っていた。驚きました。友だちは一人もいないので、誰にも報告していません。私の小説を読み、自分よりだめなヤツがいるんだなとちょっとでも思ってくれたらうれしい。そのことで社会に首の皮一枚つながっている」と喜び、今後について「僕には華やかなことは書けない。自分のことしか書けません」と私小説へのこだわりを語った。】中日新聞2011年1月18日期待通りの面白いコメントだ。【】内は記事引用。今日(1/18)の同じく中日新聞夕刊に「現代に生きる私小説」と題された西村賢太の紹介があった。書き出しは【「平成の破滅型私小説作家」と呼ばれる西村賢太さん・・・】とあり、【受賞の決め手になったのは、自身を戯画化する語り口だ】と続く。だが、その【自身を戯画化する語り口】が西村賢太の評価としてはどうかと、思う。西村自身は【自身を戯画化する語り口】を意識しているのだろうか、という疑問。戯画化というよりはむしろ懸命に書くことが戯画化したように見えるのである。一所懸命やればやるほど傍から観れば滑稽であるといったことだ。それが、西村文学の真髄であり面白さだ。今の草食系、人との付き合いをあっさりと淡白にする傾向に真っ向から対立する人間が西村賢太の小説には出てくる。そこが魅力だ。だから、惹かれる。【】内は記事引用。
2011.01.18
コメント(0)
-
第144回芥川賞
朝吹真理子と西村賢太が受賞。 その西村賢太は読んで (『どうで死ぬ身の一踊り』と 『小銭をかぞえる』 である) いたからだろうが、 近年の芥川賞は殆ど身近に感じなかったので、この西村賢太受賞は久々に芥川賞の発表に「おっ」と思った次第。 今は受賞作を読もうとは思わないが、西村賢太の受賞の言葉を「文藝春秋」で読んでみたいと思っている。
2011.01.17
コメント(0)
-
『白夜を旅する人々(三浦哲郎)』
今年の読書は、三浦哲郎とバルガス=リョサを中心にしたラテンアメリカ文学と決めている。一年でどれほど読めるかはわからないが、三浦哲郎はモザイク短編集全三巻とこの『白夜を旅する人々』など手許にある十冊、リョサは先日読み終えた『緑の家』のほかに三、四冊読みたいと思っている。『白夜を旅する人々』(1985年度第12回大佛次郎賞受賞作)を読み始めた。読んだ部分から書いていこうと思う。「るい」が漢文を習っている老師との会話から・・・【「それで、読みましたか、仕舞いまで。」「はい、やっとのことで。」「それは偉いな。」と老師は言ったが、どんな本でも読みはじめたら終りの頁まで読み通さなくてはいけない、辛いからといって途中で投げ出すくらいなら本など読もうと思わぬ方がいい、そう教えてくれたのは老師自身で、るいはただその教えを努めて守っているだけであった。】p83るいが読んだのは聖書である。【るいはさんざん手子摺って、ようやくそれを読み終えたのは、・・・】【】内は引用この一節を読んだとき、今年の目標の一つにしたラテンアメリカ文学を読むこと、それの背中を押してくれる文章にであったと思った。最後まで読み通すこと!!それである。だが、『白夜を旅する人々』も先は長いが。
2011.01.16
コメント(0)
-

『黒の試走車(梶山季之)』
『黒の試走車(梶山季之)』実質的な梶山季之のデヴュー作と解説(村上兵衛)にあった。昔、こんな話を聞いた。ある文学部の学生が、教授に梶山季之は日本文学史に残るでしょうか?という話。当時はまさか、と思ったが、今なら一作くらいは残るかもしれないと思う。その一作がこの『黒の試走車』。産業スパイ物のはしり、当時は盗聴器も無く、競争相手の会議を盗み聞く方法もその当時らしいアイディアである。女性人が色仕掛けで情報を取ろうとする場面が幾度も出てくるが、今から思えば大人しいシーンである。1962年に大映が「黒シリーズ」の第一作目として映画化(増村保造監督)したこともご存知の通りだが本書を読んで、記憶が正しければ映画はこの物語の一部だったと知った。『黒の試走車(梶山季之)』昭和48年10月30日 初版発行角川文庫
2011.01.13
コメント(0)
-
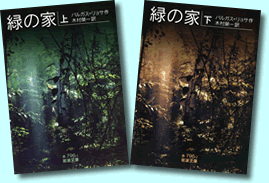
『緑の家(上)(下)マリオ・バルガス=リョサ』
2010年12月1日のブログにもう一度読むと書いています。その通り今日(2010年1月11日)上下を読み終えました。上は三度、下は二度です。訳者、木村榮一の「訳者解説」に【数多くの人物が登場し、しかも四十年に及ぶ年月の間に起こった出来事を語ったこの小説は、五つのストーリーが組み合わされ展開してゆくが、その際作者はそれぞれの物語を小さな断章に分割し、時系列を無視して並べ、さらに人物の内的独白まで織り込んでいるので、読者は戸惑いを覚えるだろう。しかし、読み進むうちに個々の断章がジグソー・パズルのピースのように徐々に組み上がって行き、少しずつ全体像が浮かび上がってくる。読者はその中から広大なペルー・アマゾンを舞台に繰り広げられるさまざまな人間たちの姿と現実が浮かび上がってくるのを目のあたりにすることになると同時に、物語小説としての面白さも満喫するはずである。】【】内、引用。この解説にあるように確かにジグソー・パズルである。だが、全体像が見えているパズルのピースを組み合わせるのではなく、どのように繋がっていくのかが分からぬまま各ピースを読んでいくのであるから、本当に分からぬままに読み進めることになるのだ。だから、二度三度と読むことで漸く全体像が把握でき、描かれているピースがどの部分のピースであるかが分かるのである。その読み解くことで体像が見えてくる、その過程が面白いといえる。小説を読む=物語を楽しむ、満喫する。それに行き着く前に通らなくてはならないジグソー・パズルの全体像の把握こそが『緑の家』と取り組む面白さだと思う。今は、漸く二度目三度目を読み終え、『緑の家』を多少は消化できたとやや満足していると同時にほっとしているのである。『緑の家 上・下(マリオ・バルガス=リョサ/木村榮一訳)』上・下 2010年8月19日 第1刷発行
2011.01.11
コメント(0)
-
『チネチッタの魂 ~イタリア映画75年の軌跡~』
『チネチッタの魂 ~イタリア映画75年の軌跡~』NHKは、2011年のイタリア統一150周年にあたるということで、今月BS-hiで、イタリアの特集をする。その中で4日に放送された。以下【】内が、NHKのHPから引いたもの・・・。【コッポラやスコセッシといった米国の巨匠たちが、チネチッタで映画を製作するケースが相次いでいます。最新鋭のデジタル技術が全盛のハリウッドに対し、今もなお熟練した職人の手仕事によるチネチッタ。そのアナログの手法が観客を魅了しています。1936年ムッソリーニ独裁政権下で、誕生したヨーロッパ最大の映画撮影所チネチッタ。ヴィスコンティ、ロッセリーニ、フェリーニなど、巨匠たちが名作を次々とここで生み出しました。親から子へ、さらに孫へと代々チネチッタの工房で伝統を引き継ぎながら一緒に働くのがチネチッタの職人の流儀。チネチッタ75年の歴史をひもときながら「夢の砦(とりで)」の秘密を解剖します】と、大上段に振りかざした番組だが、内容は井筒和幸監督が自分の好きな映画『道』が軸になっており、決してチネチッタの全貌を紹介しているものではない。井筒監督の『道』へのオマージュでしかない。番組のタイトルからはそう云うしかない。そうではなく井筒監督の『道』、というタイトルならば納得が行くし、それならば面白い番組だったのだが。こういうのを「羊頭狗肉」というのであろうか?しかし、この特集は注目である。
2011.01.10
コメント(0)
-
『チネチッタの魂 ~イタリア映画75年の軌跡~』
『チネチッタの魂 ~イタリア映画75年の軌跡~』NHKは、2011年のイタリア統一150周年にあたるということで、今月BS-hiで、イタリアの特集をする。その中で4日に放送された。以下【】内が、NHKのHPから引いたもの・・・。【コッポラやスコセッシといった米国の巨匠たちが、チネチッタで映画を製作するケースが相次いでいます。最新鋭のデジタル技術が全盛のハリウッドに対し、今もなお熟練した職人の手仕事によるチネチッタ。そのアナログの手法が観客を魅了しています。1936年ムッソリーニ独裁政権下で、誕生したヨーロッパ最大の映画撮影所チネチッタ。ヴィスコンティ、ロッセリーニ、フェリーニなど、巨匠たちが名作を次々とここで生み出しました。親から子へ、さらに孫へと代々チネチッタの工房で伝統を引き継ぎながら一緒に働くのがチネチッタの職人の流儀。チネチッタ75年の歴史をひもときながら「夢の砦(とりで)」の秘密を解剖します】と、大上段に振りかざした番組だが、内容は井筒和幸監督が自分の好きな映画『道』が軸になっており、決してチネチッタの全貌を紹介しているものではない。井筒監督の『道』へのオマージュでしかない。番組のタイトルからはそう云うしかない。そうではなく井筒監督の『道』、というタイトルならば納得が行くし、それならば面白い番組だったのだが。こういうのを「羊頭狗肉」というのであろうか?しかし、この特集は注目である。
2011.01.10
コメント(0)
-
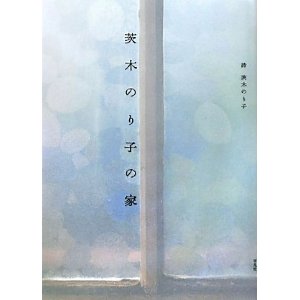
『茨木のり子の家(茨木のり子)』
『茨木のり子の家(茨木のり子)』と『歳月(茨木のり子)』家や部屋、直筆原稿の写真と詩が載っている。ポートレートや詩人たちとの写真もある。茨木のり子を知ったのは、書店に平積みされた『倚りかからず』である。数年前のこと。「倚りかからず」を読む限りにおいては、なんだか色気のない人生論的な詩を書く人だという印象。その時それ以上に詩を読むこともなかった。「倚りかからず」もはや できあいの思想には倚りかかりたくないもはやできあいの宗教には倚りかかりたくないもはやできあいの学問には倚りかかりたくないもはやいかなる権威にも倚りかかりたくはないながく生きて心底学んだのはそれぐらいじぶんの耳目じぶんの二本足のみで立っていてなに不都合のことやある倚りかかるとすればそれは椅子の背もたれだけ例によって、中日新聞(東京新聞)夕刊の匿名コラム「大波小波 2010年12月3日」は、後藤正治『清冽 詩人茨木のり子の肖像(中央公論新社)』に触れている。その内容は【「軍国少女」のイメージをひきずる凛然たるモラリスト像に傾き、はては品格賛美にいたる云々。詩がどうかとすると教訓的で、行儀が良すぎる、などという批判者は谷川俊太郎一人にとどまる・・・】【没後の遺稿詩集『歳月』には、日ごろの抑制を自ら解きはなったエロチックな詩篇も入っている。(中略)ともあれ、あまり人格者に仕立てられては、茨木本人が困るだろう】と、締めくくられている。そこで、物見高い小生は『歳月』を読んだ。亡き夫とのことが多く書かれている。「倚りかからず」しか知らなかった自分だが、ここに在る詩は、普通の詩だ。エロチックといっても夫婦のことをはみ出てはいない。やはり人格者。谷川の言は中っている。だが、『歳月』は面白く読んだ。では、その『歳月』から巻頭の詩を・・・。「五月」なすなく傷ついた獣のように横たわる落語の〈王子の狐〉のように参って子狐もなしに夜が更けるしんしんの音に耳を立てあけがたにすこし眠る陽がのぼってのろのろと身を起しすこし水を飲む樹が風にゆれている『茨木のり子の家』には本人のポートレートもある。その何点かは谷川俊太郎が撮ったものである。【】内引用。詩=全文引用。茨木のり子の家(茨木のり子)2010年11月25日平凡社歳月(茨木のり子)2007年2月17日 第1刷花神社茨木のり子 1926~2006
2011.01.08
コメント(2)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- Youtubeで見つけたイチオシ動画
- トヨタ新型セルシオ2026年登場確定!…
- (2025-11-26 02:53:07)
-
-
-
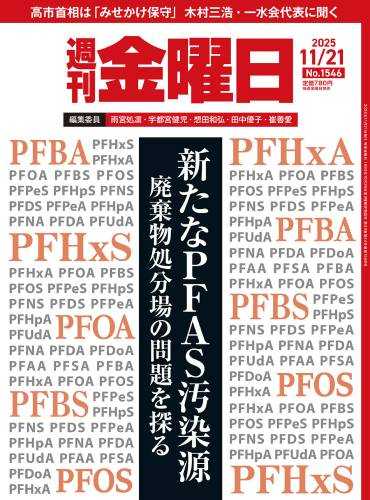
- 【演劇】何か見に行きますか? 行き…
- 劇評:劇団温泉ドラゴン『まだおとず…
- (2025-11-21 13:22:46)
-








