2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年01月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

『幻影シネマ館(佐々木譲)』
『幻影シネマ館(佐々木譲)』です。「小説すばる」に連載されたものの単行本化。佐々木譲といえば、『エトロフ発緊急電』や『笑う警官』などの推理小説作家。これは、その佐々木が映画についても可也詳しいとの証明のようなもの。 読むにつれて、だんだん面白くなる。因みに、目次から・・・、第一部 日本映画の奇妙な影響 ゴードン・ダグラス「ハード・ノーベンバー」トニー・リチャードソン「汝等の誓約」第二部の最後の章は、 あの「冒険者たち」のリメイク リュック・ベッソン「ザ・フォーカス・ポイント」 内容は、書けないので済みません。立ち読みでもよいので、一度これを、手に取られるのも一興かと。幻影シネマ館佐々木譲挿画:宇野亜喜良マガジンハウス2008年12月18日 第一刷発行
2009.01.31
コメント(0)
-
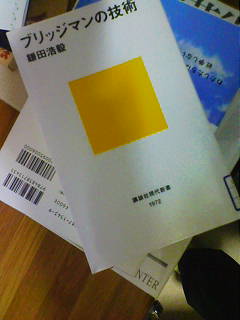
『ブリッジマンの技術(鎌田浩毅)』
『ブリッジマンの技術(鎌田浩毅)』です。この著者は、火山の研究者。有珠山噴火の折に、TVでその解説をした際、視聴者には殆ど分からない説明をしていたと知り、愕然となる。 人にものを伝えるには、とを著者なりに考えた結果の本。 ブリッジマンの技術鎌田浩毅 講談社現代新書2008年12月20日 第一刷発行
2009.01.30
コメント(1)
-
DVDで、『ブレイキング・ニュース』を見る。
以前録画した、ジョニー・トー監督の『ブレイキング・ニュース』を見る。香港フィルム・ノアールの一種。だが、変種である。ある事件に巻き込まれた警官が、犯人の銃から逃れるため、ホールド・アップをしそれがTVで流れた。警察は威信がなくなるのを恐れ手を打つ。その責任をレベッカという女性警視が持ち、ショーと称しTV中継による、警察の威信を取り戻す作戦をとる。だが、「そうは問屋が卸さない」と話は進む。 監督は話題の『エグザイル~絆~』のジョニー・トー。ドンパチの迫力は流石だ。『エグザイル・・・』もそうだが、室内の銃撃戦の作り方は独特のものがある。室内のいろいろな角度からの打ち合いは、まるで、パズルの組み合わせの様に作られている。この『ブレイキング・ニュース』のマンションを使った敵味方入り乱れた銃撃戦は、そのパズル的なところが見る側が少しでも目を離すと、辻褄が分からなくなる。同じ様に音にも、迫力と簡単に言ってはいけないと、思わせる凄まじさを感じる。 『エグザイル~絆~』のように話題にはならないが、これもジョニー・トーの佳作だ。
2009.01.25
コメント(0)
-
『納棺夫日記』その5
知人に葬儀屋がいる。彼が、音楽装を企画し、あるライブ・コンサートをする企業にその企画を持ち込んだ。現場(そのライブ・ハウス)はOKだったようだが、親会社から待ったがかかったらしい。「そんな、縁起の悪いこと・・・」というのが、理由らしい。この『納棺夫日記』を読むか、映画『おくりびと』をみれば、いかに死が厳粛であり、その厳粛な人の死を司る葬儀が、「縁起でもない」と、言われることでないと、分かるであろう。 Fさん、その親会社に、『納棺夫日記』を読んで頂くか、映画『おくりびと』を見ていただくことを提案します。
2009.01.24
コメント(0)
-

『未見坂(堀江敏幸)』
『未見坂(堀江敏幸)』です。傑作、『雪沼とその周辺』と同じ手法の短編集。だが、前作『雪沼・・・』より、全体に精彩がない。期待したのだが、残念だ。 とはいえ、堀江氏の小説を小生は好きだ。 未見坂堀江敏幸発行2008年10月30日新潮社
2009.01.23
コメント(0)
-
『納棺夫日記』その4
孫引きです。科学的でない宗教は盲目であり、宗教のない科学は危険である。~アインシュタイン~これが、168ページにある。
2009.01.22
コメント(0)
-
『納棺夫日記』その3
人は、自分と同じ体験をし、自分より少し前へ進んだ人が最も頼りとなる。p137これは、実に人の心理をついている。今まで、このように言った例を知らない。ひょっとしたら、当然過ぎて、誰も改めて言わなかったのだろうか。 実際に、仕事をしていても、専門家(自分の場合は広告だが)の言うことより、同業他社の人の意見を聞く人が多いのはその例だろう。
2009.01.21
コメント(0)
-
『納棺夫日記』その2
引用・・・、農村での老人の死体は、遺骸という言葉がぴったりで、なんとなく蝉の抜け殻のような乾いたイメージがあった。しかし、わが国経済の高度成長とともに、枯れ枝のような死体は見られなくなっていった。今日、事故死や自殺以外は、ほとんど病院死亡である。昔は口から食べ物がとれない状態になったら、枯れ枝のようにやせ細ってゆくしかなかったが、今では点滴で栄養が補給されるため、以前のように極端にやせ細った状態にならない。点滴の針跡が痛々しい黒ずんだ両腕のぶよぶよ死体が、・・・病院から運び出される。晩秋に枯葉が散るような、そんな自然な感じを与えないのである。p63~64 だれも、こんな状態で死にたいとは思わない。だが、このような枯れ枝状態の死体になるのは今や至難の業だ。本人の意思はきっと反映されまい。回りが、よってたかって、ぶよぶよの死体を作り出すのだろう。
2009.01.20
コメント(0)
-

『納棺夫日記 増補改訂版(青木新門)』
『納棺夫日記 増補改訂版(青木新門)』です。映画「おくりびと」は、これが元本のようです。映画より、ず~っと、真摯。沢山引用したいところがあります。今夜は一つ・・・、嫌な仕事だが金になるから、という発想が原点であるかぎり、どのような仕事であれ世間から軽蔑され続けるであろう。p33 当たり前のことだが、説得力がある。納棺夫日記 増補改訂版青木新門文春文庫1996年7月10日 第1刷2007年4月25日 第12刷
2009.01.19
コメント(0)
-
『俺たちに明日はないッス(タナダユキ)』
『俺たちに明日はないッス(タナダユキ)』どんより曇った空。膨れ上がる妄想と自我に押しつぶされそうな、夢も希望もない毎日をやり過ごす、高校3年男子の悶々とした気分を、『赤い文化住宅の初子』『百万円と苦虫女』のタナダユキ監督が描く。『神童』『コドモのコドモ』と映画化が相次ぐさそうあきらの幻の"性春マンガ"をもとに、山下敦弘監督とのコンビで知られる向井康介が大胆に再構成した脚本を、見事に映像化。男子ってバカね、と笑われようと、恋とも憧れとも違う、今じゃなきゃダメなんだと叫びたいのに出来ないもどかしさを柄本時生が好演。遠藤雄弥、草野イニ、安藤サクラ、水崎綾女、三輪子、みんな素敵だ。銀杏BOYZが歌う「17才」は彼らを優しく包む。苦笑とともに落涙必至。79分。 以上(青文字)は、名古屋シネマテークの紹介文。 『きみの友だち』や『コドモのコドモ』など、生徒を扱ったものを見た。平均して、月に3~4本見る自分が、2008年の公開作品のなかで、3本もこの種の作品を見たのは、こういう生徒モノが多いのだろうか? 高校生、中学生、小学生とそれぞれ扱う生徒の年齢は違うが、どれも同じ様に出来ている。 私は、『きみの友だち』を、推す。
2009.01.17
コメント(0)
-
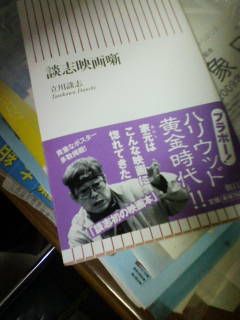
『談志映画噺(立川談志)』
『談志映画噺(立川談志)』です。 ミュージカルなんぞ、ストーリーや映像がどうのこうのってことより、踊りのシーンとか、タップの素晴らしさに酔えばいいんです。”映っているものに価値がある”というのは映画の大切な要素だから。 家元のお気に入り」として、『若草物語』『ロアーズ』『オー!ゴッド』『ブレイズ』『幸福の旅路』『禁じられた遊び』『ガンジー』『素晴らしき哉、人生!』『走り来る人々』『バウンド』『のるかそるか』の11本を挙げている。その他『ワンダとダイヤと優しい奴ら』など、古今の名作もそうでない作品も含め縦横無尽に斬っている。痛快。談志映画噺立川談志朝日新書2008年11月30日 第1刷発行
2009.01.14
コメント(0)
-

『マキノ雅弘 映画という祭り(山根貞男)』
『マキノ雅弘 映画という祭り(山根貞男)』です。山根貞男渾身の労作マキノ雅弘論です。文芸雑誌「新潮」に連載されていたものに加筆訂正をして、単行本にしたということです。1939年生まれ70歳になろうとする山根貞男です。あとがき を引くマキノ作品はわたしにとって映画の面白さの代名詞にほかならない。だからこそ、見て楽しむだけで充分なのであり、そう決めつけていたのには、あんなに途方もなく面白い映画、ただメチャクチャ楽しいだけの映画、それを論じることなど自分にできるわけがないという断念も混じっている。エッセイふうの文章を書いたことはあるが、あくまで自分なりの感想をまじえての解説でしかない。映画の面白さの代名詞なのだから、とにかくマキノ作品の好きなシーンについて、どう面白いのかをかたろう。、その作品を見ている人にも見ていない人にも、楽しさを感じ取ってもらえるように描写して、ぜひ、もう一度、あるいは初めて、その映画を見たくなるように努めよう、これがわたしの採った方法であり、実際にそういう文章になっているかどうかは読者の判断に委ねるしかない。 黒澤明のシナリオをどう料理しているか、実際のシナリオとマキノの撮った映画との比較や、コマをだぶらせる、あるいはコマを落とす手法など、盛りだくさん。なかでも、「次郎長三国志」にはページを割き、丹念に論じている。中味はとても濃厚。あとがきにあるような、エッセイふうのものではない。だからだろう、読むのに苦労する。 マキノ雅弘 映画という祭り山根貞男新潮選書2008年10月25日発行
2009.01.12
コメント(0)
-
『エグザイル~絆~(ジョニー・トー)』
『エグザイル~絆~(ジョニー・トー)』です。 2008年度公開の映画対象のキネマ旬報ベスト10、8位になった。 香港フィルム・ノアールの佳作であるとは思うが、見事なまでのスタイリッシュな点以外、特別見るべきところがあるとは思えなかった。その、かっこよさといってよい、スタイリッシュさは、度を越しており、気障でさえある。室内での拳銃の音と、薬莢が床に落ちる金属音、五人の男たちの友情(?)、そのどれもが、だからどうなの?と、からみたくなるのである。だったら、つまらぬ映画かと言えば、そうとも言えぬ。そういう微妙な映画でもある。 人に聞かれれば、見るなとは言えない。だが、私は買わない。それだけのことだ。
2009.01.11
コメント(0)
-
ETV特集「アンジェイ・ワイダ 祖国ポーランドを撮り続けた男」
「アンジェイ・ワイダ 祖国ポーランドを撮り続けた男」を、今日(1/3)の再放送でようやく録画をした。 昨年の6月15日の放送の時も、パソコンに録画をしたが、ダヴィングの際にデータを消去してしまい、失敗した。昨年11月にこの再放送をNHKのHPで見つけ、今日はダヴィングも上手くできた。めでたし、めでたし。 明日は、吉本隆明。ETV特集は、私の友である。
2009.01.03
コメント(2)
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
-

- パク・ヨンハくん!
- 500記事目の記念に寄せて ― ヨンハへ…
- (2025-11-19 16:29:25)
-
-
-

- 華より美しい男~イ・ジュンギ~
- 10月の準彼ンダー&台北公演の画像続…
- (2024-10-01 14:52:47)
-
-
-

- アニメ番組視聴録
- 11日のアニメ番組視聴録
- (2025-11-11 19:09:38)
-







