2025年05月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

エナガの幼鳥に会えました その1
今年はというか年々、エナガの親子に出会う機会が減ってきました。まず、以前はよく見つけられたエナガの巣がありません。エナガ自体も私の行く地域では減っているのかもしれません。これがエナガの幼鳥です。まだ一人ではうまく餌はとれていないようで、親が来るのを待っているようです。親の姿が見えると追いかけていきます。この子は待ちくたびれて、何かを食べようとしているのかな?新緑の中にエナガの背中を発見。餌取に忙しい親でした。エナガの子だくさん(今回は何羽いるのかはわからず)ですから、親はとても忙しそうです。ずいぶんやつれているように見えます。こちらは、ふっくらふんわりの幼鳥。顔に黒い部分が多くてかわいいです。幼鳥は目の周り(アイリング)は赤いのです。(成鳥はアイリングは黄色)こちらを見ています。なんとなく子犬に似ている?餌を見つけた親。親子です。左が親。右の幼鳥はおねだりをしていないのでおなかはすいていないのかな。(つづく)
2025/05/31
コメント(12)
-

ヒメヒオウギ/アルストロメリア
道端で出会った花たちです。まずは、毎年、楽しみにしているヒメヒオウギ。花はかなり小さいです。(2,5㎝程度)アヤメ科でフリージアの仲間です。この写真だとかなりフリージアに似ていますね。花の色は朱赤、ピンク濃淡、白などがあるそうです。私が見ているところでは白花は少なそうです。ならんで咲くと、とってもかわいい。(#^.^#)ここからはアルストロメリアです。最初に見た時から好きになった花ですが、名前がいつもこんがらがってしまって。ユリズイセン科アルストロメリア属です。
2025/05/30
コメント(11)
-

鳥撮りコレクション135「ミゾゴイ」/ツバメの受難
今年の春に出会った「ハチジョウツグミ」が134番目でした。そして、今回は鳥撮りコレクションの135番目になります「ミゾゴイ」です。名前は聞いたことがありましたが、出会いは全くありませんでした。サギ科ミゾゴイ属。ミゾゴイは絶滅危惧種(絶滅危惧Ⅱ類・・・絶滅の危険が増大しているもの)です。枝(葉)かぶりで見えにくいのですが、先に見つけた人に教えてもらって探し探して何とか見つけて撮りました。(遠いのですごくトリミングしてあります)全長49㎝くらい。日本で繁殖し、冬になるとフィリピンなど南方へ渡る渡鳥だそうです。突然飛びました。さらに遠くへ行ってしまい、ますます見えなくなっています。羽づくろいをしています。里山や森の奥深くに生息し、生態も詳しく分かっていないとのこと。「ミゾゴイ」の名前は、溝で見かけるゴイサギが由来という説と、味噌色をしたゴイサギという説(←ミゾゴイはほぼ溝にはいないし、鳥の名前は色によるものが多いから)がありました。いずれにしてもゴイサギ(の形)に似ていますね。これがゴイサギです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最近、「とことんツバメ、アマツバメ」(佐藤信敏写真・BIRDER編集部編)を読み終えました。ツバメが減っているのは営巣できる場所、餌などの減少によるところが多いですが、巣やヒナを狙われることも多く、全体の15%がカラスにやられています。さらに原因不明で巣が落ちたとされる中にカラスによって巣を落されたものを入れるともっと数値はあがるようです。近所のツバメの巣そしてスズメによるツバメの巣の乗っ取りも多く見られるようになってきているそうです。スズメは、ツバメのヒナや卵を捨ててその巣を乗っ取ってしまうのです。一番の味方である人間がツバメの敵になってきたということもあるそうです。ツバメは生きている限り同じ場所に戻って営巣するそうです。(ただし同じ巣を使うとは限らないがその近くに営巣する)古い建物を取り壊すともうその近くに巣を作れるところが見つからなかったり、店舗の出入り口の上の巣を取り払ったりなどなど。今年は、これまで毎年巣のあったところを段ボールでふさいで巣を作れなくしている建物を見かけました。もちろん、以前からかわらずにツバメを保護している人は多いですし、人口巣などを作っている人たちもいます。静かに営巣を見守ってあげたいですね。
2025/05/29
コメント(10)
-

ハーブの丘の花たち/紋白蝶
昭和記念公園のチューリップガーデン近くに小さな丘?があります。とっても狭い高低差も少ない場所ですが、そこが「ハーブの丘」と呼ばれています。チューリップが咲いているころは、中央に枝垂れ桜がありその下はネモフィラやリラリアなどがありました。そこがジャーマンカモミールがメインになっていました。カモミールの良い香りがただよっています。その中にハナビシソウ(カリフォルニアポピー)もありました。ポピーとヤグルマギクなど。ここのポピー(アイスランドポピー)はいろいろな色があります。ハナビシソウ(カリフォルニアポピー)一輪。アグロステンマがいっぱい。アグロステンマよりもムギセンノウという呼び方の方が私はわかりやすいです。('◇')ゞポピーのそばのヤグルマギクにモンシロチョウが来ました。ふわっと。少しの間、ここで吸蜜していたようです。
2025/05/28
コメント(10)
-

花の丘は赤と白2(昭和記念公園)
昨日は、ご心配をいただきましてありがとうございました。m(__)m静養を続けております。昭和記念公園の続きです。今年の花の丘はシャレーポピーの赤とカスミソウの白です。白いカスミソウの中に、虞美人草一輪。シャレーポピーよりも虞美人草という名が好きです。(#^.^#)白よりも赤が多いところ。どんより曇っていたのですが、空が少し晴れてきました。あのかわいいおうちを使いましょう。まずは手前の花を。今度は窓の向こうの花々を。手前にカスミソウを入れて。カスミソウ他を前ボケに使って。
2025/05/27
コメント(8)
-

花の丘は赤と白(昭和記念公園)1
気温の高低が激しく、体調を崩しております。仕方がないので、おとなしく録画した「世界卓球2025」の日本選手の分を二回戦以降全部見ています。('◇')ゞ二週間前の昭和記念公園の花の丘です。去年は一面のネモフィラでした。しかし、今年はシャレーポピー(虞美人草)です。ただし、なぜかカスミソウも植えられていました。まだ満開ではないですね。たまにピンクや白い花もまじっています。かわいいおうちがありました。以前、シャレーポピー一色だったことはあるのですが、今年はこの白いカスミソウが混じって。ちょっと違和感がありました。('◇')ゞ白の中に紅も何点か。ちょっとしんどいので、今日はここまでにします。m(__)m
2025/05/26
コメント(13)
-

アカボシゴマダラの春型/アザミ
季節と共に目にするものもかわっていきます。春の花から初夏、そして夏の花へ。薊が咲いていました。イメージはややや夏の花。('◇')ゞつぼみもかわいい。もうたくさん咲いていました。さて、薊のそばで出会った蝶は・・・。最初、何だろう?と思ったのですが模様を見るとアカボシゴマダラのような。しかし、アカボシゴマダラの特徴である赤い模様がありません。これは春型だからでしょう。大接近。例年はアカボシゴマダラは赤い斑点のある夏型ばかり目にしていました。今回、春型が見られてよかったです。
2025/05/25
コメント(13)
-

タイサンボクが咲いていた!
まだまだだろうと思っていたタイサンボク。それでも、一応、見上げてみたら、何と咲いているではないですか。えーっ、もう咲いているなんて。気温が高すぎる日があったからでしょうか?以前は、6月に入ってから咲くのがタイサンボクと思っていました。('◇')ゞ毎年のように見ている木です。高いところに咲いていました。ただ、花数は2つ程度であとはつぼみでした。その木の近くにもう一本タイサンボクがあります。こちらはもう少し低い所に大きな花を咲かせていました。ただ、花数はとても少なく、ツボミも数えるほどでした。ここからは、あまり大きくない児童公園です。数年前に見たことがありましたが、あまり立ち寄らない公園でした。それなのに?すでにかなりの花が咲いていました。まだ開く途中のようなものも。上を見上げると、かなりたくさん咲いています。とても良い香りが漂っていました。(#^.^#)
2025/05/24
コメント(12)
-

散歩道での新たな発見(栴檀、柑橘類)
時々通る道であれ?と思うような植物を発見。「まさか、こんなところに」としばし立ち止まりました。何年何年も通っている道なのですが、この花を見たのは初めてでした。栴檀ですよね?そうだとすると、これまでこの花を見たのは植物園と、奈良のお寺、鎌倉のお寺、東京のお寺各一か所ずつだけでした。('◇')ゞかなりたくさん咲いていました。それにしてもこれまで全くきがつかなかったなんて・・・。そして、これもこれまで気が付かなかったお花です。ミカンやレモンのような柑橘系のお花ですよね?この木のそばも何度も通ったことがあるのに、これまで足を止めたことが一度もありませんでした。実がついているのも気が付いたことがありません。何の花なのでしょう?最後は、あちこちでよく見かける花です。スイカズラですね。また、楽天ブログが書きにくくなってしまいました。( ;∀;)今回は、Microsoft Edgeではなくグーグルクロームで書いています。
2025/05/23
コメント(10)
-

ユリノキ・ホオノキ
まず、モクレン科のホオノキです。ホオノキというと、朴葉みそを思い出します。飛騨高山などで食べました。ホオノキの葉は、長さ20~45㎝(幅10~25㎝)ととても大きいものです。日本の広葉樹の中でも最大だそうです。昔からご飯やお餅をこの葉で包むのに使われたそうです。お花もとても大きいです。これは、まだ開ききっていない花です。そして、以下はユリノキです。咲き始めの頃は、花は高い所にしかなかったのですが、だんだん低いところにも咲くようになってきました。別名チューリップツリー。つぼみです。がんばって一番低い所の花をのぞいてみました。中心部にメシベがあって、そのまわりにおしべがあります。おしべの葯(花粉入れ)は2cmもあるそうです。花が終わると、枯れたつぼみのような果実ができます。
2025/05/22
コメント(10)
-

水浴びするガビチョウ
ガビチョウは大きな声で鳴く鳥です。他の鳥の声のまねもするようで、以前は「あれ?」と首をかしげたこともありましたが、最近は騙されなくなりました。( ^)o(^ )たとえば、サンコウチョウ(三光鳥)の「ホイホイホイ」とか、コジュケイの「チョットコイチョットコイ」などの鳴きまねをしたりするのです。珍しく水浴びをするところを見かけました。水辺に来ましたよ。ガビチョウ(画眉鳥)はスズメ目 ヒタキ科 の24cmくらいの鳥です。頭を突っ込んだ激しい水浴びです。ガビチョウの水浴びはこれまでほとんど目にしたことがありませんでした。('◇')ゞ「あれれ、見られてる?」「見られてるのに浴びちゃった。」と後悔するような正面顔。まるで別人(鳥)のようです。( ^)o(^ )「あついから、もういっかいしておこう。」水しぶきを見るだけでも涼しげです。('◇')ゞ目の周りの白眼鏡が印象的です。ちなみにオシドリのメスも白眼鏡をかけています。('◇')ゞ水浴びは4,5回出たり入ったり繰り返してしていましたが、ブログではあっさりとまとめてみました。「ん、じゃねー。」と立ち去りました。元々は日本には生息しない鳥でペットとして飼われていたものがかご抜けして定着したようです。ガビチョウは特定外来生物に指定されていますが、けっこう繁殖しているようですね。
2025/05/21
コメント(10)
-

魅惑のバラ2
前回からの続きです。道沿いにボランティアさんたちがお世話をしてくださっている薔薇ですが、数えきれないほどあります。特に春はよく花をつけていて香りもすばらしいです。真ん中が濃い色で、外に行くほど淡くなるグラデーション。アビゲイル、夕霧、ダブルディライト、ダイアナ・プリンセス・オブ・ウェールズなどに似た感じのバラもありました。裏がクリーム色っぽい。これからはなやかににぎやかに。これだけはわかりました。「ピエール・ドゥ・ロンサール」。(名札もありましたし。)ひらひら感、色合いがたまりません。赤いバラにもいろいろなものがありました。朱色に近いもの。もっと濃い色でおとなっぽいもの。('◇')ゞさらにシックな色合い。どのバラもみんな魅力的で時がたつのを忘れます。(*^_^*)
2025/05/20
コメント(10)
-

魅惑のバラ1
今年はバラ園に行くチャンスがまだありません。近場に毎年、たくさんバラが見られるところがあるのでそこで済ませることにしました。ただし、背景等に問題があり、バラの個別アップになってしまいます。('◇')ゞ(品種名もわかりません。)まず、この色に魅入られました。この色形もかわいらしい。巻きがなんともいえません。(#^.^#)たまに一重のバラもあります。縁取りがついてかわいらしい。奥の方が黄色いようです。寄り添って。みまもって。ちょっとおしゃれなのもありました。これは、初めてみたかもしれません。(つづく)
2025/05/19
コメント(10)
-

雨の日のバラ、雨後のシャクヤク
庭の花たちです。雨の日は庭の花と少しだけ遊びます。かなり雨が降っています。ベランダから撮っていますが、バラはかなり背が高いので見上げるようなかっこうになってしまいます。雫が二つ。右の雫は待っても待っても落ちなくて、落ちるところを撮るのは今回はあきらめました。(その後、落ちました。)バラの葉にも。雨の日より前のジョン・F・ケネディ。この色が好きです。この色も好き。名前はわかりません。('◇')ゞめだたないところにシラー・ペルビアナ(オオツルボ)がひとつ。シャクヤクは三種類あります。これは、かなり目立つ。可愛い感じの花。このシャクヤクは、たくさん咲いているのです。(*^_^*)純白も。昨日は雨で涼しめでしたが、今日はものすごく暑くなるようでおそろしいです。( ;∀;)
2025/05/18
コメント(11)
-

イチハツ・アヤメ・カキツバタ
「いずれ あやめ か かきつばた」というのは、美しいアヤメとカキツバタは非常によく似ていて区別がつきにくく、いずれも優れていて優劣がつかず選択に迷うことのたとえとしてつかわれますが、ここでは、一初(イチハツ)、文目(アヤメ)、杜若(カキツバタ)を比べてみたいと思います。イチハツアヤメ科の草花の中で開花時期が早い、一番に咲く、初めに咲くという意味で「一初」となったそうです。躑躅とのコラボ。花びらは内側に3枚、外側に3枚あります。外側の花びらにトサカのようなヒラヒラした突起があるのが特徴です。乾いた土のところで育ちます。アヤメ外側の花びらに黄色い斑紋があり網目模様になっています。湿地ではなく、乾いたところで育ちます。イチハツに少し似ていますが、この部分の網目文様が特徴です。カキツバタ外側の花びらに白い一本線が特徴です。水の中や湿ったところで育ちます。アゲハチョウが飛んでいました。(#^.^#)*花菖蒲についてはまだ見かけていませんので、写真を撮ったらアップします。 花菖蒲は水のある所で育つ植物です。
2025/05/17
コメント(11)
-

ドウダンツツジとサラサドウダン
真っ白い小さな小さな下向きの壺のような花が咲くドウダンツツジ。「満天星躑躅」とも書きます。また「灯台躑躅」とも書くのは、枝分かれする様子が昔の夜間の明かりに用いた灯台(結び灯台)に似ていることによるものだそうです。とても花が小さいので、咲いているのをつい見逃してしまったりします。('◇')ゞ樹高は40〜300 cmで、秋には葉が紅葉します。ここからは、サラサドウダンです。web上の写真で見ては憧れていました。ずっと見たことがなかったのですが、やっと出会えました。(#^.^#)「サラサドウダン」の由来は、花が風鈴のような形で紅色の筋が入り、更紗模様に似ていことから名付けられたものです。アリさんが来ていました。白いのはコゴメウツギの花です。かわいくて、きれいで、いつまでも見ていたお花でした。別名はフウリンツツジ。下向きのこの花は小さい(2~3cm)ですが、満天星躑躅よりは大きいです。
2025/05/16
コメント(11)
-

キビタキの声に誘われて
今年も夏鳥であるキビタキがやってきました。林の中の高い木の上から美しい声が降ってきます。しかし、見上げても緑ばかりで鳥の姿はちっとも見えません。首を痛めそうです。声は時々あちこち移動するので、その声をたよりにこちらも移動して探すのですがまったく見つからなくてがっかりすることもあります。すっきりした良いところにちらっとだけ出てきてくれました。\(^o^)/でも、すぐにいなくなってしまいました。今度はさらに高い木の上です。新緑はきれいですが。やっと見やすい所に。慌ててシャッターを切っています。何やら上方を気にしているような。「見返りきびたん」その後、ちょっと落ち着いたのか少し囀り始めました。大きな口をあけてうたいます。さらには、もっと口をあけて。あごがはずれない?('◇')ゞでも、またすぐにいなくなってしまいました。(おしまい)
2025/05/15
コメント(9)
-

キンラン・(ササバ)ギンラン/トンボたち
ちょっと出遅れました。('◇')ゞそういうのがかなりあります。気が向いた順にテキトーに出しております。m(__)m公園内のキンランです。いっぱい咲いていました。こちらは毎年見かけるいっぽんだけのキンラン。自生種といえるかもしれません。上から花を見る。ランという感じがします。林の中、キンランの近くにいくつかありました。たたぶんササバギンランでしょう。仲良くならんで。今季初のトンボはヨツボシトンボでした。(4月27日撮影)ヨツボシトンボの前に、オツネントンボ(成虫のまま越冬するとんぼ)などの姿も見られるはずです。ヨツボシよりも遅れてシオカラトンボのオスが。(5月8日撮影)トンボはまだあまり見かけていませんが、もうかなりの種類が出てきていると思います。
2025/05/14
コメント(9)
-

なんじゃもんじゃの正体は?
昨日に続いて白いお花です。「ナンジャモンジャ」という名前の花はいくつかある(ニレ、イヌザクラ、ボダイジュなど)ようです。今回アップするナンジャモンジャの木の正式名称は「ヒトツバタゴ」です。雪が積もったかとみまごう?ような木がありました。遠くからもめだちます。「ナンジャモンジャ」のいわれとして、このヒトツバタゴが1枚の花弁が4つに分かれて4枚に見えることから「何だこれは」が「ナンジャモンジャ」になったという説があるそうです。一枚の花弁が四つにわかれているそうですが、かなりごちゃごちゃしていますね。('◇')ゞなかなか繊細ですが、プロペラをイメージしてしまいます。この白はお天気の良い日に青空を見上げながら眺めるのが一番良い気がしました。(#^.^#)
2025/05/13
コメント(9)
-

似てる?ハクウンボクとエゴノキ
毎年、この時期になると思い出すのがハクウンボクとエゴノキです。咲く時期は若干、ハクウンボクの方が早い気がします。今年はすでにだいぶ散っていました。ハクウンボクです。エゴノキ科エゴノキ属で「白雲木」と書きます。葉っぱは丸くて大きめ。ハクウンボクとうさぎを撮りました。( ^)o(^ )ハクウンボクは、5月初旬にはすでにたくさんの落花が見られました。いっぽう、こちらはエゴノキです。5月8日の写真です。まだ蕾が多かったです。でも、見上げると咲いているのもありました。ハクウンボクよりも花柄が長く、ぶら下がるような感じがします。葉っぱはハクウンボクよりも細長い感じです。エゴノキの実を取りにヤマガラが来るのは秋ですね。(*^_^*)
2025/05/12
コメント(9)
-

ネモフィラの小さい海
今年の昭和記念公園のネモフィラは去年と比べると面積も小さいですし、起伏もない平坦なところに植えられたので、あまりおもしろくありませんでした。( ;∀;)で、ネモフィラを撮りに行ったのか、わんちゃんがメインなのか、よくわからないことになりました。('◇')ゞ犬写真が多いので花のみの写真の間にはさんでいきます。「今日はいい日だねー。」『ええ、とってもよいお日和ですこと。』2人が主役。どっちが主役?さわやかなにぎわい。堂々と。こんなおうちで過ごしたい?(ちょっと窮屈)青の中でゆったり過ごすひととき。「わたし、目立ってる?」『わたし、かわいい?』
2025/05/11
コメント(10)
-

菜の花とカワセミのミニコラボ
カワセミの続きです。少しだけ菜の花がらみになってくれました。登場しているのは、前回と同じカワセミです。こんなお顔をしているメスです。とても細いところに止まりました。揺れる揺れる。「こっちをむいてよー。」『うるさいわね、なんのよう? 今、忙しいからあそべないわよ。』なんと菜の花の中に。(#^.^#)急降下していきます。菜の花が水に映って。さらに下降。この時は特に何もゲットせずに移動してしまいました。そして、見えなくなってしまったのでした。( ;∀;)おしまい、ちゃんちゃん。
2025/05/10
コメント(13)
-

ご無沙汰しましたカワセミちゃん
いろいろとあって(←たいしたことはまったくありませんが)、カワセミ探しに出向くことが少なくなっていました。('◇')ゞ出会えるカワセミも時期的にすくなかったということもありますが。久しぶりのカワセミちゃんは、小さいけれどおいしいお魚をとりました。(#^.^#)そして上を目指して飛びあがっていきます。今度はホバリング。ホバリングからここでの餌とりはあきらめて?別の場所に移動するようです。移動先ではザリガニをとりました。よーくたたいて。こういう時は、目を保護するために瞬膜が出ます。お魚程おいしくないかもしれないけど、これも貴重な食糧です。食後は水に入りました。(水飲みかな)一瞬潜って、すぐ出てきました。さて、これからどうする?(つづきそう)
2025/05/09
コメント(10)
-

藤、白藤、ニセアカシア
今年はあちこちで藤を撮りました。有名な所には行かずに、割合と近場ばかりでしたが。ほとんどの写真がお蔵入り。その中から、少しだけ出してきました。('◇')ゞ藤の咲き始めのころでした。この藤棚のフジはそろそろ見ごろ後半かな。大好きな八重のフジ。白っぽい藤との共演も。白い藤を少し遠くから。白い藤はそれほど多くはないのでしょうか?これも、白い藤・・・ではないですね。ニセアカシアです。ニセアカシアは、見上げるような高木にたくさん咲いていました。別名ハリエンジュといいますが、棘があるのでその名がついたとか。ただし、棘のないものも品種改良されているそうです。
2025/05/08
コメント(10)
-

大空にシャボン玉飛んだ
4月26日のことです。昭和記念公園のハーブの丘でシャボン玉を飛ばすイベントがあると聞きました。用事があって、イベントの開始に何とか間に合いました。ハーブの丘にはネモフィラ、カリフォルニアポピー、リナリアなどが植えられています。ワンちゃんもシャボン玉を楽しんでいるようでした?このあたりには、ポピーやヤグルマギクも。去年も感じましたが、特に青い色のネモフィラバックになるとシャボン玉は全然目立たなくなります。こういうバックでないとね。それでも、少しでもお花と一緒に撮りたいですね。今年は「シャボン玉おばさん」とのコラボが行われたそうですが、大きいのをだしているのはおじさんでした。('◇')ゞ大きいシャボン玉は壮観です。持続時間も長めで形も変化し楽しめました。反対にすごく小さいのも出ていました。手前のホオノキももうすぐ咲きそうです。花たちもカラフルで夢の中のような。多くの人たちがたのしんでいました。
2025/05/07
コメント(13)
-

端午の節句にうさぎも登場
昨日は端午の節句、子どもの日でした。こし餡の柏餅を食べ(おとといはみそ餡のを見つけて食べたし、結構、日常的に柏餅をたべています)、しょうぶ湯に入りました。(*^_^*)たまにはポロリも出しましょう。この8月で11才になる高齢、闘病中のうさぎ(ネザーランドドワーフ)です。今年は兜だけで、弓と矢は飾りませんでした。兜に比べて目立たないポロリ。近づいてみました。今度はひとりだけ椅子の上で。あ、降りちゃだめだよ。(もう、飛び降りることもないですが)ちんまり、おとなしく。「みなさん、またおあいしましょう。」
2025/05/06
コメント(11)
-

「生誕140年記念 石崎光瑤」展へ(野鳥写真も掲載)
日本橋高島屋の8階の資生堂パーラーで食事をした後、同じ階の催事場へ。「生誕140年記念 石崎光瑤」展が行われていました。(4/23から5/6)石崎光瑤(こうよう)さん(1884~1947年)は、近代京都画壇の日本画家です。この展覧会の趣旨や画家についてはHPより以下に引用します。「富山県に生まれた光瑤は、金沢で琳派を学び、その後京都に出て、竹内栖鳳に入門。インドを旅して熱帯の風物に触れ、代表作 《燦雨》をはじめ、花鳥や風景を濃密な描写で描き、画壇の注目を集めました。 また光瑤は、日本の古画を深く学び、自身の制作に活かしました。早くから伊藤若冲に関心を持ち、若冲の代表作を発見して世に紹介したことでも知られています。本展は、光瑤の故郷にある富山県の南砺市立福光美術館のコレクションより、初期から晩年までの代表作や資料など約40件を公開し、光瑤の画業の全貌を紹介する初の回顧展です。」ここではすべてのものが撮影OKでした。ただし、ガラスケースが光ってしまって変な映り込みも出てしまいます。「白山の霊華」(1910年) 絹本着色一幅「森の藤」(1915年 ) 六曲一隻 第九回文展とても見事な作品でした。32歳でインドにむかう。「第一次印度旅行六 カシミール洲 水郷」(1917年)一巻「燦雨」(1919年) 六曲一双 第一回帝展(特選)インドで見たと思われるワカケホンセイインコがたくさん描かれていました。ちなみに、以前撮った桜の中のワカケホンセイインコ。雀と同じように花をちぎって裏側から吸蜜します。「雪」(1920年)画布着色 二曲一双 第二回帝展「麗日風鳥」(1924年)絹本着色 まさに若冲の影響大という気がします。ヤマドリ雄「春律」下絵(1928年ごろ)石崎氏はタイトルを漢字二字でつけることが多いような。例として緑蔭、寂光、豊穣、紅楓、惜春、霜月、遅日、清夏、後圃、聚芳など。ずいぶん前に出会った野生のヤマドリです。一緒に歩いたこともあります。(なぜか横並びでついてきた。)('◇')ゞ「隆冬」(1940年)六曲一隻 紀元二六〇〇年奉祝美術展オシドリのオスメス他が描かれています。以前撮ったオシドリのオス三羽とメス(左から二番目)「アオバト」(1943年)丸く膨らんでかわいい。(*^_^*)アオバトはドングリが大好き。まるのみします。「遊兎」(1946年)これが一番よかった。(←単に兎好きだから)('◇')ゞ75作品はなかなか見ごたえがあり、まったく知らなかった方のすごい作品を見られて目から鱗でしたし、若冲をほうふつとさせる作品も多くて楽しめました。
2025/05/05
コメント(8)
-

ビアズリー展から日本橋高島屋へ(資生堂パーラー)
ビアズリー展を開催している三菱一号館美術館をあとにして、今度は東京駅の東側方面にむかいます。(4月28日のことです)東京駅の近くでも、新緑を楽しめるところも。新緑は目にとっても優しいな。透明の回転ドアが気になりました。東京ミッドタウン八重洲の前を通ります。この彫刻が気になって足を止めました。帰宅してから調べたら吉岡徳仁氏の光の彫刻「STAR」であることがわかりました。高さは10mくらいあります。そして目指すはここ。日本橋高島屋。(重要文化財)エレベーターに乗ったらエレベーターガールがいてびっくり。(多分、4台とも全部有人)手動で案内をしていました。ドアを閉める時は内側の金色の格子の蛇腹までついていてすごい。ただし、エレベーターは撮影禁止。8階の資生堂パーラーへ。混雑を予想して11時すぎには入りました。まだ数席はあいていました。つれは「日本橋店オリジナル洋風御膳」・・・カボチャのポタージュ、洋風御膳(特に国産牛フィレ肉のステーキ丼がおいしい)、パフェ、コーヒーです。究極のハンバーグステーキを求め続けている私は迷わずに「ハンバーグステーキ和風ソース」(2640円)を。そしてパンを選びました。(あ、食べかけの写真だった)このハンバーグがとーってもおいしくて、今まで食べた中で一番でした。おなかの具合によっては、食後にパフェ(イチゴかチョコ)を注文しようとメニューをしっかり確認。小さめなのか1485円とお手頃価格。(2800円や3000円のフルーツパフェもあるようですが。)食後は思った以上におなかがいっぱいになってしまい、チョコパフェ等は頼まず、洋風御膳についてきたパフェを横取り・・・いえ、いただきました。(#^.^#)これも、おいしくて満足!食事を終えて空いた席がふたつみっつ出てきましたが、新たなお客さんは入ってきません。意外と人がこないものだ・・・と思いながら12時15分ごろに外に出てみると、なんと20人くらいがずらーっと座って順番を待っていました。やっぱり人気があるのですね。このあと、同じ8階で開催されているものを見に行ったのです。(つづく)
2025/05/04
コメント(11)
-
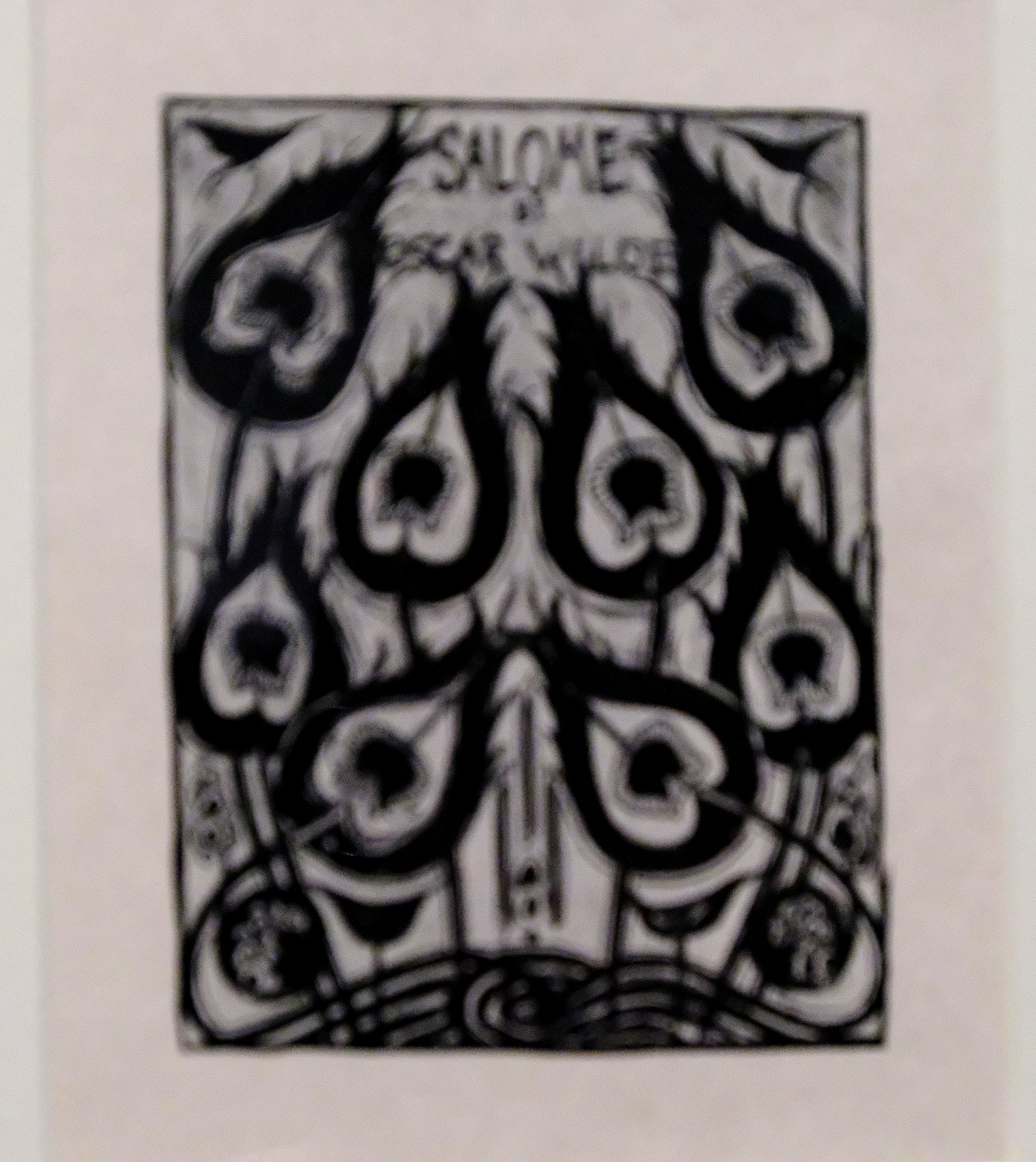
「異端の奇才 ビアズリー展」2
三菱一号館美術館で行われている「異端の奇才 ビアズリー展」の続きです。まず、エレベーターで3階まであがります。そこから順路にしたがって作品を見ながら降りていくことになります。ほぼ撮影はできませんが、一部、撮影可能なところもありました。ただし、暗いし、こんでいるので正面から写真が撮れません。ゆがんだり、ぶれたりして見にくいのはお許しあれ。「サロメ」の表紙「孔雀の裳裾」「クライマックス」展示室を出て、廊下を通って次の展示室へ。廊下の窓から外が見えます。左側が美術館の建物。見下ろす。ガラス張りの天井があったり。ポスター「イゾルデ」(リトグラフ)のような色のついた作品もありました。「髪盗み」フォトスポット等身くらいの高さのものなので、ここに立って撮影(されることが)できます。主に3階と2階をぐるぐるまわりながら降りて来て退館します。建物の正面が出口になっていました。(入る時は裏の方から)(つづく)
2025/05/03
コメント(11)
-

東京駅近くの美術展等へ1
4月28日(月)は平日。東京駅近くにお出かけ。東京駅手前で車窓から新幹線「こまち」を。東京駅の丸の内改札を出て、ドームを見上げる。東京駅付近では、以前もよく見かけた黄色いはとバスが。最近、はとバスに乗った知人に聞いたところ、乗っていた人はほとんど日本人だったそうです。それと比べると、この「スカイ バス トウキョウ」は外国人がほとんど?さて、目的地は奥の赤い建物でした。三菱一号館美術館です。その日は平日の上、月曜は美術館が休みのところが多いので(月曜に美術館に行こうする人は少ないはず)、少しは空いているかと思いましたが・・・。開園の10時過ぎに行ったら、すでにものすごくこんでいました。異端の奇才 ビアズリー展オーブリー・ビアズリー(1872-1898)は25歳で世を去りました。ブライトン出身で家計を支えるため16歳から事務員として働き、夜間に制作活動を行ったそうです。その後、有名になってからもろうそくの光のもとで絵を描いたのはそのころの名残なのでしょうか。『アーサー王の死』(T.マロリー著)、 『サロメ』(O.ワイルド著)の挿絵等で成功しました。(つづく)
2025/05/02
コメント(13)
-

石楠花、花蘇芳、紫蘭、雲南黄梅
4月中旬に見かけた花たちです。児童公園でも春らしい色とりどりの花が見られます。ピンクの可愛い花が。石楠花(シャクナゲ)でしょう。明るい春を謳歌しているような。手毬のような形になるものも。緑に映える花蘇芳(ハナズオウ)です。青空にむかって。紫蘭(シラン)もたくさん咲いていました。そして、これまで黄梅(オウバイ)だと思っていたのが、実はオウバイモドキ(雲南黄梅)だったようです。('◇')ゞ黄梅は「花の大きさが2~3cmの一重咲きで、葉が出る前に開花する」そうですが、雲南黄梅(オウバイモドキ)は「花の大きさは4~5cmで二重か八重。葉がある状態で開花する」とのこと。ということで、これはウンナンオウバイだと思います。
2025/05/01
コメント(11)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 花のある暮らし、宿根草
- 小径(その7)。ツワブキ。頭上はカリ…
- (2025-11-15 13:11:11)
-
-
-

- 泣き笑い家庭菜園・・・やっぱり手作…
- とうもろこし🌽栽培の悲劇
- (2023-07-06 12:55:36)
-
-
-

- いけばな ★彡
- 薔薇とユーカリやアカシアで ☆ 生…
- (2025-11-15 09:30:04)
-







