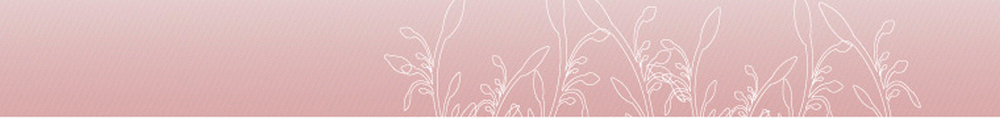-
1

発達障害の子どもに寄り添う美容師 児童書を寄贈。
発達障害の子どもに寄り添う美容師 児童書を寄贈発達障害の子どもが安心して髪を切れるよう工夫する「スマイルカット」を広めてきた美容師で、NPO法人「そらいろプロジェクト京都」代表の赤松隆滋さん(51)の活動が児童書になった。そらいろプロジェクト京都は9月、京都市内の市立小学校や総合支援学校計162校に、寄贈した。 児童書「スマイルカットでみんな笑顔に! 発達障がいの子どもによりそう美容師さん」は、赤松さんの15年以上の取り組みをもとに、安心感を与える声かけやカットの工夫を紹介。2月に出版された。子どもや保護者との体験談、イラストも盛り込まれている。作家の別司芳子さんが、赤松さんや子どもら関係者に取材をし、書き上げた。 赤松さんの活動のきっかけは2010年、児童館でのカット講座だった。保護者から「発達障害の子は美容院で髪を切るのが難しい」と相談を受け、赤松さんは「断らずにやってみよう」と応じたが、知識不足から失敗。その経験が学びの出発点となり、スマイルカットにつながった。 14年には活動を広げるため「そらいろプロジェクト京都」をNPO法人化。全国で講演や研修を行い、障害者への合理的配慮の重要性を伝えている。これまでに赤松さんが直接カットした子どもはのべ9千人を超え、スマイルカット実施店舗は全国で100以上に広がった。 しかし、「業界全体の理解は十分ではない」と赤松さんは言う。昨年4月に改正障害者差別解消法が施行され、事業者に合理的配慮が義務づけられた。しかし、美容師の国家資格の教科書には、合理的配慮の具体的な内容が盛り込まれていない。赤松さんは厚労省と、障害者が安心できるヘアカットのガイドラインを作成した。しかし、普及はなかなか進まない。 「この取り組みが当たり前になり、NPOが不要になる日をめざしたい」。赤松さんはそう語り、活動の輪を広げている。朝日新聞社【YAHOOニュース】スマイルカットでみんな笑顔に! 発達障がいの子どもによりそう美容師さん [ 別司芳子 ]丁寧な取り組み、全国的に展開して欲しいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.21
閲覧総数 33
-
2

知的障害者が暮らす場は。
知的障害者が暮らす場は人里離れた山あいにある施設に集団で生活する障害者――。昨年7月に相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で起きた殺傷事件は、こうした実像を浮き彫りにした。障害者が暮らす場を施設から地域へ移す流れは、どうなっているのか。障害者はなぜ人里離れた施設で生涯を送らなければならないのか?やまゆり園事件から半年~福祉の「家族依存」、脱却を ■施設を離れられず 地域での受け入れに壁 大阪府南部にある富田林市の近鉄富田林駅から自動車で20分ほど走ると、金剛山をのぞむ山林に囲まれた広大な敷地が広がる。面積は約82万平方メートル。東京ディズニーランドの1・6倍にあたる。 敷地内に点在する7棟の施設に、42人の子どもを含む408人の知的障害者らが暮らしている。職員が「最寄りのコンビニまで約3キロ」と言う場所にあるのが、「こんごう福祉センター」だ。 3月末、敷地の大半を占める居住区域である「大阪府立金剛コロニー」が閉鎖された。代わりに今月1日、コロニーを運営してきた大阪府障害者福祉事業団が、介護の必要性の高い高齢者に対応した施設「にじょう」を60人の定員で開所した。48人はコロニーから移り、地域での生活が難しくなった高齢の障害者も新たに入所してきた。 昼下がり、「にじょう」の一室から高倉健の「唐獅子牡丹(ぼたん)」など1960~70年代の流行歌が聞こえてきた。昭和歌謡が好きな男性(73)が集めたCDだ。 男性には知的障害がある。若い頃は自動車やねじの工場で働いていたが、78年、34歳の時に失業した。それを機に、両親に代わって面倒をみていた親類が金剛コロニーへの入所を依頼。それ以来、39年にわたって暮らしている。 「これな、妹と住んでた家やねん」。男性は壁に貼られた絵を指さした。平屋建ての建物と2人の人物が描かれている。ただ、今は「ここがええ」という。 金剛コロニーは大阪府吹田市で万博が開かれた70年に開所され、当時は定員850人で国内最大規模。「北の万博、南のコロニー」と呼ぶ人もいた。 介護を担う家族の負担を解消し、「親亡き後」も子の安心した暮らしを願う親の思いに応えるのがコロニーだった。70年代には都道府県が各地に作り、全国でコロニーブームが起きた。 だが、地域から隔離される施設のあり方への疑問はあった。81年の国際障害者年を機に障害者も地域で暮らす「ノーマライゼーション」の考えが広がると、「施設から地域へ」という動きが出てきた。 事業団は2003年度から、高齢者向けも含め障害者が少人数で共同生活するグループホームを地域に本格的に整備。16年度までに491人が移った。 別の高齢者棟で暮らす石賀良三さん(68)は6年前、グループホームに移りたいと希望したが、障害が重くて受け入れられなかった。5年前に急性膵炎(すいえん)を患い、視力や聴力は衰え、のみ込みも難しくなってきた。妹の池田隆子さん(65)は、こう語る。「地域に出て元気でなくなった時、ずっといられるわけではない。高齢者施設も病院も障害者を受け入れてくれるかわからない。家族も高齢でみられない。より安心な場が施設と考える家族は多いのではないでしょうか」 施設を出た障害者は08~12年には全国に5千人前後いたが、13年以降は2千人台にとどまる。厚生労働省の担当者は「地域移行を進めた結果、障害が重度だったり高齢だったりする人が施設に残った。新たに地域移行できる人は近年、減っている」と分析する。 とりわけ地域移行の流れから取り残されがちなのが高齢者だ。金剛コロニーの高齢化率は06年に約6%だったが、今年3月時点では約30%に。高齢者対応の「にじょう」ができた背景には、そんな事情がある。 事業団の久保田全孝(まさゆき)理事長(62)は「地域移行は進めるが、入所者の高齢化や地域に移った人が高齢になって再入所する現実への対策が必要。地域と連携し、一時的な利用など地域生活を支える安全網の役割を果たす施設をめざす」と話す。■市街地で共同生活 行動広がる 在宅生活は難しいが、施設ではなく地域で生活したい障害者の住まいとしてカギを握るのは、グループホームだ。1989年に国が新たな住まいの選択肢として制度化した。日本グループホーム学会によると、全国に約2万カ所あり、昨年12月時点で10万7千人ほどの障害者が生活している。 重症心身障害児者向けの施設を運営する社会福祉法人「びわこ学園」が1年前に整備した滋賀県野洲市のグループホーム「えまい」。平日の午後4時すぎ、電動車いすに乗った寺田美智夫さん(51)が、作業所から送迎バスで帰ってきた。木造平屋建てでリビングを囲んで個室があり、8人の仲間と暮らす。 重度の知的障害と身体障害がある寺田さんは父を亡くしてから10年以上を施設で過ごしたが、外出できるのは年に数回程度だった。昨年6月に「えまい」に移った。今は、週に2日は学園の施設に通い、3日は別法人の作業所でペットボトルのふたを仕分ける仕事をする。生まれて初めて賃金やボーナスをもらった。 「朝起きて昼は外で活動し、夜はホームで過ごす。生活にメリハリや自由がある」と寺田さん。夜のトイレ介助のタイミングや焼酎を飲む日、ネット通販の注文などを自分の意思で決められるようになった。 我が子の将来を考えた親たちがグループホームを立ち上げたケースもある。東京都練馬区のグループホーム「とぅもろう」だ。 当初は区に整備を求めたが実現しなかったため、7千万円の補助を受け、資金を借り入れてNPOを設立。昨年4月から運営を始めた。今は20~30代を中心に重い知的障害と身体障害を併せ持つ9人が利用。夜勤の看護師を置き、医療的ケアにも対応する。 設立に関わった飛田悦子施設長(55)は「都内では施設も不足しており、将来、遠く離れた県の施設に入ることになるのではないか、という心配が親たちにあった」と解説する。 課題は介護人材の確保だ。びわこ学園の職員、南方孝弘さん(51)は「重い障害のある人を支えるには手厚い態勢が必要。そのために報酬が増える仕組みを整えてほしい」と訴える。 津久井やまゆり園の事件後、神奈川県は施設の建て替えを決めたが、障害者団体などは地域移行に逆行するとして反対している。 知的障害者と家族らでつくる「全国手をつなぐ育成会連合会」の久保厚子会長は「障害がある人が望む地域での暮らし方は様々。グループホームの整備は急務だが、障害のない人たちと生活するシェアハウスなど多様な選択肢を増やすことも重要だ」と提案する。 大阪府立大の三田優子・准教授(障害者福祉)は施設の役割を「一時的に専門職が関わる拠点」と評価しつつ、こう指摘する。「障害のある人も地域で当たり前に暮らすのが本来の姿。障害のある人の魅力を発見して交流が生まれ、障害のない人も支えられる。こうした実践を積み重ねることが、やまゆり園の事件に象徴される障害者を抹殺するような考えをなくし、共生社会につながるはずだ」【朝日デジタル http://digital.asahi.com/articles/ASK4R33P8K4RUBQU001.html?rm=977】家族から遠く離れた施設暮らしが今までは多かったけど、今後は地元の地域に共生する暮らしが実践できるようになると、本当の意味での支え合う暮らしが整うのでしょうね。🌠
2017.05.07
閲覧総数 3979
-
3

米津玄師、いじめ・大ケガ・自閉症に苦しむも確かに見せつけていた“大物の片鱗”。
米津玄師、いじめ・大ケガ・自閉症に苦しむも確かに見せつけていた“大物の片鱗”DAM年間ランキング』歌手別1位など、ランキングで33冠を達成。『紅白歌合戦』では、菅田将暉『まちがいさがし』、嵐『カイト』など楽曲提供した曲が3曲も披露されるなど、2019年は“米津玄師イヤー”となった。なぜ彼は短期間でこれだけの偉業を成し遂げることができたのか。関係者たちの証言で振り返る──。この世に誕生した瞬間からビッグだった 代表曲の『Lemon』は、'18年の発売ながら、昨年の多くのチャートで1位を獲得。ライフスタイルの変化や音楽の多様化が進んだことで、国民的ヒットが生まれづらくなった昨今の音楽業界において、ここまで世代を超えて愛されるのは稀有(けう)だろう。 今や彼の楽曲や名前を聞かない日はないほど、日本を代表する歌手へと成長した米津玄師(よねづけんし)。彼の原点は、四国の徳島県にあった──。県庁所在地がある徳島市で'91年に誕生した米津。生まれたときは4500グラムもあったそうで、この世に誕生した瞬間からビッグだった。 川と海に囲まれた自然豊かな町で育ったが、過去の音楽誌のインタビューによると、《今になって思い返してみると、精神的にも肉体的にも貧しい家庭だった》と語っている。母親はチラシを作る内職をしており、決して恵まれた家庭環境ではなかったようだ。「特徴的な名前もあって、子ども時代はいじめられることも多かったみたいです。あと幼稚園のときだったかな? 遊んでいたときに人とぶつかってしまい、大出血するほど唇を大ケガして、病院に運ばれたことがありました」(実家の近所に住む住民) 現在も唇が少し腫れているように見えるのは、その名残のようだ。この出来事は音楽誌のインタビューでも、《汚いものを見るような感じで受け入れられて(中略)自分が怪獣のようなものになってしまったんだなという感覚があったなあと思いますね》と独特な表現で振り返っている。子どもの頃から普通の人になりたかった 規格外のサイズで誕生したことや個性的な名前、幼少期のトラウマなどもあり、成長とともに生きていることに居心地の悪さを感じるようになった米津。 あまり友達もおらず、休み時間などは、自分の頭の中で作りあげた架空の人物と話すことを、心の拠り所にしていたと音楽誌で語っている。《僕はずっと普通の人になりたかったんですよ、子どもの頃から。普通ではないっていう感覚によって苦しい思いをしてきた自覚もあって》 その違和感の理由がわかるのは、20歳のころ。「人とコミュニケーションがうまくとれないことなどに疑問を感じて病院を訪れたところ、《高機能自閉症》と診断されたそうです。コミュニケーション能力に乏しかったり、こだわりが強いといったことなどが特徴の病気なので、当時クラスメートになじめていなかったのも今思うと納得です」(中学の同級生) 当時の彼は、人とは違う自分にコンプレックスを感じながら、普通にできないということに悶々とするしかなかった。 そんな彼が初めて自発的に行動を起こしたのが中学2年生のとき。当時流行っていた『スピッツ』や『BUMP OF CHICKEN』などのバンドに憧れ、こんな存在になりたい! と、2万円のギターを購入。仲のいい友達を誘ってバンドを結成する。「中学の文化祭ではオリジナルの曲を披露して、みんなを驚かせていました。田舎の学校なのでオリジナル楽曲を披露するような人は、米津くんたちが初めてだったと思います」(同・中学の同級生) 当時からクリエイティブな才能の片鱗(へんりん)を見せつけていた。しかし、高機能自閉症による影響もあり、バンド仲間に自分がやりたいことをうまく伝えることができず、高校に入学してから自然消滅の形で解散してしまう。 そんなときに出会ったのが、動画配信サービス『ニコニコ動画』だった。高校在学中にニコ動を知った彼は、当時のバンド仲間で現在もサポートメンバーとして彼を支える男性に作曲した曲を演奏してもらい、音源を投稿するように。 1か月に3曲投稿することもあり、その世界にのめり込んでいった。インターネット上に居場所を見つけたこともあり、学生時代にはすでに音楽で食べていく覚悟を決めていたようだ。「“将来、絶対に売れてみせるから写真は残したくない”と学生時代から周囲に言っていたのは有名な話。メジャーデビュー前からセルフプロデュースに長けていて、取材を受けた際は自分で写真チェックをするほど、こだわりが強かった」(音楽ライター) ひとりで楽曲制作を始めたものの、バンドへの憧れは捨てきれず、バンド仲間を見つけるために高校卒業後は大阪にある美術系の専門学校へ進学する。しかし、そこで結成したバンドでもうまくいかず……。そんなときに、ヤマハが開発した音声合成技術『ボーカロイド』に出会う。「リアルな歌声を合成するためのソフトウエアで、この技術を使用したキャラクターボーカル『初音ミク』などを使って、制作した楽曲を歌わせる動画がブームになりました」(同・音楽ライター)自分の周りには支持者はひとりもいない 米津も『ハチ』名義でデビュー作『お姫様は電子音で眠る』を'09年5月にニコニコ動画上で発表。その後も動画が次々とミリオン再生を達成するなど、ボーカロイド界のトップクリエイターとして、その名が知られていくことに。「SMAPなどへの楽曲提供で知られる音楽プロデューサーのヒャダインさんもニコニコ動画の出身です。動画投稿サイトの普及で、才能さえあれば年齢や住んでいる場所など関係なくチャンスがつかめる時代になった。 20年前なら、米津さんのような地方出身でコミュニケーションが上手でないタイプは世に出ることはなかったと思います。デジタル時代だからこそ誕生した“時代の寵児(ちょうじ)”ですね」(レコード会社関係者) ボーカロイド界では頂点を極めたものの、《画面の向こうには支持してくれる人はいたものの、自分の周りにはひとりもいない》と音楽誌で吐露し、身近な人たちを喜ばせられないことに疑問を感じ始めていた。 これでは意味がないと気づいた彼は、これまで築いたものを捨て本名の“米津玄師”として活動することを決意。これが国民的歌手への序章となっていく……。 [livedoor.ニュース]色々な偶然が重なって、今の名声へと繋がっているんでしょうね。記念すべき、400万アクセスです。いつもご訪問にコメント感謝です。☄
2020.01.14
閲覧総数 3470
-
4

「ふびんで」 知的障害の娘を殺害容疑で母逮捕 北海道。
「ふびんで」 知的障害の娘を殺害容疑で母逮捕 北海道 知的障害のある娘を殺害したとして、北海道警は28日、札幌市西区西野2条3丁目、無職佐藤和子容疑者(64)を殺人の疑いで逮捕し、発表した。佐藤容疑者は「自分が死んだら娘が1人になるのがふびんだった」と供述しているという。 道警によると、佐藤容疑者は27日午前11時ごろ、自宅で娘の由紀子さん(42)の首を刃物で刺して殺害した疑いがある。由紀子さんは首に複数の傷があり、部屋のベッドで血を流して倒れていたという。 佐藤容疑者は、妹に電話で「娘を殺した」と連絡。その後、行方がわからなくなっていたが、同日夕方、北海道石狩市内で捜査員に発見された。佐藤容疑者の首には刃物で切ったような傷があり、道警は、自殺を図った可能性もあるとみて調べている。 由紀子さんは北海道江別市内の障害者支援施設に入所。平日はこの施設で暮らし、週末に自宅に戻る生活だった。16日に帰宅して以降、施設に戻っていなかったという。 【朝日デジタル http://www.asahi.com/articles/ASH5X3DFBH5XIIPE005.html 】また辛いできごとが起きてしまいましたね。我が子を「ふびん」にさせない生活、日々模索しつつ、送らないとと実感です。🌠132万アクセス達成しております。いつもご訪問にコメント、ありがとうございます。
2015.05.29
閲覧総数 772
-
5

強度行動障害の男性と家族を追ったドキュメンタリー。
強度行動障害の男性と家族を追ったドキュメンタリーテレビ朝日系の全国24社が共同で制作するドキュメンタリー番組「テレメンタリー2020」。テレビ朝日では、毎週土曜深夜(日曜早朝)に放送。7月4日(土) 深夜4:30(6月28日[日]朝4:30)からは、ABCテレビ制作の「強度行動障害 ~わが子を手放す日~」を放送する。滋賀県に暮らす強度行動障害の男性と家族を、2年半にわたって追ったドキュメンタリー。継続取材により、障害の様子と、支える家族の姿、支援が乏しい現実や、グループホームに入るまでの経緯をつづる。滋賀県守山市に住む和田智泰さん(取材開始時17歳、現在20歳)は、重度の知的障害と強度行動障害がある。強度行動障害とは、自閉症の人にあらわれる後天性の障害だ。物をたたいたり、自分自身を傷つけたり、激しい行動があらわれる。この障害がある人は日本に8000人ほどいると推測されているが、詳しい調査は行われていない。智泰さんは食事、入浴、排泄、着替えなど、生活のすべてに介助が必要で、父親の進さん(取材開始時58歳、現在60歳)と母親の泰代さん(取材開始時50歳、現在52歳)が、つきっきりで支えてきた。夜、智泰さんは自宅の中で声を上げたり飛び跳ねたりするため、週末の3日間はドライブに連れて行く。あてのない夜のドライブを4時間続ける。進さんは、智泰さんの介護を優先するため、今から5年前に会社を辞めた。その後、新聞配達と、融通のきく非正規の仕事を掛け持ちしながら、家族を支えている。しかし、夫婦ともに歳をとり、息子を支え続けることが限界になってきた。和田さん夫婦は、智泰さんが養護学校高等部に在籍している頃から、息子が暮らすための障害者の施設を探してきた。滋賀県内の施設は全て満床。京都府、奈良県、石川県、岡山県など他府県に足を伸ばして施設を探した。なかなか見つからなかったが、あるグループホームが受け入れてくれた。そもそも、障害者の施設は、全国的に不足している。特に、重い知的障害の人を受け入れる施設が足りない。制作はABCテレビ。担当プロデューサー・藤田貴久、担当ディレクター・西村美智子。ナレーターを宮城さつきが務める。[ザテレビジョン]「強度⾏動障害 〜わが⼦を⼿放す⽇〜」強度行動障害のある和田智泰さんと、母親の泰代さん(C)テレビ朝日切実な日々のドキュメンタリー、取材に応じるだけでも大変な決心だったことでしょうね。☄
2020.06.20
閲覧総数 2026
-
6

ダンスで成長 障害持つ青年の「ミラクルズ」。
ダンスで成長 障害持つ青年の「ミラクルズ」 さまざまな障害を抱える十勝の青年たちが集まったヒップホップダンスチーム「ミラクルズ」が結成されて1年余りが経過。 地道に練習を重ね、人前で踊りを披露するまでに成長した。 「ダンスは人の可能性を広げる。夢は24時間テレビへの出演」とし、さらに多くの仲間を募っている。 帯広市内でダンススタジオ「FUSION」(東2南15)を主宰する堂前幹治さん(35)が結成を呼び掛け、ボランティアで指導している。 堂前さんは、帯広柏葉高を経て、道医療大臨床心理学部卒。 中学3年生のときからヒップホップダンスを続け、テレビ番組への出演や全国・全道のコンテストで入賞するなど活躍。 22歳でダンス教室を立ち上げ、2011年には念願のスタジオを持った。 自身もコンテスト出場を続けている。 大学時代、障害を持つ人が音楽に体を合わせることによる心身の変化、いわゆる「ダンスセラピー」を研究テーマとし、「障害があってもできる。いつか障害を持つ人と一緒にダンスがしたい」と考えてきた。 7年ほど前、ダンス教室の生徒を通じて、障害などで周囲と交わることが苦手な子供らの居場所づくりを進める「おかゆの会」との関わりができ、当事者や保護者などにヒップホップダンスを教えてきた。 「さらに技術を高めたい」と願う青年10人を中心に昨年4月、ミラクルズを結成した。 現在、メンバーは知的障害や発達障害などを持つ10〜20代の12人。 「みんな心からダンスが好き。僕が遠征などでいないときも、自分たちだけで練習を重ねている。最初はできなかったステップもどんどん習得している」と堂前さんは笑顔を見せる。 5月、同会の10周年イベントで踊りを披露し、今月14日には幕別町で開かれた道障害者スポーツ大会車椅子バスケットのアトラクションで、多くの観客を前にダンスを2曲踊った。 メンバーの大松澤潤さん(25)は「最初は自信がなかったが、今は一番楽しい。もっとうまくなって、いつかはEXILEと共演したい」と前向きだ。 参加は1回500円で、衣装代などの運営費となる。堂前さんは「メンバーのダンスは自身の人生にプラスになるだけではなく、見ている人の心も打つ。ダンスをツールに社会と交流を進めたい」と話し、管内全域から仲間を募っている。 問い合わせは堂前さん(090・6690・1331)へ。【十勝毎日新聞】 ツールは何であれ、それを十二分に利用し、使いこむことで、新たな出逢いと突破口が生まれるものですね。 明るい皆さんの前向きな生き方に、EXILEとの共演も決して夢ではない、決して夢では終わらないような輝きを感じます。 26日は、夫の誕生日だったので、ささやかなお祝いを。🍻💧💦 暑中お見舞い申し上げます・・。💛 にほんブログ村 にほんブログ村
2013.07.27
閲覧総数 247
-
7

私服不許可で町に一部賠償命令 自閉症の元中学生徒、岡山地裁。
私服不許可で町に一部賠償命令 自閉症の元中学生徒、岡山地裁自閉症スペクトラム障害(ASD)で学校の制服に抵抗があるのに私服での登校が認められず、不登校になって教育を受ける権利を侵害されたとして、岡山県矢掛町立中の生徒だった女性(19)=神戸市=が町に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は20日までに、町に33万円の支払いを命じた。19日付。KYODO【YAHOOニュース】制服の文化も少しずつ変化し始めていますね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.08
閲覧総数 37
-
8

29歳年上の「交際相手」刺した殺人未遂の現行犯で男逮捕 群馬。
29歳年上の「交際相手」刺した殺人未遂の現行犯で男逮捕 群馬 群馬・明和町で4日夜、交際相手の女性と父親をナイフで刺した男が逮捕された。逮捕直後に、「携帯電話を投げ捨てられて、カッとなって刺した」と供述したのは、殺人未遂の現行犯で逮捕された大津晴紀容疑者(26)。現場となったのは、群馬・明和町の大津容疑者の自宅だった。大津容疑者は4日午後7時50分ごろ、自宅の1階リビングで、55歳の女性と口論の末、ナイフで刺し、さらに、仲裁に入った自分の父親も刺した疑いが持たれている。また、この55歳の女性について、「交際相手だった」と話しているという。刺された2人は病院に搬送されたが、大津容疑者の父親・信裕さん(51)は重傷を負い、大津容疑者が交際相手だと話す齋藤初美さん(55)は、その後、死亡が確認された。大津容疑者は犯行後、車で逃走した。そして、およそ30分後、5kmほど現場から離れた群馬・館林市内の路上で、警察官に身柄を確保された。近所の人は「(警察車両で)追いかけ回している音が、ずっと聞こえていた。パトカーが1台、ワゴン車が1台、(挟まれて)車が1台止まっていて、車の中に(人)は乗っていなかった」と話した。55歳の齋藤さんと、26歳の大津容疑者。29歳年が離れた2人は、どのような関係だったのか。齋藤さんは、埼玉県内の障害者支援のNPO(民間非営利団体)の理事長を務めていた。そして、大津容疑者は、その関連施設を利用していたという。齋藤さんを知る人は「積極的な人でしてね、自分で何でもどんどん、どんどんやっていくと、そういう人ですね。昨年あたりから、やはりグループホームを1つ増やしたということで、いろんな面で多忙なところがあったなぁっていう気がしますけどね」と話した。齋藤さんが理事長を務める、障害者施設で知り合ったとみられる2人。大津容疑者を知る人は「(大津容疑者は)素直ないい子だったよ。『福祉の仕事に就いたらしい』という話を聞いた」と話した。大津容疑者が利用していた施設の関係者は「ここ数日間、大津容疑者は施設に来ていなかった」と話す。また大津容疑者は、29歳年上の齋藤さんとは「交際関係にあった」と供述しているという。齋藤さんを知る人は「(施設では)いろんなトラブルはありますね。男女の関係は、おそらくわたしは、それはちょっと考えられない。(施設)利用者の自宅に行くのは、それほどないと思いますけどね。(自宅に)行ったということは、何か問題があって行ったのでは...」と話した。2人の間に、どのようなトラブルがあったのか。大津容疑者は、直接の動機として、「齋藤さんに携帯電話を投げ捨てられ、カッとなって刺した」と供述しているという。警察は今後、容疑を殺人に切り替え、くわしい動機などについて大津容疑者を追及する方針。【FNNニュース】 施設の理事長とその関連施設の利用者という関係、それにしても、「交際をしていた」と本人が言い張るその要因がまた、今回の大惨事を引き落とす引き金なっているとしたら、年齢差を超えた感情のもつれがあったのかもしれないですね。 親子ほどの年齢差でも、一旦真剣になると、理性を失うこともある、今後の調べを見守りたいと思います。☆彡 佐藤みゆき色えんぴつ画展 日時:2013年8月6日(火)~11日(日) 場所:ギャラリー アートラボ・ノクト東京都墨田区菊川3-9-1都営新宿線菊川駅下車 A4出口を出て右に曲がり、徒歩1分 にほんブログ村 にほんブログ村
2013.08.07
閲覧総数 265
-
9

一人っ子介護の悲哀 乗り切る5つの知恵。
一人っ子介護の悲哀 乗り切る5つの知恵 老いた親の行く末は誰もが気になる。 一人で抱え込まずに、周囲の人に頼るのと同時に、介護は「早めの情報収集が大切」だ。 そのための5つの対処法を『一人でもだいじょうぶ 親の介護から看取りまで』(日本評論社)の著書もある医療福祉ジャーナリスト・おちとよこさんに教えてもらった。【介護を乗り切る5つの知恵】(1)親の家がある市区町村で担当の地域包括支援センターに行っておく(2)早めの要介護認定の申請を心がける(3)倒れた時の「もしものときの覚書」を親に書いてもらっておく(4)もし、介護状態になっても、一人で抱え込まない。仕事は絶対に辞めない(5)公的サービスをとことん利用する。近所やかかりつけ医にも積極的に助けを請う なかでも、いちばん大切なのは、親の住んでいる市区町村で、担当の「地域包括支援センター」を調べ、できれば親と一緒に行くことだ。 地域包括支援センターは、2006年施行の介護保険法改正により、地域の高齢者の総合相談、介護支援体制づくり、高齢者の保健医療の向上などを目的として設置された。 12年4月現在、全国で約4300カ所ある。 介護の疑問や不安を相談できるうえ、介護保険の申請も可能だ。 要介護ではない高齢者のために、介護予防のためのプログラムも用意されている。 次に、「要介護認定」の申請は早めに準備することも重要。介護保険のサービスは、親が倒れたからといって、電話一本で、すぐ使えるわけではない。 各市区町村の介護窓口や地域包括支援センターなどで「要介護認定」の申請をし、認定結果が「要支援」か「要介護」で、初めて利用できる。通常、申請から結果通知まで1カ月くらいかかる。 親が倒れたとき、一人っ子は人手がない。申請の手間は意外と大きい。スムーズに介護保険サービスが利用できるよう、申請は気持ち早めにしておきたい。 万一に備え、「もしものときの覚書」を親に書いてもらうことも欠かせない。いざ、親が倒れた場合、生活費用の口座や入っている保険、飲んでいる薬のことなど、意外と知らずに困ることが多い。 特に介護している側、生活を預かっている側の親が倒れた場合は混乱する。そうしたときにもあわてないよう、生活の細々したことも聞いておくといい。「好きな食べ物も聞いておくといいでしょう。私自身、倒れた母に何を食べさせていいかわからなかったので。食欲がないときでも好きなものだと食べられるし、喜んでもらえたら子どももうれしい。好みをわかっているほうが親も子もハッピーなんです」(おちさん) これらの対処法は、一人っ子の人も、そうでない人も、重要なことかもしれない。長寿社会、親より先にきょうだいが亡くなって、一人残されることもある。きょうだいが病弱だったり、海外赴任中だったりとアテにできないこともあるからだ。誰もが心しておきたい。※週刊朝日 2014年2月14日号 [dot.asahi] 【1000円以上送料無料】一人でもだいじょうぶ 親の介護から看取りまで/おちとよこ 一人っ子でなくても、離れて暮らす場合は、これはありがたい手引きかと思います。 抱え込まないまでも、親子と言うご縁がある以上は、最低限に見守り、常に心掛けておきたいことですね。🌠
2014.02.11
閲覧総数 986
-
10

京都)発達障害児支援、就学後も すてっぷセンター。
京都)発達障害児支援、就学後も すてっぷセンター京都府京田辺市にある府立こども発達支援センター「すてっぷセンター」で10月から、学校に通う発達障害児らが専門的な社会適応訓練を受けられる放課後デイサービスが始まった。同センターには就学前の発達障害児向けの療育施設はあったが、学校に通い始めた子は利用できなかった。府は相談室も併設し、支援を充実させている。 今月12日。子どもたちが保護者らに送られ、午後3時からできたばかりの建物のデイサービスに集まってきた。小学2~6年の児童が3人ずつの2グループに分かれ、活動を始めた。 うれしい、楽しい、悔しいといった感情について書かれたプリントをもとに周りの人の気持ちを考えてみたり、ボール遊びを通して友人との関わり方を実践的に学んだり。各グループには臨床心理士や作業療法士、児童支援員、学生ボランティアらが3人ずつ付いた。午後6時前に迎えに来た保護者には、児童支援員らがこの日の活動内容を報告。城陽市から来ている3年生の児童の母親(32)は「これまで放課後には学童保育に通わせていたが、単に預かってもらっていただけだった。ここでは自分と相手とは違う感情を持っていることを丁寧に教えてくれるので子どもも少しずつ理解でき、しんどさが軽減されているようだ」。6年生の児童の母親(52)も「声かけの仕方など、人間関係で苦手なことを一から教えてくれる。他人の気持ちを考えられるようになってきた」と語る。 すてっぷセンター(0774・64・6141)は、府南部の障害児らを対象に2003年に開所。小児科や児童精神科がある診療所を持ち、発達障害と診断された子どもたちが通う施設も備える。この施設だけに通う子もいれば、地域の保育所や幼稚園に通園しながら通う子もいるが、対象は就学前に限られていた。 府北部では、府立舞鶴こども療育センター(舞鶴市)が支援の拠点となっている。 文部科学省の12年の推計では、公立小中学校の通常学級に在籍する児童生徒の6・5%に発達障害の可能性があるとされる。 府障害者支援課によると、学校に入った発達障害児が放課後に通える事業所はほとんどが民間で、増加傾向にある。現在、京都市内を含めて府内に約250あるが、支援が難しい子にはほとんど対応できていないのが現状だ。 すてっぷセンターには臨床心理士や作業療法士らがおり、専門性の高い訓練が可能だ。同課の担当者は「民間事業者の見本になるような放課後デイサービスを目指している」と言う。 府は併せて、京都市伏見区にある府発達障害者支援センター「はばたき」の相談機能を、すてっぷセンター内でも利用できる「こども相談室」を設けた。府南部の小学1年~高校3年の児童生徒やその家族が対象で、臨床心理士らが3人態勢で無料相談に応じている。 相談は電話(0774・64・6000、平日のみ)ででき、必要に応じて家庭訪問もする。診療所から紹介され、定期的に相談を受けている子もすでに5人おり、学校訪問など教育機関とも連携しているという。 こども相談室長の長谷川福美さんは「診療所などをまだ受診できていないが、子どもが発達障害かもしれないと気になっている人も、まずは電話してほしい」と呼びかけている。[朝日デジタル]就学後も継続して同じ放課後支援が受けれると、学校生活にもいい効果をもたらしてくれそうですね。☄
2019.01.20
閲覧総数 1337
-
11

息子との日々糧に 横浜の施設で事故死 障害者ガイドに母奮闘。
息子との日々糧に 横浜の施設で事故死 障害者ガイドに母奮闘 横浜市港南区の池田啓子さん(52)と会社員の夫・政弘さん(53)は2年前の春、一人息子の健人さん(当時19歳)を福祉施設での入浴中の事故で亡くした。知的障害を伴う自閉症があり、慣れないところではパニックを起こす。子育てはちょっとだけ大変だったかもしれない。でも、宝物だった。啓子さんは今、健人さんと歩んだ経験を生かし、知的障害者ガイドヘルパーとして働いている。 健人さんは3歳で自閉症と分かり、特別支援学校に進んだ。デジタルカメラで写真を撮るのが大好きで、自宅の窓から見える京急の電車によくレンズを向けていた。いつもニコニコしていたけれど、修学旅行や施設での宿泊は苦手。前夜には宿泊用の荷物を押し入れに隠していた。 それでも、親子3人でたくさん出かけた。「かわいい子には旅をさせよ」だ。飛行機の搭乗口で大声をあげたり、新幹線でじっと座っていられず、車両間の自動ドアを何度も開閉させたり。いろいろありつつも、健人さんは旅先で落ち着くと、うれしそうにして、あちこちでカメラを構えていた。16歳のときには初の海外、香港旅行も達成した。 2019年3月27日。港南区にある社会福祉法人型障害者地域活動ホーム「そよかぜの家」で、事故は起きた。1泊だけのショートステイで、職員が入浴中の健人さんから目を離した間の溺死だった。自宅に帰ってきたら、次の日には3人で、東京ディズニーシーに行こうねと約束していた。 運営法人が事故検証のために設置した第三者委員会は、入浴中にはしっかり付き添うという内規に違反していたと指摘する調査報告書をまとめた。その概要は先月、法人のホームページに、職員教育の充実や浴室の改修を含む再発防止策と合わせて掲載された。 健人さんを失って1か月がたった頃、啓子さんは「知的障害者ガイドヘルパー」の資格を取るため、県の研修を受け始めた。障害のある人の外出時に付き添い、案内をする仕事だ。「あかりの消えたような毎日を過ごしていても、あの子は戻って来ないし、喜ばない」。同じような事故を繰り返させないためにも、19年間、健人さんを育てた経験を生かしたいと思った。 その年の夏、社会福祉法人「みどりのその」(磯子区)で働き始め、知的障害がある子供の通学のサポートなどを続ける。障害のある人が働き、社会参加することを支援する事業所「ひばり茶屋」(磯子区)では、調理や接客をする利用者を見守っている。 あまり笑わない子が笑顔を見せてくれたり、「池田さんと一緒がいい」と言ってくれたり。「わたしの方が救われている」と啓子さんは話す。そんな母の姿に、空の上からきっと、健人さんがカメラを向けている。 健人さんが亡くなる事故が起きた「社会福祉法人型障害者地域活動ホーム」は、横浜市が社会福祉法人に市有地を無償貸与し、整備費や運営費なども補助することで設置・運営を支援する市独自の事業だ。「障害児・者とその家族の生活を支援する拠点」として1999年から順次開所し、現在、市内の全18区に1か所ずつある。通所やショートステイの受け入れのほか、各種相談に応じている。 旭区のホーム「サポートセンター連」の白鳥基裕センター長によると、年齢や障害の程度といった利用条件は各施設の判断に委ねられており、公立施設よりも柔軟性があるが、その分、幅広いスキルや経験が職員に求められる。センター長は「現場は常に人手不足。職員の専門性が足りないこともある」と打ち明ける。 和泉短大の鈴木敏彦教授(社会福祉学)は「民設民営でも、横浜市の事業。サービスや職員の質を維持するため、市が各施設の活動内容を評価して結果次第で改善を求めるなど、より積極的に関わっていくべきだ」と指摘する。[読売新聞 オンライン]実際に社会に出ることで、今までなかったようなご縁や絆も増えていくことでしょうね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2021.03.28
閲覧総数 282
-
12

「助けて」と言えなかった母親…赤ちゃん3人遺棄事件、 弁護人が語る"見えない生きづらさ"。
「助けて」と言えなかった母親…赤ちゃん3人遺棄事件、弁護人が語る"見えない生きづらさ"出産した赤ちゃん3人の遺体を自宅の押し入れに遺棄したなどとして死体遺棄と殺人の罪に問われた母親に、今年2月、懲役6年の判決が言い渡された。1人目は死産後の死体遺棄、2人目は困窮の末の殺人と死体遺棄、3人目は自然死後の死体遺棄という事件だった。裁判では、女性がホストに騙されて経済的に困窮していたことや、事件後にADHD(注意欠如・多動症)と診断されていたことが明らかになった。「孤立し、追い詰められた末に起きた事件だった」。法廷でそう訴えた女性の国選弁護人、田中拓弁護士に弁護活動の経緯を聞いた。(弁護士ドットコムニュース)●発達障害の特性に周囲は気づかず──今回、3人の子の遺体を遺棄した女性の弁護を担当されました。彼女には発達障害の特性がありましたが、家族にも周囲にも気づいてもらえず、兄弟と比べて幼い頃から「お金にだらしない」「片付けができない」と親から評価されず、自分だけが認められないと感じて育ってきたようでした。また、特性とそこに由来する自己肯定感の低さから、問題解決能力が極めて低く、次々と男性に騙され、唆(そそのか)されて風俗業を転々とし、引っ越しても住民票を移さず、コロナ禍においても国民一律に支給された給付金の存在も知らないなど、その場しのぎで生活しているような状況でした。交際相手を装うホストは、彼女を騙し、より過酷な環境で働かせ、彼女は交際相手を喜ばせるつもりだったところが、実際には搾取され続けていたのです。●女性視点の必要性を感じて女性弁護士に相談──どのように弁護活動に取り組まれたのでしょうか。接見時、彼女は明るくよく話し、十分コミュニケーションが取れたので、当初は発達障害を見抜けませんでした。しかし、女性の視点の必要性を感じ、女性弁護士に相談したところ、起こっている出来事の表をなぞるのではなく、生い立ちから事件まで女性としての歩みを丁寧に聞き取らねばならないと助言を受けました。妊娠・出産の大変さを経験した女性からすれば、彼女のとった行動は、あまりにもあり得ないものだったからです。そこで、改めてじっくりと話を聞き、違和感が積み重なっているところへ、協力医が現れ、精神科医師にも相談して聞き取りや検査を実施してもらった結果、ADHDと診断されました。同時に社会福祉士と連携し、更生支援計画を策定しました。これには、日弁連の「罪に問われた障がい者等の刑事弁護等の費用に関する制度」を活用し、福祉的支援の立案に必要な費用を補助してもらいました。この制度は、もともと弁護人が手弁当で足していた費用を、弁護士会の基金で援助するものです。本来は、このような費用は国選制度として支出されるべきだと思います。●責任能力に影響しない障害を軽視した裁判所──判決は懲役6年で確定しました。犯行に至った背景には「発達障害」「水商売の男性による風俗業界で働く女性に対する経済的・精神的・性的な搾取」「コロナ禍」という三つの要因が重なっています。コロナ禍が要因というのは、赤ちゃん3人の中で死産等ではなく、殺人と認定された子の事件は、コロナ禍で対人接客業が成り立たなくなった令和2年4月に発生しているからです。障害特性については裁判でも訴えましたが、裁判所は「責任能力に影響しないレベルの障害特性」をあまりに軽視し、残る二つの要因には目を向けませんでした。あくまで経緯にすぎず、動機そのものではないというのでしょう。こうした事情が量刑を判断するうえで重視されないのは妥当なのか、大きな疑問が残ります。ただ、彼女自身は、刑事手続きを通して自分の生きづらさやその原因に気づき、支援を受けての再出発を想像し、将来への希望を見出せたと感じています。彼女は必ず生き直せると信じています。●「助けて」を言えない人がいる現実──社会や周囲に求めたいことはありますか?刑事弁護をしていると、障害特性や環境の劣悪さ、虐待や搾取に遭った被害体験などの生きづらさが要因であると感じることが多いです。それが自己責任の名のもとに、悪質な事件の犯人として罰を受ける。「なぜ弱い人がさらに追い込まれるのか」と思うことがよくあります。今回の彼女のような風俗で働く人についても、「本人が好きでやっている」という認識の方もいるかもしれません。しかし、実際には発達障害や精神障害といった生きづらさを抱える人が、周囲の食い物にされているという側面があるかもしれないという目線が必要だと感じます。今回の女性は、困っていると気づきにくい、気づいてもSOSを出せない、相談できないという方でした。「助けて」と言えない人がいる。その現実を社会に知ってほしいと思います。この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。[弁護士ドットコムニュース]女性は裁判で懲役6年の実刑判決を言い渡され、その後確定した(弁護士ドットコムニュース撮影)なんとも大変な人生ですね。親や家族とすっかり疎遠となってしまったこと、果たして親の責任は?と残念に感じます。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.20
閲覧総数 55
-
13

発達障害と言われ…高畑淳子が明かしていた高畑裕太容疑者の幼少期。
NEWSポストセブン発達障害と言われ…高畑淳子が明かしていた高畑裕太容疑者の幼少期常に裕太への不安と隣り合わせ 高畑淳子「強すぎる母性愛」8月23日、宿泊先のビジネスホテルで40代女性従業員に乱暴し、俳優の高畑裕太容疑者(22才)は〇〇致傷罪で逮捕された。「性欲を抑えきれなかった」──取り調べでそう話した裕太容疑者は、「短大時代から露出狂だった」「女の子に対する執着が異常」という友人たちの証言の他、過去に出演したテレビ番組での「ぼく、性欲強くて」という発言などが“異常行動”としてクローズアップされている。加えて聞こえてくるのは、“子供を甘やかしすぎた”という母・高畑淳子(61才)の子育てを問題視する声だ。「10年くらい前に高畑さんのおうちに遊びに行ったときのことです。当時、裕太くんはもう小学校高学年くらいだったと思うけど、高畑さんは“あれはやったの?”“これはこうして”と手取り足取り状態でびっくり。すごく過保護だなと思いました」(高畑を知る芸能関係者) 芸能界に入ってからも高畑の“息子愛”は至る所で見られていた。「裕太が芸能界で生きていくと決めてから売り込みはすごかった。自分の現場に連れていってはプロデューサーや監督に挨拶回り。営業活動はマネジャーよりも熱心だったくらいです」(事務所関係者)“強すぎる母性愛”――高畑の子育てはこう評される。しかし、高畑の親子関係をひもとくと、息子を産んでから22年間、常に“不安”と隣り合わせだった背景が浮かんでくる。「裕太くんは小さな頃からアトピーで、ぜんそくもあった。それだけでなく、左耳は高音が聞き取りにくく、目は斜視気味で矯正するなど病院通いの日々。夜中に急に体調が悪くなって慌てて病院に駆け込むということは珍しくありませんでした」(高畑の知人) 桐朋学園芸術短期大学を卒業後、売れない20代を過ごした高畑が裕太容疑者を出産したのは女優としてようやく芽が出始めた時だった。「24才の時の結婚は1年半で終わりを迎え、32才で再婚、長女・こと美さん(29才)を出産。38才で裕太を授かったもののお腹にいる時に離婚しました。以降は、地元の香川から上京してきた実の両親の手を借りながら女優業と母親業をこなしてきたんです」(同前) 裕太容疑者が小さな頃、高畑は家を空けられないと地方ロケからはとんぼ帰り、化粧や服装にも構うことのない日々を送った。 前出の通り、裕太容疑者は“手のかかる子供”だった。病院通いは日常茶飯事。言葉を覚えるのも遅く、4才でやっと話した言葉は「ワンワン」。1秒でもじっとしていることができず、小学生になっても通学時にゴミ出しを頼めばゴミだけ持ってランドセルを忘れたり、ゴミを出すのを忘れて持ったまま学校へ行くこともあった。教室の机の周りはゴミや体操服など物が溢れているのが常だったという。“やんちゃな男の子”といえばその通りだが、高畑はそんな息子から目を離すことができなかった。《とにかく四六時中息子にかかわっていたから、ことちゃん(長女)の小学校時代を何も知らないのよ》 過去のインタビューではそう子育てを振り返りながら、こんなことを明かしている。 《明らかに発達障害だと言われたこともあった》“うちの息子は普通の子とは少し違うのかもしれない”“目を離したらとんでもないことをするかも”──会見でも、「ここまでとは思わなかったですが、そういう危惧というのは常にあったような気がします」と話していたように、高畑は息子に絶えず胸騒ぎを覚えていた。 発達障害と言われたことも、高畑の脳裏から消えたことはなかったという。発達障害は脳機能の発達が関係する先天性の障害で、アスペルガー症候群、注意欠陥・多動性障害などに分類される。診断される子供の数は年々増加し、文部科学省が約5万人の公立小中学校の生徒を対象に行った調査(2012年)では6.5%に発達障害の可能性があるという結果が出た。「発達障害」という言葉が広く認知されていく一方で、“周囲との少しの違い=発達障害ではないか”という不安を抱く母親も増えているという。子育て問題に詳しいジャーナリストの石川結貴さんが言う。「かつては、できない部分ではなくできる部分を評価するようにしていました。今は“普通でなければおかしい”という社会の圧力が強すぎて、子育てママたちからそうした余裕を奪っています。少しでも落ち着きがないと、“あの子変じゃない?”という空気になってしまう。当の本人とお母さんはそこまで気にしていなかったのに、周りの空気を感じて深刻になり、子供を縛り付けてしまうんです」 そうした思いが、“過保護”や“行きすぎた愛情”につながってしまうこともある。「わが子を心配するあまりの行為ですが、それが子供の判断能力を奪ったり、成長を止めてしまうなどの悪影響を及ぼしてしまうことにもなりかねません。発達障害についての正しい知識を得るよりも前に言葉がひとり歩きしてしまっています。素人の勝手な思い込みで“あの子は発達障害かも”と安易に口に出してしまう社会、それを受けて“うちの子はもしかしたら…”と過剰に反応してしまう母親、こうした構造を問題視すべきです」(石川さん) 母と同じ芸能界に進んだ裕太容疑者は“天然キャラ”が人気となり、仕事が増えていく。「空気が読めない、他の人が話していても構わず自分の話をする、共演する女優やタレントとの距離が近すぎる…天然の枠には収まらないほどの型破りキャラがバラエティーで受けていました」(裕太容疑者を知るテレビ局関係者) しかし、そんな息子の評価も、母から見れば不安材料でしかなかったのかもしれない。※女性セブン2016年9月15日号【livedoor news http://news.livedoor.com/article/detail/11962136/】わが子との距離感、特に手の掛かる男の場合は難しいものがあります。そして成人しても尚、その不安が続くならば、一概には言えないまでも、やはりどこかの専門機関に相談する勇気も必要なんでしょうね。🌠
2016.09.02
閲覧総数 2203
-
14

「障害があれば何をやっても許されるのか」 娘を殺害された母の悲痛と、5年越しの判決。
「障害があれば何をやっても許されるのか」娘を殺害された母の悲痛と、5年越しの判決「5年間、裁判での『嘘』に苦しんだ」 「障害があれば何をやっても許されるのか」 娘を奪われた母親とその親族は、2度目となる松山地裁の法廷で、やり切れない思いを訴えた。地裁での審理を経て控訴審、更に上告、そして棄却。事件の発生から既に5年が経ち、長引く裁判に翻ろうされていた。判決で認定された事実を元に、事件と裁判を振り返る。◇◇事件発生は5年前 今から5年前、2018年2月に事件は起きた。13日、愛媛県今治市の会社敷地内から、運送会社に勤めていた、当時30歳の女性の遺体が見つかった。乱暴された痕跡が残る体には、首を手で絞められた跡、さらに被害者が着用していたタイツが首に巻き付けられていた。翌日、同僚の男が殺人容疑で逮捕された。西原崇被告、当時34歳。犯行当日の夜、西原被告と被害者の女性は2人きりで仕事をしていた。被害者とは10日前に知り合ったばかりだったが、西原被告は一方的に好意を寄せていた。 職場での様子を知る関係者は、西原被告が被害者の女性と2人きりで仕事することに「異様に興奮していた」と振り返る。 ◇◇「犯行当時の精神年齢は9歳」無罪主張同年3月7日、松山地検は殺人と強制わいせつ致死の罪で西原被告を起訴。10月16日に松山地裁で始まった裁判員裁判の初公判で、西原被告は起訴内容を否認した。弁護側は、殺意を否定した上で、「西原被告には軽度の知的障害があり、犯行当時の精神年齢は9歳程度だった」「ストレスなどで行動をコントロールできず、犯行当時の記憶も失っていた」「精神障害の影響で心身喪失状態だった」として、無罪を主張。 仕事上での作業の進め方をめぐり女性に怒りを覚えた末の、無自覚な犯行だったと述べた。 ◇◇ドラレコのSDカード抜き取り「責任能力ある」 一方の検察側は、犯行現場に止められていたトラックのドライブレコーダーからSDカードを抜き取るなど、西原被告が証拠隠滅を図っていたことなどを挙げ、知的障害の程度は軽く、刑事責任能力はあると述べ、無期懲役を求刑した。 ◇◇「強制わいせつ致死」退け懲役19年 11月13日に行われた判決公判で、松山地裁の末弘陽一裁判長(当時)は、突発的な殺意による犯行とした上で、「殺人罪」と「強制わいせつ罪」を認定。しかし「強制わいせつ致死」の成立については「合理的な疑いが残る」として退け、西原被告に懲役19年の判決を言い渡した。11月27日までに、弁護側と検察側の双方が控訴。審理の場は高裁へと移った。 ◇◇高裁が「裁判のやり直し」命じる 2019年12月24日、高松高裁は、「明らかな事実誤認がある」として一審判決を破棄、審理の「やり直し」を松山地裁に命じた。 差し戻しの理由の中で、高松高裁の杉山慎治裁判長は「殺人罪と強制わいせつ致死罪の成立を前提にするのが相当」と述べた。差し戻しを命じる高裁判断を受け、西原被告の弁護側は最高裁に上告したが、棄却された。 ◇◇4年越し、2度目の地裁での審理 2022年12月5日、再び松山地裁で始まった「やり直し」の裁判員裁判。最初の裁判から既に4年が経過していた。争点を「わいせつ行為の有無」「最初に首を絞めた時点での性的目的の有無」に絞り込んで開かれた差し戻し審の初公判で、弁護側は「わいせつの意図はなかった」として起訴内容を一部否認した。 2023年3月3日。 新型コロナの感染拡大などを受け、審理はさらにずれ込んでいた。この日の裁判では、朝から証人尋問が行われ、被害者参加制度により参加した被害者の母親や親族も被告人に対して意見陳述を行った。 松山地裁41号法廷には、証言者のプライバシーを保護する目的で、目隠しのパーティションやアコーディオンカーテンがすき間なく並べられていて、傍聴席の最前列に座った記者の目の前に、大きな壁のように立ちはだかる。そのすき間をぬうようにして、慌ただしく裁判所職員が動き回る。ほどなくして、静まりを取り戻した法廷内に、すすり泣いているのだろうか、パーティションに取り囲まれた証言台に立つ女性の存在に気付く。西原被告の母親だ。 ◇◇西原被告の母親が語った言葉 母親は、事件当時に西原被告が両親と3人で暮らしていたこと、元来、人と話すことが苦手でコミュニケーションがうまくいかないことが多かったこと、仲の良い友人はいなかったことなど、西原被告の人間関係を問う弁護士に答えた。 性格について聞かれると、注意をした際に急に興奮することがあり、特に女性のかん高い声や怒った声に反応することが多く、自身も尻を「けつられた(=けられた)」ことがあったと証言。10年ほど前には、西原被告から受けた暴力が原因で病院を受診したことがあったと振り返る。 被害者への弁償について問われる。少し落ち着きを取り戻していた西原被告の母親のおえつが、再び高まる。用意した弁償金は300万円という。「はした金かもしれないが、遺族に対して精一杯かき集めた」と声を絞り出す。その上で「被害者の家族に申し訳ない、したことを一生償って欲しい」と西原被告への思いを述べた。続いて検察官から、なぜこれまでの裁判の傍聴をしなかったのか問われると「申し訳なくて、見ていられなかった」と回答。夫は過去に傍聴をしていたものの、辛さに耐えられなくなり、裁判の途中で退席したことなどを挙げた。 西原被告は、3人の刑務官に取り囲まれて座っている。上下が黒いジャージー姿で、短めに整えられた髪。両手をひざに置き、うつむき気味の姿勢で、自身の母親の証言を聞いていた。◇◇「中学のころから友人はいない」 自閉症傾向など、軽度の障害がある西原被告。14歳になると、障害者の自立支援などを行う福祉施設に入所した。共働きの両親は、1日中面倒を見ることができなかったと、その理由を説明する。差し戻し前の審理内容を把握するため、過去の裁判で行われた被告人質問の録音が再生される。スピーカーから、証言する西原被告の声が流れ出す。 「小学生のころの記憶はない」「中学生のころ、学校に友人はおらず、弟とは週に2、3回遊んでいた」人と話すことが得意ではなく、また人に話したいと思うこともなかったと証言する西原被告。中学時代には、テレビゲームやサイクリングに興味を示したと話す。一方で、この頃、線路への置石などの問題行為もあったという。 その後の、5年間にわたる障害者福祉施設での生活の中でも、話すことのできる友人はできなかったと振り返る。この施設からは、脱走して退所した。社会人になってからは、職を転々としてきたと話す。「怒るとセーブが効かなくなる性格」が災いして、人間関係のトラブルが絶えなかった。友人ができることはなく、女性との交際経験もない。審理は進み、事件に直接関連する質問が始まった。西原被告は、被害者の女性の首を絞めたきっかけについて問われると、「覚えていない、大変申し訳ないことをしたと思っている」と答えた。◇◇「なぜ人を殺してはいけないと思う?」 「なぜ人を殺してはいけないと思う?」裁判官の問い掛けに、長い沈黙を経て「法律で決まっているから」と西原被告。「では、人が亡くなったらどうなると思う?」再び沈黙ののち「分かりやすくお願いします」と回答。 やり取りは続く。「(被害者が)将来しようと思っていたことはどうなる?周りの人はどう思う?」「出来なくなる、悲しい気持ちになると思う」 西原被告が持つ「自覚」や「罪の意識」を推し量るかのような質問が重ねられていく。 「家族が用意した弁償金の300万円についてどう思う?」 「申し訳ないと思う」 「見捨てずに出所を待つと話す母親をどう思う?」 「(沈黙)」 「被害者の母親が『もう娘と旅行できない』『写真を撮ることができない』と証言したことについてどう思う?」「大変悪いことをしてしまった」 「被害者の母親が、被害者の写真を見ていると、楽しい思い出の写真なのに涙が出てくるというのはなぜだと思う?」「(沈黙)」 「反省するというのはどういう意味だろう?」「――難しい」 ◇◇やり場のない悲痛な思い 午後、被害者参加制度により参加している被害者の母親が意見を述べた。「(差し戻し前の裁判の)一審判決、懲役19年に絶望した。たったの19年なのかと、地獄に突き落とされた気分になった。強い怒りと不信感がつのった」娘を奪われた悲しみに打ちひしがれた母親の悲痛な声が法廷に響く。西原被告に対する、そして裁判所の判断に対する、やり場のない思いがあふれ出した。「娘の幸せが私の幸せだった。一緒に旅行に行き、一緒に写真を撮りたかった」 被害者の母親の意見陳述は、事件当日の詳細な状況に迫る。「当日の朝、娘に『お仕事頑張ってね』とLINEをしたところ、仕事が嫌だという気持ちを表現するかのような、不機嫌そうな表情のウサギのスタンプが返ってきた」「今となって思うと、仕事に嫌なことがあるという意思表示だったのだろう」「西原被告には、これまでに何度も女性の首を絞めるなどトラブルがあった」「免許停止の時期が間近に迫っていたトラック運転手の西原被告は、娘と2人きりになれるチャンスをうかがっていた」深い悲しみの中にあってなお、淀みのない声で意見を読み上げていく。「娘は酷い殺され方をした。今治署に安置されていた、最後の姿が目に焼き付いている」 意見は、裁判に臨む西原被告の態度にも向けられる。「控訴審に一度も出廷しなかったのはなぜか。理由が分からない、本当に無責任だ」「今年1月になって、初めて反省文を受け取った」「事件からの5年間、裁判での『嘘』に苦しんだ。奈落の底にいると感じた」 ◇◇一転「戻った記憶」 被害者の母親が非難した、裁判での「嘘」。それは、差し戻し裁判で変遷した、犯行の動機に関する西原被告の供述への指摘だった。5年前に行われた最初の裁判で「犯行当時の記憶が無い」と証言していた西原被告は、差し戻し裁判で一転「記憶が戻った」とした上で「被害女性との仕事上のトラブルに腹を立てたことが犯行に及んだ理由」と述べ、性的な目的については否定していた。 「娘との間に生まれた仕事上のイライラが原因だったと証言している。トラブルがあったとすることで、わいせつ目的だったことを隠している」「西原被告を殺して刑務所に入っても構わない。包丁で刺して殺してやる。娘を返せ」「命の償いは命で、死刑にして欲しい」 やり切れない思いが込められた被害者の母親の意見陳述を、西原被告は、身じろぎすることなく、視線を足元に落として聞き入っていた。 「明るく、自慢の妻だった」続いて、被害者の女性の夫が意見を述べた。 「西原被告はこれまでに、複数の女性に対して脅迫文を送ったり、首を絞めるなどの暴行を行っていた。段々とエスカレートして、今回の犯行に繋がった」「正しい量刑を望んでいるが、事件に向き合うことが辛い」夫もまた、控訴審に出席しなかった西原被告の態度に触れた。 「絶対に更生しないと思った」「突然に記憶がよみがえったなどと話した。殺意がわく。今すぐにでも殺してやりたい」静かな口調で、しかし収めようのない怒りの感情を表した。 「西原被告が示した障害年金で被害弁償について、ふざけるなと思った。人の命を何だと思っているのか。罪を認めて欲しい」「たった懲役19年というのは受け入れられない。わいせつ目的が無かったというは信じられない」 その上で、夫もまた、被害者の母親と同様に極刑を望む意見を述べた。 「死刑以外にはあり得ないと思う」 続いて、被害者のきょうだいも意見を述べた。「軽度の知的障害を理由にしている」「障害があるから、その特徴を逆手にとって悪用している。障害があっても社会生活をしている人は大勢いる。障害があれば何をやっても許されるのか」収めようのない心痛が、痛烈な非難の言葉となって法廷内に響いた。◇◇殺人と強制わいせつ致死「成立する」 続いて行われる、検察官による論告求刑。この裁判では、西原被告が被害者に対して、首をタイツで強く締め付ける暴行行為を行ったか▽わいせつな行為を行ったか▽強制わいせつの故意があったか――の3点が争点となると説明。検察官は、被害者の遺体を調べた医師の証言を元に「被害者が死んだと思い、運搬する目的で首にタイツを巻いて引っ張った」とする西原被告の証言は「全く信用できない」と一蹴。さらに、検出されたDNA型などから、わいせつな行為があったと主張。「心臓マッサージをした際に、指をなめた」とする西原被告の証言も否定した。また、「被害者とのやり取りからイライラを募らせて暴行に及んだ」とする動機についても「好意を抱いていた被害者に対して、死亡させる危険性のある暴行に及ぶというのは飛躍であり不自然で信用できない」と指摘。「当初からわいせつ目的があり、被害者の抵抗を排除するために、両手で首を絞め付ける暴行を加えた」と主張した。 タイツで首を絞め付けたのは、面識のある被害者へのわいせつな行為を隠すための「口封じ」だったとして、被告には殺人と強制わいせつ致死が成立すると締めくくった。その上で、西原被告に無期懲役を求刑した。 ◇◇「懲役15~16年程度の判決が相応」 一方の弁護側。最終弁論で、犯行について「仕事上の不満が募ったことによる突発的なもので、計画性が無かった」と改めて主張。暴行の内容が酷く、被害者が死亡してもおかしくない内容だったとして、殺人についての争いは無いとした上で、「わいせつの意図は無かった」と述べ、強制わいせつ致死の成立については否定した。その上で、記憶を取り戻したと証言する西原被告が「思い出したことを反省している」ことや「軽度の知的障害を抱え、自閉症傾向があり、感情の制御が難しい」といった事情、さらには西原被告が障害基礎年金から弁償金を支払おうとしていることなど、酌むべき事情を挙げ「懲役15~16年程度の判決が相応」と述べた。 ◇◇「楽しい日々をできなくした」 結審を前に、迎えた最終陳述。西原被告は、言いたいことをまとめたという紙を手に証言台に立ち、その内容を読み上げた。 「ひどい暴行をしてしまった、大変申し訳ないことをした」「楽しい日々をできなくした、大変申し訳ない」「弁償や服役など、罪を償いたい」「しかし返って来ることはない、申し訳ない」「逆の立場なら絶対に許せない」「真剣に向き合って罪を償う」「短気な性格と向き合って直していきたい」 ◇◇事件から5年目の判決 3月10日に開かれた判決公判。松山地裁の高杉昌希裁判長は、起訴内容を全面的に認め、被告に求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。 最初の裁判で懲役19年の判決が言い渡されてから、およそ4年半が経過していた。 判決の中で高杉裁判長は、一連の犯行について「強い殺意に基づいた、被害者の尊厳を踏みにじる極めて悪質で残忍な行為」「ドライブレコーダーの消去など罪証隠滅行為は卑劣」と非難した。 判決の理由が読み上げられる。 「被害者は30歳という若さで突如生涯を閉じることを余儀なくされた」「新居を構え、ゆくゆくは子どもを授かり夫とともに温かい家庭を築くことを思い描いていたのに、被告の手によってその未来を奪われた」「わいせつな行為により尊厳は大きく踏みにじられた」 被害者参加制度で意見を述べた、被害者の母親と夫の心情にも及んだ。 「女手ひとつで大切に育ててきた愛娘を失い、大きな喪失感と、被告に対する深い憎しみ、怒りから心身に不調をきたした」「心の支えとなっていた最愛の妻を失ったことが受け入れられず、思い出の場所に行って被害者の面影を探し、抱えきれない悲しみや怒りで苦しんでいる」 そして西原被告の「障害」について触れる。 「被告には自閉傾向を含む軽度知的障害があり、一般的に衝動を抑制しにくい側面があった」と認定した上で、運転手として働くなど通常の社会生活を送っていたことや、犯行時には証拠隠滅行為を取っていたことなどを挙げ「障害が犯行に与えた影響は限定的で、被告のために大きく考慮することができない」と指摘。 その上で、「被害者に落ち度があるような弁解を繰り返し、自らの犯した罪に真摯に向き合うことができているとは言い難い」「謝罪の言葉は表面的」「事件から5年近くが経過してようやく書き上げた謝罪文に弁解を記載するなど、遺族らの感情を逆なでした」と言及。 反省は不十分と言わざるを得ないと結論付けた。 そして39歳になった西原被告に対して、判決が言い渡された。前回の一審判決より重い、求刑通りとなる無期懲役だった。 ◇◇2度目の判決「今後について話し合って決める」 松山地裁の法廷で、2度目となる判決。裁判の後、西原被告の弁護士は「今後について本人と話し合って決める」とコメント。主張がすべて認められた形となった検察は「適正に判断頂けた」と述べた。 この裁判の控訴期限は3月24日。午後4時の時点で、控訴の動きはない。 ◇◇そして控訴 3月27日、弁護士などによると、西原被告は無期懲役の判決を不服として、本人の意思で、24日付けで控訴した。あいテレビ[YAHOOニュース]なんとも悲しい事件でしたね。あくまでも自分の罪と向き合えられないことが逆に障がいなんでしょうね。☄(かなりの長文、事件の経緯や今後の成り行きも気になるので敢えて全文転載しています)550万アクセス達成しております。いつもご訪問にコメント感謝です。❤にほんブログ村にほんブログ村
2023.03.30
閲覧総数 1749
-
15

涙の母親「発達障害の息子をおもちゃに」 暴行、土下座を動画撮影、被害生徒にトラウマ。
涙の母親「発達障害の息子をおもちゃに」 暴行、土下座を動画撮影、被害生徒にトラウマ大阪市の淀川河川敷で知人少年2人から暴行を受けるなどした高校1年の男子生徒(15)と母親が産経新聞の取材に応じた。発達障害で意思表示がうまくできない男子生徒に対し、少年らは「スパーリング」と称して暴行を繰り返したという。母親は「息子をおもちゃにしている。本当に許せない」と憤る。「遊ぼうや」。6月中旬の午後8時ごろ、電話で呼び出された男子生徒が河川敷に着くと、いきなり「けんかしようや」とからまれ、暴行が始まった。「やめてほしい」と伝えたが暴行は止まらず、土下座させられた上、川に入るよう命令された。「ぬれていたらばれるから」と下着姿になることも指示されたという。母親が一連の事態を知ったのは約1週間後。少年の一人が暴行の様子を撮影した動画を知人らに見せたことがきっかけだった。息子に時間をかけてゆっくりと詳細を尋ねると、重い口を開いた。繰り返し電話をかけられて呼び出されたこと、反撃を恐れ抵抗せずに暴行が終わるまで我慢していたこと…。涙ながらに「怖かった」と全てを打ち明けてくれた。被害を母親に伝えなかったのは、「シングルマザーのママに心配をかけたくなかったから」。その言葉に母親は「なぜ自分がもっと早く異変に気付いてあげられなかったのか」と涙を流した。事件後、男子生徒は少年らとの関係を断っているが、あの夜の出来事は「忘れたくても忘れられない」。深夜にふとフラッシュバックすることもあり、事件を思い出すと頭が痛くなるという。母親は「発達障害のある息子が遊び道具のようにされたことは許せない。『障害があるから守ろう』とする、そんな社会になってほしい」と訴えた。【産経新聞】男子生徒が少年らから暴行を受けた淀川の河川敷=1日午後、大阪市淀川区苛めはどの社会でもありますね。いかに日々の中で、子どもと向き合い、学校と連携を取っていくかでしょうね。この後の対応については、更に慎重に、高校生らしくのびのびと学生生活を送らせてあげたいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.19
閲覧総数 60
-
16

知的障害者のサッカークラブ、京で結成 12月に初公式戦。
知的障害者のサッカークラブ、京で結成 12月に初公式戦 知的障害がある人のサッカークラブチームが京都で結成され、12月に初の公式戦に挑む。 イレブンの力量に差があり、ルールが身に付かない選手もいるが、練習を重ねて着実に実力を付けてきた。 「チーム力は上がっており勝利を目指す」と意気込んでいる。 「FC.アスカ」。日本知的障がい者サッカー連盟に所属し、京都市や向日市などの14~37歳の14人が在籍する。 半数はほぼ初心者だが、社会人チームで活躍する選手もいる。 同連盟によると、京都で知的障害者がサッカーをする機会は、知的障害者のスポーツ祭典「スペシャルオリンピックス」のサッカープログラムや、特別支援学校の関係者が愛好者を集める場合などに限られていた、という。 近畿では京都以外にはクラブチームがあり、サッカーを楽しみ交流する場として、連盟の京都評議委員で、指導経験が豊かな篠サキ昇さん(61)=右京区=らが今年5月に結成した。 メンバーは毎月2回の練習を重ね、最近では実戦を意識したミニゲームも行うなど練習の質を高めてきた。ゲーム中にどちらのゴールを目指すか分からなくなったり、オフサイドを理解できない選手もいるが、声を掛けてカバーし合っている。 兵庫県三木市で12月1日にある全日本知的障害者サッカー選手権西日本大会が練習試合も含め初の試合だ。 24日には西京区の西総合支援学校で大会前の最後の練習をした。サッカー経験6年のパート古井宣光さん(23)=草津市=は「チームができてサッカーがもっと好きになった」と話す。 監督を務める篠サキさんは「まずは選手が大会で試合の雰囲気をつかんでくれたら。メンバーを増やして、いつかは実力に応じた2チーム体制を目指したい」と話す。 活動の問い合わせは篠サキさんの携帯電話090(6671)6977。篠サキさんの字が機種依存文字なので書き換えています。 [京都新聞] 一つの繋がりが力をつけて場を踏んでいく。 初公式戦までにこじつけたこと、何よりの朗報ですね。 体調を崩さないように挑んで欲しいです。🌠 にほんブログ村 にほんブログ村
2013.12.03
閲覧総数 679
-
17

野田洋二郎、NHK『自閉症の君との日々』ナレーションを担当。
野田洋次郎、NHK『自閉症の君との日々』ナレーションを担当RADWIMPS・野田洋次郎が2017年3月24日(金)24:10よりNHKで放送される『自閉症の君との日々』のナレーションを務める。同番組は、自閉症の作家・東田直樹を取材した2014年放送の『君が僕の息子について教えてくれたこと』と2016年のNHKスペシャル、2つの番組をまとめた総集編となる。また、東田直樹の言葉の世界は、前回のNHKスペシャルと同様に、三浦春馬が朗読で表現する。番組情報は以下のとおり。●番組情報NHK『自閉症の君との日々』2017年3月24日(金)24:10 (90分)【出演】東田直樹,【朗読】三浦春馬,【語り】野田洋次郎http://www.nhk.or.jp/docudocu/program/3229/2899048/ 【RO69 http://ro69.jp/news/detail/158021?rtw】2つの番組をまとめた総集編、以前に見逃した方も楽しみですね。🌠
2017.03.05
閲覧総数 316
-
18

立ち歩き・暴言…どう接する? 発達障害の子の対応助言。
立ち歩き・暴言…どう接する? 発達障害の子の対応助言 小学校や保育園でボランティアをする大学生たちに役立ててもらおうと、愛知県立大学の山本理絵教授(55)らが手引をつくった。発達障害の子どもとの接し方について、実例を盛り込みながら助言を送っている。 「授業中にA君は床の上で寝転んだり、席を立って本を探しに行ったり、暴言を吐いてけんかをしたりという状況でした」 手引で紹介されたボランティア学生の体験談だ。小学3年のA君は高機能自閉症の男の子。注意しても「うるっせぇ!」と暴言を吐かれてしまう。障害の特性を学び、「今は席に着く時間だったよね」と具体的に指示したり、「ずっと席に着くことができてえらかったね」と肯定的な言葉をかけたりすると、話を聞くようになった。「スクールボランティア/インターンシップのてびき」では、こうした学生たちの体験談を紹介。「板書を写そうとしない子どもをどう援助すれば」「けんかが起きたら」といった事例ごとにQ&A方式で助言している。 「学生が困る場面は似ている。想定してから行けば、安心して参加できる」。こう考えた山本教授が、2012~15年度にボランティアに参加した学生約130人のリポートをもとに完成させた。 特に発達障害の子どもへの対応を充実させた。文部科学省の12年の調査では全国の公立小中学校の通常学級に、発達障害の可能性のある子が6・5%在籍する。35人学級では2人程度いる計算になる。 同大4年の丸地彩香さん(23)も、教室を飛び出したり、物を投げたりする子に出会ったという。「困った時は先生に相談したり、専門書を読んだりしたけど、起こりうることを知っている方が良い」と活用を呼びかける。山本教授も「先生にも参考にしていただける内容」と話す。 手引は、愛知県内の全小中学校や特別支援学校などに配った。ホームページ(http://www.lit.aichi-pu.ac.jp/syogai/)でも公開している。【朝日デジタル http://www.asahi.com/articles/ASJ4T4VZWJ4TOIPE018.html】 やはり叱るよりは肯定的な語りかけが効き目があるようですね。🌠184万アクセス達成しております。いつもご訪問にコメント、感謝です。
2016.05.21
閲覧総数 480
-
19

暴言の訳、発達障害だったなんて…「30秒で泣ける漫画」の作者が描く。
暴言の訳、発達障害だったなんて…「30秒で泣ける漫画」の作者が描く漫画「夫の発達障害」の一場面=作・吉谷光平さん 夫に発達障害の疑いがあるとわかったことで、暴力や暴言の原因に納得がいった――。ツイッターに投稿した漫画「男ってやつは」が「30秒で泣ける」と話題になった漫画家・吉谷光平さんが、新聞投稿を元に描きました。漫画「夫の発達障害」=作・吉谷光平さん 夫に発達障害の疑いがあるとわかったことで、暴力や暴言の原因に納得が行き、救われた――。そんな妻が「自分を大切に生きたい」と決意を記した朝日新聞への投書に、切実な声が寄せられています。夫の暴言・無関心…発達障害では? 苦しんできた妻たち:朝日新聞デジタル 漫画「夫の発達障害」の一場面=作・吉谷光平さん 広島県の60代女性は「結婚して35年、夫の偏屈で身勝手な言動に苦しんできました」とメールを寄せました。 息子2人との七五三の記念写真に夫はいません。予約した写真館に行く間際、「わしはいいわ」と出かけてしまったそうです。祖父が残したお金を息子たちの学費に使おうとしたら、夫は平然と「もうない」。パチンコにつぎ込んでいました。義母に相談すると、女性が家庭をおろそかにしたせいだと、逆に責められたといいます。 女性は精神的に不安定になり、皿を床に投げつけるなどしました。昨秋、本屋で発達障害に関する本に出会い、「夫はまさにこれ」と確信。「特性を持っている夫やあなたは悪くない」との記述に救われたそうです。 漫画「夫の発達障害」の一場面=作・吉谷光平さん 発達障害のうち、言葉や知的能力に遅れのないアスペルガー症候群などには、相手の気持ちを想像したり、場の雰囲気を読んだりするのが苦手な特性があります。 世間的には問題なくみえる夫への不満を訴えても周囲に伝わりにくく、妻はさらに追いつめられる。医学用語ではありませんが、予言を信じてもらえなくなったギリシャ神話の登場人物になぞらえ、「カサンドラ症候群」とも呼ばれます。 カサンドラは妻に限りません。ただ、アスペルガー症候群は男性の方が多く、経済力の差や伝統的夫婦像の影響もあり、妻の方に深刻な例が目立つといいます。 漫画「夫の発達障害」の一場面=作・吉谷光平さん 夫との関係や周囲の無理解に苦しむ妻の自助会も、各地にできています。 大阪市で開かれる会を主宰する50代女性は、障害が疑われる夫との関係に約30年悩んできました。熱があり「大丈夫?」と言ってほしいのに、夫は「寝れば」。会を続けて「共感を求められるのは迷惑なのだと、夫の側に立てるようになった」といいます。 ただ、会は助言の場ではないと強調します。「言葉にすることで考えを整理し、次の一歩を見つけてほしい」。解決にならないと来なくなる人も、夫との関わり方を決めたと巣立つ人もいます。「止まり木のような形で利用してくれればいい」と話します。漫画「夫の発達障害」の一場面=作・吉谷光平さん 【よしたに・こうへい】 漫画家。サラリーマン生活や漫画家アシスタントなどを経て、月刊スピリッツの「サカナマン」でデビュー。月刊ヤングマガジンの連載「ナナメにナナミちゃん」の単行本1巻が発売中。ツイッターで公開した2ページ5コマの漫画「男ってやつは」が「30秒で泣ける」と話題に。 【withnews. http://withnews.jp/article/f0170428000qq000000000000000W03u10801qq000015077A】漫画になれば、より理解が深まりそうですね。🌠
2017.05.02
閲覧総数 1445
-
20

被告に懲役15年 発達障害考慮。
被告に懲役15年 発達障害考慮岐阜県瑞浪市で昨年5月、バーベキュー中の隣人を刺殺し、その友人に重傷を負わせたとして、殺人と傷害の罪に問われた無職、野村航史被告(27)の裁判員裁判で、岐阜地裁(菅原暁裁判長)は10日、懲役15年(求刑・懲役25年)の判決を言い渡した。「犯行の危険性は高い」と批判しつつ、量刑で発達障害の影響を考慮した。 判決によると、野村被告は昨年5月7日午後6時半ごろ、友人家族らとバーベキューをしていた会社員、大脇正人さん(当時32歳)の左下腹部を包丁で刺して殺害し、会社員男性(43)の右腕も刺して重傷を負わせた。 判決は殺意の強さを認定し、遺族の処罰感情の厳しさに触れた。一方、アスペルガー症候群による聴覚過敏があったとして「子どもの声を聞いて、小学校時代にいじめられた体験や母に包丁を向けられた体験がフラッシュバックし、ストレスが許容量を超え、声を止めようと包丁を持ち出した」と指摘した。成育過程に一定の同情ができるとも述べた。 これに対し、遺族らは弁護士を通じて「判決は到底納得できるものではない。被告自身が、なぜ事件を起こしたか真摯(しんし)に向き合ったとは思えない」とコメントした。[毎日新聞]障害を考慮に入れたとしても、幼い頃の苦い体験により、包丁を持ち出しての殺傷事件はやはり障害に関係なく罪と向き合って欲しいですね。☄
2018.10.10
閲覧総数 404
-
21

懲役3年の実刑判決 母親を殺害した44歳の男 裁判所は心神耗弱状態にあったと認める<福島県>。
懲役3年の実刑判決 母親を殺害した44歳の男 裁判所は心神耗弱状態にあったと認める<福島県> 判決によると、福島県福島市の藤田祥被告(44)は2020年5月、自宅で当時71歳の母親の首を絞めたあと、倒れた母親の胸を包丁で刺して殺害した。 福島地方裁判所の柴田雅司裁判長は「母親からの長年にわたる叱責が被告人の不安障害や発達障害の悪化を招いた」と指摘し、犯行当時は行動を制御する能力が低下した心神耗弱の状態だったと認めた。 一方で「犯行は突発的で強固な殺意に基づき危険で、強い非難に値する」として懲役3年の実刑判決を言い渡した。福島テレビ[YAHOO ニュース]44歳にもなって自立できずに親元で暮らした上に起きた、なんとも親不孝な事件ですね。服役を終えて3年後に出てきても自活できるのかも心配ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2021.03.11
閲覧総数 1693
-
22

重度障害者を受け入れ 娘のためのグループホーム。
重度障害者を受け入れ 娘のためのグループホーム脳性まひなどの重い障害のある人たちが医療的なケアを受けながら暮らせる、茨城県内では初めてのグループホームが、4月から牛久市に開設されることになりました。開設したのは、みずからの娘が重度の知的障害という、つくば市の女性です。グループホーム開設に向けた思いを取材しました。(NHKつくば支局)【看護師が常駐 医療的ケアも】牛久市に、重い障害のある人のためのグループホームが完成しました。重度心身障害者グループホーム「olu olu」(オルオル)です。障害者が住み、日中はデイサービスや特別支援学校に通うことができます。入居できる10床の個室のほか、短期入所のための部屋も1部屋用意されています。また、看護師や介護士などが常駐し、入居者は痰の吸引など医療的なケアも受けることができます。25日、開設を前に、関係者向けの内覧会が開かれ、利用を予定している障害者や家族も訪れました。脳性まひのある41歳の女性の母親は、次のように話しました。(利用予定者の母親)「施設から自宅まで車で15分くらいのところなので、もし何かあったら手を差し伸べられます。みなさんに感謝しています」【知的障害のある娘のために】グループホームを開設したのが、つくば市に住む、越戸利江子さんです。開設の動機は、知的障害のある18歳の娘の志乃葉さんでした。(グループホームを開設 越戸利江子さん)「障害区分では最も重い『6』です。体は大きいですが、発達年齢は1歳半くらいだということです」志乃葉さんは、障害の影響でみずからの体を傷つける自傷行為を繰り返してしまいます。1人でトイレに行くことも難しいため、自宅では常に家族の見守りが必要です。(グループホームを開設 越戸利江子さん)「本来であれば在宅でずっと自分の家族と一緒に生活したいという気持ちがあるんですけど、それだと本当に家族が疲弊してしまって限界になってきてしまう」【自宅近くで暮らせる施設を】茨城県内には障害者のための入所施設はありますが、志乃葉さんのような重い障害のある人を受け入れられる施設は限られるといいます。(グループホームを開設 越戸利江子さん)「病院のケースワーカーさんから『絶対に入所したほうがいいですよ』と勧められるんですけど、『どこがあるんですか?』と相談すると、だいたい、他県の山奥だったり、人里離れた場所に何年も待って、空くのを待たなきゃいけない状況」重い障害のある人たちが自宅近くで暮らし、家族も気軽に訪れることができるようなグループホームがほしい。自ら施設を設けようと決心した越戸さん。ノウハウを学ぶために一時期、社会福祉協議会で職員として働くなど準備を重ねてきました。施設は利用者にとって居心地のいい空間にしようと、好みに合わせて個室の壁紙の色を決められるようにしました。また、利用者の家族が自由に施設に宿泊できるよう布団を用意する予定です。【やっとスタートライン】娘のための施設をつくろうと思い立ってから10年余り・・・。きょう、施設の完成披露セレモニーで挨拶した越戸さんは、開設に向けた思いを語りました。(グループホームを開設 越戸利江子さん)「私の長年の夢でした。ホームを建てるため協力していただいたすべてのみなさんに感謝の気持ちを伝えたいです」(グループホームを開設 越戸利江子さん)「やっとスタートラインに立てたと思っています。本番はこれからです。まわりのみなさんに助けてもらって、支え合いながらホームで末永く生活できるように全力で取り組みたいです」越戸さんは、挨拶で多くの協力に感謝と話していましたが、社会福祉協議会の同僚たちが励ましてくれたり、地域の人たちが理解し協力してくれたりしたことが、開設への大きな後押しになったということです。娘のために施設を作りたいという越戸さんのその情熱が多くの人の心を動かして実現に至ったのだと思います。茨城NEWS WEB[NHK NEWSWEB]10年掛りの施設開所。長い年月を掛けての夢の実現、叶って良かったですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2022.03.28
閲覧総数 667
-
23

秋田の施設、クマに襲われた女性死亡 県内の死者は今年初めて。
秋田の施設、クマに襲われた女性死亡 県内の死者は今年初めて秋田県警北秋田署は20日、7月に同県北秋田市の障害者施設「グループホームつつじ」の敷地でクマに襲われ意識不明だった入所者の女性(73)が、入院先の病院で死亡したと発表した。襲われた際の顔や頭の負傷が原因だという。クマによる県内の死者は今年初めて。7月31日夜、別の入所者が玄関付近に倒れている女性を見つけ、職員が119番した。敷地内の防犯カメラには、体長約1メートルの黒い動物がごみを出している女性を襲う様子が映っていた。施設を運営する秋田県民生協会は「事故を厳粛に受け止める」として、被害防止のためセンサーライトや音が出る機器を設置するなどの対策を講じるとした。施設は同市の大館能代空港から約2.5キロの田畑が点在する地域にある。[日本経済新聞]事故以来、半月以上、治療したにも拘らず救えなかった命、残念でなりませんね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.08.08
閲覧総数 76
-
24

「ぬいぐるみを抱いて息子は家を出た」。
「ぬいぐるみを抱いて息子は家を出た」大きなぬいぐるみを抱いて道路脇を歩く姿。16歳の大治郎さんの最後の姿を捉えた映像です。このあと6日もたって、自宅から30キロも離れた一度も行ったことがない河原で、亡くなっているのが見つかりました。数分の間に自宅からいなくなった息子特別支援学校に通っていた久保田大治郎さんです。軽度の知的障害と、ADHD=注意欠陥多動性障害の傾向がありました。東京・八王子市に家族と一緒に暮らし、外出は常に家族と一緒でしたが、いつかは1人で電車に乗って旅行することが夢でした。母親の真実さんは「話していると誰もが笑顔になって、明るくなってしまうような、人をひきつける魅力的なところがある、すてきな息子でした」と振り返ります。一方で、大治郎さんは2年ほど前から、気持ちが高ぶると突然自宅を飛び出すようになりました。そのたびに真実さんは、自転車に乗って捜し、家の鍵は必ずかけるなど、できるかぎりの注意を払っていました。それなのに…去年7月19日、大治郎さんは真実さんが目を離した数分の間に自宅からいなくなり、帰らぬ人となったのです。障害児の行方不明は少なくとも年間167件死亡事案も令和5年にこども家庭庁は、全国の障害児の支援施設など「施設」の管理下において、子どもを見失った行方不明事案の発生件数について調べました。35の都道府県と700余りの市区町村から回答があり、▽令和4年度は1年間で167件起き、▽令和4年度までの3年間で3件の死亡事案があったことがわかりました。この件数は「施設」からの不明事案だけで、大治郎さんのような「自宅」から行方不明になったケースがどのくらい起きているのかは把握されていません。障害の特性で飛び出す傾向専門家によると、知的障害のほか、ADHDや自閉症などの発達障害の人の中には、特定のものにこだわり周囲が見えなくなったり、音に敏感に反応したりして、その場を飛び出してしまう特性がある人がいるといいます。また、コミュニケーション能力に不安がある人もいて、人に道を尋ねることなどが難しいため、遠出してしまった場合、そのまま帰れなくなってしまうケースも多いということです。大治郎さんの足取りを追うと…大治郎さんがいなくなったその日。帰宅後、少しふてくされた様子で玄関に寝転がっていた大治郎さん。真実さんは、台所で夕飯の準備のため、ほんの数分、大治郎さんから目を離していたその間に姿が見えなくなりました。いつもだったら見つかる近くのスーパーマーケットにも姿はなく、真実さんはいつもと違うと感じました。家族は警察にも連絡して必死に捜索。その後にわかったことですが、家を出てから1時間後、自宅近くの坂道をお気に入りのぬいぐるみを抱いて歩く姿が、通りかかった車のドライブレコーダーに写っていました。大治郎さんは、2時間近く家の周辺を歩き回っていたとみられ、その様子は近所の人が目撃したり、コンビニの防犯カメラに写ったりしていました。その後、バスに乗って駅に向かい、バスを降りる際には運賃を払えず、運転手とやり取りをしていました。駅では、駅員にトイレを借りると伝えて改札内に入り、電車で50分ほどかかる山梨県の無人駅で下車しました。無人駅の近くではガソリンスタンドを経営する男性が、ぬいぐるみを抱えてうずくまる大治郎さんを目撃していました。ガソリンスタンドの男性「ちょっと『おかしいかな』と思ったけれども、少し目を離した間にいなくなっていた。まさか、行方不明になっているとは思わなかった」そして、行方不明になったその日のうちに大治郎さんは川で溺れて、亡くなったとみられています。「どうしてここに?」一周忌のことし7月19日、家族は大治郎さんの最後の足取りをたどりました。無人駅からしばらくは、車通りの激しい国道沿いを歩き、10分ほどの場所で国道から外れて、雑草の生い茂る人けがない道を、川のほうに下りて行きました。家族は大治郎さんが見つかった場所の近くで静かに手を合わせました。父親の純司さん「一度も来たことがない場所なのに、なぜここまで来たのか、全く分かりません。障害者は時に行方不明になってしまうことがあることを多くの人に理解してもらい、『ちょっと変だな』と気になった時はすぐに声をかけてほしい。2度とこのような悲しい事故が起きないように対策が進んでほしい」“まばたきをした瞬間にいなくなる” 保護者たちが要望大治郎さんの地元、八王子市の障害児などの保護者でつくる団体が、一周忌を節目に障害のある人の見守り体制の構築を求めて、厚生労働省とこども家庭庁に要望書を提出しました。要望後、会見した保護者は、大治郎さんの件は決してひと事ではないと訴えました。くわのこの会・新島紫 会長「『まばたきをした瞬間にいなくなった』。『いっときも目を離せず、買い物もできない』などの声が保護者からは上がっています。常に緊張感を強いられる生活です。障害児は本人が助けを求めることが難しいからこそ、社会全体での見守り体制が必要です」団体が求めたのは、「SOSネットワーク」という認知症の行方不明者向けの見守りの仕組みの対象に、障害者を含めることです。SOSネットワークは市区町村が主に事務局を担い、家族などが希望した場合、名前や住所、自治体によっては顔写真などを事前に登録します。行方不明になった時に、家族が警察に届け出るとSOSネットワークに加盟する地域の公共交通機関やコンビニなどに行方不明情報が共有されます。そして、“似た人を見かけた”などの気になる情報があった際は、速やかに自治体や警察に連絡してもらうというもので、およそ8割の自治体で整備されています。また団体は、大治郎さんのように自宅からいなくなったケースも含めて、障害のある人が行方不明になる事案が全国でどの程度起きているのか、調査することも求めました。障害者支援に詳しい専門家は、保護者だけの見守りには限界があるため、障害がある人についても社会での見守りが必要だと指摘しています。早稲田大学 梅永雄二教授「保護者は、子どもが突発的に行動してしまうような時でも、『周りに迷惑かけたくない』と1人で抱え込んでしまう人が多い。しかし、保護者が24時間、子どもを監視しているわけにもいかず限界がある。一見すると、障害児かどうか分からない子どもも多く、異変を感じても、声をかけづらいことも発見を難しくしている。コミュニケーションが難しいとか、理解力に不安があるといった、認知症の人に似た課題を持っている人は多いので、同じような社会で見守っていく仕組みを早く整えていく必要がある」また、大治郎さんの事案を受けて、東京都は都立の特別支援学校の児童・生徒を対象に保護者が希望した場合、GPS端末を無償で貸し出すとして、今年度1000万円の予算を計上しました。今年度は、いくつかの学校で先行的に貸し出しを始める予定だということですが、東京都の担当者は、「飛び出す際に機器を身につけているとは限らない。機器を使った対策に加えて、地域での見守り体制の整備がやはり必要になってくる」と話していました。取材後記気になる子どもを見つけたら…警視庁に尋ねたところ、何かに困っている様子がある子どもを見かけたら声をかけ、自分や親の名前、住所が言えなかったときには、最寄りの警察署に連絡をしてほしいということです。大治郎さんが家から抱いていったのは人気キャラクターのぬいぐるみで、外出するときにはいつも持っていました。川に流されたのか見つからず、両親は同じものを買って遺影の前に置いています。2度と悲しい事故が起きないために、障害がある子どもの保護者たちの団体は、認知症の人の行方不明対策としてある既存の仕組みを活用することで、いち早い対策につながることを望んでいます。(8月1日 おはよう日本などで放送)[NHK NEWS WEB]以前にも触れた事件ですが、その後も多くの番組で取り上げられています。せめて、誰かがどこかで引き留めてくれていたら、と残念でなりませんね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.08.17
閲覧総数 54
-
25

企業、難易度増す障害者採用 定着へ働き方工夫、支援ツールも 来夏、法定雇用率引き上げ。
企業、難易度増す障害者採用 定着へ働き方工夫、支援ツールも 来夏、法定雇用率引き上げ来年7月に障害者の法定雇用率が現在の2.5%から2.7%に引き上げられることに伴い、民間企業の障害者採用は難しさを増している。健常者を含めて「売り手市場」の中、採用には個々の特性を踏まえた丁寧な選考が必要。採用後の定着も課題で、「働き方」の工夫やIT支援ツールの導入などで働きやすい環境の整備に取り組む。 キリンホールディングズは、春の新卒採用枠で障害者に、総合職と転勤がない「エリア限定職」の二つの選択肢を用意する。担当者は「学生数も限られる中、法定雇用率の引き上げで採用の難易度は年々上がっている」と指摘。音声読み上げソフトなどの支援ツールの活用に加え、障害に関する冊子を職場で配布して、障害者と健常者が共に働ける環境づくりに努める。 「1店舗1人以上の雇用」を掲げるファーストリテイリングの障害者雇用率は4.91%と高水準。国内外のユニクロやGU店舗で約1500人が働く。これまで店舗裏での作業に従事することが多かったが、作業の効率化に伴い、障害があることを客に示す「サポートカード」を身に着けて売り場でも活躍する場面が増えた。 東京都内のユニクロ店舗で働く笹岡龍斗さん(25)は、聴覚障害のためスマホのメモ機能などを駆使して接客もする。「言葉を伝えるのは難しいが、接客は好き」と笑顔で語った。 野村ホールディングスでは、傘下の特例子会社野村かがやき(東京)にグループ全体の3割程度となる120人が就職し、郵送物の仕分けや研修会場の設営などに従事している。入社後すぐに有給休暇や通院休暇の権利を付与し、毎月面談を行うなどきめ細かくサポート。就労継続が難しいとされる精神障害を持つ社員が9割を占めるが、定着率は8割に上る。 以前は一般採用枠で職を転々としてきたという勤続6年の男性社員(38)は「給与は下がったが、負担やつらさが軽減され、長く続けられている」と話す。特例子会社は年内に都内に新たな拠点を開設し、採用を拡大する方針だ。 厚生労働省の最新集計で、民間企業の実雇用率は2.4%。障害者雇用に詳しい法政大学の真保智子教授は「急速な採用活発化で雇用の質やミスマッチに懸念が残る」と指摘。「障害の状況や仕事が適しているか本人と話し合い、常に調整していくことが必要だ」と話している。 JIJI.COM[YAHOOジャパン]ユニクロで品出しを行う笹岡龍斗さん。スマホのメモ機能を使って接客も行う=8月14日、東京都江東区法定雇用率が変わるとともに、受け入れる側にも変化が問われますね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.08.28
閲覧総数 42
-
26

卒業生らに7億円賠償請求の武蔵野東学園、「吉祥寺学園」に改称へ。
卒業生らに7億円賠償請求の武蔵野東学園、「吉祥寺学園」に改称へ東京都武蔵野市の学校法人「武蔵野東学園」は8日、運営する学校の名称を2026年4月から「吉祥寺学園」に変更するとホームページ上で発表した。「名実ともに新しい学園に生まれ変わる」とし、新しい校章も公表した。武蔵野東学園は幼稚園2園と小中学校、高等専修学校を運営しており、全てに「武蔵野東」が冠されている。新たな名称はいずれも「吉祥寺学園」とし、それぞれ「第一・第二幼稚部」「初等部」「中等部」「高等専修部」とする。24年6月に新名称の商標登録を出願し、25年3月に登録されていた。 武蔵野東学園を巡っては、高等専修学校の卒業生が在籍当時、理事長に反発したことなどをきっかけに学校側が退学を通告し、後に撤回するなどして注目を浴びた。 25年4月には学園内の騒動に関する報道で入学希望者が減り、逸失利益が生じたとして週刊誌記者やこの卒業生、保護者らに7億円超の損害賠償を求める訴訟を提起していた。 学園は7月以降、「生まれ変わる」と書き込んだ新聞折り込み広告を武蔵野市内や都心部などで配布。音楽ホールや茶室、日本庭園、足湯などを新設し、設計やデザインには著名建築家の隈研吾氏が関わるとアピールしていた。27年にはインターナショナルスクールも開設する方針を示している。毎日新聞[YAHOOニュース]既に、昨年の夏から校名を変える手続きがされていたとは、知らない間にかなり話が進んでいたんですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.08.29
閲覧総数 59
-
27

韓国・障害者虐待の通報、2024年6000件超…4年連続増加、支援活動は減少。
韓国・障害者虐待の通報、2024年6000件超…4年連続増加、支援活動は減少【10月02日 KOREA WAVE】韓国で障害者虐待の通報件数が4年連続で増加し、2024年には初めて6000件を超えた。一方で、被害者への相談や支援活動は人員不足のため減少したことが分かった。 保健福祉省と中央障害者権益擁護機関が9月26日に発表した「2024年障害者虐待現況報告書」によると、2024年に全国の障害者権益擁護機関に寄せられた通報件数は6031件で、前年比9.7%(534件)増加した。2020年4208件から2021年4957件、2022年4958件、そして2024年には6031件と、この4年間増加傾向が続いている。 通報のうち虐待が疑われる事例は3033件(全体の約半数)で、前年より2.2%増加した。特に本人による通報は15.5%増、知的障害者の通報は21.1%増と、障害者自身の権利意識向上が反映された。通報者の73.7%は法的通報義務のない人で、義務者による通報の2.8倍に上った。疑い事例のうち47.8%(1449件)が「虐待」と認定された。被害者の71.1%が発達障害者で、年齢別では10代以下22.8%、20代22.6%、30代18.1%の順だった。虐待の種類は身体的虐待が33.6%で最多、次いで心理的虐待(26.5%)、経済的搾取(18.6%)が続いた。 また全体の13.0%(189件)は「再虐待」と判定され、5年前に比べて約3.9倍に増加した。18歳未満の障害児への虐待270件のうち、39.6%は親が加害者だった。 2024年、障害者権益擁護機関は虐待認定1449件に対して1万6513回の相談・支援を実施した。前年の1418件に対して1万7127回だったことと比べて減少しており、福祉省は人員不足が要因だと説明した。KOREA WAVE/AFPBB News【YAHOOニュース】2024年11月、障害者権利保障法の制定を求めて記者会見を開く光州の障害者団体深刻な問題ですね。いずれ誰でも高齢化とともに障害者になる可能性があるので、更に踏み込んで対応して欲しいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.17
閲覧総数 42
-
28

「嫌がらせしてやろうと思った」小学生2人が同級生の水筒に睡眠導入剤を混入 健康被害なし 運動会の練習中に教室に侵入し水筒持ち出し 教室の鍵紛失に気づくも校長に報告せず。
「嫌がらせしてやろうと思った」小学生2人が同級生の水筒に睡眠導入剤を混入 健康被害なし 運動会の練習中に教室に侵入し水筒持ち出し 教室の鍵紛失に気づくも校長に報告せず東京・足立区の小学校で、児童2人が同級生の水筒の飲み物に睡眠導入剤を混入していたことが分かりました。足立区教育委員会によりますと、先月26日、足立区内の小学校で、児童2人が同級生の水筒の飲み物に睡眠導入剤「メラトベル」を混入していたことが分かりました。児童2人は運動会の練習時間に教室から水筒を持ち出し、児童の1人が家から持ってきた睡眠導入剤3袋程度をトイレで混入したということです。 その様子を見た別の児童がすぐに学習支援員に報告し、水筒の中身は同級生が飲む前に処分されたため、健康被害はありませんでした。当時、教室には鍵がかけられていましたが、児童2人は鍵を持っていて、教室の中に入ることができたということです。 教員が7月に教室の鍵がなくなっていることに気づき副校長に報告していましたが、副校長は校長への報告を怠っていました。 児童2人は学校の聞き取りに対し、「(被害児童に)あまりいい感情をもってなかった。嫌がらせをしてやろうと思った」などと話しているということです。 足立区教育委員会は「児童や保護者に心配をおかけしてしまっている。1日でもはやく子どもたちの安心して通える環境を作っていく」としています。TBSテレビ【YAHOOニュース】教室に鍵を掛けてもその鍵を勝手に持ち出せてしまうとなるとあまり意味がないですね。きちんと子ども達の言動を普段から見守る態勢が必要なんでしょうね。大事に至らなくて良かったです。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.18
閲覧総数 37
-
29

佳子さまのイヤリングは「鳥取ゆかり」の工芸品 障害者の手仕事にスポットライト(鳥取)。
佳子さまのイヤリングは「鳥取ゆかり」の工芸品 障害者の手仕事にスポットライト(鳥取)1年ぶりに鳥取県を訪れた佳子さま。公務の場では、2025年も鳥取ゆかりのアクセサリーを身につけられました。 9月13日、鳥取空港に到着された佳子さま。ビビッドなピンクのワンピースにブラウンのジャケット姿で県民の歓迎に応えられました。そのコーディネートに合わせられたのが、耳元のイヤリング。こちらもつややかなピンク色です。 このイヤリングを作っているのは、境港市の水木しげるロードにある「はまゆう」。市内の福祉事業所が4年前から運営しています。事業所の利用者が作ったおにぎりや陶器と並んで店の半分ほどを占めるのは、「七宝焼(しっぽうやき)」のアクセサリー。 佳子さまがつけられたのと同じタイプのイヤリングもありました。 今回の『全国高校生手話パフォーマンス甲子園』に合わせて会場に出店していました。一般社団法人はまゆう・若原紀子代表:「びっくりが一番で、でもありがたい。おきれいな上に衣装とも合わせてすてきに飾っていただいていいなと思いました。ありがたいです」 13日、境港市の伊達市長から伝えられたそうです。イヤリングを作ったのは、重度の聴覚障害がある渡部史也さん。渡部史也さん: 「とてもうれしいです」自分が作ったイヤリングを佳子さまがつけられたと知って大喜びです。会場を訪れていた友人:「知らなかった、やばい、びっくり!」一緒に喜びました。 「はまゆう」は一般企業での就職が難しい人に「働く場」を提供する就労支援事業所で、14人の障害者が働いています。渡部さんは、ここで同じように聴覚に障害がある人と一緒に、七宝焼のアクセサリーを製作しています。七宝焼は、金属の素地にガラス絵の具を焼き付けて装飾する工芸品で、「七宝」という名の通り、美しい色彩が特徴です。古代エジプトが起源とされ、日本には奈良時代に伝わりました。 手作りで、同じものが2つとない、いわゆる“一点もの”。製作には時間と根気が必要ですが、七宝焼が大好きだという渡部さん。佳子さまがお召しになったことで、さらにやりがいを感じているようです。渡部史也さん: 「頑張ります」 佳子さまのご訪問で、鳥取の優れた手仕事にスポットがあたることになりました。山陰中央テレビ(動画あり)【YAHOOニュース】佳子様がお召しになられるもの、どれも売れ行きが半端じゃないようで、こういう形での貢献はとても有難いですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.05
閲覧総数 42
-
-

- 0歳児のママ集まれ~
- 10%OFF有😀明治 ほほえみ らくらくキ…
- (2025-10-13 19:30:04)
-
-
-

- 障害児と生きる日常
- 車椅子の子も、全盲の子も、知的障害…
- (2025-10-08 04:31:12)
-