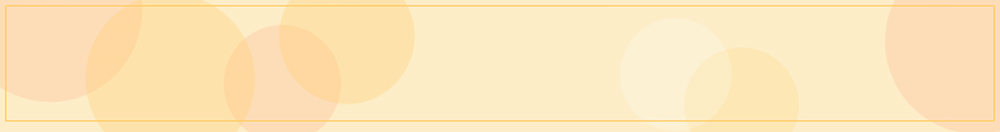2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年05月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

第5回演奏会ご来場ありがとうございました
第5回演奏会が無事終了しました。200名以上の方にいらしていただきました。ご来場された方々、どうもありがとうございました。演奏会終了後、前から4列目の座席に忘れ物がありました。梅ヶ丘駅前のARPAJON(アルパジョン)のお菓子と思われます。ホールの方と相談した結果、おそらく私たちへの贈り物だろうということで、引き取らせていただきました。出演者に心当りはないかと聞いたところ、おそらくQ社の方ではないか、ということでした。
May 16, 2009
コメント(2)
-
緊急手段
第1ヴァイオリンは、バッハのチェンバロ協奏曲について、何が悪いのか、どうすればいいのかがわからなくなってしまったので、師匠の丹羽道子先生に練習をみてもらうことにしました。一人でみてもらうよりも他のメンバーも一緒の方がわかりやすいと思い、第2ヴァイオリンとヴィオラにお願いして、練習に付き合ってもらいました。先生のご都合とメンバーの予定を合わせると、火曜の21時からしか予定が合わなかったので、21時から練習することになりました。1楽章は、あんまり音を抜かずにしっかり弾いた方がよいとのことでした。特にタイの音は抜かない方がよいようでした。第2ヴァイオリンとヴィオラの八分+十六分+十六分+八分のパターンは、最初の八分をバスっぽく、残りをバスとは別物として演奏すると良いとのことでした。八分音符と八分休符が連続したり、八分音符が続くところで走りがちなので、走らないように注意しました。第1ヴァイオリンが第3ポジションで演奏する部分の音程がよくなかったので修正しました。いつも基準にしている1(人差指)や2(中指)の両方に♭(フラット)が付いているので、音程が不安定になっていました。2楽章は、ピッツィカートの練習をしました。指の腹で、弦の真ん中に近い部分を弾くと良いようです。2楽章の終わりから3楽章の入りを練習しました。第1ヴァイオリンはザッツを八分音符でとっていましたが、付点八分でとったほうがテンポに乗りやすいとのことで、この部分を何度も練習しました。3楽章も1楽章同様、タイの音はあまり音を抜かないようにした方がよいようでした。八分音符が二つ続いてその後休符になる部分に走る傾向があったので、注意するようにしました。全体的に、バロックということで音を抜き気味にしていることが大きな問題だったようです。しっかり弾くことにより、だいぶテンポが安定してきました。また、今日の練習で曲の感じをつかむことができました。演奏会当日のリハーサルで、他のメンバーと一緒に今日の練習で得たことを試してから、本番に臨みたいと思います。それにしても、この日の練習は23時まで、2時間も見ていただきました。先生、それに付き合っていただいたお二方、ありがとうございました。(Vn: T.Y. 記)
May 12, 2009
コメント(0)
-
「狩」最後の練習
最後の練習はヴァイオリン奏者の林智之先生にみていただきました。一楽章から順に途中で止めながら見ていただきました。一楽章では、まずテンポが速くできないか聞かれました。来週本番なので、ちょっと難しいことを伝えました。目的は、もっと軽い感じにした方がよいとのこと。今の状態では 八分の三拍子に聴こえてしまっているので、八分の六拍子、つまり二拍子の感じを出せればテンポは今のままでもいいとのことでした。第1ヴァイオリンの最初のザッツの出し方にも問題があり、改善すると良くなっていきました。また、チェロは四分音符を八分音符くらいの長さで弾いていたり、スラーが切れて聴こえる箇所がありましたが、譜面に忠実に弾くよう意識するだけでも、曲におもしろみが出てきました。1楽章の繰り返しの後は、曲のイメージが掴みにくかったのですが、先生自作(?)のストーリーを聞かせていただき、イメージしやすくなりました。2楽章のメヌエットには、三拍目にfがついている部分があります。私たちはこれをきれいにフレーズに入れて表現しようとしていました。しかし先生がおっしゃるには、踊りにくい場所にわざわざsfが付いているということは、大げさにやってしまっていいのではないか、とのことでした。聴いている人は実際に踊ってはいないけど踊ってるつもりになっていて、踊りにくい場所にモーツァルト特有の冗談でわざとsfを入れたのかもかもしれない、という話をしていただきました。3楽章では、冒頭のpからsfの後の、三十二分音符の出るタイミングについて第1ヴァイオリンは悩んでいました。自分の出たいタイミングよりも、早く出てしまうのだそうです。先生から、sfの八分音符を八分音符分よりも短くして音楽を止めてしまっているからタイミングをうまく取れないのではないか、とアドヴァイスしてもらいました。これまでよりもsfの音を長めに、八分音符分延ばすと、うまい具合に三十二部音符のタイミングを取れるようになりました。また、この曲を通して一番言いたいことは、どの部分なのかと聞かれました。それに従って曲の構成を意識すると、曲にメリハリが出てきました。4楽章では、速い移弦の部分は弓を飛ばさずに、つけて弾くことを勧められました。つけて弾いても飛んで聴こえるようです。また、ときどき八分音符が転んでしまうので、転ばないように指摘されました。第1ヴァイオリンの三連符は他の楽器は音を伸ばしているだけなので、慌てないで、特に臨時記号が付いている音符は丁寧に聴かせた方がいいとのことでした。全体を通してその曲の場面を具体的にイメージすることを言われました。こうすることにより、より生き生きとした演奏を目指したいと思います。(Vc: Y.M. 記)
May 10, 2009
コメント(0)
-
七重奏 最後の練習
今日は最後の練習でしたが、昨日は朝から夜まで練習があったので、みんな若干疲れ気味でした。昨晩、ホールで通したばかりだったので、今日は練習の途中ではなく、最後に通すことにしました。その前に毎回恒例のEs-durの音階と、昨日の七澤先生練習の復習とホール練習を踏まえての調整などを行いました。音階は劇的によくなってきています。おそらく、今までの練習の中で最短時間で終えられたような気がします。七澤先生の練習の復習としては、1楽章の序奏からAllegroに入るところまでをやりました。出だしのアインザッツを変更したり、Allegroのテーマの弾き方をみっちりと教わったので、それらを確認しました。また、縦の線や音程が気になるところ、再現部の直前のCresc.をもっと効果的にするなど、要所要所を確認しました。これまで取り上げてきた曲はどれもそうでしたが、1楽章は中身が濃いため、確認することがたくさんあり、かなり時間を費やしました。2楽章は再現部を冒頭よりも音量を落とすことを確認したり、C-durに転調する前後のテンポの緩め方、ホルンのメロディーと弦の伴奏のテンポ感を確認しました。3楽章のTrioは七澤先生に落ち着いたほうがいいとアドバイスをいただいたので、それを実践するべく練習しました。4楽章は、Var.Iへの移り変わりに若干不安が残っていたので、再確認していきました。5楽章は、七澤先生のアドバイスを受けて、一部弦楽器の弓の運び方をマイナーチェンジしたので、その箇所をゆっくりのテンポで練習したり、Trioを練習しました。時間がなくなってしまったので、6楽章は冒頭の弾き方、音程の気になるところだけを練習しました。そして、最後に全楽章を通しました。昨日の先生練習を経て、だいぶ仕上がった感じがあります。さあ、あとは本番を残すのみです。当日は、午後にホールではなく、練習室で1時間ほどリハーサルをした後、夜に本番です。リハーサルでは、一度通し、残った時間で返すことにしました。それだけでは時間が足りないい場合は、空いた時間に個人練習用の部屋で、必要な楽器同士だけで確認したりすることになると思います。(Vn:K.N.記)
May 10, 2009
コメント(0)
-
チェンバロとの練習とホールリハーサル
チェンバロ奏者のチェンバロを使っての練習でした。これまで、パーセルに時間をかけて練習してしまったので、今回はチェンバロ協奏曲を重点的に練習しました。1楽章も3楽章もテンポが安定しませんでした。また、縦の線もあまり合いません。あわせるポイントを作った方がいいのか、どのようにすればいいのか具体策がわからなかったので、とにかく何度も合わせて確認していきました。ホールでの練習では、最初に通して他のメンバーにバランスを確認してもらいました。また、感想をアンケートに記入してもらいました。(Vn: T.Y. 記)
May 9, 2009
コメント(0)
-
ホール練習
本番1週間前のホール練習です。狩の持ち時間は40分くらいあったので、最初にバランスをみてから通すことにしました。ホール練習では、他の団体の方々に聴いてもらい、アンケート形式で気付いた点を指摘してもらいました。ホールでの練習後、楽屋で1時間ほど練習しました。第1ヴァイオリンは、7重奏のヴァイオリンにホール練習で気付いたことをスコアに直接書いてもらっていたので、それに沿って練習を進めました。2楽章では、第2ヴァイオリンとヴィオラの八分音符の弾き方を揃えました。3楽章では、音程の気になるところを合わせました。次回は最後の練習です。(Vc: Y.M. 記)
May 9, 2009
コメント(0)
-
七重奏 ホール練習 “残響の確認”
今日は、久しぶりにウィーンホールで演奏しました。このホールは、残響2秒以上あることが業界的に有名です。ということで、主に今回は、残響チェックです。具体的には、下記の場所について、残響の状態を見てどのように間を取るかに注意することです。■1楽章の冒頭とAllegro con brioの入り■5楽章のトリオの入り■6楽章の冒頭と Prestoの入り他のパートの音の聞こえ方について、客席では風呂場のように響くわりにはステージ上では聞こえやすくて、アンサンブル的にはやりやすいと感じました。録音を聞く限りでは、思ったよりスケールが大きい演奏で、かなり整理された演奏になっていて、珍しく自分たちの演奏を安心して聴けました(笑)。しかし、これで安心してはいけないと思って、早速、音程・バランスをチェックしました。やはり残響のせいで、フレーズの処理は直す必要があります。自分の中では、昨年購入した新しい楽器(クランポン)を使いなれてきたのもあって、響きが昨年より良くなりました。特に高音部の響きの柔らかさにびっくりしました。明日は本番前の最後の練習なので、ホール練での反省をふまえて、まだ改善の余地のあるところをみんなで直していき、最終的にお客さんにどのように楽しんでもらえるようか作戦を決めたいと思います。(Cl:P.R.記)
May 9, 2009
コメント(0)
-
七重奏 七澤先生練 “ベートーヴェン新発見”
今日は朝10時から、2回目の七澤先生練です。場所は、府中のリハーサル室で、広くていい感じです。本番まであと1週間ということもあって、テンポ作り等がかなり固まってきましたので、先生は私達の演奏の流れを崩さないでいろいろ指導してくださいました。今回大きく学んだことは、"ベートーヴェンらしい演奏"です。世の中に出回っている録音ばかりではなく、当時のベートーヴェン(ウィーンに来たばかりの頃)がどうだったのかもよく考えて演奏しましょうとのアドバイスをいただきました。ベートーヴェンと直接対話するつもりでやりましょうということですね。楽譜に何が書かれているかをよく見て、譜面の通りに忠実に演奏することで、ベートーヴェンの"非人間的な部分"をいかに表現するというのが今回の方針です。特に、フォルテとピアノの急な変化、Dur(明るい感じ)とMoll(悲しい感じ)の急な変化を忠実に表現する等です。これに関連して、フォルテマークの解釈について面白い話をしてくださいました。例えば、複数の四分音符にすべてフォルテが書いてある場合 = 四分音符にアクセントや、sf の連続 = cresc.ではないか等です。大変勉強になりました。また、音の芯(コア)をちゃんとつかむことについて見ていただきました。先生の近くに7種類の様々な録音機器が置いてあって、まるで電気屋さんのPCMレコーダコーナーです(笑)。そこで先生が録音したあとにどのように聴くかについていくつかのアドバイスをくださいました。1. "音程":自分の音だけではなく、周りの音もよくチェックすること。音程の悪いところに「×」を譜面に書いておくと、本番のときに役立つとのことです。音程以外にも音色もよくチェックするようにアドバイスをいただきました。2. 他のパートとのバランスを確認しましょう。3. テンポチェック: 自分たちの演奏のメトロノーム数値を基準として記録しておきます。何回か練習をしているうちに、結局本番は大体そのテンポに戻ってくるとのことです。今日、指摘された大事なポイントを以下にまとめます。■序奏の最初の音の出だしについて、今までのようにぼやっとではなくて、もっとスピードのある音にしましょう(初速に注意!)。これはアインザッツに強く関係します。そのアインザッツを変更することによって、音色がかなり変わりました。その後、f と p と ff の切り替えについて、もっと正確に表現するようにいろいろ修正してくださいました。■二楽章は、最初のフレーズの音程に厳しくチェックしていただきました。■三楽章のトリオのテンポは、前に行かないようにもっと落ち着いてやってください。■五楽章の冒頭のテーマについては、四分音符の処理、四分休符の取り方をもっとドイツ語的に、最初に"t"や"d"で言葉が終わるように固めに処理して、あまり流れてしまわないように注意しましょうとのことです。■六楽章について、出だしのEsは一楽章と違います。今まで少なくとも私は意識していませんでした。導入部のAlla Marciaのやり方について、ナポレオンの葬送行進曲のようなイメージで、おもちゃの行進曲ではなく、もっと深刻な感じが欲しいとのことです。fp の処理の仕方も、今まで私達が演奏するsfzとあまり区別できませんでしたが、もっとfに時間をかけてやってpまできれいに音量を落としてみると、かなり雰囲気が変わってベートーヴェンっぽくなってきました。最後の30分は、弦楽器の特訓です。楽器の持ち方、弓の乗せ方、フィンガリング等の修正で、弦楽器セッションの音が大分よくなりました。本当に実りのある素晴らしいレッスンで、七澤先生に深く感謝いたします。1時間の昼休憩のあと、4楽章の復習を行いました。Var. II から Var. III に移る瞬間および Var. IV から Var.V に移る瞬間はかなり難しかったです。みんなが納得するまで修正しました。この後はホール練です。体力を残しておこないと!(Cl:P.R.記)
May 9, 2009
コメント(0)
-
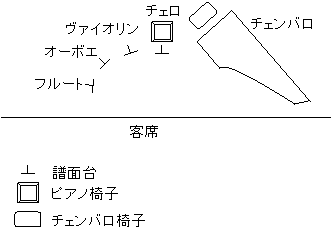
チェンバロとの練習とホールでのリハーサル
チェンバロ奏者のお父さまに運んでいただいたチェンバロを使って、初めて合わせました。まずは、並び方の確認です。舞台に向かって左から、フルート、オーボエ、ヴァイオリン、チェロ、チェンバロ、と並びました。また、フルート、オーボエ、ヴァイオリンは立奏することにしました。まずは、全部通しました。数日前、フルートの K.I. さんが前回練習の録音を聴いて、気になる部分についてメールで送ってくれていたのをみんな確認していたので、K.I.さんの指摘に関してはみんなクリアしていました。その他の場所で気になるところを確認していきましたが、比較的時間はかからず、予定よりも若干早めに終わることができました。夜は、ウィーンホールでリハーサルでした。最初に通して他のメンバーに聴いてもらいました。バランスなどはその場で指摘してもらいました。また、感想などをアンケートにかいてもらいました。(Vn: T.Y. 記)
May 9, 2009
コメント(0)
-

チェンバロ搬入
夜、ウィーンホールでリハーサルを行いました。リハーサルのために、チェンバロ奏者のお父さまがチェンバロを自宅から運んでくださるということで、せっかくなので地下の練習室で、午後の時間帯にチェンバロと練習することにしていました。先日の、ホールとの打合せに記載した通り、地下2階の駐車場の入り口から、一般用エレベータを利用して地下1階までチェンバロを上げました。足は取り外すことが出来るのですが、横幅がカバーも含めるとエレベータ入り口よりも広かったため、鍵盤に向かって反時計回りに90°回転させ、右側を上にしました。また、本体の奥行きがエレベータの奥行きより長いため、奥の部分を持ち上げて、斜めにしてエレベータに入れました。このようにして、無事にチェンバロを搬入し、地下1階の第1練習室で練習することが出来ました。
May 9, 2009
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- 人気歌手ランキング
- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…
- (2025-11-15 04:58:28)
-
-
-

- LIVEに行って来ました♪
- サーカスパフォーマーまおのライブ
- (2025-11-23 13:17:54)
-
-
-

- オーディオ機器について
- 試作スピーカー32.1(振動系の組み立…
- (2025-11-27 22:12:15)
-