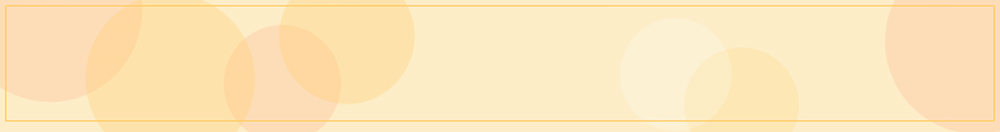2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2010年01月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
ヴァイオリンパート練習3-2
引き続き、モーツァルトをみていただきました。最初に3楽章。全体として、前に進んでいく部分と、1拍ずつ3拍子を感じて弾く部分とあるので、これを意識するといいとのことでした。例えば39小節目から八分音符での2小節間は前向きに演奏し、次の小節は1拍ずつ感じるとよいようです。74小節目からは、第1ヴァイオリンがオブリガートで、第2ヴァイオリンがメロディという認識の方がいいようです。第2ヴァイオリンは柔らかい音色でふわふわと弾いていたのですが、もう少ししっかりと芯のある音で弾いた方がいいようです。次に4楽章。冒頭のシンコペーション、第2ヴァイオリンが若干遅れるのと、休符の前の音をはっきり切ることを指摘されました。100小節目からや243小節目からの第2ヴァイオリンが八分音符で大変な動きをしているところですが、きちんと弾こうと頑張って弾いていたのですが、それだと少しうるさくなってしまうようです。気楽に適当に弾いた方がいいようです。その方が、弾けているように聴こえるようです。最後の八分音符(287小節目)が、何度やっても第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンで合いません。どうしたことでしょう。ここは持ち越しになりました。(Vn: T.Y. 記)
January 31, 2010
コメント(0)
-
ヴァイオリンパート練習3-1
ヴァイオリンパートレッスンの第3弾です。最初にドヴォルザークの3楽章をみていただきました。Bの L'istesso tempo からは espress. molto なので、pでも歌えるくらいの音量があったほうがいいようです。6連符が3つスラーで弾くところは、全てスラーを一弓で弾いていたのですが、crescendo のあるところは、弓を返すことにしました。更にその後、6連符、6連符、8連符という小節があり、しかも最後の8連符に ritardando が付いているのですが、その ritardando の感じをみていただきました。最後の C の音が上ずってしまうので、上ずらないようにするための対策を検討しました。音階を上がっていったときの G の音を高くならないようにとり、A-Hを弾いているうちに G を押さえてる1の指を真横のA線の C を押さえ、その A 線の C に合わせて E 線の C を4で押さえる。う~ん。。至難の業です。。(Vn: T.Y. 記)
January 31, 2010
コメント(0)
-
ドヴォルザークのホール練習
ホール練習でした。ホールでのリハーサルは各団体の持ち時間が60分だったのですが、この曲は通すと40分近くあるので、まず2楽章のテンポ確認と1楽章冒頭のテンポの確認をしました。その後、全楽章を通しました。これまでの練習では1~4楽章まで一回も通したことがなかったので、通し練習としては、今回が実質1回目です。なんと!2楽章で止まりました・・。2楽章は繰り返しがあるのですが、コーダから戻った後の繰り返しの確認をしていなかったのが原因です。その後は、何とか止まらずに最後までたどり着きましたが、ひやひやする場面がいくつもありました。ステージ上で弾いてみると、他パートの音がとても聴こえにくく、アンサンブルできているのかあまりわかりませんでした。後から録音を聴いてみた感想としては、全体的にテンポが安定せず、アンサンブルがうまくいっていない印象を受けます。あと、チェロがほとんど聴こえてませんでした・・(すごく遠くから音を出しているように聴こえる)。全楽章を通すことに関して、もう少し慣れる必要があるのかなと思います。残りの練習時間もわずかですが、もう少しできることはあるはず!なお、通し練習では他団体の方が客席で聴いて気付いたことをアンケートに書いてくれたのですが、今後の練習の参考にしたいと思います。ありがとうございました。(Vc: Y.M.記)
January 30, 2010
コメント(0)
-
ドヴォルザーク第7回練習
ホールでの練習に先立ち、7回目の練習を行いました。今回は4楽章の初の本格的な練習です。合奏をしながら気になる部分をピックアップ、確認し進めていきました。個人の練習では気づかなかった拍の取り方の間違いやパート間の関わりが今回の練習で気づくことができました。当初、4楽章は2時間で終わらせ、残りは他の楽章の練習をする予定でしたが、1時間近くオーバーしてしまいました。それでも4楽章の複雑さを考えたら早く終わった方だと思います。今回の練習でやっと全楽章の練習を一通り終えることができました。残り3回の練習でどこまで深められるでしょうか・・。(Cb H.H.記)
January 30, 2010
コメント(0)
-
1/30モーツァルトホール練
ホールでの練習は、自分の音しか聞こえず、慣れるまではかなり苦労しましたが、練習の最後の方ではだいぶ弾き方が分かってきました。細かい難はあるものの、ある程度曲としてまとまってきたようで、ほっとしました。これから本番まで、さらに切磋琢磨して行きたいと思います。
January 30, 2010
コメント(0)
-
ヴァイオリンパート練習2-2
引き続き、モーツァルトの1楽章をみていただきました。13小節目からトリルの掛け合いがあるのですが、昔、どこかのオケの練習で、モーツァルトでトリルはアクセントみたいなものと言われた記憶があったので、アクセント気味に弾いていたのですが、「もっとさりげなく」と言われました。その方が、その前のfとの対比のpの中で、柔らかい表現ができるようです。繰返し記号の後、四分音符に楔が付いているのですが、あまり切り過ぎない方がいいようです。その他、ヴァイオリン二人で16分音符で動くところなどを合わせていきました。(Vn: T.Y.記)
January 17, 2010
コメント(0)
-
ヴァイオリンパート練習2-1
ヴァイオリンパートレッスンの第2弾は、最初にドヴォルザークの4楽章です。この曲は、まず、冒頭がとても難しいです。まずは、第1ヴァイオリンのフィンガリングをチェックしてもらいました。冒頭の後半の部分(21~28小節目辺り)、先日師匠の師匠の譜面を見せてもらい、フィンガリングを写したのですが、それとは違うフィンガリングを勧められました。fpのすぐ後にppに落ちるところは、pとppの対比を分かるようにした方がいいようでした。(他にもいろいろ見ていただいたのですが…)最後、1と4の指でA線とE線のDのダブル弾いた後、すぐにE線の上のGを弾くのですが、上のGの音程が当たりませんでした。コツを聞いたところ、Dを弾いたら、E線の4で押さえたDの場所に1を持っていって(目視で確認)、4を押さえるといいようです。早速試すと、ばっちりでした(と言いつつ本番外したらごめんなさい!!!)。(Vn: T.Y.記)
January 17, 2010
コメント(0)
-
ロッシーニ 第3回練習
前回、前半中心の練習だったので、今回は三楽章から練習スタートさせました。前回と同様にメトロノームを使い「タテ」と音程のチェックを行いました。どうしても音源や自分のイメージがあるためメトロノーム練習をするといろいろなところが歪むのですが、それこそこの練習の求めるところです。地道な練習ですがこれをベースに練習をスタートさせることが、後々のクオリティーにつながると感じています。そうそう、今回は、前回し忘れていた音階練習を最初に行いました。曲の調であるFdur音階を繰り返し練習しました。朝一で、部屋が寒かったせいもあるのですが、なかなか音程が定まらず苦労しましたが、今後練習開始時には必ず入れていくことになる思います。三楽章のメトロノーム練習がひと通り終わり、今度はメトロノームなしで3、2、1と返しました。今回、HrとFgが早抜けしなければいけなかったので、あまり長い時間出来ませんでしたが、次回に向け、大枠の音楽のイメージと局所の課題見えてきました。(Fg: K.N. 記)
January 17, 2010
コメント(0)
-
モーツァルト「春」第6回練習
ドヴォルザークに引き続き、モーツァルトもチェロの松本ゆり子先生にみていただきました。モーツァルトの特にこの曲のテーマは「強弱の対比」とのことでした。冒頭を始めとし、全曲を通じて1小節毎や1拍毎にfを交互に繰り返す部分が多く見られます。この強弱の対比をしっかりと出すのが重要です。pからクレッシェンドがあり、次のフレーズがfで始まるとき、前のフレーズのクレッシェンドがfを超えてしまうことがありました。次のフレーズに向けたクレッシェンドと捉えた方がいいとのことです。fのフレーズが1パートだけ小節を超えた四分音符がfのままで、他のパートは小節を超えたときにpに落ちているとき、小説を超えたpでない音は、fで弾ききるのではなく、少しおさめるのが慣例になっているそうです。pで八分音符と八分休符が交互に出てくるところは、一音一音留まって弾いた方がいいとのことでした。1楽章は、再現部に入る前に calando があるのですが、第1ヴァイオリンはシンコペーションで動きます。その最後の八分音符を、次のアウフタクトと思ってタイミングを取ると再現部に入りやすいとのことでした。2楽章のテンポは、譜面の指示は Allegro ですが、あまり速くし過ぎないほうが、p-f-p-…と1拍ずつ出てくる部分を表現できるとのことでした。実際、譜面の注意書きに、「初版は Allegretto」と書かれており、先生の推測によると、最初 Allegretto と書いたけどテンポが遅すぎたから Allegro に変えたのでは、とのことでした。なので、Allegretto に近い Allegro と考えるといいのでは、とのことでした。fのフレーズが終わって、次に p のアウフタクトでフレーズが始まるとき、少し間を空けたほうが突っ込んだ感じにならないようでした。fのフレーズを、立派に弾ききってから時間をかけてpに移るとよいようです。3楽章はハ長調(C-dur)です。ドヴォルザークでも書いていますが、完全五度でチューニングをすると、ビオラ・チェロのド(C)とバイオリンのミ(E)の音は合いません。先生のアドヴァイスによると、ビオラ・チェロの解放のド(C)の音が下がりすぎてないか確認することと、この楽章だけヴァイオリンの開放のミ(E)の音を少し下げてもいいとのことでした。また、3楽章の冒頭にド(C)-ミ(E)-ソ(G)の和音が出てくるのですが、このとき、ミ(E)の音を他の音よりも柔らかめにする、音程をいじるのではなく、音色を柔らかくするとうまく調和するとのことでした。管楽器でもよくそうするようです。4楽章は冒頭が第2ヴァイオリンで始まるのですが、途中難しいフレーズがあるため、冒頭からテンポを注意して、途中も速くならないように注意して弾いていました。すると先生から、「もっと楽しそうに弾いてください」といわれ、どうにかなるかなと開き直って弾いてみると、全体の感じはよくなりました。あまり慎重になりすぎるのはいけないようです。4楽章のテーマの音形は全音符で、冒頭はそれぞれの楽器が交代で演奏します。それの伴奏でシンコペーションなど複雑なことをするのですが、全音符よりも細かい音符が大きくなってしまい、テーマの全音符が聴こえなくなってしまいます。なので、伴奏のシンコペーションは、もっと客観的になって弾いた方がいいとのことでした。しかし、あまり客観的になりすぎると、後ろ向きになってしまうようで、それでも前向き(遅れない)に演奏するように、とのことでした。モーツァルトの方がドヴォルザークよりも譜面の並びは簡単なため、より奥深い練習ができたと思います。先生からのアドヴァイスを吸収して、自分達のものとして演奏できるといいと思いました。(Vn: T.Y.記)
January 16, 2010
コメント(0)
-
ドヴォルザーク第6回練習
ドヴォルザーク第6回目は、チェロの松本ゆり子先生に見ていただきました。初めての先生練です。これまでの練習では4楽章はほとんど手がつけられていない状態なので、1~3楽章までを順番に見ていただきました。1楽章は、冒頭チェロとコントラバスで入る部分が突然入った感じなので、遠くから近づいてくる感じがいいとのことでした。また、ヴァイオリンからチェロまで各楽器に出てくる速いパッセージは、弓をもっとコンパクトに使って、長さもある程度は揃えた方がよいとのこと。1楽章は1時間15分くらいかかりました。ちなみに、ヴァイオリン2人は、別にヴァイオリンの先生のレッスンを受けてきたようで、その時言われたことの調整も合わせてやりました。休憩後、2楽章です。Aから、前向きな(明るい)雰囲気があったほうがよい。でもはしらないように(チェロ)、とか、トリオから休符できちんと切るようにしないと、その休符に入っている音符(別のパートがやっている)が埋もれて聴こえなくなってしまう、とか、3連符をゆったり弾くイメージでも大丈夫、などとの指摘を受けました。2楽章は順調(?)で、30分くらいで3楽章へ。3楽章は C-dur で始まるのですが、ヴィオラとチェロのC線が低すぎないように確認した方がよいとのことでした。ヴァイオリンのE線と合わせるのが難しくなってしまうようです。3楽章は、短くて同じような旋律が何度も繰り返される曲なのですが、風景画のように淡々とメロディーを聴かせる演奏と、メロディーの裏で動いている旋律を聴かせる演奏のどちらもありだよ、とアドヴァイスされました。今回は、メロディーの裏で動いている旋律を聴かせる方向でいくことになりました。3楽章の途中で今回のレッスンは終了しました。チェロはフィンガリングがわからない箇所も伺うことができ、充実したレッスンでした。(Vc: Y.M. 記)
January 16, 2010
コメント(0)
-
ヴァイオリンパート練習1
ヴァイオリン奏者二人は同じ先生に師事しているので、レッスンでヴァイオリンパートをみていただくことにしました。まずは、ドヴォルザークから。2時間のレッスンで、1、2楽章をみていただきました。1楽章。全体的に、3連符と付点八分や十六分音符などが同時に出てくるので、きちんと弾き分けるのがポイントとのことでした。意識すればたいしたことないのですが、まだあまりさらえてないので、油断するとリズムが甘くなってしまいます。スラーの最後にスタッカートが付いている形は、話し合った結果、分けて弾くことにしました。付点八分+十六分音符の形の付点の長さを合わせたのですが、結論を忘れてしまいました。。音を読み違えているところがあって(G を Gis に、A を Ais に)、修正しました。同じ音形で、アクセントがついているところとスタッカートが付いているところがあり、弾き分けた方がいいとのことでした。まださらえてないところがいくつかあるので、さらわないといけません。。2楽章。冒頭の形が何度も出てきますが、ピアノになるタイミングが違うので、はっきり分かるように区別しなくてはいけないのですが、これもまだ慣れておらず、油断するとうまくいきません。。同じ高さの音がスラーでつながっていることろを、弓を返したり切ったりせずに、左手の押さえる指を替えるようにしたのですが、それで大丈夫とのことでした。TRIO 部分ですが、前向きに弾くところ、少し落ち着くところという緩急の変化を付けたほうがいいとのことで、そのようにするととても弾きやすくなりました。ここに書いた以外にも、多くのアドヴァイスをいただきました。(2nd のことは全く書いてないです。。)(Vn: T.Y.記)
January 10, 2010
コメント(0)
-
モーツァルト第5回練習
前回からの練習テーマは、“次回(1/16)の先生練で、先生に全楽章をひととおり見ていただけるように準備する”です。前回は4楽章は一度通すだけで終わってしまったので、今回は4楽章中心に進めました。4楽章は、テンポが速いのとシンコペーションの形が多いため、また、ドボルザークとは違い、音符の絡み具合がそう複雑ではないために音程の違いなど粗が目立つため、細部をつめていくととても時間がかかりました。特に一番苦労したのは、冒頭からのひとくだりで、2ndバイオリン→1stバイオリン→チェロ→ビオラの順にカノンになっている部分です。全音符で動くパートと別の2つのパートが2種類の異なるシンコペーションをやるという構造で、4部音符で拍を刻むパートがいないので、思い思いのテンポ感で弾いてしまうため、最初はどうにも縦の線が合いませんでした。試行錯誤の結果、全音符で動くパートを頼りにシンコペーションを弾けばテンポ感を共有できるとわかり、だいぶ良くなりました。3時間の練習時間でしたが、最後の20分ほどを残した時点で、4楽章の最後のコーダまで行きついていませんでした。最後の部分はあきらめ、残り時間で、あわてて1~3楽章を一回通して終わりました。(縦の線、音程など大変な状態で、前回の成果はいずこへ・・・という具合でした…)とても不安が残りますが、次回の先生練、頑張ろうと思います。(Vn:K.N.記)
January 9, 2010
コメント(0)
-
ドヴォルザーク第5回練習
ドヴォルザークは、先生練前の最後の練習でした。1~3楽章は何とか通るようにはなりましたが、それでも時々、各自入る場所を間違えることがあるようです。本番1ヶ月前を目前にしているので、そろそろ入り間違いはなくして行きたいと思います。4楽章は、まだ一度もじっくり練習できていないので、先生練後の最大の課題が4楽章となりそうです。Va.H.Y
January 9, 2010
コメント(0)
全13件 (13件中 1-13件目)
1