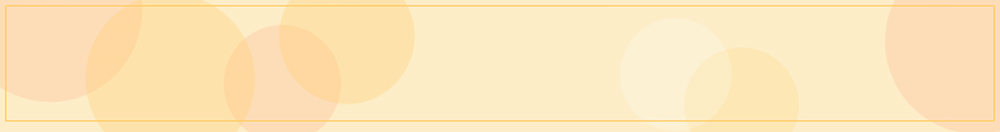2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年01月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
ブラームス弦5 第5回練習
午後の練習でしたが、前後の別団体の練習とのかねあいから、第2バイオリンが1時間強の遅刻、第2バイオリンと第2ビオラが1時間強の早退で、5人揃っての練習は正味1時間半でした...。2楽章を、演奏の方針を立てながら練習しました。Grave ed appassionato(1~31小節目)冒頭のテーマはVcが気持よく弾けるテンポにしようと思いましたが、17小節目から同じメロディーを第2ビオラの3連の伴奏と合わせてやるところでは、テンポ感のずれが生じてしまいました。相談の結果、冒頭は4分音符=39ぐらいのゆったりしたテンポで始め、曲の流れとともにテンポは多少変動させることにし、17小節目からは4分音符=45ぐらいにもっていく、という設定に決めました。Allegretto Vivace(32~79小節目)8分の6拍子の、とてもリズミックな部分です。しかし、それだけに、小節線をまたぐタイや頭抜きの出だしが多く、譜面づらが難しくなっています。譜面を勘違いしてずれてしまう部分が所々あったので、ひとつずつ確認していきました。TempoI(80~116小節目)90~94小節目は、Va&Vcが3者でメロディーを弾き、Vn2本が3連の形で3オクターブのGisを上がっていくオブリガートをやります。メロディーとVnの縦のラインを合わせることと、Vn2本のオクターブ違いの音程が難しく、集中的に練習しました。オクターブ違いの音程については、それぞれ核になる音(1st、2ndともに、3オクターブの真ん中のGis)をしっかりとって合わせるのがポイントのようです。Presto(117~163小節目)Prestoという名のとおり、軽快なメロディーです。が、今の時点では軽快なテンポでは難しいので、目標テンポは2分音符=80、練習は2分音符=64ぐらいでやることにしました。151小節目や155小節目の、第2バイオリン・第1&第2ビオラの3人で8分音符の動きが、音程がなかなかわかりづらく、カオスのようになってしまいました。今日はもう時間がなかったので、次に2楽章をやる時にとりあげることにしました。次回は2/10で、第1ビオラを除く5人で練習です。(Vn: K.N.記)
January 26, 2008
コメント(0)
-
死と乙女の第2回練習
今年の初練習でした。前回の練習で、初めて4人で一通りあわせたので、今日は、1、2楽章を細かく練習していくことにしました。冒頭の14小節は、A-F-C-A, A-F-D-A, A-E-Cis-A の和音が不安定だったので、これらを合わせました。第2ヴァイオリンは C は低め、Cis は高めに取るとよいようです。25小節目から第1ヴァイオリンが3連符の最初が前の音とタイでつながっている音形が続きますが、最初のタイの音符が長くなって、次の2個の3連符がつまってしまう傾向にありました。第2ヴァイオリンとヴィオラがずっと3連符で刻んでいるのでそれを注意深く聴きながら演奏すれば大丈夫なようですが、油断するとつまってしまうようでした。それと、第2ヴァイオリンとヴィオラの3連符の音程合わせをしました。62小節目から、ヴァイオリン二人で音程合わせをしました。102小節目からは、第2ヴァイオリンとチェロで音程合わせをしました。音程合わせばっかりやってますね。この後も、115小節目からはチェロ以外の3人で、146小節目からは第2ヴァイオリンとヴィオラで、というように、1楽章の最後までゆっくりと、ほとんど音程合わせの練習をしました。少し休憩して1楽章を通してみると、ゆっくり音程合わせをしただけなのに、とてもすっきりと合わせることができました。その後、2楽章も同じように練習したのですが、あまり時間がなく、ほとんど練習できませんでした。あと2回の練習を行うと、次は先生練になります。それまでに、4楽章まで一通り練習できるか、ぎりぎりの感じです。(Vn: T.Y.記)
January 20, 2008
コメント(0)
-

アメリカ(木五編):フルートとオーボエで半分子
演奏会に向けて、木5の練習は7回の予定。練習計画は以下の通りです。1回目:メトロノームを使ってゆっくりで良いので曲に慣れましょう2回目:メトロノームを使ってリズム、テンポ正確に3回目:自分たちなりに解釈しましょう4回目:先生練5回目:先生練6回目:先生練復習7回目:仕上げそれでは、本日第1回目の練習です。テンポを落とし、メトロノームに合わせて全楽章通しました。テンポについて、Weak pointを洗い出しました。・遅れがちな旋律・刻み伴奏の不安定箇所・掛け合いが遅れるこの問題が顕著に現れるのは、1楽章と4楽章。2小節ごと、また、4小節ごとに緩急があるので、雰囲気に惑わされるようです。どの曲でも当てはまることですが、フレーズ大きくとらえ、中だるみしないことが重要です。『体内テンポ』の修正はまだ続くであろう。。。その他、かなり音程が気になります。伴奏パートが3~4本同じ音形で動くので、音程が目立つこと目立つこと。今後、さらにテンポを落とてハーモニーを確認していく必要があります。今日は全楽章を通すだけで時間切れ。曲の難しさを感じた日でありました。*-*-*-*-*-*-*-*さて、この曲、弦楽四重奏を木管五重奏に編曲したものですが、4人で弾く曲を5人で演奏するって、どういうこと?と思われるのでは。管楽器は重音ができないので、プラス一人という説もありますが、実際、各パートをかなりシャッフルしています。フルートとオーボエは1stの旋律を半分子してます。時には2ndを担当。クラリネットは、2ndとビオラパート、ホルンは、ビオラとチェロパート、ファゴットもビオラとチェロパート。1stの旋律をどのように半分子しているかというと、高音の華やかな旋律はフルート、中音のしっとりとした旋律はオーボエが担当というパターンが多い。例えば、1楽章の最初の旋律はフルート。2楽章の旋律はオーボエ。その他、同じ旋律でも雰囲気に変化をつけるため、交互に担当させる場合もあります。フルートとオーボエは擦り合い譲り合いの精神でがんばりましょう!では、次回「ファゴットおいしすぎ♪ホルン低すぎ!」をお楽しみに(未定)
January 19, 2008
コメント(0)
-
フルート四重奏の練習4回目
年明け最初の練習でした。年明け前に一通り練習したので、1楽章の練習をしました。途中からヴァイオリン弾きのK. N.さんが見学に来てくれて、いろいろとアドヴァイスをもらいました。ありがとうございました~。まず全部を通し、その後細かく練習していきました。テーマ: 冒頭の A-E-Cis (ドミソ)の和音から合わなかったので、まずはフルート以外で音程合わせをしました。一通り音程あわせをした後、フルートも入れて合わせました。フルートがフレーズの合間でブレスをしますが、チェロはその部分ではまだフレーズの途中なので、フルートのブレスを待たずに進んでいました。ここの部分は、チェロはフルートに合わせるようにして解決しました。また、テーマの繰り返しの前などで、チェロはテーマの最後と同じようにゆっくりとおさめてしまう傾向があったので、おさめるのはテーマの最後だけにしました。第1変奏:テーマと同様に、フルート抜きで音程を合わせました。テーマでじっくりと合わせたからか、それほど時間はかかりませんでした。11小節目のヴァイオリンの装飾音符が唐突すぎだったので、フルートとニュアンスを合わせました。第2変奏:ヴァイオリンが16分音符で細かい動きをしているので、まずはヴァイオリン以外の楽器で合わせました。チェロは、四分音符のスラーを、レガートで丁寧に弾こうとして遅れてしまう傾向がありました。その後ヴァイオリンとあわせましたが、ヴァイオリンはスラーのかかり具合でリズムが崩れるところがありました。一つ一つの音符をはっきり弾こうとしていましたが、流れるように弾くことによって、大分よくなりました。第3変奏:ヴィオラが主旋律なので、まずはヴィオラ以外で合わせました。八分音符の後の四分音符が短かったので、拍どおり伸ばすことにしました。その後、ヴィオラと一緒に弾きました。ヴィオラはソリスティックなメロディーですが、他の3本の方が目立ってしまう部分があったので、音量を調節しました。第4変奏:主旋律はフルートですが、チェロは対旋律でリズミックな動きをしています。最初はチェロ抜きで合わせた後、チェロを加えました。チェロに対してフルート・ヴァイオリンの音量が大きかったので、音量を落とすようにしました。そうすると、チェロも弾きやすくなりました。最後に1楽章を通してみましたが、約3時間の丁寧な練習ができたので、とても進歩した感じでした。次回は2楽章からの練習です。(Vc: Y.M. 記)
January 14, 2008
コメント(0)
-
ブラームス弦楽五重奏 第4回練習
今日は第2バイオリンが風邪で欠席でした。お大事に!最初に、今後の練習予定について相談しました。本番までに先生練習を2回入れようということになり、第2ビオラの先生に打診してみようという話になりました。今日は、1楽章から順に流し、よくわからない箇所の確認や第2バイオリンとの要調整箇所をピックアップすることとしました。結果的に、1楽章に2時間半ほど費やし、残り1時間弱で、前回の練習でわかりかけてきた3楽章を復習することにしました。1楽章は、冒頭から中間部(83小節目ぐらい~)までのテンポ設定、曲想の運び、強弱のレンジ、アーティキュレーションなど、かなり演奏の方針を決めることができました(再現部も方針は同じ)。まだ練習不足でそのとおりにできませんが、方針が定まったことによってだいぶまとまった演奏になってきたと思います。中間部の2連と3連が出てくる箇所(83~110小節目)はやはりカオスでした・・・。前に1楽章をやったときと同じように、ゆっくりのテンポと控えめな音量で仕組みを再確認しました。練習番号5番(111小節目~)からは、第2バイオリンと調整する箇所としました。111小節目から第2バイオリンが旋律なので、そこに入る110小節目をゆるめるかどうか、第1バイオリン&ビオラと三者で順にでてくるリズミカルな音形の弾き方やつなぎなどについてです。再現部(練習番号6、137小節目~)の直前は、音楽的には非常に盛り上がるのですが、重音がたくさんでてきて難しい部分です。同じことをやっている第1バイオリンと第1ビオラで音程を合わせました。第1バイオリンの重音が非常にとりにくいのですが、第1ビオラとほとんどユニゾンになっている上の音が合わないと、耳障りになることがわかりました。上の音ははずさないように頑張らないといけません・・・。再現部は冒頭のメロディーがクライマックスの様相で出てきて、VaとVcの3本が3連音符で伴奏します。この伴奏部分を抜いて弾くかどうか検討しましたが、客観的に聴くと、べた弾きにした方が重厚な雰囲気になってよさそうでした。再現部からPiu moderato(209小節目~)までは、最初に方針を決めたせいか、すんなり進みました。Piu moderatoからは、ゆったりとしたテンポにすることを確認しましたが、最後、終わりから3小節目はTempoIで突然もとのテンポに戻り3連音符のアルペジオをかけあがります。その入りのタイミングがなかなかつかめず苦労しましたが、間をとることで解決しそうな感じでした。今後も要練習の箇所です。3楽章は、今の段階ではまだ早いパッセージが難しいので、ゆっくりのテンポで流していきました。練習番号1からの第2ビオラとVcのロングトーンの動きと、合いの手であるVnと第1ビオラの関係がわかりづらかったので、確認しました。前回の練習でとても苦労した35~80小節目の2連と3連のオンパレードの部分は、意外にもすんなり進みました。前回の練習の成果でしょうか!?練習番号5からの掛け合いは崩れてしまったので、さらにテンポを落として確認しました。Prestoからもテンポを落として弾いたものの、パート間の関係を把握するのに時間がかかりました。一度落ちると復活が難しいようです。最後に、今日はテンポを落として弾きましたが、本番テンポの目安を決めました。冒頭は4分音符=84~90ぐらい、Prestoは4分音符=110ぐらいです。次回(1月下旬)は、2楽章について今日のように方針を立てながら練習し、また、1楽章の演奏の方針を第2バイオリンに伝える予定です。
January 6, 2008
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- コーラス
- 町の文化祭で発表(11/10)
- (2025-11-26 21:03:53)
-
-
-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…
- KING of IDOL 踊るパワースポット!
- (2025-10-05 15:16:43)
-
-
-

- 70年代サブカルチャー URC, ELEC, …
- まんだらけの優待のまんだらけZEM…
- (2023-06-24 23:18:46)
-