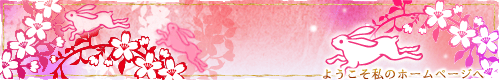2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年07月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
気が抜けた。
あまりのいそがしさから解放された今週。だいぶと気が抜けた。毎日のようにアポイントが入り、資料作成とプレゼンと締め切りモノに追われ、過ごしているうちは、ある意味何も考えなくても日々は過ぎていく。だけど、真っ白な一日になると、急に足が止まってしまう。走っている間は、休みたい、足を止めて考えたい、そうずっと思ってきたのに、一度止まってみると、何をしていいのかわからなくなる。「時間があれば~したい」と考えていたこと。いざ時間が生まれてみても、結局やろうという気が起きなかったりする。何をするにも、「時間があれば」というのは、体のいい言い訳なのかも知れない。____________________________________________________________________ドラゴン桜を読んでみた。マンガ自体、久しぶりに読んだが、これは面白い。いっぱい共感した。学校という場所の特性、子どもに対する姿勢、入試の捉え方。共感する考え方がたくさんあって、一気に読めた。おもしろい。難しいことはよくわからないが、日本という国は資本主義社会であるからして、生きていくためには、「競争」しなければならない。今の日本という国は、豊かで、モノがあふれていて、そんな時代を育ってきた僕らの世代は、何もしなくても生きていけるような、そんな幻想を持っている。幸いにも何不自由なく育ててもらったからこそ、そんな幻想を持っていた。だけど。社会人になってみて、少しずつ感じてきた。受験勉強みたいに、「見えやすい」競争ではなく、「見えにくい」競争だけど、生きていくためには、必ず競争がある。それをちゃんと意識すること。ちゃんと世の中の仕組みを知ること。まだまだ知らないことがたくさんある。これからの何十年という時間を、生き抜いていくために、もっともっと知らなければならない。もっと勉強しなければならない。学力であったり、知識であったり、生きていくために不可欠なそういうものを、いつの間にか僕らは軽く見るようになったのではないか、そんなことを改めて感じさせるマンガだった。早く続きが読みたい。____________________________________________________________________マンガ喫茶に行ってみた。ずいぶんと久しぶり。最近のマンガ喫茶は、えらい充実ぶりだ。学生時代にこんなところができていたら、きっと一日中こもってしまっただろう。久しぶりに、プレステに没頭したりする。何も生産しない、こんな時間も必要だな。当たり前だけど、スイッチの切り替えは必要だ。何もしない時間があって、何かをする時間がある。生産性がどうこうというよりも、人間の自然な感情とか欲求とかなんだかよくわからないけど、とにかくバランスというものがある。仕事は好きだけど、毎日16時間も働こうとは思わないし、海にいったり、ドライブしたり、だらだらしたりも好きだけど、毎日したいとは思わないし。今、なんだか無気力な感じになってきてるのは、この3ヶ月、自分なりにいっぱいいっぱいになりながら走ってきたからかも知れない。_____________________________________________________________________そんなこんなで思い出した。サイバーの藤田さんの離婚。「なんかキレイ事言ってるなぁ、この人。」というのが正直な感想。戦略的に、マーケティングして、ロジカルにシンキングして、そうやってこの人は、人と付き合ったり、結婚したりしてるんだろうか。「渋谷ではたらく社長の告白」は前に読んだ。まぁ、面白かったけど、感情移入はできなかったし、共感はできなかった。「あ、そう。すごいですね。」という感じ。なんだか単なる自慢話なんだよなぁ。だから面白くない。面白いと言ってる人は、本当に心の底から「共感」してるんだろうか。そうじゃなくて、いわゆる「流行」として「かっこいい」といわれている部分を、うらやんでいるだけなんじゃなかろうかと思う。_____________________________________________________________________「明日の記憶」という小説を読んだ。広告代理店の営業部長である主人公が若年性アルツハイマーになる話。人生について考えさせられる本だった。いろんな小説を読んだが、自分が50歳になったときをイメージして本を読んだのは初めてだったように思う。何もかもが自分の記憶から消えていくとしたら、それはどんなに苦しいだろう。そんな中で生きていく意味って何だろう。すごくリアルだった。映画なんかよりもずっとずっとリアルだった。何気ない日常が、少しずつ遠く離れていく。楽しい記憶も、辛い記憶も、自分の周りにいた人も、ひとつずつその記憶が消えていくとしたら。。。この本は「記憶」という切り口で、「夫婦愛」を描いた作品なのではないか、個人的にはそう感じた。とにかく、いい本だった。お薦め。でも、50歳以上の人にとっては辛くて読めないだろうな。今、自分が50歳だったら、きっと途中で読めなくなる。
2005年07月27日
コメント(0)
-
プレゼンスキル。
役員をはじめ、カンパニーの幹部がたくさん来る日。普段はなかなか話す機会のない人と話せた。そんな中、現場からの発表でマネージャーが僕を指名してくれた。活躍の場を与えてくれたことに感謝。このマネージャーがいるからこそ、今の部署は「褒めあう」文化、「尊重しあう」文化があるんだなぁと思う。前の会社との文化は全く違う。僕は今の方が好きだ。それに、こういう文化の方がうまくいくとも思う。仕事はひとりでするわけじゃないんだから。_______________________________________________________________________優れたプレゼンには笑いがある。ユーモアがある。どんな流れるようなプレゼンよりも、笑いのあるプレゼンの方が心に残る。今回はしっかり「仕込んだ」。そしてうまくいった。みんな「仕込んで」いた。マジメな部分と、笑いの部分。どちらも必要。飲みながら事業部長と話した。いつ聞いてもプレゼンのうまい人。「必ず笑いは入れる。共感を生むからな。どんなにうまくプレゼンしても そこに笑いがなかったら、必ず叱るからな(笑)」と聞いて、確かに共感した。こういうのってセンスだな。自分のキャラクターにあった笑いと、その場にあった笑いがある。関西で育った分、人よりは鍛えられているハズ。_____________________________________________________________________先は長い。新しい視点とか、新しい考えを自分なりに出してみたりして、ちょっといい気になってたけど、上の人から話を聞いてみたら、もうすでに考えていたことばかり。何歩もその先を行っている。まぁ、そりゃあそうじゃないと会社としてはダメなんだろうけど、なんかちょっと悔しかったというか、残念だったというか。いいこと思いついた気でいたらまだまだでした。ごめんなさい。って感じ。新しい何かを生み出したいと思ってたけど、まだまだ修行が必要みたい。そりゃあ何十倍も経験積んでいて、視野も広いから到底及ばんよね。むぅ。だけど、現場べったりなのは、上の人には負けない。だからこそ、現場ならではのアイデアは貴重なハズ。引き続き、新しい価値を求めていこう。
2005年07月12日
コメント(1)
-
本音のところ。
校内研修会で学校へ。こちらからの情報提供で50分話したあと、データの分析でさらに30分。その後、データを見ながらあれこれと議論する。いっぱい意見を求められ、質問される。答えてみると、納得いくこと、納得いかないこと、それぞれハッキリ話してくれる。まるで学校の一員になったように、話ができた。同じ目線に立ってみる。本音で話をする。これが「信頼関係」なんだと思う。「ぶしつけな質問になっちゃうけど、、、」「こんなこと、自分で調べろって話かも知れないけど、、、」「~くんだから、言っちゃうけど、、、」と言われて、話しかけられると嬉しい。信頼関係が少しは築けているということだから。そんなことを感じているうちに、ふと思った。結局のところ、先生と生徒との関係って、1対1になったとき、どれだけお互い本音で話せるか、に尽きるんじゃないかと。システムをいくら整えようが、何だろうが、お互いどれだけ本音を口にできるか、そこが基本なんじゃなかろうかと。____________________________________________________________________「キミは高校生の頃はいい成績とってたからわからないだろうけど、頭のいい子とは違って、学力の低い子は簡単にはいかないんだよ。」といいつつ、話を聞いてみると、あまり工夫もしてない先生がいたりする。「あいつらは、こんな簡単なこともできないんだよなぁ。困ったもんだ。」「努力とか粘りが足りないんだな。僕らの頃に比べて。」なんて言っている。ちょっとむかっとくる。そりゃあ「教える」ということに関して、あなたにキャリアは及びませんよ。だけど、僕だって大学に通っていた4年間、塾講師のバイトを一生懸命やって、毎日高校生を教えてたんです。塾だから、年が近いから、ということもあって、わからないことは「そんなん言われてもわからんもん!!」ってハッキリと言われるし、どうやったらわかるようになるんやろう、いつも考えて教えてました。そうするとね、いろんなこと試しているうちに、学力の低い子には、そういう子に通じやすい言葉だったり、例えだったりがあって、それを工夫してるうちに、子どもの視点も変わってくるんです。「同じやり方でダメなら、やり方を変えてみる」ということを、子どもにも教えたかったし、自分もそうするようにしてました。そうしていくうちに、だんだんわかってくる、だんだん楽しくなってくる。そういうことが「学びの喜び」であり、それを教えるのが、教師の仕事なんじゃないですか?子どものせいにするんじゃなくて、自分の教え方を振り返ってみたらどうですか。と、本音が言いたい。だけど言えないときもある。愛情とか、思い入れがないと、本音もなかなか言えないもんだ。_______________________________________________________________________教育に携わる仕事をはじめてから、よく思い出す。「私な、英語めっちゃ嫌いやったけど、先生のお陰でちょっと好きになった」半年間、つきっきりで教えた子から言われた言葉。その子にとっては、何気ない一言だったんだと思うけど、僕にとっては、その電話口の声がずっと残っている。すごい大事なこと教えてもらったなと思う。「教える」仕事をすることで、「教えてもらう」。やっぱり教育の仕事好きやなぁと思う。
2005年07月04日
コメント(0)
-
結果は数字に表れる。
これから2週間は、校内研修会ラッシュ。この日は大好きな英語の先生がいる学校へ。事前に何度も電話で打ち合わせ。夜遅くにも、当日朝にも電話で話す。転勤でこの学校に来られた1年前は、いつもいつも不満を口にされていた。「教員の意識が低すぎる」「素質のある子どもが入ってきているのに、ちゃんと伸ばせていない」「学校としての責任を果たしていない」1時間も、2時間も、ずっとそんな話をしていた。だけど、不満を言うだけの人ではなかった。不満を言いつつも、ちゃんとやるべきことはやっていた。他の教科は成績が上がらなくても、英語だけは上がり続けていたし、先生が担任をしているクラスは一番成績が伸びていた。そうするうちに、ひとりふたりと味方が現れ、1年たつと味方の方が多くなっていた。一人の情熱で、少しずつでも学校は変わっていくんだと思った。校長を巻き込み、教頭を巻き込み、学年主任を巻き込み、いろんな人を動かして、少しずつ学校が変わっていく。それを目の前で見せてもらった。「自分ひとりの力では如何ともしがたいから。」と言っているうちは絶対に変わらない。どれだけ強い意志を持っているか。ひとりの強い意志さえあれば、組織は変わっていくのだと思った。___________________________________________________________________結果は数字に表れる。本当にわかりやすく表れる。ちゃんと行動した人には、それに報いる数字が、何もしなかった人にも、それに報いる数字が、残酷なほどにわかりやすく現れる。データを分析すればするほどそう思った。数字を見て、その背景を聞けば聞くほど、納得した。文法問題の数字が低くて、読解問題の数字が高い。前回の結果で文法が悪かったわけではないから、ひょっとして時間配分を先生から指示したのかなと思って聞いてみたら、やっぱりその通り。「大問1と2は9分以内が目標。2分オーバーしたら飛ばして次に進むこと。」その指示通り、生徒は解いた。結果もその通りに出た。ある熱心な先生が、「こういうデータは、あくまで単なる数字でしかないし、これだけで学校を語ろうとするのは間違っている。ただ、数字は本当に正直に表れる。だからこそ、自分たちがやってきたことの振り返りを、数字をもとにして行うことは、とても重要なことなんだ。」と言っていた。ちゃんと子どもの学力を伸ばせていない教員ほど、数字をちゃんと見ようとしない。「数字だけで何がわかる」と言い訳がましく言う。果ては、「この数字は信頼できるものなのか?」と数字にいちゃもんをつける。売れない営業マンも数字をちゃんと見ようとしない。「数字以外の部分も評価して欲しい」と言う。何故数字が出ないのか、行動と重ね合わせることもせずに、そう言う。学校も企業も本質は同じだ。数字そのものは、意味を持たない。数字を行動に重ね合わせて理解することで、初めて意味を持つのだと思った。___________________________________________________________________研修会が終わって、校長先生と話をした。そこで教えてもらった言葉。「子どもは泣いてもいい。だけど、親は泣いてはいけない。」大学入試は、自分の意志を貫き、高みを目指そうとすればするほど過酷だ。それに結果は○か×かしかない。だから、どんなにがんばっても結果が×になることもある。そうして、子どもがショックを受けて、泣くこともある。だけど、それは子どもにとってはいい経験だ。一生懸命やっても、うまくいかないことがある。自分が精一杯努力しても、まだ上がいる。泣くことで、そういうことをひとつひとつ理解していく。でも、最近は「親の方が先に泣いてしまう」と言う。「つらい経験をさせたくない」とか「見てられない」と言って、子どものチャレンジする気持ちを止めてしまう。そうして、結局子どもは「泣かないまま」大人になる。だから、社会人になって、いろんな壁を乗り越えられないで逃げてしまうのではなかろうか。自分が子どもを持つのはまだ先だろうけど、この言葉はちゃんと覚えておこうと思う。___________________________________________________________________研修会は無事に終わった。今までこの先生から依頼された研修会の中では、もっともうまくいった。何より自分がそういう感触をもてたし、先生もそう言ってくれた。今まで、なかなか思い通りいかなくて、もどかしい思いだったけど、今回は少しは今までの恩返しができた気がした。以前、顧問の先生に教えてもらった「子どもは闇の中を歩いている。その先に光を当てて、未来を見せてあげるのが教員の仕事だ。」という言葉を思い出し、先生方にも「未来を見せる」話ができたと思う。「いつも、汚れ役ばかりお願いしてごめんね。本来は校内でやるべきことなのに。でも、ありがとう。後は私たちの仕事だから。」そう言って送っていただいた。渡された紙袋の中には、バーバリーのハンカチと、チョコレートが入っていた。僕のハードワークを気遣ってのチョコレート。チョコレートの袋には『ストレス社会で戦うあなたに』と書いてあって笑えた。「数あるチョコレートの中から、あえてこれを選んだんだな」と思った。確かに疲れたけど、チョコレートではなく、この気遣いとユーモアで元気になった。
2005年07月01日
コメント(2)
全4件 (4件中 1-4件目)
1