2025年10月の記事
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その125): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-8
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンク「THE VIRGIN AND CHILD(聖母子像)」。・制作年代: 約1300–1320年・制作地: フランス、パリ・素材: 砂岩(Sandstone)・修復者: Henri Boutron により修復・収蔵番号: Museum no. A.21この像の幼子イエス像の多くの部分は失われていた。現在確認できる部分・右腕の一部:マリアの胸元あたりに小さな手が伸びています。これは幼子イエスの右手 (修復部位とされる)。・体の断片:マリアの右腕に抱かれる位置に塊のような残存部分がありますが、頭部や胴体の 輪郭は失われています。・頭部の欠損:パネル説明にあるように、イエスの上半身は後世の修復対象でしたが、 現存部分から見ると大きく損傷・欠落しているのがわかります。「THE VIRGIN AND CHILDAbout 1300–20Life-size sculptures of the Virgin and Child were common in the area around Parisinthe early 14th century. Later, they were highly sought after by collectors. This example has been considerably restored, probably just before it came to the V&A in 1911. The restored areas include the head and the right arm of the Virgin, and the upper part of Christ’s body. These are now marked with white lines.France,Paris Restored by Henri BoutronSandstoneMuseum no. A.2191」 【聖母子像1300年頃~1320年頃14世紀初頭のパリ周辺では、聖母子像の等身大彫刻が一般的でした。その後、これらはコレクターたちに非常に人気を博しました。本作も大規模に修復されており、おそらく1911年にV&A(ヴィクトリア&アルバート美術館)に収蔵される直前に修復が行われたと考えられます。修復箇所には、聖母の頭部と右腕、そしてキリストの上半身が含まれており、現在それらの部分は白い線で示されています。フランス、パリアンリ・ブートロンによる修復砂岩館蔵番号 A.2191】ここは仏教美術コーナーへの入口。「BUDDHISM(仏教)」そして「17,18,38」と部屋番号が記されていた。 「Mask of Bhairava」(バイラヴの仮面)。・題材: ヒンドゥー=仏教混淆世界に属する 守護神・憤怒尊の仮面または頭部装飾像・地域: ネパールまたはチベット・材質: 鍍金金属(おそらく銅合金に金メッキ)、宝石・ガラス象嵌・特徴: ・額に「第3の眼」を持ち、超越的な知恵を象徴。 ・王冠には小さな髑髏装飾(骸骨冠)。これは「死と輪廻を超える力」を意味する。・開口した口、牙をのぞかせる表情は「憤怒相(wrathful deity)」の典型。・耳飾りや光背に細かな装飾があり、ネパール工芸の高度な金工技術を示している。ピンボケで解読不能なのでネット情報を。「BhairavaDate: 17th century (made) — Malla period, NepalDescription: The worship of Bhairava, an angry, vengeful manifestation of Shiva, is still important in Nepal. Snakes form his earrings and encircle his neck, while skulls adorn his crown. His hair is of stylised flames. This large image was used in public worship. Alcohol would be poured through the mouth from the rear; in drinking it, devotees would receive blessings from the god.Materials: Repoussé copper with gilding and paint; reverse-painted rock crystal (red),carnelian and coloured glass (imitation of emeralds, turquoises and lapis lazuli[?])Dimensions: H. 68.6 cm; W. 63.5 cmCredit line / Acquisition: Purchased; Museum no. IM.172-1913.」【バイラヴ年代: 17世紀(制作)— ネパール、マッラ朝期解説: バイラヴはシヴァ神の怒りと復讐の化身で、ネパールでは今も重要な信仰対象です。耳飾りと首飾りは蛇で表され、冠には髑髏が飾られます。髪は炎状に様式化されています。この大型像は公共の礼拝で用いられ、背面から酒を流し入れて口から注ぎ出し、それを信者が飲むことで神の加護を受けると信じられていました。材質: 鍍金と彩色を施した打ち出し銅、裏面彩色のロッククリスタル(赤)、カーネリアン、着色ガラス(エメラルド・トルコ石・ラピスラズリの模造)寸法: 高さ 68.6 cm、幅 63.5 cm取得: 購入収蔵/館蔵番号 IM.172-1913】 これも入口近くにあった像。「大成就者 ヴィルーパ」「The Mahasiddha Virupa1403–24Virupa was one of the mahasiddhas or great accomplished beings, revered inTibetanBuddhism as a tantric master. This figure was produced at the imperialworkshops ofthe Emperor Yongle. The emperor Yongle’s Buddhist art often reflected Tibetan influence. This sculpture may have been a gift to a Tibetan Buddhist temple.ChinaGilt and cast brassLent by The Rt. Hon. Sir Robert H. S. M. Barlow Family Association CollectionMuseum no. IS. 24-1959」 【大成就者 ヴィルーパ1403–24年明王朝・永楽帝治世ヴィルーパは「大成就者(マハーシッダ)」のひとりで、チベット仏教において密教の大師として尊敬されました。この像は明の永楽帝の宮廷工房で制作されたものです。永楽帝時代の仏教美術はしばしばチベット的な影響を反映していました。この彫像もまた、チベット仏教寺院への贈り物であった可能性があります。中国鍍金鋳造の真鍮バーロウ卿家コレクション寄託館蔵番号 IS.24-1959】近づいて。像の意味・人物: ヴィルーパ(Virupa, 「歪んだ者」の意)はインド密教由来の伝説的大師。・奇跡: 「太陽を止めた」伝説で知られる。修行中に日没を拒み、右手を挙げて太陽を 止めたと伝えられる。・ポーズの意味: 像の右手を高く挙げる姿は、この「太陽停止の奇跡」を象徴。・文化的背景: 明代永楽帝はチベット仏教を保護し、多数の仏像や法具を制作して贈呈。 宮廷製の金銅仏は「中国風の技法」と「チベット的な図像」が融合した 独特の様式を示す。「仏教美術」展示エリアの導入パネル「Buddhist Art in AsiaBuddhism and its arts spread across Asia as the faith emerged.This map shows where the objects in these galleries were made.」 【アジアの仏教美術仏教とその美術は、信仰の拡大とともにアジア各地に広がりました。この地図は、これらのギャラリーに展示されている作品が作られた地域を示しています。】「THE ROBERT H. N. HO FAMILY FOUNDATION GALLERIES OF BUDDHIST ART何鴻毅家族基金佛教藝術館This is one of a series of galleries exploring Buddhism and its expression through art. The story continues nearby in Rooms 38 and 40, with The Bodhisattva Path and The Life of the Buddha, and in Room 47, located near the Cromwell Road Entrance, with The Buddha Image in Asia.The Tantric Path: Rapid EnlightenmentBetween 600 and 1000 AD, a new form of teaching evolved in India, known asVajrayana Buddhism or the Tantric (Diamond) Path. It drew on existing practicesin yoga, like breath control and reciting mantras, to create a rapid path toenlightenment. All Buddhists consider enlightenment to be the highest spiritual state, a being free ofrebirth. However, followers of the Tantric Path believe it’s possible toachieve enlightenment even within one lifetime, rather than over many, as in most traditionalMahayana Buddhist thought.During the first millennium, tantra spread from India throughout much of Asia. Tantric teachings were originally communicated in secret. They encouraged the use ofpowerful methods in Buddhism, like using ritualised sexual encounters to experience higher states of consciousness. Over time these teachings were reinterpreted for celibate monks.A key aspect of tantra involves imagining deities while meditating to identify with their enlightened qualities. The images in this room represent and contain the energy ofsuch deities.These galleries were made possible by The Robert H. N. Ho Family Foundation withfurther support from the DCMS/Wolfson Museums and Galleries Improvement Fund.」【ロバート H. N. ホー家族基金 仏教美術ギャラリー(何鴻毅家族基金佛教藝術館)このギャラリーは、仏教とその美術表現を探究するシリーズの一部です。展示は、近くの38室・40室の「菩薩の道と釈迦の生涯」、さらにクロムウェル・ロード入口近くの47室「アジアにおける仏陀のイメージ」へと続きます。密教の道:急速な悟り西暦600〜1000年の間、インドで新しい教えが発展しました。これは金剛乗仏教、あるいは密教(タントラの道)として知られています。この道はヨーガの既存の修行法(呼吸法、マントラの詠唱など)を取り入れ、「迅速に悟りに至る道」を目指しました。仏教徒は皆、悟りを「輪廻から解放された最高の精神状態」と考えますが、密教の修行者たちは、従来の大乗仏教が考える「多生多劫の修行」を経ることなく、一生のうちに悟りを得ることが可能だと信じました。1千年紀の間に、タントラはインドからアジア各地に広がりました。タントラの教えは当初、秘儀として伝えられました。その中には、意識の高次状態を体験するために性的儀礼を用いるなど、強力で実践的な手法が含まれていました。その後、こうした教えは独身修行者(僧侶)向けに再解釈されました。タントラの重要な側面は、瞑想中に神々の姿を観想し、その悟りの特質と一体化することです。この展示室の仏像や仏画は、そのような神々を表し、そのエネルギーを宿すものです。このギャラリーは、ロバート H. N. ホー家族基金の支援により実現し、DCMS/ウォルフソン美術館・ギャラリー改良基金の協力を受けています。】 「The Bodhisattva Avalokiteshvara (Padmapani)・菩薩 アヴァローキテーシュヴァラ(蓮華手観音・パドマパーニ)」 ・姿態 ・しなやかに腰をひねった 三曲法(トリバンガ) の立ち姿。 ・左手は下げて施無畏印(恐れを取り除く印)に近い形を示し、右手はかつて蓮の茎を 持っていた痕跡を示します。・装飾 ・冠には多数の宝石(ターコイズ、サファイア、ガーネット等)が嵌め込まれている。 ・大きな円形の耳飾り、胸飾り、腕輪、腰帯が精緻に表現。 ・金銅に鍍金を施し、宝石で豪華に飾るのは ネワール族の職人(ネパール工房) に典型的な様式。・表情 ・半眼で静かに慈悲を湛えた表情。 ・眉間に白毫が表現され、観音の神格を強調。下記写真はネットから。歴史的背景・時代: 1300–1400年頃、ネパールの マッラ朝時代。・依頼者: チベットの仏教信徒のために制作されたと記録されています。・意義: アヴァローキテーシュヴァラは「慈悲の仏」として、特にチベット仏教で広く信仰され、 ネパール職人の高度な金工技術を通じて供養像が作られました。象徴的意味・Padmapani(蓮華手観音) は、右手に「蓮華(padma)」を持つ観音の姿を示す。・蓮は「泥中から咲きながら汚れに染まらない」ことから 清浄・慈悲・悟りの象徴。・この像は、信徒が観想修行を行い、観音の慈悲と一体化するための対象でもありました。「The Bodhisattva Avalokiteshvara (Padmapani)1300–1400Malla periodPadmapani means ‘Lotus-holder’. This figure once clasped the stem of a flowering lotus or padma, a symbol of spiritual purity. Padmapani is an important manifestation of Avalokiteshvara, the most widely worshipped of all bodhisattvas. Nepalese sculptors made the figure for Tibetan patrons.NepalGilded copper with precious and semi-precious stonesPurchased in 1909 from Major L. W. F. Hall, Indian Political Service, Central andKashmir,who found it in Lhasa, Tibet. It had been commissioned by Tibetan patrons and madeby Newar sculptors in Nepal.Museum no. IM. 39-1909」 【菩薩 アヴァローキテーシュヴァラ(蓮華手観音・パドマパーニ)1300–1400年マッラ朝時代(ネパール)「パドマパーニ」とは「蓮華を持つ者」を意味します。この像はかつて、精神的純潔の象徴である開花した蓮華(パドマ)の茎を手にしていました。パドマパーニは観音菩薩(アヴァローキテーシュヴァラ)の重要な顕現形のひとつであり、全菩薩の中で最も広く信仰されています。この像は、ネパールの職人がチベットの信徒のために制作したものです。ネパール鍍金銅製、宝石・半貴石を嵌入1909年にL.W.F.ホール少佐(インド政治局、カシミール・中央アジア担当)がチベットのラサで入手し、その後購入された。像はチベットの依頼者のためにネワール族の彫刻家によってネパールで制作されたもの。館蔵番号 IM.39-1909】「【弥勒菩薩 (Maitreya)」像。 「The Bodhisattva Maitreya100–400Ancient GandharaThe name Maitreya is derived from the Sanskrit maitri meaning ‘loving kindness’. Maitreya is the bodhisattva who, it is believed, will become the next Buddha on earth. Until that time, he resides in the heaven known as Tushita. He is shown dressed in princely attire, but also with signs of potential Buddhahood, including his raised hair-knot (ushnisha) and forehead mark (urna).North-West PakistanSchistMuseum no. IS.100-1972」【弥勒菩薩 (Maitreya)100–400年古代ガンダーラ「マイトレーヤ」という名は、サンスクリット語 maitri(慈しみ、慈愛)に由来します。弥勒菩薩は、将来この地上に現れて次の仏陀となると信じられている菩薩です。それまでの間、弥勒は「兜率天(Tushita)」と呼ばれる天界に住むとされています。この像では、王族の装いを身につけつつも、将来の仏陀であることを示す特徴を備えています。その特徴には、頭上の高い髻(ushnisha:肉髻)や、額の白毫(urna)が含まれます。所在地:パキスタン北西部材質:片岩(schist)館蔵番号:IS.100-1972】 V&A美術館の「菩薩の道(The Bodhisattva Path)」解説パネル。「THE ROBERT H. N. HO FAMILY FOUNDATION GALLERIES OF BUDDHIST ART何鴻毅家族基金佛教藝術館This is one of a series of galleries exploring Buddhism and its expression through art. The story continues nearby in Rooms 17 and 40, with The Tantric Path and The Life of the Buddha, and in Room 47, located near the Cromwell Road Entrance, with TheBuddha Image in Asia.The Bodhisattva Path: The Great WayThe word ‘bodhisattva’ was originally used to describe the Buddha before he reached enlightenment. As new teachings evolved from the 1st century BC onwards, thetermtook on a deeper and wider meaning. It began to be used for those who aimto reach enlightenment, the highest spiritual state, for the sake of others. Bodhisattvasdo this to help people escape from suffering and achieve enlightenment for themselves.A selfless way such as this contrasts with earlier teachings where enlightenment wasseen as more of a personal pursuit. The Bodhisattva Path is known in Sanskrit as Mahayana, or the ‘Great Way’, offering a new approach to life and Buddhahood. Over the first millennium it inspired a wave of art and architecture throughout Asia, with the concept of the bodhisattva at their core.In Buddhist art, bodhisattvas are usually shown wearing princely jewellery and robesofIndian royalty. Their graceful beauty is intended to mirror an inner grace and compassion.These galleries were made possible by The Robert H. N. Ho Family Foundation withfurther support from the DCMS/Wolfson Museums and Galleries Improvement Fund.」 【ロバート H. N. ホー家族基金 仏教美術ギャラリー(何鴻毅家族基金佛教藝術館)このギャラリーは、仏教とその美術表現を探究するシリーズの一部です。展示は、近くの17室・40室「密教の道と釈迦の生涯」、さらにクロムウェル・ロード入口近くの47室「アジアにおける仏陀のイメージ」へと続きます。菩薩の道:大いなる道「菩薩」という言葉は、もともと仏陀が悟りを得る前の段階を指すものでした。しかし紀元前1世紀以降、新しい教えが発展すると、この語はより深く広い意味を持つようになり、他者を救済するために悟り(最高の精神的境地)を目指す存在を指すようになりました。菩薩は、人々が苦しみから解放され、自ら悟りを得られるように助ける存在です。このような「利他的な道」は、それ以前の「悟りを個人的追求と見る考え方」とは対照的です。サンスクリット語で「大いなる道(Mahayana/大乗)」と呼ばれる菩薩の道は、新しい人生観と成仏の道を提示しました。1千年紀を通じてアジア全域で美術と建築に大きな影響を与え、その中心には常に「菩薩」の概念がありました。仏教美術において菩薩は、しばしばインドの王侯風の装飾や衣装を身につけて表されます。その優雅な美しさは、内なる慈悲と品位を映し出すものとされています。このギャラリーはロバート H. N. ホー家族基金の協力により実現し、さらにDCMS/ウォルフソン美術館・ギャラリー改良基金の支援を受けています。】The Blavatnik Hallからロンドンのヴィクトリア&アルバート美術館(Victoria and Albert Museum, V&A) の外観を再び。・左側の建物 赤レンガと白い石を組み合わせたヴィクトリア朝様式のファサード。ドーム型の塔屋が目立ちます。・中央の広い階段 近年整備された現代的なエントランスアプローチ(Exhibition Road Entrance)。 滑らかなステンレスの手すりが特徴的です。・右側の建物 古典主義的な正面玄関で、三角破風(ペディメント)と円柱が並ぶ造り。・屋上の旗 レインボー・プライド旗(LGBTQ+プライド旗)。6色版(上から赤・橙・黄・緑・青・紫)。 V&AではPride Month(主に6月)や関連イベントの期間に、連帯と包摂の意思表示として 掲揚されることがよくあるようだ。現在地は■Exhibition Road Entrance(エキシビション・ロード入口)側の中庭=Sackler Courtyard。グラウンドフロア(Floor 0) への案内表示。正面の階段を上がった先に「Medieval & Renaissance Galleries(中世・ルネサンス ギャラリー)」があることを示していた。サインポールには「0」と階層マップが描かれており、各階の展示ゾーンを俯瞰できるようになっていた。正面のガラス扉の上に「BRITAIN (1500–1760)」と表示されていた。これは ブリテン・ギャラリー(英国 1500–1760) の入口。この展示室は、チューダー朝からジョージ王朝初期にかけてのイギリス美術・工芸を扱っており、家具、インテリア、銀器、陶磁器、肖像画などを通して「大英帝国形成前夜」の文化を紹介するエリア。背後に金色の装飾(おそらくバロック様式の室内装飾や家具の一部)が見えていた。・チューダー朝 (Henry VIII 以降) 宮廷文化の影響下での家具・室内装飾。ルネサンス様式の導入。・ステュアート朝 (17世紀) 王政復古期の豪華なバロック様式や、銀器・タペストリー。・18世紀(ジョージ王朝初期) ロココ風の室内装飾や社交文化。 家具デザイナー(ウィリアム・ケント など)の作品も含まれます。「Britain 1500–1760 ギャラリー」の内部。V&A「Britain 1500–1760」ギャラリーの肖像画と工芸展示の壁面、そしてそこから繋がる18世紀の華麗なインテリア復元室。・金色に輝く非常に華麗なロココ様式の鏡(giltwood mirror)。・繊細な曲線装飾(スクロール)、貝殻モチーフ、葉飾り、頂部の立体的な装飾などが見られ、 18世紀中葉のイギリス・ロココ家具の典型的なデザイン。ネットから。この鏡は 1750–1760年頃のロンドン製ロココ様式金箔鏡 で、シノワズリの影響を強く受けています。もともと 北ヨークシャーの邸宅「Hinalaby Hall」 のために作られたもので、空想的な東洋モチーフとロココの曲線装飾を融合させた典型的な作例 と。「14 MIRROR1750–1760Chinese motifs were fashionable in Britain during the 1750s, when the Rococo stylewas at its peak. Craftsmen frequently combined Rococo scrollwork with fanciful Chinese figures, birds and animals. Carved and gilded wood Made for Hinalaby Hall, North Yorkshire Probably made in London Bequeathed by the late C.E. Wilson Todd Museum no. W.73-1939」【14 鏡1750–1760中国趣味のモチーフは、ロココ様式が最盛期を迎えた1750年代のイギリスで流行しました。職人たちはしばしば、ロココ様式の渦巻き装飾と、空想的な中国風の人物・鳥・動物の意匠を組み合わせました。材質:彫刻および金箔を施した木製制作地:ノース・ヨークシャー州 Hinalaby Hall のために製作おそらく ロンドン製作由来:C.E. Wilson Todd 氏の遺贈博物館番号:W.73-1939】 「STYLESChinoiserie1745–1760Chinoiserie was a form of decoration fashionable between 1745 and 1760. Designers were inspired by the exotic imports and fantasies of the ‘East’, porcelain and lacquer that had been imported to Europe from East Asia since the early 16th century. These imports, many of which were produced specifically for Europeans, stimulated Rococo designers to imitate and adapt oriental motifs and ornaments for a wide variety of objects. They did not distinguish between what was Chinese, Japanese or Indian, but combined motifs such as figures in Japanese dress, stylised pavilions, birds and flowers to create an exotic fantasy world. Chinoiserie appealed particularly to women. It added a new dimension to British interiors,with a lighter and more colourful approach to decoration and design.」 【スタイルシノワズリ 1745–1760シノワズリは、1745年から1760年の間に流行した装飾様式でした。デザイナーたちは「東洋」の異国的な輸入品や幻想世界に触発されました。磁器や漆器といった東アジアから16世紀初頭以来ヨーロッパへ輸入されていた品々がその源でした。これらの輸入品の多くはヨーロッパ人向けに特別に生産されたもので、ロココのデザイナーたちはそれを模倣・翻案し、さまざまな対象物に東洋風のモチーフや装飾を取り入れました。彼らは中国・日本・インドの要素を区別することなく、日本風の衣装を着た人物、様式化された楼閣、鳥や花といったモチーフを組み合わせ、異国的な幻想世界を作り出したのです。シノワズリは特に女性に人気がありました。それは英国のインテリアに新しい次元をもたらし、より軽やかで色彩豊かな装飾とデザインのアプローチを与えました。】華麗な「室内装飾復元展示」への入口。入口の装飾・扉の上部は金箔で華やかに装飾されたロココ様式のアーチ。・両脇には花綱(ガーランド)、中央には壺(花瓶)のモチーフ、さらに左右にプットー (天使の子供像)が飾られています。・中央のメダリオンには人物の胸像風レリーフがはめ込まれており、まさに18世紀ヨーロッパ 貴族邸宅の「華麗な装飾玄関口」を再現しています。・奥の部屋 見えるのは 18世紀の邸宅インテリアを移設・復元した部屋。 壁一面に金箔装飾のレリーフ(アラベスク文様、花綱モチーフなど)が施され、ロココ的な 優雅さを示していた。 シャンデリア風の燭台照明が設置され、当時の宮殿・邸宅の雰囲気をそのまま体感できる空間。「Britain 1500–1760」ギャラリー内に再現された18世紀の豪華な部屋(Period Room)。V&Aへの移設ノーフォーク・ハウス自体は 1938年に解体されたが、この音楽室の内装は保存され、1942年にV&Aに移設展示された。現在では 18世紀ロンドンのロココ室内装飾を代表する空間として、来館者が実際に「当時の邸宅に入った感覚」を味わえるようになっている。時代背景・1750年前後、ロココ様式(Rococo)がイギリス上流階級の邸宅で流行した時代のインテリア。・実際の邸宅から移設された「サロン(応接間)」や「ダイニングルーム」である可能性が高い。装飾様式・壁や天井は白地に金箔装飾(gilt stucco)で埋め尽くされ、ロココ特有の軽やかで 優雅な曲線模様。・鏡(オーバーマントル・ミラー) が暖炉の上に配置され、光を反射させて部屋全体を 広く明るく見せる工夫。・壁には燭台(シャンデリア型ウォールライト)が取り付けられ、蝋燭の光で金箔が きらめくよう設計されている。「ノーフォーク・ハウスの音楽室 (Norfolk House Music Room, 1750年代) の一部、暖炉とオーバーマントル・ミラー周辺を正面から。・暖炉 (fireplace) ・大理石製で、比較的シンプルな形状。 ・暖炉の中には装飾用の壺が置かれていた。 ・実際には暖炉の上部が視覚的な焦点となるように設計されており、炎そのものよりも 「鏡と装飾の反射効果」を楽しむ空間。・オーバーマントル・ミラー (Overmantel mirror) ・暖炉上に据えられた大きな鏡。 ・金箔のスクロール装飾(渦巻模様)、葉飾り、中央には羽ばたく鳥をあしらった モチーフが。 ・部屋の光(燭台や窓からの自然光)を反射して、幻想的で広がりのある空間を演出。・燭台 (wall sconces) ・鏡の両脇に取り付けられたキャンドル用ブラケット。 ・燭台の炎が鏡に映り込み、室内の輝きを倍加させる仕掛け。・壁面装飾 (stucco & giltwork) ・白地に金箔で植物文様が配置され、左右対称のデザイン。 ・フランス・ロココの影響を色濃く受けているが、イギリスらしくやや重厚さを保っていた。ギャラリーに再現展示されている有名な 「ノーフォーク・ハウスの音楽室 (The Norfolk House Music Room)」。デザインの特徴・ロココ様式(Rococo Style) の典型例。 ・白地に金箔のスタッコ装飾。 ・壁と天井全面に施された優雅な曲線と花綱文様。 ・大きな鏡(pier glasses)が光を反射し、部屋をより広く、豪華に演出。・グリーンのドレープカーテン ・金と白の華やかな装飾に深緑の布を合わせ、上品でコントラストの効いた色彩感覚を示す。「ノーフォーク・ハウス音楽室 (Norfolk House Music Room)」のカーテン について説明「The CurtainsThese reproduction curtains have been made in greendamask, as listed in the 1750sinventory. The silk waswoven on hand-looms in a large stylised floral designthat wasused widely in the 1750s. They have been madeas 18th-century curtains would have been with only a very slight fullness across the width. The silk fringesand tassels have been based on 18th-century examples,and the curtains are lined in a lightweight woolcalledtammy, that was often mentioned as a curtain lining in 18th-century inventories.The pulley bands from which the curtains hang are also made to an authentic patternwith pulley wheels of turned hardwood over which the silk cords run to allow thecurtains to be drawn up. The brass cloak pins on which the curtain ends are wound arebased on detail from a painting dated 1761, by Francis Cotes of his fellow artist,Paul Sandby, from the collections of Tate Britain.The reinstallation and restoration of the Norfolk House Music Room were generouslysupported by The Friends of the V&A.」 「カーテンこの復元カーテンは、1750年代の目録に記載されている通り、緑のダマスク織で作られています。絹は手織り機で織られたもので、1750年代に広く使われた大きな様式化された花模様のデザインです。18世紀のカーテンがそうであったように、幅全体にほんのわずかなゆとりだけを持たせて仕立てられています。絹の房飾りやタッセルも18世紀の実例に基づいて作られています。カーテンの裏地には「タミー (tammy)」と呼ばれる軽量のウール地が使われており、18世紀の目録でもしばしばカーテンの裏地として記録されています。カーテンを吊るしている滑車用のバンドも本格的な様式に基づき、堅木を挽いて作られた滑車の輪に絹のコードを通して、カーテンを引き上げられるようになっています。カーテン端を巻き付けている真鍮製のフックは、1761年にフランシス・コーツが同僚の画家ポール・サンドビーを描いた絵画の細部をもとにしています(テート・ブリテン蔵)。ノーフォーク・ハウス音楽室の再設置と修復は、V&A友の会(The Friends of the V&A)の寛大な支援によって行われました。」 大きな鏡(pier glasses)に近づいて。天井にも金彩レリーフが施され、視線を上へと導く。・武具のトロフィー(Trophée d’armes) ・中央:盾(メデューサの頭部が装飾されているように見えます) ・周囲:槍、矢筒、兜、旗など軍事的シンボル ・下部:人体の胸郭(筋肉を表現した甲冑または古代彫刻を模した 「解剖学的なトルソ」モチーフ)・装飾のスタイル ・これは18世紀ロココ~新古典主義に見られる「古代的武具を束ねた装飾 (武勲を讃える象徴)」です。 ・「Trophée d’armes(武勲のトロフィー)」と呼ばれ、勝利・勇気・高貴な精神を示す意匠。 ・当時の貴族邸宅では、家の権威・勇敢さ・教養を象徴するモチーフとして壁や天井に 用いられました。「Taking Tea」展示コーナー の一部。1.中央のガラスケース(棚)・上段:ティーポット ・紫砂壺(中国・宜興窯の赤褐色の急須)や磁器製のティーポット。 ・中国輸入品と、それを模倣したイギリス製(チェルシー、ウォルサム、ウースター窯など) の作品が並んでいた。・中段:ティーキャディ(茶葉入れ) ・金属製・磁器製の小型容器。茶葉は非常に高価だったため、施錠できるティーキャディに 保管された。 ・金彩が施された豪華なものは、所有者の富を象徴。・下段:銀器・陶器類 ・銀製のキャディや茶匙、磁器製の小物。 ・イギリス製のシノワズリ装飾も見られます。2.下方のテーブル上のセット ・赤地に金彩と人物文様が描かれたティーカップとソーサーのセット。 ・これは中国景徳鎮窯の輸出磁器(famille rose, 粉彩)や、それを模倣したイギリスの陶器 であろう。 ・テーブルごと展示され、実際の「ティータイム」の場面を連想させる構成。3.左右の絵画 ・左側の肖像画:女性がティーカップを手にしており、「お茶を飲む習慣」が上流階級の 嗜みであったことを表現。 ・右側のグループ肖像画:家族や仲間でのティータイム風景を描いたもの。「ティーサービス(茶器セット)」についての解説パネル「This showy tea service was produced by the Chelsea porcelain factory in Londonbetween 1750 and 1759. Additional pieces were made to allow the same service to be used for the serving ofcoffee. Tea tables were often highly decorative, and this one shows bas-relief decoration that was the speciality of a German-born cabinet-maker, Frederick Hintz.」 【この華やかなティーサービスは、1750年から1759年の間にロンドンのチェルシー磁器工場で製作されました。追加の部品も作られており、同じセットをコーヒーの供給にも使用できるようになっていました。ティーテーブルはしばしば非常に装飾的であり、この展示のものは、ドイツ生まれの家具職人フレデリック・ヒンツ (Frederick Hintz) が得意とした浅浮彫装飾を示しています。】・チェルシー窯 (Chelsea porcelain factory) ・1740年代にロンドンで創設された英国初期の磁器工房のひとつ。 ・フランスのセーヴルやドイツのマイセンに倣い、豪華で色彩豊かな磁器を製作。 ・王侯貴族や富裕層の間で大変人気があり、ティーセットやフィギュリンで知られている。・フレデリック・ヒンツ (Frederick Hintz) ・ドイツ生まれでイギリスに渡った家具職人。 ・浅浮彫(bas-relief)の装飾技術を得意とし、18世紀ロンドンで活躍。 ・特に茶器と組み合わされる「装飾的ティーテーブル」の制作で有名。「Taking Tea 1710–1760Tea was first imported from China in the mid-17th century. Tea drinking becameincreasingly popular, though doctors and moralists cautioned against the habit.Hightaxes ensured that tea remained expensive until the end of the 18th century.In polite households tea was served in the drawing room after dinner; which inthe 18th century was eaten in the early afternoon. The mistress of the housepresided over the tea table, making and serving the tea herself.Tea drinking demanded new furniture and equipment. At first, tea was served in theChinese manner (without milk), in wares imported from China. The Chinese shapes and decoration were soon copied by British manufacturers, who also began developingtheir own designs.」【お茶を楽しむ習慣 1710–1760茶は17世紀半ばに初めて中国から輸入されました。茶を飲む習慣はますます人気を博しましたが、医師や道徳家たちはその習慣に警告を発しました。高額な税金のため、18世紀末まで茶は依然として高価なままでした。上流家庭では、18世紀には昼過ぎにとる食事(ディナー)の後、応接室でお茶が供されました。家の女主人がティーテーブルの主宰を務め、自らお茶を淹れ、客に振る舞いました。お茶を飲むことは新しい家具や器具を必要としました。最初は中国風(ミルクなし)で、中国から輸入された器で供されました。これらの中国風の器形や装飾はすぐにイギリスの製造業者によって模倣され、さらに独自のデザイン開発も進められるようになりました。】 「Britain 1500–1760」ギャラリー内のファッション展示の一角。1.左のドレス(実物展示)・18世紀半ばの女性用「ローブ・ア・ラ・フランセーズ (Robe à la Française)」。・背中に「ワトー・プリーツ」と呼ばれるひだが流れるのが特徴で、豪華なブロケード (絹織物)に花模様が織り込まれていた。・上流階級女性の社交場(舞踏会やサロン)で着用された。2.右の肖像画・同時代の女性が、ドレスを着て描かれた肖像画。・広がったスカート(パニエ=脇に骨組みを入れて横幅を出す下着構造)が特徴的。・実際のドレスと絵画を並置することで、「美術作品に描かれたファッションと実物」を 直接比較できる展示になっていた。3.右下の靴・18世紀の女性用シルクシューズ。・ヒールが低めで、織物や刺繍が施され、ドレスとコーディネートされた豪華な履物。ギャラリー内に展示されている 18世紀のシルク織物サンプル のコーナー。・ガラスケースの中には、大判の布(ブロケードやダマスクなどの絹織物) が 複数掛けられていた。・多くは 花模様(花綱・花束・自然主義的な植物) をテーマとしたデザインで、ロココ様式の 色彩感覚を反映。・背景色はクリーム、淡青、金、ピンクなどで、鮮やかな彩色糸を使った織りが特徴。・これらの布は、18世紀の ドレス(ローブ・ア・ラ・フランセーズなど)や男性用ジャケット (ジャストコール) に仕立てられる前段階の「織物サンプル」として展示されていた。ピンボケであったが、見出し部分から 「Anna Maria Garthwaite」 に関する解説パネル。ヴィクトリア&アルバート博物館 (V&A, London) の館内にある フロア案内サイン の一部で、数字 「2」 が示すのは 2階(Floor 2) の展示エリア。V&Aの2階(Gallery Level 2)には、主に以下のような展示があるのだ と。・British Galleries (1600–1900 の一部) – イギリスの家具、インテリア、装飾美術・Theatre & Performance – 舞台芸術・衣装デザイン・Ceramics – 世界の陶磁器コレクション(特にヨーロッパ陶磁器)・Furniture, Textiles and Fashion – 家具やテキスタイルの展示・Architecture – 建築模型・図面「Design 1900–Now(デザイン 1900年~現代)」ギャラリーの入口。「Design 1900–Now」ギャラリー の入口近くにある解説パネル。特に 「Rapid Response Collecting(ラピッド・レスポンス・コレクティング)」 という仕組みについて説明。「Design 1900–NowHow people live, work, travel, consume and communicate have changed inextraordinary ways since 1900. Designed objects help us understand these changes.Through six major themes, each taking a period of time as a starting point, thisgalleryexplores how design has responded to the big issues people face. It looksat design as a tool for understanding the way we live together, Design 1900–Now aims to tell a story of design and society that is broad, internationaland inclusive. This is an ongoing task as museum collections are shaped by thepriorities of those who create them. In the 20th century, collecting at the V&A mostlyfocused on the work of designers in highly industrialised countries. Today, we areworking to reflect our globalised world in how and what we collect. We look forwardto adding new acquisitions to the displays and welcome your views and ideas.#design1900now」【デザイン 1900–現在人々の暮らし方、働き方、移動、消費、そしてコミュニケーションの方法は、1900年以来、驚くほど大きな変化を遂げてきました。デザインされたオブジェクトは、こうした変化を理解する手助けとなります。このギャラリーは6つの主要テーマを設け、それぞれの時代を起点に、デザインが人々の直面する大きな課題にどのように応えてきたかを探ります。デザインを「私たちの共同生活を理解するための道具」として捉え、過去・現在・未来についての問いを投げかけます。「デザイン 1900–現在」は、幅広く、国際的で、包括的なデザインと社会の物語を語ることを目指しています。博物館のコレクションは、その創設者たちの優先事項によって形作られるため、これは継続的な取り組みです。20世紀においてV&Aの収集は主に工業化の進んだ国々のデザイナー作品に焦点を当てていましたが、今日では「グローバル化した世界」を反映するように収集対象を広げています。今後も新しい収蔵品を展示に加えていくことを楽しみにしており、来館者の意見やアイデアも歓迎します。#design1900now】 「RAPID RESPONSE COLLECTINGRapid Response Collecting enables the museum to collect objects in direct responseto important moments in the recent history of design. All are immediately put on display.Design is a mirror to society and these objects are evidence of social, political,technological and economic change happening now. Rapid Response Collecting showsthat objects hold significance beyond their sometimes modest material value.You can see Rapid Response Collecting throughout Design 1900–Now. Check the plan for locations. Objects on display will change as we collect new things and the dates featured alongside them mark when they entered the V&A.#rapidresponsecollecting」 【ラピッド・レスポンス・コレクティング「ラピッド・レスポンス・コレクティング」は、近年のデザイン史における重要な瞬間に直接対応して、オブジェクトを収集する仕組みです。収集された品はすぐに展示されます。デザインは社会の鏡であり、これらのオブジェクトは現在進行中の社会的・政治的・技術的・経済的変化の証拠です。ラピッド・レスポンス・コレクティングは、物が必ずしも素材的価値に比例せず、より大きな意味を持つことを示しています。この取り組みは「デザイン 1900–現在」の展示全体で見ることができます。館内マップで展示場所を確認してください。展示品は新しい収蔵品が加わるたびに入れ替わり、ラベルに記された日付は、それらがV&Aに収蔵された時点を示しています。#rapidresponsecollecting】V&Aの「Rapid Response Collecting」展示で、日付 07.03.2023 と記された展示品。展示対象: 「Sexual and Reproductive Health App(性と生殖に関する健康アプリ)」展示日付: 2023年3月7日展示物:・スマートフォンとタブレットに表示されたアプリ画面・アイコンは避妊・妊娠・健康に関連するイラストを示していたこの展示は 「デジタル時代の性と生殖の健康に関する新しいデザイン」 を例として取り上げ、デザインが 社会課題や日常生活の変化にどう関与しているかを示すもの。「07.03.2023Sexual and Reproductive Health AppOn 3 May 2022 news leaked that the US Supreme Court intended to overturnthe 1973 landmark ruling, Roe v. Wade, which legalised abortion across the United States.On 24 June 2022 the decision came into effect, leaving individual statesto restrict access to abortion. Many have already initiated new restrictions or have banned it altogether.In response, privacy experts raised concerns that period tracking and sexual health apps, which store data remotely, could be used to monitor and apprehend those seeking an abortion.Euki rose to prominence because it is designed to put privacy first. Created in 2019by Women Helping Women and Reproductive Health, the app anonymises all data, and ensures nothing is stored remotely. Other protective measures include an auto-delete feature should a device fall into the wrong hands, and users can set PIN codes to access the app.Euki, version 22019Created by Women Help Women: Helping Women and Reproductive HealthDesigned by the NGO Women Help WomenMuseum no. CD.27:1 to 3-2023」【07.03.2023性と生殖の健康アプリ2022年5月3日、アメリカ合衆国最高裁判所が1973年の画期的判決「ロー対ウェイド事件(Roe v. Wade)」を覆す意向であるというニュースが流れました。この判決は全米で人工妊娠中絶を合法化したものでした。2022年6月24日、その決定が正式に発効し、中絶の可否は各州に委ねられました。すでに多くの州が新しい規制を導入したり、全面的に禁止したりしています。これを受けて、プライバシー専門家たちは、生理周期や性の健康を記録するアプリがリモートでデータを保存することにより、中絶を求める人々を監視・摘発するために利用されかねないという懸念を示しました。そこで注目を集めたのが 「Euki」 です。このアプリはプライバシーを最優先に設計されています。2019年に Women Help Women(女性を助ける女性たち) というNGOによって開発され、すべてのデータを匿名化し、リモートに保存されないようにしています。その他の保護機能として、デバイスが他人の手に渡った場合に自動削除される仕組みや、ユーザーがPINコードを設定してアクセスを制御する機能なども備えています。】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.31
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その124): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-7
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクロンドンの ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)の見学を続ける。有名な自動仕掛けの彫刻 「Tipu’s Tiger(ティプーの虎)」。・制作地:インド、マイソール王国(南インド、カルナータカ州)・制作年代:1793年頃・素材:木製・彩色、内部に金属の自動仕掛け・サイズ:高さ約71cm、長さ約173cm虎がイギリス兵士に襲いかかっている様子を立体的に表現。・内部にはオルガン式の仕掛け👈️リンクが組み込まれており、ハンドルを回すと 「兵士の悲鳴」と「虎の咆哮」に似た音が同時に鳴る。さらに鍵盤を操作して 音楽を奏でることも可能 と。「“Tippoo’s Tiger”Tipu Sultan was killed when the East India Company army stormed Seringapatam in 1799. The soldiers looted the city and parts of the palace. Order was restored aftertwo days by hanging and flogging some of the looters. As was usual, the royal treasury was then divided up between the army.The wooden tiger with an organ inside its body was discovered in the palace’s musicroom and shipped to London. As “Tippoo’s Tiger” it became one of the most popularexhibits in the Company’s new museum. When visitors turned the handle at the side, noises were produced that supposedly imitated the European victim’s dying wails of agony. The tiger came to South Kensington when the Indian Museum’s collection was split up in 1879.」 【「ティプーの虎」1799年、イースト・インディア会社の軍がシュリーランガパトナム(セリンガパタム)を攻撃した際、ティプー・スルタンは戦死しました。兵士たちは市街と王宮の一部を略奪しました。二日後、掠奪者の一部を絞首刑や鞭打ちに処して秩序は回復されました。慣例どおり、王室の財宝は軍隊の間で分配されました木製の虎(内部にオルガンを仕込んだもの)は宮殿の音楽室で発見され、ロンドンへ送られました。「ティプーの虎」として、それは東インド会社の新しい博物館でもっとも人気のある展示のひとつとなりました。側面のハンドルを回すと、ヨーロッパ人犠牲者の断末魔の叫びを模した音が鳴る仕掛けでした。1879年、インド博物館のコレクションが分割された際に、この虎はサウス・ケンジントン(現在のV&A)へ移されました。】Truth and Falsehood1857–66Along with Valour and Cowardice displayed nearby, these are full-size models fortwo bronze allegorical sculptures for a monument to the Duke of Wellington. Here, Truth tears out the double tongue of Falsehood and pushes aside the mask concealinghis grotesque features. His serpent-like tails are exposed beneath the drapery.LondonPlasterCompleted memorial to the Duke of Wellington (1769–1852) in St Paul’s Cathedral, LondonMuseum no. 3234-1876」 【アルフレッド・スティーヴィーヴェンス(1817–1875)《真実と虚偽》1857–66年近くに展示されている《勇気(Valour)》と《臆病(Cowardice)》とともに、これはウェリントン公爵記念碑のための寓意的なブロンズ彫刻2点の原寸モデルです。ここでは「真実」が「虚偽」の二枚舌を引き抜き、彼の醜悪な顔を覆っていた仮面を押しのけています。蛇のような尾は衣の下から露出しています。ロンドン石膏ロンドン、セント・ポール大聖堂にあるウェリントン公爵(1769–1852)記念碑のために制作収蔵番号:3234-1876】Valour and Cowardice(勇気と臆病)この像もアルフレッド・スティーヴィーヴェンス (Alfred Stevens, 1817–1875) の作品で、先ほどの 「Truth and Falsehood(真実と虚偽)」と対をなす寓意彫刻である と。・中央の女性像は「勇気(Valour)」を象徴。兜をかぶり、盾を構えた威厳ある姿で表現。・その下に押さえつけられている男性像が「臆病(Cowardice)」で、身をよじり顔を 背けている様子。・「勇気」が「臆病」を制圧するという寓意を、強烈な対比で表しているのだ と。「Alfred Stevens (1817–75)Valour and Cowardice1857–66Along with Truth and Falsehood displayed nearby, these are full-size models for two bronze allegorical sculptures for a monument to the Duke of Wellington. Indebted to the powerful figures of Michelangelo, these pieces also influenced thenext generation of artists. Stevens devoted much of his career to this monument but sadly did not live to see it installed.LondonPlasterCompleted memorial to the Duke of Wellington (1769–1852) in St Paul’s Cathedral, LondonMuseum no. 3218-1878」 【アルフレッド・スティーヴィーヴェンス(1817–1875)《勇気と臆病》1857–66年近くに展示されている《真実と虚偽》とともに、これはウェリントン公爵記念碑のための寓意的なブロンズ彫刻の原寸大モデルです。ミケランジェロの力強い人物像から大きな影響を受けたこれらの作品は、次世代の芸術家にも影響を与えました。スティーヴィーヴェンスはこの記念碑にその生涯の多くを捧げましたが、残念ながらそれが設置されるのを見ることなく亡くなりました。ロンドン石膏ロンドン、セント・ポール大聖堂のウェリントン公爵(1769–1852)記念碑のために制作収蔵番号:3218-1878】「ヒントゼ彫刻ギャラリー(The Dorothy and Michael Hintze Galleries, Gallery 21)」。18~19世紀のイギリスを中心とする肖像胸像。白大理石による写実的な表現で、政治家・芸術家・思想家・文学者などの顔立ちを残していた。手前から・William Stuart・John Raphael Smith・George II・???ヴィンチェンツォ・フォッジーニ作「サムソンとペリシテ人(Samson Slaying a Philistine)」 。廻り込んで。「Vincenzo Foggini (active 1692–1755)Samson and the PhilistinesSigned and dated 1749Here, the Old Testament hero Samson uses the jawbone of an ass to kill two ofthe Philistines who were taunting him. For this work, the Florentine sculptor Foggini reinterpreted a dramatic pose created nearly 200 years earlier by the celebratedsculptor Giambologna, whose studio Foggini had inherited. Giambologna’s marble, Samson Slaying a Philistine, is displayed in the Medieval & Renaissance gallery.FlorenceMarblePuchased by Charles Watson-Wentworth, then Lord Malton (1730–82), later 2nd Marquess of Rockingham, for Wentworth Woodhouse, Yorkshire.Museum no. A.1-1991Purchased with Art Fund support, and the assistance of the National Heritage Memorial Fund and the Murray Bequest」 【ヴィンチェンツォ・フォッジーニ(活動期 1692–1755)《サムソンとペリシテ人》1749年署名・制作旧約聖書の英雄サムソンがろばの顎骨を用いて、彼を嘲った二人のペリシテ人を打ち倒している。この作品でフィレンツェの彫刻家フォッジーニは、著名な彫刻家ジャンボローニャが約200年前に創り出し、フォッジーニが継承した工房の伝統的ポーズを再解釈している。ジャンボローニャ作の大理石像《サムソン、ペリシテ人を打ち倒す》は、V&Aの中世・ルネサンス・ギャラリーに展示されている。フィレンツェ製、大理石1730~82年頃、チャールズ・ワトソン=ウェントワース(後のロッキンガム侯爵)がヨークシャーのウェントワース・ウッドハウスのために購入。館蔵番号:A.1-1991(購入はアート・ファンドの支援、およびナショナル・ヘリテージ・メモリアル・ファンドとマレー遺贈基金の援助による)】「Pandora(パンドラ)」。・題名:Pandora(パンドラ)・作者:ジョン・ギブソン(John Gibson, 1790–1866)・制作年:1850年代・材質:大理石描写・ギリシア神話に登場する最初の女性 パンドラ を表現。・手には「パンドラの箱(壺)」を持ち、これを開けて世界に災いを放とうとする瞬間。・頭には花冠を戴き、衣は古典的なトーガ風にゆったりと drapery(衣文)をまとっている。・ギブソン特有の優雅で清澄な表現で、ヴィクトリア朝時代の「新古典主義」彫刻の代表作の ひとつ。「John Gibson (1790–1866)PandoraAbout 1860 In Greek mythology Pandora was the first mortal woman, created as a gift and punishment to men. Jupiter endowed her with a box, strictly instructing her not to open it. As Gibson put it, ‘The figure is motionless, but her mind is in full activity, labouring under the harassing feelings of intense curiosity, fear and perplexity.’ Pandora’s curiosity prevailed, and all the evils in the box were released upon humankind.RomeMarbleMuseum no. A.3-1922Given by Mrs William Penn」 【ジョン・ギブソン(1790–1866)《パンドラ》約1860年ギリシア神話において、パンドラは最初の人間の女性であり、男性への贈り物であり罰として創造された。ユピテル(ゼウス)は彼女に箱を与え、それを決して開けないよう厳しく命じた。ギブソンは次のように述べている:「像は動きを見せないが、その心は激しい好奇心、恐れ、当惑という苛むような感情に駆り立てられ、活動している。」結局、パンドラの好奇心が勝り、箱の中のあらゆる災厄が人類に放たれた。ローマ製、大理石館蔵番号:A.3-1922寄贈者:ウィリアム・ペン夫人】この「横たわる裸婦像」は・作者:エドワード・ホッジズ・ベイリー(Edward Hodges Baily, 1788–1867)・題名:Eve Listening to the Voice of Adam(アダムの声を聞くイヴ)・署名・制作年:1842年・材質:大理石・所蔵:ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A, ロンドン)・館蔵番号:468-1875・寄贈者:Wynn Ellis「Edward Hodges Baily (1788–1867)Eve Listening to the Voice of AdamSigned and dated 1842This sculpture illustrates a scene from John Milton’s poem, Paradise Lost.Turning to Adam to describe ‘a shape within the watery gleam’, Eve is told it is herown reflection. Critics admired her parted lips and raised eyes, ‘as if every sense wereoccupied in the work of listening’. Baily was re-interpreting his earlier work, Eve at theFountain (about 1818), one of the most famous sculptures of the time.LondonMarbleMuseum no. 468-1875Given by Wynn Ellis」 【エドワード・ホッジズ・ベイリー(1788–1867《アダムの声を聞くイヴ》1842年署名・制作この彫刻は、ジョン・ミルトンの叙事詩『失楽園』の一場面を表しています。イヴがアダムに向かって「水面の輝きの中にある形」について語ると、アダムはそれが彼女自身の姿であると告げます。批評家たちは、イヴの半開きの唇や上げられた目を「すべての感覚が“聞く”という行為に没頭しているかのようだ」と称賛しました。ベイリーは、この作品において、彼の初期の名作《泉のほとりのイヴ》(1818年頃)を再解釈しています。それは当時最も有名な彫刻の一つでした。ロンドン大理石館蔵番号:468-1875寄贈者:ウィン・エリス】ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A) の ヒントゼ彫刻ギャラリー(The Dorothy and Michael Hintze Galleries, Gallery 21)をさらに進む。「Zephyr and Flora(ゼピュロスとフローラ)」。「Antonio Corradini (1668–1752)Zephyr and FloraAbout 1719–23Flora was the Roman goddess of flowers and the wife of Zephyr, the west wind ofspringtime. This sculpture and the nearby Apollo Flaying Marsyas belonged to a series that Corradini made for Augustus II, King of Poland and Elector of Saxony, for his gardens in Dresden, now Germany. An important patron of the arts, Augustus II collected and commissioned works from artists across Europe.VeniceMarbleFormerly in Easton Hall, LincolnshireMuseum no. A.5-1967」 【アントニオ・コッラディーニ(1668–1752)《ゼピュロスとフローラ》1719–23年頃フローラは花のローマ女神であり、西風の神ゼピュロス(春の風)の妻でした。この彫刻と近くに展示されている《アポロとマルシュアス》は、コッラディーニがポーランド王にしてザクセン選帝侯であったアウグスト2世のために制作した一連の作品に属します。これらは現在ドイツのドレスデンにある彼の庭園のために作られました。アウグスト2世は芸術の重要なパトロンであり、ヨーロッパ各地の芸術家から作品を蒐集・委嘱しました。ヴェネツィア大理石リンカンシャー州イーストン・ホール旧蔵館蔵番号:A.5-1967】ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum, V&A) の中庭(ジョン・マジェスキー庭園 / The John Madejski Garden)から見た 博物館本館の赤レンガ外壁。・赤レンガと白い石材の対比 → V&Aを象徴する外観様式。ヴィクトリア朝ゴシック・ルネサンス様式が融合。・中央部の大アーチ窓と三連窓 → 2階部分に大きなアーチ窓、その上に三連窓が並ぶ。・装飾パネルと浮彫(レリーフ) → 彫刻的装飾が壁面に配置され、芸術と工芸の殿堂であることを強調。・池と噴水 → 写真下の部分に見える浅い池は、夏場には子どもたちが遊ぶスペースとしても有名。正面をズームして。・建築様式:ヴィクトリア朝ネオ・ルネサンス様式(赤レンガ+白石材の対比)。・中央の大アーチ窓(三連窓):下層に大きな三連アーチ、その上に小アーチ窓群を重ねた構成。・装飾メダリオン(円形・半円形レリーフ): ・両サイドに「芸術や工芸を象徴する人物群像(寓意的浮彫)」が配されています。・破風(三角形の屋根部): ・上部には金色モザイク装飾が施され、芸術家たちの姿(彫刻・建築・工芸などを象徴)が 描かれていた。・中央入口: ・入り口上部に装飾パネルと銘板があり、来館者を迎え入れる構造。・破風(三角形の屋根部): 上部には金色モザイク装飾が施され、芸術家たちの姿(彫刻・建築・工芸などを象徴)が 描かれていた。🔹 中央図像の意味 ・中央に立つのは 女王ヴィクトリア(Queen Victoria)。 彼女の足元には「OF QUEEN VICTORIA」と刻まれ、 その左側(向かって右)には「ALBERT CONSORT」(王配アルバート)と記されていた。 ヴィクトリアは、周囲の擬人像(女性像)から冠を授けられる姿で描かれており、 これは「芸術と科学の守護者としてのヴィクトリア女王」を象徴しています。 背後には「VICTORIA」の文字を掲げたアーチが描かれ、 その光輪のような形が「栄光」「啓蒙」を表します。🔹 周囲の女性像(象徴) 女王の両側に立つ女性像たちは、ヨーロッパ諸国の擬人化または芸術・学問分野の寓意像です。 ペディメント上端には各国名が刻まれています: SWITZERLAND ・ TURKEY ・ ITALY ・ FRANCE ・ BELGIUM ・ HOLLAND これらは、1851年のロンドン万国博覧会(The Great Exhibition)に参加した主要諸国を 示しており、アルバート公が主導した「諸国協調による芸術・産業の進歩」の理念を反映。🔹 下部の銘文 下方の金文字の一部が読めた: “THE ADVANCEMENT OF THE WORKS OF INDUSTRY OF ALL NATIONS ANNO DOMINI MDCCCLXI” (すべての国々の産業作品の発展を讃えて 西暦1861年) これはロイヤル・アルバート・ホールの建設理念を表した文句で、 アルバート公の遺志(Great Exhibitionの理想)を受け継ぐものです。中庭側の横手(サイドウィング)を見る。この部分は、19世紀後半に完成した「レンガ造ファサード群」の一角で、研究室・展示室・収蔵庫などが配置されていた。。中庭(ジョン・マジェスキー庭園)・2005年にリニューアルされた、V&Aの中心にある回廊式中庭。・噴水やベンチがあり、来館者が休憩する場。・周囲を取り囲む赤レンガの外壁は「19世紀ヴィクトリア時代の建築美」を体感できる空間。ジョン・マジェスキー庭園を囲む別の側・南面ファサードの一部を見る。・赤レンガ造+白石の装飾枠: 中庭を囲む外壁デザインの統一感を示しています。・アーチ型の出入口と大窓: 1階部分に三連アーチの入口、2階部分に大きなアーチ窓が並ぶ構成。・長方形パネル(上部): 建物上層には横長の装飾パネル(モザイク/テラコッタ)が設置されており、古典的な 人物群像や装飾図案が描かれています。・円形メダリオン(1階部分): 出入口の両側には円形の浮彫(レリーフ)があり、これも寓意的な芸術家・人物像を 表しているのであろう。池越しに正面左側を。再び中庭から内部へ。この一角には 記念碑的彫刻(墓碑や墓所装飾) が集中しているようであった。特に右壁面の大型浮彫は、イタリアまたは北ヨーロッパの墓碑彫刻(16〜17世紀頃) が多く、V&Aの「Monumental Sculpture」セクションに典型的な配置。「ジョシュア・ウォードの肖像(Portrait of Joshua Ward)」。「Agostino Carlini (1718–90Portrait of Joshua Ward (1686–1761)About 1760–4Joshua Ward was a renowned philanthropist who founded several hospitals for the poor.Known at the time as a ‘quack doctor’, he was not medically trained but made hisfortune by concocting popular patent medicines. This figure may have been intendedfor a planned monument in Westminster Abbey, which was never built. His hand gesture indicates generosity, while his bulky figure suggests prosperity.LondonMarbleMuseum no. A.2-1991Purchased with the assistance of funds from the bequest of Hugh Phillips, Esq.」 【アゴスティーノ・カルリーニ(1718–1790)《ジョシュア・ウォードの肖像》(1686–1761)1760〜1764年頃ジョシュア・ウォードは、貧しい人々のためにいくつかの病院を設立したことで知られる著名な慈善家でした。当時は「ヤブ医者(quack doctor)」と呼ばれていましたが、医学的な訓練を受けていたわけではなく、大衆に人気のあった特許薬を調合して財を築きました。この像は、ウェストミンスター寺院に建設が計画されていた記念碑のために意図されたものかもしれませんが、実現することはありませんでした。彼の手の仕草は「寛大さ」を示し、またそのふくよかな体格は「繁栄」を暗示しています。ロンドン大理石館蔵番号 A.2-1991ヒュー・フィリップス氏の遺贈基金の援助によって購入】サー・ロバート・テイラーによる「トマスとロバート・クロスの記念碑」(約1745年、嘆く女性像は依頼者メアリー・マーティン)・上部円形メダイヨン(レリーフ肖像) 故人の胸像が浮き彫りで表されており、没者を記念する役割を果たしています。・胸像(左側) 古代風の甲冑をまとった半身像(擬古的表現で、英雄性・徳を象徴)。・嘆く女性像(右側) 古代の擬人化像(しばしば「Grief(悲嘆)」や「Faith(信仰)」を表す)。 頭を手で覆う姿勢は典型的な「mourning figure(嘆きの姿)」です。・三角形の背景(ピラミッド形) 当時流行した記念碑デザインで、「永遠」「不滅」を象徴。18世紀の教会記念碑に頻出します。・上部の紋章(coat of arms) 故人や家系の家紋が配置されており、身分や家柄を示しています。「Probably by Sir Robert Taylor (1714–88)Monument to Thomas (1694–1732) and Robert Crosse (1671–1741)About 1745The figure in mourning represents Mary Martin, who commissioned this monumentin memory of her nephew and brother. Taylor was a successful architect who alsodesigned memorials. He is believed to have made this monument as one of hisnumerous drawings closely resembles it.LondonMarbleFrom the church of St Andrew, Nettlewell, EssexMuseum no. A.60-1969Given by the Rector and churchwardens of St Stephen’s Tye Green with St Andrew’s Nettlewell, Essex」【おそらく サー・ロバート・テイラー(1714–1788)作トマス・クロス(1694–1732)およびロバート・クロス(1671–1741)の記念碑制作:約1745年この記念碑の嘆きの女性像は、メアリー・マーティンを表しています。彼女は甥と兄を記念してこの記念碑を建立しました。テイラーは記念碑の設計でも知られる成功した建築家で、この作品は彼の多数の素描の一つと非常によく似ていることから、彼が制作したと考えられています。ロンドン大理石出典:エセックス州ネトルウェルの聖アンドリュー教会館蔵番号:A.60-1969寄贈:エセックス州ネトルウェルの聖アンドリュー教会および聖ステファン・タイ・ グリーン教会の牧師と教区役員】 ローラン・デルヴォー(1696–1778)作 Ceres(ケレス/ローマの農業の女神)。「Possibly by Laurent Delvaux (1696–1778)CeresAbout 1720This figure of Ceres, the Roman goddess of agriculture, wears a headdress of flowersand wheat, and holds a similar garland. Its base is almost certainly copied from a marble fountain. The figure would originally have been displayed in a stately home,possibly as part of a series of Roman deities. Previous owners considered it an allegorical portrait of the Duchess of Marlborough or Queen Anne, but it may simplyrepresent ideal female beauty.Britain or Southern NetherlandsOakMuseum no. A.29-1941Given by Dr W.Ll. Hildburgh FSA」 【おそらく ローラン・デルヴォー(1696–1778)作Ceres(ケレス/ローマの農業の女神)制作:約1720年この像は、ローマの農業の女神ケレスを表しており、花と小麦でできた頭飾りをかぶり、同様の花輪を持っています。台座はほぼ確実に大理石の噴水から模倣されたものです。この像は元々は大邸宅に展示されていたもので、おそらくローマの神々の一連の作品の一部だったと考えられます。以前の所有者はこれをマールバラ公爵夫人やアン女王の寓意的肖像と見なしていましたが、単に理想的な女性美を表しているだけかもしれません。制作地:イギリスまたは南ネーデルラント素材:オーク材館蔵番号:A.29-1941寄贈者:W.Ll. ヒルドバーグ博士(FSA)】更に進むと「SCULPTURE (1300–1600)」(彫刻展示室:1300〜1600年)とあり、この先のギャラリーでは 中世後期からルネサンス期のヨーロッパ彫刻 が展示されていた。展示室番号として、右上に上に小さく 「16A, 26 & 27」 と書かれていたので、16A室、26室、27室が対象の彫刻ギャラリーであることを理解。ここでは、ゴシック彫刻、ルネサンス期の祭壇片、墓碑彫刻、宗教彫像などが中心に展示されており、イタリア、フランス、ドイツ、ネーデルラントなど各地の作品を見ることができたのであった。「THE LAMENTATION OVER THE DEAD CHRIST(死せるキリストへの哀悼)」 作品全体が「ピエタ(Pietà)」=死せるキリストを悼む聖母と弟子たちの姿 の場面と。・左端:聖ヨハネ 若い弟子で、キリストの胸を支えている。青い外套と赤い衣服は彼の典型的な色彩。・中央:聖母マリア 青いマントと赤い衣をまとい、深い悲しみにうなだれつつ息子を見守る。・右端:マグダラのマリア 長い髪を垂らし、胸に手を当てる仕草で感情を表す。彼女の像はラベルにあるように 後に破損し、彩色で補修された。・中央に横たわる人物:キリスト 十字架から降ろされたばかりの姿で、腰布一枚をまとい、顔には苦悩と死の静けさが 同居している。「THE LAMENTATION OVER THE DEAD CHRISTAbout 1510–15Workshop of Andrea della Robbia (1435–1525)Large-scale groups in various materials were used as focal points for devotion inchapels and churches throughout Europe. Terracotta was particularly popular in Tuscany and around Bologna.Terracotta groups on this scale were difficult to make. The figures here were each constructed separately. Mary Magdalene on the right, is now in several pieces andprobably shattered after the first (or biscuit) firing. This prevented a second firing to fix the glazes, so instead the figures were painted.Italy, FlorenceGlazed and painted terracottaMuseum no. 409-1869」 【《死せるキリストへの哀悼》1510~1515年頃アンドレア・デッラ・ロッビア工房(1435–1525)ヨーロッパ各地の礼拝堂や教会では、大規模な群像彫刻が信仰の中心として用いられました。なかでもテラコッタ(素焼き陶)はトスカーナ地方やボローニャ周辺で特に人気がありました。この規模のテラコッタ群像を制作するのは困難でした。ここにある人物像は、それぞれ別々に作られています。右側のマグダラのマリア像は現在いくつかの断片となっており、おそらく最初の(素焼き=ビスケット焼成)段階で破損したと考えられます。そのため釉薬を施して焼成する二度目の焼きは行われず、代わりに彩色が施されました。制作地:イタリア、フィレンツェ素材:彩釉および彩色テラコッタ館蔵番号:409-1869】そしてV&A美術館の「Sculpture 1300–1600」ギャラリー内部へ。右側に見えたのは ステンドグラス(聖人や宗教場面を描いた小パネル群) の展示で、背後から光を当てて中世〜ルネサンス期の彩色ガラスの美しさを強調する展示方法になっていた。奥に立っているのは木彫の聖人像(おそらく聖母子像や聖人像)で、通路両脇にも中世ヨーロッパの宗教彫刻が並んでいた。1.左側パネル ・主題:聖ペトロ(鍵を持つ使徒ペトロ)と寄進者男性 ・描写:白髪の聖ペトロが天国の鍵を掲げ、跪く男性ドナーを祝福しています。 典型的な寄進者肖像の構図です。2.右側パネル ・主題:聖ヤコブ(巡礼杖を持つ)と寄進者女性(Adelheid) ・描写:聖ヤコブが女性の肩に手を置き、巡礼の守護者として導いています。 女性は跪いて祈る姿。「STAINED GLASSThe stained glass panels in these two galleries come from the churches of Germany,Switzerland or the Upper Rhine region of Cologne. Most were made on the Premonstratensian Abbey of Steinfeld, some for the Cistercian abbey of Altenberg.The ateliers were both broad-based in skills, and their detailed glass was cut and engraved. The Altenberg panels were later dismantled when the church was rebuiltin the 19th century. When the Altenberg glass was sold in 1819, it was bought bya private collector who then gave it to the V&A.ADÉLHILD, WIFE OF ARNOLD VON ULSF, WITH ST JAMES THE LESSAbout 1520Donating families and leading burghers often appear as kneeling donors, shown being presented by a saint.Adelheid, the donor, is shown behind a draped desk with her coat of arms clearly visibleand holding the arms of her husband. She is presented by St James the Less, apostle,who is identified by a club (his attribute). The stained glass was made for Altenberg Abbey, near Cologne.PETER VON SCHÜRFF WITH ST PETERAbout 1520Probably Cistercian Abbey of Altenberg, near Cologne.The donor of this panel, Peter von Schürff, the lawyer, was presented by St Peter holding the keys of Heaven. Such panels are typical of the period and show the importance of devout families and burghers in commissioning stained glass windows for religious institutions.」 【ステンドグラスこの2つのギャラリーにあるステンドグラスのパネルは、ドイツ・スイス、あるいはケルン近郊の上ライン地域の教会から来ています。多くはシュタインフェルトのプレモントレ会修道院のために、また一部はアルテンベルクのシトー会修道院のために制作されました。工房は幅広い技術を持ち、ガラスを切断・彫刻して精緻に仕上げていました。アルテンベルクのパネルは、19世紀に教会が再建された際に解体されました。その後1819年に売却され、個人収集家を経てV&Aに寄贈されました。アーデルヒルト(アルノルト・フォン・ウルフの妻)と聖ヤコブ(小ヤコブ)1520年頃寄進者の家族や都市の有力市民は、跪いた姿で、聖人に導かれる形で描かれるのが一般的でした。このパネルでは、寄進者アーデルヒルト夫人が机の後ろに跪き、夫の紋章を示しています。彼女を導くのは使徒聖ヤコブ(小ヤコブ)で、その象徴である棍棒を持っています。このステンドグラスはケルン近郊のアルテンベルク修道院のために制作されました。ペーター・フォン・シェルフと聖ペテロ1520年頃ケルン近郊アルテンベルクのシトー会修道院のために制作されたと考えられます。このパネルでは、法学者ペーター・フォン・シェルフが寄進者として跪き、天国の鍵を持つ聖ペテロによって取り次がれています。こうした寄進者像を伴うパネルは当時一般的で、信心深い市民や家族が修道院や教会にステンドグラスを奉納したことを示しています。】この一対のステンドグラスは、「施主とその家族が聖ヨハネに取り次がれる場面」 を表しており、16世紀ドイツ(ケルン近郊アルテンベルク修道院周辺)で流行した形式である と。●左のパネル ・主題:聖ヨハネ(福音書を持つ)と寄進者男性 ・聖人:手に聖杯を持ち、光輪を頂いていることから 聖ヨハネ(使徒ヨハネ) と 考えられます。ヨハネはしばしば「毒杯」の奇跡に関連して、杯から蛇や竜が出る 図像で表されますが、この聖杯はその象徴。 ・寄進者:聖人の前に跪く男性(施主)。黒い市民服をまとい、社会的地位の高い裕福な 市民層を示しています。・意味 ・施主が聖ヨハネに取り次がれ、神の前に祈りを捧げる場面。 ・「ヨハネの聖杯」は信仰の証、奇跡、または試練を乗り越える力を象徴。● 右のパネル ・主題:聖ヨハネ(福音書を持つ)と寄進者男性 ・聖人:大きな聖杯(ゴブレット)を持つ姿はやはり 聖ヨハネ。こちらはより典型的に 「聖杯を掲げる姿」で描かれています。 ・寄進者:中央に跪く女性、その後ろに若者(おそらく家族の息子か従者)が控えています。・意味 ・女性施主(おそらく裕福な未亡人、あるいは名家の夫人)が聖ヨハネに導かれている。 ・家族全体が祈りに参加することを示し、信仰心と社会的地位を同時に表現。●左のパネル ・主題:幼子イエスの神殿奉献(ルカによる福音書 2:22-40) ・人物: ・聖母マリア:幼子イエスを抱いて神殿へ差し出している。 ・聖ヨセフ:マリアの背後で奉献を見守る。 ・シメオン:預言者。神殿で幼子を受け取り「今こそ、御身の僕を安らかに去らせて ください」と祈る場面。 ・女預言者アンナ:奥に立ち会っている年老いた女性。神殿に仕え、 イエスを「待ち望んでいた救い主」と証言。 ・意味 ・旧約の律法に従い、長子を神に奉献する儀式を描く。 ・シメオンはイエスを「救いの光」と認め、救世主到来を宣言する。 ・「旧約から新約への移行」「神の約束の成就」を象徴。●右のパネル ・主題:神殿の奉献儀礼、もしくは寄進者を描いた場面。 ・人物: ・前景にひざまずく女性(施主/寄進者)。身分の高さを示す衣服。 ・周囲に豪華な建築装飾と聖堂内部の細部が描かれている。 ・奥には祭壇や聖像が見え、祈りの対象となっている。 ・意味 ・この場面は聖書の物語そのものというより、寄進者が神殿(教会)内部で祈願する姿を 示したものと考えられる。 ・精緻な建築描写は、神の家=教会を象徴。寄進者の信心と財力を強調。 ・左の「イエス奉献」と対をなし、「祈願と救済」「聖家族と信徒」を結びつける意図。●左のパネル ・登場人物 ・聖母マリアと幼子イエス:奥に逃れようとする姿。 ・ヨセフ:聖家族を導いている。 ・兵士:幼児を抱き上げ、剣で殺そうとする。 ・主題 ・「幼児虐殺(Massacre of the Innocents)」の場面。 ・新約聖書マタイ2章16節:ヘロデ王がベツレヘムの2歳以下の幼児をすべて殺すよう 命じた出来事。 ・意味 ・イエスを抹殺しようとする権力の暴力を表す一方で、聖家族は神の導きにより難を逃れる。 ・殉教の予兆、罪なき者の犠牲を象徴。●右のパネル・登場人物 ・中央:兵士が幼児を母親から奪い、殺害している。 ・左下:母親がひざまずき、必死に命乞いしている。 ・背景:豪華な宮殿風の建築、群衆が上から覗いている。・主題 ・同じく 「幼児虐殺」 の続きの場面。 ・複数の子どもが犠牲となり、母親たちが泣き叫ぶ描写。・意味 ・権力と残虐さの強調。イエスが「無辜の殉教者たち(Holy Innocents)」によって 守られたことを視覚的に伝える。 ・教会暦でも1月6日近くに記念される主題であり、救済史の一環として重要。●左のパネル・登場人物 ・中央の光輪を持つ人物:イエス・キリスト ・周囲の男性たち:弟子たち(使徒) ・前景の女性たち:マルタとマリア(ベタニアの姉妹)・主題 ・「ラザロの復活(Raising of Lazarus)」の前段階 ・イエスがマルタとマリアに導かれ、弟子や群衆とともにラザロの墓へ向かう場面。・意味 ・人々の悲嘆と、奇跡が起こる前の緊張感を表す。 ・イエスの力と神の栄光がまもなく示されることを予兆。●右のパネル・登場人物 ・前景:イエスとラザロ(復活した姿で白い布をまとって座る)。 ・周囲:マルタ、マリア、群衆が驚愕と喜びの表情を見せる。 ・背景:都市の建築と嘆く人々。・主題 ・「ラザロの復活(Raising of Lazarus)」本場面(ヨハネによる福音書11章)。 ・イエスがラザロを墓から呼び戻し、死者が甦る奇跡を描く。・意味 ・キリストの神的権威を強調し、復活と永遠の命の象徴。 ・後のイエス自身の復活の先駆けとして信仰的意義を持つ。4体の木彫像。左から・聖ヤコブ(大ヤコブ) 巡礼者の守護聖人。杖や書物を持つ姿で表現される。・大天使ガブリエル 翼を持ち、受胎告知の場面に登場する天使。・聖母マリア(処女マリア) 中央的存在。祭壇画では「聖母戴冠」の場面でキリストの隣に座る。・聖シモン 十二使徒の一人。巻物や本を持つ姿で表現されることが多い。「ST JAMES THE GREATER, THE VIRGIN AND THE ANGEL GABRIEL, ST SIMONAbout 1360–90The figures belonged to a now-dismantled winged altarpiece in the church of St John in Lüneburg. Until 1856, the church had over forty altarpieces. This one probablyshowed the Coronation of the Virgin, with standing figures to each side. Their robes were originally gilded to emulate the richness of goldsmiths’ work.Northern Germany, Lower SaxonyOakMuseum nos: 4845, 4847, 4848, 4846-1856」【大ヤコブ(聖ヤコブ)、聖母マリア、大天使ガブリエル、聖シモン1360〜1390年頃これらの像は、現在は解体されてしまったリューネブルクの聖ヨハネ教会の両翼祭壇の一部でした。1856年まで、この教会には40以上の祭壇画が存在していました。この一群はおそらく「聖母の戴冠」を表しており、左右に立つ聖人像を伴っていたと考えられます。衣服は当初、金細工師の作品のような豪華さを模倣するために金箔で装飾されていました。北ドイツ、ニーダーザクセン地方樫材博物館番号:4845, 4847, 4848, 4846-1856】 左手前には木彫の聖母子像(マリアと幼子イエス)が展示され、右側の壁面には ステンドグラス(ルネサンス期・ドイツ地方) が縦列に並んでいた。その奥にはさらに木彫群像が見えていた。●左のパネル・登場人物 ・中央手前:イエス(光輪を持つ男性、赤と青の衣) ・左下:水瓶を扱う従者(女性または召使い) ・周囲:食卓につく人物たち(婚礼の客人たち)・主題 ・カナの婚礼(Wedding at Cana) ヨハネ福音書第2章に記される、イエスが最初に行った奇跡。水を葡萄酒に変えた場面が 表現されています。 この場面では、従者が水瓶に水を注いでおり、イエスがそれを祝福する姿が描かれています。・意味 ・キリストが「公の奇跡」を始める最初の場面。 ・信仰の象徴として「水が葡萄酒に変わる=神の力による質的転換」が強調されています。●右のパネル・登場人物 ・中央:イエス(光輪を持つ人物、青い衣) ・右手前:白い頭巾をかぶった女性(サマリアの女) ・背景:井戸と都市建築・主題 サマリアの女との対話(Christ and the Samaritan Woman at the Well) ヨハネ福音書第4章。イエスがサマリアの井戸で女性と語り、彼女に「永遠の命に至る水」を 与えると告げる場面。 ・意味 ・異邦人や罪人とも隔てなく救いを与えるキリストの慈愛を示す。 ・「井戸の水」と「永遠の命の水」の対比が信仰の核心を象徴。●左のパネル・登場人物 ・中央上:十字架にかかるキリスト(頭上にINRIの札、光輪あり) ・両側:二人の罪人(両脇の十字架に磔刑) ・下部:聖母マリア(青衣)、聖ヨハネ(赤衣)、マグダラのマリア(長い髪)などが 十字架下に集う ・天使:左右に飛び、血を杯で受けている・主題 磔刑(Crucifixion) キリストの受難の頂点を描いた場面。・意味 ・人類の罪を贖うキリストの犠牲を象徴。 ・聖母と弟子ヨハネが傍らにいる典型的な磔刑像の構図。 ・天使が血を杯に受ける場面は、聖餐(Eucharist)との関連を強調。●右のパネル・登場人物 ・中央:キリストの亡骸を抱える人々(ニコデモやアリマタヤのヨセフとされる) ・左上:立つ人々(聖母や弟子たち) ・右下:墓に安置されるイエスの遺体 ・背景:丘と都市風景・主題 埋葬(Entombment / Burial of Christ) 十字架から降ろされたキリストが墓に納められる場面。・意味 ・「受難」のクライマックスである「死と埋葬」を示す。 ・救済史における「復活」への前段階。 ・埋葬の用具(布、香料など)が細かく描かれており、当時の信仰実践や典礼を反映。●左のパネル・登場人物 ・中央:キリスト(復活した姿、白い衣に赤いマント、十字旗を掲げる、光輪あり) ・下部:眠りこける兵士たち(墓を守るローマ兵)・主題 キリストの復活(Resurrection of Christ)・意味 ・死と埋葬を経て復活するというキリスト教信仰の中心的奇跡。 ・兵士たちは復活の瞬間を目撃できず、眠っている(聖書に基づく表現)。 ・キリストが墓から立ち上がり、勝利の旗を掲げる姿は「死に対する勝利」を象徴。●右のパネル・登場人物 ・中央:墓から出てくるキリストの亡骸(衣をまとい、光輪あり) ・前景:弟子や信者が遺体を抱え支えている ・背景:複数の弟子・聖女(光輪を持つ)・主題 キリストの埋葬(Entombment) または「墓に納められる場面」・意味 ・磔刑後の「イエスの遺体を墓に安置する場面」。 ・左の「復活」と対をなし、「死と復活」というキリスト教信仰の核心を示す。 ・哀悼に包まれた人々の姿が強調され、復活による希望への伏線となる。 この空間は 「ギャラリー21(The Dorothy and Michael Hintze Galleries)」、通称「サウス・ケンジントンの彫刻回廊」部分にあたる。ここには16〜19世紀ヨーロッパ彫刻が常設展示されていた。有名なカノーヴァ作《ナポレオンの妹ポーリーヌ像》のコピーや、ルネサンス期の胸像などが並んでいたのであった。・長い回廊式の展示室:両側に大きなアーチ型の窓(外光を取り込む構造)と、天井は 格子状の装飾パネル。・展示作品:大理石の胸像や立像が整然と並んでおり、ギリシャ・ローマ彫刻やルネサンス 以降のヨーロッパ彫刻が中心。・床のモザイク装飾:幾何学模様が敷き詰められていて、V&Aの19世紀的デザインが反映 されていまた。・中央奥には大きな立像が見え、回廊の遠近感を強調。V&Aヒントゼ・スカルプチャーギャラリー(The Dorothy and Michael Hintze Galleries, ギャラリー21付近) の中央部。ここは吹き抜けで2階とつながるポイント。アルフレッド・スティーヴィーヴェンス (Alfred Stevens, 1817–1875) の 「Truth and Falsehood(真実と虚偽)」。廻り込んで。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.30
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その123): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-6
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクヴィクトリア&アルバート博物館(V&A, Victoria and Albert Museum) の展示ケース。イスラーム美術ギャラリー展示ケースの一部。青や緑を中心とした釉薬陶器。Safavid Ceramics and Colour(サファヴィー朝の陶器と色彩)サファヴィー朝(1501–1736年、イラン)の陶器に特徴的な、1.単色釉による鮮やかな色彩表現 ・上段のコバルトブルーの大皿:白い線刻で幾何学文様(星形、放射状パターン)が 施されている。これは釉下に彫刻を加えた装飾。 ・左側の緑釉皿:唐草や花文様が施され、豊穣や自然の象徴。 ・中段の青緑色の水差し(ピッチャー)や瓶:釉薬そのものの美しい発色を楽しむため、 表面の文様は控えめ。2・スリップ(化粧土)技法による装飾 ・下段中央の小瓶(黒や赤茶色の釉色):胎土の白と対比をつけるために化粧土を使い、 表面を削ったり加飾している可能性が高い。 ・右側の白い鉢や水注:白化粧土と透明釉を組み合わせたシンプルなデザイン。「Safavid Ceramics and ColourSafavid potters created brilliantly coloured ceramics. The effect was often achievedwith glazes of a single colour. Many of these wares have moulded or carved decoration. The most unusual appears on bottles made in the 17th century, which bear scenes ofpeople and animals.A second technique used coloured slips, or liquid clay, under the glaze. Potters sometimescarved the slip away to reveal the white body beneath.In other cases, they added designsin white and other slips.」 【サファヴィー朝の陶器と色彩サファヴィー朝の陶工たちは、鮮やかな色彩の陶器を制作しました。その効果はしばしば単一色の釉薬によって実現されました。これらの器の多くは、型押しや彫刻による装飾を伴っています。最も珍しい例は17世紀に作られた瓶に見られ、人や動物の場面が描かれています。もう一つの技法では、色付きの化粧土(スリップ)、つまり液状の粘土を釉薬の下に用いました。陶工は時にこの化粧土を彫り削って下地の白い胎土を露出させることで模様を作り、また別の場合には白や他の色の化粧土を加えてデザインを施しました。】サファヴィー朝(Safavid dynasty, 16–17世紀イラン)に典型的な多彩タイル・パネル。・素材:タイル(釉薬陶板)、組み合わせパネル(複数枚のタイルで一つの大画面を構成)・制作地:イラン(イスファハーンなどが中心)・時代:サファヴィー朝(特にシャー・アッバース1世治世下の17世紀頃)・技法: ・多彩釉(polychrome underglaze painting) ・輪郭線を黒やマンガンで描き、その内側を青・緑・黄・白・褐色などで彩色 ・釉薬下彩なので、発色が鮮やかで耐久性が高い上段にある器物 ・背景の棚には、白地に藍色文様の陶器(イズニクやサファヴィーの青白磁風)が 並べられていた。 ・下段の多彩タイルと合わせて展示することで、「単色釉・青白磁」vs「多彩絵付けタイル」 という対照が際立ち、サファヴィー陶芸の多様性を示していたのであった。ネットから。1.王権の象徴 王や貴族の文化的洗練を示す。庭園での饗宴は「理想的な支配者の楽園」として表現される。2.イスラーム的楽園イメージ 流れる水、果樹、花咲く草原、糸杉はクルアーンの「楽園の園」を想起させる。3.文化的アイデンティティ サファヴィー朝期はシーア派を国教化しつつ、芸術の都イスファハーンを築いた時代。 こうした鮮やかな装飾タイルは、都市のモスク・宮殿・庭園を飾った。ズームして。人物左の人物(女性?)・緑の衣装に花文様、長い髪を左右に垂らす。・木陰から現れ、手に赤い水袋(ワインや飲料)を持つ。・繊細な顔立ちで、詩的な恋愛場面を示す「美しい恋人」像。右の人物(男性?)・青い衣服に白と黄色の刺繍。・頭には大きなターバンを巻く。・布を広げて座る姿勢 → 貴人(王侯や青年貴族)の表象。背景・糸杉・柳・果樹などが生い茂る庭園。・花の咲いた木々は「楽園」的な象徴。・下方に食器や敷物(青地に描かれた茶碗、壺、蓋物)が描かれ、宴席の場面を強調。「Iran under the SafavidsThe Safavid dynasty was established in 1501 by Shah Isma‘il. The origins was a Sufi religious order, and they established Twelver Shi‘ism as the religion of Iran. A new capital was founded at Isfahan in 1597 by Shah ‘Abbas I (1587–1629). The city was transformed into a showpiece of Safavid architecture of the 1600s,much of it has survived to this day.Many of Iran’s finest mosques, madrasas and palaces were built then. Tilework wasgiven new emphasis, using brilliant colours and elegant designs. The displays in thisgallery show examples of this Safavid architectural tilework.The first Safavid capital was Tabriz, followed by Qazvin and Isfahan from the reign ofShah ‘Abbas I. The Safavid dynasty provided a strong sense of Iranian identity, especially by adopting Twelver Shi‘ism as the religion of the state. This legacy continues today in the modern Islamic Republic of Iran.」 【サファヴィー朝期のイランサファヴィー朝は1501年、シャー・イスマイールによって創始されました。その起源はスーフィー教団にあり、彼らはイランの国教として十二イマーム派シーア派を確立しました。1597年、シャー・アッバース1世(在位1587–1629)が新しい首都イスファハーンを建設しました。この都市は17世紀のサファヴィー朝建築の粋を示す都市へと変貌し、その多くは今日まで残っています。イランの最も優れたモスク、神学校(マドラサ)、宮殿の多くがこの時期に建設されました。タイル装飾は特に重視され、鮮やかな色彩と優雅なデザインが用いられました。このギャラリーで展示されているのは、サファヴィー建築におけるタイル装飾の一例です。サファヴィー朝の最初の首都はタブリーズ、その後カーズヴィーン、さらにシャー・アッバース1世以降はイスファハーンとなりました。サファヴィー朝は国家宗教として十二イマーム派シーア派を採用することにより、イランの強固なアイデンティティを確立しました。この遺産は現代のイラン・イスラム共和国にまで受け継がれています。】この展示パネルは「サファヴィー朝と青花(Blue-and-white)」について解説。「The Safavids and Blue-and-whiteA major concern of Iranian potters in the Safavid period was to make ceramicsin the style of Chinese blue-and-white porcelain. The Chinese wares continued to beimported in great quantities, first by the Portuguese and then, from about 1620, by the Dutch and the British.Some of the Iranian wares are close imitations of Chinese originals.The Iranian potterseven copy the Chinese maker’s marks that appear on the base.」 【サファヴィー朝と青花(青と白の陶磁)サファヴィー朝時代のイラン陶工にとって重要な課題の一つは、中国の青花磁器(青と白の磁器)様式の陶器を制作することでした。中国陶磁器は大量に輸入され続け、最初はポルトガル人によって、そして1620年頃からはオランダ人とイギリス人によってもたらされました。イラン製の器の中には、中国のオリジナルに非常に近い模倣品もあります。イランの陶工たちは、中国製品の底に記された製造者の銘(窯印)までも写すことがありました。】「アードビール絨毯(Ardabil Carpet)」のコーナーへ。アードビール絨毯の概要・制作地:イラン北西部アルダビール(Ardabil)・制作年代:1539–1540年頃(サファヴィー朝、シャー・タフマースプ治世期)・寸法:およそ 10.5 × 5.3 メートル(世界最大級の手織りカーペット)・素材:絹の経糸・緯糸、羊毛パイル・技法:ペルシア結び(非対称結び)、緻密な織り「アードビール絨毯(Ardabil Carpet)」 を正面から。1.中央メダリオン・大きな円形文様(モスクの天井ドームを思わせるデザイン)・周囲に小メダリオンやランプ状の装飾が放射状に配置され、宇宙的な秩序を表現。2.吊り下げランプ・メダリオンの両端に「ランプ(吊り下げ灯火)」が織り込まれている。・一方が大きく、一方が小さく描かれているが、実際に座って見上げる位置からは遠近法で 同じ大きさに見える工夫。3.フィールド(中央地)・濃紺地に緻密な唐草文様、花、葉が無数に散らされ、永遠の庭園=楽園を象徴。4.縁取り(ボーダー)・赤や金を基調とした帯状文様が幾重にも取り巻く。・その一部に「銘文」が含まれている。銘文(詩句と署名)縁取り部分にはペルシア語詩が織り込まれていた。内容は以下のようなもの:・詩句:「私はこの敷物の地のように大地のしもべ、天国の楽園に通じる道を指し示す」。・署名:「この作品はカシャーンのマクスードによって織られた(Maqsud of Kashan)」左側の絨毯・背景:赤を基調。・文様:大きな円形メダリオンが連続する「連珠円文」的配置。・周囲に花瓶や花唐草が展開 → 「ヴェース・カーペット(Vase carpet)」群に属する可能性。・色彩:赤・緑・クリーム色など、鮮やかで装飾的。右側の絨毯・背景:赤褐色ベースに濃い藍色のフィールド。・文様:中央に細長い長方形の空間(礼拝用カーペットのニッチ風?)、周囲に唐草や 複雑な花模様。・ボーダー:波状の連続文様が枠を縁取るサファヴィー朝の「花瓶カーペット(Vase Carpet)」特徴・地色:赤を基調とし、全面を覆うように花文様が広がる。・文様:八弁花・星形花・蔓草などが反復的に配され、全体が格子状(ラティス模様)を形成。・ボーダー(縁取り):濃色地に黄色やアイボリーの大花文様が連続。・構造:中央に大きなメダリオンはなく、むしろ全面的に「花畑」のようなデザイン。花瓶カーペット(Vase Carpet)の特徴・名称の由来:デザインの中にしばしば花瓶(vase)が描かれるため。・産地:主にイラン南東部のキルマン(Kirman)で16〜17世紀に制作。・素材:絹・綿・羊毛を組み合わせた精緻な織り。・意匠の特徴: 1.花瓶から植物が伸び、フィールド一面に花が広がる。 2.格子状に構成された花唐草。 3.彩色は赤・青・金を基調とし、非常に華やか。左下コーナーをズームして。図像の詳細1. 花瓶(Vase)・画面中央下寄りに大きな花瓶があり、そこから植物や花が四方に伸びています。・これが「ヴェース・カーペット」の名前の由来。2. 花文様・赤地を背景に、黄色・青・緑の大輪の花が反復。・花はヒマワリ型、蓮華型、星形、カーネーション風など多様。・小花やつぼみが周囲に密集し、まるで庭園全体を描いたような華やかさ。3. 格子状配置・花瓶から伸びる枝葉が、全体を縦横の「格子状」に構成している。・花の配置が段階的にレベル分けされ、規則性と無限の拡がりを表現。4. 縁取り(ボーダー)・黒地に大きな花と唐草 → フィールドの赤との強烈な対比を作る。・ポーダー自体も「小さな庭」を連続的に繋げたような意匠。・制作年:1539–1540年とされる と。V&A博物館の「サファヴィー朝の絨毯ギャラリー」の一角で、壁面に垂直に展示されているペルシア絨毯。「Carpet with Floral LatticeIran, possibly Kirman1600–1700This carpet is one of a group in which the motifs are organised in a lattice pattern onseveral levels. As vases often occur in these designs, they are sometimes called“vase carpets”. The group’s weave of cotton, silk and wool is also distinctive.This example belonged to the British designer William Morris (1834–96), who used itas a source for his own work.Cotton warps (Z3/45), silk and cotton wefts, and wool pileMuseum no. 719-1897」 【花格子文様のカーペットイラン(おそらくキルマン産)1600–1700年このカーペットは、文様が複数の段階で格子(ラティス)模様に構成されたグループに属します。これらのデザインにはしばしば花瓶が描かれるため、「花瓶カーペット(vase carpets)」と呼ばれることもあります。このグループは綿・絹・羊毛を組み合わせた独特の織り方でも知られています。この実例はイギリスのデザイナー ウィリアム・モリス(1834–1896) が所蔵していたもので、彼は自身の作品の着想源として用いました。経糸:綿(Z3/45)、緯糸:絹と綿、パイル:羊毛。館蔵番号:719-1897】伝統衣装と近現代の衣装を並べて紹介していた。左側(女性衣装)・長衣(ドレス)と頭巾・赤い幾何学模様や植物文様の刺繍が特徴的。・パレスチナやシリアなどレヴァント地域の伝統衣装「ターブ(thobe)」に似たスタイル。・幾何学刺繍は「護符的意味」や「婚礼衣装」としての役割を持つことが多い。中央(短い上衣)・黒いビロード地に金糸刺繍のジャケット(上衣)・豪華な金の唐草模様 → 都市部の上流階級用、あるいは儀礼用衣装。・オスマン帝国の宮廷衣装やバルカン地方の礼装の影響も感じられる。右側(現代衣装)・白い長衣(コートドレス)・フード付きで、伝統的な女性衣装(ヴェール、アバーヤ)をモダンに再解釈したデザイン。・現代のファッションデザイナーによる「イスラム的伝統衣装の再解釈」を示す可能性が高い。「Taqsireh jacketBethlehemAbout 1900–20Bethlehem is famous for tahriri (couching), an embroidery technique where gold orsilver cord is coiled on the fabric in swirling patterns. Particularly during the British Mandate period (1918–48), woven cottons were imported from England. The maker of this jacket used a British houndstooth fabric for its lining, as a sign ofhigh status and high fashion.Metallic thread and cotton cord on velvet, cotton liningMuseum no. T.128A-1933Given by Miss H. Orwin」 【タクシーレ・ジャケットベツレヘム約1900–1920年ベツレヘムは タフリリ(tahriri) と呼ばれる刺繍技法で知られています。これは金または銀のコードを布地に渦巻き状に縫い付ける技法です。特にイギリス委任統治期(1918–48年)には、イギリスから輸入された綿織物が用いられました。このジャケットの製作者も、裏地にイギリス製の千鳥格子の布を使用しており、それは高い地位と流行性を示す印でした。素材:ビロード地に金属糸と綿コード、裏地に綿館蔵番号:T.128A-1933寄贈者:ミス H. Orwin】イスラーム建築装飾タイルの展示。青緑色のタイル片が壁面に組み合わせて配置されており、元来はモスクやマドラサなど宗教建築の外壁や内部を飾っていたものであろう。特徴色彩と素材・トルコ石ブルー(ターコイズ)やコバルトブルーの釉薬が主体。・光沢ある鉛釉を用いた陶製タイル。意匠・カリグラフィー(アラビア文字装飾) 長方形パネルにクーフィー体やナスフ体で書かれたコーラン章句や奉献文が見られる。・幾何学文様 中央の大きな正方形タイルは、星形や多角形を連ねた幾何学パターン。・植物文様(アラベスク) 唐草や蔓草模様を組み合わせ、無限に伸びる自然を象徴。近づいて👈️リンク。このタイルは、墓の入り口を囲むカリグラフィー模様のフリーズから取られたもの。ブヤンクリ・ハーンの名が刻まれており、ウズベキスタンのブハラにある彼の墓の上に建てられた壮麗なドーム型霊廟の装飾の一部。ターコイズ色の釉薬に、アラビア語カリグラフィー(浮彫)が施されていた。想定される銘文وفوق كل ذي علم عليمWa fawqa kulli dhī ʿilmin ʿalīm「あらゆる知識を持つ者の上に、さらにより深く知る御方がいる。」 → 神(アッラー)の絶対的な知識を示す表現 とネットから。「Carved TilePlease touchThis reproduction shows part of the ornamental frieze near the top of this display (2). The potter made the pattern by carving into the earthenware tile itself. The tile wasthen coated with glaze and fired.Use your fingers to see how deeply carved the tiles are. The pattern is 20 mm deep in places.」 【彫刻タイル(どうぞ触ってみてください)これはクルアーン第12章(ユースフ章, Yusuf, 12:76)の一節であると。この複製は、この展示の上部付近にある装飾フリーズ(帯状装飾)の一部を示しています。陶工は、素焼きタイルそのものに直接模様を彫り込んで文様を作りました。その後、釉薬をかけて焼成しました。指で触って、どれほど深く彫られているかを確かめてみてください。場所によっては模様の深さは20ミリに達します。】これは 「Carved Tile(彫刻タイル)」展示のバリアフリー用パネル(触知パネル)。これも「ブヤンクリ・ハン廟(Tomb of Buyanquli Khan)」展示の一部。左側(縦長の柱状タイル)・模造された柱(実際には壁面の装飾要素)に取り付けられたタイル断片。・ターコイズ色釉をかけた浮彫装飾。・下から上まで幾何学模様+唐草アラベスク+銘文帯が連続している。・頂部の四面体は「柱頭(キャピタル)」を模しており、立体的なデザイン。右側(小型タイル片)・白い浮彫で書かれたアラビア語銘文が確認できる。・書体はナスフ体的で、先ほどの「وفوق كل ذي علم عليم」 (知識の上にさらに知る御方がいる)などと系統の句。・背景は唐草で埋め尽くされ、文字と文様が一体化。上部右(大きな正方形パネルの一部)・星形・多角形が組み合わされた幾何学タイル模様。・これは「無限の秩序」「神の完全性」を象徴。「Tomb of Buyanquli KhanAt Bukhara in Uzbekistan, a magnificent domed mausoleum was erected overthe grave of a Muslim descendant of the great Mongol conqueror Genghis Khan.For a time this man, Buyanquli Khan, was the puppet ruler of much of Central Asia,but in 1358, when he tried to assert his own authority, he was assassinatedbya local warlord.Buyanquli’s tomb was built in a cemetery on the outskirts of Bukhara.The entire building was covered in tiles, inside and out.The tiles were deeply carved with inscriptions and other ornament, and covered withcoloured glazes before the final firing. This impressive technique was used inCentral Asia only for a brief period, from around 1350 to the early 15th century.」【ブヤンクリ・ハンの霊廟ウズベキスタンのブハラにおいて、偉大なモンゴルの征服者チンギス・ハンのイスラーム教徒の子孫の墓の上に、壮麗なドーム型霊廟が建てられました。この人物ブヤンクリ・ハンは、一時は中央アジアの広い範囲における傀儡支配者でしたが、1358年に自らの権威を主張しようとした際、地方の軍閥によって暗殺されました。ブヤンクリの霊廟はブハラ郊外の墓地に建てられ、建物全体が内外ともにタイルで覆われていました。そのタイルは銘文やその他の装飾を深く彫り込み、最終焼成の前に彩色釉を施すという技法で作られました。この高度な技法は中央アジアでは短期間しか用いられず、1350年頃から15世紀初頭にかけての時期に限られています。】左側(縦長の柱状タイル)をズームして。「South Asian SculptureSculpture in South Asia is primarily a religious art.The three great religions — Buddhism, Jainism and Hinduism — offer salvation throughescape from the cycle of death and rebirth. Images, as a focus of meditation andworship, play an important role in this process. Some also have a protective function.Stone images of gods and saviours began to appear about 2000 years ago. Stone reliefs were carved for temples and other religious buildings. At the temples, as became more elaborate, sculptures came to line the walls as well as occupying the inner sanctuary. There were also bronze icons, placed in temples and household shrines, and carried in processions.Hindus believe that during worship the deity actually inhabits the image. They bathe,dress, garland and offer food to their images, giving them a very different appearancefrom what you see here. Although Jain worship includes some similar actions,these are simply to focus the worshipper’s mind and help him or her on thespiritual path.」 【南アジア彫刻南アジアにおける彫刻は、主に宗教美術です。三大宗教――仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー教――はいずれも「死と再生の輪廻からの解脱」を救済の道として掲げています。その過程において、瞑想や礼拝の対象となる尊像(イメージ)は重要な役割を果たし、ときに護符的な機能も担います。神々や救世主の石像は、約2000年前に登場しました。石彫レリーフは寺院や宗教建築のために作られました。寺院がより壮大になるにつれ、彫像は壁面を飾るだけでなく、内陣にも安置されるようになりました。また、寺院や家庭の祠に置かれる青銅像や、祭礼の行列で担がれる像もありました。ヒンドゥー教徒は、礼拝の際に神が実際に像の中に宿ると信じています。そのため像を沐浴させ、衣を着せ、花輪をかけ、食物を供えます。これにより、展示されている姿とは大きく異なる外観を持つことになります。ジャイナ教においても似たような行為がありますが、それはあくまで信者の心を集中させ、精神的な道を進むための助けとされています。】「South Asian Sculpture(南アジア彫刻)」セクションに展示されている実物の彫像群。① 左端の黒色大像・材質:黒色石(玄武岩や黒色片岩が多い)・姿勢:結跏趺坐(足を組んで瞑想する姿)、右手を膝に置く =「触地印(bhūmisparśa mudrā)」の可能性。・特徴:僧衣をまとい、顔は静謐、目は半眼。頭部に螺髪(らほつ)。・信仰上の意味:これは仏陀像(Buddha)もしくはジャイナ教の「ティールタンカラ (Tīrthaṅkara)」像の典型的表現。特に両肩が裸で禅定坐像に近い造形はジャイナ像に多い。・時期:グプタ朝(4〜6世紀)から中世インド(10〜12世紀)にかけてよく見られるスタイル。② 中央の小像・材質:黄褐色石材またはテラコッタ。・姿勢:両手を胸の前で組む祈祷姿。・解釈:信徒像または菩薩像。衣装から俗人(信者像)の可能性も高い。寺院参拝者や 供養者を表す「供養者像(donor figure)」か。③ 右端の小像・材質:灰色石材。・姿勢:やや前傾、片手を胸、もう一方を下げる。・解釈:仏弟子(比丘)や菩薩像。衣装が簡素で僧形に近い。全体の展示意図・左の大像=礼拝対象(仏またはティールタンカラ)。・中央・右の小像=供養者、菩薩、弟子などの補助的像。寺院建築の壁龕や参道に置かれ、 信仰の場を荘厳した。・上部の横長レリーフ(壁彫)=仏伝や神話場面の一部。寺院の梁や門の装飾。「Buddhist Sculpture(仏教彫刻)」についての解説。「Buddhist SculptureBuddhists aim to end suffering by extinguishing desire. After achieving enlightenment,it is possible to enter nirvana and escape the cycle of death and rebirth.The religion originated in India where the historical Buddha (about 485–405 BC)discovered and taught the way to enlightenment. Buddhists also began to worship past and future Buddhas, as well as bodhisattvas, who postpone their own nirvana to help others attain enlightenment.Buddhist sculpture comes from monasteries, temples and sacred relic mounds.Some of the monasteries were housed in huge, specially excavated cave complexes.」【仏教彫刻仏教徒は、欲望を消し去ることで苦しみを終わらせようとします。悟りを開いた後は、涅槃に入って生死の輪廻を脱することが可能となります。仏教はインドで成立しました。歴史的釈迦(紀元前485〜405年頃)が悟りを得て、解脱への道を説いたのが始まりです。やがて仏教徒は、過去仏や未来仏をも崇拝するようになり、また、自らの涅槃を延期して他者の悟りを助ける菩薩(ボーディサットヴァ)も礼拝の対象となりました。仏教彫刻は、僧院、寺院、仏塔などの聖なる遺跡から伝わっています。中には、巨大な人工の石窟群に僧院が収められている例もあります。】「Buddha ShakyamuniAbout 1100–50Pala periodThe historical Buddha was called Shakyamuni (‘Sage of the Shakya clan’).He abandoned his princely life to seek a way to escape the cycle of death and rebirth.Here he is shown just before his enlightenment. Seated in meditation, he calls the earth to witness his successful resistance to the temptations of the evil god Mara. After achieving enlightenment and teaching his new way, he entered nirvana.BasaltEastern India (Patna District, Bihar)Given by the Architectural AssociationMuseum no. IM.112-1916」 【釈迦牟尼仏(Shakyamuni Buddha)1100〜1150年頃パーラ朝時代歴史的仏陀は「シャーキャ族の聖者(釈迦牟尼)」と呼ばれます。彼は王子としての生活を捨て、生死の輪廻から解脱する道を探し求めました。ここでは、悟りを開く直前の姿が表されています。瞑想する彼は、大地を証人として呼び出し、悪魔マーラの誘惑に打ち勝ったことを示しています。悟りを開き、新しい教えを説いた後、最終的に涅槃に入りました。材質:玄武岩インド東部(ビハール州パトナ地区)建築協会からの寄贈所蔵番号 IM.112-1916】左奥の入口には「SOUTH ASIA」と表示のあるアーチ型の入口。中に進むと、南アジア美術の展示室が広がっていた。1. 右手前(大きな立像と動物像)・手前の台座に載っているのは、神像とヴィークル(乗り物動物像)。・彫刻様式や姿勢から見て、ヒンドゥー神話の神(例:シヴァまたはヴィシュヌ)と その乗り物(ナンディ牛、あるいは他の動物神)であろう。2. 中央奥(3体の像)・左側:赤みを帯びた石像。豊かな装飾を伴うヒンドゥー神像(例:ガネーシャや戦神)。・中央:アーチ形の石彫は、寺院の扉口や後背光(トラーナ)として用いられたもの。 周囲に細密な彫刻が。・右側:小ぶりな像で、こちらも神像だろう。3. 左側(床に近い位置)・小さな石像が壁際に置かれていた。こちらも南アジアの宗教彫刻 (仏教またはヒンドゥー教関連か)南インド寺院の柱彫刻に多い「ヤクシャ/ガルダ/護法神像」。「寺院の門番/護法像(Dvarapala, “Temple guardian”) と。南インド(おそらくケーララ/南西インド)で 1600–1800年頃 に作られた木像(チークなど)の寺院建築彫刻で、悪魔(アスラ)を押さえつける護衛神として門や柱上の持ち送り(ブラケット)に据えられていた と。・像の怒りの表情・大きな宝冠・筋肉的な体躯、そして足元の悪魔を制圧するポーズは、 南インド寺院のドヴァラパーラ(門番神)の定型。・ドゥルガー(魔牛退治)やナーラシンハ(獅子頭)に固有のアイコン(バイシャ、 獅子頭など)が見られず、戦闘する人神が悪を踏むというより汎用の護法像。「Hindu Sculpture, Southern IndiaHinduism in southern India is conspicuous for its gigantic temple complexes, oftenforming the core of the city. Their architecture and sculpture are very distinct fromthose of the north. The deities can take different forms, and some are unique to the south.The worship too is different. As well as the Sanskrit liturgy that originated in north India, there are hymns in local languages such as Tamil. These were composed from the 6th century onwards by revered poet-saints who instituted a new form of worship centredon love for the deity.」 【ヒンドゥー教彫刻(南インド)南インドのヒンドゥー教は、その巨大な寺院建築群によって際立っており、しばしば都市の中心を形成しています。その建築と彫刻は北インドのものとは大きく異なります。神々はさまざまな形を取り、南インド独自の姿を持つものもあります。礼拝の仕方も異なります。北インドに起源をもつサンスクリット語の典礼に加えて、タミル語などの現地語による讃歌も存在します。これらは6世紀以降、尊敬される詩人聖者たちによって作られ、神への愛を中心とする新しい礼拝の形を生み出しました。】南アジアギャラリーの一角で、手前に見えているのはインドの寺院建築の石柱(コラム/ピラー) が再構成された展示。・出自:インドのヒンドゥー寺院(多くはグジャラートやラージャスターンの中世寺院遺構から 移された石柱群)。・時代:中世後期(おおむね12~15世紀)。・特徴:・各柱は砂岩や大理石で作られ、柱頭(キャピタル)には蓮弁や神像などの装飾。 ・本来は寺院の回廊やマンディラ(集会堂)を支える建築要素。 ・V&A ではこれを「インド寺院の柱廊再構成」として展示し、建築空間を体験的に理解できる ようにしていた。奥の赤い壁面に飾られているのは カラムカーリ textiles(南インドの更紗布) で、柱と組み合わせることで「宗教空間と装飾芸術の融合」を示す展示構成になっていた。「中世~ルネサンスの象牙工芸セクション」象牙細工による キリスト教宗教彫刻(聖母マリア像や信仰的場面を表現した小像)。・No. 7(左端):小型の聖人像(詳細は像の手の持ち物次第だが、聖母子像の可能性が高い)。・No. 9:無原罪の御宿りの聖母(Immaculate Conception)の大型象牙像 三日月(欠けた月)と雲/天使の群れのような基台が確認できる。 ヒスパノ=フィリピン/ゴア象牙で頻出する聖母像の構成。・No. 5(中央):壮麗な多層構造の彫刻で、キリストの受難や最後の審判の場面を象牙に 細密に刻んだ「レリクアリー(聖遺物容器)」型。・No. 10:聖母マリア像(立像、祈りの姿)・No. 8:幼子イエス(Santo Niño/Christ Child)・No. 11(右手前):祈りを捧げる女性像(多くの場合「聖母マリアの嘆き」あるいは 「マグダラのマリア」の表現と解釈される)。髪を垂らし、両手を 合わせて祈る姿。・No. 3(右端):複数の人物を積み上げた構成で、典型的な「キリスト磔刑」や「受胎告知」 場面を小型にした祭壇的オブジェの一部と推測。「ARRIVAL OF THE EUROPEANSEuropean merchant-adventurers first came to India in the wake of Vasco da Gama’s discovery of the route around the Cape of Good Hope in 1498. The Portuguesequickly set up trading posts first on the West coast of India and then in Bengal. Their main interest was in the spice trade between South-East Asia and Europe, which made use of Indian textiles largely as items of exchange for spices, but high-quality local textiles were also exported directly back to Portugal. Furniture, based on European styles but made with Indian materials, was produced by localcraftsmen both for export and for Portuguese communities in India.」 【ヨーロッパ人の到来ヨーロッパの商人兼冒険家たちがインドに初めて到達したのは、ヴァスコ・ダ・ガマが1498年に喜望峰を回る航路を発見した後のことであった。ポルトガル人はすぐにインド西海岸、さらにベンガルに交易拠点を築いた。彼らの主要な関心は東南アジアとヨーロッパ間の香辛料貿易であり、その交換品としてインドの織物が広く利用されたが、高品質な地元の織物は直接ポルトガルへも輸出された。また、ヨーロッパの様式に基づきつつインドの素材を用いた家具も、現地の職人によって製作され、輸出用だけでなくインド在住のポルトガル人共同体にも供給された。】この展示は「Pre-Mughal India(ムガル帝国以前のインド)」 の解説で、タイトルの副題は 「The Sultanate Tradition(スルターン朝の伝統)」「PRE-MUGHAL INDIATHE ISLAMIC TRADITIONIslamic kingdoms emerged in the Indian subcontinent as early as the 8th century with the arrival of the military governors sent by the Muslim caliphs of Damascus.India became the empire from which Muslim control of the entire Indian subcontinent was established. In 1206, Delhi was taken and the first Muslim sultanate was established there. From Sind in the west to Bengal in the east. By 1335 most of the subcontinent, with the exception of the far south, was brought under the control of the Delhi Sultans. The fragile confederation proved ungovernable and quickly disintegrated into a series of independent Muslim states.The courts of these Muslim rulers generated a distinctive style in the arts. Elements of the local Indian tradition, practised by local craftsmen whom the new rulers employed to design temples, were united with aspects of Islamic culture—mostobviously, the styles prevailing in Iran. The resulting Sultanate style, preserved in painting and architecture, was a blend which reflected Iranian style throughthe prism of Indian traditions.」【ムガル帝国以前のインドイスラームの伝統イスラーム王国は、8世紀にダマスカスのカリフが派遣した軍事総督の到来とともに、インド亜大陸に現れた。インドはやがて、ムスリムによる亜大陸全体支配の拠点となった。1206年、デリーが攻略され、最初のイスラーム王朝(スルターン朝)がそこに樹立された。西はシンドから東はベンガルに至るまで、1335年までには南端部を除く亜大陸のほとんどがデリー・スルターンの支配下に入った。しかしこの脆弱な連合体は統治が困難で、すぐに分裂し、一連の独立したイスラーム政権へと崩壊していった。これらムスリム支配者の宮廷は、独自の美術様式を生み出した。新しい支配者たちが雇用した現地の職人たちは、寺院の設計に従事していたが、その技術はイランで流行していた様式などイスラーム文化の要素と結合した。その結果生まれた「スルターン朝様式」は、絵画や建築に残されており、イラン的な様式をインド的伝統のプリズムを通して表現した折衷的なスタイルとなった。】 インド美術の展示ケースの一部で、ムガル期から植民地期にかけての工芸品。1.大きな黒地に象牙象嵌(inlay)のキャビネット(左)・表面には幾何学文様や花模様のほか、人間や動物の小像が細かく象嵌されています。・こうしたキャビネットは、ポルトガルとの交易期にインドで制作され、ヨーロッパへ 輸出されたり、インド在住のポルトガル人社会で用いられたりしました。2.キャビネット扉部分(中央拡大図)・左右のパネルに、人物図(多くは宮廷人物、あるいは宗教的人物)が並んでいます。・インド産の黒檀やサンダルウッドに象牙をはめ込む「象牙象嵌細工」の代表例。3.壁面に掛けられた小型パネル(右上)・花瓶文様を左右対称に描いた象牙象嵌。・ヨーロッパ輸出用の家具装飾やパネルとして人気がありました。4.棚に並んでいる金属器(右中段)・ゴロク形の容器、丸形の小箱、瓶など。・真鍮や銅合金に金銀象嵌を施す技法で、デカン地方や北インドで盛んに作られたもの。5.右下の大きな吹き口のある器(おそらく水煙管用)・金属製の豪華なパイプ部分。ムガル期の貴族が嗜んだ水タバコ(フッカー/フーカ)の 器具と思われます。象牙象嵌(inlay)のキャビネットをズームして。1. 左側:幾何学文様パネル・全体が花唐草や幾何学的なアラベスク模様で埋め尽くされています。・この部分はヨーロッパ的「装飾板」の要素が強く、宗教的図像は含まれていません。2. 中央:小区画に分かれた人物象嵌パネル・格子状に仕切られた区画に、小型の人物像(座像や立像)が一人ずつ象嵌されています。・多くは王侯風の衣装(ターバン、長衣)をまとった人物。・右下には女性楽士や踊り子と見える像もあり、これはムガル宮廷文化の要素を反映している と考えられます。・つまり「宮廷の日常」「臣下と貴族」「音楽や舞踊」といった場面が細分化して表現されている。3. 右側:大型人物象嵌パネル・中央に大きく立つ人物(豪華な衣装、宮廷の支配者像に見える)。・周囲には樹木、侍従、音楽を奏でる人々などが描かれ、宮廷の庭園風景を想起させます。・構図としては「王(あるいは総督)と従者」という典型的な権威図像これらのパネルは、インドの工芸職人が象牙象嵌で制作した「ムガル宮廷文化の場面」 をモチーフにしており、ヨーロッパの注文品(ポルトガル商人や宣教師向け)として製作されたもの と。「1. CABINET ON STANDWood, veneered and inlaid with ivoryGujarat or SindhCabinet: late 17th or early 18th centuryStand: English, mid-18th centuryIn the late 17th century two-door cabinets replaced portable ‘fall-front’ cabinets as the type most usually produced in western India. This reflected a similar changein European cabinets, which increasingly became showpieces mounted on stands. Although the form of this cabinet is based on western models, its decoration derivesfrom Mughal painting. The stand was made later, in England, and decoratedin the Chinese style.(On loan from Dr and Mrs Poteliakhoff)」 【1. 台付きキャビネット材質:木材(象牙象嵌、突板仕上げ)産地:グジャラートまたはシンド地方(インド西部)キャビネット本体:17世紀後期~18世紀初頭台(スタンド):イギリス製、18世紀中期17世紀後期になると、西インドでは持ち運び可能な「落し前板式(fall-front)」キャビネットに代わり、両開き扉付きのキャビネットが一般的に作られるようになった。これはヨーロッパにおけるキャビネットの変化と呼応するもので、ヨーロッパでもキャビネットは台の上に載せられる「見せる家具」となっていった。このキャビネットの形式自体は西洋のモデルに基づいているが、装飾はムガル絵画に由来している。スタンド部分は後にイギリスで製作され、中国風の装飾が施されている。(ポテリアコフ夫妻の貸与品)】ムガル時代~植民地初期のインド衣装や、インド更紗を使ったヨーロッパ衣装。・名称: Jama(ジャーマ)・素材: ムスリム(細いモスリン布)、銀箔装飾、甲虫(ビートル)の翅の緑色の光沢片を 縫い込んだ装飾・制作地: ビカネール(ラージャスターン州、インド)・年代: 約1855年・用途: ・1500年代から1800年代にかけて、インドの宮廷で男性が着用した衣装 ・この赤いジャーマは、豪華な銀箔の縁取りと甲虫の翅による虹色の装飾で際立っている。 ・付属の古いラベルから、かつてラージャスターンのビカネール藩王の所有であったことが 示唆される。上の赤い衣装と同じくインド宮廷で男性が着用した 「Jama(ジャーマ)」 。ただしこちらは、赤+金の豪華絢爛な儀礼用ジャーマとは異なり、より繊細で落ち着いた色調のジャーマ。・色彩: 白~生成りの地に、赤と金の小花文様が規則的に散らされている。・装飾: 袖口、襟、裾には金織りの縁取り。・形態: 長い裾を持ち、前で重ね合わせるスタイル。胸元で帯状布(パッタ)を結ぶ。・袖: 赤いジャーマと同じく長いギャザー入りの袖で、手首に密着するデザイン。「ShawlPashmina (goat hair), twill tapestry weaveKashmir, 1800–20Kashmir shawls have a long history of courtly popularity. The Mughals stronglysupported production and introduced the first floral motifs into shawl designs. Maharaja Ranjit Singh, who annexed Kashmir in 1819, was said to line the interiors of tents with them. Kashmir shawls also enjoyed royal favour abroad. Several portraits of Empress Josephine of France feature her wearing a bright red Kashmir shawl of the same style as the one displayed here.【ショールパシュミナ(山羊毛)、綾織タペストリー織カシミール、1800~1820年カシミール・ショールは宮廷で長く人気を博してきた。ムガル帝国はその生産を強く支援し、ショールのデザインに初めて花模様を導入した。1819年にカシミールを併合したマハラジャ・ランジート・シングは、天幕の内部をショールで覆ったと言われている。カシミール・ショールは海外の王侯からも愛され、フランス皇后ジョゼフィーヌの肖像画にも、ここに展示されているものと同様の真紅のカシミール・ショールを身に着けた姿が描かれている。】 「JamaMuslin embellished with silver-gilt and beetle-wing casesBikaner, Rajasthanc. 1855Made of fine muslin, the jama was worn by men at many Indian courts from aboutthe 1500s to the 1800s. This red jama is richly decorated with silver-gilt trimmingsand pieces of emerald-green wing cases from Indian jewel beetles. An originallabel found inside suggests it once belonged to the Maharaja of Bikaner, a princely state in Rajasthan.【ジャマモスリン(細布)、銀鍍金と甲虫の翅殻による装飾ラージャスターン州ビーカーネール約1855年上質なモスリン製のジャマは、1500年代から1800年代にかけて多くのインド宮廷で男性によって着用された。この赤いジャマは、銀鍍金の縁飾りとインド玉虫のエメラルドグリーンの翅殻で豪華に装飾されている。内部に見つかった元のラベルから、この衣装がかつてラージャスターンの藩王国ビーカーネールのマハラジャの所有であったことが示唆されている。】 こちらは、4点の額装されたインドの絵画展示。19世紀初頭のカルカッタ(コルカタ)で制作された「パタ絵(Kalighat painting)」様式。<「BALABHADRA, SUBHADRA AND JAGANNATHA」に対応する水彩画 と。寺院参詣者への土産・信仰画として流通したもの と。描かれているのは、オディシャ州プリーの ジャガンナータ寺院で崇拝される三神像。左から順に以下のように解釈されます:1.バラバドラ(Balabhadra / Balarama)・ジャガンナータの兄・白い顔で表され、落ち着きと力強さを象徴2.スバドラ(Subhadra)・ジャガンナータとバラバドラの妹・黄色い顔で、小柄な姿3.ジャガンナータ(Jagannatha)「世界の主」・クリシュナ神の一形態で、黒い顔・クリシュナの「暗い色=黒」を象徴している特徴・三神は 大きな円形の眼と赤い縁取り を持ち、寺院像の特徴を忠実に表しています。・手や足の表現は簡略化され、独特の儀礼的な踊りのポーズをとっています。・このような絵画は、巡礼者向けの土産や信仰用の画像として、18世紀末~19世紀初頭に カルカッタで広く制作されました。・タイトル:カーリー女神(Kali) ・制作技法:紙に水彩(カルカッタ派「パタ絵」様式) ・制作地:カルカッタ(現コルカタ、インド) ・制作年:19世紀初頭〜中頃(c. 1800–1850)・タイトル:サラスヴァティ女神(Saraswati) ・素材・技法:紙に水彩(カルカッタ派「パタ絵」様式) ・制作地:カルカッタ(現コルカタ、インド) ・制作年:19世紀前半(c. 1800–1850)「BALABHADRA, SUBHADRA AND JAGANNATHAWatercolour and tin alloy on paperCalcutta (now Kolkata)c. 1800The Jagannatha Trio, comprising Jagannatha (Lord of the World), his older brotherBalabhadra and little sister Subhadra are worshipped at the 12th-century temple of Jagannatha in Puri, Odisha. Jagannatha is a form of the Hindu god Krishna, so he is painted black to signify the dark colours associated with Krishna. The deities in thePuri temple have big circular eyes with red outlines, brilliantly evoked in the hypnoticgazes of the trio here.」 【バラバドラ、スバドラ、そしてジャガンナータ紙に水彩と錫合金カルカッタ(現コルカタ)約1800年ジャガンナータ三神像は、世界の主「ジャガンナータ」、その兄バラバドラ、妹スバドラから成り、オディシャ州プリーにある12世紀創建のジャガンナータ寺院で崇拝されている。ジャガンナータはヒンドゥー教の神クリシュナの一形態であり、そのため黒色に描かれており、これはクリシュナに関連する暗い色を象徴している。プリーの寺院の神像は、大きな円形の目に赤い縁取りが特徴であり、ここでも三神の催眠的なまなざしとして鮮やかに表現されている。】インドの宮廷支配者(マハラジャ)の肖像画。・服装:白い長衣(ジャマ, jama)に金糸刺繍の上衣を羽織り、頭にはターバンを巻き、 胸には宝飾品(真珠や宝石の首飾り)を多く掛けています。・装備:右手に長剣(タルワール、あるいはサーベル型の刀)を持ち、腰にも刀を佩いています。 武人としての権威を示す姿勢。・背景:南国の椰子の木が見える庭園のテラス。植民地期ヨーロッパ風の建築表現も含まれて おり、宮廷肖像と植民地絵画の折衷。・様式:写実的な陰影や空気遠近法から見て、ヨーロッパ人画家による油彩肖像画である 可能性が高い。18世紀後半〜19世紀初頭に流行した「Company Painting (カンパニー絵画)」の一種か、西洋画家が直接宮廷に招かれて描いたもの。「MUHAMMAD ALI KHAN, NAWAB OF ARCOT AND THE CARNATICOil on canvasby Tilly Kettleabout 1770This painting is an early example of western- style portraiture at an Indian court. The artist Tilly Kettle was one of the first English painters in India. He depictsthe pro-British Nawab of Arcot, a popular figure in Madras society. The ruler is shown dressed in lavish robes and jewels.」 【ムハンマド・アリ・カーン ― アルコットおよびカルナーティックのナワーブキャンバスに油彩画家:ティリー・ケトル制作:約1770年この絵画は、インド宮廷における西洋風肖像画の初期の例です。画家ティリー・ケトルは、インドで活動した最初期のイギリス人画家の一人でした。彼は、マドラス社会でよく知られていた親英派のアルコットのナワーブを描いています。支配者は豪華な衣服と宝飾をまとった姿で表されています。】「SCREENS OR BALUSTRADESCarved and pierced marbleNorth India1700–1850Screen panels of pierced stone were a distinctive feature of Indian architecture, especially in the northern parts of the country. These marble examples arecarved with alternating floral and non-figurative (arabesque) motifs. The screens may have been part of a balustrade on the outside of a building, such as on a terrace.」 【透かし彫りのスクリーンまたはバラスター飾り大理石製(彫刻・透かし彫り)北インド1700–1850年透かし彫り石のスクリーンパネルは、インド建築の特色ある要素で、とくに北インドで盛んに用いられました。ここに展示されている大理石の例は、花文様と非具象(アラベスク)模様を交互に刻んだものです。これらのスクリーンは、テラスなど建物外側の欄干の一部として使われていた可能性があります。】1.タンブーラ(Tambura / Tanpura) 左端の長い弦楽器。インド古典音楽における持続音(ドローン)を奏でる伴奏楽器。2.タブラ(Tabla) 中央の2つの小太鼓。北インド音楽で最も重要な打楽器。大小一対で演奏する。3.サロード(Sarod)またはルドラ・ヴィーナ(Rudra Veena) 中央右寄り、共鳴胴(瓢箪のような丸い部分)が付いた弦楽器。インド古典音楽に 使われる主要楽器の一つ。4.ヴィーナ(Vina / Saraswati Vina) 右端の瓢箪形の共鳴体を持つ弦楽器。南インド音楽(カルナータカ音楽)の代表的な楽器。5.その他の楽器 上段中央の四角い箱型の楽器は「サーランギー(Sarangi)」か「サントゥール(Santoor)」 の一部の可能性あり(擦弦あるいは撥弦楽器)。インド古典音楽の楽器展示。南インドと北インドの楽器が一堂に並べられていた。「MUSICAL WONDERSThere are rich traditions in South Asia of classical, folk and devotional music.Indian classical music consists of a series of improvisations within ragas. These are melodic frameworks, each using certain notes and progressions and evoking a particular mood. Every performance is unique.These 19th-century instruments are from the V&A collection. Some were acquiredbecause of their beautiful decoration. Many of the instruments in the collection weretransferred from London’s India Museum when it closed in 1879. The V&A acquired others from leading musicologists of the day, notably Carl Engel in 1882; and Rajah Sir Sourindro Mohun Tagore, who gave a large collection in 1890. Several of these remarkable instruments are of an unusual or experimental nature.The display formed part of a digital project ‘Musical Wonders of India’, created in partnership with Darbar Arts Culture Heritage Trust.Supported by The Helen Hamlyn Trust」 【音楽の驚異南アジアには、クラシック、民俗音楽、信仰音楽の豊かな伝統があります。インド古典音楽は ラーガ(ragas) の枠組みの中での即興演奏によって構成されます。ラーガとは旋律の枠組みであり、それぞれが特定の音階や進行を用い、特定の感情や雰囲気を呼び起こすものです。そのため、演奏は一つとして同じものがなく、常に独自のものになります。ここに展示されている19世紀の楽器はV&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)のコレクションに属するものです。その一部は、美しい装飾が評価されて収集されました。収蔵品の多くは、1879年に閉館したロンドンのインド博物館から移されたものです。その他は、当時の著名な音楽学者カール・エンゲル(Carl Engel, 1882年)や、ラージャ・サー・スーリンドロ・モーハン・タゴール(Sourindro Mohun Tagore, 1890年に多数を寄贈)によって収集されました。これらの中には、珍しい形態や実験的な性格を持つ楽器もいくつか含まれています。この展示は、ダルバール・アーツ文化遺産トラストと協力して制作されたデジタル・プロジェクト 「インド音楽の驚異」 の一部を構成しています。(左側プレート)ROBESilk, embroidered with silk and metal threadDeccan, IndiaMid–18th centuryローブ素材:絹(シルク)、絹糸および金属糸による刺繍産地:インド、デカン地方制作年代:18世紀中頃(中央プレート)CRADLEGold, set with diamonds, rubies and emeraldsHyderabad, Indiac. 1870ゆりかご素材:金(ゴールド)、ダイヤモンド・ルビー・エメラルドを装飾産地:インド、ハイデラバード制作年代:約1870年頃寄贈:ハイデラバード藩王国 第7代ニザームより協賛:ヘレン・ハムリン財団】インドの衣装(黒地に花模様のローブ)と黄金のゆりかご(Cradle)。「THE KINGDOM OF RANJIT SINGHFrom 1792 until 1839 the Punjab was dominated by the remarkable personality ofMaharaja Ranjit Singh, a Sikh leader whose unique achievement was to weld thedifferent communities of the Punjab into a powerful and stable nation. He employedEuropean mercenary officers to train his army, with brilliant success. While extendinghis frontiers by conquest he skilfully avoided confrontation with the British, the riverSutlej being accepted as a boundary between his territory and theirs. On his deaththe kingdom fragmented and after protracted conflict the Punjab was annexed by the British in 1849.」 【ランジート・シング王国1792年から1839年まで、パンジャーブは卓越した人物ランジート・シング(マハラジャ・ランジート・シング)の存在によって支配されていた。彼はシク教の指導者であり、パンジャーブのさまざまな共同体をまとめあげ、強力で安定した国家に築き上げた点が特筆すべき業績である。彼はヨーロッパ人傭兵将校を雇い入れて軍を訓練させ、大きな成功を収めた。領土を拡張する一方で、イギリスとの衝突を巧みに避け、スートレジ川を両者の領域を隔てる国境とすることで均衡を保った。しかし彼の死後、王国は分裂し、長期にわたる紛争の末、パンジャーブは1849年にイギリスに併合された。】「GOLDEN THRONE OF MAHARAJA RANJIT SINGHSheet gold, cast and chased, on a wooden coreProbably LahoreMade by Hafiz Muhammad of Multan1818 or later, the cushions modernThe first Sikh maharaja of the Punjab was famously modest in his personal appearance. However, he wanted his court setting to be as splendid as possible. The throne was made by Ranjit Singh’s leading goldsmith, probably after the Sikh army captured the important city of Multan (now in Pakistan) in 1818. Contemporary paintings of the throne show that each of the two projecting branches originally hada golden sphere. It was taken by the British from the Sikh treasury after they annexedthe Punjab in 1849.」 【ランジート・シング大君の黄金の玉座素材:木芯に金板を鋳造・彫金して装飾製作地:おそらくラホール作者:ムルタンのハフィズ・ムハンマド制作年:1818年以降(クッションは近代の補作)パンジャーブの初代シク教大君ランジート・シングは、私生活においては有名なほど質素な人物であった。しかし、彼は宮廷の場を可能な限り壮麗なものにしたいと望んだ。この玉座は、彼の宮廷を代表する金細工師によって製作されたもので、おそらく1818年にシク軍が重要都市ムルタン(現パキスタン)を攻略した後に制作された。当時の玉座を描いた絵画には、両側に突き出した枝の先端に金の球体が付いていたことが示されている。この玉座は、1849年にパンジャーブがイギリスに併合された際、シク王国の財庫から英国に接収された。】この女性肖像画は「Native Lady of Umritsur(アムリツァルの女性)」。・作者:ホレス・ヴァン・ルイス(Horace van Ruith, 1839–1923)に帰属 (近年は帰属に疑義ありとの注記もあります)。 ・年代:1880年代(c.1880–85)。 ・技法:油彩/カンヴァス。 ・所蔵:ヴィクトリア&アルバート博物館(旧サウス・ケンジントン博物館)。 館蔵番号 IS.45-1886。ネットから。・目的: 当時のパンジャーブ地方(アムリツァル)の女性が身につけた衣服と装身具を記録的に 描写するために制作されたもの。豪華なザルドージー(金糸刺繍)衣装、ナス(鼻輪)と 耳飾りを鎖で繋ぐ婚礼装束、ハトゥル(手甲飾り)、アンクレットやトゥリングなどが 克明に描かれています。 ・来歴:1886年ロンドン「植民地・インド博覧会」にアムリツァル自治体から出品され、 同年にV&Aが購入。① 衣装(テキスタイル)赤いサテン地:光沢のある赤布には、緑の糸による刺繍模様が施されており、金の縁取りで囲まれています。高価なザルドージー(金糸刺繍)の技法が見られます。青のプリーツ布:下層に広がるスカート(おそらくレヘンガ lehenga)の部分。細かいプリーツで、深い青の染色布。縁取り模様:幾何学文様(○や✕が交互に並ぶ)と金糸の刺繍が確認でき、当時のパンジャーブ地方に見られる婚礼衣装の典型的な意匠。② 装飾品(ジュエリー)手首のバングル:多数の金バングルが腕を覆うように重ねられています。部分的にエナメルや宝石が嵌め込まれたものも見えます。リングとハサトゥリ(手甲飾り):指輪から鎖が伸びて手首のバングルに繋がるジュエリー。北インドの伝統的婚礼装飾で「ハサトゥリ/パンジャ(Haath-phool, Panja)」とも呼ばれる。緑の宝石の指輪:中央の指には大きな緑色の石を用いたリングがはめられ、富と地位を示す。③ 意味合い婚礼時の装飾を克明に描いたもので、インド北西部(パンジャーブ、アムリツァル周辺)の花嫁の正装を記録的に表現した作品である と。特に「赤×緑×金」の組み合わせは婚礼色の典型で、女性の繁栄・富・吉祥を象徴します。「‘NATIVE LADY OF UMRITSUR’Oil on canvasAmritsarc. 1880This painting, shown in the Colonial and Indian Exhibition in London in 1886, is an example of the type of European academic painting being taught in the Schools of Art in India at the time.It also serves as a documentary record of costume and jewellery of the region. The woman wears a full set of head, ear, nose, neck, arm, hand, ankle and footjewellery, and a costume richly decorated with zardozi (gold wire/thread) embroidery.IS.45-1886Presented by the Municipality of Amritsar」【『アムリトサルの女性像』カンヴァスに油彩アムリトサル約1880年この絵画は1886年にロンドンで開催された「植民地・インド博覧会」に出展されたもので、当時インドの美術学校で教授されていたヨーロッパのアカデミック絵画の典型例です。同時に、この地域の衣装や装飾品を記録する資料的価値も持っています。女性は頭、耳、鼻、首、腕、手首、足首、足に至るまで完全な一式の装身具を身に着けており、衣装はザルドージー(金糸刺繍)で豪華に装飾されています。IS.45-1886アムリトサル市より寄贈】 「BRITAIN AND INDIA 1850–1900By 1850 Britain had gained control of nearly two thirds of the subcontinent, and India had become vital to Britain’s world trading system. The direction of trade had changed: the export trade in Indian cloth had collapsed dramatically, even andonce-proud markets had closed, unable to compete with machine-made goods fromthe mills of Manchester and Lancashire. Raw cotton was now being exported to Britainto be manufactured in the Lancashire mills. From the British point of view, India had tobe largely self-financing to pay for its own administration, to provide cash to maintain an army which would ensure peace and stability. Extensive revolts in northern India in 1857, known as the Indian Mutiny (or the First War of Indian Independence) showed the fragility of British control. More than a third of India remained beyond British control. More than a third of India remained beyond British control in the princely states.The British community in India was small in relation to the total population; the greatmajority were employed by government, over a half being in the army. The British weremost visible in the Presidency towns of Calcutta, Madras and Bombay, where theirarchitecture and institutions proclaimed British power and influence. Much of India remained untouched by British influence. There were changes, however, among thegrowing middle classes, that hinted by the mid-century that by 1900 the political movement that was to lead to the independence of the countries of South Asia waswell under way.」 【イギリスとインド 1850–19001850年までに、イギリスはインド亜大陸の約3分の2を支配下に置き、インドはイギリスの世界貿易システムに不可欠な存在となっていました。貿易の方向性は大きく変化し、インド布の輸出は劇的に崩壊しました。かつて隆盛を誇った市場も、マンチェスターやランカシャーの工場で生産された機械織り製品に太刀打ちできず閉鎖されました。その結果、原綿はイギリスに輸出され、ランカシャーの工場で製品化されるようになりました。イギリスの視点から見れば、インドは自国の行政費をまかない、平和と安定を保証する軍隊の維持費を賄うために、ほぼ自立採算で運営されるべきと考えられていました。1857年、北インドで起きた大規模な反乱(インド大反乱、または第一次インド独立戦争)は、イギリス支配の脆弱さを露呈しました。インドの3分の1以上は藩王国(プリンスリー・ステート)としてイギリスの直接支配を超えた地域に残っていました。イギリス人共同体は全人口に比べると小規模で、大多数は政府に雇われ、その半分以上が軍務に就いていました。イギリス人の存在が最も顕著だったのはカルカッタ、マドラス、ボンベイといった大統領管区の都市であり、そこでは彼らの建築や制度がイギリスの権力と影響力を誇示していました。一方で、インドの多くの地域はイギリスの影響をほとんど受けませんでした。しかし、19世紀半ばには新たに台頭してきた中産階級の間で変化が見られ、1900年頃までに南アジア諸国の独立へとつながる政治運動が着実に進行しつつあったのです。】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.29
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクそして中国ギャラリー(China Gallery, Rooms 44–47f)へ。V&A の中国ギャラリーでは、以下のような展示が見られた。・陶磁器(唐三彩、宋磁、青花磁器など)・彫刻(仏像、墓俑)・漆工芸や金属器・書画や家具このように、日本ギャラリーと同様に、中国美術・工芸の 歴史を通観できる構成になっていた。日本展示の隣にあった。・手前中央のガラスケースには、大型の青銅器のような中国古代の工芸品が展示されていた。・周囲には、仏像や陶磁器、彫刻などが並び、壁際のケースにも仏像や工芸品が見えた。・左側には大きな屏風や掛軸のような展示(山水画のパネル)が確認できた。・建築的には高い天井とアーチ状の白い柱列があり、展示室全体を開放的に見せていた。廻り込んで。刺繍や織物(タペストリー)作品。・左(黄色地) 花と鳥を描いた刺繍。おそらく「花鳥図」の伝統に基づき、四季や吉祥を象徴するモチーフ。 梅・牡丹・鳥などが典型的。・中央(青地) 高僧か仙人(道教の人物)を描いた刺繍。周囲に鳥や瑞兆的なモチーフがあしらわれていた。 細かい糸使いで、礼服や壁掛けに用いられたのであろう。・右(淡黄色地) 魚や水草、鳥をあしらった刺繍。豊穣・長寿・吉祥を意味する伝統的意匠。 左端には縦に並んだ 黒地の刺繍裂 があり、器物や花鳥の文様が細かく縫い込まれていた。中国ギャラリーの「Textile furnishings(室内織物調度)」に関する説明。上段(セクション解説)「LIVING – Textile furnishings The textiles shown here were made for wealthy Chinese households. While some were purely ornamental, many served a practical as well as decorative purpose. Certain sets of furnishings were reserved for use only on special occasions.」 【生活 ― 織物調度品 ここに展示されている織物は、裕福な中国の家庭のために作られたものです。 純粋に装飾的なものもあれ ば、実用性と装飾性を兼ねたものもあります。中には特別な 機会にのみ用いられた調度品もありました。】写真中央(床の上に配置された石像・石柱)・石柱(2本):仏教関連の浮彫が施されており、仏や菩薩、小型の仏塔などが段状に 彫られていた 中国の石窟寺院や墓碑用の石柱(唐〜宋代の影響を受けたもの)。・石像(手前):二体並んだ人物像を刻んだ石造彫刻。石仏や供養碑の一部であろう。背景ショーケース(左から右へ)1.赤い織物(左端) 大きな円形の文様が織り出された中国の織物。おそらく 錦織(brocade) で、仏教儀礼 または宮廷用のテキスタイル。2.金色の仏像(中央奥) おそらく 金銅仏(gilt-bronze Buddha)。唐代以降の中国仏像の特徴があり、 堂々とした坐像姿。3.青地に花鳥文の大掛布(右側) 大型の刺繍織物で、壁掛け(hanging)または衣装用の断片。 精緻な花鳥文様が施され、清代の宮廷刺繍に典型的な作例。上段(左から右へ)1.小さな青磁杯(2点) ・高台のある小型の杯。青磁釉で、宋~元代の酒器か祭器と思われます。2.丸壺(青花大壺) ・胴部に龍文が描かれた青花磁器。明代(15~16世紀頃)の景徳鎮窯に典型的なスタイル。3.灰色の双耳壺 ・灰釉陶器で、やや古い様式(唐代~宋代の影響を思わせる)。 ハンドル部に動物形の装飾がある。4.双耳大壺(青花) ・首の両側にドラゴン形の持ち手を付けた大きな青花磁器。細かな唐草文様。 明~清代の景徳鎮製と考えられる下段(左から右へ)1.青磁小壺と皿・小型の瓶と浅皿。宋代龍泉窯の青磁か、それを模した後代のもの。2.白磁皿・灰釉碗など・白磁平皿や青磁小鉢が並ぶ。白磁は定窯系統、青磁は龍泉窯系統。3.青花大皿(中央)・碗形の大皿で、花鳥唐草文が描かれている。 明代後期~清初の輸出磁器によく見られるタイプ。4.青花中皿と小皿・青花で同心円模様や花文が施されている。 17世紀頃の景徳鎮窯の作品か。5.青銅香炉(2点)・右奥にある黒っぽい青銅製の香炉(蓋付)と、さらに右の獣脚を持つ小型香炉。 いずれも明~清代の祭器。V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)中国ギャラリーにある展示の説明で、テーマは 「RULING – Pursuit of Antiquity(統治 ― 古代の探求)」「RULING – Pursuit of AntiquityThe Qing emperors considered themselves protectors of China’s cultural heritage.In the 18th century, ambitious projects were launched to build the palace collections ofantiques. The treasures amassed ranged from calligraphy and paintings by greatmastersto archaic bronze vessels and rare 12th-century imperial ru wares.Catalogues of thecollections were also compiled. This fascination with antiquity alsoinfluencedcontemporary works produced in the imperial workshop: new objects weremadein deliberate imitation of antiques from the past.Nos. 1, 7, 10, 12 and 15 from the Eumorfopoulos collection. Purchased with the assistance of the Art Fund, the Vallentin Bequest, Sir Percival David and the Universities China Committee.」【統治 ― 古代の探求清朝の皇帝たちは、自らを中国文化遺産の守護者と考えていました。18世紀には、宮廷の古美術コレクションを築くために壮大な事業が進められました。収集された宝物は、名匠による書画から古代の青銅器、そして希少な12世紀の宮廷用「汝窯(るよう)」の陶磁器にまで及びました。こうしたコレクションの目録も作成されました。この古代への憧憬はまた、宮廷工房で制作された同時代の作品にも影響を与えました。新たな作品が、過去の古美術を意図的に模倣して作られたのです。(展示品のうち、1・7・10・12・15はエウモルフォプロス・コレクションから。Art Fund、ヴァレンティン遺贈、パーシヴァル・デイヴィッド卿、中国大学委員会の援助により購入。)】壁一面に沿って設置された陶磁器の長い展示ケースで、宋~元~明~清にかけての小型の壺、瓶、盃、香炉、青磁などが並んでいた。陶磁器と青銅器などを一緒に展示。●上段・左端:青花大壺(魚文様、明代末~清初の輸出磁器に典型的)・中央:青銅器(提梁壺=持ち手付き青銅容器、戦国~漢時代を模したものか)・その右:家屋形の青銅容器(祭祀用または埋葬用の模型器の一種)・右端:三彩大壺(唐三彩に類する色釉の大壺)●中段・左:小碗や小皿(唐三彩や緑釉器を思わせる)・中央:白地に赤茶色の文様が施された陶製の注器(イスラーム陶器風、中国で模倣された 「西域風デザイン」か)・右2点:銅または青銅の水差し(唐~宋時代、中国とイスラーム文化圏との交流を示す)・右端:褐釉の注口器● 下段(ラベルが見える部分) 小型の器群(唐代~宋代の輸出陶磁)とみられる。「Chinese wine was made from rice, until the grapevine was introduced to China via the Middle East during the 2nd century BC.Scholars and literati approved of wine, believing that their creative powers werestimulated by alcohol. Consequently, many great poets and calligraphers wereknown for their love of drinking.Wine was also offered to deities and the dead during ritual worship. Jade wine cupshad an added significance for Daoist followers, who believed jade to have a preservingeffect on the body.」【中国の酒は米から造られていましたが、紀元前2世紀に中東を経由してブドウの木が中国に伝わりました。学者や文人たちは酒を良しとし、酒によって創造力が刺激されると信じていました。そのため、多くの偉大な詩人や書家たちは酒好きとして知られていました。また、酒は神々や死者への祭祀においても供えられました。玉(翡翠)の酒杯は道教徒にとって特別な意味を持ち、玉が身体に保存的な効果を与えると信じられていました。】 ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A Museum)内のミュージアムショップが隣に。「Islamic Middle East(イスラム中東)」ギャラリー の入口サイン。・展示範囲 西アジア・北アフリカを中心とするイスラム世界の工芸・美術を扱っています。 展示物は 7世紀のイスラム成立以降~現代まで に及び、地域もスペイン(アンダルス)から インドまで幅広いです。・展示される主な作品 ・イスラム陶器(特にイラン、トルコのイズニク陶器) ・金属工芸(真鍮・銀象嵌器など) ・織物(ペルシャ絨毯、カフタン、刺繍布) ・書道・写本(コーラン写本、装飾的カリグラフィー) ・建築装飾(幾何学・アラベスク模様のタイル、木彫)「Islamic Middle East(イスラム中東)」ギャラリーのイントロダクション展示 。壁面には解説文と、典型的なイスラム装飾タイル(星形・多角形の幾何学パターン)が並んでいた。「The Islamic Middle EastThe rapid rise of Islam in the 7th century AD transformed the history of theMiddle East.The religion was founded by the Prophet Muhammad, and after his death in 632 it wasruled as a religious and political state. Within 100 years it had expanded across threecontinents. By 750 it stretched from the Atlantic Oceanto the borders of India.Two hundred years later this single Islamic empire had fragmented under the numberof competing states. Despite these rivalries, the Muslim rulers of the time sharedmany ideas on culture and politics, as well as religion.This common Islamic heritage was maintained until the 1920s. By then, almostthewhole region was under European colonial control. In most Muslim societies Islam remains the most important source of law, education and culture.Throughout its long political history, art continued to be the principal means of religious expression and a key marker of status in both a religious and a political system.」 【イスラム中東紀元7世紀におけるイスラム教の急速な台頭は、中東の歴史を大きく変革しました。イスラム教は預言者ムハンマドによって創始され、632年の彼の死後、宗教的かつ政治的な国家として統治されました。その100年以内に、イスラムは三大陸に拡大し、750年までには大西洋からインドの国境にまで及びました。その200年後、この単一のイスラム帝国は、複数の競合する国家に分裂しました。しかしこうした対立にもかかわらず、当時のイスラムの支配者たちは、宗教のみならず文化や政治においても多くの理念を共有していました。この共通のイスラム遺産は1920年代まで保持されました。その頃までに、この地域のほとんどはヨーロッパ列強の植民地支配下に置かれていました。現代においても、多くのイスラム社会では、イスラム教が法律・教育・文化の最も重要な基盤であり続けています。長い政治史を通じて、芸術は宗教的表現の主要な手段であると同時に、宗教的・政治的秩序における身分を示す重要な象徴であり続けました。】「Bowl with Sailing Ship・帆船文の鉢」。「Lustre Tiles・ラスター彩タイル」。「Bowl with Sailing Ship(left)Spain, Málaga1425Málaga in Spain was still under Muslim rule when this large bowl was made.The city had been an important centre of lustre production since the early 13th century, and its wares were exported as far as England and Egypt.This bowl may have been made for the export trade. It shows a long-haul sailingship of the period with the arms of Christian-ruled Portugal on its sail.Earthenware under an opaque white glaze, with colour in and lustre over the glazeMuseum no. 486-1864」 【帆船文の鉢(左)スペイン、マラガ1425年この大きな鉢が作られた当時、スペインのマラガはまだイスラム支配下にありました。マラガは13世紀初頭からラスター彩陶の重要な生産地であり、その製品はイングランドやエジプトにまで輸出されていました。この鉢は輸出用に作られた可能性があります。帆にはキリスト教支配下のポルトガルの紋章が描かれた、当時の遠洋帆船が表されています。白濁した白釉の下に陶器胎土を用い、上に彩色とラスター彩を施す。館蔵番号:486-1864】「Lustre Tiles(right)Iran,probably Kashan1262Many innovations originated in theIslamic Middle East. Decorating glazed ceramicswith metallic lustre was one of them. This difficult technique was invented in Iraq in the 9th century. It spread over an areastretching from Spain to Iran, where thesetiles were made.The tiles are from the tomb of a descendant of the Prophet Muhammad at Varaminnear Teheran. The designs, each subtly different, are surrounded by quotations fromthe Qur’an.Fritware painted in lustre over transparent glazeMuseum nos. 1487, 1489, 18376A, C, E, F, 18388C, E-1876; 1077, 10996A, 11006」【ラスター彩タイル(右)イラン、おそらくカーシャーン1262年多くの革新的技法がイスラム中東で生まれました。金属光沢をもつラスター彩で陶器に装飾する技法もその一つです。この難しい技法は9世紀のイラクで発明され、スペインからイランに至る広範囲に広まりました。これらのタイルは、テヘラン近郊ヴァラーミンにある預言者ムハンマドの子孫の墓から出土したものです。それぞれ微妙に異なる文様は、クルアーンの引用句に囲まれています。透明釉の上にラスター彩を施したフリット陶。館蔵番号:1487, 1489, 18376A, C, E, F, 18388C, E-1876; 1077, 10996A, 11006A-1892】 ・左上の大きな青緑色の壺(ターコイズ釉壺) ペルシャ(イラン)でよく見られる12~14世紀の陶器。厚手の胎土に鮮やかなターコイズ釉を 施し、表面には浮彫文様(幾何学模様や植物文様)が見られるのが特徴です。・その下の金属製水差しや陶器 真鍮や青銅に銀象嵌を施した水差し、またガラス器・陶器も見られます。特にエジプト・ シリア地域で盛んに作られた「マムルーク様式」の金属器が含まれている可能性があります。・中央奥の長い縦の展示物(赤褐色) 建築装飾やレリーフ片と思われます。イスラーム建築の壁面を飾ったスタッコ(漆喰彫刻)や タイル断片の可能性があります。・右側のガラスケース 小型の瓶や水差し、壺など。多くはイランやシリアで制作された青釉陶器・ラスター彩陶器。「Transition from AntiquityWhen the Middle East passed under Islamic rule in the 7th century, there was nosudden break in artistic production. Early Islamic art continued much of whathadgone before. Yet it was not a simple transition from one culture to another, since the eastern and western halves of the Middle East were heirs to two distinct artistic traditions.One originated in the Sasanian empire, which had ruled Iraq, Iran and the western part of Central Asia for four centuries before the Islamic conquest. The other was the Christianised form of Roman art we know as Byzantine, which was current in Syriaand Egypt.Islamic art was formed by the merger of these two traditions, and by the gradualaddition of many new elements.」 【古代からの移行中東が7世紀にイスラーム支配下に入ったとき、芸術生産において突然の断絶はありませんでした。初期イスラーム美術は、それ以前の多くを継承していました。しかし、それは単に一つの文化から別の文化への移行ではありませんでした。なぜなら、中東の東西両半は、それぞれ異なる二つの芸術的伝統を受け継いでいたからです。一つは、イスラーム征服以前の4世紀にわたりイラク、イラン、中央アジア西部を支配していたサーサーン朝に由来するものです。もう一つは、我々がビザンツ美術として知る、ローマ美術のキリスト教化された形態であり、シリアやエジプトで広まっていました。イスラーム美術は、これら二つの伝統が融合し、さらに多くの新要素が徐々に加わることによって形成されました。】柱頭(capital、キャピタル)。・柱頭とは、建築における柱の最上部に置かれる部分で、柱と梁・アーチをつなぐ構造材。・写真のものは、ビザンツ美術やイスラーム初期美術でよく見られるスタイル。・手前の柱頭はギリシャ・ローマ建築の伝統を受け継ぐコリント式柱頭 (渦巻き=ヴォリュート装飾とア カンサス葉)に近い形式。・奥の柱頭は葉文様が細かく透かし彫りされ、より装飾的で、光を透かすことで建築空間を 荘厳に演出する特徴を持っている と。「Capitals with Realistic Decoration(bottom and centre)Spain, Córdoba950–75 and 960–80The lower two column capitals are from the palace complex of Madinat al-Zahra nearCórdoba, founded in 936. The lowest has a ‘composite’ form that is entirely Roman,except for the inscription in Arabic along the top edge. The middle capital has the same shape, but the surfaces have been decorated with plant motifs.Carved marbleMuseum nos. A.10-1922; A.55-1925Given by Dr W.L. Hildburgh, FSA」【写実的装飾を持つ柱頭(下部と中央)スペイン、コルドバ950–75年 および 960–80年下の2つの柱頭は、936年に創建されたコルドバ近郊の宮殿都市 メディナ・アズハラ(Madinat al-Zahra) からのものです。最下部の柱頭は「コンポジット式」で、完全にローマ風ですが、上端部にアラビア語の銘文が刻まれている点が異なります。中央の柱頭は同じ形ですが、表面が植物文様で装飾されています。材質:大理石(彫刻)所蔵番号:A.10-1922; A.55-1925寄贈者:W.L.ヒルドバーグ博士】「Capital with Stylised Decoration(top)Spain, Granada1370–80This column capital, made 400 years later, is clearly Islamic. It has the same basic form as the earlier examples, but the acanthus leaves have become purely abstract shapes. They were originally painted with patterns in gold as well as blue.Marble, carved and paintedMuseum no. 341-1866」【様式化された装飾を持つ柱頭(上部)スペイン、グラナダ1370–80年この柱頭は、400年後に制作された明らかにイスラーム的な作品です。基本的な形は以前の例と同じですが、アカンサスの葉は完全に抽象的な形に変化しています。当初は金と青で文様が彩色されていました。材質:大理石(彫刻および彩色)所蔵番号:341-1866】1.上部(青い星形タイル)・16角星の文様をもつタイル片。・出典:スペイン、アルハンブラ宮殿(14世紀)。・アルハンブラ宮殿は、幾何学的装飾の最高峰の一つであり、星形パターンは 「宇宙の秩序と調和」を象徴しています。2.左側(革装丁の書物の表紙)・型押しによる幾何学模様の装飾。・イラン、15世紀のコーラン表紙。・精緻な幾何学模様は、聖典を保護すると同時に、神聖性を視覚的に強調しました。3.右側(もう一つの革装丁書物表紙)・同じくイランの15世紀作品。・幾何学と唐草文様が組み合わされ、無限の繰り返しが「永遠の神」を象徴。4.中央下(彩色写本ページ)・16世紀イランの写本装飾ページ。・星形や多角形を基礎とした「幾何学的曼荼羅」のようなデザイン。・色彩豊かで、視覚的に神秘性と荘厳さを演出。「GeometryArtists in the Islamic world were inspired by the principles of geometry.With a compass and ruler, they created an infinite number of star patterns and polygons.These could be used alone or overlaid with floral and calligraphic decoration.Geometry was also important in architecture, with complex vaulting and domes oftendecorated with star patterns.The 16-pointed star (top) is from a panel from the Alhambra Palace, Spain,14th century. The tooled leather bookbindings (left and right) were made in Iran in the 15th century. The painted page (below) is from a 16th-century Iranian manuscript.」【幾何学イスラーム世界の芸術家たちは、幾何学の原理に強く触発されました。コンパスと定規を用いて、無限に広がる星形文様や多角形を生み出しました。これらは単独で用いられることもあれば、植物文様や書道的装飾と重ね合わせて使われることもありました。幾何学は建築においても重要であり、複雑なヴォールト(アーチ天井)やドームには、星形文様がしばしば施されました。上部の16角星文様は、14世紀スペインのアルハンブラ宮殿のパネルの一部です。左右の型押し革装丁の書物は、15世紀イラン製。下の彩色されたページは、16世紀イランの写本からのものです。】・上段のタイル(青・金・白の装飾):幾何学的・植物的文様で詩の世界観を 補完する装飾。・中段のガラス器(ピンクや透明の彩色ガラス):宮廷や富裕層の詩歌朗読・饗宴で 用いられた器物。・下段の大皿(青・白・黄色の彩色陶器):詩文や文学的モチーフに基づく装飾を 施した日常器。「Images and PoetryIn many Islamic societies, scenes containing humans and animals were a common type of decoration in non-religious contexts. The source of this imagery was usuallypoetry, the most highly esteemed form of secular literature.Luxury copies of narrative poems were often illustrated with fine paintings, and themore familiar episodes were depicted on palace walls and objects. Love lyrics accompanied portrayals of beautiful young men and women. Odes in praise of the ruler inspired enthronement scenes. The recitation of poems at court was depicted,as were princely activities such as hunting and playing polo.In certain times and places, however, the ban on images in religious contexts was extended to the secular sphere, and decoration was confined to calligraphic,geometric and plant-based ornament.」【イメージと詩多くのイスラーム社会において、人間や動物を含む場面は、宗教的でない文脈における装飾の一般的な題材でした。こうした図像の源は通常、世俗文学の中で最も高く評価されていた「詩」でした。叙事詩の豪華な写本はしばしば精緻な絵画で彩られ、よく知られた物語の場面は宮殿の壁や器物に描かれました。恋愛詩は、美しい若者や女性の姿とともに表現され、支配者を讃える頌詩は即位の場面を鼓舞しました。宮廷での詩の朗読の様子も描かれ、また狩猟やポロ競技といった王侯の活動も表現されました。しかし、時代や場所によっては、宗教的文脈における「図像の禁止」が世俗領域にも及び、装飾は書道的・幾何学的・植物的文様に限定されることもありました】イスラーム陶器の大鉢。・白地に黒の唐草模様 細かい蔓草(アラベスク)文様が放射状に展開しており、中心から外側へと視線が広がる 設計。イスラーム美術に特有の「無限の広がり」を象徴。・青とトルコ石色のメダリオン 唐草文の中にリズムよく配置された青の装飾モチーフが、単調さを避けるアクセントに なっている。これもイスラーム陶器の伝統的配色。・器形 高台が付いた大鉢で、儀式用または宮廷での宴席用に使われたのであろう。「Basin with ‘Golden Horn’ DesignTurkey, probably IznikAbout 1545This basin is decorated with tight concentric scrolls in black, which bear tiny leaves and flowers. This pattern is often known as the ‘Golden Horn’ design, because examples were excavated near the inlet in Istanbul known as the Golden Horn.Blue and turquoise motifs are set into the pattern. They resemble the enamelledplaques found on some silverware of the same period.Fritware painted under the glazeMuseum no. 243-1876」 【「黄金の角」文様の鉢トルコ(おそらくイズニク)約1545年この鉢は黒色の密な同心渦巻き模様で装飾され、その渦の中には小さな葉や花が描かれています。この文様は一般に「黄金の角(ゴールデン・ホーン)」デザインとして知られており、イスタンブールの入り江「ゴールデン・ホーン」付近から多数の例が出土したことに由来します。青とトルコ石色のモチーフが文様の中に組み込まれており、同時期の銀器に見られるエナメル装飾を思わせます。フリット陶器、釉下彩館蔵番号:243-1876】「オスマン帝国期のトルコ美術(Turkey under the Ottomans)」の展示解説パネル。1.白地に青・緑・赤の絵付け・白い錫釉(tin-glazed)の上に、コバルトブルー、エメラルドグリーン、トマトレッドなど 鮮やかな色で文様が描かれています。・特に「イズニク赤」と呼ばれる濃厚な赤色は16世紀半ば以降の特徴で、高級品に 用いられました。2.花文(Floral motifs)・チューリップ、カーネーション、ヒヤシンス、バラなどがよく登場します。 これらはオスマン宮廷文化を象徴する花であり、イスラム的な楽園のイメージとも 結びついていました。・花々は曲線的に絡み合い、リズミカルなパターンを構成。器の全面に生命感あふれる 「楽園的世界」を展開しています。3.シンメトリー(対称性)・花の配置や唐草文は幾何学的秩序を保ちつつ有機的に描かれています。・これはイスラム美術の重要な理念「無限の調和」と「神の秩序」を象徴しています。「Turkey under the OttomansAnatolia – the Asian part of modern Turkey – was settled by Muslim Turks fromabout 1070 onwards. In the following century a sultanate was founded there by the Seljuk dynasty. By 1300 this state had disintegrated, and a new dynasty,the Ottomans, arose. From their base in the northwest, the Ottomans conquered the rest of Anatolia and the Balkans, and in 1453 they seized Constantinople(Istanbul), which became their capital.The overthrow of the Mamluks of Egypt in 1517 and similar successes gave the Ottomans an empire that stretched from Algeria to Iraq and included the holy sites of Mecca and Medina.In the 16th century, the wealth of the Ottomans was reflected in sumptuous decorative arts. Their bold designs rarely included human or animal figures, a feature that was deliberately designed to distinguish them from those producedin Iran at this time.」【オスマン帝国時代のトルコアナトリア(現代トルコのアジア側)は、1070年頃からイスラム教徒のトルコ人によって定住が始まりました。翌世紀にはセルジューク朝によってスルタン国が建てられましたが、1300年頃までにその国家は崩壊し、新たにオスマン朝が興りました。オスマン朝は北西部を拠点にアナトリア全土とバルカン半島を征服し、1453年にはコンスタンティノープル(現イスタンブール)を攻略して首都としました。1517年にはエジプトのマムルーク朝を打倒し、同様の征服を重ねることで、オスマン帝国はアルジェリアからイラクにまで及び、メッカとメディナという聖地も支配する大帝国となりました。16世紀には、オスマン帝国の富は豪華な装飾芸術に反映されました。彼らの力強いデザインは人物や動物の図像をほとんど含まず、これは当時のイランの作品との差別化を意図していました。】 「Vase with FlowersTurkey, probably IznikAbout 1575Ceramics with a white fritwarebody were a distinctive part of Ottoman art. Potters often showed great skill in matching the designs they used to the shapes of vessels. Here tulips, carnations and other flowering plants seem to sway gently in a breeze, following the curved shape of the vase.Fritware painted under the glazeMuseum no. 232-1876」 【1 花文様の花瓶トルコ(おそらくイズニク)約1575年白い素地(フリット陶)の陶器は、オスマン美術の特色ある要素でした。陶工たちは器の形に合わせてデザインを調和させる高度な技術を示しました。この花瓶では、チューリップやカーネーションなどの花々が、器の曲線に沿ってそよ風に揺れるかのように描かれています。素材:白釉下彩のフリット陶収蔵番号:232-1876】「2 Two Tiles Forming Decorative ArchTurkey, probably IznikAbout 1575From the 1550s, white fritware was also used for wall tiles. This pair was made toframe a small niche in a wall. Niches were often used for storage, in place of furniture. They were also used for the display of objects suggesting refinement, such as a vase of flowers.Fritware painted under the glazeMuseum no. 1897&A-1897」 【2 装飾アーチを形成する二枚のタイルトルコ(おそらくイズニク)約1575年1550年代以降、白い素地(フリット陶)は壁タイルにも用いられました。この一対のタイルは、壁の小さなくぼみ(ニッチ)を縁取るために作られたものです。ニッチはしばしば家具の代わりに収納として使われましたが、花瓶のような洗練を示す物品を飾るためにも用いられました。素材:白釉下彩のフリット陶収蔵番号:1897&A-1897】オスマン帝国時代の織物・刺繍布(Textiles / Embroideries) の展示。上段・赤地に円文様(メダリオン柄) ・規則正しい円(メダリオン)が並ぶ幾何学的パターン。 ・円の中には花や太陽を思わせるモチーフが入ることも多く、「完全性・永遠」を象徴します。 ・こうした布は壁掛けや法衣、儀式用の装飾布として用いられました。下段(左から順に)1.扇状の植物文様 ・棕櫚(パーム)や蓮、あるいは生命の樹を思わせる形。 ・豊穣や生命力の象徴とされました。2.赤地に緑の円文様 ・半円形に配された葉や花が繰り返し登場。 ・モスクや宮殿で用いられた壁面装飾用の布地のデザインにも近いものです。3.金糸刺繍の花文様 ・中央に大きな花(菊や太陽を思わせる形)、周囲に唐草模様。 ・金糸を多用しており、宮廷の高位者の衣装や儀礼用の幕に使用された可能性があります。「Ottoman Silks and VelvetsThe Ottomans used luxurious silk textiles for furnishings and for men's and women's clothing. The most prestigious were velvet and complex silk weaves called kemha and seraser. These often incorporated thread wrapped with silver or gilded silver.The main centre for silk-weaving was Bursa in north-west Anatolia in Turkey.The industry was established there in the 15th century, largely to compete with Italian imports.Velvet brocade, or çatma, was used for clothing as well as furnishings, such as thethree cushion covers displayed here. The designs were created with bright motifs of metal-wrapped thread set against the silk velvet background.」【オスマン帝国の絹織物とビロードオスマン帝国では、豪華な絹織物が家具調度や男女の衣服に用いられました。最も高級とされたのはビロード(ヴェルヴェット)や、ケマ(kemha) や セラセル(seraser) と呼ばれる複雑な絹織物でした。これらにはしばしば、銀線や金箔で覆われた糸が織り込まれていました。絹織物の主な生産地はトルコ北西部アナトリア地方のブルサで、15世紀に産業として確立され、イタリアからの輸入品に対抗するためでもありました。ビロード織金襴(チャトマ çatma)は衣服だけでなく、ここに展示されている3枚のクッションカバーのように家具調度にも使われました。文様は金属糸で織り出され、絹のビロード地の上に鮮やかに浮かび上がるように表現されました。】 オスマン帝国期またはペルシャ(イラン)起源の絨毯(カーペット)展示。・左側の赤地の大絨毯 ・中央に大きなメダリオン(中心装飾模様)があり、そこから広がる放射状の唐草や アラベスク模様が展開されています。 ・周縁には細密な花文様の縁取り(ボーダー)がめぐらされ、中央の赤と青のコントラストが 強い印象を与えます。 ・このタイプはしばしば「メダリオン絨毯」と呼ばれ、サファヴィー朝イランやオスマン帝国の 宮廷織工房で製作されたものと。・右側の展示(奥の赤い地の絨毯と下の断片) ・繰り返し文様(リピートパターン)が使われ、菱形(ダイヤ型)の枠の中に花文や唐草が 配されていた。 ・下部の断片も同系統で、おそらく大きな絨毯の一部を切り取ったものか、同じ工房で 織られた装飾断片 と。「ミフラーブ(Mihrab)」 と呼ばれるイスラム建築の要素を有した暖炉。ミフラーブとは・機能 モスク(イスラム教寺院)の壁面に設けられる祈りの方向(キブラ=メッカの方向)を 示す窪み(ニッチ)です。 信徒が礼拝する際、このミフラーブの方向に向かって祈ります。・形態 この展示品のように、装飾的なアーチとタイルで縁取られた半円形・多角形の凹みが 一般的。 時代や地域によって異なりますが、特にオスマン帝国やイランのモスクでは鮮やかな イズニク陶器やタイルで覆われたミフラーブが多く見られます。・特徴 ・青・白・トルコブルーの色彩 典型的なイズニク陶器の配色で、16世紀オスマン帝国期を思わせます。 ・植物文様(唐草・花文) アラベスク文様が全面を覆い、楽園の庭を象徴。イスラム美術で好まれる「永遠性」 「神の無限性」を表しています。 ・円錐状の装飾冠 窪みの上部に張り出した円錐形の冠(カノピー)があり、礼拝空間のいイメージを 際立たせています。近づいて。Tilework Chimneypiece(タイル装飾の暖炉)・オスマン帝国の住宅や宮殿で用いられた暖炉の囲い。・1731年製作(イスタンブール、おそらくトプカプ宮殿や高位役人の館のため)。・ミフラーブと同じアーチ形・タイル装飾を持ち、外観的には酷似。ただし機能は暖炉=暖房具で、宗教的な礼拝設備ではない。横から暖炉の造形を。「Tilework Chimneypiece(タイル装飾の暖炉囲い)」 に使われていた一枚。・色彩:典型的なオスマン期イズニック陶器の配色である ・コバルトブルー(青) ・トルコブルー(ターコイズ) ・赤(鉄赤=アルメニアン・ボレ) ・緑(銅緑) の組み合わせ。・文様: ・中央から放射状に広がる青い曲線は、花弁や葉の動きを象徴し、流れるようなリズムを生む。 ・周囲に小花(カーネーションやチューリップを抽象化)が散りばめられている。 ・青い円形の文様は「ルーマル(雲形文様)」と呼ばれることがあり、トルコ・イランの 装飾芸術で好まれたモチーフ。「Tilework Chimneypiece(right)Turkey, probably IstanbulDated 1731The names around the hood are those of the Seven Sleepers. Persecuted under the Roman emperor Decius, these Christian men took refuge in a cave. They fell asleep, waking centuries later under Christian rule.The Seven Sleepers are mentioned in the Qur’an as an example of God’s protection ofthe righteous. Their names were therefore used to invoke that protection.Fritware with under-glaze decorationMuseum no. 703-1891」 中東イスラーム世界の八角形小卓(side table, coffee table)。・天板(上面) ・中央に青を基調とした幾何学的星形文様(八芒星の展開)と植物唐草。 ・典型的なイズニック陶器の色調(コバルトブルー、ターコイズ、白、赤)が見えます。 ・周囲の帯は水色と濃紺の反復文様で縁取られ、秩序と無限性を強調。・側面(幕板部分) ・白いアラベスク(植物唐草)を濃色地に象嵌したもの。 ・曲線がリズミカルに連続し、生命力と楽園を象徴。・意味と象徴 ・幾何学文様:イスラーム装飾の中心で、宇宙の秩序や神の無限性を示す。 ・花文様(唐草、チューリップ、カーネーションなど):楽園(パラダイス)を象徴し、 王朝の繁栄や祝福を表現。 ・八角形:東西世界で調和と安定を象徴する形で、イスラーム建築のドームや噴水台、 礼拝具にも頻出。「Tile-top TableTurkey, Iznik and IstanbulAbout 1560In Ottoman palaces, guests sat on a low bench, or divan, built against the wall. Trays of food and drink were set before them, resting on tables of this type.Wood faced with ebony, with inlay ofivory and mother-of-pearl; fritware painted under the glazeMuseum no. C.19-1987」 【タイル天板の卓子(テーブル)トルコ、イズニクおよびイスタンブル約1560年オスマン帝国の宮殿では、客人は壁際に設けられた低いベンチ(ディヴァン)に座りました。彼らの前には食べ物や飲み物を載せた盆が、このようなタイプのテーブルの上に置かれました。黒檀で面を張った木製の骨組みに、象牙と真珠貝の象嵌を施し、天板は釉下彩で装飾されたフリット陶器。館蔵番号:C.19-1987】オスマン帝国期のイズニク陶器(Iznik ceramics)とタイル装飾の展示。・中央のガラスケース ・16世紀後半~17世紀にかけての イズニク陶器の皿や壺、瓶。 ・白地にコバルトブルー・ターコイズ・エメラルドグリーン・赤(アルメニアンレッド)で 描かれた華やかな文様が特徴。 ・文様は 唐草(アラベスク)、チューリップ、カーネーション、ヒヤシンス、ザクロなど、 オスマン宮廷文化を象徴する植物が多い。・周囲の壁面タイル ・左側:繰り返し文様の タイル・パネル。ザクロや葉をモチーフにした連続模様。 ・右側・上部:装飾的なアーチを思わせるタイル。建築内部(モスクや宮殿)の壁面や ニッチ(壁龕)を飾ったもの。意匠と意味・植物文様: チューリップやカーネーションは、オスマン帝国の「楽園」を象徴する花。庭園文化や イスラム的な天国イメージを反映。・青と赤のコントラスト: コバルトブルーは清浄と神聖さ、赤は生命力と富を象徴。16世紀半ばに登場した アルメニアンレッドは、イズニク陶器の代表的特徴。・幾何学と反復文様: 無限性・秩序・神の創造の永遠性を表すイスラム美術の典型モチーフ。「Variety of Shape and DesignThe shapes of Iznik vessels were derived from sources as varied as metalwork (9–11), leatherwork (14) and Chinese and Italian ceramics. Models included the Chinese‘grape dish’ (2) and the Italian tondino form (15).By the 1530s, small sprays of tulips and other recognisable flowers were a commonmotif (9, 10, 15), but from the 1550s these were replaced by compositions on alarger scale. Many were originally developed for tilework (1, 3).」【形とデザインの多様性イズニク陶器の形は、金属製品(9–11)、革製品(14)、さらには中国やイタリアの陶磁器といった多様な素材や伝統から着想を得ていました。モデルには、中国の「ブドウ文皿」(2)や、イタリアの トンディーノ 形(15)などが含まれます。1530年代までには、チューリップやその他の認識しやすい花を小枝状に描いたモチーフが一般的となっていました(9, 10, 15)。しかし1550年代以降、こうした小規模なモチーフは、より大規模な構図へと置き換えられていきました。その多くはもともとタイル装飾用に考案されたものでした(1, 3)。】このタイルは 「イズニク陶器(Iznik Ceramics)」1550年以降 の代表的な装飾パネルで、オスマン帝国の華やかな宮廷文化を反映したもの と。1.中央の大輪の花 ・青(コバルトブルー)の大きな花(しばしばカーネーションやロータスに解釈される)が 中心に置かれています。 ・その周囲に赤(イズニク特有の鉄赤)の花弁が広がり、放射状のバランスを作っています。2.チューリップ文様 ・上下左右に細長い赤い花弁が伸びており、これはオスマン陶器の典型的な「チューリップ」。 ・チューリップは16世紀以降のオスマン帝国を象徴する花で、王権や繁栄のシンボルでした。3.カーネーション文様 ・外側の赤い花弁の中に、ギザギザした花弁を持つカーネーションが見られます。 ・カーネーションは生命力と永遠性を意味します。4.唐草(アラベスク)と小花 ・青や緑の唐草文様が花々をつなぐように広がり、全体を調和させています。 ・細かい小花(青や白の点状)は、天上の楽園を象徴する「無限の花園」のイメージです。5.対称構造 ・模様は上下左右に完全に対称に配置されており、イスラーム美術の「宇宙的秩序」 「神の無限性」を表しています。「Iznik Ceramics after 1550The imperial court’s patronage of Iznik ceramics was renewed during the construction of the Suleymaniye mosque in Istanbul in 1550s.The finest tiles were produced, and a bright red was added to the range of colours painted under the glaze. This was achieved with a slip made from a special clay.In the following decades, tiles of high quality were decorated in red, green, turquoise, blue on a white ground. Dishes, bottles and other vessels had similar decorationon white or coloured grounds.From the 1580s, however, standards declined and court patronage ceased. The tile industry in Iznik ceramic production was imitated by other towns (ifillegible?) and local demand. Waning importance led eventually in the 18th century to former imperial production being replaced in Istanbul called Tekfur Sarayi.」【1550年以降のイズニク陶器オスマン帝国の宮廷によるイズニク陶器の保護は、1550年代のイスタンブルにおけるスレイマニエ・モスクの建設に際して新たに強化されました。この時期に最上質のタイルが制作され、さらに明るい赤色が釉下彩の色調に加えられました。これは特別な粘土から作られた化粧土(スリップ)を用いることで実現されました。その後の数十年間には、赤・緑・トルコ青・青が白地に描かれた高品質のタイルが生み出されました。皿や瓶などの器物もまた、白地や彩色された地に同様の装飾が施されました。しかし1580年代以降、品質は次第に低下し、宮廷の庇護も途絶えました。イズニク陶器のタイル産業は他都市によって模倣され、地元需要に依存するようになりました。その結果、18世紀にはイズニクの宮廷向け陶器生産は衰退し、イスタンブルの「テクフル・サライ工房」に置き換えられていきました。】「Tiles with Repeat Pattern (top)Turkey, probably Iznik1570–80These eight tiles show two repeats of a complex pattern. It combines an oversizedarabesque in red, and fantastic blossoms formed from smaller flowers and leaves. One motif is superimposed on another, but there is no attempt to create an illusion of depth. Instead, the motifs are laid out over the flat surface of the tile.Fritware painted under the glazeMuseum no. 1886-1897」【繰り返し模様のタイル(上部)トルコ、おそらくイズニク製1570~1580年頃これら8枚のタイルは、複雑なパターンを2回繰り返して示しています。赤色の大きなアラベスクと、小さな花や葉から構成された幻想的な花々を組み合わせています。モチーフは重ね合わせられていますが、奥行きを錯覚させる意図はなく、むしろ平坦なタイルの表面全体に模様を配置しています。透明釉下彩のフリット陶器館蔵番号 1886-1897】 「Gilded Tile (above)Turkey, probably BursaAbout 1420Many Ottoman tiles and vessels originally had gilded decoration. The gold was applied cold to the finished ceramic. In many cases, it was later removed because of its value.Tiles similar to this were used to decorate the tomb of Sultan Mehmet I in Bursa.He died in 1421.Earthenware under opaque green glaze with gilded decorationMuseum no. 1676-1892」【金彩タイル(上部)トルコ、おそらくブルサ製1420年頃多くのオスマン帝国のタイルや器は、もともと金彩で装飾されていました。金は焼成後の陶器に冷間で施されるもので、多くの場合、後にその価値のために削り取られました。このようなタイルは、ブルサにあるメフメト1世(在位1413~1421)の墓を飾るために使われました。不透明な緑釉の上に金彩装飾を施した土器館蔵番号 1676-1892】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.28
コメント(1)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その121): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-4
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクV&A(ヴィクトリア&アルバート博物館/ロンドン)日本展示室に掛けられている浮世絵(木版画)。額装されているのは主に 歌舞伎や武者絵を題材にした錦絵で、江戸末期〜明治期の作品。「Legendary Women in Japanese PrintsWoodblock prints were an affordable art that could be enjoyed by people of all ages,genders and social classes. In the 19th century printed images of illustrious andnotorious women found new popularity in Japan. Going beyond conventional imagesof female beauty, government directives to improve social morality encouraged theportrayal of women of exemplary strength and skill, while literature and drama delighted in villains who were ready to bewitch and betray.These prints show not only the creativity of Japan’s printmakers, but also the many ways in which women came to be depicted: dangerous, talented and powerful.」【浮世絵に描かれた伝説的な女性たち木版画は、あらゆる年齢・性別・社会階層の人々が楽しめる手頃な芸術であった。19世紀になると、日本では高名な女性や悪名高い女性の姿を描いた版画が新たな人気を博した。従来の美人画の枠を超え、社会道徳を向上させるための幕府の指導は、優れた力と技を備えた女性像の描写を奨励した。一方で文学や演劇は、人を惑わし裏切る妖しい悪女像を喜んで描いた。これらの版画は、日本の版画師たちの創造力を示すだけでなく、女性がいかに危険で、才能に満ち、力強い存在として描かれてきたかを物語っている。】 左上:1.小野小町《女三十六歌仙》シリーズより 団扇絵右上:2.巴御前、武蔵三郎衛門有国と戦う図下 :3.安倍泰成、妖狐を退治する図1.小野小町《女三十六歌仙》シリーズより 団扇絵2.巴御前、武蔵三郎衛門有国と戦う図 をネットから。3.安倍泰成、妖狐を退治する図 をネットから。「1. Ono no Komachi, from the series The Thirty-six Immortal Women Poets1843–47Ono no Komachi, who lived during the 9th century, is one of Japan’s most celebratedpoets. Her unparalleled beauty is upheld as a feminine ideal, and her work conveyspassionate intensity. The poem in the cartouche translates to:‘It must have been because I fell asleep tormented by longing that my loverappeared to me. Had I known it was a dream, I should never have awakened.’Utagawa Hiroshige (1797–1858)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.2933-1913」 【1.小野小町《女三十六歌仙》シリーズより1843–47年9世紀に生きた小野小町は、日本で最も著名な歌人の一人である。比類なき美しさは女性の理想像として称えられ、その和歌は情熱的な切実さを伝えている。画中の詞書に記された歌の現代語訳は次の通り:『思ひつつ寝ればや人の見えつらむ 夢と知りせば覚めざらましを』「恋い焦がれて眠りに落ちたために、夢にあなたが現れたのだろう。夢と知っていたなら、決して目覚めたりはしなかったのに。」作者:歌川広重(1797–1858)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.2933-1913】「2. Tomoe Gozen fighting Musashi Saburōemon Arikuni1815–20Tomoe Gozen is Japan’s most famous female warrior. While her historical existence is debated, chronicles of the 12th-century Genpei War describe her commanding troopsand highlight her skill in archery, sword fighting and horse riding. Here, Tomoe is shown preparing to behead her opponent Musashi Saburōemon Arikuni. Prints of famous warriors became increasingly popular in the early 19th century.Katsukawa Shuntei (1770–1820)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.12602-1886」 【2.巴御前、武蔵三郎衛門有国と戦う図1815–20年巴御前は、日本でもっとも有名な女武者である。史実性については議論があるが、12世紀の源平合戦の記録には、彼女が軍勢を指揮し、弓術・剣術・馬術に優れていたことが描かれている。本作では、巴御前が敵将武蔵三郎衛門有国を斬首しようとする場面が表されている。19世紀初頭、有名武将を描いた浮世絵はますます人気を高めていった。作者:勝川春亭(1770–1820)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.12602-1886】「3. Abe no Yasunari exorcises a demon1847–48In Japanese folklore, foxes are shapeshifters with supernatural powers. The mythical Tamamo no Mae was a cruel and ambitious nine-tailed fox. Disguised as a beautifulwoman, she became the mistress of the emperor and caused him to fall ill.When exorcist Abe no Yasunari exposed her true nature with a magic mirror, she wasdefeated and turned to stone.Utagawa Kunisada (1786–1865)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.5558-1886」 【3.安倍泰成、妖狐を退治する図1847–48年日本の伝承において、狐は超自然的な力を持つ変化の存在とされてきた。伝説の玉藻前(たまものまえ)は、残酷で野心的な九尾の狐であり、美しい女性に姿を変えて帝の寵姫となり、病に陥らせた。陰陽師・安倍泰成は、魔法の鏡によってその正体を暴き、彼女は敗北して石に変じたと伝えられる。作者:歌川国貞(1786–1865)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.5558-1886】左:4.神功皇后と武内宿禰(たけうちのすくね)中央左:5.二代目 岩井粂三郎の揚巻役中央右:6.木曽のお六の櫛右下:7.厳島における弁才天の顕現が平清盛を圧倒する図「4. Empress Jingû and Minister Takeuchi,from the series Banners as Interior Decoration1844–62Before the Imperial Household Law of 1889 prevented female succession, eight ofJapan’s historical rulers were women. Empress Jingû is a mythical figure said tohave led an army into the Korean peninsula in the 3rd century. A shaman and powerful warrior, she is often portrayed carrying a sword, a bow and a quiver of arrows.Utagawa Kunisada (1786–1865)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.1373-1899」 【神功皇后と武内宿禰(たけうちのすくね)《室内装飾の旗(バナー)》シリーズより1844–62年1889年の皇室典範が女性の皇位継承を禁じる以前、日本の歴代統治者のうち8名は女性であった。神功皇后は3世紀に朝鮮半島へ軍を率いたと伝えられる伝説上の人物で、巫女的性格を持つ強力な女武者として、しばしば剣・弓・矢筒を携えた姿で描かれる。作者:歌川国貞(1786–1865)制作地:江戸(東京)技法:木版画(錦絵)所蔵番号:E.1373-1899】 「5. The Actor Iwai Kumesaburō II as Agemaki1824–25Beautiful women from the brothel district were a mainstay of prints, drama andliterature; in reality, they worked under exploitative contracts. In the kabuki theatre, female roles were played by male actors known as onnagata. Here, actorIwai Kumesaburō II plays the formidable Agemaki of the Miura brothel. Perfecting the performance of femininity, onnagata set new standards for female beauty. Some onnagata are recorded as living as women off-stage.Utagawa Toyoshige (1777–1835)Edo (Tokyo)Woodblock PrintMuseum no. E.12645-1886」 【5.二代目 岩井粂三郎の揚巻役1824–25年遊郭の美しい女性たちは、版画・演劇・文学において主要な題材となったが、実際には搾取的な契約の下で働かされていた。歌舞伎では、女性役は女形(おんながた)と呼ばれる男性俳優によって演じられた。ここでは、二代目 岩井粂三郎が三浦屋の花魁揚巻を演じている。女形は女性らしさの演技を完成させることで、新しい「女性美」の基準を作り上げた。中には、舞台を離れても女性として生活したと記録されている俳優もいた。作者:歌川豊重(1777–1835)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.12645-1886】「6.Kiso no Oroku Combs, from the series A Compendium of Famous Artisans1843–47The story of Oroku of Kiso is an example of filial piety and inventiveness. Oroku’s familywas poor, but she supported them by making combs out of a fine-grained local woodwhich, legend says, could cure headaches. In the Edo period (1615–1868), women from working households often contributed to the family business. Handmade combs from the Nagano area are still named after Oroku.Utagawa Hiroshige (1797–1858)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.2918-1913」 【6.木曽のお六の櫛《諸職人尽(しょしょくにんづくし)》シリーズより1843–47年木曽のお六の物語は、孝行心と工夫の好例である。お六の家は貧しかったが、彼女は地元産のきめ細かな木材を用いて櫛を作り、家族を支えた。その櫛は「頭痛を治す」との伝説もあった。江戸時代(1615–1868)には、働く家庭の女性が家業に従事することも多かった。長野地方の手作り櫛の中には、今も「お六櫛」と呼ばれるものがある。作者:歌川広重(1797–1858)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.2918-1913】「7. The manifestation of Benzaiten overwhelming Taira no Kiyomori at Miyajima1862Japan’s two major religions, Shintō and Buddhism, incorporate several female deities.Benzaiten is associated with water, music and eloquence, and is one of the Seven Godsof Good Fortune. This print shows her appearing to the 12th-century military leader Taira no Kiyomori. Kiyomori attributed his success in battle to Benzaiten andbuilt a temple in her honour.Utagawa Yoshitora (active 1830–80)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.13975-1886」 【7.厳島における弁才天の顕現が平清盛を圧倒する図1862年日本の二大宗教である神道と仏教には、複数の女神が取り込まれている。弁才天(弁財天)は水・音楽・弁舌に結びつけられ、七福神の一柱でもある。この版画は、12世紀の軍事的指導者平清盛の前に弁才天が現れる場面を描く。清盛は戦での勝利を弁才天の加護と信じ、彼女を祀るために寺を建立した。作者:歌川芳虎(1830–80年頃 活動)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.13975-1886】7.厳島における弁才天の顕現が平清盛を圧倒する図V&A日本展示室(Room 45, Toshiba Gallery of Japanese Art) の一角、浮世絵コーナーとは別のガラスケースを振り返って。左側 上段・蒔絵の小箪笥(黒漆に金蒔絵)・兜(武具の一部、脇に十字架が見えるため「南蛮兜」=キリスト教受容期の影響を示す可能性)左側 下段・蒔絵の箱(文箱か手箱)・日本刀(鞘入り、拵え付)中央〜右側 上段・染付磁器の壺(有田・伊万里焼様式、藍色と赤絵の彩色)・大皿(色絵磁器で人物図)中央 下段・壺型の磁器(肥前磁器)・小型の磁器人形(狛犬のような形)・小皿類「日本の陶磁器・漆工芸の国際交流」 をテーマにした展示で、江戸期の肥前磁器(伊万里焼・柿右衛門様式など)を中心に、西洋輸出向けの豪華な大皿・壺を紹介。・中央 ・大きな色絵大皿(鮮やかな瑠璃地に金彩、中央に人物図、周囲に唐草や花文様) → 有田や伊万里の大皿で、17世紀後半~18世紀輸出磁器の典型。ヨーロッパ向けの 華やかな装飾様式。・左側 ・染付や色絵の壺類 ・着物(黄色地に文様)もケース内に一部展示されているように見えます。・右側 ・青地に赤・金で装飾された壺(花瓶)数点 ・その下には小さな器群ウォーターフォール・オン・カラーズ(水の色彩滝) 千住博。・千住博の代名詞である「滝」シリーズのひとつ。・通常の墨色や単色の滝図とは異なり、多彩な縦色帯が滝となって流れ落ちるように描かれている。・ラベル解説にあったように、コロナ禍の隔離生活中、庭に刻々と変化する色彩を希望の象徴 として捉えた経験が反映されている。・滝の裏側から外を眺めたような感覚を意図しており、自然の力強さと人間の内的感情が 重ね合わされている。・江戸時代の浮世絵・工芸と並べて展示されることで、日本美術が古代から現代まで「自然」を 核心に据え続けてきたことを強調している。「Waterfall on Colors2023Often monumental in scale, Hiroshi Senju’s paintings embrace the overwhelming powerof nature. During the Covid-19 pandemic, when Senju was in isolation at his homein New York, he found hope in the constantly changing colours of his garden. The vibrant hues in this work represent a landscape as seen from behind a waterfall.Hiroshi Senju (born 1958)New York, United StatesColours on paperMuseum no. FE.69-2023」 【ウォーターフォール・オン・カラーズ(水の色彩滝)2023年平面でありながらしばしば記念碑的な規模を持つ千住博の絵画は、自然の圧倒的な力を抱擁するものである。新型コロナウイルスのパンデミックの際、ニューヨークの自宅で隔離生活を送っていた千住は、庭に絶えず変化する色彩に希望を見いだした。本作における鮮やかな色彩は、滝の裏側から眺めた風景を表現している。作家:千住博(1958年生)制作地:アメリカ合衆国 ニューヨーク技法:紙に彩色所蔵番号:FE.69-2023】再び「根付(netsuke)、印籠(inrō)、小型漆器」などの展示コーナーを。展示内容の特徴・左側の棚 ・小型の根付(netsuke)が多数並んでいる。材質は象牙・木・漆・磁器など多様で、 江戸時代の装身具として作られたもの。・中央の展示台 ・印籠(inrō)と緒締め(ojime)、それに付属する根付が組み合わせて展示されている。 ・中央下には大型の漆工芸品(蒔絵の箱)が見える。・右側の棚 ・さらに数多くの根付コレクションが並ぶ。動物・人物・神話モチーフなど。根付 (netsuke) コレクションに近づいて。・材質:象牙、木彫、漆塗り、陶磁器など多様。・形態: ・動物(犬・鼠・兎・鳥など) ・人物(七福神風、力士や僧形) ・神話・民話モチーフ(鬼、霊獣) ・抽象的な小形意匠根付は 印籠や煙草入れを帯から吊るすための留め具として17世紀から発展。江戸時代後期には、実用品であると同時に 高度な彫刻芸術に進化し、武士から町人まで愛好された。19世紀後半、ヨーロッパやアメリカでも「小さな彫刻」として収集熱が高まり、V&Aにも多数が収蔵された。V&Aの所蔵点数は数百点規模におよび、代表的な作例がこのようにまとめて展示されている と。「NetsukeTraditional forms of Japanese dress such as the kimono did not have pockets. A man would carry everyday items in containers suspended on silk cords fromthe sash (obi) around his waist. The arrangement was held in place by a toggle known as a netsuke. Netsuke were an ideal medium for inventive decoration and developed into miniature works of art. Most of the netsuke displayed here weremade between 1700 and 1870.」 【根付(ねつけ)着物などの伝統的な日本の衣服には、ポケットがなかった。そのため男性は日用品を容器に入れ、腰に巻いた帯(おび)から絹の紐で吊り下げて持ち歩いた。この吊り下げの仕組みを支えた留め具が根付である。根付は創造的な装飾表現の媒体として理想的であり、やがて小さな美術作品へと発展した。ここに展示されている根付の大半は、1700年から1870年の間に制作されたものである。】なんとか解読できました。根付と一緒に展示される 印籠(inrō)とその付属品(緒締め・根付)👈️リンク のコーナー。「SmokingTobacco was introduced to Japan by the Portuguese in the late 16th century.Despite attempts to ban it, smoking became popular among both men and women. Men carried personal smoking sets consisting of a tobacco container, a pipe and a pipe-holder. These were hung from the waist and held in place by toggles callednetsuke. Both men and women used communal smoking cabinets, which were usually made from decorated lacquer. These incorporated small braziersfor burning charcoalwith which to light the pipe.」【喫煙たばこは16世紀後期、ポルトガル人によって日本にもたらされた。禁止の試みがあったにもかかわらず、喫煙は男女ともに広まった。男性は、たばこ入れ・煙管(きせる)・煙管筒からなる個人用喫煙具を持ち歩いた。これらは腰から吊り下げられ、根付(netsuke)と呼ばれる留め具で固定された。また男女ともに、漆塗りで装飾された共用の喫煙棚(喫煙キャビネット)を使用した。そこには小型の火鉢が組み込まれており、炭を焚いて煙管に火を点けることができた。】根付(netsuke)展示ケースの全景。・4段の棚に配置され、合計30点以上の根付が並んでいる。・素材は象牙・木彫・漆など多彩。・上段には細密な象牙彫刻(群像・龍など)や動物形。・下段には黒っぽい木彫の人物や面形。「NetsukeTraditional forms of Japanese dress such as the kimono did not have pockets. A man would carry everyday items in containers suspended on silk cords from the sash (obi) around his waist. The arrangement was held in place by a toggle known as a netsuke. Netsuke were an ideal medium for inventive decoration anddeveloped into miniature works of art. Most of the netsuke displayed here weremade between 1700 and 1870.」【根付(ねつけ)着物など日本の伝統的な衣服にはポケットがなかった。男性は日用品を容器に入れ、帯(おび)から絹の紐で吊るして持ち歩いた。この仕組みを支える留め具が「根付」である。根付は創意工夫を凝らした装飾の媒体として理想的であり、やがて小さな美術品として発展した。ここに展示されている根付の大部分は 1700年から1870年の間に制作されたものである。】着物・衣装コーナーを再び。・左: ・現代的な意匠の浴衣/着物。大きなドットや幾何学模様をパッチワーク的に配置した デザイン。おそらく戦後以降の「モダン着物」か現代アーティストによる作品。・中央: ・黒または濃茶色の羽織/外套。絹地に無地あるいは渋い文様。実用的な装いか、儀礼用。・右: ・茶系の地に虎の刺繍(または友禅染)が大きく入った豪華な打掛または能装束。 力強い図柄から、武家や芝居に関わる衣裳である可能性。「Kimono for MenThe kimono is a garment worn by both men and women. Although sleeve length varies, the basic shape is the same. From the 17th century, male dress was characterised by dark colours and subdued patterns. Yet restrained exteriors often hid flamboyantlinings and under-kimono, a fashion that continued into the 20th century. Today, few men in Japan wear kimono, but in recent years there has been a revival.More and more designers cater for this growing market, giving kimono for men renewed style and panache.」 【男性用の着物着物は男女ともに着用する衣服である。袖の長さには違いがあるが、基本的な形は同じである。17世紀以降、男性の着物は暗い色調や落ち着いた文様が特徴となった。だが、その控えめな外観の下には、華やかな裏地や襦袢(下着の着物)を隠すことが多く、このファッションは20世紀まで続いた。現代では着物を着る男性は日本では少なくなったが、近年は復興の兆しが見られる。ますます多くのデザイナーがこの成長市場に注目し、男性用の着物に新たなスタイルと華やかさを与えている。】「MODERN & CONTEMPORARY(現代日本美術)」展示コーナー。極彩色の現代陶芸作品をアップで。Heart on Wave 川合 一仁。「Studio CraftsToday, many Japanese makers use traditional craft media to create unique works of art.They are supported by an extensive system of art colleges and a well-developed art market in Japan. Numerous craft associations also encourage their activities, as doregular competitive exhibitions. All the objects have been made since 2010, many ofthem very recently.」 【スタジオ・クラフト(現代工芸)今日、多くの日本の作り手は、伝統的な工芸の素材や技法を用いて、独自の芸術作品を創り出している。彼らの活動は、日本の充実した美術大学の制度や発達した美術市場によって支えられている。また、数多くの工芸団体がその活動を奨励しており、定期的に行われる公募展や競技的な展覧会も後押しとなっている。ここに展示されている作品はすべて2010年以降に制作されたもので、多くはごく最近のものである。】「1. ‘Heart on Wave’2023Kawai Kazuhito uses clay to express his nostalgia for 1980s Japan. After an initial biscuit firing, he painstakingly applies dots of glaze to his sculptures to blurthe boundaries between reality and illusion. The porcelain figurine of Ariel fromThe Little Mermaid at the top refers to Tokyo Disneyland’s opening in 1983.It was the first Disneyland outside the United States and symbolises Japan’s economic prominence during Kawai’s childhood.Kawai Kazuhito (born 1984)Kasama, Ibaraki prefectureGlazed stoneware, with a porcelain figureGiven by Hiroyuki Maki / Buffalo Inc.Museum no. FE.61-2024」 【1. Heart on Wave(波の上の心)2023年川合一仁(かわい かずひと)は、1980年代日本への郷愁を粘土で表現している。素焼きの後、彼は現実と幻想の境界を曖昧にするために、丹念に釉薬の点を彫刻表面に施す。作品上部にある『リトル・マーメイド』のアリエルの磁器人形は、1983年に開園した東京ディズニーランドを示唆している。それは米国以外で初めてのディズニーランドであり、川合の幼少期における日本の経済的繁栄を象徴している。川合 一仁(1984年生)茨城県笠間市釉薬を施した炻器、磁器製人形付き寄贈:牧浩之/Buffalo Inc.所蔵番号:FE.61-2024】こちらも「MODERN & CONTEMPORARY(現代・現代美術)」セクション。木工によるデザイン作品(おそらく屏風風の木製パネルや円形構造物)コーナー。中央に展示されているのは、木工によるデザイン作品(おそらく屏風風の木製パネルや円形構造物)で、横には椅子や織物、籠などが並んでいた。・中央の作品:格子状の木製パネルと円形の木工フレーム。伝統的な木工技法を使いながら、 現代的な抽象オブジェとして再構成されたもの。・右側:シンプルな椅子や織物(黒布)など、生活とアートの境界を意識した現代工芸。・左側:陶器・籠・白い紙造形など、素材ごとにまとめられた展示。メモリー 熊井恭子。「Studio CraftsToday, many Japanese makers use traditional craft media to create unique works of art. They are supported by an extensive system of art colleges and a well-developed artmarket in Japan. Numerous craft associations also encourage their activities, as do regular competitive exhibitions.」 【スタジオ工芸今日、多くの日本の作家たちは、伝統的な工芸の媒体を用いて独自の美術作品を制作しています。彼らは、日本における広範な美術大学の制度や発達した美術市場によって支えられています。多くの工芸協会もまたその活動を奨励しており、定期的な競技的展覧会もそれを後押ししています。】「1. 'Memory'2017Kumai Kyoko is an internationally recognised fibre artist. She created this work in remembrance of the Tōhoku Earthquake and Tsunami of2011, which caused over 15,000 deaths. Kumai works mainly with stainless steel wire. Here she has shapedthe wire into a bundle of organic forms. These represent people’s feelings about the unforgettable disaster that has had a lasting impact in Japan.Kumai Kyoko (born 1943)TokyoStainless steel wireGiven anonymouslyMuseum no. FE.57-2023」【1. メモリー2017年熊井恭子は国際的に認められたファイバー・アーティストです。彼女は2011年の東北大震災と津波(死者15,000人以上)を追悼して、この作品を制作しました。熊井は主にステンレススチールワイヤーを用いて制作を行います。ここではワイヤーを有機的な形態の束に組み上げ、それを通じて日本に長く影響を残した忘れがたい災害に対する人々の感情を表現しています。熊井恭子(1943年生まれ)東京素材:ステンレススチールワイヤー寄贈:匿名寄贈館蔵番号:FE.57-2023】「民芸・復興(Discovery and Revival)」セクションの一部で、柳宗悦の民芸運動の文脈で紹介されている作品群。手前の陶磁器・漆器・左:漆塗りの小箪笥(収納箱)・中央:緑釉鉢・黒釉壺・右:青磁花瓶・染付小壺・これらはいずれも江戸~近代にかけての実用品で、民芸運動では「無名の職人による 日常の器こそ美しい」と再評価されました。藍染の幕(のれん/幔幕の類) で、流水に菊の花、さらに上部に家紋が配された文様。「Discovery and RevivalAn interest in folk crafts arose in Japan in the early 20th century as a reaction to rapid industrialisation and urbanisation. Still active today, the Japanese Folk Craftmovement was established in 1926 by the critic and theorist Yanagi Soetsu. He and his followers collected historical folk crafts and founded museums in whichto show them.They also encouraged the preservation of traditional craft techniquesand the making of contemporary work in the style and spirit of historical models.」 【発見と復興20世紀初頭、日本では急速な工業化と都市化への反動として、民芸(フォーククラフト)への関心が高まりました。現在も活動が続いている日本民芸運動は、1926年に批評家で理論家の柳宗悦によって設立されました。柳とその仲間たちは歴史的な民芸品を収集し、それらを展示するための博物館を設立しました。また、伝統的な工芸技術の保存と、歴史的な様式と精神に基づいた現代作品の制作を奨励しました。】「5. Bedding cover1850–1900The traditional Japanese form of bedding is the futon, which comprises a mattressanda cover laid out on the floor. The cover is often decorated. This boldly patterned example was probably part of a bride’s trousseau. It reveals how subtle shading canbe achieved using only one colour. Careful mending is evidence of how greatly suchtextiles were treasured.Cotton with freehand paste-resist dyeing (tsutsugaki)Museum no. T.331-1960」【5. 布団カバー1850~1900年日本の伝統的な寝具の形は布団であり、床の上に敷かれる敷布団と掛け布団から構成されています。掛け布団のカバーはしばしば装飾が施されます。この大胆な文様の例は、おそらく花嫁の嫁入り道具の一部であったと考えられます。ここでは、1色だけを用いても微妙な濃淡表現が可能であることが示されています。丁寧に施された繕いは、このような織物がどれほど大切に扱われていたかを物語っています。素材:木綿、筒描きによる防染染色館蔵番号:T.331-1960】伊万里焼・柿右衛門様式を中心とした日本磁器(17~18世紀)。特にヨーロッパに輸出された伊万里焼や柿右衛門様式のコレクションが多く展示されている と。・上段中央の壺:色絵(赤・緑・青)で花鳥が描かれた柿右衛門様式の磁器。ヨーロッパで 特に人気が高かったスタイル。・上段左右の壺:藍一色で描かれた染付(sometsuke)、竹や花などの文様。・中段中央の大皿:色絵伊万里。赤・青・金を用いた豪華な意匠で、オランダ東インド会社を 通じてヨーロッパへ輸出されたもの。・中段右の像:獅子または象の置物(伊万里の輸出向け磁器)。ヨーロッパで装飾品として 人気を博した。・下段の皿類:いずれも染付や色絵の伊万里磁器。文様は唐草や人物図、風景など。「Porcelain for EuropePorcelain was first made in Japan in the early 17th century at kilns in and around the town of Arita. The earliest pieces were designed for the domestic market. In 1644,following the fall of the Ming dynasty, Chinese porcelain became temporarily unavailable and the Dutch turned to Japan as an alternative source for this highlysought-after commodity. Japan increased its output of porcelain, with much of it being aimed at the export market and often made in shapes copying Europeanceramics.」【ヨーロッパ向けの磁器日本で磁器が初めて作られたのは17世紀初頭、有田の町およびその周辺の窯においてでした。最初の作品は国内市場向けにデザインされていました。1644年、明王朝の滅亡に伴い、中国磁器が一時的に入手できなくなると、オランダ人はこの需要の高い商品を得るために日本を代替供給地としました。日本は磁器の生産量を増加させ、その多くを輸出市場に向け、しばしばヨーロッパの陶磁器の形を模した作品を作りました。】「南蛮貿易・キリシタン関連展示」の一部。展示内容(上段)1.螺鈿細工の小箪笥(cabinet with drawers) 漆塗りに螺鈿や金粉を施した豪華な小型箪笥。ヨーロッパへの輸出品として特に人気が ありました。2.十字架(Christian cross) キリスト教が16世紀に日本へ伝来した証拠の一つ。隠れキリシタンが所持していた可能性が あります。3.南蛮兜(nanban kabuto) ヨーロッパの兜を模した日本製の甲冑。安土桃山時代に西洋甲冑の影響を受けて制作 されました。展示内容(下段)4.蒔絵の箱(lacquer chest/box) 蒔絵技法による装飾箱。西洋の修道院や貴族の館でも保存され、装飾芸術として高く評価 されました。5.火縄銃(hinawajū / matchlock gun) 1543年、ポルトガル人によって種子島に伝来。日本で大量生産され戦国時代の戦術を変革 しました。6.刀剣(sword with European-style hilt) 柄や鍔に西洋風の装飾が施された刀。南蛮貿易期にヨーロッパとの交流を示す作品。】「Europe in JapanThe first Europeans to reach Japan were the Portuguese. Arriving in the early 1540s, they brought with them guns and Christianity. The latter ultimately proved unwelcome. Christianity was banned and the Portuguese were expelled. From 1639 the Dutch were the only Europeans permitted to trade with Japan. They were kept under close scrutinyon Dejima, an artificial island in Nagasaki Bay.Despite the restrictions placed on the Dutch, the goods and scientific knowledgethey brought with them werethe subject of both scholarly enquiry and popular interest.」【日本におけるヨーロッパ日本に最初に到達したヨーロッパ人はポルトガル人でした。1540年代初頭に到来し、鉄砲とキリスト教をもたらしました。しかし後者(キリスト教)は最終的に歓迎されず、禁教とともにポルトガル人は追放されました。1639年以降、日本と交易を許された唯一のヨーロッパ人はオランダ人だけとなりました。彼らは長崎湾の人工島・出島に厳重な監視のもとで滞在しました。制限が課されていたにもかかわらず、オランダ人がもたらした商品や科学的知識は、学問的探求や一般の関心の対象となりました。】 これは「南蛮漆器(Nanban lacquerware)」の代表的な輸出用大型箱(coffer / chest)。「Kamaboko(蒲鉾型)」のドーム状蓋をもつ大型キャビネット。・南蛮漆器は16〜17世紀、日本で欧州輸出を目的として作られた漆工芸品。「Nanban」または 「Namban」と呼ばれます。 ・輸出先に欧州貴族や宣教師が含まれ、キリスト教用具(十字架箱など)や豪華な装飾箱として 使われた例も多い。 ・技法としては、漆(urushi)を塗った上で蒔絵(maki-e:金銀粉などを散らす技法)、 螺鈿(raden:貝殻象嵌)、金銀装飾を組み合わせたもの。 ・形状として、「ドーム状/丸みを帯びた蓋」「箱体」「金属の金具・鍵・取っ手」などを 備えているものが多い。壁掛けではなく、家具・収納箱としての用途。「Lacquer for EuropeWhen the Europeans came to Japan in the mid-1500s, they were immediately by the lustre and decorative brilliance of objects made from lacquer (urushi). The Japanese soon began to produce lacquer items for export copying European shapes. Early pieces were decorated in mother-of-pearl using techniques similarto those found in China, Korea and India. Export lacquer from the 1600s onwards was decorated primarily in gold on black, and featured elaborate pictorial schemes.」【ヨーロッパ向けの漆器1500年代半ばにヨーロッパ人が日本に来航したとき、彼らはすぐに漆(うるし)で作られた器物の光沢と装飾的な華やかさに魅了されました。やがて日本人はヨーロッパの器物の形を写した輸出用漆器を生産するようになります。初期の作品は螺鈿(らでん)で装飾され、中国・朝鮮・インドで見られる技法と類似していました。1600年代以降の輸出漆器は、黒地に金を主体とした装飾が施され、精緻な絵画的意匠が特徴となりました。】「1. The Mazarin Chest1640–43This extremely high-quality lacquer chest is one of the most important pieces of Japanese export lacquer ever made. It is recorded as having been shipped toEurope by the Dutch East India Company in 1643. Its first owner was the French statesman and Catholic cardinal Jules Mazarin. The scenes on the front and sides allude to episodes from classical Japanese literature. The landscape on the lid featurestemple buildings and a castle complex.Probably Kōami workshopKyotoWood covered in black lacquer with decoration in gold and silver lacquer; silver foil and mother-of-pearl inlay; details in gold, silver and shibuichi alloy; gilded and lacqueredmetal fittings; French steel keyMuseum no. 412-1882」【1. マザラン・チェスト(Mazarin Chest)1640–43年この極めて高品質な漆塗りの大形収納箱は、日本の輸出漆器の中でも最も重要な作品のひとつです。1643年にオランダ東インド会社によってヨーロッパへ輸送された記録が残っています。最初の所有者はフランスの政治家でありカトリック枢機卿であったジュール・マザランでした。前面と側面の場面は日本古典文学のエピソードを示唆しており、蓋の風景には寺院建築や城郭群が描かれています。おそらく高阿弥(こうあみ)派工房京都黒漆塗木地に、金・銀漆による加飾、銀箔・螺鈿象嵌を施す。細部は金・銀・四分一合金(しぶいち)を使用。金銀蒔絵の金具を付属し、フランス製鉄鍵を伴う。館蔵番号:412-1882】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.27
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その120): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-3
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクこれはミャンマー(ビルマ)、マンダレー宮殿の遺物。仏教の祠および関連遺物1880年頃。ネットから。「Buddhist shrine and associated objects1880–80Shakyamuni Buddha is the main figure of this shrine.The hour-glass form beneath him is a miniature model of the Buddhist cosmos,encompassing all the possible levels of consciousness and being, which he is beyond. Burmese royal thrones of the period copied the shape of shrine bases such as this.The shrine has an accompanying manuscript chest, offering vessels and figures of the Buddha's chief disciples Sariputta (left) and Moggallāna (right) kneeling on couches.Mandalay Palace, Mandalay, Myanmar (BurmaTeak, gilded lacquer, semi-precious stones, mirrorsMuseum no. IS.511 to 31-1969」 【仏教の祠および関連遺物1880年頃釈迦牟尼仏がこの祠の中心像です。その下にある砂時計形の台座は、仏教宇宙の縮小模型であり、意識と存在のあらゆる段階を包含し、それを超越する仏を示しています。当時のビルマ王室の玉座も、このような祠の基壇の形を模して作られました。この祠には、写本を収める箱、供物の器、そして釈迦の二大弟子であるサーリプッタ(左)とモッガラーナ(右)がひざまずく姿の像が付随しています。出土地:ミャンマー(ビルマ)、マンダレー宮殿素材:チーク材、金箔漆、半貴石、鏡収蔵番号:IS.511 to 31-1969】釈迦如来坐像(Shakyamuni Buddha, Seated Buddha)。・姿勢:右手を地に触れている「降魔印(触地印, bhūmisparśa-mudrā)」を示しています。 これは釈迦が悟りを開いた際、大地を証人として悪魔を退けた場面を象徴します。・衣装:僧衣をまとい、右肩を出すインド・チベット・東南アジアに広く見られる形式。・材質:金銅製(鍍金)、光沢からみて高位の礼拝対象。・地域性:清代(18世紀頃)の中国・チベット仏教美術に属する金銅仏。東南アジア(ビルマ・タイ)のものに比べると、顔立ちや衣文表現がやや引き締まり台座の「蓮弁文様」が整然としている。チベット仏教圏(チベット〜中国)由来の金銅製・釈迦如来坐像ネットから。「Seated Buddha774–86Qing dynastyThe Buddha is shown just before his enlightenment, when he touches the ground to call the Earth goddess to witness his vow to overcome Mara and liberate all beings. This is the moment most often depicted in Tibetan and Mongolian art. The lotus aroundthe base supports the image of the Buddha serenelypoised. The image may be one ofthe large gilt-bronze figures made for the monasteriesof the Qing court, such as Yonghegong (the Palace of Harmony and Peace) in Beijing.Gilted (Gilted?)Qing dynasty, about 1700Collection: Sir Augustus Wollaston Franks」【釈迦如来坐像清王朝(774–86年頃)この仏像は釈迦が悟りを開く直前の場面を表しています。悪魔マーラを打ち破り、すべての衆生を救済することを誓った時、釈迦は大地に手を触れ、その誓いを地の女神に証明させました。この「降魔成道」の瞬間は、チベットやモンゴルの美術において最も多く描かれる主題です。台座を囲む蓮華が、静かに坐す仏陀の姿を支えています。この像は、清朝宮廷の僧院(たとえば北京の雍和宮=ラマ寺)などのために制作された大型鍍金銅像の一つである可能性があります。材質:鍍金銅制作地:中国・チベット時代:清王朝、1700年頃コレクション:サー・オーガスタス・ウォラストン・フランクス】 中国の寺院に安置されていた巨大仏像の一部であったブロンズ仏の頭部。1368年から1644年頃、おそらく明朝時代に制作されたと推定される。鋳造ブロンズ製で、カオリンで覆われ彩色されている。ロンドン、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵、アイテム番号M.3-1936・半眼の表現:瞑想的で静かな悟りの境地を示す表情。・白毫(びゃくごう):眉間に丸い隆起が見え、仏の智恵の光を象徴。・螺髪(らほつ):頭髪は小さな丸い巻き毛状で、仏像特有の神聖な特徴。・木彫の痕跡と彩色の残り:表面に剥落がありますが、元は金箔や彩色が施されていた可能性。そして日本の展示室へ。青銅製(ブロンズ)、三本脚で支えられた大きな香炉。蓋付きで、胴部には装飾文様が施されていた。「JAPANJapan is one of the most prosperous and technologically advanced nations of the world. Widely recognised for its cultural and artistic achievements, it is a country in whichrespect for tradition goes hand in hand with constant innovation and an appetitefor the new.The gallery showcases many of the highlights of the V&A’s internationally importantcollection of Japanese art. This is especially strong in the decorative arts of the Edo(1615–1868 and Meiji (1868–1912) periods. It also includes significant holdings of graphic material, notably woodblock prints, and a growing collection of contemporaryJapanese art, craft and design.Since 1986 the Toshiba Gallery of Japanese Art has offered people from around theworld a showcase for one of the world’s finest collections of Japanese art and design. All of us at Toshiba hope that the gallery continues to fascinate visitors to the V&A and to strengthen ties between Britain and Japan.」【日本日本は世界で最も繁栄し、技術的に進んだ国のひとつです。文化的・芸術的な成果で広く知られ、伝統への敬意と、絶え間ない革新、新しいものへの旺盛な関心とが共存する国です。このギャラリーでは、ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)が誇る国際的に重要な日本美術コレクションの数々を展示しています。特に江戸時代(1615–1868年)と明治時代(1868–1912年)の装飾美術が充実しており、浮世絵をはじめとする版画資料の貴重なコレクション、さらに現代の日本美術・工芸・デザインの収集も進められています。1986年以来、東芝ギャラリー・オブ・ジャパニーズ・アートは、世界でも有数の日本美術・デザインコレクションを広く人々に紹介してきました。東芝は、このギャラリーが今後もV&Aを訪れる人々を魅了し、また英国と日本の絆をさらに強めることを願っています。東芝】大型の青銅製香炉。・装飾 ・香炉の脚まわりに 孔雀(クジャク) が2羽、写実的に造形されていた。 ・孔雀は日本では「吉祥」「長寿」「美の象徴」として扱われ、仏教的には極楽浄土を 象徴する鳥でもある。・台座 ・自然の岩や樹木を思わせる複雑な造形で、その上に孔雀が佇み、香炉を支える構成。・写真の背景 ・波文(青海波)を思わせる模様の壁紙で、展示空間は日本美術ギャラリー (V&Aの東芝ギャラリー)。 ・逸話 ・当時のV&A館長が日本美術収集に熱心で、非常に高額なため政府の特別許可を得て購入 されたという背景は、日本美術が欧州でいかに強い憧憬と価値を持たれていたかを 物語っているのだ と。 この作品はまさに、明治の輸出美術・博覧会美術の象徴といえる大作なのであろう。「Incense burner1877–78This magnificent cast bronze incense burner was exhibited at the 1878 ParisInternational Exhibition. It was bought by a Paris-based dealer, who sold it to the V&A shortlyafterwards. Like many in the West at that time, the Museum’s then director was an ardent enthusiast of Japanese art. The enormous price of the incense burner meanthe had to obtain special permission from the government to buy it.Marked ‘Great Japan’,cast by kakf for Suzuki Chokichi (1848–1919)TokyoBronze with copper alloy inlay and gilded detailingMuseum no. 188-1883」 【香炉1877–78年この壮麗な鋳造青銅製香炉は、1878年のパリ万国博覧会に出品されました。その後、パリを拠点とする美術商が購入し、ほどなくヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)に売却しました。 当時の西洋の人々と同様、博物館の館長も日本美術の熱心な愛好者でありました。 この香炉の価格が非常に高額だったため、購入には政府の特別な許可を得る必要があったといいます。銘文:「大日本」鋳造:鈴木長吉(すずき ちょうきち,1848–1919)が製作。東京青銅製、銅合金の象嵌および鍍金装飾館蔵番号:188-1883】日本ギャラリー「SAMURAI」展示コーナー。近づいて。① 左側パネル(武具装飾)・主に 刀装具(とうそうぐ) が展示されていた。 ・鍔(つば):刀の持ち手と刀身の間に取り付けられる護具。 さまざまな意匠(植物・動物・文様)が見られる。 ・縁(ふち)・頭(かしら)・目貫(めぬき) などの小金具類。 ・素材は鉄・銅合金・金銀象嵌など。美術工芸的価値が非常に高く、日本独自の 細密装飾を伝える。② 中央パネル(SAMURAIと日本刀) ・「SAMURAI」と題された中央の展示は 刀剣そのもの。 ・上段には太刀や打刀。 ・中段には拵(こしらえ)付きの刀。鞘や鍔、柄が豪華に装飾されている。 ・下段には大小二振り(大小拵/だいしょうこしらえ)、武士の象徴的な佩刀形式。 ・鞘には螺鈿や蒔絵の装飾が施されたものも見られる。③ 右側パネル(刀のバリエーション) ・短刀や脇差など、刀剣の種類別に展示。 ・一部は儀礼用あるいは贈答用に製作された美術刀剣。④ ケース右端 ・わずかに写り込んでいるのは 甲冑の一部(鎧兜または当世具足)。 ・SAMURAI展示の文脈として、日本の戦国〜江戸期の武具文化を示している。刀装具の鍔(つば) を集めた展示の一部。鍔(つば)とは日本刀の柄(つか)と刀身の間に取り付ける護具。実用的には手を守る鍔迫り合い用の防御具 ですが、江戸時代には装飾性が強調され、武士の身分や趣味、美意識 を表現する芸術品となったのだ。材料:鉄、赤銅(しゃくどう)、銅合金など。象嵌(ぞうがん)、金銀鍍金、透かし彫りなどの技法を駆使。「甲冑展示」のコーナー。① 左側の甲冑(座像展示) ・兜:大きな前立(まえだて)を持つ兜。金色の装飾が印象的。 ・胴・小具足:鉄板に漆を塗り、茶色〜黒系の威(おどし)糸で編み込まれている。 ・全体印象:実戦的な印象が強く、戦国時代後期〜江戸初期の武具を思わせる。② 右側の甲冑(座像展示) ・姿勢:甲冑を着装した人形が椅子に座った状態で展示されている。 ・兜:鍬形(くわがた)ではなく、小型の立物付き。両側に金属製の 「しころ飾り(蝶翼風の装飾)」が付く。 ・胴・袖・草摺:黒漆塗りを基調とし、赤や金の縅(おどし)糸で装飾。儀礼的要素を持つ甲冑。 ・面貌:精巧な人形の顔を使っているため、来館者に武士が「生きてそこにいる」かのような 印象を与える。③ 背後の掛物 ・武士や従者、装束姿の人物を細かく描いた 武者絵巻(行列図あるいは合戦準備図)。 ・甲冑が実際にどのような場面で用いられたかを示す資料として配置されている。右側の甲冑に近づいて。「Hanging scrollAbout 1750This is an assemblage of painted images from what wasprobably once a horizontal scroll. It shows samurai putting on different kinds of armour, from undergarments through to full battle-readiness. Although not shown, putting on the bulkier and more complicated pieces of armour would usually have required assistance.Ink and colours on paperGift of Robert and Kyoko WinterMuseum no. FE.15-2015」【掛軸1750年頃もとは横長の絵巻であったと思われる図像の断片です。武士が下着から始め、完全な戦闘装束に至るまで、さまざまな種類の甲冑を着用していく様子を描いています。ここでは描かれていませんが、大型で複雑な甲冑を着る際には通常、介助者の助けが必要でした。紙本着色ロバート&キョウコ・ウィンター寄贈館蔵番号:FE.15-2015】 「Figure of a samurai dressed in armourSuit of armour about 1800; figure and stool about 1860This suit of armour has a hammered iron breastplate decorated with a Buddhist deity attacking a demon. The high-quality mail is complemented by fine textiles. The fore-crest on the helmet is an articulated dragonfly.The life-size human figure with its highly realistic features is known as an iki-ningyō(living doll). These were used both in Japan and in international exhibitions abroad, where they featured in dioramas about Japanese life and history.Armour: iron, gilded and painted copper alloy, leather, lacquer and silkFigure: wood, gofun gesso and human hair. Stool: lacquered woodMuseum nos. M.55-1922; M.326-1921」 【甲冑を着た武士像甲冑:約1800年 人形と腰掛:約1860年この甲冑は、打ち出し鉄製の胴に「仏教の神が鬼を討つ」図が装飾されています。上質な鎖帷子は精緻な織物で補われています。兜の前立(まえだて)は、可動式のトンボ(蜻蛉)です。実物大の人形は非常に写実的で、生人形(いきにんぎょう) として知られています。これは日本国内のみならず、海外の博覧会でも用いられ、日本の生活や歴史を紹介するジオラマの一部として展示されました。甲冑:鉄、鍍金および彩色銅合金、革、漆、絹人形:木、胡粉、そして人毛腰掛:漆塗木製館蔵番号:M.55-1922; M.326-1921】「Religion & Ritual(宗教と儀礼)」展示コーナーへ。武士文化の展示(甲冑・刀剣) に続いて、この「Religion & Ritual」セクションでは、日本文化の精神的・宗教的基盤である仏教芸術を紹介していた。① 仏像(右側)・材質:木彫、彩色が施されていた形跡あり。・姿:僧形に近い端正な立像で、衣の襞(ひだ)が規則的に彫られている。・ポーズ:右手を軽く上げ、左手は下げる。説法印(せっぽういん)あるいは施無畏印に近い所作。・台座:蓮華座ではなく、雲形の基壇に立つ形式。・時代:平安~鎌倉期の阿弥陀仏あるいは地蔵菩薩像を思わせる。② 仏教荘厳具(左上)・金属製の華やかな幡(はた)や瓔珞(ようらく)に相当。・鏡板状の金具から垂れ飾りが多数下がり、堂内荘厳や儀礼に用いられたのであろう。・植物文様や仏教的な吉祥文が見られる。●左パネル「Devotion and WorshipThe indigenous religion of Japan is Shinto (the Way of the Gods). It is based on worship of the deities of nature, known as kami. Prayers and offerings are made to the kami for success, gratitude, and for help in a world of dense human populations. As far-flung areas of mainland Asia, Buddhism was introduced to Japan from mainland Asia in the 6th century. With it came Buddhist painting, sculpture, metalwork andtextiles,as well as written scripture. Buddhism did not replace Shinto but co-existed withit as it still does today.」 【信仰と礼拝日本固有の宗教は神道(神々の道)であり、自然の神々(神:かみ)を崇拝することに基づいています。神々には、成功・感謝・困難な人間世界での助けを求めて祈りや供物が捧げられます。6世紀に仏教が大陸から日本に伝来すると、仏教絵画・仏像・金工・織物、さらには経典がもたらされました。仏教は神道を置き換えることなく、共存して今日に至っています。】●中央パネル「Hanging garland (Keman) with lotus flowers1600–1700The lotus flower symbolizes the human purity that can arise from the mire of the material world. The interiors of Buddhist temples were traditionally decorated with fresh flower garlands looped on ropes. Over time the practice developed of suspending metal flowers with hanging pendants, often made of hammered andgilded bronze. These were suspended from temple beams and provided decor.Hammered, pierced and gilded bronzeMuseum no. M.41A-1926」【華鬘(けまん/蓮華飾り)1600–1700年蓮の花は、煩悩の泥の中から咲く清浄の象徴です。仏教寺院の内部は、かつては新鮮な花の花環を綱に掛けて装飾されていましたが、時代が下ると、金工で作られた金属製の花と垂飾を吊るす形式に発展しました。多くは打ち出し・鍍金を施した青銅製で、梁から吊るされ寺院を荘厳しました。青銅製、打ち出し、透かし彫、鍍金館蔵番号:M.41A-1926】 ●右パネル「Figure of the bodhisattva Jizō1000–1200, with later restorationsA bodhisattva is an enlightened being who postpones his own entry into nirvana in order to help others attain salvation. Jizō is one of the most beloved bodhisattvas in Japan, and is the guardian of travelers, helping those who suffer, and is theguardian deity of children and travelers.Carved and painted woodAcquired with assistance of the Art FundMuseum no. FE.6-1983」【地蔵菩薩立像1000–1200年(後世の修復あり)菩薩とは、自らの涅槃入りを後回しにして、人々の救済を助ける悟りを得た存在です。地蔵菩薩は日本でも最も親しまれる菩薩の一つで、旅人を守り、苦しむ人々を救い、特に子供や旅人の守護仏として信仰されています。木彫、彩色Art Fundの助成により収蔵館蔵番号:FE.6-1983】仏教儀礼用の織物(袈裟)。仏教儀礼用の織物(袈裟)に添えられていた 解説パネル●左パネル「Buddhist RobesBuddhist priests in Japan wear rectangular ceremonial robes called kesa, which are draped over the left shoulder and under the right arm. Kesa are traditionally constructed from fragments of fabric, especially luxurious brocades donated by wealthy patrons. The act of sewing together remnants of fine textiles exemplifiestheBuddhist pursuit of poverty, but also demonstrates devotion and piety. The patchwork nature of the kesa garment is a symbolic representation of theuniverse known as a mandala.」 【仏教僧の袈裟日本の仏教僧は、四角い法衣「袈裟(けさ)」を身にまといます。左肩から掛け、右腕の下を通すのが特徴です。袈裟は本来、布の断片を継ぎ合わせて作られ、とくに裕福な檀家から寄進された豪華な織物が使われました。断片を縫い合わせる行為は「清貧の実践」であると同時に「信仰と献身の表れ」でもありました。また、袈裟のパッチワーク的構造は、宇宙を象徴する曼荼羅の表現でもあります。】●中央パネル「Front – Buddhist robe (Kesa)1800–1900Unlike most kesa this robe was not stitched together using small pieces of fabric. Instead, lengths of silk, woven with chrysanthemum and butterfly motifs were sewnby wide strips. It has an additional square to replicate characters from Buddhist sutras, traditionally written on textiles. Some Buddhist sects still use Siddham to copy mantrasand sutras.KyotoFigured silk with metal-wrapped weft threads and silk selvedgeGiven by Mr TA Cuthbert-ThomsonMuseum no. T.263-1927」 【袈裟(表)1800–1900年通常の袈裟と異なり、小さな布片をつなぎ合わせたものではなく、菊や蝶の文様を織り込んだ長い絹布を幅広く縫い合わせています。さらに正方形の布が付け加えられ、これは経文の文字を表すものです。仏教宗派の中には、今も悉曇(しったん/サンスクリット由来の古い書体)で真言や経文を記す伝統が残っています。京都金糸入り絹織物T.A.カスバート=トムソン氏寄贈館蔵番号:T.263-1927】●右パネル「Back – Buddhist robe (Kesa)1800–1900This sumptuous robe is woven predominantly with gold, which would have made itglitter in the light of the temple candles. Vast numbers of similar robes were produced in Kyoto, Japan’s main textile centre, during the Edo period (1615–1868). This robe wasformerly owned by the Rev. Francis Edgar Toye, an Anglican missionary who served in the British Embassy in Tokyo in the 1880s.KyotoFigured silk with metal-wrapped weft threads and silk selvedgeGiven byMr TA Cuthbert-ThomsonMuseum no. T.264-1927」 【袈裟(裏)1800–1900年この豪華な袈裟は主に金糸で織られ、寺院の灯明の光を受けてきらめいたでしょう。江戸時代(1615–1868)には、京都の織物産業の中心地でこうした袈裟が大量に生産されました。この袈裟はもともと、1880年代に英国大使館で勤務していた英国国教会の宣教師フランシス・エドガー・トイ師の所蔵品でした。京都金糸入り絹織物T.A.カスバート=トムソン氏寄贈館蔵番号:T.264-1927】打掛(うちかけ) 。打掛は江戸時代以降の武家や裕福な町人女性が婚礼や儀式で着用した上着で、特に格式高い衣裳として知られている。・形:袖口が大きく、裾が長い「打掛」形式。通常は小袖の上に羽織り、裾を引きずるように着用。・文様:全面に花文(牡丹、菊、桜などと思われる)が織り込まれ、曲線的な唐草模様と 組み合わされている。・色彩:金地を基調に、赤・青・白・緑など多彩な花を配置。きらびやかで晴れやかな印象。・技法:緻密な織り(錦織、あるいは金襴)によって花々を立体的に表現している。「6.Nō robe1980The lavishly patterned robes of the Nō theatre are among Japan’s most spectaculartextiles. This elaborate example would have been worn by an actor playing a femalerole.It was created by Yamaguchi Yasujiro, who dedicated his career to recreating the complex patterns, dyes and weaving techniques of Nō robes of the Edo period.Yamaguchi Yasujiro (1904–2000)KyotoFigured silkGiven by the makerMuseum no. FE.65-2002」 【6. 能装束1980年能楽に用いられる華麗な文様の衣裳は、日本の織物の中でも最も壮麗なものの一つです。この精緻な例は、女性役を演じる役者が着用したものでしょう。製作者は山口泰二郎(1904–2000)で、生涯をかけて江戸時代の能装束の複雑な文様・染色・織技法を再現することに尽力しました。山口泰二郎(1904–2000)京都絹織物(紋織)作者寄贈館蔵番号:FE.65-2002】日本ギャラリー「THEATRE(演劇)」コーナー に展示されている 能面(のうめん) 。5種類の典型的な面が紹介されていた。「1. Nō mask of a young nobleman (Imawaka)About 2000Masks are used to create a mood of yūgen, a Japanese aesthetic concept suggestiveof sadness, mystery, elegance and calm. This mask, representing a young man of noble birth, is used for various characters in Nō plays. These include the ghost of the 9th-century courtier and poet Ariwara no Narihira and the spirit of the 12th-century warrior poet Minamoto no Yorimasa.Suzuki Nohjin (1928–2008)KobeCarved andpainted cypressSuzuki Nohjin BequestMuseum no. FE.9-2004」 【1. 能面「今若(いまわか)」―若い貴公子の面約2000年能面は「幽玄」という日本美学を体現するために用いられます。「幽玄」は哀愁・神秘・優雅・静謐を含意する概念です。この面は高貴な生まれの若者を表し、さまざまな能の登場人物に用いられます。例えば9世紀の公卿・在原業平の亡霊や、12世紀の武人歌人・源頼政の霊などです。鈴木能臣(1928–2008)作神戸檜材彫刻・彩色鈴木能臣遺贈館蔵番号:FE.9-2004】「2. Nō mask of a young woman (Waka-onna)2000Suzuki Nohjin (1928–2008)KobeCarved and painted cypressSuzuki Nohjin BequestMuseum no. FE.10-2002」 【2. 能面「若女(わかおんな)」―若い女性の面2000年鈴木能臣(1928–2008)作神戸檜材彫刻・彩色鈴木能臣遺贈館蔵番号:FE.10-2002】「3. Nō mask of a female demon (Hannya)1650–1700Carved and painted cypressMuseum no. 578-1886」 【3. 能面「般若(はんにゃ)」―女鬼の面1650–1700年檜材彫刻・彩色館蔵番号:578-1886】「4. Nō mask of a fearsome aged deity (Harabō/akujō)1650–1700Signed: Made by Isebo Kumenokami (Kumenokami Minbu)Carved and painted cypressAcquired with the assistance of the Art FundMuseum no. FE.51-1983」 【4. 能面「鉢木(はらぼう)/悪尉(あくじょう)」―恐ろしげな老神の面1650–1700年銘文:「伊勢坊久米守(久米守民部)作」檜材彫刻・彩色アート・ファンド寄贈協力により収蔵館蔵番号:FE.51-1983】「5. Nō mask of a graceful old woman (Uba)About 1650–1700Signed: Early Uba made by IseboCarved and painted cypressMuseum no. 579-1886」 【5. 能面「姥(うば)」―優雅な老女の面約1650–1700年銘文:「伊勢坊作・初期姥」檜材彫刻・彩色館蔵番号:579-1886】「NōNō is a dance-drama performed on a sparsely decorated stage by actors who aretraditionally all male. Nō theatre originated in the 14th century under the patronageof the shōgun (military leader) Ashikaga Yoshimitsu. Richly decorated robes and finelycarved masks are used in performances informed by Zen principles of restraint, understatement and economy of movement.」 【能(Nō)能は、簡素にしつらえられた舞台で演じられる舞踊劇で、伝統的に出演者はすべて男性です。能楽は14世紀、将軍・足利義満の庇護のもとに成立しました。舞台では、華麗な装束と精巧に彫られた能面が用いられ、禅の思想に基づく「抑制」「簡素」「動作の経済性」が表現の根幹をなしています。】外套着物(打掛)「Outer kimono (uchikake)1870–90This exuberant outer kimono is embroidered with two mythical shishi (lion-dogs)on abridge over a waterfall surrounded by peonies. The scene relates to a famousKabuki play, so this may be a theatrical garment. Decorative themes on stage costumes werenot usually so literal, however, and this kimono may have been worn by a high-ranking courtesan. The pleasures of the theatre and the brothelwere closely linked.Probably KyotoPlain weave crêpe silk with freehand paste-resist dyeing (yūzen) and embroideryin silk and gold-wrapped silk threadsMuseum no. FE.7-1987」【外套着物(打掛)1870–90年この華麗な打掛は、牡丹に囲まれた滝の上の橋に立つ2匹の神獣「獅子(しし、獅子舞の獅子に通じる霊獣)」を刺繍で表しています。この場面は有名な歌舞伎の演目に関連しているため、舞台衣装であった可能性があります。ただし、舞台衣装の装飾テーマがこれほど直截的に表現されることは稀であり、この着物は高位の遊女によって着用された可能性もあります。江戸から明治にかけては、芝居と遊郭の享楽文化が密接に結びついていました。おそらく京都平織縮緬絹に友禅染(手描き糊防染)、絹糸および金糸巻き絹糸による刺繍館蔵番号:FE.7-1987】歌舞伎に関連する大判の掛軸(あるいは舞台幕/絵看板的な布絵)の展示。絵柄からみて、歌舞伎芝居の名場面を描いた布製の舞台装飾やポスター的な作品 。「KabukiKabuki is a form of popular theatre that originated in the early 17th century andcontinues to be performed today. The earliest actors were women, but because ofconcerns about their involvement in prostitution they were banned from the stage. Kabuki then developed with male actors playing both male and female roles. The costumes are lavish and flamboyant and there is extensive use of make-up. The acting, which is accompanied by music, is stylised and often very dramatic.」 【歌舞伎歌舞伎は17世紀初頭に成立し、現在も上演が続けられている庶民的な演劇形態です。最初に舞台に立った役者は女性でしたが、遊女との関わりが問題視され、女性は舞台から追放されました。その後、歌舞伎は男性役者が男性・女性双方の役を演じる形へと発展しました。衣裳は豪華絢爛で華やかであり、化粧も大がかりに施されます。演技は音楽を伴い、様式化されていて、しばしば非常に劇的なものです。】袱紗(ふくさ)。「Gift cover (fukusa)1840–70The exquisite embroidery on this fukusa conveys wishes for a long and happy marriage. It depicts Jō and Uba, an elderly couple who lived in perfect harmony on a pine-cladisland. Legend has it that when they died, their spirits occupied the trees. On moonlit nights, they return to clear the forest floor. Jō rakes in good fortunewhile Uba sweepsaway the bad.Satin silk (shusu) with embroidery in silk and gold-wrapped silk threadsMuseum no. T.236-1967」【袱紗(ふくさ)1840–70年この精緻な刺繍入りの袱紗は、長寿と幸福な結婚を願う意匠を表しています。図柄には「尉(じょう)」と「姥(うば)」という、松に覆われた島で仲睦まじく暮らした老夫婦が描かれています。伝説によれば、二人が亡くなるとその魂は松に宿り、月夜の晩には森に現れて地を清めるといいます。尉は熊手で福をかき集め、姥は箒で災厄を掃き払うとされています。素材:朱子織の絹地に、絹糸および金糸巻き絹糸による刺繍館蔵番号:T.236-1967】 「The presentation of gifts has always been an important social ritual in Japan.Gifts were traditionally placed in a box on a tray, over which a textile cover,called a fukusa, was draped. Using a cover appropriate to the occasion was a major consideration. The richness of the decoration was an indication of the donor’s wealthand the design evidence of their taste and cultural sensibilities. After being suitablyadmired, the cover was returned to the donor.」 【贈り物の儀式は、日本において常に重要な社会的慣習でした。贈答品は伝統的に、箱を盆にのせ、その上に「袱紗(ふくさ)」と呼ばれる布を掛けて差し出されました。場にふさわしい袱紗を用いることは大切な配慮であり、装飾の豪華さは贈り主の財力を示すとともに、その意匠は趣味や文化的感性を示すものでした。贈呈後、袱紗は賞賛を受けたのち、贈り主へ返却されるのが習わしでした。】4領の着物が並べられていた。「KimonoIn the Edo period (1615–1868) the kimono was the principal item of dress for both men and women. This straight-seamed robe was worn wrapped left side over right and secured with a sash called an obi. It was the pattern on the surface, rather thanthe cut of the garment, that was significant. Indications of gender, wealth,status and taste were expressed through the choice of colours, motifs and decorative techniques. The rising affluence of the merchant class created a growing market for luxury kimono.」 【着物江戸時代(1615–1868年)には、着物は男女ともに主要な衣服でした。この直線裁ちの衣は、左前に打ち合わせ、帯と呼ばれる sash で結んで着用されました。重要なのは衣服の仕立てではなく、その表面を飾る模様でした。色彩や文様、装飾技法の選択によって、性別・富・身分・趣味が表現されました。町人階級の経済力が高まるにつれて、高級着物への需要も拡大していきました。】左側「Kimono for a young woman (Furisode)1800–50On formal occasions, high-ranking women of the ruling military samurai elite would wear kimono patterns with detailed landscapes of water, islands and pines, flowers including plum, wisteria and cherry, and birds such as the crane.This kimono was made of crepe silk woven as a plain ground with paper stencils defining the landscape in thin powdered gold.The long sleeves indicate it would have been worn by a young unmarried woman.Probably KyotoPlain-weave silk crepe with freehand paste-resist dyeing (yūzen), powdered gold andembroidery in silk and gold-wrapped silk threadMuseum no. FE.28-2003」 【若い女性の着物(振袖)1800–50年頃公式の場では、支配階級である武家の高位の女性たちは、水、島、松の風景や、梅、藤、桜などの花、鶴などの鳥を細密に描いた文様の着物を着用しました。この着物は縮緬地に型紙で文様を摺箔し、さらに刺繍を施したものです。長い袖は、未婚の若い女性が着ていたことを示しています。おそらく京都製平織縮緬地、友禅染、摺箔、金糸・絹糸刺繍館蔵番号 FE.28-2003】中央「Kimono for a woman (Kosode)1800–50At Japanese weddings, paper ornaments in the shape of male and female butterflies were often wrapped around bottles of sake to symbolize the harmony of the marriedcouple.The use of this auspicious motif suggests the kimono originally worn by the bride for a marriage ceremony.The bright scarlet colour derives from safflower (beni), a popular but expensive dye.Probably KyotoPlain-weave silk with freehand paste-resist dyeing (yūzen) and embroidery in silk and gold wrapped silkthreadMuseum no. T.90-1932」 【女性の着物(小袖)1800–50年頃日本の結婚式では、雄蝶・雌蝶の紙飾りがしばしば酒瓶に結び付けられ、夫婦の和合を象徴しました。この吉祥文様の使用は、この小袖がもともと婚礼の場で花嫁によって着られたことを示しています。鮮やかな紅色は紅花から得られたもので、高価ですが人気のある染料でした。おそらく京都製平織絹地、友禅染、金糸・絹糸刺繍館蔵番号 T.90-1932】右側「Kimono for a young woman (Furisode)1800–50Here a design of pine trees among clouds is transferred to the hem of the kimono. The pine is a symbol of long life, as are the cranes flying through the clouds. Such motifs would have formed part of the bride’s trousseau and been used at the time of a wedding. The long sleeves indicate it was worn by a young unmarried woman.Probably KyotoPlain-weave silk with freehand paste-resist dyeing (yūzen), powdered gold andembroidery in silk and gold-wrapped silk threadMuseum no. T.29-1966」 【若い女性の着物(振袖)1800–50年頃ここでは、雲間に広がる松の文様が着物の裾に配されています。松は長寿の象徴であり、雲間を飛ぶ鶴もまた長寿を表します。これらの文様は花嫁道具の一部を成し、婚礼の際に用いられました。長い袖は、未婚の若い女性が着ていたことを示しています。おそらく京都製平織絹地、友禅染、摺箔、金糸・絹糸刺繍館蔵番号 T.29-1966】印籠(いんろう)と根付(ねつけ)の展示ケース。江戸時代の男性が煙草入れや薬、印などの小物を携帯するために使った携帯容器で、帯に紐を通し、端に根付を付けて落ちないようにしました。非常に装飾的で、漆工芸・蒔絵・象嵌・彫刻などの技術が凝縮され、日本美術工芸の粋を表す小物でもあります。パネル左側(青地)「Inrō(印籠)Inrō are small containers used in Japan from the 16th century.They held medicines, seals, or other small objects.Hung from the sash (obi) of a kimono, secured with a netsuke.Inrō became status symbols and works of art, especially in lacquerwith maki-e.」 【印籠(いんろう)は16世紀以降、日本で用いられた小型の容器です。薬や印、その他の小物を入れるために使われました。着物の帯(帯)から吊り下げ、根付で固定しました。印籠は身分や趣味を示す象徴ともなり、特に漆の蒔絵によって美術工芸品として発展しました。】パネル右側(番号付きリスト)展示されている印籠の 一つ一つのタイトルや意匠 が番号と共に説明されていた。例えば:1.印籠:松竹梅文様(Matsu, take, ume) – 長寿や吉祥を象徴する伝統的文様。2.印籠:武士の図(Samurai scene) – 武士や戦闘場面を描いたもの。3.印籠:動植物(Birds and flowers) – 季節や自然美を示す。…といった内容が並んでいるはずです。 さらにズームして。さらに。「InrōTraditional forms of Japanese dress such as the kimono did not have pockets.A man would carry everyday items in containers suspended from the sash (obi) aroundhis waist. The most common type of container was the inrō. This emerged in the late16th century and in time became the ultimate male fashion accessory. Inrō consisted of interlocking compartments held together by silk cords. They were most commonly decorated with lacquer, though other materials were also used.For more informationon the objects, see the label book.」 【印籠(いんろう)着物のような伝統的な日本の衣服にはポケットがありませんでした。男性は日用品を、腰に締めた帯(帯)から吊り下げられた容器に入れて携帯しました。その中で最も一般的な容器が印籠でした。印籠は16世紀後半に登場し、やがて男性にとって究極のファッション・アクセサリーとなりました。印籠は、絹の紐でまとめられた入れ子状の複数の小箱から構成されていました。最も一般的には漆で装飾されましたが、他の素材が使われることもありました。】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.26
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その119): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-2
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクロンドンの ヴィクトリア&アルバート美術館(V&A, Victoria and Albert Museum)の見学を続ける。「CAST COURTS(キャスト・コート)」は、同館の名物展示室の一つで、ヨーロッパ各地の名建築や彫刻の石膏模型(キャスト)が集められている大空間なのであった。・1873年に公開された大展示室のRoom 46a・46b 。・目的は、当時の学生や職人がヨーロッパの名作建築・彫刻をロンドンで学習できるように することでした。・イタリア、フランス、スペイン、ドイツなどの建築細部や記念碑がそっくりそのまま石膏で 複製され、現地に行かずとも全体像が理解できる貴重な教育資源であった と。1.中央左奥:ポルタ・マッジョーレ(Porta Maggiore、Rome)の模型 ローマの古代建築の複製。2.中央正面や左右:墓廟や教会のレリーフの石膏模型 イタリア・スペイン・フランス各地の大聖堂や礼拝堂から取られたもの。3.手前右側の巨大像:ミケランジェロ《ダヴィデ》像の石膏模型(複製) フィレンツェ、アカデミア美術館にある本物を 1857 年に鋳型から取ったもの。 Cast Courts のシンボル的存在。4.背後の壁面(上部):フリーズや浮彫の石膏模型 ルネサンスや古典的建築装飾のレリーフ群。「The Cast CourtsYou are walking into the 19th century. Opened in 1873, the Cast Courts show copies of architecture and artworks from around the world. These historic galleries offer a glimpseof the Victorian museum.The Courts are the strongest expression of this Museum’s founding mission as a placeof art education. The Museum’s collection provided examples to inspire artists, designersand artisans to supply better designs to Britain’s factories. Spectacular displays would also shape ‘public taste’ to help consumers become more discerning in their choices. Copies including plaster casts, electrotypes and photographswere central to this mission, and complemented the Museum’s collections of original works. Together they offereda 19th-century encyclopaedia of international decorative styles.Today the Cast Courts take us back in time. For Victorians, they were the height of modernity. In a period when travel was difficult, the Courts brought art and architecturefrom around the globe together under one roof, making the world feel smaller and more connected in a unique modern age. Compared to the dawn of the internet, a modernfascination with replication, particularly via digital media, has rekindled the relevance ofthese collections for visitors now.」 【キャスト・コートあなたはいま、19世紀に足を踏み入れています。1873年に開館したキャスト・コートは、世界中の建築や美術作品の複製を展示しています。これらの歴史的なギャラリーは、ヴィクトリア朝時代の博物館の姿を垣間見せてくれます。キャスト・コートは、この博物館の創設理念 ―― 芸術教育の場としての使命 ―― を最も強く表現しています。博物館の収蔵品は、芸術家・デザイナー・職人に模範を与え、イギリスの工場により優れたデザインを供給させるための刺激となりました。壮大な展示は「大衆の趣味」を形作り、消費者がより洗練された選択をする助けともなりました。石膏複製、エレクトロタイプ(金属複製)、写真といったコピーはこの使命の中心にあり、オリジナル作品のコレクションを補完しました。両者を合わせることで、19世紀における国際的な装飾様式の百科事典を提供したのです。今日、キャスト・コートは私たちを過去へと連れ戻します。ヴィクトリア時代の人々にとって、それは最新のモダニティの象徴でした。旅行が困難な時代に、キャスト・コートは世界中の美術と建築を一つの屋根の下に集め、世界をより小さく、よりつながりあるものと感じさせたのです。それはインターネット黎明期にも比すべき体験でした。特にデジタルメディアを通じた複製への現代的関心は、このコレクションの今日的な意義を再び呼び覚ましています。】Room46A,Bはここ。・中央手前の像: ミケランジェロ《ダヴィデ像》の石膏複製 (原作1501–1504、フィレンツェ、アカデミア美術館所蔵)。 V&Aで最も有名な複製の一つで、1873年にフィレンツェから特別に型取りされたもの。 高さは約5.17m。・背後の金色の扉: ロレンツォ・ギベルティ作《天国の門(フィレンツェ洗礼堂の東扉)》の複製。 19世紀に電気鋳造(エレクトロタイプ)で精密に再現されたもの。・壁面に並ぶレリーフや小像: ルネサンス期イタリアの彫刻や建築装飾の複製群。 特に壁上部には彩色されたパネル (ステンドグラスやフレスコの模写)も見えます。「CAST OFMichelangelo (1475–1564)David1501–4Michelangelo’s David is probably the most famous sculpture in the world, reproducedin countless copies, large and small. This life-size cast was a gift to Queen Victoria from the Grand Duke Leopold II of Tuscany. It was a peace offering, since the dukerefused to export a painting which the National Gallery in London had hoped to buy. The cast was produced from a mould made up of several hundred pieces and is reinforced with metal rods.Michelangelo carved his David from a single block of marble. David, slayer of the giantGoliath, was a symbol of civic freedom for the Florentine Republic. It was used by boththe republican government and the powerful Medici family, who effectively ruledFlorence. The statue was placed outside the Palazzo Vecchio until 1873. The marble copy thatreplaced it shortly afterwards still stands there today.CastClemente PapiAbout 1857Painted plasterFlorence, ItalyGiven by Leopold II, Grand Duke of Tuscany to Queen Victoria in 1857Museum no. Repro.1857-6OriginalMarbleAccademia delle Belle Arti, Florence」 【ミケランジェロ(1475–1564)《ダヴィデ》1501–1504年ミケランジェロの《ダヴィデ像》はおそらく世界で最も有名な彫刻であり、大きなものから小さなものまで数え切れないほど複製されています。この等身大の石膏複製は、トスカーナ大公レオポルド2世からヴィクトリア女王に贈られたものです。これは和平の贈り物であり、というのも大公がロンドンのナショナル・ギャラリーが購入を望んでいた絵画の輸出を拒否したためでした。この複製は数百個のパーツから成る型から作られ、金属棒で補強されています。ミケランジェロは《ダヴィデ》を一つの大理石の塊から彫り上げました。巨人ゴリアテを倒したダヴィデは、フィレンツェ共和国にとって市民の自由の象徴でした。この像は共和政政府と、実質的にフィレンツェを支配した有力なメディチ家の双方に利用されました。像は1873年までヴェッキオ宮殿前に設置され、その後に置き換えられた大理石の複製は現在もそこに立っています。複製(キャスト)クレメンテ・パピ作1857年頃彩色石膏イタリア、フィレンツェトスカーナ大公レオポルド2世よりヴィクトリア女王に寄贈(1857年)館蔵番号 Repro.1857-6原作大理石フィレンツェ、美術アカデミア(アカデミア美術館)】ロンドン・ヴィクトリア&アルバート美術館(V&A)の キャスト・コート(Cast Courts)西ホール に収蔵されている石膏複製の一つで、《ダヴィデ像》の複製と並んで、ミケランジェロ作品の重要な展示例。ミケランジェロ《縛られた奴隷(Dying Slave / Bound Slave)》の石膏複製。・作者:ミケランジェロ・ブオナローティ(Michelangelo, 1475–1564)・制作年:1513–1516年頃・原作:大理石、ルーヴル美術館(パリ)所蔵・主題: この彫像は、ミケランジェロが教皇ユリウス2世の墓廟のために構想した一連の「奴隷像」の ひとつです。 体をよじりながら片手を頭にあて、束縛の中で苦悶する姿が表されており、肉体の緊張と精神の 解放への願望が象徴的に描かれています。「CAST OF Michelangelo (1475–1564) The Dying Slave 1513Michelangelo carved six figures of slaves for the tomb of Pope Julius II. The project tocreate a vast monument was eventually scaled down. Michelangelo gave two of thefigures to a Florentine exile in France, who presented them to the king.In 1794 The Dying Slave and The Rebellious Slave (cast displayed nearby) werebought by the French state. They were placed in the Louvre, where they were fundamental to the appreciation and knowledge of Michelangelo’s work outside Italy.CASTMonsieur ToquiéreAbout 1869Painted plasterParis, FranceMuseum no. Repro.1869-15ORIGINALMarbleFlorence, ItalyMusée du Louvre, Paris」 【鋳造:ミケランジェロ(1475–1564)《瀕死の奴隷》 1513年ミケランジェロは、教皇ユリウス2世の墓廟のために6体の奴隷像を制作しました。しかし、この巨大な墓廟計画は最終的に縮小されました。ミケランジェロはそのうち2体をフランスに亡命していたフィレンツェ人に譲り、その人物がフランス王に献上しました。1794年に《瀕死の奴隷》と《反抗する奴隷》(近くに展示されている複製)はフランス国家によって購入され、ルーヴル美術館に収蔵されました。これらはイタリア国外でミケランジェロ作品を理解し評価する上で極めて重要な役割を果たしました。複製製作者:モンシュー・トキエール制作年:約1869年素材:彩色石膏場所:フランス・パリ所蔵番号:Repro.1869-15原作素材:大理石起源:イタリア・フィレンツェ現蔵:ルーヴル美術館(パリ)】この壁一面だけでも「古代~ルネサンスの代表的作品の複製」が集中的に並んでおり、まさにV&Aキャスト・コートの学術的ショーケースになっていたのであった。1.上部中央(壁面の大画) ・ラファエロ《アテネの学堂》(The School of Athens)複製画 本物はバチカン宮殿(ラファエロの間)にあるフレスコ画。ここでは大型模写として展示。2.中央(大きな墓廟) ・イラリオ・デ・ロッシ作《プーシェ枢機卿の墓廟》 (Tomb of Cardinal Jean de La Grange / Pucci tomb) の複製 元はイタリアにあるルネサンス期の墓廟。装飾的アーチや横たわる像が特徴。3.ガラスケース内(中央手前) ・ドナテッロ《ダヴィデ》のブロンズ像複製 ルネサンス初期を代表する裸像の一つ。本物はフィレンツェのバルジェッロ美術館。4.右下(座る男性像) ・ ミケランジェロ《ロレンツォ・デ・メディチの像》(メディチ家礼拝堂)複製 サン・ロレンツォ聖堂の新聖具室にある「黄昏」と対をなす肖像。5.左奥(黒色の横たわる人物像) ・中世またはルネサンス期の墓碑彫刻複製(詳細は未特定) 横臥する姿の騎士または聖人像。6.壁面レリーフ(右上半円形) ・聖書場面を描いたルネサンス期の浮彫レリーフの複製。ラファエロ《アテネの学堂》(The School of Athens)をネットから。こちらは複製のズーム写真をネットから。・横たわる枢機卿像(レキュンベント像) 中央のアーチの下に、眠るような姿で横たわる枢機卿が配置されていた。・アーチ内のレリーフ 聖母子像が浮き彫りで描かれ、墓全体を宗教的に守護する構図。・上下の階層構造 下段に碑文と家紋、上段に聖人像や寓意像、さらに最上部には座像と立像が並ぶ。・ルネサンス期の建築的枠組み アーチや列柱、ニッチに聖人像を収めるデザインは典型的な盛期ルネサンス様式。写真中央奥に見える大きなアーチは、サン・ロレンツォ大聖堂(フィレンツェ)の門口装飾の複製。周囲にはルネサンス期イタリアの代表的な大理石装飾や説教壇、墓廟などが並んでいた。・左手前 サンソヴィーノ《フォルリ枢機卿の墓》(モンテプルチャーノ大聖堂、16世紀初頭)・中央やや奥(円形の構造物) ピサ大聖堂洗礼堂の説教壇(ニコラ・ピサーノ作、1260年頃)の複製・右手前(張り出した形の構造物) ピサ大聖堂またはシエナ大聖堂の説教壇部分の複製・正面奥 フィレンツェのサン・ロレンツォ大聖堂正面門口(19世紀に計画されたが未完成のまま)に 基づく装飾の複製・壁面上部 デッラ・ロッビア工房による多彩色陶彫レリーフの複製群Tomb of St Peter Martyr。「聖ペテロ・マルティールの墓」(ミラノ、サン・トストルジョ教会)👈️リンク の複製。本物は・作者:ジョヴァンニ・ディ・バルドゥッチョ(Giovanni di Balduccio, 活動 1317–1349)・制作年:1338年(署名・日付入り)・場所:イタリア・ミラノ、サン・トストルジョ教会(Church of Sant’Eustorgio, Milan)・素材:大理石・依頼主:ドミニコ会修道士たち(1252年暗殺された聖ペテロ・マルティールを顕彰するため)下記写真はネットから。・基壇(下段) ・台座は赤いヴェローナ大理石の“8本の角柱(小柱)”で支えられ、各柱に8体の女性像が 寄り添います。これらは四つの枢要徳+三つの神学徳+服従(Obbedienza)などの “徳の寓意像”で、足元には対応する象徴動物が配されています (例:剛毅=ライオン、節制=混合器など)。・中段(石棺まわり) 石棺の側面には聖ペテロ・マルティールの物語を描く8場面の浮彫。 例:舵の奇跡(船の奇跡)/殉教/葬送/列聖/遺体の移送 など(全8場面が確認済み)。 場面のあいだには聖人の高浮彫像(聖ペトロ、聖アンブロジオ、聖シンプリチャーノ、 聖エウストルジョ)が入り、角(スピゴリ)には教会博士(グレゴリウス/ヒエロニムス/ トマス・アクィナス/アウグスティヌス)が置かれます。・上部(蓋〜頂部) 蓋の周りには九つの天使隊(天使・智天使・座天使…)が巡り、最上部は三尖の小堂 (エディコラ):中央に玉座の聖母子、左右に聖ドミニコと聖ペテロ・マルティール、 頂点に祝福するキリストと天使。・美徳像(女性像)は左から、 ・Obedientia(服従) … 胸に手を当て、書物を持ち、足元に従順の象徴=牛 ・Spes(希望) … 視線を上に向け、天を仰ぐような姿勢。手に花や果実をまとめた 「花束/豊穣の象徴」を持つ ・Fides(信仰) … 左手に聖杯を持つ(聖体の象徴)、胸には小さな十字架を掲げる 端正で落ち着いた表情は「信仰の確固たる心」を体現 ・Caritas(愛) …胸に子供を抱いている姿で表現、「隣人愛」「無私の愛」を象徴。 多くの中世~ルネサンス期美術において、Caritas は母性的・養育的な イメージで 表されるのが典型本物の反対側をネットから。美徳像(女性像)は左から、・Iustitia(正義) – 堂々と直立した姿勢で、威厳を示す冠(ティアラ)を戴き、衣装は繊細な 彫刻装飾を持つ・Temperantia(節制) – 手に二つの容器を持ち、液体を移し替えるような動作を象徴的に表す・Fortitudo(剛毅)– 胸の前に盾(またはライオン頭のレリーフ装飾付き円盤)を抱えている。 剛毅(Fortitudo)は勇気や耐え忍ぶ力を象徴し、ライオンはその象徴動物。・Prudentia(思慮) – 片手に「書物(知識の象徴)」を抱え、もう一方の手で衣をつまみつつ、 指を立てて考えるような仕草を見せています。視線はやや下げ、熟考する 表情で「熟慮・賢明さ」を強調。「Cast of Giovanni di Balduccio (active 1317–49)Tomb of St Peter MartyrSigned and dated 1338St Peter Martyr was a Dominican friar assassinated in 1252. In 1335 the friars ofSant’Eustorgio decided to honour him with a great memorial. With its monumental architectural form and solid standing figures, the tomb exemplifies the early Renaissance style of Northern Italy. The Museum’s cast collection includes copies ofmany great works from the region, as well as from Florence and Rome.CASTEdoardo PierottiAbout 1869Painted plasterMilan, ItalyMuseum no. Repro.1869-68ORIGINALMarbleMilan, ItalyChurch of Sant’Eustorgio, Milan」【ジョヴァンニ・ディ・バルドゥッチョ(活動 1317–1349)作聖ペテロ・マルティールの墓1338年署名・日付入り聖ペテロ・マルティールは1252年に暗殺されたドミニコ会修道士でした。1335年、ミラノのサン・トストルジョ教会の修道士たちは、彼を讃えるために壮大な記念碑を建立することを決定しました。この墓は、堂々たる建築的構成と力強く立つ人物像によって、北イタリアにおける初期ルネサンス様式の典型を示しています。博物館の石膏模型コレクションは、この地域の傑作だけでなく、フィレンツェやローマの作品も数多く含んでいます。複製(キャスト)エドアルド・ピエロッティ1869年頃彩色石膏イタリア、ミラノ所蔵番号 Repro.1869-68原作大理石イタリア、ミラノサン・トストルジョ教会】V&A美術館(ロンドン)・キャスト・コート(West Court) の奥の方を写す。左手前(円形の説教壇)・ニコラ・ピサーノ《ピサ大聖堂洗礼堂の説教壇》(1260年、オリジナル:ピサ) ・新約聖書の場面を彫刻した浮彫と、多数の人物像で飾られた円形説教壇。 ・ロマネスクからゴシック、初期ルネサンスへの移行を示す傑作。中央奥(アーチ状の大建築)・サン・ミケーレ門(ヴェローナ大聖堂ファサードの一部) ・奥に大きなアーチ構造があり、上部に聖人像を配している。 ・キャスト・コートでは代表的な「建築断面」の複製のひとつ中央(アーチ前に立つ塔状構造物)・聖ヨハネ洗礼堂の祭壇装飾(?)またはフィレンツェの墓廟の一部 ・装飾性の高い円柱型の作品。奥の位置に独立して置かれている。右手(壁際の長方形の墓廟構造物)・ジョヴァンニ・ディ・バルドゥッチョ《聖ペテロ・マルティールの墓》 (1338年、オリジナル:ミラノ、サン・トストルジョ教会) ・直前にご紹介したものと同じ墓廟が、右壁側に配置されています。移動して。・右手前: ・ミケロッツォ作「イラリア・デル・カレットの墓」(Ilaria del Carretto Tomb、 Lucca 大聖堂、 1400年代初頭)やアンドレア・サンソヴィーノ作「枢機卿トンマーゾ・ マルシェッロの墓」など、イタリア・ルネサンス期の墓碑彫刻群・中央右の大きな建築的構造物: ・アントニオ・ロッサリーノ作「マリア・ディ・アラゴナの墓」(Naples, San Domenico Maggiore, 15世紀) などに類似する荘厳な墓廟(ゴシック様式のキャノピー付き)・左奥の円形構造物: ・ニコラ・ピサーノ作「ピサ大聖堂の説教壇(1260年)」の石膏複製 ・ギリシア彫刻の古典的モチーフを取り入れ、中世からルネサンスへの橋渡し的作品とされる 名作。・奥壁面上部の長方形レリーフ群: ・各地の教会にある浮彫装飾(例えばルッカやシエナ大聖堂のファサード彫刻)を模した複製。キャストコート(Cast Courts)西ホール の一角。中央にはイタリア・ルネサンス建築の重要作例の複製が並んでいた。1. 中央奥の巨大なアーチ構造 ・ミケランジェロ《メディチ家礼拝堂の入口装飾》 サン・ロレンツォ聖堂(フィレンツェ)の祭壇建築を模した大規模な建築複製。 彫像や装飾的なアーチが再現され、ルネサンス建築の典型的意匠が見られる。2. アーチの手前・中央の八角形の構造物 ・聖ジョン洗礼盤(ピサ大聖堂洗礼堂、Nicola Pisano作) の複製 八角形の基壇に立ち、上部に洗礼用の水盤を載せた形。装飾に多くの浮彫像が配される。3. その手前の墓廟(写真中央下) ・墓碑(ルネサンス期イタリアの枢機卿墓) 棺上に横たわる像を持つ典型的なルネサンス様式の墓廟。4. 周囲に並ぶ胸像群 ・古代ローマやルネサンスの 哲学者・詩人・政治家の胸像 を複製展示。 「ギャラリー的配置」で、学術的な鑑賞用に並べられている。イラリア・デル・カレッタの墓(1406年)の本物の写真をネットから。・人物: イラリア・デル・カレッタ(1379–1405)は、ルッカの統治者パオロ・グイニージの若き妻。 出産直後、26歳の若さで亡くなりました。・作者:・ヤコポ・デッラ・クエルチャ(1374–1438) シエナ出身の彫刻家で、自然な人体表現や感情表現を先駆的に試み、ルネサンス彫刻の先駆と なりました。・制作年: 1406年頃・材質: カッラーラ大理石・所蔵: オリジナルはルッカ大聖堂(サン・マルティーノ大聖堂)に現存。イラリア・デル・カレッタの墓の横から振り返って。・両手を胸の上で組み、静かに眠る姿で表現。死後の安らぎと永遠の祈りを象徴。・頭部を支える大きな枕:両端が房飾りで結ばれており、写実的かつ荘厳な印象。・衣服の流れるような襞:当時の高位女性のドレスを反映。彫刻としての布表現が非常に巧み。・墓台部の装飾:側面に天使や花模様などが施されており、来世への希望を示唆。キャストコート(Cast Courts)へと続く回廊部分。この回廊は キャストコート本体の壮大な空間に入る前の「導入ギャラリー」 のような役割を持っており、建築断片の複製、装飾浮彫や中世・ルネサンスの石細工の写しが主に展示されていた。・長い直線回廊 両側にガラスケースや展示棚が配置され、建築装飾や小型彫刻、浮彫パネルなどの複製が 並んでいた。・床モザイク 幾何学文様や植物文様の装飾タイルが敷き詰められていた。・赤と金で彩られた円柱 キャストコートの壮麗さに調和させた装飾。・壁面展示 レリーフや建築断片(ポータル装飾や紋章)が高い位置に設置されていた。この一角は「西洋の宗教彫刻と記念碑的建築」の複製群を集めたエリアで、ローマ(古代)―ロマネスク―ゴシック―ルネサンス の大建築の名品を一度に見られるように配置されていた。1.左端:トラヤヌスの柱(Colonna Traiana)複製 ・ローマのオリジナル(紀元113年)の全周浮彫を石膏で再現。 ・高さ約35m、物語的レリーフはダキア戦争を描く。2.中央手前:ケルト十字(High Crosses) ・アイルランドやスコットランドの高十字(9〜10世紀)の石膏複製。 ・聖書場面や幾何学文様が刻まれている。3.右手前:猪(イタリア、フィレンツェ「ポルチェッリーノ」像の複製) ・本物はフィレンツェのメルカート・ヌオーヴォ。 ・幸運のシンボルとして鼻を撫でる風習で有名。4.右端:サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂の「栄光の門(Portico de la Gloria)」 ・スペイン、12世紀のロマネスク彫刻。 ・聖人・預言者・天使たちがずらりと並ぶ壮大な門の複製。5.中央奥:ロマネスク建築断片(白い壁面の装飾アーチ) ・スペインまたは南フランスの教会ファサード装飾の一部。「トラヤヌスの記念柱(Column of Trajan)」の石膏複製・オリジナル所在地:ローマ、フォロ・トラヤヌス(113年完成)・高さ:約35m(基壇含む)、このキャストも同じスケールで作られているため、 V&Aキャストコートでは最も圧倒的な存在感を放つ展示の一つです。・表面装飾:らせん状に約200m続く浮彫(約2500体の人物像)が施され、皇帝トラヤヌスの ダキア戦争(101–106年) の戦闘・工事・儀式の場面が連続的に描かれています。・複製の歴史:19世紀にフランスとイギリスで複製計画が進められ、現在のキャストコートに 左右1基ずつ(前後半に分けて鋳造)が展示されています。実際には一体の柱ですが、ここでは鑑賞しやすいように 「二分割」配置 されています。トラヤヌスの記念柱(Column of Trajan, cast)の基壇部分。1.基壇の浮彫 ・オリジナル(ローマ・フォロ・トラヤヌス)では、この基壇はトラヤヌス皇帝の遺灰を 納めた「霊廟」として機能していました。 ・側面には戦利品や武具、勝利の象徴の翼ある女神「ヴィクトリア(Victory)」などが 表されています。 ・写真中央、ラテン語の碑文(INSCRIPTIO)が見えた。これは皇帝トラヤヌスの功績を称える 公式銘文 と。 「SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS IMP CAESARI DIVI NERVAE F NERVAE TRAIANO AVG GERM DACICO PONTIF MAXIMO TRIB POT XVII IMP VI COS VI P P AD DECLARANDVM QVANTAE ALTITVDINIS MONS ET LOCVS TAN(TIS OPERIBVS) SIT EGESTVS」 【ローマ元老院と人民は、皇帝カエサル、神聖なるネルウァの子、ネルウァ・トラヤヌス・ アウグストゥス・ゲルマニクス・ダキクスに、この記念柱を奉献する。これにより、 どれほどの高さの丘が、この偉大な工事によって取り除かれたかを示すために。】 2.柱身のらせん浮彫 ・上へと続く帯状の浮彫は、トラヤヌスの 第一次・第二次ダキア戦争 を物語として描いたもの。 ・川を渡る場面、要塞建設、戦闘、皇帝の演説、捕虜の列などが連続的に彫刻されています。3.両脇のケルト十字(High Cross) ・写真左右に黒っぽい石十字が立っています。これはアイルランドの「ケルト十字」の複製。 ・本来は8〜10世紀の修道院や教会に建てられ、聖書の場面や幾何学文様が彫刻されていました。トラヤヌスの記念柱(Column of Trajan)の石膏複製の上部部分。1.柱身(シャフト) ・全体にわたってぐるぐると螺旋状に展開するレリーフは、トラヤヌス帝(在位98–117年)の ダキア戦争(101–106年) を描いたもの。 ・約200メートルの物語的レリーフが、らせん階段のように展開。2.レリーフの内容 ・ローマ軍の行軍、築城、橋梁建設、皇帝の演説(アドロカティオ)、戦闘、捕虜の列、敵の 降伏など、軍事キャンペーンの一部始終を視覚化 ・皇帝トラヤヌス自身が59回以上描かれていると。「トラヤヌスの記念柱(Column of Trajan)」の石膏複製に近づき、見上げて。オリジナル:ローマ、フォロ・トライアーニ(Trajan’s Forum)に建立・建立年代:西暦113年・高さ:約30メートル(基壇含めて約35メートル)・目的:皇帝トラヤヌスのダキア戦争(101–102年, 105–106年)の勝利を記念・特徴: ・らせん状に巻き上がる彫刻帯(フリーズ)が全長約200メートル以上にわたり続く。 ・約2,500人もの人物像が彫られており、軍事行動、戦闘、建設、皇帝の姿などが物語順に 描かれる。 ・内部は螺旋階段になっており、当時は頂上にトラヤヌスの像が置かれていた (現在は聖ペトロ像に差し替えられている)。本物の「トラヤヌスの記念柱(Column of Trajan)」の「聖ペトロ像」をネットから。サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂(スペイン・ガリシア)👈️リンク の「栄光の門(Pórtico de la Gloria, 1188年完成)」の石膏複製ネットから正面からの写真を。1.中央柱(Trumeau) ・中央の柱(トリュモー)には、聖ヤコブ(St. James, サンティアゴ)の像が立つ。 ・巡礼の守護聖人であり、この大聖堂の主祭壇下に聖遺物が安置されています。2.タンパン(Tympanum, アーチ部分) ・中央には威厳に満ちたキリストが座り、両脇に十二使徒や天使、24人の黙示録の長老 (Apocalypse Elders)が楽器を持って配されています。 ・これは 最後の審判 ではなく、天上の栄光のイメージ を表現。3.側柱の人物像 ・旧約の預言者たち(イザヤ、ダニエルなど)と新約の使徒たちが並び、互いに対話するような 動きが特徴。 ・特に「預言者ダニエル像」は柔らかい微笑みで有名。こちらが、サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂(スペイン・ガリシア)の「栄光の門(Pórtico de la Gloria, 1188年完成)」の本物の写真。(ネットから)。ここにあった黒の扉は、「ピサ大聖堂のサン・ラニエリ扉(Bonanus of Pisa 作, 1180年頃)」の複製であると。ピサ大聖堂の南翼廊にある サン・ラニエリ扉(Porta di San Ranieri、1180頃、ボナヌス・オブ・ピサ作) の浮彫パネル(全部で48枚)は、縦に6段・横に4列の構成で、キリストの生涯を時系列に物語るように並んでいる と。サン・ラニリエ扉の配置案内。「Electrotypes of Bonanus of PisaPorta di San Ranieri, Depicting Scenes from the Life of ChristAbout 1180In 1865, Giovanni Franchi made a copy of the original cast bronze doors from Pisa Cathedral through a process called electrotyping. This uses electricity to deposit copper particles into a mould, creating a three-dimensional impression of an object. The Museum commissioned the copies of the doors to record what are rare survivalsof the work of Bonanus of Pisa, a 12th-century Italian sculptor. The electrotypeswere coated with copper sulphate to mimic the bronze finish of the originals.ElectrotypesGiovanni Franchi and SonAbout 1865Bronzed copperLondonMuseum no. Repro.1865:58OriginalBronzePisa, ItalyPisa Cathedral (south transept)」【ピサのボナヌス作の電鋳複製キリストの生涯を描く「サン・ラニエリの扉」約1180年1865年、ジョヴァンニ・フランキがピサ大聖堂の鋳造青銅扉の原作を、電鋳法によって複製しました。電鋳法とは、電気を用いて銅の微粒子を鋳型に堆積させ、立体的な印象(型取り)を作り出す方法です。博物館はこの扉の複製を依頼し、12世紀イタリアの彫刻家ボナヌス・オブ・ピサの作品という、現存する数少ない遺例を記録しました。複製品は、オリジナルの青銅仕上げを模倣するため、硫酸銅でコーティングされています。複製(エレクトロタイプ)・作者:ジョヴァンニ・フランキ&サン・年代:約1865年・材質:銅にブロンズ仕上げ・所蔵:ロンドン、V&A美術館・登録番号:Repro.1865:58オリジナル・材質:青銅・場所:イタリア・ピサ大聖堂(南翼廊)】コルネリス・フロリス2世(1514–1575)による《タベルナクル(聖櫃堂/サクラメント・ハウス)》〔約1552年〕の石膏複製。オリジナルはベルギー・ゾウトレーウ(旧称ゾウトレーウ/レウ)の聖レオナール教会に現存。・フロリス作タベルナクルは教会内で聖体を安置する内装家具・フロリスの作は北方ルネサンス的な細密彫刻と寓意像の群像、小柱・ニッチ・肋の多い 多層の八角形の塔屋構成「Cornelis Floris II (1514–75)TabernacleAbout 1552A tabernacle houses the Host, or sanctified bread, used in Mass. The imposing original stone tabernacle from which this cast was made measures over 18 metres high. It was commissioned for the Church of St Leonard at Zoutleeuw (now known as Leau) in Belgium, where it still stands today. The maker, Cornelis Floris II, worked in a progressive style that fundamentally influenced 16th-century Northern European sculpture and architecture.The cast itself is a highly skilled production because of the elaborate nature of the carving. But the name of its maker is not known. We do know, however, that it wasproduced in Belgium, and presented to the Museum by the Belgian governmentin 1876 as part of the agreement brokered by this Museum’s first director, Henry Cole.The convention formalised an agreement, ‘mutually to assist the museums of Europe inprocuring casts and copies of national objects for the promotion of art’.CAST1876Painted plasterAcquired in exchange with the Belgian Royal Commission for Promoting Reproductions ofWorks of Art Museum no. Repro.1876-104ORIGINALCarved stoneProbably BrusselsChurch of St Leonard at Zoutleeuw, Belgium」 【コルネリス・フロリス2世 (1514–75)タベルナクル約1552年タベルナクルとは、ミサで用いられる聖体(聖別されたパン)を安置するものです。 この石膏複製の元となった壮大な石造のタベルナクルは高さ18メートル以上に達します。ベルギーのゾウトルー(現在はルーと呼ばれる)の聖レオナール教会のために制作され、現在も同地に現存しています。作者の コルネリス・フロリス2世 は革新的な様式で活動し、16世紀北ヨーロッパの彫刻と建築に根本的な影響を与えました。この石膏複製自体も、彫刻の精緻さゆえに高度な技術を要する制作でしたが、その制作者の名は不明です。ただし、ベルギーで制作され、1876年にベルギー政府から本館に寄贈されたことは分かっています。これは当館初代館長ヘンリー・コールが仲介した協定の一環で、ヨーロッパ各国の美術館が「自国の重要文化財の石膏複製を互いに提供し合い、美術の振興に資する」という合意を正式に結んだものです。複製(キャスト)1876年彩色石膏ベルギー王立美術作品複製振興委員会との交換により取得館蔵番号:Repro.1876-104オリジナル石彫おそらくブリュッセル製作ベルギー・ゾウトルー、聖レオナール教会】中世〜ルネサンス期の墓碑彫刻(ゴシック・リカンベント・エフィジー) の複製群。甲冑姿の騎士や、ライオンとともに眠る女性像など、各地の大聖堂や修道院にあった墓碑彫刻を石膏で複製したものが並べられているとのこと。・左側手前:女性像の足元にライオンが寄り添う姿(これは多くの場合、勇気・信仰を象徴)。 女性は祈りの姿勢ではなく、安らかに横たわる形。・中央手前:両手を胸で交差させた甲冑姿の騎士。足元には犬が彫られており、忠誠心を表す 典型的モチーフ。・奥列:赤茶色に彩色されたものもあり、石膏複製でオリジナルの彩色を模した展示。Cast ofAdam Kraft (about 1460–1509)The Schreyer–Landauer Monument・シュライヤー=ランダウアー記念碑 1490–92「Cast ofAdam Kraft (about 1460–1509)The Schreyer–Landauer Monument1490–92The Schreyer and Landauer families commissioned the sculptor Adam Kraft to create an elaborate funerary memorial. The original monument, commemorating the twofamilies, is on the exterior of the apse of the Church of St Sebaldus in Nuremberg. Its scenes from the life of Christ, the Crucifixion and the Entombment are full ofsensitively realised observational details, typical of Kraft’s work. The artist has probably included a representation of himself within the tabernacle, to the right, wearing a fur hat and carrying sculpting tools.The Museum purchased this cast of the monument from Nuremberg in 1872, at a time when curators at the South Kensington Museum (now the V&A), were responding to arenewed interest in German Renaissance architecture. The colour and texture of the cast closely reproduces the original sandstone.CastJacob Rotsamund, about 1872Painted plasterAcquired by purchaseMuseum no. Repro.1872-53OriginalStoneNuremberg, GermanyChurch of St Sebaldus, Nuremberg」 【アダム・クラフト(約1460–1509)シュライヤー=ランダウアー記念碑1490–92年シュライヤー家とランダウアー家は、彫刻家アダム・クラフトに依頼して精緻な葬祭記念碑を制作させました。オリジナルの記念碑は両家を記念するもので、ニュルンベルクの聖ゼーバルトゥス教会の後陣外壁に設置されています。そこにはキリストの生涯から「磔刑」や「埋葬」などの場面が表されており、クラフト作品の特徴である繊細で観察眼に富んだディテールに満ちています。芸術家は自らの姿も右側のタベルナクル(小祠堂)の中に表しており、毛皮の帽子をかぶり、彫刻道具を手にしています。この石膏複製は、1872年にニュルンベルクから購入されました。当時、サウス・ケンジントン博物館(現在のV&A)の学芸員たちは、ドイツ・ルネサンス建築への関心の高まりに応じていました。この複製の色彩と質感は、オリジナルの砂岩を忠実に再現しています。複製(キャスト)ヤコブ・ロツァムント作、1872年頃彩色石膏購入による取得館蔵番号 Repro.1872-53オリジナル石造ドイツ、ニュルンベルク聖ゼーバルトゥス教会】タイトル: Needling Whisper, Needle Country / SMS Series in Camouflage /Big Smile Ro1-01-01制作年: 2015年作家: ハム・キュンア (Ham Kyungah, 1966年生)素材: コットンキャンバスにシルク糸(刺繍)表面は抽象的でカラフルな渦巻き模様が広がっていますが、よく見ると中央に 「Big Smile」 という英語の文字が浮かび上がります。この「Big Smile」は、北朝鮮で広まったスローガンの一つであり、体制下で押し隠されてきた希望や表現の象徴でもあります。作品全体は、抽象模様でカモフラージュされた「隠された声」を体現しています。「1. Needling Whisper, Needle Country / SMS Series in Camouflage /Big Smile Ro1-01-012015Ham Kyungah (born 1966)Ham creates politically charged works that focus on the division of the Korean peninsula through their content and making process. Her designs are cut up and smuggled intoNorth Korea where anonymous embroiderers work on individual sections. This workconceals a hidden message in English: "Big Smile". This North Korean motto iscamouflaged by abstract patterns long suppressed by the Communist government.Ham’s ‘SMS Series’ reflects her desire to directly communicate with North Koreans.Silk threads on cotton canvasPurchase funded by SamsungMuseum no. FE.24-2016」【1. 針のささやき、針の国/カモフラージュのSMSシリーズ/ビッグスマイル Ro1-01-012015年ハム・キュンア(1966年生)ハムは、韓国半島の分断を題材にした政治的に強いメッセージを持つ作品を制作している。彼女のデザインは分割され、密かに北朝鮮へ持ち込まれ、そこで匿名の刺繍労働者たちが個々の断片を制作する。本作には英語で「Big Smile(大きな笑顔)」という隠れたメッセージが織り込まれており、それは共産主義政権によって長らく抑圧されてきた抽象模様によってカモフラージュされている。ハムの「SMSシリーズ」は、北朝鮮の人々と直接的にコミュニケーションを取りたいという彼女の願いを反映している。素材:コットンキャンバスにシルク糸サムスンの資金によって購入収蔵番号:FE.24-2016】特徴的な現代陶芸作品も。左の作品はユン・ジュチョル作「チョムジャンシリーズ」(2015-16年)の2点。「Contemporary Korean CraftDuring the Joseon dynasty (1392–1910), craft was not about producing the spectacularorthe perfect, but instead finding the right balance between elegance, practicality andeconomy of material. This approach to making was in tune with the ideas of frugality,honesty and simplicity put forward by the government at the time. Craft was versatileandcentral to Joseon daily life, but the traumatic colonial and post-colonial periods ofthe 20th century saw it shrink to near extinction.Today, there is a craft revival in Korea, with generations of artists, designers and makersdrawing inspiration from a wide range of subjects, including traditional techniques andlocal material culture. New stylistic vocabularies have emerged, long-lost skills have been recovered, and some manufacturing processes are rationalised for larger-scale production.」 【現代韓国工芸朝鮮王朝時代(1392–1910)において、工芸は壮麗さや完璧さを追求するものではなく、むしろ「優美さ・実用性・素材の節約」との適切なバランスを見出すことに重点が置かれていました。この制作理念は、当時政府が掲げていた「倹約・誠実・簡素」の思想と調和していたのです。工芸は多様で、朝鮮の人々の日常生活に不可欠なものでしたが、20世紀の植民地期および戦後期の困難な時代を経て、その伝統はほとんど消滅寸前にまで縮小してしまいました。今日、韓国では工芸の復興が進んでいます。世代を超えたアーティスト、デザイナー、制作者たちが、伝統技法や地域の素材文化を含む幅広い題材からインスピレーションを得ています。新しい様式的な表現語彙が生まれ、長らく失われていた技が再発見され、一部の製作工程は大規模生産に対応できるよう合理化されています。】 「KoreaKorea has had a continuous history as an independent nation for over 1,000 years. Its Confucian culture and long tradition of craftsmanship have been highly influential in the wider East Asian world. The rituals, architecture, painting, ceramics, lacquerwareand textiles of Korea all continue to enjoy a strong sense of national identity.The teachings of the Chinese philosopher Confucius (551–479 BCE) had a profoundinfluence on Korean culture, particularly as promoted by the court elite. His moral code emphasized hierarchy and filial piety, and promoted a respect for authority, patriarchyand social order.Most of the objects in this gallery were made for the consumption of the surroundingKorean elite. They show the Korean preoccupation with simple, plain colours and restrained decoration, along with a rich symbolism and a love of nature.This heritage is still venerated. In both North and South Korea the state offers financial support to artists who work in traditional forms and maintain traditional skills.」 【韓国韓国は 1,000 年以上にわたり、独立した国家として連続した歴史を持っています。その儒教文化と長い工芸の伝統は、東アジア全体において大きな影響を与えてきました。儀式、建築、絵画、陶磁器、漆工芸、織物などは、今なお強い国家的アイデンティティを保っています。中国の哲学者・孔子(紀元前551–479年)の教えは、韓国文化に深い影響を与えました。特に宮廷エリートによって推進され、儒教的道徳は序列と孝行を重んじ、権威・家父長制・社会秩序への敬意を促しました。このギャラリーに展示されている多くの作品は、韓国の上層階級の消費のために制作されたものです。そこには、簡素で落ち着いた色彩や抑制された装飾に対する韓国的な志向が見られると同時に、豊かな象徴性や自然への愛着も表れています。この遺産は今日でも尊重されています。北朝鮮と韓国の双方において、国家は伝統的な形式で活動し、伝統的な技能を維持する芸術家に財政的支援を提供しています。】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.25
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その118): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-1
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクヴィクトリア&アルバート博物館(V&A, ロンドン) の Medieval & Renaissance 1350–1600 ギャラリー👈️リンクを進む。1.中央手前の噴水 ・八角形の基壇を持つ噴水(well head)。 イタリア・ルネサンス期の庭園や邸宅に設置されていたもので、展示室のシンボル的存在。2.中央奥の二体の彫像 ・それぞれルネサンス期の大理石像やブロンズ像(例:「サムソン」や「プロセルピナの略奪」 など)と同系列の展示。人間の動きや肉体美を強調。3.奥に見える黒い大きな構造物 ・これは Tomb of Gaston de Foix(ガストン・ド・フォワの墓:1512頃) の複製です。 元はイタリア・ミラノのサンティ・マルチェリーノ・エ・ピエトロ教会に計画された 壮大な墓廟。 実際には未完成でしたが、そのデザインが後世に伝わり、V&A では黒い石膏モデルとして 展示されていた。4.右手壁面の大きな枠付き彫刻 ・聖母子像やキリスト磔刑を伴う宗教的浮彫(ルネサンス期の教会装飾から移されたもの)。・左側(男性像): → 「Zephyr(ゼピュロス)」とされるもの。ギリシア神話において「西風の神」で、 男性の神格。展示されている像も、筋肉質な男性の裸体像として表現されていて、足元に小さな 「息を吹くケルブ」が添えられていることで「西風」を象徴させている。 裸体で、左に布を垂らし、足元にイルカのような海のモチーフが彫られているのが特徴。・右側(男性像): → 「アポロ像(Apollo)」と考えられる像。腕に子供(小さな人物=キューピッドや音楽的 属性を持つ存在)を抱えているように見えます。これらはどちらも ルネサンス期イタリアの 神話主題彫刻 で、理想化された人体美を示す代表的な作例として並べて展示されていた。「ZEPHYR 1576 Pietro Francavilla (1548–1615)Together with the statue of Apollo nearby, this was one of a series of thirteen sculptures representing ancient Roman gods and nymphs associated with nature. Zephyr wasthegod of the west wind, redolent of springtime and flowers. He is identified by theblowing cherub by his foot.Italy, FlorenceMarbleLent by the Royal Botanic Gardens, Kew」【ゼピュロス(西風の神)1576年ピエトロ・フランカヴィッラ(1548–1615)近くにあるアポロ像と共に、これは自然に関連する古代ローマの神々やニンフを表した13体の彫刻シリーズの一つです。ゼピュロスは西風の神で、春や花を想起させる存在でした。足元に彫られた息を吹きかけるケルブ(天使像)によって識別されます。イタリア、フィレンツェ大理石キュー王立植物園からの貸与】騎馬像を中心とする大きな壁龕彫刻(レリーフ)。ズームして。上段はthe Monument Of Marchese Spinetta Malaspina(マルケーゼ・スピネッタ・マラスピーナ記念碑)であると。・原作:14世紀前半、イタリア・サルザーナ大聖堂(Duomo di Sarzana)・内容:天幕の下、馬上のマラスピーナ侯と従者。墓碑的モニュメント。・V&A展示は石膏キャスト(19世紀制作)。下段をズームして。聖母子と聖人像の小祭壇的群像(Tabernacle / Altarpiece fragments)・中央:玉座の聖母子像(Madonna and Child)・両脇:聖人像(恐らく聖ヨハネ、聖ペテロ、聖パウロ、聖カタリナなど典型的組み合わせ)・構造:アーチ型ニッチに収められた5体、赤茶色のフレームに白色大理石像。・出典:イタリア・フィレンツェ周辺のルネサンス期(15世紀前半〜中期)の作品と考えられ、 オリジナルは別の小祭壇・タベルナクルからの部分。・V&Aではマラスピーナ騎馬像キャストの下に「装飾的な補完」として配置。 上段と下段は本来別作品。 V&Aキャストコートでは、視覚的効果を高めるために上下を組み合わせ展示している と。V&Aキャスト・コートの全景。V&Aキャスト・コートは世界の有名な彫刻作品のレプリカだけを収めた部屋。1.中央奥(黒い大構造物)・ルネサンス期の教会内部を飾った内陣仕切り(オリジナルはイタリア)。・二層構造で、下層は三連アーチ+円柱、上層はバルコニーと人物像。・人物像は聖人や寓意像(信仰・希望・愛など)を表している。2.中央手前の二体の裸体像・右側:Zephyr(ゼピュロス)(西風の神)1576年、ピエトロ・フランカヴィッラ作。・左側:Apollo(アポロン)(ギリシア神話の太陽神/芸術と音楽の守護神)。・どちらもフィレンツェで制作され、自然や神話に関連する神々として庭園装飾に使われていた。3.左手前の噴水・ブロンズ製の小型噴水。キャストコートに合わせて設置されており、イタリア庭園や広場の 雰囲気を演出。4.右手前の八角形の石造物・「井戸の井桁(Well Head)」ヴェローナ産大理石製。・イタリア・ルネサンス期の邸宅中庭に設置され、紋章や寓意的装飾が施されている。サン・フェリーチェ教会の内陣仕切り(Tramezzo / Choir Screen)。・オリジナル所在地: イタリア・ボローニャの San Petronio Basilica(サン・ペトロニオ聖堂)、 またはフィレンツェの San Lorenzo(サン・ロレンツォ聖堂) の内陣仕切りと同系統の作品。・展示品:黒地と赤大理石風の柱に、白色石膏で鋳造した人物像が並ぶ。・19世紀に石膏キャストとして制作され、オリジナルはイタリア・ルネサンス建築の代表的な 教会内装の一部。・構造 ・下層:三連アーチ。赤大理石風の円柱。アーチ上に人物像。 ・上層:バルコニー形式。胸像や立像が交互に配置。 ・彫像:聖人・旧約の預言者・寓意像などが含まれる。サン・フェリーチェ教会の内陣仕切り(Tramezzo / Choir Screen)手前の石棺(tomb effigies/墓碑像) 。鎧姿で剣を持ち、手を合わせて祈る姿で横たわる「騎士の墓碑像」。サンティアゴ騎士団の騎士ドン・ガルシア・デ・オソリオ(1505–1509没)の墓碑像(アルバスター製)奥にもう一体あったのは「妻の墓碑像」・材質:オリジナルは大理石やアルバスター(雪花石膏)。展示されているのはその石膏キャスト。・姿勢:両手を合わせて祈り、騎士としての甲冑姿で横たわる。 これは典型的な「エフィジー(effigy)」様式。・足元:手前の像の足元には「ライオン」が彫られており、勇気と忠誠を象徴。・時代:14~15世紀のイングランドで多く見られる墓碑スタイル。移動して。さらに「EFFIGY OF DON GARCÍA DE OSORIODied 1509–1505Don García, a knight of the Order of Santiago, was buried in the church of San Pedroin Toledo. Though he wears chain mail and armour, his helmet has been removed andplaced at his feet, with a symbolic figure of mourning. His wife’s effigy nearby has a similar figure at her feet.Spain, ToledoAlabasterMuseum no. A.48-1910」 【ガルシア・デ・オソリオの墓碑像没年:1505–1509ドン・ガルシアはサンティアゴ騎士団の騎士であり、トレドのサン・ペドロ教会に埋葬された。彼は鎖かたびらと甲冑を身につけているが、兜は脱がれて足元に置かれ、その横には「嘆きの象徴的人物像」が添えられている。近くに安置された妻の墓碑像にも同様に、足元に小像が置かれている。制作地:スペイン、トレド材質:アラバスター(雪花石膏)館蔵番号:A.48-1910】「SIGNS AND SYMBOLSThe cross on the left breast of Don García de Osorio’s cloak shows that he belonged to the Order of Santiago, a combined military and religious order dedicated toSt James and founded in the 12th century. The lowest arm of the cross resembles a sword blade and reflects the dual nature of the Order.」 【ガルシア・デ・オソリオの墓碑像ドン・ガルシアはサンティアゴ騎士団の騎士であり、トレドのサン・ペドロ教会に埋葬された。彼は鎖かたびらと甲冑を身につけているが、兜は脱がれて足元に置かれ、その横には「嘆きの象徴的人物像」が添えられている。近くに安置された妻の墓碑像にも同様に、足元に小像が置かれている。】反対側・左側の墓碑像。・左側(手前)の棺 → 女性像(長衣をまとい、胸の上で両手を組む姿)。・右側(奥)の棺 → 男性像(甲冑姿で剣を抱えた典型的な騎士像)。・素材はいずれもアルバスター。制作はスペイン・トレド周辺(15世紀末~16世紀初頭)が多い。・背後の壁龕(ニッチ)には「聖母と子、周囲に天使」の大型浮彫があり、墓碑群全体を宗教的に 囲む配置。「Virgin of the Misericordia(慈悲の聖母)」。「VIRGIN OF THE MISERICORDIAAbout 1440–49Bartolomeo Bon (active 1421–64) and workshopA Venetian scuola, or confraternity, commissioned this sculpture to sit over the entranceto their meeting house. Members of the confraternity shelter under the Virgin's cloak. Surrounding the Virgin are prophets seated in the Tree of Jesse. They hold scrolls announcing the Coming of Christ, who is shown as a baby on the Virgin's breast. The pointed arch reflects the Gothic style of the original setting. Bartolomeo Bon was a member of the confraternity and one of the most importantsculptorsin Renaissance Venice.Italy, VeniceMoved and altered 1618 and 1828–30Istrian stone with traces of paintFrom the Scuola Vecchia di Santa Maria della MisericordiaMuseum no. 25-1883SIGNS AND SYMBOLSThe mandorla (from the Italian word for ‘almond’) was a type of halo that enclosed the entire body. It was usually used to depict moments that transcended time and space, such as Christ enthroned in Heaven in majesty. Here the mandorla forms a morse, or brooch, to clasp the Virgin's cloak.」 【憐みの聖母(ヴィルジン・オブ・ザ・ミゼリコルディア)1440~1449年頃バルトロメオ・ボン(1421–64年活動)および工房ヴェネツィアのスコーラ(信徒会、同信会)は、この彫刻を集会所の入口上部に設置するために制作を依頼しました。 同信会の会員たちは聖母のマントの下に庇護される姿で表されています。聖母を囲むのは「エッサイの樹」に座る預言者たちで、彼らは巻物を掲げ、キリストの降誕を告げています。キリストは聖母の胸に抱かれる幼子として表現されています。 尖塔型アーチは当初の設置場所のゴシック様式を反映しています。 バルトロメオ・ボン自身もこの同信会の会員で、ルネサンス期ヴェネツィアを代表する重要な彫刻家の一人でした。制作地:イタリア、ヴェネツィア1618年および1828–30年に移設・改変イストリア石(一部彩色痕跡あり)出典:サンタ・マリア・デッラ・ミゼリコルディア信徒会館(Scuola Vecchia)館蔵番号:25-1883記号と象徴マンドルラ(イタリア語で「アーモンド」を意味)は、身体全体を囲む光背の一種でした。通常、時間や空間を超越した出来事、例えば天に威厳をもって座すキリストなどを表現する際に用いられます。ここではマンドルラは、聖母のマントを留める留め具(ブローチ)の形をとっています。】サン・フェリーチェ教会の内陣仕切り(Tramezzo / Choir Screen)下から「建築的ファサード構造(コーラスクリーン/教会の内陣仕切り壁)」を。・手前:黒と赤大理石風の円柱とアーチ(V&A に再構成された Choir Screen の一部)。・奥:祭壇画(Altarpieces)が並ぶ展示スペース。多翼祭壇(polyptych)や黄金背景の板絵が 立てられている。・最遠方:さらにもう一つのアーチ越しに別の祭壇装飾(白大理石風の枠に収まった作品) が見える。後期ゴシック~ルネサンス祭壇画ギャラリー。写真に写っている多翼祭壇(altarpieces)は主に 15~16世紀のスペイン、フランドル、ドイツ圏 の作品で、どれも彩色木彫+金箔が施されていた。・左手前(黒い台座に載る祭壇画) ・フランドル地方の多翼祭壇(15世紀末頃) ・中央に「受胎告知」「キリスト誕生」「東方三博士の礼拝」など新約聖書の場面が 金箔木彫で表されている。 ・下段(プレデッラ)には聖人群の絵画が残る。「ALTARPIECE WITH THE VIRGIN AND CHILD AND SAINTSAbout 1500–10Rupert Potsch (active 1480–1530) and Philipp Diemer (active 1496–1515)The Virgin Mary sits in the centre, flanked by St Florian and St John the Baptist.The lower section was a cupboard for relics. Its two central panels, showing St Dorothyand St Catherine of Alexandria, are hinged and served as doors.A smaller door waslatercut into the panel on the extreme right, perhaps to provide storage for additional relics.Italy, Brixen/BressanoneLimewood and pine, painted and gildedPossibly from the church of San Floriano, Forno di Zoldo (Belluno)Museum no. 192-1866SIGNS AND SYMBOLSThe bearded figure on the right is St John the Baptist. He holds a lamb, known in Latinas the agnus dei, or ‘lamb of God’. In ancient rites the lamb was often offered as a sacrifice. It later became a symbol for Jesus because Christians believed thathe sacrificed himself on the cross.」【聖母子と聖人たちの祭壇画1500~1510年頃ルーペルト・ポッチュ(1480–1530頃 活躍)、フィリップ・ディーマー(1496–1515頃 活躍)聖母マリアは中央に座り、その左右には聖フロリアンと洗礼者聖ヨハネが並んでいます。下段部分は聖遺物を収める収納庫として作られました。中央の二枚のパネルには聖ドロテアとアレクサンドリアの聖カタリナが描かれており、蝶番で取り付けられて扉の役割を果たしました。右端のパネルには後から小さな扉が切り込まれ、追加の聖遺物を納める収納として使われた可能性があります。制作地:イタリア、ブリクセン/ブレッサノーネ材質:シナノキ材と松材、彩色・金箔出典:ベッルーノ県、サン・フロリアーノ教会(Forno di Zoldo)から伝来の可能性あり所蔵番号:192-1866記号と象徴右側のひげをたくわえた人物は洗礼者聖ヨハネです。彼は子羊を抱いています。ラテン語で「アニュス・デイ (Agnus Dei)」、すなわち「神の小羊」と呼ばれるものです。古代の儀式では子羊はしばしば犠牲として捧げられましたが、後にキリスト教ではイエス自身が十字架上で自らを犠牲にしたことを象徴するものとなりました。】 ・中央奥(黄金の細密彫刻祭壇) ・ドイツ・ザクセン地方、あるいはスペイン北部の工房作(15~16世紀初頭) ・小区画に分かれ、旧約・新約の場面をびっしりと物語風に展開。 ・金地背景により劇的な効果を持たせている。近づいて。・中央像:冠を戴かず立つ女性聖人像(獅子を伴っている)。これは 聖カタリナ (St. Catherine of Alexandria) または 聖マルガリタ(St. Margaret of Antioch) と 考えられます。特に足元の竜や蛇を踏む姿は聖マルガリタの典型的図像です。・周囲のパネル:金箔背景の浮彫で、新約の受難や殉教の場面がぎっしり。 左下には磔刑、 右側には鞭打ちや裁判の場面があり、物語的に展開しています。・様式:細密なゴシック様式の透かし彫り(フランドルやドイツの15世紀後半によく見られる 様式)。・彩色:ポリクローム彩色が残り、金地に赤や青の衣服の彩色が強く出ています。「THE ST MARGARET ALTARPIECEAbout 1490–1500This imposing altarpiece tells the story of St Margaret, who was martyred for refusing to renounce Christianity. It was common practice for many craftsmen to work together on such large altarpieces. The style of the elongated heads in the two lower rightpanels,so different from the others, suggests that they were made by a different artist.Germany, Hamburg or LüneburgOak, painted and gildedPossibly from the church of St John, LüneburgMuseum no. 5894-1859」 【聖マルガリタの祭壇画1490~1500年頃この堂々たる祭壇画は、キリスト教を棄てることを拒んだために殉教した聖マルガリタの物語を伝えています。このような大規模な祭壇画では、多くの職人が共同で制作にあたるのが一般的でした。右下の2枚のパネルに見られる長い頭部の表現は、他の部分と大きく異なっており、別の作者によって制作された可能性を示しています。制作地:ドイツ、ハンブルク または リューネブルク材質:オーク材、彩色・金箔出典:リューネブルクの聖ヨハネ教会から伝来した可能性あり所蔵番号:5894-1859】右手前。15世紀末から16世紀初頭の ドイツやオーストリア圏の後期ゴシック祭壇画。・中央パネル ・金地背景に、玉座に座る聖母マリアが幼子イエスを抱いています。 ・左隣には女性聖人(多くの場合は 聖アンナ または 聖エリザベト)が描かれ、三世代の 聖なる女性 ― 聖アンナ・聖母マリア・幼子イエス ― からなる「聖アンナ三世代 (Anna Selbdritt)」の図像に近いです。 ・上部には聖人たちの小胸像(預言者や聖者)が装飾的に配置されています。・左翼パネル ・聖クリストフォロス(クリストファー)が幼子イエスを肩に担ぎ、川を渡っている場面。 彼は旅人の守護聖人。・右翼パネル ・頭に王冠を戴いた女性聖人像。衣装から判断すると 聖バルバラ(塔を持つ聖人) または 聖カタリナ(車輪の聖人)。残念ながら持ち物(アトリビュート)が欠けているため断定は 難しいですが、よくセットで登場する「聖なる乙女殉教者」のひとりである と。「THE BOPPARD ALTARPIECEAbout 1520–40The central scene shows the Virgin presenting the Christ Child to her mother, St Anne. The altarpiece probably comes from the church of the Carmelites (an order of friars)in Boppard, near Koblenz. The presence of St Anne suggests that it might have been given by the local St Anne brotherhood, a lay organisation devoted to good works.France, StrasbourgLimewood and pine, painted and giltMuseum no. 152-1919」 【ボッパルトの祭壇画1520~1540年頃中央の場面には、聖母マリアが幼子イエスをその母聖アンナに差し出す姿が描かれています。この祭壇画は、おそらくコブレンツ近郊ボッパルトにあるカルメル会(托鉢修道会)の教会に由来するものです。聖アンナの姿があることから、この作品は地元の聖アンナ同信会(善行に献身する信徒組織)によって奉納された可能性が示唆されます。制作地:フランス、ストラスブール材質:菩提樹材・松材、彩色および金箔所蔵番号:152-1919】これはゴシック~ルネサンス期のステンドグラスで、「磔刑(Crucifixion)」場面を描いていると。・中央上:磔にされたイエス・キリスト・十字架の左右上部:兵士や群衆(受難の証人たち)・イエスの左側(画面右):聖ヨハネ(赤い衣、胸に手を当てる)・イエスの右側(画面左):聖母マリア(白いヴェールをまとい悲嘆に暮れる)・十字架の足元中央:マグダラのマリア(跪き、十字架に抱きついている) この場面は新約聖書のヨハネによる福音書(19章25–27節)に基づきます。イエスが十字架上で母マリアと弟子ヨハネに「これはあなたの子」「これはあなたの母」と語り、弟子たちに母を託す場面を象徴的に表しているのだ と。このステンドグラスは、ゴシック様式の教会窓の一部で、上段と下段で異なる場面が描かれている と。上段(アーケード内の場面) ・王座(玉座)に座る人物を中心に、両脇に礼拝する聖職者や天使が描かれているように 見えます。 ・王冠をかぶり、権威を持つ人物なので、キリスト王 あるいは 旧約の王座を象徴する場面 と 解釈できる。上部のトレーサリー部分 ・小型の円形パネルに、複数の聖人や聖職者が描かれています。これらは補助的に、 天上の礼拝を強調する装飾。下段(主要パネル) ・左側の人物:白い髭を持ち、本を広げる聖人。書物を持つことから 福音記者(おそらく 聖ヨハネまたは聖マタイ) を表している可能性が高い。 ・右側の人物:冠をかぶり、長い髭を持ち、王または預言者の姿。赤いマントをまとって いるので、旧約の王(ダビデ王、あるいはソロモン王) の可能性がある。写真の窓(左から右へ)1.最も左の細長い窓 ・おそらく「旧約預言者」や「聖職者」の場面を上下に分けて描いた小型パネル。 ・他の大窓の脇を飾る補助パネルで、構図的にはサイドランセット。2.左から2番目の大窓(3列×3段) ・中央にマリアが描かれており、その周囲に受胎告知、訪問、誕生など新約の場面。 ・「聖母マリアの生涯」シリーズ の窓の一部。3.左から3番目の大窓(3列×3段) ・キリストの受難を中心にした場面(鞭打ち、十字架を担う、磔刑、復活など)が描かれて いるように見えます。 ・「キリストの受難」シリーズ の窓。4.最も右の細長い窓 ・天使の合唱や聖母戴冠を思わせる天上の場面が描かれている。 ・これも補助的なランセット窓。この2枚の大窓は、V&A美術館の「ドイツ・スイスのステンドグラス」コレクションの中でも特に物語性の強いパネルである と。左の窓(3段構成)・マリア伝これは 「聖母マリアの生涯」 を描いた連作と考えられます。・上段:マリアの誕生、幼少期の奉献・中段:受胎告知、エリサベト訪問・下段:聖母の戴冠あるいはマリアへの崇拝場面(多くの聖人が跪く)右の窓(3段構成)・キリスト伝(受難伝)こちらは 「キリストの生涯(幼少期~受難)」 を物語順に示した可能性が高いです。・上段:東方三博士の礼拝、割礼(神殿での奉献)・中段:受難物語の序幕(オリーブ山の祈り、捕縛の場面)・下段:鞭打ち、荊冠、ピラトの前に立つキリストこれは精巧な木彫の祭壇衝立(リターブル / アルターピース)。・素材:濃い色合いのオーク材(黒っぽい艶のある木材)で彫刻。・構成:中央の高い尖塔を中心に、三つの主場面(左・中央・右)+上部と台座部分に細かい 場面が配置。・技法:極めて緻密なゴシック後期の浮彫(ハイ・リリーフ)で、衣の襞や人物の群像表現が 非常にリアル。・図像:中央に「聖母マリアの戴冠」または「聖母被昇天」が見られ、周囲に十二使徒や群衆 が配されています。 ・左パネル:受胎告知やキリスト誕生に関連する場面。 ・右パネル:たぶん受難(最後の晩餐や磔刑への前段階)。「ALTARPIECE WITH THE LIFE OF THE VIRGINAbout 1520The life of the Virgin was a popular subject for altarpieces. Here, the central image showsher death and assumption into Heaven. The crouching figure below represents the vanquished figure of Synagogue, a symbol for what Christians then believed to betheirtriumph over Judaism. Altarpieces like this were commonly produced in Brussels, either to commission or ready made.Southern Netherlands (Belgium), BrusselsOakMuseum no. 1049-1859」 【聖母の生涯を描いた祭壇画1520年頃聖母マリアの生涯は、祭壇画において人気の主題でした。中央の場面は、聖母の死と被昇天を表しています。その下にいるうずくまった人物像は「シナゴーグ(ユダヤ教会堂)」の擬人像で、当時のキリスト教徒にとってはユダヤ教に対する勝利を象徴するものでした。このような祭壇画はブリュッセルで一般的に制作され、注文生産されることもあれば、既製品として販売されることもありました。制作地:南ネーデルラント(ベルギー)、ブリュッセル素材:オーク材所蔵番号:1049-1859】・この展示室は「The Medieval Renaissance 1300–1600」セクションに属し、イタリアの 宗教芸術を再構成したハイライト空間のひとつ。・見上げる十字架像は「クローチフィッソ(Crocifisso)」と呼ばれる イタリア中世の磔刑像群の一例。天井からは金色に光る磔刑のキリストが。The Paul and Jill Ruddock Galleryを振り返って。右手に展示されていたステンドグラス。中央場面(中段)・左:聖母マリア(青い衣)に抱かれる幼子イエス。・右:王冠をかぶった東方三博士の一人が、黄金の器を差し出している。・主題は典型的な「東方三博士の礼拝(Adoration of the Magi)」。上段・後方で聖ヨセフと思われる男性(頭光を持つ)ともう一人の博士。下段・色鮮やかな紋章(黄地に黒点のような模様、両脇に白い翼状の装飾)。・その下に部分的なラテン語銘文(「…TE VEN…」など読める)。・寄進者家系の紋章と思われます。「The Paul and Jill Ruddock Gallery」(イタリア・ルネサンス彫刻ギャラリー)に展示されている大理石の祭壇(アルターピース)。「ALTARPIECE WITH THE CRUCIFIXION FLANKED BY SAINTSAbout 1493Andrea Ferrucci (1465 – after 1526)Tita di Roberto Salviati commissioned this altarpiece to sit above the tomb she hadbuilt for herself and her husband, Girolamo Martini. The families’ coats of arms can beseen in the bottom corners, while the presence of St Jerome (Girolamo in Italian) on the left commemorates both her husband and the church’s dedication to the saint.Italy, Fiesole (Tuscany)MarbleFrom the church of San GirolamoMuseum no. 6742-1859」【聖人たちに囲まれた磔刑の祭壇画(アルターピース)制作年代:約1493年作者:アンドレア・フェルッチ(1465年 – 1526年以降)ロベルト・サルヴィアーティの娘ティタは、この祭壇画を、自身と夫ジローラモ・マルティーニのために造らせた墓の上に設置するために依頼した。家族の紋章は下部の隅に刻まれており、左側に配された聖ヒエロニムス(イタリア語で「ジローラモ」)は、彼女の夫の名を記念するとともに、この教会の守護聖人への献堂を示している。イタリア、フィエーゾレ(トスカーナ)大理石出典:サン・ジロラモ教会館蔵番号:6742-1859】 左側・大きなアーチ型の枠に収められた祭壇画(または祭壇装飾)。・絵画には聖母子(中央)、その両脇に二人の聖人(左は聖ペテロ?鍵を持つ、 右は聖フランチェスコ?修道服と縄帯)と思われる。・上部には二人の天使がホバリングし、巻物を広げている。・枠はルネサンス期の典型的な大理石アーキトレーヴ(半円アーチ+コリント式柱)。中央・壁面に小型の彩色彫像が2体。 ・左:修道服姿の男性聖人(茶色)。 ・右:青い衣をまとった聖人像。 ・おそらくイタリアのポリクローム木彫。右側・大型の彩釉テラコッタ浮彫(デッラ・ロッビア工房の様式)。・主題は「東方三博士の礼拝(Adoration of the Magi)」:聖母子のもとに三博士が贈り物を 捧げる場面。・周囲を青・緑・黄色の華やかな釉薬の装飾帯が囲む。・ロッビア家(ルカ・デッラ・ロッビアやアンドレア・デッラ・ロッビア一派)がよく制作した 作品形式。この作品は、ルネサンス期フィレンツェを代表する陶芸一族 デッラ・ロッビア工房(Della Robbia workshop) による多彩色の施釉テラコッタ浮彫。「東方三博士の礼拝(Adoration of the Magi)」・中央:聖母マリアが幼子イエスを抱き、イエスは前に跪く博士に手を差し伸べています。・右:ヨセフ(緑の外套)も寄り添い、博士たちの贈り物を見守る。・左:三博士とその従者が列をなして、黄金・乳香・没薬を捧げる。先頭の博士は跪き、 深い敬意を表している。・背景:馬に乗った従者、遠景の都市、放牧の羊などが描かれ、物語の広がりを示す。・天上:二人の天使が飛翔しながら巻物を掲げ、聖性を強調。ズームして。さらに「THE ADORATION OF THE KINGSAbout 1500–10Andrea della Robbia (1435–1525)The arms on the lower panel show that the wealthy Albizzi family commissionedthis altarpiece. The exotic headgear worn by the kings’ followers(including an African man)signifies that they were from the East. The bright colours of the altarpiece demonstratethe skill of the della Robbia in producingtin-glazed terracotta.Italy, FlorenceTin-glazed terracottaMuseum no. 4412-1857」 【東方三博士の礼拝1500年頃 – 1510年頃アンドレア・デッラ・ロッビア(1435–1525)下部パネルに見られる紋章は、富裕なアルビッツィ家がこの祭壇装飾を依頼したことを示している。博士たちの従者が身につけている異国風の頭飾り(アフリカ人を含む)は、彼らが東方から来たことを象徴している。祭壇装飾の鮮やかな色彩は、スズ釉を施したテラコッタ制作におけるデッラ・ロッビア工房の卓越した技を示している。イタリア、フィレンツェスズ釉テラコッタ館蔵番号:4412-1857】両像とも V&A の「The Paul and Jill Ruddock Gallery」で展示されているもの彩色されたテラコッタ像(ルネサンス期イタリア、デッラ・ロッビア工房系)。左の像・特徴: 長い髭、頭巾付きの修道服(茶色と黒)、書物を抱える。 足元に動物(豚のような姿)が見える。・解釈: 聖アントニウス(St. Anthony Abbot, 聖アントニオ修道院長)像。 ・豚は彼の象徴(アントニオ修道会が豚を飼っていた歴史的背景による)。 ・修道服姿で書物を持つ姿は定型的な聖アントニオ像の表現。右の像・特徴: 青いガウンに金の縁取り、手に書物と椰子の枝(殉教の象徴)。比較的若い顔立ち。・解釈: 書物と椰子を持つことから、これは殉教した聖人の像。 聖スティーヴン(St. Stephen, 最初の殉教者)像 。「ST ANTHONY ABBOT AND ST STEPHENAbout 1500–20Workshop of Benedetto Buglioni (about 1459–1521)Unable to create flesh tones in glazes, the artist left the heads and hands of the twosaints unglazed for a natural effect. Each saint is easily identifiable by his attributes. St Anthony Abbot has a pig at his feet, while St Stephen holds his martyr’s palm and has stones attached to his head and shoulder.Italy, TuscanyTin-glazed terracottaMuseum nos. 4413, 4414-1857SIGNS AND SYMBOLSSt Stephen was the first Christian martyr. He was a deacon, meaning that he helpedthe poorer members of the congregation. Here, however, he is shown in the robes of a medieval deacon, who would have assisted priests during the Mass. He isalsorecognisable by the stones on his head and shoulder, reminding believers thathe was stoned to death.」 【聖アントニウス修道院長と聖ステファノ1500年頃–1520年頃ベネデット・ブリョーニ工房(1459年頃–1521年)釉薬で肉体の肌色を表現することができなかったため、作者は聖人たちの頭部と手を無釉のままにして自然な効果を狙った。両聖人はそれぞれの持ち物で容易に識別できる。聖アントニウス修道院長は足元に豚を伴い、聖ステファノは殉教者の象徴である棕櫚の枝を手にし、さらに頭と肩に石が付けられている。イタリア、トスカーナスズ釉テラコッタ館蔵番号:4413, 4414-1857記号と象徴聖ステファノは最初のキリスト教殉教者であった。彼は助祭であり、共同体の貧しい人々を助ける役割を担っていた。ここでは、中世の助祭の法衣をまとった姿で表されており、彼がミサの間に司祭を補助する人物であったことを示している。また、彼の頭や肩に付けられた石は、彼が石打ちによって殉教したことを信徒に想起させる。】「The Paul and Jill Ruddock Gallery」に展示されている デッラ・ロッビア工房(Della Robbia workshop) の多彩色施釉テラコッタ祭壇装飾。これは 「聖母子と天使たち」 あるいは 「玉座の聖母(Madonna in Glory)」 を表す場面。・中央 ・青い背景の中に円形のマンドルラ(光背)があり、その中に聖母マリア (または座する女性聖人)が正面向きに座っています。 ・マリアは書物を手にしており、瞑想的な姿。・周囲 ・天使たちが花輪(ガーランド)を形成するように配置され、マリアを取り囲んでいます。 ・天使はそれぞれ果実(オレンジや柑橘、ザクロ)を手に持ち、献げています。・下部 ・膝をついて祈る人物(寄進者か聖人)が聖母に向かって両手を差し出している。 ・台座部分には色鮮やかな花文様の装飾帯。・枠飾り ・側縁は白釉の植物装飾。 ・上部には小天使の顔(プットー)が並ぶ帯装飾。「Screen from Ávila Cathedral(1520–30, Spain, Ávila)」この鉄製スクリーンは、アビラ大聖堂(スペイン、カスティーリャ地方) の広大な柵の一部。材質: 鉄(Iron)年代: 1520–30年頃製作工房: ロレンソ・デ・アビラ(Lorenzo de Ávila, 1525年頃活動)工房と考えられる。構造: 細長いバラスター(balusters, 欄干の支柱)が連続して並ぶデザイン。装飾: 上部には装飾帯(鉄の透かし模様)、下部は石の基壇。用途: 大聖堂内で祭壇や私的礼拝堂を保護・仕切るためのスクリーン。「SCREEN FROM AVILA CATHEDRAL1520–30Probably by the workshop of Lorenzo de Avila (active 1525)Screens were used to protect altars and private chapels. They were common in churches across Europe. This portion of the vast screen from Avila Cathedralconsists of balusters,in a style favoured by the local ironwork specialist,Lorenzo de Avila, and his workshop. In earlier Spanish screens twisted bars were more common.Spain, AvilaIronMuseum no. [欠落]」 【アビラ大聖堂のスクリーン(仕切り柵)1520年–1530年頃ロレンソ・デ・アビラ(1525年頃活動)の工房による可能性が高いスクリーンは祭壇や私的礼拝堂を保護するために用いられ、ヨーロッパ中の教会で一般的であった。このアビラ大聖堂の大きなスクリーンの一部は、バラスター(欄干の支柱)から成り、地元の鉄細工師ロレンソ・デ・アビラとその工房が好んで用いた様式である。以前のスペインのスクリーンでは、ねじれた鉄棒を用いるのがより一般的であった。スペイン、アビラ鉄製館蔵番号:不明(表示欠落)】典礼用の聖職者衣装(Liturgical Vestments)。1.左端・金属製の司教杖(crosier, pastoral staff)・司教冠(miter, mitra)2点・典礼用の小型布(stole または maniple)2.中央〜右・赤・金地のカズラ(Chasuble):中世〜ルネサンス期の刺繍、絹織物。・深紅のカズラ:背面に大きな金糸の十字装飾。典型的な「ゴシック型カズラ」。・青緑地のカズラ:背中に縦の帯(orphrey)をもち、聖人像や装飾文様が織り込まれている。意味と用途・カズラ(Chasuble):司祭がミサを司式するときに着る外衣。色は典礼暦(祭色)に応じて 赤・緑・白・紫などを用いた。・ミトラ(Miter):司教の冠。儀式で着用し、教会内の権威を象徴。・司教杖(Crosier):司教職の象徴。羊飼いの杖に由来し、信徒を導く役割を意味する。「Tapestry with St Antoninus」(1450–1500年頃)・描かれているのは 聖アントニヌス(St Antoninus, 1389–1459)・1446–1459年までフィレンツェ大司教を務めた人物。・ドミニコ会士であったため、黒と白の修道服(habit of the Dominican order)を着用。・司教冠(miter)をかぶり、司教杖(crosier)を持ち、右手は祝福の姿勢。・周囲 ・両側に花模様の装飾帯。ルネサンス期やゴシック後期に多い意匠。 ・足元には植物文様が細かく刺繍されている。「TAPESTRY WITH ST ANTONINUS1450–1500Inscriptions on the borders identify St Antoninus, Archbishop of Florence from 1446 to 1459. He wears the black and white habit of the Dominican order, of which he was a member, and a bishop’s mitre. He also carries a bishop’s crosier and his right hand israised in blessing.Italy, possibly Ferrara or FlorenceWool and linenTapestry wovenMuseum no. 8498-1863」 【聖アントニヌスのタペストリー1450年–1500年頃縁取りの銘文により、この人物が1446年から1459年までフィレンツェ大司教を務めた聖アントニヌスであることが示されている。彼は所属していたドミニコ会の黒と白の修道服をまとい、司教冠(ミトラ)をかぶっている。また、司教杖(クロージャー)を持ち、右手は祝福のために掲げられている。イタリア(フェラーラまたはフィレンツェの可能性)羊毛と亜麻布タペストリー織館蔵番号:8498-1863】教会で用いられる典礼用金属器(liturgical vessels and objects)の展示。左から順に:1.水差し(ewer)・ミサで用いる水やワインを注ぐための器。2.聖杯(chalices, 複数)・聖体祭儀でワイン(キリストの血の象徴)を入れるためのカップ。・足部や幹に精緻な装飾が施されている。3.聖体顕示台(monstrance / ostensory)・十字架の形や塔状のものがあり、聖体(聖別されたホスチア)を展示するために用いられる。4.十字架(altar cross)・祭壇上に置かれる十字架。中央に小さな聖遺物を収めることもある。5.聖遺物容器(reliquaries, 複数)・塔や家型の小さな建物のような形。聖人の骨や遺品などの聖遺物を納める。・装飾的で信仰対象となる。ズームして。典礼用金属器の中でも特に重要な 聖遺物容器(Reliquaries) と祭壇十字架(Altar Cross) 。中央(十字架)・祭壇十字架(Altar Cross) ・銀または銅をベースにし、青いカボション宝石(エナメルかラピスラズリ)で装飾。 ・赤い石台座は後補の可能性もある。 ・祭壇の中央に置かれ、ミサの際の焦点となる。右(八角形ベースの塔型)・聖遺物容器(Reliquary, Renaissance style) ・八角形の台座と金地に青いエナメル装飾。 ・上部は塔型の尖塔で、内部に聖遺物を収める。 ・ルネサンス期のイタリアまたはフランドル工芸の特徴を持つ。さらに右奥(小型家型)・聖遺物容器(Reliquary in the form of a house or shrine) ・小型の家や礼拝堂の形。 ・聖遺物を安置することで「聖なる小聖堂」として象徴化。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.24
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その117): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館へ
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクこの日は6月9日(月)、このアイルランド・ロンドンへの旅の最終日、そしてもちろんロンドンの散策も最終日。元気に起床し帰国に向けてパッケージングも完了。私のこの日の夜のロンドン・ヒースロー空港からの帰国便は、中国国際航空・CA912便・20:25発で北京にてトランジットして羽田への予定。我が宿泊のアパートメントのチェックアウトは10時とのことで、トランクを何処に預けてロンドン最終日を楽しむか?旅友Yさんがネットで調べてくれて、Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館は、大きなトランクを預けての見学が可能、時間制限はないとのことで、ここを起点に最終日のロンドン散策を行うこととしたのであった。朝食を済ませ、9:20にアパートを出発。我が宿泊アパートは正面入口の右の門の右にある黒いアルミフェンスのドアの奥の半地階の部屋。近づいて。写真右のフェンスドアが地階への入口。青いドアが半地階にある我々の宿の部屋への入口。まるで、誰かが居住している様な宿なのであった。Walton St、エガートンテラスを進み、Brompton Roadに出て左折し、Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館に向かってトランクを転がしながら進む。右手前方に見えたのが、カトリック教会のThe Brompton Oratory・ロンドン・オラトリーのドーム。建物の概要・正式名称: Church of the Immaculate Heart of Mary (聖母の汚れなき御心教会)・通称: The Brompton Oratory(ブロンプトン・オラトリー)・所在地: ロンドン、サウス・ケンジントン地区(地下鉄サウス・ケンジントン駅すぐ)・建設: 1884年完成、19世紀後半の壮大なバロック様式のカトリック教会。特徴・ロンドンにおけるカトリック教会の中心的存在の一つ。・大きなドームとバロック風の華やかな内部装飾が特徴。・聖歌隊(Oratory Choir)の水準が非常に高く、音楽面でも有名。・隣接して「ロンドン自然史博物館」「ヴィクトリア&アルバート博物館」などがあり、 文化ゾーンの一角をなしていた。右手の細い道路沿いにあったのが 「The Return of the Prodigal(放蕩息子の帰還)」像。・場所: London Oratory(ロンドン・オラトリー/Brompton Oratory)前の道路沿い・主題: 聖書「ルカによる福音書 15章」の「放蕩息子のたとえ」に基づき、父が息子を 抱きしめる姿を表現。・設置場所: ロンドン・オラトリー(Brompton Oratory)前の屋外。・特徴: ・粗い表面のブロンズ彫刻で、人間の弱さや悔い改めを象徴。 ・同時に、父の抱擁は神の無条件の愛と赦しを示す。銘板の文字は「THE RETURN OF THE PRODIGALCHARLIE MACKESY 2005」 【『放蕩息子の帰還』チャーリー・マッケジー 2005年】ロンドン・オラトリー(The London Oratory / Brompton Oratory) の正面ファサード。17世紀ローマ・バロック様式に範をとった正面構成。特にイエズス会の母教会「サンタンドレア・デッラ・ヴァッレ(ローマ)」や「イル・ジェズ教会」の影響を色濃く受けています。・正面構成: ・下層は列柱を伴ったポルチコ(玄関ポーチ)。 ・上層は三角破風と装飾的レリーフを持つクラシカルな構成。 ・壁面には丸窓や飾り窓枠(ペディメント付き)が並び、バロック特有の重厚さと リズム感を演出。 ・素材: 白いポートランド石が使われ、威厳と清浄さを強調。これはロンドンの Brompton Oratory(ブロンプトン・オラトリー/正式名:ロンドン・オラトリー教会) に付属する Newman Shrine(ニューマン記念碑)。バロック風の記念建築で、壁面に大きく迫り出した祠堂(ニッチ)を設け、その中にニューマン像を配置。さらにその上に聖母子像を載せていた。ロンドン・オラトリー(Brompton Oratory / The London Oratory) の入口の手前に設置されていたこの建築的な「二層構造」の彫刻配置では、下段にジョン・ヘンリー・ニューマン枢機卿像(1801–1890)が据えられており、その上部に「守護・象徴像」が配置されていた。最上部の像は、聖母子像・Madonna and Child。・女性像が子ども(幼児)を抱いている。・子どもは左腕に抱えられており、母(聖母マリア)がやや身体を支えるように立っている姿勢。・ドレープ(衣のひだ)が豊かに表現され、母性的な落ち着いた雰囲気を持つ。JOHN HENRY CARDINAL NEWMAN像。1801–1890 。JOHN HENRY CARDINAL NEWMAN(ジョン・ヘンリー・ニューマン枢機卿)像をズームして。・生涯 ジョン・ヘンリー・ニューマン(John Henry Newman, 1801–1890)は、19世紀のイギリスを 代表する神学者・思想家です。もとはイングランド国教会の聖職者でしたが、後にローマ・ カトリックへ改宗しました。・業績 ・オックスフォード運動の中心人物の一人として知られ、イングランド国教会における伝統と カトリック的要素の回復を目指しました。 ・1845年にカトリックへ改宗し、その後枢機卿に叙任されました。 ・教育思想や良心論で有名であり、現代のカトリック思想に大きな影響を与えました。・列聖 ニューマンは2010年に列福され、2019年にローマ教皇フランシスコによって聖人に 列聖されました。ロンドン・オラトリー(The London Oratory / Brompton Oratory)を振り返って。そしてトランクを転がしながら最初の目的地のVictoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館 前に到着。・所在地: ロンドン、サウス・ケンジントン・創設: 1852年(1851年のロンドン万国博覧会の成果を継承して設立)・名称由来: ヴィクトリア女王と夫アルバート公にちなんで命名・特徴: 世界最大級の装飾美術・デザインの博物館。・所蔵品は約230万点。・彫刻、陶磁器、ファッション、家具、絵画、金工、写真など多岐にわたる。Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館の航空写真をネットから。Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館入口前から見上げて。・正面中央の大アーチ(ポーチ)は「ポータル」と呼ばれ、細かい彫刻が施されている。・上部には塔のようなクイーン・メアリー・タワー(Queen Mary’s Tower) がそびえる。・ファサードにはヴィクトリア時代の彫刻や装飾モチーフが豊かにあしらわれ、19世紀末の 折衷主義的なデザインを代表している。正面玄関上部に掲げられている英国王室の紋章(Royal Coat of Arms)をズームして。1. 盾(中央)盾は四分割され、イギリス連合王国を構成する王国を象徴しています:・左上・右下:3頭の獅子(England)・右上:獅子 rampant(立ち上がる獅子)(Scotland)・左下:ハープ(Ireland)2. 支持者(Supporters)・左(向かって右側):獅子(Lion) イングランドを象徴し、王権・勇気・威厳を表す。王冠をかぶっています。・右(向かって左側):一角獣(Unicorn) スコットランドを象徴。純潔と力の制御を意味し、鎖でつながれているのは 「力を制御している」ことの象徴。3. モットー(Motto)上部と下部にラテン語とフランス語の語句が刻まれています:・上部(環状帯に刻まれた文字) “HONI SOIT QUI MAL Y PENSE” 意味:「それを悪く思う者に災いあれ」 ─ イングランド最高位の勲章「ガーター勲章(Order of the Garter)」の標語である と。・下部(リボン部) “DIEU ET MON DROIT” 意味:「神と我が権利」 ─ イングランド王のモットーであり、王権神授説(divine right of kings)を象徴 と。イギリスの国章(Royal Coat of Arms of the United Kingdom)をネットから.この紋章は、イギリス王室の統一と正統性を象徴しています。・ライオンとユニコーン → イングランドとスコットランドの連合・四分割の盾 → イングランド、スコットランド、アイルランドの統合・モットー → 王権の神聖と栄誉の理念その下、正面玄関(Cromwell Road façade)上部右側にあった浮彫彫刻(relief sculpture)。この(右側スパンドレル)の場面は、女性像が建物模型(V&A館)を差し出す構図で、「Art(芸術)」が「Architecture(建築)」に博物館を授ける寓意。この(左側スパンドレル)の場面は、「知識(学問)によって導かれる労働(技術)」というヴィクトリア朝の理想主義を象徴。V&Aの設立理念 ― すなわち Art and Science united for the improvement of industry(産業発展のための芸術と科学の融合)を視覚的に示しているのだ と。・左の女性像:知識(Knowledge)の擬人像。 書物や巻物を手にしており、教育・学問・知恵を象徴。・右の男性像:労働(Labour)の象徴。 筋骨逞しい姿で、手には工具を持つなど、実践的な技術や生産を表す。スパンドレルとは 3 角形の空白で、通常は次のような 場所に汲みになって見いだされる。アーチの上部と長方形の枠の間、 隣接する 2 つのアーチの上部 と。その内部の円の間の 4 スミの1つである。 これらは、しばしば装飾的な要素で満たされている と。下記写真はネットから。その下、正面ファサードの女王像群。中央像・ヴィクトリア女王(Queen Victoria, 1819–1901) ・王冠を戴き、右手に王笏(Sceptre)、左手に宝珠(Orb)を持っています。 ・王権の正統性と大英帝国の君主としての威厳を象徴。 ・台座には「VICTORIA」と刻まれています。両脇の像・左側と右側には、黄金の剣を携えた二体の武人像(守護像)。 ・実際には「忠誠」「守護」「正義」を寓意的に表す戦士像で、女王を護る存在として 配置されています。 ・鎧姿に身を固め、手にする剣が象徴的に金色で強調されているのが特徴。ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum, V&A)正面入口の大アーチ部分。中央像 ・アーチの中央、入口扉の真上に立つ像は 聖ゲオルギウス(St George)。 ・イングランドの守護聖人で、竜を退治する伝説で有名。 ・国の守護と博物館の象徴的守護を兼ねてここに置かれています。アーチの装飾・アーチ内側の小彫刻群 アーチの層ごとに小さなレリーフ像がぎっしりと配置されており、それぞれが 芸術や産業に 関わる寓意像・職人像・知識人像 を表しています。・上部の三角形破風(ティンパヌム)部分 より大きな群像彫刻があり、「芸術と学問を通じて人類を高める」という象徴的場面を 表現しています。・両脇の柱や壁龕 装飾的な円柱と人物像のニッチ(壁龕)が並び、全体を荘厳にまとめています。この正面玄関は 1909年完成。設計者は Sir Aston Webb(サー・アストン・ウェッブ)。彼はロンドンのバッキンガム宮殿改修も手がけた建築家で、新古典主義的で荘厳な正面を設計した と。正面玄関(Cromwell Road Entrance)右側に設置されている 記念銘板(foundation stone plaque)。「THIS STONE WAS LAID BY HER MAJESTY QUEEN VICTORIA EMPRESS OF INDIA ON THE 17TH DAY OF MAY 1899 IN THE 63RD YEAR OF HER REIGN FOR THE COMPLETION OF THE SOUTH KENSINGTON MUSEUM INAUGURATED BY HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE CONSORT AND HENCEFORTH TO BE KNOWN AS THE VICTORIA AND ALBERT MUSEUM」 【この石は、インド女帝 ヴィクトリア女王陛下 により1899年5月17日、彼女の治世第63年に据えられた。この日、殿下 プリンス・コンソート(アルバート公) によって開設されたサウス・ケンジントン博物館 の完成を記念し、これ以後、この館は 「ヴィクトリア&アルバート博物館」 として知られることとなった。】左側の記念銘板(foundation stone plaque)には博物館の正式名称が「Victoria and Albert Museum」となった経緯が記載されていた。「THIS BUILDING BEING THE COMPLETION OF THEVICTORIA AND ALBERT MUSEUM, WAS OPENED BYHIS MAJESTY EDWARD VII, KING OF GREAT BRITAINAND IRELAND AND OF THE BRITISH DOMINIONSBEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA, ON THE26TH DAY OF JUNE 1909, IN THE 9TH YEAR OF HIS REIGN」 【この建物、すなわち ヴィクトリア&アルバート博物館の完成部分 は、大英帝国およびアイルランド国王、並びに海外領土の王にしてインド皇帝であるエドワード7世陛下 により、1909年6月26日、彼の治世第9年に開館された。】正面入口の中央像をクローズアップして。・像の台座に 「ALBERT」 と刻まれている通り、この像は アルバート公(Prince Albert, 1819–1861) 。・アルバート公はヴィクトリア女王の夫であり、芸術・科学・教育の振興に大きな役割を 果たした。・彼は1851年の ロンドン万国博覧会(The Great Exhibition) を主導し、その収益がこの博物館 (当初はサウス・ケンジントン博物館)の設立につながっている と。姿勢: 堂々と立ち、右手で書物(または巻物)を持ち、左手を広げて人々を導くような仕草。服装: ルネサンス風の装束にマントを羽織り、文化の庇護者・芸術の守護者として 理想化されている。表情: 正面を見据え、未来を見通すような厳粛な表情。見上げて。ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum, V&A) の側面(Exhibition Road 側のファサード)を振り返って。・左手前の建物部分: アーチ型の窓や装飾が並び、19世紀の折衷主義建築らしい重厚な外観。・右奥に見える赤レンガと白石のストライプ模様の塔: これは隣接する ロンドン・オラトリー (Brompton Oratory) の塔。・特徴的な赤白のストライプとドーム屋根は、オラトリーの外観を象徴する要素。・バナー(Cartier展): 博物館で行われた特別展の告知バナー。V&Aはファッション・宝飾・ デザインの展示でも世界的に知られています。入館案内。「WelcomeOpen10:00 – 17:45 daily10:00 – 22:00 FridayClosed 24 – 26 DecemberExhibition Road doors close at 17:45 dailyAdmission freeSome exhibitions and events carry a separate chargeGalleries may be closed occasionally without prior noticeCCTV is in operation throughout the V&AFor more information, call 020 7942 2000 or visit vam.ac.ukThe V&A’s conditions of entry apply throughout the building」【ようこそ開館時間・毎日 10:00 – 17:45・金曜日 10:00 – 22:00・12月24日~26日は休館・Exhibition Road 側の入口は毎日 17:45 に閉鎖入館料・無料・一部の特別展やイベントは別途有料(補足)・ギャラリーは予告なく閉鎖される場合があります・館内ではCCTV(監視カメラ)を稼働中です・詳細は 020 7942 2000 へ電話、または vam.ac.uk を参照・V&A の入館条件は建物全体に適用されます】 ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum, V&A)👈️リンクの館内ディレクトリ(館内案内板)。・階層(LEVELS) ・-1階(Basement): 一部の展示室・施設 ・0階(Ground floor): 正面入口、大中庭、主要なギャラリーへの入口 ・1階(Level 1): 彫刻・装飾美術・地域別ギャラリー ・2階(Level 2): ファッション、織物、家具など ・3階(Level 3): 写真、図書館、特別展示スペースなど ・4階(Level 4): 特別展示、デザイン関連・Exhibitions(特別展) ・0階: Design and Disability(デザインと障害) ・1階: Cartier(カルティエ展)・Facilities(施設案内) ・インフォメーション ・トイレ ・カフェ・レストラン ・ショップ ・エレベーター/階段Galleries(ギャラリー一覧) 右側にリスト化され、館内各フロアの主要展示(例: Sculpture, Fashion, Jewellery, Furniture, Asia, Europe, Medieval & Renaissance など)が並んでいます。ズームして。館内図をネットから。0階の配置案内図👈️リンク をネット写真をトリミングして。正面ホール(Grand Entrance Hall) の吹き抜け部分。・天井のドームから吊り下げられているガラスのシャンデリアは、アメリカの現代ガラス作家 デイル・チフーリ(Dale Chihuly, 1941– ) の作品。・作品名は 「Rotunda Chandelier(ロタンダ・シャンデリア)」。・2001年に設置され、その後2005年に再設計されて現在の形に近づきました。・鮮やかなブルーやグリーンのガラスが渦巻くように絡み合い、生命力と流動感を感じさせます。・ガラスの色彩: ・青(ブルー)と緑(グリーン)を基調とし、黄色がアクセント。 ・自然光を受けると透明感が増し、まるで水中植物や海の渦潮のように輝きます。・形態: ・無数のガラスの触手状パーツが螺旋を描き、エネルギーの爆発や生命の成長を象徴。 ・下方に向けてすぼまる形が、訪問者の視線を自然に中央へ導きます。移動して。ズームして。正面ホール(Grand Entrance Hall)のインフォメーション・デスク。・手前:円形に近い大きなカウンターが設置され、スタッフが訪問者に案内やチケット情報を 提供。・奥:正面玄関の大理石の柱列とガラス扉が見えます。ここからロンドンの Cromwell Road (クロムウェル・ロード) 側に出入りします。・上部:先ほどの「チフーリのガラス・シャンデリア(Rotunda Chandelier)」が 吊るされているドーム空間の真下に位置。「Medieval and Renaissance(300–1500)」の案内板が前方に。4世紀に成立したキリスト教ローマ帝国からルネサンス期までの幅広い時代を網羅。展示ギャラリーのひとつ、この後見学した「Medieval and Renaissance(中世・ルネサンス 1350–1600)」ギャラリー の入口付近。「Medieval & Renaissance (1350–1600)」ギャラリー(50A–50D) の入口標識。・Medieval & Renaissance (1350–1600) → 中世後期からルネサンス時代(14世紀半ば〜16世紀)の作品を展示するエリア。・50A–50D → この展示室の内部は、A〜Dの複数セクションに分けられており、時代・地域・テーマごとに 展示が整理されていた。全景をネットから。ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A) の「Medieval & Renaissance Galleries (1350–1600)」 の中心ホールで、正式には「The Paul and Jill Ruddock Gallery (Rooms 50A–50B)」と呼ばれる空間。「Medieval & Renaissance Galleries (1350–1600)」の入口付近(Gallery 50A–50D)。・天井が高く、ガラス屋根(barrel-vaulted skylight)が通る明るい空間。・大理石床と、中央に大型彫刻を円形配置した構成。・正面奥に黒い木製構造物(16世紀の聖堂の彫刻的内陣)があった。・入口付近にはMedieval & Renaissance (1350–1600)(V&A所蔵オリジナル)を中央に配置。移動そしてカメラ設定を変えて。SAMSON SLAYING A PHILISTINE(ペリシテ人を打ち殺すサムソン)・制作年:1562年頃・作者:ジャンボローニャ(Giovanni Bologna, 通称 Giambologna, 1529–1608)・材質:大理石・所蔵:ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A, ロンドン)移動して。移動して。近づいて。・ジャンボローニャがメディチ家のフランチェスコ1世・デ・メディチのために制作した作品。・これは彼の最初の大規模な重要依頼作であり、二人の人物を力強く絡み合わせ、複数の角度 から鑑賞できるよう設計されている。・当初はフィレンツェのフランチェスコ邸の薬草園の 噴水上に置かれていた。・1601年、外交贈答品としてスペインへ送られた経緯を持つ。「SAMSON SLAYING A PHILISTINEAbout 1562Giovanni Bologna, called Giambologna (1529–1608)Giambologna, working at the court of the Medici grand-dukes of Tuscany, becamethe most famous and influential sculptor of his day. This spectacular marble group, made forFrancesco de’ Medici, was his first major commission. In it, he achieved hisambition to create a two-figure group in movement, with several different viewpoints.Originally placed atop a fountain in the herb garden of Francesco’s palace in Florence,the group was sent to Spain in 1601 as a diplomatic gift.Italy, FlorenceMarblePurchased with the assistance of the Art FundMuseum no. A.7-1954」 【サムソンがペリシテ人を打ち殺す約1562年ジョヴァンニ・ボローニャ(ジャンボローニャ、1529–1608)トスカーナのメディチ大公の宮廷で活動したジャンボローニャは、その時代で最も有名かつ影響力のある彫刻家となった。この壮大な大理石群像は、フランチェスコ・デ・メディチのために制作されたもので、彼にとって最初の重要な依頼作である。作品において、彼は二人の人物を動きの中で表現し、複数の異なる視点から鑑賞できる群像を作るという野心を実現した。もともとはフィレンツェのフランチェスコ邸の薬草園の噴水の上に設置されていたが、1601年に外交贈答品としてスペインへ送られた。イタリア、フィレンツェ大理石アート・ファンドの協力により購入館蔵番号 A.7-1954】八角形の大理石製の 祭壇前飾り/洗礼盤(あるいは水盤) の一つ。「WELL HEAD WITH THE ARMS OF THE CONCOREGGIO FAMILYWell heads were oftencarved with the arms of the family that commissioned them, or – if public – of the magistrate responsible for their construction. This richly decorated well head probably stood in the courtyard of a private palace. It bears the arms of the Concogreggio family – three wheels surmounted by a helmet.Italy, VeronaLimestone, known as Verona marbleGiven by Mr J.H. FitzhenryMuseum no. A.9-1909」 【この井戸枠は 「コンコレッジョ家の紋章を刻んだ井戸枠」 と呼ばれ、1450年頃に制作されたものである。井戸枠は、依頼した家の紋章で飾られることが多く、公共の井戸の場合は、その建設を監督した行政官の紋章が刻まれることもあった。この豊かに装飾された井戸枠は、おそらく貴族の邸宅の中庭に設置されていたと考えられる。そこには、兜の上に三つの車輪を配したコンコレッジョ家の紋章が刻まれている。イタリア、ヴェローナ製。素材はヴェローナ大理石として知られる石灰岩。J.H. フィッツヘンリー氏によって寄贈され、館蔵番号は A.9-1909 である。】Well Head with the Arms of the Concogreggio Family(コンコレッジョ家の紋章を刻んだ井戸枠)。中世・ルネサンス ギャラリー(1350–1600に展示されている八角形の大理石製の祭壇前飾り/洗礼盤(あるいは水盤) の一つ。・形状:八角形の石槽(赤みを帯びた大理石)。・装飾:側面に浮彫で人物や場面が刻まれている。 ・左側:衣をまとった人物群像。 ・中央:馬上の騎士と思われる人物(円形のアーチで囲まれる)。 ・右側:別の人物像が浮彫で表現。・上縁:ロープ文様のような連続模様。1.洗礼盤(Baptismal font)・教会の洗礼儀式に用いられる水槽。・側面に聖書物語や寓意図像を刻むのが一般的。2.説教壇(Pulpit)の一部・ルネサンス期イタリアでしばしば八角形や多角形の構造が用いられた。3.大理石製の祭壇前飾りや聖水盤(holy water stoup)・聖堂入り口や側廊に置かれる場合もある。「WELL HEADAbout 1424–30Workshop of Bartolomeo Bon (active 1421–64)This functional object is also a display of flamboyant virtuoso carving.Its sides depict a shield with the arms of the Contarini family, Justice holding a sword, a putto leaningon a tree trunk, and Fortitude holding a crown. Bartolomeo Bon had been previously employed by the wealthy merchant Marino Contarini on his sumptuous palace,the Ca’ d’Oro.Italy, VeniceLimestone, known as Verona marbleMuseum no. 1842-1892」【井戸枠1424~1430年頃バルトロメオ・ボン工房(活動期間 1421–1464)この井戸枠は実用的なものですが、同時に華麗な技巧を誇示する作品でもあります。側面にはコンタリーニ家の紋章の盾、剣を持つ正義の寓意像、木の幹に寄りかかる幼児(プットー)、そして冠を持つ剛毅(フォルティトゥード)の寓意像が彫られています。バルトロメオ・ボンは、以前に裕福な商人マリーノ・コンタリーニによって、彼の壮麗な邸宅「カ・ドーロ宮殿」のために雇われたことがありました。イタリア、ヴェネツィアヴェローナ大理石として知られる石灰岩館蔵番号 1842-1892】「中世・ルネサンス(1350–1600)」ギャラリー の壁面展示。・大きな円形陶板(中央上部) 緑と黄色が鮮やかな「マヨリカ焼き(イタリアのルネサンス陶器)」の円形飾り皿です。 中央には仮面(または盾のような顔面モチーフ)が描かれ、その周囲を葉模様や果実が 取り囲んでいます。これは16世紀イタリアで流行した装飾陶器の一例で、建物の外壁や 室内装飾に用いられました。・周囲の中小の円形/盾形装飾 盾(シールド)や紋章、装飾メダリオンの数々が並んでいます。これらはルネサンス期 イタリアの家紋装飾や建築装飾断片で、実際には宮殿や公的建築の壁を飾っていたものです。 家の権威を示したり、公共空間の荘厳さを高める目的がありました。・右側の鉄製ブラケット(ランプ台のような突き出し金具) これは中世~ルネサンス期の建物で使われた鉄製の照明器具ホルダーで、壁に取り付け、 松明やランプを支えるために用いられました。「Istoriato Dish of ApolloAbout 1532–35Nicola da Urbino (active 1520s–30s)Tin-glazed earthenware, painted in polychrome, with gildingItaly, UrbinoMuseum no. 1716–1855The story of Apollo slaying Niobe’s children is told on this dish. According to Ovid’s Metamorphoses, Apollo and Diana killed Niobe’s 12 children after she insulted their mother Latona (Leto). The reverse has grotesques, including winged female masks.Given by Mr John WebbCoats of Arms (stemma)The coat of arms of a family was a symbol of their identity and authority. They weredisplayed on a wide range of objects, from buildings to domestic items. On ceramics,arms often proclaimed the ownership of a piece, its association with a particular family,or its status as a diplomatic gift.Roundels with Classical HeadsItaly, about 1475–1500Tin-glazed earthenware, painted in blue, green, yellow and manganeseFlorence or FaenzaMuseum no. C.218–1922, C.220–1922Displaying the heads of heroes of antiquity was an important feature of Renaissancedecoration. These roundels are part of a group that was made in imitation of antiquecameos. Their designs were probably based on medals, which were oftenset intopalace walls.Coat of Arms (stemma) of Pope Leo XItaly, Florence, about 1513–21Tin-glazed earthenware, painted in polychromeMuseum no. 8124–1863Giovanni de’ Medici (1475–1521) became Pope Leo X in 1513. His stemma is composed of balls (palle), the heraldic device of the Medici family, surmounted by the papal keysand tiara.」【アポロの物語を描いた飾り皿1532–35年頃、ニコラ・ダ・ウルビーノ作。錫釉陶器に多色彩と金彩で描かれた作品で、イタリアのウルビーノで制作されました。オウィディウス『変身物語』に基づき、アポロとディアナがニオベの母ラトーナ(レト)を侮辱したために、彼女の12人の子どもを殺した場面が表されています。裏面には翼のある女性の仮面を含むグロテスク文様が描かれています。紋章(ステンマ)家族の紋章は、その一族の身分や権威を示す象徴でした。建築物から日用品に至るまで広く用いられ、陶器の装飾では所有者やその家族との結びつきを示したり、外交的贈り物としての性格を持つ場合もありました。古典的頭像の円形装飾1475–1500年頃、フィレンツェまたはファエンツァで制作。錫釉陶器に青、緑、黄、マンガン色で彩色されています。古代の英雄の頭部を表すことはルネサンス装飾の重要な特徴でした。これらの円形装飾は、古代のカメオを模倣して作られた一群の作品で、その図像はしばしば宮殿の壁に埋め込まれたメダルをもとにしています。教皇レオ10世の紋章(ステンマ)1513–21年頃、フィレンツェで制作。錫釉陶器に多色で彩色。ジョヴァンニ・デ・メディチ(1475–1521)は1513年に教皇レオ10世となり、その紋章はメディチ家の象徴である「玉(パッレ)」に、教皇の鍵と三重冠(ティアラ)が組み合わされています。】 柱頭(キャピタル, capitals)。建築物の柱の最上部に置かれる装飾的要素で、古代ギリシャ・ローマ建築以来、ロマネスク、ゴシック、ルネサンスなど様々な様式で発展した。・6点(左右3列×2段)に並べられた石製の柱頭断片。・植物文様(アカンサス葉、花飾り)が中心的モチーフ。・渦巻き(ヴォリュート)を持つものもあり、イオニア式やコリント式の系譜を示唆。・中央列のものには、楽器のような格子文様や、盾・武器のような意匠も見える。・元来は建物の一部として高所に据えられ、構造と装飾を兼ねた役割を果たしていました。上のプレート。「STREET CRESSET1500–1600The earliest recorded street lights took the form of decorative iron baskets, known ascressets, which were fixed to the walls of Italian palaces. The light came from burning coils of rope soaked in pitch and placed in the cradle. These lanterns were almost exclusively used in Italy.Italy, FlorenceWrought ironMuseum no. 734-1869」 【街路用クレセット(かご型照明)1500–1600年最も初期に記録された街灯は、装飾的な鉄製のかごの形をしており、「クレセット」と呼ばれ、イタリアの宮殿の壁に取り付けられていました。光は、ピッチ(樹脂)に浸した縄のコイルを燃やし、かごの中に置くことで得られました。これらのランタンは、ほぼイタリアだけで使用されていました。イタリア、フィレンツェ鍛鉄館蔵番号 734-1869】下のプレート。「PILASTER CONSOLES FROM THE ROCCA ROVESCAS DI MONDOLFO1462–1480Probably by Francesco di Giorgio Martini (1439–1502) and workshopThese consoles,with acanthus leaves and other Renaissance decoration, came froma fort on theAdriatic coast. The fort was commissioned by Giovanni della Rovere,Duke of Sora,Lord of Senigallia and nephew of Pope Sixtus IV.Italy, Senigallia(Marche)Verona marbleMuseum no. 491-1871」 【モンドルフォのロッカ・ロヴェスカの壁柱コンソール1462–1480年おそらくフランチェスコ・ディ・ジョルジョ・マルティーニ(1439–1502)とその工房による。このコンソール(持ち送り装飾)は、アカンサスの葉やその他ルネサンス装飾が施されており、アドリア海沿岸の要塞から来たものです。その要塞は、ソーラ公でセニガッリア領主、そして教皇シクストゥス4世の甥であったジョヴァンニ・デッラ・ローヴェレによって建設されました。イタリア、セニガッリア(マルケ州)ヴェローナ大理石館蔵番号 491-1871】「中世・ルネサンス ギャラリー(1350–1600)」 の内部。1.中央の立像 ギリシャ・ローマ彫刻を模した男性裸体像が中心に置かれています。片手を上げ、古典的な 英雄像のポーズを示しています。2.奥の黒い構造物 写真奥に見える大きな黒い構造は、ルネサンス期イタリアの教会や宮殿の建築要素を 移設したもの(またはレプリカ) で、壁面いっぱいに彫刻やアーチを備えた荘厳な展示です。3.手前の円形井戸枠(Well Head) 写真左下に円形の石造「井戸枠」が見えます。先ほど解説した「Well Head(井戸枠)」に 関連する展示の一つです。中庭の装飾品であり、貴族の邸宅や宮殿に設置されていたもの。4.壁面装飾と彫刻群 左壁には祭壇建築の一部や、墓碑的な建築彫刻、また上段には盾や装飾レリーフが取り 付けられています。5.ギャラリーの雰囲気 白を基調とした空間に、明るい天窓(ヴォールト型のトップライト)が特徴的で、展示作品を 自然光で照らし出しています。左側の壁にあった「Window surround(窓枠)」。これは、ルネサンス様式の大理石製建築装飾(彫刻付窓枠または暖炉飾り)で、16世紀中期イタリアの芸術を代表する作品群に見られる構成。構造と装飾の特徴から、ヴェネツィア派または北イタリアのマニエリスム建築彫刻に属するものと考えられる と。・作品名(英) Architectural window surround・推定製作地 フィレンツェまたはルッカ(イタリア)・年代 約1550年頃(16世紀中期)・材質 大理石(carved marble)・寸法 高さ 約4.5メートル(実物大建築要素)・所蔵 Victoria and Albert Museum, London(Museum no. A.3-1912)「サビニの女の略奪(The Rape of a Sabine Woman)」のブロンズ複製。「THE RAPE OF PROSERPINAAbout 1565Probably based on a model by Vincenzo de’ Rossi (1525–87)This dramatic sculpture shows Pluto, the king of the underworld, carrying off Proserpina with whom he had fallen in love. It originally belonged to Giovan Vittorio Soderini, a leading exponent of garden design in 16th-century Florence. In promoting the use of sculpture and fountains, Soderini described water as the soul ofcities and gardens. In 1594 the bronze group was sold to Antonio Salviati, who placed it on an elaborate fountain in his palace garden (see photo).Italy, FlorenceBronze Cast byRaffaello PeriLent by the National TrustPen and ink drawing with monochrome wash, probably by Ferdinando Ruggieri (1691–1741)V&A: E.571-1975」【プロセルピナの略奪約1565年おそらくヴィンチェンツォ・デ・ロッシ(1525–1587)の原型に基づく作品この劇的な彫刻は、冥界の王プルート(ハーデース)が恋に落ちたプロセルピナをさらう場面を表しています。もともとは16世紀フィレンツェの庭園設計の第一人者であったジョヴァン・ヴィットリオ・ソデリーニの所蔵でした。ソデリーニは彫刻や噴水の使用を推奨し、水を都市と庭園の魂であると表現しました。1594年、このブロンズ群像はアントニオ・サルヴィアーティに売却され、彼の宮殿庭園にある精巧な噴水の上に設置されました(写真参照)。イタリア、フィレンツェブロンズ鋳造:ラファエロ・ペリナショナル・トラスト寄託ペンとインクに単色の彩色を施した素描、おそらくフェルディナンド・ルッジェーリ(1691–1741)によるV&A: E.571-1975】手前の彫像はJASON像。・壁面の円形装飾(右側) ・ドーナツ型の緑と黄色の装飾で縁取られた「彩色テラコッタの円形メダリオン」作品群です。 ・これらは15世紀フィレンツェの デッラ・ロッビア工房(Della Robbia family) による 代表的な装飾技法「グレーズ陶(glazed terracotta)」で作られたものです。 ・人物胸像が浮き彫りで描かれ、聖人や貴族を表していることが多いです。近づいて。「JASONAbout 1550–1600In the Renaissance, gardens were often associated with the earthly paradises of classical mythology. The story of Jason includes the sacred grove of the Golden Fleece and theGarden of the Hesperides, making him a suitable subject for a garden. This sculptureonce stood in a portico in the garden of the Palazzo Stiozzi-Ridolfi in Florence.Italy, FlorenceMarbleMuseum no. 6735-1860」【イアソン制作年代:約1550–1600年ルネサンス期において、庭園はしばしば古典神話における地上の楽園と結びつけられました。イアソンの物語には、金羊毛の聖なる森やヘスペリデスの園が含まれており、彼は庭園の主題としてふさわしい存在とされました。この彫像はかつて、フィレンツェのストッツィ=リドルフィ宮殿の庭園の回廊に置かれていました。イタリア、フィレンツェ大理石館蔵番号:6735-1860】 ナルキッソス(Narcissus)・制作年代: 約1560年・作者: ヴァレリオ・チョリ(Valerio Cioli, 1529–1599)による可能性・材質: 大理石(19世紀に石膏で補修)・出土地: イタリア(おそらくフィレンツェ)・所蔵番号: Museum no. 7560-1861「NARCISSUSAbout 1560Possibly by Valerio Cioli (about 1529–99)During the Renaissance, it was a common practice to re-work ancient Roman sculpture. Narcissus was long thought to be an example of this, but instead it was possibly made by a sculptor and restorer called Valerio Cioli. A Greek myth tells how Narcissusfell in love with his reflection in a pool. This made him a suitable subject for garden sculpture.Italy, probably FlorenceMarbleWith 19th-century plaster repairsMuseum no. 7560-1861」 【ナルキッソス約1560年ヴァレリオ・チョリ(1529–1599頃)作の可能性ルネサンス期には、古代ローマの彫刻を再加工することがよく行われました。この像《ナルキッソス》も長らくその一例と考えられていましたが、現在では彫刻家で修復家でもあったヴァレリオ・チョリによって制作された可能性があるとされています。ギリシャ神話によれば、ナルキッソスは水面に映る自分の姿に恋をしたと伝えられています。この神話は庭園彫刻の題材として非常にふさわしいものでした。イタリア(おそらくフィレンツェ)大理石19世紀に石膏による修復あり館蔵番号 7560-1861】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.23
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その116): ロンドン散策記・St. Paul's Cathedral・セントポール大聖堂-5
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンク再びセント・ポール大聖堂の北東側にあった「St Lawrence and Mary Magdalene Drinking Fountain(聖ローレンスと聖マグダラのマリア記念噴水)」の前へ。当時の飲料水供給を目的に設置された公共の飲水設備であると。上段の彫刻は聖ローレンス(殉教聖人)。ズームして。聖ローレンス(St. Lawrence, ラテン語: Laurentius) は、キリスト教における代表的な殉教聖人のひとりで、西方教会で特に崇敬を集めている。生没年:225年頃 – 258年出身:スペインのウエスカ生まれとされる職位:ローマ教会の助祭(Deacon)。当時の教皇シクストゥス2世に仕えていた。殉教の経緯・258年、ローマ皇帝 ウァレリアヌス帝 による迫害が激化。・皇帝は教会の財宝を差し出すよう命令しましたが、ローレンスは貧しい人々を前に立たせて 「これこそが教会の宝です」と告げたと伝えられます。・その結果、激怒した皇帝の命で捕えられ、鉄格子の上で火あぶりにされ殉教した と。・聖ローレンス像の持ち物 ・格子(Gridiron / Grill) ・彼が火あぶりにされた鉄格子。 ・書物または福音書 ・助祭として聖書を管理していたため。裏側には聖マグダラのマリア(Mary Magdalene)。・特徴と持ち物 ・胸の前で両腕を交差 ・悔悛(penitence)や祈りを象徴。・右手に小さな十字架を持つ ・キリストへの信仰と贖罪を表す。・足元に頭蓋骨(skull) ・「メメント・モリ(死を想え)」の象徴。 ・罪の悔い改め、世俗からの離脱、永遠の命を示す。「十字架を抱き、悔悛の象徴として頭蓋骨の上に立つマグダラのマリア」が表現されていた。特徴的な尖頭アーチ(pointed arch)と二重柱頭の柱(clustered columns)を備えたニッチ(壁龕)内に、ヨルダン川でキリストを洗礼する洗礼者ヨハネ(John the Baptist)と、聖母マリア(the Virgin Mary)に抱かれ幼子イエス・キリスト(Christ)の姿がブロンズで表されているのだ と。髭をたくわえ、外套を羽織り、杖または指し棒を持ち、赤子に向かって祝福の仕草をしているように見える人物が、東方の三博士(Magi)の一人、または羊飼い(Shepherd)、あるいは聖ヨセフ(Joseph)と考えられるのだ と。特に杖を持っている点から「羊飼いの礼拝(Adoration of the Shepherds)」の可能性が強いのでは!!とも。杖は、羊飼いの職業を示すほか、しばしば「聖ヨセフ」や「モーセ」といった聖書の登場人物と関連づけて描かれているのだ。セントポール大聖堂・St. Paul's Cathedralとのコラボ。セント・オーガスティン教会(St Augustine, Watling Street)の塔。・元は St Augustine, Watling Street 教会 ・12世紀に創建されましたが、1666年のロンドン大火で焼失。 ・その後、クリストファー・レン卿(Sir Christopher Wren)の設計で再建。 ・第二次世界大戦(1941年のブリッツ)で再び破壊され、最終的に塔だけが残存しました。・現在の役割 ・塔は保存され、近隣に移転した St Paul’s Cathedral School(セント・ポール大聖堂付属学校)の一部として 組み込まれています。移動して、ズームして(ネットから)。そして、セントポール大聖堂・St. Paul's Cathedral及びその周辺の見学を終えて地下鉄を利用しマンション ハウス・Mansion House駅からSouth Kensingtone駅まで行き下車。黄色のCircle line(サークル線)を利用。South Kensington駅の改札を振り返る。South Kensington駅前。South Kensington駅周辺の案内地図。地図の中央に「South Kensington」と駅名があり、さらに「You are here(現在地)」のマークが。・左側に大きく黄色で描かれているのが Natural History Museum(自然史博物館)、 Science Museum(科学博物館)、Victoria and Albert Museum(V&A美術館)。・右上には Chelsea(チェルシー)の文字が書かれていた。・地下鉄の South Kensington駅(Circle, District, Piccadilly line 接続)を起点に、徒歩で 博物館群にアクセスできるのがわかったのであった。これも South Kensington駅周辺の観光案内板。上部に Royal Albert Hall と Royal Brompton Hospital の表記があり、観光客向けに徒歩での所要時間がリスト化されていた。案内に書かれている徒歩時間Gloucester Road駅 → 9分Knightsbridge駅 → 17分Earl’s Court駅 → 18分Cadogan Pier(テムズ川沿い) → 18分Royal Albert Hall → 12分Harrods → 13分The Saatchi Gallery → 14分Albert Memorial → 15分Serpentine Gallery → 16分Royal Hospital Chelsea → 18分地図の特徴・中央に「You are here(現在地)」と書かれており、そこがSouth Kensington駅。・左の大きな緑色エリアは Hyde Park / Kensington Gardens。・黄色で示されているのが主要観光施設(博物館、美術館、商業施設など)。South Kensington(サウス・ケンジントン駅)出口付近の案内ボード。・左方向(←) ・Museums(博物館群) ・自然史博物館(Natural History Museum) ・科学博物館(Science Museum) ・ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum) ・Imperial College London(インペリアル・カレッジ・ロンドン) ・Royal Albert Hall(ロイヤル・アルバート・ホール)・右方向(→ CHELSEA方面) ・Royal Marsden Hospital(ロイヤル・マーズデン病院) ・Royal Brompton Hospital(ロイヤル・ブロンプトン病院)・直進(↑ KNIGHTSBRIDGE方面) ・Brompton Road(ブロンプトン・ロード) ・Fulham Road(フラム・ロード)South Kensington駅は、博物館めぐりの拠点として有名で、 駅から地下通路でそのままV&Aや自然史博物館方面へアクセスできる便利な立地なのであった。South Kensington駅前の花屋さん。バケツには、白、淡いピンク、濃いピンクと色とりどりの芍薬(しゃくやく, Peony)の花が。ふんわりした花びらが特徴。線路に沿って東に進み我が宿・アパートに向かって進む。Walton Street・ウォルトン・ストリート沿いの民家の壁には美しい黄色の薔薇の花が。ヘアーサロン・65 Walton。65 ウォルトン ストリート、 チェルシー、 ロンドン、 SW3 2HT。近づいて。造花であっただろうか?さらに。そして無事に宿・アパートに到着したのであった。1時間ほど部屋で休憩して、旅友Yさんと夕飯を食べに向かう。チェルシー(Chelsea)・Walton Street・ウォルトン・ストリートを歩く。・建物は白い漆喰仕上げのヴィクトリア様式風のタウンハウス。・奥に向かってレンガ造りの建物が連なっており、いかにも「ロンドンの典型的な住宅街」の 雰囲気。Beauchamp Place・ボーチャンプ・プレイス通りを歩く。旅友Yさんが予約しておいてくれたタイ料理レストラン・pataraに入る。Pataraはロンドン市内に複数展開している高級タイ料理レストランチェーン。店内。タイビール・「シンハービール(Singha Beer)」を楽しむ。・製造元:ブンロート・ブリュワリー(Boon Rawd Brewery, Bangkok, Thailand)・創業:1933年(タイ初のビールとして誕生)・スタイル:プレミアム・ラガー・アルコール度数:5%前後・味わい:すっきりとした喉ごしとキレのある苦味、ほんのりモルトの甘みも感じられるのが特徴。・ラベルのシンボル:タイ神話に登場する獅子「シンハー(สิงห์, Singha)」が描かれていた。私は「パッタイ(Pad Thai)」 の豪華版、ロブスター・パッタイを注文。・パッタイ(Pad Thai)の特徴 ・料理の種類:タイ風焼きそば ・主な材料:ライスヌードル、卵、モヤシ、ニラ、干しエビ、豆腐、タマリンドソース (甘酸っぱいソース)、ナンプラー、ピーナッツ、唐辛子など。 ・味わい:甘味・酸味・辛味のバランスが絶妙。自分好みにナッツや唐辛子、砂糖を加えて調整。 ・付け合わせ:砕いたピーナッツ、唐辛子、モヤシが別添えされ、混ぜながら食べるのが定番。 ・ロブスター・パッタイ 通常はエビ(クン)入りが人気だが、大ぶりのロブスターを豪快にトッピングした 贅沢な一皿を注文。そして、ビール、ワインを大いに楽しんでこの店を出る。ロンドンにある 「chisou(馳走)」 という日本食レストランが左手にあった。看板には「Japanese Restaurant」とあり、和食を提供しているようであった。・名前の由来:「馳走(ちそう)」は日本語で「ご馳走」の語源。「走り回って客をもてなす」と いう意味が込められています。・外観:レンガ造りのクラシックなロンドンの建物の1階にあり、木目調の看板とシックな 黒い外装が日本料理店らしい落ち着いた雰囲気を演出。・料理:本格的な寿司や刺身はもちろん、天ぷら、焼き魚、肉料理など幅広い和食を提供している 店として知られているようであった。メニューをネットから。Beauchamp Place・ボーチャンプ・プレイス通り沿いの住宅街を宿に向かって。・赤レンガの集合住宅 ヴィクトリア様式からエドワード様式にかけて建てられた典型的なロンドンの 高級アパートメント。 出窓(ベイウィンドウ)やバルコニー、黒い鉄柵(wrought iron)が特徴。・白い塔の建物 ・奥に見える白い建物はスコットランド教会(St Columba's Church of Scotland, London).。 ・尖塔部分が緩やかな曲線を持ち、上には十字架が掲げられているのが見えた。 ・スコットランドの旗(青地に白の斜め十字=セント・アンドリュー・クロス)が掲揚されて いるため、スコットランド系の教会施設であることが判るのであった。我が宿の近くの住宅街。・ヴィクトリア様式からエドワード様式にかけて建てられた典型的なロンドンの 高級アパートメント。・出窓(ベイウィンドウ)やバルコニー、黒い鉄柵(wrought iron)が特徴。St Columba's Church of Scotland, London(セント・コロンバ・スコットランド教会)。Pont St, London SW1X 0BD イギリス。・場所:Knightsbridge(ロンドン西部、ハイドパークのすぐ近く)に位置します。・宗派:スコットランド国教会(Church of Scotland)のロンドン拠点。・歴史:第二次世界大戦中の空襲で被害を受け、1950年代に再建。現在もスコットランド人 コミュニティや在英スコットランド人の拠点教会となっています。・外観の特徴: ・白い石造りでシンプルながら力強い塔。 ・上部に掲げられているのは、スコットランドの国旗 セント・アンドリューズ・クロス (青地に白の斜め十字)。 ・周辺の赤レンガの住宅街(ナイツブリッジらしい高級感ある街並み)とコントラストを 成しています。St. Columba’s Church of Scotland(セント・コロンバ・スコットランド教会) の案内板。ST. COLUMBA'SChurch of Scotland (Presbyterian)Welcomes all visitors・Minister(牧師) Rev. C. Angus MacLeod MA B・開館時間 午前 9:30 ~ 午後 5:00 (毎日、ただし土曜を除く) → 祈りと瞑想のために開放・聖餐(Communion) 詳細は公式サイト参照(www.stcolumbas.org.uk)・日曜礼拝(Sunday Services) 午前11:00 朝の礼拝(クレッシュ〔幼児保育〕&日曜学校あり)・12:15 pm 必要とする人々のための祈り・12:30 pm 会衆ランチ(Congregational Lunch)・夕方 夕の礼拝(Evening Worship)・フェローシップ・アワー内部の様子をネットから。ロンドンの St Columba’s Church of Scotland(セント・コロンバ教会) のすぐ近くの通りの風景。・赤レンガの連続したタウンハウス様式の建物が並んでおり、19世紀後半~20世紀初頭の 典型的な ロンドンの高級住宅街(メリルボーン/ナイツブリッジ周辺) の景観を示していた。・建物は縦に長く、白い窓枠や玄関の石造装飾がアクセントになっていた。ロンドン・ケンジントン&チェルシー王立区(The Royal Borough of Kensington and Chelsea)内の 「LENNOX GARDENS S.W.1」の通り標識。このエリアはチェルシーの高級住宅街として知られ、19世紀末に造成された 赤レンガ造りのヴィクトリア朝様式の邸宅群 が特徴。多くの建物が保存状態良く残っており、大使館や領事館、富裕層の住宅として利用されている。この周辺には スイス大使館(Embassy of Switzerland, London) がかつて置かれていたこともあり(現住所は 16–18 Montagu Place, Marylebone, London に移転)、外交関係や宗教施設との結びつきが深いエリアとのこと。旗には 「K+S」 の文字と、波をイメージさせる青いストライプ、赤い盾が描かれていた。これは Knightsbridge School(ナイツブリッジ・スクール) の校章・校旗 。以前はこの建物が 在ロンドン・スイス大使館(Embassy of Switzerland, London) であったが、現在は大使館が移転し、この場所は学校の施設になっているようであった。前日に訪ねた英国国教会・St Simon Zelotesをズームして再び見る。34 Milner St, London SW3 2QF イギリス。そして我が民宿のアパートメントに戻ったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.22
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その115): ロンドン散策記・St. Paul's Cathedral・セントポール大聖堂-4
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンク次の展示コーナーに進む「PROTECTING ST PAUL’S(セント・ポールを守る)」 セクションの大型タイトルパネル。「PROTECTING ST PAUL’S(セント・ポールを守る)」 セクションの 主要解説パネル。「PROTECTING ST PAUL’SThe Watch maintained a 24-hour vigil over the Cathedral, working in shifts day and night.Some members were stationed at lookout points on the building’s exterior to watchthe skies for enemy aircraft. Others patrolled the Cathedral’s interior, monitoring fordamage and checking for incendiary bombs.These fire spreading devices were highly dangerous as they were small and couldbecome lodged in hidden parts of the Cathedral during air raids. Members of the Watchused stirrup pumps and buckets of water and sand to put out fires before they spread.One of the biggest challenges new members of the Watch faced was finding their wayaround. As Watch Commander Godfrey Allen later remarked, it could take “even a mosteminent architect months to master all the intricate passages and staircases of the Cathedral”.」 【セント・ポールを守る見張り隊は、大聖堂を昼夜交代で守り、24時間体制の警戒を維持した。一部の隊員は建物外部の見張り台に配置され、敵機を監視した。別の隊員たちは大聖堂内部を巡回し、被害状況を確認し焼夷弾を探した。これらの焼夷弾は非常に危険で、小さく目立たないため、空襲の際に大聖堂の隠れた場所に入り込みやすかった。見張り隊は足踏み式ポンプや水・砂のバケツを使い、火が広がる前に消し止めた。新しく加わった隊員にとって最大の課題の一つは、大聖堂内部での道順を覚えることだった。後にゴドフリー・アレン指揮官が述べたように、たとえ著名な建築家であっても、この大聖堂の複雑な通路や階段を完全に把握するには数か月を要するだろう】「“The Cathedral presented a dismal and heartrending spectacle at that time and wascertainly one of the draughtiest buildings in London. Wind and rain drove throughthe unprotected windows, and caused pools of water to gather on the marble floor,particularly under the Dome.”— Dean W.R. Matthews, 1946」 【その当時、大聖堂は陰鬱で胸の痛む光景を呈していた。ロンドンでもっとも隙間風のひどい建物の一つであったことは間違いない。保護されていない窓から風雨が吹き込み、大理石の床には水たまりができ、とりわけドームの下でそれが顕著であった。」W.R.マシューズ学長(1946年)】「PROTECTING ST PAUL’S(セント・ポールを守る)」 セクションに属する展示パネル。・描かれているもの: 大聖堂ドーム内部の木造トラス(梁や支柱)の構造と、その中で警戒や作業を行う人物。・作者:アーティスト Henry Rushbury(ヘンリー・ラッシュベリー)。・制作時期:第一次世界大戦期に描かれた作品。「Artist Henry Rushbury’s atmospheric impression of the Watch on duty in the Cathedral Dome. This illustration was made during the First World War, but it shows why the manytimber supports made the Dome and roof such a big fire risk during the Blitz.」 【芸術家ヘンリー・ラッシュベリーによる、大聖堂ドーム内部で勤務する「見張り隊」の様子を描いた印象的なスケッチ。これは第一次世界大戦中に制作されたものだが、ドームと屋根を支える多数の木材が存在していたため、第二次世界大戦の大空襲(Blitz)の際には大火災の大きな危険要因となったことを示している。】この写真も「PROTECTING ST PAUL’S(セント・ポールを守る)」。・被写体:ヘルメットをかぶった二人の「Watch(見張り隊)」メンバー。・装備:手に持っているのは「消防斧(axe)」で、火災や瓦礫の除去に使用される道具。・状況:大聖堂の扉に対して、斧の使い方を実演している様子。・服装:黒系の防火服、ベルトに工具や装備を携帯。戦時下の民間防衛隊らしい実務的スタイル。「Two members of the Watch demonstrate the use of axes on a Cathedral door.」 【見張り隊の2名が、大聖堂の扉で斧の使用方法を実演している。】「‘…We are drilled everlastingly in the use of all our apparatus… One becomes, in time, a sort of Master of Hydrants – as of Arts – and an expert in stopcocks.It’s rather fun letting off a big hydrant, except when it knocks you over backwards and drowns everybody near you. That’s why they call it wet drill.’— A.S.G. Butler, Watch team leader」 【「私たちは、あらゆる装備の使い方を繰り返し訓練させられました。やがて誰もが『消火栓の達人(まるで学位のように“Master of Hydrants”)』になり、止水栓の扱いにも熟達していきました。大きな消火栓を解放するのはなかなか楽しいのですが、時には後ろに吹き飛ばされ、周囲の仲間全員をびしょ濡れにしてしまうこともあります。だからこれを『ウェット・ドリル(水びたし訓練)』と呼ぶのです。」見張り隊リーダー A.S.G. バトラー】「RECRUITMENT AND EXPANSIONBy 1940 the Cathedral urgently needed to increase its number of volunteers on theWatch, and the initial group of around 40 soon grew to 84 people, allowing for12 men to work each shift.An appeal to the Royal Institute of British Architects (RIBA) included in its job description ‘Men from 40 to 60 who can walk upstairs and not fear heights’.The number of volunteers on the Watch grew to more than 300 people as the waradvanced. Men and women came from various backgrounds, bravely placing themselves in harm’s way to protect the Cathedral. Together, they forged a great sense of camaraderie during a time of crisis.」 【募集と拡大1940年までに、大聖堂は「見張り隊(Watch)」のボランティアを急いで増やす必要があった。最初は約40名だった隊はすぐに84名に増え、各シフトに12名を配置できるようになった。英国王立建築家協会(RIBA)による募集要項にはこう記されていた:「40歳から60歳までの、階段を上れること、高所を恐れない男性」。戦争が進むにつれ、見張り隊は300名以上にまで膨れ上がった。男性も女性も、さまざまな背景から集まり、大聖堂を守るために危険を顧みずに行動した。彼らはこの危機の時代に、強い仲間意識を育んでいった。】「Air Raid Wardens’ Post(防空監視員詰所)」に関連する展示で、女性の参加を伝える重要な資料。・防空監視員(Air Raid Warden)の女性。制服と帽子を着用し、腕章を付けて。“AIR RAID WARDENS’ POST — NOT FOR USE AS A PUBLIC SHELTER”(防空監視員詰所 ― 公共の避難所としての使用は不可)と。「‘…We are drilled everlastingly in the use of all our apparatus… One becomes, in time, a sort of Master of Hydrants – as of Arts – and an expert in stopcocks.It’s rather fun letting off a big hydrant, except when it knocks you over backwards anddrowns everybody near you. That’s why they call it wet drill.’— A.S.G. Butler, Watch team leader」 【私たちは、すべての装置の使い方について絶え間なく訓練を受けました。やがて誰もが『消火栓の達人』(まるで“文学修士”のような言い回しで)となり、止水栓の扱いの専門家にもなりました。大きな消火栓を開放するのはなかなか楽しいのですが、時に勢いで後ろに吹き飛ばされ、周囲の人をびしょ濡れにしてしまうこともあります。だからこれを『ウェット・ドリル(水びたし訓練)』と呼ぶのです。】「PROTECTING ST PAUL’S(セント・ポールを守る)」セクションの展示パネルで、 見張り隊(Watch)の緊張感ある様子を伝えていた。・被写体:ヘルメットをかぶった見張り隊の隊員たち。・状況:夜間の勤務前に待機している様子で、全員が壁際に腰かけ、上方を見つめている。・服装:防空服・ヘルメット・ベルト装備。中には懐中電灯や工具を帯びている隊員もいる。・背景:壁には掲示物や額縁がかかっている。通信機器らしき装置も見える。「Members of the Watch prepare for another night’s vigil as bombs fall on London.」【ロンドンに爆弾が降り注ぐ中、見張り隊の隊員たちは夜の警戒に備えている。】 大聖堂内部での見張り隊(Watch)の活動の様子。・場面:大聖堂内部、説教壇(pulpit)のそば。・人物:ヘルメットや帽子を着用した見張り隊のメンバーたち(約8名ほど)。・様子:隊員たちは集まって打ち合わせを行い、それぞれの持ち場(duty points)へ出発する 直前の状態。・雰囲気:緊張感の中にも秩序正しく、指示を待つ人々の真剣さが伝わる。「Members of St Paul’s Watch, including a warden, stand by the Cathedral’s pulpit,ready to go to their duty points.」 【聖堂の説教壇のそばに立つセント・ポール見張り隊の隊員たち。監視員を含め、それぞれの持ち場へ向かう準備を整えている。】・人物:見張り隊(Watch)の隊員。ヘルメットには「165」と番号が刻まれている。・所作:手に持つ小型ランプを点検している。・背景:セント・ポール大聖堂のドームの図面が掲示されているのが確認できる。「A member of the Watch inspects a lamp. A plan of St Paul’s Dome can be seen in the background. Volunteers had to familiarise themselves with the Cathedral’s complexlayout for moving around during nightly blackouts.」 【見張り隊の一員がランプを点検している。背景にはセント・ポール大聖堂のドームの図面が見える。ボランティアたちは、夜間の灯火管制(ブラックアウト)の中で移動するために、大聖堂の複雑な構造を熟知しておく必要があった。】通信の重要性 を示す場面。・右側:椅子に座った見張り隊の隊員が電話で報告をしている。膝の上にはノートを置き、 状況を記録している様子。・左側:ドアの前に立つ別の隊員。シルエットが浮かび上がっており、警戒を続けていることが わかる。・背景:壁には掲示物や通信関係の資料が貼られている。「Good communications were vital for the Watch. Advance locations were set up around the Cathedral equipped with telephones to report back to the Control Station in the Crypt.」【見張り隊にとって良好な通信は不可欠であった。大聖堂の周囲には前線拠点が設けられ、電話が備え付けられており、地下聖堂(クリプト)の管制室に報告が行えるようになっていた。】 「ST PAUL’S AS A REFUGE(避難所としてのセント・ポール)」 セクションの解説パネル。「ST PAUL’S AS A REFUGEDespite the constant threat of danger, the Cathedral continued to hold daily services,thanks to the dedication of the Watch and Cathedral personnel.Three wartime weddings were conducted there, and the annual Christmas Nativity andcarol concerts were maintained. At times of greatest danger from flying bombs,services were either cancelled or held in the Crypt.The preservation and continued use of St Paul’s maintained a sense of normal life and provided spiritual comfort for the community. This was vital for public morale during the darkest days of the war.」 【避難所としてのセント・ポール絶えず危険が迫る中にあっても、大聖堂では見張り隊と聖堂職員の献身により、日々の礼拝が続けられた。戦時中には3度の結婚式が行われ、毎年恒例のクリスマス礼拝劇やキャロルコンサートも維持された。飛行爆弾の脅威が最も大きい時には、礼拝は中止されるか、あるいは地下聖堂(クリプト)で行われた。セント・ポールが守られ、使われ続けたことは、日常生活の感覚を保ち、地域社会に精神的な安らぎをもたらした。それは戦争の最も暗い日々において、市民の士気を維持するうえで極めて重要であった。】「LIFE ON THE WATCH(見張りの生活)」 セクションの 大型タイトルパネル。背景にはヘルメット姿の見張り隊員のシルエットがうっすら映し出されている。「LIFE ON THE WATCH(見張りの生活)」 セクションの展示パネルで、化学兵器に関する訓練資料表形式の資料が展示されており、毒ガスの種類・性質・影響・治療法などがまとめられている。項目例:・ガスの種類(例:クロロピクリンなど)・外観・匂い・沸点・持続性・効果(症状)・応急処置(First Aid Treatment)「Members of the Watch were trained to identify different types of gas, their effects and treatments for victims. Ultimately, this knowledge was not put to use – Germany did not deploy gas as a method of attack.」【見張り隊はさまざまな種類のガスを識別し、その影響や被害者への処置方法を学ぶ訓練を受けていた。しかし最終的に、この知識が実際に使われることはなかった――ドイツは攻撃手段としてガスを使用しなかったためである。】 「Life on the Watch」では、隊員の日常(待機・巡回・訓練)を様々な角度から紹介しており、この資料はその中でも “訓練と備え” を象徴する展示であった。ガスマスク がテーマに。・ガスマスクが箱に入った状態で整列している様子。・奥には「No. 165」と書かれた隊員のヘルメットも見える。・物資として配備されたガスマスクは、大規模に備蓄されていたことが分かる。「It was widely feared that Germany would use poison gas in attacks on Britain. The government produced almost 38 million gas masks for the population.」【ドイツが毒ガスを用いた攻撃を英国に仕掛けることが広く恐れられていた。政府は国民のために約3,800万個のガスマスクを生産した。】 人物:ヘルメットをかぶった見張り隊(Watch)の隊員。胸にはベルトと懐中電灯を装備している。表情:上を見上げる真剣なまなざしから、爆撃下での緊張感が伝わってくる。服装:標準的な黒系の防空服。「An unidentified member of the Watch. Recruitment became harder as the warlengthened, as older members reluctantly retired and many people were enrolled in other parts of the war effort.」 【身元不明の見張り隊員。戦争が長引くにつれ、新たな志願者の確保は難しくなった。年配の隊員がしぶしぶ引退し、また多くの人々が戦争努力の他の部門に動員されたためである。】休憩時間の隊員たちの姿。場面:室内で複数の見張り隊員が集まり、ティーカップを手に休憩している。雰囲気:緊張感の強い任務の合間に、安らぎを求めている様子が伝わる。背景:本棚や家具があり、聖堂内のメンテナンス用の一室を利用しているように見える「During breaks, the Watch members gathered in the Cathedral maintenance workers’ mess room. Each night they listened to the news on the wireless for updates of raids andto hear speeches.」 【休憩時間には、見張り隊員たちは大聖堂の維持管理作業員用の食堂に集まった。毎晩、彼らはラジオで空襲の最新情報や演説を聞いた。】中央の石碑・石碑には金文字で 「REMEMBER BEFORE GOD」(神の御前において記憶せよ) と刻まれています。・これは、大空襲中に大聖堂を守った人々 ― 消防士、市民ボランティア、そして 「St Paul’s Watch」と呼ばれる特別監視団の犠牲と献身を記念する言葉です。この写真も「LIFE ON THE WATCH(見張りの生活)」 セクションの展示パネル場面:地下の一室に集まった見張り隊(Watch)の隊員たち。人物:左側に座る隊員たちはヘルメットをかぶり、ランプや装備を手にしている。中には 白衣姿の女性隊員も見える。右側:立っている隊員(おそらく指揮官)が書類を手に、指示や説明を読み上げている。雰囲気:真剣に聞き入る隊員たちの様子から、任務に就く直前のブリーフィング(作戦会議)の ように見える。「Members of the Watch gather on the steps awaiting their turn for patrol duty.」 【見張り隊の隊員たちが、巡回任務の順番を待ちながら階段に集まっている。】講義・娯楽活動 に関するもの。場面:椅子に座った見張り隊員たちが、一列に並んで真剣に講義を聞いている。服装:防空服や制服姿の者が多い。ヘルメットは床に置かれている。雰囲気:緊張というよりも、学びや文化活動に集中する落ち着いた様子。「The nightly practice drills could become monotonous, so a series of lectures wasorganised in 1944 to 1945 to entertain members of the Watch.Subjects covered ranged widely, from ‘Women in Romantic Poetry’ and‘The Solar System’ to ‘Pistols and Aluminium’. In the age before streaming TV, you really did have to make your own entertainment.」 【毎晩の訓練は単調になりがちだったため、1944年から1945年にかけて、見張り隊員を楽しませる目的で講義シリーズが企画された。講義のテーマは多岐にわたり、『ロマン派詩における女性』『太陽系』『拳銃とアルミニウム』といったものまであった。ストリーミング配信のない時代、娯楽は自分たちで工夫する必要があったのだ。】④最初「PREPARATIONS FOR WARThe first volunteers spent 1939 busily making preparations for protecting the Cathedralagainst the dangers that lay ahead.Water tanks were installed on the roof, and trap doors were cut to allow for the hosesthat would be needed to put out fires. Windows in several of the Cathedral’s chapels were blacked out to prevent enemy bombers finding their target.The tombs of Lord Nelson and the Duke of Wellington were among the historic featuresthat were bricked up to protect them from bomb damage. Other treasures were sent tothe National Library of Wales in Aberystwyth for safekeeping.」 【戦争への備え最初のボランティアたちは1939年、大聖堂をこれから襲うであろう危険から守るため、慌ただしく準備に追われた。屋根には消火用の水槽が設置され、放水用ホースを通すための小扉が切られた。大聖堂内のいくつかの礼拝堂の窓は黒く塗りつぶされ、敵機が目標を見つけにくくする工夫がなされた。ネルソン提督やウェリントン公の墓など歴史的に重要なモニュメントは、爆撃による損傷から守るために煉瓦で覆われた。その他の貴重品は、安全のためアベリストウィスにあるウェールズ国立図書館へ移送された。】写真の展示パネルには大きく「AFTER THE WAR(戦後)」と書かれており、第二次世界大戦後のセント・ポール大聖堂とロンドンの再建・復興に関する展示セクションを示していた。下部に描かれている図・EXHIBIT PLAN(展示配置図) が描かれています。・円形に配置された展示の各テーマが並んでおり、その一部として「AFTER THE WAR」が 位置づけられています。・他にも INTRODUCTION(導入), THE WATCH, THE BLITZ, IN REMEMBRANCE(追悼) などが示されており、展示全体が円環状のストーリーを形作っていることがわかります。第二次世界大戦後の瓦礫からの復興作業をする姿。「AFTER THE WARIn London, and in cities across Britain and Europe, a long process of rebuilding andregeneration began. These workmen, photographed in 1950, ...」 【戦後ロンドンをはじめ、イギリスやヨーロッパ各地の都市で、長い復興と再生の過程が始まりました。この写真は1950年に撮影された作業員たちの姿です。】瓦礫処理や復興作業の場面ではなく、戦後数年を経てロンドンに平穏な日常が戻りつつあったことを象徴的に捉えた一枚です。背景のセント・ポールの大ドームと、手前で食事を取る市民の姿の対比が印象的。「AFTER THE WARLunch break at St Paul’s, 1952. Normal life gradually returned to the City after VE Day.」【戦後 1952年、セント・ポール大聖堂での昼休みの様子。VEデイ(対独戦勝記念日)後、次第に日常生活がシティに戻ってきました。】 この写真は、戦後のロンドンにおける王室とセント・ポール大聖堂の象徴的な結びつきを示しており、王室が「セント・ポール監視団」の働きを公式に認めた重要な瞬間を記録しているのだと。「King George VI and Queen Elizabeth The Queen Mother leaving the Cathedralafter a VE Day service. They are flanked by two lines of volunteers from the Watch.The Dean can be seen at the foot of the stair.」 【ジョージ6世国王とエリザベス王妃(クイーン・マザー)が、ヨーロッパ戦勝記念日(VE Day)の礼拝後に大聖堂を後にする場面。彼らの両脇には、セント・ポール監視団(St Paul’s Watch)のボランティアが二列に並んで護衛している。階段の下には大聖堂の主任司祭(Dean)の姿も見える。】戦後のセント・ポール大聖堂と「St Paul’s Watch(セント・ポール監視団)」に関連する展示資料。・左側(夕食メニュー)・右側(礼拝プログラム)・下部キャプション(展示解説)「‘From this dark period, St Paul’s Cathedral has emerged greater than ever.Amidst surrounding ruin and devastation reaching to its very walls the beautiful Domehas continued to dominate London, a daily inspiration to thousands of its sufferingcitizens and a symbol of hope throughout the world.’Godfrey Allen,St Paul’s Watch Commander」【「この暗黒の時代から、セント・ポール大聖堂はかつてないほど偉大な姿で現れた。周囲の廃墟と、壁にまで迫る破壊の中にあっても、美しいドームは依然としてロンドンを見下ろし続け、苦しむ市民の何千人にとっても日々の励ましとなり、そして世界中に希望の象徴を示した。」― ゴドフリー・アレンセント・ポールズ・ウォッチ司令官】 ⑥Dean W.R. Matthews(セント・ポール大聖堂の学長)による1946年の回想「…one of our comrades expressed the opinion that St Paul’s Watch was ‘the best club in London’ and I doubt not that many of us will forget what a bursting bomb sounds like long before we forget the cheerful fellowship we enjoyed.”— Dean W.R. Matthews, 1946」 【…仲間の一人は『セント・ポールの見張り隊はロンドンで最高のクラブだ』と語った。そして私も、多くの者が爆弾の炸裂音を忘れるよりも先に、我々が享受した陽気な仲間意識を忘れることはないだろうと思う。W.R.マシューズ学長、1946年】「I felt a lump in my throat because, like so many people, I felt that while St Paul’s survived, so would we.”— Dorothy Barton, wartime office worker」 【胸が熱くなったのは、他の多くの人々と同じように、セント・ポールが生き残るなら、私たちもまた生き残れるのだと感じたからです。―― ドロシー・バートン(戦時中の事務職員)】中央ゾーン(PEOPLE STORIES)・テーマ:「人々の物語」・内容:実際にセント・ポールを守った人々の証言、体験談、名前。・役割:外周展示を人間的な視点で結びつける中心要素。Dr. Carlyle Thornton Potter(カーライル・ソーントン・ポッター博士) を紹介する展示。「DR CARLYLE THORNTON POTTERChristian physician Carlyle Potter was a close neighbour of St Paul’s Cathedral.During World War II he helped to protect St Paul’s Cathedral when it was underthreat as a member of St Paul’s Watch.He worked at various London hospitals and joined the Watch to supplement the quotaof 40 to 50 men required to guard St Paul’s. In the crypt, they formed a small medicalunit, and Potter was one of the medical men giving emergency first aid, supported by Miss Jessie Jacob, a hospital dispenser.Dr Potter had a lifelong illness with angina but carried on without fuss. His bravery andconstant cheerful reliability also endeared him to his fellow Watch members. He showedgreat courage, continuing to serve for many years.」 【カーライル・ソーントン・ポッター博士クリスチャンの医師カーライル・ポッター博士は、セント・ポール大聖堂の近隣に住んでいました。第二次世界大戦中、大聖堂が脅威にさらされていた時、彼は「セント・ポール防衛隊(St Paul’s Watch)」の一員として大聖堂の防衛に参加しました。博士はロンドンのいくつかの病院で勤務しつつ、防衛隊に志願しました。当時、セント・ポールを守るためには40〜50名が必要とされ、地下聖堂(クリプト)には小規模な医療班が設けられました。ポッター博士はその中で救急処置を担当し、病院の調剤師であるジェシー・ジェイコブ嬢の協力を受けました。博士は生涯狭心症を抱えていましたが、決して弱音を吐くことなく活動を続けました。その勇敢さ、明るい態度、揺るぎない信頼性は仲間の防衛隊員たちに深い敬愛をもたらしました。彼は大いなる勇気を示し、長年にわたり奉仕を続けたのです。】この展示は 「爆発物処理班がセント・ポールを救ったエピソード」 で、特に市街戦での防衛の象徴的な場面 と。「George WylieSapper George Wylie was among the first to be awarded the George Cross, a medalrecognizing acts of bravery by civilians as well as military personnel.Together with Lieutenant Robert Davies and four other Royal Engineers, George helpedsave St Paul’s from an unexploded bomb. On 12 September 1940, a one-ton bomb struck near the Cathedral’s west end, also breaking a gas main.For three days, George’s team carefully worked to dig out the bomb, eventually reaching it 27 feet underground. The bomb was winched to the surface and transported toHackney Marshes, where it was safely detonated.After their success, Canon Cockin of St Paul’s treated the team to a hearty lunch in gratitude for their dangerous but vital work.」 【ジョージ・ワイリー工兵ジョージ・ワイリーは、ジョージ・クロス勲章(市民および軍人の勇敢な行為を讃える勲章)の最初の受章者の一人でした。1940年9月12日、西側の大聖堂近くに1トンの不発弾が落下し、ガス管を破裂させました。ワイリーはロバート・デイヴィス中尉や他の4名の王立工兵隊と共に、大聖堂を救うために活動しました。彼らのチームは3日間かけて慎重に掘削を進め、地下約27フィートに埋まっていた爆弾を掘り出しました。その後、爆弾は地上に引き上げられ、ハックニー・マーシュで制御爆破されました。作業成功の後、セント・ポールのコキン司祭が彼らを昼食に招き、その危険で重要な働きに感謝を示しました。】 文学・芸術の分野からセント・ポールを守った人 という位置づけの人物と。「Sir John Betjeman CBEOne of the volunteers for the Watch was the renowned poet, writer, and broadcasterJohn Betjeman.As an architectural critic and enthusiast, Betjeman deeply admired the design and historical importance of St Paul’s Cathedral. In his writings, he often celebrated the Cathedral as a symbol of London’s endurance and architectural legacy.His efforts to help protect St Paul’s during the war reflected his lifelong commitment topreserving Britain’s historic buildings. He later became a leading campaigner for savingVictorian and Edwardian architecture.Betjeman devoted much of his life to promoting the Cathedral’s history, increasing public awareness, and strengthening appreciation for St Paul’s and other landmarks.His contributions were recognised when he was named Poet Laureate in 1972, a role he held until his death.」【サー・ジョン・ベッチェマン CBEウォッチ隊の志願者の中には、20世紀を代表する詩人・作家・放送人であるジョン・ベッチェマンもいました。建築評論家であり愛好家でもあった彼は、セント・ポール大聖堂の設計と歴史的重要性を深く敬愛しました。彼の著作には、大聖堂をロンドンの不屈の象徴、そして建築遺産の象徴として称えるものが多くあります。戦時中にセント・ポールを守る活動は、英国の歴史的建造物を保存するという彼の生涯の情熱と一致していました。戦後には、ヴィクトリア朝・エドワード朝時代の建築を保存するための著名な活動家としても知られるようになりました。彼は大聖堂の歴史を広めることに生涯を捧げ、一般の人々の理解と評価を深めるために尽力しました。その功績が認められ、1972年に桂冠詩人(Poet Laureate)に任命され、生涯その職にありました。】 救護(first aid)と戦後の友の会を設立した女性・Elfreda Audsley。「Elfreda AudsleyElfreda Audsley was a gifted writer and illustrator, best known for her children’s bookQuick Quack (1931). Born and raised in London, she was working as a part-time journalist when the Second World War began.At first, she volunteered as an Air Raid Warden in Eltham. By 1943, however, she had moved to Kensington and joined the St Paul’s Watch as part of its first aid team.After the war, Elfreda played a key role in founding the “Friends of St Paul’s” group, which developed from the close relationships built among members of the Watch. Since its establishment, the Friends have contributed greatly to the preservation, life, and wellbeing of St Paul’s Cathedral.」【エルフリーダ・オーズリーエルフリーダ・オーズリーは才能ある作家でありイラストレーターで、特に児童書『クイック・クアック』(1931年)で知られています。ロンドン生まれの彼女は、第二次世界大戦が勃発したとき、パートタイムのジャーナリストとして働いていました。当初はエルサムで空襲監視員(Air Raid Warden)として志願しましたが、1943年までにはケンジントンに移り住み、セント・ポール監視隊(St Paul’s Watch)の救護班の一員として活動しました。戦後、彼女は「フレンズ・オブ・セント・ポールズ(Friends of St Paul’s)」という団体の設立に尽力しました。これは、監視隊のメンバーたちの間で築かれた強い絆から生まれたもので、この団体は創設以来70年以上にわたり、セント・ポール大聖堂の保存や活動、福祉に大きな貢献を果たしてきました。】 「WALTER GODFREY ALLENNo one had a better understanding of the complex layout of St Paul’s Cathedral thanArchitect and Surveyor, Godfrey Allen. He was an automatic choice to replacethe popular Commander of the newly-formed Watch, at an emergency meeting held in April 1941.Godfrey had dedicated himself to protecting the Cathedral, and his determination earned him the nickname ‘the Terrier’.He calmly took charge, organizing the Watch like a military unit, although a health problem soon after kept him from patrolling at the same intensity.One of the founding members of the Friends, Godfrey retired in 1956 after almost 30 years’ service to St Paul’s. When he died in 1961, aged 65, a memorial was unveiled at the Cathedral in his honour.」 【ウォルター・ゴッドフリー・アレンセント・ポール大聖堂の複雑な構造を最もよく理解していたのは、建築家で測量士でもあったウォルター・ゴッドフリー・アレンでした。1941年4月、緊急会議において、新たに結成された監視隊(Watch)の人気指揮官の後任として、彼が当然のように選ばれました。アレンは大聖堂の防衛に献身し、その強い決意から「テリア犬(The Terrier)」の異名を得ました。彼は冷静に指揮を執り、監視隊をまるで軍隊のように組織しました。しかしその後、健康上の問題により、以前のように頻繁な巡回はできなくなりました。「フレンズ・オブ・セント・ポールズ(Friends of St Paul’s)」の創設メンバーの一人でもあったアレンは、約30年の奉仕の後、1956年に引退しました。1961年に65歳で亡くなった際には、その功績を称えて大聖堂に記念碑が建立されました。】W.R. Matthews 教 dean。「Dean of St Paul’s from 1934 to 1967.A progressive character who had reorganised life at St Paul’s into a vibrant centre of activity by the time war broke out.Very much hands on during the Blitz, working alongside Watch volunteers, tackling fires and fostering community spirit.His book St Paul’s Cathedral in Wartime 1939–1945 provides one of the most vividaccounts of life on The Watch.After the war, Dean Matthews was a pivotal figure in establishing the Friends of St Paul’s and served as Chair of the Friends until he retired in 1967.」 【1934年から1967年までセント・ポール大聖堂のディーン(院長)を務めた。進歩的な性格の持ち主で、戦争が始まる頃にはセント・ポールを活気ある活動の中心に再編成していた。ブリッツ(ロンドン大空襲)の際には、消防活動や地域精神の育成において監視隊(Watch)のボランティアと共に現場で活動した。著書『戦時下のセント・ポール大聖堂 1939–1945』は、監視隊の日々の生活を最も生き生きと伝える記録の一つである。戦後は「フレンズ・オブ・セント・ポールズ(Friends of St Paul’s)」の設立に中心的役割を果たし、1967年の引退まで会長を務めた。】この三連パネルも 「PEOPLE STORIES(人々の物語)」ゾーンの展示・白黒写真+名前リスト で構成されており、当時の St Paul’s Watch メンバーを記録するもの・上部には見守り隊(Watch)に属していた人々が集まる場面の大きな写真。・下部には 名簿形式で個人名 が並んでおり、これは「人々の物語」を象徴的に示す資料。・タイトルは 「Members of the Watch 1939–1945」(1939〜1945年の監視隊メンバー)。・上部は夜間勤務中の St Paul’s Watch の姿を写した白黒写真。・下部には 名簿形式 で多くの個人名が記されており、実際に従事した人々を顕彰する意図がある。・先ほどの三連パネルと同じく、「無名の仲間たち」を記録する集合展示。円形に配置された英文が。「WE RESOLVE IN VICTORY OR DEFEAT TO PERSEVERE IN FREEDOM AND JUSTICEAND IN GOOD FAITH AND GOODWILL TO ALL PEOPLES」 【勝利にあっても敗北にあっても、私たちは自由と正義を堅持し、すべての人々に誠実さと善意をもって接することを誓う。】と。これは 第二次世界大戦の精神的誓い を象徴する言葉で、セント・ポール大聖堂前にある追悼碑の一部です。円形に刻むことで「永続性」「普遍性」「連帯」を表していると解釈されます。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.21
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その114): ロンドン散策記・St. Paul's Cathedral・セントポール大聖堂-3
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクセントポール大聖堂の裏の東側、チェーニー・レーン(Cheyne Lane)沿いの路面に八角形の石畳の囲みの中に「HERE STOOD PAUL’S CROSS」と。 ・ポールズ・クロス (Paul’s Cross) は、セント・ポール大聖堂の敷地北東角に設けられていた 屋外説教壇。・13世紀頃から設置され、ロンドン市民の前での説教や布告、政治的・宗教的演説の場 として知られた。・宗教改革期には、王権の政策や宗教的論争を市民に直接伝えるための重要な舞台となり しばしば群衆を集めた。・1643年、ピューリタン革命の混乱の中で破壊され、その後は再建されなかった と。現在の大聖堂(クリストファー・レン設計)が完成した後も、市民の記憶に残る歴史の象徴として、この場所を示す石畳が設置された。八角形は「説教壇の基壇の形」をイメージしており、訪れる人々に「ここがかつてロンドンの声が響いた場所」であることを思い起こさせるのであった。PAUL’S CROSSをネットから。その近くから、St Paul's Cathedral School(セント・ポール大聖堂付属学校) の校舎に付属している尖塔を。元 St Augustine, Watling Street 教会の鐘楼・尖塔。・場所: セント・ポール大聖堂のすぐ北側、フォスター・レーン(Foster Lane)沿い。・設計者: クリストファー・レン卿。・第二次世界大戦のロンドン大空襲(Blitz)で教会本体が破壊され、塔だけが残された。・戦後、廃墟となった教会跡は撤去され、残った塔がランドマークとして保存された。・その周辺に St Paul’s Cathedral School の新校舎が建てられ、現在は校舎と塔が一体化して 見える形になっているのだ と。・尖塔の特徴: ・独特の「洋梨型(ルイ15世風)」の尖塔を持ち、レンの設計の中でも珍しい造形。 ・三層構造で、下部は四角塔、中段は八角、上段はバロック的な曲線をもつ尖塔。 ・先端には風見鶏が立つ。ベインブリッジ・コプナル(Bainbridge Copnall, 1903–1973)作『Becket』。・『Becket』は、カンタベリー大司教トマス・ベケットの殉教を表現した作品。・トマス・ベケットは1170年にカンタベリー大聖堂で暗殺され、信仰と権威の象徴的存在と なった。・この像は1973年にロンドン市によって取得され、セント・ポール大聖堂北側の庭園に 設置されていた。「BECKETBYBAINBRIDGE COPNALLACQUIRED BYTHE CORPORATION OF LONDON1973」 【ベケット作者:ベインブリッジ・コプナルロンドン市によって取得1973年】・黒いブロンズ製で、躍動的にねじれた人体像。・手足は大きく表現され、特に手のポーズが劇的。・頭部は後方へ反り返り、殉教の苦悶や力強さを表している。・彫刻は抽象的・表現主義的で、リアルな細部よりも「感情や瞬間の迫力」が強調されて。顔をクローズアップして。・頭部が大きく後ろに仰け反り、顔の造形は抽象化されながらも「苦悶」「叫び」の表情を 感じさせる。・口元は深い切り込みで表現され、声を発しているかのように見える。・左手は大きく掲げられ、手のひらを開く仕草は「抵抗」「訴え」「神への祈り」のいずれも 連想させる。・表現主義的な強調によって、殉教の瞬間の痛みと精神性がダイレクトに伝わって来る。 この姿は、1170年にカンタベリー大聖堂で暗殺されたトマス・ベケット大司教が殉教する 瞬間を表しており、・顔の歪み=苦しみと同時に信仰を貫く決意・開かれた手=「神に委ねる」「無抵抗の殉教」 を象徴的に表していると考えられる と。この胸像は ジョン・ダン(John Donne, 1572–1631) を表した記念像。設置場所:ロンドン、セント・ポール大聖堂前の庭園(セント・ポール大聖堂南側の敷地内)。人物:ジョン・ダンはイングランドの著名な詩人であり、後に聖職者となって セント・ポール大聖堂の首席司祭(Dean of St Paul’s) を務めた。特徴:鋭い眼差しと引き締まった頬、長い顎髭が力強く表現され、彼の精神性や知性を象徴。「JOHN DONNEpoet and divine1572 – 1631」 【ジョン・ダン詩人にして聖職者1572年 – 1631年】近づいて。「詩人であり聖職者であったジョン・ダン」を顕彰しており、彼の生没年(1572–1631)が刻まれていた。ロンドンのセント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral) の特徴的な大ドームも見納めか。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)の北東側にあった「St Lawrence and Mary Magdalene Drinking Fountain」。1. 建設の目的 ・この噴水は 19世紀のヴィクトリア朝時代(1866年) に設置されました。 ・当時のロンドンは産業革命の影響で人口が急増し、衛生や飲料水の確保が重要な社会問題と なっていました。 ・公共の「飲料水噴水(Drinking Fountain)」は、清潔な水を無料で市民に提供する目的で 設置されました。2. 寄贈者 ・この噴水は サムエル・ガーニー卿(Sir Samuel Gurney) の資金援助によるものです。 ・ガーニー卿は慈善活動家であり、特に「公共飲料水運動」に深く関わっていました。 ・彼は Metropolitan Drinking Fountain and Cattle Trough Association(MDFA) という 団体の支援者で、この団体はロンドン市内に多数の公共水飲み場を設置しました。3. デザインと建築 ・設計者は E. C. Robins(エドワード・チャールズ・ロビンス)。 ・建築様式は ゴシック・リヴァイヴァル(Gothic Revival)。 ・噴水の上部には 聖マグダラのマリア(Mary Magdalene)の像 が置かれています。 ・この像の設置によって、噴水は「St Lawrence Jewry(隣接する教会)」と 「Mary Magdalene」の双方にちなんだ名称となりました。4. 設置場所 ・場所は セント・ポール大聖堂の北東側(Carter Lane と Cannon Street の交差付近)。 ・隣接する St Lawrence Jewry 教会 が名前の一部となっている理由です。 ・現在は周囲の近代建築の中に残されており、観光名所にもなっています。5. その後の経緯 ・当初は飲料水供給の役割を担っていましたが、現在は実際に水を供給していません。 ・1970年代に修復が行われ、ロンドン市の歴史的モニュメントの一部として保存されています。 ・英国指定建造物(Grade II listed building)に登録されており、文化財として保護 されています。「St Lawrence and Mary Magdalene Drinking Fountain」は、・1866年に慈善家サムエル・ガーニー卿の寄贈で建てられ、・ロンドン市民に清潔な飲料水を提供する目的を持ち、・ゴシック様式の美しい装飾と聖マグダラのマリア像を備えた公共水飲み場。ブロンズのレリーフ(浮彫)に近づいて。・左側には 母親と幼子が座り、幼子は母の腕に抱かれています。・右側には 長い髪とひげの男性が立ち、杖(あるいは棒)で岩を指しています。・背後には大きく割れた岩から水が流れ出ているように見えます。 これは旧約聖書の有名な場面で、モーセが荒野で岩を打ち、水を湧き出させた奇跡 (出エジプト記 17章、民数記 20章)を表現していると考えられます。イスラエルの民が荒野で渇き、モーセに訴えたとき、神の命によりモーセが杖で岩を打つと、水が湧き出し、人々を潤しました と。これでもかと。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral) の西正面(West Front)を正面から。セント・ポール大聖堂の南側からテムズ川方向(ミレニアム・ブリッジ方面)を。1.正面奥に見える高い煙突状の建物・これは テート・モダン(Tate Modern) 美術館。・もともと「バンクサイド発電所」として1930年代に建設され、2000年に現代美術館へ改装 されました。2.通りの雰囲気・人々が集まっているのは「Peter’s Hill(ピーターズ・ヒル)」という遊歩道。・セント・ポール大聖堂とミレニアム・ブリッジを直線で結ぶために整備された歩行者専用ルート。3.右手の赤レンガの建物・セント・ポール大聖堂の隣接建物群の一つで、オフィスや関連施設が入居しています。・建物前に黒い銅像(腰を下ろす人物像)が見えたが、これは 「The National Firefighters Memorial(全国消防士記念碑)」。「The National Firefighters Memorial(全国消防士記念碑)」3体の消防士像が、瓦礫の中で消火・救助活動をする姿を表現。・建立年:1991年(当初は「Blitz Memorial」として第二次世界大戦の消防士を追悼)・拡張:2003年に「殉職したすべての消防士」を対象に改修され、正式に 「National Firefighters Memorial」と命名。・場所:セント・ポール大聖堂南側、ミレニアム・ブリッジへ向かう Peter’s Hill の途中右側。・デザイン:彫刻家 John W. Mills による青銅像。 ・3体の消防士像が、瓦礫の中で消火・救助活動をする姿を表現しています。・背景:特に1940年のロンドン大空襲(The Blitz)で殉職した多くの消防士を悼むために 建てられたもの。・右に見える高い黒い煙突 → Tate Modern の旧発電所時代のシンボル的な煙突。・Tate Modern の後方に見えるガラス張りの三角屋根の高層ビル → サザークやサザーク・ブリッジ寄りの再開発地区の建物群再び、旧チャプター・ハウス跡にあった解説パネル。「These gardens are laid out in the footprint of the Chapter House and Cloister of Old St Paul's Cathedral which was destroyed by the Great Fire of London in 1666. The cloister was open on two sides. The Chapter House and Cloister, designed by the royal architect Inigo Jones in 1633, were regarded as the finest examples of Renaissance architecture in London and in England. Both the octagonal Chapter House and the square Cloister were reconstructed following the medieval buildings on the same site. It was here that meetings of the Cathedral's governing body, the Dean and Chapter, were held. The Chapter House was a large building with a central pillar supporting its high vaulted roof.」【この庭園は、旧セント・ポール大聖堂のチャプター・ハウス(参事会堂)とクロイスター(回廊)の跡地に整備されたものです。旧大聖堂は 1666 年のロンドン大火で焼失しました。クロイスターは二辺が開放されていました。チャプター・ハウスとクロイスターは王室建築家イニゴー・ジョーンズによって1633 年に設計され、当時のロンドン、そしてイングランドにおけるルネサンス建築の最高傑作の一つと考えられていました。八角形のチャプター・ハウス四角形のクロイスターは同じ場所にあった中世の建物を継承して再建されたものでした。ここで大聖堂の運営組織であるディーン(首席聖職者)とチャプター(参事会)の会合が開かれていました。チャプター・ハウスは大きな建物で、中央の柱が高いヴォールト天井を支えていました。】 セント・ポール大聖堂の 旧クロイスター(回廊)とチャプターハウス(参事会会堂) を描いた古い版画(挿絵)。DOMUS CAPITULARIS S. PAULI・聖パウロ参事会会堂 と。時間があったので、最後に再び屋外特設展示コーナーへ。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)西側にあった解説パネルへ。旧チャプター・ハウス跡の展示会場。展示テーマ・中心テーマ: 第二次世界大戦(特に1940–41年のロンドン大空襲:The Blitz)におけるセント・ポール 大聖堂の役割と象徴性。・主要要素: ・ドームが煙の中に浮かび上がる有名な写真 ・消火隊・市民ボランティアの活動 ・「セント・ポールの守護者(St Paul’s Watch)」と呼ばれる防衛組織の記録 ・戦火をくぐり抜けた聖堂が持つ精神的象徴としての意味「SAVING ST PAUL'STHE WATCHAND THE SECOND WORLD WAR」 【セント・ポール大聖堂を守れ火消し隊(ザ・ウォッチ)そして第二次世界大戦】 この展示は、第二次世界大戦中に空襲からセント・ポール大聖堂を守るために結成された 「セント・ポールズ・ウォッチ(St Paul’s Watch)」 という市民ボランティアの活動を紹介していた。彼らは爆弾や焼夷弾が落下した際に、屋根裏やドーム上で消火や延焼防止にあたり、大聖堂を戦火から救った。特に「ブリッツ(ロンドン大空襲)」の間、セント・ポールが瓦礫に埋もれず立ち続けたことは、ロンドン市民にとって大きな精神的象徴になったのだと。「INTRODUCTION」 「NEW BEGINNINGS: THE FRIENDS OF ST PAUL’SWith the war over, the St Paul’s Watch was no longer needed. It was disbanded aftera farewell dinner in October 1945, when heartfelt toasts were made before themembers went their separate ways.But this was not the end of the story. Life on the Watch had created such strong, lastingties of friendship and community, that some of its members decided to create a neworganisation: The Friends of St Paul’s Cathedral.Founded by Dean Matthews in 1952, the Friends raised funds for the restoration of theCathedral and promoted knowledge of its history and ongoing work. Some 83 membersattended the first meeting, but numbers grew rapidly.The Friends are a unique community who come together to enjoy our music, heritage and spiritual learning – some even volunteer with us. Membership starts at £25 a year.Find out more about joining the Friends by visiting stpauls.co.uk」 【導入新たな始まり:セント・ポール大聖堂の友の会戦争が終わり、「セント・ポール監視隊(St Paul’s Watch)」はもはや必要とされなくなりました。1945年10月の送別会をもって解散し、心からの乾杯の後、隊員たちはそれぞれの道へと散っていきました。しかし、これで物語は終わりではありませんでした。監視隊での生活によって強く永続的な友情と共同体意識が育まれたため、その一部の隊員たちは新たな組織「セント・ポール大聖堂の友の会(The Friends of St Paul’s Cathedral)」を設立することを決意したのです。1952年にマシューズ学長によって設立された友の会は、大聖堂の修復のための資金を集め、その歴史や継続的な活動についての知識を広めました。最初の会合には83人が参加しましたが、その後会員数は急速に増加しました。友の会は独自の共同体であり、音楽、遺産、そして霊的な学びを楽しむために集います。一部の人々はボランティアとして活動にも参加しています。会員費は年間25ポンドから。詳細は stpauls.co.uk をご覧ください。】INTRODUCTIONこの展示は、セント・ポール大聖堂の防衛活動(St Paul’s Watch)から、戦後の追悼と国際的な記念の場の創出へと続く流れを示しているもの。「IN REMEMBRANCEThe aftermath of the war held many challenges: reconstruction, more food rationing,and reintegration for those returning after five long years away. Time was needed too,for mourning the missing, and the dead.The St Paul’s Watch was commemorated with a dedication on a flagstone insidethe Cathedral. In 1946, a fund was set up to build the American Memorial Chapel,in tribute to the 28,000 American servicemen and women who lost their lives duringthe Second World War while stationed in Britain.Watch Commander Godfrey Allen was one of the architects who designed the Chapel.It was located in the Apse, which was reconstructed after sustaining bomb damageduring the war. The American Memorial Chapel was dedicated in November 1958with a service attended by the Royal Family.」 【追悼戦争が終わった後、人々は多くの課題に直面しました。復興、食料配給の継続、そして5年に及ぶ長い年月を経て帰還した人々の社会復帰です。また、行方不明者や戦死者を悼む時間も必要でした。セント・ポールの監視団(St Paul’s Watch)は、大聖堂内部の石畳への献辞によって記念されました。1946年には、アメリカ記念礼拝堂(American Memorial Chapel) 建設のための基金が設立されました。これは第二次世界大戦中、イギリスに駐留し戦死した28,000人のアメリカ兵士たち に捧げられたものです。礼拝堂の設計者のひとりは監視団の指揮官 ゴドフリー・アレン(Godfrey Allen) でした。礼拝堂は戦争中に爆撃被害を受けた内陣(アプス)に設けられ、修復の一環として再建されました。アメリカ記念礼拝堂は1958年11月に献堂式が行われ、王室の参列を受けました。】展示内容の案内図。1. 導入(INTRODUCTION)・目的:展示のテーマを説明し、訪問者を「戦中のセント・ポール」の世界へ導く。・内容:大聖堂が第二次世界大戦中に直面した脅威の概要。2. ロンドン大空襲(THE LONDON BLITZ)・焦点:1940~41年のロンドン大空襲。・展示内容: ・有名な「煙の中に浮かぶドーム」の写真。 ・市街地の破壊と人々の恐怖。3. 戦中の危険と被害(DANGER & DAMAGE)・焦点:セント・ポールを襲った爆撃の実態。・展示内容: ・爆弾による損傷の痕跡。 ・焼夷弾が屋根に落ちた記録。 ・爆破の危機から奇跡的に守られた出来事。4. セント・ポールの防衛(PROTECTING ST PAUL’S)・焦点:「St Paul’s Watch」と呼ばれた市民防衛隊。・展示内容: ・消火活動の様子(屋根での水バケツリレー)。 ・ボランティア市民の奮闘。 ・当時の記録写真や証言。5. 見張りの生活(LIFE ON THE WATCH)・焦点:大聖堂を守る人々の日常。・展示内容: ・夜通し続いた待機と緊張感。 ・防空壕や仮眠の様子。 ・彼らが残した日記やメモ。6. 戦後(AFTER THE WAR)・焦点:戦後復興と大聖堂の象徴的意味。・展示内容: ・国民に希望を与えた「セント・ポールの不屈のドーム」。 ・戦争終結後の追悼と記憶の継承。7. 中央ゾーン(PEOPLE STORIES)・テーマ:「人々の物語」・内容:実際にセント・ポールを守った人々の証言、体験談、名前。・役割:外周展示を人間的な視点で結びつける中心要素。この展示は、第二次世界大戦中の ロンドン大空襲・THE LONDON BLITZ(1940–41) におけるセント・ポール大聖堂の運命をテーマとしたものです。特に、・セント・ポールズ・ウォッチ(監視隊) の活躍、・焼夷弾による被害と市民・消防隊による消火活動、・爆撃後の瓦礫の中で奇跡的に残った大聖堂の姿、・そして戦後の再建と象徴的役割 を段階的に紹介していた。展示の「THE LONDON BLITZ(ロンドン大空襲)」 セクションで最も有名な場面のひとつ。・大聖堂のドームが煙の中に浮かび上がっている。・これは 1940年12月29日夜、ロンドン大空襲(Blitz)の最も激しい日 「Second Great Fire of London(二度目のロンドン大火)」の記録。「This iconic photograph was taken by Herbert Mason at the height of the London Blitz,on 30th December 1940. It immediately became an enduring symbol of Britain’swartime bravery and resilience.In Nazi Germany, the same image was used as propaganda to convince the populationthat St Paul’s had been destroyed — false evidence that the Luftwaffe’s bombing raidswere a success.」 【この象徴的な写真は、1940年12月30日、ロンドン大空襲の最中にハーバート・メイソンによって撮影された。写真は瞬く間に、イギリスの戦時下における勇気と不屈の象徴となった。一方、ナチス・ドイツでは同じ写真がプロパガンダとして利用され、セント・ポールが破壊されたかのように市民に信じ込ませる偽の証拠として使われた。】このパネルは「THE LONDON BLITZ IN NUMBERS(数字で見るロンドン大空襲)」 をテーマとする統計的な展示解説。「THE LONDON BLITZ IN NUMBERS1 millionHouses and flats damaged or destroyed in London. One in every six Londoners was made homeless at some point during the Blitz.180,000People per night sheltered in the London Underground system during the Blitz.100,000Incendiary bombs plus 24,000 high explosive bombs were dropped on London injust one night, between 6pm on December 1940 and the early hours of the next morning.43,500Civilians killed during the first eight months of attacks, with nearly half of Britain’stotal civilian deaths for the whole war occurring during the Blitz.2,136Estimated number of fires recorded by the London Fire Brigade.」【数字で見るロンドン大空襲100万ロンドンで損壊または破壊された住宅の数。空襲の間に、ロンドン市民6人に1人が住む家を失った。18万ロンドン地下鉄に毎晩避難した人々の数。10万焼夷弾に加え、24,000発の高性能爆弾が、1940年12月のある夜18時から翌朝早くまでの一晩でロンドンに投下された。43,500最初の8か月間の空襲で死亡した民間人の数。これは戦争全体におけるイギリス民間人死者数のほぼ半数に相当する。2,136ロンドン消防隊が記録した推定火災件数。】 「350September and November 1940.88German aircraft were shot down over London, and 22 RAF planes were lost,according to Air Ministry reports.57Nights of consecutive bombing, from 7th September 1940.」【3501940年9月から11月のブリッツ最盛期における空襲警報の回数。88空襲中にロンドン上空で撃墜されたドイツ軍機の数。一方で、RAF(英国空軍)の戦闘機22機が失われた(英国航空省の報告による)。571940年9月7日から続いた、連続爆撃の日数。】 「GERMANY’S WEAPONS OF WAR(ドイツの戦争兵器)」 を解説する展示「GERMANY’S WEAPONS OF WARThe Luftwaffe employed a variety of weapons and tactics to target London andother British cities.Lightweight incendiary bombs were widely used to start fires that could spread toneighbouring buildings. Mines and larger high-explosive bombs were dropped tomaximise damage.By 1944, among the most deadly threats were the ‘doodlebug’ V1 and V2 high-speedmissiles. ‘V’ was short for Vergeltungswaffe, meaning ‘vengeance weapon’. These lethalrockets were made by prisoners in Nazi concentration camps. Conditions there wereso appalling that more people died making the rockets than those killed by themin air raids. More than 500 V2 rockets were used in attacks on London.」 【ドイツの戦争兵器ルフトヴァッフェ(ドイツ空軍)は、ロンドンや他の英国都市を攻撃するためにさまざまな兵器と戦術を用いた。軽量の焼夷弾は広く使用され、隣接する建物へと火災を拡大させた。さらに、地雷や大型の高性能爆弾が投下され、被害を最大化した。1944年までには、最も致命的な脅威の一つが「ドゥードルバグ(ブンブン虫)」と呼ばれたV1およびV2高速ミサイルであった。「V」とはドイツ語・Vergeltungswaffe(報復兵器)の略である。これらの致死的なロケットは、ナチスの強制収容所で囚人によって製造された。劣悪な環境は恐るべきもので、空襲でロケットに殺された人々よりも、多くの人々が製造過程で命を落とした。ロンドンへの攻撃には500発以上のV2ロケットが使用された。】「THE LONDON BLITZ(ロンドン大空襲)」「THE LONDON BLITZFiremen battle a burning office block on Ludgate Hill, with St Paul’s visiblein the background.」 【ロンドン大空襲ルドゲート・ヒル(St Paul’s大聖堂の前の通り)で、炎上するオフィスビルと格闘する消防士たち。背景にはセント・ポール大聖堂が見える。】この写真パネルも 「THE LONDON BLITZ(ロンドン大空襲)」 の展示の一部。日付:1940年12月29日~30日の夜 → 「ロンドンの第二の大火 (The Second Great Fire of London)」と呼ばれるほどの大規模空襲。視点:焼け落ちたアーチの向こうに煙に包まれた大聖堂の塔が浮かび上がり、破壊と希望の コントラストを表現している。「THE LONDON BLITZLondon experienced such heavy bombing on the night of 29th to 30th December 1940,it was dubbed "the second Great Fire of London". The western bell towers of St Paul’scan be seen through the smoke beyond this ruined arch on the next day.」 【ロンドン大空襲1940年12月29日から30日にかけて、ロンドンは激しい爆撃を受け、それは「ロンドンの第二の大火」と呼ばれた。写真は翌日、瓦礫と化したアーチ越しに、煙の向こうに見えるセント・ポール大聖堂の西の鐘塔を写したものである。】セント・ポール大聖堂のドームを背景に立つ女性たち を捉えた戦時中のスナップ。前景:3人の女性・左の2人は制服姿(女性補助空軍 WAAF や、女性防衛隊員の可能性あり)・右の女性は市民服だが腕章を付けており、戦時における支援活動を担っていたことを示唆。背景:セント・ポール大聖堂の大ドームがはっきり写っている。大聖堂は、ロンドン大空襲中の 精神的支柱・国民の象徴であった。「DANGER AND DAMAGE(危険と被害)」 大聖堂が戦時中に直面した被害をテーマにした展示。・背景写真 ・パネルの背景には、爆撃後の修復作業か、建物内部の補強工事の様子と思われる白黒写真 が使用されていた。 ・焼夷弾や爆撃で破壊された部分を補強する足場が描かれていた。・「戦時中にセント・ポールが受けた具体的な被害」を紹介「‘None of us will, I imagine, forget the dull roar of those tons of falling masonryfollowed by the rasping sound of falling glass which seemed to continue formany minutes.’Watch Commander Godfrey Allen, recalling the night of 16th April 1941」【「我々の誰一人として忘れることはないだろう。何トンもの石材が崩れ落ちる鈍い轟音、 その後に続いたガラスが砕け散る鋭い音――それは何分もの間、鳴り響き続けていた。」 見張り隊指揮官 ゴドフリー・アレン、1941年4月16日の夜を回想して】 「RECRUITMENT AND EXPANSIONBy 1940 the Cathedral urgently needed to increase its number of volunteers on theWatch, and the initial group of around 40 soon grew to 84 people, allowing for12 men to work each shift.An appeal to the Royal Institute of British Architects (RIBA) included in its job description‘Men from 40 to 60 who can walk upstairs and not fear heights’.The number of volunteers on the Watch grew to more than 300 people as the waradvanced. Men and women came from various backgrounds, bravely placing themselvesin harm's way to protect the Cathedral. Together, they forged a great sense of camaraderie during a time of crisis.」【募集と拡大1940年までに、大聖堂は「見張り隊(Watch)」のボランティアを急いで増やす必要があった。最初は約40名で構成されていた隊は、すぐに84名に拡大し、各シフトに12人を配置できるようになった。英国王立建築家協会(RIBA)が出した募集要項にはこう書かれていた:「40歳から60歳までの、階段を上れること、高所を恐れない男性」。戦争が進むにつれ、見張り隊の人数は300名以上にまで膨れ上がった。男性も女性も、さまざまな背景から集まり、大聖堂を守るために危険を顧みず行動した。彼らはこの危機の時代に、強い仲間意識を育んでいった。】 「A DIRECT HIT‘Report very bad night, everyone behaved splendidly’This report was written by J. Green in the St Paul’s Watch logbook, on 16th April 1941. It is a typically understated account of what must have been a terrifying, life threatening experience for members of the Watch.On that occasion, the Cathedral suffered significant damage from a bomb thathit the North Transept. This was just one of many perilous incidents that the Watch hadto cope with. During another heavy air raid on London, fires raged on every side of the Cathedral after it was struck by 28 incendiary bombs.Incredibly, not a single member of the Watch lost their lives during wartime service.」 【直撃「非常にひどい夜だったが、皆立派に振る舞った」この記録は1941年4月16日、J・グリーンによってセント・ポールズ・ウォッチの日誌に書かれたものである。恐ろしいほどの、命を脅かす体験だったに違いない出来事を、典型的な英国流の控えめな筆致で記したものである。その夜、大聖堂は北翼廊を直撃した爆弾によって深刻な被害を受けた。これはウォッチが対処せねばならなかった数多くの危険な出来事の一つに過ぎなかった。別の大規模なロンドン空襲では、大聖堂の周囲の至る所で火災が燃え広がり、焼夷弾28発の直撃を受けた。驚くべきことに、戦時中、ウォッチのメンバーで命を落とした者は一人もいなかった。】「DANGER AND DAMAGEA panoramic view of destruction around the Cathedral.」 【危険と被害大聖堂周辺の破壊のパノラマビュー。】ネットから。この写真は第二次世界大戦中のロンドン大空襲(ブリッツ)後に撮影されたもので、セント・ポール大聖堂を中心に、周囲の街区が壊滅的な爆撃被害を受けた様子を示している。興味深いのは、周囲が瓦礫と廃墟に覆われながらも、大聖堂自体は奇跡的に大きく崩壊せず残ったこと。これが当時「St Paul’s Survives(セント・ポールは生き残った)」という象徴的な写真とともに、市民に大きな希望を与えたのだと。「DANGER AND DAMAGEAmid the rubble, a member of the clergy inspects two cherub figurines that survived the bombing.The cherubs pose as if they are raising their arms over their heads for protection.」 【危険と被害瓦礫の中で、聖職者が爆撃を生き延びた二体のケルブ像を調べている。ケルブたちは、まるで頭上に腕を掲げて身を守っているかのような姿勢をとっている。】ブリッツで被害を受けたセント・ポール大聖堂内部の様子を示している。瓦礫に覆われた中でなお残ったケルブ像は、壊滅的な破壊の中にあって「奇跡的な生還」や「信仰の守護」を象徴するものとして強く印象づけられたのであった。「DANGER AND DAMAGEBomb damage in the North Transept. The explosion blew a hole in the roof andthe floor below, and falling masonry landed in the Crypt.」 【危険と被害北翼廊の爆撃被害。爆発によって屋根とその下の床に大きな穴が開き、落下した石材が地下納骨堂にまで達した。】この写真は、第二次世界大戦中の空襲(ブリッツ)でセント・ポール大聖堂が受けた深刻な被害を示している。特に北翼廊の屋根から床を貫通して地下のクリプト(地下礼拝堂・納骨所)にまで崩落した様子は、建物の存続を危うくしたことがわかるのであった。「SECONDS FROM DISASTERDuring the bombing raids of 16th to 17th April 1941, a German naval mine was dropped in the North East Churchyard. It was discovered by the Cathedral’s Sub-Librarian Gerald Henderson, who spotted an object covered in green parachute silk.A naval mine disposal expert was hurriedly called in. Lieutenant Ronald James Smith hadto crawl underneath the mine to make it safe. As he began to unscrew the fuse, vibrations from a passing fire engine moved the mine and it began ticking.Smith had around 17 seconds before it exploded. With nerves of steel, he deactivated the mine with just two seconds to spare, saving himself, the Cathedral and all those inside.」【大惨事まであと数秒1941年4月16日から17日の空襲の際、ドイツ海軍の機雷が北東の墓地に投下された。大聖堂の副司書ジェラルド・ヘンダーソンが、緑色のパラシュート絹に覆われた物体を発見した。急いで海軍の機雷処理専門家が呼ばれた。ロナルド・ジェームズ・スミス中尉は、安全化のために機雷の下にもぐり込まねばならなかった。信管を外し始めたとき、通り過ぎる消防車の振動で機雷が動き、時限装置が作動し始めた。スミスには爆発までおよそ17秒しか残されていなかった。しかし彼は鋼のような神経で処理を進め、残りわずか2秒というところで機雷を解除することに成功し、自らと大聖堂、そして中にいた人々を救った。】 「DANGER AND DAMAGEBomb debris and rubble are scattered across the floor by the Cathedral’s High Altar. If you look to the left of the photograph, you can see a tall candlestick.」 【危険と被害大聖堂の高壇(ハイ・オルター)の床一面に、爆弾による瓦礫や破片が散乱している。写真の左側を見ると、高い燭台(キャンドルスタンド)が確認できる。】ネットから。この写真は、第二次世界大戦中の空襲でセント・ポール大聖堂が受けた被害の一部を示しており、瓦礫が祭壇付近にまで及んでいる衝撃的な光景を伝えているのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.20
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その113): ロンドン散策記・St. Paul's Cathedral・セントポール大聖堂-2
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクセント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)正面階段上から西側を見下ろした光景。・中央の囲われた像と噴水基壇 → これは クイーン・アン女王像(Queen Anne Statue)。 1712年に建てられた初代像が老朽化したため、現在のものは1906年に彫刻家 Richard Belt によって作られた置き換え像。 女王の足元にはイングランド、スコットランド、フランス、アイルランドを寓意する4体の 座像が配置されていた。・左手の建物群 → ロンドンの古典的な商業ビルで、現在は店舗(写真には "FIVE GUYS" の看板も見えます)。・正面奥に見える尖塔 → St Mary-le-Bow 教会 の尖塔。Wren による再建で、ロンドン市のシンボル的存在。 伝統的に「この教会の鐘の音を聞いて育った人が“コックニー”と呼ばれる」と。・右手の大きな木々 → セント・ポール大聖堂前広場を取り囲む植樹スペースセント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)西正面の左側 を下から見上げて。・右側下部 ピンク色のテントに「Welcome to St. Paul’s Cathedral」とあり、ここは観光客が入場する 際の受付口(チケットチェックなど)が設けられている場所。・中央の列柱(コリント式) 西正面の大階段上にあるコリント式円柱で、古代神殿風の構成。これはクリストファー・レン卿 が設計した「古典主義」と「バロック」の融合美をよく表している。・左上に見える円窓と塔の一部 西正面に左右対称で立つ二つの塔のうち、これは「南西塔(South West Tower)」。 時計のある北西塔とは対になっていた。 南西塔には大鐘「グレート・ポール(Great Paul)」や「グレート・トム(Great Tom)」が 収められている。・装飾浮彫 列柱の上部に聖書の場面などを表した装飾的レリーフが見えた。外壁装飾(バロック様式の装飾彫刻) の一部。1.中央の天使(Cherub/ケルブ) ・翼を持つ幼い顔の天使で、口を開いて歌っているように見えます。 ・典型的な「歌う天使」のモチーフで、聖歌や祈りを象徴します。2.周囲の花綱(ガーランド) ・バラや果実などが編み込まれた装飾的な花綱。 ・豊穣・祝福・永遠の生命の象徴としてよく使われる。3.左右のトランペットとオリーブの枝・トランペットは「神の言葉を告げるラッパ」や「最後の審判のラッパ」を 連想させる。・オリーブの枝は平和と神の祝福を意味する。西正面階段の両脇に設置された装飾的街灯(ランプ)・デザイン鋳鉄の柱には細かい装飾(唐草模様や幾何学模様)が施されており、ヴィクトリア時代らしい華麗な様式。上部の灯具部分はガス灯風のデザインだが、現在は電気照明として利用されている。・頂部の「金色のクロス」ランプの最上部には金色に輝く十字架があしらわれており、 宗教施設である大聖堂のシンボル性を強調している。・位置西正面の大階段を上がる両脇に複数設置されており、訪問者を迎える「門灯」のような 役割を果たしていた。西正面の外壁レリーフ彫刻の一部。彫刻は 「天からのマナ(Manna)の奇跡)」 を表していると。・雲のような形から 神が天からマナ(パンのような食物)を降らせる様子 が示されている。・民衆が地面に散らばったマナを拾い集め、かごや壺に入れて掲げています。・右端の人物は モーセ(Moses) と解釈され、杖(神から与えられた権威の象徴)を手に 持っています。・背後にいる人々の表情は感謝や驚きに満ち、神の恵みを喜ぶ姿が表されている。 セントポール大聖堂の外壁レリーフは、旧約・新約の場面を対比的に配置しており、 この「マナの奇跡」は 神の恵みによる救済の象徴的シーン として重要な位置を占めている と。セント・ポール大聖堂の西正面(ウェスト・フロント)の上部左側の像。聖ペトロ(Saint Peter)と雄鶏 の組み合わせ。・聖ペトロ像 ・髪と衣服の表現から、伝統的な使徒像のスタイルで描かれている。 ・手を前に合わせるような仕草は、否認や悔い改めを象徴している。・雄鶏 ・聖ペトロと切っても切れない象徴。 ・新約聖書によると、イエスが捕らえられる夜、ペトロは「鶏が鳴く前に三度イエスを 知らないと言う」と予告され、その通りに否認してしまいました(ルカ22章)。 ・鶏は「否認と悔い改め」の象徴であり、同時に「赦し」と「新たな出発」の象徴でもある。西正面(ウェスト・フロント)上部に並ぶ使徒像の右側の像。・長い髪と豊かな髭を持つ姿。・左手には書物(巻物または福音書)を抱えています。・衣はゆったりとしたローブで、胸元から大きく垂れています。これらの要素から、この像は 福音書記者または使徒のひとり(おそらく 聖ヨハネ あるいは聖パウロ)を表している と。セント・ポール大聖堂の北側(トランセプト付近から東に向かって) を。・手前の建物角は、大聖堂の側廊(aisle)からトランセプトにかけての壁面部分。・左奥に見える大きな建物は クワイヤ(聖歌隊席)や内陣の東側構造。 クワイヤの北側外壁を正面に見ている。・石畳の通路は、大聖堂の外周を巡る歩行スペースで、観光客や関係車両が利用する導線に。その先、左側にあったのがTemple Bar Gate(テンプル・バー・ゲート)・17世紀に サー・クリストファー・レン が設計した石造の門で、かつてはロンドン市 (City of London)とウェストミンスターを分ける境界に立っていた。・現在は保存のために移設され、セント・ポール大聖堂の北東側(プリテヴィ・ストリート沿い、 パテーノスター広場の入口) に設置されていた。・中央のアーチ部分は馬車や人の通行のため、両脇に小さな歩行者用のアーチがある。Temple Bar Gate(テンプル・バー・ゲート) の上部部分。この門の正面には 2体の王の像 が彫られていた:左:チャールズ1世(King Charles I)右:チャールズ2世(King Charles II)これらはイギリス王室を象徴するもので、王権と都市の境界を示す門としての性格を強調している。中央の窓の下には シティ・オブ・ロンドンの紋章(盾とドラゴン) が掲げられ、さらにその上に彫刻装飾(果実や花をあしらったモチーフ)が見える。右側のこの像はTemple Bar Gate(テンプル・バー・ゲート)正面右側の壁龕(にち)に収められている チャールズ2世(King Charles II, 在位1660–1685) の像。・頭には王冠を戴き、王としての威厳を示しています。・衣はクラシカルなドレープを強調したスタイルで、バロック彫刻らしい動きのある表現。・左手を腰に置き、右足を前に出したポーズは「王の威厳と自信」を象徴。左側のこの像はチャールズ1世(King Charles I, 在位1625–1649) の像。・王冠は戴いていませんが、王笏(杖)を持ち、王としての権威を象徴。・背筋を伸ばし、やや顔を上げた姿勢は「威厳と統治者としての自信」を示します。・右手に持つ杖は「統治権の象徴」。この地図は ロンドン市中心部(シティ・オブ・ロンドン周辺) の徒歩案内板。中央に "You are here"(現在地)が示されていて、そこから徒歩での主要スポットへの所要時間が記されていた。この地図は先ほどの詳細版。中央下に St Paul’s Cathedral(セント・ポール大聖堂) が大きく描かれ、その下に「You are here」と示されていた。Temple Bar Gate(テンプル・バー・ゲート) が現在 セント・ポール大聖堂前のパターノスター・スクエア(Paternoster Square)近く に設置されていることを示していた。パターノスター・スクエア(Paternoster Square)に建つ「パターノスター・カラム(Paternoster Column)」。・円柱のデザインは 古代ローマ風のドーリア式円柱 に近いスタイル。・頂上には黄金の「火の壺(urn of fire)」が載せられており、これは ロンドン大火 (1666年) の記憶を象徴しています。・現在のカラムは 2003年に再建されたもので、周辺の再開発の一環として設置された と。近づいて。セント・ポール大聖堂の北側広場「Paternoster Square」に立っていた。これは セント・ポール大聖堂の北側、パターノスター・スクエアを象徴する記念柱。再びセント・ポール大聖堂の西正面の南塔(South West Tower) を。・西正面には 二つの対になる塔 があり、南側(右手)の塔がこの写真の塔。・塔の上部は開放的な柱廊(コロネード)になっており、頂上には金色の装飾 (火の壺のような形)が置かれています。・中段に大きな円形の開口部(現在は時計がない部分)があり、これが北塔との大きな違い。 北塔には時計が設置されていたが、南塔には設置されていなかった。・この南西塔は 鐘楼(bell tower) の役割を持ち、聖ポール大聖堂の有名な鐘 「Great Paul Bell」や「Great Tom Bell」がかつてここに収められていた と。・特に Great Paul Bell(グレート・ポール鐘) はイギリス最大級の鐘として知られる (現在は修理中)。セント・ポール大聖堂の大ドーム(Great Dome) をTemple Bar London前から。・建築の中心 セント・ポール大聖堂の象徴であり、ロンドンのスカイラインでもひときわ目立つ存在。 高さ約111mで、世界最大級のドームの一つ。・二重構造 実際には三重構造(内殻・中殻・外殻)になっており、内部から見えるクーポラ(丸天井)、 外側から見える鉛板で覆われた大ドーム、その間に構造を支える円筒部があった。・柱廊(コロネード) ドームの基部には環状のコロネード(回廊)があり、そこから大理石の円柱が立ち並んで 支えていた。・ランタン(頂部の塔) ドームの頂点には「ランタン(灯籠塔)」があり、その上に金色のクロス(十字架)が 掲げられていたのであった。セント・ポール大聖堂の南正面(South Transept/南翼廊の外観)。1.大きな窓 下部に大きなアーチ型の窓があり、内部の「南翼廊(South Transept)」に光を取り込む 役割を果たしています。2.ポーチ(玄関部分) 半円形のポーチ(柱廊)がせり出しており、柱頭飾り付きのコリント式円柱が並んでいた。 これが「南入口(South Door)」につながる。3.三角破風(ペディメント) 上部には三角形の破風(ペディメント)があり、そこには彫刻装飾が施されているのが特徴。4.ドームとの関係 写真右上には大ドームの下部が少し見えている。南翼廊は大ドームの基部に位置する。西正面に移動して。・手前に大きく写っているのは、西正面中央のポーチ(柱廊・ポルチコ)。 コリント式の円柱が並び、上部に半円形のバルコニー風の構造が見える。・その上にある三角形の破風(ペディメント)の中央に、先ほどの 王家の紋章 (Royal Coat of Arms) が彫刻されていた。・ペディメントの頂点や両端には、彫像(寓意像) が配置。これらは信仰や徳目を 象徴する人物像。西正面の三角破風(ペディメント)部分 に見られる装飾彫刻。・中央 王冠(クラウン)を戴いた大きな王家の紋章(Royal Coat of Arms) が配置されていた。 紋章にはイングランド、スコットランド、アイルランドの紋章が組み合わされ、国家統合を 象徴。・左側 翼を持つ人物(おそらく 天使あるいは寓意像)。紋章を支える形で描かれていた。・右側 ローブをまとった人物(寓意像)と、ユニコーンの頭部。 ユニコーンはスコットランド王家の象徴で、英国王家の紋章の伝統的な盾持ち(サポーター)。・左端(部分) 獅子の顔が見えた。これは ライオンで、イングランドを象徴。 → 紋章を左右で支える「ライオン(イングランド)」と「ユニコーン(スコットランド)」が 揃っていた。外壁装飾(レリーフ)を。・中央には 二人の幼子(天使/プットー、putti) が、花綱(ガーランド)の中に表現されている。・その周囲を囲むのは 豊かな花々・果実のガーランド(花綱飾り)。 ・バラ(イングランドの象徴)、 ・アカンサス(古典建築のモチーフ)、 ・ブドウ(豊穣・聖餐の象徴) などが。・左右には 縦に並ぶアカンサス模様の柱飾り(パルメット風)が配置されていた。セント・ポール大聖堂の礼拝時間と拝観案内 を示した公式案内板。日曜は典礼中心、平日は祈りと聖餐式が組み込まれ、観光(Sightseeing)は午前から午後4時まで可能という案内。セント・ポール大聖堂の敷地(北側ガーデン付近)にあったこの像は ジョン・ウェスレー(John Wesley, 1703–1791) の銅像。ジョン・ウェスレーはイギリスの聖職者であり、メソジスト運動(Methodist movement) の創始者として知られている。彼の活動は18世紀のイングランドにおいて、福音伝道、社会改革、教育、慈善活動などを大きく推し進めた。ジョン・ウェスレーの功績・メソジスト派の創始:兄チャールズ・ウェスレーと共に活動。信仰の実践と社会奉仕を重視した。・教育・慈善事業:孤児や貧しい人々への支援、学校や医療活動を推進。・広範な伝道:馬で各地を巡り、説教回数は4万回以上とも言われる。・セント・ポール大聖堂との関わり:若き日のウェスレーはしばしばここで礼拝に参加し、 その後の活動にも影響を受けた。台座には「By grace you are saved through faith.John Wesley, M.A.Born at Epworth, 17 June 1703Died in London, 2 March 1791」 【恵みにより、あなたがたは信仰を通して救われる。ジョン・ウェスレー 神学修士1703年6月17日 エプワースに生まれる1791年3月2日 ロンドンにて逝去】と。セント・ポール大聖堂南側の庭園(St Paul’s Cathedral Churchyard Garden)に建つ「クイーン・アン記念柱(Queen Anne Statue / Memorial Column)」・建立年:1712年・目的:1702年に亡くなった 女王アン(Queen Anne, 1665–1714) を記念して建てられました。 女王アンはセント・ポール大聖堂の再建(クリストファー・レン卿による再建)の時代の 君主であり、大聖堂の完成を見届けた女王として讃えられている。・デザイン:コリント式円柱の頂部に 黄金の女神像(しばしば「アン女王像」と誤解されるが、 実際は 聖母マリア像と考えられています)が立っていた。・台座:装飾的なカルトゥーシュや彫刻が施され、基壇部には記念銘板(ブロンズ製)も。頂部の聖パウロ像(St. Paul)。聖パウロ大聖堂は使徒パウロに献堂されており、その象徴として聖パウロ像が大聖堂正面に掲げられているのだ。・黄金色:この像は金箔で覆われ、強い輝きを放っていた。・姿:聖パウロは片手に杖(あるいは槍状の杖)を持ち、もう一方の手を掲げて祝福あるいは 説教の姿勢を取っていた。・象徴:聖パウロは新約聖書における異邦人への伝道者として有名で、剣や書物と共に 表されることも多いが、この像では「杖」が強調されていた。セント・ポール十字架記念碑(St Paul’s Cross Memorial) の基壇部分。・中央には 盾形の紋章(シールド) があり、その中には 聖ジョージ十字(赤十字) が 刻まれていた。 ・これは シティ・オブ・ロンドンの紋章 を示しており、盾の左上には通常 「聖パウロの剣(Sword of St Paul)」が描かれるのですが、ここでは簡略化され 十字のみが強調されている。・紋章の上には 市の冠(mural crown) が載っており、都市の自治権を象徴。・周囲には装飾的な カルトゥーシュ(装飾額縁) が施されていて、記念碑としての格式を 示している。・上部には 天使(またはプットー=幼児像) が柱を取り巻くように配置され、聖なる守護を象徴。「ON THIS PLOT OF GROUND STOOD OLD PAUL’S CROSS WHEREAT AMID SUCH SCENES OF GOOD AND EVIL AS MAKE UP HUMAN FATE THE CONSCIENCE OF CHURCH AND NATION THROUGH FIVE CENTURIES FOUND PUBLIC UTTERANCE. THIS CROSS WAS ERECTED IN THE YEAR 1449. IT WAS DEMOLISHED IN 1643 AND FINALLY REMOVED BY ORDER OF THE LONG PARLIAMENT. THE CROSS WAS RE-ERECTED IN ITS PRESENT FORM UNDER THE WILL OF H. C. RICHARDS TO RECALL AND TO PERPETUATE THE ANCIENT MEMORIES.」 【この地にはかつて「旧セント・ポール十字架」が建っていた。そこは、人間の運命を形作る善と悪の出来事のただ中で、教会と国家の良心が500年にわたり公に語られた場所であった。この十字架は1449年に建てられたが、1643年に取り壊され、最終的に「ロング・パーラメント(長期議会)」の命により撤去された。その後、H. C. リチャーズの遺志に基づき、古の記憶を想起し永遠に伝えるために、現在の形で再建された。】移動して、セント・ポール十字架記念碑(St Paul’s Cross Monument) を下から仰いで。・中央の高い石柱(コラム) 円柱状で、コリント式の装飾が施されていた「。 これは「説教が行われた公開の場(Paul’s Cross)」の象徴として立てられていると。・柱上の黄金像 黄金色に輝く像は 聖パウロ(St Paul)。 ・右手を掲げて祝福の姿勢をとり、 ・左手には 殉教の象徴である十字架を握っている。・基壇の装飾 柱の根元部分には天使(プットー)が配され、さらに市の紋章(聖ジョージ十字)が 刻まれていた。 これは「ロンドン市とセント・ポール大聖堂との結びつき」を強調しているのだ と。黄金像・聖パウロ(St Paul) をズームして。・右手:上に掲げ、祝福または説教を示す仕草。・左手:剣ではなく 大きな十字架の杖(processional cross) を握っています。 ・剣は聖パウロの殉教の象徴ですが、この像では「宣教と殉教の両方」を示すため、 十字架の杖を持たせている。・頭部:後光(光輪)が付き、聖人であることを明示。・衣装:ローマ風の外套を羽織り、使徒・宣教者としての姿。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.19
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その112): ロンドン散策記・St. Paul's Cathedral・セントポール大聖堂-1
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンク地下鉄Mansion House駅からCannon Streetに出てSt. Paul's Cathedral・セントポール大聖堂に向かって進む。大聖堂の大きなドーム(クロスが載った頂部)がはっきり見えて来た。右手の建物の並びの向こうにドームがそびえていて、ロンドンらしい赤い二階建てバスも走っていた。・中央奥:セント・ポール大聖堂の大ドーム(世界的に有名な建築家クリストファー・レンによる 設計、完成1710年)。・左奥:大聖堂の西塔(2本の塔のうちの1本)が少し見えていた。・手前の道路:ロンドン中心部シティ地区、バス26番も走る主要な通り・Cannon Street。セント・ポール大聖堂の大ドームをズームして。・大ドーム(Great Dome):上部のランタン(小塔)と十字架がはっきり見えた。・ドラム部(Drum):大きな窓や装飾パネルが並び、外観の水平帯(コーニス)が特徴的。・下層部:一部は樹木に隠れていたが、大聖堂本体の壁面やアーチ窓の一部が確認できた。さらにドームに向かって進む。・左側:大聖堂の 大ドーム(Great Dome) が堂々とそびえています。・右側:背の高い塔は 南東の鐘塔(South-East Tower)。 ・尖ったスパイア(尖塔)の先に金色の風見(ヴェイン)が見えます。・中央から左寄り:大聖堂の南側壁面(列柱やアーチ窓)がはっきりと確認できた。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral, London) の 大ドーム(Great Dome)を間近から見上げて。・大ドーム(Great Dome) ・クリストファー・レンが設計した傑作で、高さは約111m。 ・3重構造(内側のドーム・中間の支え・外側のドーム)で形成されていた。・ドラム部(Drum) ・円柱(コリント式)に囲まれたギャラリー。 ・間に長方形の金色パネル(装飾レリーフ)が見える。 ・上部には小さな四角窓(開口部)が並んでいる。・頂上部(Lantern & Cross) ・ドームの最上部にはランタン(小塔)が載り、その上に大きな十字架。・左下の部分 ・屋根上の彫像が3体見えます。これは大聖堂の外壁を飾る聖人像の一部。セント・オーガスティン教会(St Augustine, Watling Street)の塔 をクローズアップ。・塔の本体 ・縦長のルーバー窓が正面に2つ並び、鐘楼の役割を持っている。 ・下部に円形窓(オクルス)があり、建物装飾の一部として調和。・尖塔(Spire) ・ルネサンス様式とバロック様式を融合した特徴的なデザイン。 ・途中にランタン(小塔)を挟み、その上に細長いスパイアが立ち上がっていた。 ・先端には金色の風見(ヴェイン)が輝いていた。南側に広がる庭園「フェスティバル・ガーデンズ(Festival Gardens)」 内にある噴水。1940年代のロンドン大空襲(The Blitz)で被害を受けたエリアを整備して造られた庭園のひとつ。・中央の壁面 ・石造りの壁から、獅子口のような装飾部分から水が流れ落ちていた。 ・3つの吐出口が並び、下の浅い水盤に流れ込む形式。・上部のテラス ・石壁の上はベンチが設置された遊歩道になっており、人々が腰を掛けて憩っていた。 ・左上には小さな人物像(ブロンズ像)が見えた。彫刻をズームして。・男女の若い恋人が抱き合う姿を表現。・単なるロマンスではなく、戦禍を越えて人間の愛情・絆を象徴する作品。・セント・ポール大聖堂南側の フェスティバル・ガーデンズ(Festival Gardens) に設置され、 平和と人間性の回復を示す存在となっている と。「the young lovers GEORG EHRLICH 1897–1966」 ・作品名:The Young Lovers(若い恋人たち)・作者:ジョージ・エーリッヒ(Georg Ehrlich, 1897–1966) ・オーストリア出身の彫刻家。 ・1930年代、ナチス政権下でユダヤ系芸術家として弾圧を受け、ロンドンに亡命。 ・英国で活動を続け、親密な人物像・人間の温かみをテーマにした彫刻を数多く残した。セント・オーガスティン教会(St Augustine, Watling Street)の塔を見上げて。外観:・下層はシンプルな四角い石造塔。・中央に丸窓(オクルス)と縦長のルーバー窓。・上部は装飾的な尖塔(スパイア)が載り、バロック的なデザイン。現在の用途:戦災で破壊された教会の一部が保存され、現在は St Paul’s Cathedral Choir School (セント・ポール大聖堂少年聖歌隊学校)の一部として利用されている と。歴史・元々は中世以来の教会 「St Augustine, Watling Street」 がここに建っていた。・1666年の ロンドン大火 で焼失し、クリストファー・レンによって再建。・1940年代の ロンドン大空襲(Blitz) で再び破壊され、教会本体は失われたが、 この塔だけが残された。・戦後、セント・ポール大聖堂に隣接する少年聖歌隊学校の施設に組み込まれ、今も塔が 目印となっている。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral, London) の大ドームを間近から見上げて。・大ドーム(Great Dome) ・世界的に有名なクリストファー・レン設計の象徴的部分。 ・鉛で覆われた外側ドームの曲線がはっきりと写っている「。・ドラム部(Drum) ・円柱(コリント式)が並び、間には金色パネルの装飾。 ・その下には小さな開口部がずらりと並び、ドームの軽量化と採光を兼ねている。・ランタン(Lantern)とクロス ・ドーム頂部に載る小塔(ランタン)の上に大きな十字架。 ・黄金の輝きがあり、街の遠くからも目印になる部分。・右下の外壁 ・ドームを支える本体部分の装飾壁が写り、ギリシャ・ローマ風の古典主義的な意匠が見えた。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral, London)外壁に付随する鉄製装飾門(wrought iron gate) の一つ。・装飾門(Gate) ・黒い鉄製の格子門で、中央に円形の装飾文様。 ・バロック様式らしい曲線や花模様があしらわれていた。・石造の門柱(Pillars) ・左右に白い石の門柱が立ち、その上に大きな装飾壺(ウルン, urn)が。 ・壺には花綱(ガーランド)を持つ顔(マスク)の装飾が施されており、華やかさを添える。・背景の建物 ・背後に見えるのはセント・ポールの外壁の一部(石積みと装飾帯)。移動して西正面側の入口付近を。正面左右の塔のうち、左に当たる北西塔(North West Tower)が見えた。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral, London)の案内板。「These gardens are laid out as the footprint of the Chapter House and Cloister of the Medieval Cathedral which was destroyed by the Great Fire of London in 1666.The actual remains lie a few feet below.The Chapter House and Cloister, designed by the royal mason William Ramsey in 1332,were among the first real examples of the Perpendicular style which was to dominateEnglish architecture for the next two hundred years.Both the octagonal Chapter House and the square Cloister were two-storied buildings enabling the prominent buttresses to act also as very large windows on the first floorabove an open undercroft. In the Chapter Room, which was surrounded on the first floor by an open cloistered walk, it was here that the Chapter or governing body of theCathedral held its meetings.」【この庭園は、中世の大聖堂に付属していた「聖職者会館(Chapter House)」と「回廊(Cloister)」の跡地に整備されています。これらは1666年のロンドン大火で焼失しましたが、その遺構は数フィート地下に残っています。聖職者会館と回廊は、王室の石工ウィリアム・ラムゼイによって1332年に設計され、後に200年間にわたってイングランド建築を支配した「垂直式(Perpendicular style)」の最初期の実例のひとつとされています。八角形の聖職者会館と方形の回廊はいずれも二階建てで、突出した控壁(バットレス)が一階部分の大きな開放空間と、二階の大きな窓を兼ねていました。会館の二階は回廊で囲まれた回遊式の造りとなっており、ここで大聖堂の運営を担う「チャプター(Chapter)」の会合が開かれていました。】セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral, London)の案内看板(入口ガイド)。矢印で示された入口・West Front Entrance(西正面入口) ↑・Crypt Entrance, Café and Shop(地下聖堂入口・カフェ・ショップ) ↑・North Transept Accessible Entrance(北翼廊バリアフリー入口) ↑・South Churchyard Entrance(南側庭園入口) →地図(下部の平面図)・大聖堂を上から見た模式図が描かれており、主要な入口が表示されていた。・You are here(現在地) が西正面側(Ludgate Hill 側)に示されていた。・West Front Entrance(西正面入口) と Groups Entrance(団体入口) は並んで配置。・Crypt Entrance(地下聖堂入口) は西正面を入ってすぐ北寄りに。・North Transept Entrance(北翼廊入口・バリアフリー対応) は建物の右側(北側)。・South Churchyard Entrance(南側庭園入口) は建物の南側。・左下には方位(W = 西、S = 南、E = 東)が描かれており、地図が北向きであることが分かる。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral, London)の礼拝案内板。・礼拝スケジュール(Services) ・日曜日 ・月曜~土曜・ウェルカムメッセージ(A warm welcome) ・大聖堂では、礼拝や個人祈祷のためのチャペル利用には入場料は不要。・バリアフリー入口(Accessible Entrance) ・North Transept(北翼廊入口) に車椅子対応の入口がある。移動して、セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral, London)の西正面(West Front) を正面から。中央にアン女王像(Queen Anne Statue) が。・中央:アン女王像(Queen Anne, 在位1702–1714) ・金の笏(sceptre)と王冠のオーブ(orb)を手に持ち、英国王権の象徴を示している。 ・1712年、セント・ポール大聖堂の完成(1708年)を記念して設置された。・女王像の台座周りの4体の像(寓意像 Allegorical Figures) ・イングランド(England)・写真左=三叉槍(トライデント)を持つ女性像。 ・スコットランド(Scotland)=王冠や剣を象徴する女性像。 ・フランス(France)・写真右=破れた百合の紋章を持つ姿で表現。 ・アイルランド(Ireland)=ハープを象徴とする。 ・(写真では手前2体=イングランドとスコットランドがよく見えます。)・背景:セント・ポール大聖堂の西正面ファサード ・コリント式の巨大な列柱。 ・三角破風(ペディメント)に浮彫装飾。 ・左右にそびえる2つの塔(北西塔と南西塔)。右塔には時計がはっきりと見えていた。屋上コーニス上に立つ石像。・聖パウロ(St Paul) ・剣を象徴(「信仰の剣」「殉教の象徴」)。・書物は新約聖書の書簡を表す。・中央三角破風(ペディメント / Pediment): ・白い大理石のレリーフ彫刻が施されていた。 ・主題は 「聖パウロの回心(The Conversion of St Paul)」。 ・中央上部:天からの光に照らされるキリスト。 ・左側:落馬し、地にひれ伏すサウロ(後の聖パウロ)。 ・周囲:驚き混乱する兵士や従者たち。・この場面は新約聖書「使徒行伝」第9章に記されている重要な物語で、大聖堂の守護聖人 パウロの象徴的瞬間です。ズームして。・中央上部: ・天から降り注ぐ光線(聖霊の象徴としての鳩が描かれることも多い)。 ・その光により場面全体が神聖さで満たされています。・中央下: ・馬から落ち、地にひれ伏すサウロ(のちの聖パウロ)。 ・彼の両手は天を仰ぎ、光に圧倒される姿。・左右: ・驚き慌てる兵士たちや馬。 ・右側の兵士は馬上から振り返り、光を見上げている。 ・左側の人物たちも混乱しながら中心の光に注目。アン女王像(Queen Anne, 在位1702–1714)ズームして。・モデル:アン女王(在位 1702–1714) ・セント・ポール大聖堂の完成(1708年)の時代の君主。・持ち物: ・右手に 金の笏(Sceptre)。 ・左手に 宝珠(Orb)。 ・いずれもイギリス君主の戴冠式で用いられる王権の象徴。・服装: ・王冠をいただき、豪華なマントをまとった姿。 ・首元や胸には王家の装飾文様が彫り込まれていた。西正面にある北西塔(North West Tower) を見上げて。・時計盤(Great Clock) ・塔の正面に大きな丸い時計が取り付けられていた。 ・金色の縁取りに黒い文字盤が映え、荘厳な印象を。 ・セント・ポール大聖堂のシンボルの一つ。・鐘楼(Bell Tower) ・時計の上にはバロック様式の開放的な鐘楼部分。 ・この内部には「Great Tom(グレート・トム)」と呼ばれる大鐘を含む複数の鐘が 設置されている。・塔頂 ・最上部には金色の装飾を戴いた尖塔(スパイア)。 ・建物全体の垂直性を強調し、空へ伸びる印象を与える。・建築様式 ・コリント式の柱、装飾的な彫刻帯、深い陰影を作るバロック的デザイン。 ・クリストファー・レンによる典型的な「英国バロック」の表現。北西塔(North West Tower)の大時計(Great Clock)をズームして。・文字盤 ・黒地に白のローマ数字(I–XII)。 ・外周には「分」を表す数字(15、30、45、60)が記されていた。・針 ・金色の時針・分針が取り付けられています。 ・この時の時刻は「15時12分頃」を指していた。・装飾 ・文字盤の周囲は花輪や葉模様の装飾で囲まれ、バロック様式らしい重厚感があった。西正面にある南西塔(South West Tower)を見上げて。・塔の構造 ・下部に大きな円形窓(オキュルス)があり、その周囲に装飾的な浮彫。 ・中段は円柱が並ぶ開放的なデザインの鐘楼部。 ・上部は尖塔状に絞られ、最頂部には金色の装飾(ギルドのフレイム状フィニアル)。・装飾彫刻 ・円窓の下や四隅に、人物や天使を表したバロック的彫刻が配されています。 ・豊かな陰影が建築全体の立体感を強調しています。・機能 ・この塔には大鐘(Great Paul, 英国最大の鐘)などの鐘が設置されていました。 ・反対側(北西塔)には大時計と「Great Tom」の鐘があるため、二塔は「鐘塔」と 「時計塔」として対になっています。実は セント・ポール大聖堂のこの南西塔(South West Tower)にもかつて時計が取り付けられていたのだと。時計の歴史・17世紀末~18世紀初頭 クリストファー・レンの設計で大聖堂が建設された当初、南西塔(South West Tower)にも 時計が設置されました。・18世紀後半 この時計は巨大であったものの、しばしば故障したため「信頼できない」と評判になった。・19世紀後半(1893年) 新しい大時計が 北西塔(North West Tower)に移設 され、現在の姿(黒地に金文字の ローマ数字)になった。 以降、南西塔の時計は撤去され、現在のように円形窓(オキュルス)が残っている と。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral, London)西正面広場のクイーン・アン女王像の台座に配置された4体の寓意像。・「フランス(France)」の寓意像・特徴: ・長い髪を垂らし、優雅な衣をまとっている。 ・一見すると穏やかな姿勢で、控えめに後ろを振り返っている。 ・手には百合の花(fleur-de-lis)を持つことが多く、王家フランスを象徴。 ・アン女王時代(1702–1714)はスペイン継承戦争期であり、フランスは主要なライバル国家。 ・ここでは「平和の回復」あるいは「和解したフランス」を象徴するとも解釈されます。 ・女性像で、頭にフリジア帽(自由の象徴)をかぶり、左手には巻物(あるいは本)を持っている。廻り込んで。右側:America(アメリカ)像左側:France(フランス)像・この像は アメリカ大陸(America) を寓意的に表した女性像 と。・特徴: ・頭に羽飾りのついた冠(ネイティブ・アメリカン風の headdress)。 ・上半身は半裸に近く、古代的な布をまとった姿。 ・荒々しい姿勢や衣装が「新世界」「未開の地」を象徴的に表現。これは アイルランド(Ireland) を寓意的に表した像。・ハープ(Irish Harp) は、アイルランドの伝統的象徴。 ・中世以来、アイルランドを表す国章的な意味を持つ。 ・現在もアイルランド共和国の国章やコインに描かれている。下部に「Britannia(ブリタニア:英国の象徴)」が。ズームして。・右手に持つ黄金の三叉槍(トライデント) 海の神ネプチューンの武器を象徴化したもので、 「海洋国家イギリス」の力と支配を示す。・左側の盾にはユニオン・ジャック(Union Jack) 英国連合王国の象徴。防衛と統一を意味。・足元の巻貝のような形(波のモチーフ) 海洋との結びつきを暗示し、海に囲まれた島国イギリスを示唆 と。そして、西正面(大入口)から入って中央部(ネイブ=身廊)を進む。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral, London)内部・身廊からドーム基部(クロッシング)方向を見上げた光景。移動して、ネイブ(身廊)から祭壇方向を見て。手前に大理石の洗礼盤(Baptismal Font) が。・洗礼盤(Baptismal Font) ・写真手前中央の大きな円形の大理石製の器。 ・ここで洗礼式(Baptism)が行われる。 ・堂内に入ってすぐ目に入る位置にあり、「信仰の入り口」を象徴しています。・ネイブ(Nave, 身廊) ・左右に大理石の柱が並び、バロック的な白と金の華麗な装飾。 ・シャンデリアと燭台が荘厳さを際立たせていた。・クロッシング(Crossing, 交差部)と大ドーム ・奥に見える円形の窓から光が差し込む部分が大ドームの下部。 ・ドームの内側はモザイクと装飾で彩られていた。・クワイア(Choir, 聖歌隊席)と高祭壇(High Altar) ・更に奥に見えるのが聖歌隊席と祭壇。 ・金色のバルダキン(天蓋)が輝き、焦点を祭壇に導いていた。・イコン(Icons) ・左右に見える金地のイコン(キリスト像)は現代に設置されたもので、 東方正教会風のスタイル。 ・訪問者を精神的に導く役割を持っている と。内陣(クワイア)天井モザイク装飾。1.モザイク装飾の導入 ・19世紀末から20世紀初頭にかけて、ウィリアム・ブレイク・リッチモンド (Sir William Blake Richmond, 1842–1921)によって制作。 ・元々は白壁が多かったクワイアを、金色と色鮮やかなモザイクで輝かせることになりました。2.中央ドームに続く天井部分のモザイク主題 ・創造と救済の物語 を描いた一連の図像。 ・多くの天使たちが配置され、光に包まれる天上の世界を表現。3.祭壇上部の半円形ドーム(アプス) ・中央には 復活のキリスト(The Risen Christ) が大きく描かれています。 ・両腕を広げ、白衣に包まれた姿は勝利と救済を象徴。 ・周囲には天使や聖人が集い、神の栄光を賛美している構図です。4.ラテン語銘文 ・天井アーチ部分にはラテン語の聖句が装飾的に書き込まれています。 ・これは「神の栄光」「救い」「信仰」などを賛美するフレーズ。5.両脇のパイプオルガン彫刻 ・写真の左右に見えるのは大規模な クワイア・オルガン。 ・バロック的な木彫装飾に、天使や聖人像が組み込まれています。1.大ドーム (The Great Dome) ・上方に見えるのは壮大なドーム内部で、ジェームズ・ソーンヒル卿によるフレスコ画 「聖パウロの生涯」が描かれていた。 ・ この部分は「内側ドーム」で、さらに外側・構造上の「外殻ドーム」と三重構造になっていた。2.内陣(Choir, Quire)と高祭壇(High Altar) ・写真の正面奥に見えるのが、鮮やかなステンドグラスと共に輝く 高祭壇。 ・その手前のエリアは クワイヤ(聖歌隊席) で、黒檀風の彫刻が特徴的。3.説教壇 (The Pulpit) ・写真右手に見える木製の立派な説教壇。礼拝や特別な式典で用いられる。4.床の幾何学模様 ・大理石の黒白チェック模様の床は、クリストファー・レン卿のバロック設計の美しい要素。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)の大ドーム内部天井画 を真下から見上げて。ドーム内部天井画の特徴・画家: サー・ジェームズ・ソーンヒル(Sir James Thornhill, 1675–1734)・主題: 「聖パウロの生涯(Scenes from the Life of St Paul)」・制作:1715–1719年・技法:フレスコ画ではなく グリザイユ(monochrome grisaille) 技法で描かれ、立体的に 見えるが実際は平面的。フレデリック・ロード・レイトン卿(Frederic Lord Leighton, 1830–1896)の記念碑(モニュメント)。「To the memory of Frederic Lord Leighton of Stretton, painter, sculptor, and seventhPresident of the Royal Academy of Arts.This monument is erected by his many friends and admirers.Born December 3rd, 1830. Died January 25th, 1896.He lies buried in the crypt of this cathedral.」 【ストレットンのフレデリック・ロード・レイトン卿、画家、彫刻家、王立美術院第七代会長を記念して。この記念碑は、彼の多くの友人と崇敬者によって建立された。1830年12月3日生、1896年1月25日没。彼はこの大聖堂の地下納骨堂に葬られている。】フレデリック・ロード・レイトン卿(Frederic Leighton, 1st Baron Leighton, 1830–1896)は、ヴィクトリア朝を代表するイギリスの画家・彫刻家であり、芸術界の中心的人物。芸術活動・画家として ・主に歴史画、宗教画、神話画を手掛け、華やかで理想化された人体表現と精緻な色彩が特徴。 ・「美術のための美(Art for Art’s Sake)」の理念を体現した芸術家と評される。 ・有名な作品に《Flaming June》(1895、眠る女性像を描いた代表作)がある。・彫刻家として ・晩年には彫刻にも挑み、特に「Athlete Wrestling with a Python」(1877)は大きな 評価を受け、英国における近代彫刻の先駆的作品とされる と。顔をズームして。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral) の「Friends of St Paul’s(友の会)」に関する案内広告。・上部写真:大ドーム下の礼拝スペースに集まる多くの人々。セント・ポール大聖堂の荘厳な 内部空間が強調されています。・スローガン 「Become part of the history of St Paul’s」(セント・ポールの歴史の一部になろう) 「Experience more」(さらなる体験を)・案内文 「History and future come together at St Paul’s Cathedral. If you want to have exclusive access to one of the UK’s most iconic monuments and join special members-only events, contact us at …」 (歴史と未来がセント・ポール大聖堂で出会います。英国で最も象徴的な記念建築のひとつに 特別にアクセスし、会員限定イベントに参加されたい方は、ご連絡ください。)・下部 St Paul’s Friends(支援会・会員制度)への入会案内。 ウェブサイトや電話番号(020 7246 8350)が記載されています。リチャード・ランドル・バージェス艦長(Captain Richard Rundle Burges, 1754–1797)」の記念碑。カンパーダウン海戦の英雄としての顕彰碑であると。「Sacred to the memory of Richard Rundle Burges Esquire, Commander of His Majesty’sShip The Ardent, who fell in the 43rd year of his age, while bravely supporting thehonour of the British flag, in a daring and successful attempt to break the enemy’s line,near Camperdown, on the 11th of October 1797. His skill, coolness, and intrepidity eminently contributed to a victory equally advantageous and glorious to his country. That gratefulcountry, by the unanimous act of her legislature, high in enrols his name, who under the blessing of Providence, have established and maintained her navalsuperiority, and her exalted rank among nations.」 【陛下の軍艦「アーデント」艦長リチャード・ランドル・バージェス エスクワイアの思い出に捧ぐ。彼は43歳の時、1797年10月11日、カンパーダウン沖で、敵の戦列を突破しようとする勇敢かつ成功した試みにおいて、イギリス国旗の名誉を勇敢に守りつつ戦死した。彼の技量、冷静さ、そして果敢さは、勝利に大いに寄与し、その勝利は祖国にとって同時に有利であり、また栄光でもあった。その感謝する祖国は、議会の全会一致の決議によって、彼の名を高らかに記録する。天の摂理の祝福のもと、イギリスは海軍の優越性を確立し、諸国の中で高い地位を維持してきたのである。】・左側の翼を持つ女性像 「Victory(勝利)」または「Immortal Fame(不滅の栄光)」を象徴する寓意像。 彼女は月桂冠を戴き、右手には巻物(英雄の名が刻まれた記録)を持っています。 彼女は戦死した英雄の手を取って、天上の名誉の領域へ導いています。 → 勝利と不滅の名誉を授与している場面。・英雄(右の半裸の男性像=寓意化されたバージェス艦長) 彼の右手も同じ剣の柄を握っており、二人でその剣を支えるようにしている。 → つまり「栄誉の武器を勝利の女神から受け取る」場面です。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.18
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その111): ロンドン散策記・ビートルズ ロンドン ウォーキング ツアー-5
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクSt. John's Wood(セント・ジョンズ・ウッド駅)のパネルにて「十分な予習」?を完了して、「Abbey Road(アビイ・ロード)横断歩道」に向かって進む。緑が多く、ロンドン中心部に比べると静かで高級住宅地の印象を受けたのであった。GROVE END ROAD NW8(グローヴ・エンド・ロード) の標識。この標識は Abbey Road 横断歩道まであと少し という位置を示していた。そしてGrove End Road(グローヴ・エンド・ロード)を南西に進む。Grove End Road(グローヴ・エンド・ロード)とAbbey Roadの交差点にあったのがEdward Onslow Ford Memorial(Google Mapより)。・白いオベリスク型の石碑で、基部には ライオンのレリーフ が飾られていた。・正面にローマ数字で MDCCCLII = 1852年 MCMI = 1901年 の文字が刻まれていた。 アラビア数字をローマ数字に👈️リンク。 1 = I 、 5 = V 、10 = X 、 50 = L 、100 = C 、500 = D 、1,000 = Mローマ数字の表現ルール。(後日、私も勉強します!!)これはEdward Onslow Fordの生涯を示しているのであろう。・周囲は黒い鉄柱とランプで囲まれ、保護されていた。・横断歩道の位置からすぐ見えるため、ビートルズのジャケット撮影の観光客にとっては 「目印」となっているのであった。この交差点を右折して進んだ所が目的地なのであった。このブロンズのレリーフは Edward Onslow Ford(1852–1901) 自身の肖像。助手であったAndrea Carlo Lucchesi によって制作された と。レリーフにはリボン状の帯に英語の碑文が刻まれていた。「TO THINE OWN SELF BE TRUE」 【汝自身に誠実であれ】これはシェイクスピアの『ハムレット』第1幕3場、ポローニアスの言葉からの引用である と。自分自身に真実であること、自分自身を正直に受け入れること、自己を偽らずに自分自身を表現することを意味。他人の期待や社会の圧力に惑わされず、自己を認識し、自己を尊重することの重要性を表現している と。反対側から。碑文には「TO Edward Onslow Ford RAERECTED BY HIS FRIENDS AND ADMIRERS」と。 【王立美術院会員 エドワード・オンスロー・フォードに捧ぐ。彼の友人と崇拝者たちによって建立された】 と。ズームして。・Edward Onslow Ford(エドワード・オンスロー・フォード) 19世紀後半から20世紀初頭にかけて活動したイギリス人で、この人物を記念して建てられた碑。・"Erected by his friends and admirers" 「彼の友人と崇敬者によって建立された」と。まとめると項目 内容名称 Monument to Edward Onslow Ford役割 彫刻家エドワード・オンスロー・フォード(1852–1901)への追悼碑建立 1903年7月18日(除幕)設計者 建築家 J. W. Simpson彫刻 南面:Ford作「The Muse of Poetry」の座像 北面:Lucchesi作フォード肖像レリーフ碑文等 「To Edward Onslow Ford RA — Erected by his friends and admirers」 「To thine own self be true」など所在地 Grove End Road と Abbey Road の交差点(St John’s Wood, NW8)建造物指定 Grade II 登録建造物(Historic England)この南面の台座の前には、ブロンズ像 「悲しみを表す女性像」(通称 Grief)が腰かけていた。これはフォード自身の死を悼む象徴的な像である と。そしてそのすぐ先「アビイ・ロード横断歩道(Abbey Road crossing)」に到着。この場所は特に有名なのは、1969年に発売された ビートルズのアルバム『Abbey Road』 のジャケット写真がここで撮影されたため。・前後の白いジグザグの線 、イギリスの道路標示で 「Zig-zag lines(ジグザグ・ライン)」 のある「シマウマ式横断歩道(Zebra Crossing)」が特徴。 このジグザグ線は、歩行者横断(Zebra crossing) の前後に引かれる特別な標示で、 運転者への厳しい注意区域を示している と。・今もファンや観光客が同じポーズで横断する「聖地」となっている。・背後の木々やレンガ塀、そして道路の幅も当時の姿を残している。正確な住所は Abbey Road, St John’s Wood, London NW8 で、最寄り駅はSt. John’s Wood駅(Jubilee Line) 。「アビイ・ロード横断歩道(Abbey Road crossing)」に近づいて。観光用の2階建てバスが停車中。「アビイ・ロード横断歩道(Abbey Road crossing)」👉️リンク を渡る観光客をズームして。ガイドが1969年に発売された ビートルズのアルバム『Abbey Road』 のこのジャケット写真を見せながら説明してくれた。ズームして。ビートルズのアルバム 『Abbey Road』(1969年)のジャケットをネットから。横断歩道(アビー・ロード NW8)で撮影と。・カメラは 南方向(St John’s Wood 駅側 → Abbey Road Studios 側) を向いている。・ビートルズの4人は 左(東側歩道)から右(西側歩道) へ渡っているところ。メンバーの並び(左から右へ) 1.ジョージ・ハリスン(デニム姿) 2.ポール・マッカートニー(裸足、スーツ) 3.リンゴ・スター(黒スーツ) 4.ジョン・レノン(白スーツ)撮影の裏話・撮影者:カメラマンの イアン・マクミラン が、横断歩道の真ん中に三脚を立て、 警察に車の交通を一時止めてもらって撮影。・撮影日時:1969年8月8日午前11時30分頃、わずか10分ほどで6枚撮影されたうちの1枚。・有名な「ポール死亡説」も、このジャケット(ポールだけ裸足、右足を前に出している点など) から広まったと。元ネタ・ビートルズのアルバム『Abbey Road』(1969年)の有名なジャケット写真。違い・本来はジョン、リンゴ、ポール、ジョージの4人が渡っているところを、 → このパロディでは 1人の人物と犬 が渡っている。・背景(白いフォルクスワーゲン・ビートルの車や、街並み)はそのままオリジナルの写真を 再利用しているか、合成されている。意味・世界中でビートルズの横断歩道シーンは「聖地巡礼」のようにファンが真似して撮影したり、 パロディ・オマージュ作品が数多く作られている。 この写真はその一例で、オリジナルを遊び心で再現・加工した作品である と。ネットから。これはポール・マッカートニーのアルバム 『Paul Is Live』(1993年) のジャケット写真。有名なビートルズ『Abbey Road』(1969年)のパロディとして作られたもの。🎵 背景と意味・タイトル「Paul Is Live」 は、1969年に世界的に広まった「Paul Is Dead(ポール死亡説)」を 逆手に取った言葉遊び。・「ポールは死んでいる(Paul Is Dead)」→「ポールは生きている(Paul Is Live)」という ユーモア。・これは、『Abbey Road』のジャケットに関する都市伝説(裸足=死の象徴)を意識しての 明確な冗談 と。この写真に写っているのは、・イギリスの 「モッズ文化 (Mods)」 に典型的な改造スクーター と。・そこにモッズ文化を象徴する派手なスクーターが現れるのは、「60年代ロンドン文化 (ビートルズとMods)」が同じ時代背景を共有しているため、非常に象徴的な光景。・アビイ・ロードはビートルズの象徴的な場所であると同時に、ロンドン観光の聖地。これは私ではありません。👉️リンクビートルズの『Abbey Road』アルバムジャケットを再現したもので、かつ80歳のポール・マッカートニーが一人で横断歩道を渡るシーン??Time誌の記事などにもある通り、2018年にポール自身が横断歩道を一人で渡る動画を投稿して話題になったことがある と。Abbey Road Studios(アビー・ロード・スタジオ) の正面。ビートルズのアルバム Abbey Road の録音が行われた場所として世界的に有名。Abbey Road Studios の正門(ゲート)。特徴・鉄製の黒い門:現在は一般公開されておらず、関係者以外は立ち入り禁止。・“NO ENTRY Abbey Road Studios” の看板 が掲示されていた。・両脇の白い門柱:ファンの落書きやメッセージがびっしり書き込まれており、訪問者が 思い思いのサインを残していた。・CCTVの監視カメラ:セキュリティが厳重であることが分かる。このゲートは、世界中から 訪れるビートルズ・ファンにとって「聖地」のひとつ。多くの人が Abbey Road の横断歩道で 写真を撮ったあと、この門柱にメッセージを書き込む というのが定番の流れになっている と。Abbey Road Studios 正門の門柱 のクローズアップ。左側:・白く塗られた壁面に、ファンたちが サイン・落書き・イラスト・メッセージ を無数に 残しています。・世界中から訪れた人々が、自分の名前や「The Beatles」「Love」「Peace」などの言葉を 書き込むのが定番。・写真を見ると、赤・青・黒のマーカーが多く使われており、「LOVE」「ELLE」「Milan」 「Katie」など名前やメッセージが散見された。右側:・白く塗られた門柱にびっしりと ファンのメッセージ・サイン・落書き が残されていた。・左側の門柱と同じく、世界中の観光客が訪れて名前や「Love」「Peace」「Beatles Forever」 などを書き残していた。・写真を見ると、ここには ステッカー(Spotify, Undergroundマーク, バンドのロゴなど) も 多く貼られており、落書きと混在していた。金属製フェンスの下の壁にも、全面に書き込みが。ガイドが掲げているのは・ビートルズの『Hey Jude』アルバム(アメリカ発売時は “The Beatles Again”) の ジャケット撮影時の写真。ズームして。・場所:ロンドン郊外、ジョン・レノンの自宅「Tittenhurst Park」ではなく、実は アップル本社ビル(Savile Row 3番地)ではなく、EMIの関連建物のポーチ前で 撮られたもの。・ジャケット写真: ・フォトグラファーは Ethan Russell。 ・白い柱と玄関の前に座ったり立ったりしているビートルズが印象的。 ・背景:この写真が使われたのは、アメリカで発売されたコンピレーションアルバム 『Hey Jude』。シングル盤収録曲を集めたアルバムで、日本やイギリスでも後に 知られるようになった と。ネットから。ビートルズ(The Beatles) の4人がロンドンの EMI Recording Studios(現在の Abbey Road Studios) の入口前に座っている有名なショット。左から順に:1.ジョージ・ハリスン(George Harrison)2.ジョン・レノン(John Lennon)3.ポール・マッカートニー(Paul McCartney)4.リンゴ・スター(Ringo Starr)彼らが1970年前後(『Abbey Road』制作期)にスタジオ前で休憩中に撮影されたとされるもので、ポールが裸足のサンダル姿である点が当時話題になった と。これもビートルズがEMIスタジオ(現在のアビーロード・スタジオ)の正面玄関の階段で撮影された写真。・場所:ロンドン、セント・ジョンズ・ウッドの Abbey Road Studios(当時はEMI Recording Studios)。・写真内容:4人(ジョン、ポール、ジョージ、リンゴ)が階段を並んで降りているポーズ。・時期:1960年代初頭、公式写真撮影や雑誌用フォトセッションの一部として撮影されたもの。・意味合い:ビートルズが多くの名盤を録音したAbbey Road Studiosを象徴するショットであり、 ファンにとって「アビーロード横断歩道」と並ぶ人気の撮影スポットの一つです。ネットから。これもAbbey Road Studios の正面玄関を写した写真。・扉の上に 「Abbey Road Studios」 と書かれたサインが掲げられている。・スタジオの階段に人物が座っていて、訪問者やファンが記念撮影したものである可能性が高い。・現在の「アビーロード・スタジオ」の入り口は、当時ビートルズが使っていた玄関と同じ 場所だが、看板や装飾は時代とともに変化。現在のAbbeyRoad Studios(アビーロード・スタジオ)の正面玄関ビートルズをはじめ、ピンク・フロイドやオアシスなど数多くの名盤がここで録音された。特徴・建物は19世紀に建てられた白いジョージアン様式の邸宅。・正面のドア上には現在「Abbey Road Studios」と書かれたサインが掲げられていた。・左側には丸い青い記念プレート(Blue Plaque)が取り付けられており、スタジオの歴史的価値が 示されていた。・玄関前の階段は、ビートルズや数多くのアーティストが記念撮影をした場所として有名。「逆向きに歩いている写真」もあるのだと(下記写真はネットから)。この写真は「アビイ・ロード横断歩道(Abbey Road crossing)」の パロディ写真である と。「逆向きに歩いている写真」は、アルバムジャケット用に撮影された別テイク(アウトテイク写真)であり、偶然の産物ではなく「最初から複数方向を試した」結果のひとつである と。「Abbey Road Studios(アビイ・ロード・スタジオ)」をズームして。さらにアビイ・ロード・スタジオ(Abbey Road Studios)本館の正面玄関部分 をズームして。・所在地:3 Abbey Road, St John’s Wood, London NW8 9AY・建設年代:1830年代(元はジョージアン様式の邸宅)・現在も世界的に有名なレコーディング・スタジオとして現役 と。右側にあったのがIEEE(米国電気電子学会)による記念プレート(Milestone Plaque)左側にあったのがイギリスの作曲家 サー・エドワード・エルガー(Sir Edward Elgar, 1857–1934) を讃えるプレート。「Alan Dower Blumlein filed a patent for a two-channel audio system called "stereo" on 14 December 1931.It included a “shuffling” circuit to preserve directional sound, an orthogonal“Blumlein Pair” of velocity microphones,the recording of two orthogonal channels in a single groove, stereo disc-cutting head,and hybrid transformer to mix directional signals.Blumlein brought his equipment to Abbey Road Studios in 1934 and recorded the London Philharmonic Orchestra.April 2015IEEE」【ステレオ音響再生の発明(1931年)アラン・ダワー・ブラムライン(Alan Dower Blumlein)は、1931年12月14日、「ステレオ」と呼ばれる2チャンネル音響システムの特許を出願した。この特許には、方向性音を保持するための「シャッフリング回路」、直交配置された「ブラムライン・ペア」マイクロフォン、1本の溝に2つのチャンネルを記録する方法、ステレオディスクカッティングヘッド、方向信号を混合するハイブリッドトランスフォーマーが含まれていた。ブラムラインは1934年にこの装置をアビイ・ロード・スタジオに持ち込み、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団の録音を行った。2015年4月IEEE(米国電気電子学会)】 アビイ・ロード・スタジオ(Abbey Road Studios) の左側外壁に掲げられている記念プレート(ブルー・プラーク)。内容は、イギリスの作曲家 サー・エドワード・エルガー(Sir Edward Elgar, 1857–1934) を讃えるもの。1931年11月12日、スタジオのこけら落としとして行われた最初の録音を担当したのが、イギリスを代表する作曲家 エドワード・エルガー卿 であった と。「WESTMINSTER CITY COUNCILSIR EDWARD ELGARCOMPOSER 1857 – 1934OPENED AND RECORDED IN THESE STUDIOSON 12TH NOVEMBER 1931EMI RECORDS U.K.」 【ウェストミンスター市議会サー・エドワード・エルガー作曲家(1857–1934)1931年11月12日、ここアビイ・ロード・スタジオで開館記念の録音を行ったEMIレコード U.K. により設置】1967年頃、ロンドンのアビー・ロード・スタジオ(当時EMIスタジオと呼ばれていた)でビートルズがピアノを弾いている。左から、ジョン・レノン、リンゴ・スター、ポール・マッカートニー。後ろにジョージ・ハリスンが座っている。(写真はネットから)。その先にあったのがBUS STOP「Abbey Road Studios」。 さらに先にあったのが「ABBEY ROAD NW8」。 再び引き返して、アビーロード横断歩道(Abbey Road Crossing)を。背後に見えるのが、エドワード・オンスロー・フォード記念碑(Edward Onslow Ford Memorial)。道路の両側で、白いラインがジグザグになっているのは、もうすぐ横断歩道があることを視覚的に訴えてドライバーに注意を喚起するための特殊塗装とのこと。「ジグザグ線内では原則停車禁止」ですが、歩行者保護のために止まる場合だけ例外的に許可されているとのこと。アビーロード横断歩道(Abbey Road Crossing)を渡る人の姿が絶え間なく。我が旅友の姿を。ズームして。旅友Yさんが私の写真を撮ってくださいました。有名なアルバム『Abbey Road』のジャケットに使われた定番の角度に近い場所から。ビートルズ『Abbey Road』50周年(1969–2019)を記念して制作されたマンホール蓋(特注デザイン)。・ビートルズ4人(ジョン、リンゴ、ポール、ジョージ)が有名な横断歩道を渡る姿を線画風に デザイン。背景にはアビイ・ロード・スタジオの外観がうっすらと描かれていた。・THE BEATLES – ABBEY ROAD 1969–2019 WREKIN と記されていた。・“WREKIN” はこのマンホールを製作したイギリスの鋳造会社 Wrekin Products Ltd の名前。そして一昨日・2025年10月15日(水)にロンドンの観光地で4人の巨大な日本力士がビートルズの象徴的なイメージを再現したのであった。アビーロード横断歩道(Abbey Road Crossing)ともお別れ。そして、アビーロード横断歩道(Abbey Road Crossing)の見学を終え、St. John's Wood Station まで戻る。長いエスカレーターを下る。次の散策地のSt. Paul's Cathedral・セントポール大聖堂に一人で向かって地下鉄Jubilee Lineを利用。GREEN PARK STATIONで乗り換え。利用した地下鉄Jubilee Lineの車両を見送って。Green Park 駅の Piccadilly line 連絡通路を進む。さらに。そして Piccadilly line にてSOUTH KENSINGTON駅へ。そしてCircle lineにてMANSION HOUSEにて下車したのであった。今、気がついたがかなり遠回りしてしまったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.17
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その110): ロンドン散策記・ビートルズ ロンドン ウォーキング ツアー-4
【海外旅行 ブログリスト】👈リンクOld Bond Street(オールド・ボンド・ストリート)をPiccadillyに向かって南に進む。1階に MONCLER(モンクレール) のショップが入っていた。この建物(MONCLERの入居する茶色レンガの建物)は、もともと18世紀~19世紀の住宅が改装されたものとのことで、現代は高級ブティックに転用されていた。上階はレンガ造りの古いタウンハウス風で、ロンドンらしい歴史的な外観を残していた。右隣は黒塗りの外装の建物で、こちらも18~19世紀のジョージアン様式を色濃く残したファサード。Stella McCartney(ステラ・マッカートニー) の店舗。開店時の写真をネットから。ステラ・マッカートニーは、ビートルズのポール・マッカートニーの娘で、世界的に有名なファッションデザイナー。サステナブル(持続可能)なファッションの先駆者であり、動物由来の皮革や毛皮を一切使わないコレクションで知られている と。ロンドンの旗艦店・中核店は Old Bond Street(オールド・ボンド・ストリート)やBruton Street周辺に位置しており、高級ブランドが並ぶ一等地に構えられているのだ。ステラが父ポールの影響を受けつつ、ロンドンで独自のファッションブランドを築いたことを実際に目にできる場所なのであった。ステラ マッカートニーのロゴの付いたショルダーバッグ をズームして(ネットから)。上記写真の店頭のロゴ「STELLA McCARTNEY」は小さな出っ張りを付けて点字のように浮かび上がる独特のタイプフェイス。Old Bond Street(オールド・ボンド・ストリート) のストリートサイン。・所在地:City of Westminster(ロンドン中心部、ウェストミンスター区)。表記の通り、・THIS SIDE(この側) → 1〜24番地・OTHER SIDE(向かい側) → 25〜50番地に番地が割り振られていた。・上にある装飾的な紋章は、City of Westminster(ウェストミンスター市)の紋章。・金色の王冠・十字とバラの意匠・モットー「Custodi Civitatem Domine(主よ、この都市をお守りください)」Old Bond Streetの特徴・世界的な高級ブランド街として有名。・Cartier(カルティエ)、Tiffany & Co.(ティファニー)、Gucci(グッチ)などが軒を連ねる。・北の New Bond Street と連続しており、両者をあわせて「Bond Street」と呼ぶのが一般的。・18世紀末からファッションと芸術の中心地であり続け、ビートルズ時代にもサイケデリック 文化やファッションに大きな影響を与えた界隈。Old Bond Streetを見る。・通りにはユニオンジャックの旗が連なり、観光ムードが強い通り。・右側に見える 朱色の旗「THE ROYAL ARCADE」 は有名な ロイヤル・アーケード の入口。 ・1879年に建設された小規模なショッピング・アーケードで、ヴィクトリア朝時代の装飾が よく保存されている。 ・宝飾品や高級店が多く入っている。・左側には高級ブランドの高級宝飾品・時計店「CHATILA」の旗も確認できます。ユニオンジャックの旗をズームして。右折してStafford Streetへ。 STAFFORD STREET W1(スタッフォード・ストリート) の通り標識。場所は City of Westminster(シティ・オブ・ウェストミンスター) に属している と。スタッフォード・ストリート W1 は、ピカデリー(Piccadilly) と リージェント・ストリート(Regent Street) の近くに位置。ちょうど オールド・ボンド・ストリート(Old Bond Street) の北端に接続する短い通り。Stafford Street(スタッフォード・ストリート) にある ROLEX(ロレックス)店舗 の前。このROLEX前は、ロンドンでも有名な「ラグジュアリー・ショッピングの中心地」のひとつ と。・ROLEXロゴ:緑色のアルファベット「ROLEX」。・クラウンマーク:両側にある黄色い王冠(クラウン)は、ロレックスを象徴するシンボル。 ・1925年に商標登録され、王冠は「高級」「ステータス」「信頼」の象徴。・店舗位置は Old Bond Street と Stafford Street の角 にあった。この場所は高級ブランド店街の一角 として知られている通りであると。そしてこの場所(Stafford Street の角)は、ビートルズのマネージャー、ブライアン・エプスタイン(Brian Epstein)の会社NEMS Enterprises Ltd.(ネムズ・エンタープライズ)が一時期、オフィスを構えていたビルの場所である と。ビートルズが全国的人気を得た1963年の「Please Please Me」ヒット期に使われたオフィスであった と。更に進む。ここにもSTAFFORD STREET W1(スタッフォード・ストリート) の通り標識。左折して、Denver Streetへ。その先にPiccadilly通りが現れた。「DOVER STREET W1(ドーバー・ストリート)」は、ロンドンのメイフェア地区にある通りで、ピカデリー(Piccadilly)から北に伸びていた。・メイフェアらしい高級感ある通り ギャラリー、ファッション・ブティック、レストランが多く、アート系やクリエイティブな 雰囲気があるエリアです。・アートの中心地のひとつ 有名な Dover Street Market(実際はハヤマ・リアスのコンセプトショップ)はここから 名前を取っている と(現在は別の場所へ移転済み)。・この周辺(メイフェア~ソーホー~メアリルボーン)は1960年代カルチャーの中心地であり、 当時のロンドン音楽シーンに出入りする人々(プロデューサー、デザイナー、モデル)が 歩いた「文化の回廊」の一部だった と。ピカデリー(Piccadilly・ピカデリー通り)に出ると前方右側にあった建物がThe Ritz London(リッツ・ロンドン・ホテル)。建物の特徴・場所:150 Piccadilly, London W1J 9BR ピカデリー通り沿い、Green Park のすぐ隣に位置。・建築様式:エドワーディアン・バロック様式(設計:Charles Mewès、Arthur Davis) ・1906年開業。 ・パリのリッツ(Ritz Paris)と姉妹関係を持つ。・外観の特徴: ・一階部分は大きなアーチ型のアーケード。 ・上階は整然と並ぶ窓とバルコニー。 ・屋根は特徴的な緑青色のマンサード屋根。 ・正面にはユニオンジャックとホテル旗が掲げられています。歴史的・文化的意義・英国王室や各国元首が宿泊した名門ホテル。・高級レストラン「The Ritz Restaurant」は世界的に有名。・「アフタヌーンティー」の代名詞的存在で、今も予約困難な人気。・映画や小説、音楽にも頻繁に登場。前方にGreen Park(グリーン・パーク) の入口が現れた。・正面にある 石造りの壁と門(グリーンパーク駅前の出入口)。・背景の豊かな緑は Green Park(ロンドン王立公園のひとつ)。・手前の道路は Piccadilly(ピカデリー通り)。そしてここ地下鉄グリーン・パーク駅(Green Park Station)から、このツアーの最後の訪問地の「Abbey Road」に向けて地下鉄を利用する と。ホームに向かって。地下通路を進む。・背景の 白いタイル壁に青い横帯 は、Green Park駅特有のデザイン。・足元に「Transport for London(TfL)」と音楽をテーマにした装飾があり、ここは 駅構内の「 バスキング(Busking)・路上演奏」指定エリア のようであった。・アコーディオン奏者のストリート・ミュージシャンが演奏中。「LET THE MUSIC TRANSPORT YOU(音楽があなたを運ぶ)」と。 黒から赤・オレンジへのグラデーション背景に、ギター・トランペット・ヴァイオリン・マイク・音符などが流れるように描かれており、音楽がまるで地下鉄の流れや人の流れを運ぶように表現されていたのであった。・MAYOR OF LONDON(ロンドン市長) → 市としての文化支援事業の一環であることを示していた。・BUSK in LONDON → TfLとロンドン市が共同運営する公式バスキング(街頭演奏)プログラム。 登録制で、特定の駅構内(Green Park, Southwark, Tottenham Court Roadなど)に 演奏ポイントが設定されているのだと。・TRANSPORT FOR LONDON(TfL)ロゴ → ロンドン交通局。地下鉄・バス・オーバーグラウンドなどを管轄。 「Every Journey Matters(すべての旅が大切)」という標語が添えられていた。Jubilee Line に向かって進む。ジュビリー線 (Jubilee Line) は、東ロンドンのストラトフォードからロンドン北西部のスタンモアを結ぶロンドン地下鉄の路線。ロンドン地下鉄路線図上では灰色/銀色で示されていた。ジュビリー線 (Jubilee Line)の駅名案内。Piccadilly line(1973 Tube Stock)の車両内部。 項目 数値 備考・車両全長 約 17.77 m 1両あたり・車体幅(横幅) 約 2.62 m 外寸。 車内通路は約1.2〜1.3m程度・車体高さ 約 2.88 m 地下トンネル断面に合わせた半円形屋根・車内高さ(実内寸) 約 2.1〜2.2 m 天井照明・換気ダクトを除いた人が立てる高さ・座席配置 ロングシート対面式 (片側7席×2) 端部はドアスペース・定員 約 268名 (座席42・立席226) 6両編成全体で約1600人収容可特徴的な構造・トンネル断面が「楕円ではなくほぼ円形」なので、側壁と天井が連続した丸屋根になっていた。・そのため、座席の背後(壁面)は大きく湾曲しており、 立っている人が通路の端(壁ぎわ)に立つと、壁が少し内側に出っ張っている分だけ、 肩が壁に近く、やや内側に寄る感じになるのであった。・通路中央には縦手すり(poles)が連続配置され、幅1.2mほどの狭い通路を確保。行儀よく座るウォーキング仲間達。私は立って写真撮影。そしてST.JOHNS WOOD STATIONで下車。・この駅は ビートルズの聖地・アビーロード(Abbey Road Studios) に最寄りの駅として 世界中の観光客に有名。・St. John’s Wood駅から徒歩7〜8分で Abbey Road Studios に到着。・その前の横断歩道は、ビートルズのアルバム『Abbey Road』(1969年)のジャケット写真が 撮影された場所で、ファンが必ず訪れるスポットなのであった。St. John’s Wood(セント・ジョンズ・ウッド)駅のエスカレーター。・ジュビリー線(Jubilee Line) の駅で、アビーロード・スタジオ(Abbey Road Studios) の最寄り駅。・この駅のエスカレーターは長く、両側の壁には広告ポスターがずらりと並んでいるのが特徴。・中央に階段、両脇にエスカレーターという典型的なロンドン地下鉄スタイル。・銀色に近い光沢のある金属パネルの壁面が、St. John’s Wood 駅の代表的なデザイン。ここを上がると「アビーロード横断歩道」へ徒歩10分ほどで到着。まさに ビートルズ巡礼の入り口 といえる光景なのであった。ロンドン地下鉄 St. John’s Wood(セント・ジョンズ・ウッド)駅 にあった案内パネル。「LONDON UNDERGROUND HISTORYSt. John’s Wood station tilesTake a closer lookSt. John’s Wood is one of four stations on the Underground network to feature tiles designed by artist Harold Stabler. These decorative tiles are interspersed withplain tiles throughout the station – see how many of them you can spot!Ten of Stabler’s tile designs represent the coats of arms of the Home counties. The eaglepictured at far right is a representation of Bedfordshire. At top is the crown andthree Saxon weapons representing Essex. The stag, pictured at centre, is an interpretation of the coat of arms of Hertfordshire, while the five martlets at bottom represent Sussex.Find out more at www.ltmuseum.co.uk」 【セント・ジョンズ・ウッド駅のタイルもっと詳しく見てみようセント・ジョンズ・ウッド駅は、アーティスト ハロルド・ステーブラー による装飾タイルが設置されている、ロンドン地下鉄ネットワーク内の4つの駅のうちのひとつです。これらの装飾タイルは駅全体の通常の白いタイルの間に散りばめられています ― いくつ見つけられるか探してみましょう!ステーブラーのタイル・デザインのうち10種類は、ロンドン周辺の州(ホーム・カウンティーズ)の紋章を表しています。右側に描かれている鷲は ベッドフォードシャー州 を表しています。上部にある王冠と3本のサクソンの武器は エセックス州 を示します。中央にある牡鹿は ハートフォードシャー州 の紋章を解釈したもので、下部にある5羽のマーレット(小鳥)はサセックス州 を表しています。詳しくはwww.ltmuseum.co.uk をご覧ください。】これもSt. John’s Wood 駅の装飾タイル の案内パネル。「St. John’s Wood station tilesTake a closer lookArtist Harold Stabler designed 18 decorative tiles to decorate the stations on the 1930sextension of the Bakerloo line. These included iconic London buildings such as St Paul’s Cathedral and the Houses of Parliament, as well as St. Marylebone Church and 55 Broadway, the headquarters of London Underground.The bottom tile featuring a crown and oak leaves represents Surrey, one of the ten Home counties.St John’s Wood and Swiss Cottage Underground stations were also decorated with a tile of cricketer Thomas Lord – namesake of Lord’s Cricket Ground, the home of English cricket, close to the station.Find out more at www.ltmuseum.co.uk」 【セント・ジョンズ・ウッド駅のタイルもっと詳しく見てみよう芸術家 ハロルド・ステーブラー は、1930年代のベーカールー線延伸区間の駅を飾るために18種類の装飾タイルをデザインしました。これらには、セント・ポール大聖堂や国会議事堂などロンドンの象徴的建築物のほか、セント・メアリルボーン教会、ロンドン地下鉄本社ビルの 55 ブロードウェイ も含まれています。最下部のタイルに描かれた 王冠とオークの葉 は、「ホーム・カウンティーズ」のひとつ サリー(Surrey)州 を表しています。また、セント・ジョンズ・ウッド駅とスイス・コテージ駅には、クリケット選手 トーマス・ロード のタイルも設置されています。彼は「ロードズ・クリケット・グラウンド」の名前の由来となった人物で、この競技場は駅のすぐ近くにあり、イングランド・クリケットの本拠地となっています。詳しくはwww.ltmuseum.co.uk をご覧ください。】ロンドン地下鉄 St. John’s Wood(セント・ジョンズ・ウッド)駅 の外観を。建築的特徴・開業:1939年(ベーカールー線延伸時に開業)・設計:地下鉄建築家の名匠 Stanley Heaps(スタンリー・ヒープス)・様式:モダニズム(アールデコに影響を受けたシンプルな曲線デザイン)・レンガ造りの円筒形ファサードに、白い帯状の部分がアクセントを加えています。・駅名サイン(ブルーの帯に白文字)が横一列に伸びていて、当時のロンドン地下鉄デザインの 典型。特記事項・この駅は Abbey Road Studios(アビイ・ロード・スタジオ) と ビートルズの 横断歩道ジャケット写真 の最寄駅として世界的に有名。・ホームや通路のタイルには、先ほどの Harold Stabler(ハロルド・ステーブラー) デザインの 装飾タイル(紋章・著名建築物・Thomas Lord像など)が散りばめられていた。・ロンドン地下鉄の中でも「音楽巡礼スポット」として、世界中のビートルズファンが訪れる駅。St. John’s Wood駅 構内にあるビートルズゆかりの名所 Abbey Road Studios(アビイ・ロード・スタジオ) への案内ポスター 。ビートルズファン向けに「Abbey Roadへの行き方」がユーモラスに書かれていた。「Getting to Abbey Road from Here, There and EverywhereDo you need some Help! finding Abbey Road from the station?Honey Don’t panic!It Won’t Be Long if you follow these directionsExit the station and cross Finchley Road to Grove End RoadContinue on Grove End Road for 5–6 minutesTurn right onto Abbey RoadHave a Good Day SunshineJust retrace your steps to Get Back to the station, but remember that you’ll need aTicket to Ride.Mayor of LondonTransport for London」 【「アビー・ロードへの行き方 ― ここから、あそこから、どこからでも」アビー・ロードへの行き方に Help!(ヘルプ!) が要りますか?Honey Don’t(ハニー・ドント) 慌てないで!この道順に従えば、It Won’t Be Long(すぐ着くよ)。・駅を出てフィンチリー・ロードを渡り、グローヴ・エンド・ロードへ・グローヴ・エンド・ロードを5〜6分まっすぐ進む・アビー・ロードで右折・そして Good Day Sunshine(素敵な一日を)帰りは道を逆にたどれば駅に Get Back(戻れる) けど、Ticket to Ride(乗車券) を忘れずに!】と。ビートルズの名盤 『Abbey Road』(1969年)ジャケット写真 をモチーフにしたもの。・横断歩道を渡るビートルズの4人が描かれている・左から順に ジョージ・ハリスン(デニム姿)、ポール・マッカートニー(スーツだが裸足)、 リンゴ・スター(黒いスーツ)、ジョン・レノン(白のスーツ)・ポールが裸足である点は、ジャケット同様「意味深」なイメージとして有名これが本物の写真(ネットから)。beatles abbey road ジャケット。この写真は、ザ・ビートルズ(The Beatles)のアルバム『Abbey Road(アビイ・ロード)』のアナログレコード盤で、特別仕様の 「Original Master Recording」版(モービル・フィデリティ・サウンド・ラボ=Mobile Fidelity Sound Lab 通称 MFSL)である と。ザ・ビートルズのアルバム『Abbey Road(アビイ・ロード)』のジャケットとして世界的に有名な一枚。🎵 概要・撮影日:1969年8月8日・場所:ロンドン北西部・セントジョンズウッド(St John’s Wood) Abbey Road Studios(アビイ・ロード・スタジオ)前の横断歩道・アルバム発売:1969年9月26日(イギリス)・撮影者:イアン・マクミラン(Iain Macmillan)📸 撮影の舞台裏・撮影はわずか10分ほどで行われ、警察が一時的に通行を止める形で行われた。・カメラマンは脚立の上からシャッターを切り、6枚の写真が撮影され、 その中からメンバーが全員バランスよく歩いている1枚が採用された。・写真はアビイ・ロード・スタジオのすぐ前で、現在も同じ場所が観光名所になっている。👣 メンバーの並び(左から右へ)順番 メンバー 特徴1 ジョージ・ハリスン(George Harrison) デニム姿、裸足ではない2 ポール・マッカートニー(Paul McCartney) 裸足で歩く(話題に)3 リンゴ・スター(Ringo Starr) 黒のスーツ4 ジョン・レノン(John Lennon) 白いスーツで先頭を歩く👞「ポール死亡説」との関係この写真は後年、「ポール死亡説(Paul is dead)」の象徴的証拠とされた。その理由は次の通り:・ポールだけが裸足で歩いている。・4人の服装が「葬列」を暗示している(白=牧師、黒=喪服、デニム=墓掘り人、裸足=死者)。・背後に見える白いフォルクスワーゲン・ビートルのナンバー「LMW 281F」が 「Linda McCartney Weeps(リンダが泣いている)/28歳で死んだ」の暗示とされた (実際には27歳)。もちろん、これらはすべてファンの憶測にすぎない と『ポール自身や関係者は、ポールが裸足にしたのは「暑さ」「サンダルを脱いだ」「靴がきつかった」など、ごく実際的な理由だと説明している という証言が複数あります。』と ネットから。真実は如何に!!🏛 現在の様子・この横断歩道は今も観光名所として有名で、世界中のファンが同じポーズで写真を撮る。・スタジオ前の白い壁は「ファンのメッセージボード」として知られ、定期的に塗り替えらる。・2010年にはイギリス政府により「文化遺産(Grade II Listed Site)」に指定された と。そして、予習を完了し、本物の「Abbey Road」に向かって歩を進めたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.16
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その109): ロンドン散策記・ビートルズ ロンドン ウォーキング ツアー-3
【海外旅行 ブログリスト】👈リンクLittle Argyll St(リトル・アーガイル・ストリート)をRegent St(リージェント・ストリート)に向かって進む。両側に壮麗な建物が並び、遠方に見えるのは アーガイル・アーケード風の門とドーム屋根の建物(Regent Street Quadrant の一部)。通り自体は短く、Carnaby Street 方面と Regent Street をつなぐ通りとして知られている と。Little Argyll Street の突き当たり(リージェント・ストリート側) にあるのが、有名な Apple Store Regent Street(アップルストア・リージェントストリート店)。・2004年に開店したヨーロッパ初のApple Storeで、世界的に象徴的な旗艦店・中核店舗。・2016年に大規模リニューアルされ、現在のガラス張り+大理石調のモダンな空間になった。・店内は「Today at Apple」などイベントも多く、ただの販売店というより カルチャーの 発信地的存在。・ロンドン観光の人気スポットのひとつで、世界中からの旅行者が立ち寄る と。そしてリージェント・ストリート(Regent Street)に出て左折。・Piccadilly Circus(ピカデリー・サーカス) → 直進・Trafalgar Square(トラファルガー広場) → 直進・Marble Arch(マーブル・アーチ) → 右方向右手にあったのがPaul & Shark(高級カジュアルブランド)の店舗。リージェント・ストリート(Regent Street)を南に進む。Regent Street W1(リージェント・ストリート) のストリートサイン。所在地は City of Westminster(シティ・オブ・ウェストミンスター)。オックスフォード・サーカス(Oxford Circus)駅からピカデリー・サーカス(Piccadilly Circus)駅方向へ南下するリージェント・ストリート(Regent Street)沿いの左側に建つ、いわゆる「Regent Street Quadrant(リージェント・ストリート・クアドラント)」地区の壮麗なカーブを描く建物群。ロンドン・リージェント・ストリート(Regent Street) の名所のひとつ。・1〜2階:商業テナント(ブランドショップ、カフェなど)・上階:オフィス・高級レジデンス(The Quadrant Residences)Regent Street Quadrant Block(リージェント・ストリート・クアドラント南街区)の建物。このリージェント・ストリートは、1960年代の「スウィンギング・ロンドン」を象徴するショッピング大通りで、音楽やファッションの発信地でもありました。ビートルズも当時のロンドン文化の中心地にたびたび現れ、また音楽雑誌やテレビ撮影の舞台として、この界隈が頻繁に登場。このまま進むと、ピカデリー・サーカス(Piccadilly Circus) の方向に。リージェント・ストリート(Regent Street) をさらに進む。左側に赤い旗のたなびく店「Hamleys(ハムリーズ)」が見えた。奥には緑色の丸屋根を持つ建物・RLegal Solicitors Londonが連なり、リージェント・ストリート特有の統一された曲線的な街並みが続いていた。リージェント・ストリートにある Hamleys(ハムリーズ)本店。1760年創業の世界最古の玩具店の一つで、ロンドン観光名所の一つ。世界最大級の玩具店として知られ、7フロアにわたり50,000点以上のおもちゃ・TOYSが並ぶ と。New Burlington Pl通りの次の路を右折して。New Burlington Street(ニュー・バーリントン・ストリート) の通り標識。 Heathcoat House(ヒースコート・ハウス)の先の突き当りの建物。New Burlington Street と Savile Row の角付近に位置。シンプルでモダンな外観、正面にイギリスの ロイヤル・コート・オブ・アームズ(紋章)が掲げられていた。そして前方右に見えて来たのが、サヴィル・ロウ3番地(3 Savile Row)、かつての Apple Corps本社ビル。外観はジョージアン様式に近い落ち着いた石造りで、角が丸く取られているのが特徴。ビートルズが1969年1月30日に最後のライブ「ルーフトップ・コンサート」を行った屋上がここである と。手前のビルの壁に、ロンドンでよく見られる ブルー・プラーク(Blue Plaque) が掲げられていた。ブルー・プラークは歴史的に著名な人物が暮らした、または活動した建物に設置される記念標識。「The BeatlesPlayed their last live performanceon the roof of this building30th January 1969」【ビートルズこの建物の屋上で最後のライブ・パフォーマンスを行った1969年1月30日】 但し、このビルの屋上で行われたのではなく、その前にあった当時の Apple Corps 本社ビル(3 Savile Row の比較的小さなジョージアン様式の建物) の屋上で最後のライブ・パフォーマンスが行われたのだと。ビートルズの最後のライブ「ルーフトップ・コンサート」(1969年1月30日)の写真。ネットから。1969年1月30日、3 Savile Row にあった Apple Corps 本社ビル(当時の小さなジョージアン様式の建物)の屋上。ネットから。これはサヴィル・ロウ(Savile Row)での象徴的なデモの様子 と。横断幕には「GIVE THREE-PIECE A CHANCE」(三つ揃いスーツにチャンスを!)と書かれています。これはビートルズの「Give Peace a Chance」をもじったもの。サブのメッセージとして「SAVE SAVILE ROW FROM ABERCROMBIE & FITCH」(サヴィル・ロウをアバクロンビー&フィッチから守れ)とあります。ズームして。・サヴィル・ロウはロンドンの伝統的な仕立て屋街で、19世紀以来「ビスポーク・テーラー (オーダーメイド紳士服)」の聖地とされていた。・ところが 2010年代にアメリカのカジュアルブランド「Abercrombie & Fitch」が サヴィル・ロウに進出しようとしたことに対して、伝統の崩壊を懸念する仕立て職人たちや 市民が抗議デモを行った。・その際、スローガンとして「GIVE THREE-PIECE A CHANCE」が使われた と。サヴィル・ロウ(Savile Row) の街路標識。繰り返しになるがサヴィル・ロウの特徴・18世紀から続く ビスポーク・テーラー(オーダーメイド紳士服) の聖地。・「スリーピーススーツ」の本場として、世界中の王侯貴族や著名人が顧客。・英国スタイルの象徴として「サヴィル・ロウ仕立て」という言葉自体がブランド化していた。ビートルズとの関係・アップル・コア本社(Apple Corps Ltd.) が 1968年から 3 Savile Row に置かれていた。・1969年1月30日、このビルの屋上で ビートルズ最後のライブ「ルーフトップ・コンサート」 が行われた。・そのため、サヴィル・ロウは音楽ファンにとっても特別な場所。象徴的な出来事・2000年代に「Abercrombie & Fitch」がサヴィル・ロウに進出しようとした際、地元の仕立て屋 たちが「GIVE THREE-PIECE A CHANCE」と訴えて抗議デモをしたことでも知られている (先ほどの写真)。前方左に見えて来たのが ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(Royal Academy of Arts, R.A.)。ピカデリー通り(Piccadilly) に面しており、もともとは17世紀の貴族邸宅でした。19世紀にロイヤル・アカデミーを含む学術団体の拠点となり、正面ファサードはその後ヴィクトリア時代に改修されて現在の壮大な姿となっている と。建物の特徴・ロンドンの ピカデリー に位置し、1768年創立の英国を代表する美術アカデミー。・正面は壮大な ネオクラシカル様式 のファサードで、柱や彫像の装飾が特徴的。・彫像のニッチ(壁龕)には、芸術や学問を象徴する人物像が配されている。ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(Royal Academy of Arts, R.A.)の正面壁面に並ぶ 彫像群。左端の像・LEIBNITZ(ライプニッツ) – ドイツの哲学者・数学者中央の像 ・CUVIER(キュヴィエ) – フランスの博物学者(比較解剖学・古生物学の祖)右端の像 ・LINNAEUS(リンネ) – スウェーデンの植物学者(分類学の父)ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(Royal Academy of Arts, RA) の正面(バーリントン・ハウスのファサード)・コリント式の円柱 が並び、古典建築様式を取り入れた壮麗なポーチ部分(柱廊)が印象的。・ファサード上部には、複数の 立像(彫像) が屋根の縁に並んでいます。これらは古代の神々や 寓意的人物(芸術・学問の象徴)を表しており、アカデミーの精神を象徴。・壁面の赤茶色(テラコッタ調)部分は装飾的に切り替えられており、白い石材とのコントラスト で堂々たる存在感。・ファサードに掲げられた赤い旗「RA」は、まさにロイヤル・アカデミーのシンボルで、現在の 展覧会やイベントが告知されていた。ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(Royal Academy of Arts, RA)の正面部分。赤い旗「RA」は、展覧会やイベントを告知するバナーで、現在もこのファサードの象徴的存在。ロイヤル・アカデミー正面の彫像は、上部の立像群を含め 古代の哲学者や芸術の擬人像 が配置されており、例えば:・ソクラテス(哲学)・ミケランジェロ(芸術・彫刻)・ラファエロ(絵画)・ベーコン卿(科学) などが含まれると。左から・アダム・スミス・ Adam Smith– 経済学の祖、『国富論』著者・ジョン・ロック・John Locke – イギリスの哲学者、近代自由主義の祖・フランシス・ベーコン・Francis Bacon – イギリスの哲学者、経験論の祖全景をネットから。Burlington Arcade(バーリントン・アーケード) の入口・開業年:1819年・特徴:ロンドンで最も古いショッピング・アーケードのひとつ。・場所:Piccadilly と Burlington Gardens を結ぶ細長いアーケードで、Royal Academy of Arts (Burlington House)のすぐ隣に位置。・デザイン:細長いガラス屋根の通路に沿って、両側に高級ブティックや宝飾店が並んでいた。・歴史的役割:もともとは「上流階級の女性が雨に濡れずに安全に買い物できる場所」として 建てられた と。・高級時計、宝飾品、香水、靴、紳士服などの専門店が軒を連ねています。・「Beadles(ビードルズ)」と呼ばれる制服姿の警備員が常駐しており、アーケードの伝統と 秩序を守っていることでも有名。「Burlington House(バーリントン・ハウス)」 の一部、つまり ロンドンのピカデリーにある由緒ある建物群。Royal Academy of Arts(RA/王立芸術院)が入る Burlington House の横手の入口部分。・壁に掲げられているのは RA(Royal Academy of Arts)の紋章。 ・王冠と「RA」のモノグラム(Royal Academy の頭文字)がデザイン。 ・周囲の花輪装飾は、英国を象徴する植物(バラやアザミなど)があしらわれていた。・下の鉄格子の門は、Burlington House の横通路やサービス入口の一部。・左側には Burlington Arcade(バーリントン・アーケード) への入口が少し見えている。Burlington Arcade(バーリントン・アーケード)の内部を見る。そして、Bond Street(ボンド・ストリート) にあった彫刻"Horse and Rider"(馬と騎手)。作品名: Horse and Rider作者: Elisabeth Frink(エリザベス・フリンク、1930–1993、イギリスの著名な彫刻家)設置年: 1975年場所: ロンドンのニュー・ボンド・ストリート(Cartier 前、住所 103 New Bond Street あたり)特徴:・馬にまたがる裸の男性像。英雄的でも勝利を誇るでもなく、むしろ沈思するような静けさを帯びて いるのが特徴。・エリザベス・フリンクの作品は「人間存在の脆さや内面性」を強調するものが多く、この像も 威厳よりも「内省的な人間と動物の関係」を表現している と。ロンドン・ウェストミンスター地区の通り標識で、「BURLINGTON GARDENS W1」(バーリントン・ガーデンズ、郵便区 W1、シティ・オブ・ウェストミンスター)。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.15
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その108): ロンドン散策記・ビートルズ ロンドン ウォーキング ツアー-2
【海外旅行 ブログリスト】👈リンクBroadwick StreetをCarnaby Streetに向かって進む。Broadwick Streetはソーホーの中心部にあり、細い石畳の道が特徴。この通りを抜けると「Carnaby Street・カーナビー・ストリート」に突き当たるのであった。Carnaby Street(カーナビー・ストリート)の入口手前 に差し掛かったところ。奥のほうに見える通りがカーナビー・ストリートで、さらに右に進むと、有名な「CARNABY」のゲートが出迎えてくれたのであった。カーナビー・ストリートの象徴的なウォール・モザイク(壁画)・Spirit of Soho Mural👈️リンク が左前方に見えて来た。制作は1991年、地元アーティスト Freeform Arts Trust による作品。ロンドン・ソーホー地区の 歴史・音楽・演劇・文化 を一枚の大きなモザイクで表現していた。中央には地図のようにソーホーの街並みが描かれ、その周囲に有名人や象徴的な場面が散りばめられているのであった。ソーホーの街並みをズームして。🔹全体構図・女性像の形をした都市の精霊(あるいは「都市の女神」)がテーマ。 ・胸部には “Estilo”(スペイン語で「様式」や「スタイル」)の文字。 ・彼女の身体が「街の地図」になっており、さまざまな地区や名所がモザイクで描かれている。 ・頭部や髪は波のように流れ、背後の青い曲線は海または川を示していると考えられる。🔹下部の要素(足元〜裾)・赤い電話ボックスや円柱建築(ロンドンのシティを象徴する古典的建物)が見える。・“SHREWSBURY”という文字が読めるため、これはイングランドのシュルーズベリー (Shrewsbury)の壁画。 ・赤い屋根の建物はThe Square(市の中心広場)のマーケットホール。 ・白黒の木組み家屋は、チューダー様式の旧市街を象徴。🔹中央部分・大聖堂や時計塔など、街の主要なランドマークが並びぶ。・人物の腰の位置付近にパイナップルのモチーフがあり、これはShrewsburyの名産である 異国趣味・交易・園芸文化を表すシンボル。・周囲には、劇場・フェア・農業・川の風景(River Severnなど)がモザイクで ちりばめられている。壁画の構成と意味1.中央の女性像 ・「SOHO」と胸に書かれた女性が街を抱きかかえる姿は、ソーホーを芸術と文化の母のように 表現しています。2.地図のようなパネル ・ソーホー周辺の街路(Oxford Street, Carnaby Street など)が描かれていて、観光地図の 役割を兼ねています。 ・ファッション、映画館、劇場、カフェ、クラブなどがモザイクで配置されており、60〜70年代 の文化的多様性を示しています。3.下部の著名人たち ・ソーホーと関わりのある 作家・音楽家・俳優 が描かれています。チャールズ・ディケンズや カール・マルクスなど歴史上の人物に加え、音楽関係者も。 ・直接ビートルズの肖像はありませんが、彼らと同時代にこの街から発信されたカルチャー 全体がテーマになっています。4.左右の縦パネル ・左側にはファッション、報道、メディアに関連するイメージ。 ・右側にはロンドン・パラディウム劇場など舞台芸術のシーンが描かれています。 ・これらは「ソーホー=ファッション、音楽、演劇の街」であることを示しています。5.時計と3人の人形 ・下部の時計の上に立つ3人の人形は、ソーホーを代表する文化人の象徴(演劇や文学の イメージキャラクター)。左から順に、典型的な 啓蒙時代の紳士・淑女・哲学者風の人物 が 描かれています。 ・毎時動く仕掛けがあり、観光客に人気です。下部中央にある「時計」と「歴史的人物群像」を ズームして。 ・真ん中の本には “D.K.” とあり、これはロンドンを拠点に活動した出版社 「Dorling Kindersley(ドーリング・キンダースリー)」を示しているとも言われます この壁画のスポンサー関係であると。周囲に描かれている著名人モザイク全体にはソーホーに関わりのある歴史的人物が細かく描かれていて、この部分には特に以下のような人々が含まれると。・カール・マルクス(中央奥、本を読んでいる白髭の人物) → かつてソーホーに居住し、『共産党宣言』執筆期のロンドン滞在地でした。・チャールズ・ディケンズ(青い衣装の紳士として描かれていると言われる) → 作品にロンドン下町の描写を多く残した作家。・その他、作曲家、哲学者、演劇関係者なども混じって描かれている と。時計が時を告げると、 カール・マルクスがコーラを飲み、カサノバ役のテレサ・コーネリスがウィンクし、カサノバが キスを返す と。下記3枚の写真はネットから。「THE SPIRIT OF SOHO MURALThe Spirit of Soho mural was created by the Soho community and completed in 1991.It shows Soho life and is dedicated to the people of Soho. The mural depicts St Annepresiding over local notables; her skirt and petticoats show the map of Soho,craftsmen and London landmarks. Framed underneath are the portraits of Soho’s many famousfigures. Dogs and hares are interspersed which represent a time when Sohowas a Royal hunting ground.Restored in 2006 by Shaftesbury PLC and The Soho Society, the clock was re-activatedbyThe Lord Mayor of Westminster 19th October 2006.Don’t miss:When the clock strikes on the hour: watch actress and opera singer Theresa Cornelyswink at Casanova, Casanova blows a series of kisses to Cornelys and Karl Marx takesasip of Coca Cola.」 【ソーホーの精神 壁画「ソーホーの精神」壁画はソーホーの住民たちによって制作され、1991年に完成しました。これはソーホーの生活を描き、ソーホーの人々に捧げられています。壁画には聖アンが地域の著名人たちを見守る姿が描かれており、彼女のスカートとペチコートにはソーホーの地図、職人、ロンドンのランドマークが表現されています。下部にはソーホーにゆかりのある数多くの著名人の肖像が描かれています。犬や野ウサギも散りばめられており、これはソーホーが王室の狩猟地であった時代を象徴しています。この壁画は2006年に Shaftesbury PLC と ソーホー協会(The Soho Society) によって修復され、同年10月19日、ウェストミンスター市長によって時計が再稼働されました。見どころ:毎正時になると、女優でオペラ歌手の テレサ・コーネリス がカサノヴァにウィンクし、カサノヴァは彼女に一連のキスを投げかけ、カール・マルクス はコカ・コーラを一口飲む仕掛けが動き出します。】ソーホー・モザイク壁画(Soho Mural) に描かれている人物たちの 番号付きガイドプレート。この案内板は、レリーフの人物位置番号と名前を示す「キー(key to figures)」で、計 54 名(+動物)ほどの肖像を図示しています。たとえば:番号 人名 分野/備考1 John Christopher Smith 作曲家(ヘンデルの弟子)2 John Logie Baird テレビ放送の発明者3 William Blake 詩人・画家4 William Hazlitt 文筆家・評論家5 Al Purchase ソーホー開発初期の地主6 Ann Louise de Staël フランス作家7 John Pine 彫刻師・版画家8 Joseph Nollekens 彫刻家9 Crespin サクソフォーン奏者、作曲家、指揮者10 William Hogarth 画家・版画家(ソーホー生まれ)11 Handel 作曲家12 Isaac Newton 物理学者(王立協会関連)13 Antonio Canaletto 景観画家、版画家14 Mrs. Brook 女優、ダンサー 15 Chevalier d’Eon 外交官、スパイ16 Sir Cloudesly Shovel 海軍提督 政治家17 Jean-Paul Marat 政治理論家、医師、科学者 18 Samuel Squire 司教19 Sir Joshua Reynolds 画家20 Henry Angelo 回想録作家、フェンシングの名手21 Mrs. Charles Kemble 女優22 John Snow 近代公衆衛生の父(コレラ調査)23 John Fawcett 俳優・劇作家24 David Hume 哲学者25 Mrs. Bateman 俳優・劇作家26 David Garrick 俳優・劇作家27 John Dryden 詩人・劇作家 28 Charles Kemble 俳優29 Edmund Keene 聖職者 司教30 Fanny Kelly 開拓者女性31 Richard Wagner 作曲家(ロンドン滞在経験)32 Gaston Berlemont パブ経営者33 Edmund Burke 政治思想家、哲学者、政治家34 Sir Ashton Lever 自然物収集家35 Percy Bysshe Shelley 詩人36 Maud Stanley 女性福祉活動家37 Fanny Kemble 女優・作家38 James Boswell 法律家・作家39 Josiah Wedgewood 陶芸家・事業家40 Angelica Kaufman 画家41 Peter Vanderbank 彫刻家42 Flaxman 彫刻家43 Beckford サッカー選手44 Paul Verlaine 詩人・作家45 John Hunter 政治家46 Wolfgang Amadeus Mozart 作曲家(1770年代にソーホーに居住)47 Karl Marx 哲学者・社会主義思想家(Dean Street居住)48 Theresa Cornelys オペラ歌手・興行師 49 Casanova 冒険家・作家50 Jessie Matthews 女優・ダンサー51 George Melly ブルース歌手52 Dylan Thomas 詩人・作家53 Brendan Behan 詩人・短編小説家・小説家54 Jeffrey Bernard ジャーナリスト55 Ronnie Scott ジャズ ・テナーサックス奏者ソーホー壁画(Soho Mural) の中心付近、「フルーツと地図」が広がるモザイクの拡大。ソーホーの文化的・商業的ランドマークや象徴がぎっしり詰め込まれているのであった。フルーツと野菜(パイナップル・オレンジ・ぶどうなど)・ソーホーの多文化市場・食文化を象徴。・Berwick Street Market(ベリック・ストリート・マーケット/青果市場で有名)を示していた。ソーホー壁画(Soho Mural)の右側、縦に並ぶ3つの絵は、「劇場・娯楽・酒場文化」 を象徴する部分 と。① 最上段「PALLADIUM(パラディウム劇場)・London Palladium はロンドンを代表する老舗劇場。・ビートルズが1963年10月13日に出演した「Sunday Night at the London Palladium」で テレビ放送され、一気に全国区の人気を獲得した。・この出演をきっかけに「ビートルマニア」という言葉が初めて使われた と。② 中段「カーナビー・ストリートと若者文化」・赤いカーテンに囲まれた舞台風の構図。・中央には「Carnaby Street」のゲートのようなアーチ。・1960年代の若者たち(ミニスカート、カラフルなファッション)と、買い物客や音楽シーンの 人々が描かれていた。③ 下段「パブとジャズセッション」・ソーホーのもうひとつの顔「パブ文化」「ジャズクラブ」を表現。・手前ではサックス奏者が演奏し、奥ではビールやワインを片手に議論する人々。・ソーホーはジャズやブルースの発祥地のひとつで、ビートルズも同時代にここから 影響を受けたカルチャーの中で活動していた。ビートルズとの関わり・Palladium → ビートルズが一躍スターになった場所・Carnaby Street → ビートルズのファッションや若者文化の舞台・ジャズクラブ/パブ文化 → ロンドン音楽シーンの根幹としてビートルズ世代に大きな影響 と。ソーホー壁画(Soho Mural)の左側、① 最上段「アニメーション/映画制作」・セル画、撮影用カメラ、作業机、鉛筆を走らせる制作者など、ソーホーの映像・アニメ産業を 象徴。・壁に貼られたラフスケッチや、机上の小道具(ウサギ等)は、CM・短編・実験アニメの盛んな 制作現場を暗示。・ソーホーは長年、ポストプロダクション(編集/音響/VFX)のメッカで、広告・MV・映画の 拠点が集中。②中段「衣装・舞台芸術・デザイン」・緞帳(どんちょう)や布地、ボディ(トルソー)、マイクや照明、人物スケッチ等が見え、 仕立屋・衣装部・舞台美術の町としての顔を強調。・ソーホーには歴史的に衣装店・小規模アトリエが多く、演劇・TV・映画のコスチューム 供給地として機能。・周囲の象徴図像(メダルや道具)は、職人技と表現産業の近接を示す。③ 下段「ベリック・ストリート・マーケットと“食”の多文化」・びっしり描かれた野菜・果物のレリーフ、露店、食卓、調理風景。中央のテーブルには ユニオンジャックのモザイク=多文化が“食卓”で交わることの比喩。・Berwick Street Market はソーホーの生活文化の核。移民コミュニティの台所を支え、 カフェ/デリ/屋台が混在して独特の日常風景を作る。・下縁のパンや野菜のタイル帯は、市場→街→人へ循環する活力のメタファー。ビートルズとの関わり・映像制作:ソーホーのTV/映像拠点が、ビートルズのTV露出やプロモ映像を支えた。・衣装・デザイン:カーナビー周辺の衣装文化が、彼らのビジュアル戦略 (衣装・写真・ジャケット)に直結。・多文化と場:ベリック・ストリートの市場/カフェ文化と近隣スタジオが、制作・交流の 土壌を提供。要するに、ソーホーは「映像」「装い」「場づくり」の三位一体で、ビートルズの表現力と発信力を押し上げた、ということであろう。Broadwick Street(ブロードウィック・ストリート) のサイン。場所は Soho(ソーホー)地区の中心 で、音楽史やカルチャーにとって非常に重要な通り。・Broadwick Street, Soho, London W1 ・行政区:City of Westminster(ウェストミンスター区) ・郵便区域:「W1」はロンドン中心の高級商業・文化エリア (Mayfair, Soho, Fitzroviaなど)を示す郵便コード。Broadwick Street の地下トイレ跡(現在は閉鎖中)を再び説明。ソーホー地区はビートルズが若い頃に頻繁に出入りしていた場所で、Broadwick Street のこのトイレや周辺は 当時のカルチャーやアンダーグラウンド文化の象徴 としてこのツアーに組み込まれていたのであろう。これはビートルズのアルバム 『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』(1967年) の有名なジャケット写真。下記写真はネットから。ジャケットの特徴・デザイン:ポップアーティストのピーター・ブレイクとジャン・ホーソン。 撮影はマイケル・クーパー。・コンセプト:架空の“ブラスバンドの記念写真”。色鮮やかな軍楽隊風コスチューム、 巨大なバスドラム、観客=歴史上の著名人たちの等身大カットアウトを並べ、立体の セットを組んでスタジオで撮影。・フラワーパワー全盛のサイケデリックな雰囲気を持ち、ビートルズの「変身バンド (架空のバンド)」というコンセプトを表現。・背景には歴史上・文化上の著名人がコラージュされており、総勢70人以上の人物が登場します。・前面の花壇に「BEATLES」の文字が花で描かれています。そしてカーナビー・ストリート(Carnaby Street) に入って。「Carnaby Street」のゲートアーチが前方に。Carnaby Street(カーナビー・ストリート)・場所: ロンドン・ソーホー地区。・歴史: 1960年代「スウィンギング・ロンドン」の中心地。ファッションや音楽の最先端を担い、 若者文化の象徴となりました。・ビートルズとの関わり: ・ビートルズ自身もこの界隈のブティックやクラブに出入りしていました。 ・特に彼らの音楽仲間や、同時代のローリング・ストーンズ、フー、キンクスといった バンドもこの通りのカルチャーに深く関わっています。 ・「Apple Boutique」(ビートルズが経営した店)は少し離れた場所(ベイカー・ストリート 近く)にありましたが、同じく「音楽とファッションの融合」を目指した店づくりで、 カーナビー・ストリートの流れと共鳴していました。ガイドが「TIME誌の表紙」を。・見出し: 「LONDON: The Swinging City」・発行: 1966年4月15日号・特集内容: 1960年代半ばのロンドン、 特にソーホーやカーナビー・ストリートを中心とした 「スウィンギング・ロンドン(Swinging London)」カルチャーを世界に紹介。ネットから。1966年4月15日号のTIME誌、表紙を飾った「Swinging London(スウィンギング・ロンドン)」特集・イラスト: ・背景には ビッグ・ベン、ユニオンジャック。 ・カラフルな若者たちのファッション(チェッカーパターン、ミニスカートなど)。 ・「BINGO」「DISCOTHEQ」「CAFE」「Join the Tea Set」など、当時のソーホーや カーナビー・ストリートの看板を模したポップアート風描写。 ・右下には THE WHO の文字(ユニオンジャック柄のサングラスをした若者が象徴)。 ・ロンドンの若者文化(ファッション、音楽、ナイトライフ、クラブ文化)がぎっしり 詰め込まれています。・ビートルズとの関わり ・この特集が出た 1966年4月は、ビートルズがすでに世界的人気を確立しつつ、同時に 音楽的に大きな転換期を迎えていた時期です。 ・翌5月に「リボルバー」のレコーディング開始。 ・同年8月に最後のツアーを終え、スタジオワークに専念。 ・TIME誌の特集では、直接ビートルズの写真が表紙に出たわけではありませんが, 彼らが築いたカルチャーと一体となった“Swinging London”全体を紹介する大きな役割を 果たしました。この号はアメリカをはじめ世界中で読まれ、「ロンドン=若者文化の最先端」「音楽・ファッション・アートの発信地」というイメージを一気に広めたのであった。Carnaby Street(カーナビー・ストリート) にあるシューズショップ 「OFFICE」 の店舗。店舗外壁右上に小さく「CARNABY STREET」と書かれていて、観光客に分かりやすいフォトスポット。ズームして。ロンドン・ソーホーの Carnaby Street(カーナビー・ストリート) の街路標識。Carnaby Street(カーナビー・ストリート)入口のアーチゲート。「WELCOME TO CARNABY STREET」と書かれたこのゲートは、ソーホー地区のランドマークであり、観光客の撮影スポットとしても有名。カーナビー・ストリートの歴史とビートルズとの関わり・1960年代の「Swinging London」の中心地 カーナビー・ストリートは、モッズやヒッピー、サイケデリックなどのファッション発信地で、 若者文化の象徴でした。 ビートルズ、ローリング・ストーンズ、フー(The Who)、キンクスなど多くのミュージシャン が訪れたことでも知られています。・ビートルズの足跡 ビートルズは頻繁にこのエリアを訪れ、衣装や舞台衣装を揃えました。特にジョン・レノンと ポール・マッカートニーは、革新的なファッションを求めてカーナビーのブティックに 通っていたと言われています。・当時の有名ブティック ・Lord John(カラフルなスーツで有名) ・Granny Takes a Trip(サイケデリックファッションの代表格) ・I Was Lord Kitchener’s Valet(軍服をリメイクした衣装を販売、 ロックミュージシャン御用達)アーチゲートをくぐってすぐに見えるパブ(The Shakespeare’s Head) の角を見る。Carnaby Street(カーナビー・ストリート)の北側の入口付近。建物と現在の姿・赤レンガに白い石を縁取ったゴシック風の建物で、ソーホーらしい雰囲気を残しています。・1階部分に入っているのは 「The Shakespeare’s Head」パブ。名前の通りシェイクスピアを 冠した伝統的な英国パブ。・入口の上には、シェイクスピアの胸像が飾られていて、観光客に人気の撮影スポットに なっていた。Shakespeare’s Head(シェイクスピアズ・ヘッド)パブ の全景。・シェイクスピアの看板 正面に掲げられている大きなパブサインは、シェイクスピアの肖像(マーティン・ ドレッシュアウトによる有名な版画を元にしたデザイン)。・等身大の胸像 建物の角上部に取り付けられた胸像は、シェイクスピアが通りを見下ろす姿。 案内板にも書かれていたとおり、爆撃で片手が失われていた。・案内板(赤いパネル) 「1735年に建設されたこと、シェイクスピアの遠縁による所有、周辺の歴史、爆撃で 片手が失われた胸像の逸話」などが書かれていた。シェイクスピアが通りを見下ろす姿をズームして。・像の特徴: ・青いルネサンス風の服装 ・顎に手を置き、物思いにふけるようなポーズ ・窓枠に身を乗り出す構図で、まるで通行人を見下ろしているようにデザイン像は「羽ペン(quill)」や「巻物(manuscript)」を手にしていたと考えられていると。「第二次世界大戦中に近くに爆弾が落ち、その衝撃で右手が破壊された」とあった(下記)がその真偽はいかに??「SHAKESPEARE’S HEADThe Shakespeare’s Head, which was built in 1735, was originally owned by Thomas & John Shakespeare, who were distant relatives of the poet. In its early days, the tavern stood on the boundary line that divided the lands of the Mercers Company from those of the Abbot of Abingdon, and nearby was a small estate known as Six Acre Fields. During the Victorian period, the field was a site of the riding school, belonging to Major Henry Foubert, whose name is commemorated by neighbouring Foubert Place. The present day Shakespeare’s Head overlooks Carnaby Street which was once the site of an 18th century street market and is now one of the world’s most famous shopping precincts. Dominating its northern end is the pub inn sign, which is a reproduction of Martin Droeshout’s portrait of Shakespeare when the poet was at the pinnacle of genius. On another part of the building is Shakespeare’s life size bust, which appears to be gazing down at the busy street below. A close examination of the bust will show one of the poet’s hands is missing. This occurred during World War II when a bomb dropped nearby.」 【シェイクスピアズ・ヘッドシェイクスピアズ・ヘッドは1735年に建てられ、もともとは詩人シェイクスピアの遠縁にあたるトーマスとジョン・シェイクスピアが所有していました。創建当初、この酒場はマーサーズ・カンパニーの土地とアビンドン修道院長の土地を分ける境界線上にあり、近くには「シックス・エーカー・フィールズ」と呼ばれる小さな地所がありました。ヴィクトリア朝時代には、この地はメジャー・ヘンリー・フーベールが経営する乗馬学校の敷地となり、隣接するフーベール・プレイスという地名にその名が残されています。現在のシェイクスピアズ・ヘッドはカーナビー・ストリートに面しており、この通りはかつて18世紀のストリートマーケットが開かれていた場所で、今では世界で最も有名なショッピング街のひとつになっています。建物の北側を飾るパブの看板は、マーティン・ドレッシュアウトによるシェイクスピアの肖像画を再現したもので、詩人が才能の頂点にあった時期の姿を描いています。さらに建物の別の場所には等身大のシェイクスピア像があり、忙しい通りを見下ろしているように配置されています。この胸像をよく観察すると、詩人の片手が欠けていることに気づきますが、これは第二次世界大戦中に近くに爆弾が落ちた際に損傷したものです。】ロンドン・パラディウム(The London Palladium)。こちらはロンドン・ソーホー地区にある有名な劇場 ロンドン・パラディウム。1906年に開場し、ヴォードヴィルやミュージカル、コンサートなど、100年以上にわたり世界的スターが舞台に立ってきた由緒ある会場である と。正面から。ビートルズとロンドン・パラディウム・1963年10月13日、ビートルズがこの劇場の人気番組 「サンデー・ナイト・アット・ザ・ ロンドン・パラディウム」 に出演しました。・この放送は全国に生中継され、視聴者は1500万人以上。・番組をきっかけに、翌日から英国中で「ビートルマニア(Beatlemania)」という言葉が 新聞の見出しに踊りました。・つまり、ここは ビートルズが全国的な大スターへと飛躍する転機となった場所と言えるのだ。Great Marlborough Street(グレート・マールボロー・ストリート)を歩く。この通りはロンドンのソーホーとメイフェアの境界近くを走る重要な道で、有名な カーナビー・ストリート のすぐ北側を東西に伸びていた。・EMI本社(後のAbbey Road Studiosの親会社) がこの通りに位置しており、 ビートルズのレコード制作に大きく関わったと。・また、この界隈は1960年代「Swinging London」を象徴するエリアの一つで、ビートルズを はじめとしたアーティストやファッション関係者が集う拠点であったのだ。Great Marlborough Street(グレート・マールボロー・ストリート)から東方向(オックスフォード・サーカス方面)を望む。・ 右側(白い石造りの建物) ・クラシックな銀行建築のような荘厳な造りで、現在はオフィスやショップが入っている。 ・この通り(Great Marlborough Street)は、カーナビー・ストリートのすぐ北を並行して 走っており、買い物客や観光客が多いエリア。・ ビートルズとの関わり リバティ百貨店は、ビートルズのメンバー(特にジョン・レノンとポール・マッカートニー) が衣装や雑貨を購入した場所として知られている。 サイケデリック時代のファッションの影響を強く受けた彼らは、リバティの鮮やかな柄物や 個性的なデザインを取り入れていた と。・左側(黒と白の木組み風の建物) ・これは Liberty London(リバティ百貨店)。 ・1875年創業の老舗デパートで、チューダー様式の木組み建築が印象的。 ・1960年代の「Swinging London」時代には、ミック・ジャガーやジョン・レノン、 ビートルズ関係者などが訪れたファッション拠点でもあった と。 ・「リバティ・プリント」と呼ばれる花柄や幾何学模様の生地は、ビートルズ世代の ファッションにも影響を与えた。ズームして。Argyll St(アーガイル・ストリート)の角の建物は大規模工事中。足場パイプの多さ、複雑さにビックリ!!地震の少ない国ではの姿、強風では心配!!Argyll St(アーガイル・ストリート)にあったのがMarugame Udon(丸亀製麺)ロンドン店。日本発の讃岐うどんチェーン「丸亀製麺(Marugame Udon)」のロンドン店舗。看板には 「Japanese Noodles & Tempura」 とあり、うどんと天ぷらを中心に提供 と。・ロンドンでは2021年頃から展開を本格化し、特にソーホーやカーナビー・ストリート周辺の 観光・商業エリアに出店。・日本と同様に「セルフスタイル」でうどんを選び、天ぷらやおにぎりなどをトレイに取って 会計する形式。・ロンドンでも人気が高く、ランチタイムには列ができることが多いのだ と。右手にあったのがThe London Palladium(ロンドン・パラディウム劇場)。・ロンドンの ウエスト・エンド(West End) を代表する劇場のひとつ。・1910年に開館し、エドワード様式のファサードが特徴的。・外観は列柱とバルコニーを備えた古典的な意匠で、今日でもロンドンのランドマーク的存在。見上げて。「PALLADIUM」と。・「パラディウム(Palladium)」とは、女神アテナ像のことで、都市を守護する聖なる守り 神像を指す。London Palladium(ロンドン・パラディウム)・ロンドンのウエスト・エンドにある有名な劇場。1910年開場。・1920年代〜60年代にかけて「ヴァラエティ(音楽・コメディ・レビュー)」の殿堂として 名を馳せ、エルヴィス・プレスリーやビートルズも出演しました。・特にビートルズは1963年10月13日の出演が「Beatlemania(ビートルズ熱狂現象)」を 全国に広めたきっかけとして知られている。この写真は、この発言は、1966年3月にイギリスの新聞 Evening Standard に掲載された モーリーン・クリーヴのインタビュー記事で語られた内容の一部です。その中でジョンは、「キリスト教は衰退しつつある」「ビートルズは今やイエスより人気がある」といった趣旨の発言をしていました。イギリスでは大きな問題になりませんでしたが、アメリカで 「Datebook」誌 がこの発言を取り上げたことで大炎上。南部を中心に「ビートルズのレコード焼き討ち」や「放送禁止運動」が広がり、最終的にジョンはアメリカで謝罪会見を開くことになりました。にビートルズが ロンドン・パラディウム に出演した際の有名な場面を写したもの と。・ビートルズは ITV のテレビ番組 『Sunday Night at the London Palladium』 に出演。・出演後、劇場前に大勢の若者やファンが殺到し、ものすごい熱狂状態に。・この模様をマスコミが「ビートルマニア (Beatlemania)」と呼んだのが、世界的に使われる ようになった最初のきっかけ と。この写真はビートルズとジャーナリスト・モーリーン・クリーヴ(Maureen Cleave) が一緒に写っている有名な1枚 と。モーリーン・クリーヴが真ん中に座り、その周囲を4人のビートルズが囲んで談笑しているシーン。・モーリーン・クリーヴは 『イブニング・スタンダード』紙 の音楽記者で、1960年代の ロンドン音楽シーンを積極的に取材した。・彼女はビートルズとも親しく、インタビューを通して人間的な素顔を引き出したことで 知られている。・特に 1966年3月4日付のインタビュー記事 で、ジョン・レノンが 「キリストよりビートルズのほうが人気がある」と語ったことが後に 「ビートルズ宗教発言騒動」につながり、アメリカで大きな論争を 巻き起こした と。ガイドが掲げているのは雑誌 「Datebook」(アメリカのティーン向け雑誌)。表紙には ジョン・レノン が大きく写され、これはまさに「宗教発言騒動」の渦中にあった時期を象徴する表紙なのであった と。・1966年8月号に、ジョン・レノンの「キリストより人気がある」発言を引用した記事が 掲載され、これがアメリカでの大騒動を引き起こした と。・もともと発言はイギリスの 『イブニング・スタンダード』紙でモーリーン・クリーヴが行ったインタビューの一部で あったが、Datebookがこれをセンセーショナルに取り上げたことで 誤解が広がり、 ・南部でのビートルズ・レコード焼き討ち ・公演のキャンセル騒動 ・ジョン・レノンの謝罪会見(シカゴ、1966年8月) などへと発展したとの説明が。ネットから。「JOHN LENNON: "I don't know which will go first—rock'n'roll or Christianity!"」 【ジョン・レノン: 「ロックンロールとキリスト教、どちらが先に消えてしまうのか、僕には分からない!」】と。・この発言は、1966年3月にイギリスの新聞 Evening Standard に掲載された モーリーン・ クリーヴのインタビュー記事で語られた内容の一部。・その中でジョンは、 ・「キリスト教は衰退しつつある」 ・「ビートルズは今やイエスより人気がある」といった趣旨の発言をした。・イギリスでは大きな問題になりませんでしたが、アメリカで 「Datebook」誌 がこの発言を 取り上げたことで大炎上。・南部を中心に「ビートルズのレコード焼き討ち」や「放送禁止運動」が広がり、最終的に ジョンはアメリカで謝罪会見を開くことになったのだ と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.14
コメント(1)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その107): ロンドン散策記・ビートルズ ロンドン ウォーキング ツアー-1
【海外旅行 ブログリスト】👈リンクビートルズウォーキングツアーの集合場所近くのTOTTENHAM COURT ROSD SATATION・トッテナム・コート・ロード駅出入口に辿り着く。TOTTENHAM COURT ROSD SATATION・トッテナム・コート・ロード駅)周辺にある大型ビジョン「Outernet London(アウターネット・ロンドン)」。Tottenham Court Road 駅のすぐ近く、Charing Cross Road に面した複合施設。建物の外壁と内部空間に設置された巨大LEDスクリーンが特徴的で、特に1階部分の「The Now Building」では、四方の壁と天井すべてが高解像度ディスプレイで覆われ、来訪者を取り囲む360度デジタル映像体験を提供。2022年にオープン。世界最大級の「没入型メディア空間」と呼ばれる巨大LEDスクリーン。草花の中を裸足で歩くアニメーション。Outernet では定期的にアートプログラムが更新され、自然・動物・抽象映像など多彩な作品が上映されているとのこと。The Now Trending & The Now Arcade(外部通路スクリーン) エリア 特徴 サイズ(おおよそ)Now Trending 駅前壁面に設置された大型LED 約12m × 6mNow Arcade 歩行者通路の両壁+天井を覆う3面スクリーン 各面 約10m × 4m(連続)草花が咲き乱れる野原に、長い髪の少女が立って空を見上げている姿。周囲にはミツバチなどの昆虫も飛んでおり、自然の中での静かな一瞬を切り取ったような演出になっていた。集合場所はこの先の交差点の反対側の角と旅友Yさんから。ロンドン中心部の観光用地図案内板。地図中央下部に “You are here”と示されており、ちょうど Tottenham Court Road 駅の出口付近。ここがTottenham Court Road の交差点(集合場所は手前交差点を渡った角)。交差する道路1.Tottenham Court Road(北方向へ伸びる通り) 電気街や家具店が多かった歴史があり、現在はオフィス・商業施設が並ぶ通り。2.Charing Cross Road(南へ伸びる通り) 古書店・楽譜店が有名で、レスター・スクエア方面へとつながります。3.Oxford Street(東西に走る大通り) ロンドン随一のショッピング街。西はBond Street方面、東はHolbornへ。横断歩道を渡り、集合場所へ。集合場所からOxford Street(東西に走る大通り)に沿った商店街を見る。集合場所の交差点の対角方向を見る。Dominion Theatre(ドミニオン・シアター) の壁前に設置されている巨大なオブジェの赤いハイヒール。・Dominion Theatre 1929年に開業した大型シアター。交差点北西角に位置していた。 過去には 「We Will Rock You」(クイーンの楽曲を使ったミュージカル) が10年以上も 上演され、観光客にも人気を博した。・赤いハイヒール像の意味 近年、このシアターで上演されたミュージカル 「Kinky Boots(キンキーブーツ)」 に ちなんで設置された象徴的なモニュメントである と。 ・この作品は、イギリスの靴工場がドラァグクイーン向けのブーツ製造に挑戦するという実話を もとにしたストーリー。 ・赤いハイヒールは作品のシンボルであり、劇場外観にもその象徴が残されているのであった。ロンドンのビートルズウォーキングツアーは、ビートルズの歴史や足跡を辿るための特別なガイド付きツアー。このツアーでは、ビートルズが関わった場所や重要なスポットを訪れ、彼らの音楽や文化に対する影響を学ぶことができるのであった。このウォーキングツアー参加者が受付を。このオジサンがこの日のツアーガイド。BEATLESと書かれたTシャツとキャップで迎えてくれた。参加者は20数名と。そして定刻になり、ウォーキングツアーのスタート。最初に訪ねたのがSoho Square Gardens(ソーホー・スクエア・ガーデンズ)。Soho Square(ソーホー・スクエア) の標識。ビートルズの歴史とつながる場所で、ビートルズが設立した「Apple Corps」の本社があった地域。場所を明示する看板を目にすると、「ここがビートルズの歴史とつながる場所なのだ」と実感が湧いてくる瞬間なのであった。Soho Square Gardens(ソーホー・スクエア・ガーデンズ)の中央部分。ロンドンの賑やかなソーホー地区の中にある緑豊かな小公園で、周囲を18〜19世紀のタウンハウスが囲んでいた。現在は市民やオフィスワーカーの憩いの場となっているようであった。特徴的な二つのランドマークが見えた。1.前景の白い像作者:Caius Gabriel Cibber(カイアス・ガブリエル・シバー)制作年:1681年頃材質:ポートランド石概要:・ソーホー・スクエアが「King’s Square」と呼ばれていた時代、 国王チャールズ2世を称えて中央に設置されたもの。・王はローブをまとい、手に王笏(sceptre)を持ち、足元にはイルカや貝の装飾がある。・長らく風雨で損傷していましたが、1938年に修復された。2.像の背後の建物:Tudor-style Hut(チューダー様式の小屋)・建設年:1920年代(第一次世界大戦後)・外観:黒と白のハーフティンバー(木骨)風デザイン・機能:地下に公園管理事務室および防空壕(旧時代のシェルター)があり、 上部は道具小屋・監視所として使用されてきた。・補足:現在も公園維持の設備として残されていますが、一般立入はできない と。説明を始めたガイドのオジサン。名前はRichard Porter(リチャード・ポーター)👈️リンクさん。BBCや新聞、ドキュメンタリーなどにも出演しており、国際的にも「ビートルズのロンドン案内人」として知られているとのこと。ポール・マッカートニーと若かりし頃のRichard Porter(リチャード・ポーター)さんの写真をネットから。Soho Square Gardens(ソーホー・スクエア・ガーデンズ)から向かいの茶色の建物の説明をするRichard Porter(リチャード・ポーター)さん。・27 Soho Square(ソーホー・スクエア27番地)、つまり ビートルズの会社 「Apple Corps」本社があった場所と。・時期:1968年にビートルズが設立した Apple Corps Ltd. の本社として使用。・役割 ・Apple Records(レコードレーベル) ・ Apple Publishing(音楽出版) ・Apple Electronics(発明・ガジェット系の事業) ・Apple Films など ビートルズのクリエイティブとビジネスを一手に担う拠点。・ビートルズの出入り メンバーも頻繁に訪れ、会議やレコーディング関連の打ち合わせをしていた。 ただし経営面では混乱が多く、「お金にルーズすぎてアップルがアップルを食べる」と 揶揄されたこともある。・ファンにとっての意味 一見、普通の赤レンガのビルにしか見えませんが、ここでビートルズ後期の重要な決断が 数多くなされたのだと。 現在も「ビートルズ・ウォーキングツアー」の定番スポット。Apple Corps Ltd.(アップル・コア本社)跡の建物。正面から。ガイドが手に持っている写真に写っているのは ポール・マッカートニーとファン?。こちらは共に若き日のポール・マッカートニーとRichard Porterさんが一緒に写った写真。特に Soho や Savile Row 周辺 では、1980年代以降もポールが音楽活動や仕事で訪れており、偶然ファンと撮られた写真がいくつも残っているのだと。この写真には ポールのサイン が入っているのが見えたのであった。Soho Square Gardens(ソーホー・スクエア・ガーデンズ)を公園南側から北方向を振り返って。先ほどの像とチューダー様式の小屋(黒白の建物)が、ここからでももはっきりと。ビートルズのウォーキングツアー(Richard Porter氏の Beatles in London Tour)でもよく通過・休憩地点として使われているのだと。特にMPL本社(ポールの事務所)がこの公園の北側にあるため、ツアーでは必ず立ち寄る名所である と。Soho Square から角を曲がった「Carlisle Street(カーライル・ストリート)」 。写真中央の赤レンガの建物が、Soho Square(Apple Corps 本社跡) の横顔。Google Mapにはこの建物には「MPL Music Publishing」とあり、これはポール・マッカートニーが1970年代に設立した音楽出版会社であるが、正式な住所は Soho Square(ソーホー・スクエア1番地)とのこと。「Soho Square W1」の通り名標識(Street Name Sign)が煉瓦造の壁に。この標識「SOHO SQUARE W1」が掲げられている通りこそ、ポール・マッカートニーが拠点を構えた場所そのもの。MPLビルはソーホー・スクエア北側の赤レンガの建物(写真に似た外観)で、彼自身が1970年代に取得して以来、長年にわたってビートルズ後の創作・出版活動の中心となって来たのだとガイドから。MPL Communications(エムピーエル・コミュニケーションズ) の本社ビルを正面から。・名称:MPL Communications Ltd.・所在地:1 Soho Square, London W1D 3BQ, United Kingdom・設立者:Paul McCartney(ポール・マッカートニー)・設立年:1971年・用途:音楽著作権管理・出版・制作会社(マッカートニー家のプライベート企業)・外観特徴: ・赤レンガ造のヴィクトリアン建築(19世紀後半建設) ・玄関上部に控えめに “mpl” のロゴが刻まれています(写真中央の焦げ茶色の木製フレーム部) ・建物前はソーホー・スクエアの緑地を望む絶好の立地MPL Communicationsとは・“MPL” は「McCartney Productions Ltd.」の略。・1970年、ビートルズ解散後にポール・マッカートニーが設立した 音楽出版・著作権管理会社 で、彼のすべてのソロ活動とウイングス時代の作品を管理。・現在はマッカートニー家の所有する多数の楽曲(他作曲家の作品も含む)を管理し、 世界的に有名な音楽出版会社のひとつとなっているのだ と。「mpl」の銘板(ロゴプレート)は、マッカートニーの会社を象徴する非常に有名なデザイン。・表記:小文字の mpl(Music Publishing Limited の略)・書体:やわらかな丸みを帯びたサンセリフ体・デザイン要素: ・文字の上にアーチ(曲線)が描かれている。 ・このアーチは「音楽の波」または「五線譜の一部」を象徴すると解釈されている。 ・ロゴ全体はシンプルながら上品で、外壁の木製フレームと調和している と。Soho Square・ソーホースクェアーを進む。そして次に訪ねたのがTrident Studios(トライデント・スタジオ)跡。Trident Studios(ロンドン・ソーホー、1968〜1981頃)ビートルズとの関わり・「Hey Jude」👈️リンク 録音(1968年) ・ビートルズがこのスタジオで録音した代表曲。 ・Abbey Road Studios より最新鋭の8トラック機材が導入されていたため選ばれた。 ・オーケストラを使った壮大なセッションが行われた。その他の録音・「Dear Prudence」👈️リンク・「Savoy Truffle」👈️リンク・「Martha My Dear」👈️リンク など『The White Album』収録曲の一部もここで制作。「ビートルズはAbbey Roadだけではなく、Hey JudeやDear Prudenceをこのスタジオで録音した」と。ズームして。スタジオは閉鎖され、現在は別用途(事務所など)ですが、外壁に記念プレートが設置されており、音楽史的な聖地として保存されている と。正面には青い記念プレート(Blue Plaque)が掲げられていた。このブルー・プラーク(記念プレート)は トライデント・スタジオ(Trident Studios)跡 の建物に掲げられていた。「BBC Music DayDAVID BOWIE1947 - 2016His albums Hunky Dory andThe Rise & Fall of Ziggy Stardust,and the iconic single Space Odditywere recorded here atTrident StudiosAwarded byBBC Radio LondonBritish Plaque Trust」【BBC ミュージック・デイデヴィッド・ボウイ1947 - 2016彼のアルバム『ハンキー・ドリー』と『ジギー・スターダストの興亡』、そして象徴的なシングル『スペイス・オディティ』はここトライデント・スタジオで録音された。BBCラジオ・ロンドンより顕彰ブリティッシュ・プラーク・トラスト】 説明するツアーガイド・Richard Porter(リチャード・ポーター) さん。歴史的意義トライデント・スタジオは1960〜70年代のロンドンで最も重要な録音スタジオの一つ。ビートルズをはじめ、世界的アーティストの名曲がここで生まれているのだ。主な録音アーティストと作品 アーティスト 主な作品・録音年・The Beatles : “Hey Jude”(1968年録音。アビイ・ロード・スタジオが満室のため ここで録音)・David Bowie : “Space Oddity”(1969)、“Hunky Dory”、“Ziggy Stardust”・Queen : デビューアルバム “Queen”(1973)、および “Bohemian Rhapsody” の一部・Elton John : 初期作品 “Your Song” など・Carly Simon : “You’re So Vain”・Genesis, T. Rex, Lou Reed : 1970年代ロンドン・ロックを代表する録音の多くがここで制作ビートルズがレコーディング中の様子を写した写真。「Hey Jude」のレコーディング風景写真を示しながら、「ここで実際に彼らが演奏していたのです」と。ネットから上記写真を。1968年、トライデント・スタジオ(Trident Studios)で「Hey Jude」録音時のセッション風景。・手前左:ポール・マッカートニー(ヘッドフォンをつけ、マイクに向かって歌っている)・手前右:ジョージ・ハリスン(ギターを弾いている) ・中央・後方:ブラス・セクション(トロンボーン、トランペットなど) ・仕切り板で区切られた録音ブースが確認でき、当時の録音環境がリアルにわかる。「Hey Jude」👉️リンク録音について・日付:1968年7月31日・場所:ロンドン・ソーホーのトライデント・スタジオ・理由:当時のAbbey Road Studiosはまだ4トラックしかなく、トライデントは最新鋭の 8トラック・レコーダーを導入していたため。・特徴: ・長大な7分超えのシングル。 ・オーケストラや合唱が加わり、壮大なスケール感に。 ・後半の「na-na-na…」のコーラス部分は、オーケストラ奏者や付き添い人までが合唱に 加わったと言われている。Broadwick Street(ブロードウィック・ストリート)を歩く。ガイドはここで「これからカーナビー・ストリートに向かいます」と案内し、60年代当時のロンドン文化(ファッション、音楽シーン、若者文化)とビートルズの関わりを説明してくれた。Broadwick Street(ブロードウィック・ストリート)はCarnaby Street につながる通りレコード店やスタジオが点在していた。カラフルでインパクトのある、ロンドン・ソーホー地区(Soho)にある 5つ星のホテル「Broadwick Soho(ブロードウィック・ソーホー)」の入口。正面から。「カラフルな発泡スティック(プールヌードル)」で、ホテルのエントランスをアート的に囲むようにデザインされていた。Broadwick Street(ブロードウィック・ストリート)にあったのがロンドンの音楽史ツアーで定番の立ち寄り場所、旧マーキークラブ(The Marquee Club)跡(Wardour Street) の入口跡??。この場所は Wardour Street のマーキークラブ跡そのものではなく、現在は マーキーに関連付けられて紹介される地下スペースの入口 であるようだ。ネットによるとここはBroadwick Street の地下トイレ跡(現在は閉鎖中)であったようだ。また、Tottenham Court Road駅近くの旧地下鉄口(鉄柵の階段)を「映画に登場する“リンゴが降りた階段”に似ている場所」として紹介することがあるのだ とも。マーキークラブとはロンドン・ソーホー、Wardour Street 90番地 にあった有名なライブハウス。1960年代から70年代にかけて、数え切れないほどの有名バンドが出演。ローリング・ストーンズ、ザ・フー、ピンク・フロイド、デヴィッド・ボウイ…ビートルズ自身は出演していませんが、アップル・レコードと繋がりのあるアーティストがここで演奏。Badfinger(ビートルズの弟分バンド) などもステージに立った。ガイドさん(オレンジのビートルズ帽子の方)が掲げているのは、リンゴ・スターの写真。ズームして。この写真の背景には「GENTLEMEN」「MEMBERS ONLY」という看板付きの鉄柵が見えた。リンゴ・スターがシルクハットをかぶり、片手を挙げてポーズをとっている。・この地下トイレはヴィクトリア時代に設置された公衆便所で、ソーホー地区では有名な ランドマークのひとつ。・近年は閉鎖されていて、鉄の門に南京錠がかけられていた。・2010年代以降、ロンドンでは多くの歴史的地下トイレが閉鎖または再利用され、 バーやカフェに改装されるケースもあり、この場所もその候補に挙げられたことがある と。リンゴ・スターが出演した映画や当時の写真を示しながら解説してくれた。リンゴ・スターが帽子姿で立ち、隣に別の人物がいるシーン。映画『A Hard Day’s Night(ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!)』(1964)のリンゴ・スターのワンシーン。この映画の撮影場所がここだったのであろう。覗き込んで。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.13
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その106): ロンドン散策記・トッテナム・コート・ロード駅 (Tottenham Court Road)へ
【海外旅行 ブログリスト】👈リンク朝の散歩を終えて宿に戻り、朝食を二人で楽しむ。そしてこの日は、旅ともYさんが予約してくれていた「ビートルズ ロンドン ウォーキング ツアー」に参加することに。集合場所はTottenham Court Road・トッテナム・コート・ロード駅前のドミニオン シアター近くの交差点の角とのこと。集合時間は10:30。9:45前にアパートを出て、右折してWalton Street・ウォルトン・ストリートをKnightbridge駅に向かって進む。・白い外壁のジョージアン/ヴィクトリアン様式のテラスハウスが並び、上品で統一感のある 街並みを形成。・金属製の黒い手すりやバルコニーがアクセントになっており、ロンドンの高級住宅街に 典型的なデザイン。・左側に並ぶ 白壁のテラスハウス群は連続性があり、統一感のある住宅街の景観を形成。・手前の建物は 玄関ポーチに列柱を持つ堂々とした外観で、この一帯の中でも存在感が。・右側には緑豊かな木々の姿が。右側には教会らしき建物が現れた。St Saviour’s Church(セント・セイヴィアーズ教会/チェルシー)。・住所:St Saviours Church, Walton St, London SW3 1SA UK・ネオ・ゴシック様式:赤レンガと石を組み合わせた装飾的な外観で、19世紀後半に流行した スタイル。・大窓のステンドグラス:正面の大きな尖頭アーチ窓が印象的で、内部からも光を取り込み 荘厳な雰囲気を演出。・細部装飾:窓を囲む幾何学模様のレンガ積み、縦に伸びるトレーサリー、上部のフィニアル (小尖塔)などが特徴的。・シンメトリー構成:中央に大窓と入口、両脇にやや小ぶりのゴシック窓が配置され、 全体の均整がとれています。歴史と背景・建設:1864年頃、建築家 George Basevi や Joseph Peacock の流れを汲む設計。・もともとチェルシー地区の住民のために建てられた英国国教会の教会。・現在はしばしば結婚式やコンサート会場としても利用されることがあり、音響が良いことでも 知られている と。内部の特徴1.祭壇・内陣・高いゴシック・アーチの内陣。・正面には 華やかな祭壇画(ラッカー塗装や金色装飾)。・祭壇上部には大きなステンドグラス窓があり、光に満ちた空間を演出。2.ステンドグラス・中央の大窓は キリストの生涯を描いた図像が配される。・側面窓は 聖人像や象徴的モチーフ(十字架・葡萄・羊など) がテーマ。・鮮やかな赤・青・金を基調とし、礼拝堂全体を彩る。3.身廊(Nave)・高い天井と尖頭アーチの連続。・白い石材の柱に木造の屋根梁。・座席はダークウッドで整然と並ぶ。St Saviour’s 内部の東側大ステンドグラス窓。上部(トレーサリー部分)・天使や紋章、星や花のモチーフが散りばめられている。・中央上部には 赤い翼を持つ天使(セラフィム) が描かれ、神の栄光を象徴。・両脇の天使は巻物を持ち、ラテン語の聖句を掲げている。・左:聖ジョージ(St George) ・姿:鎧をまとった若い戦士。 ・持ち物: 右手に 白地に赤十字(聖ジョージ十字)の旗槍 左手に赤い盾。 ・象徴: 竜退治伝説で知られる イングランドの守護聖人。 十字旗はイングランド国旗の起源でもあり、教会や国のアイデンティティを表す。・右:聖ペテロ(St Peter) ・姿:白髪と髭を持つ使徒。 ・持ち物: 左手に 大きな鍵(天国の鍵の象徴)。 右手に開いた書物(福音・教えを表す)。 ・象徴: キリストに「この岩の上に私の教会を建てる」と言われた弟子。 カトリック伝統では 初代ローマ教皇 とされる。中央:栄光のキリスト(Christ in Majesty)姿・王冠を戴き、荘厳な装束をまとった キリスト。・右手:祝福の印(2本指を立てて祝福)。・左手:オルブ(Orb/十字架付きの地球儀)を持つ。 ・これは 「世界の支配者」「宇宙の王」 を意味します。周囲の小像・両脇や上下に並ぶ 小さな聖人・天使像。 左右に座った人物群 → 預言者や福音記者を表す可能性。 上下の天使 → 天上の礼拝を象徴。下部の銘文 ラテン語「Iudicium」や「Domini」などが読み取れる(「主の審判」「主の御支配」)。 天使2人が巻物を広げており、審判や栄光を強調。左:聖パウロ(St Paul)・姿:白髪と長い髭を持つ使徒。紫の衣をまとっています。・持ち物: 巻物(彼の書簡を象徴)。 足元近くには 剣 が描かれることが多く、殉教の象徴。・象徴: 「異邦人の使徒」と呼ばれ、地中海世界に福音を広めた。 新約聖書の多くの手紙を書いた人物。 右:聖アウグスティヌス(St Augustine of Hippo)・姿:司教の法衣をまとい、ミトラ(司教冠) をかぶる。・持ち物: 巻物や書物(『告白』『神の国』など神学的著作を象徴)。 司教杖(クロージャー)。・象徴: 西方教会最大の神学者・教父。 恩寵・原罪・神の国などの思想で中世キリスト教に絶大な影響を与えた。St Savioursを振り返って。その先の十字路にあったのが、ロンドンの Harrods(ハロッズ百貨店)。・Knightsbridge(ナイツブリッジ)駅前、ブロンプトン・ロード沿い。・1834年創業、ロンドンを代表する高級百貨店。・レンガ色(テラコッタ調)の外壁が象徴的。・ヴィクトリア時代後期の商業建築らしく、細かな装飾が施されている。・窓枠まわりにはクラシカルな石彫装飾があり、特に2階部分は優雅なバルコニー風。・左端の部分は特に重厚で、柱や彫刻的要素が強調されています。・1階部分は現代的に改装され、ファッションブランドの店舗(例:PRADA など)が入っている。Harrods(ハロッズ百貨店) の一部で、こちらは 従業員や搬入口側、あるいは専用入口がある裏手の建物。入口には「Harrods Staff Entrance(従業員入口)」「Private Car Park Entrance(専用駐車場入口)」などの表示が確認できたその先の街並みを。・赤レンガと白い帯状装飾(ストライプ模様) の外壁が特徴的。・ヴィクトリアン様式からエドワーディアン期にかけての典型的なロンドンの集合住宅 (マンション/アパートメント)。・出窓(ベイウィンドウ)が連なり、立体感を強調。・屋根には黒いスレートやドーマー窓が並ぶ。・特にこの赤レンガと白帯のマンション群は「Pont Street Dutch Style(ポント・ストリート・ ダッチ様式)」 と呼ばれるレンガ建築の典型。・19世紀後半、裕福な中産階級や上流階級向けの高級アパートメントとして建てられた と。ロンドン・ナイツブリッジにあるHans Crescent(ハンス・クレセント)と Basil Street(ベイジル・ストリート)の角の様子。・壁面の楕円形の装飾パネル ・「HANS CRESCENT No. 3A」と刻まれていた。 ・建物の住所プレートを装飾的に示したもの。・通りの標識 ・上部に「BASIL STREET」と表記。 ・Basil Street は Hans Crescent と交差する小道で、ハロッズの北側にあたる。・国旗 ・左端にコロンビア国旗 が見えた。 ・すぐ近くに「コロンビア大使館」があることを示していた。・この前の通りはHans Crescent(ハンス・クレセント) ・ハロッズ百貨店の南東側を取り囲む半円形の通り。 ・高級ホテルや大使館が集まる一角。・Basil Street(ベイジル・ストリート) ・ハロッズの北側から東に延びる通りで、Hans Crescent と交差する。・この角は特に有名で、かつて在英エクアドル大使館があり、ジュリアン・アサンジ亡命事件で 注目された場所でもある と。Basil Street(ベイジル・ストリート)を進む。Basil Street(ベイジル・ストリート) の街並み。ハロッズ(Harrods)のすぐ北側に位置。赤レンガと白い石の帯装飾が組み合わさった典型的なエドワーディアン様式の高級アパート群。右側の建物は ベイウィンドウと黒いアイアンバルコニー が連続し、重厚感と装飾美を兼ね備えているのであった。ナイツブリッジ(Knightsbridge)駅近くの小路。・右側:深い赤色の光沢タイル(テラコッタ)が張られた外壁。・これはロンドン地下鉄の古い駅舎でよく使われた素材と似ており、ナイツブリッジ駅の 一部の外壁デザインを思わせます。・左側:現代的な褐色レンガの建物で、大きなガラス窓があり、ショップのディスプレイが 見えた。・通り:石畳の細い路地で、アーチをくぐって奥へと続く。・街灯:壁付けのランタン風デザインが複数設置されており、古風な趣きを演出。ロンドン地下鉄のKnightsbridge(ナイツブリッジ)駅の地下通路を歩く。ロンドン地下鉄 Knightsbridge(ナイツブリッジ)駅の案内。Piccadilly line(ピカデリー線)に乗車。5駅目の「Covent Garden(コヴェント・ガーデン)駅」で下車。そして地上の出口に向かって。地上に出てジェームス・ストリートを歩く。ロング・エイカー通りを東に進む。奥には英国国教会・St Giles in the Fieldsの尖塔が見えた。石畳の道・Shelton Stを進む。コヴェント・ガーデン地区にあったパブ「Crown & Anchor」が左手に。Shelton Street と Neal Street の角に位置していた。・レンガ造りの歴史的な建物。・壁一面にフラワーバスケットやプランターが飾られており、季節ごとに花で彩られると。・赤い外壁とアーチ型の窓枠が印象的で、観光客の写真スポットにもなっていた。・「Crown & Anchor」は、イギリスの伝統的なパブ名で「王冠と錨」を意味する。・海軍や王権に由来する象徴的な組み合わせで、同名のパブはイギリス各地に存在するが、 こちらは特に花装飾で有名である と。Shelton Street(シェルトン・ストリート)とNeal Street(ニール・ストリート)の路地から。Neal Street(ニール・ストリート)を見る。「OLE & STEEN(オレ & スティーン)」はデンマーク発祥の人気ベーカリー&カフェチェーン。ロンドン・コヴェントガーデンの Neal Street(ニール・ストリート)沿いにある人気スポット。黄色い入口「The The Breakfast Club」には長蛇の列が。The Breakfast Clubは、名前の通り「朝食」がテーマのカフェ&ダイナーで、ロンドンのブランチ文化を代表する人気店である と。 美味しそう!!Central Saint Giles(セントラル・セント・ジャイルズ) というカラフルな複合ビル群のうち、オレンジ色の外壁部分。トッテナム・コート・ロード駅(Tottenham Court Road)近く、St Giles High Street とEarnshaw Street の交差点付近。こちらはさらに左のCentral Saint Giles(セントラル・セント・ジャイルズ)複合ビルのオレンジ棟とイエロー棟。・建築家レンゾ・ピアノ(Renzo Piano、ポンピドゥー・センターやシャードで有名)が手掛け、 2010年完成。・ビル群全体が赤・オレンジ・黄・緑といったビビッドな色彩で彩られており、ロンドン中心部 でも強烈な存在感を放つ。Central Saint Giles(セントラル・セント・ジャイルズ) の中庭広場に設置されているアート作品。光沢のある鮮やかな赤色で縦に連なった「ねじれた8の字」のようなFRP製の抽象彫刻。作者は、アメリカ・フィラデルフィア出身の彫刻家スティーブン・ゴンタルスキー(Steven Gontarski)。作品名:Ob8(オービー・エイト) 高さ:約5mタイトル《Ob8(オービー・エイト)》は、“object” と “obey” を掛け合わせたような造語的響きを持ち、また「8=∞(無限大)」を暗示することから、「形の終わりなき連続」 を示唆しているのだ と。その先にあったのが、セント・ジャイルズ・イン・ザ・フィールズ教会(St Giles-in-the-Fields Church)。・尖塔(スパイア) ・四方に時計盤が付いた鐘楼の上に、八角形の塔屋と細長いスパイアが伸びていた。 ・頂点には金色の球(フィニアル)が輝いていた。・12世紀にハンセン病患者のための病院教会として創建されたのが始まり。・現在の建物は1733年に完成したジョージアン様式の教会。・設計は ヘンリー・フルーム(Henry Flitcroft)。尖塔部分をズームして。・四方に設置された時計盤(黒地に白のローマ数字)。・時計の上には八角形の塔屋(ランタン)が立ち、円柱に囲まれた開放的な構造。・最上部は細長いスパイア(尖塔)で、頂点に金色の球(フィニアル)が輝く。アーンショー・ストリートの先に見えたのが白い石造のファサードに、3連アーチ窓を備えた新古典主義風デザインの建物。大きく写っている高層ビルは、ロンドンの Centre Point(センター・ポイント)。近づいて。・設計:リチャード・シーファース(Richard Seifert)・竣工:1966年・高さ:約117m、34階建て・プレキャスト・コンクリートのモジュールを組み合わせたファサードが特徴。・ブルータリズム建築(Brutalism)の代表例のひとつ。 ブルータリズム (brutalism) またはニュー・ブルータリズム (new brutalism) は、1950年代 以降に多く見られるようになった建築様式である。ブルータリズムの特徴は、素材や構造を 露出させて質感を強調させることであり、打放しコンクリート(ベトン・ブリュット/生の コンクリート)やレンガを主に使用して建てられ、塗装や化粧板は使わない。 この様式では幾何学的な模様をモノクロームで表現し、これにガラスや鉄なども使用される 場合が多い とウィキペディアより。St Giles Square(セント・ジャイルズ・スクエア)に停まっていたのがフローズンヨーグルト販売用に改装された二階建てバス(ダブルデッカーバス)。・ロンドン名物の赤い二階建てバスをモチーフにしたフードトラック。・実際のルートマスター型バスを改造したもの。・屋根部分はオープンテラス風に改装され、ネオンカラーの装飾が施されていた。St Giles Square(セント・ジャイルズ・スクエア)から広場の中心的なランドマーク・斜めに傾斜した全面ガラス張りのデザインの、Tottenham Court Road 駅(Elizabeth Line / Crossrail)の出入口を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.12
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その105): ロンドン散策記・チェルシーの赤レンガの街並みを歩く
この日は6月8日(日)、ロンドンに到着して3日目の朝。旅友Yさんと、宿泊場所周辺・Chelsea・チェルシーの早朝散歩に向かう。アパートメントの前の道・St.Lennox Gardensを南に進む。我々の宿泊の部屋の前にはLennox Gardensが拡がっていた。Chelsea・チェルシーの地図。・位置・概要 ・ロンドンの西部、テムズ川北岸に位置する高級住宅街。 ・ケンジントン&チェルシー王立区(Royal Borough of Kensington and Chelsea)の一部。・歴史的背景 ・中世には王家の所有地で、ヘンリー8世やトマス・モア卿ともゆかりがある。 ・19世紀には芸術家や詩人が集まるボヘミアンなエリアとして発展。・芸術・文化 ・「キングス・ロード(King’s Road)」はファッションの発信地として有名。1960〜70年代 にはスウィンギング・ロンドンの中心。 ・サーチ・ギャラリー(Saatchi Gallery) が現代美術の拠点として世界的に知られる。 ・多くのデザイナーや音楽家が活動した街としても有名。・観光・名所 ・チェルシー薬草園(Chelsea Physic Garden):1673年創設の英国で最も古い植物園の一つ。 ・ロイヤル・ホスピタル・チェルシー(Royal Hospital Chelsea):退役軍人 (Chelsea Pensioners)の居住地で、クリストファー・レン設計。 チェルシー・エンバンクメント(Chelsea Embankment):テムズ川沿いの美しい遊歩道。・スポーツ ・サッカークラブ チェルシーFC の本拠地。スタンフォード・ブリッジ(Stamford Bridge) スタジアムがある。・暮らし・雰囲気 ・高級住宅街としても知られ、ヴィクトリア調やジョージアン様式のタウンハウスが並ぶ。 ・カフェ、ブティック、アンティークショップなどが点在し、洗練された雰囲気。我が民宿・アパートメント前のLennox Gardens(レノックス・ガーデンズ) 周辺の街並みを振り返って。・赤レンガと白いストーン装飾が特徴のヴィクトリア後期〜エドワード朝様式 (19世紀末〜20世紀初頭)。・出窓(ベイウィンドウ)、装飾的なバルコニー、繊細なアイアンフェンスが連続して並ぶ。・彫刻的な白いストーン部分(窓枠や玄関まわり)が、赤レンガとのコントラストを強調。この標識はロンドンの 「Lennox Gardens, SW1」 を示していた。・所在:ロンドン中心部の高級住宅街、The Royal Borough of Kensington and Chelsea (ケンジントン&チェルシー王立特別区) に属します。・郵便地区 SW1:ナイツブリッジやチェルシー、ベルグレイヴィアにまたがる一帯で、 ロンドンでも屈指の高級エリアに含まれます。・ガーデンスクエア形式:中央に住民専用の緑地があり、周囲を赤レンガのヴィクトリア朝〜 エドワード朝様式の住宅群が取り囲んでいます。SW の意味・SW = South Western(サウス・ウェスタン) の略。・ロンドンの郵便番号は、ロンドン中心の EC(Eastern Central)/WC(Western Central) を 起点に、方角ごとに区分されています。 ・N = North ・E = East ・S = South ・W = West ・NW = North West ・SE = South East ・SW = South West交差点の角にあったのは、ロンドン特有の テラスハウス群(連棟式住宅)の一角で、白い漆喰に覆われた建物。・ジョージアン後期〜ヴィクトリア初期様式(19世紀前半頃)の典型。・外壁を白く塗ったスタッコ仕上げ(stucco)で、上品で統一感を持たせていた。・縦長の窓が規則的に並び、ベランダや鉄製のバルコニー手すり(wrought iron)がアクセント。・屋根はフラットに近く、煙突が連続しているのも特徴。その反対側、東側の角にあったのが「英国国教会・St Simon Zelotes(聖シモン・ゼロテス教会)」。 ・住所:34 Milner Street, Chelsea, London SW3 2QF, UK ・教派:英国国教会(Anglican, Church of England) ・創建:1858–59年、建築家 Joseph Peacock による設計 ・様式:ゴシック・リヴァイヴァル様式(中世風復興)建築の特徴・外観は 灰色レンガと石造りで、尖塔(spire)と鋭角的な破風(gable)が印象的。・大きな ランセット窓(縦長のゴシック窓) が正面に配され、上部には装飾的な石彫刻。・内部は比較的小規模ながら、石造の柱とリブ・ヴォールト天井があり、静謐な雰囲気。歴史的背景・19世紀後半のロンドンでは人口増加に伴い新たな教会が多く建設され、 この St Simon Zelotes もその一つ。・名前の由来となった「シモン・ゼロテス(熱心党のシモン)」は新約聖書に登場する 十二使徒の一人。・第二次世界大戦の空襲被害を受けず、今も19世紀の姿を色濃く残している。建築的特徴(正面詳細)・大きなランセット窓(縦長ゴシック窓) が3連で配置され、その上に 円形のバラ窓(rose window) が付いていた。・窓の間には 聖人像用の小ニッチ(龕:がん) があり、現在は装飾的な意匠が。・窓まわりの石材は丁寧に削り出され、周囲の粗い石積み壁(rubble stone)と 対比されていて、視線が自然に窓へ導かれる。・下部中央の尖頭アーチは 主入口(west door)で、信徒が礼拝に入る際のメインエントランス。・入口両脇にはベンチが置かれており、地域住民に開かれた教会の雰囲気を出していた。開堂前であったので、以下の内部の写真は帰路に撮影。St Simon Zelotes Church(聖シモン・ゼロテス教会/チェルシー) の内部、祭壇と東側ステンドグラスを正面から。St Simon Zelotes Church(チェルシー)東側祭壇背後のステンドグラス(East Window)。制作は Lavers & Barraud(1859年) で、キリストの生涯を描いた連作 と。構成(左から右の5連窓)以下、ネットから🔹 第1窓(左端)・上段:羊飼いたちへの告知(Annunciation to the Shepherds)・中段:キリストの降誕(Nativity)・下段:東方三博士の礼拝(Adoration of the Magi)🔹 第2窓・上段:ゲッセマネの祈り(Agony in the Garden)・中段:鞭打ち(Flagellation of Christ)・下段:十字架を担うキリスト(Carrying of the Cross)🔹 第3窓(中央)・上段:磔刑(Crucifixion)・中段:復活(Resurrection)・下段:昇天(Ascension)🔹 第4窓・上段:聖霊降臨(Pentecost)・中段:使徒たちの宣教活動(Preaching of the Apostles)・下段:教会の拡大・群衆に囲まれる使徒(Spread of the Church)🔹 第5窓(右端)・上段:キリストの洗礼(Baptism of Christ)・中段:山上の説教(Sermon on the Mount)・下段:子どもを祝福するキリスト(Christ Blessing the Children)St Simon Zelotes Church(聖シモン・ゼロテス教会) の内部を、祭壇側から反対(西側)へ振り返って。1. 西窓(West Window) ・縦長の ランセット窓(3連) と、その上に小さな 円形窓(rose window) が配置されている。 ・東側のステンドグラスに比べると装飾性は控えめで、主に採光が目的。2. 西側ギャラリー(West Gallery) ・窓の下には オルガンが設置されたバルコニー(ギャラリー) が見える。 ・19世紀のイギリス教会建築では典型的で、聖歌隊やオルガニストが配置される場所。 ・ギャラリー下部には出入口(西扉)があり、礼拝者の多くはこの扉から入堂。3. ネイブ(Nave)と柱列 ・石造のアーチが連続し、側廊(aisles)を区切っている。 ・アーチの上部にはトリフォリウム的な壁面装飾はなく、比較的シンプル。 ・壁には赤と黄のレンガを交互に積んだ ポリクローム・ブリック が施され、ヴィクトリアン・ ゴシックらしいリズムを与えている。4. 天井構造 ・木造のトラス梁 が剥き出しになった「オープン・タイマー・ルーフ」。 ・黒く塗られた梁が天井を引き締め、縦方向の高さを強調。St Simon Zelotes Church(聖シモン・ゼロテス教会) の掲示板。上部・大きく 「St Simon Zelotes」 と教会名が表示されていた。・右には小さな十字のシンボル(英国国教会を示すマーク)。左側ポスター・Services(礼拝案内) のポスター。・「EVERY SUNDAY(毎週日曜日)」とあり、 ・11AM Holy Communion(聖餐式) ・6:30PM Evening Service(夕べの礼拝) が記載されています。・背景には教会のステンドグラスをモチーフにした図案。・下部に公式ウェブサイト www.stsimonzelotes.comのURL。右側掲示・細かい表(恐らく月ごとの予定表や、奉仕者・聖歌隊・行事のスケジュール)。・曜日や日付ごとの欄が見えます。教会のステンドグラスはこれ。・形状:四つ葉(クアトリフォイル)に近い幾何学的枠取り。・中央モチーフ:六枚の花弁(六芒星状の花文様)が描かれており、「生命」「創造」 「神の調和」を象徴。・外縁:青と赤の二重円環で囲まれており、神聖性(青)と犠牲/救済(赤)を示す典型的な キリスト教色彩象徴。・背景パターン:黒のリード線による格子模様が星型を形成し、幾何学的な安定感を。これも St Simon Zelotes Church(聖シモン・ゼロテス教会) の掲示板。上部・教会名 「St Simon Zelotes」 が表示されている。・右上には 英国国教会(Church of England)のロゴ。ポスター(中央)・St Simon’s Sunday School & Creche ・毎週日曜日 午前10時(EVERY SUNDAY 10AM–)と書かれています。 ・子供向けのサンデースクール(礼拝や聖書教育)と託児室(Creche)の案内。・ポスターの背景:地球の写真と光のモチーフ。 ・テーマは「光」と「世界」で、聖書の引用とリンク。・聖書の引用(ヨハネによる福音書 8章12節): Jesus said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life."(イエスは言われた。「わたしは世の光です。わたしに従う者は決して闇の中を歩むことがなく、 命の光を持つのです。」)真横(南側)から・大屋根(急勾配の切妻屋根) が建物全体を覆い、内部の身廊を強調。・上段には 四つ葉(クアトリフォイル)型の小窓(clover windows) が連続して並び、 装飾性を加えていた。・下段には 小型ランセット窓 と 尖頭アーチの出入口 があり、ゴシック・リヴァイヴァル様式 の典型。・壁面は粗い石積みによる質感があり、レンガ造の住宅街に囲まれて一層「中世風」らしさを 引き立てていた。写真中央の扉は、側面入口(サウス・ポーチ)、信徒が礼拝時に出入りする一般的な入り口。Cadogan Square Garden・カドゥガン・スクエア・ガーデンに向かって進む。St.Clabon Mewsを見る。ロンドン・チェルシー地区に典型的な19世紀後半の赤レンガ集合住宅(マンション/アパートメント)を見る。・赤レンガ造+白い石材の水平帯(string course) → ヴィクトリア後期〜エドワード朝時代(1880年代〜1900年代初頭)の集合住宅に典型的。・縦長の窓配置 → 下層階はアーチ型の窓、上層階は矩形の窓とし、リズムを持たせています。・中央エントランス → 彫刻的な装飾アーチとバルコニーを備えた玄関。両脇に石像風の装飾(または持ち送り)が 確認できます。・屋根周辺 → 煙突塔のような縦構造(右上)や切妻屋根の装飾があり、ゴシックとルネサンスを折衷した 「クイーン・アン様式」の影響も見られる。正面にCadogan Square Garden・カドゥガン・スクエア・ガーデン。右折してSt.Cadogan Squareを南に進む。赤レンガ造の高層マンション・ブロック(Mansion Block)を見る。ナイツブリッジ地区(Lennox Gardens 周辺)に典型的な赤レンガ街並みを追う。・左右対称の赤レンガ建築 → 道路の両側に同じ高さ・意匠の建物が並び、統一感を生み出しています。・ゴシック風装飾+クイーン・アン様式の影響 → 縦長の窓、三角破風(小さな切妻)、白い石材による窓枠アクセントなどが見られます。・マンション・ブロック(Mansion Blocks) → 19世紀後半に建設された集合住宅型の高級フラット。今も保存地区として保護され、 高級住宅として利用。ロンドン・チェルシーのDraycott Place(ドレイコット・プレイス) のストリートサイン。・カドガン家(Cadogan Estate)の開発地の一部で、現在もカドガン財団が多くの不動産を所有 している地域 と。・スローン・スクエア駅(Sloane Square Station) から徒歩5分ほどで、ロンドン中心部への アクセスも良好 と。Cadogan Gardens(カドガン・ガーデンズ) のストリートサイン。・ロンドン西部チェルシー に位置し、郵便区は SW3。・Sloane Square(スローン・スクエア)駅 のすぐ北側に広がる一帯。・「The Royal Borough of Kensington and Chelsea(ケンジントン&チェルシー王立特別区)」 に属します。チェルシー地区の赤レンガ建物の窓装飾。・窓ガラスに描かれているのは 花のデザイン。・左窓:下向きに咲く紫色の花(3輪)・右窓:白い花(2輪)・花の形状は釣鐘状で、細長い茎に垂れ下がる姿からフリチラリア(Fritillaria)属の花か?。ショーウィンドウのディスプレイ装飾。・大きな花のオブジェ: ・複数の花弁が放射状に広がる構成。 ・花弁は紙や布素材でできており、透け感のあるデザイン。 ・花弁の表面には赤い線状の模様(葉脈を模したもの)が描かれていた。 ・中央部はカラフルな装飾(小花模様のような布地や紙片)でまとめられて。King’s Road(キングズ・ロード)を東に進む。・場所:ロンドン西部チェルシーを東西に走る大通り。・起源:17世紀、チャールズ2世(Charles II)の専用道路として造られたことから 「King’s Road」と呼ばれるようになった と。・かつて「若者文化・モード発信地」として知られたが、現在では高級ファッション・ ライフスタイルブランドが軒を連ねる街 へと変貌した と。ロンドン・チェルシーの King’s Road(キングズ・ロード)をさらに進む。・中央のポールと黄色の球体ライト → これは Belisha Beacon(ベリーシャ・ビーコン) と呼ばれるもので、 イギリスにおける「横断歩道(Zebra Crossing)」を示す標識灯。 歩行者優先を明確にするために設置されている と。・街路樹 → King’s Road の特徴の一つで、大きな並木が続くことで高級住宅街らしい落ち着きを演出。・街路旗(ユニオンジャック) → 道路沿いの街灯に掲げられており、祝祭や地域イベント(Chelsea Flower Show や 王室行事)に合わせた装飾。King’s Road(SW3, チェルシー) にある有名な子供服ブランドTrotters(トロッターズ) の記念ディスプレイ。・35 Years of Trotters on the KING’S ROAD, S.W.3」 → 「キングズ・ロードで35周年を迎えるトロッターズ」。手前は赤レンガ造+白い石の装飾 を持つ 18〜19世紀の様式の建物。→ 上部に切妻(カーブを描いた破風)を持ち、中央にバルコニーが設置されていた。その奥には白い外壁のジョージアン〜リージェンシー様式風の建物が続き、歴史的な町並みの重層性が感じられたのであった。Duke of York Square(デューク・オブ・ヨーク・スクエア) に設置されていた案内板。・Zara(ファッションブランド)・Saatchi Gallery(サーチ・ギャラリー)下部にはカラフルな エリアマップ が掲示され、店舗・施設・スクエアの配置が示されていた。地図に近づいて。Duke of York Square(デューク・オブ・ヨーク・スクエア) の施設マップ。King’s Road(下側)から入ると広場に出て、奥に Saatchi Gallery(サーチ・ギャラリー) が位置しているのであった。Sir Hans Sloane(1660–1753) の像。医師・博物学者・コレクター。王立協会(Royal Society)の会長も務めました。業績・王室の侍医として活躍。・世界各地(特に西インド諸島)から膨大な自然史標本、書籍、工芸品を収集。・没後、その膨大なコレクションが国家に遺贈され、これが 大英博物館 (British Museum, 1753設立)、さらに大英図書館・自然史博物館の基礎となった。・ココアを牛乳で割る飲み方をヨーロッパに広めた人物としても知られていると。近づいて。・Sloane はチェルシーに広大な土地を所有。・彼の名は Sloane Square, Sloane Street に残り、今も地域を代表する名称となっている と。台座銘文:「SIR HANS SLOANE 1660–1753」奥にあったのがSaatchi Gallery(サーチ・ギャラリー)入口の外壁とゲート。・煉瓦造りの外壁とアーチ型の門 → ここはかつて Duke of York’s Headquarters(王立兵舎) の跡地で、歴史的建築の一部が 残されていた。・上部の彫刻 → 翼を広げた意匠が施されており、軍事施設だった歴史を示唆するモチーフ。・両脇のサイン ・右:「SAATCHI GALLERY」 と書かれた縦長の案内板。 ・左・中央:「FLOWERS」展のバナー(現代美術展覧会の告知)。Saatchi Gallery(サーチ・ギャラリー)や Duke of York Square に隣接する緑地(芝生広場)。この広大な芝生エリアは、かつて Duke of York’s Headquarters(デューク・オブ・ヨーク兵舎) のパレード・グラウンドとして使われていた場所 と。長い歴史を持つロンドンプラタナスなどが並び、都市の中に豊かな緑陰を形成。Duke of York Square(デューク・オブ・ヨーク・スクエア)内のショッピング&レストラン街 の一角。無数のユニオンジャック(英国旗)のフラッグガーランドが飾られ、祝祭的な雰囲気。ズームして。Saatchi Gallery(サーチ・ギャラリー) の外壁に掲示されていた展覧会バナー。・展覧会名: 「FLOWERS」 → 現代美術における「花」をテーマにした企画展。・会期: 30 May – 31 August・主催/協賛: 下部に Cazenove (Schroders) とあり、金融関連企業がサポートしています。・ビジュアル: 鮮やかな赤・ピンク・黄色の花(ユリやアマリリスを思わせる抽象的描写)。 → 視覚的インパクトが強く、展覧会のテーマ「花の多様性と力強さ」を象徴。この植物は葉の形・質感から「セネシオ・エンジェルウィングス(Senecio candicans ‘Angel Wings’)」であっただろうか(ネットより)?純白〜銀白色で、非常に大きく、柔らかく、ビロード状(フェルト状)の質感。初めて見る植物??二階建てバス(ルートマスター型の新型バス「New Routemaster」)。通勤客、観光客用のバスであろうか?チェルシーの King’s Road(キングス・ロード)をさらに南西方向に進む。ジョージアン~ヴィクトリア様式の連続タウンハウス。・白やクリーム色の外壁で統一感があり、窓上部に装飾的なコーニスが見られた。・屋上には煙突が並ぶ。主にレンガ造りで、屋根のリッジ(棟)に沿って積み上げられていた。・ロンドンの伝統的なタウンハウスでは、暖炉のある各部屋ごとに煙突が必要だったため、 屋根上に複数の煙突ポット(chimney pots)が並んでいるのだ と。ロンドンの 赤い二階建てバス(ダブルデッカーバス) が続く。始発の停留所まで向かっていたのであろうか?ストレリチア(Strelitzia reginae)、通称 極楽鳥花(Bird of Paradise)は美しく咲いていた。近づいて。・花の形 鮮やかなオレンジ色と青紫色の花弁が、まるで鳥(特に極楽鳥)が羽を広げたような形に 見えるため「Bird of Paradise」と呼ばれます。・葉 バナナの葉に似た大きな緑色の葉を持ち、観葉植物としても人気。・原産地 南アフリカ原産。温暖な地域で育ち、庭園や街路の植栽にもよく利用されるのだ。左手の並木道・Royal Avenue(ロイヤル・アベニュー)から、Royal Hospital Chelsea(ロイヤル・ホスピタル・チェルシー) の正門部分を望んだ風景。Royal Hospital Chelsea(ロイヤル・ホスピタル・チェルシー)・所在地:Royal Hospital Road, Chelsea, London・設計:Sir Christopher Wren(17世紀の建築家、セント・ポール大聖堂の設計でも有名)・完成:1692年・用途:退役軍人のための施設(Chelsea Pensioners の居住地)左手にあったのがPAUL(ポール)ベーカリー の店舗。右側にあったのが「Blank Street Coffee(ブランク・ストリート・コーヒー)」 の店舗。アイスクリーム店・Venchi(ヴェンキ)。・発祥:1878年創業のイタリア・トリノの老舗チョコレートブランド。・特徴: ・高級チョコレートとジェラートの専門店。 ・イタリア伝統のレシピをもとに、無添加・天然素材にこだわったフレーバーを展開。 ・ロンドンでも展開しており、チェルシーの King’s Road に店舗がある。 ・写真のショーウィンドウ: ・コーン型のディスプレイが壁一面に飾られ、視覚的にも楽しい演出。 ・中央ポスターには「EXTRA VIRGIN OLIVE OIL」の限定ジェラートが紹介されており、 オリーブオイルの風味を活かしたヘルシーで珍しいフレーバー と。ヘルスケアショップのrevital。M&S(Marks & Spencer, マークス&スペンサー)・英国を代表する大手スーパーマーケット&小売チェーン。・食料品、衣料品、家庭用品など幅広い品揃え。・ロンドンの各エリアにあり、King’s Road でも日常的に利用される便利な店。この日の朝食、そして他の飲料、食料をここで購入したのであった。King’s Road(ロンドン・チェルシー) にあった有名なランドマークのひとつ、Philosophy House(旧 Iconic 1865) の門構え。・門のデザイン ・アーチの上に2体の黒いブロンズ像(古代風衣装の人物像)が立っています。 ・中央には丸いメダリオン装飾。 ・下部に「1865 ICONS」「150 YEARS」と記された記念の文字(150周年を祝った際のもの)。・現在の施設 ・表示にある「Philosophy House」は、この建物に入っているブランドやレストランなどの 名称のひとつ。 ・King’s Road の高級感を象徴する建築で、アイコニックな門は撮影スポット。早朝散歩もここまでとして、脇道を使い引き返す。白い建物の屋根に並んでいるのは 煙突(chimneys)。・屋根の上に細長い煙突ポット(chimney pots)が複数本並んでいます。・煙突ポットは19世紀ヴィクトリア朝やエドワード朝の住宅に多く見られるもので、 1つの煙道に複数のポットを設けることで効率よく排煙できる仕組み。・煙突の土台部分はレンガ造りで、上部のポットはテラコッタ製が一般的。この白い建物は恐らく ヴィクトリア時代のタウンハウス/ヴィラ様式 の一部で、近隣の赤レンガ建築とも調和した保存地区の住宅街らしい雰囲気なのであった。Chelsea Green(チェルシー・グリーン)という小さな広場の噴水。噴水の中央には、ライオン像が。石柱の周囲に蛇口があり、もともとは飲料水用の公共水飲み場(drinking fountain) として機能していたものであろうか。そして、約1時間の早朝散歩を終えて、アパートに戻ったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.11
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その104): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-19
ロンドン・テムズ川沿いにある 旧ビリングズゲイト市場(Old Billingsgate Market) の屋根飾りを違う角度から見上げて。黄金に輝く魚の風見(weathervane)をズームして。・魚のデザイン 大きく口を開けた金色の魚で、鱗やヒレが細かく表現されています。これは市場が 魚市場 (Billingsgate Fish Market) だったことを象徴。日本の鯛焼きの如き姿。・方位を示す矢印(N・E・S・W) 装飾的な鉄細工とともに、風向きを示す機能を持っている。 実用性とともに市場のランドマーク的存在。・象徴性 「ビリングズゲイト」はロンドンにおける魚の取引の代名詞であり、風見の魚は街の人々に とって 魚市場そのもののシンボル であった。 1875年に建てられた市場建物に取り付けられ、現在もイベント会場として残る建物の屋上で 輝いていたのであった。そして旧ビリングズゲイト市場(Old Billingsgate Market)の正面アーチ部分にある鉄製装飾(wrought ironwork)に近づいて。1.中央の盾と十字 中央には大きな盾があり、その上には ロンドン市のシティ・オブ・ロンドンの紋章 (赤い十字+上部に剣) がデザインされています。 これは、建物が City of London(ロンドン市当局) の管轄であることを示す。2.魚のモチーフ 盾の下には大きな魚(おそらくサーモンやコッド)が彫られていた。 これは、ビリングズゲイト市場が 魚市場 であったことを象徴。 「金色の魚の風見」と同じく、建物全体に散りばめられた 魚のシンボル の一部。3.左右対称の装飾 盾の両側にはスクロール(渦巻き模様)やアカンサスの葉飾りがあり、アーチの枠を強調。ロンドン市(City of London)の通り名標識。「Old Billingsgate Walk(オールド・ビリングズゲイト・ウォーク)」 を示す通り名標識。郵便地区は EC3、さらに Thames Path(テムズ・パス) の一部であることが明記されていた。そしてここからは 「Dark House Walk(ダーク・ハウス・ウォーク)」。・周辺はロンドン橋(London Bridge)の東側、カスタムハウス(Custom House)と 旧ビリングズゲイト市場(Old Billingsgate Market)の間にあたる。・「Dark House」は、17世紀以前から記録に登場する古い建物名。・この建物は、船乗りや荷運び人に関連していた倉庫・宿屋であったと。・「暗い(Dark)」という名は、採光が悪く、川辺に影を落とす建物だったことに由来する と。・その後、周辺一帯が「Darkhouse Lane(ダークハウス・レーン)」と呼ばれるようになり、 現在に残ったのが「Dark House Walk」である と。その先の右側のビルの屋上奥から顔を出していた塔が、ロンドンの有名なモニュメント「The Monument to the Great Fire of London)・ロンドン大火記念塔」。再びテムズ川下流を振り返って。ロンドンの超高層ビル ザ・シャード(The Shard)・約310メートル(95階建て)。・地上1〜40階:赤 オフィス・地上40〜52階:青 レストラン(Aqua Shard, Hutong, Oblix など)・地上53〜65階:緑 シャングリ・ラ ホテル・地上68〜72階:オレンジ 展望台(The View from The Shard)・地上73〜95階:紫 先端部(サービスフロア+機械室+尖塔)と。こちらもネットから。Grant's Quay Wharfを進み、この階段を上り、London Bridge・ロンドン橋上に向かう。London Bridge・ロンドン橋。ひときわ高くそびえるのが The Shard(ザ・シャード)。歩行者が多く歩いているのが見えた。現在のロンドン橋は1973年に完成したコンクリート製の橋で、歩道が広く確保されていた。右手に尖塔が見えるのは サザーク大聖堂(Southwark Cathedral)。ロンドン最古のゴシック教会のひとつで、橋の南詰すぐそばに建っていた。London Bridge案内板。「LONDON BRIDGEOne site, many bridgesThe current bridge is one of many since the Romans built the first one close to this site 2,000 years ago:it is thought to have had a drawbridge in the centre to allow ships to sail upriver just like Tower Bridge does today.Through the centuries various wooden bridges were built, which collapsed or weredestroyed, until a stone bridge was built in 1176.This bridge lasted 600 years. Houses were built on the bridge to bring in tax revenue.In the lower right of the illustration, over the southern gatehouse, you can see the heads of executed criminals on spikes.」 【ロンドン橋一つの場所に、多くの橋現在の橋は、この場所に建てられてきた数多くの橋の一つです。最初の橋は、約2000年前にローマ人によってこの近くに建設されました。その初期の橋には中央に跳ね橋があり、船が上流へ航行できるようになっていたと考えられています。これは今日のタワーブリッジと同じ仕組みです。その後も長い年月にわたり、木製の橋がいくつも建てられましたが、崩壊したり破壊されたりしました。ついに1176年に石造りの橋が完成しました。この石橋は600年間存続しました。さらに、税収を得るために橋の上には家々が建てられていました。右下の挿絵には、南側の門楼の上に処刑された罪人の首が槍に晒されている様子が描かれています。】上記の挿絵をネットから。この挿絵は、中世から近世にかけての旧ロンドン橋(Old London Bridge) を描いた有名な図版の一つ。1.石造の橋本体 ・橋桁は多数のアーチで構成されており、テムズ川を渡る大規模な石造建築でした (1176年完成)。 ・中世ヨーロッパでは珍しい長大橋で、約600年間使用されました。2.橋の上の建物群 ・橋の両側に家屋や商店が建ち並び、小さな町のような景観を作り出していました。 ・この家並みは課税の対象であり、市の財源として大きな役割を果たしました。 ・2階建て、3階建ての木造家屋が密集し、上から見るとまるで通りそのものが川の上に 存在するように見えます。3.南側のゲートハウス ・手前右側に見える大きな城門のような建物が南側のゲートハウスです。 ・出入りを管理するだけでなく、処刑者の首を槍に掲げて晒す場でもありました。 ・イラストでも、屋根の上に多数の槍と首が描かれています。4.テムズ川の船舶 ・川には小舟や帆船が航行しており、商業と交通の拠点としての重要性を示しています。 ・アーチが狭いため、水流が強く「危険な通航地点」として知られ、船の事故もしばしば 起きました。5.背景のロンドン市街 ・奥に多数の教会の尖塔が描かれています。特に高くそびえるのは 旧セントポール大聖堂 (Old St. Paul’s Cathedral) の尖塔です(現在のバロック様式のセントポール大聖堂の 前身)。 ・ロンドンの都市景観と宗教的中心地を同時に示しています。ロンドン橋は単なる交通手段ではなく、「橋の上に家並みがある町」+「通行・課税の拠点」+「処刑見せしめの場」という多面的な役割を担っていたことを理解したのであった。名称を朱記してみました。ロンドン橋(London Bridge) に設置されている「City bridges」の解説。「City bridgesThe bridges across the River Thames are a vital part of London’s transport infrastructure. The City of London Corporation owns and maintains four road bridges, and since the dayof its re-opening in February 2002, the Corporation has taken over full responsibility for the Millennium Bridge.The bridges need expert maintenance to ensure they do their job as gateways to the Cityand to keep the river safe for transport. They jointly bear the weight of 130,000 vehiclesevery day, nearly 50 million a year.」 【ロンドン橋シティの橋テムズ川にかかる橋は、ロンドンの交通インフラにおいて欠かせない存在です。ロンドン市(City of London Corporation)は4つの道路橋を所有・維持管理しており、2002年2月の再開以降はミレニアム橋についても全面的な責任を負っています。橋は、シティへの玄関口としての役割を果たし、また川を安全に交通路として利用できるよう、専門的な維持管理が必要です。これらの橋は共同で、毎日13万台、年間およそ5,000万台の車両を支えています。】City of London(ロンドン市)の地図とともに、テムズ川にかかる主要な橋が示されていた。左から順に・Blackfriars Bridge・Millennium Bridge・Southwark Bridge・London Bridge・Tower Bridge「テムズ川の生物多様性」についての説明パネル。「LONDON BRIDGEAquatic biodiversityThe River Thames is full of life:at least 115 species of fish and 350 species of invertebrates (like estuarine shrimp or mud snails).There are dozen of types of water birds, and dozens more use the river as their migratory route and feeding ground.If the river is at low tide, you can see patches of foreshore.This foreshore is of great ecological importance, as it provides a place for algaeto grow, a base for seaweed and invertebrates, and feeding and spawning areas for fish.」【ロンドン橋水生生物の多様性テムズ川は生命に満ちています。少なくとも115種の魚類と、エビやカワニナのような350種の無脊椎動物が生息しています。また、数十種類の水鳥が見られ、さらに多くの鳥がこの川を渡りのルートや採餌の場所として利用します。川の水位が下がると、川岸の干潟を見ることができます。この干潟は生態学的に非常に重要で、藻類が育つ場所となり、海藻や無脊椎動物の基盤となり、魚の採餌や産卵の場を提供しています。】右側の生物図解・Signal Crayfish(ウチダザリガニ)・Roach(ローチ:淡水魚)・Chinese Mitten Crab(チュウゴクモクズガニ)・Pike(カワカマス)・European Eel(ヨーロッパウナギ)・Seahorse(タツノオトシゴ)テムズ川は生命に満ちている。少なくとも115種の魚類と、エビやカワニナのような350種の無脊椎動物が生息しているとのこと。ロンドン橋(London Bridge) に関する歴史と童謡「London Bridge is falling down」👉️リンク に触れたもの「LONDON BRIDGEA bridge to the pastNo one knows the real story behind the nursery rhyme about the bridge.One theory is that it commemorates an attack by the Saxons and Vikings which destroyed it.Perhaps a stronger theory is that the rhyme catalogues the slow deterioration of the medieval bridge of 1176, which lasted six hundred years, a vast period of timein which it partially collapsed twice and was severely damaged in the Great Fire of 1666.」 【ロンドン橋過去への架け橋この童謡(ナーサリーライム)の本当の由来は誰も知りません。一説には、橋を破壊したサクソン人やヴァイキングの襲撃を記念したものとされます。もう一つの有力な説は、この童謡が1176年に建てられた中世の石橋のゆっくりとした老朽化を記録したものであるというものです。その橋は600年間存続しましたが、その間に二度部分的に崩壊し、1666年のロンドン大火で深刻な損傷を受けました。】右手には歌詞が。「London Bridge is falling down,Falling down, falling downLondon Bridge is falling down,My fair lady.Build it up with wood and clay,Wood and clay, wood and clay,Build it up with wood and clay,My fair lady.Wood and clay will wash away,Wash away, wash away,Wood and clay will wash away,My fair lady.」 【ロンドン橋落ちた、落ちた、落ちたロンドン橋落ちた、わたしの美しい人木と粘土で造ろう、木と粘土、木と粘土木と粘土で造ろう、わたしの美しい人木と粘土は流される、流される、流される木と粘土は流される、わたしの美しい人】この童謡「London Bridge is Falling Down」はイギリスの子どもの遊び歌で、橋の崩壊と再建を繰り返し歌にしている点が特徴。実際にロンドン橋は、歴史上何度も崩壊や焼失を繰り返してきた と。引き返して、King Willliam Streetの歩道を北に向かって歩く。左手の建物はFishmongers Hall(フィッシュモンガーズ・ホール)。歴史・魚商人組合(Worshipful Company of Fishmongers) は、ロンドン市の中でも 最古のギルドのひとつで、13世紀初頭に起源を持ちます。・中世以来、テムズ川を通じた魚の流通・販売の権益を管理し、ロンドン市の食文化と経済に 深く関わってきました。・現在もロンドン市の Great Twelve Livery Companies(十二大ギルド) に数えられます。現在の建物は、ロンドン大火(1666年) で焼失した旧ホールを引き継ぐもの。1834年に完成し、威厳ある石造ファサード、クラシカルな列柱、上部の紋章が特徴的。内部には、組合の歴史を伝える 絵画・彫刻・記念品 が多数収蔵されている と。ロンドン橋(London Bridge)の北詰側、シティ・オブ・ロンドンに入る方向の景観。正面奥に建っている白い石造の大きな建物は Adelaide House(アデレード・ハウス) 。・竣工:1925年・特徴:当時ロンドンで最も高いオフィスビルのひとつ(高さ約43m、10階建て)・場所:ロンドン橋の北端すぐ横、テムズ川沿いに位置。・由来:名前はアデレード王妃(Queen Adelaide、ウィリアム4世の王妃)にちなむ と。Adelaide Houseのビルの前にあったのが 「Rooftop garden in 1930(1930年の屋上庭園)」 と題された歴史的な写真パネル。・花壇や芝生が整備され、都市の中とは思えない緑豊かな空間が広がっている。・人々(赤く彩色されている人物たち)は椅子に座って談笑したり、庭を散策したりと、 くつろぎのひとときを楽しんでいるのであった。Adelaide House(アデレード・ハウス)の屋上庭園から見た1930年当時の景観。・女性がジョウロを持って植物に水をやっている姿は、当時も都会の屋上庭園が生活と直結 していたことを伝えているのであった。「1932年の縄跳び写真」「Women skipping on the Adelaide House rooftop in 1932BLOOM & GROW WITH REAL PROMINENCEAdelaide House has always been a place to foster bright minds.A pioneering development, with spectacular views,helping you attract and retain the very best talent.」 【1932年、アデレード・ハウス屋上で縄跳びをする女性たち大きな存在感をもって咲き誇り、成長するアデレード・ハウスは常に優れた知性を育む場であり続けてきました。革新的な開発であり、壮観な眺望を備え、最高の人材を引き寄せ、維持する手助けをしてきました。】 このドームのある建築物の名前はGuardian Assurance Plcの建物。・所在地:68 King William St, London EC4N 7HR🏛️建築概要:かつての保険会社 Guardian Assurance Company(ガーディアン保険) の本社として建てられたもので、ロンドン金融街(シティ)の中心部、バンク交差点(Bank Junction)のすぐそばにあります。ファサード中央に見える金色のガーディアン(守護天使)の像と大時計が有名な意匠。現在は「60 Lombard Street」としてオフィスビルに転用されています。💡特徴設計:20世紀初頭、エドワード様式(Edwardian Baroque)に分類される壮麗な石造建築。頂部のドーム屋根と両翼のマンサード屋根(mansard roof)が印象的。中央部の大時計の上に立つ金色の像は、守護の象徴“Guardian”を具現化したもの。右手奥にあったのが「ロンドン大火記念柱(The Monument to the Great Fire of London)」。・正式名称:The Monument to the Great Fire of London・建設期間:1671年〜1677年・設計者:サー・クリストファー・レン(Sir Christopher Wren) とロバート・フック (Robert Hooke)・高さ:61.57メートル(202フィート) ・大火が始まった プディング・レーン(Pudding Lane) のパン屋の跡地からの距離と 同じ高さに設計されています。・目的:1666年の ロンドン大火(Great Fire of London) を記念し、また復興を象徴する 記念碑として建設。ロンドン大火とは・発生:1666年9月2日、プディング・レーンのパン屋から出火。・被害:シティ・オブ・ロンドンの大部分を焼失し、87の教会と約13,200軒の家屋が消失。・影響:ロンドンの都市計画と建築基準が大きく改められる契機となった。Monument の特徴・頂上部分:金色の炎をかたどったオーブ(火の玉)。・内部:螺旋階段(311段)を登ると、展望デッキからシティ・オブ・ロンドンとテムズ川を 一望できます。・位置:Monument Street と Fish Street Hill の交差点、ロンドン橋とタワーブリッジの 中間地点にあります。・文化的意義:ロンドンのシティにおける最も有名なランドマークのひとつで、地下鉄 「Monument駅」の名称の由来にもなっている。金色の炎をかたどったオーブ(火の玉)をズームして。ネットから。内部階段、これもネットから。ロンドン大火記念柱(The Monument to the Great Fire of London) の基壇に施された大きな浮彫(レリーフ)。・作者:カイウス・ガブリエル・シブベル(Caius Gabriel Cibber, 1630–1700)・題材:1666年のロンドン大火と、その後の復興を寓意的に表現。・配置:モニュメント基壇の西側に設置されており、通行者から正面で見える位置。ロンドン大火記念柱(The Monument)基壇の大レリーフ の上部中央部分をクローズアップ。1.左側の人物(冠をかぶった翼のある女性像)・王冠のようなものを頭にいただき、背に翼をもち、右手からは果物や穀物の束が豊かに こぼれ落ちています。・これは 豊穣(Abundance, Plenty) または 繁栄(Prosperity) を擬人化した存在。・ロンドンが再び豊かさを取り戻すことを象徴。2.右側の人物(若い女性像、オリーブの枝を持つ)・手にオリーブの枝を持ち、平和を象徴する姿。・これは 平和(Peace) の寓意像。・大火後の混乱の終息と、平和な復興時代の到来を示している。基壇レリーフの右側部分をクローズアップ。1.左の人物(長髪でマントを纏う)・王冠をいただき、中央に堂々と立っている人物は チャールズ2世(Charles II) を 寓意的に表したもの。・右手を前方に差し出し、ロンドン再建の指揮を執る姿を示している。2.中央奥の冠を被る人物・こちらも王権や統治を象徴する補助的な寓意像と解釈される場合がある。・チャールズの正統性を強調する「王権の擬人像」とされることが多い。3.右手前の人物(兜をかぶり、月桂冠を持つ)・戦士風の姿で、手に持つ月桂冠は 勝利(Victory) の象徴。・ロンドンが試練を克服し、新しい都市として「勝利」することを意味。4.最右の人物(獅子の頭を掲げる)・ライオンはイングランド王国を象徴。・王の力と国家の威厳を表している。基壇レリーフの左側部分をクローズアップ。1.中央下の女性(倒れ込む姿)・都市ロンドンを寓意化した女性像。・崩壊した都市と市民の苦悩を表現し、力尽きて横たわっている。2.左の老人(長い髭をもつ半裸の男性)・「時(Time)」を象徴する人物。・老いた姿で力強く女性(ロンドン)を支え、時間が再生をもたらすことを示している。3.右の女性(胸をはだけて優しく支える)・「真実(Truth)」または「慈悲(Compassion)」の寓意像。・ロンドンを慰め、復興への希望を伝える存在。4.背後の天使(翼をもつ)・神の加護や守護を象徴。・災厄から救済へ導く天的な存在を強調。「THE MONUMENTThe Monument, designed by Robert Hooke FRS in consultation with Sir Christopher Wren, was built 1671–1677, on the site of St Margaret Fish Street Hill, to commemorate the Great Fire of London 1666. The fire burnt from 2 to 5 September, devastating two-thirds of the City, and destroyed 13,200 houses, 87 churches, and 52 Livery Company Halls.The Monument, a freestanding fluted Doric column topped by a flaming copper urn, is 61m/202ft in height, being equal to the distance westward from the site of the bakeryin Pudding Lane where the fire broke out. Its central shaft originally housed lenses for a zenith telescope and its balcony, reached by an internal spiral staircase of 311 steps, affords panoramic views of the City. The allegorical sculpture on the pedestal above wasexecuted by Caius Gabriel Cibber and shows Charles II coming to assist the slumped figure of the City of London.ST MAGNUS THE MARTYRFish Street Hill, to the south, leads to St Magnus the Martyr, a Wren church, alongsidewhich is the ancient street which led to the medieval London Bridge.」 【モニュメント(大火記念柱)モニュメントは、ロバート・フック(FRS)がサー・クリストファー・レンと協議して設計し、1666年のロンドン大火を記念するため、1671年から1677年にかけてセント・マーガレット教会(フィッシュ・ストリート・ヒル跡地)に建てられました。大火は9月2日から5日まで燃え続け、市の3分の2を壊滅させ、13,200軒の家屋、87の教会、52の同業組合ホールを焼失させました。モニュメントは、頂上に炎をかたどった銅製の壺を戴く独立したフルート付きドーリス式円柱で、高さ61メートル(202フィート)。これは火災が発生したプディング・レーンのパン屋跡から西に離れた距離と等しい高さです。中央のシャフトは当初、天頂望遠鏡のレンズを収めるためのもので、内部の311段の螺旋階段を上った先のバルコニーからはシティを一望できます。基壇上の寓意的な彫刻はカイウス・ガブリエル・シブベルによって制作され、倒れ込むロンドン市の擬人像を助けに来るチャールズ2世を表しています。聖マグナス教会(St Magnus the Martyr)フィッシュ・ストリート・ヒルを南へ行くと、レン設計の聖マグナス教会に至ります。その横には、中世ロンドン橋へと通じていた古代の通りがあります。】ロンドン大火記念柱(The Monument)基壇のラテン語銘文。【キリスト紀元1666年9月4日、都市の東部で火災が発生した。その後2日間、猛烈な風に煽られた火は、37の教会、城門、大通り、市場、公共建物、学校、図書館、そして約13,200軒の家屋を焼き尽くし、繁栄を誇ったこの都市の大部分を灰燼に帰した。3日目には、人間の力も手段も尽き果て、まるで世界全体が最終的な炎で滅びるかのように思われた。しかし、ついに天の意志により、この宿命の火は鎮まり、あらゆる場所で燃え尽きた。】「TRANSLATION OF THE LATIN INSCRIPTION ABOVECharles the Second, son of Charles the Martyr, King of Great Britain, France and Ireland, Defender of the Faith, a most Gracious Prince, commiserating the deplorable state ofthings, whilst the ruins were yet smoking, provided for the comfort of his citizens andthe ornament of his city; remitted their taxes, and referred the consideration of the reparation of the Magistrates and Inhabitants of London to the Parliament, who immediately passed an Act that public works should be restored to a greater beauty, with public money to be raised by an imposition on coals, that churches, and the Cathedral of St Paul’s should be rebuilt from their foundations, with great magnificence; that the bridges, gates and prisons should be new made; the sewers cleansed; the streets made straight and regular; such as were steep levelled and those too narrowmade wider, markets and shambles removed to separate places. They also enactedthat every house should be built with party-walls, and all raised of an equal height in front; and that all house-walls should be strengthened with stone or brick; and thatno man should delay building beyond the space of seven years. Furthermore, he procuredan Act to settle beforehand the differences about meum and tuum (mine and yours),boundaries also being settled. An annual service of intercession was also established,and he caused this column to be erected as a perpetual memorial to posterity. Jesusit seems everywhere, London rises again, whether with greater speed or greater magnificence is doubtful. Three short years complete that which was consideredthe work of an age.」 【大ブリテン、フランスおよびアイルランドの王にして信仰の守護者である「殉教王チャールズ」の子、チャールズ2世は、最も寛大な君主として、まだ廃墟が燻っていた頃に惨状を嘆き、市民の慰めと都市の美観のために施策を講じた。彼は市民の税を免除し、ロンドンの復興に関する検討を議会と市当局に委ねた。議会は直ちに法律を制定し、公費を石炭税で賄い、公共施設をより美しく再建することを決めた。聖ポール大聖堂と諸教会は基礎から再建され、壮麗さをもって復興された。橋や城門、牢獄も新しく建て直され、下水は清掃され、通りは真っすぐ整然とされ、急な坂は平らにされ、狭すぎる道は拡幅され、市場や屠殺場は他所へ移された。また、すべての家屋は防火壁を設け、正面の高さを揃え、壁は石やレンガで補強することとされた。さらに、いかなる者も7年を超えて建築を遅らせてはならないとされた。加えて、土地の境界や所有権の争いを事前に解決するための法律も制定された。毎年の祈祷式も定められ、そして後世への永遠の記念として、この記念柱(モニュメント)が建てられた。イエスの御名のもと、ロンドンはあらゆる場所で再び立ち上がった。その復興が速さにおいて勝っていたのか、壮麗さにおいて勝っていたのかは定かでない。わずか3年にして、人々が「一世代を要する」と考えていた復興を完成させたのである。】再び見上げて。ロンドン・シティ地区に設置されている 観光・徒歩案内マップ。・テムズ川を中央にして北側(シティ側)と南側(サザーク側)が描かれている。・黒線で道路、青で川、黄で主要建物・観光地がマークされている。・外周に「15 minute walk(徒歩15分圏内)」の円が描かれており、徒歩で移動できる範囲を 示している。ロンドンの街歩き用 エリアマップ。先ほどの案内板より範囲が広く、特に Tower of London(ロンドン塔)からLondon Bridge(ロンドン橋)周辺まで がしっかり描かれていた。・中央に「You are here(現在地)」が記されており、Monument駅周辺にいることがわかる。・外周には「15 minute walk」の円があり、徒歩圏を直感的に示していた。ロンドン大火記念柱(The Monument)の前からテムズ川方向の道の奥に見えたのが「St Magnus the Martyr Church(聖マグナス教会)」の尖塔。ロンドン大火(1666年)でこの教会も焼失したが、都市復興の一環として再建。・再建:1671~1687年、サー・クリストファー・レンの設計で再建。・建築様式:バロック様式。白いポートランド石で造られ、特徴的な塔(尖塔を持つ)は 1725年に完成。・特徴: ・内部は華やかなバロック装飾が施され、祭壇や説教壇は細かな彫刻で彩られている。 ・ロンドン橋に隣接していたため、橋を渡る人々が必ず目にしたランドマーク。 ・歴史的に、ロンドン橋の入口に位置する「門の教会」の役割を果した。 ロンドンの有名な高層ビル20 Fenchurch Street(通称:ウォーキー・トーキー / Walkie Talkie)。・完成:2014年・高さ:160 m(層数 38階)・設計者:ラファエル・ヴィニオリ(Rafael Viñoly)・愛称:「ウォーキー・トーキー(トランシーバー)」・独特の上に広がるフォルムから、ロンドン市民にこう呼ばれている と。上部が張り出したデザインで、下部よりも上層階が大きい逆テーパー構造。完成当初、反射光が集中して地上の車を「溶かす」ほどの熱を発生させたため、「デス・レイ」ビルとも揶揄されました(後に修正済み)。ドームのある建築物・Monument Place前まで歩を進める。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)の西側の時計塔(West Tower with Clock)。設計は サー・クリストファー・レン、1710年に完成。ロンドン大火(1666年)の後、焼失した旧聖堂の跡地に建てられた再建聖堂。左奥に青く光る部分が見えるのは BT Tower(旧名:Post Office Tower)。1960年代に建設された高さ177mの通信塔で、ロンドンのランドマークのひとつ。急に雨が降り出し、一時避難。ロンドンの金融街「シティ(City of London)」の街並み、そして近代的な超高層ビルとクラシカルな石造建築が並ぶ典型的な光景を見ながらの雨宿り。小雨が降り続けていたので、この日のロンドン市内の散策はこれまでとし、セント・ポール大聖堂 ・St. Paul's Cathedralの散策は翌日とし、近くにあったロンドン地下鉄「モニュメント駅(Monument Station)」へ向かった。「モニュメント駅(Monument Station)」構内。そして「SOUTH KENJINTON」駅で下車。 「SOUTH KENJINTON」駅から宿泊の民宿・アパートメントに向かったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.10
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その103): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-18
ロンドン塔(Tower of London)のすぐ近く、タワーブリッジへ向かう大通り沿いロンドン・タワーヒル(Tower Hill)にある「The Liberty Bounds(リバティ・バウンズ)」 というパブを見る。20世紀初頭に建てられた壮麗な石造建築を改装したもの。アーチ窓や装飾が特徴的。観光客や地元客に人気で、ロンドン塔見学後の休憩スポットとして利用されることが多い と。ロンドン塔方向に引き返して。・左の白い塔(四角い石造の大きな塔) → これがロンドン塔の中核「ホワイト・タワー(White Tower)」です。 ノルマン王ウィリアム1世(征服王)が11世紀後半に建設した要塞で、城塞全体の象徴的存在。・ホワイト・タワーの四隅の円塔 → 角ごとに丸い塔が建っており、旗が翻っているのが見えます。・写真右奥に見える2つの尖塔 → これは タワーブリッジ(Tower Bridge) の塔上部分。ロンドン塔のすぐ東にあり、 セットで観光される名所。・手前の石壁とベンチ → 手前がロンドン塔外周の「Tower Hill」広場。観光客向けの案内板や説明パネルが 設置されていた。タワーブリッジ(Tower Bridge) の塔上部分をズームして。少しテムズ側方向に入り込んで。再び・中央奥の大きな四角い建物 → 「ホワイト・タワー(White Tower)」。ロンドン塔の中心建物で、11世紀末に ウィリアム征服王が建設。塔の四隅に丸い塔があり、屋根の上に風見が付いているのが特徴。・ホワイト・タワーの手前左側の低い城壁と塔群 → 「インナー・ウォード(内郭)」の一部で、いくつかの防御塔が見えや。特に写真左側の 四角い塔は「ミドル・タワー(Middle Tower)」や「ビーチャム・タワー (Beauchamp Tower)」方面に続く防御線の一部。・手前の広場 → 「Tower Hill」側の公開エリアで、観光客が集まる場所。石畳の広場で、外壁と堀を 見渡せるスポットであった。「ホワイト・タワー(White Tower)」をズームして。ロンドン塔前に設置されている案内パネルをズームして。この案内板に描かれている、冠を戴き、剣と盾を持った人物は、征服王ウィリアム(ウィリアム1世, William the Conqueror, r.1066–1087)「The origins of the TowerThe Tower of London is named after its oldest building, the White Tower.William the Conqueror built the White Tower in the late 1070s as a secure royal fortress.」【塔の起源ロンドン塔(Tower of London)は、その最も古い建物である「ホワイト・タワー」にちなんで名づけられています。征服王ウィリアム(ウィリアム1世)は、1070年代後半にこのホワイト・タワーを堅固な王室要塞として建設しました。】 この画像は 「バイユーのタペストリー(Bayeux Tapestry)」 の一場面を拡大したもの。・中央:「WILLELM」 と書かれている人物 → これは 征服王ウィリアム(ウィリアム1世, William the Conqueror)。 ノルマン征服でイングランド王となった本人です。・左:「ODO EPS」 と書かれている人物 → これはウィリアムの異父弟 オド司教(Odo, Bishop of Bayeux)。ノルマン征服の 主要な支援者で、軍事的にも政治的にも重要な役割を果たした。・右:「ROTBERI」 と書かれている人物 → これは ロベール伯(Count Robert, たぶんウィリアムの異母兄弟ロベール・ド・モルトゥン)。 彼もまた征服王の有力な支持者。この場面は、バイユーのタペストリーに描かれた ウィリアムの会議 (council)または戦略会談 のシーンの一部である と。このパネルは ロンドン塔(Tower of London)創建当初のイメージ図。「He built the Tower within existing Roman city walls to help defend it from attack.The castle dominated London and its people and showed the power of the new king.」【彼(征服王ウィリアム)は、既存のローマ時代の城壁の内側にロンドン塔を築き、攻撃から守る助けとしました。この城はロンドンの街と人々を支配し、新しい王の権威を示しました。】 「ロンドン塔は、最古のホワイトタワーにちなんで、タワー・オブ・ロンドンと名付けられました。征服王ウィリアムは1070年代に、王室の堅固な要塞としてホワイトタワーを建設しました。古代ローマ人が築いた市壁の内側に塔を建て、攻撃から護ろうとしたのです。この城郭は、ロンドンとその市民を支配し、新しい王の権力を誇示するものでした。」 「王宮としての塔(A royal palace)」エリザベス1世(Elizabeth I, r.1558–1603)「A royal palaceThe Tower was also a royal palace.It had grand apartments where the king or queen could stay, entertain and conduct business.」【王宮としての塔ロンドン塔は、王宮としての役割も果たしていました。そこには壮麗な居住空間があり、国王や女王が滞在し、賓客をもてなし、政務を行うことができました。】戴冠式(coronation)とロンドン塔の関係 を説明する案内パネル。・ロンドン塔と戴冠式 戴冠式に臨む王や女王は、伝統的にロンドン塔に前泊しました。ここは「王宮」としての 機能を備え、また王権の威光を示す象徴的な場所でもありました。・戴冠行列(Coronation Procession) ロンドン塔からシティ・オブ・ロンドンを横断し、ウェストミンスター寺院へ至る壮大な行列が 行われ、国民に新王を披露する儀式となっていました。・エリザベス6世の列(1559年) エリザベス1世はロンドン塔に滞在し、戴冠式前夜を過ごした後、盛大な行列とともに ウェストミンスター寺院へ向かいました。「Kings and queens, such as Elizabeth I, stayed at the Tower before they were crowned.They began the coronation procession here, travelling through the City of London, before being crowned at Westminster Abbey.」【エリザベス1世をはじめとする王や女王は、戴冠式の前にロンドン塔に滞在しました。彼らはここから戴冠行列を始め、ロンドン市内を通ってウェストミンスター寺院へ向かい、そこで戴冠を受けました。】 1547年2月19日、エドワード6世(Edward VI, 在位1547–1553)が戴冠式に先立ってロンドン塔からウェストミンスターへ行進した場面・エドワード6世の戴冠行列を描いた有名な歴史画をネットから。・左端:ロンドン塔(Tower of London) 城門を出発する国王の一行が描かれています。・中央部:ロンドン市内の街並み 建物の壁に布やタペストリーが掛けられ、市民が道端や建物の上から行列を見物しています。 道の中央を騎馬の貴族、兵士、従者が整然と進行しています。・中央の大きな建物:聖堂のようなゴシック建築 ロンドン市内の大教会堂(セントポール大聖堂とも関連する意匠)を象徴的に描いています。・右端:行列がさらに西へと進み、最終的にはウェストミンスター寺院(Westminster Abbey) に到着します。エリザベス1世(Elizabeth I, r.1558–1603)の戴冠行列(Coronation Procession)を表す図。・中央 白い衣装に王冠を戴き、華麗な天蓋(キャノピー)の下にいるのが エリザベス1世。 戴冠式に向かう際の象徴的な姿として描かれている。・周囲の人物たち 王室の廷臣や貴族たちが取り巻き、彼女を先導・護衛。 左右には、色鮮やかな衣装を身にまとった廷臣・従者たちが整列。 背後にはさらに多くの群衆が描かれ、行列の壮大さを強調。・背景 都市の建物や門が描かれており、ロンドン市内を進む華やかな戴冠行列の一場面を示している。「ロンドン塔は、王宮でもありました。王や女王が滞在し、客をもてなし、執務する立派なアパートメントがありました。エリザベス一世をはじめとする王や女王は、ここに戴冠式前に滞在しました。王室の行列はここからロンドン旧市内を通り、ウェストミンスター寺院の戴冠式に向かったのです。」 この案内板はロンドン塔のもう一つの顔、「処刑の場(A place of execution)」 を説明していた。・パネルに描かれているのは、まさに アン・ブーリン(Anne Boleyn, c.1501–1536)。・ヘンリー8世の王妃として王位継承争いの中心に立ち、エリザベス1世を産んだ後に失脚。・ロンドン塔内で処刑された最も有名な人物の一人「A place of executionFrom the 1100s, the Tower became an infamous prison.Between 1483 and 1941, 22 prisoners were executed inside the walls, ncluding Anne Boleyn, second wife of King Henry VIII, in 1536.」 【処刑の場12世紀以降、ロンドン塔は悪名高い監獄となりました。1483年から1941年の間に、城壁内で22名の囚人が処刑されました。その中には、1536年に処刑されたヘンリー8世の二番目の王妃、アン・ブーリン(Anne Boleyn) も含まれています。】ロンドン塔と処刑場「タワーヒル(Tower Hill)」。「Several hundred Tower prisoners were hanged or beheaded on Tower Hill. These events attracted vast crowds.The last public execution on Tower Hill took place in 1780.」 【ロンドン塔の囚人のうち、数百人がタワーヒルで絞首刑または斬首刑に処されました。これらの処刑は大勢の群衆を集めました。タワーヒルで行われた最後の公開処刑は 1780年 でした。】・左上の斧:斬首刑に使われた処刑具の象徴。・右上の木版画風の図:囚人が斬首される場面。処刑人(首切り役人)と立ち会う人々が 描かれています。・下の大きな絵:ロンドン塔を背景に、大観衆が集まる公開処刑の様子。壇上に処刑台が 設けられ、多くの人々がそれを取り囲んでいます。「The Beheading of the Rebel Lords on Great Tower Hill」 【反逆貴族たちのタワーヒルにおける斬首刑】ロンドン塔北側のタワーヒル(Tower Hill)での公開処刑の様子 を描いたもの。ロンドン塔を背景に、タワーヒルの大広場で多くの群衆が集まり、反逆者とされた貴族が処刑される様子を描いている。左:処刑台(黒い台)があり、赤い軍服を着た兵士たちが周囲を取り囲む。中央:膨大な群衆。見物人は立ち見や馬車の上から見守っている。右:テムズ川と塔の石壁。川には見物人を乗せた船も浮かんでいる。背景:右奥にロンドン塔(ホワイト・タワーの尖塔が)。【1100年代以降、この塔は悪名高い監獄になりました。1536年に処刑されたヘンリー八世の2人目の妻、アン・ブーリンをはじめ、1483年から1941年までの間に22名がここで処刑されました。また、ここの囚人のうち数百名が、タワーヒルで絞首刑または斬首刑となりました。処刑には、大勢の群衆が集まりました。タワーヒルの公開処刑は、1780年が最後となりました。】ロンドン塔(Tower of London)外壁とホワイト・タワー(White Tower) を北西側から。カメラをさらにテムズ川方向に向けて。・左奥に見える塔 → 風見が付いた塔は「ホワイト・タワー(White Tower)」の角塔です。ロンドン塔の中心建物。・中央の茶色い建物群 → 内郭の居住区や王宮関連の建物。後世に増築されたものが多く、煉瓦造も見えます。・中央右に連なる高い石壁 → 外郭(Outer Curtain Wall)。外側の堀とともに防御機能を果たしていました。・右端の丸い塔 → テムズ川に近い外郭の角塔。城門へつながる防御の要です。・右奥に見えるガラスの球状建築 → 近代的な建物は「シティ・ホール(City Hall, ロンドン市庁舎)」。 2002~2021年にロンドン市長庁舎として使われた、ロンドンの現代的ランドマーク。ロンドン塔(Tower of London)のビジター・センター(Visitor Centre / Entrance Pavilion) 前から西側方向を。ズームして。・左側(緑の尖塔) → All Hallows by the Tower(オール・ハローズ・バイ・ザ・タワー教会) ・ロンドン最古級の教会で、創建は西暦675年。 ・現在の尖塔部分は近世以降の再建。 ・ロンドン塔のすぐ隣にあり、塔と深い関わりを持つ教会です。・中央(小さな金色の十字架が載る屋根) → これも同教会の一部の装飾。・右奥の高層ビル → 通称 「ウォーキー・トーキー(Walkie-Talkie)」 ビル ・住所:20 Fenchurch Street ・建設:2014年完成、160mのオフィスビル ・特徴:上部が大きく広がるユニークな形。 ・最上階には「Sky Garden(スカイ・ガーデン)」という展望庭園があり、ロンドン市街を 一望できると。テムズ川とタワーブリッジ(Tower Bridge)。・奥に見える橋 → ロンドンを代表する跳開橋 タワーブリッジ(Tower Bridge, 1894年完成)。 ・ゴシック風の双塔と青い鉄骨の可動橋が特徴。 ・中央部分は跳ね上げ式で、船舶の航行に合わせて今も開閉。 ・上部のガラス床歩道「Tower Bridge Walkways」は観光名所。・手前の建物 → 川沿いの船着き場 Tower Millennium Pier(タワー・ミレニアム・ピア)。 ・テムズ川を走る水上バス(Uber Boat by Thames Clippers など)が発着する桟橋です。 ・ロンドン塔(Tower of London)の見学に来た観光客がよく利用します。・右端の黄色い模様の船 → 「London Duck Tours」などで知られる観光用の水陸両用バス風の船(遊覧船)。 デザインが派手で目立ちます。対岸の高層ビル・ザ・シャード(The Shard)と手前の軍艦・HMS ベルファスト(HMS Belfast)手前にはTower Millennium Pier・タワー・ミレニアム桟橋。カメラを右に。対岸の高層ビル・ザ・シャード(The Shard)。・高さ310m、2012年完成のロンドンで最も高いビル。・95階建てで、展望台「The View from The Shard」からロンドンを一望可能。・設計はレンゾ・ピアノ(Renzo Piano)。手前の軍艦・HMS ベルファスト(HMS Belfast)・第二次世界大戦と朝鮮戦争に参加したイギリス海軍の軽巡洋艦。・現在は博物館船としてテムズ川に係留され、Imperial War Museum が運営。・ロンドン塔やタワーブリッジ観光と合わせて訪れる人気スポット。反対方向にカメラを向けて。左からタワーブリッジ(Tower Bridge)、船着き場(Tower Millennium Pier)そしてシティ・ホール(City Hall)。ズームして。ズームして。テムズのこの風景も見納めか?これでもかとシャッターを押す。タワーブリッジとロンドンのテムズ川北岸にある桟橋・「Tower Millennium Pier(タワー・ミレニアム・ピア)」。 テムズ川の定期船(リバーボート)や観光クルーズ船の発着所として使われている。主な運行会社:・Thames Clippers(定期高速船)・City Cruises(観光クルーズ)・Thames Rockets(高速スピードボート体験)ロンドン中心部・テムズ川南岸に停泊する有名な軍艦・HMS Belfast(HMS ベルファスト)。右の建物はThe Shard(ザ・シャード)設計者:レンゾ・ピアノ(Renzo Piano)完成:2012年高さ:310メートル(当時、EUで最も高いビル)用途:オフィス、ホテル(シャングリ・ラ)、展望台、レストラン展望台名:The View from The Shard(72階・ロンドンを一望)HMS Belfast(HMS ベルファスト) が中央に。左端の丸みを帯びた建物 City Hall(ロンドン市庁舎)2002年竣工、ノーマン・フォスター設計の未来的な建築。 ※2022年に市庁舎は別地(Newham区)に移転しましたが、建物はそのまま残っています。中央のガラス張りのビル群 → More London Riverside(モア・ロンドン・リバーサイド オフィス、商業施設、レストランなどが集まる複合開発地区で、 PricewaterhouseCoopers(PwC)」のロンドン本社もここにあります。Sugar Quay Jetty・シュガー・キー・ジェティーから。・ロンドン塔のすぐ西側(Tower of London の西側/ロンドン橋寄り)。・テムズ川北岸に突き出した木製の桟橋で、現在は遊歩道・展望デッキとして整備。・ここからは、東に タワーブリッジ(Tower Bridge)、南に シティ・ホール(City Hall) を 望むことができた。Custom House(カスタム・ハウス、ロンドン税関、1817–1820年建設)。新古典主義様式の白い石造建築、長い列柱ポルチコ(柱廊)が特徴。周囲には鉄柵と青緑の街灯が。現在は HM Revenue and Customs が使用していた歴史的官庁建物だが、今は一部閉鎖・改修の段階にある と。テムズ川の観光遊覧船と、係留されている歴史的軍艦 HMS Belfast。側面に 「London Eye River Cruise」 の表示があり、ロンドン・アイ(観覧車)発着を中心に運行している遊覧クルーズ船。ピンク色の広告バナーが目印で、観光客が多数乗船していた。タワーブリッジ(Tower Bridge)方向にカメラを向けて。右手にあったのがOld Billingsgate Market(オールド・ビリングズゲイト市場)。・外観:黄褐色のレンガ造りに白い石の縁取り、1階にアーチ型の開口部。・屋根:上階にドーマー窓、角に小塔。・装飾:屋上に金色の「魚」の像(サケやチョウザメを象徴)。これは市場の性格を示すもの と。・歴史・1875年完成、建築家ホレス・ジョーンズ(Horace Jones)の設計。・用途:ロンドン最大の魚市場(Billingsgate Fish Market)。テムズ川沿いにあり、 新鮮な魚介類がここに集められた。・移転:1982年に市場機能はドックランズの新施設に移転。・現在:イベント会場・展示会・パーティ会場として利用されている と。ありし日のOld Billingsgate Marketの写真をネットから。ストリートサイン「OLD BILLINGSGATE WALK(オールド・ビリングズゲイト・ウォーク)」。 「Old Billingsgate Market(旧ビリングズゲイト市場)」のすぐ脇にあり、テムズ川沿いの遊歩道を示していいた。ロンドンの象徴的な景観のひとつ、タワーブリッジ(Tower Bridge) を正面から。Old Billingsgate Market(オールド・ビリングズゲイト市場)の前の広場を進む。建物の特徴・長いアーケード風のアーチ窓(1階部分)・黄褐色のレンガ造りに白い石の装飾・屋根のドーマー窓(丸窓付きの小屋根が並ぶ)・ファサードに等間隔で配置された柱型装飾左端の角塔部分の屋上には金色の「魚」の風見(市場の象徴)が。金色の魚の風見(weather vane)をズームして。装飾の意味・魚の形:かつてここがロンドン最大の魚市場(Billingsgate Fish Market)であったことを象徴。・金色の装飾:市場の重要性と繁栄を示す象徴的デザイン。・風見(Weather Vane):W(West)、E(East)など方角を示す。 港湾都市としてのロンドンにおいて、風向きは航行や市場にとって 重要だったため と。この日に歩いて来たテムズ川の南岸に桟橋のあったタウン級軽巡洋艦(Royal Navy, イギリス海軍)・HMS Belfast(HMS ベルファスト)を。・進水:1938年・就役:1939年8月・全長:約187m・乗員:およそ950名 と。・第二次世界大戦で活躍 ・北大西洋での船団護衛(北極海航路) ・1943年の 北岬沖海戦(バレンツ海戦) でドイツの巡洋戦艦「シャルンホルスト」撃沈に参加 ・1944年の ノルマンディー上陸作戦(D-Day) でも艦砲射撃を行い上陸部隊を支援・戦後 ・朝鮮戦争にも派遣され砲撃支援を担当・退役:1963年高さ310m(72階建て)のThe Shard(ザ・シャード)も見納め。Dark House Walkから、多くの貨物船、観光船がひっきり無しに行き交うテムズ川、そしてタワーブリッジ(Tower Bridge)を。現在もテムズ川が物流・観光クルーズの水路として活用されていることを確認できたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.09
コメント(0)
-
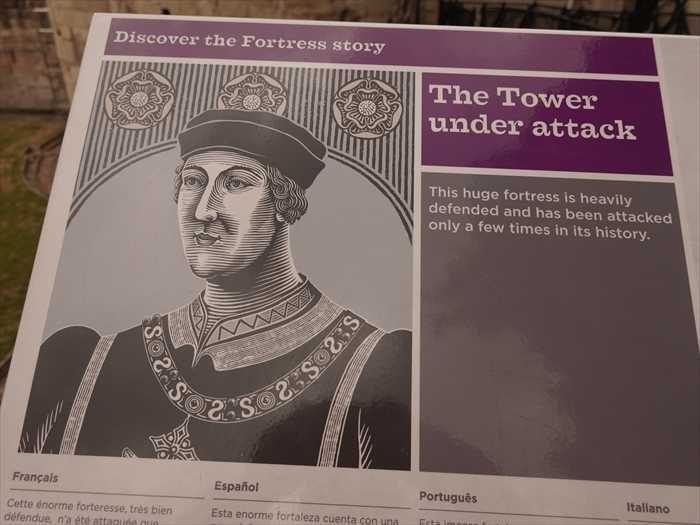
アイルランド・ロンドンへの旅(その102): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-17
ロンドン塔 Traitors’ Gate(反逆者の門) 前に設置された 陶器製のポピー(ケシの花)インスタレーション の様子を再び。タワー・オブ・ロンドンの展示解説 「The Tower under attack(攻撃を受けた塔)」「The Tower under attackThis huge fortress is heavily defended and has been attacked only a few times in its history.」【攻撃を受けた塔この巨大な要塞は強固に防御されており、その歴史の中で攻撃を受けたのはほんの数回しかありません。】 薔薇戦争時代の攻撃(1460年) を説明するもの。「In 1460 King Henry VI’s forces in the Tower were blockaded during England’s bitter ‘Wars of the Roses’.Henry was later defeated and fled to Scotland. The new king, Edward IV, added this gateway and gun platform to defend the Wharf.」 【1460年、イングランドの苛烈な「薔薇戦争」の最中、国王ヘンリー6世の軍勢はタワーの中で包囲されました。その後、ヘンリーは敗北してスコットランドへ逃亡しました。新しい国王エドワード4世は、埠頭を守るためにこの門と大砲台を増築しました。】・薔薇戦争(Wars of the Roses, 1455–1487) は、ランカスター家(赤薔薇)とヨーク家 (白薔薇)の王位継承争い。・1460年、ランカスター家側のヘンリー6世はロンドン塔に立て籠もったが、包囲され敗北。・王位はヨーク派の エドワード4世 に移り、彼は要塞の防御力をさらに強化。 ・特にテムズ川沿いのWharf(埠頭) を防衛するため、新しい門や砲台を設置した。・この強化により、ロンドン塔は中世から近世へ移行する過程で、より「火器防御」を意識した 要塞へと進化した。右側の挿絵中世写本風の彩色画で、戦場の混乱 が描かれていた。兵士たちは鎧を着て槍を持ち、激しい白兵戦を繰り広げている。倒れている兵士もおり、戦闘の苛烈さが強調されている。周囲の花や葉の装飾(ボーダー模様)は写本挿絵(illuminated manuscript)特有の様式で、王侯貴族に献上された豪華本の一部 と。ここでは「薔薇戦争」の混乱を象徴的に示しており、ロンドン塔がその戦乱の一舞台であったことを視覚的に伝えているのだ。右手に「Byward Tower(バイワード・タワー)」。・13世紀1270年代、エドワード1世 によって築かれた。・かつては「ライオン・タワー」と呼ばれる別の門塔と連結し、巨大な防御システムを形成。・厳重な防御施設で、外敵だけでなく象徴的にも「王の権力」を示す門であった。・今日では観光客のメイン入場口となっていた。 ロンドン塔の西側入口(The Western Entrance) について説明。「The Western EntranceThe main Tower entrance was once much larger and better defended.In the 1270s King Edward I created a fortified entrance with a series of gate towerssurrounded by a water-filled moat.」 【西の入口塔の主な入口は、かつては現在よりもはるかに大きく、また強固に防御されていました。1270年代、エドワード1世は水を満たした堀に囲まれた、一連の門塔からなる要塞化された入口を築きました。】ロンドン塔の西側入口と門塔群の配置図。「One of these — called the Lion Tower — was demolished in the 1850s. Today, visitors enter through the remaining gate towers.」 【これらの門塔の一つ ― 「ライオン・タワー」と呼ばれる塔 ― は1850年代に取り壊されました。今日では、訪問者は残された門塔を通って入場します。】図は「ロンドン塔(Tower of London)」の鳥瞰図(平面図風)で、城の外郭防御構造を描いている。左下に描かれている複雑なゲート群が西側入口(The Western Entrance)。一番外側が Lion Tower(ライオン塔)。かつて動物園(王室の獣舎)が置かれていた塔で、訪問者が最初に通る門でしたが、1850年代に撤去された。その奥に Middle Tower(ミドル・タワー)、さらに Byward Tower(バイワード・タワー) へと続く二重・三重の門構えになっている。そこを抜けると内側の堀を越え、ホワイト・タワーを中心とする要塞に入るのだ。The Lion Towerをネットから。写真に写っているのは 「Lion Tower(ライオン塔)」と「Middle Tower(ミドル塔)」 を再現した模型。・Lion Tower(奥の円形部分) ・円形の堅固な塔で、かつてライオンなどの猛獣を飼育したことからその名が付きました。 ・13世紀のヘンリー3世時代に建設され、19世紀(1850年代)に取り壊されています。 ・ロンドン塔の「見世物」的な役割を担い、王室動物園の一部でした。・Middle Tower(手前の門塔部分) ・外郭の防御門として、ロンドン塔の来訪者が最初に通過する門のひとつでした。 ・二重の防御構造になっており、背後に橋(跳ね橋)が架かっていました。 ・現在でも観光客はこのMiddle Towerを通って入場します(Lion Towerは現存しないため)。「中世のロンドン塔(Tower of London)」を復元した鳥瞰イラストをネットから。入城ルート(当時)テムズ川沿いの港(写真右下)から船で到着、あるいは陸路で接近。堀の外側からスロープや橋を渡って円形の Lion Tower に入る。そこから Middle Tower → Byward Tower と進み、城郭内部へ。この三重防御の「虎口」が、ロンドン塔の堅牢さを際立たせています。ロンドン塔の「ライオン・タワー(Lion Tower)」を写した古い写真パネル。・上部の白黒写真 ロンドン塔の主要な入城口のひとつだった「ライオン・タワー」を正面から見た姿です。 人々が橋を渡って塔をくぐり、城内に入っていく様子が写されています。衛兵や観光客らしき 人影も見え、入場の雰囲気が伝わります。・下部の紫地の図案 獅子(ライオン)の図柄が描かれており、これは「ライオン・タワー」の名に由来します。 かつて塔の内部には王室の獣舎(Royal Menagerie)があり、特にライオンが飼育されていました。【ロンドン塔の主要な入城口は、かつてはるかに大きく、厳重に防護されていました。1200年代に、エドワード一世が、3つの巨大な石造りの門塔と水を張った濠を増築しました。そのうちライオンタワーは、1800年代に取り壊されました。今日でも、大規模な築城に王室の権力がうかがえます。】Middle Tower(ミドル・タワー)そしてその先のByward Tower(バイワード・タワー)への通路を見る。石橋(かつては水堀に架けられていたもの)があり、その手前に Middle Tower が見えます。この案内板は「The Tower's community(ロンドン塔の共同体)」について説明。「The Yeoman Warders have been part of the Royal Bodyguard for over 500 years. They live in the Tower with their families.」 【ヨーマン・ウォーダーズ(Yeoman Warders)は、500年以上にわたり国王の親衛隊の一部を担ってきました。彼らは家族とともにロンドン塔に住んでいます。】この案内板は 「ヨーマン・ウォーダーズ(Yeoman Warders)」と堀(moat)の使われ方。「In the past, residents used the dry moat as a bowling green, tennis court and playground.Today the moat is also the starting point for Yeoman Warders’ tours, extremely popular with Tower visitors.」 【かつて乾いた堀は、住民によってボウリンググリーンやテニスコート、遊び場として利用されていました。今日では、この堀はヨーマン・ウォーダーズによる見学ツアーの出発地点でもあり、ロンドン塔の訪問者に非常に人気があります。】・Dry moat(乾いた堀) ロンドン塔を取り囲む堀はもともと水が張られていましたが、19世紀以降は排水され 「乾いた堀(dry moat)」になりました。 その後、地域の住民や守衛家族のレクリエーションの場となり、ボウリングやテニス、子供の 遊び場として活用されました。・Yeoman Warders’ tours 現在では観光客向けに「ビーフィーター・ツアー(Yeoman Warders’ tour)」が堀から 出発します。 ヨーマン・ウォーダーズは伝統衣装を身につけ、ロンドン塔の歴史や逸話を解説してくれるので、 最も人気のあるアトラクションのひとつです。ロンドン塔の乾いた堀(Dry Moat) を利用していた様子を写した歴史的な記録写真。・手前に ヨーマン・ウォーダー(Yeoman Warder/ビーフィーター) が立ち、見守っています。・場所は Byward Towerの手前。・堀の底が乾いており、数人の人々(恐らく住人や軍関係者の家族)が ボウリングのような 遊戯(lawn bowls) を楽しんでいます。【ヨーマン・ウォーダーは、500年以上にわたる王立衛兵隊です。家族と共に、ロンドン塔で暮らしています。かつての住人は、濠をローンボウリング用の芝生、テニスコートや遊び場に使いました。濠は現在、ロンドン塔の来訪者に大人気のヨーマン・ウォーダー・ツアーの出発地点でもあります。】現在のByward Towerの手前。廻り込むとMiddle Tower(ミドル・タワー)の姿が。現在ロンドン塔を訪れる観光客が最初にくぐる門として知られている。・写真に見えるのは、2つの円形の塔で構成された門構造。・塔の間に入口があり、かつては跳ね橋(drawbridge)が架かって堀を渡る形であった。・扉の上に見える大きな紋章は、王室の紋章装飾。・写真下部の「WELCOME TO THE TOWER OF LONDON」の案内板からも分かる通り、 現在の公式入場口。・歴史的背景 ・Middle Tower は 1280年代にエドワード1世によって建てられた要塞入口の一部。 ・外側には「Lion Tower(現在は消失)」があり、当時は三重の防御構造の一つであった。 ・現在は Lion Tower が失われたため、Middle Tower が外門の役割を担っている。正面から。この日はロンドン塔の内部には入らなかった。ここ、ロンドン塔・Tower of Londonを訪ねるのはこの日で3回目なのであった。2回目👉️リンクは2013年の4月に妻とロンドンに勤務する長男を訊ねて。跳ね橋(drawbridge)👉️リンクをネットから。Middle Tower 付近の花壇に植えられていた紫色の花はラベンダー(Lavender)。Tower of London Shopが前方に。・ゴシック風のレンガ造りの建物で、白い窓枠と尖った三角屋根が並んでいるのが特徴。・外壁には「Tower of London Shop」と書かれた看板が掲げられていた。近づいて。ロンドン塔観光の最後に立ち寄る場所として有名で、関連グッズ、歴史書籍、アクセサリー、模型、衣装風アイテムなどが販売されていた。ロンドン塔の正面入口付近の二重防御の門構えを見る。1.右側(白っぽい石造りの門) ・これは Middle Tower(ミドル・タワー) 。 ・外郭の最初の関門で、訪問者はまずここを通ってロンドン塔の敷地に入る。 ・円形の二基の塔があり、ここが現在の観光客の入口になっている。2.奥(少し茶色っぽい石造りで背後に見える門) ・これは Byward Tower(バイワード・タワー) 。 ・Middle Towerを通過したあとに続く、より堅牢な二重防御の門。 ・この門を抜けると、ロンドン塔の本丸に近づくのだ。 ・手前のガラス越しに見えるライオン像は、かつて Lion Tower(ライオン・タワー) が 存在したことを示す展示。 → Lion Towerは動物園の檻を兼ねており、19世紀に取り壊された と。ロンドン塔の入場周辺にあった 壁面イラスト(装飾パネル/案内壁画)。1.左端の大きな鳥・ロンドン塔を象徴する レイヴン(ワタリガラス)。・「塔のカラスが去れば、王国も滅びる」という伝説と結びついている と。2.中央の歴史的人物たち・王冠をかぶった王(エドワード一世やヘンリー八世など、塔に関連する国王たちを 象徴的に描いている)。・王妃や貴婦人たち(中にはアン・ブーリンやエリザベス一世を思わせる姿も)。・中央やや右に、ひげの男性は ヘンリー八世 をイメージした人物像 と。・その横にはテューダー朝やエリザベス朝の王族を思わせる人物が並んでいた。3.右側の金色の紋章・イングランド王家の 三頭のライオン(Three Lions) 紋章。・王権を示す象徴的なモチーフ。大きな石段の上からロンドン塔(Tower of London)を正面から。1.中央奥の白い大きな建物と四隅の塔 ・これは ホワイト・タワー(White Tower)。 ・ロンドン塔の中心であり、11世紀末にウィリアム征服王によって建てられた ノルマン様式の大天守。 ・四隅に小塔(タレット)があり、写真にも2つの塔が見えています。頂部には金色の風見や 旗竿が立っていた。2.手前右側の大きな城壁と角塔 ・これは ウェイクフィールド・タワー(Wakefield Tower) から続く外郭の一部。 ・円筒状の強固な防御塔で、外壁に沿ってテムズ川側を守る要塞ラインを構成。3.中央手前の赤レンガの建物 ・ホワイト・タワーに隣接する 王族居住用の建物群(Tudor時代以降の追加建築)。 ・今は一部管理施設や居住用として使われている。ロンドン塔の内郭西側から北西寄りを見上げて。1.手前の高い外壁(クリーム色の石造り) ・これは 内郭(Inner Curtain Wall) の一部。 ・狭間(矢狭間)が並び、垂直の雨どいが整備されていた。2.奥の円筒状の塔 ・これは ベル・タワー(Bell Tower)。 ・12世紀末に建設され、現在でも「塔の鐘(Bell of the Tower)」が収められている建物。 ・白い塔頂部に小さな鐘楼が見えるのが特徴。3.さらに奥の尖塔や屋根群 ・これは タワー・グリーン(Tower Green) 周辺に建つチューダー様式の建物や、 王族居住用の屋根群。 ・赤い屋根と複数の煙突(チムニー)が目立つのであった。 ・背景に金色の装飾が付いた尖塔が複数見えており、ホワイト・タワーの後方にある 礼拝堂や宮殿部分が重なって見えていた。1.左端の円筒形の塔 ・名称:Devereux Tower(デヴァルー・タワー) ・位置:ロンドン塔の内郭北西角に位置する角塔。 ・特徴:円筒形で、城郭の角を守る役割を担った。砲の時代には軍事的役割は減ったが、 要塞の象徴的構造の一つ。2.その背後に連なる大きな長方形の建物 ・名称:Waterloo Block(ウォータールー・ブロック) ・位置:ロンドン塔の中心部にあり、ホワイト・タワーの西側に隣接。 ・特徴:19世紀に建設された兵舎風の建物で、現在はクラウン・ジュエル(英国王室の宝物) 展示館として一般公開されている。 ・外観:窓の上に防御的な胸壁(バトルメント)が並び、上部の「持ち送り(マチコレーション 風装飾)」が特徴的。3.さらに右奥に見える小さな白い鐘楼 ・名称:Chapel Royal of St Peter ad Vincula(聖ピーター・アド・ヴィンキュラ礼拝堂)鐘楼 ・位置:インナー・ワード(内郭)の北西寄り。 ・歴史:ロンドン塔に幽閉された人物の多くがここに葬られている。とくにアン・ブーリンや キャサリン・ハワードなど処刑された王妃が眠ることで有名。ロンドン塔(Tower of London)前の広場(Tower Hill側)。ロンドンの歴史的建物と超高層ビル群のコントラスト。1.左端の緑色の尖塔をもつ建物 ・名称:All Hallows by the Tower(オール・ハロウズ・バイ・ザ・タワー教会) ・特徴:ロンドン塔に最も近い教会で、7世紀に創建。ロンドン大火(1666年)を生き残った 数少ない教会のひとつ。2.左奥の独特な曲面ガラスビル ・通称:The Walkie-Talkie(ウォーキー・トーキー) ・正式名称:20 Fenchurch Street ・特徴:上部が広がるユニークな形状で、最上階は「Sky Garden」と呼ばれる展望庭園。3.中央奥の群立するガラス高層ビル群(City of London金融街)1.手前の尖塔をもつ教会 ・名称:All Hallows by the Tower(オール・ハロウズ・バイ・ザ・タワー教会) ・特徴:ロンドン塔に最も近い教会。7世紀創建と伝わり、ロンドン最古級の教会です。 1666年のロンドン大火を生き残った希少な教会として知られます。 ・尖塔(緑色の銅屋根部分)は18世紀の再建時のもの。2.背後に大きくそびえるガラスの高層ビル ・通称:The Walkie-Talkie(ウォーキー・トーキー) ・正式名称:20 Fenchurch Street ・完成:2014年 ・特徴:上に行くほど広がる逆台形デザイン。最上階の「Sky Garden」はパブリックガーデン (展望温室)として無料公開されています。イギリス近衛兵(Grenadier Guards など)を模した人形(展示用フィギュア。・赤いチュニック(赤い軍服) ・イギリス近衛兵の象徴。 ・金色のボタンと白いベルトが特徴。・黒い帽子(ベアスキン:Bearskin) ・高さ45cmほどの熊毛製帽子。 ・ナポレオン戦争後、フランス軍擲弾兵の象徴を取り入れたと。・直立不動の姿勢 ・実際の衛兵は王室関連施設(バッキンガム宮殿、セント・ジェームズ宮殿、ロンドン塔など) で交代制勤務をしている。お顔をズームして。ロンドン塔のすぐ北側にある Trinity House(トリニティ・ハウス) の建物の塔部分。・Trinity House(正式名:The Corporation of Trinity House)・1514年に設立された英国王室特許法人。・主な役割はイングランド、ウェールズ、チャンネル諸島、ジブラルタルの 灯台・ ブイ・海上標識の管理。Tower of London(ロンドン塔)周辺の観光用地図看板。ロンドン塔(Tower of London)周辺にある 観光用案内標識(街歩きサイン)。・矢印と目的地(THE CITY方面) ・Fenchurch Street(フェンチャーチ・ストリート駅) → ナショナルレールの駅。シティ(金融街)に通勤する人に多く使われる。 ・Monument(モニュメント駅・地下鉄) → ロンドン地下鉄の駅。大火記念塔(The Monument to the Great Fire of London)の 最寄り駅。 ・The Monument(モニュメント塔そのもの) → 1666年のロンドン大火を記念して建てられた塔。上に登るとロンドンの街並みを 一望できます。All Hallows by the Tower(オール・ハローズ・バイ・ザ・タワー教会)。・創建:675年(7世紀) → ロンドンに現存する最古の教会とされる。・建設したのは バルキングの聖イリディオルス修道院の修道士。All Hallows by the Tower(オール・ハローズ・バイ・ザ・タワー教会) の尖塔部分を再びクローズアップ。・緑青に覆われた銅製スパイア(細長い尖塔)・中段に開口部とバルコニー状の部分があり、その四隅に装飾的な金球が配置されている・下部は赤レンガ造の塔で、ロンドンの古い教会建築の典型的様式背景には、現代的な超高層ビル 20 Fenchurch Street(通称「Walkie Talkie」) が写り、歴史的建築との対比が際立っていた。All Hallows by the Tower(オール・ハローズ・バイ・ザ・タワー教会) を正面から。1.正面の切妻壁(ギャブル) ・上部中央に 大きな石の紋章(王室の紋章) が刻まれています。 ・頂点には十字架が立ち、下には透かし彫りの飾り(パラペット装飾)が見えます。2.大きなゴシック様式の窓 ・縦長の格子窓が並び、尖頭アーチ風の枠組みを持っています。3.背後の緑青色の尖塔(スパイア) ・前の写真と同じく、銅製で酸化により緑色を帯びたスパイア。 ・四隅には金色の装飾球が見えた。ズームして。1.大きなゴシック様式の窓・正面中央を占める縦長の大窓・細い石の枠で縦に区切られ、上部は尖頭アーチ風。2.切妻壁上部の紋章・窓の上に イングランド王室の紋章(ライオンとユニコーンに囲まれた盾) が彫られています。3.切妻頂部の装飾・上部には透かし彫りのパラペット(欄干装飾)。・その中央に十字架、さらに背後に緑青色の尖塔がわずかに見えます。4.周辺・左にヤシのような植物、右には「母と子(Mother and Children)」の像が。・背景右上には再び「Walkie Talkie」ビル(20 Fenchurch Street)が見えた。All Hallows by the Tower(オール・ハロウズ・バイ・ザ・タワー教会)👉️リンク を別角度から。ズームして。1.手前のファサード(西正面)・煉瓦造の大きな壁面に 十字架と大窓 が見えます。・窓の上部には、紋章を刻んだ石の装飾パネル がはめ込まれています。・これは教会の復興(特に第二次世界大戦後の再建)を象徴する部分です。2.尖塔(スパイア)・背後にそびえる緑色の尖塔(銅製で緑青化したもの)は、この教会のトレードマーク。・17世紀の火災や第二次世界大戦の爆撃で破壊された後、復元されたもの。内部のステンドグラス。正面から。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.08
コメント(1)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その101): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-16
ロンドン塔(Tower of London)の外側の堀(現在は芝生)を右に見ながら進むと、その向こうに見える塔と城壁。・右手前:大きな円筒形の建物はホワイト・タワー(White Tower)の角部分。 ロンドン塔の中心となるノルマン様式の大天守。・中央の長い石壁:外郭の防御壁で、胸壁(バトルメント)と狭間(矢狭間)が並んでいた。・奥の左側:角に見える丸と四角の二つの塔を持つ建物は、テムズ川沿いに面した外門の一つ。 このあたりが「Byward Tower(バイワード・タワー)」方向。・手前左の芝生部分:元々は堀(moat)の一部で、現在は水がなく緑地化されていた。East Drawbridge(イースト・ドローブリッジ)を振り返って。外壁に開いた門と、それに架けられた木製の橋・East Drawbridge(イースト・ドローブリッジ)。本来の大手門(ミドル・タワー → バイワード・タワー)ではなく、物資搬入や兵站用、限られた関係者の出入り口 として使われた。当時は、その名の通り 跳ね橋(drawbridge) が設置され、敵襲時には上げ下げして防御性を確保した と。現在残っているのは、当時の構造を示す 固定式の木橋(常設橋)。口径13インチ(約33cm)の迫撃砲(mortar)。台座と一体で鋳造されており、おそらく海上作戦や沿岸防衛用に使うことを目的としていた。通常の大砲よりも短砲身で、高角度に弾を撃ち上げ、城壁や要塞内部へ榴弾を落とす用途に使われた と。「Iron 13-in mortar and bedCast in one with its base, probably intended for sea service or coast defence.Spanish or French, mid-18th century, and initialled ‘SG’. Possibly cast at the Saint Gervais foundry, France.xix.141ROYAL ARMOURIES」 【鉄製13インチ迫撃砲(台座付き)台座と一体で鋳造されており、おそらく海上作戦や沿岸防衛用に使うことを目的としていた。起源は18世紀中期のスペインまたはフランス製と考えられ、刻印「SG」があり、フランスのサン=ジェルヴェ鋳造所で鋳造された可能性がある。カタログ番号:xix.141ロンドン塔】テムズ川に架かるロンドンの象徴的な橋、タワーブリッジ(Tower Bridge)をこれでもかと。ロンドン塔の展示「Discover the Fortress story」の一部で、テーマは 「Supplying the Army(軍隊への補給)」「Supplying the ArmyIn the 1800s, the area around you would have been bustling with Ordnance Office workers and sailors, loading and unloading military supplies from ships.」【軍隊への補給1800年代、この周辺は兵器局(Ordnance Office)の職員や水兵たちで賑わっていました。彼らは船から軍需物資を積み降ろし、軍への補給を行っていたのです。】・兵器局(Ordnance Office): イギリス軍の兵器・弾薬・装備の管理を担った官庁。 ロンドン塔も長らく兵器庫として利用されていました。 ・テムズ川との関係: 川沿いに位置するロンドン塔は、船で軍需物資を運び入れるのに非常に便利でした。 砲や火薬、食料や装備品が次々と運ばれ、この地域は補給拠点として機能した。・イラストの意味: 背景に見えるクレーンや砲は、実際に物資が荷揚げされていた様子を表している。 前景の男性は、軍需局の監督官や兵站担当者を象徴的に描いたもの と。ロンドン塔(Tower of London)の展示で、テーマは Wharf(埠頭・川岸)と武器製造・兵器庫の歴史。「For centuries, weapon-making workshops and houses for armourers and Tower officials stood along the Wharf.Today many of the historic cannon are on display in the Tower.」【何世紀にもわたり、テムズ川沿いの埠頭には武器製造工房や、甲冑師・ロンドン塔の役人たちの住居が立ち並んでいました。今日では、その時代の大砲の多くがロンドン塔内で展示されています。】港に停泊した船から物資を荷揚げする場面。クレーンで木箱や大砲の部品を引き上げる様子が描かれている。周囲には労働者、兵士、役人らが集まっている。 テムズ川沿い「Wharf(埠頭)」に並べられた大砲群を撮影した 過去の記録写真。・長い並木道(Wharf の遊歩道) テムズ川沿いに植えられた並木の下に、大砲がずらりと並んでいた。・大砲(Cannon) 砲身は鋳鉄製・青銅製のものが混在しており、時代や製造国によって装飾や形状に違いがある。・展示形式 砲身が川の方へ向けられ、規則正しく配置されています。これは軍事運用ではなく、 記念展示の並べ方。「1800年代には、軍需品の船積みや陸揚げをする兵器局の労働者や船乗りで、この周囲の埠頭はごった返していました。何世紀にもわたり、武器作りの工房、兵器工や塔の役人の住居が埠頭沿いに立ち並びました。現在ロンドン塔には、多数の歴史的な大砲が展示されています。」 ロンドン塔(Tower of London) の象徴的な光景で、中央に見えているのが ホワイト・タワー(White Tower)、右側に写っているのが円形の外郭塔(角塔のひとつ)。・中央奥:ホワイト・タワー(White Tower) ・11世紀後半、ウィリアム征服王によって築かれたノルマン様式の大天守。 ・ロンドン塔の中心かつ最古の建物で、軍事的象徴・王権の象徴として建てられた。 ・四隅に角塔を持ち、白い石灰岩で化粧されていたことから「ホワイト・タワー」と呼ばれる。 ・上部には十字架や風見を備えた尖塔が立っていた。・右手前:円形の塔(外郭防御塔のひとつ) ・外壁に沿って並ぶ複数の塔のひとつ。Lanthorn Tower(ランソーン塔)。 ・防御・監視・収監などに使われた。 ・名前の由来 「Lanthorn(古い英語で Lantern=灯火、ランタン)」から来ていると。 舟運の目印として夜間に灯りが掲げられていた と。 → テムズ川からの出入口に近いため、象徴的な“灯台”の役割を担った と。前方を見る。・中央のアーチ門 これは 内郭の出入口(Inmost Ward の門) にあたる通路で、外からホワイト・タワーの ある中心部へ入る門です。 → 先ほどの「East Drawbridge」から渡った先にあるゲートに相当します。・右奥:ホワイト・タワー(White Tower) ロンドン塔の象徴的建物。四隅に塔を持つ石造の主塔(キープ)。 北東の角塔と旗がはっきりと。・左側:外郭の城壁と角塔群 城壁に沿って複数の塔(インナーウォードの防御塔)が見える。 近代的なロンドン・シティの高層ビル群(「ウォーキー・トーキー」など)が背後に重なり、 過去と現代の対比を生み出していた。テムズ川の対岸(サザーク地区 / Southwark) を。タワーブリッジ(Tower Bridge)を。ロンドン塔の展示「Discover the Fortress story」の一部で、テーマは 「Gateway to the sea(海への玄関口)」。「Gateway to the seaThis stretch of river is the Pool of London. It was the busiest port in the world by the 1700s.Ships landed cargoes here from around the world. Import taxes were valuable income forroyalty and government.」 【海への玄関口このテムズ川の一帯は「ロンドンのプール」と呼ばれ、1700年代には世界で最も忙しい港となっていました。世界中から船がここに到着し、積み荷を降ろしました。輸入税は王室や政府にとって貴重な収入源となっていたのです。】描かれているのはエリザベス1世?を象徴する女性像。ロンドン塔とテムズ川を描いた歴史的な港湾の絵と説明文で、エリザベス1世による「Legal Quays(合法埠頭)」の設置について解説。「Queen Elizabeth I created special docks, called Legal Quays, near here in 1559 to make sure that import taxes were paid.」【エリザベス1世は1559年、この近くに「合法埠頭(Legal Quays)」と呼ばれる特別な船着場を設け、輸入税が確実に徴収されるようにしました。】 Legal Quays(合法埠頭)・1559年、エリザベス1世が公布した規則によって設けられた公認の船着場。・それまで無秩序に行われていた貨物の荷揚げを管理し、必ず輸入税(customs duties)を 徴収できるようにした制度。・荷揚げが許されたのは「Legal Quays」のみで、違反は没収や罰金対象となった と。絵の中央奥に見えるのはロンドン塔。前景には大型帆船や小舟が描かれ、積み荷の積み下ろしの光景を伝えている。エリザベス朝期、ロンドンがすでに「世界貿易の中心地」となりつつあった様子を象徴。ロンドン塔を背景にしたテムズ川沿いの港湾(Pool of London)とLegal Quaysの賑わいを描いた版画風の作品。・背景:ロンドン塔(Tower of London) 四隅に塔を持つホワイト・タワーが描かれています。これは当時の港がロンドン塔のすぐ下に 広がっていたことを示している。・中央:木造の倉庫や小屋 船荷の一時保管や税関の役割を果たした施設。 Legal Quays では、ここで商品を検査し、関税を徴収していました。・右奥:巨大な船と造船所の足場 テムズ川の埠頭に停泊する商船、あるいは新造船の船体。大規模な海運拠点だったことが 分かる。・前景:群衆と商品 中央の群衆:男女が集まり、交易や見物で賑わう様子を表現。服装から18世紀頃の雰囲気が漂う。 手前右の樽や積荷:砂糖やタバコ、コーヒーなど植民地からの輸入品を暗示。 商人や労働者:契約交渉や荷運びを行う人々。ロンドン塔とテムズ川が「軍事要塞+貿易と税収の中心地」であったこと を象徴的に描いているのであった。【河のこの一帯が、プール・オブ・ロンドンです。1700年代には、世界で最も繁忙な港でした。ここで、世界中からの船荷が陸揚げされました。王室にも政府にとっても、輸入税は貴重な収入でした。エリザベス一世は1559年、課税品の陸揚げを支配するため、この近くに特別な「公認埠頭」を造ったのです。】ロンドン塔(Tower of London) の中でも最も象徴的な建物、ホワイト・タワー(White Tower) を外側から望んだ風景を。・中央奥:ホワイト・タワー(White Tower) ・1070年代、ウィリアム征服王が建てたノルマン様式の主塔(キープ)。 ・厚い石壁と四隅の塔を持ち、ロンドン塔の中核。 ・王権の象徴であり、軍事要塞・宮殿・兵器庫・牢獄など様々な役割を果たしました。・手前の石壁(外郭) ・内郭を守る防御壁で、胸壁(ギザギザのクレネレーション)が並んでいます。 ・この壁の内側にホワイト・タワーが立っており、二重三重の防御を形成していました。・右手前の黒い小屋(警備詰所) ・観光客の入場ルート管理やガイド拠点になっている小屋。現在の観光導線の一部。ロンドン塔(Tower of London)外郭の入口・Middle Drawbridge(ミドル・ドローブリッジ)付近 を。・中央奥:ホワイト・タワー(White Tower) ・ノルマン様式の主塔で、ロンドン塔の中心的建築。 ・四隅の塔がはっきり見え、まさにシンボル的存在。・手前の石壁(外郭)と門 ・クレネレーション(ギザギザの胸壁)を持つ防御壁。 ・写真中央やや左に、アーチ門が見えており、ここが中へ入るルートの一つ。・右端の円形塔 ・これは Lanthorn Tower(ランソーン塔)。 ・ロンドン塔南東部に位置し、テムズ川側から見上げたときに右側に写る特徴的な塔です。 ・中世には王妃の住居に隣接し、また夜間に灯りを掲げたことから 「Lanthorn(ランタン=灯火)」の名が付いた。・手前の黒い小屋(警備詰所) ・観光客の入場管理や荷物検査のためのチェックポイント。 ・現代の施設ですが、外観は歴史的景観に調和するようにデザインされている。ロンドン塔の展示「Discover the Fortress story」の一部で、テーマは 「Layers of defence(多層防御)」。「Layers of defenceMany extra layers of defence were added to the Tower over the centuries: high towers, a water-filled moat and thick walls.」 【多層防御何世紀にもわたって、ロンドン塔には数々の防御設備が追加されました。高い塔、水で満たされた堀、そして厚い石造の城壁です。】ホワイト・タワー(White Tower)の起源 を。「You can see the White Tower at the heart of the fortress, built by William the Conquerorafter taking the throne of England in 1066.The White Tower dominated London’s skyline for centuries.」 【要塞の中心にあるのがホワイト・タワーです。これは1066年にイングランド王位を獲得したウィリアム征服王によって建てられました。ホワイト・タワーは何世紀にもわたり、ロンドンの街の象徴的な姿を形づくってきました。】ロンドン塔の周囲を囲む堀と城壁、その中心にホワイト・タワーが描かれている。中世において、ホワイト・タワーが「城郭の心臓部」であることを示している。右上の挿絵は、ウィリアム征服王とノルマン人による征服を象徴する場面。18世紀頃のロンドンを描いた版画・彩色画で、テムズ川から見た 「ロンドン塔とロンドン市街」 の景観を。【数世紀を経てロンドン塔には、高い塔、水を張った濠、分厚い城壁など、何重もの防護が追加されました。要塞の中央に見えるホワイトタワーは、1066年にイングランド国王となった征服王ウィリアムが、後年建設したものです。ホワイトタワーは、長い間ロンドンの地平線にそびえたのです。】前方に見えたのがSt Thomas’s Tower。St Thomas’s Towerの位置図。・建設:エドワード1世によって1270年代に完成。・用途:王の居館の一部として設計されましたが、後に下部が水門(Traitors’ Gate)となり、 囚人の入場口に。・有名な囚人:アン・ブーリンやサー・トーマス・モアなど、多くの政治犯・宗教犯が この門を通って投獄された。ズームして。左右に円筒形の塔を持ち、中央が水門になっていた。ここが有名な Traitors’ Gate(反逆者の門)。・黒い木製の二重門 厚い格子構造の扉が閉ざされ、水路を塞いでいます。・石造りのアーチ ゴシック風の尖りアーチ。塔の下部に築かれています。・赤いポピーの花 これは2014年、第一次世界大戦勃発100周年を記念して設置されたアート展示 「Blood Swept Lands and Seas of Red」の一部。 88万8,246本の陶器製ポピーが展示され、戦死したイギリス兵士の数を象徴した と。ズームして。裏切り者の門は、ロンドン塔の歴史において欠かせない存在です。ここはテムズ川からロンドン塔へ船で渡る入口でした。長年にわたり、この裏切り者の門は多くの著名な囚人をロンドン塔へ連行するために使われてきました。最も有名な囚人の一人は、1535年に反逆罪で告発され処刑されたトーマス・モア卿です。モアは船でロンドン塔へ連行され、独房へ向かう途中で裏切り者の門を通過しました。もう一人の著名な囚人は、姦通の罪で告発され1536年に処刑されたアン・ブーリン女王です。アンもまた船でロンドン塔へ連行され、裏切り者の門を通過しました。エリザベス1世王女(アン・ブーリンとヘンリー8世の娘で、エリザベス1世女王になる前にここで囚人となっていた)は、テムズ川を下り、はしけでこの門を通過し、数年前にここで斬首された母親のことを思いました。エリザベスは歩いて脱出できた幸運な数少ない人の一人でした。ロンドン塔で行われているポピー・インスタレーション展示「The Tower Remembers」 について説明していた。「THE TOWER REMEMBERS80 years since the end of the Second World WarTo mark the end of the Second World War (1939–45), an installation of thousands of ceramic poppies flows across the Tower of London, emerging at this gate.Poppies symbolise remembrance and hope for a peaceful future.Tower RemembersCeramic poppy installationMay – November 2025Poppies by artist Paul Cummins on loan from IWM (Imperial War Museums)Installation design by Tom Piper」 【塔は記憶する第二次世界大戦終結から80年第二次世界大戦(1939–45)の終結を記念して、数千本の陶器製ポピーのインスタレーションがロンドン塔を横切り、この門から現れます。ポピーは追悼と平和な未来への希望を象徴します。陶器製ポピーのインスタレーション2025年5月~11月ポピー制作:アーティスト ポール・カミンズ(帝国戦争博物館からの貸与)インスタレーションデザイン:トム・パイパー】「The Tower at WarThe Tower remained active throughout the conflict, holding prisoners of war and offering tours for visiting soldiers. In the moat, anti-aircraft defences helped protect East London.」 【戦時下のロンドン塔ロンドン塔は戦争中ずっと活動を続け、戦争捕虜を収容したり、訪れる兵士たちに見学ツアーを提供したりしていました。堀には対空防衛が設置され、ロンドン東部の防衛に役立ちました。】左側の写真:・内容:ロンドン塔の中枢「ホワイト・タワー」前に設置された陶器製ポピーの展示。・背景:2014年の第一次世界大戦開戦100周年記念インスタレーション 「Blood Swept Lands and Seas of Red」の一部。 ・英国軍戦死者数を象徴する 888,246 本のポピーが展示されました。・象徴性:戦没者追悼と平和の願いを表現。右側の写真・内容:1941年にロンドン塔の堀に設置された バラージ・バルーン(阻塞気球)。・役割:敵の爆撃機が低空で進入してくるのを防ぎ、爆撃の精度を下げる目的がありました。・意義:第二次大戦中、ロンドン東部を含む都市防衛の一環として運用され、ロンドン塔も その拠点のひとつとなったことを示しています。1945年に撮影されたロンドン塔の夜景。・撮影時期:1945年・出来事:第二次世界大戦の終結を祝うため、ロンドン塔がライトアップされました。・映っている建物: ・中央に「ホワイト・タワー(White Tower)」が堂々と輝き、 ・周囲の城壁や塔も照明に照らされています。・雰囲気:長い戦争を耐え抜いたロンドンの象徴的な建物が、光に包まれ「勝利と平和の象徴」 として祝福された歴史的瞬間を写しています。【第二次世界大戦(1939年〜1945年)の終結を記念して、ロンドン塔では何千本もの陶器製のポピー(ケシの花)のインスタレーションが、この門から流れ出るように設置されています。ポピーは戦没者への追悼と平和な未来への願いを象徴しています。戦時中もロンドン塔は、戦争捕虜を収監したほか、兵士らに向けた見学ツアーも行っていました。また、堀には対空防衛設備が設置され、イーストロンドン(ロンドン東部)の防衛に貢献していました。】Traitors’ Gate(反逆者の門) 前に設置された陶器製のポピー(ケシの花)インスタレーションの様子を正面真上から。陶器製の赤いポピーが水面から生えているように配置され、まるで血が流れ出すかのようにデザインされていた。ポピーはイギリスにおいて第一次・第二次世界大戦で戦没した兵士の追悼の花。「St Thomas’s TowerKing Edward I built St Thomas’s Tower as a grand river entrance and luxurious royal apartments in the 1200s.This tower was originally decorated with gold window bars and painted statues.」 【セント・トーマス・タワーエドワード1世は、1200年代に壮大なテムズ川の入口と豪華な王族の居室として、セント・トーマス・タワーを建設しました。この塔は当初、金色の窓格子や彩色された彫像で装飾されていました。】ロンドン塔の St Thomas’s Tower(セント・トーマス・タワー)とTraitors’ Gate(反逆者の門) を描いた歴史的イラスト。・中央下部:テムズ川から塔へ入る Traitors’ Gate(水門) が大きく描かれています。 ・船が到着し、人々が上陸している様子が見えます。 ・この水門は王族の正式な川からの入口でもありましたが、後には囚人が運ばれる門として 悪名高くなりました。・中央の大きな白い建物: ・これは St Thomas’s Tower(セント・トーマス・タワー)。 ・もともと王の豪華な居室を備えていた塔で、内部では廷臣や高官たちの場面が描かれています。・周囲: ・兵士や荷物の搬入の様子、塔の外壁、防御施設が詳細に描写されています。 ・背景にはテムズ川沿いのロンドン市街や橋(おそらくロンドン橋)が広がっています。・装飾枠:花や植物があしらわれており、この絵が中世の写本や年代記の挿絵の一部であることを 示しています。ロンドン塔の展示パネルにある中世写本の挿絵で、当時のイングランドにおけるユダヤ人迫害を描いた場面。「Edward’s building was funded from the heavy taxes imposed on English Jews before he expelled the whole Jewish community from England in 1290.」【エドワード(1世)の建築事業は、イングランドのユダヤ人に課された重税によって賄われました。その後1290年、彼はイングランドからユダヤ人共同体全体を追放しました。】 【エドワード一世は、セント・トーマス・タワーの壮大な水門と豪華な王族用アパートメントを1200年代に建設しました。当初この塔は、黄金の窓格子や彩られた彫像で飾られました。エドワード王は、イングランドのユダヤ人に課した重税を資金源に建設を行い、1290年には、ユダヤ人共同体全体をイングランドから追放したのです。】Traitors’ Gate(反逆者の門)も見納め。ロンドンの超高層ビル The Shard(ザ・シャード)。高さ:310メートル(95階建て)→ 完成時(2012年)は西ヨーロッパで最も高いビル。デザイン:建築家レンゾ・ピアノ(Renzo Piano)による設計。→ 砕けたガラスの破片(Shard of Glass)をイメージした形状。構造:全面ガラス張りで、光の当たり方や天候によって色合いが変化。そしてタワー・ブリッジ(Tower Bridge)も見納めか? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.07
コメント(0)
-

第18回 小出川彼岸花まつり-2
花は9月末ごろには終わりますが、その後、結実することなく、花茎は萎れて枯れてしまいます。日本国内に生育する本種は、染色体数がほぼ全て3倍体(2n=33)👈リンクであるため、結実しないとされているとのこと。最初のたったひとつの不稔(ふねん)の個体から分球(ぶんきゅう)をくりかえすことで殖えてきたとしか考えようがないのであると。このことを初めて指摘したのは、現在NHKの朝ドラで放送中の牧野富太郎博士であったと(明治40年)。彼岸花は中国揚子江沿岸が原産の帰化植物であると。しかし、いつ頃、どのような経緯で我が国に入ってきたのかは諸説あり、よくわかっていないと。燃えているように見えるので「火事花」とも。5年前に訪ねた埼玉県日高市「巾着田」👈リンク、埼玉県幸手市「権現堂堤」👈リンクの見事な彼岸花を想い出したのであった。別の場所でも自撮り、ズームして。「新道橋」まで戻る。遠くには箱根・二子山が見えた。箱根火山のカルデラ内の南東側に位置し、約5,000年前の噴火で形成された溶岩ドームである。箱根駒ヶ岳、神山、台ヶ岳などとともに中央火口丘を構成する。その名のとおり、双生児のように二つの峰が並んでおり、北(右)側が上二子山1,099m高、南(左)側が下二子山1,065m高となる。花からは6本の雄しべと1本の雌しべがまるで装飾のように上方に長く突き出しているのであった。「彼岸花」を楽しむ?「アオサギ」の姿を発見。全長90cm以上。体の上面、翼の上面はうすく黒味のある灰色で、翼の風切羽は青色がかった黒色。鳥害防止用爆音機に驚いて、突然飛び立った「アオサギ」を追う。風切羽と肩の灰色の対照がはっきりしていた。羽の下面は真っ白であることを初めて知る。日本で繁殖するサギの仲間としては最大のようだ。背が高く、脚も長い。飛行姿は長い首をZ字型に曲げ、後方へ脚を伸ばし、大きな翼をゆっくりはばたいて飛んで行ったのであった。「新道橋」からさらに下流に向かって進むと見事な富士山の姿が。この日の富士山には、裾野に横にたなびく「かいまき笠雲」がかかっていた。富士山が雲の浮き輪をしているかの如くに。ズームして。この場所からの日の入りダイヤモンド富士の撮影を来年は是非!!デジカメではなかなか・・・。そして群生場所が現れた。小出川左岸の群生場所を下流に向かって進む。彼岸花には何百という品種が存在し、今も品種改良によって日々新しいものが生み出されていると。赤色のイメージが強い彼岸花ですが、他に白、赤、黄、オレンジ、ピンクなどが存在。ただ、日本では彼岸花の流通が少なく、園芸植物として人気が高くはないようだ。彼岸花の球根は毒(リコリン)があるのだと。地中に潜むモグラやネズミは、他の植物の根はかじっても、彼岸花のものはかじらないと。よって彼岸花は、よくこの小出川の如く田んぼの畔道に咲いているのは・彼岸花の根が土手や畔の土をギュッと固めてくれるため。・彼岸花は毒があるため、田んぼを荒らすネズミやモグラ・虫などの被害を防ぐためなのだと。・墓場にヒガンバナが多いのも、異臭や有毒性を利用して遺体を動物から守るためだとも。更に彼岸花は食用は厳禁だが、飢餓の時に球根の毒を水で流して利用したり、水戸黄門の命令で発行した家庭の医学書「救民妙薬」では、球根をすり下ろして患部に当てて湿布剤とした事もあったのだとも。飽食の今の時代には必要のないことですが、昔はひどい飢饉のときに毒抜きが良くできていないものを食べて命を落とした人がいたのであろう。赤い花だけに毒があるとの話もあったが、間違っているようだ。設定を変えてカップルの如き彼岸花を。それぞれ6個の花それぞれに雄蕊と雌蕊がヒゲの如くに。左の花びらの中心部は赤で、縁が白いのでやや白っぽく見えたのです。最近増えてきた白花彼岸花は花びら全体が白一色なので、この花は赤い彼岸花と、白い彼岸花の中間です。紅から白への変身の途中なのでしょうか?それとも自然交配の結果?突然変異?来年はどんな色を咲かせるのか楽しみ。白い縁取りの別の花に近づいて。こちらは7個の花がついていて、つぼみが5個、咲いている花は2個。花びらが6枚(黄色の文字・数字)、花粉の入る「やく」がついたおしべが6本(白色の文字 ・数字 ) 、少し長いめしべが1本(白色の文字)が見られます。写真はネットから。情熱の赤のカオスが広がる。「曼珠沙華」の季語はもちろん「秋」。有名な俳句がいろいろとある。・そのあたり似た草もなし曼珠沙花 正岡子規・まんじゆさげ蘭に類ひて狐啼く 蕪村・仏より痩せて哀れや曼珠沙華 漱石・あかつきは白露づくし彼岸花 伊丹三樹彦・まんじゆさげタベのひかりとなりて失す 岸田稚魚英語では、hurricane lily(ハリケーンリリー)、cluster amaryllis(クラスターアマリリス)、あるいは、近縁のハマオモト属・ヒメノカリス属と合わせて spider lily(スパイダーリリー)と呼ぶのだと。いつまでも、立ち尽くして目に焼き付けたい空間なのであった。そして富士山、大山の姿を。富士山にズームして。この橋は仮設橋か?錆の状況から古い橋のようでもあるが。農家の方が作業、移動用に架けた橋?その脇には休憩用ベンチが2台。ベンチの上には「みなさんこんにちは「小出ボーイズ」です。ぼくたち小出小学校の4年生は「小出においで」というプロジェクトで、町おこしのイベントについて考えてきました。そのなかで、ぼくたち「小出ボーイズ」は「小出川のひがん花をもっと多くの人に知ってもらいたい。」と思い、ひがん花の道をPRするきかくをいろいろとかんがえました。そして「NPO法人 サポート茅ヶ崎寒川子どもファンド」で助成金がいただけることになりました。その助成金をつかって今日の「ひがん花まつり」で3つのことをしました。①みんなが一休みできるベンチを2台つくりました。②良い写真がとれるようにスマホ(写真)台をつくりました。③オリジナルキャラクターの缶バッチとキーホルダーをつくってスタンプラリーをしている子ども たちにもPRしていくことこれからもひがん花のみちにあそびにきてね」と。小出地区の未来は輝いていると感じたのであった。頑張れ!!「小出ボーイズ」!!。さらに群生地を楽しみながら進む。神秘的な紅の森を一人彷徨うがごとし。紅万点?の花の海の如き光景。そして秋の宝石の散りばめられた庭の如くに。再び富士山と彼岸花のコラボを。紅色の花の絨毯の先には富士の姿が。人の姿もなく「紅い炎の海」を漂う。秋の儚さが舞い踊るこの場所!!これが「小出ボーイズ」の力作「スマホスタンド」。2本の帯が続く。そして仮設橋?を渡って引き返す。「実るほど頭を垂れる稲穂かな」いつまでもこうありたい。The boughs that bear most hang lowest.いや、未だ実が大きくならない私!!黄色く実った稲穂が重そうに垂れる稲田。遠くから眺めると見渡す限り黄金色に輝いている。そして富士山を背景に黄金色をした稲田との雄大なコラボレーション!これぞ大昔からの日本の秋の原風景なのであった。紅色と黄金色とのコラボ。この彼岸花は、黄金の稲田を独り占め。逆さに見ると線香花火の如くにも!!線香花火の写真をネットから。似ていませんか?頭を垂れる稲穂と凛として立つ彼岸花のコラボ。この花の名は?「ヤブラン」に似ているが??そして「新道橋」まで戻る。再び「小出川」の上流を見る。そして車に戻り「追出橋」に向かって進む。田園の中に立っていたのが、これは以前訪ねた「土地改良事業完成記念碑茅ヶ崎市芹沢中、西部地区及藤沢市打戻地区の一部は古代より小出川沿いに開田が進められ穀倉地帯と言われましたが形状不整形で道路農業用排水路等不整備にて、腰まで没する湿田のほ場でした。昭和40年(1965)頃からの経済の発展に伴ひ農業の機械化省力化の波が押し寄せて来ました。湿田の乾田化水田の一部埋立て畑地造成等ほ場整備事業の早期実施を望む耕作者の声が急速に盛上がり全員一致の賛成により芹沢西部土地改良区を設立し土地改良事業の施行に着手しました。総面積三十三○○八Ha(組合員所有面積二八三七Ha)事業費四億七千万円、以来二十年間組合員の熱意と協力に依り事業を完成しました。この事業は土地の価値観を高め農業の近代化はもとより何れの農作目にも適合できる基礎作りであるが将来の土地利用にも活用できる、甦る大地に整備しました。ここに本土地改良区事業の完成にあたり碑を建立し後世に伝へるものである。 西暦1996年 平成8年8月吉日 茅ヶ崎市芹沢西部土地改良区」下記写真は車窓から。茅ヶ崎と寒川の堺の追出橋から延びる道と芹沢の外周をまわる「根通り」の道が交差する三叉路の脇にあったのが「 追出地蔵(おんだしぢぞう)」。この地蔵様も以前にも訪ねていた。身近に医者のいなかった時代にはこの追出地蔵にお参りし、疫病神を体の中から『追い出したは』といわれています。【追出す(おんだす)】はこの地域の方言化か?いや、私の地域でも子供の頃は【追い出された】を『おんだされた』と言っていた記憶があるのだが。また花嫁行列はこの前を通ってはいけないとも。茅ヶ崎市芹沢4238-1。左側の庚申塔には地蔵像が浮き彫りにされており、台座には「西三谷講中」、横には安政二年の文字が。安政2年(1855)は安政江戸大地震の起こった年。向かって右と真ん中は丸彫りでお顔は失われていたが真ん中は新しく造られたものに代わっていた。そして「追出橋」に到着し、道路脇に車を駐めた。茅ヶ崎市芹沢3854。橋の標識を見て、この橋は「おんだしばし」と呼ぶことを知りました。「追出地蔵(おんだしぢぞう)」の近くの橋なので「追出橋(おんだしばし)」と名付けられたのであろう。上流側には、朱の花の姿はほとんど無く・・・そして人の姿は全く無く。橋の中央からズームしたが・・・。ここにも「小出川 彼岸花群生地」との案内板があったが・・・。やはり今年も猛暑の影響か?道路脇には巨大な配管が空中で「小出川」を渡っていた。神奈川県企業庁寒川浄水場からの水道用管。相模川の寒川取水堰でとられた上水道用の水が横浜市の小雀浄水場へ流れているのである。その先にも、青く細い水管橋の姿が見えた。これは自動エアー抜き弁か?銘板「横浜市水道局 小出川水管橋昭和44年11月竣工」と。昭和44年は1969年。1969年(昭和44年)のこの日、7月16日(My Birthday)に打ち上げられたアメリカ有人宇宙飛行船「アポロ11号(Apollo 11)」が月面に着陸し7月20日に人類が初めて月面に降り立ったのだ。そして打ち上げのこの日は、私は御茶ノ水の予備校の近くのラーメン屋で打ち上げの映像をテレビで見ていたのであった。そして「小出川」を渡ると再び水田の中に潜り込んでいたのであった。管の直径は1500mm程度であった。「横浜市水道局 小出川水管橋」を振り返って。昔の人の知恵で植えられた彼岸花。これまでその風景が守られているということは、金色の稲穂を背景に咲く真っ赤な彼岸花の風景を愛おしむ心が、日本人の心として連綿と受け継がれて来ているのだ!!これを再認識した早朝なのであった。『小出川 水のかがやき 曼珠沙華』『群れ咲くも 一輪もよき 曼珠沙華』『曼珠沙華 真紅な花には 毒があり』 ・・・・・詠み人知らずそして帰宅して我が庭の「白の彼岸花」。同じく我が庭の「コルチカム」。「コルチカム」は別名「イヌサフラン」とも呼ばれます。花が「サフラン」に似ていて、「サフラン」ではないところからそう呼ばれるのだとか。”イヌ”を冠した植物の多くは、有用な植物に似ているけれど”役に立たない”という意味でつけられていることが多いと。「サフラン」の赤い蕊は、薬用に用いられたり、香辛料・着色料にも用いられている。その「サフラン」に似ていて、実は”有毒植物”であるところからの命名なのでしょう。今年は、「彼岸花」の開花が遅れていますが、今の時期を代表する「彼岸花」と同じように、「コルチカム」も花が咲いている時には葉っぱが出てこず、花の後、春になると葉っぱが出てきます。いわゆる”葉見ず 花見ず”です。そう言えば、「彼岸花」も”有毒植物”。「コルチカム」と「彼岸花」は、共通点が多いようです。初秋の頃、いきなりニョキっと茎だけ出て花を咲かせる植物は、”ヒガンバナ科”のものが多いですが、「コルチカム」は”ユリ科”の花なのです。彩の寂しいこの時期の我が庭では白とピンクが目立ちます。そして今日10月6日(月)は十五夜(中秋の名月)なのです。 ・・・もどる・・・ ・・・完・・・
2025.10.06
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その100): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-15
「タワー・ブリッジ(Tower Bridge)」をテムズ川の北岸(タワー・オブ・ロンドン側)から眺める。タワー・オブ・ロンドン側(またはタワー・オブ・ロンドン周辺)」とは、ロンドン塔の近く、またはその周辺の地域を指す言葉。手前には花で飾られたアーチが置かれ、奥にノースタワー(North Tower)と、さらに向こうにサウスタワー(South Tower)が見えた。カップルが花で飾られたアーチの下で記念撮影中。タワー・ブリッジ(Tower Bridge)をフェリーターミナル・Tower Bridge Quay手前からズームして見上げて。タワー・ブリッジ(Tower Bridge)北塔(North Tower)の下部通路を歩きロンドン塔の敷地の川沿い遊歩道へと向かう。鉄製の扉があったが、基本的には24時間開いているようであった。下部通路を抜けて再びタワー・ブリッジ(Tower Bridge)を見る。ロンドン塔案内図👈️リンク。「Discover the Fortress StoryControlling the RiverFor centuries, monarchs and governments regulated traffic on the river and sent out military supplies from this wharf.In the 19th century, this part of Tower Wharf was filled with factories producing andassembling weapons.」 【要塞の物語を発見しよう川を制御する何世紀もの間、国王や政府は川の交通を管理し、この埠頭から軍需物資を出荷していました。1800年代には、タワー・ワーフのこの一帯は武器を製造・組み立てる工場でひしめき合っていました。】「Tower Bridge opened in 1894.It was designed to ease road traffic while maintaining river access to the busy Pool of London docks.」 【タワー・ブリッジは1894年に開通しました。この橋は、道路交通の混雑を緩和しつつ、ロンドンの港湾地帯「プール・オブ・ロンドン」の混み合ったドックに船がアクセスできるように設計されました。】タワーブリッジ建設中(19世紀後半)の貴重な記録写真。「数百年の間、王や女王、政府が河川交通を管理し、この埠頭から軍事物資を出荷しました。1800年代、タワーウォーフのこちら側には、兵器工場がひしめき合っていました。1894年に開通したタワーブリッジは、道路交通を緩和しつつ、繁忙なプール・オブ・ロンドンへの河川経路を維持する目的で設計されました。」「Discover the Fortress story An ancient right Henry III received angry complaints in 1261 about his representative, the Constable, who lived at the Tower. For centuries, the Constable had the right to take cargo from passing ships, but Londoners said Henry's Constable was too greedy.」【要塞の物語を発見しよう古くからの権利1261年、国王ヘンリー3世はロンドン塔に住む代理人(塔の長官)についての不満を受けた。何世紀もの間、この長官には通過する船から貨物を徴収する特権があったが、市民はその長官が欲張りすぎると訴えた。】 「Today this privilege is remembered in the Constable’s Dues ceremony.A navy ship’s crew give the Constable a barrel of wine.」 【今日では、この特権は 「コンスタブルの特権儀式(Constable’s Dues)」 として記憶されている。海軍の艦船が停泊すると、その乗組員は塔の長官(コンスタブル)にワイン樽を献上するのである。】ヘンリー三世は1261年、ロンドン塔に王の代理として住んでいた「城守」について、怒りに満ちた苦情を受け取りました。何世紀もの間、城守には通過する船の船荷を取り上げる権限がありました。しかし口ンドン市民は、ヘンリー王の城守が貪欲すぎると訴えたのです。この特権を振り返るのが「城守税」(Constable’s Dues) の儀式です。海軍の船員が、城守にワインの樽を贈るのです。「Constable’s Dues(コンスタブルの特権儀式)」 の実際の様子を撮影したもの。・海軍の白い制服を着た水兵たちが、棒に吊るされた ワイン樽 を担いで行進。・背後には ロンドン塔の城壁 が見える。・左奥には伝統衣装を着た ヨーマン・ウォーダーズ(Beefeaters) も同行しているのが 確認できる。ロンドン塔(Tower of London)の敷地の川沿い遊歩道からテムズ川越しに南岸(South Bank側)を見た風景。旧ロンドン市庁舎(City Hall, 2002–2021使用)とザ・シャード(The Shard, 310m)そしてMore London という再開発エリアで、オフィスや商業施設を見る。タワーブリッジ(Tower Bridge) を、ロンドン塔(Tower of London)側・南側の遊歩道から。ロンドン塔(Tower of London)のテムズ川沿い遊歩道に設置されている解説パネルの一つで、タイトルは「The poet and the Wharf(詩人と波止場)」。「Discover the Fortress storyThe poet and the WharfYou are on a man-made wharf, extended in the 1390s to allow ships to dock next to the Tower.Geoffrey Chaucer, more famous as a poet, managed the wharf-building work at the Tower for King Richard II.」【要塞の物語を発見しよう詩人とロンドン塔の埠頭あなたはいま人工の波止場に立っています。この波止場は 1390年代に拡張され、船がロンドン塔のすぐそばに停泊できるようになりました。詩人として有名なジェフリー・チョーサーですが、実はリチャード2世王のために、このロンドン塔の波止場建設工事を監督した人物でもありました。】 「This colourful illustration from around 1500 shows the Wharf extending all the wayacross the front of the Tower. In the distance is medieval London Bridge.」 【1500年頃に描かれたこの彩色画は、塔の前面を横切って広がる波止場の様子を示しています。遠景には中世のロンドン橋が見えます。】これは中世風の装飾写本(イリュミネーション)の挿絵で、ロンドン塔(Tower of London)とテムズ川を描いた彩色画。「英語訳I name Albion (England),so sweet in pleasant star,its flower and my delight.Adored when I behold it,the sea shall be its anger,and here, its joyful river.」 【わが祖国アルビオン(イングランド)と名づける。星のように甘美で喜びに満ち、その花は私の誇りであり慰めである。それを目にするとき、海はその怒りを、そしてこの川はその喜びを映し出すのだ。】「ここは、ロンドン塔の真横に船を着けるため、1390年代に建設された人工埠頭です。高名な詩人のジェフリー・チョーサーが、リチャード二世の下で埠頭建設工事を監理しました。1500年頃のロンドン塔の詳細図には、新たに拡張された埠頭が描かれています。遠くに中世のロンドンブリッジも見えます。」この大砲は「シー・サービス18インチ臼砲(Sea Service 18-inch mortar)」。「Iron 18-inch mortarProbably one of the large artillery pieces made in England for export to the Venetian republic in 1684. In 1716 the Venetians used such mortars to defend the island of Corfu against Ottoman Turk attacks.The chase bears in relief the Lion of St Mark, symbol of Venice. From Corfu, presented by the Ionian Government in 1842.Italian or English, dated 1684, possibly by Thomas Western.xix.138」 【鉄製 18インチ臼砲この砲は、1684年にイングランドで製造され、ヴェネツィア共和国に輸出された大型火砲の一つと考えられています。1716年、ヴェネツィア人はこのような臼砲を用いて、オスマン・トルコ軍の攻撃からコルフ島を防衛しました。砲身には、ヴェネツィアの象徴である「聖マルコの獅子」の浮き彫りが施されています。この砲はコルフ島から運ばれ、1842年にイオニア政府から寄贈されました。製造はイタリアまたはイングランドで、1684年のものであり、トーマス・ウェスタンによるものと考えられています。】「Discover the Fortress storyThe East GateThe Tower of London’s Ordnance Office stored and exported military equipment for centuries. Workers produced and tested weapons at the Tower.King Henry VIII reorganised the Ordnance Office in the 1540s to strengthen and demonstrate his military power.」【東門(イースト・ゲート)ロンドン塔の兵器局(オードナンス・オフィス)は、何世紀にもわたり軍需品を保管・輸出していました。ここでは武器の製造や試験も行われていました。1540年代、ヘンリー八世はこの兵器局を再編し、自らの軍事力を強化し誇示したのです。】 ロンドン塔(Tower of London)の古い鳥瞰図(俯瞰地図)を描いたもの。「These two huge mortars are probably from the 1600s.Cranes on the Wharf loaded cannon and heavy goods onto ships.」【これら2門の巨大な迫撃砲は、1600年代のものと考えられています。埠頭に設置されたクレーンは、大砲や重量物を船に積み込むために使われていました。】 「ロンドン塔の兵器局は、数世・・・・事務機を保管して輸出しました。労務者は、ここで兵器を作り、試験しました。ヘンリー八世は、自分の軍事力を強化して誇示するため、1500年代に兵器局を再編成しました。2つの巨大な臼砲は、おそらく1600年代のものです。臼砲や重量品の船積みには、埠頭のクレーンが使われました。」 右手にEast Drawbridge(イースト・ドローブリッジ)。ロンドン塔の東側にある補助的な門 と。「East Drawbridge(イースト・ドローブリッジ/東跳ね橋)」 の前に立つ案内板。・Tower of London入口まで:約400m と案内・通行制限:車両は最大15トンまで。さらにロンドン塔の南壁に沿って遊歩道を進む。ロンドン塔の外壁にあり「イースト・ドローブリッジ(East Drawbridge)」の近くにあった、補助的な門(Postern Gate/小門)。大きな正門(Middle Tower や Byward Tower)とは異なり、外郭の城壁に開けられた比較的小さな出入口で、人の出入りや小規模な補給などに使われた副門。「Discover the Prison storyEscape from the TowerThe Catholic priest John Gerard was imprisoned and tortured in the Towerfor being a spy, on the orders of Queen Elizabeth I.」 【牢獄の物語を発見しよう塔からの脱出カトリック司祭ジョン・ジェラードは、スパイの嫌疑をかけられ、エリザベス1世女王の命令によってロンドン塔に投獄され、拷問を受けました。】2つの肖像。左側の絵(モノクロ)・図像の内容: カトリック司祭 ジョン・ジェラード(John Gerard, 1564–1637) が、両腕を縛られて 「拷問の柱」に吊るされている場面を描いたものです。・歴史的背景: エリザベス1世の治世下で、ジェラードはカトリックの布教活動やスパイ容疑により ロンドン塔へ投獄され、拷問を受けました。とくに「ストラッパード(両手を後ろ手に縛って 吊り下げる拷問)」で有名です。意味: この図は彼の苦難と、後に奇跡的な脱出を遂げる物語の一部を象徴。右側の肖像画(カラー)・図像の人物: エリザベス1世(Elizabeth I, 1533–1603)、イングランド女王。・肖像の特徴: ・白い肌と鮮やかな赤毛を強調。 ・豪華なレース襞襟(ラフ)や真珠の首飾り、宝石を散りばめた衣装は、エリザベスの権力と 富を象徴。・関連性: 彼女の命令によりジョン・ジェラードが投獄され、拷問を受けました。二つの図版を 並べることで、「囚人とその運命を決めた君主」の対比が示されている と。「He made a daring escape from this rooftop on the night of 4 October 1597.Gerard made his successful escape climbing down the Cradle Tower by rope. He fled to a boat waiting by the Wharf below.」 【1597年10月4日の夜、彼はこの屋上から大胆な脱出を試みました。ジョン・ジェラードは縄を使ってクレイドル・タワーを降り、下の埠頭で待っていた舟へと逃げ延びました。】エリザベス1世との関連性・直接的関連:ジョン・ジェラードは「エリザベス1世の命令」でロンドン塔に投獄された。・背景的関連:エリザベス1世の厳格な宗教政策(反カトリック政策)が、彼をスパイ・反逆者と みなして処罰した原因となった。・象徴的意味:ジェラードの脱出は、エリザベス時代の宗教対立と国家権力の厳しさを象徴する 事件。「Discover the Palace storyThe Cradle TowerKing Edward III built the Cradle Tower in the 1300s as his private palace entrance.Battlements, arrow loops and two portcullises defended this important river gate from attack.」 【宮殿の物語を発見するクレイドル・タワー(The Cradle Tower)エドワード3世王は1300年代に、宮殿への私的な入口としてこのクレイドル・タワーを建てました。胸壁(防御用の壁)、矢狭間(弓矢を射るための小窓)、そして二重の落とし格子が、この重要な川沿いの門を攻撃から守っていました。】「The King arrived by boat onto a wooden jetty. Inside the tower’s vaulted ceiling is decorated with stone carvings.」【王は船で木造の桟橋に到着しました。塔の内部のヴォールト天井は、石の彫刻で装飾されています。】 中世の装飾写本(イニシャル装飾)の挿絵。描写内容・左側:王座に座る国王(王冠をかぶり、玉座に腰掛けている)。・右側:ひざまずいて文書(巻物または書簡)を国王に差し出す人物。・背景や枠は豪華に彩色され、装飾文字(大きなイニシャル)の中に場面が描かれている。「エドワード三世は、自分専用の入城口としてクレイドルタワーを建設しました。木の桟橋まで、王は小舟でやって来ました。中の丸天井は、石の彫り物で飾られています。銃眼付き胸壁、射撃孔、2つの落とし格子で、この重要な水門を攻撃から護ったのです。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.06
コメント(0)
-

第18回小出川彼岸花まつり-1
この日は9月27日(土)、早朝に、車で20分ほどの場所にある『小出川彼岸花』を訪ねに今年も行ってきました。幼馴染の友人から、ここの彼岸花がピークを迎えているとの情報をいただき今年も訪ねたのでした。第18回 小出川彼岸花まつり ・2025年9月27日(土) 10:00 ~ 15:00 小雨決行 雨天時順延 ・ところ 小出川沿い 大黒橋 ~ 寒川町青少年広場 3km ・鑑賞期間 9月下旬 ~ 10月上旬 (見頃 お彼岸の頃) ・催 し 式典 (打戻会場)、模擬店、休憩所など ・スタンプラリー開催! 9月27日(土) 9時から15時まで。今年も小出川(こいでがわ)・「大黒橋」の近くに車を停め、しばしの散策の開始。「大黒橋」には今年も横断幕が。小出川は、神奈川県中央南部を流れる相模川水系の川で、これでも『一級河川』。藤沢市遠藤の笹窪谷戸に源を発し、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの脇を流れ、駒寄川(こまよせがわ)が流入し、茅ヶ崎市と寒川町の境界河川となる。新湘南バイパスとほぼ平行して茅ヶ崎市の西部を縦断し、千の川が流入した後、平塚市で相模川の河口付近に注ぐ河川。大黒橋から彼岸花の咲く小出川を見る。堤防の高い場所にある彼岸花が見事な姿で迎えてくれた。この付近はほぼピークの彼岸花。以前も同じ事を書きましたが日本では秋の花として親しまれる彼岸花(ひがんばな)。別名、リコリスや曼珠沙華(まんじゅしゃげ)とも呼ばれ、日本特有の「彼岸」の時期に咲く花として知られている。ネット情報に拠ると様々な名前が。・彼岸花(ヒガンバナ)・曼珠沙華(まんじゅしゃげ/かんじゅしゃか)・死人花(しびとばな)・地獄花(じごくばな)・幽霊花(ゆうれいばな)・剃刀花(かみそりばな)・狐花(きつねばな)・捨子花(すてごばな)・毒花(どくばな)・痺れ花(しびればな)・天蓋花(てんがいばな)・狐の松明(きつねのたいまつ)・狐花(きつねばな)・葉見ず花見ず(はみずはなみず)・雷花(かみなりばな)・レッドスパイダーリリー・ハリケーンリリー・マジックリリー・・・・などなど。彼岸花とはヒガンバナ科・ヒガンバナ属(リコリス属)に分類される球根植物。日本や中国に広く自生し、秋の彼岸の期間(秋分の日を入れた前後3日間)だけに花を咲かせることに由来して名付けられたと。9月頃になると赤や白、ピンクなど花を咲かせるのが特徴なのです。小出川 ”彼岸花”の案内板。この付近には白の彼岸花の数は少なかった。ズームして。彼岸花を楽しめる場所は、遠藤の小出川沿いの大黒橋~追出橋の間約3km。おまつりの本会場:遠藤会場 他、打戻会場、おおぞう会場、せりざわ会場(茅ヶ崎里山公園内)山口百恵の歌『曼殊沙華(マンジュシャカ)』👈リンク♫マンジューシャカ 恋する女は~ マンジューシャカ 罪つくり~♫この曲で初めて作詞の阿木曜子が「マンジュシャゲ」を「マンジュシャカ」と発音させたのであろうか。インドの古い言葉(梵語)では「マンジュシャカ」。音写して曼珠沙華。「天上の赤い花」という意味があり、おめでたいことが起こる兆しに、天から赤い花が降ってくるという伝説があるのだと。 川沿いの道を散策。右手には「道祖神碑」が。道端の彼岸花は朝の陽光に輝いていた。路面は湧き水が。今年の「第18回 小出川彼岸花まつり」のパンフレットを通路脇の箱の中から頂きました。パンフレットの裏側。スタンプラリーも行われるようであった。今年も地元の方々が手をかけて見事に開花。白の萩の花も今年も開花していた。その隣には紫の萩の花も。ズームして。この先は仮設トイレ・ベンチも設置された休憩場所。柿の実も色づいて。ここにも「小出川彼岸花」の横断幕が。畑の温室越しに富士山の勇姿が。雪の全く無い富士山もそろそろ見納めとなるのであろう。富士山にピントを合わせて。彼岸花にピントを合わせて。これがデジカメでは限界か?彼岸花は「まず花が咲き、後から葉っぱが伸びる」という通常の草花とは逆の生態をもっている。その葉と花を一緒に見ることがない性質から「葉見ず花見ず」と呼ばれ、昔の人は恐れをなして、死人花(しびとばな)や地獄花(じごくばな)などと呼ぶこともあったのだと。またの名を曼珠沙華(まんじゅしゃげ)という。これは梵語でズバリ「赤い花」を意味する言葉だと。それにしても、これほど強烈で刺激的な「赤い花」がほかにあるだろうか。この場所の如くに畦道や川べりに群れ咲くさまは、遠目にみてもドキッとするほどのインパクトなのであった。「道の辺の いちしの花のいちしろく 人皆知りぬ我が恋妻は」万葉集 巻11-2480“いちしの花”は今の彼岸花といわれる。“いちしろく”は白とは関係なく“はっきりと”の意味で「道端に咲く曼珠沙華ではないけれど、ボクの妻があでやかで人目につく美女だってこと、皆が知っているんだ」という妻をベタほめしている男の歌であるのだと。古代すでにこの花は野面を点々と染めて人々の目をひいていたのだ。小出川と富士山のコラボ。残念がら手前の彼岸花は溢流にやられていた。そして車に戻り、いつもの別の場所に移動。車で、「小出橋」を左に見ながら、県道「大庭獺郷線(おおばおそごうせん)」に出て「新道橋」付近に移動し一時停車。獺郷という地名は、昔ところどころに沼地があり、獺(かわうそ)が多く生息していたといわれ獺の郷から村名になったと言われている。水田の下には湿地帯に生える葦の葉の地層が残っていると言われている。この道はまつりの『せりざわ会場』があった県立茅ヶ崎里山公園に行く道。ここが新道橋(しんみちはし)。川の「橋」の読みは、川が濁らないようにと、「ばし」ではなく濁点をつけずに「はし」と読む場合が多いのである。この道は県立茅ヶ崎里山公園に行く道。流れる川はもちろん「小出川」。「小出川」の両岸には稲作田園が広がっていた。「小出川 彼岸花群生地」「小出川沿いの彼岸花(曼珠沙華)は、上流の里山などから大水により球根が流れ込み、古くからこの地域に自生していました。平成15年頃から流域の彼岸花保護団体が相次いで組織され。増殖・保全活動に努めています。開花期(9月下旬頃)には、上流の大黒橋から下流の追出橋まで両岸3キロが紅の帯に染まり、西方に望む富士や箱根連山を借景に、絶好の散策コースになっています。毎年、この時期に「小出川彼岸花まつり」を開催し、来場者を歓迎しています。」附近のご案内:宇都母地神社👈リンク 雄略天皇の時代( 466年)厳粛な祭祀が執り行われたと「日本総風土記」に 記されている延喜式内社。 境内に「民具・農機具資料館」(祭礼時等に開放)がある。 (これより北東方向1.5キロ) 盛岩寺 薬師堂 昭和文化館👈リンク 盛岩寺の薬師堂は、築90余年の旧商家を再移築した古建築で、昭和文化館として 活動をしている。 堂内の薬師三尊十ニ神将は、旧東光寺の本尊で、(明治4年廃寺盛岩寺に移管) 「堂の前」の名はこれに由来する。 (これより北西方向0.5キロ)この場所にも横断幕が。2本の赤い帯が。これぞコロナ時の三密状態で。赤のカオス!!堤防上を上流にむけて歩く。ズームして。彼岸花はまっすぐな茎の上に花だけをつける。葉は花が散って後にゆっくり生まれ出る。韓国名はロマンチック。「サンシチヨ」と言い「想思華」と書く。1本の茎を共有しながら花と葉は決して出会うことはない。花は葉を想い、葉は花を思い焦がれているから「想思華」と。彼岸花は冬から春にはちゃんと葉が繁り、花をつけない寒い季節にしっかり栄養を球根に貯えているのだと。多くの植物は春に芽を出し、夏に葉を繁らせ秋に枯れますが、彼岸花はその逆。冬に葉を繁らせ春に枯れ、秋に花を咲かせるのだと。彼岸花の色別の花言葉を調べてみました。「☆白色:思うはあなた一人/また会う日を楽しみに★赤色:情熱/独立/再開/あきらめ/悲しい思い出/思うはあなた一人/また会う日を 楽しみに★黄色:追想/深い思いやりの心/悲しい思い出彼岸花は、その印象的な赤い花色から「情熱」「思うのはあなた一人」といった花言葉が生まれたといわれています。しかし、彼岸花の花は死や不吉なイメージの方が強いですよね。それは、「彼岸花を家に持ち帰ると火事になる」「彼岸花を摘むと死人がでる」「彼岸花を摘むと手が腐る」といったいくつかの恐ろしい迷信があるためです。これらは、花色や花姿が炎を連想させることと、彼岸花のもつ毒によるものとされています。決して怖い花言葉をもっているわけではないのですが、死や不吉な印象があることから贈り物として用いられることはほとんどありません。」と。途中から引き返して。この日は水の流れも濁流から清流に変わって。白と赤のコラボ。既に蕾の株は殆ど無く。花は高さ30~50㎝程度の花茎の先に、強く反り返った6枚の花被片(花びら)を持った鮮やかな紅色の花が5~7個程度付き、やや扁平な球状の花序となっている。大山の姿もはっきりと。 ・・・つづく・・・
2025.10.05
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その99): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-14
再び、タワーブリッジの北側の塔の先から、北岸の シティ・オブ・ロンドンの高層ビル群を望んで。・20 Fenchurch St (Walkie Talkie)(左端の広がった形のビル)・22 Bishopsgate(中央で最も高いビル)・The Scalpel(鋭い三角形屋根のビル)・The Cheesegrater(斜めにカットされたビル)・The Gherkin(右側の卵型ビル)・Tower of London(右下の歴史的城壁)タワーブリッジの上からテムズ川を西方向に見た光景を。・左端の尖塔状の超高層ビル ▶️The Shard(シャード) ・高さ310m、イギリスで最も高い建物。ホテル、オフィス、レストラン、展望台を含む 複合施設。・左手前の丸い階段状の建物 ▶️City Hall(旧ロンドン市庁舎) ・2002年竣工、ノーマン・フォスター設計。 ・2021年までロンドン市庁舎として使用。現在は用途変更。・中央のガラス張りの建物 ▶️More London Riverside(オフィス群) ・近代的なビジネス街で、多くの企業本社や飲食店が集まるエリア。・右奥の軍艦 ▶️ HMS Belfast(ベルファスト巡洋艦記念艦) ・第二次世界大戦で活躍したイギリス海軍の軽巡洋艦 ・現在は博物館船として公開中。移動して。タワーブリッジ (Tower Bridge) の塔を真下から仰ぎ見たアングルで。・石造りの塔(タワー部分) ・ゴシック・リヴァイヴァル様式(ネオゴシック)の特徴を持ち、装飾的な小塔や 尖頭アーチ窓が並んでいた。 ・正面の大きな円柱状の構造は、塔を補強する石柱。視覚的にも塔の力強さを強調していた。・上部の歩行者用連絡通路(Walkways) ・写真の左上に写る青色の構造物は、塔と塔をつなぐ上層の歩行者用高層通路。 ・元は橋が開いた際に歩行者が川を渡れるように設けられた と。 現在は展示・展望施設になっていた。タワーブリッジの塔を真下から見上げ、上部の2本の高層通路(Walkways)を。テムズ川越しに見た ロンドン塔(Tower of London)を見る。・中央に見える白い塔 ▶️ホワイト・タワー (White Tower) ・11世紀末、ノルマン王ウィリアム1世が築かせた石造りの主塔。 ・ロンドン塔の中心的建造物であり、世界遺産の核となる部分です。・周囲の城壁 ・テムズ川沿いに連なる厚い防御壁と塔。 ・かつては牢獄や処刑場としても使われた。・背後の高層ビル群 ・シティ・オブ・ロンドンの金融街。 ・左奥から「The Scalpel(スカルペル)」「The Gherkin(ガーキン)」 「The Cheesegrater(チーズグレーター)」などが見えた。 ・中世のロンドン塔と現代の摩天楼が対照的に並ぶ景観。タワーブリッジ (Tower Bridge) の塔を正面から見上げた迫力ある構図。上部に塔と塔をつなぐ 高層歩行者通路(Walkways)。元は橋が開いている間に歩行者が川を渡るための設備であったと。橋の中央部から北側を振り返って。タワーブリッジ (Tower Bridge) の観光施設「Tower Bridge Exhibition(タワーブリッジ・エクスペリエンス)」の入口付近を。観光客が中に入って塔内部や展望ウォークウェイ、機械室を見学できる施設の案内板👉️リンク・大きな黄色の案内パネル ・「Explore Inside Tower Bridge(タワーブリッジの内部を探検しよう)」と。 ・イラストで塔の内部や高層通路(Walkways)、機械室(Engine Rooms)などを表現。・建物の用途 ・ここはチケット売り場兼エントランス。 ・観光客はこの入口から入り、塔の上階やウォークウェイに上ることができるのであった。・チケット料金(Ticket Price) ・Adult(大人):£16.00 ・Disabled Adult(障害者大人):£12.00 ・Student(学生):£12.00 ・Senior(シニア、60歳以上):£12.00 ・Child(子ども、5〜15歳):£8.00 ・Disabled Child(障害者子ども、5〜15歳):£6.00 ・Companion(付き添い):無料 ・Under 5(5歳未満):無料壮大な塔の頂上までは206段の階段とのことで、必要に応じてエレベーターも利用出来るのであった。タワーブリッジ展示(Tower Bridge Exhibition) 内の展示スペースの一部で、橋が建設された 19世紀末から20世紀初頭のロンドンの街並みや暮らしを再現したコーナー。・古い街路標識 ・「COPPER ROW」「TOOLEY ST」「HORSLEYDOWN LANE」など、タワーブリッジ周辺に 実在した(あるいは今も存在する)道路の名前。 ・建設当時、この地域は倉庫や港湾労働者の町であり、ロンドン港の物流の拠点でした。・背景の映像/写真 ・馬車や当時の人々の姿を映し出したモノクロ写真(または映像スクリーン)。 ・タワーブリッジ完成直後の交通や生活の雰囲気を体感できます。・展示品(生活道具・商業用品) ・木製の荷車、リンゴなどの果物箱、樽、古い自転車(ペニー・ファージング)など。 ・これらは港町らしい荷役や市場の雰囲気を再現しています。・背景の肖像画 ・タワーブリッジ建設に関わった技師や関係者の肖像を模した展示。 ・中央の白髭の人物は、おそらく設計者ジョン・ウォルフ・バリー (Sir Horace Jones と 共に設計) または当時の工学者。タワーブリッジの高層歩行者通路(High-Level Walkways) 内部に設置された川面から約 42m の高さに位置するガラス床(Glass Floor)。・強化ガラスでできた長方形の床部分。・下を走る車や二階建てバス、歩行者、さらには跳ね橋が開閉する様子まで見下ろせた。・ガラス床の両脇は木製フローリングになっており、安心して歩ける設計。ウィリアム・ライオネル・ワイリーによる、1895年のタワーブリッジ開通の様子を描いた絵画。タワーブリッジ (Tower Bridge) の機械室(Victorian Engine Rooms) に展示されているヴィクトリア時代の蒸気機関。・役割 ・かつてタワーブリッジの「跳ね上げ橋」を作動させるための油圧ポンプを動かしていた 蒸気機関。 ・巨大なフライホイールとピストンで圧力を生み出し、橋の開閉を制御していた。・仕組み ・石炭を燃やして水を蒸気に変換。 ・蒸気でピストンを動かし、連結されたフライホイールを回転させる。 ・その動力を油圧システムに伝えて、橋の跳ね上げ部分を上下させていた。「Tower Bridge Exhibition(タワーブリッジ・エクスペリエンス)」を出てタワーブリッジ上から西方向(テムズ川上流側)を見る。・左手前(南岸) ・ガラス張りの球体的な建物 → 旧ロンドン市庁舎(City Hall) ・その後方にそびえる尖塔 → ザ・シャード(The Shard)、高さ310m、 ロンドンで最も高い・高層ビル。・中央の川の中ほど ・停泊している灰色の軍艦 → HMS Belfast(ベルファスト号) ・第二次世界大戦時の軽巡洋艦、現在は帝国戦争博物館の分館として公開。・右側(北岸側) ・川沿いに並ぶモダンなオフィスビル群 → シティ・オブ・ロンドンの金融街の一部。 ・写真の端に少し見えている独特の形状のビル → ウォーキー・トーキー (20 Fenchurch Street)。・さらに遠景 ・川沿いの橋がいくつも見える(ロンドン橋、カノン・ストリート鉄道橋、 サウスワーク橋 など)。移動してズーム。タワーブリッジ上から北岸方向(シティ・オブ・ロンドン側) を再び。 ・ロンドン塔(Tower of London)と背景の高層ビル群(シティの金融街)ズームして。タワーブリッジ (Tower Bridge)の北塔下から北側ゲートハウス(ノースアプローチ、North Tower 出口側)を見る。タワーブリッジから東方向(テムズ川下流側)を望んで。・一番高いタワーは Providence Tower(高さ約135m、2016年完成)。北側ゲートハウス(ノースアプローチ、North Tower 出口側)。タワーブリッジ(Tower Bridge)のゲートハウス上部装飾(ノースアプローチ側) のクローズアップ。・中央の三角形のパネル(ペディメント風) ・ロンドン市の紋章(シティ・オブ・ロンドンのコート・オブ・アームズ)が彫刻されていた。 ・白い盾に赤い聖ジョージ十字と上部に赤い剣。 タワーブリッジの彫刻は無彩色であったが、当初は彩色されていた可能性もあるのだろうか? ・両脇にはサポーター(盾を支える獅子とドラゴン)。 ・下部にはラテン語のモットー Domine Dirige Nos(主よ、我らを導きたまえ)が 刻まれている と。シティ・オブ・ロンドン(City of London)の紋章(Coat of Arms)をネットから。タワーブリッジ(Tower Bridge)の上からテムズ川を西方向(上流側)に向かって。The Shard(シャード)・高さ310m、ロンドンで最も高いビル(2012年完成)。ガラス張りの尖塔型デザイン。サウスタワー(South Tower) を南側(サザーク側)から北向きに振り返って。タワーブリッジ(Tower Bridge)の銘板(記念プレート) 。タワーブリッジの建設経緯を記した記念碑的プレート塔の基部に取り付けられており、建設時の関係者・完成年・設計者や工事監督の名前 が刻まれていた。「Corporation of LondonThe foundation stone of this bridge was laid byHis Royal Highness, the Prince of Wales (later King Edward VII)on 21 June 1886,in the presence ofHer Royal Highness, the Princess of Wales,and other members of the Royal Family.The bridge was officially opened byHis Royal Highness, the Prince of Wales,on 30 June 1894,in the presence ofHer Royal Highness, the Princess of Wales,and other members of the Royal Family.The Right Honourable Sir James Whitehead, Lord Mayor.Sir John Voce Moore, Chairman of the Bridge House Estates Committee.Engineers:Sir John Wolfe Barry, Henry Marc Brunel.Architect:Sir Horace Jones.」【ロンドン市当局この橋の礎石は、1886年6月21日、皇太子(後のエドワード7世)殿下により皇太子妃殿下ならびに王室の他の方々ご臨席のもと、据えられた。この橋は、1894年6月30日、皇太子殿下により皇太子妃殿下ならびに王室の他の方々ご臨席のもと、正式に開通された。尊敬すべきサー・ジェームズ・ホワイトヘッド卿(市長)サー・ジョン・ヴォース・ムーア卿(橋梁財団委員会委員長)技師:サー・ジョン・ウルフ=バリー卿、ヘンリー・マーク・ブルネル建築家:サー・ホレス・ジョーンズ】 これは 1982年の改修・再公開記念の銘板。「CITY OF LONDONTOWER BRIDGEThe main towers, high level walkways and the bascule rooms under the southern approach of the Bridge were re-opened to the public on 30th JUNE 1982 by the Right Honourable the Lord Mayor Sir Christopher Leaver, G.B.E., D.L., in the presence of Norman Harding, Esq., Chairman of the City Lands &Bridge House Estates Committee of the Corporation of London, John L. Bird, Esq., Chairman of the Planning and Communications Committee, and the following membersof the Corporation’s Court of Common Council:Bernard Joseph Brown, C.B.E., J.P.Sir Hugh Wontner, G.B.E., C.H., D.L.Colin Dyer, B.A., DeputyJack Fransenburg, J.P.Gordon H. Poole, J.P.Keith C. Proctor, J.P.Francis P. Wood, J.P.Edward L. Wright, C.B.E., D.L., DeputyColin W. Busby, B.A.Cecil W. Barnes, C.B.E.The cost of all necessary work being met from the funds of the Bridge House Estates Trust.ConsultantsExecutive Architects: Holford AssociatesEngineers: Mouchel, Hay & AndersonQuantity Surveyors: Kenneth H. Kendall & PartnersExhibition Designers: Robin Wade Design AssociatesContractorHolland, Hannen & Cubitts Construction (London) LtdCity EngineersG.W. Pickett, F.I.C.E., C.Eng.L.W.B. George, C.Eng., F.I.C.E., F.I.Mun.E., F.I.Struct.E.」 【ロンドン市 ― タワーブリッジタワーブリッジの主塔、高層通路、そして南側アプローチ下の跳開橋(バスキュール)機械室は、1982年6月30日、ロンドン市長サー・クリストファー・リーヴァーによって、ノーマン・ハーディング(ロンドン市 土地・橋梁財団委員会委員長)、ジョン・L・バード(都市計画・広報委員会委員長)、ならびにロンドン市議会の議員らの立ち会いのもとで、一般公開が再開された。必要とされた改修工事の費用はすべて、ブリッジ・ハウス財団信託基金から拠出された。関係者設計監修建築家:ホルフォード・アソシエイツ技術エンジニア:ムーシェル、ヘイ&アンダーソン積算監査:ケネス・H・ケンダル&パートナーズ展示デザイン:ロビン・ウェイド・デザイン・アソシエイツ施工会社:ホランド・ハンネン&キュービッツ建設(ロンドン)社ロンドン市エンジニア:G.W. ピケット、L.W.B. ジョージ】こちらの銘板は、1977年の機械更新工事に関する記録「CITY OF LONDONTOWER BRIDGEConstructed and maintained by the Corporation of London from the Bridge House Estates Trust without charge upon Public Funds. The installation of the electrical machinery for raising the bascules replacing the original hydraulic equipment was completed by the Trust in 1977.G. W. PICKIN B.Sc.C.Eng., F.I.C.E., F.I.Mun.E.City EngineerConsulting Engineers: Mouchel, Hay and AndersonContractor: Cleveland Bridge Engineering Co. Ltd.」 【ロンドン市 ― タワーブリッジタワーブリッジは、ブリッジ・ハウス財団信託基金によって建設・維持されており、公的資金(税金)を一切使用していない。跳開橋(バスキュール)を上げ下げするための水圧式機構を電動機械に置き換える工事は、1977年に信託基金によって完了した。ロンドン市技師長:G.W. ピッキンコンサルティング・エンジニア:ムーシェル、ヘイ & アンダーソン施工業者:クリーブランド・ブリッジ・エンジニアリング社】ノースタワー(North Tower)をテムズ川の桟橋(北岸東)手前から見上げて。タワーブリッジ北塔(North Tower)下部にある階段状のリバーアクセス(階段桟橋)。ノースタワーのテムズ川に面した基部、つまり橋脚の脇に設けられていた。・元々は メンテナンス用 や小舟の着岸用のアクセスとして作られたと。・観光用の船着場ではなく、関係者が川面に降りるための補助的施設。・階段に藻や苔がびっしりついていることから、満潮時と干潮時の水位差で水没する 「潮汐階段(tidal stairs)」 の性質を持っていた。タワーブリッジ桟橋(Tower Bridge Quay)入口にあった「Thames River Sightseeing(テムズ川観光クルーズ)」のチケット売り場ブース。タワーブリッジ(Tower Bridge)のサウスタワー(South Tower)側 を、川辺の桟橋(Tower Bridge Quay )の前から撮影。その先にあったのが「Girl with a Dolphin Fountain(少女とイルカの噴水)」。・作者:David Wynne(デヴィッド・ウィン)・制作年:1973年・モチーフ:少女とイルカが共に跳ね上がる姿を表現しており、水の動きと一体化した ダイナミックな造形が特徴タワーブリッジを背景に。背後に The Tower Hotel(タワーホテル) が。少女がイルカの背にしがみつきながら舞い上がる姿を表現しており、水の流れが生命感を加えていた。・少女は 逆さまに宙を舞うポーズ をとっており、イルカに軽く手を添えていた。・髪は水の流れを受けて広がっているように造形され、波や水しぶきを象徴。・素材はブロンズ像で、年月を経て緑青(ろくしょう)が浮かび、独特の深みを持って。・少女の表情は柔らかく、まるで水中で安らかに遊んでいるかのよう。タワーブリッジの東側(下流側) のテムズ川沿いから。・中央の二つの塔 ・手前(右側)が 北塔(North Tower/シティ・オブ・ロンドン側) ・奥(左側)が 南塔(South Tower/サザーク側)・特徴的な部分 ・下層に車道(A100 / Tower Bridge Road)が通る可動橋部分。 ・上層に歩行者用の「高層通路(Walkways)」が塔と塔を結んでいた。 ・塔の上部には金色の装飾が輝いて。・背景右奥 ・三角の尖塔状の超高層ビルは The Shard(シャード)(高さ310m、イギリスで最も高いビル)。 ・サザーク駅・ロンドンブリッジ駅近くに位置。Potter’s Fields Park(ポッターズ・フィールズ公園)のリバーサイド遊歩道沿いにあったのがThe Timepiece Sundial・タイムピース日時計。「The Sundial at Potter’s Fields(ポッターズ・フィールズ日時計)」とも呼ばれていると。大きな金属製の環(リング)が傾けて設置され、その中心を斜めに貫く棒(スタイル)が影を落とす構造の日時計。外周には点字のような浮き出し模様があり、時間を読むことができるのであった。タワーブリッジの2つの塔と吊り桁を背景に。彫刻家: Wendy Taylor 作、1973年設置。左側:マスト(帆船を模したモニュメント)、大砲(展示物)。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.05
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その98): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-13
さらにテムズ川の南岸を下流に向かって進む。左側にあったのが、HMS Belfast のリバーサイド・ビジターセンター(入口)。・場所:南岸の The Queen’s Walk(ロンドン橋とタワーブリッジの中間)。 運営は Imperial War Museums(IWM)。・入場:この入口でチケット購入/引き換え。見学目安は 1.5〜2時間。最終入場は閉館より少し早め。・船内の見どころ ・艦橋・操舵室(ブリッジ) ・作戦室(Ops Room) ・主砲塔(6インチ三連装):砲撃体験展示あり ・機関室/ボイラー室 ・居住区(メス・医務室・理髪室など)HMS Belfast の入口脇にあった「NINE DECKS TO EXPLORE(見学できる9層)」案内板。主な見どころ・04(最上部):フラッグ・デッキ/オープンブリッジ周辺 ― 甲板上からの眺望が良い。・03:アッパーブリッジ一帯 ― 航海設備や見張り関連。・02:ホイールハウス(操舵室)/艦橋内部。・01:艦橋基部・上部構造の付け根 ― 指揮通信区画への入口。・1(主甲板):6インチ主砲塔 A・B、居住区、甲板上の各装備。・2:ギャレー(厨房)、医務室、メスなど生活区画。・3:オペレーションズ・ルーム(作戦室)、通信室、発令所へ続く区画。・4:機関区 ― ボイラー室/エンジンルーム(迫力ある見学ポイント)。・5(最下層):弾薬庫・薬莢庫/揚弾機、操舵機構の一部など。タワー・ブリッジ(Tower Bridge)(跳開橋+吊り橋、1894年完成)を南岸(The Queen’s Walk)から下流=東向きに見る。・写真左は、HMS Belfast・巡洋艦ベルファスト記念艦への見学用桟橋。・タワー・ブリッジ(高架歩廊は海面上約42m。 bascule〈可動桁〉は閉じた状態)・橋の向こう遠景にカナリー・ワーフの高層群。タワー・ブリッジ(Tower Bridge)をズームして。・両塔:高さ約65 m。・上段の高架歩廊(Walkways):川面上約42 m。ガラス床区画あり(有料見学)。・下段の可動桁(Bascule):中央スパン約61 m。閉じて車両(赤い2階建てバス)が通行中。・斜材のチェーン部分は吊り橋の機能。・架橋:1894年(建築設計ホレス・ジョーンズ、土木ジョン・ウォルフ・ベリー)。・可動機構:当初は蒸気油圧、1976年に電動油圧へ更新。・橋は通航予定船の事前申請で開閉(観光向けに定時開閉は設定なし)。・色:現在の青×白は1977年の女王即位25周年に合わせた再塗装以来の配色。・奥に見える高層群はドックランズ/カナリー・ワーフ。橋の開閉👈️リンク をこの眼で見たいのであったが・・・。南岸(The Queen’s Walk)を更に進むと、前方に現れたのが旧ロンドン市庁舎 City Hall(More London/現・London Bridge City 内)。設計は Foster + Partners(ノーマン・フォスター)、2002年完成。2021–22年に GLA(ロンドン市長・議会)はロイヤルドックスの“The Crystal”へ移転し、この建物は現在は市庁舎ではないとのこと。形状:日射熱を抑えるために北へ傾いた楕円体のガラス外装。内部は議場を囲む ヘリカル(螺旋)スロープが象徴的。手前の階段状空間は屋外円形劇場 “The Scoop”。イベント時の会場になる と。対岸のロンドン塔(Tower of London)をズームして。・ホワイト・タワー(White Tower) ・ノルマン様式の主塔(1070年代、ウィリアム1世)。 ・四隅の小塔と、17世紀に付けられた鉛張りのドーム屋根と風見が見えます。・その手前に見えるのが内郭の高い城壁(カーテンウォール)、さらに川沿いに外郭の城壁。 胸壁のクレネレーション(狭間)が連続していた。・画面右手の低い石塀と門は、外郭の出入口の一つ(一般入場口はこの先の内側)。 ロンドン塔は、王宮・要塞・造幣局・刑務所など多用途に使われ、現在は王冠宝器 (クラウン・ジュエルズ)の保管場所。世界遺産にも登録されている。南岸=HMS Belfast 側から北岸=シティを望む。左 → 右へ1.HMS Belfast の艦尾(White Ensign) 〔手前・左端〕 — 巡洋艦ベルファストの白船尾旗。2.Cheval Three Quays(40 Lower Thames St)〔川沿い・中央手前〕 — ガラス張りで バルコニーが段状に並ぶサービスアパートメント。3.20 Fenchurch St “Walkie-Talkie” 〔背景・左端寄り〕 — 画面左奥、曲面の外観が一部見切れ。4.22 Bishopsgate 〔背景・左寄り〕 — 最も背が高い長方形のタワー。5.8 Bishopsgate 〔背景・22の手前/右隣〕 — 角ばった高層、22 に接して見える。6.The Scalpel(52 Lime St) 〔背景・中央〕 — 先端を斜めに“切り落とした”ような鋭い屋根線。7.100 Bishopsgate 〔背景・右寄り〕 — 直方体で段差のある質量感のタワー。8.10 Trinity Square(元 Port of London Authority)〔右端奥・樹木の上〕 — 低い円形ドームが 覗く建物。(中)9.Uber Boat by Thames Clippers 〔川面中央〕 — テムズの高速ボート。再びタワー・ブリッジ(Tower Bridge)をズームして。・画面左=北塔(Tower Hill 側)・画面右=南塔(Southwark 側)写っている部位:・上段の高架歩廊(川面上約 42 m)・下段の可動桁(bascule)(中央スパン約 61 m、この写真では閉)・両側の吊り部材(チェーン)北塔(Tower Hill 側)をズームして。南岸(Potters Fields Park 付近)から下流=東向き。塔の左から伸びる青いケーブルは北側アプローチの吊り部、塔の右へ延びるのが上層の高架歩廊。・塔高:約 65 m・高架歩廊の高さ:川面上 約42 m(内部にガラス床区画)・開閉機構:当初は蒸気油圧、1976年以降は電動油圧・現行塗色(青×白)は 1977年 の再塗装以来の配色南塔(Southwark 側)をズームして。反対側(画面外右)に南塔(サザーク側)があり、上部でも2塔間を歩廊が結んでいた。再び「ロンドン塔」をズームして。 旧ロンドン市庁舎 City Hall(More London/現・London Bridge City 内)を横から。The Scoop(屋外円形劇場)/More London(現:London Bridge City)。・中央奥の尖塔はThe Shard(310 m, 2012)。・右のカーブしたガラス棟=2 More London Riverside(川沿いオフィス)・手前はイベント「Summer by the River」設営エリアLondon Bridge City(More London)一帯の触知式ブロンズ模型(tactile map)。場所は The Scoop(屋外円形劇場)付近のテラスに設置され、周辺地形と主な建物を立体で示していた。以下、Tower Bridge・タワーブリッジをこれでもかと。旧ロンドン市庁舎(City Hall, 2002/Foster + Partners)を振り返って。The Queen's WalkからTower Bridge Road(タワーブリッジ・ロード)・A100へ上がる石段を進む。タワーブリッジ (Tower Bridge)の車道部分Tower Bridge Road(タワーブリッジ・ロード)・A100を南側から北側へ向かって見る。・手前に見える石造のアーチ門は、タワーブリッジの「南塔」基部。・橋の 南側(サザーク地区):Tower Bridge Road が A2(Great Dover Street)や A3 方面に接続。・橋の 北側(シティ・オブ・ロンドン側):Tower Hill や A1210, A1203(East Smithfield) 方面に接続。タワーブリッジの 南塔(South Tower) のアーチ下から、北塔(North Tower)側を見て。・車道を走っているのはロンドン名物の二階建て観光バス。・左右に歩道があり、青い鉄製の欄干(手すり)が特徴的。タワーブリッジの 北塔(North Tower)を正面から見上げて。・中層に複数の窓が整然と並ぶゴシック風デザイン。・上部は尖塔屋根(スレート葺き)、四隅に小塔(タレット)、頂点に金色の装飾が 施されていた。タワーブリッジ (Tower Bridge) の公式サイン。・上部に City of London(シティ・オブ・ロンドン) の紋章が描かれていた。・赤い聖ジョージ十字の盾と、剣(聖ポールの象徴)、左右に支えるドラゴンが特徴。 下に大きく TOWER BRIDGE と刻まれていた。この標識は、タワーブリッジの石造部分(塔やアプローチの壁面)に設置されていて、観光客の撮影スポットとしても有名。橋の 南側(サザーク地区側)から北方向(シティ・オブ・ロンドン側)を見て。北塔(North Tower)が正面に。北塔(North Tower)をズームして。テムズ川越しに見たシティ・オブ・ロンドンの高層ビル群。右下には ロンドン塔(Tower of London) の城壁が見えた。1.20 Fenchurch Street(ウォーキー・トーキー / Walkie Talkie) ・左端にある、上部が広がった独特の形の高層ビル(高さ160m)。 ・最上階には「Sky Garden」という展望施設があります。2.22 Bishopsgate(中央の最も高いビル) ・高さ278m、シティで最も高い超高層ビル。 ・2019年完成。ガラス張りで階段状に見えるデザイン。3.The Scalpel(52 Lime Street) ・22 Bishopsgate の右手、鋭い三角形の屋根を持つビル。 ・高さ190m。保険会社の本社が入居。4.The Cheesegrater(Leadenhall Building) ・さらに右奥に見える、斜めにカットされた形状の高層ビル。 ・高さ225m、通称チーズおろし。5.30 St Mary Axe(ガーキン / The Gherkin) ・右奥、卵型をしたガラス張りのビル。 ・高さ180m、シティの象徴的建物。テムズ川南岸、タワーブリッジ付近から西方向を望んで。1.手前の丸い建物:City Hall(旧ロンドン市庁舎)2.奥にそびえる尖塔型の超高層ビル:The Shard(シャード、正式名:Shard London Bridge)3.川の右手に見える軍艦:HMS Belfast(巡洋艦ベルファスト記念艦)タワーブリッジ (Tower Bridge) の 南塔(South Tower) を正面から見上げた光景。・左右の青い吊り桁(サスペンションチェーン):タワーブリッジ特有のスカイブルーの鉄骨。・塔のデザイン:ゴシック風の装飾と窓の配置。四隅の小塔(タレット)、頂部には金色の装飾。ズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.04
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その97): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-12
The Golden Hinde・ゴールデン・ハインドの帆先の前を通過し進むと前方にあったのがサザーク大聖堂(Southwark Cathedral)。ロンドンのサザーク地区、テムズ川の南岸、ロンドン・ブリッジ駅の近くにあった。正式名称: The Cathedral and Collegiate Church of St Saviour and St Mary Overie, Southwark歴史:・起源は7世紀頃の修道院にさかのぼり、12世紀にノルマン様式の教会が建てられた。・13世紀にゴシック様式へと拡張され、その後も増改築を経て現在の姿になっていた。・1905年に正式に大聖堂(Cathedral)に昇格した。建築様式: ゴシック様式を基調とし、ヴィクトリア時代に修復された部分もある。特徴:・高い四角い塔と八角形の尖塔。・外壁は明暗のコントラストが強い石積み。・内部には著名人(シェイクスピア、ジョン・フレッチャーなど)と関係する記念碑がある と。サザーク大聖堂(Southwark Cathedral) の内部・大聖堂の身廊(中央の長い通路部分) を祭壇方向に向かって。・ゴシック様式の典型である リブ・ヴォールト天井(Rib Vaulting)・交差リブが格子状に走り、天井を支える美しい構造。三連窓(トリフォリウム形式)になっていた「シェイクスピア記念窓(Shakespeare Memorial Window)」。上部(トレーサリー部分) ・紋章(Shakespeare familyの紋章)と記念銘文。 ・左右に白地の小パネルに英語の追悼文が書かれています。中央パネル ・復活したキリストが光を受けて両手を掲げる姿。 ・下部には天使や寓意像。 ・キリストを中心に「シェイクスピアの作品も神の創造の栄光に属する」という象徴。左パネル(Old Plays) ・『夏の夜の夢(A Midsummer Night’s Dream)』の妖精たち。 ・『オセロ』『マクベス』などの劇からの登場人物。 ・背景に豊かな植物文様。右パネル(Histories & Comedies) ・『ハムレット』(剣を持つ人物)。 ・『ヘンリー五世』など歴史劇の英雄。 ・『テンペスト』のアリエルらしき存在も確認可能。ジョン・ギャワー(John Gower, 1330頃–1408)の墓(tomb monument)。ジョン・ギャワー は中世イングランドの詩人で、ジェフリー・チョーサー(『カンタベリー物語』の作者)の同時代人かつ友人。・横たわるギャワーの像: 赤い法衣に身を包み、頭は三冊の本(彼の三大著作)に枕するよう に置かれていた。・壁画部分(アーチ内): ・中央に聖母マリア像。 ・左右に女性像(おそらく寓意的人物=慈愛・知恵・信仰などを表す)。・ゴシック様式の装飾: 赤・緑・金で鮮やかに彩色され、細部はヴィクトリア時代に補彩。・碑文: 黒地に金文字でラテン語の墓碑銘。頭を三冊の本に載せているのは、彼が 三言語詩人(ラテン語・フランス語・英語)であることを象徴しているのだと。こちらは、「シェイクスピア記念碑(Shakespeare Memorial)」。・設置:1912年、俳優サム・ティムス(Sam Timms)によって建立。・場所:大聖堂の南翼廊(South Transept)。・作者:彫刻家 Henry McCarthy によるブロンズ像。・寝そべる姿のシェイクスピア ・枕に肘をつき、片手で植物(ローレルやアイビー)を持つ。 ・リラックスしたポーズで、知的で芸術家らしい雰囲気を表現。・背後の浮彫 ・ロンドンの旧グローブ座(The Globe Theatre)が描かれている。 ・シェイクスピアが活動したサザーク地区との関わりを強調。・台座部分の銘文 ・シェイクスピア作品からの引用。 ・しばしば『テンペスト』や『ハムレット』からの言葉が刻まれる。バラ・マーケット(Borough Market) 周辺には多くの観光客の姿が。テムズ川南岸を走る鉄道の高架下を歩く。ロンドンでも特に観光客と地元客で賑わうフードマーケットなので、週末には写真のように非常に混雑するのであった。バラ・マーケット(Borough Market)内にある人気フードスタンドのひとつ、「Truffle / Trufeles」の店舗。看板にあるメニュー:「WILD MUSHROOM RISOTTO (made with SPELT)」 ・野生キノコのリゾット(スペルト小麦を使用) ・この店の看板メニューで、観光客に大人気であった正面には玉ねぎが大量に吊り下げられていて、マーケットらしい活気を演出。ロンドンのランドマーク 「ザ・シャード(The Shard)」。場所:ロンドン・サザーク地区、ロンドン・ブリッジ駅(London Bridge Station)のすぐ隣。完成:2012年設計者:イタリアの建築家 レンゾ・ピアノ(Renzo Piano)高さ:310メートル(西ヨーロッパで最も高い建物の一つ)特徴:・外観はガラスの破片(shard)のように尖っていることから名前が付いた。・下層はオフィス、中層はレストランやホテル(シャングリラ・ホテル)、上層には展望台「The View from The Shard」がある。・夜にはライトアップされ、テムズ川南岸のシンボルとして輝く。Southwark Street(A3200)に架かる鉄道橋(Borough Market の西側、Stoney Street 付近)をズームして。Southwark Street(A3200)をまたぐ鉄道橋、いわゆる Borough Market Viaduct の南側アーチ橋。この銀色のボウストリング(アーチ)橋が道路をまたぎ、そのすぐ東側がバラ・マーケット、西へ進むとサウスワーク・ブリッジ方面。「ロンドン橋」方向に向かって進む。 南側アーチ橋をくぐると、先程訪ねたSouthwark Cathedra・サザーク大聖堂の南側外観。1.手前の連続する尖頭小破風(トリプルの小三角屋根)と縦長のランセット窓 …内陣南側の側廊と小礼拝堂列(13世紀ゴシック)。2.奥の大きな三角破風に丸窓(オクルス) …南翼廊(South Transept)の外壁。3.さらに背後で四角い上部に胸壁をめぐらした中央塔(Crossing Tower)。4.画面右端の茂みの先(画面外)が東端(内陣・Lady Chapel)方向、左奥が身廊(Nave)/ 西正面方向。サザーク大聖堂の 南側(南翼廊前)を見上げて。中央塔(Crossing Tower) 四角い塔頂に胸壁(バトルメント)と四隅の尖塔(ピナクル)。塔自体は中世 (ペルペンディキュラー様式期)の部分が核で、現在の外装は19世紀に整えられています。 最上部には 聖ジョージ旗(イングランドの十字旗)。外付け時計 南面に張り出す金色の文字盤の外時計。19世紀の修復時に、市民の時刻表示用として 設けられたタイプ。南翼廊(South Transept)の切妻正面 中央の円窓(オクルス)と、その下に三連ランセットへつながる構成。 両脇には小さな角塔(タレット)が付き、屋根稜線には十字飾りが立っていた。ロンドン橋(London Bridge)の南詰・東側にあったのが「Howard Kennedy LLP」ビル。 これはNo.1 London Bridge(ナンバーワン・ロンドン・ブリッジ)とも。ロンドン・ブリッジの南詰(テムズ川南岸)に建つ1980年代のポストモダン建築で、格子状の小窓と、建物の一角を大きくくり抜いた巨大ポータル(吹き抜け)が外観の特徴。ロンドン橋(London Bridge)周辺の案内地図。「You are here」と。 道路の反対側にあったのが「City of London の境界標(Dragon Boundary Mark)」。 「CITY OF LONDONLONDON BRIDGEREBUILT 1967–1973 BYTHE CORPORATION OF LONDONFROM BRIDGE HOUSE ESTATES FUNDSHAROLD KNOX KING, CBE, CEng, FICE, FIMunE, FRICSCITY ENGINEERCONSULTING ENGINEERS — MOTT, HAY & ANDERSONCONSULTANT ARCHITECTS — WILLIAM HOLFORD & PARTNERSCONTRACTORS — JOHN MOWLEM & COMPANY LIMITED」 【シティ・オブ・ロンドンロンドン・ブリッジ1967年〜1973年に、シティ・オブ・ロンドン当局がブリッジ・ハウス・エステーツ基金を用いて再建した。市技監:ハロルド・ノックス・キング(CBE, CEng, FICE, FIMunE, FRICS)コンサルティング・エンジニア:モット、ヘイ & アンダーソン設計監理建築家:ウィリアム・ホルフォード & パートナーズ施工:ジョン・モウレム & カンパニー社】境界標「ドラゴン・バウンダリー・マーク」 をアップして。・ドラゴンは City of London の紋章の支持獣(supporter)。・盾の意匠が 市章: ・白地に赤い十字=聖ジョージ十字 ・盾の左上の赤い剣=聖ポールの剣(シティの守護聖人)・翼を立てたドラゴンが盾を支える。舌・翼裏が赤。・シティへの“入口”に据えられ、ここから市域(Square Mile)ですという境界を示す と。ロンドン橋(London Bridge)の袂から、テムズ川の上流を見る。手前の橋は Cannon Street Railway Bridge(キャノン・ストリート鉄道橋)。右岸の二つの塔の建物が Cannon Street Station(駅舎)、その向こう左奥に見える白い大きなドームが セント・ポール大聖堂。ズームして。そしてロンドン橋(London Bridge)上または南詰付近から、下流(東)方向を向いてタワー・ブリッジ(Tower Bridge)を見る。画面中央:タワー・ブリッジ 1894年完成。建築:Horace Jones、技術:John Wolfe Barry。 跳開橋+つり橋式/塔高約65m・高架歩廊は約42mNo.1 London Bridge(ナンバーワン・ロンドン・ブリッジ)前の石段を下りテムズ川沿いの遊歩道へ。London Bridge(南岸)から東(下流)へ “Thames Path” を直進するときの行き先一覧。現在地は「●YOU ARE HERE」。テムズ川南岸(The Queen’s Walk/Hay’s Galleria 付近)から、北岸=シティ側を見て。左から右へ。1.白い養生シートの建物(Old Billingsgate の“西側”にある別の河岸ブロックの改修中)2.Northern & Shell Building(10 Lower Thames St) ― 段状の青いガラス3.Old Billingsgate(旧ビリングズゲイト市場) ― クリーム色の長いアーチ窓4.Custom House(税関) ― Old Billingsgate のさらに東(右端)HMS Belfast・巡洋艦ベルファスト記念艦が前方に。その後方にタワー・ブリッジ、その奥にカナリー・ワーフの高層ビル群。・艦種:タウン級軽巡洋艦(エディンバラ亜種)・建造:ハーランド&ウルフ社(ベルファスト)・進水:1938年/就役:1939年・主寸法:全長約187m、速力約32ノット・兵装(就役時):・6インチ(152mm)砲 3連装×4基=12門・4インチ(102mm)高角砲 連装×6基=12門・2ポンド“ポンポン砲”、20mm機銃、魚雷発射管(21inch)など・搭載機:当初は水上機(カタパルト)を運用、その後撤去・乗員:平時約800、戦時には1,000名超主要な経歴・1939年11月:北海で機雷に触れて大破。大規模修理・近代化(船体補強/レーダー・ 対空兵装強化)を受け 1942年 に復帰。・1943年:北極海船団護衛に復帰。ノースケープ海戦(12月)で第10巡洋艦戦隊旗艦として 行動し、戦艦シャルンホルスト撃沈に貢献。・1944年6月:ノルマンディー上陸作戦(D-Day)で沿岸砲撃(連合軍の英・加方面を支援)。・朝鮮戦争(1950–52):極東配備。北朝鮮沿岸の艦砲射撃・封鎖任務に従事。・1963年 退役。解体を免れ、1971年 テムズ川に係留公開。1978年 からインペリアル・ウォー・ ミュージアム(IWM)が所管。いま見られること(見どころ)・主砲塔(A・B・X・Y):三連装6インチ砲(艦首2基/艦尾2基)。・操舵室・艦橋/作戦室(Ops Room)/エンジンルーム:当時の装備を実物展示。・D-Day 砲撃体験展示:主砲塔内で発射音や指揮命令の再現。・塗装:第二次大戦期のアドミラルティ迷彩を再現。・係留場所:タワーブリッジ上流側、南岸(The Queen’s Walk) — ロンドン橋とタワーブリッジの中間付近。・HMS Belfast・ベルファストはタウン級で最大級の1隻で、戦後まで長く第一線で使われた。・ノースケープ海戦では、レーダー管制と照明弾(スターシェル)で敵を捕捉し、味方主力の 砲戦開始を助けたことで有名。南岸(Hay’s Galleria~Queen’s Walk)側から 北岸=シティ を望む〈上流=左/下流=右〉。左 → 右(手前=川沿い → 奥=高層群)1.Old Billingsgate(旧ビリングズゲイト市場) 川沿い左端のクリームイエロー色・アーチ窓の歴史建築。2.20 Fenchurch Street “Walkie-Talkie” 中央の“頭でっかち”なガラス高層。最上部に Sky Garden。3.22 Bishopsgate(Walkie の左後方) 背後にのぞく最も背の高い箱形のタワー。4.The Scalpel(52 Lime Street)(Walkie の右後方) 斜めに切り落としたような鋭い屋根線のタワー。5.(Scalpel の右)100/8 Bishopsgate いずれか 角ばった直方体の高層。このアングルでは 100 と 8 が重なりやすく、外装の陰影からは 100 Bishopsgate の可能性が高い。6.Custom House(税関) 川沿い右手の長い古典様式の白系ファサード(樹木の列の背後)。Hay’s Galleria(ヘイズ・ギャレリア)のアトリウム内にあったロンドン・ブリッジ・シティの季節イベント告知ボード。「LONDON BRIDGE CITYSUMMER by the RIVERGO WITH THE FLOWLose yourself in new experiences.Reconnect with friends. Feed your curiosity and your appetite.」 【ロンドン・ブリッジ・シティサマー・バイ・ザ・リバー流れに身をまかせて新しい体験にどっぷり浸ろう。友人たちと再びつながり、好奇心も食欲も満たそう。】Hay’s Galleria(ヘイズ・ギャレリア)のアトリウム内部。テムズ南岸、London Bridge と Tower Bridge の間にある複合施設で、19世紀の河岸倉庫Hay’s Wharf を再生して1980年代に開業 と。・頭上:鉄とガラスのアーチ屋根(再開発時に設置)。全天候型の回廊空間に。・両側:当時の煉瓦倉庫の外壁を残したオフィス/店舗フロア。・中央付近(植栽の奥):黒い船型の動く彫刻 “The Navigators”(David Kemp, 1987)が 置かれていた。・このアトリウムはイベント「Summer by the River」などの会場にもなるようだ。Hay’s Galleria(ヘイズ・ギャレリア)の中心にある、動く噴水彫刻「The Navigators(ザ・ナビゲーターズ)。・作者:デイヴィッド・ケンプ(David Kemp)・制作年:1987年 ・川を往来した商船や機械仕掛けの船を、魚の頭部や外輪、煙突、滑車や歯車の意匠で “スチームパンク”風に表現。・船首の魚(またはクジラ)型フィギュアヘッド、側面の外輪(パドル)、 多数の煙突/ホーン/舵輪。・作動時は噴水の水流や一部可動部が動く👈️リンク とのこと。クイーンズ・ウォーク沿い、HMS Belfast 周辺の案内板。「● YOU ARE HERE」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.03
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その96): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-11
そして「ミレニアム・ブリッジ (Millennium Bridge)」手前まで進む。・正式名称: London Millennium Footbridge・種類: 歩行者専用吊り橋・開通: 2000年(ロンドン・ミレニアムを記念して建設)・設計: サー・ノーマン・フォスター(建築家)、アラム(彫刻家)、アラップ社(構造設計)・構造: スリムで近未来的なデザインが特徴。ケーブルは低く張られていて、橋がまるで 空中に浮いているように見える。 南側(手前側) → テート・モダン (Tate Modern)、シェイクスピアズ・グローブ座へと。北側(対岸) → セント・ポール大聖堂 (St Paul’s Cathedral)へと。この吊橋の奥にも高層ビル群(シティ・オブ・ロンドンの金融街)が見えるのも特徴。長い列が出来ていたが、この時期「Anthony McCall: Solid Light」👈️リンク の展示会が6月29日までの予定で開催されていた。 ズームして。「McCALL」の文字が。 アンソニー・マッコール・Anthony McCallはイギリス生まれでニューヨークを拠点とするアーティストで、「ソリッドライト」インスタレーションで知られている と。再び「ミレニアム・ブリッジ (Millennium Bridge)」を。テムズ川に架かる鋼製の歩行者専用吊橋で、2000年に完成。開通当初は人々の歩行と共鳴して橋が揺れる「ウーブリー・ブリッジ (Wobbly Bridge)」として有名になったが、その後補強工事が行われ、現在は安定。奥に見える大きなドームはセント・ポール大聖堂 (St Paul's Cathedral) 。17世紀末、建築家クリストファー・レンによって設計され、ロンドンの象徴的なランドマークとなっている。北岸側 (City of London 側) にセント・ポール大聖堂があり、橋を渡るとその正面方向に続くように配置されていた。再びテート・モダン(Tate Modern)を。左手前にミレニアム・ブリッジの南端が見えた。ここから橋を渡ると、先ほどの写真のようにセント・ポール大聖堂に続く。右側の青い看板には「TATE PLAY」と書かれており、テート・モダンが行っているワークショップや体験型プログラムの案内サイン。再び高い黒い塔を見る。これは旧発電所時代の煙突(chimney)。建物中央にそびえ立ち、テート・モダンのシンボル的存在となっていた。高さは約99メートルあり、ロンドンのスカイラインの一部としてもよく目立つのであった。この行列は??行列の前には、「Cardinal Cap Alley(カーディナル・キャップ・アレイ)」 の案内が。「Cardinal Cap Alley(カーディナル・キャップ小路)」という小道の名前が。・Cardinal’s Cap(枢機卿の帽子) は、かつてこの地区にあったタヴァーン(居酒屋・酒場)の 名前から来ています。・サザーク地区(Southwark)は、シェイクスピア時代には芝居小屋・酒場・歓楽街として 知られたエリアで、多くの小路や建物に当時の名残があります。・この路地は、テムズ川沿い(Bankside)から奥へ続く狭い小道で、観光ツアーでもよく 紹介されるスポットのひとつ。ガイド付きツアーの一行が、この路地入口の説明を受けているようであった。テムズ川南岸にある 「シェイクスピアズ・グローブ座 (Shakespeare’s Globe Theatre)」。・円形に近い多角形の構造 16世紀末~17世紀初頭に存在したオリジナルのグローブ座を再現したもの。・白い漆喰の壁と木骨組み (ティンバーフレーム) チューダー様式を思わせる伝統的な造り。・藁葺き屋根 (thatch roof) ロンドン市内で許可された数少ない藁葺き建築のひとつで、当時の劇場の雰囲気を忠実に 再現。シェイクスピアズ・グローブ座(Shakespeare’s Globe Theatre) の外壁に掲示されている公演ポスター。左側のポスター・演目: Romeo and Juliet (ロミオとジュリエット)・作者: ウィリアム・シェイクスピア・内容: 永遠の悲恋を描いたシェイクスピア四大悲劇のひとつ。・評価コメント: “Immersive… highlights the attraction of youth”(没入感があり…若さの魅力を引き出している) “Hilarious, heartbreaking”(爆笑と胸を打つ感動)など・チケット: 6ポンドから(Globe Theatre Tickets from £6)右側のポスター・演目: The Crucible(『るつぼ』)・作者: アーサー・ミラー(Arthur Miller)・内容: 1690年代のセイラム魔女裁判を題材に、集団ヒステリーと政治的弾圧を描いた20世紀 アメリカ演劇の傑作。冷戦期の「赤狩り」にも通じる社会批評劇。・キャッチコピー: “Whose freedom will you sacrifice for your own?” (自分の自由のために、誰の自由を犠牲にしますか?)テムズ川に架かる サウスワーク橋(Southwark Bridge)。1921年に完成した鉄製アーチ橋で、橋脚が少なく、歩行者や車の交通量は比較的少なめの橋。緑と金色を基調とした装飾が特徴で、両側には小さな塔状の構造が見えた。背景にはシティ・オブ・ロンドンの金融街の高層ビル群が。セント・ポール大聖堂の直径約34mの大ドーム、そしてバロック様式の双塔を見る。サウスワーク橋 (Southwark Bridge) を振り返って。橋のアーチが低く広く設けられており、船舶の通行を考慮した構造?になっていた。手前の橋がキャノン・ストリート鉄道橋 (Cannon Street Railway Bridge)。鉄道専用の橋で、キャノン・ストリート駅に直結。橋脚の上に緑色の鉄骨構造があり、その上を鉄道が走る。・両端の塔(白い屋根付きの煉瓦の塔) これは キャノン・ストリート駅 (Cannon Street Station) の象徴的な塔。 1866年に建てられた初代駅舎の一部で、当時のヴィクトリア朝様式を残している。背景には高層ビル群(シティ・オブ・ロンドン)が。ロンドンの超高層ビル 「ザ・シャード (The Shard)」。・高さ: 約310m(95階建て)で、英国および西ヨーロッパで最も高いビル。・竣工: 2012年・設計: イタリア人建築家レンゾ・ピアノ(Renzo Piano)・形状: 「ガラスの破片(Shard of Glass)」をイメージした鋭角なデザイン。 上に行くほど細くなり、空へ突き刺さるようなシルエット。ロンドン・ブリッジ駅 (London Bridge Station) の真上に建ち、テムズ川南岸(サザーク地区)にそびえているのであった。移動してキャノン・ストリート鉄道橋 (Cannon Street Railway Bridge) を。鉄製アーチ橋・サウスワーク橋越しにセント・ポール大聖堂を。サザーク地区にある Clink Prison Museum(クリンク監獄博物館)の入口付近。レンガ造りの倉庫街の一角にあり、細い路地(Clink Street)に面していた。窓の大きな工場風の建物は、この地区がもともと河岸倉庫や工業施設だった名残を感じさせた。Clink Prison(クリンク監獄) は、12世紀頃から19世紀まで使用されていたイギリス最古級の牢獄の一つ。「Clink(カチャンという音)」という言葉は、ここに由来し「牢屋」を意味する俗語になった と。実際の監獄は既に失われているが、この博物館では中世から近世の刑罰や囚人生活を再現展示 と。Clink Prison Museum(クリンク監獄博物館) の入口外壁に取り付けられている装飾で、鉄製の檻(アイアンケージ)に入った骸骨の模型。これは「ギビット(Gibbet)」や「アイアンケージ」と呼ばれるもので、中世〜近世ヨーロッパで刑罰や見せしめとして使われた。死刑囚や重罪人の遺体を鉄製の檻に入れて街道沿いや橋の上に吊るし、人々への警告としたのだと。サザーク地区(Southwark)はかつて治安が悪く、監獄や処刑場が多くあった。Clink Prisonもその象徴であり、この檻はその歴史を伝える象徴的なディスプレイとなっていた。Clink Prison(クリンク監獄) を示す青い記念プレート(ブルー・プラーク風)。「London Borough of SouthwarkThe Clink 1144–1780Most notorious medieval prisonVoted by the People」 【サザーク区(ロンドン特別区)クリンク監獄(1144–1780)最も悪名高い中世の監獄人々の投票によって選出】博物館入口の看板赤と黒の文字で「Clink Prison Museum」と掲げられており、歴史的テーマパーク的な雰囲気。入口は監獄を思わせる格子デザインになっていた。Clink Prison(クリンク監獄) は、サザーク地区に存在した牢獄で、1144年から1780年まで使用された。宗教的な迫害、債務不履行、社会的逸脱などさまざまな理由で人々が投獄され、「ロンドンでもっとも悪名高い監獄」として恐れられた。「Clink」という言葉自体が「牢屋」を意味する俗語になったのも、この監獄が由来と。現在は実際の建物は残っておらず、代わりに「Clink Prison Museum」として歴史を伝える博物館が整備されていた。・赤い盾(シンボルマーク) 盾の上には 交差した鍵と鎖の意匠が描かれていた。 ・鍵:監獄を象徴 ・鎖:囚人拘束や刑罰を象徴 ・背景の黒い棒(槍や棍棒のように見える)も監獄の警備や処罰を示唆しています。・下部の白い看板(英文) "YOU ARE ENTERING THE ORIGINAL SITE OF THE CLINK — THE PRISON THAT GAVE ITS NAME TO ALL OTHERS" (あなたはいま「クリンク」の元の跡地に入ろうとしています ― 他のあらゆる牢獄にその名を 与えた監獄です)・入口の様子 鉄格子のゲートがあり、館内展示(拷問器具や囚人生活の再現)が始まる雰囲気を強調していた。 右側には「TICKETS OFFICE(チケット売場)」のサインも見えた。Clink Prison Museum(クリンク監獄博物館) の案内看板。「The Clink Prison London Bridge1144 – 1780Real History!PRISONERS THIS WAY →FREE PHOTO BEHIND BARS(鉄格子の後ろで無料写真撮影Educational and fun for all ages(教育的で全年齢が楽しめる)(拷問部屋を体験できる展示)(犯罪と刑罰の展示)」 クリンク監獄博物館 – 営業時間夏期(7月〜9月)毎日営業10:00 – 19:30冬期(10月〜6月)月曜〜金曜 10:00 – 18:00週末 10:00 – 19:30Winchester Palace(ウィンチェスター宮殿)の遺構の大きな石造の壁面。・大きな石造の壁面 ゴシック様式の3連窓と、その上に円形窓(バラ窓)が残っていた。 現在は外壁の一部だけが保存されていた。・バラ窓(Rose Window) かつての壮麗な大広間(Great Hall)の西壁にあった装飾窓。ガラスは失われていたが、 窓枠の石細工が遺構として残っていた。英文主要部分「Winchester PalaceThe Great HallThese walls are all that remain of the Great Hall of the powerful bishops of Winchester, one of the largest and most important buildings in medieval London.The hall was built in the early 13th century … (以下省略、一部読み取り)In the 14th century, the hall was extensively remodelled … a splendid rose window was added …The palace had many buildings including a prison, brewery and butchery …The palace remained in use until the 17th century, when it was divided into tenements, housing and warehouses.The ruins were rediscovered in the 19th century.【ウィンチェスター宮殿 ― 大広間(Great Hall)ここに残っているのは、かつて強大な権力を持っていたウィンチェスター司教の大宮殿の大広間の遺構であり、中世ロンドン最大級・最重要の建物のひとつでした。・建設: 13世紀初頭・改修: 14世紀に大規模な改装が行われ、壮麗なバラ窓が加えられました。・宮殿の施設: 牢獄、醸造所、屠殺場なども併設され、司教領の権威を示すものでした。・衰退: 17世紀に入ると使用されなくなり、住居や倉庫に分割されました。・再発見: 19世紀に遺構が再発見されました。】Winchester Palace Garden(ウィンチェスター宮殿ガーデン) の内部の様子。「BANKSIDE OPEN SPACES TRUSTWINCHESTER PALACE GARDENWINCHESTER PALACE GARDENThis shady sunken garden was created in 2014 by Bankside Open Spaces Trust,alongside local people, English Heritage, Schroders and Southwark Council.The garden is nestled in the remains of the undercroft of Palace of the Bishops of Winchester’s Great Hall. Many of the plants you see were popular in late medieval gardens …Winchester Palace is an English Heritage site. The garden is managed by Bankside Open Spaces Trust and our team of volunteers.BANKSIDE OPEN SPACES TRUSTBankside Open Spaces Trust is an environmental and volunteering charity working toprovide outstanding green spaces and outdoor activities that enhance the health and wellbeing of urban communities.We oversee and care for over 19 community spaces including: Red Cross Garden, Marlborough Sports Garden, Crossbones Graveyard, Tate Modern Community Garden and Waterloo Millennium Green.」 【ウィンチェスター宮殿ガーデンこの日陰の沈床庭園は2014年に Bankside Open Spaces Trust が地域住民、イングリッシュ・ヘリテッジ、シュローダー社、サザーク区議会と協力して整備しました。庭園は、かつてのウィンチェスター司教宮殿大広間(Great Hall)の地下部分の遺構に設けられています。ここに植えられている多くの植物は、中世末期の庭園で人気のあったもので、日陰の環境にも適しています。ウィンチェスター宮殿は English Heritage によって管理されている史跡で、この庭園は Bankside Open Spaces Trust とボランティアチームが維持管理を行っています。】廻り込んで、Winchester Palace(ウィンチェスター宮殿)Great Hall の遺構を再び。・バラ窓(Rose Window) 壁の上部に残る大きな円形窓。14世紀に増築された Great Hall(大広間) の装飾で、当時の 壮麗さを象徴しています。現在は石枠だけが残り、ガラスは失われていた。・3連窓(Lancet Windows) 壁の中段に3つ並ぶ尖頭アーチ型の窓(ゴシック様式)。この部分からも大広間の規模と格式が 想像された。・下部の石積みと庭園 先ほどの「Winchester Palace Garden」と同じく、遺構の足元は沈床庭園として整備され、 中世風の植物が植えられていた。現代的な木製プランターと遺構の対比が印象的。・左側の入口アーチ 石造りの出入口が残り、かつてこの建物が実際に利用されていた構造であることを物語っていた。Winchester Palace(ウィンチェスター宮殿)Great Hallの遺構を南側(通り側)から見た全景。・沈床庭園(Sunken Garden) 写真の手前には緑の植栽が整備されており、これは2014年にBankside Open Spaces Trust に よって作られた「Winchester Palace Garden」。 中世風の植物が植えられており、遺構と一体化した憩いの場になっていた。両脇には現代的な住宅やオフィスが並び、かつての宮殿跡が現代の街並みに埋め込まれるように保存されている様子がわかるのであった。帆船・The Golden Hinde(ゴールデン・ハインド号) の入場案内看板。テムズ川南岸(サザーク)に係留されている The Golden Hinde(ゴールデン・ハインド号) の復元船。横から。元のゴールデン・ハインド号は、エリザベス1世時代(16世紀)の探検家・私掠船船長サー・フランシス・ドレーク(Francis Drake) の旗艦。1577~1580年にかけて世界一周航海を成し遂げ、イギリス史上の偉大な航海として知られる。The Golden Hinde(ゴールデン・ハインド号)の復元船の航海中の姿をネットから。・実物は16世紀の帆船 サー・フランシス・ドレーク(Francis Drake)が1577–1580年の世界一周航海で使用した船。・特徴 ・全長:約37メートル ・排水量:約300トン ・武装:大砲18門程度を搭載 ・外装には当時のエリザベス朝風の装飾が施されている と。「The Legend of Mary OverieLegend suggests that before the construction of London Bridge in the tenth century, a ferry crossed here.Plying his trade across the River Thames was a ferryman named John Overs, who, with his wealth and apprentices, kept the Thames ferry.He made such a good living that he was able to acquire a large estate on the south bank of the river.John Overs, a notorious miser, devised a plan to save money. He would feign death, believing that his family and servants would mourn, fast, and thereby save food andprovisions.However, when he carried out his plan, his servants, far from grieving at his death, were so overjoyed that they broke into wild celebration.One of them leapt on his bed, to the horror of all, and struck his master dead.The ferryman’s distressed daughter Mary, lost in her sorrow, with no heart to enjoy the inheritance, fell from affluence and gave her wealth to the poor.Mary was so overcome with grief and misfortune that she devoted her inheritance to founding a convent instead of marrying.From this convent grew the priory church of St. Mary Overie, later known as St. Saviour’s, and finally becoming the present Southwark Cathedral.Thus, the memory of John Overs and, more especially, of his pious daughter Mary Overie,lives on in the stones of Southwark Cathedral.」【メアリー・オヴァリー伝説伝説によれば、10世紀にロンドン橋が建設される以前、この場所にはテムズ川を渡る渡し船がありました。その渡し船を営んでいたのが、ジョン・オヴァーズという船頭で、財を成し、多くの弟子や使用人を抱えてテムズ川の渡しを営んでいました。彼は大変裕福になり、川の南岸に大きな屋敷を構えるほどでした。ところがジョン・オヴァーズは悪名高い守銭奴で、金を節約するために奇妙な計画を立てました。すなわち、自分が死んだふりをすれば家族や使用人は悲しみ、断食して食糧を節約するだろうと考えたのです。しかし実際に計画を実行すると、使用人たちは悲しむどころか、彼の死を大いに喜び、狂喜して祝いました。そのうちの一人が寝台に飛び乗り、驚くべきことに主人を打ち殺してしまいました。船頭の娘メアリーは、深い悲しみに打ちひしがれ、財産を享受する気持ちを持てませんでした。彼女は裕福な身から転落し、富を貧しい人々に分け与えました。そしてあまりの悲しみと不運のために、結婚の道ではなく、相続財産を修道院の創建に捧げることを決意しました。この修道院から「聖メアリー・オヴァリー教会」が生まれ、後に「セント・セイヴィアーズ教会」となり、最終的には今日のサザーク大聖堂へと発展しました。かくしてジョン・オヴァーズ、そして何よりも敬虔なその娘メアリー・オヴァリーの記憶は、サザーク大聖堂の石に今も息づいています。】 このパネルは「史実の航海(1577–1580)」と「復元船の航海(1973年以降)」を対比しており、特に 20世紀に5度の世界一周を成し遂げた唯一の船 という点を強調していた。「THE GOLDEN HINDEWorld CircumnavigationsIn 1577 the Golden Hinde set sail from Plymouth. Commanded by Francis Drake, she became the first English ship to sail through the Strait of Magellan and into the Pacific. Drake raided Spanish ports and ships, and sailed as far north as present-day California. The Golden Hinde then crossed the Pacific, sailed around the Cape of Good Hope, and returned home in 1580, becoming the first English ship to circumnavigate the world.The replica reconstruction of the Golden Hinde was launched in April 1973. She successfully followed Drake’s route and has since completed several more world circumnavigations. Between 1979 and 1980, she sailed 30,000 miles to commemorate the 400th anniversary of Drake’s voyage. In 1980–81, she circumnavigated again, and in 1986–87 completedanother global voyage.The Golden Hinde has sailed across the Atlantic, Pacific, and Indian Oceans, and has visitedports in North America, Australia, Japan, and beyond. She is the only ship in the 20th century to have completed five world circumnavigations. Today she is permanently berthedat St. Mary Overie Dock in London, serving as a living museum and education centre.」【ゴールデン・ハインド号世界一周航海1577年、ゴールデン・ハインド号 はプリマスを出港しました。フランシス・ドレークの指揮のもと、この船は初めてマゼラン海峡を通過し太平洋へ入ったイギリス船となりました。ドレークはスペインの港や船を襲撃し、現在のカリフォルニアまで北上しました。その後、ゴールデン・ハインド号 は太平洋を横断し、喜望峰を回って1580年に帰国。イギリス船として初めて世界一周を達成しました。この船の復元レプリカは1973年4月に進水しました。復元船はドレークの航路をたどることに成功し、その後もさらに複数回の世界一周航海を行いました。1979〜1980年にはドレーク航海400周年を記念して3万マイルを航行。1980〜81年、さらに1986〜87年にも世界一周を成し遂げました。ゴールデン・ハインド号 は大西洋・太平洋・インド洋を航行し、北米、オーストラリア、日本などの港を訪れました。20世紀に5度の世界一周を果たした唯一の船です。現在はロンドンのセント・メアリー・オヴァリー船渠に恒久的に係留され、生きた博物館・教育センターとして公開されています。】 The Golden Hinde(ゴールデン・ハインド号) の船首部分。・船首にある 黄金の牝鹿(ハインド:雌ジカ)像 が船名の由来を象徴しています。 「Hinde(ハインド)」とは古い英語で「雌ジカ」を意味します。・黄金色に塗られた雌ジカが、まるで海を駆けるかのように取り付けられています。・船体は黒い木材に赤と黄色の斜めストライプの装飾が施され、16世紀エリザベス朝時代の 戦闘船らしい威厳を示しています。・この船は1577年に出港し、フランシス・ドレークの指揮で 初めて世界一周を果たした イギリス船 となりました(帰還は1580年)。「THE GOLDEN HINDE FUTURE」案内板とオーク材の切り株。この大きな切り株は、ロンドンに展示されている帆船 「ゴールデン・ハインド(The Golden Hinde)」 の修復用に準備されたオーク材である と。「The Golden Hinde FutureThis oak stump plays a small role in the major changes happening at The Golden Hinde.A skilled team of shipwrights is refitting the ship, using oak from naturally fallen trees. The large trunk and branches of this tree from East Grinstead were carefully milled forthe ship’s stem, beakhead, deck beams, knees, and pin rails. In the future, this very stump will also become part of the ship.You can donate here to help preserve the life of this rare example of Tudor seafaring heritage.」 【ゴールデン・ハインドの未来このオークの切り株は、ゴールデン・ハインドで進められている大きな変化の中で、小さな役割を果たしています。熟練の造船職人チームが、自然に倒れた木から採れたオーク材を使って船を修復しています。イースト・グリンステッド産のこの木の大きな幹や枝は、船首材、船首像(ビークヘッド)、甲板梁、船体補強材(ニー)、ピンレールとして丁寧に加工されました。将来的には、この切り株自体も船の一部になる予定です。ここで寄付することで、この稀少なチューダー時代の航海遺産の命を延ばすことができます。】テムズ川に架かる Cannon Street Railway Bridge(カノン・ストリート鉄道橋) と、その両端に残る 旧カノン・ストリート駅(Cannon Street Station)の塔を振り返って。ロンドンの金融街「シティ・オブ・ロンドン」の高層ビル群をテムズ川越しに見た景観。・右の大きなビル(曲面ビル) 20 Fenchurch Street(通称: Walkie Talkie ウォーキー・トーキー) ・2014年完成 ・最上階に「Sky Garden(スカイ・ガーデン)」があり、ロンドンの展望スポットとして人気。・中央の丸みを帯びたビル(卵型) 30 St Mary Axe(通称: The Gherkin ガーキン) ・2003年完成 ・ロンドンのランドマーク的存在。ノーマン・フォスター設計。・左奥の四角いガラス張りビル群 ・22 Bishopsgate(左端の一番高いビル) 2020年完成、278mの超高層ビル。現在ロンドンで最も高いオフィスビル。 ・その手前に見える斜めにカットされた外観のビルは The Scalpel(スカルペル, 52 Lime Street)。・川辺の白い古典的建物 Custom House(カスタム・ハウス) ・19世紀に建てられた関税局の建物。現在は改修計画中。・右端の橋 London Bridge(ロンドン橋) ・写真手前に一部が写っている灰色の橋。現在の橋は1973年完成。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.02
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その95): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-10
10月になりましたが、我が「アイルランド・ロンドンへの旅」のブログ・備忘録はまだまだ1ヶ月以上続きますので、ご笑覧ください。 再び、テムズ川から見たロンドンの典型的な景観。手前に川、その向こうに橋と都市のランドマークが広がっていた。左側・St Paul’s Cathedral(セント・ポール大聖堂) ・大きな白いドームと尖塔が目立ちます。 ・17世紀にクリストファー・レン卿が設計したロンドンの象徴的建築。中央手前(橋)・Blackfriars Bridge・ブラックフライアーズ橋 ・赤と白の鉄骨アーチが特徴的な橋。中央奥(橋)・Blackfriars Railway Bridge(ブラックフライアーズ鉄道橋) ・上を走るのはテムズ川を横断する鉄道路線で、Blackfriars駅のホームが橋上にある。右側(高層ビル群) ・一番右端、台形状のビルが20 Fenchurch Street(Walkie Talkie ビル)。右側(高層ビル群)をズームして。左から・Signature by Regus - London Tower 42(茶色のビル、183m)・22 Bishopsgate(ロンドンで最も高いオフィスビル、278m)・The Cheesegrater(Leadenhall Building)(三角形に傾いた形、225m)・The Scalpel(鋭い刃のようなシルエット、190m)Tate Modern(テート・モダン美術館) 付近、Bankside(バンクサイド) に設置されている歩行者用の地図案内。・この地図は 「Legible London(レジブル・ロンドン)」という街歩き用サインシステム の一部。・徒歩での移動時間を示しているのが特徴で、観光客が迷わず歩けるように工夫されています。・特にここでは テート・モダン、セント・ポール大聖堂、ロンドン・アイ といった観光名所に 徒歩で行ける距離感を強調。地図中央に "You are here"(現在地) と書かれており、テムズ川南岸の Bankside、Tate Modern のすぐそばであることが示されていた。この写真の看板はロンドンのテムズ川沿い、South Bank(サウスバンク)エリアにあった。「This is a residential area.Please respect our neighbours while enjoying this space.」 【ここは住宅地です。この場所を楽しむ際は、近隣住民への配慮をお願いします。】テムズ川北岸のランドマーク建築と橋を。中央奥の建物・Shell Mex House(シェル=メックス・ハウス) ・1930年代に建設されたアールデコ様式の大規模ビル。 ・正面中央上部に大きな時計があり「ビッグベンに次ぐロンドンで2番目に大きい時計」。 ・かつては石油会社 Shell-Mex and BP Ltd. の本社として使用された。手前の橋・Waterloo Bridge(ウォータールー橋) ・第二次世界大戦中に建設され、1942年に完成。 ・設計は Sir Giles Gilbert Scott(セント・ポール大聖堂の修復や赤い電話ボックスのデザイン でも知られる建築家)。テムズ川サウスバンクにある Oxo Tower(オクソ・タワー)。 Oxo Tower(オクソ・タワー) のタワー基部の入口と階段を。Oxo Tower(オクソ・タワー)・高さ約69mの塔部分デザイン・白いアールデコ調の塔に、縦に並んだ円形と菱形の窓が配置されていた。・窓の形で「OXO」の文字を表現しているのが最大の特徴。・上部には緑色の銅製の屋根(尖塔)が載っていた。現在は利用されていない?木製の桟橋。テムズ川から Blackfriars Railway Bridge(ブラックフライアーズ鉄道橋)越しに、背後のロンドン中心部を望んで。手前・Blackfriars Railway Bridge(ブラックフライアーズ鉄道橋) ・赤と白の鉄骨装飾を持つアーチ橋。 ・その奥には、Blackfriars 駅のプラットフォームが川をまたぐように造られていて、 列車が行き交うのであった。・St Paul’s Cathedral(セント・ポール大聖堂) ・17世紀にクリストファー・レン卿が設計した、ロンドンを象徴するバロック様式の大聖堂。 ・大ドーム(Great Dome) が中央に堂々とそびえていた。高さ約111m。 ・ドームの左右にある二つの尖塔は 西正面の双塔(West Towers) で、建物正面(西側)に 配置されていた。ズームして。ドームと西正面の塔がセットで見えており、まさにセント・ポールの特徴的なシルエット。テムズ川の北岸、Blackfriars Bridge(ブラックフライアーズ橋)付近の建物群を。左側(尖塔と緑色の屋根のある建物)・City of London School(旧校舎) ・1882年建設のヴィクトリア様式の建物。 ・黒い尖塔と、特徴的な緑青色の屋根。 ・元々はシティ・オブ・ロンドン・スクールの校舎であったが、現在は文化施設・イベント などに利用されていいる と。右側(大きな列柱のある白い建物)・Unilever House(ユニリーバ・ハウス) ・1930年代に建てられた本社ビルで、現在もユニリーバの拠点として使用。 ・古典主義的な大列柱のファサードが特徴。 ・2007〜2008年に改修され、現代的なオフィス機能を。テムズ川沿いのブラックフライアーズ橋への道路下の地下トンネル歩道にあった陶板タイルの壁画(歴史的風景画の再現)。描かれていたのは、・旧ブラックフライアーズ橋(Old Blackfriars Bridge) ・1769年に完成した最初のブラックフライアーズ橋を描いた図。 ・石造の多アーチ橋で、中央に大きなアーチ、両端に複数の小アーチを持っていた。 ・このデザインは当時の版画(18世紀の銅版画)をもとにしている と。・川の情景 ・橋の下を小舟や帆船が行き交い、川面には多くの人々の営みが描かれていた。 ・手前には川を眺める人物や荷物を運ぶ船なども見え、当時のテムズ川のにぎわいを 伝えていた。この壁画もテムズ川沿いの通路に設置されている陶板タイル絵 で、描かれているのは橋の建設風景。・石造アーチ橋の建設過程 ・巨大な木製の支保工(仮設の骨組み)を使い、石を積み上げてアーチを構築している様子。 ・川面に杭や足場を立て、石材を一つずつ積んでいる。 ・完成したアーチと、まだ工事中のアーチが並び、建設途中であることが強調されていた。・作業する人々 ・アーチ上や足場に職人や作業員が描かれている。 ・当時の工法がわかる貴重な記録画。・右端の帆船 ・材料の運搬に船が使われていたことを表現。 ・テムズ川が物流の動脈だった様子が伺えた。この壁画も、初代ブラックフライアーズ橋(1760年代建設、1769年完成) の工事風景。・巨大な木製の仮設構造(センタリング) ・アーチ橋を建設する際に、石が積み上がるまで支えるための木組みの骨組み。 ・完成後に外される一時的な構造物で、18世紀の橋梁建設の典型的な工法。・半完成の石造アーチ ・左側のアーチでは、すでに石材がある程度積み上げられている。 ・右側はまだ木組みの形が強調され、工事の進捗が対比的に示されていた。タイル壁画のキャプション部分。「PART OF THE BRIDGE AT BLACKFRIARSAS IT WAS IN JULY 1766Published by John Boydell, Cheapside」 【ブラックフライアーズの橋の一部1766年7月当時の姿チープサイドのジョン・ボイドル出版】・Blackfriars Bridge(ブラックフライアーズ橋)・最初の橋は1760年から建設され、1769年に完成。・設計者は ロバート・ミルン(Robert Mylne)。・このキャプションは、建設途中(1766年時点)の姿を描いた版画を元にした と。テムズ川から見たセント・ポール大聖堂と旧ブラックフライアーズ橋を描いた歴史的版画の再現。・中央奥:St Paul’s Cathedral(セント・ポール大聖堂) ・クリストファー・レン卿設計、1710年完成。 ・大きなドームと両脇の双塔が特徴的で、当時のロンドンのスカイラインを象徴していました。この陶板タイルの壁画は、19世紀後半のブラックフライアーズ橋周辺の光景を描いた版画の再現。壁画シリーズは、・1760年代:初代橋の建設途中(John Boydell)・1797年:完成後の景観(Thomas Malton)・1860年代:鉄道橋と駅の登場(Illustrated London News)と、時系列でロンドンの交通発展を描き出していた。2代目ブラックフライアーズ橋の開通を祝う行列の様子を描いた歴史的版画の再現。この陶板壁画はセント・ポール大聖堂を背景にしたブラックフライアーズ橋とテムズ川を描いた歴史的な版画の再現。Blackfriars Bridge(ブラックフライアーズ橋)は 2代目ブラックフライアーズ橋(1869年完成)を描いたと考えられると。現代のロンドンのテムズ川沿いのパノラマを描いたカラフルな都市風景画。近づいて。ブラックフライアーズ橋(Blackfriars Bridge) と、その隣に残されている 旧鉄道橋の橋脚跡。右側の赤い円筒状の構造物は、初代ブラックフライアーズ鉄道橋(1864年完成) の橋脚跡。鉄道需要拡大で橋自体は撤去されたが、橋脚だけが現在も川に残っているのだ と。隣接する新しい鉄道橋(現行のBlackfriars Railway Bridge)がすぐ横に架かっているのだ。テムズ川に架かるブラックフライアーズ橋下からロンドンの金融街(シティ・オブ・ロンドン)を望む風景。川面中央付近の細い歩道橋は ミレニアム・ブリッジ(Millennium Bridge)。2000年に開通した歩行者専用吊橋で、テート・モダンとセント・ポール大聖堂を結んでいる。その後方には、前述したロンドンの シティ地区の高層ビル群が。ズームして。右に目を移すと、セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)が。その前に広がる低層の灰色の建物群は シティ・オブ・ロンドン・スクール(City of London School) の校舎。ズームして。さらにドームをズームして。ブラックフライアーズ鉄道橋(Blackfriars Railway Bridge)を振り返って。この橋は石の橋脚と鉄製のアーチ構造を持ち、その上に ガラス張りの屋根 が長く続いています。この屋根は ブラックフライアーズ駅(Blackfriars Station) の一部で、テムズ川をまたぐ形で駅舎が広がっているのが大きな特徴。2012年に改修され、駅のホーム全体がテムズ川の上に広がる形となったのだと。上の屋根には太陽光パネルが設置されており、環境に配慮した「ソーラー駅」としても有名 と。「テムズ川を跨ぐ駅舎を持つ唯一の橋」、ブラックフライアーズ鉄道橋なのであった。One Blackfriars(ワン・ブラックフライアーズ) と呼ばれる超高層ビル。・愛称:「The Vase(花瓶)」とも呼ばれる独特の形状を持つ建物。・高さ:約 170m、50階建て。・竣工:2018年。・用途:高級住宅を中心に、ホテルやレストラン、商業施設が入っている。・設計者:建築家イアン・シンプソン(Ian Simpson)によるデザイン。テムズ川を下る 「Uber Boat by Thames Clippers」。・テムズ川を走る高速通勤・観光用のカタマラン型(双胴船)フェリー。 西は パットニー(Putney) から、東は ウーリッジ(Woolwich Arsenal) まで 全長約25kmにわたって停留所を持ち、観光地やビジネス街をつないでいる と。テムズ川を下る 「Uber Boat by Thames Clippers」を追う。テムズ川南岸にある 「BANKSIDE(バンクサイド)」の観光案内マップ。バンクサイドとは、テムズ川南岸、ロンドン橋(London Bridge)とブラックフライアーズ橋(Blackfriars Bridge)の間に広がる地域。歴史的には劇場・倉庫・造船所が多かったエリアで、現在は文化・芸術・観光の拠点に再開発されているのだ と。中央の大ドームはセント・ポール大聖堂 (St Paul’s Cathedral)。クリストファー・レン卿による設計(完成1708年)。ロンドン大火(1666)の後に建てられたバロック建築の傑作。左の双塔は大聖堂西正面の鐘楼。左右対称に建てられており、教会正面の特徴的なシルエットを形成。手前の赤レンガ建物群はテムズ川沿いのバンクサイド(Bankside)エリアの施設。テート・モダンの近くにあり、川沿い散策でよく目にする建物。Uber Boat by Thames Clippers と違い、この「London Eye River Cruise」は観光解説付き・周遊型 で、通勤や移動のための定期便ではない と。テムズ川南岸の名所 テート・モダン (Tate Modern) の 煙突タワー。・高さ 99メートル のレンガ造り。・発電所時代の象徴をそのまま残しており、テート・モダンのランドマーク的存在。・上部は展望フロア「Blavatnik Building(新館)」とつながり、テムズ川や セント・ポール大聖堂を望む絶景スポットになっている と。この建物は元は火力発電所(Bankside Power Station)・設計者はサー・ジャイルズ・ギルバート・スコット(赤電話ボックスのデザインでも有名)。・1947年から1981年まで稼働していた発電所。現在は美術館・2000年に現代美術館「テート・モダン」としてリニューアルオープン。・ロンドンでも人気観光スポットのひとつで、ピカソ、ダリ、ウォーホル、草間彌生などの 作品を収蔵。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.01
コメント(0)
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-
-

- アメリカ ミシガン州の生活
- いよいよ日本へ本帰国
- (2025-01-11 13:13:28)
-
-
-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印
- 周防國・長門國一ノ宮巡りday1(錦帯…
- (2025-11-18 00:00:11)
-
-
-

- 中国&台湾
- 亡父の故郷•長春に行ってまいりまし…
- (2025-09-19 17:17:04)
-







