2025年09月の記事
全34件 (34件中 1-34件目)
1
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その94): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-9
さらにテムズ川の右岸を下流に向かって進む。テムズ川のサウスバンク側から見上げた Hungerford Bridge(ハンガーフォード鉄道橋)と Golden Jubilee Bridges(ゴールデン・ジュビリー歩行者橋)。テムズ川北岸にある Savoy Pier(サヴォイ・ピア) に停泊している観光船を見る。サウスバンク・センター(Southbank Centre) に設置されていたアート作品。・鮮やかな赤色の金属製ベンチ。 座面と背もたれが大きく波打つようにカーブし、通常の「直線的なベンチ」の概念を崩している。 部分的に座ることはできるものの、姿勢は不安定になり、遊具のように体験的な要素が強い。こちらは、・真っ赤な金属フレームで作られた「円環型のベンチ」。・通常のベンチが途中で丸く曲がり、そのまま「ループ」になったようなデザイン。・内側に座ることはできますが、かなり不思議な体験になる仕掛け。・作品名 Modified Social Bench NY #10・作者 Jeppe Hein(イェッペ・ハイン) デンマーク出身の現代美術家(1974年生まれ) インタラクティブな彫刻や体験型の公共アートで知られる・制作年 2015年・素材 粉体塗装されたアルミニウム(Powder-coated aluminium)サウスバンク・センター(Southbank Centre)の前にある有名な黄色い階段(Yellow Staircase)。・鮮やかな黄色に塗られた外階段。・直線的な上り階段の上に、特徴的なスパイラル状の踊り場が設けられていた。・コンクリート造の「ブリュタリズム建築(Brutalist architecture)」のSouthbank Centreに、 強烈なアクセントを与える存在。背景の建物はSouthbank Centreの一部である Queen Elizabeth Hall。サウスバンク・センターの建物(クイーン・エリザベス・ホール周辺)の壁から突き出しているステンレス製の曲がったパイプ状オブジェ。作者はデンマークの現代美術家 Jeppe Hein(イェッペ・ハイン)。作品シリーズの一部で、タイトルは 「Appearing Rooms」や「Modified Social Benches」と同じ公共アート群。テムズ川サウスバンクにある Festival Pier(フェスティバル・ピア)の入口。・ロンドンの水上交通網「Thames Clippers(Uber Boat by Thames Clippers)」の 停泊所のひとつ。・観光クルーズ(City Cruisesなど)やチャーター船の発着にも利用される。・青いゲートとチューブ・ラウンドル(ロンドン交通局の円形マーク)+ボートアイコンが特徴。・入口を通って桟橋に下り、浮桟橋から船に乗り込む。テムズ川に架かる ウォータールー橋(Waterloo Bridge)が前方に。・テムズ川のサウスバンク(South Bank)とノースバンク(Strand側)を結ぶ主要橋。・南岸側はサウスバンク・センター、北岸側はSomerset House(サマセット・ハウス)付近。ズームして。・アーチ型のコンクリート橋。・現在の橋は第二次世界大戦中に建設され、1945年に完成。・戦時中の労働力不足から、建設には多くの女性労働者も従事し、 「Ladies’ Bridge(女性たちの橋)」という愛称でも知られる と。テムズ川沿い(サウスバンクやヴィクトリア・エンバンクメントなど)でよく見られた 「Dolphin Lamp Posts(イルカ街灯)」。ネットから。街灯の柱の基部に、3匹のイルカ(実際は神話的な魚=「スタイライズされたイルカ」)が絡みつくように配置。・頂部にランプが設置されている。・鋳鉄製で黒塗り、装飾的なビクトリア朝スタイル。ロンドンの遊歩道に埋め込まれている 「Jubilee Greenway(ジュビリー・グリーンウェイ)」 の路面プレート。Jubilee Greenway とは・概要 ・ロンドンに整備された長距離ウォーキング&サイクリングルート。 ・総延長は 60km(37マイル)。 ・2012年、エリザベス2世の在位60周年(ダイヤモンド・ジュビリー)とロンドン五輪開催を 記念して開設された。・ルートの特徴 ・ロンドンの主要な観光名所や公園をつなぐ「環状ルート」。 ・テムズ川沿いのサウスバンク、グリニッジ、オリンピックパーク、ハイドパーク、 ケンジントンガーデンズなどを通る。 ・「The Queen’s Walk(サウスバンク遊歩道)」もその一部。・シンボル ・路面に埋め込まれた緑色のプレートが目印。 ・月桂樹の輪の中に、王冠とドーム型建築(ロンドンのセントポール大聖堂を象徴)が 描かれていた。サウスバンクのナショナル・シアター(National Theatre)前 にある彫刻「London Pride(ロンドン・プライド)」「LONDON PRIDEFRANK DOBSON CBE RA1886–1963Commissioned forTHE FESTIVAL OF BRITAIN 1951GIVEN BY MARY DOBSON 1987AND PLACED ON THE SOUTH BANKAssisted generously by Lynton Property & Reversionary Plc andThe Henry Moore FoundationARTS COUNCIL OF GREAT BRITAIN」【ロンドン・プライドフランク・ドブソン CBE RA (1886–1963)1951年「英国フェスティバル」のために制作。1987年、メアリー・ドブソンにより寄贈され、サウスバンクに設置された。Lynton Property & Reversionary社およびヘンリー・ムーア財団の協力を得た。英国芸術評議会。】 概要・作品名:London Pride・作者:フランク・ドブソン(Frank Dobson, 1886–1963)・制作年:1951年(1951年の「Festival of Britain(英国フェスティバル)」のために委嘱)・素材:ブロンズ像造形・2人の裸婦像が向かい合って座っている構成。・ふっくらとした量感を持つ女性像は、ドブソンが好んだ有機的で人間的なスタイルの典型。・近代的かつ古典的な均整を意識した造形で、「都市と人間の生命力」を象徴しているとも 解釈されます。ローレンス・オリヴィエ像(Statue of Laurence Olivier)。・人物: サー・ローレンス・オリヴィエ(Laurence Olivier, 1907–1989) 20世紀を代表する英国の俳優であり、映画監督。シェイクスピア劇の舞台と映画で特に有名。・場所 ロンドンの ナショナル・シアター(National Theatre) 前、サウスバンクに設置。・・建立年: 2007年(彼の生誕100周年を記念して設置)・デザイン: 彫刻家アンジェラ・コナートン(Angela Conner)による作品。 オリヴィエはシェイクスピア劇「ハムレット」の姿で、手に剣を掲げて立っている。・意味: ナショナル・シアターの初代芸術監督(1963–1973)としての功績を称えている。 彼はナショナル・シアターの設立に尽力し、イギリスの舞台芸術を国際的に発展させた中心人物。「LAURENCE OLIVIER O.M.ACTOR1907 – 1989Baron Olivier of BrightonFounding Director of the National Theatre1963–1973More than two hundred, mainly theatre and film people and institutions, contributed to the Laurence Olivier Centenary Statue Appeal made by his son Tarquin, who said –“Larry was finite.He was exciting, prodigious, funny,and is still part of what makes life worth living.So is his creation the National Theatre.”The principal contributors were –Individuals:Lord Attenborough CBE, Dave Clark, Dame Judi Dench CH, Mrs Laurence Evans,Ronald Falk, Albert Finney, William Goldman, Paulo and Katharina Guidi, Sir Anthony Hopkins CBE, Bill Kenwright, Professor Terry Knapp, Mark Knopfler, Sir Ian McKellen CBE, Michael Moore CBE, Paul Newman, Zélia and Tarquin Olivier,Geoffrey Palmer OBE, Lord Palumbo, Dame Joan Plowright CBE, Lady Jane Rayne, Hon. Robert Rayne, the Redgrave Family, Cliff Richard, Lord Rothschild O.M. GBE, Jean Simmons OBE, Dame Maggie Smith, Elizabeth Sutter, Liz Villiers, Ken Ward, and the people of Dorking where Olivier was born.Institutions:The Garrick Club, the Central School of Speech and Drama, National Theatre Foundation, Cameron Mackintosh Foundation, Equity, ITV, Noel Coward Estate, Shepperton and Pinewood Studios, the Spotlight, West End Theatre Managers, the British Film Institute, Southbank Centre, and Granada Ventures (who also gave permission to use the image ofHamlet taken from his 1948 film to which they have the performing rights).This statue was unveiled on 23rd September 2007,by Richard Attenborough and members of the original company.」 【ローレンス・オリヴィエ O.M.俳優1907–1989ブライトンのオリヴィエ男爵ナショナル・シアター初代芸術監督1963–1973「ラリー(オリヴィエ)は唯一無二だった。彼は刺激的で、途方もなく多才で、ユーモラスで、そして今も人生を生きる価値あるものにしている存在だ。彼の創造物 ― ナショナル・シアター ― もまた同じである。主な寄贈者:個人リチャード・アッテンボロー卿、デイヴ・クラーク、ジュディ・デンチ女史、ローレンス・エヴァンズ夫人、ロナルド・フォーク、アルバート・フィニー、ウィリアム・ゴールドマン、パウロ&カタリーナ・グイディ、アンソニー・ホプキンス卿、ビル・ケンライト、テリー・ナップ教授、マーク・ノップラー、イアン・マッケラン卿、マイケル・ムーア卿、ポール・ニューマン、ゼリア&タークィン・オリヴィエ、ジェフリー・パーマー卿、パルンボ卿、ジョーン・プロウライト女史、ジェーン・レイン夫人、ロバート・レイン卿、レッドグレイヴ一家、クリフ・リチャード、ロスチャイルド卿、ジーン・シモンズ女史、マギー・スミス女史、エリザベス・サッター、リズ・ヴィリエ、ケン・ウォード、そしてオリヴィエの生まれ故郷ドーキングの人々。団体・機関ギャリック・クラブ、王立演劇学校、ナショナル・シアター財団、キャメロン・マッキントッシュ財団、演劇組合 Equity、ITV、ノエル・カワード財団、シェパートン&パインウッド撮影所、スポットライト、ウエストエンド劇場経営者協会、英国映画協会(BFI)、サウスバンク・センター、グラナダ・ヴェンチャーズ(1948年映画『ハムレット』のオリヴィエの映像使用権提供)。この像は2007年9月23日、リチャード・アッテンボロー卿とオリジナル・カンパニーのメンバーによって除幕された。】「ナショナル・シアター(National Theatre)」。・所在地: テムズ川右岸(サウスバンクエリア)、ウォータールー橋とサウスバンク・センターの 間に位置。・建築様式: 1976年竣工、建築家 デニス・ラスダン(Sir Denys Lasdun) 設計による コンクリート造の代表的な ブリュタリズム建築。・特徴: 幾何学的で重厚な打ち放しコンクリートの構造が特徴で、しばしば賛否が分かれる 建築ですが、20世紀イギリス建築の象徴的存在です。ナショナル・シアターは3つの主要劇場を持ちます:・オリヴィエ劇場(Olivier Theatre) – 1,150席。古代ギリシャ劇場に着想を得た円形劇場形式。・リトルトン劇場(Lyttelton Theatre) – 890席。プロセニアム型。・ドーフマン劇場(Dorfman Theatre、旧Cottesloe Theatre) – 400席の小劇場、 柔軟な舞台構成が可能。ローレンス・オリヴィエ像(1989没)は、彼がナショナル・シアターの 初代芸術監督(1963–1973) を務めたことを記念して建てられた。像はこの建物のすぐそばに置かれており、彼の功績を讃えているのだ と。これも ナショナル・シアター(National Theatre, NT) の建物。背後の建物は、ナショナル・シアターの リトルトン劇場(Lyttelton Theatre)が入る部分。ここにも、South Bank London(サウスバンク・ロンドン) の観光案内板が。左側のパネル・上部に「EXPLORE SOUTH BANK(サウスバンクを探訪)」と書かれていて、地図が表示。・テムズ川右岸(南岸)に沿って、主要なランドマークが描かれています。 ・Royal Festival Hall ・National Theatre ・Southbank Centre ・BFI Southbank ・Oxo Tower ・Gabriel’s Wharf など。・観光客向けに散策ルートや食事・文化施設の位置がひと目でわかるようになっていた。右側のパネル・「DINE IN STYLE(おしゃれに食事を)」という宣伝パネルで、サウスバンク周辺の レストランや飲食店街を紹介するものです。・「DISHES AFTER THE SHOW」とあることから、劇場(ナショナル・シアターや サウスバンク・センター)で観劇した後に立ち寄れる飲食エリアを推していることが分かります。サウスバンク(South Bank, London)観光マップを再び。テムズ川の対岸(北岸)にある セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)。・設計者は クリストファー・レン卿(Sir Christopher Wren)。・1710年に完成したロンドンを代表するバロック様式の大聖堂。・巨大なドームはロンドンの象徴的シルエットで、高さ約111m。・ナポレオン戦争勝利の感謝礼拝や、チャーチル首相の国葬、チャールズ皇太子とダイアナ妃の 結婚式などが行われました。サウスバンク(South Bank)の遊歩道沿いにある木製の彫刻ベンチ。・大きな木材を丸ごと削り出して作られたアートベンチ。・曲線的なデザインで、龍や魚、波など自然モチーフを思わせる形状。・側面には文字が刻まれていた。「THE THAMES WILL CARRY HER SONS FOREVERBRUNO • CONRAD • MAX1991/2 – 2011」 【テムズ川は永遠に彼女の息子たちを運ぶだろうブルーノ・コンラッド・マックス1991/2 – 2011】・これは メモリアル・ベンチ(追悼のためのベンチ) と考えられます。・「Bruno, Conrad, Max」は恐らく若くして亡くなった人々(兄弟または友人たち)の名前。・年号「1991/2 – 2011」は彼らの生没年を示している可能性が高く、10代~20歳前後で 亡くなったことを意味しているようです。・「テムズ川が彼らを永遠に運ぶ」という表現は、川を魂の安息・記憶の象徴として いた詩的な追悼文。サウスバンク(テムズ川南岸)の遊歩道に設置された 展望案内板 。対岸(シティ・オブ・ロンドン側)の建物やランドマークを図と共に示していた。上記のパネルと同じ方向の写真を。ロンドン・ウォータールー橋(Waterloo Bridge)から見たテムズ川北岸の建物案内プレート上記のパネルと同じ方向の写真を。テムズ川のサウスバンク(South Bank)遊歩道に設置されていた 巨大なティーカップのパブリックアート(ベンチ兼オブジェ)。・デザイン ・傾けられたティーカップから液体(紅茶・コーヒーのようなもの)が流れ出し、その流れが 固まってベンチのように座れる形になっています。 ・カップの外側には青い花模様が描かれており、イギリスの伝統的な陶磁器 (ブルー&ホワイトの食器デザイン)を思わせる意匠。テムズ川沿いにはこのような遊び心あるアート作品が点在しており、街歩きやイベントの一環として楽しめる仕掛けになっているのであった。ロンドンのテムズ川南岸(South Bank)にある高層建築群。左端(緑の尖塔付き時計塔) ・Oxo Tower(オクソ・タワー) ・1920年代に建てられたアールデコ様式の建物。 ・タワーに「OXO」の文字窓があり、現在はアートギャラリーやレストランが入っています。 ・サウスバンクのシンボルのひとつ。中央(ガラス張りでカーブした近代的ビル) ・One Blackfriars(ワン・ブラックフライアーズ) ・ニックネームは The Vase(花瓶) または The Boomerang(ブーメラン)。 ・2018年竣工の高級集合住宅タワー(高さ約170m)。 ・そのユニークな流線型デザインが目を引きます。・右端(四角い縦ラインが強調された高層ビル) ・South Bank Tower(サウスバンク・タワー) ・1972年竣工、当初はオフィスビル「King’s Reach Tower」として使用。 ・近年リノベーションされ、住宅やオフィスが入る高層複合施設(高さ約111m)。この3つが並ぶことで、サウスバンクの「古典×近代×現代」建築のコントラスト を象徴する風景になっているのであった。ユニークな パブリックアート(体験型アートベンチ/ブランコ)。・巨大な 「😂(涙を流して笑う顔)」の絵文字 が立体化され、厚みのある円盤状の造形に なっていた。・上部からチェーンで吊るされており、まるで 「スイング(ブランコ)」 のように揺れる仕掛け。・背面側は椅子のようにえぐられていて、そこに座って写真を撮れるデザイン。・全体が鮮やかな 水色と黄色のコントラスト で、観光者にフォトスポットとして人気が出るよう 工夫されているのであった。テムズ川越しに見た ロンドン金融街「シティ・オブ・ロンドン(City of London)」の高層ビル群。右側(個性的な外観の高層ビル)・20 Fenchurch Street(通称: Walkie Talkie / トランシーバー・ビル) ・右端にある、上部が広がったユニークな形のビル(2014年竣工、160m)。 ・最上階は「Sky Garden(スカイガーデン)」として展望施設になっています。・中央やや右 ・The Scalpel(スカルペル、52 Lime Street) ・尖った刃のような形。2018年完成。・122 Leadenhall Street(通称: The Cheesegrater / チーズおろし) ・三角に傾斜した形の高層ビル(2014年竣工、225m)。中央やや左・22 Bishopsgate ・最も高い四角いビル。2020年完成、278mで現在ロンドンで一番高いオフィスビル。・The Gherkin(ガーキン、30 St Mary Axe) ・写真のビル群の中ほど、やや低いドーム状のガラス張りビル(2003年竣工、180m)。 ・背景に重なって見えにくいですが、この方向から確認可能。・前景 ・Blackfriars Railway Bridge(ブラックフライアーズ鉄道橋) ・赤と白の鉄骨装飾が見える橋。 ・上はテムズ川を渡る鉄道路線(Blackfriars駅を通る)。ズームして。左側にのセント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)を入れて。サウスバンクの遊歩道に展開されている 一連のパブリックアート展示/イベントインスタレーションなのであった。この展示は WhatsApp(ワッツアップ)による体験型プロモーション・インスタレーション。「Imagine you shrank and walked inside a WhatsApp Chat.It would be just like this!Yep, and just like it is on your phone, everything in this chat is private.Legit no one, not even WhatsApp, can see your personal messages.」 【もしあなたが小さくなって WhatsApp のチャットの中を歩いたらどうなるでしょう?まさにこんな感じです!そう、スマホ上と同じように、このチャットのすべてはプライベート。本当に、WhatsApp でさえも、あなたの個人的なメッセージを見ることはできません。】これは 「WhatsApp Chatの中に入る」体験型インスタレーション で、サウスバンクに設置された WhatsApp公式の広告・PRイベント展示のようであった。テムズ川を泳ぐ犬を発見。テムズ川で泳ぎながらボトルをくわえて。犬種はラブラドール・レトリーバーやその近縁種に見えたが。テムズ川の環境保全のボランティア活動中??なのであろうか。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.30
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その93): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-8
「ロンドン・アイ(London Eye)を真下から見上げて。・中央の白い巨大な支柱 ロンドン・アイを支える主軸部分。観覧車の片側から斜めに支えが伸びる「片持ち式構造 (カンチレバー式)」になっているのが特徴。・放射状のワイヤー(ケーブル) 自転車の車輪のスポークのように張られており、リム(外周の観覧車部分)を安定させて います。 → ロンドン・アイは世界最大級の「スポークホイール型観覧車」として有名。・外周のゴンドラ 上部に沿ってガラスカプセルが連なっているのが見えた。・ロンドン・アイは片側支持方式(片持ち構造)で支えられており、観覧車全体を一方の支柱から 引っ張る形。・スポーク(鋼鉄ケーブル)は片側から張られているため、巨大な自転車のホイールのような 美しいデザインが強調されている。「ロンドン・アイ(London Eye)の搭乗ゲート付近には長い列が。移動して「ロンドン・アイ(London Eye)」を真下から再び見上げて。・中央の支柱とハブ(回転軸) ロンドン・アイは片持ち式(カンチレバー構造)で支えられており、片側から巨大な支柱が 伸びています。写真の中央に見える「円筒部分」が回転の中心軸。・放射状のケーブル(スポーク) 自転車の車輪のように外周へ放射状に張られたケーブル。 これがリム部分を支え、観覧車の安定性を保っている と。「ロンドン・アイ(London Eye)」の搭乗エリアのすぐ横にある「London Eye Pier(ロンドン・アイ桟橋)」の入口 を見る。・中央の青い案内板 「Boat Ticket Sales & Pier Entrance」と書かれており、ここが テムズ川クルーズ船の桟橋入口。・ロンドン・アイ・ピア(London Eye Pier) ・位置: ロンドン・アイの直下、テムズ川沿い。 ・運営: Uber Boat by Thames Clippers(高速船サービス)。 ・利用: ・観光用のリバークルーズ ・通勤通学向けの定期船(東はグリニッジ、西はパットニー方面まで) ・特徴: 観覧車を楽しんだ後に、そのまま川からロンドンを眺める観光ルートとして人気。テムズ川越しに「ホワイトホール・コート(Whitehall Court)」を望む.・建設: 1884年・様式: フレンチ・シャトー風のヴィクトリア朝建築・現在は「ロイヤル・ホースガーズ・ホテル(The Royal Horseguards Hotel)」や 高級マンションとして使用されている と。ズームして。「Knife Edge Two Piece(ナイフ・エッジ・ツーピース)」 という抽象彫刻。・作者: ヘンリー・ムーア(Henry Moore, 1898–1986) 20世紀を代表するイギリスの彫刻家。人体をモチーフにした抽象作品で知られます。・作品名: Knife Edge Two Piece(ナイフ・エッジ・ツーピース)・制作年: 1962–65年頃・材質: ブロンズ・設置場所: ロンドン・アイやカウンティ・ホール近くのサウスバンク遊歩道「JUBILEE ORACLEBY ALEXANDER 1980Mankind is capable of an awarenessthat is beyond the limits of everyday life.My monumental sculptures are createdto communicate with that awarenessin a way similar to classical music.Just as most symphonies are not meantto be descriptive, so these works do notrepresent figures or objects.— Alexander」 【ジュビリー・オラクルアレクサンダー作 1980年人類は、日常生活の範囲を超えた「気づき(意識)」を持つことができる。私のモニュメンタル・スカルプチャー(大規模な彫刻)は、その気づきと対話するために創られたものである。それはクラシック音楽と同じような方法で行われる。ほとんどの交響曲が写実的に何かを描写するためのものではないように、これらの作品も人物や物体を表すものではない。— アレクサンダー】ロンドン・アイ(London Eye)とウェストミンスター宮殿(国会議事堂)、ビッグ・ベン(エリザベスタワー) を同時に捉えて。前方に現れたのが 「ゴールデン・ジュビリー・ブリッジ(Golden Jubilee Bridges)」。・種類: 歩行者専用の吊り橋(ツインブリッジ)・完成: 2002年(エリザベス女王在位50周年「ゴールデン・ジュビリー」を記念して建設)・場所: ・中央にある鉄道橋 「ハンガーフォード橋(Hungerford Bridge)」 を挟 む形で両側に架けられた歩道橋。 ・テムズ川を渡り、サウスバンク(ロンドン・アイやカウンティ・ホール 側)とノースバンク(チャリング・クロス駅付近)を結んでいる。テムズ川越しに ウェストミンスター宮殿(国会議事堂)とビッグ・ベン(エリザベス・タワー) を望んだ風景で、手前に写っているのは 「Westminster Pier(ウェストミンスター桟橋)」。ピア(Pier)とは桟橋・船着、ロンドン中心部観光(国会議事堂・ロンドン・アイなど)と結びついた交通拠点となっていると。その先にあったのが、Hungerford Bridge(ハンガーフォード橋)と、その両側に付設された Golden Jubilee Bridges(ゴールデン・ジュビリー・ブリッジ:歩行者橋)。・中央の黒い鉄橋部分 これは鉄道橋 Hungerford Bridge で、南側の Waterloo Station(ウォータールー駅) と北側の Charing Cross Station(チャリング・クロス駅) を結んでいる。 1845年に最初の橋が完成し、鉄道用として現在も使われている。・両側の白い斜張構造の歩道橋 これは Golden Jubilee Bridges(ゴールデン・ジュビリー橋) で、2002年に完成した。 名前はエリザベス2世即位50周年を記念したもの。両側に人専用の通路があり、テムズ川を 歩いて渡りながらロンドンの景観を楽しめるのだ。・奥に見える大きな建物(アーチ型のガラス屋根) これは Charing Cross Station(チャリング・クロス駅) の駅舎。鉄道がこの橋を渡って この駅舎へと。ズームして。・白い斜張構造(ケーブルと支柱) これは Golden Jubilee Bridge(ゴールデン・ジュビリー橋) の支柱部分。 両側に歩行者専用の橋があり、テムズ川の眺めを楽しみながら渡ることができる。・奥の赤茶色のアーチを持つ建物風構造物 これは Hungerford Railway Bridge(ハンガーフォード鉄道橋)の橋脚にある装飾的な 塔状の建築。 19世紀のレンガ造構造が残されており、橋の近代的な補強と組み合わせられているようだ。Charing Cross Station(チャリング・クロス駅) を正面から。・中央の大きなアーチ型のガラス屋根 これは Embankment Place(エンバンクメント・プレイス) と呼ばれる駅上部の オフィスビル(1991年完成)。特徴的な半円形ガラスファサードが駅舎の目印になっている。・駅(Charing Cross Station) 19世紀に開業したロンドン中心部のターミナル駅のひとつ。南東イングランド方面 (ケント州など)へ向かう列車の発着駅。 この駅舎に接続しているのが先ほどの Hungerford Railway Bridge(鉄道橋)。壮麗な白い建物は、ロンドンのテムズ川北岸にある Royal Horseguards Hotel(ロイヤル・ホースガーズ・ホテル)とその周辺の建物群。尖塔(タワー)や切妻屋根が並ぶ姿は、まるでフランスの古城のような雰囲気。19世紀後半(1880年代頃)建設されたと。テムズ川サウスバンク(South Bank)、Westminster Pierから歩いてすぐの場所にあったのがクラシックなメリーゴーラウンド(Carousel)。きらびやかな装飾と照明、そしてカラフルに塗装された木馬が並ぶ典型的なイギリス伝統の回転木馬。テムズ川サウスバンクにある屋外フード&ドリンク会場 「Between the Bridges」 の入口とバーエリア。ロンドン中心部、ウォータールー橋(Waterloo Bridge)〜ブラックフライアーズ橋(Blackfriars Bridge)あたりを中心とする南岸の一帯を特に「サウスバンク」と呼ぶのだと。Southbank Centre(サウスバンク・センター) に設置されているイベント告知看板。・イベント名: New Music Biennial(ニュー・ミュージック・ビエンナーレ)・開催日程: 2025年7月4日(金)〜7月6日(日)・内容: Discover the UK’s Best New Music (イギリスで生まれる最高の新しい音楽を発見しよう) → UKの新進気鋭の作曲家やアーティストによる現代音楽・実験音楽などを紹介する音楽祭です。・会場: Southbank Centre(サウスバンク・センター) (ロンドンのテムズ川南岸にある大規模な芸術複合施設)サウスバンク(South Bank)の案内。場所はちょうど Golden Jubilee Bridge(ゴールデン・ジュビリー橋)南側の階段付近。Golden Jubilee Bridges(ゴールデン・ジュビリー橋) への石段があった。Golden Jubilee Bridges(ゴールデン・ジュビリー橋:歩行者専用橋)をテムズ川の川岸から。Golden Jubilee Bridge(ゴールデン・ジュビリー橋) の歩行者通路上から。ズームして。Hungerford Bridge(ハンガーフォード鉄道橋)の南端付近は工事中であった。鉄道橋部分が、鉄骨や橋桁が足場に囲まれていた。テムズ川南岸(South Bank)の遊歩道から 国会議事堂(Houses of Parliament)とビッグベン(Elizabeth Tower) を望んで。Hungerford Bridge(ハンガーフォード鉄道橋)+ Golden Jubilee Bridges(歩行者橋) の橋脚部分をアップで。・中央の赤レンガと石の装飾アーチ → これは Hungerford Bridge(鉄道橋)の橋脚に設けられた塔状の装飾構造物。 19世紀の橋の基礎部分が残されており、鉄道橋の歴史的デザインの一部 と。テムズ川越しに見た 英国国会議事堂(Palace of Westminster) と ビッグベン(エリザベス・タワー, Elizabeth Tower) の眺め。中央に見える黒いガラス張りの船は観光用のリバークルーズ船。屋上デッキに多くの観光客の姿が。英国国会議事堂(Palace of Westminster) と エリザベス・タワー(Elizabeth Tower, 通称ビッグベン) のクローズアップ。下を横切るのは Westminster Bridge(ウェストミンスター橋)。右側の時計塔が正式名称:Elizabeth Tower(エリザベス・タワー)、通称「Big Ben(ビッグベン)中央の大きな塔Central Tower(中央塔)。国会議事堂の中庭(Central Lobby)の上に建ち、最も繊細なゴシック装飾を持つ部分。上にはユニオンジャックが掲げられていた。テムズ川北岸・対岸に立つ 「国王空軍記念碑(Royal Air Force Memorial)」をズームして。さらに。・白いポートランド石で造られた塔の上に、金色の翼を広げたワシの像。・基部には第一次世界大戦中に殉職した英国空軍兵士を追悼する碑文が刻まれている と。・第二次世界大戦以降も、空軍戦没者全体の追悼の場として扱われているのだ と。再びテムズ川北岸 Whitehall Court(ホワイトホール・コート) の建物群を。建物は複合施設で、一部は Royal Horseguards Hotel(高級ホテル) として使用、一部は官庁関連施設や高級アパートメントとして利用 と。テムズ川の上流を振り返って。このアングルは「ロンドン・アイ × ビッグベン × 国会議事堂 × テムズ川」を一枚に収められる絶好の撮影スポットなのであった。ひっきり無しに通過する観光船。左側・大観覧車 London Eye。ロンドン南岸(South Bank)のシンボルで、高さ135m。・下部に見える乗降ステーションが桟橋に張り出しています。中央の川・白い観光船 → 「City Cruises」などのリバークルーズ船。・黒いガラス張りの船 → モダンな観光船(Thames Clippers系など)。・川面には複数の観光船・定期船が行き交っており、Westminster Pier と London Eye Pier の 間を行き来する姿が見られます。右側奥・ゴシック様式の国会議事堂(Palace of Westminster)。・高くそびえる時計塔が Elizabeth Tower(通称ビッグベン)。・手前の橋は Westminster Bridge(ウェストミンスター橋)。Golden Jubilee Bridges・ゴールデン・ジュビリー橋下からテムズ川越しに 「クレオパトラの針(Cleopatra's Needle)」 と「Shell Mex House(シェル・メックス・ハウス)」 を写した光景。テムズ川沿いに立つ クレオパトラの針(Cleopatra’s Needle)をズームして。・中央のオベリスク ・紀元前1450年頃、ファラオ・トトメス3世の時代にエジプトのヘリオポリスで建立。 ・高さ約21m、重さ約180トンの赤色花崗岩製。 ・1819年にエジプトからイギリスに贈られ、1878年に現在の位置(Victoria Embankment, テムズ川北岸)に設置されました。・背後の大きな白い建物 ・Shell Mex House(シェル・メックス・ハウス) ・1932年建設。かつて石油会社Shell-Mex and BPの本社ビル。・基壇のスフィンクス像(左右) ・オベリスクを守護するかのように、左右にブロンズ製スフィンクス像が配置されています。 ・実際の古代エジプト様式を模した19世紀の鋳造作品。基壇のスフィンクス像(左)。再びSouth Bank(サウスバンク)の案内板で、特に Royal Festival Hall(ロイヤル・フェスティバル・ホール) 周辺を起点とした地図を。近づいて。テムズ川周辺の徒歩圏観光スポットが示されていた。主要施設(黄色で強調表示)・Southbank Centre(サウスバンク・センター)・Royal Festival Hall(ロイヤル・フェスティバル・ホール)・BFI Southbank(英国映画協会シネマ)・National Theatre(ナショナル・シアター・Queen Elizabeth Hall・Hayward Gallery(ヘイワード・ギャラリー)・London Eye(ロンドン・アイ) も少し左下に描かれていた。現在地はここ「You are here」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.29
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その92): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-7
ロンドンのウェストミンスター橋(Westminster Bridge) を渡り終わる手前から。この建物は 「County Hall(カウンティ・ホール)」。・建設: 1911年着工、1922年完成(建築家 Ralph Knott 設計)・特徴: テムズ川の南岸に位置し、白い石造の壮大な外観と緑色の屋根窓が特徴。 正面にはライオン像などの装飾があります。・歴史: かつてはロンドン郡議会(LCC)、後に大ロンドン議会(GLC)の本部として使われて いました。・現在: ロンドン水族館(SEA LIFE London Aquarium)、ロンドン・ダンジョン、シュレック・ アドベンチャー、そしてホテル(London Marriott Hotel County Hall)やオフィスとして 利用されている と。「サウスバンク・ライオン(South Bank Lion)」。・材質: コーツウェルズ産の人工大理石(コーツウェルズ・ストーンを混ぜたコート・ストーン)で 作られています。・製作年: 1837年・製作者: William Frederick Woodington(ウィリアム・フレデリック・ウッディントン)・元の設置場所: このライオンは、かつてランベス(Lambeth)にあった 「ライオン・ブリュワリー(Lion Brewery)」のシンボル像でした。・現在の場所: 1951年のフェスティバル・オブ・ブリテンの後、現在の County Hall(カウンティ・ホール)前、 ウェストミンスター橋の南側たもとに移設されています。サウスバンク・ライオンの近くの横断歩道を渡り川沿いの石段を下る 。ウェストミンスター橋の南岸側からの「Bridge Arch Photo」。手前の石造りのアーチの形が「額縁」となり、その中に ビッグ・ベン(エリザベス・タワー) とウェストミンスター橋 が収まるのであった。遊歩道の先にあったのが、テムズ川南岸にある 「National COVID Memorial Wall(ナショナル・コロナ追悼の壁)」。・場所: テムズ川のサウスバンク、セント・トーマス病院(St Thomas’ Hospital)の外側の壁沿い (ウェストミンスター宮殿の対岸に位置)・特徴: 無数の赤いハートが壁一面に描かれていた。・意味: 各ハートは新型コロナウイルスで亡くなった人々一人ひとりを象徴。 多くのハートには名前やメッセージが書き込まれており、遺族や友人たちの想いが。・始まり: 2021年春、COVID-19犠牲者の遺族団体「Covid-19 Bereaved Families for Justice」 によって自発的に描かれ始めたもの。・全長: 約 500 メートルに及び、テムズ川沿いに続く大規模な市民追悼モニュメント。テムズ川南岸から、「Big Ben・ビッグ・ベン」と「Palace of Westminster・ウェストミンスター宮殿」を。こちらは「Big Ben・ビッグ・ベン」と「Westminster Bridge・ウェストミンスター橋」。再び、「サウスバンク・ライオン(South Bank Lion)」と「County Hall(カウンティ・ホール)」を正面から。 そして「St Thomas' Riverside Garden」を訪ねた。 位置 テムズ川南岸、セント・トーマス病院の敷地内にある小さな庭園。ウェストミンスター宮殿 (国会議事堂)とビッグ・ベン(エリザベス・タワー)を正面に望む絶好の場所にあります。風景 この庭園は花壇が整備されており、色とりどりの草花を前景に、対岸の国会議事堂を背景に 入れて撮影できるため、観光客や写真家に人気のスポット。関連 すぐ横には先ほどの 「National COVID Memorial Wall(コロナ追悼の壁)」 が続いており、 庭園と壁の両方を訪れる人が多いのであった。公園内にあった「Mary Seacole Memorial Statue」。人物: メアリー・シーコール(Mary Seacole, 1805–1881) ジャマイカ生まれの看護師。クリミア戦争で傷病兵を支援したことで知られる。 人種差別によりナイチンゲールの看護団には加われなかったが、自ら資金を集めて前線に赴き、 兵士たちから「Mother Seacole(シーコール母さん)」と慕われた。像の設置: 2016年、ロンドンのセント・トーマス病院前に建立。 作者はマーティン・ジェニングス(Martin Jennings)。特徴:シーコールが自信に満ちて前に歩み出る姿を表現。 近づいて。シーコールが自信に満ちて前に歩み出る姿を表現。台座には”MARY SEACOLE NURSE OF THE CRIMEAN WAR 1805-1884”彼女の言葉 “Wherever the need arises, on whatever distant shore. I ask only to be remembered for what I have done.”も。(必要とされる場所なら、どんな遠い国であろうと。私はただ、自分の成したことを人々に 覚えていてほしいと願うのみです。)と。背後の大きな円盤は、彼女がクリミア戦争で通った「戦場の地形」をモチーフにしたレリーフ。メアリー・シーコールが看護活動を行った クリミア戦争(1853–1856) の戦場を象徴しており、彼女が「どんな遠い場所でも必要とされれば赴く」という姿勢を現しているのだ と。「Fountain of St Thomas’ Gardens(セント・トーマス・ガーデンズの噴水」 。背後に見えるのは エリザベス・タワー(Big Ben) と国会議事堂、右手に ウェストミンスター橋。近づいて。・建立年: 1963年・目的: セント・トーマス病院の新しいガーデン整備事業の一環 として設置。 病院の敷地が戦後の再開発で整えられる際に、川沿いの庭園を「癒やしと休息の場」と するためのシンボル的存在として建てられた。・特徴: ・ステンレス製のモダンな抽象彫刻。 ・中央の彫刻は「二つの翼が開いて水を受け止める」ような形。 ・噴水として機能し、晴れた日には水しぶきと光の反射できらめく と。ビッグ・ベンに焦点を合わて。移動して。公園を後にして、引き返して「サウスバンク・ライオン(South Bank Lion)」とのコラボを。遊んでみました。「RIVER THAMES」沿いのMAP。下流に向かって大きく東方向に蛇行しているのであった。再び「サウスバンク・ライオン(South Bank Lion)」を見上げて。東京・日本橋の三越本店前にあるライオン像(1914年設置)。これは ロンドンの高級百貨店「Selfridges(セルフリッジズ)」前のライオン像 をモデルに制作。その セルフリッジズのライオン像 は、実は ウッディントン作「South Bank Lion」と同系統のデザイン に強く影響を受けているのだ と。東京・日本橋の三越本店前にあるライオン像(1914年設置)をネットから。Westminster Bridge・ウェストミンスター橋越しにBig Ben・ビッグ・ベンを。テムズ川対岸(ノースバンク側)を。① 金色の像のモニュメント ・川沿いの木々の間から見えている金色の像は、 ・「ロイヤル・エアフォース記念碑(Royal Air Force Memorial)」 。 ・建立年: 1923年 ・目的: 第一次世界大戦で亡くなった RAF(英国空軍)の兵士を追悼するため。 ・特徴: 白いポートランド石の柱の上に「黄金の翼を持つ勝利の女神像」が立っていた。② 奥に見える白いドーム状の建物 ・これは チャリング・クロス駅(Charing Cross Station) の再開発部分である エンバンクメント・プレイス(Embankment Place)。 ・アーチ型のガラスファサードが特徴で、1980年代末〜1990年代に建て替えられた。③ その周囲の建物 ・ホワイトホール・コート(Whitehall Court) と呼ばれるヴィクトリア朝の建築群。 ・現在はホテル(ロイヤル・ホースガーズ)や高級住宅として利用されている と。少し進んでズームして。右側・ロンドン・アイ(London Eye, 2000年開業、全高135mの巨大観覧車)・テムズ川南岸(サウスバンク)の代表的ランドマーク中央奥・テムズ川対岸に見えるのは「サマセット・ハウス」や「キングズ・カレッジ・ロンドン」などを 含む ノースバンク(ノース・エンバンクメント沿い)の建物群。・特に中央に見えるやや低い「アールデコ様式」の建物は Shell Mex House(シェル・メックス・ ハウス)(1931年建造、かつてシェル石油本社)。時計塔を持つことで有名。下部の川辺・白い遊覧船(テムズ川クルーズの船)。・水上に延びる歩道橋は ゴールデン・ジュビリー・ブリッジ(Golden Jubilee Bridges)。 (ウォータールー橋とチャリングクロス駅近くの鉄道橋に併設された歩行者橋)再びWestminster Bridge・ウェストミンスター橋越しにBig Ben・ビッグ・ベンを。ズームして。我が人生の見納め!!? 以下、これでもかと。ロンドン・アイ(London Eye)が目の前に。右側にあったこの入口はロンドン・サウスバンクにあった 「SEA LIFE London Aquarium(シーライフ・ロンドン水族館)」 のエントランス。その隣にあったのが、County Hall(カウンティ・ホール) 内にあるアトラクション施設 「Shrek’s Adventure! London(シュレック・アドベンチャー!ロンドン)」 の入口。子供向けだけでなく、ファミリー全体で楽しめるインタラクティブ体験型アトラクション施設 と。だいぶ歩いて来ました。多くの観光船がWestminster Bridge・ウェストミンスター橋下を通過して。アトラクション施設 「The London Dungeon(ロンドン・ダンジョン)」 の入口。・上部に赤いロゴ「The London Dungeon」。・両脇に石造りのゴシック風装飾、特に右側にはフードをかぶった人物像(僧侶や死刑執行人を 思わせるデザイン)。・入場口にはチケットカウンターの案内(Box Office / Booking)。「The London Dungeon(ロンドン・ダンジョン)」 の案内看板。・上部に赤文字のロゴ 「The London Dungeon」・キャッチコピー: “LIVE AND BREATHE LONDON'S DARKEST HISTORY” (ロンドンの最も暗い歴史を、息づかいまで感じよ)・中央のポスター: ・黒い外套をまとった人物の後ろ姿 → 切り裂きジャック(Jack the Ripper) を象徴 ・テキスト: “HUNT DOWN JACK THE RIPPER” (切り裂きジャックを追え)・下部にはチケット購入案内: “BOOK NOW IF YOU DARE. THEDUNGEONS.COM/LONDON”(勇気があるなら今すぐ予約を。公式サイト:thedungeons.com/london)と。「London Eye(ロンドン・アイ)」 を真下から見上げて。・開業: 2000年(ミレニアムを記念して建設され「Millennium Wheel」とも呼ばれました)・高さ: 135m(当時は世界最大の観覧車)・ゴンドラ: 32基(ロンドンの行政区「32区」を象徴)、各カプセルは最大25人乗りで空調完備。・所要時間: 1周およそ30分。・年間利用者: 約350万人(ロンドンで最も人気の観光名所の一つ)。「FISH & CHIPS」の店で休憩。 「FISH & CHIPS」を注文。休憩後に再びロンドン・アイ(London Eye) を真横に近い位置から見上げて。・観覧車のゴンドラ(カプセル) ・大型のガラス張りカプセルが複数見えていた。 ・各カプセルは最大25名収容、空調完備で360度の視界を楽しめる と。・搭乗エリア(下部の建物部分) ・写真中央下に写るガラス張りの部分は、乗客が乗り込む「搭乗プラットフォーム」。 ・ロンドン・アイは完全停止せず、ゆっくりと回転しながら乗降が行われている と。・支柱とワイヤー ・右上から延びる巨大な支柱と放射状のケーブルが、観覧車全体を支えていた。 ・ロンドン・アイの特徴的な構造美を強調。・背後(左奥) ・木々の向こうに見えるのは「ホワイトホール・コート(Whitehall Court)」など、 ノースバン・ク側の建物群。再びWestminster Bridge・ウェストミンスター橋越しにBig Ben・ビッグ・ベンそしてPalace of Westminster・ウェストミンスター宮殿の全景を。こちらが、「London Eye Ticket Office(ロンドン・アイ チケットオフィス)」 の入口。サウスバンクの County Hall(カウンティ・ホール) 建物内にあった。ロンドン・アイ本体のすぐ隣にあり、観覧車に乗る前にここでチケットを購入するようだ。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.28
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その91): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-6
Parliament Square Garden・パーラメント・スクエア・ガーデンの南東、の角からロンドンの国会議事堂(Houses of Parliament / Palace of Westminster)を見る。1.右手の大きな塔(ヴィクトリア・タワー / Victoria Tower) ・国会議事堂の南西端にある塔。 ・イギリス国旗(ユニオンジャック)が掲げられており、議会の開会中に掲揚されます。2.中央の複雑な尖塔群 ・ゴシック・リヴァイヴァル様式で19世紀に再建された部分(建築家チャールズ・バリーと オーガスタス・ピュージンの設計)。 ・上に立ち並ぶ装飾尖塔(ピナクル)が印象的です。3.左手前の屋根が長い建物(ウェストミンスター・ホール / Westminster Hall) ・1097年に建てられた、現存するウェストミンスター宮殿で最も古い部分。 ・中世以来、戴冠式の饗宴や裁判(例:チャールズ1世の裁判)など歴史的行事の舞台と なりました。 ・現在も国葬や重要な追悼式に用いられます(例:2022年エリザベス2世女王の棺の安置)。1.左の時計塔(エリザベス・タワー / Elizabeth Tower) ・一般的に「ビッグ・ベン(Big Ben)」と呼ばれる部分。 ・実際の「ビッグ・ベン」は塔内の大鐘の名称。 ・1859年に完成、ゴシック・リヴァイヴァル様式の代表的建築。 ・時計盤の下に「D(Dominus)」「S(Salvator)」「F(Fecit)」などのラテン語銘が 刻まれています。2.中央から右にかけての長い屋根の建物(ウェストミンスター・ホール / Westminster Hall) ・1097年に建てられた、現存する宮殿部分の中で最古のホール。 ・巨大な木造の天井(ハンマービーム屋根)は中世建築の傑作。 ・歴史的に王室儀礼や裁判の場として使用され、近年では国葬や重要な追悼式に用いられる (例:2022年エリザベス2世の安置)。3.背景左奥に見える観覧車(ロンドン・アイ / London Eye) ・テムズ川対岸(サウスバンク)にある大観覧車。 ・この写真の撮影地点から、ちょうど国会議事堂の横越しに見えた。ロンドンの国会議事堂(Palace of Westminster)北側に広がる「パーラメント・スクエア庭園(Parliament Square Garden)」 を再び。1.林立する旗 ・英国各自治体・海外領土・王室関連機関などの公式旗や、各国・各都市・各自治体を表す 旗が並んでいた。 ・特定の記念日や国際会議(例:コモンウェルス関連イベント、国際首脳会議)にあわせて 掲揚されることが多いと。2.奥の建物(白い石造建築) ・HM Treasury(財務省)」や「Government Offices Great George Street」と呼ばれる 官庁街の一角。 ・古典主義・バロック復興様式のデザインで、威厳のある外観。ビッグ・ベン(Big Ben)の手前から奥にかけて広がるゴシック様式の建物群が ウェストミンスター宮殿(Palace of Westminster, Houses of Parliament)。・左側(旗が立つ塔) これは ヴィクトリア・タワー(Victoria Tower) 。 宮殿南西角に建つ高さ98mの塔で、国会関連の文書を収蔵する 議会文書館(Parliamentary Archives) が入っている。 英国国会開会式の際にはここから国王(女王)が議事堂に入る伝統ルートとなる。・左手前(石の塀と大屋根) ウェストミンスター・ホール(Westminster Hall) の外壁部分。 宮殿で最も古い建物で、国葬・戴冠関連行事・国賓演説などに使われます。 ・右奥(木々の向こう、尖塔が並ぶ建物) これは ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey) の西端部分。 (国王戴冠や王室の結婚式・葬儀が行われる大聖堂)。右:ウェストミンスター・ホール(Westminster Hall)東側の付属建物部分大屋根の本体から張り出す、19世紀再建時のゴシック風の増築部分。特徴的な小尖塔と石造りの装飾が並んでいる。窓はゴシック様式の尖頭アーチ窓で、内部からは議会関連の部屋へ繋がっている。正面の大きな白い建物群は、ホワイトホール(Whitehall)沿いの政府庁舎 。特に目立つ中央塔を持つ建物は、かつての「旧財務省(Old Treasury Building)」で、現在は英国政府の官庁街(HM Treasuryや内閣府) が入るエリア。左端に見える塔屋は 旧公共記録局(Public Record Office)や官庁街の建物群 の一部。手前の通りは Parliament Street(ホワイトホール通りに連続する区間) で、右奥へ進むとトラファルガー広場方面に続く。各国の国旗が並んでいた。白い塔は、セント・マーガレット教会(St Margaret's Church, Westminster) の塔。・中央奥:エリザベス・タワー(時計塔) イギリス国会議事堂(Palace of Westminster)の北端に位置。 時計台自体が「ビッグ・ベン」と呼ばれることが多いですが、正確には「ビッグ・ベン」は 中の大鐘の愛称。・手前:鉄柵と門、警備の警察官 ここは 国会議事堂(Palace of Westminster)の関係者出入口(セキュリティゲート) のひとつ。 警備が非常に厳重で、一般の観光客はここから中に入ることはできません。エリザベス・タワー(Elizabeth Tower)、ビッグ・ベンを再び。・時計盤: 白地に黒いローマ数字、青い針、そして縁取りは金色装飾。 直径は約7mあり、世界でも最大級の四面時計のひとつです。・ゴシック様式の塔: 上部は尖塔(スパイア)に細かな装飾が施され、鉄製の冠のような構造物が特徴。St. Margaret’s Church(聖マーガレット教会) の鐘楼を振り返って。 ロンドンのウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)前の正門入口前。 ・演奏者は スコットランドの伝統衣装(タータンチェックのキルト、羽根飾り付きボンネット、 スパッツ) を着用。 ・演奏している楽器は バグパイプ(Great Highland Bagpipe)。スコットランドを象徴する楽器。 ・背景に見える黒い鉄柵と石柱は、ウェストミンスター寺院の敷地を囲むフェンス。 ・柵に取り付けられた茶色の案内板に「Visitor Entrance」「Ticket Office」とあり、 これは寺院見学用の入場口方向を示していた。1.演奏者の衣装 ・赤と黒を基調にしたタータンチェック柄のキルト。 ・黒い上着に赤い袖口。 ・頭には 羽根飾り付きの軍隊式ボンネット(スコティッシュ・ボンネット/バルモラル型) を かぶっていた。 ・胸やバグパイプの袋に銀色の装飾(飾り金具)が施されており、観光客向けの 舞台衣装として華やか。2.バグパイプ ・標準的な「グレート・ハイランド・バグパイプ」。 ・チェック柄のカバーはキルトとお揃いで統一。3.スコットランドの「グレート・ハイランド・バグパイプ」の場合、通常 3本のドローン管 が 付いていた。 ・バス・ドローン(Bass Drone) ・一番長い管。 ・低い音(1オクターブ下の持続音)を出します。 ・テナー・ドローン(Tenor Drones) ×2本 ・やや短い管が2本。 ・同じ高さの音を出し、バス・ドローンを補強する役割。時計塔「エリザベス・タワー(Elizabeth Tower)」を見上げて。高さ:96メートル。時計盤:直径約7メートル、鉄骨とガラスで構成されており、金色の縁飾りが施されていた。鐘:重さ13.5トンの大鐘「ビッグ・ベン」が有名で、英国国会(ウェストミンスター宮殿)の 象徴として親しまれている。ウェストミンスター宮殿(Palace of Westminster, Houses of Parliament) の一部を、木々の間から。ウェストミンスター宮殿(Palace of Westminster)を北側のBlidge Street側から。 ・ゴシック・リバイバル様式のファサード(外壁)が長く連なっており、垂直に強調された尖塔 (ピナクル)が一定間隔で配置されていた。・大きな縦長の窓(トレーサリー付きのゴシック窓)が並んでおり、内部は ロング・ギャラリー (Long Gallery)や議会関係の廊下部分に相当。Westminster Bridge・ウェストミンスター橋の手前から、「ロンドン・アイ(London Eye)」 と、その手前にある「ブーディカ像(Boadicea and Her Daughters)」を。1. ロンドン・アイ(London Eye)概要:2000年に完成した高さ135mの観覧車。テムズ川南岸に位置し、ロンドンの ランドマークのひとつ。特徴:32のカプセル(各25人乗り)があり、1周に約30分。市街を一望でき、天気がよければ 40km先まで見渡せる と。象徴性:新世紀を記念して建設され、「ミレニアム・ホイール」とも呼ばれた。2. ブーディカ像(Boadicea and Her Daughters Statue)・場所:ウェストミンスター橋の北側、ビッグ・ベン近く。・人物:ブーディカ(Boudica, oadiceaとも表記)は古代ケルトの女王で、紀元60〜61年に ローマ帝国支配に反抗し大蜂起を率いたことで知られている。・像の構成: ・ブーディカ女王が戦車に立ち、槍を掲げている姿。 ・両側に二人の娘たちが共に立っている。 ・戦車は二頭の馬に引かれており、馬は力強く前脚を上げて突進する様子が表現されていた。・建立:19世紀後半に建てられ、ヴィクトリア時代の民族的誇りを象徴する記念碑となっている。「ブーディカと彼女の娘たちの戦車像(Boadicea and Her Daughters Statue)」をズームして。1. 中央の人物(ブーディカ女王) 姿勢:戦車の上に立ち、右手を高く掲げ、槍を持っています。これは「反抗の決意」と 「戦いの指導者」としての姿を象徴しています。 衣装:古代ケルトの女王らしい長いドレスをまとい、頭には冠(ティアラ)を載せています。 表情:威厳を持ち、正面を見据えています。民族の指導者としてのカリスマ性を強調した造形。2. 両脇の二人の娘 姿勢:戦車の左右に立ち(または腰かけ)、母と共に戦いに臨む姿。 象徴:ブーディカが「家族をも巻き込んで祖国のために戦った」ことを表しています。 造形の違い:片方は片腕を前に伸ばし、もう片方は戦車の縁に身を寄せています。若さと 無垢さが強調され、母の力強さと対比されています。3. 戦車と馬 馬:2頭の馬が前脚を高く上げ、突進する瞬間を表現。口を開け、躍動感あふれる姿は 「戦いへの突入」を象徴しています。 戦車:古代ケルト式の戦車。車輪の造形はシンプルですが、力強さを示しています。全体の構図:母(女王)が立ち、両娘が支え、馬が突進するという、前進のエネルギーに満ちた構図。移動して反対側から。・娘(右側) 戦車の縁に腰掛け、やや前かがみに身を乗り出しています。衣装はシンプルで、 母と対比して「若さ」や「無垢さ」を象徴しています。テムズ川(River Thames)とロンドン・アイ(London Eye)。「London Eye」という名前は「ロンドンを見渡す巨大な目」というイメージから付けられたもので、都市全体を象徴的に眺められるランドマークとしての役割を示すための呼称であると。当初は 「Millennium Wheel」 と呼ばれていた。しかし、記念事業の一過性の名前ではなく、ランドマークとして長く親しまれるために「Eye」という普遍的で象徴的な名称が採用されたのだと。エリザベス・タワー(Elizabeth Tower)を振り返って。ズームして。 ウェストミンスター橋(Westminster Bridge)からウェストミンスター宮殿(Palace of Westminster)を振り返って。正面に見える部分は、細長い垂直線を強調した尖塔 と、格子状に分割された大きな窓が特徴。「セント・スティーブンズ・タワー(St Stephen’s Tower)」と呼ばれる翼部の一角。赤い2階建てバス(ロンドン名物の「ルートマスター」)と一緒に、典型的なロンドン観光写真になっていたのであった。ウェストミンスター橋(Westminster Bridge)上には多くの観光客の姿が。ウェストミンスター宮殿(イギリス国会議事堂)をテムズ川側から見た西面 の姿。ウェストミンスター橋(Westminster Bridge)をさらに進む。正面に見える大きな建物は、かつての ロンドン郡庁舎(London County Hall)。現在は ロンドン水族館(Sea Life London Aquarium)、ロンドン・ダンジョン、そして観光ホテルやオフィスが入っている と。テムズ川の南岸(ランベス側)から、ウェストミンスター宮殿(イギリス国会議事堂, Palace of Westminster)を振り返って。テムズ川(River Thames) の下流方向(東方向)を見る。右側の建物 ウェストミンスター宮殿(Palace of Westminster, 英国国会議事堂)のリバーサイド・ ファサード(川沿いの外壁)。 手前に見えるのは「ヴィクトリア・タワー側の南端部」。中央奥に見える橋 ランベス橋(Lambeth Bridge)付近。ウェストミンスター宮殿(イギリス国会議事堂, Palace of Westminster)を再び。ロンドン・アイ(London Eye)を再び。ウェストミンスター橋(Westminster Bridge) に設置されている特徴的なガス灯風のランプをズームして。・色:濃いグリーンに金色の装飾 が施されている。・ランプ:上部に 三灯式の六角形ランタン。・装飾:中央には金色で「V R」のモノグラム(Victoria Regina=ヴィクトリア女王)を象った 紋章が入っていた。・様式:ヴィクトリア朝ゴシック・リバイバル風デザイン。ウェストミンスター橋(Westminster Bridge)上空を飛ぶ飛行機の姿を。・飛行機は ヴァージン・アトランティック航空(Virgin Atlantic Airways)。・尾翼の赤いカラーと「Virgin」のロゴ → ヴァージン・アトランティックの象徴的デザイン。・エンジンも赤色 ・機体側面に「Virgin Atlantic」の文字も読み取れた。これでもかと!!ズームして。再びテムズ川の 上流方向(西側)に見えた、ランベス橋(Lambeth Bridge)を。橋の背後には、テムズ河南岸(Vauxhall・Nine Elmsエリア)に立ち並ぶNine Elms / Vauxhall 開発地区のビル群が見えた。ロンドンの テムズ川観光クルーズ船の姿が。観光客の姿はなかったが、帰路か? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.27
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その90): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-5
ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の堂内に設置された説教壇(pulpit, 説教台)。後方に見えている精緻な金の柵は High Altar(高壇祭壇)を囲むスクリーン の一部。近づいて。説教壇(Pulpit)の特徴・用途 礼拝時に聖職者がここに立ち、説教や聖書朗読を行うための壇。・装飾 黒地に金色の細工が施されており、ルネサンス〜バロック風の豪華な装飾が特徴。 周囲にリース状のモチーフや植物文様、金色の縁取りが見られる。・構造 ・上部に「張り出した天蓋(sounding board)」が設置され、声を反響させて聴衆に 届きやすくする役割を果たしている。 ・側面・前面には聖書を置くための台と手すりがあり、下から階段で上る形式。(回廊)に面する窓のステンドグラス。中央パネルを見ると、聖人が槍(または十字の杖)で竜を退治している場面が描かれています。これは伝統的に 聖ゲオルギウス(St. George) として表されることが多い主題。聖ゲオルギウスはイングランドの守護聖人で、「竜を退治する聖人」として有名。右側に赤い竜が大きく描かれており、その足下に聖人が立っています。背後に後光(光輪)を帯びており、聖人としての神聖さを示しています。ヘンリー7世記念礼拝堂(Henry VII’s Lady Chapel) の内部。1.扇形ヴォールト天井(Fan Vaulting) ・天井全体が華麗な扇形ヴォールトで覆われており、これはイギリス後期ゴシック (垂直様式)の最高傑作のひとつ。 ・特に Henry VII Lady Chapel の最大の特徴。2.騎士団旗(Knights’ Banners) ・天井から下がっている色鮮やかな旗は、ガーター騎士団(Order of the Garter) の 騎士の紋章旗。 ・Lady Chapel はガーター騎士団の「礼拝の場」としても使われます。3.ステンドグラス窓 ・正面の大窓はゴシック様式の高窓で、彩色ガラスがはめ込まれている。・天井の構造 ・イギリス後期ゴシック(垂直様式)の最高傑作とされる「扇形ヴォールト (Fan Vaulting)」が全面に広がっています。 ・幾何学的かつレースのように精緻な石細工は、この礼拝堂の最大の特徴。・吊り下げられた旗(バナー) ・両脇に並んでいるのは ガーター騎士団(Order of the Garter)の騎士の紋章旗。 ・ガーター騎士団はイギリス最高位の騎士団で、女王(王)が総長。 ・騎士任命者の旗が礼拝堂に掲げられます。・窓 ・奥に高いステンドグラス窓が見え、光が差し込む構造は Lady Chapel 正面そのもの。「Henry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂)」 の一角を見上げて。1.黒い木彫の聖歌隊席(Choir Stalls) ・礼拝堂両脇に並ぶ精巧な木製の聖歌隊席。 ・黒く塗られ、上部には金色の十字が掲げられており、ガーター騎士団の席としても 使われています。 ・この席には、騎士団のメンバーの紋章や名が記録され、椅子の上にヘルメットや紋章飾りが 置かれることもあります。2.頭上に掲げられた旗(バナー) ・騎士団の紋章旗で、ガーター騎士団(Order of the Garter)の騎士それぞれを表しています。 ・各旗にはその騎士の家系や個人の紋章が描かれ、現役騎士の間は掲げられています。3.背後の高窓 ・ゴシック様式の大きなステンドグラス窓が背景に見えます。 ・礼拝堂内は全体的に明るく、天井の扇形ヴォールトと一体となった荘厳な雰囲気を 形作っています。Henry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂) の内部、正面側(東端)を再び。1.ステンドグラス窓 ・中央に縦に並んだ大きなステンドグラス(赤や青を基調)が。 ・両脇の窓は青色が強く、中央の窓と色調が異なるのが特徴。2.下部の彫像群 ・窓下には、多数の小像(聖人・王族・天使など)を並べた精緻な彫刻帯があります。 ・礼拝堂内部の最も豪華な装飾部分の一つです。3.ガーター騎士団の旗 ・左右に掲げられている色鮮やかな旗は、ガーター騎士団(Order of the Garter)の 騎士の紋章旗。 ・それぞれの旗が現役騎士を表している。4.天井の扇形ヴォールト ・上部には Henry VII Lady Chapel 特有の「扇形ヴォールト」が広がっていた。中央のHenry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂)東端の大ステンドグラス窓をズームして。・ゴシック様式の縦長窓 ・尖頭アーチの内に、縦に細長いパネルが多数並ぶ典型的な後期ゴシック様式。 ・上部はさらに小窓(トレーサリー)に分割されていた。・彩色(赤・青・白を基調) ・赤と青が中心で、人物や場面が描かれていた。 ・上段と下段で異なる場面が配置されているのが見てとれた。Henry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂)東端の「大中央窓」の左側窓。・色彩 ・ほぼ一面が「青と白」の抽象的な模様で構成されています。 ・中央の大窓(聖母マリアや聖人が描かれた具象的なステンドグラス)とは対照的で、 こちらはモダンなデザイン。・主題 ・この青い窓は、1940年のロンドン大空襲(The Blitz)で破壊された旧ステンドグラスの 代わりに、戦後に新しく制作されたもの。 ・主題は「空・光・星」といった抽象的なモチーフが中心で、戦後の再生・希望・平和を象徴。Henry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂)東端の「大中央窓」の右側窓。聖歌隊席(Choir Stalls) を下から見上げて。移動して正面から。1.黒い木彫の聖歌隊席(Choir Stalls) ・上部に金の十字架が並び、各席の上には ガーター騎士団のヘルメットと紋章飾り(crest) が 置かれている。 ・これは騎士団のメンバーを示す伝統で、現役の騎士に割り当てられる。2.吊り下げられた旗(Banners) ・騎士団の紋章旗。 ・各旗はその騎士(あるいは貴族家系)の紋章を描いている。 ・ガーター騎士団の礼拝堂としての性格が強調されている。3.上部の彫像群 ・背後の壁に並んでいるのは、聖人や王、天使像。 ・Lady Chapel の壁面にはこのように多くの小像が整然と並んでいた。 ・この部分は特に「リブ・ヴォールトと一体化した壁龕装飾」として有名。4.天井装飾 ・アーチの下に見えるのは、扇形ヴォールトの一部。 ・天井から下がる金色の飾りも見え、全体に壮麗な印象を与えていた。ズームして。1.兜と紋章飾り(Crests) ・各席の頂上に置かれた兜(ヘルメット)と、その上に家系を表す動物やシンボルの飾りが。 ・例えば、馬や鳥、神話的動物などが見えます。 ・これらは現役のガーター騎士に割り当てられた「個別のシンボル」。Henry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂) の中心にある、ヘンリー7世と王妃エリザベス・オブ・ヨークの墓所(Tomb of Henry VII and Elizabeth of York)。1.天蓋付きの墓所(Canopy Tomb) ・黒い鉄柵に囲まれ、金色の天蓋(バルダキン)に覆われていた。 ・天蓋の上部には 王冠を戴いた紋章盾と二人の天使像 があり、王権を象徴。2.祭壇正面 ・中央には聖母子像の絵が掲げられていた。 ・墓所は単なる埋葬場所ではなく、礼拝対象としての祭壇の機能も持っている と。3.位置 ・Lady Chapel のほぼ中央に配置され、周囲を取り囲むようにガーター騎士団の聖歌隊席が 並んでいた。 ・この礼拝堂自体がヘンリー7世によって建設されたため、その中心に彼と妃の墓が 置かれていた。ヘンリー7世とエリザベス・オブ・ヨークの墓所の祭壇中央に掲げられた絵画。・題材:聖母子像(Madonna and Child) ・聖母マリアが幼子イエスを抱いている伝統的な図像。 ・マリアは頭を傾け、優しく子を見つめる姿勢で表されている。 ・幼子イエスは裸で立ち、片手を上げていた。・背景 ・背後に2本の柱(古典様式)が描かれており、ルネサンス的な建築要素を感じさせます。 ・上部には果物や花のガーランド(飾り)が描かれ、生命と豊穣を象徴。Henry VII’s Lady Chapel(ヘンリー7世記念礼拝堂) 内の大きなステンドグラス窓のひとつ。1.構造 ・ゴシック様式の高窓で、尖頭アーチの中に縦長のパネルが多数並んでいる。 ・上部にはトレーサリー(石の透かし彫り)で小窓が細かく分割されている。2.デザイン ・この窓は、宗教的な物語や人物像ではなく、紋章(heraldry)を中心に描いた ステンドグラス。 ・王家や騎士団、貴族家系の紋章が色鮮やかに並んでおり、背景は比較的透明度が高い ガラスで構成。 ・赤・青・金の紋章モチーフが縦に多数配置されているのが見えた。北翼廊(North Transept) の一角、Sir George Villiers(ジョージ・ヴィリアーズ卿, 1592–1632)とその妻メアリー・ボーモント(Mary Beaumont)の墓碑。この碑文はラテン語で書かれており、Sir George Villiers とその妻 Mary Beaumont を讃える内容。「英語訳To the memoryof Sir Edward Villiers, knight,an exemplar of such great virtues as are rarely united in one man.When he departed this life,he had lived 56 years, 11 months, and 12 days.His surviving wife, Mary Beaumont,with their sons Edward, George, John,and their daughters Susanna and Frances,bound together in most harmonious wedlock,at last, for her most beloved husband,with words of devotion and with most loving tears,set up this monument.He died on the 8th of February, 1607,in the 66th year of his age.」 【ここに記憶す騎士エドワード・ヴィリアーズ、一人の人間にこれほどまでに優れた美徳が備わっていることは稀である。彼はこの世を去りしとき、56年11か月12日の生涯を生きた。彼の後に残された妻メアリー・ボーモントは、息子エドワード、ジョージ、ジョン、娘スザンナとフランセスとともに、もっとも調和に満ちた夫婦の絆を胸に、ついに最愛の夫のために、敬虔なる言葉と愛の涙をもって、この碑を建てた。彼は西暦1607年2月8日に没し、66歳であった。】・男性像(手前・鎧を着て横たわる人物)これは Sir Edward Villiers。 ・鎧姿で描かれており、右手を胸の上に置き、騎士としての身分と忠誠を示しています。 ・足元には小さな「動物像(多くはライオンや犬)」が置かれるのが通例で、勇気や忠実を 象徴します。・女性像(奥・赤いローブをまとって横たわる人物)これはその妻 Mary Beaumont, Countess of Buckingham。 ・頭にヴェールをかぶり、祈りの姿勢を取っています。 ・赤い衣服は高位の淑女の象徴で、夫に並んで眠る姿は「夫婦の結合が死後も続く」ことを 意味します と。ウェストミンスター寺院の回廊(Cloisters)。・写真中央に見えるのは、ゴシック様式の尖頭アーチと精巧な石彫の窓飾り(トレーサリー)を 持つ回廊の壁。・下部には細い柱が並び、その奥は回廊の歩廊部分になっています。・手前は芝生の中庭(cloister garth)で、修道院時代の僧たちが祈りや瞑想を行った場所です。回廊(Cloisters)の役割:ウェストミンスター寺院は元々ベネディクト会修道院として建てられており、この回廊は 修道士の生活の中心空間。・回廊は四辺で囲まれた中庭をもち、食堂(refectory)、図書室、寝室などに通じていた。・現在は見学者も通れる場所で、展示や記念碑(戦争記念プレートなど)も設置されていた。回廊(Cloisters)と北西塔の外観。手前はCloister Garth(クロイスター・ガース)と呼ばれる回廊に囲まれた中庭。元々は修道士が瞑想や読書、祈りを行った空間。現在は観光客が散策可能であった。左手にそびえる二本の塔は ウェストファサードの北西塔(North West Towers)。高い垂直の白い柱は、身廊(Nave)や翼廊を支える フライング・バットレス(飛梁)。回廊(Cloisters)から内陣(Sanctuary / Choir)と南翼廊(South Transept)方向を見上げた景観。1.フライング・バットレス(Flying Buttresses)・左側の高い外壁に沿って張り出しているアーチ構造がフライング・バットレス。・ゴシック建築の特徴で、巨大な窓を持つ高い壁を外側から支えています。・ステンドグラス窓を多く設けるために必須の構造。2.中央の高い塔屋風の部分・内陣(Sanctuary)の南側付近。・下部に尖頭アーチの大窓、上部に八角形の小塔(turrets)が見られます。・内部は聖歌隊席や聖壇近くにあたる重要な部分。・右手に鋭角の見えた八角屋根(コーン型)はChapter House(会議室) の屋根。 ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の正面(西正面)付近から、北方向にあったのが、・Methodist Central Hall Westminster(メソジスト・セントラル・ホール)。・1912年に建てられたメソジスト教会の本拠であり、現在は国際会議・コンサート・式典なども 行われる多目的ホール。・第二次世界大戦後、最初の国連総会が開かれた歴史的建物。中央やや左の高い石柱は・The Crimean War Memorial(クリミア戦争記念柱)、または Broad Sanctuary Memorial Column (聖ジョージ像付き記念柱)と 呼ばれるモニュメント。・19世紀半ばのクリミア戦争で戦死した近衛兵を記念して建てられた。・最上部の人物像 ・聖ジョージ(St. George):イングランドの守護聖人。 ・手に槍(または剣)を掲げ、足元にはドラゴンを踏みつけている。 ・「聖ジョージと竜退治」の象徴で、勇気と信仰の勝利を示す。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の西正面入口(West Front)。1.大窓(中央上部) ・ゴシック様式の大きなステンドグラス窓。 ・内部は西端の大窓(West Window)として知られ、宗教画ではなく幾何学模様のガラスが 多いのが特徴。2.聖人像の列(ニッチ内の彫像群) ・西正面中央に並ぶ像は、20世紀の殉教者たちの像(Ten Modern Martyrs)。 1998年に設置された比較的新しい像群で、伝統的な聖人だけでなく、20世紀に殉教した 人物を讃えている。 ・例えば: ・マクシミリアノ・コルベ(ナチス収容所で殉教したポーランドの神父) ・マルティン・ルーサー・キング牧師(アメリカ公民権運動の指導者) ・オスカー・ロメロ大司教(エルサルバドルで暗殺されたカトリック大司教) ・アフリカやアジアで殉教した人物など。ロンドンのパーラメント・スクエア(Parliament Square) を写したもの。右側には有名な時計塔 「ビッグ・ベン(エリザベスタワー)」 がそびえていた。中央の広場(Parliament Square Garden)には、各国の著名人の像が並んでいたのであった。(ガンジー、ネルソン・マンデラ、ウィンストン・チャーチルなど)。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.26
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その89): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-4
さらにWestminster Abbeyのステンドグラスをカメラで追う。・左側の人物(青衣・冠) ・王冠をかぶり、青いマントを纏った王の姿。 ・伝統的に「聖王エドワード懺悔王(Edward the Confessor)」として描かれることが多い姿。 ・ウェストミンスター寺院はエドワード懺悔王が創建した修道院を前身とするため、彼の像や 窓は特に強調されています。・右側の人物(赤衣・冠) ・王冠と赤いマント、手に巻物(法や統治を象徴)。 ・「ヘンリー3世(Henry III)」を描いている可能性が高いです。 ・ヘンリー3世はウェストミンスター寺院の再建(13世紀ゴシック様式への改築)を行った王で、 エドワード懺悔王の聖性を顕彰しました。ステンドグラス最下段にラテン語の銘文が帯状にあり、左窓には「EDWARDUS CONFESSOR REX」。右窓には「HENRICUS TERTIUS REX」 などと王名が記されていた。人物をズーム。再びウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の内陣(Sanctuary)とクワイア(Choir)方向 を。・ゴシック様式の高いリブ・ヴォールト天井 縦方向の高さを強調する垂直線が続き、イングランド・ゴシックの典型的なスタイル。・左右に並ぶ巨大なパイプオルガン 精緻な装飾が施されたオルガンは、合唱隊席(Choir Stalls)の上部に設置。・手前の金色の装飾スクリーン(Rood Screen / Choir Screen) ゴシック・リヴァイヴァル様式で復元された荘厳なスクリーンで、聖域と参拝者の場を区切る 役割を果たす。左側:アハズ王 (King Ahaz)・赤いマント、王冠、笏を持つ。・旧約聖書『列王記』などに登場、ユダ王国の王。偶像崇拝の傾向が強く「不信仰な王」として 描かれる。右側:ヒゼキヤ王 (King Hezekiah)・青いマント、王冠、笏を持つ。・ユダ王国の王で、宗教改革を行い偶像を排し、神への信仰を回復させた「善王」として知られる。人物をズームして。このステンドグラスは 旧約聖書に登場するユダ王国の王 を描いた窓であり、左:アハズ王(King Ahaz) ― 在位16年右:ヒゼキヤ王(King Hezekiah) ― 在位29年左側:ヨシャパテ王 (King Jehoshaphat)・青いローブ、王冠と笏を持つ。・南ユダ王国4代目の王で、在位25年(列王記上22章・歴代誌下)。宗教的改革を進め、 神殿礼拝を強調した。右側:ヨラム王 (King Jehoram)・赤いローブ、王冠を戴く。・ヨシャパテの子、ユダ王国の5代目の王。在位8年。バアル崇拝を導入し「悪王」として描かれる。人物をズームして。このステンドグラスは 旧約聖書のユダ王国の王 を描いており、・左:ヨシャパテ王(King Jehoshaphat) ― 在位25年・右:ヨラム王(King Jehoram) ― 在位8年さらにユダ王国の歴代の王を並べたステンドグラスが続いていたのであった。左側:アハズ王 (King Ahaz)・赤衣、王冠と笏を持つ。・南ユダ王国12代の王。在位16年(列王記下16章・歴代誌下28章)。 偶像崇拝を行い「悪王」とされた。右側:ヒゼキヤ王 (King Hezekiah)・青衣、笏と巻物(律法書?)を手にする。・アハズの子でユダ王国13代の王。在位29年(列王記下18章・歴代誌下29章)。 宗教改革を行い、アッシリア侵攻の危機に信仰をもって立ち向かった「善王」。このステンドグラスは「親子二代のユダ王」を描いていた。左:マナセ王(King Manasseh)・白い衣に赤マント、王冠を戴く。・ヒゼキヤ王の子でユダ王国14代の王。最長の55年間在位。偶像崇拝を強め、歴代の中でも 最悪の王とされるが、晩年に悔い改めたと伝えられる。右:アモン王(King Amon)・青衣に王冠。マナセの子で15代の王。・在位はわずか2年で暗殺され、その子ヨシヤに王位が継承された。以上、これらのステンドグラス配置の特徴は・各窓は左右2名の王を一対で描写・下部に ラテン語・英語銘文 で「KING XXX REIGNED YY YEARS」と刻まれている・王冠を戴き、色分けされた衣装(赤=偶像崇拝傾向の王、青=信仰的な王)という対比の意匠が 見られるのであった。再び、ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)身廊(Nave)の西端方向を見る。・身廊西端(West End) に巨大な二層の窓があり、そこに「ユダ王国の王たち( Kings of Judah)」が縦列で並んでいた。・各窓は 上下二段構成 × 左右ペア で、一対ごとに2名の王が描かれる形式。・合計で 10対(20名程度)が描かれていた。・実際の歴代ユダ王は20人(ソロモン以降〜ゼデキヤまで)なので、全王が網羅されている シリーズ と。このステンドグラスは、ウェストミンスター寺院の身廊西端・大窓の下段にあるステンドグラスの一部 で、今まで見てきた「ユダ王国の王シリーズ」とは異なり、旧約〜新約の物語場面(主に神殿に関する場面)を描いた物語窓。左側(左ランセット)最下段・「SOLOMON DEDICATES THE TEMPLE」・ソロモン王が神殿を奉献する場面。香炉・祭壇と共に祈る姿。中段・「HEZEKIAH SHOWS THE TREASURES TO ENVOYS」・ヒゼキヤ王がバビロンの使者に宝物を見せる場面。上段・「JOSIAH READS THE BOOK OF THE LAW」・ヨシヤ王が律法の書を民に読み聞かせる場面。宗教改革を象徴。右側(右ランセット)最下段・「JESUS IN THE TEMPLE」・少年イエスが神殿で教師たちと議論する場面(ルカ2章)。中段・「PURIFICATION OF THE TEMPLE」・イエスが神殿から商人を追い出す場面。上段・「CHRIST AMONG THE DOCTORS」・神殿における律法学者との論争(こちらも幼少期イエスのエピソード)。ズームして。西端大窓下段にある一枚で、今度は「歴代の王と新約の場面」を組み合わせた構成に。上段(左ランセット)・王冠とマントをまとった王の姿。・これまでのユダ王国の王シリーズと同じ様式。上段(右ランセット)・同様に王冠とマントを着けた別の王の像。・これもユダの王を表す連続シリーズの一部。上部の円形トレーサリーには「天上のキリスト」または「神の小羊」の象徴的図像が配置されていた。人物像をズームして。上段:ユダ王国の王(王冠・マント姿の二人)。下段:復活したキリスト(または昇天)と信徒たち。ウェストミンスター寺院 (Westminster Abbey) の「無名戦士の墓 (Tomb of the Unknown Warrior)」。「BENEATH THIS STONE RESTS THE BODYOF A BRITISH WARRIORUNKNOWN BY NAME OR RANKBROUGHT FROM FRANCE TO LIE AMONGTHE MOST ILLUSTRIOUS OF THE LANDAND BURIED HERE ON ARMISTICE DAY11 NOV: 1920, IN THE PRESENCE OFHIS MAJESTY KING GEORGE VHIS MINISTERS OF STATETHE CHIEFS OF HIS FORCESAND A VAST CONCOURSE OF THE NATION.THUS ARE COMMEMORATED THE MANYMULTITUDES WHO DURING THE GREATWAR OF 1914–1918 GAVE THE MOST THATMAN CAN GIVE, LIFE ITSELFFOR GODFOR KING AND COUNTRYFOR LOVED ONES HOME AND EMPIREFOR THE SACRED CAUSE OF JUSTICE ANDTHE FREEDOM OF THE WORLD.THEY BURIED HIM AMONG THE KINGS BECAUSE HEHAD DONE GOOD TOWARD GOD AND TOWARDHIS HOUSE.+ + + IN CHRIST SHALL ALL BE MADE ALIVE + + +」 【この石の下には名も階級も知られぬ一人の英国の戦士の遺体が眠る。彼はフランスからここへ運ばれ、この国で最も顕著なる人々の間に葬られた。1920年11月11日の休戦記念日、ジョージ五世国王、国務大臣たち、軍の総司令官たち、そして全国から集まった群衆の臨席のもとで。ここに記念されるのは、1914–1918年の大戦において、人が捧げうる最も大いなるもの ―すなわち命そのものを捧げた<無数の人々である。神のために、国王と祖国のために、愛する者と家庭と帝国のために、正義という神聖な大義のために、そして世界の自由のために。彼を王たちの中に葬ったのは、彼が神とその家(神の家=教会)に良きことをなしたからである。キリストにあってすべての者は生きるであろう。】歴史的背景・埋葬:1920年11月11日(休戦記念日)・埋葬場所:ウェストミンスター寺院・身廊中央部・意義:第一次世界大戦で命を落としたが、身元不明の兵士を代表して葬られた。・国王ジョージ五世、首相ロイド・ジョージらが参列。・この「無名戦士の墓」は、世界で最初期の「無名戦士記念碑」として各国に広まるきっかけと なった。ナーブ(nave=身廊)中央付近から内陣(sanctuary, choir, high altar 方向)を東側に向かって見上げて。聖歌隊席(Choir Stalls)。内陣(Sanctuary, High Altar)の手前、ナーブ(Nave/身廊)と内陣を区切る部分に位置。1.装飾スタイル・ゴシック様式の華やかな尖塔アーチ装飾。・金色の木彫細工と青地の布張り背景。・赤いシェード付きのランプが並ぶ。2.刻まれている名前・紋章・左から順に AUSTRALIA(オーストラリア), CANADA(カナダ) と国名が確認できる。・その上には 各国の紋章(Coat of Arms) が掲げられている。・中央部分には赤地に金文字で HIGH COMMISSIONER(高等弁務官) と書かれた席。3.意味・これらの席は、ウェストミンスター寺院における重要な儀式(特に戴冠式や国王即位式)で、 英連邦の代表(High Commissioners)が着席するための場所。・英連邦諸国は英国王を元首とする連合体であり、戴冠式などの国家儀礼に際して公式代表が 招かれる・Choir Stalls の両側には、こうした 英連邦諸国を象徴する席(プレートと紋章付き) が並ぶ。再び、内陣(Sanctuary/Quire 付近)を東向きに見上て。天井(Vaulting)・見えるのは壮大な リブ・ヴォールト(rib vault)。・白い石造天井に金色のボス(天井装飾結節)が連なっているのが特徴。・ゴシック建築の典型的な垂直性と荘厳さを強調している。両側のパイプオルガン・左右に大規模な パイプオルガンのパイプ群 が壁を覆うように配置。・このオルガンは戴冠式や国葬など、寺院の大儀式に欠かせない。前景の金色の装飾ゲート・手前に見えるゴシック様式の三角破風(ピナクル付き)は、・内陣(Sanctuary)とクワイヤ席を区切るスクリーン(Choir Screen / Rood Screen) の一部。・金色の繊細な透かし彫りと、中央の円形メダイオン(十字紋章)が特徴的。身廊(Nave)と内陣(Choir / Sanctuary)、そして北・南の翼廊(Transepts)が交わる 交差部(Crossing) を下から見上げて。天井はゴシック様式のリブ・ヴォールト(rib vault)で、金色のボス装飾がリズミカルに配置されていた。1.クリアストーリー(Clerestory)窓・高所に設けられた大きな窓から光が差し込み、空間を明るく演出。・窓は二連窓+円形窓という典型的なゴシック様式。2.トリフォリウム(Triforium)回廊・中層に見えるアーチ列の部分は、トリフォリウムと呼ばれる回廊。・ここもウェストミンスター寺院の特徴で、細身の柱が連続して垂直性を強調している。3.下部:祭壇部・手前下に見える金色のパネルは、High Altar(大祭壇) の背後にあるリードスクリーン。・王室儀式の中心的舞台。近づいて。これでもかとバラ窓を。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)のクワイア(Choir/聖歌隊席)から大祭壇(High Altar)を見た光景(ピンボケでしたのでネットから)。手前(左右の木製席)・ここは クワイア席(Choir stalls)・ゴシック風の尖塔型装飾が施された木製の高い背もたれ。・赤いランプシェードが付いた燭台がずらりと並び、夜間や儀式の際に荘厳な雰囲気を演出します。・ここには聖歌隊や聖職者が座り、聖歌を歌う場となります。中央通路(Quire Aisle)・クワイア席の間を進む参道。・この先に大祭壇(High Altar)とその背後のリードスクリーン(Reredos)が見えています。大祭壇(High Altar)・金色に輝く壮麗な装飾。・中央の絵画部分は 「最後の晩餐」を描いたモザイク/彩色パネル。・戴冠式の際に国王・女王が跪き聖別される場所です。背後の高窓(East End Clerestory)・大きなゴシック様式の尖頭アーチ窓。・そこから柔らかな光が差し込み、祭壇を神聖に照らします。大祭壇(High Altar)とコスマティ床(Cosmati Pavement)。 1. 大祭壇(High Altar)・金色の壮麗なリードスクリーン(Reredos)が背景に立ちます。・中央パネルは 「最後の晩餐(The Last Supper)」 を描いたモザイク/彩色作品。・キリストと十二使徒が描かれ、聖体の秘跡(Eucharist)の象徴です。・両脇には聖人像が立ち、天蓋風の装飾が重厚さを加えている。2. コスマティ床(Cosmati Pavement)・1268年にヘンリー3世がイタリアから職人を呼び寄せて造らせた、大理石・ガラス・貴石を 使った幾何学模様の床。・円・四角・三角が組み合わされ、宇宙と永遠を象徴。・中央円は「宇宙の中心」を表すとされ、戴冠式で王が立つ場所。・英国王の戴冠はここで行われ、エリザベス2世(1953年)、チャールズ3世(2023年)も この床の上で戴冠した。3. 位置と機能・この空間は サンクチュアリ(Sanctuary) と呼ばれ、聖域の最も重要な場所。・王の戴冠式の際には、「戴冠の椅子(Coronation Chair)」 がこのコスマティ床の中央に 置かれる と。ウェストミンスター寺院の大祭壇(High Altar)背後のリードスクリーン(Reredos)中央部。1. 上部の銘文(ラテン語ではなく英語) 最上段に金文字で刻まれている文章: “THE KINGDOMS OF THIS WORLD ARE BECOME THE KINGDOMS OF OUR LORD AND OF HIS CHRIST” ➡ 新約聖書「ヨハネ黙示録 11章15節」からの引用。 意味は:「この世の国は、我らの主とそのキリストの国となった」。 → キリストが全世界の王であることを示し、戴冠の場にふさわしい言葉。2. モザイク画の場面中央の大きなモザイクは 「最後の晩餐(The Last Supper)」。・中央:キリスト(後光付き)・左右:12使徒たち(ユダはしばしば別の位置・表情で描かれる)・様式:19世紀ヴィクトリア時代に再構築されたモザイクで、ゴシック様式の金色背景に映える。3. 周囲の装飾・上部は金色のゴシック様式の「天蓋装飾」(crocketed canopy)。天上界の象徴。・左右には聖人像が立つ(楽器や巻物を手にし、旧約・新約の預言者・使徒を象徴)。・下部(祭壇前の白大理石部分)には 紋章(シールド)模様 が並び、歴代の修道院・王家と 関係するもの。大祭壇(High Altar)側から、振り返って西方(身廊・正面入口方向)を見て。こちらはうまく撮れました。ウェストミンスター寺院・北翼廊(North Transept) の一角へ。以下の武人の彫像(ひざまずく2人の騎士と甲冑飾り)や、横たわる女性像(Lady Catherine St John)もこの一帯に位置していた。南翼廊にあったサー・フランシス・ヴァーノン(Sir Francis Vere, 1560–1609) の墓碑。・彼はエリザベス1世時代の著名な軍人で、オランダ独立戦争で活躍。・ウェストミンスター寺院の南翼廊(South Transept, Poets’ Cornerの反対側)に立派な モニュメントが残されていた。・特徴的なのは、武人の像が棺を担ぐように配置され、上に兜が置かれている構図。正面から。Lady Catherine St John(カタリナ/キャサリン・セント・ジョン)墓。女性が横たわって肘枕をし、くつろいだような姿勢で表現されていた。服装は16世紀末~17世紀初頭の貴婦人のドレス(ラフ襟、長い袖、プリーツスカート)。北翼廊(North Transept) にある大規模な墓廟で、サー・ジョージ・ヴィリアーズ(Sir George Villiers, 1550–1606)とその妻メアリー・ボーモントの墓碑・Monument of Sir George Villiers and Dame Mary, Countess of Buckingham。・大きな天蓋(キャノピー)をもつ建造的なモニュメント。・下段には横たわる夫婦の遺体像、その両側に祈る姿の像が配置されていた。・上段の四角いパネル部分には浮彫(レリーフ)があり、茶色がかった石材 (大理石・アルバスター)で作られていた。・大きな キャノピー(天蓋) に支えられた棺。・棺の手前側に 甲冑姿の3人の息子像 がひざまずいて祈っている姿。 息子3人(甲冑・跪像:写真の手前側) ・John Villiers(後のパーブック子爵) ・George Villiers(後の初代バッキンガム公) ・Christopher Villiers(後のアングルシー伯) ・反対側(壁側)にもドレス姿でひざまずく女性像がいる と。聖エドワード礼拝堂近くにあったのがウェストミンスター寺院の700年の歴史を持つ戴冠式の椅子「戴冠の椅子(Coronation Chair)」をガラス越しに撮影。材質:オーク材装飾:かつては金箔や彩色が施され、動物や使徒の像も描かれていたと伝わります。獅子像:椅子の脚部には4体の金色の獅子が配置され、王権の象徴を示します。 現在見える獅子像は19世紀に補修されたものです。椅子の背面には、多くの落書き(見学者や聖職者による名前・記号)が残されており、中世から近代までの参観者の存在を示していると。ウェストミンスター寺院での戴冠式中のエリザベス2世女王 の写真をネットから。西大窓(West Window) のステンドグラスを再び。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.25
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その88): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-3
Westminster Abbeyの堂内に入る。案内図。①The north transept 北翼廊(聖堂の横断部、北側の翼)②The choir 聖歌隊席(クワイア)/聖歌隊席部分 ③The sanctuary 内陣(祭壇周辺の聖域)④The Chapel of St. Edward 聖エドワード礼拝堂⑤The Lady Chapel 聖母マリア礼拝堂(通称:レディ・チャペル)⑥The south transept 南翼廊(聖堂の横断部、南側の翼)⑦The main nave 中央身廊(大身廊)⑧The cloisters 回廊(クロイスター)⑨The Chapter House 参事会室(チャプター・ハウス)⑩The Pyx Chamber ピクス室(Pyx=聖体容器を保管する部屋)入口直後の北の翼廊にあったのが、ウィリアム・マーレイ(初代マンスフィールド伯, William Murray, 1705–1793) の記念碑。1.中央上段・マンスフィールド伯爵本人が裁判官のローブとカツラを身にまとい、裁きの座に座る姿で 表現されています。・威厳ある椅子は円形で、ギリシア風の幾何学文様が施されています。2.両脇の寓意像・左:Justice(正義) — 右手を掲げ、断固とした態度を示す女性像。・右:Wisdom(知恵) — 頭に兜をかぶり、大きな書物を手にする女性像 (アテナ/ミネルヴァ的姿)。3.基壇部・マンスフィールド家の紋章(盾と星、王冠)と、ファスケス(権威の象徴)などが飾られて います。4.背景アーチ下の三像(後方の人物群)・立像①:裁き(Justiceの補助的表現) ・巻物を持つ人物。法と判例の継承を象徴。・立像②:知恵(Wisdom / Eloquence) ・演説や弁論を思わせるポーズ。 ・マンスフィールド伯の弁論能力・雄弁を象徴。・立像③:力または秩序(Fortitude / Authority) ・堅固な姿勢で佇む。 ・秩序の維持と法の強さを象徴。「"Here Murray long enough his country's pride is now no more than Tully or than Hyde".Foretold by Ar. Pope and fulfilled in the year 1793 when William Earl of Mansfield diedfull of years and of honours: of honours he declined many: those which he accepted were the following: he was appointed Solicitor General 1742, Attorney General 1754,Lord Chief Justice and Baron Mansfield 1756, Earl of Mansfield 1776. From the love which he bore to the place of his early education, he desired to be buried in this cathedral (privately) and would have forbidden that instance of human vanity, the erecting a monument to his memory, but a sum which with the interest has amountedto two thousand five hundred pounds was left for that purpose by A.Bailey Esqr. ofLyon's Inn, which at least well meant mark of esteem he had no previous knowledge or suspicion of and had no power to prevent being executed. He was the fourth son of David,fifth Viscount Stormont, and married the Lady Elizabeth Finch, daughter to Daniel, Earl of Nottingham by whom he had no issue. Born at Scone 2nd March 1704. Died at Kenwood 20th March 1793.」 【ここに眠るのは、長らく祖国の誇りであったマーレイ。今や彼もまた、トゥリー(キケロ)やハイドと同じく過去の偉人にすぎない。詩人ポープによって予言され、1793年に成就した。この年、ウィリアム・マンスフィールド伯は、数多の栄誉と長寿の末に没した。彼は多くの栄誉を辞退したが、受けたものは以下の通りである。法務次官(Solicitor General, 1742年)法務長官(Attorney General, 1754年)王国高等法院長官・マンスフィールド男爵(Lord Chief Justice & Baron Mansfield, 1756年)マンスフィールド伯爵(Earl of Mansfield, 1776年)彼は若き日に学んだこの大聖堂への愛情から、人知れずここに埋葬されることを望み、虚栄の証としての記念碑の建立を固く禁じたであろう。しかし、彼の遺志により少なくとも2,500ポンドが遺され、利子を含めて3,500ポンドに達し、これによってこの記念碑はリヨンズ・インのジェームズ・ベイリー氏によって建立された。彼は敬意と尊崇の念からこれを遂行したのであり、遺贈の存在を事前に知っていたわけでも、拒む権限があったわけでもなかった。彼は第5代ストーモント子爵デイヴィッドの四男として生まれ、ノッティンガム伯ダニエルの娘エリザベス・フィンチ夫人と結婚したが、子はなかった。1704年3月2日、スコーンに生まれ、1793年3月20日、ケンウッドにて没した。】裏側に廻って。「沈思の若者像(Melancholy / Meditation)」が半ば隠れる形で配置されていた。大きな円筒形の台座にラテン語「UNI ÆQUUS VIRTUTI」と。「UNI ÆQUUS VIRTUTI」・「ただ一人、徳(美徳)に比肩する者」・直訳すると「徳にのみ比するに値する唯一の人」・意味合いとしては「その人物(マンスフィールド伯)の価値は、美徳に等しいただ一つの存在」 という称賛の表現」 であると。ウェストミンスター寺院の「法曹関係者のコーナー(Lawyers' Corner / North Transept の一角)」 を。・正面奥に見えるのは北翼廊(North Transept)の突き当たり。・写真右手に並んでいるのは法曹関係者(判事・法学者)や政治家の記念碑群。 胸像や立像が壁に沿って配置されていた。・その中に ウィリアム・マーレイ(初代マンスフィールド伯, 1705–1793) の大きな記念碑も 含まれていた。北翼廊(North Transept)の北端正面(北壁)上部のステンドグラス。ズームして。さらに近づいて見上げて。北翼廊突き当たり(北壁)のバラ窓(Rose Window) を正面から。バラ窓(Rose Window)の特徴・位置:ウェストミンスター寺院北翼廊の最上部中央。・様式:放射状に広がるゴシック様式の tracery(石枠)で、中心から花弁状に彩色ガラスが展開。・中心部:中央円盤に キリスト(栄光のキリスト/Christ in Majesty) が座している姿。・周囲:放射状のパネルには、旧約・新約の人物や天使、聖人、王冠を戴く象徴的存在が 配置されている。・色彩:赤・青・金を基調とし、花のような繰り返しパターンで「天上の調和」を表現。・北翼廊のバラ窓の直径は、おおよそ10メートル と。中心をズームして。先程見た外からの写真を再び。バラ窓の下層に展開する上下2段構成の一群のステンドグラス。縦長の尖頭アーチ窓が連続して並び、その中に 聖人や預言者の人物像 が一人ずつ描かれていた。上段(Clerestory)6人左から右へ:1.聖人像(緑の外套) – 預言者、もしくは旧約の人物か。緑は「希望・再生」の象徴。2.聖人像(青い衣) – 使徒(ヨハネ?)の可能性。青は「信仰・霊性」を象徴。3.聖人像(茶色系の衣) – 預言者または使徒。茶は「謙遜・労働」を意味。4.聖人像(赤の外套) – 殉教者を示す場合が多い(例:聖ペテロ、聖パウロ)。5.聖人像(白衣+赤外套) – 教会博士か、殉教した司教系聖人。白衣は「純潔」、 赤は「血の殉教」。6.聖人像(青衣+巻物?)– 預言者か使徒で、「巻物=神の言葉を伝える」役割を示す。下段(Triforium 上部窓)6人左から右へ:・聖人像(茶色系の衣) – 預言者系(例:アモス、ハバクク)。質素な衣装は「旧約の預言者」を 想起させる。・聖人像(赤マント+白衣) – 殉教者使徒か、教父(例:聖アンブロシウス)。赤は殉教、白は 清浄を表す。・聖人像(青衣、巻物を持つ) – 典型的に旧約預言者(イザヤ、エレミヤ)。巻物=予言の象徴。・聖人像(緑衣+主教冠=司教像) – 確実に「司教聖人」。西方教会博士(例:聖グレゴリウス、 聖アウグスティヌス)の可能性。・聖人像(青衣+書物を持つ) – 書物=福音書記者の象徴。おそらく 「福音記者(エヴァンジェリスト)」の一人。・聖人像(赤外套+冠?)– 詳細未確認、王的な聖人(例:聖エドワード懺悔王)の 可能性もあり。北翼廊(North Transept)東側壁にあった記念碑群。正面中央:James Stanhope, 1st Earl Stanhope(第1代スタンホープ伯ジェームズ・ スタンホープ, 1673–1721)記念像。 軍服風の姿で立ち、足元に戦争を象徴する具象彫刻が見られます。右奥(大きな台座に劇的な群像):General Sir James Outram(ジェームズ・アウートラム卿, 1803–1863)記念碑。 インドでの功績を記念するモニュメントで、英雄的な姿が 高台に立ち、下部には兵士や象徴的人物が表現されています。北翼廊は「ステーツマン(政治家の角)」とも呼ばれ、チャタム伯やパーマストン子爵、スタンホープ伯ら多くの政治家・軍人記念碑が集中していた。海軍軍人たちを讃える記念碑。碑文に刻まれているのは次の3名の海軍士官:・Captain William Bayne(ウィリアム・ベイン艦長, 1730–1782)・Captain William Blair(ウィリアム・ブレア艦長, 1741–1782)・Captain Lord Robert Manners(ロバート・マナーズ卿艦長, 1758–1782)いずれもアメリカ独立戦争期(特に西インド諸島での戦闘)で戦死した若きイギリス海軍の英雄たち。彫刻の構成上部中央:勝利の女神ニケ(Victory)像。ラッパを持ち(吹き)ながら戦勝を告げる姿。左側:女性像(おそらくブリタニア Britanniaを象徴)、盾と槍を持つ。中央:円形のメダリオン(肖像)に戦死した艦長たちの顔が彫り込まれている。下部:海の神(ネプチューン/トリトン的存在)が横たわり、海戦を象徴する。右手奥には別の擬人像が配置され、全体として「海軍の栄誉・犠牲・勝利」を表現。北翼廊(North Transept)西寄り壁面、有名な「Statesmen’s Corner(政治家・軍人の墓所)」の一角にあった像。主な特徴と人物1.中央奥の大きな黒い墓碑とバロック風の建築的モニュメント・これは Sir Francis Vere(フランシス・ヴェア卿, 1560–1609) の墓所。・オランダ独立戦争に従軍したイングランド軍人で、スペインとの戦いで名を馳せました。・棺の上には「甲冑姿で眠るヴェア卿」が彫られ、その周囲を戦士像や寓意像が囲んでいます。2.その手前に並ぶ3体の立像・これらは 17〜18世紀の著名人物(多くは聖職者や政治家) の記念像です。・左から順に ・18世紀の神学者/司教像 が並ぶ。 ・中央と右の像も聖職者で、手に聖書や巻物を持つ姿が多い。 ・写真だけでは個々の名を断定しづらいですが、位置的に John Conduitt(アイザック・ ニュートンの義理の息子)、William Wilberforce(奴隷貿易廃止の活動家) などが 北翼廊の近隣に並んでいた。General James Wolfe。ジェームズ・ウルフ将軍(ケベックの戦いで戦死) の墓碑。南翼廊のPoets’ Corner入口付近の並びに隣接して配置されていた一枚。現代英国の芸術家が制作した抽象ステンドグラス。マルク・シャガール(Marc Chagall)風のモダンな作風で知られるが、第二次世界大戦後に破損した窓を置き換えるために設置されたもの と。ウェストミンスター寺院では、戦後に失われたゴシック期の窓の一部を「伝統的再現」ではなく「現代アート作品」で補っている。そのため、この窓も「平和」「再生」「自然の命の流れ」をテーマにした抽象的作品になっている と。もうひとつは縦長二連窓のステンドガラス。・細かいパネル分割に多人数の場面(人物・紋章・聖書場面)を描く。・赤・青・茶の強い彩色、モザイク的に人物が重なっていた。・下部には白地に黒文字で説明文(寄進銘)が入っていた。ここは ウェストミンスター寺院・南回廊(South Transept)の一角、いわゆる Poets’ Corner(詩人のコーナー)近辺で上記のステンドガラスの下部。・手前は現在の「受付・インフォメーションカウンター」として使われている場所・後方の壁面に並ぶ胸像や碑文は、詩人や文人の記念碑(17〜19世紀のものが多い)・左上の抽象的ステンドグラスは 20世紀以降に設置された現代作品・右上の細密ステンドグラス(二連窓)は 19世紀ヴィクトリア朝の新制作窓南翼廊の Poets’ Corner を。・手前に黄色い受付カウンター(前の写真と同じ)・左右の壁面にぎっしりと文学者や詩人の胸像・記念碑・奥の壁全体を占める巨大な記念碑群(多層アーチ型ニッチの中に多数の立像)・天井はゴシック様式の高いリブ・ヴォールト、細長い窓から光が入っている奥に見える大記念碑・奥に大きく写っているのは 、ウィリアム・マーレイ(初代マンスフィールド伯, William Murray, 1705–1793) の記念碑。大きな記念碑は ウィリアム・マーレイ(初代マンスフィールド伯, William Murray, 1705–1793)の記念碑。この記念碑の奥に配置されているアーチ下の3体の像は、寓意像(Allegorical figures)で、マンスフィールド伯爵の生涯・功績を象徴しています:上段のアーチ下の3体の寓意像・中央:Prudence(思慮深さ/慎重さ) ・長衣をまとった立像。慎重さ・遠見の徳を象徴。・左:Diligence(勤勉)または Labour(労働) ・半裸で横たわる男性像。肉体労働や努力を象徴。・右:Fortitude(不屈/忍耐)・肉体をひねる姿の男性像。逆境に耐える力を表現。南翼廊・Poets’ Corner の一角にある記念碑のひとつ。。ジョン・ドライデン(John Dryden, 1631–1700) の記念碑。・イギリスの詩人・劇作家・批評家で、王政復古期を代表する文学者。・1700年に埋葬され、1720年にこの豪華なモニュメントが建立。・金色の装飾と横たわる黒い石像が特徴。ウェストミンスター寺院の側廊(サイドアイル)南廊を撮影。・ゴシック様式の尖頭アーチが連続する天井(リブ・ヴォールト) を見上げる構図。・左右に連なる円柱列は 身廊(ネイヴ)または翼廊の側廊部分 に典型的な意匠。・奥に見える光はステンドグラス窓いやピンボケ。Westminster Abbey の Poets’ Corner(南翼廊の南壁)にある記念碑群 。左:Matthew Prior(詩人)の記念碑中央:Nicholas Rowe(劇作家・詩人)の記念碑右:Congreve あるいは同時代詩人の碑の一部これも「詩人の隅(Poets’ Corner)」にあった ジョセフ・アディソン(Joseph Addison, 1672–1719) の記念碑。・中央に横たわる姿の大理石像:左手に本を持ち、落ち着いたポーズをとる人物がアディソン。・周囲に2体の寓意像(左:瞑想する女性像、右:静かに佇む女性像)、さらに上部に 小さな天使像。・左側に円形レリーフの肖像と「MICHAEL WILLIAM BALFE(1808–1870)」と刻まれた 作曲家の別碑が付随して設置されているのもPoets’ Corner特有の配置。フランシス・アトバリー主教(Francis Atterbury, 1663–1732) の記念碑。・中央:横たわる姿の大理石像(枕に寄りかかる姿の司教像、足元に天使像)。・上部:黒大理石の背景に金色装飾付きのカーテン風デザイン。・下部:2体の幼児(プットー)が膝まずいて支える構図。・両側:右に書物を手にした人物像、左に思索する姿勢の人物像(寓意像)。ジェームズ・プレスコット・ジュール (James Prescott Joule, 1818–1889) の記念碑。1. 左下の銘板・Joseph Dalton Hooker (1817–1911) のレリーフ肖像 → 植物学者、ダーウィンの友人でもあり、キュー植物園の発展に貢献した人物。2. 中央の白い銘板・James Prescott Joule (1818–1889) の記念碑銘 ・「ニュートン、ハーシェル、ダーウィンの列に並ぶ人物として」称えられている ・エネルギー保存の法則、熱の機械的当量を確立した物理学者 ・「ジュール (J)」の単位名で有名3. 壁面上部の円形レリーフ(5点)左から順に:・黒のレリーフ:別の科学者(暗いため識別困難、ニュートンかハーシェルの可能性あり)・白のレリーフ:アイザック・ニュートン (Isaac Newton)・白のレリーフ:ウィリアム・ハーシェル (William Herschel)・白のレリーフ:チャールズ・ダーウィン (Charles Darwin)・黒のレリーフ:別の科学者?ウェストミンスター寺院 (Westminster Abbey) 内部、北翼廊(North Transept)。1.高いゴシック天井のリブ・ヴォールト・細い柱が天井に伸び、リブ・ヴォールト(交差リブ穹窿)が明確に見えています。・ウェストミンスター寺院特有の縦に強調されたゴシック様式。2.右壁に沿った記念碑群・白い大理石の壁に、人物の胸像や碑文が並んでいます。・これは「科学者・政治家・文化人の記念碑」が並ぶ一角。3.奥に見えるステンドグラス・廊下の先端に明るく見えるステンドグラス。ステンドグラスをズームして。・中央に 赤と青の衣をまとった立像が描かれています。・頭部は光輪に縁取られた人物で、聖人またはキリスト像と考えられます。・手に持つものははっきり見えませんが、巻物か本のように見えるため「聖職者」や 「預言者」か。・具体的な人物名は??二連のランセット窓には、聖人像が描かれていた。左側の窓(赤衣の人物の下) ・IN MEMORY OF BARON STRATHCONA AND MOUNT ROYAL B. 1820 ドナルド・アレグザンダー・スミス(Donald Alexander Smith, 1st Baron Strathcona and Mount Royal, 1820–1914) を記念した献辞右側の窓(青衣・冠の人物の下) ・A GREAT CANADIAN IMPERIALIST AND PHILANTHROPIST D. 1914 「偉大なカナダの帝国主義者であり慈善家」=同じく ストラスコナ卿を指しています。 没年「1914」は彼の死去の年と一致。二連のステンドグラスは 人物(聖書の預言者と王)そのものの顕彰 ではなく、「ストラスコナ卿(Donald Alexander Smith, 1820–1914)」を記念する献窓。これもウェストミンスター寺院の北翼廊(North Transept)の 記念ステンドグラス(二連ランセット窓)。左:旧約のダビデ王(King David)・王冠をかぶり、甲冑のような服装。・右手に剣を持ち、左手に盾。・「戦う王」の姿。右:ソロモン王(King Solomon)・青い衣、王冠をかぶり、笏を持つ。・王権的象徴が強い。これも北翼廊(North Transept)にある壁面墓碑(モニュメント) の一つ。・中央像 ・若い女性像が胸に手を当て、片膝を立てるような姿勢。 ・周囲には天使(プットー)が取り囲んでいる。・左右の小像 ・左下の天使は板(本や碑板)を持ち、頬杖をつく。 ・右下の天使は巻物のような物を持っている。・下部中央の盾形紋章 ・赤・金・黒の彩色が見える。これは被葬者の家紋。北翼廊(North Transept) にある壮大な記念碑群の一部。上部中央の大記念碑・エドワード・ヴァーノン提督 (Admiral Edward Vernon, 1684–1757) の記念碑・2体の女性像が巻物を掲げ、その上に円形の肖像レリーフ。・白大理石製、バロック風。下部中央の楕円形の銘板・紋章の上に配置された楕円形の碑文。・これは サー・チャールズ・ノールズ (Sir Charles Knowles, 1704–1777) の記念碑。 ヴァーノン提督と同時代の海軍軍人。ヴァーノン提督記念碑(Admiral Edward Vernon, 1684–1757) の上部にある二連ランセット窓。・左窓の人物 ・青い衣をまとい、王冠を戴いている。 ・左手に巻物のような物を持つ。 ・預言者的な性格を帯びた王、賢王ソロモンか?右窓の人物 ・赤い衣をまとい、王冠を戴く。 ・右手に杖(笏)を持つ。 ・王としての権威を強調 、ダビデ王か?北翼廊(North Transept)の大窓(北窓/North Window) 。・窓はアーチ型の大規模なステンドグラスで、複数段に人物像が並んでいた。・上段・中段には 旧約聖書の預言者・王・使徒 と思われる人物群。・下段には 紋章・王冠・盾 が描かれ、イギリス王室や貴族の寄進を示す。・様式的に、これは 1722年にサー・ジェームズ・ソーンヒル (Sir James Thornhill) が デザインし、18世紀以降修復が繰り返された「北ローズ窓とその下の長窓群」の一部。上段3人・族長(中央アーチ最上部)左:ABRAHAM(アブラハム)中央:ISAAC(イサク)右:JACOB(ヤコブ)中段7人・大預言者・王左から右へ:1.Moses(モーセ)2.David(ダビデ)3.Isaiah(イザヤ)4.Jeremiah(エレミヤ)5.Ezekiel(エゼキエル)6.Daniel(ダニエル)7.Solomon(ソロモン 北大窓(Great North Window) の下半分。下段(7人:十二小預言者の一部)8.Hosea(ホセア)9.Joel(ヨエル)10.Amos(アモス)11.Obadiah(オバデヤ)12.Jonah(ヨナ)13.Micah(ミカ)14.Nahum(ナホム)下段:紋章(Heraldic Panels)最下段の小窓群には、当時の王家・寄進者・国家を象徴する 紋章 が並びます。左から順に:1.王冠とイギリス王室の紋章(赤い盾)ー王室の象徴2.チューダー王朝のバッジ(バラ・王冠)3.イングランドの獅子(ライオン)ーイングランド王権の象徴4.大英帝国を象徴する大紋章(Royal Arms・ロイヤル・アームズ)ー王国統合の象徴5.白馬の姿、ケント州(Kent, England)の紋章6.都市や諸侯の紋章ー複合的デザイン。寄進者の家紋を含む7.寄進者の家紋・盾形紋章北翼廊 (North Transept) にあるウィリアム・ピット(小ピット, William Pitt the Younger, 1759–1806)首相の記念碑。・中央に立つのは「ピットを象徴する像」で、右手を上げ演説するような姿。・左右には寓意像(アレゴリー像)が配置されています。 ・左の人物:半裸の男性、頭を支え、抑圧・困難からの解放を示す。 ・右の人物:女性像、感謝や支援を象徴。・上部壁面にはラテン語の銘文帯が走っており、ピットの政治的功績を讃えています。歴史的背景・ウィリアム・ピット(小ピット)は18世紀末~19世紀初頭のイギリス首相。・最年少(24歳)で首相に就任し、ナポレオン戦争期のイギリスを指導。・財政改革、海軍強化、フランス革命に対抗する外交で知られる。・ウェストミンスター寺院には、父(大ピット、チャタム伯ウィリアム・ピット)の記念碑も 南翼廊にあり、親子で顕彰されている。「THIS MONUMENTIS ERECTED BY PARLIAMENT,TO WILLIAM PITT,SON OF WILLIAM, EARL OF CHATHAM,IN TESTIMONY OF GRATITUDEFOR THE EMINENT PUBLIC SERVICES,AND OF REGRET FOR THE IRREPARABLE LOSS」 【この記念碑は議会によって建立された。チャタム伯ウィリアムの子、ウィリアム・ピットに。彼の卓越した公共への奉仕に対する感謝の証として、そして、その取り返しのつかぬ喪失を惜しんで。】身廊(Nave)から内陣(Choir / Quire)方向を見る。1.高いゴシック天井(リブ・ヴォールト)・縦に強調された列柱と交差リブ天井が印象的で、13世紀以降の英国ゴシック様式をよく 表しています。2.中央奥に見える金色の装飾スクリーン・これは クワイヤ・スクリーン(Choir Screen / Rood Screen) と呼ばれる仕切りで、 身廊(Nave)と聖職者の礼拝区画(Choir)を分けています。・ゴシック様式に金色装飾が施されており、その両脇にはモニュメントが配置されています。3.さらに奥に見える高い窓・これは 東端(High Altar / 内陣祭壇) の背後にある大窓(イーストウィンドウ)で、 祭壇正面を照らしています。近づいて。さらにクワイ。ヤ・スクリーン(Choir Screen / Rood Screen) をズームして。1. 中央部(アーチの上の三角形部分)・ゴシック様式の尖塔型装飾(トレーサリー模様と緑・赤・金色の彩色)。・中央には円形のバラ窓風装飾。・これは「祭壇側」と「身廊側」を分ける象徴的な装飾部分。2. 左右の大アーチ(中に彫像モニュメント)・左側(写真左) ・大きな地球儀を支える人物像が特徴。 ・これは天文学・地理学を象徴する寓意像を含むモニュメント。・右側(写真右) ・鎧姿の人物と座る女性像。 ・勇気や徳を寓意化した像。 ・どちらも実際には著名人記念碑の一部(詩人・科学者などのメモリアル)。アイザック・ニュートン卿(Sir Isaac Newton, 1642–1727)の記念碑・墓。上部・黄金の地球儀の上に横たわる女性像は「天文学」を象徴。・地球儀には黄道帯の星座や大航海時代の地図が描かれている。・これはニュートンの「万有引力」や「天体運動の法則」を象徴。中央・ニュートン本人を表す像が、落ち着いた姿勢で左手を頬にあて、右手を書物に置いている。・周囲の小さな天使(プットー)は、天球儀や本を持ち、学問の象徴を示している。下部レリーフ・子供たち(プットー)が様々な科学実験をしている様子が刻まれています。 (例えば、分度器・天体儀・天文学的観測器具などを扱っている)英訳「Here liesIsaac Newton, Knight,who, with almost divine intellect,set forth the motions and shapes of the planets,the paths of comets, and the tides of the ocean,shedding the light of mathematics upon them.He explained the rays of light and the origin of colors,which no one before had even guessed.Diligent, faithful, almost divine interpreterof Nature, of Antiquity, and of the Holy Scripture,he asserted the majesty of Almighty God philosophicallyand expressed the simplicity of the Gospel with humility.Mortals rejoice that there has existedsuch and so great an ornament of the human race.Born 25 December 1642,Died 20 March 1726/7.」 【ここに眠るアイザック・ニュートン卿。ほとんど神に近い精神の力をもって、惑星の運行とその形状、彗星の軌道、海の潮汐を解き明かし、数学の光をもってそれらに照らした。また、光線とそこから生じる色彩を説明し、これを先に推測した者は誰一人いなかった。彼は、自然・古代・聖書の勤勉で忠実、そしてほとんど神のごとき解釈者であり、全能なる神の威光を哲学的に示し、福音の単純さを謙虚に表現した。人類は歓喜す、このように偉大な栄光が人類に存在したことを。1642年12月25日生1726年3月20日没(グレゴリオ暦では1727年)】移動して。「天文学者アイザック・ニュートン卿(Sir Isaac Newton)」の墓の近くにあった窓。この窓は 「ニュートン記念窓(The Newton Memorial Window)」 と呼ばれ、1972年にステンドグラス作家 Hugh Easton によって設計された。・深い青色を基調とした抽象的デザイン:従来の聖書物語や聖人像の図像ではなく、 惑星・星座・天体をイメージしたようなモチーフ。・丸型のメダリオン枠内に球体(地球・月・惑星)が描かれていた。・いくつかの枠には ラテン語や英語の銘文(科学者名や研究成果を示すもの)が刻まれている。ニュートンの科学的業績(重力理論や光学、数学など)を称えるデザイン。ガラスに描かれているのは惑星軌道・光の分散・プリズム効果を抽象的に表したモチーフ。科学者たち(ニュートン、ダーウィン、ケルヴィン卿など)の名も記されていた。右側にあったのがジョゼフ・アディソン伯爵(Earl of Mansfield, William Murray, 1705–1793) の記念碑・墓。・被葬者: William Murray, 1st Earl of Mansfield(1705–1793) イギリスの著名な裁判官。 ロンドン大火後の保険裁判や、奴隷制関連の「サマセット事件(1772)」で 「奴隷はイングランドの土 に足を踏み入れた時から自由である」と事実上の判決を下した ことで知られている と。記念碑の造形: ・中央の人物像:マンスフィールド伯本人。ローブをまとい、落ち着いた姿勢で座っていた。 ・周囲の寓意像(アレゴリー): ・右側に立つ女性像は「正義(Justice)」を象徴。剣と天秤を持つことが多い。 ・左側には「勇気(Fortitude)」または「叡智(Wisdom)」を象徴する女性像が寄り添う。 ・下部には正義を求める人々(しばしば奴隷を象徴する像)が配置され、伯の人権的な判決を 象徴する。 ・上部の横たわる像は「沈思する哲学」または「真理の探求」を示していると解釈される と。ニュートンの墓のすぐ近くの床にあったのが、スティーブン・ホーキング博士の墓。ホーキング博士は理論物理学・宇宙論の分野でブラックホール研究を革新し、「車椅子の天才」として世界的に親しまれた。その墓碑は「科学と人類の知の探求の象徴」として、ニュートンやダーウィンと並び、未来世代に語り継がれる場所となっているのだ。碑文:「Here lies what was mortal of Stephen Hawking」【ここに、スティーブン・ホーキングの肉体が眠る】と刻まれていた。数式:中央にはホーキングが導き出した「ブラックホールの温度」を示す公式が刻まれていた。 T=hc³/8πGMkT:ブラックホールの“温度”(ハッキング温度)h:量子の定数c:光の速さG:万有引力定数M:ブラックホールの質量k:ボルツマン定数この式は、スティーブン・ホーキングが提唱したホーキング放射における黒体(ブラックホール)の温度を求めるためのものです。この式は黒体の質量Mに反比例するため、質量が小さいほど温度が高くなると。すなわち、ブラックホールが「完全に暗黒」ではなく、量子効果によって放射(ホーキング放射)を行い、最終的に蒸発して消える可能性を示したもの と。しかしながらも、全く理解できていないまま書いています!!デザイン:背景には宇宙を象徴する同心円状の模様が描かれ、無限の広がりと彼の理論の 宇宙的意義を象徴しているのだ と。2018年3月に76歳で死去した「車いすの天才宇宙物理学者」スティーブン・ホーキング博士の追悼式が6月15日、ロンドンのウェストミンスター寺院で執り行われた。博士の遺灰は、同寺院に眠るアイザック・ニュートンやチャールズ・ダーウィンら高名な科学者の墓のそばに埋葬された と。写真はネットから。こちらはチャーチル卿は「バトル・オブ・ブリテン」で英国を勝利に導いた指導者であり、この石は「英国の存続を守った戦い」と「チャーチルのリーダーシップ」を共に記念する象徴。なお、チャーチル本人の埋葬地はウェストミンスター寺院ではなく、オックスフォードシャーのブレナム宮殿近くのブレイデン教会墓地にあります。この石は「記念碑」として寺院に置かれています。「REMEMBERWINSTON CHURCHILLIN ACCORDANCE WITH THE WISHES OFTHE QUEEN AND PARLIAMENTTHE DEAN & CHAPTER PLACED THIS STONEON THE TWENTY-FIFTH ANNIVERSARY OFTHE BATTLE OF BRITAIN15 SEPTEMBER 1965」 【第二次世界大戦時の英国首相、ウィンストン・チャーチル(1874–1965)を記念するもの。エリザベス女王と議会の意向に従い設置されたことを示す。ウェストミンスター寺院の「院長と参事会」によって設置「バトル・オブ・ブリテン(1940年)」の25周年記念にあたる1965年9月15日に設置。】再びステンドグラスを追う。1.左の縦窓(赤衣の人物)・王冠を戴いたように見える人物。・衣は赤+白、足元に王権を象徴する「球体(オーブ)」らしきものが確認できる。・おそらく 聖王・王権に関わる人物(聖エドワード懺悔王や、旧約の王) を表現している。2. 右の縦窓(青衣の人物)・青いローブを着て、右手に長い杖(牧杖に近い形?)を持つ人物。・頭には冠ではなく花冠または聖人の光輪の表現。・書物を持っているようにも見えるので、預言者・使徒・学者聖人 を象徴する人物 と。1. 左の縦窓・王冠を戴いた人物(白+青+赤の衣)。・右手に「笏(王笏・Sceptre)」、左手に「オーブ(宝珠)」を持つ姿。・これは典型的に「キリスト教国王の権威」を表す図像で、聖エドワード懺悔王(Edward the Confessor) を描いている可能性が非常に高いです。 ・ウェストミンスター寺院はエドワード懺悔王が建立したため、彼の像はしばしば ステンドグラスに登場します。2. 右の縦窓・青衣の人物、頭に冠を戴いている。・右手に杖、左手に書物を持っているように見える。・聖母マリア、または別の聖王/聖女(例えば聖マーガレットや聖ヘレナ)の可能性が ありますが、衣の色と書物を持つ姿からは「知恵・教えの象徴となる女性聖人」が 考えられます。人物をズームして。1.左の人物(青衣の王冠人物)・青いローブ+金色の王冠を身につけています。・手には「宝珠(オーブ)」を持ち、王権の象徴を示しています。・足元の銘文には「IN MEMORY OF QUEEN…」と読める部分があり、これは「ある女王を 記念して奉献された窓」であることを示します。 → 人物は 聖王(Edward the Confessor か、あるいは象徴的な王像) の可能性が高い。2.右の人物(赤衣の司教)・赤と白の礼服、司教冠(ミトラ)をかぶっています。・右手に「牧杖(クロージャー)」を持ち、明確に司教(Bishop)を示す姿。・足元の銘文には「LUCIVS FIRST CHRISTIAN KING」 のような文字列が読み取れます。 → これは伝説上の ルキウス王(King Lucius) を指す可能性が極めて高いです。 ・ルキウス王は2世紀ごろ、ブリテンで最初にキリスト教を受け入れた王とされる伝説的人物。人物をズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.24
コメント(0)
-

「酔芙蓉」咲く
危険な炎暑の毎日が続いていましたが、今年も、我が家の庭の『酔芙蓉』が漸く毎日花を開き出して来ました。今年の開花遅れについてネットで少し調べてみましたが、次のような結論となりました。(1)水分不足連日の猛暑で土壌の水分が蒸発しやすく、根からの水分吸収が追いつかなくなる ことがあります。水分が不足すると、花を咲かせるためのエネルギーが足りなくなり、 蕾がつく数が減ったり、蕾が途中で枯れてしまったりします。(2)高温ストレス植物も人間と同じように、高温ストレスを受けます。高温が続くと光合成の 効率が落ち、 生育が停滞します。その結果、花のつきが悪くなる、花が小さくなる、 といった影響が 出ることがあります。今年の花は、例年に比べてやや小さいのは事実です。(3)開花時期のずれ今年の異常な暑さによって、開花時期がずれてしまった可能性もあり、 開花が遅れていることもあり、今回はこれに当たると考えます。先週までは熱中症のニュースばかりで、思わず気持ちが塞がることもしばしば。しかし、先週末9月20日の「彼岸の入り」からかなり涼しくなって来ました。「彼岸の入り」とは秋の彼岸の始まりの日で、この慣用句「暑さ寒さも彼岸まで」は、夏の暑さや冬の寒さが彼岸の頃には和らぎ、過ごしやすくなることを意味しています。これは春分の日や秋分の日(彼岸の中日)を境にして、季節の移り変わりを体感できることから生まれた言葉です。そんな時に我が家の花をじっと眺めると、よい意味で「無」になれる、そして時間毎にその花の色が変わって行く姿に、神秘性そして生命力を感じるのです。一昨日の朝も雲ひとつ無い晴天、熱くなりそうな日のスタート。遠く平安の頃から観賞され、人々に愛されて来たという芙蓉の花。古くから栽培されているにもかかわらず、ムクゲと違って変異が出にくく、品種はあまり多くないようです。その数少ない園芸品種の一つがこの『酔芙蓉』。『酔芙蓉』は、朝のうちは純白、午後には淡い紅色、夕方から夜にかけては紅色に変わるのです。酒を飲むと顔色がだんだんと赤みを帯びるのに似ていることからこの名がついたといわれています。芙蓉は、全国各地の庭先や公園など、どこででも目にすることができますが、群生している名所となると寺の境内が多いでは。『酔芙蓉』となるとなかなか群生しているところは少なく、千本以上あるところは珍しいようです。『酔芙蓉』の花は短命で、一日花のはかなさに諸行無常の教えを悟り、蓮の花に似て仏教の縁を重ねることが出来るのです。朝の、純白の花です。時間は早朝7:20。純白というより既に淡~~いピンクが。「酔芙蓉」の名前の由来は、朝に純白で咲き始めた花が、時間とともに徐々にピンク色に、そして夕方には濃い紅色へと変化する様子が、酒に酔って顔が赤くなる姿に似ていることからつけられたのだ。この変化は花弁の中のアントシアニンという色素が増加することで起こり、気温にも影響されるのだと。遠くから見ると純白に見えるのですが・・・・。葉の上部の脇に花びらが5枚で椀状の10~15cmぐらいの大輪の花を咲かせています。八重の酔芙蓉もありますが、我が家のものは一重のもの。濃いピンクの部分が花弁化した「雄しべ」そして白い部分が「雌しべ」。そして時間は10:10過ぎ。花片全体が淡いピンクに染まり始めて来ました。頭をもたげているのが雌しべの「柱頭」。我がミツバチが放花中。花粉を求めに来ているのでしょう。ほろ酔い状態。葉は手のひら状に浅く3つから7つに裂け、互い違いに生える(互生)こちらにもミツバチ嬢が。そして14:20過ぎ。だいぶ酔が廻って来ました。花弁(はなびら)全体が濃いピンクに。雄しべ、雌しべの色は変わらないようです。既に酔が廻って、花の形を保てなくなって来たものも。そして既に酔い潰れている花も。16時過ぎ、夕日を浴びて。こちらは完全に酔い潰れて急性アルコール中毒症か?前日からの二日酔いが残っている? 若い頃の自分の姿が重なるのです。そして翌朝には地面に落ちて。以前にも何回か書きましたが酔芙蓉と言えば思い出すのが、高橋治(1929-2015年)の小説「風の盆恋歌」。『死んでもいい。不倫という名の本当の愛を知った今は――。ぼんぼりに灯がともり、胡弓の音が流れるとき、風の盆の夜がふける。越中おわらの祭の夜に、死の予感にふるえつつ忍び逢う一組の男女。互いに心を通わせながら、離ればなれに20年の歳月を生きた男と女がたどる、あやうい恋の旅路を、金沢、パリ、八尾、白峰を舞台に美しく描き出す、直木賞受賞作家の長編恋愛小説。』富山県八尾市で開かれる「おわら風の盆」👈️リンク を主な舞台として、お互い家庭を持つ男女の悲恋を描いた物語。「風の盆」とは9月の初め二百十日の風の吹く頃、収穫前の稲が台風などの被害に遇わないように祈る祭。盆と云うから先祖や故人を偲ぶ行事かと思っていましたが、豊作を願う祭なのです。その割には静かな祭で、哀調を帯びた三味線と胡弓の伴奏に合わせて越中おわら節が淡々と唄われ、編み笠を深くかぶった男衆や女子衆が、うつむき加減に顔を隠すようにして踊ります。初秋の越中の里に哀調漂わせて唄い踊られる風の盆、その幽玄で美しい世界が、小説の中で見事に描かれています。さらに度々登場するのが酔芙蓉。朝白く咲き夕方赤くなって散っていく一日花、意識下に死を想いながら夢とうつつの間を行き来する二人、その生の儚(はかな)さ、哀しさを象徴しているのです。そして、石川さゆりの「風の盆恋歌」👈️リンク 作詞:なかにし礼 作曲:三木たかし♪♪♪蚊帳の中から 花を見る咲いてはかない 酔芙容若い日の 美しい私を抱いて ほしかったしのび逢う恋 風の盆 私あなたの 腕の中跳ねてはじけて 鮎になるこの命 ほしいならいつでも死んで みせますわ夜に泣いてる 三味の音 生きて添えない ニ人なら旅に出ましよう 幻の遅すぎた 恋だから命をかけて くつがえすおわら恋唄 道連れに♪♪♪そして牧野富太郎の歌『我が庭に 咲きしフヨウの 花見れば 老ひの心も 若やぎにけり』が好きな酒好きの私 なのです。 ・・・おわり・・・
2025.09.23
コメント(1)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その87): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-2
この像は、ジョージ・キャニング(George Canning, 1770–1827)。・イギリスの政治家・首相。・外交官としても名高く、19世紀初頭に外務大臣を務めました。・アメリカ大陸の独立国に対する承認を推進し、モンロー主義にも影響を与えたことで知られます。・1827年に短期間だけ首相を務めましたが、在任中に急逝しました。・制作:リチャード・ウェストマコット(Richard Westmacott)・除幕:1832年パーラメント・スクエアに建てられた最初の像であり(1832年設置)、広場における記念像の先駆けとなりました。マハトマ・ガンディー像 (Mahatma Gandhi, 1869–1948)。・建立年:2015年・彫刻家:フィリップ・ジャクソン (Philip Jackson)・位置:チャーチル像に対面する位置、ネルソン・マンデラ像の近く(広場南寄り)・特徴: ・伝統的なインドの衣(ドーティ)をまとい、落ち着いた姿で立つ。 ・静かで精神性を象徴する姿が強調されている。・意義: ・インド独立運動の指導者であり、非暴力・不服従運動を世界に広めた人物を称えて建立。 ・インド政府からの寄贈によるもので、イギリスとインドの歴史的関係を象徴する存在。エイブラハム・リンカーン像 (Abraham Lincoln, 1809–1865)。・建立年:1920年(アメリカ合衆国からイギリスへの贈呈)・彫刻家:オーガスタス・セント=ゴーデンス (Augustus Saint-Gaudens) の原型を基にした鋳造・特徴: ・片手を横に垂らし、もう片方の手で衣を持つ、落ち着いた立ち姿。 ・背後の椅子(議長席のような意匠)が特徴的。・意義: ・アメリカ合衆国第16代大統領として、奴隷解放宣言や南北戦争での指導で知られる人物を称える。 ・アメリカとイギリスの友情の象徴として設置。ネルソン・マンデラ像 (Nelson Mandela, 1918–2013)。・建立年:2007年・彫刻家:イアン・ウォルターズ (Ian Walters)・特徴: ・両手を広げ、演説中の姿を強調した自然なポーズ。 ・彼が好んで着用していた「マディバ・シャツ(Madiba shirt)」姿で表現されている。・意義: ・南アフリカの反アパルトヘイト闘争の指導者であり、初の黒人大統領となった人物を称える。 ・「自由と和解の象徴」として、英国における人権と民主主義の価値を示す記念碑像の配置図をネットから。・北東(Parliament側) ・チャーチル像(Winston Churchill)・北辺(英国首相などの列) 左から順に: ・パーマストン卿像(Viscount Palmerston) ・ダービー伯像(Earl of Derby) ・スムッツ像(Jan Smuts) ・ロイド・ジョージ像(David Lloyd George)・南西側 ・ネルソン・マンデラ像(Nelson Mandela)・西側 ・ディズレーリ伯爵像(Benjamin Disraeli) ・ロバート・ピール像(Sir Robert Peel)・南東(Houses of Parliament側、噴水手前) ・リンカーン像(Abraham Lincoln)そして 新しく加わった像:・南辺中央 に、ミリセント・ギャレット・フォーセット像(Millicent Fawcett) が設置されていた。パーラメント・スクエア(Parliament Square)広場からエリザベスタワー(通称ビッグ・ベン)と国会議事堂(パレス・オブ・ウェストミンスター) を背景にして。手前に掲げられている旗は、イギリス連邦(Commonwealth of Nations)加盟国の国旗。イギリス最高裁判所(The Supreme Court of the United Kingdom)。・場所:ロンドンのウェストミンスター地区、国会議事堂(ビッグベン)や ウェストミンスター寺院のすぐ近く。・建物名:もともとは「ミドルセックス・ギルドホール(Middlesex Guildhall)」として 建てられた建物で、1906~1913年に建設されたネオ・ゴシック様式の建築。・現在の役割:2009年から改装され、イギリスの最終上訴裁判所である「英国最高裁判所」として 使用されています。・特徴: ・白いポートランド石による壮麗な外観。 ・正面入口上部には彫刻が多く施されており、法律や正義を象徴する像や装飾があります。 ・建物内部には裁判所の公開ギャラリーや展示スペースもあり、観光客も見学可能。背景に見えている丸屋根の建物は メソジスト・セントラル・ホール (Methodist Central Hall Westminster)イギリス最高裁判所(UK Supreme Court) の塔部分をクローズアップ。1.塔のデザイン・ネオ・ゴシック様式で、直線的な垂直ラインを強調した堅牢な印象の塔。・四隅には小塔(角塔)があり、中世の城郭建築を思わせるデザインに。2.装飾帯(フリーズ)・塔の上部には彫刻帯(フリーズ)があり、植物文様や人物像が配置。・これは「法と正義」を象徴する寓意彫刻で、建物全体に散りばめられていた。3.ユニオン・ジャック(Union Flag)・塔の頂上にはイギリス国旗(Union Jack)が掲げられていた。・最高裁判所が「国家の法の最終権威」であることを示す象徴的な掲揚。4.開口部(アーチ窓)・塔の中央には大きな開口部があり、鐘楼のように空間が抜けていた。・実際には鐘は設置されていないが、ゴシック建築の「鐘楼(Bell Tower)」を模したデザイン。そしてウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)北翼廊(North Transept)正面 を外から見る。移動して、以下ネットから。・左側の尖塔 ・正面の左(北)に立つ高い方の尖塔(ピクナル)。・右側の尖塔 ・西正面の右(南)に立つ高い方の尖塔(ピクナル)。 ・左塔と対称をなす。・北翼廊の大扉口(ポータル) ・下部に三連の尖頭アーチ形入口(ポータル)があり、それぞれに装飾的なタンパン (半円形や三角形の彫刻部分)が見えた。 ・中央扉が最も大きく、両脇にやや小さい入口が対になっています。・ 大バラ窓(North Rose Window) ・大扉口の上にある大きなゴシック様式の大きな「ステンドグラス バラ窓(ローズウィンドウ)」 ・ステンドグラスは13世紀のゴシック様式を模しつつ、19世紀ヴィクトリア朝の修復によるもの。 ・聖書の物語や歴代の聖人が鮮やかな色彩で描かれています。 ・西日を受けて堂内を美しく照らします。・王の彫像群(Kings & Saints Statues) ・西正面の扉上部の壁龕(にち)に並ぶ像。 ・イギリス史上の王や聖人、殉教者などを表している。 ・1998年には「20世紀の殉教者」像(マルティン・ルーサー・キング、マクシミリアノ・コルベ 神父など)が新たに加わった。・中央尖塔飾り(Pinnacle / Central Decoration) ・西正面中央上部にある尖塔状の飾り。 ・左右の塔と全体のバランスを整える要素。 ・細かいトレーサリー(石の透かし彫り)が特徴。近づいて。北翼廊正面の中央扉口(North Transept Central Portal) のクローズアップ。ゴシック建築特有の「タンパン(tympanum:三角形の半円形彫刻部分)」と「聖人像」が見えていた。1.タンパン上部のキリスト像・最上段中央に座すのは 栄光のキリスト(Christ in Majesty)。・手を挙げて祝福の姿勢をとり、両脇には天使たちが控えています。2.中段の十二使徒像・キリストの下の列には、**十二使徒(Twelve Apostles)**が並び、巻物や書物を持って 立っています。・ゴシック様式の典型的な「最後の審判」関連の構図を思わせます。3.下段の聖人・旧約の人物たち・さらに下には旧約聖書や歴史上の聖人たちが彫刻され、聖堂に入る人々を迎える象徴的存在と なっています。4.中央柱像(トランソン像)・両扉の間の中央柱(trumeau)に立つのは、聖母子像(Virgin and Child)。・聖母マリアが幼子イエスを抱いており、入口を通る信徒を見守ります。5.アーチの装飾(Archivolts)・アーチ部分(アーキヴォルト)には、小さな円形の中に多数の彫像(預言者、天使、聖人、 寓意像)が並んでいます。・外周に向かって同心円状に配置され、荘厳な「天国の階層」を表す典型的なゴシック意匠。移動して。ウェストミンスター寺院 北翼廊中央扉口のトランソン像(Trumeau Figure)、つまり 聖母子像(Virgin and Child)。1.像の位置・これは三連扉口の中央の「柱(trumeau)」に設置されています。・大扉の中央支柱に立つ像は、ゴシック建築では「教会の守護者」として極めて象徴的な役割を 担います。2.聖母マリア・聖母は優雅な衣をまとい、片腕で幼子イエスを抱いています。・もう一方の手にはしばしば「花(バラや百合)」を持つ姿で表され、純潔と信仰を象徴します。・この像では、マリアの手元に花束(恐らくバラ)が確認できます。3.幼子イエス・イエスは冠をかぶり、右手を軽く挙げる祝福のポーズをしています。・左手には巻物や小さな球体(オルブ=世界の支配権を象徴する球体)を持つ場合もありますが、 この像は手を開いた自然な仕草に見えます。・王冠を戴くことから「王なる救い主(Christ the King)」の意味が強調されています。4.建築装飾との一体化・像の上には小さな尖塔型の天蓋(バルダキン)が彫刻され、まるで聖母子を神殿に祀るかの ように強調。・周囲の細やかな葉飾りやパターンと一体化し、「聖なる門を通過する者を守護する聖母」の 役割を果たします。北翼廊の大バラ窓(North Rose Window)を見上げてズーム。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の北側身廊(North Nave Aisle)の外観 。先ほどの「北翼廊(North Transept)」のすぐ東側から東方(内陣方向)へと続く部分。二層構造となっており、下層は大きな尖頭アーチ窓(ステンドグラス)、上層は小型の丸窓(ローズレット/円窓)を含む二連窓の組み合わせとなっていた。 典型的なゴシック様式の「高窓+側廊窓」のリズムを示している と。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)入口付近の案内看板。看板の構成(左から右へ)1.左端パネル ・"Come and be inspired by a thousand years of history." → 「1000年の歴史に触れ、感動してください。」2.左から2番目 ・"We’re usually open for visiting from Monday – Saturday. Tickets are available at westminster-abbey.org or at the door." → 「通常、月曜から土曜に拝観いただけます。チケットは公式サイトまたは入口で購入できます。」3.中央 ・"We hold services here every day and you are welcome to join us." → 「ここでは毎日礼拝が行われています。ぜひご参加ください。」4.右から2番目 ・"For more information about visiting and worshipping with us, please see our website and social media channels." → 「拝観や礼拝に関する詳しい情報は、公式ウェブサイトやSNSをご覧ください。」5.右端 ・白文字で "Entrance →"(矢印付き) → 入場口を案内。ウェストミンスター寺院前の広場(Dean’s Yard / Broad Sanctuary 付近)から見た建物群。正面に写っているのは Dean’s Entrance(ディーンの門/ウェストミンスター寺院参事会関係の建物)1.中央のゴシック風建物・これは Sanctuary / Abbey Offices(ウェストミンスター寺院関連の事務棟・住居)。・ヴィクトリア朝ゴシック様式(19世紀)の建物で、尖頭アーチの入口、装飾的な窓、 城郭風の小塔が特徴。・入口は「Dean’s Entrance(参事会入口)」とも呼ばれ、僧院・参事会施設に通じる。2.右奥の白い覆い・修復工事中の建物(写真右手)。足場と白いシートで覆われています。3.右端の石柱(Victoria Tower Gardens側の記念碑)・ゴシック風の尖塔型モニュメント。・これは「The Column of St George」ではなく、The Westminster Column / Queen Victoria Memorial に類するもの。周辺には複数の記念碑が並んでいます。4.左端の石塀・ウェストミンスター寺院回廊(cloister)へと続く石造の境界壁。5.手前の広場・観光客が集まる Broad Sanctuary(ブロード・サンクチュアリ) の一角。・ウェストミンスター寺院参観の出入りや、観光ツアーの集合場所として使われていた。ウェストミンスター寺院前の広場(Broad Sanctuary / Parliament Square の西側) に立つ有名な記念柱・「The Crimean War Memorial(クリミア戦争記念柱)」。・建立:1861年・場所:ウェストミンスター寺院の北西側(Broad Sanctuary広場)・制作者:ジョージ・ギルバート・スコット(Sir George Gilbert Scott)設計・形式:高い赤色花崗岩のコリント式円柱クリミア戦争記念柱(Crimean War Memorial)の 上部像の一体をズームして。・王冠を戴いた人物:イングランド王・聖王エドワード(Edward the Confessor, 1042–1066) 長い髭をたくわえ、王冠をかぶって玉座に座る姿。・ウェストミンスター寺院を創建した君主として知られる。・右手に笏(sceptre/王笏) を持ち、左手は巻物または書物を押さえる姿勢。・周囲は小さなゴシック様式の天蓋(バルダキン)で飾られている。・像の台座部分に刻まれている文字は 「EDWARD THE CONFESSOR(聖王エドワード証聖王)」。こちらはヘンリー6世(Henry VI, 1421–1471)・在位:1422–1461, 1470–1471(イングランド王)・背景:ランカスター家の王として即位。しかし薔薇戦争の渦中にあった不遇の王。・信心深い人物として知られ、カリスマ的な敬虔王とみなされました。・学問振興に尽力し、イートン校やケンブリッジ大学キングス・カレッジを創設。・王としては政治的に弱く、最終的にヨーク家に敗れ、ロンドン塔で非業の死を遂げます。・没後、聖人視されることもあり(非公式の聖人として崇敬)。クリミア戦争記念柱(Crimean War Memorial)基壇部分の碑文。「To the memory of those educated at Westminster School who died in the Russian andIndian wars (1854–1859),whether on the battlefield or from wounds or sickness.Some were in early youth, others full of years and honours,but all alike gave their lives for their country.This column was erected by their old schoolfellows,as a token of sorrow for their loss, of pride in their valour,and in the firm assurance that the remembrance of their heroism,in life and in death, will inspire their successors at Westminsterwith the same courage and self-devotion.」【1854年から1859年のロシア戦争(クリミア戦争)およびインド戦争において、戦場で、あるいは負傷や病で命を落としたウェストミンスター・スクールで学んだ者たちを追憶して。若くして倒れた者も、長く生きて名誉を得た者もいたが、いずれも等しく祖国のために命を捧げた。この記念柱は、彼らの旧友・同窓生たちによって建てられた。その死を悼み、勇敢さを誇り、そして確信をもって願う。彼らの英雄的精神の記憶が、生涯と死を通じて、後に続くウェストミンスターの者たちを奮い立たせ、同じ勇気と献身を抱かせることを。】 ウェストミンスター寺院のすぐ近くにあった「Methodist Central Hall Westminster(メソジスト・セントラル・ホール・ウェストミンスター)」。1.メソジスト教会の本拠・世界メソジスト協議会(World Methodist Council)の主要施設。・礼拝堂として機能すると同時に、キリスト教活動の拠点。2.国際会議の場・1946年:国際連合第一回総会の開催地。・以降も世界的会議・集会に利用される。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の西正面(West Front)。西正面(West Front)であるが、地理的には南側にあたる場所にあった。中世ヨーロッパの大聖堂は 原則として東向きに建てられた。すなわち、祭壇(High Altar)があるのが「東端」=キリスト復活の象徴。参拝者は西から入り、東を向いて祈る形。そのため、入口がある正面は「西正面(West Front)」 と呼ばれるのが伝統であると。ここが、観光客が入場する主要なファサードで、二本の塔を持つ荘厳な立面が特徴。1.二本の西塔(West Towers)・左右にそびえる高さ約69mの二本の塔。・18世紀(1722–1745)に建設。建築家ニコラス・ホークスムーア(Nicholas Hawksmoor)の設計。・ゴシック様式に合わせてデザインされましたが、実際はジョージアン期の後補部分。2.大窓(Great West Window)・正面中央にある大きな窓。・19世紀のヴィクトリア朝ゴシック修復時にステンドグラスが入れられた。・王室や聖人の姿が描かれている。3.三連ポータル(Entrance Portals)・下部に3つの入口。中央扉は最も大きく、主要な入場口。・扉上部のタンパンには彫刻装飾が施されている。4.彫像列(Kings and Queens Statues)・扉上部、横一列に彫像が並ぶニッチ(小壁龕)が設けられている。・これは20世紀に追加された「20世紀の殉教者たち(The Modern Martyrs)」の像。 例:マキシミリアノ・コルベ神父(アウシュヴィッツ殉教)、マルティン・ルーサー・キング・ ジュニアなど。5.時計とバラ窓・左塔に時計、右塔に小さなバラ窓が設置されている。・機能的かつ装飾的要素として左右対称性を補強。西正面(West Front)をズームして。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)西正面(West Front)中央扉の上部に並ぶ像列。・これは 「20世紀の殉教者たち(The Ten Modern Martyrs)」 の像群です。・1998年に設置された比較的新しい彫刻で、聖人像ではなく「20世紀に信仰や正義のために殉じた 人物」を称えていた。・上段に英国王室の紋章や紋章群が並んでいた。並ぶ人物(左から右へ)👈️リンク1.マキシミリアノ・コルベ(ポーランドのカトリック司祭、アウシュビッツで犠牲に)2. マニコ・ダニエル (コンゴの殉教者)3.ワン・ジーメン(中国のルター派殉教者)4.グランド・ダッチェス・エリザヴェータ・ロマノヴァ(ロシア正教)5.マルティン・ルーサー・キング Jr.(アメリカの公民権運動指導者)6.オスカー・ロメロ大司教(エルサルバドル、虐殺された大司教)7.ディートリヒ・ボンヘッファー(ドイツの神学者、ナチスに処刑)8.エスター・ジョン(パキスタンのキリスト教徒女性殉教者)9.ルシアン・タピエディ(パプア・ニューギニアの殉教者)10.ヤンニ・ラウェンス(南アフリカの反アパルトヘイト活動家)この像列は、中世の聖人列ではなく 現代までの信仰・人権・正義のために命を捧げた人物を称える というメッセージを持つ、ウェストミンスター寺院の中でもとても象徴的な新しい装飾。左から3体を。1.マキシミリアノ・コルベ(ポーランドのカトリック司祭、アウシュビッツで犠牲に)2. マニコ・ダニエル (コンゴの殉教者)3.ワン・ジーメン(中国のルター派殉教者)こちらは、左から3~7番目(ネットから)。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey) の掲示板にある 礼拝スケジュール表(1–8 June 2025)。・期間:2025年6月1日(日)〜6月8日(日)・対象:訪問者向けに「毎日の礼拝時間」や「特別行事」の予定を知らせる掲示・曜日ごとに欄があり、以下のような情報が記されています ・時間(例:11:30am、3:00pm など) ・礼拝の種類(Holy Communion, Matins, Evensong, Sung Eucharist など) ・場所(Nave, High Altar, St Faith’s Chapel など) ・音楽隊(Choir of Westminster Abbey など) ・特別な式典や記念日の明記・主な礼拝の種類 ・Holy Communion(聖餐式):キリスト教の中心的な儀式 ・Matins(朝の祈り) ・Sung Eucharist(聖餐式、合唱付き) ・Evensong(夕の祈り、合唱隊による) ・Organ Recital(オルガン演奏会) などウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の南側(クロイスター側)外観を。・右側(大きな建物) ゴシック様式の ウェストミンスター寺院の南側外壁。 高窓(トリフォリウムのステンドグラス)や、飛梁(フライング・バットレス)がよく見えた。 画面手前は 南翼廊(South Transept) にあたる部分で、この奥に「詩人のコーナー (Poets' Corner)」があった。・左奥の建物 これは St Margaret’s Church(聖マーガレット教会)。 ウェストミンスター寺院の付属教会として、長く「国会議員の教区教会」とされてきた建物。 寺院と並んでユネスコ世界遺産に含まれています と。廻り込んで。St Margaret’s Church(聖マーガレット教会) 。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)のすぐ隣に建っていた。聖マーガレット教会(St Margaret’s Church)の概要・創建:12世紀末(約1150年頃)、ベネディクト会修道士たちが近隣の信徒のために 建てたのが起源。・現在の建物:主に 1486–1523年 に再建された後期ゴシック様式(垂直様式)。 その後も修復・改築が繰り返され、現在の姿になっています。・位置関係:ウェストミンスター寺院の西側に隣接し、両者は同じ敷地に立っています。・役割:ウェストミンスター寺院は国王の戴冠式・王室行事・国家的儀式に使われるため、 一般の地域住民はここで礼拝しました。のちに 英国国会議員の教会 (the parish church of the House of Commons) としても用いられた。セント・マーガレット教会(St Margaret’s Church, Westminster Abbey)の鐘楼(タワー部分)を見上げて。15世紀後期から16世紀初頭に建てられたゴシック様式。現在の建物は1523年に奉献された。塔の四面に青い文字盤の時計が設置されているのが特徴で、訪問者に時間を知らせていた。塔は垂直に伸びる窓と、塔頂部の角に小さなピナクル(尖塔)が配置されていた。「St Margaret’s ChurchWestminster AbbeyVisitors are welcome to this beautiful church. The present building, consecrated in 1523, is the third on the site. Since 1614 St Margaret’s has been the church of the House of Commons.Windows commemorate Caxton and Milton, who worshipped here, and Raleigh, who is buried in front of the altar, under the glorious window made for King Henry VIII and Catherine of Aragon in c1520.After about nine hundred years of service as a parish church for the people of Westminster, St Margaret’s was placed under the care of the Dean and Chapter of Westminster by Parliament in 1973.It is still in regular use for worship and for recitals of music.」【聖マーガレット教会(ウェストミンスター・アビー)この美しい教会へようこそ。現在の建物は1523年に聖別されたもので、この地に建てられた3代目の教会です。1614年以来、聖マーガレット教会はイギリス下院の教会として用いられてきました。内部の窓は、ここで礼拝したキャクストンとミルトンを記念し、また探検家ローリー卿は祭壇前に葬られています。その上には、1520年頃にヘンリー8世とアラゴンのキャサリンのために造られた壮麗なステンドグラスが輝いています。約900年にわたってウェストミンスター市民のための教区教会であった聖マーガレット教会は、1973年に議会の決定によりウェストミンスター寺院の学頭団の管理下に置かれました。現在も礼拝や音楽のリサイタルの場として活用されています。】 この建物は イギリスの最高裁判所(The Supreme Court of the United Kingdom)。建物の概要・名称:Middlesex Guildhall(旧名)/現在は「最高裁判所(UK Supreme Court)」・場所:ウェストミンスター寺院の向かい、国会議事堂(Parliament Square)の北西角に位置・建設:1906–1913年に建設、ネオ・ゴシック様式の公共建築・用途:かつては Middlesex 郡の治安判事裁判所として使われ、その後 2009年に大規模改修を経て 「英国最高裁判所」として開所建物の特徴・外観は 白いポートランド石を使ったネオ・ゴシック様式・正面中央にバルコニー、上部には細かいゴシック装飾(トレーサリーや尖塔状の装飾)・屋根上には ユニオンフラッグ(英国国旗) が掲げられていた・内部には歴史的なステンドグラスや彫刻も残されており、裁判所としての機能に合わせつつ 文化財的価値も持つ建物ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の西正面ファサード。再びビッグ・ベン(エリザベス・タワー)を見る。右側:エリザベス・タワー(通称ビッグ・ベン)。 奥には英国国会議事堂(パレス・オブ・ウェストミンスター)が連なっていた。中央広場:芝生の一帯は Parliament Square(国会議事堂広場)。ここには各国の指導者や 偉人の銅像が多数立ち並んでいます(チャーチル、ネルソン・マンデラ、ガンディーなど)。左奥:白いドーム屋根を持つ建物は、政府関連施設や歴史的な建物が並ぶエリア (TreasuryやWhitehall方面)。旗:広場の周囲に多くの国旗が掲げられていた。 特別な式典や議会関連行事、あるいは国際的な記念日の際に掲揚されることがあるとのこと。ウェストミンスター寺院周辺に設置されている案内板(観光解説サイン)。黒地に線画のレリーフが刻まれており、視覚障害者にも触れて理解できるように設計された「触知案内板(tactile information board)」となっていた。1.上段中央の大きな線画パノラマ・周囲の街並み・建物・人々(パレードの様子や観光風景)を線画で表現。・観光名所が立体的に配置され、位置関係が理解できるようになっています。2.下段のランドマーク紹介・左から順に、主要な建築物や記念碑の図と名称が刻まれています: ・ネルソン記念柱(Nelson’s Column) ・バッキンガム宮殿(Buckingham Palace) ・女王陛下の紋章(Royal Arms / Queen’s Emblem) ・ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey) ・そのほか、議会関連の建物や記念像3.右端:地図・ロンドン中心部(ウェストミンスター地区)の地図が刻まれており、位置を点字とともに 確認できるようになっています。4.左端:説明文と点字・英語による解説文の下に点字が併記されています。・点字は視覚障害者向けの情報提供を目的としており、場所の歴史や建築の意義を要約。「Royal Wedding 2011Broad Sanctuary links Parliament Square to Victoria Street. It is also part of the ceremonialroute to Westminster Abbey. On 29 April 2011 Prince William of Wales (newly created Dukeof Cambridge) arrived here to marry Miss Catherine Middleton, and the couple wereconveyed past this spot in the 1902 State Landau on their way back to Buckingham Palaceafter the wedding service was completed at the Abbey.This is also the route taken by the Gold Coach in the Coronation procession, when newsovereigns come to Westminster Abbey to be anointed and crowned. In April 2002 thefuneral procession of Queen Elizabeth The Queen Mother moved slowly past this spotfrom Westminster Hall to the Abbey.The Abbey Church of Westminster was consecrated in 1065, and the following yearEdward the Confessor was buried here. It became the resting place of most English Kingsand Queens from Henry III in 1290 to George II in 1760. Thirty-nine English Sovereignshave been crowned here, and, since 1919, the Abbey has been the setting for a numberof royal weddings, including that of The Princess Elizabeth and The Duke of Edinburghin 1947.Nearby is 16th century St Margaret’s Westminster, where fashionable weddings and parliamentary memorial services are held. Westminster Hospital stood on the site wherenow the Queen Elizabeth II Conference Centre is.Originally built in 1834, the hospital was founded as a Charitable proposal for relievingthe sick and needy and their distressed persons. It was a handsomely castellatedneo-Gothic building, which was finally demolished in 1950. It must have looked similar tothe neo-Gothic 1913 building which now houses the Supreme Court.」 【内容要約(日本語)・2011年のロイヤル・ウェディング 2011年4月29日、ウィリアム王子(ケンブリッジ公)とキャサリン・ミドルトンの結婚式が ウェストミンスター寺院で行われ、この場所を通り、1902年製のステート・ランドー馬車で バッキンガム宮殿へ戻った。・戴冠式・葬列の経路 ゴールド・コーチによる戴冠式行列もこのルートを通り、2002年4月にはエリザベス皇太后の 葬送行列もここを通過した。・ウェストミンスター寺院の歴史 ・1065年に聖別。翌年にエドワード証聖王が埋葬。 ・以降、1290年ヘンリー3世から1760年ジョージ2世まで、イングランド王室の主要な埋葬地に。 ・39名の君主が戴冠し、1919年以降は多数のロイヤル・ウェディングの舞台に。 ・例:1947年エリザベス王女とフィリップ殿下の結婚式。・周辺の建物 ・16世紀建立のセント・マーガレット教会:社交界の結婚式や議会追悼礼拝の場。 ・かつてのウェストミンスター病院(1834年創設):慈善目的のネオ・ゴシック建築、1950年に 取り壊され、現在はエリザベス女王会議センター。 ・病院の外観は、現在英国最高裁判所が入る1913年のネオ・ゴシック建物に似ていたとされる。】黒色レリーフ式案内板の 下段部分(ランドマーク紹介)。視覚障害者向けに凹凸で刻まれていて、触って確認できるようになっていた。上段のパノラマ線画では、実際の街並み(人の行列や馬車、建物群)が表されており、下段ランドマークとの対応関係を理解できるようになっていた。下段に刻まれているランドマーク(左から右へ)1.Nelson’s Column(ネルソン提督記念柱)・トラファルガー広場に建つ有名な記念柱。・ナポレオン戦争で活躍したネルソン提督を顕彰。2.Central Hall Westminster(セントラル・ホール・ウェストミンスター)・1912年完成のメソジスト系会議ホール。・国際会議・式典の会場としても有名。3.The Queen Elizabeth II Conference Centre(エリザベス女王会議センター)・1986年開設。国際会議、展示、式典が行われる大規模施設。・ウェストミンスター寺院の向かいに位置。4.The Supreme Court(英国最高裁判所)・2009年設立。建物自体は1913年完成のネオ・ゴシック様式。・旧ミドルテンプル病院の跡地に立つ。5.Memorial to the Women of World War II(第二次世界大戦における女性の記念碑)・2005年に建立された戦争記念碑。・戦時中に従軍・労働に従事した女性たちを顕彰。6.Westminster Abbey(ウェストミンスター寺院)・1065年に奉献。歴代英国君主の戴冠式・結婚式・葬儀の場。・王室と国家の象徴的な宗教施設。7.簡略地図(Map)・案内板の右端に、周辺地図が刻まれている。黒色レリーフ式案内板の 地図部分(Jubilee Walkway / ジュビリー・ウォークウェイの案内図)・ジュビリー・ウォークウェイは、ロンドン市民や観光客が徒歩で主要スポットを巡れる 「都市の記念回廊」。・ロンドン中心部を走る Jubilee Walkway(ジュビリー遊歩道) のルートマップ。・テムズ川に沿ってカーブした経路が描かれ、主要な観光地やランドマークが線画で示されていた。「The Jubilee Walkway was established to commemorate the Silver Jubilee of Her MajestyQueen Elizabeth II in 1977.It is one of London’s premier walking trails, passing many historic buildings and views.」【ジュビリー・ウォークウェイは、1977年のエリザベス女王在位25周年(銀婚式)を記念して 設けられました。 ロンドンの主要な遊歩道の一つで、歴史的建造物や名所を巡ることができます。】と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.23
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その86): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-1
この日は6月7日(土)、旅友Yさんとロンドン観光の初日。アイルランドは旅友4人の旅であったが、前日早朝に、アイルランド・ダブリン空港からHさんは子供、孫の待つアメリカへ、そしてSさんは帰国の途に就いたのであった。旅友Yさんと私は、ダブリンからここロンドンへ。そして3泊4日のロンドン観光に。しかし、宿泊場所のみ同じアパートメントで、観光はそれぞれ別行動でも良いとの合意が出来ていたのであった。よってこの日はYさんは、オペラの鑑賞、私はテムズ川沿いの観光へと別々に。私は8:30過ぎにアパートを出て徒歩にてSouth Kensington駅へ向かう。South Kensington駅前にあった「ベーラ・バルトーク(Béla Bartók, 1881–1945) の記念像」。 台座の周囲にはたくさんの葉がデザインされ、音楽の広がりや自然との結びつきを表現しているのであった。台座には「BELA BARTOK」と刻まれていた。・ハンガリー出身の作曲家・民族音楽学者・ピアニスト。・20世紀を代表する音楽家のひとりで、近代音楽の巨匠として知られている。・自国や東欧各地の民謡を収集・研究し、それを作品に取り入れたことで有名。・ピアノ曲《子供のために》、オーケストラ曲《管弦楽のための協奏曲》などが代表作。・この像は ハンガリー政府からロンドン市に寄贈 されたもの と。・サウス・ケンジントンは、ロンドンの中でも 芸術・科学・音楽の中心地 とされるエリア。 ・ロイヤル・アルバート・ホール(世界的音楽ホール) ・ロイヤル・カレッジ・オブ・ミュージック ・ヴィクトリア&アルバート博物館 ・自然史博物館地下鉄・South Kensington駅の入口を再び。ディストリクト線、サークル線およびピカデリー線の3路線が乗り入れている。私の目的地は「Westminsuter」駅。 「District and Circle lines←Eastbound platform 2」 ディストリクト線、サークル線 案内図。Circle lineに乗車して、「WESTMINSTER」で下車。 乗車して来たCircle lineの車両を。ロンドンの地下鉄は、・車両自体に路線カラーは塗装されていない・色分けはあくまで路線図・駅案内のための識別用 なのであった。地上に出て、ロンドンを象徴する時計塔、通称 「ビッグ・ベン(Big Ben)」を見上げて。・正式名称:エリザベス・タワー(Elizabeth Tower)→ 2012年、エリザベス2世即位60周年を記念して改名された。・ビッグ・ベンという呼び名は、塔そのものではなく、内部にある大時鐘(Great Bell)の愛称。 しかし現在では、時計塔全体を「ビッグ・ベン」と呼ぶのが一般的になっているのだ と。この通称 「ビッグ・ベン(Big Ben)」👈️リンクを訪ねるのは、2013年4月以来なのであった。・完成:1859年・設計者:建築家 チャールズ・バリー卿 と助手 オーガスタス・ピュージン・様式:ネオ・ゴシック様式・高さ:約 96メートルこの場所はウェストミンスター宮殿(国会議事堂) に付属しているのだ。Westminster駅 から地上に出てすぐの場所に位置しているのだ。手前には、観光用2階建バス(屋根なし)・Open-top sightseeing busが。その前の屋根のあるバスは「Open-top double-decker bus」と呼ばれているのだ。 ビッグ・ベン前のこの道(Bridge Street/ウェストミンスター橋通り付近)は、観光用2階建バス(屋根なし)・Open-top sightseeing busの観光ルートのハイライトの一つで、ロンドン中心部を巡る定番コースに含まれているのだ。2階部分の屋根がない為、360度の視界で街の名所を楽しめるのだ。建築様式・ゴシック・リヴァイヴァル様式(ネオ・ゴシック) ・19世紀ヴィクトリア時代に流行した「中世ゴシック建築の復興」スタイル。 ・設計は チャールズ・バリー(国会議事堂全体の設計者)と、 詳細装飾は オーガスタス・ウェルビー・ピュージン。 ・特徴: ・尖塔(スパイア) ・ゴシック風のトレーサリー(装飾窓枠) ・精緻な石彫装飾と縦に強調された外観 ・鉄骨と石材を組み合わせた構造(当時の最新技術)修復の歴史・19世紀完成直後(1859年) ・初代の鐘が割れて作り直されるなど、早い段階から補修が必要になった。・20世紀〜 ・第二次世界大戦で国会議事堂が空襲を受けたが、塔と時計は比較的無事だった。・1950年代・1980年代 ・老朽化のために部分修復や清掃。・2017〜2022年:大規模修復工事 ・足場で完全に覆われ、エリザベス女王在位70周年の記念年に合わせて復元。 ・主な修復内容: ・時計機構の分解・清掃・部品交換 ・塔の石材補修と再塗装 ・腐食した鉄骨の補強 ・元の色彩への復元(黒塗りだった針や数字枠を、当初の青と金に戻した) ・新しいLED照明を導入し、夜間ライトアップが鮮やかに時計塔の時間は9:15。ロンドンの象徴的な時計塔、通称 ビッグ・ベン (Big Ben) 👉️リンク の上部をズームして。・ビッグ・ベンは塔の名前ではなく、中にある「大時鐘(Great Bell/大きな鐘)」の愛称。・塔全体の正式名称は Elizabeth Tower(エリザベス・タワー)。 2012年にエリザベス女王即位60周年を記念して改称されました。・ビッグ・ベンの文字盤のデザインの特徴 ・直径:7m、世界最大級の四面時計の一つ。 ・ガラス板製 文字盤は約300枚の乳白色ガラス板で構成(ステンドグラスのように組み込まれている)。 ・鉄枠 鉄製の骨組みでガラス板を支える。細かな放射状の格子が美しい幾何学模様を 作り出している。 ・数字(ローマ数字) 外周に黒のローマ数字。 視認性を重視しつつ、装飾的にデザイン。 ・ラテン語銘文 各文字盤の下にラテン語が刻まれている: "DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM VICTORIAM PRIMAM" (「主よ、我らの女王ヴィクトリア一世をお守りください」) ・装飾 針や外枠には金箔が施され、ヴィクトリア時代らしい華やかな意匠。 近年の修復で、針の色が黒→青へ戻された(当初のデザインに復元)。ビッグ・ベンは「ヴィクトリア朝の技術と芸術を象徴する建築」であり、近年の修復で完成当時の姿に最も近い姿に戻った と。イギリス国会議事堂(Palace of Westminster) を見る。手前の緑の木の向こうに見えるゴシック風の建物は、セント・マーガレット教会(St Margaret's Church)。移動して。ロンドンのビッグ・ベン(エリザベス・タワー)と国会議事堂(パレス・オブ・ウェストミンスター)を正面から。左側の高い時計塔・「ビッグ・ベン」で知られる エリザベス・タワー(Elizabeth Tower)。中央〜奥にかけての建物群・パレス・オブ・ウェストミンスター(国会議事堂)。・ゴシック・リヴァイヴァル様式の尖塔や装飾が特徴。右手の大きな窓のある建物・セント・マーガレット教会(St Margaret’s Church)。・ウェストミンスター寺院の隣にあり、庶民や下院議員の礼拝に使われた教会。・世界遺産に含まれる。右奥に見える塔と旗・国会議事堂の中央塔やヴィクトリア・タワーの一部。・イギリス国旗(ユニオン・ジャック)が掲げられていた。Government Offices Great George Street(GOGGS) と呼ばれる巨大な官庁ビル。・建設時期:1900〜1917年にかけて段階的に完成・建築様式:エドワーディアン・バロック(Edwardian Baroque) ・ポートランド石の外装 ・堂々としたコーニス(軒蛇腹) ・四隅に角塔を配置した対称的デザイン・設計者:John Brydon(途中で亡くなり、Sir Henry Tannerらが引き継ぎ完成)・場所:ホワイトホール通りとグレート・ジョージ・ストリートの角 (ビッグ・ベンの北西側すぐ)主な入居官庁 現在この建物には複数の省庁が入っています。代表的なものは: ・HM Treasury(財務省) ・Cabinet Office(内閣府) ・以前は教育省や労働省も入居していた歴史ありつまり、「Government Offices Great George Street」 が建物全体の正式名称で、その中に 財務省(HM Treasury) が主要なテナントとして入っているという形。そしてParliament Square Garden・パーラメント・スクエア・ガーデンを訪ねた。いくつかの像が並んでいた。まずはSir Winston Churchill statue・ウィンストン・チャーチル像。ズームして。・第二次世界大戦時の英国首相 Sir Winston Churchill(1874–1965)。・1973年に除幕されたブロンズ像(彫刻家:Ivor Roberts-Jones)。・外套を羽織り、ステッキを手にしている姿。・台座には「CHURCHILL」と刻まれていた。移動して斜めから。デイヴィッド・ロイド・ジョージ(David Lloyd George, 1863–1945) の像・職業・役割:イギリスの政治家、第40代首相(1916–1922)・業績 ・第一次世界大戦期の首相として戦争を勝利に導いた ・戦後の講和会議(ヴェルサイユ条約)に参加 ・社会改革(年金制度・失業保険の拡充など)を推進した自由党の指導者ジャナール・ヤン・クリスティアン・スムッツ(Jan Christiaan Smuts, 1870–1950) の像。背後に見える白亜の建物は Government Offices Great George Street(旧財務省/現:HM Treasury)。・人物概要 南アフリカの政治家・軍人・哲学者。2度にわたり南アフリカ首相を務めました。 第一次・第二次世界大戦で英国側に協力し、ウィンストン・チャーチルとも親交が深かった人物。 国際連盟(League of Nations)の設立に関わり、後に 国際連合憲章の起草 にも影響を 与えました。・像の特徴 軍服姿で直立し、両手を後ろに組んだ姿。威厳と冷静さを象徴しています。 台座には "CHRISTIAN SMUTS 1870–1950" と刻まれています。・設置年 1956年、彫刻家 Jacob Epstein によって制作されました。背後に映っていた建物がまGovernment Offices Great George Street(HM Treasury)、そして、その中央にそびえる 塔(ドーム型の尖塔付き)。初代パーマストン子爵(Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston, 1784–1865) の像。・本名:Henry John Temple(ヘンリー・ジョン・テンプル)・称号:第3代パーマストン子爵(Viscount Palmerston)・政治経歴: ・外務大臣を長く務め、対外政策において「ガンボウ外交」(砲艦外交)を展開 ・ヴィクトリア朝期に二度、イギリス首相(1855–1858、1859–1865) を務めた ・「自由主義的帝国主義者」として知られる・エピソード: ・外交において強硬姿勢をとり、国民からは人気があった ・1865年に亡くなる直前まで首相職にあった(現役首相で死去した最後の人物)顔をズームして。振り返って。この像は、先ほどの スムッツ像(南アフリカの政治家) や チャーチル像 などと並び、パーラメント広場を囲む「歴代の首相・世界的指導者像」の一部を形成していた。ジョージ・カニング(George Canning, 1770–1827) の像。・生没年:1770–1827・政治経歴: ・トーリー党の政治家 ・1827年に首相就任(わずか4か月で病没) ・外相としては、自由主義的な外交を展開し、特にラテンアメリカ独立を支持・評価: ・短命の首相だが、雄弁家として知られた ・当時のイギリス外交を大きく動かした人物第14代ダービー伯爵エドワード・ジョージ・ジェフリー・スミス=スタンリー(Edward George Geoffrey Smith-Stanley, 14th Earl of Derby, 1799–1869)・生没年:1799–1869・政治経歴: ・保守党の指導者 ・イギリス首相を3度務めた人物(1852, 1858–59, 1866–68) ・「イギリス史上最も短い政権」を含むが、合計で約4年在任 ・「現代保守党の形成者」のひとりその他の功績: ・ホメロス『イリアス』の英語翻訳者 としても有名 ・政治家でありながら文人としての側面も持つネットから。カニング、パーマストン、ダービー は、いずれも 19世紀の首相経験者 で、パーラメント広場に揃って並んでいたのであった。パーラメント・スクエア(Parliament Square) の一角から、イギリス国会議事堂(ウェストミンスター宮殿, Palace of Westminster) を望んで。1.中央左(長い屋根の建物) ・ウェストミンスター・ホール(Westminster Hall) ・1097年建立、国会議事堂で最も古い部分。王の戴冠式の祝宴や国家的行事の会場として有名。 ・屋根は中世の「ハンマービーム天井(Hammer-beam roof)」が内部に広がります。2.右側の高い塔 ・ヴィクトリア・タワー(Victoria Tower) ・宮殿の南西角に位置する巨大な塔(高さ98m)。 ・現在は国会文書の保管庫(Parliamentary Archives)として使用。 ・写真ではユニオンジャックが掲揚されています。3.奥に見える尖塔 ・中央やや左奥:セント・スティーヴンズ・タワー(現・エリザベス・タワー) はこの角度 からは隠れ気味ですが、手前の建物越しに別の塔(中央塔や聖ステファンの尖塔)が見えて います。4.右端の白い回廊状の建物 ・聖マーガレット教会(St Margaret’s Church)の一部ではなく、ウェストミンスター寺院の 一角に連なるクロイスター風の建築。 ・広場からは国会議事堂と大聖堂に囲まれるように見える位置です。ミリセント・ギャレット・フォーセット(Millicent Garrett Fawcett, 1847–1929) の像。・イギリスの女性参政権運動のリーダー。・穏健派の NUWSS(National Union of Women's Suffrage Societies, 全国女性参政権協会連合) を率い、非暴力的手法で女性の投票権獲得に尽力しました。・1918年に女性参政権が部分的に認められたとき、その功績は非常に大きなものでした。・特徴: ・フォーセットが手に掲げている布には彼女の言葉 "COURAGE CALLS TO COURAGE EVERYWHERE" (「勇気はあらゆる場所の勇気を呼び覚ます」) ・台座には女性参政権運動に関わった59人の女性と4人の男性の肖像レリーフが刻まれていた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.22
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その85):ダブリン空港からロンドン・ヒースロー空港へ-2~宿泊アパートメント
飛行機がロンドン中心部の東〜南東エリアを旋回しながら着陸態勢に入った時に画面左上に見えたのが、巨大な白いドームは The O2(旧称:Millennium Dome)、その周囲はグリニッジ半島(Greenwich Peninsula) 。テムズ川が大きく蛇行して流れていた。白いドーム屋根(The O2)はロンドンでも非常に目立つランドマーク。対岸(手前側)は Canary Wharf(カナリー・ワーフ)地区で、高層ビル群が見えた。写真をネットから。ミレニアム・ドームは、単一の屋根を持つ構造物としては世界最大規模のものである。その外観は100mの高さの黄色いマストに吊られた巨大な天幕である。ちょうど正円を12等分した位置に立つマストは、12の「時間」と「月」を表現し、グリニッジ標準時の役割を象徴している。屋根は貝殻のように波打った円形であり、直径は365mであるが、この数字も「1年=365日」を象徴した値となっている。1951年の英国博覧会に際して建造された Dome of Discovery を回顧する意味をも持つ と。ロンドン・シティ空港(London City Airport, LCY)。細長い滑走路が東西方向に伸びており、その両側がドック(水路)に囲まれているのが大きな特徴。手前の大きな白い建物群は ExCeL London(エクセル・ロンドン国際展示場)。その奥(北東側)に滑走路が続き、さらに向こうは ロイヤル・ドックス(Royal Docks) と呼ばれるエリア。テムズ川上空を大きく旋回。左手にロンドン・シティ空港(London City Airport, LCY)。グリニッジ公園?Wimbledon Park Lake(ウィンブルドン・パーク湖)。湖の右側に見える白い大きな屋根は、Wimbledon Parkのイベント用仮設テント。そのすぐ手前にあるオレンジ色の面は、テニスコート(クレー系コート)。湖自体は細長い楕円形で、ボート遊びやカヌーなどのアクティビティが行われる場所小さな中州(島)があり、数隻の船が係留。これはRiver Thames のクラム・アイランド・Clam Island周辺。手前に大きく蛇行して流れているのがテムズ川。川沿いに緑地が広がっており、これは リッチモンド・パークやその周辺の緑地。遠くに見えたのがQueen Elizabeth II Storage Reservoir・ウィンブルドン・パーク湖と Island Barn Reservoir??Twickenham Stadium(トゥイッケナム・スタジアム)。イングランド代表ラグビーの本拠地で、収容人数は約 82,000人。世界最大級のラグビー専用スタジアムとして知られている。写真でも楕円形で屋根がぐるりと囲む特徴的な形が確認できた。茶色い低層ビル(角に丸いドームのような構造)が Hounslow Civic Centre(旧ハウンズロー庁舎)。現在は閉鎖されている と。中央~奥:広大な緑地は Lampton Park(ランプトン・パーク)。奥の白い屋根の巨大な建物群:これは West London Audi(大規模自動車販売施設)や近隣の流通倉庫群。ヒースロー近くにある Topgolf Surrey。実際にはこれは Topgolf Chiswick / Topgolf Hounslow と呼ばれる施設で、ロンドン西部にあるゴルフ練習場(打ちっぱなし)。芝生の上に 青いマットにカラフルな円(ターゲット) が配置されていた。飛行機はもう着陸態勢に入り、ヒースローの北東側をぐるっと旋回しながら進入しているところ。奥に大きく見えている水面は Queen Mary Reservoir(クイーン・メアリー貯水池)。Queen Mary Reservoir はヒースロー空港の南西約5 km にあり、RWY27L 進入時に機体左側(南寄り)に視認できたのであった。写真左側に見える赤茶色や白系の 高層住宅群 は、ロンドン南西部の Hounslow(ハウンスロー)地区 にある集合住宅群。この工業団地は、ヒースロー空港の東側・フェルサム寄りに広がるNorth Feltham Trading Estate(ノース・フェルサム・トレーディング・エステート)。左手に見えているのはA30 Great South West Road。空港南側を東西に走る幹線道路。そして滑走路・RWY27L に着陸。ヒースロー空港のターミナル5に向かって進む。我がBA便が到着した場所はヒースロー空港のターミナル5。 ロンドン・ヒースロー空港(London Heathrow Airport)のターミナル5(Terminal 5)。中央にある円形の高架道路は、ターミナル5のアクセス道路・連絡通路で、出発/到着エリアへの車両動線を整理する構造。Heathrow Airport・ロンドン・ヒースロー空港での入国手続を無事終えて、地下鉄を利用してSOUTH KENSINGTON STATION(南ケンジントン駅)に到着。ロンドン・地下鉄MAP(一部)。サウス・ケンジントン駅 (South Kensington station) は、ロンドン・ケンジントン&チェルシー区にある、ロンドン地下鉄の駅である。ディストリクト線、サークル線およびピカデリー線の3路線が乗り入れていた。South Kensington(サウス・ケンジントン)は、ロンドン中心部西側にある高級住宅街・文化エリア。ロンドン市中心部から西に約4km、ケンジントン&チェルシー区に位置。SOUTH KENSINGTON STATION(南ケンジントン駅)を振り返って。「SOUTH KENSINGTON STATION」。駅前には多くの白い建物が。旅友がナビを利用して、この日から3連泊の民泊アパートメントに向けて進む。私はその後ろを追いかけるのみ。駅前の花屋の脇を通り、ペラム(Pelham)・ストリートを東に進む。リュックを背負い、重いトランクを転がし、いや引っ張りながら歩道を進む。ここを右折。そしてこの先の正面の瀟洒な赤レンガの建物が我が民泊アパートメント。駅から約10分程、この正面の1階が我々のゲストハウス・宿泊アパートなのであった。日本で言ういわゆる「民泊」なのであった。「民泊」とは一般的に個人が所有する住宅やマンションなどの一部または全部を、旅行者や短期滞在者に宿泊場所として提供するサービスのこと。 階段を下りた所が、我が部屋の入口。手前の壁にハードキーの箱があり、ネットで送られて来たパスワードをsetすると、箱が開きハードキーが入手出来るのであった。そしてツインのはずの部屋が、ダブル!!よって、私は応接間に逃げて、このソファーを移動して、ベッドを作り、このソフアーで3泊したのであった。しかし、トイレ、シャワールーム、私のベッドルームとなった居間、そして冷蔵庫、電子レンジ、 IHクッキングヒーター、調理器具、食器類が全て完備したキッチンがそろっていたのであった。よって私のBED ROOMにもテレビが。一休みして、夕食の店に向かったのであった。ビールを楽しむ。しかし、この後は空腹そしてこの日の疲れもあり、カメラ撮影を忘れてしまったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.21
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その84):ダブリン空港からロンドン・ヒースロー空港へ-1
アイルランド最終日のダブリン市内観光を終え、ホテルに戻り部屋で一休み。74歳にして再び異国の街を歩き、歴史と現代文化が混じり合うダブリンを五感で味わったのであった。石造の建築物が語る過去、通りに響く音楽、そして旅友と二人で歩き、また路面電車に揺られながら見る街の景色。そのすべてが、これからも心のアルバムに残り続けること間違いなしなのであった。そしてホテルの近くのバス停・「Parnell Square West」からDublin Airport行きのバスに乗車しDublin Airport👈️リンク・第2ターミナルへ。ターミナル内で、エスカレーターに乗り出国手続きに向かう。ここを上がると保安検査場(Security Screening)エリアへ。ターミナル2の保安検査後エリア(出発ゲート前の免税・飲食ゾーン)を。免税店やレストランが並ぶ出発ゲート前のメインフロアを、エスカレーター上から見下ろして。中央左:レストラン&カフェ(木目調のカウンターが印象的)中央右:「Boots」(英国系ドラッグストア)や「Beauty」コーナー搭乗ゲート案内板を確認。「15:30 LONDON LHR」の搭乗ゲートが307であることを確認。搭乗ゲート307はこちらの方向。別のモニターで再確認。エスカレーターに乗れと。通路が夕焼けに染まった如くに。様々な色の着色フィルムが。窓に黄色の着色フィルム(またはデザインガラス)が入っているため、全体がオレンジ〜黄色がかった色調に。搭乗ゲート付近からブリティッシュ・エアウェイズ(British Airways)の旅客機を。ゲートナンバー301ー307Aを発見。案内に従って進む。BA-837便の私のチケット。搭乗ゲートは301と。座席はネットで窓側を予約していたのであった。そしてBA-837便に搭乗。時間は15:23。機窓からエールフランス(Air France) の エアバス A220-300 型機を見る。アエール・リンガス(Aer Lingus) の エアバス A330 型機。エアリンガス(Aer Lingus)は、アイルランドの航空会社で、同国のフラッグ・キャリア・国を代表する航空会社である。垂直尾翼のマークはアイルランドの象徴とされるシャムロック(Shamrock)、マメ科のクローバー(シロツメクサ、コメツブツメクサ)など葉が3枚に分かれている草の総称である。コーポレートカラーの緑色はアイルランドのナショナルカラーである。ダブリン空港・管制塔。そして飛行機が漸く動き出した。時間は15:50。突然、大粒の雨が。そして離陸して雨雲の中へ。そして離陸後、40分ほどでイギリス上空へ。飛行ルート。ダブリンから東へ飛んで、リヴァプール付近をかすめ、オックスフォード南方を通過してロンドンにアプローチするコース。機窓から田園地帯がひたすら眼下に。ロンドン・ヒースロー空港に向かって徐々に降下して行く。右下の水面は Queen Mary Reservoir(クイーン・メリー貯水池)。白っぽく見える建物群は Staines-upon-Thames(ステインズ・アポン・テムズ)周辺の工業団地や流通施設。ロンドン西部にある Queen Mary Reservoir(クイーン・メアリー貯水池)が眼下に。・ロンドン・ヒースロー空港の南西約10km・1924年に完成したテムズ川水系の巨大な貯水池・面積は約2平方キロメートル(700エーカー)・テムズ水道局(Thames Water)が管理し、ロンドン市内の水供給に利用されている正方形に近い人工的な形状が特徴で、上空からも非常に目立つのであった。ロンドンの Heathrow Airport(ロンドン・ヒースロー空港) が上空から見えて来た。・滑走路が2本、東西方向に平行して並んでいるのがはっきり見えた。・左(北側)が 北滑走路(09L/27R)、右(南側)が 南滑走路(09R/27L)。・滑走路の間に多数のターミナルビルと駐機場(エプロン)が配置。・写真中央の大きなエプロンは ターミナル5(BA=ブリティッシュ・エアウェイズ専用)。コルンブルック給水場(Colnbrook)付近とWraysbury Reservoir(レザボア) のあたり。写真中央をカーブして走る道路は 、M25本線に関連する新設工事中の高架・付け替え道路。ロンドン郊外の住宅街 を真上から見下ろす。ロンドン北部の Enfield(エンフィールド区)内の住宅街。写真右下に緑地が見えており、これは Enfield Golf Club。Enfield・エンフィールドの街並みが眼下に。長い三角形の人工湖は William Girling Reservoir(ウィリアム・ガーリング貯水池)。・場所:ロンドン北部、エンフィールド区(Enfield)に位置。・建設:1930年代に建設されたテムズ川水系の給水用貯水池。・用途:ロンドンの飲料水供給のための重要な施設。その手前にEdmonton・エドモントンの市街地が拡がる。こちらはKing George VI Reservoir(キング・ジョージ6世貯水池)。手前に浄水処理場・Thames Water North London.その南(写真右)にはEdmonton Solid Waste Incineration Plant(固形廃棄物焼却場)。テムズ川のテムズ・バリア(Thames Barrier)。ロンドンを高潮や洪水から守るための巨大な可動防潮堰で、1982年に完成。その向こう(テムズ川の北側・写真右上あたり)には、緑の中に赤い屋根のチャールトン・アスレティックFCの本拠地「ザ・ヴァレー・スタジアム」が見えた。川の手前(南岸)には再開発地区が広がっており、これは ロイヤル・ドックス地区(Royal Docks)。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.20
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その83):Dublin市内散策(21/)・
St Stephen's Greenの前にあったのがダブリン・ユニテリアン教会(Dublin Unitarian Church)。石造りグレーの壁面にゴシックスタイルの尖塔、左手に入口ポーチ、中ほどに高い尖塔付きの構造。デコレイティブ・ゴシック(装飾ゴシック)様式で、狭小な敷地に建てられた教会。・灰色花崗岩による石造外壁と、ゴシック様式の尖頭アーチ窓。・中央の小尖塔(ベルタワー)・30m強と、その下の八角形の開口部。・大窓の縦長のトレーサリー(石の窓枠装飾)。・左下に半分見える黒地金文字の円形プレート(歴史的建物の案内)。・ベルファスト出身の建築事務所「Lanyon, Lynn & Lanyon」による設計。 1861〜63年に建造された。「UNITARIAN CHURCHTHIS CHURCH WELCOMES ALL WHO WISH TO WORSHIP IN A SPIRIT OF FREEDOM REASON AND TOLERANCE」【ユニテリアン教会この教会は、自由・理性・寛容の精神で礼拝を望むすべての人々を歓迎します。】 ・上部のシンボルは「聖火を灯した杯(Flaming Chalice)」で、ユニテリアン・ユニバーサリズム(Unitarian Universalism)の象徴。自由な探求、真理の追求、人間性の尊重を表す。・「Freedom(自由)」=信仰や思想の自由を尊重する姿勢。・「Reason(理性)」=盲目的な信仰ではなく、理性的な理解と議論を重んじる価値観。・「Tolerance(寛容)」=異なる信条・文化・背景を持つ人々を受け入れる包容力。・このメッセージは、教会が特定の教義や宗派にとらわれず、誰でも歓迎するという開放的な 方針を表す と。下記の写真はネットから。ユニテリアン教会(Unitarian Church Dublin)の内部にある、壮麗なステンドグラスと八福(Beatitudes)を刻んだ祭壇部。ステンドグラス下には、マタイによる福音書5章3〜10節からの八福が英語で刻まれている。1.Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven. 心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。2.Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. 悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。3.Blessed are they that hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. 義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。4.Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. あわれみ深い者は幸いです。その人たちはあわれみを受けるからです。5.Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God. 平和をつくる者は幸いです。その人たちは神の子と呼ばれるからです。6.Blessed are they that have been persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven. 義のために迫害されてきた者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。美しいステンドグラスの詳細もネットから。1.左端 – “DISCOVERY” ・緑のローブを着た人物(学者・錬金術師風)が薬瓶や器具を扱っている様子。 ・背景には棚や窓、炎のような光源があり、知識探求や発見を象徴。2.左から2番目 – “TRUTH” ・鎧を身に着け、松明を掲げる若い戦士の姿。 ・光をもたらす「真理の探求者」または「信仰の守護者」を象徴。3.中央 – “INSPIRATION” ・赤い外套を纏ったキリスト像。背後から輝く光と天を示す背景。 ・神からの霊感や導きを象徴。4.右から2番目 – “LOVE” ・母親が幼子を抱き、前には2人の子どもが立つ。 ・無償の愛や慈愛、家庭の温かさを象徴。5.右端 – “WORK” ・鍛冶屋のような人物が鉄を打っている。背景に道具や炉が描かれる。 ・労働や勤勉の尊さを象徴。そしてSt. Stephen's Green駅からトラム「LUAS(ルアス)」👈️リンクに乗る。「Faiche StiabhnnaSt. Stephen's Green(セント・スティーブンズ・グリーン)」。 ・上段の「Faiche Stiabhnna」はアイルランド語(ゲール語)での名称。・Faiche は「芝生地・草地・緑地」を意味し、・Stiabhnna は「スティーブン(Stephen)」の属格形("の"所有格)。・直訳すると「スティーブンの草地」=「St. Stephen’s Green」。路線マップ。この St. Stephen’s Green 駅 は、ダブリン路面電車 Luas(ルアス) の グリーンライン(Green Line) の駅。ネットから路線図を。乗車したLuas(ルアス)ライトレールのグリーンライン(Green Line)。車窓から、セント・スティーブンズ・グリーン公園(St. Stephen’s Green)北西角にあるフス記念門(Fusiliers’ Arch)を見る。・正式名称:Fusiliers’ Arch・建設年:1907年・目的:第二次ボーア戦争(1899–1902)で戦死したロイヤル・ダブリン・フュージリア 連隊兵士の慰霊・構造:ローマの凱旋門風の花崗岩アーチ・位置:St. Stephen’s GreenのGrafton Street側入口にあたるSt. Stephen's Greenの北側の路線の急カーブからDawson Street方向を見る。右側に見えたのが「The Mansion House」。・用途:ダブリン市長(Lord Mayor of Dublin)の公邸・建築年:1710年・建築様式:ジョージアン様式・特徴: ・正面中央に鉄製の装飾キャノピー(車寄せ) ・ペディメント(三角破風)にダブリン市の紋章 ・屋上にアイルランド国旗、ダブリン市旗、EU旗・歴史的意義: ・1715年以来、歴代のダブリン市長が公式行事や来賓接待を行う場所 ・内部には「ラウンド・ルーム(Round Room)」があり、1821年に ジョージ4世歓迎晩餐会が開かれた 「St Ann's Church of Ireland」。・所在地:Dawson Street, Dublin 2・宗派:アイルランド国教会(聖公会)・建築様式:ゴシック・リヴァイヴァル・建設開始:1720年(完成は19世紀)・特徴: ・外壁は灰色石造 ・正面に大きな尖頭アーチと赤い木製扉 ・上部に複数の小アーチ窓・内部: ・ヴィクトリア朝時代の装飾が残る ・食事支援活動「Soup Kitchen」でも知られる Dawson Streetの右側にあった、この建物はRoyal Irish Automobile Club(RIAC)本部ビル。・名称:Royal Irish Automobile Club (RIAC) Headquarters・所在地:34 Dawson Street, Dublin 2・建築様式:ネオクラシカル様式(花崗岩造、列柱と装飾アーチ)・特徴: ・ファサードは重厚な石造で、1階にアーケード状の窓 ・上層階にコリント式の柱とバルコニー ・屋上には緑青色のドーム(写真の左上に見えた)そして見えてきたのが、今回のダブリン市内散策で既に2回訪ねた、トリニティ・カレッジ・ダブリン(Trinity College Dublin) の正門(Front Gate)付近。正門(Front Gate)を車窓から。トリニティ・カレッジ・ダブリン(Trinity College Dublin)の北側外観を、道路(College Street/Westmoreland Street)越しに。トリニティ・カレッジの西北角に位置する、正面玄関部から少し北寄りの建物を。高い窓とコリント式列柱と屋上のバラスター(欄干)を見る。「Trinity」駅で下車し振り返る。「Thomas Moore Statue(トーマス・ムーア像)」を再び。 ・名前:Thomas Moore(1779–1852)・職業:アイルランドの詩人・作詞家・歌手・代表作: ・『アイルランド旋律集(Irish Melodies)』 ・「The Minstrel Boy」「The Last Rose of Summer」など・像の場所:ダブリン市中心部、トリニティ・カレッジの西側、College Green付近・制作年/作者:1879年、Christopher Moore(彫刻家)・特徴: ・ケープを羽織り、右手に書物(または巻物)を持つ立像 ・台座正面に "MOORE" の文字刻印 ・台座の四隅に装飾(ハープなどアイルランド文化を象徴するモチーフ)ダブリン中心部にある有名なパブ 「Cassidy’s Bar」 ・特徴: ・黒地に金文字の看板「CASSIDY’S」 ・窓上部に植物の装飾 ・窓にギネス(Guinness)ロゴのネオン ・店先にビール樽(ケグ)が積まれており、補充日や開店前の光景・人気ポイント: ・ギネスやクラフトビールの品揃え ・店内の壁や天井にポスターやポップカルチャー装飾 ・観光客だけでなく地元客にも人気のカジュアルなパブO’Connell Bridge(オコンネル橋)の手前(南側)から北方向を見て。O’Connell Bridge(オコンネル橋)を渡る。「ダニエル・オコンネル像(Daniel O’Connell Monument)」。何回目!!?? オコンネルストリートに立つ「ウィリアム・スミス・オブライエン(William Smith O’Brien)像」 「フランシスカン修道士神父テオバルド・マシュー(Father Theobald Mathew)像」 「パーネル記念碑(Parnell Monument)」。 「アンバサダー・シアター(The Ambassador Theatre)」。 「ロトンダ病院(Rotunda Hospital)」の本館。 Dominick駅近くのカラフルなアート。壁面に「VIBES ODYSSEY」の文字がポップな緑色グラデーションで描かれていた。文字の間に、カラフルな人物や動物のイラストそして背景にパープル系の植物や抽象模様。・中央にヘッドフォンを着けた女性のリアルな肖像画・背景はオレンジ色と黒の木々シルエット・左右にカラフルなグラフィティ文字と花のイラスト・作者サイン:「Aches」など、ダブリンの有名ストリートアーティストの一人によるもの と。そしてこのダブリン観光最終日の市内観光を終えてホテル「Maldron Hotel Parnell Squareマルドロン ホテル パーネル スクエア」に戻ったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.19
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その82):Dublin市内散策(20/)・St Patrick's Cathedral・聖パトリック大聖堂-2
St Patrick's Cathedral・聖パトリック大聖堂の内陣の散策を続ける。配置案内図。このステンドグラスは細長い単窓構造で、物語的場面よりも象徴と紋章的モチーフを中心に構成されていた。ズームして。1.最上部の円形メダリオン ・王冠付きの金色のハープ(アイリッシュ・ハープ)が描かれていた。 ハープ:アイルランドの文化的・政治的アイデンティティの象徴。 ・アイルランドの国章であり、しばしば愛国心や民族的誇りを象徴。2.中央上部の雲型パネル ・内部に海や岸辺の景色が描かれていた。おそらく寄進者の故郷や重要な港町を表す図像。3.中央下部の円形メダリオン ・赤と青の幾何学的花模様を中心に、緑のガーランドで縁取られた装飾。 ・ケルト風のデザイン要素が見られる。 ・連合王国の花の象徴(バラ=イングランド、アザミ=スコットランド、シャムロック= アイルランド)を組み合わせたデザイン。4.最下部の帯状カートゥーシュ ・英文の献辞が描かれていた。 "In memory of those who fell on the H.M.S. Aboukir, Hogue, Cressy, 1914"(推定) この3艦は第一次世界大戦の1914年に北海で沈没した英国巡洋艦。 この窓は海軍戦没者記念として設置されたものであろうか。このステンドグラスは縦長の単窓構造で、上から下に向けて物語性と象徴性を持つ3つの主要セクションが。最上部(アーチ頂部) ・図像:小さな円形内に王冠と王笏、玉座など王権の象徴が描かれているように見える。 ・意味:神から授けられた王権、または勝利と統治の正統性の象徴。中央部(メインパネル) ・人物:中央の壮年〜老年の男性は、鎧とマントをまとい、手に長剣を持つ。 髭を蓄え、頭には冠か兜を着けている。 ・両脇:両側に青い兜と鎧を着けた護衛兵が立つ。 ・足元の文字:『King Cormac of Cashel Bishop & Martyr A.D. 908』 ・意味: ・描かれている中心人物は カッシェルのコーマック王 (Saint Cormac mac Cuilennáin, 908年没) アイルランド南部マンスターの王であり、学者・司教でもあり、戦死して殉教者と された人物 ・王冠・剣・護衛兵は王としての権威と戦いの勝利を象徴。最下段をズームして。・中央の図柄:翼を持つ天使が盾(青地に金色の獅子)を抱える構図。・盾の周囲のリボン文字: 「VIRTUTIS NAMURCENSIS PRAEMIUM」のラテン語標語. 【ナミュールの勇気への褒賞】、ナミュールは現在のベルギーの地名 と。 この標語は、1695年のナミュール包囲戦(英蘭同盟戦争中)での功績を記念するもので、 英国陸軍の一部連隊が使用した伝統的モットーです。特にロイヤル・マンスター・ フュージリアーズ連隊やその前身部隊にゆかりがある と。・左右の装飾:左上の赤い盾に金色のハープ(王冠付)、右下のドラゴン風意匠。・下部の銘文:「In memory of the Officers non-commissioned Officers and men of the Royal Irish Regiment who fell in the South African War 1899–1902.」の献辞。 【1899年から1902年の南アフリカ戦争において戦死した王立アイルランド連隊の士官・ 下士官および兵士を記念して。】画像のステンドグラスはややピンぼけしていますが、構図から判断すると、中央に白い衣の人物(おそらくキリストか聖人)が立ち、その上下に小さな場面や象徴図案が入っていた。下部にはアイルランドの象徴である金の竪琴(アイリッシュ・ハープ)が緑の背景と共に描かれているようである。下部にハープがあることから、アイルランド部隊やアイルランド出身兵士への追悼を意図している?ネットから。この窓は、聖人(多くの場合、戦士聖人や守護聖人)を上段に描き、その下に実際の戦場や兵士を描くという二段構成で、第一次世界大戦や南アフリカ戦争など、教会にゆかりのある部隊の戦没者を追悼しているのであろう。ズームして。このステンドグラス窓は、2つの主要な場面に分かれた構成になっていた。上段 ・中心人物:長い赤いマントと鎧を着た聖人または守護聖人のような人物が立って 手には長い剣を持ち、もう一方の手で盾を支えている。 ・頭部の背後には金色の後光(光輪)が描かれ、人物の聖性や象徴性を示している。 ・盾の意匠:紋章が描かれており、この窓が特定の都市・部隊・家系を記念している。 ・周囲の装飾:植物文様や幾何学模様のステンドグラスが人物を囲み、上部には青を基調 とした紋章が配置されている。下段 ・場面描写:軍服姿または歴史的服装の人物たちが描かれ、戦争や戦闘に関連した出来事を 表現している。 ・中央の人物は倒れているか、座っている兵士で、仲間に支えられている場面にも見える。 これは殉職や犠牲を象徴する図像であろうか。下部銘文 ・銘板部分に白地の文字があり、 寄進者や追悼対象(特定部隊・人物名)が記されていた。 ・「IN LOVING MEMORY OF ...」という追悼の定型文が含まれており、戦没者を記念する 軍事記念窓であることが強く示唆される。説教壇(pulpit)は石造で、ゴシック・リヴァイヴァル様式の精緻な彫刻で装飾されていた。1.三方に立つ人物像 ・聖書や巻物を持った人物像が3体。これは旧約・新約の預言者や福音書記者(Evangelists)を 象徴している。 ・各像の背後には、縦長の尖頭アーチ型の枠内に文字(聖句や名前)が刻まれている。2.中央の人物 ・左手に巻物を持ち、右手でそれを示すような姿勢。 ・背後の枠内には、聖書の一節と思われる英語の彫刻が刻まれていた。移動して別角度から。八角形の構造、各面には人物像が配置されていた。セント・パトリック大聖堂(ダブリン)の西端(West End)側を見る。1.建築様式 ・尖頭アーチ(Pointed Arch) ・リブ・ヴォールト天井(Rib Vault) ・高いクリアストーリー窓(Clerestory Windows) → 縦長の3連窓(トリフォリウム構成)が見えた。2.中央壁面・大窓の下に石造の装飾的なポータル(アーチ枠+破風飾り)。・上部中央には小さな彫像(十字架か人物像)。3.左右の構造・アーケード(大アーチ列)・中間層に細長い二連アーチの開口部(ギャラリーまたはトリフォリウム)。・高層にランセット窓を配置。大聖堂内の三連ランセット窓の大型ステンドグラスで、かなり細かい物語パネル構成になっていた。セント・パトリック大聖堂(ダブリン)東端の大窓(East Window)で、キリストの生涯や聖書の物語を連続場面で描いたもの。中央列:キリストの生涯(受胎告知 → 誕生 → 洗礼 → 十字架刑 → 復活)左列:主に旧約聖書の場面(アダムとイブ、ノアの箱舟、モーセの律法授与など)右列:新約聖書後半や使徒行伝の場面(聖パウロの改宗、聖パトリックの伝道など)5連の尖頭アーチ型ランセット窓に収められたステンドグラス群。聖堂の側廊または内陣のトランセプト付近にあり、中央の3枚が主要人物、両端の2枚が小場面で構成されていた。ズームして。左から順に1.最左端(小型) ・下部に小さな人物群像があり、上部は花形文様。 ・祭壇奉仕や寄進の場面を象徴する可能性。2.左から2番目 ・後光を持つ聖人(青と赤の衣、左手に書物を持つ姿)。 ・女性聖人(聖母マリア、または聖カトリーナ等)の可能性が高い。3.中央 ・王冠を戴き、赤いマントと金の鎧を着た人物。 ・右手に剣または杖、左手に盾を持つ姿。聖ジョージや聖マイケル、あるいは アイルランド王族の守護聖人像の可能性。4.右から2番目 ・黒い修道服(白いスカプラリオ付)を着た男性聖人。 ・ドミニコ会、シトー会、またはアウグスティノ会の聖人(例:聖ドミニコ、聖ベルナルド)と 思われる。5.最右端(小型) ・最左端と対称的な構図で、聖書や教会のシンボルモチーフ。中央祭壇背後に設置された三連のランセット型ステンドグラス窓で、左右に聖人像、中央に物語場面が縦に配された構成になっていた。左から右へ1. 左窓(上下2場面) ・上段:女性聖人(冠を戴き、右手に書物、左手にパームの枝) → 殉教者の象徴(パーム枝)を持つことから、聖アグネス、聖カタリナ、 または聖セシリア等の可能性。 ・下段:別の女性聖人(白衣+赤マント、両手に百合) → 百合は純潔の象徴であり、聖母マリアや聖アグネスの図像によく見られる。2. 中央窓(上下3場面) ・最上段:白衣の天使が殉教者(または兵士)を迎える場面。 ・中段:王冠を戴いた人物が群衆に囲まれ祝福されるか、または都市の門前での儀式。 ・下段:船に乗る人物の場面(使徒の航海や聖人の伝道を示す)。 → この構成から、中央窓は一人の聖人(または使徒)の生涯を順に描いている 可能性が高いです。3. 右窓(上下2場面) ・上段:女性聖人が子供を抱く(または施しを与える)場面 → 聖エリザベス、聖アンナ、または慈善活動を行った女性聖人像に近い。 ・下段:女性聖人が花を持ち、もう一人の人物と対話する場面。 → 教えや導きの象徴。パトリック大聖堂の北側廊(North Aisle )の端部の窓。北側廊(North Aisle )の端部のステンドグラス。中央パネル・場面:「エルサレム入城(The Entry into Jerusalem)」・人物:中央にロバに乗ったキリスト、青い外套と赤い下衣、頭には後光(光輪)。 右側には城門前で迎える人々、左側には弟子たちや群衆。・物語背景:受難週の始まり、キリストがエルサレムへ入城する場面。群衆が衣やヤシの枝を 道に敷き、彼をメシアとして迎える。左パネル・場面:エルサレム入城に先立つ、または同行する弟子や民衆。・人物・服装:青や緑のローブをまとった男性群像。手に衣を持ち、キリストの進む道に 敷こうとしている動作。・象徴:謙遜と歓迎の心を表現。右パネル・場面:群衆が喜びと期待を込めてキリストを迎える。・人物・服装:赤や緑の衣を着た女性や子どもを含む群衆。抱き合ったり、 顔を向けて祝福の視線を送る。・象徴:救世主到来の喜びと、信仰共同体の一致。下部装飾パネル(トレーサリー部)・中央列(中央パネル下):赤と緑を基調とした植物文様(アカンサスやブドウを想起させる)と 円形の幾何模様。生命と救いの象徴。・左右列:同様の植物文様と幾何学パターン。左右対称性が強く、全体の調和を演出。・象徴的意味:ブドウや蔓はキリストと信者の結びつき (ヨハネ福音書15章「わたしはまことのぶどうの木」)を暗示する。大聖堂内の北翼廊に位置する、記念碑とステンドグラス窓がセットになった部分。・下部中央の構造物 コリント式円柱を持つ古典様式の記念碑で、内部には壺(葬送用のアーバン)型の彫刻が あります。これは埋葬や記念の対象人物を顕彰するモニュメントです。上部には家紋か 紋章があり、人物や家系を示している可能性があります。・左右の小型記念碑 左側はゴシック風アーチを持つレリーフ板、右側は縦長の碑文パネルで、装飾的な 円形モチーフや家紋付き。・背後のステンドグラス窓 3連の高窓(トリフォリウム形式に近い縦長ランセット)で、各パネル内に円形の メダリオン(ラウンドパネル)が縦に連続しています。モチーフは花文様や幾何学的 パターンが中心で、人物描写は少ない(あるいは無い)ため、礼拝堂の物語窓というより 装飾的な窓に分類されます。ウィリアム・コナー・アール・オブ・ハリントン(William Conyngham, Earl of Harrington)記念碑 と。ネットから。1. 建築構造・様式:新古典主義的デザイン・柱:両側に配置されたコリント式円柱(黄色味がかった大理石風の装飾)・ペディメント(破風):上部に三角形の破風と、その中央に家紋の盾・台座部:中央奥に黒色石材背景、ニッチ内に装飾付きの大きな葬送用の壺(葬儀壺)2. 主体(中央の壺)・葬送壺(Funerary urn) 装飾的なガーランド(花綱)模様と、頂部には炎(永遠の命の象徴)・台座前面に浮き彫りの肖像メダリオン(恐らく被葬者の横顔)3. 象徴要素・壺と炎:魂の不滅・復活信仰の象徴・家紋盾:故人の身分と家柄を示す・コリント式柱:威厳・高位の象徴4. 周囲の付属碑文・左右の壁面に別人物の小型記念銘板あり・左下のゴシック型枠には宗教的浮き彫り像、右側には別の記念銘文パネルこのステンドグラスは、三連の縦長パネルで構成され、中央に象徴的な「生命の木」と群衆を配し、左右に異なる人々の姿を描いた場面。モチーフと構図から、新約聖書の「最後の審判」や「天国の招き」「義人の集い」を象徴的に表現している可能性が高いのだ と。中央パネル・上部:枝いっぱいに実をつけた生命の木(赤や橙色の果実はしばしば永遠の命や救いを象徴)・中央部分:青い衣の人物(キリストあるいは聖母マリア)と、その周囲に集まる人々・下部:安らぎの表情を見せる人々、祝福を受ける構図・象徴:救済、天国への導き、神の国の豊かさ左パネル・上部:生命の木の枝が広がる・中〜下部:多くの人物が上方(中央パネル)を仰ぎ見ている構図・衣装は茶や赤など質素な色調が多く、群衆の中には高齢者や子供も・象徴:義人の列、天国へ招かれる人々、神の御国へ向かう巡礼右パネル・上部:同じく果実を実らせた枝・中部:青・茶色の衣を着た人物たちが会話するか、中央を見つめる・下部:同じく多くの人々が集まり、上方を仰ぐ・象徴:聖人・預言者・使徒、または救いを受ける信者たち全体構成の意味・生命の木が三つのパネルにまたがって描かれ、神から与えられる永遠の命を象徴・果実は「命の実」や「救いの恵み」を意味し、人々はその下に集う・中央の人物はキリストまたは聖母マリアで、両脇の群衆は救済を受ける者たち・背景の青は天国や神の領域を象徴下部を。大聖堂南翼廊西側廊にあったMonument Dedicated to Archbishop Richard Whately II (リチャード・ワトリー2世大司教に捧げられた記念碑 )構成(上下二段構えの記念モニュメント)① 上段(壁龕彫刻) ・中央像:椅子に腰かけ、右手に頬を当てて物思いに耽る女性像 → 古典的な「悲嘆(Grief)」や「思慮(Contemplation)」を象徴する姿勢 ・両脇の小像:幼児像(プットー) ・左側:花輪(勝利や不滅の記憶の象徴)を持つ ・右側:何かを抱えており、豊穣や時間経過を暗示する可能性 ・建築枠:二本の大理石化粧円柱と三角ペディメント(古典主義様式) ・上部隅飾り:左右に小さな座像(天使か寓意像)② 中段(銘文パネル) ・大理石に刻まれた碑文(被葬者の功績・経歴を記す) ・下部に葉飾りの浮彫(月桂樹やアカンサス葉)③ 下段(棺型彫刻・レキュンベント像) ・横たわる人物像:実物大の被葬者像(手は胸の上、衣服は僧服や儀礼衣) ・枕:繊細な彫刻で布の質感が表現されている ・周囲に低い手すり(真鍮製)Richard Whately II , Doctor of Sacred Theology, Archbishop of Dublin.英語訳(原文はラテン語)。「In memory ofRichard Whately, Doctor of Sacred Theology, Archbishop of Dublin,who, for the truth of Christ, for the welfare of the Church, and for the good of mankind,exercised his episcopal office with tireless care for 32 years.He fell asleep in the Lordon the 8th day before the Ides of October (8 October) 1863,in the 77th year of his age.His dust lies in the Church of the Holy Trinity,the other cathedral of this diocese."Even though he is dead, he shall live." (John 11:25)」 【ダブリン大主教、神学博士リチャード・ホウエリーを記念して。キリストの真理のため、教会の救いのため、人々の善のために、32年間にわたり疲れを知らぬ献身で司教職を果たした。主にあって眠りについたのは、1863年10月8日、享年77歳であった。その遺骨は、この教区のもう一つの大聖堂である聖三一教会に眠る。「たとえ死んでも、生きるのである」 (ヨハネによる福音書 11章25節)】近づいて。ネットから。「聖パトリック(St. Patrick)―アイルランドの使徒(The Apostle of Ireland)」ゴシック様式の尖頭アーチが連続する回廊越しに、奥の礼拝堂を見る。奥には祭壇風の構造物と大きな彫刻(人物像)が見え、その前に観光客や参拝者が立ち入れないよう赤いロープが張られていた。このステンドグラスは、聖書の場面を上下に3つのパネル構成で描いていると。① 最上部パネル ・雲の中、天使や光に囲まれた場面が描かれています。これは復活や昇天の象徴的描写である。② 中央パネル ・中央に立つ人物は赤い外套と青いローブをまとったキリスト。右手を上げ、祝福の姿勢を 取っています。 ・背景には緑の丘や建物が見え、説教や教えを行っている場面の雰囲気です。 ・下の帯状部分には献辞や聖句と思われるラテン語/英語の文章が入っています。③ 下部パネル ・白い衣をまとったキリストが右手を掲げ、群衆に向き合っています。 ・見上げる人々の中には女性や弟子と思われる人物が描かれており、手前には墓から出てくる 人物(包帯のような布に巻かれている)がおり、これはラザロの復活(ヨハネ福音書11章)を 示していると考えられます。 ・左下の女性はマリア(マルタの姉妹)で、涙を流しつつ喜びの表情を浮かべています。総合的解釈 この窓はキリストの奇跡と教えをテーマにしており、下部に「ラザロの復活」、中央に 「説教するキリスト」、上部に「天国の栄光(または昇天)」という物語的構成になっています。 こうした縦の物語構成は、信者が下から上へと視線を上げながら信仰の核心に近づくという 象徴的意味も持っています と。ゴシック様式の大聖堂内部から外部の回廊や中庭方向を見た構図で、特徴的な建築要素や装飾が見られたのであった。1. 前景(手前) ・尖頭アーチ(Pointed Arch) ・ゴシック建築の代表的な形状で、天井の荷重を効率的に分散します。 ・両脇の円柱には、柱頭(キャピタル)に植物や抽象模様の装飾が見えます。 ・木製二枚扉 ・おそらく聖堂内の出入口扉。 ・上部には照明が設置され、訪問者に温かみのある光を提供。2. 中景(アーチの向こう側) ・ランスロット型の装飾柵(バラスター)と金色のオーナメント ・柵上に6基ほどの金色の球形装飾が並び、旗竿や槍先のようなデザイン。 ・儀礼的または象徴的な意味を持つ可能性が高い。 ・縦に垂れる旗(バナー) ・細長く垂れ下がった複数の旗が、奥の空間に沿って並びます。 ・歴史的な紋章や騎士団旗である場合が多い。3. 奥(背景) ・外壁(石造ゴシック様式) ・灰白色の石で構築され、二連の尖頭アーチ窓を備える。 ・中央のバルコニー(手すりは金属製の細密な装飾)からは、中庭や行列を見ることが可能。 ・垂直的構図 ・アーチ → 装飾柵 → 外壁窓 という縦の流れが強調され、ゴシック建築の高さと奥行きを 感じさせます。この案内板は 「Map of the Churchyard」(教会墓地の地図) で、セント・パトリック大聖堂(St Patrick’s Cathedral)南東側の墓地エリアについて説明していた。・中央の道が南北に走り、両側に大小の墓石区画が配置。・北端に Marsh’s Library(マーシュ図書館)・南西端に Cathedral(大聖堂本体)・4つの番号が notable graves(著名な墓)を示していた。著名な墓(番号順)1. Louisa Robinson (1860–1948) と Denis Johnston (1901–1984)・ルイーザ・ロビンソン:小説家、短編作家、批評家。1900年代初頭に活動。・デニス・ジョンストン:劇作家、BBCのプロデューサーでルイーザの息子。・墓石にはケルト十字が彫刻されている。2. Captain John McNeill Boyd (1812–1861)・1861年2月、ダブリン湾で嵐から船員を救おうとして殉職した海軍士官。・英雄的行動を讃えられ、セント・パトリック大聖堂内部にも記念碑がある。3. Archbishop Narcissus Marsh (1638–1713)・元トリニティ・カレッジの学長で学術振興に尽力。・1707年にMarsh’s Libraryを設立。・墓は元は図書館内にあったが、後に大聖堂墓地に移された。4. The Very Revd The Hon Henry Packenham (1787–1863)・9世紀中頃の大聖堂修復に尽力した聖職者。・個人的な資金も投入して修復を進めた人物。南東側の教会墓地に出る。オベリスク型の墓碑。No.2「Captain John McNeill Boyd(1812–1861)の墓」であろう。近づいて。Captain John McNeill Boyd(1812–1861)・経歴 イギリス海軍士官。アイルランド出身。 1861年2月、ダブリン湾で起きた嵐の際、救助活動に参加して殉職。・功績 彼は部下の命を守るために危険な状況へ赴き、英雄的行動で広く称えられました。 セント・パトリック大聖堂の内部にも彼を讃える記念碑があります。・墓の特徴 ・高い四角い基壇の上に立つオベリスク形 ・側面に銘板と浮き彫りの紋章 ・周囲に柵や金属製ケージ(墓荒らし・動物対策と思われる)が設置セント・パトリック大聖堂(ダブリン)の南東側にある教会墓地(Churchyard)の一角で、複数のケルト十字型墓碑が並んでいた。1.手前左 ・ケルト十字型の墓碑 ・台座の銘板には「Daphne Elizabeth Griffin (1912–1987)」および 「Victor Gilbert Benjamin Griffin (b.1924)」と刻まれていた。 ・Victor G. B. Griffinはセント・パトリック大聖堂のDean(主任司祭)を務めた人物。2.右奥 ・大型のケルト十字(ハイクロス風)墓碑 ・高さがあり、装飾模様が刻まれている。 ・基壇部は無装飾の石造。3.背景 ・平板型や立板型の古い墓石が点在。 ・境界フェンスが見え、教会敷地の外と接している場所。近づいて。この墓碑は、Victor Gilbert Benjamin Griffin(1924–2017)と、その妻と思われる Daphne Elizabeth Griffin(1932–1998)の記念碑。「In MemoriamDAPHNE ELIZABETH GRIFFIN1932 – 1998VICTOR GILBERT BENJAMIN GRIFFIN1924 – 2017DEAN OF SAINT PATRICK’S CATHEDRAL1969 – 1991」 Victor G. B. Griffin は、1969〜1991年にセント・パトリック大聖堂のディーン(Dean) を務めた人物20世紀後半のアイルランド聖公会において重要な宗教指導者であり、社会正義や包括的な教会のあり方を推進したことでも知られているのだ と。東方向へ移動して。1.手前左・シンプルな石造の十字型墓碑。・基壇と墓囲い部分が残り、中央は土が露出。2.中央やや右・背の低い台座型墓碑(四角い基壇上に小さな壇を持つ)。・上部が欠損している可能性あり。3.奥・ケルト十字型墓碑(先ほどの写真の右奥に見えたものと同じ位置) → これにより、撮影地点がほぼ同じ区画であると特定可能。4.背景・墓地の東側フェンスと、奥には通りを歩く人影が見える。・左奥の建物は大聖堂付属施設またはMarsh’s Library側の建物。大聖堂南側墓地の一角からセント・パトリック大聖堂(Saint Patrick’s Cathedral, Dublin)の外壁を見上げて。左側は回廊、正面は身廊南側の外壁。・建築様式:ゴシック様式(13世紀起源)・壁面:石灰岩と砂岩の混合で構成され、灰色と褐色がまだらに見える積層。・窓:尖頭アーチのステンドグラス窓(3連窓)。・上部装飾: ・4本の尖塔(ピナクル)が垂直線を強調。 ・屋根の縁には鋸歯状の城郭風パラペット(クレネレーション)。そして再び聖堂内に入り、ゴシックアーチの扉聖堂出口へと。セント・パトリック大聖堂(Saint Patrick’s Cathedral, Dublin)の出口通路の天井を。1.建築様式・ゴシック様式の尖頭アーチ(Pointed Arch)・天井は交差リブヴォールト(Cross-ribbed Vault)・壁・天井ともに明るいクリーム色で塗られ、石造部分とのコントラストが鮮やか。2.扉・両開きの木製扉(濃い赤茶色)・鉄製の装飾ヒンジ(唐草模様)St Patrick's Cathedral・聖パトリック大聖堂を大いに楽しんだのであった。内部はステンドグラスから差し込む柔らかな光が、聖堂内に神秘的な色彩を落としていたのだあった。高くそびえるゴシック様式の天井リブが、荘厳な空間と静謐な響きを生み出し、大理石の床モザイクが、幾何学模様と色彩で礼拝堂を華やかに彩っているのであった。また、聖歌隊席(クワイア・ステール)の彫刻細工が、歴史の重みと職人技を物語るのであった。そして、著名人の記念碑や墓碑が並び、アイルランドの歴史と文化を大いに感じることが出来たのであった。また外部からは鋭く天を突く尖塔(Spire)が、ダブリンの空に凛として聳えているのであった。灰色の石造りの外壁が、年月を経た荘厳な風格を醸し出し、大きな尖頭アーチの窓が、ゴシック建築特有の優美なリズムを刻んでいたのであった。そして、聖堂を囲む芝生と庭園、墓地が、都市の中に静寂と安らぎを与えてくれたのであった。セント・パトリック大聖堂(Saint Patrick’s Cathedral)を後にして東に歩き、Bishop Streetを進む。そしてDiggers Street Upperと Redmonds Hill Streetとの交差点へ。中央の建物の名称はJohn O’Gowan’s Barでレンガ造4階建ての角ビル。外壁にアイルランド国旗・アメリカ国旗・EU旗などが掲揚。ダブリン市内のオージンストリート を南に向かって進む。そしてこの先の交差点を左折。R110・Cuffe Streetには観光用馬車の姿が。 ・・・もどる ・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.18
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その81):Dublin市内散策(19/)・St Patrick's Cathedral・聖パトリック大聖堂-1
ダブリン城の「State Apartments」 を後にして、再び10時から入堂可能な「Christ Church Cathedral・クライストチャーチ大聖堂」の内部に入り、ステンドグラスや 様々な彫刻等を楽しんだのであった。その際のブログは既にアップ済みである。「Dublinia・歴史博物館」👈️リンク を振り返って。「Dublinia・歴史博物館」👈️リンク は、アイルランド・ダブリンにある歴史体験型ミュージアムで、バイキング時代から中世のダブリンの暮らしや文化を、実物大の復元街並み・模型・映像・体験展示を通して紹介している。Christ Church Cathedral に隣接しており、両施設は屋内通路の「中世アーチ橋」で結ばれているのであった。 次の目的地は「St Patrick's Cathedral・聖パトリック大聖堂」。ダブリンの Christ Church Cathedral 南側交差点から、北西方向を見る。レンガ造のオフィスビル。角に時計塔が。 R137・Patrick Streetを南方向に歩く。「St. Patrick’s Park(セント・パトリック公園)」 の案内板。「St. Patrick’s ParkFáilteThis park is provided for the enjoyment of your community. Please act responsibly tohelp us to keep it clean, green and safe for all to use.We welcome your feedback and comments on this park. Please contact the Parks Team:T. (01) 222 5278 or email parks@dublincity.iePark Gates will commence closing at the following times・January – 4:30 pm・February – 5:00 pm・March – 6:00 pm・Time Change – 7:00 pm・April – 8:00 pm・May – 9:00 pm・June – 9:30 pm・July – 9:30 pm・August – 9:00 pm・September – 8:00 pm・October – 7:00 pm・Time Change – 6:00 pm・November – 5:00 pm・December – 4:30 pmWebsite: www.dublincity.ieComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath(ダブリン市議会)」 【セント・パトリック公園ようこそこの公園は地域の皆さんの憩いの場として提供されています。誰もが快適に利用できるよう、清潔で緑豊かで安全な環境の維持にご協力ください。公園に関するご意見やご感想を歓迎します。下記までご連絡ください:公園チーム:電話 (01) 222 5278 またはメール parks@dublincity.ie公園の門の閉鎖時間(各月)1月:午後4時30分2月:午後5時3月:午後6時(夏時間切替時)午後7時4月:午後8時5月:午後9時6月:午後9時30分7月:午後9時30分8月:午後9時9月:午後8時10月:午後7時(冬時間切替時)午後6時11月:午後5時12月:午後4時30分】左手に「St. Patrick’s Park(セント・パトリック公園)」。中央広場の方向を見る。これから訪ねる「St Patrick's Cathedral・聖パトリック大聖堂」の北側に拡がる大きな公園。「St Patrick's Cathedral・聖パトリック大聖堂」 の西塔を北側から見上げて。・アイルランド最大の教会建築で、灰色の石造ゴシック様式。・画面中央は大聖堂の西塔(West Tower)で、高い尖塔(スパイア)と四隅の小尖塔が特徴。・時計盤が中段部に設置され、その上部には細長い尖頭アーチ窓(鐘楼の開口部)。「St Patrick's Cathedral・聖パトリック大聖堂」 西塔の南西門付近、歩道沿いに設置された現代アート作品 と。形状 ・2つの尖塔状(コーン形)の金属彫刻。 ・左(小さい方):緑青(銅が酸化した色)を帯びたブロンズ。 ・右(大きい方):黒褐色でテクスチャのある表面。配置・大聖堂を囲う黒い鉄柵の外側、歩道上に設置。・背後に見える石造の構造物は大聖堂の外塀の柱。作者・作品名・この場所にある彫刻は、アイルランド人彫刻家 Michael Warren による抽象作品。・ダブリン市内の歴史的建造物周辺に現代彫刻を設置する試みの一環として設置された。意味合い(解釈)・尖塔形は大聖堂のスパイア(尖塔)を抽象化したもので、宗教的シンボルと現代芸術の 融合を意図。・2つの高さや質感の違いは、時代の移ろいや視覚的リズムを表現。「St Patrick's Cathedral・聖パトリック大聖堂」の来訪時間案内板。「SAINT PATRICK’S CATHEDRAL – DUBLINVISITING TIMESMonday – Friday 09:30 – 17:00Saturday 09:00 – 18:00Sunday 09:00 – 10:30 13:00 – 14:30 16:30 – 18:00BOOK TICKETSVisit our website to buy admission tickets and view service times.」 【聖パトリック大聖堂(ダブリン) – 見学時間月曜~金曜:午前9時30分~午後5時土曜:午前9時~午後6時日曜: 午前9時~午前10時30分 午後1時~午後2時30分 午後4時30分~午後6時チケット予約公式ウェブサイトで入場チケットを購入し、礼拝時間等の詳細を確認できます。】西塔 を下から見上げて。St. Patrick’s Cathedral(聖パトリック大聖堂) の柵に取り付けられた装飾盾(エンブレム)。鮮明な写真をネットから。ダブリン市の歴史的紋章をもとにしたデザイン。・中央の大図 ・大きな木(オーク・ナラの総称 の木か?) 幹に「蜂の巣」がかけられ、蜜蜂が飛び交っています。 これは「教会共同体の勤勉さと協力」を象徴しているのだ と。 ・右側の人物 ・「参事会員(カノン、聖職者)」を表し、蜂の巣を世話している ・ミトラ(司教冠)をかぶり、法衣をまとい、胸に十字架を掲げている。 ・上部の紋章 ・中央:イギリス王室の紋章 ヘンリー四世(1399~1413)時代に紋章に一部に改定が加えられた。 当時のフランス王シャルル五世(1364~1380)がそれまでの百合の花を ちりばめた紋章を三個の百合の花の紋章に変えた。 それを受けてイングランド王の紋章に組み込まれているフランスの部分も 三個の百合に変えたのである。 この紋章はエリザベス一世まで11人の王によって200年にもわたって 使用された。 ・左右の小盾(十字の紋章) ・左側:チューダーローズ(Tudor Rose) イングランドの象徴で、バラ戦争(ヨーク家の白バラとランカスター家の 赤バラ)の和解を表す「チューダー朝の紋章」。 ダブリンの聖パトリック大聖堂は、16世紀に宗教改革やイングランド支配と 深く関わったため、この紋章が加えられている。 ・右側:黄金の格子模様(四角い網目状のデザイン) これは「ポートキュリス(Portcullis/城門の落とし格子)」と。・下部の紋章 ・中央の人物 ・頭に「ミトラ(司教冠)」をかぶり、赤いマントを纏っています。 両手を前で合わせて祈りの姿勢をとっているように見えます。 ・これは聖パトリックその人、あるいは聖パトリック大聖堂の 「大主教位(Archbishopric)」を象徴しています。 周囲をアーチ形(大聖堂の建築を思わせる)で囲まれており、「聖堂の守護聖人」で あることを明示。 ・左右の小盾 ・左:白地に赤い斜十字(セント・パトリック十字) アイルランドの守護聖人パトリックを直接示すシンボル。 現在の「ユニオン・ジャック」の構成要素のひとつとしても知られます。 ここでは「聖パトリック大聖堂」という奉献の性格を示す。 ・右:この盾の右側は、アイルランドを象徴するハープの紋章(青地に金のハープ) で、 後にアイルランドの国章として定着したものであり、現在の国章の直接的な原型。 左側は赤字に金色の「斜めに交差する模様」や「獅子/斜線」に似た意匠がある。 この盾は「ダブリン大聖堂参事会(Chapter)」のシールに含まれる heraldic quarter で、「アイルランド教会内の大主教座(Archiepiscopal See of Dublin)」の紋章的要素 を示している と。西塔(West Tower) を真下から見上げて。・様式:ゴシック様式(14世紀頃の建築要素を多く含む)・外壁材:灰色の石灰岩による組積造・構成: 1.下層 ・尖頭アーチ型の大窓(玄関ポータル上部に配置) ・小さな聖人像のニッチが入口上にあり 2.中層 ・細長い尖頭アーチ窓と装飾ニッチ 3.上層 ・丸窓(時計盤がはめ込まれている) ・さらに上に鐘楼部の大きな尖頭アーチ開口部 4.塔頂部 ・隅部に小塔(ピナクル) ・本来は尖塔(スパイア)があった可能性もあるが現状は平らに近い形 St. Patrick’s Cathedral(聖パトリック大聖堂)南側の翼廊入口(サウス・トランセプト入口)を正面から。正面から。・入口ポータル ・ゴシック様式の尖頭アーチ(Pointed Arch) ・アーチ周囲に複数の縁取りモールディング ・木製の両開き扉 ・左右には鉢植えの植物が配置され、訪問者用の出入口として使用中・上部構造 ・ポータルの上には小窓(尖頭アーチ窓) ・両脇に二本の塔状構造(ピナクル)がそびえる ・さらに上段にはクリンゲート(城郭風の歯型装飾)・側壁の窓 ・高く細長い尖頭アーチ窓 ・ステンドグラスがはめ込まれていると考えられるこの南翼廊入口は、大聖堂内部の横断廊(トランセプト)部分に通じ、観光客や礼拝者の出入り口として使われていた。西塔(West Tower) を南側から見上げて。St. Patrick’s Cathedral(聖パトリック大聖堂) 内部に設置されたデジタル案内スクリーンで、入場料や展示案内が表示されています。入場料金(Admission Fees)・Adult(大人):€11.00・Senior(シニア、60歳以上):€10.00・Student(学生):€10.00・Infant(幼児、0〜5歳):無料・Child(子ども、6〜12歳):€5.50・Family(家族、2大人+2子ども):€31.00Senior(シニア、60歳以上)内部の南側通路(サウスアイル) を東方向に向かって撮影。複数の彫像と記念碑が並んでいた。1. 左手前の彫像・台座に刻まれた銘文によれば、この人物は John McNeill Boyd(ジョン・マクニール・ボイド)。・彼はアイルランド出身の英国海軍士官で、1861年2月のダブリン湾での嵐に際し、部下の 救出活動中に殉職した英雄。・像は彼が片手を前方に伸ばし、海を指し示すようなポーズ。・台座には彼の経歴と殉職の経緯が刻まれています。2. 左奥の彫像・直立姿勢で腕を組む男性像。・この像は大聖堂に多くある政治家・軍人・聖職者の記念像の一つ。3. 建築背景・天井はゴシック様式のリブ・ヴォールト。・床は幾何学模様のタイル(赤・黒・黄色系)。・奥には大聖堂の中心部(クワイヤ・内陣)へのアーチ開口が見えた。廻り込んで。St. Patrick’s Cathedral(聖パトリック大聖堂)内部、西端(ウェストエンド)付近を東側から見た。大きな三連尖頭アーチ窓(ステンドグラス)が西壁上部に設置されていた。西端部の三連ステンドグラス(West Window)のクローズアップ。3枚の縦長パネル(中央が最も高い)。各パネルには円形(メダリオン)モチーフが上下に並び、その中に聖書の場面や聖人像が描かれていた。このステンドグラスの円形パネルには、上部に 「ARMAGH(アーマー)」 と記されており、アイルランドの都市アーマー(聖パトリックの主要拠点のひとつ)に関する場面を描いている。右側:司教冠(ミトラ)をかぶり、司牧杖(クロージャー)を持つ人物は 聖パトリック 。 祝福の右手を上げ、左手に杖を持つ典型的な姿。左側奥の二人:王冠をかぶった男性とその傍らの女性。王はおそらくアーマー地方の支配者。中央下:跪く男性。聖パトリックに書簡か巻物を差し出しているように見えます。 これは領土や教会権の委譲、または改宗を象徴している可能性があります。背景右側:塔や城壁のある都市風景、アーマーの象徴として描かれたと。聖パトリックが三つ葉のクローバー(シャムロック)を使って三位一体を説く場面。右側人物:司教冠(ミトラ)をかぶり、司牧杖(クロージャー)を持つ人物が聖パトリック。 右手には三つ葉のクローバーを掲げ、人々に教えを説いています。中央の二人: ・黄色の衣の男性は杖を持つ旅人または弟子のような姿で、聖パトリックの説明を受けている様子。 ・その左の赤衣の男性も聖パトリックを注視。背景:緑の草地と花模様。聖パトリックが自然物(クローバー)を使って信仰を説明したという 伝承に合わせた自然背景です。聖パトリックが若くしてアイルランドに奴隷として連行される場面を描いたもの。中央人物(少年):若き日のパトリック(まだ司教になる前)。金色の衣を着せられ、 両腕をつかまれています。表情は驚きと恐怖を示しています。周囲の人物:・右側の男たちがパトリックを連行しており、手はしっかりと彼の腕を押さえています。・左奥には船があり、数名の人物が乗り込み準備をしている様子。・船の背景には海や海岸線が描かれ、異国への連行を示唆。下部パネル(小窓):・左側はパトリックが家の中か野外で作業または逃げようとする姿。・右側はパトリックが羊や野営地のそばに座り込み、奴隷として牧羊の仕事をする様子。George Nugent-Temple-Grenville(初代バッキンガム侯, 1753–1813)。・左手を腰に当てたポーズ・胸に大きく輝く 聖パトリック騎士団(Order of St Patrick)の星章 と綬・たっぷりした儀礼マント・エドワード・スミス(Edward Smyth)作(1783年)このステンドグラスは、ダブリンのセント・パトリック大聖堂(St Patrick’s Cathedral)北側廊にあるもので、すぐ前に立っている彫像は初代バッキンガム侯爵(George Nugent-Temple-Grenville,1st Marquess of Buckingham)。図柄の中心には、赤いマントを羽織った高位聖職者(恐らくカンタベリー大主教や聖パトリック騎士団関連の人物)が描かれ、その周囲に白い衣を着た聖職者や信徒が集っています。背景や枠飾りには、聖パトリック騎士団や王権を示す装飾モチーフ(王冠・盾・紋章)も見られます。つまりこの窓は、バッキンガム侯爵のモニュメントとセットで制作され、彼の功績と騎士団・王室への奉仕を象徴する追悼ステンドグラスになっていると考えられます と。サー・ロバート・ボイド艦長(Captain Robert Boyd)の記念像。ステンドガラス中央には、甲冑姿の人物(聖ミカエル大天使とみられる)が描かれています。翼を広げ、右手に長い槍(または旗竿)を持ち、頭上には王冠と赤いマントを示す紋章的装飾が描かれています。聖ミカエルは戦いの守護聖人であり、軍人や戦死者の記念に用いられることが多いモチーフです。ボイド艦長は1811年、海戦(アラス戦役)において戦死した人物で、このステンドグラスは彼の勇敢さと忠誠心を象徴する戦士聖人(聖ミカエル)のイメージと関連付けられています。William Bedell Stanford(ウィリアム・ベデル・スタンフォード)像。スタンフォードは20世紀アイルランドの古典文学者であり、トリニティ・カレッジ・ダブリンの教授、また政治家(上院議員)でもありました。像では学者らしくガウンをまとい、左手に書物を持っています。セント・パトリック大聖堂(ダブリン)の身廊(Nave)から内陣(Choir)方向を見て。セント・パトリック大聖堂(ダブリン)の内陣西側の上部にある5連窓のステンドグラス。位置:内陣(Choir)の西壁、トリフォリウム(triforium)上部、尖頭アーチ天井直下。形状:中央3枚の大きな尖頭アーチ窓と、左右にやや小さい補助窓の5連構成。主題:中央の3つの窓には人物像が描かれています。 1.左から2枚目:聖人風の人物・聖コルンバ(St Columba) 光輪を持つ、右手には巻物のようなもの。 2.中央:赤い衣と王冠を持つ人物・聖パトリック(St Patrick)。聖王を示唆。 3.右から2枚目:黒と白の修道服姿の女性・聖ブリジッド(St Brigid)、聖女。左右端(1枚目と5枚目):人物小像や聖書場面が上下に配置されている装飾的窓。内陣東端の三連ステンドグラス。中央の祭壇の背十字架の後に位置する主祭壇窓。下の写真はネットから。中央: 上段:白衣の人物が群衆に説教している場面(キリスト、または使徒)。 周囲に複数の聖人や信徒。 下段:ひざまずく人物に祝福を与える場面。 特徴:中央は信仰の中心人物(多くはキリストまたは聖パトリック)配置。右: 上段:赤と緑の衣を着た人物が書物と羽ペンを持ち、書き記す場面(聖福音記者または使徒)。 下段:白衣の人物が子どもを抱きかかえ祝福する場面。 特徴:宣教・教えと慈愛を象徴。左: 上段:白衣に赤マントをまとった人物。片手に羊飼いの杖(または巻物)、 もう一方の手で指差す姿。聖職者・預言者型。 下段:緑衣の人物が書物を持ち読んでいる場面。 特徴:教導・預言の象徴。「ボイル家記念碑(The Boyle Family Monument)」・建立者:リチャード・ボイル(Richard Boyle)卿 ・“初代ヨーク男爵” とも呼ばれ、アイルランドの大法官・高位官僚を歴任。 ・王室の枢密顧問官(Privy Counsellor)、アイルランド財務総監 (Lord High Treasurer of Ireland)も務めました。・建立時期:1620年代・様式:17世紀初期ルネサンス様式の墓碑彫刻。黒大理石と金彩を多用し、柱とアーチ構造で区画。・目的:ボイル家の功績を記念し、夫妻とその家族のために造られた墓碑。 上部 ・両側のニッチ(小壁龕)に、礼服姿の人物が祈る像が安置されており、中央には家紋を掲げる装飾。 ・金彩のカルトゥーシュや飾り唐草が見られる。中段 ・左右に立つ礼拝者像(恐らく親族または象徴的な証人役)。 ・中央の二つの横臥像(ゴンザント様式): ・上段:鎧姿の男性像(リチャード・ボイル卿本人)。 ・下段:王冠を戴いた女性像(キャサリン・フィントン夫人、Countess of Cork)。下部(銘文プレート) ・金文字で長文の英語碑文が刻まれており、夫妻の肩書き・役職・徳行・子孫への願いが 記されています。 ・結びはラテン語で、没年月日と「喜びの復活を待つ」というキリスト教的希望の表現が 添えられています。「THIS MONUMENT WAS ERECTED FOR THE RIGHT HONORABLE Sr RICHARDBOYLE LORD BOYLE BARON OF YOUGHAL VISCOUNT OF DUNGARVAN EARLE OF CORKE LORD HIGH TREASURER OF IRELAND OF THE KINGS PRIVY COUNCELL INTHIS REALM AND ONE OF THE LORDS JUSTICES FOR THE GOVERNMENT OF THIS KINGDOM IN MEMORIE OF HIS MOST VERTUOUS AND RELIGIOUS WIFE THE LADIE KATHERINE COUNTESS OF CORKE AND THEIR POSTERITY AS ALSO OF HISGRANDFATHER Sr ROBERT WESTON SOMETIME LORD CHANCELLOR OF IRELAND AND ONE OF THE LORDS JUSTICES FOR THE GOVERNMENT THEREOF WHOSE DAUGHTER ALICE WESTON WAS MARRIED TO Sr GEOFFRAY FENTON Kt PRINCIPAL SECRETARY OFSTATE IN THIS REALM AND THEY HAD ISSUE THE SAID LADIE KATHERINE COUNTESS OF CORKE WHO LIETH HERE INTERREDHER SAID FATHER AND GRANDFATHER WHOSE VERTUES SHE INHERITED ON EARTH ANDLIETH HERE INTERRED WITH THEM ALL EXPECTING A JOYFULL RESURRECTION QUA OBIIT DECIMO SEXTO FEBRUARII 1629」【この記念碑は、尊敬すべきリチャード・ボイル卿(ヨール男爵、ダンガーヴァン子爵、コーク伯爵、アイルランド大蔵卿、国王枢密院議員、そしてこの王国統治のための法務卿の一人)のために建立された。ここには、彼の最も徳高く敬虔な妻、コーク伯爵夫人キャサリン、そしてその子孫を記念し、また彼の祖父であるロバート・ウェストン卿(かつてアイルランドの大法官、ならびにこの国の統治を担った法務卿の一人)、その娘アリス・ウェストン(サー・ジェフリー・フェントン卿、アイルランド王国国務長官に嫁した)も記されている。キャサリン伯爵夫人はその父および祖父と共にここに葬られており、生前に彼らの美徳を受け継ぎ、この地で共に復活の日を待っている。彼女は1629年2月16日に亡くなった。】 トマス・ジョーンズ(Thomas Jones, 1550頃–1619)とその家族の墓碑モニュメント。ジョーンズはダブリン大主教であり、アイルランドの大法官を務めた人物です。モニュメントは上下二層構造で、人物像がそれぞれの役割と象徴を表しています。最上部・ドクロと紋章 ・ドクロは死と復活の象徴。 ・紋章はジョーンズ家の家系と地位を表す。上段(中央の祈る像)・人物:トマス・ジョーンズ大主教(中央) ・赤いローブと白い襟巻きは高位聖職者の装束。 ・両手を合わせて祈る姿は、敬虔な信仰と死後の魂の平安を願う象徴。・左右の碑文: ・左碑文:トマス・ジョーンズと妻マーガレットの没年・役職を記録。 ・右碑文:ジョーンズの息子・娘婿など家族の名前と経歴。下段(横たわる像と周囲の人物)・中央の横たわる人物: ・鎧を着た男性像はジョーンズ家の親族(恐らく息子または娘婿で騎士)。 ・鎧姿は軍人または騎士階級の身分を表す。・周囲の跪く人物: ・左右の赤いローブの女性像は未亡人や娘たちで、祈りの姿勢は死者への追悼と家族の信仰を象徴。 ・背景の立像(黒衣)は男性親族で、祭壇に向かって祈っている。・祭壇上のミニチュア頭部像(中央): ・故人の胸像を表現し、記憶の永続化を意味。下段の写真をネットから。1.中央の祈る二人の立像 ・黒衣の男性像と赤いローブの女性像。 ・故人の夫、または近親者を表すと推定。 ・両者とも祈りの姿勢で、死者への追悼を象徴。2.両脇の小像 ・子供や親族を示すことが多く、「家族全体での信仰と追悼」を意味。 ・小像が跪いている場合、亡き者への敬意を強調。このステンドグラスは3つの縦パネル構成で、上段と下段にそれぞれ物語場面が描かれています。全体としてはキリストの受難の場面(パッション)の一部を表しており、上半分と下半分で物語の連続性があります。構造と物語順(上→下)上段(3つの縦パネル)1.左パネル:兵士たちが群衆を押し分けて進む場面 ・青い衣の兵士、赤いマントの役人風人物。 ・群衆は驚きや抗議の表情。 ・場面推定:イエスが捕縛された後、裁判や刑場へ連行される途中。2.中央パネル:白衣のイエスが前進する姿 ・後光(光輪)が明確に描かれており、中心人物。 ・後ろには兵士、前方には何かを持つ人物。 ・場面推定:十字架刑へ向かう道(ヴィア・ドロローサの一部)。3.右パネル:屈強な兵士がイエスを引き立てる ・緑の衣の兵士、赤茶のマント。 ・力強い動きで引きずるような描写。 ・場面推定:嘲弄または護送の場面。下段(3つの縦パネル)1.左パネル:聖母マリアと聖女たち ・青いマントの女性は聖母マリア、白いヴェールの女性はマグダラのマリアと推定。 ・哀悼の表情でイエスに手を伸ばす。2.中央パネル:イエスと会話する人物 ・イエスは十字架を背負っているか、もしくは刑場に向かう途上。 ・会話相手はシモン(十字架を代わりに担ぐ)またはベロニカ(顔を拭く場面)の可能性。3.右パネル:女性に抱きしめられるイエス ・近親者か敬虔な弟子。 ・慰めと惜別の象徴。著名人物の記念像群を再び。手前から1.Henry Richard Dawson (1792-1840), dean of St. Patrick's Cathedral.2.Gerald Fitzgibbon (1837-1909), dean of St. Patrick's Cathedral.3.The Marquess of Buckingham (1804-1876), grand master of the Knights of St. Patrick.4.James Whiteside (1804-1876), lawyer.5.John McNeill Boyd (1812-1861), sea captain.6.George Ogle (1742 - 1814), politician.赤いローブの男性(キリスト)と、青いローブでひざまずく女性(聖母マリアまたはマグダラのマリア)の姿。意味:復活したキリストがマリアに現れる「Noli me tangere(我に触れるな)」場面か、受胎告知の場面にも似るが背景構成から復活後の出会いの可能性が高い。上段中央人物:・白いローブに金色の帯を締め、赤いマント状の後光を背に立つ人物。顔は意図的に光輪の光で 白く表現。・左手に杖(牧杖または王笏)、右手は掲げたような構え。3連(左・中央・右)にわたる縦長の物語連作で、それぞれの縦列に複数の円形パネル(メダリオン)が連なっています。全体的に、細かい場面ごとに色彩豊かで、外枠の幾何学的文様が各場面を縁取っている典型的なゴシック様式物語窓。先ほどの三連の大ステンドグラス(中央が最も高いランセット窓)の中央部分をズームして。各窓には円形または菱形の枠に物語場面が収められており、聖書の一連の出来事を順に描いていた。中央の窓(大ランセット) 最上段:洗礼者ヨハネがイエスをヨルダン川で洗礼する場面。 中段上:イエスが弟子たちに教えを説く場面(山上の説教)。 中段下:奇跡(盲人の癒しや病人を治す)を行う場面。 下段:最後の晩餐や弟子たちとの食事。左の窓 最上段:船や海の描写(嵐を静める奇跡)。 中段上:魚を持つ弟子(五千人の給食の奇跡)。 下段:ペテロの召命(舟上のキリスト)。右の窓 最上段:ゲツセマネの祈り(十字架前夜)。 中段上:鞭打ちまたは裁判の場面。 下段:十字架を担うキリスト。ゴシック様式の高いリブ・ヴォールト天井のもとに設置された壁付けの記念碑(モニュメント)。3枚の縦長ランセット窓で構成された大きな作品で、中央のパネルに十字架とキリスト磔刑の場面が描かれている。全体的に青や白を基調とし、周囲に群衆や兵士、嘆き悲しむ人物などが配置されていた。構成(左から右)1.左パネル ・群衆や兵士、木々の背景が見え、十字架への道や磔刑前の場面を表現している可能性が あります。 ・下部には女性(おそらくマリアやマグダラのマリア)と思われる人物が描かれています。2.中央パネル ・高くそびえる十字架の上に磔刑のキリスト。 ・下部にはローマ兵や弟子、嘆く女性たちが集まる場面。 ・背景は青い空と雲で、全体が中央に視線を集める構図です。3.右パネル ・磔刑後の場面や見守る人物。 ・下部には跪いて祈る人物(ヨハネ、あるいは兵士の百人隊長)が描かれているようです。銘文(読み取り)左パネル下部THIS WINDOW IN MEMORY OFBORN 1847 DIED中央パネル下部HAS BEEN ERECTED BY EDWARD CECIL 1ST EARL OF IVEAGH 1914(この窓は第1代アイヴァ伯エドワード・セシルによって1914年に建立された)右パネル下部BY HIS CHILDREN EARL OF IVEAGH STO THE SEE IS LOVE(アイヴァ伯の子供たちにより、その愛の証として)このステンドグラスは3連の尖頭アーチ型窓で構成され、キリスト教の受難と贖いの象徴をテーマにしていた。中央パネル・上部:磔刑のキリスト(十字架上のINRI標識付き) ・囲には天使と十字架の両脇にある装飾的パターンが描かれています。・中段:背景に丘(おそらくゴルゴタ)と都市の城壁。・下部:「神の子羊(Agnus Dei)」の図像。旗を持ち、封印された書物や祭壇上に立つ姿で 描かれており、キリストの犠牲と勝利を象徴します。左パネル・上部に聖母マリアと思われる女性像(青と白の衣装、祈りの姿)。・彼女の下には花のモチーフや紋章的な装飾があり、献堂者や教会の紋章を表している可能性が あります。右パネル・上部に聖ヨハネ(使徒ヨハネ)と思われる男性像(緑のマント、書物を持っている可能性あり)。・下部の意匠は左パネルと対称的構図で、別の紋章的モチーフが見られます。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.17
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その80):Dublin市内散策(18/)・ダブリン城(Dublin Castle)-6
さらに、ダブリン城(Dublin Castle)のステート・アパートメント(State Apartments)内の見学を続ける。「Apollo Room(アポロの間)」。・壁面の大きなレリーフ:古代神話(おそらくギリシャ神話、音楽や芸術の神アポロやミューズに 関する場面)が描かれた浅浮彫。・18世紀風の室内装飾:青緑色の壁、白いモールディング(額縁状装飾)、クラシカルな暖炉。・赤いビロード張りベンチと金色の脚:ダブリン城のステートアパートメント特有の家具様式。・シャンデリア:クリスタル製で、アイルランド18世紀貴族邸宅の象徴的要素。古代神話を題材にした装飾パネルであり、石膏または漆喰の浅浮彫で、18世紀末から19世紀初期の新古典主義様式が特徴。左側のレリーフ・雲の上に立つ人物が、片腕で子供(あるいは小さな人物)を抱え、もう一方の手を 差し出している構図。・背景にはもう一体の人物像が浮かび上がっている。・構図的に、ギリシャ神話のヘルメス(マーキュリー)と幼児を救う場面や、神が人間を天上に 導く場面を思わせます。右側のレリーフ・雲の上に座る半裸の男性神(筋肉質)が、周囲の人物や動物とともに描かれています。・神の足元には翼を持つ馬(ペガサス)らしき姿があり、または四頭立ての戦車 (太陽神アポロのチャリオット)を暗示している可能性があります。・これらの特徴から、太陽神アポロの登場シーン、あるいはオリンポスの神々の集いを描いた ものと推測されます。左側のレリーフ・中央の人物は腕を高く掲げ、片足を大きく踏み出しており、飛翔感のあるポーズ。・その足元には3人ほどの小さな人物(天使やプットー)が雲の上に座っています。・背後には翼を持つ鳥(または神話の動物)を伴っているように見えます。・解釈としては、勝利や栄光の女神ニケ(Victory)、または伝令の神ヘルメス(マーキュリー)を 寓意的に描いている可能性があります。右側のレリーフ・Peter De Gree(1737–1817)作《Diana》(1786年)です。・豊穣の女神(Ceres / Demeter) を描いたものと考えられます。・ギリシャ神話:デメテル(Demeter)、ローマ神話:ケレス(Ceres)は 農業と収穫を司る女神で、人間に穀物と耕作を与えた存在。・中央の女性像(女神)は雲上に座し、右手には 小麦の束(sheaf of wheat) を持っています。 左手には 果物の入った豊穣の角(cornucopia, ホルン状の器) を抱えています。 これらはいずれも豊穣と収穫の象徴。・周囲には愛らしい小天使、幼児像・プットーが描かれており、女神の周囲で飛び交い、 麦の穂や果実を運んでいます。 下方のプットーは大きな麦の束を持ち、さらに右下の雲には豊作を象徴する収穫物が 表現されています。。暖炉の上と両脇に配置されたレリーフが。左側(大型・縦長)・空を飛ぶ女性像が右向きに描かれ、手には弓を持っているようにも見えます。・足元には2体のプットー(小天使)が雲の上で遊ぶ姿。・弓を持つ女性神という点から、狩猟と月の女神アルテミス(ローマ名:ディアーナ)、 あるいは春の到来を告げる神話的寓意と考えられます。中央(中型・横長/暖炉上)・左側で楽器(竪琴かリュート)を奏でる人物と、それを聴く複数のプットー。・奥には半裸の人物(神話の登場人物)が座り、やや物語的な場面を構成。・音楽演奏の場面はアポロとミューズの集い、または牧歌的な神々の宴を表す可能性があります。右側(大型・縦長)・雲の上に立つ人物が手を伸ばし、足元に小さな人物が浮かんでいる構図。・背景にはもう一体の人物が飛翔する姿。・構図から判断すると、天界での神の導きや英雄の昇天を表す場面で、 寓意的には「栄誉」「勝利」を象徴。右端(小型)・小天使や人物が雲の上で戯れている場面。・装飾的要素が強く、他の大型パネルのストーリーを補完する役割。Upper Yard(アッパー・ヤード/上中庭)を、建物内の窓から見る。アッパー・ヤードは、18世紀にジョージ王朝様式で再整備された際に整形された中庭で、王権の威厳を象徴する空間であった。歴史的には衛兵の閲兵や馬車の乗降、来賓の歓迎式典などに利用された。現在も公式行事(国賓歓迎、記念式典など)の舞台になることがあるとのこと。中央奥(西棟):3階建ての石造建物で、中央の入口はかつての兵舎や管理事務室の一部。 現在は一部が展示施設として利用されていた。左側に見えたのは、有名な「Bedford Tower(ベッドフォード・タワー)」。1.中央:Bedford Tower(ベッドフォード・タワー)・1761〜1771年にジョン・スマート設計で建設された時計塔。・ジョージアン様式の象徴的建築で、かつては兵器庫や宝物庫としても使われた。・上部の緑色のドーム屋根は銅葺きで、遠くからも城のランドマークとして目立ちます。2.Bedford Gate(ベッドフォード門)・時計塔の下部にあるアーチ状の門。・馬車や兵隊の出入り口として使われた歴史を持ちます。 イギリス国王ジョージ3世(在位1760–1820)。・ジョージ3世は、アメリカ独立戦争やナポレオン戦争期の国王として知られ、 アイルランド統治にも深く関わった人物。・彼の治世下でアイルランド議会は1801年に廃止され、グレートブリテン及びアイルランド 連合王国が成立しました(連合法)。・騎馬肖像は王の威厳と軍事的指導者としての役割を象徴し、宮殿や総督邸の儀礼空間に 飾られました。「Synnott Family CollectionThe portraits on display in this room are on loan to Dublin Castle from the Synnott family. They depict figures connected with Irish political and cultural history over several centuries, many of whom also had close links to Dublin Castle. To the left of the oval portrait above the fireplace is a depiction of Robert Devereux, 2nd Earl of Essex (1565–1601). Lord Essex was beheaded under the orders of Queen Elizabeth I following his unsuccessful tenure as Viceroy of Ireland in 1599. To the right of the oval portrait is a painting of Lord Edward Fitzgerald (1763–1798), who planned the Irish rebellion against British rule in 1798. Having been wounded during his arrest on the eve of therebellion, he was briefly detained in Dublin Castle. He later died from his injuriesin Newgate Prison and is buried in the crypt of St Werburgh’s Church, which adjoinsDublin Castle. Above the door to the next room is a portrait of the celebrated Irishwriter Jonathan Swift (1667–1745), author of Gulliver’s Travels, who was born just beside Dublin Castle.」 【シンノット家コレクションこの部屋に展示されている肖像画は、シンノット家からダブリン城に貸与されているものです。これらは何世紀にもわたり、アイルランドの政治史や文化史に関わった人物を描いており、その多くはダブリン城とも深い関係を持っていました。暖炉の上の楕円形の肖像画の左には、ロバート・デヴァルー(1565–1601)、第2代エセックス」伯爵が描かれています。エセックス卿は1599年にアイルランド総督としての任務に失敗した後、エリザベス1世女王の命により斬首されました。楕円形肖像画の右には、エドワード・フィッツジェラルド卿(1763–1798)の肖像があります。彼は1798年にイギリス統治に対するアイルランド反乱を計画しましたが、蜂起前夜に逮捕される際に負傷し、短期間ダブリン城に拘留されました。その後、ニューゲート監獄で負傷がもとで亡くなり、ダブリン城に隣接するセント・ワーバーグ教会の地下墓所に埋葬されています。隣室への扉の上には、有名なアイルランド人作家ジョナサン・スウィフト(1667–1745)の肖像画があります。彼は『ガリヴァー旅行記』の著者で、ダブリン城のすぐそばで生まれました。】THE WEDGWOOD ROOM(ウェッジウッドの間)。1849年のセント・パトリック・デイ舞踏会での部屋の様子が描かれている と。ネットから。「THE WEDGWOOD ROOMThe so-called Wedgwood Room derives its name from the blue and white decorative scheme that recalls the distinctive colours of Wedgwood pottery. It was completed in 1777 as the lobby or ante-room to the adjoining Gothic Room. In 1849 it became the Billiard Room, when a new billiard table of the best description was ordered at a cost of £145.10s. The room is shown here as it appeared for the St Patrick’s Day Ballof 1849. On that occasion, a Mr. Bergin disguised the billiard table by transforming the room into an exotic indoor garden. The scene included a small fountain, vases filled with brilliant gold fish, orange trees and ornamental cages, in which song-birdsheightened the décor with their warblings.」 【ウェッジウッドの間通称「ウェッジウッドの間」という名称は、ウェッジウッド陶器の特徴的な青と白の配色を想起させる装飾様式に由来します。この部屋は1777年に、隣接するゴシックの間へのロビーまたは控えの間として完成しました。1849年にはビリヤード室となり、最高品質の新しいビリヤード台が145ポンド10シリングの費用で導入されました。ここに描かれているのは、1849年のセント・パトリック・デイ舞踏会での部屋の様子です。その際、バーギン氏がビリヤード台を覆い隠し、部屋全体を異国情緒あふれる室内庭園に変身させました。演出には小さな噴水、金魚を泳がせた壺、オレンジの木、そして小鳥たちがさえずる装飾用の鳥かごが使われ、華やかさを一層引き立てました。】左上:エンブレム・ヴィクトリア女王治世下の英国王室紋章右下:1897年当時のアイルランド総督であったGeorge Henry Cadogan, 5th Earl Cadogan(第5代カドガン伯爵)の個人紋章彩色エンブレム部分に近づいて。・年代:「1897」・王冠:上部に英国王冠(Imperial State Crown)のレリーフ。・中央の盾形紋章(クォータリング) 1.第一象限(左上):イングランドの紋章(赤地に金の3頭の獅子 passant guardant) 2.第二象限(右上):スコットランドの紋章(黄地に赤の立ち獅子) 3.第三象限(左下):アイルランドの紋章(青地に金の竪琴) 4.第四象限(右下):再びイングランド紋章(対称配置のため)・外周のモットー(青帯部分): "HONI SOIT QUI MAL Y PENSE"(悪意を抱く者に災いあれ) ※ガーター騎士団のモットー・下部の金色文字:"GOD SAVE THE QUEEN"(女王陛下万歳)「ON MARCH THE 15TH 1897A BANQUET WAS GIVEN BYHIS EXCELLENCY EARL CADOGAN K.G.LORD LIEUTENANT OF IRELANDIN ST PATRICK’S HALLWHEN TWO HUNDRED AND FIFTY TWO GUESTS WERE PRESENTTO CELEBRATE THE 60TH YEAR OF THEREIGN OFHER MAJESTYQUEEN VICTORIA」 【1897年3月15日アイルランド総督カドガン伯爵閣下(K.G.)によってセント・パトリックス・ホールにおいて晩餐会が催された。出席者は252名にのぼり、女王陛下ヴィクトリアの治世第60周年を祝った。】ここもダブリン城(Dublin Castle)のSt Patrick’s Hall(セント・パトリックス・ホール)。・天井画:イタリア人画家ヴィチェンツォ・ヴァルドリーニ(Vincenzo Valdrè)が描いた 新古典主義様式のフレスコ画で、ジョージ3世時代(1780年代)に制作されたもの。 王政や騎士道の寓意が描かれています。・シャンデリア:豪華なクリスタル製で、ホール全体を均等に照らすため3基が吊るされています。・壁面の色調:上部が白と金の装飾、下部は紺色を基調にしており、鏡や旗が飾られています。・旗(バナー):左右に掲げられているのは、アイルランド聖パトリック勲章 (Order of St. Patrick)の騎士の紋章旗。各旗は歴代騎士の個人紋章を 表しています。・柱:金色に塗られたコリント式の円柱がホールを区切り、上階のギャラリー部分を支えています。歴史的役割・アイルランド総督の就任式・晩餐会:このホールはアイルランド総督の公式行事の中心舞台でした。・勲章叙任式:アイルランド聖パトリック勲章の授与式がここで行われました。・祝典・舞踏会:特に1897年のヴィクトリア女王即位60周年記念晩餐会 (ダイヤモンド・ジュビリー)が有名です。St Patrick’s Hall(セント・パトリックス・ホール)内部、窓の上部に掲げられている紋章旗(Heraldic Banners)の一部をクローズアップして。これらはアイルランド聖パトリック勲章(Order of St Patrick)の騎士(Knight)の個人紋章旗。St Patrick’s Hall(セント・パトリックス・ホール) 天井画。18世紀末にイタリア人画家ヴィチェンツォ・ヴァルドリーニ(Vincenzo Valdrè)によって描かれた新古典主義様式の作品。この天井画は、ジョージ3世治世下のアイルランドを理想化して描いた寓意画の一つで、アイルランド(Hibernia)が女神たちや人々に囲まれ、繁栄と平和を享受する姿勝利・学問・芸術・商業が国を支える様子を象徴的に表しているのだ と。こちらは、18世紀末にヴィチェンツォ・ヴァルドリーニ(Vincenzo Valdrè)によって制作された新古典主義的な歴史画。・中央人物:古代ローマ風の甲冑を身につけた指揮官が、机上の地図や書類を指差しています。・右側の人物群:軍装の兵士や高官たちが、地図や作戦計画に注目している。・左側の人物群:市民風の服装の男性たちが、指揮官の指示を受けるような様子。・背景:樽や荷が積まれており、補給物資や港湾活動を示唆。・全体構図:戦役や遠征の前の作戦会議、または都市防衛の計画場面を描いているように見える。ズームして。奥側の長方形画・翼のある人物と複数の人々が描かれ、穏やかな場面構成。・アイルランドへの祝福や平和の寓意を示す可能性が高い。St Patrick’s Hall(セント・パトリックス・ホール) で行われたアイルランド大統領就任式の場面。2004年11月11日に行われたメアリー・マッカリース大統領第2期就任式を描いた作品で、アイルランドの画家ジェームズ・ハンリーが制作したものSt Patrick’s Hall は、アイルランド大統領就任式の正式会場として使われているのだ と。・中央の人物:演壇に立つ女性は、アイルランドの初の女性大統領 メアリー・ロビンソン (Mary Robinson) と思われます(在任 1990–1997)。・周囲の列席者:政治家、宗教指導者、司法関係者、外交官など、アイルランド社会の 主要な代表者。・背景の二階ギャラリー:制服姿の儀仗兵と音楽隊。・上部左右:St Patrick’s Hall の特徴的な金色のコリント式円柱と、壁面の紋章旗 (Order of St. Patrick の騎士旗)。・中央上部:アイルランド国旗が掲げられています。「The inauguration of Mary McAleeseto her second term as President of IrelandSt Patrick's Hall, Dublin Castle11th November 2004Commissioned by the Office of Public WorksArtist James Hanley RHA」【アイルランド大統領メアリー・マッカリース第2期就任式ダブリン城 セント・パトリックス・ホール2004年11月11日公共事業庁(Office of Public Works)委託画家 ジェームズ・ハンリー(RHA)】 「ST PATRICK’S HALLSt Patrick’s Hall is one of the most important ceremonial rooms in Ireland and is wherethe Irish President is inaugurated every seven years. In its origins as the mid-eighteenth-century castle ballroom, English artist Vincenzo Waldré began the painted ceiling, finishing the central panel in 1788. The surrounding panels were completed in 1790.The hall represents the relationship between culture and politics in eighteenth-centuryIreland. As a venue for balls, banquets and meetings, it was an important setting. In addition to hosting state functions, the hall was the meeting place of the Knights ofSt Patrick, a chivalric order established in 1783 and modelled on the English Order ofthe Garter.Mounted perhaps on the platform at the far end of the hall are three thrones, representing the King and Queen of the United Kingdom and the Prince of Wales. Since independence, the thrones have been removed, but the hall remains the setting for major ceremonial occasions, such as the inauguration of the President.」 【セント・パトリックス・ホールセント・パトリックス・ホールは、アイルランドで最も重要な儀式の場のひとつであり、アイルランド大統領の就任式が7年ごとにここで行われます。もともとは18世紀半ばの城の舞踏室として建てられ、イギリスの画家ヴィチェンツォ・ヴァルドレが天井画制作に着手し、中央パネルを1788年に完成、周囲のパネルは1790年に完成しました。このホールは、18世紀アイルランドにおける文化と政治の関係を象徴しています。舞踏会、晩餐会、会議などの場として重要な役割を果たし、公式行事のほか、1783年に創設された聖パトリック騎士団(英国のガーター勲章を範として設立)の集会所でもありました。ホールの奥の壇上には、かつてイギリス国王・王妃・プリンス・オブ・ウェールズを象徴する3つの玉座が設置されていました。独立後は玉座は撤去されましたが、大統領就任式など、主要な儀式の場として今日も使われています。】ピーテル・アールツェン(Pieter Aertsen, 1508–1575) の作品で『マルタとマリアの家のキリスト(Christ in the House of Martha and Mary)』を描いたもの。・前景の静物は肉・魚・野菜・パンなどの豊かな食材が前景を大きく占めている。 アールツェンは「静物画の祖」と呼ばれ、宗教画の前景に生活感あふれる食卓や市場の品々 描いています。・背景の奥の建築空間に、イエスがマルタとマリアに語りかけている場面が小さく描かれている。 マルタは食事や奉仕に気を取られ、マリアはイエスの話を聞いている。 ルカによる福音書 10:38–42 の場面である。ネットから。「Dublin Castle was the seat of English, and later British rule in Ireland from 1204 until 1922. Created in the eighteenth century, the State Apartments served as a residence for the Viceroy, who represented the British monarch in Ireland. During the early months of each year, usually from January to March, the Viceroy, and occasionally the visiting British monarch, played host to a series of entertainmentsin the State Apartments. Known as the "season", these festivities included balls, banquets and royal ceremonies.On 16 January 1922, the last ever Viceroy handed Dublin Castle over to Michael Collins and the government of the newly-independent Irish state. Since that historic moment, a tradition of state ceremony has been maintained in these rooms. Successive Irish governments have continued to use them for important national events, such as state dinners and commemorations. Since 1938, each one of Ireland's presidents hasbeen inaugurated in St Patrick’s Hall, the grandest of these spaces. The image aboveshows President Éamon de Valera outside the State Apartments after his inauguration, in 1959.Over the centuries, those entertained in the State Apartments have included Benjamin Franklin (1771), the Duke of Wellington (1807), Daniel O’Connell (1841), Queen Victoria(1849, 1853, 1861 & 1900), Charles Dickens (1858), Cumann Markievicz (1919), Princess Grace of Monaco (1961), John F. Kennedy (1963), Charles de Gaulle (1969), Nelson Mandela (1990) and Queen Elizabeth II (2011).」【ダブリン城は、1204年から1922年まで、アイルランドにおけるイングランド、そして後にはイギリスの統治の中心地でした。18世紀に造られたステート・アパートメンツは、副王(Viceroy)の公邸として使われ、副王はアイルランドにおける英国君主の代表を務めました。毎年1月から3月にかけて、副王は(時には英国君主も)ここで一連の催しを主催しました。これらの催しは「シーズン」と呼ばれ、舞踏会、晩餐会、王室の儀式などが含まれていました。1922年1月16日、最後の副王がダブリン城をマイケル・コリンズと新たに独立したアイルランド国家の政府に引き渡しました。この歴史的瞬間以来、この部屋では国家儀礼の伝統が守られ続けています。歴代のアイルランド政府は、国賓晩餐会や記念行事などの重要な国家イベントでこの場所を使用してきました。1938年以来、歴代のアイルランド大統領は、これらの空間の中でも最も壮麗なセント・パトリックス・ホールで就任式を行っています。上の写真は、1959年の就任式後にステート・アパートメンツの外に立つエイモン・デ・ヴァレラ大統領を写したものです。長年にわたり、このステート・アパートメンツには数々の著名人が訪れています。ベンジャミン・フランクリン(1771年)、ウェリントン公爵(1807年)、ダニエル・オコンネル(1841年)、ヴィクトリア女王(1849年、1853年、1861年、1900年)、チャールズ・ディケンズ(1858年)、コンスタンス・マルケビッチ(1919年)、モナコ公妃グレース(1961年)、ジョン・F・ケネディ(1963年)、シャルル・ド・ゴール(1969年)、ネルソン・マンデラ(1990年)、エリザベス女王(2011年)などです。】 そして見学を終え、ステート・アパートメンツ(State Apartments)にある壮麗な大階段(Grand Staircase)まで戻る。ダブリン城(Dublin Castle)のビジターセンター(Visitor Centre)のチケットカウンターを再び振り返って。ビジターセンターの入口付近にある案内表示ウォール。・中央の壁面表示 ・大きく「DUBLIN CASTLE」と施設名 ・住所・連絡先 ・開館時間(Opening Hours) ・ガイドツアー情報(Guided Tours) ・自由見学(Self-Guided Visits)の案内 ・入場料金の案内・アイコン案内 ・左側にトイレ(Toilets)への案内矢印と、男女・多目的・ベビーチェンジ設備のピクトグラム ・車椅子マークからバリアフリー対応であることがわかる・右奥の通路 ・さらに奥に続く扉があり、恐らくスタッフエリアまたは別展示室への入口・案内スタンド ・壁際に2つのパンフレットスタンド(イベント案内や特別展示のチラシなどが置かれる)・右端 ・現在開催中または直近の特別展ポスタービジターセンター付近にある男性用トイレの内部。State Apartments(国賓室)入口ロビー付近。ダブリン城(Dublin Castle)の内部展示スペースの一角を撮影したもの。中央の赤い円柱と左右の壁龕(ニッチ)に展示物が配置され、クラシックな建築装飾と現代的な展示が組み合わさっていた。Entrance Hall, Dublin Castle, Davison & Associates。狩猟女神アルテミス・Artemis。外に出てダブリン城(Dublin Castle)内の「アーチ門(Main Gate/Civic Sword Gate)」の古代ローマの軍神 マルス(Mars)をズームして。さらに。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.16
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その79):Dublin市内散策(17/)・ダブリン城(Dublin Castle)-5
「Apollo Room 」の白い壁の絵画を見る。 アポロ ルームの床は、OPW・Office of Public Works(公共事業庁) の建築家レイモンド マクグラスがこの部屋のために特別にデザインしたドネガル カーペットで覆われていた。・レイモンド・マクグラス(1903年 - 1977年)は、オーストラリア生まれの建築家、 イラストレーター、版画家、インテリアデザイナーでした。・彼は 1940 年にロンドンからアイルランドに移住し、公共事業委員会 (現在の OPW) で 働きました。・1948 年に彼は OPW の主任建築家に任命され、1968 年までその職を務めた。・この期間中、彼はアラス・アン・ウアタライン、ダブリン城、および海外のさまざまな アイルランド大使館で働いていました。・彼はまた、レンスター・ローンの慰霊碑も設計したカーペットの模様は、その上にある アポロ天井のデザインを引き立てるように設計されています。カーペットをズームして。壁に近づいて。暗い背景に人物4体が描かれていた。タイトル:Tobias Taking Leave of his Parents(両親に別れを告げるトビアス)作者:Nicolas Tournier(1590-1637)主題と特徴・『トビト書(Book of Tobit)』より、若者トビアス(Tobias)が両親と別れて旅に出る場面。 ・トビアスを導く天使ラファエル(Raphael)が傍にいることが多い構図。 ・表情やしぐさが感情的で、出発への躊躇や後ろ髪を引かれる思いが伝わるデザイン。左から順に:・父トビト(Tobit):青と茶の衣服を着ていて、暗い影の中で目が見えないことを示す表現。 ・母ハンナ(Hannah):顔が明るく照らされ、涙を拭っている。別れを悲しむ感情が 表現されている。 ・トビアス(Tobias):赤い外套と茶色のベストを着て中央に配置。右手に杖を持ち、 父の言葉を聞いている/指示を受けている様子。 ・天使ラファエル(Raphael):右端。灰色の翼を持ち、髪は茶色、暗い衣服。 右肩や胸が露出していて、柔らかな印象を伴うが守護者としての 強さも表現。ネットから。十字架を中心に据えたキリストの受難を描く三連祭壇画。上段・下段とも、中央に磔刑(キリストの十字架刑)、左右パネルには他の聖人や場面が描かれている典型的な形式。1941年1月28日の火災後の Apollo Room(アポロの間)の様子。「In the early hours of 24 January 1941, a major fire broke out in the State Apartments. The fire cast a huge column of smoke, sparks and flames into the night sky, destroying one room and severely damaging another. In 1964 a restoration project commenced. This image records the works in progress. As part of the scheme, the Apollo Room, which had been rescued from a nearby Georgian townhouse in 1912, was inserted to fill part of the space left behind by the fire. The room derives its name from the figure ofApollo at the centre of its plasterwork ceiling. Dating from 1740s, this ceiling arrived at Dublin Castle in eleven separate pieces that were painstakingly reunited. Serving once again, it is a superb example of eighteenth century craftsmanship.」 【1941年1月24日未明、ステート・アパートメントで大規模な火災が発生しました。炎は夜空に巨大な煙、火花、炎の柱を巻き上げ、1室を焼失、もう1室に深刻な損害を与えました。1964年、修復プロジェクトが開始され、この写真はその作業の様子を記録したものです。その計画の一環として、1912年に近隣のジョージアン様式タウンハウスから救出されたアポロの間が、火災で失われた空間の一部を埋める形で移設されました。この部屋の名称は、漆喰天井の中央に描かれたアポロ像に由来します。1740年代に作られたこの天井は、11の別々の部材に分けられた状態でダブリン城に運ばれ、丹念に再構築されました。そして再び用いられることとなり、18世紀の卓越した職人技の素晴らしい例となっています。】腕を縛られ、天井へと目を向ける男性像。そして「The State Drawing Room」・国賓応接室 へ。「The State Drawing Room・ステート・ドローイング・ルーム」は1838年に創設され、主に歴代総督夫人(総督の妻たち)の正式な応接室として、またアイルランドの廷臣との謁見のために使用されました。1907年と1911年の王室訪問時には、アレクサンドラ女王とメアリー王妃もこの部屋で賓客を迎えました。現在、この部屋にはダブリン城コレクションの中でも最も重要な絵画の一つ、17世紀を代表するヨーロッパの肖像画家、サー・アンソニー・ヴァン・ダイクによる晩年の肖像画が所蔵されています。この部屋は現在も、アイルランド大統領が来訪する要人を迎える際に使用されています と。赤いダマスク調の壁布、金色の額縁と家具、豪華なソファの組み合わせ。壁面構成(左から右へ)1.左端・全身肖像画(赤い軍服の男性) おそらく19世紀初頭の英国陸軍高官または王族。胸章や飾緒(アグレット)から 高位軍人であることが分かります。2.左上段中央・胸像肖像画(赤い軍服の男性) こちらも高官の肖像。軍服の意匠や顔立ちから、左端の人物と同時代・同系統の人物像。3.左下段中央・静物画(机上の書物や紙、楽器など) 「トロンプ・ルイユ」(だまし絵)的なリアルな描写。芸術・学問・音楽を象徴するモチーフ。4.中央大型・風景画(樹木と空の情景) 大きな木と淡い光の背景が特徴。夕暮れまたは朝焼けを表す可能性が高い。5.右上端(部分)・女性の半身像(ピアノまたは机に肘をつくポーズ) 髪型とドレスから19世紀半ばの女性肖像。6.右下端(部分)・小型肖像または場面画 服装・ポーズから宗教画または歴史画の一部に見える。「THE STATE DRAWING ROOM」の白黒写真。ヴィスカウント・ウィットボーン(Viscount Whitelaw)による1865年の改装後の姿を記録したもの と。 「THE STATE DRAWING ROOMThe term drawing room comes from the practice of withdrawing to a moreprivate space in a grand household, usually after formal dinners. Such roomswere most frequently occupied by ladies, who used them to withdraw from thecompany of the gentlemen. The State Drawing Room was created as a new roomin 1838 and was used by successive Viceroys (the lords of the Viceregency) to holdaudiences with Irish notables. During the royal visits of 1902 and 1911, QueenAlexandra and Queen Mary also received guests in this room. This photographshows the room after its redecoration in 1865, when Sir Whitworth wasresponsible for its design and its splendid ceilings and mirrors remainmuch admired. It is still in use today by the President of Ireland for thereception of visiting dignitaries.」 【国賓応接室(The State Drawing Room)「Drawing Room(応接室)」という言葉は、大邸宅において正式な晩餐の後に、より私的な空間へ“withdraw”(退く)習慣に由来します。こうした部屋は、特に淑女たちが男性の付き合いから離れるために利用することが多くありました。この「国賓応接室」は1838年に新たに設けられ、以後、歴代のアイルランド総督(ヴィサロイ)がアイルランドの名士たちと謁見する場として使用されました。1902年と1911年の国王訪問の際には、アレクサンドラ王妃やメアリー王妃もこの部屋で客を迎えています。この写真は、1865年の改装後の様子を写したもので、設計を担当したサー・ウィットワースによる壮麗な天井や鏡は今も高く評価されています。現在もアイルランド大統領が、訪問する要人を迎えるために使用しています。】1.手前・赤いビロード張り・金縁の長椅子(ソファ)・上に青白磁の花瓶(恐らく中国景徳鎮またはヨーロッパの模倣品)を3点並べたテーブル・赤いビロードと金色のロココ様式装飾の中央椅子(conversation chair)2.左側壁面・大理石の暖炉と、その上に床から天井までの大きな金縁鏡・鏡の左側にテーブルと赤い椅子・鏡右側に縦長の女性肖像画(格式ある衣装、恐らく王族または貴族婦人)3.中央奥の空間・白い円柱(柱頭は金色のアカンサス装飾)・その向こうにもう一つの暖炉と大きな鏡・暖炉両脇に黒背景の肖像画4.右奥・赤いカーテンと長い窓列・窓間の台座に置かれた白い胸像(大理石製)The State Drawing Room の西壁〜南壁寄りの絵画を。左側(上下2段)1.上段左:女性肖像(青いサッシュと白いドレス) ・王族または貴族婦人像。おそらく18世紀〜19世紀初頭。2.下段左:人物画(暗背景、ロマン派的タッチ) ・光と影のコントラストが強く、肖像というより場面画の可能性あり。中央大型3. 中央:女性全身肖像(白と銀の衣装、椅子に座る) ・威厳のある姿勢と衣装から高位貴族か王妃。 ・両側に黒い燭台彫像と置時計。右側(上下2段)4. 上段右:全身立像(細身の女性、薄色ドレス) ・背景が淡く、肖像形式は19世紀中頃の宮廷画風。5.下段右:小型肖像(人物の半身、暖色系背景)廻り込んで反対側から。「サウサンプトン伯爵夫人エリザベス・リー(Elizabeth Leigh, Countess of Southampton)」。 著名な画家サー・アンソニー・ヴァン・ダイク(Sir Anthony van Dyck)による晩年の作品と。・全身肖像(銀色の衣装)・宮廷風のドレス姿で座るポーズ・背景には建築的モチーフ(柱・壁)Queen Caroline(カロライン王妃)の肖像画。青いビロード地に白いサテン、宝石や毛皮で縁取られたマントを身につけて。片手を台(またはテーブル)に置き、正面を見据える半身像。・フルネーム:Caroline of Ansbach(アンスバッハのカロライン)・生没年:1683年3月1日 – 1737年11月20日・出身:神聖ローマ帝国アンスバッハ侯領・地位: ・イギリス王ジョージ2世の王妃(1727–1737) ・プリンス・オブ・ウェールズ妃(ジョージ2世が即位前)・功績と影響: ・教養と政治手腕に優れ、夫ジョージ2世の治世における重要な助言者 ・哲学者ライプニッツや詩人アレキサンダー・ポープなど学識人とも交流 ・藝術の庇護者としても知られる「Studio of Peter Lely(ピーター・レリー工房)制作、17世紀の淑女の肖像」。The State Drawing Room の暖炉と鏡のある壁面(東寄り)。1. 中央・大理石暖炉 白い大理石製で、縁は金色の装飾付き鋳物。暖炉上には精緻な金色装飾の大鏡があり、 向かいのシャンデリアや柱が映り込んでいます。・両側の赤ビロード椅子 金縁のロココ様式椅子で、背もたれと座面は深い赤のビロード張り。訪問者向けの 展示用として配置。2. 左側壁面(暖炉左)・左上:暗い背景に人物肖像(黒衣をまとい白襟、17世紀オランダ・フランドル風)・左下:風景画(右上から光が差すドラマティックな構図)3. 右側壁面(暖炉右)・右上:修道士風の人物肖像(白衣の修道服、机に向かって座る)・右中央:人物画(上半身裸で横たわる構図、神話画または寓意画・右下:小型風景画(建築物または城砦)4. 鏡に映る背景(扉奥)・隣室にも赤いカーテンと長椅子、シャンデリアが見える。・イーゼルに展示物らしきパネル。大理石彫刻「Bust of Philippe II, duc d’Orléans・オルレアン公フィリップ2世の胸像」。バロック後期〜初期ロココの宮廷肖像彫刻で豊かな装飾と写実性、衣装のしなやかな彫り込みが特徴。やや左を向く半身像、堂々とした威厳で、衣装は甲冑風の胸当てに百合紋(フルール・ド・リス)、王族の証であるサッシュ(幅広の布帯)を身につけて。・生没年:1674年8月2日 – 1723年12月2日・身分:フランス王族、ルイ14世の甥・称号:オルレアン公(2代)、フランス摂政(1715–1723)・役割: ・ルイ14世没後、幼いルイ15世の摂政として政務を司る ・軍事、芸術、学問の保護者として知られる ・宮廷の政治改革や外交政策にも影響 そして隣の部屋「The Throne Room(玉座の間)」。1.建築・装飾・壁は白基調に金色の装飾柱とガーランド(花綱)模様・上部の楕円形金縁フレーム内に馬や狩猟場面の絵画・大型のシャンデリアと天井の金装飾2.機能・ダブリン城の State Apartments(国賓室) の中心的な儀式用空間・歴代アイルランド総督が公式の場で用い、現在も儀典的用途に利用1.見事なシャンデリア 非常に特徴的なデザインで、金色の葉状装飾が放射状に広がり、中央に黒色部分が見える 複雑な構造。 このタイプのシャンデリアは、19世紀のヴィクトリア期後半〜20世紀初頭の復古装飾 スタイルに多く見られます。2.天井・装飾 白地に金色のモールディング(額縁状装飾)と花綱(ガーランド)のレリーフ。 天井の四隅には光を反射する浅いドーム状パネル。3.壁面装飾 金縁の円形フレームに収められた楕円画(動物や人物を描いたもの)。 The Throne Room(玉座の間) の玉座(Throne)。 ・金色のフレームに赤いビロード張りの椅子。 ・背後には濃い赤〜紫系のベルベット垂れ幕。 ・玉座は高い台座の上に置かれ、周囲は赤いロープで囲われています。 ・この椅子はジョージ朝様式を基調にしており、左右に流れる曲線的な肘掛けと、 頂部の王冠状装飾が特徴。ダブリン城 The Throne Room(玉座の間) の歴史的なモノクロ写真。この写真は1839年の改装後の部屋を写したもの と。「Formerly known as the Presence Chamber, this room was created in 1788. It was once the epicentre of royal ceremony in Ireland. From the throne, the Viceroy received addresses of loyalty on behalf of the British monarch. During royal visits, the monarch appeared in person, holding levees (royal receptions) in the space.In the nineteenth century the room was also used for swearing in several of the Lord Mayors of Dublin. The throne was made for the visit of King George IV in 1821 and was later used by Queen Victoria and King Edward VII.The last monarch to use it was King George V, in 1911. This image shows the roomafter it was remodelled in 1839. It was described in a publication by Charles Dickens,in 1866, as being "a-blaze with gold" and forming "a very glittering spectacle indeed".」 【かつては「プレゼンス・チェンバー(Presence Chamber)」として知られていたこの部屋は、1788年に造られました。ここはかつてアイルランドにおける王室儀式の中心地でした。玉座から、副王(Viceroy)はイギリス国王を代表して忠誠の辞を受け取りました。王の訪問時には、この場所で君主自らが出席し、レヴェー(王室公式謁見)を行いました。19世紀には、この部屋はダブリン市長の就任宣誓にも使用されました。玉座は1821年のジョージ4世の訪問のために作られ、その後、ヴィクトリア女王やエドワード7世も使用しました。最後にこの玉座を使用した君主は1911年のジョージ5世でした。この写真は1839年の改装後の部屋を写したものです。1866年、チャールズ・ディケンズはこの部屋を著作の中で「黄金に輝き(a-blaze with gold)、実にまばゆい光景を成している(a very glittering spectacle indeed)」と記しています。】ダブリン城 State Apartments の長い回廊部分の 「The Portrait Gallery(肖像画ギャラリー)」。この回廊は、The Throne Room や The State Drawing Room など主要部屋同士を結び、同時に展示空間としても機能。歴代アイルランド総督(Lord Lieutenant of Ireland)を描いたコレクションが並んでいた。1.建築的特徴・左右に白い壁と円柱・天井にはシャンデリアが連続・窓は右側全面に並び、自然光が豊かに入っている・床は木製パーケット(板張り)2.展示構成・左側の壁に、金色の額縁入り肖像画が連続して掛けられている・顔ぶれは歴代アイルランド総督(Viceroys)や高官の肖像で構成されていることが多い・赤いロープと台の上に、中央に寄せた調度(壺や彫像)が並んでいる振り返って。チャールズ・スチュワート(Charles Stewart)、ロンドンデリー侯爵(Marquis of Londonderry)。ダブリン城 State Apartments の Portrait Gallery(肖像画ギャラリー) に展示されている服装:・青いサッシュとガーター勲章(Order of the Garter)の礼装・金糸刺繍の軍装風ジャケット・左手に手袋を持つ、公式肖像によく見られるポーズThomas Phillip, Earl de Grey, K.G.(トーマス・フィリップ・アール・ド・グレイ)。額の銘板に1841年と記されていた。このモノクロ写真は1903年の国王訪問(エドワード7世時代)前後に、Firz and Son社によって広報目的で撮影されたもの。よって、おそらく1900年代初頭(約1903年前後)の写真 と。「THE PORTRAIT GALLERYThis room takes its name from the series of historic portraits of Irish Viceroys that havehung on its walls since 1849. Originally, the room was intended as a new purpose-builtreception room. The photograph shows the room set for a formal dinner. It was alsoused by successive Viceroys (the British monarch’s representatives in Ireland) for largereceptions and levees. The painting immediately visible on the far wall is ofViscount Wellesley, painted by Sir Martin Archer Shee, who was Lord Lieutenant ofIreland from 1821 to 1828. During the royal visit of 1903, Queen Alexandra andQueen Mary also received guests in this room. The photograph was commissioned byFirz and Son to publicise the life associated with the Viceregal Court. The room is stillin use today by the President of Ireland for the reception of visiting dignitaries.」【ポートレート・ギャラリーこの部屋は、1849年以来壁に掛けられてきたアイルランド総督(Viceroys)の歴史的肖像画の連作にちなんで名付けられました。当初は、新たに目的を持って建設された公式接待室として計画されました。写真は、正式な晩餐会のために整えられた部屋を写しています。また、この部屋は代々のアイルランド総督(英国君主のアイルランドにおける代理人)によって、大規模なレセプションやルヴェー(公式謁見会)にも使用されました。奥の壁に見える絵画は、1821年から1828年までアイルランド総督を務めたウェルズリー子爵を、マーティン・アーチャー・シー卿が描いたものです。1903年の国王訪問の際には、アレクサンドラ王妃とメアリー王妃もこの部屋で来賓を迎えました。この写真は、総督宮廷の生活を宣伝するためにFirz and Son社によって撮影されました。現在もこの部屋は、アイルランド大統領が賓客を迎えるために使用されています。】 天井中央の漆喰(プラスター)装飾とシャンデリア。この天井装飾は18世紀後半から19世紀初頭のジョージアン様式に典型的な楕円形モチーフで、内側に羽根状の渦巻き文様(アカンサスの葉を模したデザイン)が施されています。中央から吊り下げられているのはクリスタル製のシャンデリアで、ポートレートギャラリーの他の装飾と同様、格式高い公式空間を演出するための意匠。ウェッジウッド・ルーム(Wedgwood Room)。・丸天井と淡い色調:写真には、淡いブルーグレーの壁と装飾を持つ丸天井が写っており、 さらに上方採光のドーム型天窓が特徴。名称の由来:・「Wedgwood Room」は、そのブルーとホワイトの装飾(Wedgwood陶器を彷彿とさせる配色) に由来して名づけられた。部屋の用途と特徴:・この部屋は1777年に新古典主義様式で完成し、後にカスルのビリヤードルームとして使われて いました。19世紀には、トップライト(上部の天窓)を通して光が差し込む空間に一時的な 室内庭園(鳥や噴水を含む並木)を設置し、舞踏会の際の涼感空間として用いられた。1.左端の像 裸像で、布を肩から掛け、片手を胸に添えた女性像に見えます。ギリシャ・ローマ神話の 女神像(ヴィーナスやヘーベ)を模した新古典主義作品か。2.中央の像 2体の人物が彫られた構成像で、片方は裸体男性、もう片方は布をまとった女性のように見えます。 構図からすると、神話や寓話の一場面を表しているのでは。3.右端の胸像 白い大理石の男性胸像。ローマ風の衣装で、政治家や学者など歴史的人物をモデルにした作品。左側の彫像題材:ヘラクレスの幼少期。特徴:左腕に毛皮(ネメアの獅子皮に似た意匠)を掛け、右手で何かを支える姿。ふくよかな 体型や柔らかいポーズは、神話に登場する幼神像の典型です。象徴物:毛皮は勇気や力の象徴ですが、幼少像では「将来の偉業」を予兆する意味合いが強いです。 この像は毛皮が強調されており、ヘラクレスであろう。右側の彫像題材:アポロン特徴:全裸の青年が片手を樹木に掛け、もう片手に小物を持っています。 樹の幹には矢筒が掛けられています。象徴物:弓矢と矢筒は狩猟の神アポロンやアルテミスの持ち物。全体の均整の取れた体型と 落ち着いた表情から、古代ギリシャ彫刻のアポロン像を基にした新古典主義作品と 考えられます。・左側の胸像 古代風の男性像で、額が広く、短く刈った髪。肩から胸までを覆う古典的なトーガ風衣服を まとっています。哲学者や政治家の肖像を模した可能性があります。・右側の胸像 より現代寄りの写実的表現で、髪には月桂冠(ローレル)が見えます。これは詩人や劇作家 などの文化人の象徴的装飾で、文学や芸術功績を示すことが多いです。・中央の円形レリーフ 翼を持つ人物(おそらくギリシャ神話のニケ=勝利の女神、または時を司るケーロス)が 左向きに飛翔し、二人の幼子を抱いています。 薄い衣が風に舞い、全体に動きがあり、空中を飛ぶイメージが強調されています。 下方に小さな鳥が飛んでおり、空や自由の象徴として配置されていいます。 ウェッジウッドのレリーフらしい白地と浮き彫りによる軽やかな構図です。・彫刻家 ベルトル・トーヴァルセン(Bertel Thorvaldsen) の有名な円形レリーフであると 《夜(Natten / Night)》 の図柄(19世紀初頭)。 翼をもつ女性が二人の眠る幼子(眠り=ヒュプノスと死=タナトス)を抱えて飛ぶ姿で、 下にはフクロウが伴います――これが《夜》の定型モチーフ とネットから。ギリシャ神話に登場する弓矢の束を伴う人物像で、おそらくアポロン(Apollo)。・ギリシャ神話の光明・音楽・予言の神であると同時に、弓矢の名手としても知られる神。・若き狩人の姿で表される場合も多く、特に新古典主義の彫刻では理想化された青年像として 制作されます。薄いブルーグレーの壁色に、白い浮き彫りのメダリオンと花飾りが連なる装飾帯(ウェッジウッドのジャスパーウェアを思わせるデザイン)。壁上部の半円形扇模様(ファンモチーフ)壁の上部に見られる扇形のレリーフは、この部屋のニッチ(壁のくぼみ)部分の典型的な装飾で、ほかの部屋ではあまり見られないと。ズームして。特徴・右手は頭の後ろに軽く置かれ、やや体をひねった休息ポーズ。・左手を樹木の幹に掛けている。・樹の幹には矢筒(quiver)が掛けられ、複数の矢が納められている。・全裸の青年像で、均整の取れた新古典主義的な体躯表現。・樹は単なる支持材ではなく、狩人であることを示す象徴的要素。この像は、全裸の男性が両手に持った革ひも(または帯)を広げ、左脚を後ろの支えに軽く預けて立っている姿。後方の支えは積み石や円柱状の形をしており、古典的な背景を思わせます。筋肉の描写が精緻で、頭には月桂冠のような冠を着けています。ズームして。題材としては、古代ギリシャ・ローマ彫刻の著名なモチーフの一つで、「ディオメデス」「ディオスクロイ」「アスカニオス」など若い英雄や運動競技者をモデルにした復元彫像である可能性があります。隣の部屋「Council Chamber(評議会室)」への入口。 「Council Chamber(評議会室)」 ・階層:2階(英国・アイルランド式で1st Floor、日本式で2階) ・エリア:State Apartments(ステート・アパートメント)中央付近 ・隣接する部屋: ・西側:**Portrait Gallery(肖像画ギャラリー)**と接続 ・東側:**State Drawing Room(ステート・ドローイングルーム)**方面へ通じる廊下・配置の特徴: ・赤い壁面と暖炉がある長方形の部屋 ・会議用テーブルが中央にあり、壁面をびっしりと肖像画が囲む ・一方の扉はPortrait Galleryに直結名称:Council Chamber(評議会室)用途:歴代の総督や行政官、貴族などが会議や公式行事を行った場。現在の展示:主に歴史的人物の肖像画コレクション。特徴的な構造: ・高い天井と豪華なシャンデリア ・壁面上部まで連なる額装 ・暖炉上にも大型肖像画を配置 ・豪華な木製テーブルと革張りの椅子赤い軍服を着た将官が白馬に跨る姿。18世紀末~19世紀初頭のアイルランド総督(Lord Lieutenant of Ireland)や高位将官の肖像か?1.肖像画(左上)・着座した高官(恐らくアイルランド総督や高位裁判官)・赤い法服や儀礼服、白いウィッグを着用・執務机と書類が描かれ、行政的職務を象徴2.肖像画(右上)・聖職者(黒い聖職服、白いクレリカルカラー)・書物を持ち、教育や宗教的役割を示唆3.肖像画(左下)・黒い服の男性、白シャツ、胸元に布を差し込み・手元に書類とペン、法曹界・議員などの人物像である可能性大Picture Gallery(旧称 Portrait Gallery)内の一角で、見えているのはCouncil Chamber方向への扉。壁面には大型の宗教画・歴史画が並び、特に中央下段の大画面はバロック期を思わせる劇的構図で、他の3点も宗教的場面や聖人を描いた作品。右上の絵はキリスト磔刑の場面の一部(十字架を担うキリスト)を描いたものと。様々な絵画が所狭しと。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.15
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その78):Dublin市内散策(16/)・ダブリン城(Dublin Castle)-4
アイルランド風景画や地方の建物を描いた作品群を集めたコーナー。作者はコンスタンスとカジミール両名の可能性があり、それぞれが訪問時に風景を描いた作品が展示されていた。制作時期は特に1902年・1903年の夏で、Żywotówka(現:ウクライナ中部)の家族領地で制作された。近づいて。装飾やレイアウトから見ても19世紀末〜20世紀初頭の作品が多い印象。技法・作風は、厚塗り(インパスト)、鮮やかな色彩、素早い筆致が特徴で、象徴主義・印象主義・社会的リアリズムが融合したスタイルであると解説されていた。「Poland and UkraineIn the summers of 1902 and 1903, Constance and Casimir travelled to his family’s estate in Żywotówka. The region (today in central Ukraine) was then part of theRussian Empire in which the Markievicz family had settled as upper-class Polish landowners.Constance absorbed her Polish family’s tales of historical rebellions and was moved by the conditions of the peasant tenantry. Her growing class consciousness was not met by equal sentiments from Casimir, but they shared an interest in peasant and rural life, themes common in European painting of the period. The thick impasto, vivid colours andquick brushwork of canvasses produced during these visits recall the Markieviczes’ Parisian training.As proponents of modern and European art in Dublin, their own work varied between symbolist, impressionistic, and social realist approaches. Although political upheavalsand waning interests meant neither Casimir nor Constance fully developed a professional painting practice, these works evidence their early ambition for an art that united emotion, colour, expression, and experience of nature.」 【1902年と1903年の夏、コンスタンスとカジミールは彼の家族が所有するジヴォトゥフカの領地を訪れました。この地域(現在のウクライナ中部)は当時ロシア帝国の一部で、マルキエヴィチ家は上流階級のポーランド地主としてここに定住していました。コンスタンスはポーランドの家族から歴史的な反乱の物語を聞き、農民小作人の生活状況に心を動かされました。彼女の高まる階級意識はカジミールと同等の共感を得ることはありませんでしたが、二人は農民や農村生活への関心を共有していました。これらは当時のヨーロッパ絵画に共通するテーマでした。彼らがこの訪問期間に制作したキャンバスは、厚塗りのマチエール、鮮やかな色彩、素早い筆致が特徴で、パリでの美術訓練を思い起こさせます。ダブリンにおける近代・ヨーロッパ美術の支持者として、彼らの作品は象徴主義、印象派、そして社会的リアリズム的な手法の間を行き来していました。政治的激動や関心の薄れにより、カジミールもコンスタンスも本格的な職業画家としての活動を十分に展開することはありませんでしたが、これらの作品は、感情・色彩・表現・自然体験を一体化した芸術を追求した彼らの初期の志を示すものです。】このパネルは「Poland and Ukraine」セクションを含む展覧会の 謝辞(Acknowledgements)。「This project is an initiative of the Embassy of the Republic of Poland in Dublin, marking Poland’s Presidency of the Council of the European Union in January – June 2025, and celebrating the important historical and cultural links between our two countries.We are grateful to all of the private and public lenders to the exhibition: Małgorzata Malkiewicz, Tadeusz Malkiewicz, Libicki family, Edward Walsh and Constance Cassidy, Sir Joslyn Gore-Booth, Dermot and Muriel McAuley, Hugh Lane Gallery, National Gallery of Ireland, Crawford Art Gallery, The Model – Niland Collection, United Arts Club, National Museum of Ireland, Pearse Museum, National Library of Ireland, UCD Special Collections, Public Record Office of Northern Ireland, and the National Library of Poland.Many thanks also to:OPW/Dublin Castle: Rosemary Collier, Katie Morrisroe, Samir Eldin, Angela Cassidy and Dave Hartley; Irish-Polish Society: Patrick Quigley and Jarosław Płachecki; Lauren Arrington; Andrea Lydon; Brian Crowley; Katarzyna Gmerek; Deirdre Kelly; Wanda Ryan-Smolin; David Britton; Jan Filip Libicki; Rafał Wolski; Pamela Cassidy; Artisan Frames; Irish Art Services; and Scully Art Services.Curators:Emily Mark-FitzGerald, University College DublinKathryn Milligan, National College of Art and DesignProject Coordinators:Nikola Sękowska-Moroney, Embassy of the Republic of Poland in DublinWilliam Derham, OPW – Dublin CastleDesign:Vermillion Design」 【このプロジェクトは、ダブリンにあるポーランド共和国大使館の主導によるもので、2025年1月〜6月のポーランドの欧州連合理事会議長国就任を記念し、両国間の重要な歴史的・文化的つながりを祝うものです。展示に出品された作品の私的および公的貸与者に感謝いたします:マウゴジャタ・マルキエヴィチ、タデウシュ・マルキエヴィチ、リビツキ家、エドワード・ウォルシュとコンスタンス・キャシディ、ジョスリン・ゴア=ブース卿、ダーモット&ミュリエル・マコーリー、ヒュー・レーン・ギャラリー、アイルランド国立美術館、クローフォード美術館、ザ・モデル - ニランド・コレクション、ユナイテッド・アーツ・クラブ、アイルランド国立博物館、ピアース博物館、アイルランド国立図書館、ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン 特別コレクション、北アイルランド公文書館、ポーランド国立図書館謝辞(追加)OPW/ダブリン城:ローズマリー・コリアー、ケイティ・モリソロー、サミール・エルディン、アンジェラ・キャシディ、デイヴ・ハートリーアイリッシュ=ポーリッシュ・ソサエティ:パトリック・クィグリー、ヤロスワフ・プワヘツキローレン・アリントン、アンドレア・ライドン、ブライアン・クロウリー、カタジナ・グメレク、ディアドラ・ケリー、ワンダ・ライアン=スモリン、デイヴィッド・ブリトン、ヤン・フィリプ・リビツキ、ラファウ・ヴォルスキ、パメラ・キャシディ、アーティザン・フレームズ、アイリッシュ・アート・サービス、スカリー・アート・サービスキュレーターエミリー・マーク=フィッツジェラルド(ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン)キャスリン・ミリガン(ナショナル・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン)プロジェクト・コーディネーターニコラ・シェンコフスカ=モロニー(ダブリン・ポーランド共和国大使館)ウィリアム・ダーハム(OPW – ダブリン城)デザインヴァーミリオン・デザイン】Casimir Markievicz(カジミール・マルキエヴィチ)のGirl in Yellow(黄色い服の少女)。この肖像画は、短い黒髪の少女が黄色い服を着て横向きに座っている構図で、背景は青や紫、赤の縦の短いストロークで描かれていた。作者は肖像画にも秀でており、特に色彩の強調と背景の装飾的筆致を好んだ と。作者:Casimir Markievicz(カジミール・マルキエヴィチ)作品名:Girl in Yellow(黄色い服の少女)制作年:不詳(n.d. = no date)技法:Oil on canvas(キャンバスに油彩)所蔵先:Lissadell House(リッサデル・ハウス所蔵)「Music for a NationConstance’s exposure to the Polish quest for independence inflected her own understandingof Ireland’s struggle. In the early 1910s Constance adopted a popular Polish patriotic hymn, Z dymem pożarów (“With the Smoke of Fires”), written in 1846 by Kornel Ujejski withmusic by Józef Nikorowicz, as Hymn on the Battlefield, which she dedicated to the Irish Citizen Army. The song was taught as a marching tune to Na Fianna Éireann, the nationalist youth organisation she founded in 1909, and later popularised by singer Gerard Crofts.The Polish hymn’s opening line “with the smoke of the fires, and with the dust of fraternalblood” refers to the Galician peasant uprising of 1846, and the clash between Polish nobilityand peasantry that turned “brother against brother” and delayed the cause of independence. Probably inspired by the song’s rousing melody and its themes of Polish resistance, Constance’s adoption of the song also unwittingly foreshadowed the clash ofthe Irish Civil War.」【国のための音楽ポーランド独立への探求に触れた経験は、コンスタンスのアイルランドの闘争に対する理解に影響を与えました。1910年代初頭、コンスタンスはポーランドの愛国的な賛歌 Z dymem pożarów(「炎の煙とともに」)を取り入れました。この歌は1846年にコルネル・ウイェイスキ(Kornel Ujejski)が作詞し、ユゼフ・ニコロヴィチ(Józef Nikorowicz)が作曲したもので、彼女はこれを Hymn on the Battlefield(戦場の賛歌)としてアイルランド市民軍に献じました。この曲は、彼女が1909年に創設したナショナリスト青年組織ナ・フィアナ・エールン(Na Fianna Éireann)の行進曲として教えられ、のちに歌手ジェラルド・クロフツ(Gerard Crofts)によって広く知られるようになりました。このポーランドの賛歌の冒頭の一節「炎の煙とともに、兄弟の血の塵とともに」は、1846年のガリツィア農民蜂起と、ポーランドの貴族と農民との衝突を指しています。この衝突は「兄弟同士が争う」状況を生み、独立の大義を遅らせました。おそらく、この歌の鼓舞的な旋律とポーランド抵抗のテーマに感化されたコンスタンスによるこの曲の採用は、皮肉にもアイルランド内戦における衝突を予見することにもなったのです】 「Later Life and LegacyThe unconventional lives of Constance and Casimir were bound together by marriage and politics, but their diverging temperaments, interests, and political allegiances caused them to spend much of their lives apart. After Constance returned to Dublin in 1913, she maintained a public profile in nationalist politics, while Casimir stayed mainly in Paris, developing a portrait practice and enjoying the life of the United Arts Club.In August 1914 Casimir joined the Russian Army, enlisting in the Chevalier Guards commanded by Grand Duke Nicholas. He was posted to various locations in Ukraine, including the war front near Lviv, moved to Kyiv, Moscow, and finally to Warsaw in 1918, where he worked as a journalist and novelist. Throughout this turbulent period of the Irish Revolutionary era, Constance remained in Ireland, involved in the Easter Rising, the War of Independence, and the Civil War. In 1927, after her release from prison, Constance reconciled with Casimir and they lived together briefly in Dublin, before he returnedto Poland.In the last years of his life, Casimir continued to paint and write – dabbling in journalism, drama, and novel writing. He died in 1932 in Warsaw, survived by his daughter Maeve and son Stanislas.」【晩年と遺産コンスタンスとカジミールの型破りな人生は、結婚と政治によって結びついていましたが、性格や関心、政治的立場の違いから、二人は生涯の多くを別々に過ごしました。1913年にコンスタンスがダブリンへ戻った後も、彼女はナショナリスト政治の公的活動を続ける一方で、カジミールは主にパリに滞在し、肖像画制作を行いながら、ユナイテッド・アーツ・クラブの生活を楽しみました。1914年8月、カジミールはロシア軍に加わり、大公ニコライが指揮するシュヴァリエ近衛隊に入隊しました。彼はリヴィウ近郊の前線を含むウクライナ各地に配属され、その後キーウ、モスクワを経て、1918年にワルシャワに移り、ジャーナリストや小説家として活動しました。この間、アイルランド革命期の激動の中で、コンスタンスはアイルランドに留まり、イースター蜂起、独立戦争、内戦に関わっていました。1927年、彼女が刑務所を出た後、二人は和解し、短期間ダブリンで共に暮らしましたが、カジミールは再びポーランドへ戻りました。晩年、カジミールは絵画と執筆を続け、ジャーナリズム、演劇、小説に取り組みました。1932年、彼はワルシャワで死去し、娘メイヴと息子スタニスラスがその後を継ぎました。】 カジミール・マルキエヴィチの『ヘンリク・ヤクバニス教授の肖像』(1913年)。「Casimir MarkieviczPortrait of Professor Henryk Jakubanis (1913)Oil on canvas. Libicki Family Collection, PolandAfter leaving Ireland, Casimir relied on theatre work and portraiture commissions of notable Poles, such as this portrait of Henryk Jakubanis, a Polish classical philologist and philosopher, who worked at the Saint Volodymyr University, Kyiv and later at theCatholic University of Lublin. Vivid colouring and impressionistic treatment of thebackground signal a change in Casimir’s painting style, along with the more relaxed portrayal of the sitter.」 【カジミール・マルキエヴィチ『ヘンリク・ヤクバニス教授の肖像』(1913年)油彩・キャンバス リビツキ家コレクション(ポーランド)アイルランドを離れた後、カジミールは演劇活動や著名なポーランド人の肖像画制作を中心に活動しました。本作はその一例で、モデルとなったヘンリク・ヤクバニスはポーランドの古典文献学者・哲学者で、キーウの聖ヴォロディミル大学やルブリンのカトリック大学で教鞭を執りました。鮮やかな色彩と背景の印象派的な表現は、カジミールの画風の変化を示すものであり、同時にモデルをよりリラックスした姿で描いています。】「UACHTARÁIN na hÉIREANNThe PRESIDENTS of IRELAND」【アイルランド大統領】👈️リンクこの壮麗な新古典主義様式の回廊は、ここに描かれている1888年当時の姿で、1758年に設計された と。「This great Neoclassical corridor, shown here as it appeared in 1888, was designed in 1758. It provided access to a series of public reception rooms on the left and to the Viceregal quarters, including the State Bedchamber, the Viceroy’s Study and the Vicereine’s Boudoir, on the right. At its far end, it led to the Privy Council Chamber. It was to this room that each new Viceroy processed, led by a ceremonial delegation of grooms, pages and aides-de-camp, when being sworn into office. In the Privy Council Chamber, the Viceroy received the Irish Sword of State before processing back to the Presence Chamber to take his seat on the throne.」【この壮麗な新古典主義様式の回廊は、ここに描かれている1888年当時の姿で、1758年に設計されました。左側には一連の公的な接待室が並び、右側には副王の私的区域(国賓寝室、副王の書斎、副王妃の居間)へと通じていました。奥には枢密院会議室があり、新任の副王は就任の際、儀典係、侍従、従官からなる儀礼的な随行団に導かれてここへ進みました。枢密院会議室では、副王はアイルランドの国璽の剣(Irish Sword of State)を受け取り、その後、再びプレゼンス・チェンバー(Presence Chamber)へ戻り、玉座に着席しました。】 この肖像画はエイモン・デ・ヴァレラ(1882年~1975年)で、1959年から1973年までアイルランド大統領を務めた。下段英文「Eamon de Valera"Our nation mourns a great loss beyond our state ... at the members of our parliament."Eamon de Valera (1882–1975) was a major figure in modern Irish history. Born in New York, he held numerous political offices in a career that spanned more than half a century. Among these were TD (Member of Parliament) for Clare, Minister for External Affairs and Taoiseach (Prime Minister).In 1959, he succeeded Sean T. O'Kelly to become Ireland’s third President. He was re-elected in 1966. In his second inaugural address, he acknowledged Douglas Hyde for defining the stature of the office. As president, he welcomed many high-profile visitors to the State Apartments at Dublin Castle, including Princess Grace of Monaco(1961), John F. Kennedy (1963), and Charles de Gaulle (1969). April 30, he wasthe oldest President to serve office.」 【エイモン・デ・ヴァレラ「我が国は、国家の枠を越えた大きな喪失を悼む…」 ― 議会の議員たちの言葉エイモン・デ・ヴァレラ(1882–1975)は、近代アイルランド史における重要人物であった。ニューヨークに生まれ、2歳からアイルランドで暮らした。50年以上にわたる政治経歴の中で、クレア選出の国会議員(TD)、外務大臣、首相(タオイシーチ)など数々の要職を歴任した。1959年、ショーン・T・オケリーの後任としてアイルランド第3代大統領に就任。1966年に再選され、第2期就任演説では、初代大統領ダグラス・ハイドが大統領職の威厳を確立した功績を称えた。大統領として、ダブリン城の迎賓室にモナコ公妃グレース(1961年)、ジョン・F・ケネディ(1963年)、シャルル・ド・ゴール(1969年)など、多くの著名な来賓を迎えた。4月30日、彼は歴代最高齢で在任した大統領となった。】ショーン・T・オケリー(1882年~1966年)の肖像で、1945年から1959年までアイルランド大統領を務めた。「Seán T. O’Kelly"Co-operating together, I hope that we shall be able to do great things for Ireland."Ireland’s second President, Seán T. O’Kelly (1882–1966), was born in Dublin. In 1915, he became a founder member of Sinn Féin and in 1916, he served as aide-de-camp toPatrick Pearse during the Easter Rising. Following Irish independence, he rose through the ranks of government to become Minister for Finance and Tánaiste(Deputy Prime Minister).O’Kelly became President on 25 June 1945. In his inaugural address, he followedDouglas Hyde’s example by speaking exclusively in Irish. He was re-elected unopposed for a second term in 1952. This term concluded with an historic State visit to theUnited States of America in 1959. There, he addressed a joint session of the Houses of Congress on St Patrick’s Day (17 March). The visit gave a considerable boost to the visibility and standing of the office of President.」【ショーン・T・オケリー「協力し合えば、アイルランドのために偉大なことを成し遂げられると信じています。」アイルランド第2代大統領ショーン・T・オケリー(1882–1966)はダブリン生まれ。1915年、彼はシン・フェイン党の創設メンバーとなり、1916年にはイースター蜂起でパトリック・ピアースの副官を務めた。アイルランド独立後、財務大臣やターナシュタ(副首相)など政府内の要職を歴任した。1945年6月25日、大統領に就任。就任演説では、ダグラス・ハイドの例にならい、全編をアイルランド語で行った。1952年には無投票で再選を果たす。2期目の任期は、1959年の歴史的なアメリカ合衆国への国賓訪問で締めくくられた。この訪問では、セント・パトリックス・デー(3月17日)に米国議会両院合同会議で演説を行い、大統領職の知名度と地位を大きく高めた。】 エイモン・デ・ヴァレラ(Éamon de Valera) の肖像画。彼はアイルランドの政治史における最重要人物の一人であり、国家の指導者として長く活躍した。生誕地:ニューヨーク(アメリカ)経歴:・1916年イースター蜂起に参加し、後にアイルランド独立運動の指導者となる。 シン・フェイン党党首として活動。・アイルランド自由国の成立後、複数回にわたり首相(Taoiseach)を務める。・1959年〜1973年まで第3代アイルランド大統領。功績:・1937年憲法の起草を主導し、現行のアイルランド憲法(Bunreacht na hÉireann)を制定。・独立国家としてのアイルランドの形を確立した立役者。「Éamon de Valera“We have an importance far beyond our size … or the numbers of our people.”Éamon de Valera (1882–1975) was a major figure in modern Irish history. Born in New York, he held numerous political offices in a career that spanned more thanhalf a century. Among these were TD (Member of Parliament) for Clare, Minister for External Affairs and Taoiseach (Prime Minister).In 1959, he succeeded Seán T. O’Kelly to become Ireland’s third President. He wasinaugurated on 25 June and was re-elected in 1966. In his second inaugural address,he broke with the tradition, established by Douglas Hyde, of delivering the address exclusively in Irish. As President, he welcomed many high-profile visitors to the StateApartments in Dublin Castle, including Princess Grace of Monaco (1961), John F. Kennedy (1963) and Charles de Gaulle (1969). Aged 90, he was the oldest President to leave office.」 【エイモン・デ・ヴァレラ「我々の重要性は、その国土の広さや人口数をはるかに超えている。」イモン・デ・ヴァレラ(1882–1975)は、近代アイルランド史の主要人物であった。ニューヨークで生まれ、50年以上に及ぶ政治活動の中で数々の公職を務めた。その中には、クレア選出の国会議員(TD)、外務大臣、そして首相(タオイサハ)が含まれる。1959年、彼はショーン・T・オケリーの後を継ぎ、アイルランド第3代大統領となった。6月25日に就任し、1966年に再選。2期目の就任演説では、ダグラス・ハイドが築いた「演説をすべてアイルランド語で行う」という伝統を破った。大統領として、彼はダブリン城のステート・アパートメンツに多くの著名な来賓を迎えた。モナコのグレース公妃(1961年)、ジョン・F・ケネディ米大統領(1963年)、シャルル・ド・ゴール仏大統領(1969年)などが訪問している。90歳で退任し、在任を終えた時点で最年長の大統領であった。】Cearbhall Ó Dálaigh 1974–1976カーヴァル・オダリー1974年~1976年(大統領在任期間)。「Cearbhall Ó DálaighNíl aon bhunreacht ag Uachtarán faoi Bhunreacht na hÉireann, ach b’fhéidir go mbeadh uachtarán in ann téama a bheith aige.Mar thoradh ar bhás tobann Erskine Childers in bhliain 1974, tar éis níos lú ná ocht mí óchuaigh sé i gcathaoir mar Uachtarán, ceapadh Cearbhall Ó Dálaigh (1911–1978) marcheannasaí ar Rugadh an Dálaigh i gCathair Chill Mhantáin agus sháraigh sé go mór mar abhcóide, ag éirí ina dhiaidh sin mar Ard-Aighne agus mar Phríomh-Bhreitheamh na hÉireann. Sa bhliain 1973, tháinig sé chun bheith ina bhreitheamh i gCúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach. D’éirigh sé as an ról sin chun teacht chun bheith mar ochtú Uachtarán na hÉireann an 19 Nollaig 1974.Ceapadh le Childers, shamhlaigh sé go mbeadh níos gníomhaí aige mar Uachtarán. Tháinig dearcadh áfach as a chaidreamh míshocair leis an rialtas, áfach. I mí DheireadhFómhair 1976, tháinig teannas chun solais nuair a thug Paddy Donegan, an tAire Cosanta, “unís uafásach náire” ar an Dálaigh a chumhacht mar Uachtarán a fheidhmiú chun billereatha a tharchur chuig an gCúirt Uachtarach. Agus coig air faoin eachtra sin, d’éirigh anDálaigh as oifig an 22 Deireadh Fómhair.」ネットで翻訳【カーヴァル・オダリーアイルランド憲法は大統領にテーマを持つことを定めていないが、大統領がテーマを持つことは可能だ。」1974年、エルスキン・チルダーズ大統領が就任からわずか8か月足らずで急逝したため、カーヴァル・オダリー(1911–1978)が後任として任命された。ウィックロー州で生まれたオダリーは、弁護士として大きな成功を収め、後にアイルランドの司法長官、そして最高裁判所長官を務めた。1973年には欧州共同体司法裁判所の判事となったが、その職を辞して1974年12月19日にアイルランド第8代大統領に就任した。チルダーズの後任として、オダリーはより積極的な大統領像を描いていた。しかし、政府との関係は不安定であった。1976年10月、防衛相パディ・ドネガンが、現行法案を最高裁に付託するというオダリー大統領の権限行使を「ひどく恥ずべき行為」と呼んだことから緊張が表面化した。この事件を受け、オダリーは同年10月22日に大統領職を辞任した。】 Erskine Childers(アースキン・チルダーズ) 。キャプションには在任年 1973–1974 とあり、彼がアイルランドの第4代大統領であった と。「Erskine Childers'I am humbly aware of the great honour conferred upon me at this ceremony.'Erskine Childers (1905–1974) was born and raised in London. Having moved to Ireland, he served as TD (Member of Parliament) for Longford-Westmeath, and later for Monaghan, eventually becoming Minister for Health and Tánaiste (Deputy Prime Minister).Childers was sworn in as the fourth President of Ireland on 25 June 1973. His election asthe State’s second Protestant (Church of Ireland) President was viewed by some as symbolically significant, coming at a time of growing sectarian conflict in Northern Ireland. He hoped to expand the role of President but quickly became frustrated by government’s reluctance to support his approach. In May 1974, he visited Belgium. This landmark trip was the first State visit by an Irish President to a European country. Just six months later, Childers died suddenly from a heart attack. He remains the only Irish President to have died in office.」 【アースキン・チルダーズ「この式典で私に授けられた大いなる名誉を、謙虚に受け止めています。」アースキン・チルダーズ(1905–1974)はロンドンで生まれ育った。アイルランドに移住後、ロングフォード=ウェストミーズ選出の国会議員(TD)を務め、のちにモナハン選出となり、最終的には保健大臣およびターナシュタ(副首相)に就任した。チルダーズは1973年6月25日にアイルランド第4代大統領として就任した。彼は同国史上2人目のプロテスタント(アイルランド国教会)出身の大統領であり、これは北アイルランドで宗派間対立が激化していた時期にあって象徴的に重要な意味を持つと一部で見なされた。彼は大統領の役割を拡大しようと望んだが、政府が彼の方針を支持しようとしないことにすぐに失望した。1974年5月にはベルギーを訪問。この歴史的訪問は、アイルランド大統領として初めての欧州諸国への国賓訪問であった。しかし、そのわずか6か月後、チルダーズは心臓発作により急逝した。彼はいまなお、在任中に亡くなった唯一のアイルランド大統領である。】大理石(または石膏風仕上げ)の装飾壺(装飾用の大型の花瓶)。新古典主義(ネオクラシカル)様式を踏襲しており、18世紀末~19世紀初頭の英国やアイルランドの邸宅で好まれたデザイン。第6代アイルランド大統領・Patrick Hillery(パトリック・ヒラリー)。「 Patrick Hillery“This is a time for courage and conviction.”Dr Patrick Hillery (1923–2008) was born in County Clare and trained as a medical doctor.In 1951, he was elected as a TD (Member of Parliament) for Clare. He went on to holdseveral cabinet positions, among them Minister for External Affairs. When Ireland joinedthe EEC (now the EU) in 1973, he was appointed European Commissioner forSocial Affairs, and Vice-President of the European Commission.Hillery was elected unopposed as the sixth President of Ireland in 1976 and was swornin on 3 December. In 1983, he commenced a second term in office, becoming the onlyIrish President to secure two terms without contest. Hillery’s years as President broughta renewed sense of stability to the office. A lasting legacy of his presidency is Gaisce –The President’s Award, which was established under his patronage in 1985. It is stillpresented annually to high-achieving young people.」 【パトリック・ヒラリー「今は勇気と信念が必要な時だ」パトリック・ヒラリー博士(1923–2008)はクレア州に生まれ、医師としての訓練を受けました。1951年、クレア選出のTD(国会議員)に当選し、その後、外務大臣を含む複数の閣僚職を歴任しました。1973年、アイルランドがEEC(現在のEU)に加盟すると、欧州委員会の社会問題担当委員および欧州委員会副委員長に任命されました。1976年、ヒラリーは無投票で第6代アイルランド大統領に選出され、12月3日に就任しました。1983年には2期目を開始し、選挙戦を経ずに2期務めた唯一のアイルランド大統領となりました。大統領としての任期中、彼は職務に新たな安定感をもたらしました。彼の大統領職の永続的な遺産の一つが「ガイスク – 大統領賞」であり、1985年に彼の後援の下で創設され、現在も優秀な若者に毎年授与されています。】アイルランド第7代大統領・Mary Robinson1990–1997「Mary Robinson“The Ireland I will be representing is a new Ireland – open, tolerant, inclusive.”1990 marked the beginning of a new decade and with it, the election of a Presidentwho spoke of representing “a new Ireland”. Mary Robinson (1944–) was inaugurated as Ireland’s seventh President on 3 December 1990. Born in County Mayo, she was a prominent academic, barrister, senator and human rights campaigner prior to her election as President.Robinson’s presidency was one of several firsts. She was the first woman to hold theoffice; the first President to visit the United Kingdom, where she met Queen Elizabeth II in 1993; and the first President to address the Houses of the Oireachtas (Irish Parliament)on two occasions. She resigned just before the end of her term in 1997 to become United Nations High Commissioner for Human Rights. Described by the Taoiseach(Prime Minister) of the day as a “luminous presidency”, Robinson’s term is often viewed as a transformative one.」 【メアリー・ロビンソン「私が代表するアイルランドは、新しいアイルランド ― 開かれ、寛容で、包摂的な国です。」1990年は新しい10年の始まりであり、それと共に「新しいアイルランド」を代表すると語る大統領が選出された年でもあった。メアリー・ロビンソン(1944年〜)は、1990年12月3日にアイルランド第7代大統領として就任した。メイヨー州生まれの彼女は、大統領選出前から著名な学者、弁護士、上院議員、人権活動家として知られていた。ロビンソンの大統領任期は、いくつもの「初」を記録した。彼女は大統領職に就いた初の女性であり、1993年には英国を公式訪問してエリザベス2世女王と会見した初めての大統領となった。また、アイルランド議会(オイレアハタス)で2度演説を行った初の大統領でもあった。1997年、任期終了直前に辞任し、国連人権高等弁務官に就任。 当時の首相から「輝かしい大統領職」と評された彼女の任期は、しばしば変革期として位置付けられている。】再び第8代アイルランド大統領Mary McAleese・メアリー・マッカリース。「Mary McAleese‘The theme of my presidency, the eighth presidency, is building bridges.’Mary McAleese (1951–) was born and raised in Belfast. She rose to prominence as abarrister and, at the age of 24, was appointed Reid Professor of Criminal Law atTrinity College Dublin. In 1994, she was appointed Pro-Vice-Chancellor ofQueen’s University Belfast, becoming the first woman to hold the position.McAleese’s inauguration as the eighth President of Ireland took place on 11 November 1997. Aged 46, she was the youngest President to enter office. In her inaugural address,she expressed pride at being the first President from Ulster, and she went on to build‘bridges’ of reconciliation as part of the Northern Ireland peace process. She was electedfor a second term in 2004. Her initiatives as President included celebrating 12 July –a holiday associated with the Unionist community in Northern Ireland; becoming the first President to visit an Orange Hall; and inviting Queen Elizabeth II to make the first Statevisit by a British monarch to Ireland since independence in 1922. That historic visit tookplace in May 2011.」 【メアリー・マッカリース「私の大統領職、すなわち第8代大統領職のテーマは“架け橋を築くこと”です」メアリー・マッカリース(1951–)はベルファストで生まれ育ちました。弁護士として頭角を現し、24歳の時にダブリン大学トリニティ・カレッジで刑法のリード教授に任命されました。1994年にはベルファストのクイーンズ大学で副総長に任命され、この職に就いた初の女性となりました。第8代アイルランド大統領としての就任式は1997年11月11日に行われ、46歳で史上最年少の大統領となりました。就任演説では、アルスター出身として初めての大統領であることへの誇りを語り、北アイルランド和平プロセスの一環として「和解の架け橋」を築く活動を進めました。2004年には再選を果たしました。大統領としての取り組みには、北アイルランドのユニオニスト(英国との連合支持派)社会に関係する祝日「7月12日」の記念行事への参加、大統領として初めてオレンジ・ホールを訪問したこと、そして1922年の独立以来初めて英国君主(エリザベス2世女王)を国賓としてアイルランドに招いたことなどが含まれます。この歴史的訪問は2011年5月に行われました。】第9代アイルランド大統領・Michael D. Higgins(マイケル・D・ヒギンズ)。「Michael D. Higgins‘My presidency will be a presidency of transformation … a presidency of ideas.’Michael D. Higgins (1941–) was born in Limerick and was raised in County Clare. He is a poet, academic, writer and former politician. In 1973, he was appointed to Seanad Éireann (the Irish Senate) and from 1987 to 2011, he served as a TD (Member of Parliament) for Galway West. In 1993, he became Ireland’s firstMinister for the Arts.Michael D. Higgins was sworn in as the ninth President of Ireland on 11 November 2011.At a time of rising emigration and economic uncertainty, his presidency focussedon ‘original thinking’ and the development of ideas for the Ireland of the future. In 2014, he made the first State visit by an Irish President to the United Kingdom. During that visit, he spoke of Ireland’s cherished independence from Britain, but alsoof a closeness between both countries that ‘once seemed unachievable’. In 2018, he was re-elected as President for a second seven-year term.」 【マイケル・D・ヒギンズ「私の大統領職は変革の大統領職であり、理念の大統領職となるだろう」マイケル・D・ヒギンズ(1941–)はリムリックに生まれ、クレア州で育ちました。詩人、学者、作家、そして元政治家でもあります。1973年にアイルランド上院(Seanad Éireann)の議員に任命され、1987年から2011年までゴールウェイ西選出のTD(国会議員)を務めました。1993年にはアイルランド初の文化芸術大臣に就任しました。2011年11月11日、第9代アイルランド大統領に就任。当時は移民増加や経済的不安が高まる中で、「独創的な発想」と「未来のアイルランドのための理念の構築」に重点を置きました。2014年には、アイルランド大統領として初めて公式にイギリスを訪問。その際、イギリスからの独立というアイルランドの大切な歴史に触れるとともに、かつては実現不可能と思われた両国の親密な関係についても語りました。2018年には再選され、2期目(7年間)の任期に入りました。】アイルランド大統領の肖像と紹介パネルが並ぶ、豪華なアーチ型天井の回廊。暖炉の上と右側壁面に飾られた3枚の絵画が。暖炉上:・赤い法服と白いファー付きローブをまとった男性の肖像画。・首には金色のチェーンとメダル、髪は白く長い巻き毛(おそらく法曹関係者か高位裁判官)。・額縁は金の装飾が施されたバロック調。ズームして。この人物は?? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.14
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その77):Dublin市内散策(15/)・ダブリン城(Dublin Castle)-3
ダブリン城(Dublin Castle)のState Apartments に収蔵されている絵画・彫刻コレクションの見学のために開館の10:00を待つ。そして10:00になり開館。ダブリン城(Dublin Castle)内の「ステート・アパートメント(State Apartments)」にあるグレート・ステアケース(Great Staircase)前へ。赤いカーペットと金の手すり飾りが特徴の、儀礼用の大階段(Grand Staircase)。カーテンは濃赤色のドレープに金の縁取り。儀式的・格式ある印象を与えるのであった。この階段は、国王や女王、賓客がステート・アパートメントの公式行事に向かう際に使用する象徴的な導入空間であると。この階段を上がると、以下のような部屋へつながっていた。1.Throne Room(玉座の間)2.State Drawing Room(謁見室)3.St. Patrick’s Hall(セント・パトリックス・ホール)4.Battleaxe Landing(戦斧の間)中央の像。窓の中央に小像が飾られており、光を背にしてシルエット状になっていた。「Michael Collins(マイケル・コリンズ)像」。・Michael Collins(マイケル・コリンズ)(1890–1922) アイルランド独立運動の指導者の一人。アイルランド独立戦争(1919–1921)では、 IRA(アイルランド共和軍)の諜報活動を組織し、ゲリラ戦を展開しました。 1921年の 英愛条約 に署名し、アイルランド自由国の成立に大きく貢献しましたが、 この妥協的な条約が国内で分裂を招き、1922年の内戦中に暗殺されました。 その死はアイルランドにとって大きな衝撃であり、英雄的な存在として今日まで 記憶されています。・像の特徴 小像は、両腕を組んで立つコリンズの姿を表現しており、軍服姿で毅然とした態度を 示しています。 これは、彼のリーダーシップと独立への強い意志を象徴していると解釈できます。・展示の意味 ダブリン城はイギリス統治時代に総督府として使われてきた象徴的な建物です。 その中の State Apartments にコリンズ像が置かれていること自体が、歴史の逆転 (植民地支配から独立への転換)を示す記念的な配置と考えられます。この絵画は、キリスト教美術における非常に典型的な主題である「ピエタ(Pietà)」または「十字架降架(The Deposition / The Descent from the Cross)」を描いたもの。・中央の人物:十字架から降ろされた後の イエス・キリスト。頭には いばらの冠 を着けており、 体は布に包まれて横たわっています。・左後方の人物:キリストの遺体を支えている男性は、伝統的に ヨセフ・アリマタヤ (または ニコデモ)とされることが多い。この絵画もまた、キリスト教美術において非常に重要な主題の一つである「キリストの埋葬(The Lamentation / Entombment of Christ)」または「ピエタ」に属する作品。登場人物:1.中央下部:亡くなった イエス・キリスト の遺体。2.キリストの右側(赤い衣の女性):多くの場合、マグダラのマリア。涙を流しながら キリストに触れている。3.キリストの頭を支える男性:伝統的には ヨセフ・アリマタヤ や ニコデモ。4.黒い服の女性(後方中央):聖母マリア。喪服を着て祈るようにうなだれている。5.右手前の男性:たらいに手を入れていることから、ニコデモ が遺体の香油塗布や洗浄を している場面かもしれません。6.背景の人物たち:他の弟子、女性たち(例:サロメ、マルタなど)と考えられます。 右手の壺を持った女性は、香油壺を持つマグダラのマリアの象徴かも しれません。キリスト教美術における壮大な主題「最後の審判(Last Judgment)」を描いた作品。下部(地上):・多くの裸の人々が混乱し、叫び、引きずられたり、落下したりしている様子が見えます。・地獄に落ちる罪人や、天に召される義人たちが混在。・地面から引き上げられる者・落とされる者が描かれており、救済と裁きの瞬間を表しています。上部(天上):・雲に乗る神的存在(おそらく キリスト)と、周囲に天使や聖人たちの姿。・天使はラッパ(審判の開始を告げる)を吹いている可能性あり。・左右に分かれた構図は、天国へ行く者と地獄へ堕ちる者の二極構造を暗示しています。「State Apartments(ステート・アパートメンツ)」 に関する展示パネル。「THE STATE APARTMENTSDublin Castle was the seat of English power in Ireland for over 700 years. In the eighteenthcentury, the medieval castle was gradually transformed into a Georgian palacefor the Viceroy (the King’s representative) and the British administration.Designed by the architect Thomas Burgh, the State Apartments formed the public rooms for official state functions, such as balls, receptions, banquets, and court gatherings.Located on the first floor, the State Apartments followed the sequence of a grand house, with reception rooms leading to a throne room and private chambers.On 16 January 1922, the last Viceroy handed Dublin Castle over to Michael Collins andthe new Irish government. This symbolic moment marked the foundation of the IrishFree State, which would later become the Republic of Ireland.Today the ceremonial State Apartments are used for state functions such as presidential inaugurations, official visits, and diplomatic receptions.」【ステート・アパートメンツダブリン城は、700年以上にわたりイングランドのアイルランド支配の拠点でした。18世紀になると、中世の城は徐々に改築され、副王(イギリス王の代理人)と英国統治機構のためのジョージ王朝風の宮殿へと姿を変えていきました。建築家トーマス・バーグ(Thomas Burgh)によって設計されたステート・アパートメンツは、舞踏会、レセプション、晩餐会、法廷の集まりなど、公式の国家行事のための公的な部屋として使用されました。これらの部屋は1階(日本でいう2階)に位置し、壮麗な邸宅の構成に従っており、謁見室から玉座の間、そして私的な居室へと続いています。1922年1月16日、最後の副王がダブリン城をマイケル・コリンズと新しいアイルランド政府へと引き渡しました。この象徴的な出来事は、後にアイルランド共和国となるアイルランド自由国の誕生を意味するものでした。現在、この儀式用のステート・アパートメンツは、大統領就任式、公式訪問、外交レセプションなど、国家的な儀式の場として使用されています。】 この絵画は、聖書に登場する「放蕩息子の物語(The Parable of the Prodigal Son)」を描いたもの。・手前左側には豪華なごちそうや果物、酒などが散乱しており、享楽にふける場面が 描かれています。・右側中央では、女性たちとともに贅沢な生活を送る若者が描かれており、金銭や贅沢な暮らしが 見て取れます。・背景の建物の中には別の人物たちが描かれており、物語の後半の場面(悔い改めや帰郷)へ つながる暗示かもしれません。この写真には、3枚の異なる様式・主題の絵画が壁に展示されている様子が。この絵画は、キリスト教美術において非常に典型的な主題のひとつである「聖ヒエロニムス(St. Jerome)」を描いた作品。・老人の裸身上半身(しばしば苦行者や隠者の象徴)・長い白髭・頭蓋骨(スカル)を持っている(死と瞑想、儚さ〈memento mori〉の象徴)・本・聖書に手を置いている(聖書翻訳に携わったことを象徴)・暗い背景に強い光が当たるカラヴァッジョ風の明暗対比(キアロスクーロ)強い光と闇のコントラスト、肉体表現のリアリズムから見て、バロック期(17世紀)のイタリアまたはスペインの画家による作品と考えられる と。グレート・ステアケース(Great Staircase)の反対側を見る。「グランド・ステアケース(The Grand Staircase)」に関する説明を提供。「THE GRAND STAIRCASE“This great imperial staircase of three broad flights was a historic visual statement ofpower and has been immortalised with a now world-famous image of debutantes inwhite presentation gowns being received with choreographed elegance on the StateApartments’ landing by Ireland’s Lord Lieutenant and members of his court. Originallythis castle was so ill-lit that, in their high-heeled shoes, debutantes and presentationwomen given to the Viceroy, often assisted by the Presentation Marshal, had to clingto the staircase walls for balance, giving the stairwell the temporary title, ‘the wailing wall.”— From the Dublin Castle Guidebook」【グランド・ステアケース(大階段)この壮大な3層構造の大階段は、権力の視覚的象徴として歴史的に重要なものであり、白いドレス姿のデビュタント(社交界への初登場の若い女性たち)が、アイルランド副王(ロード・リューテナント)とその廷臣たちによって、国家アパートメントの踊り場で迎えられる様子を描いた、現在では世界的に有名となった画像によって不朽のものとなっています。当時、この城は非常に薄暗く照明が乏しかったため、ハイヒールを履いたデビュタントや紹介される女性たちは、階段の壁にしがみついて登らなければならなかったといいます。このことから、この階段は一時的に『嘆きの壁(the wailing wall)』と呼ばれることもありました。- ダブリン城ガイドブックより】 聖書の有名な場面「足を洗うイエス(Christ Washing the Disciples’ Feet)」を描いたもの。非常に特徴的な構図と光の表現から、レンブラント(Rembrandt)やその周辺のオランダ黄金時代の画家たち(17世紀)による様式に近い作品 と。・中央の人物は上半身裸に布をまとい、足を洗ってもらっているように見える。・その足元で跪いて作業をしている人物がいる(おそらくイエス・キリスト)。上品な額縁に収められた男性の肖像画。肩にかけた青い帯(サッシュ)は、貴族・勲爵士・政治家・騎士団の象徴であることが多く、名誉職や高位の官職に就いていた可能性を示唆 と。アイルランド総督(Lord Lieutenant of Ireland=Viceroy of Ireland)か?ジョン・ウィリアム・ポンソンビー 第4代ベスバラ伯(John William Ponsonby, 4th Earl of Bessborough)。アイルランド総督(Lord Lieutenant of Ireland)を務めた人物(在任:1846–1847)このベスバラ伯の肖像は、星章やバッジを身につけた格式ある姿で描かれていた。ダブリン城(Dublin Castle)の中庭にある「ダブリン・ガーデン(Dublin Gardens)」を上から眺めた景色。円形の芝生と、その外周を囲む歩道、さらに背景に見える城壁と近代的なビル群が特徴的。1916年のイースター蜂起(Easter Rising)に関わった指導者たちを描いたもの と。蜂起の指導者たちが処刑される前に撮影された写真や記録を元に描かれたペン画。1916年のイースター蜂起の指導者 ジェームズ・コノリー(James Connolly) に関する記念文が刻まれているプレート。「IN THIS ROOMJAMES CONNOLLYSIGNATORY TO THEPROCLAMATION OF THE IRISH REPUBLICLAY A WOUNDED PRISONERPRIOR TO HIS EXECUTION BYTHE BRITISH MILITARY FORCESAT KILMAINHAM JAIL AND HIS INTERMENTAT ARBOUR HILL12TH MAY 1916」 【この部屋でジェームズ・コノリーアイルランド共和国樹立宣言の署名者は、負傷した捕虜として横たわっていた。それは、彼がキルメイナム刑務所でイギリス軍によって処刑され、その後アーバー・ヒルに埋葬される前のことであった。1916年5月12日】こちらは、アイルランド語(ゲール語)で記したプレート。ステート・アパートメンツ(State Apartments)内にある「アーチ型天井の豪華な廊下」。・装飾様式 白地に金色のレリーフを施した豪華な天井装飾が特徴で、円形や楕円形のパネルには花や葉の モチーフが浮き彫りになっています。 このような金色と白の組み合わせは、18〜19世紀の新古典主義(Neoclassical)建築装飾に 多く見られます。・アーチ構造 複数の連続した半円アーチが廊下に奥行きを与え、遠近感を強調しています。 アーチ部分にも細かいモールディング(額縁状の装飾)が施されています。・用途 この廊下は「ステート・アパートメンツ」内の主要な動線のひとつで、公式行事や一般公開時 には訪問者が各部屋へアクセスする際に通るエリアです。 現在は壁に肖像画や説明パネルが並び、小規模な展示ギャラリーとしても使われています。ズームして。ダブリン城(Dublin Castle)の無料音声ガイド案内が。「DUBLIN CASTLEÉist anseo lenár dtreoráí fuaime saor in aisce. Scan an QR códListen to our free audio guide here. Scan the QR code[QRコード]https://www.dublincastle.ie/audio_guide」【ダブリン城こちらで当城の無料音声ガイドをお聴きください。QRコードをスキャンしてください。(QRコード)】 柔らかな光と陰影の中で、両腕を前に組んで頭を乗せる姿勢の少女。様々な作品が。全身を縦長の構図で描いた女性の肖像画で、豪華な金の額縁に収められていた。「Casimir MarkieviczA Polish Artist in Bohemian Dublin (1903–1913)」 【カジミール・マルキェヴィチはダブリンの芸術・文学界(ボヘミアン・ダブリン)で活躍したポーランド出身の画家】「Art, theatre, and liberation: these common threads linked the lives of Casimir and Constance Markievicz. Constance Gore-Booth (1868–1927), the daughter of Anglo-Irish gentry, was destined tobecome one of Ireland’s revolutionary heroines. Casimir Markievicz (1874–1932), a Polish gentleman born in Ukraine, was an artist with an irrepressible zest for life and adventure.In Ireland, the name ‘Markievicz’ instantly conjures the figure of Constance; this exhibition seeks to bring Casimir back into the frame, re-positioning him as a central playerin Dublin’s bohemian life before the Revolution.They met as art students in Paris and married in London in 1900, and from 1903–13‘Casi and Con’ made Dublin their home. In a city teeming with rival theatrical factions, writers, philosophers, and visionaries of the Irish Revival, they pursued their artisticambitions. It was a decade of competing visions of what art could be, of how theatre and art might inform politics (and vice versa), and of the uncertain fate lay ahead forIreland as a nation.For Casimir, this meant experimenting with new forms of artistic self-expression. For Constance, this was the beginning of her political awakening. They also found themselves in dispute with these movements of possibility and promise – some realised,and others not – and of Casimir’s place in a city where (in the words of W.B. Yeats) a ‘terrible beauty’ would soon be born.」 【芸術、演劇、そして解放——これらの共通した糸が、カジミールとコンスタンス・マルキェヴィチの人生を結びつけました。コンスタンス・ゴア=ブース(1868–1927)は、アングロ・アイルランド地主階級の娘として生まれ、やがてアイルランドの革命的ヒロインのひとりとなる運命にありました。カジミール・マルキェヴィチ(1874–1932)は、ウクライナ生まれのポーランド紳士で、抑えきれない人生と冒険への情熱を持つ芸術家でした。アイルランドでは、「マルキェヴィチ」という名前はすぐにコンスタンスの姿を思い起こさせます。この展示は、カジミールを再び舞台に呼び戻し、革命前のダブリンのボヘミアン文化生活における重要人物として位置づけ直そうとするものです。2人はパリで美術を学ぶ学生として出会い、1900年にロンドンで結婚しました。1903年から1913年まで、「カジ」と「コン」はダブリンを拠点としました。その頃のダブリンは、ライバル関係にある演劇団体、作家、哲学者、そしてアイルランド復興運動の理想家たちで溢れており、2人はそこで芸術的野心を追求しました。それは、芸術がいかにあるべきか、演劇や美術が政治に(あるいはその逆に)どのように影響し得るか、そしてアイルランドという国家にどのような運命が待ち受けているのかをめぐる、異なるビジョンがせめぎ合う10年間でした。カジミールにとって、それは新しい芸術的自己表現の形を模索することを意味しました。コンスタンスにとっては、政治的覚醒の始まりでした。2人はまた、数多くの可能性と約束に満ちた運動と関わり合い、その一部は実現し、また一部は実現しませんでした。そして、W・B・イェーツの言葉を借りれば、「恐ろしい美」が間もなく生まれようとしていた都市において、カジミールは自らの立ち位置を見出そうとしていたのです。】アイルランド聖パトリック勲章(Order of St. Patrick)の叙任式または会議の場面を表している場面と。「Artistic Life in DublinWhen Casimir and Constance moved to Dublin in 1903, it was a city bubbling with artistic energy and overlapping social circles. The couple’s arrival conveniently coincidedwith Hugh Lane’s project for establishing a gallery of modern art in Dublin, which openedin temporary premises on Harcourt Street in 1908. Their acceptance by Dublin’s artistic community was greatly aided by their friend George Russell (AE) who introduced themto some of the city’s leading artistic and literary lights. Together with Russell and others, they were co-founders of the United Arts Club in 1907. A magnet for the city’s Bohemianartists, writers and entertainers, the club was the setting for larger-than-life personalitiesin its gatherings.Meanwhile, the couple were also a fashionable feature of elite “Dublin Castle” sets whoattended regular balls and garden parties. Perceived as an exotic foreign aristocrat,Casimir was welcomed as a guest of honour, until politics combined with their personallives made these two overlapping worlds no longer reconcile.」 【ダブリンでの芸術生活1903年にカジミールとコンスタンスがダブリンに移り住んだ当時、街は芸術的な活気と、重なり合う社交界に満ちていました。夫妻の到着は、ヒュー・レーンがダブリンに近代美術館を設立する計画とちょうど重なり、その美術館は1908年にハーコート・ストリートの仮設会場で開館しました。夫妻がダブリンの芸術界に受け入れられるうえで大きな助けとなったのは、友人のジョージ・ラッセル(AE)でした。ラッセルは夫妻を、街の著名な芸術家や文学者たちに紹介しました。夫妻はラッセルらと共に、1907年にユナイテッド・アーツ・クラブを共同創設しました。このクラブは、ダブリンのボヘミアン芸術家、作家、芸人たちを惹きつける場であり、その集まりには個性豊かな人物たちが顔を揃えました。一方で夫妻は、「ダブリン城」社交界の華やかな顔ぶれとしても知られ、定期的に開かれる舞踏会や園遊会にも出席しました。異国の貴族としてのカジミールは名誉ある客として迎えられましたが、政治と私生活の問題が重なった結果、この二つの重なり合う世界はもはや両立できなくなっていきました。】赤い壁面が印象的なダブリン城(Dublin Castle)内の展示室の一角。カジミール・マルキェヴィチ(Casimir Markievicz)関連の展示エリア。この肖像画は 「ミセス・エリー・ダンカン」 を描いたもので、画家は <カジミール・ドゥニン・マルキェヴィチ伯爵(Count Casimir Dunin Markievicz)。「Casimir MarkieviczPortrait of Ellen Duncan (c.1913)Oil on board. United Arts Club, DublinEllen Duncan (1850–1937) was a central figure in the promotion of visual art in Ireland. A champion of Hugh Lane and the effort to establish a gallery for modern art, she servedas the gallery’s first curator from 1911–1922. Casimir and Constance were also involvedwith Lane’s campaign, and worked alongside Duncan on the foundation committee for the United Arts Club, with Duncan appointed the Club’s honorary secretary in 1910.」 【カジミール・マルキェヴィチエレン・ダンカンの肖像(約1913年)板に油彩 ダブリン、ユナイテッド・アーツ・クラブ所蔵エレン・ダンカン(1850–1937)は、アイルランドにおける視覚芸術振興の中心的存在でした。彼女はヒュー・レーンと、近代美術のためのギャラリー設立の取り組みを支持し、1911年から1922年までそのギャラリーの初代キュレーターを務めました。カジミールとコンスタンスもレーンの運動に関わっており、ユナイテッド・アーツ・クラブ設立委員会でダンカンと共に活動しました。ダンカンは1910年、このクラブの名誉書記に任命されました。】ヴワディスワフ伯爵の肖像(1860)。「Boleslaw SzańkowskiPortrait of Count Władysław (1860)Oil on canvas, Local Family Collection, PolandBoleslaw Szańkowski (1873–1953) was a leading Polish portrait painter who studied in Munich under... He continued his studies in Paris before moving to St Petersburg, becoming the French court's official portraitist. He was finally to settle in Warsaw in the 1890s.[中略 – ピンボケで不明な部分]Szańkowski also painted a number of works in Montparnasse, Paris, and in Warsaw. In addition to portraits, he restored a number of important works in Poland.」【ボレスワフ・シャニコフスキヴワディスワフ伯爵の肖像(1860)キャンバスに油彩、ポーランドの地方家族コレクション所蔵ボレスワフ・シャニコフスキ(1873–1953)は、ポーランドを代表する肖像画家の一人で、ミュンヘンで学び、その後パリでも研鑽を積みました。サンクトペテルブルクに移り、フランス宮廷の公式肖像画家も務めました。1890年代に最終的にワルシャワに定住しました。[中略 – 判別不能部分]また、パリのモンパルナスやワルシャワでも多くの作品を制作しました。肖像画のほか、ポーランドにおける重要な美術作品の修復にも携わりました。】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.13
コメント(0)
-

我が菜園の朝顔の花
我が家の横の菜園に咲く朝顔の花です。名前の通り夏の朝に咲く花、朝顔。日本で古くから親しまれている花ですが、薬草として中国から伝わったのが始まりと言われています。江戸時代には愛好家によって品種改良が進み、観賞用として栽培されるようになりました。大輪朝顔などの人気はこのころから出始めました。鉢植えで育てることができる朝顔ですが、品種によってはグリーンカーテンとしてネットに這わせて楽しむこともできるのです。朝に咲くことから朝顔という名前が付けられましたが、朝の何時ごろに咲くかご存知ですか?日の出が関係しているように思われますが、実は、朝顔が咲く時間は前日の日没の約10時間後と言われています。夏至のころには朝顔が咲く時間は遅くなり、冬至に近づくほど日没が早まるので、朝顔の開花時間も早まります。さらに、朝顔をじっと観察すると、成長の仕方が一方向であることに気づきます。右巻きか左巻きか、ご存知でしょうか? 朝顔のツルは右巻きで生長していきます。右巻きか左巻きかは横から見て判断するので、ややこしいのですが、真上から見ると左回りに成長していきます。これは遺伝的に決まっているものだそうです。これは、大輪で美しい星咲きの花。花の中心から放射状に延びた白いすじが星のように見えるかわいらしいアサガオ。花は最大で直径10~13cmと大輪で見応えがあります。右側には、透き通るような青紫の花を咲かせる西洋大輪アサガオ。ズームして。中心は白から黄色にグラデーション。鮮やかな赤紫〜濃紫の花色。花弁の縁に白い覆輪(ふちどり)があり、華やかな印象。中心部は淡い桃色から白にグラデーションし、放射状の筋が強調されて。園芸品種によく見られる「縁取り咲き」や「絞り咲き」の変化朝顔の一種。純白の朝顔の大輪。ズームして。左の花:淡い藤色〜白に近い薄紫で、中心にかけてほんのり赤みを帯びたグラデーション。右の花:濃い紫色で、ほぼ黒に近い深い色合い。同じ株でも色合いが大きく異なる花をつけることがあり、これも「変化朝顔」や交配品種の特徴のひとつです。写真ではすでにしおれかけている花も見え、アサガオ特有の「朝に咲いて昼にしぼむ」一日花の性質が現れていたのです。「絞り咲き(しぼりざき)」と呼ばれるタイプ。紫を基調とし、白い筋や斑(まだら模様)が放射状に入っている。一枚ごとに模様の出方が異なり、まるで絵筆で描いたような芸術的な風合い。花の中心は白く抜けて、淡いグラデーションが広がっている。江戸時代の「変化朝顔」ブームでも人気が高かった咲き方。青空に映えて。中心から放射状に紫の筋模様が広がっています。紫の筋は太さや濃淡が不規則で、手描きの筆跡のように個性があります。花の中心は淡いピンクを帯び、白から紫へのグラデーションが美しい。絞り模様の入り方は一輪ごとに違うため、毎日異なる表情を見せてくれるのです。そしてこれは?アサガオではありません。これは、「花オクラ」。花オクラ(別名:トロロアオイ)は、その名の通り花を食べるエディブルフラワー(食用花)で、一般的なオクラのようなサヤではなく、淡白でオクラに似た風味と粘り気のある食感が特徴。生でサラダや和え物にするとシャキシャキした食感が楽しめ、加熱すると粘り気が増してとろりとした食感になるのです。見た目も美しく、おひたし、酢の物、天ぷらなど、幅広い料理で楽しめるのです。近づいて。オクラとよく似た美しいレモンイエローの花を咲かせる「花オクラ」。■おひたし美しい色合いを活かしておひたしにするのも定番。酢を加えたお湯でゆでると鮮やかな色を保ちやすい。加熱するととろりとした粘り気が強くなるので、オクラに似た食感も楽しめます!できたてをすし酢をかけて食べるのはもちろん、冷やして食べてもおいしいのです。■天ぷら花オクラの天ぷらもぜひ味わってみてほしい一品。花に薄く衣をつけさっと揚げましょう。花びらを一枚ずつ揚げてもよいですし、つぼみをそのまま揚げても大丈夫。サクサクの衣と粘り気のある花オクラのもっちりとした食感の違いが楽しい。ほんのりと苦味があり、オクラ特有の香りも。最後に朝顔の花が昔から日本人に愛されている理由を調べてみました。朝顔(アサガオ)は、奈良時代に中国から薬草として伝来し、平安時代以降は観賞用として日本人に広く親しまれるようになりました。日本文化に根付いた理由はいくつかあるようです。1. 花の特徴と日本人の感性・清らかさと儚さ 朝に咲き、昼にはしぼむ一日花。短い時間に鮮やかに咲く姿は、日本人が大切にする 「もののあはれ」「はかなさの美」と深く共鳴しました。・鮮やかな色彩 青・紫・桃色などの涼やかな花色は、夏の暑さの中に清涼感を与え、視覚的にも人々を 惹きつけました。2. 生活文化との結びつき・江戸時代の園芸ブーム 江戸庶民の間で「変化朝顔(葉や花びらが珍しい形になるもの)」の栽培が流行。 見世物的な人気もあり、浮世絵や瓦版でも盛んに取り上げられました。・夏の風物詩 朝顔市(入谷・駒込など)が江戸から現代にまで続いており、鉢植えを縁側に置き、 行燈仕立てで涼を呼ぶ光景が「夏の日本らしさ」を象徴。3. 文学や芸術への影響・和歌・俳句に詠まれる題材 例:「朝顔に釣瓶取られてもらひ水」(加賀千代女)など、身近な暮らしとともに詠まれました。・意匠としての利用 着物や団扇、屏風などの模様として広く使われ、夏を表す典型的な文様となりました。4. 象徴的な意味・儚い命の象徴 → 無常観や「一期一会」の精神と通じる。・愛情・絆の象徴 → つるを伸ばしてからみつく姿が「縁」を思わせ、恋愛や人との結びつきに たとえられました と。この浮世絵は の作品・「美立候花競(みたて はなの くらべ)」 と。・女性を季節の花に見立てた美人画シリーズで、ここでは「朝顔」と「美人」が対になっています。・江戸後期、園芸ブームの中で「朝顔=夏の風物詩」として特に人気が高く、浮世絵の題材と しても多く描かれました と。 ・・・おわり・・・
2025.09.12
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その76):Dublin市内散策(15/)・ダブリン城(Dublin Castle)-2
ダブリン城の敷地内にある「Dubh Linn Garden(ダブ・リン・ガーデン)」の入口に到着。左手に「DUBH LINN GARDEND(ダブ・リン庭園)「Dubh Linn」はアイルランド語で「黒い池」という意味で、ダブリンの語源」と。中央に「THE CHESTER BEATTY LIBRARY AND GALLERY OF ORIENTAL ART」と。【チェスター・ビーティー図書館および東洋美術ギャラリー】「Dubh Linn Gardens(ダブ・リン庭園)」の解説パネル。「The Dubh linn GardensThese were laid out on the site of the Dubhlinn (‘Black Pool’ in Gaelic), from which Dublin gets its name.The deep pool or harbour was formed near where the River Poddle met the River Liffey. The Norse King of Dublin and later the Anglo-Norman Lords of Dublin, the Earls ofOrmond and the English Viceroys made their stronghold on this strategically important site, selected for its defensible qualities and its direct river access to the Irish Sea.The gardens are arranged in a circular design which is inspired by early Celtic and Druidic traditions. The intricate design also includes references to traditional manuscriptdesign and to the layout of the adjoining Dubhlinn site.」 【ダブ・リン庭園この庭園は「Dubhlinn(ダブリン)」=ゲール語で「黒い池」と呼ばれる場所に造られました。現在のダブリンの地名はこの池に由来しています。この「黒い池」や天然の港は、ポドル川(River Poddle)がリフィー川(River Liffey)に合流する地点に形成されました。ダブリンのノース人の王や、その後のアングロ・ノルマン人の領主、オーモンド伯爵家、さらにイングランド王室の副王たちが、この戦略的に重要な地に拠点を築きました。この場所は、防御に適しており、アイリッシュ海への直接アクセスが可能であったことがその理由です。現在の庭園の配置は、円形デザインとなっており、これは古代ケルトやドルイド教の伝統に着想を得たものです。さらにこのデザインには、古典写本の装飾文様や、かつてここにあった「Dubhlinn(黒い池)」の位置を示す意匠も組み込まれています。】点線------の場所が「Dubh Linn Gardens(ダブ・リン庭園)」。円形の芝生広場には、ケルト風の迷路模様が描かれていた。中央には注意書きの立て札が設置されていた。「芝生には立ち入らないでください」と。 この芝生の迷路状の模様は、ケルト的な渦巻き模様(スパイラル・モチーフ)を意識したもので、Dubh Linn Garden の特徴的な意匠。訪問者が誤って模様を踏み荒らさないよう、このような注意が設けられているのであった。芝生を刈り込むと、下記の如き模様が現れるとネットの写真より。この模様は「ケルトのスパイラル(Celtic spiral)」や「ラビリンス(迷宮)」と呼ばれ、地面に直接刻まれたような形で現れるのだ と。全体が中庭を占めるほどの大スケールで、上から見下ろすことで全容が見える仕掛け。象徴的意味1. ケルト的宇宙観と再生・ケルト文化では、スパイラル(渦巻き)模様は命の循環・再生・進化を象徴します。・螺旋は生命の始まりから成長・死・再生に至る旅を表し、時間や魂の流れを可視化する象徴 とされています。2. 迷宮としての人生の旅・ラビリンス(迷宮)は、「人生の探求の道のり」を意味します。・入口と出口が一体化した構造をとることで、「行き着く先は自己の中心」という 精神的・哲学的な意味を表します。真上からの写真をネットから。アイルランドの「Garda Memorial Garden(ガーダ記念庭園)」へのもう一つの入口。この庭園は、アイルランドの国家警察である「アイルランド警察庁(An Garda Síochána)」の殉職警官を追悼するために設けられたメモリアルスペースである と。上部にアイルランド語と英語で以下の碑文が彫られていた。・GARDÍN CUIIMHNEACHÁIN AN GHARDA SÍOCHÁNA・GARDA MEMORIAL GARDEN左の石板はアイルランド警察の紋章と。・渦巻く模様と中央のハープを特徴とするこの紋章は、An Garda Síochána の公式エンブレム。・ハープはアイルランド国家の象徴であり、警察組織が国家の秩序を守る立場であることを 表している と。再び円形の芝生広場を見る。写真奥に見えるのは、ダブリン城のCoach House Gallery(コーチ・ハウス・ギャラリー)。ゴシック風の城壁風の意匠と尖塔が特徴。現代建築と並んで建っている様子は、過去と現在が共存する空間であることを象徴していた。この花はトーチリリー(Torch Lily)?それともレッドホットポーカー(Red Hot Poker)?それとも??現代的な衣装(キャップ・半ズボン・スニーカー)を身に着けた若者が、古典的彫像の切り落とされた頭部に足を乗せるという、強い象徴性と挑発的な構図を持つ現代彫刻。題名:「David and Goliath(ダビデとゴリアテ)」制作者:Jam Sutton(ジャム・サットン)古典的なダビデとゴリアテのモチーフを現代風にアレンジしたもので、ストリートウェアをまとった若いダビデがゴリアテの生首の上に座っている様子が描かれている。この作品のオリジナルは2015年制作で、カララ大理石から彫刻されています。本作品はその 3Dスキャンによる拡大レプリカで、現代で最も現代的な芸術媒体の一つである3Dプリンターを用いて制作されたのだと。こちらには「渦巻(スパイラル)モザイク彫刻」が。ガラスまたは似た素材で制作された青と白の渦巻く蛇(もしくは二匹の蛇が絡み合った形)で表現されていた。ケルトの象徴としての「蛇」は、再生・癒し・知恵を意味するとされ、スパイラル模様に落とし込まれているのであった。作品名は不詳であるが、通称として “Serpent Pool” または “Garden of Eden Serpent” と呼ばれている と。作者として Sarah Daly(サラ・デイリー) の名前がいくつかの資料で言及されているとも。迷路(ラビリンス)の後方には、ダブリン城のCoach House Gallery(コーチ・ハウス・ギャラリー)と中庭側の棟(Chester Beatty Libraryの隣)の建物の姿が。ダブリン城の南側にあるCoach House Gallery(コーチ・ハウス・ギャラリー)のファザードをズームして。建築様式:ノルマン様式+ゴシックリバイバル風の装飾(後期再建)さらにズーム。建築家 Jacob Owen(ジェイコブ・オーウェン) によって設計され、1834年に完成した建物。もともとは Dublin Castle(ダブリン城)の厩舎(馬車小屋)として利用されていた。特徴:背の高い防衛用の塔(バスティオン)と、歯型のような胸壁(battlements)が並ぶ、 中世城塞風の意匠構造の役割:元々の城壁の一部としての防衛機能は失われており、現在は景観・象徴的建築 として再建されたもの。背景にある建物は城内施設や近代ビルが一部混在。写真左:State Apartments(ステート・アパートメンツ) 18世紀から19世紀にかけて増築された新古典様式の建物。英国統治時代には 副王(Viceroy)の公邸として使われ、現在は公式行事(大統領就任式など)に使用 される。写真右:Record Tower(レコード・タワー) 13世紀(1228年)築の現存最古のダブリン城の一部。もとは防衛用の塔で、現在は 展示やアーカイブにも利用されている。丸型で、城塞建築としての堅牢性を象徴する 構造写真右端:Chapel Royal(チャペル・ロイヤル) ゴシック・リヴァイヴァル様式の礼拝堂(1814年完成)。英国国教会の礼拝用に 建てられ、内部の彫刻・木彫細工も見応えがある。現在は展示スペースとして 使用されることも。キャットミント(Catmint)であろうか!?学名:Nepeta faassenii または Nepeta × faassenii特徴:ミントに似た爽やかな香り(猫が好むことで知られる) 小さなラベンダー色の花が穂状に密集して咲き、やや這うように広がる。 乾燥や暑さに強く、ナチュラルガーデンやボーダー植栽に最適。Record Tower(レコード・タワー)をズームして。建造は約1228年、ジョン王(King John)時代。直径は約9.5〜10メートル程度、高さ20m以上か。壁の厚さは場所によって約3メートル近くにも達すると(基礎部付近)。移動して。名前の「Record」は「記録」の意で、かつて記録文書の保管庫(archive)としても使われていたことに由来する と。ダブリン城の敷地内にある Chester Beatty Library(チェスター・ビーティー図書館)の正面入口。左側(ガラス張りのエントランス)・「GIFT OF A LIFETIME(生涯の贈り物)」 の大きな文字が目を引きます。 → Chester Beatty が遺贈した膨大なコレクションが、まさに「一生に一度の贈り物」で あることを示すメッセージ。・入口には期間限定の特別展のバナーが掲示されています。写真では 「SIAM」展 (タイ関連の特別展) の告知が見えます。「Chester Beatty・チェスター・ビーティ図書館」の壁には現代的な壁画(パネルアート)が展示されていた。歴史上の人物や聖人、あるいは神話・宗教・文化にまつわるアイコニックな肖像画を現代風に再解釈したパネル。スタイルはビザンティン的、ケルト的、ヒンドゥー風などが混在しており、多文化的で象徴的なテーマ性を意識した現代アートの可能性が高いとのこと。左側をズームして。左の絵・タイ(シャム)の仏教美術 赤い冠をかぶった神話的存在(おそらく「デーヴァ」あるいは宮廷人物像)が装飾的に 描かれていた。・Chester Beatty のコレクションにはタイの写本挿絵や仏画が多く含まれており、その代表的な イメージが使われている と。中央の絵・日本の浮世絵 和服姿の女性(おそらく遊女あるいは舞妓)が団扇のような文様と共に描かれていた。・江戸時代の浮世絵の典型的な構図で、Chester Beatty には葛飾北斎や喜多川歌麿などの 浮世絵版画コレクションが含まれている。右の絵・インド・ムガル帝国の細密画(ミニアチュール) 豪華な装身具を身につけ、ターバンを巻いた王侯貴族の肖像。・おそらく「シャー・ジャハーン」や「ジャハーンギール」といったムガル皇帝の図像。 インド細密画は Chester Beatty コレクションの柱のひとつ。右側をズームして。左の絵・インド細密画(ラージプート/ムガル周辺) 白い衣装に黒いサッシュを掛け、黄金の後光(ハロー)を背にした王侯。・手には花を持ち、権威とともに優雅さを示す典型的な宮廷肖像。 インド・ラージプートやムガル宮廷美術の系統に属す と。中央の絵・ヨーロッパ中世写本絵画/宗教画 青衣の女性は聖母マリア、赤衣の女性は聖エリサベト。・これはキリスト教美術の定番テーマ「聖母マリアと聖エリサベトの出会い(Visitation)」を 描いた場面。Chester Beatty には膨大な中世写本コレクションがあり、その代表例の一つ。右の絵・現代的な西洋挿絵/絵画 黄色の縞模様のローブを着た若者と、肩越しにとまるオウム。・線描のシンプルさ、ユーモラスな造形から、西洋の20世紀以降の挿絵・風刺画・ 児童文学挿画の類。・「古典的な宗教画・インド美術」と対照的に、モダンで軽やかな作品を示す位置づけ と。Dubh Linn Garden(ダブ・リン庭園)内にあった、噴水仕立ての抽象彫刻。2体の人型にデフォルメされた抽象的なフォルムが並び、その一方が炎(トーチ)らしきシンボルを掲げる形の作品。2003年にアイルランドで開催されたスペシャルオリンピックス世界夏季大会に関わったボランティアを讃えるためのメモリアル彫刻であると。彫刻は2体の抽象化された人物像と、上部にオリンピックの聖火(Flame of Hope)をあしらった構成で、スペシャルオリンピックスのロゴをモチーフにしています。周囲には、2003年大会に貢献した約30,000人のボランティアの名前が刻まれたブロンズのプレートが設置されています とネットから。作者:John Behan(ジョン・ベハン)2003年12月8日にダブリン城のDubh Linn Gardenで除幕式が行われ、アイルランド首相(Taoiseach)によって正式に披露されました とも。ツルオドリコソウ (蔓踊子草、Lamium galeobdolon)??別名:キバナオドリコソウ、ラミューム、 シソ科オドリコソウ属 と。「Dubh Linn Garden・ダブ・リン・ガーデン」を一周して再びCoach House Gallery(コーチ・ハウス・ギャラリー)のファザード方向を見る。「アイルランド警察記念庭園(An Garda Síochána Memorial Garden)」には円形のモニュメントが2つ並ぶ。裏側に移動して。・白と黒の2つの石片が、互いに寄り添うように配置された抽象彫刻。・対称性と調和を示しており、「異なる文化の融合」「東西の知の調和」を象徴しています。・素材のコントラスト(白い大理石と黒い石)は、Beatty のコレクションが「西洋と東洋」 「宗教と世俗」「古代と近代」といった二元性を超えて融合していることを暗示。作品名: A Reflection on the River Liffey(リフィー川への想い)作者: Rachel Joynt(レイチェル・ジョイント) – アイルランドの彫刻家。 都市空間・パブリックアートを多く手掛けることで知られる。設置年: 2003年(記録によって多少前後する可能性あり)場所: ダブリン城の南庭・Dubh Linn Garden 内、記念モニュメントエリア素材: ガラスと金属による彫刻作品(円形ガラスは水の波紋や年輪、時間の経過を表現) と、ネットから。銘板の文言:「A REFLECTION ON THE SUDDEN LOSS AND SUFFERINGOF THE FAMILIES OF THOSE HONOURED」 【突然の喪失と苦しみに対する思い ——称えられた方々のご家族に捧げて】と。・このガラス彫刻は、犠牲となった人々の追悼碑 として設置されたもの。・「sudden loss(突然の喪失)」は、不慮の事故や災害・事件で命を落とした人々を暗示。・「suffering of the families(家族の苦しみ)」に光を当てている点が特徴的で、残された人々の 悲しみに寄り添う意味を強く表現しています。・ガラスの同心円模様は「波紋」を思わせ、個人の死が家族や社会に広がる影響を象徴していると 解釈できます。こちらは、公務中に亡くなった国家職員たちを追悼する記念モニュメント群の一つであると。形状:黒と白の大理石(または類似素材)による2つの有機的な半月形が、向かい合うように 設置されていた。象徴性:陰陽のような形状からは、生と死、喪失と記憶、闇と光といった対比的なテーマを 象徴している。アイルランド共和国の警察機関に関する追悼碑の銘板。「IN REMEMBRANCE OF ALL DECEASED MEMBERS OF AN GARDA SÍOCHÁNA,DUBLIN METROPOLITAN POLICE AND THE ROYAL IRISH CONSTABULARY」【アン・ガルダ・シオカーナ(アイルランド共和国警察)、ダブリン首都警察、 王立アイルランド警察隊の全ての故人を追悼して】 「An Garda Síochána Memorial Garden(ガーダ・シオカーナ慰霊庭園)」に設置された解説パネル。 「An Garda Síochána Memorial Garden honours the members of An Garda Síochánawho were killed in the service of the State.Dublin Castle is associated with An Garda Síochána since the foundation of the State.It is the location where An Garda Síochána affirmed its authority as the National PolicingForce on 9th February, 1922, thereby commencing the phasing out of the Royal Irish Constabulary which ended its policing role in August of that year.In choosing The Dubhlinn Gardens at Dublin Castle as the location of An Garda Síochána Memorial Garden, the historical associations of the Organisation with Dublin Castle werevery much to the fore front. Its proximity to the Garda Museum at Dublin Castle andits access from central Dublin enhances the location.The present configuration of The Dubhlinn Gardens dates from 1994 when it wasdeveloped by the Office of Public Works as part of the preparation for Ireland’s Presidencyof the E.U. in 1996The principal concept behind the design of this Memorial Garden is the way that sudden unexpected death brings an abrupt end to the natural cycle of life which all livingcreatures share. The image of a tree trunk felled before reaching maturity exposingthe rings which represent each year of life is the basis for the design of the garden.The concentric rings of different widths are reflected in the layout of the paving inthe garden. The radiating rings also represent the ripples in the surface of a pond.The seemingly solid structure of the granite wall is pierced by a sharp glass shardrepresenting the fragility of life. The names of the members of An Garda Síochánawho were killed prematurely are inscribed in stone on the Roll of Honour in this Garden.Additionally, a specially commissioned glass sculpture made by Killian Schurmanncommemorates the sacrifice of the families left behind. A specially commissionedstone sculpture made by Jason Ellis is a tribute to all deceased members ofAn Garda Síochána.The Garda Síochána Memorial Garden was officially opened on the 15th May,2010 by An Taoiseach, Mr. Brian Cowen T.D., in the presence of the Garda Commissioner,Mr. Fachtna Murphy, members of An Garda Síochána serving and retired and relativesof those whose names are recorded herein.」 【アイルランド警察記念庭園(An Garda Síochána Memorial Garden)は、国家に奉仕する中で命を落としたアイルランド警察(An Garda Síochána)の隊員たちを称えています。ダブリン城は、国家創設以来、アイルランド警察と深い関係を持ってきました。1922年2月9日、アイルランド警察が国家警察機関としての権限をここで正式に宣言したことにより、王立アイルランド警察隊(Royal Irish Constabulary)の段階的な解散が始まり、その年の8月に警察機能を終了しました。アイルランド警察記念庭園の設置場所として、ダブリン城内のダブリン庭園(Dubhlinn Gardens)が選ばれたのは、警察組織とダブリン城との歴史的なつながりが強調されたためです。また、ダブリン城内にある警察博物館(Garda Museum)に近く、ダブリン中心部からのアクセスが良好な点も、この場所の価値を高めています。現在のダブリン庭園の構成は、1996年のEU議長国就任の準備の一環として、1994年にアイルランド公共事業庁(Office of Public Works)によって整備されました。この記念庭園のデザインの背後にある主要なコンセプトは、「予期せぬ突然の死が、すべての生き物に共通する自然の生命のサイクルを突然断ち切る」という考え方です。成熟する前に伐採された木の幹に現れる年輪のイメージ――それぞれの年輪が1年の人生を象徴する――が、庭園デザインの基礎となっています。異なる幅の同心円が、園内の舗装パターンに反映されており、同時にそれは池の水面に広がる波紋も表現しています。一見して堅固に見える花崗岩の壁は、ガラスの破片によって突き破られており、これは命のはかなさを象徴しています。任務中に命を落としたアイルランド警察隊員の名前は、庭園内の「名誉の記録板(Roll of Honour)」に石で刻まれています。また、キリアン・シュアマン(Killian Schurmann)による特別制作のガラス彫刻は、残された遺族の犠牲を称えるものです。さらに、ジェイソン・エリス(Jason Ellis)が特別に制作した石彫作品は、亡くなったすべてのアイルランド警察隊員に対する賛辞として設置されています。この記念庭園は、2010年5月15日、当時の首相(An Taoiseach)ブライアン・カウエン(Brian Cowen)氏により公式に開園されました。式典には、警察長官ファハトナ・マーフィー(Fachtna Murphy)氏、現職および退職したアイルランド警察隊員、そして名前が刻まれている方々のご遺族が出席しました。】「チェスター・ビーティー図書館(Chester Beatty Library)」への案内看板。・ダブリン城の敷地内にある有名な博物館・図書館。・世界中から集められた貴重な写本、絵画、書籍、美術品などが所蔵されています。・特にアジア・中東・ヨーロッパの宗教・芸術資料が充実。FREE ADMISSION(入場無料)上部の赤い円内に「CEAD ISTEACH SAOR IN AISCE」(アイルランド語)と英語で併記。Museum of treasures from across the world ・下部には「世界中の宝物の博物館」というキャッチフレーズ。 ・アイルランド語表記: Músaem lán le seoda ó chian is ó chóngar ・Chester Beatty(チェスター・ビーティ図書館) はこの看板から 150メートル先の左方向 と。別のDublin Castle・ダブリン城案内図をネットから。「DUBH LINN GARDEND(ダブ・リン庭園)から「Capel Royal」に向かって引き返すと 「Capel Royal」への入口手前には写真展示が。 「チャペル・ロイヤル(The Chapel Royal)」 の案内。チャペル・ロイヤル(The Chapel Royal, Dublin Castle)の正面入口上部にあるステンドグラス部分を真正面から捉えたものゴシック様式のステンドグラス(王冠とハープの紋章)。左側にアイルランドの象徴であるアイリッシュ・ハープ(王冠付き)。右側には、イングランドの薔薇、スコットランドのアザミ、アイルランドのシャムロックを組み合わせたロイヤル・ユナイト・シンボル。この構図はまさに王政下のアイルランド統治時代の象徴。アイルランドの著名な宗教指導者「ジェームズ・アッシャー(James Ussher)」大主教。堂内とステンドグラスの写真。ステンドグラスをネットから。ダブリン城内のチャペル・ロイヤル(Chapel Royal, Dublin Castle)に設置されていた「イギリス王室の紋章(Royal Coat of Arms of the United Kingdom)」の彫刻の写真。これもチャペル・ロイヤル(The Chapel Royal at Dublin Castle)の内観正面奥に重厚な装飾が施されたパイプオルガンがあり、礼拝や式典に使われた重要な楽器。この絵は、1850年頃に開催されたクラレンドン卿による公式舞踏会(Viceroy Clarendon's State Ball about 1850)を描いたものです。舞台はおそらくダブリン城(Dublin Castle)内のセント・パトリック・ホール(St Patrick's Hall)で、当時のアイルランド副王(Viceroy)によって主催された華やかな社交の場が再現されています。この舞踏会の時期は、ちょうど大飢饉後のアイルランド(Great Famine, 1845–1852)にあたり、飢餓と貧困が深刻な中で、上流階級の生活は華やかに続いていたことへの批判もありました。「State Apartments」の内側外壁は補修作業中であった。ズームして。赤レンガ?雨樋の補修であろうか? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.12
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その75):Dublin市内散策(14/)・ダブリン城(Dublin Castle)-1
Christ Church Cathedral・クライストチャーチ大聖堂を後にして、東方向に歩く。ダブリン城(Dublin Castle) の敷地内、アッパー・ヤード(Upper Yard) の入り口にある石造りの門が現れた。ダブリン城は13世紀初頭(1204年頃)、イングランド王ジョンの命で建設が始まった。城は防衛拠点として機能するため、四方に高い石壁と堀(moat)が巡らされていた。この堀は、ポドル川(River Poddle)の流れを取り込み、水堀(水のある堀)として利用されていた。実際、ポドル川は現在も地下を流れており、城の下を通過しているのだ と。この太鼓橋の下は現在埋め立てられているが、元々は堀や防衛溝が存在していた空間である と。ダブリン城(Dublin Castle)内の中庭(Upper Yard)に入る石造アーチ門と橋.石造アーチ門は、Upper Yard(アッパー・ヤード)と呼ばれる中庭への主要な出入口の1つ。ダブリン城(Dublin Castle)の配置案内図。近づいて。1 Dublin Castle Ticket Office チケット売場(入口案内所)2 State Apartments 国家行事用の部屋群(一般見学可)3 Viking & Medieval Excavation ヴァイキングと中世遺構の展示エリア4 Chapel Royal 礼拝堂(歴代総督の使用)5 Record Tower 城で最も古い塔(13世紀)6 Dubh Linn Garden 城裏手の公園エリア7 Coach House Gallery アートギャラリー(展示あり)8 Terrace Café カフェスペース9 Hibernia Conference Centre ハイバーニア会議センター (会議や公式イベントに使用される施設)10 Bedford Hall ベッドフォード・ホール (かつてのバンケット会場、現在も多目的に使用)11 Printworks Conference Centre プリントワークス会議センター (大規模イベントや展示会、会議等に対応)12 Chester Beatty チェスター・ビーティ図書館・美術館 (貴重な写本・東西の美術コレクションを所蔵)13 Revenue Museum 税務博物館(Revenue Museum) (アイルランドの税制の歴史を紹介)14 Revenue Commissioners 税務当局(国税庁本部の一部) (事務所棟)15 Assay Office 貴金属検査局(アッセイ・オフィス) (金・銀などの純度を検査・認定)16 Garda Museum ガルダ博物館(警察博物館) (アイルランド警察の歴史・資料を展示)ダブリン城(Dublin Castle)内の「アッパー・ヤード(Upper Yard)」と呼ばれる中庭の様子。写真に見えるのは 「アーチ門(Main Archway)」の内側から見た建物中庭を囲むこの一連の建物群は、18世紀以降に整備されたジョージ王朝様式の公共建築であり、左側の建物は旧軍事用途、右側の建物はかつての「副王(Lord Lieutenant)」の公邸や政庁部門であった。「アーチ門」と「八角形の時計塔付き建物・Bedford Tower(ベッドフォード・タワー)」。 ダブリン城(Dublin Castle)内の「アーチ門(Main Gate/Civic Sword Gate)」を北側(中庭側)から南方向に見る。この門は、Upper Yard(アッパー・ヤード)と外部をつなぐ主門であり、通常「Main Gate」または「Civic Sword Gate」と呼ばれている と。頂上には剣を掲げた人物像が立っていた。通称:「Civic Sword」像。この像は、明確な歴史的人物ではなく、市民権・統治権の象徴(Civic Authority)としての擬人像と考えられている と。主に以下の特徴があるのだと:右手に掲げた長い剣(または槍):「市民の権利と統治の正当性」を象徴(剣に見えるが、 直線的な棒状で槍とも解釈可能)軍装風の服装: 古代ローマ風の軍装スタイル(市民の守護者、都市の防衛)足元のライオンの頭: 「勇気」「権威」「支配力」の象徴。しばしば国家や権力の 象徴として用いられる頭部の羽根付き兜: 戦士・防衛者の姿を表す(ローマ兵のヘルメット風)設置場所: 旧城門の上、通行者の頭上に立ち、都市と城の「守護者」を 象徴する役割ダブリン城(Dublin Castle)の中心的構造物のひとつ、「Bedford Tower(ベッドフォード塔/ベッドフォード・タワー)」。建設時期: 1750年代(ジョージアン時代)建築様式: ジョージアン様式+ロココ的装飾を一部含む構造: 八角形の塔身に銅葺きのドーム屋根(緑青により緑色)役割: 18世紀当初:城の兵器庫(Armoury)の一部 現在は儀礼的シンボル塔として保存・公開時計: 東西南北四方に時計文字盤を配置、視認性を高めている ・右手前(白い三角破風の建物): State Apartments(ステート・アパートメンツ)の入口がある建物。 かつては貴族や賓客を迎えるレセプション・エリアとして使用された。現在は博物館施設。・右側中央(国旗の掲揚): ガバメント棟(Government Buildings)一部。 国旗(アイルランド三色旗)が掲げられており、迎賓施設の一部でもある。・左奥に伸びる建物 :19世紀以降に再建・改修された行政系建物。同一様式のアーケードが続くことから、 ジョージアン建築の統一感が見られる。・背後に見える塔状の建物: Bedford Tower(時計塔)の一部がクレーンの左下に少しだけ写っていた。こちらは「パレス・ストリート門(Palace Street Gate)」この門は「Palace Street Gate」で、ダブリン城の北東側に位置し、現在のシティ・ホール(Dublin City Hall)近く。門の上には、「正義の女神(Lady Justice)」の像が立っていた。上部には、天秤と剣を持った「正義の女神(Lady Justice)」の像が載っており、西洋では裁判・法・秩序の象徴。他の門と異なり、この女神像は目隠しをしていない(blindfoldなし)点が特徴 と。 ズームして。天秤(Scales): 公平さ、証拠の重さを量る剣(Sword): 正義の厳しさ、裁きの権力目隠し(Blindfold): 偏見のない裁き(※この像は目隠しをしていません)このポスターは、犯人検挙のために発行されたもので、当時の懸賞金£1,000は非常に高額(現在の貨幣価値で約13万ポンド=約2,600万円以上)に相当この案内板は、Bedford Tower(ベッドフォード塔)に関する情報を伝えていた。 「DUBLIN METROPOLITAN POLICE.£1,000 REWARDSTOLENFrom a Safe in the Office of Arms, Dublin Castle, during the past month, supposedby means of a false key.Bedford Tower, 1761 ADThis is the centrepiece of the north side of the Upper Courtyard, which is one of the most beautiful architectural compositions in Dublin.It was occupied successively by the Dean of the Chapel Royal, the Second Secretary, the Master of Ceremonies and the Viceroy’s aide-de-camps. The balcony was used by State musicians.In 1907 the diamond Chains of Office of the Knights of St. Patrick were stolenfrom the ground-floor library of the then Office of Arms.The mystery of what became known as the missing‘Irish Crown Jewels’ has neverbeen solved.This is now the Bedford Hall Suite and Castle Hall conference facilities.【ダブリン首都警察懸賞金 1,000ポンド盗難ダブリン城内の紋章官事務所にある金庫から、過去1か月以内に盗まれた。偽の鍵を使ったと考えられる。ベッドフォード・タワー(1761年建造)ここはアッパー・コートヤード(上の中庭)の北側の中心に位置し、ダブリンでも最も美しい建築構成の一つとされています。この塔は、チャペル・ロイヤル(王室礼拝堂)付きの司祭、第二書記官、儀典長、副王の副官らが順に使用していました。バルコニーは国家音楽家たち(State musicians)が使用していた場所でもあります。1907年には、聖パトリック騎士団(Knights of St. Patrick)のダイヤモンド装飾の官職チェーンが、当時の紋章官事務所(Office of Arms)の1階図書室から盗まれました。この事件は後に「アイルランドの王冠の宝石(Irish Crown Jewels)失踪事件」として知られるようになりましたが、いまだに解決されていません。現在は「ベッドフォード・ホール・スイート(Bedford Hall Suite)」および「キャッスル・ホール(Castle Hall)」という会議施設として使用されています。】「チャペル・ロイヤル(Chapel Royal)」。ダブリン城構内に位置する、19世紀初頭・1814年に建てられた英国国教会様式の礼拝堂。チャペル・ロイヤルは、ベッドフォード・タワー(Bedford Tower)やステート・アパートメントと並び、アッパー・ヤード(Upper Courtyard)を構成する代表的建築のひとつ。ダブリン城の北東側に位置するCork Hill Gate(コーク・ヒル門)を外側から。外へ出るとすぐに Dublin City Hall(ダブリン市庁舎) や Lord Edward Street に通じていた。「Cork Hill Gate」と「Civic Sword Gate」は、場所は同一ですが、呼び名や意味合いが時代や文脈によって異なるのだと。Cork Hill Gate:現代の公式名称 城の北東側の出入口。 Cork Hill通り(市庁舎 City Hall 側)に面しています。Civic Sword Gate:歴史的・儀礼的文脈での名称(18〜19世紀) ダブリン市長が「市の剣(Civic Sword)」を手にしてこの門を通る儀式に ちなんだ呼び名。王権への忠誠を表す儀式の場でした。この案内板は、ダブリン城(Dublin Castle)の見学ツアーに関する情報、料金を示していた。「WELCOME TO DUBLIN CASTLE,a place where Irish history has been made for over 1,000 years.On this site, kings and queens have held court, Irish presidents have been sworn intooffice and old orders have been swept away through rebellion and revolution.Once the centre of British rule in Ireland, from 1204 to 1922, the Castle is now the setting for some of the Irish nation's most important state ceremonies.Come with us on a tour through time, from a hidden underground excavationto the magnificent Chapel Royal and State Apartments, from British rule toIrish independence and beyond.」 【ダブリン城へようこそここは、アイルランドの歴史が1000年以上にわたり刻まれてきた場所です。この場所では、歴代の王や女王が裁判を開き、アイルランド大統領たちが就任の宣誓を行い、そして旧体制が反乱と革命によって一掃されてきました。ダブリン城は、1204年から1922年までアイルランドにおけるイギリス統治の中心地であり、現在ではアイルランド国家における最も重要な国家儀式の舞台となっています。ぜひ私たちと共に、時を超えたツアーへお出かけください。地下に隠された発掘跡から壮麗なチャペル・ロイヤルや国家の間(State Apartments)へと進み、イギリス支配の時代からアイルランド独立、そしてその先へと、歴史をたどる旅が始まります。】ダブリン城(Dublin Castle)の「State Apartments(国家の間)」の正面玄関この建物は、Upper Courtyard(上の中庭/アッパー・コートヤード)の東側に位置。ダブリン城の見学コースでは最も主要な建物の一つで、次のような重要な部屋へ通じていた。・Throne Room(玉座の間)・St. Patrick’s Hall(セント・パトリックス・ホール)・State Drawing Room(控えの間) などこの建物内の部屋では、かつてイギリス統治下のアイルランド総督(Lord Lieutenant)が国家行事を行っていたほか、現在も大統領就任式などの重要な儀式に使われている。現在はガイドツアーやセルフツアーで内部を見学することができ、アイルランドの政治的・歴史的変遷を伝える展示空間として機能しているとのこと。ダブリン城(Dublin Castle)Upper Courtyard(アッパー・コートヤード/上の中庭)の 北側と東側を。1.中央左側の三角破風(ペディメント)を持つ建物 ・Bedford Hall / Castle Hall(旧Office of Arms)) ・ここはかつてアイルランド騎士団(Knights of St. Patrick)のためのダイヤモンドの 「チェーン・オブ・オフィス(Chains of Office)」が保管されていた場所であり、1907年に アイルランド王冠宝石”(Irish Crown Jewels)が盗難された場所 と。2.右手の角の建物(オレンジ色系の壁、窓が多い) ・State Apartments(ステート・アパートメンツ)への一部 ・議場・レセプション用の国家的施設が入っており、右端に見えるのは「Civic Sword Gate」 (市民の剣の門)。3.最も右端の石造アーチ門: ・Civic Sword Gate または Ship Street Gate ・城の南側へ通じる主要な門。 ・上部に剣を掲げる像(JusticeまたはFortitudeとされる像)が立っているのが特徴。「WelcomeVISITOR OPTIONSA Guided Tour option includes a visit to the Underground Medieval Section, the Chapel Royal and 18th century State Apartments. (1 hour)A Self-Guided visit is available to the State Apartments (30 minutes approximately)ORVisitors can also choose to view the Medieval Section and Chapel Royal by Guided Tourand then self-guide through the State Apartments. (Full Price Ticket applies)」 The rest is omittedOPENING HOURSDaily: 09:45 – 17:45Last admission: 17:15】【ようこそ見学オプション・ガイド付きツアー には、以下の見学が含まれます: 地下の中世セクション、チャペル・ロイヤル(王室礼拝堂)、18世紀のステート・ アパートメント。 所要時間:約1時間・セルフガイド(自由見学) の場合は、ステート・アパートメントの見学のみ(約30分) または・ガイド付きで中世セクションとチャペル・ロイヤルを見学し、その後にセルフガイドで ステート・アパートメントを見学することも可能です(この場合もフルチケット料金が 適用されます)】途中 略・開館時間 毎日:09:45 ~ 17:45 最終入場:17:15】「The State Apartments1680–1830 ADFormerly the residential and ceremonial quarters of the Viceroys (Deputies of the British Monarch) and the Viceregal Court, and the focus of fashionable social life, they are nowthe most important ceremonial rooms in Ireland.The State Apartments include the former State Bedrooms, the Drawing and ThroneRooms, the Portrait Gallery, St. Patrick’s Hall and George’s Hall.St. Patrick’s Hall, the venue for prestigious State functions, including the inauguration ofthe Irish President, was last used for such by British monarchs in 1911.Upon her first state visit to Ireland, Queen Elizabeth II spoke in St. Patrick’s Hall in 2011.」 【ステート・アパートメント(国家公式室)1680~1830年かつては英国王の代理である副王(ヴァイスロイ)とその宮廷が住まいとし、また格式高い社交の中心でもあった空間で、現在ではアイルランドで最も重要な儀式用の部屋群となっています。ステート・アパートメントには、かつての王室用寝室、謁見室、玉座の間、肖像画ギャラリー、セント・パトリックス・ホール、ジョージ・ホールが含まれています。セント・パトリックス・ホールは、アイルランド大統領の就任式など、格式ある国家行事の会場として使用されており、1911年にイギリス王室が最後に使用した記録があります。2011年、エリザベス2世女王が初めてアイルランドを国賓として訪れた際も、このホールでスピーチを行いました。】「クロック・タワー(Clock Tower)」を中心とした「ベッドフォード・タワー(Bedford Tower)」 ダブリン城の「Civic Sword Gate(シヴィック・ソード・ゲート)/Cork Hill Gate」の上に設置されていた「正義の女神(Lady Justice)」を再び。ダブリン城の「Upper Yard(上の中庭)」にある門の上に設置されているこの像は、勇気(Fortitude)または武勇(Valour)を象徴する寓意像(アレゴリカル・スタチュー)。時計塔(Clock Tower)のクローズアップ。Upper Yard(アッパー・ヤード/上の中庭)の北側中央に位置する建物の上部。中世のダブリン城(Medieval Dublin Castle)に関する解説パネル。Medieval Dublin CastleCaisleán Bhaile Átha Cliath sna Meánaoiseanna「This Great Courtyard corresponds closely with the almost rectangular Castle establishedby King John of England in 1204 AD.It became the most important fortification in Ireland and functioned as the seat of English rule and the centre of military, political and social affairs. At various timesit housed the Chief Governors of Ireland, Treasury, War Office, Privy Council, Courts of Justice and the Parliament. It remained in continuous occupation and wasadapted to suit changing requirements, in particular following the great fire of 1684when it became a palace rather than a fortress.It was here, on 16th January 1922, that Michael Collins received the handoveron behalf of the new Irish Government.」 【中世のダブリン城(アイルランド語:Caisleán Bhaile Átha Cliath sna Meánaoiseanna)この「グレート・コートヤード(大中庭)」は、1204年にイングランド王ジョンによって築かれたほぼ長方形の城郭とよく一致しています。この場所は、アイルランドで最も重要な防衛施設となり、イングランド統治の本拠地として機能しました。また、軍事・政治・社会活動の中心地でもありました。さまざまな時期に、アイルランド総督、財務省、陸軍省、枢密院、裁判所、議会がここに置かれました。この城は長年にわたり使用され続け、特に1684年の大火の後は、要塞ではなく宮殿として改修されていきました。ここで1922年1月16日、マイケル・コリンズが新しいアイルランド政府を代表して城の引き渡しを受けました。ステート・アパートメント(State Apartments)は南側の建物群を占め、カンファレンス・センター(Conference Centre)は西側の横棟および北側の棟を、税務署(Revenue Commissioners)は北東隅にある旧アイルランド官房長官室の周辺に配置されています。】「グレート・コートヤード(Great Courtyard)」 を東側から。左側のゴシック建築:チャペル・ロイヤル(Chapel Royal)・19世紀初頭(1807〜1814年)に建設されたゴシック・リヴァイヴァル様式の礼拝堂。・英国支配時代、アイルランド副王や英国王族の礼拝所として使われました。・建物の外観は、尖塔型の装飾やランセット窓(尖りアーチ窓)などが特徴。現在では展示・コンサート・ガイドツアーの場として使用されることもあります。右側の円塔:レコード・タワー(Record Tower)・13世紀のオリジナルの防御塔で、現存する唯一の中世部分。・ダブリン城がもともと要塞(fortress)だった頃の面影を残す構造。・厚い石壁と小窓、防御用の城壁構造を備えています。名の通り、かつては重要文書の保管所(記録保管塔)として使用されていました。レコード・タワー(Record Tower)・建設年代:1204年以降、13世紀初頭・建築様式:ノルマン様式(円形石造塔、防御構造)・特徴: ・厚い石壁とわずかな小窓(攻撃に備えた設計) ・上部にある櫓(マシュキュレーション風の装飾)は、矢や石を落とす防御構造の名残を 模している ・現在も原形を保つ、ダブリン城で唯一残る中世要塞部分ダブリン城(Dublin Castle)の外壁に設置された案内パネルの一部で、中央右側に見えるのが「レコード・タワー(Record Tower)」「The Record Tower is one of the oldest surviving parts of Dublin Castle, and one of the oldest buildings in the city of Dublin.It was constructed between and 1228 and was the largest of four round towers that formed the corners of the medieval castle of Dublin. Over the centuries, two of thesetowers disappeared entirely while a third, the Bermingham Tower, was rebuilt in the 1770s andcan be seen from the Castle’s Dubh Linn Gardens today.During its 800 years, the Record Tower served as a medieval wardrobe, where garmentsand other precious items were stored. It became a prison in the late 1500s and remainedin use until the 1700s. The upper rooms were refurbished for the storage of public records, giving the tower its name. The base of the tower housed prisoners awaiting execution, including notable Irish rebels Henry and John Sheares in 1798 and Robert Emmet in 1803.Between 1811 and 1813, an extra floor was added to the Tower and it was turned into a repository for important state papers and documents. It was at this time that it becameknown as the 'Record Tower'. It continued to fulfil this purpose up until the early 1990s, when the records were moved to the National Archives of Ireland.In conjunction with Fáilte Ireland, the Office of Public Works has embarked on a majorproject of conservation and redevelopment of the Record Tower. This building has stood as silent witness to the nation's history for 800 years, as it unfolded in and around thehistoric complex of Dublin Castle. It will soon reopen to the public and its fascinating stories told once more.」 【レコード・タワー(記録の塔)は、ダブリン城に現存する最古の部分の一つであり、ダブリン市内でも最も古い建物の一つです。この塔は、1204年から1228年の間に建設され、ダブリンの中世の城を形作っていた四隅の円塔の中で最大のものでした。数世紀のうちに、これら四つの塔のうち二つは完全に失われ、三つ目の塔であるバーミンガム・タワーは1770年代に再建され、現在もダブリン城のダブリン庭園(Dubh Linn Gardens)からその姿を望むことができます。800年の歴史の中で、レコード・タワーはかつて中世の「ワードローブ(衣装部屋)」として使われ、衣類や貴重品の保管場所とされていました。16世紀後半には牢獄として利用されるようになり、18世紀までその用途が続きました。その後、塔の上層部は公文書の保管のために改装され、これにより塔は「レコード・タワー(記録の塔)」と呼ばれるようになります。塔の下層部分には、死刑を待つ囚人たちが収容されており、中には1798年の反乱に関与したヘンリーとジョン・シアーズ兄弟や、1803年の反乱指導者ロバート・エメットといった著名なアイルランド人反逆者たちも含まれていました。1811年から1813年にかけて、塔にはもう一階が増築され、国家の重要な文書や記録の保管庫へと改修されました。この時期に正式に「レコード・タワー」と呼ばれるようになり、1990年代初頭までその役割を果たしていました。その後、保管されていた記録はアイルランド国立公文書館へと移されました。現在、Fáilte Ireland(フォールチャ・アイルランド)との協力のもと、公共事業局(Office of Public Works)は、この塔の保存と再開発のための大規模プロジェクトに着手しています。この建物は、800年にわたり、ダブリン城という歴史的複合施設の中で展開されてきたアイルランドの歴史を静かに見守ってきた証人であり、間もなく再び一般公開され、その魅力的な物語が人々に語られることでしょう。】チャペル・ロイヤル(Chapel Royal)の側面(北面または西面)を捉えたもの。背景右奥にはレコード・タワー(Record Tower)の一部も見えていた。「The Chapel RoyalThis Chapel was designed by Francis Johnston and opened by Lord Lieutenant Whitworth at Christmas 1814. It replaced an earlier church.It is an exceptional example of Gothic Revival architecture and functioned as the King's Chapel in Ireland as well as that of the Viceroy, his household and staff.The oak galleries and stained-glass chancel windows display the coats of arms of successive Lord Lieutenants and senior Dublin Castle officials, which were painted/carved either during their terms of office or afterwards.The first guest preacher was Thomas Lewis O'Beirne, the Bishop of Meath, and the lastwas the Bishop of Tuam, John Orr, in 1922, just before the Lord Lieutenant of Ireland left.」 【チャペル・ロイヤルこの礼拝堂はフランシス・ジョンストンによって設計され、1814年のクリスマスに総督ホイットワース卿によって開かれました。それ以前の教会に代わるものでした。この建物はゴシック・リヴァイヴァル建築の傑出した例であり、アイルランドにおける国王の礼拝堂として、また総督とその家族や職員の礼拝堂として機能していました。オーク材のギャラリー(回廊)やステンドグラスの内陣窓には、代々のアイルランド総督やダブリン城の高官たちの紋章が描かれ/彫刻されています。これらは彼らの在任中または退任後に設置されました。最初のゲスト説教者は ミーズ司教トマス・ルイス・オバーンであり、最後の説教者は トゥアム司教ジョン・オールで、彼が説教したのは1922年、アイルランド総督が退任する直前のことでした。】「チャペル・ロイヤル(Chapel Royal)」の正面(西面)入口。建物名:Chapel Royal(王室礼拝堂)竣工年:1814年(クリスマスに落成)設計者:フランシス・ジョンストン(Francis Johnston)建築様式:ゴシック・リヴァイヴァル様式(Gothic Revival)用途:英国統治下におけるアイルランド総督とその家族・職員のための礼拝堂。上部に城郭風のギザギザ(=クレネレーション)が施されており、防御的な中世の城を模したデザイン。「チャペル・ロイヤル(Chapel Royal)」の南面。左端:レコード・タワー(1204〜1228年築)中央〜右:チャペル・ロイヤル(1814年完成)この南面はダブリン城の「中庭(Upper Yard)」側に面していた。ダブリン城(Dublin Castle)の西面を南西方向から。写真中央から左へレコード・タワー(Record Tower) 1204〜1228年頃に建てられた、ダブリン城に現存する最古の部分。中世の円形防御塔で、19世紀には記録文書保管庫に転用され「Record Tower」と呼ばれるようになりました。 チャペル・ロイヤル(Chapel Royal) ネオ・ゴシック様式で1814年に完成した礼拝堂。レコード・タワーの右隣に連なる尖塔のある」壁面群がそれにあたります。 上級裁判所棟(Upper Castle Yardの北西翼) レコード・タワーに接続する形で左側に見える古典主義的ファサードの建物。18世紀以降の再建で、国家の行政機能を担ってきました。ダブリン城(Dublin Castle)の構内案内バナー。Gairdíní Dubh LinnDubh Linn Gardens ダブ・リン庭園(Dubh Linn ガーデンズ)Músaem Chester BeattyChester Beatty Museum チェスター・ビーティー図書館・美術館ダブリン城敷地内で開催されている展覧会の案内看板「The Fine Art of TextileContemporary artists explore the expressive potential of an ancient art formFringe Collective & Guests&The Wild Donegal Tweed ProjectCurated by Judith CunninghamFRINGE COLLECTIVE:Amanda Jane Graham ・ Bernie Leahy ・ Carmel Brennan ・ Jennifer Trouton ・ Sandra DeeryGUEST ARTISTS:Alice Maher ・ Michael Cullen ・ Orla Kaminska ・ Paula Stokes ・ Shani Rhys James06.06.2025 – 24.08.2025Chapel Royal, Dublin CastleMonday to Saturday: 10am – 5pmSunday & Bank Holidays: 1pm – 5pmLast entry: 4:45pmFree Admission」 【テキスタイルの美術— 現代アーティストが、古来の芸術形式の表現的な可能性を探る —フリンジ・コレクティブ & 招待作家たち&ワイルド・ドニゴール・ツイード・プロジェクトキュレーター:ジュディス・カニンガムフリンジ・コレクティブの作家アマンダ・ジェーン・グラハムバーニー・リーヒーカーメル・ブレナンジェニファー・トラウトンサンドラ・ディーリー招待作家アリス・マハーマイケル・カレンオルラ・カミンスカポーラ・ストークスシャーニ・リース・ジェームズ会期: 2025年6月6日~8月24日会場: ダブリン城 チャペル・ロイヤル ・月〜土曜:午前10時〜午後5時 ・日曜・祝日:午後1時〜午後5時 ・最終入場:午後4時45分 ・入場無料】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.11
コメント(0)
-

我が家からの夏の夕焼け
この日は8月29日(金)の18:30。我が家の近くからの西に空の夕焼けです。出かけていた妻が帰宅し、西の空が美しく染まっていると。慌ててカメラを持って外に出る。富士山の姿も確認できた。今年の夏の気温は毎日35度超えが続くのであった。さらに湿度が高い日が続いているのであった。つまり大気中の水蒸気が多いので(たとえ湿度の数値は低くても、気温が高ければ大気の飽和水蒸気量が上がるので水分の絶対量は多くなる)、それだけ赤以外の光が散乱されやすく、最も波長の長い赤い光だけが残る。その結果として、雲が真っ赤に染まる美しい夕焼けが生じやすくなるのである。単純に、夏こそ夕焼けが最も美しいと感じているのである。これこそが最大の理由なのです。夕焼けは俳句では秋ではなく夏の季語。昔の俳人たちが、ちゃんと観察していたからこそでしょう。もう一つのポイントは、夏には西空だけでない、他の方位の雲までが染まるチョット大げさですが「全方位の夕焼け」が見られるのです。我が家の周辺は、残念ながら水田や池はありませんが、あれば夕焼けに染まる水面の光景も見えるはずです。夏場の夕焼けは赤が強く茜色に染まることが多いですが、冬場は黄金色の夕焼けがよく見られます。なぜこのように見え方が変わるのでしょうか。繰り返しになりますが「夏と冬の夕焼けの色が違って見えるのは、空気中に含まれる水蒸気の量が関係しています。空気中の水蒸気が多いと、波長の短い光は散乱してしまい、波長の長い赤色光が散乱されずに目に届きやすくなります。そのため、夏の夕焼けは冬よりもいっそう赤色が強まって見えるのです。とくに台風の接近前や通過後などは、空気中の水蒸気がより一層多いので、赤色が濃くなった燃えるような夕焼けや、不気味とも感じられる紫色に近い夕焼けが見られることもあります。一方、空気が乾燥して水蒸気が少ない冬の夕焼けは、赤色に比べて波長が短い黄色やオレンジ色の光も散乱されずに届きやすくなります」とネットから。富士山の姿をズームして。夏の夕焼けの主な特徴は・強い赤色やピンク色、紫色: 夏の空気は水蒸気量が多いため、太陽光が届くまでに波長の短い光が散乱され、波長の長い 赤い光が残りやすくなります。このため、夏は特に赤が強調され、ピンク色や不気味な紫色に 近い色合いになることもあります。・雲が赤く染まる: 湿度が高く水蒸気が多いと、その水蒸気によって光が散乱され、雲が赤く染まります。 そのため、夏には雲が幻想的に彩られる夕焼けが多く見られます。燃えるような夕焼け: 特に大気中の水蒸気が多い台風接近前や通過後などでは、色がさらに濃くなり、燃えるような 美しい夕焼けが見られることがあります。・美しさの条件 適度な雲: 夕焼けを赤く染めるには、ある程度の雲が必要不可欠。 水蒸気とチリ・埃: 夏の高い湿度は水蒸気量を増やす要因。 水蒸気に加えて、空気中の塵や埃も光を散乱させることで、空全体がふんわりと赤く染まる のを助けますじわじわと赤い色が薄くなって。そして東の空には。そして18:32。「夏の夕」、「夏の宵」を楽しんだのであった。 一般的な「夕焼けの言い換え」をネットで調べてみました。・夕陽(ゆうひ)/ 夕日(ゆうひ):太陽が沈む際に空が赤く見える現象そのものを指します。・落日(らくじつ):地平線に沈む太陽、日没を意味します。・残陽(ざんよう)/ 斜陽(しゃよう):沈みゆく夕日、あるいは夕暮れの太陽を指します。・逢魔が時(おうまがとき) / 黄昏(たそがれ):日が暮れて空が薄暗くなる頃を指し、 詩的な表現としても使われます。 と。 ・・・おわり・・・
2025.09.10
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その74):Dublin市内散策(13/)・Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂)4/4
Christ Church Cathedral(クライスト・チャーチ大聖堂)クリプト内に展示されている中世の墓石(tomb slab)の一つ。・形状:頭部側がやや広く、足元側に向かって細くなる典型的な中世の 石棺蓋(grave cover)の形。・彫刻: ・上部中央に顔(おそらく被葬者、または聖職者を示す)。 ・中央に長い茎を持つ装飾的な十字(クロス)文様。四つ葉や花弁に似た意匠は、 14〜15世紀頃のゴシック様式で見られるタイプ。・素材:地元の石灰岩(limestone)と考えられる と。先ほど、案内があった「The Listening Bench」の案内パネル。 「Christ Church Cathedral DublinThe Listening BenchWelcome to the Listening Bench where you can hear a selection of Christ Church Storiesabout the life of the cathedral today and some of the people who are a part of it.Please pick up a handset to hear instructions.This bench is wheelchair accessible and you can listen to the interviews withyour hearing aid via the induction hand-piece.1.Màirin Johnston, local historian and author2.Ellie Kisyombe, founder of Our Table3.Canon Roy Byrne, Precentor4.Cherinet Ayele, musician5.Louisa Santoro, CEO, The Mendicity Institute6.Maureen Reid, Sacristan」 【クライスト・チャーチ大聖堂(ダブリン)リスニング・ベンチようこそ「リスニング・ベンチ」へ。ここでは、クライスト・チャーチ物語の中から、大聖堂の今日の活動や、それに関わる人々についてのセレクションをお聞きいただけます。指示を聞くには、受話器を手に取ってください。このベンチは車椅子で利用可能で、補聴器をお使いの方は誘導用ハンドピースを介してインタビューをお聞きいただけます。1.メーリン・ジョンストン(地元の歴史家・著者)2.エリー・キショムベ(「アワ・テーブル」創設者)3.キャノン・ロイ・バーン(礼拝主任)4.チェリネット・アエル(音楽家)5.ルイーザ・サントロ(メンディシティ・インスティテュートCEO)6.モーリーン・リード(聖具係)】「The Listening Bench」。 操作部。・多言語対応: ・英語(English) ・ドイツ語(Deutsch) ・フランス語(Français) ・スペイン語(Español) ・イタリア語(Italiano) → 上部のボタンで言語を選択できます。・ 操作方法: ・選択ボタンを押すと、その言語で案内音声やインタビューが再生されます。 ・右側のハンドセット(受話器)を持ち上げて耳に当てて聞きます。 ・上部には補聴器用の誘導ループ受信ポイント(白い楕円形部分)もあります。「Treasures of Christ Church」展示コーナーの金メッキ銀器(gilt silver plate)コレクションの一部.廻り込んで。「The 1777 Plate CollectionFollowing the theft of the "1684" plate in 1777, the dean and chapter purchased a new set of communion plate from Messrs Pickett & Rundell, London at a cost of nearly £500 (Irish pounds). It was made by James Young, a London goldsmith and comprised two chalices with matching covers, two patens, an oval alms dish and a pair of candlesticks.The large oval alms dish has a reeded border with bands of fruit, flowers and foliage and the centre panel shows a depiction of the Last Supper. The chalices are highly decorated with the sacred monogram "IHS" and stand on circular feet. The two plates, possibly designed as patens, also bear the sacred monogram "IHS" within a chased sunburst motif.Following the purchase of the plate some of the stolen "1683" plate was recovered. The 1777 plate was used daily until replaced by a set of plate presented by Henry Roe, the whisky distiller who funded the restoration of Christ Church, in 1878. The candlesticks from the 1777 suite remained in use into the 1950s. In 1951, a single candlestick and the large alms dish were given on loan for the Festival of Britain and were held in the Lincoln Usher Art Gallery. They were described by one commentator as being "probably the most beautiful eighteenth-century church silver in the British Isles".」 【1777年の聖餐用銀器コレクション1777年、「1684年製」の聖餐用銀器が盗難に遭った後、学長と参事会はロンドンのPickett & Rundell社から新しい聖餐用銀器セットを購入しました。費用はほぼ500アイリッシュ・ポンドで、製作はロンドンの金細工師ジェームズ・ヤングによるものです。このセットには、蓋付きの聖杯2つ、パテン(パンを置く皿)2枚、楕円形の施し皿1枚、燭台2基が含まれていました。大型楕円形の施し皿は、果物や花、葉の帯状装飾を持つ縁取りがあり、中央パネルには「最後の晩餐」が描かれています。聖杯には「IHS」の聖なるモノグラムが高度に装飾され、円形の台座に立っています。パテンと思われる2枚の皿にも、放射状の光輪模様の中に「IHS」のモノグラムが刻まれています。この購入後、盗まれていた「1683年製」の銀器の一部が回収されました。1777年の銀器は、1878年にクリスト・チャーチ修復の資金を提供したウイスキー蒸留業者ヘンリー・ローから寄贈された銀器セットに置き換えられるまで、日常的に使用されました。1777年セットの燭台は1950年代まで使用され続けました。1951年には、このセットの燭台1基と大型施し皿が「フェスティバル・オブ・ブリテン」に貸し出され、リンカーン・アッシャー美術館に展示されました。ある評論家はこれらを「おそらく英国諸島で最も美しい18世紀の教会用銀器」と評しました。】「The 1684 Plate CollectionIn December 1683, the dean and chapter of Christ Church purchased this set of communion plate to replace an earlier set which they sold to St Canice’s Cathedral, Kilkenny. The “new” plate included four silver-gilt chalices and patens, a pair of silver-gilt candlesticks, two flagons and two alms dishes. The maker was Robert Smythier, a London goldsmith and the donor was John Parry, dean of Christ Church (1666–1677) and bishop of Ossory (1672–1677).On 9 January 1689, the cathedral chapter decided to move the plate and records from the cathedral to safety in England due to political instability in Ireland.The records moved but the plate was buried under the coffin of Thomas Cartwright, bishop of Chester, who had come to Dublin with King James II. The bishop died whilstin Dublin and was buried in the choir of Christ Church on 15 April 1689.Following the Battle of the Boyne in 1690, the plate was recovered and returned to daily use. In 1777, the plate was stolen but the pieces on display here were later recovered. The dean and chapter ordered that the recovered plate should be kept securein the cathedral’s iron chest in a vault. Some of the recovered pieces of plate were damaged in the theft and were repaired by the goldsmith William Hughes.」 【1684年の聖餐用銀器コレクション1683年12月、クライスト・チャーチの学長と参事会は、それまで使用していた古い聖餐用銀器セットをキルケニーの聖カニス大聖堂に売却し、その代わりとしてこの新しいセットを購入しました。この「新しい」銀器セットには、金鍍金の聖杯とパテン4組、金鍍金の燭台1対、」大型ピッチャー(フラゴン)2個、施し皿(アルムズ・ディッシュ)2枚が含まれていました。製作者はロンドンの金細工師ロバート・スミザイアーで、寄贈者はクライスト・チャーチの学長(1666–1677)でありオソリー司教(1672–1677)でもあったジョン・パリーでした。1689年1月9日、アイルランドの政治的不安定さから、大聖堂参事会はこの銀器と記録文書をイングランドに避難させることを決定しました。記録文書は移送されましたが、銀器はチェスター司教トマス・カートライトの棺の下に埋められました。カートライト司教はジェームズ2世と共にダブリンに来ており、ダブリン滞在中に亡くなり、1689年4月15日にクライスト・チャーチの聖歌隊席に埋葬されました。1690年のボイン川の戦いの後、この銀器は回収され日常使用に戻りました。しかし1777年に再び盗難に遭い、現在展示されているものは後に回収された品です。参事会は、この回収品を大聖堂の金属製チェストに保管するよう命じました。盗難の際に損傷を受けた品もあり、それらは金細工師ウィリアム・ヒューズによって修復されました。】左の展示ケース ・聖杯(chalice):金鍍金のものと銀製のものがあり、聖餐式でワインを供する際に使用。 ・パテン(paten):平皿状で、聖餐式のパン(ホスティア)を載せる。 ・解説パネルにより、製作年代や製作者が特定されている(恐らくロンドンの金細工師によるもの)。右の展示ケース ・フラゴン(flagon):ワインを保存・注ぐ大型の取っ手付きピッチャー。 ・聖杯(chalice)とパテン:同様に聖餐式用。 ・これらは銀製で、彫刻や刻印による装飾が施されている。Church Plate(教会用聖器) コーナーの説明文。「Treasures of Christ ChurchChurch PlatePlate is a general term for objects made of precious metals such as gold and silver, used for the celebration of the Eucharist. The chalice holds the wine and the paten holds the bread.In these display cases you can see a selection of plate used in the cathedral and in other churches across the city of Dublin.In the furthest case, you can see the collection of plate purchased by the cathedral in 1683. In 1689 the plate was buried for over a year under the coffin of Thomas Cartwright, Bishop of Chester, in the Quire upstairs. This was to protect it during aperiod of political unrest.」 【クライスト・チャーチの宝物教会用聖器(Church Plate)「プレート」とは、金や銀などの貴金属で作られた器物の総称で、聖餐式(エウカリスト)のために用いられます。聖杯(チャリス)はワインを、パテンはパンを載せます。これらの展示ケースでは、大聖堂やダブリン市内の他の教会で使われてきた聖器の一部をご覧いただけます。最も奥のケースには、1683年に大聖堂が購入した聖器コレクションがあります。1689年には政治的動乱の時期にそれを守るため、1年以上にわたり、2階クワイア(聖歌隊席)のトーマス・カートライト(チェスター主教)の棺の下に埋められていました。】銀製聖器が並ぶ。写真に見える展示品と説明(パネル内容)1. Paten(パテン) ・製作者: Robert Smythier, London, 1684 ・寄贈者: John Parry(Christ Church 学長 1666–1677、オソリー司教 1672–1677) ・パテンは聖餐式でパンを載せる皿で、通常チャリス(聖杯)とセットで用いられます。2. Chalice(チャリス/聖杯) ・製作者: Robert Smythier, London, 1684 ・同じく John Parry の寄贈品。 ・ワインを入れて聖餐式で用いられる器。3. Flagon(フラゴン/大型の酒器) ・製作者: Robert Smythier, London, 1684 ・同じ寄贈者による一対の一つ。 ・聖餐式でワインを保管・注ぐための大型容器。クリプト内展示解説「Books and Manuscripts(書籍と写本)」セクションの案内「Chapter Act BookAfter the Reformation, Christ Church was reformed as a ‘secular’ cathedral, without amonastery, and the Augustinian prior and canons became the Dean and Chapter.The new Chapter kept records in a series of Chapter Act books. The Chapter Act Bookyou see here is the oldest still surviving and covers the period from 1574–1634.」 【チャプター・アクト・ブック宗教改革後、クライスト・チャーチは修道院を持たない「世俗」大聖堂として改革され、アウグスティノ会の修道院長および参事会員は、学長(ディーン)と参事会(チャプター)となりました。新たな参事会は、一連の「チャプター・アクト・ブック(議事録)」に記録を残しました。ここに展示されているチャプター・アクト・ブックは現存する中で最も古いもので、1574年から1634年までの期間を記録しています。】この筆記体かつ17世紀頃の英語書式は手書きの古文書!?石造りの壁のくぼみ(ニッチ)の中に模型や建築部材の断片が展示されている様子。戦没記念碑のひとつで、上部に碑文パネルと紋章、下部に人物と馬のレリーフが彫られていた。・三角形の頂部:紋章(盾・兜飾り)とリボン状のモットーが刻まれていた。・下部のレリーフ: 軍服を着た騎兵の姿。右腕を前方に指し示すポーズは、突撃または前進命令を象徴するもの。 左手は手綱を握っており、横に馬が並んでいます。馬は軍用馬(騎兵用)を表し、戦場での 役割を強調。 この構図は、19世紀のイギリスやアイルランド出身の騎兵将校記念碑によく見られる様式 と。・中央のレリーフ:氷山と2隻の帆船 → 北極探検を象徴し、航海の舞台となった氷海を表現・艦名:H.M.S. Enterprise と H.M.S. Investigator は、19世紀半ばの英国北極探検船。 ポート・レオポルド(現カナダ・ヌナブト準州)は北極海探検の拠点の一つ。・聖句引用:「I am the resurrection and the life...」(ヨハネ福音書11章25節) → 死後の復活と永遠の命を象徴「IN MEMORY OF HENRY MATHIAS ASSIST. SURGEON OFH.M.S. ENTERPRISE; WHO DEPARTED THIS LIFE JUNE 15th 1849,IN HIS 26th YEAR, AT PORT LEOPOLD, LAT. 74° N.ERECTED BY THE OFFICERS OF THE ARCTIC EXPEDITION COMPOSEDOF H.M. SHIPS "ENTERPRISE" AND "INVESTIGATOR" AS A JUST TRIBUTETO HIS VARIED TALENTS AND GREAT MORAL WORTH."I am the resurrection and the life, saith the Lord.」 【ヘンリー・マシアス追悼 英国海軍艦船「エンタープライズ」乗組の副軍医。 1849年6月15日、北緯74度ポート・レオポルドにて、 享年26歳で逝去。 この記念碑は、北極探検隊(H.M.S.「エンタープライズ」および「インベスティゲーター」)の将校たちにより、 彼の多才な能力と高潔な人格に対する正当な敬意として建立された。 「わたしは復活であり、命である、と主はいわれる】「THIS TABLETSACRED TO THE MEMORY OFGEORGE RENNY M.D.DIRECTOR GENERAL OF THE MEDICAL DEPARTMENTOF THE ARMY IN IRELANDWAS ERECTED BY THEROYAL COLLEGE OF SURGEONSAS A TRIBUTE OF GRATITUDE FOR HIS SERVICESAT THE FOUNDATION OF THE COLLEGEAND OF RESPECT FOR THE CONDUCTDURING A CONNECTION WITH IT WHICH LASTEDFOR SIXTY FOUR YEARSDr RENNY WAS BORN IN SCOTLAND IN 1757AND DIED AT THEROYAL HOSPITAL OF KILMAINHAMIN 1848, AGED 91 YEARS"I will, and with his word, to him faith the Lord.」 【この銘板はアイルランド陸軍 医療部門総監ジョージ・レニー 医学博士 の記憶に捧げる。この銘板は、王立外科医学院が彼の学院創設時の功績と、64年にわたる学院との関わりにおけるその品行を称え、感謝の意を表して建てたものである。レニー博士は1757年、スコットランドに生まれ、1848年、91歳でキルマイナム王立病院にて亡くなった。「わたしは望み、そしてその言葉と共に、主は彼に信仰を授けられた。】ガラスケース内には様々な展示物が。・木製の柄付き器具(左手前) 長い木製の柄に金属製の先端が付いた道具で、穴のある形状から杓子(しゃくし)や 柄杓型の道具、もしくは古代の調理用・儀礼用の器具と考えられます。・動物の小像(中央) 金属製の馬や犬のような形の小型彫像が2体展示されています。 ・馬型は軍馬または儀礼馬の象徴かもしれません。 ・小型犬型はおそらく狩猟・家畜に関連する意匠。・植物モチーフの金属細工(右奥) 葉の形をした金属装飾品。祭壇や建築装飾、もしくは軍服の飾り(徽章)であった可能性が。・丸型のメダリオンまたは印章(右手前) 赤色や金属色が見え、コインや勲章、封蝋印章などの可能性が。「Treasures of Christ Church Cathedral DublinThis exhibition marks the publication of Treasures of Christ Church Cathedral, Dublin, published … (不鮮明) … The book tells the history of Christ Church through a selectionof fascinating objects from the cathedral collection.From Viking bones to medieval manuscripts, memorials, swords to Victorian … (不鮮明) …the cathedral’s long and … (不鮮明) … centuries of history. The objects on display give a unique insight into the life of the cathedral and its place at the heart of Dublin.Some of the objects from the book are shown in these cases, with others on permanent display throughout the cathedral. Copies of Treasures of Christ Church Cathedral, Dublin are available in the Cathedral shop.LARGE PRINT CAPTIONS AVAILABLE」【クライストチャーチ大聖堂の宝物ダブリンこの展示は、『クライストチャーチ大聖堂の宝物(Treasures of Christ Church Cathedral,Dublin)』の刊行を記念するものです。本書は、大聖堂の歴史を、聖堂の所蔵品コレクションの中から厳選した魅力的な品々を通して紹介しています。ヴァイキング時代の遺骨から中世の写本、記念碑、剣、ヴィクトリア時代の品々まで、大聖堂の長い歴史を物語る展示物が並びます。これらの展示物は、大聖堂の歴史や、ダブリンの中心におけるその役割について、特別な洞察を与えてくれます。本書に掲載されている品の一部は、これらの展示ケースに、その他は大聖堂内の常設展示として展示されています。『クライストチャーチ大聖堂の宝物』は大聖堂のショップで購入可能です。大きな文字サイズの解説文もご用意しています。】 エリス家(Ellis family)の記念碑。左右に胸像があり、中央に家族の名前と経歴が刻まれていた。左側胸像・人物:The Right Rev. Dr. Welbore Ellis・肩書き・経歴 ・生まれはKilcolman Hall, Co. Kilkenny ・Bishop of Meath(ミーズ司教) ・Christ Church CathedralのDean(主任司祭) ・没年:1831年3月7日、享年79歳・記載内容は彼の出身地、教会での職務、没年、教区への功績を称えるもの。中央パネル・主題:Mrs. Diana Ellis とその家族の記録・記載されているのは、彼女の結婚歴と子どもたちの生没年。・最初の夫:Henry Agar Esq.(Gowran Castle, Co. Kilkenny)・再婚相手:George Dunbar Esq.(Christ Church埋葬)・子どもたち:John, William, John, Philip, Charles, Diana Ellis など複数の名前と没年日が列挙。右側胸像・人物:Mrs. Diana Ellis・肩書き・経歴 ・Henry Agar の未亡人で、George Dunbar と再婚 ・上記の子どもたちの母 ・1829年1月30日没・彼女の生涯を讃える文が刻まれていた。そして地下にあるギフトショップへ。写真とは違うが、自分用のTシャツを購入。クリプト内の「Nathaniel Sneyd(ナサニエル・スニード)氏の記念碑」。Nathaniel Sneyd について・生年:おそらく 1767 年頃・職歴: ・アイルランド議会の議員(MP for County Roscommon) ・Clonfertの知事・死因: ・1824年、ダブリン市内で銃撃を受け死亡。・当時、この暗殺事件は政治的動機か精神疾患による犯行かで議論された と。「Sacred to the memory of Nathaniel Sneyd, Esq.,formerly Governor of County Roscommon and Member of Parliament forthe City of Dublin.In him were united the qualities of a refined gentleman, an upright magistrate,and a loyal friend.He was struck down by the hand of an assassin in the prime of his life on July 18th, 1824,and was deeply mourned by his family and friends.」 【ロスコモン州知事およびダブリン市選出の国会議員を務めたナサニエル・スニード氏の思い出に捧ぐ。彼は洗練された紳士としての品格、公正な治安判事としての誠実さ、そして忠実な友人としての情を兼ね備えていた。1824年7月18日、その盛年にして刺客の手により命を落とし、家族や友人から深く惜しまれた】と。近づいて。横たわる男性 ・半裸で横たわる姿は、生命を奪われたスニード本人を象徴します。 ・枕やクッションに頭を預け、手を胸に置く姿は、死の安らぎと同時に非業の死を暗示しています。 ・古典的なギリシャ・ローマ風の裸体表現は、英雄や高潔な人物の理想化された姿を表します。覆面の女性像 ・片手で顔を覆い、もう一方の手を前に置く姿は、深い悲嘆を示す古典的ジェスチャーです。 ・女性は未亡人や近親者、あるいは「悲嘆(Grief)」を擬人化した寓意像と考えられます。 ・足元にはドレープ状の衣が流れ、ローマ風の荘厳な雰囲気を醸しています。全体の象徴性 ・この構図は19世紀前半の英国・アイルランドの葬送彫刻によく見られる 「美化された死と永遠の追悼」の形式。 ・暗殺という暴力的な最期にもかかわらず、彫刻では苦悶の表情を避け、 穏やかな眠りのように表現することで、故人の尊厳を保とうとしています。そして「Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂)」の内陣の見学を終え外に出る。 先日の往路でもアップした、Christ Church Cathedral(ダブリン) の1870年頃の姿を示す立体模型と、その各部名称の凡例。近づいて。Christ Church Cathedral(ダブリン)1870年頃の模型 を斜め方向から撮影したもので、手前に「Skinner’s Row」という通り名が見えます。模型の屋根や建物部分にはアルファベットの刻印があり、前の銘板の凡例と対応していた。Christ Church Cathedral(クリストチャーチ大聖堂/ダブリン) を南東側から再び見上げて。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.10
コメント(0)
-
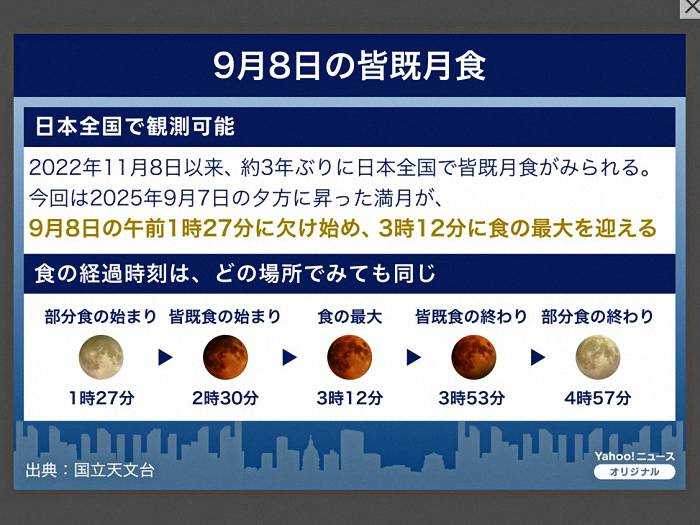
皆既月食を追う
昨日、9月8日(月)早朝に、満月全体が地球の影の中に入り込んで月の表面に太陽光が当たらなくなる「皆既月食」が3年ぶりに観測できたのであった。 今回は前日、2025年9月7日(日)の夕方に昇った満月が、9月8日(月)の午前1時27分に欠け始め、3時12分に食の最大を迎える。そして3時53分に皆既月食が終わり、部分食も4時57分に終了すると。わが町からの皆既月食のタームテーブルをネットから作成。半影食が始まるのは0時27分と。そして食の最大は上記の如く3時12分、皆既食の終りは3時53分、部分食の終りは4時57分、そしてこの日の月の入は5時29分と。上記を絵にした皆既月食の見え方。皆既月食は、太陽からの光によってできた地球の影の中を月が通過するときに見られる現象。 つまり、太陽-地球-月が一直線にならんだ時に見られるものなので、つねに月は満月ということになる。 「上弦の月の月食」とか「三日月の月食」というのは絶対におきない。地球の影には大きく2つの種類がある。 一つは「本影」と呼ばれる影で、太陽からの光が全く届かない部分だ。 本影の部分から見ると、太陽は地球によって完全に隠されてしまっている。もう一つは「半影」と呼ばれる影で、本影の外側に大きく拡がった部分だ。 ここは太陽の光の一部が届く部分で、ここから見ると太陽の一部が地球からはみだして、部分日食の状態に見えるはずだ。地球の軌道と月の軌道は、一致しているわけではないので、月が満月のたびに月食がおきるようなことはない。また、本影と月の経路も一様ではなく、ときには月の一部が本影をかすめたり(部分月食という)、月全体が本影にすっぽりつつまれたり(皆既月食)するのだ。皆既月食になると、月は地球の本影の中に入ってしまうが、完全に暗くなってしまうわけではなく、わずかに赤味をおびて見える。地球の大気の中を太陽光が通過するとき、その光は大気によって曲げられて(屈折して)月まで届き、ほんのりと月を照らします。このとき、光の成分のうち波長の短い青い光は大気に散乱されるためほとんど月まで届きません。一方、波長の長い赤い光は散乱されにくく、月まで届いて月面を照らします。このため、月は真っ暗になることはなく、赤っぽい色に見えるのです。大気中の塵や水蒸気の量によって、非常に濃い茶色や赤色のように見えることもあれば、明るいオレンジ色のように見えることもあるのだと。そして、腕時計のアラームを食の最大となる前の3時にして起床。パジャマのままカメラを持って外に出る。西方向の空には皆既月食の赤い月の姿が。時間は3時12分。そして皆既月食終了直前。時間は3時50分。左斜め上方が少し白くなり始めて来た。東の空には輝く星の姿が。土星の姿であっただろうか?時間は皆既食終了直後の3時55分。左斜め上方がじわじわと白くなり始めて来た。3時58分。ズームして。4時10分。4時16分。4時21分。4時27分。赤さもほとんど無くなって来た。4時40分。月の表面の模様が見えてきました。4時45分。東の空も赤く染まって来た。部分食の終了直前の4時56分。部分食の終了直後の5時00分。周囲の風景の中に。5時2分。大学の高層校舎をズームして。そして5時2分でカメラ撮影を終了。この9月の満月は「コーンムーン」と呼ぶと。 農事暦(The Old Farmer's Almanac)によると、アメリカでは2025年9月の満月を「コーンムーン(Corn Moon/トウモロコシの収穫月)」と呼ぶのだと。今後日本で見られる月食。これから3回は月と日にちが一緒の日。来年のひな祭りの日の皆既月食は18時49分20秒から始まると。最大食に時間は20時33分。寝不足の心配はなさそう。そして2029年1月1日の皆既月食は0時7分からと。そして最大食は1時52分。2028年から2029年に変わる夜、除夜の鐘を聞いた直後に皆既月食が見られるのだと。元旦の早朝から皆既月食が見られるとは!!私もこの時まで頑張ろう!! ・・・おわり・・・
2025.09.09
コメント(0)
-
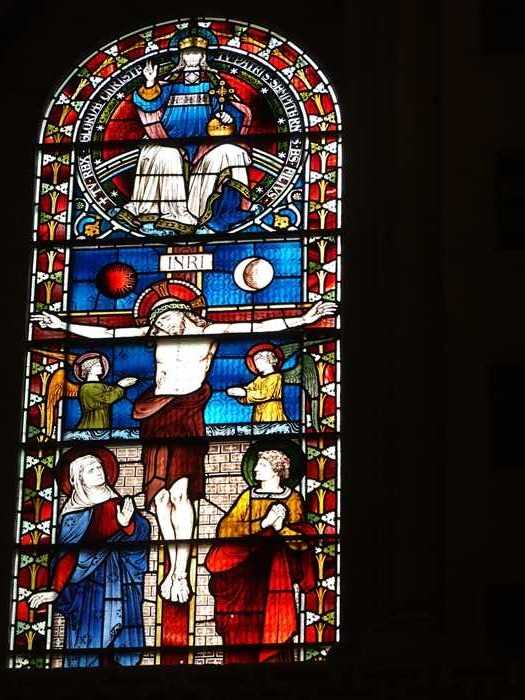
アイルランド・ロンドンへの旅(その73):Dublin市内散策(12/)・Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂)3/4
北側壁面にある窓のひとつ、祭壇に向かって左手側(聖歌隊席の北側)に位置。この「磔刑とキリストの栄光」の構図は、内陣側面窓の伝統的配置テーマのひとつで、祭壇背後(東端)ではなく側面に置かれる場合が多い と。南側の内陣側廊の最東端。上段:聖家族と訪問者(おそらく東方の三博士の一場面、または宮殿でのやり取り)下段:聖家族(マリア・幼子イエス・ヨセフ)への礼拝場面新約聖書の降誕・幼年期の物語で、伝統的に南側の連続窓に配されるテーマ。上段をズームして。これも身廊、南側通路、南、東から2番目上段:羊を担ぐ人物(「善き羊飼い」または羊飼いの召命の場面)下段:鍬や杖を持つ二人の人物(農耕や旅立ち、あるいは兄弟に関する寓話的場面)これらは旧約的・寓話的テーマで、南側窓列の物語構成の一部。これも身廊、南側通路、南、東から3番目下段にオルガンや楽器を弾く人物(おそらく詩篇作曲者ダビデや聖セシリア)が描かれ、南列の旧約音楽主題と一致。中、下段をズームして。パイプオルガン製作または演奏の場面を描いたもの。中央の人物 白い長衣をまとい、座って鍵盤を弾く人物。聖書や伝統美術においては、 ユバル(Jubal)(創世記4:21)とされることが多い。 ユバルは旧約聖書で「竪琴と笛を奏でる者の祖」とされ、楽器製作や音楽の起源を象徴する と。周囲の人物 背後に立つ2人:笛(またはシャルメ)と弦楽器を奏でる人物。 手前右下:オルガンの送風装置(ふいご)を操作する少年。背景の白い鳩 鳩は聖霊や平和を象徴し、音楽が神聖な賛美であることを表す。 内陣南側(右側)の西寄り、聖人列(特に天使・守護聖人テーマ)の並びの中に。上部の場面・中央にひざまずく人物(罪人や異端者を象徴)を、両側から二人の人物が導いている構図。・これは審判や救済の文脈に関連する場面で、下部の「悪を打ち負かす」ミカエルの場面と 対になっています。下部の場面・白い衣と緑のマントをまとい、剣を手にする有翼の人物が、赤い悪魔(または竜)を足元に 踏みつけています。・剣を振り下ろす姿は、ヨハネの黙示録(黙示録12章)における「天の軍勢の長・ミカエルが 竜を倒す場面」に基づくもの。・下の円形飾りに「MICHAEL」の文字。南面のステンドグラス案内図。南側入口付近(南側通路の西端) にあるステンドグラス。南側通路の最も西寄り、観光案内や掲示板が設置されているエリア上部に位置。この窓のモチーフは、上下2段構成で聖人像が描かれており、南列の物語順には含まれず独立した装飾的・記念的窓となっている と。上段をズームして。「ダニエル書」に描かれるダニエルが獅子の穴から救われる場面。中央の人物が預言者ダニエル、背後の天使が彼を守護しており、両脇にはおとなしく伏すライオンが描かれている。下段をズームして。火の炉の中の三人の若者(シャデラク、メシャク、アベド・ネゴ)と彼らを守る天使を描いている。背景の炎と天使の翼が象徴的で、彼らが火の中でも無傷で守られた奇跡を表す。Strongbow(ストロングボウ)像。12世紀のノルマン征服者リチャード・ド・クレア(Richard de Clare, 2nd Earl of Pembroke)の墓を示すもの。リチャード・ド・クレアは「Strongbow(強弓)」の通称で知られ、1170年のアイルランド侵攻で大きな役割を果たしたノルマン騎士。クリアストーリー(Clerestory)窓の一部を撮影。南側廊(South Aisle)上方、主身廊(Nave)との境界壁上部にあたります。下段の尖頭アーチ部分は装飾的なトリフォリウム(Triforium)で、実際には通路ではなく装飾壁面。この窓は物語場面ではなく、幾何学的パターンや色ガラスを主体とした意匠で、南列の下段に並ぶ物語パネルとは異なる系統の装飾が。Christ Church Cathedral の身廊(Nave)から東(内陣方向)を望んだ全景。Christ Church Cathedral 東端・内陣(Chancel)正面の左右2連の大きなステンドグラス。 これは最も東の壁(East End)の中央高窓で、祭壇のすぐ背後にあります。位置 先ほどの内観写真(身廊から東方向を見た写真)の最奥に見えていた窓がこれです。構造・二連の尖頭アーチ窓(左・右)・各窓は上下3段の物語パネルで構成・上部に小円窓(ラウンドの石細工装飾)があり、その下に2連窓が並ぶ主題(推測)光の強弱や構図から推測すると、・左列:キリストの復活、聖母マリア、受胎告知など・右列:聖霊降臨、東方三博士礼拝、幼少期のキリストの場面といった新約聖書の主要場面が並んでいた。カテドラルの司教座(Bishop’s Throne)。・中央の椅子 ゴシック様式の高い背もたれと尖塔状の飾りを持つ木製の椅子は、ダブリン大司教の公式座席 (Cathedra)です。大聖堂が「Cathedral」と呼ばれるのは、この司教座が置かれているためです。・垂れ布(バナー) 背後に掛けられているバナーには、青地に銀の逆Y字(パラル形)と5つの黒い十字が 描かれています。これはダブリン大司教区の紋章で、アイルランド聖公会(Church of Ireland)に 属します。・位置 司教座は通常、内陣(Chancel)の南側に置かれ、聖職者席(choir stalls)の一部として 組み込まれています。この写真の背景にも、内陣南側のステンドグラスやパネルがわずかに 見えます。大司教座に掲げられたダブリンおよびグレンダロッホ教区の旗。Christ Church Cathedral(ダブリン)南側の出入口付近。場所 このドアは南廊(South Transept)に近い位置、つまり南壁にあり、外部に直接出られる扉。 訪問者の入退場口や緊急出口としても使われていた。上部のステンドグラスアーチ上部には小型の縦長ステンドグラスが1枚あり、彩色は赤・青が目立った。南側側廊(South Aisle)を東方向(内陣方向)から西に向けて。・右奥の明るい部分は南側の西端(南玄関)方向。・左に見える細長い縦窓は、外壁上部に並ぶ高窓(クリアストーリー窓)で、下部は ベンチが設置された壁面。・奥(西端)の壁中央に縦長のステンドグラスが1枚。 この窓は「南西端窓(West end of South Aisle)」にあたる。・色タイルによる幾何学模様が中央に伸び、左右に石列・ベンチが並んでいた。・天井は、交差リブ・ヴォールトが側廊の全長にわたって連続していた。・西正面(West Front)から東方向(内陣方向)を見た全景 。・西端の主入口付近から中央身廊(Nave)の中心軸に沿ってカメラを。・上部に見える5連の尖頭アーチ窓が「西正面大窓(Great West Window)」で、外部からもよく 見える特徴的なファサード要素。この大きなステンドグラスは、5つの縦長のランセット窓(lancet windows)で構成されており、それぞれに2〜3名の人物が描かれていた。主題:旧約・新約の預言者や使徒、聖人たち中央列上部にはキリスト(または聖母マリア)が玉座に座している姿が。それを囲むように旧約の預言者、福音記者、使徒などが楽器、書物、巻物などの象徴を持って描かれていた。ズームして。左上 DAVID ダビデ王。 赤いローブに 王冠をかぶり、ハープ(リラ)を奏でる姿。詩篇作者として有名で、キリストの 家系の祖先。左下 JESSE エッサイ(イザイ)。 ダビデ王の父。系図の起点として描かれ、「エッサイの根」はキリストの系譜を象徴する。 花を持っており、「エッサイの木」への示唆。右上 SOLOMON ソロモン王。 ダビデの息子。知恵の王として知られ、杖と書物を持って描かれることが多い。 ここでは王笏と巻物を所持。右下 REHOBOAM(レハブアム) ソロモンの子で、ユダ王国の初代王。王笏と巻物を手にし、王権の継承を象徴している。バラ窓(Rose Window)の一つで、キリスト教における象徴と徳(Virtues)を主題とした構成。【中央の円】・人物:キリスト(おそらく「善き羊飼い(The Good Shepherd)」)・持ち物:羊飼いの杖(牧者の象徴)、周囲に2匹の羊・背景の語句: ・赤字で「LOVE」(愛) ・縁取りに「JOY(喜び)」「PEACE(平和)」「LONGSUFFERING(寛容)」などの文字・象徴:聖霊の実(Fruits of the Spirit) を象徴する。これは新約聖書・ガラテヤ人への 手紙5:22–23 に基づく。身廊から見て内陣・聖歌隊エリアへの境界部分、十字架交差部(tower crossing)の下部から。天井中心には三位一体の盾紋、右手(北翼廊側)にはパイプオルガン。前景の精緻なアーチ構造は、ヴィクトリア朝時代に設けられたスクリーン(choir screen)で、これは内陣と身廊(Nave/Nave)を隔てる区切りとして機能。これもまた、建築家G. E. Streetによる1875年の改修によるもの と。地下クリプト(Crypt)内にあった記念碑(墓碑)。ロココ風の装飾(スクロールやアカンサスの葉)を持つ楯形カルトゥーシュ(楯形装飾枠)と、両側に垂れ下がる花綱(ガーランド)が彫刻されていた。これが有名なLord John Bowes(ジョン・ボウズ卿)記念碑。・場所:大聖堂地下クリプトの南側通路(南壁側)に設置。・人物:ジョン・ボウズ卿(†1767)はアイルランドの大法官(Lord Chancellor of Ireland)を 務めた人物。・造形:大理石彫刻で、ローブをかけた女性像(悲嘆を象徴する「グリーフ(Grief)」の擬人化像) が棺の上に座り、片手で布を持ち上げています。背後のレリーフには盾形紋章や 戦勝記念のトロフィー、右側には倒れた壺(生命の終わりの象徴)。・製作時期:1767年の没後、18世紀後半に制作。・作風:新古典主義の影響を受けたロココ的ディテールで、当時の葬礼彫刻に典型的な構図。・像の構成: ・左側の女性像は、悲嘆(Grief)または信仰(Faith)の擬人化。ヴェールを被り、片手で棺を 覆う布を持ち上げています。 ・布の下から現れるのはジョン・ボウズ卿の浮き彫り肖像(典型的な18世紀の法服と巻き毛の かつら)。 ・背後には紋章やトロフィーが彫刻され、右奥には倒れた壺(生命の終わりの象徴)が見えます。・被葬者:John Bowes, 1st Baron Bowes(1691–1767) ・アイルランド大法官(Lord Chancellor of Ireland)を務めた法曹界の重鎮。 ・1767年没後、この記念碑がクリプト南壁側に設置された。「Sacredto the Memoryof JOHN LORD BOWESlate LORD CHANCELLOR OF IRELANDWho died in the Seventy Sixth Year of his AgeJuly the 22nd One thousand Seven hundred Sixty SevenThis Monument is ErectedBy his affectionate BrotherRUMSEY BOWES Esq.of BINFIELDBERKS」 【ジョン・卿(ロード)・ボウズ前アイルランド大法官の思い出に捧ぐ。彼は享年76歳にして1767年7月22日に逝去した。この記念碑は、彼を愛する弟ラムジー・ボウズ(エスクワイア)バークシャー州ビンフィールドの人によって建立された。】Lord John Bowes(ジョン・ボウズ卿)記念碑の奥・アーチ型の空間にも彫刻作品が。奥にあったのが、大きな石造のイングランド王室の紋章(Royal Coat of Arms)と、それを両側で挟む二体の人物像。盾形紋章を掲げるライオンとユニコーン(イングランド王家の伝統的な紋章保持者)。盾の中にはイングランド、スコットランド、アイルランドの紋章が四分割で配置されていた形跡が。下部リボンにはモットー"DIEU ET MON DROIT"(フランス語:「神と我が権利」)が刻まれていた。これはイングランド王室の公式標語 と。英国王室の紋章👈️リンク。両側の人物像:17世紀〜18世紀初頭の服装をまとった男性像で、王権を象徴する宮廷人物 または当時の権力者を表す と。左の人物像右の人物像旧ダブリン市庁舎(Tholsel, Dublin)を描いた19世紀以前の版画。ネットから。クリプト内部の一角で、石造アーチが連続する通路部分。・写真中央やや右にある木製案内パネルと大型金属製チェスト(献金箱または保管箱)は、 クリプトの南側通路西寄りに置かれている展示物と一致します。・さらに奥に見えるガラスケース内の赤い布の展示は、クリプト内の宝物展示コーナー (Treasures of Christ Church)の一部。・天井は中世以来の石造ヴォールト(半円形アーチ)、床は近年改修された石板敷き。クリプト内にある小窓部分で、外光を取り入れるための格子付き窓。・構造:厚い石壁に穿たれた縦長の開口部で、外側に鉄製の格子が設置されていた。・用途:クリプトは地下にありながらも完全な密閉ではなく、こうした小窓で通風と採光を 確保していた。「The Nuremberg Chest」。「Christ Church CathedralThe Nuremberg ChestThe Nuremberg Chest is a large iron-bound chest, which probably came from Nuremberg, Germany, in the 1680s, and was used to store important cathedral documents.Traditionally, such chests belonged to government officials and were fitted with three ormore locks, which meant that several key-holders had to be present to open them. The Christ Church Nuremberg Chest has four locks.The chest seems to have been in the possession of the cathedral since new, but is specifically mentioned in July 1688 when it was used to transport cathedral records to safety in England. Later an entry in the proctor’s accounts refers to “bringing the said chest and records home”.」 【クライスト・チャーチ大聖堂ニュルンベルクのチェスト(Nuremberg Chest)この「ニュルンベルクのチェスト」は、大型の鉄で補強された木製の箱で、1680年代にドイツのニュルンベルクからもたらされた可能性が高く、大聖堂の重要な文書を保管するために使われました。伝統的に、この種のチェストは政府役人が所有し、3つ以上の錠前を備えていました。複数の鍵を持つ人物が同時に立ち会わなければ開けられない仕組みです。クライスト・チャーチのニュルンベルク・チェストには4つの錠前があります。このチェストは新造時から大聖堂が所有していたようですが、特に1688年7月の記録に登場します。このとき、大聖堂の記録を安全のためイングランドへ運ぶのに使用されました。後年、プロクター(財務係)の会計記録には「このチェストと記録を持ち帰った」と記されています。】クリプト内に展示されている金色の十字架付き装飾スタンド。廻り込んで。イーグル・リクターナ(Eagle Lectern)と呼ばれる、聖書を載せて朗読するための演台。・鷲の背に広げた聖書を置き、鷲が神の言葉を世界に運ぶ象徴的意味を持ちます。・金色(真鍮または鍍金)で作られており、儀式用具として非常に格式の高いもの。ネットから。「James II and Christ ChurchChrist Church is an Anglican cathedral and has been since the dissolution of the Priory ofthe Holy Trinity in 1541.However, for a brief time in 1689–90 the cathedral reverted to Roman Catholicism under the reign of King James II. Father Alexius Stafford, one of James’s private chaplains, celebrated Mass here for him in 1689 when James came to Ireland to try and recoverhis kingdoms.The plain brass candlesticks and the wooden tabernacle – for keeping the consecratedbread and wine – used by Father Stafford during this mass can be seen in the case to your left. Little did Father Stafford or James II know that the elaborate church plateusually used was buried under a coffin beneath their feet.」 【ジェームズ2世とクライスト・チャーチクライスト・チャーチは英国国教会(アングリカン)の大聖堂であり、1541年に聖三位一体修道院(Priory of the Holy Trinity)が解散して以来、その地位を保っています。しかし、1689年から1690年にかけての短期間、ジェームズ2世の治世下で、この大聖堂は一時的にローマ・カトリックに戻りました。ジェームズの侍祭の一人であるアレクシウス・スタッフォード神父は、1689年にジェームズが自らの王国を取り戻すためアイルランドに来た際、ここで彼のためにミサを執り行いました。このミサの際、スタッフォード神父が使用した真鍮の燭台と木製の聖櫃(聖別されたパンとぶどう酒を保管するためのもの)は、左手の展示ケースで見ることができます。スタッフォード神父もジェームズ2世も、その足元の棺の下に、通常使用される豪華な教会用食器が埋められていることを知る由もありませんでした。】案内板に記載されていたジェームズ2世(James II)とアレクシウス・スタッフォード神父のミサ関連展示。展示内容・中央:木製の聖櫃(tabernacle) ・聖別されたパン(聖体)やワイン(聖血)を保管するための祭具。 ・ドーム型の上部構造とアーチ型の入口があり、金箔や彩色の装飾が残っています。 ・1689年にスタッフォード神父がジェームズ2世のために行ったミサで使用されたものとされます。・左:聖書または典礼書(ゴールドの布表紙)・中央前面:金製の聖杯(chalice)・右:真鍮製の燭台(plain brass candlestick)・右奥:平らな銀皿(教会用食器の一部)「Treasures of Christ ChurchWilliamite PlateThe beautiful collection of silver-gilt altar plate in the case to your left was commissionedby King William III for use in his royal chapel in Dublin. It was made by the Londongoldsmith, Francis Garthorne.The large alms dish in the centre of the case shows the Supper at Emmaus, when Jesus,who had risen from the dead, appeared to two of his followers at dinner in the town of Emmaus.The dish was ordered on 26 December 1693 but was not delivered until 14 April 1695. The long production period was probably due to the amount of detailed metal workinvolved.」 【クライスト・チャーチの宝物ウィリアマイト・プレート(Williamite Plate)左手の展示ケースにある、美しい金メッキ銀製の祭壇用食器セットは、ダブリンにある王室礼拝堂で使用するために、ウィリアム3世によって注文されたものです。製作はロンドンの金細工師フランシス・ガースホーンによるものです。ケース中央に展示されている大型の施し皿(アームズ・ディッシュ)には、復活したイエスがエマオの町で2人の弟子に夕食の席で現れた「エマオでの晩餐」の場面が描かれています。この皿は1693年12月26日に発注されましたが、納品されたのは1695年4月14日でした。この長い製作期間は、非常に精緻な金属細工作業が必要だったためと考えられます。】上記案内板で説明されていたウィリアマイト・プレート(Williamite Plate)の現物展示。内容と特徴・中央上段: ・大型の施し皿(alms dish) ・中央には「エマオでの晩餐」の場面が精緻なレリーフで描かれています。 ・周囲はアカンサス文様などのバロック風装飾で縁取られています。左右上段: ・大型の燭台(candlestick)2基(左側) ・蓋付きタンカード(covered tankard)とピッチャー(右側)下段中央: ・金製聖杯(chalice) ・小型皿(patens または小施し皿)2枚製作背景 ・製作者:ロンドンの金細工師 フランシス・ガースホーン(Francis Garthorne) ・年代:1693年発注、1695年納品 ・発注者:イングランド国王ウィリアム3世(William III) ・用途:ダブリンの王室礼拝堂での祭儀用中央上段: ・大型の施し皿(alms dish) ・中央には「エマオでの晩餐」の場面が精緻なレリーフで描かれています。 ・周囲はアカンサス文様などのバロック風装飾で縁取られています。大型の燭台(candlestick)2基。蓋付きタンカード(covered tankard)とピッチャー。「LISTENING BENCH(リスニング・ベンチ)」はこちらと。・体験型展示の一部で、ベンチに座ってイヤホンやスピーカーから流れる解説や物語を聞くことが できるスポット。・内容は大聖堂の歴史や著名な出来事、埋葬者の物語、建築に関する説明など多岐にわたる と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.09
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その72):Dublin市内散策(11/)・Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂)2/4
残念ながらChrist Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂)への入堂時間は10時からとのことで、まずはダブリン城に向かったのであった。そしてダブリン城見学の帰路にここの内部の見学をしたのであった。よって続けてここに継続してアップします。Christ Church Cathedral(クリスト・チャーチ大聖堂) を南東側から見上げて。・中央塔(central tower):四角形平面で、上部に4つの角塔と尖った屋根を持つ。 鐘楼としても使用され、鐘は観光ツアーでも見学可能。・後陣(apse)と放射状礼拝堂(radiating chapels):写真右手に見える部分。 円形または多角形の小礼拝堂が後陣の周囲に配置されていた。・バットレス(控え壁)と尖頭アーチ窓:典型的なゴシック様式の外観を形成。・交差部(crossing):塔の下の部分が身廊(nave)と翼廊(transept)の交差点。・石造の質感:中世(12世紀初期創建)からの石材が基礎に残り、19世紀の大規模修復 (ジョージ・ギルバート・スコット設計)による部分も多い。「SERVICESMonday, Wednesday, Friday 10:00 Morning Prayer 12:00 Peace Prayers 12:45 Midday Eucharist 17:00 Evening PrayerTuesday and Thursday 10:00 Morning Prayer 12:00 Peace Prayers 12:45 Midday Eucharist18:00 Choral Evensong Sunday 11:00 The Cathedral Eucharist 15:30 Choral EvensongThere is no charge to attend services.All are welcome!Christ Church Cathedral DublinThe spiritual heart of Dublin」【礼拝スケジュール月曜・水曜・金曜 10:00 朝の祈り(Morning Prayer) 12:00 平和の祈り(Peace Prayers) 12:45 正午の聖餐式(Midday Eucharist) 17:00 夕の祈り(Evening Prayer)火曜・木曜 10:00 朝の祈り(Morning Prayer) 12:00 平和の祈り(Peace Prayers) 12:45 正午の聖餐式(Midday Eucharist)18:00 合唱付き夕の礼拝(Choral Evensong)日曜 11:00 大聖堂の聖餐式(The Cathedral Eucharist) 15:30 合唱付き夕の礼拝(Choral Evensong)礼拝への参加費は不要です。どなたでも歓迎します!ダブリン・クリスト・チャーチ大聖堂「ダブリンの精神的中心地」】バロック様式の胸像付きモニュメント。台座部には赤い大理石に刻まれたラテン語の碑文があり、その上に人物胸像と二人の天使(プットー)が彫刻されていた。「Memoriae sacrumTHOMAE PRIOR;Viri, si quis unquam alius, de patria Optime meriti;Qui, cum prodesse mallet quam conspici,Nec in senatum cooptatusNec consiliorum aulae particeps Nec ullo publico munere insignisRem tamen publicam Mirifice auxit et ornavitAuspiciis, consiliis, labore indefesso.Vir innocuus, probus, pius,Partium studiis minime addictus,De re familiari parum sollicitus.」【この記念碑を トーマス・プライアに捧ぐ。もし他に類を見ないほど 祖国に尽くした人物があるならば、まさにこの人である。彼は、目立つことよりも役立つことを望み、元老院に選ばれることもなく、 王宮の評議会に加わることもなく、いかなる公職の栄誉にも輝くことはなかったが、 それでも公共の事業をその指導・助言・絶えざる労苦によって驚くほど発展させ、装った。無垢で、正直で、敬虔な人物であり、党派的な争いに与することは全くなく、私財についてはほとんど関心を持たなかった】 ダブリンのChrist Church Cathedral(クリストチャーチ大聖堂)の内部(ネーブ:中央身廊)を、後方から祭壇方向に向かって。・高いヴォールト天井:交差リブ・ヴォールト(ribbed vault)の構造・二層構造の側壁:下層に大きな尖頭アーチのアーケード、その上にクリアストーリー窓・石造の尖塔アーチと列柱・中央通路両側に並ぶ椅子席(パイプ椅子ではなく木製座席)・奥の祭壇上部にステンドグラス窓さらに近づいて。中央身廊(ネイブ)から内陣(コーラス、聖歌隊席)越しに祭壇と東端の窓を望む。更に近づいて。・手前に見えるのは、コーラススクリーン(Rood Screen)の頂部と、その上に立つ 十字架(磔刑像)。・背後のステンドグラスは、左右2枚の尖頭アーチ窓に区切られ、上から下に3つの場面が 描かれていた。・窓上部中央の円形部分(ローズレット)は石細工で、植物や幾何文様の彫刻。・窓の外枠はゴシック様式特有の装飾アーチ(チェブロン模様)で縁取られていた。内陣のステンドグラス👈️リンクを。左側の窓(上から下へ)・復活のキリスト:白い衣、背後に光輪、両腕を広げた姿。左右に天使または弟子・受胎告知か復活後の出会い:座る青衣の女性(聖母マリアまたはマグダラのマリア)と立つ人物・園の中の祈る姿:樹木と祈る人の構図(ゲッセマネの祈りの場面にも似る)右側の窓(上から下へ)・聖霊降臨:上方中央に鳩(聖霊)、炎と光輪を受ける人々・三賢者の礼拝(東方三博士):贈り物を捧げる場面・子どもたちとキリストまたは幼児洗礼の場面放射状リブ・ヴォールト天井と内陣の側面の連続するステンドグラス窓。天井構造・黒い円柱から放射状に伸びる白いリブが交差し、中央のボスストーンで結ばれている。・リブ間は石材で埋められ、ゴシック様式特有の高い天井。壁面構造・五連の細長い尖頭アーチ窓(ステンドグラス入り)・各窓の間には細い柱があり、上部には小さな装飾アーチ。・中央上部に小さな円形窓(オクルス)が配置され、外光を取り込む。ステンドグラスの内容・左から順に聖人や使徒と思われる人物像。・彩色は赤・青・黄色が強く、19世紀ヴィクトリア朝時代の彩色スタイルに近い。右の3面を。側廊のステンドグラスを追う。・上段:白い衣を着た人物(天使)が杖を持ち、赤い衣の人物に何かを告げている。背景は青と金。 これは「復活の朝、天使が墓の見張り兵に告げる場面」や「天使による宣告(受胎告知や夢告)」 などに似ている。・下段:青い衣の女性が倒れている人(または亡くなった人)の頭を抱いており、周囲に数人の 人物が集まっている。キリストの十字架降架後の「嘆き(ピエタ)」場面や、聖人の死の場面では。上段・白い衣を着た人物(天使または復活したキリスト)が立っており、足元に倒れている2人の 人物(兵士)が見えます。・背景は赤色で強調され、劇的な場面を表現。・この構図は「復活の朝、墓の見張り兵が天使の出現に打たれて倒れる場面」 (マタイ28章4節付近)によく似ています。下段・中央の人物(青い衣)は後ろから押さえられ、もう一人の人物に腕をつかまれている。・これは「イエスの捕縛」(ゲッセマネの園での逮捕、ヨハネ18章やマルコ14章)を描いている 可能性が高いです。・左の人物は剣を持っているようにも見え、ペテロの可能性があります。上段・白い衣を着た人物(キリスト)が群衆の前に立ち、兵士や役人と対面している様子。・周囲には赤い衣の人物や青衣の人物がいて、中央人物に注目している構図。・これは「ピラトの前のイエス(裁判)」、あるいは「嘲笑を受けるキリスト」の場面か (ヨハネ18〜19章)。下段・中央に裸上半身の人物(キリスト)が描かれ、両側の兵士が彼を縛っているか、 鞭打とうとしている。・これは「鞭打ちの刑(Flagellation)」の場面(マタイ27章26節、ヨハネ19章1節)。上段・十字架に横たえられた人物(キリスト)が描かれ、周囲の人々が釘打ちの作業をしている。・白衣の人物が釘を打ち、他の人物が足を押さえているように見える。・これは「十字架への釘打ち(Crucifixion – Nailing to the Cross)」の場面で、ヨハネ19章や マタイ27章の一場面。下段・青い衣の人物(聖母マリアまたは女性信者)が赤い衣の人物とともに倒れた人物の上半身を 抱き上げている。・周囲に複数の人物がいて、悲しみや驚きの表情をしている。・この構図は「十字架降架後の嘆き(ピエタ)」や「地に倒れたキリストを支える場面」。説教壇(pulpit)の彫刻部分。おそらく人物像は 新約聖書の四福音書記者(マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ) または主要な使徒たちを表している と。木製大型パイプオルガンを正面から。移動して見上げて。木製パイプオルガンの手前横から・手前の大きな木製パイプオルガンは、聖歌隊席(Choir)上部のオルガンロフトに設置されて いるもの。・奥に見える半円形アーチと窓は、西端部(Nave West End)の壁。・窓下の暗い石造部分は、ノルマン様式の古い構造の一部で、ゴシック改修時にも保存された箇所。・オルガンの下を通って、ネイブ後方から聖歌隊席に入る動線になっている。パイプオルガン付近の壁面にある記念碑の一つであったか?文字が書かれていたが。Christ Church Cathedral(ダブリン) に所蔵されている有名な遺物・「Strongbow’s Heart(ストロングボウの心臓)」・中身:かつてはノルマンの騎士 Richard de Clare(通称 Strongbow, 12世紀) の心臓が 納められていたとされる・材質:鉛製の心臓形容器、鉄製の帯で補強されている・展示:クッションの上に置かれ、ガラスケースで保護・歴史: ・Strongbow は1170年にアイルランド遠征を行ったノルマン貴族 ・彼の遺体はChrist Church Cathedralに埋葬され、心臓だけを別に保存したと伝えられる ・2012年、この心臓は盗難に遭ったが、2018年に回収され再展示されたChrist Church Cathedral(ダブリン) 内の一角で、石造アーチ壁面に二つの異なる時代の要素が組み合わされていた。上部・大きな四角い石板にレリーフ彫刻・中央に紋章(ハーラルディック・シールド)があり、左右に立つ人物や動物が盾を支えている 「サポーター」型の構図・上には兜(ヘルム)や羽飾り、下にはリボン状の装飾がある・石材は古く、恐らく17〜18世紀以前の記念碑や王室紋章下部・小型の現代的ステンドグラスパネル・主題はキリストの顔(茨の冠を被った受難のキリスト)・背景は赤・黄・水色で抽象化された幾何学模様・額縁に収められ、壁に直接埋め込まれているキリストの顔のステンドグラスパネルをズームして。聖母マリアのイコン(Icon of the Virgin Mary) が祈祷・献灯スペースに設置されていた。・主題: ・聖母マリアの胸像(肩から上)、やや右下に首を傾げ、憂いを帯びた眼差しを向けている ・この表情は「受難を予感する聖母(Mother of Sorrows / Our Lady of Sorrows)」や 「優しき聖母(Tenderness)」タイプのビザンティン・イコンによく見られる・色彩: ・衣は深紅色(マフリオン、外套)で、内側に青色の服(チトン)を着用 ・赤は神の愛と犠牲を、青は聖性と純潔を象徴・光背(円形の後光): ・薄い赤線で描かれ、背景は金箔で覆われている ・金箔は永遠性・神性を意味・額装: ・周囲は金地に草花文様が描かれ、上下左右に小さな赤宝石風の装飾モチーフ ・額の中央や四隅に幾何学的・植物的デザイン記念銘板の一部であっただろうか?各アーチの頂部には紋章や彫刻(植物文様、盾形紋章など)が。これらは大聖堂に埋葬または記念されている聖職者・信徒・有力市民の記念プレートなのであろう。このステンドグラスは2連窓構成(左窓・右窓)で、上下に2場面ずつ、合計4場面の物語が描かれていた。おそらくキリスト受難〜復活の場面を連続的に描くシリーズの一部。左の窓・上段: ・白い衣の人物(天使または復活のキリスト)が墓前に立ち、手前に倒れる兵士たち ・背景は赤で、復活の劇的瞬間を強調 ・「復活の朝」(マタイ28章2-4節)に対応・下段: ・中央に両手を広げた白衣のキリスト、周囲には喜びや驚きの表情の弟子たち ・「昇天」または「復活後の顕現」(ルカ24章やヨハネ20章)に類似右の窓上段: ・白衣の人物(キリスト)が群衆や兵士とやり取り ・「ピラトの前のイエス」(ヨハネ18-19章)や「嘲笑の場面」の可能性下段: ・赤い外套の人物(イエス)と、オリーブの枝を持つ人々の群れ ・「エルサレム入城」(ルカ19章36-38節)の場面と考えられる有名なロシアの聖像画家 アンドレイ・ルブリョフ(Andrei Rublev)による「三位一体」(The Trinity)のイコンに基づく絵画。・主題: ・創世記18章に描かれる「マムレの樫の木の下でアブラハムを訪れた三人の天使」を モチーフにした、三位一体の象徴的表現・人物: ・左:神の父(創造主)を象徴、赤と金の衣 ・中央:神の子(キリスト)を象徴、赤と青の衣、中央の聖杯は受難と贖いを示す ・右:聖霊を象徴、青と緑の衣、生命と成長を意味・背景: ・左後方の建物はアブラハムの家(または教会) ・中央奥の木はマムレの樫(生命の木) ・右奥の山は霊的上昇の象徴・構図: ・三人が輪を作るように座り、視線と手の動きで互いを結びつけている ・中央の杯を囲む三者の姿は、愛と一致の神秘を表現Christ Church Cathedral(ダブリン) 内の側礼拝堂(Side Chapel)。・中央祭壇 ・白い祭壇布に花模様の縁取り ・上には小型の燭台が2つと中央に十字架・背後の三連ステンドグラス ・各窓は上下に複数場面を持ち、キリストの生涯や受難の一部を描いている ・中央の窓は磔刑(Crucifixion)場面が中心 ・左右は聖書の物語や聖人の場面・周囲の石造アーチ ・小型の尖頭アーチと赤い座面(聖職者席 / Sedilia) ・壁面には小アイコン(聖人画)が均等に配置・右側の旗(バナー) ・ケルト十字の刺繍と「Girls’ Friendly Society Ireland」と書かれている ・アイルランドの女子友愛会(キリスト教奉仕団体)を示すこの三連ステンドグラスは、中央の磔刑(Crucifixion)を中心に、キリストの受難と復活を描いた典型的な構成であると。中央パネル(主題:磔刑)1.最上部円形 ・白い鳩(聖霊)と神の象徴(冠や王座) ・天上の父なる神の栄光を示す場面2.中央大場面 ・イエス・キリストが十字架に磔にされている ・左に聖母マリア、右に使徒ヨハネ ・十字架の上には「INRI」(ナザレのイエス・ユダヤ人の王)3.下段 ・リストが鞭打ちを受けている場面(Flagellation) ・兵士が柱に縛りつけて打っている左パネル(主題:受難前の場面)1.最上部円形 ・玉座のキリスト(Pantocrator)または天上での栄光2.上段 ・ピラトの前で裁きを受けるイエス(Ecce Homo場面)中央パネル(主題:磔刑)3.下段 ・ゲッセマネの祈り(園での苦悶) ・イエスが地にひれ伏し、天使が杯を示す右パネル(主題:受難後〜復活)1.最上部円形 ・復活のキリストまたは天使による栄光の象徴2.上段 ・復活の朝、天使が墓の前でマリアたちに語りかける3.下段・キリストがマグダラのマリアに現れる(Noli me tangere「わたしに触れるな」)まとめ・構造:三連パネル(左=裁きと祈り、中央=磔刑、右=復活)・物語順: 1.ゲッセマネの祈り(左下) 2.ピラトの裁き(左上) 3.鞭打ち(中央下) 4.磔刑(中央) 5.復活の朝(右上) 6.マグダラのマリアへの出現(右下)このステンドグラスは、縦長1枚のランセット窓で、上から下にかけて物語が展開している と。左側単独窓上部パネル・天上の場面 翼を持つ天使と、神の玉座(または復活したキリスト)らしき人物が雲の中に立っています。 → 神の祝福や召命の象徴と思われます。中央小円(メダリオン)・中に杖を持つ人物が描かれています。 → これは聖職者または預言者の象徴的肖像。下部大パネル・場面:一人の人物が書物や巻物を持ち、もう一人が座って受け取っている構図。・背景にアーチ窓の装飾があり、室内でのやり取りを表しています。・主題としては「聖典の授与」「教育」「教えの伝授」を示す可能性が高いです。1.上段(大きな長方形パネル)・右側の兵士(鎧と盾を持つ)が剣を振り下ろす姿。・左側の人物(跪く女性または男性)が打ち据えられ、背後に天使がいる構図。・これは聖マティアスの殉教や、彼に関する迫害の場面を象徴している可能性が高い。2. 中段(円形メダリオン)・聖マティアス(Matthias) の胸像像。・周囲はゴシック様式の幾何学装飾。・使徒マティアスは、ユダ・イスカリオテの代わりに使徒団に加わった人物(使徒言行録1章)。3. 下段(大きな長方形パネル)・赤背景に二人の人物が向かい合い、手に果物や花を持っている。・下部にはラテン語銘文: "FRUCTUS FLUIT PER IESUM CHRISTUM" (「実りはイエス・キリストによって流れる」)・豊穣や霊的な実りを象徴する場面で、聖マティアスの教えや伝道による成果を暗示。この2連の縦長ステンドグラスは、左右それぞれに複数の場面が縦に並び、聖書物語の連続場面を描いている。構成は上から下に読み進める形。左側の窓(2場面構成)上段・玉座に座る人物(冠または頭飾り)と、それに跪く人物たち。・王または権威者と、聖人・使徒の謁見場面と見られます。・周囲にいる人物は、助言者や証人の役割。下段・背後に樽や桶のような物が置かれ、人物たちが槍や棒を持つ。・殉教や逮捕の場面を示している可能性があります。・前景では、立つ人物が座り込む人物を指差すような構図。右側の窓(3場面構成)最上部(小円または尖頭パネル)・天使や聖霊(鳩)など、天界を示す象徴。上段・複数の人物が屋外で会話または説教をしている場面。・立つ人物の周囲に人々が座って聞いている構図から、教えや説法の場面。中段・白い衣をまとい十字架を持つ人物が壇上に立ち、周囲の人物がひざまずく。・これは復活または天啓の場面の象徴的表現。全体的テーマ・左右とも、信仰の宣教 → 権威への対面 → 迫害や殉教 → 天的栄光 という流れを含む物語構造。・中世以降のステンドグラスに見られる典型的な使徒伝承や聖人伝の構図に近いです。この縦長のステンドグラスは、上下2つの物語場面を持つ構成で、使徒または聖人の生涯の一場面を表している。上段・階段を上る人物(緑の衣)が壇上の人物へ何かを捧げる場面。・背後に集まる群衆(赤・青の衣)が見上げる構図。・背景にはアーチ型の建築意匠が描かれ、屋内(宮殿または神殿)での出来事を示唆。・宗教的儀式や宣教の様子と考えられます。中央円形メダリオン・白衣の人物(胸像)が描かれ、下に**"Philip"** らしき文字が見えるため、・これは使徒フィリポ(Philip the Apostle)の象徴的肖像の可能性が高いです。下段・赤い帳の前、椅子に座る人物と、立つ人物が向かい合い、 書物や巻物を手渡しているように見える場面。・背景に柱や建物が描かれており、公的・宗教的な場面。・教義の授与や説法の象徴的描写と解釈できます。全体テーマ・上下で「説教・教えの授与」という連続テーマが表現され、 中央のメダリオンがこの窓の主題人物(フィリポ)を特定。・キリスト教美術における使徒の生涯を順序立てて描く典型的な構成。祭壇周囲の南側(向かって右手)壁面の一部で、ゴシック様式の尖頭アーチ型ニッチの中に東方正教会風のイコン(聖像画)が並び、その下には小さな説明プレートが。手前にはキャンドル台が設置され、祈りや献灯の場になっていた。このイコンは、聖ゲオルギウス(聖ジョージ)による竜退治の場面を描いたもの。・人物:聖ゲオルギウスは白馬にまたがり、槍で黒い竜を突いています。赤いマントと鎧姿で 描かれ、頭には金色の光輪(聖性の象徴)。・竜:黒い体に赤い鱗の腹部を持つ竜が、地面に倒れこみ、槍を受けています。・背景:右上には城壁の上からこの戦いを見守る人々の姿。・構図:東方正教会の伝統的イコン画法で、人物や動物は象徴的に描かれ、背景は金色の平面で 聖性を示しています。そして「ロバート・フィッツジェラルド、第19代キルデア伯爵の記念碑」👈️リンク。 この彫刻は、Robert Fitzgerald(1675〜1743)、第19代キルデア伯爵を追悼して制作されたもので、教会内の南トランセプト に設置されていた。トランセプトは、教会堂建築において、身廊(メインの通路)に直交する形で設けられる翼廊のこと。彫刻家は、Henry Cheere(ヘンリー・チア)。「To the Memory of ROBERT Earl of KILDAREThe Nineteenth of that Title in Succession,And in Rank the first Earl of Ireland.He married the Lady MARY O’BRYEN,Eldest Daughter of WILLIAM Earl of INCHQUIN;By whom he had Issue Four Sons and Eight Daughters of which NumberOnly JAMES the present Earl, and the Lady MARGARETTA Survived Him.Together with the Titles, He inherited the Virtues of His Noble Ancestors;And adorned every Station He possessed with Honour and Justice.Directed the whole Course of His life.The Daily Devotions of His Family,And the Public Worship in the Church,Were by His Regular Attendance.Cherished and Recommended:Tho’ possessed of a great Estate,He managed it with particular Prudence and Oeconomy,In order to give a freer Course to His many & great Charities.He was a disinterested Lover of His Country,Without any Affectation of Popularity:And was Beloved by all, not because He fought itBut because He Deserved it.He was A most Tender and Affectionate Husband, An Indulgent, and Prudent Father,A Sincere, and Steady Friend.His Disconsolate RelictIn Testimony of Her Gratitude, and Affection,And the better to Recommend to His Descendants The Imitation of HisExcellent Example Caused this Monument to be Erected.He Died the 20 Day of FebruaryA.D. 1743, in the 69th Year of His Age.」【キルデア伯爵ロバートを記念して。この称号を継いだ第19代であり、地位においてアイルランド第一位の伯爵であった。彼はインチクィン伯ウィリアムの長女、メアリー・オブライエン夫人と結婚し、4人の息子と8人の娘をもうけた。そのうち、生前に存命であったのは、現キルデア伯ジェームズと、娘マーガレッタのみであった。称号と共に、彼は高貴な先祖の美徳をも受け継ぎ、その身分にふさわしく、名誉と正義をもって務めを果たし、生涯を通してその道を歩んだ。家族の毎日の祈りや、教会での公の礼拝に、彼は常に欠かさず出席した。広大な領地を所有しながらも、彼は特別な慎重さと倹約の精神でそれを管理し、数多くの大きな慈善事業に自由に資金を注ぐことができた。彼は見返りを求めぬ、祖国を愛する者であり、人気を装うことなく、求めたからではなく、その人格ゆえにすべての人に愛された。彼はきわめて優しい、愛情深い夫であり、思いやりがあり、賢明な父であり、誠実で揺るぎない友人であった。深く悲しむ未亡人は、感謝と愛情の証として、またその卓越した生き方を子孫への手本とするために、この記念碑を建立させた。彼は1743年2月20日、69歳で亡くなった。】 正面から。棺に寝かされ横たわる伯爵の遺体を、悲しみの表情で抱く妻(Lady Mary)と、遺児として生存していた2人の子(James、後にリーンスター公となる長男と娘のMargaretta)が描かれていた。中央:夫の遺体を見つめる妻(Lady Mary O'Brien) ベールを被り、深い悲しみに沈む表情。左手は頬に添えられ、右手は夫の胸元付近にあります。 表情は静かながらも、彫刻の繊細な布の質感や陰影が感情を際立たせています。左奥:若い娘(マルガレッタ) 母の肩越しに寄り添い、手を軽く添えて慰める姿。母子の接触が家族の絆と悲しみを象徴。下部:伯爵(ロバート・フィッツジェラルド) 髪は当時流行のカツラ(パリ風ロング・ペリウィッグ)。衣服はレースの襟や刺繍が精緻に 表現され、18世紀アイルランド貴族の格式を反映しています。ロマネスク様式の聖ローレンス・オトゥール(St Laurence O'Toole)礼拝堂。このステンドグラスは、聖ルカ(Saint Luke)をテーマにしたもの。・聖母マリア(青いマントを纏い、頭光を持つ)と幼子イエス。・マリアの衣装色(青と白)は純潔と天を象徴。・幼子イエスは正面を向き、祝福のジェスチャーはなく抱かれた姿。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.08
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その71):Dublin市内散策(10/)・Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂)1/4
「Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂)」が前方に。・写真左の大きな建物: → クライストチャーチ大聖堂(Christ Church Cathedral)本体。 アイルランド国教会(アングリカン)のダブリン主教座聖堂であり、12世紀にノルマン人に よって建てられたロマネスク様式とゴシック様式が融合した建築。・中央奥のアーチ状の通路: → 通称「シナジー・ブリッジ(Synod Hall Bridge)」。 このアーチ橋は大聖堂と向かいの建物(旧シナジーホール)をつないでおり、博物館展示や 管理施設として使われている建物への連絡通路となっています。・右の建物(やや奥): → 元々はシナジーホール(Synod Hall)で、現在は「Dublinia(ダブリニア)博物館」という バイキングと中世ダブリンの体験型歴史博物館として利用されています。ズームして。Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂) ・創建:1030年頃(ハムダール=ヴァイキング王による) ・改築:1172年頃、ノルマン人指導者ストロングボウ(Richard de Clare)による拡張。 ・特徴:地下納骨堂(クリプト)、ストロングボウの墓、バイキングとノルマンの融合した 建築、合唱席など。Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂) の側面(南側)をズームして。手前中央の突き出た部分をズームして。これは大聖堂本体から突き出した小聖堂(チャペル)または構造上の付属室。特徴は以下の通りと: 特徴 解説アーチ状のドア ロマネスク様式を彷彿とさせる円形アーチの木製扉。三連アーチの開口部 中央部に見られる3つの小アーチは、中世風の窓あるいは装飾的要素。丸窓(円形の開口) 光を取り入れるための開口部で、象徴的な配置。装飾のない壁面 石材の質感がそのまま残され、修道院風の質素な趣を見せています。この突き出た構造はしばしば「アプス(後陣)」や「チャプター・ハウス(参事会室)」などと解釈されることがありますが、クライストチャーチ大聖堂の場合、地下納骨堂(Crypt)や礼拝室に通じる部分とも考えられます と。移動して。Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂) の「西面(West Side)。近づいて「西正面(West Front)」を 。Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂) に隣接する シナーズ通り(Synod Hall / Synod House) と、それをつなぐストーンブリッジ(空中廊下/連絡橋) を西側(Lord Edward Street 方面)から見上げて。ストーンブリッジ(空中廊下/連絡橋)をズームして。さらに、クライストチャーチ大聖堂(Christ Church Cathedral)と、隣接するSynod Hall(現 Dublinia 博物館)とを繋ぐ有名な連絡橋(Sky Bridge / Footbridge)。◆アーチ部分 丸みを帯びたローマンアーチ(ロマネスク様式)で構成。重厚な石造りで、 街道をまたいでいます。◆ 窓(開口部) 小さな円形(オクルス)や狭長の尖塔アーチ窓(ランセット窓)など、 中世風の意匠が並びます。小さなバラ窓のような構成です。◆ 突き出し部 左上部の三角屋根の小尖塔(ペディメント付き)は、橋の頂部装飾です。 装飾性と垂直性を強調しています。◆背後の建物 ネオ・ゴシック様式の建物で、かつて教会会議場だったものを (Synod Hall) 改修し、現在はDublinia(中世・ヴァイキング博物館)として公開されて います。窓や石積みの細部に注目すると、現代的な復古デザインであることが わかります。◆細部の意匠 開口部の周囲には、装飾的な柱頭・小アーチトリミングが施されており、 建築全体に「教会的・修道院的な荘厳さ」を与えています。東側に隣接するSynod Hall(シノッド・ホール)を正面から。現在この建物は、Dublinia(ダブリニア)ヴァイキング&中世博物館として活用されている と。観光案内サインポスト。アイルランド語(Gaeilge)と英語の併記で、主要な観光スポットや文化施設への徒歩ルートが示されていた。Christ Church Cathedral, Dublin(ダブリン・クライストチャーチ大聖堂)を南側から。・創建:約1030年(シトリック・シルケンベアード王による)・様式:ノルマン様式とゴシック様式の融合・管轄:アイルランド国教会(Church of Ireland)・特徴:大規模な地下納骨堂(クリプト)、美しいステンドグラス、ネオゴシック再建(19世紀)・中央奥の高い塔:鐘楼(bell tower)、建物のランドマーク的存在。・左側のファサード:尖頭アーチ窓や控え壁(バットレス)が並ぶ典型的なネオゴシック。・右側の八角塔屋根の部分:聖具室(sacristy)や礼拝室が含まれます。・手前の旗: ・青い旗:EU旗 ・緑白オレンジ:アイルランド国旗 ・虹旗:LGBTQ+フレンドリーな姿勢の表明と思われます。Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂)の鐘楼(bell tower)をズームして。形状:四角形の堅牢な石造り塔。上部には尖塔(スパイア)が載る。屋根:ピラミッド型のスレート屋根。塔の四隅にはミニタレット(小塔)付き。窓:各面に尖頭アーチの2連ランセット窓。鐘音を通すための開口部(ルーバー)付き。装飾:クレネレーション(城のようなギザギザの胸壁)あり。中世の要塞風。上部の十字架:屋根の頂点にはクロス(キリスト教の象徴)が立っている。立体模型(ブロンズ・モデル)。視覚障害者の方にも触って構造を理解してもらう目的で設置されており、1870年ごろの姿を再現している と。アルファベットと対応建物名のプレートが手前に設置されており、視覚障害者が指で個別確認可能。クライストチャーチ大聖堂(Christ Church Cathedral Dublin) のオーディオガイド・ツアーの内容を紹介するもの。「Explore three sides of the cathedral’s amazing story with our audio guideChrist Church Cathedral Dublin・Power and Politics・Christ Church and The City・Music and Spirituality」【オーディオガイドで巡る、大聖堂の驚くべき3つの物語クライストチャーチ大聖堂(ダブリン)・権力と政治・クライストチャーチと都市(ダブリン)との関係・音楽と霊性(信仰)】歴史的・社会的・宗教的コンテクストの中で大聖堂を体験できるように工夫されているのであった。Christ Church Cathedral(クライスト・チャーチ大聖堂)の南正面(South Front)。・左側に長く続く側廊(南壁)があり、ランセット窓が連なる構造。・写真中央の突き出た部分が南翼廊の正面入口(South Transept Entrance)。・四角形の塔が背後に確認でき、これは建物の交差部上にある中央塔(Crossing Tower)。 上部にはバトルメント(城郭風の縁飾り)が施され、尖塔(スパイア)が。南側外壁(南面 / South Elevation)を見る。・右端にあるファサードには正面玄関とバラ窓(rose window)が見えた。・中央の高い塔(中央塔/Central Tower)は、教会の交差部(transeptとnaveの交点)に位置。・左に続く長い部分が身廊で、写真の左端方向が西側。南正面の中央部分、すなわち南トランセプト(南翼廊)の外壁を真正面から。・中央の円形窓はバラ窓は花弁状に放射線状の石材トレーサリーを持つゴシック様式。・中央塔(bell tower)は背後に立ち上がる四角形平面の鐘楼で、クライストチャーチの ランドマーク的存在。ロマネスク〜初期ゴシックの堅牢なデザインが踏襲。・窓(ランセット・ウィンドウ) 上層の3つの細長いランセット窓は、内部のステンドグラス窓(主題:キリストと美徳)と 一致。 特に下層の中央の2列の窓はバラ窓直下に位置し、この内部にも大きなステンドグラスが はめ込まれていることが写真から確認できるのであった。移動して、南東方向から北西方向を見る。写真右側がアプス(内陣・祭壇方向=東側)。アプスとは、教会堂の奥、祭壇がある半円形の部分を指す言葉。ズームして。南東側の庭園にあったのが、ティモシー・シュマルツ(Timothy Schmalz)による「ホームレスのイエス像(Homeless Jesus)」。この像は以下のようなテーマを象徴しているのだと。・貧者・弱者への共感と連帯・「あなたがたが最も小さな者にしたことは、わたしにしたことだ」(マタイ福音書25章40節) という聖句の視覚的表現・現代における社会的無関心に対する挑戦 南側の側廊壁には連続する尖頭アーチ窓と扶壁(フライング バットレス)が並ぶ。引き返して、大聖堂南側の中庭(南ポーチとチャプター・ハウスの前)から南面の左側方向を見る。正面にバラ窓が2つ。3種類の旗が。左:レインボーフラッグ(プライド旗)中央:アイルランド国旗(Irish Tricolour)右:欧州連合(EU)旗左:レインボーフラッグ(プライド旗)・意味:LGBTQ+の尊厳、多様性、平等、社会的受容を象徴する旗。・詳細:もともとは6色が基本(赤、橙、黄、緑、青、紫)ですが、現在はさらに多様性を示す 新デザイン(Progress Pride Flagなど)も使われます。・備考:教会や公共機関が掲揚することで、LGBTQ+コミュニティへの包摂的姿勢を示します。なぜ教会でプライド旗が掲揚されているのか?クリストチャーチ大聖堂(Christ Church Cathedral)は、アイルランド国教会(聖公会系)に属しており、近年では多様性と包摂性を掲げる姿勢を示しています。このような背景から、プライド月間(6月)や特定のイベント時に、プライド旗を掲げることが一般化しているとのこと。中央:アイルランド国旗(Irish Tricolour)・構成:縦三色(緑・白・オレンジ)・意味: ・緑:カトリック系(ナショナリスト) ・オレンジ:プロテスタント系(ユニオニスト) ・白:平和と和解 ・公式採用:1937年(アイルランド憲法下)右:欧州連合(EU)旗・構成:青地に12の金色の星(円形)・意味:・星の数は「完璧」や「完全性」の象徴(加盟国の数とは無関係)・円形は「団結と調和」を表現・アイルランドはEU加盟国(1973年加盟)観光案内標識を。英語とアイルランド語(アイルランド・ゲール語)の併記。・Halla na Cathrach City Hall 市庁舎・Caisleán Bhaile Átha Cliath Dublin Castle ダブリン城・Barra an Teampaill Temple Bar テンプル・バー(文化・飲食街)・Coláiste na Tríonóide Triity College トリニティ・カレッジ(大学)・Músaem Uisce Beatha ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.07
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その70):Dublin市内散策(9/)・O'Connell Street(オコンネル通り)~Winetavern Street(ワインタバーンストリート)
この日は6月6日(金)、アイルランド観光の最後の日。旅友のHさんは、孫の住む米国に向かって早朝4時にこのホテルから予約済みのタクシーで、ダブリン空港へ、そしてSさんは1時間遅れの早朝5時にダブリン空港へと向かったのであった。私も6時過ぎに起床し我が部屋のベッドをカメラに。そして、7時過ぎに「Maldron Hotel Parnell Square・マルドロン ホテル パーネル スクエア」 を出て、この日の最初の目的地の「Dublin Castle・ダブリン城」に向かってYさんと徒歩で向かう。途中、左手にあったのが「Abbey Presbyterian Church・長老派教会」。 「Garden of Remembrance・ガーデン・オブ・リメンブランス(追悼の庭)」の正門前を通過。アイルランドの独立運動で命を落とした人々を追悼するための場所。1916年イースター蜂起をはじめ、1798年の反乱、1803年、1848年、1867年、そして1919~1921年の独立戦争など、複数の世代にわたる戦いが対象 と。アイルランド語で「Tabhair cuimhneachan tiomnaíodh dóibh siúd a thug a beatha ar son saoirse na hÉireann」 【この記念碑は、アイルランドの自由のために命を捧げた人々に捧げられています。】と。その先にあったのがダブリンバス(Dublin Bus)のバス停「Parnell Square」。 時刻表、12分間隔で運転されているようであった。「ロトゥンダ病院(Rotunda Hospital)」の尖塔が斜め前方に姿を現した。・場所:Parnell Square、Garden of Remembranceのすぐ隣(東側)・建設:1757年開院。世界最古の産婦人科専門病院の一つ・特徴的な建築要素: ・この写真に写る銅緑色のドーム屋根付き塔(カッパーグリーンの色) ・隣接するRotunda Chapel(礼拝堂)やThe Rotunda Rooms(元は集会・舞踏会場)も有名「中央郵便局(General Post Office / GPO)」の屋上に立つ寓意像(Allegorical Statues)をズームして。ダブリン中心部のランドマークとして知られる 「Spire of Dublin(スパイア・オブ・ダブリン)」または正式には「Monument of Light(光の記念碑)」 を下から見上げて。場所:O'Connell Street(オコンネル通り)の中心高さ: 約120メートル(世界で最も高い彫刻の一つ)完成: 2003年設計者:イアン・リッチー・アーキテクツ(Ian Ritchie Architects)素材: ステンレス鋼(鏡面仕上げ)特徴:下部はやや太く、上部へ行くほど細くなる円錐形 上部は夜間にライトアップされ、「光の柱」となる建設目的:アイルランドの新時代の象徴として設計され、古いネルソン・ピラー (Nelson's Pillar)に代わる記念碑として設置された。下部はやや太く、一部の鏡面仕上げがアクセントになっていた。背景と歴史 ・ネルソン・ピラーという旧記念塔が、1966年にIRAによって爆破された後、長らく その跡地が空いていました。 ・1998年のミレニアムを記念して新たなモニュメント建設が決定され、2003年に完成。 ・近代アイルランドの都市美学・再生の象徴とされます。「Spire of Dublin」からN Earl St方向の「Portal(ポータル)」と呼ばれる双方向ライブ映像を映す円形スクリーンを見る。Portal(ポータル)👈️リンク とは?リトアニアのアーティスト・Benediktas Gylys 氏の創作による、大型の円形パブリックアート作品。各都市に設置されたポータルにはカメラとスクリーンが組み込まれており、異なる都市に設置されたポータル同士で24時間ライブ接続されます ダブリンのポータルは オコンネル通り(O’Connell Street)付近に設置されており、GPO(中央郵便局)とスパイア(The Spire)が視界に入る設置位置です。「GPO(General Post Office/中央郵便局)」が前方右側に。建築的特徴・正面に6本の巨大なイオニア式円柱を備えた堂々としたファサード。・切妻(ペディメント)上部には3体の彫像があり、中央にはアイルランド国旗を掲揚。・これらの彫像はギリシャ神話に由来する寓意像 と。オコンネル通り(O’Connell Street)の反対側にあったのが「クレアリーズ百貨店(Clerys Department Store)」。 ダブリンの中心部 O’Connell Street(オコンネル通り) に位置する歴史的建築物、「General Post Office(GPO / 中央郵便局)」を正面から。 ・このGPOは、1916年のイースター蜂起の中心地として非常に有名。・独立を求めるアイルランドの反乱軍がこの建物を占拠し、パトリック・ピアースがここから アイルランド共和国の独立宣言を行いました。・英軍との激しい戦闘によって建物は大部分が破壊され、現在見られるのは再建された ファサードとその一部。・現代においても、GPOはアイルランド独立の象徴的建築物とされ、これらの像も国家理念の 可視的表現として機能している。ペディメント(三角破風)上にある3体の彫像は、アイルランド国家を象徴する寓意像。寓意像(アレゴリー像)とは、抽象的な概念や思想を、具体的な人物や物体、物語などで表現したもの。中央:Hibernia(ヒベルニア)持物:姿勢:槍(または長杖)を持ち、頭上に王冠を戴く象徴:アイルランド国家そのもの解説:ラテン語でアイルランドを意味する「Hibernia」は、女性像として擬人化され、 国家の威厳と独立精神を表します。 槍は防衛・独立の象徴、王冠は主権を表す右側:Fidelity(フィデリティ/忠誠)持物:翼のついた兜、杖(カドゥケウス)を持つ象徴:忠誠心・信頼解説:鍵=秘密や信頼を守る象徴、犬=忠誠・献身の象徴動物。 国民の忠誠と国家への信頼を表している。左側:Mercury 持物:翼のついた兜、杖(カドゥケウス)を持つ象徴:通信・商業解説:ローマ神話の商業と通信の神。翼付きの兜=スピードと機敏さ、 杖(カドゥケウス)は交渉・交易・平和の象徴。郵便通信と商取引の重要性を表現。この像は、ダブリンの目抜き通りオコンネル・ストリート(O’Connell Street)に建つ「ジム・ラーキン(Jim Larkin)像」。・製作者:オリバー・シェパード(Olivier Sheppard)・建立年:1977年・像のポーズ:両手を高く上げた姿。演説中の情熱的な瞬間を表現・この像のポーズは1913年のロックアウト時に群衆へ演説する彼の姿を表したものであり 労働者の権利を訴える力強いメッセージ、または団結の呼びかけを象徴している と。この像は「ウィリアム・スミス・オブライエン(William Smith O'Brien, 1803–1864)の像」。後方に見える尖塔は「スパイア・オブ・ダブリン(The Spire of Dublin)」で、どちらもオコンネル・ストリートに位置。生年–没年:1803年 – 1864年職業:政治家、作家、ナショナリスト活動:1848年の「ヤング・アイルランド運動」指導者の一人。武装蜂起を企てたが失敗し、 逮捕・流刑にされた。後に恩赦を受けて帰国。思想:立憲君主制の下でのアイルランド自治を支持。ナショナリズムと文化的独立を訴えた人物。「ダブリンの路面電車「ルアス(Luas)」ゲール語(アイルランド語)で「Speed」を意味するLuas(ルアス)はダブリンで運行している路面電車。南北に走るグリーンライン(Green Line)と東西に走るレッドライン(Red Line)があり、平日であれば朝5時半頃から夜は24時頃まで比較的短い間隔で電車が走っているのであった。「ダブリンの路面電車「ルアス(Luas)」を利用し、「Four Courts Luas Stop」で下車。リフィー川に向かって「チャンセリー・プレイス」を南に歩き「O'Donovan Rossa Bridge・オドノヴァン ロッサ橋」を渡る 。 ダブリンの西方向を望んだ街路の風景で、奥に見える尖塔をもつ建物は「Christ Church Cathedral(クライスト・チャーチ大聖堂)」。 「Christ Church Cathedral(クライスト・チャーチ大聖堂)」をズームして。「Fr.マッシュー橋」の見える上流側を見る。 改修工事中のドームのある教会は「Church of the Immaculate Conception - Adam and Eve's」👈️リンク。正式名称: Church of the Immaculate Conception(無原罪の御宿りの教会)通称: Adam and Eve's Church(アダム&イヴ教会)所属: フランシスコ会(Franciscan Order)建設年: 現在の建物は1930年代に完成(地下礼拝堂などはそれ以前)所在地: Merchant's Quay, Dublin 8, アイルランド建築様式: ネオゴシック様式の要素を持つ背景: カトリック弾圧時代(17世紀)には「アダムとイヴ」という名の居酒屋を 偽装聖堂として使用していたのが由来 なぜ「Adam and Eve's」なのか? ・17世紀のイングランド統治下でカトリック信仰が禁じられていた時代、信者たちは 「Adam and Eve’s Tavern(居酒屋)」の地下でミサを秘密裏に行っていました。 ・そのため、現在の教会もその伝統を引き継いで「アダム&イヴ教会」と呼ばれています。正面から(写真はネットから)。正面に金文字で書かれているラテン語の銘文は:「SUB INVOC. MARIÆ. IMMACULATÆ. REFUGII PECCATORUM」 これは以下のように翻訳されます:【罪人の避難所である無原罪のマリアの御名において】(直訳:無原罪のマリア ― 罪人の避難所 ― の御名の下に)中央上部の銘文「D.O.M.」:ラテン語の略で、Deo Optimo Maximo(最善にして至高なる神に)。 キリスト教建築における奉献の言葉。屋根上の三体の像: ・中央:聖母マリア(無原罪の御宿り) ・両側:聖人または天使観光案内標識の右側上部には「1.Ardeaglais Theampall Chríost → Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂) → 中世創建のアングリカン教会の大聖堂 2.Dublinia(ダブリニア) → バイキングと中世ダブリンをテーマにした体験型博物館。 3.Halla na Cathrach → City Hall(シティホール) → ダブリン市庁舎。美しいロタンダと18世紀の建築。 4.Caisleán Bhaile Átha Cliath → Dublin Castle(ダブリン城) → ノルマン時代から続く要塞・行政施設。現在は政府行事などでも使用。 5.Ardeaglais Phádraig → St. Patrick's Cathedral(聖パトリック大聖堂) → アイルランド最大の教会堂。ジョナサン・スウィフトが学長を務めた。 6.Ardeaglais Theampall Chríost → Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂) → 中世創建のアングリカン教会の大聖堂。Winetavern StからAdam and Eve's Church(アダム&イヴ教会)のドームを見る。こちらからは、工事用の仮設足場は見えなかった。裏側から見る。「Adam and Eve's Church(アダム&イヴ教会)」の特徴 ・灰色の石造り: アイルランドの伝統的な石材である石灰岩を使用。質実剛健な印象。 ・大きな丸窓: 半円形アーチの大窓が採光を担っています。内陣のステンドグラスにもつながっています。 ・建物全体が高くて直線的: 中世風のロマネスク様式を思わせるシンプルな形状。バロックやゴシックのような装飾過多 ではありません。 ・屋根上のクロス(十字架)と鐘楼: キリスト教教会であることを象徴。小さな鐘楼(ベルタワー)も見えます。 ・左奥に柱と彫像が見える: これは正面ファサード(前面入口)部分の装飾です。そちらから見ると古典様式の円柱と 像があり、建築的に非常に荘厳です。「Wood Quay Venue」(ウッド・キー・ヴェニュー)の方向を示すとともに、公園の入場制限時間を案内していた。Wood Quay Venueとは? ・Wood Quay(ウッド・キー)は、ダブリン市の中心部、リフィー川沿いの地区で、 バイキング時代の遺跡が発掘された重要な場所です。 ・Wood Quay Venueは、その近くにあるイベント施設/展示会場で、文化イベントや会議、 展覧会などが行われます。 ・この施設はダブリン市議会(Dublin City Council)によって管理されています (案内板の最上部にある市のロゴもその証です)。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.06
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その69): Dublin市内散策(8/)・Jeanie Johnston~アビー教会~The Temple Bar~O'Connell Street Upper
「EPIC The Irish Emigration Museum」の見学を終え、River Liffey・リフィー川に出て「Seán O'Casey Bridge・ショーン・オケイシー橋」を渡る。 左手に見えたのが停泊している帆船「Jeanie Johnston(ジーニー・ジョンストン号)」Jeanie Johnston(ジーニー・ジョンストン号)・オリジナル建造年:1847年(アイルランド大飢饉時代)・用途:移民船として、アイルランドからカナダやアメリカへ移民を運んだ・特徴:この船では一人の死者も出さずに航海を終えたという点で有名・現在の船体:2000年代に復元されたレプリカ・役割:移民の歴史や大飢饉を伝える博物館船として、見学ツアーも実施中その先に見えたのが「Samuel Beckett Bridge(サミュエル・ベケット橋)」。 ・開通年:2009年・設計者:スペインの建築家・技術者 サンティアゴ・カラトラバ(Santiago Calatrava)・形式:斜張橋(cable-stayed bridge)・構造的特徴: ・アイルランドのハープ(アイリッシュ・ハープ)を模したデザイン ・橋自体が90度回転して開閉可能(通航用に可動する)👈️リンク よって、下記のJeanie Johnston(ジーニー・ジョンストン号)は閉じ込められて いないのであった。Jeanie Johnston(ジーニー・ジョンストン号)19世紀のアイルランドからの移民の歴史を象徴する帆船であり、現在はダブリン市内のリフィー川沿いに停泊する博物館船(再現船)として公開されているのであった。・船種 三本マストの木造帆船 高さ32m。・建造年 オリジナル:1847年/再現船:2002年完成・船内では当時の移民の生活や航海の様子を再現。・現在地 アイルランド・ダブリン、リフィー川沿い(カスタムハウス・キー)・用途 オリジナル:移民船(カナダ、アメリカへの移送) 再現船:博物館・教育・文化遺産・元船は10回の航海で2,500人以上の移民を北米へ運びながら、1人の死者も出さなかった。Jeanie Johnston(ジーニー・ジョンストン号)の帆を張った姿をネットから。「Samuel Beckett Bridge(サミュエル・ベケット橋)」から上流側の「The Custom House」のドームを見る。 先ほど訪ねた「Scherzer Rolling Lift Bridges」を再び。 リフィー川(River Liffey)沿いのバス停「Dublin City Centre (Custom House Quay)」に停車するDublin Express(ダブリン・エクスプレス)。 ・表示:「782」「HOTFAST」・行先:Dublin Airport(ダブリン空港)行きオコンネル橋(O'Connell Bridge)を見る。橋の上を複数のダブリンバス(緑・黄色)が走行中。ダブリンのオコンネル通り(O’Connell Street)南端付近を北向きに見た景観。中央の灰色の建物はFormer National Bank Building。・所在地:オコンネル・ストリートとダーメ・ストリート(D'Olier Street)の交差点角・建設年:1890年代・建築様式:フレンチ・ルネッサンス様式(屋根の急勾配や石材の装飾が特徴)・用途の変遷: ・元はNational Bank(ナショナル銀行) ・その後Ulster Bankとして使用され、現在はレストランや商業施設として再活用されています左側の像:Henry Grattan(ヘンリー・グラタン)像・Henry Grattan Monument・場所: College Green(トリニティ・カレッジ正門の向かい)・除幕: 1876年・設計: John Henry Foley により制作開始、完成は Thomas Brock・構成: ・中央にヘンリー・グラタンの立像 ・台座には4体の寓意像(自由、信教、統治、国家)そして、赤レンガの塔屋が目を引くのはIrish Nationwide Building Society旧本店。ダブリン市中心部(オコンネル通り周辺)から見た、アビー教会(Abbey Presbyterian Church)方面の景観。中央奥:St Andrew's Church(セント・アンドリュー教会) ・建設年:1860年竣工(現建物、何代目か) ・建築様式:ヴィクトリアン・ゴシック様式 ・特徴: ・高く鋭くそびえる尖塔(スパイア) ・灰色の石材で構成された重厚な外観 ・アーチ窓、バットレス、装飾的な彫刻が施された正面ファサード ・現用途:現在は教会としての機能はなく、観光案内所(Dublin Tourist Office)や 展示イベント会場などに使用されています。右側:かつてのUlster Bank(アルスター銀行)本店ビル ・重厚な石造ルネサンス様式建築左側:1970年代のコンクリート系モダニズム建築(市庁舎関連またはオフィスビル)ギフト ショップ・Carrolls Irish Giftsに立ち寄る。自分用そして土産用のCAP・帽子他を購入。アイルランド国内、特にダブリン市内に多数の支店がある土産店チェーンであると。主に観光客向けのアイリッシュギフトを取り扱っており、以下のような商品が人気 ・アランセーターやTシャツ ・クローバーやケルト文様の雑貨 ・ギネス関連商品 ・アイリッシュチョコレート、紅茶、雑貨などダブリン中心部、セント・アンドリュー通り(St Andrew Street) にあるモニュメントMonument Name: Crann an Oir(クラン・アン・オール/金の木)・アーティスト:Eamonn O'Doherty(エイモン・オドハーティ)・設置年:1991年・素材:金属(主にブロンズ製)、石(アーチ部分)英語名:“Tree of Gold”そしてアイルランド・ダブリンで最も有名なパブの一つ The Temple Bar(ザ・テンプル・バー)へ。真っ赤な外観と壁一面の花飾りで非常に目立つ夜間はイルミネーションで装飾されており、観光写真の定番スポット店名が「THE TEMPLE BAR」と店の外壁・赤い看板に複数箇所に記載されていた1840年創業の老舗パブアイルランドウィスキーの種類が特に豊富(世界最大級の品揃え)。伝統的なアイリッシュ音楽の生演奏が毎晩のように行われる。オイスター(牡蠣)などのアイルランド料理も楽しめる。名前の由来は、この地域一帯が17世紀にSir William Templeという人物の土地であったことから「Temple’s Bar(テンプルの小道)」と呼ばれるようになり、のちに「Temple Bar」として定着したのだと。夜になれば(ネットから)。TEMPLE BAR通り。Temple Bar通りは、アイルランド・ダブリン中心部にある歩行者専用の石畳の通りで、ダブリン市内の中でも最もにぎやかで観光客に人気の高いエリア「テンプル・バー地区(Temple Bar District)」のメインストリートのひとつ。多くのアイリッシュパブ、レストラン、ライブハウス、クラブが密集し、毎晩のように生演奏の伝統音楽(アイリッシュ・ミュージック)が。通りにはストリートパフォーマーや大道芸人も。ギャラリーや小劇場(Project Arts Centre など)、アートショップ、クラフト雑貨店なども点在していたのであった。「Buskers Bar」にて早めの夕食。時間は18:30前。アイルランドでの4人での最後の夕食を楽しんだのであった。Hさんは、明早朝の便で米国に住む娘さん・お孫さんに会いに行くのであった。そしてSさんも、その1時間遅れの便で帰宅の途に。Yさんと私は、翌日の夕方の便で、ロンドンへと向かうのであった。Oliver St. John Gogarty’s Bar(オリバー・セント・ジョン・ゴガティーズ・バー)。名前の由来はアイルランドの詩人・医師・政治家であり、文化人であったOliver St. John Gogarty(オリバー・セント・ジョン・ゴガティ)(1878–1957)にちなんで名付けられているとのこと。外壁は明るい黄色と黄緑色を基調に装飾され、非常に目立つのであった。建物全体に多数の国旗(アイルランド、米国、スウェーデン、日本、他)が掲げられ、観光客に歓迎ムードを演出。正面中央にはオリバー・セント・ジョン・ゴガティの銅像が立っていた(写真中央の人物像)。外壁に「BAR」「RESTAURANT」「ACCOMMODATION」と大きく書かれており、多目的施設であることが強調されていた。毎晩、アイリッシュトラッド(伝統音楽)の生演奏が行われ、外国人観光客に非常に人気 と。細い路地・Price's Lane(プライス・レーン)に掲げられていたのがダブリンのストリートアート&文化プロジェクト 「The Icon Walk(アイコン・ウォーク)」の案内板。「The Icon Walka registered charity, presents:THE PURPOSE OF THE ICON WALKIrish identity, that charming something that is largely regarded with a smile around the planet and which draws millions to visit this island nation.We are who we are and what we are, possibly as a result of chasing rainbows, mythical myths, druid’s spells or leprechauns gone inane from losing their crocks of gold.Celtic Tigers anyone? Perhaps; but not likely.More realistically we are the product of ourunique culture. This is how the distinct qualityis explained in a biography of G.B. Shaw by Frank Harris;"Like Shaw most of the greatmen of the Irish renaissance had to leave Ireland to provetheir greatness but at least they were born there. They breathed from infancy it's strangeair of realism and mysticism, it’s dignity with poverty, it’s love of scholarship, it’s wit as distinguished from gaiety and never got it quite out of their systems.”This walk through a gallery of Irish icons painted by a number of artists, living here in Dublin, attempts to allow one a sampling of this culture and hopefully whet the appetite to explore it further.We admit that we have omitted many more clues to this investigation than we haveincluded, and this is not a “best of” list but simply an introduction to those whom,among the many, we think will excite, deepen, flavour andinform your visit and your understanding of the Irish enigma.Take your time and enjoy the stroll through this slice of Irish land and when finished paya visit to our artists at The Icon Factory.」 【アイコン・ウォーク(登録慈善団体)がお届けするアイコン・ウォークの目的アイリッシュ・アイデンティティ――それは、世界中で親しみをもって微笑まれ、多くの人々をこの島国へと引き寄せる、どこか魅力的で捉えどころのない「何か」です。私たちが今ある姿、そして私たちの在りようは、もしかすると、虹を追い求めたり、神話のような伝説やドルイドの呪文、あるいは金貨の壺を失って正気を失ったレプラコーンなどの影響かもしれません。ケルティック・タイガースの影響? あるかもしれませんが、おそらく違うでしょう。もっと現実的に言えば、私たちは独自の文化の産物です。この特異な気質については、フランク・ハリスによるG・B・ショーの伝記にこう記されています「ショーと同様、アイルランド文芸復興の偉人たちの多くは、自らの偉大さを証明するためにアイルランドを離れなければならなかった。だが、少なくとも彼らはアイルランドに生まれた。彼らは幼いころから、現実主義と神秘主義の奇妙な空気を吸い、貧しさの中に誇りを持ち、学問を愛し、陽気さとは異なる機知を身につけ、それらは決して彼らの中から消え去ることはなかった。」このウォークでは、ダブリン在住の複数のアーティストたちによって描かれたアイルランドの象徴的な人物たちのギャラリーを通じて、その文化の一端を味わっていただき、さらなる探求への意欲を掻き立てることを目指しています。私たちは、この文化探求において、実際には取り上げきれなかった手がかりの方がはるかに多いことを認めています。これは「ベスト版リスト」ではなく、多くの中から、皆さんの訪問をより魅力的にし、理解を深め、味わいを加え、アイルランドという謎に満ちた存在を読み解く助けとなるであろう人物たちを紹介する、あくまで導入としての試みです。どうぞゆっくりと、このアイルランドの一片を巡る散策をお楽しみください。そして散策が終わったら、ぜひ「アイコン・ファクトリー」のアーティストたちの元へもお立ち寄りください。】「STARTING – WALL 1 AND 2.We have included remarks, observations, humour on many of the walls and on individual images which we hope will prove informative. We will not include these here. We intend for you to do this, to process them as part of your own individual experience. We know that no one, anywhere, has attempted this kind of process that you are about to engage in and that we will not know its efficacy until enough people have taken this short walk.We will speak to you again at the conclusion of the journey; let’s begin.When we Irish took over the governance of most of this island in 1922, we needed toform an identity of our self, firmly rooted in the new nation, its history and traditions. Thus began a process which continues even today. Back then we were mostly Catholic and republican and we even fought among ourselves about what being republican meant.Ontology is a metaphysical inquiry, inaugurated by Aristotle into what it means to behuman, however we have a more challenging task. We want to understand whatit means to be Irish and how we got that way.As we entered the 1920s there was a strong tradition of quality among the artisans, those who produced goods both functional and ornate, mostly for sale to the supporters of the crown. This group got a lot smaller after independence and many emigrated and standards suffered. Those who now got patronage from church and state did alright and Harry Clarke was an extraordinary Stained Glass Artist who received commissions from church and commerce.Wall One shows his work which is buried behind bars in a building now in the hands ofNAMA, an agency set up to protect the assets of the Irish Nation. They do this by turning the lights off and allowing this cultural treasure to go to seed. Attempts, to have it back-lit for you to enjoy, fell on deaf ears and we present it now as photographs in an obvious failing attempt to show a modest example of his work.Wall 2 samples the progression of outerwear from the twenties with the intention ofhonoring the quality of Irish materials. We produced great linen, tweed, lace, wool, leather but wore and used them in very conservative styles right up to the sixties when the world changed. The Clancy Brothers created a worldwide demand for Irish traditional sweaters. Half the homes in the West of Ireland were alive with thesound of knitting and traditional ballads.Irish designers joined the revolution and gave us popular style clothing.The years following the setting up of the Free State were cruel for the Irish and no less the world at large, a civil war, the failure of the German state, followed by the Great Depression and then World War II, were not fertile ground for the emergence of prosperity in a small island on the periphery of Europe. A general malaise took hold across the land. This was not helped by a very Conservative governance takingits lead from an equally conservative church overly intrusive in the lives of the citizenry. Millions left in search of opportunity. But change as coming, effected mainly by a culture created in post-war America and in the still dominant shadow of a diminishing empireacross the Irish Sea which was experiencing a cultural revolution of its own.」 【出発点 ― 壁1および壁2私たちは、多くの壁面や個別の画像に注釈や観察、ユーモアを込めています。それらが皆さんにとって有益であることを願っていますが、ここにすべてを記すことはしません。代わりに、それらを自ら体験し、読み解き、皆さん一人ひとりの体験の一部として受け止めていただきたいのです。このようなプロセスは、これまで世界のどこでも試みられたことがなく、皆さんがこれから関わろうとしているこの試みにどれほどの意味があるかは、十分な人々がこの短い道のりを歩んで初めて分かることでしょう。旅の終わりに、またお話ししましょう。さあ、始めましょう。1922年、私たちアイルランド人がこの島の大部分の統治を引き継いだとき、新たに生まれた国家、その歴史と伝統にしっかりと根ざした「自分たち自身のアイデンティティ」を築く必要がありました。こうして始まったこのプロセスは、今日に至るまで続いています。当時の私たちは、ほとんどがカトリックで共和主義者でしたが、そもそも「共和主義とは何か」について、私たち自身の間でも議論や対立があったのです。存在論とは、「人間であるとは何か」を問う形而上学的な探究であり、その問いはアリストテレスによって始められました。しかし、私たちにはそれ以上に困難な課題があります――「アイルランド人であるとはどういうことか」、そして「私たちはどのようにしてそうなったのか」を理解することです。1920年代に入った頃、アイルランドには、実用的かつ装飾的な製品を製作する職人たちの間で、高い品質を重んじる強い伝統がありました。これらの品々は主に、イギリス王室支持者たちに向けて販売されていたのです。しかし、独立後、この職人層は大きく縮小し、多くの人々が国外へと移住したことで、品質の水準も低下しました。一方で、教会や国家からの支援を受けることができた人々はうまくやっていました。その中でも、ハリー・クラークは傑出した存在であり、教会や商業界からステンドグラスの制作を依頼される、非常に優れた芸術家でした。ウォール1では、彼の作品を紹介していますが、その作品は現在、NAMA(アイルランド国家資産管理庁)が管理する建物の格子の奥に「埋もれて」います。NAMAはアイルランドの資産を守るために設立された機関ですが、実際にはこの文化財の照明を消したままにしており、劣化を放置しているのです。この作品を裏から照らし(バックライト)て鑑賞できるようにする試みもなされましたが、当局には聞き入れられませんでした。そのため、私たちは今、せめてもの策として、その作品の写真を掲示し、彼の作品の一端だけでもご覧いただこうとしています。ウォール2では、1920年代から1960年代にかけてのアウターウェア(外衣類)の進化を紹介しています。これもまた、アイルランド産素材の品質を称えるためのものです。リネン、ツイード、レース、ウール、革など、私たちは優れた素材を生産していましたが、それらは長い間、非常に保守的なスタイルで使用されていました。その潮流を大きく変えたのが1960年代――世界が大きく変わった時代です。クランシー・ブラザーズの活躍によって、アイルランドの伝統的セーターに世界的な需要が生まれました。アイルランド西部の家庭の半数では、編み物と伝統的なバラッド(物語歌)の音が響いていたといいます。アイルランドのファッションデザイナーたちもこの「革命」に加わり、流行のスタイルを私たちに届けてくれたのです。】「TESCO express」というイギリス系のスーパーマーケット前では、伝統的な観光用の馬車が歩道を走っていた。市内を流れるリフィー川(River Liffey)、そして中央に見えている橋は、ダブリンを代表する有名な歩道橋・ハーフペニー橋(Ha'penny Bridge)。・正式名称: ウェリントン橋(Wellington Bridge)・通称: Ha'penny Bridge(ハーフペニー橋)・完成年: 1816年・特徴: ・鋳鉄製の美しいアーチ型橋で、歩行者専用 ・かつて橋を渡るのに「半ペニー(Ha'penny)」の通行料が必要だったことが名称の由来です ・ダブリンのランドマークとして最もよく知られた橋のひとつこの橋はダブリン中心部、テンプル・バー地区(左岸)とオコンネル通り周辺(右岸)を結んでいます。背景に見える緑色のドームは、Four Courts(フォー・コーツ)の屋根で、アイルランドの最高裁判所などが入る歴史的建物。再び「The Spire of Dublin(ダブリンのスパイア)・別名: Monument of Light(光の記念碑)・建設年: 2003年・高さ: 120メートル・材質: ステンレススチール・設置場所: O’Connell Streetの中央、旧ネルソン・ピラーの跡地・意味・目的: ・モダンなアイルランドを象徴する記念碑として設計されました ・夜間には上部がライトアップされ、遠くからも視認可能路面電車はLuas(ルアス)という名前のダブリン市内を走る路面電車(トラム)。Rotunda Hospital (ロトゥンダ病院)。●世界最古の産科病院の一つ ・1745年、産科医バートロメウ・モスが「未婚の妊婦や貧しい女性のために安全な出産環境を 提供する」という理念で創設。 ・1757年には現地(Parnell Square)にロトゥンダ病院が正式開院。 ・当時の名称は "The Dublin Lying-in Hospital"(ダブリン産院)。●世界初の病院併設コンサートホール ・モスは資金調達のためにロトゥンダ(円形建築)ホールを建設。 ここで音楽会や催し物を開催し、病院の運営資金を得た。 このホールは現在の「The Rotunda(ロトゥンダ・ホール)」として残っており、 イベント会場として使われている。●医学教育の拠点 ・18~19世紀には産科医育成の中心地でもあり、世界中から学生が集まった。 ・現在もトリニティ・カレッジやUCDなどの医学部と連携し、臨床教育を提供。そして、ダブリン最後のホテルの「Maldron Hotel Parnell Square・マルドロン ホテル パーネル スクエア」に徒歩で戻ったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.05
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その68):Dublin市内散策(7/)・EPIC The Irish Emigration Museum(EPIC アイルランド移民博物館)-4
アイリッシュ・パブの伝統的な音楽セッションの様子を展示として再現した空間。「Eating and DrinkingThe Irish have made significant contributions to the world of food and drink and the Irishpub is a standard for genial hospitality and friendly socialising throughout the world.Although food in Ireland benefits from outstanding fresh ingredients, for members of the Diaspora, the taste of home is just as likely to be cheese and onion crisps, invented inIreland in the 1950s.While Irish food and drink have travelled the world, making whiskey and soda breadfamous, the Irish Diaspora has also contributed to the menus of others in othercountries. A number of French wine houses were founded by Irish emigrants or their descendants, e.g. the group known as the Wine Geese, while the French cognac houseHennessy was established by Richard Hennessy, an Irish officer in the army of Louis XV.」 【食と飲み物アイルランド人は、食と飲み物の世界において重要な貢献をしてきました。そしてアイリッシュ・パブは、世界中で温かなおもてなしと友好的な交流の象徴とされています。アイルランドの料理は、優れた新鮮な食材に恵まれていますが、ディアスポラ(海外に移住したアイルランド人)の人々にとっては、故郷の味といえば、1950年代にアイルランドで発明された「チーズ&オニオンクリスプ(ポテトチップス)」かもしれません。アイルランドの食や飲み物は世界中に広がり、ウイスキーやソーダブレッド(ソーダパン)を有名にしました。また、アイルランド系ディアスポラは、他国の料理メニューにも影響を与えてきました。たとえば、フランスのいくつかのワインハウスは、アイルランド出身の移民やその子孫によって設立されたもので、「ワイン・ギース(Wine Geese)」として知られるグループもあります。さらに、フランスのコニャック・ブランド「ヘネシー」は、ルイ15世の軍に仕えていたアイルランド人将校リチャード・ヘネシーによって創設されました。】アイルランドの伝統的なパブの内部を再現した展示空間。石造りのアーチ天井と木製のカウンター、壁の装飾、丸テーブルとスツール(背もたれのない椅子)、天井からのペンダントライトなど、雰囲気のある内装が特徴。現代アイルランドのアーティストやクリエイターたちを紹介する展示空間。左側:・ELIZA GRIFFOREX(イライザ・グリフォレックス) → 白黒の線画(風景画)と思われる作品が展示されています。・PHILIP TREACY(フィリップ・トレイシー) → オレンジ色の大きな帽子をかぶった人物の写真。彼は世界的に有名なアイルランド出身の 帽子デザイナーです。正面(映像): ・映像スクリーンには、カラフルなヘッドドレスをつけた人物が映されています (おそらくファッション系の展示の一部)。右側:・EDWARD QUINN(エドワード・クイン) → 海岸または砂浜に立つ人物のような写真。彼は主にモナコを拠点に活動したアイルランド人 写真家で、芸術家や著名人のポートレートで知られています。・ORLA KIELY(オーラ・キーリー) → 色とりどりのパターン柄。アイルランドを代表するテキスタイル&ファッションデザイナーで、 ミッドセンチュリー風の柄が特徴です。この展示は、「アイルランドの創造性」や「現代芸術」をテーマにしたセクションであり、アート、ファッション、写真、デザインといった分野で国際的に活躍するアイルランド系アーティストを紹介していたのであった。アイルランド出身の写真家 Edward Quinn(エドワード・クイン) に関する展示。グレース・ケリー(モナコ公妃)と思われる人物のポートレート写真が大きく表示されており、これはエドワード・クインが撮影した有名な写真の一つです。彼は1950年代から60年代にかけて、ヨーロッパのセレブリティ文化、特にフランス・モナコの上流階級を撮影したポートレート写真で知られています。第16ギャラリー「Creating and Designing(創造とデザイン)」に展示されているアイルランド系および国際的な芸術家を紹介するコーナー。左:FRANCIS BACON(フランシス・ベーコン) ・出身:1909年 ダブリン生まれ(イギリス系アイルランド人) ・職業:画家(特に20世紀を代表する具象表現主義) ・作風: ・歪んだ人体や苦悶の表情など、強烈で感情的なポートレートが特徴 ・死、暴力、存在の不安などを主題とする・展示作品(推定): ・《Self-Portrait》(自画像)あるいは《Head》シリーズのひとつ ・重層的な筆致と歪曲表現により、内面の不安や人間存在を描く右:JUAN O'GORMAN(フアン・オゴルマン)・出身:1905年 メキシコ生まれ(父がアイルランド人移民)・職業:画家・建築家・功績: ・メキシコのモダニズム建築と壁画運動を支えた重要人物 ・ディエゴ・リベラ、フリーダ・カーロとも交流・展示作品: ・自画像を中心に、複数の人物と建築的背景を織り交ぜた構成 ・教育、芸術、建築への深い関与を視覚的に語る壁画的スタイルフランシス・ベーコン(Francis Bacon) に関する説明パネル。「FRANCIS BACONFrancis Bacon was born in Dublin in 1909 to English parents. He grew up in Kildare, but left Ireland at 17.Widely acknowledged as one of the most important painters of the 20th century, Bacon’s work is concerned with suffering, violence and cruelty, expressed through the human figure. He had a very troubled relationship with Ireland – being the child of an Anglo-Irish family during the struggle for independence created a sense of conflict and tension that is visible throughout his art.Although he never lived in Ireland again, after his death the London studio where heworked was dismantled and reassembled in the Hugh Lane Gallery in Dublin.」【フランシス・ベーコンフランシス・ベーコンは1909年、イングランド人の両親のもと、ダブリンで生まれました。キルデアで育ちましたが、17歳でアイルランドを離れました。20世紀で最も重要な画家の一人と広く認められているベーコンの作品は、苦悩・暴力・残酷さを人間の肉体を通じて表現するものでした。彼はアイルランドと非常に困難な関係を抱えていました。アイルランド独立闘争の最中、アングロ・アイリッシュ(イギリス系アイルランド人)家庭に生まれたことが、内的な葛藤と緊張感を生み出し、それは彼の芸術の中に明確に現れています。彼はアイルランドに再び住むことはありませんでしたが、死後にロンドンのアトリエが解体され、ダブリンのヒュー・レイン・ギャラリーに再現されました。】 「Cedric Gibbons(セドリック・ギボンズ)」の説明パネル。「CEDRIC GIBBONSOne of the most lauded art directors in US film history, Cedric Gibbons is today bestremembered as the designer of the iconic Oscar statuette. Born in New York to Irish parents, Gibbons was educated in Brooklyn and studied architecture at the Art Students League of New York before becoming a draughtsman for Edison Studios in New Jersey.Gibbons designed almost 1,500 film credits as art director for the newly-formed studio MGM from the 1920s to 1950s, and won 11 Academy Awards for his work. These include Grand Hotel (1932), Pride and Prejudice (1940), The Yearling (1946), Little Women(1949), and An American in Paris (1951). He also designed the interiors of the familyhome he shared with his wife, Mexican actress Dolores del Río, a notable early Latinafigure in Hollywood. His clean modernist aesthetic shaped MGM’s production style and influenced the careers of later designers such as William Ferrari (1913–89), Hans Dreier(1885–1966) and Carroll Clark (1894–1968), and institutions like the Pasadena ArtInstitute and Museum of Modern Art.A founding member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, he is perhaps best known for designing the Oscar statuette itself, which was first awarded in 1929. It was sculpted by George Stanley and modelled on Mexican actor Emilio Fernandez, who agreed to pose nude for the design. The enduring image has become an iconic symbol of cinematic excellence.」【セドリック・ギボンズアメリカ映画史上、最も称賛された美術監督の一人であるセドリック・ギボンズは、今日ではアカデミー賞(オスカー像)のデザインをした人物として最も知られています。ニューヨークでアイルランド系の両親のもとに生まれ、ブルックリンで教育を受けた後、ニューヨークのアート・スチューデンツ・リーグで建築を学び、ニュージャージーのエジソン・スタジオで図面製作を担当しました。ギボンズは1920年代から1950年代にかけて、設立間もない映画会社MGMの美術監督として約1,500作品に携わり、アカデミー賞を11回受賞しました。代表作には『グランド・ホテル』(1932年)、『高慢と偏見』(1940年)、『子鹿物語』(1946年)、『若草物語』(1949年)、『巴里のアメリカ人』(1951年)などがあります。彼は妻であるメキシコ人女優ドロレス・デル・リオ(ハリウッド初期のラテン系女性スターの一人)と住んだ家のインテリアも手がけました。ギボンズのモダニズム的な洗練された美意識は、MGMの作品スタイルを形成し、ウィリアム・フェラーリ、ハンス・ドライヤー、キャロル・クラークといった後のデザイナーたちや、パサデナ美術館やニューヨーク近代美術館などの機関にも影響を与えました。また彼は、映画芸術科学アカデミー(AMPAS)の創設メンバーでもあり、最も有名なのはやはりオスカー像のデザインでしょう。像自体はジョージ・スタンリーが彫刻し、メキシコ人俳優エミリオ・フェルナンデスがモデルとして裸でポーズを取りました。この像は、映画の卓越性を象徴する永遠のアイコンとなっています。】 詩人ウィリアム・バトラー・イェイツ(W. B. Yeats)の映像インスタレーション。「StorytellingPerhaps the most enduring idea Ireland is that it is a country of stories and storytellers. With four Nobel laureates of Literature to its name, Ireland can be proud of its literary stature. The books, poems and plays of Ireland have reached across the world, often carried by actors from Ireland, such as Pierce Brosnan, or of Irish heritage, such as Princess Grace of Monaco, née Grace Kelly.The Irish ability to tell a good story has also helped broadcasters, comedians and journalists. Nellie Bly, whose grandfather emigrated from Derry / Londonderry tothe United States, was a pioneering 19th century investigative journalist.She travelled around the world in 72 days – emulating and bettering Jules Verne'sfictional character Phileas Fogg. More recently, Terry Wogan was the voice of the BBCRadio for many listeners, not to mention the quintessential Eurovision commentator.」【ストーリーテリング(物語の語り手たち)アイルランドを最も象徴する概念の一つは、「物語と語り手の国」であるということです。文学分野で4人のノーベル賞受賞者を輩出したこの国は、文学的な地位に誇りを持つことができます。アイルランドの書籍、詩、戯曲は世界中に広まりました。しばしば、それらはアイルランド出身の俳優(たとえばピアース・ブロスナン)や、アイルランド系の人物(たとえばモナコのグレース公妃、旧姓グレース・ケリー)の力で広められました。優れた物語を語るアイルランド人の能力は、放送者・コメディアン・ジャーナリストたちにも恩恵を与えました。たとえば、19世紀の調査報道記者として先駆的な存在であったネリー・ブライ(彼女の祖父はデリー/ロンドンデリーからアメリカへ移住)は、ジュール・ヴェルヌの架空の登場人物フィリアス・フォッグを模して、72日間で世界一周を達成したことで知られています。より近年では、テリー・ウォーガンがBBCラジオの名声ある声の持ち主として、多くの聴取者に親しまれ、ユーロビジョンの解説者としても象徴的な存在でした。】 「Storytelling(ストーリーテリング)」ギャラリー内で投影されている、「古代アイルランドの語り部「Seanchaí(シャンカヒー)」に関する説明。「SEANCHAÍAn ancient Irish oral storyteller whose tradition carried on through centuriesToday the legacy of the Seanchai inspires Irish actors, comedians, broadcasters and writers」【シャンカヒー(Seanchaí)古代アイルランドの口承による語り部であり、その伝統は何世紀にもわたって受け継がれてきました。今日では、このシャンカヒーの遺産が、アイルランドの俳優、コメディアン、放送者、作家たちにインスピレーションを与え続けています。】 Seanchaí(アイルランド語発音:シャンカヒー)は、アイルランドの伝統的な口承の物語伝承者であり、文字を用いずに神話・伝承・歴史・詩などを記憶し、語り伝える役割を担っていました。ケルト文化に深く根ざした存在であり、今日のアイルランド文学・演劇・メディアに多大な影響を与えています。第17ギャラリー「Storytelling 2」内の展示の一部。この空間では、アイルランドの移民たちが世界の舞台芸術、映画、テレビにおいていかに活躍してきたかを、視覚的かつ臨場感ある演出で紹介していた。もう一方のシアタールーム。第17ギャラリー「Storytelling 2」の終盤、「Comedy Club」セクション(スタンドアップ・コメディ)を表しています。第18ギャラリー「Literature(文学)」。奥の壁面(青地に白文字)多数の職業や肩書きが描かれていた:・Wordsmith(文の匠)・Wit(機知)・Director(映画監督)・Essayist(随筆家)・Journalist(記者)・Scriptwriter(脚本家)・Poet(詩人)・Actor(俳優)・Broadcaster(放送人) など中央に引用された言葉が:「NOBLE WORDS COME FROM A NOBLE HEART. LOOK OUT.COULD YOU STAND AT IT YOURSELF?— James Joyce, Ulysses」 【気高き言葉は気高き心から生まれる。気をつけろ。君はその場に立てるか?】 壁一面の書棚(左側)光に照らされた精巧なレプリカの革装丁風の書籍群が並びます。一見するとリアルな蔵書のようですが、アイルランドの文学的蓄積と豊かさを象徴する演出です。棚の色彩のグラデーションは、文体・ジャンル・時代を暗示しているとも解釈されます。 第18ギャラリー:Becoming Irish(アイルランド人になる)の展示空間。このギャラリーは、アイルランドにルーツを持たない人々が「アイルランド人」としてのアイデンティティを築いていくプロセスを描いています。帰化、婚姻、文化的同化など、血縁や出生に関わらず「アイリッシュになる」ことの意味を多角的に考察します。「on the move(移動中/移民としての旅)」 というテーマにフォーカスした展示エリア。「It is the entitlement and birthright of every person born in the island of Ireland, which includes its islands and seas, to be part of the Irish nation. That is also theentitlement of all persons otherwise qualified in accordance with law to be citizens of Ireland. Furthermore, the Irish nation cherishes its special affinity with people ofIrish ancestry living abroad who share its cultural identity and heritage.」 【アイルランド島(およびその島嶼・海域)で生まれたすべての人々には、アイルランド国家に属する権利と生得の資格がある。また、法律によりアイルランド市民となる資格を持つすべての人にも、同様の資格がある。さらに、アイルランド国家は、海外に住むアイルランド系の人々との特別な親近感を大切にし、彼らがアイルランドの文化的アイデンティティと遺産を共有していることを尊重する。】現代のアイルランド人女性がパスポートを持ち喜んでいる場面。帰化・再取得・帰国者・海外在住者などの象徴的表現。「ディアスポラ(離散した人々)とアイルランドとのつながり」をテーマに。右上:「diaspora tiesFor millions with Irish heritage, the passport is a symbol of identity and family connection.」【ディアスポラの絆アイルランド系の何百万もの人々にとって、パスポートはアイデンティティと家族のつながりの象徴です。】「finding rootsMaura Dade left Ireland for the US in 1951, aged 29.She and her husband raised a family in the US, but died never having returned to Ireland.Her daughter Cindy didn’t know much about her mother’s early life.When she died, Cindy decided to move to Donegal, the town where her mother grew up.She’s since written books about her family history, and even met long-lost cousins in Cork.Many people from Irish backgrounds, especially second and third generation Irish abroad,look to Ireland with interest.Some also see Irish passports as prized possessions.」 【ルーツをたどるモーラ・デイドは1951年、29歳でアメリカに渡りました。彼女は夫とともにアメリカで家庭を築きましたが、生涯一度もアイルランドには戻りませんでした。娘のシンディは、母の若い頃のことをほとんど知りませんでしたが、母の死後、母が育った町ドニゴールに移り住むことを決めました。彼女は家族の歴史に関する本を執筆し、コークで長らく音信不通だった従兄弟とも再会しました。アイルランド系の人々、特に海外に住む第2・第3世代のアイルランド系の人々は、アイルランドに強い関心を持っています。中にはアイルランドのパスポートを貴重なものと見なす人もいます。】中央右:「return migrationAisling O'Reilly’s grandparents were Irish immigrants to the US.She grew up in New York but often visited her grandparents in Ireland.After college in 2005, she returned to Ireland to work in the charity sector.She loved the sense of community she found there, and in 2020 she moved again –this time with her partner and two young sons.Aisling says, “Even though I was born in the US, I always felt connected to Ireland.Moving here as an adult just made me even more connected to those ties.”」 【エイシュリン・オライリーの祖父母は、アメリカへのアイルランド移民でした。彼女はニューヨークで育ちましたが、よく祖父母のいるアイルランドを訪れていました。2005年に大学を卒業後、彼女は慈善団体で働くためアイルランドに戻りました。そこで見つけたコミュニティの感覚を気に入り、2020年にはパートナーと2人の息子とともに再びアイルランドへ移住しました。彼女はこう語ります:「私はアメリカ生まれですが、いつもアイルランドとのつながりを感じていました。大人になってここに移住したことで、その絆はさらに深まりました。】左下:「eligibilityIreland’s history of emigration has created a wide diaspora of people of Irish descent.As of 2020, there were around 17 million people eligible for Irish citizenship through descent.Ireland allows anyone with an Irish citizen parent or grandparent to apply for citizenship.This has led to a major increase in passport applications – over 1 million in 2019 alone.Irish passports are often sought for practical reasons, like easier EU travel.But for many, they also represent identity, pride and a renewed connection to Ireland.」 【市民権の資格アイルランドの移民の歴史により、アイルランド系の広範なディアスポラが生まれました。2020年時点で、血縁を通じてアイルランド市民権を取得できる人は約1700万人と推定されています。アイルランドでは、アイルランド市民の親または祖父母を持つ人が市民権を申請できます。その結果、パスポートの申請は大幅に増加し、2019年だけで100万件を超えました。アイルランドのパスポートは、EU内の旅行が簡単になるなど、実利的な目的でも求められますが、多くの人にとって、それはアイデンティティ、誇り、そしてアイルランドとの新たなつながりの象徴でもあるのです。】右下写真はおそらく、1990年FIFAワールドカップでのアイルランド代表チームであり、その多くが国外(特にイギリス生まれ)の選手だったという歴史的背景を象徴していると考えられます。キャプションの正確な読み取りは困難であったが、「スポーツを通じたディアスポラの貢献」といったテーマが強調されているのではと。「移民と亡命者(Immigrants & Exiles)Some left Ireland for adventure, but many other departures were marked by trauma and exclusion.」 【ある者は冒険を求めてアイルランドを離れたが、多くの人々の出発は、トラウマや排除を伴う形で去る者が多かった。】写真右上は移民として海外に渡ったアイルランド人家族の姿。デモ行進の写真のプラカードには:「OUT OF OUR WAY: IRISH & QUEER & FIGHTING」【どけ、私たちの道を塞ぐな:アイルランド人で、クィア(性的少数者)で、闘っている!】これは、アイルランド出身の LGBTQ+ の人々が、差別と戦いながら海外で声を上げている姿を表しています。左下:「Banishing Irish」 アイルランド政府や宗教団体が、社会的に不都合とされた人々(特に未婚の母親など)を 国外に送り出す、あるいは隠すようにしていた政策に言及しているものと見られます中央下:「foreign adoptionsFrom the 1940s to the 1970s, thousands of Irish children were issued with passportsto allow them to be taken overseas for adoption. Many of the young people being adopted were so-called ‘illegitimate’ children born to unmarried mothers in religious-run mother-and-baby institutions and in other institutions, such as publicand private hospitals. For much of the 20th century, Irish unmarried mothers wereleft with no choice but to relinquish their children. Taoiseach Micheál Martin issueda state apology in 2021 to survivors of mother-and-baby institutions andcounty ‘homes’.」 【海外養子縁組1940年代から1970年代にかけて、数千人のアイルランドの子どもたちが海外で養子縁組されるためにパスポートを発行されました。養子に出された多くの子どもたちは、いわゆる「非嫡出子(婚外子)」であり、未婚の母親のもと、宗教団体が運営する母子ホーム(母と子の施設)や、公立・私立の病院などの施設で生まれた子どもたちでした。20世紀の大部分において、アイルランドの未婚の母親たちは、子どもを手放す以外に選択肢がない状況に置かれていました。この事実に対し、ミホール・マーティン首相(Taoiseach Micheál Martin)は、2021年に国家として謝罪を行い、母子ホームや地方の「ホーム」に収容されていた生存者たちに向けたものとなりました。】右下:「Daniel Doherty」 ・ダニエル・ドハーティは、1950年にアイルランドで生まれ、すぐにアメリカに養子に 出されました。・生後6週間で米国に渡り、70年後(2021年)に初めてアイルランド国籍のパスポートを取得。・自身のルーツを探し、アイデンティティと向き合った物語を象徴しています。この展示全体は、「移民」の美談的な側面だけでなく、苦難・強制・社会的排除といった負の歴史をも記録し、語り継ごうとするものであった。Gallery 19: Global Footprint 。右手の展示パネルには、「making a nation(国家をつくる)」の展示が続いており、アイルランドの国民形成とパスポートに関する説明があった。正面スクリーンでは、帰属意識やアイデンティティに関するインタビュー映像が上映されており、アイルランド系移民の経験や国籍の持つ意味を扱っていると推測されます。「making a nationThe introduction of the Irish passport was an important statement of national sovereignty.」 【アイルランドのパスポートの導入は、国家主権を示す重要な宣言だった。】「the northThe 1956 Nationality and Citizenship Act made Irish citizenship more easily availableto people born in Northern Ireland. For some, an Irish passport was proof of their national identity and cultural heritage.The Tyrone-born civil rights activist Bernadette Devlin chose to travel with Irish documentation even after her election to the British parliament. ‘It never occurredto me to get anything other than an Irish passport,’ she said. ‘I have been an MP since 1969; I was born an Irish citizen in 1947.’ The 1998 Good Friday Agreement acknowledged the right of Northern Irish people to hold either Irish or Britishcitizenship – or both.」【北アイルランド1956年の「国籍および市民権法」により、北アイルランドで生まれた人々にとってアイルランド市民権がより取得しやすくなりました。一部の人々にとって、アイルランドのパスポートは、自らの国民的アイデンティティと文化的遺産の証でした。ティロン県出身の公民権活動家バーナデット・デブリンは、英国議会議員に選出された後も、アイルランドの書類を使って渡航することを選びました。彼女はこう述べています:「アイルランドのパスポート以外を取得しようなんて考えたこともなかったわ。」「私は1969年から国会議員を務めていて、1947年にアイルランド市民として生まれたの。」1998年の「ベルファスト合意(グッド・フライデー合意)」は、北アイルランドの人々に、アイルランド市民権またはイギリス市民権、またはその両方を保持する権利を認めました。】「War & Peace(戦争と平和)」。展示は第二次世界大戦中のアイルランド移民の経験に焦点を当てています。「to britainThe outbreak of war put a halt to free movement across Ireland and the United Kingdom. For Irish as well as British citizens, war brought fear, separation and loss.UK industry faced an immense labour shortage, and Irish emigrants helped to fill the gap. More than 100,000 Irish people took on employment during wartime, working in Britain’s defence services, nursing and construction.」【戦争の勃発により、アイルランドとイギリス間の自由な移動は制限されました。アイルランド人もイギリス人も、戦争によって恐怖、別離、そして喪失を経験しました。イギリスの産業は深刻な労働力不足に直面し、それを補うために10万人以上のアイルランド人が戦時中にイギリスで働きました。彼らは防衛、看護、建設などの分野に従事しました。】 「occupied franceNazi occupation was a persistent threat for the several hundred Irish emigrants in France.Writer Peig Sayers wrote letters pleading with the Irish government to help bring home her son who was trapped in France. Many Irish citizens were also caught upin the occupation and forced to register with German authorities, while some even ended up in Nazi prisons.In 1944 Mary Elmes — later awarded a posthumous Righteous Among the Nations medal — helped to rescue Jewish children from deportation to Nazi camps, savingmany lives in the process.」【占領下のフランスナチスによる占領は、フランスに住む数百人のアイルランド移民にとって常に脅威でした。作家ペイグ・セイヤーズは、フランスに取り残された息子を帰国させるようアイルランド政府に嘆願する手紙を書いています。多くのアイルランド市民も占領下でドイツ当局に登録させられ、ナチスの刑務所に入れられた者もいました。1944年、後に「諸国民の中の正義の人」勲章を追贈されたメアリー・エルムズは、ユダヤ人の子どもたちをナチスの強制収容所への送還から救い、多くの命を救いました。】「in limboLaws have shaped — and at times blocked — the lives of Irish emigrants.During World War II, a number of Irish people found themselves in legal limbo.When Irish-American artist Francis Bacon returned to Britain after a trip to Dublin, he was interrogated by customs officers on suspicion of carrying subversive literature.Others were left stateless. Without official paperwork from Britain or Ireland, they werestuck in neutral territory, unable to claim any citizenship or protection.」 【宙ぶらりんの状態で法律はアイルランドからの移民たちの人生を形づくると同時に、時にはその道を阻んできました。第二次世界大戦中、何人かのアイルランド人は法的な宙ぶらりんの状態(legal limbo)に置かれることになりました。アイルランド系アメリカ人の芸術家フランシス・ベーコンが、ダブリンへの旅の後にイギリスへ戻った際には、反体制的な文書を所持している疑いで税関職員から尋問を受けました。他の人々は無国籍のまま取り残されました。イギリスやアイルランドのいずれからも公式な書類を得られず、どの国の市民権も保護も主張できない中立地帯に閉じ込められてしまったのです。】「global pathsIrish passports have facilitated travel across the world, whether for work,love or intellectual freedom.」 【世界へ続く道アイルランドのパスポートは、仕事、恋愛、知的自由を目的とした世界各地への渡航を可能にしてきました。】「on the road“My friends here are paralysed with horror at the thought of anyone going on a five-month trip with only a saddle bag of luggage, but the fact is that the further you travel the less you find you need and I see no sense in frolicking around the Himalayas with a load of inessentials.So I’m down to two pens, writing paper, Blake’s poems, map, passport, camera, comb, toothbrush, one spare pair of nylon pants and nylon shirt – and there’s plenty of room left over for food as required from day to day.”— Road diary entry of travel writer Dervla Murphy while cycling in India in 1963.」 【旅の途中でこちらの友人たちは、たったひとつの鞍袋に荷物を詰めて5か月間の旅に出るなんて話を聞くと、恐怖で身がすくむようです。でも実際には、旅をすればするほど、自分に必要なものは少なくなると気づくもの。私はヒマラヤを余計な荷物でうろうろすることに意味を感じません。だから私は、ペン2本、便箋、ブレイクの詩集、地図、パスポート、カメラ、くし、歯ブラシ、ナイロンの替えパンツとシャツ一枚を持って旅しています。そして日々必要な分の食料を入れるスペースは十分残っています。】「to canadaTrisha Higgins still has the sealed box OAPs (Old Age Pensioners) used to send home to Ireland filled with tea, clothes, and other essentials.She and her partner emigrated to Canada from rural Limerick in the 1980s andsettled in Halifax, Nova Scotia.She has worked as an outreach coordinator for the Irish Society of Nova Scotia and sings in two Irish choirs.」 【カナダへトリシャ・ヒギンズはいまだにOAP(年金生活者)がアイルランドに送っていた、紅茶や衣類、生活必需品の詰まった箱を大切に保管しています。彼女とパートナーは1980年代にリムリックの田舎からカナダに渡り、ノバスコシア州ハリファックスに定住しました。彼女はノバスコシア・アイルランド協会のアウトリーチ・コーディネーターとして活動し、2つのアイルランド合唱団で歌っています。】アイルランドからの移民の姓(Family Names / Surnames)が多数パネルに表示されていた。大きく強調された姓:「CUNNINGHAM」「MCLOUGHLIN」「MCBRIDE」「LYNCH」「TWOMEY」などは特に目立って表示されており、アイルランド移民の中でも人数や影響力が大きかったことを示唆しています。背景に見える数字:・例:「455 LYNCHs emigrated to the United States」 → 「LYNCH姓の人が455人、アメリカに移住した」という意味です。・「732」という数字も右下に見えます(おそらく別の姓に関する人数)。最後に 「FEEDBACK STATION(フィードバック・ステーション)」 。・来館者が展示に対する感想や満足度を評価・送信するための タッチスクリーン型の端末。・画面には、選択式の質問(5段階評価のバー)が表示されていた。そして、これは入館時に頂いた、EPIC The Irish Emigration Museum(アイルランド移民博物館)のパスポート風ガイド冊子の表面と裏面。そして「スタンプ・パスポート」の見開きページ。各セクション一覧(20セクション)番号 英語タイトル 和訳 1 An Open Island 開かれた島 2 Leaving the Island 島を去る(アイルランドからの出国) 3 Arriving in a New World 新世界への到着 4 Belief 信仰(宗教・精神的支柱) 5 Hunger, Work, Community 飢餓・労働・コミュニティ 6 Conflict 紛争 7 State and Society 国家と社会 8 Influence 影響力 9 Changing the Game ゲームチェンジャー(社会改革者・先駆者)10 Playing the World 世界での活躍11 Discovering and Inventing 発見と発明12 Leading Change 変革を導く13 Achieving Infamy 悪名を得た人物たち(悪役・物議を醸した人々)14 Music and Dance 音楽と踊り15 Eating and Drinking 食と飲み物(アイルランドの食文化)16 Creating and Designing 創造とデザイン17 Storytelling 1 物語の伝承①18 Storytelling 2 物語の伝承②19 Celebration 祝祭20 Connection つながり全ての展示コーナーでスタンプを頂いたのであった。そして、全ての見学を終え、地上階へエスカレータにて。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.04
コメント(0)
-
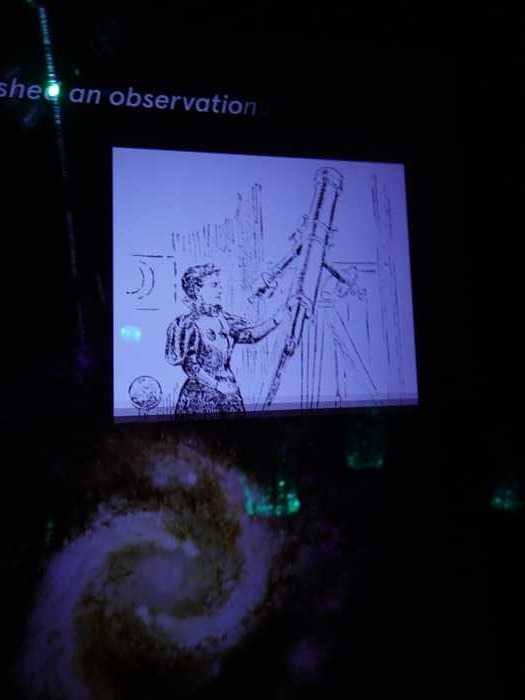
アイルランド・ロンドンへの旅(その67):Dublin市内散策(6/)・EPIC The Irish Emigration Museum(EPIC アイルランド移民博物館)-3
9世紀後半〜20世紀初頭の服装の女性が望遠鏡を操作している線画。「アイルランド出身女性科学者が宇宙の解明に貢献した」と。Margaret Lindsay Huggins(マーガレット・リンジー・ハギンズ)生没年:1848–1915職業:Astrophysicist(天体物理学者)出身地:ダブリン(Dublin)「Studied sunspots from the age of 10」【10歳から黒点(sunspots)の研究を始めた】画面下部には、黒点を映した太陽像の写真が表示されていた。主な業績: ・恒星や星雲のスペクトル写真撮影の先駆者。 ・夫と共に星の化学組成や運動を分析し、天体の物理的理解に貢献。 ・19世紀末の科学界において女性が主導的に活動した稀有な存在。中心に明るいバルジ(膨らみ)を持ち、そこから渦を巻くように腕が広がっている。これは典型的な渦巻銀河の構造。宇宙空間に無数の岩石が浮かぶ小惑星帯(asteroid belt)の写真か?小惑星帯とは? ・主に火星と木星の間に位置する帯状の領域。 ・太陽系形成時に惑星になり損ねた物質が残ったとされる。 ・代表的な天体:ケレス(準惑星)、ベスタ、パラスなど。この画像は、EPIC博物館における「アイルランド人の宇宙への貢献」を讃える展示の一部で、銀河→太陽→黒点→小惑星という宇宙スケールの旅を視覚的に展開しているのであった。そして次の展示はアイルランド系の著名な子孫たちを紹介するセクション。「アイルランド人の「世界への影響」の多様性(科学・政治・芸術など)。」 この展示は、ベルナルド・オイギンス(Bernardo O’Higgins)に関するもの。彼は、アイルランド系移民の子孫として南米で活躍した代表的な歴史人物の一人。・生没年:1778年 ~ 1842年・出身地:チリ(父親はアイルランド出身のアンブロシオ・オイギンス)・功績: ・チリ独立の父と呼ばれる。 ・スペインからの独立戦争を指導し、初代チリ共和国の最高指導者(Supreme Director) に就任。 ・独立後、奴隷制の廃止や土地改革、教育制度の充実などを推進。右上には第40代アメリカ合衆国大統領・ロナルド・レーガン(Ronald Reagan)の姿が。ロナルド・レーガン(Ronald Reagan)。・生没年:1911年~2004年・第40代アメリカ合衆国大統領(任期:1981年~1989年)・元ハリウッド俳優・カリフォルニア州知事を経て大統領に就任。・「レーガノミクス」やソ連との冷戦終結に向けた強硬外交などで知られる。・Great-Grandfather from Tipperary → 曽祖父がアイルランド・ティペラリー県の出身 と。展示パネル ・上段:アメリカ国旗を背景にした大統領演説中の写真 ・中央左:「Ronald Reagan」の文字とスピーチ用マイク(演説シーン) ・中央右:共和党全国大会(風船や拍手のシーン) ・下段左:星条旗に囲まれた演説会場の映像 ・下段右:アイルランド国旗が並ぶ演壇に立つレーガン(アイルランド訪問時)バラク・オバマ(Barack Obama)に関するもの。アイルランド移民の血筋が、アメリカの最高権力者にまでつながっている と。アイルランド系の血筋を持つ世界的リーダーを紹介する中で、彼もその一人として取り上げられていた。バラク・オバマ(Barack Obama) ・生年:1961年 ・第44代アメリカ合衆国大統領(2009年〜2017年) ・アメリカ初のアフリカ系大統領として歴史に名を刻んだ人物。 ・オバマの母方の先祖にあたるFulmuth Kearney(1830年生まれ)がアイルランドの County Offaly(オファリー県)Moneygall村の出身。 ・1850年ごろ、アメリカに移民として渡った。「Meet the Notorious Irish(悪名高きアイルランド人たち)」このセクションは、歴史的に「悪名高い」「一癖ある」と言われたアイルランド系移民やその子孫たちを紹介するコーナー。「Notorious(ノートリアス)」という語は… ・単なる「悪人」ではなく、 ・社会的に注目され、物議を醸した、あるいは型破りな人物、 ・あるいは「犯罪的な側面を持ちながらも魅力的・伝説的」な人物を含むのだ と。「アイルランド人の移民が世界で果たした多様な役割」をあらゆる角度から紹介。 ・「英雄」だけでなく、 ・「悪党・革命家・流れ者・海賊」なども含め、 ・アイルランド人のグローバルな影響力の広がりを示していたのであった。「Meet the Notorious Irish(悪名高きアイルランド人たち)」セクションの壁面パネル(新聞見出し風)展示このセクションでは、「アイルランド人の移民は、時に社会の周縁や地下世界でも存在感を示した」という歴史の一面を、ユーモラスかつ皮肉を込めて伝えていたのであった。「Achieving Infamy(悪名を馳せた人々)」セクションの締めくくりを象徴する展示。「Achieving InfamyOf course not everyone who left Ireland went on to lead an exemplary life. Some achieved notoriety through criminal exploits while others were infamous due to their bad luck.One such unlucky figure was Mary Mallon. Known to the popular imagination as Typhoid Mary, she spent 26 years in isolation after it was discoveredshe was a healthy carrier of typhoid fever and had caused 51 outbreaks of the deadly illness during her career as a cook in the northeastern United States before the First World War.Less pitiable members of our rogues' gallery include George Barrington, a London-based pickpocket who was eventually caught and transported to Australia, and "Machine Gun" Kelly, an American gangster who was imprisoned at Alcatraz.Outlaws like Ned Kelly in Australia and William McCarty, aka Billy the Kid, in the USA are often considered romantic figures of freedom and rebellion, despite their violent stories.」【悪名を馳せた人々もちろん、アイルランドを離れた人すべてが模範的な人生を歩んだわけではありません。中には犯罪行為によって悪名を馳せた者もいれば、不運によって知られることになった人もいます。そのような不運な人物の一人がメアリー・マロン(Mary Mallon)です。「腸チフスのメアリー(Typhoid Mary)」として広く知られ、第一次世界大戦前にアメリカ北東部で料理人として働いていた際に腸チフスの健康保菌者であり、この致命的な病気の流行を51回も引き起こしたことが判明した後、26年間も隔離生活を送りました。より同情の余地が少ない「悪名高きギャラリー」の面々には、ロンドンを拠点としたスリのジョージ・バリントン(後に逮捕されオーストラリアへ流刑)や、「マシンガン」ケリー(アルカトラズ刑務所に収監されたアメリカのギャング)などがいます。また、オーストラリアのネッド・ケリーやアメリカのビリー・ザ・キッド(本名:ウィリアム・マッカーティ)のような無法者たちは、暴力的な背景を持ちながらも、自由と反抗のロマン的象徴とされることが多いのです。】 この文章は、EPIC博物館の「移民の物語は栄光だけではなく、影の部分もある」というテーマを表現する核心メッセージ。特に: ・無法者(outlaw)と英雄のあいだの曖昧さ ・不運と誤解によって悪名を得た人物(例:タイフォイド・メアリー) ・移民の苦しみと社会からの排除といった現代的にも共鳴するテーマが、展示を通して伝わって来たのであった。この展示パネルは、アイルランド移民によって世界に広がった音楽とダンスの伝統について紹介。「Music and Dance: Sharing the TraditionThe Irish love of a tune travelled with them when they left in search of a better life.The mass emigration of famine times in the mid-19th century saw the music and dance of Ireland carried to Britain and America. In time, some of these forms were adapted and became part of popular entertainment on the American stage. The early 20th century arrival of new technologies – sound recording, radio and cinema – brought Irish talent to even bigger audiences.」 【音楽とダンス:伝統を分かち合うアイルランド人の音楽への愛は、彼らがより良い生活を求めて旅立つときにも、常に共にありました。19世紀半ばの飢饉時代の大量移民により、アイルランドの音楽とダンスはイギリスやアメリカへと運ばれました。やがてその一部は形を変え、アメリカの舞台芸術の一部として定着していきます。20世紀初頭には、録音技術・ラジオ・映画といった新たな技術の登場により、アイルランドの才能はさらに多くの観客へと届くようになりました。】この展示コーナーが伝えているポイントは: ・アイルランド移民は文化(特に音楽・ダンス)を持って旅立った。 ・それは新天地(特にアメリカ)で融合・進化し、ミュージカル・ショー・映画などへ。 ・テクノロジーの力で、その伝統が大衆娯楽の主流に躍り出た。代表的な例には: ・アイリッシュ・ダンス → 「リバーダンス」などに発展 ・ケルト音楽 → カントリー音楽やフォークのルーツの一部に「移民の旅立ち(The Departure)」を表現した映像演出の場面。 ・飢饉、貧困、抑圧から逃れるために、多くのアイルランド人が19世紀〜20世紀にかけて 海外へ移住。 ・多くはアメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスへ。 ・この映像は、その瞬間の「不安」「希望」「哀愁」を象徴的に描いたもの。次は「アイルランド音楽と詩の伝統」を象徴する展示の一つで、トマス・ムーア(Thomas Moore)とその名作「Moore’s Melodies(ムーアの旋律)」に焦点を当てていた。「Moore’s MelodiesThomas Moore’s collection of Irish Melodies, published between 1808 and 1834,was extremely popular among Irish emigrants in the 19th century.His lyrics, which were often sentimental and patriotic, were set to traditional Irish tunes, and they helped preserve a sense of Irish identity abroad.The melodies were shared in songbooks and performed in drawing rooms andpublic halls across Britain, America, and beyond.」 【ムーアの旋律トマス・ムーアの『アイルランド旋律集』は、1808年から1834年にかけて発表され、19世紀のアイルランド移民たちの間で非常に人気を博しました。彼の歌詞は、しばしばセンチメンタルで愛国的なものであり、伝統的なアイルランド民謡に合わせて書かれていました。これらの旋律は、国外におけるアイルランド人のアイデンティティの保持に大きく貢献しました。楽譜は歌集として配布され、英国・アメリカなどの社交室や公会堂で歌われました。】「音楽と文化の保存」に関する展示の一部で、フランシス・オニール(Francis O’Neill)という人物に焦点を当てていた。「To Preserve and ProtectDuring the closing decades of the 19th century, an ambitious undertaking to collect,preserve and publish Irish traditional music was masterminded by a Chicago Chief ofPolice, Cork native, Francis O'Neill (1848–1936).O'Neill's books included hundreds of unpublished tunes collected from immigrantmusicians, whom he also photographed and recorded on his Edison phonograph.」【保存し、守るために19世紀末、アイルランドの伝統音楽を収集・保存・出版する壮大な試みが行われました。その中心人物となったのは、アメリカ・シカゴの警察署長であり、コーク出身のフランシス・オニール(1848–1936)です。オニールの著作には、移民音楽家から収集された未出版の楽曲が数百曲以上収められており、彼は彼らを写真に撮影し、エジソンの蓄音機で録音することも行っていました。】この展示は、「移民が新天地で文化を失うどころか、それを保存・記録・継承しようとした」事例のひとつとして、オニールの活動を紹介しているのであった。「アイルランド移民と音楽録音産業の関わり」を示すセクションの一部であり、1920年代のアイリッシュ・ミュージック黄金時代に焦点を当てています。「The Record BusinessAt the moment when the record business became a commercial reality, a number ofexceptionally talented Irish immigrant musicians were in New York, the centre of the music business.Ellen O’Byrne De Witt, who founded an Irish music shop in New York, saw thepotential for quality recordings and her foresight helped create the "Golden Age" ofIrish music recording in the 1920s.」【レコード産業レコード産業が商業的現実となったその瞬間、数多くの優れたアイルランド系移民音楽家たちが、音楽産業の中心地であるニューヨークに集まっていました。エレン・オバーン・デ・ウィット(Ellen O’Byrne De Witt)は、ニューヨークでアイリッシュ・ミュージックの専門店を開いた人物であり、良質な録音の可能性を見出した先見の明により、1920年代の「アイリッシュ音楽録音黄金時代」を築く上で重要な役割を果たしました。】 Ellen O’Byrne De Witt とは? ・アイルランド系移民女性。 ・ニューヨークに音楽ショップを開き、演奏家とレコード会社をつなぐ存在に。 ・彼女の推進によって、伝統音楽が商業的に録音・流通されるきっかけが生まれました。 ・その結果、1920年代のアイリッシュ・ミュージック・レコーディングの黄金期が到来。アイルランド系移民コミュニティの集団写真を大型パネルで再現。「つながり、団結するアイルランド系移民」を象徴する目的で展示。海外に渡ったアイルランド人が、新天地でもコミュニティを築き、アイデンティティを保ったことを示すもの。写真に写る人々の数と密度が、結束力の強さと人数の多さ(移民の規模)を視覚的に訴えているのであった。「移民と社交文化(とくにダンスホール)」に焦点を当てたもので、アイルランド系移民が新天地で人と出会い、繋がり、未来を築いていった様子を描いている と。「Meet on the Dance FloorIrish societies, county clubs and dancehalls, filled with familiar accents and a home from home atmosphere, were important meeting places for immigrants in Americancities. It was common for a newly-arrived immigrant to be introduced at such gatherings to those Irish already established. Sometimes the new arrival had a job before the evening was over.There were 27 dancehalls in greater New York during the 1920s providing steady work for immigrant musicians, as well a meeting place for young men and women. Introductions on the dance floor often led to marriage.」【ダンスフロアで出会うアイルランド系の社交団体、郡人会、ダンスホールは、馴染みあるアクセントと言葉、そして「故郷のような雰囲気」に満ちた空間であり、アメリカ都市部における移民たちの重要な出会いの場でした。新しく到着した移民が、こうした集まりですでに定住している同郷のアイルランド人に紹介されることはごく一般的でした。時には、その夜のうちに仕事が見つかることさえあったのです。1920年代のニューヨーク大都市圏には、27のダンスホールがあり、移民音楽家にとって安定した仕事の場であると同時に、若者たちが出会う場所でもありました。ダンスフロアでの紹介が結婚に至ることも珍しくありませんでした。】 「アイルランド系音楽家と録音文化」に関する展示の一部で、ウィリアム・マラリー(William Mullaly)とジェームズ・モリソン(James Morrison)という2人の伝説的音楽家を紹介しています。金色の蓄音機(グラモフォン)ホーンの演出が、録音技術の歴史的雰囲気を際立たせています。この展示は、以下のようなメッセージを伝えています: ・「録音技術の発展」がアイルランド伝統音楽の保存と普及を可能にした ・アイルランドからの移民たちは、単に演奏者であるだけでなく、文化の継承者・記録者でもあった ・彼らの録音は、100年以上たった今でも再生可能であり、文化遺産として残っている「 WILLIAM MULLALY(ウィリアム・マラリー) ・楽器:コンサーティーナ(Concertina) ・活動時期:主に1920年代 ・意義: ・アイルランド伝統音楽の演奏家としては、最初期に録音されたコンサーティーナ奏者の 一人。 ・コンサーティーナという比較的マイナーな楽器を、録音・商業流通という形で残すことに 成功。 ・移民先のアメリカで録音されたレコードが、母国アイルランドにも逆輸入される形で 知られる。」「JAMES MORRISON(ジェームズ・モリソン) ・楽器:フィドル(バイオリン) ・生年:1893年(スライゴー県出身) ・活動拠点:アメリカ・ニューヨーク ・意義: ・1920年代〜30年代にかけて、アイルランド伝統フィドルの最重要人物の一人。 ・同時代のマイケル・コールマン(Michael Coleman)と並び称される。 ・自身のバンドを率いて多くの録音を残し、アメリカ移民社会でアイルランド音楽の象徴的存在 となった。」 アイリッシュ・ステップダンスとアメリカのタップダンスの融合と影響を視覚的に表現したビデオ・インスタレーションの一場面.「From Folk to CountryIrish music had a considerable influence on the development of music in the United States. The music skills brought by Irish and other immigrant groups combined with existing forms to create American folk music.Fiddle players with their repertoire of dance tunes – particularly lively reels and hornpipes– seem to have made the biggest impression. Uilleann pipers were also heard in different American settings but their uniquely Irish sound limited their appeal. The transition from the fiddle neck to the finger board of the banjo – an instrument of Afro-American origin – was not difficult for a musician to make and this allowed many fiddlers to adapt to thebanjo's rise in popularity.These two instruments became particularly associated with the new American soundwhich developed in the east coast and southern regions of the country – areas knownas Appalachia and the Ozarks – and which laid the foundations for Country and Western.」 【フォークからカントリーへアイルランド音楽は、アメリカ合衆国における音楽の発展に大きな影響を与えました。アイルランド系やその他の移民たちが持ち込んだ音楽の技術は、既存の音楽スタイルと融合しアメリカン・フォーク・ミュージックを生み出しました。特に、リールやホーンパイプといったダンスチューンのレパートリーを持つフィドル奏者は、最も強い印象を残したようです。ユニークな音色を持つイーリアン・パイプも一部で演奏されましたが、そのあまりにアイルランド的な響きがかえってアメリカの主流にはなりにくかったようです。一方、フィドルからバンジョーへの移行は比較的容易でした。バンジョーはアフリカ系アメリカ人起源の楽器であり、その人気の高まりとともに、多くのフィドル奏者が演奏に取り入れるようになりました。このフィドルとバンジョーという2つの楽器は、アメリカの東海岸や南部、特にアパラチア山脈やオザーク地方で発展した新しいアメリカ音楽と密接に結びつき、のちのカントリー&ウェスタン音楽の土台を築くこととなりました。】「Step Together(共にステップを)」の解説パネルです。アイルランド系移民のダンス文化が、アメリカでどのように変化・融合していったかを紹介していた。「Step TogetherTo this day, the yardstick of how well a piece of Irish dance music is played is the observation "it would make you want to get up and dance!" The Irish preoccupation withrhythm was usually what defined a good dancer and those men and women who excelled in the art stood out and were often revered in their communities.This admiration for a good dancer travelled with the immigrants and solo step dancing or clogging became a feature of stage shows. When other ethnic elements were combined with Irish steps – African-Americans had their own distinctive steps or shuffles – a new hard shoe style of dancing was created. This style was adopted by stage dancersand made its way to Broadway shows and into Hollywood musicals.」 【共にステップを今日に至るまで、アイルランドのダンス音楽がうまく演奏されているかどうかの基準は「思わず踊り出したくなるかどうか」という点にあります。アイルランド人はリズムに強いこだわりを持っており、それが優れたダンサーを定義する要素でした。そして、その芸に秀でた男女は地域社会の中で際立った存在となり、しばしば敬意をもって称えられました。この「優れたダンサーへの憧れ」は移民と共に旅をし、ソロのステップダンスやクロッグダンス(木靴ダンス)は舞台ショーの見どころの一つとなっていきました。他の民族の要素がアイルランドのステップと組み合わさると──たとえばアフリカ系アメリカ人の独自のステップやシャッフルなど──新たな「ハードシュー・スタイルのダンス」が生まれました。このスタイルは舞台のダンサーたちに取り入れられ、ブロードウェイのショーやハリウッドのミュージカルにまで発展していったのです。】Seosamh Ó hÉanaí(ショーサム・オ・ヘナイ / Joe Heaney)。「Sing a StoryEmigrants from Ireland's western seaboard travelled with their sean-nós (old style) songs. These were sung unaccompanied and in the Irish language. One of the greatest exponents of sean-nós was Connemara-born Seosamh Ó hÉanaí (1919–1984), who sang in English folk clubs and whose talents led to teaching positions in American universities.Singing in English was widespread in other parts of Ireland. These songs told stories of love, emigration, sporting encounters and war. Imported, these songs becamethe models for new compositions, about the railways, cowboy life, the civil war, mining,work injustices and other aspects of daily life.Many performers with no Irish heritage have been influenced by Irish songs. Versionsof Irish tunes have been recorded by Bob Dylan, Louis Armstrong and Johnny Cash.」【物語を歌うアイルランド西海岸出身の移民たちは、sean-nós(シャン・ノース、古い様式)の歌を携えて旅立ちました。これらの歌は無伴奏で、アイルランド語で歌われました。sean-nós の偉大な担い手の一人が、コネマラ出身の ショーサム・オ・ヘナイ(Seosamh Ó hÉanaí、1919–1984)です。彼はイングランドのフォーククラブで歌い、その才能からアメリカの大学で教鞭をとるまでになりました。アイルランドの他地域では、英語で歌われる歌が広まりました。これらは、恋愛、移住、スポーツの出来事、戦争といった物語を語るものでした。移民とともにアメリカに持ち込まれたこれらの歌は、鉄道、西部開拓、南北戦争、鉱山労働、労働の不正義など、日常生活に関する新たな作曲の手本となりました。アイルランドにルーツを持たない多くのアーティストたちも、アイルランドの歌から影響を受けています。 アイルランドの旋律を元にした楽曲は、ボブ・ディラン、ルイ・アームストロング、ジョニー・キャッシュといったアーティストたちにも録音されています。】「アイルランド移民と舞台芸術」に関係する内容が紹介赤いカーテンに囲まれた「小劇場」風のディスプレイでは、モニターに白いドレスを着た人物が登場する映像が流れていた。有名なアイルランド系の舞台女優、またはオペラ歌手のパフォーマンスを紹介する映像か?ミュージカルやバラエティ・ショーにおけるアイルランド系移民の貢献を示しているのであろう。アイルランド系の著名なクラシック音楽家たちを紹介する展示「Classical Concerts」の一部。左から1.John McCORMACK 1884年アイルランドのアスローン生まれの世界的なテノール歌手。2.John FEENEY 1896年、メイヨー州スウィンフォード生まれのバリトン歌手。3.Victor HERBERT 1859年ドイツ生まれ(アイルランド系)。作曲家、チェリスト、指揮者。4.Marie NARELLE 1870年、オーストラリア生まれの歌手。本名は Catherine Mary Ryan。アメリカ音楽界におけるアイルランド系音楽や歌の影響を示す「Tin Pan Alley(ティン・パン・アレー)」に関するもの。「Tin Pan AlleyThe place where popular music was made.In the early 20th century, a number of music publishers and songwriters set up businessin a part of New York City that became known as Tin Pan Alley. It was here that the sheet music industry flourished and where the business of creating and marketing popular songs took off.Irish American composers and lyricists were among the most successful. They included men like Chauncey Olcott, Ernest R. Ball, and George M. Cohan.The songs they created often sentimentalized Irish identity, telling tales of emigration, motherly love, and longing for the old country. The popularity of these songs helpedto shape perceptions of Irishness in America and beyond.」 【ティン・パン・アレーポピュラー音楽が生まれた場所20世紀初頭、ニューヨーク市の一角に数多くの音楽出版社や作詞・作曲家が拠点を構え、この地域は「ティン・パン・アレー」として知られるようになりました。ここでは楽譜産業が繁栄し、ポピュラー音楽の創作と販売が本格的に始まりました。アイルランド系アメリカ人の作曲家や作詞家たちは、その中でも特に成功を収めました。彼らの中には、チャンシー・オルコット、アーネスト・R・ボール、ジョージ・M・コーハンといった人物が含まれます。彼らが生み出した楽曲はしばしばアイルランド人としてのアイデンティティを感傷的に描き、移民の物語や母の愛、故郷への郷愁などをテーマにしていました。こうした楽曲の人気は、アメリカ国内はもちろんのこと、国境を越えて「アイルランドらしさ」への認識を形成する一助となりました。】「Classical ConcertsTraditional music and song had been aural traditions, learned ‘by ear’ and repetition.Formal instruction in music was not, in general, available to the majority of people.There were exceptions who received classical training and had successful careersperforming in concert halls around the world.」 【クラシック・コンサート伝統音楽や歌は、聴覚によって伝承され、「耳で聞いて」学び、繰り返しによって身につけられてきました。音楽の正式な教育は、一般的に多くの人々には提供されていませんでした。しかし、例外としてクラシック音楽の訓練を受け、世界各地のコンサートホールで成功したキャリアを築いた人々もいました。「A Global SensationDuring the mid-1990s, the Irish dance show Riverdance developed modern forms of Irish dance and music for global audiences.When the original seven-minute television presentation was being planned by RTEEurovision Producer Moya Doherty (and the subsequent expanded stage show, with music by Bill Whelan and directed by John McColgan)the lead female dancing part was taken by a Long Island Irish dancer of Mayo parentage,Jean Butler, and the lead male dancer in the original Eurovision staging of Riverdance and in the expanded full-length stage show that followed was Michael Flatley, a Chicago-born champion dancer whose father had emigrated from Sligo.Colin Dunne, a Birmingham-born championstep-dancer with Irish parents, later became lead dancer in Riverdance.Following its debut at the 1994 Eurovision Song Contest, the show opened in Dublinin 1995 and quickly became a global phenomenon with up to four versions of Riverdance touring the world simultaneously.In the 22 years since the show opened it has become an Irish cultural icon with the lead roles often being performed by dancers born in Canada,Australia, New Zealand, Scotland, England and the US.」 【世界的センセーション1990年代半ば、アイルランドのダンスショー《リバーダンス》は、アイリッシュ・ダンスと音楽の現代的な形を発展させ、世界中の観客に届けられるようになりました。最初の7分間のテレビ放送が、RTÉ(アイルランド放送協会)のユーロビジョン・プロデューサー、モヤ・ドハティによって企画されていた際(その後、音楽はビル・ウィーラン、演出はジョン・マッコルガンによって拡張されたステージショーが制作された)、女性の主役ダンサーにはメイヨー県出身の両親をもつロングアイランド在住のアイルランド系ダンサー、ジーン・バトラーが選ばれました。そして、オリジナルのユーロビジョン版《リバーダンス》、およびその後に制作された全長ステージショーで男性の主役を務めたのは、父親がスライゴーから移住してきたシカゴ出身のチャンピオン・ダンサー、マイケル・フラットリーでした。後に、アイルランド人の両親をもつバーミンガム出身のチャンピオン・ステップダンサー、コリン・ダンが《リバーダンス》の主役を引き継ぎました。1994年のユーロビジョン・ソング・コンテストでの初披露の後、1995年にダブリンで正式に公演が始まりました。そして、このショーは瞬く間に世界的な現象となり、最大4つの《リバーダンス》のカンパニーが同時に世界各地を巡回する規模となりました。初演から22年の間に、このショーはアイルランド文化の象徴的存在となり、主役の多くはカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、スコットランド、イングランド、アメリカ合衆国などで生まれたダンサーたちによって演じられています。】「Hollywood to Broadway」。ピンボケにて解読不能。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.03
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その66):Dublin市内散策(5/)・EPIC The Irish Emigration Museum(EPIC アイルランド移民博物館)-2
工場で作業する女性たちの歴史的映像。彼女たちはおそらく第二次世界大戦期または戦後の産業労働者であり、細かい部品の組み立て作業を行っているようであった。アイルランドから海外に移住した人々(特に女性)が、現地で工場や技術職などに従事した歴史を紹介しているのであった。特に第二次世界大戦中・戦後のイギリスなどでは、アイルランド系女性の労働力は重要視されていたのだ と。看護師の制服を着た3人の女性。アイルランド出身の女性が海外で看護師や医療従事者として活躍した歴史を紹介しているのであった。「The night before leaving, they are bidding goodbye And it’s early next morning, their heart gives a sigh They do kiss their Mothers and then they do say“Fare thee well, dearest Father, we must now go away.“」 【旅立ちの前夜、彼らは別れの挨拶を交わし、翌朝早く、胸が痛む。母に口づけをし、そしてこう言うのです。“さようなら、最愛のお父さん。私たちは行かねばなりません“】1200年代〜1700年代にかけてのアイルランド史の暗黒期を紹介。「1200s–1700sIreland suffered campaigns ofconflict, land confiscation and plantation」【1200年〜1700年頃アイルランドは、紛争、土地の没収、そして植民という一連の攻撃的な政策に苦しめられた。】この展示は、アイルランドがイングランド王国によって侵略・支配された時代を示している と。・conflict(紛争): 12世紀後半から始まるイングランドの侵攻(ノルマン人の到来)に始まり、アイルランド 各地で反乱や内戦が頻発しました。・land confiscation(土地没収): 特に16〜17世紀の九年戦争(1594–1603)やアイルランド連邦戦争(1641–1653)の後、 反乱に関与したアイルランド人の土地が没収された。・plantation(プランテーション): 没収された土地には、イングランドやスコットランドからのプロテスタント移民が送り込まれ、 先住のカトリック系アイルランド人を排除して「植民」する政策が進められた。 → これをPlantation of Ulster(アルスター植民)などと呼ぶ と。この時代は、アイルランド人にとって文化的・社会的抑圧の時代であり、後の大量移民(ディアスポラ)につながる重要な歴史的契機なのであった と。アイルランド系移民者は軍事・平和維持活動に関与した と。映し出されているのは、軍服を着た若者の胸像(ブロンズ像)で、おそらく国際平和維持活動に関わったアイルランド人兵士の記念像であろう。アイルランド大飢饉(Great Famine, 1845–1852)を象徴的に表現していた。雪または霜に覆われた荒れた畑で、一人の人物が地面を掘るこの光景は、飢餓によって荒廃した農地や、収穫の望みが絶たれたジャガイモ畑を暗示しているのであった。アイルランド大飢饉ではジャガイモ疫病(ポテト・ブライト)によって主食が壊滅。約100万人が餓死し、さらに100万人以上が海外(アメリカ、カナダ、オーストラリアなど)へ移民。イギリス政府の不十分な対応や土地政策が、多くの死者と社会的崩壊を招いた と。パトリック・サーズフィールド(Patrick Sarsfield)。Patrick Sarsfield(1655年頃 – 1693年)はアイルランドの軍人で、ウィリアマイト戦争(1689–1691)中にジャコバイト側で戦いました。1691年のリメリック包囲戦後、「ワイルド・ギースの飛翔(Flight of the Wild Geese)」と呼ばれる多くのアイルランド兵士のフランス亡命を主導。その後、フランス軍に仕え、オランダとの戦闘中に戦死 と。「ConflictAlthough Ireland's small army is now best known for its role in UN peace-keeping missions, the Irish have a long, proud military history. From Patrick Sarsfield, who led the flight of the Wild Geese, to Brendan (Paddy) Finucane, the Spitfire pilotwho was the RAF's youngest ever wing commander, Irish soldiers have served with honour in many armies.From the sixteenth century on, enlisting in foreign armies was a familiar escape from unrest or poverty at home. The British army has been a major beneficiary – the Wicklow village of Newtownmountkennedy saw the highest concentration ofWorld War I deaths of Britain and Ireland. Women have also been affected, either asfamily members or camp followers, or more rarely as combatants, often living as men.」 【紛争アイルランドの小規模な軍隊は、現在では国連の平和維持活動での役割で最も知られていますが、アイルランド人には長く誇り高い軍事の歴史があります。「ワイルド・ギース(野生の雁)」の脱出を導いたパトリック・サーズフィールドから、スピットファイアのパイロットであり、英国空軍(RAF)最年少の航空団司令官となったブレンダン(パディ)・フィニュカンに至るまで、アイルランド人兵士たちは多くの軍で名誉ある任務を果たして来ました。16世紀以降、外国軍への入隊は、国内の不安や貧困から逃れる手段として一般的でした。イギリス軍はその最大の受益者であり、ウィックロー県のニュートンマウントケネディ村は、イギリスとアイルランド全体で最も多くの第一次世界大戦戦死者を出した村です。女性もまた影響を受け、家族の一員や兵士の随行者として、あるいは稀ではありますが男装して戦闘員として参加する者もいました。】アイルランドにおけるカトリックへの抑圧政策を示すもの。画面には次のような内容が映し出されていたのであった。「A series of laws aimed to force Catholics to:Swear an oath to Elizabeth I of England as supreme spiritual governor1559 Act of SupremacySuffer death, imprisonment, transportation, or … The 1641 Rebellion Acts」 【カトリック教徒に強制するための一連の法律:・イングランド女王エリザベス1世を「最高宗教統治者」として誓うことを強要・1559年 至上権法(Act of Supremacy)・死刑、投獄、流刑、または……1641年反乱関連法に基づく刑罰に苦しむこと】背景・1559年 至上権法(Act of Supremacy) エリザベス1世が制定した法律で、イングランド国教会の最高統治者(Supreme Governor) として君主の権威を明記。これにより、ローマ教皇の権威を否認しない者は反逆者とされた。・1641年反乱(Irish Rebellion of 1641) アイルランドのカトリックがイングランド統治に対して起こした大規模反乱。これにより プロテスタントとの対立がさらに激化し、後のクロムウェルのアイルランド征服へとつながる。1652年の土地再分配法(Act of Settlement 1652)およびクロムウェルのアイルランド侵攻におけるカトリック聖職者の迫害を伝えるもの。「UNDER THE ACT OF SETTLEMENT 1652 CATHOLIC CLERGY COULD BE EXECUTED IF CAPTURED.REV. ROBERT BARRY WAS AMONG THE CATHOLIC CLERICS HUNTED DOWN AFTEROLIVER CROMWELL’S INVASION OF IRELAND.」 【1652年の土地再分配法(Act of Settlement)により、カトリック聖職者は捕らえられた場合、処刑される可能性がありました。ロバート・バリー師(Rev. Robert Barry)は、オリバー・クロムウェルのアイルランド侵攻後に追跡されたカトリック聖職者の一人でした。】イングランド側(特にクロムウェル派や議会派)の視点を再現したナレーションか登場人物のセリフであり、1641年のアイルランド反乱(Irish Rebellion of 1641)を指していると考えられる。「since their murderous rebellion was put down・・・・」 【彼らの殺人的な反乱が鎮圧されて以来。・・・・】単に「苦難の歴史」としてだけでなく、移民たちが新天地で社会に貢献し、変化に適応していった「前向きな側面」も強調。「After all, emigration is not just a chronicle of sorrow and regret.It is also a powerful story of contribution and adaptation.」 【結局のところ、移民の歴史は悲しみと後悔の記録だけではありません。それはまた、貢献と適応の力強い物語でもあるのです。】地下の展示通路の一部であっただろうか?石造アーチ天井:アーチ型の石造の天井と壁は、19世紀の倉庫(CHQ Building)を再利用した EPICミュージアムの特徴である と。1995年にアイルランドの詩人シェイマス・ヒーニー(Seamus Heaney)がノーベル文学賞を受賞したことを記念したもの。「1995Poet Seamus Heaney wins the Nobel Prize in Literature, joining the three previousIrish Nobel Laureates in literature,William Butler Yeats (1923),George Bernard Shaw (1925), andSamuel Beckett (1969)」 【1995年詩人 シェイマス・ヒーニー が ノーベル文学賞 を受賞。これは、アイルランド出身の以下の3人の先人たちに続く快挙である:・ウィリアム・バトラー・イェイツ(1923年受賞)・ジョージ・バーナード・ショー(1925年受賞)・サミュエル・ベケット(1969年受賞)】アイルランド系移民のスポーツ分野での功績や文化的影響を紹介する一場面。「WHAT A PLAY · NOW TAKING THE LEAD · HERE COMES JOHNNY」【なんというプレーだ! いまリードを奪った! ジョニーが来たぞ!】 「スポーツと移民の功績」セクションの一部であっただろうか?「スポーツ展示セクション」の一角。上部には格子状のフレームに、スポーツ選手が連続動作する様子を描いたストロボ的な動きのシルエットが浮かんでいた。来館者が操作しているのはマルチタッチ式のインタラクティブスクリーンで、アイルランド系移民が関わったスポーツ分野の功績、人物、映像などを体験的に閲覧できる展示。「スポーツと移民」セクションの一部で、プロジェクション映像とインタラクティブアートが組み合わさった展示空間。画面全体は緑と黒のモザイク状のグリッドで覆われており、中央が徐々に透明化(ピクセルが消えていくように)され、背景にラグビーかゲーリックフットボールの映像が現れて来たのであった。アイルランドのスポーツ文化と移民のつながりを象徴するセクション。左:青いジャージ(Aerolineas Argentinas) アルゼンチンのアイルランド系ゲーリック・フットボールチーム ロゴ:「Aerolineas Argentinas(アルゼンチン航空)」とあり、アイルランド系移民が 南米で設立したクラブチーム?中央:白とオレンジのバスケットボール型ユニフォーム ゲーリックバスケット(国際的展開の一環)、またはアメリカのアイルランド系クラブの可能性。右:赤と黄のジャージ(サイン入り) ベルギーやスペインにあるアイルランド系クラブのチーム?世界中のアイルランド系移民がゲーリック・アスレチック協会(GAA)のスポーツを通じて繋がっていることを示している。ゲーリック・フットボール👈️リンクは1チーム15人のプレーヤーによって行われ、長方形の競技場には両側にH型のゴールがある、アイルランドで最も人気のあるスポーツである。サッカーとバスケットボールの技術を要するスピーディーなゲームである。左:黒・緑・赤・白のユニフォーム 国旗モチーフのデザイン(南アフリカ共和国の国旗に類似) 南アフリカにあるGAAクラブ中央(白黒のユニフォーム) イギリス国内のアイルランド系クラブ右(黄・緑・黒のユニフォーム) アメリカのGAAクラブアイルランド系移民が世界各地でゲーリックスポーツを実践していることを象徴するユニフォームやスポーツ用品が並べられていた。 「GAA Equipment & Memorabilia ・South Africa Gaels GAA jersey ・St Joseph’s Swansea GAA jersey (Wales) ・Pittsburgh GAA jersey (USA) (Signed by Team) ・Manhattan Gaels GAA souvenir pin ・Handball ・North Syracuse GAA souvenir patch ・Poster advertising the now legendary 1947 All-Ireland Gaelic football final in the New York Polo Grounds ・Gaelic football」 【GAAの用具と記念品 ・南アフリカ・ゲールズのGAAユニフォーム ・セント・ジョセフズ・スウォンジー(ウェールズ)のGAAユニフォーム ・ピッツバーグ(アメリカ)のGAAユニフォーム(チームのサイン入り) ・マンハッタン・ゲールズのGAA記念ピンバッジ ・ハンドボール(ゲーリック・ハンドボール) ・ノース・シラキュース(アメリカ)のGAA記念ワッペン ・現在では伝説とされる1947年の全アイルランド・ゲーリック・フットボール決勝戦 (ニューヨークのポログラウンドで開催)のポスター ・ゲーリック・フットボール】GAA(Gaelic Athletic Association)はアイルランドの伝統スポーツ(ゲーリック・フットボール、ハーリング、ハンドボールなど)を統括する団体。ハーリング(Hurling)👈️リンクの国際的な広がりを紹介する展示.左:「EUROPE(ヨーロッパ)」 ヨーロッパにおいてもアイルランド移民によってハーリングが根付いている右:「ARGENTINA(アルゼンチン) 「Hurling matches were played weekly until World War I stopped the import of hurleys」 【第一次世界大戦がハーリー(ハーリング用のスティック)の輸入を止めるまで、ハーリングの 試合は毎週行われていた。】ハーリング(Hurling)は、アイルランド発祥の伝統的な球技で、ゲーリック・アスレチック協会(GAA)によって支えられている競技。19世紀末から20世紀初頭にかけて、アイルランド移民が多く渡った国々(例:アルゼンチン、オランダ、アメリカ)でも普及。アルゼンチンでは第一次世界大戦前まで盛んにプレーされていたが、ハーリー(木製スティック)の供給が戦争の影響で困難になったため、試合は衰退したという。これもハーリング(Hurling)展示コーナーの一部。ユニフォーム姿の男性たちが笑顔で手を振っている、古い時代のチーム集合写真(おそらく20世紀前半)。「Playing the WorldThe Gaelic Athletic Association (GAA) is a pillar of Irish society, so it is not surprising thatIrish emigrants have brought Gaelic games with them around the world.Today a fifth of the GAA’s clubs are outside Ireland. The majority are in theUnited Kingdom, the United States and Australia, but Gaelic games are also thrivingin such unexpected places as Malaysia and Kuwait.The global GAA has a long history: Argentina saw Gaelic games flourishing before World War I cut off access to the supply of Irish ash for making hurleys, the sticks used to carry and hit the ball in hurling.Although the games associated with the GAA, primarily hurling and Gaelic football, have historically been played in other countries by Irish-born immigrants, this has started to change in recent years. Players and even whole teams with little or no Irish connection are playing outside Ireland, as Gaelic games prove their worth even without the cultural history.」【世界でプレイされるゲーリック・ゲームゲーリック・アスレチック協会(GAA)はアイルランド社会の柱であり、アイルランド系移民たちが世界中にゲーリック・ゲームを広めたのは当然のことです。現在、GAAクラブの5分の1がアイルランド国外に存在しています。大半はイギリス、アメリカ合衆国、オーストラリアにありますが、マレーシアやクウェートといった意外な場所でもゲーリック・ゲームは盛んに行われています。国際的なGAAの歴史は長く、たとえばアルゼンチンでは第一次世界大戦以前にゲーリック・ゲームが盛んでしたが、その戦争がハーリング用のスティック(ハーリー)を作るためのアイルランド産トネリコの輸出を断ち切ってしまいました。GAAに関連する競技、主にハーリングとゲーリック・フットボールは、長らくアイルランド生まれの移民によって他国でも行われてきましたが、近年では状況が変わりつつあります。アイルランドにほとんど、あるいはまったく縁のない選手やチームがアイルランド国外で競技に参加しており、文化的な背景がなくてもゲーリック・ゲームの価値が証明されているのです。】 ゲーリック・ゲームの世界的な広がりを象徴するインスタレーション作品。中心から外へ放射状に広がる光ファイバー状の構造体 → ゲーリック・ゲーム(特にハーリングやゲーリック・フットボール)の精神と文化が、 アイルランドから世界中に拡がっていったことを象徴しています。青や緑に光るライティング → アイルランドの伝統色(緑)とスポーツのエネルギー(青)を表現。人間の眼球の虹彩と血管網を強調した映像表現か?「アイルランド文化のグローバル展開」を示す展示で使用されている映像演出であろう。・アイデンティティの核心(目)を通じて、ゲーリック文化を見る/見られる・視神経のような「つながり」を世界中に張り巡らせるアイルランド人の精神・目を通じた「体験」=見ることによる共感や文化的継承氷の結晶(クリスタル)と雪の結晶(スノーフレーク)をモチーフにした映像インスタレーションの一場面。アイデンティティの多様性と個性 ・雪の結晶は「二つとして同じものが存在しない」とされる ・→ アイルランド系ディアスポラ(移民)の多様な存在を象徴冷たい地で育つ「文化の核」 ・氷の結晶=厳しい環境(国外)で結晶化したアイルランド文化 ・海外に根を張るゲーリック精神や文化の「純度・硬度」ネットワーク的な連なり ・結晶構造は、前のネットワーク構造と連続性がある ・= 世界中に広がるアイルランド系住民とその文化的絆アイルランド出身の女性科学者 Dame Kathleen Lonsdale(キャスリーン・ロンズデール女史)に関する展示の一部。「First female professor atU...Dame Kathleen Lonsdale(1903 – 1971)CrystallographerFrom Kildare」 【初の女性教授初の女性教授(おそらく University College London)キャスリーン・ロンズデール女史(1903年 – 1971年)結晶学者キルデア出身(アイルランド)キャスリーン・ロンズデール女史(1903年 – 1971年)結晶学者キルデア出身(アイルランド)】植物の葉の表面を顕微鏡で拡大した映像。背景には葉脈(veins)が網のように広がり、そこに細長い構造物(おそらく菌糸(hyphae)や繊維)のようなものが交差していた。・自然界におけるネットワーク構造の可視化・生命のつながりや情報伝達の視覚表現・科学とアートの融合映像展示ベンゼン(benzene)および六塩化ベンゼン(hexachlorobenzene)の構造解明に関する展示。「Discovered the structure of benzene and hexachlorobenzene」【ベンゼンおよび六塩化ベンゼンの構造を解明した】タンポポ(dandelion)の変化を映像で表現している場面。中央には、まだ開いている途中のオレンジ色の花(タンポポの花)が。背景には、タンポポの綿毛(種子と冠毛:pappus)が精細に広がっている。「生命の構造」や「自然界のパターン」「拡大されたミクロの世界」などをテーマに 。ロバート・ボイル(Robert Boyle, 1627–1691)について紹介。「Robert Boyle (1627–1691)Natural Philosopher,Chemist, Physicist,and InventorFrom Waterford」 【ロバート・ボイル(1627年〜1691年)自然哲学者、化学者、物理学者、そして発明家ウォーターフォード出身】ロバート・ボイルはアイルランド出身の著名な科学者で、「近代化学の父」と称される人物。特に有名なのは:・ボイルの法則(Boyle’s Law):気体の体積と圧力の関係を表す法則 (温度一定のもとで、気体の圧力と 体積は反比例する)・実験に基づいた自然科学の方法論を重視し、錬金術から近代化学への移行を象徴する存在・科学革命期の王立協会(Royal Society)の創設メンバーの1人ロバート・ボイルの法則(Boyle's Law)について説明。「Coined Boyle's Law:If the volume of a gas is decreased,the pressure increases exponentially」 【ボイルの法則を定式化:気体の体積が減少すると、圧力は指数関数的に増加する】アイルランドの天文学者ローズ・オハロラン(Rose O’Halloran) についての紹介。「・Made and published maps of sunspots ・Rose O’Halloran (1866–1930) ・Astronomer ・From Tipperary」 【・黒点の地図を作成し、出版した ・ローズ・オハロラン(1866年〜1930年) ・天文学者 ・ティペラリー出身】地球を宇宙空間から見た映像の一部で、ほぼ半分が暗闇に覆われた状態(昼夜の境界「ターミネーター」)で表現されていた。 ・地球の生命圏の脆弱性と美しさ ・科学者たちの業績がどのように地球観・宇宙観に寄与したか ・人類が理解し始めた「地球という存在」の全体像 ・マクロ視点(宇宙)とミクロ視点(結晶、細胞、原子)のつながり を表しているのであろう。太陽の表面を描いた映像。太陽のダイナミックなエネルギー活動や、核融合による膨大なエネルギー放出を視覚的に示しているのであった。黒点(sunspots)の地図を作成・公表したことで知られているRose O'Halloran(1866–1930)の業績を視覚的に示しているのであろう。「Made a year-long sky survey in Auckland, New ZealandRose O'Halloran(1866 – 1930)AstronomerFrom Tipperary」 【ニュージーランド・オークランドにて1年間にわたる天体観測調査を実施ローズ・オハローラン(1866年 – 1930年)天文学者ティペラリー出身】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.02
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その65):Dublin市内散策(4/)・Custom House Quay(カスタム・ハウス・キー)~EPIC The Irish Emigration Museum(EPIC アイルランド移民博物館)-1
さらにリフィー川に沿って歩きLoopline Bridgeを潜ると左前方に現れたのが、Custom House Visitor Centre・歴史博物館。アイルランド政府によって整備された公共の歴史展示施設で、アイルランドの近代史とカスタム・ハウス自体の歴史を中心に紹介していた。この日は入館しなかったがCustom House Visitor Centre の展示内容をネットから。1. 1921年「カスタム・ハウス襲撃(Burning of the Custom House)」 ・アイルランド独立戦争中(1921年5月25日)のIRAによる放火攻撃。 ・建物の大部分が炎上し、多数のアイルランド共和国軍兵士が捕えられた歴史的事件。 ・展示では: ・焼失したアーカイブ(記録)と建物の被害状況 ・攻撃の政治的・戦略的背景 ・英国当局の反応 ・関係者の証言や回想録(映像・音声あり) ・復元作業の記録(1930年代の再建)2. カスタム・ハウスの建築史とジェームズ・ガンドン ・建築家 James Gandon による設計の背景(1780年代) ・建築素材(ポータランド石、アイルランド産石灰岩など) ・ドームや彫像、河川女神像の象徴的意味 ・建設当時のダブリンの街の姿と経済活動(港町としての重要性)3. 税関・港湾とアイルランド経済の発展 ・18~19世紀の関税行政の中枢としての役割 ・輸出入品の管理、税金徴収の仕組み ・港湾労働者や役人の生活、制服、帳簿など実物展示 ・アイルランドの商業・物流の変遷も紹介4. アイルランド国家の形成とダブリンの変遷 ・アイルランド独立(1922)への道のりを描く年表と解説 ・カスタム・ハウスが政治の象徴として果たした役割 ・国旗、憲法草案、ダブリンの都市計画なども展示5. 展示の形式 ・パネル展示(英語・一部はアイルランド語との併記) ・タッチスクリーンのインタラクティブ解説 ・模型(建物全体・ドーム内部など) ・映像:事件の再現ドキュメンタリー、関係者インタビュー ・子ども向けワークシート、学校団体用ガイドありリフィー川越しのCustom House Visitor Centreの写真をネットから。カスタム・ハウス(The Custom House)正面上部に掲げられている石造の紋章(紋章装飾)をズームして。下記写真はネットから。正面ファサードの特徴1.中央ドーム: ・緑青色の銅製ドーム ・ドーム下には四方に時計(四面時計) ・頂上に立つ像は「Commerce(商業)」の女神像で、商業の象徴であると。2.コリント式列柱(中央玄関部): ・大きな柱で構成されたポーチ ・ギリシャ神殿風のペディメント(三角破風)には彫像が並ぶ3.彫像群:・ペディメントや屋上にはアイルランドの主要河川を象徴する川の女神像が多数配置されている・建物の東西両端にも彫像装飾が見える(王冠付きの盾とライオンなど)4.建築様式:・新古典主義建築(Neoclassical)・対称的な構造、アーチ、列柱、幾何学的均整が特徴頂上に立つ「Commerce(商業)」の女神像を見上げて。正面から。(ネットから)左から順に1. Mercury(マーキュリー) ・左端、翼のある兜と杖(カドゥケウス)を持つ青年神。 ・商業・流通・旅行の守護神。 ・古代ローマ神話由来、商業建築によく登場する。2. Plenty(豊穣) ・農産物・穀物・花輪などを持つ女性像。 ・アイルランドの土地の豊かさ、穀物貿易の象徴。3. Industry(勤労) ・道具や織機、歯車などを持つことが多い。 ・この像は女性で、衣服を整えながら堂々と立ち、勤勉と産業を象徴。 ・中央の正面寄りに配置。4. Neptune(ネプチューン) ・最右端、三叉槍(トライデント)を持つ男性像。 ・海の神として港湾都市ダブリンの性格を示す。 ・アイルランドの貿易が海上輸送に依存していたことを象徴。掲げられた2つの旗・左側:アイルランド国旗(緑・白・橙) ・独立国家としてのアイルランドを象徴・右側:欧州連合旗(青地に12星) ・EU加盟国としての現在のアイルランドの立場を示すカスタム・ハウス(The Custom House, Dublin)のドームを斜めに見上げて。カスタム・ハウス(The Custom House, Dublin) の中央正面入口(ポーチ部)を見上げて。巨大なコリント式円柱・正面入口は2本の巨大な円柱に支えられたポルティコ(列柱玄関)に包まれています。・柱頭はこの角度では見えないが、通常この建物ではコリント式(花飾り付き)を採用。アーチ上部の彫刻(ケンタウロス風の顔)・ファンライト上部には、ギリシャ・ローマ風の神話的な顔面彫刻(キメラ?)が。 ・恐らく建物の設計者 ジェームズ・ガンドンが用いた装飾様式で、知性・威厳・監視を 象徴するモチーフと。 ・顔の上にはリボン装飾や小花模様が配置され、全体として荘厳かつ幾何学的に 整えられていた。ドブリン中心部を流れるリフィー川(River Liffey)に架かる「タルボット記念橋・Talbot Memorial Bridge」を見る。「タルボット記念橋・Talbot Memorial Bridge」の袂の建物を見る。とんがり屋根の小さな塔は、Busáras(ダブリン中央バスターミナル) の近隣にある St. Mark’s Church(旧教会施設) の一部。中央右赤レンガの建物は廃墟化した元倉庫または住居跡であろうか?。おそらく19世紀後半~20世紀初頭に建てられたレンガ造の典型的ジョージアン様式。前方に現れたのがビジネス センター「IFSC House」。ダブリンの国際金融地区である IFSC(International Financial Services Centre) 内にある象徴的なオフィスビルで、金融業や多国籍企業が集中するエリアの一部を構成 と。「IFSC HOUSE」と。International Financial Services Centre(国際金融サービスセンター)。その先にあったのが、アイルランド・ダブリン港エリアにある非常に特徴的な可動橋「Scherzer Rolling Lift Bridges(シャーツァー式転轍可動橋)」。地元では「North Wall Scherzer Bridges」とも呼ばれていると。ダブリン港のNorth Wall Quay(ノースウォール埠頭)に架かっている、2連の小型可動橋。 ローリングリフトブリッジ(ROLLING Lift Bridge)は、可動橋の一種で、水上交通を通過させるために跳ね上げる際に、転動機構を使用して開閉する橋。この橋は、カウンターウェイトを使用して、橋が開く際の動きをバランスさせているのだ と。これは 1913年の「Scherzer Rolling Lift Bridge Company」(米シカゴ)による広告(Ad) で、当時の可動橋技術の中でも特に画期的だった Scherzer式跳ね上げ可動橋(Rolling Lift Bridge) を大々的に宣伝する内容。「Scherzer ROLLING Lift Bridges cost less than other movable bridgesbecause they are the Extreme of Simplicity.Scherzer ROLLING Lift Bridges are used all over the world because they use the onlyprinciple for moving a bridge that anyone would consider for moving any kind of land traffic. They ROLL (or rock) a short distance on part of a wheel, just as all land traffic rolls all distances on whole wheels.But Scherzer ROLLING Lift Bridges have a great advantage over other ROLLING stock. They do not use friction-causing axles, trunnions and journals to support the bridge. Using only part of a wheel, they do away with this constant trouble and expense.Scherzer ROLLING Lift Bridges ROLL upward and back awayfrom the water, leaving the channel entirely clear in thirtyseconds, also forming a signal and barrier against accidents.Or they roll forward and down, closing the channel in thirtyseconds. Traffic has practicallyno interruption becauseScherzer ROLLING Lift Bridges do not start to open until avessel is almost upon them and they close before it is morethan a few feet away.Scherzer ROLLING Lift Bridges combine economy, simplicity,efficiency. They adapt to movable bridges the greatestmechanical principle—the ROLLING principle.Scherzer Bridge foundations are simpler and cost less because Scherzer Bridges are simpler and weigh less than any other movable bridge.ScherzerROLLING Lift Bridge Co.Main office: Monadnock Block, Chicago, U.S.A.」 (Deep waterways carry raw materials inland. Factories increase, population and landvalues go up. Railroads must distribute the finished materials away from the deep waterway. Everyone is benefited because business is stimulated.)【シャーツァー・ローリング・リフト・ブリッジは、他の可動橋よりもコストがかかりません。なぜなら、それは極限まで単純化された構造だからです。シャーツァー式ローリング・リフト・ブリッジは世界中で使われています。というのも、この橋は「橋を動かす」という行為において、あらゆる陸上交通の移動手段として誰もが思い浮かべる唯一の原理を応用しているからです。つまり、橋は車輪の一部の上を転がる(または揺れる)だけで短い距離を移動します。これは、すべての陸上交通が完全な車輪によってあらゆる距離を移動するのと同じ理屈です。しかし、シャーツァー・ローリング・リフト・ブリッジには、他のローリング式構造と比べて大きな利点があります。それは、摩擦の原因となる車軸やトラニオン(旋回軸)、軸受けを使用せず、橋を支えているという点です。車輪の一部だけを使うことで、これらの絶え間ないトラブルと費用を排除しています。シャーツァー式ローリング・リフト・ブリッジは、橋桁を水面から上方へ、かつ後方へ転がすようにして持ち上げ、わずか30秒で水路を完全に開放します。この動作はまた、事故防止のための信号や障壁の役割も果たします。また、橋は前方に転がりながら降下し、水路を閉じるのにも30秒しかかかりません。交通はほとんど妨げられません。というのも、シャーツァー橋は船がほぼ至近まで近づくまで開き始めず、船が通過すると数フィート以内で閉じるからです。シャーツァー・ローリング・リフト・ブリッジは、経済性、簡素性、効率性を兼ね備えています。この橋は、可動橋に最も優れた機械原理——ローリング(転がす)原理を適用しているのです。シャーツァー橋の基礎構造はより簡単で、建設費も安く済みます。なぜなら、シャーツァー橋は他のどんな可動橋よりも構造が単純で、重量も軽いからです。(深い水路は、原材料を内陸部へ運びます。工場が増え、人口が増加し、土地の価値も上昇します。鉄道は、完成した製品をこの深い水路から各地へ配送しなければなりません。こうして経済活動が活性化することで、誰もが恩恵を受けるのです。)シャーツァー・ローリング・リフト・ブリッジ社本社:米国イリノイ州シカゴ、モナドノック・ブロック】「タルボット記念橋・Talbot Memorial Bridge」を再び。その先にSt. Mark’s Church(旧教会施設)も再び。リフィー川北岸の遊歩道、FSC地区(International Financial Services Centre)にある有名な彫刻群・Famine Memorial(飢饉記念像)👉️リンク。作者: Rowan Gillespie(ローワン・ギレスピー) アイルランドの著名な彫刻家(1948年生)制作・設置: 1997年 アイルランド政府とIFSCの再開発プロジェクトの一環で設置この彫刻群は、1845年~1852年の「アイルランド大飢饉(Great Famine)」で餓死・移民を余儀なくされた無数の人々を追悼するものであると。彫像の特徴: ・合計7体のやせ細った男女(大人・子ども) ・手に鍋、布包み、赤ん坊を抱く姿 ・足元は裸足やぼろぼろの靴 ・前かがみで港に向かって歩き出す姿勢(=「出国」・「脱出」)表すもの: ・飢餓 ・絶望 ・故郷を捨てて移民船に向かう人々の行進 ・アイルランドの移民史と記憶の継承写真左側の人物像:・フードをかぶった女性・胸に赤ん坊を抱きしめるように持ち、両手の指を大きく開いた姿・憔悴した表情で、やや上を見上げている・→ 母性・苦しみ・祈り・絶望の象徴右側の人物像:・帽子をかぶった男性 ・腕に大きな包み(布に包まれた荷物)を抱える・頭を少し下げ、視線は落ちているように見える ・→ 労働者・責任・疲労・喪失の象徴肩に子どもを背負った父親像。骨と皮ばかりになったような痩せた男性が、気を失った、または死亡した子どもを肩に背負って歩いている。男性の首は前に垂れ、極度の疲労・悲しみ・絶望感が表情と姿勢から読み取れます。子どもはだらりと垂れ下がり、生気がない姿が。正面から。目:大きく開き、焦点の定まらない瞳。 → 飢餓による衰弱、または喪失による絶望を象徴。口:半開きで、歯がむき出しになっている。 → 言葉を失った苦しみ、あるいは叫びを抑えた状態を表す。皮膚:ひび割れ、荒れた質感。 → 飢饉による病や栄養失調、疲労の蓄積を表現。頭部全体:うつむきがちに前に傾いている。 → 負担の重さ、精神的な疲弊。そして、この後に訪ねたEPIC The Irish Emigration Museum(EPIC アイルランド移民博物館)。EPIC アイルランド移民博物館の前にあった歴史的構造物Customs House Dock Entrance Arch(カスタムハウス・ドック入口アーチ)。建設時期:18世紀末(約1790年代)由来:元々はこの一帯にあった倉庫施設の出入り口アーチの一部関連施設:すぐ隣にある建物は、かつての「Customs House Tobacco Store」 (税関たばこ倉庫)で、現在は「CHQビル」として再活用されていた。構造:灰色の切石(石灰岩)を積み上げた堅牢な造り アーチ部は放射状のヴォールト状(円弧構造)そして4人で入館。EPIC The Irish Emigration Museum。「EPIC」は:"Every Person Is Connected(すべての人はつながっている)"の意と。入館受付。「WELCOMEAt the heart of Ireland's story is the movement of our people. The Irish identity has been shaped by migration. People left and still leave our island for many reasons, some pushed by circumstances at home, others pulled by opportunities abroad.Many emigrant stories are linked by common motivations and shared experiences.Today, these emigrants and their descendants number over 70 million people, in all four corners of the globe. Here, we tell their stories.」 【ようこそアイルランドの物語の中心には、私たちの人々の移動があります。アイルランド人としてのアイデンティティは、移民によって形づくられてきました。人々はさまざまな理由でこの島を去り、そして今も去り続けています。なかには故郷の事情に追われるようにして、またなかには海外での機会に引き寄せられて旅立った人もいます。多くの移民の物語は、共通する動機や体験によって結ばれています。現在では、これらの移民とその子孫の数は世界中で7,000万人以上にのぼります。ここでは、彼らの物語を語っていきます】インタラクティブな映像ガイドには館長?の姿が。展示ギャラリーのテーマ構成と主な内容EPICの展示は以下4つのカテゴリーに分類されている と。1. Migration(移民の歴史) ギャラリー(ギャラリー1〜2) ・紀元500年以降のアイルランド人の移民パターンを紹介。 ・宗教布教、飢饉(Great Famine)、社会・宗教的迫害、犯罪者の流刑、外国紛争への 関与などをテーマにした展示。2. Motivation(移民の動機)(ギャラリー4〜7) ・飢饉や貧困、宗教迫害、機会追求など、移民を決断した背景を具体的な事例と共に解説。3. Influence(移民が与えた影響)(ギャラリー8〜18) ・政治、ビジネス、アート、文学、科学、音楽、スポーツなど、世界中で活躍した アイルランド出身者の功績紹介。 ・グレース・ケリー、ジョン・F・ケネディ、ブラッド・オバマや、意外なルーツをたどれば チェ・ゲバラの先祖もアイルランド出身など、約300名以上の移民に関する ストーリーを収録4. Diaspora Today(今日のディアスポラ)(ギャラリー19〜20) ・世界全体でアイルランド系人口が7,000万人以上に及んでいる現状を示唆。 ・「Irish Family History Centre」で個人の家族史やDNA調査が可能な サービスコーナーも装備「PASSAGE OF YEARS(年月の経過)」Galleryの入口。展示エリアのひとつには、来館者が写真や映像を撮るスポットとしても設計された「体験型・視覚演出空間」も。光の柱(LEDパネル)の通路:柱状のLEDディスプレイに自然風景(海・川・森など)が映し出されていた。「An Open Island(開かれた島)」というパネル。「An Open IslandWe start with memories of the land left behind.Images of unforgettable Irish landscapes –the Maumturk Mountains of Connemara,the Ring of Kerry, the Giant’s Causeway andKillarney National Park – have been carriedin the hearts of emigrants on long voyagesto foreign shores.For thousands of years Ireland’s geographicaland cultural landscape has been shaped bywaves of people arriving and departing.Ruined stone cottages and overgrownlazy-bed furrows pay testament to Ireland’slong history of departure. The diverse, richand varied character of its people trulyreflects Ireland’s story of emigration.For those who left, Ireland is a beautiful,often mythologised, homeland.」 【開かれた島私たちは、置いてきた土地の記憶から出発します。忘れがたいアイルランドの風景──コネマラのマウムターク山脈、ケリー周遊路、ジャイアンツ・コーズウェイ、キラーニー国立公園──これらの情景は、遠く異国の地への長い航海の中で、移民たちの心に抱かれ続けてきました。何千年にもわたり、アイルランドの地理的・文化的風景は、人々の「到来」と「旅立ち」の波によって形づくられてきました。崩れかけた石造りのコテージや、草に覆われたレイジー・ベッド(伝統的な畝)は、この地が長きにわたって「旅立ちの地」であったことの証しです。アイルランドの人々の多様で豊かな個性は、まさにこの移民の歴史を物語っています。故郷を後にした人々にとって、アイルランドは美しく、そしてしばしば神話的に語られる「心の故郷」なのです。】金属製の帆船模型が複数並び、背景には映像モニターが。「Watch the routes travelled by Irish emigrants over the centuries」 【アイルランド移民が何世紀にもわたって辿ったルートをご覧ください】アイルランドからの移民の出発地点と初期の航路を示す展示の一部。地図にはアイルランド全土の主要な港町が赤い点で示されていた。白字の説明文:"The first settlers depart from harbours in the east for Britain's west coast"【最初の移民たちは、アイルランド東部の港からイギリス西海岸へと出発した】これは、アイルランドからの初期の移住者(settlers)が、主にアイルランド東海岸の港を利用して、イングランド・ウェールズ・スコットランドの西海岸へ渡っていったことを示していた。アイルランドから世界各地へと広がった移民ルートを視覚的に示した地球儀型のインスタレーション。イギリス、ヨーロッパ、北米、南米へと次々に。Gallery 3: "The Journey"であっただろうか?放射状に広がる無数の金属製オール(櫂)は、アイルランドから世界へと放たれる無数の移民たちの出発を象徴。上部に浮かぶように設置された帆船模型は、時代と共に使われてきた移民船の発展を表す: ・帆船(18〜19世紀) ・蒸気船(19世紀中頃〜) ・航空機(20世紀中盤以降、奥の方にジェット機らしき形も)Gallery 「Arriving in a New Land"(新天地への到着)」 に関係する展示。Howard Family Trunk(ハワード家のトランク)。「Howard Family TrunkThis trunk has been in the Howard family since the 1930s and has been half-way aroundthe world, and back. It was bought by Henry and Mary Howard who lived in Cork. Henry worked in the local shipyards but when these started closing, the family decided to emigrate to England in 1938. Before leaving they bought this trunk from a second-handshop and you can see the original owner's initials (ST) on the side.They packed their possessions into the trunk and set sail for Liverpool with their six children: Gertie, Mary, Sadie, Archie, Harry and George.The family settled in Birkenhead (near Liverpool) where Henry worked in the famousCammell Laird shipyard. Birkenhead was heavily bombed by the Luftwaffe in 1940 and 1941 but the Howard family survived, becoming part of the local parish community ofSt Werburgh’s. In 1951 Archie married Eva (née Daley) and they too had six childrenincluding their son, Peter.In 1958, Henry and Mary moved back to Ireland along with their beloved steamer trunk. As Gertie, Archie and Harry were married they stayed in England, but Mary, Sadie and George followed their parents to Ireland. The family opened a guest-house inWaverley Avenue in Fairview (Dublin), and remained there until 1963, before sailing back across the Irish Sea, complete with trunk, to reunite the family.In 1981 Peter and his wife Jean immigrated to South Africa where, like his grandfather, he hoped to secure a brighter future. Peter recalls the relief he felt when the trunk arrived in Johannesburg with their personal items. Returning to England in 1985, trunk in tow, they settled in Warrington, with the trunk eventually becoming a toy boxfor their grandchildren.In 2021, Sadie Howard died shortly after her 100th birthday. The family have since donated the trunk to the museum so its story, spanning three generations and over eight decades, can live on.」 【ハワード家のトランクこのトランクは1930年代からハワード家に受け継がれており、地球の半周以上の旅をして再び戻ってきました。このトランクはコークに住んでいたヘンリーとメアリー・ハワード夫妻が購入したものです。ヘンリーは地元の造船所で働いていましたが、閉鎖が始まったため、1938年に一家でイングランドへ移住することを決断しました。出発前に彼らは中古品店でこのトランクを購入し、側面には元の持ち主のイニシャル「ST」が見られます。家族は所持品を詰め込み、6人の子ども(ガーティー、メアリー、セイディー、アーチー、ハリー、ジョージ)とともにリバプール行きの船に乗りました。一家はリバプール近郊のバーケンヘッドに落ち着き、ヘンリーは有名なキャメル・レアード造船所で働きました。バーケンヘッドは1940年と1941年にルフトヴァッフェ(ドイツ空軍)の激しい爆撃を受けましたが、ハワード一家は生き延び、地元のセント・ワーバーグ教区共同体の一員となりました。1951年、アーチーはエヴァ(旧姓デイリー)と結婚し、2人の間にも6人の子どもが生まれました。その中に息子ピーターがいます。1958年、ヘンリーとメアリーはこの愛用の蒸気船用トランクとともにアイルランドへ戻りました。ガーティー、アーチー、ハリーは結婚していたためイングランドに残りましたが、メアリー、セイディー、ジョージは両親とともにアイルランドへ移りました。家族はダブリンのフェアビュー地区ワーヴァリー・アベニューでゲストハウスを開業し、1963年までそこに暮らした後、再びアイルランド海を渡ってイングランドへ戻り、家族全員が再会しました。1981年、ピーターと妻ジーンは南アフリカに移住します。祖父と同じように、より良い未来を求めてのことでした。ピーターは、ヨハネスブルグに到着したときにこのトランクが無事に届いていたときの安心感を今も覚えていると言います。1985年、彼らはイングランドに帰国し、ウォリントンに定住しました。このトランクはその後、孫たちのおもちゃ箱として使われました。2021年、セイディー・ハワードは100歳の誕生日の直後に亡くなりました。その後、家族はこのトランクを博物館に寄贈し、この3世代・80年以上にわたる物語が永く語り継がれることとなったのです。】歴史を通じて国外へ渡ったアイルランド移民を代表する6名を示しています。背景の映像に表示されている名前と人物像は以下の通り。左から右へThomas Quinn ・聖職者・宣教師系の人物と推定されます。 ・典型的な黒い衣服とロザリオを持つ姿から、カトリック教会関係者で、移民先で宗教的支援を 行った可能性があります。Anne Carey ・近代的な服装で、1960〜1980年代頃の女性移民を表現しているようです。 ・キャリア・移動の自由・自己実現を求めた世代の象徴とも考えられます。Katherine McDonagh ・19世紀中葉の服装で、恐らく大飢饉時代の女性移民。 ・荷物も持たず、慎ましい身なりから、困窮した農民階級を象徴。Dónall Mac Amhlaigh ・アイルランド語名で、1950年代のイギリス移民労働者として知られた実在の人物。 ・『Dialann Deoraí(移民の日記)』という著作で、労働移民の体験を記録しました。John Boyle O'Reilly ・19世紀のスーツ姿。詩人、新聞編集者、社会活動家。 ・若き日にアイルランドで囚われ、後に脱走してアメリカへ渡り、アイルランド独立運動の 支援者となりました。Annie Moore ・アメリカ・ニューヨークのエリス島に到着した最初のアイルランド人移民(1892年) として有名な実在の人物。 ・15歳の少女で、米国移民史の象徴。これら6人は、EPICの展示の中でも「移民の多様性」と「時代背景の違い」を象徴するために選ばれているのであった。「TEACHING(教育)」修道女はおそらくナイジェリア、インド、あるいはフィリピンなどに派遣されたアイルランド系の教育宣教師で、読み書きを教えている場面。子どもは現地の生徒であり、多民族・多言語地域におけるアイルランド人の教育活動の成果を象徴しているのであった。美しいステンドグラス風円柱。カラフルな幾何学模様がステンドグラス風にデザインされていた。この装飾は、おそらく教会建築や移民の「多様性」や「統合性」を象徴しているのであろう。「UNITING COMMUNITIES」 【地域の人々を結びつける共同体を団結させる】「EducationIn Ireland, education has always been seen as essential to progress. When the English regime tried to suppress Irish culture and education in the sixteenth century, “Irish Colleges” were set up across Europe to preserve it. Mícheál Ó Cléirigh (c.1590–c.1643), who compiled the manuscript known as “The Annals of the FourMasters” was educated at such a college in Louvain, Belgium.It is not surprising that the Irish, believing in the value of education, have tried to bringthe benefits of education to less privileged parts of the world. There are strong ties particularly between Ireland and some educational systems in Africa. For example, the Jesuit Father Michael Kelly has been referred to as the Grandfather of Zambian education, having lived there for over 50 years, establishing schools and becominga leader in the campaign against HIV and Aids.」 【教育アイルランドでは、教育は常に進歩のために不可欠なものと見なされてきました。16世紀、イギリス支配がアイルランドの文化と教育を抑圧しようとした際、「アイリッシュ・カレッジ(Irish Colleges)」がヨーロッパ各地に設立され、それを守ろうとしました。「四人の修道士の年代記(The Annals of the Four Masters)」として知られる写本を編纂したミヒャール・オ・クレーリィ(Mícheál Ó Cléirigh, 約1590年〜1643年)も、ベルギー・ルーヴァンにあったそのようなカレッジで教育を受けました。教育の価値を信じるアイルランド人が、世界の恵まれない地域に教育の恩恵を届けようとしてきたのは、驚くことではありません。特にアイルランドとアフリカの一部の教育制度との間には強い結びつきがあります。たとえば、イエズス会のマイケル・ケリー神父は、ザンビアの教育の祖父と呼ばれ、50年以上にわたって現地に住み、学校を設立し、HIVとエイズに対する運動のリーダーとしても活動しました。】「ChristianityOne of the oldest and most enduring reasons for Irish people to migrate is because they felt an overarching sense of purpose: to spread faith, to educate or to help thosein need. Irish missionaries, medical staff, educators and aid workers have travelled toalmost every part of the world – going wherever they felt the need was greatest andleaving a profound impact.Although many of these migrants left a positive legacy in their adopted countries, othersfailed to achieve what they hoped. In some cases, they inflicted prejudice and misery on their host countries.However, many founded schools and hospitals or provided emergency relief or medical aid to those of all nations and faiths. Today, many Irish emigrants continue to leavethe island to provide aid to those who need it most.」 【キリスト教アイルランドの人々が移住した最も古く、そして長く続いた動機の一つは、「信仰を広めること、教育を施すこと、困っている人々を助けること」といった大義の意識です。アイルランドの宣教師、医療従事者、教育者、援助活動家たちは、世界中のほぼすべての地域に渡航し、必要が最も大きいと感じた場所へ向かい、深い影響を残してきました。多くの移住者は、移住先の国に前向きな遺産を残しましたが、一部は期待された成果を上げることができず、時には偏見や苦しみをもたらす結果になったこともありました。それでも、多くの人が学校や病院を設立したり、緊急支援や医療援助を、国籍や宗教を問わず必要とする人々に提供しました。今日でも多くのアイルランド人移民が、援助を必要とする人々を助けるために島を後にし続けているのです。】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.01
コメント(0)
全34件 (34件中 1-34件目)
1










