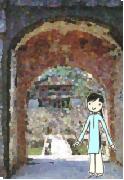全46件 (46件中 1-46件目)
1
-
本当に相手によろこんでもらうために
まずぼくの知り合いの失敗談からベトナムで事務所をかまえ働いていたIさん(日本人男性)は、信頼できるベトナム人女性と出会い、いろいろとお世話になっていた。男と女といっても、70才のおじいさんと日本語を学ぶ大学生の娘なので色恋沙汰ではない。Iさんは日頃お世話になっているお礼をしたくて、その娘さんを日本食レストランに招待したり、有名ホテルのラウンジで甘いものをごちそうしたりしていた。日本語を勉強している学生に日本食を食べさせてあげたい、高級な店で(Iさんにとっては格別高い料金ではないけど)おししいものをごちそうしたい、そういった善意からの招待だった。でもその善意は相手をよろこばすどころか、かえって相手に重荷を与えただけにすぎないことにやがてIさんは気付く。その大学生がベトナム人にはめずらしくIさんに本音を語ったからだ。前にも日記でちらと書いたが、ベトナムに割り勘はほとんど存在しない。Iさんが招待しておごったことには何も問題はないのだが、問題はその代金が通常のベトナム人の感覚では高すぎたことだった。ベトナムではおごってもおごられても礼を言ったり恩着せがましいことも言わないが、常々そのお返しをする機会を考えている。返せもしないような高額な食事をごちそうになったりすると、善良な人ならよろこびよりも困惑のほうが大きくなる。このお礼をどのようにして返せばいいのかと。ベトナムにも金持ちはたくさんいる。そういった人との付き合いなら別に気にすることはないだろうが、一般的な暮らしをしている普通の人々と付き合うなら、彼らがいつか次の機会に無理なくお返しができる程度の店を選ぶべきだ。そしてそのほうが絶対によろこばれる。高級な店では押し黙っているかもしれないが、庶民の店では「なんじゃこのチェーは。あたしゃもっとおいしい店を知ってるぞい。今度つれていっちゃる」とか、「日本人のくせにええ店しっとるやんけ。いけるやんかこのフォーは」などと会話もはずむでしょう。とある金持ちの外国人に自分の給料1ヶ月分ぐらいの食事をおごってもらって、たのしい時間をすごせるか?ぼくは過ごせない。プライドが傷つけられるだけだ。Iさんはぼくもよく食事に連れて行ってくれた。もちろん他のベトナム人もいっしょに。けどもう高級店には行かない。どこにでもあって安い、けどおいしい店に連れて行ってくれた。ぼくはそんなIさんが好きでい。
2005年08月04日
コメント(1)
-
ベトナム歌詞翻訳1
ビオラさんリクエストにより、ベトナム人歌手ミータムの歌詞を翻訳します。ベトナムではどえらく有名な女性歌手です。私は恥ずかしながら聴いたことがないのですが、ビオラさんに送ってもらったベトナム語の歌詞を訳しながら、メロディーを想像するのはなかなかたのしかったです。原文も合わせて掲載しておきます。ベトナム語がわかる方、誤訳等がありましたらご指摘お願いします。幼いころを思い出す家族の愛情に包まれた暮らし子守唄で寝かしつける母の面影をずっと覚えている幼いころを思い出す家族の愛情に包まれた暮らしやさしく教え諭してくれた父をずっと覚えている涼やかで澄んだせせらぎのような母の言葉を私が大人になるようにと言ってくれた父の言葉を父母の愛情は深く刻み込まれ、私が歩む人生の糧となる幼いころをずっと覚えているずっとずっと忘れることなく決して忘れないたとえ私がどこに流されて行こうと母の愛情は海のように果てがなく父の愛情は空のようにはるかに※母がくれた言葉を忘れはしない父がくれた言葉を忘れはしないたとえ喜びがあろうと悲しみがあろうと、もしくは頂に登ろうとも愛情のこもったやさしい母の言葉をいつまでも忘れない愛情のこもった父の教えをいつまでも忘れない私は誰よりも父と母を愛しているから
2005年08月02日
コメント(2)
-
オム真理教
ベトナム語で「オム」とは「抱く、抱きしめる」という意味です。バイクタクシーはセーオムといいます。バイクの後ろに乗ると運転手をオムするのでセー(車)オム(抱く)というわけです。 お触り可の飲み屋はビアオム。これは説明不要でしょう。 オムの用語説明はこれぐらいにしといて本題に入ります。ぼくはハノイでこう思いました。好きな人をぎゅっとオムするときほど、人生で貴重な瞬間はないのではないかと。 これは真理だ、揺るがぬ真理だ、そう思ったぼくは、身近な人たちにこの真理を伝えました。そしてその中のばかな数人は信徒となりました。こうしてできたのが「オム真理教」です。 現在信徒4名です。門戸はいつでも広く開けております。みなさん、いかがですか?
2005年07月22日
コメント(2)
-
「bui」に関する一考察
ベトナム語に bui という言葉がある。味覚に関する形容詞であるのだが、辞書によると嗅覚や触覚にも関係のある言葉のようだ。ベトナム語辞典(ブイ・カック・ヴィエト他編、言語辞典センター、1992)によると、 bui : Co vi ngon hoi beo beo nhu vi cua lac, hat de, dua……であり、ベトナム語辞典(ヴァン・タン編、ハノイ科学出版社、1991)によると、 bui : Noi thuc an co bot, co vi beo va thom, nhu lac, vung……と書かれている。 ピーナッツ、栗、胡麻、椰子のようにほどよく油っ気があり、よい香りがし、そして美味しいといったところか。buiはたったの一語で、旨味、芳香、食感(油)を同時に喚起させるなかなか曲のある言葉のようだ。 buiの語感をあますことなく包括する日本語はちょっと思いつかない。ためしに越日辞典(文化出版社、1997)を引いてみると「香ばしい」と書いてあった。「香ばしい」もいい線いっているが、「油っこさ」が伝わってこない。他言語の辞書も引いてみる。 越英辞典(ブイ・フン編、世界出版社、1995) bui : have a nutty flavour, tasty 越英辞典(ダン・チャン・リエウ他編、ベトナム社会科学院、1994) bui : having a buttery taste 越漢辞典(何成他編、南条印書館、1960) bui : 芳香可口 「nutty」、「buttery」ともになかなかおもしろいがいま一歩。「芳香可口」は油っこさが伝わってこないし、四語(二語?)も使っている時点で反則。英語も中国語も日本語同様buiの訳出には苦労しているようだ。 Lac cang nhai cang thay bui. これはどの辞書にもよく出てくる例文である。「ピーナッツは噛むほどに旨味が出る」。無難な訳としてはこんなところか。 しかしこれではbuiが包含する「芳香」、「ほどよい油っこさ」という語感がこぼれおちてしまっている。かといってその語感を余すことなく伝えようとすれば、長ったらしいリズム感の欠けた間抜けな訳文になってしまうだろう。 身も蓋もない言い方をすれば、翻訳不能であるのだ。もちろん実際に翻訳する際には、一語一語に拘泥してストイックに正確な訳に努めることよりも、原文の持つ雰囲気、フィーリング、リズムを再現することの方がずっと重要であるとは思うが。 buiのように「翻訳不能」な言葉は世界中の言語にあまた存在するであろうが、理解不能であるわけでは決してない。そして、日本語の語彙系統では扱いにくいこのような言葉にこそ、異文化に触れる新鮮な驚きがそっと埋められているに違いない。
2005年07月13日
コメント(4)
-
ハンサム・ボーイ
「あんたかっこいいね、映画スターみたいや」こんなセリフを言われたことがあるか?世の中ハンサム・ボーイは多しといえども、ここまで言われたことのある人は、あまりいないだろう。そんじょそこらのハンサム・ボーイでは、まあ聞かずに終える人生だ。世の中そんなに甘くないのだ。だが私は言われたことがある。ベトナム中部の街、クイニョンの屋台で。夜もふけてうすぐらい屋台。ホビロン(北部風に言えばチュンビッロン)を食べさせてくれる屋台だった。ホビロンとは、あの有名な孵化しかけのアヒルの卵を茹でたやつ。ビールのつまみに最高なのだ。隣には酔っ払いのじいさん。私が外国人だと知り、ろれつのまわらない英語で話しかけえてくる。当時(約10年前)私はまだ挨拶程度のベトナム語しか知らなかったのだ。私も面倒だが無視するわけにもいかぬので、英語で答える。じいさん、周りの人たちに自分が英語を話せることを示せて得意そう。私並にへたくそな英語だったが。そしてじいさんは言う、冒頭のセリフを。「ユ アー ベリベリ ハンサム ライカ ムービー スター!」一生に一度聞けるか聞けないかのセリフなのだろうが、とくにうれしくはなかった。へべれけじいさんに暗い暗い屋台で言われても・・・。賭けてもいい、じいさん、見えてないでしょう?
2005年07月03日
コメント(0)
-
越南男児、越南女子、日本女子を敵にした夕べ
数年前のハノイで、日本語を勉強するベトナム人学生とベトナム語を勉強する日本人学生の交流会が催された。場所は東京大学のベトナム研究拠点、正式名称は忘れた。私も人数あわせのために半ば無理やり参加させられた。参加者は双方10名づつほど。女性が7割ほどを占めていた。ベトナムの男子学生にはかのヴォー・グエン・ザップ氏の孫がいてびっくりした。独立闘争の英雄ヴォー・グエン・ザップの孫が日本語を勉強しているとは・・・。ベトナムの学生はみな日本語が非常に上手だった。日本人学生のベトナム語よりもうまい。自然、場の会話は日本語が多くなる。情けなや、我々日本人学生・・・。議題、というかただの雑談の話題は男女関係へとうつろう。ベトナムでのデートは必ず男がすべて金を出すね、そうね、日本では男が出す金額のほうが多いと思うが、女が出すこともあるね、そうなの?、そうよ、といった他愛もないことをうだうだ語り合う。正直、退屈な私・・・。半分聞き流していると、話題はいつのまにか日本人女性によるベトナム男性礼賛となっている。ベトナム男性はすごく優しい、親切、マメ、誠実・・・越南男児、まんざらでもない顔。越南女子、社交辞令でも日本男児を褒める気配なし。数少ない日本男児、反論する度胸もないのか従順に耳を傾けている。何やっとんねん、お前らは!反論せい、反論せんか!!日本男児に立ち上がる気力なし。これやから有名大学のエリートどもは使えん。しょうがない、俺が代弁してやろう、越南男児、越南女子、そして日本女子どもよく聞け、俺の日本語とベトナム語ちゃんぽんの熱弁を!「ベトナムの男性は確かにやさしい。細やかな心配りもできる。でもそれは結婚する前までだ。あくまで結婚する前までだ。結婚後の越南男児を見よ。働かない、家事もしない、おまけに妻を殴る蹴るの狼藉三昧。もちろんすべての人がそうではない。結婚後もやさしく、一生懸命働く夫もいる。だが、そうでない人がたくさんいるのも事実だ。しかもプライドだけは高い。職がないとかいうのは言い訳だ。選ばなければ職はいくらでもある。でも、肉体労働をするぐらいなら、妻を働かせてぶらぶらしてるほうがマシというわけだ。こんな男性がやさしいか?」しーん・・・・・・。場は静寂、まことに静寂。ちょっと言い過ぎたか?越南男児、うつむく。越南女子からも反論なし。日本女子、ちょっと敵意のまじった眼で私をねめつける。日本男児、心の中で拍手(たぶん)。しかし表向きは場に合わせて白けた振り。卑怯者め!私の発言は感情的になったこともあり、誇張されている。ベトナム人男性、そんな悪人ではない。けど、半分図星でもある。だから越南男児も女子も反論できなかったのだ。実際、働かない男は驚くほど多い。一家の家計は女性が支えているというケースは、全然稀ではない。ベトナムに専業主婦はほとんどいない。共働きか妻のみ職を持っているかのどちらかだ。日本では働かない男はクズ扱いされ、非常に風当たりが強い。でもベトナムでは働かなくても別にどうってことない。非難もされない。そしてベトナム女性は本当に働き者なのだ。いいなあ、越南男児・・・。
2005年07月02日
コメント(0)
-
覚悟
私は旅行会社で働いている。外国人のお客さんも多く、ベトナム人も私の知り合いを中心にたくさんいる。日本のパスポートを持っているということでどれほど優遇されているか、ベトナム人の査証手配をするとよくわかる。ベトナムパスポートで査証を取らずに行ける国は本当に少ない。先日もフランスの査証(シェンゲン査証)手配をした。日本パスポートを持っていれば、査証はもちろん要らず、パスポートを持って行くだけでいい。しかしベトナムパスポートだと、査証が必要で、しかもやたらと提出する書類が多い。申請書、パスポート、写真、往復航空券。ここまでは理解できるが、まだまだ必要書類がある。銀行残高証明書、旅行保険の証券、宿泊証明書、日程表、外国人登録証のコピー。さらに今回はフランス大使館の判断で、雇用証明書と休暇証明書の提出まで求められた。これだけの書類をそろえるのは一苦労だ。でもまだフランスはマシなほうで、これがイギリスだと銀行残高証明書は受けつけず、過去6ヶ月の出入金記録のある銀行通帳の原本(!)提出が求められる。もちろん就労や留学査証ではなく、ただの観光査証でこれなのだ。フランスもイギリスも、まだ代理申請は認めている。しかしアメリカとなると、代理申請も認めていない。しかも面接(!)が必要なのだ。英語ができない人はどうしろというのか。一言も英語を知らなくとも、英語の申請書を自分で記入せねばならない。しかもアメリカに滞在するわけではなく、米国内空港で乗り継ぐだけでも、査証を事前に取得せねばならないのだ。あまりに非道すぎる、そう思いまっせ、アメリカさん。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※「世界市民」と言う人たちがいる。国という「想像の共同体」に縛られ、ナショナリズムやレイシズムに囚われていては、戦争や様々な面での不平等さは解消されず、そんな世界では人類に未来はないと。望ましい未来を築くには「世界市民」としての連帯が不可欠だと。しかしベトナムに行き、「ぼくたち同じ世界市民」と言っても、誰が共感するだろうか。おそらく多くの人が首を傾げて、「いや、俺はベトナム人だ」と答えるだろう。もしくは「○○族だ」と言う人もいるかもしれない。イラクやアフガニスタンでも同様であろう。そして、皮肉屋さんならこう言うかもしれない。「そうか同じ世界市民か、では同志、国籍を交換しよう」実際、「世界市民」という思想に共感しているのは、経済先進国で恵まれた境遇を享受している人たちだけだ。そして「世界市民」を唱えている人たちのなかで、「いいよ」と言える覚悟のある人がいったいどれだけいるのか。素晴らしい思想であることは認めるが、口にするには相当の覚悟がいる言葉だろう。そして、そのような覚悟を胸に発言し行動している人なら、私は本当に尊敬する。
2005年07月01日
コメント(0)
-
ベトナム人の英語が理解できないわけ
「英語に標準語はない」何かの本でそう読んだことがあります。その根拠として、以下のような説明がなされていたと記憶しています。アメリカ、イギリス、シンガポール、ナイジェリア、オーストラリア・・・。それぞれの国で話されている英語はそれぞれの特徴があり、どれが正しくてどれが標準と決めることはできない。さらに世界の多くの人々が己の母語が通じない相手とコミニケーションする手段として、英語を用いている。日本人と中国人、タイ人とイタリア人が英語で会話をする。日本語でもなく中国語でもなく。そのような「世界言語」であるため、標準がどうのこうのというより、通じ合えばそれでよし。英語とはそういう言語なのだ、と。日本人は英語の発音が下手だと言われています。おそらく多くの日本人がそう自己採点していると思います。私もその一人です。実際、私の英語は文法も発音もデタラメ。でもたいていの場合、それでも通じました。デタラメ過ぎて通じなかったこともありますが、多少のデタラメだったら大丈夫。英語は「ぶれ」に強く、許容範囲の広い言語なのです。上記の本の影響もあり、デタラメだって別にかまへん、通じりゃええねん、そう曲解して開き直っていた私ですが、ベトナムでさっぱり理解できない英語に出くわしてしまいました。ベトナムでも普段から外国人と英語で会話する機会の多い人は、理解可能な英語を話します。ここで問題にするのはそのような実践経験はほとんどないが、英語の勉強はしているというベトナム人です。私はハノイで英語の家庭教師をしているという男子大学生に会い、彼は何事か早口で話しかけてきました。私はまったく理解できないばかりか、何語を話しているのかさえ分かりませんでした。いままで相手の英語が理解できなかった経験は自慢じゃないが山ほどあります。英語のニュースを聞いてもチンプンカンプン、その程度のレベルなので。でも解らないなりにも英語が話されていることぐらいは理解できました。「何語で話してんの?」「えっ!?英語やけど・・・」ベトナム語の会話で彼が英語を話していたことが判明しました。気を取り直して耳を傾けてみると、確かに英語だった。でもほとんど解らない・・・。何度か同じような経験をし、「なぜ一部のベトナム人の英語が理解できないか」という疑問に、私は自分の英語力の未熟さを棚上げして、私なりの回答を出しました。結論から言うと、ベトナム人の英語と日本人の英語は非常に相性が悪い、最悪のマッチングだということです。そしてその相性の悪さが如実に現れるのが末子音です。例えば「mac」、「mat」、「map」、「mach」。アメリカ人なら「マッ(ク)」、「マッ(ト)」、「マッ(プ)」、「マッ(チ)」と、()内は微かに発音するのだと思います。日本人なら「マック」、「マット」、「マップ」、「マッチ」でしょう。ではベトナム人ならどうか。ベトナム人なら「マッ」、「マッ」、「マッ」、「マッ」です。正確に言えばそれぞれ微妙に違う「マッ」なのですが、日本人の耳には同じ「マッ」に聞こえます。ベトナム語では末子音は発音しないので(発音しなくても口や舌はc、t、p、chの位置に動かす)、英語にもそのルールを適用してしまう傾向があります。逆に日本人は末子音の発音を強調し過ぎてしまう。日本語にはn以外の末子音で終わる単語がないからです。「パッポー、パッポー」ホテルのレセプションでそう言われて、理解できる日本人がどれほどいるでしょうか。私は何度も聞き返してやっと理解できました。彼が「パスポート」と言っていることを。「アイックリ、アイックリ」これは「アイスクリーム」のことでした。多少デタラメの英語でもかまわない、通じればいいのさ、私はいまでもそう思っています。でも逆方向にずれたデタラメ英語同士だと、お互い通じない。許容範囲の広い英語といえども、やはり範囲はあるのです。おそらく通常の観光でベトナムを旅行する場合は、外国人との会話に慣れない「純粋越式英語」にはあまり遭遇しないと思います。ですが、もし幸運にも遭遇することがあったら、想像力を駆使して相手の英語の末子音を補い、自分の英語はわざと末子音を落として話してみたりという「高等テクニック」をたのしんでみてください。もしくは「純粋日式英語」で相手も面食らわせてやりますか。
2005年06月26日
コメント(1)
-
「子供の結婚」 第6章 初夜
「子供の結婚」 タック・ラム著 岩井訳初夜 きょうは一日本当に疲れた。花嫁側の人たちは夜になってようやく帰り、ぼくの家では芸者を呼んで、ドンチャン騒ぎが夜中まで続いた。エビのような口元をした数人の芸者が、ぼくの頭を撫でてはくすくす仲間内で笑い合うのだ。本当に腹が立つ。 こんな夜更かしは今までしたことなかったので、眠たくて眠たくて今にも目蓋がくっつきそうだ。ふとお金のことを思い出し、財布と紙の包みを開けてみると、3ドンと300スーが入っていた。やった! どこに隠そうかと算段していると、母がどこからか駆けつけてきて、電光石火でお金をひったくって行ってしまった。残念でならなかったけど、あえて苦情は言わなかった。 ベッドに入ってうつらうつらしはじめたとき、母が来てぼくを引っ張り起こして言った。 「嫁がいるのになんで独りで寝てるんだい!」 そして母はちょっとしたアドバイスを耳打ちしてくれたので、ぼくはすこし意を強くすることができた。ぼくは大胆にも寝間着のまま、手探りで妻の待つ寝室へと向った。 寝室のドアの前まで来たが、ぼくは全身が震えて胸がドクンドクンと高鳴り、逡巡するばかりでそこから一歩も踏み出せない。根性を見せるときじゃないか! 膝はまだ震えていたけど、意を決してドアを押すと、ベッドの端に腰掛けていた妻にばったり遭遇した。くわばらくわばら。 ぼくはとても直視することができず、そんなものは存在しないかのようなふりをした。ぼくの目は鶏を探していた。母は、部屋に入ったらまず頭を折った鶏を探し、それをすぐに食べれば妻はもうぼくに危害を加えることはない、と教えてくれたのだ。 それなのに当惑の末やっと鶏おこわが置いてある場所にたどり着いたと思ったら、なんてこったい、鶏の頭はどこかに消えちゃって、ひょろひょろの首だけが寂しく残されているじゃないか。 ヤバ過ぎる! この女、鶏の頭を食べちゃったのか? だとしたら、ぼくをいじめ殺しかねないぞ。椅子に腰掛け考えてみるが、熟考すればするほど不安が抑えられなくなって、どうすればいいのか分からなくなる。 ぼくはずっと待っているというのに、どうして彼女は眠ってくれないんだろう。目は二つとも閉じられているが眠ってはおらず、頬杖をついて鶏をじっと凝視し振り向こうともしない。 ベッドの竹が軋む音がしたと思うと、しばらくして豚のような鼾が聞こえてきた。やっとほっとして、ぼくはベッドに近寄った。目を大きく見開いて妻がぼくの何倍大きいか見当してみると、優に四倍は超える。なんたるデブ! 勇気を出してそっと妻の傍らに身を横たえ、死力を尽くしてやっと掛け布団をすこし引っ張ることができた。どうやらさっき、彼女は酔いで眠りに落ちたらしい、ごそごそ動いて咳払いをしていたかと思うと、突然腕をぼくの首の上にドスンと落とした。ぼくは息ができなくなって、必至に押しのけて、なんとか九死に一生を得る。 急いでベッドの隅に退避し、身体を丸めて咳をするのもためらいながら息を殺す。ぼんやりと、妻がぼくの髪を鷲づかみにして、薪をかち割るみたいにぼくをぶん殴るシーンを想像した。まるでテオの母親のドゥンおばさんが、旦那を叩きのめしているときのように。 そして、ぼくは眠りの淵へと引きずり込まれていった。おわり(風化紙、27号、1932年12月)
2005年06月25日
コメント(2)
-
「子供の結婚」 第5章 家に帰る
「子供の結婚」 タック・ラム著 岩井訳家に帰る 昼時に花嫁宅を辞した。巡察の若い男が数人面倒を起こしてきた。すでに4ハオも渡したというのに、彼らは満足しないのだ。父は怒って紐を引き千切り、花瓶ごと机をひっくり返した。 連中は罵り喚きながら走り去って行った。 家に着いたけど、あっちの儀式が終わればこっちで儀式が待ち受けている。もう疲れて膝に力が入らないけど、まだまだ終わらない。これから行われる婚姻の儀がもっともヤバイのだ。 ぼくは既に恥ずかしさの絶頂だというのに、紳士淑女の皆様方は、「夫は小さいのに妻はでかい」とか、「夫はネズミ、妻は巨象」とか、「夫があんな子供では何も分かっちゃいないのよ」など、好き勝手に品定めしてくださる。 本当に恥ずかしい。さらに儒者がすべて漢読みで朗唱したとき、ぼくが木偶の坊のように呆然と立ちすくんでいたら、人々の間からクスクス笑い声がもれた。チラッと柱の陰に隠れているスー嬢を見てみると、彼女は口をもぐもぐ動かしながら熱心に拝んでいたが、何を祈願しているのかぼくには知る由もなかった。つづく
2005年06月24日
コメント(0)
-
「子供の結婚」 第3章 花嫁を迎えに
「子供の結婚」 タック・ラム著 岩井訳花嫁を迎えに 母屋に戻ると、親戚たちが既にたくさん集まっていた。誰もが真新しい服に身を包み、すごく嬉しそうに見える。友達同士でワイワイやるんだったらかまわないけど、きょうはみんな花婿を見物に来てるわけで、ぼくはもう恥ずかしくてこっそり逃げ出したい気分だ。だけど逃げ出すわけにもいかない。 いまや爆竹に火が点けられ、青い煙がモクモク立ち込めていいにおいがする。不発の爆竹で遊ぼうと何個か拾おうとしたら、父がぼくを睨み付けたのであきらめた。 表の路地に出てみると、人々が取り澄まして悠然と二列に並んでいる。なんでこんなにたくさんの人が見に来てるんだろう。しかも大部分がぼくと同じぐらいの年端もいかぬ子供だ。そいつらはぼくを指さしては、ひそひそと何かを言い合っていた。ぼくは恥ずかしくて母の背に隠れたが、なんの解決にもならない。するとまたもやティーの奴が大きな声で叫んだ。 「おまえ嫁もらいに行くんか、おうおう、またきれいな服着て」 幸いなことに、花嫁の家はそれほど遠くはなく、ほんのすこし歩けば着いた。 なんだ、バーさんちじゃないか。それなのにぼくの母はずっと隠していた! けど、誰と結婚するのかぼくが今の今まで訊かなかったというのも可笑しな話だ。バーさんちの娘といえばあの小太りの女か。井戸のところでときどき見かけるあの娘に違いない。 バーさんの家に入ると、人々は既にたくさん集まっていた。ごちそうを載せたお盆が次から次へと運ばれてくる。笑い声や話し声がにぎやかにこだまするが、だんだんと酔っ払いのだらしない口調になっていく。ぼくはといえば、ハノイ動物園のサルでも見物するかのような周りの人たちのせいで、恥ずかしくて何も喉を通らない。「花婿だ」、「花婿だ」とあっちでもこっちでも人々の声が上がり、ぼくはもう泣き出したかったが泣いてどうなるわけでもない。 花嫁を連れ帰るのを請う頃合いになると、さらにややこしいことになった。花嫁側はきっかり100ドン要求した。ぼくの母は20ドンまけさせようとするが、相手側は頑としてはねつけ、頑として花嫁を渡そうとはしなかった。そして両家は声を荒げはじめ、ぼくは心配になりはじめた。1ドン2ドンをめぐる永遠に続くかのような値段交渉の末、ようやく85ドンで折り合いが付いた。それ以上は一銭たりとも譲れないというわけだ。 部屋の戸が開き、花嫁が歩み出てきた。数人の娘が花嫁の周りに付き従っている。そのなかにはスー嬢もまじっていて、彼女はぼくを見て微笑んだ。 はっきりと顔を見ることはできなかったけど、花嫁はぼくの二倍はあろうかという大柄で肥えた女で、ぼくは背筋が寒くなった。寺院に参拝に行き、そのとき花嫁もぼくの横で拝んでいたけれど、ぼくには花嫁を直視する度胸がなかった。 人々は地面に御座を敷き、そしてバーさんとバー婦人がサップ台の上に座り、ぼくたちに跪拝させた。バーさんは不安定な姿勢で腰掛け、ときどき髭をなでてはとても得意そうな様子を見せていた。バー婦人は息も付かず一気に長々としゃべり出したが、ぼくには何を言っているのかさっぱり分からなかった。けれどバー婦人がお金の詰まった財布二つと赤い紙の包みを持ってきたとき、中にたっぷりお金が詰まっているだろうことは、ぼくにも理解できた。そしてバー婦人は鷹揚に言った。 「ほれ、婆がおまえたち夫婦に少ないけどお金を用意してやったよ。将来家を出て独立して暮らすときに、これで土地を買って商売でもしてお互い助け合うんだよ」 ぼくは恐くてお金を受け取っていいのか分からなかったけど、父が目配せをしたので屈んで受け取った。うわぁ、なんて重いんだ! かなりの大金に違いない。これだけあれば思う存分お菓子が食べられるぞ。つづく
2005年06月22日
コメント(0)
-
「子供の結婚」 第2章 結婚の日
「子供の結婚」 タック・ラム著 岩井訳結婚の日 今朝、寒かったので布団の中でぐずぐずしていたら、父がぼくを引っ張り起こし目をギョロつかせて言った。 「起きんか! お前は嫁を迎えに行く服を着なくちゃならんのだろう」 急いで跳ね起きて離れに行ってみると、人々が忙しそうに立ち回っていた。ライスペーパーで包んでいる人、豚肉を挽いている人。何房かのビンロウの実を詰めた丸い木箱が数箱あり、真っ赤なフランス製の布が巻かれている。 朝食をちょっとつまんでから服を替えに行った。母が衣装箱を開けて服を取り出す。叔母や近所のテオの野郎までが様子を見に集まって来た。最初、ぼくは真っさらの紅染めされた絹の半袖シャツを着た。一度も洗濯されていないズボンは、長くて硬くて歩くとゴワゴワする。腰に縮緬の帯を締める。二重に巻くがまだ長い。 晴れ着の着付けがここまで終わると、母は薄い朱色の着物とお椀の口ほどもあるかという大きな花をぼくに渡した。おいおい、綺麗過ぎるよ! 叔母がその着物の布地は中国の錦で、一着10ドンはする代物だと言った。けどどうしてこんなにぶかぶかで長いんだろう、膝まで裾が垂れ下がってきている。 「それでいいのよ、大きくなったらちょうどよくなるんだから」 母はそう言うと、今度は頭に巻く布と新しい靴をぼくに渡した。たとえ五年後だってまだぶかぶかのままだろう布と靴だ! 着替えが終わり、鏡を出して我が身を映し、ちっとは大きくなったか見てみる。母はぼくをあっちに行かせたりこっちに行かせたりする。ぼくはぶかぶかで恥ずかしくてたまらないというのに。テオの野郎が手を叩いて笑う。 「花婿らしくなってきたじゃねえか」 ぼくまでつられて浮かれた気分になってきた。あとは唇に紅をひけば、これで男前の一丁あがりってわけだ。つづく
2005年06月20日
コメント(0)
-
「子供の結婚」 第1章 お膳立て
「子供の結婚」 タック・ラム著 岩井訳お膳立て ここ最近、叔母は遊びに来るたびに、ぼくの両親となにやらひそひそ相談事をしている。しかもそれがどういうわけか、ぼくの結婚についての話みたいなのだ。ちょっと待ってよ、ぼくが嫁をもらうっていったいなんのために? ぼくは懸命に考えてみたけど分からない。ぼくに分かることといえば、嫁をもらうっていうのは綺麗な服を着て、爆竹が鳴らされ、そしてお小遣いがもらえるかもしれないってことぐらい。 ぼくは毎日ティーと一緒に庭で棒打ち(ダイン・カン)に興じていたが、近所のテオが歌う声はぼくらの耳にも聞こえてきた。 茄子にゃイチモツ生るように 女にゃ夫が、男にゃ妻が…… それはそのとおりかもしれない。けどそれは大きくなってからの話で、まだ14になったばかりのぼくには、所帯を持つということがどういうことなのか想像もつかないのだ。 きょうの午後、ぼくはまるで法事の日のように簾が掛けられ御座が敷かれ、家の中が何かの準備でごった返しているのを見た。そして父と母ときたらひそひそと相談し合って、なにやらものすごくあやしげだ。ぼくの結婚式の準備でもしてるんじゃないか。そう思うと不安でたまらなくなり、全身の感覚がなくなってきて、ティーの奴が棒打ちに誘いに来ても応える気にもなれない。 明かりを点す時分になると、母はぼくを部屋に呼んで寝台(ファーン)に座らせ、ぼくの服のボタンをいじりながらこう囁いた。「明日母さんがお前に嫁をもらってやるからね。素直に言うことを聞けば、父さんが小遣いたんまりくれるはずさ。うちは子宝に恵まれず男のお前が一人いるだけだろう、嫁をもらって女手を増やして、母さんが歳を取ったときに楽させておくれよ」 ぼくは全身が痺れて硬直したまま、何て言ったら良いのか分からず、涙が滲んできて、ただただ泣きたかった。 母はこうも言った。「もう披露宴の準備で大金をはたいてしまったし、礼物も全部用意してあるんだよ。あんまり聞き分けのないこと言ってると、父さんに死ぬほどぶたれちまうだろうよ」 その夜、ぼくは寝返りを打つばかりで一睡もできなかった。嫁をもらうということがどういうことなのか、不安なこころもちでぼんやりと考えながら。つづく
2005年06月19日
コメント(0)
-
タック・ラム紹介
タック・ラムは1910年ハノイに生まれ、主に1930年代に多くの作品を残したベトナムの作家です。川口健一氏訳の『農園の日差し』という短編集で、日本にもすでに紹介されています。 この本の中に短編「二人の子供」も訳出されています。この短編は、私が初めて原文で読んだベトナム文学作品でした。ベトナム語を原文で読む際、それが新聞記事であろうが教科書の長文であろうが、それぞれの単語、文章の意味を把握するのに精一杯で、ベトナム語の文体をたのしむ、なんて余裕もなく、はっきり言えば苦痛を伴う作業でしかありませんでした。その程度の語学力のときにこの「二人の子供」を読みました。大げさに言えば、衝撃でした。まず、文章がわかりやすく、そしてなにより静かで美しい文体。引き込まれるように読み、辞書を引くことに苦痛も感じませんでした。そしてつっかえつっかえ時間をかけてしか読めない程度の語学力でも、タック・ラムの文章の持つ不思議な魅力を感じ取れることができる、ということに、感動を覚えました。ベトナム語を学んでよかったなあ、そう素直に思えた瞬間です。そのタック・ラムの作品を、拙い訳ですが紹介したいと思います。「子供の結婚」という短編です。『農園の日差し』に紹介されている他の作品とは違い、文章の美しさで読ます短編ではなく、タック・ラムが軽い気持ちで(たぶん)書いたユーモラスな作品です。
2005年06月18日
コメント(0)
-
悪あがき
昨年の晩秋ベトナムに行ったとき、本を一冊買ってきました。生活のちょっとした知恵が満載されている、「おばあちゃんの知恵袋ベトナム版」といった感じの本です。ぱらぱらめくりながらかいつまんで読んでいるとなかなかおもしろい。市場で良い鶏やアヒルを選ぶ知恵、という欄もあり、自身の経験を思い出しながら読みました。ベトナムの市場では、鶏やアヒルが生きたまま売られてるのがあたりまえの光景です。市場で買ってぶらさげて帰り、家で絞めて食べる。私も一度鶏を二羽買ってきて、ベトナムの友人に手伝ってもらいながら絞め、鶏パーティーを催したことがありました。首を切られた鶏が、死ぬ直前にものすごい力で抗う感触がいまも手に残っています。この「最後の抗い」のことをベトナム語で“vay chet”と言うんだよ、友人がそう教えてくれました。鶏を食したあとに皆でモノポリーをやったのですが、破産寸前のくせに最後の悪あがきをみせる往生際の悪いベトナム人に「“vay chet”しやがって」とつっこんでやりました。本の話に戻りますが、市場で良い鶏やアヒルを選ぶ際の知恵としてこのようなことが書かれていました。鶏やアヒルを売買する際に、目方が料金の目安になります。やはり肥えて重量のあるものに高い値が付くので、売り手は市場に持っていく前に餌を口に押し込んで無理やり大量に食べさせる。それぐらいならまだ許せますが、たちの悪い奴だと翼の付け根の内側、脇のあたりに注射で水を注入するのだそうです。だから購入する前に、翼をひろげて脇の辺りに注射痕がないかどうかチェックすべし、と「知恵袋」に書かれていました。絞めて毛をむしり、内臓を出して解体し、それから料理をする。それだけでも大変なのに、市場で選ぶのも一筋縄ではいかないようです。奥が深いなあ。いつかまたベトナムで生活する機会に恵まれたら、再度挑戦してみたいと思います。失敗するかもしれませんが、今度は友人の手は借りず、自分一人でやってみたいです。
2005年06月15日
コメント(2)
-
あいさつ
ベトナムでよく訊かれたこと。「家族が恋しいか?」ベトナムでの生活はたのしかったし、とくにホームシックにはかかっていなかったので、当初は正直に「いや、別に」と答えていた。すると相手は決まってちょっとびっくりした表情を浮かべる。そんな奇抜な回答だったかしらん、とその度にぼくはかるい違和感を感じていたのだが、ベトナムでの暮らしが長くなるにつれ、おぼろげながらそのギャップの原因が解ってきた。ベトナムでは、家族と遠く離れて暮らすことは寂しいことであり、そのような状況下で家族を恋しく思わない人はいるはずがない、という共通認識が、異議を挟む余地もなく確固として形成されている。ベトナム人は家族をとても大切にする。そして家族のことを大切にしていないと受け取られかねない発言は、まさしく「異端宣言」なのだ。「家族が恋しいか?」という問いの答えはイエス以外にあり得ず、問うた側も当然その答えを期待しているので、ノーで返されると意表を突かれてびっくりしてしまう。「先日はどうも」「どうもって、何が?」こんな「どうも返し」をされたら、日本人だってびっくりする。「家族が恋しいか?」は質問ではなく、一種のあいさつで、答えはすでに決まっているのだ。しかもただの社交辞令ではなく、相手の寂しさを慮ってはげましてあげたい、という気持ちのこもったあいさつであることも解ってきた。そのような思いやりに対して、ノーとは言えない。そのことに気付いてから、ぼくはイエスと答えるようになった。単身で来日しているベトナム人に会ったら、みなさんもぜひあいさつしてみてください。
2005年06月12日
コメント(0)
-
「んもー!!」
あなたが独身の男性なら、ベトナムでこのような会話をしたことがあるに違いない。<シチュエーション>たとえば列車やバスの中で。 初対面のおじさんが外国人のあなたに興味を示し、話しかけてくる。「どこからきた?」「日本」「何才だ?」「○○才」「結婚しているか?」「まだだ」「ベトナムの女性についてどう思う?」「きれいだ」おじさん、近くにいる若いベトナム娘を指差しながら、「じゃあ、こいつと結婚しなよ」「いいね」「んもー!!」娘、ちょっとしなをつくっておじさんを叩く。時と場所は違えど、毎回決まって同じ会話、そして「んもー」。恐るべきワンパターン。これからベトナムに行く計画があり、せっかくだからベトナム語を挨拶程度は覚えようと考えている方、「日本」、「自分の年齢」、「まだ」、「きれい」、「いいね」。この5つの単語で十分初対面のベトナム人とうちとけられます。参考までに。日本:nhat(ニャット)年齢:すんません、自力で調べてください。まだ:chua(チュア)きれい:dep lam(デップ ラム)いいね:co chu(コー チュー)上級編として、違うパターンを。「じゃあ、こいつと結婚しなよ」のあとに、「いいね」ではなくこれを言う。Ta ve ta tam ao ta.Du trong du duc ao nha van hon.※カタカナ表記は省略します。カタカナ読みしても絶対通じないので。ベトナム人に上記の文字を見せて、発音を習いながら耳で覚えてください。直訳すると、「ぼくは我が家の池で水浴びするよ。澄んでいようが濁っていようが、やっぱり我が家の池が一番さ」といった感じになる、ベトナム語の決まり文句です。これを上述のシチュエーションで言うと、ベトナム女性もきれいだけれど、ぼくはやっぱり同国同郷のヨメはんがいいな、という意味になります。長くて覚えるのは大変でしょうが、きっちり覚えてかませば、大受けまちがいなし。保証します。
2005年06月12日
コメント(2)
-
中部高原探訪記7(最終回) ~気も狂わんばかり
ホテルのロビーに酒とつまみが用意され、宴会がはじまった。酒はruou canと呼ばれる大きな甕に入れられた発酵酒。竹のストローで飲むようになっている。順番に互いにすすめながら(というか、強制しながら)酒をチューチュー吸って飲む。すこししか飲まなかったら、「もっと飲め」とブーイングが飛ぶ。おそろしい世界なのだ。 たばこも箱を皆で共有し、たがいにすすめながら吸う。ベトナムでは、普段はたばこを吸わないが誰かといっしょに飲んだりするときだけ吸う、というカジュアルスモーカーが多い。健康に気遣っている面も確かにあるかもしれないが、たばこが高いのも理由のひとつだろう。安いたばこもあるが、おいしくないし、そんなものを吸っているとステータスに傷がつくので、ある程度の社会的地位のある人なら最低でも一箱1万ドンぐらい(約80円)のものを吸う。ステータスなんて気にしなくていい人は、水たばこを吸う人が多い。竹のパイプに水を入れ、ぶくぶくいわせながら吸うやつです。これは安い。くらくらするぐらいきついですが。 定番の酒のつまみにまじって、テト料理も供される。テト料理といえばバイン・チュン。もち米の中に豚肉や緑豆を入れ、バナナの葉でくるんで湯でる。おいしいのだが、やたらと大きい上に腹にたまるので、たくさん食べられるものではない。どの家庭でも大量につくるため、何軒も新年のあいさつにまわると、またバイン・チュンですか・・・と見たくもなくなる。おいしんだけどね、本当に。 宴も終了し、酔っぱらって自室に戻ってベッドに倒れこんでいると、ノックの音が。開けるとホテルのおばさんが手にバイン・チュンを持ち佇んでいる。 「せっかくの正月なのに一人じゃ寂しいだろう。まだまだたくさんあるから持ってきたよ。食べなさい」 またバイン・チュンかい・・・ 正直そう思いました。でもおばさんの心遣いは本当にうれしかった。正月に一人でいることは、日本でも寂しいこととされているが、ベトナムでは「気も狂わんばかりに寂しいこと」というのが社会通念になっている。ホテルの人たちは、私の寂しさを慮って身内の宴に誘ってくれ、そしてバイン・チュンの差し入れまでしてくれたのだ。ありがとう、それ以外に感謝の言葉も思いつかない。言葉が出ないなら態度で示せ。残さず食ってやろうじゃないか。このおにぎり10個分ぐらいはあるかという気も狂わんばかりに巨大なバイン・チュンを! おわり
2005年06月11日
コメント(4)
-
中部高原探訪記6 ~青空なのだ
バイクでバンメトートに向かった。空は気持ちよく晴れている。こんな広くてきれいな青空を見たのは本当に久しぶりだ。空は青く、緑は濃く、土は赤い。私の見慣れたハノイの冬とは大違いだ。ハノイの冬はいつでもどんよりしていて、霧雨が絶えず降り、やたらと湿度が高い。ベトナムにもこんな広々とした大地と空があったか、風を切りながらそんな感慨にひたる。 バンメトートの中心の広場では、ちょっとした市がたっていた。日本の初詣を思わせるような、さまざまな屋台が軒を連ねている。目立ったのはギャンブル屋台だ。ベトナムではギャンブルは法律で禁止されているはずだが、大っぴらに繁盛していた。丸い板を手でぐるんと回し、回っている間にダーツを投げる。円の面積の約半分は青で、約半分は赤。そして20分の1ほどを黒が占める。客は青か赤に賭ける。当たれば同額の払い戻し。外れれば没収。黒にダーツがさされば、胴元の総取り。わかりやすくていい。大人も子どもも紙幣を握り締めながら、大いに盛り上がっていた。 帰りにものすごく長い下り坂があった。このような坂では、ベトナム人はバイクのエンジンを切る。すこしでもガソリンの消費を減らすためだ。私もまねしてエンジンを切ってくだった。下り終わってエンジンをかけようとすると、キーがない。差したままにしておいたのだが、坂の途中で落としてしまったのか!? バイクを停め、自分の間抜けぶりを呪いながら坂道を登る。上まで坂を上り、そして下るがバイクのキーはみつからない。どうしよう。プレイクはまだまだ先だというのに。でもベトナムでは困ることも多いが、なんとかなってしまうことも多いのだ。 こんな田舎道でも数百メートルおきには人家がある。そしてベトナムの道路脇には「修理屋」がやたらと多い。 なにか技術を身につけようと思い立ったとき、日本人は道具から入る。そして本を読んだり教えてもらったりして技術を習得しようとする。欧米人は技術の習得が先に来て、その後己の技術に応じた道具をそろえる。ベトナム人は道具よりも技術よりも、まず看板を出す。たとえば「バイク修理」といった看板を。 というのは大げさなのだが、そうも思いたくなるような素人くさい片手間修理屋がたくさんいる。でもそんな修理屋でも紆余曲折しながらもなんとか修理してしまうのだ。今回は数人の男がなんだかんだと言い合いながら、どうやったのかわからないがエンジンがかかるようにしてくれた。悪い人たちはこうやってバイクや車を盗むのか。とにかく助かった。ありがとう、うさんくさいおじさんたち。 プレイクに着いた頃には真っ暗になっていた。バイクを貸してくれた兄さんに鍵を失くしたことを報告。謝って追加で5万ドン支払ってゆるしてもらった。ごめんなさい。 夜はテト(正月)の宴会だ。ぼくも唯一の宿泊客としてご招待にあずかる。さあ、飲むか。つづく
2005年06月10日
コメント(0)
-
中部高原探訪記5 ~暴動
街の中心部にあった宿に決めた。そこそこ大きなホテルだが、宿泊客は私一人だった。あたりまえか、いまはテト(旧正月)休みだからなあ。 この小旅行は2001年2月のことなのだが、このすこし前に中部高原で暴動があった。ベトナムでは私の知る限りまったく報道はされていなかった。知り合いのベトナム人に訊いても、誰も知らなかったし。だがハノイに住む日本人の知り合いは皆知っていた。外国では報道されていたみたいだ。 私も詳しいことはわからないのだが、以下のような経緯で発生した暴動らしい。1995年以降はコーヒー景気に活況を呈していた中部高原であったが、ベトナム各地から移民が押し寄せ、先住民と新たな移住者の間に軋轢が生じていた。先住民の移住を強いるダム建設なども不満を増大させる原因となった。そして2000年にコーヒー価格暴落し、不満が最高点に達し、今回の暴動につながった。中心になったのはプロテスタントの団体らしい。海外に居住する反共的な越僑団体の扇動があったともいわれている。 そのような事情もあり、村にお邪魔させていただいてお墓を見させてもらうには、ちゃんとした案内人が必要になる。ひとりでぶらりと入り込むのはこのような状況下では得策ではないし、礼儀にもかなってないだろう。だが頼りにしていたツーリストインフォメーションはテト休みだ。通常なら、ここで車やガイドの手配ができるのだが。無計画過ぎたか。まあいい、今回は村訪問はあきらめよう。てきとうにぶらぶらするぜ。つづく
2005年06月08日
コメント(0)
-
中部高原探訪記4 ~ゲロ爆弾
フエになんとか到着。20時間ぐらいかかったか・・・。背中が痛い。フエで一泊してリフレッシュする。 翌朝、早朝にフエのバスターミナルに行く。ザライ省のプレイクまで一気に行くつもり。バンメトートまで行くというミニバスがあった。車掌役のおばちゃんと話すと、プレイクも通るということなので、乗ることにした。料金は5万ドンとのこと。 大型バスだろうとミニバスだろうと、ローカルバスはぎゅうぎゅうに客を詰める。そして出発。途中、何人もが車酔いでもどしていた。ベトナム人は車に弱い人が本当に多い。大人も子供もじゃんじゃん景気良く吐く。私の横に座っていた推定12才ぐらいの女の子も、窓から顔を出し何度も吐いていた。その女の子の眼光は、この年齢にして酸いも甘いも知り尽くした経営不振の場末のマダムのように荒みきっていた。車酔いがつらいんんだろうなあ。私も子どものころはよく車酔いをしたので、その辛さはよくわかる。遠足の度に吐いていた。 「ブランコに乗って遊ばへんから酔うねん」 当時担任の女の先生にそういわれて、子供心なりに「でたらめいいやがって」と腹を立てた記憶がある。 でも窓を開けて窓から直接吐くのはやらなかったぞ。ちゃんとビニール袋に吐いていた。いや、正確に言えば、同じく苦しくなって通路に横たわっていた同級生の顔の上に吐いたこともある。でもそれはビニールをもらいに行こうとして間に合わなかった不可抗力だ。窓から吐くと窓に吐瀉物がはり付くし、後ろの人に迷惑がかかるじゃないか。うかつに後ろの人も窓を開けていたら大惨事になるぞ。家の用事で買出しにでも来ていたのか、ひとりでバスに乗っているのはえらいと思うが。 前のおばさんはちゃんとビニールに吐くのだが、そのビニールを窓からぽいぽい捨てていた。おそろしい。ベトナムでバイクに乗るときは十分注意したほうがいい。バスを追い抜いたりまたは追い抜かれたりするとき、ゲロ爆弾が飛んでくるから。 ハイヴァン峠を越えて、ダナン、ホイアンを通り過ぎ、とうとうクイニョンの手前に辿り着いた。早朝にフエを出たというのに、空はもう薄暗くなりかけている。ここから1号線とおさらばし、西に進路を取るはずなのだが、ミニバスはその分岐点のT字路のところで停まってしまった。運転手とおそらくその妻の車掌がなにやらこそこそ話している。停車がちょっぴり長引きそうな雰囲気なので、私は外に出て、身体を伸ばす。車掌のおばさんが他のバスを止めてそのバスの車掌となにやら交渉している。そしてこちらに戻ってきた。 「あっちのバスに乗っとくれ。この車はもうここで終わり。お金は向こうの車掌にそれぞれの代金分私から払うから」 気まぐれバスめ。バンメトートまで行くと言ってたじゃないか。でもぼくも他の乗客も文句は言わず、乗り換える。車掌同士の清算も済み、発進。これでめでたしめでたしのはずだったのだが、そうは問屋が卸さなかった。 乗り換えた乗客は10名ほどだったのだが、そのうち私を含む7名がプレイクまでで、あと3名の親子がバンメトートまで行くことになっていた。しかしさきほどのバスの車掌はえげつない悪知恵を働かせて全員プレイクまでと偽り、プレイクまでの代金でしか清算していなかったのが判明したのだ。 新たなバスの車掌はバンメトートまで行くなら追加代金を払えと言い、3人親子の父親と母親は金はすでにさっきの車掌のおばさんに払ってあると反論する。ベトナム人はこういった口論は派手にやる。声高に主張しないと負けてしまうからだ。でもどちらも被害者。許せんのは気まぐれバスのおばさん車掌。こすいまねしやがって。私はもとからプレイクが行き先なので実害はなかったが、怒りふつふつとわきました。気分が悪い。 おんぼろバスは坂道をあえぎながら登る。外はもう真っ暗で景色はみえない。やっと念願のザライ省が近づいてきた。遠かったなあ。ローカルバスでのべ30時間以上はかかっただろう。今夜はゆっくり寝て疲れを癒そう。つづく。
2005年06月05日
コメント(5)
-
中部高原探訪記3 ~オトシゴおじさん
まずはフエまでバスで向かう。バスターミナルにはフエ方面行きのバスがいくつか停まっている。どのバスにも乗客がすでにちらほら乗っていて、どれが最初に出るのかわからない。ええい、一番乗客の多いバスに乗っておけば間違いはなかろう。他のバスの強引な客引きを振り払い、乗り込む。 ベトナムのローカルバスの座席は狭い。特に前後の幅が狭い。私はベトナムでは大柄な部類に入るので、うかつに窓際に座り閉じ込められると辛いことになる。足を斜めに伸ばせるように通路側を確保する。 座席が埋まり、通路のスペースも徐々に埋まりだす。通路といっても立つわけではなく、どこからか出してきた銭湯の腰掛風イスに座る。足の踏み場がもうないぐらいに混雑している中を、売り子が強引に割り込みながらさまざまなものを売る。パン、ビニール袋に入れたジュース、とうもろこし、果物、ゆで卵、たばこ、ガム、宝くじ、サングラス・・・。乗客は各々食料をひろげ、ゴミを床に散らかしながら食べる。 エンジンがかかった。ようやく出発だ。売り子はあわててバスから降りる。 乗客のすべてがフエまで行くわけではなく、途中で降りる人もいれば、途中で乗る人もいる。ベトナムにバスターミナルはあるが、バス停はない。降りたいときは降りたい場所で降りると叫び、乗りたいときは乗りたい場所で手を上げてバスを止めればいい。 街を抜け、田舎の道に差し掛かったころに、ひとりのおじさんが前に進み出て、大きな声で演説をはじめる。手に何かを持っていて、その品をしきりとアピールしている。最初は何を言っているのかよく解らなかったが、次第に飲み込めてきた。おじさんは手に持っている怪しげな小さい物体を乗客に売りつけようとしているのだ。といっても、おじさんも乗客なのだが。 おじさんは長い前口上を中断し、通路に腰掛けている人々を掻き分けながら乗客全員に商品を配りだした。いや、配るというより無理やり手に押し付けていった。私の手元にも来た。それは干した一対のタツノオトシゴだった。 おじさんは再び前に戻り、仕上げの口上をのたまう。 「高級なタツノオトシゴだよ。オスメス一対のタツノオトシゴ。焼酎に漬けてごらん、おそろしいほど精が付くから。どこでも買えるモノじゃないよ。それもたったの6万ドン。さあ買った買った。買う人は手を挙げて!」 だれが買うねん。6万ドンといったら400円ちょい。日本の物価で例えると、5千円札を一枚出すぐらいの覚悟がいるのだ。おいそれとポンと出せる額ではない。そもそも安くとも干したタツノオトシゴなんて欲しいか?要らないね。売れないよ、売れるわけがない。寂しくうなだれるおじさん、となるはずが・・・ 「ムア!!(買う)」 えっ!? なんとけっこうな数の人が手を挙げてムア宣言を高らかに表明しているではないか。私の小賢しい常識、通じず。おじさんは当然といった面で買う人からは代金を、買わぬ人からはオトシゴを回収してまわる。やるなあ、おじさん。 まだフエにつかない。中部高原はまだまだ遠い。バス旅はつづくのだ。
2005年06月03日
コメント(1)
-
中部高原探訪記2 ~バスで行くよ
ハノイからザライ省の省都プレイクまでバスで行くことにしました。そのバスについてすこし説明をします。 ベトナムの長距離バスは、おおまかに二種に分けることできます。ひとつはローカルバス。各町のバスターミナルから発着し、あとはヒッチハイクの要領で、乗りたいところで乗り、降りたいところで降りるバスです。もうひとつは外国人旅行者が主に乗るバスです。ハノイ-ホーチミン間を主要路線にし、主だった都市で乗り降りできます。 おもしろいのはなんといってもローカルバスです。時刻表は無きに等しく、十分な乗客が集まれば出発します。座席はもちろん通路にも人がごったがえし、もうこれ以上入らんだろうすし詰め状態のところに、さらに売り子が何人も乗り込んできてあらゆる商品を売り歩きます。それにまたみんな荷物がやたらと多い。座席の下はもちろん、バスの上にも大量の荷物が積み込まれる。自転車やバイクも天井に積まれる。冷房はもちろん効いていない。 外国人用バスはこのような混沌とは無縁で、座席数以上に人が乗ることもない。日本の高速バスをそのままイメージして遠からずといったところ。ほぼ定時運行ですし、快適さでもローカルバスに数段勝る。でも、つまらない。 私よりもベトナム文化に精通し、ベトナム語に堪能で、ベトナム各地に足を運んだ日本人はごまんといます。ですがそんな私でもこれなら負けないのでは、と密かに自負していることがいくつかあります。そのうちのひとつがローカルバスです。私ほどローカルバスに乗った日本人はそうはいまい、そう根拠もなく自負しています。この中部高原を訪れる旅日記では、ローカルバスを紹介することが肝になります。当初はザライ族のお墓の彫刻をこの目で見たい、という動機で出立したわけですが、結末をばらしてしまうと、この目的は果たされず、結果的にはいたって尻すぼみなエピローグとなってしまうのです。私の情熱が冷めたのが原因ではなく、不可抗力な要因がいくつか重なったためなのですが。 前ふりがやたらと長くなってます。いつ出発するんだ。もうじきです。でも今回はまだ出発しません。次回です、たぶん・・・。つづく。
2005年06月01日
コメント(0)
-
中部高原探訪記1 ~きっかけ
ハノイの美術館には、とことん失望させられました。ろくなものがないのです。美術の心得も素養もない私が評価するのは傲慢かもしれませんが、素人目からみても駄作ばかり、それが正直な感想でした。 入場料を払ったことを後悔しながら別館の二階をたいした期待もせずみて歩いていたとき、一点の彫刻が眼に入りました。木彫りの鳥の彫刻で、荒々しいながらも気品があるように感じられました。「何者だ、こいつを彫ったのは?」そう思いながら説明を読んで見ると、中部高原に住むザライ族がお墓のまわりに立てる彫刻であると記してありました。 ザライ族?そういえばハノイに住むベトナム人に、「おまえはザライ族に似ている」といわれたことがあったっけ。すばらしい彫刻の伝統があり、私に似ているというザライ族、うーん一方的な親近感と興味がわいてきました。中部高原に行きたい、いや行かねば。そう短絡的に思い立ち、私はテト休みを利用して中部高原へと出立しました。どうなることやら。 つづく
2005年05月30日
コメント(3)
-
逆カルチャーショック
日本人の友人とハノイにある日本料理屋に行ったとき、カルチャーショックを受けました。 「冷奴ください」 「すいません、豆腐をちょっと切らしてしまいまして、申し訳ないです」 平身低頭そういわれました。日本でなら当たり前のことなのですが、久しぶりに日本文化に触れた私は、不覚にもびっくりしてしまいました。 ベトナムで注文した品が切れていたときには、「het roi(なくなった)」と素っ気なく言われるのが常です。その素っ気なさにすっかり慣れていたものですから、懇切丁寧な日本式の弁明が、かるいカルチャーショックだったわけです。 日本式が優れているですとか、ベトナム式が合理的だなどと、優劣を付けるつもりは毛頭ありません。それぞれ個性的でいいじゃないですか、そう思います。 しばらく東京で暮らしたのち、数年前に生まれ故郷の大阪に帰ってきたときも、カルチャーショックを受けました。場所は御堂筋線の西中島南方駅近くのとある回転寿司屋でした。そこでは、我が眼を疑うネタがぐるぐる回っていました。 軍艦巻きの上にたこ焼き・・・ 個性的でいいじゃないですか、とは、思えませんでした。寿司とたこ焼きは別々に食べようよ。
2005年05月28日
コメント(2)
-
男無酒是旗無風
ベトナムで酒を飲むとなると、それはすなわち一気飲みを意味します。焼酎ならチェンと呼ばれるお猪口で、ビールなら当然グラスで、杯を何度も合わせてはそのたびに一気飲みです。この一気飲みを「100%」と言います。100%と言われて杯を合わせると、必ず飲み干さねばなりません。これが何度も繰り返されます。ベトナムでは自分のペースでしみじみ飲む、なんてクールな態度はゆるされません。 あまり飲めない人は、うまく断る術を身に付けねば身がもたないでしょう。「いやあ、もう飲めません」といっても聞き分けよく引き下がってくれる人はほとんどいませんから。でも私にいい知恵があるわけではありません。酒好きなので断ることはなかったもので・・・役立たずですみません。 ですが、断る人を断れなくする必殺(?)の台詞はきっちり習得してきました。 Nam vo tuu nhu ky vo phong. 日本語に直訳すると、「酒を飲まない男は、風のない旗のようだ」、です。 だらしなく垂れ下がった旗のようだぜ、酒を飲まない男は。酒を飲んで男らしくはためけ。そういうキツイお言葉です。そこまで言われるとなかなか断り切れるものではありません。 「わたし女やから・・・」 これ以外にやりかえすうまい台詞が何かないものでしょうか。
2005年05月27日
コメント(0)
-
青いバナナを盗め
バナナネタ、続きます。 ベトナムのハノイに住んでいたころ、胸のあたりに小さなできものがたくさんできました。痒いうえに掻きすぎると痛くもなる。不快指数が我慢ならないほど高まり、ベトナム人の友人に相談してみたのですが、その友人が教えてくれた治療法がふるっていました。 「青いバナナを盗め」 それが友人の助言でした。 「え?」 要領を得ない私に、友人がしてくれた補足説明をまとめると、以下のような手順になります。 1.青いバナナが生っている木を探す。 2.かっぱらう。 3.もいだ断面から染み出してくる透明の液を患部に塗る。 「要するにへたの辺りから染み出る液を塗ればいいんだな?」 「そうだ」 「バナナを買ってきてもいいんだろ?」 「だめだ」 「木から直接もがないとだめなのか?」 「そうだ」 「じゃあ持ち主に断ってからもいでもいいんだろ?」 「だめだ」 「盗まないとだめなのか?」 「そうだ」 そうかいそうかい、そこまで断言するなら盗んでやろうじゃないか。ハノイといっても私が居候していた家はハノイのはずれで、近所は庭付きの家がほとんど。まだまだ畑もたくさん残っているようなのどかな地区なので、バナナの木を見つけることに苦労はありません。薄暗くなるのを待ち、近所の庭からバナナを失敬してやりました。それを持ち帰って塗り、翌日また・・・。これを数日間続けていると、痒みはましになりできものも心なしかおさまってきたような気がする。 半信半疑どころか「一信九疑」だった私ですが、案外効いちゃったわけです。民間療法侮るべからず、盗め療法恐るべし。「盗まなくても効くんじゃないか」という疑惑は、依然くすぶっているわけですが・・・。 余談ですが、日本にもこの「盗め療法」と似た言い伝えがあることを帰国後知りました。既婚女性がなかなか妊娠できない場合に、十五夜の晩に供えられた団子や里芋を盗んで食べよといわれていたそうです。 ベトナムのバナナの場合は、たとえ盗みがばれても理由が理由ですので、咎められることはないそうです(でも見つかると効果はなくなる)。そしてほとんど誰もがこの治療法を知っているとのこと。日本の場合も、「十五夜団子は盗まれるほど縁起がいい」と寛容な態度を示していたそうです。でもこの風習を今でも知っている日本人はどのぐらいいるのでしょうか。現代日本でやる場合は、ちょっとした覚悟が必要かもしれません。参考:『旧暦で読み解く日本の習わし』 大谷光男監修 青春出版社
2005年05月23日
コメント(2)
-
バナナの木を植える
私はお酒を飲んで酔っぱらうと、たまに逆立ちします。主に「酔っぱらってるやろ」と言われて、「酔ってへん」ということを頼まれもしないのに証明するときに逆立ちます。子供のころからなぜか逆立ちがすきで、時間を持て余しているときには畳の上で何度も何度もやったものでした。三子の魂なんとやら・・・。 ベトナム語では、逆立ちすることを「バナナの木を植える」と表現するそうです。なかなか粋な言い回しではないですか。たのしくお酒を飲んで、日本各地にバナナをいっぱい植えてやりましょう。
2005年05月22日
コメント(2)
-
水くさい
ベトナムに住んでいて最初に驚いたことは、ベトナムに割り勘はほぼ存在しないということです。誰かと食事に行ったり飲みに行ったりすると、必ず誰か一人が勘定を済ませることになる。そして「ありがとう」やら「ごちそうさま」なんて言葉を、支払いを済ませた人に対して言うこともない。これにも当初はとまどいました。おごってもらって「ありがとう」と言うと、怪訝な顔をされるし、逆におごってもお礼の一言もないため、厚かましいやつらよと誤解する始末。おごってもらって礼を言うなんてことは水くさいことであり、また機会があればお返しにごちそうすればよいのだと、数ヶ月目にようやく気づいた私でした。
2005年05月21日
コメント(2)
-
生き馬の目
見知らぬ人に対しては「生き馬の目を抜く」ようなことを悪びれもせずやってのけるベトナム人って、たまにいます。そこまではいかなくとも、油断ならない人が多い、と言うことはできると思います。あくまで日本人の感覚から言って、ですが。 でもいったん親しくなり信頼関係を築くと、ベトナム人ほど頼もしい人たちはいません。困ったときには骨身を惜しまず助けてくれます。まあそれは、貴方も友人に対してそのように接しなければいけないということでもあります。信頼できる友人から助力を求められたら、全力で応えましょう。 親しくともなんともない人から、図々しい要求をされることもあります。というか、非常によくあります。そんな場合は無理せずできる範囲で応えるか、断ってしまえばいいでしょう。
2005年05月20日
コメント(0)
-
しまっていこう!
一人でいろんな国をぶらぶら旅行していたと言うと、「男だからできるんだよね」とか、「私もやってみたいけど、女だから」、 なんて言われることが割によくある。女性には男性以上の危険が付いてまわるのが事実だということはぼくも認めるし、そのために行動が制限されたり、気苦労が増えたりするのは気の毒にも思う。けど女性特有の危険が存在しているように、男性特有の危険もまた確実に存在しているのだ。 とりあえず一例として、ヨルダンのとある町での話。この町で、ぼくはホテルの屋上にテントを張っていた。屋上だと宿泊代が安くなるし、共同のシャワーやトイレが使えてしかも安全なのだ。 屋上で空や街並みを眺めてのんびりしてから、共同の洗面台に顔を洗いに行った。蛇口の水を出しっぱなしにしながら顔を洗っていると、なんだかお尻の辺りにツンツンと異物があたっているのを感じた。なんだろうと振り返ると、下半身裸の大柄の男が背後に立っている。彼は自らのそそり立ったモノでぼくの尻を突き、「ミスター、ミスター」と、熱く囁いた。なぜ見知らぬアラブ人に気安く我が尻をツンツンされなくてはならないのかという正当な憤りを感じる暇もなく、ぼくは玉消て、じゃなかった魂消て逃げた。腕っぷしでは到底かないそうにない、ごつい男だったのだ。階段を駆け下りて一階に行き、ホテルの人に告げ口した。「ストレンジ・マン・ツンツン・ミー!」と、言いたいところであったが、そんな表現では当然通じない。なんとかへたくそな英語で事情を説明、洗面台に出没したストレンジ・マンはめでたくホテル・マンに追い出された。彼は宿泊客ではなく、勝手に入り込んだ闖入客だったそうだ。 フィリピンのとある島のとある町でのこと。べつに地名を特定するのを避けているわけではなく、ヨルダンの町と同様名前を忘れてしまったのだ。けど確か「キャロル」に似た名の町だった。というのは、この町に向うバスの中で車掌に行先を告げて料金を払うとき、間違って「キャロル」と言って、バス中を爆笑に包ませたのをぼくはよく覚えている。なんでそんな間違いをしたかというと、そのときバスで「オーキャロル、ベイビーアイラブユーソー」なんて歌詞の古い歌が流れていたからだ。「おい、こいつキャロルだってよッ!」 乗客にドッと笑うタイミングを絶妙に提供し、自らも心底可笑しそうに笑った車掌をぼくはよく覚えている。そこまで可笑しいかと思わないわけでもなかったけど、くだらないことにここまで心底笑える人間に悪い人はいない、ような気がしないでもない。 その仮名キャロルという町でぼくが泊まった宿はひどかった。狭くてかび臭い部屋、マットも掛け布団もない木製の寝台に(ござは敷いてあった)、鍵がかからないどころかきちんと閉まることを頑なに拒絶する立て付けの悪いドア。シャワーはもちろんなく、水浴びは一階の中庭にある大きな瓶から水をすくって浴びるのだ。けどそんなことに苦情が言いたいわけではない。それらの貧弱な設備を見てもなお、宿泊することに決めたのはぼくだから。 その夜は遅くまでビールを飲んでいた。フィリピンはビールを飲むのが楽しい国だ。ビールが安くておいしいし、生バンドの演奏が聴ける飲み屋も多い。屋台でカニをしゃぶりながらビールを飲むのもいい。そしてゴーゴーダンスをステージで観せる飲み屋も多かった。ゴーゴーダンス?と訊かれても、ぼくにもそのへんのジャンル区分がよく分からないのだが、とにかくステージの上で女の子が脱ぎながら踊り、それがゴーゴーダンスと呼ばれていたのだ。こういう妖しい店でも、隣りに女の子を呼ばずビールを飲んで観ているだけなら、健全な飲み屋よりちょっとビールの値が上がるだけで、入場料や席料なんてものもない。 てなわけで毎晩酔っぱらっていたわけだが、その夜もふらふらになって宿に戻り、服を脱ぎ捨て、固くてねぎらいのない机のようなベッドに突っ伏した。いつもなら昼前まで目が覚めることはないのだが、その夜はまだ日が差しはじめる前に目覚めた。なんだか下腹部がくすぐったいのだ。首をもたげると、髪の長い女がぼくの下腹部を丹念に舐めていた。もちろん驚いたが、気持ちがよかったし、これはひょっとしてすごくラッキーな状況なのではないか、タナボタやん、なんて邪念が頭をよぎったりもした。けれど髪で隠れて顔が見えない。顔も見ずにラッキーと決め付けるのは早計というもの。そんなことを考えていると、彼女はぼくが起きたことに気付き、唇を下腹部から離し顔をぼくの方に向けた。部屋が薄暗いながらも、彼女は「彼女」という人称代名詞が生物学的に相応しくないヒトであることがわかった。 なぜそんなすぐにわかったかというと、ぼくは「彼女」を昼間のうちにすでに見知っていたからだ。ぼくはその彼女風彼が働いている食堂で飯を食べ、目線も何度か合わせていた。こんな田舎町でも彼のような人が、特殊ではない普通の食堂で、昼間なにげなく働いているということに驚いて、彼の強い意志なのかそれともここでは迷惑をかけない程度の「異質」な人に対するおおらかで寛容な空気が存在するのだろうか、などと考えながら、彼に不躾な視線を送っていた。その視線を彼は「彼女」なりの解釈で受けとめたちゃったのかも。それでこの状況。彼は華奢な体格で、ヨルダンのストレンジ・マンのときのような肉体的恐怖は感じなかったけど、やっぱりゾッとしない。 「出てけ!」 ぼくは毅然とした態度で言うが、彼は動かない。 「出てけっちゅうねん!」 さらに語調を強めて膝でかるく相手の胸を小突くと、彼はすごすごと立ち去った。 ヨルダンの男にしろフィリピンの男にしろ、こんな一直線的愛情(?)表現ではちょっとマズイんじゃないかとぼくなんかは思う。異性間だって「好き、すなわち、ファック」では、なかなかうまくいかないんじゃないか。まずは言葉から、そして段階的にプロセスを踏んでくれれば、ぼくだって逃げたり邪険にしたりせず、丁重にお断りすることもできたはずなのだ、たぶん。 以上はぼく自身の体験談で、今となっては笑い話だし、当時でさえそれほど深刻に受けとめていたわけではない。けれど他人の体験ならば、ちょっと笑えない話を聞かされたことがある。 被害者は30代の日本人男性A氏で、彼はトルコからシリアへ陸路で国境を越えた。しかしシリア側には時間も遅くなっていたこともあり、町に向うバスもタクシーも見当たらない。歩いて行くにも遠すぎる。入国・出国手続きをする税関の建物や金網を除けば、目に映るのは殺伐とした荒れ地のみ。A氏は途方に暮れた。けれど旅ではたいていの困難は人々の親切によりなんとかなってしまうもので、そのときも国境警備でもしていたのか軍のジープが通りかかって、乗せてくれる上に軍の施設に無料で泊めてくれることになった。渡りに舟とA氏はジープに乗り込む。ジープには4人の軍人が乗っていた。ジープは荒れ地を疾走する。空はさらに暮れはじめる。ジープは人気のない所で(といっても人気のある所を探すほうが難しかっただろう)停車した。そしてA氏は必死の抵抗むなしく、4人の屈強な男に可愛がられてしまった。たまには人々の親切の届かない困難が待ち受けているときもあり、どうにもならないときもあるのだ。 ぼくはこの話をAさんから直接聞いたわけではない。人伝に聞いた話で、真実であるかどうかはわからない。でもありえない話じゃない。ぼくもトルコからシリアに陸路で黄昏時に国境をを越えたことがある。そのときはタクシーが一台客待ちしていた以外は、どんな交通手段もなかった。そしてその付近はたまらなく殺伐とした風景だった。たとえA氏がフィクション上の人物であったとしても、あの国境地帯ではそういう事件が起こって不思議ではないし、その被害者がぼくであった可能性ももちろんゼロではない。そう思うと、ケツの穴が縮む思いだ。縮むだけならいいけど・・・。 日常生活でも起こりうるあらゆる災厄が、旅先では降りかかる確率を倍倍にさせて待ち受けている。勝手が分からない土地に行くのだから、それは当然だ。男が見落としがちな性的災厄ももちろん待ち受けている。そして何とかなってしまうときもあるが、何ともならないときもある。男だからといってその種の危険は大丈夫と慢心せず、ケツの穴締めてかからんとマズイですぜ。
2005年05月16日
コメント(0)
-
サパ トレッキングツアー 第2回
一泊二日のトレッキング・ツアーに申し込む。値段は15ドルとちょっと高い。外国人しか参加しないのも当然か。同行者はハノイから道連れの日本人二人、そしてサパ在住ガイドのクイ君。クイは二十歳のキン族で、日本人二人は元同級生Aと会社からハノイに派遣された語学研修生Kさん。 町を出て、沢沿いに下る。沢を挟む丘陵の斜面には、棚田が重なりトウモロコシの焼畑がひろがる。小学校に寄ったり、フモン族の家でお茶によばれたりしたあと、川原で昼食をとる。フモン族の男の子二人が渓流を石で堰きとめて遊んでいる。二人とも小学校低学年ぐらいのとしごろか。ぼくらはそれを眺めながら、なんにせよ子どもが遊んでいられるってのはいいね、などとのんきな会話を交わしていた。しかし彼らはただ遊んでいるわけではないことがじきに判明する。 川を堰きとめ、本流のわきに細い支流をこさえ、しばらく水が流れるままにしておいてから、支流を塞ぎ、上流と下流二手に分かれて支流に迷いこんだ小さな魚やオタマジャクシやヤゴなどを追いつめて手づかみでビニール袋に入れていく。晩飯のおかずをとっていたのだ。上流の男の子が岩の下に手を入れたかと思うと、すばやく手を抜いた。そして河原に落ちていた棒切れをつかみ、岩の下から気味の悪いぶよぶよしたかたまりをかき出し、棒に絡めて水から引き上げ、岩に叩きつけた。そして何度も何度も棒切れで叩く。近寄って見てみると、それは蛭だった。すでに打ちのめされて赤い血を垂れ流している。「血を吸われたのか」とぼくが訊くが、男の子は首を振り、「水牛の血」、とそっけなくベトナム語で言った。 ガイドのクイが棒切れで蛭を突ついて遊んでいる。そしてぼくのほうを向き、「きょうの晩飯のおかずは蛭だよ、イワーイ」、うれしそうに言う。「てめえが食え」という言葉を飲みこんで、ぼくがやりかえす。「忘れずにもっていけよ、クイ。米焼酎に浸けるんだ。蛭酒だよ。きっとキクぜ」。ベトナム人はなんでも酒に浸ける。熊を丸ごと一頭酒を満たした水槽にぶち込んだり、そしてカラスやトカゲやうす気味悪い虫なんかを手当たりしだいなんでもぶち込んで、そしてどの酒も決まって「キクぜ」で形容されてしまうのだ。ひょっとして蛭酒なんてすでに定番になっているのかもしれない、そう思い至り、自分で言ってゾッとする。不安気にクイの顔色をうかがうと、クイは名案といった感じに肯き、「そりゃキクだろうな、血もあるし」、そう言って笑った。冗談でよかった、ぼくは胸をなでおろす。 夕方には今夜泊めてもらう家に着いた。ザイ(Giay)族の家だ。高床ではなく平土間のつくりだった。タイー(Tay)・ターイ(Thai)系の彼らは高床の家に住むことが多いのだが、地域によっては平土間の場合もあるらしい(1)。ザイ族の家族とはほとんど話す機会がなかった。遠慮してかぼくらとは別の間にいつもいるし、ぼくらも無理に近づこうとはしなかった。食事はまったくそのままキン族風。キン族がオーガナイズしているツアーだ、きっと少数民族の食事なんか外国人の口に合うはずもないと決めつけているんだろう。ぼくらはがっかりしながら、ハノイで食べ飽きている春巻をつつき、持参のフモン族特製のリンゴ酒をあおる。すこし甘すぎるが、まあいける。ぼくらは酔いつつも、けっこう真剣な会話を交わした。少数民族が多数を占める「僻地」の観光地化について、観光客であるぼくらのあるべき姿勢について。 少数民族が自身や自身の生活を観光名物化することによって、現金収入を増やし、そして豊かになるという。それは確かに一面真実だろう。けれどサパに限っては、その現金収入は微々たるもんだ。例えばぼくらはこの一泊二日のトレッキング・ツアーに一人15ドル払った。三人で45ドルだ。そのうち少数民族に流れる金額はいくらもない。ツアー会社から支払われるだろう一泊の宿泊代金だけだ。多く見積もったとして一人1ドルで3ドル。それだけだ。3ドルだって彼らにとっては決して小銭ではないが、あまりに取り分が少ない。残りはすべてキン族の懐に収まるようになっている。サパ近辺の少数民族は、彼らで話し合い、現金収入の途として観光化を自ら決断したわけではなく、外国人とキン族によって観光化されたのだ。そして金になるおいしいところを独占されたまま、細々と土産物などを売り歩いている。堂々とサパの町中で土産物店を開いているのはすべてキン族だ。観光化して現金収入をふやすにしろ、しないにしろ、それは当事者であるそれぞれの地域の少数民族の意見がもっと反映され、そして観光化を具体化するときに彼らがもっと主導的になるべきなのではないか。 ぼくらはそんな話をする。そして話しつづける。キン族をワルモノに仕立ててそれで終わる話なのだろうか。ぼくらはいったい何様なんだ。観光化による恩恵のおこぼれすらあずかっていない多数の村人たちの眼に、ぼくらのような闖入客はどのように映っているのだろうか。ぼくらは、「何しにきた、さっさと出て行け」とつっけんどんにあしらわれても、返す言葉なんて何もないんじゃないのか。でも道すがらに出会った人々は、なぜ大人も子どもも、土産物を売りつけるわけでもないのに、こんなにもにこやかにやさしく迎えてくれるのか。ぼくたちは彼らの心の寛(ひろ)さに感謝するだけでいいのか・・・。 翌日は別の道を通って、サパへと帰る。Aは川の飛び石をつたうときに足を滑らせ半身ずぶぬれになる。Kさんとクイは田んぼにはまり泥だらけに。運動神経が抜群で、長野の山小屋で二年働き山道に慣れているぼくは、他人の不幸を尻目に軽口をたたきながら、軽快に歩を進める。そして、みじめな連中のウラミをすこし買う。 サパに着いたときはさすがの健脚のぼくも疲れた。AやKさんは膝がわらっている。冷えたビールがうまい。鹿鍋も猪のステーキもうまい。誰だ、サパにうまいものなんてないと言ったやつは。宿に戻り、ベッドのジャンケンをする。三人いても、ベッドは二つしかないのだ。サパの初夜ではぼくが勝ち、AとKさんがベッドを共有したので、今回ぼくはジャンケン辞退を謙虚に申し出る。二人はビールが入って気が大きくなっているのか、辞退する必要はないと言う。お言葉に甘えてジャンケンすると、またぼくが勝った。「ヨッシャ!」、小さくガッツポーズを決めると、「ヨッシャじゃねえ!!」、二人が怒りをあらわに。だからぼくは最初に辞退したじゃないか。二人はぼくのまっとうな抗弁を無視して、勝者を罵る。ぼくはまた、みじめな連中のウラミをすこし買う。(終わり)
2005年05月15日
コメント(0)
-
サパ トレッキングツアー 第1回
ベトナム北部山岳地帯のサパという小さな山間の町は、避暑地として、または種々の少数民族の村を訪れるトレッキング・ツアーの拠点として有名だ。キン族(狭義のベトナム人)観光客はおもに前者の目的で、外国人観光客はおもに後者の目的でこの町にやってくる。キン族はみやげもの屋をひやかしたり、少数民族が民族音楽にあわせて踊るのを観賞するのがせいぜいで、トレッキング・ツアーに参加することはほとんどない。彼らにとって歩くことに金をかけるなんてことは馬鹿げた発想であり、歩くのは貧乏人に任せておけばいいのだ。「サパに行くんだけど、サパでは何がおいしいのかな」。ハノイでキン族の友人たちに訊いてみたが、「何もない、すべてまずい」、誰もが侮蔑をかくそうともせずそう言いきった。 ハノイ市の片すみに数年前に建てられた民族学博物館は、ベトナムにある他のどの博物館、美術館、記念館よりも充実し洗練されているが、訪れるのは少数の外国人だけで、閑古鳥が鳴いている。既存の高速道路から民族学博物館まで引かれたこれまた新しいアスファルト舗装道路は、走る車もないというのに四車線はあろうかという堂々たるしろもので、子どもたちの格好のサッカー場と化している。「あんなもんつくって何になんねやろ、少数民族の暮らしがちょっとでも良うなるゆうんかい」 大学院で人類学を学び、ハノイをフィールドに研究をしている日本人Uさんがそう言っていた。ぼくはなかなか興味深くこの博物館を見学したし、その中身の充実ぶりにも感心したけれど、Uさんの言うことも一理ある。少数民族にとっての民族学博物館は、動物にとっての動物園と大差ないのかもしれない。そういう言い方は語弊があるかもしれないが、金を使う優先順位が本末転倒しているという意味では、Uさんの言うことは確かにそのとおりだと思う。 サパの市場でフォー(うどんみたいなもの)を一杯ひっかけた。五分もあれば撤収できそうな、屋台に毛が生えた、もしくは屋台の毛が抜けたような店が、いくつか軒を連ねて市場の一角を占めている。ぼくが座ったフォー屋のおばさんは、ぼくが日本人であることを一目で見抜いた。慧眼なり。多くを語らない限り(ぼくのベトナム語の発音はひどい、もちろん文法も)、外国人と露見することは滅多になかったのだけれど。人によっては、ぼくが自分で日本人だと白状しても、「おまえの両親も日本人か」と疑り深く目を光らせたり、「おまえは断じて日本人じゃない、いや、キン族でもないな、中部高原のザライ族だ」とか、「おまえは中部の海辺に住みついている漁師だ」なんて言ってくれる人までいるくらいだ。そこまで限定するかと半ばあきれ、その揺るぎない確信はどこから湧いてくるのかと半ば感心したものだ。 とにかくぼくはフォーを食べていた。他のテーブルには民族衣装を着たフモン族の男も数人いた。そこへ欧米人の白人カップルがやってきた。彼らは二人とも、首から立派なカメラをさげていた。彼らはフモン族の男たちに挨拶し、写真を撮ってもいいかとジェスチャーで示してから、パチパチと撮りだした。そしてしらじらしいフレンドリーな笑顔をはりつけ、肩を組んで一緒に写真におさまったりしている。フモン族の男たちは困ったようなひかえめな微笑を浮かべている。温厚な人たちだ。普通、食事中にこんなことをされれば腹も立つというのに。ぼくはその欧米人カップルの無神経さを苦々しく思いながら、鳥取砂丘での出来事を思い出していた。 数年前、鳥取の友人宅に遊びに行ったとき、その友人に誘われるままキャンプに参加した。友人は外国人の知り合いが多いやつで、キャンプに参加したのは、ぼくと友人を除くと全員外国人だった。中学や高校、または英会話学校なんかで英語教師をやっている人たちが企画した、サイクリング&ビーチキャンプだった。自転車でキャンプをする海岸に向う途中、休憩を兼ねて砂丘に寄った。そこでぶらぶらしていると、日本人の若い女性数人が近づいてきて、一緒に写真を撮りたいと言いだした。そのときぼくはカナダ人カップル二人と一緒にいたのだけれど、ぼくはお呼びでなくて、カナダ人二人がお呼びであった。挨拶も何もなしにいきなり一緒に写真をとは、なんて非常識な女なんだと思ったが、カナダ人二人は苦々しいスマイルを浮かべながらもちゃんと一緒に写ってやった。もちろんシャッターを切ったのはぼくだ。彼女たちが遠ざかったあと、カナダ人の男が例の写真女たちを称して、「ティピカル・ジャパニーズ(典型的な日本人だな)」と皮肉っぽく口もとを歪めて言った。返す言葉もない。そして、「あの女たちは俺たちのことをマスコットか何かだと思ってるんだろう」、そう言葉を継いだ。 そのときはマスコットとはうまいこというなと感心して笑っていたが、サパの食堂で欧米人カップルのしらじらしいフレンドリーなスマイルを見ていると、彼らにとってフモン族の男たちはマスコットなんだろうな、そう思えてしょうがなかった。彼らにとって大事なのは、フモン族の男たちとの一期一会ではなく、帰国して友人に見せる写真なのだ。 つづく
2005年05月15日
コメント(0)
-
バオ・ニン紹介 2
バオ・ニン氏に私も一度お会いしたことがあります。東京外国語大学でバオ・ニン氏を囲む会のようなものが催され(正式な名称忘れました)、そこでお会いしました。バオ・ニン氏はウイスキーとた煙草をのみながら、参加者の質問に鷹揚に答えていました。講義室内で堂々と煙草を吸うすがたがクールでした。 私はバオ・ニン氏の短編「侵略軍のバイオリンの音」を読み、カミュの『転落』を思い浮かべました。バオ・ニン氏に『転落』を意識したかどうかを訊いてみたかったのですが、訊けずじまいでした。 残念でしたが、バオ・ニン氏は魅力的な方でした。同じスモーカー仲間だと確認できただけでもうれしかったです。
2005年05月13日
コメント(0)
-
バオ・ニン紹介 1
バオ・ニンはベトナム国外ではもっとも名の知れた現代ベトナム人作家だと思います。代表作は『戦争の悲しみ』というベトナム戦争(北ベトナム側の表現だと抗米救国戦争)を題材にした長編小説です。内容もさながら、訳者が正確に訳していないという批判も飛び出し、「改竄疑惑」としてもすこし話題になりました。英語からの重訳ですので多少の誤訳は致し方ないと思いますが、確かに訳者が想像をたくましくしすぎた箇所もあるようです。 私の大学の恩師が、日本ペンクラブの作家をベトナムに案内したときにバオ・ニン氏とお話する機会があったそうです。日本の作家は『戦争の悲しみ』に感銘を受けていたため、あの部分がよかったと具体例を挙げて賛辞を送るのですが、バオ・ニン氏はキョトンとしておられたそうです。後ほどあたってみると、日本語訳には出てくるその場面が、原文(ベトナム語)ではまったく記されていなかったとのことです。 翻訳とは「まったく新しい作品をつくりあげることだ」、という考え方もあるかもしれません。ですが翻訳と名のる以上は翻訳としての節度をまもるべきであり、まったく新しい場面をつくってしまうとそれはもう翻案小説となってしまうように思います。
2005年05月13日
コメント(0)
-
ファンシパン登山記 六日目(最終日)
列車は早朝ハノイに着く。ハノイ駅からホアンキエム湖まで歩く。宿が開きはじめるまでまだ時間があるので、湖の畔で座って待つ。この湖はハノイ市民憩いの場所であり、ハノイのシンボルでもある。ベトナム人は早起きの人が多く、早朝に健康のための運動をする人も多い。バトミントン、怪しげなエアロビクス、怪しげな太極拳もどき、見たこともない怪しげな体操、などなどをしている。日本人の感覚からすると、怪しい動きにあふれている。この早朝というのが、なかなかたのしめる時間帯なのだ。ベトナムに旅行したなら、一度早起きしてみてください。 旧市街のほうにぼちぼち歩き出し、ひさとみが今晩泊まる宿を見つける。ぼくは夕方のフライトで帰国するので、今晩は機中泊。ハノイは以前ぼくが住んでいた懐かしの都。もっとゆっくりしたかったが、時間がないのでしょうがない。荷物を部屋に置いて、朝飯を食べに行く。 ハンザー市場近くのうなぎが売りの店に入る。うなぎ春雨、うなぎ粥、うなぎスープなどのメニューがある。ぼくらはお粥をたのんだ。揚げパンをちぎって入れる。滋養もありお腹にも優しい完璧な朝食だ。もちろんおいしくて、料金は50円ほど。 食後ハンザー市場をひやかす。ぼくはハノイの市場ではこのハンザーが一等気に入ってる。ミーハーな外国人の異国趣味と、現地の生活に触れてみたいというわがままな欲求両方に過不足なく応えてくれる市場だ。ここより大きな市場は他にもあるが、ハンザーが一番だと思う。 まずは定番の陶器屋でみやげ物を物色する。品揃えも多く、安い。しかも売り子のお姉さんの胸元が拝めたりする。梱包したりするとき、地べたにしゃがんでするからね。 次は乾物屋へ。友人に干したタツノオトシゴを頼まれているのだ。オス・メス一対で500円ほどする。タツノオトシゴは高い。これを焼酎に漬けて飲むと、精がつくと言われている。友人はこの「タツノオトシゴ&酒→精力絶倫」説を信奉しているのだ。あとかわはぎに似た乾物も買う。ベトナム語でカーボー(牛魚)と呼ばれる魚のもの。これもおいしい。後日日本在住のベトナム人に訊いたところ、河豚に形状の似た魚らしい。でも毒はない。 市場にはもちろん屋台もある。チェーを食べながら一息入れる。食べながら昼飯の算段。食べたいものはいっぱいある、行きたい店もいっぱいある。しかしぼくに残されているのはあと一食のみ。強行日程や哀し。悩んだ末に、ここは奇をてらわず定番ブンチャー(漬け麺)に決める。動くのが面倒なので、市場近くの店に移動。炭火焼の香ばしい肉を適度に甘みのあるタレに香草などといっしょに入れる。そこにブン(米から作った細麺)を漬けて食べる。日本人なら誰もがうまいと言う味でしょう、これは。揚げ春巻きをトッピングに付けるのもまた好し。 腹は満ちた。次は疲れたからだを癒すべく、サウナ&マッサージに行くか。これもハンザー市場近くの中級ホテル付属のところがあるので、歩いていく。ハンザー市場付近は本当に便利だ。このロケーションもポイントが高い。 サウナ&マッサージは一時間で500円弱。外国人料金を取るところも多く、もっと高いところもある。ベトナムのマッサージは露出の多いお姉さんもしくはおばさんがやってくれるちょっと怪しげなところがほとんど。通常女性が来るところではないのだが、ひさとみも付いてきた。 まずはサウナ。シャワールームの奥に付属している、狭い本当に狭い空間がサウナルーム。腰掛に座り、バルブをひねるとグゴーというすさまじい音をたてながら、下方より湯気が噴き出してくる。このサウナを「ガス室」と言ったのは、確か『行けベトナム街道』の著者池部さんだったと思う。不謹慎だが言いえて妙。あまりのすさまじい水蒸気に閉めるバルブの位置が見えなくなり、必死に探して死にかけたことあり(火傷はした)。閉めずともサウナから出ちまえばよかったんだけど。 シャワーで汗を流したあとにマッサージ。ベトナムのマッサージはタイ式。ときに痛いが悪くない。それにお姉さんと触れ合えるし。最後のほうに調子に乗って胸をもませてもらってたら、先に終えてかえりがけのひさとみにドアの窓越しに見られた。ちょっとバツが悪かった。お姉さんにチップを渡してぼくも部屋を出る。 そろそろ空港へ向かわねば。さよならハノイ。今回は時間がなくてお世話になった知り合いの方々には会えなかった。マッサージ行く時間はあったのかと、つっこまれそうだが。また来る、必ず来るから。(おわり) ↓あやしい体操@ホアンキエム湖
2005年05月12日
コメント(0)
-
ファンシパン登山記 五日目
ああ、膝が痛い。いや膝だけでなく、どこもかしこも痛い。こんな強烈な筋肉痛はいつ以来だろう。生まれて初めてかもしれない。ひさとみもかなり痛そうだ。ふたりしてぎこちない歩行動作。油の切れたロボットのように藪の中に入り、用を足す。トイレなんてないので野糞。その後火にあたりながら朝のコーヒーをいただく。今日でこのひたすら歩く山行は終わる。仕舞いまで歩けるだろうか、ちょいと弱気になりながら膝頭をなでる。ひさとみもねじの緩んだピノキオみたいな歩き方で藪から戻ってくる。その顔はどこか浮かない。 「どうした、足痛い?」 「うん、足も痛いけど・・・うんこ踏んだ」 「うんこ?」 藪のなかで落ち着くポイントを探しているとき、図らずも、まあ図るわけもないけど、うんこを踏んでしまったらしい。 「まだ新しかったわ」 さらに詳しく形状をきいてみると、どうやらぼくがついさきほど産み落としたものらしい。そりゃ浮かない顔も当然だろう。でもぼくはおかしくてたまらなかったので、テーとクオンに報告する。二人もげらげら笑い出す。ひさとみの靴はぼろぼろで、すでにつま先には穴が開いていた。それをクオンが穴のことを口(くち)という意味のベトナム語で表現してからかっていた。ぼくはクオンが穴のことを口、口というのを聞いて、ついぽろりとこう言ってしまう。 「ひさとみの靴はクソ喰った」 クオンとテーが笑いころげる。ぼくもおかしくて大声で笑う。いま冷静に思い返すとなにがそこまでおかしいかと首を傾げたくなるが、そのときはおかしくてしょうがなかった。たぶんぼくが馬鹿なんだろう。 小屋番のズンさんとはここでお別れ。お礼も兼ねて、ぼくの紺色のパーカーをプレゼントする。安物で使い古しなのであまりうれしくはなかったかもしれないけど。いっしょにたのしくお酒を飲めてうれしかった。ありがとう、本当に。食料を食べきったため荷物がなくなったテーが、ぼくらのテントやらを持ってくれる。重い荷物が膝にこたえるだろうと不安だったため、好意にあまえさせてもらった。 今日はまた違った道を歩いてサパまで帰る。稜線沿いの道が、景色もよく気持ちよい。最後には少数民族の村を通った。沢沿いにある、こじんまりとした美しい集落だった。棚田はもう借り入れが済んでいた。刈り入れ前だともっと美しかっただろう。家のなかをのぞいたわけではないが、その暮らしぶりの質素さは一見してわかる。暖房器具のない夜は寒いだろう。まじめにこつこつ働いても現金収入はわずかであろう。 日本では屋内に入れば夏でも涼しく冬でも暖かいのがあたりまえになっているが、ここではそのような空間はどこにもない。経済発展途上地域における森林伐採などの環境問題を考えることは大切なことだと思うが、同時に自分たちの足元をきちんと見ることを忘れちゃならんだろう。焼畑農業をやっている人々より、薪にして売り飛ばすために不法に森林を伐採している人々より、日本人のほうがあきらかにエネルギーを無駄使いしている。ぼくにも偉そうなことを言う資格はもちろんないのだけど。 サパでクオンとテーに別れを告げる。たのしい三日間だった。クオンとテーにとっては仕事としての三日間だけど、彼らもたのしかったと感じてくれていたら、ぼくは本当にうれしく思う。さらば三角またきて四角。多謝。 町の美容院で洗髪をしてもらう。これがまた気持ちいい。洗顔や顔剃りもやってくれる。ベトナムにきたらぜひ美容院には立ち寄るべし。50円から100円ぐらいでやってくれる。体はきたないままだが、すこしはさっぱりした。 この日の夜行列車でハノイに帰る。強行日程なのだ。今回も二等寝台の下段を取っておいたぼくら。でも運悪く相部屋はむさくるしい男ばかり。不貞寝しながら、「むさくるしい」と文句を垂れていたら、ひさとみがひとさし指を口にあてだまれの合図。 「誰も日本語なんて聞いてへんて」とぼくが言うと、 「いわいさんの上の人、日本人・・・」 ひさとみが小声で言った。上をのぞくと『地球の歩き方』と添い寝しているむさくるしいお方が確かにひとり・・・。 「聞こえてた?」 「絶対聞こえてた」 そうですか。ごめんなさい。売店で買った缶ビールを飲みますか、とりあえず。つづく
2005年05月12日
コメント(0)
-
ファンシパン登山記 四日目
夜はさすがに寒かった・・・。小屋といっても、すきまだらけで半分野宿のようなものなのだ。テントをもってきてよかった。小屋のなかにテントを張ったのだ。凍えながら外に這い出すと、もう火がおこされていて、コーヒーをいれてくれている。そしてインスタントヌードルで腹ごしらえして、いざ登頂。 テントや寝袋などの大きな荷物は小屋に置いてきているので、荷物が軽い点はきのうより楽。でも標高差約900メートルを登らなくてはいけない。最初はまず沢に向かって下っていく。せっかくここまで登ったのに、返せこの標高差・・・。まあ、ぐちを言ってもはじまらない。人生山あり谷あり、上等だ。 このあたりの道は登山道というわけではなく、この山で生活の糧を得ている人たちがふだんから使っている生活道だ。銃をかつぎ、しぶい藍色の民族衣装を身に着けた少数民族の男たちと何度かすれちがう。小鳥を撃つらしい。また、蜂の巣を探している男や、木の実を拾って歩く女ともすれちがう。山のてっぺんに登りたい、そんな酔狂な目的のために闖入している自分がとてつもなくばかに思えてくる。実際ばかなんだろう。 沢を越えて登りはじめると、なかなか険しい道になってくる。ここからはひたすら上り。岩にはりついて登らなければならないポイントもある。だが難しいポイントにはロープが張ってあり、特別な技術はいらない。素人でも通常の運動神経があれば十分登れると思う。問題はやはり技術よりも体力。ぼくもひさとみも健脚の部類に入り、30代のわりには体力もあるほうだと思う。でもきつかった。同程度の標高の山はいくつか日本で登ったことがあるが、どこよりもきつかった。日本の山は道が整備されているからかもしれない。それとも連夜の宴会のせいか?いや、そんなことはない。道のせいだ、きっと・・・。 へこたれながらもちゃんと頂上にはたどり着いてきた。ガスで10メートル先も見えなかった。頂上からの景色が見られないのは本当に残念だったけど、てっぺんで食う昼飯はやっぱりうまい。このままハングライダーかなにかでピューンと麓まで飛んでいきたい・・・。でも歩いて下るしかない、あたりまえだけど。 下りはある意味上りよりきつかった。足元がすべりやすいため、何度も転びかける。ひさとみは実際に転んでた、しかも何度も。勾配が急な坂を、不安定な足場を確保しながらひたすら下るのは、膝に負担がかかる。体力的にはまだ耐えられたが、膝は限界ぎりぎりで痛かった。 前泊したポイントにたどりつき、着替えをして火にあたりると、なんともいえない幸せな気持ちになれた。なんたってビール最高にうまいしね。夜飯の準備は、テーやクオンにズンさんがてきぱきとやってくれる。山にいるのを忘れるぐらい豪華な食事をつくってくれた。豪華というのは食材が高価という意味ではなく、手間を惜しまずつくられたおいしい食事という意味なり。 食後はまたもや宴会。ズンさんは昨晩以上に杯がすすみ、酔っぱらってひさとみに抱きついたりなんやかやとセクハラ三昧。「ズンさん侮れんわ」とはひさとみの言。まあ無礼講ということで、いいじゃないですか。ねちねちした陰性のセクハラは見てるほうも気分悪いけど、ズンさんのは陽性だから。てなわけで、今夜も更けていくわけです。 つづく
2005年05月12日
コメント(0)
-
ファンシパン登山記 三日目
旅行会社のオフィスに午前9時に集合する。ひさとみはモン族の流しの土産売りにつかまり包囲される。ぼくは道往く人々を眺めながら、数枚写真を撮る。9時をちょっと過ぎたころに、ガイドのクオンとポーターのテーがやってきた。あいさつをして、早速ジープに飛び乗る。途中、景色のきれいなポイントや、「銀の滝(Thac Bac)」などに寄り、登山口に到着。ジープと運転手はサパに引き返した。 さいなら。 この登山口が標高約1,500メートルで、今夜泊まることになっているところが2,200ぐらいだったと思う。でもうろ覚えで自信なし。メモを取らんとな。所要時間は5時間ほど。道は日本の登山道ほどは整備されていないが、それほど悪くはない。ただ荷物が重く、アップダウンを繰り返すので、ちょっときつい。ぼくらはテント、寝袋、食料、水3リットルほどをザックに詰めていたので、重くてしょうがない。その他着替えやらなんやらもあるし。でも後からわかったことだが、食料や水なんかはそんな大量に持っていかなくてもよかった。飲み水が汲める渓流がかしこに点在してた。食料もポーターのテーが十分かついでくれていたし。無駄な荷物だった。夏ならテントもいらないので、なるべく軽装で行かれることをおすすめします。 昼飯はパンに野菜やチーズなどを挟んでほおばる。食後には果物。寛いでいるときに、ガイドのクオンがいろいろと説明してくれる。20年ほど前にこのあたりで山火事があった。丸焼けになって大きな動物はいなくなってしまったらしい。確かにこのあたりには高い樹があまりない。くろこげになって残っているやつはあるが。でももう20年も経っているのだから、動物がもどってきてもよさそうなもんだが。それとも植生が変化して、彼らが住みにくいところになったのか。それとも食い尽くしてしまったか。山火事以外の原因もあるのだろう。 ほかにもクオンとテーはいろいろ話をしてくれた。クオンはもうこれが50回目のファンシパン登山となるベテランで、テーは今回が初仕事となるとのこと。クオンは山に登るのが好きなわけではなく、あくまで仕事としてガイドをやっているとおしえてくれた。 「でも経験を積んでいけば、所属している旅行会社で別の仕事、たとえばデスクワークなんかも任せられるようになるんだろう」 ぼくはそう訊いてみたが、 「そんなことはない」 クオンがちょいとやけ気味に答えた。 確かに同じ山に客を連れて何度も何度も登るのは、よほどのもの好きでないかぎりたのしいことではないだろう。まあぼくも好きでもない仕事のために毎朝電車に乗っているわけで、その点は大差ないが。 ぼくとクオンのエンゲル係数も大差ないかもしれない。でも決定的に違うことは、ぼくやたいていの日本人は、行こうと思えば世界中のたいていの場所に行けるが、クオンやテーやたいていのベトナム人は、行きたくともなかなか行けるものではない、ということだ。経済的な理由もあるし、査証の問題もある。クオンは日本に興味がありいつか行ってみたいと言った。それは一日本人として素直にうれしい。 「そのときはぼくんちに泊まりなよ」 クオンはわらって肯いたが、その目は実現を信じている風ではなかった。そしてクオンは正しいだろう。分別があれば、そんなことを信じるなんてできないのが現状だ。さびしくて、残酷な会話だった。 昼食後、ぼくらは歩き続ける。本日は晴天なり。青空を背景に写真を撮る。明日も晴れてくれるといいが。いまは乾期のため雨の心配はさほどないが、頂上付近がガスで覆われていると景色どころか10メートル先も見えなくなるからなあ。できれば360度のパノラマ風景を眺めてみたい。 重い荷物にかなりひざがへばってきたころ、やっと本日寝泊りするポイントに到着。渓流のそばにあるちょっと開けた場所に、ビニールシートで覆われた限りなくテントに近い小屋が出現する。荷物をおろして一休みしてると、小屋番のズンさんが火をおこしてコーヒーを淹れてくれる。いくらベトナムといえども、晩秋の山は寒い。火にあたりながら飲むコーヒーはインスタントだけど最高。薪が燃えているのをながめていると、本当に飽きない。明滅するおき火ほどうつくしいものがこの世にあるか。ないね、とぼくは言いたい。 夕飯は盛り沢山だった。揚げ春巻き、キャベツとトマトの野菜炒め、煮込んだ鹿肉、スープ、ほかにもなんかあったなあ、忘れたけど。日本の米もうまいが、ベトナムの米も負けず劣らずうまい。日本のように冷めてもうまい米ではないが、軽くて胃にもたれない。ごはんの炊き方も違う。まずお湯を沸騰させ、そこに米を入れる。沸騰したら蓋を開けて湯を捨てる。そして直火があたらず火力の弱いところに置き、しばらく蒸らせば完成。米が違えば炊き方も食し方も違ってくる。日本然り、ベトナム然り、それぞれの国の先人たちが受け継いできてくれた智恵なのだ。 夕食後は当然酒、つまり米焼酎だ。ベトナムでは自分のペースでしみじみ飲む、なんてクールな態度は許されない。杯を合わせては一気飲み、ひたすらそのくり返し。ズンさん、ひさとみ、ぼくの三人は酒が好き。クオンはそれほど好きではないが飲める。テーは一口だけのお付き合い。 酔うほどに座は盛りあがりを呈する。「いわい」や「かおる」(ひさとみの名前)はベトナム人には覚えにくく発音しづらくやってらんないという苦情が出て、ベトナム名をつけることになった。ぼくは数年前ハノイ留学時代に自分でつけた「ナム」があるのでそれにする。ひさとみはズンさん命名で「ニャット」になる。 漢字にするとナムは「男」もしくは「南」。ニャットは「日」。ベトナムもかつては漢字を用いていた漢字文化圏であり、漢字が元となった音がたくさんあるのだ。現代のベトナム人のほとんどは漢字を読み書きできないけど、ナムやらニャットがどういう意味を持っているかはあたりまえだが知っている。ベトナム語はおおまかに三層にわけることができる。ベトナム語固有の言葉、漢字が元となる言葉(漢越語)、そして英語やフランス語などからの外来語。そのへんは日本語とそっくりだ。まあ、日本ほど外来語にあふれてないけど。 話がそれた。とにかく何度も杯を重ねてどんちゃん騒ぎ。明日こそ本番の登頂の日だというのに・・・ 。前後不覚となり、テントにもぐりこむ。明日の朝は早い。 つづく
2005年05月11日
コメント(0)
-
ファンシパン登山記 二日目
早朝3時か4時頃、ラオカイ駅到着。目と鼻の先に中国がある、国境の町だ。外はまだ暗い。駅前には客待ちのバイクタクシーやミニバスがうようよと待ち構えている。ここからサパまで車で一時間弱ほど。料金はミニバスで2万5千ドン。数年前は確か1万5千ドンだったのに、値上がりしたようだ。サパへのぼる道も、以前と比べると格段に良くなった。数年前は気を抜くと頭を天井にぶつけるようなでこぼこ道だったけどなあ。 窓から見える景色は美しい。棚田や畑が渓流を挟んで朝日に照らされている。いまはもう11月なので、さすがに刈り入れが終わっているが、夏なら緑、秋なら稲穂の黄金色の棚田が見られるはず。 サパに来るのはぼくは4度目、ひさとみは2度目。いつもお世話になっている贔屓の宿屋に直行する。毎回宿の名前を覚えておこうと思うが、覚えられたためしがない。いまももう忘れてる。馬鹿みたいに平凡でありふれた名前なのだが・・・。サパ中心部にある教会近くにある、感じが良くて安い宿で、ツインの部屋で6万ドンほど。部屋は清潔で温水が出る。そして何よりもこの宿のテラスがおすすめ。眺めが良くて思わず体操したくなる。繰り返すが、おすすめ。でも名前を覚えてないのにすすめられても困るか。 サパの町並みはほんの数年前と比べても様変わりしてた。派手な色の大きな建物が増えている。でも市場は以前と変わらぬたたずまいで、すこしほっとする。この市場の屋台で朝食を食べた。お決まりのフォー。寒いのであったまる。以前は4千ドンだったが、6千ドンになっていた。単にぼられただけか?屋台ばかりではなく、肉、魚、野菜、果物なんかももちろん売られている。小規模ながらなかなか活気がある。別棟の離れ市場には土産物屋や乾物屋がひしめきあっている。こちらは薄暗くあまり人気もなかった。 ぶらぶらサパ郊外を散歩する。15分も歩くとさすがにけばけばしい建物は視界から消え、ぽつんぽつんと素朴な家々が道の両脇に点在している。たいていの家が犬を飼っており(もちろん放し飼い)、彼らは闖入者を警戒すべく、入口でキッとぼくらを睨み付け、吠える。いかにも有能、という感じの犬たちだ。愛玩用のペットではなく、きっちり仕事をしている欠かせない存在としての犬。こういう犬を見ているのは気持ちがいい。人間と犬の正しい関係であるように思う。まあ、下手すると何かの機会に食膳に供されたり、食用に売られたりすることもなきにしもあらずですが。 田畑に混じって、薔薇を植えているところも意外と多い。蕾を新聞紙でくるんで大切に育てている。明日は「先生の日」で、生徒・学生が日ごろお世話になっている先生に一輪の薔薇を贈るそうだ。明日は山に入るので見られないだろうが、臨時の花屋が鮮やかな色と香りをふりまいて、町を賑わすのだろう。 サパ中心部に戻り、市場の脇の通りをしばらく下ったところにある旅行会社兼宿屋で、明日の山登りの手配を済ます。2泊3日の行程、ガイドとポーターが一人づつ同行の手配で、確か一人60ドルくらいだった。朝食2回、昼食2回、夕食2回付き、車が入れるところまでのジープ往復送迎付き。妥当な金額だろう。 夜は市場近くのレストランで食事をとる。レストランの名前はずばりそのまま「ファンシパン」。ここの鹿鍋がおすすめ。おいしい。メニューには載ってないが、頼めばこさえてくれる。日本の鍋もおいしいが、ベトナムの鍋もいける。鹿肉もこりこりしててうまい。明日からは歩き詰めのハードな3日間となるので、今夜はほどほどにしておくべきなのだろうが、ついつい瓶ビールを何本も空けてしまう思慮浅いぼくら。ひさとみといるとなぜ毎晩宴会になってしまうんだろう・・・。つづく
2005年05月11日
コメント(0)
-
ファンシパン登山記 一日目
ぼくは関西空港からバンコク乗り継ぎで、ひさとみは成田からベトナム航空直行便でベトナム入り。ハノイ空港に着く時間がてんでばらばらだったので、ハノイ鉄道駅の近くで落ち合う約束をした。ひさとみはタクシーの運転手にぼられて空港で両替したベトナムドンの大半を失う。相場は10ドルなのに30ドル相当のベトナム・ドンを奪われたらしい。ばか・・・。ぼくはタバコでタクシーのシートに穴を開けてしまった。10ドル払って、フレンドリーな笑顔で礼を言い、そそくさと別れる。無理言って空港から飛ばしてもらったのに、とても感じのいいお兄さんだったのに……、ごめんなさい。 ハノイ在住の友人もぼくらの待ち合わせ場所に来てくれ、事前に買っておいてくれた列車の寝台切符を渡してくれる。そして午後9時半発の列車に乗りこむ。ぎりぎりかろうじて間に合う。 ぼくらが取った寝台は中国風に言えば硬臥、いわゆる二等寝台。一室に6人、下段・中段・上段の三段式が向かい合って二列ある。段によって微妙に料金が異なる。いちばん高いのは下段で、ぼくらは下段を予約しておいた。下段は腰掛けることもできるので、使い勝手がいいのだ。中段・上段は腰掛けることはままならず、ねっころがるしかない。なので、中・上段の住人は、眠くなるまでは他人の下段に腰掛けているのが通常の光景である。とにかく疲れていてただ早く横になって寝たい、という人は、上段にしたほうがいいかもしれない。中段は下段の座り心地を考慮してはねあげられてしまう可能性大なので、避けたほうが無難。もちろん私は寝るから私のベッドからのいてちょうだい、と言えばのいてくれるが、ベトナムでそれをやるのも野暮なような気がする。 列車が発車してしばらくは、同部屋の住人はみな下段に腰掛け、持ち込んだ果物なんかを食い散らかしながら、ぺちゃくちゃとおしゃべりしている。幸運にも、ぼくらは若くてかわいいベトナム三人娘と同部屋となる。実家のラオカイに帰省するハノイの高校生らしい。当然、果物のおすそわけなんかをいただきながら、楽しい時を過ごす。さいさきよし。 つづく
2005年05月11日
コメント(0)
-
「侵略軍のバイオリンの音」 連載第5回(最終回)
「侵略軍のバイオリンの音」 連載第5回(最終回) バオ・ニン著 岩井 訳 一筋の閃光が光った。街の上空で、稲光が走り出した。雲の上では雷鳴が轟いていた。 「ええ、雨が降りそうですね」ボン爺さんはそう言ったが、そのまま話し続けた。「銃弾が飛んできたのはほんのひとときでした。その後フランス軍の応射の音にすべてがかき消されました。屋根瓦、漆喰の壁、窓ガラスが、砕け飛び散りました。フィリップは大声で発砲を制止させ、突入を指示しました。兵士たちは四方から家の中へ突入しました。家の中からは一発の銃弾も発砲されず、兵士たちはなんの障害もなく乱入しました。フィリップは彼らには従わず、庭の真ん中に立ち、手を腰に当てていました。時を置かず、兵士たちは捕えたベトミンと一緒に出てきました。頭に包帯の巻かれたフランス人の負傷兵も支えられながら出てきました。彼こそシャム猫を見て、家に飛び込んでいったあの兵士だったのです。彼はベトミンに頭を殴打され銃を奪われただけで、決して殺されたわけではなかったのです。そしてベトミンたちときたらですね、フランス人が思っていたような大人数ではありませんでした。知っていますか、なんとたったの三人だったのです。最初に引きずり出されたベトミンは女性でした。まだ若く、長い髪が乱れていました。伍長が彼女の腕をねじ上げ、ぐいぐいと押しながらフィリップの前に連行しました。フィリップは、通訳させるために大声で私を呼びました。彼は手を伸ばし彼女の顎をグイと持ち上げ、名前と属している部隊を訊きました。彼女は黙秘し、目を見開いてフィリップを見返しました。私は、彼女が私の通りの自衛部隊で傷兵の看護をしていたのを知っていましたが、彼女の名や家の番地までは知りませんでした。彼女は学生のようでした。そう思ったのは、彼女がまだうら若く、フランス語を理解したからです。彼女と同じ部隊の二人の男が家から引きずり出され、庭に転がされたとき、彼女は憤慨して、フィリップにフランス語できっぱりとこう言いました。『負傷した捕虜をこんな非人道的に扱うことは許されていません!』。フィリップは皮肉っぽく笑い、彼女を手で強く押し退けました。フィリップは、庭の煉瓦敷きの所でぐったりと横たわっている二人のベトミン負傷兵に近づき、彼らのそばに転がっていた、いましがたフランス兵が放り置いた自動小銃を屈んで拾いました。押収された武器はこの自動小銃一丁、床尾板の割れた歩兵銃一丁、そして一振りのサーベルだけでした。フィリップは弾倉を取り出して調べました。弾倉は空でした。歩兵銃もすでに弾が切れていました。フィリップは今度はサーベルを手に取り、振りまわしました。彼は微笑を浮かべていました。しかし私は恐ろしさで身体の震えが止まらず、思わず一歩あとずさ後退りました。不意にフィリップが地面にサーベルを叩きつけ、女兵士のほうに歩み寄り、彼女をキッと睨みつけて言いました。私は一語一句たがわず記憶しています。『この土地、この家は、私の、私の父の、私の妹のものであって、我々フランス人のものだ。あなた方は我々の家と土地を不法占拠しているのだ。言わせていただくが、主人である我々が、あなた方下僕を懲らしめているに過ぎない。私たちは下僕どもと戦争しているわけではない。戦争じゃないんだから捕虜もクソもないってわけですよ、おわかりですか、お嬢さん』」 「そして……」爺さんはゴホゴホと咳きこんだ。「そして、そう言い終わるや否や、フィリップはサッと背を向け、支え合いなんとか半身を起こしていた二人の負傷捕虜のほうへズカズカと歩み寄りました。フィリップはリボルバーを抜き、なんの予告もなしに引金を引きました。二人に向けて、交互に何発も銃弾を撃ち込みました。私は、いや私だけではなく、その場にいた兵士たちでさえ、一斉に凍りついたように硬直しました。雷に打たれたかのような五発の銃声がや止み、辺りは時が止まったかのように静まりかえりました。そして……そしてですね、耳をつんざく、腹を切り裂くような痛々しい悲鳴が、天に轟きました。女兵士は暴れ、伍長の手による縛めを振りほどき、電光石火で駆け寄るやサーベルを拾い上げ、身を屈めて突き上げました。しかし……フィリップの方が一瞬速く、のけ反って剣先をかわすや、引き金を握り残っていた弾丸をぶっ放しました。女兵士の身体がぐらりとかし傾ぎました。空を斬ったサーベルが煉瓦の上に落下し、鋼の刃から火花が散りました。そのとき、伍長が肩に担いでいた銃を構え、銃口を彼女に向けました。他の兵士たちもそれを契機に我に返ったか、一斉に銃を構えました。その直後に、私は駆け出しました。通りに飛び出し、フランス兵を押しのけて走りました。私を遮る者は誰もおらず、止まれ、と叫ぶ者さえおりませんでした。たとえ叫んでも、私には聞こえなかったでしょうがね。庭では銃声が猛り狂い、轟音が響き、空気がビリビリと震えました。私は走って走って走りました。頭の中で炎が明滅し、野蛮な死刑執行の銃声が耳にこびりついて離れませんでした。力尽きて、ハンコー通り近くの泥まみれの路地裏で突っ伏して気を失いました。やがて意識が戻り、人気のない通りを身体を引きずりさまよいました。涙がとめどなく溢れてきて……。私は一介の小市民に過ぎません。低劣で意志薄弱な小市民に過ぎません。しかし私は植民地主義兵士たちがこれほどまでに野蛮で下劣であったとは、思いもよらず、理解もできず、測り得もしませんでした。それから歳月が過ぎたのちでも、ペギー家で現出した光景は、未だに脳裏にまざまざと焼き付いています。その痛ましさに、私は言葉を失います」 「私はハノイがフランスに占領されていた期間ずっと、チャイガンに人目を忍んで、あらゆる重労働で生計を立てながら暮らしておりました。意志薄弱で厭世的な私に、解放区に飛び込む度胸があるはずもありませんでしたが、再度フランスの手先に堕すつもりもありませんでした。また、私の大切な人たちと、断腸の思いで絶縁せねばなりませんでした。私がいくら敬愛したところで、彼らはフランスに付き従っているのですから。私の家族も四七年の春には疎開先から戻ってきました。私の父と兄たちは、以前にも増してフランスに重用されました。家族が私の行方を懸命に探していることは知っていましたし、私も家族のもとへ帰りたくてなりませんでしたが、かなわぬ願いでした。一度、四七年の秋の日暮れ時に、私はどうしても自分の気持ちを抑えることができず、ノ ン菅笠を目深にかぶり、無謀にもソレ通りを歩いて我家へと向ったのです。私の家は、まだそれほど暗くもないのに、電灯が庭を燦燦と照らしていました。庭には車が一台停められていて、シェパード犬が鉄格子沿いを落ちつきなくうろついていました。ベランダにはトリコロール三色旗が風にパタパタはためいていました。ペギー家の家はというと、以前とちっとも変わらず、古めかしく、苔むして黴がはえて、排他的な佇まいでした。しかし銃撃戦と惨殺事件の証跡は、まったく跡形も留めていませんでした。風がひとしきり通りに吹き込んできて、バンランの木の葉がぱらぱらと舞い散る音が聞こえてきました。私はまたゆっくりと歩を進めました。するとですね、なんということでしょう、あの痛ましくもの哀しいバイオリンの音がどこからともなく聞こえてきたのです。ということは、ソフィーがあの懐かしの家に帰ってきたということです。私はまるで眼前に見るかのように、彼女をありありと思い描くことができました。あの美しく、優しい、澄んだ盲目の瞳のフランス少女を。しかし私は駆けるように歩を速め、耳を塞ぎました。それから五四年の十月まで、私はその慣れ親しんだ通りに、歯を食いしばって誘惑を断ち、近寄りませんでした。私は見たくも、聞きたくもありませんでした。あの絶妙なバイオリンの音色に、私は我慢がならなかったのです。それは侵略軍のバイオリンの音で、事実そのとおりで、ほかにどう考えることができたでしょう……」 雨が滝のように降りそそぎ、そしてひととき雨足が弱くなったが、雷光は依然閃いていた。私は裁判所のわきの雨を凌げる場所から離れる気がまだしなかったが、老人は雨のなかへ消えていってしまった。私は雨を眺めながら、彼の話を聞いていた。話が途切れて、ふと顔を向けると、彼は音も立てず、私に挨拶もなく立ち去っていたのだ。私は彼が雨のなかに潜り込んで消える前に、七二年にアメリカがフランス大使館を爆撃したとき、彼は大使館近くの防空壕に隠れていた、という話をしていたのを覚えている。彼は他の人と一緒に、瓦礫に埋もれた人々の救出を手伝った。「私は大使が瓦礫の山から引きずり出されるのを見ました。べっとり血まみれになっていて、そしてすでに死んでいました」 「その事件後、私はフランスを赦してやることができるか、と自問をくりかえしました。どれほどの時間と、年月と、崩れた煉瓦と、砕けた瓦と、人命を注ぎ込めば、百年に及ぶ侵略で植民地主義フランスがこの国にもたらした死と災禍の深淵を埋めることができるのでしょうか」 彼はそう問いを残し、消えていった。稲妻走る空のもと、私も雨のカーテンの奥へと老人に続いた。老人の人影はどこにも見当たらない。しかしサッと吹き抜けた雨混じりの風に、誰かがあるメロディーを口笛で吹いているような音が聞こえてくる ──われ想いしやかの大地、わが故郷(ふるさと)とそしてパリ……(『二〇〇〇年度傑作短編集』二〇〇〇)
2005年05月10日
コメント(0)
-
「侵略軍のバイオリンの音」 連載第4回
「侵略軍のバイオリンの音」 連載第4回 バオ・ニン著 岩井 訳 ボン老人は力なく座り、うつむいた。彼は私のことなどすっかり忘れ去り、知覚は際限のない領域へと流されてしまったかのようであった。 「ある日、西暦の二月中旬に差しかかったころでしたが、私は思いもよらぬ知人と邂逅しました。一台のジープが、労役に従事していた私たちのそばで急ブレーキをかけました。フランス人の男がジープから跳び降り、軍靴をカッカッと鳴らして駆け寄ってきました。『おい! ――フランス人は叫びました―― おい、ああ、やっぱり君じゃないか、なんでこんな所にいるんだい、なんでこんな目にあっているんだい、君は随分と変わったね』。そのフランス人はだみ声で、頬髭をはやしていましたが、それはかつての隣人であるフィリップ・ペギーでした。彼も随分と変わり果てていて、兵服、拳銃、軍靴、ヘルメットなどを身に付けたフランス人の一敵兵であるという符合を除けば、なんら昔の面影が見出せないほどでありました。しかし、フィリップは私にとても親切にしてくれました。彼の口利きのおかげで、私は重労働から解放されたのです。彼は私の家族が善意で彼の父と妹をかくまった話を知っていました。現在ソフィーは父親と一緒にハイフォンにお居り、そして彼女はハノイが早く平定され少女時代の愛すべき我家に戻ることを切望している、とフィリップは言いました。フィリップはジアラン通りに駐在している彼の兵舎に私を連れていきました。私は一日休んでから、フィリップ付きの通訳として従事せねばならなくなりました」 「ああ、なんということでしょう ――老人はしわがれた嘆き声をあげた―― これで私もフランスの一味としての一歩を踏み出してしまったというわけです。たとえそれが数日というほんの僅かな期間であったとしても。その数日間、私はフィリップの車に同乗し、前線近くまで潜入しました。車は通りの角に隠れ、拡声器をバリケードのほうに向けました。私は投降を呼びかける言葉、時には甘い約束の言葉、時には脅迫の言葉を通訳せねばなりませんでした。もちろんそんな真似はしたくありませんでしたが、だからといって私にどうすることができましょうか、従うよりほかはなかったのです。そして一方で、正直に申しますと、私は自己を正当化する理屈を懸命に探し出しました。知らず知らずのうちにフランス人の論調に飛びついて、ハノイの破壊や流される血をできるだけ少なくする努力に、とにかく私も一助しているのだと自分に言い聞かせていました」 「しかし投降を呼びかける拡声器の声を聞き、バリケードを出てフランスに屈しようとする者など誰一人としていませんでした。連区内の戦闘は、日毎に激烈さを増しました。長引く停滞にイライラを募らせ、私に通訳を強いるフランス軍の言葉は、日毎に高圧的になっていきました。二月一五日の朝、投降勧告の車がロパゾー広場に停まり、朗々とフランス軍司令部の最後通牒を読みあげました。何日の何時までにベトミンの残存勢力拠点が白旗を掲げなければ、一斉攻撃を加えるという旨でした。ロパゾー広場の傍にはドンスアン地区での凄まじい戦闘の痕跡がそのままに残されていました。賑わいを見せていた街が血のこびりついた戦場と化したのです。霧雨のなか、火はもう消えていましたが、まだあちらこちらで煙が立ちのぼっていました。北風が灰を舞い上げ、視界を遮りました。砕けた煉瓦、粉々の屋根瓦、折れた梁木(うつばり)……。黒焦げになった戦車が散見され、キャタピラは千切れて飛び散り、運転していた兵士が戦車の出入口に引っかけられたかのような体勢で死んでいました。この身の毛もよだつ激戦のあと、比較的平穏な日が数日間続きました。たまに銃声が聞こえてきましたが、いずれも単発でした。フランス軍は手痛い反撃を受け兵力を消耗し、一時攻撃の手を緩めねばなりませんでした。しかしベトミン側も非常に困難な情勢でした。フィリップの言動をとおして、私はフランス軍の勝利にもはや疑いの余地がないことを知りました。『フランス軍は慎重に、堂々と、人道的に勝利を勝ち取るであろう』。フィリップはそう言いました」 「しかしハノイは、侵略者たちに勝利を決定づける機会を与えませんでした。二月一八日の朝、炎が空の一角を真っ赤に染めましたが、街中はシンと静まりかえっていました。第一連区はもぬけのからでした。あれほど厳重な包囲網にもかかわらず、ベトミンは突如どこかに消え去ってしまったのです。この神懸り的退却により、フランス軍は極めて滑稽な勝利を押しつけられたかたちとなり、勝利したというのに実際には大敗を喫したかのようでした。都市を占拠できたというのに、占領者はほっと一息つくこともできず、嬉しくもなんともなかったのです。押し黙り、疲弊した兵士たちは、銃を構え二列になり、人気のない路地のなかへ注意深く進入していきました」 「狙撃される危険に頓着せず、フィリップは旧市街の表通りから路地裏までありとあらゆる場所にジープを走らせ捜索しました。私はフィリップがいまさら何を望んでいるのかまったく理解できませんでした。街路のゾッとするほど静まりかえった空気のなかで、投降を呼びかける拡声器はもはや語られるべきこともなく、恥ずかしそうに口をつぐみ、たまに喉に骨が刺さったかのようにガーガーと音を洩らすだけでした。ジープの上でフィリップの横に座っていた私は、寒さと恐怖のため、ガタガタ震えていました。通りの両側には、人影はおろか開かれている扉もなく、話し声も聞こえず、そして見られているような視線さえもまったく感じませんでした。にもかかわらず、走り過ぎる家一軒一軒から、またはそれぞれの庇や壁や通りの角から、目には見えず無言ではありますが、強烈な敵意のようなものが立ちのぼっているように感じ、私は気が気でありませんでした」 通りの向かい側にある家の二階の窓が、突如開け放たれ、一人の女性がベランダに出てきて通りを見下ろした。ボン老人の話し声が気になったのだろうか。しかし実際は、老人の話し声は耳もとで囁くように小さかった。 「また戦闘が再開されるのではと恐れ慄いていた私でありましたが、実際銃撃戦が始まった場所に直行せねばならぬと知らされたとき、虚を突かれたような思いでした。また戦闘が始まったんですよ。今度は第一連区ではなく、無線で指令を聞き終えたフィリップが私にこう言いました。『おい、ベトミンの拠点がまだ残っていたらしいぞ。しかも俺の家の通りだ!』。クアンチュオン通用門から、フィリップは車の向きを変え、全速力でソレ通りに向けて車を飛ばしました。私たちはソレ通りの端まで来ると、赤いヘルメットを被った兵士を満載したトラックの後ろに付けて、ジープを走らせました。トラックは我家の門の真ん前でブレーキをかけました。私たちが到着すると、すでに黒人兵の一団が邸宅を取り囲んでいました。それは私の家ではなく、ペギー氏の家でした」 ホアンキエム湖の畔からリー・トゥオン・キエット通りに向って、一陣の突風が吹き抜けていった。ひんやりとした、湿っぽい風だった。サウの木がザワザワと風に揺れ、葉が大量に舞った。じきに暴風雨になるかもしれない、ボン爺さんにそう伝えたかったが、私は黙っていた。 「一人の伍長が、彼の指揮下の斥候隊が偶然ベトミンを発見した、とフィリップに報告しました。ペギー氏の家の門を横切ったとき、軒下に丸まって日光浴をしているシャム猫を目に留めた一人の兵士が、不審を抱いたというのです。空家なのになぜ猫は居残っているのだろう、もしや家に人がいるのだろうか、と。その兵士は家の中に様子を見に行きました。しばらくして悲鳴が聞こえ、兵士は二度と戻ってきませんでした。二時間以上が経過し、兵士たちは何度か侵入を試みましたが、家の中から銃弾を浴び、退却を強いられました。二人が死に、三人が負傷しました。帰ってこない兵士を加えれば、六名がやられたわけです。伍長は少なくとも十人のベトミンが立てこもっていると見積もりました。ベトミン側の火力は相当強力である、伍長はそう進言しました。しかし、それにしては家の中が静かすぎるように思えました。兵士たちは通りに突っ立ち、家の周りを所在なく取り囲んで格好の的になっているにもかかわらず、家の中からは狙い撃つ気配すら感じられないのです。フィリップが投降を勧告したときですら、撃ってきませんでした。私がフィリップの言葉を通訳し、拡声器の大音響がこだましてもなお、家の中は静まりかえっていたのです。まったく奇妙でした。しばらくして、彼らは弾を撃ち尽くしてしまったのではないか、と私は思い至りました」 老人は頭を垂れ、深い沈黙の中へ重々しく下降していった。随分と長い沈黙だった。私はため息をついた。爺さんは顔を上げ、今度は彼がため息を洩らした。 「先ほどお話したように、戦闘が勃発した最初の夜のうちに、私の通りの自衛部隊は二つに分断されました。私のいた半分は工芸学校に追いやられて、そしてもう半分はソレ通りで挟まれ身動き取れない状態に陥りました。大通りの間を斜めに走っているあの通りがソレ通りです。フランス軍はこの大通りに兵を集め、このあたりは装甲車や兵士で昼夜を問わず賑わっていました。完全に包囲されている仲間たちに、もはや退路は残されていませんでした。どの方角に跳び出そうとも、フランス軍にぶち当たらずには済まないのです。各家の地下壕に身を潜めているほかに仕様がありませんでした。夜更けに彼らは突破口を見つけるため、そしてあわよくばフランス軍に奇襲を加えようと、闇夜に忍び出しました。まだ私が死体処理班で働かされていたころ、捕虜仲間が、ホアロー監獄近辺の通りでは、狙撃されたり、刺されたり、銃を奪われるフランス兵がまだいる、とひそひそ噂しておりました。その後、フランス兵がシェパード犬を使ってその大胆不敵なベトミンたちを一網打尽にした、という噂も耳にしました。しかし残っていたベトミンがまだいたのです。彼らは完全に包囲され、追い詰められていました。彼らは不気味な静寂を保ち、発砲しませんでした。それとも投降の決意を固めたのでしょうか。実際、つかむ藁さえない状況だというのに、なぜ銃を下ろさないのでしょうか。『あなた方はベトミン本隊に見捨てられました』、私はフィリップの言葉を通訳しました。二ヶ月の間、声を嗄らしてあちこちで投降を呼びかけましたがまったく効果がなく、フィリップは功をせ急いていました。彼は大胆にもジープを庭のなかにまで入れ、拡声器をまっすぐ屋敷のほうに向けました。私、運転手、フィリップの三人は、十分な射程距離の前でその身を無防備にさらし、何度も投降勧告を行いました。それでも撃ってこないということは、ベトミンが投降を望んでいるのはもう明らかでした。『縦一列になって、一人ずつ順番に、両手を頭より高く上げて出てきなさい。一フランス軍士官の名誉にかけて、あなた方全員の生命の保証と国際戦争捕虜条約に従い処遇することを誓います』、この居丈高な言葉の直後でさえ、私たちが撃たれることはありませんでした。しかし、フィリップが『あなた方はベトミン軍もベトミン政権も、すでに投降していることを知らないのですか』と言葉を継いだとき、私が通訳するいとまもなく、銃弾が飛んできました。自動小銃の一斉射撃により、車のてっぺんに取りつけられた拡声器が弾け飛び、フロントガラスは砕け散り、そして銃弾が運転手の肩を貫通しました。フィリップは車から転がり降りて銃弾を避けました。しかし私ときたら車の中で茫然自失、座りこんで微動だにできませんでした」 つづく
2005年05月10日
コメント(0)
-
「侵略軍のバイオリンの音」 連載第3回
「侵略軍のバイオリンの音」 連載第3回 バオ・ニン著 岩井 訳 老人はまた咳の発作に襲われたが、話をや止めはしなかった。 「一九四五年の初秋(訳註:旧暦)に、希望が見えてきました。連合軍の勝利により、日本軍もフランス人囚人に手荒な真似はできないだろうと私は思ったのです。ペギー家の受難もきっと終わりを告げ、ソフィーと再会できるであろう、私はそう信じました。しかし、しかしですね、終戦後に待ち受けていたのは平和ではなく、酷烈な侵略でした。私の甘い期待は裏切られ、フランス人はファシストたちが残した深い傷痕の痛みを我々ベトナム人と共有するためではなく、日本軍の何倍も大胆で暴虐な略奪者として舞い戻ってきたのです。秋の蜂起のあと、そして独立式典の直後、南部で英仏連合軍が戦闘を開始したことを知り、たとえソフィーがまだ生きていたとしても、この侵略戦争が続く以上、私たちが相まみえることは二度とないと思いました。そして事実そのとおりでしたよ。二度と相まみえることは……」 爺さんの顔は暗くて見えなかったが、私は赤くなった彼の鼻先やうつろな眼をありありと想像することができた。 「十年ほど前、通りがかりの西洋人が、偶然私の家の軒下で雨宿りをしました。家の前で私は新聞スタンドを開いていたのですが、そのフランス人の客は雑誌を手に取り、パラパラと眺めていました。ページを繰りながら、彼はあれこれ私に話しかけてきました。彼は私のフランス語にたいそう感心し、私もすぐに彼に好感を抱きました。外はどしゃ降りでしたし、雨が止むまでお茶を飲みながらおしゃべりでもと、私は彼を家の中に招きました。彼は名刺を私に手渡し、その名刺にはザン・ペギーと印されていました。彼の名字に私の記憶は強い衝撃を受けました。私は言葉を選び、それとなく探りを入れながら、昔の話を語りました。彼には植民地時代にインドシナに滞在していた親戚は一人もいませんでしたが、私の話にたいへん興味を示し、もう少し詳しく話すようせがみ、熱心に耳を傾けてくれました。話が終わると、彼は非常に嬉しそうに、一年間のベトナム滞在中私のような人物をずっと探し求めていたが見つけられなかった、任期が終わり明日帰国の途につくというときに、このような思いがけぬ出会いがあるとはなんという天の巡りあわせだろう、と言いました。『あなたはフランスの友人であります。いや、それ以上にフランス国への功労者です』。彼は改まってそう言いました。帰りぎわに、彼はペギー父子三人の名前と年齢、そしてソレ通りの住所を教えてほしいと申し出てくれました。そしておよそ半年後、フランス大使館のパーティーの招待状が突如私のもとに届けられたのです。まさに青天の霹靂でありましたが、それでも私は一張羅を羽織って、パーティーに参加いたしました。フランス大使館に入ったのはそれがはじめてでした。そしてそこで、私はパリからの贈り物をいただいたのです。それはとても美しい新品のバイオリンでした。バイオリン・ケースの中にはザン・ペギー氏の手紙が入っていました。手紙の中でザンは、懸命の努力の末に、私の昔の隣人たちがたどった運命の行方が確認できた、と報告していました。彼は悔やみを述べ、私の胸中を察すると書いていました。なぜなら、私の古い友人たちは、皆すでにこの世を去っていたからです。息子はディエンビエンフーにて戦死。娘は六十年代初頭にサイゴンで亡くなりました。父親は同じ年に、同じくサイゴンで死にました。ザンは、私とペギー家兄妹の間の友情が何よりの証しである、美しく感動的なフランスとベトナムの過去に対して、一若年フランス人として敬意を表したいという旨で、バイオリンを贈ってくれたのです。そして手紙の末尾に、『あなたはフランスの友人であります』と厳かに書き添えてありました」 「しかしですね、私を称讃し、お門違いな贈りものまでしてくれるとは、ザン・ペギー氏は完全に私の話を誤解していたようです。もう何十年もフランス語を使っていなかったので、私のフランス語が以前のように的確ではなかったことも誤解を招く一因だったでしょう。そしてまた、ザンのように若い世代の人は、現在のフランスの祖先である植民地主義フランスについて何も知らないということです」 しばらくの沈黙のあと、爺さんは口を開いた。 「あなたもきっとご存知でしょうが、フランス植民地軍は予備協定までハノイに立ち入ることは許可されていませんでした。一方民間人は、日本軍降伏後すぐにフランス人街の自らの家に続々と帰ってきました。しかし私たち家族の隣人、ペギー父子は、依然行方知らずのままでした。彼らの家は、ベトナム民主共和国政権に市街防衛委員会の本部設置のため借用されました。私は自衛団員であったため、何度もその家に出入りしました。邸宅は徴発されましたが、ペギー家の家具や財産は手つかずのままでした。部屋の中の配置もほとんど変わっていませんでした。ソフィーの部屋には、私が以前読んで聞かせてやった幾冊もの本が棚に残されており、門外のバンランの木が見下ろせる窓ぎわに置かれた小さな木机には、彼女のバイオリンがそのままに置いてありました。そしてシャム猫が一匹、窓際で寝っころがって日向ぼっこをしていました」 「正直に白状いたしますと、銃声が轟いた一九日の夜になる直前まで、私は心中戦争は起こらないのでは、と甘い期待を抱いていました。私はフランスから何がしかの善意が提示され、歩み寄りがなされるのではないかという希望を、秘かに温め続けていたのです。なんといってもあのフランスなのですから。名立たる文明人であるフランス人が好戦的な蛮族であるはずがない、私はそう考えていたのです。それに、ようやくファシストのくびきを逃れ自由を勝ち取ったばかりだというのに、フランスが独立を踏みつけにし、我々の自由を再度略奪しようと虎視耽々と狙っているなんて法がありますか。しかしですね、平和を切望する気持ちと熱烈な愛国心は相反するものではありません。ドー郊外の父方の田舎に疎開する家族に、私は従いませんでした。私は独立の誓いのもと、ハノイに残って自衛団の仲間と生死を共にする覚悟を決めていました。一九日の夜になり、明かりが消され銃声がこだましたとき、恐ろしくはありましたが、私はためらうことなく、私たちの街が戦場と化したはじめての夜の中へ、バリケード目指して突入していきました」 記憶を手探りしているかのような沈黙が流れ、ボン爺さんは続けて語った。 「おそらくその日のハノイ防衛の偉業について、あなたは何度も耳にし、何度も何かの本で読まれておいででしょう。ひょっとすると私よりも詳しいかもしれませんね。なぜなら、実を言いますと、私はあまりよく知らないのです。抗戦の熱意は溢れんばかりでありましたが、戦闘に関する知識は皆無に等しかったのです。作戦を遂行する心構えはできておりましたが、いざ遂行する段になると混乱に陥ってしまったのです。真っ暗闇の市街で、銃弾の音が轟々と鳴り響きました。時々、地をも揺るがす爆発音も聞こえてきました。炎が天高く噴き上がり、空や雲を赤々と照らしました。しかも街のいたるところで戦闘が繰りひろげられていますので、全体の戦況が把握できるはずもありませんでした。一連の銃声のあと、我々は勝利したという報せがあったかと思えば、そのすぐあとに、バリケードは破られフランス軍は四方から押し寄せてきている、というまったく逆の報せが届くといった具合です。明方になると、敵の装甲車が南門からカロ通り沿いに侵攻してきました。そのうち一台がソレ通りへと折れ曲がり、機銃掃射をしました。ベッド、箪笥、机、椅子、毛布、マットなどで築かれていたバリケードは、瞬く間に燃えあがりました。私たちは銃弾の雨の中、退却を余儀なくされました。幾人もが次々と撃たれ路上に突っ伏しました。司令官や副司令官までもが銃弾に倒れました。中隊は二つに分断されました。半分は防衛委員会本部を守るためペギー氏の家に退却し、もう半分は――私も含まれていたのですが――バィック・ゲ工芸学校に逃れました。私たちのソレ通りは、このように全国抗戦が始まって数時間も経たないうちに、敵の手に落ちてしまったのです」 「工芸学校にしても、長くは持ちこたえられませんでした。白状いたしますが、私は目の前が真っ暗になり、何がなんだかわからない状態で、ただ流されるまま仲間のあとについて逃げまといました。どうやってたどり着いたのかは分かりませんが、私はいつの間にかバーオホ病院の敷地に転がり込んでいました。クリスマスの夜を迎えるまで、フーゾアン通りからアジアホテルにかけては、まさに激戦区でありました。戦争はゲームじゃない、とはよく言ったものです。戦争は驚天動地の出来事で、人の心を試す灼熱の窯であります。熱狂に駆られて最初の一歩を踏み出すのはたやすくとも、勇気を振り絞りさらに歩を進めるのは、それがたとえたったの一歩であっても、非常に難しいものです。ハンボン通りのほうに退却するという命令が下されたとき、私はぐずぐずとためらい、身を隠している場所から這い出し、銃火のもとをくぐりながら通りの向こう側へと渡っていく仲間のあとを追うことができず、とうとう病院に取り残されてしまいました。そして私は捕えられ、他の数人とともにカインノン庭園に引き立てられました。そして強制労働に従事させられて……結局、三千日に及ぶ抗仏戦争で、私が従事できたのは全部でたったの三日間だけだったのです……」 「私は死体処理班に回され、来る日も来る日も死体を載せた荷車を、背を丸め頭を垂れて押しました。非常な重労働で体もきつかったのですが、何より心が痛みました。私たちは冬の雨の中をさまよい、木の下で、壁のわきで、階段で、倒れた家の瓦礫のなかで死んだ同胞の死体を回収せねばならなかったのです。そのころ、前線はドンスアンやドンキン・ギアトゥックといった区域に収斂していました。敵の手に落ちた各区域は、次第に銃声も聞かれなくなっていきました。荒廃し、無秩序で、崩壊した街並みは、北風冷たい霧雨のなか、死んだようにひっそりと横たわっていました。ほとんどすべての死体は共同墓地に埋めねばなりませんでした。もっとも大きな共同墓地は、あの高等裁判所のすぐわきの、今ではアムフー市場となっている場所にありました。一本の通りが端から端まで掘り下げられ、その年の冬にフランス軍に殺された男の死体、女の死体、子供の死体を埋める共同墓地となりました。それは炎がギラつき、雷鳴が轟き稲光が走る冬であり、同時に、未だかつて経験したこともない、身を切り骨まで染み込んでくるような寒い冬でした。テト正月を過ぎるとさらに寒さが増しました」 つづく
2005年05月09日
コメント(0)
-
「侵略軍のバイオリンの音」 連載第2回
「侵略軍のバイオリンの音」 連載第2回 バオ・ニン著 岩井 訳 「当時の数年間、ハノイは安心して住めるような場所ではなく、食べることも眠ることもできないほど、延々と動乱に奔走させられる有り様でした。しかしフランス人街だけは、依然として泰平の世のような雰囲気でした。部分的には平時より泰平であったかもしれません。それは媚びへつらいの泰平でした。フランス本国が大敗したのちも、ハノイのフランス人は変わらず平穏に暮らしていましたが、すでに権勢は失われ、年々凋落の一途をたどっていました。縮こまって震えていたわけです。彼らの邸宅も、肩と首をすぼめていました。通りは萎靡たる佇まいでした。どの通りもさびれて人っ子ひとり見当たらない有り様で……しかしですね、まさにそのような厭世的な情景が当時の私の心情にはぴったりだったんです。ザンソレ通りの紫の花を咲かせたバンランの並木道を一人で散策していたとき、すすり泣くようなバイオリンの音が聞こえてきて、私は自分がヴェルレーヌの詩に出てくる秋風に舞う枯葉であるような錯覚にとらわれました。当時のソレ通りはですね、それはひっそりとしておりました。私の茫漠たる記憶によると、現在のトニュオム通りよりも狭く、そして長かったような気がします。通りの終極が見えないほど長く、寂寥たる通りでありました。その頃、毎朝毎夕、私が家を出る時分や帰宅する時分になると、決まっていつも門前の路地で私を待ちかまえていたかのように、バイオリンの音が流れてきました。私は、そのバイオリンは終日息をひそめて待ち受けていて、私の足音を聞いてはじめて音を奏でているのではないか、と想像いたしました。まさに絶妙の旋律でありましたが、なぜこれほどまでに痛ましく悲しく、明日への予感と過ぎし日々への愛惜を喚起させるのでしょう。フランス人少女の心への無限の同情で私の心は締めつけられ、そしてですね、悲しいかな、私にはまったく関係がないというのに、私はわけもなくフランスに同情を覚えてしまいました」元法律学校生の老人は、言葉を詰まらせた。私は話を打ち切って立ちあがる決心もつかず、自己満足的で愚にもつかぬ、完全に消去されたあらゆる種の過去の記憶がぼそぼそと語られるのを座って聞き、時間を浪費する以外になかった。 「そのバイオリンを弾いていたのは、私の家の近所に住むペギー家の娘、ソフィーでした。ペギー家は裕福ではなく、古ぼけた二階建てが彼らの住居でした。家の壁はもう何年も塗り替えられておらず、漆喰が陽に灼けていました。ペギー氏は一風変わったフランス人でした。ひっそりと暮らし、温和でもの静かな方でした。ベトナム人はおろかフランス人とさえも、ペギー氏はつきあいを避けている様子でした。通りに面し庭へと続く鉄の門は、一年中開かれることがないかのようでありました。しかし、私にはペギー家と知り合うための窓口がありました。もちろんペギー氏とではなく、彼の子供たちとです。ペギー氏は妻に先立たれていましたが、再婚せず二人の子供を育てていました。男の子と女の子です。男の子はフィリップといい、私と同年でした。ソフィーは三つ下でした。ソフィーは生まれてすぐ母親を亡くしていました。そしてもっとも気の毒なのは、ソフィーは目が見えなかったということです。小さな頃から盲目でした。外見は普通の目とまったく変わりがありませんでしたが、何も見ることができなかったのです」 老人は話を中断し、上衣のポケットを探り、ハンカチを引っぱり出して汗を拭った。私は何も言わず、黙って見ていた。 「私とフィリップは、私たち一家が引っ越してきたばかりの日に、すぐ友達になりました。私たちが十二か十三のころで、ベトナム人とフランス人を分け隔てる壁は、私たちが成長したときに直面したときほどはまだ高くなかったのです。さらに私の家とペギー家の敷地の境は、煉瓦の壁ではなくただ鉄格子で遮られているだけでした。鉄格子越しに私とフィリップは声を掛け知り合いました。フィリップは遊びに来るよう私を誘いました。彼は妹の面倒を見なければならなかったので、私の方に来ることはできなかったからです。『ぼくの妹、目見えない、かわいそう』、彼はそう言いました」 「フランスの子供にはめずらしく、ペギー家の兄妹はとても人が善く、とくにソフィーはそうでした。ベトナムで生まれたせいか、痩せて発育の悪い体格、黒髪、神秘的な瞳、うっとりするような声、そして優しく穏やかな人柄でありました。私は彼女を非常に愛しく思いました。フィリップが不在のときも、私はよく遊びにいきました。私たちは庭を一緒に散歩したり、庭の端の見張り台で寄り添い座って涼をとりました。二人とも無口なたちで、話すこともあまりなく、私がソフィーに物語を読んで聞かせることが多かったです。詩を読むこともあり、彼女がバイオリンを聴かせてくれるときもありました。私は彼女がバイオリンを練習するのを何時間でも黙って座り、聴くことができました。私がそばにいるとき、彼女はとてもうれしそうでした。声をあげて笑うときもありました。私のおかげで、彼女は少しずつ片言のベトナム語を話すことができるようにもなったのです」 老人は大きく息を吐き、沈んだ声色で続けた。 「しかしなんといっても私とペギー家兄妹の関係は、世間から見れば非常識な友情であり、日に日に体裁悪く白い目で見られるようになりました。私たちの固い絆を守りとおすのは不可能でした。歳を取り思慮深くなるにつれ純真さを失い、次第に偏見に侵されていき、心は行き違い、友情は薄れていきます。まずは私とフィリップでした。絶交したわけではありませんが、次第にお互い距離をおくようになりました。兄と疎遠になれば、当然妹との友情も難しいものとなります。私は次第に足が遠のき、そして彼らの家に行くことも完全になくなりました。さらに時勢も変化しました。一九四〇年から、情勢は日増しに深刻になっていきました。フィリップは大学には入りませんでした。ある日、私は彼が軍装で帰郷してきたところを目にしたのです」 老人は煙草の箱を引っぱり出し、口に咥え火を点けた。彼は一息吸って咳込み、続けて口いっぱいけむりを吸いこんではまた咳込んだ。彼は煙草を揉み消した。 「一九四五年のテト正月のあと、日本がクーデターを起こしフランス人を蹴散らしました。たった一夜で、日本の皇軍がハノイを奪い取ったのです。フランス人は捕らえられ、トラックに載せられ連行されました。ひっそりとしたソレ通りが、急に兵士の足音や銃剣のガチャガチャ鳴る音で騒々しくなりました。しかしですね、それほど物々しい状況にありながら、私の家族は大胆にもあるフランス人一家をかくまったのです。そう、それがペギー一家でした。私の父とペギー氏は顔見知りではありましたが、決して親密な間柄ではありませんでした。予期せぬ事変により、一番近くに住んでいる上流階級のベトナム人一家に過ぎなかった私たちが、突如彼らにとって唯一の頼みの綱となったのです。その夜、銃声がこだまし、街の異変の報せを受けたペギー氏は、着の身着のまま大慌てで、ソフィーの手を引き裏庭へ飛び出し、鉄格子の隙間に体を押し込んで私の家に逃れてきました。恐ろしくて恐ろしくてなりませんでしたが、私の父はペギー氏とソフィーをかくまうことを引き受けました」 「当然ながら、この命をかけた義挙は私たち一家を不安に陥れました。しかし、私は秘かに血が騒ぐのも感じていました。どんなに危険な状態であるにせよ、それは平穏で退屈な日常や、私たち一家や私自身のぬくぬくとした生活を揺るがす、思いがけない刺激でありました。その非日常性に私は興奮しました。私は自分が勇敢で、義侠心に満ちていることを誇りに思いました。そして父が応接間で日本軍の指令官をもてなしているとき、私は地下の酒蔵でペギー親子のそばにいて、ともに恐怖を分かちあっていたのです。私とソフィーは手を握りあいました。激情が込み上げてきて、私はソフィーが逃避行を強いられている天女のように感じられました。こんなことを言うとあなたはお笑いになるでしょうね。しかしこのような状況で、腹の内にヒロイックな気分が湧いてこない者などいるでしょうか」 私は緩慢な動作で手を上げ、口を蓋ってあくびをした。トランクの底から掻き出された、陰鬱な恋愛話を聞かされるのだろうと私は覚悟した。 「私たち家族の冒険は長くは続きませんでした。ペギー父子が私たちの家に隠れていたのはたったの二日だけだったのです。三日目の朝、憲兵が家になだれ込んできました。まるで事前に密告があったかのように、家宅捜索やあれこれ尋問することもなく、日本軍司令官は流暢なフランス語で、私の父にかくまっているフランス人を即座に引き渡すよう要求しました。私の父は罪に問われることはなく、私たち一家、誰一人として拘引されるようなことはありませんでしたが、私はソフィーが不憫でならず、とめどなく涙が溢れてきました」 つづく
2005年05月09日
コメント(0)
-
「侵略軍のバイオリンの音」 連載第1回
「侵略軍のバイオリンの音」 連載第1回 バオ・ニン著 岩井 訳 七月十四日〔訳注:フランスの国家記念日〕の機に、私は招待にあずかりフランス大使館にやってきた。招待状には七時と記載されていたが、少し遅れてしまい、会場にはすでにフランス人もベトナム人も大勢集まっていた。パーティーは始まってけっこうな時間が経っているようであった。立食パーティーで、電車の中でもないのにだるくて疲れるうえに、各々が好き勝手に蠢きひしめきあっているのだからかなわない。 クーラーがぐわんぐわんと喘いでいたが、人いきれや煙草のけむりで重苦しい空気を軽やかにするには力不足で、女性の香水の匂い、男性の香水の匂い、化粧品の匂い、靴墨の匂い、料理の匂い、そして各種の強い酒の匂いが会場内に充満していた。人々はベランダや庭に出ることを余儀なくされ、会場は次第に人影疎らになっていった。 庭で会話に興ずる声は室内ほど喧しくはなく、穏やかに響いた。時々、誰かにくすぐられたかのような女や男の嬌声があがった。どの男も女も、手には酒の入ったグラスか料理をのせた皿を持ち、もしくはその両方を両手に抱え、四、五人のグループごとに集り、飲み食いしながら競って囀っている。誰もが礼儀正しく、美しく艶やかであった。とくに女性は、高価な服で着飾っていた。男性はフォーマルに決め、折り目正しく、背広やネクタイや革靴を優雅に着こなして、各自の声望や人品と釣り合いが取れていた。商売人、劇作家、歌手、老学者、若年学者、慈善家、仲買人。誰もが高貴さを引き立たせる表情を張り付け、立ち居ふるまいはすべてフランス流であった。また、言語もフランス語であった。あるフランス人青年がウィットを効かせた言葉をペラペラとしゃべると、間髪入れず周りの食客でフランス語に精通している者がドッと称賛の笑い声をあげ、一方ただ母国語を知っているのみの私のような者は、慎重に喜びを湛えた顔でひかえめに微笑むのであった。爪先立ちになり、理性を失うほどに感服し、そのジョークに秀でた外国人を呆けたように見つめている女性もいた。 ひときわ明るくなっている庭の一角で、きわ立って賑やかな十名ほどの一群がいた。はっきりと誰なのか確認したわけではなかったが、彼らの楽しそうで放縦な様子から、同業の若い男女の集まりであると察し、私はそそくさと退散せねばならなかった。大使館の門の近くまできたとき、慌てていた私はゆっくりと歩いていた老人にぶつかり押し倒してしまった。私は取り乱しながらも謝罪した。「気にしないでください、なんともありませんよ」、老人は言った。「私も今晩はちょっと酔ってましてね。しかしまた早いお帰りですね、作家さん」私は面食らった気持ちを押し殺し、老人を見た。私は彼を知っていた。老人は他の誰でもない、ナムボ通りの端にある新聞スタンドの主人であった。彼のパーティー衣装は擦りきれ、ネクタイはどこのデザインなのか、まるで祭にはためく三角の幟のようであった。そしてガリガリに痩せているため、シャツもベストもだぶだぶであった。小柄で、背は曲がっていた。私は肘を支え、表通りまで彼を連れていった。 「今年の国家記念祭は盛大ですね」老人はしわがれた声で言った。「また大勢集まったものですな。おそらく、フランスの連中は二十年前に大使館を吹き飛ばしたアメリカの爆弾さえも、敬慕し続けたいんでしょうね」涼やかな風が通りに沿って吹き抜けていった。トニュオム通りは夜も更けて車の数も減り、歩道を行き交う人も疎らであった。私は老人の傍らで、ゆっくりと歩いた。老人の名はボンといったが、彼と同じ通りの人々は未だに彼を「ムッシュ」と呼んでいると聞く。 「私が思うに、あなたはこの老体がいったいなんの資格があってこんな立派なパーティーにかかずらい、出入りしているのだろうと訝っておいででしょう、そうじゃありませんか。しかしですね、今晩限りのことではなく、もう慣例なんですよ。大使館でちょっとした催しものがあれば、決まって私のところに招待状が届きます。そして私は参加します。誰も私のことなど知っちゃいませんけどね」彼は酒くさい息を吐いたが、呂律はしっかりとしていた。靴をズルズル引きずりのろのろと歩いたが、足取りは確かだった。そして彼の言葉は回りくどかった。 「大使館の儀典局の職員でさえ、私がどういう人物なのか知りはしないでしょう。前任者から手渡された名簿を引き、飽きもせず私の名前と住所を印刷済の招待状に書き込み続けます。招待状は郵便で私の手に届きます。私はその紙を見せて、門をくぐるというわけです。誰も問い質したりしませんよ。何度も大使館に出入りして、正門も裏門も、まっすぐな通路も曲がりくねった通路も知り尽くし、各種の招待宴の迎賓形式にも通暁いたしました。私はグラスと少しの料理をそっと手に取り、人々の間に割って入るようなことはせず、でしゃばるような真似もしません。人目のつかない場所を探し、何もしゃべらず、話しかけず、人々が話しているフランス語が周囲に響き渡るのに耳を傾けます。フランスの流儀が充満する空間の片隅で、ぽつねんと身をひそませているのです」 私の横で足を引きずって歩いている奇態な人間の一連の独白により、私は気おくれするのを感じはじめた。私はちらりと横目で見た。街灯の光が逆光となり、老人の顔はいっそう血色悪く見えた。 「しかしでしゃばりたくないのなら、なぜわざわざパーティーに潜り込まねばならないのかと、あなたは考えておいででしょうね。きっと、あなたは私のために恥入っておいででしょう。非常識で、混血の、外国かぶれな老いぼれだと私を評価しているに違いありません」 私は、老人のことを詳しく知る光栄には未だあずかっておらず、そのため、あれこれと邪推できるはずもありません、とモゴモゴ言おうとしたが、老人は即座に私の言葉を遮った。 「言葉を選ぶ必要はありませんよ。私を不愉快にさせるのでは、などと気遣わなくてよろしいのです。なぜなら、事実はまさにあなたが考えているとおりなんですから。訂正するとすれば、私はおよそ外国かぶれではありません、フランスだけなんです。私はフランスのほとんどすべてを好ましく思っています。この機にあなたに告白させていただきますが、私は正真正銘、ハノイに取り残された最後のフランスの亡霊なんですよ」 老人の突然の荒唐無稽であからさまなもの言いに、私は別段驚きはしなかった。私は平静に聞いていた。聞くだけなら造作もない。それに世間の人々が心情を吐露するのに耳を傾けるということにかけては、私には天賦の才があった。 「まだ子供のころ、私たちの祖先はガリア人であると暗記せねばならなかったとき、当然のことながら、そんなことは大嘘であると私もよく分かっていました」。爺さんは長い間押し黙って歩いたのち、また例のしゃがれ声で話し出した。「しかしですね、そのころ私や友人たちはこんな風にいつも歌っていましたよ ――われ想いしやかの大地、わが故郷(ふるさと)とそしてパリ……」 ザトゥオン通りの端まで来て、私と爺さんは歩道のカフェで足を止めた。私たちは腰を下ろし、黙りこくって、スプーンでカラカラと掻き混ぜた。ホアロー監獄わきのホテルの建築現場では、まだ騒々しく作業が続けられていた。 「ほら、見てごらんなさい」ボン爺さんが指差して言った。「人々は仏属時代の最後の瓦礫を取っ払おうとしているところです。誰もそれを惜しみませんし、誰も惜しまなくて当然なんですけどね」 ため息を洩らし、老人はゆっくりと話し続けた。 「昔の通りはいまよりずっと静かでした。通りを一区画分端から端まで歩いても誰にも遭わず、自身の影と足音がくっついてくるだけでした。当時、頭でっかちで痩せ細っていた私は、散策するのが唯一の楽しみで、よく一人で気晴らしにぶらぶら歩き回ったものです。私は騒々しい場所や人の多い場所は避け、閑静で人影疎らなフランス街を好んで歩きました。ボニファシ通り、ハレ通り、ザーブイ通り……時も移ろい五十年が経ようというのに、私の記憶の中では、未だにいくつかの通りは旧称のままなんです。その通りの住居は高級邸宅ばかりで、高い塀に囲まれ門は厳重に閉じられていて、まるでちょっとした宮殿のようでした。そしてどの通りも強い日差しが当たらず、涼やかでありました。昔は、私たちの家族もこの通りに住んでいたんですよ。ザンソレ通りです。ほら、あの家ですよ」 ボン爺さんは椅子から身を起こし、腕を上げ、つい先ほど私と老人が通ってきたトニュオム通りの奥を指差した。 「当時、この地区で暮らすベトナム人は非常に稀でした。私たちの近所の高級邸宅も、家主はすべてフランス人でした。フランス人と私たちの間に近所付き合いはあまりありませんでしたが、私の家族の生活水準や生活様式が彼らより上であったとは言わないまでも、引けをとっていたわけでは決してありません。フランス人ができることは私たちにもできました。大事なのは平等ですからね」 爺さんは自慢気に鼻を鳴らした。 「もし世界大戦がなければ、私は家族にパリへ遊学させてもらうはずでした。しかしフランスは占領されてしまい、日本軍がインドシナに侵攻してきました。やむなく私は法律学校に入りました。そのころの私は、瞑想や思索にばかり耽り、不安のために涸れて磨り切れていました。私は独白を好みました。哲学のほかにも詩や賦に対する造詣を深めました。スタンダールやフローベールの小説の思想に親しみ、ユーゴー、ボードレール、ランボー、そしてヴェルレーヌの無数の詩句を諳んじました。そのなかでもやはりヴェルレーヌですよ、ヴェルレーヌ……コーヒーカップは飲み干され、そして座り続けることに飽くが、老人は未だ話に飽くことを知らず……」 「その当時、世間には日本に迎合する輩が横溢しておりました。しかし私は、傲慢で粗野な彼ら官兵たちを好くことがどうしてもできませんでした。私はフランス文明が野蛮な連中の非道を再び治めてくれる日がくるのを、秘かに心待ちにしておりました。しかし私は単にそう願うだけで、現実からは完全に逃避していたのです。ベトミンが学生たちに秘かに撒いたビラがあり、私も読む機会がありましたが、そんなものは少しも信用しませんでした。フランスでさえ日本に抗し切れなかったのに、ましてや、ですよ。我々がどれほど力強くとも奴らを追い払うことなどできやしない、私はそう考えました。そして分不相応な大志を抱いている疑いのあるすべての友人から、私は静かに距離をおきました。私は若さを古ぼけた本の山に埋葬しました。私は飢饉にさえも背を向けるほど、目を閉じ耳を塞いで暮らしておりました」 老人は大儀そうにネクタイの結び目をゆるめた。話し疲れたのか、彼の禿げあがった頭部が汗で光った。 つづく
2005年05月09日
コメント(0)
全46件 (46件中 1-46件目)
1