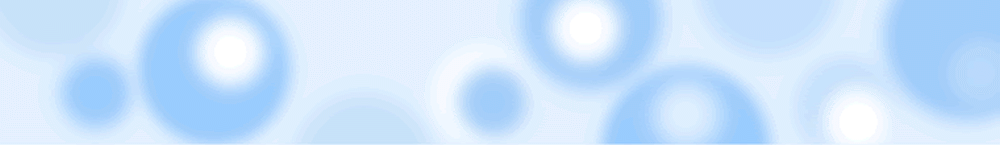PR
カレンダー
キーワードサーチ
 New!
こたつねこ01さん
New!
こたつねこ01さん冬も少しずつ進んで…
 New!
木昌1777さん
New!
木昌1777さん今日のおやつ「くる… New! クレオパトラ22世さん
TOKYOタクシー New! エンスト新さん
山中湖・お宿は「w…
 みぶ〜たさん
みぶ〜たさん子育て支援の見学と…
 7usagiさん
7usagiさんネコ様とガーデニン… 結柄yueさん
お買い物 満々美人 Grs MaMariKoさん
旅人てつきちのトー… Tabitotetsukitiさん
〜旅するように暮ら… tabimizukiさん
サイド自由欄
●現代レイキ
◆土居 裕著
実践レイキヒーリング入門 ・ 癒しの現代霊気法
レイキ宇宙に満ちるエネルギー
●ヘミシンク
★坂本 政道著
楽園実現か、天変地異か
★まるの日 圭著
誰でもヘミシンク・サラリーマン異次元を旅する
●心理学(NLP)
▼山崎 啓支著
マンガでやさしくわかるNLP
▼椎名 規夫著
自分とまわりを変える魔法のNLP実践トレーニング
最近カウンセリングに関係する本を、何冊も読んでいる
ヒプノを勉強しだして、こちらのほうに意識がいっているのだ
以前、心理学の勉強をした時、これは占い師と対峙する内容で私がこちらの世界にくるのは、難しいと考えていた
だから一通りは勉強したものの、それを生かす方向には動かなかったそれがヒプノを勉強して、カウンセリングの道に興味を持ったのである
それは従来のカウンセリング方法と、違っていたからだ原因から入るカウンセリングではなく、未来を見据えたものだった
原因は? というと、原因の特定は必要としないものである
結果の前には必ず原因が有る、という考え方できた私にとっても
これは、新鮮な考え方であった
何か家族に問題が発生すると (例えば登校拒否の子供)家族が、誰に原因が有るのかと犯人探しになってしまう
そして、その原因が自分ではないかと
それぞれが、自分を責めたり、或いは相手を責めたりと
結局何の解決も無いまま、悪循環を繰り返してしまうのだ
原因の特定は必要としないただ、解決すればいいのだから‥ というものである
米国の高名な家族療法家、S・ミニューチンの文献に次のような記述がある
夫婦の葛藤を母親が父親と娘との葛藤に変化させることによって
夫婦は葛藤を迂回させる。
子どもを通して夫婦間の話し合いをすることは、夫婦のサブシステムが
いかにも調和しているかのような錯覚を起こさせる。
夫婦は自分たちの問題を子育ての問題へと迂回させ
子どもの逸脱行動を強化する。
こうした両親の迂回は、子どもを攻撃する形をとったり
子どもを病気で弱いものと見て、保護するために結合したりする
子どもは両親の喧嘩を仲裁する為に、病気になったりするのだ病気になれば両親も、喧嘩している場合ではなくなる
だから子どもは、健康になれないのだ健康になったら両親が喧嘩して、もしかしたら離婚するかもしれない
病気で居ることが、子どもにとって必要不可欠な事態となってしまっている
だから家族ぐるみで、問題に取り組まなければならない子どもの病気が、必ずしも子どもだけの問題でないという事例である
-
★ブロック 2014年07月06日
-
★進めないのは何故? 2014年05月29日
-
★想いのすり替え 2014年03月16日