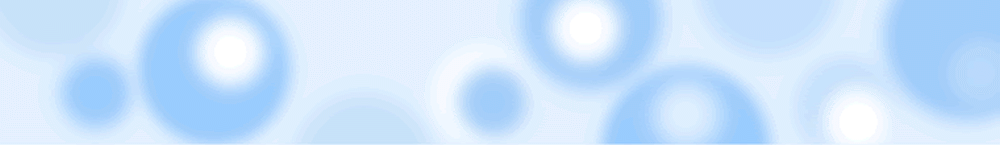PR
カレンダー
キーワードサーチ
 New!
木昌1777さん
New!
木昌1777さん公園の紅葉と法要へ… New! クレオパトラ22世さん
ニッポンエール す… New! エンスト新さん
空き時間の2回目?
 こたつねこ01さん
こたつねこ01さんお久しぶりです
 7usagiさん
7usagiさん山中湖・お宿は「w…
 みぶ〜たさん
みぶ〜たさん【お知らせ】しばら…
 Tabitotetsukitiさん
Tabitotetsukitiさんネコ様とガーデニン… 結柄yueさん
お買い物 満々美人 Grs MaMariKoさん
〜旅するように暮ら… tabimizukiさん
サイド自由欄
●現代レイキ
◆土居 裕著
実践レイキヒーリング入門 ・ 癒しの現代霊気法
レイキ宇宙に満ちるエネルギー
●ヘミシンク
★坂本 政道著
楽園実現か、天変地異か
★まるの日 圭著
誰でもヘミシンク・サラリーマン異次元を旅する
●心理学(NLP)
▼山崎 啓支著
マンガでやさしくわかるNLP
▼椎名 規夫著
自分とまわりを変える魔法のNLP実践トレーニング
京都の下京区にある開花堂カフェを紹介していた番組は、「カンブリア宮殿」であった。
40年前までは市電の車庫として機能していた場所に、3年前カフェとしてリノベーションしてお店を開いたのが、開花堂だった。
実はこのカフェ、京都の意外な老舗が経営していた。「開花堂カフェ」は、飲食業が本業ではなかったのである。
このカフェで、珈琲豆を保管して使っているのは、本業で作っている茶筒だという。
このカフェの正体は、京都の茶筒の老舗で「開花堂」。
茶筒の素材はブリキ、真鍮、そして銅の三種類。
値段は‥高い、ちょっと買うのに勇気が必要になるお値段だった。
でも、これが次々売れている。というのも、その茶筒の機能の素晴らしさにある。
茶筒の蓋を軽く上に乗せるだけで、勝手に蓋の重みで降りて行き、ピタッと閉まるのである。
「凄い!なんて気密性が高い茶筒なの!」これはこれは、大変な職人技である。
創業は1875年、日本で初めてブリキを使って茶筒を作ったお店である。
それまではお茶を、大きな木箱に入れて保管していた。
簡単に持ち運びなど出来ない大きさの木箱である。
現在の職人は8人で、分業制で行なっている。全て手作りで、創業当時から作り方は同じである。
この茶筒を作る工程が、130以上もあるというから驚く。なので一日に作れる量は多くない‥40個ほどしか作れないという。
海外展開もしていて、これが随分と売れているというのだが、えっ?何故海外で茶筒が??
その答えというのが、日本では茶筒として使っているが、
海外ではその気密性の良さから、
お茶ではなく、色々な食材の保管として使っているのである。
私がもう一つ驚いたのが、とんでもない進化を遂げた茶筒だということ。見た目は茶筒なのに、使い方にびっくりした。
一見普通の茶筒なのだが、蓋を開けると何と!音楽が聞こえてきた。
何と何と‥スピーカーとしての機能が付いているのである。
そして蓋を閉めると(重さで勝手に閉まる)音が消えてしまうのである。
これはパナソニックと開花堂が共同開発したスピーカーで、商品名が「響筒」と言う。
なんて画期的な考え、なんて素晴らしい発想だろうか!
かつて廃業寸前の危機があった開花堂。
こういう現在に合う商品作りが、廃業を回避して生き残り、
更に売上を伸ばしていくことになる。
我々も、常に頭を柔軟にして、
枠に捕らわれない発想をすることが生き残っていく道だと、
教えられた番組であった。