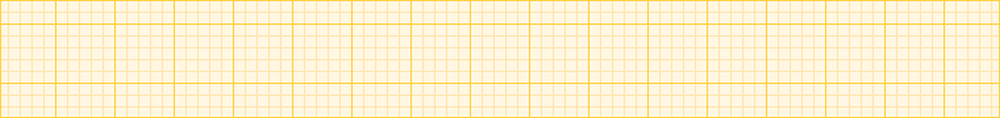2012年07月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-

南山大など運営の法人、新たに92億円の運用損
駒沢大学は、金融機関に損害賠償を求める訴訟を起こしましたが・・・南山大など運営の法人、新たに92億円の運用損南山大などを運営する学校法人「南山学園」(名古屋市昭和区)が、運用に失敗した金融派生商品(デリバティブ)取引の解約により、2011年度までの3年間で計約92億円の損失を出していたことが17日、分かった。 同学園では09年にも約68億円の解約損が判明しており、金融派生商品による損失は最終的に計約160億円に達した。損失は経常的資金や有価証券の売却益をあてて埋め合わせしており、同学園は「教育、研究活動に支障はない」としている。 同学園によると、解約損は、09年度が約29億5000万円、10年度が約26億5000万円、11年度が約36億7000万円。判明している08年度分約68億1600万円と合わせると、160億8600万円になる。同学園は05年に金融派生商品で資産運用を開始したが、08年のリーマン・ショックの影響などで多額の含み損が発生。一度に全て解約すると、学園運営に支障を来す可能性があるため、リスクの高い金融派生商品から順次解約を進めていた。高リスク商品の解約は今年3月までに完了しており、同学園は来月にも外部の有識者らで構成する「資産運用問題総括委員会」の初会合を開くなどして、今後、運用当時の幹部の責任追及などを検討する。同学園法人事務局長の蒔田一(まきたはじめ)理事は、「総括委員会の報告をもとに再発防止を図りたい」としている。(2012年7月18日17時35分 読売新聞)【送料無料】金融商品にだまされるな!価格:1,575円(税込、送料無料) 【内容情報】(「BOOK」データベースより)日本で販売されている金融商品は問題だらけ。特別な仕組みの預金や個人向けの年金保険など、巧妙なワナの仕掛けられた商品が大手金融機関で堂々と売られている。その上、恐ろしいことに、窓口の販売員側もその問題点を自覚していないことが多い。本書では、豊富な図版と広告例を通じて、「金融商品のワナ」の見破り方と、数少ない良質な金融商品の使い方を解説する。
2012.07.18
コメント(12)
-

為替デリバティブ:大手4行、顧客と和解で、計500億円規模の損失処理
8月からは、5年前に発行されて、ゼロ円償還の仕組み債訴訟が急増します。為替デリバティブ:大手4行、計500億円規模の損失処理大手銀行4行が、中小企業などに過去販売した為替デリバティブ(金融派生商品)に関連し、2012年3月期に合計で500億円規模の損失を処理していたことが17日、分かった。歴史的な円高でデリバティブの評価損を抱えた顧客と和解を進めているためだ。円高の収束は見通せず、今後も増加する可能性がある。関係者によると、みずほ銀行は約300億円、三菱東京UFJ銀行は約100億円、りそな銀行は約65億円、三井住友銀行が数十億円の損失を計上。三井住友信託銀行や地方銀行の一部も損失処理した。【送料無料】ハイリスク金融商品に騙されるな!価格:1,575円(税込、送料無料)【内容情報】(「BOOK」データベースより)「為替デリバティブ」「金利スワップ」「ディフィーザンス」「パワー・リバース」…会社が倒産しそう?個人で大損を被った?大丈夫、打つ手はあります。今後、騙されないためにも必読。【目次】(「BOOK」データベースより)第1章 買わされたハイリスク金融商品で企業倒産!/第2章 大学、自治体、大企業でも被害続出/第3章 デリバティブの正体/第4章 金融機関に問題あり!/第5章 金融トラブル解決法/第6章 銀行との交渉は怖くないー企業再建のプロ、洲山からの提言/第7章 個人がハイリスク金融商品から身を守る方法
2012.07.18
コメント(0)
-

サイゼリヤが168億円賠償請求 デリバティブ損失巡り
サイゼリヤが168億円賠償請求 デリバティブ損失巡りレストランチェーンのサイゼリヤが6月上旬、BNPパリバ証券など同証券グループ3社を相手取り、計168億円の損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こしたことがわかった。2007年と08年に結んだデリバティブ(金融派生商品)取引の契約で損が出たという。 訴状やサイゼリヤによると、ハンバーグやソースをオーストラリアの子会社から輸入する際に為替変動で損が出るのを防ぐため、07、08年に、BNPパリバ証券などとデリバティブ取引の契約を結んだ。それぞれ1豪ドル=78円、1豪ドル=69.9円で豪州ドルを買うことになっていて、いずれも当時の相場より約1~2割、安く豪ドルが買えた。 しかし、為替相場が契約より円高豪ドル安に振れると、豪ドルの購入価格が加速度的に高くなっていく仕組みだったため、その後の円高豪ドル安で大きな損を被ったという。サイゼリヤは09年8月期決算で二つの契約の解約金として153億円の損失を出した。 【送料無料】 仕組み債(デリバティブ組み込み債券)家計を蝕む「金融詐術」の恐怖 / 吉本佳生 【単行本】価格:1,470円(税込、送料込) ここ数年、住宅地やそのターミナルに銀行の新店がオープンするケースが増えている。長く撤退ばやりだったのが、一転して「消費者立地」に。その狙いは、高齢者を中心とした「小金持ちの貯蓄」という。言葉巧みに勧めてくる「安全かつ高金利」な金融商品には、「詐術」が込められたデリバティブ関連も少なくないようだ。 著者が最悪の金融商品に選定するのが仕組み債(デリバティブ組み込み債券)だ。具体的には「東証マザーズ指数2倍連動債」「リスク10倍・10銘柄ED債」が両横綱。 共に元本全額損失のリスクが驚くべき高さになる設計だが、ほとんどの顧客にはその危険性がわからない。悪名がとどろいているにもかかわらず、一般人の認識は薄いという。 「地方自治体や大学のデリバティブ汚染は、リーマンショックから3年以上経過しても、ほとんど解決していない」。少なくとも個人資産はそれから守るべきことを、本書は教える。
2012.07.08
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-
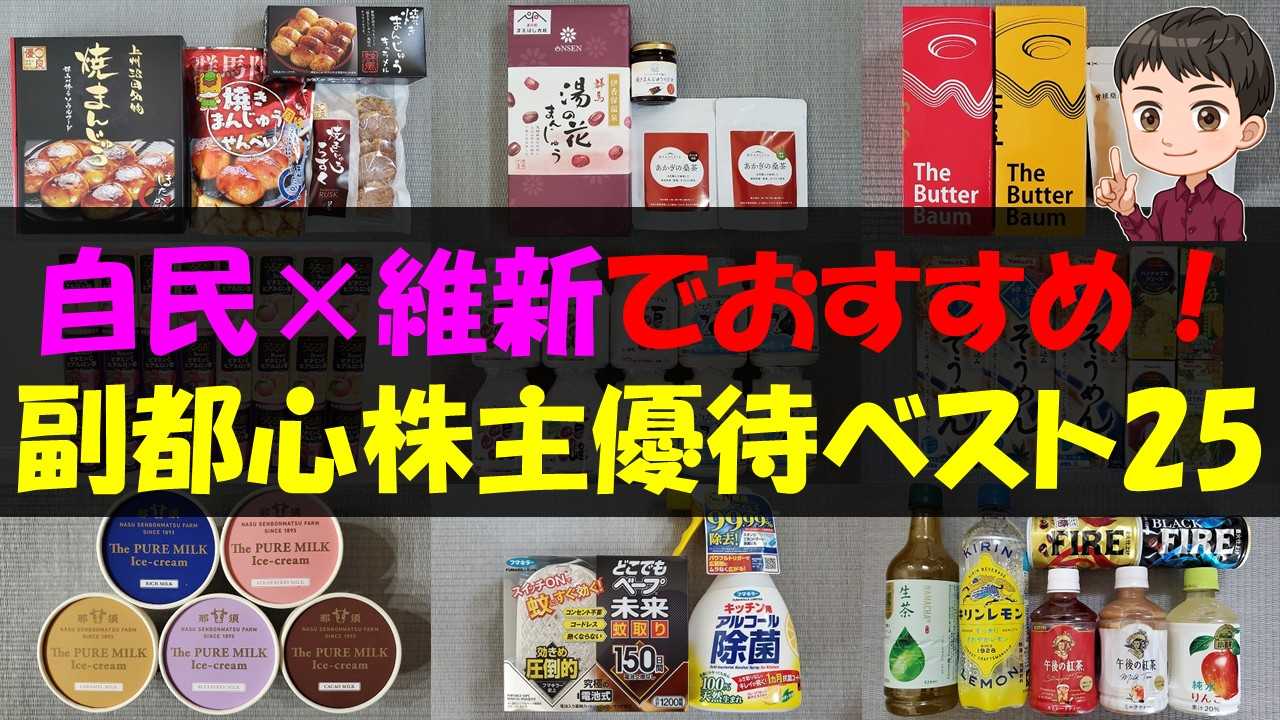
- 株主優待コレクション
- 【大阪】自民×維新でおすすめ!副都…
- (2025-11-19 18:00:06)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- ブラックフライデー2h全品 半額〜…
- (2025-11-19 18:48:00)
-