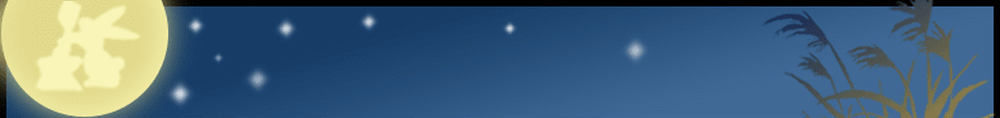2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2004年02月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
多言語育児(3)モノリンガルの警戒心
【コミュニケーションの為の第二言語習得方法提案(5)】ここで、日本での「外国語育児の始め方」に関する提案から海外で日本語話者の親が子供に日本語を教える場合への提案と個人的体験の紹介に移るが、実は、これは海外在住家庭だけでなく日本で「英語(外国語)育児」をしている家庭にも参考になると思う。(と、言うと、何となく偉そうだが...^^;)日本語と英語(外国語)を入れ替えてみると海外での日本語育児と日本での外国語育児の共通点に驚き、お互いに親近感も湧くのではないだろうか。両者は、実は、とてもよく似ているのだ。お互いの体験談や成果を交換しあって参考にできたら素晴らしい。さて、「海外での日本語育児」は、両親とも日本語話者か或いは片親だけが日本語話者か、また、その場合、非日本語話者は単言語話者(モノリンガル)か多言語話者かで、かなり違って来る。家庭での日本語教育が、最も困難になるのはおそらく、片親が殆ど日本語を話せない場合だろう。特に片親が日本語に全く興味が無い場合や「外国語や多言語教育」に対して警戒心の強い場合は非常に難しくなる。日本語をあきらめる親も出てくるのではないだろうか?本人の意志・選択によって子供と母国語ではない外国語で話すのではなく他人の意志・願望・強制によって子供と母国語で話す事を「禁じられる」のは明らかな人権の侵害だ。実際には、ここまで強硬な態度を取る配偶者は少数だろうが、ここまで頑なではない親・義理家族を不安にさせ、不満を生み出す、多言語育児方法がある。それは、徹底的な「一親一言語主義」だ。例えば、日本語話者である親は子供に対して日本語以外は一切使わない、という方法だ。これは、多言語育児方法の中で最も効果的だと一般的に言われており、実際に、非常に効果の高い方法だと思うが日本語のわからない配偶者や親戚にとってはストレスの元となる場合もある。本人達が、多言語話者の場合は、この傾向はぐっと弱まるのではないかと思うが一つの言語しか話せず、しかも、外国語に対して苦手意識や警戒心があると、このストレス値は高くなりがちだ。ストレスまでいかなくとも疎外感を味わう事もあるだろう。それが、結果的に不安や不満につながる。こういった場合、どうしたら良いのか?よく聞く対策は、子供には日本語で通し、それを逐一、周囲が理解る言葉に訳す方法だ。ちょっと面倒くさそうに聞こえるが実行している人の話では、慣れるものらしい。だが、この方法で、全て、円満解決となるわけではない。なぜなら、実際には、外国語に警戒心のある人は「一体、親子がどんな内容の話をしているか」に興味があるのではなく自分の目の前で自分の理解らない言葉が話されている事自体が既に我慢できないからだ。私の印象では、英語しか話せない保守的な英語話者にこの「外国語警戒心」が強い様だ。私は現在「中流・保守的・白人」英国人が大部分の地域に住んでいるのだが、ロンドン等の外国人や移民の方が多いんじゃないかと思える様な国際的な都市と比べて、外国人・外国語への警戒心は高い。ロンドンで日本語や中国語を話していても誰も見向きもしないがこの近所で、英語以外の言語を話していると大人も子供も敏感に反応する。私達家族の場合は、既に、完璧に「外人」外見なのでそれほど驚かれる事は無いが大陸ヨーロッパ人である親が母国語で子供に話し掛けたりすると端から見ていてもおかしいくらい、周囲が反応している。同じ村に住むスペイン人の友人によると、彼女の家の近所の人や学校の保護者の中にも、友人が子供達とスペイン語で話す事に反感を持つ人が非常に多いらしい。何度も皮肉を言われたり「何で英語で話さないのか?」と聞かれたり批判されたりしたそうだ。また、友人の子供が通う公立の小学校にスペイン人の子供が入学した時、友人は、先生から「家でも英語で話す様に親に伝えてくれないか?」と頼まれたらしい。この話が出た時は、思わず「それを直接伝えられないほど親は英語が話せないのにどうやって英語で子供と会話するんだっ????」と笑ったが友人は、笑いながらも、かなり真剣に怒り呆れていた。その学校は、カトリック系で、欧州から駐在している家庭が少なくないのに、それでも、この程度の認識なのだ。私も、長男や次男が公立小学校付属Nursery(幼稚園)に入った時同様の事を経験している。長男の場合は、英語も、何とか話せたし理解できたのだがクラスメート(長男以外は全員英語しか話さない英国人)よりも英語力がかなり劣った為、心配され「家でも英語を話してくださいね~」と担任からアドバイスされた。次男の時は、この小学校にも、バイリンガル児童が増えており最初は何も言われなかったのだが、幼稚園から小学校へ上がる時期(誕生月によって9月と1月に分かれる)を決定する際「長男と次男が英語で話すように仕向けるべきだ」と、校長先生に笑顔で力説された。今は、逆に「英語力が飛躍的に伸びているので問題無い」と、こちらから学校に依頼している「英語補助教育」を次男は受けさせてもらえていない。単に英語で会話ができる力と、学習の基礎となる英語力は全く別物なので、一週間に一度でもこの英語補助の時間があるのと無いのとでは大違いなのだがどうも多言語児童体験(^^;)が少ない学校はこの違いを軽視している様だ。我が家の様な夫婦とも非英語話者家庭の場合だけでなく片親、特に母親が非英語話者の場合にも、子供の「表面的ではない深層の英語力」は、両親が英語話者の場合に比べて劣る可能性が高い。これは、英語の「底力」の様なもので、綴り方や機械的な文法が中心の学校の英語のテストでは見えないし、学校は、学校でテストの成績さえ良ければ後は構わない(構いたくない)のだ。ちょっと話がそれたが、以上の様に学校で文句を言われるだけではない。会話の輪の中に入っている人の前でその人のわからない言語で話すのは非常識・無作法だ、という意識は、どの国でも大体あると思うのだが英国の場合は、これが非常に強い様で、例えば、ショッピングの際、店員の前でウザヲと私が中国語で会話すると「今、何とおっしゃったんですか?」と店員から聞き返されるという経験を何回かしている。状況的に、それがウザヲと私の「私語」であるのが明白なのに、わざわざ、明らかに英語ではない会話の内容を聞こうとするのは自分には理解らない言語で話されるのが不愉快だからではないかと思う。ウザヲが中国語で私に質問し、私が即、店員に聞く場合は「きっと通訳しているんだな」と納得する様で不満顔をされる事は無い。英語話者の前で子供達に日本語で何か言うと英語話者から「大丈夫ですか?」と聞かれる事も多い。これは、ただ単純に心配している場合もあるのだが、実は「今、何て言ってたんですか?」と無礼にならないように、やんわりと聞き返しているのでもある。以上の様な体験は日本で「英語(外国語)育児」をしている人にもあるのではないだろうか?日本も、外国語に警戒心を持つ単言語話者が多い国だ。では、運悪く(^^;)、「単言語話者」環境で多言語育児をする場合、どうしたら良いのだろうか?考えられる対策は以下の二つ。1.徹底的な一親一言語主義を突き通す。(どんな状況でも、子供とは日本語しか話さない。)(↑日本語で話した後に訳す等のフォローも含む。)2.日本語がわからない人がいる時は日本語を使わない。私が採ったのは2の方法だ。家の外でも日本語は話しているのだが実際の会話の輪の中に日本語がわからない人が入ったら日本語は極力使わない。どちらの方法を選ぶかは、家庭の言語状況の影響も受けるかもしれない。我が家では、そもそも、ウザヲは、全く一親一言語ではなかった。彼は、教養のある中国人(^^;)なのだが、標準語(中国語で「普通話」と呼ばれる)はかなり訛っているし、よく発音を間違える。標準語・日本語・英語と、流暢と言えば流暢とも言えるのだが完璧に話せるのは「上海語」だけだ。ちなみに、中国での方言と標準語は外国語並みに違い、お互い通じないのが普通だ。日本の方言と標準語の関係とは全く異なる。だから、私は、ウザヲには、なるべく上海語を使う様に促していた。(そのココロは「子供に、間違い、教えないでくれ~」...)だが、ウザヲは「だって上海語、通じないんだも~ん」と子供達が一番反応する日本語を多用していた。上海語を使う様になったのは、私が、子供達に上海語を少し教えて使わせる様にしてからだ。その後、今では、上海語・中国標準語・英語・日本語と全く無意識に気分に合わせて選んでいる。ウザヲと私の会話は「中国(標準)語」だが長男は父には英語か日本語で話し掛け次男は父には日本語で話し掛ける。二人とも、中国語を使うのは挨拶と父に何か頼む時だけだ。中国語は、アクセサリーの様な存在だ。そんな訳で、我が家の場合、家では、日本語が多用されているので家の外で殆ど日本語を話さなくても家の中での埋め合わせが容易にできた。私は、家で日本語話者の親が子と過ごす時間がたくさんある家庭では外で日本語以外を使っても、あまり大きな影響は無いのではないかと思う。第一言語が確立されていない乳幼児に対して使う言語が統一されていないと混乱を与えるという意見もあるが私は、日本語の理解らない人がいる時だけは日本語を使わないという条件を明確にしておけば混乱は防げると思っている。乳児でさえ、言葉が使われる状況の違いを感じ取っているものなのだ。「一親一言語主義」を徹底している人は臨機応変な多言語育児に懐疑心や警戒心や時には敵対心さえ抱く事もある様で「絶対、徹底させなきゃダメ」「ちょっとでも混ぜたら最後」等と脅かす人もいない訳ではない(^^;)。だが、一親一言語を、ちょっとでも緩めてしまったら全てが壊滅する、という事は無い。むしろ、少し緩める事で長続きする場合もある。日本語が続けられなくなるのは臨機応変な多言語育児方法が原因なのでは無く子供が日本語以外で話し掛けて来た時の対応が子供の性格に合っていなかったり(日本語以外はダメと拒否される事が逆効果になる子供もいる)子供に日本語を続けさせる事の意義を納得させられなかったり子供の動機付けの失敗等が原因となる事が多いのだ。多言語環境は家庭によって千差万別でありさらに、多言語育児は、同じ家庭内でも子供の年齢と発達に則して頻繁な軌道修正が必要だ。最終的には、子供と子供の置かれた言語環境をじっくり冷静に観察して試行錯誤するしか方法は無いのではないだろうか。例えば、同じ薬が、違う人に同じ様に効くとは限らず個人個人に合わせた処方が必要な様に多言語育児は家庭ごとに最適な方法が異なる。同時に、子供の言葉は、子供が置かれている言語環境を反映したものに過ぎないという事を親は忘れてはならないと思う。片親が努力したからできた、努力しなかったからできない、という様な単純なものではない。子供の言葉は、親の成績表ではないのだ。(続き)
February 14, 2004
コメント(28)
-
多言語育児(2)「外国語の始め方」提案
【コミュニケーションの為の第二言語習得方法提案(4)】ところで、外国語は何歳でも導入できるが、その導入方法は、子供の年齢や性格に合わせて親が工夫を重ね試行錯誤するしかないと思う。巷で評判になっている方法や、説得力のある本を読み、実行に移しても子供が全く乗って来ない事も少なくない。この場合、子供に合わせて少しずつ変化させてみるか自分なりの方法を編み出すかしかないが子供は、日々成長しているので、いったん試した方法を、しばらくたって試してみたら乗って来る可能性もある。ただ、どの方法を取るにしても親子ともどもストレスがたまらない方法が一番だ。よく雑誌等で広告を見かける幼児英語教材にしても、随分、高額なものもある様だが、それを買った為に「お金をかけたんだから、もとをとらなきゃ!」と無理をする様になっては、元も子も無い。教材を手作りするにしても、親が作る過程を楽しめるのならいいが「やっとできた~」と完成後、すぐ子供に壊されてショックを受ける様だったら、やる必要は無い。外国語の導入がうまく行くかどうかには、かける金額や苦労の多寡は関係無い。何よりも、親子で楽しむ事が第一だ。例えば、nursery rhymes のCDやDVDにしても子供が嫌がる可能性は非常に高い。うちの子供達二人を見ても、長男と次男でこの手のDVDが好きだった時期は、バラバラだったし両方とも3~4歳の頃には、見向きもしなくなっていた。ただ、二人とも、children’s poems/verses と呼ばれる児童詩は、今でも大好きだ。韻を踏んでいるので読んでいても聴いていても気持良く、内容も面白いので、子供だけでなく大人も楽しめる。BBC等から傑作集や有名作家のCDも多数発行されている。だが、この様な詩は、そもそも意味がわかって面白いからこそ楽しめるのであって、全く英語がわからない状態でこの詩のCDから英語が導入できるかどうかは疑問だ。それでも、この手のCDは大体うまい役者が絶妙な味で朗読しているのでBGMの様にながら聴きして、耳を慣らすという方法もあると思う。(これは、子供が嫌がらないかぎりは何歳でも使える方法だ。)児童への外国語の導入で一番肝心なのは、何と言っても「いつも聞いたり使ったりする言葉とは違う言葉があるんだな~」と、認識させ、できれば、興味を持たせる事なのだから「やらないよりはやった方がいいか?」程度のノリで気軽に始めて見て、子供の反応や様子を考慮に入れて随時、軌道修正(或いは方向転換)していけば良いと思う。さて、ここで素朴な疑問だ。時々「英語ができない親」を対象にした「英語育児」の本を見かける事がある。過激な表紙の宣伝文句に反し中身は非常にまともである事も少なくないのだが、「全く」英語のできない人が家庭で子供に英語を教えられるだろうか?私の答えは「う~ん、そりゃ無理だろうな~」だ。英語の導入をするだけでも、英語の知識は必要だ。だが、「英語ができない人=英語が全くできない人」ではない。日本では、英語に苦手意識を持ち、実際には、ある程度の知識は持っているのに「もう英語だめ。さ~っぱり~」等と自己暗示をかけてしまっている人が多い。そして、このタイプの人が、英語育児に関する本を読むことで「英語苦手→英語全然ダメ」の自己暗示が解ける事もあるかもしれない。それで、親自身が、英語を楽しめる様になったとしたらそれはそれで素晴らしい事だと思う。よく考えてみれば、英語塾が繁盛するのは自己暗示ではなく本当に英語が出来ない親が子供には英語で苦労させたくないとの親心で子供を塾に送るからだろう。最近では、「インター」と呼ばれる、英語で教える学校や幼稚園も人気を博しているらしい。しかし、不幸な事に、これらの塾は、やはり玉石混交である。英語が得意な人ならば比較的容易に見分けられるのだが全くできない人には難しいかもしれない。英語のお稽古もピアノや水泳のお稽古と同じ様なものだが上達が明白なピアノや水泳と違い、子供の英語の上達具合を英語のできない親が把握する事は非常に難しいのではないだろうか?私は、塾については、子供が楽しんで通っている塾だったら、それはそれなりの役目を果たしているので良いがもし、金銭的に無理をしながら通わせるのであったらそのお金をためて、外国旅行をした方が良いと思っている。もっとも、なかなか親が休みを取れない家庭も多いしこのあたりは、一概には言えないのだろう。けれども、塾に通わせる余裕の無い家庭の親が外国語を諦める理由は何も無い。外国語の存在を子供に認識させる事は、誰にもできる。一日中、外国語のCDを聴きっぱなしにしたり子供が嫌がるのに強制したりという事が無い様に注意し少しずつ、様子を見ながら、適度に「外国語」に触れさせる...「外国語」って面白いんだよ、恐くないよ、と子供に教える...それだけでも十分ではないだろうか。ひょっとしたら、子供と一緒に外国語に触れているうちに自分も、もっと学習したくなるかもしれない。外国語に苦手意識を持たない子供を育てるには親子で外国語を楽しむのが何よりだ。一方、外国語がある程度以上出来る親は、もう少し積極的な外国語の導入ができるだろう。例えば、本の読み聞かせだ。「本物(ネイティブ)」の外国語に実際に触れる機会が無い場合はできれば、その外国語のプロが読むCDも同時に聴いてみた方が良いと思うのだがともかく親の読み聞かせに勝るものは無い。ただ、これも、子供によっては一概に言えないのだ。読み聞かせられるのが大嫌いっという子供もいる。うちの長男が、そうだった。7歳頃から読書が大好きになり、9歳現在、一~ニ日に一冊は読みきる様になったが絵本、特に読み聞かせには興味を示さなかった。次男は、2~3歳までは、やはり読み聞かせが嫌いだったが4歳くらいから大好きになった。こんな例もあるから、この子は絵本・読み聞かせ嫌いだ、と決め付けずに、何度も、挑戦してみる価値はあるのだがどうしても絵本の嫌いな子には、その子の好きなTV番組の外国語版を見せるという方法がある。我が家では、ウルトラマンを中国語・日本語で見たり戦闘レンジャー系番組(Power Rangers)やトランスフォーマー(Transformers)遊戯王(Yu-Gi-Oh).....等を英語・日本語で見る事が子供達にとって良い刺激になった。一緒に番組を見ながら「~って、どういう意味?」と聞かれる度に教えてやる事で、かなり単語や表現を覚えた。以前、旅行の際、ポケモンのフランス語版DVDを購入した事もある。子供達は、全くフランス語がわからないのにも限らずかなり真剣に見入っていた(しかも何度も繰り返し見ていた)のだがだからといってフランス語が少しでもできる様になった訳ではないので全く知らない外国語の習得にTVや映画を見る事が即効的効果を持つとは思えない。それでも、こうやって、少しでも、外国語に触れる事がもたらす効果は決して軽視できない。実は、私がフランス語のラジオを聴いていた時4歳の次男が突然「これ、ポケモンとおんなじ」と言った事がある。次男の耳には、ポケモンDVDのフランス語の印象が残っていたのであった。ところで、近年、日本でも、外国語で育児する外国語が流暢な日本人親が増えている様だ。そして外国語育児・多言語育児に対する批判も多いらしい。この批判は、母親に向けられる傾向が強い。おそらく、日本の一般的家庭では母国語が確立していない乳幼児のコトバの発達に最も影響力を与えるのは母親である事が多いからだろう。だが、これは全面的な否定も肯定もできる問題では無い。核家族で、子供が一日に聞く言葉の大半が母親から発せられる様な家庭と祖父母と同居している様な母親以外に日本語を話す大人が実際の育児に大きく関わっている家庭では母親が子供のコトバの発達に及ぼす影響は違う。それから、育児する親の「外国語」が堪能であっても「本物(ネイティブ)」では無い場合にも周囲の批判は強くなると予想される。日本語が堪能だが「本物の日本語」ではない英語ネイティブの両親が日本以外の国で日本語で子育てしている状況や、あるいは、関西出身の読者は東京人がアクセントのめちゃくちゃな「寒い関西弁」で子育てをしている状況.....を想像してみてほしい。「何故?」と不思議に思う人は少なくないのではないか。違和感を持つ人もいるだろう。だが、これが標準語あるいは東京弁となると話は違う。東京人である私は、関西人が「東京弁もどき」あるいは「標準語もどき」で育児をしていても「何故?」とは思わない。ただ、自分が「本物の方言(東京弁は方言っぽくない...)」を話せないので「本物の方言」を話せる人が敢えてその方言を子供に教えないのは「え~~~っっ、もったいない~~っ!!」と感じるだけだ。さらに、よく聞く批判の一つに、「本物」に触れる前に「似非(エセ)」を導入する事へ対する危惧がある。これは、「似非」と同時に「本物」にも触れさせる事である程度、影響の強さが緩和されるかもしれない。また、既に「本物」を知り「本物」に触れて育った子供に親が「エセ外国語」で話し掛ける分には害は無いだろう。唯一、害があるとしたら、子供が嫌がっているのに強制する場合だろうか?対象が乳幼児の場合、子供自身の考えではなく周囲の思惑が、育児の方向に影響を与える事が多い。特に一人目育児の場合は、尚更だ。周囲の意見と自分の意見が全く違った時親に最も必要なのは、自分と異なる意見を個人的攻撃と感情的にとらえる事なくあくまでも冷静に謙虚に受け止める判断力とできるだけたくさんの子供達と豊かな愛情で接し我が子を客観的に観察する目を養う事だ。実は、母国語以外の言語で育児している親は、世界中にたくさんいる。国際結婚家庭や移民家庭で、周囲から強制され母国語育児を諦める親も少なくない。そんな親には、自ら母国語育児を捨てて外国語育児を選択する親の気持は理解しがたいだろう。そして、外国語育児を選択する親も母国語育児を諦めざるを得ない親の気持は理解しがたいと思う。ちなみに、私個人は、自分が100%自信を持て自分自身が子供時代を過ごした言語で育児をしたかったので幼児中国語や幼児英語も知ってはいたが息子達はバリバリの「幼児東京弁」で育てた。乱暴なコトバも俗語も何でも教えた。それが自然な成り行きだったのだ。周囲に中国語や英語しか理解らない人がいる時は子供達に対しても自然に幼児中国語や幼児英語が出て来るのだが私と子供達しかいない時は、自然に東京弁になっていた。長男は、6歳頃から(はっきり覚えていない)日本語に対してもかなり英語で答える様になったがそんな時でも、私からの発話は全て東京弁なので話している途中で、いつの間にか日本語にシフトする事も少なくない。また、話の内容によって英語と日本語を使いわけている。もうじき5歳の次男は、まだ、家族の誰に対しても日本語が主だ。(続き)
February 13, 2004
コメント(7)
-
多言語育児&幼児英語教育への提案(1)
【多言語育児の悩みと提案1(コミュニケーションの為の第二言語習得方法3)】第二言語の習得には、臨界期がある、と言われている。ある一定の年齢を過ぎると完璧に習得する事は不可能だとする説だ。日本では、これを悪用した「英語商売」が盛んな様だ。「○歳では遅すぎる!」初めて子を持った親にとって、こんなに焦る言葉は無いだろう。ましてや、日本には、英語コンプレックスを持つ人が少なくない。自分がこんなに苦労した英語の習得(あるいは挫折)過程を我が子には味合わせたくない...自分には届かなかった夢を子供に与えてやりたい...そう思うのは自然な親心だ。だが、どうも、ネットで聞いたり眺める限りでは日本の英語商売は、本当に玉石混交で(石の方が多い?)なかには悪徳としか思えないものもある様だ。海外在住者の集まるサイトの掲示板では日本の英語熱に向けて警鐘を発する声が高い。そして、その海外組の警鐘に対して、「英語に触れる機会が高い有利な位置にいる人達には理解らない」という日本在住組の反発もあるのだそうだ。双方とも、もっともだと思う。海外に住み子供に苦労しながら日本語を教えている日本人には悪徳英語商売の売り文句がいかに「嘘八百!!!」であるか自らの体験から「一目瞭然」である事が多い。バイリンガル環境など多言語環境にある家庭にとっては第二言語どころか、第一言語の確立でさえ大変なのだ。日本語ネイティブである日本人親が一緒に生活しながら教えていても日本から離れて暮らす子の日本語は、維持するだけでも一苦労なのだ。日本で英語を教えるのは、海外で日本語を教えるよりも悪条件である事の方が多い。それが、悪徳商売の大胆な宣伝文句の様に「ちょっとやそっと英語の幼稚園や塾に通ってネイティブ並みになるはずがないだろっ(そもそも、幼児のネイティブ並みって....??!!)」「英語ができない親がネイティブ並みの英語力を持つ子を家庭で育てられるはずがないだろっ」「どんな高額でも学習教材中心でネイティブ並みになるはずがないだろっ」「そんな事より、肝心の日本語はどうするんだよっ」.....等々、自分自身の普段の苦労も重なって、つい「目を覚ませよ~っっっ」的発言となってしまいがちだ。だが、日本で精一杯、英語を、と頑張っている親にはその発言は「おせっかい」「上から見下げた意見」と聞こえるるのではないか?そもそも幼児に英語学習・英語育児を実行している親は親でやはり玉石混交(...と人を評するのは失礼なので言い替えると)各人各様の事情があるのに、海外からくる批判は時として「全ての日本で子供に英語早期教育をしている親」に向けて一般論として発されがちな印象を与える。これでは、「海外で日本語」と同様の真剣さと知識を持ちながら「日本で英語」と努力・試行錯誤している親は苦い気持にならざるを得ないだろう。しかし、駐在員家庭や帰国子女や国際結婚家庭は内情を知らない第三者から自分達の置かれている(いた)環境を気軽に見当違いに「うらやましがられ・ねたまれ」たり、苦労と努力の成果を自然の成り行きの如く軽視される事が少なくない。特に、学校や家庭で常に現実と直面し、時には親からの理解も得られず何とかがんばる以外には選択肢も与えられない子供達にとって「外国に住んでいたから・親が外国人だから」外国語が喋れると、うらやましがられたり、ねたまれたりするのは怒り・我慢・絶望(・その他もろもろ)の限界への挑戦かもしれない。もっとも、よく理解っていない人から「大変ね~」と妙に同情されるのもまた迷惑なんじゃないかと思うが....。だから、多言語環境の波にもまれながら生きて来たという意識が強ければ強いほど「必要性が無いにも拘わらず」多言語教育を選んだ家庭に対し複雑な心境が生まれるのは無理も無い。真面目に多言語教育に取り組む家庭はともかく脳天気に悪徳英語商売の宣伝文句を信じている親を見たら思いっきりカツを入れたくなるだろう。悪いのは、悪徳商売人で無邪気な親じゃないとわかっていても..だ。だが、反目し合う可能性があるのは「海外組」と「日本組」の組み合わせだけではない。海外組には海外組なりに「派閥」ではないがそれぞれの事情によって、自他ともに細かく分類され他グループに対し、時には、排他的な感情を持つこともある。例えば、日本語補習校。これは、基本的に、海外駐在員家庭の子供が日本人学校以外の学校(現地校=その国の学校や国際学校)に通う場合、日本に帰国した際、日本の学校へついて行けるように土曜日に、日本の学校に即したやりかたで国語を教える学校だ。国によっては、算数や理科まで教える学校も少なくないようだ。そして、時々、海外在住者の参加が多いネット掲示板で、話題にのぼるのが、この補習校での「駐在組」と「永住組」の静かな対立だ。(実際には、たとえ表面的だけでも、仲良くやっているんじゃないかと思うが....)どうも、自分達で選んだわけでもないのに命令で就学児童をかかえながら外国に駐在させられその期間さえ定かではない事が多く、帰国したら帰国したで、金銭的余裕があり他の道を選べる家庭以外は確実に日本の受験戦争に巻き込まれる....そんな駐在員家庭にとって「日本へ帰国する予定も無いのに」「日本語が得意でない子供を無理に補習校に入れて」「補習校のレベルを下げる」永住組、特に国際結婚家庭は、疎ましい存在らしい。(この傾向は、中学受験を控えた小学生を抱える家庭に強いようだ。)手結川家の子供達は、週末中国語学校に通っているのでロンドンの補習校とは縁が無く、友人から小耳に挟んだ情報しかないがここでは、確か数年前、補習校の本校(?)とは別に「国際部」が設けられた。(↑現在も存続しているかどうか詳細不明。)日本語を、読み書き以前に、まず満足に話す事どころか少数だが理解する事さえできない子供達には本人にあった教え方で日本語を習得させるべきだという考えで生まれたのだと思うが、その設立には将来の帰国に備えて真剣に勉強せざるをえない子供達の邪魔をしないでくれ、とい隠れた本音がありそうだ。しかし、もともと、子供を補習校に通わせる国際結婚家庭にとっては日本語を母国語とする日本人の子から刺激を受けさせたり子供達どうし日本語を使える環境を与えるのが目的でもあるため日本語のできない(あるいは達者でない)子供達が集まる国際部はいまひとつ人気が無かったらしい。また、現実的に、補習校へ通わそうとする国際結婚家庭の子供が日本語を理解できないくらい日本語初心者であることは少なく幼稚園・小学校入学レベルでは、まだ、なんとか日本人家庭の子についていくことが可能だという印象を与えることもその理由のひとつだろう。もちろん、以上に挙げた例とは異なり異なる言語環境にある家庭が情報交換する集まりも、たくさんあるのだが(その方が多い、と思いたいが)異なる言語環境にある家庭間での交流が少なかったり、利害関係が複雑に絡んでくるとお互い排他的・反目的な印象を抱くこともあるのではないだろうか。だが、海外での日本語教育・育児、日本での早期外国語教育・外国語育児にせよ出発点が「親心」であるところ習得させたい言語に子供が触れる時間も体験も限られているところなど、共通点はたくさんあるのだからお互いの意見を交換する事は大変良い刺激になるはずだ。同じ環境にある家庭の体験談の方が、より具体的で即効的に役立ったり、励みになるのは事実だと思うが異なる環境にある家庭の体験も、実は、非常に参考になる。うらやましいと思ったり、お気楽と思ったりした他グループにもそのグループ独自の悩みがある事に気づくだけでも大きな収穫だ。☆☆☆さて、ここからは、まず、多言語育児について個人的体験から生まれた提案を書かせていただこうと思います。(↑つまり、専門的な意見では、無いという事です。^^;)ちなみに、ここで、「多言語育児」と総称するのはバイリンガル育児・バイリンガル教育・早期外国語教育など....幼児・小学生を対象にした、学校教育ではない、家庭や塾中心の育児や教育のことです。☆☆☆多言語育児を考えている人に、まず、提案したいのは「臨界期論(○歳までにやらないと習得できない)」に、惑わされない事と子供の人格を尊重するという事だ。母国語以外の言葉を導入するのは何歳でも構わないと思う。生まれてから、すぐに始める方が反抗期に入ってから始めるより楽だろうが何歳だから手遅れという事は無い。逆に、国際結婚などで海外に住み、子供に日本語を教えたいと思っている人は赤ちゃんがおなかにいる時から(特に妊娠後期)日本語で話しかけたり、日本語で本を朗読したり意識的に日本語で話す機会を多く設けると良い。臨月の胎児は、母の声、母の言葉を聞き生まれた時点で、母の声だけでなく、母の体内で聞いていた母の言葉(語感・リズム感など)つまり母国語を認識して反応するそうだ。もっとも、胎児時代話しかけていなければ駄目、というわけでは全く無い。多言語育児は何歳からでもできる。ただ単に、子供の年齢が大きくなればなるほどより多くの工夫と努力が必要になるだけだ。だが、この外国語の導入で注意が必要なのは、母国語以外の言葉を導入する場合だ。親が、語感・発音を完全に把握していない言語を「無闇に」乳幼児に話しかけるのは、やめた方がいい。周囲にその言語の話者がいない場合は特に要注意だ。親にとっての外国語を導入する場合は子供が、「いつも使っている・聞いている言葉とは違う言葉だな」と意識できるような「特別な時間や状況」を作って耳だけでなく、体全体で、その言葉に触れられるようにしたら良いと思う。英語の導入に関しては、私のお勧めは「Nursery Rhymes」だ。 「Nursery Rhymes」とは、韻をふんだ児童詩(詞)のことで民間伝承も創作もある。日本ではマザーグースが有名だ。児童詩といっても、古い「Nursery Rhymes」には、歴史的背景の濃いかなり残酷な内容の歌もあるがここでは、深く意味を考える必要は無い。これは、まず、韻を楽しむものだ。この韻が身についていると、英語のリズム感だけではなく将来、スペルを学習する時にも役に立つ。この「Nursery Rhymes」が朗読されたCDを子供を抱っこし、韻に合わせて体を動かしながら聴いたり時には、声を出して部分的に繰り返したりしては、どうだろう。「Nursery Rhymes」には手遊びが入っている事もあるのでDVDやビデオで楽しむのも一案だ。小学生や幼稚園児が先生と一緒に「Nursery Rhymes」を朗読したり歌ったり遊んでいるようなDVDも英国では、たくさん出版されている。日本でも、同様のDVDやビデオは製作・発売されていると思う。DVDやビデオでの場合も、やはり、子供一人で見るのではなく、親が一緒に体を動かし、ところどころで反応・反復しながら楽しむのが重要だ。英国の児童教育に関する本でも「Nursery Rhymes」は「読み書きの基礎」となる、と強調されていた。小さい時に覚えておけば将来的に非常に役立つと思う。(続き)
February 10, 2004
コメント(19)
-
【外国語学習方法☆提案】コ(略)第二言語習得方法☆晩期編2
【はじめに】以下に書く習得方法は、一提案にすぎません。最も重要な事は、飽きずに続けられる自分にあった学習方法を自分で見つけ出す事です。特に英語圏に現在お住みで英語ができないと悩んでいらっしゃる方にお伝えしたい事があります。「英語が出来ない=頭が悪い」のでは決してありません。英語ができないのは、集中して英語を聴く時間が足りなかったり選んだ学習方法が自分に適していなかったり英語圏に住んでいても英語を使う必要が無かったり人の目を気にし過ぎていたり.....と様々な理由からです。とにかく、集中して「聴く」時間・口を慣らす時間(音読など)を短時間でも良いから毎日設けられる様な生活を意識的に過ごし、実際に英語で話す時は、人に笑われる事をおそれず、むしろ、笑われたらネタ獲得くらいの広い心とサービス精神を持つ事、堂々とした態度・大きくハッキリした声と発音で一つ一つの単語よりも文全体のリズム感・イントネーションに留意しながら話す事、自分で英語表現を考えて作るのではなく聞き手が慣れている常套句(常用表現)を暗記し活用する事.....等を常に心がけていれば必ず英語は上達します。☆☆☆さて、言語は(なんらかの障害がある場合を除き一般的に)「聴ける→話せる→読める→書ける」の順に習得される。よく、英語は読めるが話せない、という人がいるが日本人で英語会話ができない人の言う「読める」はおそらく、機械的な「読解・暗号解読」にとどまると思う。文学作品を「読む=理解する=堪能する」為には「会話」ができる事が前提だ。文学作品でなくとも、例えば、電子メールの文章でさえ会話(=口語)ができなければ正確な理解は難しいだろう。よって「聴ける」事は言語習得の基礎となる。聴けなければ喋れないし読めないし書けない。それなのに、この「聴く力」は、意外に軽視されている。それは、「聴く」のが、難しいからなのではないだろうか。私は、小さい頃から短波ラジオが趣味だったので自分の理解できない言葉を長時間聞くのが苦痛にならない。しかし、理解のできない言葉を長時間どころかちょっと聞くだけでも我慢できない人もいるだろう。そんな人が、「聴く」訓練を続けるのは至難の技かもしれない。このタイプの人は、ダラダラと外国語のラジオを聴いたりせずまず、日本語と外国語の短文・単語が代り代り入っているフレーズ集の様なCD等を集中して聴くべきだ。(↑単語だけのCDは、語感がつかめないので駄目。)集中できる時間には個人差があるから、自分が集中できる「限度」まで、やればいいと思う。毎日、何分・何時間ではなく、その日、その日の「自己限度」までやる。これは、外国語を聴くのが苦にならない人も同じである。同じ内容を示す短文をわかる言葉とわからない言葉で聴き細かい発音の習得の為に単語を両方の言葉で聴く、この繰り返しを自己限度までやる。そして、同時に、息抜き的に、ラジオを聴いたり映画やテレビを見たりすればいい。英語に関しては、Nursery Rhymes(マザーグースの様な韻をふんだ詩・詞)や詩の朗読を聴き英語の音を楽しめる事ができたらもっと効果的だと思う。とにかく、この繰り返しを限度まで続ける。一週間だろうが一ヶ月だろうが文字無しで聞けるところまで続ける。この文字無しの状態に、どうしても耐えられなくなったらそこで、あきらめては、全ておじゃんになるので文字を導入するしかないが、文字の段階に入っても聴く訓練は必ず続ける必要がある。文字の導入は、自分がCDで聴き続けたフレーズ本を読む。その読み方には方法がある。まず、一通り、わかってもわからなくてもざざぁ~っと早い速度で目を通す。これも、自己限度が来るまで、何度も、早い速度で繰り返して読む。この繰り返しは多ければ多いほど効果的だがもう飽きてどうしようもなくなったら、日本語の意味を読んでから、ゆっくり読む。このまま読み続けてはいけない。1ページなり、1章なり、自分で把握できる「まとまり」で切って同じ部分を、また、聴く。読んだら聴くを繰り返す。その後、CDについて真似して発音する。これを繰り返したら、今度は日本語の意味を見てから、学習している言語で答える(発音する)。そして答えを聴き、また、繰り返す。この繰り返しを毎日(たまに休んでもいいが....)自己限度まで繰り返しているとある日突然、ラジオや映画・テレビの言葉が、すんなり理解できる様になる。その段階に到達したら、今度は、フレーズ本を卒業して自分が興味を持っている分野の本(CD付き)を探す。探すといっても分野によっては不可能だったりと、なかなか難しい。なんとか付き合えそうな内容のもので妥協するしかないだろう。そして、まず、その本を自己限度まで聴く。長さにもよるが、始めから最後まで通して聴いてもいいし同じ所を繰り返して聴いてもいい。とにかく、何日、何週間でもいいから、文字無しで聴ける所まで聴く。その後、文字を導入する。その時も、フレーズ本と同じ要領で、1段落ごと、あるいは1ページごとに切り、最初は、意味を考えずに、すばやく読む。これを何回も繰り返した後、我慢できなくなったら今度は、意味を考えながら、ゆっくり、辞書をひかず、通して読む。これを、また、何回か繰り返す。そして、それも我慢できなくなったら、はじめて全体の意味を調べる。辞書をひくのが嫌いな人も少なくないので最初から対訳がついたものを選んだ方が便利だと思う。そして意味が把握できたら、また、同じ部分(きりの良いまとまり)を聴く。読んだら聴くを繰り返す。その次に、発音にうつる。まず、まとまった短い文章を聴いて真似して発音する。それを繰り返したら、今度は、自分で発音した後に当該文章を聴いて、どこが違うか比べてたら、もっと効果的なのだが、この練習は、この段階ではしなくても良いと思う。場合によっては(必要に応じて)、ここで書く練習を導入しても良い。書く練習は、まとまった文章を音読した(或いは聴いた)直後文章を見ないで書き、照合訂正を繰り返す。(書くかわりにコンピューターに入力しても良い。)ところで、以上に書いたやり方で、一番の問題は、かなり退屈になりがちな事だ。だから、毎日、少しずつ長期間とは考えず習い始めで興味がある時に「短期集中」した方がいい。また、日本人の英語の様に文法知識や単語の基礎が十分にある言語については、「フレーズ本の次の段階」から始めても良いと思う。以上の訓練の後、聴く力に少し自信がついて来たらラジオを集中して聴く、映画・TVを楽しむ等日常生活で楽しみながら聴く練習の開始だ。これも、短時間徹底的に集中して聴く時間と「ながら聞き」の時間と、単に楽しむ時間とを交互に取り入れて、とにかく、長時間聴く。聴けば聴くほど良い。(徹底的に集中して聴く時間が多くなればなるほど効果がある。)聴く力がかなりついたら、今度は口を慣らす練習だ。私が実際に行なった練習はドラマ等見ながら役者の真似をしてセリフを言ったり(↑DVDが普及した現在では非常にやりやすい練習だと思う。)新聞の短いコラムや占いや相談のコーナーの音読だった。(↑最初は、一通り素早く目を通した後、熟読してから音読する。)(↑意味が一目瞭然で理解出来る様になったら音読のみで可。)余談だが、音読については、私は今でも毎日短時間だが練習している。英語を日常的に使う様になって20年になるが、それでもこの音読を欠かすと、口がうまくまわらない気がする。☆☆☆最後になるが、言葉の上達には「使う」事が重要だという意見を時々耳にする事があるのだが、これには若干の疑問を感じる。「使う」必然性から、言語学習への動機が高まったり、真剣になったり、場慣れする、という利点は、確かにあるし、英語圏に住み、英語の基礎が十分あるのに喋れない、と感じる人は「使う」事によって進歩すると思う。だが「使う」で注意したいのは、「使う」事の必然性だ。「練習」の為に、相手の意向も考えず外国人に話しかけたり「練習」の為に外国人を含むサークル等に参加する...これでは、主客転倒ではないだろうか。外国人に話し掛けたり、サークルへ参加する事は外国語を話す為という練習目的ではなく、意見交換をしたり、日本・地域の情報や文化を紹介したり不慣れな状況で困っている人を助けたり....等言語を超える内容があってこそ行われるべきで同時に相手への尊重が欠かせないと思う。そして、この相手を尊重する事こそ、コミュニケーションの基礎なのだ。(続き)
February 8, 2004
コメント(23)
-
【英語の悩み】コミュニケーションの為の第二言語習得方法☆晩期編1
今日は、部室で、うめ八師匠からリクエストのあった(?)「英語の勉強方法」について書こうと思います。英語以外の言語にも通じる内容であり、外国での母国語学習や幼児の外国語学習についても書く予定なので【コミュニケーションの為の第二言語習得方法☆晩期編】という長ったらし~い題を付けました。また晩期というのは、幼児外国語教育が早期なら臨界期を過ぎれば「晩期」か?との、勝手な個人的命名ですので、どうぞ、ご了承を(^^;)。☆☆☆さて、よくネットで「英語圏に何年住んでも英語が喋れない」という日本人の悩みを読む。これは非常に孤独な悩みだ。同じ立場にある人以外には理解してもらえないからだ。日本には英語に対して苦手感・コンプレックスの強い人がたくさんいる。でも、そんな人達でさえ、無意識・有意識のうちに「外国(特に英語圏)に住めばうまくなるのに~」と信じている事が多く「英語の国に住んでも英語が喋れない人」っていうのは「アタマ悪い・なまけ者・社交性ゼロ...等々」なんじゃないか?と思いがちなのだ。「そうか、世の中、甘くないんだな~」と思う人もいるだろうがそんな人でさえ「私が同じ状況だったら、もっと努力してる...」と密かに思ったりもするんじゃないだろうか。冒頭の悩みを抱えている人も、日本を出るまでは、同じ様に考えている事が多く、だからこそ「もう何年も住んでいるのに、まだ喋れない」という心理的圧力をさらに強める事になる。そして、この悩みには、さらにヒエラルキーがあって、海外移住の理由が駐在の人は永住の人を密かに「見下し」、永住でも、日本人夫婦の人は、国際結婚の人を密かに「見下し」国際結婚でも、配偶者が日本語を喋れる人は、配偶者が日本語ダメなのに英語を「まともに」喋れない人を「見下す」。ここで、「見下す」と書いたが、実際には軽蔑感情を持つ事は少なく、むしろ、表面的だけでも、「私も英語だめなの~」と、お互い、和気藹々とした雰囲気で慰め合っているのではないかと思う。ところで、対象となる言語が英語以外の場合、この様な圧力は減る。英語は、なんといっても、学校で何年も勉強した言語だ。全く一から始める言語でもないし、一般的に大変に難解というイメージのある言語でも無い。だから、余計に、できない事がコンプレックスとなりやすい。しかし、このコンプレックスほど、語学習得の邪魔になるものはないのだ。コンプレックスは捨てようと思って簡単に捨てられるものじゃない。どちらかと言えば、時とともに、自然に消滅しているものだ。だから、コンプレックスを捨てろ、とは言わない。だが、コンプレックスがあるなら、それを利用して「お笑い芸人」になるべきだ。*******英語が苦手で悩んでいる皆様(海外・日本在住を問わず)英語ができない事で笑われたら、笑いを提供した自分を誉めましょう!英語人にとって、あなたのコンプレックスなんて、どうでもいい事なんです。英語人にとっては、意志の疎通を図る=目的を達成する事が第一です。英語人が見たいのは「びくびくした自信の無い暗い顔」ではなく「明るい笑顔」です。*******一旦「お笑い芸人」となったら、今度はもっと笑わせたい...という欲が出てくる。そして、英語人をもっと「意図的に」笑わせる為には、英語学習が欠かせないのだ。これが、やる気につながる。実は、私が英語を真剣に学習しはじめた発端もこの「お笑い芸人根性」だった。晩期第二言語習得には「完璧」に到達するという状態は無い。常に向上心を持ちながら訓練し続ける、という永遠に続く道程だ。私の英語は、既に、コミュニケーションには全く問題が無い。時事問題でもゴシップでも病院でも、全く困らない。英語の本も、かなり専門的な本でもスラスラ読めるし書くのにも全く困らない(いまだにスペルは苦手だが...)。こう書くと自慢している様にも聞こえるが(また、同時に、そう聞こえる事がコンプレックスの顕れなのだが)「私の様に、晩期から英語を始めても、この程度には絶対なれますよ!」というつもりで、私の「現況」を書いている。そして、私は母国語である日本語であれ、第二第三第四..言語であれ言語学習は、死ぬまで現在進行形として継続するつもりなのでこの現況は、あくまで現況に過ぎない。現在、私の英語は、コミュニケーションには全く支障が無いが完璧からはほど遠い。発音はネイティブではないし、書く時には間違わない様な文法も会話で間違えたりする事もあるし咄嗟に言われたウィットに富むセリフが聞き取れない事もあるしそんなウィットに富むセリフも、なかなか咄嗟に出で来ないし語彙に関しても、俗語や子供独特の言葉、専門用語など毎日、新しい言葉が出てくる。先行き長いのである。でも、まだ、できない事がたくさんあるからこそウキウキ・わくわくする。もう、生きてるだけで楽しい、という状況である。ただ、ここまで、言葉を楽しむ「境地(というのもなんだが)」に到達しない人、というか、到達する必要の無い人もたくさんいる(むしろ、その方が多い?)と思う。生活に支障の無いレベルに到達すればいい日常会話ができる様になればいい本や映画が楽しめる様になればいい...等々目標地点は各人各様だが目標は、どうであれ、習得方法は共通しているのだ。☆まず、第一に、言語習得の際、絶対忘れてはならないのは「学習する言語の背景にある文化や歴史を尊重する」事だ。愛せれば尚良いと思うが、愛せなくてもいいが尊重し、理解しようとする努力は必要だ。それができないのなら、その言語を学ぶ必要は無い。その言語や文化とは、しょせん、縁が無かったのだ。生きる為に、ある言語が必要となる場合もあるだろう。でも、そんな最小限の目的に達する為にもある言語を生み出した背景への「尊重」をしてほしいと私は思う。特に、英語は、世界共通言語として、一つの「道具」の様に扱われる事が多い。だが、英語は、英国の歴史の中で英国人に育まれて来た、生きた、肉も血もある、言葉なのだ。単語や表現は言うまでもなくアルファベットの文字一つ一つにも長い物語があるのだ。それは、日本語と同じである。語学に対するコンプレックスを打破する為に言語を道具とみなす様な学習方法もあるかもしれないが基礎に尊重の精神が無ければ長く学習し続ける事も、本当に理解する事も難しいと思う。(続き)
February 7, 2004
コメント(14)
-
何故「糾弾」に反対するか(続)&人権
*2月2日付・日記「虐待・糾弾ではなく認識を」続編**「何故、私は、犯罪者への糾弾に反対するか?」*加害者の罪が軽すぎる、現在の法律は被害者よりも加害者を優遇している、という様に一般市民の「不公平感」が強くなればなるほど加害者と家族に対する一般市民からの糾弾社会的制裁は強まるものだと思う。実は、英国でも、一般市民の「不公平感」が加害者への「糾弾・制裁」を強くしている。私も、感情的には、この不公平感を味わう事が多い。本当に一見すると信じられない話が多いのだ。例えば、3年前・去年と新聞で大々的に騒がれた、この事件と顛末。場所は、英国の農村。何度も自宅である小さな農場が盗難の被害にあった一人暮らしの農民がついに強盗二人を撃ち、一人を射殺、もう一人を負傷させた。結果的に農民は4年の実刑で服役し、生き残った方の強盗は、別の犯罪で、農民と同時期に服役したがちょうど農民より一週間前に出所となった。この事自体もかなり一般市民の神経を逆なでする事になったのだが大反響を呼んだのは、その後だ....。その強盗(前科何百件!のふだつきチンピラと新聞に書かれていた)は、農民に足を撃たれ負傷した事によって精神的トラウマを負った・性生活に影響を及ぼした...等肉体的障害は殆ど残っておらず全て精神的影響なのだが日常生活に支障をきたす様になった事に対して農民に賠償金を要求するという、民事訴訟を起こしたのだ。しかも、本人に収入が無いので国税を使っての訴訟だ....。(↑最終的に訴訟を取り下げたか進行中かは不明)(この強盗は、犯罪以前以後、続けて生活保護を受けているらしい)全く悪夢の様な成り行きなのだが、この事件で、私が一番怒りを感じるのは、何よりも、警察だ。農民が何度も保護や調査や対策を依頼していたのに全く、なんの対処もしなかった。「人が死ぬまで門を出ない」と揶揄されて仕方が無い。「軽」犯罪に対処する「余力」が無い警察の現状を公的に嘆いていた。もちろん、当時の警察の処置に対して警察内部で「厳重な調査」が着手されたが、その調査結果は、どうなったのか、結果が出たのかどうか、事件自体ほど騒がれていない。(いつも、大体、こうなる。)もちろん、全ての英国警察が、おそまつなのではなく地域差も大きいのだが...。同時に、現況に対処しきれていない役所や制度・政府にも強い怒りを感じている。例えば、現在の英国の福祉制度を見るとどんなに規制や制度を改正してもその抜け穴に突進して悪用する犯罪者は後を絶たないのに抜け穴を最初から仮定して柔軟性のある制度を作る事がなかなかうまく行っていないしどうも各役所・機関の協力体制が整っていない、というか、最初っから、違う役所どうしが協力する気が無いんじゃないか?と感じる事が非常に多い。「学習困難」関係の本の大部分でも、各公的機関及び研究者どうしの連帯活動や協力意識の乏しさが大きな問題点として挙げられていた。このあたりは、日本でも、随分、状況が似ているかもしれない。私的には、この農民が執行猶予を与えられず実刑に服したのは間違いだったと思う。彼には、隔離される必要は無かった。彼は、一般市民にとって危険な存在では無い。自分自身の財産、そして、生命に危機を与えられた事がこの事件を引き起こした。もし、適切な保護を受ける事ができれば刑務所で管理される必要は全く無いはずだ。実は、この強盗二人組みはジプシーでそれが、今度は人種差別問題をも引き起こしすったもんだ状態にもなってしまったのだが農民出所後、射殺された強盗(ティーンエイジャー)の一族が「仇を討つ」と公言した為、この農民と彼の小さな農場は、現在24時間体制で警察に保護されている。じゃ、最初から、刑務所に入れず、自宅で警察が24時間体制で警備(実質的には軟禁?)しても良かったんじゃないか.....とも思うのだがおそらく警備にかかる予算「殺害された加害者兼被害者」の家族への配慮人種差別判決と糾弾される事への危惧?純粋的に法律的問題(過失殺人に対する刑罰の規定)等、様々な要因が絡んでか、4年の実刑判決となった。(規定により、実際に服役したのは2年だと思う。)この判決は、農民にとって、不公平だったと私は今でも思っている。だが、当時、ラジオの討論番組やタブロイド版(大衆)新聞の投書欄で「強盗は射殺されて当然」という意見がさすがに少数派なのだが、出て来た時には非常に複雑な暗い気持になった。裁判でも、農民に強盗を殺す意志があったか故意か過失か自己防衛かという点が焦点だったのだが、その際も「英国人の家は城。城を守る為には殺人も仕方が無い」という意見も結構多数出て来て、それに対しても複雑な気持になった。気持は理解るのだが、どうしてもこの感情が野放し状態で社会的制裁につながる事に莫大な危機感を持つのだ。この危機感・危惧は、ちょっと体罰に関する複雑な思惑にも通じる。どこまでが、しつけの体罰で、どこからが虐待か?体罰は、どれもが虐待へ発展する可能性を秘めているのではないか?....という思惑だ。犯罪者への社会的制裁で、一番私がおそれているのはこれが犯罪者の家族への社会的制裁に発展しやすい点だ。犯罪者の家族も、ある意味、被害者なのである。世間からの制裁が厳しい社会では、完全に被害者になる。これは、絶対に間違っていると私は信じている。だが、犯罪者の糾弾として湧き上った強い感情は時として方向を失う。人の命、特に児童の命が犠牲になった事件では冷静さを保つ事は、非常に難しい。こんな時は、普段、ちょっと悪い事をしている様な人にも正義感が沸き上がり、犯罪者を糾弾せずにはいられなくなったりするものだ。刑務所で小児事件の服役者が他の服役者に襲われたりするのはこの一例だと思う。だから、普段から、辛い環境でもまっとうに精一杯生きているという自負感を持つ人だったら強い怒りを感じるのは当然至極の事なのだ。しかし、私は、ここで、冷静さを失ってはいけないと思う。まず、犯罪者を糾弾する事に、どんな建設性があるだろうか?私が、まっさきに思い付くのは「見せしめ的効果」だ。「こういう罪を犯すと、こういう末路が待っている」というものだ。公開処刑は、この目的を持っている。だが、現代社会、というより、具体的に、英国や日本でこの「見せしめ効果」が、どれだけ犯罪の発生を阻止しているのだろうか?自分のしている事が犯罪だと認識しながら犯罪に走りざるを得ない犯罪者の方が多いのではないか。この走りざるを得ない、という所には大きな個人差があって処々の事情で、不本意ながら犯罪に至るという、世間の同情をかいやすい犯罪者から徹底的に自分さえ良ければいい、という倫理観念、公共道徳意識に全く欠如する犯罪者まで含まれるのだ。これだけ、多種多様の犯罪者を糾弾する事によって犯罪の成立が防げるだろうか?私の答えは否だ。私は、いくつもの数字が組み合わさって金庫の錠が開く様にいくつもの要因が組み合わさって犯罪の発生に結びつくと考えている。この要因の中には犯罪者の「人としての弱さ」等、犯罪者自身の内的要因も入っているが公的手段・制度の確立で防ぐ事が可能だと私が信じて止まない外的要因の占める割合が非常に高いのではないだろうか?だから、犯罪者の糾弾よりもまず、コントロールできるはずの外的・環境的要因を押さえ、新たなる犯罪の発生を事前に阻止する、これが、何より最優先だと思うのだ。一方、犯罪者の人権は、どうだろう?冷静な状態にある人であれば犯罪者の家族の人権が保護されるべきでありそれを侵害する事は、新たな犯罪である、という事が容易に理解できると思う。だが、犯罪者自身の人権は?犯罪者の人権も守るべきだ、と心の底から言う為には、かなりの冷静さ、無関心とも誤解されるほどの冷静さが必要とされるのではないだろうか。でも、犯罪者にも人権はあるのだ。人権は、人を問わない。人権は罪を犯したから奪われる物ではない。罪を犯さず、まっとうな人生を歩んでいる事に対してご褒美として贈られる物でもない。人権は、人と共に発生するのだ。被害者の人権と加害者の人権は相反し拮抗する。この二つの人権のバランスをとる為に加害者に対する社会的制裁は起こるのだとも思う。被害者の人権の侵された分だけでも加害者の人権は侵されなければどうしても不公平感はぬぐいきれないのではないか?被害者が殺された場合、被害者の人権は全く否定された事になる。その場合、加害者の人権も全く否定されるべきだろうか?この人権と人権の衝突を解決する事は非常に難しい。それは、冷静さを失っている時にはできない作業だ。一歩間違えると、人権という概念そのものが危機にさらされる綱渡りだ。犯罪者への感情的「糾弾」は、この綱をゆらすものだ。だが、ゆらすべきなのは綱ではなく、社会の土台自体ではないのか?実は、この加害者と被害者の人権の衝突の解決に関しては私の考えはまとまっていない。今まで「冷静さ」を主張して来ながらこんな事を言わざるを得ない自己の未熟を恥じるが正直に告白してしまうとこの件に関して、現在の私は心に従っているのではないかとも思う。息子が生まれた時、私は、私が生んだ命だと思った。でも、今は、そう思わない。この命は、私の体を通して生まれて来た、と思っている。子は親に与えられたのではなく親に預けられた。親は、子の誕生と共に発生した人権を大切に保護しながら、社会に返還する。その繰り返しで社会が継続して行く。人権は未来そのものだ。そんな事を私は肉体的に親となった後精神的に親となっていく過程で考える様になった。子供がティーンエイジャーとなり体格的に大人と変わらなくなっても子供には子供なりの幼さがある。そんな幼い体、自分の子供達だけでなく社会中の子供達の幼い体その中に、小さくともった火、それが、現在の私にとっての、人権なのだ。そして、そんな小さな火を消さない様に小さな火が大きな未来に結びつく様に守って行く事それが、私の社会人としての使命、責任だ。だからこそ、その小さい火を守る為にも冷静さを失ってはならない、と、私は考えるのだ。
February 5, 2004
コメント(12)
-
母を憎む兄・つぐないの育児
以前日記にも書いたが、私が17歳の時に亡くなった母は私にとって最愛の人だ。故人だから、こう言えるのかもしれないが...。しかし、同じ女性を母とする兄は、母を憎んでいた。母が兄を憎んでいたとは思えない。(兄が本当に母を憎んでいたとも私には思えない。)だが、この二人は、とにかく仲が悪かった。記憶にある限り喧嘩が絶えなかった。母が亡くなった時、兄は葬式にも帰って来なかった。それでも、母の死後(それも十何年もたった後に)兄の口から母への憎しみを聞いた時、私は驚愕した。兄は、母も兄を憎んでいた、と断言する。既に親になっていた私は「そんなはずないよ。子供を憎む親なんていないよ。」と言った。兄は、ちょっと考えて答えた。「そうかもしれない。お前が生まれるまでは可愛いがってくれたと思う。」兄は続けた。私が生まれてから、母は私だけを愛していた...母にとって兄は邪魔な存在だった....と。兄は、心の病で入院している。もう二十年以上になる。子供時代は、おそらく、今は随分認識の高まってきた「学習困難症」の影響を受けていたかもしれない。父によると、学校から何回か、専門医に見せてはどうかと助言されていたのだが母は断固として拒否していたらしい。兄は確かに、少し変わっていた。歴史の年号や人名、図画等に対する記憶力は非常に良いのに学校の勉強は全くできず、活動的でもなかった。また、子供の頃は、近所のおさななじみと仲良くしていたのだが学校では、友達と、うまく関われず、いじめられる事もあった。私とは5歳近く違うので子供時代の兄の記憶は殆ど無い。全て、父が語った事だ。父によると、兄は、5歳まで、明るく活発で頭も良い子だったらしい。それが、二階に干してあった布団とじゃれて庭に墜落してから(無傷だった)頭がおかしくなった...と父は信じていた。5歳。そうか...私が生まれた頃か....。私が兄と同じ小学校に入学してからはしょっちゅう先生や上級生から比較された。実は、近所の人による比較は、その以前からあった。兄は、大人しく、目が大きく睫毛が長いというちょっと女の子の様な可愛い顔をしていた。反対に、私は、暴れん坊で、常に反抗期で育てにくい幼児であっただけでなく協調性も無く、幼稚園を中退するはめになっていた。その為、周囲の私達兄妹に対する評価は、常に「男と女が逆だったら良かったね。」今だったら、こんなセリフ、心の中で思ったとしても親でも口に出さないんじゃないかと思うのだが、当時は、学校の先生でもそんな事を言うそういう時代だったのだ....。私は大きくなるにつれ兄を疎ましく思う様になった。母と兄だけでなく兄と私も仲が悪かった。喧嘩ばかりしていたのだが細かい事はあまり覚えていない。ただ、兄に関して二つ記憶に残っている事がある。一つはまだ兄が小学生で私が幼稚園の頃(か幼稚園中退後)。兄は機関銃のオモチャを私は、人形かぬいぐるみか何かをおくられたのだが武器系のオモチャが大好きだった私は怒ってゴネて大喧嘩になり、最終的に兄の機関銃を叩き壊し、兄の背中を歯形がくっきりつくくらい噛んだのだった。兄が大泣きしたのを覚えている。母に怒られたかどうかは、全く記憶に無い。だが、兄を思う度に、この事を思い出し自責の念にかられる。二人の子の親になった今、長男が、次男の無条理な大ゴネに泣かされるとまるで、その時の償いの様に長男を抱きしめ慰めている自分がいる。もう一つはおそらく兄が中学生くらいの頃。当時、友達の少なかった兄にも親友ができ(兄と似たタイプの大人しい子で趣味の話で盛り上がっていた)母も私も喜んでいたのが記憶に残っているのだが同時に、まだ、イジメっ子にもちょっかいを出されていた。ただ、それほど、陰湿なイジメという訳ではなくどちらかと言えば、ドラエモンのジャイアンとのび太みたいな感じであったらしい。ある日、その、家でも時々名前が出るイジメっ子が家に、兄を、呼びに来た。今考えてみると、たんに遊びに誘いに来たのかもしれない。だが、当時、まだ血の気の多い小学校低学年だった私は「(ばかやろー、また、お兄ちゃんをイジメに来たな)」という、おそらく兄をかばう妹の気持ちもあったんだろうが、むしろ「(てめー、うちの家族をなめるんじゃねぇ)」という、縄張りを荒された憤りで爆発し「とっとと帰れ~っ、この短足っ。」とかなんとか言いながら、そのジャイアンに二階の窓からゴミ箱のゴミをぶっかけた。(注:生ゴミではありません。たぶん、クズ紙など...)そして、相手は「なんだ、この男女(おとこおんな)、ブス~っ」とかなんとか捨てゼリフを残しながら立ち去った。実は、セリフ自体は覚えていないのだが当時、男の子と女の子が喧嘩になった場合「短足」「ブス」というのは決まり文句だったのでこんな感じだっただろうと思う。この後、兄と、そのイジメっ子の関係が悪化したかどうかは全く記憶に残っていない。が、その子が家に来る事は二度と無かった。また、この件で、感謝された記憶も、怒られた記憶も、全く無い。ただ、この事件は、周囲の「男と女が逆だったらよかった」説を強めたのは確かだ。一方兄の私に関する記憶というのは「赤ちゃんの頃は可愛かった」につきる。確かに、乳児時代の私と仲良く遊ぶ兄の写真は、当時、家にもたくさん残っていた。兄は、私が生まれた時、とても喜んでいたらしい。今は、「妹がいてよかったと思っている」と言ってくれる。でも、ひょっとしたら、毎日、薬で押さえている状態なので何とか、おだやかな言葉が出せるのかもしれない。他方、母については理解しようとはしているが、怒りを消化できていない様だ。もともと、兄の母に対する怒りと私に対する怒りとは比べものにならない。私は、単なる、要因のひとつに過ぎない。兄が欲していたのは私の愛では無く、母の愛だ。私は対象外なのだ。そして、生きている私と違い既に他界した母への感情は、どう持っていったらいいのだろう。母の私と兄に対する育児が公平であったかどうか私にはわからない。母の育児自身は、あまり記憶に残っていない。覚えているのは私の母に対する愛情と母の私を心配したり可愛がったりしている表情だ。以前、アダルトチルドレンという本を読んだ事があるがどちらかと言えば、私の母は、そのアダルトチルドレンの母の様なタイプだったと思う。だが、私は、全く、アダルトチャイルドではない。もしかしたら、母は、何がなんでも結局自分の思い通りにしてしまう私の性格を理解して全て諦めて、その事で、少しリラックスしてのんびり私を育てられたのかもしれない。自分で、こんな事を言うのもなんだが(もう大昔の事だから言うが)小学校高学年以降の私は、万事に要領が良く、学校での成績も良く明るく自信に満ち、常に母への愛を表明する子供だった。兄の育児で挫折感を味わっていたかもしれない母にとって問題児だった幼児時代を超越した後の私はある意味、「救い」だったかもしれない。それでも、母が兄を憎んでいたはずはない。母は、兄も愛していた.....と、私は信じている。じゃぁ、兄と私を同じくらい愛していたのか?との疑問には答えられない。兄をより愛していたのではないかとも思う。だが、そんな事より何より、親の子供達に対する愛は同じくらい、なんて、言葉で表現できるものじゃないのだ。比較なんてできないのだ。子への感情は親によって違うと思うから断言できない。だから、これは、私個人が子供に持つ感情だ。私は、息子達二人を100%愛している。二人への愛は比較できない。二人とも、それぞれ100%愛しているのだ。私と長男、私と次男の関係はそれぞれが全く独立した比較の対象には成りようがない存在なのだ。でも、一人一人の子供は母にとっての一番になりたいと望んでいるんじゃないだろうか。私も、そうだった。私も、母にとっての「一番」になりたかった。母の「唯一」にはなれないのが明白だったからせめて「一番」になりたかったのだ。そんな思いから、母と兄が大喧嘩をした後に見せ付ける様に要領良く母に甘える、という、かなりせこい行為もした.....。そして、そんな過去の罪悪感に対する償いを、今、私は、長男と次男の育児を通してしているのではないかと常々感じている。だから、次男が生まれた後、長男が「ママ、あっくんとコージとどっちが好きなの?」と聞き始めた時、私は、こう答えていた。「あっくんはママの世界で一番大切な宝物だよ。コージは、あっくんの為に生んだんだよ。だから、コージは、あっくんとママの宝物なんだよ。」それでも、しつこく「どっち?」と聞かれた時は「もちろん、あっくんだよ。でも、コージには内緒ね。」と答えてしまった。この回答の是非はわからない。でも、「同じくらい」と言いたくなかったのだ。長男と次男が喧嘩をする度に兄が報われなかったと信じている兄の母への愛を思い同時に、母への愛を独占したかった自分の姿を次男に見出し辛い気持になる。喧嘩両成敗と、どっちも怒って二人を互い互いに抱きしめ一体どうするのが一番いいのかと悩む。とにかく、二人に、二人とも愛しているんだと伝えるので精一杯だ。次男は、もうじき5歳。この子は、まだ「ママ、あっくんとコージとどっちが好き?」と聞いた事は無い。だが、喧嘩の際、長男が、こう言い放った事がある。「ママ、コージに言ってよ。どっちが一番好きなのか言ってよ。」一瞬詰った後、こう答えた。「あのね、手の平と手の甲と、どっちか選べって言われたらどうする? 一番とかじゃないの、どっちも宝物なの。」だが、長男は、しばらく考えた後「ぼく、手の平にする。」と表明し、それを聞いた次男は「だめ~っ、コージが、そっちなの~っ」と手の平も甲もわかっていないのに主張し二人は、また、喧嘩を続けたのであった.....。公平じゃなくてそれぞれが唯一な関係子供達に、うまく伝える事ができるんだろうか?
February 4, 2004
コメント(27)
-
「虐待」糾弾ではなく、まず認識を...
前回に続き、重い日記になりそうだ。「重い・軽い」と呼ぶのは適切ではないと思うのだがどう表現していいかわからない。どう書けばいいのかわからないけれど自省の心を持ちながら書かずにはいられない事、そんな内容の日記だ。こういう日記を書くと更新ができなくなって全く日記にならない。でも、やっぱり書かずにはいられない。虐待。虐待事件は増えているのだろうか。それとも、以前は闇にほうむられていた事件も明るみに出る様になったのだろうか。考え付く事は、明るみにならない闇に葬られた「虐待」は莫大な数にのぼっているだろう、という事。数の多さが問題なのでは無く、ひとつひとつの虐待が深刻な一時を急ぐ死活問題だという事。そして現在、この一分一秒も起きているだろうという事。人が虐待に至る時、色々な要因が絡んでいると思う。人は虐待をする生き物として生まれて来ているとは思えない。人は真っ白の状態で生まれて来る。そして生まれた直後から、様々な色にさらされその色にそまったり、そまらなかったりする。虐待事件が明るみになった時虐待者本人はもちろん、その家族(時には子供まで)にも「世間の怒り」がぶつけられる。でも、怒りをぶつける世間は、一体、何様なんだろう?殆どの人に残虐性は備わっている。残虐性を全く持たない人が存在するかどうか私にはわからないがとりあえず断定はしたくない。だが、少なくとも、私自身や、私の子供達にまで残虐性はある。ただ、同時に存在する「優しさ」や「正義感」や「同情」や...様々な「人らしい感情」が同じく「人の感情」である残虐性を遥かにしのぐ事によって残虐性が行動に移されるのを防げるのだ。もちろん環境も影響する。ストレスの多い環境では残虐な行為が起きやすくなるだろう。家庭内暴力は暴力を与える者が受ける者より力量的・立場的に優位な存在であり密室で行われるところが暴力の中でも最も卑劣だ。そして子供に対する虐待は家庭内暴力の中でも最も卑劣なのだ。でも、その卑劣さを糾弾できるほど世間は、私達一個人は、卑劣からは程遠い存在なのか?私は、自分の卑劣さを知っている。だから、自分の限界・精神的弱さも知っている。だから、今まで何とか人の道からはずれずに生きてくる事ができた。でも、これからも自分の信じる「人の道」に忠実に生きる事ができるかそれは断言できない。このまま無事、まっとうしたい、と強く思い努力しているが断言できるだけの力が自分にあるかどうか100%自信が無い。自分の弱さを知っているからだ。人は、時として、感動的な強さを発揮する。でも、同時に、悲しいほど弱いのだ。だから、人を「こうあるべきもの」と強い存在として期待してしまうのは危険だと思っている。人の弱さを「特異」とし人の強さを「当然」と考えるのは危険だ。人は弱い者という認識から発展しその弱さを補う様な柔軟だが強い制度を作る社会の方が人に強さに期待し弱い制度を作る社会より安全だ。虐待について言えば虐待は当然起こるもの虐待をする親が特異な存在なのではなく親であれば虐待に至るか虐待の一歩手前で踏みとどまるかという状況を経験する事が十分に有り得るものなのだと全ての大人と子供が認識する事、その方が、行き場の無い怒りに「はけ口」を見つけるよりもずっと難しいが、ずっと建設的だ。ひとりでも多くの人が虐待の危険信号を知って虐待されている子供を救う事(それは同時に親を救う事にもつながる)ひとりでも多くの子が虐待について知り虐待の現場から逃げ出す力を持つ事そして何よりも重要なのはその子達が逃げ出せる場所がある事危険を察知した人が危険を報告し任せられる機関がある事虐待を体験した子供が大人になっても引き続き受けられるサポート制度がある事虐待に対する認識を交通事故の様な常識レベルにまで高める事怒りのはけ口を探す前にしなければいけない事はたくさんあるのだ。虐待を生き抜いた人を私は尊敬している。だから、虐待された人が将来虐待をする可能性・傾向が云々という「確率」を読む度、心が重くなる。一個人の様々な歴史や背景を確率や数字で語ってほしくない。虐待を受けた人が「~%の割合で」虐待を繰り返すんじゃない。虐待を受ける様な環境で育たざるを得なかった人がその虐待が起きやすいストレスの高い環境から逃れざるを得ないそんな環境の悪連鎖を払拭できない社会が虐待の連鎖を生むのだ。虐待の過去を持たない者は虐待の過去を克服した人の力を評価し同時に、無邪気な無知から虐待の過去を再び凶器として使う事が無い様に認識を高めるため努力しなければいけないと思う。虐待を経験しなかった者がどこまで虐待を理解できるのかわからない。でも、虐待を生き抜いた人達がたどって来た道程一つ一つを尊重し虐待体験者の声を真摯に聞く事はできる。そして、社会全般と社会に生きる個人個人が虐待を特別視せず交通事故防止と同然の常識と行動を以って危険な状態にある子供達を救える様な制度を作り救える様な「常識」を作り上げる為にも虐待体験者の声は不可欠なのだ。他人の弱さを糾弾するのではなく他人の弱さに直面する事によって自分の弱さを見つめる。それが、社会の脆さに冷静に対処し社会と社会に生きる子供と大人を救う為に欠かせない第一歩だと思う。
February 2, 2004
コメント(25)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-

- MIX(雑種)だってかわいい!
- 青葉区みたけ台『Guri's Kitchen』さ…
- (2025-11-21 12:13:25)
-
-
-

- 猫の里親を求めています。
- *みにゃさんの愛、募集ちぅ-2024年1…
- (2025-10-19 01:27:40)
-