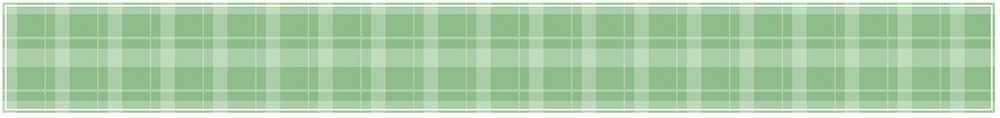2011年05月の記事
全55件 (55件中 1-50件目)
-
エランテスの入賞花
エランテス属の交配種、グランディオセ‘シューティング・スターズ’AM/AOSです。花の真ん中奥が透き通った感じになっていて距もあります。温室内のサクララン、蔓が延びて大変なことに(^^;)シュロの花ミヤコワスレ今朝は7℃まで下がり寒かったです。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.12マイクロシーベルトでした。
2011.05.31
コメント(4)
-
プラティステレ属
プラティステレ属の原種、ステノスタキアです。プレウロタリスに近い属で中米に広く分布する小型種、これで2寸鉢、見るのに虫眼鏡が欲しいです。
2011.05.31
コメント(0)
-
プロステケアとホヤ
プロステケア(旧エンシクリア)属の原種、ビテリナです。メキシコ、グアテマラの標高1500~2600mに自生する着生ランです。ミニカトレヤ程度の管理ですが夏は涼しく管理します。はホヤ(サクララン)天の川「彦星」
2011.05.30
コメント(4)
-
透き通る萼弁
プレウロタリス属の原種、ヘミローダです。同じ葉から数年に渡り不定期に咲きます。南米の中高地産なので、夏は涼しく湿度は高くと言いますがこの個体はとても丈夫です。は断崖の女王と呼ばれるイワタバコ科レクステイネリア属の植物で、別名をブラジリアンエーデルワイス、学名シンニギアレウコトリカと言う多肉植物です。球根があり、小さな種をまいて繁殖するそうです。
2011.05.30
コメント(2)
-
ハーベヤナムとまだ頑張るデンドロ達
デンドロビューム属の原種ハーベヤナムです。ベトナム、タイ、ミャンマーに自生します。ペタルの欠刻は芸術品ですね(^^;)ノビル系のデンドロもあとからまた咲いたりしていますこちらの雨はまだ大したこともなくまだ小雨程度ですが夜半過ぎから明日午前中にかけて強まる予報です。
2011.05.29
コメント(4)
-
地味な色合いの2属
ポラーディア属の原種、リビダです。メキシコからペルーにかけてとベネズエラの標高1600m前後に自生する着生ランです。エピデンドラム→エンシクリア→アナケイリウムと変更を続け、2004年にこのポラーディア属となりました。一昨年の7月にジュメさんに戴いたものです。そしてこちらはトリゴニディウム属の原種、エガートニアナムです。メキシコ、エクアドルに自生する着生ランです。マキシラリアの近縁属ですが宇宙人に見えてしまいます
2011.05.29
コメント(4)
-
真っ赤なコチョウランとビワ
ファレノプシス属の交配種、ソゴー・ローズです。先日紹介したビワですがダメになった花ガラ摘みをしていたらなんと今頃出てきた花芽があるのにびっくりしました。半年遅れてこれから花が咲いて秋までに実るのでしょうか(^^;)なにせ、昔食べたビワの種を播いたものですからこちらの寒さに合わせた開花と結実の新パターンをあみだしたのかもしれません
2011.05.28
コメント(14)
-
ステレオキラス属
ステレオキラス属の原種、ダラテンシスです。タイ、ベトナムの標高800~1400mに自生します。薄暗くなってから撮ったのでピンボケになってしまいましたm(_ _)m明日撮り直して差し替えておきます。差し替えるつもりでしたが大したことが無いので追加しておきます。
2011.05.27
コメント(6)
-
アスコセントラムの赤花
アスコセントラム属の原種、カービフォリウムです。スリランカ、インド北東部、ミャンマー、タイ、ラオスに自生します。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.12マイクロシーベルトでした。
2011.05.27
コメント(12)
-
シーズン最後のミス・ショーナン
リカステ属の交配種、ショールヘブン‘ミス・ショーナン’です。今年は結局4輪で終わってしまいました。これが最後です。またいつか去年一月のような開花を目指したいと思います。棚下のこぼれ種からのアマリリス去年ジュメさんに戴いた白雪芥子10芽でて6本花が上がりました(^o^)/
2011.05.26
コメント(10)
-
デンドロ原種、フルギダム
デンドロビューム属の原種、フルギダムです。パプア・ニューギニアの標高1300mまでに自生します。昨日載せたビワの隣のシュロになんと花が付きました。はなはなさんも紹介していた5枚花弁のツツジこちらのツツジは二段重ね、名前は?
2011.05.26
コメント(0)
-
ノドサとパープラタの交配
ブラソカトレヤ属の交配種、モーニング・グローリー‘H & R’です。原種同士ブラサボラ・ノドサとカトレヤ・パープラタの交配です。Bc.Morning Glory‘H & R’この花を見て、パープラタにワークハウゼリを使ったらどんな花になるのかなと興味が湧きます。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.13マイクロシーベルトでした。
2011.05.26
コメント(4)
-
シランの交配
ブレティラ属の交配種、ストリアタ × オクラセア(シラン × 黄花小白笈)です。hiroroさんより戴きました。なんとガストロルキスやチシスとの交配が可能ということで、ウチにまだ咲き残っているガストロルキスにかけてみることになりました。これから咲くチシスもあるのでそれにも交配してみます(^o^)/hiroroさんにはすでにガストロルキスとガンゼキランとの × 交配実生もして戴いており、早いものはここまで来まして、数年後の花がとても楽しみです。また12月にビワの開花を載せましたら袋掛けのアドバイスを戴きかけたのですが、ほとんど寒さでのように全滅したと思っていたら数カ所の花芽の一部が実を付け始めました。収穫ができるようになるのかまだ判りませんが楽しみです。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.14マイクロシーベルトでした。
2011.05.25
コメント(10)
-
白とオレンジのセロジネ
セロジネ属の交配種、メモリア・ウィリアム・ミコリッツ‘バーンハム’です。まだ咲き始め、3輪くらい咲くでしょうか?今年は出来が悪いです(ToT)
2011.05.24
コメント(4)
-
ピンクのミルトニオプシス
ミルトニオプシス(旧ミルトニア)属の交配種、ジーン・カールソン‘ディザイアー’です。Mps.Jean Carlson‘Desire’昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.12マイクロシーベルトでした。田植え、機械植えがようやく終わりました、あとは明日父とシルバー人材の方に補植をお願いしてあります。
2011.05.24
コメント(2)
-
コチョウランのルデマニアナ
ファレノプシス属の原種、ルデマニアナです。フィリピンの標高300~600mに自生します。今日は田んぼの真ん中で田植え機故障、古い機械なので中のベルトが切れてプーレの軸に絡みついてもう一本も切れそうです。部品が近くの営業所にないので、取り寄せてもらい早ければ明日の午後から残り半分植えたいですが、、、
2011.05.23
コメント(8)
-
バーケリア
追加写真を撮ってみました。バーケリア属の原種、スペクタビリスです。メキシコ、ニカラグアに自生する着生ランです。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.13マイクロシーベルトでした。
2011.05.23
コメント(2)
-
オンシ・フスカタムのアルバ
オンシジューム属の原種、フスカタムfma.アルバです。パナマ、コロンビア、エクアドル、ペルーに自生します。以前はミルトニア属ワーセウィッチーとされていました。普通種の花はこうです去年11月の花
2011.05.22
コメント(8)
-
リンコボラ
リンコボラ属の交配種、デイビッド・サンダーです。原種同士リンコレリア・ディグビアナとブラサボラ・ククラタの交配です。Rcv.David Sander昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.11マイクロシーベルトでした。
2011.05.22
コメント(0)
-
バルボの大株
バルボフィラム属の原種、フェイスタムです。フィリピン、ルソン島の山岳地帯、標高1200m前後に自生する着生ランです。なんとこの株、尺鉢からはみ出すほどになって17輪付きました。
2011.05.21
コメント(6)
-
白いパフィオ
パフィオペディラム属の交配種、デパールです。原種同士、デレナティーとプリムリナムの交配です。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.12マイクロシーベルトでした。
2011.05.21
コメント(2)
-
デンドロ、パープレウム
デンドロビューム属の原種、パープレウムです。マレー半島、ニューギニア島、ブーゲンビル島、カロリン諸島、フィジーの標高150~1000mに自生する着生ランです。全部で八房付きました。不定期咲きで、花保ちがいいです。とは言いつつこの個体はいつも5,6月のようで、白花の個体は1,2月のようです。デンドロついでにこちらのほうが不定期にあちこち咲いてくれるデンドロビューム属の交配種、スノーボーイ‘ロマンス’そして先日ピント外れだったデンドロビューム属の原種、フィンブリアタムfma.オクラタム別の株に花が付いたので撮り直してみましたが、、、
2011.05.20
コメント(2)
-
クサビのミニカトレヤ
カトレヤ属の未登録交配(C.オルペティー x C.インターメディア,アクィニー)です。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果も0.13マイクロシーベルトでした。今朝の最低は6℃でしたが、朝日が当たるのでハウス内は7時には既に30℃近くになります。6時半には内張りと外側の天窓を開け、7時過ぎには外気も17℃、サイドも肩まで開けます。今日は午後からもち米の田植え、ここだけ乗用田植え機が入らないので歩行型の4条植えを引きまわさなければなりません(^^;)
2011.05.20
コメント(6)
-
ビフレナリアの白花
ビフレナリア属の原種、ハリソニエ var.アルバ です。ブラジル産の着生種です。普通種はこんな花
2011.05.19
コメント(4)
-
クサビの出ないWings of Fire
デンドロビューム属の交配種、フロスティー・ドーン‘ウィングズ・オブ・ファイヤー’です。Den.Frosty Dawn‘Wings of Fire’本来ならペタルに赤が入るクサビ花の筈ですが、全くクサビが出ません。ハワイのH&R社によると凄い高温で咲かせないと出にくいらしいです。写真で見つけた時は綺麗で個性的なクサビがお気に入りだったのにとても残念です。こんな花ならベラ・マリーのほうが綺麗です(^^;)昨日午後のこちらの環境放射能測定結果も0.13マイクロシーベルトでした。昨日の朝の最低は2.5℃で降霜ぎりぎりでしたが今朝は5℃と上がってきました、遅霜の心配がやっとなくなりました(^^;)
2011.05.19
コメント(4)
-
パープラタの筋花
カトレヤ(旧レリア→ソフロニティス)属の原種パープラタ fma.ストリアタ‘ドラシ’です。ブラジル原産です。ストリアタは筋花を指す変種名です。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.13マイクロシーベルトでした。
2011.05.18
コメント(8)
-
ミニカトレヤと戴き物
カトレヤ属の交配種、トーキョー・マジック‘レア’です。次第に白弁になりますが咲き始めは黄色っぽいです。今日はsirokurousagiさんから色々戴きました。後列左HTバラ、ヨハン・シュトラウス、優しいピンクのバラのようで楽しみです♪右はガーベラ、手前はマリーゴールドとラベンダーですsirokurousagiさん、PCが立ち上がらなくなってしまったとのこと、何とか復活できますように祈っております。そう言えば2年前にsirokurousagiさんに戴いたミニバラのスノーシャワーにも蕾か20位付いてこれから楽しみです。30年前からあるウチの唯一のバラにも蕾が出ていました
2011.05.17
コメント(2)
-
バルボの原種、ブルメイ
バルボフィラム属の原種、ブルメイです。マレーシア、スマトラ、ボルネオからフィリピン、パプアニューギニア、オーストラリアにかけての標高50~800mに自生する着生ランです。花の形がマスデバリアっぽくて面白いですね(^o^)/昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.12マイクロシーベルトでした。
2011.05.17
コメント(4)
-
カトレヤ原種同士の交配
カトレヤ属の未登録交配、原種同士、レオポルディーとシレリアナの交配です。レオポルディーは大型で、シレリアナは小型ですが交配により草丈30cmのちょうど良い大きさになっています。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果も0.13マイクロシーベルトでした。水道水からはずっと未検出です。
2011.05.16
コメント(3)
-
トリコピリアのその後
トリコピリア属の原種、ラモネンシスです。原種のスアビスとマルギナータの自然交雑種と言われています。先月1房は終わり、残りの4房が咲きました。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.13マイクロシーベルトでした。
2011.05.15
コメント(6)
-
原種フィンブリアタム
デンドロビューム属の原種、フィンブリアタム var.オクラタムです。インド、ミャンマー、タイ、中国南部に自生する着生ランです。ピントが合っていませんでしたm(_ _)m去年ドームでグランプリの品種ですが花命は短いです。
2011.05.14
コメント(4)
-
ピンクのパフィオ
パフィオペディラム属の交配種、マジック・ランタンです。原種同士、ミクランサムとデレナティーの交配です。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.12マイクロシーベルトでした。
2011.05.14
コメント(4)
-
マスデ、コクシネア
マスデバリア属の原種、コクシネアです。コロンビアの標高2400~3100mに自生するクール系でマスデバリアの代表種と言えます。原発の1号機、炉心溶融が起きていましたね(>_
2011.05.13
コメント(6)
-
しけてしまったアスコセントラム
アスコセントラム属の原種、クリステンソニアナムです。ベトナムの海抜100~150mに自生する着生ランです。前回のように咲かせたかったのですが今年は花がしけてしまいました、植え替え時期が来ているようです。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.14マイクロシーベルトでした。
2011.05.13
コメント(6)
-
デンドロ交配種とブラシアのその後
デンドロビューム属の交配種、ジャンヤです。原種同士、ラウェシーとクリソグロッサムの交配です。先日のブラシアがさらに大きくなりました。約38cmあります
2011.05.12
コメント(2)
-
ミクロペラと代かき
ミクロペラ属の原種、ロストラタ、北東インド、バングラデシュ、タイに自生する着生ランです。カマロティス属パープレアも異名同種、リップが上向きになります。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果も0.13マイクロシーベルトでした。代かきが終わりました。は毎年この時期に綺麗な県道の土手左側にウチの田んぼ約25アール(2500平方メートル)があります。ここから反対側を見ると磐越自動車道が見えます。こちらの田んぼ2枚約16アールは上をあぶくま高原道路が走っています。あと二カ所計27アールも代かき終了で来週末に田植えの予定です。
2011.05.12
コメント(6)
-
バンダ、デニソニアナ
バンダ属の原種、デニソニアナです。タイ、ミャンマー、ベトナム、雲南に自生します。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.13マイクロシーベルトでした。今日はこれから水田の代かきです。
2011.05.11
コメント(6)
-
カクチョウラン
ファイウス属の原種、タンカービレエ(=カクチョウラン)です。先日はアルバ(白花)を載せましたが、これが普通種です。東南アジアからニューギニア島にかけて自生します。
2011.05.10
コメント(4)
-
リップの黒いデンドロ
デンドロビューム属の交配種、ヘミメラノグロッサムです。ベトナムの標高1400~1500mに自生します。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.13マイクロシーベルトでした。
2011.05.10
コメント(2)
-
サイコプシス
サイコプシス(旧オンシジューム)属の交配種、カリヒ‘ビッグ’原種同士、クラメリアナとパピリオの交配です。この属は同じ花茎に数年に渡り花を付けるので、咲いている花が終わっても花茎を切らずに置きます。前回1月に咲いた花茎です。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果も0.14マイクロシーベルトでした。
2011.05.09
コメント(10)
-
パフィオ、ローウィー
パフィオペディルム属の原種、ローウィーです。インドネシアとマレーシアの標高900~1500mに自生します。最初の花が元気なうちに最後の花まで咲いてくれます。今年は何輪並んでくれるかな~
2011.05.08
コメント(4)
-
母の日のエビデン
エピデンドラム属の交配種、ジョゼフ・リー‘マザーズ・デイ・カトウ’です。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.14マイクロシーベルトでした。
2011.05.08
コメント(6)
-
小型のビフレナリア
ビフレナリア(旧ステノコリネ)属の原種、オーレオファルバです。ブラジル原産で夏~秋咲きとありますが、結構不定期です。
2011.05.07
コメント(4)
-
ミニカトレヤ
リンコレリオカトレヤ属の交配種、メモリアル・ゴールドです。実生なのでリップに赤が出るものと出ないものがあります。Rlc.Memorial Gold昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.13マイクロシーベルトでした。
2011.05.07
コメント(4)
-
ピンク系パフィオ
パフィオペディラム属の交配種、デロフィラムです。原種同士、デレナティーとグラウコフィラムの交配、次々と3,4輪着けます。ウチのスノードロップもようやく^^手前からユキヤナギ、カエデ、レンギョウ
2011.05.06
コメント(2)
-
マキシラリアの小花
マキシラリア属の原種、リンゲンス‘キュート’です。メキシコ南部からコロンビア、エクアドルにかけての標高300~1700mに自生する着生ランです。一月にも咲きましたが今頃も咲くのですね(^o^)/昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.13マイクロシーベルトでした。hiroroさんの質問に答えるための追加写真
2011.05.06
コメント(4)
-
イグネアとカルーセル
マスデバリア属の原種、イグネアです。南米コロンビアの標高2800~3200mに自生する栽培困難とされる種です。先月載せたのは右の小さいほう、左の大きい個体が今度咲きました。ついでには交配種のカルーセルです。
2011.05.05
コメント(8)
-
クモランの極大輪花
ブラシア属の原種、ベルコーサ‘プロスティテュート・スパイダー’です。メキシコからベネズエラにかけて自生する着生ランです。スパイダー・オーキッド(クモラン)と呼ばれています。普通種は花の大きさが11cm程度ですが、この個体は36cmあります。昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.13マイクロシーベルトでした。
2011.05.05
コメント(12)
-
マリー親子
デンドロビューム属の交配種、ドーン・マリーです。原種同士フォーモサムとクルエンタムの交配です。そしてこれにベラチュラムを交配して丈を短めにしたのがベラ・マリーです。ユスラウメの花ソルダムの花戴き物のイカリソウ
2011.05.04
コメント(4)
-
オドント、シルホサム
オドントグロッサム属の原種、シルホサム(キルホサム)です。コロンビア、エクアドルの標高1600~2200mに自生します。栽培やや困難のクール系に入ります。次第にリップ以外は白くなります。今年は斑点が少なくて白花みたいです。去年の花ピンクの椿昨日午後のこちらの環境放射能測定結果は0.14マイクロシーベルトでした。
2011.05.04
コメント(8)
全55件 (55件中 1-50件目)
-
-

- どんなお花を育てていますか?
- キンモクセイ
- (2025-10-20 19:00:03)
-
-
-

- 泣き笑い家庭菜園・・・やっぱり手作…
- とうもろこし🌽栽培の悲劇
- (2023-07-06 12:55:36)
-
-
-

- ガーデニング・家庭菜園・園芸・花な…
- パートレット洋梨の剪定は終わってい…
- (2025-11-15 10:48:49)
-