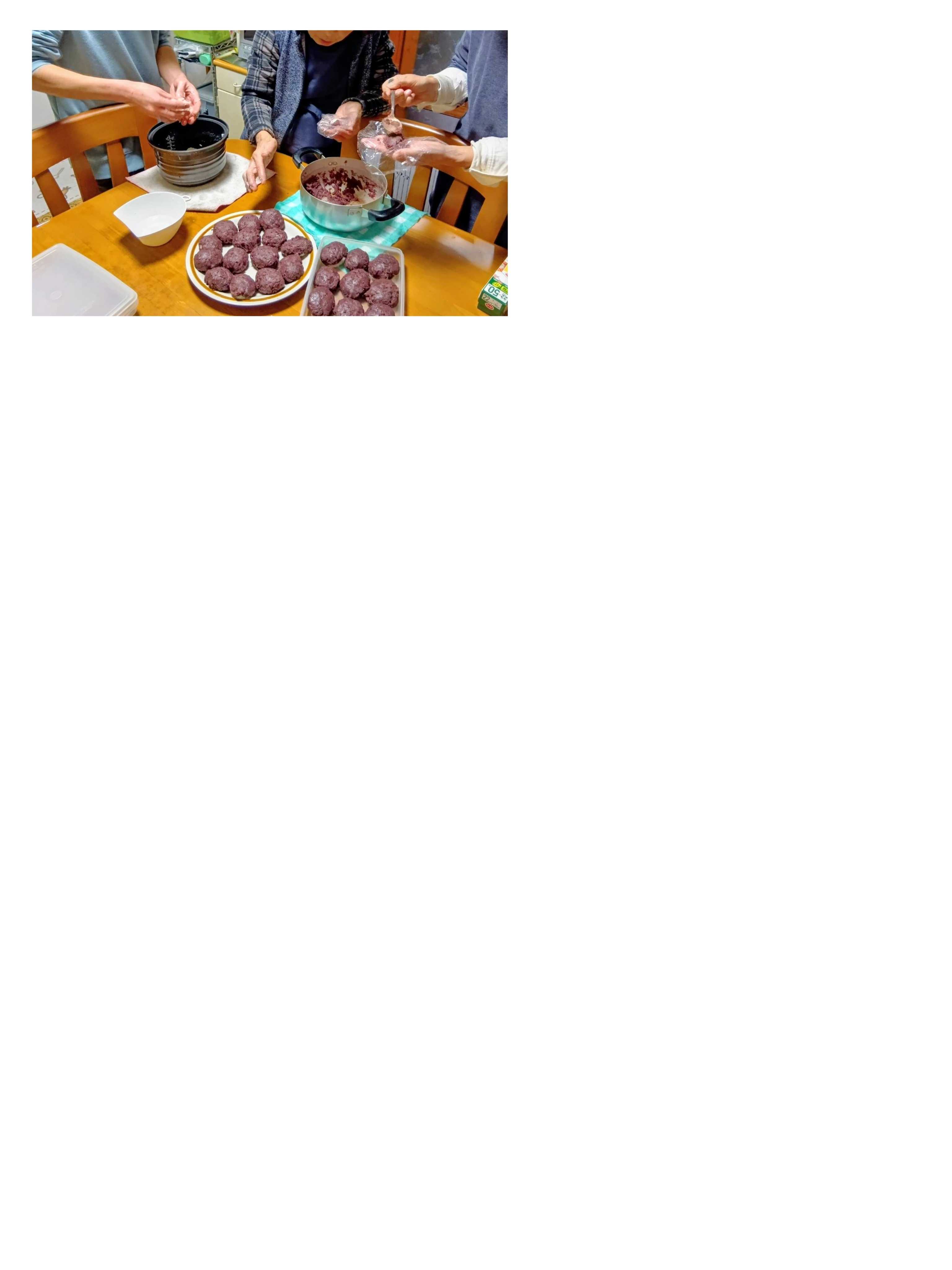2006年01月の記事
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
ちょっと心配
ライブドア関連で自殺された方、エイチ・エス証券でしたよねちょっと心配去年の記事ですが、、、、エイチ・エス証券、オリエント貿易買収、子会社化!(6/22) エイチ・エス証券は22日、商品先物取引会社のオリエント貿易の株式を51.6%取得し、子会社にしたと発表した。オーナーから株式を取得。オリエント貿易は外為ドットコムの親会社でもある。
Jan 28, 2006
コメント(0)
-
雨の降る日曜は幸福について考えよう
ちょっとやさしいタイトルに惹かれて読んでみました。橘さんという方の本。前から気になってはいた生命保険についても書いてありました。http://www.hoken-erabi.net/index.htmここにいろんな情報がありそうなので、検討してみます。朝日生命って(私が入っているとこでもあるのですが)ソルベンマージンがよくありません。もっとも残りの掛け金期間が少ないので、このままにしようかと思ってはいますが、、メインの生保のほうは安全そう。
Jan 27, 2006
コメント(0)
-
経団連が10年前に予測した日本の未来
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/vision/macro.html経団連が10年前の1996年に2020年までを予測した資料がここに残っています。著作権の問題はあるでしょうが、一部貼り付けてしまいました。当たらないものなんですね、、、消費税が5%なら2005年の国債残高は430兆、GDP比では61%。現実は国債残高500兆以上、GDP比では100%当時はドル円は2010年が90円、2020年は80円、そして2020年には日本のGDPが米国にほぼ匹敵すると予測しています。この円高のときに国際金融局長だった榊原英資氏の「為替がわかれば経済がわかる」を読んでみましたが、これはとてもよい本だと思います。ソロスとの付き合いやアジア通貨危機のことが書かれています。現在は、年金では800兆の不足が予測されていますが、これからは高次の医療機関には、個人の思い通りに受診できなくなるでしょうから、そこまでは不足しないだろうと思っています。いまは人生の最後の6ヶ月に費やされる医療費が全体の60-70%くらいを占めるようですが、今後は若い人にもっと医療費を費やす時代が来ることになるのでしょう。高度な医療を望む人は、自分のポケットからどうぞということになると思います。医療もそうですが、福祉のほうも(介護保険)いずれは破綻しそうですね、、、KKRでしたか、あの詐欺のような商法と似てませんか?1万円払えば、10万円使えるというのは、、、、国債依存度はすでに40%を超えています。http://www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/research/r050301japan.pdf
Jan 25, 2006
コメント(0)
-
発想が転換?
この銘柄をいくらで買ったかが気にならなくなっている自分がいます。というか、もうすでに忘れている状況です。それよりも会社の時価総額にたいして、自分が思う価値はどうなのかということを気にするようになっています。まあ、暴落がくれば、どうなるかはわかりませんけど、、、、でも、もう気にならないと思っています。単にいくらも持っていないせいではないように思いたいのですが、、、そう考えるとトヨタの10分の1の時価総額である任天堂は、世間にとって、それだけの価値があるか結論を出しかねています。
Jan 24, 2006
コメント(0)
-
為替、日米金利差、機械受注、輸入物価指数、実行実質為替
為替、日米金利差、機械受注、輸入物価指数、実行実質為替と並べてみて、今後の為替について考えてみた。輸入物価指数は平成バブル以来の高さになっている。輸入物価指数は原油を100%米ドル換算で産出しているのでこの影響が大きいと思う.これまでは機械受注の上昇の中腹くらいで、日米金利差が縮小しはじめ、それと相前後して円安へと向かっていたようだが、、いまはたくさんの国債を抱えて、金利は上げられないということころか?いずれにせよドルを買うなら、実行実質為替の値よりも低い位置から買い始める必要があると思う。三井物産フューチャーズで原油の需給を見ると、改善しているようだが、それでも上げているのは、地政学的リスクを騒ぎ立てているためか?このリスクはハッタリ??GSはプットを大量に買っているが、1990年2月のモルガン?のように一気に売り崩すつもりなのだろうか?
Jan 22, 2006
コメント(0)
-
投資資金を元に
1)株式(小額)1週ほど前に投資資金のほとんどを元に換えました.長城汽車を少しづつ買っています.今月はこれだけの予定.次は中国のトイレタリー製品を扱う会社を探してみる予定.日本株は任天堂だけを所有中.また少し円安になり,株価も落ち着いたら,この資金は円に少し戻すかもしれません.ジェトロではA株も海外投資家に開放と報じています.http://www5.jetro.go.jp/jet-bin/pro1.cgi/kouhou.html2)資産運用(すこしまとまった額)妻とも話し合い,FXはやめて,少しづつ外貨MMFから購入していくことにしました.為替の予想はプロでも難しいようですので,115円以下は少し買い.110円以下はもう少し買い.105以下はもっと買いくらいの目安で,5年間ほど継続することにしています.額がまとまったら,120円で少し売り,125円でもう少し売り.ただ5年後にはある程度のドルを保有することを目処にします.それからポンドを少し買う機会を考えています.先進国でもっとも高齢化の心配が要らない国ですので.
Jan 18, 2006
コメント(0)
-
ブッヒェンヴァルト収容所とReiter症候群
ハンス,ライターというドイツ人医師は当時のプロシャ陸軍中尉がある奇妙な関節炎に罹患していることを発見した.後には赤痢の後などに集団発生する関節炎として認められ,彼の名を冠してReiter症候群と名づけられた.いまは赤痢などもまれになり,性交渉後のクラミジア感染による多発関節炎としてもReiter症候群が有名になっている.彼はその後ナチスに入り,アウシュヴィッツとならぶ絶滅収容所として知られているブッヒェンヴァルト収容所に勤務.そこでチフス菌による人体実験によって大量にユダヤ人を虐殺した.このような過去があるため,最近はユダヤ人の圧力により?Reiter症候群という呼称を欧米ではやめるようになっている(概ね70%の人は「反応性関節炎」と呼ぶ).しかし日本ではいまもReiter症候群と呼んでいる.以下は国家試験問題30才の女性。慢性関節リウマチがあり、さらに肝・脾腫、 リンパ節腫張、貧血および末梢血好中球減少が認められる。 漿膜炎の所見はない。最も考えられるのはどれか。 Sjogren症候群 Felty症候群 Reiter症候群 Hans Reiterの名前は英米ではこのまま抹殺されていくのだろうか?ユダヤ人も結構厳しいんですね,,,,その人がその後どうであれ,あくまでも病名なので発見した人の名前を用いても良いと思うんですが,,,
Jan 11, 2006
コメント(1)
-
国家のプライマリーバランス
フランス男さんコメントありがとうございます. http://fp.st23.arena.ne.jp/keio/k0512.htm こちらのブログの12月26日に2012年を目指していたプライマリーバランスがいまの小泉改革による1年前倒しの可能性が出てきており,2006年度はさらに削減することで,このまま企業利益が継続すれば,,,とあります.国債残高も名目GDPも東証時価総額も同じ500兆円くらいなんですね,,PSRが1ということになります.PERは22倍くらい?PBRは国民の貯金残高が地方を合わせた借金よりは上で300兆円くらいはよゆうがあったでしょうか?よって株主資本は300兆円PBRはだいたい1.8-2倍くらいか,,,これよりも有利な株を探して買っておけばよい??ROEは長期的には株価上昇に沿ったものとなる.売上(GDP)と借金(国債)が同じくらい.利益率(ROE)がどれだけあるかが問題.企業のROEは団塊の世代が引退することで上昇するでしょう.多少のでこぼこはあっても,,,,1980年代のように主に企業の利益から税金を取っていたのを,消費税を上げることで,今では企業からの税収は22%を占めるに過ぎません.,段々と企業は若返って元気になりそうですね,,,いまは金利ゼロなので,物価上昇を考えると,マイナス金利になる.すなわち借金しても資産を得たほうが正解.ただし構造計算が間違っていないものを,,,日銀が拙速にマイナス金利を解消しない限り,この傾向は継続する.中央銀行の逆をいけ!ですね?そして団塊の世代が得た退職金は,高値で買ってしまった家を建てた借金を返すのに使われ,余ったお金は,その他消費をすることで,結局は銀行に回る.国債を買う負担が軽減された銀行は,別の投資先へお金を回す余裕が出る.信用乗数の上昇.投資の一部は海外へ流出する(円安?).いまの企業は設備投資を増やし,機械受注の長期上昇はしばらくゆっくりと継続する.よって円安も長期的にはゆっくりと進行する.物価も円安に伴い上昇するため,庶民の生活が少し苦しくなるが,企業はゆっくりと(若者はもともと団塊の世代よりは給料が安い)給料を上げる.現在,IP(米国の鉱工業生産,ハイテク除く)の対前年比を見るとほぼ底打ちで,実数では上昇.かつ日本の時間外労働時間および鉱工業生産の出荷在庫バランスも対前年比で底をうち,上昇を開始してます.そこでここから1,2年は米国の景気回復に伴い,米国株価に呼応するように,多少の調整をはさみながらも,長期的には日本も上昇を続けるように思うようになってきました.話がうますぎるでしょうか?双日への投資で借金に苦しみながらも,活力を取り戻そうとする過程は少し勉強になりました.ちょうど平成バブルのときに,それまでは泣かず飛ばずだった総合商社も「やっと良くなってきたね」といわれるようになったときに,あのバブルははじけたのです.いまの株価は少しスピードが速すぎますが,もう少しゆっくり育てば,じっくりとかなり上まで行くような気がします.
Jan 10, 2006
コメント(3)
-
台湾のマクロニクス
売上の対前年比はプラスですが、前月比はダウン。結局、在庫がさばけたということになるのか、、、増産しているわけでは、ないんですね。
Jan 9, 2006
コメント(0)
-
GDPと株式時価総額
東証一部の時価総額は533兆円http://www.tse.or.jp/STATISTICS/01.html名目GDPは502兆円http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/qe053-2/jissuu.htmlということでGDP比で100%を超えましたね。http://www.dai-ichiasset.co.jp/dai_0704-05.html米国の120-140%よりは下ですが、、歴史的な日米の株式時価総額とGDP比率は以下にデータがあります。http://www.fullpower.jp/fanda.pdf現在の株式時価総額/GDP,106%はこれからの40歳代人口増加を加味しても、高齢化率が1980年代とは異なり、まずまずのレベルにまで達したように思うのですが、、、高齢化率は1989年が12.3%2006年が20%2040年が32%程度です。また地価が上昇して、資産バブルになるんでしょうか?民俗学者の柳田國男は「お伊勢参り」ブームの周期性を指摘していますが、このようなマスヒステリーは60年に一度と思われ、今回は平成バブルから15,6年しか経ていませんので、マスヒステリーは生じないと思っています。「投資遊学のすすめ」には「日本人は投資に際しての基本的なことを知らないのでは、」という文言がありますが、今年は資産運用について、家族でじっくりと話し合ってみようと思う次第です。私の言うことはいつも当たらないのですけど米国では年老いた低所得者は、十分な医療を受けられませんので、早く亡くなります。このため低所得者の人口構成は若い人が多く、言い換えれば回転が速いといえます。いっぽう、高所得者は十分な医療を受けられますので、長生きが出来ます。日本では低所得者、高所得者とも同じレベルの医療を受けられます。ここに日本の高齢化問題があるわけですが、、怒られるでしょうか?こんなにはっきり言ってしまうと、、、、米国では低所得と高所得者の2つの国が混合した状況であり、合計の平均寿命は日本よりかなり低いのですが、おそらく高所得者の寿命は相当長いでしょう。このような2つの国が混合した米国では、人口構成上、常に若い低所得者の供給がなされ、年老いた低所得者は早めに生涯を終えることで、国が負うべき社会保障の負担が少ないのが現状ではないかと思います。言い換えれば、米国は移民を受け入れることで国内に低コストの植民地を持っているようなものです。ごく一握りのアメリカンドリームに魅せられ、たくさんの移民が米国に渡っているわけですが、、、現実は甘くないと言うことを、、、希望を求めてオクラホマからカリフォルニアに向かった農民が、現実はもっとひどかったことを思い知らされるスタインベックの「怒りの葡萄」の世界はいまも現実なのです。あるいは「風とともに去りぬ」のpoor whiteの世界がいまも現実なのです。日本でも少し前までは同じでした。国民皆保険の前は、、、井伏鱒二の「本日休診」ではお金のない人があっけなく亡くなって行きます。これって相場と似ていますよね、、一握りの大もうけした人と多くの失う人たち、、、あちらでは東欧やアジアや中南米から、最近きたばかりだという人たちにたくさん会う機会がありました。日本がこれから移民を受け入れてもほぼ手遅れなのですが、移民を受け入れても社会システムを米国のように変更しなければ、いずれは同じことになるのではないでしょうか?あるいは英国のように10-20年間くらい医療の質を落とし、先進国の中でもっとも年金の心配が要らない国に生まれ変わるという方法もあるのですが。ちなみに英国の移民受け入れはヨーロッパでは最も低い部類に属しています。私としては日本は英米いずれの国にもなってほしくありません。もっとゆっくりとした変化で、みんなが受け入れられるような国になってほしいのですが、、、
Jan 9, 2006
コメント(8)
-
今年は資産運用をテーマに
資産運用をテーマに1)外貨MMF2)確定拠出型年金3)海外のインデックスファンドなどを視野に準備を始めています。株を買ったのは2004年が最初なのですが、山一證券がつぶれたときはテレビを見てびっくりしました。電力債を買っていたので、、、結局は大丈夫で、全額戻りましたが、、こう考えるとあのころのひどい状況とは隔世の感がします。投資の額を大きくするには、まず取り扱い会社をよく調べないと、あのときの状況を忘れていない妻が納得しないので、、そういえばジムロジャースは資金凍結から戻れたんでしょうか?10月の114.82円を割りましたね、誰が円を買っているんでしょうか?
Jan 8, 2006
コメント(0)
-
為替と株価テクニカルと機械受注の関係
為替と株価テクニカルと機械受注の関係チャートの上と下が切れていますが、機械受注のピークと円安はほぼ一致しています。時期は1.5-2年くらい違いますが。為替は機械受注のピークとほぼ一致するまで円高になるのではないでしょうか?130円くらいはその時期は2006年末から2007年初頭ころ。株価のテクニカルに高い時期(ピーク)では、一時的に円高になります。その目安は前月の円安を上回る額で円高になること。また過去3回の株価ピーク(テクニカルピーク)でドルを買っておけばわかるように、損はしないようです。115円を基準に示しています。今の株価は長期(2000年4月で日経は連続性を損なっている)で考えた場合、大証修正平均は30000円超に相当し、機械受注と同じラインで伸びています。要するに平成バブルのときと同じように株価は上昇しています。PERが当時よりも低いのは設備投資額が当時よりもずっと低く、企業利益はまあまあ当時より高いからです。この利益の高い傾向は今後も景気の波を受けながら続くでしょう。なぜなら政府は国債を元気になった企業に引き受けてもらわないといけないからです。これから数年後???金利が上がる可能性が高い国債の引き受け手はそれ以外にないでしょうから。これ以上の株価上昇は米国の株価が上昇を開始してからかも、、、企業の経常益は高いのですが、機械受注額については、これまでほど高いわけではありません。たとえば森精機、当時一世を風靡した1980-90年代初頭の利益率と比較するとわかりますが、今は売上が上がっても、利益率は何分の一です。これは企業の競争力が決して当時の飛ぶ鳥を落とす勢いに戻ったわけではありません。おそらくは主には労働分配率が上昇した結果で、団塊の世代が退職するとともに改善すると思いますが、、、日本の誇る国際間競争力も落ちているのではないのでしょうか?2001年に始まる2次的物価上昇、WTIの上昇は景気の過熱を抑え、ゆっくりとした景気上昇に寄与しているように思いますが、、、オイルサンドや月島などが開発しているバイオマスなどの代替エネルギーが採算ベースに乗るまで、原油高が結局はいきつくんでしょうか?イノベーションが今回起きるのでしょうね、イノベーションがコンドラチェフの底に出現することになっていますが、それはITではなくエネルギー革命なのかもしれません。次回の米国景気の高さは原油によって、ある程度抑制されるんでしょうね。日本の輸入物価指数はこの1年で25%も上昇していますので、今年はさすがに人口動態の改善を上回るほどよい状況とは思えないのですが、、、、米国サイクル(ハイテク除く)については、前回はすっ飛ばしていますが、それまでは見事に鉱工業生産サイクルと一致しています。今回は実数を月次でみても上昇しているので、これから対前年比も上昇すると思っています。このように考えると真のバリューとは、参入障壁の高さをいかに維持しうる企業であるかに尽きるのではないかと思います。そしてそれらの企業を手に入れる時期(機械受注が低下しているある時期で、悲観の円安から転換し、上昇している時期)はみんなが悲観した時期ということになるのではないかと思います
Jan 7, 2006
コメント(0)
-
ちょっとショックなデイトレ派
http://www.all-navi.jp/fx/?c=adw&a=s1上のリンクで自分の性格がデイトレ派か長期投資派かを診断することができます。私は、、、、デイトレ派でした。今度は、わざと自分とは正反対の答えを入力してみたら、、、、長期投資派になりました、、、うーーんそうだったのか、、
Jan 6, 2006
コメント(4)
-
ビジネス英語の雑記帳をリンク
面白そうなブログなのでリンクしました.12月末のブログ米国の長短金利差が逆転したことが書いてあります.5年ぶりとか,,,この金利差が1-2%に開いたときはリセッションが来ていたようです.短期金利は政策で決まり、長期金利は債券市場が決める。短期金利が上がったのに、長期金利が低いのは景気の先行きに対して慎重な姿勢であることが読み取れるということ。ということで今度は米国の金利を調べてみます。政策金利は見ていたのですが、、、http://tottocobkhinata.cocolog-nifty.com/bizieizakkicho/
Jan 6, 2006
コメント(2)
-
任天堂も
任天堂も好調で,年初から良い滑り出し.DS品切れの報道マクロニクスでは大増産中なんでしょうね.
Jan 6, 2006
コメント(0)
-
私がドルを買いだした理由
まだ5年以上先のことでしょうが,子供が留学することを念頭においています.多分するでしょう,,,そのときのために少しばかりドルを持っておいて,応援しようと考えています.スワップというのは相手の通貨との金利差から,毎日利息がもらえることを,FXを行なってみて初めて知りました.この分野も専門用語が多くてわかりにくいですね.ロールオーバーとか,,,将来,インフレが来て,金利が急上昇せざるをえなくなると,日本も1990年代のスエーデン,クローネのような動きになるのだろうか?
Jan 5, 2006
コメント(0)
-
ドルを買ってみました.
今年に入って,ドルを買ってみました.FXで2倍レバレッジ.私の場合は少し買わないと,ちゃんと勉強できないようです.スワップポイントというのを今日は調べ,私の使っている会社のイートレのスワップポイントは他社の半分くらいしかないことが判明,,,,会社によってこんなに違うのか,,最近の新聞でFXの会社の経営に注意という記事があったので,他にどんな会社があるのか調べてみると,,よさそうなのがオリックス証券(こっちは大手の経営)とマネックス証券(証券のナイター営業というのもあり便利そう,ミニ株もある,,ここは大手??)何年も放置していた米国の銀行口座を秋に解約して,送られてきた小切手を円に換えたのですが,やっぱり残しておけばよかったかなと少し後悔しています.
Jan 4, 2006
コメント(0)
-
持ち家について
自分の経験から、、、1987年に持ち家を購入しました。この直前にNTT株が初めて放出され、売出しが108万円だったと思います。私はこのときにNTT株を購入するか、家を買うかで考えましたが、結局は家を買いました。当時、IPOの権利は得ていたのですが、、、株は買いませんでした。NTT株はその後すぐに300万を突破、、、まず株を買って、それを売ればまったくのタダで家を購入でき、貯金も温存できたことになり、残念なことをしました。結果論ですが、、、当時、大学の友人だった中には1億、2億を株で儲けていたものがおりましたが、最後は大損して、医院が銀行管理に陥る状況に至ったようです。やはり投機的な方法は多くの場合、長続きできるものではないように思っています。さて持ち家のほうですが、土地の価格は当時よりも上昇しに、18年住んだ家のほうは、今はほとんど価値がないものと思っています。月々の家賃を払ったと考えて、約10年で元を取り、その後の8年はタダで住んでいるような感じで考えています。家自体の値段は1200万円でした。もっとも修繕費用は要していますが、、、また18年まえの家と土地が、現在は土地だけの価値で総額がおおむね同じになったような状況になります。こう考えると18年間ほぼタダで住んでいるという考えも成り立つと思います。1972年の列島改造で高騰した土地は、当地では上昇が止まり、その間のインフレにより、1987年には相対的に底値になったと考えています。弟はその数年後に別の地で家を購入しましたが、土地はすでに半値になったと嘆いております。やはり長期的な視点からライフスタイルを考えるのは大切なことです。金利面を考慮に入れていないのは問題ですが、土地の分は当時の自己資金でまかなえました。家部分も返済にはそれほど年数を要しませんでした。安普請ですので、、床材料などは自ら塗料を塗った上で業者に渡しました(多分30万円くらいは節約になった。駐車場も自ら設計を発注し、近くの鉄工所に作らせています。相場を知り、出来ることは自分でやると安く上がります。少なくともぼられません)。子育てが終われば、もはや家は大切ではありませんので、今後は家を建て替える考えは毛頭ありません。メンテをしながら、家賃がタダになった家に長く住もうと思っています。また子育てが終われば、移動する自由が私たち夫婦には手に入ります。そのときは今の家を貸してキャッシュフローを得ながら、子供の後についていって、孫の世話でもしながら小さなアパートにでも住めばよいと思っています。守るべきものは小さくする工夫が必要であると思っています。以上のような経験から、土地の値段がすでに底値になった地域で、必要最小限(家賃を払ったと考えて10-15年程度で元が取れる)の家を持つことは悪い話ではないように思います。stareyesさんが言われていますように、土地を含まない家自体の価格で1000万程度の中古住宅で、長持ちする作りであれば検討する価値があると思います。安間伸さんが言われていますように、手放したい人がいる物件を丹念に探していけば、自分に有利な裁定が成り立つように思います。投資については、あくまでもお金を捨ててもよいと思った時期に捨ててもよいと思うような銘柄に投じるということを、勉強させてもらった次第です。
Jan 3, 2006
コメント(0)
-
ダウと米鉱工業生産
ダウと米鉱工業生産(IP変換)に密接な関係があるようです。ピンクは対前年比です。問題はこれが何によってもたらされたかですが、、、これを米国の40歳台の人口構成と比較してみますと、日本同様に人口構成は株価や鉱工業生産に長期的に影響を与えているようです。現在の米国の住宅バブルは金利上昇により多少調整されそうですが、長期的には安定した状況になるのではないでしょうか?少なくとも日本のように30年前の地価に落ちるほどの暴落はないように思います。「長期投資家は最大のギャンブラーである」
Jan 3, 2006
コメント(0)
-
米国鉱工業生産指数 IP 対前年比と日本
米国鉱工業生産指数(IP)対前年比と日本の鉱工業生産出荷在庫対前年比と日本時間外労働時間対前年比日本と異なり米国の鉱工業生産指数の対前年比は1992年を大底に、その後2000年までずっとプラスです。日本は1997年にアジア通貨危機で株価は下落、しかしこのときの米国、ドイツなどは株価が史上最高値を更新中でした。ダウは大きな差がつきました。さらに1998年のロシアデフォルトでトドメ、、、さて米国鉱工業生産指数の対前年比は2004年夏から下落中。このため日本の株価も2004年12月までは低迷しました。日本では新興市場の上昇に次いで、6月から大型株も上昇。これはマクロ指標で企業利益が最高であるにもかかわらず、積極的な設備投資を控え、オーナー利益=株主への配当増加につながり、低金利もあいまって株価は上昇。チャートを見ると、まだ米国鉱工業生産指数の対前年比は底を打ったか、完全に明らかではありません。1)ハイテク産業を除いた企業のサイクルは緑の線で示したようなサイクルであることが知られている。2)チャートでも明らかなように、日本の鉱工業生産出荷在庫循環モメンタムは米国鉱工業生産指数よりも先行して底を示すことが多いのですが、底からの上昇を示している。同時にモメンタムよりは少し遅れて上昇する傾向がある時間外労働対前年比もすでに上昇を開始している。よって米国景気はほぼ底と思っています。欧米人は肉食で攻めは強いが、守りは弱い。日本人は草食で守りは強いが、攻めには弱い。バフェットは日本人的で下がってきた株を買いますが、彼がウォルマートなど米国株を大量に買いだしています。おそらくGMのショックでウォール街は自国経済に警戒し、まだ様子を見ているのではないでしょうか?そこをバフェットは買っている?http://plaza.rakuten.co.jp/ossanpower/diary/200512310000/
Jan 2, 2006
コメント(0)
-
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。以下は企業法人統計の製造業青が経常益ピンクが設備投資黄色が経常益-設備投資のオーナー利益?です。今の日本はかつてないほどオーナー利益が高くなっています。もっともこの6期はピークのまま上下していませんが。1989年は大証平均が39500円でピーク。その時点の経常益よりも、今は高い。現在の大証平均は30500円ここから先は本間宗久が言ったように人の心が相場を決めるのかもしれません、、、1990年初頭、平成バブルがはじけるときには、現物買いの、日経先物売りが極めて顕著だったようです。しかし、米国の景気サイクル(ハイテク産業を除く=いつものチャートで示している線です)は今が底でこれから上昇に転じます、、、、これが今の日経が上昇している理由と考えています。つまり先取り。それともファンダメンタルに基づいた戻し?100%景気に先行するといわれる米国株価はこの1年動いておらず、この上昇がないかぎり、日本株は調整をすると思います。多分17200円くらいをピークに、、、その後はもっと上に行く?これは初夢かもしれませんが、、
Jan 1, 2006
コメント(2)
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
-

- 株主優待コレクション
- ブルーノから株主優待が届きました♪
- (2025-11-25 00:00:14)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 【楽天】寒い季節に◎母は納得、息子…
- (2025-11-24 20:10:04)
-