2006年07月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
為替のひとつの仮説
円ドルに関する人間の心理変化を、経済指標から表現できないかを考えているんですが、、、、たとえばステップ1:原油高、、ステップ2:原油高で困るのは、輸入国とくにエネルギー効率の悪い国ステップ3:マクロと株価上昇、それに遅れて金利上昇開始、ステップ4:金利上昇は続く、くわえて原油高も長く続くと1.5年後くらいには、徐々に商品に反映され、経済を蝕み始めるステップ5:そして今、、、新たなステップ1:何らかの事象がトレーダーに不安を抱かせる。米国の巨額赤字とドル高傾向(2005年12月)ステップ2:ある権威者が不安を肯定するような発言している事を知るステップ3:過去に該当するようなデータを調べるステップ4:疑念が確信へと変化するステップ5:やがてトレンドが始まり、それを裏付ける。ステップ6:円高になる、、、ステップ7:今度は日米金利差と日本の政治家が選挙日程を気にして、消費税引き上げに関する甘い認識を示し、日本の財政破綻への不安が再浮上する、、、このような心理変化を経済指標の推移から表現できないか考えているんですが、、、一応、経済指標に基づいて、為替の順位相と逆位相、その転換点という観点で為替変化を捉えられないだろうかと考えています。今日は仕事で疲れているので、チャートだけ示します。追記1)先日のチャートで示しましたように,日米金利差の逆数が機械受注の線にヒットするあたりが金利のピークである(過去3回正しい).2)金利のピークは円高である.3)現在は為替がマクロ指標ブレンドに対して位相が正の関係となっている.ある程度の円高にこれからなるが,未来のどこかで位相がマクロ指標ブレンドに大して逆の関係になる時が来る.その時点でいつものとおり,機械受注の線に合わせて円安トレンドに戻っていく(過去3回正しい)というのが,私のシナリオです.位相の転換は人間心理の転換というかコンセンサスの転換を意味するものと考えているんですが,ある程度円高にならないと生じないのかもしれませんが,,,円高がきたら106円,101円がきたら追加買いを行ないます.本当はこないような気がしているので,それ以上は考えていなかったのですが,NZドルを少し動かそうかとか考えています.
Jul 31, 2006
コメント(0)
-
今月のポートフォリオ 追記しました
ポートフォリオをまとめてみました。13銘柄の加重平均指標はPER 17.7 PBR 2.2 ROE 14.0 PSR 2.2 配当2.8%ただコカコーラと任天堂をはずすとPER 10.811.8PBR 1.2ROE 9.5PSR 1.21.0に低下し、グレアムの基準PER*PBR
Jul 30, 2006
コメント(3)
-
こんな不景気はじめて
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/07/27/20060727000043.htmlこんな不景気はじめて韓国のタクシー運転手の嘆きです.タクシー景気は庶民経済の風向計エネルギー効率は日本よりよくないんでしょうけど,,日本と中国のハザマに挟まれた感じなのかな?売上の減少を各社がタクシー台数を増やして補おうとして,さらに過剰になり,自滅する現象.これは平成バブル後しばらくしての日本でも観察された現象.韓国もこれから何年か厳しいのかもしれません.電機産業では日本企業がノウハウが漏れないように国内に工場を移し始めており,以前のようにすぐにマネして,価格で勝負という作戦がとれないようです.歩留まりが上がらないため,大型液晶では日本メーカーの価格のほうが優位に立つ現象が観察されます.中国は韓国よりもエネルギー効率がはるかに悪いんだけど,ほんとに大丈夫なんだろうか?といいながらも今月は香港経済日報と博智国際の2銘柄購入.2つとも他のブログの方を参考にさせていただいたものですが,,これで証券投資額は投資用資金の5%になりつつあり,13銘柄となった.いつの日か中国も任天堂を輸入してくれるようになれば,大ブレイクなんでしょうけど,,,,中国の格付けは韓国を上回る状況,,http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/07/28/20060728000009.htmlFRBのベージュブックによればボストンだったかでは車の売上が20%減となっている.http://www.federalreserve.gov/FOMC/BeigeBook/2006/20060726/1.htm元気なのは中国,そして今後の日本?UFJの嶋中さんは来年もドル安と予想,,,,ドルの買い増しは来年かも,,http://www.ufji.co.jp/shimanaka/weekly/2006/rate060724.pdf
Jul 29, 2006
コメント(6)
-
大証修正平均 追記しました
去年の秋から暮れごろは大証修正平均がどのくらいか気にされた時期もありますが、現在の大証修正平均(2000年以前の日経平均と連続性が非常に高いとされる)は28000くらいです(矢印の先の白丸)。これを1978年からの長期系列で示し、また日米金利差と株価の関係を見てみます。また米国の鉱工業生産と日本の鉱工業生産の出荷指数を示します。分析しようかと思いましたが、今日は仕事が忙しく疲れたので、また今度にします。米国のダウは少し足踏みのようですが、個別に見ると高配当の銘柄の株価がじりじり上昇しているのには気がつかれていますか?追記1)プラザ合意以前の1978年から米国金利がピークのときにドルを買っておくのは,2年くらいのスパンで考えると6回中6回とも正しい.2)ただしプラザ合意後の超円高を見れば判るように,やめ時は注意を要することが1回あった.それは日本がバブルに突入しているとき,,,ここまで書いて気がついたこと,今の日本,,バブル途上じゃないですよね,,ここで超円高は中国との整合性がとれないし,,3)今回の合意はどの程度重みを持っているのか?おそらく日本が米国債をどんどん売るほどの状況になることはないはず.それに1981年はコンドラチェフの山であり,60年スパンで考えると金利のピーク,今は谷に向かっているので,次は金利の底である.4)ということで米国金利ピークは円高になっているので,ドル買いと結論する.5)株価について1990年の平成バブル後,1995年は例外的に金利のピークでありながら株価が上昇している.これは超円高不況からの立ち上がりで,米国の株価上昇につられるように上昇した.いまはちょっと違う.それは大証修正平均でみると鉱工業生産出荷と株価の乖離を見ると判る.現在は十分に上がった状態であり,1995年の円高不況からの立ち上がりのような株価の上昇はあまり期待できないと思うのだが,,ただし法人税は当時と異なり下がってはいるのでPER的には低く,株主有利な時代になっているといえるのだろうけど.6)証券に関しては,姿勢を低くしてもっと判りやすい局面を待つことにする.少しずつの買い増し程度で,,ただし今回の景気で平成バブルのようなヘッドアンドショルダー型のバブルを形成するなら,それは中国と考えている人が多い.個別銘柄の基本は逆張りだが,長期的な流れに逆らうことは無謀.証券は中国を主体に考えていく.米国では債券のような銘柄と債券を主体.1990年が日本バブル,2000年が米国バブル,2010年はどこかで大バブル?2010年にもし来るとするとバブル以前の10年くらいに通貨が大きく動いた国はどこだろう?ロシア?
Jul 27, 2006
コメント(0)
-
円とドル、そして任天堂とフェイス 追記しました
1987年からのチャートで判ることは以下のとおり。1)日米金利差、米国の金利が概ねピークになるまで円高になる。(過去3回とも正しい)2)機械受注と円ドルでは、私が使っているチャートで機械受注額とほぼ同じ高さまで円安は進む(過去3回正しい):現在でいえば145円前後予測される。現在の分析1)米国金利がもうすぐピークとなれば、円高はここで概ねおしまい、機械受注、鉱工業生産ともまだ伸びており、2008年初頭からの景気サイクルにつながれば、2009年3月頃に145円程度の円安ピークを迎える。もし次の景気サイクルで失速すれば、円安は早まり2008年初頭ごろに145円の円安ピークを迎える。2)米国金利が今後さらに上昇し、日本金利がそれほど上昇しなければ、さらに一段の円高がある。3)以上の転換点は2006年8月から2007年2月頃までの今回の景気ピーク時に明らかになる。この期間に急速な円高を迎えれば、その後は円安へ(当たり前か)。この期間に125円を超える円安になれば、その後は円高に推移し、たぶん2009年夏までそれは続く。この場合は1)で述べたよりもさらに長期で今回の景気が続く事が前提。4)つまり、2006年7月時点では急速な125円程度の円安シナリオは考えにくく、ここから米国金利ピークを確認する頃までは、ある程度円高に進む。米国金利も今後もうすこし高くなり、その後横ばいになる。ここで2008年初頭からの景気サイクルにつながれば、2009年3月頃に145円程度の円安ピークを迎える。というのがメインシナリオと考えた。金利のピークあるいはその継続は原油が米国の消費者物価に反映し、その価格が明らかに落ち着いた頃までと考えた。5)原油、日米マクロ指標、国債金利をそれぞれ予測して、円高の目安はどのくらいかと考えたが、108円くらい?でも米国金利ピーク後に原油、株価、マクロなどがグンと下落すれば、もっと円高になると考えた。でも、ないような気がするが。米国については下方修正が相次いでいるとはいうけれど、、6)GSの今後6ヶ月で98円になるという予測レポートは原油も株価もマクロも下落することを暗に示唆しているのか?ソロスは2年間ドルが下落するだろうとささやいているが、彼のささやきは時に相手の反応を見るために使われるという。7)ということで、今もっているドルは保持しながら、円高になれば106円、101円で買い増しする予定。というか円高になれば買い増しする事に決めているので、あえて予測する必要性は薄いのだが、、、8)為替ヘッジをしていない任天堂は円安になると利益が激増するのは知られているが、ホルダーとしては為替の推移による、こちらの利益動向が気になる。いまはびっくりするほど好調な株価。急騰したメガチップスから去年の12月はじめに乗り換えたが、それから起算すると60%くらい上昇した。9)米国金利については今年の11月まで上昇すると想定し、それまでは円高傾向になると考えている。ここまで書いておいて、間違ったら恥ずかしいが、何らかの仮説を立てて、そのシナリオが来ない場合も含めて対策をとっておいたほうが気が楽だと思う。10)それにしても持ち株のフェイス、ほぼ半値まで下落した。ナンピンしたいのだが、もう2番底にタッチしているような感じだし。ただ金額倍率はまだ2.9倍くらい。この率はまだ去年の12月初めと同じレベル。金額倍率がこんなに高くなければ、買い増ししたいところだが、今月は待ってみる事にする。追記:チャートからもう一ついえることは日米金利差(いまの場合はほとんど米国金利)が最大になった時点でも,機械受注額は道半ばであるということ.(過去3回正しい).したがって,今回の景気は現時点でも単なる踊り場で,ここで米国が金利を下げ始めれば,今後さらに大きな上昇が残っている可能性があると読める.それが株価につながるのかは判らないが,ということで,少しずつだが毎月,証券購入を継続.いずれ円安は来るだろうし,株も,まだ上昇余地があるかもしれない.またこのチャートだと機械受注と金利の線がヒットしたあたりが金利のピーク(過去3回正しい)なので,ドルでずっと保持する場合には,そろそろ短期債券から長期債券に変えておくことは,概ね正しいと思う.8月は下がった株のナンピンと短期債券の一部を長期債券に変更する作業を行なおうと思っている.
Jul 25, 2006
コメント(0)
-
バフェットが引き受けたプット
バフェットは下がらないほうに賭けたということは、プットを売ったと言う事になるのですが、どのくらいのだったんでしょうか?プット売りはノックイン債券とおなじようなものと思うのですが、、http://www.irnet.co.jp/k-report/archives/2006/06/post_20.htmlITバブル後の止めを刺したという負のスパイラル
Jul 22, 2006
コメント(0)
-
「大いなる逆張り」
301回目のブログです。http://www.1ban.co.jp/「大いなる逆張り」立花証券の会長さんの退任前の最後のメッセージ業界では自主規制があり、活字ではあからさまに「売れ」とは書けないということを創業者の石井さんは述べていたと思います。投資を開始してからちょうど2年の折り目であり、悲観的に考えてこれから5年間、2011年まで次の相場が来ないことを想定して、そのときまでに資金のどのくらいを証券に投資しても良いか、自問してみました。投資資金の概ね25%、これをゆっくりとドルコスト平均法のように個別銘柄を考えて買っていくという手法なら、長く続けていけそうに思います。時には少し売りながら日本株についても、もう少し醒めたところで見直してみようと思います。ところでカブドットコム証券、なかなかよさそうですね。シニア割引拡大、、、ゆっくり買うのに適したプチ株というのもあるし私にとってはちょっと魅力的です。
Jul 22, 2006
コメント(2)
-
勘定あって銭足らず
今日は早起きして、すこし勉強中。ちょうど2年前の今日、投資をはじめた。ブログも300件になった。岩戸景気からいざなぎ景気まで、1961年から68年までの7年間、株価は低迷し、昭和40年不況のような状態に今後なったとしても、投資を続けていられるか、自問しているが、、、、やはり全体の資産を考慮しながら、学びながら本当にゆっくり買っていくしかないように思う。年初来対TOPIXではたぶん初めて+15%を超えた。設備投資を示唆する機械受注額は2002年1月の底と比較して約49%増加した。時間軸も前回よりかなり長いので、総額(面積)は相当大きいものになった。勘定あって銭足らず。キャッシュフローの推移を良く見て、黒字倒産(特に中国)に注意しておこう。そもそもバリュエーション変動の標準偏差が最も大きいのは鉱業、海運。ファンダメンタルリターンの標準偏差が最も大きいのも同じ。しかも長期循環であり、キチンサイクルのような短期循環ではない。不動産もたぶんそうだろう。バフェットのいうROEの低い企業は、成長がむしろ害になる事があるというくだり、、企業が得た利益だけを再投資して将来への成長資金をまかなう場合を考えると株主資本の成長率(ルックスルー利益の成長)はROEを上回る事はできない。ROEの低い企業で借り入れの大きい企業はそもそも競争力がなく、景気循環ごとの利益変動が大きい、、アビチャイナ?今回の景気で上昇した企業のROEのうち、どの程度が景気循環によるものであるかについて、いずれよく検証してみよう。グロースに見えても景気が悪化すれば、どのくらいメッキがはげるのかについても、、
Jul 21, 2006
コメント(4)
-
USドル
http://www.mbf-fx.com/blog5/こちらの方は,NZドル買い推奨USドルについては先週GSが今後6ヶ月で98円に下落するというレポートを紹介されています.そうですよね.NZドル有利なら,USドルは下落するシナリオが成り立たなくてはなりません.このシナリオ,少し無理があるようにも思うんですが,,,あるいは経団連が1995年に予測した日本破綻?シナリオである。超円高により企業が傷み、その後超円安に向かうというシナリオなんでしょうか?当方のウエイトはNZドル4%,USドル28%,CP(JPN yen)48%どっちに動くのか,しばらく様子見.強い円高になればさらに33%追加する予定USボンド(長期)を購入した後の為替ヘッジの方法について検討中.以下は現時点で考える目標のasset allocationです。
Jul 21, 2006
コメント(0)
-
金額倍率 追記しました
http://www.traders.co.jp/investment/margin/transition/transition.asp金額倍率、、去年の12月と同じくらいですね、まだ。悲観しながらも、恐怖より、まだまだ期待を持った悲観が多いんでしょうねいざなぎ景気などでは、大型株がいよいよ下がり始めると、需給関係から一時的に小型株が上昇する現象が見られたようですが、マクロが今年暮れから下がり始めると、同じ現象がみられるかもしれません。秋に新興市場を安く買っておけば、そういうカウンターが効くかもしれません、、グレアム投資というかバフェットが若い頃やっていたシケモク投資も有効になるかも。噴き値売りというか、、これをworld wideで考えると、大型市場がいよいよ下がり始めると、小型市場のインドや中国の上昇が一時的にみられ、今のうちに安いところを買っておくとカウンターが効く可能性があるということかもしれません。今のところもっともパーフォマンスが良いのは中航科工、12銘柄中もっとも恐る恐る買った銘柄です。年初来:対TOPIXでは+14.5%、基準価格は10460円対TOPIXで良いように見えるのは毎月買い増ししているので、直近に買った銘柄がすぐに下がらないため見かけ上成績が良くなっているようにみえるに過ぎません。バフェットの年次成績がSP500が悪い時にも、対SP500でよいように見えるのは、逆張りのため同じような現象が生じているのかもしれません。このような現象はさわかみファンドでも観察されます。下がり始めは相対的に成績がよく、下がり始めても落ちにくいのは逆張りをしているからにほかありません。これがバリュー投資というものの特徴ではないんでしょうか?
Jul 20, 2006
コメント(0)
-
気になるのは
気になるのは,ファイザーなどほとんどの製薬会社大手は昨年から今年にかけて,韓国から工場をいっせいに引き上げていることですね.あからさまにはしてませんが,北朝鮮リスクはけっして低いものではないと企業は真剣に考えているんではないでしょうか?なんだか南半球の通貨に惹かれるものを感じてしまいます.http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/04/20/20060420000046.htmlコカコーラの足元も安泰ではありません.ホルダーとしては気になるところ,,,朝鮮日報,,なかなか良い情報が得られます.http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/07/18/20060718000041.html
Jul 19, 2006
コメント(4)
-
双日とフェイス
双日とフェイス両者とも2番底に向かっていますね.特に双日はちょうど2年前と似た感じ,,,あのときは8月はじめがセイリングクライマックス.今日は364円,2年前はたしか378円で買った.もっとも今回は米国金利上昇,為替円安傾向と2年前とはいろんな意味で異なっているが,,,ハンセン、ダウ、日経と並べて見比べているんですが、月足でみるとピークをつけるのはもっとも日経が早く、つまり下がり始めるのも最も早い、また立ち上がるのはもっとも遅いんですね。つまりどこよりも熱しやすく、冷めたときは羹に懲りて膾を吹くのが日本人なのかも、、、ハンセン、ダウ、日経の平均指数の円換算と機械受注の推移を見比べているんですが、買っても良いぎりぎりまで日経が落ちてきているような気がします。月足テクニカル的には、多分まだwaitと思いますが、少しHKドルを円に戻しておこうかとも思います。でも今年の11月以降をどう読むかですよね、、、思いのほか景気が落ちないのか、それとも一気に落ち込むのか、、、米国鉱工業生産と日本の勤労統計が発表になっていましたのでマクロ指標を更新。悪くない、今月もすべて上向きだし、スピードも悪くないんですが、、、しかし8月8日の米国政策金利発表までは相場は弱そうですね、
Jul 18, 2006
コメント(0)
-
40%下落した株は、60%上昇した株と相殺される
30%下落した株は、40%上昇した株と相殺され、40%下落した株は、60%上昇した株と相殺され、50%下落した株は、100%上昇した株と相殺される今年はひとつも売らずに12銘柄を集めてみて、、、上の言葉が実感として判りました。流れを当てにして、銘柄選択が甘くなるとうまくいかないし、予想不能なファクターも伴う。何かの本に「成長投資家は循環投資家のカモ」と書いてあったけど、どういうことかというと、買う時は成長投資家を自称し、下がりだすと豹変して、売り急ぐために循環投資家の餌食になるということであった。つまり一貫性のなさが「カモ」になる原因なのだろう。ミスターマーケットの餌食、、、上に行っても売らないなら、下に行っても売らないこと。上に行ったらすぐ売るなら、下に行ったらなおさらすぐに売ること。これなら一貫性がある。今もっている12銘柄、、持っていることを忘れようと努めているが、、次は景気循環に基づいたインデックス投資を検討中、こちらは完全な「循環投資家」になるわけだが、、個別銘柄は「売らない方針」。その一方で無機的なインデックスを相手に景気指標を基にした「循環投資家」を演じる。このような2面性を持つ事は、やはりカモになるということだろうか?個別銘柄とインデックスとの間に本質的な違いを見つけることができればよいのだが、、それはその企業を十分熟知する作業が必要ということになるが、それほど時間に余裕があるわけではないし、、、その一方でアセットアロケーション中には為替に注目した外国MMFを所有している。これなどは安く買って、上がったら売りの際たるもの。もう一度、投資方針を見直してみる必要がある。いずれにせよ逆張りという点では一貫性を持ちたい。皆が欲しない時期、銘柄、通貨を引き受ける方針なら、皆が必要とするときに手放すのが自然なような気がしている。上がったものから売っていき、だれも買ってくれないものはずっと持っている???これじゃだめか?バブル期に購入し、値下がりしたゴルフ会員権をずっと償却せずに、含み損を抱える経営者のようなもの、経営や運用にはそれなりの結果責任が伴うが、それを回避しているようにも思える。自分は一家の主たる経営者であり、結果にたいする責任は一定期間で結論を下す必要がある。あまり短いとプロのファンドマネージャーと同じなってしまうので困難。ちなみに研究の場合は、質の低い論文を大量生産する傾向がある日本とは異なり、米国では2年に1本くらいの割合で質の高い論文がでればまず標準的である。どのくらいが適当かは判らないが、年3回くらいは検討し、シュロス親子のように平均4年間の保有くらいではどうなのだろう?景気循環を期間を考慮に入れると当たらずとも遠からずか、、買う前に自問すべき言葉「半分になっても持っていられるか?買い増ししたいと思うか?否ならば最初から持つな」でも難しいですよね、実行するのは、、なかなか
Jul 17, 2006
コメント(0)
-
Asset Allocation
投資用資金をどのように考えるかですが、山崎元さんや木村剛さんの本を参考に、現在のAsset Allocationをまとめてみました。NZ-MMFについては債券というよりも証券のつもりでいたほうが無難と考えています。8%程度の証券を半年で購入したと考えています。1年目のAsset Allocationとしては、債券中心であり、まあまあなのではないかと思います。現在の証券投資額はNZ-MMFと同額程度ですが、次はこの辺をもう少し考えていこうと思います。日本円のキャッシュフローがあるわけなので、為替については円が高い時には円を使って生活し、ドルが高い時にはドルを使って生活するというような考え方が正しいのかな?それなら、藤巻さんのようにほとんどすべてをドル建てにして、必要な時は米ドルMMFをおろして使うというのもシンプルでよいのかもしれません。投資用資金の75%を外貨建てにしても、生活防衛資金とキャッシュフローが円建てなので、それでよいと考えています。
Jul 16, 2006
コメント(0)
-
中間選挙
何を待っているか?前回の中間選挙は世界貿易センタービル崩壊後を受けて、珍しく与党が勝利。今回の共和党はこのままでは勝ち目なし。金利はすでに上限に近く、引き上げ終了となれば、原油関連銘柄の上昇、、今年に入っての交易条件の悪化(輸入物価指数の上昇=原油の上昇)は厳しく、何らかの米国政府を主体とした先進国の強力なアクションを期待、、、景気もその辺がピーク、、、金利高によるドル高マジックだけでは乗り切れないはず、、アクションがなければ、資金のほとんどは債券のままに、、株式も配当重視の基本バリュー戦略共和党も座したまま敗北することはないと思うが、、GMも救えない、、、今回のエネルギー問題は前回の中間選挙あたりが発端だし、、輸入物価指数が下がれば、今の経済の強さからして、株価は上昇、少なくとも下がる事はない。これはバフェットの読みと一致する。中国は2008年の北京オリンピックをこえて2017年まで堅調となる大バブルもきたしうる。(東京73年まで、韓国もオリンピック後同じく9年間堅調だった。)すべてはエネルギー次第、、http://www.hkd.meti.go.jp/hokpp/humanenergy/030118/index.htm
Jul 15, 2006
コメント(0)
-
今月買ったのは
今月買ったのは HKETホールディングス経済日報集団香港の新聞がこれで2銘柄になりました。ウエイトは7%くらい。これで12銘柄になりました。銘柄をかえているとはいえ、今年は毎月買って、売っていませんので、ドルコスト平均法のような状態です。今日は少し円安になっていますね。
Jul 13, 2006
コメント(0)
-
ポートフォリオの再検討
本日の株価でポートフォリオの再検討中です。個別銘柄のリターンは今年の配当分を含みますが、基準価格は株価を円換算したものです。配当は購入時価格に対するものです。1)米国はダウ銘柄が少しずつ上昇中ですね、、、2)中国は自動車株が再び上昇開始3)日本は任天堂の配当利回りが現在1.91%ほどマクロ指標、景気サイクルとも上向き。こうして上昇機運に乗るのも良いんだけれど、やはりどこかで席を立つべきなんでしょうね、、、今年は売らないつもりで、少しづつ買い進んできましたが、、、たとえば年3回とかValueの面からポートフォリオを見直すことが良いように思えてきました。これでマクロ分析からバリュー評価まで2年かけた勉強も一段落。今月は中国株を1銘柄注文中。株式の投資配分は中国5:米国3:日本2くらいに考えています。
Jul 12, 2006
コメント(0)
-
ポートフォリオを見直し
自分のポートフォリオをPER,PBR,ROEでまとめてみるととても割安株を目指しているとはいえない状況を自覚。経済指標のことにばかりとらわれて、いつのまにこんなになっていたのか、PER高すぎ、、見直しが必要、、
Jul 11, 2006
コメント(0)
-
中国の原油輸入量 先ほどのは間違いのよう
http://news.goo.ne.jp/news/reuters/keizai/20060626/JAPAN-218672.html?C=S昨年は輸入量の伸びが減少、今年は急上昇、、、[北京 26日 ロイター] 中国の税関当局によると、5月の原油輸入量は前年比20.5%増の1239万トンだった。 5月の軽油輸入は同38.8%減の1万5492トン。燃料油の輸入は同53.2%増の248万トンだった。 ガソリン輸出量は同60.6%減の26万4579トン。軽油輸出は同40.2%減の7万9123トンだった。 1─5月の原油輸入量は前年比17.9%増の6155万トンとなった。以下は1年前の記事 2005年上半期原油輸入の伸びが大幅鈍化 2005/07/26(火) 10:40:03更新 中国税関によると、中国の2005年上半期(1-6月)の原油輸入量は前年同期比で3.9%増の6340万トンで、伸び率が大幅に鈍化したことが分かった。25日付で香港・経済通などが伝えた。 中国税関の統計では、2004年上半期の原油輸入量は2003年上半期と比べて、34.8%という高い伸び率を記録していた。それに対して、2005年上半期の伸び率は3.9%増にとどまった。6月の原油輸入量は前年同月比で0.1%減の1125万トンだった。 軽質ディーゼル油の6月の輸入量は前年同月比で86.9%減の3.34万トン、燃料油の6月の輸入量は同19%減の255万トン、ガソリンの6月の輸出量は同8.7%減の45.81万トン。中海コンテナ、少し戻しませんかね?ここはBDIバブル、金バブル、大豆バブル、つぎつぎとバブルが生じはじけていくさまが経時的に見れますhttp://investmenttools.com/futures/bdi_baltic_dry_index.htmhttp://www.nykline.co.jp/ir/library/market/index.htm
Jul 11, 2006
コメント(0)
-
鉱工業生産
メモです。7月13日が日本鉱工業生産7月14日が日銀金融政策決定会合7月17日が米国鉱工業生産8月8日が米国政策金利予測2006年11月 日米鉱工業生産ピーク 2007年12月 1ドル140円現在の輸入物価指数2006年5月 133.6 過去の輸入物価指数の推移132.3 1979年5月136.8 1979年6月144.2 1979年7月151.7 1979年8月156.9 1979年9月162.9 1979年10月175 1979年11月184.4 1979年12月200.8 1980年1月214.1 1980年2月217 1980年3月219.7 1980年4月206.6 1980年5月200.4 1980年6月203.1 1980年7月208.2 1980年8月203.5 1980年9月197.9 1980年10月200.4 1980年11月198.6 1980年12月195.3 1981年1月198.3 1981年2月201.7 1981年3月205.7 1981年4月210.6 1981年5月213.1 1981年6月216.6 1981年7月217.8 1981年8月215.1 1981年9月215.9 1981年10月212.3 1981年11月207.8 1981年12月210.3 1982年1月217.2 1982年2月220.5 1982年3月223.1 1982年4月218.2 1982年5月224.2 1982年6月229.1 1982年7月231.4 1982年8月234 1982年9月238.8 1982年10月これがコンドラチェフの山 1981年、1982年しかし1980年代と今は違う、今はコンドラチェフの谷の前の2次的物価上昇の時期。よって早晩、原油価格は下落し、先進国は軒並み、これまででもっとも低金利になるのではなかろうか?これから買うなら債券のような株、相場から忘れ去られているようなもの、、、、米国株 ダウジョーンズの高配当銘柄は少しづつ上昇しているような、、、少し混んできたか??今月で実際に投資をはじめて丸2年になりました.振り返ってみると早かったです.いろんなことを学んだと思いますが,どのような手法にせよ近道はないと感じています.最初は毎日一喜一憂,今は週1回くらい一喜一憂,持っていることを忘れられる心境になるまでは,なかなか時間がかかりそうです.月1回,持ち株集計とマクロ分析時に投資について考えても,それほど結果が変わらないように思えています.
Jul 10, 2006
コメント(2)
-
中国のバブルは来るのだろうか?
中国のバブルは来るのだろうか?チャートには交易条件の逆数=悪化(輸入物価指数-輸出物価指数)を加えています。輸入物価指数の上昇は概ね原油が主体となります。このような交易条件の高さは1985年以来です。原油高から中国の交易条件も日本以上に悪化しているかもしれません。1985年はドル安が容認され、その後10年に及ぶ円高が続きました。交易条件の歴史的悪化を乗り越えた時に、日本はバブル領域に到達。要するに円高になったため、輸入物価指数が急速に低下、輸出物価指数が上昇して、交易条件が一気に改善しました。消費経済が豊かになり、バブルへ、、、中国も元の切り上げが予想されますが、今の資源高相場が崩壊した時に、一気に交易条件が改善し、株価はバブル領域に向かう?それはROEが高い中国?なんて考えています。ただ1985年当時の日本ほど付加価値の高い物を中国が生産しているとは思えないので、おそらくは2030年とかもっと先の話ではないかと思いますが、、今の中国はまだエネルギー効率が非常に悪いと言う点でも、日本とは異なっています。また輸入物価指数が上昇しているにもかかわらず、金利が上げられない日本は長期的には通貨下落の主役になりうると思うのですが、、、また金利上昇による国債価格下落は、大量に保有する金融機関の資産減少を招く事になります。
Jul 9, 2006
コメント(2)
-
米国鉱工業生産の出荷ー在庫循環
http://www5.cao.go.jp/keizai3/shihyo/2006/0626/733.html米国鉱工業生産の出荷ー在庫循環が2月ピーク最近の鉱工業生産の米国サイクルは25ヶ月程度これは日本も同じで在庫の少ない状態が続いている.デフレが進行すると期間が短くなり,チャートが針のようになると,何かに書いてあった.今回の景気でデフレ脱却ならサイクルも少し長くなるはずだが,,,分析では生産、在庫管理の技術が上昇し、在庫率を低く抑えることが可能になったことから、在庫調整に要する期間が短くなったとしている.在庫が少ないことはよいことだが,出荷ー在庫循環を経済指標として過去と比較するときには注意か必要かも.日米マクロとしては1)日本鉱工業生産 出荷ー在庫2)米国鉱工業生産 指数3)日本製造業30人以上の時間外労働時間の対前年比の3つをブレンドして判断しているが,個々の数値に大きな乖離がないか気をつけておいたほうがよさそう.
Jul 8, 2006
コメント(0)
-
イヌに税金
イヌに税金がかかるかつての日本ではイヌを飼うことに,市町村が税金をかけていたようです.中国では年間数万円の税金がかかるので,イヌを飼うことは大変な贅沢のようです.日本も財政が厳しいですから,そのうちペットにも住民税のようなものがかかるようになるかも,,,国民負担率を調べていてみつけたブログです.http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/f2fd3e181bb2681a49256fe90016edfe/746895bb765031e0492570d1008142e4?OpenDocument
Jul 7, 2006
コメント(2)
-
法人税の上昇
簡単なメモです日銀のレポートからhttp://www.boj.or.jp/type/ronbun/ron/wps/kako/data/cwp00j06.pdf仮説ステップ0:人口構成の若さ、1950-60年代の日本、低い国民負担率、国民皆保険、年金の登場ステップ1:1970年代の日本。法人税の上昇が株主利益を妨げた=国民負担率の上昇ステップ2:なぜ国民負担率が上昇したか、高齢化と人口ピラミッド、1980年代の上昇は通貨の切り上げ、PERの上昇、すなわちearnではなく、priceの単なる上昇ステップ3:高いPERは正当化(=これはマスヒステリーへとつながる。いろんな株価指標(PSR,PEGなど)を用いて正当化され、株主利益が損なわれても、そこそこ株価は維持されるステップ4:高いPERの崩壊、あるいは通貨切り下げ、あるいは両者が発現する。ステップ5:歴史は繰り返すが、その国がステップ0に戻るには百年以上を要する。海外から投資する立場なら、GDPに対して実質国民負担率が低い国は、ROEが高く、投資対象に値する。earnの上昇、priceの上昇、それに通貨の上昇の3つを享受できる。引き上げ時期は通貨の切り上げ、PERの上昇を経て、マスヒステリー状態のとき。もしそれが判らなくても、他国と比較して高いPERを容認する時期。潜在国民負担率は税および社会保障負担分に財政赤字、不良債権分を推定で加えて求める。あるいは国民給付率(国民負担+財政赤字)の高さは、株主利益と相反するものであると考えてよい。米国の場合は累積の貿易赤字も考慮に入れるべき?すごい額になって、かつ急速に上昇しているが、、、株価がどうして上下するのか判らず、その不安から経済の勉強を始めて1年、、やっといろんなブログで言われていたことが、見えてきた感じです。いろんなことを知るにつけ、株価を客観的に見れるようになってきたともいえます。そろそろ、この勉強もペースダウンしてもよさそう。投資も4ヶ月に1回くらいで、、よさそう。指標分析も毎月でなく同じくらいでよさそう。いろんなものにリスクを分散して、素人でもおやっと思うくらいの時をなんとなく待つのがよさそう。以上がこの1年の勉強の結論のようです。
Jul 5, 2006
コメント(0)
-
歴史から見た外国債券投資
「歴史から見た外国債券投資の意義」という年金総合研究センターのレポートによれば,1980年初頭(コンドラチェフの山)の債券金利は15世紀以来500年ぶりの高金利であったようです.16世紀,17世紀は金利が下がり続ける時代であったようです.そして少し前の日本の金利は歴史上初めての最低金利,第2位は1600年代初頭のイタリアで1.1%というのがあるそうです.いったい金利ってなんだろう,通貨価値てなんだろうという根源的な疑問が生まれてくるような歴史です.sunspot 太陽の黒点サイクルからすると,株価は2003年が大底のような気がするんですが,,,ちなみに資源国通貨である豪ドルとNZドルの両者の関係をsunspotサイクルと比較すると面白いです.http://www.pfa.or.jp/top/syuppan/pdf/saiken_kenkyukai04.pdf
Jul 5, 2006
コメント(0)
-
バイアンドホールド戦略
ERP累積指数をみると1970年代以降の日本株式のリターン(プライスではなく、ルックスルー利益と解すべきか?)は債券と変わらないことを示している論文です。つまりリスクに対するプレミアムがないことを示しています。http://www.saa.or.jp/publication/2005yamaguchi.pdf1970年代までは企業利益の上昇によって株主はそれなりの利益を得ていたが、それ以降の30年はPERのうち、earnではなく単にpriceのほうが上昇したこと(PERの上昇)により、平成バブルまでは見かけの利益を得ていたということになります。バフェットがいうようにROEが低いと株主の利益にはならないことを示しているものと思われます。バイアンドホールド戦略が正しくない期間は思いのほか長期間続く事があるのかもしれません。著者は失われた30年と表現しています。法人税の高さが株主の利益を失わせた、リスクプレミアムが失われた主要因、、、米国については高くなったPERがこれから低下するのでしょうが、それはEが減らずともPが減る事によるものなのでしょう。長くとも景気循環単位で短期的に上昇したら売るのが、現在の日本株式については正しい戦略のように思えます。バフェットが永久保有銘柄としたコカコーラも、今は売っていればよかったと言ったそうですが、長期的なプライスの下落を後になって理解したということなのかもしれません。この論文は大変ためになりました。日本、米国とも超長期的な株式の漫然たる保有はたとえEが一定であっても、今後のPの減少により、、利益を得られない可能性がありますねえ、、リスクに対するプレミアムがない市場でテクニカルに過熱を示しているなら、株式の漫然たる保有は丸腰で戦場にいるようなものかもしれません。タイミング(もっと言えばこれから市場が過熱してくれそうか、冷えそうか)が大事といえます。日本のPERは米国と大差ありません。時価総額における金融業のシェアというのはなかなか面白い視点です。
Jul 4, 2006
コメント(2)
-
常温核融合
医学とは関係のない常温核融合の文献ですが,将来は普通の家庭でも安全な核融合から簡単に電気を取り出し,原子力発電所がいらなくなるかも,,1:E . Yamaguchi and T. Nishioka :”Direct Evidence for Nuclear Fusion Reactions in Deuterated Palladium”, ”Frontiers of Cold Fusion” Frontiers Science Series No. 4,Universal Academy Press,(1993)179-188.2:「実験ノート 重水素透過による Pd 多層膜上での元素変換の観測 」固体物理 Vol.39 No.4 2004に掲載されている岩村康弘氏の論文阪大でも再現性を確認しており,ステップ1:2005年?からイタリアと日本でまず放射性同位元素を用いて実験結果を再確認するステップ2:産業ベースにスケールアップとされているようですが,どのへんまで進んでいるんでしょう?http://wwwcf.elc.iwate-u.ac.jp/jcf/mlist/00212.htmlこれによると2年程度でステップ1を確認後、商業ベースを考えるようです。2007年ごろでしょうか?ただエネルギー問題、すなわち過剰熱については、いまのところそれほどすごいものではないかもしれません。それよりも核廃棄物を無害化する技術として期待されているようです。ただこちらにはコンタミ(他から混じった)の可能性を示唆する意見もありますが,岩村康弘氏の実験は再現性があり注目されているようです.http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_fusion
Jul 4, 2006
コメント(0)
-
為替について考えてみる 追記しました
何度も登場している私が使っているマクロ、テクニカル、為替、株価、金利の一体化チャートなんですが、、、円ドルの為替の動きと、日米マクロブレンド(具体的には日米鉱工業生産と日本の時間外労働時間対前年比)が逆の動きをしているのに気がつきます。いまは昨年末よりもマクロ指標が良くなっており、それに応じて円高になっています。榊原さんの本では、2000年から2003年の動きをいろんな経済的な出来事と絡めて解説してあるのですが、このチャートを見る限りでは日米マクロブレンドの逆をいっていれば、そして機械受注の高さを注目してれば、為替は読めるという事になってしまいます。単なる偶然の一致なのか、これから注意していきたいと思います。今のマクロの方向を見ると11月までは105円くらいの円高になるのが順当であると言えますが、、、ブログを回ると皆の意見が異なり、面白さはつきません。ただいずれにせよ、時期はわかりませんが、チャート上で機械受注の額に並ぶ円安ドル高が来る事を仮説として、ドルを保有しています。それにしても米国金利高はドル高というグリースパンマジックのシナリオがバーナンキに変わった今回も生きているのか?あるいはソロス(彼の神通力はまだ残っているのでしょうか?)のいうこれから2年はドル安という意見、、市場の皆がどちらのシナリオを選択するのでしょうか?私自身も少なからぬドルを保有している点から緊張を持って注視しています。なおチャートにはテクニカル指標が国債先物金利よりも上の時は買いと書いてありますが、単なる仮説ですので気にしないでください。これにマクロ指標をあわせて考えるとうまく成り立つように思います。ならば今年の3月からはずっと売りですが、私自身は少しずつ買い進んでいます。そのせいか4月をピークに投資成績は振るいませんが、、、やはりタイミングも大事なのでは思うのですが、とりあえず何をしたら良いかよくわからないので11月までは静観して行くことにしています。また米国政策金利の動向を見ると1929年の大恐慌時のゆっくりとした金利下げとは異なり、株価下落時の急速な金利下げによってグリーンスパンが市場との対話を大切にしていた事がよくわかります。彼は非常にうまく金利を下げたのではないでしょうか?そして株価が安定したとみるやマイナス金利を解除して、マクロ指標を注視しながらも決然と金利を上げ住宅バブルの火消しをおこなっているように思えます。バーナンキはどうなんでしょう?1929年の大恐慌と日本の平成バブルという2つの見本があるのでうまく舵取りをしてくれるように思うんですが、、、あとはグリーンスパンを試したように(1987年秋のブラックマンデー、その後の急上昇、あのときは日本はバブル真っ最中、今回は中国??)、市場がバーナンキの手腕を試す時期がくるのではないでしょうか?今年の秋にでも???バーナンキの側近たちはそのようなシナリオに当然備えているものと読んでいますが、、、そのときは多分、金利引き上げを見送り株価が再上昇し、マクロ指標も良好な9月頃?なんて考えたりしながら見守る事にします。これを書いている時にゼロ金利解除を日銀が来週検討する事をテレビは報じています。このまま日本の金利を上げずに現在の設備投資(機械受注)が過剰になると、中国のオリンピックブームが終わった時にマイナス金利のこの国から資金が海外へ逃げ、いずれ大幅な円安を招くのではないのでしょうか?
Jul 3, 2006
コメント(0)
-
6ヶ月のまとめ
チャートは基準価格対TOPIX1月 02月 +4.2%3月 +8.7%4月 +8.9 %5月 +8.2%6月 +11.4 %7月 +9.3 %対TOPIXでは善戦していますが、基準価格では3ヶ月連続でマイナスでした。
Jul 2, 2006
コメント(0)
-
米国債の利回り
米国の政策金利が5から5.25%に上昇。野村の米国債利回りも先月と比較して上昇。チャートは5月と6月の利回りの違いを示します。横軸が償還時期。10年物が5%を超えてきました。米国の醒めつつある住宅ブームと北京オリンピックが終わったあとのことを考えているんですが、日米とも鉱工業生産、機械受注などのマクロ指標は非常に悪く、米国の政策金利も非常に低くなっていると思うんですが、、、米ドルMMFを長期債にすこしづつ換えるタイミングを考えています。日米のマクロ指標は今年に入っても強いものが続いていますが、日本の株価は2006年11月までの分をこの4月までに先取りした感じがします。株価は半年先のマクロを見ている?ガソリンがまた結構上がりましたが、税金分が少ない米国ではもっと直撃を受けているはず。それに住宅ローンの返済増、住宅価格の下落、、、これは日本が平成バブルのあとに生じた土地バブルと同じわけですが、政策金利は2000年の6.5%までは行かないような気がするんですが、、、日本の場合はあの時点(土地バブル)で宮沢さんが金利を上げすぎたことが失われた10年につながったとされてもいるようですし、、、日本の場合は平成バブル、土地バブル、1995年まで円高になったわけですが、米国の場合にはどうなるんでしょう?以前にバフェットが心配して、他国通貨に分散投資をしたのは、このような理由からだったんでしょうか?今は米国株価は一定か上がる事はあっても、下がる事はないオプションを引き受けているようですが、その真意は?トルコの通貨が今年は暴落しているようですが、どこの国の銀行が融資していたんでしょう?アジア通貨危機のときにはインドネシアルピーの暴落では韓国の銀行が融資しており、半年後くらいに韓国の通貨が下落したわけですが、、、ソロスはアジア通貨危機では大もうけしたようですが、そのすぐあと、まさかのロシアのデフォルトでは20億ドルの大損をしています。これだけの大国ならありえないとしたソロスの想像以上の出来事が生じたわけですが、人生何だってありうるという教訓になりますねえ、、、
Jul 2, 2006
コメント(0)
-
歴史的なGDP
1820年のGDP、首位は中国(29%)、次いでインド(16%、英国のものだった)、フランス、英国(5.2%)、ロシア、日本、オーストリア、スペイン(アルゼンチンがスペインから独立)、米国(1.8%)、プロシア1992年のGDP、首位は米国、次いで中国、日本、ドイツ、インド、フランス、イタリア、英国、ロシア、ブラジルこうしてみると上位のメンバーは同じようなもの。鎖国政策で植民地もなかった日本が1820年代ですでに世界6位であり、米国GDPを上回っていたんですね。これから招来する人口減少もそれほど悲観すべき事ではないのかもしれません。100年間のバイアンドホールド作戦が有効だったのは、米国株式では正しくても、ほかの国ではどうだったんでしょうか?日本はGNP1000ドル当たりのC排出量は、世界最少で米国の半分以下、中国の10分の1と最高の技術力がある。日本は大富豪はいないし、また極端に貧しい人もいない。米国は上位20%の人々が金融資産の85%を所有し、下位80%の人々が所有する金融資産は15%しかなく、ローン漬け消費経済であり、石油・天然ガスに支えられた構造になっている。米国人の食事の意外な質素さは今も同じです。米国の医療費はGDPの15%で日本の約2倍。富の偏在は激しく、市民にとって日本のような最先端の医療は高値の花である。米国市民の破産の原因の約半分は医療費であり、毎年200万人が医療費によって破産する。それは自分の命にこだわるといとも簡単に家族がホームレスに陥れられる容赦ない世界である。世界で最も成功したとされる日本の医療システムを米国型に移行することが、国民の選択であれば、それも仕方ない。しかし近い将来、気の毒な多数の日本人たちの姿が目に浮かぶのは私だけなのだろうか?それから基軸国通貨ゆえの政策金利高イコールドル高というグリーンスパンマジック、、いつものこのシナリオに私も投資しているが、、、バーナンキに変わり、このシナリオに変更が来るのかどうかは、8月から11月までに明らかになるのだろうと思っている。2002年5月のムーディーズの国債格下げでも為替はなぜか円安にならず、その後1年ほどで円高に振れてきた。この原油高でもっとも影響を受けにくい日本の通貨価値が上昇するのが論理的には正しいような気がするが、あまり論理的に考えないで、深みにはまらない程度の額を長い目でみて投資をしたほうがよさそうである。2002年5月の124円よりも円安になる理由は金利以外に見当たらないのだが、、1)論理的には金利の相違は為替変動に影響を与えないはずなのだそうだ。2)鉱工業生産、機械受注などのマクロ指標は今のほうがはるかに良好。3)日米両国の財政問題は2002年と比較して大きく改善したとも悪化したともいえないのではないか?4)資源価格の上昇は明らかに米国に不利。証券投資のほうが理由がつきやすいのではないか思うようになっている、、、、
Jul 1, 2006
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 人を使うのは大変です。
- (2025-11-27 06:58:46)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 楽天レビュー、信じていい?私がレビ…
- (2025-11-26 22:00:05)
-
-
-
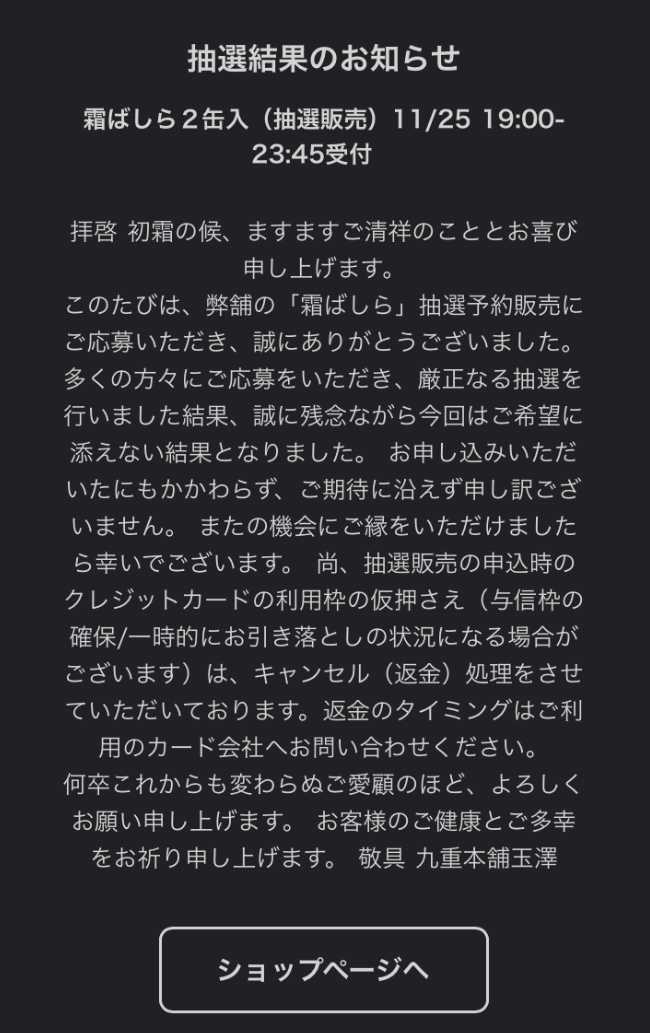
- 株式投資日記
- またまた上がってきた日経平均株価
- (2025-11-27 07:00:05)
-







