2006年04月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
結局、資本主義というのは
資本主義というのは、結局どこかに植民地がないとダメなのではないのだろうか?あるいは、外に植民地を求められなくなると、国内の誰かが植民地の役割を担わなくては、結局は成り立たないのだろうか?古くはローマ帝国のようにそう思わせる記事が以下に、、、http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060430it11.htm?from=top国内に植民地が散在(個人別)しているのが米国中国は地域格差国民全体が比較的裕福になったとき、日本では1989年?すでに転落の道筋はできていたということなのだろうか?なんかスタインベックの「怒りの葡萄」が思い浮かびます。オクラホマには行ったことはないのですが、、、オーキーがカリフォルニアに向かったときの希望とやがて来る絶望と、、そういえば日本の棄民といわれる政府主導の中南米への移民もそうでした、、貧しくても自由のある人間が、その自由さえも奪われていくさま、それが植民地。トーマスモアのユートピアを信じている人は今の日本にはほとんどいなくなったように、、、
Apr 30, 2006
コメント(2)
-
今月のマクロとテクニカル
まだ機械受注が入力されていませんが(発表はまだ)それに時間外労働時間も発表待ち日本もテクニカル的には2004年7月ころと同じくらいに落ち着いてきた感じです。あのときに私が買ったのは積和不動産中国、双日、日産車体でした。今の円高がもう少し継続することで、このレベルの日経になじむためにも、もう少し冷ましてほしいところ。サイクルはIT産業を除いた米国の平均的景気サイクルを示しています。日本は1年早く先取りしてしまった感じなのかも、、、そして中国もそれよりは少し遅れたが、先取りしてしまったのかも、、、このくらいで中国もおさまれば(金利政策でブレーキ?)、中国は日本よりも冷静ということになるのではないのでしょうか?となると、次の上昇は米国でしょうか?日本の人口動態からは今年の日経平均は16220円でイーブン2012年のピークには22000円と予想米国の鉱工業生産は3ヶ月連続で足踏み状態。交易条件も少し低下気味というか、高値安定(原油高の影響)ということで、私が日本株に戻るのは今年の暮れくらいでしょうか?それまでは外貨をゆっくり買うくらいか、米国のバリュー株かインデックスを買うくらいか?円は一時的に110円か111円くらいになるかも(願望かもしれませんが)これまでは日経の月足のテクニカルがピークを迎え(今回もすでに迎えたと思います)、機械受注が上昇しているうちは、基本的には円安、ドル高。それにしてもバフェットの言う「みんなが貪欲なとき」は警戒し、「打ちひしがれているとき」に買う、これはサイコロなどのテクニカルに通ずるものがあるのかもしれません。上昇する株価の頭を一時的な円高がこつんとたたくときが、株価のピークのようです。今回の一時的な円高は1月に続いて2回目ですから、株価は順次下がっていくのではないでしょうか?
Apr 29, 2006
コメント(0)
-
今月のポートフォリオ
今月は中国のEVOCを購入。購入価格は購入手数料を含む現在株価は外貨購入後の為替変動を含めており,円での価値から逆算しており,現在の株価を正確に表現しているものではありません.毎月ドルコスト平均法のような感じで、中国、日本、米国のどこかの銘柄を買っている感じになっています。現在8銘柄、概ね20銘柄までこんな感じで行く予定基準価格は11123円で3月よりは150円くらい低下。長期的な見通しとしては、1)現在はコンドラチェフの谷の前の最後の原油価格の上昇と先進国の金利上昇局面であろう。2)概ね2010年から2013年に金利は底を迎える(コンドラチェフの谷)3)円安は130円から135円くらいまで(2007年から2008年ころ)4)日本の金利は多少上昇せざる得ないが、先進国の金利が現在の上昇後に再び低下を始めることで、当面の破綻は免れる。ただし2012年から2013年ころまでにどれだけ財政改革が進行しているかであろうが、おそらくダメか?過去の他国の歴史を見ると行き着くところまでいくのだろう。5)2012年ころに日本の株価はピークを迎える.現在既に大証修正平均で30000円を越えているが,2012年頃には平成バブルの頂点を越える40000円くらいまで到達してから,下落を迎える.6)NZドルは太陽の黒点周期、エルニーニョ、水不足と関連して11年周期で2016年ころ次のピークがくる。物価と金利の大底であるコンドラチェフの谷ではNZドルも大底を迎える。7)コンドラチェフの谷ではイノベーションが生じ、次の覇権国が台頭する。それは現在のところ中国と考えられているが、まだ判らない。8)コンドラチェフの谷では相対的に円高になっているだろうから、その辺に外貨資産を最大にしておく.物価安なので資源国通貨は下落9)一応、次の想定覇権国である中国についても、一度マイルドなクラッシュを2010年から2012年ころに迎えて、今の矛盾を解消。その後伸びていくと思われる。意外に別の国かもしれないので、注意は怠らない。10)日本は他の先進国より10年はやくデフレに至り,回復も他国よりは少しはやい時期に訪れる.11)バフェットの言うように来るインフレでは,固定資産の少ない企業が傷つかないので,それを念頭に入れておく.12)今もってる中海コンテナなどの海運業は,落ちるときは本当にどこまでも落ちる景気敏感株の代表であることを自覚しておく.13)万一,核を含んだ紛争がおきるとしても,それは北半球.南半球の通貨はそのヘッジとして,所有しておく.以上のようなイメージで進めていこうと思っています。
Apr 29, 2006
コメント(0)
-
EVOC とBank of America
中国株のEVOC は買えていましたがBank of Americaは急騰して買えませんでした。どうもタイミングが悪いです。ゆっくりしすぎなのかもしれませんが、28年連続増配銘柄なのですがBank of Americaの口座をずっと持っていたんですが、去年の秋に解約して、そのお金で買おうと思っていたんですが、、、
Apr 28, 2006
コメント(0)
-
日本国債
若き知http://fp.st23.arena.ne.jp/keio.htmこの方の本を以前2冊ほど読んだことがあります。国債ディーラーの方です。オフショアが話題になっていますが、日本国債どうなんでしょう?本当に言われているほど危ないのか、判らなくなってきています。この方は「日本国債は危なくない」という本を書かれています。ポートフォリオの一部に日本国債を組み込むべきか、最近よく考えこんでいます。本当にハイパーインフレは来たしうるのか、、、わが事を振り返れば、かつて医師過剰が騒がれましたが、これだけ増えてても、(エリートの定義には人口10万人当たり150人以下の職業というのが含まれているのですが、もうとっくにそうではなくなっています。たしかに20年以上前と比較すると地位的には低下したなあとは思うのですが、、、)いまテレビでは医師不足が話題になり、東大よりも医学部への志向が強まっていると週刊誌は述べています。かつて人口爆発を懸念したローマ会議、、、マルサスの人口論、、、いったいどうなったんでしょう。かつて経営不振で自殺未遂をした経営者は今では一部上場企業の経営者になっているし、、、本当に、先のことはわかりませんねえ。少しなら日本国債を買っておいてもよいのかなと思いつつあるこのごろです。米とNZのMMFはあわせると、今回の円高で保有株式の2-3倍くらいの額を買い増ししました。月末か5月初めにはちゃんと計算しようと思っています。NZ:貿易赤字の予想でしたが、黒字に転じています。政策金利は据え置き。ちょっと面白そうです。
Apr 27, 2006
コメント(0)
-
ドル安
ひさびさのドル安ですね.USドルが114円台,NZドルが71円台.どちらのMMFも買い増しました.今日はカナダドルの政策金利発表 3.75%から4%へ着実に上昇しています.注文した中国株はEVOCが買えているはずですが,米国株はバンクオブアメリカを注文,こっちは買えたんだろうか?面倒なので明日確認.連休にかけて今年も動きがありそうです.YahooUSAで中国と米国をみて,Livedoorで日本と中国をみてるんですが,日本,中国,米国が一緒に見れるようなところはないんだろうか?
Apr 25, 2006
コメント(2)
-
シノペック上海がライブドア証券で検索一位?
H株ではシノペック上海がライブドア証券で検索一位?なんかあったんだろうか?木村剛さんの資産運用に関する本を読む素人投資家は20銘柄に分散して、持ち続けろ、、、資産は外国債券(MMF)、日本株、日本債券、それにできたら外国株式ゆっくりと時間を分散して購入せよ私が行いつつあることと同じですね、、日本債券を除いては
Apr 23, 2006
コメント(0)
-
NZドルとCPI
NZドルとCPIを検討してみるためにCPIの対前年度比を4半期ごとにチャートにしました.大きく動くほうが食品,動きが小さいのはトータルです.CPIが上昇するときは債券を買うなというのは,おそらく自国の債券を買うなということでしょう.NZドルを円から見た底値は,2000年後半から2001年前半ですので,CPIは対前年度では上がっている時期です.NZの人から見れば,2000年後半から2001年前半の自国CPIが上昇しているときに,外国に投資をしたら,為替の面では大損していますね.ということは日本の円もCPI上昇前に,外貨に換えておくべきなのかな?もう遅いだろうか?NZの人は現金を持っているか,ゆっくりと下がっている株を買っているのが正解だったのか,,,,まして日本から見れば,為替は有利で,株も下がっていれば,2000年後半から2001年前半にゆっくりNZの株を買っていれば大正解だったんですね.それにしてもNZの物価上昇は食品に関しては,今回は(去年の水不足あまり影響を与えていない)それほどではないんですが,原油高の影響なんでしょうか,トータルでは高い水準にあります.中国のCPIはどうなんだろう?こっちが投資の主力なんですが,,,外貨に換えたら,すぐに株式を入手せずによく見極めて,半年単位で考えて,行動するのが大事なようです.
Apr 22, 2006
コメント(0)
-
H株指数
本業多忙のため、更新が滞りました。H株指数いつのまにか7000越えているんですね窓開けて、、、といっても時価総額の大きい銘柄に左右されすぎの指標だし、少ない構成銘柄で頻繁に入れ替えがあるので、あまり目安にはならないのかもしれませんが、、当面は、少し円高になってきたので、また香港ドルに換えておくことにNZの消費者物価指数が発表になっています.「CPIが上昇するときは債券を買うな」といわれていますが,NZドルに投資するということは,これに反する行動になるわけですが,MMFは債券なので,,,,スワップも同じなんでしょうね,,,,まあ,ほんの少しなので,為替を念頭に置いておくために.それから,とにかく下がっていくものを,少しずつ買っておくように,,
Apr 22, 2006
コメント(0)
-
ニュージーランドドリーム
ニュージーランドドリームhttp://www.geocities.jp/kiwidream1997hp/NZドルのことを調べていて、見つかったのですが、NZのいろんな事情が紹介されていて、楽しいところです。ところで、この方が以下のところに米国の本質(本性?)について、書かれたページがあります。http://www.geocities.jp/kiwidream1997hp/america.html勉強になりました。経済は単純に、数値ではなく、政治が複雑に絡んでいることを、、、私が好きな医学の基礎研究とは別世界です。これまでも、supreさんとか、フランス男さんとかに指摘され、教授されてきましたが、政治については、今ひとつピンとこなかったのですが、、、、、米国のことですが、私もかつて住んでいて、思い当たることがあります、、、このかたの説明を読んで、ほぼ納得がいきました。でもあまり、政治のことなど考えたくないですね、バリュー投資でこれからもいきたいと思います。下がっているもの、みんなに振り向かれないもののなかから、価値のあるものを探していこうと思います。これは私がこれまで行ってきた研究目的と同じ姿勢ですので、この方が無理がありません。私には流行についていく生き方が向いていないので、、、
Apr 15, 2006
コメント(0)
-
NZドル
NZドル、、羊毛相場がかなり上がっていますが、どうなんでしょう?少し上がるんでしょうか?対ドルでは円安が進んでいますし、
Apr 14, 2006
コメント(2)
-
ブログ開始から1年
今日でブログを始めてから1年になりました.投資の勉強をはじめてからは,もう2年以上過ぎました.なんか結構はやかったです.今日は「投資遊学のすすめ」を読んでいて,少し胸を打たれたことについて,,94-95ページ,高福祉国家のスカンジナビアの人たちについて「国のために払う税金なんて高いとは思ってもいないし,そんな環境で働くのはばからしいなんて,夢にも思っていないのである.かえって,そんな環境だからこそ,働いているのかもしれない.」私がこの彼らの発言を聞いたとき,思わず襟元を正したのであった.かつての日本人が持っていたはずの精神ではないかと.現在の日本人がどこかに置き忘れてしまった大切なものを,教えられたような気がしたのである.ちょっとこの言葉にはぐっときましたので紹介します.でも,またそんな感じに,いずれは戻るような気がしています.という期待を込めながら,,,,株式のほうも,売る気がなくなってしまってからは,閑です.アメリカが強気になっていないようなので,なにか買ってみようかとは思うんですが,,,
Apr 13, 2006
コメント(0)
-
中国の石油、電力需要
中国の石油、電力需要少し供給過剰な予想が出ています。NTTドコモ どうかなと思っているんですが、買残が非常に多いので様子を見ています。でもイランの懸念が出ており、今月も何か買ってみようとは思っています。まだ決めてませんが、中国は時価総額の小さい、財務優良銘柄、日本はドコモ?、米国はバンクオブアメリカとかメルクなんか?ちなみに中国のH株指数を元に、そのときに買っても良い株式総額を決めています。全部買うと予算オーバーしそうなので、様子を見ながら、、為替も同じでそのときのレートで買う総額をあらかじめ決めています。http://money.www.infoseek.co.jp/MnJbn/jbntext/?id=12bloomberg15aucArkxP9TVg
Apr 12, 2006
コメント(0)
-
中国の自動車株
1月に買った長城汽車、アビチャイナともに好調です。為替の上昇もあり、長城汽車は90%くらい上昇、アビチャイナは決算発表を契機に5割くらい買値から上昇しています。2月に買ったシノペック上海も上昇していますが、前2者と比べればわずかです。やっぱり誰が見ても安いという銘柄は、市場が強気になったときはよく上昇するというのが、この2年間の実感です。今、気がついたのですが私のブログの左にあるチャート、フェイスが思い切りあがっています。なにかあったのでしょうか?今日はお酒を飲んでしまい、もう眠いので明日調べてみます。
Apr 11, 2006
コメント(1)
-
有機EL
パイオニアも三洋も撤退した有機EL、、結局どこがものにするんだろうか?それともこのまま消えていくんだろうか?http://ckido8.yz.yamagata-u.ac.jp/pc/OLEDnews/OLED_news_060315sanyo.htmそういえば工場作りに難航していた?京セラは?http://www.semicon-news.co.jp/news/htm/sn1675-j.htm
Apr 10, 2006
コメント(2)
-
投資遊学のすすめ
「投資遊学のすすめ」からの引用です。「事にあたり思慮の乏しさを憂うなかれ、およそ思慮は平生黙座静思の際においてすべし、有事にいたり十に八,九は履行されるものなり。」西郷隆盛のことばとか、、、、所有株式はなにも動かしていませんが、Contrarianを目指して、株式投資用のキャッシュを約4倍に追加し「有事」を待っています。
Apr 8, 2006
コメント(2)
-
原油の在庫が
http://www.mbfutures.com/market_info/fundamentals/fm06crude_oil.htm原油の在庫が増えているようです。商品が下がると資源国通貨は、、、弱気安間さんの「からくり」シリーズの第2弾を読みました。まえに第3弾を読んでいますが、これも非常にためになります。今度ブログをはじめられたようです。http://wildinvestors.cocolog-nifty.com/blog/
Apr 5, 2006
コメント(0)
-
NZの羊頭数
NZの羊頭数が1980年代以来初めて増加したことを伝えるNZ統計局のニュースです。The 27 percent rise in lambs born to ewe hoggets (1.4 million) was a significant contributor to the increase.というのは2005年は2004年よりも27%もラムの出生が増えたということなのでしょう。干ばつだと頭数が減るはずなのですが、、、そうはなっていません。羊毛相場のほうは今後、弱含むんでしょうか?ドルに対して弱含むといっても、円安ドル高の流れのもとでは、円に対してはそれほどでもないかもしれませんがチャートはNZの羊毛相場ですが、昨年より高く、急上昇しているのですが、、なかなか難しい通貨です。それから米国の新築住宅の在庫が増えてきています。中古市場が主体とはいえ、そろそろ供給過剰なのかもしれません。英国では03年にかけて顕著な住宅価格の上昇が見られ、金利上昇をまねき、ポンド高になっていますが、、、ドルのほうも、そんな感じでこれから上昇すると考えています。133円くらいで来年の夏ごろピーク?http://www5.cao.go.jp/keizai3/shihyo/2006/0403/712.htmlFirst Increase in Sheep Numbers Since 1980sThe national sheep flock increased to 39.9 million in 2005 Statistics New Zealand said today. Figures from the 2005 Agricultural Production Survey show hogget numbers were up 11 percent on 2004 and this was the major driver behind the 2 percent rise in total sheep numbers. This is the first increase in total sheep numbers since the 1980s. From a peak in 1982, sheep numbers showed a downward trend before stabilising from 2002.At 30 June 2005, there were 33.2 million lambs, up 4 percent on the 2004 figure. The 27 percent rise in lambs born to ewe hoggets (1.4 million) was a significant contributor to the increase.Livestock numbers in Manawatu-Wanganui increased 8 percent for both sheep and dairy cattle, 9 percent for beef, and 6 percent for deer. This reverses the movement seen in 2004, when sheep, beef and dairy cattle numbers decreased. The Manawatu-Wanganui region experienced major flooding in February 2004.The 2005 Agricultural Production Survey included questions about horticulture production. Survey results show a general decline in the area planted in pipfruit between 2002 and 2005. The area planted in apples decreased to 10,980 hectares, down 6 percent on 2002, while the area planted in pears was down to 720 hectares, almost one-quarter less than the 2002 figure.The total area planted in avocados increased to 3,400 hectares in 2005, up 9 percent from 2002. The Bay of Plenty had 56 percent of total avocado plantings in 2005.
Apr 3, 2006
コメント(2)
-
帝国データバンクの企業倒産件数
帝国データバンクの企業倒産件数は2005年5月から個人情報保護法のため、従来法では集計が困難になったとして集計法が変更になっています。2005年4月の倒産件数は旧方法では948件、現在の方法では605件おおむね現在の件数を1.57倍すると、古いデータと比較できるのかもしれません。2006年2月の倒産件数は777件であり、概ね1220件ほどになると推定。2005年春ころよりは2割ほど増えています。http://www.tdb.co.jp/tosan/jouhou.htmlこれは四半期別チャート1989年ころは6ヶ月で3000-4000件、2000年ころは10000件2003年ころは9000件、2004年ころは7000件と減少、2005年はそこそこ新方式になって件数は一見減少しているが、もうそろそろ増えだしてきたようである。また負債総額のほうは件数減少にも関わらず、徐々に大きくなってきている。景気サイクル的には今後、上向きと思うけど、、、、本日のフェイス、ストップ高、、もしかすると私にとって初めてなのかもしれません。あるいはメガチップスであったのかもしれませんが、、、気にしていなかったので、よくわかりません。ストップ安はもう何度も経験していますが、、、
Apr 3, 2006
コメント(0)
-
私の使っているチャート
私の使っているチャートです。1987年からのデータが入っています。米国のハイテクを除いた産業の景気サイクルを目安にして、日経平均のテクニカル分析としては、ボリュームレシオとサイコロをミックスしています。ベースとなる人口動態は日本人の40歳代の人口推移に高齢化率を考慮したもの以上の3つをベースにおりおりの為替、日米金利差、交易条件(悪化は主に原油価格に左右される)、機械受注(設備投資の先行指標、為替にも関与する)鉱工業生産(出荷-在庫対前年比と出荷-在庫の実数)時間外労働時間(30人以上の製造業)米国の鉱工業生産を毎月1回入力しています。日本が昨年6月から12月まで上昇し一服、中国が11月から上昇開始(出遅れはまだある)、米国もそろそろもう少しあがるのではないでしょうか?NZドルについては、長期的に考えると2007年に62円くらい、2010年に50円くらいになるのではと想像しています。その後上昇へと鉱工業生産の出荷-在庫では1987年以降未曾有の在庫不足が日本では続いています。中国経済では過剰生産=過剰在庫(特に自動車)のため、薄利多売に走っているようです。これって平成バブル時に過剰在庫を抱えた日本と似ているような気がします。いままでの先進国への輸出に加えて、余った製品を彼らが売る先は開発途上国のようです。自動車の場合にはキューバやロシアに進出している長城汽車でしょうか、、まさにかつて日本が通った道を歩んでいますね、、、いったいいつごろに中国はハードランディングするんでしょうか?中国の場合は自国内に安い労働力(植民地のようなもの)を抱えていますが、これは地域格差であり、米国のような能力に応じた格差ではありません。結局は日本と同様にインフラ整備を十分に展開する以前に、中国も失速するんでしょうけど、、
Apr 2, 2006
コメント(0)
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
-

- 政治について
- 電磁波照射されると皮膚が赤系に変化…
- (2025-11-26 00:42:34)
-
-
-
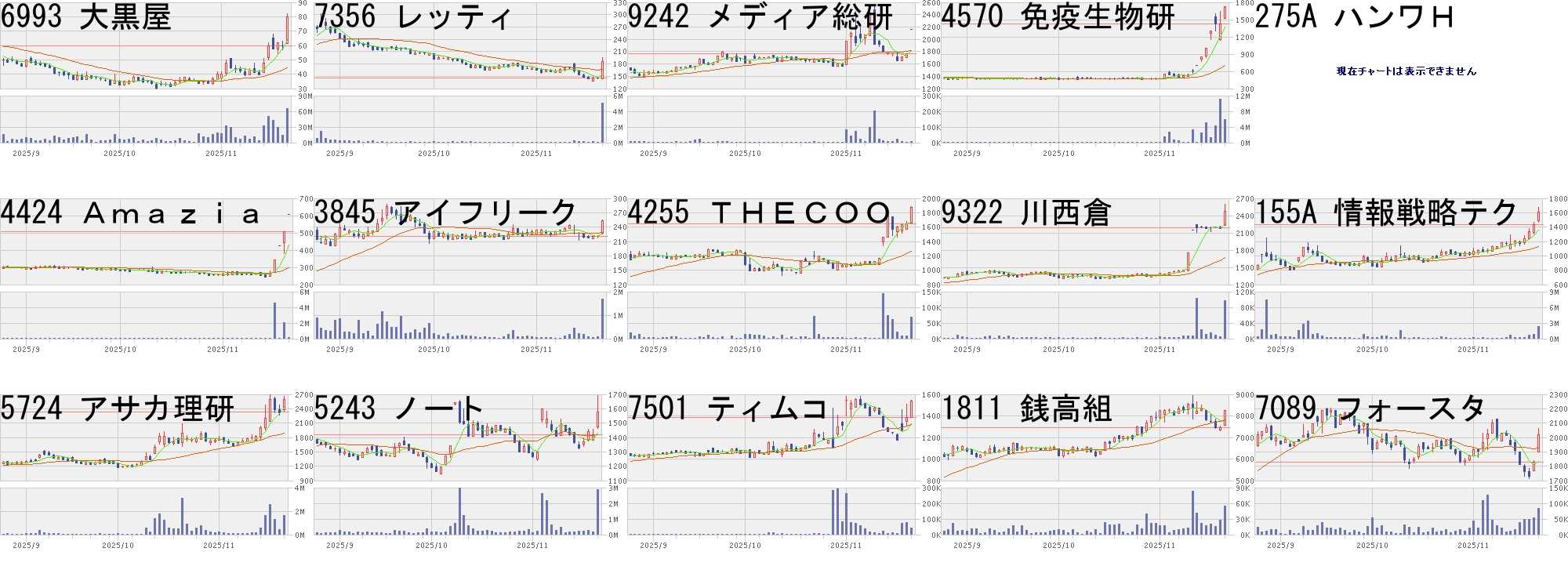
- 株式投資でお小遣いを増やそう
- 本日の急騰・急落株
- (2025-11-25 20:59:24)
-
-
-

- 楽天写真館
- 26 日 ( Wednesday ) の日記 旅 …
- (2025-11-26 04:00:04)
-







