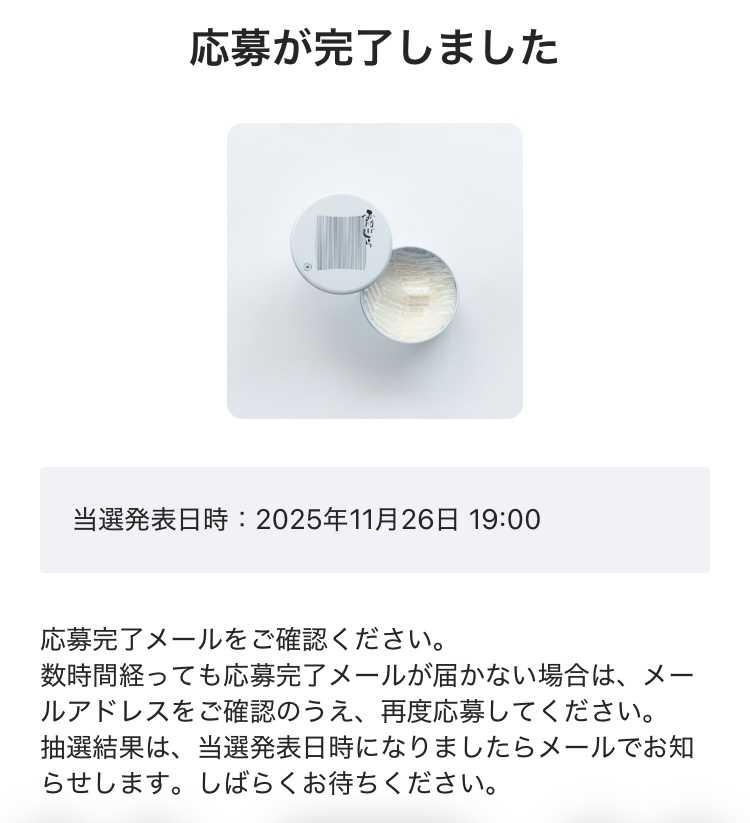2006年05月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
これからしばらく円安にならない理由
これからしばらく円安にならないとして、その理由を考えているんですが、海外勢が日本株を売り終わった円のうちまだ予定額をドルに戻しきっていないということはないんでしょうか?今回は株価が2倍にもなったわけですし、投入金額よりも相当多い額をドルに戻す必要があるんではないでしょうか?機械受注がピークを打ってもしばらくは円安になるわけでしょうし、、、、つまり、決済は機械受注のピーク以降に来るわけでしょうし、、、先物で為替ヘッジして日本株を買ったものの多いんでしょうけど、全部ではないでしょうし、、、それがいつも観察される現象、株価のピーク付近での一時的な円高なんではないんでしょうか?いつの時点で一時的な円買いから円売りになるかというと、2005年からの株価上昇も結構大きかったので、、、彼らが2004年秋から2005年春まで買った分を相手の身になって考えると、もうちょっと円安に転じるまで時間を要するのかもしれません。逃げる時間がもう少し必要ということなのでしょうか?それに乗じて、ほかの海外勢が力づくで超円高に持ってくることは、今回はないように思いますが、、やはり今回の機械受注がピークをうち、低下する時に加速度をつけて円高にして、日本を痛めつけておいてから、超円安を狙うというのが、私がその立場であれば成功率が高く、狙いどころのような気がします。機械受注のピークを十分に見定めてからのほうが、コンセンサスというか、流れに応じて、過熱を引き起こすことになり成功率は高いと思います。また直近の山が高い(円安)ほど、低くするときの最後の過熱は強いものになると思います。私がもし日本を狙うんだったら、前回の135円を越える140円くらいの円安になることを望んで、そこから急な超円高(95円くらいの)を2011年くらいに持ってきて、財政再建が間に合わないことをコンセンサスとして皆が得た時点で、踵を返すように超円安に持っていくことを考えますが、、、もっとも1997年のアジア通貨危機のパターンはちょーど現在のような円安傾向のなかの中腹で一時的な円高ピークの時点で8月にタイバーツに対して仕掛けられたわけですが、ソロスはその記憶をみんなに呼び覚まそうとしているんでしょうか?この原油高で痛んでいるのは、外貨準備高が急減している国があるとすればどこなんでしょうか?去年の夏にすこし話題に登ったインドネシアですか?また地震で大変な目にあっていますけど、、あるいはフィリピン?http://www.bk.mufg.jp/report/ecorev2005/review20050916.pdf先日、山崎さんという方の新刊を読んで、外貨MMF(ようするに為替)は期待リターンの低い、ゼロサムゲームの投機であると書かれていました。経済学の理論的にはそのことを判っていたのですが、この本で得心が行きました。あまり為替にのめりこまず、先ほども書きましたように4年くらい円高が続いても大丈夫なくらいゆっくり買おうと思って額を定めました。メインは小額でも本道の株式です。残り資金を円高ならば少しづつ損しなそうな時にだけ外貨MMFに振り向ける感じのシステムにしております。
May 30, 2006
コメント(2)
-
次は何を買おうか? 追記しました
中国株は6銘柄所有していますが,長城汽車(2倍近くまでいったが失速中)とEVOC(今年初めてのほぼ2倍株)以外は買値よりも下がっている状況です.テクニカル指標は売りを示していますので,ゆっくり考える時間がありそうです.このテクニカル指標(サイコロ,ボリュームレシオ,金額倍率をブレンドしたドルコスト平均法のようなもの)は毎月1回,株を買う(あるいは売る)金額をはじき出してくれます.今回の景気は2001年末ごろから少しずつ購入指示が出て,ずっとある程度証券を保持するように指示していましたが,このままあまり下がらないと,もう3ヶ月くらいで全ての証券を売り切るように指示するかもしれません.これまで積み重ねてきたマクロも確認します.これからは適切な額を導き出す仕組みはまだ作っていません.ABCDEとか5段階くらいの大まかな評価をつけようかと思っています.また同時に購入してよい外貨MMFの金額(為替レート,インデックス,その他をブレンドしたドルコスト平均法のようなもの,ドル円の中立的なレートを設定し,ドルインデックスの低下傾向と両国の長期的な金利差からそのレートを順次増減した.証券の購入額も加味して債券購入額を決定)もはじき出します.アセットアロケーションから考えて,概ね4年くらい円高傾向が続いても購入していけるように総額を設定.無理しない程度の額でゆっくりとしたタイミング投資はドルコスト平均法よりも効率的なような気がするのですが,,,長城汽車:過当競争で先行きを悲観されている中国の自動車産業に魅力を感じたのが今年の1月でした.いずれ小規模なメーカーの免許は取り消されるらしいですし,むしろチャンスかも.悲観されているうちに買っておいて,そのまま強いものに巻かれろという感じでどんどんと合併されるなかで,自動的に勝ち残り企業の株主になることを目論んでいるのが本音です.EVOC:どうみても安かった.でも何かあるのではと怖かったので買うのが遅かった.まだ判りませんけど.落ちるのを待っているのは,参入障壁が高そうな会社です.1)中国の宝石会社.結構下がってきていますが,まだ買いません.これだけ原材料の金が上がっているのだから,今期は減益になってもらって,さがるのを待ちます.2)米国かスイスの製薬会社.お得意先の日本がいよいよジェネリックの時代に突入.訴訟不安も多い.さらに市場のセンチメントが落ちれば,よい買い物ができるかも.技術は折り紙つきだし.中国でも薬は売れると思うが,,,3)日本はアニメやゲーム関係.でもPERが高すぎ.政府は2030年までに米国並みにGDPの5%がコンテンツ事業になると予測(年率7%成長).任天堂とフェイスは少し持っている.4)欧州の銀行.ドルMMFを持っているので,ユーロにヘッジしたい.5)香港の新聞.オリエンタルプレス.少し持っています.資本コストが低い.利益のほとんどを配当にまわせる余裕.価格を半額にできる強さ?今回値上げしたようですけど.本土にもっと進出して伸びてくれれば,,,豊かになれば新聞だって複数見るんではないでしょうか?6)PBRが2倍のDisneyはよいと思うんですが,,,買いました.任天堂と同じ発想ですが,,7)PBRが6倍のCocaColaはこの15年で最低のPBRになっている.,,,買いました.参入障壁の高い,変わるものがない企業?でも日本ではコーラブームは終わっています.私は週2本くらい飲んでいます.以上のように,非常に甘い考えで個別銘柄を買ってきたことが判りました.もっと勉強しなくてはなりません.追伸:日本国債をまだ買っていませんでした.変動金利型を外貨MMFと同程度あるいはそれよりすこし少ないくらいの額を購入しようと思います.こちらはタイミングがいらないので気が楽です.証券あまり下がらないですね,証券を買う時期は今年はもうないのかもしれません.
May 29, 2006
コメント(3)
-
日本は貿易収支の黒字で支えられている
日本は貿易収支の慢性的な黒字で支えられているわけですが,チャートのように2005年度から貿易収支は減少していますが,珍しいことに慢性赤字のサービス収支がかなり改善しています.なぜか調べてみると,輸送や旅行の赤字は減っていませんが,その他のサービス収支が改善しています.その内訳は建設の黒字が2倍くらいに増加し,保険の赤字が半分に減っています.何がおきているんでしょうか?もう少し考えてみます.先進国中で最も死亡率が高そうなのはやはり日本のような気がします.Dollar indexをみると長期的にドル安が定着し,2012,13年頃に再浮上するシナリオもあるかもしれません.日本の40歳代の人口動態はその少し前頃にピークを迎えます.いずれにせよコンドラチェフの谷の前の2次的物価上昇(現在の原油高)は米国(とくにGM)を蝕むでしょうし,Federal Funds Rateの金利低下場面では,これまでとルールが変わって,機械受注に左右されず1990年初頭-中頃のような円高にすすむ可能性はあるのかもしれません.これは一番いやなシナリオです.http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/pol041.html円が80円台だった1995年の円高不況における経団連の提言では公共投資基本計画630兆円の前倒しを求めています.いまの日本がこれを(円高)をやられたら,ひとたまりもなさそうですね.1995年の経団連が2010年に構造改革がすすまなかった場合のシナリオを以下に転載します.一時的に円レートが急上昇後,競争力を失い円安に向かう,,,,,現状放置ケース (年平均値、%)┌──────────┬─────────────┐│ │ 1995~2010年 │├──────────┼─────────────┤│実質経済成長率 │ 0.5%~2%弱 ││消費者物価 │ 0.5%~1.0% ││完全失業率 │ 3%台半ば→4.0%台へ ││経常収支(対GDP比) │ 2.0%→-0.5% へ │├──────────┼─────────────┤│円レート │一時的に急上昇後、競争力喪││ │失に伴い反転、円安に向かう│コンドラチェフの谷の前の物価上昇,それで痛手を負うのは,オイルショック同様に米国であり,燃費のよい日本車が飛ぶように売れ,急激な円高へ,そこで競争力を失い,反転し,超円安へと向かう,,,,,結論:いままでのルールに反して,このまま円高に向かうなら,ゆっくりと確実にドルを買っていく方針.円安に向かうなら,これ以上買い増ししない.日本は2012年度までにプライマリーバランスを達成しようとしていますが,OECDがそれでは遅いということを言っているらしく気がかりです.それにしてもかつての日本のように外貨を貯めこみ,貯蓄率が高い中国.有効に使われないお金がたくさんある国はいずれ使わないうちにその価値を失う仕組みになっているといったのはケインズでしたっけ?いずれにせよ,日本が厳しい局面を迎える前に,もう一回急速な円高が来ると思います.そのときを注意深く待ってみます.私の考えるメインシナリオは次の機械受注の底打ちの辺りです.今回の機械受注は非常に大きなものになりそうですし,その後に来る落差が危険だと思います.その円高後にくる円安が過度となれば,日本政府の最後の頼み,大量の米国債が放出されるということになるのでしょうか?こんな自己破壊はソロスの住む米国も含めて誰も得しないような気がするんですが.ユーロが高くなってきているのも判るような気がしますが,,,ところで人民元はともかく,香港ドルは将来どのようになるんでしょう?
May 29, 2006
コメント(0)
-
当たらぬとも遠からず
相変わらずアセットアロケーションを考えています。もう半年くらい、、、当たらぬとも遠からずが目標なんですが。大体当たっていればよいという感じ。それがどういうものかまだ判っていません。結局、前回ブログのように19世紀からの金利とPERを遡ることになってしまいました。このアプローチは私の仕事と同じです。新しいことをやるためには100年以上過去の論文を遡って、動物実験を何年も繰り返し、そして事に望んでいます。人間は変われませんね。経済は面白いです。これもやはり人間の営みであることが実感として判って来ました。でも、これに実際の自分のお金の相当額を賭けるのは躊躇してしまいます。判らないものにはやはり投資できませんし、、、、ただ外貨には今回は結構な額を投資しました。基本的には機械受注のグレーゾーンの下なら買っておいて、そんなに損はないと思います。それにしても2011年ころは、ドル高円安で決まりと思っていましたが、そうともいえないシナリオも頭に浮かんでいます。ずいぶん時間がかかってしまいましたが、やっと証券、債券の流れをコントロールするような長期的方針が固まりました。結論:1)今の日本証券は、それまで十分準備してきたものにとっては1年くらい前から売りだと思います。準備が遅かった私のような者にとっては、もう当分終わっているようです。2)米国は為替的にnominalなインデックスからは長期的な弱気の傾向です。でも今月の109円は買ってよかったと思います。3)短期的に円高か円安かは判りません。概ね114-115円くらいで中立と思います。2,3年後には110円くらいになりそうですが、、、、、機械受注の傾向的にはドルが上昇してもよいと思いますが、日本企業の採算ラインが104円、米国として守るべきGMなどが立ち直るモラトリアムが必要なことから、2年くらい通常の流れよりも円高傾向を覚悟することも必要かもしれません?4)さて、継続的な円高傾向が続けば、その次の景気における日本企業の収益に影響を与えそうです。これまでのような十分な円安がないと企業収益は次は望めないのではないでしょうか?5)いろんなことを念頭に置きながらも、最も大切なのは、その企業および国家が世間にとって長期的に必要とされることが必要だということが理解できてきたように思います。そこには参入障壁が存在するよい企業、よい国家を目指しているかということになるのではないかということを、、、、「投資遊学のすすめ」はこれを教えてくれていたんでしょうか?私の誤解でなければよいのですが、、、6)書庫にある投資関連の本はさらに半分に減らせそうな気がしているのは自分の慢心でしょうか?チャートのピンクはドルレート薄い黄色は米国政策金利シアンはnominalのドルレート紫の縦線は機械受注です。グリーンスパンは2000年から素早く金利を引き下げたことにより、米国証券はかつてほど、つまり1929年とは異なり、著しく低下しませんでしたし、また金利も十分下げしろを準備して、後任に託したわけです。バーナンキがどのような手腕を発揮しても、前回ブログのようなPERは長期的にはそのまま維持できるようには思えないのですが、、、日本も含めてですが、、競争的な通貨切り下げが先進国間で生じるのでしょうか?相対的にその国の通貨が安くなったら、その国のよい企業に投資しようと思います。個別では銀行と製薬をまだ持っていないので、次はこれも求めようと思っています。どこの国になるのかはわかりませんが。それにしてもいつも誤字だらけのへんな日本語で申し訳ありません。これはお酒を飲むとブログを書くためですが、、、いずれにせよこれで経済の動向を加味したタイミングに関する勉強は一区切りにします。この流れに身を任せながら、来月からは個別企業の将来について考えていきます。これで勉強は以下のうちで第3段階に入ったと思います。1)証券の基本的バリューとは何か2)経済とは人間の営みが基本である3)個別企業の将来とは、、、
May 28, 2006
コメント(3)
-
米国金利とPER
チャートの左が米国PER、右が金利です。(FedralFundsRateは左軸です)こうしてみると金利のカーブを約19年遅れで株価がなぞっているように見えます。また2000年をピークとした米国株価は1929年ピークの株価と類似しています。これから類推すると年単位で考えると反発で上がることはあるし、一定のこともあるが、しばらく下がることはないと読めます。ただし長期的には下がるでしょけど、、そのまえに1回はPER30を越えそうに見えます。バフェットは本当は長期投機家なのではないのだろうか?なお移動平均線は太陽の黒点周期である11年移動平均にしました。
May 24, 2006
コメント(0)
-
このまま下落すると
このまま下落すると私のテクニカル指標は月足で7月には打診買いを示すかも。サイコロとvolume ratioと金額倍率を組み合わせたものですが、、そういえばバフェットはインデックスのプットの引き受けをしたとか下がらないほうにかけたということになるらしいですが、、、未確認事項いつごろまでの期限かは判りませんが。
May 23, 2006
コメント(0)
-
中国の不良債権に関するメモ
中国への投資を今年の初めから行っていますが、この2,3か月は中国にモノを売って儲かりそうな企業(CocaCola,Disney)とか香港に本拠を持つ新聞社などに投資をするようにしています。以下は投資メモです。中国の国有銀行の不良債権は対GDP比で40%。(日本に換算すれば200兆円)日本の銀行の不良債権は対GDP比で6%~11%。これでも崩壊せずに成り立っている理由は?中国側の経済学者1)これほど多くの不良債権を抱えているにもかかわらず、中国の銀行は経営を続けており、取り付け騒ぎも起きていない。(わが国は大丈夫といっている国ほど危ないんではないのだろうか??)2)GDP年率7~8%の経済成長を維持しており、金融危機は発生していない。3)銀行の不良債権はある意味で国債である。中国の国債の対GDP比率は 16%に過ぎない。この数字は、世界で最も低い水準である。4)イタリアの政府債務の対GDP比は90%、日本は140%。反対側の経済学者1)発表されるGDPほど高くない。信頼性に乏しい数値。2)金持ち優遇。儲けた人間の海外逃亡。投機的株式市場。3)膨大な余剰人口私の意見1)確かに日本の財政よりはましな状況なのかもしれないが、まだ発展途上でこの債務なら、先行きは厳しいかも。2)中国農業人口の4億人(過剰人口となり)は第2次産業の担い手として都市部へ進出し、農業の改革はそれ以降になる(なぜなら最初に農業を改革すれば一気に余剰人員は失業し、いくところがなくなる)日本ではこの50年で農業人口は10分の1に減少し、単位面積あたりの労働投入時間は6分の1に減少した。水田耕作面積は半分に減少した。要するに30倍の労働効率化が日本では半世紀で生じ、余剰人員が第2次産業の担い手となった。それでも米国農業には太刀打ちできず、太刀打ちできる目処が立つ前に日本は衰退を遂げることになるわけですが、、、中国のメインシナリオはどっちだろう?日本のように長期的な発展を遂げ、先進国に伍することができるだろうか?あるいはアルゼンチン(この国はどうしてダメになったのだろう?やはり国民性だろうか?100年以上前に米国と覇権を競った国なのに)、ブラジル、メキシコのように崩壊するのだろうか?古い記憶:1)日本も安い労働力を背景に、「安物の国」=私が中学生のころは、米国の同年代からこのように言われていた。2)ジーパンにmade in USAと記した日本製の偽物ジーンズが海外で出回り、米国が苦言を呈したこともあった。このときの言い訳:USAとは宇佐のことである。日本の宇佐は日本書紀にも登場する1000年以上前?からある由緒正しい市名であり、まだ建国より200年に満たない米国などに英語表記をするなといわれる筋合いはない、、、、、、記憶に多少の誤りはあるかもしれませんが、宇佐市が「米国がわれわれに苦言」を呈するのはお門違いとの態度表明。3)中国がもし先進国に伍して、覇権を得る事ができるとしても、それは60年以上後の次のコンドラチェフサイクルになるのだろう。しかし私の本音は「無理」だと思います。すでに日本人も80年代から浮かれてしまい、失いつつある質実剛健、質素倹約。中国も貧しいときはそうであっても、少し裕福になると忘れ、思い上がる体質は日本と同じあるいはそれ以上の国ではないだろうかと思います。今は様子見程度の投資にしておいて、オリンピック終了後で経済が急降下すれば、インデックスとかに投入するくらいだろうか?
May 21, 2006
コメント(2)
-
つれづれに思うこと
投資に関する本も150冊くらいになり、少し前にそのうちの半分くらいを廃棄しました。まだ書庫にはまだ70冊以上の本があるわけですが、いま自分の机上に残っているのは、わずかな本だけになりました。その机上にある本が「投資遊学のすすめ」なのですが、この本は私が持っている投資の本の中ではとても異質な本ですが、かなり考えさせられました。自分なりに思うことは、平成バブルがはじけ、日本人はたしかに自信を失ったと思うのですが、それでもまだ失いきっていないという感じがします。おそらくこの国は、あるいは国民が本当に貧乏になって、打ちのめされて、はじめて目が覚めるのではないかという気がします。日本はまだそのレベルには達していないのではないのでしょうか?今年に入って日本への投資に興味を失っているのは、上述した状況に対する懸念が強いためのようです。
May 19, 2006
コメント(2)
-
それにしても任天堂
任天堂、それにしてもよく上がります。ありがたい話ですが、持ち株とはいえ、この円高では強気になれないのですが、、、ただ、製品の値段付けはとてもよいので期待していますが。2年ほど勉強してみて、上がりだすと皆が好感を持って評価する状況がやっと肌でわかってきました。やはり、ある程度へそ曲がりの逆張りがよいのかもしれません。
May 18, 2006
コメント(0)
-
基本的な投資方針について
私にはこれからもっと円高になるのか,円安になるのか短期的にはよく判りませんが,今後数年間の基本方針をここに記しておこうと思います.ステップ1:金融資産は半分を外貨で持つ(現在は35%,海外口座(残しておけばよかったです!)への移動はまだです).こうすることで円が上がろうが,下がろうが,資金の移行が完成した時点の平均レートで為替がfixされ,円で換算して考えなければ,全体の資産はあまり変動が無くなる.なるべく円高傾向のときに移行するように心掛ける.ステップ2:国内,国外資産とも短,長期債券,証券に配分する.ファンダメンタルおよび月足のテクニカルを加味しながら,幾分かのタイミングを図ったアセットアロケーションを実施する.証券についてはグレアムの考え方を中心に,参入障壁によるプレミアムを考慮して銘柄を決める.グローバルな優良企業については円建てとドル建ての両方の証券,債券を有してもよいこととする.例えばトヨタモータークレジットはドル建てでは利息が5.17%.またインデックスにも配分する.ステップ3:母国通貨の変動により,著しい円安となれば,母国の政策金利は他国と比較して自ずと上昇し,それに応じた株価になると考えられる.著しい円安では,それに応じて運用資金を少しづつ外貨を母国通貨に戻す.あるいは著しい円高となれば,それに応じて運用資金を外貨に変換する.国の借金である日本国債の購入者は日本人自身であり,いまのところ海外からの購入はほとんどない.しかし明らかな通貨の切下げが生じた場合でもデフォルトとまでは至らない場合をメインシナリオとして想定する.日本国債を海外でも買ってもらえるように2005年政府はIR活動をはじめたが,米国の政策金利が毎回0.5%刻みで上昇しているのに,この金利で,この格付けでは買ってくれる外人はいないだろう.トヨタやキャノンなど優良企業は海外の投資対象となっているが,日本国債を買ってくれるようにはなっていない.現在の先進国の政策金利が再び低下し,底を迎える時期.その時期に日本は他の先進国と同等の金利を提示し,国債格付けもあげておく必要がある.そうすれば海外からの資金を自国に呼び込めるだろう.政府が2011年を目標として財政改革を急いでいる以上,先進国の政策金利に伍するべきデッドラインは2010-2012年の時期ということになるのだろう.そこでossanpowerとしては2010年までにステップ1と2を完成させて,アセットアロケーションの練習をすべて終えておこうと考えています.今後もし日本がデフォルトを生じ,著しい通貨の切下げとなれば,日本人は非常に貧乏になるだろう.しかし,その場合でも10年ー20年くらい後には,それがバネとなって再び経済再建がなされるものと思われる.中国がかつて自国通貨を10分の1に切り下げたように.政治的緊張が高まった場合も想定して,南半球の通貨にも一定額の投資を行なっておく.もし,おきるとすれば北半球.南半球にまで核は飛んでこないでしょうし,,,自宅については,考え方によっては減価償却がすでに済んでおり,修理しながらなるべく長く住む工夫をする.しかしこれにこだわらず,海外に居住する自由も確保しておく.いまはフラットな米国のイールドカーブを見ながら,次にどちらに変化するのかを見ておこうと思います.http://japan.pimco.com/LeftNav/Late+Breaking+Commentary/IO/2006/IO_01_2006.htm
May 18, 2006
コメント(0)
-
頭にゲンコツ
今回の円高は株価にとって,頭にゲンコツを食らったようなものでしょうが,目を回してはいても,床に倒れるほどには思えないのですが,,,消費経済の米国でも,急激なドル安は,ガソリン価格(米国の方が税が安い分だけ原油価格がガソリン価格に直結しやすい)が跳ね上がることになり,さらに進行すれば両政府とも為替に対する懸念の声明を出すのではないでしょうか?ブッシュは支持率を気にしているでしょうし,そのあたりを見定めておこうと思います.現在,日本2銘柄,中国6銘柄,米国2銘柄を所有しています.いまのところ順調なのは,任天堂,長城汽車,EVOCでおおむね50%くらい上昇中.ただ他の銘柄はけっこう軟調です.
May 16, 2006
コメント(0)
-
ちょっと不安なディズニー
以下のような記事を見つけました.業績不振初年度の中国国慶節を挟んだ大型連休に香港を訪れた客は、香港の旅行業界が予測した70万人、香港政府見込みの50万人を大きく下回る42万人であったことが判明し、香港ディズニーランドが香港観光の目玉になると期待した関係者の落胆を呼んでいる。ディズニー側は東京ディズニーランド開園時の方針と同様、「開園から4年の業績次第では、閉園も含めて事業を見直す事がある」としており、香港ディズニーランドはこの状況のままでは存続の危機にある。2006年 1月10日、米ディズニーパーク&リゾート社は業績不振を理由に、香港ディズニーランド・リゾートのディズニー側総責任者であるドン・ロビンソンを更迭した。香港ディズニーランドの動員は最大滞流者数3万人の5割から6割と言われ、サービス内容やトラブルに関する報道が影響し、中国本土からの来園者が予想を大きく下回ったものと思われている。後任にはディズニー・クルーズラインを立ち上げた実績のあるビル・アーネストが起用され、開園から4ヶ月で抜本的な改革が行われる。しかしその後も、春節の前売り券をめぐってトラブルとなり、ディズニー社を相手取り訴訟を起こす構えを見せる者が現れる問題が発生している。去年は香港にオープン,2010年には上海で着工する予定のディズニーですが,値段が高いと裁判まで起きる始末とは,,,,オープン2ヶ月で入場料を値引きをしているようです.東京の方は値上げしているんですが,,少し早すぎたんでしょうか.日本の場合は国内が十分成熟してから保護主義を解除したわけですが,グレープフルーツなどは私が中学(35年前)のときに解禁になりました.しかし中国はかつて通貨を10分の1に切り下げ,一気に資本主義への開放政策をとっています.どこかでハードランディングするかもしれませんね.中国への投資は傾倒せずに,ほどほどがよいのかもしれません.いまのところ新聞,自動車,石油化学,ソフトウエア,海運などを保有していますが,持っていて安心なのは新聞ですね.バフェットを見習い,保険,宝石,家具,靴屋など比較的人気のなさそうなサービス業がよいのかなと思うしだいです.幻滅!?「夢の国」 香港ディズニーランド(産経新聞 2005/10/02) 【北京=福島香織】9月12日にオープンしたばかりの香港ディズニーランドが早くも悪評にさらされている。中国人客のマナーの悪さに加え、大気汚染や高い料金とで、夢の国はすっかり色あせた格好。上海にディズニーランドを誘致する計画も取りざたされており、香港政府が投じた224億5000万香港ドル(1香港ドル=約15円)あまりの回収を危ぶむ声は少なくない。「これがディズニーランドとは思えない」香港現地記者はそう指摘した。所かまわず子供に立ち小便をさせる母親、禁煙区でたばこをふかし、たんを吐き散らす男たち。9月18日には、演劇の座席をめぐり男性2人が殴りあいのケンカをして上演が30分遅れる事態もあった。 全体の3分の1を占める中国本土からの客にとっては、175-350香港ドルの入場料やミネラルウオーター1本10香港ドルはばか高い。「金額に見合うサービスでなかった」と、入場料と交通費の返還を求める裁判まで起きる始末だ。 スタートからつまずいていた。12日の開幕式は今年最悪のスモッグに襲われ「呼吸疾患のある人は室内で待機しなければならなかった」(28日付青年参考)。テーマパークのあるランタオ島は自然豊かなリゾート地だったが、大気汚染だけでなく海洋汚染で近海に生息する野生のピンクイルカへの影響などが懸念されている。 香港政府は、年間入場者を600万から1000万人と見込んで12年以内に投資の回収は可能とそろばんをはじく。しかし、香港科技大学工商管理学院経済発展研究センターの雷鼎鳴主任は中国紙上で「たとえ毎日3万人が入場しても、年間利益はわずか10億香港ドル」と見通しの甘さを指摘する、これに追い打ちをかけたのが、香港の4.7倍の規模を持つ上海ディズニーランド構想だ。上海市はすでに土地を用意しているとされる。 ディズニー側は今後5年以内にアジアで新たなテーマパーク建設はないと言明するが、香港紙・信報(15日付)は「香港だけでも集客が困難なのに、上海ディズニーランドができればその末路は想像に難くない」と、危機感を募らせている。
May 16, 2006
コメント(0)
-
バンガードウェズリーインカムファンド
今月は米国のDisney(配当1%)と中国のOriental Press(配当5%)を買いましたが、ほかにバンガードウェズリーインカムファンドを買う事にしました。これは米国の長期債券60%と配当が高い米国株式40%を組み合わせたファンドです。毎年比較的安定した利益が得られているようです。個別にBank of Americaなどを買おうと思っていたのですが、こちらのファンドでは組み入れ銘柄の上位に入っているので、これで代用すれば十分かなという気がしてきました。1980年代以降の年平均利益率は10%と優れています。ただし、80年代、90年代、現在と徐々に金利レベルが低下していますので、直近の数年は平均5%とそれほど高くありません。また為替変動にも注意が必要になるのですが、いまの110円というレートは悪くないレベルと思います。またUSドルMMFも買い増ししています。また米国株式のインデックスファンドとしてはバンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンドにしようと思いますが、今年は見送り、来年以降に開始することになりそうです。日本株式のインデックスファンドとしては、ETFのTOPIX連動型上場投資信託を使うことにしました。ただTOPIXのETFと中国株のETFは今月は見送りです。日経がもう少し落ち着いたあとに考えます。これで資金の35%が外貨建てになり、85%が債券あるいは現金、15%が株式になります。そういえばNZドルのMMFが80万少々あるのですが、これは忘れることにしました。来年の春以降に思い出す予定です。
May 14, 2006
コメント(0)
-
日本株のインデックス売買
毎月、日本株のインデックスを買うことにしました。購入の元になる計算式は以下のとおり5000/(月足のサイコロ10月*2-volume ratio-35)*25000/日経平均これを少しアレンジして、チャートに示します。横軸がテクニカル指標、斜め縦軸が日経平均バフェットがいうようにみんなが警戒しているときにというのを加味しながらも、長期的には少しづつ買い増しできるようなイメージで作りました。また日本の人口構成から22000円以上では市場がよほど警戒しているとき以外は買わないようなイメージを持たせました。あとはこのチャートに、月々のマクロ指標をもとに重み付けを行って多少アレンジをすることにします。これでアセットアロケーションのうち日本株と外国債券については完成しました。外国株式ですが、インデックスについてはバンガードのファンドと中国株のETFを定期的に買うことにしました。日本債券については直接買い付け(2年、5年程度まで)、待機中資金のMRF、預貯金などで当面運用します。とういことで日本株インデックスはテクニカル主体のタイミング投資、国際株式インデックスは定額投資、外国債券は為替主体のタイミング投資ということになりました。もちろん個別株投資として各国のバリュー株の投資も引き続き行っていきます。
May 14, 2006
コメント(0)
-
ニュージーランドの交易条件
統計局の輸出物価指数と輸入物価指数から交易条件を求めました.4半期ごとで前期との比較したもの交易条件はこの3期ほど悪化しています.交易条件の悪化というのは,景気がよいことの表れとされています.日本も今は近年にないほど悪化しています.どうなんでしょうね?日本は円安基調が(一時的?)円高へ方向転換をきたしていますが,NZドルは米ドルに対し,方向転換はしないのだろうか?オーストリアの代表的株価指数にASX50という株価指数があるんですが,2003年から押し目もなく上昇中です.米国の保有銘柄のコカコーラとディズニーとも比較的順調な滑り出しのような気がします.
May 10, 2006
コメント(1)
-
円高ですね
円高ですね。今日は中国ではオリエンタルプレス、米国ではDisneyが約定しました。円高になるほど割安で購入できるので、よいのですが。MMFもUSは買い進んでいます。それにしてもNZは69円台に入りました。こちらのほうはもう自動売買に近い状態なので、今週末くらいに次の買いを進めることになります。ただウエイトについてはこれでよいのか迷っているところ。個別株式については今の指数ではあと2つ買うのがよいところという状況です。予算上、それで当分静観になります。なんか明日の米国の政策金利次第という状況ではないのでしょうか?
May 9, 2006
コメント(0)
-
Disney
AppleのSteve Jobsが大株主のPixerをDisneyが買収した話に注目しています。http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0605/06/news005.htmlDisneyにとって非常に大きな買収になるわけですが、、そのうち安く買えるチャンスはないだろうかと、、、これでSteve Jobsは個人ではDisneyの最大の株主になるわけです。AppleとDisneyとPixer思わず応援したくなる組み合わせです。
May 7, 2006
コメント(1)
-
インデックス投資
連休最終日です。ようやくアセットアロケーションみたいなものが出来上がりました。妻:外国債券(US-MMF主体、一部NZ-MMF、為替変動投資)私:インデックス投資と個別投資(日、米、中を最大20銘柄まで)こちらは為替およびインデックス変動投資(このマトリックスを作るのが複雑で、本日なんとか完成)1)日本:TOPIX ETFかノーロードのインデックスファンド2)中国:2800と2828のインデックスETF3)米国:バンガードのトータルストックマーケットインデックスファンド配分:当面は妻が50%、私が25%、残り25%は当面日本円で資産の移行に際しては、為替動向と株価指数によって、何をどれだけ投資するか大枠を決めました。
May 7, 2006
コメント(0)
-
コカコーラのPBR
持ち株のコカコーラのPBRは現在6倍くらい.どう考えてもバリューとは思いがたい値なのですが,,,2年位前に読んだ「バリュー投資入門」には,1990年以降コカコーラのPBR(PERではありません)は6倍から20倍と書いてあったように記憶しています.バフェットが買ったときもPBRは6倍でした.彼は2000年頃に売らなかったことを悔やんでいるようですが,,のれんを考慮した資産バリューでは歴史的には妥当ということになると思うのですが,,,2年前に読んだ「ウオール街に勝つ方法」では下げ相場に強い「基本バリュー戦略」として主力銘柄(その業界トップの大型銘柄)で配当が高いものが歴史的によいということなので,それを主体に次の米国,中国銘柄を考えています.さらにもう少し待ってから,上げ相場に強い「基本グロース戦略」としてPSRが1.5以下で,先の上昇相場でよく値上がりした銘柄を加えようと思います.バーナンキの発言がFRB議長にふさわしからぬと言われ始めているようですが,市場から見くびられると,心配.ボルカーからグリーンスパンに交代した年の秋にいまも語り草になるブラックマンデーが生じたわけですが,市場がそう思えば,クラッシュは来るかもしれません.
May 6, 2006
コメント(1)
-
2000年-2003年の為替
見にくいチャートなのですが、機械受注(ブルー)が明らかにピークを打ってから、月次の日経テクニカル指標(チャート上辺の線が肌色、ドットが赤の線)が底をうち、それをくぐりぬけるように、円安がピークを迎える。その後は明らかに円高に振れ始め、それを合図に株価が上昇を開始する。1995年から1998年までの円安2000年から2002年までの円安とも同じシナリオで進んでいます。今回はどうなんでしょう?日本の鉱工業生産の出荷在庫バランスは2002年春にプラスに転じてから、今回は息が長くずっとプラスです。私のチャートは1978年からのものなのですが、出荷-在庫がプラスになったのは2000年の7ヶ月間(1%程度のプラス)のみで、2002年までの約30年間はほとんどすべてマイナスで推移していました。在庫過剰(今の中国?)状態が日本では生じていたといえます。ところで今の日本は出荷-在庫がプラス10%越えという、過去30年間見られなかった現象がすでに27ヶ月間連続しており、まだ明らかな低下は見られてません。米国の鉱工業生産のサイクルもこれから上昇を向かえる時期であると思われ、この現象は2006年暮れから2007年初頭まで認め、その後低下するとすれば、機械受注もそれに応じて2007年後半まで上昇を続けるはずです。それならば、機械受注と呼応して、円安もピークを迎えるのは早くて2007年暮れ、通常なら2008年というのが現在考えているシナリオです。また機械受注がピークを迎えるのは、鉱工業生産の出荷-在庫がゼロバランスとなった時点であると予想しています。すくなくともその時点までは、円安であると考えています。金利も上限に張り付くのは、2006年暮れから2007年前半ではないでしょうか?4月下旬から5月には、カナダも豪州もまだ利上げを行っていますし、、、また為替と株価で考えると、中国の株価が歴史的なピークを迎えても、そこで円には換えず、中国の債券に投資する。そのうち為替(元)のピークを迎えるまで、それを保持したあとで、日本円に戻すというのが正解な気がします。また現在の日本の株価もまだ少し上があるように思います。この辺は2月ころのミスター円の見解と同じなのですが、、、
May 5, 2006
コメント(0)
-
ミスター円
ミスター円といわれた方の発言ですが、たしか1月か2月ころはある番組の終わりに、株高円安を主張されていました。しかし最近、夏に向けて1ドル110円に向かって円高が進むであろう。さらに夏から年末に向けて1ドル100円に向けて円高が進むと。まあそのときによって事情は変わるのでしょうけど、、、、気づかれている方はほかにもいるようで、あるブログによれば、昨年は円高になると円高、円安になると円安と3回ほど修正されているようです。目先の2,3ヶ月のことを言われていると解釈したほうがよさそうです。視聴者が何を求めているかについて、承知されていれば、短期的には、、、長期的には、、、、などといっていただければありがたいと思います。今後は、あまり気にしないことにします。為替変動に応じて決めた額を買うことにしていますので。過去3年におけるNZドル・円とUSドル・円の関係は円ベースにした通貨間ではもっとも相関関係が低いようなので、両者のバランスをとりながら、外貨資産を増やしていくのを基本にしています。為替取引のかたのなかにはポンスイなんかはUSドル円と逆の相関のようで、それを購入している人もいるようです。FXには私自身は税金面を考えると手を出せません。NZドルは豪ドルとも相関を失い、昨年末より豪ドルからみても下落をしていますので、いずれ誰もがNZドルに興味を失ったころ、たぶん2010年から2011年ころに妻の資産でFXを用いだすようなイメージで考えています。いずれにせよ再び円高局面がくるのであれば、非常にありがたいのですが、あまり期待はしていません、、
May 5, 2006
コメント(0)
-
EVOC
8285 EVOC が昨日14%くらい上がっていました。けっこう、元気ですね。財務などから計算して割安度を求めていますが、まだ安全マージンは50%以上あると思います。中海コンテナよりも割安ではないかと思っています。
May 3, 2006
コメント(0)
-
ドルが112円
昨晩、USドルが112円まで円高になったので、買い増し。結構、動きますね。130円想定で買っており、130円から112円までの分を平均114円くらいで買えたと思います。為替については,円USドル,円NZドルだけでなくて,NZ-USドル,NZ-豪ドルのチャートをライブドアファイナンスでみるようにしたところです.これだと今回は円高ではなく,ドルが下落したことがよく判ります.為替と外貨MMFの方は連休中にはシステムを軌道に乗せ,次は外国株式のインデックス投資の準備に取り掛かっています.これについては,どのくらいのポジションを取るべきか考えています.今年の秋から冬までに行なうことは以下の4つ.1)個別株式投資銘柄を20前後(日,米,中)2)US-MMF,NZ-MMFのポジション3)外国株式インデックスのポジション4)日本国債のポジションあとは海外口座を再度設けるかもしれません.
May 2, 2006
コメント(0)
-
結局、米ドル、NZドルのMMFは
結局、4月に米ドル、NZドル(MMFが主体)は、私と妻の分を合わせると保有証券時価総額の概ね7倍ほど買っていました。思いのほか大きかった。これでは債券投資家ですね。MMF投資は初めて1ヶ月なのにこれではちょっと多すぎ、、、もうすこし私と妻で意思の統一を図る必要があるようです。買値は米ドル115円程度、NZドル72円程度が主体。アセットアロケーションについて連休中に妻ともっと勉強するつもり。バランスを考えなくては。それにしても株担当である私自身の気の小ささよ、、、
May 1, 2006
コメント(0)
全24件 (24件中 1-24件目)
1