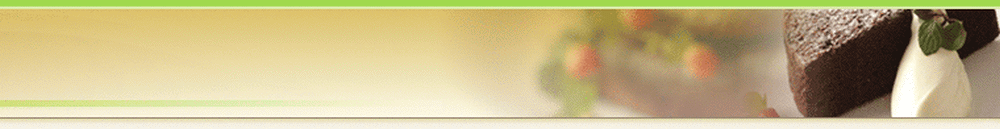PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
カテゴリ: 舞台
先日「文楽を楽しむ会」にて文楽人形のかしらの修理・制作をしているかたと、床山さんの実演つき解説を聞いてまいりました。
文楽人形のかしらは樹齢60年以上の檜を彫って作りますが、木の芯を使うとひびわれるので芯を避けるにはそのくらい大きな木でないとだめなのだそうです。日本にはもうないので、輸入ものとのこと。鬘の人毛も疾うに日本では手に入らず、中国の奥地の少数民族のかたにブラシについた毛をとっておいて貰うのだそうです。それを苛性ソーダで煮てから染めるとのこと。
人形の鬘は人間用と違い、髷、鬢などパーツごとに釘で打って留めます。人形の頭には釘のあとがたくさん。

公演ごとに胡粉を塗り、ベンガラなどで化粧します。だんだん厚塗りになっていくので、20年ほどしたら全部剥がすそうです。釘穴がたくさん開いたところなどは部分的にとりかえてゆき、50年ほどするとほとんどいれかわっていることになるそうです。大体使われている木の樹齢と同じくらいの間使えるとのこと。
こんな仕掛けのかしらも。

梨割りといって、その他大勢の斬られ役です。目がキョロキョロします。ブラックユーモアというのか…
「日高川」(安珍清姫のお話)の清姫の髪を結っているところです。無我夢中で追っていくので、髪をわざとくずし(「がったり」)、あとで髷がほどけるようにしておきます。きれいにほどけるとこの仕事の喜びを感じるそうです。

床山さんの道具。鬘のパーツや櫛。クジラのひげも使います。鬘は前の方は人毛。髷はヤクという動物の毛。糸に毛を数本ずつ結びつけたものを胴の板に穴をあけたもの(左下のカチューシャのようなもの)につけておき、人形に直接釘でつけます。

昔ながらの通気性のよい行李に入れています。プラスチックケースだとカビや虫がつくそうです。

文楽の鬘についてはこちらをごらんください。
鬘司庵
今日から東京公演が始まります。いつもチケット争奪戦に悩まされますが、今月はまだチケットがあるそうですので、百聞は一見にしかず、ぜひご覧になってみてください。
文楽人形のかしらは樹齢60年以上の檜を彫って作りますが、木の芯を使うとひびわれるので芯を避けるにはそのくらい大きな木でないとだめなのだそうです。日本にはもうないので、輸入ものとのこと。鬘の人毛も疾うに日本では手に入らず、中国の奥地の少数民族のかたにブラシについた毛をとっておいて貰うのだそうです。それを苛性ソーダで煮てから染めるとのこと。
人形の鬘は人間用と違い、髷、鬢などパーツごとに釘で打って留めます。人形の頭には釘のあとがたくさん。

公演ごとに胡粉を塗り、ベンガラなどで化粧します。だんだん厚塗りになっていくので、20年ほどしたら全部剥がすそうです。釘穴がたくさん開いたところなどは部分的にとりかえてゆき、50年ほどするとほとんどいれかわっていることになるそうです。大体使われている木の樹齢と同じくらいの間使えるとのこと。
こんな仕掛けのかしらも。

梨割りといって、その他大勢の斬られ役です。目がキョロキョロします。ブラックユーモアというのか…
「日高川」(安珍清姫のお話)の清姫の髪を結っているところです。無我夢中で追っていくので、髪をわざとくずし(「がったり」)、あとで髷がほどけるようにしておきます。きれいにほどけるとこの仕事の喜びを感じるそうです。

床山さんの道具。鬘のパーツや櫛。クジラのひげも使います。鬘は前の方は人毛。髷はヤクという動物の毛。糸に毛を数本ずつ結びつけたものを胴の板に穴をあけたもの(左下のカチューシャのようなもの)につけておき、人形に直接釘でつけます。

昔ながらの通気性のよい行李に入れています。プラスチックケースだとカビや虫がつくそうです。

文楽の鬘についてはこちらをごらんください。
鬘司庵
今日から東京公演が始まります。いつもチケット争奪戦に悩まされますが、今月はまだチケットがあるそうですので、百聞は一見にしかず、ぜひご覧になってみてください。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[舞台] カテゴリの最新記事
-
スカーレット・ピンパーネル August 3, 2008 コメント(14)
-
Me and My Girl June 10, 2008 コメント(10)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.