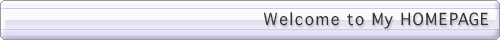***
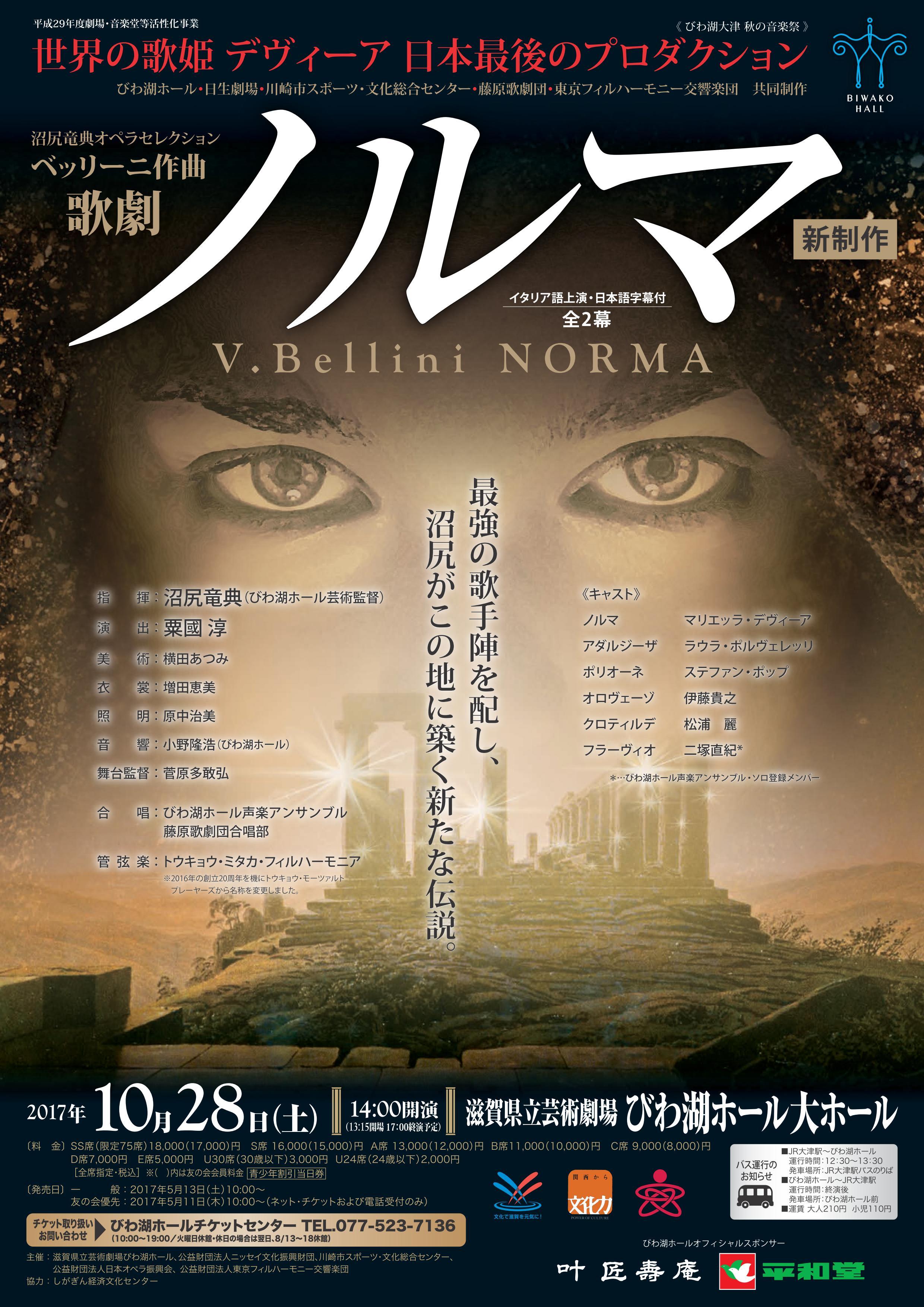 沼尻竜典オペラセレクション
沼尻竜典オペラセレクションベッリーニ作曲 歌劇『ノルマ』全2幕〈イタリア語上演・日本語字幕付〉
びわ湖ホール/日生劇場/川崎市スポーツ・文化総合センター/藤原歌劇団/東京フィルハーモニー交響楽団 共同制作公演
2017年10月28日(土)14:00開演
びわ湖ホール(大津)
指揮:沼尻竜典 Ryusuke NUMAJIRI(びわ湖ホール芸術監督)
演出:粟國 淳 Jun AGUNI
衣裳:増田恵美 Emi MASUDA
照明:原中治美 Harumi HARANAKA
舞台監督:菅原 多敢弘 Takahiro SUGAHARA
ノルマ マリエッラ・デヴィーア Mariella DEVIA
アダルジーザ ラウラ・ポルヴェレッリ Laura POLVERELLI
ポッリオーネ ステファン・ポップ Stefan POP
オロヴェーゾ 伊藤貴之 Takayuki ITO
クロティルデ 松浦 麗 Rei MATSUURA
フラーヴィオ 二塚直紀* Naoki NIZUKA
*…びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー
トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア
***
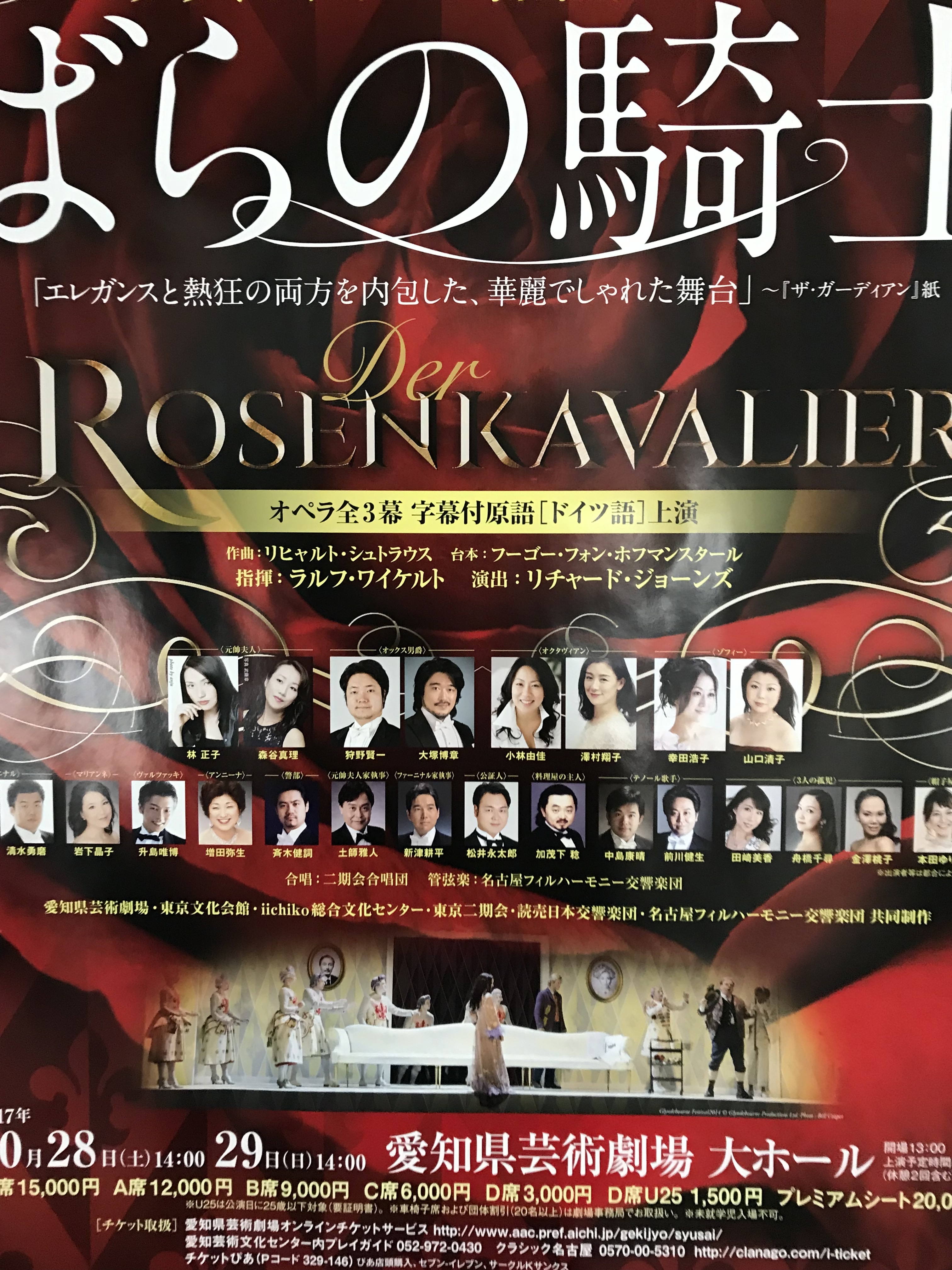
R.シュトラウス作曲 オペラ『ばらの騎士』(全3幕、ドイツ語上演)
名古屋公演 DAY2
愛知県芸術劇場・東京文化会館・iichiko総合文化センター・東京二期会・読売日本交響楽団・名古屋フィルハーモニー交響楽団 共同制作
2017年10月29日(日)14:00
愛知県芸術劇場大ホール
指揮:ラルフ・ワイケルト
演出:リチャード・ジョーンズ
元帥夫人:森谷真理
オックス男爵:大塚博章
オクタヴィアン:澤村翔子
ファーニナル:清水勇磨
ゾフィー:山口清子
マリアンネ:岩下晶子
ヴァルツァッキ:升島唯博
アンニーナ:増田弥生
警部:斉木健詞
ファーニナル家執事:新津耕平
元帥夫人家執事:土師雅人
公証人:松井永太郎
料理屋の主人:加茂下 稔
テノール歌手:前川健生
ほか
合唱: 二期会合唱団
管弦楽:名古屋フィルハーモニー交響楽団
***
土曜日に大津で『ノルマ』、日曜日には名古屋で『ばらの騎士』を観ました。どちらも、年長の女性が、年若い女性に、自分の思い人を取られてしまうお話。そして、前者の演者と後者の物語の内容の間に、時の移ろいという共通点を感じた2日間でした。
デヴィーアの舞台を前回観たのは、たぶん初台の劇場での『ルチア』だったと思います。見事な歌唱でした。それ以前にも、何度か彼女の歌を聴きましたが、その歌はいつも完成度の高いものでした。こうあってほしいという、まさに、そういう歌。しかし、教科書的とも言える彼女の歌の、僕はあまり良い聞き手であったとは言えません。正直に言うと、不遜にも、その歌を少しつまらなくも感じてもいました。
今回のノルマは、瑕疵はあったものの、見事としか言いようがないようなものでした。声の衰えを、力任せにごまかさず、情緒に流れないdisciplineのある入念な歌。そこにあったのは、まさに崇高な歌でした。今までの、おのが不明を恥じました。あの声と技を維持するために、彼女がいかに厳しく自らを律してきたのか、それを身に染みて感じ、畏敬の念を抱かざるを得ませんでした。
アダルジーザを担当したメゾは、立派に役割を果たしていたと思いますが、デヴィーアの音色が若々しいものでしたので、ちょっと彼女よりも年長に聞こえてしまったのが残念。今回、楽しみにしていたポップは、テノールの声を聴く喜びを十分に味わわせてくれました。日本人キャストの方々も十分に役割を果たされていましたね。沼尻さんの棒は、とても几帳面。粟国さんの演出は、既視感のあるものでした。
日曜日の『ばらの騎士』の演出は、土曜日に歌われた林さんのマルシャリンで7月に東京で観ていました。なんとなく、ルイス・キャロルの物語の世界のような演出ですよね。名古屋の公演では、出だしのホルンは見事だったものの、その後の会話主体で音楽が進む第1幕のアンサンブルは、オケが舞台上の歌に寄り添えず、僕の耳には崩壊寸前のものに聞えました。1幕が終わったら、帰ろうかと思ったくらい。でも、マルシャリンのモノローグあたりから、雰囲気が一変。オケの奏でる音楽に、びっくりするような変化が起きたのです。なんとも馥郁たる香りが漂ってくるような思いにとらわれました。東京での公演になかった「香り」が、この名古屋の公演にはありました。指揮者とオケの組み合わせでしょうか。前日の沼尻さんの棒とは異なり、ワイケルトさんのそれは、もっと音楽を大づかみにしたようなもの。それがアンサンブルの緩さに繋がったと同時に、銀のばらにふりかけられたペルシアの香油のような、この「香り」をもたらしたように思いました。名古屋に生活の場を移して、それなりの年月が経ちましたが、今回、初めて名古屋フィルの音色に聴きほれました。実は一度も足を運んだことがないのですが、その定期演奏会にも行ってみようかとも思いました。
お目当てだった森谷さんのマルシャリン。渋谷で聞いたステンメのものに近い印象。暖かく、細やかでありつつも大きな歌。ちょっと気になったのが、調子が万全ではなかったのか、第1幕では、会話調の歌ということもあるけど、本来の声が出てくるに時間がかかり、第3幕の登場時には、押し出すように声を出そうとして、ちょっと叫びがちになっていたように聞こえたこと。5月に豊橋で聴いたレオノーラでは、そのような印象は一切受けなかったのですが。まさか、蝶々さんの影響?
***
「名古屋のおやじ」さま、速報の感想をいただき、誠に感謝です。
ノルマは私は川崎公演、「名古屋のおやじ」さまは大津公演、
「ばらの騎士」は私はDAY1で「名古屋のおやじ」さまはDAY2鑑賞と、
結果良かったです。やはり見なかった日もとても気になりますもの。
東京公演でもお互い逆の日を見てたとは徹底してますよね!面白い偶然です。
私は「名古屋のおやじ」さまの感想を読んで、ばらの香油がただよってきたような気がしました。
ありがとうございます!
-
新宿オペラ「ドン・カルロ」Day1 2025年11月22日
-
オペラ「高野聖」再演@高崎 2025年11月16日
-
「羊飼いの王様」終演後アフタートーク 2025年11月11日
PR
サイド自由欄
TENOR

小原啓楼

Ten.笛田博昭~2016
Ten.笛田博昭2017
公式サイト

小野弘晴(テノール)
UPCOMING

Ten.城宏憲 INDEX 2014~2017

Ten.又吉秀樹 INDEX
Ten.又吉秀樹2017

Ten.澤崎一了~2017
澤﨑一了2018~2019

Ten.小堀勇介2015
小堀勇介2016~2017
小堀勇介2018
小堀勇介2019
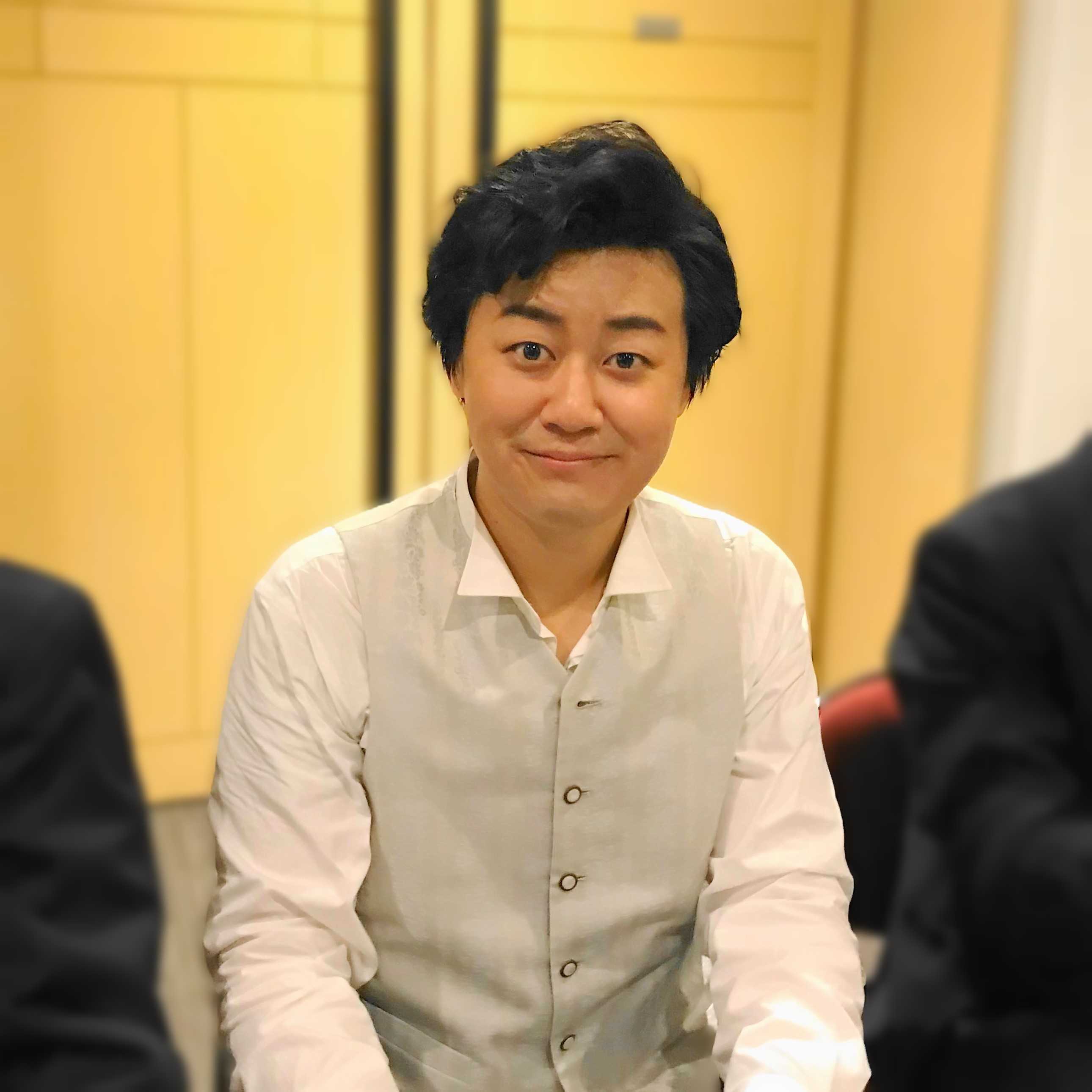
金山京介
2025

吉田連
UPCOMING
Ten.吉田連

Ten.前川健生

伊藤達人
UPCOMING
PAST

Ten.宮里直樹
UPCOMING
PAST
~2017
2018~2019

下村将太 テノール
2025

工藤和真
UPCOMING
PAST
BARITONE

青山貴
UPCOMING
2015
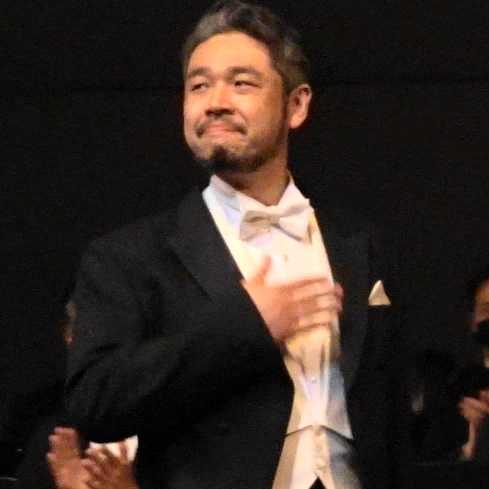
KS Tomohiro Takada, Bariton 概要
2024~2025

Bar.大沼徹
UPCOMING
2015~2016
2017
2024
His repertory 1

今井俊輔
UPCOMING

高橋洋介
UPCOMING
PAST

飯塚 学
UPCOMING

小林啓倫
UPCOMING
PAST

清水勇磨
UPCOMING

大西宇宙
UPCOMING

池内 響
UPCOMING
PAST
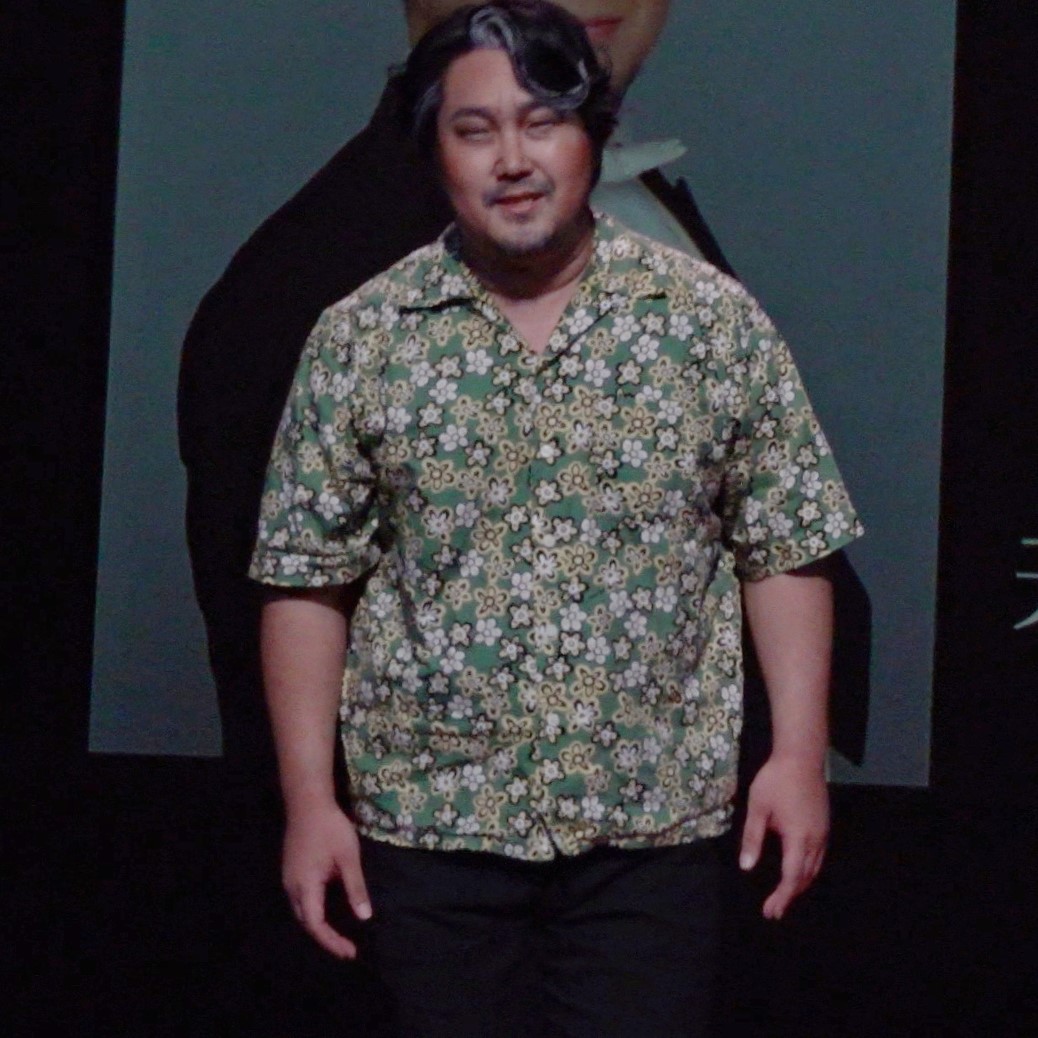
井出 壮志朗
UPCOMING
PAST
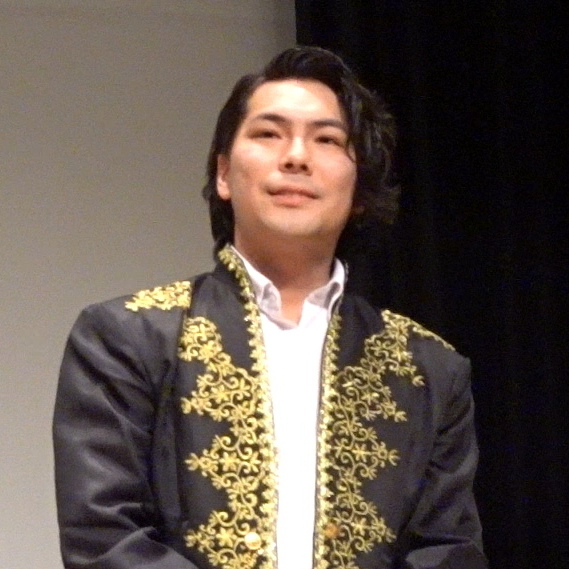
市川 宥一郎
UPCOMING
PAST

大塚博章
UPCOMING
Bs-Br大塚博章 2014-2015

Bs-Br狩野賢一2015

Bs河野鉄平

後藤春馬(バス・バリトン)
UPCOMING

水島正樹
UPCOMING
IL DEVU
HIGHLIGHT 2014
Francesco Meli Il Trovatore
Micheal Fabiano La traviata
Juan Diego Flórez IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Tézier vs Kaufmann La forza del destino
OperadeLyonJapan tourHoffmann
Stefano Secco Madama Butterfly
Bryan Hymel Guillaume Tell
Dmitry Korchak I Puritani
Celso Albelo Lucia di Lammermoor
Teatrodell'OperadiRomaJapantour2014
Wolfgang Koch Arabella
Lawrence Brownlee I Puritani
Tomasz Konieczny Das Rheingold
Torsten Kerl Die tote Stadt

Best Opera 2024

Best Opera 2023

Best Opera 2022

Best Opera 2021

Best Opera 2020

Best Opera 2019

Best Opera 2018 Index
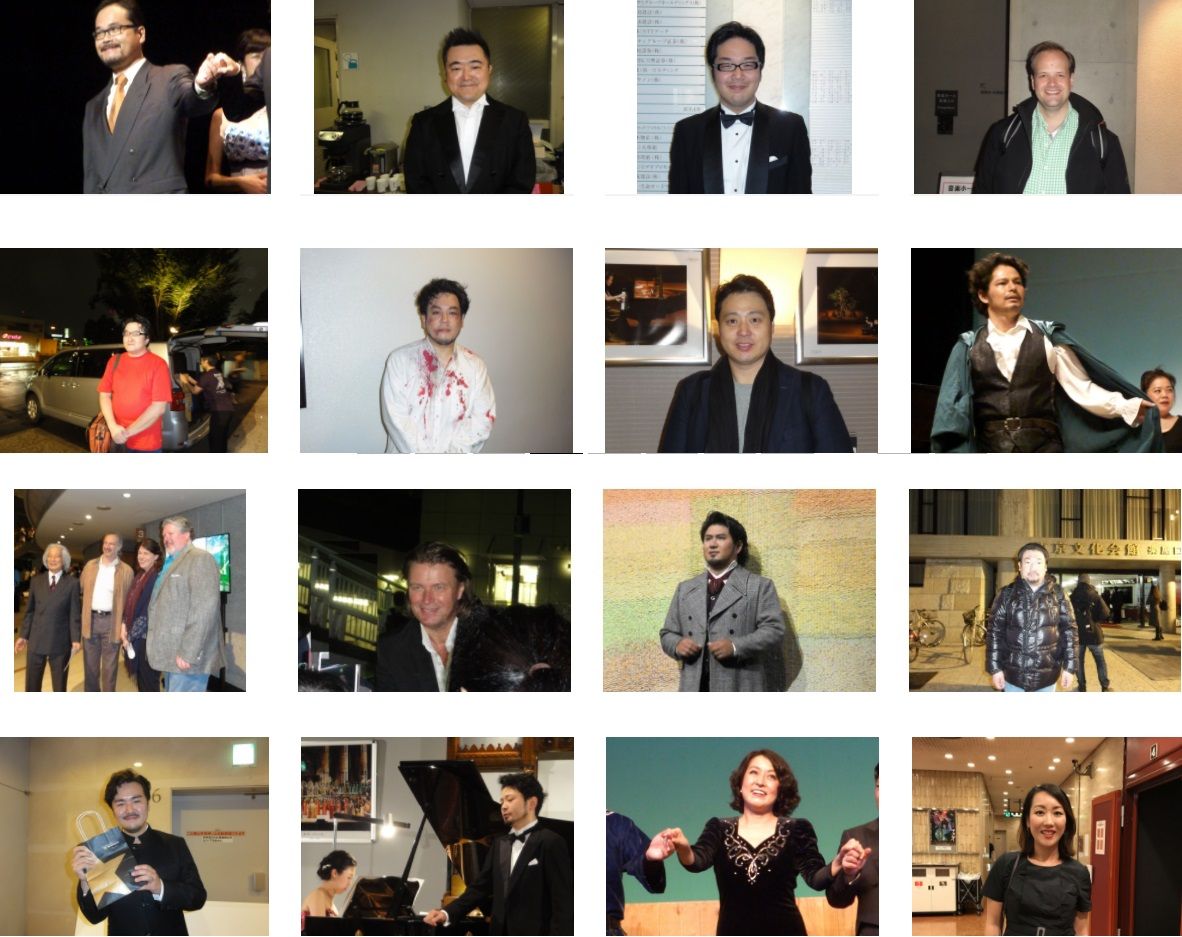
Best Artists in Opera 2017
Best Opera 2017
Photo:©Shevaibra, courtesy of the artist

2016 Best Opera

2015 Best Opera
2014 Best Opera
2013 Best Opera
2012 Best Opera
2011 Best Opera and Ballet
2010 Best Opera and Ballet
2009 Best Opera and Ballet
2008 Best Opera and Ballet
[BALLET]
2009
2008 Ballet Top 10 in Japan
2008 BALLET INDEX
What's New 2007
What's New 2006
Past Articles 2005
Past Articles 2004
Past Articles 2003
[OPERA]
Simon Keenlyside What is NEW ?
Robert Gambill
What's new
Biography
2008 Opera Top 10 in Japan
2007 Top 10
What is NEW ? 2006
What is NEW ? 2005
STAGE What is NEW ?
Second Top -Sheva's Sporting World
Football
[José Mourinho - Chelsea 2007 Index]
[José Mourinho - Chelsea 2006 Index]
What Mourinho said - 抱腹絶倒モウリーニョ語録
Last edited 1 Jul 2007
FOOTBALL What is NEW ?
2005
Tennis
2006
Roger Federer First time in JAPAN - AIG Japan Open INDEX
Cinema, Books brand new and privat
Cinema
2005年5月3日
音楽関係更新 Classical Music
BOOKS 2006
BOOKS 2004年
1月31日 Books by Jeffery Deaver
AMP DANCERS INDEX
NEW ADVENTURES Dancers Index
Cooper Company Dancers Index
Adam Cooper Index
Matthew Hart Index
Jesus Pastor Index
Damien Stirk Index
Andrew Corbett Index
Will Kemp Index
Isaac Mullins Index
Ballet Choreographer Index
Matthew Bourne Index
Ballet Company Index
Ballet Pieces Index
Musical Index
LINKS
Theatre official
Bayerische Staatsoper
Bayreuther Festspiele
Lyric Opera of Chicago
MET
Royal Opera House
Salzburger Festspiele
Teatro alla Scala
Wienerstaatsoper
ZurichOperaHouse
New National Theatre,Tk
Tokyo Nikikai
Singers official
Takashi Aoyama
Aris Argiris
Johan Botha
Fabio Maria Capitanucci
Massimo Cavalletti
Markus Eiche
Alex Esposito
Burkhard Fritz
simonkeenlyside.info
Wolfgang Koch
Tomasz Konieczny
Zeljko Lucic
Alexey Markov
Tetsuya Mochizuki
Ryoichi Nakai
Evgeny Nikitin
Toru Onuma
Takashi Otsuki
René Pape
Detlef Roth
Andreas Schager
Jörg Schneider
Kasumi Shimizu
Yuri Vorobiev
Koji Yamashita
Kwangchul Youn
Operabase Artist
Orchestra
Berliner Philharmoniker
NHK Symphony Orchestr
Opera Fan Blog
Alex Vinogradov(Valenci
By The Thames(dognora
Cafe Klassiker H(Hiroto
猫の日記(camelstraycat
FOOD FOR SOUL(Sarda
東海岸-音楽、食(Kinox
Impression(娑羅)
In fernem Land(galahad
Intermezzo
ネコにオペラ(kametaro)
Opera Chic
OperaOperaOper(Madok
右舷日記(starboard)
taqkkawanamiさんのブログ
備忘録(euridice)
Ballet Fan Blog
きょんのバレエ日記(きょん)
Web Radio
Oe1 Programm
Bayern 4 Klassik
Deutschlandradio Kultur
NDR Kultur
RBB Kultur
BBC Opera on 3
RAI radio3
WFMT-Chicago
Sydney ABC
Radio New Zealand Conc
operacast
劇場座席数・残響時間
SITE MAP
Sheva's Blog( What people tweeted )
Since Apr 2003
キーワードサーチ
カテゴリ