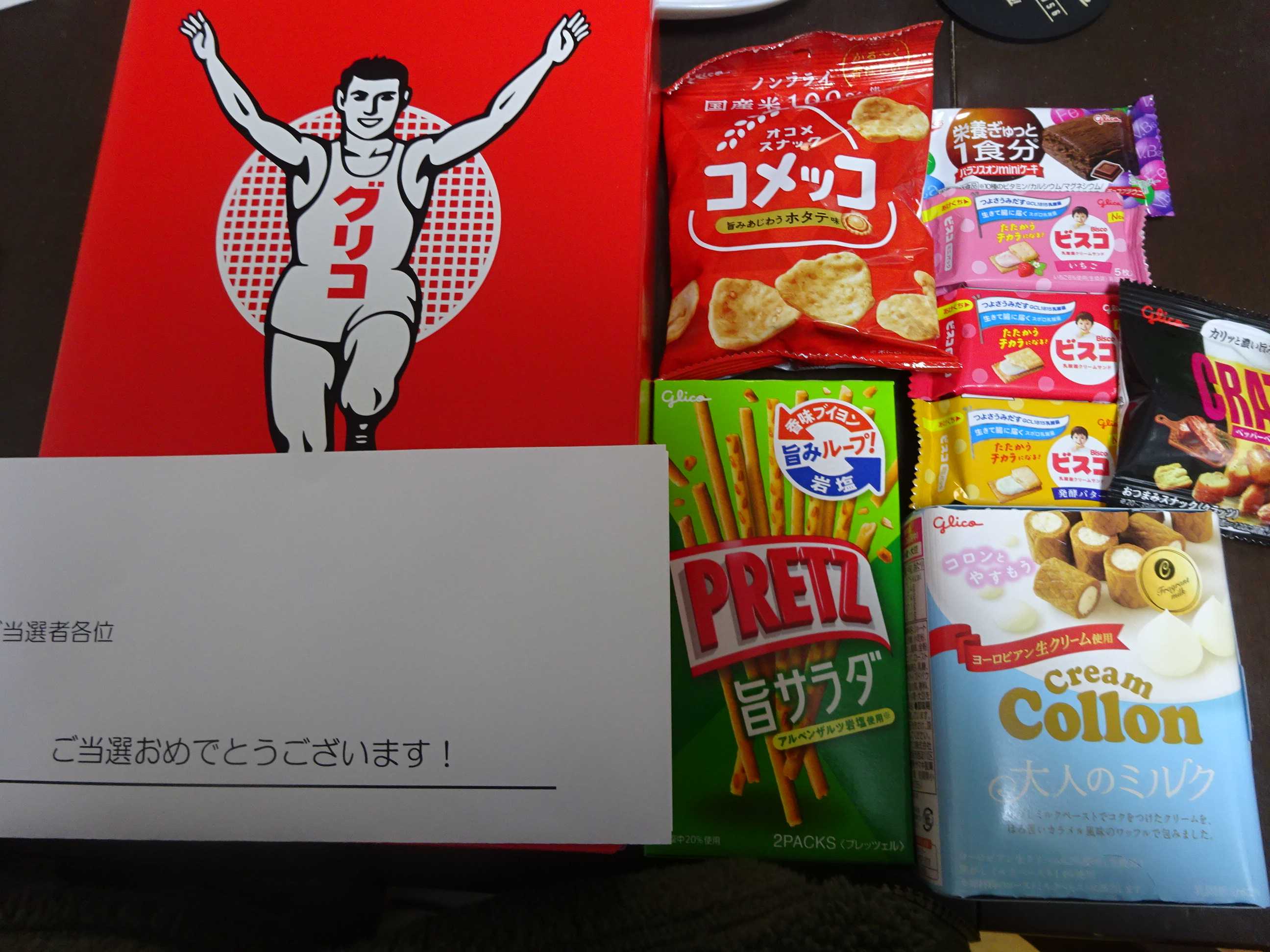2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年05月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
『ロッキーへの手紙』
たぶん去年の話だったと思うけど深夜何気なくつけたテレビに、ニホンカモシカのこどもが映っていた。何らかの事情で自然からはぐれてしまった野生動物を保護し野性に帰す活動をしている、宮城県の武田さんという人がお母さんとはぐれたらしいニホンカモシカの赤ちゃんを預かり森に帰すまでのドキュメンタリー。このカモシカの名を「ロッキー」という。甘えん坊のロッキーは、武田さんを親のように慕う。べったりくっついて甘えてくる。野性に戻すことに備えて体力をつけさせるべく、外に散歩に出ても最初は武田さんの後を「ポコン、ポコン」とひたすらついてくるだけだったロッキー。成長するにつれ、ロッキーが野生に帰る時が近づいてくる。森で遊ばせると、だんだんひとりきりで遊ぶ時間が長くなってゆく。そしてあるとき突然森の奥へと帰っていってしまう。テレビでは森へ帰ったかのように見えたロッキーが武田さんの呼びかけに応えて戻ってきてさらにしばらく後に本当に森に帰ってしまうところまでが描かれていた。一連の映像として見るとさっきまで人なつっこかったロッキーがひとたび森へ帰ってしまえばそんなことまるで忘れてしまったかのような顔になってしまっているところに武田さんの感じたであろうさみしさを共有しつつ野生ということの清々しさを感じた。人がごはんを整えていたことも、寝床を用意していたこともおいしそうにそれを食べて、寝床で満足そうに眠っていたことも野生に戻れば忘れてしまうのだ。それを止めることはできない。このロッキーのことが今年の1月ごろ、本になった。本ではさらにその後のロッキーとの再会が描かれている。宮城県の森から奥羽山脈へ向かうロッキーが安全に高速道路を渡れるよう武田さんが最後の手助けをする。さらにその後のロッキーがどうなったのかたぶん誰にもわからない。ロッキー、元気にしているといいなあと、こんなに遠くにいても思う。このドキュメンタリー、できればもう1回見たい。。。 『ロッキーへの手紙』武田修 アメーバブックス 2006
2006.05.31
コメント(6)
-
お嬢度も甚だしい
うちのハムスター(メスのジャンガリアンの“はな”)、上の前歯を悪くしたのでこないだ下の歯を切ってもらった。小さい時からずうっと青菜のしかもいちばんみずみずしくってやわらかい部分をかじるのが大好きだったのにそれ以来大きな葉を入れておいても噛み切るのが難しいらしく食べ残すようになった。そこでおとといは葉を細かくちぎってあげた。食べた。にんじんも好物だが硬くてとても齧れないと思い、やわらかくて甘そうな採りたてをすりおろしてあげた。食べた。あっという間に完食。本人はいたって満足そうであった。すっかりお嬢な。。。このはなごろう、ハムスターフードなどはお湯でふやかして与えるためえさの長時間の放置ができない。なので朝晩2回に分けて少しずつ与える。おなかがすくと寝床から出てきてえさを探す。そのタイミングで用意できていなかったら「チゥチゥ」って切なそうに鳴く。そしてがっくりとまた寝床に帰っていく。このところ帰宅時間が不規則な私。ハムフードはすぐにはふやけない。はなごろうが起きてきておねだりするまでに帰ったらとりあえずお湯を沸かしてなんとか泣かせないように備えたい。しかしさっきも「チゥチゥ」って鳴いた。何ごとかと思ってのぞいてみたけど何も困ったことはなさそう。本人は寝床にいる。もしかして寝言?
2006.05.30
コメント(4)
-
Mr. Kuranosuke
昨晩「チューボーですよ!」を観ると佐々木蔵之介氏が堺正章巨匠とペスカトーレを作っていた。この蔵之介さん、もともと好感度が高い!と思っていたのだけど出身地が同じ、出身校が同じ、なのだった。世代もまあかぶっているし、過ごした校舎も近いみたいで、もしかしたら学校の時にすれ違ったりしているかもしれない!と思ってさらに親しみが湧く。たまに有名な人の中に、親近感を覚える人がいる。過ごしてきた環境に共通点がある、年代が同じ、というのはこの場合大きな要素でいわゆるファン的心理とはたぶんちょっと違って「ああ~あなたもいろいろたいへんなんですなあ~」と勝手に大変具合を心配したり「これはできとしてはどうなんでしょう?」と冷静な友達風に芸を云々したりまるで「今度会ったらこれを言うとこう」みたいに思う(迷惑)。そして蔵之介さんは私の思う京都風な人であるところもなつかしみを感じるのであった。この「京都風な人」、定義が難しいけど私の中に確実に基準がある。わりと思い浮かべやすい京都の人の知り合いのうち4分の3がこの基準に合致する。この人が京都出身と聞いて、「ああ、だからか」と妙に何かを納得したものだ。このたびこれを書くにあたって蔵之介さんのプロフィールを再確認していて大変近いところに友達がいることに気づいた。彼女にはぜひ今度聞いてみよう!そして「間宮兄弟」もそろそろ観よう!よければみなさんも観ましょう!!
2006.05.28
コメント(14)
-
かごしまさくらじま
鹿児島旅行2日目。念願の桜島へ。初日の霧島からもほんとは見えるらしいのだがあいにく曇り気味で見えなかった。ホテルの窓にむかって従業員さんが身振り手振りで描いてくれた「こんな感じに見えるはずです」という図を想像だけする。鹿児島市に到着し、港へ。ところが桜島、かすんでいてやはり見えない。島の下のほうだけ見えていて、どうやらあの辺にあるらしい、ということだけがわかる。がっくりしながら船に乗り、島へ渡る。桜島温泉。「南無観世音大菩薩」と背中に書かれた浴衣を着て混浴の露天風呂に入る。波打ち際の露天風呂。お湯に塩分が多いせいか、半身浴でもすぐに汗が出る。折しもテレビ番組のロケが行われている。出演陣のひとりに舞の海が。「あ、舞の海だ」と私。「知らん」と、きっぱりはっきり友達が言い、あせる。のぼせたので波打ち際に出て水に浸る。ふと振り返るとカメラが。舞の海の旅番組で、海に向かって足を投げ出している女の後姿が出ればそれが私です。(しかし何の番組なんだろうか)桜島には泊まらず、再び船に乗り戻る。夜中に大雨。明けて翌日、からっと晴れた一瞬、てっぺんまで桜島が見える。あとで写真に撮ろうと思いつつもまずは県立図書館へ(友が調べ物をするというので)。しかしその間にまた桜島は見えなくなってしまった。桜島。見えそうで見えない。この感じは阿寒湖?写真はぼんやりの桜島。can you imagine it?
2006.05.24
コメント(13)
-
かごしまきりしま
以前からずっと見てみたかった桜島を見に鹿児島へ。楽しみは2日目に取っておいて、まずは霧島温泉郷へ行く。南九州は全然行ったことがなく桜島、霧島、高千穂、などなどなんだか趣のある地名を見るだけでもわくわくする。山深くにある霧島温泉。さぞや静寂な、と思ったら案外人里だった。霧島神宮にお参りをして、樹齢700年の杉の木を見上げる。巨木大木を見上げるのは大好きだ。お土産やさんのおばちゃんにすすめられるままに森林浴になってるかな、と思いながらぶらぶらと高千穂牧場へと歩く。ところが1キロくらいと聞いていた道、なかなかたどりつかない。地図もあやふやなものしかなく不安になる。道中初めて遭遇したヒト、農作業中のおじさんに道を尋ねる。ところがおじさん、高千穂牧場と聞いて瞬間絶句する。そして、「あのねえ、とりあえずこの道をまっすぐ行って次の角を右に曲がって…」と説明を始めたものの言葉が続かず「…あれに乗って!」と軽トラックの荷台を指差すのであった。荷台にしがみつきながら走ること10分あまり。なるほどこの道程を口で説明するのは無理でしょうとも。てくてく歩いた道をどんどん引き返しふりだし以前に戻る。私ども「霧島神宮から1キロくらいと聞いたんですけど~」おじさん「そうよ1キロくらいよ」要するに根本的に間違っていたのね。ありがとうおじさん。見ず知らずの一般の人に送ってもらうのは初めてだ。おじさん「どこまで帰るの?」私ども「丸尾のバス停まで」おじさん「帰りはどうするの?」私ども「…あ、もうタクシーに乗ります。すみません」おじさん「じゃああのホテルから乗ればいいから」と、丘の上のホテルを指差す。すみません無計画で。帰りの私たちはもう丘の上まで歩く元気もなく牧場までタクシーを呼びつけました。お金で解決の大人旅行。じゃあはじめから乗れば…
2006.05.23
コメント(5)
-
おなかのぐるぐるの。
胃部内視鏡検査。いわゆる胃カメラである。初めて胃カメラを飲んだのが、17、8のころなので私の胃弱年数は対年齢的にかなり長い。しょっちゅう胃を壊しているのでもう何回になるだろう。この胃カメラ以前はそんなに意識していなかったので気づかなかったが看護士さんやお医者さんが、患者の身体的負担について、他の検査より非常にナーバスだ。検査を受ける前に麻酔として、液状の薬剤を口に含む&注射を施してもらうのだけど口に含む液体は10分ほど含みっぱなしでこれが案外苦しい。看護士さんのいわく「つらくなったら吐き出して大丈夫ですからね」そして注射はどうやら通常より痛いものらしい。そこでまたのたまわく「痛いですよ~がんばってくださいねえ~」ここまでの過程をたんたんとこなしていよいよ胃カメラ。「がんばってくださいねえ~」って、先生も看護士さんも"ひしっ"という雰囲気でむやみやたらになぐさめはげましてくれる。それが余計に恐怖心をそそる。途中からなされるがままにだらだら~っとすごしたので大丈夫だったけど直前にそうやってびびらされたせいかほとんど気絶したいくらい(まあ、それほどの苦しさではないけど)おなかの中に差し込まれるチューブ状のカメラを一気に吐き出したいくらい(まあ、実際長いもので吐き出せっこないけど)の、苦しみ。初めて受けた頃には「上手ですねえ」と医者に言ってもらい医者と看護士の超日常的な雑談の中案外楽に済ませた。今となっては超日常的な雑談とは患者のためを思ってのこととわかる。今日は夜になってもまだおなかの中に異物感がある。以前のお医者はつくづく名医だったんだなあと思いながらでも今日のお医者さんはざっくばらんな女の人で同性&とっつきやすそうな雰囲気も込みでそうは言っても上手だった、と思う。この検査の場合、お医者さんの雰囲気も大切だ。この人ならもう一回うけてもいいかも。とカメラを扱うお医者を語れるくらいに胃弱経験が豊富なのであった。ああ~ほんの十数分の検査だけどつかれた~
2006.05.19
コメント(12)
-
健康週間
上の歯のなくなったはなごろう(ハムスター・もうすぐ2才)の下の歯がのどの奥に向かって伸びているので切ってもらった方がいいのかと思い獣医さんに見てもらった。ふだん歯のチェックをしようとしても体全体で拒否し、小さい手でふんばってやだやだって言うのでなかなか見えないのだがお医者さんはさすがで「ふ~ん、そうですねえ」、といいながらはなごろうの下あごをめくってペンチでぱちぱちと、爪を切るくらいの気軽さで切ってくれた。巣にいるはなごろうを無理やり引きずり出して診察台に乗せたので以来すねてしまって巣に入らず、そのへんで適当に寝ている。あんたのためやのに・・・。まあでもとにかく、また伸びてくるまでしばらく安心。今日は私がMRIの検査を受けた。筒みたいな装置に入って断層写真をとるやつだ。受けたことのある人の経験談では・まっくら・うるさい・注射針をさしたまま受ける(30分~1時間)とのことで針をさされるのに苦手意識が強い上にしかもさしっぱなしってヤダ~とどきどきしながらのぞんだ。でもささなかった。安心して横になっていると、案の定眠気が。検査部位にもよるのか、真っ暗にはならなかったが音は確かにかなりうるさい。古典的な土管(ドラえもんとかでよく野原においてあるやつ)の表面を敵襲に遭った武士が銅鑼を鳴らすかのような力強さでがんがん叩いているのを内側から聞くような感じ。いったい何の音なんだろう。。。でもものともせず寝てしまった。横になるとすぐ眠れるたちなのであった。夢を見かかった頃に起こされ、雨の中をぼーっとしながら帰る。結果は今度。このところはなごろうも私も病院づいている。あしたは人間ドックだ。
2006.05.17
コメント(8)
-
『イッセー尾形のとまらない生活2006 in ひょうご』
先週、ひょんなことから知人に譲ってもらったチケットでイッセー尾形の一人芝居を観に行く。この人の芝居、ビデオで見たことはあったが、ぜひ生で見たいと思っていたのだった。旧作新作取り混ぜて、選りすぐりの7編+アンコールの1編を見る。イッセー尾形が次々といろんな人物を演じていく。学校の英語の先生酔っ払いのサラリーマン修理好きの電器屋夫を殺した女性ピザ屋の若者等々一人芝居なので、台詞は本人の発するものだけ。でも、対する相手の台詞を容易に想像させる。そして他の人物の台詞を想像させるだけならまだしも演じられた中のひとつではイッセー尾形演じる室内楽のカルテットの一員「彼女」の奏でる音が他の団員の奏でる音、さらには四重奏の楽曲さえイメージさせた。このところ少しラジオドラマについて考えている私。音声としての言葉だけでイメージを紡ぐことと一人だけが演じてその人を取り巻く世界を表出させることとどこか共通点があるような気がしつつ、一人芝居の台詞から相手の台詞を音声としての台詞のやり取りから、ある映像を想像させるように書くそのことを考えて途方にくれる。ましてひとつの楽器の音で楽曲を連想させるそういう音作りとそこで奏でられる音にそこまでの想像力を喚起させる力を持たせる芝居作りにはあ~すごいなあと思う。と、まじめな感想を書いてしまったのだけど一番最初に思ったことはこの人おかしいんじゃあ!?ということだった。芝居と芝居の合間イッセー尾形は舞台上で着替え、観客の前で役柄を変えていく。大人の男の人の着替えをこんなにまじまじと見ていいのか?という疑問が湧く。でも目を離せない。この、イッセー尾形にどことなく似ている上司がいる。共通点を発見しては芝居の余韻に浸りつづけるのであった。
2006.05.16
コメント(2)
-
理想の女性像
『Heaven?』佐々木倫子。私の持ち物ではないけど身近にころがっていたので読んだ。以前も読んだことがあるので2回目だけれどもこれはフランス料理店が舞台になっている漫画作品だ。この料理店のオーナーである女性。非常にワガママでマイワールドが確立されている。このオーナーに振り回される従業員たち。いかに彼らが苦労しようとも、そんなことに彼女は全く頓着しない。この作者の作品に『動物のお医者さん』がある。H大学獣医学科にて繰り広げられることがらが描かれる。そこで主人公たちの先輩として登場する「菱沼」という女性。天然ボケが著しく、でものほほんと周りを和ませる(気がする)。彼女たちが私の理想の女性だ。そんな風にありたいと思うけど現実はそうではない。少々天然ボケな要素は私にもあるけど「天然」なことを自覚している時点で彼女たちにはかなわない。そして傍若無人になりきれない小心者なところも。。。この佐々木さんの漫画、わりと好きなんだけどこの人の特徴として、しょっちゅうツッコミが毛筆体というか重めの明朝体で画の上にあらわれる。それが苦手な人もいるそうだ。天然なキャラを描きつつこんな風なツッコミを入れてしまうこの佐々木さんには天然一辺倒になりきれない人柄の私との共通性を感じてしまうのであった、でも自分をとりまく環境を客観視できるのもひとつの才能だ。きっと。
2006.05.13
コメント(12)
-
ラジオドラマ『世界の中心で愛をさけぶ』
この夏、大学で放送脚本を学ぶ予定でどうやらラジオドラマの企画なるものも立てるらしいので図書館にて発見した、ラジオドラマCD『世界の中心で愛をさけぶ』を借りてみる。この『世界の中心で愛をさけぶ』(いつ見ても書いてもながっ!!)、小説が大ベストセラーだったこともあって、当時本を借りてはみたけれど最初の3行で芸風の違いをひしひしと感じたために、半時間かからずだだーっと読みきって、結局やはり、あ、そう、という感想だった。なのであんまり期待してないのだけどまあ、原作を読んでいるから勉強にはもってこいだと思いこれがいったいラジオドラマになるとどうなるのか!?という興味も薄くあったのだった。昨晩CDをかけてみた。が、ソッコウ眠ってしまったのでよくわからなかったあ。ただどうやら主人公格の女の子が私と同じ誕生日な設定らしかった。それだけが妙に記憶に残っている。それ以外には、さすがラジオドラマだけあって一般市民であるはずの登場人物の語りの滑舌がよすぎるのに違和感があった。まあ、ラジオなのでそれはそうなんだろう。寝てしまってほとんど聞いてないのであんまり何ともいえない。今日これから聞こうか、いやでも間違いなくすぐ寝てしまうし…どうしよう…う~ん。。。おやすみなさい。
2006.05.12
コメント(10)
-
一家離散中
うちは4人家族だ。父母姉私。現在4人で5軒の家がある。父はS県R市。母は東京のK市。姉は上海。私はK市。5軒目はあまりに田舎で普段は使ってない。この好き勝手に暮らしてる4人がお正月やら連休やらにはそれなりに集まったり(集まらなかったり)する。普段気楽に過ごしているせいか家族といえどもひとつところに集まる期間には限界がある。他の3人がどうかは知らないが連休のうちの何日かを家族と過ごしてみて、私の場合は2泊3日が限界なことがわかった。ずうっと毎日一緒に暮らしていた頃は気づかなかったけどうちはどうもみんな似てなくてばらばらなのでいざ何かをしようという段になると案外まとまりがない。父はきちんとした人だけどマイペース母は几帳面なところもありつつでものほほんとしてマイペース姉はひたすらマイペース(実際には気を使っている節もあるけど妹の私から見れば他を超越して著しくマイペースだ)。とにかくあんまり人に合わせてる風なところが見えない。私は末っ子だったので他の3人の意向を聞いてしまうと別に賛成なわけではなくてももうどれでもええわ、という気分になるのであった。子どもの頃がどうだったかもう忘れたけど今回気づいたのは、収拾がつかないときは、とりあえずまとまりやすい意見に合わせとこう、と思う自分がいることだ。ふだんの私自身はわりと人の意見を聞かない方であんまり人に合わせない。それがこの家族の中ではこれだ、いったいどうなってるんだ、という気分だ。なので限界は2泊3日。それ以上4人で過ごすと気分は廃人だ(ちょっと大げさ)。というわけで連休明け、一人の時間を満喫しているのであった。でもたぶんあんたもマイペースだよと、家族からは言われると思う。そして結局、いつも甘やかされているのは私なんだろうなあと思ったりする。今回は内緒でお父さんにお小遣いをもらった。いい年をして。
2006.05.09
コメント(12)
-
夏にむけて
世に言うゴールデンウィーク。変則勤務の私としては世間と休みがずれているもののまま、よく休んだ年だった。その連休最終日。なんだかとても暑かった。連休中、仕事と休みを取り混ぜた結果疲労もそれなりにたまっているもののあまりの暑さに夜になって突然、部屋に敷いていた生成り色のカーペットを外した。まあ、単に、洗濯機での洗濯ではとれにくいものをこぼしたせいなのだけどとにかくそれで、現在は夏仕様の敷物なし。ワンルーム+キッチンの、床は全面フローリング。ラベンダーのオイルを垂らした布で水拭きをするラベンダーの香りはおおむね好みだけど時によってはニンニクの香りを彷彿とさせて用いられないことがある。今日の場合は大丈夫。こっくりと重い色でお気に入りの床を拭いてすっきり。実際夏は毎年乗り切れるかどうか不安になるほどに苦手でといいつつ元気者なのでたいてい乗り切れることはわかっているのでつまり、単に嫌いなのだった。少しでも涼しい日が多くありますようにと願いつつ。写真はうちの床と現在作成中の木綿で絞りの楽々スカート。だんだん気分が夏になってきております。
2006.05.08
コメント(10)
-
借りてみる
ここ数年、図書館で本を借りるというのを単純に楽しめていないのだけど縁もゆかりもない図書館に行く機会があったので仕事柄、ついつい気になってしまうあれやこれやを一切無視して借りることに没頭してみる。すぐ返すので読みふける本は除外で借りたのが1 おしゃれなニット(編物の本でした)2 きれいなスカート(洋裁の本でした)3 野菜ひとつでできること(料理の本でした)4 ゼロから始める中国語(始めないけど語学の本でした)5 活発な暗闇(江國香織編・詩集でした)6 ミネラルウォーターガイドブック(水の本でした)7 芥川賞90人のレトリック(芥川賞受賞作家の文章が載ってました)8 言いまつがい(糸井重里著・言い間違いを集めた本でした)並べてみて、この本のまとまりから浮かぶ読者像を考えてみる。う~ん、独身女性として、あまりにありがちなラインナップだ、と反省。なんというか、同年代同性の読書人をイメージした場合に実際にはどうかわからないけどいかにもこういうの借りそうな人がいそうな。1~3は目も当てられない。4がもっとマイナーな言語であったり5の詩集が、せめて明治以前の文豪か、または句集歌集であったりすると、お?と思うかも。6と8は漠然と時機を逸している。まあ、7は、ちょっと芸大学生っぽくていいかな、と思う。しかし結局読まなかった。。。自分が素でどんな本を借りるのか、観察してみるのは結構おもしろい。今度またやってみよっと。キャラをいろいろ変えて、いくつかパターンを作ってみるのも楽しいかも。
2006.05.05
コメント(20)
-
『江戸の誘惑』ボストン美術館所蔵浮世絵コレクション
日本でいえば明治初期、来日アメリカ人ビゲロー氏が収集しボストン美術館に寄贈したという浮世絵コレクションを市立博物館にて観覧する。浮世絵といえば版画、との知識があるけれど今回の展覧会では主に肉筆作品がとり上げられている。明治新政府の時代日本古来の文化・芸術は顧みられずもっぱら西洋文化がもてはやされていたという。そんな中、日本文化を好んで下さったビゲロー氏のおかげで今回のような浮世絵コレクションをを今日に至っても観ることができる。単純にありがたいことなのであった。などという感想を用いて日本文化史のレポートを作成しつつ思うにはいま私の住んでいる部屋はもともとは職場の同期のAさんの住んでいたところだ。彼女はつねづね日本人社会の閉塞感を感じていてあるときついにパリに移住してしまった。そしてもう8年くらいになるだろうか。彼女は私にとってはめずらしく思うところを語り合える人でお互いの変わり者具合を違和感なく受け容れられる相手だったと思う。でもなんだかパリに行かれてからは気持ちが疎遠になってしまって(そして「なんだか」と言いつつその原因は何となく私自身にはわかっているものの)でも日常しょっちゅう会いたくなる人のひとりだ。そのAさんがパリに自身の着物を送ろうとしたところ盗難にあってしまい届かなかったそうだ。その着物が見つかったのかどうか知らないままだけど今回の浮世絵コレクションにて描かれた繊細な着物の柄にずいぶんうれしくなった。こういう繊細な画風はきっと日本人特有のものと思い欠点はあると思うけど、日本人も捨てたものでないと思う。私の知っているときより少し年をとった彼女が時に祖国を懐かしんでくれたらいいなあと思う。若い頃にはそのことを、うまく説明できなかった。私は今でもその時の、彼女のその部屋に住んでいる。パリ。彼女が今もそこにいるかどうかはわからないけど足跡を感じながら長期滞在してみたい私にとって、そんな街になってしまった。
2006.05.01
コメント(6)
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
-

- 株式投資日記
- NISAの米国株の損益率は+56.41%に上…
- (2025-11-23 18:34:23)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 【泣き寝入りしない!】楽天お買い物…
- (2025-11-23 20:30:04)
-