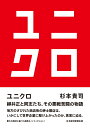2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年01月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
久しぶりの人たち
以前在学した学校の部活の同期+αで宴会をする。以前ここに書いた、まるとくさんの友達でもある。福岡に転勤になっていたM氏が5年ぶりに戻ってきたので、というのが名目。M氏とはゆうに5年は会ってない。それ以外も前回いつ会ったのか、記憶にさえない人が多い。わりと厳しい部活であったので3年間みっちり苦楽をともにしたわりには人間関係が薄い。。。だけどもみんな、私にとっては“友達”という言葉について思うときに一番に浮かぶ人たちだ。久々に会うとちょっと緊張するけど、すぐなじむ。なじむ、というのも、社会人になってこの方、めったに経験しない感覚だ。日常的に人となじまない、どこにいてもちょっと浮いてる感覚がある。たぶん多くの人がそうなんじゃないかな、と思うけど・・・。でも不思議なのは昔の友達が決して自分と似てるわけではないことだ。で、考える。けっこうみんな個性が強くてばらばらなのでなじむと思うのは錯覚でたぶん、それぞれの浮き方が既知のものだから意外性が薄いだけだと思う。まさにまるとくさんのときにも書いたようにふ~ん、って流せるそんな感じ。悪い意味ではなく。帰りに、こういう場合の定型句として「またね~」と声をかける。確かにまたね、ではあるけれども次に会うのは2年後か、3年後か???まあたぶんいつか会うでしょう。
2006.01.30
コメント(8)
-
源氏物語第二部
『源氏物語』といえば類まれなる貴公子・光源氏の、幾多の女性遍歴と栄耀栄華にあふれた一生を描いた物語だが光源氏の物語として、第一部と第二部があるのをご存じだろうか。第一部は第三十三帖「藤裏葉(ふじのうらば)」で終了する。源氏は准太上天皇という、一臣下としては最高の位に上りつめ息子の夕霧は結婚。娘の明石の姫君は帝に入内する。源氏の屋敷を、帝と上皇(朱雀院)がそろって訪れる(行幸する)場面で終わるこの巻は一族の安泰と更なる栄華を予感させる要素が次々に語られる。次の「若菜上(わかなのじょう)」より、第二部が始まる。この巻は、源氏の兄、朱雀院が病をきっかけに出家を志し出家後の心配の種である年若い娘、女三宮を源氏に降嫁させようと決心するところから始まる。 朱雀院の帝、ありし行幸ののち、そのころほひより例ならず悩みわたらせ給ふこの「ありし行幸」とは「藤裏葉」にて語られていたものだがあの巻の華やかな行幸の場面からうって変わって唐突に朱雀院の病について語り起こされるこの一文は第二部の重い世界にふさわしい。第二部では、この女三宮の降嫁が源氏の晩年に暗い影を落とす。女三宮は源氏の友人(昔“頭の中将”と呼ばれた人物である)の息子、柏木と密通し、不義の子、薫を出産する。源氏は、若かりし頃の自らの過ち(父帝の女御であった継母、藤壺との密通)に思いを至らせながら、薫を抱くことになる。女三宮という、位高い正妻の存在は源氏の最愛の恋人、紫の上を苦しめ、やがて病に至らせる。病気の紫の上は出家を願うが、源氏がそれを許さない。紫の上は残念に思うが、自分が出家した後の源氏の嘆きを思うと、強硬に主張することができない。この第二部の物語は、どこかおとぎ話めいていた第一部の世界と大きく様相を異にする。登場人物の多くがそれぞれの苦悩を抱えそれと同時に愛情ゆえの葛藤に悩まされる。しかし、源氏を取り巻く表面的な状況は、第一部を継承し、またそれを越えてさらに華やかになっていく。高貴な姫皇女の降嫁と彼女の出産がそれだ。栄華の裏にひそむ、翳をたたえた世界。そして紫の上の、源氏を思う心の深さ。ただ我が身の悲しみを思って紫の上を出家を許さない源氏と対照的に紫の上の苦悩が綿々と綴られる。第二部の終わり、結局紫の上は出家することなく死んでしまう。その一年後、いまだ失意の中にある源氏は、紫の上からの文を焼き、出家の準備をする(「幻」の巻)。続く「匂宮」の巻では源氏はすでに亡く、物語を担うのは薫の世代となっている。「幻」と「匂宮」の間に、「雲隠」という巻があり、そこでは源氏の出家なり死去なりが描かれたとされているが、本文はない。もともとあったのかどうかも定かではないが、少なくとも現存しない。巻の存在さえ、紫式部自身の意図によるものか、後世の人の挿入か、諸説あるようだ。後世挿入説が有力だったかと思うが、いずれにせよ、長く語りつづけられた光源氏の一生とその陰影に満ちた終わりに思いをはせる時その空白の巻の存在が、読後に広がる余韻に深みを与え沈静化させる。光源氏とその物語はもう終わりを告げた。ゆっくりとひと呼吸おいて読者は「匂宮」に始まる「宇治十帖」の世界に入って行くことができるのだと思う。
2006.01.27
コメント(8)
-
スクーリング終了につけて、
通信の大学のスクーリング、「言語表現演習1」が終了。今回のは国文学(古典)の講義で1日目 平安朝の文学2日目 平安頃までの国語表記について3日目 今昔物語についてだった。もともと好きなので、どれも楽しく聞いた。でもこのラインナップは、、、以前在籍した大学で履修した講座と見事にかぶっている。いわゆる変体仮名を読む機会こそ少なかったけど…。あんまり人に言う機会はないけど前回の大学の結果、専門は平安朝文学ということになる。いちおう。リンク友が書いてくれていたけど、卒論は「源氏物語」についての考察。いちおう。。今回の大学で常に心の片隅に思うことは前回の大学でお世話になった先生に恥ずかしくないレポートを書こうということだ。けっこうまじめなのである。というわけで「レポートの書き方」は有益そう、かつ楽しそうだけど履修しないことに決めた。けっこう頭が固いのである。といっても前回の大学では部活中心にやってしまったのであんまりえらそうなことは言えない。でも卒論だけはがんばった。「源氏物語」、あらすじご存じでしょうか?ちょっとこれについて書いてもいいでしょうか??(「いい」と言われなくてもきっと書くぞう、という気分) つづく
2006.01.25
コメント(12)
-
2じゃなくて1。
在籍している通信制の大学のスクーリングが今日から3日間なので久々に登校。言語表現演習1の2。今回は張り切って授業前に4回生の教室をのぞいてきました~~~というのはうそですみません、教室を思いっきり間違えました~。早く着いて座っていると入ってくるのはなぜか見知らぬ人ばかり。おまけに卒業の話なんかしてるし。気が早いなあ、おかしいなあと思ったけどまさか自分が間違っているとは微塵も思わないたちなので・・・。始業5分前になって突然「間違えた!」とひらめく。時々お見かけする、いかにも教室を間違えたと思しき、「突然荷物をまとめて忽然と消える人物」になってしまいました~。ばれてなければいいけど(←ばればれ)。でも、さすが4年生の教室だけあってみんな落ち着いた雰囲気。(↑通信なので別にそんなことはない)隣の教室は1年生だったけど、さすがに若さあふれる賑やかさ。(↑同上。でも今年はほんとに若いらしい)などと、無理やりな感想を抱きながら正しい教室に向かう。なんとか間に合ったら、あーごんさんがいた!キョチさんもいる~!あーうろたえた。その時の私のうろたえ加減といったらあーごんさんがスローモーションで3回くらい振り返った、、、感じがするくらいにはうろたえておりました。あ、今日は、昨晩緊張のあまり夢にまで見た、リンク友の真遊さんに会えました~ばたばたとちらりだったけど。学校は楽しい。。。
2006.01.23
コメント(10)
-
また、がぜだ。
ずっとのどが痛いと思っていたらどうやらまた風邪になってたらしく今朝から鼻もぐずぐずに。(鼻もはずして洗いたい。そういえば。)予定があってやむをえず阪急電車でふた駅ほどのところに出かけたけど来週の予定も重要であるためとにかく風邪を手ばなしたくたまたま前を行くオジサンの背中をもらってくださりませんかのう~とひしと見つめる。まったく誰でもいいんだけどいつになく熱いまなざしで。でもオジサンはもらってくれませんでした~いかに迷惑であろうともあしたは誰かもらってくれますように♪
2006.01.21
コメント(9)
-
のどのいといたき
先日引いた風邪のどだけがしつこく治らない。たんがからみでもすれば、それが異物を取り去ってくれそうな気がするけどいがいがするだけでたんもからまない。なにやら常に引っかかってる感じなのでしょっちゅうせきこむ。激しくせきこみすぎて目の前がちかちかする。突発的に眼圧も上がる感じがする。最近お気に入りの龍角散も効かない。水なんかでうがいしても、あのクリアなサワヤカさが物足りない。気持ちとしてははちみつぐらいにどろっとしたものでうがいしたいくらいだ。ごぼりごぼりと。できればのどをひっくり返して表に出していがいがをブラシかなんかで徹底的に取り除きつめたく冷やした水あめでもたっぷり塗って湿布にしたい。ひんやり~っと気持ちよさそう~、というイメージで寝よ。
2006.01.20
コメント(6)
-
スケジュールに淡白
リンク友の日記を読んで思い出した。私も年末に今年の手帳を買っていた。別のリンク友は、「ほぼ日手帳」を推薦されていたので検討したけれども買ったのはその真反対をいくような月間スケジュールが基本のもの。月間だけでは書くところが少ないので見栄を張っていちおう週間スケジュールもついてるものにした。が、事足りるのだ。月間スケジュールで、充分。日々書くことがないというわけではないと思うけど好みとしてものごとの一覧性を求めるタイプなんだと思う。殊に社会生活上は全体の流れとか雰囲気が見えないと、自分の言動を決めかねて困ることがある。(だから私は人見知りだ。特にお互いの間合いがちょびっとだけできつつあるような、ちょっとした知り合いが苦手だ。)そういう傾向が手帳選びに反映してるんではないか(…?)と思う。選ぶ時にはこのようないろんなことをくどくどと考えてそれなりのこだわりを持って購入する割に今年、すでにそれを持ち歩いていない。というか、今年の場合持ち歩いたことがない。。。日々の覚えのための、ある意味で日記がわりとして手帳をまめに活用することには憧れがある。だけど書き込むとしてもそれはは多くの場合事後だ。しかも半月以上たってから思い出して書くという、小学生の絵日記を彷彿とさせる。。。そしてそれさえ毎年前半までもてば良い方だ。そしてまた別のリンク友みたいに手帳を複数冊活用するなんて夢のまた夢で著しく尊敬だ。心底「えぇ~!?」だ。
2006.01.16
コメント(10)
-
謎の空白地帯
いつ行っても道に迷う場所がある。神戸・三宮駅の南東の一帯だ。時々行く洋服屋さんと時々のぞく雑貨屋さんと、その他気になる食べ物やさんが点在している。つい最近も歩いたが、やっぱり迷ってしまった。もうあきらめようとしたころに突然目的地が見つかる。毎回迷うので正しい道がわからない。ひとつの店を探して迷っている間は不思議とその他の店も見かけないのでおぼろげにルートを頭に描いてみてもその店とその近辺の道なんとなく、という関係しかできあがらない。なので、それぞれの店の位置関係はいまだに不明確だ。位置関係ないのでは?とさえ思う。と言ってもそんなに広い範囲ではない。東西の道4本くらいと、南北の道1本の周辺(たぶん)。なのにたったそれだけとは思えないほどぐるぐる歩き回ってしまう。ときどき道端で呆然とたたずむ。この広さは、こっそり空白地帯があるに違いない。地図を見たらきっと、雲か波線が書いてあることだろう。
2006.01.14
コメント(6)
-
『豆腐小僧』京極夏彦
「豆腐小僧」は江戸末期にはやった妖怪らしい。この妖怪を登場させて、京極夏彦が新作狂言を書いた。破れ笠をかぶり、手には豆腐を乗せた丸盆を持った豆腐小僧。小僧と言っても見た目は小柄なおじいさん。この緊張感のかけらもない妖怪らしからぬ妖怪の悩みは誰も自分のことを知らないということ。そして人を驚かせたことがないということ。この豆腐小僧と太郎冠者が出会う。が、太郎冠者も豆腐小僧を知らない。小僧を見てもこわくも何ともない。さみしい豆腐小僧。そこへ、太郎冠者の主人である大名が通りかかる。そうとは知らず、驚かせてみようとする二人。そうとは知らない大名。。。室町ごろに現在のような形式が整ったとされる狂言はその多くが古典作品だ。しかし時代を経てもこのように時々新作が作られその中には受け継がれて古典に混じって長く演じられていくものもある。この『豆腐小僧』の場合はきっと後世まで残っていくと思う。そのくらいおもしろい。何も難しいことは書かれていない。豆腐小僧が愛嬌があってかわいらしい。大名は厳しく怒りっぽい上司のような感じ。狂言の形式自体のパロディもある。途中、大名が太郎冠者を見つけ、太郎かどうかを確認するために「太郎冠者、おるかやい」と呼びかける。太郎は答えるつもりはなかったが、つい習慣で「は~~っ」と答えて前に出てしまう。主人に「おるか」と呼びかけられて「は~っ」と登場するのが狂言の定型としてあるのだ。いわゆる狂言らしさを笑えるのは新作の強みだ。京極さん、非常に上手だ。こういうのを読むと、狂言台本を書きたくなってくる。
2006.01.13
コメント(2)
-
そういえば
このようにガス爆発でも起きなかった私ですが阪神の大震災のときはさすがに目が覚めました。よく大地震の前にドーンって音がしたと言われますがそれは知りません(やっぱり)。気が付くと洗濯機の脱水中みたいに揺れていて咄嗟に「噂に聞くポルターガイストとはこれか!」と思いました。大きな本棚が倒れこんでいて暗闇の中でそのぼおっと白いものを見てお化けだと本気で思い目を凝らしてはいけない、と布団にもぐりこんでもう一回眠ろうとしました。しばらくして隣家の人が「ガスくさいよ」と大きな声で言い(向かいの木造アパートが全壊していたのです)それでようやく地震だったのかと気づく始末。大きな災害や事件にあった人はたぶんみんなそれぞれのストーリーがあって問われるままに語るうちに知らず「語り」が形成されその語りが一種のカタルシスになっているんだと実感する。私のストーリーにも続きがあります。建物の中はこわいのでその全壊したアパートに住んでいた後輩と道端で夜明けを待っていた時にものすごい音とともに土の匂いが沸き立ちました。それは初めての経験だったけど、近くの家が倒壊したのだと直感しました。あの時の土の匂い。神戸みたいな大きな街の阪神間と呼ばれる整然とした住宅地であんな生々しい土の匂いは。あれは間違いなく生きたものの匂いだ。そういえば今年もそろそろ震災の日です。
2006.01.11
コメント(8)
-
そもそも
今回の風邪、一番の原因はうちのお風呂のガス給湯器が不調なせいだ。うちはいつの築か知らないけれど、わりと古い建物でおそらくこの給湯器は昭和30~40年代のものと思われます。最近とみに不調でまずだいいちに、温度調節のつまみが回らない。毎日使っていたものがある日突然さびついたようで動かなくなりそれ以来ぬるま湯を湯船に満たしては沸かして入る。シャワーはもれなくぬるま湯。ガスやさんによれば水の量を絞れば湯温は上がるとのことだけどガス給湯器の不完全燃焼が怖くて水量を抑えられない。なお悪いことに元栓も同時期にさびついたらしく締まらない。よって温度は上がらないとわかっていても大量にお湯(ぬるま湯)を出して使ってしまう。こどもの時、隣の家がガス爆発を起こし全焼した。うちの家は大丈夫だったけどそれ以来ガスと火がちょっと怖い。まあ怖いのは火だけではなくて水も怖いのであんまり深い意味はないけどとにかくガスは苦手だ。理科室のガスバーナーを扱うのもこわかった。アルコールランプでいいやん。とはいえそのガス爆発の時、私は気づかず寝ていた。すごい音だったそうだ。でも知らないものは知らない。眠りの深さは今でも自慢だ。
2006.01.10
コメント(10)
-
がぜだ
早々に風邪だ。風邪を引いても高熱が出たりはしないのが常日頃物足りないくらいなのだが今回はめずらしく高熱の気配が。これは測ってみねばなるまい、ふだんなまけてる体温計に、実力を見せる機会ぞ、と呼びかけつつ引出しを開けるが、ない。一体どこへ失えるというのか。。。探す気力はもうなく寝る。翌日、体調が小休止したところで再び体温計捜索。引出しの奥から水銀式の婦人体温計を発掘する。見ると38度までしか測れない、が今度は、いっそ振り切ってやれ!と思い測る。しかし残念ながら37度後半しかない。惜しい。昨日見つけていればと悔やまれる。こういうときは人と話をしていてもまず聞けない。“自動割愛モード”というのが作動し話の初めっから結論を求めてそれ以外を耳が適当に端折る。ややこしい話のときは、ひととおり聞いた後で良心を振り絞って“要約モード”に入れる。「要するに」と人の話を適当に要約する。ただし基本的に話を聞いていないために相手に再度説明をさせるという悪循環に陥る。申しわけないけど、でもまた聞けない。札を掛けておきたい。いかに込み入っていようとも50字以内に要約してください(50字以上は放送事故を起こします)とでも。
2006.01.08
コメント(14)
-
をぐら。
何年ぶりかで、家にある百人一首を出してみる。子どものころから家族でお正月によく遊んだ。と言ってもかるた取りではなく「坊主めくり」として。長いことやってないのでルールは詳しく覚えてないけど順々に札をめくっていって殿が出れば自分の札に坊主が出たら手持ちの札を全部“場”に流す姫が出たらその時点で流れてる札を全部もらえるで、枚数の多い人の勝ち、だったような。とにかく何年も激しく遊んだために札のふちが傷んでいる。姉にはお気に入りの札があって殿(正確には身分的に必ずしも殿ではない)では三条院姫(正確には身分的に必ずしも姫ではない)では相模妹の私はそれがうらやましくてなんとかお気に入りを見つけようとしたことがある。そこで書いてある和歌まで適当に吟味して選んだのが周防の内侍、または式子内親王。しかし周防の内侍は後ろ向き式子内親王はようわからん頭巾をかぶっているためビジュアル的に地味。そこでさらに選んだのが持統天皇。しかしもひとつ顔がこわかった。結局こどものころの私としてはお気に入りの札は見つからなかった。でもある時デパートで百人一首を見てものによって絵もちがいその人のとっている姿勢さえもちがうことを発見しいたくショックを受けた。周防の内侍が前を向いてるのが中でも衝撃だった。をぐら百人一首の札は万国共通で登場人物の格好は同じと思っていた。そんなわけあるかー!と今では思うけどでも実際わりと顔を覚えてしまってるから他の札ではヤダー!と思う。うちの百人一首、永久保存決定。 画像はその式子内親王。 ぼやけ写真ですが。。。
2006.01.02
コメント(18)
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- お買い物マラソンで後悔しない!体型…
- (2025-11-22 22:00:05)
-
-
-

- 楽天写真館
- 23 日 ( Sunday ) の日記 寒さ…
- (2025-11-23 07:39:44)
-