2025年06月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
6/7, 14 東響 (川崎定期 第100回、名曲全集 第208回 2025年6月)
ミューザ川崎シンフォニーホール 14:00〜 4階左手 <6/7> モーツァルト:交響曲第25番 ト短調 K.183 ロッシーニ:スターバト・マーテル ソプラノ:ハスミック・トロシャン メゾソプラノ:ダニエラ・バルチェッローナ テノール:マキシム・ミロノフ バスバリトン:マルコ・ミミカ 東響コーラス 東京交響楽団 指揮:ミケーレ・マリオッティ <6/14> チャイコフスキー:幻想的序曲「ロメオとジュリエット」 チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35 <独奏アンコール> コリリアーノ:レッド・ヴァイオリン・カプリース プロコフィエフ:バレエ組曲 「ロメオとジュリエット」 モンターギュ家とキャピュレット家 / 少女ジュリエット / マドリガル / メヌエット / 仮面 / ロメオとジュリエット / タイボルトの死 ヴァイオリン:ティモシー・チューイ 東京交響楽団 指揮:ミケーレ・マリオッティ 最後のエントリーから3週間ほど......正直あまり聞いてないのは事実ではあります。まぁ、このくらいでも普通より多いんだろうとは思いますが。 東響、というよりはミケーレ・マリオッティ祭りという感じです。そもそもは気まぐれでスタバト・マーテルをやるというので聞きにいったら、思いの外良かったので、翌週も聞きにいったというところ。 結果的にどちらもあまりいい席で聞いてはいなかったのですが.... まずは7日のスタバト・マーテル。実は誰が歌うかちゃんと見てなかったのだけど、バルチェローナだったのですね。そうと分かっていれば、もうちょっといい席買ったのに........まぁ、本来、このタイミングで行くのか、という状況だったので、仕方ないんですけどね。 まぁ、歌唱的には悪くなかったのだと思います。ただ......そうねぇ.......合唱は東響コーラスなので、アマチュアベースなのですが、だからあまり悪くいう気も本来ないんだけど、ちょっとこう.....ラテン語に聞こえなかったかなぁと。日本語だよね.....という。ラテン語とかイタリア語って日本語の発音に近いとか言うんですけどね。でも、やっぱり、音韻というかイントネーションというものがあるのであって。そういう意味では、悪いとは言わないけれど、ちょっと日本語に聞こえるというか.......まぁ、ラテン語じゃないなぁと。 具体的に何処がどうで、どうすれば改善出来るんだ、言ってみろ、って言われると難しいんですけれどもね。正直、具体的にどの言葉の何処がどう、と指摘出来るわけではないんだけれども。でも、そう聞こえてしまうのは、そうなんですよ。 プロの合唱だって出来てないとこはいっぱいあるので、まして基本アマチュアベースだから、そう指弾するつもりもないんですけどね。 オーケストラ。実は7日に聞きに行った時は、翌週も来るつもりではなかったんですけどね。ただ、この日聞いたら、結構良かったのですね。正直、大体東響は音が硬くてフォルテになると一本調子の音になるよな、というのが基本の評価だったんだけれど、この日は割といい演奏。硬いっちゃ硬いけれど、まぁ、曲が曲ですから、あまり気にならない。それにはやはり指揮者の指導もあるでしょう。にしても、前半のモーツァルトも、ロッシーニも良かった。なんていうんでしょうね。モーツァルトがまずちゃんと外連味のない端正な演奏。で、ロッシーニも同じく。硬くならず、叫ばずに。こういうのがね、いいんですよ。 14日は、しかし、チャイコフスキーとプロコフィエフなんですよね。まぁ、チャイコフスキーはまだしも、プロコフィエフは流石にね.....とはいえ、昨今の東響からすれば、随分柔らかいなとは思いますが、とはいえ........ねぇ........... 演奏としては悪くなかったとは思います。やはり指揮者の薫陶が効いているのでしょう。 マリオッティ、記憶はないのですが、ボローニャで振っていて、ペーザロ出身らしいし、まぁ多分どっかで聞いてるんじゃないかとは思うんですが......覚えてないけれど、いい指揮者じゃないかと思います。
2025年06月21日
コメント(0)
-
アルフレード・ブレンデル 逝去
https://www.bbc.com/news/articles/cjmmmrl4mz7ohttps://www.theguardian.com/music/2025/jun/17/celebrated-pianist-and-writer-alfred-brendel-dies-aged-94 アルフレート・ブレンデル、という表記だと思うのですが、d終わりなのでアルフレード、になってるんだと思います。ブレンデルがロンドンでなくなったそうです。享年94歳。2008年くらいに演奏の第一線から退いていて、そうか、もうそんな前に引退していたか、と思うのであります。 ブレンデルは時々聞く機会があった筈ですが、覚えてるのは、学生、まだ未成年の頃に来日公演で聞いたのと、引退する前にザルツブルクで聞いたのと。 学生の頃というのは、1980年代ですね。神奈川県民ホールで、確か母親が連れてけというので連れてった覚えが。最後がシューベルトのD.959のソナタだった記憶があって、生であの曲の演奏を聞いたのはあれが初めてだったかな。元々D.960の方が断然好きだったのだけれど、それ以外もいいじゃないか、と開眼したのがあの演奏だった。実は、その頃ブレンデルはシューベルトのソナタを2度目の全集で入れていて、しかし、個人的には、ブレンデルは繰り返しを結構省くので、本当はあまり好きではなかったんですけれども。ただ、演奏それ自体は良かった。今でも彼の録音はいいなぁと思います。 ザルツブルクは、2008年だったかと思うのですが、夏の音楽祭。たまたま追加販売みたいな感じでチケットが出たのを買ったのだったと思います。行ってみたら祝祭劇場の舞台上の席。時々、完売状態の人気公演で、そういう席セットするんですよね。ハイドンと、あとなんだったかな。実はあまり覚えてない。時差ボケてたし。思えばあれが最後だったのだと思います。 なんかね、こっちもいい歳になってきて、こういう、昔から好きだった人が亡くなって追悼記事が....みたいなのは増えちゃうんですよね。だから、あまり書くのもなぁ、とは思うんだけれど、ブレンデルはやっぱり書いてしまうかな。 今にして思うと、彼のようなタイプの網羅型と言いたくなるようなピアニストは、減っているのかなとも思わなくもないです。ピアノソナタならベートーヴェンとシューベルトは2度づつ全集を入れているし、モーツァルト、シューマンの演奏は定評があった。この辺を中心に、バッハ、ハイドン、リストあたりがレパートリーとして思い浮かぶ......という、ドイツ系の重鎮ピアニストだった......と言いたいのだけれど、ちょっと重鎮って感じでもないんですよね。なにしろ70代で引退してしまったので。決して若いとは言えないんですが、現役でもオピッツとかシフとかいますしね。シフはまだ71歳とかなのか.....なるほどねぇ。 シフもですが、ブレンデルは歌曲伴奏もそこそこやっていて、ゲルネとの共演もあったかと思いますが、なんといってもフィッシャー=ディースカウとの冬の旅が忘れ難い。ディースカウの冬の旅の録音としては必ずしも高い評価を得ていない感はあるのですが、個人的にはディースカウの声がやや衰え始めているというのも含めて、冬の旅の1stチョイスだと思っています。 今は、こういう人は流行らないんでしょうね。でも、私がクラシックを聞き始めた頃は、こういう演奏家がそれぞれの分野にいて、外連味は無いし、時にはつまらないという声はあれど、安定した技術と解釈の演奏で、良くも悪くもそこから出発していろんなものを聞いていった、そういう基点の演奏家の一人だったと思います。youtubeとか基本タダで聞けるものをよく言えばスーパーフラットに聞ける環境というのは、それはそれでいいのかも知れないけれど、自分としては、いざとなればそこに戻ることで見直せる、そんな基点を持っていたことというのは、悪くない、むしろ幸せなことだったのかなと思ってはいて、その一人がブレンデルだったな、と、改めて思うのであります。R.I.P.
2025年06月18日
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
-
-
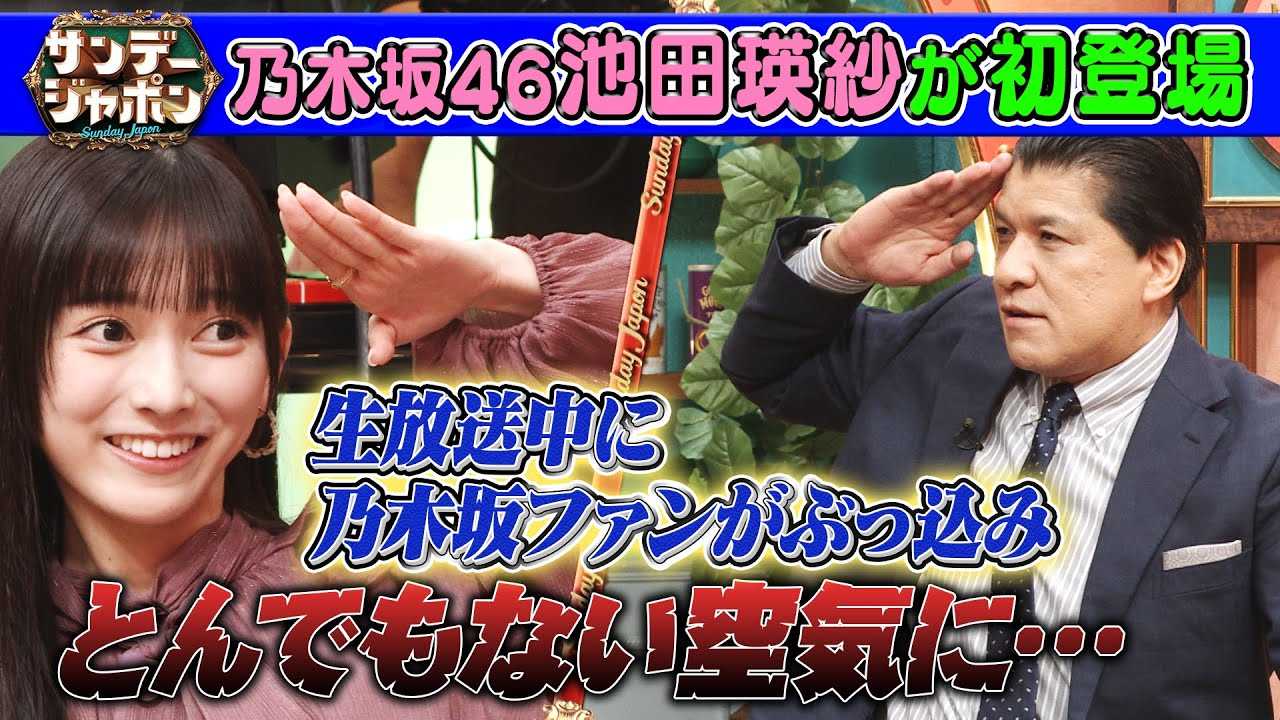
- 今日聴いた音楽
- ☆乃木坂46♪【アイドル界の二刀流】池…
- (2025-11-27 06:59:56)
-
-
-

- ☆モー娘。あれこれ☆
- 【森戸知沙希・伊勢鈴蘭(アンジュル…
- (2025-11-27 07:10:05)
-







