2024年01月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
LFJ2024の出演予定
もう年末に出ていたようですが、書く機会がなかったので...... LFJ出演予定の演奏者情報が一部出ています。 https://www.lfj.jp/lfj_2024/teaser/pdf/LFJ2024_lineup_1228.pdf 日本の一応ちゃんとしたオケとしては、東フィルと群響と新日が出るのだと。他に、兵庫県芸術文化センター管、横浜シンフォニエッタ、東京21世紀管................ねぇ...............そして、これだけ呼ぶ以上、恐らく海外からは来ないのでしょうね。ロシアのオケはともかく、シンフォニア・ヴァルソヴィアとか、もう来ないかな。 小曽根真の名前はないけれど、中川英二郎とエリック・ミヤシロの名前が。そして山下洋輔も初めて登場すると。久しく聴きにいけてないので、これはいいなぁと。 他には、2019年に来たカンティクム・ノーヴムが再来日。あとは、まぁ....... そして今年は、ホールA、C、D7に加えてG409も公演をやるそうです。ふむ。まぁ、悪くないですね。ただ、去年にも増してお客は戻ってくるだろうから、争奪戦だなぁ.......まぁ、ボツボツ行こうと思います......
2024年01月31日
コメント(0)
-
1/28 藤原歌劇団「ファウスト」
東京文化会館 14:00〜 4階右側 グノー:ファウスト ファウスト:澤崎一了 メフィストフェレス:伊藤貴之 マルグリート:迫田美帆 ヴァランタン:井出壮志朗 シーベル:但馬由香 ワグネル:高橋宏典 マルト:北園彩佳 藤原歌劇団合唱部 NNIバレエアンサンブル 東京フィルハーモニー交響楽団(オルガン:浅野菜生子) 指揮:阿部加奈子 演出:ダヴィデ・ガラッティーニ・ライモンディ まだ12月の公演で書いてないのもあるんですけれどもね。ちょっと気になったので早目に書いておこうかと。 藤原歌劇団の都民芸術フェスティヴァル参加公演、土日で2公演あるうちの2日目です。ダブルキャストのいわばBキャスト相当というところでしょうか。土曜日は村上敏明と砂川涼子、メフィストフェレスが来日組なのに対して、若手といった面々ですから。 で、先に終演後から書くのですが、終演後ぶらぼおおおに混じってブーイングのような声が。いや、正直、発声が酷いので、どっちか定かではなかったんですけれどもね。ただ、o音で終わってるようには聞こえなかったので、あれはブーイングだったんじゃないかと思うのでね。明らかにメインの歌手陣に対してだったので。指揮者出て来たら出なかったし。 4階の脇なんぞで聞いてましたので、まぁ、実のところよく分からないといえば分からない、ですけどね。ただ、こっちはこっちでもう30年以上東京文化会館では見聞きし続けているので、大体どんな塩梅か分かるっていやぁ分かるかな、とも思ってます。 率直に言って、今日はほぼ期待してませんでした。出演はA代表じゃないし、前回の藤原、去年9月の二人のフォスカリは、全体として悪くないとはいえ力不足は否めなかったし。そういうつもりで聞いていたのですが、実際には、かなりまともな出来でした。 圧倒的な出来とは言いません。声量も場内を圧するような人はいなかったし。でも、その分、どのキャストもきちんと丁寧に歌っていたと思います。なにより力任せに押し切る、無理やり声を絞り出すような歌い方ではなかった。唯一それはどうかな、と思ったのは、最後の第5幕、マルグリートが恐れ慄き神の救いを求める重唱のところで、ちょっと金切り声になってたかな、というくらい。この場面は、まぁ、そうなるとすればここだよね、という場面。むしろそれ以外では丁寧に歌っていたと思います。気になる場面はなかった。つまり、少なくともメインキャストに関する限り、東京文化会館の4階までちゃんと聞こえる程度には歌えていたのですよ。ということは、新国なら楽勝だと思います。 もしもこの歌唱陣にブーイングするならば、今の新国の公演殆ど全てでブーイングするのが筋というものです。私は行かないけど二期会だったら座布団やペットボトルが投げつけられるレベルなんじゃないかしら。もしあれがブーイングなのだとするならば、一体何故それがブーイングに値するのか、基準というのか、まぁ、論拠を明確にすべきです。気分でするものじゃないですよ、ブーイングなんて。ちょっと出来が悪いくらいでするものではない。言葉を伴わない以上、単に出来が悪い程度でやるもんじゃないですよ、少なくとも今時の日本では。何某かそれ以上に批判されるべきものがあって初めてするようなものです。気分でやったのなら不見識も甚だしい。こういう場に来るべきではないです。 勿論、こちらはブラヴォーもしなかったですけどね。そこまで素晴らしい出来と思ったわけではない。でも、ちゃんとしてましたよ。今時の、藤原を初めとする日本の団体が上演する公演としては、こんなものじゃないかしらん。少なくとも「こんなもの」の中ではかなりちゃんとした出来だったと思います。敢えて言えば、残念ながら、と言ってもいいかも知れないけれど。良くも悪くもこれくらい出来れば今は上出来なんだと思います。 合唱は、今回は藤原歌劇団合唱部単体。まぁ、やっぱり、そのくらいはやってもらわないとね。 発音は、フランス語はよく分からないですが、石投げられるほどじゃなかったとは思うんですけどね。どうなんでしょうね。 オケは東フィル。今日は裏で定期演奏会をやっていた筈なのですが、かなりいい演奏でした。本来だと裏はオーチャードホールなんで言ってる筈なのですが、期せずして被ってた上に1月はプレトニョフなので......お察し下さい。こちらは、だから、やっぱりBキャストなんじゃないかと思うのですが、ちゃんとしてましたですね。指揮は藤原初、と言いますが、そもそも私は聞いたことない人だと思います。あちこちでやってる人みたいですが、何処かのそれなりのオケの常任とかやってるというわけではなく、売り出し中ってところですね。指揮もやはり丁寧。少なくともこの日の演奏はまずまず良かったと思います。敢えて言えば、思い返すに、はて、このオペラをどういう音楽として構築しようと思ったのか、というのはちょっと見えなかったかも知れません。まぁ、このオペラにそういうのどこまで求めるのか、という話ではあるんですけれどね。 演出。これは、どうだろう......... 舞台装置らしい装置は無いといえば無くて、3つの縦長の投影装置が色々に動いて舞台を構成する。まぁ、それは、お金ないんだな、というところなんでしょう。それはいいんだけど、問題は、投影される映像。これがちょっと残念な感じで、何がダメかというと、映像が全然舞台に合ってないんですね。 最近は舞台で映像を使うのはかなり一般的になって来ましたが、しかし、適切に使えているかというと、これがかなり怪しい。よくあるのは、今回もそうなんですが、映像に情報を詰め込み過ぎるんですね。 映像というのはそれ自体がかなり情報を盛り込むことが出来るので、舞台で使う映像でも往々にして同様に情報を詰め込んでしまうんですね。加えて、観る側も、映像に関しては、TV映像なんかであるように、画面それ自体を視野に収めながらある程度隅々まで見えてしまう。慣れてるんですね、そういうのに。 ところが、オペラや演劇のような舞台の場合、そこまで舞台の隅々までは見ていないし、見えない。舞台というのは映像を画面で見るのと違って、リアルにそこにある「もの」として、縦、横、奥行きまである範囲を見ているものなので、隅々まで見ないし、情報量は多くない。いや、情報量が少ない、というよりは、そこにある「もの」という時点で、映像ではあまり重視されない質感のような、質的に違う情報が入ってるというところでしょうか。 たとえば、オーソドックスな舞台装置の場合、教会なら教会でそういう書割があったとして、その書割はその場ではほぼ変わらないんですね。変えるとすれば装置そのものを動かすとかしなければいけないので、限度がある。ところが、映像でなら、これは変化させるのは簡単なので、どんどん変えられてしまう。でも、そうすると、見る方としては、舞台上の実際の人やものと無関係に映像が勝手に動いているように見えてしまう。それと、今回は、所々で絵画の映像と思しき、花の絵を出したりするのですが、これが色々に変わり過ぎる。映像が舞台に関係なく喋り過ぎるんですね。無論、映像を作っている方としては、この場面ではこういう意味の絵を出そう、それをこう変えよう、という考え方で、照明のように変えているのだと思いますが、それは映像に語らせ過ぎだと思います。少なくとも今回は。 じゃぁどうすればいいのか、というと、取り敢えず私の見解は、舞台と映像のシームレスな融合は無理で、かつ、やはり現実の舞台の実際の姿の方が勝つので、それを邪魔しないような映像の出し方にするしかないのだと思います。情報量の多い、意味を持ち過ぎた映像は、やはり舞台とは親和性が低くなってしまうと思います。 もう一つの問題は、映像の質。そんなに質の悪い映像というわけではないんですよ。ただ、映像の質感と、舞台で見えているものの質感とが合わないんですね。演出ノートを読むに、演出家としては闇と光、特に闇に対するこだわりが強いようなのだけれど、そもそも映像って闇と相容れないですからね。それもあって、舞台上の実際の質感は映像に相性が悪いのだけれど、それ以上にそもそも映像自体の質感が合ってない。だから、全然違うものが同じところにあるような見え方でして。 演出解釈的には、特に読み替えてるわけでもなく、まぁ、オーソドックスに近いと思います。そういう面ではあまり気にはしなかったのだけれど、そういうわけで、あまり感心できない感じでした。
2024年01月28日
コメント(0)
-
1/19 イアン・ボストリッジ
神奈川県立音楽堂 19:00〜 前方右手 シューベルト:白鳥の歌 D.957 〜 レルシュタープの詩による歌曲 愛の使い / 戦士の予感 / 春の憧れ / セレナーデ / 住処 / 異郷にて / 別れ ベートーヴェン:遥かなる恋人に寄す op.98 シューベルト:白鳥の歌 D.957 〜 ハイネの詩による歌曲 アトラス / 彼女の肖像 / 漁師の娘 / 街 / 海辺で / ドッペルゲンガー 同 D965A 〜 ザイドルの詩による歌曲 鳩の便り <アンコール> シューベルト:さすらい人の月に寄せる歌 D.870 弔いの鐘 D.871 夕映の中で D.799 テノール:イアン・ボストリッジ ピアノ:ユリウス・ドレイク ボストリッジ。何度も聞いていますが、コロナ明けでは初めてじゃないかしらん。 そう。ボストリッジはなんだかんだ来日の度に聞いてますし、そもそもはもう20年以上前にシューベルティアーデに行って聞いたのが最初。確かフェルトキルヒの音楽学校か何かの教室みたいな小さい会場で、演奏者のすぐ横みたいな席で、水車屋を聞いて圧倒されたのがはじまり。以後国外でも何度か聞いていますが、シューベルティアーデには行きにくくなってしまったので、あまり外では聞いてないかな。シューベルティアーデとか、また行きたいけど、難しいなぁ、休みが.......... 今ドイツ歌曲を歌わせたら、確かにトップクラスに入る人でしょう。というか1、2を争うと言うべきか。 来日しているのですが、リサイタルはこれを除くと首都圏では平日にトッパンホールでやるだけ。あと、札響の東京公演にブリテンのセレナーデを歌いに出るらしいのですが.........うむー。トッパンホールで平日ねぇ.......行きにくい......... ともあれ白鳥の歌だし、これは聞いておこうと思って買ったのでした。 ドイツ歌曲の第一人者みたいな存在でありながら、ボストリッジはイギリス人です。なので、やはりちょっとドイツ語には違和感があります。それ言ったらお前のドイツ語なんぼのもんやねん、と突っ込まれればもう一言もないのですが、分かってしまうものは分かってしまうのだから仕方ない。聞けば聞くほどそれは分かってしまいます。まぁ、こちらが聞いて思っている以上に、ネイティヴ・スピーカーのような達者な人にはむしろ違和感がなかったりするのかも知れませんが..... 文句の言いどころは、これくらい。まぁ、控えめに言って極上でした。分かっているけれど、実際こうも凄いかと。 白鳥の歌がメインですが、今回は、前半でレルシュタープの詩に付けた歌を、後半はまずベートーヴェンの「遥かなる恋人に寄す」を歌い、その後に白鳥の歌のハイネの詩に付けた歌を、最後にザイドルの「鳩の便り」を歌って終わるという構成。まぁ、途中ベートーヴェンを挟んだだけ、とも言えますが。 ボストリッジは、スエードかベルベットかというような生地の黒いジャケットに灰色のスラックスで、白いシャツにノーネクタイで登場。ドレイクも白シャツにノーネクタイは変わらず。考えてみると歌い手としては理に適っているけれど、意外と珍しいかも知れません。 ボストリッジは昔から身体を動かして歌うスタイル。よく動くんですよね。とはいうものの、リズムをとっているような動きではなくて、揺らすとかいうのとも違う。むしろ動き回るという感じに近い。演技とも違いますし。強いて言えば、話す時に身体を使って身振りを交えて話す、というのは無意識にあるものだけれども、あれに近いんでしょうか。珍しいタイプだと思います。鶴田浩二か東海林太郎か、というような直立不動というのもまぁ実際にはそんなにないのだけれども、歌曲の場合はそんなに動かす人はあまりいないと思うのでね。 ただ、それが歌唱に悪影響を及ぼしているかというとむしろ逆なのでしょう。それが一つのスタイルとなって出来上がっている気はします。思えば、昔々に聞いた水車屋の頃から、そういうスタイルでした。よく動いて、ひょろっとした細っこい身体全体で歌っていました。それがまたあの歌曲集の場合には合ったものだけれども、白鳥の歌でもそれは変わりません。 とはいえ、ボストリッジのドラマティックなスタイルは、後半で本領を発揮。前半も悪くなかったけれども、後半は一気にギアを上げた感じ。レルシュタープの歌が何処か甘いところを感じさすとするならば、ベートーヴェンは結構筋肉質の音楽で、劇的緊張が一気に高まった感じ。ボストリッジの全身で歌うようなスタイルには合ってます。そしてそのまま白鳥の歌後半のハイネの詩による歌曲へ。この日の白眉はハイネの二曲目、彼女の肖像でしょうか。歌に於いて、フォルテ、フォルティッシモとはこういうことなのだよ、と見本を見せられるが如し。普通、ハイネの歌の中では、一番劇的に激しいのはドッペルゲンガーだと思われると思うのですが、ボストリッジの今日の歌では、この「彼女の肖像」の最後が最大のフォルティッシモ。ここは「君を失ってしまった!」と嘆くところですが、しかし、曲調的には静かに入っていく曲で、実際、そこまで歌い上げない人もいるくらい。ここをボストリッジはホールの壁も割れんばかりに歌ったのですね。叫ぶのではない。大音声、というのとも違う。あくまで歌。歌としてmaxまで持っていく。県立音楽堂はもう70年以上前に建てられた、現役のホールとしては最古参の部類だと思うのですが(日比谷公会堂とか旧奏楽堂くらいですかね、他には)、確かに1000人くらいしか入らないホールとはいえ、ここでホールの容量が不足していると思ったことはないんですよね。そのホールに収まり切らないんじゃないか、と思ってしまうようなフォルティッシモの歌唱。 ここでこれならドッペルゲンガーはどうなってしまうのか、と思ったのですが、ドッペルゲンガーも凄かったけれど、そこまでの柄の大きさではなかった。むしろ、内に向けて刺さってくるような、そんな鋭さを持つフォルティッシモ。どちらがどう、というのではなく、それぞれの歌に於いて表現を突き詰めた結果、なのでしょう。 歌としては、好みの問題もあるけれど、むしろ本編よりもアンコールの3曲がより響いた気はします。 正直、この白鳥の歌の後だと、まぁ時間的にはともかく、アンコールやるのか、無くてもいいくらいだけどな、と思う中でのまずは「さすらい人の月に寄せる歌」。これもいい歌なのだけれども、それに続けての2曲目。弔いの鐘、としていますが、死を告げる鐘、などともいう。伴奏の鐘を模した響きが印象的で、穏やかに聞こえてその実迫るものがある歌ですけれども、白鳥の歌とは打って変わってしみじみと歌い上げる。これで終わってもいいくらい、いや、下手なものをこれ以上重ねても仕方ない、というと思うところに、最後に「夕映の中で」。思わず唸らされるような見事な選曲。そして見事な歌唱。 私はもともとドイツ歌曲からクラシックを聞き始めたようなものなので、やはりドイツ歌曲は好きという以上にホームポジションなのですが、なかなか最近はいい歌が聞けなかったりするのだけれど、本当に久し振りに、ドイツ歌曲を堪能させてもらいました。最近も聞いてないわけではなかったんですけれどもね。でも、こういう歌を聞くのは本当に久しぶり。近年のボストリッジの来日でも、ここまで気の入った歌はあまり聞けなかったんじゃないかな。あのハイネは、珍しくずっと覚えてるんじゃないかという気がします。正直、コンサートの記憶って、そんなにしっかり覚えてるもんじゃないんですよね、我ながら。年に1、2公演くらいかも知れません。後々まで覚えていそうなのは。その中でも、シューベルティアーでのボストリッジの水車屋は、細部はともかく、自分でも珍しく感動したことがあるとすればあの時くらいじゃないだろうか、という記憶が残るものだったのだけれども、そこまで行かずともずっと覚えているかも知れないと思います。 確か、ボストリッジって、私より年上だったように思うので、もうそろそろ還暦くらいなんじゃないかと思うんですけれどもね。なにしろシューベルティアーデで聞いたのは20年以上前だから、少なくとも50代にはなっている筈なんだけれども、ちょっとそうは思えない歌だなぁと。ヴンダーリッヒなんかとはまたちょっと違う意味で永遠の若者的なところを感じます。勿論、音楽家としては、物凄く成熟していると思うのですけれども。 公演後にサイン会をやるというけれど、今更CDって言っても持ってるし....と思ったら、来週発売の新著がフライングで販売、というのでそれを買って、サインももらってきました。なんかイニシャルだけみたいなアレな感じのサインだけど.........そういえば前に所沢でももらったかな。あの時はプログラムにもらったんだったか。 トッパンホールのとかは、どうすっかなぁ.......いまいちピンとこないし、これくらいのものが聞ければと思わなくもないけれど、これほどのものはなかなか聞けないかも知れないしなぁ、無理までせんでもいいかなぁ、とか思いつつ。
2024年01月20日
コメント(0)
-
1/7 阪田知樹
みなとみらいホール 14:00〜 1階右側 ベリオ:水のクラヴィーア ショパン:24の前奏曲 op.28 シューマン:クライスレリアーナ op.16 バルトーク:戸外にて Sz.81/BB 89 <アンコール> バルトーク:3つのチーク県の民謡 ガーシュイン(ワイルド編):アイ・ガット・リズム ピアノ:阪田知樹 順序は前後するけれど、ニューイヤー系のコンサートの前にこちらも。 率直に言って、最近の日本人若手ピアニスト、反田恭平を筆頭にその辺の連中にはあまり付き合う気が起きません。ようつべとかで盛んに「発信」したりして、ビッグマウスなので露出は多いようだけれど、別にこちらが時間を割いて付き合う程の面白さはなさそうだし。 なので、基本的にあまり聞きに行く気は起きないのですが、にも関わらず足を運んだのは、まずもって暇だったところに、そこそこの割引チケットが出ていた。そして演目です。バルトークの「戸外にて」が一番のお目当て。ベリオはともかく、どれもそれほど珍しくはないといえば珍しくないけれど、この中で昨今割とプログラムに組まれるのはクライスレリアーナくらいじゃないでしょうか。24の前奏曲は勿論よく知られているけれど、リサイタルで組まれるのはあまり多くない。そして、戸外にては、知られてはいるだろうけれど、そんなには聞けない。正直、日本の若手ピアニストが組む演目としては、渋い。 実際行ってみると、客の入りはあまりよくなくて、3階席とか多分ガラガラだったでしょう。2階席もどうだったんだろう。全体としても半分入ってたかな、どうだろう、という感じ。1階は空席は結構あるとはいえそれなりに埋まっていましたが。まぁ、それだから割引チケットも出たのでしょうけれども。 で、演奏はというと、これが思いの外よかった。この人がどういう露出の仕方をしているのかはよく知りませんが、少なくともプロフィールにはやれようつべがどうしたのインスタがどうのなんて書いてないので、そこを主戦場と思っている訳ではないのでしょう。やってるかどうかは知りませんが。演奏で勝負する、まぁ、古いタイプといえば古いのかも知れませんが、そういうことなのかも。だからいい、って言ってる訳ではないですよ。 前半はベリオとショパン。ベリオの曲はよく知らなくて、ふーん、と思って聞いているうちにあっけなく終わってしまって、あら?という感じ。なのでよく分かってません。音は綺麗でしたね。曲としても、演奏としても。 で、そのまま席を立たずに24の前奏曲。 24の前奏曲としてリサイタルで聞くのは、いつ以来だろう。小山実稚恵がオーチャードのシリーズの中でやっていたと思いますが、そのほかではあまり聞かない。正直、あまり「映え」ないんですよね。全曲、みたいにしてやるなら、練習曲なんかの方がむしろ賑やかだし。オール・ショパン・プログラムとしても、前奏曲集は知られている割に地味だし。いろんな要素が入っていて、面白くはあるけれど、あまりリサイタルではやらないんですよね。 でも実際にこうやって聞いてみると、いわばショパンのショーウィンドウのようなもので、色々な相貌が次々と立ち現れるので面白い。この日の演奏もそれぞれの性格を表して、かつ全体としては端正な演奏で、飽きることがない。 後半はクライスレリアーナと戸外にて。まぁ、クライスレリアーナは、曲としては好きな人は好きなのだろうけれど、私はそれほど好きではないので....いい演奏ではあったと思います。 戸外にて。これが個人的にはお目当て。殊に第4曲の「夜の音楽」は、嘗て吉田秀和が「私の好きな曲」という連載で紹介した文章があって、これが素晴らしい内容なので是非一読願いたい、というのはまぁ私じゃうまく説明出来ないので、というところなのだけれども、他の4曲が人間の音で作られているのに対して、これは夜の戸外で聞こえてくる音、人間ならざるものたちの音 - といっても妖怪の類ではなくて自然界の音なのですけれども - をピアノ曲にしたようなもの、と言えばわかるでしょうか。まぁ、一度誰かの演奏で聞いて下さい。といっても録音も決して多くない。まして生演奏ではなかなか。なのでこれを楽しみにしていたのですが、これがとても良かった。 人間ならざるものの音、自然界の音、と言ったけれども、そもそもそういう環境というのは本当になくなってしまった。私が子供の頃、もう40年以上前ですけれども、その頃は田舎に行けば夜はTVを消せばかなり自然の音が聞けたけれども、今はもう難しいかも知れない。いや、聞けるところはまだ沢山あるんだと思うのですけれども、それなりに頑張らないとそういう環境には身を置けないのでは。そういう情景を鮮やかに描き出した曲なのですが、それをまた見事に具現化してみせた。実際にそういう場に身を置いて、耳を研ぎ澄まして聞き入った経験があるのではないかと思わせる、そういう演奏でした。 アンコール前のMCでも話していましたが、バルトークが好きらしく、なるほど。 敢えて何か言うとすれば、アンコール、アイ・ガット・リズムは、演奏は悪くないですけれども、うーん。どうせならもっと他のもの聞きたかったかな。まぁ、好きなもの弾くのがアンコールってものですからね、いいんですけれどもね。 正直、期待せずに出掛けただけに、大いに満足して帰って来たのでした。
2024年01月14日
コメント(0)
-
12/29 新国立劇場「くるみ割り人形」
新国立劇場 18:00〜 4階左端 チャイコフスキー:バレエ「くるみ割り人形」 クララ/こんぺい糖の精:米沢 唯 ドロッセルマイヤーの甥/くるみ割り人形/王子:井澤 駿 ドロッセルマイヤー:中島駿野 ねずみの王様:小柴富久修 ルイーズ/蝶々:奥田花純 雪の結晶:飯野萌子、廣川みくり スペインの踊り:原田舞子、朝枝尚子、中島瑞生 アラビアの踊り:渡辺与布 中国の踊り:広瀬 碧 ロシアの踊り:木下嘉人 花のワルツ:中島春菜、吉田朱里、渡邊拓朗、仲村 啓 東京少年少女合唱団 東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:アレクセイ・バクラン 振付:ウエイン・イーグリング これまた年末恒例になってきた、新国立劇場の「くるみ割り人形」。実はバレエも観ないわけでもないのではありますが、最近はそこまで拾ってられないという感じでもあって、あまり行かなくなりました。でも、くるみ割りは観る。第九じゃないけど、ツリーがでっかくなるのを見ないと気が済まない感じになってきました。まぁ、実際、くるみ割りは話もよく分かってるし平和だし、音楽もよく知ってるし、その割にそこそこ面白いし、みたいなのはあります。 この演出というか振付も結構長く使っているかと思いますが、慣れた目にはあまり不満は感じません。よく出来ていると思う。くるみ割りは最近では新国でしか観ていませんか、海外で何度か観たことはあるけれど、これはそこそこ見やすくていいと思っています。 踊りの良し悪しを云々出来るほどバレエをよく見ている訳でもないからあまり論評はしませんが、花のワルツなど見ていて「へぇ」と思ったのは、意外と群舞が揃っていないこと。交差するような、つまり、安全に関わるようなところはきちんとしていて安心感があるのだけれど、例えば手の動きとか、結構バラついている。てんでん勝手にやっている訳ではなくて、動きとしては揃っているけれど、細部が意外と揃っていない。何年か前、いつ頃か忘れましたが、新国で白鳥の湖を見た時は、もっとカチッと揃えようとしていた感じなのだけれど、今回は、「揃わない」というよりは「無理に矯正しない」という感じ。あとで人に聞いたのですが、最近はバレエでも必ずしもカチッとマスゲームみたいに揃えていこうというのでなく、人によって個人差はあるのだから、動きは合わせても形の同質性を無理に追い求めない、という傾向は一般にあるのだそうで。そういうもんなのかねぇ、とも思うけれども、確かに今回の群舞はやはり踊り手の身体に違いはあるし、だから、動きは合っていても形が綺麗に揃う訳ではない。ただ、それが不快だったかというと決してそんなこともなく、踊りとしてはそういうものとして楽しく眺めていたのですけれどもね。最近はそうなのねぇ。 音楽はまたしても安定の東フィル。指揮のバクランはウクライナの国立バレエで振っていた人だそうで、よくこなれてました。安心して聞いていられるし見ていられる演奏。 というわけで全体としては良かったんじゃないかというところでした。チケット代は少し上がっているんじゃないかなと思うのですが、どうだろう?そこそこお客さんは入っていたし、まぁそういうことならそれでいい、ということなのでしょう。これも安定的に長く続けて、風物詩として定着して欲しいなとは思います。
2024年01月13日
コメント(0)
-
12/24 東フィル第九
オーチャードホール 15:00〜 3階正面 ベートーヴェン:「献堂式」序曲 op.124 交響曲第9番 ニ短調「合唱付き」op.125 ソプラノ:光岡暁恵 アルト:中島郁子 テノール:清水徹太郎 バリトン:上江隼人 新国立劇場合唱団 東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:出口大地 今年、というか去年、というか、今シーズンは第九は結局1度しか聞きませんでした。いつもはN響くらいは聞くのですけれども、今年は指揮が下野。いらねーよ、ということで、結局これだけ。 東フィルは今シーズンは出口大地。ハチャトゥリアンコンクール優勝凱旋で東フィルを振ったのは確か去年、いや一昨年でしたが、2023年は第九に登場。今年は定演に再登場ということで、期待の新人というところでしょうか。いや、言えば、嘗ての下野同様外連味の多い、古典派やらないプログラムといえばそうなんですが、この人の場合ちょっと違うんですよね。スカした感じがないというか.........そもそも名を成したのがハチャトゥリアンコンクールだから、まぁ、そういう路線だよね、という。今度の定演もハチャトゥリアンとファジル・サイとコダーイのプロ、という。でも嫌味に感じないのは、小理屈とかがないからなのかなと。まぁ、言えば第九だってベートーヴェンだし。ま、依枯贔屓ですね。うん。 第九の前座に一曲やって休憩入れるスタイル。「献堂式」序曲というのは、あまり聞いた覚えのない曲ですが、作品番号では第九の一つ前なんですね。ふーん。まぁ、それなりに鳴らしごたえのある曲でしょうか。10分やって15分休憩。 後半の本編。 まずまずいい出来だったと言っていいと思います。 まず、オケがよく統制が取れいて良かったかと。特に第三楽章冒頭、木管から弦へと繋がっていく受け渡し、ここはとてもよかった。なかなかこうはいきません。これだけで十分及第点ですが、全体としてもまとまりよく、安心して聞ける演奏でした。 一方合唱は難あり。バランスが悪くて、男声が全然負けてしまうんですよね。そもそも人数でも負けてるし。これを言うと、第九あるある、という話とも言えるのですが、しかし、そもそもこれは東フィルの公演で合唱は新国立劇場合唱団。つまり、第九あるあるでよくあるアマチュアじゃないんですよ。例えば東響が東響コーラスとやる、とか、そういうパターンなら、まぁ、プロじゃないですからね。合唱の良し悪しとは別に、人数のバランスが取れなくても仕方ないかも知れないけれど、プロの団体なんだからさ。しかも負けっぷりが人数差以上なんですもの。それはちょっとダメだろうと思いますよ。上手い下手は......まぁ、独唱陣共々、あまり言いますまい。独唱は、出来不出来があったのは確かかなと。まぁ、全体に、オケがいい出来だったので、主にオケ聞いてましたのでね。正直もう歌唱に関してはどうでもいいことにしました。 指揮者の責任は無くはないのだけれども、まぁ、破綻はさせてないし、陣容はほぼ選択権無いでしょうからね。健闘したと思いますよ。次の登場が楽しみです。 そして第九としては、まぁ、これが聞けたので結果的には十分だったかなと。
2024年01月13日
コメント(0)
-
12/17 小曽根真クリスマス・ジャズナイト (2日目)
オーチャードホール 15:00〜 1階後方 第1部 M1: “Jungle” (Makoto Ozone) M2: “Mr. J.J.” (Jeff“Tain” Watts) M3: “Deviation” (Makoto Ozone) M4: “Jean Pierre” (Miles Davis) 第2部 M5: “Carrots or Bread” (Makoto Ozone) M6: “Park Hopper” (Makoto Ozone) M7: “Improvisation” M8: “No Strings Attached” (Makoto Ozone) アンコール “Happy Christmas” (John Lennon・Yoko Ono) ピアノ:小曽根真 トランペット:エリック・ミヤシロ/岡崎好朗/松井秀太郎/ジョーイ・クレリ トロンボーン:中川英二郎/半田信英/藤村尚輝/小椋瑞季 サックス:岡崎正典/馬場智章/岩持芳宏/ニコラ・カミニティ/タル・カルマン ベース:小川晋平 ドラムス:きたいくにと 本当は、アンコールに女性の歌い手さんが出て来たんですけどね、名前忘れちゃった....... 毎年末恒例の小曽根真のオーチャードクリスマス公演。大体毎年平日公演だったり、休日があっても売り切れだったりするのですが、今回は珍しく両日土日公演で、一般前売り前に気付いたので、どうにか。 no name horsesメンバーを基本に、若手や海外勢を入れたメンバーでの公演です。テナーサックスを吹いてたカルマンさんがなかなか色気のある音を出しておりました。 セットリストは上記の通り、公式サイトから引っ張って来ましたが、当然曲毎に編成をあれこれ変えての全2時間。まぁ面白かったです。いつも通り。 それだけかい、って言われると、まぁ、それだけなんですけどね。面白かったー、で完結してしまうのではあります。分析すればいろいろあるのかも知れませんが、まぁ、そういうのもあっていいかなと。
2024年01月08日
コメント(0)
-
謹賀新年
というわけでもう1月7日の夜も更けておりますが、一応松の内なので、明けましておめでとうございます。 年末はそれはそれであれこれ聞いたりちょっと旅行、これは珍しく音楽まるで関係なし、に行ったりしている内に年が明け、年明けも多少聞きに行ったりする内に7日なのであります。まぁ色々ありましてね。年末分からぼつぼつ書いていこうと思います。 今年は.........そうねぇ。特に抱負らしい抱負もないんですけれども。思い返せば去年は今までよりは聞きに行ってない気はします。今年もそんな感じになるのか、それともならないのか。まぁ、言うほど変わりはなかろうと思いますが。ただ、なにしろ円安傾向は止まりませんのでね。やはり為替の影響を容赦無く受けるのがこの業界ですから、日本円ベースで暮らしている身にはどうしても数は減るんだろうなと思ったり。まぁ、ぼちぼちやってきますよ。
2024年01月07日
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-
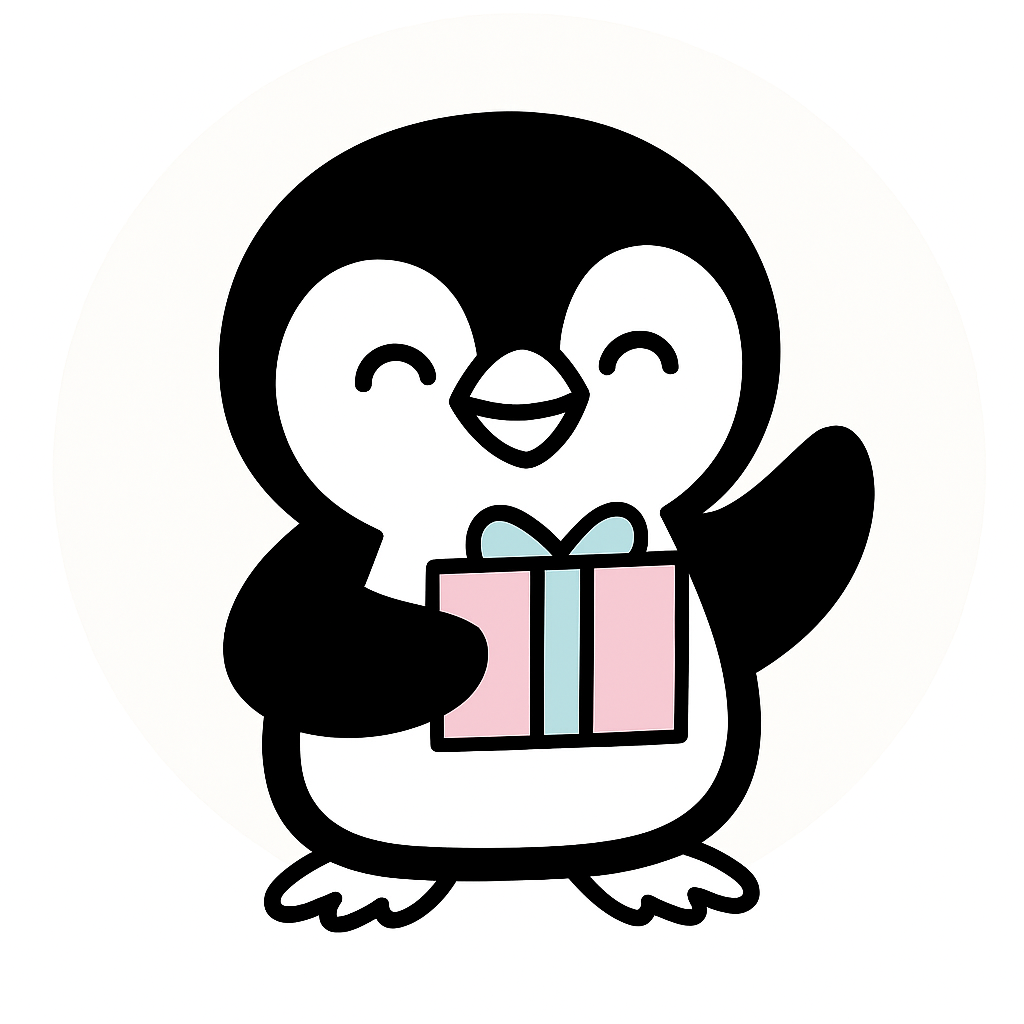
- やっぱりジャニーズ
- 楽天予約 SixTONES Best Album「MILE…
- (2025-11-20 16:44:46)
-
-
-

- きょう買ったCDやLPなど
- The Beatles(ビートルズ) 『アン…
- (2025-11-20 11:02:10)
-
-
-
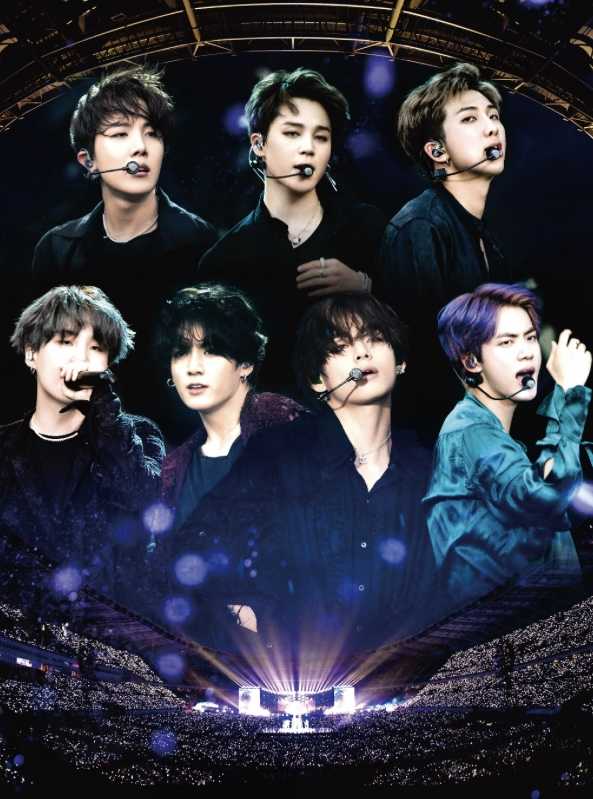
- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…
- (2025-11-21 18:37:01)
-







