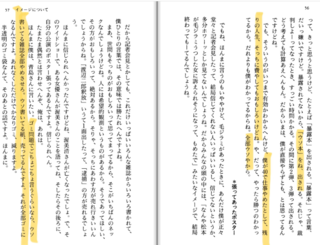リリックにて自身をKing、王様と表現するアーティストはいるが、周囲からKingと評されているアーティストは、こと日本においてはMURO以外に思いつかない。
さらに、ZEEBRAは「今回の曲でのMURO君との競演は念願だったね。東の横綱と西の横綱が曲を作る、みたいな」と表現した。この発言時、ZEEBRAはDragon Ashとの『Grateful Days』を経て、『MR.DYNAMITE』をドロップした後であり、最も有名なヒップホップアーティストになっていた。にもかかわらず、MUROに敬意を表し、横綱と表現したのだ。このことからも、MUROのKingたる所以が感じられる。
また、King of Diggin productionナンバー2でもあるDEV-LARGEは「MUROは兄弟、親みたいなもの」と尊敬をこめて語る。さらに、アメリカから日本に戻ってきたことについて、MICROPHONE PAGERの影響があるともいう。
これほどの敬意をシーンの重鎮から受けているものの、評価の高さに見合うほどの一般ファン層がいるわけではない。
Nitro Microphone Underground(以下:Nitro)が結成され、ファーストアルバムをドロップすると、その音とラップは、リスナーの99%近くを虜にした。そんな彼らは「MICROPHONE PAGERを意識した」と語っており、blast編集部(休刊となったHIPHOP雑誌)は「NitroはMURO派とTWIGY派のラップにわかれている」とまで分析し、その影響力を指摘した。
しかし、MICROPHONE PAGER自体が、Nitroに魅了されたリスナーから高い評価を受けてはいない。そこが不思議な所である。96年頃から起こった日本語ラップバブルに関してもそうだ。その時に夢中になったアーティストにMICROPHONE PAGERを挙げる人よりも、KING GIDRAやBUDDHA BRANDを挙げる人の方がずば抜けて多い。それは、ツイッターのフォロワー数にも如実にあらわれ、ZEEBRAが9万人に対し、MUROは2万5千人で止まっている。
ということは、シーン以外には影響力を持っていないのでは、と思いきや、Nitroよりさらに下の第四世代、DO・JBM・SIMONがドロップした『日本語ラップ イズ デッド?』ではMICROPHONE PAGERのリリックが数多く引用されている。彼らはMICROPHONE PAGERがリリースしていた頃、高校生だった。つまり、リスナーに対する影響力がない訳ではない。
この噛みあわない評価はMICROPHONE PAGERだけではなく、MUROにもあてはまる。LunchTimeSpeaxが牽引する水戸では、MUROがアルバム『PANRHYTHM』をドロップした年、そのアルバムを今年の一枚に挙げないDJやMCはいなかった。とにかく凄い影響力を誇っていた。しかし、その年、blastが毎年行なう誌面でのアワードに、『PANRHYTHM』は入っていない。blastだけでなく、各音楽媒体のアワードにも、である。さらに言えば、CDセールス的にも売れたとは言い難い、無難な数字だった。
何故、こういったかみ合わない状況が起こるのだろうか?
MUROは、時代が生む流行を意識していないのかもしれないと私は思う。‘売れるもの’とは時代に合ったものだと言われる。買う側は時代を意識して買うし、取り上げる側も時代に合ったものを取り上げる。
94年頃にリリースされた曲を今聞き比べるとわかりやすい。
KING GIDRAはコール&レスポンスというHIPHOP文化を見事にサビに取り入れた。BUDDHA BRANDは日本語英語ではなく、本場の英語と古き日本語を混ぜたバイリンガルスタイルを作り出し、日本人も聞き入れられる本場の英語を取り入れた。
では、MICROPHONE PAGERは? 正直、文面にするのが難しい。何と言うか普通なのだ。悪い意味ではなく、たとえるなら、アメリカの旧譜の中にMICROPHONE PAGERの音が入っていても違和感を覚えない。何かを打ち出すというより、自分の道を進む。日本で売れるかではなく「本場アメリカでも負けないレコードを作りたい」(MURO)。だから、わかりやすさを求めるリスナーを惹き付けなかったのかもしれない。
そして、ソロになったMUROはより独自の道を進む。
99年。日本語ラップは転換期を迎えた。DragonAshの出現により、ラップの格好良さが認識され、アンダーグランドにいたアーティスト達にも目が向けられるようになった。HIPHOPの激しいビートなどが評価を受けるようになった中、MUROがメジャー第一弾に選んだ音は、なんとジャズだった。次にリリースした『THE VINYL ATHLETES』は玄人好みの黒い音。さらに、『El carnaval』では、流行る前にもかかわらず、ラテンを取り入れた。現在、Popなビートが好まれている。ここに『smile in your face』のような音を持ってくれば、セールスに繋がる確率は高い。しかし、MUROは『Tokyo Tribe 2』のように、これぞHIPHOPという音を選択している。
時代に媚びず、自分の音を追い続ける。もちろん、様々なジャンル、新譜も含め‘DIG(掘る)’ことも忘れない。その様々なジャンルの音が数々のMIXで表現されている。時代を踏まえつつも、決して時代には媚びない。ゆえにラッパーとしてはセールスに繋がらないことのほうが多いかもしれない。その反面、このスタイルがDJとしてJAY-Zをはじめ、多くの大物達から敬意を受けている。
MUROは語る。今のシーンが決して良いとは思っていないことを。自分で変えられるなら変えたいとも。しかし、ポップな音で結果を出して、そこから変えるのではなく、自分自身の音であくまでも勝負するようだ。
「色々な音を使う中で、これってHIPHOPなのかな、と思ったんですけど、須永辰緒さんに「これはHIPHOPだよ。MUROの作る音は全部キックとスネアが太い」と言われました(笑)」
というように、MUROの体にはHIPHOPが染み付いている。FT-R(クラブカルチャーTV)でも
「音作りの基本はレコード2枚でキックとスネアをループすること」
と語っていたように、‘太さ’こそMUROというイコールがあるのだ。
そんな自分を曲げないスタイルだからこそ、同じ立場にあるアーティスト、またアーティストを目指す若者から敬意を表されるのだろう。
blast休刊前のコラムに「Is Japanese HIPHOP DEAD?」という題があった。その問いに対する答えがここにある。
Japanese HIPHOPを追求しているMUROは自然と種をまいている。それを物語るように、そこからNitroやJBMという花が咲いた。
だから私は、「Is Japanese HIPHOP DEAD?」という問いに対し、「いいえ、日本語ラップは生きています」と力強く答えられる。
MUROが見合う評価をリスナーから受けるのはまだまだ遠い未来なのかもしれない。ただ、いつか受けるのは間違いない。巨匠が死んでから名をはせるのと同じように。
【このカテゴリーの最新記事】
- no image