カテゴリ: 映画
普段は定休日の火曜日に映画を観るのだが、仕込みを終えて帰って来ると倦怠感に襲われて観る気が失せる事も少なくないので、最近は目先を変えて月曜日の夜に観る事にしている。
次の日が休みだと思うと多少は気持ちも軽くなり、前向きに映画を観ようという姿勢になる(笑)。
今週は月曜日だけでなく火曜日にも鑑賞したので、ジャンルが違うものを2本。
どちらの作品も狙いは悪くないのだが、今一つ説得力に欠けるため中途半端な印象を受けた。
(まあ、ジャームッシュ監督は寧ろそこを狙ったような気もするが…笑)
感想に比べて、余談がかなり長くなってしまったので悪しからず。
【9人の翻訳家 囚われたベストセラー】… 満足度★★★
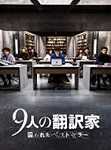
映画【ダ・ヴィンチ・コード】で有名なダン・ブラウンの小説『インフェルノ』の出版時に、「違法流出防止のため各国の翻訳家を秘密の地下室に隔離し翻訳させた」という実話をヒントに描かれた密室ミステリー劇。
思わせぶりな描写で観る側の好奇心と緊張感を煽る割には、肩透かしに終わる展開が目立つため、実際に謎解きが始まる頃には気持ちが醒めてしまった。
真犯人にあまり感情移入できなかったのも、評価が下がった要因。
【デッド・ドント・ダイ】… 満足度★★★

僕はホラー映画を(怖いから…笑)基本的には観ないのだが、今回はジム・ジャームッシュ監督がゾンビ映画を撮ったという事で食指を動かされた。
当然グロテスクな描写はありつつも、全体的には人を食ったような緩さがあり、ホラーというよりコメディに近い。
生前に好きだった物を求めて彷徨うゾンビ達の姿が、どことなく生きている人間と同じに感じたのは、ジャームッシュ監督ならではの皮肉だろうか。
ここからは余談になるが、最近読み始めた戸谷洋志の著書『ハンス・ヨナス 未来への責任』に興味深い事が書いてあった。
『唯物論的一元論において、原則的に生命は存在しないし、存在するべきでもない。
その世界においてもっとも正統なあり方は「死体」である。
そこでは生命は死体としてのみ存在しうるのである。
(中略)それが、ヨナスの考える、西洋における生命観の歴史の帰結なのである。』
これだけだと、何の事か意味が分からないと思うので、もう少し詳しく説明しよう。
原始の時代、人間はこの世に存在するもの全てに生命があると考えていた。
空も大地も風も、あらゆるものが生きており、この世界に生きていないものは存在しない、と考えられていた。
そして、当然ながら、人間もこの自然の一部であり、自然と同じ原理のもとで存在していた。
ドイツの哲学者ハンス・ヨナス(1903~1993年)は、こうした太古の世界観を「生命論的一元論」と呼ぶ。
しかし、この生命論的一元論はある矛盾を抱えていた。
それは「存在=生命」と考える世界観では、「死」を説明できないという事である。
全ての存在に生命があるなら、死体も死体なりの仕方で生きていなければならなくなる。
この矛盾を克服すべく人間が生み出した世界観が、死後も存在し続ける「魂」の領域と、死によって滅び行く「肉体」の領域という二元論だった。
肉体は、そこに魂が一時的に宿る事で生命として存在しているだけであり、それ自体が生命である訳ではない。
この二元論は「人間と自然」「精神と肉体」とを分断し、その後の西洋の歴史を決定的に規定する事になった。
とは言え、二元論が生命を巡る最終的な答えになった、という意味ではない。
何故なら、この相反する二つの原理が、どうして一つに結び付きこの世界に存在しているのか、両者は果たしてどのような関係にあるのか、という疑問が残るからである。
ヨナスは、この二つの原理を統合しようとする世界観を「唯物論的一元論」と呼ぶ。
唯物論的一元論とは、端的にはこの世界から魂を消去した世界観であり、生命を死の一部として説明する事に他ならない。
ヨナスによれば、この世界観を最も先鋭化させた学問が、生物学である。
生物学において試みられるのは、生命を、その身体を構成している微小な物体へと還元し、その組成によって解明する事である。
生物は器官へと分解され、器官はたんぱく質へ、たんぱく質は炭素原子へと分解される。
しかし、炭素原子そのものは生きておらず、単なる物質に過ぎない。
そうである以上、身体を理解する事、生命を理解する事は、飽くまでも生命を死んだ物質の集塊として説明する事を意味する。
このように、現代科学がどれだけ脳や筋肉、血液や器官の仕組みを解明しようと、それは飽くまでも物質としての機能の話であり、何故それが「生命」としてこの世界に存在し、「私」として今を生きているかは説明できない。
現代科学の知見に立てば、人間は未だに「物質(=死体)」の域を出ておらず、その意味で僕達は正に「生ける屍(ゾンビ)」なのだ。
そう考えると、昨今やけにゾンビ映画が流行っているのも、その根底には「物質」から「生命」へと本能的に回帰しようとする西洋の生命観が影響しているのかも知れない、とさえ思えて来る。
ジム・ジャームッシュ監督がそこを描こうとしたのだとしたら、やはり彼は天才だ。
劇中に登場するゾンビ達が生前の記憶に従って動いているというのも、決して荒唐無稽なアイデアではない。
現在の脳科学の研究では、人間が日常的に行っている意思決定のほとんど(8~9割)は、意識ではなく無意識の部分で行われる事が分かっている。
例えば、指を曲げる時、僕達が「指を曲げよう」と考えるよりも先に、脳は指を曲げる指令を筋肉に伝えている。
正確には、脳が指令を発してから約0.1秒後に「指を曲げよう」という意識が生まれ、約0.3秒後に実際に指が動く。
この0.2秒のタイムラグのせいで、人間は「自分で考えて動かした」と錯覚しているに過ぎない。
信じ難い事だが、僕達の意識は、脳の指令に対して後追いで理由を付けているだけなのだ。
僕達が「指を曲げよう」と意識するから脳が指令を出すのではなく、脳が指を曲げる指令を出すから僕達に「指を曲げよう」という意識が生まれる。
これを「受動意識仮説」と呼ぶ。
また、人間の感情や思考、行動には、脳内で分泌されるドーパミンやオキシトシンといった神経伝達物質の働きが大きく作用している事が分かって来ている。
こうした研究結果が真実ならば、僕達にはそもそも自由意思など無い事になる。
僕達が意識しようとしまいと、脳は指を曲げるだろうからだ。
人間は、実際はただ脳が出す指令に従って動いているだけなのに、一人で勝手に「私は(自分の意思で)生きている」と思い込んでいる、間抜けな生き物になってしまうのだ。
それは、ジャームッシュ監督が描いたゾンビ達と何も変わらないだろう。
あぁ、そうか…。
だから【デッド・ドント・ダイ】は、ホラーでもありコメディでもあるのか(笑)。
この問題の答えが知りたければ、こちらの書籍を。

『ハンス・ヨナス 未来への責任 やがて来たる子どもたちのための倫理学』 [戸谷洋志]
次の日が休みだと思うと多少は気持ちも軽くなり、前向きに映画を観ようという姿勢になる(笑)。
今週は月曜日だけでなく火曜日にも鑑賞したので、ジャンルが違うものを2本。
どちらの作品も狙いは悪くないのだが、今一つ説得力に欠けるため中途半端な印象を受けた。
(まあ、ジャームッシュ監督は寧ろそこを狙ったような気もするが…笑)
感想に比べて、余談がかなり長くなってしまったので悪しからず。
【9人の翻訳家 囚われたベストセラー】… 満足度★★★
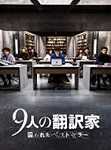
映画【ダ・ヴィンチ・コード】で有名なダン・ブラウンの小説『インフェルノ』の出版時に、「違法流出防止のため各国の翻訳家を秘密の地下室に隔離し翻訳させた」という実話をヒントに描かれた密室ミステリー劇。
思わせぶりな描写で観る側の好奇心と緊張感を煽る割には、肩透かしに終わる展開が目立つため、実際に謎解きが始まる頃には気持ちが醒めてしまった。
真犯人にあまり感情移入できなかったのも、評価が下がった要因。
【デッド・ドント・ダイ】… 満足度★★★

僕はホラー映画を(怖いから…笑)基本的には観ないのだが、今回はジム・ジャームッシュ監督がゾンビ映画を撮ったという事で食指を動かされた。
当然グロテスクな描写はありつつも、全体的には人を食ったような緩さがあり、ホラーというよりコメディに近い。
生前に好きだった物を求めて彷徨うゾンビ達の姿が、どことなく生きている人間と同じに感じたのは、ジャームッシュ監督ならではの皮肉だろうか。
ここからは余談になるが、最近読み始めた戸谷洋志の著書『ハンス・ヨナス 未来への責任』に興味深い事が書いてあった。
『唯物論的一元論において、原則的に生命は存在しないし、存在するべきでもない。
その世界においてもっとも正統なあり方は「死体」である。
そこでは生命は死体としてのみ存在しうるのである。
(中略)それが、ヨナスの考える、西洋における生命観の歴史の帰結なのである。』
これだけだと、何の事か意味が分からないと思うので、もう少し詳しく説明しよう。
原始の時代、人間はこの世に存在するもの全てに生命があると考えていた。
空も大地も風も、あらゆるものが生きており、この世界に生きていないものは存在しない、と考えられていた。
そして、当然ながら、人間もこの自然の一部であり、自然と同じ原理のもとで存在していた。
ドイツの哲学者ハンス・ヨナス(1903~1993年)は、こうした太古の世界観を「生命論的一元論」と呼ぶ。
しかし、この生命論的一元論はある矛盾を抱えていた。
それは「存在=生命」と考える世界観では、「死」を説明できないという事である。
全ての存在に生命があるなら、死体も死体なりの仕方で生きていなければならなくなる。
この矛盾を克服すべく人間が生み出した世界観が、死後も存在し続ける「魂」の領域と、死によって滅び行く「肉体」の領域という二元論だった。
肉体は、そこに魂が一時的に宿る事で生命として存在しているだけであり、それ自体が生命である訳ではない。
この二元論は「人間と自然」「精神と肉体」とを分断し、その後の西洋の歴史を決定的に規定する事になった。
とは言え、二元論が生命を巡る最終的な答えになった、という意味ではない。
何故なら、この相反する二つの原理が、どうして一つに結び付きこの世界に存在しているのか、両者は果たしてどのような関係にあるのか、という疑問が残るからである。
ヨナスは、この二つの原理を統合しようとする世界観を「唯物論的一元論」と呼ぶ。
唯物論的一元論とは、端的にはこの世界から魂を消去した世界観であり、生命を死の一部として説明する事に他ならない。
ヨナスによれば、この世界観を最も先鋭化させた学問が、生物学である。
生物学において試みられるのは、生命を、その身体を構成している微小な物体へと還元し、その組成によって解明する事である。
生物は器官へと分解され、器官はたんぱく質へ、たんぱく質は炭素原子へと分解される。
しかし、炭素原子そのものは生きておらず、単なる物質に過ぎない。
そうである以上、身体を理解する事、生命を理解する事は、飽くまでも生命を死んだ物質の集塊として説明する事を意味する。
このように、現代科学がどれだけ脳や筋肉、血液や器官の仕組みを解明しようと、それは飽くまでも物質としての機能の話であり、何故それが「生命」としてこの世界に存在し、「私」として今を生きているかは説明できない。
現代科学の知見に立てば、人間は未だに「物質(=死体)」の域を出ておらず、その意味で僕達は正に「生ける屍(ゾンビ)」なのだ。
そう考えると、昨今やけにゾンビ映画が流行っているのも、その根底には「物質」から「生命」へと本能的に回帰しようとする西洋の生命観が影響しているのかも知れない、とさえ思えて来る。
ジム・ジャームッシュ監督がそこを描こうとしたのだとしたら、やはり彼は天才だ。
劇中に登場するゾンビ達が生前の記憶に従って動いているというのも、決して荒唐無稽なアイデアではない。
現在の脳科学の研究では、人間が日常的に行っている意思決定のほとんど(8~9割)は、意識ではなく無意識の部分で行われる事が分かっている。
例えば、指を曲げる時、僕達が「指を曲げよう」と考えるよりも先に、脳は指を曲げる指令を筋肉に伝えている。
正確には、脳が指令を発してから約0.1秒後に「指を曲げよう」という意識が生まれ、約0.3秒後に実際に指が動く。
この0.2秒のタイムラグのせいで、人間は「自分で考えて動かした」と錯覚しているに過ぎない。
信じ難い事だが、僕達の意識は、脳の指令に対して後追いで理由を付けているだけなのだ。
僕達が「指を曲げよう」と意識するから脳が指令を出すのではなく、脳が指を曲げる指令を出すから僕達に「指を曲げよう」という意識が生まれる。
これを「受動意識仮説」と呼ぶ。
また、人間の感情や思考、行動には、脳内で分泌されるドーパミンやオキシトシンといった神経伝達物質の働きが大きく作用している事が分かって来ている。
こうした研究結果が真実ならば、僕達にはそもそも自由意思など無い事になる。
僕達が意識しようとしまいと、脳は指を曲げるだろうからだ。
人間は、実際はただ脳が出す指令に従って動いているだけなのに、一人で勝手に「私は(自分の意思で)生きている」と思い込んでいる、間抜けな生き物になってしまうのだ。
それは、ジャームッシュ監督が描いたゾンビ達と何も変わらないだろう。
あぁ、そうか…。
だから【デッド・ドント・ダイ】は、ホラーでもありコメディでもあるのか(笑)。
この問題の答えが知りたければ、こちらの書籍を。

『ハンス・ヨナス 未来への責任 やがて来たる子どもたちのための倫理学』 [戸谷洋志]
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021.11.28 20:37:01
[映画] カテゴリの最新記事
-
ものぐさ映画評(part62) 2023.11.28
-
1939年の女性達… 2023.09.28
-
ものぐさ映画評(part61) 2023.09.20
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Calendar
Keyword Search
▼キーワード検索
© Rakuten Group, Inc.









