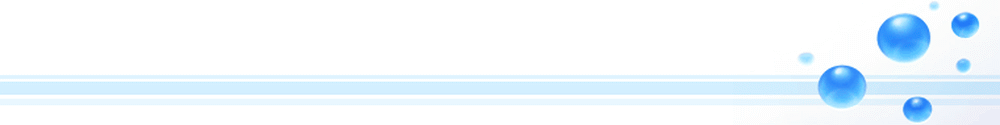2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年08月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
泣ぐ子(ご)は居ねがぁ!
豪石せよ、アキタ・ケン。豪石(ごうしゃく)とは、 主人公アキタ・ケン(秋田県在住・農業)が、謎の石の力によってネイガーに変身するときの掛け声であり、また、その超神変身現象を指す言葉である!秋田の正義と平和を愛する主人公、アキタ・ケン(秋田県在住・農業)は、悪の組合長セヤミコギ率いるホジナシ怪人たちと日夜戦いつづけるのです。ネイガーの名前の由来は、『泣ぐ子(ご)は居ねがぁ!』『悪り子(ご)は居ねがぁ!』というナモミハギの叫び声から。日本海沿岸に広く伝わる来訪神「ナモミハギ」の伝承をモチーフとした、秋田発のオリジナル・ヒーローです。ナモミハギは大晦日や小正月に山から里へ下りてきて、人々の怠惰を諌め、来たる年に祝福を与えていく歳神(としがみ)様です。全国でも秋田県男鹿市の「ナマハゲ」は有名で、荒々しい振る舞いと大きな音で邪気を祓います。秋田県にカメムシが大量発生した。県民はやる気を失い、悪臭になすすべがない。この事件は秋田壊滅を目論む悪の組織・だじゃく組合の仕業だった。秋田の平和を守るため、正義のヒーロー・ネイガーが今、立ち上がる!中身に関してはどこに出しても恥ずかしくない?!変身ヒーローモノとして完璧に仕上がっている。真面目な戦闘シーンでもだじゃく組合のやっていることがマヌケすぎて笑えてしまうのはご愛嬌で本人達は大真面目でもはたから見れば馬鹿馬鹿しいことにしか見えないのはだじゃく組合の特性、ネイガーとアラゲ丸がシメるとこはきっちりシメるため、テンポがよく読んでて飽きない。問題があるとすればそれは秋田弁が全開なとこでしょうかw正直な話、ドラゴンエイジで秋田弁全開ってそれはいいのかと問い詰めたくもなるが、多少のムチャは承知なようだ、流石角川書店!一応注釈はついてて何となるが、しかし、秋田県民さえも出てくる秋田弁でわかんないのがチラホラあるらしい。。。
August 25, 2007
コメント(2)
-
貞本エヴァ
テレビ放映の1年位前から少年エースで連載している、TVアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のマンガ版のこと。由来は、作者でありアニメ版のキャラデザインを担当した貞本義行氏からがアニメの完全コミカライズではなく、微妙に作中の設定や性格を変え、貞本氏の考えによって本編を再構築しているため病的に内気だったシンジの性格が皮肉屋の我侭に変わっている点やレイがやや明るく、自分の心情をモノローグで語る、使徒が12体しかいない、ゲンドウが本編よりも父親らしい、「母親が自殺した」というアスカの設定が「試験管ベイビーである」に変更、チルドレン3人の三角関係描写が顕著、トウジが初号機に殺される、などが主なアニメ版との相違点が結構ある。突然長期にわたって休載するのが特徴で、過去に1年以上の長期休載がこれまでに2度あり、また順調でも隔月掲載ペースなど、原作のあるマンガとしては進行がかなり遅い。結果、異常なまでの連載長期化を引き起こすこととなった。開始当時、一体誰が、アニメ終了から今に経っても完結しないなどと予想しただろうか?エヴァとサイコが同時休載した時の雑誌は、抜け殻のようであったが、それを救ったのはどっかの「かえる」だがそれは別の話。『宇宙戦艦ヤマト』『機動戦士ガンダム』に続く第3次アニメ革命と言われるアニメの方も普通に放映されて、普通に終わっていれば、エピローグに対して賛否両論がでなかったと思うんだよねぇ。9月1日にはヱヴァンゲリヲン新劇場版の公開が控えていて、更に米国での実写映画のプロジェクトが進行しているらしい。。。とりあえず、TV放映最終話や映画版(旧)とも違う完結の仕方に注目したい!
August 22, 2007
コメント(2)
-
ふたり鷹
『ふたり鷹』は『週刊少年サンデー』(小学館刊)で連載されていた新谷かおる原作の作品で、テレビアニメも1984年9月27日から1985年6月21日まで、フジテレビ系列にて放送されたらしいが、記憶に無いw同じ名前と誕生日を持つ、沢渡鷹と東条鷹。沢渡鷹は暴走族では無いが公道レーサー。東条鷹と出会うことで族との関わりを断ち切る。数奇な因縁で結ばれたふたりの「鷹」が、耐久二輪レースの世界でライバルとして互いに高め合い、2人の出生の秘密などと言ったメロドラマ的な要素も織り交ぜながら2人が同じ目標へと進んで行き、共に頂点を目指す姿を描くマンガです。新谷かおるの女性キャラは大概佐伯かよの奥様が手伝うことも合って可愛いかったり、終盤に出てくるオリジナル・レースマシンが現実離れしているデザインなのが凄かったりと、読んでいて飽きないwふたり鷹は言うまでもなく鷹という名前が付いた2人の男の物語ですが、本当はふたり鷹とは名ばかりの「母子鷹」で読めば分かりますが、真の主人公は沢渡鷹ではなく母親の「沢渡緋沙子」であるのは疑う余地も無いw吉村秀雄、森脇護などの実在の人物も登場している。。。(一部「エリア88」のキャラクターも混じっていたりする)初期の新谷作品ではエンターテインメントとしては1.2を争う面白さだと思う。
August 21, 2007
コメント(3)
-
薔薇のマリー
砂の薔薇は1989年「月刊アニマルハウス」8月号より連載、月刊アニマルハウスから「ヤングアニマル」に誌名変更・リニューアル後も連載は継続。単行本は全15巻。夫と子供をテロリストの空港爆破によって失い、悲しみを払拭しようと対テロ傭兵組織 CATという民間軍事部門のメンバーであるマリー・ローズバンクが、薔薇の形に見える傷跡から「薔薇のマリー」と呼ばれ、仲間達と戦っていく物語です。このマンガにでてくる女性たちの強さ女性としての魅力的なこと、メンバーも個性あふれていて大変魅力的であります。テロで夫と子供を失ったマリーが、復習とテロ撲滅をかけてテロリスト集団グリフォンと対峙するというストーリーからして、名作「エリア88」を髣髴とさせる。新谷かおるは戦争モノを書かせると輝きが増す、と思うのは私だけではないはず。メカニックの描写は独特のパースが松本零士から受け継がれ、さらに昇華されたものとなっており、独特の新谷ワールドが健在する。現存するマンガ家でこれを継承できているものはいない。最後のほうでは大どんでん返しがあったりと、とにかく面白いです。
August 20, 2007
コメント(2)
-
His blood is burning...やつの血は燃えている
B・B (Burning Blood) こと『B・B』は、石渡治によるボクシングマンガ。週刊少年サンデーに1985年24号から1991年9号の間連載された作品。燃える血を持つという意味からB・Bと呼ばれる高校生・高樹と、宿命のライバル・森山仁との戦いをハードに描く。「B・B」は一応ボクシングマンガではあるのだが、決してそれだけに留まらぬ、非常に奥が深くスケールの大きい作品であり、自分がサンデー読者になったキッカケは確実にこのマンガの続きが読みたかったからである!!それほど当時夢中になって読んだマンガの1つです。高樹が、天敵・森山との宿命の対決を求めて、一撃必殺の「10cmの爆弾」をフィニッシュブローとして生み出した。恐らくボクシングマンガの技では最強の必殺技。(「リンかけ」の連中は別格w)高校ボクシング界から暗黒マフィアの世界、傭兵を経て、世界を舞台に戦っていく物語。リングに炸裂する青春の怒り!バイクの爆音とペットの響きの中で男のドラマ、B・B(Burning Blood)はトランペットを持てば右に出る者はなく、ケンカをすればかなうものなし、なのにいつも本気になれず、海を漂う茶色の小瓶のよう。そんな中見つけだした「本気」は、ボクサーへの道。。。B・Bには娘の高樹愛(通称・ラブ)がいるのだが、父と一緒に世界中を旅して回ることになり、父親譲りの抜群の身体能力を生かし、サバイバル技術や格闘術など、様々なものを吸収してゆく。およそ四年間旅した後、アメリカの友人達に預けられて一通りの教育を施され、12歳の時に小笠原へと移住。そこで、あるスポーツと運命的な出会いを果たすことになるのだが、それはまた別の機会に。。。まだ読んだことない方にかなりお奨めしたい作品です。
August 19, 2007
コメント(2)
-
「だーいじょうぶ!まーかせて!」BY 神谷明w
【究極超人あ~る】、1985年から1987年にかけて「週刊少年サンデー」において連載された、SF学園コメディマンガ。第19回星雲賞マンガ部門受賞。オタク系マンガの代表というか、基本みたいな作品で、ゆうきまさみの代表作のひとつ。連載開始と同時に、びっくりするほど話題を振りまいた歴史的作品です。春風学校の光画部が撮影旅行先で出会ったのは、池の中から自転車をこいで現れた、みょ~なヤツ。夏だというのにガクランで、なぜか下駄ばきのR・田中一郎くん。実は彼、アンドロイドだったのです。一応主人公は「R・田中一郎」、テーマは「光画部」の部活動。でも主人公はどんどん影が薄くなってしまいには消えるし、鳥坂先輩やたわばさんなどの暗躍によりまともな部活動をしたのは数える程度、元ネタ探しを始めるとかなり深い作品でもある。というのも、ほとんどが実在の人物や場所、事件などを元ネタもしくはモデルにしているからであり、さらにパロディも含むからである。この辺「OUT」出身のゆうきまさみらしい内容ではある。このマンガで出てくる「光画部時間」などを実践していた人も結構多いらしい。。。ちなみに「光画部時間」とは「定められた時間の前後2時間ずつの幅を取る」ことを指す(鳥坂・談)さらに飯田線との競争「下山ダッシュ」に挑戦する人もホントに結構いる。「逆光は勝利」などは写真の基本なので参考書代わりにする人もいるとかいないとかw。「光画」とはいわゆる写真の古い呼び方なので、本来なら「光画部」=「写真部」なのだが「あ~る」の影響により本来の意味はかなぁり薄まり、別の意味の方が広まって(広められて)しまう。ちなみに「光画部」が実際した・する高校は意外にあるもんである。当然そこでは「あ~る」がバイブルとされている事が多いようだ。ゆうきまさみの同時期の作品「鉄腕バーディー(旧)」(舞台が同じ場所)ならびに次回作「機動警察パトレイバー」「じゃじゃ馬グルーミン★UP!」にも鳥坂たちと共に何度か顔を見せている。この作品を見るとなんとなく懐かしい気持ちにさせられてしまう。それはおそらくこの作品の中には日本がまだ色々な意味で豊かであった時代の何かが詰まっているからではないだろうか。OVAも製作され、その原作にはない物語・完全オリジナル、何が面白いのか説明は難しいw 笠原弘子が歌うエンディングを聞くとなんとなくせつない気持ちになる。更に挿入歌「飯田線のバラード」を歌っているのはタイムボカンシリーズの歌でも有名な山本正行氏だったりする。R・田中一郎の声を担当していた塩沢兼人が事故で急逝するまでは、テレビアニメ化という噂も何度か上がったことがあるらしく勿体ない話である。
August 14, 2007
コメント(2)
-
一番マイナーな作品
「鋼鉄の狩人」は長谷川作品の最初のロボットマンガ、恐らく一番マイナーな作品。背中の長剣、腹の短剣、弓矢などを武器に、森の中を縦横無尽に跳びまわる狩人は、ロボットアクションのカッコ良さを再認識させてくる。長谷川作品におけるロボットアクションの基本ともいえる作品。舞台は20世紀の7000後の地球。突然、異常に成長し始めた木々によって、地上は覆い尽くされ、人々は木々の枝の上で生活していた。そこでは、文明、国家は衰退し、木々の上で生活するために、疑似生体有機脚=サイバス(いわゆるロボットみたいな物)が発達し、力こそが世界を支配していた。巨大樹木で覆われてしまった世界で活躍する、他のサイバスは材料の90%以上が木製なのに対して、戦争中に作られたゼロインアービックはそのほとんどが金属。争いを憎み、争いを生む人を避け、森の中で自然と共に暮らすゼロインは、いつしか「鋼鉄の狩人」と呼ばれる。人工冬眠から目覚めたアイアンキッドは自分を世話してくれた少女を助けるために、人々に恐れられている人工知能で動くサイバス鋼鉄の狩人に戦いを挑む。弱い物を助けるための力を得るために。。。「樹木に覆われた世界」という設定が「クロノアイズ」に登場したものと同一だが当初は同一時間軸の出来事と考えていたわけでは無いらしく、「大外伝」作成時に同じでも別に問題ないだろうと思ったらしく、オフィシャル設定になったらしいw恐らく入手困難ですので、余程のファンで無い限りお奨め出来ませんw
August 13, 2007
コメント(2)
-
ホントに漂流。。。
『轟世剣ダイ・ソード』(ごうせいけんだいそーど)は、正統少年マンガの王道をひた走り、しかし古臭くなく?、『マップス』などと並ぶ作者の代表作の1つで、主人公・百地王太はじめ中学生550人が学校ごと剣と魔法の異世界「泡の中央界」へ飛ばされる冒険ファンタジーマンガである。学校ごと異世界に飛んでしまったり(ほどんど「漂流教室」だが、ホントに漂流(航海?)してしまう・・・)、本作は「大人数が学校ごと異世界へ飛ばされる」というシチュエーションから『漂流教室(楳図かずお)』と比較されることがあるが、同作とはかなり異なり基本的に明るい雰囲気で展開する作品である。刀がロボットになったり(トランスフォーマーな世界・・・)、設定の奇抜さがなかなかです。 掲載雑誌が途中で変わったほか、6巻までの連載のあと、いきなり終了してしまい、残りの7巻を「全読み切り」で出版するなど、なかなか侮れない。全校生徒550名とともに校舎ごと消滅した九江州(くえす)中学は、異世界「泡の中央界」に飛ばされた。それは白き常魔の国テルテ・ウィタスと北国との争いの中で行なわれた、「ダ・イスォウド(主たる者の力)」争奪戦に巻き込まれたためであった。北国の軍勢の真っ只中に出現した九江州中学校舎は奇怪なモンスターの襲撃にさらされる。その混乱の中、百地王太はダイソード(ダ・イスォウド)の封印を解き学校を守ることに成功する。テルテ・ウィタスの魔法使い、ユーリナ・タ・カラから事情を聞いた百地王太、千導今夜ら九江州中学一行は元の世界に帰るためテルテ・ウィタスを目指す。掲載誌の変更などで、野に埋もれてしまった感のある作品だが、ちょっとでも興味を持ったら、是非とも手にとって欲しい。
August 12, 2007
コメント(3)
-
筑波研究学園都市の地下には。。。
先日調べ物をしているとこんな資料を発見した。これはその資料の一部である。。。。【地球の敗北が決定的となりつつあった某月某日、数種類の野生動物とともに獣戦機のデーターは日本の「つくば」の地下に建造されつつあった、対異星人の拠点「ZOO」に送り込まれた。。。】やっぱりあったんかい!あの下に秘密基地がw筑波研究学園都市(Tsukuba Science City)とは、約300に及ぶ研究機関・企業と約1万3千人の研究者(博士号取得者は約5千600人)を擁する世界有数の学術・研究都市であり、田園都市である。1960年代以降に開発された。地理的な範囲は行政的に茨城県つくば市と同じと定義され、「研究学園地区(約2,700ha)」と「周辺開発地区」に大きく分けられる。更に新世紀エヴァンゲリオン 戦略自衛隊技術研究所技術研究本部 FNS地球特捜隊ダイバスター ダイバスター秘密研究所 ゴジラVSメカゴジラ G対策センター などが、あるんではないかといわれているw。。。『超獣機神ダンクーガBURN』は、長谷川裕一のマンガ作品である。1997年から1998年にかけて月刊少年エース増刊・エースダッシュに連載された。超獣機神ダンクーガのリメイクまたはスピンオフ的な作品。もともとは超獣機神ダンクーガのリメイク企画の一環としてのコミカライズであったが、アニメ企画が流れたためにマンガのみが連載された。超獣機神ダンクーガとは多少共通点があるものの、TVの続編にあたる2007年放送のアニメ『獣装機攻ダンクーガノヴァ』とも違う。ダンクーガのデザインも、大まかな部分だけが流用されていて、細部はオリジナルですので、アニメのマンガ化を期待されている方はご注意を。 舞台は21世紀初頭、フォアと呼ばれる侵略者により侵略された。人類はすべての権利を奪われ、獣のように、物のように扱われていた。しかし、人類はそのままで終わるはずはなかった。地下にもぐり、反撃の機会をうかがい続けて13年、侵略者のテクノロジーを解析し、対抗しえる武器「ダンクーガ」が開発された。ダンクーガを駆り、獣戦機隊”BURN”と呼ばれる風間翔児、富士野双葉、炎条寺ユーリ、深森静香の4人がフォアに向かって戦いを挑む。シリアスな展開のハードSFロボットマンガです。主人公の風間翔児も、長谷川作品にしてはめずらしくクールですが、内面は実に人間くさいキャラクターです。4人のメンバーの人間関係がからむエピソードや、獣の特性を持つ獣戦機ならではのエピソードなどを盛り込みながら、フォアの正体、人類の開放に向かってストーリーが進んでいきます。さらに翔児とフォアの前線指令であるシャピロとのからみでは、長谷川節が炸裂する作品です。
August 11, 2007
コメント(2)
-
星雲賞受賞作品
ある日、未来はやってくる!!フツーの高校生・西郷大樹は突然、奇妙な連中に襲われる。混乱する大樹に仲間になれと迫る彼らは「時空神の目(クロノアイズ)」と名乗った──!平凡な高校生だった少年、西郷大樹は「知力、体力に優れているが、死んでも歴史に大きな影響がない」という理由でクロノアイズ(いわゆるタイムパトロール)にスカウトされた。しかしそれは超過去から遠未来へ、地球から銀河の反対側へと時空を越える大冒険と巨大な陰謀の始まりだった! タイムパラドックス、巨大ロボット、アンドロイド、人工生命、恐竜・・・ああ、並べ始めたらきりがなく、これだけ盛り込んでおきながら理屈っぽくないのはまさしくSF要素てんこ盛りのマンガ物語はタイムパトロールの隊員にされてしまう少年の話。こう書いてしまうと素っ気もないが、しかし長谷川裕一の少女好きは、間違いないw実に「勇ましく戦う女の子」をかなり好んで描きます。やたらと女の子が登場する。それもボーイッシュなのが多い。実に長谷川らしい。タイムパトロールというと、孤独なスパイものの様な話が多いが、クロノアイズはそういった作品群とは正反対の多人数でしかも”あっけらかん”としたお話にまとまっているしかし能天気ではない。ちゃんとSFしているのです。例えば、「タイムパラドクス」と「パラレルワールド論」も この作品ではきっちり解釈をしてあるところを大いに評価したい。星雲賞(せいうんしょう)は、前年度中に発表もしくは完結したSF作品を対象として、部門ごとに一番に選ばれた作品に贈られる作品で「クロノアイズ」は受賞している。
August 10, 2007
コメント(2)
-
お祭り騒ぎ?!で後日談?!
「マップス」「逆襲のギガンティス」「轟世剣ダイ・ソード」「機動戦士クロスボーン・ガンダム」などのマンガ作品や東映特撮作品のSF考証本「すごい科学で守ります!」など幅広く活躍の長谷川裕一。自作品のクロスオーバーのみでスーパーロボット大戦風のストーリーを構築するという手法を用いた、各作品の後日談。名づけて「長谷川裕一ひとりスーパーロボット大戦 大外伝」という同人誌です。事の起こりは自身の同人誌の後書きでも書いてあるが2000年の夏にスーパーロボット大戦αをプレイ中に「いいなー、こういうマンガ描きたいな。。。」と思ったらしく、で、考えた末、自分独りで出来ることに気が付いたらしいwこの本を出すまでに色々とロボットの出てくるマンガを描いてきて、たまには思いっきりハメを外して自作オールスター競演をやりたくなったらしい。更に【クロノアイズ】と【ダイソード】に出てくる「金子」というキャラクターが同一人物かと読者からの問いかけに端を発し、(実は使いまわしらしだったらしい。。。が、最近は【マップスネクストシート】で5人兄弟の二男が登場している(未確認))同じキャラにしてしまえと、成ったらしい。ただ【マップス】を出すかは結構悩んだらしい。戦力バランスを崩しかねないほど強力だし(星の1つや2つ平気で壊せる破壊力あるし。。。w)で、悩んだあげく母艦扱いで参戦を決めたらしい(感覚で言うと「マクロス」や「アイアンギアー」の様になぐるける出来る方の母艦の設定らしい)。恐らく探しても見つからないと思いますが、もし発見したら、(長谷川裕一ファンで)読んだことの無いならば買いです!!
August 7, 2007
コメント(2)
-
映像化してないのでサンライズ的には非公式w
原作:富野由悠季 マンガ:長谷川裕一(長谷川氏色が強い作品だが、富野氏もきちんと原作を書いている)月刊少年エースの創刊号から連載されていた作品。劇場公開されたガンダムF91から10年後の世界を描いたストーリー。F91の主人公シーブックとセシリーが作った組織(宇宙海賊)に主人公トビアが成り行きで加わり木星帝国と戦っていく。ちなみにF91は続編がTVシリーズで放送されるはずだったが、劇場版の興行成績が振るわず、企画が凍結されたために劇場版で張られた伏線を用いた展開になっている。そう、まさにF91とビクトリーをつなぐ限りなくオフィシャルに近い外伝な訳です!作中にはビクトリーに繋がるキャラクターもちょろちょろ出てきます。ファースト(79)に引き続き、Z(87)ZZ(88)と来て、逆襲(93)。F91(123)そしてV(153)と続いていく宇宙世紀シリーズですが、F91とVをつなぐ一部分としてクロスボーン(133)は書かれたわけです。F91が元々TVシリーズにするはずで多設定であったため、そこから生まれたクロスボーンです。しかし、絵が違うためF91が好きな人には勧めることは出来ません。が、クロスボーン単体で見た場合少しZZ気味ですが良質なものには仕上がっていると言えます。これも正史でもいいかもと思えます。富野節の効いた重厚さをもちながら、実にエンターテイメント的で燃える展開のストーリーです!特に、この作品の持つニュータイプに対する意識は興味深い。ファーストから逆シャアまで続く感覚からすると、目からウロコ。特にアニメと違うマンガという表現を使ったガンダムの中では最高傑作でしょう クロスボーンガンダムの後日談で冗談めいた内容が多々あり、コピーされたアムロの脳を搭載したMSと戦う話などが出てきますので、生真面目なガンダムファンの方にはオススメ出来ません(笑)。また、本編とも毛色が違う感じです。数あるアナザーガンダムワールドの中でも、満足させてくれるものの一つです。ちゃんと計算し、策も立て、その上、全力全開で強敵に挑む。だからこそ、展開そのものは同じであっても新鮮に楽しめ、そして納得できるのだと、真に、名人芸とはこういうものである。燃える台詞が出てくるので、これは本当にガンダムか?と疑ってしまいます。その一例。「お前の取るべき道は二つある。一つは何も聞かずに地球に帰り。。。全てを忘れ、貝のように口をつぐむこと。そして、もう一つは。。。我らと共に。。。真実に立ち向かうことだ」お奨めです!!!
August 6, 2007
コメント(2)
-
V、V、V、ビクトリー♪
『超電磁大戦ビクトリーファイブ』は、長谷川裕一のマンガ作品である。大の『スーパーロボット大戦シリーズ』のファンである作者が、「誰も描かないから、自分で描いちゃえ」とばかりにいわゆる超電磁シリーズをもとに描き上げたクロスオーバー作品である。スーパーロボットマガジンvol.1(2001年7月)- vol.13(2003年7月)まで連載。マニアの間では、ガルーダ・ハイネル復活編の第2部の方が人気のようですが、改めて見ると第1部もなかなかの傑作です。 ロボットアニメの傑作エピソードには欠かせない黄金パターンを男(とオタク)の熱き血潮流るる長谷川氏、何もかもいい意味での予定調和!あざとさなど微塵も感じさせず、『様式美』にまで高めた王道パターンで、見る物を大いに『乗せて』くれます。 敵役も、悲しくも気高ささえ感じさせる生き様、死に様は、かつての長浜美形悪役を彷彿とさせてくれます。コンバトラーV、ボルテスV、そしてダイモス。それぞれのストーリーと設定をうまく絡めた基本設定を作り上げます。ボアザン、キャンベル、バーム、そして地球という4つの文明が遭遇し、その出会いから産まれる様々な出来事をうまくまとめていきます。「異文化コミュニケーション(笑)」 じゃなくって「異文化間の愛」です。不幸な出会いを、不幸で終わらせないのが長谷川節!王族、貴族の血筋、末裔たちが、呪われた血との戦いを見せてくれます。 やっぱ長谷川裕一にハズレ無し!? 掲載紙が休刊し、『知る人ぞ知る』で埋もれさせてしまうには惜しい傑作です。
August 5, 2007
コメント(0)
-
この星の明日の為に。。。、俺達は闘う!!!
『スーパーロボット大戦α THE STORY』マガジンZで短期集中連載されたマンガ。恐竜帝国の攻撃で危機におちいる連邦軍。しかもマジンガーZが乗っ取られてしまい、マジンガーVSゲッターロボの戦いが。。。展開としては、ロボット美少女の三姉妹が光子力研究所を襲う、永井豪版マジンガーでも出てくるエピソードを下敷きにしていて、迫力ある展開になっている。『スーパーロボット大戦α』では既に滅びてしまっている恐竜帝国が、続編の『α外伝』で復活するのを踏まえ、『α』以前の恐竜帝国壊滅を描いたストーリー。ということになっているけど、ゲームをプレイしていない人には何が何やらようわからん(苦笑)。いや、色々なロボットを一同に会してという基本コンセプトは好きなんだけど、何でも集めりゃいいってもんじゃない、組み合わせを考えて欲しいというわけで。。。でこのコミックは当然ゲームを前提としているのだから背景としてMSなんかもいるんだけど、メインとなるのはマジンガーZとゲッターロボの激突だから、これは違和感なしで燃える展開である。しかも原作からガミアQ3や、ミリオンβ・ダイオンγ・バイオンθの「マジンガー軍団」まで引っ張ってきながら、単なるお遊びでなくしっかと活かしているあたりが作者の力量だなぁ正直言っちゃえば『真ゲッターロボVSネオゲッターロボ』なんかよりも、こういうアニメを見たかったよなーと思ったりして(笑)
August 4, 2007
コメント(2)
-
上を見る者。。。その向こうにある星を見る者。。。
機動戦士ガンダムSEED C.E.73-STARGAZER- 原作:矢立肇・富野由悠季 マンガ:守屋直樹月刊ガンダムエースで2007年1月号~5月号にかけて連載されていた守屋直樹氏によるスターゲイザーのコミカライズが単行本化。単行本化にあたって、本編では描かれていないスウェン、セレーネ、ソルのその後のオリジナルストーリーを新規描き下ろし掲載 ガンダムSEED STARGAZERのマンガ版。 展開自体はほぼアニメと一緒。物語は、ユニウスセブン落下直後からの物語です。 本編のDESTINYでは語られなかったサイドストーリーですね。ただ、細かい描写がアニメよりも増えて(1話のジンに乗っているのが子供だと分かるシーンの描写、スウェンの台詞の追加、スウェン、ミューディ、シャムスの三人の関係についての描写など)、何よりもアニメでは語られなかった、後日談が語られるのは大きい(ページ数で言えばオマケ程度のものだが)ただ、マンガ版がアニメよりも面白いかというと微妙な所だ。追加シーンが無駄とは言わないが、本編を追うに当たって必ずしも重要なシーンではないということ。そして、最後のエピローグは、アニメのラストで満足している人には、余計な話と感じるかもしれない。また戦闘シーンについてはアニメの方が面白く感じた。 良い所、悪い所と言ったが、アニメの最後のシーンでは納得いかず、ちゃんと白黒はっきりさせたい人は、この本を購入されてはいかがだろうか。少なくともあなたの得たい答えは得られるはずだ。 一つ言える事は、MS1機落とすのにそこまでしなくても。。。っと思う。最後に、このマンガのカバーを外すと、オマケの1コマが見られるただそれを見るのは、マンガを読み終わってからにするのを勧めておく。たくさん死んでいく兵士がいるのは戦争としては当たり前です。それほど、戦争が厳しいものだと何故分からないのか? 「SEED&D」はそれを無視した作品だったから「戦争」を題材にしているのなら「人を殺してかっこいい」なんて思わせちゃいけないなと思う。内容は短編でしたが、私的には良い作品だったと思います。
August 3, 2007
コメント(0)
全15件 (15件中 1-15件目)
1