2007年08月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

とてつもない日本
安倍さんの人気が低迷する中、 麻生さんの人気は、じわじわ上昇しつつあるようです。 安倍さんの『美しい国へ』を読んだので、 一緒に麻生さんの本も購入して、読んでみました。 文章として、一冊の本として、 そして、政治家が書いた書物として、 その完成度においては、安倍さんの『美しい国へ』の圧勝。 特に、前半部分において、麻生さんのは「読みづらい……」と感じました。しかし、読み進めるに連れて、そのちょっと癖のある文体にも慣れ、時折見られる表記間違い(「ソビエト社会主義連邦共和国 」p.89)等にも目をつむり、逆に、そこに描かれている内容の斬新さに、引き込まれていったのです。『美しい国へ』にはない視点、そして新しい感覚が、大いに感じられました。日本という国が、外国にどう受け止められているのか、日本という国が、アジアで、そして世界でどのようなことが出来るのか、そんなことを改めて考えさせられる内容でした。さすがに、現役外務大臣の書いたものだけあって、説得力がある。特に、麻生さんの得意分野(?)である「マンガ」についての記述は、とても面白い。「ジャパニメーション」「Jポップ」「Jファッション」の広まりなどは、なかなか、日本にいて実感できないものだけに(TVや新聞等のニュースでも、あまり採りあげられない)、興味深かった。また、「高齢化」や「格差感」についての記述も、多面的・多角的に考察されたもので、ともすれば、一面的になりがちなマスコミ等の有り様・危うさを私たちに、しっかりと伝えてくれるものでした。それでも、やはり現役政治家ということの壁からか、最後の最後には、ちょっと「言い切れていない」まま終わっている感じがします。この「あやふや感」は、『美しい国へ』では、あまり感じなかったもの。安倍さんと麻生さんとの違いが、結構表れている気がしました。
2007.08.19
コメント(0)
-

美しい国へ
8月27日に、やっと内閣改造が行われるんだとか。 それにしても、参議院選での自民党惨敗後の安倍さんは、 本当にお気の毒なくらいの状況が続いています。 海外に出かけて気分一新、今度は良い人事になりますように! さて、本著が出版された時点では、安倍さんは、 小泉首相に負けず劣らずの、とっても人気のある若き官房長官。 拉致問題における活躍振りも、注目の的でした。 その人物が、自民党総裁選で勝利して、ついに総理大臣に。当時の内閣支持率は、非常に高く、そんな状況の中で、総理が、事ある毎に「美しい国」を連発したものだから、この本も、本当によく売れました。そして、およそ一年の月日が、流れ過ぎました。人生、一瞬先は闇ですね……。 ***祖父・岸信介さん、大叔父・佐藤栄作さんという二人の首相経験者、そして、中曽根政権で外務大臣を務めた父・安倍晋太郎さん。これら自民党の中核として活躍した人々に囲まれて育った彼が、彼らの意志を引き継いで、日米関係を重視しながら、憲法改正を目指すのは、当然の成り行きでしょう。また、「安保反対」声が日本中に響き渡る、強力な逆風の元、身の危険を感じる事態に追い込まれながらも、日米安保条約を自然成立させ、「私のやったことは歴史が判断してくれる」の一言を残した祖父の姿は、安倍晋三さんに、かなり大きな影響をもたらしているように思います。本著、第1章に見られる「千万人といえども吾ゆかん」とか、「たじろがず、批判を覚悟で臨む」などの言葉は、その最たるもので、今、現在の安倍さんの行動は、まさに、この言葉を体現したものでしょう。安倍さん、想像以上のスゴイ粘り腰です!しかしながら、岸さんの場合には、新安保条約の批准書交換の日に、混乱の責任をとる形で、総辞職しています。おじいちゃん以上に、孫は意志が固い「闘う政治家」ということか……。でも、おじいちゃんは、辞任直前に暴漢に襲われ、瀕死の重傷を負っている……。まぁ、今回の状況と、その時との状況とでは、かなりの違いがあるので、そんな余計な心配をしなくても、大丈夫かな? ***本著を読んで、安倍晋三という人物について感じたことは、基本路線としては納得できるし、その姿勢も評価できるということ。ただ、それを、より具体的に、形として実現していく際、周囲から、良い支援が得られていないのではないかということ。首相と言えども一人の人間。国家運営に関わる、全ての事柄について専門家というわけにはいかないし、自分一人の判断で、全て完璧にやりこなせるとも思えない。そう言う意味で、自分の身近に誰を置き、力になってもらえるかは、かなり重要。安倍晋三さんの、現時点における最大の弱点は、やはり人事。国務大臣選任の失敗は、現在の苦境をつくり出す最大原因となってしまいました。また、教育再生会議のメンバー編成を見ても、同様のことが言えます。ひょっとして、安倍さん、本当は知らない・分かってないことが多すぎる?だから、ちゃんとした人を選ぶことが出来ない?それを、修正してくれる人が、周囲に誰もいないの?それとも、「我が道を行く」とばかり、誰の忠言も受け入れないとか?そう言う意味でも、8月27日の内閣改造は、見物です。
2007.08.19
コメント(0)
-
個人優先のイチロー チーム優先の松井
プレジデント 2007.9.3号のテーマは 知っている人だけが得をする お金の新常識60さて、今回は、特集ページに辿り着くまでに、ちょっと引っかかる記事が。それは、松井秀喜の「大リーグ日記」。この連載記事も、今回で100回目を迎えました。この連載記事、プレジデントのページをめくり始めると、最初の方に掲載されているものなので、野球好きの私は、とりあえずは、ここはちゃんと読んで先に進んでいくのですが、たいてい、そんなに引っかかることもなく、次のコーナーへと向かうのです。ところが、今回はちょっと違った。私としては、個人的に、かなり引っかかってしまった。それは、次の部分 イチローにはワールドチャンピオンになることよりも大切なことがあったのか。 落胆したのは、大型契約を結んだ際のイチローのコメントであった。 「平均年俸500万円だとしたら、 弥生時代からプレイしないと達成できない数字なので、 その評価ってすごいと思うんですよ」 もし松井秀喜がイチローと同様の契約を結んでも、 こうしたコメントを口にすることはないだろう。以下、松井の「チーム優先」の考え方を賛美し、それは、松井が何度も優勝の美酒を味わい、勝つことの喜びを知り尽くしているから。それに比べてイチローは、オリックス、マリナーズと新興チームで、自分の存在をアピールすることを生きがいにしてきたので……まぁ、こういう論調です。松井秀喜の「大リーグ日記」というタイトルで、会社組織で生き抜いていく人たちをターゲットに書かれた記事だから、まぁ、こういう事になるのかも知れませんが、この文を書いた人って、本当に、イチローのこと、ちゃんと見ているのか?と思ってしまったのは、私だけでしょうか? ***オリックス時代には、阪神大震災の起こった1995年にリーグ優勝。翌年には、長嶋巨人を4勝1敗で倒し、日本一に上り詰めている。また、マリナーズにおいても、入団した2001年には、アメリカンリーグ西地区で優勝している。確かに、オリックスは、日本一になった翌年に3位、それ以後はBクラスに低迷。マリナーズも、2002、2003年は2年連続で93勝をしながら、プレーオフ進出は逃し、それ以後低迷(今年は、ちょっと頑張っていて西地区2位につけている)というように、常に勝ち続けているチームではなかった。しかし、WBCにおける、日本代表チームでの活躍を見ても分かるように、彼のチームに対する献身ぶりや、勝利への執念は、並々ならぬものがあると感じます。イチローが個人を優先し、チームを軽視するような選手とは、とても思えないのですが、皆さんは、いかがお考えですか?
2007.08.11
コメント(0)
-
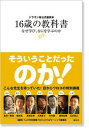
16歳の教科書
何といっても、講師陣の豪華さには目を見張るものがある。 私などは、それだけで、この本を買ってしまった感すらある。 そして、本著を読み終えた今、思うことは、 これだけのメンバーの文章が、ずらっと並べらると、とってもスゴイということ。 まず、「国語」は、金田一秀穂さん。 祖父は、金田一京助さん、父は、金田一春彦さん。 この日本語学会権威の二人の血を引く、まさにエリート中のエリート。 でも、文章を読むと、 祖父や父の偉大さゆえのプレッシャーに押しつぶされることなく、逆に、新しい時代感覚を確実に反映した、独自の路線を歩まれていることに感心させられる。 そして、「理科」は、ベストセラー『99.9%は仮説』の著者、竹内薫さん。 ほんとうの意味での型破りになるためには、 まず『型』を身につける必要があるんです。この言葉の意味は、深くて重い。「自分らしさ」「個性」を前面に押し出そうと、躍起になっている若者たちに、この言葉を、そっと贈りたい。続いて「社会」は、東京都で、民間人初の公立中学校長になった藤原和博さん。私は、藤原さんの著作は『「ビミョーな未来」をどう生きるか』をはじめ、『人生の教科書〔よのなかのルール〕』『公立校の逆襲 いい学校をつくる!』『中学改造』と、何冊か読ませてもらったし、実際に講演会に出かけて、お話を聞かせて頂いたこともあるので、取り立てて目新しい部分はなかったものの、藤原さんについて、予備知識0(ゼロ)の人には、とても分かりやすく、納得できる内容にまとめられています。さらに、課外授業「心理(モチベーション向上術)」は、石井裕之さん。『なぜ、占い師は信用されるのか?』『一瞬で信じ込ませる話術 コールドリーディング』の著者として知られている人。「自分の得意分野をつくるには」の部分は、高校生だけでなく、社会人にとっても、示唆に富んでいるのでは?その他の部分を担当している方たちの文章も、それぞれに味があって面白い。逆に、高校生にとっては、それらの実践家の方たちの文章の方が、より具体的で、心に響くかも知れない。参考書ばかりでなく、時には、こういう類の本を読むことも、高校で学んでいく上で、たいへん意義のあることです。
2007.08.11
コメント(0)
-

鋼の錬金術師(17)
今巻は4話収録。 でも、お話としては、あんまり進展がなかったなぁ……。 *** 「第66話 雪の女王」では、 謎のホムンクルスが登場し、 アームストロング少将率いるブリッグズ兵たちとの戦闘を繰り広げる。 最後は、フリーズ。「第67話 この国のかたち」では、「完全な不死の軍団」の狙いが明らかに。ある目的のため、国はつくりあげられたのだった。レイブン中将とオリヴィエの駆け引きが見物。「弟68話 家族の肖像」は、またしても、昔の話に逆戻り。エドとアルが、まだ小さな子供の頃のお話で、父が、妻と息子たちを残し、家を出て行くシーン。話が現在進行形の所に戻ると、穴の中に化け物登場。「第69話 ブリッグズの礎」では、謎のホムンクルスのお仕事が判明。そして、駆け引きを終えたオリヴィエは、怒りの一撃を喰らわす!最後には、ウインリーまでもが、ブリッグズにやってきて……というところで、あっけなく終了……。 ***それにしても、『鋼練』って、本当にストーリー展開が、超スローで、1巻当たりの中身が、何かとっても薄いような気が、最近しています……。『ONE PIECE』と比べると、作品として持っている力の差が、全然、迫っていかないというか、離れていく一方のような気が……。期待していただけに、とっても残念。荒川さん、『獣神演武』の方で、お忙しのでしょうか?……。
2007.08.11
コメント(1)
-

一度も植民地になったことがない日本
著者のデュラン・れい子さんは、 女性初のコピーライターとして博報堂に入社し、活躍された方。 退社後、スウェーデン人と結婚し、芸術に関わる仕事を始める。 そして、現在、東京と南フランスを往復する生活を送っておられる。 この本が面白いのは、新聞や雑誌などでは、多分紹介されることはないであろう、 ごく普通の人たちの会話が満載で、そこから彼らの日本人観が伝わってくること。 もちろん、著者と、著者の直接関わる人たちとの会話が中心となるから、 芸術関係の仕事をしている人が多いし、人数もそう多いわけではない。また、外国に行って、外国人に囲まれながら過ごしていると、母国を思う心、つまり愛国心というのは、否が応でも高まるものらしい。デュランさんの記述や発言には、それが強く感じられるものが目立つ。櫻井よしこさんや藤原正彦さんの書物を読んで感じたことと、似ている。しかし、その部分を割り引いて読んでみても、この本に書かれていることは、なかなか興味深いし、新鮮。『世界の日本人ジョーク集』と共通する面白さがある。日本に住んでいると、「日本」と「アメリカ・ヨーロッパ」というふうになぜかアメリカとヨーロッパとは、一括りにしてしまいがちだが、実は、アメリカとヨーロッパとは、やはり別々の地域だし、そこに住む人たちの感覚や思いには、かなり違いがあるようだと、本著を読んで、改めて感じた。それどころか、同じヨーロッパの国同士でも、それぞれに感じていること、考えていること、腹の中で思っていることは違うらしい。アジアやアフリカといった、別の地域に住む人たちに対しては、ヨーロッパ人同士の、強烈な連帯感を示すものの、実は、それぞれの国同士の関係・思い・感情は複雑。かなりドロドロとしたものが、奥底には潜んでいる……。でも、そんなものを乗り越えて、ヨーロッパの人たちが、EUという組織を成立させていることは、正直スゴイと思う。日本人が「自分はアジア人だ」と認識できない、というような内容が、本著の中にも出てくるが、今後はそれを乗り越えていく必要が、大いにあると思う。ヨーロッパ人に出来ることだから、アジア人にもきっと出来るはず。
2007.08.11
コメント(0)
-

キミがこの本を買ったワケ
タイトルも表紙も、とっても良くできていて、 思わず、本屋さんで手にとって、中を覗いてみたくなりました。 最初の5ページは、たった1行ずつ、問いかけの文が書かれているだけ。 嫌でも、次々にページをめくってしまう…… そこに書かれているのは、 まさに今、この本を手にしている自分自身のことじゃないですか! 目次に並んでいるタイトルも、興味を引くものばかり。 本当に上手いなぁ……、そして、買ってしまいました。 ものを売り込もうとするならば、 まずは、相手のガードを、ちょっとだけ下げさせること。 いったんガードが下がってしまえば、次は、とっても簡単! これが、セールスマンやコンビニの商品陳列に見られるテクニック。なるほど、これは納得です。 人は、買うものを決めずに店に行くことがほとんど。 それじゃあ、なぜ、お店に立ち寄るのかというと、新しいものを求めて。う~ん、これは、私にはあまり当てはまらないかも……。でも、ネットで、色んなサイトをあちこち見て回る理由は、まさに、これですね!新情報に新商品、探しまくっています! 一番手よりも、二番手や三番手、 主役よりも、ちょっと脇で光っているポジションが好き。これは、納得できる部分が大いにあります。私のこれまで熱中したものを振り返ると、まさにコレ!でも、公衆トイレで、どの場所のものを選ぶかは、違うなぁ……。しかし、エレベーターのポジショニングは、思わず納得!こんな感じで、大いに納得の部分もあれば、私は、ちょっと違うなぁ……という部分もありました。でも、第2章の広告の話は、文句なしに面白い!第3章の話は、人間の行動やその奥に潜む心理を的確についています。第4章の話には、著者との間に、ゼネレーションギャップを感じる部分がありました。最初、タイトルを見た時、広告や流通の話が主の本だろうな、と思っていたけれど、社会学・行動学・心理学的な内容を扱った本でした。まぁ、何にしても面白い本で、あっという間に読んでしまいました。
2007.08.11
コメント(0)
-

千里眼の教室
ちょっとさぼっているうちに、 「千里眼」シリーズで未読のものが、2冊もたまってしまったので、 いつもの本屋さんに出かけて、まとめて購入。 まずは、『千里眼の教室』の方から読み始めました。 美由紀さん、オープニングから、またまた派手に暴れまくってくれますが、 度々、このパターンだと、ちょっと人間性を疑いたくなる……。 地下街をF1マシンで追い回したり、 自衛隊基地に強行突入して、F15Jをかっぱらって乗り回して、 本当に何のお咎めも無しで、その後自由に動き回れるの?というか、そんな人間に、それに直接関わる仕事の続行を、誰が認める?また、独立国を宣言した高校が、自分たちの独力で収入を獲得し、インターネットを駆使して、様々な商品を購入することは、可能だと思いますが、それの搬入を、周囲の警察等が、黙って見過ごすとは、とてもとても……。ちょっとばかり、リアリティに欠けすぎているような気が、今回はしました。まぁ、最後まで読めば、今回のお話のとっかかりそのものが、かなり突飛な状況を想定したものだと分かりますから、これぐらい、何ていうことはないのかも知れません。松岡さんの、これまでの作品に比べると、残念ながら、ちょっと……でした。いじめや自殺、社会格差などの最近の話題に、酸素欠乏症の治療、いつものように、様々な事柄を鮮やかに交えて、ストーリーは展開しているのですが、出版のペースが早いためか、練度がやや低下しているような気がしました。
2007.08.11
コメント(0)
-

オーケストラ楽器別人間学
『のだめカンタービレ』コミックス巻末、 「取材協力ありがとうございました!」の欄に登場する 茂木大輔さん(NHK交響楽団主席オーボエ奏者)が、この本の著者。 今、見直すと、そのことは、ちゃんとコミックスにも書いてありました。 でも、私は、そんなことに全く気がつかないままに、本書を購入していました。 そして、本著を読み終えて、しばらく経った頃、本屋さんに立ち寄った時、 同じ本が、やけにたくさん平積みしてあり、その帯に「のだめ」が、描かれてるのを見て、 「あ~、そう言えば、どこかで見た名前だと思った。」と理解した次第。本著は、プロの楽器演奏者を、著者が楽団の中で観察し、そこから得られた情報を、綿密に分析して書かれたもの。まぁ、学問的には、かなりいい加減なもののようですが、書かれてある内容は、ズバリ的を得たものと感じます。それは、アマチュアの楽器演奏者ですら、その担当楽器と、演奏者の性格との間には、相当な関連性があると、私自身も強く感じていたからです。本当に、それぞれのパートの性格ってあるんですよね。その、パート別性格がつくられていく要因を、それぞれの楽器の、楽曲における役割や、その楽器の醸し出す音質・音域・旋律等を分析し、著者自身の独断や、周囲の声も取り込みながら書かれたのが本著。その結果、楽器演奏に携わっている者なら、誰でもが納得できる内容のものに仕上がっています。「この有名人なら、こんな楽器を担当しそう」という部分は、とても興味深く、「自分ならこれを演奏させたい」とか、色々考えながら読んでました。ただ、『文庫版特別研究』の部分は、突然、化学・化学していたり(苦手です……)、かなりマニアックな内容だったりしたので、なかなかついていけなかったです……。
2007.08.06
コメント(0)
-

子供なんかにナメられたらアカン!
著者の長田さんは、とてもエネルギッシュでパワフルな方。 彼女が行う「メンタルケア」によって、 不登校や引きこもり、非行に陥った子どもたちが、 本当に見事に変わっていく姿は、読んでいて実に痛快。 その変化の原動力となっているのは、 手の施しようがないと思わるような超難題に対しても、 長田さん自身が、いつも、全精力を傾けて、 全身でぶつかっていく姿勢。そのプロ意識と気迫には、圧倒されると共に、大いに驚かされてしまいました。まぁ、それぐらいのものを持ち合わせていなければ、あの子どもたちを、変えることは出来なかったでしょう。しかし、長田さんは、闇雲に動いているわけでは決してありません。そこには、きちんとした計算と先の見通しがありました。それは、「親が変わらないと、子供は変わらない」ことをしっかり押さえていることと、かつて似たような問題を抱え、それを乗り越えた人を帯同して行くこと。「親がその気にならないうちは、自分からは動かない」最初のいくつかの事例は、そのことを裏付ける好例。どんなに優れた教育者でも、その人だけで出来ることには限界があります。ましてや、子供にとって一番影響力のある親の協力を得られない時には……やっぱり、どうにもならない……。また、『死にゆく者からの言葉』を書かれた鈴木さんも、様々な問題にぶつかっている人を帯同して、いろんな人に会いに出かけていました。それは、問題にぶつかっている人に、色んな人に出会う中で気付きを与え、考えや行動に変化をもたらそうというものでした。やはり、自分にとって身近に感じられる存在からの働きかけは、大きいということでしょう。
2007.08.06
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- 山と食欲と私 エクストリーマーズ …
- (2025-11-21 12:38:54)
-
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 『最後の恋も2度目なら』
- (2025-11-23 00:00:13)
-
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去
- (2025-04-08 00:00:18)
-







