-
1

「紅芯大根の煮物」
紅芯(こうしん)大根は、名前のとおり実の中心部が赤い大根です。普通の大根、と言うとおかしいですが、スーパーでよく見かける青首大根が細長いのに対して、紅芯大根は球形に近く、上半分の皮は青首大根と同じく緑色で、下半分が白いです。青首大根に比べて皮が硬いのは赤かぶのようですが、生で食べても大根だきのように煮ても、かぶとは違って実の組織が緻密ではないということが判ります。今回は関東煮きのように、ちくわと一緒に煮いてみました。以前も煮汁が赤くなることがあったので、もしやと思っていましたが、案の定ちくわが赤く染まりました。赤と言っても、ビーツを使ったボルシチや飛騨の赤かぶ漬けのような真っ赤ではなく、赤紫に近い色合いです。もしかして、煮汁の酸性度で赤くなったり青くなったりするのかも、と思いましたが、酢を垂らすなどの実験はしませんでした。でも、天然色素ですから、それなりの栄養はあるのでしょう。近郊農家が作っている野菜ですが、思わぬ出会いでした。
2024年03月11日
閲覧総数 1299
-
2

「かつお菜」
かつお菜というのは、下の写真でお判りのように、とても大きな菜っぱです。今回、福岡・天神のスーパーで買ってきたものは、長さが45cmありました。寒くなって旬を迎え、「一の市」というセールに出ていましたが、3枚で158円は、地元の人も「安い」と言います。かつお菜は、博多のぶり雑煮には欠かせません。しっかりとした軸から、かつおのような?いいだしが出ると言われますが、青々としていて大きく育つのが、縁起物として使われる理由でしょう。ふつうは生や漬け物では食べず、繊維に直角に細く刻んで、煮物や炒め物にします。きょうは葉っぱ2枚を、細く切った薄揚げ2枚分と一緒に煮浸しにしました。軸は、白菜やチンゲンサイよりもずっと堅いです。ちくちくした突起もあります。これを1cm幅ぐらいに刻み、大量になったので中華鍋でまず油で炒めましたが、青菜のさだめとて、かさはかなり減りました。そこへ薄揚げを加え、アゴだしと酒、醤油で調味して、しばらく煮付けてから火を止めました。そのまま冷まして、味を含ませてから食べましたが、まったく煮崩れることなく、軸は「堅い」まま。でも、これが「硬くはない」のです。サクッとした不思議な食感で、こんな菜っぱは初めて食べました。青い葉や揚げは、まあ普通ですが…。4人で葉っぱ2枚は、充分に食べごたえがありましたが、ほんとうに軸のうまみを味わいました。こんな美味しいもの、九州でしか手に入らないのが残念です。大阪には九州人も多いですし、出回ればいいのにと思いますが。
2012年12月02日
閲覧総数 176
-
3

「さわらのあらの塩焼き」
買い物に行ったら売り場の隅々まで見て回りますが、特に魚売り場を見るのが好きで、切り身のパックが値引きになっていたり、あら扱いのかつおのたたきが出ていたりすると、すぐにパクッと飛び付きます(^O^;)。今回は、さわらのあらを買いました。以前に、はまちのあらの塩焼きや、ぶりのあらの塩焼きを作ったことがありますし、あらを使った鮭の南蛮漬けもときどき作ります。さわらも南蛮漬けで良かったんですが、違う食べ方をしようと思い、塩を振って塩焼きにしました。さごしの塩焼きと同様、さわらのあらでも美味しいです。
2019年09月09日
閲覧総数 3056
-
4

「豚肉とこぶ高菜の炒め物」
もう春先のことで、だいぶ前になりますが、高菜の一種のこぶ高菜を買って、木綿豆腐と炒めた「こぶ高菜のけんちゃん」などにして食べておりました。その頃に作ったものですが、ここで書いておかないと書きそびれるので、紹介する次第です。とはいえ、何てことない豚肉との炒め物です。こぶ高菜は繊維が硬いので、まず軸と葉に分け、軸は小口切りか斜めそぎ切りにします。葉はざくざくと刻みます。これに合わせて、薄切りの豚肉も細長く切っておきます。中華鍋に切った豚肉を置き、酒、しょうゆ、中華だしの素、サラダ油を加えて混ぜます。点火して中火にし、煎るように炒めます。いったん出た水分がなくなりかけたら、刻んだこぶ高菜を加え、軸に火が通るまで炒め合わせます。これで充分に美味しい炒め物のできあがりですが、水溶き片栗粉で軽くとろみをつけても食べやすくなるでしょう。わたしの作り方だと、最初に豚肉に混ぜるしょうゆの量で最終的な味付け(塩分)が決まりますので、ご注意ください。
2022年04月29日
閲覧総数 929
-
5

「錦糸卵」
バラずしの飾りなどに使う、細切りの薄焼き卵です。上手に焼いて丁寧に細く切れば、綺麗に仕上がるのでしょうが、ここではちょっとズルい方法をご紹介します。ただし、わたし自身もこの作り方に完全に納得しているわけではありません。料理人の作るホンマモンの錦糸卵は、もっとふわふわして美味しいのだろうと思いつつ、アマチュアはアマチュアなりに工夫を重ねる毎日です。材料:小麦粉大さじ1~2杯、粉と同量かやや多めの水、卵1コ、塩少々、油。作り方:1)小麦粉に水を少しずつ加えて混ぜる。てんぷらの衣よりややゆる めに。2)よく溶けたら卵を加え、よく混ぜて、お好みで塩で調味する。 3)薄く油を引いたフライパンを熱し、煙が出たら卵液を少なめに流し、 弱めの中火で、フライパンを傾けて薄く広げる。4)あちこち膨らんで、 端がチリチリしてきたら、箸などで裏返す(意外と丈夫です)。5)裏を 焼くときは焦がさないように。6)まな板に取り、冷めてから細く切る。卵100%の「薄焼き卵」から小麦粉100%の「お好み焼きの台?」まで、その中間のどのへんまでが「卵焼き」と言えるのか。確かに、卵が多いほど黄色く作れます。また、卵100%だと切るときにボロボロになったりしますが、小麦粉を入れると切りやすく、切り口も滑らかに仕上がります。小麦粉は「そんなにたくさん粉を使うのか」と思うぐらい使っても、細切りすればちゃんと錦糸卵に見えます。なお、手順の中で、粉に「水を混ぜる」のをお忘れなく。水に「粉を入れる」と溶け残りができますので、気をつけてください。
2005年05月19日
閲覧総数 1040
-
6

「ジャンボししとう」
先日作った「焼きししとう」は、実の薄さと、それによる食感が特徴かと思います。今回、スーパーでジャンボししとうというのが出ていたので、買って食べてみましたが、わりあい実が肉厚で、ピーマンに近い食感でした。ただし、3本のうち1本は辛かったので、やはりピーマンではないのですね。なり柄のすぐそばにくびれがある万願寺とうがらしとも違いますが、刻んで炒め物に入れたり、空煎りしてしょうゆとかつおぶしを掛けたりして、いただきました。
2015年08月02日
閲覧総数 70
-
7

「洋酒チョコレート」
なんだか、わたしの中では懐かしい響きさえします。もう今や、ウイスキーやブランデーなどをひっくるめた「洋酒」という言葉を、あまり聞かなくなりました。でも、わたしの思い出にあるのは、小学生のころ、こづかいを握りしめて駄菓子屋でいろいろ迷って買ったものの中で、洋酒びんの形をした、ほんのふた口程度のチョコレートの中に、液状の酒?が詰めてあり、ウイスキーなら赤とかいうように、酒の種類によって違う色の銀紙で包んであったものです。メーカーは忘れましたが、洋酒チョコレートにはブランデーとかラムとか種類がいくつかあり、たしかにいくつか食べ比べると多少は違うかな、という程度の当時の味覚でした。学校の社会見学で行ったビール工場で酔ってしまったことがありますが、洋酒チョコレートで酔わなかったことからして、酒への耐性があったものと思われます(^_^;)。当時は「大人の味」というわくわくした気分で食べていましたが、今ならどうでしょう。別々に味わいたい、などとぜいたくなことを思うでしょうか。最近は身近にないので、よく分かりませんが。砂糖菓子の中に洋酒を詰めたウイスキーボンボンというのがあり、洋酒チョコレートはこれの発展形かもしれません。今では洋酒に限らず、日本酒や焼酎を使ったボンボンもあるそうです。もともと、チョコレートはウイスキーなどに相性の良いアテですから、洋酒チョコレートが作り出されたのは、必然と言えるかもしれません。14日はセント・バレンタイン・デー。トリュフや生チョコレートが全盛の昨今ですが、つい当時30円程度だったお菓子を思い出しました。
2008年02月13日
閲覧総数 4
-
8

「屠蘇」
おとそは、大人にとって正月の楽しみのひとつかもしれませんが、昨今は飲酒運転取り締まりが強化され、朝のお祝いでいただくのが、はばかられるようになってきました。わが家では、正月3が日の祝いの食事のときにいただくお酒(清酒)を「おとそ」と呼んでいましたが、正式には日本酒ではなくみりんを使ったハーブ酒です。みりんに、屠蘇延命散という調合された粉を袋に入れて浸し、成分を溶かし出して飲みます。厄払いの効能があるお酒なのだそうです。屠蘇延命散は、山椒やシナモン、陳皮(干したみかんの皮)などが入っています。バンショー(ホットワイン)を作るときに、赤ワインに混ぜて煮出すための混合物にそっくりです。きっと体を温めるような成分が多く含まれているのでしょうね。バンショーも甘い香りがして飲みやすい飲み方ですが、屠蘇は、ベースがみりんですから、すでに甘いです。そこへ香りを添加することで、口当たりもよくなり、せいぜい飲み過ぎに気をつけて、ということになります。ただし、屠蘇散の成分が出すぎると、味がくどくなります。おとそを、わが家が普通のお酒で代用していたのは、父にはたぶん美味しくなかったからでしょう。先日、知り合いから良いお酒をいただきました(Cさん、ありがとうございます)。来年も元日と2日は、夫婦双方の実家に、年始あいさつに(子たちのお年玉をもらいに)行くため車を運転するので、朝はいただけませんが、帰宅した夕方以降に、1年の無事を祈って「おとそ」をいただこうと思います。
2008年12月25日
閲覧総数 11
-
9

「日照紅茶」
日照というのは、中国山東省にある市の名前です。中国にはいろんな種類のお茶がありますが、紅茶はそれほど有名ではありません。ただし、この日照紅茶というのは、高級茶なのだそうです。今回は中国のお土産としていただきました。袋には、竜眼やライチの香りがするなどと書いてあります。どんな香り・味なのか楽しみですが、まずはふだん飲むほかの紅茶と同じように淹れてみました。ポットのお湯を鍋に入れ、くみたての水を少し加えてから沸かします。くみたての水は、冷たいこともあって、空気が多く溶け込んでおり、沸かしたときに泡がいっぱい出て、茶葉からエキスが充分出るまで、葉を浮かしておく効果があるのかもしれません。さて、沸騰して大きな泡が立ってきたら、茶葉を投入して、火を止めます。茶葉の量は、小さじ軽く山盛り1杯が1人前の見当ですね。数分すると、浮いていた葉っぱが次第に沈み始めます。あらかた沈んだところで、全体を軽く混ぜ、茶こしでこして、各自のカップに注ぎます。水色(すいしょく)は明るいめの赤色です。香りは、ほのかに、いわゆる中国茶らしい香りと、やや甘い香りがしますが、ライチかどうかは解りませんでした。そして味は、適度な渋みとかすかな甘みがある、美味しい紅茶でした。何より驚いたのは、水分を吸って広がったあとの茶葉です。一般的なお茶の葉よりも縦に細長く、これは新芽に近いところだけで作っているお茶だからだ、ということなのだそうです。なるほど、これは触れ込みどおり、高級茶ですね。
2015年03月14日
閲覧総数 568
-
10

「大門素麺」
そうめんの産地は全国に多くありますが、富山県の大門(おおかど)素麺は形状が独特です。普通のそうめんは真っすぐな乾麺ですが、大門素麺は丸まっています。正確には、紙を両側から巻いたというか、eと9のしっぽ同士をつなげたような形で、350g分の麺なら、全体が縦横約12cm角、高さ約5cmのコンパクトな小包状になっています。茹でる際には、この丸まった麺の中央でバキッと2つに割り、湯に入れます。茹でれば普通の麺と変わりありません。富山平野もそうですが、砺波平野も水に恵まれた米どころです。きっと裏作として麦もよく穫れるのでしょう。加えて冬場に冷え込むのがそうめん作りには向いています。丸まった乾麺はユニークですが、イタリアのパスタでも、細手の麺は丸めてあるものがあります。かさばるのが難点としても、折れて粉々になりにくいという利点もあるのでしょう。食べた感じは奈良の三輪素麺ほど細くはないものの、その分コシが強く、もちもちして美味しいそうめんでした。大阪はきのう28日から急激に冷え込み、きょうはまだ9月なのに最高17度という異様な低温でした。27日のさわやかな運動会日和からは一転です。そのため5月にお土産として買い、長く置いてあった大門素麺も、冷やそうめんでいただく予定を変更し、きゅうきょ「にゅうめん(煮温麺=にうんめんの転と言われる)」にしました。硬めに茹でて水で締めた麺に熱い汁を張り、かまぼこ、ほうれんそう、しいたけの佃煮などの具を乗せました。体が、温まりました。
2008年09月29日
閲覧総数 176
-
11

「続・あられ(きりこ)」
いただいた草餅が硬くなったので、きりこにしてみようと思い、包丁で小さなさいの目に切りました。それをフライパンで、弱火でコロコロ煎っていましたが、生乾きだったためか、複数個が固まってしまいました。それでも、全体に火が通って軟らかくなり、表面が少しきつね色になったのを見て、しょうゆをじゅわっと回し掛け、全体に絡めてすぐに火を止めました。かりかりのあられにはなりませんでしたが、硬かった餅も、まずまず香ばしく食べられました。
2014年05月11日
閲覧総数 25
-
12

「さわらのあらの唐揚げ」
さわらやさごしのあらが安く売られていると、これは「買い」だと思ってよく買います。骨を除いて食べやすい大きさにし、小麦粉をまぶして油で揚げて酢じょうゆに漬けると、「さわらの南蛮漬け」や「さごしの南蛮漬け」ができます。ただし、南蛮漬けは作ったその日より、翌日以降になって、揚げた衣だけでなく魚の身にも酢がしみたほうが美味しいので、その日は食べません。だから、そんな日は南蛮漬けとは別に何か、魚の一品を用意する必要があります。とはいえ、家族にしてみると、昼間から魚を揚げる香ばしいにおいがするものですから、できたての南蛮漬けを食べたいという声も出ます。そこで、わずか数時間しか漬けていない南蛮漬けを、おかずにほんのわずか添えることもありますが、翌日以降に、ちゃんと漬かって、一緒に漬け込んだたまねぎなど野菜のうまみがしみた南蛮漬けを出すと、違いを分かってくれます。でも、家内などは「漬ける前の揚げただけの魚も香ばしそうで美味しそう」と言うのです。そこで、さわらのあらを買ったときに、南蛮漬けにはせず「揚げただけのさわら」をおかずにしました。料理名は「唐揚げ」としていますが、小麦粉をまぶして揚げただけで、塩もこしょうも何も振っていません。それでも魚自体の塩分と揚げた衣の香ばしさで、何も付けなくても美味しくいただけます。もちろん、マヨネーズやタルタルソースをかけてもいいです。衣のカリカリした食感が美味しいですが、冷めた後でも、電子レンジで軽く温めるといいでしょう。
2021年05月01日
閲覧総数 108
-
13

「寒餅」
寒餅(かんもち)というと、雪国などでかきもちを縄で縛り、何枚もつるして乾燥させたものを指す場合と、単に「寒の期間」に搗いた餅を指す場合があるようです。家内が気に入って生協でよく買うのは後者のほうで、写真にあるように、えび、黒豆入り、よもぎ、黒糖を搗き入れたものをセットにしたものもあります。ねこ(なまこ形の餅)を、厚さ約1cmに切った形をしています。小寒(寒の入り)から節分ぐらいまでしか売り場に並ばないようです。わたしは今までなじみがありませんでしたが、家内が毎冬買うこともあって、最近のおやつはこの寒餅を網で焼き、軽く膨れさせたものを食べることが多いです。ただし、赤、白、緑はいいのですが、茶色い黒糖入りは、どんなにこまめに返しても、たいてい網に一部がくっつき、焦げてしまいます。きのう、ふと思いついて、かたくり粉を取り粉として平たい面に薄くこすり付け、そして網で焼くと、いくら膨れても全くくっつかず、きつね色にまで焼けて大成功でした!
2014年02月16日
閲覧総数 459
-
-

- オトコの手料理
- 美味い鯛ラーメンの秘訣は。
- (2025-11-30 08:41:59)
-
-
-
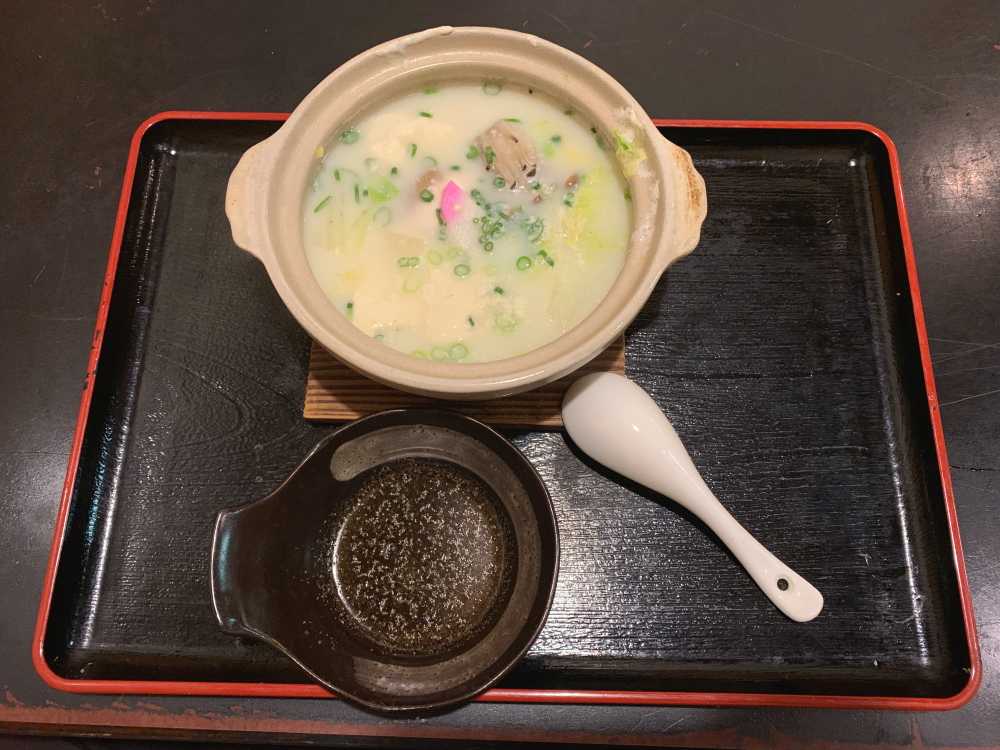
- ご当地グルメ
- 佐賀県嬉野市 和庵 武蔵 hanareの嬉…
- (2025-11-21 23:36:28)
-
-
-

- 今夜のばんごはん
- 酔いヨイタイム(*^o^)/\(^-^*)
- (2025-11-30 19:38:34)
-







