2024年12月の記事
全47件 (47件中 1-47件目)
1
-

2024年を振り返って、そして正月の準備を
今日は2024年の大晦日、今年1年を振り返ってみたい と。前半部分のキャプション・写真等はネット・「読売新聞オンライン」👈️リンクから転載させていただきました。読売新聞の2024年十大ニュースは下記のごとし と。【1位】石川・能登で震度7石川県能登地方を震源とするマグニチュード7・6の地震が1月1日午後4時10分、発生した。輪島市、志賀町では震度7、七尾市や珠洲市、穴水町、能登町でも震度6強を観測。気象庁は2011年の東日本大震災以来となる大津波警報を発表し、石川、富山、新潟、山形各県など広い範囲に津波が到達した。12月17日までの集計で、この地震による直接死は228人、避難生活のストレスなどによる関連死は石川県で241人。富山、新潟両県での関連死を含め、地震による死者は計475人に上った。死者数は、平成以降の自然災害では東日本大震災、1995年の阪神大震災に次いで3番目の多さとなった。輪島市や珠洲市は、県庁所在地の金沢市から100キロ・メートル以上離れていて、小さな集落が山あいに点在しているため、集落につながる道路が土砂崩れなどでふさがれて一時、救助や支援の手が届かない「陸の孤島」となった。地震による断層のずれに伴い、能登半島北部の沿岸を中心に、「数千年に一度」とも言われる大規模な隆起も発生した。国土地理院の解析によると、隆起の高さは、輪島市の一部で4メートルに達し、海岸線も約90キロ・メートルの範囲で、最大約240メートル海側にせり出した。その影響で、港湾施設などに被害が出た。地震後に大規模火災が発生した輪島市の朝市通り周辺では260棟以上が焼失した。「輪島朝市」は通りの漆器店や土産物店に加えて、海産物などの露店も並び、奥能登を代表する観光名所で、被災した建物の公費解体などが進められている。店主有志らは全国で「出張朝市」を開いた。【2位】大谷 初の「50―50」米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が9月19日、メジャー史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成した。ナショナル・リーグの本塁打王と打点王の2冠に加え、最優秀選手(MVP)にも選出されるなど圧倒的な輝きを放った。昨年12月、長くプレーしたエンゼルスから10年総額7億ドル(当時約1015億円)の大型契約でドジャースに移籍。右肘手術の影響で投打「二刀流」は封印となったが、「走・打」で実力を発揮した。今季は打率3割1分、54本塁打、130打点、59盗塁を記録し、2年連続の本塁打王、日本人初の打点王となった。ドジャースはナ・リーグ王者としてワールドシリーズ(WS)に進出し、アメリカン・リーグを制したヤンキースと対戦。大谷選手は、第2戦で左肩を負傷しながらも第3戦以降も1番指名打者で出場し、チームはヤンキースを破って4年ぶりのWS制覇を果たした。11月21日には、「満票」でナ・リーグMVPに選ばれた。ア・リーグでの2021、23年に続き、2年連続3度目のMVP。シーズンを通して主に指名打者として出場した選手では初めての選出となった。受賞が決まり大谷選手は、「皆さんに評価してもらって光栄というか、すごくうれしい気持ち。(満票は)来年以降も頑張りたいという気持ちにさせてくれた」と語った。ドジャースは来年3月18、19日に東京ドームでカブスと対戦する。【3位】パリ五輪メダル 日本45個第33回夏季五輪パリ大会が7月26日に開幕し、8月11日まで17日間にわたって熱戦が繰り広げられた。日本は海外開催の夏季五輪で過去最多となるメダル45個(金20、銀12、銅13)を獲得した。国・地域別の金メダル数では米国、中国の40個に次ぐ3位で、総数でも6位だった。開会式はセーヌ川とその周辺で行われ、閉会式には米俳優トム・クルーズさんが登場し、五輪旗を受け取った。32競技329種目に約1万1000人が出場し、日本選手団も海外開催の夏季五輪では最多となる約400人が出場した。陸上女子やり投げで北口 榛花 選手が優勝。日本女子がマラソン以外の陸上種目で金メダルを初めて取った。体操男子の団体総合決勝で、日本は最終種目の鉄棒で中国を逆転して優勝。岡慎之助選手は個人総合、種目別鉄棒でも金を獲得した。また、馬術は総合馬術団体で92年ぶりのメダルとなる銅を獲得し、選手らは平均年齢が40歳を超える自分たちを「初老ジャパン」と呼んで話題となった。【4位】新紙幣 20年ぶり日本銀行は7月3日、20年ぶりとなる新紙幣の発行を始めた。肖像は、1万円札に日本資本主義の父といわれる実業家の渋沢栄一、5千円札には女子高等教育の先駆者の津田梅子、千円札には細菌学者の北里柴三郎が採用された。1万円札の肖像が変わったのは、1984年に聖徳太子から福沢諭吉になって以来、40年ぶり。裏には東京駅の丸の内駅舎が描かれた。新たなお札の「顔」になった人たちのゆかりの地では、カウントダウンイベントが開かれるなど「新紙幣フィーバー」に沸いた。新紙幣は、偽造を防ぐため、傾けると肖像が立体的に動いて見える「3Dホログラム」を世界で初めて採用。額面の数字を大きくし、触って種類が識別できるマークを紙幣の種類によって違う位置に配置するなど、誰もが使いやすいユニバーサルデザインも目指した。【5位】闇バイト強盗 続発8月以降、東京、千葉、埼玉、神奈川を中心に「闇バイト」による強盗事件が20件以上発生した。10月15日には横浜市の住宅で、70歳代男性が室内に押し入ってきた男らに暴行を受けて死亡、現金約20万円などが奪われた。一連の強盗事件の実行役らの大半が「X(旧ツイッター)」などSNSでの募集に応じ、事件に加担していた。逮捕された実行役や現金回収役らは約50人に上り、その約8割は10~20歳代だった。警察庁は、SNSで闇バイトについて検索した人に注意喚起の広告を配信するほか、実行役らのスマートフォンの解析を強化する緊急対策を明らかにしている。【6位】衆院選 与党過半数割れ第50回衆院選が10月27日投開票され、自民党は「政治とカネ」の問題を受けて大敗し、公明党を合わせた与党で総定数465の過半数(233議席)に届かず、少数与党に転落した。与党の獲得議席数は、自民党191、公明党24の計215。自民党は選挙戦終盤に、政治資金問題を巡って非公認となった候補が代表を務める党支部に対しても、党本部が2000万円を支出したことが判明し、批判を招いた。野党は明暗が分かれた。立憲民主党は公示前から50議席増の148議席と伸長し、国民民主党も公示前の7議席から4倍となる28議席を獲得した。日本維新の会は6議席減の38議席だった。【7位】自民新総裁に石破氏自民党総裁選が9月27日、投開票され、元幹事長の石破茂氏が第28代総裁に選ばれた。8月に退陣を表明した岸田文雄首相の後継を巡り、立候補に推薦人が必要となった1972年以降で最多となる9人が出馬。石破氏は1回目の投票では2位だったが、決選投票で高市早苗経済安全保障相を破り、逆転勝利した。10月1日の国会で第102代首相に指名され、石破内閣が発足した。発足直後に読売新聞社が実施した緊急全国世論調査では、内閣支持率が51%と、内閣発足時の調査としては岸田内閣(2021年10月)の56%よりも低かった。【8位】日航機・海保機 羽田で衝突1月2日午後5時47分頃、東京都大田区の羽田空港で、新千歳(北海道)発羽田行き日本航空516便(エアバスA350―900型機、乗客乗員379人)と、海上保安庁羽田航空基地所属の「みずなぎ1号」(ボンバルディアDHC8型機、乗員6人)が滑走路上で衝突、炎上した。日航機側は全員脱出したが、海保機は機長を除く5人が死亡した。管制官は海保機側に出発順1番を意味する「ナンバーワン」と伝えて「滑走路手前の停止位置まで走行せよ」と指示したが、海保機は滑走路へ進入し、着陸してきた日航機と衝突した。海保機は能登半島地震の被災地に支援物資を届けるため、新潟空港へ向かう予定だった。事故を受け10月には、滑走路誤進入や誤出発を防ぐ「滑走路状態表示灯(RWSL)」の新設工事が始まった。【9位】ノーベル平和賞 被団協が受賞ノルウェーのノーベル賞委員会は10月11日、2024年のノーベル平和賞を、被爆者団体の全国組織「日本原水爆被害者団体協議会(被団協)」に授与すると発表した。広島、長崎の被爆体験の伝承などを通じて核兵器の廃絶を訴え続けてきたことが高く評価された。12月10日には、代表団がノルウェーのオスロで開かれた授賞式に出席。長崎で被爆した田中 熙巳代表委員が講演し、核兵器廃絶を改めて訴えた。日本からの平和賞受賞は、非核三原則を提唱した1974年の佐藤栄作元首相以来で2例目。【10位】「紅麹」サプリで健康被害小林製薬は3月22日、 米麹こめこうじ の一種である紅麹の成分を配合したサプリメントを摂取した人が腎臓の病気になったとして、「紅麹コレステヘルプ」など3種類の製品を自主回収すると発表した。厚生労働省は9月、原料から検出された青カビ由来の「プベルル酸」が、腎障害を引き起こした原因物質だと特定したと発表。サプリ摂取との関連が疑われる死者は100人を超えた。11位以下は次の通りと。11位 猛暑、夏の平均気温が過去最高タイ 8,470(34.3%)12位 円安、34年ぶり1ドル160円台 7,463(30.2%)13位 日経平均株価がバブル期超え 6,108(24.8%)14位 内部告発問題で失職の兵庫県知事が再選 5,583(22.6%15位 「南海トラフ地震臨時情報」初発表 5,499(22.3%)16位 静岡地裁、袴田巌さんに再審無罪 4,917(19.9%)17位 自民、派閥の政治資金問題で39人処分 4,843(19.6%)19位 漫画家の鳥山明さん死去 4,687(19.0%)20位 岸田首相が退陣表明 4,035(16.4%)21位 日本の探査機、月に初着陸 3,838(15.6%)22位 政治資金問題で安倍派議員逮捕 3,823(15.5%)23位 DeNA26年ぶり日本一 3,644(14.8%)24位 日銀、マイナス金利解除 3,596(14.6%)25位 北陸新幹線、金沢―敦賀間延伸開業 3,481(14.1%)26位 世界的指揮者の小沢征爾さん死去 2,652(10.7%)27位 俳優の西田敏行さん死去 2,608(10.6%)28位 名目GDP、世界4位に転落 2,558(10.4%)29位 「佐渡島の金山」が世界文化遺産に 2,547(10.3%)30位 H3ロケット打ち上げ成功 2,302(9.3%)【その他】 2024年「今年の漢字」は「金」12月12日(木)、京都・清水寺にて2024年の「今年の漢字」が発表された。◆今年の漢字は「金」記念すべき30回目を迎えた今年の漢字。森清範貫主が揮毫し、今年の漢字は「金」と発表された。応募総数は、22万1971票となり「金」はこれまで、2000年、2012年、2016年、2021年でも選ばれており、今回が5回目の選出となった。第1位の理由は、“光”の金として「数多くの『金』メダル獲得に沸いたパリオリンピック・パラリンピック」「大谷翔平選手が50-50達成と3回目のMVP獲得で値千『金』の活躍」「佐渡『金』山が日本で26件目の世界遺産に登録、20年ぶりに新紙幣が発行されたことも話題」とスポーツ選手の活躍や、佐渡金山、新紙幣発行などのトピックを挙げた。一方、“影”の金としては「政治とカネ・裏『金』問題などで政局が大きく変わり、衆議院議員選挙で与党過半数割れ」「全国で闇バイトによる『金』目当ての強盗事件が多発し、多くの国民が不安に」「止まらない物価高騰で家計を圧迫」と、2024年印象的だった「金」にまつわるニュースなどを理由とする人が多かったそう。2024年「新語・流行語大賞」は「ふてほど」私にとっては、「不適切にもほどがある!」を略した「ふてほど」、このテレビからの発表時に初めて聞く言葉であったが・・・・。 個人的に我が十代ニュースは3つのみ・順不同であるが★一度も寝込むことなく健康な1年であった。一昨年8月には、【耳下腺腫瘍】の切除手術で8日間の市民病院での入院、その後12月末にも【大腸ポリープ】の切除手術で1泊2日の入院であったが、その後も順調に回復し、今年の2年点検でも両方とも問題はないとの診断結果であった。★この秋に元上司、元部下が相次いで膵臓癌で逝ってしまった。合掌。★今年2024年も我がブロクは1日も休むことなく皆勤賞。そして二人暮らしの我が家の重大ニュースは唯一つ①今年の私達夫婦は自宅でコロナ、風邪や発熱等で寝込むことも全くなく、「無病息災」で 大晦日の今日の日を迎えられた事に感謝。 妻も半世紀以上の長年の仕事も昨年11月で卒業し、家事に専念してくれ、毎金曜日は 横浜まで趣味の歌を歌いに皆勤賞で通ってくれたのであった。 独立している子供たち家族も元気に越年、来年も1月12日に長男、長女家族が我が家に来ると。 久しぶりの家族【全員集合】なのである。そして今年の徒歩による散策そして毎日アップしたブログアップを振り返ってみた。★1月謹賀新年そして初日の出👈リンク片瀬西浜海岸からの元旦の富士山の勇姿。菜の花を愛でに👈️リンク★2月今年も熱海・糸川桜へ👈リンク今年も河津桜を愛でに👈リンク★3月よもぎ団子を楽しむ👈リンク「藤沢地名の会」・「春の御所見南を歩く~宮原・獺郷・打戻の史蹟を訪ねて~」👈リンク★4月「三浦氏の本拠地 衣笠を歩く」👈リンク三浦安針墓(安針塚)👈リンク★5月湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に行く👈リンク平塚・花菜(かな)ガーデンへ👈リンク★6月自治連の親睦旅行・豊洲~川越へ👈️リンク豊洲。川越。熱海・ジャカランダの花を愛でに👈️リンク★7月富士山五合目へのバス旅行👈️リンク第72回湘南平塚七夕祭り👈️リンク★8月座間市ひまわりまつり👈️リンク江の島灯籠 2024へ👈️リンク市制70周年 佐倉花火フェスタ2024👈️リンク★9月秋分の日の夕焼け👈️りんく小田原城下を歩く-1👈️リンク★10月片瀬の『龍口寺 竹灯籠』へ👈️リンク小田原城下を歩く-3👈️リンク★11月二子玉川周辺を巡る👈️リンク明治神宮外苑 いちょう並木へ👈️リンク小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅👈️リンク★12月創建700年の遊行寺・大イチョウ ライトアップ👈️リンク今年も地元の「天嶽院」の紅葉を愛でに👈️リンク★大晦日そして正月飾りも既に1週間程前に購入済み。我が家の正月飾りの準備も昨日30日に完了しました。門松は12月28日までに飾るか、12月30日に飾るのが良いとされています。その理由は、 29日に飾るのは語呂合わせで「29(二重苦)」に通じ縁起があまりよくないとされているからです。また、12月31日に飾るのは「一日飾り」といい、一日前にぎりぎりで飾ると、神聖な気持ちでゆっくりと正月を迎えられないので、その日には飾らないことにするのだと、半世紀以上前に亡き父より。鏡餅は今年も神棚用、床の間用に2個購入し組み立てました。箱を開けて見ると。組み立てて床の間に。神棚。全てを下し濡れタオルで1年の埃を落としました。そして2尺の牛蒡注連も新たに購入し奉納しました。玄関のしめ飾り。今年もシンプルなものに。そして門飾り。松と輪飾りを。松と裏白(うらじろ)と紙垂(しで)今年の紙垂は例年のものとは異なっていましたが。短かかった?暑かった!!、そして毎日、大谷翔平選手の活躍に励まされた2024年。大晦日の「年越しそば」と「除夜の鐘」をと。世界の平和が確実に実感できる新たな年・2025年へ!! との願いを込めて。本日も我がブログへのアクセスありがとうございます。アクセスいただいた皆様も元気に良き新年をお迎えください。そして来年も我がブログをご笑覧いただきたくよろしくお願い申し上げます。そして2025年へのカウントダウン。2025年まで残り12時間。そして元旦は初日の出を見に!! と。良き新年をお迎え下さい。 2024年 完
2024.12.31
コメント(1)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その17): 明治村9/16 第四高等学校物理化学教室
「鉄道局新橋工場」を後にして、「レンガ通り」に向かって進む。ここが「1丁目」と「2丁目」との境界のようであった。右手にあったのが「千早赤阪小学校講堂」であったが、後ほどにと。左手奥にあったのが「第四高等学校物理化学教室」。正面の案内板には書かれていなかった理由は、ここが正門入口ではなかったからなのであった。最後に訪ねた正門入口は「レンガ通り」に面していたのであった。「2丁目15番地 第四高等学校物理化学教室👈️リンク <登録有形文化財>旧所在地 金沢市仙石町建設年 明治23年解体年 昭和39年移築年 昭和40年建築面積 137.6坪構造 木造平屋建寄贈者 北陸財務局」この建物は、第四高等学校の物理化学教室で、後に金沢大学へと引き継がれた。近代化を進める明冶政府は自然科学教育に重きをおき、このような実験ができる教卓を備えた教場を建設した。屋根に出ている煙突は煙や有毒ガスの発生する実験を行うためのドラフトチャンバーという小室の換気装置である。明冶村へは、もとはH型であった建物の、中央部分にあった階段教室を中心に移築している。工事監督は文部省技師の山口判六、設計も同じく支部省所属の久留正道である。両者とも西洋建築を学んでおり、この階段教室も研究による理論の裏付けをもとに設計された。」教室内の廊下からの出口から入る。「⑮第四高等学校物理化学教室 明治二十三年」長い廊下が続く。高い天井と大きな上げ下げ窓が印象的な廊下。右手の「谷口吉郎・土川本夫顕彰室」に入る。ここ明治村は、建築家の谷口吉郎と、名古屋鉄道株式会社会長の土川元夫の発想と決意によって誕生した。両氏は金沢の第四高等学校で同級生で。この建物の一室は、2人の偉人の功績をたたえる顕彰(けんしょう)室として、両氏の遺品などを展示しているのであった。「取り壊された「鹿鳴館」が、私に明治建築の保存を願望させた。」「明治村には、模型は造っていません。すべて本物を持ってくることにしています。」と。「谷口吉郎・土川本夫 顕彰室谷口吉郎・土川元夫顕彰室について1965 (昭和40)年・3月18日、博物館明治村はこの地10棟ほどの建物が移築保存された博物館としてスタートしました。そしてこの1890 (明治23)年創建の第四高等学校物理化学教室は、この博物館明治村の設立に多大な寄与を為した二人、谷口吉郎(当時東京工業大学教技)と土川元夫(当時名古屋鉄道式会社副社長)が、ともに学生時代を過ごした建物でもあります。この両氏が、第四高等学校の同窓会で交わした、明治時代の建物を移築・展示する野外博物館の構想が、博物館明治村の設立へと繋がりました。本顕彰室では、博物館明治村が設立された経緯をニ人の生涯と功績に重ねてご紹介いたします。明治村を創立した二人を繋いだこの建物が、当館についてより深く知ることができ、創立者が明治村に注いだ情熱と願いに触れていただける場所となれば幸いです。」草創期の明治村1965 (昭和40)年3月18日、博物館明治村は移築建造物14件を公開展示する野外博物館として開村して以降、開村10年目で敷地面積を100万m2、移築建造物総数40件を数えるまでになりました。また、各種企画展示の実施、昭和42年からは京都市電の動態展示の開始や明治村茶会の開催など、博物館としての活動も多岐にわたりました。ここでは当時のポスターや村内地図、当時の谷口、土川両氏の様子を、ニ人をおさめた写真と講演・著作の記録から、明治村草創期のあゆみをご紹介します。」正面に胸像が。「土川本夫像」。「平和塔(ピースパゴタ)」このピースパゴダの模型は金沢市の谷口吉郎・吉生記念金沢建築館の所蔵作品で、同館と博物館明治村の連携協定に則って、明治村が借用、展示させていただいているものと。パゴダ(pagoda)は東洋における宗教建築の塔を意味する英語。「平和塔(ピースパゴタ) 【模型】」「棟札」「博物館明治村に移築されている第四高等学校物理化学教室と、熊本の第五高等学校化学実験場く重要文化財>は、2014年3月に公益社団法人日本化学会化学遺産委員会より、「明治政府が中等・高等教育において実験を含めた自然科学教育を極めて重視していたことがうかがえる責重な資料」として、化学遺産に認定されました。いずれの建物も当時の学校建築の第一人者で文部省技師の山口半六が工事監督、久留正道が設計を担当しました。第五高等学校化学実験場、第四高等学校物理化学教室ともに演示実験を行う講義室(階段教室)の黒板の裏側にドラフトチャンバーが備えられていますが、その他の点では、第四高等学校物理化学教室が建物全体ではなく切り縮めて移築されていることもあり、相違点が見受けられます。図面や写真で見比べてみましょう。」「理科教室をのぞく」「ドラフトチャンバー」。「ドラフトチャンバーについてドラフトチャンパーは欧米ではFume hood、Fume cupboardと呼ばれる排気装置です。19世紀半ば以降に理化学実験室に備えられるようになったもので、ドラフトチャンバーが実験室に備え付けられる以前は、多くの科学者たちが実験の際に有毒ガスを吸い込むなど事故が絶えませんでした。創建時のこの建物にはドラフトチャンバーが図1のように8か所あったと推定されますが博物館明治村へ移築されたのは化学講義室と用意室の間の一か所のみです。」「このドラフトチャンバーの機構はごく単純なもので、アルコールランプやプンゼンバーナーなどで煙道に暖かい空気を送り込み、上昇気流を発生させます。その後、実験で生じたガスや粉じんをドラフト内に収め戸を閉めることで、有毒なガスなどを煙突から排出し室内にガスなどが充満することを防ぐものです。」「ドラフトチャンバー側面図黒板の裏側がドラフトチャンバーと呼ばれる排気装置になっています。ドラフトチャンバーという言葉は英語ですが、欧米ではFume hood、Fume cupboardと呼ばれています。この教室で行うのは、講義内容を理解させるための演示実験です。教師は、黒板の裏側の用意室で準備された実験装置を受け取り、教卓上で演示し、ガスなどが発生する場合は黒板を下ろし、排気を促します。」「五つの高等中学校の設計者たち明治政府の留学生として、フランスで建築を学んだ山口半六(やまぐちはんろく)1858 (安政5)年一1900 (明治33)年1858年、松江藩士山口禮行の次男として松江で生まれ、1871 (明治4)年、大学南校入学。1876年に文部省留学生として、パリの工業中央専門学校(Ecole Centrale des ArtsManufactures)留学。卒業後、パリ郊外のイヴリー市の煉瓦製造工場で研修し、1881年、帰国。日本郵船勤務後、1885年に文部省技師となり、五つの高等中学校(旧制高等学校)始めとする学校建の設計監督にあたる。1892年、文部省を退職し関西を拠点に設計や都市計画を行い、1900年に没。明治時代にフランスで学び、様式にとらわれない数少ない建築家の一人と評される。」工部大学校でコンドルに建築を学び、多くの学校建築を担当久留正道(くるまさみち)1855 (安政2)年一1914 (大正3 )年1855年、江戸に生まれ、1874 (明治7)年工学校を経て、1881年工部大学校卒業。その後、工部省、内務省を経て、1886年、文部省入省。山口半六とともに高等中学校の設計に携わる。1893年、のちに帝国ホテルの設計者となるフランク・ロイド・ライトに大きな影響を与えたシカゴ・コロンプス万国博覧会日本館(鳳凰殿)を設計、また学校建築の基本となる『学校建築図説明及設計大要」(1895年)を著したといわれる。1911年、文部省退職。階段状の化学教室。設計者の久留正道は西洋建築の理論や技術の研究を行い、これに基づいて設計を行った と。階段状の化学教室の中に入り見上げて。奥から。「机学生の使用する机。そして教卓も、この建物のために設計されたことが図面資料からもわかります。教卓は化学講義室のものには流し台が設置されており、物理・化学それぞれの機能に応じたものとなっています。理化学の講義室はどの学校も階段教室を採用しており、実験室とは明確に区別されています。」玄関ホール。壁面は白漆喰で仕上げられています。「谷口𠮷郎 1904-1979」。「土川元夫 1903-1974」。「八校生青年像」。近づいて。もう一つの教室へ。「日本の化学実験室のルーツをたどる日本からの留学生長州五傑長州藩からイギリスへ派遣された、井上馨(左下)、伊藤博文(右上)、井上勝(中央)、山尾庸三(右下)、遠藤謹助(左上)の5人のこと。1863 (文久3)年出発、ロンドン到着後は、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのウィリアムソンのもとで学ぶ。井上馨と伊藤博文は翌年帰国しますが、残る3人はさらに勉強を続け、専門技術を身につけ帰国。帰国後、伊藤博文が初代内閣総理大臣になったのをはじめ、井上馨は初代外務大臣、井上勝は鉄道局長、山尾庸三は工部卿、遠藤謹助は造幣局で造幣技術を確立するなど、近代日本を支える存在となりました。薩摩留学生薩英戦争の際にイギリス側の捕虜となった五代友厚が、薩摩藩に対して提出した上申書に基づき、薩摩藩がイギリスへ派遣した留学生。1865年4月17日、視察員4名、留学生15名が現在の鹿児島県いちき串木野市羽島沖から出航.ロンドン到着後、多くの留学生はユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで学び、約一年後に帰国しました。一行の中には初代文部大臣となる森有礼(右側写真、前列左)、開成学校の校長となる畠山義成(右側写真、後列左)、帝国博物館初代館長となる町田久成(左側写真、前列中央)などがいます。ウィリアムソンイギリス人化学者のウィリアムソンはリービッヒの教え子の一人です。彼は親日家でもあり、彼のもとへは、幕末に長州や薩摩からイギリスへ派遣された長州五傑や薩摩留学生が訪れ、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのウィリアムソンの学生実験室で学びました。多くの留学生たらは帰国後、初代内閣総理大臣の伊藤博文や初代文部大臣の森有礼など明治政府の要職についています。リービッヒ(Liebig, J. )日本の理化学教室の原点は、ドイツ・ギーセン大学のリービッヒの学生実験室と考えられています。ヨーロッパでは伝統的に理化学教育は「劇場型」といわれ、あたかも役者が舞台で演技を見せるように教師が机上で学生へ実験を見せるものでした。これは実験を学びたいという学生には不向きでした。リービッヒによって考案されたのが、ギーセン大学における学生実験室です。これは通常、演示実験をおこなう講義室に隣接して設けられた準備室が派生的に学生の実験室として用いられるようになったものです。リービッヒのもとで学んだのはドイツ人学生だけでなく、ヨーロッパ全土、ひいてはアメリカ大陸にも及び、教え子たちが、学生実験室を各地へ広めていきます。」当時の卒業証書。「学校数・学生数の推移」。「第一高等学校 卒業証 明治31年」。「東京帝国大学 卒業証書」。「精密天秤」。「消防ポンプ模型」。「「旧制第四高等学校由米の物理実験機器コレクション」とは管された厘ーてす.「旧制第四高等学校由来の物理実験機器」コレクションは、1994(平成6)年に金沢大学教養部物理教室から石川県教育委員会へ移管された日本で最大の物理実験機器コレクションです。これらは1877 (明治10)年に設立された石川県中学師範学校、1881年に設立された石川県専門学校時代を経て1887年に開校した第四高等中学校(1894年に第四高等学校と改称)が、1950 (昭和25 )年に閉校するまでの60年余りの間に人手し、授業などに供されたものてす。第四高等学校が閉校した後は、金沢大学法文学部、理学部、教養部物理教室へと引き継がれましたが、1993 (平成5)年の金沢大学のキャンパス移転に伴い、約90点が金沢大学資料館へ移管されました。残りの約700点は、翌年石川県教育委員会へ移管され、現在石川県立自然史資料館(2006年開館、移管当初は石川県自然科学博物館資料準備室)て保管されています。大切に保管されてきたこれらの実験機器を通して、実験を用いた科学教育によって近代日本という新しい時代を切り拓いてきた歴史に触れることは、見学者の皆さんの未来を築く糸口となると信じています。”LAB(ラボ)”へようこそこの部屋の名称”LAB”は英語の”LABORATORY”(実験室)の略称です。19世紀後半から20世紀前半にかけて使用された実験機器を展示するとともに、皆さんに科学をより身近に感じていただく場としたく”LAB”と命名しました。19世紀20世紀は、科学やその研究のための実験機器が急速に発展した時期ですが、変化が激しかったため、科学の発展に寄与した機器が不必要とされたり、また「何のために、どのように」用いたのかわからなくなり、数多くの受験機器が廃棄の運命に遭いました。ここに展示されているものは、1877(明治10)年代から1950(昭和25)年に、第四高等学校(全身の学校も含む)で使用され、その後今日に至るまで、幸いにも大切に保管されてきた実験や演示に用いられた機器です。博物館明治村では、石川県教育委員会および石川県立自然史資料館のご好意を得、この度膨大なコレクションの一部を借用させていただき、展示させていただくこととなりました。ここに展示した実験機器はまさにこの学び舎・第四高等学校物理化学教室で用いられたものです。建物とともにこれら実験機器をご覧いただくことで、学生たちが実験に勤しんでいた当時の息遣いを感じていただけましたら幸いです。 博物館 明治村」「旧制第四高等学校由来の物理実験機器コレクションより光って、なに?リンゴが木から落ちるのを見て「すべてのものには重さがある (万有引力の法則)ことを発見したとされるイギリスの科学者ニュートン(1643-1727)は、実は数多くの「光」の研究も行っています。彼は暗くした室内で、小さな穴をあけた窓から一筋の光を取り込みプリズムに当てると虹のような7色の光に分かれ、さらにもう一つプリズムを通すことによって7色の光が再び白色となることを発見しました、ニュートンはこれを基に、「光は粒子てある」どいう説を発表しましたが、同時代の科学者ホイへンス(1629-1695 )やフック(1653-1703)は「光は波動である」とニュートンに反論しました。19世紀になるどマクスウェルが「光は電磁波の一種である」ことを証明し、20世紀初頭にアインシュタイン(1879-1955 )が「光の粒子説」を復活させ、現代では「光は粒子と波動の両方の性質を持つ」と考えられています。光の3色を示すRGBは赤(Red )緑(Green )青(Blue)の頭文字て、3色を重ねると白色となります。色の3原色は「赤」「青」「黄」で3色を重ねると黒色になります。印刷などでよく用いられるCMYKはC (Cyan :青十緑) M(Magenta:赤+青) Y(Yellow:赤+ 緑) K(Key plate:墨)の絡称です。」「光の三原色 色の三原色」。「検眼レンズ」。「検眼レンズ分類 光学製造者 不明製造年 1914 (大正3 )年近視、遠視、乱視などの度数を調べるためのレンズ。レンズの把手に度数を示す数字が記されている。 石川県教育委員会 所蔵 石川県立自然史資料館 保管」「旧制第四高等学校由来の物理実験機器コレクションより」「ネオンはガスかな?ネオン(Ne)は、クリプトン(Kr)、キセノン(Xe)とともに1898年イギリスの化学者ラムゼーによって発見された「貴(希)ガス」と呼ばれる元素です。元素周期表では貴ガスはすべて一番右側の族に属しています。ネオンは実用化されて、1910年に世界で初めてパリでネオン管によるイルミネーションが飾られました。」「元素周期表」。「ネオンに用いられている硝子と瓦斯の種類で様々な色を呈することを示したものです。ウラニウム(ウラン)硝子やクロム硝子は緑がかった色、コバルト硝子は青味がかった色がガラスに現れ、ネオン、ヘリウム(He)、アルゴンはそれぞれ電圧をかけると赤や緑などに発色します。ガラス管の中央部には尖った部分が見えることから、管の内部を真空にしたことがわかります。」展示されているネオンサインの裏側には次のような記載があリます。「旧制第四高等学校由来の物理実験機器コレクションよりはかる長さや重さ、かさ(体積や容積)をはかる単位は、国際的のみならず日本国内においてすら、統一された単位は近現代になるまでなかったと言っても過言ではありません。日本ては中国由来の「尺貫法」が伝統的に用いられ、長さは「尽」、重さは「貫」を基準とする単位を用いてきました1875 (明治8)年に度量衡取締条例が施行され、1尺=約30.304 cm、l匁(1/1000貫) = 3.756521と定め、各県に一つずつそれぞれの「原器」を置くことが定められました。1886年に日本は、度量衡の国際的な統一を目的として1875年成立したメートル法条約に加盟しました。メートル法ては、長さ・重さ・体積・面積のほかに時間の単位も定められました。その後、1891年には日本国内ては度量衡法が定められ、従来の尺貫法とメートル法のニつの単位が併存しました。1921(大正10)年に度量衡改正(メートル法)法案が成立しましたが、度量衡の切換は容易に進まず、1959(昭和34)年に尺貫法の使用が禁止され、メートル法の使用義務付けられました。しかしながら、現在「一寸先は闇」という言葉が用いられているなど、尺貫法は皆さんの身近にまだまだあるのではないてしようか・・・。」「メートル法」と「尺貫法」。「蒸気機器分類 熱学製造者 不明製造年 1881(明治14)~1887(明治20)年頃」「紫外線物質鑑識装置分類 流電製造者 株式会社島津製作所 京都製造年 1931(昭和6)年」「ウォームギヤ模型」、「テンプの運動説明器」👈️リンク。再び、高い天井と大きな上げ下げ窓が印象的な長い廊下が見る。この後訪ねた「第四高等学校物理化学教室」を見る。「レンガ通り」に向かって進む。こちらが「レンガ通り」に面した「第四高等学校物理化学教室」の正面側。約60年前に中学校、高等学校では化学を学び、そして大学では化学を専攻した高齢者の「化学屋」の、楽しいそして懐かしい復習の時間なのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.31
コメント(0)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その16): 明治村8/16 三重県庁舎-3~二重橋飾電燈~鉄道局新橋工場・明治神社
「展示室 明治の宮廷家具」と。現在、迎賓館赤坂離宮となっている東宮御所は、明治42年(1909)に竣工し、当時皇太子であった大正天皇のために建てられました。設計の中心となった片山東熊は、建築家として建物を設計するのみならず、室内装飾においても多くの業績を残しています。花鳥の間は、「饗宴の間」とも呼ばれ、晩餐会などに使用された部屋です。「明治の宮廷家具博物館明治村には約400点の宮廷家具を所蔵しています。その中から、明治42(1909)年に竣工した東宮御所(大正大皇の皇太子時代の宮殿)の創建当初の家具を紹介いたします。背景に使用している写真は竣工当時の室内を写した写真(東宮御所写真帖)です。これらの家具が明治村へもたらされた当初は、家具が使用された部屋などの情報は、ほとんどありませんでしたが、東宮御所写真帖や宮内庁所蔵の資料から、明治村所蔵家具が使用された部屋の多くが判明しました。」「孔雀(くじゃく)之間」。皇太子用の客室としてしつらえられたもの と。「孔雀(くじゃく)之間孔雀之間の室内装飾は「明治工業史」によるとフランス18世紀末様式で。天井には花鳥や楽器等が描かれた油絵が用いられ、壁面の中央に飯田新七が納めた「孔雀にボタンと文鳥に桜」を刺繍したものが飾られ、室名の由来ともなっています。残りの壁面は石膏の型抜きの装飾が用いられ、カーテンは飯田新七が納めた淡い紅色の織物が用いられています。家具を納入したのはフランスのパリに拠点を置くフールジノア(Fourdinois,Henri 1830ー1910) です。彼はフランスだけではなく他のヨーロッパ王室へも家具を納入し、東宮御所の大部分の部屋の家具を納入し、東宮御所室内装飾に功績があったとして、日本政府より明治40 (1907)年勲五等旭日章を授与されています。」「紅の間」。「紅(くれない)の間紅の間は皇太子の謁見所・狩之間と朝日之間の間に位置する部屋で、控えの間とされたものです。他の多くの部屋と同じようにフランス18世紀末様式で装飾され、壁はローズ色に花束模様、カーテンは淡紅色の織物が用いられ、家具はフランスのフールジノアが納めたものです。」「狩の間」。正面の立派な家具は、家具作家Reisnerが1780年代にベルサイユ宮殿に納品されたものとかなり似ているとのこと。移動して。ズームして。「朝日の間朝日の間の室内装飾は「明治工業史」によるとフランス18世紀末様式で。天井には「旭日」に朝霧が昇り桜花に映ずる間において神女が玉馬に鞭ち香車を駆るの図」が描かれ室名の由来ともなっています。柱はノルウェー産の大理石、壁面には曽和嘉一郎が納めた草色の菊の御紋が織り出された金華山織が用いられたと記載されています。室内の家具を納入したのはフランス人エンシェル(Hoentschel,Georges 1855-1915)で、彼は、1900年のパリ万国博覧会、1904年のセントルイス万国博覧会の内装なども手がけた。フランス有数の室内装飾家で、フランす勲章・レジオン・ドヌール・オフィシエを受賞している。」「朝日の間」。「三重県庁舎」を後にして振り返る。前方にあったのが「二重橋飾電燈」。「1丁目11番地 二重橋飾電燈(かざりでんとう) <登録有形文化財>旧所在地 東京都千代田区千代田建設年 明治21年解体年 昭和38年移築年 昭和40年構造 鋳鉄製飾電燈寄贈者 宮内庁二重橋は江戸時代には西の丸下乗橋(木橋)と呼ばれた。二重橋の呼び名の起こりは堀の水面から橋までの高さが高く直接に橋梁を架ける事が困難なため、中間に橋桁を渡し、これを土台としてその上に柱を立て更に桁を渡して橋を架けたため、あたかも橋が二重になって見えたのでこの名が生まれた。この下乗橋は木橋のため老朽化し、明治21(1888)年鉄橋に架け替えられた。その後、さらに昭和39(1964)年この鉄橋は昭和宮殿の建設にあたり、鉄橋と飾電燈と共に更新された。「二重橋飾電燈」越しに「三重県庁舎」を見る。「鋳鉄製の飾電燈(かざりでんとう)」。皇居造営にともない架け替えられた二重橋には、橋の西側両端に並んで6基の飾り電灯がつけられていました。明治村には、そのうちの一つが移築されています。飾り電灯は、高さ5.2mの鋳鉄製でドイツのHARKORT社によって製造さられました。全体を植物意匠のネオ・バロック様式で飾る。角壺形の基部に立てた主幹上に1灯を掲げ、四方の腕から各1灯を吊る。火屋(ほや)は卵形で、笠は放射状に蔓を巻き上げる。安定した重厚な基部が軸部を支え、軸部から出た葉文様の丸鋼で出来た4本の枝が軽々と大きなグローブを吊り下げています。飾り電灯の周りを囲む鉄柵には、二重橋とそのたもとにあった唐草模様の鋳鉄製欄干を利用しています と。ズームして。皇居前広場から皇居に通じる、石橋の上に設置されていた6基の飾り電灯のうちの1つ。もともと、この場所には江戸時代から「西の丸大手橋」と呼ばれる木橋が架かっていました。明治宮殿の造営につき、石橋に架け替えられた際に、橋とともに造られたのがこの電灯です。設計は皇居造営事務局の技手であった久米民之助、欄干の装飾は河合浩蔵によるもの。岡山産の大島花崗岩造りによる眼鏡橋でした。両側に高さ114cmの石の手すりを備え、その間に高さ174cmの男柱を備えた造りに。さらに片側3本の計6本、それぞれの男柱石の上に、青銅鋳造の飾りが6基取り付けられていました。灯器には、四方に旭日(あさひ)と獅子の頭がデザインされ、腕木はアカンサスを模しています。電球グローブは真球を採用しています と。二重橋飾電燈の周囲を囲むフェンス。近づいて。唐草模様の鋳鉄製欄干。石段の先にあったのが「鉄道局新橋工場」。そして石段を上り「鉄道局新橋工場」に向かって進む。「明治神社」の案内板も立っていた。紅葉をズームして。「1丁目12番地 鉄道局新橋工場 <登録有形文化財>旧所在地 東京都品川区建設年 明治22年解体年 昭和41年移築年 昭和41年建築面積 140.4坪構造 鉄造平屋建銅板葺寄贈者 日本国有鉄道鉄道局新橋工場は東京新橋駅構内に鉄道の木工場として建てられた。この建物は、構造技術の面では鉄道寮新橋工場にならって造られたものであるが、鋳鉄柱に「東京鉄道局鋳造」の銘があり、国産鉄造建築の初期例といえる。大正8年(1919)に大井工場に移築され第二旋盤職場として昭和41年(1966)まで使用された。昭憲皇太后御料車 (5号御料車) <鉄道記念物> 製造年 明治35年御料車とは天皇・皇后・皇太后・皇太子のための特別な車輛のことで、5号御料車は最初の皇后用御料車として製作された車輛である。全長16m余、総重量約22tの木製2軸ボギー車で、車内には皇室技芸員の橋本雅邦・川端玉章が描いた天井画、拭き漆で仕上げられた壁面など、華麗な内装が施されている。明治天皇御料車 (6号御料車) <鉄道記念物> 製造年 明治43年この御料車は明治時代に製造された6両の御料車のうち最後のものである。車輛の全長は20m余、総重量約33.5tの木製3軸ボギー車である。この車輛は歴代の御料車の中でもっとも豪華な車輛といわれ、車内天井に貼られた蜀江錦(しょっこうきん)、御座所内の金糸の刺繡や七宝装飾、また螺鈿(らでん)装飾、木画といわれる木象嵌(もくぞうがん)など日本の伝統的な工芸技術の粋を集めたものといえる。」建屋内には二両の御料車が展示されていた。「明治天皇御料車 (6号御料車)」(左)「昭憲皇太后御料車 (5号御料車)」(右)順路に従って右方向へ進む。「明治村 錦絵れきし探偵団」。「憲法発布宮城二重橋御出門之図 楊洲周延画 明治22(1889)」。内部に鎮座する「明治神社」。東京代々木にある明治神宮を10分の1に縮小した社殿。「明治神社明治時代は日本を近代化するよいう目標に向かって邁進した時代でした。その中心に、また、多くの人々の精神的な支えとして明治天皇があられました。崩御後の大正九年、明治神宮が造営され、昭憲皇太后とともに祀られました。そのご神殿は、日本建築史研究の重鎮、伊藤忠太博士の下に造営されましたが、第二次大戦で消失、戦後、神社建築の第一人者、角南(すなみ)隆氏の設計で復元されました。当館は、開村四十周年を前に、明治村邸内社の造営を計画し、明治神宮にご相談申し上げたところ、明治神宮と同じ姿の縮小社殿(十分の一)の造営を許可くださいました。平成中七年、「明治神社」と命名いただき、併せてご神体を頂戴いたし、お祀りする事となりました。すでに移築保存してあります数々の文化財建造物と同様に、ご見学頂ければ幸いです。」」明治神社についてこの明治神社は、東京代々木にあります明治神宮ご社殿の、厳密に10分の1に作られた縮小社殿です。明治神宮は、明治天皇と昭憲皇太后をお祀りする神社で、大正9年(1920)創建されました。その折に造営された社殿は、当時の建築歴史界の重鎮、伊藤忠太博士の設計になる建物でした。第二次大戦で焼失、その後、神社建築の第一人者であった角南隆氏を中心に、新しい社殿が建てられました。平安時代以来の伝統的な「流れ造」を元に、軸組木部の細部意匠に新しい形を施した建物です。二十世紀初頭にヨーロッパで興った近代建築革命の、日本的な解釈の一例と言えます。左側の「明治天皇御料車 (6号御料車)」「明治天皇御料車 6号御料車 鉄道記念物製造年・工場:明治43年(1910)・新橋工場製6号は明治天皇用の御料車として製作された車輛で、明治天皇の崩御後も、大正・昭和初期まで使用されたものです。車内は順に大膳室・侍従室・天皇御座所・侍従室・御寝室・お手洗室となっています。室内は明治の工芸の粋を集めたもので、蒔絵・螺鈿・七宝・彫金・刺繍・木象嵌などを駆使した内装は、歴代御料車の中で最も優雅な車輛と称されるほどです。また、この6号は御料車として初めて3軸ボギー台車が使用され、それまでの2軸ボギー台車のものに比べ乗り心地の点でも改良されたものになっています。 昭和34年10月14日 鉄道記念物指定 東海旅客鉄道株式会社所有」。「明治天皇御料車 6号御料車」を横から。御料車とは皇室専用の特別列車で、天皇や皇后が公式行事や旅行の際に使用した車両です。御料車は、一般の列車と異なり、皇族のために特別に設計され、豪華な内装と当時の最先端の技術が施されています。そしてこちらは「昭憲皇太后御料車 (5号御料車)」「昭憲皇太后御料車 5号御料車 鉄道記念物製造年・工場:明治35年(1902)・新橋工場製御料車とは天皇・皇后・皇太子・皇太后のための特別車輛です。5号は初の皇后用車輛として製作されたもので、車内は順に大膳室・女官室・御座所・御寝室・化粧室兼御閑所・供奉員室となっています。室内の天井には、当時を代表する画家、橋本雅邦の「桜花紅葉」、川端玉章の「帰雁来燕」が描かれているなど芸術品としての価値も高い車輛です。また、ここに敷かれているのは鉄道開業当初にイギリスから輸入して使われたものと同じ「双頭レール」と呼ばれるレールです。 昭和34年10月14日 鉄道記念物指定 東海旅客鉄道株式会社所有」「昭憲皇太后御料車 5号御料車」を横から。御料車5号初の皇后陛下用(当時の美子皇后 後の昭憲皇太后)の車輛として、明治35(1902)年、新橋工場で製造されました。外側の塗装は当初は深紅色の塗料でしたが、大正4(1915)年頃、漆塗に変更されています。車輛は前方から大膳室・女官室・御座所・御寝室・御閑所と御化粧室・供奉員室に分かれており、全長16.129mです。車内の装飾は、皇室の紋である「菊」とともに、美子皇后のご出身の一条家の家紋「藤」が各所にあしらわれているのが大きな特徴といえます。御料車5号の装飾について 女官室女官室には皇后陛下御乗降口が設けられています。入口扉を支える蝶番は銀製で、菊唐草が彫られ、螺子山にも菊花が彫られ、普段目に付かないところまで装飾を施す、細やかな配慮がうかがえます。室内天井には、橋本雅邦が描いた桜と紅葉の天井画が用いられています。御料車5号の装飾について 御座所御座所の天井は、桐の柾板に川端玉章により「帰雁来燕」が描かれています。雁は渡り鳥で日本で冬を越し、春になると繁殖のため北の方へ帰って行きます。「帰雁」は俳句の「春」の季語にもなっています。燕も渡り鳥で、春になると繁殖のため日本へ飛来し、秋になると南方に帰って行きます。中央の天井には金砂子で雲が表現され、下から見上げると菊文様のランプシェードが取り付けられています。川端玉章作「帰雁来燕」。御料車5号の装飾について 御座所御座所内には有職文様などに用いられる立涌の中に藤模様の濃紅色の緞子が腰張りに使用され、同じ文様の裂地が椅子張りにも使用されています。写真からは確認できませんが、長椅子の下には暖房用と思われる管が設置され、皇后のご健康に配慮したと想像されます。背掛布は菊の御紋と菊唐草風の生糸の刺繍がなされ、濃紅色の椅子張地を一層華麗なものにひきたてています。御座所。御料車5号の装飾について 御寝室と御閑所御寝室の天井は女官室と同じ橋本雅邦により、桜と紅葉が一本の木として描かれています。室内には桑や楓材を彫刻したものが装飾として用いられています。御料車は夜間走行することはありませんでしたが、体調がすぐれない時などに御寝室は利用されました。御閑所とはトイレのことで、漆の避箱(便器)が用いられ、ガラスは藤が描かれた摺りガラスが用いられています。「御寝室内天井」。「寝台」。そして「明治天皇御料車 6号御料車」。「明治天皇御料車 6号御料車」を横から。「御料車6号明治天皇用としては最後となる明治43(1910)年に製造された車両で、その内部の装飾などの美しさから「走る宮殿」との異名があります。外観は菊と桐の御紋が取り付けられ、車両の窓上部にも小型の菊や桐、鳳凰などが装飾されています。車両の全長は20.728mで、前方から大膳室・侍従室・御座所・侍従室・御寝室・御厠の順に配されています。御料車6号の装飾について 侍従室侍従室は御座所の両側に2箇所設けられていますが、こちらの侍従室の方が、やや広くなっています。いずれにも天皇陛下御乗降用の引出式階段が設けられています。室内の装飾は、天井に御座所と同じく蜀江錦が張られ、出入口扉の上部の欄間部分は漆・螺鈿で装飾されています。ここで特筆すべきは、折り上げ支輪部分の木象嵌です。楓の木目の美しい板に、鳥と雲、植物の図を表現しています。「蜀江錦の天井ど漆・蒔絵の欄間」。「御料車6号の装飾について 御座所蜀江錦(しょっこうきん)天井には蜀江錦と呼ばれる錦が用いられています。蜀江錦とは、もともとは3世紀、三国時代の中国の蜀の国(現在の四川地方)で、良質な赤地の絹織物が生産されたところからその名が付けられています。花文などを中央に配した八角形と四角形を組み合わせた亀甲分が代表的な文様とされ、今日ではこの文様が裂の名前とされるようになりました。ここでは、八角形の中央に皇室の紋、十六重弁の菊花(表菊)が様々な金糸を用いて織り出されています。七宝(しっぽう)御座所出入口上部の欄間には中央に十六弁表菊の飾りと、七宝で鳳凰を描いたものが取り付けられています。七宝の技法は下部の扉の漆の表現方法にあわせた技法が使用されています。漆・螺鈿(らでん)御座所出入口の扉には色漆が用いられ、加えて、鳳凰・桐・蝶・草花が夜光貝などの螺鈿で装飾されています。「御座所」。御料車6号の装飾について 御座所刺繍玉座の上部には花菱文の紋織りに、金糸で十六重弁の菊花(表菊)と金糸・銀糸で桐・小菊・唐草が刺繍されています。小菊の芯にあたる中央部分は地とは異なる技法を用い、立体感を出した写実的な作品となっています。金工(きんこう)十六弁表菊や唐草をモチーフにした錺金具は、各所にあしらわれ、その量はおびただしく、宮殿の装飾に引けをとらないほどです。調度品玉座は花菱文と十六弁表菊が織り出されたものと紫色天鵞絨(ビロード)で張られ、背あては金糸で十六弁表菊と唐草が刺繍されています。窓はガラス戸・網戸・日除けと三重になっており、御座所のみ玉座の背面に通路が設けられています。「御座所」。御料車6号の装飾について 侍従室侍従室は御座所の両側に2箇所設けられていますが、こちらの侍従室の方が、やや狭くなっています。いずれにも天皇陛下御乗降用の引出式階段が設けられています。出入口の把手にも細かな装飾が施され、細かな魚子に菊の御紋が打ち出され、扉に用いられている蝶番にも菊花が彫られています。室内の装飾は、天井に御座所と同じく蜀江錦が張られ、出入口扉の上部の欄間部分は漆・螺鈿で装飾されています。ここで特筆すべきは、折り上げ支輪部分の木象嵌です。楓の木目の美しい板に、鳥と雲、植物の図を表現しています。御料車6号の装飾について 御寝室と御厠御寝室の室内は御座所とほぼ同じ内装で、片側に寝台が設置されています。寝台の前後には菊の御紋を彫刻した装飾が取り付けられ、金糸で飾った濃紅色のカーテンが取り付けられています。寝台の反対側には御剣御璽(みつるぎぎょじ)を納める棚が設けられています。左側が御剣台、右側が御璽台とされています。御剣は三種の神器のひとつの「草薙の剣」、御璽も三種の神器のひとつ「八尺瓊(やさかに)の勾玉」を指します。これは常に天皇の近くにこれらの御璽などを置かなければならないという慣例があったためと考えられています。御厠側には摺り漆金蒔絵で装飾された御化粧台が置かれています。御厠は御料車としては初めて漆塗りの洋式便器が備えられています。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.30
コメント(0)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その15): 明治村7/16 三重県庁舎-2
正面側には二層のベランダが廻らされていて間口が54mに及ぶゴージャスで美しい洋館。2階のベランダからこの後に訪ねた「鉄道局新橋工場」を見る。ベランダを北西方向に歩き、正面の突き出た玄関方向を見る。「三重県指定伝統工芸品」の展示が行われていた。「三重県指定伝統工芸品👈️リンク三重県は、温暖で豊かな自然に恵まれ、また、古来より東海道という国の大動脈が通じており、お伊勢まいりに全国から多くの人々が集まったことから、経済産業大臣指定の伝統的工芸品(伊賀くみひも、四日市萬古焼、鈴鹿墨、伊賀焼)及び伝統的工芸用具(伊勢形紙)をはじめとした、多くの特色ある伝統工芸品が生まれ、今に受け継がれております。これらのうち、100年以上の歴史を有しながらも小規模な産地であるため、通商産業大臣の指定を受けることのできない工芸品を、「三重県の伝統工芸品」として県が指定し、郷土の伝統工芸の維持・発展を図っています。」「三重県指定伝統工芸品マークひらがなの”み"を変形した黒のラインで三重県を表し、同時にカギの組み合わさった形で伝統工芸品と、赤い四角形を頭として座って工芸を作る匠の姿を表現している。」「明治の三重と伝統産業」展示コーナー。「明治の三重と伝統産業このたび、旧三重県庁舎の一角を利用して、写真による明治の三重と伝統工芸品を紹介することになりました。明治40年(1907年)には、三重県津市で東海地方ではじめて「関西府県聯合共進会」(産業展示会)が開催されました。今回の写真展示は、明治村にふさわしいものとするため、この共進会の観覧者のための案内書(カイドブック)として発行された「三重県案内』を中心に使用し、当時の三重県の風景や産業・風俗などの一端を紹介しております。また、三重の風土と歴史のなかで育まれてきた伝統産業のうち、100年以上にわたる伝統的な手法による製造技法が受け継がれて、現在も私たちの生活のなかに溶け込んでいる伝統工芸品の展示も行っております。旧三重県庁含に合わせて、これらについてもこ覧いただたいと思います。」「明治の風景」。「伝統産業の風景」。「伊賀焼茶道が興隆した室町・桃山時代に茶の道具として注目されるようになりました。江戸時代中期以後には、耐火性の高い伊賀陶土の特質をいかした日用食器などが焼かれるようになりました。」「桑名萬古焼有節萬古の急須型の注文を受けてその秘宝を知ったくり物師佐藤久米造が1840年頃開窯しました。彼に技法を習った陶工も維新前後に輩出し、街道の土産物として栄えました。」「尾鷲わっぱ「尾鷲めんつ」とも呼ばれています。尾鷲地方で産出される尾鷲の檜材で作った曲げ物を漆塗りで仕上げた丸い弁当箱のことで、江戸時代から山仕事に行く人々に愛用されています。」「日永うちわ伊勢神宮の参拝客の土産品として約300年前から作られ、図柄は美しい美人画などが多く、色あざやかなため床の間の装飾用にも使われています。丸のままの竹を使用し、骨の数も多いため、弾力に富んでいます。」「伊勢一刀彫伊勢神宮参拝者への土産品として、古くから伊勢路に伝わる一刀流は、神宮御造営に奉仕する多くの宮大工たちが作った民芸品として発達し、最近では新しい作風も取り込まれています。正月には頒布の〇〇伊勢神宮干支守の製作が中心となっています。」近づいて。県知事席。大先輩と一緒に。桑名萬古焼の花瓶であっただろうか?「応接室」。休憩用椅子に使ってよかったのであろうか?再びベランダに出て。「展示室 明治の時計」。明治時代に製作され、実際に使われていた輸入・国産時計を展示していた。時計のデザインを見比べながら明治の時計の数々を楽しむことが出来たのであった。ここに展示されている時計は定期的にネジを巻いていますので、一部の時計は現在も時を刻み続けています と。「昔と今と時の稱呼比較」(右)。東風俗 福つくし「ふくどく」。作者 橋本周延/画年代 明治中期 明治22年(1889)伊東深水作「夜会巻」昭和39年伊東深水作「ボンボン時計」昭和42年(1967)。「厠(かわや)(トイレ)コーナー便所はどこでも家の隅っこか外にあって、子供にとっては夜は暗くてちょっと怖いところでした。たまった糞尿(大便や小便)は、くみ取り口という所からくみ出され、田畑の肥料に利用されました。うしろにその時に使う『肥桶』があるから、一度かついでみてね。」『肥桶』。「桶かつぎ明治時代は桶を使って水をくんだり、肥料となる糞尿を運んでいました。こぼしてしまったら大変ですね!」便器。「便器あれこれ・・・やさものの便器は江戸時代の終わりごろ、現在の愛知県の瀬戸市や常滑市て作られるようになりました。形はそれまでの木製の便器をまねていたのて、角ばった形てしたが、焼く技術も難しく、地震などて壊れやすい形でもありました。明治24年の濃尾地震の後、今よく見るような丸い形の便器が急速に広まったといわれています。」「染付大便器」。「染付朝顔型便器」。「手揚げ桶「水くみ桶」とも呼ばれ、水1斗(約18リットル)が入るように造られています。」「服わらいこの子たちを明治時代の人に変身させてあげましょう!明治時代には、なかったものもまざっているから気をつけてね!」「人力車」。廻り込んで。「人力車にのってみよう!人力車は明治2年(1869)に和泉要助・鈴木徳次郎・高山幸助の3人が横浜の居留地で外国人たちが乗っていた馬車をヒントに考案製作し、翌3年に日本橋で開業したのが始まりと言われています。それまでの駕籠に比べ1人で仕事が出来、しかもスピードも速いことから、日本各地で急速にその営業台数が増えました。しかし、実際は料金も高く、利用できたのは一部のお金持ちだけでした。その後、SLや電車といった大量輸送の乗り物や手軽な自転車の普及とともに次第に姿を消していきました。」「湯たんぽ」「こたつ」「御櫃(おひつ)と箱膳御櫃とは、桶のような形をしたふた付きの容器で、炊いたご飯を入れておくものです。飯びつやおはちとも呼ばれます箱膳は、卓袱台(ちゃぶだい)などのひとつの食卓が普及するまで、用いられていました。普段は食器類をしまっておき、食事の際は、蓋(ふた)を返して使用しました。(手前)炭火式アイロン。炭火式アイロンは明治時代から普及したアイロンで、外国から輸入されたことをきっかけに、日本でもたくさん作られるようになりました。まだ家庭には電気が普及していなかったため、炭火式アイロンも火のしと同じように、炭火を使って布のしわをのばしました。 炭火式アイロンにはふたがついているため、炭火が飛んで布を焦がすことがなくなりました。また、炭火を燃やしてでた煙を外に出し、燃えやすくするための煙突がつきました。アイロンのうしろには空気穴がついていて、温度が下がると空気穴を開けて空気を送りました。「こて、火のし、湯のし、炭火アイロン、電気アイロン」。「自転車」。「自転車自転車は1800年代初めにドイツ人が発明したと言われ、日本へはそれから約50年後の江戸時代末期に鉄輪をはめた前輪駆動のミショー型自転車が、外国人によってもたらされたと考えられています。その後、明治3年頃にはひとこぎでより多く進むために前輪を大きくしたオーディナリー型自転車が登場しましたが、運転が難しく事故も多かったため、明治20年頃から現在とほぼ同じ形をしたセーフティー型へと変わっていきました。」「三重県庁舎」の2階ベランダから再び「鉄道局新橋工場」を見る。「三重県庁舎」の南側2階ベランダから正面玄関方向を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.29
コメント(0)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その14): 明治村6/16 三重県庁舎-1
「森鴎外・夏目漱石住宅」を後にして、「偉人坂」を下って行った。1丁目の「森鴎外・夏目漱石住宅」から「三重県庁舎」方向へ向かう下り坂の石畳の道。「⑬三重県庁舎」案内板。「⑬三重県庁舎」。正面から。「三重県令(現在の知事)岩村定高の発案による洋風県庁舎。明治13年(1880)には明治天皇も行幸され、昭和39年(1964)まで使用されました。明治政府が急速に地方行政の整備を進めると県令はこのような洋風庁舎を新築することが多くなりました。三重県庁舎は、間口が54mに及ぶ大きな建物で、玄関を軸に左右対称となっており、正面側に2層のベランダがめぐらされています。 中央に玄関と車寄を置き、前面にベランダをつけて左右対称とする構成は、明治9年(1876)に建てられた内務省庁舎にならったもので、明治初期の木造官庁舎の典型といえます。設計者は当時、県の土木掛にいた大工の清水義八。清水はその後、同市内に造られた三重県尋常師範学校・蔵持小学校(1丁目3番地)も手がけました。」と。「1丁目13番地 三重県庁舎 <重要文化剤>旧所在地 三重県津市肇町建設年 明冶12年解体年 昭和39年移築年 昭和41年建築面積 267.4坪構造 木造ニ階建寄贈者 三重県三重県庁舎は県令(現在の知事)岩村定高の発案による洋風の庁舎で、三重県の大工、清水義八をはじめとする三重県土木掛によって手がけられた。明冶13年(1880)には明冶天皇も行幸され、昭和39年(1964)まで使用された。明冶6年(1873)明冶政府が急速に地方行政の整備を進めると、開明的な県令はこのような洋風序舎を新築するようになった。正面にニ層のべランダを廻らした左右対称の構造は、明冶9年(1876)に建てられた内務省庁舎を模している。また扉や窓、さらにその額縁は西洋から伝えられた目塗りという技法で塗装されている。清水はその後同市内に造られた三重県尋常師範学校・蔵持小学校(現在明治村内所在)も手がけた。現在、建物内では、明冶20年(1887)に改築された知事室など主要な室内を再現しているほか、明冶の時計、明治の宮廷家具などの展示室が常設されている。」「⑬三重県庁舎 明治十二年」。ショーケースには「明治偉人隊」案内が。「博物館明治村公式おもてなし隊明治偉人隊明治偉人隊とは令和元年5月1日に現世へ甦った明治の偉人。現代の若者の体を借り、歌や踊り、お芝居を通して明治時代の価値、魅力を存分に伝えるべく、活動中。」と。「福澤諭吉」、「松井須磨子」、「津田梅子」・・の名が。基壇と礎石、円柱、エンタブレチュアは、古代ギリシャ・ローマの神殿に由来した構成。出入口や窓も洋風の要素として、半円アーチや円弧アーチの形が取り入れられていた。移動して。明治村には映画のロケ地となった建物がたくさん、あった。「坂の上の雲」のロケ地となった建物の一つがこの「三重県庁舎」である と。「スペシャルドラマ 坂の上の雲」👈️リンク ポスター。司馬遼太郎が10年の歳月をかけ、日露戦争とその時代を生きた明治の青春群像を渾身の力で書き上げた「坂の上の雲」を原作として描く人間ドラマ。明治維新によって、はじめて「国家」というものをもち、「国民」となった日本人。近代国家をつくりあげようと少年のような希望を抱きながら突き進んだのが「明治」という時代であった。松山に生まれた3人の男、バルチック艦隊を破る作戦を立てた秋山真之、ロシアのコサック騎兵と対等に戦った秋山好古、そして俳句・短歌の革新者となった正岡子規。彼らは、時代の激流に飲み込まれながら、新たな価値観の創造に立ち向かい、自らの生き方を貫き、ただ前のみを見つめ、明治という時代の坂を上っていった。生まれたばかりの「少年の国」である明治の日本が、世界の中でいかに振る舞っていったかを描く。入口左には「案内板」が並ぶ。「作品に見る松山の風景」👈️リンク。かっての士族町を歩きながら、ふと構想された小説「坂の上の雲」。司馬さんの大好きだった子規が、仲間とともに、明日を夢見て語りあった青春の日々を彼らのふるさと松山に見る----。①坂の上の雲ミュージアム②松山城③萬翠荘④二之丸史跡庭園⑤ロシア兵墓地⑥松山中学校・勝山学校跡⑦秋山好古・真之兄弟銅像⑧秋山兄弟生誕地⑨子規堂⑩秋山好古の墓⑪明教館⑫四国霊場第五十一番札所石手寺⑬道後温泉本館⑭子規記念博物館」小説「坂の上の雲(さかのうえのくも)」。「坂の上の雲」は、司馬遼太郎の歴史小説。明治維新を成功させて近代国家として歩み出し、日露戦争勝利に至るまでの勃興期の明治日本を描く。「産経新聞」夕刊に、1968年(昭和43年)4月22日から1972年(昭和47年)8月4日まで1296回にわたり連載された。「「まことに小さな国が、開花期を迎えようとしている」この書き出しで始まる「坂の上の雲」は、日本を代表する作家である司馬遼太郎の長編小説です。司馬氏はこの小説の中で、松山出身の正岡子規、秋山好古、真之の三人を当時の日本人の代表としてとらえ、日本人がどのように生き、振る舞ったのか、そして明治から激動の昭和日本へと向かった時代背景を、克明に描いています。この小説のあとがきには「のぼってゆく坂の上の青い天にもし一朶の白い雲がかがやいているとすれば、それのみをみつめて坂をのぼってゆくであろう」と書かれていますが、「坂の上の雲」から読み取れる主人公たちの生き方、そして歴史の教訓は、司馬氏が21世紀に生きるわたしたちに送るメッセージなのです。」「時代を語り、物語を彩る人たち」夏目漱石 本名、金之助、子規とは、東京大学予備門時代に知り合い、第一高等学代に交友がはじまる 根岸の子規宅を訪れたこともある。明治26年の帝大卒業後、東京高等師範学校に務めたが、 人生の目的を見出せず鎌倉で参禅。明治28年4月、愛媛県尋常中学の英語教師として赴任した。 そのころ、日清戦争に従軍して肺結核を悪化させた子規が神戸須磨での療養後に帰郷、漱石の 下宿先である愚陀仏庵に転かり込む。この愚陀仏庵での共同生活は、漱石が文学の世界に入る きっかけとなった。 漱石は、留学先のロンドンで子規の訃報(ふほう)を受け取った、帰国後、高浜虚子が主幸する 「ホトトギス」に「吾輩は猫である」を発表したのを機に、「坊っちゃん」など多くの名作を 書き、明治を代表する作家となった。陸羯南 本名、中田実。津軽出身。上京し、秀才養成のために創設された司法省法学校で、子規の叔父・ 加藤拓川と友人になるが、学校運営に抗議し、退校処分になる。渡仏する加藤からおいを頼むと 託されたのは、太政官文書局の翻訳官だったころ、職を転じ、明治22年、新聞「日本」を 創刊するが、硬派の論説新聞として政府を攻撃したため、たびたび発行停止処分を受けた。 反骨の士としての顔を見せる一方で徳にあつく、帝国大学文科大学を退学した子規を社員に 雇い、母や妹も呼び寄せて自分の家近くに住まうことを勧め、子規が新聞以外で書くことを 温かく見守るなど、「此様(このよう)な人はあまり類がないと思う」と子規か感謝し続けた 人でもあった。高浜虚子 子規の高弟としてその偉業を大成する虚子も、最初は、東京にあこかれる純情な中学生だった。 子規と知り合ってから文学に「小説家になりたいから、鷗外か露伴の弟子になれるようあっせ んしてほしいと手紙を送ったり、高等学校を中退し、碧梧桐とともに子規に入り込んだりと、文学 青年の一途さを見せて子規を当惑させる。 戦地で従軍して結核を悪化させた子規を須磨保養院で献身的に看護◯時期に子規から後継者に なってほしいと望まれたが固辞した。死期にある子規を慰めてさまざまな会を開き、筆が 執れなくなってから代わって口述筆記するなど、子規の創作を最期まて支えた。河東碧梧桐 本名、秉五郎。子規没後、「新傾向俳句」の旗手となり、自由律俳句の俳人たちが傾倒する など、虚子とともに子規の高弟として双璧をなした。碧梧桐が「秉公」と呼ばれていた 中学生のときに、べースボールを通して子規と出合う。 幼少時は秋山真之とも交わり、餓鬼大将だった「秋山のしゅんさん」が先頭に立ってけんか するとき、「われわれ悪童どもは胸が一杯になってきて、天下に恐いものはいないという ような勇気やら安心感が湧いた」と、晩年に当時のことを語った。また真之が若き日、共に 文学をやろうと子規と誓い合った仲だということにも懐かしみを感じ、好んで人に披露した。「登場人物紹介小説『坂の上の雲』の主人公と周辺の人びと「松山が生んだ近代俳句の祖 正岡子規 1867~1902」・楽天家子規の夢、青春・喀血、退学、小説家断念 ・・・ 挫析と文学への執念・文学的生命をかけて「君を送りて 思ふことあり 蚊帳に泣く」 子規は、アメリカへ留学する友人秋山真之に送別の俳句を書いて、新聞にのせているのだ。「海軍連合艦隊参謀 秋山真之 1868~1918・「秋山の淳ほと悪いやつはいない」・世界の海軍をみる・人生観を変えた日本海海戦・戦術のエキスパートに「本日天気晴朗ナレドモ波高シ」 このことばが生まれたのは、1905年(明治38年)5月27日の早朝のこと。 当時日本と戦争中だったロシアは、ヨーロッパのバルト海に配備していたバルチック艦隊を 日本海に向かわせていたのだが、これを発見した日本の連合艦隊は東京の軍令部に対し、 「敵艦見ユトノ警報ニ接シ、連合艦隊ハ直チニ出動、之ヲ撃滅セントス」という電文を送る。 この末尾に付け加えられた一文が、「本日天気晴朗ナレドモ波高シ」。 これは、これから決戦に向かう心意気を表した名文として知られているが、実はこの一文には 深い意味が込められていたのだと。 この一文を付け加えたのは、日本海海戦の作戦を考えた海軍参謀の秋山真之(さねゆき)。 秋山は、頭の切れる天才的な戦術家であったが、彼はこの一文で何を伝えようとしたのか? 秋山真之の深い意図とは? 「本日天気晴朗ナレドモ波高シ」 まず、この一文の前半「天気晴朗」の4文字には重要な意味があった。 バルチック艦隊は日本海に面したロシアの軍港・ウラジオストクを目指していたが、そこに 入港されると日本としては実にやっかい。ロシアに制海権を奪われてしまう可能性があったから。 そのため敵艦を取り逃がすわけにはいかなかったのだが、実は日本海軍には、過去に濃い霧の ため敵に逃げられた苦い体験が何度もあったのだと。 こうした中で出されたメッセージ「天気晴朗」。 これは、霧で敵艦を見失う可能性が小さいことを端的に伝えていたのです。 では「本日天気晴朗ナレドモ波高シ」の後半部分、「波高シ」にはどんな意味が込められて いたのか? これには、大きく2つの意味がありました。 まず1つ目。 当初、日本海軍は小型艇による先制攻撃を予定していた。 ところが、波が高いと小型艇は出撃できない。 つまり「波高シ」の3文字は、このプランを取りやめることを示していた。 そして2つ目。 小型艇の出撃がない場合、戦いは大型艦同士による大砲の撃ち合いになる。 大砲は波が高いと命中率が下がりますが、そこで重要になってくるのが水兵の砲撃技術。 この点、日本の連合艦隊は訓練をしっかり行っていたので、砲撃の精度はロシアより高いと 自信を持っていた。 つまり「波高シ」という3文字は、日本有利の状況で進むこれからの戦いの行方を暗に 知らせるものであった と。 一見、文学的に聞こえる一文「本日天気晴朗ナレドモ波高シ」。 実は、冷静な情勢分析を伝えたことばでもあったのだ と。「陸軍”騎兵の父” 秋山好古 1859~1930・貧乏から抜け出すための官費の学校・生涯の仕事となる騎兵の道へ」・戦いの日々・・・・陸革大将から郷土の私立中学校の校長に「男子は生涯一事をなせば足る」 この言葉は、人生において一つのことをやり遂げるだけで、その人生は十分価値があるという 深い意味を持っています。この言葉には、以下のような思想や価値観が含まれています。1. 人生の意義は自己実現にある ・人生の成功は、多くのことを達成することではなく、自分の信念や情熱を持って一つの ことに集中し、それをやり遂げることにあるという考え方です。 ・「一事」は特定の仕事や目標だけでなく、自分が心から価値があると感じる「使命」や 「夢」を指すこともあります。2. 量より質の重視 ・多くのことを中途半端に手がけるよりも、一つのことを深く極めることの重要性を 説いています。 ・人生の質や充実感は、達成したことの数ではなく、その深さや影響力にかかっているという 教えです。3. 集中力と執念の美徳 ・一つのことを成し遂げるためには、長期間の努力や困難の克服が必要です。この過程 そのものが人生を豊かにし、人間としての成長を促します。 ・成功には忍耐と執念が不可欠であり、その姿勢が美徳とされています。4. 人生の有限性の認識 ・人生は有限であり、すべてを達成することは不可能です。そのため、自分のエネルギーを 何に注ぐべきかをよく考え、選んだ一つのことに専念すべきだというメッセージでも あります と。小説『坂の上の雲』の主人公と周辺の人びと「「坂の上の雲」登場人物相関図」をネットから。「明治の日本海軍--秋山真之と広瀬武夫の交流陸軍出身の西郷従道は、明治18 (1885)年~23年、明治26 (1893)年~ 31年にかけて海軍大臣を務めました。西郷と、海軍兵学寮卒で日本海軍きっての軍政家である山本権兵衛は、明治の日本海軍をともに育てた名コンビでした。懐の深い西郷海軍大臣のもと、山本はその手腕をいかんなく発揮し、大胆な海軍改革を遂行していきました。日清戦争後のロシアを中心とする三国干渉で、「臥薪嘗胆」の機運が国内世論においても高まるなか、山本を中心に明治29年から10ヵ年におよふ海軍拡張計画が起案され、西郷の後押しによって第10回帝国議会で議決されます。この計画のなかで山本が特に力を入れたのが建艦であり、甲鉄戦艦6隻、一等巡洋艦6隻等からなる「六六艦隊」の創設が目指されました。すべて英・仏・独の造船会社へ発注するなど巨額の資金が投入され、「六六艦隊」のなかで最後の建艦となった戦艦「三笠」は日露載争の2年前、明治35年3月に日本海軍に引渡されたのです。明治33年4月30日、英国で建造中の「三笠」を視察したのが欧州留学中の秋山真之と広瀬武夫。将来を期待された若手海軍将校の二人は、4月25日から6月14日にかけて英・仏・伊・独をめぐり、「六六艦隊」のうち戦艦「朝日」、一等巡洋艦「吾妻」・「八雲」のほか、各地の軍港や製鉄所を調査しています。4年後に勃発した日露戦争において、広瀬は戦繿「朝日」の水雷長として、真之は連合艦隊参謀主任として旗艦「三笠」に乗組み、対露作戦に臨みました。」「広瀬武夫明治30年6月からロシアに留学、情報収集につとめ、海軍ーのロシア通として知られるようになる。明治33年には、秋山真之らとヨーロッパの視察旅行を実施した。」「乃木希典と秋山好古博物館明治村に残る「学習院長官舎」は、陸軍大将・乃木希典が学習胱の第10代院長(明治40年1月31日~大正元年9月3日)を務めていたころに建てられました。松山出身で「日本騎兵の父」と呼ばれる秋山好古は、副官に「俺と乃木大将とは何処か似ているよ」と時々語っていたといわれています。乃木と好古の間にはどのような交流があったのでしようか。伝記「秋山好古」に描かれたエピソードをいくつか紹介します。フランスでの出来事明治20 (1887)年1月から明治21年6月にかけての約1年半、当時陸軍少将であった乃木希典は、ドイツ軍の兵制・兵学研究のためドイツに留学しました。これは、普仏戦争(1870-71年)にドイツがフランスに勝利した結果、明治19年に日本の陸軍がこれまでのフランス式兵制からドイツ式兵制へと転換したことに起因しています。一方の秋山好古は、陸軍での流れと逆行して、明治20年7月からフランス騎兵について学ぶことになるのです。日露戦争での出来事秋山好古が率いる騎兵第一旅団は、奥保鞏(やすかた)率いる第ニ軍の戦聞序列に編入され戦地へと向かい、明治37年5月の遼東半島上陸後、北上する第ニ軍の最左翼で任務にあたります。明治38年1月には、日本陸軍最大の危機であった「黒溝台の戦い」を何とか耐え忍びました。一方、乃木希典率いる第三軍は旅順攻略後の明治38年1月に北上を開始し、第一・ニ・四軍に合流。日本軍とロシア軍が大兵力を投入し、日露戦争最大の戦いとなった「奉天会戦」(明治38年3月)では日本軍の最左翼にあり、ロシア軍の右翼を包囲・攻撃しました。好古率いる騎兵第一旅団は、奥第ニ軍司令官からの命令により乃木第三軍に所属され、奉天会戦を乃木とともに戦っています。明治38年8月、アメリカのポーツマスで日露講和会議が開かれていた頃、戦地では乃木希典◯◯三軍配下の駐留地を巡視し、◯◯のもとを訪れました。」「秋山真之1904(明治37)年2月、日本とロシアの間で戦争がはじまり、」「鉄子の部屋」。「鉄子の部屋」では、明治村が所蔵する鉄道資料が展示されていた。輸入レールや閉塞器、時刻表や切符など、鉄道ファンはもちろん、大人や子どもも楽しめる資料が公開されていた。「タブレット閉塞器」1.タブレット タブレットとは、金属製の円盤または楕円形のプレートで、区間ごとに固有の識別情報が 刻印されています。2.閉塞区間 単線区間では、ある一定の区間を「閉塞区間」と定め、一度に1列車しか進入できないように しています。3.タブレット閉塞器の動作 ・列車が閉塞区間に進入する際、運転士は駅でその区間のタブレットを受け取ります。 ・タブレットを持っている列車だけがその区間に入ることを許されます。 ・区間の終わりの駅で運転士がタブレットを返却します。4.タブレット閉塞器本体 タブレット閉塞器は駅に設置され、タブレットの発行や回収を行います。閉塞器同士は電気的に 連動しており、片方の閉塞器でタブレットが取り出されると、もう片方ではタブレットが 取り出せない仕組みになっています。メリット ・同一区間に複数の列車が進入する事故を防止できる。 ・機械的で信頼性が高く、電気や通信がない時代にも利用可能。左から「土岐口」「駄知」の文字が。駅名なのであろう。私が子供の頃、市内の江ノ電でこのタブレットが使われていたのを、何回か見た記憶があるのだ。これが「タブレット」。日本鉄道地図。大日本全図。左からポスター、寿語録、鐵道案内圖。「名古屋一宮犬山間電車開通」ポスター。「ポスター名古屋 一宮犬山間 電車開通名古電気鉄道株式会社 明治45年/大正元年 発行久保田金僊 画 色刷石版現在の名古屋鉄道犬山線につながる路線の開通「大正元年8月6日)を告げるポスター。起点が「柳橋」になっている点など、現在と異なる点も多い。また「開通記念絵葉書」「郡部線時刻表」と比較してみると、路線が延伸して行く様子、駅名の変遷がわかります。」「鐵道壽語祿」。「東海道鉄道寿語録(すごろく)西京(京都)七條駅を「ふりだし」に、東京・新橋駅で「あがり」となるすごろく。新橋駅到着後は、儀装馬車1号で皇居から行幸される天皇のお姿を見ることが出来るストーリーは、明治21年から23年の、明治宮殿竣工、大日本帝国憲法発布、帝国議会開設など、国家的行事が重なった時期を彷彿とさせるものです。また東海道線全通は明治22年7月です。」「東京市街電車鐵道案内圖」「東京市街電車鉄道案内三電車合同線各電車停留所及乗換所一覧表」。様々な国での使用レール。近づいて。「レールのふるさと」。1.ベスレム製鋼株式会社 アメリカ 18752.アルバニー&レッBスラー製鉄会社 アメリカ 18803.スクラントン・スチール アメリカ 18804.モス・ベイ製鋼 イギリス 18825.カンブリア製鋼会社 アメリカ 18836.新ロシア工業 ロシア 18957.ナデージダ工場 ロシア 19028.カーネギー鉄鋼会社 アメリカ 19049.南ロシア・ドニエブル金属工業 ロシア 1904 10.ドルトムント鉱山製鉄連合(株) ロシア 190711.キャンメル社 イギリス 190712.テネシー石炭 アメリカ 1927「コントローラー」。「コントローラーこのコントローラーを製作したブラウン・ボべリ(BROWN-BOVERI)宅に1891年スイスのバーゼルで創業し、1986年にスウェーデンのアセア(ASEA)社と合併し、現在はABB社となっています。このコントローラーは北陸鉄道山代線で使用されたものです。」コントローラは電動車の速度や動作を制御する装置。運転士がレバーを回すことで、抵抗器やスイッチを切り替え、モーターの出力を変化させたのだ。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.28
コメント(0)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その13): 明治村5/16 森鴎外・夏目漱石住宅
紅葉に囲まれた遊歩道を北に進む。陽光が欲しいのであったが。前方左に現れたのが「森鴎外・夏目漱石住宅」。「森鴎外・夏目漱石住宅旧所在地 東京都文京区駒込千駄木町建設年 明治20年解体年 昭和38年移築年 昭和39年建築面積 39.2坪構造 木造平屋建寄贈者 斎藤文根この建物は当初は医学士中島襄吉の新居として建てられたものであるが、明冶の文豪森鴟外と夏目漱石が時を隔てて借りた家である。鴎外は朋冶23年から1年半ほどこの家に仕み、『文づかひ』などの小説を書いた。約13年後、漱石が明治36年から約3年住み、『吾輩は猫である』を書いて文壇でその名を高めた。文中ではこの家の様子をよく描写している。住宅としては玄関脇の張り出した和室(書斎)、台所から座敷への中廊下は住宅の近代化の先駆けとみることができる。なお、漱石が住んでいた頃、書斎の東北隔に幅6尺・奥行3尺で西向きの押入があったことを示す痕跡が発見されたが、資料不足のため復元を行っていない。」「漱石さんのお宅訪問住宅内の一部を、文献や古写真などをもとに、夏目漱石が「吾輩は猫である」を執筆した当時の様子に再現しています。漱石になりきって写真を撮ったり、漱石の本を持ってきて読んでみたり、いろいろな楽しみ方で漱石が住んた家を満喫して下さい。」玄関を見る。「漱石のこどもたち千駄木町にあった、この家の前で撮った写真(明治39年ごろ)。左から長女:筆子さん、 次女:恒子さん、 三女:栄子さんです。」田の字型の平面をベースにした明治時代の典型的な中流住宅の間取り。玄関を入ると左側・南面に突き出した八畳書斎は陽当り良好のようであった。小物まで忠実に再現されている台所・炊事場。近づいて。浴室用桶も。左横が風呂場入口引き戸。摺鉢、酒徳利も。近づいて。「明治時代の台所左の絵はアメリカ人の動物学者E・Sモースによって描かれた。明治10年代頃の東京にあった台所です。絵が描かれた当時、ガスや電気、水道は整備しておらず、煮炊きをするには、かまどや七輪に薪や炭で火をおこし、洗い物などをするためには、外にある井戸から水を汲んできました。夏目漱石が住み始めた当初は、絵と同じように、現在土間になっているところにあったと考えられます。この家の台所は、現在の台所と室内の様子はずいぶん異なりますが、明治時代の一般的な家庭の台所の様子を伝えています。右の写真は、明治時代の中ごろに外国人の写真家によって撮影された、台所でタ食の準備をしている様子です。明治時代の一般家庭の台所では、野菜を切る、すり鉢を使うなどの調理は座って行いました。そのためまな板には、座ったままでも力が人るように足がついています。また、ご飯を炊くためにかまどで火をおこしている女性がいますが、ご飯を炊く、という作業ひとつをとってみても、当時の調理には時間と手間がかかっていました。台所で使う道具は今と変わらないものもありますが、その使い方や人の姿勢、そして調理の手間などには大きな違いがありました。」「都市の家屋の台所日本人のすまい E・S・モース」明治時代の中ごろに外国人の写真家によって撮影された、台所でタ食の準備をしている様子。「飯櫃(めしびつ)釜で焚いたご飯を入れておく木製の器。「おひつ」「おはち」とも呼ばれます。」「膳料理を食べる時にのせる台。家族がひとつの食卓で食事をするようになる前は、ひとりひとりの膳に料理をのせて食事をしました。」六帖客間には森鷗外と夏目漱石のパネルが。明治村の人物のパネルには身長と体重が書かれているのが面白いのであった。奥には6帖間、8帖客間、5帖寝室、その北側に6帖子供部屋、その東に6帖の茶の間、女中部屋が続く。「夏目漱石慶応3年(1867)1月5日~大正5年(1916)12月9日東京都出身身長 158.7cm体重 52.3kg」「森鷗外文久2年(1862) 1月19日~大正11年(1922) 7月9日島根県出身身長 161.2cm」「森鷗外・夏目漱石住宅について森鷗外・夏目漱石住宅が明治村に来た経緯この家は、明治20(1887)年頃東京の千駄木に、医学土・中島襄吉の父で、東京で商売を営んでいた中島吉利によって建てられました。住んだ時期は異なりますが、森鷗外、夏目漱石という明治時代を代表するニ人の文豪が借りて住んだ住宅です。奇跡的に戦争や震災の被害を免れ、昭和25(1950)年に東京都の史跡に指定されます。しかしながら、昭和37(1962)年に所有者であった斎藤家が土地を売却することとなり、史跡の指定が解除されます。これにともない、明治村では建物を譲り受けて、移築する運びとなりました。昭和38(1963)年に解体工事が始まり、解体された村料が明治村へ運ばれた後、昭和39(1964)年6月1日から約6ヶ月かけて移築工事が完了しました。移築に際しては、建物の部材に残る痕跡や古図面などを参照しましたが、書斎東面の押入など資料不足により復元しなかった箇所や、補強のために補ったものなどがあります。現在建物内では、文献や古写真などをもとにして、夏目漱石がこの家に住んでいた当時の様子を一部再現しています。この家に住んだ二人の文豪名前:森鷗外(本名:林太郎)生没年:文久2(1862)年・大正11(1922)年この家に住んだ時期:明治23(1890)年10月・明治25(1892)年1月東京大学医学部を卒業後、陸軍軍医となります。その後ドイツ留学を経て軍医として要職に就きながら、小説や医学、文学、美学の評論や、海外の小説や戯曲など多数の著作を残しました。この家に移り住む明治(1869)年の一月には、代表作「舞姫」を発表。その後.「舞姫」と同様にドイツ留学時の経験をもとにした「文づかひ」を発表したり、文芸雑誌「しがらみ草紙」の創刊などにも携わりました。親交のあった人:樋口一葉(1872-1896)歌人・小説家森鷗外が幸田露伴、斎藤緑画とともに創刊した文芸雑誌「めさまし草」で、代表作「たけくらべ」が高く評価されました。名前:夏目漱石(本名:金之助)生没年慶応3(1867)年・大正(1916)年この家に住んだ時期:明治36(1903)年・明治39(1906)年12月英語教師を経てイギリスに留学。帰国後は東京帝国大学などで英文学を教えながら、小説家としても創作活動を始めます。明治40(1907)年に朝日新聞社に入社した後は、職業作家として数多くの作品を残しました,代表作である「吾輩は猫である」は、この家での生活がモデルとなっているほか、「坊っちゃん」や「草枕」といった作品も、夏目漱石がこの家で幕らしていたときに発表されたものです。親交のあった人:正岡子規( 1867-1962 )俳人・歌人漱石と同じ年に生まれ、第一高等中学校で出会って以降、子規が病で命を落とすまで、お互いの作品を批評し合うなど交友が続きました。」たくさんの本や筆が並べられており、当時のままを忠実に再現していた。ここでは、漱石になりきって写真撮影をすることも可能であった。八帖客間。床の間には掛け軸が。最後の作品「明暗」の下書き原稿(複製)を発見!漱石自身が執筆した文字を見ることができるのは、なんともいえない特別感なのであった。漱石専用の原稿用紙のデザインからも、アートな一面が垣間みられたのであった。廊下側から八帖客間。その奥に六帖茶の間。六帖茶の間。移動して。五帖寝室と奥に六帖間。ガラス戸越しに外を見る。何と書かれていたのであろうか?師匠から「空斎の及第せしとき 貧乏な進士ありけり時鳥(びんぼうなしんしありけりほととぎす)」湯浅康孫(漱石の門下生)に漱石が贈った句とのこと。書院欄間の透かし彫り。竹が画かれていた。前庭の石碑。庭にあった鴎外の詩『沙羅(ナツツバキ)の木』「褐色の根府川石に白き花はたと落ちたりありとしも青葉がくれに見えざりしさらの木の花」。詩: 森鴎外作この石に刻まれているのであろうか?南側の前庭から五帖寝室(左)、鉢帖客間(右)を見る。8帖書斎前から。八畳書斎の猫。「猫の家」と呼ばれていた夏目漱石の家。「吾輩は猫である」のモデルとなったのは、夏目家に迷い込んできた一匹の猫でした。全身が黒ずんだ灰色の虎斑の子猫で、爪の先まで黒かったようです。」そして紅葉を楽しみながら。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.27
コメント(0)
-

今年も地元の「天嶽院」の紅葉を愛でに(その5)
再び参道まで戻る。山門前から。山門脇の紅葉。「山門」の屋根を見上げて。山門を潜って。「仁王像」と「山門」を再び。「山門」右手の大きな台座に鎮座する「聖観世音菩薩立像」を見る。ズームして。そして県道312号線・田谷藤沢線に向かって「六地蔵尊」が並んでいた。通りに面し通行人に語り掛けるような優しいお顔で。道路沿いのフェンスの影が地面に映り込んで。「温顔和楽」と刻まれた石碑。「和楽」とは なごやかに楽しむこと。互いにうちとけて楽しむこと。常にこのお地蔵様のごとくに「温顔和楽」の日々でありたいが。右から、「ほかほか地蔵」。「らくらく地蔵」。「ふくふく地蔵」。「にこにこ地蔵」。「すくすく地蔵」。「いきいき地蔵」。振り返って。この石碑には「純未生流之碑」と刻まれていると。先程訪ねた「鐘楼」方向を見る。白塀の角にあった石碑。これも以前、訪ねた際のブログにて高校時代の友人から教えて頂きました。「古松談般若(こしょうはんにゃを だんじ)幽鳥弄真如(ゆうちょう しんにょ をろうず)」👈リンク という一対の禅語の言葉であると。古い松の木が風に吹かれて悟りの智慧を説き、山奥に棲む鳥が真実の教えを説きながらさえずっている。すなわち、周囲を見渡せば森羅万象が等しく尊い教えを説いている。この世界そのものが悟りの世界にほかならない と。再び「聖観世音菩薩立像」に向かって歩く。この坂を上ると墓苑が拡がっているのだ。「八幡桜」。「八幡桜」。「鎌倉八幡宮若宮大路の段葛より移植された晋山(しんざん)記念の桜である。八幡桜の銘は𠮷田宮司による。 平成廿八年降誕祭 天獄院廿九世正三謹誌」「聖観世音菩薩立像」を見上げて。お顔をズームして。「慈光遍照」と刻まれた石碑。「お大師様(空海)は、常に私どもにお救いの御心「慈光(じこう)」を遍(あまね)く照らされておられますので、いつでもお大師様の存在を感じる心をお持ちください。そしてお大師様を心に念じながら合掌して『南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)』をお唱えすることにより、本来自身に備わっている穢(けが)れのない清浄なる心の鍵が開き、御仏に包まれ抱かれている境地と共に、どんな場面でも常に仏様と共に歩んでいるという安らぎと喜びを実感できると思います。」と。「聖観世音菩薩立像」前から、我が友人が卒業された「藤沢市立藤ヶ岡中学校」を見る。「聖観世音菩薩立像」前から「山門」を。白壁に映る我が姿を自撮り。そして山門の額縁に入った「天嶽院」の紅葉を最後に。今年の「天嶽院」の紅葉も見納め。 ・・・もどる・・・ ・・・完・・・
2024.12.26
コメント(0)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その12): 明治村4/16 碧水亭~西郷従道邸
「聖ヨハネ教会堂」を後にして、紅葉を楽しみながら「明治村」の散策道を北東方向に進む。右手に「和食処 碧水亭」の案内板。「和食処 碧水亭」。入鹿池と日本庭園を見渡せる和食処であると。案内板。「和食処 碧水亭」入口正面。「宮沢賢治のえび天そば宮沢賢治の好物の天ぶらそばに、同じくお気に入りのサイダーを組み合わせました!」と。1600円。その下に様々なメニューが案内されていた。店内の写真をネットから。「天丼定食」か。カエデの紅葉。水鉢に浮かぶモミジ葉。そして次に訪ねたのが「⑧西郷従道(つぐみち)邸」。明治初期の貴重な洋館建築の一つ。西郷隆盛の弟、西郷従道が建てた住宅のうち、接客用に設けられた洋館。従道は陸海軍の大臣を歴任していたため、在日外交官の来客も多く、明治22年(1889)には明治天皇の行幸も仰ぎました。設計にはフランス人レスカスが関与していると伝えられ、建築金具や階段などをフランスから取り寄せているほか、2階には日本三景が描かれた陶板で飾った暖炉も設置されています。この建物は耐震性を高める工夫がなされています。屋根には軽い銅板が葺かれ、野地板が斜めに張られているほか、外壁は柱間に落とし込んだ本実下見板張りとなっています と。移動して見上げて。「1丁目8番地 西郷従道邸旧所在地 束京都目黒区上目黒(西郷山)建設年 明治10年代解体年 昭和38年移築年 昭和39年建築面積 76.8坪構造 木造ニ階建銅板葺寄贈者 日本国有鉄道」この建物は西郷隆盛の弟、西郷從道が建てた住宅のうち、接客用に設けられた洋館である。從道は陸軍の大臣を歴任していたため、在日外交館の来客も多く、明冶22年(1889)には明冶天皇の行幸も仰いだ。設計にはフランスレスカスが関与していると伝えられ、建築金具や階段などをフランスから取り弁せているほか、2階には日本三景が描かれた陶板で飾った暖炉も設置されている。この建物は耐震性を高める工夫がなされており、屋根には軽い銅板が葺かれ、壁の内側にはおもりとなるように煉瓦が埋め込まれていた。」西郷従道邸横のモミジ。ズームして。青空であれば・・・・。玄関ポーチ。玄関ポーチの天井は、細かい菱組天井になっていた。二階はフランス窓風に。「建物ガイド 西方従道邸」案内板。玄関の内側から。玄関ホールの「西郷從道天保14年( 1843 ) 5月5日 明治35年(1902)鹿児島県出身身長160Ccm (推定)」ここにも「建物ガイド 西郷從道邸」「明治村 錦絵れきし探偵団」。「顕舞蕗の略面」楊周延画」。玄関ホール。玄関ホールの天井。「豆知識この部屋の天井は、鉄板を押して成形したものが張られています.近代以前の建物に多く見られる『石彫」『木彫』などの装飾を、産業革命によって生まれた大量生産品で代用するようになったものです。」しかし、明治10年頃の日本では超高級品に値いしました.ニ階べランダでも見られます。絵画。誰の作品であっただろうか。私の姿も映り込んでしまっていたが。客用食堂・応接室。移動して斜めから。ティーカップ。客用食堂の窓の外には紅葉が。ティーカップと大皿。西郷従道邸案内図。2階の見学は不可であった。書斎。玄関わきの北側の部屋。書斎の天井を見上げて。落ち着いた質素?な照明。客用の食事場所か。椅子はバルーンバックチェア。テーブルの脚は、テーパードで、フルーティングが施された、アダムフル―テッドと呼ばれもの、窓際のカウンタ―テーブルの天板が大理石、側面には彫刻がついてる とネットから。書斎の丸テーブルが絨毯の上に。さらに書斎を。執務用の机か。左手前方に世界地図。「西郷従道が取り組んだこと戦のあとを考えて台湾出兵の都督となった西郷從道は、原住民同士の争いを利用しながら、相手が降伏すれば優しく、歯向かえば家を焼き尽くすなど、徹底的に攻撃するというやりかたで、ニ度と台湾が日本に敵対できないことを目指した。西南戦争でも、武器購入、各地の士族動向の調査、兵士の人員調整などを行い、戦後の反乱防止に努めた。」独立した軍を目指して台湾出兵や西南戦争の後、病死を除く、「天皇のために戦った」戦死者に対し、東京の招魂社にて合祀の祭礼を行う。このような軍人を祀る招魂社をよリ権威づけるため、從道はその社号の変更を求め、まもなく「靖国神社」となった。以後、「靖国神社」は神社の中でも別格扱いとなり、軍の権威も高められた。さらに政府から距離をとり、軍事行為を行いやすくするため、天皇直属の軍令組織、参謀本部の設置を申請。その後も從道は大山巌とともに、天皇の軍事式典への積極的な参加を求め、天皇と軍の関係を密接にしていく。欧米に学び、軍の規模を拡大海軍大臣時代、アメリカを訪問した從道は、アメリカ軍に関して、軍事予算は議会の力で削減されているが、将校の技術は備わっているため、政府さえ許せば簡単に軍事力は強くなる国だと評した。帰国後、現状日本では独立国の海軍の規模ではないとして、軍事予算の拡張に努めた。開拓と交通を重視農商務卿時代、從道は北海道開拓に力を入れていた。北海道を視察した上で、本土の人々に北海道移住を勧めた。また日本の海運業は郵便汽船三菱会社と共同運輸会社が競合していたが、從道は海運業の発展を考え、両社の合併を勧告し、日本郵船会社が設立された。法律よりも国家の存続内務大臣時代、ロシア良太子が滋賀県で巡査に斬りつけられる大津事件が発生した際、從道はロシアとの戦争を懸念して、加害者の死刑を望んでいた。対して大審院長児島惟謙は、法に基づき処理すると主張、從道は「法律は国家を減ぼすものた」と激怒。児島は「その時々の利害で法律が変われば、それこそ国家が滅びる」と強く反論し、從道は黙り込んだ。結局死刑は適用されず、從道は事件の責任をとって内務大臣を辞任した。」「西郷従道の経歴天保14 (1843)年 薩摩藩士西郷吉兵衛の子として生まれる、名は「慎吾」とも「竜介」 ともいわれる嘉永5 (1852)年 両親が死去、兄吉之助(隆盛)によって育てられる。この頃、伊地知正治 の下て論語などを学ぶ。同僚からはものおぼえが悪かったためばか者と ばれる安政2 (1855)年 藩主の茶坊主となり、「龍庵」と号す 茶道や華道、薙刀や撃剣を学ぶ明治2 (1869)年 政府から東京滞在を命じられる 東京赤坂青南の茶園を購入し、別荘を建てる明治3 (1870)年 薩摩藩士 得能良介の娘清子と結婚明治7 (1874)年 台湾出兵の功により、勲一等を与えられ、その給料を資金に目黒の屋敷を 購入、赤坂の別荘は手放す。後に明治村に移築される洋館が同所に建てられる明治13 (1880)年 借金の肩代わリとして品川御殿山の土地を購入。牝牛放牧等を行う明治14 (1881)年 従兄の大山巌とともに栃木県那須原を開拓明治17 (1884)年 長男従理がアメリカで病気になり、10歳で死去明治33 (1900)年 東京三年町の本邸を有栖川宮家に売却したことにより、目黒の別荘を本邸に する明治35 (1902)年 胃がんにより死去」「西郷従道ゆかりの人々赤は薩摩出身、青は長州出身、黒はその他●大山巌 おおやまいわお 從道の従兄、よく家出をして、大山家に泊めてもらっていた 栃木県の那須原開拓を従道と共に行う●大久保利通 おおくぼとしみち 幼なじみ、從道は大久保を深く暮う 從道がつく役職をしばしば決定●樺山資紀 かばやますけのり 從道と同町出身、台湾出兵の際、副官として従軍。 また從道のボディガードの手配などもしていた●山本権兵衛 やまもとごんべえ 海軍省に属し、上司である從道に反対して自分の意見をよく述べていた。 海軍の人員整理などを從道と共に断行した●黒田清隆 くろだきよたか 酒乱で暴言をよくいうため、藩閥政府から距離を置かれていたが、從道には信頼をおいていた●松方正義 まつかたまさよし 同じ薩摩閥として從道を信頼しており、自分が総理大臣を辞める際、真っ先に打ち明けている●井上馨 いのうえかおる 自身を藩閥政府の調整役と認識し、同じく調整役をよく担う從道に薩摩閥の人間の説得など を任せることがあった●木戸孝允 きどたかよし 海外への植民地獲得に舵を切る姿勢を痛烈に批判、台湾出兵で台湾開拓を主張する從道を 狡猾だとした●山県有明 やまがたありとも 陸軍御などを務め、從道と共に軍事の諸制度の創設に努める 基地の立地や人事に関し、よく從道と相談をしていた●伊藤博文 いとうひろぶみ 政治的行動では基本的に歩調を合わせ、從道は周りから伊藤系と呼ばれる 甲申事変後の処理として共に清に向かい、天津条約を締結させる●品川弥ニ郎 しながわやじろう 從道が農商務時代の部下で、事務処理一切は品川に丸投げしていた 共に政府よりの政治結社「国民協会」を立ち上げる●大限重信 おおくましげのぶ 台湾出兵の析、本国で出兵に関わる事務を担当し、従道から日本で働きたい台湾人の仕事の 斡旋などを頼まれる 従道を「子どものようだ」と可愛がっていた」流れるような曲線を描いたまわり階段は、見た目の美しさはもちろん、昇り降りが大変楽という優れたものです。手に優しくなじむ手すりとともに、上方へと人をいざないます。しかし、2階の見学は出来なかった。「建物のみどころピンボケ!!」「建物に見られる地震対策西郷従道邸の西洋館はフランス人の建築家レスカス(J.Lescasse)と棟梁鈴木孝太郎が関与したと伝えられている。レスカスは、明治10年に日本建築とその耐震性に関する論文を発表し、屋根構造の強化と軽量化などを提案している。西郷従道邸の西洋館はその耐震設計の応用と考えられている。地震対策・垂木を省略し、母屋へ直接野地板を打ち付ける・屋根に瓦ではなく銅版を敷く・1増の壁に高さ約1メートルまでのレンガを充填」「西郷従道邸の来歴と役割上日黒から明治村西郷従道邸は明治10年代(1870代後半)に、東京都目黒区上目黒に建てられ、広大な敷地内には居住用の和館、回遊式の日本庭園もあった。現在建物があった場所は菅刈公園として知られている。西郷従道の亡さ後、昭和16(1941)年にいたるまで、次男の西郷従徳り本邸となっていた。その後所有者が点々とし、最後に日本国有鉄道の所管となるが、建物の老朽化が進み、維持管理が困難になったため、昭和37年10月財団法人明治村が譲り受け、昭和39年7月に移築工事を完了した。」「移築中のあの場所」。「上目黒から明治村」。「西郷従道邸敷地図」。「西郷従道邸の解体材どこにあるのでしょうか?」そして「寝室」。近づいて。洒落た陶器。「夫人室」陶器類。壁には。時計、菓子入れ。暖炉置き場。そして「西郷従道邸」を後にして、その先にあった「森鴎外・夏目漱石住宅」に向かって進む。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.26
コメント(0)
-

今年も地元の「天嶽院」の紅葉を愛でに(その4)
参道の横にある道を「山門」方向に向かって進む。紅葉の木々の先に「山門」が垣間見えた。ズームして。陽光に輝く真っ赤に紅葉したモミジ葉を追う。陽光を浴びて、真っ赤に染まったモミジの葉は、まるで燃えるような鮮やかさを放っていた。その深紅の色合いは、冬の訪れを感じさせる一方で、秋の終わりを彩る華やかな贈り物の如し。葉の縁はほんのりと黄金色に輝き、風に揺れる度に光の加減で一層鮮やかさを増し、まるで赤い宝石のように輝きながら、空気の中に温かみをもたらしていたのであった。静かな晩秋の午後、モミジの葉はその美しさで心を包み込んでくれたのであった。参道方向に引き返して。灯籠の先、石舟の上に「不動尊」。再び石段の上から山門方向のモミジの紅葉トンネルを見る。ズームして。さらに。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.25
コメント(0)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その11): 明治村3/16 文豪碑~聖ヨハネ教会堂~学習院長 官舎~
三叉路のロータリーにあった「文豪碑」。「博物館明治村」は1966年に第14回菊池寛賞を受賞したと。(左)「東海テレビ賞」(中央)「山本有三記念 郷土文化賞 昭和五十六年四月」(右)廻り込んで。そして「聖ヨハネ教会堂」の屋根が姿を現した。ズームして。⑥聖ヨハネ教会堂➡️案内板。紅葉を楽しみながら「聖ヨハネ教会堂」に向かって進む。明治期の衣装を村内でレンタルしたという女性たちと会話しながら。「聖ヨハネ教会堂」を正面から。日本聖公会京都五条教会堂として建設された教会堂。2階が会堂、1階は日曜学校や幼稚園に使われていました。中世ヨーロッパのロマネスク様式をベースに、細部にゴシックのデザインをまじえた外観が特徴。正面の左右には高い尖塔が建てられ、奥に十字形の大屋根がかかる会堂が配されています。2階の会堂の内部は十字形の平面になっていて、小屋裏現し(こやうらあらわし)も。アーチ形の方杖と鉄筋が組み合わされた独特な小屋組の細い骨組みにより、実際よりも広く感じさせる造りです。正面の妻と交差廊の両妻には大きな尖塔アーチの窓が設けられ、美しいトレーサリーの模様が浮かび上がるとともに、室内に光をふんだんに取り込みます。京都の風土に合せて使ったといわれる天井の竹のすだれが明るい光を反射し、内部の印象は非常に開放的です と。正面の左右にある高い尖塔にズームして。「1丁目6番地 聖ヨハネ教会堂 <重要文化財>旧所在地 京都市下京区河原町通五条下ル建設年 明冶40年解体年 昭和38年移築年 昭和39年建築面積 108.3坪構造 木造煉瓦造ニ階建銅板葺寄贈者 日本聖公会京都教区」聖ヨハネ教会堂は1階を日曜学校や幼稚園に、2階を会堂として夜用していたプロテスタントの一派日本聖会の教会堂である。設計は朋冶13 (1880)年に来日したアメリカ人宣教師で建築家のガーディナーである。1階を煉瓦造、2階を木造、屋根に軽い銅板を葺いた構造は耐震性に配慮しているといえる。正面人口の尖頭アーチに見られるように、細部はゴシック風にデザインされている。本格的な洋風建築のこの建物は、現存する明治期のキリスト教教会堂の代表的なものの一つである。」左:2階平面図 右:1階平面図入口から見上げて。正面人口の尖頭アーチは、ゴシック風のデザイン。尖頭アーチ下の人の形に見えるものは「三つ葉」であると。建物細部のところどころにゴシック風の尖頭アーチが見られるが、とりわけ正面入口のものは必見。レンガ積みの角柱から柱頭飾りを挟んで、レンガ積みのきれいなアーチが立ち上っているのであった。奥の欄間に配された2つの三葉形アーチの窓や、板扉の大形の金具のデザインも中世風のもの。既にクリマス用の飾りも。教会内部。十字形平面になっている2階の会堂内部は、小屋裏を現し、柱などの骨組みが細く見えることで、広さを感じさせます。そして竹材が豊富に使われていたのであった。暑い京都市だけに、竹を使ったこのような構造に設計された と。照明。祭壇。プロテスタントの教会の祭壇は、次の特徴がある。十字架がシンプルで、キリスト像は刻まれていない内装は簡素で、絵画や偶像が置かれていない。聖餐台とされることが多い。プロテスタントの教会では、聖書以外の宗教的権威や伝統、特に偶像や聖像に対する礼拝を厳しく禁じています。これは、宗教改革時にカトリック教会の聖像使用が大きな論争の一因となったため。プロテスタントの教会では、一般的にカトリックの礼拝堂と比べて装飾品が少なく、簡素感があるのだと。リード・オルガン👈️リンク。リード・オルガンは、足踏み式の“ふいご”が風力源となり、手鍵盤を押すことによってフリー・リードに風を送り、開放させることで音が鳴る仕組みとのこと。クルフ&ウォレン社製の大形・豪華なリード・オルガン と。ここにも。スミス・アメリカン社製のリード・オルガン と。足元に空気を送る空気ペダルが確認できた。「明治時代のオルガンの音色を新しい時代に蘇らせたい!」トレーサリー(幾何学模様装飾)のステンドグラス。この教会がまだ京都に建っていた頃の昭和9年(1934)、室戸台風の来襲によりこのトレーサリーのステンドグラスは破損してしまった。平成10~11年(1998~1999)の保存修理の際に復原され、往時の華やかさがよみがえったのだと。見上げて。正面に移動して。ケースに入った「聖洗盤」とのこと。祭司たちがその水で手と足を洗い、きよめるためのものとのこと。「◯主一禮◯」の文字があったが。階段入口の、こちらには四葉の印が。そして外に出て、再び周囲の紅葉を追う。次に訪ねたのが「⑦学習院長官舎」。「学習院長 官舎」。東京目白の学習院敷地内に建てられた院長官舎。学習院は江戸末期に京都で始まり、皇室や華族の子弟を教育する学校として明治10年(1877)に創立。明治17年(1884)、宮内省所管の官立学校として発足しました。当初は千代田区神田錦町にありましたが、麹町、四谷を経て、明治41年(1908)にまだ郊外であった目白に移転しました。この官舎が建てられたのは、目白に移転した翌年のことです。当時の学習院院長は、第10代にあたる乃木希典。希典は日露戦争の終結後、明治39年(1906)に軍事参議官という閑職に補せられ、翌40年(1907)1月から学習院長を兼任することとなりました。建物は木造で、2階建ての和館と洋館が接続した形。洋館部分は、執務室・応接室・大広間からなり、公的なスペースとして使われていたようです。設計者は、文部省技師久留正道であることがわかっています。「1丁目7番地 学習院長 官舎 <登録有形文化財>旧所在地 東京都豊島区目白建設年 明治42年解体年 昭和37年移築年 昭和39年建築面積 48.5坪構造 木造ニ階建寄贈者 学習院大学学習院長官舎は学習院長の公邸で、接客や実務を行う洋館と、住まいとしての和館とをつないだものである。官公庁をはじめとする公的な場は、生活の場よりも早くから洋式化し始めたため、明冶後期にはこのような和洋を折衷する形式がみられた。創建当時、第10代院長であった陸軍大将乃木希典は、この建物に入居せず、学生と寝食を共にするために総寮部(寄宿舎の事務棟の一室を居室とした。そのため当初院長官舎は、皇族学生の寮として使用された。車寄には鋳鉄で学習院の校章「桜」が付けられた、鉄の庇がもうけられている。」廻り込んで。周囲の紅葉。「学習院長官舎 ガイド建物内部を、ボランティアスタッフがガイドいたします。①1 1 : 4 0 ~②1 4 : 3 0 ~所要時間約1 5分」玄関ポーチ。乃木希典(のぎまれすけ)。乃木希典(のぎまれすけ)山口県出身寛永2年(1849)11月11日~大正元年(1912) 9月13日身長162cm(推定)」「乃木希典 略年譜」内部の見学。洋館と和館を繋ぐ階段室。移動して。応接間?居間。外に出て振り返って。「碧水亭」案内板。「日本庭園」と。この庭園は明治時代の代表的な庭園技術を採用して作ったものでかなりの山の傾斜を利用してアカマツ、雑木林を生かし実に写実的に作られているのであった。 数寄屋門風の門越しに「学習院長官舎」方向を見る。この「日本庭園」の先に「⑩東京盲学校車寄」👈️リンク があったが、この日は訪ねることが出来なかった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.25
コメント(0)
-

今年も地元の「天嶽院」の紅葉を愛でに(その3)
そして「中雀門」の左側にあった「寺務所」。石塔。玄関前にあった「仲良し地蔵」。「猫の侵人を防ぐため、扉を閉めさせて頂いております。用の方はインターホンにてお呼び頂き扉を開けてお入り下さい。」と。扁額「香積」。「香積」は寺院の厨房、転じて寺務を行う場所とのことであると師匠から。「總受附」と。以下3枚の写真は、以前に訪ねた時の写真。「寺務所」の中。以前に頂いた「御朱印」。スタンプ。「寺務所」の「火灯窓・花頭窓(かとうまど)」。中央に四角い穴の空いた石碑の名は??自然石を刳って作ったのであろうか、「手水場」が。水面には、「舟落葉」・モミジ葉が浮かぶ。近づいて。「大悲願力透徹救永劫」と。そして「鐘楼」。梵鐘をズームして。安永3年(1774年)の銘のある梵鐘。総高161.8センチメートル、口径81.6センチメートル、鐘身111センチメートル。銘文の文中には「功徳山早雲禅寺天嶽院北条氏繁公草創」とある と「鐘楼」前から参道を見る。「鐘楼」の先、右手にあった「六地蔵」は赤ではなく白の帽子、マフラーを。「庫裡」を横から。近づいて。「東司」は手洗い。手洗の中の額に書いてあった言葉を紹介させて頂きます。「禪寺では御手洗のことを東司(とうす)と申します。一、佛殿(ぶつでん)ニ、法堂(はっとう)三、僧堂(そうどう)四、庫裡(こり)五、山門(さんもん)六、東司(とうす)七、浴室(よくしつ)以上が禪寺に於ける七堂伽藍であります。」と。休憩所「黄楳亭」。この奥に「鶴夢楼」があった。「早雲閣」。法事等?で、食事が出来る建物のようである。「早雲閣」。玄関前には「仲良し地蔵」。近づいて。「早雲閣」前から「鐘楼」を見る。「鐘楼」の先には参道のモミジの紅葉が。廻り込み梵鐘をズームして。参道方向に戻る。「不動殿」横の道沿いに建っていた祠。三体の石仏が祠の中に。大小三体の石仏。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.24
コメント(0)
-
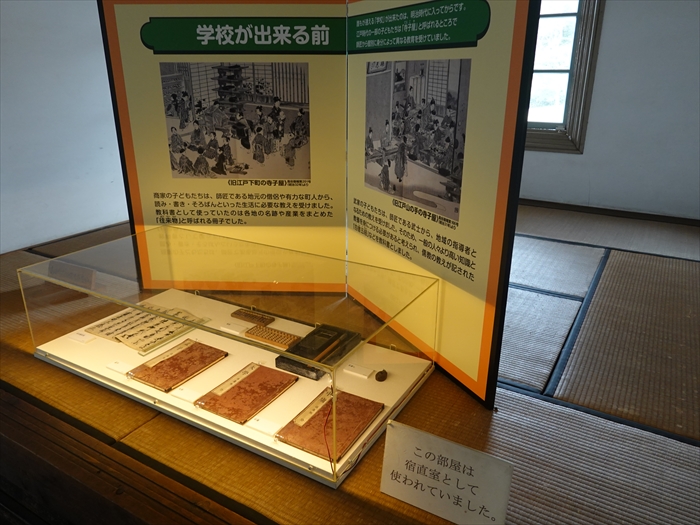
小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その10): 明治村2/16 三重縣尋常師範学校・蔵持小学校-2~近衛局本部付属舎~赤坂離宮正門哨舎
「三重県尋常師範学校・蔵持小学校」の見学を続ける。「学校が出来る前」「学校が出来る前誰もが通える「学校」が出来たのは、明治時代に入ってからです。江戸時代の一部の子どもたちは「寺子屋」と呼ばれるところで師匠から個別に身分によって異なる教育を受けていました。」「旧江戸下町の寺子屋商家の子どもたちは、師匠である地元の僧侶や有力な町人から読み・書き・そろばんといった生活に必要な教えを受けました.教科書として使っていたのは各地の名跡や産業をまとめた「往来物」と呼ばれる冊子でした。武家の子どもたちは、師匠である武士から、地域の指導者となるための教えを受けました。そのため、一般の人々より高い知識と教養を身につける必要があると考えられ、儒教の教えが記された「四書五経」などを教科書としました。」手前に「五つ玉算盤(そろばん)」、「筆」も展示されていた。教科書の孟子・大學・中庸も。「三重県尋常師範学校・蔵持小学校旧所在地 三重県名張市蔵持 建設年代 明治21年(1888)明治19年の師範学校令により、小学校教師の養成を目的として各県に一校ずつ尋常師範学校が設けられることになり、明治21年この建物が三重県の尋常師範学校本館として津市に建てられた。昭和4年蔵持小学校の校舍の新築に際し、蔵持村に売却・移築された。設計は三重県庁舍ど同じ清水義八の手になり、E字形て左右対称のニ階建てあったが、明治村に移築保存するに際し、特色ある中央玄関部分と右翼の約2分の1のみ復原した。」「蔵持小学校について明治8年9月蔵持小学簡易科授業所が、土地の廃寺を利用して開設された。これが今日の蔵持小学校の前身であり、明治25年校名が蔵持村立蔵持尋常小学校と改称された。明治42年新校舎をたてて校地を移転、当建物を蔵持小学校学舎として、使用することとなった。その後変遷を経て、昭和29年名張市立蔵持小学校と現在の名称となった。昭和47年新校舎の落成に伴い、同年旧学校が明治村へ移築された。なお昭和初年の卒業生は、1学年35名前後であった。」「三重県尋常師範学校について師範学校は、小学校の教員の養成に当る学校であった。明治政府の重点施策であった教育善及の方針に沿い、師範教育の充実は三重県でも、明治6年頃から活発に行われ、明治8年三重県師範有造学校が創設、10年には三重県師範学校が設立された。明治19年師範学校令の公布により、師範学校は高等と尋常の2種類に分けられ、高等師範学校は官立で東京に、尋常師範学校は府県立で各府県に1か所設置されることとなった。これにより、三重県師範学校は、明治20年3月三重県尋常師範学校と改称され、明治21年にその本館として建てられたのがこの建物である。明治31年4月三重県師範学校の名称に戻り、昭和18年4月官立三重師範学校と改称後、昭和24年5月設立された国立三重大学学芸学部(現教育学部)の母体となった。」当時の二重県尋常師範学校校舎(三県教育史より)の写真。「小學校教員免許証」、「月俸金」、「三重縣地誌略」、「師範学校 国文教科書」、「校印箱」「証書・成績表」。「明治時代の学校で使われたもの証書・成績表明治時代初め頃の学校では生徒が進級するために、半年に一度の厳しい試験が行われ、試験の点数か悪いと進級することができませんでした。進級試験は、1886 (明治19)年の小学校令と「小学校ノ学科及其程度」が出されると年に一度となり、さらに1890 (明治23)年の第ニ次小学校令で廃止となります。これによって同じ年に入学した子どもたちは、同じ年に卒業できるようになりました。」「明治時代の学校で使われたもの明治時代に誕生した学校では、多くの子どもが、一度に同し内容を学べるように工夫された道具が使われました。この時使われていたものは、改良が重ねられ現代へと受け継がれています。それぞれの道具はどのように使われていたのでしょうか?幻燈器。近づいて。「明治時代の学校で使われたもの時鐘寺小屋の子どもたちは、自分の都合の良い時聞に勉強を教わりました。しかし明治時代の学校では時間割にそった時間の中で授業が行われ、集団行動を学ぶ′場ともなりました。そのため、学校の子どもたちへ一斉に時間を知らせるための道具が必要になりました。その役割を果たしたのが、この「時鐘」と呼ばれる鐘です。現在のチャイムのように、授業の始まりと終わりに用務員が鐘を鳴らし、授業区切りを知らせていました。」教科書から見る明治時代の学校教育・「学校の誕生」・「翻訳教科書の誕生!」学校教育の見直し・1879(明治12)年 学校制度の見直し!・1880(明治13)年 教科書の見直し!・森有礼の改革!教育による思想統一・教育勅語・尋常小学校が6年制に・検定教科書から国定教科書へ!「学校の誕生1872(明治5)年小学校ができる!明治政府は、差別なく国民全員か学校に通うことで、国民一人ひとりが出世し、仕事に励み豊かな生活を送ることができると考えました。そこで1872年に全国を約5万3千の学区に分け、各学区に学校を作ることを目指し「学制」が発布され小学校か設置されました。当時小学校は「尋常小学校」と呼ばれ、6歳から13歳までの8年間通っていました。翻訳教科書の誕生!文部省か制定した教則には、「標準教科書」が提示されますが、当時はアメリカをはじめ、イギリス、フランスの教科書を翻訳した教科書が使われました。」教室内。机の上の板を開けて中に収納できるようになってる機能的な机。私が小学校時代にもあったような記憶が。当時を懐かしむ大先輩の旅友を。先輩の旅友も。「明治村錦絵れきし探偵団」「学校生徒体操之図」揚州周延 画。教室の窓越しの紅葉を。窓にカメラのレンズを当てて。「明治時代の学校で使われたもの体操用具1878 (明治11)年に文部省は、ヨーロッパやアメリカを手本とした教育制度を整えていく中で、教科が作られていながらも行なわれていなかった「体育」の授業を始めるために、お雇い外国人として、アメリカ人のリーランド(G. A. Lealand)を招きました。ここに展示されている用具を使った体操は「普通体操」と呼ばれ、子どもたらは号令に合わせて体を動かしました。」「唖鈴(あれい)」、「棍棒(こんぼう)」。唖鈴(あれい)とは、柄の両端に球形のおもりをつけた体操用具で、ダンベルとも呼ばれます。鉄製や木製などがあり、上下させたり振ったりして筋肉を鍛練します。棍棒とは、人が握り振り動かすのに適度な太さと長さを備えた丸い棒のこと。原始時代から現代に至るまで使用されている。新体操・男子新体操・こん棒投で使われる手具。懐かしい教室の油の染み込んだ床をズームして。再び「緋毛繊」の敷かれた休憩ベンチと紅葉のコラボ。学校入口の歴史を感じさせる石段を。次に訪ねたのが「④近衛局本部付属舎」。「1丁目4番地 近衛局本部付属舎<登録有形文化財>旧所在地 東京都千代田区建設年 明治21年解体年 昭和42年移築年 昭和52年建築面積 59.6坪構造 木造平家建寄贈者 宮内庁この建物は、明治20年皇宮警察署庁舎として着工されたものだが、工事中に用途が変更され、宮城の守護と儀杖に当たる近衛局(明治22年、近衛師団と改珎)の本部となったものである。付属舎であるこの建物は、その右側にある2階建本館と湯沸所兼渡廊下で連絡していた。明冶44 (1911)年に師団本部は移転したため、皇宮警察本部がここに移り、坂下護衛所として使用された。現在は復原されてないが、創建当初、アーケードの間には錬鉄製の華やがな手摺があった。」「間取図」。近衛局本部付属舎内に入って。「博物館 明治村 Guidance center」明治村住民登録で1年間、何度でも明治村が楽しめます! と。「デジタル住民登録標をお持ちの方」の特典建物内では明治村の住民登録を行っていた。住民登録をすると登録日翌日から1年間何度でも明治村に入村できる。明治村住民登録票を掲示することで平日の駐車料金無料、土日祝は300円割引(原付を含む自動二輪車は100円割引)になる。登録日の翌日より翌年の登録日まで利用可能。・大人 3,500円・大学生、シニア(65歳以上) 2,500円・高校生 2,300円・小・中学生 1,300円2024年4月より住民登録票をデジタル化したと。夏目漱石(左)と西郷従道の写真(右)。左から幸田露伴、島崎藤村、伊藤博文、乃木希典。左から伊藤博文、北里柴三郎、西園寺公望、森鴎外。「明治村 ロケ地ガイド」👈️リンク明治村でロケが行われた作品、建造物が登場する作品明治時代の貴重な建造物や街並みが復元されている事などから、映像作品のロケに使われることも多いとのこと。・社長繁盛記(1968年公開。映画)・春の波涛(NHK大河ドラマ、1985年)・美濃路殺人事件(1987年発表。内田康夫による小説)・デビルマン(2004年公開。映画)・劒岳 点の記(2009年公開。映画)東京パート(参謀本部陸地測量部・主人公の測量官の 自宅など)や列車シーンの撮影に使用された。・板尾創路の脱獄王(2010年公開。映画)・レオニー(2010年公開。日米合作映画)・NHKドラマ 坂の上の雲(2009年~2011年12月)・run for money 逃走中(2010年11月23日。フジテレビ系列)- 明治時代の東京という設定で ゲームが行われた。・ごちそうさん(NHK連続テレビ小説。2013年10月 - 2014年3月)・花子とアン(NHK連続テレビ小説。2014年3月 - 2014年9月)・タイムスクープハンター(NHK総合テレビ)・Fate/Zero(博物館明治村に展示されている聖ザビエル天主堂などの多数の建造物がモデル として使用されている)・俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」としてゲッツされた件(博物館明治村に移設された 旧西郷従道住宅をモデルとした建物が登場する)・恋愛ラボ(作中に登場する私立藤崎女子中学校の校門は博物館明治村の正門がモデルと なっている)・ゴールデンカムイ(建物の一部が作中の建物のモデルとして使用されている)・わろてんか (NHK連続テレビ小説。2017年10月 - 2018年3月)・半分、青い。(NHK連続テレビ小説。2018年4月23日の放送で、主人公がデートで 博物館明治村を訪れる場面が登場する[24])・まんぷく(NHK連続テレビ小説。2018年10月 - 2019年3月)・明治東亰恋伽(2019年4月 - 5月、テレビ神奈川ほか)・新幹線変形ロボ シンカリオンZ(テレビ東京。2021年6月25日の放送で、ザイライナー HC85ヒダのZコードを解除する重要なカギを握る場所として登場する)・エール(NHK連続テレビ小説。2020年3月 - 2020年11月)・虎に翼(NHK連続テレビ小説。2024年4月 - 2024年 9月 )など多数「明治村 Information インフォメーション」。そして「⑤赤坂離宮正門哨舎」。木造銅板葺き、八角形の平面で、洋風の正門にあわせて白壁に丸屋根、頂上に飾りをのせた洒落たデザインになっていた。「1丁目5番地 赤坂離宮正門哨舎 <登録有形文化財>旧所在地 東京都港区赤坂 建設年 明治41年解体年 昭和48年移築年 昭和58年 建築面積 0.6坪構造 木造平屋建寄贈者 総理府哨舎(しょうしゃ)とは、門番が立哨(りっしょう)している建物で、これは赤坂離宮正門両脇の内外に離宮警備のために設けられた4基の哨舎の一つである。赤坂離宮(現迎賓館)は、当時皇太子であった大正天皇のための東宮御所として明冶42年(1909 )に竣工した明治を代表する洋風宮殿である。本館北側に広大な前庭を配し、周囲に高い鉄柵がめぐらされ、その中央に、洋風正門が設けられ、脇にこの哨舎が置かれた。」内部には、旧所在地の「赤坂離宮(現 迎賓館)」の正門の写真が。左から「⑤赤坂離宮正門哨舎」、「④近衛局本部付属舎」、「③三重県尋常師範学校・蔵持小学校」案内板「⑥聖ヨハネ教会堂 ⑧西郷從道邸 ⑨森鴎外・夏目漱石住宅 和食処 碧水亭 (へきすいてい)」坂道を上って行った。右手のこの池の名は?紅葉が池の水面に映り込んで。紅葉をズームして。陽光が射し込めば、紅葉がもっと輝くのであったが。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.24
コメント(2)
-

今年も地元の「天嶽院」の紅葉を愛でに(その2)
参道の石段を上る。左右に狛犬、その先中央に「中雀門(ちゅうじゃくもん)」。左手には多くの石像、石碑が並んでいた。石段の上から「山門」を振り返って。燈籠・「八角青銅燈籠」(右)。燈籠・「八角青銅燈籠」(左)。獅子像(右・阿形)。獅子像(左・吽形)。次に訪ねた「不動殿」前には、石舟の如き鉢?の上に乗った「聖観音菩薩像」が。巨大な手水鉢なのであろうか。「感應」と刻まれていたが。「感應」とは仏語で人に対する仏の働きかけと、それを受け止める人の心。また、信心が神仏に通じること と。優しいお顔の「聖観音菩薩像」。二人の童子が支える蓮華座に結跏趺坐で鎮座する「聖観音菩薩像」。二重円光を背負い、左手に開蓮を持つ、右手の印相は来迎印。左下に「龍の吐水口(とすいこう)」。日本では昔から龍神が水を司る神さまとして崇められてきた。水はすべてのいきものにとって命の源。命をつなぐ水は尊いものであり、神道(自然信仰)では穢れや邪気を祓う神聖なものとされた。神社の手水舎で、左手、右手と水をかける行為は、心身を清めるために行うもので、この水を「龍神から出ている水」と見せることで「神聖な水である」ことを表現しているのである と。「相生松(あいおいのまつ)」。相生松とは、雌株・雄株の2本の松が寄り添って生え、1つ根から立ち上がるように見えるもの。また、黒松と赤松が1つの根から生え出た松のこと と。「相生松」碑。「昭和平成伽藍恢興之碑」「昭和」の文字がひっくり返した鏡文字のようになっていたが、「昭和」の『異体字』であると以前に国文学科卒の師匠より。右手にあったのが「不動殿」。「不動尊」碑。内陣に近づいて。見事な彫刻の「常香炉」。不動殿には「不動明王像」、「大黒天像」、「愛染明王像」を安置。中央に「不動明王像」が鎮座。右手に「大黒天像」。左手に「愛染明王像」。見事な「天蓋」。ズームして。石段方向を振り返って。「不動殿」と「浄聖殿」との間の石庭の如き庭を見る。「道元禅師御道詠の碑」「峰の色 渓(たに)のひゞきも 皆ながら 我釈迦牟尼の 聲と姿と」。【季節の移ろいとともに変わってゆく峰々の色、そして聞こえてくる谷川のせせらぎ、自分を取り囲んでいる自然の姿そのものの中に仏(釈迦牟尼)の姿を見る、道元禅師の澄んだ心の有り様を素直に感じさせてくれる歌。仏は、お経やお堂の中だけにいるのではありません。山や川や海や雲や、世の中全てのなかに仏はいます。】とネットには。再び、歩いて来た「山門」方向を振り返って。その先右手に、入母屋造銅板葺で妻入の「浄聖殿」大棟と向拝の唐破風に獅子口、軒廻りは一軒繁垂木で組物は舟肘木、拝は猪目懸魚で唐破風の兎毛通も猪目懸魚、妻飾は狐格子。両開きの桟唐戸と上に菱格子欄間、脇間に花頭窓本尊の「千手千眼観世音菩薩坐像」を安置。扁額「浄聖殿」。この日は「法要中つき、お参りは本堂にてお願いいたします」と。「浄聖殿」内に安置されている本尊「千手千眼観世音菩薩像」をパンフレットから。像高34.5センチメートル、総高83センチメートル、玉眼、金色相、寄木造の坐像。室町後期の作と。そして切石敷の参道を進んで行くと正面に切妻造銅板葺の「中雀門」。左右に白壁の築地塀のような回廊を設けた中雀門を通して本堂(法堂)が見えた。近づいて。「功徳山 早雲禅寺 天嶽院」と。扁額は「湘中早雲禅寺」。「常香炉」越しに「本堂・法堂」を見る。中雀門の真ん中に「常香炉」が置かれ、香炉に乗っている鞠を踏む唐獅子と、左右の取っ手部に取り付けられた阿形吽形の龍が参拝者を迎えてくれたのであった。「常香炉」には寺紋の「北条鱗」が。鎌倉の北条と小田原の北条(後北条)。家紋も同じ三つ鱗のようでいて微妙に違うらしい。「正三角形の三つ鱗」は、「鎌倉時代の北条氏(特に得宗家)」が使用していたと言われている。一方、「二等辺三角形の三つ鱗」は得宗家以外の北条氏や「戦国時代の後北条氏」が使用しており、「北条鱗紋」と呼ばれる事がある。ただ、得宗家が二等辺三角形の三つ鱗を使用していた形跡もあるのだと。こちらに関しては厳密にどちらが使用していたかを区分するのは難しいと言えるのだ と。中雀門内側、中央上方。通して入る日の光が独特の雰囲気をかもし出す、弓欄間( ゆみらんま / 火焔欄間 かえんらんま )。中雀門内側、向かって右上の「欄間彫刻」。中雀門内側、向かって左上の「欄間彫刻」。「法堂」をパンフレットより。法堂の前は基本的に白砂で構成するのも、昔の儀式用の礼の場という名残であると。「本堂・法堂」の内陣をパンフレットから。佛師松久宗琳謹作 一佛両祖を奉安する。(釈迦牟尼佛、道元禅師、螢山禅師)。「相中留恩記略所載」もパンフレットより。天嶽院の歴史は真言宗の古寺「不動院」から始まる。源頼朝公が治承四年(1180年)、伊豆に兵を挙げ鎌倉を目指す途中立ち寄り、 不動明王様に大願成就の祈願をされたとの伝説がある。明応四年(1495年)、北条早雲公によって伽藍の一寺が創建され、「不動院」を改め曹洞宗の禅寺とし、虚堂玄白禅師を迎えて開山とした。天正四年(1576年)四世住職の代に伽藍は焼失するが、玉縄城主北条綱成・氏繁公父子によって伽藍が復興された。 更に紀伊大納言徳川光貞卿の信仰篤く、六世住職の代に七堂伽藍が完成された。この姿が上の写真「相中留恩記略」巻之十八に記載されている。なお天正十九年(1591年)十一月、家康公から三十石の朱印地を賜った事実がある。安政二年(1855年)二月二十六日、二十二世住職の代に再び火災にあい、大伽藍はことごとく焼失した。焼失を免れ現存する総門(山門)は江戸中期に水戸光圀公が建立したと伝えられる。昭和五十一年(1976年)春伽藍復興に着手、二十年余を経て平成十年(1998年)七堂伽藍を室町時代の様式に統一して復興した と。「本堂・法堂」の右手に入母屋造桟瓦葺の僧堂(座禅堂)があった。寺号の早雲禅寺から扁額の書は「雲堂」であろうか。「不論上智下愚、莫簡利人鈍者」の文字が。「上智下愚(じょうちかぐ)を論ぜず、利人鈍者(りじんどんしゃ)を簡(えら)ぶこと莫(なか)れ。」と。道元禅師が、正しい坐禅をあまねくすべての人々に勧めるために記した「普勧坐禅儀.」の一文であると 。(ふつう世間では思い(アタマ)の智愚ばかりを問題にしているわけだが)坐禅するということにおいては、まるきり人間的智慧・才能の世界ではないのだから,人間の利口・馬鹿、学問のあるなしは問題ではない。)と。「中雀門」前から、山門方向をズームして。「中雀門」の左側にあったのは、国旗掲揚用のポールか?「中雀門」の前、「淨聖殿」の対面に建つ入母屋造銅板葺の「寺務所」があった。参道側入口玄関前には赤い帽子、マフラーの「掃除小僧」の姿が。「掃けば散り 払えばまたも塵積る 人の心も庭の落ち葉も」。「木々の色鮮やかな紅葉に目を奪われ、葉が落ちる様子に少しの物悲しさを覚えます。はらはらと庭先で積もる落ち葉は、日々増えて毎日掃いてもきりがないように感じます。今月のことばは、そんな落ち葉の様子を人の心になぞらえた道歌です。心は常に清浄でありたいと願うものの、人との小さな摩擦や日々の出来事で、簡単に人の心はささくれ立ちます。苛立ちや怒り、自分の価値観で凝り固まった自尊心は少しずつ塵のように自分の中に溜まっていくのかもしれません。宮城顗先生のことばに、次のようなものがあります。「いつとはなしに積もってしまう塵とは、自分の体験のみを絶対的なこととして誇る自負心、驕慢心であります。どこからともなくにじみでてきて肌をおおってしまう垢とは、自分のしたことや考えについての執着心であります。その塵と垢とを払い除かないかぎり、努力すればするほど人をへだて差別し、軽蔑する人間になってゆくのです。人々への愛に生きているつもりが、いつしらず、愛に生きている自分自身への自己満足と自己固執にすりかわり、人々がその愛に生きる自分を理解しないときには、逆にその人々を軽蔑し、憎みさえしてしまいます。」自分では気づかないそのような心を掃き清めるのは、一日の終わりの感謝のことばではないでしょうか。静かに一日を振り返り、真摯にわが身を問いかける、そして他者にかけてもらったあたたかいことばや出来事を思い出し、一日が無事に過ごせたことに感謝の思いを抱きます。「ありがとう」の思いでその日を閉じ、「ありがとう」の心を明日へと繋ぎます。感謝とわが身を振り返る生活が、知らず知らず積もっていくわが身の塵に、少しでも気づくきっかけを与えてくれるのではないでしょうか。」とネットには。「掃除小僧」に近づいて。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.23
コメント(0)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その9): 明治村1/16・往路~第八高等学校正門~大井牛肉店~三重縣尋常師範学校・蔵持小学校-1
「国道155号」、「県道195号線」を利用して次の目的地の「明治村」に向かう。途中、「ローソン 犬山入鹿池店」で弁当を購入し、車内で腹ごしらえ。そして「明治村」の「大駐車場」に到着し、「明治村」の入口に向かって歩く。駐車場内の木々も見事に紅葉していた。「明治村」入口への道沿いの紅葉を楽しみながら進む。そして前方にチケット売り場が現れた。その先に煉瓦造りの大きな明治村の正門が。入村券うりば開村:9時30分閉村:16時00分入場券は大人2500円、高校生 1500円、小中学生 700円とやや高価。ご案内村営バス 運行中 1日乗降自由 小学生以上 500円京都市殿 運行中 1乗車料金 大人 500円、小学生 300円蒸気機関車 運行中 片道料金 大人 700円、小学生 500円4本の門柱からなる「明治村の正門」。赤煉瓦と白御影石を積み、扉や柵に鉄材を軽やかに使ったデザイン。「第八高等学校正門構造 煉瓦造この門は高等学校令により名古屋に開校した第八高等学校正門であり、明治期の代表的な洋式門である。赤煉瓦と白御影石を積み、扉や柵に鉄材を軽やかに使ったデザインは、明治期に導人されたネオ・ルネッサンス様式である。明治四十ニ年(一九〇九)に建造されて以来、わが国の学校制度改革と運命を共にした由緒ある教育の門である。昭和ニ十四年の学制改革により新制名古屋大学教養部の正門となり、ついで昭和四十年に校舎が名古屋市立大学に移管され、正門もまた名古屋市の所有に帰した。その後取り壊される運命になり、昭和四十五年三月から明治村正門となった。 旧所在地 名古屋市瑞穂区 建設年 明治四ニ(一九〇九) 解体年 昭和四三年(一九六八) 移築年 昭和四五年(一九七〇 ) 寄贈者 名古屋市」「博物館 明治村」。入村すると右手に「ミュージアムショップ」が。「明治村の沿革戦後の日本は荒廃から立ち直る過程において過去の多くの貴重な建築を無思慮に破壊する事態を迎えた。それは「過去とは背に廻った未来である」ということを忘れた悲しむべき現実であった。その現実に対して、先人達が努力と名識によって営々と築きあげてきた明治建築を、破壊から少しでも救済し、保存してその文化を自ら語らせるために開かれたのが明治村である。明治村は建築家谷口吉郎と実業家土川元夫によって発議された。二人は学生時代の僚友であり、企業活動としてではなく、日本の現状を憂うる同志として文化財保護のために青春の友情を温め立ち上がったのである。土川元夫が社長であった名古屋鉄道は、現在の明治村の地、大和時代安閑天皇紀の入鹿屯倉(いるかみやけ)の古代史の謎を秘めた自然豊かな入鹿池畔の広大な地を明治村のため提供した。明治村が財団法人として発足したのは昭和三十七年(1962)であった。工事は多数の人々の支持をうけ進捗した。入鹿池畔の自然を大切に保存しながら、ようやく博物館明治村が開村されたのは昭和四十年(1965) 三月十八日である。開村当時の明治村は、遙々(はるばる)と北海道から移築された石造りの札幌電話交換局、京都の聖ヨハネ教会堂、東京で森鴎外と夏目漱石の両文豪が奇しくも相前後して住み、数々の名作を残した由緒ある住宅をはじめ、全国各地から破壊寸前に救済移築された建築や、電車などの施設物15件に過ざなかった。それが開村三十五年目の西暦二千年十月現在では建築物六十三件となり、その中には国民共有の国の重要文化財に指定された建築物も既に十件に達し、博物館の敷地も開村当時の二倍近くの一〇〇万平方メートルに拡げられている。明治村は建築を主体とする野外博物館であるが、個々の建物はまた独立した小博物館としてそれぞれに屋内展示がなされている。また建物自身も入鹿池と尾張富士の風光にとけこみ、こよない散歩の場を提供しているので、リクリエーションの場として利用されることを願うものである。 博物館 明治村」。「明治村からの言葉あなたを、明治村は心から歓迎いたします。ここに立たれたあなたは、すでに明治村の人であり、明治村はあなたの村です、あなたのおとずれを、明治の人々は明治村とともに、どんなにか待っていたでしょう。明治村は日本の近代化に力を尽くした人々の、精神と努力の結晶をあるがままに、あなたのまえに顕示(あらわ)しています。明治村に保存される数々の建物や、資料の一つ一つの歴史の心を読み取り、それを日本の進歩と幸福への目盛りとし、また道標として時代に引き継がれるのもあなたです。あなたと祖先や子孫たちの、自由で明朗な対話の村であることを、明治村はつねにねがっています。すくすくと生い茂る木や草や、さえずる小鳥や風や水のしずかなきらめきを、今日のあなたの伴侶として。美しい明治村の道を歩いてください。」「村内各種ガイドご案内」。「明治村 村内地図」👈️リンク。約100万㎡という広大な敷地面積を誇る明治村。正門のある1丁目から北口のある5丁目まで、5つのエリアがある。1日では回りきれない広さなので、各エリアごとにポイントを絞って散策することをおすすめしています と。1丁目👈️リンク・・・正門を抜けると文明開化の風が吹く2丁目👈️リンク・・・赤レンガ通りに並ぶ和洋折衷の街並みを歩く3丁目👈️リンク・・・入鹿池を望む絶景とともに楽しむ名建築4丁目👈️リンク・・・病院・硝子製造所・鉄道寮など近代化する時代を巡る5丁目👈️リンク・・・SLが走り抜け、東洋と西洋の文化が混ざり合う街「明治村×文豪ストレイドッグス」案内板。博物館明治村では、「博物館 明治村×文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬見聞録」謎解きゲームを開催!本コラボ限定の完全オリジナルストーリーで、作中の異なる時間軸で巻き起こる、3つの事件を体験できます。各コースクリアでオリジナルステッカーをプレゼント!!初心者から上級者まで楽しめる難易度別コースが用意されています と。入村記念写真の撮影場所、手前のパネルには「明治157年11月27日 明治村」と。明治村のため和暦は明治の累計157年に。「1丁目➔●聖ヨハネ教会堂 240m●西郷従道邸 280m●森鴎外・夏目漱石住宅 360m1丁目の保存建築物。①第八高等学校正門②大井牛肉店③三重県尋常師範学校・蔵持小学校④近衛局本部付属舎⑤赤坂離宮正門哨舎⑥聖ヨハネ教会堂(重要文化財)⑦学習院長官舎⑧西郷從道邸(重要文化財)⑨森鷗外・夏目漱石住宅⑩東京盲学校車寄⑪二重橋飾電燈⑫鉄道局新橋工場と明治天皇・昭憲皇太后御料車(鉄道記念物)⑬三重県庁舎(重要文化財)B正門テラスC和食処 碧水亭Dミュージアムショップ1丁目マップ。「1丁目・2丁目ガイドツアー集合場所(参加無料)」「②.大井牛肉店」へ。入口。「口上 當店にて明治調の牛鍋(すきやき)を営業致し 居候に付き賑々敷く御来店の程御願申上候 明治村大井牛肉店 主人敬白」と。入口を見上げて。「1丁目2番地 大井牛肉店<登録有形文化財>」。旧所在地 神戸市中央区元町建設年 明冶20年頃解体年 昭和41年移築年 昭和43年建築面積 29.8坪構造 木造2階建寄贈者 岸田伊兵衛大井牛肉店は、岸田伊之助が開業した牛肉販売と牛鍋の店を兼ねた商店である。慶応3年(1867)に神戸の開港にともない、入港する外国人相手の商売が興り、この店も神戸に入港する外国船に牛肉を提供したのが始まりといわれている。正面は神戸の外国商館や住宅を模して2階にべランダを設け、コリント式の柱で飾った西洋風だが、玄関は鶴をあしらった唐破風庇を取り付けて日本風の趣を醸し出している和洋折衷の意匠に特黴がある。店の入口左右の「大井」をあしらった腰石は、明治時代の商家建築の特色のひとつであり、ショーウィンドウを併置する店構えに移行する過程を示している興味深いものである。」この日のメニュー看板。文明開化の味 牛鍋:松(6000円)・竹(5000円)・梅(5000円)明治ニ〇年頃、牛肉販売と牛鍋の店として建てられたのが、大井牛肉店です。巷では「牛肉食わねば開化不進奴(ひらけぬやつ)」と粋がる風潮から、牛鍋が全国に広がっていきました。飛騨牛おいしい肉牛を育てるためには血統がとても大切です。生まれた牛の5代。前までの血統でその牛の価値が決まるとも言われています。もらろん飛騨牛も血統を大切に育てられています。飛騨牛の血筋を逆にたどると必ず「安福号」にたどり着きます。「安福号」は昭和五六年から飛騨にある岐阜県肉用牛試験場にて飼育されました。「安福号」の名前は当時の県如事である上松陽助氏によってつけられたものです。以来「安福号」の血を受け継ぐ牛は3万頭余り飼育されております。」店内。只今満室でございます と。「飛騨牛」のブロックが並ぶ。暖簾にも牛鍋を楽しむ姿が。食事場所は急な木製階段を上がった2階にあった。2Fのテーブル席の写真をネットから。奥のパネルには「昔なつかしい炭火で味 明治村名物料理 牛鍋」と。私の写真はピンボケの為、下記写真はネットから。「見本は二人前です」と。次に訪ねた建物に向かって進む。「③三重縣尋常師範学校・蔵持小学校」。「③三重縣尋常師範学校・蔵持小学校 明治二十一年」。入口を正面から。玄関のアーケード、2階に設けられたベランダ教室部の窓などに洋風建築の特徴が見られる。「三重縣尋常師範学校・蔵持小学校<登録有形文化財>旧所在地 三重県名張市蔵持建設年 明治21年 解体年 昭和47年移築年 昭和48年建築面積 110.6坪構造 木造ニ階建寄贈者 名張市この建物は当初、小学校教師の養成を目的とする三重県尋常師範学校の本館として津市に建てられ、その後、昭和3年(1928)名張市に移築されて蔵持小学校として使われた。明治村へは、官庁建築に多い左右対称形のE字型の校舎の一部、特色ある中央玄関部と右翼の2教室のみが移築された。設計者は旧三重県庁舎(現在明冶内所在)と同じく清水義八である。玄関のアーケード、ニ階に設けられたべランダ、教室部の窓などに洋風建築の特徴が見られる。また、三重県庁舎と細部のデザインを比較すると、地方の棟梁の洋風意匠受容の過程を知ることができる。」明治村へは、官庁建築に多い左右対称形のE字型の校舎の一部、特色ある中央玄関部と右翼の2教室のみが移築された。移築されたのは、この水色の部分のみ。「あのシーンはこの場所で!~明治村内で撮影したシーンの説明とミニ・エビソードを紹介! ~明治の小学生が授業を受けている様子を蔵持小学校の教室で撮影。第1回の冒頭に流れた明治という時代を語るドキュメンタリー映像の一部で放送された。(第1回「少年の国」2009.11.29放送)」「オリジナルボイスガイド」QRコードにQRコードに近づいて。「登録有形文化財第23-0065この建造物は貴重な国民的財産です文化庁」2階への階段。「緋毛繊」の敷かれた休憩ベンチ。紅葉とのコラボ。「緋毛繊」の敷かれた休憩ベンチで一休みする先輩旅友のお二人。建物背面。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.23
コメント(0)
-

今年も地元の「天嶽院」の紅葉を愛でに(その1)
この日は12月21日(土)、この秋も多くの場所の黄葉・紅葉を楽しんで来たが、地元市内にある「天嶽院」の参道の紅葉も美しいので、今年も訪ねたのであった。近くに住む高校時代の学友から、この「天嶽院」の紅葉の進捗状況をLINEで写真付きで送ってもらっていらのであった。駐車場に車を駐め、この日も散策開始。「天嶽院」の「山門」は西向きに建っているので、紅葉の参道に陽光が入りこむのは14時過ぎからが良いのである。この日も14時過ぎに到着。入口から、仁王像の立つ山門を見る。「参道」入口の門柱。この門柱に書かれている文字は、数年前に、これも我が高校時代の友人Sさんから教えて頂きました。「雨花知佛境 流水識禅心」と。「雨花佛境を知り 流水禅心を識る」と。「雨花知佛境」(右側)の門柱。「流水識禅心」(左側)の門柱。「山門」とその前の「寺号標石」と「金剛力士像・仁王像」。近づいて。「寺号標石」には「天嶽院」と。・真言密教の古寺「不動院」から始まる。・治承四年、源頼朝公は、伊豆で挙兵、鎌倉を目指すが、途中「不動院」に立ち寄り 不動明王様に大願成就祈願をされたとの伝説がある。・明応四年、北条早雲公によって伽藍の一宇が創建され、「不動院」を改めて曹洞宗の禅寺とし、 虚堂玄白禅師を迎えて開山。・天正四年、火災に遭い伽藍は全焼。・中興開基 玉縄城主北条綱成公、氏繁公父子。・再中興開基 紀伊大納言徳川光貞卿。・昭和平成伽藍復興。功徳山 早雲禅寺 天嶽院(てんがくいん)」。所在地:神奈川県藤沢市渡内(わたうち)1丁目1-1頂いたパンフレットから「天嶽院境内案内図」を。「嶽」の字について学びました。 【https://okjiten.jp/kanji342.html】👈️リンク より「---北条早雲公開基の古刹--- 天嶽院」文明年間(1469年 - 1487年)に「虚堂玄白」が草庵を営んだ。この草庵を「玉縄城主、北条綱成」が「北条早雲」を弔うために寺院として創建。虚堂を開山、早雲を開基とした。 天正19年(1591年)11月、徳川家康より朱印地30石を賜る。パンフレットより。「功徳山早雲禅寺 天嶽院」。パンフレットより。「金剛力士像・仁王像」・阿形像。上半身をあらわにした2体は、筋骨隆々。カッと両の目を見開いて、睨みをきかす迫力たっぷりの表情。左手に長い金剛杵(こんごうしょ)を抱え、右手の五指を下に向けて大きく開いて。長い金剛杵(こんごうしょ)。この金剛杵はあらゆるものを打ち砕けるほど硬く、金剛力士はこれを用いて仏敵や業魔を粉砕するのだと。移動して。お顔をズームして。「金剛力士像・仁王像」・吽形像。左手に短い金剛杵(こんごうしょ)を抱え、右手の五指を正面に向けて大きく開いて。短い金剛杵(こんごうしょ)。大きな手のひらを正面に。これが意味するものは??以下、「chatGPT」からの回答です。『仁王像は、仏教における「守護神」として、仏法を守り、信者を悪しきものから守る役割を担っています。掌を正面に向けることには、以下のような象徴的な意味があります:「掌を向けて守る」という意味:仁王像は、掌を正面に向けて構えることで、悪しき存在を押し返す、もしくは封じ込めるという意味が込められています。このポーズは、「悪を寄せ付けず、仏教の教えを守り続ける」という守護的な力を表現しています。「加護を与える」:掌を広げて前に向けることで、仏の慈悲や加護が施される象徴として捉えられます。このポーズは信者に対して保護や祝福を与える力があることを示しています。「宇宙の調和」:また、掌を正面に向けることは、宇宙の調和や力を象徴するとも考えられます。仏教の守護神として、仁王像は宇宙の秩序を守る存在であるという意味合いもあります。このように、仁王像や吽形像の掌を正面に向けたポーズは、単に「守る」だけでなく、「悪を退け、加護を与え、調和を保つ」という多層的な意味を持っています。』と。お顔をズームして。「功徳山 天嶽院」の掲示板。「直心 是れ道場なりつねに素直な心 ひたむきなこゝろであるならどんな場所でも心をみがくことができる」道場というのは建物や形態ではない、心の問題である。真っ直ぐな、素直な心が道場である。正直な心、自己を偽らない心が道場である と。そして山門前から。「参道」の「モミジトンネル」を望む。そして「山門」を額縁にして、モミジの参道を。「山門」を潜りながら。モミジのトンネルに続く切石敷の参道....石畳とその左右に敷き詰められた苔の緑が絨毯のようで美しいのであった。しかし、今年は赤の輝きが、こころなしか薄いようであった。「参道」を歩く。モミジのトンネルの中から眺めた石段上の堂宇境内。今年も「言葉はいらない!!」。さらに参道を進む。「千寿桜」。「千寿桜天正十九年夏日 徳川家康公御手植」と。さらに参道を進む。「山門」を振り返る。午後2時過ぎの逆光にモモジ葉が輝く。ズームして。参道の先には石段が。石段前から「中雀門」、「法堂」を見る。再び「山門」を振り返る。陽光に輝くモミジ葉を独り占め!!「山門」を参道からズームして。苔の上に舞い落ちたモミジは自らのエピローグへと。この日の風で石段下に吹き寄せられたモミジ葉。近づいて。 ・・・つづく・・・
2024.12.22
コメント(0)
-
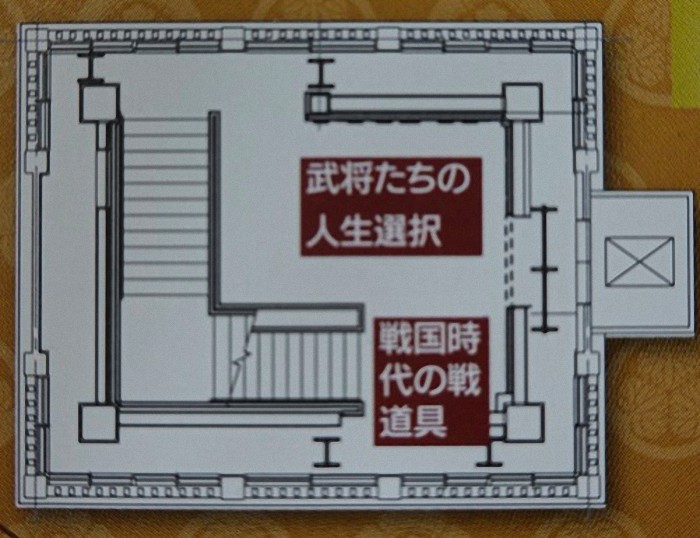
小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その8):小牧山歴史館3/3
最上階の展望を楽しんだ後は、階段を下りて3階へ。3階の配置図。3階 は「戦国クイズコーナー」になっていた。小牧山にゆかりのある信長、信雄、家康のそれぞれに関する人生を、クイズ形式でたどることができるようであった。「武将たちの人生選択」。戦国時代の戦道具を等身大イラストで紹介し、使用方法などについての知識を深めることができるのであった。火縄銃。槍・馬印。2階に再び立ち寄って。信長がなぜ小牧山を選んだのか、また、小牧・長久手の合戦がどのように展開していったのかを2面スクリーンによる映像で紹介していた。映像 ①信長と小牧山(約5分) ②小牧・長久手の合戦(約8分)と。2階は戦国時代の尾張国についての展示されていた。2階配置図。信長の小牧山城築城や、息子の信雄(のぶかつ)・家康連合軍がなぜ小牧山を本陣としたのか……といった想いや背景などが、パネルや映像(ミニシアター)で紹介されていたのであった。一角には、秀吉軍と信雄・家康連合軍の小牧・長久手の合戦の模様が描かれた屏風図が展示されていた。「小牧長久手合戦図屏風天正12年(1584) 3月に始まった小牧・長久手の合戦は、当初、大規模な戦いは行われず、小牧付近で織田信雄・徳川家康連合軍と羽柴秀吉軍の両軍が対峙し、にらみあいの状態が続いていました。4月6日、秀吉軍が家康の本拠地である岡崎城を攻めるため、極秘に進軍しました。これを察知した家康軍は追撃隊を編成して進車、長久手の地で秀吉軍を攻め、勝利をおさめました。この長久手の合戦のうち、4月9日の合戦の状況を描写したのが小牧長久手合戦図屏風です。小牧長久手合戦図屏風は現在10点ほどが伝わっていて、詳細については異なる部分が多く見られます。展示してある写真パネルの合戦図屏風は徳川美術館所蔵のもので、本来は長篠合戦図屏風とあわせて一双として伝えられているものです。小牧長久手合戦図屏風のうち、最も古いとされる成瀬家本と比べると、画面右下の川(香流川か)の幅が広くて色も薄いこと、中央部の雨池が草の生え方で湿地帯のように表現されていること、中央やや左の家康軍鉄砲隊の発砲を、黒煙で表現してあることなどの特徴があります。」中央部分をズームして。「金地に日の丸の幟」は徳川家康の馬印。小牧山で秀吉軍と対峙していると思われていた家康が長久手に突如現れたことで、秀吉軍は戦意をくじかれ、長久手の戦で敗北へとつながりました。」「秀吉軍の池田勝入の闘死の様子。右に立つ長田伝八郎は池田勝入の首を取り、右手に勝入の◯けていた黒母衣に包んだ首を抱え、左手には勝入の刀を持っています。首を取られた勝入が背負っているのは母衣の骨組みです。」ネットから。長田伝八郎は長久手合戦図屏風で池田勝入の首を討ったとして描かれている武将。永井直勝の右手の黒母衣に首が包まれているのが分かります。また、左手で恒興の名刀を掴んでいます。首級を奪われてしまった池田恒興(池田勝入信輝)。「小牧長久手合戦図屏風」より。(ネットから)。火縄銃。「豊臣秀吉の朱印状 永禄4年(1561)尾張国春日井 郡小松寺門前弐百三拾六石之事如前々令寄附訖全可寺納者也文禄四年八月三日印小松寺」。「森長可禁制札 天正12年(1584)禁制 小松寺一 当手軍勢乱妨狼藉之事一 放火之事一 山林竹木伐取之事 右條々堅令停止訖若 違背者於在之者速可 罪科者也仍如件天正拾弐三月廿七日 長可 花押」「池田恒興軍陣制札 天正12年(1584)條々 小松寺一 当手軍勢乱妨𦵧藉之事一 放火之事一 山林竹木伐取事 右條々堅令停止○(己の下に十) 若令違背者於在之者、 可処厳科者也仍如件天正拾弐三月十四日 恒興」「織田信雄安堵状 天正10年(1582)当寺領高頭参拾弐貫文余 但 私徳 弐拾四貫余如前々今以不可有相違其外何も可任先判旨者也仍如件天正拾年 八月十一日 花押小松寺 并 遍照寺 門前」「小牧山歴史館」の見学を終え、外に出て見上げる。「主郭の形状と主郭へ至る虎口主郭(城の中心部)のこの場所は、台形状に外側に張り出しています。発掘調査により、この形状は大規模な盛土をして造られたこと、また、この下にある1段目の石垣(石垣l)は、他に比べて大きな石材を用いて造られていることがわかったことから、ここには建物があったと考えられています。この場所から北西方向を見下ろすと、北側から曲輪002へと続く現在の園路があり、曲輪002に差し掛かる部分の園路の両側には石垣が配置されています。その部分は主郭へ至る登城路の虎ロ(城の出入口)であった可能性があり、登城経路は、現在の園路とやや方向が違い、石垣に沿った経路であったと考えられます。」「岐阜城」案内パネル。何とか!!「岩崎山」案内パネル。「岩崎山」。岩崎山砦跡(いわさきやまとりであと)は、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いの折り、秀吉方が築いたとされる砦の跡である。稲葉一鉄・貞通親子らが4千の兵を率いて布陣した。砦の規模は分かっていないが、岩崎山の頂上や熊野神社境内にあったと言われている と。「山頂から北をのぞむ小牧山は、濃尾平野の中央にそびえる標高85.9mの独立丘陵です。さえきるもののない眺望の良さは、戦国時代に城として使われたとき、大きな利点でした。ここからは、信長、家康がいた時の周辺の城や砦を見渡すことができます。織田信長居城時 永禄6 ~ 10年(1563 ~ 67 )「信長公記」(太田牛ー著)には、清須城を本拠地としていた信長が先にニ宮山(本宮山)を移転先に挙げ、のちに小牧山に城を移したと書かれています。このころ、小牧山の北にある犬山城、小口城などはまだ信長の勢力範囲ではありませんでした。小牧・長久手の戦い 天正12年(1584)小牧山に本陣を置いた織田信雄・徳川家康連合軍に対して、犬山城・楽田城に本陣を置いた羽柴秀吉軍は小牧山の北~北東に複数の砦を置きました。両軍の軍勢は、織田・徳川軍 約1万5千人羽柴軍 約10万人と言われています。」「小牧山歴史館」の裏側に廻って。「花崗岩の巨石」。「正面にある花崗岩の巨石は、小牧山城の主郭(山頂部)の大手(表)虎ロの開口部にあたるこの位置に、石垣構築時に据えられたもので、小牧山の北側約3kmにある岩崎山から搬入された可能性があります。現在はニ石に割れていますが、当初は約2m四方の立方体状の一つの石でした。西側(奧側)の石垣とつながっていたと考えられますが、どのようなつながり方をしていたか不明です。なお、花崗岩が割られたのは、慶長10年(1610)に始まった名古屋城築城にあたり搬出するために割られたと考えられ、矢穴や〇に十字の刻印などが残っています。」この先(木階段を下る)でご覧いただけます。上の写真を。大手道横の自然岩盤の上に最上段の石垣が。廻り込んで。「大手道小牧山城の大手道は、南麓の大手口から中腹まで真っ直ぐに延び、東側へ右折れした後、「コ」の字型の屈曲を繰り返して山頂の主郭に至ります。ここは、中腹で右折れした後3回目の屈曲部分で、北側(右側)と東側は人工的に切り立てられた岩盤とその上に積まれた石垣に、南側(左側)は道下の石垣によって画されています。発掘朝査により、この部分の幅員は6 ~ 7mであったこと、路面の一部には、砂礫を主とする土を岩盤面の上に敷き、現代の浸透性舗装のように水はけを考慮していたところがあったことを確認しています。」当時の小牧山城の想像図をネットから。小牧山城推定想像図をネットから。転落石。石垣跡。そして大手道を下って発掘現場を見る。大手道横の発掘現場。一度、このような発掘現場の体験をしたいのだが。発掘調査が完了した現場は、ブルーシートで養生されて。「発掘調査中 史跡小牧山大手道トレンチ調査」と。よって「大手道の一部を通行規制します」と。「タブの木」。「市の木 タブの木関東以南の海岸地方に多く群生する。当地方ではあまりみられない木であるが、小牧山にのみ自生している。花は五月頃咲き、九月頃灰褐色の実を付ける。昭和四拾七年公募により市の木になる。小牧市。」「小牧山杉並木」碑。帰路は「大手口」とは反対側にある「搦手口」に向かって下る。「現在地」はここ。そして小牧山北駐車場に戻り、次の目的地の「明治村」に向かったのであった。時間は11:20。9:20から2時間の滞在であった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.22
コメント(0)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その7):小牧山歴史館2/3
「上御園遺跡出土遺物」。「上御園遺跡の調査では、街路、掘立柱建物、溝、井戸などの遺構とともに、瀬戸美濃産の陶器(天目茶碗、皿、すり鉢他).素焼きの土器(鍋、釜、皿他)、磁器、金属製品などの遺物が数多く出土しています。特に.鍛冶屋町と推定された地点からは、鍛冶に関連するふいごの羽口、銭滓、銅滓、坩堝などが多く出土し、江戸時代の村絵図や明治時代の地籍図に小字として記された町の名前が.織田信長の小城下町に由来するものであることが明らかとなりました。出上した銅線や釘、小札(甲冑の部品)などの金属製品は、厚い錆に覆われて種類が判別できないものも多くありました。このため、錆の進行を止めるとともに、可能な限り錆を落とし、常設展示ができるよう保存処理を行いました。」「上御園遺跡出土金属製品」。写真撮影用コーナー。家紋が描かれた屏風も。左から五三桐紋:織田信長、織田木瓜紋:織田信長、三つ葉葵紋:徳川家康・五三桐紋は足利義昭を報じて上洛した際に義昭より賜った。名誉紋。・織田木瓜紋は信長の父、織田信秀が主君の尾張守護の斯波氏から賜ったとされる。 (朝倉氏という説もあり)通常の「五瓜に唐花」に比べると花弁が細い。・三つ葉葵紋・徳川葵紋は、3枚の葵の葉を頭合わせに並べて、通常の太さの丸で囲う。 江戸幕府の将軍家、徳川家の家紋。日光市日光東照宮の神紋、東京増上寺の寺紋、 京都市清凉寺の寺紋。撮影用陣羽織。私も陣羽織を着用して。ズームして。2階:戦国時代の尾張国以下、ネットから。戦国時代の尾張国。賤ヶ岳の戦い。小牧・長久手の合戦への道。小牧山城周辺の戦い。小牧・長久手の合戦以後の主な出来事。小牧・長久手の合戦講話後の秀吉と家康。織田信雄の挙兵。信長の家臣団。織田弾正忠家。2階の戦国時代の尾張国についての展示。信長の小牧山城築城や、息子の信雄(のぶかつ)・家康連合軍がなぜ小牧山を本陣としたのかといった想いや背景などが、パネルや映像(ミニシアター)で紹介されていた。3階:戦国クイズコーナー。3階は「戦国クイズコーナー」と題して信長・信雄(のぶかつ)・家康のそれぞれに関する人生をクイズ形式で、すごろくのように進んで遊べるコーナー。歴史のことが詳しくなくても「へ~そうだったんだ!」と楽しみながら学べるコーナーである と。戦国時代の戦道具。「火縄銃」。槍、馬印。そして4階・最上階へ。4階 展望室に到着床面の航空写真に、主に小牧・長久手の合戦で築かれた砦の位置を示すことで、信雄・家康軍と秀吉軍の距離感や戦略を体験できるのであった。歴史館の最上階は濃尾平野が一望できる展望室。今回リニューアルしたひとつが、この床の航空写真。主に小牧・長久手の合戦で築かれた砦の位置を示すことで、秀吉軍と信雄・家康軍の距離感や戦略を体感できるよう工夫がされているのであった。最上階からの眺望、犬山方面。遠くに、右側から伊吹山地、左側から養老山地で迫る、関ヶ原方面になるようだ。ズームして。右側にカメラをふって。犬山城が見えると!?これが犬山城であっただろうか。名古屋の市街地方面。名古屋飛行場(県営名古屋空港)が中央に見えた。名古屋飛行場は航空法上の正式名称であり、空港施設の通称は県営名古屋空港。航空自衛隊小牧基地と隣接しているため小牧空港とも呼ばれる。大手道、発掘現場を見下ろして。再び犬山市方向。気象条件が良ければ、槍ヶ岳、乗鞍岳、御嶽山、木曽駒ケ岳が見えるようであったが。ズームして。「史跡小牧山主郭地区整備工事史跡小牧山では、織田信長が小牧山築城時に築いた石垣などを、発掘調査成果に基づいて復元する史跡整備工事を実施しています。小牧山歴史館周辺を5つの工区に分け、順次実施設計と整備工事を行い、令和7年度の整備完成を目指しています。令和3年度未には、第5工区(山頂北側工リア)が、令和4年度未には第1工区(山頂西側工リア)の整備工事が完了し、令和5年4月1日(土)より一般公聞しています。」その下に上空から見た第1工区(令和5年4月10日撮影)。小牧山歴史館の南側上空からの撮影。史跡小牧山主郭地区整備工事各工区の位置。整備(第5工区)の概要。整備(第1工区)の概要。石垣復元の整備工事。復元した石垣は、下図エリアでご覧いただけます。(☆5工区・1工区)。再び名古屋市街地をズームして。右側に中村区の高層ビル群。愛知県犬山市南部に位置する標高275mの山・尾張富士方向をズームして。尾張富士の右側に本宮山・293m。中央アルプスの姿はやはり見えなかった?。案内写真。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.21
コメント(0)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その6):小牧山歴史館1/3
「小牧山城跡」の「観音洞」を後にしてさらに「小牧山歴史館」を目指して坂道を上る。「現在地」はここ。「大手道の一部を通行規制します」と。さらに進む。「現在地」はここ。「あいち森と緑づくり事業里山林整備事業あいち森と緑づくり税を活用して、小牧山の樹木整備を行いました。」頂上を廻り込むように上って行った。石垣の裏込石として使われていたと考えられる大量の礫。小牧山城の発掘調査現場から出土した、大量の裏込石の集積場所の光景。あまりに大量なため、側面を石垣のように積んだ箇所や、算木積の場所もあるようです。職人さんたちの遊び心??。近づいて。栗石ともよばれる小石と、表の大石の組合せが、地震時に遊び部分がクッションとなり、大雨時の水のはけ口ともなる。小牧山城でも大量の裏込石が使われていたことは、注目すべきこと。「史跡小牧山主郭地区~織田信長が築いた小牧山城~山の岩盤に築いた石垣」案内板。「大手道から頂上の主郭(曲輪001)に到る主郭地区の史跡整備に向けて、遺構の遺存状況を確認するため、平成16~19年度にわたり4次の試掘調査を実施しました。曲輸001を取り巻くように設けられた上段の曲輪021と曲輸023(現在地)を画する崖状の法面の調査では、小牧山の岩盤層の切り立ちの上に築かれた石垣を確認することができました。近世城郭に多い水堀の底から立ち上がる平城の高石垣は、松の胴木を松丸太留めした上に基礎の根石を据え、間石を詰めながら積み石を組んでいきますが、ここでは、小牧山の自然の地形を活かし、岩盤を基礎としてその上に積み石をしたり、切り立つ露出した岩盤の崖そのものを石垣に見立ていたようです。石垣は、一部で2段の積み石が残っていたのみで、天端石は失われていました。石垣の上段となる曲輸021の端部は、黒色土と砂礫層(岩盤が2~5cm大に細かく砕かれたもの)が交互に積まれて造成されていました。曲輸023の崖際では、裏込石として使われていたと考えられる大量の礫(丸礫、角礫とも)の堆積を検出しました。 小牧市教育委員会」「小牧山歴史館」の南側下の発掘現場を見下ろす。「小牧山歴史館」を見上げて。木製の階段を上る。茶色の巨石で造られた石垣。花崗岩が割られたのは、慶長10(1610)に始まった名古屋城築城にあたり搬出するために割られたと考えられ、十字に掘られた矢穴などが残っていた。「花崗岩の巨石正面にある花崗岩の巨石は、小牧山城の主郭(山頂部)の大手(表)虎ロの開口部にあたるこの位置に、石垣構築時に据えられたもので、小牧山の北側約3kmにある岩崎山から搬入された可能性があります。現在はニ石に割れていますが、当初は約2m四方の立方体状の一つの石でした。西側(奥側)の石垣とつながっていたと考えられますが、どのようなつながり方をしていたか不明です。なお、花崗岩が割られたのは、慶長10(1610)に始まった名古屋城築城にあたり搬出するために割られたと考えられ、矢穴や○に十字の刻印などが残っています。」「小牧山歴史館」前か南西方向を見る。「小牧山歴史館建築主 平松茂基本設計 城戸久実施設計 城戸武男 建築事務所施工 株式会社 長瀬組 長瀬美之着工 昭和42年4月15日竣工 昭和43年3月26日規模 鉄筋コンクリート造4階建 延 629.21m2」この小牧山歴史館(旧 小牧市歴史館)は、平松茂氏(故人:小牧市名誉市民)が私財を投じて建設し、小牧市に寄贈されたものとのこと。鉄筋コンクリート造、三層四階建てで、高さは19.3m、4階展望室の高さは約14m(標高100m)。「小牧山歴史館入館案内開館時間 午前9時~午後4時30分 (最終受付午後4時15分)休館日 第3木曜日 (祝日と重なった場合はその翌日) 年末年始(12月29日から1月3日)入場料 (1階は無料て入場いただけます。) 小牧山城史跡情報館(れきしるこまき)との両館共通人場券 【一般】200円 【団体】(30名以上)100円 18歳以下無料」展望場所から「清州城」が見えると。小牧山城の天守閣から見た眺望(名古屋方面)。城の姿は何処???さらにズームしたが。昭和天皇の巡幸を記念する石碑。「御野立聖蹟」と書かれた石碑)は、昭和2年(1927)の陸軍特別大演習に視察に訪れた昭和天皇陛下が休息されたのを記念して建てられたものと。「小牧山歴史館入館口」。史跡小牧山山頂の小牧市歴史館は、これまでの歴史民俗資料展示から、戦国時代の小牧山を中心とする展示へと全面改装を行うため、令和4年12月より休館していた。名称を小牧市歴史館から小牧山歴史館とし、令和5年4月1日にリニューアルオープン。頂いたパンフレット。「(旧小牧市歴史館)小枚市歴史館(現小牧山歴史館)は、名古屋市在住の実業家、平松茂氏(故人・小教市名誉市民)が、私財を投じて建設し、昭和43年3月に小牧市に寄贈されたものです。建物の外観は、京都の西本願寺 飛雲閣を摸しており、鉄筋コンクリート造、3層4階建てで、高古は19.3mです。開館以来、小牧市の歴史民俗資料を展示してきましたが、令和4年度に小牧・長久手の合戦など戦国時代の小牧山についての展示内容に全館改装し、令和5年4月1日に「小牧山歴史館」としてリニューアルオープンしました。リニューアルした当館では、織田信長や徳川家康など、戦国時代の武将たちがなぜ小牧山を選んだのか、地形や戦略などからその謎にせまります。」「史跡 小牧山史跡小牧山は、小牧市に所在する戦国時代の城郭跡で、市の中心市街地西側に位置する、標高85.9m、面積約21haの小山です。小牧山は、城として永禄期と天正期の2回利用されました。初めて利用されたのは、永禄6年(1563)で、織田信長は小牧山に城を築き清須から居城を移しました。小牧山の南に大手口を設け、大手道を直線的に中腹まで登り、右に折れて屈曲しながら山頂の主郭に至ります。発掘調査によって、主郭の周囲には2 ~ 3段の石垣が巡っていたことがわかりました。石垣は、自然石を使用した野面積みで構築され、傾斜角70度で積み上げられています。石垣背面の裏込石が崩れた土層からは「佐久間」と墨書された石材が見つかっており、築城時の工事分担や家臣の関わりを紐解く鍵となりました。主郭南東側の二段下の曲輪では、信長の館の一部である可能性のある屋敷建物の一部を確認し、また、主郭東側では、庭と推定される玉石敷や立石を確認していることから、小牧山城の当時の姿や機能を知る上での大きな成果となりました。小牧山城に移った信長は、犬山方面を支配下に置き尾張を統一するとともに、積極的に美濃攻略を行いました。4年後の永禄10年には美濃の稲葉山城を攻略し、岐阜と名を改め居城を移しました。これにより、小牧山城は廃城となり、東西1km、南北1.3kmの範囲で山の南に整備されていた城下町は一部を残して衰えました。小牧山城が廃城となってから17年後の天正12年(1584 )、羽柴(豊臣)秀吉軍と織田信雄・徳川家康連合軍による小牧・長久手の合戦が起こりました。信雄と家康の軍勢は、信長の城跡に大規模な改修を行い、堅固な陣城を築きました。山麓を取りまくニ重の土塁や堀、虎ロなどは、この時に築かれたものです。小牧附近では大規模な戦いは起こらず、戦の収束に伴い小牧山城は再び廃城となります。規在、小牧山に残る城の遺構はこの時の小牧山城の姿です。江戸時代には尾張藩、明治時代には尾張徳川家の手厚い保護を受け、山中の堀や土塁などの残存状沢は非常に良好であることから、日本の城郭史上、貴重な資料となっています。昭和2年(1927)国の史跡に指定、昭和5年には徳川家から小牧町(当時)へ寄贈きれ、現在に至っています。小牧市教育委員会では、小牧山におけるこれまでの発掘調査成果を基に、城郭遺構を復元する整備工事を実施しています。東麓の帯曲輪地区では、永禄期の武家屋敷群の区画跡や、天正期に改修した土塁と堀を復元しました。南麓では、天正期に築いた土塁と堀を復元し、実際にその様子を観察していただける観察デッキを設置しました。山頂の歴史館周辺では、令和3年度から令和7年度までの5か年をかけて、永禄期の石垣等の復元整備を進めており、整備工事が完了したエリアでは復元した遣構をご覧いただくことができます。」1階配置図。小牧山歴史館に大きく関わりのある2名の銅像。左が小牧山に歴史館を建てるため、私財を投じた実業家「平松茂(ひらまつしげる)」。右は尾張徳川家の19代当主「徳川義親(とくがわよしちか)」。義親の時代まで尾張徳川家の所蔵だったものを、昭和5年に小牧町(現小牧市)へ寄贈し、以降一般公開が可能となった と。「平松 茂小牧山に城を建てるため、資材を投じた実業家1966(昭和41)年、小牧山を訪れた名古屋市在住の実業家・平松茂氏が山頂に城を建設することを思いつきます。当時の小牧市長・神戸眞氏に寄贈を申し入れたことから建設が具体化しました。京都の西本願寺飛雲閣をモデルとした鉄筋コンクリート造、3層4階建てで、高さ19.3mの建物は、1967(昭和42)年4月に起工、翌年3月に竣工、翌年3月に竣工し、小牧市へ寄贈され、4月に小牧市歴史館として開館しました。1969(昭和44)年、83歳で永眠した平松市氏の墓所は、個人の遺志により歴史館がいつも見える、野口の龍洞院の一番高いところに建てられています。徳川義親小牧山を手厚く保護し、小牧町への寄贈を決意」1584年(天正12)年、小牧・長久手の合戦では、この地に織田信長・徳川家康連合軍の陣が置かれました。江戸時代になると尾張徳川家は小牧・長久手の合戦で家康が天下を取るきっかけとなった小牧山を重視。「神君家康公ゆかりの地」として一般の入山を禁止して手厚く保護しました。明治時代以降、紆余曲折を経ながらも、小牧山は尾張徳川家の所有が続きました。1927(昭和2)年小牧山は国の史跡に指定されますが、徳川義親氏は、内務大臣(当時)あてに史跡指定願を提出されるなど指定にあたって尽力され、1930(昭和5)年には小牧山を小牧町(当時)へ寄贈されました。1985(昭和60)年には義親公の遺徳を後世に伝えるため、銅像が作られました。歴史館の1階は「小牧の歴史」フロア。ここは無料エリア。小牧の旧石器時代から現代までの歴史や、小牧山城などの歴史を紹介するエリア。「小牧市の紹介」👈️リンク小牧市の地形、地質市域は、北東部から南西部に向かって次第に低くなっており、標高が最も高い北東部にある天川山(279.6m)と、最も低い南西部の巾下川と五条川の合流点付近(6.8m)の差は270m以上あります。小牧山は美濃帯と呼ばれる中生代のチャートからなっていて、織田信長が築いた石垣には主に小牧山のチャートが使われました。小牧市の成り立ち人 口 令和4年(2022) 150,819人 増加傾向である。「狩猟から稲作へ」小牧にはじめて人が住む小牧にはじめて人が住みだしたのは、今から約8000年前の縄文時代からです。市内ではそれより前の、今から約1万2000年前の旧石器時代の石器も出上していますが、このころは動物を追って移動しながら生活していましたので、住居を造って定住的な生活をしはじめたのは、縄文時代からです。狩猟や採集を中心に生活を営んできた縄文時代から、稲作中心の弥生時代に移ってからも小牧には人が住み、集落を形成していました。調査された弥生時代の遺跡は少ないですが、南外山や北外山では銅鐸や住居跡、墓などが見つかっています。出上した土器などから、小牧市に弥生文化が伝わるのは、弥生時代中期頃です。「古墳が築かれた時代」。むかしのお墓古墳時代には、弥生時代に造られていた平面形が四角く、四辺を溝で囲った方形周溝墓や上抗墓の他に、新たに大型のお墓である「古墳」が造られるようになります。占墳の形や規模にはさまざまなものがありますが、埋葬方法などによって大きく2つに分けられます。竪穴式石室や石棺・木棺を埋葬する竪穴式の構造を持った、前~中期の古墳と、横穴式石室を持ち埋葬品も質素な後期古墳です。前~中期の古墳からは銅鏡や鉄剣などの権力の象徴を表す副葬品が出土しています。この地域を治めた豪族の墓であると考えられ、被葬者は原則として一人です。一方、後期古墳は数も多く、何回も使用する家族墓の性格を持っといわれ、古墳に葬られる人の層が広がったと考えられます。小木(こき)古墳群 小牧で最も規模の大きな古墳群です。古墳時代前期に作られた宇都宮神社古墳などです。三ツ山(みつやま)古墳群 5世紀初めに造られたとされる古墳群です。宇都宮神社古墳 小木古墳群の中でも最も保存状態が良く、中心的存在で、全長59メートル、後方(円)部は 直径34メートル、高さ6.5メートルを測る前方後方(円)墳である。後方(円)部頂上には 社殿が建ち、昭和初期の社殿建設の際に竪穴式石室から三角縁獣文帯三神三獣鏡 (県指定有形文化財)が出土した。「律令国家の時代」。古いやきものと幻の大山寺飛鳥時代に、現在の法律にあたる「律令」が制定されて以後、平安時代の初めごろまでを律令国家の時代とも呼びます。7世紀後半、小牧市東部を中心とする丘陵(現在の桃花台ニュータウン)では、陶器の生産が始まりました。同じころ、この丘陵の北側では、山岳寺院である大山寺が創建されました。篠岡古窯跡群(しのおかこようせきぐん)尾張は古代窯業の中心地の一つで、現在の桃花台ニュータウンを中心とする丘陵では、飛鳥時代から平安時代にかけて100基以上の窯が築かれ、篠岡古窯跡群と呼ばれています。飛鳥時代(7世紀)から奈良時代(8世紀)には須恵器と呼ばれる釉薬を用いない灰色硬質のやきものを焼いており、ここで焼かれた陶器や硯などが、藤原京(奈良県)の中央官庁で使われていたことが判明しています。平安時代(9世紀後半)に入ると、伝統的な須恵器とともに、釉薬を用いた薄緑色の灰釉陶器や緑釉陶器を焼くようになりました。平安時代の末期(12世紀)には、灰釉陶器は、釉薬を用いない山茶碗と呼ばれる粗雑な焼き物に変化し、12世紀前半に終焉を迎えました。大山廃寺跡 国指定史跡小牧市北東部の丘陵中腹、大山の集落から稚児川をさかのぼった標高200mほどの山中にある山岳寺院跡で、尾張平野を見下ろす眺望の地です。創建当初は塔など、瓦を葺いた本格的な礎石建物を有していましたが、平安時代には掘立柱建物となり、火災で焼失するなど盛衰をくりかえしながら、鎌倉・室町時代にもかなりの規模を持っていました。現在でも山中の各所にはかって堂が建っていたと見られる平地が多数残っており、伝説に「大山三千坊」といわれた往時をしのぶことができます。「武士の時代」。たたかいの時代へ室町時代の半ば、織田氏が尾張の守護代に任命されて以来、小牧はその支配下に置かれていたようです。織田氏の支配をうける前後、平手氏の小木城、西尾氏の大草城、堀尾氏の南外山城が築かれ、それぞれの区域に支配が及んでいたようです。小牧付近の大きく情勢が変わったのは、信長が桶狭間の戦いで今川氏を破った後です。信長が小牧城を築き、天下人への足掛かりを築き始め、本能寺の変で斃れた後は、尾張の支配者は織田信勝、羽柴秀次、福島正則と代わり、関ヶ原の戦い後は徳川家の支配となり江戸時代となりました。「江戸時代の発展」。小牧のまちのはじまり1616(元和2)年、尾張藩主徳川義直は居城を清須城から名古屋城へ移します(清須越し)。それに伴い尾張藩は名古屋城から春日井、小牧を経て中山道へ抜ける新たな街道(上街道(木曽街道))の整備に着手します。この上街道の整備にあたり、小牧のまちに、1623(元和9)年に小牧山の南から現在の市街地に移転されました。町場は小牧宿として整備され、商工業の中心地となりました。小牧はもともと水利に恵まれた土地ではなく、小さな河川やため池に頼った農業をしていました。このため、尾張藩は現在の犬山市に入鹿池を構築してそこから用水を引いたり、木曽川から直接水を引くため、木津川用水や新木津川用水を開削するなどの大土木工事を行い、新田開発にあたりました。小牧宿小牧宿は、宝暦年間(1751~64)のものと推定される『小牧宿絵図』から、下町・中町・本町・横町・上之町に区割りされていたことがわかります。また、この街道の東側には東馬場町、西側には西馬場町も形成されていました。小牧宿は、他の宿場町同様、間口が狭く奥行きの深い町屋形式とよばれる地割りとなっていました。街の南端には木戸があり、木戸の南西に高札場がありました。下町の西側には尾張徳川家の別荘・小牧御殿(後には小牧代官所)がありました。下町と中町の境界付近には小牧宿の本陣を代々務めた江崎善左衛門の屋敷があり、間口六間半の大きさでした。中町・本町は商人の家屋が多く、まっすぐ北上すると戒蔵院に突き当たります。戒蔵院から東が横町で、街道は横町から北へかぎ状に曲がり、北上した先が上之町です。岸田家 市指定有形民俗文化財岸田家は、上街道(木曽街道)小牧宿の下町にあり、江戸時代に名字帯刀を許された旧家で、幕末には小牧村の庄屋や本陣の機能を補佐する脇本陣を務めました。岸田家には、瓦葺で中二階建ての母屋が残っていて、出格子や障子張りの出入り口、屋根に祀られた屋根神の祠などが小牧宿当時の姿を窺わせます。母屋は間口が広く、土間(にわ・にわみせ)と二列六室(みせ・ひかえ・ちゃのま・なかじき・ざしき・ぶつま)の三列の部屋をもつ大規模な町屋です。中二階は、薪等の燃料を貯蔵するところでしたが、北側は押入れの天井から出入りする隠し部屋があるのも著しい特徴です。岸田家は1800年ごろに一般的な町屋として建設され、天保年間(1830~43年)に大改造が行われ、現在の姿になりました。「小牧の近代」。大山で焼かれた大山焼明治時代、小牧の産業の中心は農業でした。主要な作物は米・麦で、その他に繭なども生産していました。大正期に入ると養蚕技術の進歩に伴い、養蚕業が盛んになり、勃績・製糸業の発展へとつながりました。篠岡大山では明治時代のはじめ、大山窯が開窯され、犬山焼に似た焼き物「大山焼」が焼かれていました。江戸時代には藩の許可がないと陶器生産はできませんでしたが、明治になると自由化され、各地に窯が築かれますが、大山窯はその一つです。大山窯大山窯では最初は染付や赤絵などの磁器が焼かれていましたが、明治38年(1905)に株式会社が設立されたのに前後して陶器が焼かれ、製品として各地に出荷されましたが、わずか5年で廃窯を迎えました。創垂館 (そうすいかん)創垂館は、1888(明治21)年、小牧山山頂西側の曲輪に、愛知県知事の発案で、迎賓館として建設されました。近世の伝統に基づく格式のある書院造の建築で、広い書院座敷があり、桧主体の良質な建築材を用いた、極めて上質な建造物です。翌年、小牧山とともに尾張徳川家の所有となり、明治から大正期には小牧山で同家主催の園遊会が催されました。1930(昭和5)に小牧山とともに小牧町(当時)へ寄贈を受けた後、1949(昭和24)年には現在地(青年の家東側)に移築されました。創垂館は建物のもつ文化財的価値とともに、竣工から移築を経て、小牧山の明治期から現在に至る歴史を有する建物として、後世に渡りその価値を伝え適切に保存するため、2020(令和2)年度から保存修理工事を実施し、迎賓館としての当時の姿に復原しました。「小牧市の文化財」。「小牧の文化財とまつり」。小牧市には、織田信長が居城として初めて築いた小牧山城をはじめ、歴史と文化があふれています。3つの映像から、小牧市に息づく文化財やまつりの魅力にふれてみてください。●田縣神社の豊年祭👈️リンク●小牧神明社の秋葉祭👈️リンク●小牧の文化財👈️リンク「小牧山と城下町の姿」。「小牧山と城下町の姿」。「史跡小牧山の歴史」。「小牧山の歴史」解読不能。「概要」「小牧山模型(縮小複製)」小牧中学校が所蔵していた模型は無彩色で木地。小牧小学校が所蔵していた模型。「代々、小教村の庄屋や小牧山守を動めた江崎家が尾張徳川家より下賜された「小牧山模型」をもとに、大正期に作成したとされる縮小模型。江崎家所蔵の模型と同様に、小牧山城を立体的に記録した貴重な資料である。小牧中学校が所蔵していた模型は無彩色で木地のままだが、小牧小学校が所蔵していた模型は江崎家のものと同様に、全体が録色に彩色されている。」「小牧山城の発掘調査小牧山では昭和61年(1986)以降、緑地整備」や史跡整備に伴い発掘調査を実施しています。その結果、織田信長の時代(永禄期)や小牧・長久手の合戦の時代(天正期)の小牧山の姿が次第にあきらかになりつつあります。永禄期の遺構小牧山を居城とした信長は、山中に多数の曲輪を配置し、城を築きました。また、小牧山の東の麓には一辺45m四方の武家屋敷を配置しました。」東南隅には最大規模である一辺75m武家屋敷を設け、ここに自らが居住したものと推定されています。発掘された永禄期の遺構としては、武家屋敷を区画する堀や土塁、井戸などがあります。また、頂上付近や大手道の調査では石垣が見つかり、従来考えられてきた土の城のイメージではなく、石の城であったことが判明しました。曲輪城の平坦な一区画のことで、堀や土塁などで内側を防御しています。小牧山東麓の帯曲輪地区には、堀や土塁で区切られた武家屋敷が数多く配置されていました。堀小牧山の東麓から北麓にかけて、約45mの間隔で山麓から放射状に伸びる堀が発見されました。この堀は、武家屋敷を区画していたもので、堀の規模は幅2m以上、深さ1.5m以上で断面がV字型の薬研堀で、傾斜角が50度にも及びます。天正期の遺構小牧・長久手の合戦の際、徳川家康は織田信長の城跡である小牧山城に大規模な改修を行い、堅固な陣城を築きます。このときの主な遺構は、小牧山の麓を取り巻く二重の土塁や堀、中腹を取りまく堀や虎口などです。土塁土塁は、外部からの敵の侵入を防ぐ目的で、土を高く盛り上げて、堤防のような形をしています。小牧山の麓の土塁は、幅10m、高さ303m程で外側の傾斜角は40度と急で、内側の傾斜はゆるくなっています。土塁の外側には堀がありましたので、堀の底から測ると土塁の高さは5mにもなります。虎口城の出入り口を虎口といい、小牧・長久手の合戦の際には、山麓に5か所の虎口を設けています。小牧山の東麓に設けられた、東を向いた2か所の虎口では、虎口の前面に深い堀を配するなど、他の虎口には見られない強固な造りとなっています。これは、東麓が敵方である豊臣秀吉が布陣した方向に向かう位置にあたるためと考えられます。小松山城から「発掘された土器類」。上段 左から皿:土師器 室町時代(16世紀中頃)皿:土師器 室町時代(16世紀中頃)鉢:瀬戸・美濃室町時代(16世紀中頃)丸皿:瀬戸・美濃室町時代(16世紀中頃)小天目茶碗:瀬戸・美濃室町時代(16世紀中頃)下段 左から内耳鍋:土師器 室町時代(16世紀中頃)茶釜型釜:土師器 室町時代(16世紀中頃) すり鉢:瀬戸・美濃室町時代(16世紀中頃)「小牧山城下町の発掘調査」案内パネル。永禄6年(1563)に小牧山を居城とした信長は、小牧山の南の原野に東西1km、南北1.4kmの規模の町を新たに築きました。小牧城下町は東西・南北に整然と街路が配置され、南側には堀と土塁で東西約1kmの惣構が築かれていました。城下町東部にあたる新町遺跡や西部の上御園遺跡の発掘調査で、城下町跡が確認され、近年の測量図等を使った城下町復元の研究成果が有効であることが確認されました。【新町遺跡】新町遺跡は小牧山城の南端から南に300メートルの地点に所在します。小牧中学校の移転に伴い平成6年から8年にかけて発掘調査を実施しました。調査の結果、東西45m、南北95mほどの武家屋敷、下級武士団または商工業者の居住域を確認しました。武家屋敷跡からは井戸、掘立柱建物。○などが確認され、出土した遺物からいずれも永禄期のものと判明しました。また信長の岐阜への移転後は、廃絶されていることも明らかになりました。【上御園遺跡】小牧城下町の西部に位置し、商工業者が居住した紺屋町・鍛冶屋町・新町と推定されている部分にあたり、平成16年から19年にかけて発掘調査を実施しました。調査では、調査区域のほぼ全域から、土坑940基、井戸22基、掘立柱建物36棟などの多数の遺跡が見つかりました。織田信長以前には集落があった様子がなく、織田信長が原野に城下町を築いたこと、織田信長の岐阜移転後も、町の一部が残り、江戸時代の初めに宿駅として小牧山の東へ移転するまでの間、継続したことが確認されました。さらに、発掘成果の分析から、直線的な東西・南北の道路と区画溝で区画された長方形街区に間口が狭く、奥行きの深い短冊形地割が配置されていたことが確認されました。標準的な1軒の町家を見てみると、間口が6~7mで、奥行は55~65m、街路に面して掘立柱建物が建てられ、街路から30~35mの間は井戸や土坑などが配置された生活空間で、その奥はその奥は区画溝までの間が、畑か庭であったとみられます。これは、江戸時代に一般化する城下町の原型にあたり、織田信長当時としては最先端の先進的な町づくりが行われたことを示しています。「上御園遺跡調査全体図」。上段左から皿(土師器):室町時代(16世紀中頃)小牧城下町・新町遺跡出土燈明皿(瀬戸・美濃):室町時代(16世紀中頃)小牧城下町・新町遺跡出土建水(瀬戸・美濃):室町時代(16世紀中頃)小牧城下町・新町遺跡出土 端反皿(瀬戸・美濃):室町時代(16世紀中頃)小牧城下町・新町遺跡出土丸皿(瀬戸・美濃):室町時代(16世紀中頃)小牧城下町・新町遺跡出土天目茶碗(瀬戸・美濃):室町時代(16世紀中頃)小牧城下町・新町遺跡出土下段左から片口(瀬戸・美濃):江戸時代(17世紀前半)小牧城下町・上御園遺跡出土耳付水注(瀬戸・美濃):江戸時代(17世紀前半)小牧城下町・上御園遺跡出土志野丸皿(瀬戸・美濃):安土桃山時代(16世紀後半)小牧城下町・上御園遺跡出土皿(土師器):室町時代(16世紀中頃)小牧城下町・新町遺跡出土燈明皿(瀬戸・美濃):室町時代(16世紀中頃)小牧城下町・新町遺跡出土建水(瀬戸・美濃):室町時代(16世紀中頃)小牧城下町・新町遺跡出土 「小牧山城下町」「清須から小牧山へ居城を移した織田信長は、同時に小牧山の南に広がる原野に、新たに城下町を築きました。その範囲は東側は合瀬川(木津用水)付近、西側は河岸段丘の端と推定されます。城下町の南端部には土塁と堀からなる惣構が東西に築かれましたが、現在は土塁の一部とみられる高まりが外堀神社の境内に、堀が総堀用水として残るのみとなっています。城下町に築かれた街路は東西南北に直線に伸び、その一部は現在も利用されています。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.20
コメント(0)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その5): 小牧山城跡-4・大手道~小牧山稲荷神社~吉五郎稲荷~観音洞
「れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)」を後にして、山頂にある「小牧山城跡・小牧山歴史館」に向かって登城する。幟「徳川家康本陣の地 小牧山城」。「小牧山歴史館(山頂)」への案内板。右手に「桜の馬場」。「小牧山のふもとに造られた二重の土塁と堀1584 (天正12)年の小牧・長久手の合戦で、小牧山に陣を敷いた織田信雄、徳川家康連合軍は、羽柴(豊臣)秀吉と対峙するため、織田信長の城であった小牧山城を改修し、山のふもとにニ重の土塁と堀を造りました。この場所の東側には、合戦の時に造られた内側の土塁が続いています。ここから南側にある堀の底までは約9mの深さがあります。」織田信雄、徳川家康連合軍が造った内側の「土塁」・「堀」を見る。「土塁」・「堀」の先に「大手道に繋がる「虎口」、道路の先に「小牧市庁舎」が確認できた。展望台。「小牧城下町小牧山に城を造った織田信長は、山の南側に城下町を造りました。当時はここから町の様子が見えたことでしよう。町は南北1.3km、東西1kmの広さで、東西、南北に道が通り、町の南側に造った土塁(土を積み上げて造ったかべ)と堀(地面を掘って造った大きな溝)により町が囲まれていたと考えられています(写真1)。町の中は身分や仕事の種類によって住む場所が分かれており、町の中央から西部には染物をする人や戦いの時に着る鎖の部品や刃物などを作る人などが、町の東部には武士が住み、寺がありました。城下町の東部にあたる新町遺跡の発掘調査をしたところ、土塁と堀で囲まれた屋敷地の中に建物や井戸が見つかりました(写真2 )。屋敷のある場所の全部は調査できませんでしたが、その大きさは南北19m東西45mの広さと考えられます。城下町の西部にあたる上御園遺跡の発掘調査をしたところ、南北6~7m、東西55 ~ 65mの細長い敷地に、道に面したところに建物、その奥に井戸などがあり、その奥は畑か庭で、一番奥に溝があるという様子がわかりました(図1)。溝は、町を区切る境にもなっていました。」「城下町の範囲とおもな道」。小牧山城は城の周りに堀がなく、城下町にも惣堀(町全体を囲む堀)もなく、防御性には乏しく、当時の戦闘用の城とはまったく違うものといえそうだが、となるといったいこの城は何なのか、信長は何のために作ったのか、その謎はさらに深まっているのだ と。堀、土塁の先に「小牧市役所」方向を見る。前方右に「大手口」の石段を再び。「史跡小牧山案内」。「小牧山の樹木市のほぼ中央に孤立する古生活の山で、昔から保護され、自然林の大木が育っていたが、コイサキの大群の生息により、木々が衰退し、大正以降ニ度にわたる台風によって被害をうけた。しかし、一部にシイ・カシ・カエデの自然林に近い状態が残り、タブオガタマの古木やユズリハ・カクレミノ・モチノキ・アオキなども多くその樹皮には、リュウメンシダや大形のイワガネゼンマイ・アスカイが見られる。乾燥部には、べニシダの仲間が群落を作っている。」さらに大手道方向に進む。「小牧山ランニングコース利用者のみなさんへこのコースは、市民のみなさんの日頃の運動不足を解消し、健康体力の向上をはかるために設定しました。利用される方は、下記の点に注意して楽しくご利用下さい。1走る前に必らず準備運動すること2自分のペース、能力に応じて走ること3歩行者、下り坂等、特に気をつけて走ること4体の調子の悪い時は、ただちにやめること5このコースでの夜間利用は禁止いたします6ジョギング中に気分が悪くなったりした時は、歩いて休息するか中止してくださいなお、コースの利用上における傷害、事故等について、市、教育委員会では責任を持てません お問い合わせ・小牧市教育委員会 TEL(0568) 72ー2101」「大手道コース」案内板。そしてこちらが、「大手道」。「市教育委員会では令和3年度から、戦国時代の武将・織川信長が山頂周辺に築いた2 ~ 3段の石垣や、南麓から山頂へ至る大手道の一部などの復元整備を進めています。令和5年度には、大手道沿いに切り立てられた岩盤と、その上に築かれた石の復元整備を行いました。」「10月1日から山頂周辺の石垣等復元整備工事に伴い、一部立入禁止となります。」と。「大手道」をズームして。織田信長が歩いたこの道を歩きたかったが!!この日は訪ねなかったが、ここが「小牧市役所前」からの「小牧山城」の「大手口」。以下4枚の写真はネットから。上の石段の先を見に折れた道が「大手道」。この先、左手にあるのが「徳川源明公墓碑」。「徳川源明公墓碑尾張藩中興の祖といわれた尾張徳川家九代藩主徳川宗睦源明(むねちかげんめい)公の墓碑である。元々は、尾張徳川家の菩提寺である名古屋市東区の建中寺にあったが、昭和二十八年に行われた区画整理のため、移転を余儀なくされ、徳川家に縁が深い小牧山のこの場所に移設されたものである。 平成二十二年十二月 小牧市教育委員会」と。その先の左手にあったのが「小牧山稲荷神社」。「小牧山吉五郎👈️リンク 稲荷社縁起天正の昔より小牧山は樹木鬱蒼と茂り数万羽の五位鷲の棲息地で又附近一帯は森林竹林が続き狐狸が多く棲息していた。そして小牧山には老狐吉五郎又山中藪には藤九郎。お林山のお梅。下津山の助五郎。岩崎山の勘八。二子山の文治郎。下原山の銀九郎等々色々面白い名のついた狐がいた。就中小牧山の吉五郎は尾北一圓の大親分格で魅力妖力霊力ともに勝れ近在の里人もその神通力に心服す。さきに郷党の人人相計り小牧山吉五郎稲荷社を創建し、これを祀る。事後霊験あらたかに崇敬するもの更に多く参拝者日々絶えることなく今日に至る。」社号標石「小牧山稲荷社」。一の石鳥居。扁額「小牧山稲荷神社」。その先に朱の鳥居が並ぶ。朱の鳥居を潜って。正面に拝殿が姿を現す。石製の灯明台。お稲荷様(右)。お稲荷様(左)。落ち葉の清掃をされているオジサンの姿が。正面に「拝殿」。近づいて。その奥に「本殿」。昭和11年に建てられたこの神社の本殿には、吉五郎が祭られている と。「小牧山初里姫竜王大神」と書かれた多くの白地の幟が。近づいて。「小牧山初里姫竜王大神」。稲荷神社の左奥に鎮座。近づいて。引き返すと、右側にも朱の鳥居があった。「𠮷五郎稲荷保安林」碑。山の裾野の小高い場所に「拝殿」そして小さな「本殿」を「蝋燭立て」越しに。こちらは昭和11年に創建された新しいもののようだ。手前に「拝殿」。「本殿」。“吉五郎”と言う小牧山の狐の親分を祀っている と。さらに「小牧山歴史館」に向けて坂を上る。「現在地」はここ。前方左には開けた場所があった。「観音洞」と。左前方に石碑が立っていた。「間々乳観音出現霊場」と。「間々乳観音出現霊場」は、ここ小牧山の中腹西側の曲輪上にあり、千手観音が出現したという伝承が残る場所。通称「観音洞」と呼ばれているのだ。石碑に近づいて。廻り込んで。「観音洞👈️リンク明応の頃・・・。乳の出ない妻に食わせようと、子孕み鹿を撃ちに小牧山に登った麓の狩人が、七匹の子鹿を連れた子孕み鹿を見つけて撃っと、子鹿は七つの石に、母鹿は観音像と化した。狩人はこれを見て殺生を悔い、その地に草庵を結び観音像をねんころに祭った。後に観音を祭る草庵は間々に乳観音として移転👈️リンクしたが、草庵の跡地は観音洞と呼び親しまれ現在に至っている。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.19
コメント(1)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その4): 小牧山城跡-3・れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)(2/2)
「小牧山に関わる先人たち」。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康。「歴史の舞台 小牧山屏風の白い模型に映し出された合戦図の絵はプロジェクションマッピングの映像。来館者が視聴ゾーンに入るとセンサーにより自動で戦国時代の小牧山に関する映像コンテンツが展開されるのであった。その隣にも映像が。「変わる小牧山 小牧山今昔」。そして壁には多くのパネル展示が。「試掘からはじまる試掘調査の目的小牧山城には、永禄期(織田信長の居城時)と天正期(小牧・長久手の合戦時)の遺構がありますが、平成10年(1998)度の「史跡小牧山整備計画基本構想」では、整備の主たる時代設定を天正12年とし、永禄期の遺構については発掘調査に基づき整備を行うとされました。その後、小牧山山東麓の旧小牧中学校用地の調査で、永禄期の遺構に重要な発見があり、小牧・長久手の合戦時の改修がどのようなものであったかを明らかにするとともに、下層の信長の小牧山城の実態を明らかにした上で、整備方針を確定することが必要になりました。史跡整備の基礎資料を得るため、平成16年度から19年度の4か年にわたり主郭地区の試掘調査が行われました。試掘調査により、小牧・長久手の合戦時の遺構と、信長の築城時の遺構の貴重な調査結果が得られ、調査結果を活かし、より具体的な復元整備の方針が示されました。」試掘調査のおもな成果●第1次試掘調査(平成16年度) <大手道付近に小牧・長久手の合戦の改築の痕跡が>●第2次試掘調査(平成17年度) <主郭周辺の斜面には石垣が>●第3次試掘調査(平成18年度) <土橋付近の構造を確認>●第4次試掘調査(平成19年度) <岩盤上に築かれた石垣を確認>」「小牧山の発掘と整備の歩み1中世から近代の小牧山の歴史中世以前の小牧山の姿はよくわかっていませんが、古くは信仰の地であったようで、小牧山北西の間々観音寺(間々観音)の寺伝によると、中世に小牧山から現在地に移されたとあります。戦国時代の永禄6年(1563)には、織田信長が小牧山に初めて城を築き、清須(愛知県清須市)から居城を移しました。さらに、小牧山に初めて城を築き、清須(愛知県清須市)から居城を移しました。さらに、小牧山の南側には計画的に城下町を築きました。永禄10年(1567)の美濃攻略後、信長は稲葉山城(岐阜城・岐阜県岐阜市)へ移り、小牧山城は廃城になりました。天正12年(1584)の小牧・長久手の合戦では織田信雄・徳川家康連合軍の主陣地となり、大規模な改修が加えられました。小牧山は江戸時代には尾張徳川家の所有となり、家康公「御勝利御開運の御陣跡」として大切に保護されました。一般の入山が禁止されたことにより、山の中の土塁や堤などの遺構が良好な状態で遺されました。明治以後は官有地、民間、愛知県と所有者が変わり、一般に開放された時期がありましたが、明治22年(1889)に再び尾張徳川家の所有になり、一般の入山も禁止されました。史跡指定後の小牧山小牧山は歴史的に価値があり、遺構の保存状態も良いことなどから、昭和2年(1927)10月26日に国の史跡に指定されました。同年11月から小牧山再び一般に開放きれ、昭和5年には尾張徳川家から小牧町(当時)に寄付されました。太平洋戦争を経て、山の状況は大きく変化しました。昭和22年(1947)に東麓に小牧中学校が建設されたことをはじめとして、山頂の展望台(昭和30年)、青年の家(昭和39年)、市役所本庁舎(昭和40年)、小牧市歴史館(昭和43年)といった公共施設、他にも駐車場やし尿中継槽が設けられ、園路の拡張も行われました。これらの建設にあたって発掘調査は行われておらず、遺構の記録は古城絵図等の他には、史跡指定時に作成された測量図が残っているだけでした。写真左:小牧山山頂の展望台(昭和39年撮影)中 央:小牧市歴史館(開館当時)(昭和43年撮影)写真右:旧小牧市役所庁舎(昭和44年撮影)」「小牧山の発掘と整備の歩み2」史跡小牧山 帯曲輪地区の発掘調査と整備の実施昭和50年(1975)ごろから平成時代にかけては、史跡小牧山を「自然に親しみ歴史に触れることができる魅力ある山」とするよう、「小牧山整備基本調査報告書」(昭和59年)、「小牧山緑地整備 (北麓) に伴う小牧山史跡整備計画」(昭和62年)等で、整備の方針が定められました。昭和61年(1986)度、帯曲輪地区北部で史跡小牧山における最初の発掘調査が実施され、調査結果に基づき土塁等の復元が行われました。翌昭和62年度からは駐車場、し尿中継槽など史跡にふさわしくないものの撤去が始まり、平成10年(1998)度には小牧中学校が史跡外に移転しました。小牧中学校の跡地では、後述の「史跡小牧山整備計画基本構想」に基づき、平成10~14年度に発掘調査(平成10・11年度は試掘調査)を実施し、平成13年度から調査結果に基づく遺構復元等の整備が行われました。写真左:発掘調査時の土塁断面(小牧山北東麓)中 央:史跡公園として整備された帯曲輪写真右:復元された土塁(搦手口)※ 帯曲輪地区・・・小牧山の北麓から東麓にかけて、山を取り巻くように配置された曲輪群「史跡小牧山城と周辺の発掘と整備の歩み」。「佐久間石出土第3次発掘調査(平成22年度)で、主郭北西斜面から墨の文字が書かれた(墨書)石垣石材が出土しました。墨書は刻印と同じく、城郭が割普請で築城されたことを裏付けるものです。墨書は草書体で「佐久間」と記されており、「佐久間石」の通称でよばれています。「佐久間」の文字からは、織田家の宿老佐久間信盛に代表される佐久間一族の存在がうかがわれます。「佐久間石」は、佐久間一族が小牧山城主郭石垣の築造に関与していた可能性を示す貴重な資料です。※ 刻 印・・・石の所有や責任分担を示すために、石垣の石材に刻まれた図や記号※ 割普請・・・石垣づくりなどの工事を分担して行うこと墨書石垣石材はれきしるこまき常設展示室内に展示中と。墨書石垣石材は、主郭北西斜面の上段石垣背後の石垣の崩落に伴う裏込石の流出・堆積土中から出土しました。(図4★印付近)」「石垣は3段あった3段目石垣主郭下の北西から北東にかけて、2段目石垣の斜面に曲輪051とよばれる平坦地があります。第7次発掘調査では、1・2段石垣と並行して、曲輪051の外周に築かれた、3段目石垣を確認しました。それまでは小牧山城の主郭は2段の石垣に囲まれていたと推定していましたが、第7次発掘調査で、3段目の石垣が主郭北西斜面~北斜面へと延びることが確認されました。その後の発掘調査で、3段目の石垣は主郭東斜面まで続くことが確認されました。」腰巻石垣3段目石垣の上部には曲輪051の外周をなす土の法面が続き、築石や裏込石は確認できませんでした。このことから、3段目石垣は曲輪051の端部の高さまで積まれていなかった可能性が上の曲輪051の崩落を防ぐ擁壁の機能を持つ「腰巻石垣」であったと考えられます。」※法面・・・人工的な斜面※築石・・・石垣本体の石※裏込石・・石垣を崩れにくくするために石垣の石の裏側に詰め込んだ石※腰巻石垣・土塁などの下部だけに積まれた石垣」「石垣の発掘続く第4 ・5次発掘調査は、主郭の南斜面と南東斜面で行われました。いすれの斜面でも屈曲を繰り返しながら主郭を囲む上段の石垣と、それに並行する下段の石垣が確認されました。この調査区域では、下段壁面は石垣が築かれている部分と、垂直に削平した岩盤の部分からなっていました。玉石敷と石枡遺構主郭北西斜面の下段石垣◯の平坦部上に、拳大の玉石が敷き詰められているのを確認しました。また、玉石敷部分の北と南から石枡状の遺構が見つかりました。この石枡は、雨水などの水を一か所に集めて地中に流して処理する、浸透桝のような機能を果たしていた可能性があります。」「主郭を取りまく石垣途切れることなく続く石垣小牧山山頂付近の西~北西斜面には、発掘調査が行われる前から石垣の一部が露出していましたが、第1・2次発掘調査により、露出していた石垣ををはさんで左右の斜面からも石垣が確認されました。これにより、主郭の西~北西斜面には、石垣が途切れることなく続いていることを確認しました。上下段違いに築かれた石垣第2次発掘調査では主郭北斜面の発掘が行われました。北斜面では、平行方向に築かれた上下段違いの石垣が確認されました。上段の石垣は、第1次発掘調査により西~北西斜面で確認された石垣から続くものでした。延びる、つながる上下2段の石垣第3次発掘調査では、主郭北西斜面で約35mにわたり、上下2段の石垣を確認しました。第3次発掘調査で確認した石垣は、「根石(最下段の石)」を中心に石垣の列が良好な状態で残っていました。また、石と石の間を埋める「間詰石」という小さな石も残っており、築城当時の石垣のありのままを確認することができました。」「主郭へ、虎口はここに!築城時の小牧山城には、主郭~の登城路が2つありました。山の南斜面で屈曲を繰り返しながらも主郭に至る大手道、山の北側から主郭に通じる搦手道です。江戸時代前記に描かれた「春日井郡小牧村小城絵図」には、大手道と搦手道から主郭に入る2つの虎口が描かれています(前者赤円内・後者緑円内)。第8次発掘調査では、この2つの虎口を確認しました。3つ目の虎口は第10次発掘調査では、小牧山の西側から主郭に至る登城路の西側をはさむ位置に、石垣の列を確認しました(紫円内)。これまで存在を知られていまかった、主郭への虎口と推定されます。側溝の石組みと礎石も見つかる①は搦手道虎口付近の発掘時の状況です。山側壁面に石垣を確認しました。さらに、この石垣に沿って、側溝の石組みと礎石1石を確認しました。門のような建造物があったのではないかと推定されます。大手道の虎口大手道をはさむ石垣の2つのライン(赤破線)が確認きれ、虎口の形状と主郭に至る大手道の経路が明らかになりました。屈曲部の巨石は築城時のものではなく、昭和期の石階段建設時にこの位置に移されたものです。」「大手道は広く迫力満点第9次発掘調査(平成28年度)と第12次発掘調査(令和元年度)により、主郭南西斜面で築城時の大手道の跡が明らかになりました。築城時の大手道は、山の岩盤を削平して設けられており、下の略図(図9)で示したようい復元整備前の◯路(登城路)より、はるかに広い道幅がありました。また大手道の山側には、垂直に削り加工した岩盤と、その上に積まれた石垣からなる壁が聳えていたことが判明しました。発掘調査により、大手道の0登城路の規模や構造が予想以上に大がかりであったことが判明しました。小牧山城は、主郭だけでなく大手道にも、連続する石垣と岩の壁を思わせる岩盤が連なり、登城者を圧倒する築城プランを有していたことが推定されます。」「信長の館か?初めてみつかった屋敷建物の一部小牧山城主郭南斜面下の曲輪023から、建物の一部と推定される礎石列を確認しました。建物の北側の壁沿いに、玉石敷と排水用の側溝を伴うことが確認されました。出土品も高級建物付近の曲輪023からは、天目茶碗や青磁の小椀なども出土しました。信長の館か?岐阜城 (岐阜県岐阜市)や安土城(滋賀県近江八幡市)の山頂付近には、信長のための特別な生活空間が設けられていました。山頂付近という遺構の位置、精緻な玉石敷の存在、高級な焼き物が出土してたことなどを考えあわせると、今回の発掘調査で確認した遺構は、信長の館の一部であるという可能性が出てきました。令和5年度にも曲輪023の発掘調査が行われましたが、第11次調査で確認した礎石に対比する礎石は発見されませんでした。礎石の性格を確認するためには、さらなる調査が必要です。」「庭園の跡か?主郭東側の搦手口付近の2段目石垣部の曲輪で、玉石敷遺構を確認しました。これまでの主郭地区の調査で確認された玉石敷遺構は、建物跡や排水施設を伴っていましたが、今回の玉石敷ではそれらは確認されず、異なる用途、機能で設けられた可能性があります。玉石敷は広範囲にわたっており、意図的に据え置かれたとみられる立石が確認されました。また、植栽痕や立石の抜取痕の可能性のある円形状に玉石の敷かれていない箇所もありました。これらのことから「枯山水」のような庭園に伴う石敷遺構である可能性が推定されます。」「眠っていた石垣石垣の発掘により一躍脚光を浴びた小牧山城ですが、発掘調査以前から、山頂付近に石垣の一部を露出していました。「春日井郡小牧村小城絵図」では、小牧山城主郭西斜面の一部に石垣の表現が描かれています(赤円内)。この場所は主郭地区発掘調査が行われる以前から、石垣が露出していたところです。これ以外の主郭斜面は他の斜面と同じように土の法面として描かれています。この絵図は描かれたのは、織田信長の小牧山城築城後約90年を経た、江戸時代前記の慶安年間(1648~1652)頃といわれています。これを見る限り江戸時代前期には、主郭をめぐるほとんどの石垣をめぐるほとんどの石垣がすでに埋没していたことがうかがえます。」「石は役割をもつ石垣の大小様々な石石垣本体の石、石垣をより〇〇にするため、・・・・??」「小牧山の発掘と整備の歩み3近世城郭への転換点~小牧山城平成16年(2004)度からわれた主郭地区発掘調査により、織田信長時の小牧山城の姿が徐々に明らかになってきました。主郭の周囲や大手道壁面で確認きれた石垣は、小牧山城郭築発掘調査の大きな成果の1つでした。これら石垣の発掘により、信長が築いた小牧山城は、土に城が主流であった中世城郭から、後に総石垣を有するようになる近世城郭への転換点にあたる城として、歴史的に価値の高い史跡であることが明らかになりました。石垣の他にも、予想を上回るスケールを擁した大手道、信長の館や庭園の可能性があるための一時的な陣城と評価されたこともあった小牧山城ですが、先進的な築城プランで築かれた画期的な城として、一躍脚光を浴びることになりました。」発掘の成果を整備に、そして発掘調査は続く主郭地区第一次発掘調査終了後の平成21年(2009)3月、「史跡小牧山主郭地区整備基本計画」が策定されました。同計画に、史跡小牧山の発掘調査を活かし、主郭を取り巻く石垣の遺存状態を考慮しつつ、復元整備や修復を行うことが示されました。同計画修正版では主郭地区Aゾーン(主郭とその周囲)を5つの工区に分け、石垣、虎口、登城路の復元整備を行うことが示されました。令和3年(2021)度から工区ごとに復元整備工事が行われ、令和5年度末現在、3つの工区の復元整備が完了し、令和6年度は第3Ⅰ工区の整備工事が行われています。主郭地区発掘調査21年目となる令和6年度は、大手道の発掘調査を行っています。令和7年度以降も小牧山の発掘調査は続いていく予定です。」奥には作業部屋があった。「発掘道具ここに展示されているのは発掘調査で使用する道具です。同じ道具が二つ並んでいますが、向かって左が使う前、右が使い込んだものです。違いを見てみましょう。」発掘品がビニール袋に入れられて並ぶ。令和3年までの発掘調査をもとに作成された主郭地区(山頂)イメージ図。「発掘作業員さんにきいてみました」史跡小牧山の発掘は新聞に何度も取り上げられました。●佐久間石出土●山頂を囲む石垣確認●登城者を圧倒する大手道の石垣が見つかる●石垣は三段あった!!●庭園の可能性を示す玉石と巨石出土●山頂付近に館跡が見つかる「◯景図で見る信長・家康の小牧山城」永禄期 小牧山城推定想像図 作画:平手 卓氏 築城年:永禄6年(1563) 築城主:織田信長永禄6年(1563)織田信長が自らの手で初めて城を築いたのが小牧山城です。信長は、清須から小牧に移り、永禄10年(1567)に美濃の稲葉山城を攻略し岐阜と改め移るまでの4年間、居城としました。山頂に至る主要道である大手道は、中腹まで直線的に登り、中腹から東に折れて屈曲しながら山頂の主郭に至ります。発掘調査により、主郭周囲には二段から三段の石垣が巡り、また、主郭南東側二段目石垣下の曲輪では、信長の館の可能性のある屋敷跡の一部を、主郭東側の曲輪では庭園と推定される玉石敷や立石を確認しました。小牧山の東から北の山麓にかけて、土塁と堀によって区画された武家屋敷群が築かれていたことがわかり、中でも東南部の区画は一辺が75メートルと小牧山城で最大の規模であるため、信長の館があった場所とも考えられます。小牧山城築城と同時に、信長は城の南に小牧山城下町を整備しました。規模は南北1.3km 東西1kmに及び、発掘調査により城下町域の東部は武家屋敷が、西部は商工業者の居住する町の様子が明らかになってきました。図中の建物は、発掘調査で存在が確認できたものもありますが、当時の小牧山城の様子が記録されている絵図や文献がなく、不明な点が多いため、一部推定で描かれているところもあります。【用語解説】 曲輪・・・堀、土塁、石垣などで囲まれた平坦な一区画 堀 ・・・敵の侵入を防ぐため、城の周囲などに掘られた溝 土塁・・・土を盛り上げて築いた土手、堤信長時代の「永禄期 小牧山城推定想像図 作画:平手 卓氏」近づいて。特徴的な真っ直ぐの大手道があり、山城部分は城の機能を有していたが、麓部分は屋敷の集まりであり、防御的機能はあまり有していなかった と。家康時代の「天正期、家康時代の小牧山城」。基本的な構造は変わりませんが、山城部分は真っ直ぐだった大手を屈折させ新たに堀を増設、麓部分も全体を堀と土塁で囲み防御力を高めていることがわかるのであった。「天正期 小牧山城推定想像図 作画:平手 卓氏築城年:天正12年(1584)築城主:織田信雄・徳川家康連合軍天正10年(1582)本能寺の変による織田信長の死後、跡目争いを発端に、天正12年(1584)羽柴秀吉と織田信雄・徳川家康連合軍が争っ戦いが小牧・長久手の戦いです。犬山城を占拠し清須方面へ南下しようとする秀吉軍に対し、信雄・家康連合は小牧山城をわずか5日で改修したとされ、主な改修場所は、山の中腹の堤.土塁、虎ロの◯◯、山麓を囲む二重の土塁と堀、5か所の虎口などと考えられます。小牧山南側の大手道東ガイダンス広場に復元している土塁の高さは、約8mに、土塁と堀との高低差は6mあり、防御が強固なものであったことが本図からも窺い知ることができます。信雄・家康連合軍は、小牧・長久手の戦いでて8か月ほど小牧山に陣を敷きましたが.その後は廃城となります。江戸時代に入ると、家康ゆかりの地として尾張徳川家の手厚い保護を受けました。そのため、遺構の保存状態は良く、現在でも山中のいたるところで小牧・長久手の戦い当時の堀や土塁をご覧いただくことができます。【用語解説】虎口・・・城の出入り口曲輪・・・堀、土塁、石垣などで囲まれた平坦な一区画堀 ・・・敵の侵入を防ぐため、城の周囲などに掘られた溝土塁・・・土を盛り上げて築いた土手、堤」「土の城から石の城へ」手前に置かれた石の模型に手をかざすと、プロジェクションマッピングが動き出すのであった。小牧山山頂で確認された石垣の1・2段目を実際のサイズで再現していた。プロジェクションマッピング映像を模型に投影することで、石垣の今の姿や、推定される小牧山城築城当時の姿をわかりやすく伝えてくれるのであった。多くのサイン入り色紙も展示されていた。テレビでお馴染みの千田嘉博先生。日本100名城の選定委員も務めた小和田哲男先生。「御城印」を頂きました。「続日本百名城」のスタンプ。「登城記念スタンプ」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.18
コメント(0)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その3): 小牧山城跡-2・れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)(1/2)
「小牧山城 土塁断面展示」を通過し城内に入ると左手に散策道が続いていた。前方に曲輪跡・405が拡がっていた。曲輪配置図をネットから。曲輪跡・405が○。前方の桜の樹も開花していた。「四季桜四季桜。交雑コヒガンの園芸品種.花は白一極淡い紅色の5弁花です。秋一初冬と春に咲きますバラ料」大手口まで450mと。1段上の遊歩道に石碑があった。この「希望台」碑は、小牧山の東側、現在の史跡公園の場所に小牧中学校があった時、開校10周年記念に、昭和32年(1957)建立されたものであるとのこと。校歌の第四番が刻まれているのだと。「希望台」は、生徒会、卒業生、同窓会の寄付により建設されたもので、小牧中学校のシンボルであった と。『姿け髙き 雪の峰 仰ぐ理想の いや髙く 登る歩毎の たくましく よき町 国を夢みつゝ 生命の限り 伸びゆかん』と。「創立四十周年記念 移転建立 同窓会」と。左手にあったのが「曲輪402・帯曲輪地区」。「曲輪402 発掘調査の解説史跡整備前に行った発掘調査は、かってここにあった中学校の運動場造成で全体に削平を受けていたため、削平の影響が少ない土塁際や堀の存在が予想される部分に限定して行いました。曲403a (現在地)と曲輪402を区画する堀は、幅3m、深さ約2mの規模をもっています。堀の形態は断面がV字形の部分と底が平坦な部分があります。この堀の南側で土塁の積み土の痕跡を確認し、曲輪402は土塁に取り囲まれていたことを明らかにしました。また、昭和2年に作成された小山の地形測量図をみると、堀は曲輪402の北西角まで続かず、北西角付近に出入口があったものと考えられます。曲輪402は、一辺が75mあり、山麓部分で最大規模の曲輪であることから、小牧山城を築いた織田信長の居館があった可能性があります。」右手の高台、木々の奥にあったのが「小牧山 創垂館」。ここは、今回訪ねなかったので、この後に頂いたパンフレット👈️リンク を。「小牧山と創館の由緒創亜館は史跡小牧山の南東側中腹に建つ。ここに初めて城を築いたのは織田信長で、永禄6年(1563)に、山頂に石垣を備えた主郭、その西側から南側の山中に曲輸を設けた。信長の跡目争いとして、羽柴(豊臣)秀吉と織田信雄・徳川家康連合軍が戦った「小牧・長久手の戦い」が天正12年(1584)に始まると、徳川家康は、小牧山城を改修して本陣をおいた。江戸時代になると、小牧山は徳川家康の「御勝利御開運の御陣跡」とし尾張藩の「留山」となり、保護された。版籍奉還後は明治政府の所有るとなったが、明治6年(1873)には愛知県の所有となり、「小牧公園」として一般に公開された。明治21年、山頂西側の曲輸に、愛知県の迎賓館として創垂館が建設されたが、その翌年に小牧山は尾張徳川家に払い下げられ、盛大な園遊会が、明治から大正期にかけて開催された。昭和2年年(1927)、小牧山が史蹟に指定され、昭和5年には、尾張徳川家から小牧川町に寄付された。昭和24年、創垂館が現在地に移築され、昭和39年には、西隣に小牧市青年の家が建設され、創垂館は生涯学令和4年3月にかけて保存修理が行われた。」そして前方に見えて来たのが「れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)」。「れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)周辺にあった曲輪」案内。「れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)周辺にあった曲輪小牧山城は、曲輪(平らな所)、堀(大きな溝)、虎ロ(出人口)などの配置から、主郭地区、西側曲輪地区、大手曲輪地区.西側谷地区、帯曲輪地区の5地区に区分されています(図1 )。この辺りは大手曲輪地区の東の端にあたり、同地区は、大手道の両側に造られた曲輪群からここまでに約20の曲輪があります。かってはここに東西に細長い3つの曲論(曲輪216・217・218 ) がありましたが(図2)、1947 (昭和22)年に中学校を建設する時に3つの曲輪の大部分が削られてなくなりました。なお、中学校は、1998 (平成10 )年に史跡整備のため、小牧山の外へ移転するまでの約50年間ここにありました。れきしるこまきは、中学校の校舎があった場所建てられ、曲輪218の位置にあたります。建物南側ひさしの高さがほぼ曲輪218の地面の高さ、建物屋根のてっぺんの高さがはぼ曲輪217の地面の高さです(図3)整備では、曲輪の姿を元に戻してはいませんが、曲輪217と218の範囲を表す輪郭線の一部を、建物の周りではタイルの色を変えたり、石をべて表示し、建物の裏側では低木を並べて表示しています。」図1(左):小牧山城の地区区分図図2(右):れきしるこまき (小牧山城史跡情報館) 周辺にあった曲輪(拡大図)図3(下):曲輪があった時と現在の地形断面図「れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)」の正面に廻り込んで。史跡小牧山(小牧山城) 愛知県小牧市堀の内一丁目1番地 他 1927(昭和2)年10月26日国指定 指定面積 205,956.23㎡小牧山は、平野の中にとび出た小山で、山の頂上の標高は85.9メートルです。1563(永禄6)年、尾張国(現在の愛知県北西部)を支配していた織田信長は、美濃国(現在の岐阜県南部)の斎藤氏を攻めるため、小牧山に城を造り(小牧山城)、それまで住んでいた清須城(現在の愛知県清須市)からここに来て住みました。また、山の南側には城下町を造り、家臣や商人を住まわせました。しかし、4年後に信長は、斎藤氏を攻めて稲葉山城へ移ったため、小牧山城は使われなくなりました。1584(天正12)年、小牧・長久手の合戦といわれる戦いが起き、織田信長の子どもの織田信雄と徳川家康が小牧山城を本陣としました。この時、小牧山城は改修されて、山のふもとを一周する土塁(土を積み上げて造ったかべ)や堀(大きな溝)などが新しく造られました。戦いはこの年のうちに終わり、その後小牧山城が城として使われることはありませんでした。小牧山の中には城として使われていた時の土塁や堀などがよく残っていて、1927(昭和2)年に、文化財として大切に残していく場所として、国の史跡に指定されました。「れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)」入口。「れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)」と。「ご案内開館時間:AM9:00~PM5:00休館日 :第3木曜日(但し祝日の場合は翌平日) 年末年始(12月29日~1月3日)入場料 :常設展示室入場料 大人 一般 200円、 団体(30人以上) 100円 18歳以下 無料」幟「小牧山城史跡情報館 れきしるこまき」。上部に織田信長「織田木瓜紋」、その下に徳川家康「三つ葉葵紋」。幟旗「織田信長」、「徳川家康」、「厭離穢土 欣求浄土(おんりえど ごんぐじょうど)」と。「極楽浄土に往生する(生まれ変わる)ことを心から願い求めること」という意味で、浄土宗で使われる「信ずる者への救いの道」つまりは「篤(あつ)く信ずれば、来世では幸せの世界が待っている」という教えである と。「ようこそ れきしるこまきへ」。戦国時代、織田信長が城を築き、小牧・長久手の戦いの主要な舞台となった小牧山。そのふもとに立つ「れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)」は、小牧山の歴史や文化のほか、貴重な自然を案内してくれるガイダンス施設。頂いたパンフレット。小牧山の頂上には小牧城を模した資料館があったが、最近の発掘調査でわかったことを展示するため麓に新しく作ったもので、実物大の石垣模型やITを駆使したビジュアル解説など斬新な設備の館であった。「小牧山のふもとに建つれきしるこまき(小牧山城史跡情報館)は、鉄骨造、延べ床面積約1,000m2の平屋建てで、小牧市のシンボルである小牧山の歴史や文化、残された貴重な自然をみなさんにお伝えするガイダンス施設です。常設展示室では、発掘調査で明らかとなった織田信長が築いた小牧山城の石垣や城下町、小牧・長久手の戦いなど、小牧山を取り巻く歴史を、模型や映像を多く使ってわかりやすく紹介しています。また、企画展示やワークショップ、講演会や講座を行うスペースを設けており、小牧山に関する最新の情報を提供する施設です。平成26年度(2014)より基本構想の策定を始め、平成29年度(2017)に建設工事を開始。平成31年(2019) 4月25日に開館をいたしました。」展示室の入口ホール。床には、「小牧山城案内図」が大きく描かれていた。サンルームの如き通路にも各種案内板が。「小牧山 ヒストリーギャラリー」。小牧市のシンボル小牧山は古来より人々のくらしとともにありました。織田信長の居城移転によって歴史の表舞台に上がって以来、羽柴(豊臣)秀吉、徳川家康とも深くかかわりを持つ山となりました。近年の発掘調査により新たな姿も明らかになってきました。原始・古代・中世太古:小牧山のはじまり古代・中世:祈りの山、小牧山戦国(信長と小牧山)1563(永禄6)年:小牧山城を築く。 信長は小牧山に居城を山の南側に城下町をつくった。1565(永禄8)年:信長、「麟(りん)」の花押を使いはじめる。 天下太平の世の象徴ともいわれる麒麟の「麟」の文字を花押にしたと考え られている。1567(永禄10)年:美濃を攻略する。 信長は稲葉山城の斎藤龍興を下し、岐阜と改称すると、小牧山から居城を 移した。織豊 (秀吉・家康と小牧山)1584(天正12)年:小牧・長久手の合戦。織田信雄・徳川家康連合軍と羽柴(豊臣)秀吉の間で 行われた戦い。 小牧に残る砦跡。小牧付近には両軍の砦が数多く築かれた。近世 (江戸時代)1650(慶安3)年頃:小牧村古城絵図を作成。 小牧山は尾張藩領となり、一般の立ち入りが禁止され、山守頭の江崎氏 らにより大切に保護された。1841(天保12)年頃:各村の庄屋が村の絵図を作成。 尾張藩に提出された村絵図からは、小牧山の周囲に竹垣が築かれ、一般 の入山が禁止されていたことや、松・竹が生えていたことがわかる。 また、田畑の中に城下町の名残の規則的な道路や地名も見られる。 近現代1888(明治21)年:創垂館の建設。 迎賓館としての役割を備えた施設として建設された。1890(明治23)年 : 尾張徳川家、小牧山で園遊会を催す。 旧藩士を招き、開かれた園遊会。2日間で約7000人が訪れた。1927(昭和2)年:小牧山、国の史跡となる。 国の史跡に指定されたのを機に一般公開された。1927(昭和2)年:陸軍特別大演習。 昭和天皇の指揮のもと、小牧山を中心に陸軍の大演習が行われた。1947(昭和22)年:小牧中学校の建設。 小牧山の東のふもとを整地して、町立中学校が建設された。1955(昭和30)年:山頂に展望台を設置。 小牧山頂上に展望台がつくられ、小牧山の新名所となる。1959(昭和34)年:伊勢湾台風、襲来。 伊勢湾台風は、小牧山にも大きな被害を与えた。1965(昭和40)年:市役所を建設。 小牧山の南側のふもとに建てられた。2012(平成24)年、史跡外に移転 後、跡地では土塁などが復元された。1968(昭和43)年:小牧市歴史館、開館。 平松茂氏が資材を投じて建設し、小牧市に寄贈した資料館。飛雲閣(京 都)を模してつくられた。2017(平成29)年:続日本100名城に認定される。 古くより「著名な歴史の舞台」であった小牧山。近年の発掘調査により 「優れた文化財・史跡であること」「時代を代表する存在であること」が 確認され、認定された。小牧山の歴史はこれからも続く・・・」「小牧山城が続日本100名城に選ばれました。」正面から。日本城郭協会が、広く城郭ファンとともに選定を行う「続日本100名城」に小牧山城が選ばれました。「優れた文化財・史跡であること」「著名な歴史の舞台であること」「時代・地域の代表であること」の3点を満たしていると認められたことから選出されました。これは「日本100名城」。「小牧山ヒストリーギャラ―」にあった「続日本百名城 認定書 小牧山城」の写真をカメラに。本物は小牧市庁舎内にあると。様々な開催ポスターが。円形のエントランスホールのパネル写真は秋の紅葉と野鳥たち。左手に「常設展示室入口」案内。館内には小牧山城の様々な模型が展示されていた。「小牧城下町復元模型」。「小牧城下町復元模型」。紺屋町とか鍛冶屋町のように、一箇所に同じ業種の手工業者を集めていたと。また、まちのインフラとして下水道が造られていたと。「小牧山城 主郭周辺石垣 推定復元模型」廻り込んで。近づいて。3段の石垣模型(もけい)。最上段の石は、非常に大きな石を用い、3段目は腰巻状になっている と。大手口模型。三方を石垣に囲まれた枡形状の虎口。虎口は、主郭南側虎口が大手口、東側が搦手口と、2ヵ所で確認されている。大手口は、桝形状の方形の平らになる面が存在していた。平坦な面は、向かって左側と正面が巨石を利用した石垣で、左南端に直方体の花崗岩巨石(1.7~2m四方、推定約23t)が位置。右側は、石垣は残ってはいないが、石垣の背後の裏込め石が残り、ここも石垣であったことが確実であると。大手口は、三方を石垣で囲い込まれた四角形の空間を持つ構造だった。東側の搦手虎口は、主郭が東側に方形に張り出す北面の石垣を、搦手口の左側を規制する石垣として利用していた。この石垣に沿って、一部側溝(排水路)と推定される石組が伴い、礎石が確認された。この礎石は、門礎石と考えられ、主郭で初めて確認された建物遺構になった と。「小牧山城 主郭周辺石垣 推定復元模型 作:平手卓氏永禄6年(1563)織田信長が自らの手て初め城を築いたのが、、小牧山城です。清須から小牧に移り、永禄10年(1567)に美濃の稲葉山城を攻略し岐阜と改め我聞し岐阜ど改め移るまでの4年間居城としました。発掘調査から、主郭範囲にはニ段から三段の石垣が出入口を除いて、ほぼ途切れることなく巡っていることがわかりました石垣は上段から順に、石垣Ⅰ、石垣Ⅱ、石垣Ⅲと呼称しています。いずれも石垣の基底部を残すのみでしたが、石垣背後に入れられた裏込石から推定した高さは、石垣Ⅰは3.1~3.5m、石垣Ⅱは1.2~1.3m、石垣Ⅲ2.0~2.6mでした。石垣Ⅰは、一石2トン以上の巨石て構成されていました。石垣Ⅱは、約50cmの自然石て構築され、石垣Ⅰと並行するように築かれていました。また、山本来の岩盤を壁状に切リ立てて、石垣面と併用している部分も見られました。石垣Ⅲは、石垣Ⅱよりやや小ぶリの約30cm の自然石で構築されていました。その上に、造成土による斜面が継ぎ足され、石垣約1mと造成土約1mで計2mのいわゆる「腰巻石垣」であったことがわかりました。石垣石材は、ほとんどがチャート(小牧山産)で、ごく一部に花崗岩(岩崎山産)を用いていす。構築技法は、野面積み、布積みで、勾配は約70度です。当時は、石垣を一度に高く積む技術が発達していなかったため、セットバック繰り返して段築状に石垣を積むことで、下から主郭付近を見上げた時、あたかも一続きの高い石垣が構築されているように見えるという視覚効果をもたらせていたことがわかりました。【用語解説】野面積み・・・自然石を加工せずに用いて積み上げる方法布積み ・・・石垣の横方向の石の列がほぼ揃って並ぶ積み方腰巻石垣・・・岩盤や土塁の下部にだけ築かれた石垣セットバック・上段を下段より後退させること」その周囲には発掘調査の写真が。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.17
コメント(0)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その2):小牧山城跡-1
そして「小牧山北駐車場」に到着し、「小牧山城跡」の散策を開始する。時間は9:23。小牧市小牧一丁目1番地。「小牧山順路案内図」小牧山(こまきやま)は、愛知県小牧市にある標高86mの山。かつて織田信長の居城であった、小牧山城(日本の城)があった。現在は山全体が公園となっており、桜の名所としても知られる。公園の分類は「史跡公園」。なお現在、山頂にある天守閣風建物は、1967年(昭和42年)に建てられたものである とウィキペディアより。現在地はここ「小牧山北駐車場」。遊歩道を東に向かって進む。左手にあったモニュメントは?。そして「北駐車場口」から歩いて城内に入る。「史跡小牧山案内小牧山歴史館小牧・長久手の合戦など戦国時代の小牧山を中心に紹介する展示施設です。れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)小牧山のガイダンス施設です。小牧山を取り巻く歴史を模型や映像を使って紹介しています。小牧山創垂館昭和21年に小牧山の迎賓館として建設された建物です。令和3年度に保存修理工事が完了し、見学や貸館利用をすることができます.。」案内図。「現在地」はここ。「小牧山」の航空写真をネットから。これもネットから。現在、山頂にある天守閣風建物は、1967年(昭和42年)に建てられたものである と。京都府京都市の「飛雲閣」をモデルとしており、小牧市内の歴史資料や考古・民俗資料が展示されていたのであった。「土塁断面展示施設」。土塁断面。小牧山城の土塁の断面を見ることができるように展示されていた。右側の「土塁断面展示」は大きなアクリル板で保護。移動して。近づいて。左側。各種「案内板」が左壁に。「小牧山城の概要戦国時代~織田信長が築いた小牧山城~永禄期今から450年ほど前の永禄6年(1563) 、織田信長は、美濃攻略の戦略拠点として小牧山城を築き、清州城から居城を移した。また、信長は、小牧山南麓に城下町を計画的に整備した。4年後に美濃の斎藤龍興を攻略して稲葉山城(岐阜)へ移ると、小牧山城は廃城となるが、その間、小牧は城下町として栄えた。安土桃山時代~徳川家康が改修した小牧山城~天正期織田信長が小牧を去って17年後の天正12年(1584)3月に、小牧・長久手の合戦が起こり、犬山方面から南下する豊臣秀吉軍に対抗して、織田信雄・徳川家康連合軍が小牧山城を改修し本陣とし、約8か月にわたり対峙した。徳川家康は小牧山城の土塁を高め、堀を深くするなどの防御工事をわずか5日間で完成させている。現在、小牧山に残る城の遺構は全体的統ーのとれた姿で、この時(天正期)の小牧山城の姿と考えられる。」「土塁について小牧山の麓を取り巻く堀と土塁は、発掘調査によって、小牧・長久手の合戦のときに、徳川家康の軍勢によって造られたことが明らかになっている。小牧山の北麓から東麓にかけては、織田信長居城時には武家屋敷が配置されていたが、その跡地を使って堀とニ重の土塁を造った。現在残る土塁は、内側の土塁で、幅12m、高さ3m程で、外面の傾斜角が約40度、内面の傾斜角が約30度である。外側の地表からの高さは約5mとなり、外部からの侵入を防いでいた。土塁の断面を観察すると、信長時代の武家屋敷跡を整地して、その上に掘りを掘った土を積み上げて、肌を固めた構造で、急造されたことがよくわかる。土塁断面土層の解説①黒色土層 土塁が造られる前の土層、この上面が信長時代の地表。②整地土層 何種類かの土を敷いて叩き固めて、土塁の基盤を造っている。③黒褐色土層 堀から掘り上げた土を積む(最初は黒っぽい土)④黄色土層 堀を掘り進み地山の黄色土を積みあげている。⑤褐色土 仕上げは、土塁内側の土を掘って、土塁内側へ積み上げている。」「小牧・長久手の合戦」時の小牧周辺における両軍の布陣。青:豊臣秀吉軍 赤:徳川家康・織田信雄連合軍。小牧・長久手の合戦関連主要城館図。史跡小牧山遺構分布図。小牧山城ポスター。「土の城」から「石の城」へ 信長の城 小牧山城小牧山城 土塁断面展示を通過し城内に入る。「史跡 小牧山 帯曲輪地区発掘調査の解説」案内板。「小牧山の歴史と帯曲輪地区の解説永禄6年(1563)、織田信長は、清須から小牧山に居城を移し、新しい尾張の政治経済の中心地として城と城下町を整備しました。信長は、小牧山の山頂から麓まで多数の曲輪を設けて、山全体を城としました。しかし、その4年後、信長は岐阜へ移り、小牧山城は廃城となり城下町も衰えました。信長が岐阜へ去った17年後の天正12年(1584)には、小牧・長久手の合戦が起こります。犬山から清須をめざして攻め込もうとする豊臣秀吉の軍勢に対して、徳川家康と織田信雄の軍は、信長の城跡に山麓を取り巻く堀や土塁を築くなどの大改造を行い、堅固な城を築きました。両軍は、にらみあいを続けましたが、小牧付近ては大規模な合戦は起こらず半年後には両軍ともに撤退し、小牧山城は、その後、使われることはありませんでした。小牧山の麗は、帯曲輪地区と呼ばれています。山全体を取り巻く土塁のすぐ内側にあたり、細長い平地が分市し、多数の軍勢を収容する機能がありました。これは小牧・長久手の合戦のときの姿で、信長の城であったときは、堀で区画された武家屋敷が配置されていました。整備工事では、小牧・長久手の合戦当時の土塁や曲輪の姿を復元しましたが、信長時代の武家屋敷の堀や井戸も一部復元しています。」帯曲輪地区東部 遺構推定復元図写真は発掘調査航空写真小牧・長久手の合戦のときに造られた土塁の他に織田信長当時の武家屋敷の跡(曲輪を区画する堀や井戸)が土塁の下から発見されました。信長時代には、堀で区画された一辺45mほどの武家屋敷が連続して配置されていたと考えられます。(写真は、曲輪404の北側から曲輪405-1cまでを調査したときの航空写真です。曲輪404 上空から曲輪405-1cの方向を見ています。)発掘された曲輪。「曲輪城の平坦な一区画を曲輪と呼びます。江戸時代の城で本丸・二の丸などと呼ばれるものと同じです。曲輪には様々な機能を持ったものがありますが、小枚・長久手の合戦のとき山麓の帯曲輪地区では、山を取り巻く土塁と山裾の間に細長い平地が続き、多数の軍勢を収容する機能をもったと考えられています。織田信長の小牧山城ではまだ山を取り巻く土塁は造られておらず、曲輪は堀によって幅45m程の多数の区画に分割され、一辺45m程の方形の武家屋敷の跡と見られています。のま朝のとみられています。南東隅の曲輪402は、一辺75m四方と他に比べて大きく、信長の居館ではないかと推定されています。なお、小牧山城の曲輪には「曲輪405-1C」といったように全て記号番号がつけられています。(写真は、曲輪402の北側・東側の一部から曲輪404の南側の一部にかけての範囲を調査したときの写真です。)出土遺物帯曲輪地区からの出土遺物はあまり多くありません。信長時代の武家屋敷が使われたのは4年間と短く、武家屋敷の人口はあまり多くないことが原因とみられます。小牧・長久手の合戦のときの出土遺物には、戦場での一時的な利用ですので、さらに少なくなっています。出土遺物は、瀬戸・美濃窯施釉陶器と土師器が多く、城下町からの出土品と大差ありません。(写真は、曲輪404と曲輪405-1a4を区画する信長時代の堀から、摺鉢の破片や土師器の◯や◯が、まとまって出土したときのものです。)堀、井戸、土塁 案内。「堀小牧山の東から北の麓からは、約45mの間隔で山から放射状にのびる堀が発見されました。この堀は、小牧・長久手の合戦で作られた土塁で埋められていて、織田信長の城当時のものです。この当時の尾張での武家屋敷の規模はおおむね45m四方ですので、これは武家屋敷が規則的に配置されていたものと考えられます。堀の規模は幅2m以上、深さ1.5m以上で断面がV字型の薬研堀で、傾斜角が50度にも及びます。整備工事では、堀が土塁よりも先に作られていたことを示すため、土塁の一部を石積みで切り取り堀が土塁の下に入っていく様子を復元しました。(写真は、曲輪404と曲輪405-1aを区画する堀で、最大幅3.2m深さ1.7mを測ります。土塁が築かれる際に一部が埋められました。)」土塁の下から織田信長当時の武家屋敷の井戸が発見されました。井戸は素掘りで直径約2m、深さは3.2m以上あります。井戸の底部にはめられていた井戸枠の木材がいったん引き抜かれた後、再度、とめて井戸底へ投げ捨てられた状態で発見されました。発掘調査では、井戸の上部構造は明らかになりませんでしたので、整備工事では、時代の絵巻物で見られる井戸を参考に復元しました。(写真は、井戸の内側から、井戸枠の木材がまとまって見つかったときのものです。)復元された「井戸」。内部を覗く。「土塁土塁は、江戸時代の城では石垣にあたるもので、外部からの敵の侵入を防ぐ目的で土を高く盛り上げて、堤防のような形をしています。小牧山の麓を取り巻く土塁は、当初は堀をはさんで二重になっていましたが、今では内側の土塁が残っているだけです。この土塁は、幅10m、高さ3m程の規模で外側が急傾斜で内側の傾斜がゆるくなっています。土塁の外側には堀がありましたので、堀の底から測ると土塁の高さは5mにもなります。小牧山を取り巻く土塁は、織田信長の城にはありませんでした。この土塁が造られたのは小牧・長久手の合戦のときで、徳川家康の軍勢が短期間に築いたものです。土塁の断面の様子は、土塁断面展示施設で見ることができます。(写真は土塁断面展示施設の場所を発掘したときのものです。大別して下から黒色土、褐色土、礫が混じる黄色土の順で積まれている様子がわかります。)現在地はここ。さらに曲輪跡(くるわあと)を進む。周辺の変移模式図。◆永禄期(織田信長 小牧山城 築城時) 武家屋敷が造られ、井戸が掘られた。◆天正期(小牧・長久手の合戦時) 堀と二重の土塁が造られ、武家屋敷跡を造った土が土塁に積まれた。◆江戸時代から現在 外土塁がなくなり堀が埋められた。内部は中学校用地となり、曲輪が埋められ、土塁も一部 削られた。◆復元整備の標準的断面 「発掘された井戸(永禄期)の遺構井戸の解説このあたりは、織田信長の時代には、小牧山の麓を取り巻くように武家屋敷が配置されていた。小牧・長久手の合戦では、この屋敷跡を壊して堀が掘られ、土塁が築かれた。信長時代の武家屋敷の井戸は、土塁の下から発見された。井戸は、素掘りで、直径約2m、深さは3.2m以上で、底に近いあたりには曲物の井戸枠がはめられていた。井戸は、武家屋敷の廃絶時に、人為的に埋められ、井戸枠材は一度引き抜いてから、井戸の中へまとめて投げ捨てられていた。井戸の上部構造は発掘調査で明らかにできないため、同時代の絵図をもとに推定復元した。」この先にも遺構があった。左に:永禄期と天正期の遺構 ◆堀 (永禄期) と土塁 (天正期) の縦断図 ◆堀 (永禄期) の横断図右に:史跡小牧山遺構分布図パネル表記が劣化して解読不能であった。曲輪405-1b。桜が開花。四季咲き桜であっただろうか。「史跡 小牧山 帯曲輪地区発掘調査の解説」案内板。近づいて。「史跡小牧山 帯曲輪地区発掘調査の解説帯曲輪地区の解説現在は、帯曲輪地区と呼んでいる小牧山の麓部分は、永禄6年(1563)に織田信長が城を築き、稲葉山城(現岐阜城)へ移るまでの4年間を居城とした時期と、天正12年(1584)の小牧・長久手の合戦で、織田信雄・徳川家康連合軍がここを本陣とした時期とでは使われ方が異なります。信長居城時には、堀などで区画された多数の曲輪に分かれており、この区画は一辺が45m程の方形になる武家屋敷と考えられ、北側から南側にかけて同規模の武家屋敷が連続して配置されていました。南東隅には一辺75mの最大規模の武家屋敷(曲輪402)が配置され、信長の居館ではないかと推定されています。これらの武家屋敷は、信長が岐阜へ移った時に廃絶されました。小牧・長久手の合戦時は、信長の城跡に改修を加え、山の麓部分には山全体を取り巻く土塁が築かれました。武家屋敷があった麓部分は、土塁のすぐ内側となり、一部を除き堀が埋められ、細長い平地となり、多数の軍勢を収容する機能がありました。整備では、小牧・長久手の合戦当時の土塁や曲輪を復元するとともに、信長居城時の武家屋敷の堀や井戸を部分的に復元しました。」「史跡小牧山案内小牧山歴史館小牧・長久手の合戦など戦国時代の小牧山を中心に紹介する。れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)小牧山のガイダンス施設です。小牧山を取り巻く歴史を模型や映像を使って紹介しています。小牧山創垂館昭和21年に小牧山の迎賓館として建設された建物です。令和3年度に保存修理工事が完了し、見学や貸館利用をすることができます.。」「小牧山城跡 山北橋口」から城内を見る。正面に東公衆トイレと休憩所。白地の幟「小牧・長久手の戦い 徳川家康本陣の地」と。「案内板」。「市教育委員会では令和3年度から戦国時代の武将・織田信長が山頂周辺に築いた2 ~ 3段の石垣や、南麓から山頂へ至る大手道の一部などの復元整備を進めています。令和5年度には、大手道沿いに切り立てれた岩盤と、その上に築かれた石垣の復元整備を行いました。」「曲輪 405-2」と城内案内柱。ここにも「小牧山城」ポスター。正面の東公衆トイレと休憩所に向かう。「休憩所」を見る。休憩所に展示されていたパネルの紹介。「小牧山の自然位置北35度17分 東経136度54分標高85.9m 総面積約21ha地質小牧山は、約2億5千万年前の古生代に海の底に堆積した秩父古生層の残丘です。この古生層は濃尾平野の基盤につながっていて、侵食から残った部分が、小牧山や小牧市東部の山地、金華山などのように小山になっているものです。小牧山では、チャート、砂岩、粘板岩などが見られます。植物小牧山は、戦国時代から安土桃山時代に城として使われたため、城の中心であった南斜面を中心に、樹木はほとんど伐採されたと見られます。江戸時代に入ると、尾張藩が一般の入山を禁止するなど手厚い保護を行った結果、植生が回復してきました。江戸時代後期の小牧村絵図を見ると松がたくさん生えています。これは、伐採後の小牧山にニ次林として松を中心とする植生が回復してきたためとみられます。現在では、さらに植生が回復して、松はほとんど見られず、この地域本来の安定したシイ・カシ類、クスノキ、タブノキ、オガタマノキ、タマノキ、サカキ、ヤブツバキを中心とする常緑照葉樹林やコナラ、アカメガシワ、ハゼノキ、キリなどの緑広葉樹林に移行しています。戦後、サクラやスギ、ヒノキなどの植樹が行われたり、公園的な整備が行われて、自然植生ではない部分も多くあります。以下 略」「小牧山の歴史」👈️リンク。「小牧城下町織田信長は、清須から小牧山へ居城を移した際、商工業者も清須から移住させ城下町を築きました。城下町の規模は、小牧山から南へ約1.5km、東西約1kmの範囲で、城下町の南端には、堀と土塁からなる惣構を東西1kmにわたって築きました。惣構には、2か所の虎口があったことが江戸時代の古城絵図に描かれています。しかし、この虎ロの形態は、小畋・長久手の合戦当時のものと考えられていて、惣構にも徳川軍による大改造が行われたことがわかります。小牧城下町は、織田信長が岐阜へ去った際に、規模を縮小しますが、町屋部分の一部はその後も存続します。小牧・長久手の合戦では、小牧村庄屋の江崎善左衛門が徳川方について道案内を務めたりしています。江戸時代に入ると、城下町の名残の町場は、新たに整備された上で街道沿いの原野(現在の小牧中心市街地)へ宿駅として移転したため、城下町は田畑となり「元町」などと呼ばれるようになりました。城下町は、江戸時代に田畑となったため、江戸騎代の村絵図や明治初期の地籍図(土地の区画を所有者ごとに表した図面、地租課税の基礎資料として明治政府が作成しました)に当時の地割をよく残していました。大正年間に始まった耕地整理や最近の都市化によって、今では城下町の痕跡は地下に残るだけになりました。村絵図を見ると、整然と東西方向と南北方向に道が走っていることがわかります。地籍図を詳しく見ると、道路によって区画された長方形の中に、間口が狭く奥行きの深い地割りが密集して並んでいるのが見てとれます。このような区画は城下町の西半分に顕著で、それに対して町の東側では、比較的大きな方形の区画が多くなっています。つまり、信長の小牧城下町は、西側に商工業者を集住させ、東側に武士団と寺院を計画的に配置したと考えられています。平成6年から実施した城下町東側の新町遺跡の発掘調査では、武家屋敷跡や下層武士団の居住域と見られる区画溝などを発見し、信長の小牧城下町の存在を実証しました。この城下町東部では城下町はすぐに廃絶されて、それ以降人が住んだ形跡は全く認められず、信長の岐阜移転にともない田畑に変わったと見られます。」「小牧山城の遺構小牧山の域郭遺構は、廃絶されて400年以上が経過していて、長い年月の間に、風雨で削られたり理もれていたりして、その後成長しに林の中で、城当時の姿から大きく変わっています。しかし、現在でも、小牧山の山中を丹念に観察すれば、土塁や掘、曲輪(城の平坦な一区画)などの痕跡が認められます。また、現在では残っていない地形が、昭和2年の地形測図に記されているものもあります、このように、現況地形や古地図を検討することで、ある程度、当時の姿を推定することができます。このようにして堀や土塁、虎ロ(城の出入口)、曲輪を推定復元したものが、図1の遺構分布図です。小牧山の城郭遺構には2つの時期があります。永禄6年(1563)の織田信長の城と天正12年(1584)の小牧・長久手の合戦のときの陣城です。今、残っている城郭遺構は、最終的に徳川軍が使った天正の小牧山城の遺構です。ではこの天正の小牧山城を考察して見ましょう。小牧山城は、図2のように大きく5つの地区に分けることができます。小牧山城には、麓と中腹に土塁と堀で構成された重要な防御ラインがあります。この防御ラインでは、特定の虎口を通らないと内部へ進ことができない構造になっています。中腹から山頂にかけての城の中心部では、堀で東西2地区に分けられています。中腹から麓にかけては、山麓を一周する堀と土塁のすぐ内側の長細い区画の地区、山の南斜面の大形の曲線が多数分布する地区、不整形な曲輪が分布する西の谷の地区の3つに分けることができるのです。主郭地区(山頂を中とする曲輪群)中腹の堀と尾根中央部を南北に切断する堀で囲まれる城の中枢部です。この地区への4か所の出入り口があります。大手道が堀を土橋で渡ってジグサグに主郭へと続くほか、東と北に虎口があり、西の曲輪群とは堀を渡る土橋で連結されています。西側曲輪地区(山頂西側尾根上の曲輪群)主郭地区の西の尾根上に分市する曲輪群で、中腹の横堀と尾根中央部を切断する堀で区画されています。この地区は、主郭地区を西側から守る役割を果たしたと考えられます。大手曲輪地区(南斜面中腹の巨大なテラス状の曲輪群)南斜面の中腹の堀から山麓まで、大手道の左右に分布する曲輪群で、面積が大きく、物資の集積や兵士の訓練の場として利用されたと考えらます.西側谷地区(西北部の曲輪群)屋敷跡伝承地を中心に西の谷に築かれた曲輪群で、不整形なのが特色で、新たに築いた城の遺構ではなく、中世の寺院跡をそのまま利用した可能性が高い部分です。帯曲輪地区(山を取り巻くように配置された細長い曲輪群)ニ重の土塁と堀のすぐ内側に南側の大手曲輪地区を除いて山麓を巡る形で配置された曲輪群で、東から北にかけて幅が広く、西で幅が決くなっています。大軍勢を収容して、防御や出撃の準備をしたと考えられています。東側に2か所、北側と西側に1か所ずつの虎口があり、大手口を含めると、小牧山城の山麓の虎ロは5か所になります。」「小牧山城の史跡整備史跡小牧山には、戦後、小牧中学校、青年の家、市役所本庁舎、歴史館などの公共施設が相次いで建設されましたが、近年になって、史跡本来の姿に戻そういう声が高まり、まず、小牧中学校が移転して、その跡地(帯曲轤地区東部)の史跡整備を実施しました。以下 略」「史跡小牧山 帯曲輪地区発掘調査の解説帯曲輪地区の解説小牧山は、山全体が城郭です。小牧山城は、永禄6年(1563)に織田信長が築き、天正12年(1584)の小牧・長久手の合戦で徳川家康が大改造しました。城の麓の部分は、帯曲輪地区と呼ばれています。山全体を取り巻く土塁のすぐ内側にあたり、細長い平地が分布し、多数の軍勢を収容する機能がありました。このような形に城跡が完成したのは、天正12年です。信長の城当時には、山を取り囲んでいる土塁はなく、帯曲輪地区は、堀などで区画された多数の曲輪に分かれていました。この区画は一辺が45m程の方形になるものと推定され、武家屋敷跡と考えられます。小牧山東南隅に堀と土塁で囲まれた一辺75mの最大規模の武家屋敷(曲輪402)が配置され、北へ向かって一辺45m程の同規模の武家屋敷が連続して多数配置されていました。これらの武家屋敷は、信長が岐阜へ移ったときに廃絶されました。整備事業では、小牧・長久手の合戦当時の土塁や曲輪を復元しましたが、信長時代の武家屋敷の堀や井戸も部分的に復元しています。」「史跡 小牧山 帯曲輪地区東部 発掘調査の解説」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.16
コメント(0)
-

創建700年の遊行寺・大イチョウ ライトアップ:その5
「大書院の光のインスタレーション作品」の鑑賞を終えて、「黒門」からの「大イチョウ」を見る。「大イチョウ」に向かって歩く。「竹の灯り」越しに。「遊行寺宝物館」を正面から。「遊行寺開山七百年記念特別展 藤沢のおぐり」👈️リンク が令和6年10月5日(土)~12月16日(月)で開催中であった。「大イチョウ」の黄金の輝きをカメラで追う。「大イチョウのライトアップ」は、言葉では尽くせないほどの美しさが眼前に。夜空に浮かび上がる黄金色の葉は、まるで星々が地上に舞い降りたかのような輝きを放つのであった。その光景は、自然の壮大さと人々の手による美しい演出が調和した、まさに幻想的なひとときなのであった。静寂の中で風に揺れる葉の音が、光に照らされたイチョウの荘厳さを一層引き立て、訪れる人々の心に深い感動を与えるのであった。この光のアートは、時間が止まったような感覚とともに、心の奥深くに刻まれる瞬間を提供してくれたのだ。樹齢700年以上とも言われるこのイチョウの巨木は、昼間に見ても圧倒されるその存在感が、夜になると光の魔法によってさらに引き立てられるのであった。足元に目を向ければ、散り積もったイチョウの葉がライトの光を受けて地面に金色の絨毯を敷き詰めたような光景を作り出していたのであった。木の根元から夜空へと伸びる幹は、長い歴史を物語る力強さを感じさせると同時に、その圧倒的な大きさが夜の静寂の中で一層神聖さを帯びて。「大イチョウ」の大木の下に立ち見上げると、自分が光の中に包み込まれるような感覚を。その光景には、日本の秋が持つ詩的な情緒と、古木がたたえる悠久の時の流れが織り込まれており、心を深く癒す力が。このライトアップは、単なる観光名所を超え、生命の美しさと自然の奇跡を再認識させる瞬間を提供してくれる、まさに「感動の光景」なのであった。再び「遊行寺」の本堂を背景に。樹齢700年以上の幹には大小の乳根が。イチョウの老木に見られる大小の乳根(ちちね)は、まるで自然が紡ぎ出した独特の芸術作品。重厚な存在感を持つ大きな乳根は、まるで地上に向かって力強く垂れ下がる縄や布のよう。年月を重ねたその表面には、ひび割れや独特の凹凸が刻まれ、生命の歴史を語るかの如し。力強くも優雅なその姿は、大木が大地に深く根ざし、地球とつながる象徴。小さな乳根は控えめでありながらも愛らしい存在感を放ちつ。細く繊細なそれらは、木が新たな命の一部を伸ばしているような印象を。ちょうど細い糸や垂れた滴のように、柔らかく優しい動きを感じさせるのであった。そして「上弦の月」を。地上そして上空からの「上弦の月」からと、同時ライトアップ。そして感動のままに、遊行寺の境内を背にして「いろは坂」を下る。この石段は、阿弥陀様の四十八願にたとえて、四十八段と呼ばれている。春には両脇の桜で花のトンネルとなり、訪れる人々の憩いを与えてくれるのだ。平成19年(2007)に大改修が行われた。地元の方々には、いろは四十八文字から、「いろは坂」の愛称で親しまれているのであった。「真徳寺」の山門。山門先の石碑に我が影を。この石碑の表面には仏様のお姿が線刻されているのをこの時は忘れていたのであった。スイマセン!!合掌、合掌、合掌∞・・・・・・・・・・・・・∞。「惣門」を振り返って。「藤沢市ふじさわ宿交流館」横のライトアップ。静かに白色の灯りが灯る。「藤沢市ふじさわ宿交流館」入口。藤沢宿「高札場跡(こうさつばあと)」。高札場とは、幕府や領主が決めた法度(はっと)や掟書(おきてがき)などを木の板札に書き、人目のひくように高く掲げておく場所のこと。神奈川県の東海道では、9つの宿場にそれぞれ1カ所ずつある と。いずれも江戸から京都に向かって街道の右側に設置されているのだ と。「旧東海道・藤沢宿」案内板。「遊行寺橋(旧大鋸橋)・高札場跡江戸から東海道を進むと、東海道第六の宿、藤沢宿内の遊行寺橋(旧大鋸橋)で境川(片瀬川)を越えて鎌倉郡から高座郡に入ります。橋を渡って、右手が大久保町。橋のたもとに高札場があり、公定運賃の定め、キリシタン禁制など、徳川幕府の重要法令が掲示されていました。高札場は屋根付きで高さ約3.6m、横幅5.4m、縦幅1.8mの規模であったと。左手(南側)には「江の島一ノ鳥居」が建てられていた。江の島弁財天の遙拝の鳥居で、東海道と別れて鳥居をくぐれば、「江の島道」です。」この附近はライトアップされていなかった。歌川広重「東海道五拾三次〈狂歌入東海道〉藤沢」(草津市蔵)ネットから。狂歌「松吟庵清風うちかすむ 色のゆかりの ふち沢や 雲井をさして 登る春かな」「東海道五十三次 藤澤宿」。歌川広重(初代) 嘉永(1848~54)本図は、遊行寺の門前町としても栄えた藤沢宿の黄昏時を描いた作品。宿についた旅人を提灯をつけて迎える女や客引きをする留女の姿が生き生きと描かれている。広重の代表的な東海道シリーズの一つ。揃物名が隷書体で書かれているので俗に「隷書東海道」という。「保永堂版」東海道シリーズに次いでよく知られた揃物。ネットから。「旧東海道 藤沢宿」案内地図。「東海道藤沢宿の成り立ち・しくみ」案内板。以前の私の写真を。「「東海道分間延絵図」は江戸幕府が東海道の状況を把握するために、道中奉行に命じて作成した詳細な絵地図。この絵は東海道の13巻のうち藤沢宿の部分にあたります。絵図には、問屋、本陣、脇本陣、寺社、高札など、当時の藤沢宿の姿が丹念に描かれています。藤沢宿 藤沢宿は慶長6年(1601年)東海道の宿場となり、後に戸塚宿、川崎宿が追加され五十三次の第6番目の宿場となりました。天保14年(1843年)の記録では、宿場の人数4089人、家数919軒でした。大山道や江の島道が分かれる観光地としての賑わいに加え、周辺農村からの物資の集積地として繁盛しました。宿場の機能がなくなったあとも、明治時代から昭和初期にかけては、交通の要所として地の利を生かした問屋業などで栄え、その面影を残す土蔵や町屋がわずかに残っています。」「江の島弁財天道標」。梵字(ぼんじ)の下に「ゑ(え)のしま道」。近づいて。「江の島弁財天道標この石柱は、江の島 への道筋に建てたれた道標(どうひょう)の一つです。江の島弁財天道標は、管(くだ)を用いて鍼(はり)をさす管鍼術(かんしんじゅつ)を、江の島で考案したという杉山検校(すぎやまけんぎょう)(杉山和一、1610~1694)が寄進したと伝えられています。現在、市内外に十数基が確認され、市内所在のうちで十二基が藤沢市の重要文化指定されています。いずれも頂部のとがった角柱形で、その多くが、正面の弁才天を表す梵字(ぼんじ)の下に「ゑ(え)のしま道」、右側面に「一切衆生(いっさいしゅうじょう)」、左側面に「二世安楽(にせあんらく)」と彫られています。この文言(もんごん)は、江の島弁才天への道をたどるすべての人の現世・来世での安穏・極楽への願いが込められています。市役所新館脇歩道橋付近に移設されていましたが、新庁舎建設にともなう歩道橋周辺の整備により、「江の島道」の路傍にあたるこの地に移設したものです。 2015年(平成27年)11月 藤沢市教育委員会」「歌川広重 東海道五十三次 藤澤」。ネットから。「東海道五十三次之内藤沢(行書東海道)製作時期:天保13年(1842)。板元:江崎屋吉兵衛このシリーズは表題の書体から俗に行書東海道と呼ばれます。 画面右に江の島一ノ鳥居、左に大鋸橋 (現遊行寺橋)を描いています。大鋸橋を通っているのは東海道で、この鳥居が東海道から江の島道への入口になっています。 橋の上の人物が担いでいるは御神酒枠(大山から水や酒を持ち帰るためのもの)で、一行が大山詣の帰りであることが分かります。」現「藤澤橋」交差点の石灯籠。この場所の歴史ある橋は実は現遊行寺橋(旧大鋸橋)であり、立派な造りのこの藤沢橋は昭和に入って架けられたものであるということを知らない人も多い。ここは様々な時代で「藤沢宿の玄関」となった場所。鎌倉時代には鎌倉に向かう入り口、そして遊行寺の入口でもあり、江戸時代には宿場町の入口として見附が置かれた場所、更に江の島へと向かうスタート地点等ハブ交差点。「藤沢橋」交差点。「トランスボックス「浮世絵」写真ラッピング」👈️リンク。「歩いて見よう 藤沢宿」と書かれた、藤沢宿にちなんだ浮世絵箱が遊行通り四丁目商店街より国道467に合流した地点より藤沢橋まで両側の歩道際に22ヶが並んでいるのだ。「東海道 五十三次 藤澤(隷書東海道)このシリーズは表題の書体から俗に隷書東海道と呼ばれ、保永堂版、行書版と共に三大傑作シリーズの一つ。藤沢宿の夜の風景で、右側にある鳥居が江の島一ノ鳥居(江の島道入口)、左手にあるのが大鋸橋(現遊行寺橋)。宿場に着いた人々と客引きをする宿の人々の様子が描かれ、にぎわいが感じられる」。「藤澤 五十三次 神谷伊右衛門お岩霊藤沢宿の立場「四ッ谷」に歌舞伎の外題『東海道四谷怪談』をかけて役者による見立にした作品。左の神谷伊右衛門役に二代中村翫雀(がんじゃく)、右のお岩(霊)役に嵐璃珪(りかく)という二人の大坂の歌舞伎役者が描かれている。上部に描かれた絵は大鋸橋(現遊行寺橋)と江の島一ノ鳥居の組み合わせという藤沢宿の風景」。花屋には様々な種類の「シクラメン」が並んでいた。Y字路のここにも「江の島弁財天道標」。梵字(ぼんじ)の下に「ゑ(え)のしま道」。左側面に「二世安楽(にせあんらく)」と「旧東海道・藤沢宿■江の島道・江の島弁財天道標藤沢宿内の遊行寺橋(旧大鋸橋)で境川を越えた左手(南側)には、かつて「江の島弁財天一ノ鳥居」があり、ここから江の島 へ向かう境川沿いの道が「江の島道」です。鳥居の脇には「ゑのしま道」と刻まれた江島弁財天道標 がありました。これは元禄 時代(17世紀後半)に杉山検校 が沿道に奉納したと伝えられるもので、現在も道沿い等に十数基が残っています」。パブリックアート。作者/山本一樹(やまもとかずき)「QUIESCENT ELAN」解読不能。「遊行通り北入口に、宇宙人あるいは奇怪な虫を思わせるモニュメントがあります。藤沢市発行の案内書*によれば、このモニュメントは、遊行寺の鐘をモチーフにした「QUIESCENT ELAN」という作品。QUIESCENT とは英語で、沈着・静止、ELANは、鋭気・飛翔・情熱の意味。反対の言葉を結び付け将来への躍進を表現したとあります。翼を付けた鐘のようにも、大空に帆を挙げて飛翔しているようにも見えます。案内書に「アートがつなぐ過去・現在・未来」というキャッチコピーがつけられているように、この作品は、藤沢宿から江の島へ向かうこの古道(遊行通り)を未来へとつなぐ道標なのかもしれません。」とネットから。JR藤沢駅に向かって「遊行通り」を歩く。再び遊行寺の絵、時宗(開祖・一遍上人)の紋・折敷に三(おしきにさん)の紋が描かれていた。「遊行通り」にもイルミネーションが。「歌川広重「東海道五拾三次 藤澤 遊行寺」」。そして「サンパール広場(藤沢駅北口ペデストリアンデッキ)」を歩く。「ビックカメラ」を見る。そして藤沢駅に到着し、小田急線を利用して帰途についたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・
2024.12.15
コメント(0)
-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その1):「小牧山城跡」への往路
この日は、11月27日(水)、5年ぶりにいつもの旅友2人と「香嵐渓」の紅葉めぐりに向かう。2泊3日の旅、初日のこの日は自宅を5時に愛車で茅ヶ崎の先輩旅友宅へ向かう。そこから旅友の愛車に乗り換えて二宮の大先輩旅友宅へ。東名高速道路「秦野中井IC」から、この日の最初の目的地の「小牧山城跡」へとひたすら進む。「御殿場JCT」手前、前日からの雨はあがったが、空は一面の雨雲が残っていた。御殿場ICを通過して「新東名高速道路」へと。一面の白の世界に突入。久しぶりのホワイトアウトの如き光景。そして「NEOPASA 駿河湾 沼津SA 下り」で最初のトイレ休憩。NEOPASA(ネオパーサ)という名称は、新東名高速道路とともに新しさを表現するための「NEO」とパーキングエリアの略称「PA」、サービスエリアの略称「SA」を組み合わせて作られた造語である と。ロゴデザインの煌(きら)びやかな星は流れるスピード感を感じさせ、NEOPASAをみんなの「目指す場所」「集う場所」「希望の場所」として未来に導く新東名をイメージしているのだ と。東の空はオレンジ色に染まって来ていた。時間は6:49。刻々と変わる東の空の色の変化を追う。右側に「駿河 ベーカリー&カフェ NEOPASA駿河湾沼津 下り店」。大きいキャラクターの立体看板が目印。「駿河湾」そして「沼津港大型展望水門 びゅうお」の方向を見る。この日は、旅友の愛車に、私の愛車の「高齢者マーク(四つ葉マーク)」を貼って。正しい向きは??3人で議論!!「(左)もみじマーク (右)四つ葉マーク 」。高齢者マークには旧型のもみじマークと新型の四つ葉マークの2種類があります。旧型のもみじマークは黄色と橙色の水滴のようなデザインが特徴。もみじマークは1997年から使用されてきました。2011年からより色彩が豊かな四つ葉のクローバーとシニアの「S」を組み合わせたデザインの高齢者マークを導入し、これまでのもみじマークのイメージが一新されたとのこと。なお以前のもみじマークは今でも使用することが可能です。高齢者マークには、もみじマークと四つ葉マークの2種類があることを認識しておきましょう と。高齢者マークは何歳から貼るものなのか現在では70歳以上のドライバーが車を運転する場合はいかなるときも、高齢者マークを車に貼りつけて走行することが求められています。そもそも高齢者マークは1997年に75歳以上のドライバーを対象に道路交通法改正により導入されたものですが、2002年に対象が70歳以上のドライバーに引き下げられました。そして現在に至るまで70歳以上の高齢者が車を運転する場合は、車に高齢者マークを貼りつけることを推奨されています。ただし、すべての70歳以上のドライバーに高齢者マークを付けることが求められているわけではありません。70歳以上75歳未満の場合は「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき」のみに高齢者マークを付けることが求められています。そして75歳以上になると、すべてのドライバーに高齢者マークを付けることが求められています。現在の道路交通法では・75歳以上の高齢者マークの義務化は当分適用せず努力義務・加齢により体の機能が低下し車の運転に影響を及ぼす恐れのある70歳以上のドライバーは 努力義務(75歳未満を削除)そして今に至るまで高齢者マークの使用は、あくまでも高齢者個々人努力目標となっています。高齢者マークを貼ることは、現状においては努力義務なので、高齢者マークを貼らなくても罰則に問われることはありません。ただし高齢者マークを貼っている車への禁止事項があるのだ。高齢者マークを貼っている車は初心者マークを貼っている車と同様に、周りの車が安全に走行するための配慮をしなくてはいけません。このため、危険を防止するためにやむを得ない場合を除いては、高齢者マークの車に幅寄せしたり、無理な割込みをした場合は道路交通法違反となり反則金 大型車(中型車を含む) 7,000円 普通車・二輪車 6,000円 小型特殊 5,000円 とのこと。正しい向きは特に決まっていないようですが、下が標準のようです。四つ葉マークは、黄緑、緑、黄色、オレンジ、の4色で構成されています。色の変化は時計回りに、加齢を示しているのであろう。四つ葉のクローバーとシニアの「S」を組み合わせたデザインで、白いラインで「S」が表現されているのだと。私の愛車への高齢者マークも向きを変更しました。富士川を渡ると、前方の山々の裾野には雲が棚引く。ズームして。ズームして。「新清水IC」手前。「清水PA」の先の路肩には事故車?が。「新安倍川橋」を渡る。「新東名藤枝PA上り線」手前。青空が姿を表す。「伊太谷川」手前。「浜松SA」手前から「浜松風力発電所 立須の峰」を見る。浜松風力発電所は、静岡県浜松市北区の引佐町から滝沢町にかけての山頂に設置された10基の風力発電所。総出力 20MW風車数 10基運転開始 2009年11月メーカー ENERCON製造国 ドイツ機種 E82-E2単基出力 2MWハブ高さ 78mローター直径 82m と。「浜松いなさJCT」手前9kmを走る。正面の「浜松風力発電所 立須の峰」。「浜松いなさJCT 800m」。新東名高速道路本線、引佐連絡路、三遠南信自動車道を接続するジャンクション。鳳来峡、東名高速道路への分岐点を通過。正面の山裾に大きな穴が!!大規模な崖崩れで出来たのであろうか??そして愛知県豊田市にある「伊勢湾岸自動車道」に入ると、前方に現れたのが「豊田アローズブリッジ」。「伊勢湾岸自動車道」・豊田アローズプリッジ(旧称:矢作川橋)は、第二東名高速道路と東海環状自動車道の共有区間となる豊田ジャンクションと豊田東ジャンクション間の一級河川矢作川渡河部に建設された。橋梁形式は4径間連続PC・鋼複合斜張橋であり、橋長は820 m (最大支間: 235 m)、上下線一体構造(8車線)の総幅員43.8。を有する、第二東名高速道路の中でも最大級の橋梁であり、波形鋼板ウエプ橋としては世界最大支間となる と。「豊田JCT」が前方に。「東名高速道路」に再び入る。「小牧IC」手前は渋滞ぎみ。そして山の上に、最初の目的地の「小牧山城跡」が山の上に姿を現したのであった。時間は9:17。 ・・・つづく・・・
2024.12.15
コメント(1)
-

創建700年の遊行寺・大イチョウ ライトアップ:その4
そして次に訪ねたのが「鐘楼」の先にあった「中雀門」。「中雀門」は安政6年(1859)に紀伊大納言徳川治宝が寄進、建立された。向唐門(むかいからもん)様式で作られている。境内の建造物の中でもっとも古く、紀伊大納言徳川治宝公の寄進により、安政六年(1859)に建てられた。 明治の大火を含め度重なる火災でも焼け残っていたが関東大震災で倒壊、その後以前の姿に復元され平成二十年四月大改修が完成した。四脚門で、高さ約6m、幅約2m70cm。「大イチョウ」を振り返って。「大イチョウ」の上空に「上弦の月」。「大イチョウ」をズームして。「大イチョウ」と「遊行寺宝物館」。「遊行寺宝物館」。そしてこちらが「寺務所」への「黒門」。うすねずみ色の「黒門」から「寺務所」正面を見る。濃いピンクにライトアップされた樹。「中雀門」を「御番方」側から見る。「藤沢市指定重要文化財(建造物)平成二七年(二◯一五)十月一日指定中雀門安政六年(一八五九)に紀伊大納言徳川治宝(はるとみ)が寄進、建立されました。清浄光寺はたびたび火災にあっていますが、この中雀門は明治十三年(一八八〇)の藤沢宿大火の際にも焼失を免れた境内現存最古の建物です。大正十ニ年(一九ニ三)の関東大地震で倒壊したものを、引き起こして補修し、今に至っています。向唐門(むこうからもん)造りで、高さ約6.4m、幅は約2.7m(左右柱間内寸)です。正面破風及び屋根大棟側面と鬼瓦に菊の御紋、下り棟鬼瓦に徳川家の葵紋が刻まれています。勅使門としは閉門していますが、現在は遊行上人が出立帰山する時や、開山忌行列等の諸行事に合わせて開門されています。」「光のアート展示」会場に向かう。再び振り返って。大書院や中廊下では、辻堂神台にある藤沢市アートスペース「アーティストプラットフォーム」事業として、藤嶺学園藤沢中・高校の生徒と、湘南工科大学総合デザイン学科中尾研究室が共同制作した作品『光を結ぶ、光を掬う、光を聴く』が展示されていた。「展覧会にあたって本展覧会では、藤沢市アートスペース事業、アーティストプラットフォームで制作した作品を展示しています。アーティストプラットフォームは、アーティストとともに市内の学や青少年施設などに出向き、作品の共同作業などを通してアーティストと生徒の交流を促す出張事業です。表現活動をとおして生徒・アーティスト双方が固定観念にとらわれない多角的な視野を育むことを目的とし、生徒にとっては文化芸術に対する関心を抱かせる契機に、アーティストにとっては今後の作品づくりに良い影響をもたらす機会を創出しています。今回は、湘南工科大学総合デサイン学科中尾研究室の研究生、学生と中尾教授が講師となり、藤嶺学園藤沢中・高等学校の生徒とともに作品の共同制作をしました。遊行寺のライトアップに合わせた光のインスタレーション作品をせひこ篷賞ください。藤沢市アートスペースについて藤沢市アートスースは、辻堂駅北口から徒歩5分の場所にあるココテラス湘南ビルの6階を利用した、藤沢市の美術振興施設です。若手アーテストの創作活動に対する支援や様々な企画展、ワークショップ、講座などを開催。アートの新たな可能性を見出し、地域とのつながりを深めながら活動しています。」「光を結ふ、光を掬う、光を聴く本作は、LEDテープライト、映像、サウンドを素材とした光のインスタレーション作品です。3、5、7個に分けたLEDライトの花結びとサウンドをひとつの島と見立て、それらを3箇所に配置しました。それは、光の庭、光の枯山水です。光の映像を借景とした光の庭を光の音に耳を傾けながら散策、こ鑑賞ください。光を結ぶ・・日本の伝統技法「花結び」をLEDテープライトで再現、光が多彩に結ばれます。光を掬う・・境内の様々な光の表情が映像として掬い取られ、再び放出、投影されます。光を聴く・・「結ばれた光」と「掬われた光」は音に変換され、光の響きとして立ち上がります。中庭の枯山水の「光の庭」を見る。映像も。「如意宝珠(にょいほうじゅ)」と。如意宝珠とは、仏教において願いごとがすべて叶えられるという不思議な宝の玉を意味する言葉。如意宝珠には、次のような功徳があると信じられていると。思いどおりに宝や衣服、飲食を出す病気や苦悩をいやす悪を除去する濁った水を清らかにする災禍を防ぐ光の庭を再び。そして「御番方」を正面から。「遊戯三昧」とは自由気ままに遊びほうけること。 物事にふけって、夢中になること。 もとは仏教のことばで、何ものにもとらわれることなく、自由であることの意。 「三昧」は、あることに一心になって他のことをかえりみないこと と。「御番方」AI案内。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.14
コメント(0)
-

二子玉川周辺を巡る(その15): 静嘉堂文庫正門~大蔵通り~二子玉川商店街通り(大山道)~「玉川高島屋 」連絡ブリッジ~二子玉川駅前
「大蔵通り」まで坂を下り帰路に。二子玉川駅に向かって「谷戸川」の沿って歩く。バス停「岡本もみじが丘」のお洒落な待合室を右手に見る。「谷戸川」に架かる「やのはし」を渡る。その先にバス停「やのはし」。右手に「静嘉堂文庫」正門。「公益財団法人 静嘉堂」と。「静嘉堂文庫(せいかどうぶんこ)」案内板。静嘉堂文庫は、東京都世田谷区岡本にある専門図書館。日本および東洋の古典籍及び古美術品を収蔵する。東京都千代田区丸の内の静嘉堂文庫美術館で収蔵美術品を一般公開している。「大蔵通り」まで戻りこの交差点を左折。「ガーデンハウス」前を右にカーブ。川に沿って瀬田四丁目を進む。前方に「NTT瀬田前」交差点。この交差点を右折。「二子玉川商店街通り(大山道)」を進む。さらに進むと、左手に「世田谷区立二子玉川小学校」。「二子玉川商店街通り(大山道)」と。二子玉川駅出入口から北西へ約360m、国道246号沿いから北方面へ450mほど続く商店街。前方に国道246号バイパスの高架が現れた。国道246号バイパスの高架を潜ると右手に「柳通り」。「柳小路 入口」。右手に彫刻作品。「哀喜行」。「大貝滝雄「哀喜行」」「玉川高島屋 」連絡ブリッジ。本館と南館を繋ぐ連絡通路。ここにも彫刻作品「冷たい空から500マイル」。第4回たまがわ野外彫刻とテキスタイル展の作品 と。「菊地伸治 冷たい空から500マイル」。既に年末のイルミネーションの準備・トナカイも。そして「二子玉川駅」前を走る国道246号に出て、この日の散策を終了したのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・
2024.12.14
コメント(0)
-

創建700年の遊行寺・大イチョウ ライトアップ:その3
「本堂内」を見る。「清浄光寺」の勅額は後光厳天皇宸筆。外陣と内陣に分かれ、内陣は僧座・尼座・鏡縁に分かれる時宗独特の様式。欄間の彫刻類が美しい。本堂須弥壇に鎮座する阿弥陀如来坐像、平安時代後期作と伝える。穏やかな表情で。「いろは坂」を登りつめた処が山門跡で、明治13年に焼けるまで銅屋根の仁王門あり、「藤沢山(とうたくさん)」と書かれた東山天皇の勅額(ちょくがく=天皇などが寺院に特に与える直筆の書で記された額)があったと。そして現在は本堂内にあるとのことからこれがそうなのであろう。本堂前から「大イチョウ」を振り返る。空には「上弦の月」。ズームして。「本堂 内陣」の左側。再び阿弥陀如来坐像を斜めから。ズームして。正面から再び。「寄心能登観同月 能登に心を寄せ同じ月を観る」「再興能登」 遊行七十五代 他阿一浄上人 書「本堂 内陣」の右側。「遊行藤澤山御歴代上人」の位牌が並ぶ。右から「南無寶勝如來 :宝勝如来に感謝します。 宝勝如来・・・宝の誘惑に惑わされず勝った如来(仏さま) 南無妙色身如來 :妙色身如来に感謝します。 妙色身如来・・・美しい身体の如来(仏さま) 南無甘露王如來 :甘露王如来に感謝します。 甘露王如来・・・天から甘露のように教えを降り注ぐ如来(仏さま) 南無廣博身如來 :広博身如来に感謝します。 広博身如来・・・のど元を広く開けて飲食させる如来(仏さま) 南無離怖畏如來 :離恐畏如来に感謝します。 離怖畏如来・・・怖れや不安から離れさせる如来(仏さま) と。いつまでも座っていたい空間なのであった。本堂内の見事な透かし彫り彫刻を追う。木鼻。照明。天井。そして「本堂内陣」を出て、「大イチョウ」を。「大イチョウ」の上に「金星」。「光のアート展示光のインスタレション作品を展示しています。「遊行の光」に彩を添えるアート作品をぜひご鑑賞くたさい。」再び「大イチョウ」を追って境内を戻る。「竹の灯り」。大イチョウの枝の間から「上弦の月」。ズームして。そして「鐘楼」を見る。ズームして。この鐘楼は南北朝時代、正平11年、北朝の延文(えんぶん)元年(1356)に造られています。当時の遊行寺の住持は遊行八代他阿渡船(とせん)上人です。この上人は遊行上人として初めて佐渡に渡って念仏勧進された方で、記録によると、佐渡を巡り終わって越後柏崎に上陸、国内を遊行中、その年の12月22日に藤沢遊行寺に独住されていた遊行六代一鎮上人が入寂されています。本堂とのコラボ。廻り込んで。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.13
コメント(0)
-

二子玉川周辺を巡る(その14):松本記念音楽迎賓館~岡本八幡宮
「堂ヶ谷戸橋」を渡り「堂ヶ谷戸坂」を上って行った。世田谷区岡本2丁目と3丁目の間 (国分寺崖線)、坂下の堂ヶ谷戸橋から、旧アルジェリア大使館の西脇から国分寺崖線を上る坂。旧アルジェリア大使館。以前は俳優の池部良の自宅で、その後アルジェリア大使館となり、2009~2013年に大使館が三田への移転した後、不使用状態となっているという。建物は現存し、外壁に経年劣化の跡が見られるものの、綺麗な状態で厳重に管理されていた」。門の脇にはかつて国旗が掲げられていたポールも残っていた。この交差点を右折して50mほど進むと右手にあったのがコンサート ホール「松本記念音楽迎賓館」。東京都世田谷区岡本二丁目32番15号に所在する、1973年(昭和48年)建築された音楽教育の建造物である。掲示板にはコンサートのポスターが。「松本 音楽迎賓館公益財団法人 音楽鑑賞振興財団」と。通用門から中庭に入る。「松本記念音楽迎賓館は、パイオニア創業者であり、公益財団法人音楽鑑賞教育振興会の設立者の松本望・千代夫妻の居宅として建築された。2001年(平成13年)、夫妻の遺志を継いで、音楽教育の実践の場にと、一般にも利用できる記念館として開館した。松本望(まつもと のぞむ 1905(明治38年)- 1988年(昭和63年))は 、キリスト教の牧師の二男として神戸に生まれた。若い時、楽器の音色に興味を覚え、音楽の世界に進むことになる。ある時、アメリカ製のダイナミックスピーカーに出会い、魅了されたことがきっかけで、スピーカーの製作に没頭することになった。1928年(昭和3年)、谷山千代と結婚し、二男四女をもうけた。1937年(昭和12年)、ダイナミックスピーカーの開発に成功した。1938年(昭和13年)、福音商会電機製作所を創設、スピーカーの製造を始める。1941年(昭和16年)、有限会社に改組して社長となる。1947年(昭和22年)、福音電機に改組。1961年(昭和36年)、パイオニア株式会社に改称した。1985年(昭和60年)、セパレート型ステレオやレーザーディスクの開発、商品化に成功した。その後、30年以上にもわたって経営の先頭に立って事業を推進した。また、1967年(昭和42年)パイオニア音楽鑑賞教育振興会(現・財団法人音楽鑑賞教育振興会)を創設、私財を投じて音楽教育全般の育成に力を注いだ。」とウィキペディアより。「松本記念音楽迎賓館」のエントランス。コンサート会場をネットから。エントランスの奥には、「健仁寺垣(けんにんじがき)」の如き塀が。そして歴史を感じさせる「数寄屋門」風の庭門が置かれていた。日本庭園への入口であっただろうか。「下馬」と刻まれた石碑。下馬とは、そこより先の乗馬を禁ずることで、下馬碑はその場所を示す碑をいう。「健仁寺垣(けんにんじがき)」の如き塀を見る。「松本記念音楽迎賓館」を後にして、さらに東に進む。見事な赤松。そして右側にあったのが社号標石「岡本八幡宮 北参道」。「岡本八幡宮」の裏側からの参道が続いていた。「岡本八幡宮 北参道」。参道の坂を下って行く。境内に入ると、右手の急な石段の下には石鳥居が見えた。こちらが、表参道なのであろう。ズームして。そして「岡本八幡宮」の拝殿。岡本八幡神社の創建年代は不詳だが、新編武蔵風土記稿には岡本村に記載されている神社が当社のみで、岡本村の開村当時よりの鎮守社であったと考えられるとのこと。祭神 誉田別命境内社 稲荷太神宮愛宕合祠、天満宮祠祭日 例祭10月第1土日曜日住所 世田谷区岡本2-21-2。近づいて。御神体は30cmばかりの木像である。「新編武蔵風土記稿」には「除地一段、小名河原ニアリ、本社ニ間四方、南向ナリ、神体ハ木像ニテ長サー丈許其作ヲ伝へズ坂下ニ石ノ鳥居ヲ立、石階60段アリ、例祭ハ9月27日、(下略)」と記しているが、現在の堂宇は大正11年に改築しており、石段も明治12年8月に再建し、50段である。坂下に石の鳥居が立ち、高い石段をよると松やけやきの大木が生い茂り、小島のさえずりがきこえ、いかにも村の鎮守らしい宮居である。鳥居のほとりに天保5年と記した手洗鉢が放置されている。祭礼は10月の第1、土、日の2日間行なわれる と別のネット説明から。こちらは「神楽殿」。狛犬(右)。狛犬(左)。拝殿の見事な彫刻。「社殿改築紀年碑」。「神輿庫」。神輿をネットから。「八幡宮」碑。拝殿に向かって左手にある、境内社の「天満宮」。近づいて。「天満宮」碑。拝殿の右側にも石塔群があった。「大神宮」(左)と「稲荷神社」(右)と刻まれた石社。その横にも。「三峯神社」。「淺間大社」。そして「岡本八幡宮」を後にして、北参道を戻るり、「大蔵通り」に向かって進む。急な石段を下って行った。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.13
コメント(0)
-

創建700年の遊行寺・大イチョウ ライトアップ:その2
「大イチョウ」と「遊行寺 本堂」のコラボ。「遊行寺墓苑案内所」入口にあった「観音像」。本堂に向かって進む。参道の左手。参道の右手。本堂正面のライトアップ。境内の参道脇にも竹細工にLED電球を組み込んだ「竹灯(あか)り」が。近づいて。黄金に輝く大イチョウは、まるで大地に広がる太陽の光を集めたかのような壮麗な存在。その葉は無数の小さな扇のように輝き、一枚一枚が黄金の布を織り成すように重なりあう。ライトアップされた大イチョウの輝きは、夜の静寂に溶け込みながらも、一際目を引く幻想的な美しさを放っていた。木全体が光を浴びて輝き、その輝きは訪れた人々の心に暖かな灯火・ともしびをともすが如し。その堂々たる姿は、自然の偉大さと四季の移ろいの美しさを物語っています。風に揺れるたび、葉の間から光がこぼれ、木の下を歩く者にきらめく金色の雨を降らせるような幻想的な風景を作り出していたのであった。本堂は、大イチョウとは異なり静かに淡く青く輝く。提灯の白き輝き。そして「一遍上人像」。ズームして。移動して。赤くライトアップされたモミジを背景に。ズームして。青い光に照らされた一遍上人の像の背景には鮮やかな紅葉が広がっていた。一遍上人は両手を合わせて合掌し、静かな祈りの姿を。その神聖な姿と、背景の紅葉の色彩が調和し、荘厳かつ幻想的な雰囲気を醸し出していた。さらに。光の演出がこのシーンをさらにドラマチックに引き立てているのであった。秋の風情や仏教的な静けさが感じられる、印象的な光景なのであった。紅葉もイチョウの黄葉に負けじと。本堂を再び正面から。露盤宝珠を乗せた宝形造銅板葺の御堂に置かれた「常香炉」が手前に。本堂前には、静かなそして素朴な蝋燭の灯りが。「本堂」前右手の「地蔵堂」。露盤宝珠を乗せた宝形造銅板葺の地蔵堂。大正十二年(1923)の関東大震災で倒壊後、その後、東日本大震災を機に、震災・風水火災で亡くなられた方々の鎮魂の為に発願し平成二十六年に再建された のだ。扉の上部の隙間から「日限地蔵様」のお顔をズームして。「なでなで地蔵」。私も今更ながらであるが頭を「なでなで」。堂内の「日限地蔵菩薩(ひぎりじぞうぼさつ)」。お顔をズームして。地蔵菩薩は、お釈迦様亡き後、この世で私たちを救ってくださる仏様。なかでも「ひぎり地蔵菩薩」は、日を限ってお参りをすることによって願いがかなえられるので、全国各地で信仰をあつめています。遊行寺の門前は、東海道の藤沢宿として栄え、江戸・明治・大正の頃には、道中安全をお祈りするために、お地蔵さんを詣でる人々で賑わいました。しかし、大正12年の関東大震災で遊行寺も本堂など多くの建物が倒壊し、地蔵堂も倒壊したため、応急処置を施して本堂内に安置されてきました。このたび全国宗門寺院および檀信徒皆様の協力で、平成の大修理として解体修理しましたところ、胎内から『少病少悩』等の文字と「享保六年辛丑年四月廿四日」の日付が発見され、江戸庶民の信仰がしのばれます。平成26年6月に修復を終え、関東大震災から約百年ぶりに再建された地蔵堂に安置されました。輝きを増したお地蔵さんは、偉大な法力を備え、交通安全・安産成就や子どもの成長安寧の他、病魔退散・健康長寿といったご利益を施してくださいます。 平成26年9月15日 時宗総本山 清浄光寺(遊行寺)と。本堂を「地蔵堂」前から。ズームして。常香炉にも寺紋・「折敷に三文字紋」・「隅切三(すみきりさん)」が入っていた。本堂に更に近づいて。木鼻(左)。「登霊臺(とうれいだい)」の扁額は紀伊大納言・徳川治寶(とくがわはるとみ)筆。徳川治寶は「中雀門」の建立者でもある と。淡い青の色合いが幻想的。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.12
コメント(0)
-

二子玉川周辺を巡る(その13):丸子川~岡本公園 民家園
閉まっていた「旧小坂家住宅」の見学は次の機会とし、「馬坂」を引き返し、「世田谷区立 岡本下山公園」まで戻る。「世田谷区立 岡本下山公園」の前にあったのが、「東急バス」のバス停「静嘉堂文庫」。「丸子川」に沿って「世田谷区立岡本公園民家園」に向かって歩く。川には多くのカモの姿が。マガモのツガイであっただろうか。前方にバス停「民家園」。右手前方に「八幡橋」。「岡本公園 民家園」案内板があった。前方に「岡本公園 民家園」駐車場。「岡本公園(民家園)周辺案内図」。「現在地」はここ。「世田谷区立 岡本公園」。「世田谷区立岡本公園 民家園」案内プレート。ここにも、先ほど訪ねた「旧小坂家住宅」と同じ休園日情報が書かれていたのであった。「休園日 月曜日(月曜日が祝・休日の場合は翌平日)」と。「民家園 職員出入口」と。近づいて。ここが「管理事務所」なのであろう。廻り込むと竹林が現れた。「岡本公園」には「案内板」が。「世田谷の誇る歴史遺産岡本隧道この案内板から右50m先、民家園の左奥に石垣囲いの蒲鉾型の扉があり「岡本隧道」という字が刻まれています。隧道とはトンネルのことで、扉の中は、高さ2m、幅2.5mのトンネルになっていて、そこには直径80cmもある送水管が通っていて、その長さは120mにも及びます。1921年(大正10年)、当時の豊多摩郡渋谷町(現在の渋谷区)では、多摩川の水を町に引き込もうと、大規模な水道工事を始めました。砧下浄水場で取水・浄化した水は駒沢給水所、三軒茶屋を経て渋谷に至り、地下の送水管は南西から北東へ直線的に世田谷を跨いでいます。水は、駒沢給水所までは揚水ポンプのカで高く持ち上げられ、給水所から渋谷までは自然の重力で送水されました。砧下浄水場を出てすぐに、この岡本の台地を横断しますが、揚水ホンプの負荷を少なくする工夫として送水管専用のトンネルが利用されました。これらは、1923年(大正1 2年)に竣工した近代水道の建造物であり、今でも珍しい施設で、極めて貴重な歴史遺産です。 駒沢給水塔風景資産保存会・世田谷区」前方に「岡本公園 民家園」入口は閉鎖されていた。休憩ベンチ。「民家園 -------→」案内板。「世田谷区立 岡本公園民家園」「振替休園日」と。「世田谷区立 岡本公園案内図」。「掲示板」。「世田谷区立 岡本公園民家園」案内図。「11月の岡本公園民家園・次太夫堀公園民家園」案内書。ポスター「令和6年度 せたがや 民家園まつり」。「世田谷区立次大夫堀公園民家園」案内書。「きしべの道 案内板」。「現在地」はここ。「72 せたがや百景岡本民家園とその一部復元されたかやぶきの民家は、18世紀未に建てられた旧長崎家の母屋を増改築したものといわれています。国分寺崖線の雑木林によく溶け込んでいます。民家園では、四季折々の年中行事が再現され、広く区民に開放されています。」「73 せたがや百景静嘉堂文庫旧三菱財閥の故岩崎弥之助・小弥太氏によって収集された膨大な文化財の収集館です。和漢20万冊の古典籍を保存し、永く後世に伝えることを使命として活動している専門図書館です.美しい庭は、自由に散策できます。」「きしべの路「きしべの路」は、国分寺崖線に沿って残る豊かなみどりや水辺の風景をたどりながら、かっての暮らしと文化を訪ね歩く路です。上の写真のような案内サインや路面のサインを目印にお出かけください。」「丸子川親水公園仙川の水神橋際に始まる丸子川は、国分寺崖線に沿って大田区へ流れています。丸子川は、江戸時代初期に小泉次大夫と多くの農民の手により開削された六郷用水の一部で、世田谷区では俗に「次大夫堀」とも呼ばれてきました。丸子川親水公園は、水神橋から下山橋までの区間で、水辺の遊歩道に沿ってここ岡本公園民家園や岡本静嘉堂緑地に続きます。」「国分寺崖線の位置国分寺崖線の「崖の連なり」は、立川市から国分寺市などを経由し、世田谷区から大田区へと延長約30kmにわたっています。世田谷区内では南西部に位置し、多摩川と野川に沿って約8km続き、高さ10 ~ 20mの斜面からなります。」岡本公園内の敷地内には小川が流れていて、池や橋もあった。湧水の流れであろうか。湧水場所であっただろうか。水面は陽光を反射して。再び竹林を望む。石仏であっただろうか?再び竹林を。「丸子川」を見る。さらに「丸子川」に沿って進む。この先を右折して「堂ケ谷戸橋」を渡る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.12
コメント(0)
-

創建700年の遊行寺・大イチョウ ライトアップ:その1
この日は12月8日(日)、朝のNHKのニュースで、藤沢市にある「藤澤 遊行寺(清浄光寺)」では、開山700年を迎える今年、市指定天然記念物「大イチョウ」の見頃に合わせ、境内にて本堂や大イチョウのライトアップを2024年12月7日~22日の期間に実施していると。また、大書院や中廊下では、藤沢市アートスペース「アーティストプラットフォーム」事業として、藤嶺学園藤沢中・高等学校の生徒たちと、湘南工科大学総合デザイン学科中尾研究室が共同制作した作品展示「光を結ぶ、光を掬(すく)う、光を聴く」を実施しているとのことで16時過ぎにバスで向かったのであった。遊行寺で初のライトアップイベント「遊行の光」開催!のポスター。バス停「遊行寺前」で降車し、遊行寺に向かって歩く。「遊行寺橋 (旧 大鋸橋)」から「境川」の下流を見る。ここが旧東海道の道である。前方に見えたのが、「藤沢橋」。「境川」の上流を見る。「遊行寺橋(ゆぎょうじばし)」を渡り振り返る。江戸時代に大名行列が渡ったといわれる橋で、旧東海道が境川を渡るところに架けられていた。擬宝珠のついた赤い欄干のこの橋は、時宗総本山遊行寺の門前の橋である。現在の橋は、昭和35年に造られたPC桁橋である。先に進むと右手にあったのが「藤沢市ふじさわ宿交流館」そして「遊行寺 惣門」前に到着。その両脇には歴史を感じさせる灯籠、その奥には石垣と築地塀も。 境内配置図。大きな寺号標石「時宗 総本山 遊行寺」👈️リンク。清浄光寺(しょうじょうこうじ)は、神奈川県藤沢市にある時宗総本山の寺院。藤沢山無量光院清浄光寺と号す。近世になって遊行寺(ゆぎょうじ)と通称され、明治時代より法主(ほっす)・藤沢上人と遊行上人が同一上人であるために通称の遊行寺の方が知られている。藤沢道場ともいう。「遊行寺 惣門」に近づいて。現在の惣門は、主柱の後に控柱をもつ4本足で、屋根が無く、主柱の上部を横木が貫く大きな黒の冠木門(かぶきもん=門柱にぬきをかけたもの)。これが「遊行寺」の「惣門」。今日では遊行寺の黒門とも呼ばれているのだ。天保 10 年(1839)成稿の「相中留恩記略」挿図や明治初めの境内図では、この門は「惣門」とあって黒門とは書かれません。姿も今とは違い、冠木門に屋根がついた薬医門の形式で、基壇もある。そしてなにより黒く見えません。江戸後期の境内図で、門全体を茶色に塗ったものもあるので、やはり黒くなかったのでしょう。一説に大書院への門(現在は中雀門の隣)がもともとの黒門だともいわれ、確かにどの図でも黒く描かれています。とすればこのころ惣門は「黒門」と呼ばれていなかったのではないか とも。日本三大黒門の一つといわれますが、他の二つがはっきりせず、どうも根拠はないようです。そして、明治 13 年(1880)「清浄光寺境内絵図面明細書目」 (清浄光寺文書)の「総門」の項からは、桁行 3 間 1尺(約 570 ㎝)、梁間 2 間 3 尺(約 450 ㎝)、棟高 1 丈 4 尺(約 420 ㎝)、屋根は銅板葺きで、紀伊藩主徳川治宝が 染筆した「登霊台」の額が掛けられていたとわかります。「藤沢山日鑑」は文政 13 年(1830)5 月 25 日(17 巻) に、この額が届いたと記します と右に「時宗 總本山」と彫り文字に墨入れした大きな木札がかかっている。当本山の正式名称は、「藤沢山 無量光院 清浄光寺(とうたくさん むりょうこういん しょうじょうこうじ)」と号す。近世になって遊行寺と通称され、明治時代より法主・藤沢上人と遊行上人が同一上人であるために通称の「遊行寺」の方が知られているのだ。右側には石垣と築地塀が青く輝いていた。惣門前には、高さ約2m80cmの青銅製の灯籠が対になって建立されていた。青銅製の灯籠(右)。「清淨光寺( しょうじょうこうじ)」と。青銅製の灯籠(左)。そしてライトアップされた「いろは坂」を上って行った。この場所は、桜の並木であるのでピンクにライトアップされていた。美しく輝く球形の竹灯籠。近づいて。60cmほどの球形の竹ボール・竹灯り。さらに進むと前方に黄金の輝きが現れた。そして右手にあったのが「眞徳寺」。寺号標石「赤門 眞徳寺」。朱の山門を正面から。「真徳寺」。この大きな石碑には仏像が線刻されているようであった。再び球形の竹灯籠に近づいて。竹細工に電灯を組み込んだ「竹灯(あか)り」。そして「いろは坂」を更に進むと左手にあったのが「時宗 眞淨院」。寺号標石「時宗 眞淨院」。「いろは坂」を上り終わり大きな「石門」前に到着。この石門は山門跡となる。右の「石門」前には「当山今月(12月)の行事」案内木札が並んでいた。左の「石門」。石門には時宗の「宗紋・「隅切三」(すみきりさん)」が。一遍上人は延応元年(1239)、 伊予(いよ・愛媛県松山市)の豪族である河野家の次男として誕生した。 幼名は松寿丸といい、父は河野七郎通広(こうのしちろうみちひろ) 、祖父は河野四郎通信(みちのぶ )。一遍の俗名は河野時氏といって伊予国の土豪の家系。隅切と呼ばれる、4角形の隅を切り落としたような8角形の枠に、漢数字の「三」を配しており、この8角形が、食器や供物を載せる盆「折敷」(おしき)に似ているため、この枠のある紋を「折敷紋」とも呼ぶとのこと。伊予国(現在の愛媛県)の「大三島神社」の神紋でもあると。「三」の文字は大三島神社の「三」であると言われているとのこと。貞秀の錦絵にも描かれた楼門の山門は明治13年(1880)に焼失。楼門に掛っていた「藤澤山」の扁額(公式サイトによると東山天皇の直筆による勅額)は本堂内にあるとのこと。歌川(橋本)貞秀「東海道名所之内 (御上洛東海道) 藤沢 遊行寺」をネットから。そして正面一面に「大イチョウ」黄金の輝きが。遊行寺・本堂もライトアップされて。「大イチョウ」の樹齢は、幹の太さから七〇〇年以上と。「市指定天然記念物昭和四十六年(一九七ー)七月五日指定大イチョウ 樹高約 21m 幹回り 710cmひときわ大きなイチョウで、遊行寺境内のシンボルとなっています。境内最大の巨木は、市内で一番太い木でもあります。かつては高さが約31mありましたが、昭和五十七年 (一九八二)八月の台風で地上6mの辺りで幹が折れてしまいました。今、樹木全体がずんぐりとした形に見えるのは、この時の折損のためです。折れた幹の中は空洞で炭が入っていたので、過去に火災に遭ったことがあるようです。雨で腐らないよう折れた部分にトタン板を張って防いだところ、樹勢が回復しました。平成四年(一九九二)の調査で686cmだった幹回りは、平成二十年の計測では710cmと太くなっていました。樹齢については、指定時の調査では幹の太さから約六五〇~七〇〇年と推定されました。その後、台風で幹が折れた際に行われた折損部材の年輪測定では二五〇年だったので、それ以上の樹齢であることは確かです。ただし、イチョウの古木は根元の外周から生えた若木が育ち、元の木が枯れて中心が空洞になることがあるので、元来の樹齢は不明とせざるをえません。イチョウは中国原産で、日本への渡来は早くても十二世紀以降のこと、遊行寺の創建は正中二年(一三二五)なので、何れにせよこれをさかのぼることはないでしょう。雄株なのでギンナンはなりませんが、晩秋の黄葉はみごとです。例年十一月下旬から十二月上旬に色づきます。平成二十年(二〇〇八)九月〔藤沢市教育委員会〕」「大イチョウ」の黄金の輝きを見上げて。黄金の輝きの隙間から「上弦の月」を見る。 ・・・つづく・・・
2024.12.11
コメント(0)
-

二子玉川周辺を巡る(その12): 瘡守稲荷~馬頭観音・辯才天~下山稲荷社~旧小阪家住宅・裏門~馬坂~旧小阪家住宅・表門
「大空閣寺」を後にして、北側にあった世田谷区瀬田4丁目30の住宅街の道を西に向かって進む。右手にあった民家の立派な門。その先、左にあったのコミュニティーセンター「瀬田地区会館」。世田谷区瀬田4丁目18−11。「瀬田地区会館」。「瀬田地区会館」ご案内。地下1F、地上2Fの、会議用の大きな部屋が複数あるようであった。右折して進むと、左手にあったのが「瘡守(かさもり)稲荷神社」。世田谷区瀬田4丁目32−19。「瘡守稲荷」。「手水舎」。「石鳥居」。その先に「瘡守稲荷」の社殿。狛狐(右)。狛狐(左)。拝殿に近づいて。瘡守稲荷神社の創建年代は不詳ですが、江戸時代には病平癒の社として多くの参詣者があり、「多摩川のきれいな石を持ちかえり、病気が全快すると多摩川から石を拾い、倍にしてかえす習慣があった」と。祭神:倉稲魂命(うかのみたまのみこと)。名前の「ウカ」は穀物・食物の意味で、穀物の神。須佐之男命と神大市比売(大山祇命の娘)との間に生まれ、大年神の妹神である。また、伊勢の外宮にお祀りされている豊受大御神とはご同体と云われている。伏見稲荷大社を始め全国にある稲荷神社のご祭神として広く信仰されており、人々より親しみを込め「お稲荷さん」と呼ばれている。「お稲荷さん」といえば狐ですが、なぜ狐かと云うと、それは倉稲魂神の別名である御饌津神(みけつかみ)からきており、狐の古称「けつ」というのが混同してしまい、同一視されるようになったと。農耕の神、商工業の神、商売繁盛の神として信仰されているのだ。扁額「正一位 瘡守稲荷神社」。賽銭箱の設置はなかった。内陣。そして「瘡守稲荷神社」を後にして、次の交差点を左折して、西に向かう。ここ「稲荷神社前」交差点を左折。途中、右折して北に向かうと左手に小社があった。小社の下に石碑が2基。世田谷区瀬田5丁目11−28。「馬頭観音」(左)と「辯才天」(右)。左の馬頭観音は大正6年(1917)3月の造立。願主は当時の当主であろう西尾権太郎氏である。右の弁財天はもっと古く、天保7年(1836)11月の年号が記されている。交差点まで引き返し、さらに西に進み、突き当りの1本手前の世田谷区瀬田5丁目7の路地を南に向かう。「旧小坂家住宅」の屋敷を右に見ながら、周辺道路を進む。「世田谷区立 瀬田四丁目旧小坂緑地 東門」案内板。「東門」方向に進む。前方右手に「東口」。その先の突き当りを右折すると右手に神社があった。「下山稲荷社」。小坂家住宅の屋敷神だったのだろう。 屋敷神の稲荷としては相当立派である。かつては「八幡稲荷八万」と言われ、稲荷神社と八幡神社はそれぞれ4万ずつあると言われていたと。 実際には稲荷が32,000柱、八幡が14,000柱らしい。ただ、屋敷神としての稲荷はどこまでカウントされているのか??。しかし、この神社の名前の判るものは、この表示のみ。 屋敷神の稲荷であったからだろう。内陣。多くの狐様が鎮座。「とうかん坂」と。この「とうかん坂」は静嘉堂文庫の入口前にある旧小坂家住宅の緑地の南側の階段坂。 ちょっと見には公園の中の遊歩道っぽいが、実は江戸時代からある崖線の上下を結ぶ道のひとつであると。 この日は下りであったが、20mの高低差を一気に登る階段はなかなかきついのであろう。「とうかん」の意味、漢字は??「とうかん坂」を下ると、角にあったのが「旧小阪家住宅」の「裏門」。旧小坂家住宅は、世田谷区指定有形文化財。信濃銀行取締役、信濃毎日新聞社長、衆議院議員などを歴任した小坂順造氏(1861~1960)が昭和12年に別荘として建てた屋敷。明治から昭和にかけて、都心から玉川電車で往来でき、多摩川が近く緑の多い国分寺崖線のこの一帯には、財界人、政治家などの週末住宅としての別邸が数多く建てられた。小坂氏の本宅は渋谷にあったが、空襲で消失し、戦後はここを本宅とした。現在は、世田谷区が寄贈を受け、公圄内の文化財として一般に広く公開、利用されているのだ。周辺の「樹林地図」。「世田谷区立 瀬田四丁目旧小坂緑地」掲示板。「旧小阪家住宅」の「裏門」入口。「世田谷区立 瀬田四丁目旧小坂緑地」案内板。近づいて。開園時間:午前9時30分~午後4時30分までその下のボードには開門時間 9:30~16:15 と。この時点では、その下の文字には気が付かなかったのであった。そして「大蔵通り」を進み、その先の交差点を右折して坂道を上って行った。この坂は「馬坂」と。世田谷区瀬田4丁目と岡本1丁目の間、 “岡本静嘉堂文庫”(静嘉堂緑地)の正門前から北西に上る坂道(国分寺崖線の坂)。それまでの坂道があまりにも勾配が急なため、人は上り下りできても馬はどうすることもできなかった。そのため別に勾配の弱い道をつくり、馬も楽に往復出来るようにしたので、この名がついたとのこと。坂下は東北東に向かって、坂上は北に向かって上り、長さ130m、高低差15m、平均斜度7度の急坂なのであった。そしてこの先が「旧小阪家住宅」の「表門」入口。手前には「世田谷区立 瀬田四丁目旧小坂緑地世田谷区指定有形文化財旧小坂家住宅」と。「表門」横の案内板。近づいて。さらに。瀬田四丁目旧小坂緑地は、世田谷区の緑の生命線である国分寺崖線の斜面樹林の一部であり、国内には区指定有形文化財「旧小坂家住宅」と、紅葉と竹林が美しい湧水の流れる庭園があります。ここは、かって衆議院議員などを歴任した小坂順造氏の別邸として利用されていました。多摩川が近く、国分寺崖線の緑が多いこの地域一帯には、明治から昭和にかけて建てられた別邸が多くありました。都心から玉川電車で往来できるこの辺りは、当時の財界人の週末住宅として絶好の立地でもありました。昭和12年に建てられた「旧小坂家住宅」は、別邸として現存する貴重な近代建築です。木造和風平屋建(一部2階建)で、萱葺き風の古民家を思わせる外観を持ち、南向きの斜面を利用した庭園と一体となった美しい景観を形成しています。また、庭園部分はコナラやトチノキなどの大きな樹木が武蔵野の雑木林の面影をとどめており、崖面からあふれる貴重な湧水は園内に潤いを与えています。散策路や木道を回遊しながら、国分寺崖線のみどりとみずを身近に感じられる空間となっています。ぜひお気軽にお立ち寄りください。 平成28年3月※この国分寺崖線の自然的環境を活かした旧小坂家住宅と庭園を後世に残すため、世田谷区が 公園緑地として取得し、平成10年から一般公開しています。」「掲示板」に近づいて。開園時間 午前9時30分~午後4時30分まで休園日 毎週月曜日 但し 月曜日が祝日の場合は次の平日 年末年始(12月29日~1月3日)この日は、11月5日(火)、前日の11月4日は『振替休日』であったので休園日であったのだ!!「旧小阪家住宅」案内図に近寄って。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.11
コメント(0)
-

二子玉川周辺を巡る(その11):大空閣寺
「瀬田玉川神社」を後にして、次の目的地の「大空閣寺」に向かって、世田谷区瀬田4丁目の住宅街を進む。世田谷区瀬田4丁目21の道路脇にあった石仏群。「観音像」と。そして、その先20m程の場所にあった「大空閣寺」に到着。世田谷区瀬田4丁目21−15。石碑が並ぶ「福智圓滿 十三まゐりの本尊 虚空蔵菩薩」碑。「大空閣寺」碑。「圓滿 地蔵菩薩」碑。正面に本堂。真言宗豊山派寺院の大空閣寺は、如意山と号す。大空閣寺は、大正元年に虚空蔵行者聖慶大僧正が豊多摩郡戸塚町(新宿区高田馬場)に創建、昭和10年当地へ移転した。玉川八十八ヶ所霊場38番。大空閣寺は東京都に於ける唯一の虚空蔵霊場で、丑年・寅年生まれの方の守り本尊 と。人は、この世に生を受けた瞬間から、地球の公転運動の影響を受けるとする説があります。干支は十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)と十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)を組み合わせた60年を周期とする数詞のことで、古来より暦をはじめ時間、方位などに用いられてきました。そのように数値化された干支、特に十二支には、それぞれに対応した守護本尊が定められています。生まれ年の干支ごとの守護本尊が人の運気に影響を与えるとされる所以は、こうした説が根本となっているのだ と。本堂前の寅。私の干支はこの寅なのだ。こちらは「丑」。本堂の正面。扁額「如意山」。内陣の扁額は「大空閣」「玉川八十八ヶ所霊場第三十八番札所」。「手水場」。「聖観世音菩薩」像。「弘法大師像」・「南無大師遍照金剛」。観音堂。「觀世音」と。「常施餓鬼観音」像。通称は「ハーモニカ観音・出世観音」とのこと。聞き覚えのない菩薩さまだが、餓鬼道で苦しむ衆生に食事を施して供養する「施餓鬼」に通じているのか? だとすれば、祖霊以外のいわゆる無縁仏など一切の精霊の供養であろうか。「中宮殿」。納骨堂とのこと。内陣。ズームして。「宗旨・宗派を問わずご利用いただけます。」と。「開山 聖慶大僧正碑」。大空閣寺の開山虚空蔵行者聖慶大僧正の碑左「観音堂 聖慶廟(しょうけいびょう)」一周忌などの法要が行える会場も納骨堂と同じ施設内に完備しているとのこと。本堂前を横から。再び「丑」。本堂・内陣。ズームして。本堂の左脇にあった、こちらはどなたなのでしょう?「輪違」の宗紋があったが。 七福神の布袋尊(ほていそん)であっただろうか。「大空閣寺」。脇門越しに本堂を見る。移動して。ズームして。本堂屋根の「宝珠」。脇門にあった石碑「圓満地蔵菩薩」。阿修羅道の衆生を救い導くと云われる「十一面観音」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.10
コメント(0)
-

二子玉川周辺を巡る(その10):瀬田玉川神社
「慈眼寺」を後にして、往路を引き返し、次に訪ねたのが「瀨田玉川神社」、石段の上に「一の石鳥居」が見えた。世田谷区瀬田4丁目。社号標石「瀨田玉川神社」。裏面には「天皇陛下喜寿記念 平成二十二年十二月吉日」と。「一の鳥居」。「神様クイズ瀬田玉川神社へ、ようこそお参り下さいました。全国に鎮座する神社ですが、意外と知らないことも多くあります。そこで、神社についてちょっと賢くなるクイズを用意しました。この先からクイズが現れます。その答えは、参道を先に進むとあります。あなたは何問正解できるでしょうか?ぜひ、チャレンジしてみてください 瀬田玉川神社社務所」「問題 1神棚(宮形)の両側に供えられる植物は、一般に何でしようか。」「問題 1 の答え「榊(さかき)」【解説】榊は、古くは常緑樹の総称でした。青々と生い茂る樹木は、生命力の象徴であり、また生気を宿すものとも考えられ、様々な神事に用いられてきました。古事記や日本書紀にも、八百万(やおよろず)の神々が天の岩屋へお隠れになった天照大御神に対して、五百箇真坂樹(いおつのまさかき)に玉鏡・幣を掛けて祭事を行ったことが記されており、神聖なご神木として重視されてきたことが窺えます。ちなみに、植生の関係から、南関東以西では葉の淵にギザギザのないマサカキが用いられますが、北関東以北から岩手県南部辺りまでは、ギザギザのあるヒサカキが用いられます。さらに北の地域になると、イチイやスギなどか用いられることもあります。」「問題 2瀬田玉川神社の正参道にある鳥居の形態について、正しい答えを次の3つからお答えください①明神鳥居(みようじんとりい)②神明鳥居(しんめいとりい)③山王鳥居(さんのうとり〕) 難易度 ★★」「問題 2 の答え②神明鳥居(しんめいとりい)【解説】鳥居の内は、神さまがお鎮まりになる御神域を示します。その形態は、六十種類以上もあると言われています。代表的なものに、鳥居上部の横柱が一直線になっている神明鳥居、この横柱の両端が上向きに反っている明神鳥居、明神鳥居の横柱上部に合掌形の破風(はふ)のついた山王鳥居、朱塗りの稲荷鳥居などがあります。」「問題 3狛犬(こまいぬ)の起源となった地域はどこでしようか。正しい答えを次の3つからお答えください。①古代ローマ②古代中国③古代メソボタミア 難易度 ★★★」「問題 3 の答え③古代メソポタミア【解説】諸説ありますが、狛犬の起源は古代メソポタミアで神域を守る百獣の王・ライオンの像であるとされます。ここから西にエジプトに行くとピラミッドを守るスフィンクスになり、東に行くと唐草模様が装飾されたり、高麗犬と呼ばれたり、沖縄ではシーサーになったりと、地域の特徴を備え変化しながら、日本に伝わってきたと考えられます。その役割は、神さまのお使いとして神域を守り、邪気を祓うことを担います。また、狛犬の表情は地域によって実に多様です。一般に向かって右側の狛犬が「阿形(あぎよう)で口を開いており、左側の狛犬が「吽形(うんぎょう)」で口を閉じていて、右が雄、左が雌で子供を抱いていたりするものもあります(※阿吽の呼吸)。」「問題 4現在、お賽銭箱には、金銭をお供えしますが、昔はお米がお供えされていた。〇か☓か?」「問題 4 の答え「 ◯ 」【解説】現在もそうですが、ご神前にはその土地で収穫された物を中心にお供えされます。私たちは祖先の時代から豊かな自然に育まれて暮らし、秋になると米の稔りに感謝をして刈り入れた米を神様にお供えしました。こうした信仰に基づき、米を白紙に包み「おひねり」としてお供えするようになりました。その後、貨幣の普及とともに米の代わりに、金銭をお供えするようになります。そもそも米は、天照大御神がお授けになられた貴重なものとされ、人々はその大御恵(おおみめぐみ)を受け、豊かな生活を送ることができるよう祈ったのです。金銭をお供えすることも、この感謝の気持ちにかわりません。ご自分の気持ちを表して、お参りしましょう。」「問題 5お参りの際に鳴らす鈴の意味とはなんでしょうか。(複数回答あり)」「問題 5 の答え【回答】多くの神社では、拝殿の中央、ちょうど賽銭箱の真上あたりに、大きな鈴が吊られており、参拝者はこれを振り動かして鈴を鳴らし、お参りをします。当社では、巫女が神事で用いる神楽鈴を鳴らして、お参りいただいております。この鈴は、清々しい音色で参拝者を敬虔な気持ちにするとともに参拝者を祓い清め、神霊の発動を願うものと考えらています。『古語拾遺』には、天の岩屋(あまのいわや)にお隠れになられた天照大御神の心をひくために、天鈿女命(あめのうずめのみこと)が鈴を付けた矛を持って舞ったことが記され、宮中では天皇陛下が天照大御神を御親拝なされる際に、女性で祭祀を司る内掌典(ないしょうてん)が、御鈴を鳴らして奉仕することがあるように、神事における鈴振りは今日においても重要な意味を持っています。」「治水事業で消滅した「千年の森」を再生したい」👈️リンク参道をさらに進む。七五三の参拝に向かう家族の姿も。「狛犬」(右)。「狛犬」(左)。一対の石灯籠、その先に二の石鳥居。「東宮殿下演習の砌野立所の記念として松树を植ゑければ(計連婆) 新田神社々司尾崎◯作謹詠」碑東宮殿下とは昭和天皇。大正4年(1915)の演習に際して休憩された東宮殿下(昭和天皇)御野立所の石碑であり、その後ろに植樹した松も育っていた。「可幾里なき 日つきの皇子能 三さ可えを わ可松うゑて 祈る御氏子」【限りなき 日嗣の皇子の 御栄えを 若松植えて 祈る御氏子】大正四年十月廿七日 京西小学校長 小川銀八郎敬?書」二の鳥居に近づいて。ここにも「瀨田玉川神社」。「手水舎」。「掲示板」。社殿を正面から。瀬田玉川神社は、永禄年中(1558~70)に創建と伝えられ、寛永3年(1626)に字下屋敷から字滝ケ谷辺へ遷座したといいます。明治7年村社に列格、明治41年社号を御嶽神社から玉川神社へ改号した と。さらに近づいて。社号 玉川神社祭神 伊弉諾尊・伊弉冉尊・事解命境内社 大国社、稲荷社、三峯社、天満社、祓戸社、八幡社。狛犬(右)。狛犬(左)。社殿の唐破風屋根。蟇股の彫刻。ここにも歴史を感じさせる狛犬(右)。ここにも歴史を感じさせる狛犬(左)。社殿内陣では、七五三の祈祷が行われていた。七五三は、古くからの風習である3歳の「髪置(かみおき)」、5歳の「袴着(はかまぎ)」、7歳の「帯解(おびとき)」に由来するといわれています。「髪置」は男女児ともに行われた儀式で、この日を境に髪を伸ばし始めました。また、「袴着」は男児がはじめて袴を着ける儀式で、「帯解」は女児がそれまでの幼児用の付紐をやめ、大人の帯を締める儀式であると。扁額「瀬田玉川神社」。大きな龍の「絵馬」。「絵馬掛所」。絵馬掛所に1年程度掛けられていた絵馬、もしくはその年に奉納された絵馬はおおむね年末に焼かれ、絵馬供養されるのだとか。右手奥に「神楽殿」。「瀬田玉川神社例大祭(宵宮)2024・奉納舞」👈️リンク をネットから。「社務所」。こちらは二の鳥居から拝殿の間に建つ鳥居。ここにも兎年の大きな絵馬が。「正一位稲荷神社」。「正一位稲荷神社」の参道。「正一位稲荷神社」。左手には小祠…というよりか神棚が上屋の中に。先程訪ねた隣の「慈眼寺」を望む。「戦役紀念碑」。「明治三十八年 戦役紀念碑 希典書」と。「玉川神社寿詞」碑。「玉川神社寿詞」。ここは「車祓所」と。そして、参道を下ったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.09
コメント(0)
-

二子玉川周辺を巡る(その9):慈眼寺
正面に「慈眼寺」の楼門が見えて来た。山門は楼門で、現在の東京都区部の寺院では珍しい。門内には四天王が配され、屋根には鴟尾が乗る。真言宗智山派の寺院。正式には喜楽山教令院慈眼寺。徳治元年(1306年)、旅僧が、滝ケ谷戸崖から掘り出された降三世明王像を祀って創建。天文2年(1533年)に現在地に移転した と。扁額「喜楽山」。寺号標石「真言宗智山派 喜楽山教令院慈眼寺」。楼門内には四天王が。「四天王の配置」図。四天王は、東西南北の4方を守る役目の4人(神)組。「四天王」はグループ名で、構成メンバーは持国天、増長天、広目天、多聞天となります。それぞれの役割は、以下の如し。持国天:国を支える増長天:恵みを増大させる広目天:広く見通せる目をもつ多聞天:仏の教えを多く聞く本堂に向かって、右前から右回りに「持国天・増長天・広目天・多聞天」という配置となっていた。楼門の正面・右側から「持国天(じこくてん)」。持国天は四天王の一体、東方を護る守護神として造像される場合が多く、仏堂内部では本尊に向かって右手前に安置されるのが原則である。その姿には様々な表現があるが、日本では一般に革製の甲冑を身に着けた唐代の武将風の姿で表される。持物は刀の場合が多い。例えば胎蔵界曼荼羅では体色は赤く、右手を拳にして右腰に置き、刀を持つ右手を振り上げて仏敵を威嚇し、左手を腰に当てる姿に表されていた。正面からなんとか。「持国天」。「持国天国を支える東方の守護神四天王のうち東方を護る神々の将軍現名ドゥリタラーシュトラは文字通り「国を支える者」という意味だ。右手に剣を持ち、左手で刃を支える姿の像が多いが、一定ではなく、右手で剣を振り上げて左手は腰に置いたり、逆に左手に刀を持ち、右手は腰に置く像もある。仏堂では本尊を北として、右方前方に置かれる。」足下の邪鬼を踏みつけていた。「増長天」。正面からなんとか。「増長天」。「増長天仏法と信者を守る南方の守護神四天王のうち南方を護る神々の将軍。現名ヴィルーダガは「増大した者」の意で大きな力を持つ武神のこと。左手に三叉の鉾(戟)を持ち、邪鬼を踏みつけるか岩座に立つ。左手は、腰にあてる像と、太刀を持つ像がある。中国古代の鉄人の姿で鎧は革製のものを表している。仏教では本尊を北として左方前方に置かれる。」こちらも、足下の邪鬼を踏みつけていた。「多聞天」。正面からなんとか。「多聞天」。「多聞天戦国武将の信仰をあつめた北方の守護神四天王のうち北方を護る神々の将軍。インド・中国の東方にある日本では武将の守護神にもなる。原名ヴァイシュラヴァナを「多く聞く者」と訳して多聞天と呼ばれる。また、その音から毘沙門天ともいい、単独で除災招福の神として祀られる。右手で宝塔を掲げ、左手で鉾又は棒を持つ姿が普通。仏堂では本尊を北として、右肩後方に置かれる。」こちらも、足下の邪鬼を踏みつけていた。「広目天」。正面からなんとか。「広目天」。「広目天千里眼を持つ西方の守護神四天王のうち西方を護る神々の将軍。原名ヴィルーバークシは「千里眼のような不思議な力がある目を持つ者」と考えられて広目天と呼ばれるようになった。右手に筆、左手に巻物を持って書きつけている姿が特色。武人の姿だが、四天王の中では穏やかな表情である。竜王を従えるという。仏堂では本尊を北として、左方後方に置かれる」。こちらも、足下の邪鬼を踏みつけていた。楼門の先に「本堂」。本堂は昭和50年建立。本尊は大日如来。「弘法大師ご誕生千二百五十年記念塔」。弘法大師・空海(774-835)は、宝亀(ほうき)5年(774年)6月15日、現在の香川県善通寺市にお生まれになりました と。境内の建物は外装工事中であった。案内書。一枚岩を彫り抜いた手水場。「本堂」に近づいて。「本堂」前の「興亜観世音菩薩像」。宝冠をいただき円光をつけ、身に条帛・裳(正しくは裙)をまとい、 天衣をかけて、蓮華座の上に、ややうつむきかげんにお立ちになっています。昭和15年に造立され、現在は本堂正面の右手にありますが、旧本堂の頃は、本堂正面にありました と。五重塔型燈籠。平成9年(1997年)瀬田大塚園納 と。さらに「本堂」に近づいて。1975年(昭和50年) - 現本堂を建立 と。扁額「慈眼寺」と。「玉川八十八ケ所霊場 第三十七番霊場札所」と。昭和期に入り、川崎大師平間寺を一番寺として、 弘法大師有縁の古刹を巡る八十八ヶ所に構成されたものです。 もちろん、四国八十八ヶ所霊場巡拝を写したもので、 慈眼寺は第三十七番霊場札所になります。 第八十八番霊場の宝幢院(東京都大田区西六郷)まで、神奈川の横浜市から川崎市、東京の世田谷区、大田区、品川区を辿る巡拝路です と。「釈迦塔」は昭和54年建立。移動して。墓地側から。「掲示板」。「弘法大師一千百三十年忌報恩塔」。無縁塔。「故陸軍歩兵伍長勲八等功七級柳田行雄靈」碑。「弘法大師一千年忌報恩供養塔」(右)「法篋印塔(左)と六地蔵尊」(手前)「弘法大師一千年忌報恩塔」。「法篋印塔」。墓地を望む。「本堂」を墓地から見る。「釈迦塔」の扉にもあったこの操舵輪にも似た紋は、「輪宝」という真言宗の宗派門であることを師匠から教えていただきました。「慈眼寺」の墓地から、次に訪ねた「瀬田玉川神社」を見る。明治維新の神仏分離までは、隣の瀬田玉川神社の別当寺であった と。「寺務所」を振り返って。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.08
コメント(0)
-

二子玉川周辺を巡る(その8): 敬親寺~カトリック瀬田教会~将監山遺跡~笠付庚申塔
「玉川大師」を後にして、次に隣りにあった日蓮宗の寺を訪ねた。「日蓮宗 常住山」。「敬親寺」。世田谷区瀬田4丁目13−4。参道を進む。右手に「六角宝塔」。正面に「本堂」。右手に石仏。合掌する石仏・「常不軽菩薩尊像」。「我深く 汝等を敬ふ 敢て 軽慢せず我深敬汝等不敢軽慢常不軽菩薩品常不軽菩薩尊像「心を拝む』昔、出合う人ごとに合掌して歩く修行僧がいました。拝まれた側の人は、訳が分からず戸惑ってしまい、中には「やめないか!」と、石を投げる者まで出てきました。しかし修行僧は、「あなたの心には、仏さまになれる宝の珠(たま)があるのです。私はあなたの心に手をあわせているのです」といい、決して拝むことをやめようとしませんでした。この修行僧の名は常不軽菩薩(じょうふきょうぼさつ)。「どんな相手であれ、絶対に相手を軽んじない」ということを実践された菩薩さまだったのです。たとえ相手が自分の嫌いな人や苦手な人であっても、その姿やその行動だけでなく、相手の心を拝むように努めましよう。そして自分自身の心をも拝めるようにもなりたいものです。」「本堂」正面に到着。ガラス戸越しに内陣を見る。扁額「敬親 両親閣 五十八世 日信」と。切妻平入りというか、巨大な流造りのような建物で、向拝部分が小部屋のようになっていた。本堂の「壁」には漆喰仕上げの白波が。倒れかけている上人の墓石。この寺は「敬親玉川教会」ということから、布教のための拠点みたないなところで、参詣用の寺とは違うようであった。さらに西に向かって進む。車道と歩道の境には、丸い石を切ったものが、車止めの目的で埋め込まれていた。右折して、次の目的地の「カトリック瀬田教会」に向かって坂を上る。突き当りを右折して進むと右手に入口があった。「アリアの宣教者 フランシスコ修道院」と。マリア像であっただろうか。さらに東に進むと「カトリック 瀨田教会」の入口があった。銘板には「聖アントニオ 神学院、フランシスコ会 聖書研究所」の文字もあった。左手の銘板。「FRANCISCAN FATHERSST.ANTHONY SEMINARY」と。「カトリック 瀨田教会」掲示板。「カトリック 瀨田教会」聖堂正面。瀬田教会は1951年にフランシスコ会の神学院建築のために、シニューゼンベルグ神父によって瀬田の丘の土地が購入され、フランシスコ会聖アントニオ修道院の付属教会として発足された。世田谷区瀬田4-16-1。「シニューゼンベルグ神父」像であろうか?案内板。「聖アントニオ修道院 (旧神学院)」の中庭。中庭の「聖フランシスコ像」。「カトリック 瀨田教会」の奥の十字架。「カトリック 瀨田教会」聖堂入口の掲示板。「聖堂」の内陣。「カトリック 瀨田教会 アントニオ会館」。中庭には「将監山遺跡」柱。昭和49年に縄文土器などが出土し、昭和57年の発掘でもナイフ型石器や縄文•古墳時代の土器が多数出土しているようだ。中世の頃、雅楽の笛師:柳田将監が入定した伝承もある直径9mの塚があり一帯を”将監山(地元の人は、しょうぎやま)”と呼んでいるだようだ。「カトリック 瀨田教会」を後にして、来た道を引き返す。次の目的地の「慈眼寺」に向かって進むと、左手前方にあったのが「傘付庚申塔」。ここが「慈眼寺」の参道のようだ。笠付庚申塔 (左) と笠付庚申塔の標石と庚申塔と馬頭観世音菩薩 (右)世田谷区瀬田4丁目11−25。「傘付庚申塔」。唐破風笠付の角柱型庚申塔は元禄10年(1697)の造立。青面金剛像と三猿の図柄で、願主16人の名前と荏原郡瀬田村の銘がある。庚申塔 (左) と馬頭観世音菩薩 (右)向かって右に並ぶのは、駒型の庚申塔で摩耗が進んでいるが、青面金剛像と三猿の図柄で、造立年は享保16年(1731)とある。 その隣りは、馬頭観音で、こちらは新しく大正11年(1922)のもの。願主は中嶌忠次の銘。 この庚申塔から右に進むと、慈眼寺の山門が聳えていた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.07
コメント(0)
-

明治神宮外苑 いちょう並木へ(その5):聖徳記念絵画館
「神宮軟式球場噴水」前の開催中の「東京クリスマスマーケット 2024」の横断幕。「明治神宮外苑 いちょう並木」を後にし振り返る。そして東京都道414号四谷角筈線を北方向に歩き、「聖徳記念絵画館」への入口に到着。入口左にあった「明治神宮外苑案内図」。現在地はココ。「明治神宮外苑の舗装」案内板。「明治神宮外苑の舗装明治神宮外苑の舗装は、東京市(当時)でも大規模で本格的加熱アスファルト混合物を用いた舗装であり、1926年(大正15年)1月に完成しました。この工事は、我が国においてワービット工法を採用した最初の工事であったばかりでなく、アスファルトは国産品(秋田県豊川産)を使用し、当時の最新鋭機による機械施工が行なわれました。この舗装は長い年月の使用に耐え、左図の濃色の箇所(下の写真)が66年間(1992年改良)にわたって車道として使われてきたことは、驚嘆に値します。また、この案内板の前の舗装は当時のまま現存しており、日本における車道用アスファルト舗装としては最古のものです。「当時の工事概要 ワービット工法について(1)発注者:明治神宮造営局 粗粒度アスファルトコンクリートを(2)施工面積:59,096m2 下層に敷き、上層には富配合のアスファルト(3)施工費用:167,135円 モルタルを薄く敷均し、上下層を同時に転圧して(4)工期:1924年5月~1926年1月 仕上げる工法 (5)監督者:工学博士・藤井眞透」新宿区土木部による案内板に、ワービット工法の施工時の写真があった。案内板には、1993年に採取した舗装断面の実物が埋め込まれていた。「土木學會選奨土木遺産 2004 聖徳記念絵画館前通り」。「あるけあるけ日本ウォーキング協会は、東京オリンピック開催中の1964年(昭和39年)1 0月17日に、ここ新宿区の明治神宮外苑絵画館前から世田谷の東京五輪記念世界青少年キやンプに向けて第1回大会を開催しました。私たちは、運動発足40周年を記念して、八田一郎初代会長による機関紙の題字「あるけあるけ」を掲げ、ウォーキング運動発祥記念碑といたします。 2004年(平成16年) 10月1 /日 (社)日本ウォーキング協会」「聖徳記念絵画館」を正面から。神宮外苑の中心的な建物で、幕末から明治時代までの明治天皇の生涯の事績を描いた歴史的・文化的にも貴重な絵画を展示している。維持管理は宗教法人明治神宮の予算で賄われており、他からの援助は一切受けていないとのこと。ドーム型屋根の「聖徳記念絵画館」をズームして。・着工: 1919年(大正8年)3月5日・竣工: 1926年(大正15年)10月22日・鉄筋コンクリート2階建て。面積: 延べ4700 m2。・高さ: 約32 m(ドームの頂上部) 幅: 約112 m 奥行き: 約34 m。・設計原案: 小林正紹(公募による選定)・実施設計: 高橋貞太郎、小林政一正面に「国立競技場」。「一角獣(ユニコーン)の像」。阿吽のユニコーン像 。このモデルは麒麟であると。首の長いキリンではなくて、想像上の生き物である麒麟。そもそもは中国の伝説上の動物とのことで、幸せを呼ぶシンボルとされ、また、才能の傑出した人のことをたとえたりもされ、良いことづくしのモチーフだと。なお2対の麒麟の間にあるものは旗を立てる台で、特別な時には旗が掲揚される。この日は、日本国旗が掲揚されていた。移動して。ズームして。明治神宮外苑 いちょう並木を望む。さらにズームして。「東京クリスマスマーケット2024」の入口。アート×グリム童話を体験できる日本最大級のクリスマスマーケット本イベントは、ヨーロッパ各地で愛され続ける「クリスマスマーケット」の伝統を継承し、ドイツ・ドレスデンをモデルに2015年からスタート。今年で10周年を迎えるこの特別な年、グリム童話やヨーロッパの童話をテーマにアートの要素をふんだんに取り入れた「クリスマスピラミッド」が会場を幻想的に彩ります。クリスマスピラミッドを中心に、物語のような装飾やアートワークが施されたマーケットの中で、ヨーロッパの冬の風物詩を東京で体験できるのだと。配置案内図。入場料金。明治神宮 東京クリスマスマーケットのクリスマスピラミッド。イベントシンボルの“クリスマスピラミッド”がリニューアル!グリム童話×アートが交差する幻想的なデザイン!今回、10周年を記念して、今までのくるみ割りをモチーフとしたデザインから、ドイツやその周辺の民話を集めた童話集「グリム童話」やヨーロッパの童話を題材として、新しい「クリスマスピラミッド」を作成。日本でも、なじみの深い「眠れる森の美女」や「赤ずきんちゃん」「ブレーメンの音楽隊」といった物語がクリスマスピラミッドの中で表現されていると。移動して再び明治神宮外苑 いちょう並木を。さらにズームして。振り返って「聖徳記念絵画館」のドーム型屋根を再びズームして。地階と主階の二階構造。主階は、地上二階の展示フロアを指し、中央に大理石張りの大広間があり東西をこの広間で区分し、東側に日本画、西側に洋画を展示しております。中央大広間天井ドームは、最高部で床上27.5m、鉄筋コンクリート内側に金網張りモルタルを施し、ブラスター塗り及び石膏レリーフを取付けドーム部分を淡青色に、その下のレリーフ部分を淡黄褐色に着色している。画室は、採光のためガラス天井を設け、欅材以外の部分は、ブラスター塗りとし、日本画室は淡黄褐色、西洋画室は、淡青色で中央ドームの色彩と同じ着色です。主階へは、正面大階段を上り表広間から中央大広間に至り、その先に裏広間がある。地階は、地上一階のことで、事務所・絵画館学園用として使用しているフロア。「樺太国境画定標石」「樺太国境画定標石時 明治三十九年六月~四十年十月所 樺太日露境界明治三十七、八年の日露戦役の講和条約でカラフトの北緯五十度以南は、日本の領土となりました。その境界を標示するため、日露両国委員は、明治四十年九月四基の天測標と十七基の小標石を建てて境界を確定しました。この境界標石は、外苑創設に際し、明治時代の一つの記念物として、樺太庁が之を模造し外苑に寄贈したものです。当時苑内北方隅の樹間に在りましたガ、この度、全国樺太連盟よりの、これが顕影周知方の篤い要望に応えて、絵画館前の現地に移し整備配置しました。日本側の菊の紋章の背面には露国のの紋章が刻んであります。又、聖徳記念絵画館の壁画「樺太国境画定」(安田稔画)には、両国委員が境界標を建設する光景を史実に基づいて描いた絵画が展示されております。昭和五十四年六月二日 明治神宮外苑」「聖徳記念絵画館」の壁画「樺太国境画定」(安田稔画)は、両国委員が境界標を建設する光景を史実に基づいて描いた絵画であると。再び「聖徳記念絵画館」を振り返って。右手には案内板が2枚。石碑そしてその後ろには松が。「御鷹の松」碑澁澤榮一書 時年八十又七「此の松昔は霞乃松とて名高く徳川三代将軍放鷹のをり樹下に憩ひて鷹の名をそのまゝ遊女の松と呼ばれしが又御鷹の松とも稱するに至れり當時の古松は枯れてこれは二代目なりと云ふ元は北方五十間の地境妙寺境内に在りしを大正八年此処に移植したり 大正十五年七月 明治神宮奉賛會」「お鷹の松(おたかのまつ)大正7年(一九一八)明治神宮外苑競技場(現・国立霞ヶ丘競技場)造成のために買上げた霞岳町の敷地内に境妙寺という古寺があった。昔、徳川三代将軍家光(一六○三〜一六五一)が鷹狩の途中この寺に休息していたところ、江戸城から飛び去っていた、「遊女」と名づけた愛鷹が飛んで来て、庭前の松の枝に止まったので家光は大へん喜び、この松をその鷹の名をとって「遊女の松」と名づけたと伝えられる。後の世の人々が「お鷹の松」或いは地名をとって「霞の松」とも呼んだ。碑文にある二代目の松(樹齢推定二○○年 高さ四メートル)は昭和三十九年、東京オリンピック開催のための拡張工事の際に取り去られ、碑石は競技場代々木門内に移設されていたが、このたび現在地に移し、新たにこれに黒松を配したものである。 昭和五十四年十月 明治神宮外苑」「国立競技場」からの入口にあった「聖徳記念絵画館」案内板。近代日本のあけぼの、壁画に見る幕末明治の歴史徳川幕府を改め、日本史上空前の、大改革が断行された、明治維新。西欧の諸国が300年を費やした近代化を、明治天皇を中心に、僅か40年ばかりで成しとげた、輝かしき明治の時代、世界に誇る、館内展示の80面の名画か語る日本近代化への飛曜の姿、歴史事件の数々。そして、引き返して再び「聖徳記念絵画館」を。「木名 飛登つばた古" 阪谷芳郎書」と刻まれた石碑。「此の樹は古くより青山六道能辻に在りて俗尓六道木又ナンジヤモンジヤとも呼べり吾邦尓稀奈る毛の登て植物學者乃注目春類所とな里舊時の位置をそ能まゝ耳維持し来り大正十三年天然記念物として指定せられたる毛能那李(ものなり)大正十五年七月 明治神宮奉賛會 右原樹は昭和八年枯死したるによ里嘗て其樹より 根分けして育てたるを昭和九年十一月植ゑ継ぐ」「ひとつばたご(なんじゃもんじゃ)この木は、和名「ヒトツタバコ」俗名「ナンジャモンジャ」と呼ばれるたいへん珍しい木で、五月初旬の満開時には、白い清楚な花が、まるで雪を被ったように美しく咲き誇ります。幕末(一八六〇年代)の頃、ここから南へ約四〇〇メートル行った六道の辻という場所(現在のテニスクラブ付近)の近くに「六道木」と呼ばれる珍しい名木(なんじゃもんじゃ)がありました。明治三十六年(一九〇三)、樹齢百数十年と言われたこの木の価値に注目した白井光太郎博士(元帝国大学教授)が、国に対して、この木の保護を願い出た結果、大正十三年(一九二四)十二月、天然記念物の指定を受けましたが、昭和八年(一九三三)、遂に枯死しました。その後、白井博上が根接ぎ法により得たと伝えられる「二代目六道木」を昭和五十三年(一九七八)に、ここ絵画館前に植樹し、多くの方にご覧いただいておりましたが、平成ニ十六年(二〇一四)、その木も寿命を迎え枯死しました。そして、平成二十八年(二〇一六)、明治神宮外苑創建九十年を記念し、二代目六道木の実生を苑内で育てた「三代目六道木」をここに移し植えています。初代の勇姿は、今も聖徳記念絵画館の洋画七十四番「凱旋観兵式」(小林万吾画)でご覧いただけます。平成ニ十八年三月吉日 明治神宮外苑」「ひとつばたご(なんじゃもんじゃ)」。「初代 なんじゃもんじゃ」の写真。洋画七十四番『凱旋観兵式』小林万吾「ニ代目 なんじゃもんじゃ」。「なんじゃもんじゃ」の花。そしてこの日の目的地の新宿駅に向けて、JR信濃町駅に向けて歩く。「信濃町歩道橋」から、「青山1丁目」方向を見る。ズームして。中央左の高層ビルは「パークアクシス青山一丁目タワー」。「つば九郎(つばくろう)」つば九郎は、日本プロ野球・東京ヤクルトスワローズのマスコットキャラクター。背番号2896。語呂合わせでの「ツバクロウ」である。チーム名にもあるように、ツバメをモチーフとしたキャラクター。名前の由来は、ツバメの古称「つばくろ」と、「鍔迫り合いに強く、苦労(九郎)しながら接戦をものにする」という意味がこめられている。ただし、つば九郎本人はそのことを知らず、「大人の事情」とあまり気にしてはいない。なお、本来ツバメは渡り鳥だが、つば九郎は、「ツバメ界の最先端をゆく進化したツバメ」とされ、日本の四季変化に対応することが可能である。反面、恋したツバメと冬には別れてしまうので恋が長続きせず、彼女いない歴10958日という状況である とウィキペディアより。そして新宿駅西口へ。東京都港区白金台に所在する松岡美術館(まつおかびじゅつかん)の保有する絵画が紹介されていた。「「若い女」(写真) マリーローランサン」。「若い女」(写真) マリーローランサンネットから。「リュシアン・ドーデの肖像(写真) ピエール=オーギュスト・ルノアール」。「リュシアン・ドーデの肖像(写真) ピエール=オーギュスト・ルノアール」。ネットから。「若い女の胸像(マーサ嬢)(写真) アメデオ・モディリアーニ」。ネットから。「三彩馬(写真) 唐時代」。「三彩馬(写真) 唐時代」。ネットから。そして、道に迷いながらも、元同僚と合流して「居酒屋 一兆 新宿本店」に到着したのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・
2024.12.06
コメント(1)
-

二子玉川周辺を巡る(その7):玉川大師(2/2)
「玉川大師」の「地下仏遍照金剛殿」を後にして、境内右の仏像群を訪ねた。この像の名は?「為岡田善次郎菩提也」と。どのような人物か?像の足元には動物の姿が。廻り込んで。「常香炉」。廻り込んで。「不動明王」(右)と「愛染明王座像」(左)。「不動明王像不動明王像は、忿怒の相と言う顔をしている。右手に剣、左手に羂索(けんじゃく)という縄を持ち、背中に火炎光背を背負った姿が一般的。忿怒の相は、悪を仏の道に導くという決意の表れで、火炎で煩悩を焼き払い、右手の剣は人々の煩悩を断ち切る、左手の縄は煩悩から抜け出せない人を吊り上げてでも救い出す。個人的には可愛いい息子の為に悪い道に行ったら叱る親心の様なイメージ」。「愛染明王座像」。6本の腕をもち、獅子の冠をかぶる愛染明王(あいぜんみょうおう)の像。めらめらと燃えるように逆立つ髪の毛、眉を吊り上げてにらみつける目、牙をみせて大きく開けた口。全身で怒りを表わす姿に、誰もが特別な力を感じる坐像。愛染明王は、愛の仏として知られており、男女関係をつかさどるイメージが強くあるが、ときには敵対する者を呪(のろ)う一方で、子孫繁栄を約束するなど、さまざまな祈願をかなえると信じられていた。手にしている弓矢は祈願の成就の象徴。巨大な「弘法大師像」。移動してお顔を。「玉川の秘佛の大悲 みにうけて 大師とともに生きる よろこび」。「弘法大師髙野山初尋入記」碑。「弘法大師髙野山初尋入記弘法大師嵯峨天皇より弘仁七年七月八日髙野山を賜り開創す 大師初めて南山に尋ね入し砌山中に黒白ニ匹の紀州犬を従えし一人の狩人あり 親しく大師の後先となりて道案内す遂に山上平原の幽地に至る 名づけて髙野という 狩人忽然と姿を消す これ髙野山地主天王丹生津姫命の春属 狩場大明神にほかならざるなり」「鳥獣供養塔」。弘法大師が高野山に初めて尋ね入った際に、山上に案内した狩場明神の連れていた二匹の犬は紀州犬だったとして、その紀州犬を供養する塚。首輪をした二匹の犬が浮き彫りされていた。「六地蔵」。緑の中に多くの石仏が並ぶ。「水子地蔵尊」。近づいて。「水子地蔵尊」。「有縁無縁地蔵尊」。近づいて。「ぼけ封じ觀世音菩薩」。「ぼけ封じ觀世音菩薩」。「ぼけ封じ関東三十三観音霊場 第十番札所 玉川大師」碑。「ぼけ封じ觀世音菩薩」を正面から。近づいて。深く!!お参りいたしました。「安産子育地蔵尊」。「安産子育」。「地蔵尊」。近づいて。さらに。「手水鉢」。再び「玉川大師」の「本堂」を振り返って。入口まで戻り。ここにも鬼の姿の如き仏の姿が。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.06
コメント(0)
-

二子玉川周辺を巡る(その6):玉川大師(1/2)
そして「玉川大師」前に到着。「地下佛殿 玉川大師」。正面に「玉川大師」の「本殿」。世田谷区瀬田4丁目13−3。寺号標石「寶泉山 玉眞密院(ほうせんざんぎょくしんみついん)」。真言宗智山派の寺院。創建は大正時代で、龍海大和尚により大師堂が、その後6年の歳月をかけて、昭和9年(1934年)に竜海阿闍梨が地下仏殿を建立。地下仏殿は地下5メートルの深さの場所に、長さ100メートルにも及ぶ総鉄筋コンクリート造りの拝殿であり、日本でも有数の地下霊場。裏側には「為弘法大師鴻恩報謝 兒童 招福開運 也大寺標奉納開眼施主株式会社サンリオ 社長昭和六十二年十月二十一日 山主」と。石垣の如きものは?「奉納之施主 松岡康栄 松岡セツ子」と。手水場。「本堂」の「唐破風」。「唐破風懸魚」。「奥之院 地下佛殿」と。この石仏は?インド風?な石仏。反対側にも向かい合うように。「本堂」の周り歩廊より、後ほど訪ねた石仏群を見下ろす。御朱印 案内。1000円と高価!!各種願札 これも2000円と。「地下遍照金剛殿玉川大師略縁起玉川大師は高野山奥之院の清流「玉川」に縁み 此の地に開山龍海大和尚 大正十四年大師堂建立 昭和三年より六年の歳月をかけ地下佛殿完成。地下佛殿は御本尊弘法大師の大慈悲を具現する。遍照金剛殿にして本堂より境内一円に及ぶ地下の参道は巨大な大日如来の胎内、胎蔵界マンダラを かたどっている。特に奥之院には四國八十八ヶ所霊場及び西國三十三ヶ所霊場を悉く請来され四國遍路と西國巡礼さながらに順拝修行の結縁が授かる道場である。石佛、大理石、御影石像、三百数尊体安置内拝は九時より五時迄 當山」「インド伝来 長寿の銅羅(ドラ)」「長寿の銅羅鐘というのは音だけでなくの鐘の響きが重要です。鐘の響きこそお釈迦様のご説法のお声と言われています。お釈迦様のご長命のように延々と続きますように。手を合わせ、願い事をし、一突き100円~お納めください。」本堂内に入る。祭壇に近づいて。800円を支払い、地下佛殿を見学した。見学に当たり、事前に案内書を読むようにと手渡された。ここが、地下仏殿へ降りる階段。様々な仏像に囲まれて。そして、急な階段を下り、暗黒の世界に。階段を下りて右を見たらすでにこの状態……真っ暗……「一寸先は闇」って言うけど、1㎜先も見えない。足元も天井も両壁も、何も見えない。ただ左右にある壁に添える手と、地面に付く足裏の感覚だけ。まったく光がないから目が慣れるなんてことは絶対にない世界は初めての体験。しかし「地下佛殿」は写真撮影禁止なのであった。地下仏殿は地下5mの深さの場所に、長さ100mにも及ぶ総鉄筋コンクリート造りの拝殿であり、四国88箇所と西国33番霊場のお大師さま・観音様が鎮座しており、日本でも有数の地下霊場と。お遍路の方法は、「南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)」と心の中で唱えながら地下参道を歩き、自分の数え年の番号の石仏を拝んでくるというシンプルなもの。そうすることで、災いから身を守ってくれるのだと。仏の胎内をかたどっているという参道は、ところどころ傾斜があり、暗闇が続いた。ひたすら真っ暗なので恐怖を感じたが、声を押し殺し心を無にして進むことで、煩悩が放たれるといわれているのであった。暗い道を抜けると大殿堂が現れ、約300体の石仏に圧倒された。これらの石仏を拝むと、四国88カ所と西国33所を巡ったのと同じご利益があるのだと。以下の写真は、全てネットから、見学順は記憶にないため順不同。「信條 寶泉山 玉眞院 玉川大師一つ ご本尊さまに帰依し 縁起の真理をさとりこの身が御本尊さまと一つのいのちである ゆるざない安心を確立しよう一つ 正しい知恵によって マンダラ世界に生さ真実の自己にめざめて 弘法大師のおしえを 現代にひろめよう 一つ こころと ことばと おこないを整え 共につくしあう和合の生活を実現しよう誓い一つ 大いなる力にめざめ 尊いいのちを生かします一つ 迷わず 怖れず 力をつくして励みます一つ つくしあいの家庭と 社会をきずきます三帰礼文人身受け難し今既に受く。仏法聞き難し、今既にに聞く。此の身今生に度せずんば 更に何れの生に於いてか この身を度せん。大衆諸共に 至心に三宝に帰依し奉る。 自ら仏に帰依し奉る。当に願わくは衆生と共に 大道を体解して 無上意を発さん。 自ら法に帰依し奉る 当に願わくは衆生共に 深く経蔵に入りて 知恵海の如くならん。自ら僧に帰依し奉る。当に願わくは衆生とともに 大衆を統理して一切無礙ならん。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.05
コメント(0)
-

明治神宮外苑 いちょう並木へ(その4):全国工芸職人展
「全国工芸職人展」を訪ねた。「全国工芸職人展」(旧・森のやきものフェア)は毎年、いちょうが「黄葉(こうよう)」する季節に行われる物産フェア。多彩な工芸品が展示販売されていた。毎年11月中旬から12月上旬まで、青山通りから聖徳記念絵画館に向かって約300メートル続く」146本のいちょう並木が黄金色に染まる。落ち葉で埋め尽くされた並木道はまさに黄金色の「いちょうのトンネル」。このいちょう並木と聖徳記念絵画館の間の広場に特産品の販売店や飲食店が出店しているのであった。明治神宮外苑 いちょう並木の右奥に入口があった。「2024年 第11回 全国工芸職人展」日時:11月21日(木)~12月8日(日) 10:00~17:00会場:【明治神宮外苑】イチョウ並木隣接の権田原会場入場料:無料会場案内図。近づいて。キッチンカー、テントが並ぶ。養老乃瀧グループ。「ふくしま糀味ラーメン」。さらに進む。盆栽。まゆ工芸。さかたや・石焼き芋。五平餅。狭山茶。さらに奥へ鮎塩焼。大道芸。奥にあったのが「御観兵榎について」案内板。「御観兵榎についてこの外苑の敷地は、もと陸軍の青山練兵場で、明治天皇の御台臨のもとにしばしば観兵式が行われ、なかでも明治二十三年(一八九〇)二月十一日の憲法発布観兵式や、明治三十九年(一九〇六)四月三十日の日露戦役凱旋観兵式などは、特に盛大でありました。聖徳記念絵画館の壁画「凱旋観兵式」(小林万吾画)にその時の様子が描かれており、当時の盛儀が偲ばれます。明治天皇がご観兵される時は、いつもこの榎の西前方に御座所が設けられたので、この榎 を「御観兵榎」と命名し永く保存しておりましたが、平成七年(一九九五)九月十七日老令(樹令二百余年)の為台風十二号余波の強風により倒木しました。遺木の一部は聖徳記念絵画館内に名木「ひとつばたご」の遺木と共に保存されております。平成八年(一九九六)一月、初代御観兵榎の自然実生木(推定樹令六十年)を苑内より移植し、「二代目御観兵榎」として植え継ぎました。 平成八年一月吉日 明治神宮外苑「初代 御観兵榎」榎 にれ科えのき属、樹齢二百余年と推定される。幹廻り、二・二メートル 高さ、 九メートル 枝張り、十六メートル碑石 石材は伊豫(愛媛県)青石、天然石題字 東郷平八郎 書 明治三十八年日本海海戦においてロシアバルチック艦隊を壊滅させた、 当時の連合艦隊司令長官 東郷神社の祭神前方左に「御観兵榎」碑。「御観兵榎 伯爵東郷平八郎書明治天皇には明治二十年青山練兵所設置以来恒例の觀兵式又は憲法發布及び凱旋観兵式に親臨あらせ・・し節に此の榎の下 御馬を駐めさせ・・・大正十五年七月明治神宮奉賛會」黄葉と紅葉のコラボ。近づいて。オカリナ 生演奏中。オカリナ製作&演奏 白井進👈️リンク水引で造ったかんざし類。大道芸 バルーン(風船芸)。草木染め山口・伝統工芸品、着物、帯。そして出口に向かう。出口。再び、明治神宮外苑 いちょう並木をカメラに。和服姿で記念撮影するカップル。お顔から外国人のようであったが。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.05
コメント(0)
-
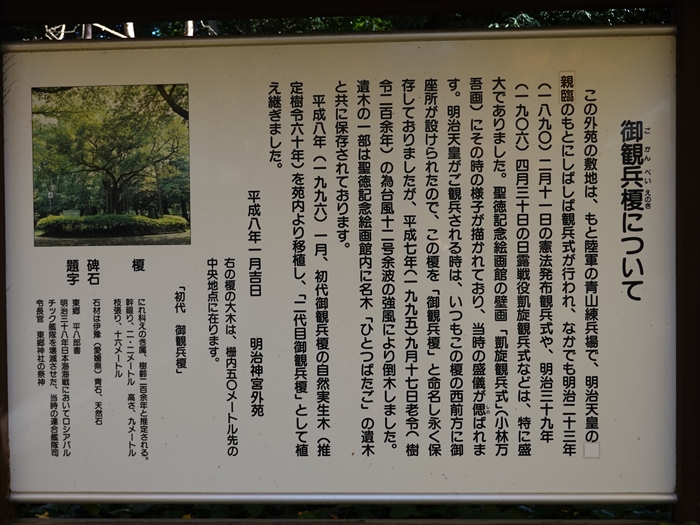
明治神宮外苑 いちょう並木へ(その3):明治神宮外苑 いちょう並木(2/2)
歩道右側にあったのが「御観兵榎についてこの外苑の敷地は、もと陸軍の青山練兵場で、明治天皇 の御台臨のもとにしばしば観兵式が行われ、なかでも明治二十三年(一八九〇)二月十一日の憲法発布観兵式や、明治三十九年(一九〇六)四月三十日の日露戦役凱旋観兵式などは、特に盛大でありました。聖徳記念絵画館の壁画「凱旋観兵式」(小林万吾画)にその時の様子が描かれており、当時の盛儀が偲ばれます。明治天皇がご観兵される時は、いつもこの榎の西前方に御座所が設けられたので、この榎 を「御観兵榎」と命名し永く保存しておりましたが、平成七年(一九九五)九月十七日老令(樹令二百余年)の為台風十二号余波の強風により倒木しました。遺木の一部は聖徳記念絵画館内に名木「ひとつばたご」の遺木と共に保存されております。平成八年(一九九六)一月、初代御観兵榎の自然実生木(推定樹令六十年)を苑内より移植し、「二代目御観兵榎」として植え継ぎました。 平成八年一月吉日 明治神宮外苑 右の榎の大木は、柵内五〇メートル先の中央地点に在ります。「初代 御観兵榎」榎 にれ科えのき属、樹齢二百余年と推定される。幹廻り、二・二メートル 高さ、九メートル 枝張り、十六メートル碑石 石材は伊豫(愛媛県)青石、天然石題字 東郷平八郎 書 明治三十八年日本海海戦においてロシアバルチック艦隊を壊滅させた、当時の連合艦隊 司令長官 東郷神社の祭神」「二代 御観兵榎」。「左前方に眺望む円屋根・白亜・石造の建物聖徳記念 絵画館THA MEIJI MEMORIAL PICTURE GALLERY近代日本のあけぼの大壁画にみる幕末・明治の歴史開館時間:10:00~16:30(最終入館16:00)休館日/水曜日(祝日の場合は直後の平日休館)施設維持協力金 500円 入場の際にお納め下さい。徳川幕府を改め、日本史上空前の大改革・明治維新が断行され、西欧の諸国が300年を要した国家の近代化を、僅か40年ばかりで成しとげた輝かしき明治の時代。当代一流画家の筆に成る館内展示の80面の大璧画が、明治天皇を中心に、わが国近代化へと飛躍の姿・歴史事件の数々を静かに語りかけてくれます。生きた明治史の教室といえましよう。」「聖徳記念 絵画館」。明治天皇と昭憲皇太后の生涯の事績を伝える80点の絵画を展示する、神宮外苑のシンボル。ギャラリーは2つのエリアに分けられ、東側には日本画、西側には洋画を展示。縦約3m、横約2.7mの大壁画が、画題の年代順に展示されており、当時の出来事を時代を追って見ることができる。明治天皇の生涯での主要な出来事が描き出されており、一流画家による優れた芸術作品でありつつ、政治、文化、風俗の貴重な歴史史料でもある。T字路・神宮軟式球場噴水前の歩道から「明治神宮外苑 いちょう並木」をカメラで撮影する多くの人々の姿が。私もその群衆に混じって。車の姿が少ない時に、懸命にシャッターを押したのであった。そして振り返って「神宮軟式球場噴水」越しに「聖徳記念 絵画館」を見る。「神宮外苑 聖徳記念絵画館前・総合球技場」では、2024年11月19日(火)〜12月25日(水)の期間で「東京クリスマスマーケット2024 in 神宮外苑」👈️リンク が開催されていた。「聖徳記念 絵画館」をズームして。そして先程と反対側の並木道を、「青山2丁目交差点」に向かって進む。横断歩道の信号待ち時にシャッターを押す。「神宮軟式球場噴水」前のカメラ撮影の人々の姿を振り返って。そして横断歩道を渡り、イチョウ並木の下を進む。車の来ない時を待って、反対側の並木の姿をカメラで追う。地面に近い位置から反対側の並木を。絵画館方向を振り返って。「青山2丁目交差点」方向を。「秩父宮ラグビー場」入口から「明治神宮外苑 いちょう並木」を振り返って。ズームして。さらに。正面に見えるのが「秩父宮ラグビー場」。再び「明治神宮外苑 いちょう並木」まで引き返して。「絵画館」方向を。再び「青山2丁目交差点」に向かって。「青山2丁目交差点」手前まで戻り、「明治神宮外苑 いちょう並木」を振り返る。「青山2丁目交差点」角・西側の「江戸城枡形門(江戸城石垣移築)」。「外苑いちょう並木」入口にあるこの石塁は、かつて江戸城を支えていた石垣で、旧国立競技場ができた1958年以前にあった明治神宮外苑競技場のもの。そして神宮外苑造営の際に建設されたものであるとのこと。関東大震災後のバラック建設の指揮官であり、小学校の鉄筋コンクリート化を推進した建築構造家・佐野利器が計画・建設したとのこと。移動して。「明治神宮外苑 いちょう並木」が雲一つない青空を背景に。ズームして。横断歩道を渡りながら。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.04
コメント(0)
-

二子玉川周辺を巡る(その5):瀬田夕日坂~東急田園都市線・誇線橋~瀬田アートトンネル
「行善寺」を後にして、寺の北側の路を方向に進み長い石段を下る。右折して東急田園都市線に沿って坂道を北に向かって進む。横断歩道の右手にあったのが「瀬田夕日坂」。世田谷区瀬田1丁目29番と瀬田2丁目12番の境界を西に下る短い坂道。行善寺坂の坂上を少し西に行ったところにあった。ここ、坂下はちょうど東急田園都市線がトンネルから外に出るあたりで、見晴らしの良い場所。「瀬田夕日坂」と。この「瀬田夕日坂」という坂名は、近年、瀬田地域の住民によって名付けられたもののようだ。西向きに下る坂なので、おそらく夕日が美しく見えることから名付けられたのだろう。このプレーの制作も「多摩美術大学工作センター」なのであろう。東急田園都市線の誇線橋(こせんきょう)を渡る。用賀駅方面を見る。二子玉川駅方向を見る。東急田園都市線の誇線橋の階段を下る。右折し、急な坂道をさらに下る。さらに右に折れて進むと前方にトンネルが姿を現した。「瀬田アートトンネル」。国道246号線の下を横断する瀬田ずい道を改築し、照明とモザイク壁画が美しいアートトンネルとして再生した。暗い・臭い・恐いなどの悪いイメージがあるトンネルの概念を一変する見事な芸術作品である と。「瀬田アートトンネル」。美しいアーチ形状のトンネルと明るい照明が、夕暮れにも関わらずトンネル内を明るく照らし出していた。トンネルの上は、国道246号「玉川通り」。世田谷区瀬田32。銘板に近づいて。「瀬田アートトンネル」。トンネル内の両方の壁面には、淡い色彩のモザイク壁画が描かれていた。この壁画が、照明に映えて美しいのであった。ズームして。モザイク壁画は、地元の美術大学のボランティアによって制作されたのだと。その壁画を明るくソフトなライティングがやさしく包むのであった。トンネル内を進みながら、モザイク壁画をカメラで追う。そして全長48.5mの「瀬田アートトンネル」を通過し振り返る。さらに次の目的地の「玉川大師」に向かって進む。「世田谷区瀬田四丁目1」と。右手前方に「玉川大師」の看板が現れた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.04
コメント(0)
-

明治神宮外苑 いちょう並木へ(その2):明治神宮外苑 いちょう並木(1/2)
「青山2丁目」交差点に到着。「青山二丁目」交差点からの「明治神宮外苑 いちょう並木」を見る。明治神宮外苑は、明治天皇と昭憲皇太后のご遺徳を永く後世に伝えるために、全国国民からの寄付金と献木、青年団による勤労奉仕により、文化・スポーツの普及の拠点として、大正15年(1926)10月22日に明治神宮に奉献された。青山通り口から外苑中央広場円周道路に至る約300mのこのいちょう並木は、11月中旬ごろより黄葉が始まり11月下旬になると黄金色に輝くのである。「明治神宮外苑 いちょう並木」の先、正面に「聖徳記念絵画館」。4列146本のいちょう並木であると。ズームして。「青山2丁目交差点」の」横断歩道を渡り、「明治神宮外苑 いちょう並木」方向に進む。右手奥の1.5mほどの高さの石垣は「江戸城枡形門(江戸城石垣移築)」とのこと。石垣越しにズームして。「明治神宮外苑之記」碑。「明治神宮外苑之記明治神宮奉賛會總裁元帥陸軍大将大勲位功二級載仁親王篆額明治四十五年七月明治天皇遽に不予にましまし、尋で大漸に渡らせらるヽや、上下憂懼措く所を知らず、二重橋外日夜を連ね市民の沙上に拝跪して御平癒を祈る者万を以て数ふ、其の三十日遂に崩御あらせらるヽに及び、億兆悲慟天地為に黯澹たり、八月の初め東京市民は葵藿向日の至誠を披瀝し、山陵の地を帝都に卜せられんことを内願す、其の桃山に決定せらるヽに及び、更に神宮の奉祀を懇請し、帝国議会も亦其の議を決せり、是に於て政府は神社奉祀調査会を置き、委員を挙げて審議せしめ、神宮鎮座の地を郊外代々木に相せり、大正三年四月昭憲皇太后崩御あらせらるヽに及び、合祀の事を治定あらせられ、明治神宮造営局を置き社殿を営ませ給ふ、然れども国民孺慕の心は之を以て足れりとせず、明治神宮奉賛会を興し、神宮外苑を設け、以て記念の事業を永遠に遺さんとす、事 天聴に達し畏くも御内帑金三十万円を賜ふ、天下翕然として貲を献じ、遠く海外に在る者亦争ひて之を賛く、是に於て衆議旧青山練兵場を以て外苑の地に擬定す、蓋し此の地は大帝屡観兵の式を行はせられ、彼の憲法発布の慶典及び日露戦役の凱旋に当りて其の儀特に厳粛を極めさせられたる遺躅を留め、且つ大葬に際しては亦実に葬場殿を置き給ひし所なるを以てなり、奉賛会は先つ政府より此の地の提供を受け、進みて隣接の地を購ひ合せて十五万五千坪を得たり、乃ち工事を造営局に託して、地域を修治し、林泉を布置し、葬場殿の故址は樹を植ゑて之を標す、其の前方に聖徳記念絵画館を建て、大帝並に皇太后御一代の重要なる御事蹟に関する画幀八十を館中に掲ぐ、多くは御事蹟に縁故ある縉紳若くは公私団体等の献納に係り、当代名家の手に成れるものなり、苑の東辺に憲法記念館を置く、館は原と赤坂仮皇居に在り、大帝親臨して帝国憲法及び皇室典範制定の議を重ね給ひし所にして、公爵伊藤博文に賜ひしものなり、苑の西辺に競技場・野球場・相撲場等を設く、起工以来十閲年、其の間総裁伏見宮貞愛親王殿下薨去あらせられ、閑院宮載仁親王殿下後を承けて此の事業を完くし給へり、而して国民上下洪恩の万一に報い奉らんとし、至情の溢るヽ所或は労役に服し、或は貲財を献じ、但後れんことを是れ懼れ、人をして遠く仁徳天皇の古を想見せしむるものあり、嗚呼大帝の盛徳大業は誰か仰ぎ奉らざらん、皇太后の淑範懿行は誰か慕ひ奉らざらん、今此の苑の設け一に仰慕の微意を寓せり、若し夫れ今後来りて神宮を拝するもの、内苑の崇高森厳なるには俯仰の間粛然として威霊の尊きを感じ、外苑の曠遠開豁なるには優游の中穆然として恩徳の深きを思ふものあらん、内外両苑相須ちて神域の規模是れ備はり、神人相和して国運愈隆昌なるを致すに至らん、玆に外苑工事全く唆り、之を神宮に奉献するに当り、事の顛末を略叙して後人に告ぐと云爾 大正十五年十月 明治神宮奉賛会会長正二位勲一等公爵 徳川家達撰」 「明治神宮外苑の記石碑の題字 「明治神宮外苑之記」 明治神宮奉会 総裁 閑院宮載仁親王殿下の篆書(てんしょ)撰文 明治神宮奉賢会 会長 徳川家達石材 東北仙台産の板岩 高・地表四メートル 幅・一、八メートル 厚・〇、三六メートル碑文の大意明治四十五年(一九一ニ)七月三十日に、明治天皇(第一ニニ代の天皇・今の天皇の高祖父)、大正三年(一九一四)四月十一日には、昭憲皇太后(明治天皇の皇后)がお亡くなりになりました。これを伝え聞いた国民の間から、御二方の御神霊をお祀りして、御遺徳を永遠に追慕し、敬仰申し上げたいという機運が高まり、その真心が実って、大正九年(一九二〇)十一月一日、代々木の地に、明治神宮の御創建となったのであります。明治の時代は、日本の歴史を通じて、政治・経済・文化・スポーツ等の各方面において、驚くべき躍進を遂け、近代国家としての基盤が確立されましたが、その原動力となられた天皇の偉大な御事蹟と御聖徳の数々を、永くに伝えたいものと、明治神宮外苑の造営が進められることになりました。これがため、明治神宮奉賛会が設けられ、天皇が御在世中、しはしば陸軍観兵式を行わせられ、又、御葬儀がとり行われた旧青山練兵場の現在地に、皇室の御下賜金をはしめとして、ひろく全国民の献金と、真心のこもった労働奉仕により、十余年の年月をかけて、大正十五年(一九ニ六)十月に、明治神宮外苑は完成しました。苑内には、天皇・皇后御ニ方の御一代の御事蹟を、有名画家が描いた八十枚の大壁画ガ揚げられている白亜の殿堂、聖徳記念絵画館を中心に、野球場、競技場その他の多くの優れた運動施設が設けられ、御仁徳をお偲びしつつ、青少年の心身鍛練の場として、或は遊歩を楽しむ人々の憩いの苑として、崇高森厳の気漲る(みなぎる)内苑と相俟(ま)って造成されたもので、永く後世に残されるものであります。外苑造成工事全く成り、奉質会より明治神宮に奉献するに当り、事情の概要を記し、後の世の人々に伝えるものであります。 大正十五年十月 明治神宮奉質会 会長 徳川家達」澄み渡る青空が背景に広がり、イチョウの黄色い葉の鮮やかさを引き立てていた。この色のコントラストは、秋の澄んだ空気感を感じさせるのであった。イチョウの葉が光を受けて輝き、まるで金色のカーテンが円錐状に広がっているような印象。葉の密度が高く、ボリューム感がたっぷり。右手のイチョウの樹はこれからが本番。「銀杏並木いちょう(銀杏・公孫樹)銀杏は、現存する最も古い前世界の植物の一つです。地質学上中生ジュラ紀(一億五千万年前、巨大な恐竜が棲息していた時代)に地球上にひろく分布し、生育していた樹種です。従って、その化石の発見は極地より南北両半球、中国・日本にまで及んでおります。氷河期の到来により、多くの地方では、銀杏樹は絶滅しましたが、温暖な気候を保ち得た中国では死滅を免れ、生育を続けて現在に至っております。日本の銀杏は、この中国より渡来した樹種で、現在では街路樹・防火樹・庭木としてひろく植えられてあり、「東京都の木」ともなっております。現在では東南アジア以外ではほとんど植えられておりません。並木の総本数は一四六本(雄木四四本・雌木一〇ニ本)四並列の銀杏の大木が作り出した、世界に誇り得る銀杏並木の景観。これを通し、正面に白亜の絵画館を望む人工自然美の素晴らしさ。若葉・青葉・黄葉・裸木と四季折々の美しさ。長年にわたる管理、手入れの良さが見事な樹形を作り出しております。この、明治神宮外苑は大正十五年(一九ニ六)十月ニ十に日の創建でありますが、その苑地造成に当たり、青山通り正面からの直線主要道路は、左右歩道の両側に植樹帯を取り、銀杏樹をもって四条の並木を造成することになりました。これは、銀杏樹が、樹姿端正・樹高よろしく・緑量も豊富・気品高く・公害にも強く、威厳を保ちつつ年間を通しての来苑者に好景観を呈示し、外苑の広幅員街路の並木として最適なものとの考えによるものです。この外苑の銀杏樹か、この世に実生えたのは、造園界の泰斗・折下吉延博士(外苑造成時の庭園主任技師・昭和四十一年ハ十六歳で没)が、新宿御苑に奉職中の明治四十一年(一九〇ハ)新宿御苑在来木の、銀杏樹から銀杏を採集し、これを種子として代々木の宮内省南豊島御料地内(現在の明治神宮内苑)の苗圃に蒔いたことによります。その後、苗圃の木々はすくすくと成長し、その数一六〇〇本にもなりました。外苑造苑に当たり、この銀杏樹を採用することとなり、既に樹高六メートル内外に成長していた、これら多数の中より候補樹を選抜し、更に並木として適格になるよう、年々樹形を整えてきたものを、大正十ニ年(一九一三)に植栽したものです。直路四条の並木と、途中西折して女子学習院正門(現秩父宮ラグビー場)に至るニ条の並木も同時に植えられております。最高ニ十四メートル・目通り周りニメートル八十センチ、最低十七メートル目通り周り一メートル八十センチのものを、樹高順に青山口より降り勾配に従って植えられております。絵画館を眺む見事な遠近法の活用です。この銀杏が、苗圃で実生えてより実に八十有余年、外苑に植栽されてより早や七十年、このように雄大に・見事な樹形を保ちつつ成長しております。銀杏樹は植生の環境、手入れが適当であれば、その成長量がいかに偉大であるかを、如実に物語っております。樹木の運命は、その立地の適不適によって決められるものでしようが、よき所で、よく育てられ、よき場所に植えられた樹木ほど幸運なものはないでしよう。同じ時期に、同し苗圃で育てられてきた、これら多くの兄弟木は、世にも希なる幸福な樹木と言えましよう。今後幾百年、これら兄弟木の銀杏は生長に生長を続けて老大成し、その偉大なる勇姿を発揮し、外苑々地と融和し、我々に見事な人工自然美を楽しませてくれることでしょう。 平成御大礼の日 之を建つ 平成二年十一月十一日 明治神宮外苑」「明治神宮外苑案内図」。近づいて。「これからもずっと、四列のいちょう並木を守ります今と変わらず、お楽しみいたたくために、ルール・マナーを守りましよう。*以下のような行為はご遠慮ください。・横断歩道以外での横断・車道上での撮影・植栽帯(いちょうの根元)への立入り 明治神宮外外苑」並木道が奥へと続き、視線が自然と奥へと導かれるのであった。樹の根元そして地面には黄色い葉が散り、歩道に柔らかい雰囲気を与えていた。イチョウの葉でバラの花を作っている女性の手元を撮影させていただきました。イチョウ並木の黄金の輝きは、秋のこの時期に見られる自然の美しさの一つ。まるで黄金の海が広がるような光景なのであった。まさに秋の豊かな色彩の象徴であり、心を癒し、感動を与えてくれる瞬間。風に舞い散る葉が光を反射して、まるで黄金の粒子が空中を漂っているかのように。『金色の ちひさき鳥の かたちして 銀杏ちるなり 神宮の路に・・・詠み人知らず』。そして黄金の並木の下には、中国語も空中を漂っているかのように。暫し、キャプションは無しで黄金の輝きを!!左奥には「秩父宮ラグビー場」への並木道が。ズームして。反対側の並木道からも中国語が舞い込んで来るのであった。さらに「神宮軟式球場噴水」前のT字路に向かって進む。再びキャプション無しで。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.03
コメント(0)
-

二子玉川周辺を巡る(その4):行善寺(2/2)
そして、なぜか山門から真正面に本堂が建てられていない。本堂を正確に撮ろうとするとこんな感じになる。天水桶(右)には「奉納 獅子山」と。天水桶(左)。扁額「獅子山」。本堂に掲げられた獅子山と書かれた山号の額は、明治時代の官僚で書家の金井之恭(正四位勲三等)の書である と。「本堂」前の石灯籠(右)。灯りが灯されていた。「本堂」前の石灯籠(左)。「行善寺」の「本堂」を正面から。内陣。ズームして。御本尊:阿弥陀如来像。さらにズームしたが・・・。本堂右に吊るされていた「殿鐘」👈️リンク。これが鳴り出すと、「そろそろ法要がはじまるよー」という合図になるのだ と。打ち出し(始まりの合図)は、四回鳴らされるのだと。「本堂」の軒下を見る。「木鼻」。右手に「客殿」。ズームして。「供養塔 南無阿弥陀仏」。近づいて。「本堂」の南側に拡がる墓地を望む。ズームして。「六地蔵」と「慈母地蔵尊」か。赤ん坊を抱いている御姿はとても優しく見えた。その右側にも石仏が。近づいて。「奉造立庚申供養」と。左側の石仏。「三界萬霊塚」。「三界萬霊」と。「観音像」。「令和六年 年回表」。年回表は年回忌表ともいい、亡くなった人の命日ごとにめぐってくる年忌(周忌、回忌)を確認できる表である。本堂の右手にあった「行善寺八景」碑。「行善寺八景」入口門。この日の「行善寺八景」行善寺は街道である大山道に面していて、しかも眺めのいい国分寺崖線の先端に位置していることから、風光明媚というと大袈裟ですが、境内からの眺望は江戸時代に行善寺八景として知られていた。なんでも徳川将軍家も遊覧の際にしばしば立ち寄ったと。例えば天保3年に徳川家慶将軍が玉川鮎御成の際に長崎家で休息しているが、こういった折に行善寺にも立ち寄ったのかも と。その他、多くの文人墨客が訪れたと。残念ながら住宅街が広がっていて多摩川すら見えなかった。ズームして。冬に天気が良ければ、真白き富士山頂が見える と、ネットから。見学を終え山門に向かって進む。入口にあった大きな堂宇を再び訪ねた。内陣。ズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.03
コメント(0)
-

明治神宮外苑 いちょう並木へ(その1):青山通り
この日は2024年11月30日(土)、都内新宿駅近くで13時から開かれた久しぶりの元同僚との昼飲み会に参加。テレビでは神宮外苑のいちょう並木は真っ黄色に色づいている、とのことで、朝9時過ぎに自宅を出て向かったのであった。小田急線を利用して中央林間へ、そして田園都市線、半蔵門線の直通電車を利用して「青山1丁目」駅で下車。「青山1丁目」交差点に出る。正面にあったのが、「赤坂警察署青山一丁目交番」。最初の目的地の「外苑いちょう並木」まで240m と。近づいて。この先、右側に「外苑いちょう並木」。「青山通り」の横断歩道を渡り、南側を進むとビル前にあったパブリックアートの作品。「水の鼓動―絆― 高濱英俊」と。1957熊本県生まれ。1985年東京芸術大学大学院修了。水をテーマに石を使って制作する彫刻家。廻り込んで。御影石による作品。ビルの名は「帝国データバンク本社ビル」。港区南青山2丁目5−20 。ししてその先にあったのが2024年3月1日(金)に竣工した「ポーラ青山ビルディング」。青山通りに面した上空30mに浮かぶシンボリックなパブリックアートは、現代美術作家SHIMURAbrosによる作品「悠久の光景」で、時空を超えて豊かに広がる大樹をイメージしているとのこと。◆SHIMURAbros(シムラブロス)・プロフィールユカ(1976年生まれ。多摩美術大学 デザイン科卒後、英国セントラル・セント・マーチンズ大学院にて修士号を取得)とケンタロウ(1979年生まれ。東京工芸大学 映像学科卒)による姉弟ユニット。「映画」にまつわる作品や、その解釈を拡げた意欲作を次々と発表。ポーラ美術振興財団在外研修(2014 年)を契機に活動拠点をベルリンに移す。現在は同地にてオラファー・エリアソンのスタジオに研究員として在籍。主な展覧会に、文化庁メディア芸術祭(アート部門優秀賞受賞)カンヌ、ベルリン国際映画祭での上映、国立新美術館(東京)、ヘッセル美術館 and CCSバードギャラリー(ニューヨーク)など。2023年には、ACC Asian Cultural Council Japan Grant Programグランティーに選ばれた と。時空を超えて豊かに広がる樹葉をイメージした高さ約8m、横幅4mに及ぶ作品を、青山通り側の外壁から大きく張り出すように設置した と。「悠久の光景」は、石炭紀にあたる約3億年前に繁栄したシダ植物「シギラリア」をモティーフに表現したとのこと。これもSHIMURAbros作「つぼみ」。淡い七色の光が路面に。シダの胞子が地上に落ち、芽吹く様子を表現した「つぼみ」と。移動して。SHIMURAbros「待合のリゾーム」。シギラリアの幹をかたどった立体で、ベンチにもなる?ビルの西側の植栽の中にも、像が。板東優作「風化の詩」。板東優作「緑のメモリー」。1998 Bronze 170 x 62 x50 cm。 ・・・つづく・・・
2024.12.02
コメント(0)
-

二子玉川周辺を巡る(その3):瀬田貝塚跡~行善寺(1/2)
「法徳寺」を後にして、「行火坂」を下り、ナビに従い途中を右折して世田谷区瀬田1丁目の住宅街を北に進む。右手の「わかな保育園」の塀にあったのがモニュメントには「わかなすくすく通り」と。多摩美の学生さんによる地域案内板であるとのこと。その先を左折して進むと、右手前方に朱記の案内柱があった。「瀬田貝塚跡」石柱。【おもいはせの路二子玉川駅から九品仏浄真寺までのコースです。右の写真のような道標や路面のサインがあります。世田谷の自慢の風景、国分寺崖線。春には若葉が芽吹き、萌える木々。夏にはせせらぎの水音、涼しげな水面。秋には雲が流れ、紅葉を照らす月の光。冬には白い富士山、真っ赤なタ焼、四季折々の風景は無限の価値があります。】縄文時代前期(紀元前7000~5000年)の貝塚遺跡だそうで、発掘調査では竪穴式住居跡や貝殻が確認されているとのこと。ムラ的な場所だったのであろう。 その場所に江戸時代は大山街道が通り、現在は二子玉川という一大商業ゾーンがあるというのは、このエリアが人間の集まる場所として適していたということなのであろう。住宅街の一角にあるので難しいのかもしれませんが、説明版や発掘時の写真が展示されていると、訪問者には有難いのだが。こんな高台のところ近くまで海岸が接近していたとはビックリ。右折して「行善寺坂」を上って行った。左前方に「行善寺」の入口門が現れた。正面から。寺号標石「浄土宗 獅子山 西光院 行善寺」と。「行善寺」案内板。下には「せたがや八景 81.瀬田の行善寺と行善寺坂 昭和59年10月選定 世田谷区」と。「獅子山西光院 行善寺(浄土宗)行善寺の歴史は古く、その前身は、享禄(きようろく)ニ年(一五二九)に、芳蓮社印誉伝公上人(ほうれんしゃいんよでんこうしようにん)を開山として建てられた小庵であった。この地を拠点とする小田原北条氏の家臣・長崎氏は、その小庵のところへ、小田原から長崎氏建立の道栄寺を移して、西光院行善寺と改めた。当寺が立地する台地からは、いくつかの遺跡・、遺構がみつかっている。平成十五年に行った発掘調査では、瀬田遺跡の弥生時代の環濠と、長崎氏の拠点・瀬田城(砦)のものと思われる段切遺構、掘立建物跡が確認された。行善寺からの眺望は絶景で「玉川八景」、「行善寺八景」と称され、江戸幕府将軍も遊覧した名所であった。門前の道は、寺名にちなみ「行善寺坂」または「行火坂」と呼ばれてきた旧道・大山道である。 令和六年一月 世田谷区教育委員会」「掲示板」。入口門から「行善寺」境内に入り正面に「山門」を見る。世田谷区瀬田1丁目12−23 。境内にあった「三又ヒノキ」。世田谷区の名木百選に指定されている と。「保存樹木 樹種 ヒノキ」「保存樹木樹木は、空気をきれいにするなど、都市の環境改善に役立っています。 樹種数量 ヒノキ外5種9本 指定番号第 第135 ~ 141号 第143 ~ 144号 指定年月日 昭和52年10月5日この樹木は、世田谷区みどりの基本条例によリ指定されたものです。 世田谷区」見上げて。境内右側にあったこの「堂宇」の名は?帰路に訪ねることにする。境内左側にあった「堂宇」の名は「観音堂」。右の石柱には「成田山分教會高津村二子新盛講中・・・」と。左の石柱に「多摩川新四國八十八ヶ所第三十八番」と書かれていたが、今は近所の大空閣寺が第三十八番になっているようだ。右手の手水鉢四隅に鉢状穴がある。これらの穴は「盃状穴(はいじょうけつ)」と呼ばれているものである と。盃状穴の存在は、実は世界中で確認されており、最初に学会で発表されたのは1627年のスウェーデンでした。穴はペッキングという方法で彫られたもので、一説によると女性のシンボル(性器)を意味するそうです。古いものは、海外ではペトルグリフ(岩や洞窟内に刻まれた彫刻)やストーンサークル(環状列石)など、国内では西日本一帯に多く存在し、磐座いわくらなどでも確認されていて、子孫繁栄(子宝)や死者の蘇生、病気平癒などを願って彫られたものとされます。縄文時代のものや古墳の石棺に彫られたものもあり、世界遺産「神宿る島」宗像むなかた・沖ノ島と関連遺産群の一部である大島(福岡県宗像市)北部の馬蹄ばてい岩にある盃状穴も同時期のものと推定されています。「本堂再建 貳拾周年記念之碑」。「観音堂」に近づいて。左脇に近世の講中碑や童子像、石碑がまとめられていた。「成田山 天下泰平 供養塔 講中村々安全」と。内陣。「如意輪観音像」が祀られていた。右手にも石灯籠と石碑。奥には大きな石碑も。「征清紀年碑趣旨(英霊) 日清戦役における戦没者の慰霊顕彰 同 従軍者の顕彰碑文* 台座部分:従軍者の御芳名刻印(村別)* 碑前面 大丈夫のうちこむ大刀の益鏡 光りかゞやく御代と也けり 波たかき千里の海の外にまで ひひくみ国の凱歌の声 虎の伏す高麗唐土の果まても 名をとゞろかす日本ますら雄 天皇の尊き稜威の旗風に なひかぬ国はあらしとそおもふ 明治31年1月3日 建立*正三位子爵 海江田 信義 書」。境内左手奥にひっそりと「猫塚・ね古塚」碑が立っていた。「猫塚・ね古塚」碑。かつて多摩川で鮎漁が行われており花街として盛んだった頃に、三味線を作るために皮を取られた猫の供養として造られた。当時は料亭街の中にあったが境内に移された と。「猫塚」。「猫塚」の後ろにあった石仏。「観音堂」横の石仏群。近づいて。「山門」。1876年(明治19年)の火災で焼失せずに残った。建立年代は木鼻の渦紋等から江戸末期と推定されている と。小さいが厳かな雰囲気がある山門をくぐる。境内は石畳と石が敷かれている。木の手入れも行き届いていて、空気が凛としているのであった。山門の屋根にも「獅子山」と。山門をくぐると正面にあったのが「観音像」。近づいて。さらに。これでもかと。左手に持つ壺からは聖水がポタポタと流れ落ちていた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.02
コメント(0)
-

二子玉川周辺を巡る(その2):法徳寺
「法徳寺」への急な坂道「行火坂」を上って行くと、左手に「山門」が現れた。世田谷区瀬田1丁目7−7。寺号標石「浄土宗 福來山 壽光院 法徳寺」。「福来山 法徳寺本尊、阿弥陀如来浄土宗に属し、永禄元年(一五五八)法阿因公和尚によって開山した。開基は、瀬田の旧家の祖先である白井法徳(重安)、父は、基経といった、基経は足利義明の家来であったが、父子で瀬田の地に農民となり、子重安が開いたものである。境内にある筆塚の碑は明治初期、寺子屋の師、大塚貞三郎のために近在の瀬田、用賀、岡本などの門弟一同がたてた記念碑である。昭和五十三年三月世田谷区教育委員会」山門左手にあった「墓石・石仏群」。多くの「墓石・石仏群(地蔵立像など)」が積み上げられていた。近づいて。「浄土宗 福來山 法徳寺」碑。その一番上に駒型の庚申塔があった。造立年は不詳。青面金剛像と三猿の図柄で、7名の願主とともに瀬田村の銘があった。石段途中から「墓石・石仏群」を見下ろす。境内に入ると、左手には桜花浄苑【世田谷納骨堂・永代供養】の納骨堂があった。「桜花浄苑」。中央に合掌した形の永代供養墓「祈りの塔」。そして「江利チエミの墓」であると。江利チエミの全身を模ったような墓石らしい。俳優・高倉健と結婚していた。多彩なタレントだったが45歳でこの世を去った と。女性の立像が大理石で造られており、像の前に楽譜が刻まれた碑があった。『Tennessee Waltz“思い出なつかしあのテネシーワルツ”👈️リンクTennessee Waltz 1937~1982』とありました。近くには夫である俳優故高倉健さんの自宅があったようだ。墓石は奥の墓地の中にあるとのこと。江利チエミ(本名 久保智恵美)さんの墓石は奥の墓地の中にあるとのこと。ネットから。こちらは「ペット供養墓碑」と。「ペット供養墓碑」。「Forever」と。「手水場」。井戸には懐かしい「手押し井戸ポンプ」👈️リンクが置かれていた。「原理」👈️リンク です。子供の頃は我が実家にもありました。スイカを大きな風呂敷で包み、井戸の水面まで吊るし、冷やした懐かしい記憶があります。季節により、井戸の水面が大きく変化していた記憶もあります。この後訪ねた「瀬田玉川神社 例大祭」案内。「葬儀斎場・法要施設・多目的ホール」であっただろうか。左手に小さな御堂と石仏が。「地蔵堂」。「三千萬遍供養塔」と。正面から。近づいて。内陣。地蔵菩薩像。赤子を抱いた石仏。「水子地蔵尊」。近づいて。左手奥にあった墓地を望む。「本堂」前の石灯籠(右)。「本堂」前の石灯籠(左)。「法徳寺」の「本堂」。浄土宗寺院の法徳寺は、福來山 法徳寺と号す。永禄元年(1558年)法阿因公和尚が開山、瀬田の旧家 白井家の祖先である白井五郎兵衛重安が開基し、芝 西應寺の末寺として創建された。嘉永4年(1851年)大塚貞三郎が芝光塾という寺子屋を開き、小学校が開校される明治初期まで続いた と。御本尊 阿弥陀如来。「常香炉」。「福來香」と。賽銭箱にもなっているようであった。扁額「福來山」。内陣。江戸時代に作られた阿弥陀如来立像が本尊[。その他に、十一面観音菩薩立像、地蔵菩薩立像、誕生釈迦仏立像がある と。「筆塚」。使い古した筆の供養のために、筆を地に埋めて築いた塚。芝光塾(芝光堂)を開いた大塚貞三郎の頌徳碑として、1881年(明治14年)に門人たちによって建てられた と。刳り貫かれた石碑に小さな仏像が。近づいて。「本堂」を振り返って。青銅製灯籠に近づいて。隣りにあった「法徳寺」が経営する「わかな保育園」。再び「葬儀斎場・法要施設・多目的ホール」を。境内を引き返すと「三千萬遍供養塔」の横にはカエルの姿が。南無~~~。地下にある納骨堂をネットから。壁には納骨されている方々の戒名が記されていた。納骨堂。以下2枚はネットから。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.12.01
コメント(0)
全47件 (47件中 1-47件目)
1
-
-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印
- 後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 6…
- (2025-11-28 00:00:14)
-
-
-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…
- 奥只見湖♫
- (2025-11-27 21:51:41)
-
-
-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…
- エグゼクティブラウンジ 朝食 ヒル…
- (2025-11-26 00:10:04)
-







