-
1

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその3
前方の五差路を左折して進む。藤沢市本鵠沼3丁目13−19付近。左手前方にあったのが「堀川大師(地蔵)堂:準四56番霊場」。その前の造成工事中の場所は相模準四国八十八箇所の開創者の浅場太郎右衛門・浅場家の本家である と。よって、当時は浅場家の本家の屋敷の角に「堀川大師(地蔵)堂:準四56番霊場」があったのだ。造成中の土地・屋敷が広く、以前は広い敷地内には庭木が青々としていたのであろう。 堀川大師(地蔵)堂に近づいて。[浜道堀川大師(地載)堂:準四25番震場お堂の中には、安永九年(1790)の銘がある地蔵菩薩像(向かて右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められています。江戸期の新四国八十八簡所案内にも、”浜道地蔵堂”と書かれていることから、この地蔵菩薩のお堂がある所を巡礼地としたものと見られます。弘法大師像には、文政三年(1820)の年銘と、台座には堀川講中と刻字されています.御詠歌:のりの舟 出る津寺と いろくすも うの浜道に つとひよるらんお堂隣にある、2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮影て、右側が宝暦十ニ年(1831)、左側が宝永六年(1709)の作。お堂前の標柱も、天保ニ年(1831)堀川講中により建てられたものです。】御詠歌の意味は【仏さまの教えという“法(のり)の舟”が出て行く港のようなお寺だと聞いて、いろいろな人びとが、この浜道を通って、朝早くから(熱心に)お参りして来ることでしょう】と。「堀川 弘法大師堂」。 「相模準四国八十八ヶ所 堀川地蔵菩薩堂とほつおや(遠つ祖)の みたま(御霊)まさしく 有あけの 影さやかにぞ す(澄)める堀川第五十六番 金輪山泰山寺」 【遠い祖先の御霊が まさしくそこに宿っているように、有明の月の光が 澄んだ姿で 堀川を照らしている。】堀川とは現在の境川の旧称の一つ。藤沢市域を南北に流れる 境川(横浜市青葉区〜藤沢〜江の島に至る河川)は、時代・地域によってさまざまな呼び名がありました。境川の主な古名・堀川(ほりかわ)・境の川・境河・高座川(たかざがわ)・藤沢川(ふじさわがわ)このうち 堀川(ほりかわ) は、▶ 鵠沼・片瀬・藤沢宿の周辺で古くから用いられた名称で、江戸初期〜明治にかけて文献に登場しま と。古語で「堀」は、単に掘った溝ではなく境界・領域の区切りとしての水路を表すことがあります。境川は、・武蔵国と相模国・高座郡と鎌倉郡の国境・郡境になっていたことから、“境を示す川=堀(境界の水路)”= 堀川という説であると。左:弘法大師像右:地蔵菩薩坐像左:弘法大師像、椅子に座り、左手に数珠、右手に独鈷杵(とっこしょ)を持つ。独鈷杵とは、両端に1本の突起がある密教の法具で、古代インドの武器が起源。煩悩を打ち砕く仏の智慧の力を象徴し、チベット仏教や日本の真言宗、天台宗、禅宗などで用いられます。右:地蔵菩薩坐像。右手に錫杖(しゃくじょう)、左手に宝珠(ほうじゅ)を持つ坐像。造成工事中の浅場家の本家の広大な敷地跡。「鵠沼における淺場家の本家は、現在の藤沢市に相当する地域にあった「原の淺場太郎右衛門」です。この家は、明治時代初期に鵠沼を代表する豪農であり、水田、畑、山林などを広く所有していました。戦後に鵠沼を離れたため、浅場家に関する資料は現在見つけることが非常に困難となっています。 ●本家の名称: 原の淺場太郎右衛門●本家の特徴:・明治初期に豪農として知られていた。・水田、畑、山林などを広範囲に所有していた。・当時の屋敷には「千両箱のうだつ」が上がっていたという。・当時21軒あった淺場家の総本家とされていた。」 在りし日の「浅場家の本家の広大な敷地」をGoogle Mapから。 そして次に訪ねたのが、100mほど東側、小田急江ノ島線沿いにあった尼寺・本真寺。[本真寺 通称「尼寺」夢想山本真寺(浄土宗)。本尊阿弥陀如来。創建は明治36年(1903)、颯田本真尼により下鰯(現鵠沼海岸三丁目)の細川家別邸に布教及び日清戦争病没者の供養のため「慈教庵」として開山されました。しかし、関東大震災て慈教庵は倒壊。翌年現在地に移転し仮本堂を建立し、昭和10年(1935)に再建されました。震災後何時から本真寺と号されたかは不明です。現在は男性の住職てすが、昭和8年に書かれた『現在の藤沢』(加藤徳右エ門著)には、”本庵は全部尼僧にして男気なし”と記されています。境内には「文士宿」の異名で知られる旅館東屋の初代女将長谷川ゑいの墓や、鵠沼海岸別荘地を開発した伊東将行の墓碑もあります。][【颯田本真】弘化2年(1845) ~昭和3年(1928)愛知県生まれの尼僧。慈善事業家。現在のボランティア活動家の草分け的存在。全国の地震や津波などの被災地に衣類等の援助物資を送るとともに、自身でも被災地に足を運び救援活動を行っていました。本眞尼を敬慕する人たちが関東での布教を懇願し、なかでも細川糸子という人が三河まて本真尼を訪ね熱心に依頼しました。再三の要請に心が動かされ、鵠沼の細川家の所有地の一角に慈教庵を結び布教活動を行いました。昭和10年の再建を見ず、昭和3年に故郷の三河で入寂。「布施の行者」と尊称された颯田本真の生涯は、書籍等にも綴られています。 参考:鵠沼を巡る千ー話「第0155話 慈教庵創建」]颯田本真尼をネットから。ここ鵠沼に来たのは、本真寺の前身となる説教所「慈教庵(じきょうあん)」を開設した支援者の一人に招かれたからだと。山号の「夢想山(むそうざん)」は、本真尼が同庵を訪れる10年ほど前に見た夢の光景と、鵠沼の光景が似ていたからだという。境内にある池を跨ぐ小さな朱塗りの太鼓橋。仏教寺院の「放生池」を模したもの。朱塗りの太鼓橋の先には観音堂(供養堂・題目堂)が。「鵠沼海岸開拓者 伊東将行之墓」👈️リンク。鵠沼別荘地開拓創始者として、また多くの文人達が逗留した旅館「鵠沼館」や「東屋」を築いた伊藤将行のお墓。本堂を斜めから。宗派: 浄土宗山号: 夢想山歴史:もとは「慈教庵」という庵が鵠沼海岸にありましたが、大正12年(1923年)の関東大震災で倒壊しました。大正13年(1924年)1月、尼僧の**颯田本眞尼(さったほんしんに)**によって、現在の位置に仮本堂が建立され、再興されました。颯田本眞尼は「全国6万戸を救った尼僧」としても知られています。境内:境内はこじんまりとしていますが、手入れが行き届いており、静かで美しい雰囲気です。朱塗りの太鼓橋が特徴的な景観を作り出しています。本堂前の石造三重塔。動物供養塔。三界萬霊塔。本堂を正面から。薬師瑠璃光如来像。右手:施無畏印(せむいいん)「恐れることはない、安心しなさい」と示す手左手:与願印(よがんいん)「願いをかなえる、救いを与える」印 そして、万病に効く薬が入っていると信じられている「薬壺」を持つ。 五劫ごこう思惟しゆい阿弥陀仏。五劫思惟阿弥陀仏は、通常の阿弥陀仏と違い頭髪(螺髪らほつ)がかぶさるような非常に大きな髪型が特徴です。「無量寿経」によりますと、阿弥陀仏が法蔵菩薩の時、もろもろの衆生を救わんと五劫の間ただひたすら思惟をこらし四十八願をたて、修行をされ阿弥陀仏となられたとあり、五劫思惟された時のお姿をあらわしたものです。五劫とは時の長さで一劫が五つということです。一劫とは「四十里立方(約160km)の大岩に天女が三年(百年という説もある)に一度舞い降りて羽衣で撫で、その岩が無くなるまでの長い時間」のことで、五劫はさらにその5倍ということになります。そのような気の遠くなるような長い時間、思惟をこらし修行をされた結果、髪の毛が伸びて渦高く螺髪を積み重ねた頭となられた様子を表したのが五劫思惟阿弥陀仏で、全国でも16体ほどしかみられないという珍しいお姿です。落語の「寿限無寿限無、五劫のすり切れ」はここからきています。屋根瓦(本瓦)を積み重ねて造った塔・「瓦塔(がとう)」瓦を積み重ねて造った塔を 瓦塔(がとう) といい、本来は奈良時代の古寺(例:法隆寺・飛鳥寺・元興寺など)で発見されることが多い、貴重な遺構の形式。しかし江戸時代以降にも、庶民の信仰や講中の寄進で作られた「模造瓦塔」「供養瓦塔」 が実在。本真寺のこれは、まさにその後者の系統と考えられる と。近づいて。境内の六地蔵。笑顔が可愛らしい六地蔵。こちらも。「尾﨑恒子(おざき つねこ)」供養塔。本真寺は、ジャーナリスト・作家である横山源之助の恋人であった尾﨑恒子ゆかりの寺院。 詳細は以下の通りと。尾﨑恒子:横山源之助が明治40年頃から亡くなるまで関係を持った恋人とされる人物。源之助の臨終にも偶然居合わせた友人と共に立ち会っている。関係:横山源之助の墓所が元々あった場所から鵠沼の本真寺に改葬され、後に尾崎恒子と彼女の娘である梢もこの寺に埋葬されている。 このように、本真寺は横山源之助と尾﨑恒子の墓所がある、ゆかりの深い場所 と。境内の地蔵尊。近づいて。「延命地蔵(子育地蔵)」であっただろうか。再び朱の太鼓橋を反対側から。御堂の内陣。三体の仏像(+小像数体) が安置されていた。左:大黒天中央:観音菩薩(聖観音or如意輪観音)右:地蔵菩薩朱の太鼓橋越しに本堂を見る。こちらが本真寺の山門。 山門脇にある「不許葷酒肉入門」の石碑「葷」の意味は「ニンニク、ニラ、ネギ、ラッキョウ、ショウガ」の総称。精がつく食べ物なので、酒、肉と共に、修行の妨げになるということ?「葷酒肉」は私の大好物であるが、この日は山門をくぐらせて頂いたのであった。「私たちの宗旨(しゅうし)名称 浄土宗宗祖 法然上人(源空) (承安五年—西暦一一七五年〜建暦二年—西暦一二一二年)開宗 承安五年(西暦一一七五年)ご本尊 阿弥陀仏(立像・座像)称名 南無阿弥陀仏教え 阿弥陀仏を深く信じ、ひたすら南無阿弥陀仏とお念仏を称えるだけ でどんな罪深い人でも救われるお経 お釈迦様が説かれた 「無量寿経」「観無量寿経」「阿弥陀経」の三部経を大切にしております本堂のご本尊に、先ず合掌」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.27
閲覧総数 212
-
2

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその2
鵠沼海岸7丁目の住宅地の路地を最初の目的地に向かって進む。この先が最初の目的地であった。藤沢市鵠沼海岸7丁目21−8。右手に大きな石碑があった。松岡静雄先生之庵趾碑。[この場所は、かつて海軍大佐であり言語学者・民族学者の松岡静雄が退役後に居を構えた場所です。明治十一年(1878)生まれ、松岡家の7男。民俗学の大家 柳田国男を兄に持ちます。海軍きっての吉語学者であり、病により退官した後、精力的に言語学・民族学を研究し、「日本古語大辞典「太平洋民族誌」 「ミクロネシア民族誌」等の多数の著書を残しています。関東大震災後の大正十ニ年末、鵠沼・堀川集落の南に隣接する納屋(ないや)地区に移り住みました。この庵を《神楽舎(ささらのや)》と名付け、在野の言語学者として日々研究を重ねていました。次第に、教えを乞う人々が集まり“神楽舎講堂”と呼ばれるようになり、湘南国語研究会というものをつくって、この舎から「国語と民族思想」というものを発刊していました。昭和11年(1937) 5月23日松岡静雄が逝去した翌年、先生を基う弟子たちにより石碑「松岡静雄先生之庵趾」が建立されました。くくコラム> >民俗学の大家柳田國男線の人々:松岡静雄と丸山久子と鵠沼民俗学者丸山久子は、20歳のころよリ父が鵠沼海岸に家を建て、この近くにあった神楽舎の講義にも参加していました。静雄の長女と丸山久子は、高等学校時代の同級生だったという縁もあり、静椎の没後も松岡家の人々との交流は生涯にわたります。静雄の妻の誘いを切っ掛けに、久子は柳田国男の講演「国語の将来」を受講します。これを機に本格的に民俗学を学ぶようになり、世田谷にある柳田の自宅て行われた研究会にも熱心に通っていました。昭和十七年頃からは、柳田の助手を務めるようになりました。 参考資料:『地名の会会報 117号』遠藤の民俗ー丸山久子の足跡と仕事ー粂智子著]海軍退役後、神奈川県藤沢市(当時は藤沢町)鵠沼に居を移すが、直後に起こった関東地震では、遭難死した東久邇宮師正王の遺骸を運ぶために軍艦を相模湾に回航させたり、遭難死した住民26体の遺骸を地元青年団が荼毘に付す際の指揮を執ったりしたという逸話が残っている。震災後は鵠沼西海岸に居を構え、神楽舎(ささらのや)と名付けて言語学、民俗学を研究し、同じ軍人出身の「岡書院」店主岡茂雄の勧めもあり、十数年で多くの著作を残した。また、扇谷正造をはじめ多くの青年たちが訪れて学んだ とウィキペディアより。海軍時代の松岡静雄(ウィキペディアより)。家族・親族実父:松岡操 - 儒者、医者実母:たけ兄姉 松岡鼎 - 医師 松岡俊次(早世) 井上通泰(松岡泰蔵) - 国文学者、歌人、医師 松岡芳江(早世) 松岡友治(早世) 柳田國男 - 民俗学者弟 松岡輝夫(松岡映丘) - 日本画家柳田 國男は、日本の官僚、民俗学者。 東京帝国大学法科大学を卒業して農商務省官僚となり、貴族院書記官長まで昇り詰めた。退官して約20年を経た1946年に枢密顧問官に補され、枢密院が廃止されるまで在任した。 日本学士院会員、日本芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章者。位階・勲等は正三位・勲一等。松岡家兄弟らの写真(前列右より、松岡鼎、松岡冬樹〔鼎の長男〕、鈴木博、後列右より、柳田國男、松岡輝夫〔映丘〕)没後1938年(昭和13年)、弟子たちによって建てられた「松岡静雄先生之庵趾」碑。裏面には何か書かれていたのでろうか?おそらく建立年月・建立者名などが刻まれている??「松岡静雄先生之庵趾」碑を後にして、次の目的地に向かって鵠沼海岸7丁目の住宅地内を進む。左手に石鳥居が現れた。ここが「高根地蔵尊」。藤沢市鵠沼海岸7丁目19−11。石鳥居前での説明を聴く。石鳥居の奥に小さな御堂が建っていた。石鳥居を潜って進むと目の前には木製の「地蔵堂」が。 近づいて。「高根地蔵尊」。 地蔵堂の内部に安置されていた「高根地蔵尊」。今でもお地蔵さまの足元には、子供の病が治ったお礼として奉納された小石が山のように積み上げられているのであった。 [高根地蔵神楽舎に近く堀川部落の南側に、高根地蔵はあります。“高根”はこの辺りの小字名て、昔は田の畦道の中に小さな祠がありました。天保十四年(1843)ニ月、堀川部落の開祖山上新右衛門建立したものです。鎌倉時代のある合戦で、とあるやんごとなき若者を負い郎党四人を伴った武者が最後をとげたのを村人が弔ったという伝承があります。明治初年には、祠堂改築のため盛土を崩したところ、刀身ニロ、断碑片若千、土器十ニ枚が発見されたと云われます。その後、松岡静雄の発起て祠堂が建立されました。『現在の藤沢』加藤徳右衛門著(昭和8年刊行)には、次のように記されています。「部民はこの地蔵に触れると必ず生命に関する程の祟ありと恐れ、安政五年頃より毎年九月四日追善供養をおこなって今日に及び、以来恐ろしき祟りも絶え、小児の疾病本復を祈れば殊に霊験あらたかでえあると云われ四時香華の絶えぬものたり」 ]以下もネットから 『藤沢の民話』第一集の山口紋蔵氏からの聞き書きには、鎌倉時代との説もあるので引用しよう。藤沢の高根地蔵藤沢町鵠沼堀川海岸にある高根地蔵と云う伝説の霊験あらたかの地蔵がある。この地蔵は天保十四年二月四日鵠沼堀川部落の開祖山上新右衛門が建立したもので鎌倉時代の合戦に或るやんごとなき若君を負い郎党四人を引具した武者がこの地まで落ちのびたが武運拙なく遂に敢なき最後を遂げたるを村人等が之を悼み茲に葬むりしものと伝う。明治初年両堂改築の為め盛土を取崩した処刀身二口、断碑片若干、土器十二枚を発見したと当時鑑識の明なく徒に散逸したものたりと。部民はこの地蔵に触れると必ず生命に関する程の崇ありと恐れ、安政五年頃より毎年九月四日追善供養をおこなって今日に及び以来恐ろしき崇りも絶え、小児の疾病本復を祈れば殊に霊験あらたかであると云われ四時香華の絶えぬものたり。この逸名の小公子と忠臣の冥福を祈り一面郷土史跡記念物として保存の為の同所の海軍予備大佐松岡静雄氏等の発起で出来た小さな祠堂が建てられている と。決して歴史の教科書には載らないような名もなき武将であろうが、確かにここに存在した歴史の秘話に触れることができるのも、このような「小さな地域史」探訪の醍醐味なのであった。「高根地蔵尊」をズームして。その先を右折して、鵠沼新道線を進む。コモダ歯科医院手前の路地を左折。藤沢市鵠沼海岸3丁目3−1。「しらす直売所 田むら丸」前には列が。藤沢市鵠沼海岸7丁目15−15。毎朝しらす漁をして釜揚げしらすを作っているオジサンと製造販売しているオバサンが二人でゆるりと営んでいる湘南しらすの直売所である と。美味そう!!小田急線に沿って北に歩く。そして次に訪ねたのが「浜道堀川大師(地載)堂:準四25番霊場」。藤沢市鵠沼海岸7丁目4−16。この日、最初の相模準四国八十八箇所霊場。「第二十五番 南無大師偏照」まで読み取れる石柱が建っていた。「南無大師偏照」の下に「金剛」と続くのですがありませんでした。[浜道堀川大師(地蔵)堂:準四25番霊場お堂の中には、安永九年(1780)の銘がある地蔵菩薩立像(向かって右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められています。江戸期の新四国へ十へ箇所案内にも、”浜道地蔵堂"と書かれていることから、この地蔵菩薩のお堂がある所を巡礼地としたものと見られます。弘法大師像には、文政三年(1820)の年銘と、台座には堀川溝中と刻字されています。御詠歌:のりの舟出る津寺といろくすも うの浜道につとひよるらんお堂隣にある、2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮彫で、右側が宝暦十ニ年(1762)、左側が宝永六年(1709)の作。お堂前の標柱も、天保ニ年(1831)堀川講中により建てられたものです。]「浜道 弘法大師堂」。 本家四国八十八ヵ所津照寺の御詠歌の木札が掲げられていた。「準四国八十八ヶ所法の舟 入るか出るか この津寺 迷ふ吾身を もせたまへや第二十五番 宝珠山津照寺」 【仏の教えという救いの舟に、私は今、乗るべきか乗らざるべきか迷っている。 この寺に立ち止まる私の迷いを、どうか仏さま、正しい道へお導きください。】と。堂の中には、安永九年(1780)の銘がある地蔵菩薩立像(向かって右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められていた。地蔵菩薩立像をズームして。弘法大師像をズームして。隣の2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮彫。右側が宝暦十ニ年(1762)、左側が宝永六年(1709)の作 と。いずれも「青面金剛」や「三猿」が彫られていたが、彫られた石の素材や像の姿かたち、さらに剥離摩耗などの違いが見てとれます。左側が宝永6(1709)年、右側が宝暦12(1762)年と、50年以上差がありますが、左の方が形態をよりとどめていた。こうした歴史を積み重ねてきた石塔・石仏などは、区画整理や道路拡張などによって一か所にまとめられることが多いとのこと。しかし、この堂の前の通りは古い地図を見ると昔から続いている道。庚申塔は、おそらく別の場所から移動されてきたのだと思うのだが、こうしたものが残っていることは、歴史を大切にされてきた証だと思うのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・
2025.11.26
閲覧総数 225
-
3
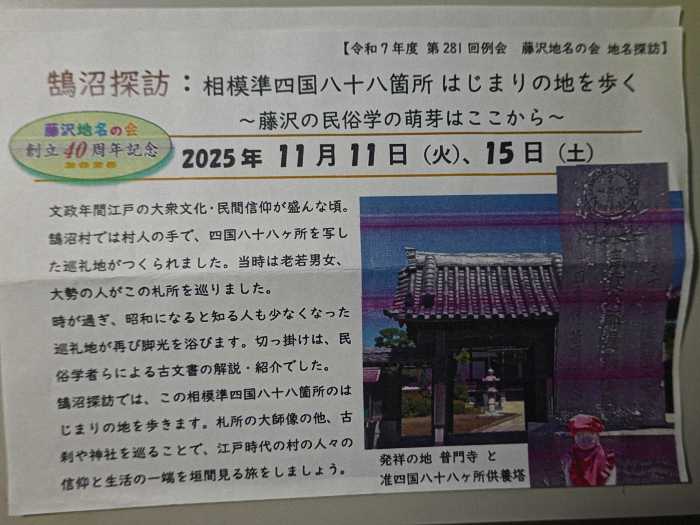
鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその1
この日は2025年11月15日(土)、「藤沢地名の会」主催の【令和7年度第28回例会・藤沢地名の会 地名探訪】・「鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩く」に参加しました。「文政(1818年~1831年)年間(は)江戸の大衆文化・民間信仰が盛んな頃。鵠沼村では村人の手で、四国八十八ヶ所を写した巡礼地がつくられました。当時は老若男女、大勢の人がこの札所を巡りました。時が過ぎ、昭和になると知る人も少なくなった巡礼地が再び脚光を浴びます。切っ掛けは、民俗学者らによる古文書の解説・紹介でした。鵠沼探訪では、この相模準四国八十八箇所のはじまりの地を歩きます。礼所の大師像の他、古刹や神社を巡ることで、江戸時代の村の人々の信仰と生活の一端を垣間見る旅をしましょう。」 ●予定コース鵠沼海岸駅→松岡静雄先生之庵趾→高根地蔵→準四25番→準56番→本真寺→原の辻→茂兵衛の辻→大東観音・準四79番→準四41番→斎藤家長屋門→普門寺・準四5・47・88番→藤森稲荷→浅場太郎右衛門墓→昼食(宿庭町内会館)・法照寺・準四48番→空乗寺→宮の前首塚→共同墓地・準四63番→万福寺→皇大神宮:解散(午後2時半頃予定)予定コース(都合により一部変更することがあります)[ 7.0km程度、高差なし]※準四:相模国八十八箇所の霊場番号、弘法大師像の場所日時:令和7年(2025)11月11日(火),15日(土) 2回開催(同じ内容です) ※小雨決行、荒天の場合11月18日(火)に延期します。集合:午前10時00分 小田急線鵠沼海岸駅改札前集合 (午後2時半ごろ 皇大神宮で解散予定)参加費:一般7 0 0円、会員2 00円 (資料代と保険料を含みます)定員 :両日とも3 0名 計6 0名 (先着順、会員もお申し込みが必要です)申込日 :11月3日(月)~11月7日(金) 受付専用電話 電話 070-9040-2614 (担当:布施) ※お電話は9:00ー17:00の間にお願いいたします.持ち物:弁当、飲み物、ゴミ袋、雨具10:00集合とのことで9:10に自宅を出て、小田急線鵠沼海岸駅に40分ほどで到着。改札出口で地名の会の方が迎えてくれ、集合場所を案内してくださいました。藤沢駅方面の線路沿いの空き地の集合場所には既に10人ほどが到着済み。受付をし会員会費200円を支払う。この日の散策用資料(全20ページ)をいただきました。そして定刻10:00になりこの日の案内人の方からこの日の散策ルートの紹介が始まった。参加人数は15名、2班(8名、7名)に分かれてそれぞれに案内人の方が付いてくれたのであった。私は7名の2班にてスタート。鵠沼海岸3丁目5の道路を北西に進む。左手にあったのが、入口表札から法華宗本門流の晴明庵。鵠沼海岸駅周辺👈️リンクの昔からの路を進む。鵠沼海岸郵便局(藤沢市鵠沼3丁目)前の細い商店街の路地を進む。この通りは、実は“近代以降につくられた道路”ではなく、江戸~明治期以前から存在した「鵠沼村の生活道」を引き継いだものと。道がゆるくカーブし、幅が急に狭くなる地点もあった。これは近代の都市計画で作られた道路には見られず、江戸~明治の農道の曲がり方(地形に沿う道)と同じ特徴であると。つまり、この曲がり道は、昔の地形に沿っていたために残った“古道の線形”と言えるのだと。今回、主催者の「藤沢地名の会」さんからいただいた資料を[ ]つきで転記させていただきます。転記することにより、私のこの日の散策地の歴史等の復習が主な目的です。[【=鵠沼地域の概要=藤沢市域は、歴史的にみても古くは鎌倉幕府、江戸幕府の周縁地域に当り、現在も東京近傍の地域として、中央の政治的・文化的影響を受けて発展してきました。藤沢南部の鵠沼地域は、東に境川、西に引地川、南は湘南の海に囲まれ、北は旧東海道の辺りまでになります。鵠沼から茅ヶ崎一帯に続く砂丘地帯は、海の波や潮流によって形成された砂州が、堆積した砂が風によって運ばれ小高い丘になったものです。鵠沼地区全体がなだらかな平地になっており、高い場所ても海抜10m程度です。【鵠沼の歴史】奈良時代、相模国司が記した『相模国封戸租交易帳』には、土甘(とがみ)郷という地名があり、古くからこの辺りに集落があったと見られています。さらに、北部にある皇大神宮は、土甘郷の総社であったと云われます。平安後期、大庭氏が荘園を伊勢神宮に寄進し“大庭御厨(おおばみくりや)“👈️リンクが成立しました。鵠沼はこの大庭御厨に含まれます。源義朝らが鎌倉から越境乱人した事件が「天養記」に記され、その場所は鵠沼てあったとみられています。鎌倉時代から室町時代、京から鎌倉への”鎌倉街道”がこの地を通っていました。中世の和歌や紀行文に登場する“砥上が原(とがみがはら)”という地名は、この辺りが荒野てあったことを示す地名です。また、鎌倉にほど近いため、鎌倉末期からの戦乱に巻き込まれていたと見れれています。江戸時代になると、鵠沼村の北西部を皇大神宮の周辺を中心に農を営む集落が発達してゆきます。江戸初期には、鵠沼村は2家の旗本(大橋氏・布施氏)の知行地と天領になりました。大橋領は江戸中期に上知(幕府に返す)となりますが、布施家の領地は幕末まで続きます。砂地が多いため田圃は鵠沼北部川沿いに集中しますが、南部の海岸地帯では地引網による漁が行われ生活の糧となります。また、江戸後期には、砂丘地帯が幕府の鉄炮場として使われていました。また、東海道・藤沢宿と江の島をつなぐ“江島道”が村内を通っており、境川を渡る場所は石上の渡し(または石亀の渡し)と呼ばれ、江島参詣に訪れた旅人の道中記にも度々登場しています。明治時代になると、鵠沼にも新時代の波が押し寄せます。海岸が海水浴場として注目されると、我が国初の別荘分譲地が開発力ぐ立ち上がります。明治35 (1902 )年9月1日に、藤沢一片瀬駅(現:江ノ島駅)間に江之島電気鉄道(現江ノ電)が開通、碁盤の目状の整備された別荘地には東京から移り住む人もありました。さらに、鵠沼海岸を目の前にした旅館東屋は、「文士宿」の異名で知られ、多くの文人が集いました。また、江の島と湘南の海の美しい景色は芸術家らにも愛され、鵠沼海岸は東京からほど近いリゾート地として人気を博していきます。戦後、鵠沼南部は別荘地の名残を留めつつ、比較的緑が多い閑静な住宅地が形成されていきます。鵠沼北部も、藤沢駅にほど近い利便性の高さから商業地・住宅地も増え、藤沢市の中心市街地となりました。また、交通の便がよく、環境にも恵まれている鵠沼は、現在では藤沢市内13地区の中で最も人口が多い地域になっています。] [【鵠沼の集落】明治初期の鵠沼村には 14 の集落があり、戸数も 300 戸に満たない村でした。その中でも、人口の集中した集落は 9 つ(上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川)で、この辺りを鵠沼本村といい、いずれも皇大神宮の氏子集落です。ほとんどの家は農業を生業としていましたが、網元を営む家も数軒あり、鰺・鯖・鰯・カマスなどを主に獲っていたそうです。明治時代に入ると漁法の革新により盛んになり、漁業組合もできましたが、現在では堀川網一軒が残るのみになりました。]明治初期の鵠沼村。鵠沼地区の小字名・集落名(下記はネットから)上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川の9村の位置図。ここ「鵠沼地区宗教史年表」👈️リンクから。 左:明治時代の鵠沼村の集落と小字右:現在の鵠沼地区の住居表示 をネットから。相模国準四国八十八ヶ所👈️リンクとは。[=四国遍路とは= 参考:「四国路八八ヶ所巡礼の歴史と文化」 森正人著古来、四国は都から遠く難れた修行の場でした。弘法大師(空海)もこの地で修行され、八十八ヶ所の寺院などを選び四国八十八ヶ所霊場を開創されたと伝わります。中世には修験者が、未開の地(四国)の弘法大師の霊場を巡る修行が行われていたことが知られています。四国遍路の成立時期については諸説あり、江戸時代にはいってからと見る説が有力です。四国遍路の特徴は、札所寺院の本尊は、阿弥陀如来もあれば弥勒菩薩もあり、さらに宗派も真言宗だけではありません。四国八十八ヶ所の寺院に共通しているのは、本堂の他に大師堂があり、このニつを参拝することが求められている点です。※お砂踏み~現代の四国八十八ヶ所巡り~参考: (ー社)四国八十八ヶ所震場会四国八十八ヶ所霊場各札所の「お砂」をそれぞれ集め、その「お砂」を札所と考えて「お砂」を踏みながらお参りするこです。そのご利益は、実際に遍路をしたことと同じであるといわれております。江戸時代には、四国八十八ヶ所霊場を模し新四国、島四国、八十八ヶ所などと呼ばれるうつし霊場やお砂踏み道場などが日本全国に数多く造られました。=相模国準四国八十八ヶ所=相模国準四国八十八ヶ所は、文政年間に鵠沼村堀川の浅場太郎右衛門によって作られ、現鎌倉市の西部から、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の各地に札所が置かれました。その経緯は、浅場太郎右衛門の父が、下総国相馬郡に本四国を写した霊場を見たことに端を発します。後に、鵠沼の近辺にも作りたいと普門寺の住職善応密師に相談し、弟子の浄心を派遣し、霊場の砂土を採ってこさせました。相模の霊場は、元々御堂のある場所や墓地を選び、霊場の砂を埋めた上に、大師像を安置しました。その事情は、江戸時代の巡礼案内書にも記されています。この霊場の完成は、父の十七年忌(文政四年(1821))を期して、息子の浅場太郎右衛門が大師像を造り各地に設置したという説が有力です。その根拠は、大師像のいくつかの年銘が、文政3、4年であることにあります。霊場番号については、本四国が阿波から1番、2番と巡礼道の順に振られているのに対し、相模の札所番号はバラバラてす。震場として選んだ場所それぞれを、本四国の震場と環境が似ている、名前が似ているなど、何らかの類似点を見出し割り振ったのではないか見られています。なお1番札所の感応院👈️リンクは普門寺の本山であります。1番と結願の88番札所(普門寺)の2箇所は、本四国とは関係なく決められたものでしょう。この霊場をつくった縁によるものか、感応院の「霊簿記」には浅場太郎右衛門の名が大旦那扱いで記名されているそうてす。=藤沢の「相模国準四国八十八ヶ所」研究=創設当初は巡礼者でにぎわっていた相模国準四国八十八ヶ所も、時代が過ぎ戦後になると巡拝する人もほとんどなく、「藤沢市史」等に戦前の大師講の様子が僅かに記されている程度でした。(「藤沢市史第7巻」民俗編 第六章 信仰と民間療法)] 私の「四国八十八ヶ所霊場巡り」👈️リンクは車での移動であったが、既に2015年に結願しているのだ。[昭和30~40年代、忘れ去られていた相模準四国八十八箇所について、江戸時代に書かれた巡礼案内書が読み解かれました。一つは、茅ヶ崎の南湖金剛院が所蔵していたもの。もう一つは、鵠沼堀川の山上家が所蔵していたものです。これらの古文書から、相模国に八十八ヶ所を創設した経緯、各札所の御詠歌、お勧めの巡礼行程など判明しました。その後、平成になり「鵠沼を語る会」の有志の方々によリ弘法大師像が安置されている位置も調査され、一冊のガイドブックにまとめられました。なお、山上家本の方は、鵠沼に住んていた民俗学者丸山久子氏が解読し発表されました。]相模国準四国八十八か所の順路をズームして。以上 ポイントを纏めると●相模準四国八十八箇所の概要 ・概要: 四国八十八箇所の写し霊場で、弘法大師石像が各札所に祀られています。 ・構成: 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡寒川町、横浜市泉区にまたがる88か所の札所。 ・起源: 江戸時代の文化・文政期に普門寺の善応師と鵠沼(くげぬま)の浅場太郎右衛門が 発願し、文化3年(1806年)に計画されました。 ・ご利益: 四国霊場を巡るのと同等のご利益があるとされ、手軽に巡拝できることから 流行しました。 ・現状: ・明治時代の神仏分離令や関東大震災、開発などにより、廃寺・移転・消失した札所が あります。 ・昭和50年代以降、調査が進み、現在では85体の弘法大師像が残っていることが 確認されています。 一部の札所では、ウォーキングイベントなども開催されています。相模国準四国八十八か所の札所リストをネットから。・相模国と呼ばれたエリアの弘法大師霊場。・霊場札所の御本尊は、弘法大師石仏となる。・堂となっていても、屋外に石仏が祀られているだけのケースもある。・開創者の浅場太郎右衛門は鵠沼村の住人で、善応は88番普門寺の住職だった人物。・慶応4(1868)年の神仏混淆廃止、明治2(1869)年の神仏分離、廃仏毀釈、さらに 関東大震災によって廃寺や廃堂となった札所が多い。・結果、札所の移動もかなりあり、弘法大師の石仏が行方不明のケースもある。・当時の札所配置で、春の彼岸の際に4日ほどで巡拝する人が多かったようだ。・不定期ながら、巡拝ウォーキングのイベントなども開催されている。霊場の写真もネットから。鵠沼の弘法大師像堀川の淺場太郎右衛門父子二代の発願になる「相模國準四國八十八箇所」のうち、鵠沼村内に置かれたものは次の9か所である。この他に法照寺境内には、もう1体の弘法大師像が小堂内に安置される。手前が第48番札所の大師像とされる。相模國準四國八十八箇所の概略は第0084話、詳細は相模国準四国八十八ヶ所を参照されたい。第七十九番 大東観音堂第六十三番 毘沙門堂第五番 原地蔵堂 地蔵立像と併置第二十五番 濱道堀川地蔵堂 地蔵立像と併置第五十六番 堀川大師堂 地蔵坐像と併置第四十一番 苅田稲荷社第四十七番 密嚴山遍照院普門寺大師堂第四十八番 善光山天龍院法照寺第八十八番 密嚴山遍照院普門寺本堂=結願札所鵠沼地区地蔵尊・弘法大師像年表 西暦 和暦 月 日 記事1654 承応 4 5 吉 石上の地蔵菩薩立像、造立(鵠沼最古の石仏。昔は石上の 渡し場近くにあった)1655 承応 5 石上稲荷神社境内の地蔵菩薩立像、造立(遺失)1670 寛文10 8 16 本鵠沼2-4-36大東町内会館裏の地蔵菩薩立像(南無阿弥陀仏)、造立1780 安永 9 11 吉 鵠沼海岸7-4-17地先浜道地蔵堂の地蔵菩薩像(立像丸彫り)、造立1820 文政 3 6 吉 法照寺境内の第48番札所弘法大師石像(坐像丸彫)、造立1820 文政 3 6 吉 鵠沼海岸7-4-17地先浜道地蔵堂の第25番札所弘法大師像(坐像丸彫)、 造立1820 文政 3 6 吉 浅場邸内の準四国八十八箇所霊場第56番札所弘法大師像(坐像丸彫)、 造立1820 文政 3 本鵠沼5-10-21苅田稲荷の第41番札所弘法大師像(坐像丸彫)、造立1821 文政 4 3 浅場太郎右衛門、普門寺境内に大師石像と大師堂建立1843 天保14 2 4 堀川山上新右衛門、鵠沼海岸7-19-12に地蔵尊立像・高根地蔵堂造立1943 昭和18 日本精工拡張で東毘沙門堂準四国第63番大師像を鵠沼墓地 髙松家墓所に移動1958 昭和33 1 20 鵠沼松が岡4-19-5小田急線一木通り踏切脇の地蔵菩薩立像、造立1986 昭和61 11 21 鵠沼神明3-4(鵠沼墓地)の延命地蔵、造立1995 平成 7 関根善之助、普門寺境内に大師堂建立、寄進 ・・・つづく・・・
2025.11.25
閲覧総数 293
-
4

龍の口竹灯籠へ-2
本堂の手前、右奥にあった日蓮大聖人像を撮ったが・・・。昼間であれば。しっとりと闇に沈む竹筒の奥、ひとつの小さな灯が、まるで呼吸するように揺れていた。外の冷たい夜気とは対照的に、内側の竹肌は炎にあたためられ、淡く琥珀色に染まり、何十年も風雨にさらされてきた竹の表情までも優しく浮かび上がっていたのだ。龍の口竹灯籠の灯りは、ただ“照らす”のではなく、見る人の心に柔らかな静寂をしみ込ませ、急ぐ時間の歩みをふっとゆるめてくれるのだった。大書院手前の「幻想庭園」。夜の闇を背景に、光・竹・水・そして“物語”がひとつの舞台のように組み上げられていた。 ■ 空間の主役 ―― 龍の姿画面右側に横たわる流木から形づくられた龍は、まるで今にも息をし、闇へと舞い上がるかの如くに。赤い点の“目”がほのかに光り、静寂のなかに潜む力を象徴しているようでもあった。近づいて。■ 流れる光 ―― 水と竹の呼応左下の竹灯籠の群れは、柔らかい切り抜き模様から光がこぼれ、白い霧に反射してゆらゆらと漂っていた。それはまるで地から立ち上る気のよう。■ 背後に浮かぶ天女の影竹垣に映し出された天女は、光の線がかすかに震えながら形を保っており、龍が天へと昇る時に現れる導き手の如くに。龍と天女が同じ画面に収まることで、“龍口”という土地の伝承性がとても濃く演出されていた。そして右下の水面は青く照らされ、龍が棲む清浄な池のイメージ。竹の黄色い光と対比することで、「地の灯」と「水の灯」が呼応していた。様々な角度から。青い水面に散った緑の光は、ただの反射ではなく、水の上に咲く星の花の如くに。ひとつひとつの光は鋭く、しかし水のゆらぎに合わせて静かに形を変えながら漂っています。まるで、「夜の池に、緑の星座が降りてきた」そんな印象であった。青の深い水底は夜空のようで、その上に落ちた緑の光は瞬き、淡く滲み、やがてまた別の姿に生まれ変わるのであった。■ 流れる光 ―― 水と竹の呼応左下の竹灯籠の群れは、柔らかい切り抜き模様から光がこぼれ、白い霧に反射してゆらゆらと漂っているのであった。それはまるで地から立ち上る気の如くに。■ 竹の灯りがつくる、やわらかな陰影手前の丸い竹格子の灯りは、光が細かい編み目を通って外へこぼれ、周囲にやさしい揺らぎの模様を落としていた。■ 奥に浮かぶ竹細工の明かり後ろの吊り灯籠は、竹の表皮を薄く削ったような柔らかな曲線を持ち、まるで小さな行灯(あんどん)が枝先にとまっているかの如し。木の葉がわずかに揺れると、灯りもふわりと呼応し、“晩秋の息づかい”を感じさせるのであった。ズームして。■ 編み目からこぼれる、温かな光竹の細かな輪の連なりが無数の小さな“窓”となり、そのひとつひとつから温かな光がこぼれ出ていた。強い光を受け止めながらも、編み目がそれを和らげて。そして、その先右側にあった龍の竹灯籠。■ 闇に浮かぶ金色の龍切り抜かれた竹の隙間から漏れる灯りが、鱗、爪、髭、そしてうねる体の曲線を鮮やかに浮かび上がらせていた。灯りは一点ではなく、竹一本一本に宿っているため、龍の輪郭は“燃えるような揺らぎ”をまとい、まるで今にも息を吹きかけて動きだしそうに。右側には「龍」そして「竹かぐや」の文字も浮かび上がっていた。 左側下には、山門先の境内に並ぶ竹灯籠の姿が。ズームして。■ 闇から現れる龍の横顔横から見ると、光が竹の奥から溢れ、彫り抜かれた線のひとつひとつが浮き彫りのように立体的に浮かび上がっているのであった。細長い鱗の並び、胸の張り、うねる胴の曲線――どれもが光の強弱と陰影で生命感を帯びて見えたのであった。山門先の境内に並ぶ竹灯籠の姿を見下ろして。龍口寺・大書院。その前には、竹灯籠が横向きに地面に置かれ、ただの“道の明かり”ではなく、歩く人を静かに導く、光の川のように見えたのであった。■ 線となって流れる灯り細長い竹に空けられた無数の丸い穴から、白い光が点々とこぼれていた。その光が連続すると、まるで夜の大地の上に一本の光の流線が描かれているように。歩くたびに、視線の先へすっと伸びていくその線は、流れゆく川のようでもあり、星座を地面に散らしたようでもあったのだ。近づいて。■ 粒が生む「光の流れ」竹の中を流れる光が、そのまま大地へ滲み出して。大小の丸い穴からこぼれる光は、ひとつひとつが金色の粒のように。その粒が密になったり疎になったりしながら曲線を描くことで、まるで光自身がしなやかに蛇行する一本の川になっているのであった。「遠藤笹窪谷公園竹灯籠エリア藤沢市で最も豊かな自然が残されている場所の一つである「遠藤笹窪谷公園」の【ほたるのタベ】イベントで使用された灯籠が並べられています」。 そして仁王門まで下り、「龍口刑場趾」を見る。■龍ロ刑場跡とは?龍ロ刑場跡(神奈川県藤沢市片瀬3丁目)は、鎌倉時代に設けられた処刑場で、現在の龍ロ寺周辺に位置する歴史的霊場です。1271年、日蓮聖人(日蓮大聖人)が幕府の弾圧を受け、「龍ノロの法難」として知られる処刑未遂事件の舞台となりました。この時、日蓮は斬首されそうになったものの、伝説によれば江の島方面から光の玉が飛来し、処刑が中止されたとされます。この出来事が「龍ロ法難」として日蓮宗の四大法難の一つに数えられ、現在は龍ロ寺がその歴史を伝える場所となっています。周辺は住宅地に変わっていますが、過去の処刑場の記憶が残っているとされています。 再びテント作りの「受付」を見る。 そして龍口寺前交差点を通過する江ノ島電鉄の車両を。神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目にある江ノ島電鉄と道路併用のカーブが、江ノ島電鉄・龍口寺前交差点。江ノ島電鉄は、江ノ島駅のすぐ東側、龍口寺前交差点付近から鎌倉方面の神戸橋交差点までが、道路併用区間で、龍口寺前交差点のR=28mは、普通鉄道としては日本一の急カーブとなっているのだ。そして江ノ島電鉄・江ノ島駅に到着。ポスター「SHONAN SUNSET」。夕陽に照らされた雲が、赤、橙、紫へと滑らかに溶け合い、まるで空全体が燃えているかのよう。湘南の空が時折見せる、“奇跡の色彩”が完璧に捉えられていた。 遠くに見える富士山は、赤く染まる空に黒い影として浮かび、堂々とした存在感を放って。このシルエットこそ、湘南の夕景が人の心を惹きつける大きな理由のひとつ。「江ノ島」駅。 鎌倉行きの電車が入線。■江ノ電はどこで列車すれ違いするのでしょうか?鵠沼、江ノ島、稲村ヶ崎、長谷の各駅と、鎌倉高校前-七里ヶ浜間にある峰ヶ原信号場ですれ違います。鵠沼と稲村ヶ崎は島式(1面2線)、江ノ島と長谷は対面式(2面2線)です。峰ヶ原信号場には客扱いをするホームはありません。島式ホームとは、ホームの両側が線路に接している形状のこと。まるで線路が島を取り囲んでいるかのように見えることから島式ホームと呼ばれています。そして利用した藤沢駅行きの電車が。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・
2025.11.24
閲覧総数 360
-
5

龍の口竹灯籠へ-1
すばな通りを進むと、右手にあったのが江ノ島電鉄「江ノ島」駅。 江ノ島電鉄「江ノ島」駅前の小鳥オブジェ・通称『江のピコ』。小鳥のオブジェ付きの車止めの名は「ピコリーノ」。地元の女性が季節に合わせて手編みのカラフルな衣装を着せ替えていることで有名で、観光客の人気スポットになっている。もともとは、子どもがポールに飛び乗って怪我をしないようにという安全対策の工夫として小鳥のデザインが採用されたもの と。踏切を渡り、「江ノ島駅」を見る。 そして目的の「龍の口竹灯籠」の行灯(あんどん)型の照明 。和紙風のパネルに、幾何学模様(和柄・アイヌ文様にも近い図形)がプリントされていた。模様は矢羽根、山形(杉綾)、菱形などを組み合わせたデザイン。「龍口明神社(元宮)」の石鳥居が左手に。もともとは龍口(たつのくち)の龍口寺西隣に建っていたが、安政2年(1773年)に龍口が片瀬村(現藤沢市片瀬)に編入されて以降、境内地のみ津村の飛び地として扱われた。鎌倉時代には刑場として使用された時期もあり、氏子達は祟りを恐れ、長年移転を拒んでいたという。大正12年 (1923年)、関東大震災により全壊、昭和8年 (1933年)に龍口の在のままで改築したが、昭和53年(1978年)に、氏子百余名の要望により、江の島を遠望し、龍の胴にあたる現在の地へと移転した。なお移転後の現在も、旧境内は鎌倉市津1番地として飛び地のまま残っており(周りは藤沢市片瀬)、拝殿・鳥居なども、移転前の姿で残されている。扁額は「龍口明神社」。「第十五回 龍の口竹灯籠」のポスター。・開催日: 2025年11月14日(金)、15日(土)・時間: 午後5時~午後8時・場所: 龍口寺境内(神奈川県藤沢市片瀬3-13-37)・内容: 龍口寺境内に約3,000基の竹灯籠が並べられ、ろうそくの光に包まれる幻想的な秋の夜を楽しむイベント。詣者のご先祖様の供養や願いごとの祈願も行われると。龍口寺境内に並べられた約3,000基の「竹灯籠」に灯るロウソクの光に包まれながら本堂前に施餓鬼壇を整え、参詣の方々のご先祖様や、亡くなられた方のご供養や、お願いごとなどの祈願を行います。竹灯籠の灯りが描き出す幻想的な夕べを大切な人とお楽しみください と。灯籠奉納受付所のテントが前方に。「奉納者芳名板(ほうめいばん)」が右手に。 龍口寺の仁王門(山門)前の「第十五回 龍の口竹灯籠」の入口の飾り。複数の竹灯籠を組み合わせたゲートが設置されていた。● 左側の竹灯籠の刻字「龍 口 寺」1本の竹に「龍」「口」「寺」の3文字が、節と節の“間”に1文字ずつ縦に配列されていた● 右側の竹灯籠の刻字「藤 沢 市」(同じ構造)● 中央下部の竹筒「竹灯籠」と刻まれた短めの竹灯籠が金属製U字ガードレールの前に置かれている。仁王門。扁額「龍乃口」と。 仁王門の先の石段。山門前の石段を斜めから。山門は元治元年(1864)竣工で、欅造り銅板葺。大阪雲雷寺の発願で、豪商鹿島屋某が百両寄進し建立された。正面から。短い竹筒の上部を斜めに切られた竹灯籠が中央、左右に並べられ、内部に本物の蝋燭が灯されていたのであった。LED ではなく蝋燭の灯りが特徴。蝋燭の灯りの特徴。・光が 揺らいでいる(ゆらぎのある光)・光の色が 温かみの強い橙色で、中心が明るく外側が徐々に弱まる・切り口から漏れる光が不均一で自然な形状をしている・同じ灯籠でも光の強弱が微妙に違う・LED特有の白っぽさ・均一な広がりがない上部から覗くが如くに。龍の口竹灯籠会場図。山門の両側に置かれた和傘が刻々と色・模様が変化する、プロジェクションライト(模様投影ライト)が照射されて。左側。右側。「アメリカデイゴ(亜米利加梯梧)」の花もライトアップされて。バナナのように反り返った形 をしている赤い花をズームして。山門を潜ると参道の両側には、多くの竹灯籠(たけとうろう) が びっしりと並んでいた。大小さまざまな竹灯籠。斜めの切り口から炎の橙光が漏れるのであった。光がひとつひとつ微妙に揺らぎ、均一ではない自然な光のゆらめきが生じている。LED光ではなく蝋燭のため、光の揺れ方・明滅の仕方が柔らかいのであった。参道の右側に並べられた竹灯籠は、渦巻き状・曲線状の軌跡を描いて配置されていた。移動して。竹灯籠一つひとつの内部で灯る蝋燭(ろうそく)は、・揺らぎのある光・中心が明るく、周囲が自然に減衰する光・個体差のある微妙な強弱を持っているのであった。大書院への石段にも竹灯籠が並び、その上にも竹灯籠のオブジェの姿が。ズームして。裏側から見ても絵柄模様が判らなかった。周囲は暗く、灯籠だけが明るいため、コントラストが高く、光の形状が際立つのであった。竹筒は一本一本、太さ・節の位置・切り口の角度が僅かに異なる。その差が光の強弱として現れ、LED照明とは違う自然な揺らぎとなって視覚に訴えるのであった。竹灯籠の光が地面や石段に反射し、弱い二次光が全体の明るさを底上げしていると感じるのであった。手水舎手前を。大本堂とのコラボ。闇に沈んだ境内の土の上に数え切れぬほどの小さな灯りがまるで呼吸するように揺れていた。ひとつひとつは、竹の内奥で燃える小さな炎にすぎないのに、寄り添い、並び、つながるとまるで大地そのものが灯っているかのようであった。渦を描く火の道は、見えない風の手に導かれ、やがて階段の灯りへと吸い込まれていく。その先には、古い寺の影が青白い光に照らされて、息づいているのであった。炎は風に怯えながらも、一瞬のために命を燃やし、闇の中で人の心をそっと照らしていた。立ち止まったその場所だけ、時が静かに、柔らかく、滲むように流れていたのであった。左手には浄行菩薩像が。大本堂前。大本堂前から山門方向を見下ろして。参道には多くの見物客の姿が。 ・・・つづく・・・
2025.11.23
閲覧総数 420
-
6

片瀬西海岸からの夕景-1
この日は11月15日(土)、朝から鵠沼へ「藤沢地名の会 地名探索」に参加し15時前に終了し解散する(後日ブログアップ予定)。17時から始まる片瀬・龍口寺で開かれている「第15回 龍の口 竹灯籠(たけとうろう)」を観に小田急片瀬江ノ島駅に向かう。片瀬江ノ島駅構内には大型のクラゲの水槽が設置されているのだ。半透明のミズクラゲでゆったり浮遊する様子は実に幻想的なのである。クラゲ水槽に近づいて。クラゲ水槽は改札内へのコンコースにあり乗降客は早速記念写真やスマホに撮っていた。この水槽は少し離れた場所にろ過装置が設置されていて、配水管を通し水質管理、水温調節、異常が生じれば新江ノ島水族館に即伝わる仕組みなどが備えられているのだと。同館クラゲ担当の方は毎日、餌やり、海水の状況、ミズクラゲの姿の確認など行うのだ と。ミズクラゲ(Aurelia aurita)をズームして。特徴は・体が円盤状で透明。・中央に四つ葉のクローバー状の“4つの輪”(=生殖腺)が見える。・触手は細く短い と。■ どこに生息している?・世界中の温帯〜熱帯海域に広く分布。・日本では沿岸部ならほぼどこでも見ることができる。・港湾や内湾など、やや富栄養化した場所にも多い。1. 傘の縁に細かい“フリル状のひだ”が並んでいるミズクラゲ最大の特徴は、傘の縁に多数の触手(短いタテガミ状)がずらりと並ぶこと。この縁の部分だけがくっきり写り、「レース」「羽毛」のように見えたのであった。・薄くて平たい傘 横から見ると、ミズクラゲは扇形・半月形に見えることがある。・傘表面に模様が無い タコクラゲ、サカサクラゲ、アマクサクラゲなどは模様があるが、 ミズクラゲは透明で模様がほぼ無いのだと。傘をゆっくり収縮→拡張のリズムで動いていた。主に“漂う”生き物で、潮流や水流に大きく影響されるのだと。小田急電鉄・片瀬江ノ島駅(2020年改築の新駅舎)。この駅舎は、日本でも珍しい 「竜宮城(りゅうぐうじょう)をモチーフにした駅」 として有名。■ 1. 竜宮城をイメージした外観・建物全体が「浦島太郎がたどり着いた竜宮城」をモデルに設計・朱色・金色・青緑の屋根という華やかな配色・千鳥破風・唐破風、曲線の軒先など“神社建築+竜宮城”のデザイン → 江ノ島観光の玄関口として象徴的な駅舎に仕上がっている■ 2. アーチ形の入口(白い「門」)・写真中央の白いアーチ部分は、・竜宮城の入口「門」のような造形を模しており、・曲線を強調した意匠になっています。■ 3. 金色の装飾・屋根の各所に金箔風の装飾が施され、・「竜宮城の豪華さ」を演出。そして片瀬西浜にある片瀬漁港に向かって進む。片瀬江ノ島駅前(駅前ロータリー付近)から美しい夕日の姿が現れた。時間は17:12。この場所のこの日の日没は17:37と。椰子(ヤシ)と夕日のシルエット。フェニックス(カナリーヤシ)。江ノ島周辺のランドマーク的な植栽で、リゾート感を演出しているのであった。国道134号線が前方に。江ノ島周辺ならではの植栽である フェニックス(カナリーヤシ) が逆光でくっきり浮かび上がり、晩秋の江ノ島らしいドラマチックな夕景が眼前に拡がったのであった。まっすぐ伸びた高いヤシの木は、江ノ島周辺によく植栽されているフェニックス・カナリエンシス。幹が真っすぐ、頭頂に大きな扇状の葉、シルエットが非常に美しい樹形なのであった。夕日との相性が抜群で、まさに「湘南らしい風景」を象徴しているのであった。雲の下に空隙(すきま)があり、太陽光がそこから漏れていた。晩秋・初冬特有の澄み切った空気によって、黄金色が強く出ていて、海面からの反射光が写真下部を明るく照らしているのであった。江の島漁港の整備完了を記念して、「無事故を祈願して」建てられたという「海の詩」の像。■ 作品名海の詩(うみのうた)■ 作者親松 英治(おやまつ えいじ)日本の彫刻家で、湘南地域に複数の作品を残しています。■ 所在地片瀬漁港(片瀬海岸)の広場江ノ島水族館の少し西側、片瀬漁港荷捌き場の前に設置。■ モチーフ海の生命力人と魚が一体化したような躍動的造形「海とともに生きる片瀬・江の島」の象徴的作品 と。「海の詩」のシルエットが完全に夕日と重なり、“躍動感”が強調された写真が撮れたのであった。移動して、江の島を背景に。片瀬漁港(片瀬江の島漁港)から見た相模湾の夕日 を捉えて。手前が片瀬漁港の内湾。静かな水面が夕日の光を伸びやかに反射していた。片瀬漁港の外側の防波堤には人影が見え、散歩や写真撮影をする人が立ち並んでいるのがわかるのであった。雲の下側が切れているため、雲と地平線の隙間から光がこぼれる“ドラマチックな夕焼け” の典型的パターンを捉えることが出来たのであった。非常に薄くだが、遠くに箱根・伊豆半島の山影が見えた。条件が良い日はこの位置に富士山のシルエットも現れるのだが、この日は富士山は雲に隠れて。海面の反射(グラデーション) が主役になっていたのであった。片瀬漁港の外側の防波堤をズームして。その手前には、水面の黄金の“光の道”(サンロード)が現れていたのであった。太陽から海面にまっすぐ伸びる光が美しく、静かな片瀬漁港の雰囲気を引き立てていた。片瀬漁港から江の島を望む夕景を。漁船の静かな佇まいと、江の島シーキャンドル(灯台)のシルエット、そして海面に映る柔らかな光が融合して、まさに “片瀬漁港らしい夕景”なのであった。写っているのは片瀬漁港の定置網・釣り船・遊漁船など。写真中央の船には「第十八ゆうせい丸」と読み取れる文字があり、実際に片瀬漁港に所属する船。太陽が雲に隠れて、水面の黄金の“光の道”(サンロード)が姿を消した。夕陽が沈みゆく空の中で、雲の縁だけが薄く金色をまとい、まるで空が自らの境界をそっと縁取っているように白い輝きが静かに滲んでいるのであった。雲のふちに夕陽の光が当たって、白くきらりと光っている。まるで雲が輪郭だけ輝いて浮かび上がっているようなのであった。そして沈みゆく太陽が厚い雲の下からわずかに顔をのぞかせ、その光が雲の縁を内側から焼き付けるように再び白く輝く。闇へと沈む雲の下で、陽光だけが最後の抵抗のように鋭い光の縁を刻んでいるのであった。沈む陽が雲の縁を白く照らし、港の水面まで夕光が流れ込む時間なのであった。停泊した漁船の影が静かに伸びて。いつまでも佇んで見つめていたい時間、空間なのであった。ズームして。太陽に近い部分は、黄色・白色・ややオレンジが混ざった高輝度の輝きが確認できる時間なのであった。反射の中心は太陽直下にあり、強い橙色の帯(光の道)が水面に伸びていた。水面は完全な静水ではなく、小さな揺れ(リップル)があるため、反射光が細かな線状に分解されて揺れて見える状態なのであった。太陽は水平線に向かって。円形がほぼ完全に見える状態に。厚い雲の縁は太陽が真下にあるため、逆光によって輝く「エッジライト」現象が発生しているが如くに。 ・・・つづく・・・
2025.11.21
閲覧総数 400
-
7

片瀬西海岸からの夕景-2
太陽が再び顔を見せ、見事な光の帯が。反射光が細かく分断され、光の帯がざらついた質感で揺れて見えていた。手前側は比較的影になっているため、反射光の明るさがより強く際立つ状態で。光の帯の先端の砂浜で遊ぶ親子連れ。これは典型的な「サンロード(太陽の道)」と呼ばれる現象。「太陽の道」とは、弱い風が吹き、水面に小さな波が立つなど特定の条件が揃った時に、水面に光が反射して道の様に見える自然現象を指す。ズームして。太陽が水平に伸びる雲に一部隠されている状態を正面から。太陽の上半分は雲の上に出ており、下半分は雲の下から。海面には太陽の光がまっすぐ縦に反射していて、明るい光の帯が海の表面に伸びていた。水面は大きく荒れてはいませんが、小さなさざ波があり、光の帯が細かく揺れた模様に。空は太陽の周りが濃いオレンジ色で、上の雲は暗く、下の方へ行くほど赤みのある色に変わって。遠くの海は影になっていて、徐々に暗く見えて来たのであった。片瀬西浜から平塚方面へ向かって、長い砂浜がゆるやかに湾曲しながら続いている様子が見えた。相模湾沿いの特徴で、江の島を基点にして西方向へ大きな弧を描くように海岸線が伸びていた。伊豆半島がプレート運動で北北西へ押し込まれているため、相模湾全体が湾口が開いた弓形の地形になっているのだ。相模川・酒匂川などの河川が運んだ砂が、沿岸流によって東へ運ばれ、藤沢・茅ヶ崎方面に供給されることで砂浜が維持されているのだ。明るい光の帯(サンロード)が次第に弱くなり始めた。太陽をズームして。夕日が水平に伸びた雲の隙間から見えている場面。太陽はほぼ沈む直前で、細長い楕円形のように見えて来た。雲に隠れているため、上半分が覆われ、見えている部分が横に押しつぶされたような形なって来たのであった。海面が適度に揺れているため、光は一本の線ではなく、細かく分かれた光の筋が連なって帯状になっている状態に変化して。手前の海面では光が広がり、ゆらぎを伴った反射となり、光の帯がやや太く見えて来た。全体として、夕日が海面に強く反射してできる、典型的な日没時のサンロードが。太陽が水平線上部の黒い雲に隠れて、これがこの日の日没の如くに。空全体は夕方の光で淡い橙色から赤みへと変化し、上層の雲も同じ色調に染まって来た。水平線上部は暗く影になっており、その上に太陽の明るい部分だけが強く浮き上がって見えているのであった。この日の日没を追う。そしてこの日の太陽は完全に水平線上の雲に隠れて。江の島の姿を。江の島シーキャンドルの灯りは未だ。ゆるやかに湾曲する西浜からの砂浜の光景を見る。真っ赤に色づいた太陽が地平線近くに沈み、相模湾の海面からは光の帯が完全に消えて。海は夕方の暗さを帯び、表面にはわずかな揺れだけが残り、静かな水面が一様に赤みを含んだ淡い光を受け止めていたのであった。相模湾全体が静まり、光も影もゆっくりと均されていく、落ち着いた夕暮れの瞬間なのであった。江の島を背景にした、片瀬漁港周辺の夕方の光景。左奥には江の島シーキャンドル(展望灯台)があり、島全体が落ち着いた薄暗い色に包まれて来たのであった。西浜を後にして国道134号を江の島入口方向に向かって歩く。辻堂方面を振り返って。関東ふれあいの道「関東ふれあいの道」は、一都六県を巡る自然歩道です。沿線の豊かな自然にふれ名所や史跡を訪ねながら、古里を見直してみませんか。⑥ 湘南海岸・砂浜のみちこの道は、県内17コースのうちの6番目です。ここから江の島を背に国道134号を西へ、新江ノ島水族館、湘南海岸公園を通り、鵠沼橋の西縁には聶耳(ニェアル)記念碑が建っています。鵠沼橋を渡るとサイクリングロードに入り、右手に松林、左手に砂浜を眺めながら歩くと、茅ヶ崎柳島海岸が終点です。途中、海に浮かぶ烏帽子岩(えぼしいわ)や平島を見ることができます。終点からは、国道134号を渡って、北へ600mくらい歩くと、浜見平団地バス停(茅ヶ崎駅行)に到着します。片瀬橋から境川の河口そして江の島を見る。上流側には小田急線・片瀬江ノ島駅に続く弁天橋を見る。江の島上空も僅かに赤く染まって。江の島入口交差点の横に建つマンション群。小田急線・片瀬江ノ島駅を弁天橋越しに見る。片瀬江の島観光案内所のすぐ横、江の島へ渡る橋(弁天橋)に向かう歩道沿いに設置されている沿道アート(ストリートモニュメント) 。天に昇るモダンなイメージの龍が。折しも観光客を乗せた人力車が2台。中国人であっただろうか?国道134号「江の島入口」交差点越しに江の島を見る。 すばな通りを江ノ島電鉄・江ノ島駅方向に進む。「塩バニラ君」と。名物江の島塩バニラ・ソフトクリームの店。口に入れると塩気→甘味→塩気と風味が移り変わるのだと。「すばな通り」とは神奈川県藤沢市・片瀬江ノ島駅前から江の島弁天橋へ向かう商店街(約250m)の通り。観光客が江の島へ渡る際に必ず通る“江の島参道の入口”にあたります。江ノ電「江ノ島駅」、湘南モノレール「湘南江の島駅」から江の島に向かう道。「すばな通り(洲鼻通り)」の名前の由来は、この地域に古くからある地名 「洲鼻(すばな)」 に基づくと。● “洲鼻” の意味「洲(す)」= 川口や海辺にできる砂州(砂が堆積した細長い土地)「鼻(はな)」= 地形が突き出した部分(岬のような意味)つまり「海に向かって細長く突き出した砂州の先端部分」を意味する。江の島の付け根(片瀬側)は、昔は砂州が東西に伸びる地形で、まさに「洲鼻(すばな)」と呼ぶのにふさわしい土地であった と。「ここは すばな通り 江ノ電江ノ島駅」碑。 ハラミステーキカレー・ピザの店「Kalae Ribs kitche」。すばな通りを北へ進むと左側に「道標」と案内板。江の島弁財天道標。この道標は、平成十一年一月、ここより170メートル南の洲鼻通りの地下から、道路工事中に発見され、追加の指定を受けたもの と。「市指定重要文化財(建造物) 昭和四十一年(1966)一月十七日指定「江の島弁財天道標」この石柱は、江の島への道筋に建てられた道標の一つです。江の島弁財天道標は、管を用いて鍼をさす管鍼術を、江の島で考案したという杉山検校が寄進したと伝えられ、現在市内外に十数基が確認され、そのうち市内の十二基が藤沢市の重要文化財に指定されています。すべて頂部のとがった角柱型で、その多くが、正面の弁財天を表す梵字の下に「ゑのしま道」、右側面「一切衆生」、左側面に「二世安楽」と彫られています。この文言は、江の島弁財天への道をたどるすべての人の現世・来世での安穏・極楽への願いが込められています。この道標は、平成十一年(1999)一月、ここより170メートル南の洲鼻(すばな)通りの地下から、道路工事中に発見され、追加の指定を受けたものです。 平成二十六年(2014)三月 藤沢市教育委員会 」 「湘南しらす」の幟旗の店。 「湘南生しらす井 ¥1,450」と。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・
2025.11.22
閲覧総数 392
-
8

牛久大仏へ(その3)
牛久大仏の胎内への入口。■ 牛久大仏・胎内構造(参考)階層 名称 内容地下 光の世界 阿弥陀如来の光を表す演出空間1F 知恩報徳の世界 壁いっぱいの金色の万体仏2F 蓮華蔵世界(ご慈光の世界) 絵画・展示3F 霊鷲山の間 説法の場を模した空間4F (機械室) —5F 展望室(地上85m) 窓から外の景色を眺望※「光の世界」は実際には地下フロアに位置しています。牛久大仏の内部「光の世界」(地下・胎内 1階)。阿弥陀如来像(あみだにょらいぞう) の小型立像で、背後に大きく放射状に広がる 後光(ごこう) が特徴。「光の世界」は牛久大仏の胎内の入り口であり、・阿弥陀如来の十二の光・救済の光・浄土の入り口を象徴した空間。足元には賽銭箱が置かれていた。ズームして。牛久大仏の胎内 2階「蓮華蔵世界(れんげぞうせかい)」 の内部通路。「光の世界」に続く通路にあたる空間。胎内 2階「蓮華蔵世界(れんげぞうせかい)」 に展示されている光の書(ライトアップ書作品)「本願:阿弥陀如来の根本の誓い「四十八願」の総称。浄土真宗ではとても重要な言葉 無碍光(むげこう):阿弥陀如来の「十二光」のひとつ “さまたげられることのない光”“無限の智慧の光”」 万燈会(まんとうえ):無数の灯り(ろうそく・灯籠)を供え、仏や霊に追善供養する 法会(ほうえ) のこと。 牛久大仏でも、夏の行事として「万燈会」が開催され、 夜の大仏と灯りの幻想的な雰囲気が人気である。 そのため胎内展示にも「万燈会」という書作品が並べられていた。大仏胎内1階の香りは蓮花(はす)の香りです。知恩報徳の世界(2階)阿弥陀如来への報恩感謝の気持ちで、祖師の御化導としての写経をさせていただきましよう と。「東本願寺 浄土真宗東本願寺派 本山」。ここは牛久大仏の内部、展望階(地上85m)へ向かう導線付近の壁面装飾。『空と佛 SORA × HOTOKE地上120m 世界一の大仏様と天空の眺め』“地上120m” は牛久大仏の総高を指し、“天空の眺め” は 大仏胸部(地上約85m)に設けられた展望室からの景観を表していた。さらに進む。額の下の札に書かれている文字:浄土の阿弥陀如来(切り絵)額の右下の小さなラベル:阿弥陀如来立像この作品は、阿弥陀如来(阿弥陀仏)を切り絵で表現したもの。・背後の放射状の光(光背)は「十二光仏」としての阿弥陀如来を象徴・足元の蓮華は「極楽浄土」の象徴・右手を上げ左手を下げた姿は「来迎印(らいごういん)」で、 亡くなった者を浄土へ迎えるときの姿素材が金色で描かれており、切り絵としては非常に豪華な表現。世界最大青銅製の大仏様ギネス世界記録:1995年に登録されました各部寸法・全長 120m・展望台 85m・総重量 4000t・左手の平 18.0m・顔の長さ 20.0m・目の長さ 2.5m・口の長さ 4.0m・鼻の高さ 1.2m・耳の長さ 10.0m・人差指 7.0m(比較図)自由の女神(40m)奈良の大仏(14.9m)階層表示4・5F 蓮華山の間3F 知恩報徳の世界(20m)2F 知恩報徳の世界1F 光の世界牛久大仏 ギネス証「WORLD RECORDGUINNESS BOOK OF RECORDSTHE TALLEST STATUEIS A BRONZE STATUE OF BUDDHA120 METRES HIGHIN USHIKU CITY, JAPANSTRUCTURALLY DESIGNED AND BUILTBY KAWADA INDUSTRIES, INC.AND COMPLETED IN 1993PETER MATTHEWS NORRIS McWHIRTER(Peter Matthews の署名) (Norris McWhirter の署名)」【世界記録ギネスブック(ギネス世界記録)世界で最も高い像は、日本・牛久市にある高さ120メートルの青銅製の大仏像です。この像は 川田工業株式会社 によって構造設計および建設され、1993年に完成しました。(ピーター・マシューズ、ノリス・マクウォーター署名)】 「光雲無碍(こううんむげ)浄土真宗でよく用いられる言葉で、・阿弥陀如来の光明(智慧の光)は、雲に遮られることなく、すべてを照らす・どんな迷いや煩悩があっても妨げられず、平等に救いが及ぶという教義を表す語」 と。右足親指先端の実物大模型牛久大仏の右足親指は、長さ:約1.7m人がすっぽり入るほど巨大で、展示されている模型はその 先端部分 をそっくりそのまま再現したもの と。世界一背が高い大仏浄土真宗東本願寺派・本山東本願寺の開祖・親鸞聖人ゆかりの地である、常陸の国。その地に仏都の中心的なものとして建立されたのが、台座をふくめると120mもの高さになる青銅製立像「牛久阿弥陀大仏」です。この茨城県牛久市にある世界一背が高い大仏は、胎内に入ることができ、地上85mまでエレベーターで上がることができます。総重量は4000t。目の長さ2.5m、耳の長さ10m、人差し指7mという大きさです。浄土庭園本願荘厳の庭(図中の各名称)・正覚の滝(しょうがく)・四十八願の石(しじゅうはちがん)・大心海(だいしんかい)・願船亭(がんせんてい)・因位の流れ(いんい)・悲願の湧泉(ひがんのゆうせん)・願力廻向の流れ(がんりきえこう)・横超の橋(おうちょう)浄土庭園・牛久阿弥陀大仏・本願荘厳の庭・群生海(ぐんじょうかい)・發遣門(はっけんもん)・定聚苑(じょうじゅのその)・正門御本尊(東本願寺御本尊阿弥陀如来立像)四天王寺の宝塔心柱をもって制作された鎌倉時代前期の名作。東京都の有形文化財に指定されている。親鸞聖人御旧跡(~関東における親鸞聖人の足跡~)建保二年(一二一四年)四十ニ歳の春、親鸞聖人は妻子をともなって常陸の国へと移り住まわれ以降、約二十年間にわたってこの地で布教の日々を送られました。稲田を中心に教化を進められ、以降、筑波山、鹿島など各地をまわり布教された親鸞聖人の足跡は、数多くの寺院や旧跡、伝説などによって、今もしのぶことができます。浄土真宗の根本聖典となる「顕浄土真実教行証文類」(教行信証)」は、この間に著されたものであり、その完成年をもって浄土真宗立教改宗の年(一ニニ四年)としています。「親鸞聖人略年譜親鸞聖人は承安三年(一一七三)京都日野の里にてお生まれになりました。養和元年(一一八一)九才のとき、青蓮院において慈円僧正のもとで出家され仏教を学ぶため比叡山に登られ、横川の常行三昧堂で修行された聖人は、どうしても自らの問題を解決できませんでした。建仁元年(一二〇一)二十九才のとき山をは下りられ六角堂に百日間こもられてのち、吉水の法然上人のもとへ行かれました。法然上人のもとで阿弥陀如来の本願による完全な他力念仏(浄土門)を学ばれました。聖人は、阿弥陀如来の本願による念仏の教えは、すべての人々に平等であり、釈尊がお生まれになったのは、この教えを説くためであったと確信し、布教活動をされました。しかし、承元元年(一ニ〇七)三十五歳のとき、念仏禁止の法難にあい越後(新潟県)に流罪になりました。(法然上人は土佐へ流罪)五年後赦免になりましたが、しばらく越後にとどまりました。聖人は、 四十二歳の頃、越後から常陸の国(茨城県)笠間の郡、稲田郷に移られました。稲田を中心に精力的に布教活動を行い、念仏の普及につとめられました。その間、『教行信証』の執筆に力を注ぎ、浄土真宗の教えを文章で著しました。それは阿弥陀如来の本願を信じ、念仏申せば、仏となるという教えであります。六十歳を過ぎてから聖人は、京都に帰ることになりました。京都での聖人は、著述に精進されました。今日残る浄土和讃など親鸞聖人の著作の多くは、晩年に書かれました。幾多の出会いを順縁とし、多くの苦悩を逆縁とし、ますます信仰を深めていった親鸞聖人は、弘長ニ年(一ニ六ニ年)十一月二十八日京都の僧坊にて逝去されました。」 2021年(令和3年)1月12日(火曜日)読売新聞にて掲載された記事です。「渦巻く思い、受け止めて」 牛久大仏胎内の2階には大仏建造に関する資料が展示されていた。頭部の鉄骨模型。牛久大仏(全高120m)内部の骨組み(鉄骨フレーム)を、縮尺模型として表現したもの。実物の牛久大仏は、外側が青銅パネル、内部が鉄骨構造(ビルのような構造)で作られていた。写真の模型は、その内部構造がどのように組まれているかを分かりやすく示した、「立体トラス構造モデル」であった。実際の牛久大仏の内部構造(豆知識)・鉄骨総重量:約6,000トン・鋼板(ブロンズパネル)枚数:約3,000枚・内部は「展望台」「写経の間」などがある複層構造・建築方式は「スチールフレーム構造(鉄骨造)」で、巨大建築物そのもの。牛久大仏の顔と手の骨組みの模型。「高さ100メートルの大掃除」と御本尊。高さ100メートルの大掃除日本一大きい牛久大仏で、秋のお彼岸に年に一度の大掃除が行われた。清掃員は大仏の眼からロープにぶら下がり、高さ約1 0 0メートルにある大きな顔の汚れをプラシなどで手際よく流して行く と。牛久大仏の外部メンテナンスでは:・外壁の清掃(高圧洗浄)・銅板継ぎ目の点検・腐食・亀裂の有無チェック・塗装補修・避雷針の点検・受雷による金属疲労の検査などが行われていると。牛久大仏は落雷を頻繁に受けるため、避雷設備は特に重要である と。作業員がロープアクセス(高所作業技術)で清掃のため大仏の「まぶた部分」から外部へ出る場面の写真をネットから。写真位置は大仏の目の高さ(約80m前後)にあたるのだと。螺髪の清掃に向かう清掃作業員。これもネットから.春には桜の花が。エレベーターで牛久大仏の高さ85mの展示室・展望台まで上がる。(写真はネットから)牛久大仏の展望窓。牛久大仏の展望窓(胸部の高さ約85m地点)から見下ろした景色 。窓の隙間から見えているのは、大仏の足元に広がる 牛久浄苑(うしくじょうえん) という大規模な霊園。「お胸の部分の三本の窓この窓は、右端から見ても左端から見ても、同じ景色が見えます。三つの窓は、私達が迷わす信心を深める為心を一つにさせて頂けることを表現しております。」 参道と發遣門。こちらも参道と發遣門。白い建物の屋上一面に並ぶ太陽光パネル。「大仏比較図」左から順に🗿 牛久大仏(120m)・台座まで含めた総高 120m・地上85mに展望台(胸の位置)・立像として世界最大級・奈良の大仏(約18m)の約6〜7倍の高さ🏛️ 国会議事堂(高さ 約65m)・牛久大仏の半分強ほどの高さ・比べると大仏がいかに巨大かよくわかる🗽 自由の女神(台座込み 40m前後)・ニューヨークの自由の女神・牛久大仏の3分の1ほどしかない🗿 奈良の大仏(14.9m)・こちらは有名な東大寺の大仏・牛久大仏は奈良の大仏の「約8体分」の高さに相当■ 牛久大仏の圧倒的なスケールがわかる図この図からわかるポイント:牛久大仏(120m)は、→ 国会議事堂(65m)の 約2倍→ 自由の女神(40m)の 約3倍→ 奈良の大仏(15m)の 約8倍と、世界最大級の圧倒的な高さを誇ることが一目でわかるのであった。「仏教四大聖地」 を紹介している展示。① 成道の地(悟りの地)ブッダガヤ(右上)お釈迦さまが菩提樹の下で悟りを開いた地大塔(マハーボディ寺院)が有名仏教徒なら一度は訪れたい最重要聖地② 初転法輪の地 サールナート(左上)最初に説法をした場所(初めて“法”が転じた=初転法輪)ダメークストゥーパ(円筒形の大塔)が象徴仏教布教の始点③ 涅槃の地 クシナガラ(右下)お釈迦さまが入滅(亡くなった)された地横たわる涅槃像が安置されている未だ静かな雰囲気が残る聖地④ 誕生の地 ルンビニー(左下)お釈迦さまが生まれた地(現在のネパール)アショーカ王の石柱や池などが残る四聖地の中で最も穏やかな場所① 初転法輪の地 サールナート(左上)お釈迦さまが悟りを開いた後、初めて説法した場所写っている巨大な建造物は ダメーク・ストゥーパ(Dhamek Stupa“初めて法を転じた(初転法輪)” 聖地として世界中の仏教徒が巡礼に訪れる② 成道の地 ブッダガヤ(右上)菩提樹の下でお釈迦さまが “悟りを開いた” 場所写真は マハーボディ寺院(大菩提寺)仏教世界で最も重要な聖地の一つ③ 誕生の地 ルンビニー(左下)ネパールにあるお釈迦さまの生誕地アショーカ王の石柱 や、生誕の池がある世界遺産にも登録されている④ 涅槃の地 クシナガラ(右下)お釈迦さまが入滅(亡くなった)した場所長い涅槃像が安置される静寂の地パネルには「釈尊入滅の地」と説明があるはず牛久大仏内部では、ただ仏像を見るだけでなく、仏教の歴史・釈迦の歩みを学ぶためのミニ資料館 となっていた。この四枚の写真パネルは、釈尊の人生の重要な四か所(四聖地)をまとめて紹介している展示である。牛久大仏の胎内 4・5階「霊鷲山(りょうじゅせん)の間」 にあった金色の御仏(みほとけ)を安置した納骨堂(霊位奉安室)●霊鷲山の間(れいじゅせんのま)・牛久大仏の胎内で最上階付近(エレベーターで上がれる最上部)・三日月状の黄金の空間・数千体の金色の阿弥陀仏が並び、納骨ができる部屋として機能●金色の仏像一体ずつが「御霊(みたま)」を供養する際の御仏・各一つの棚が「一霊位」・中には遺骨または遺品が納められている場合がある・「永代供養」のための区画として申し込めるつまり、これは一般的にいう「納骨堂」「霊座」「永代供養墓」にあたるもの。ここが胎内の最上部で、静寂と光に包まれた空間であった。牛久大仏・胎内「霊鷲山の間」 にある永代供養の奉安者名(霊位)を記す名簿塔(霊位掲示柱)「南無阿彌仏」 「万燈会」。 これも 牛久大仏の胎内(4〜5階・霊鷲山の間)にある「胎内仏(小仏像)を安置した納骨壇(納骨棚)」牛久大仏の内部・納骨堂(霊堂)の中央祭壇(ご本尊前)。・阿弥陀如来の名号「南無阿弥陀仏」の掛け軸・周囲に多数の小金仏(観音像)が並ぶ・金色の荘厳された空間■ 左右にある仏像阿弥陀如来立像(胎内仏) の見本牛久大仏の胎内に奉安される小仏像(約20~30cm)極楽浄土へ導く阿弥陀如来を現したものその後ろの光背は「放射光」と呼ばれ、阿弥陀の無量の光明を表します■ 胎内仏奉安(永代経)主な内容(案内板から読み取れる部分)・胎内仏に亡き人(先祖・家族など)の法名を記す・牛久大仏胎内の「霊鷲山の間」に半永久的に安置される・毎朝・毎夕、さらに年忌にあわせて永代経(供養)が営まれる・供養料(永代経志納金)が一口 20万円(案内板に明記)・希望により複数口の申し込みも可能・法名(戒名)、俗名、没年月日などを記録し管理仏教で最も重要な象徴のひとつ「蓮華(れんげ)」蓮は泥の中から清らかな花を咲かせるため、「迷いの世界(煩悩)から悟りへと開く清浄さ」 を象徴。牛久大仏の胎内にある「写経(写仏)・休憩スペース」。壁に掛けられているのは、写仏(しゃぶつ)作品・仏さまの線画に、花や季節のモチーフを加えた彩色写仏・背景に筆文字(願い・法語)・作者による手書きの書と絵が組み合わされた奉納作品牛久大仏では参拝者が写仏をして奉納することもでき、その代表的作品が展示されていることがあるとのこと。座布団の並んだ段状の座席は 写経や写仏、または法話・瞑想などを行うための座席 と。ズームして。写経・写仏体験コーナー」で、写真の二人は 写経(または写仏)をしているところ。「宗教の共通点(しゅうきょうのきょうつうてん)信じること感謝すること奉仕すること(ほうしすること)」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.19
閲覧総数 352
-
9

牛久大仏へ(その4)
牛久大仏の内部見学を終えて、地上へ。「本願荘厳の庭(ほんがんしょうごんのにわ)」・本願(ほんがん) 阿弥陀仏の「本願」(衆生を救う誓願)を意味します。・荘厳(しょうごん) 仏教語で「飾り整えること」「厳かに美しく整えること」。 仏や浄土を荘厳=美しく表現する、という意味があります。・庭(にわ) そのまま「庭園」。つまり 「本願に基づいて荘厳(美しく整え)られた庭園」 という意味で、牛久大仏周辺にある浄土庭園の一部(日本庭園)を指す案内板牛久大仏の敷地内にある 「本願荘厳の庭」 の一部、つまり日本庭園の中心となる 池泉回遊式庭園 の景観。① 池泉(ちせん)庭の中心に広がる大きな池で、水面に周囲の木々が映っていた。池泉回遊式庭園は、日本庭園の中でも歩きながら景観を楽しむタイプで、牛久大仏の庭園でも代表的な構成。② 配石(石組)右側に大きな岩が配置されていた。これは山や島を象徴し、庭園の構図に重心と静けさを与える伝統的な手法。③ 滝口と流れ左奥には小さな滝(流れ)が見えた。水が動くことで庭に生命感を与え、「浄土」の象徴としても用いられていた。④ 植栽(松・低木・刈込)池の周囲には松やサツキ、日本庭園らしい丸く刈り込まれた低木を配置。これらの植栽は四季を感じるために計算されて配置され、春の花・夏の緑・秋の紅葉・冬の雪景色を楽しめるのであった。■ この場所の意味牛久大仏の庭園は「浄土の世界」をイメージして造られており、・水面の静寂・石の安定感・緑の優しさなどが調和した、非常に落ち着いた雰囲気の庭となっていた。滝口と流れ。「大心海(だいしんかい)阿弥陀如来(あみだにょらい)は大海のように広く深い慈悲と智慧のお心ゆえに「大心海」とも言われます。この池は阿弥陀如来そのものを顕わしています。」 ● 「大心海(だいしんかい)」とは?仏教で阿弥陀如来の心を形容する言葉で、「大海のように広く、深く、限りない慈悲と智慧を持つ」という意味がある。「心」が海のように無限に広がり、すべての存在を受け入れ救うという阿弥陀如来の性質を表した表現。● この庭園の池=阿弥陀如来を象徴看板にあるとおり、この池は単なる景観要素ではなく、阿弥陀如来の大いなる心を象徴するために造られた池 です。浄土庭園では、水面に「浄土」を表す意味があり、牛久大仏の庭園でもその伝統が受け継がれている。アジサイの花が開花中。近づいて。牛久大仏の胸部にある三つの長方形のスリット窓(展望窓)を下から見上げて。・大仏の胸(胸部外壁) を下からアップで撮影。・中央に 縦長の窓が3つ・下には袈裟(けさ)のひだを表した曲線の外装パネルが見えた■ この三つのスリット窓の役割① 展望窓(胸部展望室)牛久大仏の内部にはエレベーターで上がれる展望フロアがあり、高さ約85m付近(胸の位置)に展望室があった。そこから外を見るために設けられているのが、この3つの窓。② 外から見るとスリット状に見える理由・仏像の外観デザインを損なわないように細い形になっていた・内部の明かりが外に漏れさせない工夫でもある と。構造上、強風の影響を受けにくい窓形状■ この位置から見える景色胸の展望室からは牛久市一帯、天気がよければ筑波山遠方にはスカイツリー、反対側は霞ヶ浦方向まで見渡せる非常に見事な眺望とのことだが、この日は曇天で視界はあまり良くなかった。再び牛久大仏を正面から。ズームして。戻りながら、牛久大仏の境内にある「売店エリア(仲見世通りのような商店街)」 の様子を。青唐辛子 ちびっこみそ、れんこん関係の商品、にんにく味噌漬けごぼう、野沢菜、きゅうりなどの漬物などが並んでいた。牛久大仏の入口付近に並ぶ土産店のひとつ・「時代屋」。特に 漬物・佃煮・味噌・干し芋・れんこん加工品 など、茨城らしい特産品を多く扱っている店。牛久大仏の「阿弥陀如来像(立像)」を描いた絵馬。牛久大仏のスタンプ(御朱印ならぬ“記念スタンプ”)。丸い頭、柔らかい表情、赤ちゃん風の体型で描かれているのは阿弥陀如来をデフォルメした「子ども阿弥陀さま」 です。・頭の粒々 → 螺髪(らほつ)のデフォルメ・手を合わせている → 合掌(礼拝)・衣は阿弥陀如来の定型の袈裟(衣紋)・足は結跏趺坐ではなく、キャラ風に簡略化牛久大仏の巨大さとは対照的に、親しみを持ってもらうための“癒やしキャラ” に仕上げられていた。御朱印を頂きました。光雲無礙(こううんむげ)意味:阿弥陀如来の光明(慈悲の光)は、雲のようにすべてを覆い、何ものにも遮られることなく(無礙)、すべての衆生に届く。浄土三部経(特に『無量寿経』)に基づく思想で、“阿弥陀仏の光はあらゆる人を隔てなく照らす”という浄土真宗の中心思想。中央の角印は「東本願寺印」(ひがしほんがんじ)を 篆書体(てんしょたい)で分割して図案化したものであろうか。そして帰路へ。大黒PAにてトイレ休憩後、横浜ベイブリッジを渡る。海運業・T.S. Linesの大型トラック。横浜ランドマークタワーがある「横浜みなとみらい21」地区を望む。日本船籍の大型クルーズ客船「飛鳥Ⅲ(Asuka Ⅲ)」。船籍港 日本/横浜全長・全幅 230m×29.8m総トン数 52,265GT喫水 6.7m航海速力 最高20ノット横揺れ減揺装置 フィン・スタビライザー乗客数 740名乗組員数 約470名客室数 381室 (全室海側バルコニー付き)そして、定刻に無事到着し、この日の日帰り旅行を終えたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.20
閲覧総数 330
-
10

牛久大仏へ(その2)
牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)をデザインした絵馬。大仏型の絵馬も、外国人の方が書かれたものがチラホラと。木製の絵馬に青色で牛久大仏の全身シルエットが印刷されていた・右手は「施無畏印(せむいいん)=恐れを取り除く印」・左手は「与願印(よがんいん)=願いを叶える印」・蓮の台座に立つ姿も忠実に描かれていた・紐(赤色)を通して奉納できるようになっていた發遣門(ほっけんもん)牛久大仏の参道に設置された門で、参拝者を阿弥陀如来の世界へ“送り出す”という意味を持つ門。二階建てのガラス張り建築。上階に額(扁額)があり「發遣門」と書かれていた。門の向こうに大仏が一直線に見える参道の構図。左側に石仏が配置されていた。「發遣門(ほっけんもん)」の内部にあった親鸞聖人像と梵鐘(ぼんしょう)。① 親鸞聖人(しんらんしょうにん)像浄土真宗の宗祖牛久大仏は「阿弥陀如来」+「親鸞聖人の教え」を基盤として建立された発遣門の内側に祀られている理由は参拝者が“阿弥陀の教えへ送り出される”象徴 のため像が手に持つのは「念珠(ねんじゅ)」と「杖」 ② 梵鐘(ぼんしょう)寺院で鳴らす伝統的な大きな釣り鐘発遣門内に置かれているのは珍しい配置彫刻には八葉蓮華(はちようれんげ)や唐草模様が確認できるチェーンにつながっている木の撞木(しゅもく)で打てるようになっていた 親鸞聖人像を正面から。参道と牛久大仏。ズームして。牛久大仏が「發遣門(ほっけんもん)」の2階のガラス窓に映り込んでいた。手前には黄金の釋迦三尊像のお姿が。ネットから。釋迦三尊像 釋迦牟尼佛 弥勒菩薩 阿難尊者参道の左手には池が。「群生海「群生」とは、すべての生きとし生けるもののこと。この池は現世そのものをあらわし、水辺を埋め尽くす四季折々の花々はうつろいゆくこの世の無常をあらわしています。」 再びズームして。「お花畑のご案内」。 参道前方に大きな香炉の姿が。牛久大仏の「桜&芝桜エリア」への案内看板。春になると、・ソメイヨシノ・八重桜・芝桜(ピンク色の絨毯)が同時に満開になるため、牛久大仏の春の名物になっている のだと。八重桜と芝桜(ピンク色の絨毯)のコラボ。参道右手にあったのが牛久大仏の「鐘つき堂(自由に撞ける梵鐘)」日本一の大香炉と牛久大仏。近づいて。日本一の大香炉を振り返って。「あじさい 六月中旬~七月中旬」案内板。 「花菖蒲(ハナショウブ)」。そして「紫陽花(アジサイ)」。 牛久大仏を見上げて。ズームして。■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■手の印 ・右手:施無畏印(せむいいん) 「恐れを取り除く・安心を与える」 ・左手:与願印(よがんいん) 「願いを叶える・救いを与える」 牛久大仏の最も象徴的な姿勢。 ■蓮台の上に立つ姿 写真の下部に巨大な蓮弁(れんべん)が見える → 阿弥陀如来が極楽浄土に立つことを象徴 ■外側の造形 ・青銅の板を貼り合わせた外殻 ・なめらかな衣紋のライン ・胎内に入れる構造(右胸あたりに展望窓)背中側から見上げて。背中側にも深い衣紋(えもん:布のしわの造形)が刻まれており、下から見ると立体的に浮き出て見えたのであった。牛久大仏の台座の周囲にはサツキの刈り込み生け垣が波のごとくに。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.18
閲覧総数 405
-
11

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-6
★六会地区 歴史年表-16年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 49年 1974 今田地区に県立藤沢工業高等学校創立 小野田寛郎、フィリピン・ (現藤沢工科高等学校) ルバング島より帰国👈️ 50年 1975 スエズ運河開通👈️ 藤沢市人口 ニ六五九七五名 52年 1977 亀井野小学校創立 藤沢市あづま保育園石川に開園 県立藤沢北高等学校石川山田に創立 県立藤沢養護学校開校 53年 1978 亀井野保育園開園 鶴山洋子、円行につくし乳児園開園 今田、鯖神社境内に太平洋戦争 戦死者の「忠魂碑」建立 第一回公民館ふるさとまつり開催 六会地区生活環境協議会発足 石川市民の家開所 54年 1979 太平洋戦争戦死者七四名の慰霊碑を 東名高速道路、 雲昌寺境内に建立 日本坂トンネル👈️ 内自動車火災事故発生 55年 1980 石川、伊沢良一「イザワ テニスガーデン」開設 藤沢市立またの保育園開園 六会市民の家開所 56年 1981 天神小学校創立 湘南台中学校創立 西俣野の曹洞宗花應院本堂庫裡の 改築工事落成 57年 1982 西俣野御嶽神社梵鐘成る 58年 1983 開業医、三木洋「相模国四国八十八箇所 (弘法大師像をめぐりて)発行 59年 1984 石川東部区画整理事業完了に伴い 天神町誕生 60年 1985 西俣野史跡保存会会長、渋谷彦三 「小栗判官一代記」を発行 小栗塚市民の家開所 61年 1986 藤沢市民総合図書館完成 六会地区民生委員・児童委員協力者 会議発足 ★六会地区 歴史年表-17年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料平成時代 平成元年 1989 今田、円行の大部分が湘南台地区へ 移行される 六会地区は石川・亀井野・西俣野・ 天神町と今田・円行の一部となる 六会地域子供の家「どんぐりころりん」 開所 2年 1990 六会市民センター・公民館、 地下体育室完成 6年 1994 石川小学校創立 六会市民センターに地区福祉 窓口開設 7年 1995 六会駅橋上駅舎と東西を結ぶ オウム真理教による 自由通路完成 地下鉄サリン事件👈️発生 8年 1996 日本大学「バラ園」開設 9年 1997 六会ふるさと音頭完成 六会地区くらし・まちづくり会議発足 第一回湘南ねぶたまつり開催 10年 1998 六会駅から六会日大前駅に改名 12年 2000 六会地区防災リーダー連絡会発足 15年 2003 天神ミニバス開通 (六会日大前駅西口天神町循環バス) 16年 2004 六会市民センター石川分館設置 新潟県中越地震👈️発生 県立藤沢北高等学校が県立長後 高等学校へ統合 19年 2007 新潟県中越沖地震👈️発生 22年 2010 六会地区地域経営会議発足 23年 2011 宮城県亘理郡山元町に自転車・ 東日本大震災👈️発生 ヘルメット等寄贈 (六会地区震災支援金) 24年 2012 新潟県柏崎市北条(きたじょう)地区と 六会地区との地域間交流の覚書を 取り交わす 25年 2013 六会地区郷土づくり推進会議発足 六会日大前駅周辺バリアフリー化 工事始まる 小田急線六会一号踏切取り付道路 安全対策実施 26年 2014 六会市民センター・公民館建替えに 熊本大地震👈️発生 伴い仮庁舎に移転 28年 2016 新六会市民センター・公民館完成 29年 2017 天皇退位、2019年4月末に 衆院選で自民大勝、民進 が分裂 森友・加計政権揺るがす 「ものづくり」信頼揺らぐ 30年 2018 平昌五輪で日本は冬季最多 13メダル。フィギュア・ 羽生結弦は連覇 西日本豪雨、死者220人超 日大アメフト部選手が 危険タックル。スポーツ界 で不祥事相次ぐ 日産・ゴーン会長を逮捕 テニス・大坂なおみが 全米オープン優勝 31年 2019 はやぶさ2、小惑星 「リュウグウ」への着地 に成功 大リーグ イチロー引退 ★六会地区 歴史年表-18年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料令和時代令和元年 2019 【以下 後日記入】 天皇陛下が即位。「令和」 に改元 ラグビーW杯日本大会開幕、 日本8強 京都アニメーション放火、 36人死亡 消費税率10%スタート 東日本で台風大雨被害、 死者相次ぐ 2年 202 コロナ感染拡大 緊急事態宣言 志村けんさんら死去 東京五輪・パラ 1年延期 安倍首相 辞任表明 菅首相誕生 新内閣発足 3年 2021 コロナワクチン接種 熱海で土石流・27人死亡 眞子さま 小室圭さん 結婚 大谷メジャーMVP 4年 2022 知床観光船 沈没事故 安倍元首相撃たれ死亡 大谷2桁勝利2桁本塁打 村上 56本塁打・三冠王 W杯日本代表16強 5年 2023 WBC14年ぶり優勝 最強侍 列島沸く ジャニーズ性加害問題 大谷メジャー本塁打王 藤井竜王史上初八冠 阪神38年ぶり日本一 6年 2024 石川・能登で震度7 新紙幣 20年ぶり パリ五輪メダル 日本45個 大谷 初の「50―50」 闇バイト強盗 続発 7年 2025 善行長後線開通 ・・・つづく・・・ ・・・完・・・
2025.11.15
閲覧総数 400
-
12

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-5
★六会地区 歴史年表-14年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代昭和21年 1946 NHKのど自慢開始👈️ 極東軍事裁判👈️ 23年 1947 第一回市長公選、無投票で飛嶋繁当選 学校教育法に基づき新制六会中学校発足 旧横須賀海軍無線送信所の兵舎を仮校舎 とする 24年 1948 六会に市役所の支所(旧六会村役場)設置 一ドル三六〇円の 日本大学農林高等学校創立 為替レー ト設定 市制施行一〇周年、市歌・市章制定 ソ連からの引揚船 大船駅と小田急六会駅間にバス運転開始 舞鶴港に到着 湯川秀樹👈️ ノーベル物理学賞 25年 1950 六会中学校校舎増築完成 朝鮮戦争勃発👈️ 日本大学藤沢高等学校へ改称 藤沢市人口 土棚円行耕地整理組合結成 八四五八一名 会長に高瀬知治就任 26年 1951 市内各小学校で完全給食開始 第一回紅白歌合戦放送 日本航空発足 27年 1952 部落長を自治会長に改称 六会小学校の給食調理室完工 韓国李承晩ライン👈️ 設定宣言 28年 1953 六会中学校校歌👈️制定 テレビ放送開始 👈️ (広田俊夫作詞、市川達雄作曲) 六会小学校六〇周年記念事業の校庭 整備工事完成 六会慰霊塔除幕式挙行 29年 1954 六会地区体育振興協議会設立 第五福竜丸ビキニ環礁で 下土棚の精米所閉鎖される 被爆(水爆実験)👈️ 自衛隊発足 👈️ 青函連絡船「洞爺丸」👈️ 遭難事故発生 30年 1955 六会中学校増築工事完成 第一回水爆禁止大会(広島) 石川山田橋竣工 神武景気始まるテレビ・ 亀井野の平川秀雄、六会幼稚園を創立 電気洗濯機・電気冷蔵庫 六会駅近くの山林の一部が造成され、 普及(三種の神器) 三期にわたって分譲地として販売始まる 第一〇回国民体育大会 開催(藤沢を中心会場に) 31年 1956 亀井神社の参道が改修される 六会地区有線放送電話開通 32年 1957 六会小学校の図書館完成 南極観測隊昭和基地開設👈️ 六会中学校にプール完成 33年 1958 横浜開港一〇〇年 34年 1959 石川中の塚に市汚物処理場起工 メートル法実施 石川丸石公民館落成 伊勢湾台風上陸👈️ 石川に市農村青年研修所新設 藤沢市民交響楽団誕生 35年 1960 市制ニ〇周年記念式挙行 36年 1961 いすゞ自動車(株)藤沢工場操業開始 インスタントコーヒー 、 プレス工業(株)操業開始 即席ラーメン発表 住宅開発始まる ダッコちゃんブーム ★六会地区 歴史年表-15年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 37年 1962 堀江謙一ヨット世界一周 👈️ 国産第一号炉に原子の火 38年 1963 亀井野地区の工業用水工事中、 トンネル内で五名生き埋め、 三名死亡事故 発生 39年 1964 六会中学校増築工事落成 東海道新幹線開業 👈️ 下土棚市営住宅起工 東京オリンピック開催 東京オリンピック聖火リレー藤沢市内 「高砂丸」👈️ 通過 北部第一区画整理事業認可(一九八四年 完了) 40年 1965 六会小学校体育館落成 名神高速道路開通👈️ 猿田彦大神の石廟市の文化財に指定 藤沢市の人口 一七五一八三名 41年 1966 六会地区社会福祉協議会発足 敬老の日 六会地区青少年育成協力会発足 体育の日設定 善行小学校創立、生徒数 四一五名 (六会小学校内に仮設) 円行石川の一部に桐原町誕生 小田急線湘南台駅開設 42年 1967 六会中学校体育館落成 北部学校給食合同調理場が六会中学校の 敷地内に開設 桐原公園開設 石川の伊沢暁ガソリンスタンド設置 藤沢北郵便局、下土棚に開設 富士見台小学校創立 石川の畑信裕ハタ・オートキット開設 (洋蘭の温室経営) 43年 1968 東京府中、三億円事件 発生👈️ 全国一一〇の大学で 学園紛争起こる 44年 1969 藤沢市農業協同組合設立 (村岡・藤鵠・明治・六会・御所見・ 小出の各農協合併) 老人福祉センター「やすらぎ荘」開設 45年 1970 湘南台幼稚園設立 国産初の人工衛星 六会行政センター(市民センター)改築開館 打ち上げ成功 石川の角田ヨシ方の「梅の木」市の 「おおすみ」👈️ と命名 天然記念物に指定 大阪万国博覧会開催👈️ 六会地区自治会連合会結成 三島由紀夫ら楯の会、 六会中学校コンピューター教育の実験授業開始 自衛隊乱入、割腹事件 下土棚、善然寺本堂起工式 発生👈️ 県立ゆうかり園開園 藤沢市人口 ニニ八九七八名 46年 1971 六会小学校前歩道橋完成 大相撲、大鵬引退👈️ 俣野小学校創立 (優勝三ニ回) 六会郵便局町田線沿いから六会駅前に移転 西俣野初老(五〇才~六〇才)を対象に 常磐会結成 (会員五十名) 六会地区交通安全対策協議会発足 六会地区防犯協会発足 47年 1972 今田郵便局開設 札幌冬季オリンピック 下土棚が長後地区へ編人される 開催👈️ 石川東部土地区画整理組合結成、 沖縄日本復帰👈️ (組合員一五〇名) 連合赤軍、浅間山荘 亀井野に六会東部土地区画整理組合結成 事件発生👈️ (組合員五三〇名) 横井庄一、グアム島で発見 田中角栄通産大臣 「日本列島改造論」発表👈️ ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.14
閲覧総数 816
-
13

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-4
★六会地区 歴史年表-12年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料大正時代大正元年 1912 六会村人口 三九四九名 東京市よりワシントン 戸数 五九五戸 ポトマック湖畔に桜三〇〇〇本 六会村西俣野に瞽女淵記念碑建立 寄贈👈️ 2年 1913 横須賀海軍水道完成(水源は中津川) 藤沢警察署亀井野駐在所設置 (旧道亀井野下 下山酒店先下屋敷側) 3年 1914 厚木県道改修工事完了 桜島大噴火👈️ 六会村人口 四四七七名 戸数 六一〇戸 第一次世界大戦始まる👈️ 4年 1915 第九代六会村村長に加藤九右衛門 第一回全国中学校野球👈️ (亀井野)再選 大会大阪で開催 六会村下土棚、長谷川巳之助、 厚木県道沿いで酒屋を開業 5年 1916 長後・戸塚間ツルヤ自動車バス運行 開始 広田清治、尋常高等六会小学校校長に 任命 6年 1917 六会村 人口 四五八四名 戸数 六三一戸 (亀井野 一六一戸 今田 三七戸 下土棚 九六戸 西俣野 八七戸) 六会村吏員給料 村長一二〇円 助役 一〇〇円 収入役 一〇五円 書記 九八円 7年 1918 第一〇代六会村村長に杉山松五郎 第一次世界大戦終結👈️ (今田)就任 藤沢に初めて電話架設 米価高騰により各地で暴動発生 六会村下土棚東側に電灯点る (六会村で最初) 8年 1919 藤沢町田線(藤沢町5町田町)が県道に 認定された 9年 1920 第一回国勢調査実施 11年 1922 六会村青年団結成、団長に尋常高等 六会小学校長の広瀬正治就任 六会村下上棚、金子春吉自転車業を開始 12年 1923 六会村に自転車が見られるようになる 関東大震災発生 六会村の被害死者一五名 負傷者一四名 行方不明一名 家屋全壊七五七棟 半壊五九六練 13年 1924 第一一代六会村村長に広田兵蔵(土棚)就任 尋常高等六会小学校訓導塚越喜一、高一 児童約四〇を引率し大山登山実施 大山登山の歌(広田俊夫作詞)成る 14年 1925 尋常高等六会小学校同窓会設立、 ラジオ放送開始👈️ 初代会長小倉喜一 東京六大学野球リーグ戦 六会村処女会結成、初代会長小泉セイ 始まる👈️ 東京~上野間に地下鉄開通★六会地区 歴史年表-13年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代昭和元年 1926 六会村、晩霜のため桑・茶の被害甚大、 桑相場高騰 六会村青年・処女会・同窓会の機関誌 「六会の叫び」第二号発行 2年 1927 六会村下土棚消防組結成、初代組頭に 第一回都市対抗野球大会 金子友治就任 始る(最初の野球実況放送) 大正天皇御崩御 3年 1928 六会村亀井野駐在所改築移転 第九回オリンピック、アム 六会村亀井野下より西俣野上を経て ステルダム大会、初めて 大船に通ずる道路(大船用田線)開通 日章旗上がる(織田幹雄、 鶴田義行)👈️ 4年 1929 第一二代六会村村長に飯田伝之輔 世界一周ドイツ飛行船 (俣野) 就任 ツェッペリン伯号霞ヶ浦に 小田原急行鉄道、江の島線開通 着陸👈️ 六会駅開設 片瀬江の島~新宿間の運賃 九五銭 初の国産ウィスキー・ 六会村役場新築落成、二階家となる サントリー発売 6年 1931 六会農民組合結成、組合員五四名 小作料の引下げを目指す 7年 1932 一三代六会村村長に長谷川周作 チャップリン来日👈️ (亀井野)就任 五・一五事件勃発👈️ 8年 1933 六会村下土棚、模範耕地整理組合結成、 国際連盟を脱退👈️ 組合長矢地要吉 六会村石川の秋本信善、秋本漬物工場 発足 六会村産業組合創立、組合長渡辺時蔵 横須賀海軍通信隊六会分遣隊、六会村 亀井野に駐屯 六会村 人口 四九三〇名 戸数 七二一戸 9年 1934 尋常高等六会小学校教員広田俊夫、 渋谷駅前に忠犬ハチ公の 郷土史「六会読本」を編纂刊行 碑が立つ👈️ 11年 1936 第一四代六会村村長に小菅一鉱 二・二六事件勃発👈️ (土棚)就任 尋常高等六会小学校校庭に二宮金次郎 銅像建立 六会村電井野の長谷川敏夫、町田線沿に 六会郵便局を開設 12年 1937 御所見・六会両村境に県立診療所設立 日中戦争始まる👈️ (盧溝橋事件) 14年 1939 第一五代六会村村長に小倉久武(亀井野) 就任 15年 1940 藤沢市制施行 国民服令公布👈️ 16年 1941 初代市長に大野守衛就任 米穀配給通帳制実施👈️ 太平洋戦勃発 (真珠湾攻撃)👈️ 17年 1942 六会村藤沢市へ合併 金属回収令👈️ 六会村人口 四九九六名 (神社・寺院の仏具・梵鐘等 職業内訳 農業五七〇戸 工業二 戸 強制供出) 商業 一四〇戸 公務・自由業 二四戸 爆撃機本土初空襲 その他 六石 六会消防団は藤沢市警防団となる 18年 1943 下土棚の白山神社の梵鐘供出 日本大学農獣医学部創立 19年 1944 下土棚に海軍横須賀通信学校 藤沢分校開校、その後横須賀海軍電測 学童集団疎開実施👈️ 学校と改称 20年 1945 広島・長崎に原爆投下👈️ 農地調整法改正公布 第一回国民体育大会開催👈️ ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.13
閲覧総数 435
-
14

牛久大仏へ(その1)
利根川の排水機場。道の駅 発酵の里こうざきに立ち寄る。千葉県香取郡神崎町にある、発酵食品をテーマにしたユニークな道の駅「発酵の里こうざき」、住所:千葉県香取郡神崎町松崎 855。「発酵」をテーマにした全国でも数少ない道の駅。味噌、醤油、酒といった発酵食品が盛んな地域で、発酵文化を「食」と「体験」で発信していた。建物は「新鮮市場」「発酵市場」「レストラン」「カフェ(はっこう茶房)」など複数のゾーンで構成。観光案内板「発酵の里 こうざき」。左側のマスコットキャラ:「なんじゃもん」(神崎町のシンボルキャラクター、巨大な樹の精霊)発酵の魅力が詰まった「発酵市場」。全国から集めた発酵食品をとりそろえた、土産ショップ。店に入ると、みそやしょうゆ、甘酒、チーズ、漬けもの、日本酒など約500種類の商品がずらり。店内で土産物を買う旅友。親しい「仁」の文字がある日本酒。 仁勇(じんゆう)ラベルに大きく「仁勇」と書かれている緑色の瓶。蔵元:鍋店(なべだな)株式会社所在地:千葉県香取市(佐原)利根川流域の代表的な酒蔵のひとつ青ラベル(本醸造)赤ラベル(辛口)緑ラベル(純米)など複数の種類が並んでいた。仁勇は利根川流域(“水郷地域”)でもっともよく見かける地酒の一つであると。「鍋店 神崎酒造蔵」や「寺田本家」など、地元酒蔵の甘酒や酒かすを使った商品も豊富。新利根川大橋。利根川を渡る。すぎのや本陣 阿見店で昼食。稲敷郡阿見町、国道125号線バイパス沿いの店舗。蕎麦、うどんと各種セットが充実している和食レストラン。そば定食を楽しむ。そして目的地の牛久大仏が姿を表した。牛久大仏👈️リンク を訪ねるのは2021年以来、4年ぶり。・全高120m(台座含む) → 自立型の青銅仏として世界最大級・建設:1993年・参拝者は内部に入ることができ、 ・地下1階:蓮華蔵世界 ・1階:知恩報徳の世界 ・2階:御慈光の世界 ・3〜5階:展望室(地上85m) までエレベーターで上がれた。・周囲には広い庭園と小動物公園もあり、家族連れにも人気 と。牛久大仏の入口案内板。近づいて。正式名称:牛久大仏(正式には「牛久阿弥陀大佛」)所在地:茨城県牛久市久野町2083右側に大仏の全身写真下部に ギネス世界記録 認定 のロゴ → 「世界最大の青銅製仏像」として登録された記念牛久阿弥陀大仏(内部フロア説明)案内板には、大仏内部の各階の施設が紹介されていた。1F:光の世界・青い光に満たされた幻想的な空間・参拝前の「心を整える場所」という意味合い2F:知恩報徳の世界・阿弥陀如来への信仰や感謝をテーマにした展示・仏教美術や資料が並ぶ3F:御慈光の世界(銅板写経の間)・約3万枚の金色の小さな仏像が並ぶ荘厳な空間・「写経」を奉納する場所として知られる4F(外周部):展望室(地上85m)・牛久市や関東平野を一望できる大パノラマ・晴れていれば筑波山がよく見える5F:御膳台・大仏内部の最上部・一部は構造上のスペース(一般公開はフロアによって制限あり)牛久大仏の大きさ(案内板の比較表)大仏の高さ(本体):100m蓮台(台座):10m総高さ:120m→ 自由の女神(約93m)より高いその他、奈良の大仏や鎌倉大仏との高さ比較も描かれていた。牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)エリア全体の案内図。■ 1. 牛久阿弥陀大仏(中央) 敷地の中心にそびえる高さ120mの大仏。 内部に入れる日本でも珍しい巨大仏です。🌼 周辺の庭園・スポット■ 2. 牛久浄苑(うしくじょうえん) 大仏の背後に広がる広大な霊園エリア。春は桜、初夏は新緑が美しい場所。■ 3. ふれあいガーデンテラス 大仏横にある花壇と散策路。 季節ごとの花が楽しめるスポットです。■ 4. 大香炉(だいこうろ) 大仏前にある大きな香炉。 参拝前にお線香を供える場所です。🌷 花エリア 写真の左側に広がるカラフルな場所。■ 5. 群生海(ぐんせいかい) 季節の花々(ネモフィラ、コスモス、ポピーなど)が一面に咲き誇る広場。■ 6. 釈迦三尊像 三体の仏像が並ぶ厳かなエリア。写真にも小さく写っていた。🌳 その他の見どころ■ 7. 定業苑(じょうごうえん) 休憩所やお土産コーナーのある施設付近。車椅子対応のトイレもある。■ 8. 本願荘厳の庭 滝や池がある和の庭園。涼しげな雰囲気で、写真によく合うスポット と。■ 9. 本願荘厳の滝(右下) 庭園内にある滝。流れ落ちる水が美しい場所。■ 10. 想い出処「浄蓮門」(入り口付近) 入場ゲート近くのお土産・記念写真スポット。牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)内部へ入るための「大仏入口」案内板。「東本願寺 牛久阿弥陀大仏」→ 牛久大仏の正式名称で、宗派は浄土真宗東本願寺派。牛久大仏の「入場受付・料金案内」付近。■ 1. 営業時間(上部の紫の帯) 季節によって営業時間が変わる。 3〜9月(平日) 9:30〜17:00 3〜9月(土日祝)9:30〜17:30 10〜2月(平日・土日祝)9:30〜16:30 ※最終入場は閉園30分前まで■ 2. 料金案内(中央の大きな表) 大仏胎内or園内散策の料金が。● セット券(庭園+大仏胎内) 大人:800円 子ども:400円● 入園券(庭園のみ) 大人:500円 子ども:300円入場チケット。移動しながら牛久大仏を。これは 牛久大仏の「顔の模型」 。「大仏様のお顔は、この模型1000個分のボリュームに相当します。」と。「大仏入口(順路)」案内板。 通路のマンホールは牡丹(ぼたん)文様のモチーフ・中央に大きな花弁・両側に蕾(つぼみ)・周囲に茂る葉という構成で描かれており、典型的な牡丹唐草や牡丹文様の構成。牡丹は、仏教美術でも寺院装飾でもしばしば用いられる吉祥文様(めでたい文様)で富貴、高貴、美、吉祥を象徴すると。牛久大仏世界最大 120M 青銅製仏像鎌倉時代、御開山親鸞聖人は、常陸国(茨城県)で、他力念仏の教文を人々に伝えられるとともに、浄土真宗の根本聖典となる「教行信証」のご執筆にかかられました。 このご著書の成立年をもって、浄土真宗立教開宗の年(1224年)とされております。そして、立教開宗からおよそ800年の時代を超えてそのゆかりの地に、東本願寺第25世興如上人のご発願により、人類救済、世界平和の願いを込めて西方極楽浄土の主である阿弥陀如来(牛久大仏)が建立されました。牛久大仏の一部を実物大で再現した展示物のひとつでこれは大仏の頭頂部「螺髪(らほつ、大仏さまの髪の毛)」=頭の盛り上がり部分の実物大模型「この螺髪は阿弥陀大仏の頭部螺髪と同じものです。概 要 直径 1m 重さ 200kg 総数 480ケ」 牛久大仏の総重量は4,000t、顔の長さ20m、左手の平18.0m、目の長さ2.5m、鼻の長さ1.2m、とすべてが規格外の大きさ。牛久阿弥陀大仏阿弥陀如来は方便法身の大尊形として顕現されたもので、高さは阿弥陀如来の十二の光明にちなみ120m。その尊形を外から仰ぎみるだけでなく、胎内で阿弥陀如来の広大無辺なる本願の世界を体感することができます。四季の移り変わりや朝夕の光により、また見るものの心により、さまざまな表現を見せてくれる阿弥陀大仏、その御慈悲とは常に智慧と慈悲に満ち、すべてのものをやさしく包み込みます。地上高 高さ 120m重 量 本体主鉄骨 3,000トン 外殻鋼板重量 1,000トン左 手 挙手 18.0m親 指 直径 1.7m足の爪 長さ 1.0m人差指 長さ 7.0m 目 長さ 2.5m 鼻 高さ 1.2m 口 長さ 4.0m 耳 長さ 10.0m顔の大きさ 20.0mラホツ(頭部) 直径 1個1m 重さ 200kg 全体 480ケ基壇部 高さ 10m蓮台部 直径 30m 高さ 10m製造期間 10年再び牛久大仏(牛久阿弥陀大仏) 園内マップ「SORA × HOTOKE(そら × ほとけ)」の案内板。■ 左上:園内写真と名称● 大香炉(だいこうろ) 大仏の正面にある巨大な香炉● 群生海(ぐんせいかい) 季節ごとの花が広がる花畑エリア● 釈迦三尊像 ミニ仏像が三体並んだエリア● 浄蓮門(じょうれんもん) 入口付近の門と休憩場所■ 中央地図(園内図) 観光スポットがイラストで示されており、色分けされているのが特徴● 牛久阿弥陀大仏(メイン) 園内中央に大きく描かれた大仏像 胎内(内部)に入るルートもここから● ふれあいガーデンテラス 花畑・フォトスポットがある休憩エリア● 本願荘厳の庭 滝や池、水のある庭園● 仲見世 お土産・軽食・物販が集まるエリア● 足湯苑 無料または低料金で利用できる足湯施設● 駐車場(P) 園全体にアクセスしやすい大きな駐車場● 現在位置(YOU ARE HERE) 赤色の表示で、案内板のある場所が指示されています。牛久阿弥陀大仏を正面から。青空であれば(ネットから)。 ・・・つづく・・・
2025.11.17
閲覧総数 507
-
15

芝・愛宕 散策(その1)
増上寺黒門を出て右に曲がって進むと、増上寺の建物群からぽつんと離れて旧台徳院霊廟惣門(きゅうたいとくいんそうもん)があった。増上寺山内の南端に位置する台徳院霊廟は、寛永9年(1632)に造営されたもので、2代将軍徳川秀忠の廟所。芝の徳川家霊廟の中で、最も規模が大きく、地形の起伏を利用した壮麗な建築群を誇っていた。しかし、昭和20年(1945)の戦災に際して、罹災を免れたのはわずかにこの惣門、勅額門、御成門、丁字門のみで。惣門が現地に保存され、それ以外の門は狭山不動寺(埼玉県)へと移築されて現存。台徳院霊廟惣門は2代将軍徳川秀忠(台徳院)の霊廊惣門で3代将軍徳川家光が建立させたそうで、左右に金剛力士像を配置した立派な門。朱漆塗りの入母屋造八脚門で朱色が鮮やかで美しく歴史を感じたのであった。惣門自体が重要文化財の上、左右に配置されている木造仁王像は港区の有形文化財に指定されており、風格十分。阿像。 吽像。 惣門を潜り反対側から。 三間一戸の八脚門.屋根は入母屋で,前後に唐破風。唐破風には多くの黄金の徳川家・葵のご紋が。 水路跡。 更に日比谷通りを進むと右手に芝東照宮(しばとうしょうぐう)が。祭神は徳川家康。神体は徳川家康寿像。旧社格は郷社。日光東照宮、久能山東照宮、上野東照宮と並ぶ四大東照宮の一つとされる。増上寺の脇の道まで戻ると目の前に東京タワーの姿が再び。東京タワーの下の道を進むと前方に愛宕グリーンヒル森タワー愛宕マークヒル等の高層ビルの姿が見えた。 右手には東京プリンスホテル。 芝公園三丁目の交差点を左折すると、左手にあったのが雲晴院。浄土宗寺院の雲晴院は、松浦肥前守室(雲晴院尼)が檀主となり寛永10年(1633)建立、増上寺十七世照譽上人了學大和尚が遊學院と号して開山、後年法名より雲晴院と改号したと。聖観世音菩薩像。 左手に鎮座する石仏。 本堂。 「雲晴院」 と書かれた扁額。愛宕グリーンヒル森タワー、愛宕マークヒルと虎ノ門ヒルズ森タワー。 愛宕グリーンヒル森タワー、愛宕マークヒルの間にあるのが青松寺(せいしょうじ)。青松寺は、港区愛宕二丁目にある曹洞宗の寺院。山号は萬年山(ばんねんざん)。山門の扁額には「青松禅寺」 と緑の地に青の文字で。山号の「萬年山(ばんねんざん)」と書かれた扁額も。 山門の両脇には、薮内佐斗司作の仁王像が立っていた。左右、それぞれに向かい合って2体ずつという配置は永平寺で見たことがあったが、珍しいのであった。四体の像は「四天王」(してんのう)と呼ばれ、仏教世界観の中の須弥山(しゅみせん)の頂上に住まう帝釈天に仕え、仏法を守護することを念願としていると。それぞれの足元には、仏の示す親切がまだ分からない邪鬼を踏みつけているのだ。増長天(ぞうちょう)。世界の南方を守護する。五穀豊穣を司る。やり、戟を持つ。広目天(こうもく)。浄天眼をもって観察し、世界の西方を守護する。悪心をいさめ、仏心を起こさせるはたらきを司る。筆と巻子を持つ。反対側にも。左は多聞天(たもんてん)。夜叉を率いて世界の北方を守護する。毘沙門天ともいう。仏の道場を護って説法に耳を傾ける。剣と宝塔を持つ。また福徳を司るとして個別に信仰されている。右は持国天(じこくてん)。世界の東方を守護する。国を支える役を司る。芝というこの様な場所に、この様な大きな四天王を奉る立派な寺院があることに感激したのであった。中雀門。本堂。本尊は釈迦牟尼如来、脇侍に文殊、普賢の両菩薩を従えていると。「萬年山」と書かれた扁額。本堂前の仁王像・阿像。吽像。右手に観音聖堂。ここは礼拝堂とのこと。自己の内面と向かい合い、観音様の優しいまなざしに包まれて、穏やかなときをすごすことのできる空間であると。「観音聖堂」 と書かれた扁額が。坐禅堂の西側におわす観音菩薩像。愛宕神社交差点角にあったのが伝叟院。曹洞宗寺院の伝叟院は、愛宕山と号す。伝叟院は、青松寺第十世十洲補道大和尚が開山となり、正保3年(1646)に開創。現在曹洞宗大本山総持寺の出張所を兼務している模様。この寺は大正大震火災の際本区横死者の火葬場となつた場所であると。境内には百十数人の無縁の精霊を弔ふ為建設された、震災記念聖観世音菩薩像が立つ。此銅像は總高一丈六尺、帝室技藝委員高村光雲、並に山本瑞雲の原型を高橋凌雲が鋳造し、対象十五年九月一日に開眼供養したと。境内には別の石仏も。
2017.04.02
閲覧総数 314
-
16

世田谷区 九品仏・淨真寺の紅葉を愛でに(その1)
この日は2024年12月23日(月)、都内・有楽町で10数年来の海外旅行の旅友との飲み会に参加しました。毎年、この時期に都内に行く時には、途中下車して世田谷区内にある『等々力渓谷』そして『浄真寺』を訪ねることにしていますが、今年は『等々力渓谷』、『等々力不動尊』はパスして東京・世田谷区奥沢にある『浄真寺』を訪ねました。小田急線、田園都市線、東急大井町線を利用して「九品仏」駅で下車し、徒歩にて直ぐに『浄真寺』の参道の入口に到着しました。この地にはサギ科のシラサギ(白鷺)とラン科のサギソウ(鷺草)にまつわる悲話が伝わります。そのサギソウは世田谷区の花とされ、境内の「さぎ草園」では毎年8月上旬に多くの花を咲かせるそうです。「シラサギ」とは、ほぼ全身が白いサギ類の総称であり、シラサギという名前のサギがいるわけではないようです。『浄真寺』の山号は九品山(くほんざん)で、九品仏(くほんぶつ)とは後ほど触れるように、同寺に安置されている9躰の阿弥陀如来坐像のことを言うのです。「浄真寺参道」碑。「ニ〇一四~ニ〇三四年 浄眞寺「平成 令和」九品佛大修繕事業」大勧進」案内。「浄眞寺」のHPには「昭和三十八年(1963)に九躰の阿弥陀佛像と釈迦牟尼佛像の計十躰が東京都重要文化財に指定されました。保存状態として、各十躰の漆箔の浮き上がり、矧ぎ目の損傷や化佛の脱落割損が多く認められ、東京都と世田谷区の文化財関係者が綿密なる協議の上、平成二十六年(2014)より一躰ずつ、計十躰の修繕を公益財団法人「美術院」国宝修理所に遷座し二十年以上に亘る大修繕を実施する運びとなりました。つきましては、この仏縁により未来に引き継ぐ希代の大修繕事業(大勧進)の趣意をお汲みとり下さり、絶大なる御協力と御支援を賜りますよう懇願申し上げる次第でございます。」と。「九品佛参道界隈」案内碑。「九品佛参道界隈」案内図。文字がハッキリ見えるように、2枚の写真を繋げています。「浄真寺」のHPよりも案内図を。九品仏淨眞寺 境内図<昔> 参照:江戸名所図會。案内図にあった切絵図。「総門」の切絵図。「せたがや界隈賞世田谷区では、昭和59年から平成4年までの隔年で、区民の皆さんに愛され、親しまれている世田谷区の街なみ形成のモデルとなる、魅力的な界隈を「せたがや界隈賞」として表彰してきました。「九品仏参道界隈」は浄真寺境内と参道周辺で良好な界隈が形成されていることから、昭和63年に「第3回せたがや界隈奨励賞」として表彰しました。」絵の右下に書かれている「お面かぶり」とは、江戸の時代より3年ごとに、この寺で奉修される「阿弥陀如来二十五菩薩来迎会」のことで、無形文化財に指定されているのだ。「上野毛五島美術館一帯」切絵図。「おもいはせの路おもいはせの路とは、玉川地域の緑と水の資源や歴史・文化資源をめぐるルートを、散歩道として提案したものです。この路には季節や時の流れとともに表情を変える古代から現代までのさまざまな顔が見えます。この路を歩くとき、人はいろいろと思いをはせるということで、この名を付けました。友達と、恋人と、親子で、夫婦で、あるいは一人で歩いてみてはいかがですか。」五島美術館は、東京都世田谷区上野毛の閑静な住宅街の中にある私立(財団法人)の美術館。国宝「源氏物語絵巻」をはじめとする数々の名品を所蔵する美術館として、展覧会を中心に幅広い活動を展開している人気の美術館」 と。参道の入口右側にあったのが「玉川警察署 九品仏交番」。世田谷区奥沢7丁目34−1。「総門」に向かって、黒松並木の参道を進む。右手には「禁銃猟 警視廳」と三面に刻まれた石碑があった。背面には建てられた年が書かれていて、明治32年(1899年)と。「この辺りでは銃を使っての猟は禁ずる」という警視庁が出した明治時代の告知であると。当時のこの地域一帯はほとんど人が住んでおらず、雑木林ばかりの土地であった。狩猟もやりやすかった時代。この石柱はそういった古い時代の名残なのであろう。この後、境内にも同様な石碑が建っていたのであった。ここにも「2014年~2034年 浄眞寺「平成 令和」九品佛大修繕事業」大勧進」案内が。九品仏の駅名にもなって親しまれる浄眞寺は、上品上生仏より下品下生の九品阿弥陀仏が奉安されております。この度、元禄以来の大修繕を行うこととなりました。未来に受け継ぐ、この大修繕事業に値遇を得ることは、稀代の勝縁と思し召し、大勧進に広く皆様のご協賛を賜りたく存じます。浄財を喜捨(きしゃ)された芳名は、結縁交名帳に記録し九品佛像の臺座内に永久保存します。詳しくは事務所、龍護殿にございます趣意書をご覧頂ければ幸甚です。 九品佛浄眞寺 住職 清水英碩」参道の紅葉したモミジを見つけて。「総門」が前方に大きく見えて来た。約200mの長さの参道には黒松を中心に植栽されていた。入り口の参道は「二河白道(にがびゃくどう)」を表しているのだと。火の河と荒れ狂う河に挟まれた白い細い道、白道は浄土往生を願う信心の道で一心不乱に念仏を唱えて極楽浄土へ渡ろうということを意味している と。樹齢30年以上の黒松の間に次世代を担う黒松の苗木を植樹し成長しているのであった。参道の中程の右側には九品仏広場という公園があり、参道と調和した雰囲気の良い、子供達の遊び場となっていた。その先左手には、三界萬霊塔・供養塔・庚申塔など8基の石塔・石仏が並んでいた。左側の石碑群に近づいて。中央に「奉寄進庚申供養塔」と刻まれた石碑が。右側の石碑・石仏群に近づいて。「お地蔵様」(左)と板状駒型庚申塔「・青面金剛像」(右)で、青面金剛像に三猿が彫られている。造立年は寛文十二年(1672)と比較的初期の庚申塔。その30年ほど前に鎖国となり、20年後には元禄文化の華が咲いた時代のものである。反対側から振り返って。モミジ葉が朝の陽光に輝いていた。そして「浄眞寺 総門」前に到着。「掲示板」。2024年末、2025年正月の予定が書かれていた。九品山唯在念佛院浄真寺(くほんさんゆいざいねんぶついんじょうしんじ)は浄土宗寺院。越後国村上泰叟寺の珂碩(かせき)上人を請うて延宝6年(1678)に創建されたものであると。総門前の石段の中央の手摺には「舟の櫓」を表した手摺が。「総門」に掲げられている扁額「般舟場(はんじゅじょう)」。常に行道念仏して現前に諸仏を見奉る「般舟三昧」する道場であり、参拝者に願往生の心を自然に発さんが為に書かれたものであるとのこと。「般舟三昧」とは浄土教で説く精神統一法。諸仏現前三昧、仏立 (ぶつりゅう) 三昧ともいう。7日ないし 90日間この三昧を行えば現前に仏を見ることができるのだと。「九品佛浄眞寺総門」と。書体は篆書体か?「新東京名勝 選外十六景 奥沢 九品仏」と刻まれた石碑。右手に「創建の由来」案内板が置かれていた。「創建の由来当山はひろく「九品仏」の名で親しまれているが、正式には「九品山在念仏院淨眞寺」といい、浄土宗に属し、境内約12万m2 ( 3万6十坪)は往古の面影を保存する都内有数の風致地区である。開山は江戸時代初期の高僧「珂磧(かせき)上人」で、四代将軍徳川家綱公の治世延宝6年( 1678 )に、奥沢城跡であったこの地を賜り、浄土宗所依の経典である観無量寿経の説相によって堂塔を配置し、この寺を創建された。「江戸名所図絵」に描かれている堂塔の配置と現状とはほとんど変わりはないが、昭和40年に本堂・仁王門とも茅葺きを銅板葺に改修した。」「創建の由来」案内板の後ろに「筋塀(すじべい)」という種類の塀があり、そこには定規筋(じょうぎすじ)と呼ばれる白い線が5本引かれていた。もともとは門跡寺院(もんぜきじいん)の証として5本の線を引いたのが始まりと。定規筋の数が寺の格式を表すようになり、3本、4本、5本のうち5本が最高ランクとされていると。門跡寺院とは、皇室一門や公家の方が出家して住職を務める寺院のことをいい、古くより皇室と関わりのある格式高い寺院とされているのだ。「九品佛道」と刻まれた石碑が「総門」右手奥に。そして「総門」下から、紅葉に輝く境内を。紅葉のピークを迎えた境内。例年より2週間程遅れていたのであった。左手にあったのが後ほど訪ねた「焔魔堂」。「焔魔堂」の参道右側の紅葉を追う。赤い帽子、前掛けの石仏に近づいて。「淨真寺」碑。「焔魔堂」その手前に「三途の川」に架かる橋。「三途の川」に架かる橋の前の石仏。「焔魔堂」の前を右に折れた奥にも5体の石仏が並んでいた。六体の石仏に向かう参道の紅葉を追う。「総門」を境内から見る。三体の石仏が仲良く並ぶ。こちらにも石仏が。「筋塀」前の紅葉。「六地蔵」であっただろうか?六道(地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人、天)の入口に立ち、衆生の苦を救うと言う有り難い地蔵様たち。そして引き返しながら見上げて。ここにも石仏群が。ズームして。こちらにも。 ・・・つづく・・・
2025.02.16
閲覧総数 110
-
17

成田山新勝寺へ
ここ5ヶ月ほど、アイルランド・ロンドン旅行記を長々とアップしてきましたが、今日からは、その後の旅行についてアップさせていただきます。この日は6月13日(金)、成田山新勝寺に自治会役員仲間と向かいました。成田山新勝寺の総門に向かって進む。右手奥に見える大きな屋根の建物が総門で、その先に仁王門や大本堂へと続きく。道の両側には土産屋さんや飲食店が並び、参拝客でにぎわう場所。このあたりは「成田山表参道」と呼ばれ、うなぎ料理や和菓子のお店が多いことで知られているのだ。成田山新勝寺の総門(そうもん)が前方に現れた。総門は新勝寺の表玄関にあたる荘厳な門で、平成19年(2007年)に建立された比較的新しい建築物。門の前には「成田山金剛力院新勝寺」と刻まれた大きな石柱があり、参拝者が記念撮影をしている様子が見えるのであった。この総門をくぐると、次に「仁王門」、そして「大本堂」へと続いていた。ちなみに、総門の屋根は銅板葺きで、木組みの細工や装飾も非常に見事で、伝統的な寺院建築の美しさが感じられたのであった。成田山新勝寺案内図。地図の下の方(南側)から参道を通って入ると、次のような順に主要な伽藍が並んでいた。1.総門(そうもん) — 表玄関2.仁王門(におうもん) — 金剛力士像が守る門3.大本堂(だいほんどう) — 成田山の中心、本尊・不動明王が祀られている4.三重塔(さんじゅうのとう) — 色鮮やかな重要文化財5.釈迦堂(しゃかどう) — 旧本堂6.光明堂(こうみょうどう) — 江戸時代初期の建築7.平和の大塔 — 新しい時代のシンボル塔(仏舎利奉安)また、右上の方には広い池と庭園が描かれており、ここは成田山公園。春は梅や桜、秋は紅葉が美しい散策スポットになっているのだ。ネットから。名称:総門(そうもん)所在地:千葉県成田市 成田山新勝寺建立:平成19年(2007年)再建形式:入母屋造(いりもやづくり)、重層門特徴:伝統的な木造建築で、組物(斗きょう)や彫刻が極めて精巧。屋根の反りや飾金具などに荘厳な意匠が施されています。🔹中央の扁額(へんがく)中央に掲げられている額には成田山(なりたさん)」と。これは成田山新勝寺の山号(さんごう)であり、正式名称:成田山金剛王院新勝寺(なりたさん こんごうおういん しんしょうじ)宗派:真言宗智山派本尊:不動明王(ふどうみょうおう)所在地:千葉県成田市成田1番地創建:天慶3年(940年)開山:寛朝大僧正(かんちょうだいそうじょう) その起源は、平将門(たいらのまさかど)の乱を鎮めるため、朱雀天皇の勅命によって、 寛朝僧正が京都・東寺から不動明王を奉じて成田に来たことに始まります。 戦乱が収まった後も、不動明王は「ここにとどまりたい」と示したため、寛朝が堂宇を建立し、 これが成田山新勝寺の始まりとされています。通称:「成田不動」「成田のお不動さま」・成田山(なりたさん) 「成田」は地名ですが、「成(なる)」=成就・成功、「田」=豊穣を意味することから、 「すべての願いが成就し、豊かに実る地」という吉祥的な意味もあります。・新勝寺(しんしょうじ) 「新たに勝つ寺」すなわち「平和と安寧の勝利を祈願する寺」という意味。 開山の際、平将門の乱を鎮めるために護摩修法を行い、「戦乱を鎮める=勝利する」という 願いから名付けられたのだと。総門を振り返る観光客そして我が旅友。その先に仁王門。仁王門。新勝寺の境内入口正面石段を登ると阿形、吽形の二力士像を安置した仁王門がある。その正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)、左側に口を閉じた吽形の蜜迹金剛(みしゃくこんごう)、裏仏には右側に広目天、左側に多聞天が安置されており、境内の入口にあって伽藍守護の役目を担う。この仁王門は、3間1戸の八脚門であり、屋根正面は千鳥破風及び軒唐破風、背面は軒唐破風付きの入母屋造の銅板葺である。組み物は三手先で、軒は二軒の扇垂木である。両側面の壁には、ケヤキの一枚板を用いるなど、堅牢で宏壮に建造され、材料、工法とも優れており江戸時代末期の特色が見られる。また、頭貫上の各柱の間には、後藤亀之介、天保2年(1831)の竹林の七賢人、司馬温公瓶割りなどの彫刻が施される。建立は、棟札の記述から文政13年(1830)である。名称:仁王門(におうもん)建立:文久元年(1861年)構造:入母屋造(いりもやづくり)・銅板葺(どうばんぶき)・二重門(にじゅうもん)重要文化財指定:1958年(昭和33年)場所:成田山表参道の終点、大本堂へと続く石段の手前に位置仁王門は、成田山新勝寺の表玄関にあたる壮麗な山門で、参拝者が俗世から聖域へと入る「結界の門」としての役割を持ちます。門の中央には、ひと際目をひく大きな赤い提灯が掲げられていた。「魚がし」と書かれた大提灯は、東京・築地の魚河岸の旦那衆が、1968年に奉納したもの。紙張りのように見えるが骨部分は砲金(青銅の一種)製で、重量が800キログラムにもなる と。正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)。左手に堂庭御護摩受付所横の「光輪閣」入口門。「光輪閣」脇門へと進む。「光輪閣」。1975年(昭和50年)建立本坊(寺務所)及び客殿を備える地上4階・地下2階の建物四階「光輪の間」は千数百人が、一度に入れる480畳の大広間がある。一階が受け付け・二階から四階は坊入りなどの接待をする客殿。明治天皇成田行在所碑。明治14年と明治15年に明治天皇が宮内庁下総御料牧場へ行幸(ぎょうこう)する時に成田山を行在所(あんざいしょ)と定めた。御座所として御駐泊になられたのが明治天皇行在所です。光輪閣後方にある行在所は2014年に修復した と。三重塔。日光東照宮の五重塔と成田山の三重塔が日本で一番絢爛豪華であろう。二軒の板垂木で有名。他の社寺では見ることが出来ない見事な造りである。厚さ20cm以上ある板に雲水紋が彫られていた。三重塔心柱の墨書きには、下記の様に書かれています。棟梁は「櫻井瀬左衛門」の宮大工としての、素晴らしい技術棟 梁 常州那珂郡羽黒村 桜井瀬左衛門次棟梁 同国同郡 中野左五兵衛 同国茨城郡笠間 藤田孫平次 竜の尾垂木彫刻 下総国武射郡堺村 伊藤金右衛門彫物師 江戸○○住 無関圓鉄 羽目板「十六羅漢図」彫刻 法起寺(ほっきじ)の三重塔(国宝)が現存最古の三重塔である。創建は慶雲3年(708年)近づいて。三重塔は、宝永6年(1709)に起工され、正徳2年(1712)に完成した中規模な塔です。心柱の墨書から、宝暦7年(1757)、享和元年(1801)、安政5年(1858)に修理されたことがわかります。高さ約25メートルのこの塔は、初重(第一層)の柱や長押に地紋彫を施し、各重の尾棰を竜の彫刻とし、二間の板軒に雲文が浮き彫りされており、極彩色を施すなど華麗な塔です。この塔は、近世の塔としては、全体の均衡もよく、良質であり、江戸時代中期以後にみられる過飾な建物の、早い時期の遺例として貴重なものです。周囲の十六羅漢の彫刻は、島村円鐡の作です。塔内には五智如来が安置されています。なお建立の際には、佐倉城主から成田の並木及び三之宮神社の松17本と将門山(佐倉市)松5本が寄進されています。板垂木。ズームして。常香炉。聖徳太子堂。移動して。1992年建立の聖徳太子堂。成田山新勝寺の聖徳太子堂は、1992(平成4)年に建立され、2007(平成19)年に修復された。日本の仏教興隆の祖である聖徳太子の理念にもとづき、世界平和を願って建てられました。堂内には、大山忠作画伯の壁画が6面に渡り描かれており、聖徳太子像が奉安されています。聖徳太子像。大山忠作画伯の壁画が堂内六面にあります。写真では牡丹・白鷺・菊が見えた。常香炉を振り返って。左から、三重塔、一切経堂、鐘楼。一切経堂、鐘楼をズームして。巨大灯籠。移動して。石段上から仁王門を見る。常香炉と本堂。仁王門前から総門を見る。参道の両側には石灯籠が並ぶ。
2025.11.16
閲覧総数 407
-
18

熱海・MOA美術館へ(その5)
重要美術品 「聖徳太子立像」 康俊 鎌倉時代 元応2年(1320年)。【朱の袴をつけて合掌するこの童子形像は、聖徳太子伝に基づいて制作された太子二歳のときの姿とされ、その形によって南無仏太子像とも呼ばれているhttp://www.moaart.or.jp/?collections=231】 鎌倉時代に入ると、弘法大師空海の幼少像とされる稚児大師像などのように、高僧や偉人の幼年時代を思慕する思想によって童子形の造形が見られるようになるが、本図の太子二歳像もその一例である。この像は、小児の愛らしい姿や柔らかな肌の感触と、鎌倉彫刻に共通する凜とした厳しさの見られる相好とが合致して、聖徳太子の英邁な智慧の輝きをよく示した作例ということができる。】 重要文化財 「聖観音菩薩立像」奈良時代 8世紀。【この像は頭部に三面宝冠をつけて立つ菩薩像で、宝冠正面の龕中に如来坐像が表されており、左手に蓮華の蕾を持ち、右手の先は首から下がった瓔珞(ようらく)を執る。頭頂部から台座までを一木から彫り出す技法で制作された檀像で、ほぼ直立しているが、腰には少し動きが見られる。】 面相や体部の表現などは、柔らかく穏やかなものとなっており、そこに仏像彫刻における日本的特色を見ることができよう。http://www.moaart.or.jp/collections/225/】重要文化財 「阿弥陀如来立像」 鎌倉時代 13世紀。【上品下生(じょうぼんげしょう)の来迎印を結び、雲上の蓮華座に立って極楽浄土より来迎する姿を表した阿弥陀如来像である。細部まで神経の行き届いた精緻な作りを示すこの作風は、鎌倉時代初期の大仏師快慶によって生み出された快慶様(安阿弥様)と呼ばれるものである。http://www.moaart.or.jp/?collections=229】鎌倉初期の彫刻界に興った新風が、写実的で力感にあふれた様式を示した中にあって、比較的穏やかで端正な作りの像を生んだ快慶一門の手になるものと思われる。台座裏には宝徳3年(1451)の修理銘があり、体部の金泥(きんでい)や台座などはこのときに手を加えたものであろう。】杉本博司 「月下紅白梅図」平成26(2014)年、個人蔵 。月明かりが照らし出した、紅白梅図を「月夜の梅」に見立てたというもの。この原寸大の新旧ダブル紅白梅図屏風を一堂に見ることができたのは、この期間、この会場に限られ貴重な時間と空間であった。しかしこれは絵画それとも写真?そして最後に同じく「杉本博司 「海景-ATAMI」」 を鑑賞する。杉本博司氏のこの発表会への熱きメッセージ。 杉本博司氏の代表作「海景」シリーズのうち、熱海の海を撮影した多くの作品が発表されていた。 水平線の高さを統一して撮影された海には、島や船や港が一切見えない。ただ空と海と光のみ。この海が生命の原点であるというメッセージを与えてくれる作品。 私のカメラのピンボケではありません。混沌の空と海か? 光の母の陽光が水面に。 そして美術館のあとは茶の庭を最後に散策。 この「唐門」は、もと神奈川県大磯町の三井家別邸城山荘内にあったもの。片桐門。天正18年(1590年)に片桐 且元(かたぎり かつもと)が薬師寺の普請奉行を務めた際、馬上のまま出入りしたという宿舎の正門。その後奈良慈光院に移され、ついで昭和十六年、神奈川県大磯町の三井家別邸城山荘内に移築されていたが、現在これも、ここMOA美術館内に移築されているのです。茶室「一白庵」では、お抹茶と和菓子が味わえるようです。光琳屋敷。尾形光琳が1712年に京都に建てた屋敷の再現。現存している図面などを元に建てているそうで、2階には16畳の画室があると。屋根と屋根の間に少し立ち上がっている小さい屋根のように見える物が「うだつが上がらない」といって用いられる「梲(うだつ)」。目庭の紅白の垂れ梅も開花。内部。土間から。照明が美しかった。極めて広い和の世界。 中庭。近くには竹林も。二條新町 そばの坊。和食・甘味 花の茶屋。茶室 「樵亭(しょうてい)」。備前池田藩の筆頭家老、伊木忠澄(1818~1886)は、晩年三猿斎と号し、茶の湯三昧の余生を送り、岡山の荒手屋敷には20に余る茶室が設けられていました。この茶室は、そのうち「大爐の間」と呼ばれた茶席を移築したものです。「樵亭」の名称は、この茶室の襖絵に、当館が所蔵する「樵蒔絵硯箱」伝 本阿弥光悦(重文)の蓋表にある樵夫と同様の図案が描かれていることにちなんで名付けられたと。「茶の庭」にはここ「樵亭」の露地に加え「光琳屋敷」、茶室「一白庵」などに多くのカエデ類が植えられており、見事な紅葉も楽しめる事間違いなしなのであった。 そしてMOA美術館をあとにし、再びエスカレーターで下る。 再びドーム型の「円形ホール」で、プロジェクションマッピングを楽しむ。いつまでも見つめていたい空間と時間。 正面エントランス横の石積みと滝。 帰路はバスではなく徒歩にて熱海駅に向かう。途中の遊歩道沿いの梅園にて梅を楽しむ。 青空が再び姿を現す。 そして見事な大島の姿がくっきりと。 そして前方下に熱海駅と新幹線の姿が。 今年、1月に続けてのこの日の熱海散策であった。糸川・熱海桜、熱海梅園、熱海サンビーチ、貫一お宮の松、起雲閣、MOA美術館と熱海の観光SPOTはほぼ制覇したのであった。残るは伊豆山神社+御朱印そして初島か?伊豆山神社は今週のMOA美術館の紅葉見物時に訪れたいと考えているのである。 MOA美術館の展示作品は基本的に全て写真撮影可であったので、写真を撮りまくったが今回のブログには、撮影した写真と共に、MOA美術館のコレクションページをリンクさせていただいた。これは、時間のあるときに、このブログに自らアクセスしMOA美術館の展示作品そしてその歴史を更に学んでみたいからなのである。 ---------------完--------------
2017.02.25
閲覧総数 572
-
19

『港・ヨコハマ』を巡る(その19): 往路~桜木町南改札口前~桜木町駅前広場~東横浜駅の碑~YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅~桜木町駅北改札東口~鉄道発祥の地
この日は8月19日(金)、天候も回復したので、久しぶりに『港・ヨコハマ』を訪ねることに。2019年の9月に『港・ヨコハマ』を巡る で(その18)までアップしたが、まだまだ訪ねていない場所があったので、更に!と思っていたが、この日に『落穂拾い』を決断し向かったのであった。前回訪ねた2019年9月はコロナの前。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、2019年12月初旬に、中国の武漢市で第1例目の感染者が報告されてから、わずか数カ月ほどの間にパンデミックと言われる世界的な流行となった。わが国においては、2020年1月15日に最初の感染者が確認されたのであった。そして2020 年1月から2月にかけて、アジア各国を周遊してきた大型客船ダイヤモンドプリンセス号(DP 号)船内で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の集団感染が起きた。DP 号船内では 3,711人の乗員・乗客のうち、最終的に672名の感染が報告されたのであった。DP号は2020年2月3日に、ここ横浜港大黒ふ頭に接岸し、乗員・乗客の検疫が始まるとともに、無症状者、軽症者は主に関東地方各地および遠方の医療施設へ、医療を必要とする中等症、重症者は主に神奈川県内の医療機関に転送された。患者の転送は2020年2月3日から3月1日まで続いたのであった。そして神奈川県内12施設に転送されたCOVID-19感染者は70名にも及んだのであった。そして現在も継続しており、8月26日時点 のおいて全国の感染確認数19,413人、死亡者数321人、それぞれ延べ人数としては感染確認数1821万2025人、死亡者数3万8582人の深刻な状況が継続しているとのことである。上記の如きコロナの影響で、ここ1年以上は我が住む市の隣都町の『社寺旧跡』巡りをひたすら巡り続けて来たが、気分転換もあり、再び『港・ヨコハマ』を巡ることにしたのでもあった。この日も早朝に自宅を出発し、小田急線で湘南台駅に。そして横浜市営地下鉄で桜木町駅に向かったのだ。そして35分程で桜木町駅に到着。JR桜木町駅周辺の地図をズームして。JR根岸線 桜木町駅西口へのエスカレーターを上る。エスカレーターを下り、振り返る。「野毛ちかみち」は、はにかんだピエロがお出迎え!「ちかみち」は「地下道」それとも「近道」それとも「両方」の意か?ーーがこの日・(その19)の散策ルート。桜木町駅周辺を散策。JR桜木町駅南改札前(西口)が前方に。南改札口を出た正面には、なんと柱一つ一つが桜木町駅や鉄道にまつわる資料展示スペースになっていたのであった。「桜木町にやってきた鉄道車両初代横浜駅は新橋駅と同じく、アメリカ人建築家、R・P・プリジェンスの設計で、この場所から関内駅方面へ120m程の地に位置し、華麗な外観を誇りました。」「追憶の野毛・桜木町駅」「庶民の街として親しまれてきた野毛、またその玄関口として街の変遷を見守って来た桜木町界隈は、いつの時代も人々の活気ある息吹を感じ取る事ができます。野毛の風景 明治から大正、昭和まで、桜木町周辺の写真が展示されていた。夕焼けのような演出も相まって、ノスタルジックな雰囲気が。」「2代目桜木町駅舎と昭和40年代半ばの街初代横浜駅舎は改装を重ね、大正時代まで使用された。その後2代目駅舎は初代駅舎とほぼ同し位置に建てられた。駅が終点であった頃は、左写真のように左右対称の姿だったが、根岸線の開通、延伸とともに展示模型のような形になった。」「昭和の桜木町駅プラットフォーム昭和40年代、奥に見える商店街は間もなく消えようとしている。駅のプラットホームは街の移り変わりを見つめて来た。「横浜停車場」(初代桜木町駅)と「桜木町駅」( 2代目)の位置左 1883 (明治16)年の地図(青色)十2020 (令和2)年の地図 初代横浜停車場(初代桜木町駅)の歴史 1872(明治5)年 横浜停車場(初代横浜駅)開業 1915(大正4)年 横浜駅移転につき、桜木町駅に改名 1923(大正12)年 関東大震災のため駅舎等消失右 1932(昭和7)年の地図(緑色)十2020 (令和2)年の地図 2代目桜木町駅の歴史 1927(昭和2)年 2代目駅舎完成(関東大震災の4年後) 1964(昭和39) 根岸線延伸に伴い、駅舎の一部改築 1989(平成元)年 駅舎移転に伴い、旧駅舎はその設割を終え、解体」「鉄道が発信する文化鉄道創業時に、早くも横浜停車場の構内で商いをする人たちが現われました。以来、鉄道に関連した数多くの商売や文化が生まれてきました。・構内販売の変遷・明治~昭和 停車場と周辺の風景・鉄道がテーマの趣味と芸術」「鉄道旅行のお楽しみ江戸期の旅は徒歩による信仰と巡礼が目的でした。明治期、鉄道が利用されるようになると、やがて旅の目的は観光や仕事など、多様なものとなりました。・時刻表と観光案内詩のはじまり・鉄道の旅路で楽しんだ様々な飲食・明治~昭和 横浜ゆかりの名物たち「明治の横浜・鉄道路線案内明治初期、当時の人々にとって鉄道への関心は高く、多くの錦絵が残されましたり開業時の路線は現在でもほぼ同じルートをとりながら、高度に複線化されています。浮世絵展示が画面スクリーンに表示され、数秒ごとに桜木町駅にまつわる様々な絵に変わっていくのでついつい長居してしまいそう。この映像で桜木町駅周辺にたくさんの跡地が今も現存していることもわかります。・神奈川駅・鶴見駅・横浜の鉄道史跡 横浜には明治から昭和にかけて鉄道関連の史跡が数多く存在します。「横浜の鉄道史跡 横浜には明治から昭和にかけての鉎道連の史跡が多く存在します。」①神奈川駅跡②3代目 横浜駅跡③高島ヤード跡④2代目 横浜駅跡⑤鉄道発祥の地記念碑と初代横浜駅長室跡⑥東横浜駅跡⑦汽車道と橋梁⑧旧横浜駅プラットホーム跡⑨鉄軌道と転車台跡⑩外国人鉄道技術者の墓「錦絵」が画面に次々と。「河崎鶴見川蒸気車之図」。「横済ステーション蒸気入車之図」。「横浜新埋地高嶋町掲屋三階造海岸遠景之図」。「横浜鉄道蒸気出車之図」。「初代横浜駅と発着場の情景」初代横浜駅は新橋駅と同じく、アメリカ人建築家、R・P・プリジェンスの設計で、この場所から関内駅方面へ120m程の地に位置し、華麗な外観を誇りました。「初代横浜駅舎 半立体模型明治--大正の頃、初代横浜駅は観光スポットであった。桜木町駅時代も含め、多くの古写真が残っている。」「初代横浜駅乗車場 半立体模型明治初期、鉄道を題材にした錦絵が数多く出版された。和と洋が混在した人や街の様子がイメージできる。」「開業直前の横浜停車場1872 (明治5)年の舂頃に撮影されたと思われる横浜停車場の写真です。これにより鉄道創業期の客車の様子など、新たな発見がありました。」「鉄道創業の地・桜木町駅(旧横濱停車場)日本人と鉄道の出会いは江戸時代の末期でした。明治時代になるとその導入が決定し、1872 (明治5)年、横浜と新橋の間で日本初の営業運転が始まりました。・日本人と鉄道の出会い・鉄道敷設の計画と工事 1869 (明治2)年、明治政府は鉄道建設を決定し、英国から技術者や機材を導入しました。・双頭レール 明治初期の鉄道創業当時は、英国から輸入された錬鉄製の双頭レールが使用された。 このレールは上下対称の形状になっており、裏返して再利用する予定だった。 (実際には再利用されなかった) 当駅、新南口に隣接するJR桜木町ビル1階には、1873年製の双頭レールか設展示されています。・華やかな開業式典 1872 (明治5)年新暦の10月14日、秋晴れのもとで執り行われた開業式典の記録。」「日本人と鉄道の出会い」。「鉄道敷設の計画と工事1869(明治2)年、明治政府は鉄道建設を決定し、英国から技術者や機材を導入しました。」「華やかな開業式典」。「日本の産業を支えた横濱停車場鉄道開業の翌年、1873 (明治6)年9月、横浜~新橋間の鉄道による貨物営業が始まりました。以来、横浜は日本の産業における重要な物流拠点となりました。・貨物輸送のはじまり 創業期の貨物輸送は貨車75両で始まづた。 ・明治初期の貨物 1873(明治6)年の貨物営業開始時の輸送量は合計2千トン程度であった。初期の貨車には 家畜車、魚車、木材車などがあったが、その後、鉄道延伸のための工事に必要な土砂車が 増加した。鉄道網が拡がった1897 (明治30)年の貨車は、全国の官営と私鉄あわせて1万両を 超え、輸送量は876万6千トンとなった。」・延伸する鉄道路線 明治中期になると、地方の生産地と港を結ぶ鉄道は日本の新たなる産業の芽を育みました。「延伸する鉄道路線明治中期になると、地方の生産地と港を結ぶ鉄道は日本の新たなる産業の芽を育みました。」「みなとみらい時層マップ明治初期から平成までの海岸線の変化を俯瞰しながら、この地区の産業や街並みの発展を「時間を旅する」感覚で観察すると、新たな発見があるかもしれません。「明治初期の周辺地図」。明治:横浜開港後、臨海地区には港湾の付帯施設として、造船と鉄道という2つの 産業が生まれ発達しました。それに伴い、周辺の海は急速に埋め立てられました。大正:造船と鉄道流通の関連産業は、戦前から戦後にかけて最盛期を迎え、昭和 日本の高度成長期を支えてきました。昭和末期になると、これらの産業は転換期を 迎えます。現在:「みなとみらい21地区」となって、この一帯は日本屈指の国際ビジネスセンターとなり、 さらに、これまでの産業遺産を活かした観光地として、進化と発展を続けています。「みなとみらい地区の記憶明治から昭和までの臨海地域は造船と鉄道物流の拠点で、この街のシンボル的存在でした。現在は国際的なビジネスと観光の街として生まれ変わリました。」「YES’89横浜博覧会 横浜博覧会は「宇宙と子供たち」をテーマとして1989年(平成元年)に開催されました。 これを機に、みなとみらい地区は大きく変貌、発展しました。」「造船産業の隆盛 明治半ば、付近の臨海地域に横浜港の付帯施設として造所所が設けられました。 その後、日本の基幹産業の一翼を担い、昭和末期まで稼働していました。」「鉄道流通の拠点 鉄道はその開業以来、横浜港をはじめその付帯施設に関連する流通を支えました。 そして日本の貿易や工業の発展とともに貨物の取扱量は増加しました。」そして駅舎を後にして、この日の散策の本格的なスタート。正面に久しぶりに見る「横浜ランドマークタワー」の姿が。「横浜ランドマークタワー」は、神奈川県横浜市西区みなとみらいの超高層複合ビル。「横浜みなとみらい21」地区の開発を主導した三菱地所が建築・設計・保有している。1990年3月20日に着工し、1993年7月16日に開業した。タワー棟は、地上70階建て、高さは296.33mで、超高層ビルとしては、あべのハルカス(300.0m)に次いで日本で2番目に高い。また、構造物としては東京スカイツリー(634m)、東京タワー(332.6m)、あべのハルカス、明石海峡大橋(298.3m)に次ぐ日本で5番目の高さである。桜木町駅前広場の右手、歩道橋への階段の下にあった「昔の桜木町駅前」の写真。「この光景は、明治20年(1887)頃の初代横浜停車場(現桜木町駅)前を撮影したものです。写真中央の噴水塔は、高さ約4.4m、重さ約1.3tの鋳鉄製で、日本初の近代水道創設を記念して設置され、往来する方々に親しまれていました。この噴水塔は、現在、横浜市保土ケ谷区の横浜水道記念館に保存されています。」と写真右下部に。この姿は竣工当時の新橋停車場に酷似しているのであった。この塔の下部はその名も『獅子頭共用栓(ししがしら きょうようせん)』と呼ばれていたと。そう言えば、日本の水道事業は、明治20年(1887年)に横浜で初めて近代水道が布設されたことから始まったのだ。これは当時、外国の窓口であった港湾都市を中心に、海外から持ち込まれるコレラなどの伝染病が、水を介して広がり蔓延するのを防ぐことを目的としたもの。横浜に続いて、明治22年に函館、明治24年に長崎と、港湾都市を中心に次々と水道が整備されて行ったのであった。この辺は、私の昔の仕事の関係で。現在、横浜市保土ケ谷区の横浜水道記念館に保存されている噴水塔の写真。桜木町駅前のワシントンホテルを見上げる。そして正面に案内プレートがあった。ここにも何か書かれているようであったが解読不能。「東横浜駅の碑」と。案内板が2枚。『ここに駅があった 大きな貨物駅だった 往時は六十五万トンが発着 多くの人が働き汗を流した ある時代は生糸だった ある時代は疎開荷物だった ある時代は進駐軍輸送 それに輸入食料だった そしてこの駅はいつの時代も 市民の生活とともにあった 一九七九年十月 この駅の使命は終わった かって日本の鉄道開業の 栄えをになった駅 追憶のなかに永遠 東横浜駅』「東横浜駅について 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社明治五年汽笛一声新橋を発した日本初の鉄道の終着駅横浜はこの地でした。時を経て横浜駅は現在の位置に移り、この地の駅は客貨の機能を分離して桜木町駅、東横浜駅となりました。さらに幾星霜、国運いよいよ隆昌に向かう我が国現代史の過程において、鉄道の果たした役割はかぎりなく大きいものがありました。この間市民生活の一部としてその責めを全うした貨物駅東横浜は昭和五十四年その終焉を迎えました。いまこの地は新しい都市みなとみらいとして秀麗かっ壮大な偉容をととのえつつあります。古より世のため人のために日々営まれる活動に支えられて、暮らしが、社会が、街並みが時代に応じて生き生きと発展するさまは無量の感慨を私たちに与えてくれます。この碑文は東横浜駅廃止に際し往時ここに汗となみだをながした人びとの意をうけて書かれたものです。 平成十八年三月」つまり、東横浜駅は新橋-横浜駅間の鉄道開業時の初代横浜駅のあった場所に位置し、貨物専用駅として大正4年12月に開業。1979年(昭和54年)10月1日に廃止された と。「桜木町駅西口」を振り返る。「桜木町駅前広場」を「横浜ランドマークタワー」方向に進むと正面にあったのが「YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅」。「YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅」の前から「ランドマークタワー」を。横浜市は、下水道事業のPRと市の魅力発信などを目的としてポケットモンスターのキャラクター「ピカチュウ」とコラボレーションしたマンホール「ポケふた」を、みなとみらい21地区周辺に2019年8月5日(月)から設置した と。「YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅」を正面から。桜木町駅前と横浜ワールドポーターズ前を結ぶ"日本初"の都市型循環式ロープウェイ「YOKOHAMA AIR CABIN(ヨコハマエアキャビン)」が2021年4月22日(木)に運行開始。【全 長】 約1,260m(片道約630m)【最大高さ】 約40m【ゴンドラの特徴】・36台(1台の定員:8名)・バリアフリー対応・冷房完備・夜間景観を演出【事業主体】 泉陽興業株式会社(よこはまコスモワールド 運営会社)【営業時間】10:00~22:00 とのことでこの時はまだ動いてはいなかった。【運 賃】 片道券:大人 1,000円、子ども(3歳~小学生) 500円 にビックリ!!「ランドマークタワー」、階段状の建物「みなとみらい東急スクエア」を見る。その右奥に見えたのが「横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)」、大観覧車「コスモクロック21」。桜木町駅の北改札東口の出口に向かって進む。線路下の通路を進み西口に出ると左側に案内板があった。「温故知新のみち 鉄道発祥の地」。「鉄道発祥の地明治5 (1872)年、品川一横浜間で日本初の鉄道事業の仮営業(本営業は新橋ー横浜間)が開始されました。現在の横浜駅から桜木町駅までの土地は埋立によリ造成され、初代横浜駅(現桜木町駅)が置かれました。鉄道資機材は横浜港から陸揚げされ、横浜から工事が進められました。駅舎は米国人建築家R. P.プリジェンスによリ設計され、ほぼ同しデザインの新橋駅と初代横浜駅は双子の駅と称されました。鉄道事業にはエドモンド・モレルをはじめとする外国人技師が携わり、現在の掃部山(かもんやま)公園には外国人技師の拠点となる官舎が建てられました。掃部山は鉄道開業後も鉄道院用地として利用され、山の地下水が鉄道用水に用いられたことなどから、当時は「鉄道山」と呼ばれていました。明治20 (1887)年に横浜ー国府津間が開通し、初代横浜駅は中間駅となりました。この際行われたスイッチバック運転は輸送能率が悪かったため、貨客利用の増加に合わせ、大正4 (1915)年には現在の高島町駅付近に横浜駅を移転し、初代横浜駅を経由しない新路線が整備されました。あわせて初代横浜駅は桜木町駅へと改称されました。大正7(1918)年には2代目横浜駅と桜木町駅間が高架化され、桜木町駅は京浜線(現在のJR根岸線)の専用駅になりました。大正12 (1923)年には、震災により桜木町駅(初代横浜駅)は駅舎を失いますが、昭和2 (1927)年に移転開業した3代目横浜駅と共に新たな駅舎が建てられました。現在の駅舎は平成元( 1989 )年に建てられました。平成16(2004)年、みなとみらい線の開通により、東横線の桜木町駅が廃駅となりました。それにともない、桜木町駅の整備が行われて、平成26 (2014)年には北改札が新たに開設されました。」「絵葉書「横浜停車場」(明治末~大正初期)・(様浜開港資斟館所蔵)」。「初代横浜駅に停車する列車、(横浜開港資料館所蔵)」。「横浜停車場遠景(明治初期撮影)・(長崎大学附属図書館所蔵)」。「桜木町駅」周辺の観光案内図。現在地は、北改札西口出口。「温故知新のみち」とは安政6年の開港以来、横浜の成長と共に大きく変貌してきた西区のまち。立ち止まってよく見てみると、積み重ねられてきた様々な西区の魅力が見えてきます。「温故知新のみち」はそんな西区の歴史資源を楽しむことができる散策ルートです。横浜開港に尽力した偉人たち、みなとまちの発展を支えた地域、西区の歴史に思いをはせながら、少しゆっくリ歩いてみてください。きっと新たな発見があリます。「横浜実測図 明治14 (1881)年(中央図書館所蔵)」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.08.30
閲覧総数 573
-
20

黄色の花々そして黄色の新芽
我が家の庭や養蜂場所のある農園への畦道には、春の各種の黄色の花々が咲いています。まずは『カタバミ』。葉は、ハート型の3枚がとがった先端を寄せあわせた形。花びらは5弁。庭や畑の雑草としてお馴染みであり、やっかいな植物の1つ。近寄ってみると結構かわいい花であるが、草取り時の苦労を知っている人にはやや辛い花の一つ。『菜の花』菜の花と言えばもちろん黄色。春、一面に広がる黄色の菜の花畑は壮観で、代表的な春の風物詩。花ではないが『ニセアカシヤ』の黄色い若葉。我が養蜂場に植えてあるもの。この花の蜜は、レンゲ花はちみつに続いて日本では人気が高く、ハチミツの女王とも呼ばれています。『黄金マサキ』。この時期の新芽は、菜の花のような明るい黄色。同じ時期にベニカナメモチが真っ赤に色づくのと同じように黄金マサキは、真っ黄色に色づき鮮やかな色を競っているのです。『八重ヤマブキ』。太田道灌の歌『七重八重 花は咲けども 山吹の 実のひとつだに なきぞ悲しき』で知られた花。戦国時代の武将太田道灌が、ある日狩りの帰途、にわか雨に降られ手近な民家に雨具(蓑笠)を借りに立ち寄ったところ、その家の娘が何も言わず山吹の枝一枝を差し出した、という故事が伝えられているのです。そして「‘実の'と‘蓑'の掛け言葉」、それがとっさにわからなかった太田道灌は発奮して勉学に励んだといわれていると。『タンポポ』。黄色の花と白い綿毛が美しい。そして我が家の庭の『芍薬』。初めての開花ですが、華やかに咲き誇る花姿は何とも言えません。最後に自宅近くの「JAわいわい市場」の園芸コーナーの花々。『オンシジューム』。黄色の小さな花が無数に咲く可愛いイメージの洋蘭。沢山の花が咲く姿は豪華。『胡蝶蘭』。黄色の花弁に、中心の赤いリップが映えています。『金魚草』。花のかたちが金魚のように見えるため金魚草(キンギョソウ)の名前がついています。『マリーゴールド』花はカラフルな色合いで我々の目を楽しませてくれますが、花が目立つ本来の理由は虫たちの関心を惹いて受粉に利用するため。と言うわけで、虫たちの目には人間の目で見たものとは違う色の花が映っているです。上記の黄色の花は、虫たちには周囲が白、中心が赤く見えているとのこと。http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-473897/A-bees-eye-view-How-insects-flowers-differently-us.html
2011.05.13
閲覧総数 1691
-
21

肥後細川庭園の紅葉ライトアップへ
この日11/27(火)は高校時代の学友であり、呑み友達の海外勤務商社OBそして現役の大学教授と3人で肥後細川庭園 松聲閣「秋の紅葉ライトアップ~ひごあかり~」を見に行って来ました。肥後細川庭園は東京都文京区目白台にある文京区立の公園。改修工事に伴い新名称を公募し、2017年3月18日、「新江戸川公園」から改称されたのだと。肥後細川庭園では12月2日(日曜日)まで(よって昨夜で終了しています。)「秋の紅葉ライトアップ~ひごあかり~」を開催中で「ヤマモミジ」や「エノキ」など、日々紅葉は鮮やかになり、夜のライトアップでは、池の水面に幻想的な風景を映しだしていた。自宅から小田急線、田園都市線、半蔵門線、有楽町線を利用して江戸川橋駅まで1時間40分の長距離移動。江戸川橋駅から神田川沿いを徒歩で15分弱で待ち合わせ時間17:30前に到着。既に都内に在住の二人は私を待ってくれていた。そして17:30からのライトアップ開園(ライトアップは、17時30分から21時まで(入場は20時30分まで))に300円を支払い入場。このライトアップの為か?雪吊りの如き象形も所々に。白壁への青のライトアップも幻想的。ウィキペディアによると「ここ一帯は江戸時代中頃まで幕臣の邸宅があったところであった。その後、幾度かの所有者の変遷を経て、幕末に細川家の下屋敷になり、明治時代には細川家の本邸となった。1960年に東京都が当地を購入し、翌年には公園として開園。1975年、文京区に移管されて現在にいたる。当地付近は目白台からの湧水が豊富な地点で、その湧水を生かした回遊式泉水庭園を主体とした公園となっており、江戸時代の大名屋敷の回遊式泉水庭園の雰囲気を現在でも楽しむことが出来る」と。池の周囲の散策の小路を進む。小路の両側には小さなランタンが並べられていた。庭園内では、熊本県を拠点として活動を行っているCHIKAKEN〈ちかけん〉による、竹を素材とした美しい光の演出「竹あかり」が。幻想的な世界に、芸術的な竹灯篭の優しい光に包まれて、心に温もりを感じるのであった。これぞ「和のイルミネーション」。かぐや姫が出てきそうな幻想的な世界。モミジの老木の幹も負けじと輝いていた。この日は風が無く、池は鏡の如くにライトアップされた紅葉の姿を映し出してくれた。鏡の池の幻想的な姿を楽しみながら、池の周りをシャッターを押しながら進む。石灯籠も白く輝いていた。「逆さモミジ」と「逆さ雪吊り?」の共演。そして「紅葉」と「黄葉」の共演も楽しんだのであった。雪吊りの象形の縄の数も多く金沢の兼六園に負けまいと。晩秋の夜空に美しく映える紅葉と光の競演が楽しむ。カメラを横にそして縦にと忙しく。以前に池に映り込む紅葉を楽しんでいたら、石を投げ込む輩が。係員が大声で止めなさいと叫んだが、暗くて誰かは解らず。しかし、水面の波紋の余韻も美しかったのであったが・・・・。園内の松聲閣の部屋の灯りも水面に美しく。紅葉も輝いて。カエデの幻想的な紅葉ライトアップは圧巻。紅く色づきはじめた楓のトンネルの如くに。ここに月の姿も・・と欲張り・・・。青も水面に映り。更に散策の小路を進む。「雪吊り」と紅葉ライトアップのコラボを楽しむ。紅葉ライトアップも、照明が当たっている枝と照明が無い枝が微妙に光のアンジュレーションを創り出していた。それにしても無風そのもの。水面にはっきり映る姿は息を飲む美しさ。上の写真を180°回転してアップしてみました。モミジの朱や黄に松の緑が重なる美しい色の対比を楽しむ。雪吊りは北陸地方の冬の風物詩と思っていたが・・・。散策路の下に熊本地震復興支援のあかり「灯火カップ」が見えて来た。緑葉のライトアップも幻想的。朱や黄そして緑のカオスの世界。区立関口台町小学校の児童による熊本地震復興支援のあかり「灯火カップ」。趣向を凝らしたさまざまな灯りがやさしく庭園を照らしていたのであった。『KUMAMOTO』の文字が。クマモンの撮影スポット。人の数もそれほど多くなく。松の緑も輝いて。再び「竹あかり」を楽しむ。何個の穴が空いているのであろうか、そして直線と曲線の共演。もう1周巡りたかったが、二人の姿は既に見当たらなかったので諦める。園内の松聲閣にて、熊本復興ドラマ「ともにすすむ サロン屋台村」の特別上映や、熊本県玉名市所蔵の刀剣「同田貫正国(上野介)」の特別展示など、熊本地震復興&観光PRの特別展示も行っていた。肥後菊は一重咲き。様々な色に姿を変えた「カスミソウ」。『ONE PIECE(ワンピース)』と「くまもん」がコラボ。「ルフィ」の姿も。そして肥後細川庭園 松聲閣「秋の紅葉ライトアップ~ひごあかり~」を堪能したあとは近くのインド料理屋「プージャ(PUJA)」で料理とアルコールをこれも堪能。店を出て友二人と別れ私は江戸川橋に向かって目白通りを歩く。早稲田大学 大隈会館前を通る。早稲田大学キャンパス案内図。この辺りは私にとっては何故か初めての場所なのであった。リーガロイヤルホテル東京。そして帰路も往路と同じコースで22:30過ぎに帰宅したのであった。
2018.12.03
閲覧総数 186
-
22

旧東海道を歩く(川崎~保土ケ谷)その2・横浜市鶴見区:熊野神社~京急鶴見駅前
『旧東海道を歩く』ブログ 目次横浜市鶴見区内の旧東海道を更に下る。『市場の一里塚』慶長9年(1604)、徳川家康は街道を整備し、一里ごとに5間四方の塚を築いた。塚には榎などの樹木を植え、旅人の里程の目安とした。ここは江戸より五里目の塚に当たり、横浜市内で最初の一里塚。明治9年(1877)地租改正にあたり払い下げられ、左側の塚が現存していると。昭和初期まで塚の上には榎の大木が繁茂していたと。『市場の一里塚』説明板。「慶長 9年(1604)徳川幕府 は、江戸 から京都 までの街道 を整備し、あわせて宿場を設け、交通の円滑を図りました。里程の目標と人馬の休息のための目安として、江戸日本橋から一里(約4km)毎に街道の両側に五間四方(9m四方)の塚を 築造し、塚の上には榎(えのき)を植えました。ここは江戸より五里目の塚に当たり、市内で最初の一里塚です。明治 9年(1877)地租改正 にあたり払い下げられ、左側 の塚が現存しています。昭和初期まで塚の上には榎の大木が繁茂していました。昭和8年(1933)6月「武州橘樹郡市場村一里塚」(添田担書)の碑が建立されました。平成元年(1989)横浜市地域文化財として登録されました。」稲荷社。斜めから。『市場村一里塚由来記』「昔街道一里毎に塚を築き塚上に榎を植えて標示とした。 これを一里塚といい、江戸日本橋を起点に東海道に造られた。 市場村一里塚もその一つで、今(昭和三十八年)から三百六十年前、即ち慶長九年、 徳川家康が東海・東山・中山の諸道を修理する時築いたもので、明治初年までは 相対して道の両側に同じ塚があったが取りこわされ一方のみ残る。 日本橋から数えて五里(二十粁)に当る。 永い間風雨にさらされ土が崩れ流れるので、地元有志これを惜しみ、 昭和二十五年八月、大谷石をもって土止めをし、こえて三十八年五月補修を加え、この碑を建つ。」そして旧東海道を左手に折れ、第1京浜に向かう。この場所は箱根駅伝の1区から2区への鶴見中継点。大手町読売新聞東京本社前~鶴見までの第1区(21.4㎞)のゴールで有り鶴見~戸塚間の第2区(23.2㎞)へのスタート点。鶴見中継所にある 「明日へ走る」 のブロンズ像。 来年の正月2日には何処の大学がこの場所で首位で襷を引き継ぐのであろうか?結果は「東洋大学」であった。横浜市のマンホール。舵輪の中に横浜の象徴の一つであるベイブリッジが描かれていた。文字がないので雨水用のものか?旧東海道に戻ると鶴見区市場下町9に庚申地蔵尊が。宝暦4年(1754)造立、願主は鈴木二右衛門とのこと。一里塚から200m程の右側には下町稲荷。「鶴見川」の手前にある小さなお稲荷様。前方に鶴見川に架かる鶴見橋の姿が。右手に折れ金剛寺に立ち寄る。真言宗智山派寺院の金剛寺は、光明山遍照院と号す。脇門から境内へ。金剛寺の創建年代等は不詳ながら、嵯峨天皇(809-823)の代に尊慶法印が草創、熊野神社の別当を勤めてきたともいい、かつては市場村内の金剛寺畑と称される場所にあったと。寛永年間(1624-1645)に秀尊(明暦2年寂)が中興、金剛寺と称していたが、江戸時代末期に院号遍照院を通称としていたと。玉川八十八ヶ所霊場11番、東海三十三観音霊場9番、東国八十八ヵ所霊場10番。子育て地蔵尊。真言宗と中興の祖・興教大師(こうぎょうだいし)像。弘法大師が入定(にゅうじょう)されてから約300年後、高野山が活力を失いつつある時、その状況を憂い、弘法大師の教えを再興するために様々な改革をしたのが、この興教大師覚鑁上人(こうぎょうだいしかくばんしょうにん)(1095-1143)。穏やかな祈りの姿。そして鶴見川・鶴見川橋を市場下町公園から見る。江戸時代より橋の名は「鶴見橋」と呼ばれきたが、大正15年(1926)に京浜第一国道(国道15号)が開通すると、国道に架けられた橋に「鶴見橋」の名称を譲り「鶴見川橋」と改称された。現在の橋は平成8年(1996)に架け替えられたバスケットハンドル型ニールセンローゼ橋と呼ばれる構造のアーチ橋。2本のアーチが内側に傾斜し最高点で間隔が狭くなるカゴの取っ手のようなデザインが特徴的。鶴見川橋から東海道本線の鉄橋を見る。鶴見駅側の橋のたもとに残る『鶴見橋関門旧跡(つるみばしかんもんきゅうせき)』。柱には「旧東海道鶴見橋 旧名称武州橘樹群鶴見村三家」と書かれていた。文久2年(1862)の生麦事件後、幕府は攘夷派浪士の取り締まりのため、川崎−保土ケ谷間に番所を設置。鶴見橋(現鶴見川橋)には5番番所が設けられた。『鶴見橋関門旧跡』説明板。「安政6年(1859)6月、横浜開港とともに、神奈川奉行は、外国人に危害を加えることを防ぐため、横浜への主要道路筋の要所に、関門や番所を設けて、横浜に入る者をきびしく取り締まりました。鶴見橋関門は、万延元年(1860)4月に設けられ、橋際のところに往還幅四間(約7メートル)を除き左右へ杉材の角柱を立て、大貫を通し、黒渋で塗られたものでした。文久2年(1862)8月、生麦事件 の発生により、その後の警備のために、川崎宿から保土谷宿の間に、20か所の見張番所が設けられました。鶴見村には、第五番の番所が鶴見橋際に、その出張所が信楽茶屋向かいに、また、第六番の番所が今の京浜急行鶴見駅前に設けられました。明治時代に入り世情もようやく安定してきましたので、明治4年(1877)11月、各関門は廃止されました。なお第五番・第六番の御番所は、慶応3年(1867)に廃止されています。」『寺尾稲荷道』石碑。さらに道の反対側の鶴見図書館の前には、寺尾、小杉分岐点道標と馬上安全寺尾稲荷道道標が。是より25丁と記されていた。横浜市鶴見図書館前には旧東海道の説明板が置かれていた。海に面して景色が優れていた鶴見や生麦は、川崎宿と神奈川宿の間の「間の宿(あいのしゅく)」としてにぎわい、名物「よねまんじゅう」を商う店や茶屋が繁盛したと。英文でも説明されていた。図書館前のユニークな形状のモニュメント?二口金一作 「旅立ち」。1993(平成5)年に鶴見区で開催された彫刻の展示会「横浜ビエンナーレ」に出展され奨励賞を受賞した彫刻作品とのこと。鶴見駅の近くには『鶴見神社』が。この神社の左前に梅干で有名であった「しがらき茶屋跡」がある。鶴見神社はもとの杉山大明神で、1400年前の推古天皇の時の創建という。六国史の一つ、続日本後紀(承和7年、833年)には、武蔵国都築(つづき)郡杉山の社として記されているから古い。横浜・川崎の間では最古の社とのこと。大正9年に鶴見神社と改称されている。旧東海道は、鶴見駅前を通り、再び第一京浜国道と交わるが、そのまま横断し、生麦の魚河岸通りに入る。鶴見神社 境内。手水場。岩の上の狛犬。拝殿。『鶴見神社境内貝塚』説明板。「横浜市指定史跡時代は弥生時代末期から古墳時代前期。平成20年2月の発掘調査で本殿前の東西5-8m、南北約10mの範囲に厚さ70-80cmの貝層が良好な状態で遺存することが確認された。この貝層を構成する貝種は2枚貝ではカガミガイ、ハマグリ、巻貝ではイボキサゴが主体であり、8種以上の鹹水産貝種からなっている。この時代のの貝塚が良好に保存されている例は少なく、貴重な遺跡です」『神輿の伝説』寛文年代(1661~)、鶴見川から天王河岸に流れ着いた神輿を、村人が引き揚げて当社に納めたと伝わる。 又、上流の川崎市小倉にも同じ言い伝えが残されていて、旧小倉村鎮守・天王社の祭礼の折、村人が鶴見川で神輿を洗っていて流れ出し、鶴見村方向へ流れ去ったと伝わっている。以来、小倉では鶴見神社祭礼時、かげ祭りを行うと言い伝えが残っていると。『境内末社』。大鳥神社、正一位上町稲荷大明神、秋葉神社、関神社、祖霊社…と続き、最後には寿老人が祀ってあり、本殿の後ろには富士塚が鎮座していた。祖霊社と寿老人の間に、同じような摂社がある。『境内奥の富士塚』。境内の奥、本殿裏に現存する富士塚の頂に富士浅間社 が鎮座する。富士塚の下には様々な石碑が。『寺尾稲荷道道標 』。「寺尾稲荷道道標は、旧東海道の鶴見橋(現鶴見川橋)付近から寺尾・小杉方面への分岐点にあった三家稲荷に建てられていたもので、一村一社の神社合祀令によって、大正年間に三家稲荷が鶴見神社境内に移された時に、移されたと思われます。昭和三十年代前半頃に、鶴見神社境内に移されていた三家稲荷の鳥居前の土留め作業を行った際、道標が埋没しているのが発見されました。正面には「馬上安全 寺尾稲荷道」右側面には「是より廿五丁」左側面には「宝永二乙酉二月初午 寛永三庚午十月再建 文政十一戊子四月再建之」とあり、二度建替えられ、この道標が三代目であり、当時の寺尾稲荷に対する信仰の篤さをうかがい知ることができます。寺尾稲荷は、寺尾城址の西山麓に祀られ、現在は地名が馬場となったことから馬場稲荷と呼ばれていますが、古くは寺尾稲荷と呼ばれていました。江戸時代には馬術上達がかなえられる稲荷として知られていました。」『清明宮』。清明宮の祭神はノーベル賞候補とも言われた作家・三島由紀夫と、楯の会メンバーで三島と共に自決した森田必勝。このように社祠の形で三島由紀夫を祀っているお宮は日本でもここだけではなかろうか。40回目の命日にあたる2010年11月25日に建立されたとのこと。1970年11月25日、三島氏と楯の会メンバーは自衛隊市ヶ谷駐屯地に総監を人質にとり、バルコニーから演説。自衛隊の決起・憲法改正を訴えた後に割腹自決した。享年45。続いて楯の会学生長だった森田必勝も自決。享年25。なぜ鶴見神社に三島由紀夫氏なのか?ネットで調べてみると、こんな記載を発見。鶴見に、三島氏が作家デビューしたての頃、毎夜のように通っていた「仔馬」というBARがあったと。三島氏が創設した「楯の会」のメンバーが、彼を祀る神社がないことから、その縁を受けてこの鶴見神社内に「清明宮」を遷座させたのだと。社の横には、三島由紀夫氏の筆跡からおこした石柱が建っていた。『鶴見の田祭り』説明板。鶴見の田祭りは、今から約700年前の鎌倉時代からこの鶴見の地に受け継がれてきた伝統ある行事が明治維新後の1875年(明治5年)に中断されてしまったが昭和62年に奇跡的に復活をとげた芸能であると。そして『清月』に立ち寄る。鶴見名物「よねまんじゅう」は、かながわ名産100選にも選定。店内。『お江戸日本橋』の歌の2番の歌詞の中で「六郷渡れば川崎の万年屋、鶴と亀とのよねまんじゅう」と唄われているのだ。私も土産に「よねまんじゅう」を購入した。そして京急鶴見駅近くの旧街道を進む。右手にホテルテトラ鶴見が。そして入口に歓迎の人形が。胸には『ハゲ割』・・・・・・・の書き込みがぶら下がっていた。同行の旅友Sさんが記念撮影。二人もこのホテルに宿泊すれば500円割引間違いなしなのであった。 ・・・その1・・・に戻る ・・・つづく・・・
2019.01.05
閲覧総数 1067
-
23

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その58)・長福寺
【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次「菱沼八王子神社」を後にして、西に進むと右手に「茅ヶ崎市立松林小学校」の東門が現れた。ガザニアの花に似ていたが。そしてこちらが「松林小学校」の正門。校内には、パナソニックエコシステムズ(株)のサボニウス型風車・『風かもめ』が。小型の風力/太陽光発電システムでありサボニウス型風車にひねりを持たせた型式のもの。そしてクランク状に進むと左手にあったのが「長福寺」。神奈川県茅ヶ崎市松林3丁目11−52。寺号標石「高野山真言宗 菱沼山長福寺」。「一願不動」碑と「為太田家先祖菩提 護摩堂建立」碑。「一願不動昭和五十九年弘法大師御入定千百年御遠忌大法会を記念して建立されました。伊豆の願成就院の本尊不動明王(國宝)を勧請しました。護摩堂は太田政光氏の特別志納により建築されました。」四阿の先に「一願不動」。中央に「大聖不動明王像」一願不動に一つだけの願いごとを一心に祈願すれば必ず叶えてくれるといわれている。「大聖不動明王像」。「矜羯羅童子(こんがらどうじ)」正面左前にあどけなく、清浄無垢な愛らしい矜羯羅童子が。「制旺迦童子(せいたかどうじ)」。眉間にしわを寄せ、ロをへの字にしたきかん気で今にも動き出しそうな「制旺迦童子」。心を和ませる木彫像。句碑であろうか。境内には大山古道吟行の句碑、鴫立庵芳如の句碑、水越梅二の結願歌碑などがあるとのことだが。学友が茅ヶ崎図書館まで出向き、調べて下さいました。「踏みて来し 雲雀か(賀)起臥の 野芳し(か(香)ん(无)ば(者)し) 九一題」「縁起略記一、高野山真言宗菱沼山薬師院長福寺と号す一、創建は鎌倉期末と伝承。本尊薬師如来を安置一、正保年間大道法印中興一、明治ニ年赤羽根満蔵寺を併合一、大正十一年関東大震災に本堂庫裡倒壊一、大正十四年四月本堂再建一、昭和四十七年四月新本堂落成 棟梁 太田文雄」弘法大師御誕生千ニ百年を記念して本堂新築を発願 資を有縁に募り昭和四十五年八月工を起し同四十七年四月ニ日の吉日を期して理趣三昧の法莚を設けてその竣工を祝し、山運の隆昌檀信徒の繁栄を祈る 住職二十八世 隆玄」左「盆栽 山野草塚」碑、中央「南無大師遍照金剛」碑、右「唖蝉坊(あぜんぼう)句碑」。一番右手の「唖蝉坊句碑」。「河豚食ふて北を枕に寝たりけり」。「六地蔵」。正面から。「生かせいのち 同行二人」碑。「修行大師像」。近づいて。境内の池。石の上には「亀」が昼寝?「結願の 寺にわが杖 おさめきて 寂しくあれど 心やすらぐ」。水越梅二之作品 と。私も「四国八十八ヶ所お遍路の旅」👈リンク の結願の寺・大窪寺では同じ心境に。裏面には「四国八十八ヶ所霊場巡拝の同行当山総代水越梅二氏は歌集「遍路」を出版された遍路の心普く一切に及ぶことを念じ八十八首の中より結願の一首を刻す昭和五十八年春彼岸建之 幻住 隆興誌」と。水越梅二氏は茅ヶ崎市の初代収入役で、昭和22年から昭和43年まで21年2カ月もその地位に と。「宝篋印塔」。ズームして。この石碑には??後日、我が学友がこの寺をわざわざ訪ねて下さり現地調査の上、解読して下さいました。石碑は「般若心経」であるとのこと。『羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶 般若多羅 茅村書』碑文の読みは「ぎゃてい ぎゃてい はらぎゃてい はらそぎゃてい ぼじそわか はんにゃたら」さらに碑文には「往(ゆ)ける者よ 往ける者よ 彼岸に往ける者よ 彼岸に全く往ける者よ 悟りよ 幸あれ」 と。 石仏群。「お遍路の 誰もが持てる 不仕合(ふしあわせ) 白象」であると国文学専攻の学友から。森白象の三男が亡くなり、遺骨を携え四国巡礼に出たとき、遍路の心にはそれぞれの思いと影があることを思い詠んだもの と。「わ(王)す(春)れ傘して梅か(可)香の偲ばる(者)ゝ 十八世鴫立庵芳如」。この句碑の裏面に「昭和二十八年に長福寺に九一の雲雀の句碑が建てられた時、傘を忘れて帰った芳如に届けた住職隆玄宛て礼状の末尾の一句」だと記してあります。(抜粋、一部省略)。石灯籠。寺務所。「本堂」正面。扁額「長福寺」。歴代住職の墓石が並ぶ。無縫塔ではなく五輪塔。「墓誌」「子育地蔵尊」。「寄進 大子堂一宇 子育地蔵尊」碑。「子育地蔵尊」と「大師像」。境内の「稲荷社」。「安霊塔」。ズームして。「聖観音像」であろうか。「阿字の子が 阿字のふるさと 立ちいでて またたちかえる 阿字のふるさと」「【阿字】とは大日如来という仏様を表し、【阿字のふるさと】は大日如来のおられる清らかな世界、いわゆる『あの世』のことをいいます。これは、「私たちの誰もが元々は阿字の世界にいて、修行のためにこの世界へ生まれ、そして再び阿字の世界に戻るのだ。」ということを詠んだ歌です。一般的には人が亡くなると「あの世へ行く」と言いますが、この歌では「あの世に帰る」と表現されているのです。つまり、亡くなった人とは再びあの世(=阿字のふるさと)で再会することができるということです。愛する人とのお別れは悲しみの極みです。しかしあの世は愛する人と再会できる場所なのです。また会えるその日まで、私たちは今をしっかりと生きていかなければいけません。」と。「安霊塔建立の由来四国八十八ヶ所札所を巡拝した川辺義治氏夫妻は深く弘法大師に帰依しこの世に生をうけた人はみな有縁であるとの信念から安霊塔の建立を発願された。浅岡光雄氏はこの趣旨に賛同協力されて平成六年八月完成同月十一日施餓鬼会当日開眼法要を修行 長福寺第二十九世隆興」「六地蔵」。こちらは「水子地蔵尊」。小高い芝生の丘の上に石碑。山を上る僧侶の姿?が描かれていた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.06.04
閲覧総数 660
-
24

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸
「神奈川県立近代美術館 葉山館」の屋外展示作品を楽しんだの後は、県道207号線・森戸海岸線を横断し振り返る。そして、道路沿いにあった案内板。「趣きのある美術館と日本庭園山口蓬春(やまぐち ほうしゅん)記念館国登録有形文化財この先右折」と。案内に従い、狭い坂道を上って行った。山口 蓬春(1893年10月15日 - 1971年5月31日)は、大正時代から昭和時代後期にかけて活躍した日本画家。本名、三郎(さぶろう)。文化勲章受章者。この道は「蓬春こみち」と。細い坂道・「蓬春こみち」を上って行った。大きな石垣、そこに槙の新緑の生け垣が。そして「山口蓬春記念館」前に到着。鉄骨製の入口にガラス製ドアが。鉄骨製はややこの場所には不似合い。「山口蓬春記念館」👈️リンク 館案内板。料金:一般 600円。「生きものを愛でた蓬春」が開期:2024年4月6日(土) ~ 6月2日(日)【前期】で開催中であった。花や鳥、魚や小動物など「生きもの」を描くことは、古くから東洋では花鳥画として知られ、その多くの作例は時代を越えて人々を魅了し続けています。山口蓬春(1893-1971)は、そのような伝統的な画題を学びながらも新しい日本画の創造に邁進しました。昭和9年(1934)に野鳥の保護や調査を目的とした「日本野鳥の会」が創設されますが、蓬春はその発起人に名を連ねており、彼の野鳥や自然に対する造詣の深さがうかがえます。「花鳥畫の、作品の優劣は、その作家の自然への愛の深さと、観察のカの如何とのみが決定すると謂っていい。」(山口蓬春「花島去を描く心」「邦畫リ4月号、昭和10年〔1935〕)と述べていた蓬春。愛犬をわが子同然にかわいがる彼の作品には、生命への愛情をも実感できるほか、数多くのスケッチからは制作に対する真摯な姿勢が伝わってきます。本展ては、蓬春の日本画作品及びスケッチ・模写、ならびに彼が蒐集したコレクションを展示し、蓬春と「生きもの」という観点からその画業を探ります とネットから。その先左手にあった美しい健仁寺垣(けんにんじがき)風の竹垣。この日は、時間の関係上、入館はパス。道路から「山口蓬春記念館」の建物を見る。以下の「山口蓬春記念館」👈️リンク の写真3枚はネットから。1階の和室。庭園が見下ろせる大きな窓が開放感いっぱいの画室。山口蓬春「新宮殿杉戸楓杉板習作」昭和43年(1968) をネットから。「山口蓬春記念館」の生け垣の前を西に進む。右手には別の建物の木製の脇門があった。数寄屋門風の簡易引き戸の門。そして左手にあったのが「旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘」。この建物は一般公開されていないようであった。旧金子堅太郎葉山別邸恩賜松荘は、明治から昭和にかけて活躍した政治家金子堅太郎の別邸として、葉山御用邸に近い三ヶ岡の山を背負い正面に海を望む斜面地に所在します。金子堅太郎(1853~1942)は、福岡藩の修猷館で学んだ後、明治4年(1871)、私費留学生として岩倉使節団に藩主とともに随行し渡米、ハーバード大学で法律学を修めました。帰国後は明治憲法の草案起草に参画し、後には伊藤博文の下で農商務相や司法相、枢密顧問官などを歴任した人物です。金子堅太郎は明治20年代から現在の葉山一色公園付近に別荘を構えましたが、大正8年の御用邸付属邸建設に伴い、大正11年頃、現在の地に転出しています。関東大震災後には、葉山別邸はほぼ常住の住宅として使用されたことが記録に残っています。現在地への移転に伴い、建物の一部が移築されたと伝えられ、照憲皇太后が訪問された「松の間」がそれに当たるとされますが、明治期創建の移築は部材の一部など限定的であったようです。戦後、所有者が変わり、昭和30年頃に改修が行われていると考えられますが、皇太后訪問時に使用された「松の間」の記憶を継承するべく、大正期の金子堅太郎別邸時代の意匠を強く意識していたことがうかがわれます。平成19年にも改修が行われていますが、現在に至るまで由緒ある別荘建築として大切に住み継がれています。「松の間」には、変木の床柱や琵琶棚をもつ床の間と床脇を設け、部屋境の欄間は銅板に梅花のすかし模様と竹をあしらった質の高い意匠が施されています。旧金子堅太郎葉山別邸恩賜松荘は、明治20年代に海岸沿いに設けていた別荘が、御用邸付属邸建設に際し、大正11年頃に移転するという歴史を継承しており、御用邸とともに歩んできた葉山の歴史を反映する重要な建物です。以下の2枚の写真はネットから。旧金子堅太郎葉山別邸恩賜松荘の座敷8畳「松の間」。こちらは「旧金子堅太郎葉山別邸 米寿荘」。そして引き返して、再び「一色海岸」へ。「旧ベルンハルド・モーア邸」この美しい建物は、ドイツ人の建築家アルヌルフ・ペッツォルドが戦前に設計した。今ではペッツォルドの名前を知る人も少ないと思うが、彼の設計で現存するのは筆者はここしか知らない。ハーフティンバー様式で木材の部分は濃い青で綺麗に維持されているが、近くで見ると少し塗料の剥がれた木材が年季を感じさせる。戦前の所有者は日本シーメンス社長、ベルンハルド・モーアであった。シーメンスは当時からドイツ有数の大企業だ。ここは歴史的建造物等の指定を受けていないがその価値は十分にある。現オーナーの意向であろうか とネットから。「三ケ下海岸」方向を見る。葉山御用邸、長者ヶ崎方向を見る。そして再び県道207号線に戻り、右手の山の裾野に建っていた建物は「旧鹿島守之助別邸( 旧住友家麻布邸)」。1903(明治35)年、麻布に旧住友邸として建てられた。住友家15代吉左エ門友純邸宅。1935(昭和10)年葉山に移築。この建物も、一般公開されていないようであった。「三ケ下海岸」と「一色海岸」の間にあった岩場を振り返る。長者ヶ崎をズームして。潮の満ちた長者ヶ崎の割れ目からは三浦半島の先端方向も見えたのであった。「三ケ下海岸」バス停前のプール付き?の建物の入口。再び、「三ケ下海岸」と「一色海岸」の間にあった岩場を。岩場をズームして。大きなプール?のある建物。入口には「WATABE & CO.」と書かれていたが。岩場には海鳥?が2羽。右手の「はやま三ヶ岡山緑地」の斜面は緑に覆われていた。その先、左手にあったのが「鹿島 葉山研修センター(旧小田良治別邸)」。「鹿島 葉山研修センター」。鹿島建設の葉山研修センターは、明治から昭和にかけて活躍した、実業家・小田良治の元別荘建物。銅葺き屋根の緑青が良い味を醸していますが、意外とシンプルな外観。しかし広い敷地にゆったりと建てられたその様は、実に存在感があった。照明や建具、ステンドグラスなど今では考えられないほど手の込んだものを使っていると。窓ガラスはドイツ製、床の大理石はイタリア製と建築材料は すべて外国から取り寄せたそうです。森戸海岸線からの写真をネットから。。銅葺き屋根の緑青が良い味を醸していますが、意外とシンプルな外観。「一色海岸」、「葉山御用邸」方向を振り返って。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.23
閲覧総数 1118
-
25

地元の神社に初詣
「湘南海岸」の初日の出と白き富士山を見た後は、地元に戻り、いつもの「亀井神社」に初詣に。石鳥居の扁額も「亀井神社」。藤沢市亀井野554。境内の社務所・札所。新たに昨年六月に立った「御由緒」碑。「不動ヶ岡の先住民族は此の地に定住すると農地の開拓にのりだした。そして彼等の中には信仰心の厚い者もいた、即ち不動の森を霊山ときめ法華の教を信じた。當時の信仰「の流れとして経文一文字を一石に書き塚を作る之が経塚であり水に因んで不動明王を祭り不動堂を作った。それが不動様の初めである。天正十八年(一五九〇年)明治のはじめ日本は神国なりと時の政府は各村落に社を作り神を崇拝するように命じた。私達のお不動様も亀井神社と名を改め村の鎮守社となる。祭神 天軻句突知命(あめのかくつち、火の神様)。當社は源義経四天王亀井六郎の祈願せし○にして天正十八年堂宇建立 宝永年中岡部和泉守崇敬厚く社殿を改築せりと傳う。大正十二年大震災により社殿鳥居等崩壊せしを後日氏子中にて再建す。」お焚き上げ場。石段上の社殿を見る。手水舎。龍の吐水口からは水が。亀の像も。右手池のほとりのに石鳥居。「社殿」に向かって石段を上る。今年は「社殿」前には国旗・日の丸がなかった。社殿。「社殿」にも注連縄が。蟇股の彫刻が見事。社殿の右側にあった「経塚」。「大震災復興記念碑」。「大震災復興記念碑」と篆書で書かれた題字(篆額)を右から上下の順で社殿前から境内を見る。社殿脇には「身代わり不動尊祠」。こちらの蟇股の彫刻も見事。「不動明王」と「地蔵さま」。「身代わり不動尊」と「社殿」を振り返る。「身代り不動尊」への参道と両側には真っ赤な「幟」が。参道には大きな石燈籠が。「身代り不動尊」への石鳥居。そして自宅に戻る途中に、もう一社・「地神社」にも初詣。「地神社」は「地神の森公園」内にある。境内。狛犬(阿形像)。狛犬(吽形像)。「山之神」と刻まれた石碑が右手に。素朴な「手水舎」が左手に。「地神社」と刻まれた石碑。「社殿」。御祭神は埴山姫命(はにやまひめのみこと)。土を司る神。肥沃な(ひよく)田畑の土、陶器を作る粘土もその支配の範疇で、農業・陶磁器製造業・造園業・土木関係の職業などに縁の深い神様であると。近づいて。扁額「地神社」。そして帰宅して「亀井神社」で頂いた「守護矢」を神棚に奉納しました。
2022.01.02
閲覧総数 325
-
26

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その56)・妙覚院~茅ヶ崎バイオマス発電所~宝積寺
【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次「西光寺」を後にして山の下を巡る道を進む。「中赤羽根 自然環境保全地域この自然は、県民共通の貴重な財産とし子孫に伝えるかけかえのない宝物てす。草や木や、野生の動物を大切に。ゴミは必す持ち帰りましよう。」山道を上って行った。イノシシが出て来そうな山道を一人で。スマホの案内に従い進む。そして到着したのが「妙覚院 (日興門流 正信会)」。1977年(昭和52年)に、日蓮正宗(宗門)の信徒団体であった創価学会の言動を批判し続けた為、1980年に日蓮正宗(総本山・大石寺)から擯斥処分を受けて分離独立した宗教団体である。2022年(令和4年)現在は、宗教法人「正信会」と任意団体の「日蓮正宗 正信会」と「冨士大石寺正信会」の3つの団体に別れているとのこと。神奈川県茅ヶ崎市赤羽根3081−70。「日蓮正宗 妙覺院」とあったが、建物の外見は民家そのものであった。「妙覺院」を後にして、進むと左手奥にあったのが医療法人社団湘南健友会が運営する「介護老人保健施設 湘南の丘」。神奈川県茅ヶ崎市赤羽根3685。山道を下っていくと、竹林の中に。タケノコは成長し既に1m以上になっていた。山道を出ると正面にあったのが貸し市民農園「富士見ファーム赤羽根」。多くの方が菜園作業をされていた。次に足を延ばし(株)都実業グリーンリサイクル茅ヶ崎営業所を訪ねた。茅ヶ崎市では、ごみの減量を推進するため、庭木などの手入れを行った際に出る剪定枝について、令和3年4月からリサイクルを開始しているのだ。現役時代の仕事の関係上、気になる施設なのであった。「茅ヶ崎バイオマス発電所」案内板。「バイオマス」とは、生物資源(bio)の量(mass)を表す言葉で、再生可能な生物由来の有機性資源(化石燃料は除く)の総称。なかでも木材由来のバイオマスのことを「木質バイオマス」と呼びます。 発電方法は、端材や木質チップを直接燃焼させて発電する「蒸気タービン方式」と、木質バイオマスをガス化して燃焼させる「ガス化-エンジン(ガスタービン)方式」に分かれる。都実業と利久ではこのうち「蒸気タービン方式」を採用し設備化したのであった。木質バイオマスを裁断しチップ化しこれを燃焼させ、ボイラーにて蒸気を発生させ発電して、余剰電力を売電して収入を得る仕組み。この事業所施設の名称は「利久株式会社 茅ヶ崎バイオマス発電所」。「茅ヶ崎バイオマス発電所」。2021年8月1日より稼働開始と。場内に山積みされた木質チップを搬送車に載せ、焼却炉へ移送。木質バイオマスの木質チップをズームして。発電機仕様ボイラー型式:N-500 型、自然循環式水管ボイラー 使用燃料:木質チップ蒸気タービン型式:抽気復水タービン 発電出力:1,990kW / h少し移動してズーム。上空からの写真をネットから。 【http://miyako-jitsugyo.com/info/】よりそしてひたすら歩いて次の目的地の「宝積寺」の入口に到着。奥に「宝積寺」の山門が見えた。大きな駐車場の角には石碑が。左に「馬頭観世音」碑。その隣に「禅宗 宝積寺」碑。その先にも石碑が。「庚申供養塔」。寛政12年(1800)9月山伏角柱日月・「庚申供養塔」・三猿(台石)正面右側「寛政十二庚申」 〃左側「九月吉祥日」左側面「赤羽根上村中」「身代地蔵尊」。そして「宝積寺」の「山門」を正面から。駐車場の奥にあった石仏群。左の「招福布袋」像。笑顔の「布袋様」に近づいて。石仏が三体左:六十六部三千人・・の文字が。中央:高座郡・・・赤羽根村中右:明和ニ乙酉年(1765) 観音供養・・・「双体道祖神」であろうか。肩に手を置いて頬よせて。「山門」。寺号標石「曹洞宗 宝積寺」。「不許葷酒入山門」と。「山門」に近づいて。扁額「稲荷山」。「縁起宝積寺創建 慶長ニ年 西暦一五九七年本尊 観世音菩薩開山 冷室長厳大和尚 慶長五年十月廿日示寂伽藍倒壊 関東大地震 大正十二年九月一日 一九ニ三年本堂再建 昭和四十五年 一九七〇年薬師堂創建 慶安元年 一六四八年 再建 昭和五十三年 一九七八年」「山門再建成就碑」。庫裡であろうか。「宝積寺」の文字が。「薬師堂」。「薬師堂再建記念碑」。扁額「薬師堂」。「寶樹殿庫裡建設記念碑」。扁額「寶樹殿」。境内の見事な松。右から左へ10m以上もあっただろうか。根元を見る。石碑の文字は「雲外松」であろうと学友から。根元方向から。樹齢は100年以上か?廻り込んで。根元をズームして。本堂の扁額「寶積寺」。「妙染一貞法尼顕彰碑」。「かながわの100人」に選ばれたときに建てられた顕彰碑とのこと。「村野もと子」と現代風の名前であるが江戸時代に生きた女性。「長閑なる 雨の名残りの 露なるに おりてかざらん 山桜花」 「空に立つ うき名を何に つつままし おほふ計(ばかり)の 袖しなければ」裏面には野村もと子幼名直(生年不詳~天保八年九月一日 一八三七年没)は上赤羽根村名主小沢家の娘であって 歌の師加藤千蔭の門下に入り春夏秋冬恋歌六十九首の短歌一首の長歌を編した。「もと子家集(編者注 歌集か)」を天保六年(一八三五年)四月刊行当時の女流歌人として豊かな教養知識をもって歌才を認められる。昭和五十五年(一九八〇年)「かながわの一〇〇人」に女流歌人として選せられる昭和五十七年十一月吉日 小沢家十八代 小沢卓一 長男 雄市 建立 宝積寺四十世 大活俊雄 雲外良憲 敬書「寶積寺本堂再建記念碑」。「宝篋印塔」。祠の中に石仏が。近づいて。そして再び「本堂」を振り返り「宝積寺」を後にしたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.06.02
閲覧総数 794
-
27

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その29): 吉田松陰佐久間象山相会処(徳田屋跡)~洲崎町内会館~新井町内会館~東叶神社(1/)
「東渡船場」で「愛宕丸」から下船して、乗船した浮き桟橋(西渡船場)を振り返る。「東渡船場」の入口にも「浦賀の渡し」と。入口の左側には石柱と案内板が。「吉田松陰佐久間象山相会処(徳田屋跡)」ここ、神奈川県横須賀市の「浦賀の渡し」付近にある旅館・徳田屋跡の石碑。幕末の思想家・吉田松陰と佐久間象山が徳田屋で面会を行なった歴史的事実があるとのことで「吉田松陰・佐久間象山 相会処(徳田屋跡)」と石碑に刻まれていた。「徳田屋徳田屋は江戸時代から明治・大正期まで続いた浦賀を代表する旅館です創業は明らかではありませんが、寛政の改革を行った松平定信が相模・伊豆の沿岸を視察した折に宿泊したという記録からすると、1700年代の終わり頃 には存在したことがわかります。しかし、正式に旅宿(御用御宿)となったのは文化8年(1811)3月のことであり、これが浦賀の旅館の始まりです。ペリーが来航した嘉永6年(1853)6月には黒船を見聞するために吉田松陰が二度目の宿泊をして、ここで佐久間象山と会っています。これより前の、安政2年(1855)には、木戸孝允(桂小五郎)が浦賀奉行所・ 与力中島三郎助に造船技術の教授を得るために来訪した折に泊まっています。数多くの武士や文化人が徳田屋に宿泊し、ここから日本を見、世界を見て時の移り変わりを認識して、近代日本が誕生したことを考えると、徳田屋の果たした役割は大きかったことが分かります.その徳田屋はこの東浦賀の地にありましたが、大正12年(1923)の関東大震災の際に倒壊して姿を消しました。 横須賀市文化スポーツ観光部」「吉田松陰佐久間象山相会処(徳田屋跡)」はこの建物のあった場所に。この建物は震災後に建てられた建物のようであった。ネットからの下記の写真には、上記建物の前に石碑と案内板があったようだ。「東渡船場」を振り返って、乗って来た「愛宕丸」を見る。「東渡船場」入口近くに置かれていたこの象と女性像のモニュメントは??「東渡船場」近くにあった「ELMAR URAGA TERRACE CAFE」が客呼び用に置いたものか。次の目的地の「東叶神社」に向かって南に進む。左にあったのが「洲崎町内会館」。横須賀市東浦賀2丁目11−20。「州崎 (地名の由来)東浦賀町2丁目のこのあたりを洲崎といいます。その地形からわかるとおり、浦賀湾にふっくらと張り出した洲の先頭部ということに由来します。洲崎の山の手には 江戸時代の初期に三浦按針(ウイリアム・アダムス)の屋敷があり、按針が勧請した社があったと記録されていますが、その場所は分かっていません。この近くの東叶神社の裏山は、戦国時代の1556年、三浦半島が房総の里見軍に攻められたため、北条氏康が築城したといわれる浦賀城があった所です。この城は、後北条氏時代の三浦半島水軍の根城でした。山頂は平坦で、東京湾と対岸の房総半島が一望できます。浦賀奉行所与力・中島三郎助と子の墓が東林寺にあります。 浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探検くらぶ」その先右手にあったのが「新井町内会」と書かれた建物。横須賀市東浦賀 2-20-1。この倉庫は?民家のものか?そして正面に「東叶神社」の境内が現れた。「現在地」はここ。「浦賀湾」方向に廻り込むと「叶神社」案内板が。「叶神社祭神 應神天皇(誉田別命)由緒 養和元年(一一八一)辛丑年八月十五日京都高雄山神護寺僧文覚祈願奉勅命石清水八幡宮ヲ 勧請ス 夫ヨリ文治二年丙午年源頼朝公一事創業ノ際願意成就ノ意ニ基キ叶大明神ト尊称シ奉ル 叶神社 祭事 一月一日 歳旦祭(さいたんさい) 二月節分 節分祭(せつぶんさい) 二月十七日 春祭(祈念祭) 六月三十日 大祓式(おおはらえしき) 七月十八日 身代り弁天例祭 九月十五日 例大祭 十一月二十二日 秋祭(新嘗祭) 十二月三十一日 大祓式 東 叶神社々務所」参道正面入口。社号標石「叶神社」。「日西墨比貿易港之碑」「日西墨比貿易港之碑👈️リンクMonument of Trade between Spain・Mexico・Manila via Uraga慶長3年(1598)、徳川家康はスペイン(西)領メキシコ(墨)から新製錬技術を導入するため、スペイン領マニラ(比)からメキシコのアカプリコ港へ向かうスペイン商船(ガレオン船)を浦賀湊に寄港させるよう交渉した。そのため、慶長5年に上陸した英人ウイリアム・アダムス(日本名・三浦按針)を顧問とし、江戸邸のほか三浦郡逸見村の采地と浦賀邸を与えた。三浦按針はマニラにも渡海し浦賀貿易再開のために尽力した。江戸・浦賀・静岡・伏見・大坂にはフランシスコ会修道院が創設され、浦賀洲崎にはスペイン人を保護する高札が立てられた。この浦賀貿易を管轄していたのが船奉行向井将監忠勝である。浦賀湊には前フィリピン総督ロドリゴ・デ・ビペロ・イ・アベルサやメキシコ国王の使節セバスチャン・ビスカイノが訪れ、三浦按針建造のブエナ・ベントゥーラ号はロドリゴの帰国のために提供され浦賀を出帆し、幕府船として初めて太平洋航路横断を果たした。伊達政宗の遣欧船サン・ファン・バウティスタ号もスペイン国王使節ディエゴ・デ・サンタ・カタリナを乗せ入港している。三浦按針の母国との通商成立は来日から14年目であり、その3ヶ月後の慶長18年12月全国にバテレン追放令が公布された。元和2年(1616)貿易港は長崎・平戸に限定され、三浦按針が平戸への移住を余儀なくされるまで、浦賀は長崎と並ぶ東国唯一の国際貿易港として重要な役割を果した。2019年4月吉日 建碑発起人 浦賀湊を世界文化遺産にする会撰 文 日本海事史学会 鈴木かほる建碑賛同人 東叶神社氏子会寄付者一同(裏面に記載)施 工 石平石材店 <注>裏面」右手に「手水場」。その脇にあった「昭和五十二年市制施行七十周年記念横須賀風物百選東叶神社祭神は、京都の石清水八幡宮と同じ応神天皇(第15代の天皇)です。この神社は、養和元年(1181)8月15日、高雄山神護寺の僧文覚が、源氏の再興を願って石清水八幡宮の霊を迎えたことに始まるといわれ、その後、源頼朝によって、その願いが叶ったことから叶大明神の名で呼ばれるようになったと伝えています。また、このほか新編相模国風土記稿や皇国地誌残稿などには、この神社に関する記事が載っています。神社の裏山を明神山と呼び、標高は約50メートルです。後北条氏の頃、しばしば房総半島の里見水軍が、三浦半島に攻撃をかけてきましたので、それを防ぐために、この明神山に水軍を配置しました。山頂には、この神社の奥宮があり、その左手に「勝海舟断食の場」の標柱が立っています。明神山の素晴らしさは、よく保全された自然林で、木々の種類も豊富なことです。特にウバメガシの自生は、県内でもこの明神山と城ヶ島だけで、ここが分布の北限とされています。この学術的に貴重な明神山一帯は、「県指定天然記念物・叶神社の社叢林」となっています。」手水鉢には「灌洗(かんせん)」の文字が。「灌洗(かんせん)」とは「そそぎ洗うこと」。龍の吐水口(とすいこう)をズーム。そして「力石」が二つ。境内右手、水手舎の傍らに久助・十吉等、当時の怪力の名が刻まれた楕円形(40~60㎝)の力石が奉納されていた。「神奈川県指定天然記念物叶神社の社叢林 昭和五十一年十二月十七日 東浦賀町二丁目五十九番一他浦賀湾の東岸丘陵の突端斜面に位置する叶神社の社林は、標高53mの山頂まで見事な常緑広葉樹林で被われている。山頂部付近はスダジイ・マテバシイ林で占められ、一方斜面部はタブノキ林で被われている。高木層は、樹高20~22mのタブノキが優先しており、亜高木層はモチノキ、シロダモ、ヤブニッケイ、ヤブツバキ、イヌビワが生育している。低木層には、トベラ、アオキ、ヤツデ、オオバグミ、ムラサキシキブなどが見られる。林床に出現する植物の種数も多く、キヅ夕、テイカカズラ、ビナンカズラ、ヤブラン、キチジョウソウ、ツワブキ、イノデ、ベニシダ、オオバノイノモトソウなどが生育している。神奈川県はもとより、関東地方でも珍しく自然度が高く安定した郷上林を形成している。三浦半島沿岸部に残された数少ない自然林として学術的な価値も高く、天然記念物として指定されたものである。また、叶神社の裏山一帯は、浦賀城跡といわれており歴史的にも貴重なところである。 令和三年九月 横須賀市教育委員会」境内の巨大なご神木・銀杏も新緑に輝いていた。石段の上に拝殿の姿が。「おみくじかけ」。おみくじを「結ぶ」のでは、神様とのご縁を「結ぶ」為であると。神様とのご縁を結ぶ事によって、物事を良い方向に導いて頂く、という事。もちろん、何事も自らの努力が大切ではありますが、それに加え神様とのご縁があれば、それは更に良い方へと向かって行くことになるのだと。「神社参拝の基本作法」案内板。「源頼朝が大願成就したパワースポット叶神社(東)御祭神 誉田別命(ほんだわけのみこと)御利益 心願成就「頼朝に始る武家政権の歴史を支えた神社」養和元年(1181)京都神護寺の僧文覚が源家の再興を発願し、石清水八幡宮を当地に勧請され、もし源氏の再興実現せし折は、永く祭祀を絶たざるべしと祈念したところに始まるとされている。その後、文治2年(1186)には源頼朝公が源家再興願意成就の意を込めて神号を改め、叶大明神と尊称されたと伝えられている。社殿に昇る石段の両脇に植えられている蘇鉄はこの時に頼朝公が縁深い伊豆の地より移植奉納されたと伝えられている。境内に祀られている「身代わり弁財天」は種々の難事の身代わりになると言われており、幅広く多くの方々の信仰を集めている。また、幕未に勝海舟が明神山に籠もって断食修行をした際に使用した井戸が今も境内に残っている。」「叶神社案内略図」。①拝殿 ⑨産霊坂修築記念碑 ②厳島神社(身代り弁天) ⑩勝海舟断食跡③勝海舟禊の井戸 ⑪本殿(奥の院)④不動尊石刻碑 ⑫東照宮⑤神輿庫 ⑬神明社 ⑥湊稲荷社 ⑭住友重機殉職者慰震塔⑦芭蕉句碑 ⑮産震坂(むすびざか)道標⑧惠仁志坂(えにしざか)道標」「縁結び守り「勝海舟 縁の「勝守」御朱印等の案内が窓に貼られていた。」「耀真山永勝不動尊(ようしんざんえいしようふどうそん)の由来明治維新前には、神仏習合といって、叶神社は別当耀真山神寺(べっとうようしんぎんえいじんじ)として古儀真言寐醍醐寺派三宝院に属し、横浜の金沢から三浦半島 全域において、本山格の寺格をもった修験道の寺院を兼ね、歴代の宮司は、同時に真言宗の大僧都、真言修験の大先達を兼ねていました。叶神社には、不動尊が現在もお祀(まつ)りされており、このお不動様の像は嘗ての真言修験の寺院、耀真山永神寺のご本尊とも伝えられています。こちらのお不動様の石彫を通して、耀真山永神寺のご本尊、即ち耀真山永勝不動尊をお参りして頂けます。」拝殿前の石段の右には石仏が安置されていた。不動明王であろうか。段脇右を奥に進むと、鳥居があって、その奥には洞穴があった。「身代り弁天御神徳御祭神 厳島媛命 例祭日 七月十八日東浦賀の産土神である叶神社の境内社として、神秘な岩窟内に祀られる厳島神社はもともと海上交通の安全と戦の勝運を司る神として尊崇されており誠に霊験あらたかであります。 古よりこの弁天様を信仰された人々が海上の遭難や交通事故、はたまた難病などあらゆる不慮の事態に直面し、身命の危機に晒されても必ず弁天様が示現なされて身代わりとなられ災禍からお守り下さったという例には枚挙に暇がありません。 この様な御神徳が三浦半島を始め近郷近在の方々の篤い信仰をあつめております。弁天様を信仰なされて限りなき御神徳を享受されんことを祈念いたします 叶神社々務所」岩窟内に、厳島媛命がお祀りされ、不慮の事態に直面し身命の危機に晒されても必ず弁天様が示現なされて身代わりとなられ、災禍からお守り下さる と。扁額「叶神社 辯天社」岩窟内陣。身代わり弁天の横には、また別の手水石そして龍の吐水口(とすいこう)からか聖水が。「勝海舟 断食修行の折使用の井戸この流水は、右奥にある「勝海舟断食修行の折使用の井戸」から汲み上げている水です。比叡山延暦寺の高僧よりご託宣が伝えられ、この流水を硬貨に掛け流し常に身に着けることにより、弁天様のお力も相俟って、開運と金運のご利益が得られるとされております。流水を掛け流した硬貨を納めるお守り袋を社務所にて五百円で頒布致しておりますので、ご利用下さい。」勝海舟 断食修行の折使用の井戸。近づいて。「勝海舟 断食修行の折使用の井戸」と。拝殿への石段を上ると、途中踊り場の右側にあった「蘇鉄」。蘇鉄は、源頼朝公が緑深い伊豆の地より移植奉納されたと伝えられている。同じく左側にあった「蘇鉄」。「この蘇鉄は源頼朝公 源家再興の折 伊豆より移植奉納されたものである」と。さらに拝殿への石段を見上げて。この日は5月3日(憲法記念日)の祝日、日の丸が掲げられていた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.05.27
閲覧総数 645
-
28

浜離宮恩賜庭園へ(その2)
「特別名勝 特別史蹟 東京都浜離宮恩賜庭園」の入口門・大手門渡櫓跡を振り返って。入口右側の大手門渡櫓の石垣。大正時代の「大手門渡櫓」の写真をネットから。「ようこそ浜離宮恩賜庭園へ ご入園・ご利用案内」。「入園券をお買い求めください」。受付・券売所。65歳以上150円のチケットを買う。庭園内に入る。左奥にあった巨木。「クスノキ」と。その先にあった見事な老松。「三百年の松👈️リンクおよそ300年前の宝永6 (1709)年、6代将軍徳川家宣(いえのぶ)がこの庭園の大改修を行った(その頃から「浜御殿」と改称された)頃に植えられたものといわれ、現在では、都内最大級の黒松となっています。」「」100年後には「四百年の松」と改名?近づいて。黒松の中を見るとたくさんの支柱が木を支えているのであった。隣りにあったのは赤松か?樹皮が剥がれたところは、赤味を帯びた地肌が見えるのであった。廻り込んで「三百年の松」を見る。「内堀」に架かった木橋から「築地川」からの取水場所を見る。このには水位調整用のゲート等はないようであった。「築地川」からの取水場所から繋がる「内堀」。「内堀」には所々に石段が設置されていた。荷揚げ用のものであったのだろう。 「木橋」を振り返って。「ダイサギ」であっただろうか?「ダイサギ」の嘴(くちばし)は、繁殖期には黒く、冬は黄色くなる。春から夏にかけて黒くなり、秋から冬にかけて黄色くなるという特徴があるとのこと。庭園にには巨木が緑豊かに。「内堀」に沿って南方向に歩く。190m高さの都市型賃貸住宅・アクティ汐留が正面に見えた。「内堀」案内板。「内堀こは浜離宮恩賜庭園で「内堀」と呼ばれています。江戸時代、京都や大阪あるいは長畸などから船で連ばれてきた物資を江戸城に入れるための中継施設でした。現在、お花畑や広場になっているあたりには「籾倉」と呼ばれる倉が建てられていました。また、内堀の護岸は間知石を用いた石積みでつくられ、荷揚げ用の階段も設けられていました。工事のときに行われた発掘調査では、現状の石積みの背後に埋もれた船着場や、木製の水道管の樋管(ひかん)と思われる構造物などの江戸時代の様々な遺構が発見されました。平成21年に行われた修復工事では、2か所の荷揚げ用の階段も復元しました。」内堀平面図。「濱御殿絵図 寛政年間(1789~1800)頃の絵図」「船着場の遺構(発掘時の写真)石積の背後から。写真のよいな階段状の船着場が見つかりました。」「浜離宮恩賜庭園園」の変遷👈️リンク本園の価値を把握するため、本園の歴史的変遷及び周辺環境の変遷を以下に整理する。歴史的変遷本園の歴史は、将軍の鷹狩の場であった場所を、承応3 (1654)年に松平綱重が埋め立てて屋敷としたことに始まる。4代将軍家綱の時代に将軍家の別邸となり、歴代将軍が舟遊びや鷹狩を楽しみ、公家や僧侶等を接待する場所として使われた。明治に入ると皇室の離宮となり、外国貴賓の接待や皇室行事の場となるなど重要な役割を担った。その後、大正12 (1923)年の関東大震災、太平洋戦争の空襲と、2度の大きな被害を経て、昭和20 (1945)年に東京都に下賜され、翌年、都立の庭園として一般に開放された。史資科をもとに、創設から現在までの所有者及び名称の変遷を、下表に示す。「旧浜離宮庭園の所有者及び名称の変遷」本園の歴史的変遷を、所有者や特徴的な事象を踏まえ7つの時代に区分した。時代ごとの変遷と特徴的な事象を下表に示す。「本園の時代区分」「浜離宮恩賜庭園のうつりかわり①、②」案内。「浜離宮恩賜庭園のうつりかわり①6代将軍 徳川家宣(1662~1712)将軍在職:1709(宝永6)~1712(正徳2)◆綱豊は家宣と改名◆御庭を大改修◆大手門や橋、中島の御茶屋、清水の'御茶屋、海手の御茶屋、観音堂、 庚申堂等を建てた◆浜奉行を置いた◆観艦式を行った◆公家の接待の場として活用浜離宮恩賜庭園の歴史は、1654 (承応3 )年、4代将軍徳川家綱の弟 徳川綱重がこの地に屋敷を構えたことに始まる。1704 (宝永元)年、徳川綱重の子 徳川綱豊が叔父の5代将軍綱吉の養子となったことから、この地は将軍家の別邸となり、浜御殿と呼ばれるようになった。「浜御殿御指図」と「浜御殿 間取図」浜御殿の位置左の間取の浜御殿は、享保九年(一七二四年)の大火で焼失、再建されなかった。能舞台や清水の御茶屋が設けられていた。下図は、航空写真に御殿を位置づけたもの。東京農業大学准教授服部勉先生の指導による。御殿の南端からは、庭が眺望できた。御成御門、御庭ロ御門の位置も推定できる。「浜離宮恩賜庭園のうつりかわり②8代将軍 徳川吉宗(1684~1751)将軍在職:1716(享保元)~1745(延享2)◆吉宗は、この地を実学の実験場として活用◆サトウキビや薬草の栽培◆狼煙の実験や西洋騎馬術の訓練を実施◆浜御殿の役人を大幅に削減◆5代、6代将軍の側室の館を建築◆象を飼育象の飼育については「享保13(1728)年6月7日、広南(いまのベトナム)から、中国の貿易商が長崎に、牡牝(オスメス)2頭の象をつれてきたそうです。牡は7才、牝は5才でしたが、牝は上陸3ヶ月後の9月11日に死亡、その後、牡は長崎の十善寺で飼育され、翌年の5月に江戸将軍家に献上されることになりました。一行は長崎を享保14(1729)年3月13日に長崎を出発、4月16日に大阪、4月26日に京都到着。京都では中御門天皇の上覧があったそうです。この時、上覧には官位が必要なことから、象に『広南従四位白象』の官位が与えられたという話まであります。(諸説あり)そして、5月25日に江戸、浜離宮に到着、そこで27日の将軍上覧まで休んでいました。『徳川実記』によれば、当日、吉宗は江戸城大広間から象を見たようで、この時、幕府御用絵師・狩野古信がその時の絵を描きました。象はしばらく浜離宮で飼育されましたが、年間飼料代200両、食料の世話、番人を殺すなどの事故があったため、民間に払い下げられることになりました。享保17(1732)年に幕府直営の象舎が中野に造られ、押立村の平右衛門、中野村の源助、柏木村の弥兵衛の三名が世話をし、象舎は見物人で賑わい饅頭も売れたと伝わります。さらに彼らは象の糞が疱瘡の薬であると言って売り出して大もうけしたらしい。(糞ではなく涙だという説もあり)商魂たくましいですね(笑)そして、象は寛延(1748~51)年頃、死んだそうです。可哀そうに異国で孤独に死んでしまった哀れな象でした。皮は剥がされ、頭蓋骨と牙、鼻の皮が源助に与えられたそうです。これがいま、中野宝仙寺に伝わる『馴象之枯骨』(じゅんぞうのここつ)です。しかし、残念なことに第二次世界大戦の最中、一部を残し焼失してしまいました。」とネット👈️リンク から。「1732年(享保17)年頃の 浜御殿絵図」。「浜離宮恩賜庭園のうつりかわり③11代将軍 徳川家斉(1773~1841)将軍在職:1787(天明7)~1837(天保8)◆家斉は、8代将軍吉宗の曾孫◆御庭への関心が高く、大改修を行う◆松の御茶屋、鷹の御茶屋、燕の茶屋、お伝い橋、新銭座鴨場等を設けた◆浜御殿への御成は、将軍在位50年間に248回と最多。 その主な目的は、鴨場での放鷹であった「歴代将軍の来訪回数」。下記の表は、松平綱豊が5代将軍綱吉の嗣子となり、本園が徳川将軍家の所有となった宝永元(1704)年から浜御殿が廃止された慶応3 (1867)年までの163年間を集計したものである。「1799(寛政11)年頃の 御浜御殿ノ絵図」。「浜離宮恩賜庭園のうつりかわり④122代天皇 明治天皇(1852~1912)天皇在位:1867(慶応3)~1912(明治45)◆延遼館が建てられ、迎賓館として諸外国の要人をお迎えし、舞踏会等が行われた。◆明治天皇は、明治維新後荒廃していた鴨場の復興を命じた◆1883 (明治16 )年から観桜会を実施 1916 (大正5 )年まで続いた「1884(明治17)年 五千分一東京図部分(参謀本部 陸軍部測量局)浜御殿は、1866 (慶応2)年に海軍所となり、園内に大砲が据付けられた。明治維新後、1869 (明治2)年に延遼館が完成。延遼館とその周辺の土地は外務省所管。1870 (明治3)年に従来の御庭の部分が宮内省の所管となり、浜離宮と称される。1874 (明治7)年に延遼館以外すべての園地が、1884 (明治17)年には園全体が宮内省の所管となった。」「延遼館跡(えんりょうかんあと)」方向を見る。近づいて。「延遼館跡延遼館は、イギリス王子が国賓として来日することを契機に、外国要人の迎賓館として明治2 (1869)年5月に政府によって建てられました。明治12 (1879)年7月には、アメリカのグラント将軍(第18代アメリカ大統領)が、約2ヶ月滞在しました。その後も、多くの国賓を迎え、鉄道開業式など国の行事の際にも使用されましたが、明治22(1889)年12月、老朽化のために取り壊しが決定し、ほどなくしてその歴史に幕を閉じました。」延遼館正面。高層ビルを背景に緑溢れる「浜離宮恩賜庭園」内を歩く。「内堀」に沿って南に向かって。ビジネスセンタービルや高層住宅が林立。赤松。影の姿も美しかった。後ほど訪ねた「内堀」に架かる木橋をズームして。ここを渡ると「籾倉(現お花畑)」に行けるのであった。さらに南方向・奥に向かって進む。藤棚。左に折れて「あずま屋(休憩所)」方向に進む。土産物売り場「濱見世」案内板も。「花木園」案内。「内堀」の先、先ほど訪ねた築地川からの取水場近くに架かる木橋を振り返る。この花はサルスベリ?ズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.09.11
閲覧総数 294
-
29

3か月でマスターする数学・『水平線はどれくらい先?』
NHKで放送されている「3か月でマスターする数学」を録画して、学生時代の復習?をしています。4月から始まった「3か月でマスターする」シリーズ。世界史に続く第2弾「数学」が6月26日から始まったのです。「学生時代、数学の授業やテストに苦しみ、良い思い出がないという人も多いのでは。でも大丈夫です!」と。 全12回からなるこのシリーズ、題材は基本的に中学校の数学の教科書から選定していると。MCはNHK・塚原愛アナウンサー。秋山仁さん(東京理科大学栄誉教授)、横山明日希さん(数学教育者)、ヨビノリたくみさん(教育系YouTuber)3人の数学教育のプロが、それぞれのアプローチで数学の楽しさや奥深さをじっくりレクチャー。数学の歴史的背景や生活との関わりなど、幅広い話題を提供します。目指すは「数学との仲直り」。あなたも一緒に大人の学び直しをしませんか!?」と。そして、この日は「水平線はどれくらい先?」と。この日の教材部分。『海岸に立って』!!何もしないでのんびり海を眺めるのはリフレッシュの一つでは。見渡す限りの広い海の先に水平線が見える場所があります。水平線とは空と海が接する線で、文字からするとまっすぐ、水平であるべきですが、地球が丸いため、実際の水平線は曲がって見える・・・と。しかしこれはそう感じるだけで正確には正しくはないとのこと。すなわち、「水平線を眺めると地球が丸いのが分かる」という表現は、ある程度正しいですが、条件が伴うのです。肉眼で見た際、地平線や水平線がわずかに湾曲していることを感じることができるのは、高い場所にいる場合や、広大な水面を見ているときです。例えば、飛行機の高度や、高い山、あるいは海上などの広い場所であれば、地球の丸みを実感しやすいです。しかし、日常的な高さからでは、その湾曲は非常に微妙であり、はっきりと確認できるほどではありません。よって、地球の丸さを水平線を見て完全に理解するのは難しいものの、特定の条件下では湾曲が感じられるため、部分的には正しいと言えます。すなわち、地球の水平線の湾曲を肉眼で感じられるのは、約10,000メートル(10km)以上の高度に達したときです。この高度に達すると、水平線の湾曲が肉眼でもはっきりと見えるようになります。一般的な旅客機の巡航高度(約10,000メートル~12,000メートル)では、機窓から水平線・地平線が湾曲しているのが確認できることがあります。一方で、山や建物の上から地平線・水平線を見ても、通常はその湾曲を感じ取ることは難しく、飛行機のような高度が必要です と。下の写真の如き場所からは、水平線は直線にしか見えないので、水平線・地平線が湾曲しているのは確認できないと。下の写真の水平線上に、青い直線ーーーーを引いて見ました。さて、この日の本題ですが、写真の右の水平線に沈んで行く船は海岸からどのくらい離れているでしょうか?そして水平線に浮かぶ街並みはどのくらい離れた場所?。光は直進しますから水平線より下は見えません。A点から見れば遠くの船ほど上部しか見えないのは地球の曲率によって見えなくなると昔の人は既に考えていたとのこと。また周囲を海で囲まれた島の高い山に登って四方をみわたせば、なんとなく地球が丸いことを感じる事ができたのです。船乗りなど漠然とではあっても知っていたはずなのです。皆既月食の時、月に写る地球の影が丸いことから地球が丸いことも知っていました。さて、この日の学習テーマに戻りますが、人が海岸線に立ち、そこから見える水平線までの距離は、目の高さがわかれば計算することができるのです。地球は丸いので、その断面は円で近似することができます。その円の半径をrとして、図のように地面から高さhのところに目の位置があるとしましょう。そして、そこから見た水平線までの距離をxとすると、xは目の位置から地球に引いた接線の長さになります。地球の半径rを6371000m、海岸に立ったときの海面からの目の高さがh=1.6m(目の高さ)とすると、下記の如き計算となるのです。下図の如く『三平方の定理』から計算します。そしてx=4515m=4.515kmとなります。「水平線の彼方」と言うほどなので、はるか遠いイメージがあるかも知れませんが、たった4.5km先しか見えていないのです。みなさん、もっと遠く数十km先と思っていたのでは!!もしも、自転車で海の上を進めるとしたら20分で着くくらいの距離なのです。丘の展望台などに立って、海面から150mの高さに目を置いて海を見ているという場合は、目の高さが100倍になりますから、水平線までの距離は10倍の45.15kmとなるのです。この船舶の動画👈️リンクは、見えている水平線の僅か遠方を航行しているものです。船の下部は隠れており、上部のみ見えています。さらに水平線の先を航行する船舶。船の最上部しか確認できません。江戸時代に歌川広重によって描かれた浮世絵「冨士三十六景伊勢ニ見か浦」が下の絵。水平線のはるかかなたに富士山が描かれています。描かれているのはいいとして、これを描いた場所が問題なのです。約4.5km先しか見えないはずの水平線に、富士山が見えるわけがない?。ということは、歌川広重は、想像で富士山を描いたのでしょうか。ところで「何km離れた場所から富士山は見える?」👈️リンク計算の結果は、約220km以内であれば富士山は見えると。そして、三重県伊勢市の二見浦。富士山までの距離は、約200km!!。よって、浮世絵の富士山も想像ではなく、実際に見えていたのだと推測できるのだと。逆に言うと、富士山の頂上から見れば、計算上では、三重県の二見浦まで見えるということ。高さが高ければ高いほど、遠くまで見えるということなのです。当たり前のような話ですが、遠くまで見える距離が一気に伸びるのです。下図が、理論上、富士山頂から見える日本国内の範囲です。纏めて見ますと●始めに登場した自分の1.6mの目の高さからは、4.5km●富士山の3,776mだと、約220km●東京スカイツリーの展望台の450mだと、約76kmまで見えるようです。 これは、富士山の麓くらいまでの距離。●世界一のエベレスト。8,848.86mだと、約337kmまで見える。 ちなみに、日本までの距離は4,000km以上。よって全然見えない!!。 世界一とはいえ、地球の丸さには勝てないわけです!!。●上空10,000m、飛行機の機窓からは約380km 羽田空港上空10,000mからは名古屋くらいまで見えるということです。スカイツリーから見える富士山の姿をネットから。ケータイやカーナビなどでは、さまざまな方法を利用して位置情報を取得しているのだ。次にその仕組みを見ていきましょう。その中心になるのがGPS(Global Positioning System/汎地球測位システム)。「もう1つ、カーナビの例を紹介します。「GPS衛星」👈️リンクは自身がいるBから地表までの距離aを情報として持っています。そして車Aが現時点でいる場所から発信した電波が衛星に届くまでの時間によって衛星がいるBまでの距離cを計算できます。次に、衛星と地球を最短距離で結んだ点CからAまでの距離bを三平方の定理によって求めます。これで車Aがどんな円周上にいるかわかりますが、まだ車の位置は1点に定まっていません。そこで同様の操作を3つ以上の衛星について行うことで車Aの位置を1つの場所に特定することができます。このように『三平方の定理』を使うことで、カーナビは精度を高めているのです。」 4機以上の衛星で衛星測位は可能ですが、安定した位置情報を得るためには、より多くの衛星が見えることが望ましいです。しかし、GPS衛星は都市部や山間部ではビルや樹木などに電波が遮られて可視衛星数が減り、位置情報が安定的に得られないことがあります。2018年11月から、「みちびき・QZSS(Quasi-Zenith Satellite System)」は4機体制で運用を開始しており、このうち3機はアジア・オセアニア地域の各地点では常時見ることができます。みちびきはGPSと一体で利用できるため、安定した高精度測位を行うことを可能とする衛星数を確保することができます。GPS互換である「みちびき・QZSS」は安価に受信機を調達することができるため、地理空間情報を高度に活用した位置情報ビジネスの発展が期待できます と。順序が逆になりましたが、ところで『三平方の定理』とは、2辺の長さをa、b、斜辺の長さをcとする直角三角形において成り立つ、次の定理です。斜辺cの2乗は、他の辺a、bをそれぞれ2乗した数の和に等しいのです。直角三角形では、2つの辺の長さがわかると、三平方の定理を使って他の1辺の長さが計算できることを覚えていますか??また、三平方の定理の逆も成り立ちます。3辺の長さがa,b,cの△ABCにおいて、a^2+b^2=c^2が成り立つならば、△ABCは直角三角形であるということも言えるのです。※「^2」は自乗・2乗の意味。この『三平方の定理』は下記のごとく証明できるのです。まず、三角形の内角の和は180°=90°+x°+y°内接する小さな正方形の赤く示された角度┓+x°+y°=180°なので┓=180ー(x°+y°)=180°-90°=90° よって内接する四方形も正方形なのです。中の正方形の面積を計算しますと『三平方の定理』が導けるのです。そして、昔の人はどのように地球の大きさを求めたか?「地球の大きさを初めて測ったひとアレクサンドリア(エジプト)に住んでいたエラトステネス(紀元前3世紀ころ)は、アレクサンドリアから南にあるシエネの井戸の底には太陽の光が当たるのに、自分が住んでいるアレクサンドリアの井戸の底には太陽の光が当たらないということを知りました。工ラトステネスは、この理由を「地球が球体である」ことで説明できると考えました。シエネの太陽高度角が90度であるのに対して、アレクサンドリアでは、太陽の高度角は82.8度(影の角度は7.2度)と測定し、ニつの都市の間の距離を、旅人の旅行行程から5,000スタジア(925km)と求め、地球の大きさは、1周46,250kmになると計算しました。」繰り返しになるが、さらに詳細を。紀元前230年頃、ギリシャのエラトステネスは、初めて地球の大きさを求めた。彼はシエネという町では夏至の日の正午に深い井戸の底まで太陽の光が差し込むことを知った。またシエネの北にあるアレキサンドリアで夏至の日の正午に太陽の位置と天頂とのなす角度が360°1/50倍=7.2°となることを測定した。さらに、シェネとアレキサンドリアの間をキャラバンが50日かかって歩いていたことから、シエネからアレキサンドリアまでの距離を求めた。シエネからアレキサンドリアまでの距離は925kmとなることから地球の全周は46250kmと。よって地球の半径は7400kmを導き出したと。ウィキペディアによると地球の半径: 6,371 kmであるので、誤差約16%の精度で紀元前でも算出していたのであった。「日本人で最初に地球の大きさを測ったひと日本人で最初に地球の大きさをはかった人は、伊能忠敬です。伊能は、地球の緯度1度の長さから地球の大きさを求めるために測量に出かけたといわれています。第一次測量では奥州街道をまっすぐ北上しながら測量と天文測量を行い、緯度度1度の長さを27里余り(106km)と求めました。また、第ニ次、第三次測量で緯度一度の長さを28.2里(110.7km)と求め、地球の大きさは、1周約39,900Kmと計算しました。」現在解っている地球一周の正確な距離は、赤道上を東西に一周する場合が約4,0077km、北極と南極を通るように南北に一周する場合で約40009kmとなり、少しだけ赤道の方が長くなっています。よって約220年ほど前に伊能忠敬は、99.5%の精度で測量していたことになるのだ。そして最後に、月面から「地球の出」の写真を。「地球の出」とは、月の地平線から、地球が上ってくるようにみえる現象をいいます。月の自転周期と公転周期は同じなので、月はいつも同じ面を地球に向けています。これは逆にとらえると、月の表側のある地点に立って地球を見た場合、いつも同じ場所に地球が浮かんでいるように見えることになります。月の表側の真ん中付近ではいつも頭の真上に地球は見えますし、月の南極や北極、裏に近い端の方では月の水平線上に見えるでしょう。このため、南極や北極を飛行している宇宙船から、月の地平線上に地球が出てくる「地球の出」や、逆に地球が地平線の下に消えていく「地球の入り」をみることができるのですと。月周回衛星「かぐや(SELENE)」が2008年9月30日、「満地球の出」👈️リンクの撮影にも成功。そして「満地球の入り」👈️リンクも ・・・つづく・・・
2024.09.21
閲覧総数 772
-
30

アイルランド・ロンドンへの旅(その121): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-4
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクV&A(ヴィクトリア&アルバート博物館/ロンドン)日本展示室に掛けられている浮世絵(木版画)。額装されているのは主に 歌舞伎や武者絵を題材にした錦絵で、江戸末期〜明治期の作品。「Legendary Women in Japanese PrintsWoodblock prints were an affordable art that could be enjoyed by people of all ages,genders and social classes. In the 19th century printed images of illustrious andnotorious women found new popularity in Japan. Going beyond conventional imagesof female beauty, government directives to improve social morality encouraged theportrayal of women of exemplary strength and skill, while literature and drama delighted in villains who were ready to bewitch and betray.These prints show not only the creativity of Japan’s printmakers, but also the many ways in which women came to be depicted: dangerous, talented and powerful.」【浮世絵に描かれた伝説的な女性たち木版画は、あらゆる年齢・性別・社会階層の人々が楽しめる手頃な芸術であった。19世紀になると、日本では高名な女性や悪名高い女性の姿を描いた版画が新たな人気を博した。従来の美人画の枠を超え、社会道徳を向上させるための幕府の指導は、優れた力と技を備えた女性像の描写を奨励した。一方で文学や演劇は、人を惑わし裏切る妖しい悪女像を喜んで描いた。これらの版画は、日本の版画師たちの創造力を示すだけでなく、女性がいかに危険で、才能に満ち、力強い存在として描かれてきたかを物語っている。】 左上:1.小野小町《女三十六歌仙》シリーズより 団扇絵右上:2.巴御前、武蔵三郎衛門有国と戦う図下 :3.安倍泰成、妖狐を退治する図1.小野小町《女三十六歌仙》シリーズより 団扇絵2.巴御前、武蔵三郎衛門有国と戦う図 をネットから。3.安倍泰成、妖狐を退治する図 をネットから。「1. Ono no Komachi, from the series The Thirty-six Immortal Women Poets1843–47Ono no Komachi, who lived during the 9th century, is one of Japan’s most celebratedpoets. Her unparalleled beauty is upheld as a feminine ideal, and her work conveyspassionate intensity. The poem in the cartouche translates to:‘It must have been because I fell asleep tormented by longing that my loverappeared to me. Had I known it was a dream, I should never have awakened.’Utagawa Hiroshige (1797–1858)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.2933-1913」 【1.小野小町《女三十六歌仙》シリーズより1843–47年9世紀に生きた小野小町は、日本で最も著名な歌人の一人である。比類なき美しさは女性の理想像として称えられ、その和歌は情熱的な切実さを伝えている。画中の詞書に記された歌の現代語訳は次の通り:『思ひつつ寝ればや人の見えつらむ 夢と知りせば覚めざらましを』「恋い焦がれて眠りに落ちたために、夢にあなたが現れたのだろう。夢と知っていたなら、決して目覚めたりはしなかったのに。」作者:歌川広重(1797–1858)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.2933-1913】「2. Tomoe Gozen fighting Musashi Saburōemon Arikuni1815–20Tomoe Gozen is Japan’s most famous female warrior. While her historical existence is debated, chronicles of the 12th-century Genpei War describe her commanding troopsand highlight her skill in archery, sword fighting and horse riding. Here, Tomoe is shown preparing to behead her opponent Musashi Saburōemon Arikuni. Prints of famous warriors became increasingly popular in the early 19th century.Katsukawa Shuntei (1770–1820)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.12602-1886」 【2.巴御前、武蔵三郎衛門有国と戦う図1815–20年巴御前は、日本でもっとも有名な女武者である。史実性については議論があるが、12世紀の源平合戦の記録には、彼女が軍勢を指揮し、弓術・剣術・馬術に優れていたことが描かれている。本作では、巴御前が敵将武蔵三郎衛門有国を斬首しようとする場面が表されている。19世紀初頭、有名武将を描いた浮世絵はますます人気を高めていった。作者:勝川春亭(1770–1820)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.12602-1886】「3. Abe no Yasunari exorcises a demon1847–48In Japanese folklore, foxes are shapeshifters with supernatural powers. The mythical Tamamo no Mae was a cruel and ambitious nine-tailed fox. Disguised as a beautifulwoman, she became the mistress of the emperor and caused him to fall ill.When exorcist Abe no Yasunari exposed her true nature with a magic mirror, she wasdefeated and turned to stone.Utagawa Kunisada (1786–1865)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.5558-1886」 【3.安倍泰成、妖狐を退治する図1847–48年日本の伝承において、狐は超自然的な力を持つ変化の存在とされてきた。伝説の玉藻前(たまものまえ)は、残酷で野心的な九尾の狐であり、美しい女性に姿を変えて帝の寵姫となり、病に陥らせた。陰陽師・安倍泰成は、魔法の鏡によってその正体を暴き、彼女は敗北して石に変じたと伝えられる。作者:歌川国貞(1786–1865)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.5558-1886】左:4.神功皇后と武内宿禰(たけうちのすくね)中央左:5.二代目 岩井粂三郎の揚巻役中央右:6.木曽のお六の櫛右下:7.厳島における弁才天の顕現が平清盛を圧倒する図「4. Empress Jingû and Minister Takeuchi,from the series Banners as Interior Decoration1844–62Before the Imperial Household Law of 1889 prevented female succession, eight ofJapan’s historical rulers were women. Empress Jingû is a mythical figure said tohave led an army into the Korean peninsula in the 3rd century. A shaman and powerful warrior, she is often portrayed carrying a sword, a bow and a quiver of arrows.Utagawa Kunisada (1786–1865)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.1373-1899」 【神功皇后と武内宿禰(たけうちのすくね)《室内装飾の旗(バナー)》シリーズより1844–62年1889年の皇室典範が女性の皇位継承を禁じる以前、日本の歴代統治者のうち8名は女性であった。神功皇后は3世紀に朝鮮半島へ軍を率いたと伝えられる伝説上の人物で、巫女的性格を持つ強力な女武者として、しばしば剣・弓・矢筒を携えた姿で描かれる。作者:歌川国貞(1786–1865)制作地:江戸(東京)技法:木版画(錦絵)所蔵番号:E.1373-1899】 「5. The Actor Iwai Kumesaburō II as Agemaki1824–25Beautiful women from the brothel district were a mainstay of prints, drama andliterature; in reality, they worked under exploitative contracts. In the kabuki theatre, female roles were played by male actors known as onnagata. Here, actorIwai Kumesaburō II plays the formidable Agemaki of the Miura brothel. Perfecting the performance of femininity, onnagata set new standards for female beauty. Some onnagata are recorded as living as women off-stage.Utagawa Toyoshige (1777–1835)Edo (Tokyo)Woodblock PrintMuseum no. E.12645-1886」 【5.二代目 岩井粂三郎の揚巻役1824–25年遊郭の美しい女性たちは、版画・演劇・文学において主要な題材となったが、実際には搾取的な契約の下で働かされていた。歌舞伎では、女性役は女形(おんながた)と呼ばれる男性俳優によって演じられた。ここでは、二代目 岩井粂三郎が三浦屋の花魁揚巻を演じている。女形は女性らしさの演技を完成させることで、新しい「女性美」の基準を作り上げた。中には、舞台を離れても女性として生活したと記録されている俳優もいた。作者:歌川豊重(1777–1835)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.12645-1886】「6.Kiso no Oroku Combs, from the series A Compendium of Famous Artisans1843–47The story of Oroku of Kiso is an example of filial piety and inventiveness. Oroku’s familywas poor, but she supported them by making combs out of a fine-grained local woodwhich, legend says, could cure headaches. In the Edo period (1615–1868), women from working households often contributed to the family business. Handmade combs from the Nagano area are still named after Oroku.Utagawa Hiroshige (1797–1858)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.2918-1913」 【6.木曽のお六の櫛《諸職人尽(しょしょくにんづくし)》シリーズより1843–47年木曽のお六の物語は、孝行心と工夫の好例である。お六の家は貧しかったが、彼女は地元産のきめ細かな木材を用いて櫛を作り、家族を支えた。その櫛は「頭痛を治す」との伝説もあった。江戸時代(1615–1868)には、働く家庭の女性が家業に従事することも多かった。長野地方の手作り櫛の中には、今も「お六櫛」と呼ばれるものがある。作者:歌川広重(1797–1858)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.2918-1913】「7. The manifestation of Benzaiten overwhelming Taira no Kiyomori at Miyajima1862Japan’s two major religions, Shintō and Buddhism, incorporate several female deities.Benzaiten is associated with water, music and eloquence, and is one of the Seven Godsof Good Fortune. This print shows her appearing to the 12th-century military leader Taira no Kiyomori. Kiyomori attributed his success in battle to Benzaiten andbuilt a temple in her honour.Utagawa Yoshitora (active 1830–80)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.13975-1886」 【7.厳島における弁才天の顕現が平清盛を圧倒する図1862年日本の二大宗教である神道と仏教には、複数の女神が取り込まれている。弁才天(弁財天)は水・音楽・弁舌に結びつけられ、七福神の一柱でもある。この版画は、12世紀の軍事的指導者平清盛の前に弁才天が現れる場面を描く。清盛は戦での勝利を弁才天の加護と信じ、彼女を祀るために寺を建立した。作者:歌川芳虎(1830–80年頃 活動)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.13975-1886】7.厳島における弁才天の顕現が平清盛を圧倒する図V&A日本展示室(Room 45, Toshiba Gallery of Japanese Art) の一角、浮世絵コーナーとは別のガラスケースを振り返って。左側 上段・蒔絵の小箪笥(黒漆に金蒔絵)・兜(武具の一部、脇に十字架が見えるため「南蛮兜」=キリスト教受容期の影響を示す可能性)左側 下段・蒔絵の箱(文箱か手箱)・日本刀(鞘入り、拵え付)中央〜右側 上段・染付磁器の壺(有田・伊万里焼様式、藍色と赤絵の彩色)・大皿(色絵磁器で人物図)中央 下段・壺型の磁器(肥前磁器)・小型の磁器人形(狛犬のような形)・小皿類「日本の陶磁器・漆工芸の国際交流」 をテーマにした展示で、江戸期の肥前磁器(伊万里焼・柿右衛門様式など)を中心に、西洋輸出向けの豪華な大皿・壺を紹介。・中央 ・大きな色絵大皿(鮮やかな瑠璃地に金彩、中央に人物図、周囲に唐草や花文様) → 有田や伊万里の大皿で、17世紀後半~18世紀輸出磁器の典型。ヨーロッパ向けの 華やかな装飾様式。・左側 ・染付や色絵の壺類 ・着物(黄色地に文様)もケース内に一部展示されているように見えます。・右側 ・青地に赤・金で装飾された壺(花瓶)数点 ・その下には小さな器群ウォーターフォール・オン・カラーズ(水の色彩滝) 千住博。・千住博の代名詞である「滝」シリーズのひとつ。・通常の墨色や単色の滝図とは異なり、多彩な縦色帯が滝となって流れ落ちるように描かれている。・ラベル解説にあったように、コロナ禍の隔離生活中、庭に刻々と変化する色彩を希望の象徴 として捉えた経験が反映されている。・滝の裏側から外を眺めたような感覚を意図しており、自然の力強さと人間の内的感情が 重ね合わされている。・江戸時代の浮世絵・工芸と並べて展示されることで、日本美術が古代から現代まで「自然」を 核心に据え続けてきたことを強調している。「Waterfall on Colors2023Often monumental in scale, Hiroshi Senju’s paintings embrace the overwhelming powerof nature. During the Covid-19 pandemic, when Senju was in isolation at his homein New York, he found hope in the constantly changing colours of his garden. The vibrant hues in this work represent a landscape as seen from behind a waterfall.Hiroshi Senju (born 1958)New York, United StatesColours on paperMuseum no. FE.69-2023」 【ウォーターフォール・オン・カラーズ(水の色彩滝)2023年平面でありながらしばしば記念碑的な規模を持つ千住博の絵画は、自然の圧倒的な力を抱擁するものである。新型コロナウイルスのパンデミックの際、ニューヨークの自宅で隔離生活を送っていた千住は、庭に絶えず変化する色彩に希望を見いだした。本作における鮮やかな色彩は、滝の裏側から眺めた風景を表現している。作家:千住博(1958年生)制作地:アメリカ合衆国 ニューヨーク技法:紙に彩色所蔵番号:FE.69-2023】再び「根付(netsuke)、印籠(inrō)、小型漆器」などの展示コーナーを。展示内容の特徴・左側の棚 ・小型の根付(netsuke)が多数並んでいる。材質は象牙・木・漆・磁器など多様で、 江戸時代の装身具として作られたもの。・中央の展示台 ・印籠(inrō)と緒締め(ojime)、それに付属する根付が組み合わせて展示されている。 ・中央下には大型の漆工芸品(蒔絵の箱)が見える。・右側の棚 ・さらに数多くの根付コレクションが並ぶ。動物・人物・神話モチーフなど。根付 (netsuke) コレクションに近づいて。・材質:象牙、木彫、漆塗り、陶磁器など多様。・形態: ・動物(犬・鼠・兎・鳥など) ・人物(七福神風、力士や僧形) ・神話・民話モチーフ(鬼、霊獣) ・抽象的な小形意匠根付は 印籠や煙草入れを帯から吊るすための留め具として17世紀から発展。江戸時代後期には、実用品であると同時に 高度な彫刻芸術に進化し、武士から町人まで愛好された。19世紀後半、ヨーロッパやアメリカでも「小さな彫刻」として収集熱が高まり、V&Aにも多数が収蔵された。V&Aの所蔵点数は数百点規模におよび、代表的な作例がこのようにまとめて展示されている と。「NetsukeTraditional forms of Japanese dress such as the kimono did not have pockets. A man would carry everyday items in containers suspended on silk cords fromthe sash (obi) around his waist. The arrangement was held in place by a toggle known as a netsuke. Netsuke were an ideal medium for inventive decoration and developed into miniature works of art. Most of the netsuke displayed here weremade between 1700 and 1870.」 【根付(ねつけ)着物などの伝統的な日本の衣服には、ポケットがなかった。そのため男性は日用品を容器に入れ、腰に巻いた帯(おび)から絹の紐で吊り下げて持ち歩いた。この吊り下げの仕組みを支えた留め具が根付である。根付は創造的な装飾表現の媒体として理想的であり、やがて小さな美術作品へと発展した。ここに展示されている根付の大半は、1700年から1870年の間に制作されたものである。】なんとか解読できました。根付と一緒に展示される 印籠(inrō)とその付属品(緒締め・根付)👈️リンク のコーナー。「SmokingTobacco was introduced to Japan by the Portuguese in the late 16th century.Despite attempts to ban it, smoking became popular among both men and women. Men carried personal smoking sets consisting of a tobacco container, a pipe and a pipe-holder. These were hung from the waist and held in place by toggles callednetsuke. Both men and women used communal smoking cabinets, which were usually made from decorated lacquer. These incorporated small braziersfor burning charcoalwith which to light the pipe.」【喫煙たばこは16世紀後期、ポルトガル人によって日本にもたらされた。禁止の試みがあったにもかかわらず、喫煙は男女ともに広まった。男性は、たばこ入れ・煙管(きせる)・煙管筒からなる個人用喫煙具を持ち歩いた。これらは腰から吊り下げられ、根付(netsuke)と呼ばれる留め具で固定された。また男女ともに、漆塗りで装飾された共用の喫煙棚(喫煙キャビネット)を使用した。そこには小型の火鉢が組み込まれており、炭を焚いて煙管に火を点けることができた。】根付(netsuke)展示ケースの全景。・4段の棚に配置され、合計30点以上の根付が並んでいる。・素材は象牙・木彫・漆など多彩。・上段には細密な象牙彫刻(群像・龍など)や動物形。・下段には黒っぽい木彫の人物や面形。「NetsukeTraditional forms of Japanese dress such as the kimono did not have pockets. A man would carry everyday items in containers suspended on silk cords from the sash (obi) around his waist. The arrangement was held in place by a toggle known as a netsuke. Netsuke were an ideal medium for inventive decoration anddeveloped into miniature works of art. Most of the netsuke displayed here weremade between 1700 and 1870.」【根付(ねつけ)着物など日本の伝統的な衣服にはポケットがなかった。男性は日用品を容器に入れ、帯(おび)から絹の紐で吊るして持ち歩いた。この仕組みを支える留め具が「根付」である。根付は創意工夫を凝らした装飾の媒体として理想的であり、やがて小さな美術品として発展した。ここに展示されている根付の大部分は 1700年から1870年の間に制作されたものである。】着物・衣装コーナーを再び。・左: ・現代的な意匠の浴衣/着物。大きなドットや幾何学模様をパッチワーク的に配置した デザイン。おそらく戦後以降の「モダン着物」か現代アーティストによる作品。・中央: ・黒または濃茶色の羽織/外套。絹地に無地あるいは渋い文様。実用的な装いか、儀礼用。・右: ・茶系の地に虎の刺繍(または友禅染)が大きく入った豪華な打掛または能装束。 力強い図柄から、武家や芝居に関わる衣裳である可能性。「Kimono for MenThe kimono is a garment worn by both men and women. Although sleeve length varies, the basic shape is the same. From the 17th century, male dress was characterised by dark colours and subdued patterns. Yet restrained exteriors often hid flamboyantlinings and under-kimono, a fashion that continued into the 20th century. Today, few men in Japan wear kimono, but in recent years there has been a revival.More and more designers cater for this growing market, giving kimono for men renewed style and panache.」 【男性用の着物着物は男女ともに着用する衣服である。袖の長さには違いがあるが、基本的な形は同じである。17世紀以降、男性の着物は暗い色調や落ち着いた文様が特徴となった。だが、その控えめな外観の下には、華やかな裏地や襦袢(下着の着物)を隠すことが多く、このファッションは20世紀まで続いた。現代では着物を着る男性は日本では少なくなったが、近年は復興の兆しが見られる。ますます多くのデザイナーがこの成長市場に注目し、男性用の着物に新たなスタイルと華やかさを与えている。】「MODERN & CONTEMPORARY(現代日本美術)」展示コーナー。極彩色の現代陶芸作品をアップで。Heart on Wave 川合 一仁。「Studio CraftsToday, many Japanese makers use traditional craft media to create unique works of art.They are supported by an extensive system of art colleges and a well-developed art market in Japan. Numerous craft associations also encourage their activities, as doregular competitive exhibitions. All the objects have been made since 2010, many ofthem very recently.」 【スタジオ・クラフト(現代工芸)今日、多くの日本の作り手は、伝統的な工芸の素材や技法を用いて、独自の芸術作品を創り出している。彼らの活動は、日本の充実した美術大学の制度や発達した美術市場によって支えられている。また、数多くの工芸団体がその活動を奨励しており、定期的に行われる公募展や競技的な展覧会も後押しとなっている。ここに展示されている作品はすべて2010年以降に制作されたもので、多くはごく最近のものである。】「1. ‘Heart on Wave’2023Kawai Kazuhito uses clay to express his nostalgia for 1980s Japan. After an initial biscuit firing, he painstakingly applies dots of glaze to his sculptures to blurthe boundaries between reality and illusion. The porcelain figurine of Ariel fromThe Little Mermaid at the top refers to Tokyo Disneyland’s opening in 1983.It was the first Disneyland outside the United States and symbolises Japan’s economic prominence during Kawai’s childhood.Kawai Kazuhito (born 1984)Kasama, Ibaraki prefectureGlazed stoneware, with a porcelain figureGiven by Hiroyuki Maki / Buffalo Inc.Museum no. FE.61-2024」 【1. Heart on Wave(波の上の心)2023年川合一仁(かわい かずひと)は、1980年代日本への郷愁を粘土で表現している。素焼きの後、彼は現実と幻想の境界を曖昧にするために、丹念に釉薬の点を彫刻表面に施す。作品上部にある『リトル・マーメイド』のアリエルの磁器人形は、1983年に開園した東京ディズニーランドを示唆している。それは米国以外で初めてのディズニーランドであり、川合の幼少期における日本の経済的繁栄を象徴している。川合 一仁(1984年生)茨城県笠間市釉薬を施した炻器、磁器製人形付き寄贈:牧浩之/Buffalo Inc.所蔵番号:FE.61-2024】こちらも「MODERN & CONTEMPORARY(現代・現代美術)」セクション。木工によるデザイン作品(おそらく屏風風の木製パネルや円形構造物)コーナー。中央に展示されているのは、木工によるデザイン作品(おそらく屏風風の木製パネルや円形構造物)で、横には椅子や織物、籠などが並んでいた。・中央の作品:格子状の木製パネルと円形の木工フレーム。伝統的な木工技法を使いながら、 現代的な抽象オブジェとして再構成されたもの。・右側:シンプルな椅子や織物(黒布)など、生活とアートの境界を意識した現代工芸。・左側:陶器・籠・白い紙造形など、素材ごとにまとめられた展示。メモリー 熊井恭子。「Studio CraftsToday, many Japanese makers use traditional craft media to create unique works of art. They are supported by an extensive system of art colleges and a well-developed artmarket in Japan. Numerous craft associations also encourage their activities, as do regular competitive exhibitions.」 【スタジオ工芸今日、多くの日本の作家たちは、伝統的な工芸の媒体を用いて独自の美術作品を制作しています。彼らは、日本における広範な美術大学の制度や発達した美術市場によって支えられています。多くの工芸協会もまたその活動を奨励しており、定期的な競技的展覧会もそれを後押ししています。】「1. 'Memory'2017Kumai Kyoko is an internationally recognised fibre artist. She created this work in remembrance of the Tōhoku Earthquake and Tsunami of2011, which caused over 15,000 deaths. Kumai works mainly with stainless steel wire. Here she has shapedthe wire into a bundle of organic forms. These represent people’s feelings about the unforgettable disaster that has had a lasting impact in Japan.Kumai Kyoko (born 1943)TokyoStainless steel wireGiven anonymouslyMuseum no. FE.57-2023」【1. メモリー2017年熊井恭子は国際的に認められたファイバー・アーティストです。彼女は2011年の東北大震災と津波(死者15,000人以上)を追悼して、この作品を制作しました。熊井は主にステンレススチールワイヤーを用いて制作を行います。ここではワイヤーを有機的な形態の束に組み上げ、それを通じて日本に長く影響を残した忘れがたい災害に対する人々の感情を表現しています。熊井恭子(1943年生まれ)東京素材:ステンレススチールワイヤー寄贈:匿名寄贈館蔵番号:FE.57-2023】「民芸・復興(Discovery and Revival)」セクションの一部で、柳宗悦の民芸運動の文脈で紹介されている作品群。手前の陶磁器・漆器・左:漆塗りの小箪笥(収納箱)・中央:緑釉鉢・黒釉壺・右:青磁花瓶・染付小壺・これらはいずれも江戸~近代にかけての実用品で、民芸運動では「無名の職人による 日常の器こそ美しい」と再評価されました。藍染の幕(のれん/幔幕の類) で、流水に菊の花、さらに上部に家紋が配された文様。「Discovery and RevivalAn interest in folk crafts arose in Japan in the early 20th century as a reaction to rapid industrialisation and urbanisation. Still active today, the Japanese Folk Craftmovement was established in 1926 by the critic and theorist Yanagi Soetsu. He and his followers collected historical folk crafts and founded museums in whichto show them.They also encouraged the preservation of traditional craft techniquesand the making of contemporary work in the style and spirit of historical models.」 【発見と復興20世紀初頭、日本では急速な工業化と都市化への反動として、民芸(フォーククラフト)への関心が高まりました。現在も活動が続いている日本民芸運動は、1926年に批評家で理論家の柳宗悦によって設立されました。柳とその仲間たちは歴史的な民芸品を収集し、それらを展示するための博物館を設立しました。また、伝統的な工芸技術の保存と、歴史的な様式と精神に基づいた現代作品の制作を奨励しました。】「5. Bedding cover1850–1900The traditional Japanese form of bedding is the futon, which comprises a mattressanda cover laid out on the floor. The cover is often decorated. This boldly patterned example was probably part of a bride’s trousseau. It reveals how subtle shading canbe achieved using only one colour. Careful mending is evidence of how greatly suchtextiles were treasured.Cotton with freehand paste-resist dyeing (tsutsugaki)Museum no. T.331-1960」【5. 布団カバー1850~1900年日本の伝統的な寝具の形は布団であり、床の上に敷かれる敷布団と掛け布団から構成されています。掛け布団のカバーはしばしば装飾が施されます。この大胆な文様の例は、おそらく花嫁の嫁入り道具の一部であったと考えられます。ここでは、1色だけを用いても微妙な濃淡表現が可能であることが示されています。丁寧に施された繕いは、このような織物がどれほど大切に扱われていたかを物語っています。素材:木綿、筒描きによる防染染色館蔵番号:T.331-1960】伊万里焼・柿右衛門様式を中心とした日本磁器(17~18世紀)。特にヨーロッパに輸出された伊万里焼や柿右衛門様式のコレクションが多く展示されている と。・上段中央の壺:色絵(赤・緑・青)で花鳥が描かれた柿右衛門様式の磁器。ヨーロッパで 特に人気が高かったスタイル。・上段左右の壺:藍一色で描かれた染付(sometsuke)、竹や花などの文様。・中段中央の大皿:色絵伊万里。赤・青・金を用いた豪華な意匠で、オランダ東インド会社を 通じてヨーロッパへ輸出されたもの。・中段右の像:獅子または象の置物(伊万里の輸出向け磁器)。ヨーロッパで装飾品として 人気を博した。・下段の皿類:いずれも染付や色絵の伊万里磁器。文様は唐草や人物図、風景など。「Porcelain for EuropePorcelain was first made in Japan in the early 17th century at kilns in and around the town of Arita. The earliest pieces were designed for the domestic market. In 1644,following the fall of the Ming dynasty, Chinese porcelain became temporarily unavailable and the Dutch turned to Japan as an alternative source for this highlysought-after commodity. Japan increased its output of porcelain, with much of it being aimed at the export market and often made in shapes copying Europeanceramics.」【ヨーロッパ向けの磁器日本で磁器が初めて作られたのは17世紀初頭、有田の町およびその周辺の窯においてでした。最初の作品は国内市場向けにデザインされていました。1644年、明王朝の滅亡に伴い、中国磁器が一時的に入手できなくなると、オランダ人はこの需要の高い商品を得るために日本を代替供給地としました。日本は磁器の生産量を増加させ、その多くを輸出市場に向け、しばしばヨーロッパの陶磁器の形を模した作品を作りました。】「南蛮貿易・キリシタン関連展示」の一部。展示内容(上段)1.螺鈿細工の小箪笥(cabinet with drawers) 漆塗りに螺鈿や金粉を施した豪華な小型箪笥。ヨーロッパへの輸出品として特に人気が ありました。2.十字架(Christian cross) キリスト教が16世紀に日本へ伝来した証拠の一つ。隠れキリシタンが所持していた可能性が あります。3.南蛮兜(nanban kabuto) ヨーロッパの兜を模した日本製の甲冑。安土桃山時代に西洋甲冑の影響を受けて制作 されました。展示内容(下段)4.蒔絵の箱(lacquer chest/box) 蒔絵技法による装飾箱。西洋の修道院や貴族の館でも保存され、装飾芸術として高く評価 されました。5.火縄銃(hinawajū / matchlock gun) 1543年、ポルトガル人によって種子島に伝来。日本で大量生産され戦国時代の戦術を変革 しました。6.刀剣(sword with European-style hilt) 柄や鍔に西洋風の装飾が施された刀。南蛮貿易期にヨーロッパとの交流を示す作品。】「Europe in JapanThe first Europeans to reach Japan were the Portuguese. Arriving in the early 1540s, they brought with them guns and Christianity. The latter ultimately proved unwelcome. Christianity was banned and the Portuguese were expelled. From 1639 the Dutch were the only Europeans permitted to trade with Japan. They were kept under close scrutinyon Dejima, an artificial island in Nagasaki Bay.Despite the restrictions placed on the Dutch, the goods and scientific knowledgethey brought with them werethe subject of both scholarly enquiry and popular interest.」【日本におけるヨーロッパ日本に最初に到達したヨーロッパ人はポルトガル人でした。1540年代初頭に到来し、鉄砲とキリスト教をもたらしました。しかし後者(キリスト教)は最終的に歓迎されず、禁教とともにポルトガル人は追放されました。1639年以降、日本と交易を許された唯一のヨーロッパ人はオランダ人だけとなりました。彼らは長崎湾の人工島・出島に厳重な監視のもとで滞在しました。制限が課されていたにもかかわらず、オランダ人がもたらした商品や科学的知識は、学問的探求や一般の関心の対象となりました。】 これは「南蛮漆器(Nanban lacquerware)」の代表的な輸出用大型箱(coffer / chest)。「Kamaboko(蒲鉾型)」のドーム状蓋をもつ大型キャビネット。・南蛮漆器は16〜17世紀、日本で欧州輸出を目的として作られた漆工芸品。「Nanban」または 「Namban」と呼ばれます。 ・輸出先に欧州貴族や宣教師が含まれ、キリスト教用具(十字架箱など)や豪華な装飾箱として 使われた例も多い。 ・技法としては、漆(urushi)を塗った上で蒔絵(maki-e:金銀粉などを散らす技法)、 螺鈿(raden:貝殻象嵌)、金銀装飾を組み合わせたもの。 ・形状として、「ドーム状/丸みを帯びた蓋」「箱体」「金属の金具・鍵・取っ手」などを 備えているものが多い。壁掛けではなく、家具・収納箱としての用途。「Lacquer for EuropeWhen the Europeans came to Japan in the mid-1500s, they were immediately by the lustre and decorative brilliance of objects made from lacquer (urushi). The Japanese soon began to produce lacquer items for export copying European shapes. Early pieces were decorated in mother-of-pearl using techniques similarto those found in China, Korea and India. Export lacquer from the 1600s onwards was decorated primarily in gold on black, and featured elaborate pictorial schemes.」【ヨーロッパ向けの漆器1500年代半ばにヨーロッパ人が日本に来航したとき、彼らはすぐに漆(うるし)で作られた器物の光沢と装飾的な華やかさに魅了されました。やがて日本人はヨーロッパの器物の形を写した輸出用漆器を生産するようになります。初期の作品は螺鈿(らでん)で装飾され、中国・朝鮮・インドで見られる技法と類似していました。1600年代以降の輸出漆器は、黒地に金を主体とした装飾が施され、精緻な絵画的意匠が特徴となりました。】「1. The Mazarin Chest1640–43This extremely high-quality lacquer chest is one of the most important pieces of Japanese export lacquer ever made. It is recorded as having been shipped toEurope by the Dutch East India Company in 1643. Its first owner was the French statesman and Catholic cardinal Jules Mazarin. The scenes on the front and sides allude to episodes from classical Japanese literature. The landscape on the lid featurestemple buildings and a castle complex.Probably Kōami workshopKyotoWood covered in black lacquer with decoration in gold and silver lacquer; silver foil and mother-of-pearl inlay; details in gold, silver and shibuichi alloy; gilded and lacqueredmetal fittings; French steel keyMuseum no. 412-1882」【1. マザラン・チェスト(Mazarin Chest)1640–43年この極めて高品質な漆塗りの大形収納箱は、日本の輸出漆器の中でも最も重要な作品のひとつです。1643年にオランダ東インド会社によってヨーロッパへ輸送された記録が残っています。最初の所有者はフランスの政治家でありカトリック枢機卿であったジュール・マザランでした。前面と側面の場面は日本古典文学のエピソードを示唆しており、蓋の風景には寺院建築や城郭群が描かれています。おそらく高阿弥(こうあみ)派工房京都黒漆塗木地に、金・銀漆による加飾、銀箔・螺鈿象嵌を施す。細部は金・銀・四分一合金(しぶいち)を使用。金銀蒔絵の金具を付属し、フランス製鉄鍵を伴う。館蔵番号:412-1882】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.27
閲覧総数 388
-
31

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その22):64番・前神寺
【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク64番札所:前神寺(まえがみじ)横峰寺を後にし平野林道の坂道をひたすら下る。途中料金所前を通過。平野林道の往復料金は普通車1,850円、マイクロバスは2倍の3,700円と高価?駐車料金を500円と考えれば、片道は普通車で650円前後。冬季の積雪被害等の維持管理費を考えるとビックリするほど高くはないかとも・・・・・。再び車窓から黒瀬湖の眺望を楽しむ。国道11号線を右折し、前神寺方面に向かうと正面に石鎚神社の一ノ大鳥居が。二ノ鳥居の手前を左折し、讃岐街道を進むと、前神寺の大きな駐車場に到着。駐車場の周囲には桜が満開で迎えてくれた。横峰寺から前神寺までの走行ルート。車を降り散策開始。前神寺 境内配置案内図。「惣門をくぐって参道を進み左に折れて薬師谷川をわたると右手に手水場、鐘楼が左手に庫裏・納経所がある。そして右に折れると左に大師堂、穴薬師が右には金毘羅堂、修行大師像、水子地蔵菩薩像が並び、浄土橋を渡ると右に水が滴り落ちるお滝不動明王像、弁財天祠、稲荷社祠がある。石段を上がるとすぐに護摩堂、薬師堂があって、最も奥に本堂が建つ。本堂右の丘に石鉄権現堂がある。参道の鬱蒼とした杉・檜の木立や古い灯籠が何基も立ち並ぶ境内には、老樹が生い茂り、深山幽谷の佇まいを見せている。」惣門を背に境内に向かって進み極楽橋を渡る。三界萬霊像。手水舎。鐘楼。祖師「善識上人」左と「善尭上人」。現住職は佐々木善康氏とのこと。大師堂。金比羅大権現。金比羅大権現の隣の石塔。その隣に弘法大師像。水子地蔵菩薩像。十三仏像。浄土橋を渡る。お滝不動尊。1円玉を投げて、貼りつくとご利益があると。不動尊にはたくさんの硬貨が貼りついていた。中には5円玉10円玉も。護摩堂。本尊は不動明王。弁財天。薬師堂。江戸時代には西条藩主である松平家の信仰も集め松平氏は東照宮をまつり、三葉葵の寺紋を許したとのこと。石鉄権現堂への石鳥居と階段。御札、お守り等の売店。多くの石仏が並ぶ。本堂。「役小角によって開かれた霊峰石鎚山 (1982m) の麓にあり、役小角が石鎚山で修行を積んだ後、蔵王権現を感得し蔵王権現像を彫り、後に病気平癒を祈願し成就した桓武天皇(782年〜805年)によって七堂伽藍が建てられ金色院前神寺として開かれたと伝えられる。文徳天皇、高倉天皇、後鳥羽天皇、順徳天皇、後醍醐天皇など多くの歴代天皇の信仰が厚かったことでも知られる。後に空海(弘法大師)も巡錫している。このとき空海は2度石鎚山を登ったといわれる。当寺は、横峰寺とともに山頂の弥山に存在する石鉄権現の別当寺にあたり、東側の遥拝所でもあった。江戸時代には西条藩主である松平家の信仰も集め松平氏は東照宮をまつり、三葉葵の寺紋を許した。本寺は里前神寺と称されることもあるが、これは海抜1400mあたりにある前神寺の出張所を奥前神寺と呼び区分するためでもある。奥前神寺は本来、現在の成就社であったが、明治の神仏分離令により分離独立し、奥前神寺と里前神寺ともに石鎚神社となり、当寺は廃寺となる。その時、本尊と権現像と僅かの寺宝は持ち出し、その後、1878年(明治11年)に現在地に里前神寺が再興され、さらに今宮道の最終地点に奥前神寺が再興され、さらにロープウエイ開通翌年に山上駅の上の現在地に奥前神寺が移転され現在に至る。」1972年(昭和47年)の再建。入母屋造で屋根は緑の銅板葺き。石鈇山 金色院 前神寺(いしづちさん こんじきいん まえがみじ)宗派 真言宗石鉄派本尊 阿弥陀如来創建 奈良時代の初期開祖 役小角所在 愛媛県西条市洲之内甲1426番地本尊真言 ”おん あみりた ていぜい からうん”本堂にて参拝。石鉄大権現。扁額。石鉄権現堂から本堂・境内を見る。石鉄権現堂の階段。「石鉄山蔵王大権現宝前報恩謝徳也」。「石鉄山縁起之事」。67歳の女性の心願成就の報国。方丈・客殿横の階段。中央に忠霊塔、右に弘法大師千百五十年御達忌報恩謝徳也。肩のネズミも可愛い、可愛らしい稚児蔵。大師堂。方丈、客殿。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。納経所前から、境内の大師堂(左)と鐘楼(右)を。日野駒吉像。すし屋を経営する傍ら四国遍路のお先達になられた人物の石像。四國霊場巡拝五拾度、小豆島四國巡拝百度、石鎚登山壱百度と。中 昌運像。石槌山修験道の先達とのこと。駐車場に向かって戻る。桜の先には惣門が見えた。惣門。参道方面を惣門前から。駐車場から方丈、客殿を見る。 ・・・つづく・・・
2018.05.25
閲覧総数 1062
-
32

湖東三山~香嵐渓への紅葉狩り・その5(金剛輪寺 1/2)
湖東三山・西明寺の紅葉を堪能し、その余韻を身体に感じながら次の金剛輪寺(こんごうりんじ)に到着。金剛輪寺の前に駐まる観光バスの黒の車体には真っ赤な紅葉の姿が映っていた。金剛輪寺の黒門。黒門の中央につるされていた大きな朱の提灯には「聖観音」と。そして裏の境内側には『松峯山 金剛輪寺』と。金剛輪寺は、滋賀県愛知郡愛荘町にある天台宗の寺院。山号は松峯山。地名から松尾寺ともいう。本尊は聖観音菩薩、開基は行基とされる。西明寺、百済寺とともに湖東三山の1つに数えられる。黒門の正面左側の紅葉。黒門の正面右側の紅葉。この寺の御詠歌『わけいりて 佛の恵み 松の峰 嵐も法の 聲かとぞきく』。「近江西国三十三箇所」第十五番、本尊聖観世音菩薩」と刻まれていた。黒門を潜ると右側に拝観受付所が。『境内案内図』。 【http://kongourinji.jp/precinct/】より『参拝順路』朱に染まった紅葉の混沌空間の下の参道を進む。 途中、大きな野猿が木に登っていく姿を発見。見上げるとこれも真っ赤な大きな尻が。緑の苔の上に赤、黄の濡れ落ち葉・散り紅葉が一面に。我もこの中の一枚にならぬようにと。モミジ葉が一枚クモの糸に繋がれて。参道脇の黄色の世界が迎えてくれた。そして歩を進めていくと、今度は赤の世界が待っていてくれた。そして再び黄色の世界が。またまた赤の世界が現れる。正面に『西谷堂』。ご本尊は阿弥陀如来と。赤い涎掛けの地蔵様が二体。右は『阪神大震災犠牲者追悼』と刻まれ、左側には『平和祈願』、『戦没者追悼』と刻まれた石柱の後ろに平和地蔵が。正面に『赤門』が。未だ紅葉していない緑葉のモミジが存在感を示していた。黄葉アーチの先に親地蔵尊が見える、そこが『白門』のあるところで名勝庭園への入り口になっていた。名勝庭園経由で千体地蔵参道へ出てそこを上り詰めて本堂へ至るコースを選んだ。白門前の『親地蔵尊』。『国宝 己を忘れて他を利する』と刻まれた石柱。庭園の入口の『白門』。白門を入ると目の前が本坊の明寿院。名寿院の紅葉。『名勝 金剛輪寺名寿院庭園』説明板。池泉回遊式庭園。桃山、江戸初期、中期の三庭からなり、作者不詳だが、老杉蒼松の自然を背景とし、灯籠泉石樹木の配置等、素晴らしく、晩秋の深紅に染まる色鮮やかな紅葉は「血染めのもみじ」と広く知られていると。観音様のやさしい心が満ち、湖東三山一の名園古庭であり、国の名勝にも指定されていると。庭園へは右の門から入る。庭園の入口の門の瓦屋根には落ち葉が積もり。本坊明寿院玄関。本坊・明寿院はかつては学頭所として使われた建物で、昭和52(1977)年に火災で書院、玄関、庫裏を焼失。現在の建物は翌年再建されたと。欄間に掲げられた「堪忍」の文字が印象的。明寿院境内に建つ護摩堂が紅葉の奥に。江戸中期の1711年(正徳元年)の建立。護摩堂に近寄って。明寿院本坊の南・東・北の三方を囲むように庭園があり、心の字池が3庭を結んでいる。3つの庭は、作庭された年代がそれぞれ異なる池泉回遊(ちせんかいゆう)鑑賞式(かんしょうしき)の庭園で、それぞれが名勝に指定されている。桃山時代に造られた庭は、「石楠花(しゃくなげ)の庭」と呼ばれ、庭の中央に架けられた優雅な石橋のそばに、鎌倉時代に作られた苔むした多くの石が配され、品格のある雰囲気。春になると、庭のそばにある護摩堂のカキツバタやシャクナゲが鮮やかに咲き、華やかになるのだと。池の底にはモミジ葉が沈み、これも美しい光景。本坊前から本坊庭園を部屋越しに見る。人の入らない瞬間にシャッターを。本坊庭園も紅葉の真っ盛り。明寿院中庭。江戸初期の庭園庭の中央には優雅な石橋が架けられ、鎌倉時代に作られたという宝篋印塔(ほうきょういんとう)が配された、品格のある古庭。再び池に沈むモミジ葉を。護摩堂を別の場所から。江戸中期の1711年(正徳元年)の建立。明寿院南庭。桃山時代の庭園。龍の襖絵。茶室『水雲閣』案内板。本坊の前から眺めた「東庭」の核心部は、こんな景観。この池は左右に長く伸びており、築山は左の峰と右の峰に分かれ、その鞍部に大きな三尊石。これと対面するように島に石の五輪塔。 築山の上部は背の高い楓の紅葉、築山の斜面と池の手前にサツキの玉刈り込みが。この庭は「桃山の庭」と称されているが、作られたのは江戸時代らしいとのこと。右手奥には茶室・水雲閣が。江戸中期の庭は、滝から池に水が流れ・・池の中に七福神の宝船を表わす岩でできた舟が配されていた。 ・・・つづく・・・
2018.12.11
閲覧総数 212
-
33

旧東海道を歩く(三島~原)その8:沼津・正覚寺~神明塚古墳
『旧東海道を歩く』ブログ 目次旧東海道の沼津片浜を歩く。右手に『諏訪神社(諏訪宮)』の鳥居が。更に200mほど進むと左手にあったのが『臨済宗 普門山 正覚寺(しょうかくじ)』。正面が本堂。どこか日本のお寺ではないような屋根が変わっていた。正覚寺は今から約300年前、原の徳源寺第9世方室玄策(ほうしつげんさく)禅師を開山に迎え、小諏訪の旧東海道ぞいに徳源寺の末寺「自覚庵(じかくあん)」として創建された。本尊は薬師如来(やくしにょらい)。境内の『水子地蔵』。『水子地蔵御和歌』。『白衣観世音』。『忠霊塔』。和菓子屋・『甘陽堂』。老舗の菓子店。洋菓子、和菓子の製造販売。餅・羊かんなどの和菓子が特に人気。静岡県産の卵をふんだんに使っているカステラはしっとりして人気の菓子であると。左手に少し折れて『高野山 真言宗 浮島山 清玄寺』を訪ねる。清玄寺の庭と本堂は一般家庭の中にあるような感じであった。境内で持参のリンゴを食べながらしばしの休息。境内の『観世音菩薩像』。地蔵様が3体。本堂内部。正面に『青面金剛像』、右手に『宝珠禅地蔵』。ズームで。そして旧街道沿い右手に『八幡宮』の参道が。次に訪れたのが『日蓮宗 妙秀山 栄昌寺』。山門。本堂。栄昌寺は、慶長5年(1600年)珠光院日宝(松野永精寺19世)を開山に創建された草庵が起源。享保2年(1717年)客殿が建立された。明和3年(1766年)仏像が奉安され、享和3年(1803年)庫裏が建立された。明治9年(1876年)境内に有斐館(沼津市立片浜小学校の前身)が置かれた。現在の本堂は明治39年(1906年)に建立されたもの。境内には、七面堂があり七面大明神、鬼子母尊神、清正公大神祇が安置されている。また本堂前には推定樹齢350年の巨大なソテツがあった。扁額には『妙秀山』と。『七面堂』。七面堂には七面大明神、鬼子母神、清正公(加藤清正)大神祇が奉られていると。南無妙法蓮華経と刻まれた石碑。『若有聞法者無一不成仏』とも刻まれていた。「法華経を聞く人は一人として成仏しない者はない」と。更に旧東海道(県道163号線)を進む。更に進むと大諏訪に在る『吉祥院・天満宮』が右手に。右側が『大諏訪天満宮』、左側が『承光山吉祥院』。『大諏訪天満宮』。神社幕には星梅鉢の紋が。鐘楼。『水子供養像』。左側が『承光山吉祥院』。「寛文5年正月(1665年)に沼津市岡宮の大本山光長寺の末寺として本山第25世日淳聖人が創建された。元和(1615年)の頃、片浜大諏訪の海岸で漁業の網の中に天神様の御木像(約30㎝)が入り、そのお姿の神々しさに網元の浅沼家で大切に祭られておりましたが、寛文5年光長寺25世貫首日淳聖人が師範として仰ぐ日簉上人の隠居寺を創建するに当たり、天神堂を建立し吉祥院と称し、以後御神体を大事にお祭りしてきました。明治初年の廃仏毀釈の神仏分離令が出されましたが、その難を免れ神仏習合のまま現在に至っております。御神体には宝徳元年5月(1449年)の年号が記されております。御開帳は50年に1回とされ、平成14年に1千百年祭があり、記念事業として本殿を建立し御開帳いたしました。学問の神様として、又地域の守り神様として篤い信仰を集めております。」と。『吉祥院』と書かれた扁額。吉祥天は天神様こと菅原道真の菅原家が信仰していた仏教の神様。『筆塚』。『願満具足天一千年祭』と刻まれた石碑。民家と民家の間にあったのが『松長一里塚跡碑』。日本橋から数えて31番目の一里塚。旧大諏訪村と旧松長村の境目は一里塚です。現在は跡形もなく一里塚碑だけが。境目にあるので松長の一里塚、大諏訪の一里塚とも呼ばれたと。しかし、碑の横面に刻まれた説明書きには「江戸より30里の地」と刻まれていた記憶があるのだが・・・・????。一里塚跡から暫く進むと街道左手に『日蓮宗 光法山 蓮窓寺』が。この蓮窓寺の山門は以前は松長陣屋の裏門(四脚門)を移築したものだったと。しかし老朽化が著しかったので、現在は新しい山門に建て替えられた。創建は江戸時代前期で松長陣屋代官三好義観の寄進に依ると。本堂。『蓮窓寺』は、寛文2年(1622)沼津市下河原の妙海寺20世修善院日根上人による開創で、境内には七面堂がある。本堂には元禄2年(1689)の釈尊涅槃図があると。扁額には『蓮窓寺』と。旧東海道を隔てて蓮窓寺の北側にある『神明塚古墳』へ。住宅街の細い道を抜けた先に南面して墳丘への石段があり、墳丘の上には『神明宮』が。その左(西側)方向。社が建つのが後円部で、西側に前方部がついている。『神明宮』説明板。創紀は元和2年(1616)3月と伝えられ、3~4世紀に築造された古墳の頂きにある。以来380年鎮守社として氏子、地域住民の崇敬を集めてきた。その間幾多の風雪にあうも区民一帯で保存に努めてきた。明和9年(1772)老朽化により再建、大正8年1月隣境失火により類焼、灰燼となり直ちに再建に着手、同10月現在の社屋が落成した。以来、維持補修に努力し今日に至っていると。墳丘の上の『神明宮』。『神明塚』と刻まれた石碑。『神明塚古墳』。「この古墳の発見は戦後まもなくのことで、昭和23年には前方後円墳であることが確認されました。その際、後円部頂に神明社が鎮座することから、神明塚古墳と呼ばれるようになりました。昭和56年、地元自治会から保存整備の要望書が提出されたことで、保存整備に向けた測量調査及び発掘調査が実施されました。また、平成15年には、沼津市史編纂に伴う再発掘調査も行われています。その結果、この古墳の全長は約53m、後円部径約37mであることが判明し、また後円部と比べて前方部が短い形をした、古墳時代の中でも比較的古いと考えられる墳丘形態をもつことがわかりました。埋葬施設としては後円部頂で粘土槨の一部が確認されており、箱形木棺の使用が想定されています。神明塚古墳は、出土した土器の年代から古墳時代前期(3世紀~4世紀)に築造されたと考えられます。沼津市には3基の前方後円墳が残されていますが、この年代はそれらの中でもとりわけ古い年代であるといえます。」 その7 に戻る。 ・・・つづく・・・
2019.04.15
閲覧総数 373
-
34

旧東海道を歩く(掛川~見付)その8:袋井市・木原大念仏~磐田市・三本松刑場跡
『旧東海道を歩く』ブログ 目次許禰神社の角にあった『長命寺・笹田源吾供養塔』まで80mと。「戦国時代、袋井市域は徳川家康と武田勝頼の合戦の場となりました。天正6(1578)年頃には徳川方が優勢となり、遠江の武田方の城は大東町の高天神城だけとなりました。武田方は徳川方の情勢を探るため、高天神城にいた笹田源吾(篠田源五)を偵察に出しました。8月10日夜、木原村まで来ているところを徳川方に味方する木原村の住人太郎兵衛らが加わり、これを討ち取りました。徳川家康はこの手柄をたいへん喜びました。その後、平和な時代となりましたが、村には疫病や災害などの悪いことが続き、太郎兵衛にも不幸がありました。これらの災難は笹田源吾や武田と徳川の戦いにより戦没した人々の悪霊の祟りだという噂がおこり、これらの人々の悪霊を鎮めるために、地蔵が建てられました。この地蔵は現在でも丸野家の子孫の方々によって四百年間大切に祭られています。」更に旧東海道を進むと右手の水路の上にあったのが袋井市指定無形民族文化財『木原大念仏』案内板。「「木原大念仏」は 静岡県西部(遠州地方)の各地に残る「遠州大念仏」の一つ。武田信玄と徳川家康が戦った“三方ヶ原の戦い”の犠牲者を供養する目的で始まった念仏踊りで現在は宗教色は薄れて娯楽性の強い行事となっている。現在各地に70ほどの“組”があり、8月のお盆の時期に新盆の家々をめぐり, 横笛や太鼓などに合わせて念仏を唱えながら踊り死者の霊を弔う。」横には夢舞台東海道『木原』道標が。見付宿坂まで一里二町・4.1km。県道413号線合流地点手前まで進む。左手に案内板が姿を現す。『木原』「木原は 元亀三(一五七ニ)年に武田信玄 が徳川家康 を破った三方原の戦いの前哨戦(木原畷の戦い)の地としてしられています。また 武田勝頼 軍の斥候(せっこう)笹田源吾 に由来する「木原大念仏」(市指定無形民俗文化財)の発祥の地でもあります。地区内には 原寸大に復元された木原一里塚をはじめ木原権現社(武内許禰(こね)神社)長命寺笹田源吾の墓や供養塔 徳川家康腰掛石など多くの歴史遺産が残っています。」県道413号線に戻り進むと狭い水路の上で袋井市から磐田市にはいる。これが灌漑用?水路。この付近は田園地帯が拡がっていた。磐田市中心街に向かって進む。磐田市の汚水マンホールの蓋。デザインは、磐田市岩井にある桶ヶ谷沼に生息するベッコウトンボ。この蓋はここから「磐田駅南」交差点方向に何枚もあったが、羽の黄色のエポキシ?が抜けてしまっているものが多かった。酉島交差点の先、右側にあったのが『曹洞宗 廣福山 全海寺』。『廣福山 全海寺下馬地蔵』。「当山は天文十一年(1542年)家康公の父広忠が曹洞宗天龍院末寺として草創開山する。」『六地蔵尊』。『手水舎』。『本堂』。扁額には『全海禅寺』と。本堂の横の御堂は改修工事中。太田川に向かって進む。そして太田川、橋の名は三ヶ野橋(みかのばし)。右の橋は現国道1号線、太田川橋。国道1号線の横には菜の花畑が拡がっていた。菜の花畑の中で写真を撮るカップルの姿が。訪ねたかったが、時間の関係で諦める。三ヶ野橋を渡り左折し旧東海道を進む。『旧東海道松並木』「東海道 は、奈良時代から平城宮と地方を結ぶ交通路として主要な役割を果たしていた。特に鎌倉時代以降になって整備されてきたが、江戸時代に幕府は、江戸を中心とした五街道を制度化そ、道中奉行をおき宿駅を設置し、道路の改修・並木の植樹・一里塚の築造などの整備をした。特に、東海道には力を入れた。東海道は、それぞれの時代によってうつり変っているが、見付宿の東はずれから三ケ野地内までは、この道路が江戸時代の東海道々筋であった。松並木は、後世補植されて、現在に続いている。 おねがい 交通規則を守って、自己防止にご協力下さい。」夢舞台東海道『三ヶ野』道標。その先が『鎌倉時代の古道』。この場所にはいくつもの道筋が穿かれ、磐田(見付)へとつづいていた。その道筋も旧東海道が整備される以前の鎌倉古道を始め、江戸時代の古道、明治の道、大正時代の道、更には「質道」、そして昭和の道、平成の道と全部で7本の道が集中していることから「三ヶ野七つ道(みかのざかななつどう)」と呼ばれているのだと。『明治の道(緑のトンネル)』碑。進んで行くと急な坂が始まった。これが『大日堂・三ヶ野七つ道』の始まり。この三ヶ野一帯は戦国時代の元亀3年(1572)に甲斐の武田信玄の遠州侵攻の戦いの舞台となった場所で家康軍との小競り合いが起こった場所として知られています。この時の武田軍は3万の兵、一方、家康軍はその半分の1万の兵ということで、家康はいちはやく撤退を決意します。しかし武田軍は執拗に家康軍を追撃してきます。家康軍は浜松へ戻るため三方ヶ原を辿るのですが、家康の生涯の中で最悪の敗戦と言われている戦いこそが「三方ヶ原の戦い」。ほうほうの体で浜松城へ逃げ帰った家康は、この戦で死の恐怖を味わったと言われているのだ。さらに上り坂を登って行った。すると突然坂道の左側にかなりの急勾配の坂道の入口が現れた。ここが江戸古道の入口。坂を登り終えた五差路に『従是鎌田山薬師道碑』が。この角から南に約1.5kmの所に「鎌田山(かまださん)金剛院(こんごういん)醫王寺(いおうじ)」と称される、天平時代に聖武天皇の勅命を奉じて、行基菩薩(ぎょうきぼさつ)が山内の名木で薬師如来の尊像を敬刻され、ご本尊として祀ったのが始まりと伝えらる醫王寺があり、この角はその参道入口だったとのこと。見付宿はここを右折。逆に左に曲がると『江戸の道』であると。『三箇野 車井戸之跡』そして左には『明治の道』。昔、この辺りは水に困っており、その醫王寺によって滑車で汲み上げる井戸が掘られ、車井戸と呼ばれたと。磐田市三ケ野台の住宅街を進む。右手に『三ヶ野立場跡』。峠の茶屋の前の庭、野鳥と思いレンズを向けたが・・・・。旧東海道を左に折れ『二子塚古墳』を訪ねた。5世紀後半に造られた前方後円墳で、三ケ野台地にあり、出土品は馬形埴輪・人物埴輪で埴輪と実物がセットで発見された珍しい例だそうで、銅鏡も見つかっていると。しかし、説明書き等はみつからなかった。左手に進むと『緑ヶ丘霊園』、『善導寺』へ。『従是西見付宿』。説明用の地図も。江戸時代分間絵図に画かれた街道、榜示杭も画かれていた。『榜示杭とは!』。「榜示杭は、街道に沿った村や宿の境を示す標柱です。 ここは見付宿と岩井大久保・西貝塚大久保との境界でした。 文化三年〈千八百六〉に発行された東海道分間延絵図〈おおくぼ〉に【御料榜示杭】の表示があり、その下に境界を表す記号赤丸印があります。」現在の街道の様子。『旧東海道 行人坂』。『「行人坂」のいわれ』行人坂:愛に月待日待の山伏勧進せしゆゑにかくはいへり、・・・意訳しますと『ここには行人(山伏)が多く住んでいて、村のまつりごとや社会奉仕に携わっていたので、この坂を行人坂 と言うようになった。この資料は井原西鶴 が晩年に執筆し、元禄の初めに発行され度々再版された「一目玉鉾」の見付の処に書かれた文です。東京目黒の行人坂は有名ですが、時代的にはここの坂の方が早くから有ったようです。この坂 は急勾配で、江戸時代の見付東坂と同じくらい急でした。」『行人坂』の登り終わると旧東海道は県道413号線に合流した。磐田市富士見町にある歩道橋を渡り道路の反対側に向かう。歩道橋から桜の咲く小さな丘が目の前に。ここが『「鈴ヶ森の刑場跡(三本松刑場跡)』らしいが・・・・。この刑場を有名にしたのは、あの大盗賊である日本左衛門の首がここで晒されたこと。遠州金谷の生れで美濃から相模の八か国で、五十人~六十人の盗賊団を率いて暴れまわった、といわれる大盗賊でしたが、江戸の火付盗賊改方に捕えられて、江戸で斬首されこの地に運ばれ晒し首になったといいます。遠州の鈴ヶ森という名前がついている刑場跡ですが、江戸の品川宿のはずれにも鈴ヶ森刑場があり以前訪ねた。どちらが先に鈴ヶ森という名前を使ったかというと、江戸の品川の鈴ヶ森と。江戸の鈴ヶ森刑場が設けられたのは、あの慶安の乱(由比正雪の乱)が起こった慶安4年(1651)に共謀者である丸橋忠弥を処刑するために設けられたのが江戸の鈴ヶ森の始まり。ということは日本左衛門が活躍したのが延享の時代ですから、慶安の乱からおよそ100年後のこと。おそらく遠州鈴ヶ森という名は、江戸の刑場を代表する鈴ヶ森の名前を拝借したのではと。しかしこんな立て札が立っていた。「此処は刑場跡ではない。見附形状跡は、昭和三十一年(1956)国道一号線改良工事により道路傍下に埋没された。此処は、見付府内に刑場が在った事を記すため、史跡碑建立の場として所有者玄妙寺が管理しているものである。 見付 本立山妙源寺」。 その7 に戻る ・・・つづく・・・
2019.05.28
閲覧総数 2025
-
35

旧満州:中国・東北地方7名所大周遊8日間』の旅へ:8日目(6/26) 帰路:大連日航飯店~大連空港~成田空港~我が家
この旅行の最終日(7月26日)は日本への帰国の日、早朝4:30前には起床する。『大連日航飯店』の部屋からの光景。時間は5:01。早めにフロントに行きチェックアウトし、朝食のサンドイッチをもらい、ロビーで食べる。そして出発の時間6時には全員揃い、大連空港に向けてバスで出発。昨日夜に歩いた『旧日本橋・現勝利橋』を渡る。『俄罗斯风情街』の1本東側の上海路を走ると、ここにも旧ロシア人街風の建物が。こちらにも。『北海公園』を左に見ながら『先进街』に向けてバスは進む。右手に『东联路』。『迎賓路』を大連空港に向かって走る。『大连国际机场宾馆(Dalian Intl Airport Hotel ホテル)』が前方に。『迎賓路』沿いの地球儀の如きモニュメントには中国の姿が。『大連国際空港駐車場入口』が前方に。『大连国际机場集团』ビル。大連国際空港ターミナルが姿を現す。正式名は『大連周水子国際空港(だいれんしゅうすいしこくさいくうこう)』開港時から現在の正式名称にも含まれている「周水子」という名前は、ここが周水子という地名であったことが由来で、近くにも周水子駅ある。市街地の北西に位置し、旅順北路に面していて、街の中心地から車で約20分の場所にある。また、大連空港は軍民共用空港であるため、中国人民解放軍の軍用機も駐機・離着陸している。町に近く、歴史ある空港であるが、その限界に近付いており、大連金州湾国際空港(Dalian Jinzhouwan International Airport)が渤海の金州湾の埋立地に建設中であるとのこと。『大连国际机場』ターミナルビルに到着。『DALIAN』の文字。これは英語名。漢字は『大連』で簡体字・『大连』ではなかった。チェックインカウンターに並ぶ。利用便は中国南方航空 CZ629 8:20発 成田空港行き。しばし空港待合室からの景色を楽しむ。空港横には住宅街がギッシリと。そして定刻に搭乗開始。この飛行機は中国の航空会社の『海南航空』。その後ろに管制塔が。そしてほぼ定刻に離陸。時間は8:40。利用便はエアバス『A321』便。離陸し大連湾海上に出て大きく左に旋回。眼下に『和尚島』が。今回の離陸後の飛行ルート。旋回し再び遼東半島上を飛行。大連の街並みが眼下に。そして飛行機は黄海上空を南下し、ソウル南部から韓国を横断し日本海へ。そして日本海を能登半島方面に向かう。そして離陸後1時間弱で食事が配られた。そして金沢市上空から富山市上空へ。右手眼下には、立山連峰の白き山々が見えて来た。北アルプス北部『白馬岳』、標高: 2,932 mであろうか?北アルプスの山々。そして東北地方を斜めに横断し、いわき市手前で大きく右旋回し南下し成田空港へ。そして成田空港に着陸。時間は日本時間の12:10。飛行時間は予定通り約2時間50分あまり。青空は垣間見えたが、未だ梅雨空。飛行機を下り、利用した中国南方航空便を振り返る。到着ゲートを進む。日本に戻ったことを実感する『迎』の文字が今回も迎えてくれた。武田双雲氏の書であるようだ。そして入国、税関手続きも無事完了し、トランクも受け取る。お世話になった添乗員、旅友に挨拶を済ませ、旅友Sさんの愛車に乗り帰路につく。新空港自動車道・成田料金所を通過。東関東自動車道・幕張を通過。湾岸道路の東京港トンネル。東海JCT手前を通過。渋滞もなく順調に進む。そして横浜新道に入り、無事我が家の駐車場まで送ってもらったのであった。時間は14:30で成田空港から1時間30分で到着したのであった。戦後74年を経た、旧満州:中国・東北地方7名所を8日間で訪ねる旅であった。訪ねた都市は下記の7都市の各名所。★黒龍江省 ハルビン(哈爾浜)★吉林省 長春(旧 新京)★遼寧省 瀋陽(旧 奉天)、本渓、丹東(旧 安東)、大連、旅順★哈爾浜(ハルビン)中国旧満州(現在の東北地方。中国では「偽満州」とよぶ)の哈爾浜市は中国最北の黒龍江省の省都で、人口1060万に達する大都会であった。もともとは旧帝政ロシアによって19世紀末から20世紀初頭にかけて建設された街で、その後の日本統治を経た現在でもロシア風の建物が多く残されるなど、歴史的にも観光地的にも興味深い街なのであった。ロシア正教やユダヤ教などの教会が残り、異国情緒ただよう街並みは、他の中国の都市とは異なる雰囲気を有していたのであった。しかし、今回この街では、ロシア人はほとんど見かけなかったのであった。東方の小パリ・小モスクワとも呼ばれていて、広場や公園の管理も徹底され美しい街並み。冬はマイナス20~30度にもなり、壮麗な氷雪祭りも有名とのことだが、冬の哈爾浜(ハルビン)の街並みそして中国で5番目の大河であり全面凍結する松花江の世界三大氷祭りも訪ねて見たいと思ったのであった。『中央大街』はアジア最大の石畳の目抜き通り。ハルビンを代表する歴史的な大通りで、ロシア語でキタイスカヤと呼ばれ、昔は中国人街であったと。その規模は、全長1450m・幅21.34m(内、車道の幅は10.8m)。ロシア統治時代の建築物が数多く残され、「東方のパリ」とも称される西洋風の街並みが一直線に松花江に向かい、南は経緯街(十字街)から北は松花江防洪記念塔まで伸び、大いに賑わっていたのであった。一つ心残りは『侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館』を訪ねる事が出来なかったこと。★長春(新京)満州国時代の首都で新京と呼ばれていた街。そのため、当時のゆかりの施設が多数あった。代表的なものが「偽満皇宮博物院」で、溥儀の宮廷府を博物館にしたものであった。そして当時の関係資料、写真が多数展示されていたのであった。緝煕楼は中に入ると階段も廊下も皇宮と言うには余りに狭く、部屋も大変質素であった。観光客が多く、廊下ですれ違うのもたいへんなほどで、芥川龍之介が「夢魔」と形容したあの巨大な北京の紫禁城からすれば、溥儀にとっては、まるで物置に住んでるみたいに感じていたのではないであろうかと。★瀋陽(奉天)奉天は清朝の故地であり、郊外には北陵(歴代の皇帝陵墓)があった。市内中央部中街に位置する瀋陽故宮は、清朝の初代皇帝、太祖ヌルハチ(努爾哈斉)と2代皇帝、太宗ホンタイジ(皇太極)により建立された皇城であった。北京の「故宮」の12分の1の大きさではあったが、500以上の部屋を持つ70以上の建物が建ち並び、満州族の威厳と風格が感じられたのであった。そして『大政殿』前での清代の舞踊劇を楽しんだのであった。大都会の中にあったが、この一角だけ昔の中国らしい空間で、時間の流れもゆっくりになるような感覚を味わえたのであった。その他観光ルートには尽きるところがない瀋陽。★本溪本渓水洞(ほんけいすいどう)は遼寧省にある鍾乳洞で、内部のほぼ全体が池になっていて電動船での見学であった。鍾乳洞の長さは2800メートルとのことであったが、内部のライトアップが私にやや興ざめなのであった。私としては『金州観光』に変えて欲しかったのであったが。★丹東丹東は鴨緑江を隔てて朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)と接する国境の街であった。朝鮮族が約2万人居住していて、中朝貿易最大の物流拠点であり、その7割以上がここを通過すると言われているとのことであった。朝鮮戦争の際に国連軍の爆撃によって破壊され不通になっている鴨緑江に架かる『鴨緑江断橋』を先端まで歩いて見学し、『鴨緑江』のクルージングも。米朝首脳会談のため、金正恩朝鮮労働党委員長が鉄道で中国に向かって渡った『中朝友誼大橋』など、メディアをにぎわせる話題に事欠かない場所だが、対岸に拡がる北朝鮮の新義州の建物と丹東の高層ビル群の林立する姿を目の当たりにし、国交があり友好国?そして最大の輸出入国である中国との北朝鮮の国境の現実である事もこの旅行で知ったのであった。★大連遼東半島の南端にあり、「北海の真珠」とも呼ばれる港町。黄海と渤海に面し、海を挟んで南側には山東半島がある。坂道の多い街並みには洋館が立ち並び、エチゾチックな雰囲気が漂っていた。19世紀末に帝政ロシアの租借地となり、1904年の日露戦争以降は日本の支配地となったのだ。この時に造られた放射線状に並ぶ道路や大同広場(現中山広場)、大和ホテル(現大連賓館)などが今も残っていたのであった。大連は、ロシアが中国に進出した際、フランスのパリのような街にしようと開発した場所。したがって、中国には珍しいハイカラな街並みが未だの残っていたのであった。日露戦争で勝利した日本は、そのロシアの考え方を受け継ぎ、美しい街の建設に努めたのだと。日露戦争については、司馬遼太郎の渾身の大著『坂の上の雲』が。大連~旅順を訪ねた今、もう一度『坂の上の雲』を読み返して見たいと思っているのである。そして、昨年、2018年5月7、8日に北朝鮮の金正恩委員長の2度目の訪中となった際に中朝首脳会談が行われた『大连棒棰岛』も訪ねることが出来たのであった。★旅順日露戦争の戦跡=「聖地」?をめぐったのであった。激戦地となった203高地、ロシア軍の堅固な要塞がそのまま残る東鶏冠山、乃木大将とステッセルの会見の舞台である水師営など見どころは尽きなかったのであった。戦跡周辺の山の木々は、あえて伐採されて戦争当時の殺伐とした雰囲気を感じるようにされているのではとも。旅順の戦跡を巡ることによって、日露戦争で斃(たお)れた多くの兵士に思いを馳せ、彼らの犠牲の上に現在の日本の発展と満洲の躍進があることを再確認したのであった。そして今回の旅行で一番感じたことは、満洲国時代に日本人によって建てられた建造物が、戦後74年経た現在でも数え切れないほど残っていて、その多くが今も重要な施設として大切に使われ保存されていたこと。中国人にとって見れば、ある意味では『負の遺産』であり、直ぐにでも破壊しても不思議ではなかったと私は感じているのであるが。あくまでも個人的な考え方であるが一つの理由は、この『負の遺産』をナショナリズムの高揚につなげようとする側面があった事は否めないであろう。つまり、植民地支配という負の歴史が刻まれた建造物を憎悪の感情から短絡的に破壊してしまうのではなく、それらを敢えて残すことによって、その負の歴史を乗り越えて、現在の中国の発展があるのだ、という意識を中国国民に植え付けようとしているのではないかと。そしてもう一つは、「歴史的・文化的価値の認識」の側面。満州国時代の建造物の歴史的・文化的価値が中国人にも理解されたということではと。首都・ 新京(現・長春)の官庁街に多く取り入れられた「帝冠様式」は、五族協和という満洲国のイデオロギーを体現した建築様式であったが、戦後の国民党政府、さらには中華人民共和国が成立した後も、同様の様式がそのまま「民族形式」という名の下で採用され、中国ナショナリズムを体現する様式になったのではなかろうか。特に近年では、中国の対外的な開放が進み、多くの観光客が期待できるようになったために、こうした歴史的建造物を積極的に観光資源として活用し、ツーリストマネーに繋げようとする動きが加速しているのも否定できないのではと。そして我々の今回のツアーもこのツーリストマネーに繋がる動きの上にまさしく載っかっているのであった。しかし一方で韓国では、日本による支配は恥ずべき歴史であり、日本の近代建築や敵産家屋は否定性に満ちた「負の遺産」という認識があるため、破壊すべき、との声も多いとのことが以前の報道で。ちなみに日本統治時代の名残は、韓国では「日帝残滓(일제잔재、イルチェジャンジェ)」と呼ばれていると。「残滓」は残りかすという意味。建物に限らず、言葉や文化も同様だと。しかし一方では、京城府庁舎として使われていた建物は、2012年までソウル市庁舎として使われていた。老朽化もあり、その後ろに建てられた新庁舎に機能が移ったが、文化財に指定されるとともに今は図書館としてリニューアルを遂げ、新たな形で活用されていることも事実のようだが。災害や戦争など死や苦しみと結びついた場所を旅する行為は「人類の悲しみの記憶を巡る旅」であり、悲しみを経験した人々に思いを馳せ、悼み、祈る気持ちを抱き、これを子供たちに伝えていくことも我々の義務であるとも考えているのである。そして、私の部屋にあるテレビは今『第2次世界大戦後に旧ソ連・シベリア地域に抑留されて亡くなった日本人の遺骨として厚生労働省の派遣団が5年前に持ち帰った16人分の遺骨について、日本人のものでない可能性が高いことを、厚生省は昨年から把握していたにもかかわらず公表していなかったことが7月29日、明らかになった。』とのニュースが。最後に中国東北部の都市開発、新幹線網の発展のスピードに驚いたのであった。今回訪れた都市は、日本以上にビルの高層化が進み、高速道路網の発展にも驚いたのであった。大都市内での車の過剰に拠る渋滞は更に深刻化していた事は明らかであったが、都市を繋ぐ高速網の発展のスピードは目を見張るものがあった。そして新幹線網の発達にも驚いたのであった。利用した新幹線は、日本国内の新幹線と勘違いするほどのスピードと安定感を有していたのであった。そして新幹線の駅舎は、空港ロビーとこれも勘違いするほどの造りになっていたのであった。中国の新幹線技術の発展は、川崎重工業が東北新幹線「はやて」をベースに技術供与したものであると。中国側はこれを「独自開発した」と主張して国際特許出願にまで踏み切ったのだと。JR東日本と組んで新幹線の車輌(技術)を提供した川崎重工業の契約が杜撰で「技術を盗んでください」といっているようなものだったことが、新幹線技術を中国に盗まれる原因となったのだと。川崎重工業とJR東日本による中国への新幹線技術の売り込みに一貫して反対していた人物は「中国に新幹線のような最先端技術を売ることは国を売るようなものだ」とまで言って反対していたのだと。中国側は「技術供与を受ける際、巨額の特許料を支払っている。合法的な使用は“盗作”にはあたらない」と反論しているのだと。「350kmの技術があるのに、なぜ250kmの技術を盗まなければならないのか」とも。日本国内の鉄道網の整備が飽和状態となる中、海外に活路を求めざるを得なかったのだとも。高速鉄道に加え、地下鉄などの数多くの大型の都市鉄道計画を持つ巨大市場、中国に目がくらんだのだとの指摘も。侃々諤々(かんかんがくがく)の中で真相は如何に??中国高速鉄道網。中国の高速鉄道網は、運行開始から10年の間に猛烈なペースで拡大。営業距離は17年末時点で約2万5,000キロと日本(約3,100キロ)の8倍に達し、世界一の高速鉄道大国に成長しているのだと。 【https://www.nna.jp/news/show/1787778】よりそして最後に、このツアーは参加人数11名の少人数、男性4名、女性7名の賑やかな、いや賑やかすぎる?そして当然ながら女性優位の旅であったのだ。しかも平均年齢は70歳前後であろうか。しかし、年齢的なことも在り、全員が「PUNCTUAL」そのものであった。集合時間の10分前には既に全員が揃っているのが当たり前の中でのツアーであった。しかし、ベテラン添乗員&現地添乗員が、匠の技で女性陣?をコントロールし、途中からは、ツアー仲間同士が毒舌を交えた冗談や会話が出来る、楽しい旅となったのであった。そして今回のベテラン添乗員への感謝と、また何処かで一緒に旅をしたいと思っているのである。さて次回の海外の旅は何処へ?ブルガリア、ルーマニアの5つの世界遺産を訪ねる旅であろうか? ・・・もどる・・・ ・・・完・・・
2019.08.14
閲覧総数 1377
-
36

『港・ヨコハマ』を巡る(その16):三溪園(2/4)
先程横から見えた沢に架かる石橋を渡って更に進む。緑に覆われた『十三重石塔』。『聴秋閣(ちょうしゅうかく、旧二条城移築三笠閣)』も重要文化財。緑のモミジ葉が陽光に輝く。「『聴秋閣』は元和9年(1623)三代将軍徳川家光が上洛した際に、佐久間将監に命じて京都二条城内に建立されました。当初は三笠閣という名前でした。その後これを乳母春日局に賜り、局はそれを夫の稲葉候の江戸邸内に移しましたが、明治14年(1881)には更に牛込若松町の二条公邸に移築、大正11年、三溪園に移築されました。」『聴秋閣』は内苑でも一番奥の渓流沿いに建てられ、山間の中にひっそりと現れる洒脱な楼閣といった趣きで、新緑や紅葉の頃には色づく木々とあいまって特に秀麗な姿を見せてくれると。緑のモミジ葉で覆われた楼を見上げて。外観は小さな楼閣を乗せた二層構造で、正面から見た時には中央上部に楼が突き上がり下層が横に広がっていますが、横から見た時には上下とも同じ幅になっています。さらに楼の下の主室を中心に左右非対称の異なる内部構成になっており、それに合わせて屋根の構成も変化をつけるなど、その見る位置によって様々な顔を見せる複雑妙味な建造物です。『春草廬(しゅんそうろ)』。『春草廬』は三畳台目の茶室で、後掲の月華殿と共に宇治三室戸寺の金蔵院にあり、当時は9つの窓があることから、九窓亭と呼ばれていました。有楽斎は利休十哲(りきゅうじってつ)のひとりとされる茶人だ。躍り口脇の刀掛けの踏石は稲葉と名づけ、岐阜県稲葉山より持ち来たもの、庭前の手洗石は京都嵯峨天竜寺にあったもので、夢窓国師が使用されたものだそうです。ガラス戸に映った景色も見事。春草廬からの小道の傍らには苔むした石棺などが置かれ、ここは特に奈良の風情が色濃い場所だ。『石棺』。奈良は海竜寺付近から出土した5~6世紀の石棺。それより100年以上も古い石棺の蓋古代に思いを寄せつつ進んだ先に待つ、窓が多く優しい華やかさを感じさせる小さな空間。更に緑の散策路を進む。『蓮華院』。もとは、現在の春草廬の位置にありましたが、 第二次世界大戦後に竹林にある茶室という構想のもとに現在の位置へ再築されました。 二畳中板(にじょうなかいた)の小間と六畳の広間、土間からなっています。土間の中央にある太い円柱と、その脇の壁にはめ込まれている格子は、宇治平等院鳳凰堂の古材と伝えられています。 蓮華院という名は、三溪が茶会を催した際に広間の琵琶床に、奈良東大寺三月堂の不空羂索観音が手に持っていた 蓮華を飾ったことに由来しています。『横笛庵』草庵風の茶亭で素朴ながら風趣のある建物です。 建物内に横笛の像が安置されていたことから横笛庵と称されています。 横笛の像は、戦争の際に失われました。横笛は、高倉天皇の中宮 建礼門院に仕え、平清盛の従者である斉藤時頼(滝口入道)と悲恋に終わった女性です。 横笛が、他の人々の恋が実ることを願って、時頼から寄せられた千束の恋文で作った己の像は、 「縁結びの像」として知られていました。(2人の悲恋話については、高山樗牛による"滝口入道"という小説が有名です。)『海岸門』を潜る。こちらも御門と同様に京都西方寺から移築されたものである。魔除けの桃瓦が写真左に。鬼瓦は阿吽でこちらは阿形。『松風閣展望台』に向かって進む。狭い山道。『三溪園 昔むかし 9 御谷館』。「御谷館は、もと鎌倉・鶴岡八幡宮境内に併存していた神宮寺の僧房であったといわれる建物。明治41(1908)年に移築され、来園者の休憩用にあてられたようであるが、詳しくは不明。大正4(1915)年に焼失した。」『三溪園 昔むかし 10 造成中の内苑(大正10年頃)』。「当時一般に公開されていたのは、現在の外苑部分で、内苑は原家のプライベート・エリアであった。写真では公開部分との境に仮説の塀が設けられ、その向こうに資材置き場であろうか、簡易な建物が見える。土塁を経て中央の臨春閣から上方にのびる瓦屋根は、源 頼朝の木像(現在は東京国立博物館所蔵・重要文化財)を安置した源公堂と、月華殿までの石段上に設けられた回廊の姿である。いずれも戦時中に取り払われ、現存しない。」秋にはオオスズメバチがいそうな坂道。岩がゴロゴロした場所には、木製階段が。『松風閣跡地』。『三溪園 昔むかし 12 松風閣』。「初代・善三郎が別荘として明治20年ごろに築造した建物で、その名称は伊藤博文によるものである。写真はレンガ造の玄関部分で、窓などに中国風の意匠が見られる。断崖に立ち東京湾の絶景を望むことができる松風閣は、三溪の代となり本邸・鶴翔閣が建てられると、重要な客をもてなす、いわゆるゲストハウスとして増築がなされた。大正5(1916)年には、アジア人初のノーベル賞受賞者であったインドの詩人・思想家のラビンドラナート・タゴールがアメリカへの講演旅行の途中、ここに数ヶ月間滞在し、詩「さまよえる鳥」をのこしている。また、その一室”観山の間”には三渓が支援した中でも最も好んだ日本画家下村観山が描いた「四季草花図」の障壁画があったが、大正12(1923)年の関東大震災により建物とともに消失した。」そして松風閣跡を南側に登ると展望台に着く(展望台に松風閣の名が残る)。階段を上り展望台へ。展望台から東京湾の豊浦町、本牧埠頭の景色を楽しむ。『JXTGエネルギー(株) 根岸製油所』。南本牧ふ頭のコンテナクレーンが並んでいた。手前には『首都高速湾岸線』が。『三溪園 昔むかし 11 聚星軒(じゅせいけん)』竹を編みこんだ壁など、中国風の意匠が特徴の建物。明治20(1827)年ごろ、松風閣とともに原家初代・善三郎が築造したもののようであるが、大正12(1923)年の関東大震災により倒壊し、現存しない。周辺には、中国で産する太湖石の石組みなどが今も残り、善三郎の中国趣味の一端がかいま見える。展望台を後にして、尾根道を下る。大明竹が覆いかぶさるような径を抜けると、樹々の合間から三重塔が見えて来た。三溪園のシンボルともいえる建物。そのちょっと手前、径の左側に石の仏像が置かれていた。名付けて『出世観音』と呼ばれていると。三溪園あるいは三溪と縁の深かった文化人たちの多くが、文化勲章の栄誉を受けているという事実から、なんとなく呼ばれるようになって来たようであった。そして『重文 旧燈明寺三重塔』三溪園のシンボルのように中央の山上に建つ三重塔は、京都府相楽郡加茂町燈明寺にあったものを、大正3年3月に移築したもの。1485年の建立で、関東地方では最古の塔であると同時に、移築されたものとはいえ、横浜市最古の建築物。塔の先端までの高さは24mで、全体が安定感のある優美な姿をしていると評価されています。勿論、国の重要文化財に指定されている。建築様式としては、典型的な和様と呼ばれる形式で、室町時代の特徴をよく備えていると。各層に欄干付の廻縁が設けられ、斗供を始め細部も室町のしきたりに添っている。現在関東地区に所在する木造の塔としては最古のものになるのだと。三溪園の『大池』が下方に見えた。『旧燈明寺三重塔』からの本牧の町並みの眺め。ここ三重塔の丘から大池越しに眺めると、住宅地の先には横浜港のクレーンの先端がずらりと揃って見え、さらにベイブリッジの橋塔がかすかに望むことが出来たのであった。三重塔をズームで見上げる。ところで、この塔の心柱ですが、一層目の屋根裏から立ちあがっていて、一層目は仏像が置かれる空間になっているのだと。実はこの心柱ですが、地面に接した心礎から立ちあがっている場合と、ここの塔のように一層目の天井から立ちあがっている場合があると。これは時代の変化によるもので、古くからの塔は前者のように地面から立ちあがっているのだが、後者の例は、平安末期以降見られるようになった構法であると。 【https://ameblo.jp/sankei-mietaro/entry-12202404368.html】より『初音茶屋(はつねぢゃや)』。その昔『初音茶屋』では、来園する人に麦茶を振る舞う、「麦茶接待」が行われていた。 「ひとはかり浮く香煎や白湯の秋」と、その様子を詠んだのが、芥川龍之介。『三溪園 昔むかし 15 初音茶屋』「開園当時、三渓園には誰もが自由に出入りできたばかりでなく、無料の湯茶サービスもあった。その場所の一つがこの初音茶屋である。中央の炉に煤竹の自在かぎで吊るされた真っ黒な鉄瓶には絶えず湯がたぎり、白湯に米・小麦粉を煎って香ばしくした香煎を入れたものや温かい麦茶がふるまわれたという。大正4(1915)年三溪園を訪れた芥川龍之介は、友人であった三溪の長男への手紙にこの湯茶接待の印象を書き、”ひとはかり浮く香煎や白湯の秋”という句を詠んで締めくくっている。また、別の記録では、屋根を葛が一面に這いまわりその蔓の端が六方の軒に垂れ下がっていたとあるが、写真はまさにその風情である。」更に進むと梅林・『臥竜梅(がりょうばい)』が拡がっていた。三溪園は古くから梅の名所としても有名で2月から3月にかけて、約600本ある白梅・紅梅などが見事な花を咲かせる。竜が地を這うような枝振りの「臥竜梅」、花弁の根元にある萼が緑の「緑萼梅(りょくがくばい)」など、珍しい梅も見ることが出来ると。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2019.10.01
閲覧総数 356
-
37
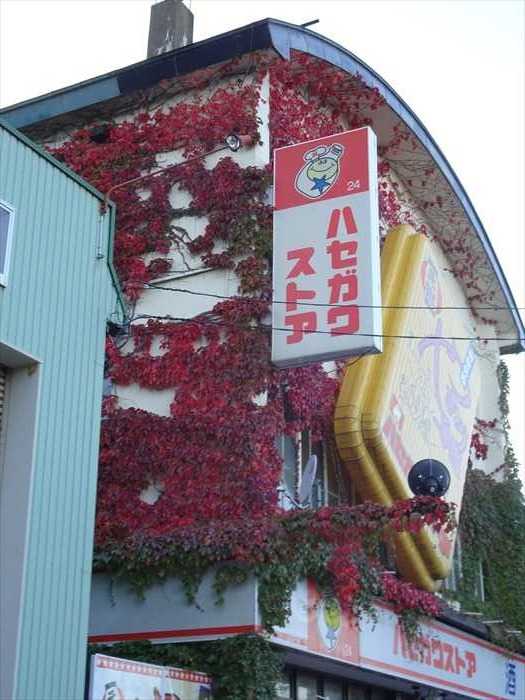
「はるばる来たぜGoto函館」(その4): 函館市内観光・赤い靴の少女像~新島嚢海外渡航の地碑~基坂周辺
別の駐車場に移動し、更に函館の街の散策を続ける。駐車場の前にあった建物の壁一面には紅葉した蔦が。海峡通りの交差点の角にあったのが「赤い靴の少女像「きみちゃんの像」」函館港の見える場所にあったが、海を背中にして。「赤い靴」の歌碑 野口雨情作詞 本居長世作曲♫赤い靴(くつ) はいてた 女の子 異人(いじん)さんに つれられて 行っちゃった横浜の 埠頭(はとば)から 汽船(ふね)に乗って 異人さんに つれられて 行っちゃった今では 青い目に なっちゃって 異人さんの お国に いるんだろう赤い靴 見るたび 考える 異人さんに 逢(あ)うたび 考える♫」像の作者は函館出身の彫刻家・小寺真知子さん。野口雨情作詞の童謡「赤い靴」のモデルとされる少女・きみちゃんの像。1903(明治36)年、きみちゃんは、お母さんのかよさんと一緒に静岡県から函館へと移り住み、その後、母親は後志管内留寿都村の農場に入植したが、病弱だったきみちゃんはアメリカ人宣教師に預けられ、函館が母子の別れの地になったと。2009年、母と別れた地といわれる函館に設置された。靴の部分が赤くなっていた。親子の絆の大切さを伝えるべく、2009年8月、函館開港150周年に合わせて設置された。台座を含めて高さ約160センチメートルのブロンズ立像で、イタリアローマで製作された。国道279号(海峡通り)の交差点から「八幡坂(はちまんざか)」を見る。函館山からの夜景と並んで、函館のビュースポットとして紹介されることが多い坂。赤レンガ倉庫が立ち並ぶウォーターフロントの先を進むと、函館山へ導いてくれるのがこの「八幡坂」。両歩道脇には、坂上まで手すりつきの階段が整備され、冬には歩道にロードヒーティングが施されているとのこと。坂名は、河野政通の館跡地(現在の元町公園付近)から移設された函館八幡宮があったことに由来すると伝えられていると。大火の被害を受けて1880(明治13)年に現在の谷地頭町に移ったものの、その後も坂の名称は残されたのだと。そして少し戻り「金森赤レンガ倉庫群」を見る。そして車で「緑の島」駐車場まで行き、直ぐに引き返して訪ねたのが「新島襄 海外渡航の地碑」。地碑は、同志社大学から記念碑面を寄贈された1952(昭和27)年の2年後に建立。後方に「緑の島」。「緑の島」は函館港の万代・港町泊地浚渫工事によって生じた土砂を利用し、港内を護岸で囲って確保した処分場工事によって誕生した埋立地であり、埋立土量は約70万m3。「緑の島」の活用については、水族館や第三セクターによるウォーターフロント開発の中核施設建設などの計画があったが、2007年(平成19年)に事業断念を表明し、現在は多目的広場、カラー舗装広場、石畳広場そして駐車スペース(約200台)になっていると。「新島嚢海外渡航の地碑新島襄は、新知識を海外に求め、吉田松陰の海外渡航の失敗を考慮し、渡航地を箱館に選んだ。元治元年( 1864年)江戸から来て、ニコライ主教(ハリストス正教会2代主教)に日本語を教えたりなどして脱出の機会を待っていたが、同年6月14日(新暦7月17日)深夜、福士成豊(日本最初の官立気候測量所開設者)の助力により、この地から国禁を犯して海外渡航に成功した。上海経由で渡米した新島襄は、修学10年の後、明治7年( 1874年)に帰国し、翌8年京都において同志社大学の前身である同志社英学校を創立した。この碑にある「男児志を決して千里を馳す自ら苦辛を嘗む豈(あに)家を思わんや却って笑う舂風雨を吹く夜枕頭尚夢む故園の花」の漢詩は、新島襄の自作自筆によるもので、元治2年( 1865年)香港での作である。渡航前の名前は新島七五三太であったが、航海中に船長から「ジョセフ」の名をもらい、路して「襄」の字をあてた。明治23年( 1890年) 48歳で没。函館市」「新島嚢海外渡航の地碑」から「金森赤レンガ倉庫群」を見る。ベイエリア西にあった新島襄のブロンズ像はどこに行ってしまったのであろうか?そして「海上自衛隊函館基地隊」。掃海部隊が駐留しており、津軽海峡および宗谷海峡の海峡警備の拠点である。北海道における海上自衛隊の代表的な基地隊であり、アメリカ海軍艦船の寄港も多い。門柱には「海上自衛隊箱館警務分遣隊」と。左手には護衛艦「はまゆき」の主錨が展示されていた。「箱館運上所跡欧米5か国との通商条約に基づき、安政6年( 1859年)、箱館は横浜、長崎とともに開港し国際貿易港となった。これにともない、税関の前身である運上所が設けられた。開港翌年の入港外国船は、商船30隻、捕鯨船21隻、軍艦13隻の計64隻であった。貿易では、輸入はほとんどなく、韓出は中国向けの昆布が4分の1を占め、そのほか、いりこ、するめ、干あわびなど海産物が上位をしめていた。明治5年( 1872年)、運上所は税関と改称された。昭和43年( 1968年)、海岸町中央埠頭に港湾合司庁舎が完成し、税関も同庁舎に移転した。なお、明治44年( 1 91 1年)に築された庁舎は、木造ルネサンス風の洋風建築であったが、昭和47年( 1972年)に取り壊された。 函館市」そして「箱館運上所跡」の正面の「基坂」のグリーンベルトにあったのが「三蹤碑(さんしょうひ)」。グリーンベルトの真ん中にある赤御影石の地球儀の上に青銅の鳳凰が羽を広げた大きな石碑が「明治天皇御上陸碑」。台座となる塔の部分と地球儀は花崗岩製。その上に乗る羽を広げた青銅製の鳳凰は、宝来町にある高田屋嘉兵衛銅像の作者としても知られる函館出身の彫刻家・梁川剛一氏が手がけたもので、まるで生きているかのような躍動感と存在感が。「明治天畠上陸記念碑赤御影石の地球儀の上に、青銅の鳳凰が羽を広げた碑は、明治天皇が明治9年( 1876年)、東北・北海道巡幸で来函の際の、旧税関桟橋への上陸を記したものである。同14年( 1881年)に再び来道の際、小樽から陸路函館へ巡幸し、ここから乗船して青森へ向かった。明治9年の下船・乗船と同14年の乗船で、計3回となることから、「三蹤碑」とも呼ばれている。この碑は、函館出身の彫刻家・梁川剛ーの作で、昭和10年( 1935年) 9月7日に除幕された。同16年( 1941年)に7月20日を「海の記念日」と定めたのは、明治天皇の明治9年( 1876年)の巡幸の際、7月1 8日に離函し、20日に横浜に帰着したことを記念したものである。平成8年( 1996年)から国民の祝日「海の日」となった。」そしてその先に「基坂(もといざか)」と「函館山」が。交差点の角にあったのが、不動産仲介業「相馬(株)」の建物。1913(大正2)年築のルネサンス風事務所建屋。ぺディメント(西洋式切妻破風)など特異な意匠。基坂と電車通りの交差点に建ち、西部の街並みのランドマーク的存在。伝統的建造物。電車通り側にある入口。ズームで。木造2階建ての鉄板葺き屋根に突き出た窓(ドーマー窓)は、ルネッサンス様式。軒先や窓枠などに目を凝らすと、随所に洒落た装飾が見受けられます。そして「函館市北方民族資料館」 北海道函館市末広町21−7。資料館の入口。アイヌ民族や北方民族に関する資料館。こちらは「基坂」側の入口。そして路面電車「函館市電」。路面電車が走りはじめた1913(大正2)年の函館は、北海道の表玄関として活況を呈しており、それまでの馬車鉄道に代わって颯爽と登場した姿は、街で注目の的であったと。今でも、市民の日常の足として、また観光客には移動の足として、広く親しまれていると。そして「基坂」を登って行く。「基坂」と書かれた柱の横には「はこだて観光案内」が。「基坂(もといざか)通」と刻まれた石碑。函館山山麓から函館港方面にのびる坂の一つである基坂は、明治時代に坂を下った所に里数を測る基点となる里程元標(りていげんぴょう)の木柱が立っていたため名付けられた。明治40年(1907)8月に起きた大火で、基坂にあった主要施設の殆どが焼失してしまい、大火後から数年に渡り基坂では旧函館区公会堂をはじめ豪華絢爛な建物が次々と建設されていった。現存する建物で旧北海道庁函館支庁/明治42年(1909)築、旧イギリス領事館/大正2年(1913)築、 相馬株式会社/大正3年(1914)築など。石畳の「基坂」を上って行く。「諸術調所跡諸術調所とは、箱館奉行所の研究教育施設で、蝦夷地の開拓と警備に必要な人材育成を目指して、安政3年( 1856年)に設立された。教授は五稜郭設計で有名な武田斐三郎で、蘭学はもとより、測量・航海・造船・砲術・築城・化学などを教え、亀田丸でロシアまで操縦航海するなと実践を重んじた教育を行った。元治元年( 1864年)、斐三郎が江戸開成所(現・東京大学の前身)の教授に転出するまで、門人多くを教育し、前島密(郵便制度創始者)、井上勝(鉄道制度創設者)など明治日本の動脈を作った優秀な門下生を輩出した。同志社の創設者「新島襄」が箱館からアメリカへ密航したのも、諸術調所に入るために箱館にやってきたのに、斐三郎が江戸へ出てしまっていたための行動であったとも言われている。内外共に多難な幕末期、開明的で進取果敢の精神に満ちた人々と学舎があって、その成果を全国に及ぼした事実は、市民の誇りとするところであり、その魂は常に新しい時代の開拓のために生き続けるだろう。」花壇の中に像が並ぶ。パブリックアート「ハイカラさん」。西洋風のドレスをまとった明治期の貴婦人がモデル。日傘を手にしてベンチに座る女性のすました表情が印象的で、高さは約1.5メートル。「ハイカラさん」岡本銕二(てつじ)作文明開化華やかし時代にタイムスリップしてみませんか”Let's sit together”作品のベンチには、貴婦人の横に大人1人が座れるスペースがあった。作者は「一緒に写真を撮るなど、実際に作品に触れながら鑑賞を楽しんでほしい」と。基坂通のハイカラさんの先にも彫刻が。「旅を続ける男」 峯田義郎作左ひざの上には小鳥が乗っていた。そして像にしては珍しい?サングラス姿。「旅を続ける男」 峯田義郎「人間(ヒト)は 何故 旅を続けるのだろうか」と刻まれていた。道路の反対側には「函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区保存地区は、弥生町、大町、末広町、元町あよび豊川町の各一部て、面積約1 4 . 5へつタールの範囲てす。函館は、安政6年(1859年)に長崎・横浜とともに、我ガ国最初の開港場として開かれ、以来、外国買易や北洋漁業の基地として、また、北海道の玄関口として繁栄してきたまちてす。この保存地区は、その中心的な役割を果たしてきたところてあり、現在でも、旧外国公館や各宗教施設、洋風の公共施設や煉瓦造の倉庫群、掘割りなどのほか函館独特の上下和洋折衷様式の町家や洋風・和風の住宅等か混在して、異国情緒豊かな町並みを形成しています。函館市では、こうした町並みを、末長く後世に伝え残すため、昭和63年12月に函館市西部地区歴史的景観条例により「伝統的建造物群保存地区」を定めました。平成元年4月には北海道で初めて、国の「重要伝統的建造物群保存地区」として選定を受け、貴重な町並みの保護保存に努めています。」「異国への夢」佐藤正和作黒船が来航した時代、船員となって 世界を旅する夢を抱く箱館の少年。佐藤正和は、1973 北海道函館市生まれ。「基坂」周囲の観光案内図そして「旧イギリス領事館(開港記念館)」1913(大正2)年築、1934年まで領事館として使用。1992年改装して開港記念館として一般開放。2009年、全面リニューアル。内部にはティールーム、英国雑貨店併設。1859(安政6)年の開港とともに、アメリカ、ロシアに次いで函館では3番目に開設された領事館。最初は当時、現在の弥生小学校付近にあった称名寺内に仮設、1863(文久3)年に現在のハリストス正教会(函館市元町3)付近に新築した後は、幾度かの大火に見舞われ、現在の建物は1913(大正2)に竣工したものです。1934(昭和9)年に領事館としての役目を終えて閉鎖され、1992(平成4)年に復元されて以降は、開港記念館として一般開放されている。函館市指定文化財(有形文化財)。旧イギリス領事館の窓枠の青と白壁の建物。「函館市旧イギリス領事館(開港記念館)営業案内板」「旧イギリス領事館(開港記念館)箱館にイギリス類館が新かれたのは、安改6年( 1859年)日本最初の貿易港として開港した時のことで、箱館ではアメリカ、ロシアに次いで3番目の領事館として、初代領事ホジソンが称名寺に開設した。文久3年( 1863年)に現在の元町のハリストス正教会の西隣に領事館を新築したが、数度の火災にあった。この建物は、イギリス政府工務省上海工事局の設計により、大正2年(1913年)に竣工したものであり、昭和9年(1934年)の閉鎖まで領事館として使用されていた。平成4年( 1992 ) 8月からは、開港記念ホール、開港の歴史を伝える展示室、旧外国公館の雰回気の中でお茶やお菓子を楽しめるカフェを設け、一般公開している。 函館市」」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2020.11.16
閲覧総数 312
-
38

「はるばる来たぜGoto函館」(その23):日の出~大沼公園
10月20日(火)、この日はこの旅行・「はるばる来たぜGoto函館」の3日目。この日の朝もエレベータホールからの日の出をカメラで追う。山の端がだんだんと鮮やかのオレンジ色に変わって来た。時間は6:05過ぎ。上空が赤く染まった「函館山」。そして、手前には多くのビニールハウスが。ここ北斗市は北海道内で最も早くから野菜の栽培に取り組んでおり、北海道内有数の長ネギ、トマト、キュウリ、ホウレンソウ産地になっているとのこと。「五稜郭タワー」。手前には北海道新幹線の線路が。そしてこの日の日の出の直前。そして日の出。時間は6:11。そして、この日も二重の日の出が。そしてこの日の出発。この日は、「大沼国定公園」から道道43号線で太平洋内浦湾入口に面する「鹿部町(しかべちょう)」に出て、その後はひたすら海沿いの国道278号を走り「渡島半島」を一周して「五稜郭」を訪ねその後、「立待岬」まで行く、いつものように忙しいハードな行程。ホテルの前の道路にあった北斗市の雨水マンホール蓋。市内当別にある「トラピスト修道院」と、「北海道新幹線」をデザインしたマンホール。新幹線の車両が決まる前のデザインであるため、鼻が短めになっているのだと。朝の陽光を浴びるホテルを振り返る。この朝も脚長オジサンを自撮り。3日目のこの日・11月20日は「亀田半島」を―の如く一周することに。まずは北上して「大沼国定公園」を巡り、太平洋内浦湾沿いの鹿部町から国道278号、道道231、635号線で「恵山岬」へ。そして再び新八幡町の分岐まで戻り、再び国道278号で日ノ浜町へ、そして再び道道635号線を利用して恵山の火口原駐車場へ。その後も国道278号に戻り左に津軽海峡を見ながら「志苔館跡」、「五稜郭」、「四稜郭」、「立待岬」等を訪ねたのであった。道道1176号線を北上し、この先を左折し国道5号を「大沼」方面に進む。国道5号の遊歩道には赤いサルビアの帯が。「大沼トンネル」を通過する。「西大沼」交差点からは。山頂付近が白くなった「北海道駒ヶ岳」が姿を現す。右折して、道道338号・大沼公園線を走る。そして車窓から「小沼」と「北海道駒ヶ岳」を見る。函館本線に沿って進む。函館本線の「大沼駅」に立ち寄る。「大沼駅」前広場にあった「大沼公園観光案内図」。「小沼」と「大沼」の間を走る道道338号線・大沼公園鹿部線を更に進む。そして右に折れ、沼畔近くに車を駐め「大沼」の散策開始。「大沼」と「北海道駒ヶ岳」の勇姿。そして風のない沼面に見事な「逆さ駒ケ岳」の姿が。沼面に映る盆栽の如き島の光景を楽しむ。一両編成の函館本線の姿も。鏡の如き沼面。「大沼」と「北海道駒ヶ岳」の勇姿。ズームして。「剣ヶ峯と呼ばれる大沼方面から見て左側に尖った部分が標高1,131 mのこの山の最高点。いろいろなアングルで。レストラン「ターブル・ドゥ・リバージュ」周辺の紅葉。レストラン「ターブル・ドゥ・リバージュ」前の広場の紅葉は始まっていた。レストラン「ターブル・ドゥ・リバージュ」の角に「虚子の径」と刻まれた石碑が。この径が「虚子の径」と呼ばれているのであろう。「虚子の径 俳人高浜虚子曽遊(そうゆう)の地昭和十四年五月二十三日 折柄来函中の虚子は 、この日大沼吟行を思い立ち、糸夫人と五女高木晴子、その夫高木餅花、六女高浜章子、それに内藤松籟、阿部慧月と共に杖を引かれ、この場所にあった旅館「湖月」の2階で小句会が行われた。その折虚子が一人俳句を作り乍ら湖畔を逍遥した道である。爾来この地を「虚子の径」と名付け、多くの俳人達が四季折々に訪れ親しんでいる。」虚子句碑は大沼公園駅近くの大沼婦人会館敷地内に建立されていると。「駒ヶ嶽聳えてここに沼の春」高浜虚子(1874-1959)は明治-昭和時代の俳人、小説家。明治7年2月22日生まれ。中学時代から正岡子規に師事。明治31年「ホトトギス」をひきつぐ。一時小説や写生文を書いたが大正2年俳句に復帰。客観写生、花鳥諷詠(ふうえい)をといて俳句の伝統擁護につとめた。昭和29年文化勲章受章。芸術院会員。昭和34年4月8日死去。85歳。愛媛県出身。旧姓は池内。本名は清。句集に「虚子句集」「五百句」、小説に「俳諧師」「柿二つ」などがあると。木々が「大沼」の水面に映り込み。上の写真を逆さにしてみましたが、全く違和感はなし。大沼での漁業用のボートであろうか。「島巡りの路」の一部を歩くことにした。ここは「湖月橋(こげつばし)」。「大沼」の水面からは霧が湧き上がっていた。「湖月橋」。「大沼公園散策マップ」。大沼の湖畔遊歩道は、青の点線で大沼に浮かぶ小島や多数の橋を巡る「島巡りの路」の他、「森の小径」「大島の路」と合計3つある。「森の小径」は20分のコースで、「島巡りの路」の一部を歩く短縮コース。「大島の路」は、15分コースだが景色も良く、名曲「千の風になって」のモニュメントもあり、時間がない方にはこちらがお勧めだと。「島巡りの路」は所要時間50分の散策コースとのことだが、その一部を歩く事としたのだ。。「湖月橋」を渡る。「湖月橋」を振り返る。道道338号線に架かる赤い桁の「月見橋」。この写真の「月見橋」の奥は、「白鳥台セバット」と呼ばれ、大沼国定公園の一角で、冬でも湖面が凍結することなく、渡り鳥の休息場所になっており、オオハクチョウやカモなどの野鳥を間近に見ることができるのだと。あまり聞き慣れない「セバット」という言葉。地元では「狭まった場所」を意味するそうです。大沼国定公園は、大沼と小沼と蓴菜沼(じゅんさいぬま)の3つの湖沼からなり、ここ「白鳥台セバット」は大沼と小沼がつながっている、まさに狭まった場所。冬は湖面のほとんどが凍結して氷の厚さは60cmほどにもなるが、この付近だけは水の流れがあって冬でも凍結することなく、冬の渡り鳥の休息場所となっているのだと。冬の「白鳥台セバット」の光景を【ネット】から。例年12月下旬から3月上旬にかけて、越冬するオオハクチョウを見ることができるのだと。大沼、小沼両湖が全面結氷する冬も水面が顔をのぞかせ、カモやカワアイサ、ミコアイサといった水鳥の憩いの場所となっている。オオワシやオジロワシなどが飛来することもあり、バードウォッチングを楽しむ人々で賑わうと。 「金波橋(きんぱばし)」紅葉が青空に映える。野鳥の姿が。カモであろうか。見事な盆栽が2つ。大沼や小沼の湖中に点在するこれらの大小の島々は、数度の大噴火の際の岩屑なだれがつくった「流れ山」であると。岩屑なだれ堆積物の表面には、直径数mから数百mにおよぶ丘状の流れ山地形が形成され、大沼周辺一帯には多くの流れ山が分布しているのだと。右手の盆栽。漁業用の小舟が水面を走り去る。大沼の水面にはボール上の浮きが所々に。大沼に仕掛けられている網は川エビを獲るためのもの。10月中旬から12月下旬にはワカサギ漁の小定置網も張られると。これらは大沼名産の佃煮に加工されていると。小舟の波紋が「逆さ駒ケ岳」の姿を隠す。「袴腰橋(はかまごしばし)」。「日の出橋」が見えた。「袴腰橋」から見る「北海道駒ヶ岳」。水面に映る姿を追って。別の盆栽の如き島。僅かに風が出て来た。「東宮殿下 御展望之地 大正十一年七月十日」東宮殿下とは昭和天皇のことであろう。そして「日の出橋」を渡る。この先の島は「アイヌ島」と呼ばれている。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2020.12.05
閲覧総数 264
-
39

沖縄本島一周の旅へ(その29):【4日目・9/28】 泡瀬塩田跡~泡瀬ビジュル~中村家住宅~吉の浦火力発電所~護佐丸公之御墓~沖縄成田山福泉寺
「平安座海中大橋」を後にして県道37号線の海岸線を北に引き返し、途中左折して33号線➡85号線を利用して次の目的地・「泡瀬塩田跡」に向かってひたすら進む。そして「泡瀬塩田跡」に到着。沖縄市泡瀬3丁目32−1。「泡瀬塩田跡之碑」。「泡瀬塩田跡之碑一七六八(尚◯一七)年頃、無人の小島であった泡瀬に首里・那覇から移住者が入植し、農業のかたわら島の南西砂州に続く干潟を開拓し、「入浜式塩田(シンナー)」を作り製塩業を興した。廃藩置県(明治十二年)を境に「泡瀬」の製塩業は急速に発展し、一九〇五(明治三)年頃には、県内一の生産量を誇る。「アーシマース」は県下にその名を馳せた。製塩業と樽皮製造業は戦前の「泡瀬」の発展を支える二大基幹産業であった。戦後、一九四六(昭和二一)年には製塩業は復活し、一九五〇(昭和二五)年に沖縄製塩株式会社が設立された。一九五五(昭和三〇)年入浜式製塩法を改良、真空蒸発釜を導入、新工場を設立したが一九七二(昭和四七)年沖縄の本土復帰に際し、塩専売法の適用を受けて製造を停止、二百年に亘る製塩の歴史は幕を閉じた。広大な塩田地は、一九七三(昭和四八)年の干潟事業によって埋立てられ住宅地になった。本碑周辺は塩田跡地の一角である。」「泡瀬塩田風景」。泡瀬塩田は、18世紀中頃、高江洲義正という男が初めて移住し、干潟を利用して入浜式塩田による製塩をしたのが始まりとされていて、高江洲義正の製塩技術は首里勤務の時に那覇の泊りなどで修得したものと推測されている と。ネットから「泡瀬塩田風景」を2枚。石碑の「泡瀬塩田風景」は下の写真のようであった。「入浜式塩田」の光景。「入浜式塩田」は日本に近世初期から行われた製塩施設。遠浅海岸の満潮水位以下の場所に堤防を築き、その内側に砂層地盤の塩田を設けたもの。塩田は溝によって短冊形に仕切られ、潮が満ちてくると堤防に設けられた樋門を通って溝から海水が塩田に浸透する仕組みで、太陽熱で水分が蒸発すると塩田の砂に塩分が付く。それをかき集めて海水をかけて濃厚な塩水 (鹹水) をとり、釜で煮つめて製塩を行なった。干満差が大きく遠浅の瀬戸内海沿岸を中心に発達し、近世から昭和年代にいたるまで、長く日本における製塩の中心をなしたが、1950年代に流下式塩田に転換した と。「ハマトリ」のオバちゃんの姿。日本復帰当時の「泡瀬塩田」周辺の地図。旧「泡瀬集落」の北部に「ぐるくん公園」がありその中央に丘があったが。沖縄県の県魚、「ぐるくん(タカサゴ)」の名前を冠した公園。しかし、丘に登ってみても上の方には特に何もなくその向こう側に砂場とすべり台があるだけ。すべり台以外の遊具は特に無く、つまりは、「ぐるくん」と名前が付けられている理由は良くわからずじまいであったが・・・。次に近くにあった神社「泡瀬ビジュル」を訪ねた。「ビジュル」の語源は、<賓頭慮(ビンズル)――不動の意>。十六羅漢の中の第一の尊者で、その名前の意味は不動であるという。「ビジュル」とは、石神のことで、その石神を信仰する、いわゆる石体信仰の態容をなすもので、沖縄県下に91カ所あるといわれる。泡瀬の「ビジュル」の形態は、自然の陽石を思わせるもので、安置される場所は神社にならって神殿をつくり、扉の奥深くにビジュルを祀っている。御利益は無病息災、子安(子育て或いは子授け)、航海、交通の安全。上記の祈願をするので、住民は年中行事として、ビジュル物参りをする習俗があると。祭祀は専ら、男性司祭者にゆだねられており、その係を「ビジュルヒチ」といい、ここ泡瀬の場合は、義正翁の末裔にあたる高江洲義総氏がその役目を果たしているとのこと。沖縄市泡瀬2丁目1。「泡瀬ビジュル」の「一の鳥居」。「泡瀬ビジュルの由来」碑。「泡瀬ビジュルの由来泡瀬はその昔「あせ島 」「あわす小離 」と称され高原村より東へおよそ九町、隔海に突出した無人の小島で、自然に形成された砂州と南西には広い干潟を有していた。一七六八年頃、読谷山間切の在番役を退役した樊氏高江洲 (筑登之親雲上 )義正は、初期の居住者としてこの地に入植し、広い砂州と干潟を開墾して、農耕のかたわら塩を焚き安住の地をここに定めた。ある日、漁猟に出た義正は海面に浮かぶ霊石をみつけてもちかえり霊験あらたかなるビジユル神 として、島の西側磯のほとりに石祠を建てて安置し、信心したのがビジュル神信仰 の始まりといい伝えられている。旧暦の九月九日にはビジュル参りの例祭があり、無病息災、子安、子授けなどの祈願に参詣者がたえない。一九三八年(昭和十三年)有志の尽力で旧石祠を改修して、社殿と二基の鳥居内外玉垣が建立され境内が整備された。一九八三年(昭和五十八年)泡瀬土地区画整理事業 にともなう土地の全面嵩上げ工事の際に境内を拡張し、社殿と一の鳥居、二の鳥居はそれぞれ四尺嵩上けして移設、一の燈籠を新設、玉垣を改築した。」「泡瀬ビジュル(社殿、鳥居、手水鉢」案内板。「泡瀬ビジュル(社殿、鳥居、手水鉢) 沖縄市指定文化財 平成21(2009)年3月27日指定泡瀬ビジュルの由来については、泡瀬の初期開拓者である高江洲義正が、海に浮かぶ霊石を見つけて持ち帰り、ビジュルとして祀ったのがはじまりといわれている。現在のビジュルは、昭和13年に改修されたものである。ビジュル参詣(ビジュルムヌメー)は旧暦9月9日に行われ、祈願の内容は子安、子育て、旅の安全などである。現在でも各地からの参拝者がたえない。桁行1間(1,820㎜)、梁間1間半(2,800㎜)、高さ約12尺(3,940㎜)の一間社流造り、鉄筋コンクリート造、人造石洗出し仕上げである。従来木造とすべき建物を鉄筋コンクリート造りとし、鉄筋コンクリート造りでは難しい屋根の曲線や円柱、梁、桁、貫、斗、垂木などを丁寧に仕上げてある。昭和13(1938)年に旧石の祠を改修し、社殿と2基の鳥居、灯籠、手水鉢、内外玉垣を鉄筋コンクリートで建立した。昭和58(1983)年、泡瀬土地区画整理事業にともなう土地の全面嵩上げ工事の際に境内を拡張し、社殿と一の鳥居、二の鳥居はそれぞれ四尺嵩上げして移設、一の灯籠を新設、玉垣を改修した。また、手水鉢は、昭和61(1986)年9月に竣工した。指定対象は、昭和13年に改修、建立された社殿と2基の鳥居、手水鉢である。それらは、当時の建築技術を知る上で貴重である。「二の鳥居と社殿」。「社殿」に近づいて。桁行1間(1,820㎜)、梁間1間半(2,800㎜)、高さ約12尺(3,940㎜)の一間社流造り。鉄筋コンクリート造りとし、鉄筋コンクリート造りでは難しい屋根の曲線や円柱、梁、桁、貫、斗、垂木などを丁寧に仕上げてあった。「絵馬掛所」。「子宝祈願」。「安産祈願」。「泡瀬ビジュル」のお守りなどが販売されている社務所「千秋堂」。近づいて。「千秋堂無人の小島泡瀬の地に首里、那覇からの移住者が入植し、定住を始めたのが一七六八年頃と伝えられています。当時「泡瀬島」は美里間切高原村の属地でしたが、1903年(明治36年)に県令により高原村から分離され泡瀬村が創設されました。二〇〇三年(平成十五年)の泡瀬村設立一〇〇周年を迎えるにあたり、その記念事業の一環として泡瀬ビジュルの社務所・千秋堂を建立する。」表道に面した入口の横には、「泡瀬土地区画整理事業記念碑」が。「泡瀬土地区画整理事業記念碑中頭郡東部地域唯一の商工業地として、繁栄していた泡瀬は、第二次世界大戦の戦災により壊滅し、引き続き米軍の軍用地として接収された。昭和四十二年二月から昭和四十五年七月までに、この軍用地の大半が返還されると、地主組合による土地区画整理事業が計画され、認可申請はしたが施工するには至らなかった。そこで当時県会議員であった現衆議院議員、復興期成会会長 小渡三郎氏からの強い要請を受けた県当局によって、県の事業として推進されることになった。工事は県土木部都市計画課によって施工され、昭和五十三年に着工し、八年後の昭和六十一年三月に竣工した。総工費三十六億五千万円、施工面積は、戦前の泡瀬住宅地と塩田跡地、公有水面埋立地などを含む凡そ七十七ヘクタール(約二十三万坪)である。この泡瀬の区画整理地域は、快適な居住環境として蘇り、泡瀬繁栄の基盤は確立された。ここに画期的な事業の竣工を記念してこの碑を建立した。」沖縄市の「汚水マンホール蓋」。市の木・ビロウと市の花・ハイビスカスをデザイン。中央に沖縄市の市章、下部に「おきなわし」「おすい」の文字。 そして次に訪ねたのが「中村家住宅」。中頭郡北中城村大城106。石塀に囲まれた「中村家住宅」。中村家住宅は戦前の沖縄の住居建築の特色を全て備えている建物。沖縄本島内では、第二次世界大戦の沖縄戦を経てこのように屋敷構えがそっくり残っている例は極めて珍しく、当時の上層農家の生活を知る上にも貴重な遺構であるとのことで、1956年(昭和31年)に琉球政府から、1972年(昭和47年)復帰と同時に日本政府によって国の重要文化財に指定された。約280年の歴史をもつ民家。約1500平方mの敷地にシーサーをのせた赤瓦屋根の母屋、高倉、豚舎など5棟が建っている。中村家は当時豪農だった。中村家の先祖である賀氏(がうじ)は、護佐丸(中城城主)が読谷(本島中部)から城を中城に移した際に、築城の師としてこの地に移り住んだと伝えられている。古い沖縄の民家の建築様式で、人々の生活の様子がしのばれるのであった。「国指定重要文化財 中村家住宅」。門扉は開いていたが、この日は休館日となっていた。中に人の姿があったので、入っていったが結婚式前の「前撮り」が行われていたのであった。そこへ係の女性が現れ、今日は休館日なのでご遠慮くださいと。やむなく外に出て。門を入った正面突き当たりには「ヒンプン(屏風)」と呼ばれる石積みの目隠塀があり、中国の屏風門(ぴんふぉんめん)の琉球化したものであると。わざわざ目隠しをすることからも、一般庶民の住宅にない手法がここでもよくわかったのだ。この日の午前中に訪ねた「屋部の久護家」にもあった「ヒンプン(屏風)」なのであった。「中村家住宅 👈リンク中村家住宅は沖終本島中部の豪農の屋敷跡で、国指定第要文化財に指定されています。屋数地内には高倉や畜舎、井戸などが備えられておリ、当時の上層農家の生活を知ることができます。」。「中村家住宅」を後にして、県道146号線を下る。眼下に見えたのが「沖縄電力(株) 吉の浦火力発電所」。ここは石炭火力発電所ではないようであった。新たな埋立が不要で、大型LNGタンカーの着岸が可能であることから、新日本石油(後のENEOS)沖縄油槽所跡地が選定された。沖縄電力初のLNG(液化天然ガス)火力であり、初のコンバインドサイクル発電方式を導入した発電所となる。天然ガスの一部は都市ガス用として、2013年~2014年度をめどに沖縄ガスに供給されることが2009年に公表され、2015年8月12日に沖縄ガスへの供給を開始した。2012年6月に1号機が試運転を開始し、同年11月27日に営業運転を開始。2013年5月23日には2号機が運転を開始した。LNGは化石燃料の中で単位発熱量あたりのCO2発生量が最も少ない燃料。また、コンバインドサイクル方式はガスタービンと蒸気タービン両方で発電機を回すことから、従来の汽力発電方式(蒸気タービンのみの発電)と比べて発電効率が高く、より少ない燃料で同じ量の電気を作ることができるのだ。これらの特性から、吉の浦火力発電所の発電電力量(kWh)あたりのCO2排出量は沖縄電力の火力発電所の中で最も少なく、地理的・地形的な特性から火力発電に頼らざるを得ない沖縄電力にとって、温暖化対策の要の発電所と言えるようだ。LNGを貯蔵するために容量14万kLのタンク2基と、LNG輸送船が接岸するためのバース、LNGを陸上に運ぶ配管橋など約1350mの設備も確認できたのであった。そして次に訪ねたのが「護佐丸公之御墓」。この西側には以前に訪ねた「中城城跡」👈リンク がある場所。中頭郡中城村泊886。「護佐丸公之御墓」碑。石段を上がって行くと、中城城跡近くの台グスクと呼ばれる丘の麓にあった。1458年勝連按司「阿麻和利」を総大将とする王府に攻められた護佐丸一族党が、三男盛親を残し中城城で無念の死をとげた。謀反の疑いも晴れ1686年にその子孫毛氏豊見城家八代目盛定によって、王府から拝領した土地に建てられたものである。「毛國鼎護佐丸之墓」と刻まれた石柱。護佐丸(生年不詳-1458年)」は恩納村出身の15世紀に活躍した琉球王国(中山)の按司。大和名は中城按司護佐丸盛春(なかぐすくあじごさまるせいしゅん)、唐名は毛国鼎(もうこくてい)。1422年、第一尚氏王統の第2代国王となった「尚巴志」は二男「尚忠」を北山監守に任じ、「護佐丸」を読谷村の「座喜味城」に移して北山の統治体制を堅固にした。その後「護佐丸」は「座喜味城」に18年間居城し、中国や東南アジアとの海外交易で黎明期の第一尚氏王統の安定を経済的にも支えたのだと。次に訪ねたのが「沖縄成田山福泉寺」。最初に訪ねたのが「交通安全祈願の社」。中頭郡中城村伊舎堂617。「シーサー」(右)。「シーサー」(左)。「交通安全祈願所」の内陣。内陣には不動明王像が・・・。「参拝御案内成田山では、ご信徒の皆様の家内安全 商売繁盛 交通安全 開運厄除などのさまざまのお願いをすべて御護摩という法要儀式を通じご本尊≪不動明王≫に祈願しております。又、成田山のお守りはお不動様が御分体となって皆様方が災難にあわれるような時に皆様のみがわりになって災難をよけてくれますので「みがわりお守り」と言われております。」「水子地蔵尊」。「祖先霊供養 水子霊供養」と。「生目八幡大明神」近づいて。手前に「おかけ水」が。明神様のお顔に3度おかけし、自身や周りの人の目の健康をお祈りするとのこと。「人生の幸福は五体健全にして家庭円満なるに勝れるはなし 然るに種々の病に苦しむ人数知れず殊に生れながらにして明るい世界があたえられない者又不幸にして美しき両眼を失明され悲しみに暮れて居られる方あるいは眼悪く苦しみ淋しき人生を何の因縁因果か業かわからねど美観を感ぜず見る楽しみも出来ない方々多し 我が亡き母も其の類にもれず医術を尽くし種々の薬効の甲斐もなく遂に眼病治ゆすることなく遷化せり我もし力強く祈りて眼病治ゆせばとこゝに生目八幡大明神を建立し奉る 世の人々の不自由なる目に光明を授け賜らんことを祈ろう南無生目の神 影清く照らす生目の氷鏡 末の世までも曇らざりけり生前の母の目に捧げこゝに沖縄県民の目の不自由なる方々に生目の神の御利益があります様衷心より祈念する。」そして「沖縄成田山福泉寺」の「拝殿」が石段上に。成田山福泉寺は、沖縄県の中部、中頭郡中城村にある真言宗山派の大本山、成田山新勝寺(千葉県)を総府とした「成田山」の末寺です。交通安全、商売繁盛、学業成就、家内安全などの参詣はもちろんのこと、毎年、初詣でには多くの人が訪れる、沖縄中部で指折りの初詣スポットでもある と。再び「沖縄電力(株) 吉の浦火力発電所」。ズームして。左側に1号&2号ガスタービン建屋と煙突が。右側にLNGタンクが2基。LNG タンク概要・ 容 量:140,000kL・ 直 径:75.2m・ 側板高さ:31.8m PCLNGタンク方式が採用されている。従来の金属二重殻LNGタンクとPC (Prestressed Concrete)構造の防液堤を一体化している点が大きな特徴である と。「全景写真」をネットから。液化天然ガス(LNG:Liquefied Natural Gas)は、天然ガスを-162℃まで冷却し液化させたもの。液化すると体積が約600分の1になることで、タンクローリーや鉄道での輸送やタンクでの大量貯蔵が可能になる。なお、日本で供給されているLNGの大半は、海外から外航船で輸入されている。またLNGは、石炭や石油に比べて燃焼時のCO₂(二酸化炭素)や酸性雨や大気汚染の原因とされるNOx(窒素酸化物)の発生量が少なく、SOx(硫黄酸化物)とばいじんが発生しない、環境負荷の低いエネルギーとしても注目されているのである。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.11.02
閲覧総数 325
-
40

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その12):長雲閣こみち~神奈川県立美術館
「森山社」を後にして、県道207号線に向かって、葉山町一色の住宅街の道を進む。「長雲閣こみち」。長雲閣とは、総理大臣や陸軍大臣を歴任した、桂太郎氏の別荘のこと。日露戦争の前後には、政府要人たちが度々会議に使用したそうです。現在は、この小道に名前が残るのみ。古い時代に想いを馳せつつ、さらに進みます。「長雲閣こみち」。県道沿いのレストランの塀に「桂太郎別荘・長雲閣跡」の案内が掛かっていた。が、私が聞いた話では、県道から少々入った建物である。下の写真は、「長雲閣こみち」と、中央に建物が写っているが、その建物が、数年前まで桂太郎別荘とされていた。しかし地元歴史家よると、ここではなく、向かい側の建物がそうだと変更になったのだと。「桂太郎別荘跡」はここであっただろうか?日露戦争前後には、政府要人による重要会議が別荘を中心に度々開かれている。司馬遼太郎原作「坂の上の雲」でも「葉山会議」と称して登場している。そして再び県道207号線に出て北上する。左手にあったのが「神奈川県立近代美術館 葉山館」。奥にあったのが屋外にある常設展示。2003年の開館以来、一部作品の入れ替えや追加を経て、2016年に旧鎌倉館から移設された9点が加わり、現在は彫刻20点が庭園に、壁画2点が建物内に常設されている。葉山館のイラストマップ「彫刻はどこにいるの?」(館内無料配布)と一緒に、一色海岸に臨んだ庭園を散策しながら野外彫刻を楽しんだのであった。三浦郡葉山町一色2208−1。茶色の石材で。中島幹夫 NAKAJIMA Mikio『軌 09 Orbit 09』1966年館内では「吉田克郎展」が、開催されていた。「吉田克朗展 -ものに、風景に、世界に触れる」会期:2024年4月20日(土)〜6月30日(日)。武蔵野美術大学の教授だった美術家、吉田克朗の全貌に迫る初めての回顧展と。吉田克朗『触“春に”V』。これまでほとんど紹介されることのなかった作品や、さらに油彩から版画作品までを網羅し展示していると。県道沿いには幟が立っていた。駐車場の横にあったアルミニウム&大理石の作品。清水九兵衛 KIYOMIZU Kyuubei『BELT』1978年駐車場から「神奈川県立近代美術館 葉山館」を見る。小田 襄 ODA Jo『円柱の展開 Development of a Cylinder』1983年李 禹煥 LEE Ufan『項 Relatum』1985年「神奈川県立近代美術館 葉山館」入口。若林 奮『地表面の耐久性について』ホセイン・ゴルバ Hossein GOLBA(1956~)『愛の泉 Fountain of Love』イラン出身のホセイン・ゴルバの作品『愛の泉』。最初イタリアのチェレ彫刻公園の水飲み場として制作された。樹木の幹を鋳造、他の部分を蝋型で付加。「愛」の意味とは?「飲料水 Drinking Fountain右下のボタンを踏むと水が出ます」との案内も。水桶には二人の顔が。さらに葉山館だけの作者からの「おまけ」も足元に。強く踏むと、ボタンを踏んでいる足に水がかかるのであった。鈴木 昭男『「点音(おとだて)」プレート・葉山』2012年。『地平の幕舎』。鉄板でテントのような形を。鉄の赤錆がいい色を出していた。保田春彦 YASUDA Haruhiko『地平の幕舎』1993年『天地の恵み Blessings of the GOOD Earth』。眞板雅文 MAITA Masabumi『天地の恵み Blessings of the GOOD Earth』2003年『ハーモニーⅡ HarmonyⅡ』。波乗りジェーンって感じで。富樫 一 TOGASHI Hajime『ハーモニーⅡ HarmonyⅡ』1972年ここが先程訪ねた「葉山しおさい公園」からの連絡通路。「開門時間土曜日・日曜日・祝日の近代美術館開館日のみ午前10時30分~午後4時まで」「三ヶ岡遺跡神奈川県立近代美術館葉山の建設に伴い、この地にあった三ヶ岡遺跡が発掘調査され、主に古墳時代から平安時代(4 ~ 10世紀)にかけての集落の跡が発見されました。この遺跡で特筆されることは、海浜に立地する特徴を活かした平安時代の製塩跡が見つかったことです。ムラの跡 竪穴住居が22軒、掘立柱建物が1棟密集して発見されました。ほとんどが6 ~ 7世紀のもので、継続して居住していたことがわかりました。製塩跡 約2X6mの範囲に火を受けて赤く硬くなった地面があり、そのそばから多量の土器が打ち捨てられたままに出土しました。また海水を煮詰めるためのものか、石組炉の跡も2基発見されています。」「製塩跡」と「竪穴住居跡」。『イノセンス-火 Innocence:Fire』。西雅秋 NISHI Masaaki『イノセンス-火 Innocence:Fire』1991年西雅秋『大地の雌型より』2003-5年葉山漁港の4隻の木造船にコンクリートを流し込み、ひっくりかえして木部を外したもの。「一色海岸」を望む。西雅秋『大地の雌型より』の一部。アントニー・ゴームリー『Insider Ⅶ』1998年山口牧生 YAMAGUCHI Makio『棒状の石あるいはCosmic Nucleus aBar of Stone,or Cosmic Nucleus』1976年『揺藻(ゆれも) Swaying Alga』。空 充秋 SORA Mitsuaki『揺藻(ゆれも) Swaying Alga』1985年湯村光『Stone Work – Stream』1987年柳原義達(1910~2004) YANAGIHARA Yoshitatsu『裸婦 座る Sitting Nude』原型 1956年(鋳造 1964年以前)『こけし Kokeshis(Japanese Wooden Dolls)』。近づいて。イサム・ノグチ(1904-1988)は、日本人の父とアメリカ人の母の間に生まれた、20世紀を代表する世界的な彫刻家。彫刻はもちろん庭園や舞台芸術、家具そして照明のテザインも手がけるなど、現代彫刻の可能性を大きく押し広げ、作品と活動を通して世界各地て愛されつづけている芸術家である と。イサム・ノグチ Isamu NOGUCHI『こけし Kokeshis(Japanese Wooden Dolls)』1951年『石人 Stone Man』1966年(古墳時代6世紀後半の扁平石人の複製(岩戸山古墳[福岡県]出土・現在大分県日田市に設置)イサム・ノグチ Isamu NOGUCHI『こけし Kokeshis(Japanese Wooden Dolls)』を振り返って。これは、展示物ではなく、石製の休憩場所のようであった。「レストラン オランジュ・ブルー」。イサム・ノグチの作品を別の場所からも。最後に「神奈川県立近代美術館 葉山館」を再び振り返って。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.22
閲覧総数 833
-
41

浅草を歩く(その2):浅草寺-2・浅草寺歴史案内板~宝蔵門~五重塔
さらに「宝蔵門」に向かって進む。左側には、提灯が並ぶ。「浅草寺のご本尊は聖観世音菩薩さまです。お参りの時は、合掌して『南無観世音菩薩』とお唱えしましょう 金龍山浅草寺」 浅草、浅草寺の歴史についての案内板が並んでいた。「一、浅草のあけぼの浅草は利根川・荒川・人間川が運ぶ上砂の堆積によって作られた。古墳時代末期に人々が住んでいたことは、浅草の本坊・伝法院(でんぽういん)に残る「石棺」が示している。この東京湾に面した浅草は、はじめ漁民と農民の暮らす小さな村であったろうが、やがて隅田川舟運による交通の要衝として、また、観音様の示現による霊地として歴史的あけぼのを迎えるのである。二、ご本尊の示現「浅草寺縁起」によれば、推古天皇三十六年(六ニ八)三月十八日の早朝、隅田川(当時の宮戸川)で魚を捕る檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)兄弟が一躰の仏像を感得した。三、浅草寺の草創ニ人の漁師が感得した仏を郷司の土師中知(はじのなかとも。名前には諸説ある)に示した処、聖観世音菩薩像とわかった。そこて、この兄弟は深く帰依し、中知は自ら出家し、自宅を寺に改めて尊像を祀ったのが淺草寺の始まりである。この三人を祀ったのが「浅草神社(三社さま)」である。一方、そうした縁起とは別に、十人の童子がアカザという草で堂を建てたという伝承もあった。四、慈覚大師中興の開山となるご本尊が示現して十七年後、大化元年に勝海上人(しようかいしようにん)が浅草寺に来られ、観音堂を建立し、ご本尊を秘仏と定めた(秘仏の由来)。その後、天安元年(八五七)慈覚大師円仁(えんにん)が比叡山(天台宗の総本山)より来寺し、ご秘仏に代わる本尊ならびに「御影版木(みえいのはんぎ)」を謹刻された。板木が作られたことは、参拝者が増えてきたことを物語るものだろう。五、平公雅堂塔伽藍を建立平安時代中期、天慶五年(九四ニ)安房の国守であった平公雅は京に帰る途次、浅草寺に参拝した。その折、次は武蔵の国守に任ぜられるように祈願した処、その願いがかなったことから、そのお礼に堂塔、伽藍を再建し、田地数百町を寄進したと伝える。その伽藍に法華堂と常行堂の二堂があったことから浅草寺が天台宗の法の流れに属していたことが知られる。」 六、源頼朝の参詣治承四年(一一八○)、源頼朝は平家追討に向かうため浅草の石浜に軍勢を揃えた際、浅草寺に参詣して戦勝を祈った。やがて鎌倉に幕府を開いた後も 信仰を寄せた。鎌倉鶴岡八幡宮造営に際しては浅草から宮大工を召している。このように武将や文人らの信仰を集めた浅草寺の霊名は次第に全国に広まっていった。七、徳川将軍の篤い保護天正十八年(一五九〇)江戸に入った徳川家康は天海僧正の勧めで浅草寺を祈願所と定め、寺領五百石を寄進した。元和四年(一六一ハ)には家康を祀る「東照宮」の造営を認め、随身門(現、ニ天門)も建立されるなど浅草寺への信任は篤かった。寛永年間に観音堂が炎上した際も徳川家光により慶安ニ年(一六四九)再建された。以後、関東大震災にも倒壊せす、国宝観音堂として参詣者を迎えた。だが、昭和ニ〇年の東京大空襲により焼失、現在の本堂は昭和三十三年に再建された。八、江戸時代 境内と奥山の賑わい江戸の繁栄とともに浅草寺の参詣者も増え、やがて江戸随一の盛り場となった。江戸文化の最盛期、境内には百数十の神仏の祠堂(しどう)が建ち並ぶ庶民信仰の聖地となる一方、奥山では松井源水のコマ廻し、長井兵助の居合抜き、のぞきからくり、辻講釈などの大同芸や見世物が参詣者を喜ばせ、水茶屋・揚枝店・矢場(やば)なども立ち並んだのである。さらに春の節分をはじめ季節の行事は大変な賑わいを呈した。明治に人って、浅草寺の境内地は「浅草公園」となり、その第六区が興行街となって日本の映画史、演劇史の上に大きな足跡を残した。同十五年鉄道馬車が開通、同ニ十三年には浅草一帯を眠下に望む「十ニ階」が開業されるなど、浅草は文明開化のさきがけを誇った。九、浅草寺の寺舞(じまい)戦後、東京の復興は浅草の復興でもあり、地元の祈りでもあった。昭和三十三年に本堂が再建されたことを記念して「金龍の舞(きんりゅうのまい)」、昭和三十九年には宝蔵門(旧仁王門)の落慶記念に「福聚宝の舞(ふくじゅたからのまい)、昭和四十三年には東京百年祭を記念して「白鷺の舞(しらさぎのまい)が、それぞれ浅草寺縁起や浅草芝居の由来を受けて創作され、縁日に奉演されている。「浅草名所七福神日本の福神信夘は室町時代に恵比寿・大黒天をはじめとして、商業の盛んな京都方面で発達しました。その数は次第に増えて七福神となりましたが、当初、その顔ぶれは一定ではありませんでした。七という数の根拠には諸説ありますが、一種の聖数と考えられます。京都を中心に盛んとなった七福神信仰ですが、七福神すべてを巡拝する風習は十八世紀末~十九世紀初めに江戸で成立しました。江戸名所七福神も江戸では有名でしたが戦後に中断し、一九七七年(昭和五十ニ年)に再興されて今日に至るものです。なお、福神の働き(ご利益)は次の通りです。恵比寿 漁労・商売の守護。大黒天 五穀豊穰(食物) 出世を司る神。弁財天 知恵・音楽・財福を司る神。毘沙門天 四天王の一つ。 財宝・勇気・決断を司る神。福禄寿 幸運・生活の安定 長寿を司る神。寿老人 延命長寿を司る神。福禄寿 と同一とする場合もある。布袋尊 弥勒菩謹の化身とされる人神。 福徳・家庭円満を司る神。浅草名所七福神 浅草寺 大黒天 浅草神社 恵比須神 待乳山聖天 毘沙門天 今戸神社 福禄寿 不動院 布袋尊 石浜神社 寿老神 鷲神社 寿老人 吉原神社 弁財天 矢先神社 福禄寿」 そして正面に「宝蔵門」が大きく見えて来た。「浅草観光案内図」と「浅草の観光行事」 。「宝蔵門」。「宝蔵門 台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺宝蔵門は、大谷米太郎 の寄進で、昭和三十九年に浅草寺宝物の収蔵庫を兼ねた山門として建てられた。鉄筋コンクリート造で重層の楼門である。外観は旧山門と同様に、江戸時代初期の様式を基準に設計されている。高さ二十一・七メートルある。下層の正面左右には、錦戸新観、村岡久作の制作による、木造仁王像を安置している。浅草寺山門の創建は、「浅草寺縁起」によると、天慶五年(九四二)、平公雅によると伝える。仁王像を安置していることから仁王門とも呼ばれる。その後、焼失と再建をくり返し、慶安二年(一六四九)に再建された山門は、入母屋造、本瓦葺の楼門で、昭和二十年の空襲 で焼失するまでその威容を誇っていた。 平成十八年三月 台東区教育委員会」 雷門をくぐり、人通り賑やかな仲見世を歩いてゆくと、前方に堂々たる朱塗りの楼門が参拝者を迎える。浅草寺山門の宝蔵門である。門は初層が五間で、両端の二間には仁王像を奉安し、中央の三間が通行のために開口している。仁王像が安置されていることからもわかるように、この門はもともと仁王門と呼ばれていた。『浅草寺縁起』によれば、平公雅が天慶5年(942)に武蔵守に補任され、その祈願成就の御礼として仁王門を建立したのが創建という。以来、数度の焼失と再建ののち、徳川家光の寄進により慶安2年(1649)に落慶した仁王門が、昭和20年まで諸人を迎えていた。今に伝わる錦絵の数々に描かれた仁王門は慶安の門である。昭和20年(1945)、仁王門は東京大空襲により観音堂・五重塔・経蔵などとともに焼失する。昭和39年(1964)に大谷重工業社長・大谷米太郎ご夫妻の寄進により、鉄筋コンクリート造り、本瓦葺きで再建された。経蔵を兼ねて伝来の経典や寺宝を収蔵することから、仁王門から宝蔵門と改称された。宝蔵門に収蔵されている経典とは、「元版一切経(国の重要文化財)」である。もとは鎌倉の鶴岡八幡宮に収蔵されていたものであるが、明治の神仏分離の際にあわや焼却処分されるところを、浅草寺に深く帰依していた尼僧の貞運尼が買い取り、浅草寺に奉納したという由緒をもつ。この「元版一切経」を鎌倉から浅草まで運ぶ際に助力したのが、町火消し十番組の組頭・新門辰五郎である。境内にあった新門の門番を務めたことから新門と名乗り、安政年間(1854~60)に浅草寺の経蔵を寄進している。戦災で経蔵は焼失したが「元版一切経」は疎開しており無事だった。宝蔵門は篤信の人びとに守られた宝物とともに、多くの参拝者の安寧を見守っている。「浅草寺」額京都・曼殊院門跡の良尚法親王筆の模写 と。「小舟町」と書かれた「大提灯」。高さ 3.75m・幅 2.7m、重さ 450kg。 日本橋小舟町奉賛会より平成26年(2014)10月奉納掛け換え(4回目)。「吊灯籠」 高さ 2.75m、重さ 1.000kg 銅製。 魚がし講より昭和63年(1988)10月奉納掛け換え(2回目)仁王尊像(木曾檜造り 重さ 各約1,000kg)「阿形像」 ネットから。「仁王様(阿行)昭和39年(1964)に、現在の宝蔵門の再建に際し、仏師の錦戸新親氏によって制作された。総高5. 4 5メートル、重さ約10 0 0キログラム、木會檜造りである。仁王さまのご縁日は8日。身体健全、災厄除けの守護神であり、所持している金剛杵は、すべての煩悩を破る菩提心の象徴である。この仁工さまは、宝蔵門にあって、日々参詣諸人をお迎えし、人々をお守りしている。」 「仁王様(吽行)ネットから。「仁王様(吽行)昭和39年(1964)に、現在の宝蔵門の再建に際し、仏師の村岡久作氏によって制作された。総高5. 4 5メートル、重さ約1000キログラム、木會檜造りである。仁王さまのご縁日は8日。身体健全、災厄除けの守護神であり、所持している金剛杵は、すべての煩悩を破る菩提心の象徴である。この仁工さまは、宝蔵門にあって、日々参詣諸人をお迎えし、人々をお守りしている。」 「五重塔」 日本で最も有名な五重塔のひとつが、浅草寺の境内にある五重塔。その高さは約53.32mで、ビルでいうと15~20階だてに相当します。浅草の五重塔は西暦942年に建てられたと言われています。江戸時代には寛永寺、池上本門寺、芝増上寺にある五重塔と合わせて「江戸四塔」と呼ばれ親しまれてきましたが、太平洋戦争の時の空襲で一度焼失してしまいました。いまの五重塔は焼失した後に場所を改めて建て直したものです。現在元の場所には石碑が建っています。五重塔の先端にあるのは「相輪」と呼ばれる金属製の装飾。これは、露盤、伏鉢、請花、九輪、水煙、竜舎、宝珠などが組み合わさったもので、上部に位置する「宝珠」が最先端にある。「相輪」案内図。 上から順に宝珠:仏舎利(釈迦の骨)が納められる。竜舎:奈良時代から平安時代の高貴な者の乗り物水煙:火炎の透し彫り。火は、木造の建築物が火災に繋がるため嫌われ、水煙と呼ばれる。 お釈迦様が火葬されたことをあらわす。九輪(宝輪):五智如来と四菩薩を表す。9つの輪からなる[注釈 1]。受花(請花):飾り台。蓮華の花。伏鉢(覆鉢):鉢を伏せた形をした盛り土形の墓、ストゥーパ形。お墓を表している。露盤:伏鉢の土台。宝珠は仏舎利が納められるため、最も重要とされる。 なお、中心を貫く棒は「擦」(または「刹管」)と呼ばれる。 また、仏舎利は塔の中に安置されていることもある。そしてこちらは「東京スカイツリー」の最上部をズームして。 正面に「浅草寺 本堂」。 「宝蔵門」を「本堂」側から見る。 「大わらじ高さ 4.5m・幅 1.5m、重さ 500kg、藁 2,500kg使用。山形県村山市有志より平成30年(2018)10月奉納〔昭和16年(1941)の初回以来、8回目〕わらじは仁王さまのお力を表し、「この様な大きなわらじを履くものがこの寺を守っているのか」と驚いて魔が去っていくといわれている。」 右側。左側。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.13
閲覧総数 193
-
42

浅草を歩く(その5):浅草寺-5・弁天山 扇塚~松尾芭蕉の句碑~時の鐘~弁天堂~普閑の歌碑~添田啞蝉坊碑・添田知道筆塚~都々逸塚碑~地蔵菩薩像 阿弥陀如来像~旧五十重塔跡~旧仁王門礎石~神木~二天門
「浅草寺」の散策を続ける。 次に訪ねたのが、石段の上にあった「弁天堂」。本堂南東にある小高い丘は、弁財天を祀る弁天堂が建つことから弁天山と呼ばれる。弁財天は池中の小島に祀られることが多いが、弁天山もかつては池の中にあった。現在、池は埋め立てられて公園となっている。弁財天は七福神のなかの唯一の女神である。弁天堂のご本尊は白髪であるため、「老女弁天」と通称されている。この弁財天は神奈川県藤沢市の江ノ島弁天、千葉県柏市の布施弁天と並んで「関東の三弁天」として名高い。弁財天は、十二支の「巳の日」が縁日で、この日は弁天堂の扉が開かれて法要が営まれる と。 「扇塚」碑。浅草寺境内の弁天山に、二代花柳徳太郎師が建立した「扇塚」があった。日本舞踊では扇子をよく使うが、「扇塚」は古くなり、使えなくなった扇子に感謝し、供養するところ。 一年に一度、初代から四代(現在)花柳徳太郎ゆかりの人たちが集まって、扇の供養をしている と。「君諱徳太郎田代氏 明治十一年七月十一日浅草に生る 六歳叔父初代寿輔の養子となり 其薫陶を受く 同二十四年十三歳西郷邸に於て英照皇太后御前舞踊鶴亀を演ず 同三十六年初代寿輔歿後大正十二年迄花柳家元を継承 同三十八年柳櫻会創立公演九十八回に及ぶ 大正七年初代寿輔嗣子芳三郎に家元を譲り大正十二年自ら分家家元となり 昭和三十四年十一月三日多年舞踊界に盡瘁せる功に依り紫綬褒賞を授与せらる 同三十八年一月十二日歿す 享年八十六歳安隆院達道寿徳居士と諡して深川増林寺に葬る 二代徳太郎故人の遺志に依り茲に此碑を建つ 昭和三十九年四月 二代花柳徳太郎 蘭垌 野田朗書」と刻まれているとネットから。「扇入 泉徳右衛門」と刻まれた石箱。職業 日本舞踊家肩書 泉流家元(初代)本名 田代 民平生年月日 大正13年 4月13日経歴 幼少時より父母に師事。昭和15年泉流を創設、初代家元となる。古典の他、 創作舞踊に取り組み、軽妙、酒脱な芸風で高度な芸境を示した。代表作に 「あたま山」「芸阿呆」がある。所属団体 日本舞踊協会受賞 紫綬褒章〔平成1年〕 芸術祭賞優秀賞〔昭和45年 47年 48年 50年 51年 52年 53年 55年〕、舞踊批評家協会賞〔昭和55年〕、花柳寿応賞(第12回)〔昭和57年〕、 舞踊芸術賞〔昭和61年〕没年月日 平成3年 10月29日 (1991年)家族 父=花柳 徳太郎(初代)、母=花柳 徳太郎(2代目)、妻=泉 摩津枝(舞踊家)、 長女=泉 徳右衛門(2代目)「松尾芭蕉の句碑」。 「くわんをん(観音)の いらか見やりつ 花の雲 はせを」と。 「松尾芭蕉の句碑くわんをんの いらか見やりつ 花の雲 はせを俳諧紀行文『奥の継道』などを著した松尾色蕉は、寬永二十一年(一六四四)伊賀上野(現、三重県上野市)に生れました。芭蕉という俳号は、深川の小名木川ほとりの俳諧の道場「泊船堂」に、門人が芭蕉一枚をえたことに由来します。独自の蕉風を開き「俳諧芭蕉」の異名をとった松尾芭蕉は、元禄七年(一六九四)十月十二日、大坂の旅舎で五十一年の生涯を閉じました。この句碑は寛政八年(一七九六)十月十二日、芭蕉の.一〇三回忌に建立され、元は浅草本堂の北西、銭塚不動の近くにありましたが'戦後この地に移建されました。八十三歳泰松堂の書に加えて、芭蕉のスケッチを得意とした、佐脇嵩雪が描いた芭蕉の座像が線刻してありますが、二百年の風雪を経て、碑石も欠損し、碑面の判読も困難となっております。奥山庭園にある、『三匠句碑」(花の雲 鐘は上野か 浅草か)と共に、奇しくも「花の雲」という季語が詠みこまれております。平成二年四月吉日 浅草観光連盟」 石段を上りきると右側にあったのが「時の鐘」。 「時の鐘」をズームして。「時の鐘(浅草寺) 台東区浅草二丁日三番江戸時代、人々に時刻を知らせる役割を果たしていたのが時の鐘である。当初、江戸城内にあったが、江戸市街地の拡大にともない日本橋本石町にも設置され、さらには浅草寺や寛永寺(上野山内)など、九個所でも時を知らせた。鐘の大きさは、高さ二・一二メートル、直径一・五二メートル。鐘銘によれば、撰文は浅草寺別当権僧正宣存で、元禄五年(一六九二)八月、五代将軍徳川綱吉の命により、深川住の太田近江大掾藤原正次が改鋳し、その費用として下総(現、千葉県)関宿藩主牧野備後守成貞か黄金二百両を寄進した。この鐘は、時の鐘として、あるいは浅草寺の梵鐘として、さまざまな文学作品にも登場しているが、中でも松尾芭蕉の句花の雲 鐘は上野か 浅草かは、あまりにも有名である。昭和二十年三月の東京大空襲で火を浴びたが無事に残り、今なお昔のままの姿を見せている。なお、鐘楼は同空襲で焼け落ち、昭和二十五年五月再建されたものである。 平成十一年三月 台東区教育委員会」 そして正面に「弁天堂」。 「弁天堂弁天山と呼ばれる小丘の上に立つこのお堂は、昭和五十八年に再建されたもの。ご本尊は白髪のため「老女弁財天」といわれる。関東三弁天(神奈川県江ノ島・千葉県柏市布施と合わせ)の一つとされ、小田原北条氏の信仰が篤かった。境内の鐘椄の鐘は、元禄五年(一六九二)五代将軍徳川綱吉公改鋳の江戸時代の「時の鐘」として、芭蕉の句『花の雲 鐘は上野か 浅草か』で有名。現在は、毎朝六時に役僧が撞き鳴らし、大晦日には「除夜の鐘」が点打される。弁財天さまのご縁日は、「巳の日」で、堂内にてお参りができる。 金龍山浅草寺」 「弁天堂」の手前左にあった石碑は「普閑の歌碑」。「かかるとはおもひさだめし・・・」の歌を刻んでいる と。(浅草大百科より)。嘉永5(1852)年の建立。 「聖観音真言梵字の碑」 新吉原の山口巴屋が天保8(1837)年に奉納した碑。「上部に聖観音の種字「サの字」。中部にオン・アロリ・キヤ・ソワカ・ボロン。下部に弥陀の種字キリーク」(浅草大百科より引用)再び「弁天堂」。手を合わせる和服姿の女性は日本人!? 「添田啞蝉坊碑・添田知道筆塚」。「添田啞蝉坊碑・添田知道筆塚建碑 唖蝉坊碑 昭和三十年十一月二十八日 筆 塚 昭和五十七年三月七日添田唖蝉坊 本名・平吉 筆名は唖蝉坊のほか不知山人、のむき山人、凡人など。神奈川県大磯に生まれる。 昭和19年(1944)2月8日歿。享年73歳。明治20年代の壮士節の世界に入り、のち演歌の作詞、 作曲、演奏に従事。作品は「四季の歌」「ストライキ節」「ラッパ節」「ああ金の世」 「金色夜叉の歌」「むらさき節」「奈良丸くづし」「マックロ節」「青島節」「ノンキ節」 「生活戦線異状あり」など。著書に「浅草底流記」「唖蝉坊流生記」「流行歌明治大正正史」 ほか。添田知道 唖蝉坊の長男。東京出身。昭和55年(1980)3月18日歿。享年77歳。父唖蝉坊とともに演歌の 作詞、作曲に従事したあと作家活動に入る。筆名は知道のほか、さっき、吐蒙。演歌作品に 「東京節」「復興節」「ストトン節」など。著書に新潮文芸賞受賞の長編小説「教育者」 「利根川随歩」「演歌の明治大正史」などがある。 浅草の会」 「情歌二六号 都々逸塚 亀屋忠兵衛」碑。明治百年を記念して1967年(昭和42)に建立された。亀屋忠兵衛と刻まれている。亀屋忠兵衛は都々逸作家で、1962年(昭和37)に『都々逸下町 亀屋忠兵衛情歌集』を出版している。都々逸(どどいつ)とは、江戸末期に初代の都々逸坊扇歌(1804年-1852年)によって大成された口語による定型詩。七・七・七・五の音数律に従う。・立てば芍薬 坐れば牡丹 歩く姿は 百合の花(作者不詳)・人の恋路を 邪魔する奴は 馬に蹴られて 死んじまえ(作者不詳) が有名だが。弁天山を下りて浅草神社方向に進む。「浅草寺」の「宝蔵門」、「五重塔」は左手奥に。 次に訪ねたのが「二尊仏」の裏側にあった「地蔵菩薩像 阿弥陀如来像」。 中央 地蔵菩薩像。右 阿弥陀如来像。左 阿弥陀如来像。「地蔵菩薩像 阿弥陀如来像中央にお地蔵さま、左右には阿弥陀さまが奉安されている。中央のお地蔵さまは、我々衆生を苦しみから救ってくださる仏さま。左右に奉安される阿弥陀さまは、西方極楽浄土にあって無量の智慧と慈悲の光で我々衆生を救済してくださる仏さま。この三体の仏さまは、江戸時代より穏やかに我々を見守られている。右 阿弥陀如来像 寛文十一年(一六七一)造立中央 地蔵菩薩像 享保十一年(一七二六)造立左 阿弥陀如来像 延宝五年(一六七七)造立 金龍山浅草寺」 北に進むと、左手に再び藤棚が。その先、右手にあったのが「旧五十重塔跡」碑。旧国宝浅草寺五重塔は、本堂東南に位置し、塔内には、宝勝(ほうしょう)、妙色(みょうしょく)、広博(こうはく)、甘露(かんろ)、離怖畏(りふい)の、五智如来尊像が安置されていました。この塔は、上野寛永寺、芝増上寺、谷中天王寺の五重塔と並んで「江戸四塔」のひとつに数えられ、長きに渡って人々に親しまれましたが、昭和20年(1945)3月14日の東京大空襲によって焼失しました と。「旧五十重塔跡五重塔とは、仏舎利(釈迦の遺骨)を奉安する仏塔の一つで、古くから寺院に建立されてきた。この場所は、江戸時代の慶安元年(一六四八)、徳川家光 によって再建された旧国宝の五重塔(木造・高さ三十三メートル)が建立されていた場所で、現在の五重塔とは反対側に位置していた。浅草寺の五重塔は、天慶五年(九四二)平公雅 により創建され、その後いく度か炎上するもその都度再建されている。江戸時代、家光再建の五重塔は、上野寛永寺・谷中の天王寺・芝の増上寺の塔とともに「江戸四塔」として親しまれていた。また、歌川広重 ・歌川国芳 などの浮世絵 の格好の画題としても全国に知られ、朱塗り・碧瓦(未申にあたる裏鬼門の方角の第三層には、羊角猿面の鬼瓦が葺かれる)の美しい姿を見せていたが、昭和二十年(一九四五)の戦災で惜しくも焼失した。 金龍山 浅草寺」 この場所◯にあったと、ネットから。「東京百景 浅草公園」。 旧五重塔の写真。明治時代・一九〇七年前後の写真。「旧仁王門礎石」 三個の巨大石が並んでいた。近づいて。「旧仁王門礎石慶安二年(一六四九)十二月二十三日、旧本堂と共に三代将軍徳川家光公により、再建落慶した旧仁王門(国宝指定現宝蔵門と同規模)は、三百年間浅草寺山門として江戸・明治・大正・昭和と時代の変遷を見つめ、文学、絵画、芸能など往時の文化にたびたび登場してまいりましたが、残念ながら昭和二十年(一九四五)三月十日の東京大空襲により本堂・五重塔(家光公建立・国宝)と共に炎上焼失いたしました。その後、現本堂に続き昭和三十九年(一九六四)四月一日、仁王門を宝蔵門と改めて同跡地に再建されました。この三つの大石は宝蔵門再建に際して旧仁王門の跡地より昭和三十七年二月六日に掘出された礎石です。旧仁王門には十八本の大木柱があり、それそれに基礎石がありましたが、戦火に遭い、ひび割れ破損し、原型をとどめる大礎石三個を選び保存しました。石材は「本小松石」で上端の仕上げ面は約一・二m角、柱受けのホゾ穴があり、最大幅は約一・四m角、高さ約一m。この礎石の下部と周囲は十~十五cm径の玉石と粘土で突き固められていました。江戸の人々の息吹を感じると共に、平和を祈る記念碑として受継ぎたいと存じます。 浅草寺」 「宝蔵門」と「五重塔」。 「浅草寺の神木・いちょう」。 「浅草寺の神木・いちょう浅草寺本堂東南に位置するこのいちょうは、源頼朝公が浅草寺参拝の折、挿した枝から発芽したと伝えられる。昭和五年に当時の文部省より天然記念物に指定されたが、昭和ニ十年三月十日の戦災で大半を焼失した。今は天然記念物の指定は取り消されたが、あの戦災をくくり抜けた神木として、今も多くの人々に暮われている。 金龍山 浅草寺」 「五重塔 展望 地点」と。 近づいて。ここからの写真を。右奥にあったのが「浅草 二天門」。本堂の東に建つ朱塗りの門で、今の門は慶安2年(1649)に浅草寺の東門として創建された。当初は随身門といわれ、豊岩間戸命、櫛岩間戸命を守護神像(随身像)として左右に祀っていた。明治17年(1884)、神仏分離によって随身門に安置されていた随身像は、浅草神社に遷座されて、鎌倉の鶴岡八幡宮から広目天と持国天の像が奉納された。このとき名称を随身門から二天門と改めた。この二天の像は、昭和20年(1945)に修理先で戦災にあって惜しくも焼失し、現在の持国・増長の二天像は、昭和32年(1957)に上野・寛永寺の厳有院(四代将軍徳川家綱霊廟)から拝領した像。門に向かって右が持国天、左が増長天である。二天門は境内に残る江戸時代初期の古建築として貴重であり、国の重要文化財に指定されている。平成22年(2010)に改修を終え、創建当初の鮮やかな姿によみがえった。表側から。この二天門は、慶安2年(1649)頃に浅草寺の東門として建立されたようであるが、江戸時代を通じて浅草寺観音堂の西側に建てられた東照宮の随身門と伝えられ、随身像が安置されていた。なお浅草寺の東照宮は元和4年(1618)に建立されたが、寛永8年(1631)と同19年の火災によって浅草寺の他の諸堂とともに焼失し、その後東照宮は江戸城内の紅葉山に移された。明治初年の神仏分離令によって門に安置された随身像は、仏教を守護する四天王のうち持国天増長天の二天像に変わり、名称も二天門と改称した。現在安置されている二天像は、京都七条の仏師、吉田兵部が江戸時代初期(17世紀後半)に制作したもので(東京都指定有形文化財)、昭和32年に寛永寺巌有院殿(四代将軍徳川家綱)霊廟の勅使門から移されたものである。二天門は昭和25年、国指定重要文化財に指定された。 平成23年3月 台東区教育委員会」 「増長天(左)・持国天(右)(江戸時代前期・吉田兵部藤房作・都重宝)」 (ネットから)。増長天(左)。持国天(右)。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.16
閲覧総数 150
-
43

我が菜園の朝顔の花
我が家の横の菜園に咲く朝顔の花です。名前の通り夏の朝に咲く花、朝顔。日本で古くから親しまれている花ですが、薬草として中国から伝わったのが始まりと言われています。江戸時代には愛好家によって品種改良が進み、観賞用として栽培されるようになりました。大輪朝顔などの人気はこのころから出始めました。鉢植えで育てることができる朝顔ですが、品種によってはグリーンカーテンとしてネットに這わせて楽しむこともできるのです。朝に咲くことから朝顔という名前が付けられましたが、朝の何時ごろに咲くかご存知ですか?日の出が関係しているように思われますが、実は、朝顔が咲く時間は前日の日没の約10時間後と言われています。夏至のころには朝顔が咲く時間は遅くなり、冬至に近づくほど日没が早まるので、朝顔の開花時間も早まります。さらに、朝顔をじっと観察すると、成長の仕方が一方向であることに気づきます。右巻きか左巻きか、ご存知でしょうか? 朝顔のツルは右巻きで生長していきます。右巻きか左巻きかは横から見て判断するので、ややこしいのですが、真上から見ると左回りに成長していきます。これは遺伝的に決まっているものだそうです。これは、大輪で美しい星咲きの花。花の中心から放射状に延びた白いすじが星のように見えるかわいらしいアサガオ。花は最大で直径10~13cmと大輪で見応えがあります。右側には、透き通るような青紫の花を咲かせる西洋大輪アサガオ。ズームして。中心は白から黄色にグラデーション。鮮やかな赤紫〜濃紫の花色。花弁の縁に白い覆輪(ふちどり)があり、華やかな印象。中心部は淡い桃色から白にグラデーションし、放射状の筋が強調されて。園芸品種によく見られる「縁取り咲き」や「絞り咲き」の変化朝顔の一種。純白の朝顔の大輪。ズームして。左の花:淡い藤色〜白に近い薄紫で、中心にかけてほんのり赤みを帯びたグラデーション。右の花:濃い紫色で、ほぼ黒に近い深い色合い。同じ株でも色合いが大きく異なる花をつけることがあり、これも「変化朝顔」や交配品種の特徴のひとつです。写真ではすでにしおれかけている花も見え、アサガオ特有の「朝に咲いて昼にしぼむ」一日花の性質が現れていたのです。「絞り咲き(しぼりざき)」と呼ばれるタイプ。紫を基調とし、白い筋や斑(まだら模様)が放射状に入っている。一枚ごとに模様の出方が異なり、まるで絵筆で描いたような芸術的な風合い。花の中心は白く抜けて、淡いグラデーションが広がっている。江戸時代の「変化朝顔」ブームでも人気が高かった咲き方。青空に映えて。中心から放射状に紫の筋模様が広がっています。紫の筋は太さや濃淡が不規則で、手描きの筆跡のように個性があります。花の中心は淡いピンクを帯び、白から紫へのグラデーションが美しい。絞り模様の入り方は一輪ごとに違うため、毎日異なる表情を見せてくれるのです。そしてこれは?アサガオではありません。これは、「花オクラ」。花オクラ(別名:トロロアオイ)は、その名の通り花を食べるエディブルフラワー(食用花)で、一般的なオクラのようなサヤではなく、淡白でオクラに似た風味と粘り気のある食感が特徴。生でサラダや和え物にするとシャキシャキした食感が楽しめ、加熱すると粘り気が増してとろりとした食感になるのです。見た目も美しく、おひたし、酢の物、天ぷらなど、幅広い料理で楽しめるのです。近づいて。オクラとよく似た美しいレモンイエローの花を咲かせる「花オクラ」。■おひたし美しい色合いを活かしておひたしにするのも定番。酢を加えたお湯でゆでると鮮やかな色を保ちやすい。加熱するととろりとした粘り気が強くなるので、オクラに似た食感も楽しめます!できたてをすし酢をかけて食べるのはもちろん、冷やして食べてもおいしいのです。■天ぷら花オクラの天ぷらもぜひ味わってみてほしい一品。花に薄く衣をつけさっと揚げましょう。花びらを一枚ずつ揚げてもよいですし、つぼみをそのまま揚げても大丈夫。サクサクの衣と粘り気のある花オクラのもっちりとした食感の違いが楽しい。ほんのりと苦味があり、オクラ特有の香りも。最後に朝顔の花が昔から日本人に愛されている理由を調べてみました。朝顔(アサガオ)は、奈良時代に中国から薬草として伝来し、平安時代以降は観賞用として日本人に広く親しまれるようになりました。日本文化に根付いた理由はいくつかあるようです。1. 花の特徴と日本人の感性・清らかさと儚さ 朝に咲き、昼にはしぼむ一日花。短い時間に鮮やかに咲く姿は、日本人が大切にする 「もののあはれ」「はかなさの美」と深く共鳴しました。・鮮やかな色彩 青・紫・桃色などの涼やかな花色は、夏の暑さの中に清涼感を与え、視覚的にも人々を 惹きつけました。2. 生活文化との結びつき・江戸時代の園芸ブーム 江戸庶民の間で「変化朝顔(葉や花びらが珍しい形になるもの)」の栽培が流行。 見世物的な人気もあり、浮世絵や瓦版でも盛んに取り上げられました。・夏の風物詩 朝顔市(入谷・駒込など)が江戸から現代にまで続いており、鉢植えを縁側に置き、 行燈仕立てで涼を呼ぶ光景が「夏の日本らしさ」を象徴。3. 文学や芸術への影響・和歌・俳句に詠まれる題材 例:「朝顔に釣瓶取られてもらひ水」(加賀千代女)など、身近な暮らしとともに詠まれました。・意匠としての利用 着物や団扇、屏風などの模様として広く使われ、夏を表す典型的な文様となりました。4. 象徴的な意味・儚い命の象徴 → 無常観や「一期一会」の精神と通じる。・愛情・絆の象徴 → つるを伸ばしてからみつく姿が「縁」を思わせ、恋愛や人との結びつきに たとえられました と。この浮世絵は の作品・「美立候花競(みたて はなの くらべ)」 と。・女性を季節の花に見立てた美人画シリーズで、ここでは「朝顔」と「美人」が対になっています。・江戸後期、園芸ブームの中で「朝顔=夏の風物詩」として特に人気が高く、浮世絵の題材と しても多く描かれました と。 ・・・おわり・・・
2025.09.12
閲覧総数 1875
-
44
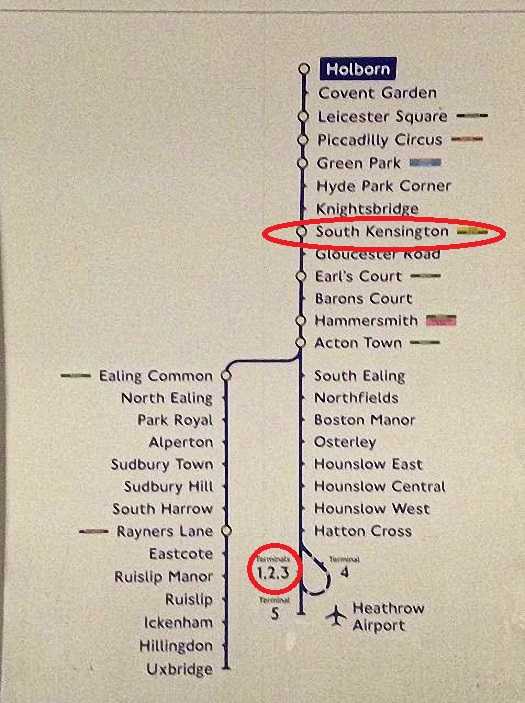
アイルランド・ロンドンへの旅(その132): ロンドン散策記・日本への帰路-1
Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館まで戻り待ち合わせ場所の博物館のクロークに到着。時間は15:45。トランクを受け取り、地下鉄サウスケンジントン駅から Piccadilly Line・ピカデリー線にてヒースロー空港に向かう。地下鉄サウスケンジントン駅は博物館、美術館の多いロンドンでも指折りの博物館であるロンドン自然史博物館とヴィクトリア&アルバート博物館の最寄り駅。Piccadilly Lineの路線図。SOUTH KENSINGTON駅。Piccadilly Lineの車両が到着し乗車。そしてHeathrow Airport・ロンドン・ヒースロー空港駅に到着し、第2ターミナルを目指す。ヒースロー空港ターミナル2の正式名称はThe Queen’s Terminal(ザ クィーンズターミナル)。ヒースロー空港と女王エリザベス2世の長年の結びつきに敬意を表し、「The Queen’s Terminal」と称されることになったと。2014年6月にオープン。スターアライアンス加盟の航空会社が中心となるターミナルである。T2以外のターミナルでは、スターアライアンスの航空会社は乗り入れしていない。ロンドン・ヒースロー空港(London Heathrow Airport)第2ターミナル「The Queen’s Terminal」の館内マップ(出発エリア)。主に出発客向けの構造を示しており、上階(Departures upper level)と下階(Departures lower level)の2層に分かれていた。全体構成ターミナル名称:Terminal 2 – The Queen’s Terminalゲート範囲:B28–B49(サテライト棟「T2B」へは地下通路“via subway”経由)フロア構造:Upper Level(上階):チェックイン、手荷物預け、セキュリティゲートLower Level(下階):免税店・飲食・搭乗ゲートへのアクセス✈️上階(Departures upper level) ・中央部に「You are here」の表示(現在地)があり、その先が Security(保安検査場)。 ・左側(West Wing): ・チェックインゾーンA〜D(スターアライアンス系航空会社) ・店舗例:WHSmith, Caffè Nero など ・右側(East Wing): ・チェックインゾーンE〜H ・店舗例:Pret A Manger, Travelex, Heathrow Family Lounge ・セキュリティ通過後、下階へエスカレーター・階段で降り、出国エリア(免税・搭乗口)へ 移動。🛍 下階(Departures lower level) ・出国後の主要なショッピング・飲食エリア。紫色ゾーンが店舗区域を示す。 ・ Shopping(買い物)、 Food and Drink(飲食)、Services(サービス)🚇 移動ルート ・Gates B28–B49 へは「T2B via subway」からアクセス(自動歩道付きの地下通路で 約5〜10分)。 ・保安検査後、案内標識に従って進むと「Flight Connections」や「T2B」分岐があった。別便で帰国する旅友Yさんと別れる。出発案内板。チェックイン、 Security(保安検査場)を通過し出国手続きも完了。帰路の利用便は中国国際航空・北京でトランジットし羽田空港へ。搭乗ゲートはB31。案内板に従って進む。ヒースローはハブ空港としての機能も大きいため、「ロンドン体験が空港内だけになる人も結構多い」と。そんな背景もあり、T2にはロンドンの街中にある、ありとあらゆるジャンルの店が揃っていた。建物内にはショップ33軒とレストランなどの飲食施設17軒が入っているとネットから。有名百貨店・ハロッズ。有名百貨店ハロッズはもとより、日本人に人気の英国雑貨キャスキッドソンが出店。有名ブランドのブティックも軒を連ねており、バーバリーやポールスミスなど英国を代表するブランドはもちろん、さらにT2には、百貨店ジョン・ルイスが空港内初出店。ロンドンをモチーフとしたグッズの他、アイルランドのデザイナー、オーラ・カイリの各種アイテムを揃えたコーナーもあった。スマイソン(Smythson)は、ロンドンに拠点を置く英国の文房具、革小物、日記帳、ファッション製品の製造販売店。百貨店John Lewis・ジョン・ルイス。NATURALLY FIRST FOOD店・LEON(レオン)。搭乗口B31はターミナル2Bの最奥の搭乗口◯。B31,B32の案内板。そして15分ほど歩いて搭乗口B31に漸く到着。多くの乗客の姿が。ほとんどが中国人のようであった。予約便は20:25発、中国国際航空(CA)・CA938+TP8328 の共同運航便。TP8328はTAPポルトガル航空(英語: TAP Air Portugal)。搭乗開始時間を待っていると、放送で機体に「技術的トラブル」があり修理中の為、出発が遅延すると。待つこと2時間以上、ひたすら搭乗開始の放送を待ったが・・・・・。これが登乗予定便であったが。途中、技術員が懸命に対応中であるのでもう少し待って欲しいとの放送が繰り返された。しかし、その後突然に「フライトは機体故障によりキャンセル」との放送。 乗客の中国人が騒ぎ出して放送の聞き取りが困難に。席を離れて係員の近くまで行くと、代替便の時間は現在調整中であるが、明日の午後の便となるであろうと。引き返して、入国手続を再度行い、手荷物受取所( Baggage reclaim)でトランクを回収して欲しい。ホテル、移動バスは現在調整中であると何とか理解した。Arrivals、Baggage Reclaimの案内に従い引き返す。入国手続きを行い手荷物受取所( Baggage reclaim)に到着。漸く、荷物が出てきたが私のトランクがななかな出てこない!!そして私他3名?のトランクが「ロストバゲージ」!!よって、他人が持って行ってしまったのではなさそうと理解はしたが。ネットから。預け荷物の半券(控え)&航空券を持ち係員のところへ。別の係員の所に連れて行かれ、カタコトの英語を駆使して事情を説明。・My baggage didn't come out!!・I am looking for my suitcase, but it is missing!! This is my claim tag!!・Could you find out where is my baggage?・My baggage nummber is “○○・・・○◯” .・How long will it take to receive my baggage?!・???????????????????・ロストバゲージ対応のカウンターへは連れていかれずに。・トランクの形状、色、材質、荷物の中身等を説明。 トランクはスマホで写真を撮っていたので写真で説明できたのであった。・トランクに入れてはいけないものは入っていないことを強調。 整髪用スプレーが入っているが、小型・100cc以下であり問題ないはずと。★明日までに探しておくので、明日の再チェックイン時に再度同じ説明をしろと!!★ホテルへの移動バス内で乗客が待っているから、早く戻って乗れと!! やむなく、この日は諦めて、別の係員にバスへと連れて行かれたのであった。ビジネスクラスの乗客が乗り込んだバスに連れて行かれる。・宿泊ホテルはバスで10分ほどの Hilton London Heathrow Airport Terminal 5・ヒルトン ロンドン ヒースロー エアポート ターミナル 5 と。・四つ星★★★★のホテル。・代替便は明日16:00発 と。・ホテルから空港への送迎バスは12:00に出発すると。・夜食が欲しい方は、部屋へのルームサービスが無料で利用可能と。・その他にもいろいろと言っていたが、聴くのも疲れて・・・???そしてホテルに到着。6階にあったツインの部屋に転がり込む。夜食も取らずに、シャワーだけ浴び、着替えも出来ず、疲れもあって爆睡したのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.07
閲覧総数 422
-
45

ソラ豆の種蒔き~植え付けそして我が菜園の今
久々の趣味の農作業のブログアップです。今年も10/29(月)にソラ豆の種蒔きを行いました。ネットで種を2種類購入しました。『河内一寸そら豆』。そら豆中最大粒の大阪伝統種。耐寒、耐病性強く、栽培し易い晩生種。二粒莢が六、七割を占める品種。そしてもう1種は『打越緑一寸そらまめ』こちらは3粒莢率が高く、むき実販売で緑色が引き立つ極濃緑。青果用として粉質で食味が良い多収品種。開けてみるとこの真っ青な色で驚き。種子消毒と書かれた名前がチウラム・キャプタン。調べてみるとチウラムは殺菌剤で鳥などの忌避剤にもなる薬品。そしてポットに種蒔き用の土を入れ一粒づつ丁寧に種蒔きしました。種のおはぐろを斜め下方に向けて土に押し込み、種の頭部がわずかに見えるくらいに浅まきに。9日程で発芽し12日目の11/10の状態です。スナップエンドウも併せて種蒔きしこちらも発芽しています。発芽した種が野鳥等に突かれないように不織布(ふしょくふ)でトンネルを造りました。トンネルの中です。そして発芽から5日目の11/15(木)の状況です。順調に成長し、葉の数も4枚ほどになって来ました。そしてこの日・11/15(木)に畑に植え付けを行いました。ソラマメは、低温に合わないと花が咲かないので、暖地や中間地では、秋10・11月に種を播くのです。マルチはシルバーマルチを敷いて植え付けました。シルバーマルチはそら豆の天敵であるアブラムシを防ぐ効果が高いのです。苗の間隔は50cmほどとしました。12月に入ったら、霜除け用に、目の細かい防虫ネットをトンネル掛けし、併せて北風を防ぐ予定です。そして今朝(11/29)の自宅横の菜園のソラ豆の状況です。葉の数も増え8枚ほどになっています。苗を早く植えすぎて育ち過ぎて(本葉が10枚以上)になると、寒害にあいやすくなるので植え付け時期に注意が必要なのです。そして今写真をアップして気がついたのですが、葉の中央にアブラムシを発見したのです。これから消毒したいと思っています。ソラマメは、来春4月末から5月初めになり、さやが下に垂れてくると収穫の時期なのです。初めは空を向いているのが、重さを増すと135度ぐらいになります併せてサヤの背筋が黒褐色になったら収穫の時期。開花後約35~40日が目安なのです。ぱっと見て、収穫時期が分かるのは便利なのです。そして我が菜園の今朝の状況です。まずはスナップエンドウ。1週間前に定植しました。そしてブロッコリーは毎日楽しんでいます。カリフラワーも巨大に。白菜。こちらはタマネギ。イチゴも今年も孫のイチゴ狩り用に多めに。そして我が菜園の隅の皇帝ダリアも開花の真っ最中なのです。
2018.11.29
閲覧総数 247
-
46

旧東海道を歩く(掛川~見付)その9:磐田市見付・三本松御旅所~遠州見付宿 脇本陣跡
『旧東海道を歩く』ブログ 目次旧東海道を見附宿方面に更に進む。日本橋からの距離は243.4km。『三本松御旅所』。「御旅所は神輿巡航の際、神輿が休む場所です。見付天神裸祭や祇園祭の神輿はこの御旅所まで渡御し、御神酒の献上や祝詞の奏上が行われます。また裸祭の道中練りもここで折り返します。 」『三本松橋 別名なみだ橋』かつてこの先の街道筋に遠州鈴ヶ森(三本松)刑場があり、罪人を見送る縁者がここで涙を流し見送ったのであろう。見付東坂上にある大正4年(1915年)建立の『秋葉山 常夜燈』。この灯篭は大正時代に建てられたものだが信仰の厚さが見受けられます。見付東坂を下る。左手に『東海道と愛宕山』の案内板が。「見付宿を一望できる愛宕山には、愛宕神社が鎮座し火防の神として人々の信仰を集めました」とあります。この付近は秋葉神社といい、愛宕神社といい火防に関する神様が信仰を集めるようです。『愛宕神社』への階段を登る。『愛宕神社』社殿。社殿の左側、山の上に石碑が見えたので更に道なき斜面を登る。『阿多古山一里塚跡』の石碑。磐田市指定史跡 『阿多古山一里塚』「関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、東海道の整備を進め、慶長9年(1604)には1里塚に距離の目安として小山(塚)を築きました。これが一里塚で、磐田市内には宮之一色と見付にありました。見付の一里塚は、愛宕神社が鎮座する愛宕山にあったことから、愛宕神社の旧名から「阿多古山一里塚」と呼ばれます。一里塚は5間(9m)至宝の土台に高さ2~3mの円形の小山を築き、塚の上には榎や松などを植えました。明治時代に也多くは壊されてしまいましたが、阿多古山一里塚は見付地区の財産として街道の両側に残され、昭和42年11月3日に旧磐田市の史跡に指定されました。阿多古山一里塚は、江戸から62番目にあたり、北の一里塚には、椎、南の一里塚には松が植えられたと言われています。」愛宕神社の境内からは、見付宿の宿場町を眼下に見ることが出来た。愛宕神社をあとにし見附宿中心に向かう。ここには川があったのでしょうか?橋がモニュメントとして架けられていた。道路右手奥に『見付天神社』の石鳥居が正式には矢奈比賣神社で、「裸祭り」が8月の中旬に行われると。この神社は訪ねず、ここからの写真のみ。『祈 幸せをもたらす元号でありますように』と店の窓に早くも『令和』の元号が。現代版道標も。旧東海道『見付宿場通り』を更に進む。『見付宿史跡』案内図。 【http://www.asa1.net/siseki-meguri/mituke/index.html】より。整備された歩道には見付を代表する「見付宿」の当時の姿や磐田市の花、鳥などがタイルに埋め込まれていて見事。かなり道路は広く旧道とは思えないのであった。『見附十七小路』という表示も歩道路面に。寺院・神社・史跡等の位置が記されており、史跡巡りには便利であろう。「小路の奥に明治中頃にできた浜松市始審裁判所見付出張所(後の法務局)があったことから小路の名称となりました。現在は住宅地となり、その面影はありません。」『JA遠州中央 見付支店』が右手に。その前に『東海道・見付宿』の当時の地図が。『東海道分間絵図』道中図(どうちゅうず)は、江戸時代に作成された陸路や海路を記した絵地図で、今日の道路地図と観光案内を組み合わせた要素を持つ。元禄3年(1690)に遠近道印(おちこちどういん)が「見返り美人図」で知られる菱川師宣(ひしかわ・もろのぶ)と共に製作した「東海道分間絵図」は、代表的な道中図のひとつであり、1/12,000の実測図上に河川や橋梁・宿場町・一里塚名所旧跡などが師宣の絵によって詳細に描かれている。江戸時代に描かれた見付宿/東京国立博物館所蔵。『東海道見付宿案内板』こちらは現代の地図のようであった。『天神の木 東坂梅塚』。梅塚というのは、見付天神の祭りの夜、怪物に娘をさしだした家の前にそのしるしとして植えたものだといわれていると。鎌倉時代の話であると。『丸中 大橋商店』屋号丸中は江戸時代に浜松にて中兵衛という米屋を営んでいたことに由来。明治10(1877)年に酒屋を始め、現在四代目。店の裏には今でも当時のトロッコが働くと。『曹洞宗 宣光寺』。地蔵堂内には日本三代地蔵の一つとされる高さ1.4mもある平安時代作の木彫り座像「延命地蔵菩薩」があると。この地蔵は、徳川家康が追っ手から逃れるために見付の街に火を放った時、幼児の姿になって、やけどを負いながらも火を消して回ったという言い伝えがあり、身がわり地蔵さんとも呼ばれていると。そのほか、境内には、徳川家康寄進の梵鐘もあると。『地蔵小路』。「小路の奥手には延命地蔵をご本尊とする宣光寺があります。昔からお地蔵ご開帳の日には大変なにぎわいを見せていたことから地蔵小路とよばれてきました。」今之浦川に架かる橋が前方に。『今之浦川』、火の見櫓であろう。鉄骨造 (アングル),櫓型,4本脚,むくり屋根,銅板葺きの火の見 櫓の頭頂部とユニークな形状。『中川橋』。『大見寺』の案内板と『東海道見付宿』石碑。旧『寺小路』と刻まれた石碑。見事な灯籠。山門。『大見寺の文化財』。「見付端城(みつけはじょう)中世には、境内に今川氏によって築かれた城がありました。江戸時代の絵図には、大見寺を取り囲むように見付端城の土塁が描かれています。現在もこの土塁の一部が西と南にわずかに残っています。良純法親王供養塔(墓)法親王は、107代後陽成天皇の第八皇子で、万治2年(1659)頃縁あって見付に滞在しました。弟子だった大見寺第11代住職によって供養塔が建てられた。鳥人・幸吉の墓岡山県出身で江戸時代中頃に、日本で初めてグライダーのような翼で空を飛びました。晩年、見付で暮らしたといわれている」大見寺の境内の桜も満開。『三界万霊供養塔』。本堂。『日照山 光明院 大見寺』『日照山』と書かれた扁額。『浄土宗歌 月かげの いたらぬ里は なけれども 心にぞすむ』。芍薬の花も終わりか。様々な石碑、石仏が境内に。境内社。境内から山門を見る。見付十七小路 『寺小路』。「大見寺に通じることが小路名称の由来です。また大見寺境内には、三代将軍徳川家光の休憩所「御茶屋御殿」があったことから「御殿小路」ともよばれていました。」 静岡銀行前に『問屋場跡』。残念ながら説明案内板は見当たらなかった。『御証文屋敷、安間平治弥邸跡』「平次弥は本名弥平次。名は禮、字は伯啓、号は九渕と称し、漢字の素質があって詩文もよくした。徳川家康から代官に任命され、甲州武田軍を退去させた功績で家康に平次弥と改名させられ、名字帯刀を許されて、見付に住むように申しつけられた。庭には清水が湧出し年中枯れる事が無く、之を家康に薦めたので「御清水」というようになった。家康の休息場として利用されたといい、今も清水が中川に流れ込んでいる。町名もこれにあやかって、清水町という。安間家には代官からの証文が残され、「御証文屋敷」と呼ばれていた。」更に旧街道を進む。反対車線側にも隠れるように。『遠州見付宿 脇本陣跡』。説明案内板はここにもなし。『酒の無いよな極楽よりも落ちて地獄の鬼とのむ』と。懐かしい手押し井戸ポンプの姿が。 その8 に戻る。 ・・・つづく・・・
2019.05.29
閲覧総数 1699
-
47

『旧満州:中国・東北地方7名所大周遊8日間』の旅へ:3日目(6/21-4) 長春:伪满洲皇宫博物院(その3)・緝煕楼~勤民楼~興運門
更に伪满洲皇宫博物院の見学を続ける。これは「緝熙楼(しょうきろう)」といわれる建物で、溥儀や皇后の婉容(えんよう)、第三夫人の譚玉齢(たん ぎょくれい)の寝宮だったそうだ。まずは2階への階段を上る。古い建物のこの階段には独特な、なにかを感じさせてくれるのであった。溥儀の『漢方薬庫』溥儀は、青年時より薬好きで、専用の薬局を設けていたのだと。『婉容皇后(えんようこうごう)の書斎』。「1931年暮れ、満洲事変勃発後、溥儀が日本陸軍から「大清帝国の復興である新国家(満州国)」の皇帝となるよう要請を受け受諾し、天津を脱出して満州へ移住。静園から溥儀が去ったことを知った婉容は、溥儀から満州に来るよう求められたが皇后の身分にも皇帝のもとへも戻る意思がないと断ったが、関東軍の命を受けた金璧輝こと川島芳子に「皇帝が大連で亡くなったため葬儀に出席してもらいたい」と欺かれ、満州に連れ出された。溥儀が2年間の執政を経て1934年3月1日に皇帝に即位すると、婉容もまた皇后となるが、皇后に相応しくないと見なす関東軍の意向により、公式の場に姿を見せることはほとんどなく、告天礼の儀式にも、即位式に参列することも叶わなかった。6月7日、訪満していた秩父宮雍仁親王による勲章伝達式に際しても、関東軍は婉容を謁見させたくなかったが、「伝達式には皇帝・皇后ともに出席すべし」との日本政府の主張により例外的にこれを受け入れた。婉容は勲一等宝冠章受賞の儀式でもその後の宴でも、さらに12日に行われた満州国皇帝による招宴の席でも、噂されていたような中毒症状を見せることもなく、健康そのものの様子で儀式に臨み宴の女主人役を務めた。しかし自由のない閉塞的な暮らしと皇后としての振る舞いも許されない状況の下でアヘンへの依存は高まり、1935年頃には新しい衣料を購入することもなくなった。溥儀の弟溥傑の妻であった嵯峨浩は、1937年秋頃の様子として、アヘン中毒の影響から婉容の食事の様子に異常な兆候があったと自伝に記している。」と。『婉容皇后の寝室』。結婚以来、一度も溥儀とベットを共にしなかった。その寂しさを紛らわすため、溥儀の家来と浮気。その結果、溥儀からの愛は無くなったと。『婉容の応接間』はアヘン吸引室。婉容は、満洲国時代になると、日本ぎらいもあって、アヘンにおぼれて、公式の場所にほとんど姿をみせなかったと。以前は第一夫人の婉容がアヘンを吸っている様子がロウ人形で再現されていたとのことだがこの日はロウ人形はなかった。。『婉容の応接間』西洋知識豊富・英語堪能、琴・書画ともに優れた婉容の応接間。しかし、アヘン中毒となった婉容に、来訪すべき客はいなかった。『理髪室』。日本人津田という人がおかかえの床屋さんだったようです。清朝皇帝は「龍髪」という習慣があり、切った髪を黄色い絹に包み、日付を書いて保存していたと。また、溥儀が日常使う注射器をここで消毒していたと。なんでもホルモン注射をしていた模様。『溥儀の書斎』このにも以前は、溥儀と語り合おう吉岡安直の二人のロウ人形が椅子に座っていたようであったがこの日はここのロウ人形の姿もなかった。読書・習字の場。吉岡安直の指導を受け政治活動を行った場所。『溥儀の寝室』。1932年から1945年までの寝起きをしていた部屋。『溥儀の寝室』のベッドの手前。『溥儀の仏間』神仏信仰は清朝歴代皇帝の伝統。溥儀は歴代清朝皇帝同様熱心な仏教信者。この仏間で読経、占い、運命判断、祭事などをみずから行っていたとのこと。『溥儀の浴室』。右側が浴室、左側がトイレであろうか。第三夫人の『譚玉齢(たん ぎょくれい)の応接室』。1920-1942。北京に満州族の貴族の子として生まれ、17歳の時、当時32歳の溥儀の側室となる。22歳で病死。他他拉貴人(たたらきじん)の名でも呼ばれる。温厚でおだやかな性格で、最も寵愛を受けたといわれているが、宮仕えの5年後わずか22才で謎の死を遂げており、溥儀はそれを後々まで日本軍による毒殺と疑っていた。「私の妻は…私の貴人は、非常に私との仲がよかったのであります。年は若くて23でありました。あるとき私の貴人は病気になりました。彼女は中国を愛し、即ち中国の国家を愛する人間でありました。そうして貴人は常に私に向って、今はやむをえないから、できるだけ忍耐しましょう。そうして将来時が来たならば、失った満州国の地を中国にとり返すように致しましょう、と語っておりました。しかしながら、私の貴人は日本人に殺されたのであります。」と、愛新覚羅溥儀の著・『わが半生』には書かれていると。偽満皇宮博物院における緝煕楼(しゅうきろう)の一階の東側では、溥儀や皇后、皇妃の生活写真が展示されていた。この時代は、カメラの普及も進んでおり、古い写真も数多く残されていたのであった。写真館の溥儀と婉容。1922年、正妻の婉容と結婚した溥儀(左)と婉容。溥儀と婉容。婉容。婉容は、北京で生まれたが、天津で育って英語を含めた西洋的な教育を受けていた。17才の時に、溥儀の皇后として迎えられたが、溥儀の同性愛的性向あるいは性的不能によって、夫婦仲は冷えていき、アヘンに手を出して、重篤な中毒に陥って行ったのだ。溥儀が満州国皇帝となると婉容も再び皇后になったが、アヘン中毒と日本人嫌いのため、公式の場にはほとんど姿を見せず、最後は身なりにも気を使わないような精神的錯乱に陥って行った。婉容は、満州国皇后時代に愛人を作り、娘を出産するが、生まれた子供は、すぐに彼女の前から姿を消してしまう。本人には、親族の手で育てられていると告げられたが、実際は溥儀の命を受けた従者の手によって、ボイラーの中に投じて殺害されたと。日本の敗戦後の逃亡の際に溥儀一行から置き去りにされて、共産党軍の手におち、吉林省延吉の監獄内でアヘン中毒の禁断症状と栄養失調のため、孤独の内に死亡したといわれているのだ。第2夫人の文繍(ぶんしゅう)。位階は淑妃。婉容が皇后に迎えられる前日に、側室として紫禁城に迎えられたのが、13才の文繍。紫禁城の中で、溥儀や婉容とともに過ごす日が続く。天津の日本租界に移ってから溥儀のもとから逃亡して、3日後に離婚の訴訟を裁判所に申し出ると溥儀が慰謝料を支払うことになって、離婚は成立して、文繍は平民に戻った。文繍は、私立学校の先生になったが、皇帝の側室であったことが世間に広まったことから退職を余儀なくされたと。1931年、溥儀との離婚を裁判所に申請して認可され、溥儀が慰謝料5万5千元を支払うことで離婚が成立した。この時の離婚の条件は、文繍が生涯結婚をしないというものであったと。最後は45才で、飢え死にに近い状態で亡くなったと。北京故宮長春宮の婉容。婉容の写真が並ぶ。溥儀と婉容そして二人の妹と一緒に。天津静园での溥儀夫妻。婉容。北京故宮にて自転車に乗る婉容。婉容の弟・潤麒と一緒に。日本公使館にて。天津にて溥儀の誕生日に時の写真であると。満鉄経営の湯崗子(とうこうし)温泉(現在の遼寧省鞍山市の湯崗子駅の東)の対翠閣(たいすいかく)門での溥儀夫妻(左)と1932年3月8日長春での溥儀夫妻。第三夫人の譚玉齢(たんぎょくれい)(中央)と愛新覚羅溥傑(満州国皇帝愛新覚羅溥儀の弟)の妻・嵯峨浩(左)。1943年の4番目の妻・李玉琴 (り・ぎょくきん)(右)と1957年の李玉琴 (左)。関東軍としては、満州国皇帝に世継ぎができる必要があった。そこで側室を迎えることを溥儀に勧めた。関東軍の手で集められた候補のうち、新京市内の料理屋の店で働く労働者階級の娘の15才の李玉琴が選ばれた。皇帝の側室というよりは、召使のような扱いで、廃人と化した皇后婉容を最後まで世話した。溥儀の収容所時代に、離婚することになたと。1982年の李玉琴 。そして溥儀の最後の妻(5人目)は李淑賢( り・しゅくけん)、看護婦をしており、戦後、溥儀と結婚する。溥儀の死後、その意志に基づき、彼の後半生の手記を書き上げた。1962年結婚。二人の結婚生活は仲睦まじかったと伝わっている。ちなみに、溥儀にとって生涯唯一の恋愛結婚でもあったと。『譚玉齢の応接間』1937年に溥儀と結婚。溥儀に愛されていたが1942年22歳の若さで急病にかかり死去。元は溥儀が食事をした食堂を、1937年以降、譚玉齢の応接間に改造。溥儀の妹達はよく来訪し、譚玉齢と雑談した。『譚玉齢の書房』元は溥儀の書房。1937年以降、譚玉齢の書房に改造。読書・習字だけでなく、琴を弾いたりした。また、溥儀に生活用品を編むこともあった。『譚玉齢の寝室』婉容はアヘン中毒になり、文繍は逃げ去っていたため、満洲時代になって15才の譚玉齢 を1937年側室に迎えた。溥儀との仲は良かったのだが、重い病に。清朝以来の習慣で漢方薬医に治療をさせるが、衰弱していく一方であった。この病気は御用係りの吉岡の耳に入り、日本人医師に診察させるよう勧めた。吉岡の言葉に反対できない溥儀は、日本人医師に治療を行わせる。栄養剤の注射と輸血を行ったその晩に譚玉齢は急死してしまう。譚玉齢は、愛国心が強く関東軍に反感を持っていたために、吉岡の指示によって暗殺されたという疑いがわいて来たと。溥儀は後の東京軍事裁判で、譚玉齢は吉岡に毒殺されたと証言したのだと。『西御花江園』入口。「西御苑は、偽満州国の初期に、吉黒榷運局の花園の敷地に造られたのである。敷地面積は2200m2以上である。園内にいろいろな草花と木が植えられ、東屋や築山が池に映って美しい景観となる。東御苑ができていないとき、溥儀と宴用はよくここへ遊び楽しみに来る」『西御花江園』案内表示。『勤民楼』溥儀が清王朝復活の大志を示すため「天を敬い祖を則り政に勤め民を愛す」という清王朝の家訓より命名。政務・式典・来賓接待・宴会を行った場所。ここにも入りたかったが、今回のコースには入っていない模様であった。『勤民楼👈リンク』に関心のある方は・リンクにアクセスしてください。『勤民楼』前庭部。『勤民楼』出口門は『迎晖門(迎暉門)』。『宮内府』、『興運門』に向かって進む。『宮内府』入口。暢春軒。溥儀の妹たちが暮らしたところで、寝室や応接室などがあった。溥儀の実父が訪ねてきた時にもここに滞在したとのこと。ちなみに、この博物院に展示されている家具はほぼほぼ全てレプリカで、本物は文化大革命時にすべて失われてしまったらしい。偽満州国では宮内府大臣の下に日本人次長を置いていた。次長は名義上は大臣の補佐であるが、人事・財務等のすべての行政権を持ち偽満州国政権を制御していた。総務処は職員の監督・指揮をする。各書類の保管や、宴会・賞与および職員の任免・賞罰等の事項を管理していた。正面に『興運門』の内側が。9:10で止まっている時計。溥儀が長春から逃げる時間で、時が止まっているのだと。『興運門』の表側。皇帝のシンボル「ランの花」の紋章。また、門に描かれている龍は皇帝の証であると。林の奥に多くの馬の姿が。奥には『御用乗馬場』があった。溥儀も実際に遊んだ乗馬場であると。そいて柳の並木の下を出口(入口)に向かって進む、黄色の花にはミツバチが。『紫椴』、『菩提樹の花』であるようだ。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2019.07.12
閲覧総数 1600
-
48

「はるばる来たぜGoto函館」(その29): 日浦岬~旧戸井町立鎌歌小学校~旧戸井線コンクリートアーチ橋
国道278号を更に進むと、前方に「日浦岬」の姿が見えて来た。そしてズーム写真には「日浦岬灯台」が映っていたのであった。日浦トンネルの手前を左折した突き当りが「日浦岬」。岬に向かって進んでいくと、階段があった。そこを進むと、灯台に向かう道になっていた。先に進みたかったが、橋には立ち入り禁止のチェーンが張られていたので諦めたのであった。階段を上がっていくと見えるのがこの「日浦岬灯台」であったが・・・。 【https://twitter.com/AeugMsz006/status/1007103376373440512/photo/1】よりそして「日浦岬灯台」。塗色構造:白塔形灯 質:群明暗白赤光 明6秒暗2秒明2秒暗2秒 (赤光は分弧) Oc(2) W R 12s光達距離:13.0海里塔 高:9.5メートル灯 高:23メートル初 点 灯:昭和26年3月 【http://ryujinkai84.blog.fc2.com/blog-entry-447.html】より「一男死亡の地」碑。一男さんがこの地で不慮の死を遂げたのであろうか?柱状節理の岩場には青い海水が入り込み白波に。そして振り返ると「恵山」の姿と、地熱発電調査の水蒸気がこの時も。ズームして。「日浦漁港」には小さな漁船が。日浦はイカ類がよく釣れることで知られているのでイカ釣り船であろう。海の安全祈願の地蔵様か?これから向かって行く戸井漁港の先に浮かぶ「武井(むい)ノ島」が見えた。右の島には鳥居があり「弁財天」が祀られていると。江戸時代 漂流船がこのあたりに漂着し 乗っていた人が全員無事という「伝説」👈リンク もあるという。このため 「神の島」とも呼ばれるらしい。日浦トンネルが出来る前は、ここに道が出来ていたのであろうか?自然の状態の柱状節理を目の前で見ることが出来たのであった。両側が崖になっており、それがどちらも柱状節理、まさに圧巻。「柱状節理」は主に火成岩に見られる現象で,露頭に見られる規則性のある割れ目をいう。 火成岩に節理ができるのは、熱いマグマが約700~1000℃で固まって岩石になり、その後、常温に冷える過程で体積がわずかに収縮するためであると。角柱の断面は六角形のことが多いが、必ずしもそうではなく、四角形、五角形、七角形、八角形のものもあると。一般的には、時間をかけて冷えるほど太くなるのだと。崖下には、崩れた柱状節理がごろごろしていた。ということは、こんなのが崩れてくる危険は常にあるということ、我々もむやみに両側の崖に近寄らないで中央を歩いたのであった。「日浦岬」を後にして、更に国道278号を進むと、「武井ノ島」の姿もじわじわと変化して行った。そして旅友Sさんの希望で、国道から斜め右に分岐して狭い坂を上る。「戸井町立鎌歌(かまうた)小学校」と書かれた門柱があった。旅友Sさんの話によると、俳優・火野正平さんが相棒・チャリオ(自転車)に乗って日本全国を巡るNHK「日本縦断 こころ旅」。935日目の10月2日の放送はこの先の函館市戸井町からであったと。横浜在住の版画家・佐々木孝さんの手紙を元に「こころの風景」と題して旅したのだと。佐々木さんの思い出は函館市の「鎌歌」。故郷を思う佐々木さんは、その地名が忘れ去られてしまう前に、廃校になった母校の小学校跡や鎌のように曲がった入江がある海の風景を訪ねてほしいと火野正平さんへ依頼をしたのだと。撮影の日はあいにくの悪天候で、火野正平さんは悪戦苦闘したが、たどり着いた元小学校の門には今も「鎌歌」の文字があったと。「鎌歌小学校」跡地にあった建物。そして国道278号に戻る坂の途中から「日浦岬」方面を見る。前方に見えたのが「戸井トンネル」。「武井の島展望台」👈リンク 下の岩場。道路の脇には海鳥が日向ぼっこ中。嘴、脚の色から「セグロカモメ」であろうか。そして戸井町内を通過し更に進み亀田半島の最南端にある「汐首岬」近くを通過。国道278号の別称「恵山内浦ライン 戸井町」と書かれた支柱を車窓から。その先にあったのが「北海道~本州 最短の地 17.5km」案内板。その先には下北半島の姿が見えた。車を駐めたかったが駐車場がなくカーブもあり諦めたのであった。北海道~本州 最短 17.5km。一方現在青函トンネルが通っている近くにある北海道最南端の松前町白神岬 と津軽半島の竜飛崎までは19.2kmあるのだと。かつて青函トンネルルートの候補としてあがっていたようですが、深さと海流といった問題があったため断念し、現在の青函トンネルが出来上がったのだと。更に進むと右手にあったのが「旧戸井線コンクリートアーチ橋」。 民家前の空き地に車を駐める北海道函館市汐首町。「はこだて施設ご案内」。ズームで。「戸井線」は昭和11年に着工を開始し、昭和18年に中断された未完成の鉄道路線。日中戦争時代、戸井町に軍事要塞を作る際に資材運搬また兵員輸送を目的として、五稜郭から戸井町までの29.2kmを結ぶ線路として建設されていたものであったと。1937(昭和12)年、北海道建設事務所の所管で五稜郭側から工事着手、1942(昭和17)年に瀬田来まで路盤工事は完成し、湯の川まではレールも敷設されたが、資材不足により中止。 1944(昭和19)年「鉄道敷設法」戦時特例が公布、この特例では戦力増強など緊急に鉄道が必要な場合は敷設が認められたが、実際に行われたものはなく、戸井線の工事も再開することはなかったのだと。 【http://www.hk-curators.jp/archives/684】より戦時中だったこともあり、資源節約の為に鉄筋を使用せずコンクリートで出来ていると。しかし、その後太平洋戦争が勃発し資源不足に陥り工事は中断された。その後も工事は再開されることなく、未完成のまま現在に至っているのだと。工事中断以降、補修されることもなく長年放置されているという現状もあり老朽化が進んでいるのだとか。元は軍事物資輸送用で1937年に着工。五稜郭~戸井駅までの29.2kmを結ぶ予定だったが、大東亜戦争の戦況悪化による資材不足で、戸井までの約2.8kmを残して建設が中断したのだと。歴史を感じたのであった。しかし80年以上前の技術で作って海岸沿いの塩害もある中で、メンテナンスしていないのに この状態は凄い!!と感じたのであった。道路を渡り、空き地から振り返ると、「汐首岬灯台」の上部が僅かに顔を出していたのでズームで。旧戸井町 マンホール蓋。イメージキャラクター・トーパスちゃんはタコで、シュノーケルをし、手(足)には指がある。トーパスちゃんを中心に海の仲間たちが多数(ヒラメのような魚、イカ、ウニ、カニ、コンブのような海藻など。魚と海藻以外は擬人化した顔が描かれている)。上下に扇面型の文字枠があって上部には「戸井町」、下部には「おすい」の文字が入っていた。そして国道278号を進んでいくと、左手前方はるかに「函館山」の姿が見えて来たので車を駐める。ズームで。更に。函館山山頂の鉄塔の姿もズームで。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2020.12.11
閲覧総数 1195
-
49

綾瀬市の神社仏閣を巡る その1: 弁財天~蓼川神社~安産子育出世地蔵~風車公園~子之神神社~目久尻川
【綾瀬市歴史散歩 目次】👈リンク私の住む藤沢市は、鎌倉市、横浜市戸塚区・泉区、大和市、綾瀬市、海老名市、寒川町、茅ヶ崎市の6市1町と市境を接している。コロナ禍で不要不急の外出の自粛要請の中で、自分の体力維持も同時に重要であるため3密(密集、密接、密閉)、そして飛沫感染によるリスクの少ない、屋外の散歩としてマスクの完全着用の下での隣接市の神社仏閣を訪ねることを始めているのである。先日は横浜市戸塚区、泉区にまたがる「鎌倉古道」を歩いたがこの日は、隣接する「綾瀬市」の神社仏閣を訪ねる目的で我が車で向かい無料駐車場に車を駐め散策のスタート。最初に訪ねたのは綾瀬市の最北に近い東名高速道路に近い「弁財天」。綾瀬市大上9丁目25。綾瀬市立北の台小学校の南側にあった小さな社の「弁天社」。鳥居の扁額は「弁才天」。「社殿」の扁額は「亀甲山白糸七面大天女」。「弁財天亀甲山白糸七面大天女といい、明治の末ころに造立されました。当時の綾瀬では養蚕が盛んであり、この下の低い場所に建てられた製糸工場に蛇が入り込み白くミイラ化したものを真綿でくるんで祀ったのが初まりといわれています。現在は、山野講中で大切にされています。」「お願い 賽銭を盗ないで下さい 弁天様管理者一同」と。何重にもチェーンが巻かれ南京錠が。その中に賽銭箱が納められていた。世知辛い世の中ですが、これも新型コロナの影響か。この写真を撮っている私の姿を、通りかかった自転車のオバチャンがじっと見ているのであったが・・・・。幸い尋問等はなかったのであった。東名高速に架かる橋を渡ると「蓼川神社(たでかわじんじゃ) 」が左手に。綾瀬市蓼川2-12-42。「社殿」。御祭神は大山祇命 ( おおやまつみのみこと )、菅原道真( すがわらみちざね )。「蓼川神社(たでかわじんじゃ)蓼川は上下に分かれていましたが、上分の鎮守は大山祇命を祭る山神社と素盞男命を祭るハ坂神社、下分は菅原道真を祭る天満宮てした。それが明治四十二年(一九〇九)に合祀されて蓼川神社となりました。境内には、享保二十一年(一七三六)造立の双体道祖神をはじめ数多くの石造物ガ安置されており、また庚申堂には正徳三年(一七一三)に造立された青面金剛像(庚申塔)が祭られています。」江戸後期天保十四年の「地神塔」が境内に。こちらは天保十五年の「地神塔」。そして道を戻り、次に訪ねたのが「安産子育出世地蔵」。「安産子育出世地蔵 願文山法正寺」の寺号標。扁額「願文山法正寺」。格子窓から内陣を。中央に「青面金剛像(合掌・六臂)・三猿」。寛政8年(1796)10月。多くの「庚申塔」を中心とする石碑が並んでいた。そして県道42号線・藤沢座間厚木線を南下し「風車公園」に立ち寄った。綾瀬市大上2丁目にある公園。複合遊具が揃う遊具広場、少年サッカーや少年野球などでも使うことができる多目的広場、テーブルベンチなど休養施設か設置されたふれあい広場の3つのエリアにわかれていた。「風車公園」案内板は・・・・・。遊具広場。遊具広場内で一番大きな遊具の頂上には風車がついており、ハンドルを回すことで子ども一人で自由に動かすことが可能とのこと。ツリー型のジャングルジム。ロープウェイ?。そして綾瀬市の雨水・汚水マンホール蓋。市の木「ヤマモミジ」を描いた雨水用マンホール蓋。下部に「あやせ」「あめ」の文字。こちらは、市の花「バラ」を描いた汚水用マンホール蓋。下部に「あやせ」「おすい」の文字。次に訪れたのが「子之神神社(ねのかみじんじゃ)」。綾瀬市寺尾中1ー3ー38。社号標「寺尾 子之社」。石段を上り参道を進む。「手水舎」。「本殿」と手前に「御神木」。「石灯籠と狛犬」(左)。「石灯籠と狛犬」(右)。「拝殿」。御祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)[別名]大国主命(おおくにぬし)。綾瀬市早川にある五社神社の兼務社となると。慶長十年(1605)に勧請されたという棟札があり、現在の本殿は文久元年(1861)に建造され、さらに大正十五年(1926)に再建されたもの。向拝の見事な彫刻。木鼻の彫刻。扁額「子之社」。子とは北の方角をいい、子之神とは北方をつかさどる神のことを言うのだと。「拝殿と本殿」。「御大禮紀年改築碑」。「御大禮(ごたいれい)」とは、天皇の即位にともなう一連の儀式の総称。昭和天皇の御即位の時のものであろう。「神輿殿」。こちらにも御神木のクスノキ。「社務所」。歴史を感じさせる石碑。「子之神神社」を後にし、西に進むと「目久尻川」に架かる「伊勢下村橋」が。「伊勢下村橋」の欄干には河童が2体。「昔むかし、いつのころからか海老名市を流れる目久尻川(めくじりがわ)に河童(かっぱ)が住みつきました。目久尻川の河童はしだいに数を増やし、食料不足となってしまいました。そのため、河童たちは夜になると川の近くの農作物を盗むようになりました。始めのころは隠れて盗み食いをしていたものの、やがて手当たり次第に田畑を荒らすようになりました。しだいに河童による農作物の被害は拡大し、村人たちも頭を悩ますようになったところで、田畑を荒らしているのは河童の仕業だということがわかりました。怒った村人たちは手に手に鎌などを持ち、河童を退治するために目久尻川へと向かいました。村人たちは次々に河童たちをとらえ、最後まであばれていた河童の親分も取り押さえることに成功。処刑のさいには親分を川のほとりの砂の上に引き据えて、今までの恨みをこめて河童の目を刃物でくじり取り(えぐり)ました。この河童の目を「くじり取った」というところから、川へ目久尻川という名前がつけられたというのが、目久尻川の名前のひとつだといわれています。」とネットから。冬支度姿、マスクをかけた、河童とは判らない完全防備の姿で。こちらは男の子と。欄干には様々な姿の河童君の姿が。そしてこちらはカッパの「女の子」であると。町の方が四季折々、お色直しをされていると。橋の上流側の欄干の両端に。「目久尻川」とその先に「相鉄本線」の線路を見る。「目久尻川」を再び渡る。小園地区の目久尻川にかかる「小園橋」の脇にある「かっぱ伝説」。橋のたもとには3匹の河童たちの姿が。石の上で膝をかかえた河童と、その前で寝そべる河童。水面から半身をのぞかせている河童と、どの河童像も個性豊かなのであった。「小園橋昔は目久尻川改修前の位置に架けられ、国の費用で工事をしたので、国役橋と呼ばれていたようです。ここには浜田の駅(うまや)からひさご塚に出て、俗に四十坂と呼はれる急坂を下った古道が通っていました。」 ・・・つづく・・
2021.02.06
閲覧総数 1075
-
50

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その28):海老名市消防庁舎~海老名市役所
【海老名市歴史散歩】 目次「大谷観音堂」を後にして、「観音通り」を北上して「根下バス停前」交差点まで来る。左側に「観音堂」らしきものがあった。海老名市大谷北2。少し戻り、田んぼの中の道を西に進む。収穫間近の田んぼが拡がっていた。「中部営農組合」に稲刈りを依頼しているのであろうか。手で刈り取られた稲が数束道路脇に。そして別の田んぼにも同様な表示が。右手奥にあったのが「アツギ(株)」のビル。日本の繊維製品の製造・販売メーカー。旧厚木ナイロン工業(株)。海老名市大谷北1丁目9-1会社の所在地は海老名市であるが、社名に相模川対岸の町である「厚木」の名前を使用したのには次の理由がある と。会社設立前に近隣にある厚木基地に連合軍総司令官ダグラス・マッカーサーが降り立った。そこで創業者の堀氏は「世界中に知れ渡った厚木の名を社名にすれば、いちから宣伝しなくても済む」とひらめいたことから と。ただし厚木基地は厚木市内ではなく、綾瀬市と大和市にまたがった地域にある。所在地に近い厚木駅も厚木市内ではなく海老名市にある。ちなみに発明学会前会長豊沢豊雄の著書によると厚木ではないからアツギ株式会社と命名したとあるのだ と。そして「海老名高校東側」交差点を通過し「海老名市役所」に向かう。更に北に向かって進むと左手にあったのが「海老名市消防庁舎」。海老名市大谷816。「海老名市消防庁舎」の入口玄関。台座に「和」と刻まれた消防士像。玄関から中に入ると様々な消火機材が展示されていた。腕用ポンプ(手押し消火ポンプ)。長岡市から譲り受けたものであろうか。ミニ消防自動車。纏(まとい)。そして様々な種類のミニ消防自動車。梯子車。救急車。交差点の角にあったのが「神奈川県警察 海老名警察署」。更に進むと左手にあった「海老名市役所」に到着。海老名市の市章旗がはためく。「海老名市役所」の駐車場側の玄関から内部に入る。 海老名市イメージキャラクター 「えび~にゃ」が迎えてくれた。名前 海老名市イメージキャラクター えび~にゃ性別 女の子誕生日 平成23年(2011年)1月28日(い~にゃ~の日)住所 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1 海老名市役所性格 やさしい性格で、こどもから大人まで仲良くなれる! やんちゃで、楽しいことが大好き!特徴 あたまは「えび」、からだは名産の「いちご」の白ねこ特技 ダンスを踊ること 『EBINAダンス』をいっしょに踊ろうにゃ! 海老名市内をリポートすること その名も“えび~にゃリポ~タ~”!好きな 海老名で採れるいちごや梨などの果物、トマトやレタスなどの野菜食べ物 海老名はおいしいものがたくさんにゃ!えび~にゃのひみつ おなかからいちごの香りがする… ハイタッチをすると、なぜか笑顔になり、幸せが訪れる…経歴 『ゆるキャラ®グランプリ2012』 865キャラ中、第19位 『ゆるキャラ®グランプリ2013』 1,580キャラ中、第18位 『ゆるキャラ®グランプリ2014』 1,699キャラ中、第16位 ※女の子キャラとしては、全国1位!!内部の壁には市民の作品であろうか、絵画等の作品が展示されていた。「七重の塔」のミニチュア。市民からの寄贈品のようであった。「住みたい 住み続けたいまち 海老名」。絵画がここにも。「ともに認め合うまち・海老名宣言 ~かかわり・つながり・ささえあい~海老名市は、 あらゆる障がいへの差別をなくし 、人としての権利が守られ、障がいがあってもなくても、誰もがその人らしく安全・安心に暮らすことができるように、ともに認め合うまちをめざして、次のことを宣言します。一 「障がい」は決して特別なことではなく、誰にでも起こり得ることです。 私たちはお互いに、多様な人格と個性・生き方を認め合い寄り添う社会、偏見や差別のない 共生社会をめざします。一 「障がい」ゆえの生きづらさを抱えながら生活している人が大勢います。私たちはお互いに 勇気を持って言葉かけをしていきます。一 海老名市は、「障がい」について関心を持ち、理解を深め、寄り添う気持ちが持てるよう、 ともに認め合うまちづくりを推進します。 」「海老名市の花 PR中!」。「海老名の特産品」も展示されいた。日本酒「いづみ橋」、「えびなの里」。海老名市内で栽培された米、「山田錦」100%を原料とした、吟醸酒。「七重最中」。「杏の実」と「苺風味の牛皮」の2種類で、国分寺の七重の塔がかたどられた、風味豊かな最中である と。「吟味豚」。豚肉は、国内産で、専門家がじっくり吟味したもの。味噌は、アレンジを加えた特製オリジナル味噌。お肉に味噌の味と香りがしっかりとしみ込み、おかずに、ビールにぴったり と。そしてこちらが正面玄関なのであろう。海老名市庁舎の落成記念として市の発展と繁栄を願って制作されたこの記念像。台湾の彫刻家の朱銘氏の作品で、人が両手を広げ大きな心で温かく迎え入れる姿を太極の十字手に倣って表したものであると。「海老名市役所」を後にして、来た道を戻る。途中「コメダ珈琲海老名大谷店」の角を右折して西へと進む。左手にあったのが「神奈川県立海老名高等学校」の正門。相模川に繋がる水路を渡る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.10.22
閲覧総数 359
-
-

- 旅のあれこれ
- 旅ブログ さんふらわあ ふらの
- (2025-11-25 15:36:54)
-
-
-

- 中国&台湾
- 高市首相、台湾有事での 「集団的自…
- (2025-11-27 19:34:43)
-
-
-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…
- エグゼクティブラウンジ 朝食 ヒル…
- (2025-11-26 00:10:04)
-







