[ミステリ] カテゴリの記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-

「恋の花詞集」 【橋本治】
「序」の「青葉茂れる桜井の」から、「霧深きエルベのほとり」まで64曲とりあげ、それぞれの歌の生まれた時代、なぜその歌が受け入れられたかなどについて述べている。 歌の解説でもあるのだが、その歌が流行した背景を考察する方が重点が置かれている。 かといって、社会の風潮をあれこれ並べるというわけでもなく、例えば、「青い山脈」のところでは、歌詞の分析から時代を読み解くということもしている。 やはり著者は頭がいいし、文章もうまい。ロカビリー青年というのは、実は“宝塚の男役の男版”みたいななんなんですね。女にうけるのは当たり前です。(p355)なんて、常人には思いも至らない。 昭和40年までの歌だけなので、社会風俗なんてわたしは覚えていないのだが、一つだけ、「そう言えばそんなことがあった」というのがあった。成人の日を前にしたバスガールの振り袖姿(p331)というものだ。 成人の日になると、バスの前に並んだ振り袖姿の集合写真を見た記憶がある。 そうか、あれは、「自分で働いて自分の晴れ着が買える」ということだったのか。 「星は何んでも知っている」の「木ぼりの人形」の謎も、この本で解けた。 人形といったら「フランス人形と日本人形と温泉コケシ」しかなかった時代に若い娘がにぎって眠るとしたら、それは新しく入ってきたもので、「小さなインディアンの人形」だろうというのだ。 知っている歌もあれば知らない歌もあった。 美空ひばりが笠置シズ子のマネから出発したなんてしらなかった。 「若いお巡りさん」が三番では夜勤明けに納豆屋さんに呼びかけているのも知らなかった。 その納豆屋は学校に通っているのだ。子どもの納豆売りなのだろう。 なぜこの本を書いたかというと、橋本治は歌謡曲が大好きだからなのだ。 だからといって誉める一方というわけではない。変なものは変だ、でも、好きだ、なのだ。 いきなりとんでもない声で「逃げた女房にゃ 未練はないが」と、ほとんど未練丸出しで歌う一節《ひとふし》太郎の声に、まともな人ならみんな仰天した。(p432)というところは読んでいて笑ってしまった。 でも、橋本治は、この歌に時代を感じ取り、これを受け止めた日本の人々の精神に思いをはせ、この歌のすごいところをちゃんと示すのである。 疑問に感じたところ。『青い山脈』の映画の舞台になったのは海のある、温泉のある、暖かい伊豆半島なんですね。(p247) つい最近見たばかりなのだが、てっきり、原作と同じように東北なのだと思っていた。 言われてみると、暖かい土地の話のような気もするなあ。 楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2007.11.16
コメント(0)
-

「翼ある闇」 【麻耶雄嵩】
講談社ノベルス。1993年6月5日。 長編ミステリで、著者のデビュー作。 凝りに凝っている。 京都の近くのヨーロッパ風の洋館(古城?)蒼鴉城での連続殺人と、それにまきこまれた名探偵、そしてその友人。 その友人の方が主人公で、その一人称で語られる。 基本的には、謎解きを中心にしているのだが、仕掛けは二重三重で、また、いわゆる「人間ドラマ」の部分があまりにも濃厚であるために、内容はぎっしり詰まっている。 とにかく、手元にあるものは何でも使おうという若さが感じられる。 副題が「メルカトル鮎最後の事件」で、なるほどこれでは最後の事件になるわけだ。 トリックの部分は、違う人間の頭部と胴体が密室で発見された理由の所は、「いくらなんでもそんなことはないだろ」といいたくなるが、それが真実かどうかは、確認されないままになっている。 登場人物が聖書の故事にやけに詳しいのは、作者の趣味なのだろうか。 同じ作者のものは、「鴉」を読んだことがある。 二作に共通するのは、「過去の清算」である。 封印されたはずの過去を解き明かし、清算することが主眼となっている。 特にこの「翼ある闇」ではその傾向が強い。 また、メルカトル鮎は、どちらにも登場するが、作者にとって重要なのは、この人物なのではなかろうか。 おそらく、この人物は、主人公の一部なのだ。もちろん、物語の中では、一人の独立した人格として登場し、ほかの登場人物にもそう見えているのだが、主人公のある面を、違う角度から描いたものなのだろう。 野崎六郎の解説は、最近のミステリ界について論じたもので、何も知らない私には何のことかわからない。 しかし、珍しく、ワープロではなく手書きで書いたものらしい。 「与《くみ》する」ではなく「組みする」、「見返り」ではなく「見返えり」という表記が見られる。 表記といえば、「まじまじ」と書くのが普通の所で、二度目の「まじ」が、「く」を縦長にした踊り字になっている箇所(p204)があったのが不思議だった。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。
2007.03.23
コメント(0)
-

「羊たちの沈黙」 【トマス・ハリス。菊池光・訳】
新潮文庫。1989年09月 映画化されたそうだが、見ていない。 クラリス博士というのが唐突に出てくるが、そういう趣向なのだろうと思っていた。 翻訳者による解説で、実は連作の第2作だということで、作者は、読者にとっては既知の人物として書いているのだ。 ミステリなので、細かいことは書かないでおく。 専門用語などが出てきて読みにくい面はあるが、ミステリとして良くできていて、読者を引き込む力を持っている。 読み方が悪いのか、昆虫がどれだけ役に立ったのかわからなかった。 内容とは別に、訳文でのカタカナ表記が気になった。 「データ・ベイス」「テイブル」は、それぞれ、日本語における外来語としては「データ・ベース」「テーブル」と表記するのが普通だろう。 「フッドを外す」(p79)は、最初は意味がわからなかったが、「hood」で、日本語では「フード」と表記するものだと思われる。 「ブーティーク」も、日本では「ブティック」だ。 これが悪いというのではない。 翻訳者もまた文筆家であり、自分がどのように表記するかということに自分なりの考えがあって当然だ。 編集者が表記について注文をつけることも考えられるが、自分の表記を押し通せるだけの力がある人なのだろう。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。
2006.12.28
コメント(0)
-

「誰もわたしを倒せない」 【伯方雪日】
「挌闘技を真っ向から取り上げた初の本格ミステリ」というのにひかれて読んでみた。 「挌闘技」といっても、武術ではなく、プロレスといわゆる「総合挌闘技」の世界。その中であった殺人事件と、登場人物の人生が描かれる。 プロレスファンとしては、プロレス面を描いて欲しいところだが、ミステリなので、当然、事件と謎の方が中心になっている。 ライガーとサムライとカシンを会わせたようなレスラーの話が出てくるが、事件に飲み込まれてしまう。 それでも、「ああ、あれがモデルだな」と、モデルになったレスラー、事件が思い浮かぶのが楽しくはある。 視点が入れ替わるので、慣れるまでは読みにくい。「ふんふん」と軽い気持ちで読んでいると、思いがけない人物の視点で描かれていたりして驚く。 プロレスファンの視点から最も面白かったのは、笹川吉晴による解説。 ミステリ作家をプロレスラーに見立てているのが、「なるほど」と思わせる。 松本清張のエリートへの怨念に猪木との共通点を見いだしているのはさすが。 主要な登場人物である「犬飼優二」に船木誠勝のイメージを重ねている。わたしもそう思った。 おそらく解説者がうっかり書き漏らしたのだろうが、船木誠勝の本名は船木優治で、作者はそのことを意識して「犬飼優二」という名にしたのかもしれない。 ミステリなので、本筋に関わることは控える。 気になったところ。 「若干二十五歳のカリスマレスラー」(p148)。最近は、本来は二十歳をいう「弱冠」を「若い」という意味で使うことが多くなっているが、「若干」では全く違う。これでは二重の誤り。 第四話に「チョークスリーパー」が出てくるが、チョークなら、のど仏にも跡が残るのではないだろうか。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。
2006.11.27
コメント(0)
-

「ある閉ざされた雪の山荘で」 【東野圭吾】
この作者の名は何度も目にしたことがあったのだが、初めて読んだ。 ペンションに集められた若者7人。いずれも、ある舞台のオーディションの合格者。 豪雪のために周囲から孤立し、外部と連絡が取れなくなったという設定だけを知らされて稽古が始まるが、架空のはずの殺人事件が、現実のものとなっているとしか思えなくなる。 という設定のミステリ。 本格ものでありながら、本格もののパロディめかした書き方で、登場人物のために「そして誰もいなくなった」などが用意されていたり、ミステリ談義があったりする。 三人称と一人称が混在しているような書き方なのだが、実はその書き方にも意味がある。 非常に凝った構成になっている。 ミステリなので、詳しく内容を書くことはできない。 非常に面白く、一気に読んだ。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。
2006.11.03
コメント(0)
-

「モーダルな事象 桑潟幸一助教授のスタイリッシュな生活」 【奥泉光】
文芸春秋社。2005年7月30日。 初めてこの著者の本を読んだ。「新・地底旅行」は新聞連載時に何回分か読んだのだが、1回あたりの分量が少なすぎて話が頭に入らず、途中で購読紙が代わったりして全部は読まなかった。 漱石が好きらしいと、それで知った。 この本の文体は饒舌多弁で不必要と思える情報が過多で、諧謔に満ちている。 こういうものは、よほどエネルギーがなくては書けまい。 文章が長いのだが、面白いので飽きることはない。しかし、話はなかなか進まない。 元夫婦があちこち出かけては食事や起床時間のことでもめたり、互いの知識や推理を披露しては、少しでも自分が優位に立とうとするあたりが実によく書けている。 さて、物語はというと、無名のまま終わった作家の原稿が発見され、しがない短大助教授がそれを紹介する役目を引き受けたことから事件に巻き込まれ、幻想の世界で恐怖を味わい、殺人事件が起こり、女性ジャズシンガーと編集者の元夫婦が探偵気取りで真相解明に乗り出し……と、ミステリーのようなのだが、謎解きが中心なのではなく、つまるところ、助教授の内面に大きな変化が起こり、元夫婦はそれなりの関係を維持していく、と、こう書くと説教くさいように見えてしまうのだが決して左様な堅苦しい話ではないのであって、エンターテインメントである。 SFの要素もあって、幻想の世界でなのか現実になのか過去と行き来し、それまでに存在していた円環をくずことになる。 と、話の内容を紹介しようとしてもしきれない。 今までに私が読んだことのあるものの中で、強いて何に似ているかというと、諸星大二郎の「暗黒神話」を思い起こさせるところがあった。 表現として、視覚に訴える部分が強い。 新聞記事は新聞記事のコピーの体裁をしており、雑誌の記事はゴチック体か太字。手書きの手紙は教科書体。 見た目の印象が違う。 表記で目立つのは、コンクリートは必ず「混凝土」に「コンクリート」とルビが振った書き方にしてあること。 これは漱石に用例があるかどうか知らないが、漱石の文章のような雰囲気を出したいのだろう。 気になったのは「病膏肓」(p457)。文字は正しく「膏肓」(こうこう)となっているのに、ルビは「やまいこうもう」になっている。「病膏盲」は「肓」を「盲」と見誤ったために生じた表記。「肓」は「もう」とは読まない。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください
2005.09.27
コメント(0)
-

「新・探偵物語 2 国境のコヨーテ」 【小鷹信光】
(著者:小鷹信光|出版社:幻冬舎文庫|発行年月:2001年10月) なぜこのシリーズを読むのか。 それは、あのテレビドラマと松田優作の幻影を追っているからだ。 表紙も明らかにテレビの工藤俊作、すなわち松田優作である。 しかし、読んでいるうちに、これはテレビとは全く関係のない話だということはわかる。いや、読む前からわかっている。 それでも幻影を求めて読むのだ。 読んで、全く違うからと言ってがっかりするかというと、そういうことはない。 面白かった。 舞台はアメリカとメキシコの国境地帯。 人捜しの仕事をしていた主人公は、思わぬ事件に巻き込まれてしまう。 n何もしなくても国境を合法的に越えられるところを、「少しでも早く」という理由で非合法に越える場面がある。 ある集まりに間に合うようにということなのだが、「国境のコヨーテ」に関わるためにはこれが必要なのだ。 文体はあえて翻訳調にしてある。 長さの単位はフィートやマイル。「ペッカリー(ヘソイノシシ)のようにずんぐりした左の男は左手を、ビッグホーン・シープ(オオツノヒツジ)のようにひょろっと首の長い男は右手を」(p48) というところなど、意識してこうしているのだろう。 このシリーズでまだ読んでいないのはあと1冊。 残さず読みたいと思う。
2005.05.19
コメント(0)
-

「朝霧」 【北村薫】
[著者:北村薫|出版社:創元推理文庫] シリーズ第四作。 第一話「山眠る」は主人公の「私」が大学を卒業する直前の時期。 第二話「走り来るもの」と第三話「朝霧」は就職後。 第二話でいきなり就職して三年目になっており、第二話と第三話は時間がつながっている。 殺人や盗みのような警察が絡むような事件ではなく、日常生活に潜む謎を解き明かす。その謎の設定にいつも感心する。 そして、恐くなる。 主要な登場人物は善人ばかり。 しかし、謎の背景には闇があるのだ。 第一話の小学校の校長、第二話のリドルストーリー。 底知れぬ暗黒を背景にして演じられている舞台劇のように思えることがある。 背景が暗いだけにかえって演じている人物が明るく浮き上がって見える。 人物がそろって明るいから、そこだけを見ていると明るい話なのだが、背景に目を向けると底知れぬものを感じる。 もちろん、登場人物は皆、背景が暗黒であることを知っているのだ。 また、周到な伏線に驚く。最初から、かなり先のことまで考えて書いているのがよくわかる。 主人公の人生はあらかじめ決まっていて、その節目節目を描いているというわけだ。
2005.03.18
コメント(2)
-
「赤き馬の使者 探偵物語2」 【小鷹信光】
赤き馬の使者(著者:小鷹信光|出版社:幻冬舎文庫) シリーズ第2作。 第1作と同じく、過去の清算が主題となっている。 中心は、主人公の過去ではなく、かつて関わった家族の謎。 作者は、第1作を書いた時から、この話まで頭の中にできていたのだろう。この話までで、工藤俊作の過去の清算は終わる。 最初に出版されたのは1980年。 読んで、あの頃は、電話をかけるには、10円玉が必要だったのだなあと、当時は当たり前だったことを新鮮に感じてしまった。 解説では、テレビの『探偵物語』とは切り離してとらえた方がいい、と主張している。 それはそれで正しいのだが、切り離すのは難しい。 表紙は紛れもなく松田優作の似顔絵だ。 文庫に収められたのも、テレビでの再放送がきっかけだったのではないかと思う。 解説よりもあとに〈付記〉があって、主要舞台である「鹿射」は架空の町だと断っている。 調べてみたら、「鹿射」ならぬ「鹿討」という駅が富良野線にあった。 〈付記〉では、「人物、場所、施設などもすべて虚構である」とまで断っている。 これを読んで何か誤解した人でもいるのだろうか。
2003.05.22
コメント(0)
-

「鴉」 【麻耶雄嵩】
鴉(著者:麻耶雄嵩|出版社:幻冬舎文庫) 長編ミステリ。文庫で549ページもある。 人間関係が複雑に絡み合っているのだが、土台になっているのは、主人公の、弟への屈託した思い。過去を精算するために現在がある、というパターン。 主人公と弟の名が、可允(かいん)と襾鈴(あべる)というあたりで、そんな名前を付ける親がいるわけないだろう、と思うが、なぜそういう名になっているのかは最後で明らかになる。 外界から隔絶した村が舞台。どうやって隔絶を保っているのかはわからない。金属製品はどこから手に入れているのだろう。 村の設定は、諸星大二郎風。 殺人があり、主人公による謎解きがあり、どんでん返しがある。 メルカトルという人物が何者なのかは結局わからないが、ほかの作品に登場する探偵役らしい。 長くても退屈せずに読み終えたが、どうもなじめない。
2002.06.11
コメント(0)
-

「邪馬台国はどこですか?」 【鯨統一郎】
邪馬台国はどこですか?(著者:鯨統一郎|出版社:創元推理文庫) 歴史ミステリの連作短編集。 第三回創元推理短編賞の最終選考まで残った表題作を中心に、文庫で書き下ろしたもの。 カウンター席だけのバーを舞台に、登場人物はつねに四人。議論だけで話が進んでいく。 邪馬台国は岩手にあった、という表題作を始め、釈迦は悟りを開いていなかった、明智光秀の謀反は信長の意向によるものだった、など、通説を覆す結論を先に提示し、それを論証していく。 聖徳太子非実在説は目新しくはないし、明治維新の黒幕が勝海舟だった、というのは『氷川清話』を読めば察しがつくことだが、それらを論証してみせるところに作者の技量が感じられる。 バーが舞台だが、飲み物は水割りが多い。つまみも何種類も出てくるが、つまみの説明がもっとあってもいいのでは。 面白いのが、著者略歴。「国学院大学文学部国文学科卒業。」 これだけ。 ところが調べてみると、国学院大学には、「国文学科」というのは存在しないのだ。1997年に「日本文学科」というのはできたが、それ以前は「文学部文学科」に日本文学も中国文学(というより漢文学)も含まれていた。 この略歴には何か意味があるのだろうか。
2002.06.06
コメント(0)
-

「ひまわりの祝祭」 【藤原伊織】
ひまわりの祝祭(著者:藤原伊織|出版社:講談社文庫) ハードボイルド・ミステリーである。 時間経過は長くなく、発端から終わりまでの期間は短い。一ヶ月はたっていないのではないか。 「僕」の一人称。 主人公の造形が、「絶対にこんな人間はいない」というタイプなのだが、読んでいるうちに不自然に思えなくなるのは作者の力量によるのだろう。最初のうちは、決して走ったりしそうにない感じなのだが、終盤にさしかかると、一日のうちに人並みはずれた運動量を見せる。 「ひまわり」については、いろいろ調べて書いたようだ。説得力がある。 気になるのは、過去が重要であること。 過去を清算するために現在がある、という設定なのだ。 最近読んだ、小鷹信光の「探偵物語」もそうだった。(これは20年以上前のものではあるが) こういう、ウェットなハードボイルドをネオ・ハードボイルドというのだろうか。
2002.06.04
コメント(0)
-
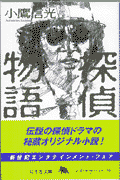
「探偵物語」 【小鷹信光】
探偵物語(著者:小鷹信光|出版社:幻冬舎文庫) 1979年から翌年にかけて日本テレビで放送された「探偵物語」の原案。(原作ではない) 当時大好きだったし、その後再放送も何度も見た。原案者のこの小説があることは知っていたが、雰囲気が違うようなので読まずにいた。 それが最近文庫化されたので、読んでみた次第。 ナンシー、かほり、服部刑事、松本刑事と、登場人物の名前を見ると、企画段階から関わっていたことが分かる。とくに、ナンシーとかほりは、俳優の名前そのままなので、出演者が先に決まっていて、それにあわせて設定を作っていったものらしい。 小説はハードボイルドではあるが、ウェットである。ハードボイルドというのはもっと乾いた感性のものかとおもっていたのだが、この小説はそうではない。 非常に狭い人間関係の中で話が進んでいく。偶然に見える出会いが多いようにみえるが、それは皆必然だったということになっている。 最後の方で、なぜ黒崎が撃たれなくてはならなかったのかはよく分からない。 しかし、なるほどこういう書き方もあるのか、こういう小説もあるのか、と新鮮だった。続編も読んでみようかと思う。 なお、解説で、主人公が下北沢に事務所をかまえていることを、テレビとの類似点としているが、テレビでは、渋谷である。 また、初版だけの誤植ではないかと思うが、表紙カバーの著者紹介で、一九六三年生まれ、となっている。これがほんとうなら、「探偵物語」当時は十六歳になってしまう。一九三六年生まれか?
2002.05.21
コメント(0)
-

「虚無への供物」 【中井英夫】
虚無への供物(上)(下)(著者:中井英夫|出版社:講談社) その名はずっと前から知っていたが、初めて読んだ。 推理小説ではあるのだが、推理小説を書こうとして書かれた小説ではなく、トリックの考察が多くの部分を占めているものの、そういうことよりも、「ザ・ヒヌマ・マーダー」の背景となっているものを書きたかったようだ。 小説を書いたのではなく、自分の中にあったありとあらゆるものを一気に吐き出したもの、という印象を受けた。
2001.08.11
コメント(0)
-
「秋の花」 【北村薫】
秋の花(著者:北村薫|出版社:創元推理文庫) 人の心の闇を覗く小説である。 ホラー小説よりも恐ろしい。シリーズ初の長編だが、事件が中心になっているわけではない。最初と最後、そしてところどころで触れられている、という印象が残る。 日常生活の中で、気づかずにいるだけだが、ふと振り向くとすぐ後ろに闇が存在していることがあるのだ、ということが語られている。 登場人物の中に、悪意で行動する人間は一人もいない。だからこそ怖いのだ。 このシリーズの表紙は、高野文子で、どれにも、同じ姿勢の主人公のイラストが描いてある。髪型と服が違うだけだ。そして、どれも沈んだ表情をしている。十年前に発表されたものなので、全部読んだ上で文庫版の表紙を書いたのだろうが、改めて高野文子の感性の良さに感心させられた。
2000.01.17
コメント(0)
-
「夜の蝉」 【北村薫】
夜の蝉(著者:北村薫|出版社:創元推理文庫) 女子大生を主人公としたシリーズの二作目。 相変わらず、犯罪の犯人探しではなく、日常生活の中のちょっとした事件の謎を解く。 しかし、謎解きはむしろ添え物であって、主人公の内面の成長が主題であるようだ。 主要な登場人物がそろいもそろって博学多識なのが現実離れしているが、これは小説であって現実ではないのだからしがたがない。
1999.11.10
コメント(0)
-

「猿丸幻視行」 【井沢元彦】
猿丸幻視行(著者:井沢元彦|出版社:講談社) 第26回江戸川乱歩賞受賞作。ずっと昔から気になってはいたのだが、いままで読む機会がなかった。ミステリというよりはSFだと思うのだが、ミステリの範囲はすでに20年前にここまで広がっていたのだな。 話は面白い。よくできているし、よく調べてある。特に、人麻呂から猿丸になったのではなく、その逆であるとという発想が秀逸。ただ、暗号解読のくだりと、終わりの方で会話だけで謎の解明がなされるところがややわかりにくい。 また、あくまでも折口の目で見たものしか知り得ないはずなのに、そうなっていない部分もあってちょっと残念。 しかしこれを26歳で書いたというのだから大したものだ。世の中にはすごい人がいるんだなあ。
1999.06.29
コメント(0)
-
「空飛ぶ馬」 【北村薫】
空飛ぶ馬(著者:北村薫|出版社:創元推理文庫) 最初の一話を読んだところで、これは、アームチェア・ディティクティブであり、『九マイルは遠すぎる』なんだな、とは分かる。一人称で、主人公の名前が明かされないところは『血の収穫』というところか。 最も感心したのが、事件が殺人や盗みといった大きなものではないことである。日常生活の中に起こるかもしれないことを謎として設定しているのがすばらしい。 陰惨な殺人事件が起こり、犯人の過去やら出生の秘密やらが明らかにされていって……というのも否定はしないが、こういった、日常的なことを事件として考え出す方が困難なことだろう。 ただ、十九歳の主人公が物知り過ぎるのが気になるが、ま、そんなことまで言い出したら、そもそも小説というものが成り立たないわけで、よしとしましょう。
1999.06.18
コメント(0)
-

「リング」 【鈴木光司】
リング(著者: 鈴木光司|出版社:角川書店) こういう話だったのか。なるほど。 勢いがあって最後までぐいぐい読ませるものがある。 しかし、どうも引っかかるものがある。例えば、なぜ最初に死ぬ四人は、スッと死ぬのではなく、ああいう死に方をしなくてはならなかったのか。それが説明されていない。 一番納得できないのが、横浜に住む少年が南箱根でビデオを録画する時に、放送されているのとは違うチャンネルに合わせてしまったのではないか、ということになっているのだが、箱根は神奈川県なので、チャンネルは同じはず。 昔はこういうものはSFに分類されていたものだが、今ではそういうことはないらしい。帯にも解説にもSFの文字はない。
1999.01.19
コメント(0)
-
「六の宮の姫君」 【北村薫】
六の宮の姫君(著者:北村薫|出版社:創元推理文庫) 名の明かされない女子大生を主人公としたシリーズ第四作。 円紫師匠はあまり出てこない。主人公がほとんど独力で謎を解いていくのだが、その謎は犯罪などではなく、なぜ芥川龍之介は「六の宮の姫君」を書いたのか、という謎なのである。 作者が昔興味を持って調べたことがもとになっているらしいが、見過ごしてしまいそうな細かい点に着目して調べていくたちの人なのだろう。だからこそ、こういうミステリーが書けるわけだ。 老大家の思い出話として、芥川が「あれはキャッチボールだ」と言ったことが出発点になるのだが、これは作者の創作のはず。結論を導き出すために作り出したのだろうが、違和感がない。 このシリーズを読んでいて漠然と感じていたことなのだが、主人公も円紫も、というより、どの登場人物も、他人からはうかがい知ることのできない孤独感を抱えて生きているように思えてならない。 さりげなく描写される登場人物のしぐさにそれが表れているように思うのだが。
1999.01.14
コメント(0)
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
-

- 楽天ブックス
- 【特製フォトしおり付き】二宮和也の…
- (2024-11-12 23:26:03)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- IMA 2024 Autumn/Winter Vol.42 の続…
- (2024-11-12 15:36:41)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 死はすぐそばに アンソニー・ホロヴ…
- (2024-11-11 19:50:46)
-







