2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年04月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
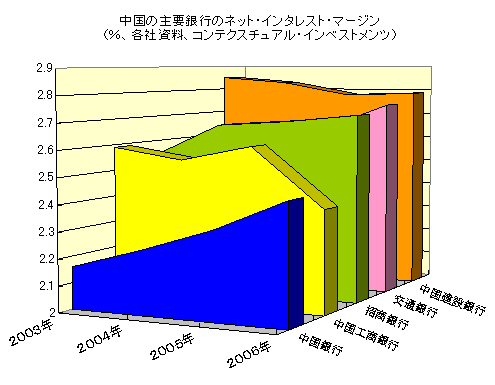
第83回 中国の金融サービス・セクター(その4)
今日のまとめ 1.ネット・インタレスト・マージンは利鞘の指標 2.総資産利益率では中国建設銀行が安定的にリードしている 3.ノン・パフォーミング・ローン比率では各行とも随分改善した ここ数日の間に中国建設銀行と招商銀行が相次いで決算発表しました。これで中国の主要銀行の2006年の決算が出揃ったことになります。そこで各行の営業の内容を比較検討してみたいと思います。ネット・インタレスト・マージン 銀行の収益力を見るひとつの尺度が調達金利と貸付金利の差額であるネット・インタレスト・マージンです。特に中国の銀行はフィー・ビジネスのような商品が未だ発達しておらず、貸付主体のシンプルな経営構造ですからネット・インタレスト・マージンを見ることは有効だと思います。この数字は当然、大きければ大きいほど良いです。下のグラフを見ると中国建設銀行のマージンが2.79%と2006年の時点でここに掲げた5行中一番大きいばかりでなく、過去においても比較的高い水準をコンスタントに維持していることがわかります。交通銀行は2003年の時点では2.54%でしたが2006年には2.75%へと着実に拡大しています。招商銀行も2003年の時点では同じく2.54%でした。2006年のマージンは2.72%です。これら三行に比べると中国銀行(2.54%)と中国工商銀行(2.39%)のマージンは見劣りします。なお、最近、人民銀行は預金金利、貸付金利をそれぞれ引き上げつつありますが、換金性の高い預金であるデマンド・デポジットはこの利上げの対象外でした。従って最近の利上げはデマンド・デポジットによる調達の比率が高い中国建設銀行などにとってはネット・インタレスト・マージンの拡大要因であると言えます。総資産利益率(ROA) 次に同じく銀行の収益性の尺度のひとつである総資産利益率(ROA: Return on Asset)について見てみましょう。この数字も高ければ高いほど良いです。ここでも中国建設銀行が他行より高い利益率(0.92%)を示しています。中国銀行(0.96%)、招商銀行(0.81%)、交通銀行(0.78%)らも改善基調にあります。その中で中国工商銀行(0.71%)が伸び悩んでいることが読み取れます。ノン・パフォーミング・ローン比率 ノン・パフォーミングというのは「焦げ付き」という意味です。従ってこの指標は貸付総額に対する焦げ付き比率を示しています。当然、数字が小さければ小さいほど好ましいです。このグラフを見ると一番ノン・パフォーミング・ローン比率の高い中国銀行でも4.24%(2006年)とまずまず容認できる水準です。特に中国の銀行はかねてから不良債権が多いことで知られていましたから昔を知る人が見たら最近のノン・パフォーミング・ローン比率は随分良い数字のように思えます。ただ、これらの数字が改善したのは主に中国政府からの資本注入によるバランスシートの「大掃除」が寄与している部分が多く、経営努力によるものだけではありません。なお中国建設銀行のノン・パフォーミング・ローン比率の山が低いのは注入のタイミングが早かったからです。おおまかに言えば最近になって資本注入された銀行ほどノン・パフォーミング・ローン比率の改善が遅かったという風にも言えるでしょう。なお、これは余談ですが今回の中国の四大銀行の相次ぐIPOのように上場しなければいけない案件が幾つか待機している場合、株の売り出し元(この場合、中国政府とそのファイナンシャル・アドバイザー達)は最初に一番内容の良い案件をぶつけるというのは投資銀行業界の常識です。その理由は最初に出来の悪い会社をIPOしてそれがズッコケたら、後に続くIPOが出せるものも出せなくなってしまうからです。さらに一発目のIPOが成功して人気になれば二番手以降の案件の発行条件も売り手側に有利な条件へと誘導できる利点もあります。ですから四大銀行のうちの一番手が中国建設銀行であり、最後が中国農業銀行(これは未だ出ていませんが)であるという事実は深く考えてみる価値のあることなのです。焦げ付きに対するカバレッジ・レシオ 次に焦げ付きに対する引当金がどれだけとってあるかの比率について見ます。この数字は高ければ高いほど良く、100%を超えていれば現在わかっている焦げ付きローンに関しては「カバー出来ている」と解釈します。もちろん、現実には銀行のバランスシートの健全性は信用市場の置かれた環境などに左右されて刻々と変化してゆくものですからカバレッジ・レシオが今100%を超えているからといって安泰という風には断言出来ません。投資家が特に気をつけるべきシナリオというのは上で見たノン・パフォーミング・ローンが上昇、つまり焦げ付き額が増えているにもかかわらずカバレッジ・レシオが下がってくるようなケースです。大体、焦げ付きというのは融資先の多くが返済に困っている状況(それは不景気のときなどにそうなります)に増えるものですが、そういう時こそ慎重な経営者は引当金を積み増すものです。しかしそうすると利益に響きますから軟弱な経営者はついつい目先の決算を良く見せる誘惑に負けてしまうわけです。幸い上のグラフで見たように現在の中国の銀行のノン・パフォーミング・ローン比率は安定的に推移しています。さらに下のグラフに見られるように各行はカバレッジ・レシオを引き上げつつあり、その意味では「ちゃんと正しいことをやっている」と評価できます。尤も中国工商銀行の70.56%(2006年)というカバレッジ・レシオにはちょっと寂しいものがあります。ティア・ワン・キャピタル・レシオ 最後に中国の銀行の自己資本(コア)比率をチェックしておきます。この数字は勿論、大きいことに越したことはありません。しかし不況などで銀行の経営環境が厳しくなる場合を除いて普段は株価を占う上で重要な尺度ではありません。
2007年04月19日
-
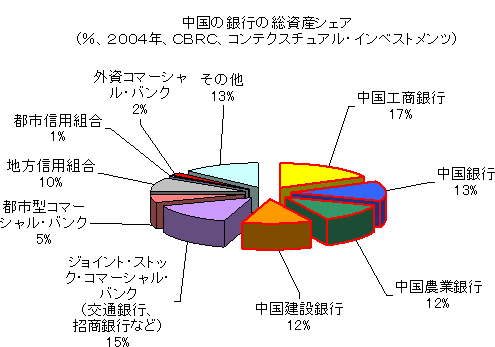
第82回 中国の金融サービス・セクター(その3)
今日のまとめ 1. 四大銀行は元を辿れば同じルーツである 2. 専門銀行としての業務分野の棲み分けはぼやけつつある 3. 国有企業中心の融資から個人向け融資へのシフトが各行の課題である■国策銀行としてスタート 共産主義下の中国では人民銀行が中央銀行の役割を果たすとともに預金を集めたり貸付をしたりという商業銀行の役目も果たしていました。1970年代の後半から中国の経済改革の一環として銀行制度も改変され、人民銀行の持つ中央銀行としての機能とそのほかの商業銀行としての機能が分離されました。商業銀行業務はさらに4つの専門分野に分割され、建設およびインフラストラクチャー整備に対する融資を司る中国建設銀行(0939)、都市部における商業への融資を司る中国工商銀行(1398)、農業部門への貸付を司る中国農業銀行、為替や貿易ファイナンスを司る中国銀行(3988)という4つの専門銀行が設立されました。これが現在中国の銀行セクターにおける総資産シェアで全体の過半数を超える所謂、「四大銀行」のルーツです。そういう歴史的経緯から四大銀行の持つ国策銀行的色彩は例えば1987年に深センで創業した招商銀行(3968)やその歴史を1908年まで遡る交通銀行(3328)とは一線を画しています。 1980年代初頭になると四大銀行は自分の専門領域以外の分野で他行と競争することが許されました。 こうして各行間の棲み分けの境界線はだんだんぼやけていったわけです。2005年の末での各行のセクター別融資残高の内訳は下の図のようになっています。 こうしてみると確かに中国建設銀行は不動産・建設セクターへの融資比率が高いですし、中国銀行は貿易・サービスセクターへの融資比率が高いです。しかし全体のバランスから考えるとそれらの差異は殆ど問題にならない程度だと思います。■個人への貸付に傾斜 融資先を分析する際、上で見たような産業セクターによる分類ではなく、融資先企業のオーナーシップ、つまり国有企業か民間企業か?という観点から分析する方法もあります。この観点では中国工商銀行の融資の55%、中国建設銀行の融資の47%が国有企業向けです。あくまでも一般論ですが国有企業は内容の芳しくない企業が多いのでそれらに対する融資の比率を今後下げてくることが好ましいと思います。また、中国の場合、個人に対する貸付はまだまだ他の先進国に比べると少ないです。下のグラフは各国の銀行の貸付に占める個人向け貸付の比率を示したものです。 同じ問題を別の角度から見てみましょう。今度は個人向け貸付をGDPの規模と比較してみると下のグラフのようになります。このことからも中国の個人向け市場はまだまだ成長余地があることがわかります。 従って今後の各行の課題としてはリテール・バンキング(個人に対する小口銀行サービス)を充実させてゆくことが鍵になると思います。そこでリテール・バンキングのひとつの代表商品であるクレジット・カードの普及率をみると下のグラフのようになります。 中国におけるクレジット・カードの普及が遅れていた理由は規制が厳しかったことに加え、全国ネットの支払いインフラストラクチャーの構築の遅れ、さらに最近まで消費者信用情報システムが無かったことなどが影響しています。しかし最近ではクレジット・カード業務を認可された銀行が増えているのに加え、「チャイナ・ユニオンペイ」と呼ばれる銀行間の統一情報システムが構築されたこと、さらに人民銀行が全国ネットの消費者信用情報システムをスタートさせたことなどから今後の成長に弾みがつくと予想されます。 一方、リテール・バンキングのもうひとつの代表商品である住宅ローンに関しては2001年末の時点で5,598億人民元だったローン残高は2005年末までに1.8兆人民元まで伸びました。なお、昨今の不動産市場の過熱に鑑み中国政府は不動産セクターにおける融資基準を引き締めています。
2007年04月17日
-
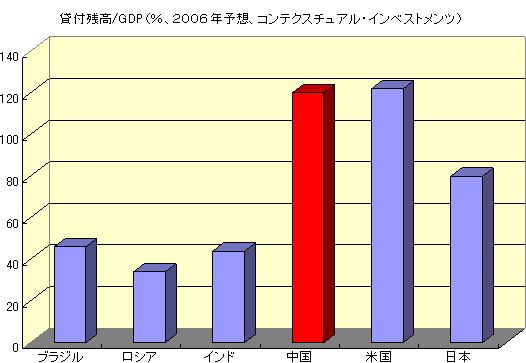
第81回 中国の金融サービス・セクター(その2)
今日のまとめ 1. 貸付残高対GDP比で見ると既に中国は世界で最も銀行業が浸透している 2. 中国は間接金融型の経済である 3. 中国の銀行は十分な貸付余力がある 4. 野放しな貸付成長は安定的マクロ経済運営の観点から好ましくない■中国における銀行サービスの普及度 或る国においてどのくらい銀行サービスが浸透しているかを知るひとつの尺度が融資残高をGDPの規模と比較してみるやり方です。これで言うと中国の融資残高は既にGDPの120%に届こうとしており、アメリカと並んで世界で最も銀行業が浸透している国であると言えます。 但し中国の場合、法人向け貸付がその殆どを占めており個人向け融資は融資全体の11%に過ぎません。次に銀行の総資産を比較してみるとここでも中国のそれは日本を凌駕しています。 これは或る意味で中国は既に「オーバー・バンクト(Over banked)」、つまり銀行サービスが過剰になっていることを示唆していると思います。ただ、それに対する反論として中国の経済はアメリカのような直接金融(株式や社債による資金調達)型ではなく、間接金融(銀行融資による資金調達)型なので上で見たような状況になっているのだという議論も出来るでしょう。下のグラフは調達手法別のシェアを示しています。■貸付成長が中国の銀行の課題ではない 中国の銀行の預金残高と貸付残高の推移を見ると次のグラフのようになっています。最近は預金残高の伸びのほうが著しいことがわかります。 この結果、預金のどれくらいが貸付に回っているかを示すローン・ツウ・デポジット・レシオを見ると2000年には80%だったのが2005年には68%に下がっています。これは一般的には中国の銀行はまだまだ貸付余力があるということを示しています。次に世界の主要国における貸付残高の成長率をみると中国はBRICsの他の国々に比べると成長率は低いです。 ここで重要なのは貸付残高の成長というのは「高ければ高いほど良い」という性格のものではないという点です。事実、中国政府は無秩序な貸付競争を抑えるためにリザーブ・リクワイアメント・レシオをぐんぐん引き上げるなど、いろいろな方策を繰り出して貸付残高成長率を大体15%程度に押さえ込むのに躍起になっています。 この背景には中国政府が無秩序な固定資産投資の増加を抑えようとしていることがあります。 つまり、マクロの経済政策との整合性という観点からも野放しな貸付の成長というのは好ましくないわけです。
2007年04月11日
-
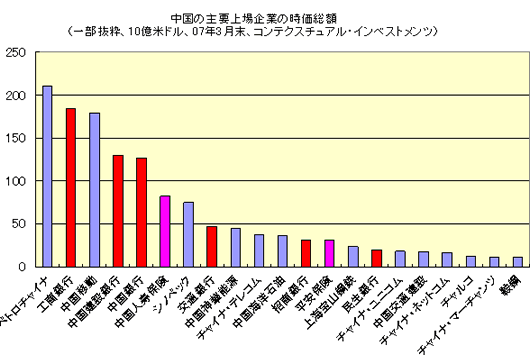
第80回 中国の金融サービス・セクター(その1)
今日のまとめ 1. 金融サービス・セクターは中国株で最も重要なセクターである 2. それらの銘柄の大半は過去2年くらいの間に新規上場された 3. それは中国株全体の成長性を底上げする効果があった 4. 同時に中国株全体のPERも押し上げられた■変貌する中国株式市場 中国の金融サービス・セクターは時価総額という観点からすれば中国株式市場の中で最も重要なセクターであると言えます。下に示したのは中国の大型株の時価総額のグラフですが、このうち銀行株は赤で、保険株はピンク色でハイライトしてあります。 興味深い点としてはこれらの金融サービスの銘柄の大半が過去2年くらいの間に上場された比較的新しい銘柄だということです。このため中国株式市場の性格は極めて短期間の間にそれまでのエネルギーや通信に偏った市場から金融株主体の市場へと変貌しました。このことは株式市場にとってどういう意味を持つのでしょうか? それを考えるために中国の大型株をEPS成長率(横軸)とPER(縦軸)というふたつの要因に基づいてプロットしたのが上のグラフです。EPS(Earnings Per Share)とは一株当たり利益のことを指します。またPER(Price Earnings Ratio)とは株価収益率のことを指し、株価をEPSで割り算した数字です。円の大きさは時価総額の大きさを示しています。斜めに引いた青い線はEPS成長率とPERが等しくなる均衡点を示しており、換言すれはPEG(PE to Growth)レシオで1になる直線です。PEGレシオ = PER ÷ EPS成長率(→これが1以下なら「割安」と考える) すると上のグラフで青線より右下の半分に属する銘柄は成長率に照らしてPERが割安であると考えられ、逆に青線より左上の半分に属する銘柄は割高であると考えられるわけです。さて、このうち青線より右下に入っている銘柄には工商銀行や中国建設銀行など、大型銀行株が多いのに気がつきます。携帯電話会社である中国移動を除いたら、殆どが最近新しく上場された銘柄です。このことは一連の銀行株の新規上場は中国市場全体の平均EPS成長率を底上げする効果があったことを示唆しています。 2年前の中国株式市場における重鎮はペトロチャイナと中国移動でした。これらの銘柄はPER(縦軸)で見ると比較的低い位置にあります。中国人寿保険や工商銀行などはペトロチャイナや中国移動より縦の軸で見ると上に位置します。つまりPERが高いわけです。これは一連の金融サービス株が加わったことで中国株全体の平均PERが吊り上げられたという風にも解釈できます。 さらに青線より右下(つまりPEGレシオで1以下)の銘柄が沢山加わったために中国市場全体の平均PEGレシオは押し下げられたという風に解釈して良いでしょう。これは利益成長と株価を天秤にかけるという評価方法からすると中国市場全体の割安感が強まったことを意味します。■中国株の金利敏感度は高まったか? さて、これだけ大挙して銀行株が新たに加わると印象としては中国市場全体の金利敏感度は高まるかのように感じられます。なぜなら通常、欧米の株式市場の場合、銀行株は金利敏感株であると理解されているからです。その場合、一般論として利下げは金利敏感株にとってプラスに働き、逆に利上げは金利敏感株にとってマイナスに働くと理解されています。しかし中国の銀行株の場合、必ずしも利上げは銀行の収益にとってマイナスにはなりません。例えば3月18日に実施された貸付金利と預金金利の27bpの利上げは銀行にとってプラスに働きました。このような結果になる理由は中国の銀行の資金調達および運用の構造に因るところが大きいです。中国の銀行の調達サイド(貸借対照表のうちの liabilitiesの側)を見ると預金のうちの4割が要求払い預金(demand deposit=当座預金などいつでも引き落とせる預金)となっており今回の利上げでは要求払い預金の金利(現行0.72%)は利上げの対象とされませんでした。つまり調達サイドのうち4割を占める部分は影響を受けなかったわけです。一方、運用サイド(貸借対照表のうちのassetの側)、つまり貸付金利は上がったわけですから全体を合計してみた場合の利鞘(ネット・インタレスト・マージン)は拡大したことになるのです。「利上げ=銀行株にとってマイナス」と一概に言えないことがこれでおわかり頂けたかと思います。
2007年04月09日
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- ひとり言・・?
- PC入力時の手首・肘用ゲルクッション
- (2025-11-19 22:39:26)
-
-
-

- つぶやき
- 楽天ブラックフライデーまず購入した…
- (2025-11-21 06:00:04)
-
-
-

- 楽天写真館
- 21 日 ( Friday ) の日記 寒い…
- (2025-11-21 05:25:14)
-







