2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年06月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
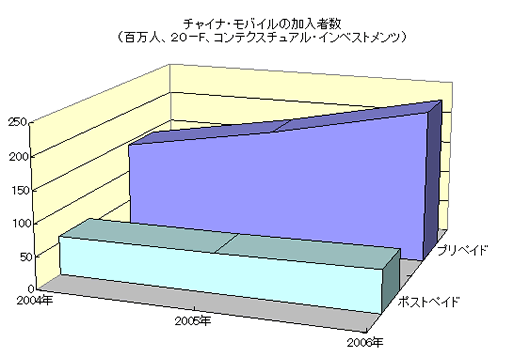
第91回 中国の通信セクター(その2)
今日のまとめ 1. 地方展開が鍵になる 2. プリペイドのARPUは安定している 3. MOUはプリペイド、ポストペイド共に順調に伸びている 4. 事業規模の大きい企業が有利である■地方展開が鍵 中国の携帯電話市場は都市部における普及率は高いですが地方ではまだまだです。従って当面の各社の業績は地方への展開が上手く行くかどうかにかかっています。チャイナ・モバイルを例にとると新規加入者の50%は地方からです。中国の地方の人々の現在の購買力は1994年頃の都市部の住民の購買力にほぼ匹敵します。一人当たりの可処分所得の伸び率では現在は地方のほうが都市部よりすこし高くなっています。但し地方の可処分所得が都市部より伸びている理由は生産性が向上しているからではありません。政府が地方の住民に対する援助策を講じているからです。具体的には90年代はじめに約5%だった地方の個人の実効税率は現在0.5%まで下がっています。但し既に地方の個人の実効税率が0.5%に下がっているということは別の見方をすればもう限りなくゼロに近いのでこれ以上、下げる余地はありません。つまり今後は地方での可処分所得の伸び率は鈍化すると予想されるわけです。下のグラフはチャイナ・モバイルの加入者数の伸びを示したものです。プリペイドというのは或る一定の金額を前払いする料金制度で、支出額が前もって把握しやすいため比較的低所得者層の利用者に好まれます。ポストペイドというのは月末に使った分に応じて請求される料金制度です。今後地方への展開が進むとプリペイドの全体に占める比率はさらに上昇すると思われます。 そこで投資家としては「プリペイドが主流になってもマージンは大丈夫か?」ということが心配になると思います。そこでプリペイドとポストペイドのARPU(Average Rate Per User=平均単価)を比較してみたいと思います。 なるほど確かにプリペイドのARPUはポストペイドよりかなり低いです。ただプリペイドのARPU自体はずっと横ばいで値引きのプレッシャーは感じられません。一方、ポストペイドの顧客のARPUはじりじり上がっているのでこれらをブレンドした平均ARPUはじり高しています。一方、MOU(Minutes of Use=通話時間)はどうでしょうか?。下のグラフはチャイナ・モバイルのMOUです。これを見るとプリペイド、ポストペイド共にMOUは上昇トレンドを描いています。 地方に展開するためにはカバレッジ(通話可能範囲)を広げる必要があります。またプリペイドが主流になるということは比較的低いマージンで、かつ量を沢山こなすビジネス・モデルになります。するとスケールの大きい業者のほうが有利になります。チャイナ・モバイルは現在のマーケット・シェアが68%で他の業者を圧倒しています。このため財務的にも同社は他社よりスケール・メリットがあるので利益が出やすい体質になっています。
2007年06月25日
-
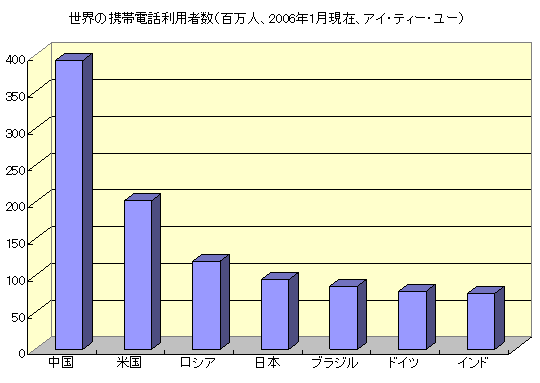
第90回 中国の通信セクター(その1)
第90回 中国の通信セクター(その1)今日のまとめ 1. 中国の携帯電話市場は既に世界一 2. 普及率ではまだまだ成長余地を残している 3. 需要のスウィート・スポットにまさしくさしかかっている 4. 中国市場のMOUは高い■世界一の携帯電話市場 携帯電話会社の株はエマージング諸国の株式に投資する際、格好の投資対象である場合が多いです。その理由は人々の可処分所得が増えたら最初に購入されるのが携帯電話だからです。中国の携帯電話利用者数は2007年4月の時点で既に4.7億人に達しています。これはもちろん世界一です。 しかし既に利用者数が世界一だから中国の携帯電話市場の成長局面は終わったと考えるのは早計です。実際、中国の携帯電話の普及率は2006年末の時点で36%に過ぎません。■携帯電話市場の成長の段階 一般に開発途上国では国民の殆どは所得が低すぎて携帯電話を持ち歩くことは出来ません。そういう国では外国から来ているビジネスマンや政府関係者などごく限られた人が携帯電話の主な利用者です。その場合、携帯電話の料金は会社の経費で落ちるなどの特典がある場合が多く利用者は電話料金には余り頓着しません。これらの国における携帯電話会社は 比較的シンプルなネットワークを構築し、庶民の所得水準からするととても手が出ないような高値に利用料金が設定されることが通例です。アフリカなどの国の携帯電話市場はこのグループに入ります。しかし国民の所得が向上し携帯電話の普及率が25%を超えてくるあたりから利用者の大半はごく普通の市民になります。すると電話料金やハンドセットの値段が少しでも下がると利用者の数はそれに敏感に反応して急伸するのです。別の言い方をすればサービスのコストを下げることによる需要喚起のセンシティビティー(感応度)が高まるという風に言えるでしょう。この局面では大きなネットワークを既に構築し、沢山の加入者を勧誘できる立場にあるリーダー企業が最も恩恵を蒙ります。中国の携帯電話市場は今、まさしくこのスウィート・スポットにさしかかっており利用者は順調に伸びています。ところが更に携帯電話が行き渡ると値引きによる需要喚起のセンシティビティーは再び低下します。例えばアメリカの場合、既に携帯電話の普及は飽和状態に達しており、値引きしても簡単に加入者を増やすことは出来ません。■中国の携帯電話市場の特色 先ず中国の携帯電話市場のユニークな点として利用者一人当たりのMOU(Minutes of Use:利用時間)が極めて大きいという点です。中国人はお喋りが好きという風にも言えます。携帯電話が余り普及していない国では普通MOUが高いケースが多いのですが利用者の裾野が広がるにつれてMOUは下がるのが一般的です。しかし中国の場合、利用者数が増えてもMOUは高止まりしています。これは中国の携帯電話市場が携帯電話会社にとって魅力ある市場であることを意味します。なぜなら電話会社の売上の内訳を見るとエア・タイム(通話時間)の長さに連動する売上の部分(利用料金:下の図の水色部分)はとても大きいからです。
2007年06月21日
-
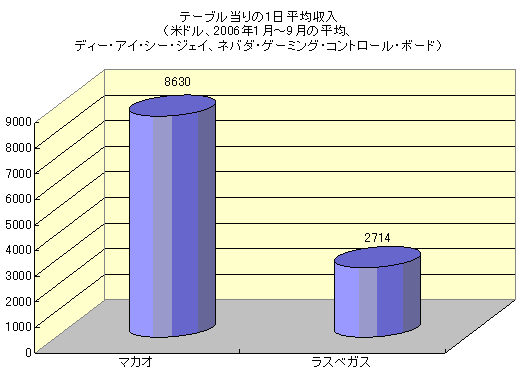
第89回 マカオのゲーミング・セクター(その2)
今日のまとめ 1. ベネチアンの開業はマカオにとって大きな節目である 2. 供給過剰で各社の業績が低迷するリスクがある 3. 長期で見れば先行投資こそが最大の需要刺激要因である大きな節目を迎えるマカオ マカオは今年の夏に大きな節目を迎えます。ラスベガス・サンズ(LVS)のベネチアン・マカオの開業がその節目です。マカオ半島からコーズウェイを渡った対岸のタイパ島に浅瀬を埋め立てて作られた新しい目抜き通りがコータイ通りです。そのコータイ通りで最も重要なカジノがベネチアン・マカオなのです。同カジノは総工費2900億円という大規模開発で、先にオープンしたメルコPBLエンターテイメント(MPEL)のクラウン・マカオの総工費600億円を遥かに凌ぐ規模です。ベネチアン・マカオの開業は9月頃が予定されています。ベネチアンは当初テーブル数850、スロット・マシン数4100で開業し、ゆくゆくは総テーブル数1150、スロット・マシン数7000まで拡張される予定です。スケール・アップ出来るか? さて、投資家が注目している点としてはベネチアンの開業でいままで専らマカオ半島に集中していた観光客がどのくらいタイパ島に流れてくるか?という点です。ごく単純化した説明をすればマカオがスタンレー・ホーのSJMにより独占されていた時代はマカオ全体のカジノ収入はほぼ横ばい、つまりゼロ成長をずっと続けていました。それが2002年に独占が終了し新規参入が許されたのをきっかけにマカオのカジノ収入は年率平均23%で成長してきたわけです。この年率23%成長という数字は立派な実績だと言えます。しかし前回見たとおり今計画されている各社の設備投資計画によるとマカオ全体のキャパシティー(ゲーミング・テーブルの可能着席数+スロット・マシン数)は2006年からむこう5年間で一気にこれまでの3.8倍に膨れ上がります。これを年率に換算すると約40%成長に相当します。マカオ全体のカジノ収入は到着観光客数に左右されますから今までの観光客到着数の実績を大幅に上回るペースでは成長できないと思います。つまり短期的には需要と供給のバランスが崩れ各社の業績が低迷することが考えられるわけです。さらにタイパ島に娯楽性に富んだ魅力的なカジノが相次いでオープンするとマカオ半島のほうが逆に廃れることも可能性としては無いとは言えません。実際、ラスベガスの場合、ラスベガス通りに大型のカジノが相次いでオープンしたので旧市街のほうはすっかり廃れてしまいました。各社のコータイ通りでの戦略 ここでコータイ通りにおける各社カジノの位置関係を整理すると先ずコータイ通りの両側の大部分はラスベガス・サンズの所有です。ラスベガス・サンズは自社のブランドであるベネチアンを核テナントとして先ず最初にオープンし、今後、フォーシーズンズ・ホテル、シャングリラ・ホテル、シェラトン・セント・リージス、コンラッド・ヒルトン、フェアモント・ラッフルズという一流ブランドでコータイ通りを固める予定です。コータイ通りに面した土地でラスベガス・サンズの所有になっていない敷地は二箇所だけです。具体的にはコータイ通りの北端の空港側の敷地はメルコPBLエンターテイメントのシティ・オブ・ドリームスの建設予定地となっています。またコータイ通りの南端の本土からの観光客の通過するイミグレーション・オフィスの付近はイー・サンらが企画するTVシティーが配置されます。一方、コータイ通りを離れた場所としてはベネチアンの裏がギャラクシー・コータイです。それから特筆すべき点として既存のマカオにおける最大勢力であるSJMはコータイ通り周辺に殆どプレゼンスが無いことに注意を払うべきです。別の言い方をすれば人の流れがコータイ通りに移ればラスベガス・サンズが勝ち、逆にコータイ通りが閑散となればSJMの勝ちという風にも言えます。収入構造の変化 このような立地上の変化に加えてカジノの収入構造の変化も注意深くフォローする必要のある問題です。下の図はマカオとラスベガスのカジノのテーブル当りの一日平均収入(average win per day)を示したものです。 このグラフで見るとマカオのギャンブリング・テーブルはラスベガスのそれより3倍以上もテーブル当りの収入が高いことがわかります。これはマカオの顧客がハイ・ローラーと呼ばれる、大きな賭けを好む玄人っぽい客筋であることを示しています。テーブル当りの生産性が高いことは歓迎すべきことですが、ハイ・ローラーの人口はマカオのキャパシティーが増加したからといってそれに合わせて増えるとは限りません。一般の観光客などへギャンブル人口の裾野が広がるにつれてテーブル当りの掛け金は下がり、テーブル当りの生産性が減少するのはほぼ間違いないと思います。問題はそのテーブル当り収入の下落がどの程度か?ということです。このように今のマカオはベネチアンの開業という大イベントを目前に控えて投資家の不安が極点に達している状態だと言えます。リスキーな賭けはラスベガスで経験済み それではなぜラスベガス・サンズをはじめとする各カジノ業者はマカオにおける事業の成功に自信を持っているのでしょうか。その理由は彼らにとってこの手のリスクはラスベガスで経験済みだからなのです。例えば典型的なラスベガスの事業家であるウイン・リゾーツ(WYNN)のスティーブ・ウインの場合、シーザース・パレス、ミラージュ、べラジオ、ウイン・ラスベガスと次々に大型のカジノをオープンしてきました。そしてそのたびごとに新しい主力カジノから上がる税引き前利払い前利益(EBITDA)はどんどんスケール・アップしたのです。大型カジノが着工されるごとに投資家やラスベガスの地元の住人は「こんどこそ需要が追いつかないのではないか?」と心配しましたが、そのたびごとにそれは杞憂に終わってきたのです。別の見方をすれば新しいカジノやアトラクションに対する先行投資こそがラスベガスのカジノ市場のパイの成長を促す最大の需要刺激要因だったという風にも考えられます。実際、最近オープンしたウイン・マカオはラスベガスでスティーブ・ウインが培ったノウハウをフルに活用した、大変洗練されたホテル/カジノに仕上がっています。また、ベネチアン・マカオは大成功を収めたラスベガスのベネチアンのレプリカ(コピー)であるため基礎工事のリスク(コータイ通りは埋立地です)を除いた施工ならびに工程管理上のリスクは最小限であるといえます。そのほかのリスク4月末からマカオから最も近い本土の省である広東省からマカオに渡る際のビザの申請手続きが変更になりました。具体的にはビザを申請してから発給を受けるまでの待機期間がこれまでの3日から10日に延長されました。また一回の申請で受けられるビザがこれまでの2回分から1回のみに制限されました。これにより本土の人がマカオを訪れる際の面倒が若干増えたと言えます。現在までのところこの新しい規則が客足に影響している形跡はありませんがほんのちょっとしたルール変更がマカオのカジノの経営環境に影響を及ぼしうることを投資家は痛感しました。
2007年06月12日
-
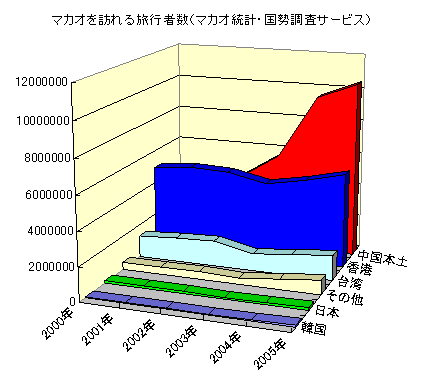
第88回 マカオのゲーミング・セクター(その1)
今日のまとめ 1.マカオでは6社の業者が営業を許可されている 2.マカオの立地はデモグラフィー的には将来性が高い 3.可処分所得の向上と歩調を合わせた開発が望ましい 4.ラスベガスの集客ノウハウと資本力が怒涛のように押し寄せている 5.キャパシティーの急増、コータイ通りへのリロケーションなどがリスク 歴史 マカオは1999年までポルトガルの植民地でした。マカオのカジノは40年にわたってスタンレー・ホーのSTDMが独占してきました。しかしラスベガス型の地域再開発を目指すマカオ特別行政区政府は2002年から新規のカジノ・ライセンスを交付し競争を促す政策を打ち出しました。既にライセンスを保有していたSTDM(その後SJMに社名変更)に加えてウイン・リゾーツ(ティッカー:WYNN)とギャラクシーが新しくライセンスを受けました。さらにより一層競争を促すためマカオ特別行政区は所謂サブ・ライセンス(ライセンスの又貸し)を認め、これによりラスベガス・サンズ(ティッカー:LVS)はギャラクシーから、MGMミラージュ(ティッカー:MGM)はSJMから、メルコPBL(ティッカー:MPEL)はウインからサブ・ライセンスを導入しました。つまり合計6社が競争する構図がこうして成立したわけです。 マカオを訪れる旅行者の増加について マカオは自動車で3時間以内のところに1億人、飛行機のフライト時間3時間以内のところに10億人の人口が居住しており、その後背地の大きさゆえに大きな可能性を秘めています。2002年まではマカオは専ら香港からの旅行客に依存していました。しかし下のグラフに見られるように最近では中国本土からの旅行客が増えています。過去5年の成長率で言えば中国本土からの旅客が年率35.7%成長、香港が年率2%成長、台湾が年率2.5%成長、日本が年率3%成長、韓国が年率21.6%成長、その他が年率15%成長となっています。中国からの旅行者の増加は新しいカジノのオープンが相次いでマカオの魅力が上がっていることに加えて個人旅行解禁や旅行の際に持ち出せる金額が増えていること、中国人の可処分所得が向上していること、交通インフラの整備などによると思われます。 ラスベガスの場合、潜在顧客の所得水準というのは余り大きな問題ではありませんでした。しかしマカオの場合、上で述べたマカオ近郊に居住する中国人の多くはまだ所得水準が低く仮にマカオへ旅行したとしても余り豪勢に散財するだけの財力はありません。実際、マカオへの旅行者の過半数が泊りではなく日帰りを選んでいます。最近中国でもその数が増えている一部の裕福層を別とすれば当面のカジノの拡張はこの中国人の可処分所得の上昇とのバランスを考えながら押し進められるべきです。 集客ノウハウと資本力の移植 アメリカでは昔はギャンブルはおとなの娯楽であり、暗いイメージがありました。しかしラスベガスは業界ぐるみでイメージの向上に努め、テーマに基づいたアトラクションを次々に建設したり施設の高級化を図ったりしました。その結果、今ではラスベガスはギャンブルをしなくてもファミリーで楽しめるような場所になっています。このようにラスベガスの業者が何十年もかけて研ぎ澄ましてきた集客・経営ノウハウと資本力が今回、極めて短期間のうちにマカオに移植されることになりました。これらの要因から既にマカオのゲーミング・レヴェニュー(カジノ関係の売上高)は去年68.5億ドルにまで成長し、ラスベガスをはじめて抜きました。 過去5年間のゲーミング・レヴェニューの成長率はマカオが年率約23%、アトランティック・シティが3.1%、ラスベガスが4.9%です。なおマカオはゲーミング・レヴェニューに対する依存度が極めて高いのに対してラスベガスはゲーミング・レヴェニュー以外の売上への分散が進んでいることに注意する必要があります。具体的には見本市や社員旅行、会議、カンファレンスなどにより集客するほか小売(ブランド・ブティックの招致など)、エンターテイメント、不動産分譲などが展開されています。このためそれらを合計した売上規模ではマカオはラスベガスに遠く及びません。勿論、マカオが向かおうとしている方向性はラスベガス型の総合的カジノ・コンヴェンション複合都市ですから将来的にはマカオの売上構成はラスベガスに近似したものとなると予想されます。 これまでの競争、これからの競争 最近マカオでオープンしたカジノとしてはサンズ・マカオ、ウイン・マカオ、ギャラクシー・スターワールド、グランド・リスボアなどが挙げられます。これらのカジノは概ね所期の営業成績予想を上回る成功を収めています。これらの施設は既存のカジノ地区であるマカオに立地しており、人の流れや交通インフラの面での問題はありませんでした。しかし、今後計画されているプロジェクトの大半はマカオからコーズウェイを渡ったタイパ島に位置しています。浅瀬を埋め立てた場所に新しい目抜き通り、コータイ通りが計画されています。このコータイ通りはちょうどラスベガスの旧市街に対するラスベガス通りに相当するわけです。もともと旧市街から発展したラスベガスはより空港に近く、更地の土地がふんだんにあったラスベガス通りに移ったことで大きくスケール・アップしました。 このように、今、コータイ通りで試みられていることはラスベガスで実行されたリロケーションと共通する点が多いのです。しかし最初にこの交通の便の悪いタイパ島に進出する業者は人の流れが増えてくるまで暫くの間、苦しい営業を強いられると思われます。現在のところ5月にオープンしたばかりのクラウン・マカオが孤軍奮闘しているわけですが今年の後半にラスベガス・サンズのベネチアンが開業すれば人の流れが変わるだろうと見られています。 各社がどういうスケジュールで設備投資するかを示したのが次のグラフです。 これを見ると現在のマーケット・シェア・リーダーであるSJMはラスベガス・サンズのベネチアンの開業とともに第一位の座から滑り落ちることがわかります。なおテーブル数(カジノの収益の柱ですから経営指標として意味があります)だけでは各社がどのくらいそれぞれのプロジェクトに力を入れているかは把握しきれません。なぜなら会社によってお金のかけ方がかなり違うからです。 一番豪勢なラスベガス・サンズの場合、設備投資額をギャンブリング・テーブル数で割った「テーブル当たり初期投資額」は328万USドルです。一番予算をかけていないギャラクシー・メガ・リゾートの場合は155万USドルです。つまりラスベガス・サンズの方が施設に倍以上のお金をかけているわけです。ラスベガスとマカオのカジノを比較するとマカオの方がギャンブリング・テーブル当たりの生産性が高いことは昔から指摘されてきました。これはマカオがハイ・ローラーと呼ばれる玄人っぽい客筋を主に相手に商売してきたことと関係があります。カジノのライセンスが独占的に付与されており、競争が無い環境下ではこういう大口顧客相手の商売の方がマージンも高く、旨味があります。 しかしそれでは需要の裾野は広がりません。マカオ特別行政区政府が目指しているのは明るいイメージのマス・マーケットです。資本力で圧倒的なアメリカのカジノ業者を次々に招き入れたことはマカオにおける競争がより設備ないしは演出に力点を置いた「軍拡競争」時代に突入することを意味します。したがって当面のリスクとしては2007年~2009年にかけて加速度的に増加する各社のキャパシティーにちゃんと需要が追いつくのか?という点です。下のグラフはマカオ全体の設備別の投資計画を示したものですが比較的初期投下資本の少なくて済むVIPテーブルの増加量に比べて一般テーブルやスロットの増加量の方が多いことが目をひきます。これは今後マカオで競争してゆくには莫大な資本を動員でき、しかもそういう大金を投入して建設したアトラクションがちゃんと魅力ある、高品質のものに仕上がるかどうか?というエクセキューション(実行)力が問われることを示唆しているのです。
2007年06月05日
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- ひとり言・・?
- PC入力時の手首・肘用ゲルクッション
- (2025-11-19 22:39:26)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 茅野市の…
- (2025-11-20 17:35:54)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-







