2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年09月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
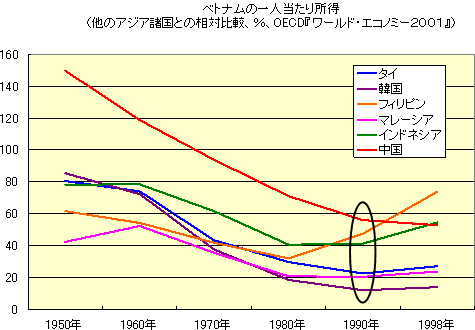
第102回 ベトナムの経済 (その1)
今日のまとめ 1. 高度成長国の多くは一度経済のひどい低迷や破綻を経験している 2. ベトナム経済も長く険しい道のりを歩んできた 3. ドイモイ政策の発表される直前のベトナムのインフレ率は700% 4. ドイモイ政策導入後農業とサービス業が最初に立ち直った■出遅れ 中国やインドやロシアなど、最近高度成長を遂げている国々には或る共通点が見出せます。それはこれらの国の経済の発展段階のある時期に各国とも経済のひどい停滞や混乱や破綻を一度経験しているということです。そうした経済の低迷はその国の提供する財やサービスの価格を極端に低くリセットする効果があり、それが価格競争力の面で圧倒的な優位に立つことが出来る機会を提供するのです。勿論、ベトナムの場合も例外ではありません。ベトナムの場合、1954年のジュネーブ会議以降、独立国としての道を歩み始めたのですが最初は極めて険しい道のりであったと言えます。下のグラフからもわかる通り、他のアジア諸国に対してベトナムは相対的地位の低下を経験したのです。 このグラフはそれぞれの年のアジア諸国の所得を100とした場合、ベトナムの所得がその何パーセントに相当するかをグラフ化したものです。例えば中国の 1950年の所得に比べるとベトナムは149.9%、つまりベトナムの方が49.9%豊かだったわけです。ところがベトナムはどんどん中国より困窮化し、 1998年までにはベトナム人の一人当たり所得は中国の半分程度になってしまいました。つまりこのグラフは右肩下がりになればなるほどベトナム人の相対的所得水準は低下していることを意味するのです。実際、1990年頃まではアジアの全ての国に対してベトナムはアンダー・パフォームしていることが読み取れます。(唯一の例外はフィリピンで対フィリピンでは1980年頃からベトナムが差を縮め始めています。これはフィリピンの経済の低迷が原因です。)ベトナムの経済が駄目だった原因は言うまでも無く1950年代から1980年頃まで絶え間なく続いた一連の戦争にあります。ベトナムは疲弊し切った経済をテコ入れするために1986年にドイモイ政策という経済改革を打ち出します。その結果、1990年頃を境にベトナムの相対的地位は盛り返し始めます。■ハイパー・インフレと貿易赤字 1986年当時の同国の経済の疲弊度合いはインフレ率と貿易収支の数字からもうかがい知ることができます。ドイモイ政策が発表される直前のベトナムのインフレ率は年率700%を超えていました。 また、輸入額が輸出額の2.44倍に達し、ソ連など外部からの経済支援が無い限り国家運営の破綻は免れない状況になりました。 1980年代のベトナムは共産党の下で国民はソ連を除く外国企業や外国人との接触は極力避けるように指導されていました。このことは経済運営はもちろんのこと輸出を目指す製造業や農業も外からのノウハウを取得しにくい状況に置かれていたことを意味します。■ドイモイ政策 ドイモイ政策は1986年の第6回共産党大会で正式に発表されました。そこでは経済のてこ入れをするために利用できるツールは全て積極的に使ってゆこうということが提唱されました。具体的には財政政策、金融政策、賃金政策、価格政策などの面で新しいことを試すことが提案されたのです。そして政府が国家にとって戦略的に重要だと考えていない分野に関しては徐々に私有財産を認め、市場経済を認めることにしました。とりわけ外国との自由貿易、外資の導入、農業分野のてこ入れ、日用品などの消費財の増産が決められました。 ドイモイ政策導入直後はサービス業と農業が著しく成長しました。この一方で工業セクターが一旦マイナス成長に落ち込んでいるのは重厚長大型の計画経済モデルに依拠した重工業への支援を止める決定を下したことが影響しています。
2007年09月25日
-
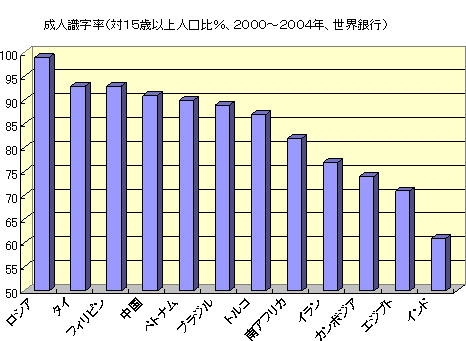
第101回 ベトナムの社会と政治
今日のまとめ 1. ベトナム人は起業家精神が旺盛である 2. ベトナムの女性の社会進出は進んでいる 3. 農業セクターが経済のバックボーンである 4. 地域により気質に差がある 5. 政治のプロセスは不透明である 6. ベトナム人は試行錯誤を重んずる■起業家精神 ベトナムは共産主義の国ですが庶民の気質は資本主義国の国民に近いです。例えば昼間の仕事がお役所勤めとか学校の先生であっても家に帰れば内職のひとつでもかけもちして複数の収入の途を確保するのが良い亭主であるという価値観があります。お金儲けのやり方をいちいち指導しなくてもベトナム人はよりお金が儲かるようにいろいろ工夫します。つまりベトナム人には生来の起業家精神というものが備わっているのです。一般にベトナム人は勤勉ですし読み書きなどの基礎教育も発展途上国の中では極めて行き届いているので雇う側としては即戦力になりやすいです。■がんばる女性 またベトナムでは女性が強いし、働き者です。実際、アフリカ諸国を除けば15歳から24歳の労働力参加率で女性が男性を上回っている国はベトナムくらいのものです。■農業の重要性 ベトナムは現在も基本的には農業国です。農業セクターの就業人口は1990年の84%から2005年には56.7%にまで下がってきましたが、まだ過半数の国民が農民であることには変わりありません。 ドイモイ政策(経済改革)導入後のベトナムの経済が比較的上手く行った理由として土地改革や農業製品の海外輸出の拡大が上手く行ったことが挙げられると思います。その農業の生産性なのですが実は豊かなイメージとはウラハラにあまり一人当たり生産性は高くありません。 これには地域によって格差が大きいことも影響しています。具体的には中部沿岸地域は土地が痩せていて耕作に不向きですし、北部のレッドリバー・デルタ地方などは限られた土地に人口が多すぎることが主な原因です。南部のメコン・デルタの生産性が突出している点に注目して下さい。また中部高地はコーヒーの栽培などが寄与しています。■地域による気質の差 ベトナムが基本農業国であり、しかも地域によって豊かさが大きく異なるということはそれぞれの地域に暮す人々の性格や価値観に少なからぬ影響を与えています。例えば中部沿岸地域は歴史的にベトナムの中で最も貧しい地域なのですが、ここは学問が盛んでホー・チ・ミンをはじめ数々の政治家や学者を輩出しています。南は自然に恵まれており人々の気質は穏やかで、商売などに対する関心が高いです。レッドリバー・デルタなどの北部は共産党のルーツの土地であり、政治色が強いですし、南の人たちを見下したところがあります。■ベトナムの政治 ベトナムの政治を考える上で最も重要なファクターはその継続性だと思います。ベトナムはずっとマルクス・レーニン主義を提唱する共産党によって指導されてきたため、ドイモイ政策の導入時などの社会の変化の節目にあっても急激な変化や混乱はありませんでした。このような体制の持続性はマイナス面も持っています。それは共産党の意思決定のプロセスが不透明で外部からわかりにくいことです。政体としては党書記、大統領、首相の所謂、「トロイカ体制」が採用されており、首相は副首相、大臣、地方の人民委員会のリーダーの選任権を有しています。また、公的機関の設立、改組などの権限も有しています。一方、大統領は首相の解任の動議をする権限を持っています。大統領と首相は党大会で選出されることになっています。ベトナムは地方の権限が強く、またコンセンサスによる意思決定を重視します。このことはなかなか改革が起こりにくいことを意味しますし、党に対するコネがあることが人々の暮らしに重要になってきます。エリートの門閥主義や責任の回避の傾向が強いこともベトナムの政治の特徴です。ベトナムのリーダーは大きな改革を好まず、一歩一歩慎重に踏みしめながら対応してゆくことを好む傾向があります。ベトナムのリーダーは外国から押し付けられたアジェンダには容易に迎合しない頑固さを持っています。ですから例えば外国の経済アドバイザーの助言などは殆ど聞き入れません。また、試行錯誤は悪いことではないという考え方があり、先ずスモール・ビジネスなどの民間のイニシアチブを黙認し、それが上手く行っていることが確認されると政府が後付け的に追認することもしばしばあります。
2007年09月18日
-
第100回 ベトナムの歴史(2)
2007年09月12日
-
第100回 ベトナムの歴史(1)
今日のまとめ 1. ベトナム人の一部はもともと中国から流れてきた 2. 植民地支配に対抗する考えとして共産主義が台頭した 3. ベトナムはフランスにも米国にも中国にも勝ったという自負がある 4. 欧米の制度に対する猜疑心は根強い■ベトナム人の由来 べト(Viet=越)人は3000年ほど前に揚子江の南の地域から移ってきたと言われています。南に移住したべト人だからベトナム(VietNam=越南)というわけです。彼らはレッド・リバー(紅河)デルタ、つまりハノイ周辺地域に定着しました。中国との地理的な近さもあってベトナムは常に中国からの支配を受けましたが10世紀に中国の政治が弱体化した隙に独立を果たしました。その後9世紀に渡ってベトナムは独立を保ち、中部ベトナムのチャム族を支配下に入れ、さらにメコンデルタをカンボジアから奪い、ラオスの大部分も傘下に入れました。こうして19世紀にフランスが出てくるまでベトナムは独立を維持しました。■フランスの登場とホー・チ・ミン この間、ベトナムは中国と15回戦いを交えており、その度ごとに中国を追い返すのに成功しています。しかしフランスに対しては屈し1887年に植民地となりました。ベトナム人はこの屈辱を深く根に持ち、フランスに支配された以降も民族主義的なリーダーが次々に登場して植民地からの脱却を試みました。そのような独立を模索する動きの中で次第に西側の個人主義的なリベラルさを主唱するグループとホー・チ・ミンに代表される共産主義を唱えるグループとに分かれたのです。ホー・チ・ミンは若い頃にベトナムを離れ、商船の給仕係として世界中を訪れ、1917年にフランスに渡っています。第一次世界大戦で疲弊したフランスを自分の目で見て、ベトナムを支配している宗主国がいかに弱体化しているかを実感するとともに欧州における当時の最先端の労働運動に次第に関わってゆきます。特にフランスの左翼活動家達との交流はホー・チ・ミンを単なる愛国主義者から世界の思想の潮流をちゃんとわきまえた近代的な革命家へと変えました。ホー・チ・ミンは写真館で写真の修正の仕事をしていましたが、在仏ベトナム人愛国者団の中心メンバーとしてその名声を次第に高めてゆきました。それまで「バ」という名前だったのを「グエン・アイ・コク(阮愛国)」に変えたのもフランス時代です。当時のパリの雰囲気は戦時下で経済はボロボロ、折からモスクワではボルシェビキ党が政権を握ったというニュースが入ってきました。パリのカフェでは左翼のインテリが夜遅くまで革命論議に熱中するという具合です。ホー・チ・ミンはスイスから帰ってきたアナルコ・サンジカリストでレーニンとのコネもあるジュール・ラボーと親交を深め、フランス革命のルーツなど革命思想の理論的、歴史的背景をしっかり勉強する機会に恵まれました。こうしてホー・チ・ミンはフランス共産党の創立メンバーに名前を連ねるほど中心的な位置で活動したわけです。植民地主義に対抗するための手段は共産主義以外に無いという彼の考え方はこのような経験から醸成されたのです。■北と南 長い海外生活から帰国したホー・チ・ミンは1941年にべトミン(ベトナム独立同盟=つまり共産党の前線)を組織します。当時のベトナムはドイツと同盟関係にあった日本が、ドイツに占領されドイツの実質的な傀儡政権となった仏ヴィッシー政権と共同管理するという形式を取っていました。第二次大戦後、列強は疲弊した自国の復興に忙しく植民地では力の真空状態が生じます。それまで機が熟すのを待っていたべトミンはこれを機会にベトナム民主主義共和国(Democratic Republic of Vietnam=略してDRV)を樹立します。べトミンは北ベトナムの市民をセルと呼ばれる組織単位で再編成し、隣人の相互監視や密告、自己批判など中国の共産党が援用していた手法を実施しました。それまでの村々の長は解任、粛清され、農業の共同管理が始められました。1954年から56年にかけて実施された農地改革では裕福な地主から土地や財産を没収しました。このときは約50万人にのぼる国民が刑務所に収容されたり強制労働に従事させられたりしました。推定では10万人近い市民が処刑されたといわれています。このため地主の多くは南ベトナムに逃れました。こうした共産党のやり方に反感を持つ勢力は南に第二政府を樹立します。これがDRVの北ベトナムに対する南ベトナムというわけです。フランスは共産主義国ではないので当然この第二政府の方を支持しました。そして北の内紛に乗じて軍隊を北ベトナムに派遣し、一時は共産党をハノイから追い出し山の中まで追い詰めました。しかしその後形勢が逆転し1954 年にフランスはディエンビエンフーの戦いで敗れ、正式にベトナムから手を引くことを定めたジュネーブ協定を結びます。■べトコンの由来 共産党はハノイに戻り、一旦は「民主主義共和国」を名乗って共産党以外の党派を懐柔し、協調するかのように見せました。しかし、ひとたび権力の座につくと血なまぐさい粛清で共産党以外の勢力を一掃してしまいます。一方、暫定的な境界を形成していた17度線以南の南ベトナムではバオダイ(保大)帝を奉りベトナム国(State of VietNam)が成立します。その後首相のゴ・ディエン・ジェムはバオダイを退け、大統領制、議会政治に基づいたベトナム共和国(Republic of VietNam)に名称を改変します。こうして北ベトナムも南ベトナムも自分が唯一の正当な政府だと主張するに至ったわけです。北ベトナムは世界の社会主義国、共産主義国の支持を得て、一方の南ベトナムは西側諸国の支持を受けました。さて、ベトナムはジュネーブ協定により1954年に独立し、統一選挙を実施するはずでした。しかしジュネーブ協定は細目が不明瞭でいろいろな解釈の余地を残していたばかりでなく協定の実施を監視するはずの国際管理委員会がカナダ、インド、ポーランドからなるメンバー国間の意見の不一致で統一選挙そのものすら実施されませんでした。こうしてなしくずし的に分断に合意する協定が調印され、フランスは南ベトナムを去ったのです。さて、北ベトナムは限られた耕地面積に比べて人口密度が高く、さらに農地改革の際、その土地にもっとも適した耕作を行う知恵を蓄えた農民の多くを農地から追い出してしまい、農業の経験に乏しい共産党による共同管理は深刻な減産を招きました。これが深刻な食糧危機を招き、北ベトナムは豊かな南ベトナムに影響力を伸ばすため1956年くらいからしばしば南で政府の転覆を狙う活動を展開します。これが1960年から 62年にかけての解放のための戦争(War of Liberation)へと発展するのです。このように南ベトナムに潜伏し、政府転覆活動に従事する北の活動家のことをべトコン(VietCong=越共、南ベトナム解放民族戦線)と呼びます。■米国の関与 米国のベトナムとの関わりは1950年頃に遡ります。当時米国はマーシャル・プランに基づいてフランスに経済支援をしていました。その一環でフランスの対ベトナム政策にも協力したわけです。当時の米国の期待するところはフランスが速やかに南の民族主義グループと和解し、インドシナ(ベトナム、ラオス、カンボジアなどの地域)の独立を認めるという事でした。しかしフランスは先に述べたように1954年のジュネーブ会議までベトナムの支配に固執します。中国で共産党が実権を握ると米国、英国、フランスの各国は南アジアが共産主義拡散の防波堤として戦略的に極めて大事であると考え、南の民族主義グループを支援します。この決定の背景には若しベトナムが共産党によって支配されると共産主義の影響力がゆくゆくはタイ国などにまで波及するという、所謂、「ドミノ(将棋倒し)・セオリー」が広く米国の国民に受け入れられていたことも影響していると思います。フランスが去った後の空白に乗じて北から潜入した南ベトナム政府転覆活動に対抗し、共産主義の拡散を防止するという名目でアメリカは1962年から南ベトナムに派兵しはじめます。当時は南ベトナムの兵士を養成する時間が足らず、特に60万人を数えた南ベトナムの軍隊を指揮できるリーダーの育成が最も遅れていました。1966年の米国議会におけるマクセル・テーラー将軍の公聴会での質疑応答の記録によると米国の軍事顧問のベトナムへの派兵はこうした「現地の軍隊が自力で治安維持ができるようになるまで米国が指導する」という、現在のイラクにおける米国の関与の仕方と酷似した考え方に拠っていました。南ベトナムの人々は北の共産党を恐れてはいましたが、かといって当時の南ベトナムの政府に全面的に信頼を置いていたかと言えばかならずしもそうではありませんでした。それはフランスがバオダイ帝を「お飾り」的に擁立し、さらに米国がゴ・ディエン・ジェム大統領のように長くベトナムを離れていて草の根の支持が無い人物を支持したことなどにもよります。■泥沼化 南ベトナムに潜入してくる北のテロ分子を、南ベトナムの軍隊を訓練してこの掃討に努めるという作戦が成果を上げないことにしびれを切らした米国は1965年に北爆を開始します。こうしてゲリラ戦争は大掛かりな全面戦争へと拡大したのです。その後、テト攻勢、フエ事件を経て米国は再び1972年に大掛かりな北爆を敢行します。1973年にお互いに厭戦気分になった北ベトナムと米国はパリ協定を結びアメリカ軍は完全撤退しました。その後も北ベトナムと南ベトナムの戦争は続きましたが米国の後ろ盾を失った南ベトナムは次第に劣勢となり、1975年4月に南ベトナムは無条件降伏します。第100回 ベトナムの歴史(2)へ >>
2007年09月12日
全4件 (4件中 1-4件目)
1










