2014年08月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
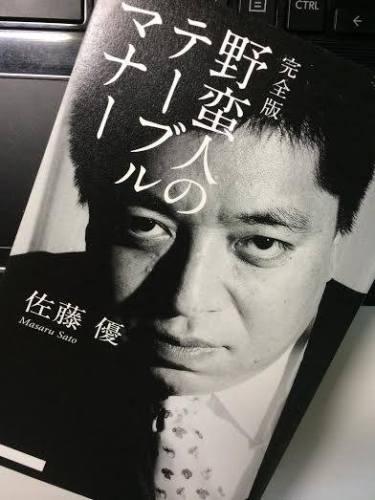
佐藤 優 著 「野蛮人のテーブルマナー」
その圧倒的な知識と、豊富な人生経験が必ずや含まれているという思いで、氏の本に、つい手を伸ばしてしまう。 冒頭にある「ことわりがき」を以下、“”部 引用 “本書は、2006年から、2008年まで、月刊「KING」に連載されたものを、初めて完全なかたちでまとめたものです。 連載は、単なる出来事の解説ではなく、事実の背景、経緯をいかに分析して解釈すべきかを読者に提示する、という視点で書かれました。 そのため本書では、当時の歴史の文脈の流れの中での視点を尊重するため、時代背景、人物のプロフィール、出来事については、あえて雑誌連載当時のままにしています” 以下、目次 第一章 野蛮人脈を作るテーブルマナー 第二章 騙されずに情報をとる技法 第三章 危機からサバイバルする方法 第四章 仕事の終わらせ方 「あっ、そうなの!」「へえ~~!」という部分を、とりあえずいくつか抜粋引用 “筆者は、外務省が外交活動で真の国益のためになるならば、その小道具としてワインを用いることは大いに結構と考える。しかし、外務官僚が自己保身のための政界、メディア工作に高級ワインを用いることは、税金の無駄使い以外のなにものでもない。飯倉別館のワイン貯蔵庫にメスを入れれば、外務省の構造的問題が見えてくる” “夏目漱石の「こころ」や「それから」くらいの長さの小説を全文暗記することだ。筆者自身の経験から言うと、集中的に取り組めば、1か月程度で「こころ」を暗記することができた。そうなると脳内の記憶の倉庫がきれいに整理され、情報交換したときに相手が言ったことが正確に記憶、再現できるようになる” “筆者自身は右翼・保守陣営に所属していると考える。筆者の理解では、人間の理性を信頼し、合理的な計画で理想的社会を構築できると信じる者が左翼・市民主義陣営を作っている。これに対して、人間の理性や知恵は、しょせん限界があるものなので、合理的な計画で作った社会などろくなものではないと諦め、人知を超えた伝統や文化、さらに神様や仏様を尊重するのが、筆者の理解するところの右翼・保守陣営である” “直接関係しないような出来事間の連簡に気づくためには、本を読むことである。しかし、読み方にコツがある。ぶどうの搾り汁を樽に入れて、数年寝かさなくては芳醇なワインにならないのと同じように、本から得た知識は一定期間を経ないと身につかない。この辺を意識しながら、筆者は独自の読書法をとっている。一日、原則として6時間の読書時間をとる” “高畠と漱石を今のうちに読んでおけば、数か月後に深刻になる新自由主義的改革路線の見直しについて議論するときに役立つ” 知識と経験、そして「胆力」がある人が書く本は面白い。 --------------------------------------------------------------------------元大学教授の、精魂込めた「燭楽亭」手づくりチョコ!--------------------------------------------------------------------------薬円台、いち押しのカフェ「シンシア」--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- 銀座 「苗」--------------------------------------------------------------------------アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------
2014年08月31日
コメント(0)
-
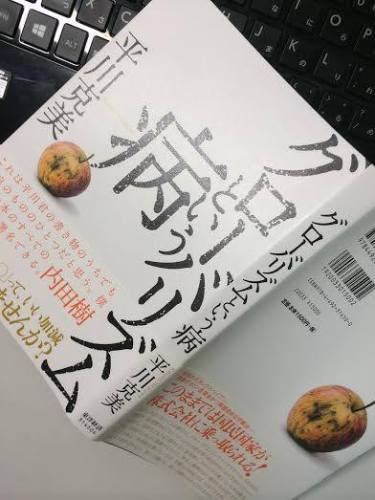
平川克美 著「グローバリズムという病」
帯に内田樹氏が書いている、この本のすべての頁に同意署名できるという言葉に思わず頷いてしまう。 まずは裏表紙から “わたしはアメリカという国が好きであり、アメリカ人の友人も多い。したがって、本書に書かれた事柄はアメリカに対する失望でもなければ憎悪でもない。ただ、グローバリズムというイデオロギーがこの国で生まれ、それが歴史の必然であり、グローバル戦略を持たなければ生き残れないなどと信じている人々の多いことに、危惧を覚えるのだ。” 以下、目次 第一部 グローバリズムはどこから来たのか 第二部 国民国家を乗っ取る株式会社 第三部 グローバリズムはどこへ行くのか 21世紀に入る前後から、言われ出したグローバルスタンダードという言葉。何かと言うとこの言葉が何の疑問もなく前提条件として、呪文のように唱えられて早20年近くが過ぎようとしている。 いつの頃からか、この行きつく先の殺伐とした風景がぼんやりと浮かぶようになってきた。 以下、本文から “グローバリズムというイデオロギーは、国体国の関税や、商習慣をめぐるシステムの正当性を争う政治的対立から生まれてきたものではなく、国家などもともと眼中にない富裕層と、かれらが支配している多国籍企業が、国家そのものに挑戦するという、歴史上類例のない構図を生み出したということである” グローバリズムとどう対峙していくかというと、あまりにも巨大なうねりで無力になってしまうが、歴史を俯瞰して、自身が感じていることを見失わずに、グローバリズムとどう距離を置いて付き合っていくかというのが無理のない考えなのだろうか? ともあれ、百年後二百年後から見て今の時代がどう見えるのか、流行語に惑わされずに、グローバリズムとグローバリゼーションは違うということを押さえた上での大局的な目線で生活していくことが肝要と感じる。 --------------------------------------------------------------------------元大学教授の、精魂込めた「燭楽亭」手づくりチョコ!--------------------------------------------------------------------------薬円台、いち押しのカフェ「シンシア」--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- 銀座 「苗」--------------------------------------------------------------------------アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------
2014年08月30日
コメント(0)
-
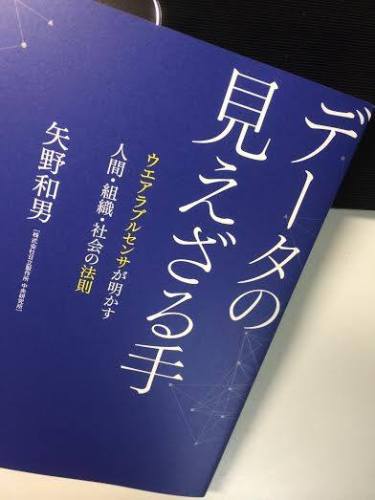
矢野和男 著 「データの見えざる手」
メルマガ「平成進化論」の著者が「凄い本を読んだ。大興奮中」とタイムラインで紹介していた本。それを見てすぐにアマゾンで手配をした。 副題には「ウエアラブルセンサが明かす人間・組織・社会の法則」とある。 これだけでは何のことかぴんとこない。 まずは裏表紙の解説を引用 “日立中央研究所で2006年に開発されたウエアラブルセンサによる人間行動の研究が、いま、人間・組織・社会の理解を根本から変えようとしている。著者自身を含め、これまでのべ100万人以上の行動を計測、その身体活動、位置情報、センサをつけている人どうしの面会などを記録した「ヒューマンビッグデータ」が、人間や社会に普遍的に見られる「法則」や「方程式」を次々と明らかにしているのである。そのデータから明らかになる「法則」とはいかなるものか。法則の理解は、私たちの生活や社会をどのように変えるのか。世界を変えつつある新たなサイエンスの登場を、世界の第一人者が自ら綴る!” 以下、目次 第一章 時間は自由に使えるか 第二章 ハピネスを測る 第三章 人間行動の方程式を求めて 第四章 運と真面目に向き合う 第五章 経済を動かす新しい「見えざる手」 第六章 社会と人生の科学がもたらすもの この中の小見出しには魅惑的な言葉が並ぶ。以下一部その紹介 万物を支配するエネルギー保存則は人間にも効く 右肩下がりの分布が社会を支配するという謎 身体運動は伝染する。ハピネスも伝染する 人との再会は普遍的な法則に従って起きる 1/Tの法則はメール返信などほかの行動にも 行動は続けるほど止められなくなる 1/T分布はU分布と同じもの 最適経験=フローを測る 運は人との出会いによってもたらされる 新たな「見えざる手」が世界の新たな「富」をもたらす サービスと科学を融合させる、データの指数関数的拡大 近年ビッグデータということで、その解明にパワーシフトしてきているが、その考え方を先取りしたような形で、かなり前から取り組んでの定量的結果に裏打ちされた理論になっている。 これからの社会を考える上でのヒントとなるキーワードが至る所に散りばめられている。 もう一度人生があったら、ぜひとも取り組んでみたい仕事と思わせる内容でもある。 最後に、以下、本文から抜粋引用 “実は、アダムスミスは「国富論」と「道徳感情論」という二つの本を書いている。前者は経済的な豊かさの本質を、後者は人間らしい生き方の意味を説く。そして、この両者は合わせて一つの理論を作っている。経済性の追求と人間らしさというのは両者が強調しあってうまくいく体系であることがスミスの主張だった。しかし、スミス以降、このうち、経済性のみを限られたデータにもとづいて追及することが普及した結果、人間らしさの追求が置き去りにされた。そもそも、スミスが言いたかったのは、経済性と人間性とは、相反するものではなく、互いに関係しあうことだった。このスミスの考えが、いよいよ大量データと知的なコンピュータの出現により可能になったのである。” --------------------------------------------------------------------------元大学教授の、精魂込めた「燭楽亭」手づくりチョコ!--------------------------------------------------------------------------薬円台、いち押しのカフェ「シンシア」--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- 銀座 「苗」--------------------------------------------------------------------------アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------
2014年08月29日
コメント(0)
-
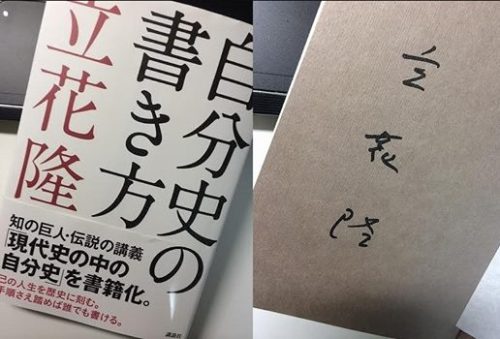
立花隆 著「自分史の書き方」
自分史という言葉は、ここ数年とても気になっていた。 今年は自分史フェスティバルのイベントと休暇がうまく重なったので参加してみた。フェスティバル自体は二回目だとか。 そこでのエンディング講演としての立花隆氏から紹介があった図書を帰り際に購入した。 以下、目次 はじめに 自分史を書くということ 第一章 自分史とはなにか 第二章 自分の年表を作る 第三章 なにを書くべきか これは実際に「立教セカンドステージ大学」での授業の記録がベースということで、具体的な内容に落とし込まれていてわかりやすい。 還暦前後のシニア世代は、セカンドステージへのステップとして自分史を書く適齢期でもあるらしいし、そう実感もする。 私の履歴書の庶民版という感じ。身近にありそうな話題で親しみやすい。 ここで紹介されている、いくつかのパターンの年表と事例が書く上にとても参考になりそう。 特に最初に作成する年表は、縦軸に何を持ってくるか構成イメージを考えるだけでも楽しい。 「自分史を現代史の中に自分史を重ねてみる」「歴史の曲がり角はいつも目の前にある」という意識で捉えるとの発言は、書くという動機づけにも、最適なアドバイスと感じる。 何かとても面白い課題が与えられた気分である。 --------------------------------------------------------------------------元大学教授の、精魂込めた「燭楽亭」手づくりチョコ!--------------------------------------------------------------------------薬円台、いち押しのカフェ「シンシア」--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- 銀座 「苗」--------------------------------------------------------------------------アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------
2014年08月27日
コメント(0)
-
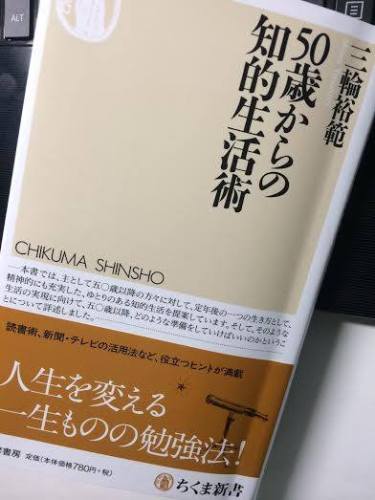
三輪裕範 著 「50歳からの知的生活術」
50歳を一回り過ぎてしまったが、この手の本に触手が伸びてしまう。今現在の生活の仕方を再度確認するためかもしれないな。 内容的には今まで読んだ同類の本に出てくる内容の繰り返しのようでもある。 以下、目次 第一章 知的生活が定年後を充実させる 第二章 テーマを見つける 第三章 50歳からの読書法 第四章 50歳からの新聞・雑誌・テレビとのつき合い方 第五章 50歳からの知的アウトプット 以下、本文から抜粋引用 “人間の社会では、いつの時代においても通用するものと、その時代時代によって変化するものとがあります。俳人の松尾芭蕉は、これを「不易」と「流行」という言葉で表現したのですが、特に50歳以降の定年前後世代の方々は、それまでの年代のように、「流行」を一辺倒に追いかけることから多少ギアチェンジして、「不易」と「流行」のバランスを少しずつ変化させていく必要があります。 つまり、一方では時代の風である「流行」を敏感に感じとりながら、もう一方では、時代に左右されない永遠の「不易」もしっかりと見据えていくことが大切だということです” もともと流行には疎いところがあったのだけれど、はやりすたりは横目でチラリと見る程度にして、「不易」の部分を一つひとつ確認し、噛みしめながら過ごすのがきっと良いのだろうな。 などと、セミの声を聞きながら‥‥‥ツラツラと、、 --------------------------------------------------------------------------元大学教授の、精魂込めた「燭楽亭」手づくりチョコ!--------------------------------------------------------------------------薬円台、いち押しのカフェ「シンシア」--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- 銀座 「苗」--------------------------------------------------------------------------アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------
2014年08月26日
コメント(0)
-

このような再会もある
先日、駅のホームに貼りだしてあった~書と資料でたどる生誕百年~種谷扇舟展のポスターが目が留まった。そこで早速訪ねてみた。 氏が立ち上げた白扇書道会の展示に併設しての展覧会。 年表を見ると、浅見喜舟や尾上紫舟に師事して書道への道を深めていったようなことがうかがい知れる。 中国で取った拓本と共にその臨書らしきものも展示されている。顔真卿の拓本などもあり、顔真卿の書は面白いと話していた当時が甦った。筆を丸く入れて、離すときの抜き方などの特徴を教えてもらった時を思い出す。 若い時に郭沫若と交流があったことを示す写真と書簡も展示されていた。中国にも百回近く訪問していたということで、その文化交流が果たした功績も多大である。 一連の作品が展示されていたので、そこを貫く生き方や考え方も自ずと浮かび上がってくる。 80歳の時に今までの人生を振り返り書いたという、肉筆で書かれた原稿用紙が80枚展示されていた。全てを読めなかったが、読むほどに、改めて素晴らしい教育者であったと感じる。そんな再会のひと時。 --------------------------------------------------------------------------元大学教授の、精魂込めた「燭楽亭」手づくりチョコ!--------------------------------------------------------------------------薬円台、いち押しのカフェ「シンシア」--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- 銀座 「苗」--------------------------------------------------------------------------アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------
2014年08月24日
コメント(0)
-

自分史フェスティバル的な一日
以前から気になっていた自分史。昨年はフェスティバルの案内を見ていたが日程の都合が合わず、今年は幸いに盆休みと重なったので足を向けてみた。 午前中はまずは村田裕之氏の講演「なぜ、人は自分史を書きたくなるのか? スマートエイジング時代、その意味とシニアビジネスの役割」を聞いた。 氏の人柄が伝わってくる。ヒロシマアーカイブの紹介も。日本は世界に先立つ高齢化社会であり、世界は「ショーケース」として日本を注目している。ロールモデルになり世界へ貢献。自分史つくりを支援するのがこれからの企業=シニアビジネスの役割とのこと。 そのあと各ブースを見て回る。商業的にも、シニアが増えて、これからの発展が望まれ、その黎明期的な感じ。 目的とする夕方の立花隆氏の講演までかなり時間が空いている。とりあえずPCを持ってきたので、近くの小さな電源カフェで休憩、ここがまた心地よい。人がほとんどいない、静かにBGMが、読書と企画立案タイムということで休息。4時間ほどを過ごす。 パンフレットをみて、パネルディスカッションがあることに気がついて会場に場所を移動、テーマは「自分史の広がりから何が生まれるのか」 3人の若手によるそれぞれの切り口からのディスカッション。最後に須磨佳津江キャスターが、歴史は権力者によって書かれてきた。今、私たちはより多くの人が路地裏の歴史を表すことができる時代、ディティールに真実があるという言葉で見事に締めくくった。 続いてエンディング記念講演と題して立花隆氏の講演。テーマは「自分史のすすめ~自分史倶楽部~」 現代史の中に自分史を重ねてみるとよい。歴史の曲り角はいつも目の前にある。その記録者の視点を持つとよいというインパクトのある提言。 それと、何よりも第二次大戦や広島、長崎、アウシュビッツなど歴史の証言者が間もなく消えてゆくことへの懸念を表明、確かに。 タイムキーパーが提示する時間を大幅にオーバーした熱のこもった講演だった。 以下、全体からのキーワードやキーフレーズ 颯爽といつもの道を外れることができる、日野原重明先生、エピソード記憶、テーマを見つけて仲間を集う、ターニングポイント、居住地の移動、人生企画書、何をしたいかに有効なツール、話をできる場所を作ると勝手に元気になる、写真などの活用、年表と人間関係のマップ、縦軸をどう構成するか、年表の作成方法はそれぞれ、自分史で日本を元気に 約4時間近く、久しぶりに講演と接した日だった。 最後に氏のサイン本「自分史の書き方」を購入して会場を後にした。 --------------------------------------------------------------------------元大学教授の、精魂込めた「燭楽亭」手づくりチョコ!--------------------------------------------------------------------------薬円台、いち押しのカフェ「シンシア」--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- 銀座 「苗」--------------------------------------------------------------------------アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------
2014年08月14日
コメント(0)
-
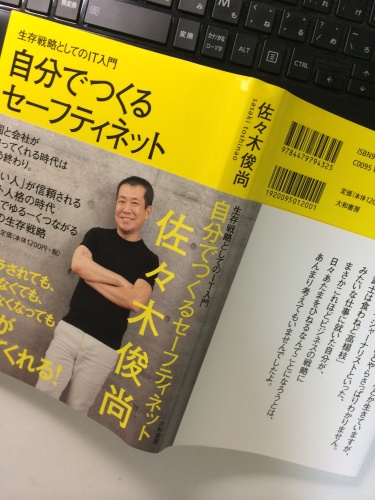
佐々木 俊尚 著 「自分で作るセーフティネット」
この方の書物は波長が合うのか、好きでよく読む。ネット社会のこれからを読み解く上での道しるべになる。 今回は、いつもと違って語調もフレンドリーな柔らかい言いまわしになっているのが面白く感じたが、、まずは、目次 1.セーフティネットは自分でつくる時代 ―― 一生安泰はもう終わり2.総透明化社会の時代 ―― 自分を丸見えにすることで得られるもの 3.ゆるいつながりの時代 ―― 強すぎる「きずな」は「同調圧力」を生み出す 4.見知らぬ人を信頼する時代 ―― だからフェイスブックがある5.「善い人」が生き残る時代 ―― 嘘がつけないネットでは、善い人も悪い人も丸見え6.生き方そのものが戦略になる時代 ―― 善悪は宗教や道徳を超える 著者の特徴はキーワードをいくつか立てて、それを軸にストーリーを展開するという方法。今回のキーワードの一つは「理の世界、情の世界」か? 以下、生き方そのものが戦略になる時代の項から、引用“生存戦略として、見知らぬ他人を信頼すること 生存戦略としての、多くの人との弱いつながり 生存戦略としての、善い人 生存戦略としての、自分の中途半端な立ち位置を知るということ これが、本書のシンプルな結論です。そしてこのシンプルな結論こそが、わたしたちの社会に「情の世界」を取り戻し、グローバリゼーションという強い「理の世界」と対抗させていくことができる。そしてわたしたちは、再び安らかなセーフティネットを取り戻していくことができるでしょう。” 結論に至るプロセスは読んでのお楽しみ。この仮説は、いい線をいっているという感じがする。 --------------------------------------------------------------------------元大学教授の、精魂込めた「燭楽亭」手づくりチョコ!--------------------------------------------------------------------------薬円台、いち押しのカフェ「シンシア」--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- 銀座 「苗」--------------------------------------------------------------------------アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------
2014年08月03日
コメント(0)
-
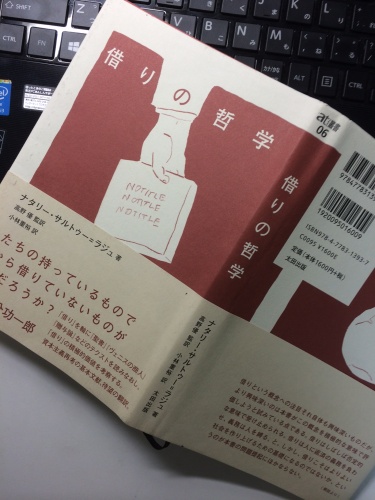
ナタリー・サルトゥー=ラジュ 著 「借りの哲学」
ここのところ本を読み進められていない。停滞の原因の最大のものは、1冊の本を読み終えなければという強迫観念。 途中で気が進まない時は、いつもはすぐにあきらめるのだが、いろいろと清算できずにある「借り」がたくさんある身として、最後まで読みたいという気持ちもあったのか、何となく手放せないでいた。 カバンの中に入れたままで、機会を見ては開こうとしていたのだけど、、 半分ほど読んだが、ここで一区切りつけるために、、、 以下、はじめにから 少し長くなるが引用、 “《借り》というのは、人間関係を反映したものだ。人間関係は複雑である。だから《借り》も複雑である。誰かからどのくらい《借り》を受けて、きちんと清算したかどうかなど、わかるものではない。だったら、《借り》は《借り》として受け入れ、世の中の役に立つかたちで返していけばよい。もし借りから自由になりたいと思ったら、その方法が一番である。要するに、上の世代から受けた《借り》は、下の世代に返せばよいのだ。 いま私たちに必要なのは、そのようにして、《借り》を伝えていくことである。そういう発想がなければ、祖先たちが残してくれた地球環境―上の世代が手をつけずにいてくれた私たちへの《贈与》である地球環境を下の世代に伝えていくこともできない。 また、それと同時に必要なのは、「貨幣を媒介とした、《等価交換》を絶対視する資本主義経済」の暴走を止めて、社会に《借り》の概念を復活させることである。それによって、私たちは、弱者を切り捨てるのではなく、いちばん助けの必要な人に力を貸すことができる。そうやって、かって助けられた人がその借りを社会に返し、またそこで助けられた人がその《借り》を社会に返していく―その連鎖が続いていくようにするのである。 私たちが目指すのは、過度に発達した資本主義経済のなかで、「自分には《借り》がない。いまの自分が持っているものはぜんぶ自分の力で得たものだ。だから、人に分けてやる必要はない」とうそぶく新自由主義的な自律した人間ではない。また、その犠牲になって、とうてい返せない《負債》を抱え、自立を失ってしまった人々でももちろんない。《借り》の概念をもとに、お互いが助け合い、弱い部分を補い合いながら、それでもひとりひとりが自律している―そういった人間である。” ある意味、資本主義社会の限界が感じられるような時代において、興味深いことがたくさん書いてある。また、機会を見つけて開いてみたい。 --------------------------------------------------------------------------元大学教授の、精魂込めた「燭楽亭」手づくりチョコ!--------------------------------------------------------------------------薬円台、いち押しのカフェ「シンシア」--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- 銀座 「苗」--------------------------------------------------------------------------アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------
2014年08月02日
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1










