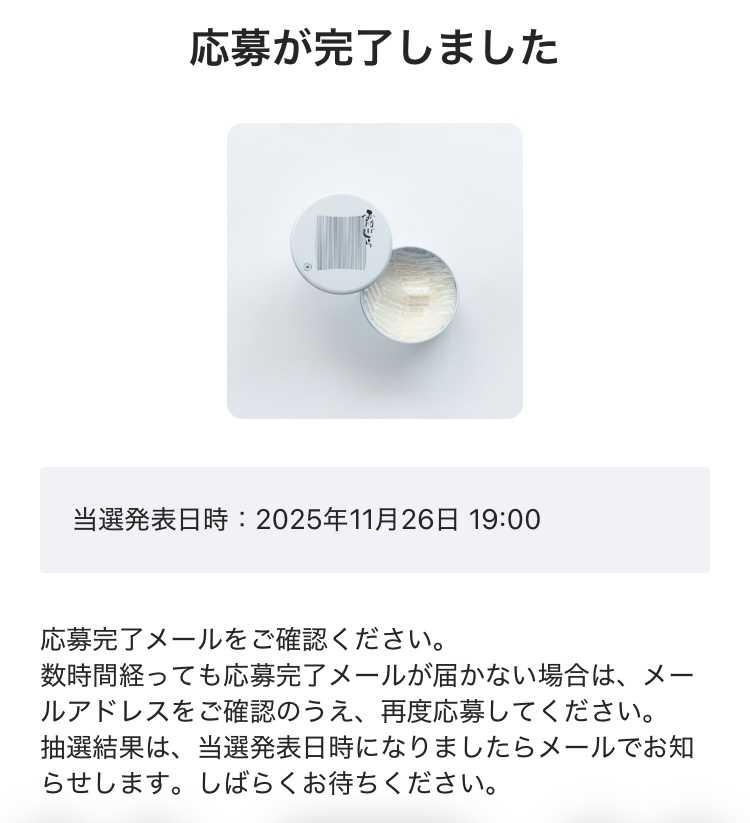2006年07月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
レバノン情勢を考える
レバノンにおけるイスラエルとヒズボラの紛争に関して、調停の動きが活発化してきました。24日にはアメリカのライス国務長官がレバノン入りし、シニオラ首相と会談。ヒズボラに国境線から20キロ後退する事や、武装解除の受け入れなどを迫っています。また、EUのバローゾ委員長は複数のEU諸国がレバノン派兵を検討している事を発表し、イスラエルのオルメルト首相もこれを歓迎する意向を示しました。 が、こうした西側諸国の調停への動きに対し、ヒズボラのナスララ党首はあくまでも武力による抵抗を継続する意思を表明しており、先行きはまだ不透明です。 ヒズボラはシーア派イスラム教徒を中心とするレバノンの民兵組織で、82年のイスラエル軍レバノン侵攻時に、その被害が大きかった南レバノンの住民が先頭に立って創設されました。主にシリアやイランが兵器や資金の援助元になっていて、ヒズボラとイスラエルの抗争はシリア・イランによる代理戦争の側面を持っています。 当時のレバノンは75年当時から続くキリスト教徒とイスラム教徒による内戦の真っ最中で、シリアの介入やPLO(パレスチナ解放機構)のヨルダンからの転進により、国内は混迷していました。 その最中に行われたイスラエルの侵攻の目的は、PLOの排除と、キリスト教徒勢力を援助して、親イスラエル的政権をレバノンに樹立する事でした。目的の半分、PLOの排除はほぼ成功しますが、その後を引き継ぐようにしたヒズボラの激しい抵抗と、イスラエルが援助していたキリスト教派民兵によるパレスチナ人虐殺事件の発生などによって、イスラエルは内外ともにレバノン侵攻への批判が高まり、85年までにレバノンからほぼ撤退する事になります。 それでもイスラエルは南部国境地帯に軍を展開し、親イスラエル武装組織を援助してヒズボラと交戦し続けていましたが、2000年には損害に耐え切れず、レバノン南部から撤退する事になります。 中東最強のイスラエル軍に「勝利」したヒズボラは大いに株を上げ、レバノン国内での影響力は増大。レバノンの「国家内国家」と呼ばれるほどに勢力を拡大しました。 しかし、勝利したはずのヒズボラには逆風が吹き始めます。 レバノンでは事実上の占領軍であるシリアへの反発が強く、その援助を受けているヒズボラも、次第に市民の支持を失い始めました。 追い討ちを掛けるように、反シリア派政党による新政府が発足すると、シリアの影響力をレバノンから排除しようとするハリリ首相(当時)の活動もあり、レバノン情勢安定化を求める国連安保理決議1559が2004年に採択されます。これはレバノン駐留シリア軍の早期撤退とともに、ヒズボラの武装解除を求めるものでした。 しかし、武装民兵組織であるヒズボラにとっては、武力こそ存在意義であり、力の源泉でもあって、この決議には強く反発します。 そこで、政治的危機に陥ったヒズボラが自らの存在意義を誇示するために取った方針が、イスラエルとの武装闘争強化でした。ヒズボラはイスラエル領内に進出し、イスラエル兵士7名を殺害、2名を拉致して、これをイスラエルで捕らえられている政治犯釈放のための取引材料にする事にしました。この越境攻撃・拉致事件が、今回の紛争の火種となったわけです。 今回のヒズボラの行動には前例があり、2000年に殺害した3人の兵士の遺体と、拉致した実業家の身柄を返還する代わりに政治犯の釈放を要求する事件を起こしています。この時のイスラエルは、レバノン撤退後で疲弊していた事もあり、交渉による打開を選択。2年に及ぶ交渉の末、政治犯400名の釈放に応じています。 ヒズボラがこの「成功経験」を念頭においていたのは間違いないと思われますが、彼らはイスラエルも経験に学ぶものだと言う事を忘れていました。そして、今回イスラエルが経験から学んだ事とは、「ヒズボラといくら交渉しても、また拉致事件を起こされるだけで、話し合いは無駄だ」と言う事だったでしょう。 2000年の撤退後、イスラエルはヒズボラに対しては政治的包囲網を形成する事を念頭に行動していて、安保理決議1559の履行を求める他、レバノン政府に対しても、ヒズボラ対策を進める事を要求していました。 それが一転して、今回の大規模な空爆・侵攻になったのには、もちろんヒズボラへの報復もあるでしょうが、他にも複数の狙いがあるように思えます。列挙してみると……・ヒズボラの弱体化・レバノンに打撃を与える事で、レバノン政府・国民の受けた衝撃を、今回の事態を招いたヒズボラへの怒りに転化させ、レバノンとヒズボラの離反を引き起こす・敢えて大規模な攻撃を行う事により、国際社会の介入を引き出す と言ったところでしょうか。少なくとも、イスラエルが数名の兵士が誘拐された事に過剰反応し、理性を失っているという見方は、明らかに適切ではないと思います。 今後のイスラエル・レバノン情勢に関しては、ヒズボラとその背後にいるシリア・イラン、レバノン派兵を提案したEUの動きが焦点になって来るでしょう。紛争の長期化を懸念する声もありますが、少なくともイスラエルに紛争長期化の意思はないと考えるのが自然です。 ただでさえ、イスラエルはガザ地区とヨルダン川西岸でパレスチナ人武装組織ハマスとの抗争を抱えており、二正面作戦は望むところではありません。既にEU諸国の派兵提案に対し、「ヒズボラの武装解除に強い権限を持つ事」を条件として前向きになっているのが、その表れと言えます。本音を言えば、レバノンをEUに任せて、対ハマス作戦に専念したいというのがイスラエルの意思でしょう。 一方で、レバノンへの影響力を回復したいシリア、今回の紛争を自らの核疑惑への煙幕に使いたいイランとしては、紛争が長期化してくれたほうが好都合であり、ヒズボラへの援助を続ける事は確実と思えます。 EUとしては、派兵の規模とシリア・イランの説得が課題となるでしょう。鍵を握るのは、EU最大規模の派兵能力を持ち、かつレバノンとシリアの旧宗主国で、政治的にも太いパイプを持つフランスです。フランスがシリアだけでもうまく説得できれば、今回の問題突破に道が開けるのではないかと期待されるところです。 さて、今後の和平プロセスを考えてみる前に、当事者たちの要求を考察してみましょう。項目1のほうが優先順位は上になります。イスラエル1.拉致された兵士の即時身柄返還2.ヒズボラの武装解除ヒズボラ1.武装解除拒否2.パレスチナ人の地位向上 まず、イスラエルは兵士の身柄返還に関しては絶対に譲れないはずです。人的資源が少なく、それでいて四方に敵を抱えるイスラエルにとっては、国民一人でも見捨てる事は世論が許しません。 ヒズボラは武装解除を絶対拒否しようとしています。武装解除は同時にヒズボラの発言力を失わせるものだと考えています。イスラエルは一見武装解除にこだわっているようですが、ヒズボラの武器がイスラエルに向けられないと言う保障さえあれば、妥協は成立しそうです。 となると、落とし所としては、一旦停戦した上で、ヒズボラは兵士の身柄を返還。国境から20キロ圏(イスラエルに対するロケット攻撃の射程外)へのヒズボラの後退(アメリカ案)や、停戦監視軍の派遣(EU案)を双方が飲む形になるのでは、と思います。 この案の場合、当面ヒズボラのイスラエルに対する武力行使は不可能となり、実質的な安全が確保されます。ヒズボラも武装解除をしなくて済みます。 問題はイランで、長期戦を望む同国が、ヒズボラ内の武装闘争路線継続を訴える過激派を扇動・援助する可能性があります。その場合、休戦破りや停戦監視軍へのテロの可能性が考えられます。それを織り込んだ上で和平プロセスを進めるしかないかもしれません。レバノンへの武器流入を厳しく監視する必要が出てくると思われます。 ともあれ、アメリカとEUの二強が調停に乗り出し、イスラエルにヒズボラの早期武装解除は難しいと言う認識が出てきているため、停戦―和平の可能性は出てきたと思っても良いでしょう。国連は9月以降にレバノンへのPKO派遣を検討し始めています。 この中で日本ができる事はと言いますと、調停には参加しないほうが良いでしょう。日本はパレスチナ問題にコミットできる手がかりを持っていません。 それよりも、レバノンを大々的に支援するのが得策と思われます。今回の紛争も含め、レバノンが火薬庫的役割を担わされているのは、同国の不安定さが周辺諸勢力の介入を許す元になっているからです。 内戦以前のレバノンは金融と観光で潤った国でした。レバノンが独力でヒズボラの跳梁を抑えられる実力を持ち、シリアとイスラエルの双方に対して中立を保てるよう支援するのが、今後の紛争勃発を抑止する最良の策であると私は考えます。 それにしても、今回の紛争についての日記は結構見受けられるのですが、大半が「大虐殺」をやったイスラエルとアメリカと、何故か日本を激しく批判する内容になっています。 確かに殺害した数が多いのはイスラエルでしょうが、紛争の引き金を引いたのがヒズボラだということが無視されている気がするのは何故なんでしょうねぇ…… なお、国連緊急援助調整官室のエーゲランド室長がレバノンを訪問しての談話。「ヒズボラは卑怯にも一般市民のなかに紛れ、過去2週間にわたるイスラエルとの武力衝突で一般人数百人の犠牲者を出している」
2006.07.25
コメント(2)
-
命令違反の重み
イラク派遣の命令を拒否し、軍法会議に掛けられることになった米陸軍のアーレン・ワタダ中尉の事が話題になっているようです。 配属先が米軍の進めるRMA(軍事革命)の象徴的存在の一つ、ストライカー旅団であることを考えると、ワタダ中尉はなかなか優秀な士官なのでしょう。 その彼がイラク行きを拒否し、イラク戦争は間違っていると発言している事について、反戦を訴える人の中には彼の行為を賞賛し、全面的に肯定した上で、軍法会議に掛けることを決定した米陸軍を批判し、中尉を無罪にすべきだと主張する意見があります。 一方で、主張には一定の理解を示すが、その行動(命令拒否)には賛同できないし、それは裁かれて然るべき、とする意見もあります。 私の意見は後者に属します。ワタダ中尉がイラク戦争を間違っている、と主張し、開戦を決定したブッシュ政権を批判する事は、彼の自由であり、尊重します(賛同するかどうかは別問題)。 しかし、彼がそのように主張するのであれば、軍を除隊してから主張するべきだと私は考えます。それ以前に、そもそも彼は軍隊に入るべきではなかったと思います。彼が入隊した2003年3月とは、まさにイラク戦争が開戦したその瞬間だったのですから。 軍隊と言うのは、強大な暴力を行使できる集団です。もし軍隊が暴走すれば、たいていその結果は悲惨なものにしかなりません。 それ故に、軍隊は暴走しないように幾重にも鎖が掛けられています。「軍人は命令に絶対服従すべし」というのもその一つです。 もちろん、その命令が自分の確実な死を意味するような理不尽なものであれば、それに抵抗することはできますが、基本的には命令は絶対です。 生命を張って任務を遂行する軍隊にあっては、それは犠牲を少なくするためにも必要なことです。命令無視は、無視した当人だけでなく、同僚や部下の生命を危険にさらすばかりでなく、戦いの行方を左右する事さえあり得ます。 例えば、ある部隊長が、敵に隙が見えるからと待機命令を無視して敵陣に突撃したとします。しかしそれは罠で、突出した彼の部隊は集中攻撃を受けて壊滅。そのために今度は自軍の陣地に大きな隙ができてしまい、そこへ敵が集中攻撃を掛けて…… 先週の大河ドラマ「功名が辻」は賤ヶ岳合戦の話でしたが、この合戦がまさに上に挙げたような例の典型で、佐久間盛政の命令違反が柴田勝家勢全軍の崩壊に繋がったと言う話でした。 軍隊では命令無視は非常に危険な事態を呼び込む可能性があるために、絶対的に忌避すべきものとされます。結果によっては、良くて左遷。悪ければ即決で銃殺という事も珍しくはありません。その基準はきわめて厳格なものであり、仮に命令無視が良い結果を生んだとしても、処罰からは免れません。 1985年、日航ジャンボ機墜落事故がありました。この時、自衛隊の第一空挺団長は出動命令を出してくれるよう上層部に掛け合ったのですが、当時自衛隊のヘリは夜間飛行能力が低く、上層部は二次遭難の危険ありとしてそれを却下しました。 しかし、団長は指揮下のヘリ部隊に独断で出動を命令。その結果、迅速な救助活動が行われ、4名の生存者救出に繋がりました。 人命救助という観点では間違いなく英雄的行動をなした第一空挺団長ですが、彼は命令無視の廉で職を追われ、左遷されました。 この話を理不尽だと思う人は、人間としては正しい感性の持ち主だと思います。私も元空挺団長の事は気の毒だと思います。 ですが、軍隊と言う組織の規律を守ると言う観点で見れば、空挺団長の行動は誤りであり、彼に下された処罰は正しいものでした。仮に、こうした命令違反が結果オーライで許されてしまえば、その事が第二第三の命令違反を生み、いつ重大な結果を生むか知れないからです。 実は旧日本陸軍は結果オーライで命令違反を許してしまう傾向の強い組織でした。現地派遣軍が勝手に戦端を開いた満州事変でも、事変を演出した責任者である石原莞爾、板垣征四郎といった現地軍幹部には処罰は下されていません。満州国建国という「結果」を出しているからです。 これが日本的情緒と合わさると、結果出しているどころでない重大な規律違反であっても、やった当人の心情を察して免罪しよう、という考えすら出てきます。2.26事件で反乱将校たちに同情し、彼らの罪を軽くしようとした陸軍上層部の将軍たちがいた事は有名な話ですね。 こうした「結果さえ出せば、命令違反しても問題ない」と言う風潮は、後の日中戦争や太平洋戦争で命令違反や参謀の私物命令(正当な権限なしに出される命令)乱発を招き、その多くは敗北に直結し、遂には国を滅亡の縁に追いやりました。 どんな事情があれ、明確な規律違反を不問にする事は、組織のモラルハザードを招きます。そして、軍隊は強大な力の持ち主であるがために、モラルハザードを起こせば、その弊害も巨大なものとなります。ワタダ中尉は自分の信じる正義を遂行する前に、まずそれを考えてみるべきでした。 どんなにバックボーンとなる信念や理想が正しかったとしても、正しい事のためなら何をしても良い、と考える事は、絶対に間違っています。 そう考えた瞬間から、人間は日本赤軍やアルカイダの同類に成り果てます。 歴史上、多くの人間を死に追いやったのは、悪ではなく、己の正義を疑わなかった者たちだった、と言う事実を忘れてはならないでしょう。「人間は自分の愛するものを美しいと見なすように、自分の信じるものを聖なるものと見なす」(エルネスト・ルナン)
2006.07.13
コメント(0)
-
G.N.さんとの対話・番外(ミサイル問題編)
G.N.さんから名指しで意見を求められているので、個人的な分析も含めて意見を述べてみましょう。 まず、額賀長官、麻生大臣の談話ですが、これは国際的な常識で言えば、ごく当然の反応です。日本は現時点で北朝鮮の弾道ミサイルに対し、効果的な防御手段はありません。 これは、北朝鮮が国力不相応に日本に対し、強い発言力を得ている理由でもあります。「こちらの要求を聞かなければ、弾道ミサイルを撃ち込むぞ」という恫喝に対し、何の反撃も防御もできないのでは、相手に強い態度に出られるわけがありません。 額賀・麻生両氏の発言は、今はともかく近い将来に日本が北朝鮮に対する防御・反撃手段を確保する可能性を示すことで、弾道ミサイルを突きつけての相手の恫喝に対して、牽制する意図を持ったものと分析されます。当然、北に伝わることを計算しての発言です。 北朝鮮にまだ理性的な分析能力が残っていれば、両氏の発言から「日本に強い態度に出過ぎれば、強硬な反撃を招く恐れがある」 と結論付けられるでしょう。 これらの発言は直接的な対談ではありませんが、相手に間接的にメッセージを送ると言う意味で、外交の一手段と考えられます。>今までも多数あった北朝鮮のミサイル演習をちょっと大げさに発表しただけで まず、今回の演習は7発という今までに無い発射数と、新型の「テポドン2」が初めて発射されたと言う点で、たまに行っている対艦ミサイルの発射演習とは全く性質が異なります。 前回の弾道ミサイル発射は、98年に「テポドン1」を三陸沖に落としたものですが、これによって北朝鮮はアメリカから発射の自粛と引き換えに経済援助を含む外交上の成果を引き出しています。 ますます苦しくなる国内事情を背景に、北朝鮮がもう一度同じ事をしようと考えることは、十分あり得ます。 今のところ北朝鮮は明確なメッセージを出していませんが、何を言ってくるにしろ、武力恫喝を背景とした手前勝手なルールで交渉しようとする相手に対しては、それに乗らないことが重要です。 >同じ同盟国の韓国はさすがに良識があってか、「騒ぎすぎ」と一喝している。それも当然だろう。 こちらは全く「当然」ではありません。宥和主義にも程があります。韓国の現政権がやっている事は、武力恫喝の容認であり、ナチスの伸張に屈したチェンバレンと同様の誤りです。 なお、この韓国政府の対応は、同国の主要新聞では激しい批判の対象になっています。【社説】韓国政府・国民の内面に生じた「安全保障の穴」(朝鮮日報:7月7日)【社説】危機対処ろくにできない政府なんて信じられるか(中央日報:7月8日)[社説]「野次馬」盧武鉉政府 (東亜日報:7月6日) こうした新聞の反応こそ「当然」です。>後はアメリカにとって戦費をどれだけ節約して日本と韓国に負わせるかが課題だ。日本と韓国が被害を受けると、その後アメリカが復興のための投資をすることによってさらにアメリカ資本は増加するし。日本よありがとう。 実のところ、アメリカが自ら北朝鮮を攻撃する必要性は、ほとんど無いと言っても過言ではありません。中東ではイラクに正面切って開戦して勝てるような国は無く、アメリカが出張るしかありませんでしたが、朝鮮半島では韓国にその意思さえあれば、北朝鮮に圧勝できるだけの戦力があります。 もちろん在韓米軍は参戦するでしょうが、主役になることはありえません。 自衛隊が参戦する必要性も無いでしょう。それどころか、政治的に非常に拙い問題を引き起こしかねないので、日本がやると言っても、米韓ともに止めると思われます。 軍事的には、日本や韓国が受ける被害は、核でも使われない限り、ほとんど皆無で終わるでしょう。問題は、日本では「ほんのわずかな被害」でさえも、世論が許容できないであろう、という事くらいでしょうか。 問題は「戦後」です。北朝鮮は世界最貧国の一つであり、環境破壊の程度もきわめて深刻で、あらゆる産業が半世紀近く遅れています。「復興」するとすれば北朝鮮の方なのでしょうが、おそらく利益よりも遥かに負担の方が勝るでしょう。ドイツが統一から四半世紀近く経った現在でさえ、東西格差を埋めきれないでいるのを見れば、北朝鮮の武力併合は「アメリカ資本を増やす」どころか、むしろ重大な負担をもたらすものにしかなりません。何しろ北朝鮮国民にはまともな購買力さえないのですから。 従って>何が何でも北朝鮮に対して武力攻撃を行いたいアメリカ大統領ブッシュ というのは、G.N.さんの(おそらくは"ブッシュ=戦争愛好者"という先入観による)分析の誤りです。アメリカは北朝鮮に対しては武力行使の意図をほとんど持っていないというのが、私の分析です。理由を整理すると・韓国軍単独で北朝鮮は打倒しうる。・北朝鮮を武力で打倒するメリットはほとんど無い。・北朝鮮を援助して再建するくらいなら、自助努力で立ち直ってもらいたい。 と言ったところでしょうか。 武力行使があるとすれば、テポドン・シリーズに載せられる実用核弾頭が開発され、それによる攻撃が現実的な可能性として切迫した際に、発射基地を先制攻撃する、くらいでしょう。 アメリカ(及び日本)の対北政策における最善のシナリオは、北朝鮮を国際社会に復帰させ、国力ギャップを埋めつつ段階的に韓国との統一を進めることだと考えています。>もし本当に防衛長官額賀(あるいは安部)の言うように北朝鮮のミサイル施設を先制攻撃したら、全面戦争になるのは必至だ(これはナナシイさんや鳩さんなどもみとめるだろう)「安倍」は「麻生」の間違いでしょうか? それは良いとして、北朝鮮の弾道ミサイル施設に対する先制攻撃を行っても、全面戦争になる可能性はほとんど無い――杞憂と私は考えます。 何故かと言うと、北朝鮮にはこの弾道ミサイルを除けば、ごく少数の特殊部隊を潜入させる以外、日本を攻撃する手段が無いからです。 北朝鮮のカードは弾道ミサイルのみであり、それが無くなれば他に打つ手はありません。北朝鮮の軍備は韓国への南進に特化して整備されており、海を渡って日本に侵攻する能力は持っていないからです。 ミサイル基地が破壊された時点で北朝鮮が日本に対する戦争を遂行する能力は失われ、全面戦争を戦う事は不可能になります。 日本としては、弾道ミサイルを破壊してしまえば、それで国土の安全を守ると言う目的は達成され、それ以上の戦闘は不要です。特殊部隊の潜入に対しては、入国審査の厳格化と日本海の警戒強化で、潜入以前に発見してしまえば問題ありません。 端的に言うと・北朝鮮には、対日全面戦争を戦う「能力」・日本には、対北全面戦争を戦う「必要性」 が、それぞれ欠けているため、全面戦争になどなりようがありません。北朝鮮は「全面戦争も辞さない」と言っていますが、自らにその能力が無いことは彼らも自覚しているでしょう。これは額賀・麻生両氏の発言同様、強硬的な意見を述べることで、相手にメッセージを送っているのです(かなり空回りしてますが)。>国連の制裁決議に関しても北朝鮮を刺激し追い詰めるものであることには変わりない。 制裁が何か悪いことのように聞こえますが、制裁決議が通ったとしても、それは孤立の道を選んだ北朝鮮の自業自得です。私にはそうとしか言いようがありません。 先日の日記でも書きましたが、先軍主義を取る北朝鮮においては、最優先のルールは軍事力を背景にした恫喝であり、相手国がそれを行ってくることが、彼らにとって最も強く「意思」を受け取りやすいものです。自分にも理解できるルールだからです。 >断固として外交政策で解決する のは当然ですが、それですら額賀・麻生氏のような「こちらも武力を整えるぞ」という圧力なしには、北朝鮮には伝わりにくいのです。 北朝鮮に宥和主義で臨む事の誤りは、98年のクリントン政権と、現在の韓国政府の醜態が証明しています。北朝鮮が新たなルールでプレイする事を学習するまで、日本は彼らのルール(恫喝)でもこちらが圧倒していることを教えてやるしかないでしょう。「胸元に銃剣を突きつけられているうちは、決して和解などしない」(ベンジャミン・フランクリン)
2006.07.11
コメント(0)
-
さらにG.N.さんとの対話
今回は早めにG.N.さんから答えが返ってきました。活発なのは良いことです。 さて、今回も見ていきましょう。 >ナナシイさんも米軍のイラク武力侵攻を「理不尽なもの」として捉えているようである。 いいえ、理不尽とは思っていません。 結果的に大量破壊兵器は見つかりませんでしたが、イラク戦争開戦前は有るのか無いのかはっきりしておらず、白黒つけるのに必要な国連の査察も、イラクは拒否し続けていました。その状況下で「フセイン政権を打倒して、イラクに査察を受け入れさせない事には、イラクの危険性を否定できない」 というアメリカの主張を覆す事は難しかったと思われます。 フセイン政権が査察に全面協力するのでなければ、戦争以外でイラクの大量破壊兵器問題に決着をつけることは難しく、その点で「開戦理由」自体は理不尽なものではなく、正当性があると考えます。>私たちはこう考える。イラク軍が米軍と同じくらいの兵力を持っていたら、まず、米ソの冷戦と似たような構造が出来上がっていただろう。「同じくらいの兵力」ではありません。「撃退もしくは侵攻を断念させるだけの戦力」です。 俗に「攻者三倍の原則」と言って、普通は攻撃側が防御側の三倍の戦力を投入する事が必要である、とされています。つまり、防御側であるイラクに必要なのは、米軍の3分の1ということになります。 実際には、米軍といえど全ての戦力をイラクに投入できるわけではないので、イラクが必要とする戦力は、米軍全兵力の5分の1も必要ないでしょう。 実際のイラク戦争では、米英軍の投入兵力が22万に対し、イラク軍は42万でした。「攻者三倍」どころか半分以下の兵力であり、開戦前は米英軍の敗北・苦戦を予想する分析もありました。 もっとも、この計算はイラク軍と米軍の「質」が同等の場合に限られるので、あまり正確では有りません。「戦力」とは数だけでなく、兵器や兵士の質も含まれるので、専門家でも計算は難しいものなのです。 ただ言えることは、もしイラク軍の装備・兵士の質等が米軍と同等だったら、米軍は撃退されていたでしょうね(そもそも侵攻すら出来なかったでしょうが)。 >冷戦の構造下でアラブ世界対西側(?)世界の(イラク国内も含めて)地域紛争が絶えないだろう。要するに、平和とは程遠い世界になっていることだろう。 実際には、冷戦時代のほうが地域紛争の発生は少なく抑えられていました。米ソ両国が同盟の盟主として、紛争をコントロールしていたからです。冷戦時代のことを「パクス・ルソ・アメリカーナ(ロシアとアメリカによる平和)」という事もあります。 現代の地域紛争の多くは、冷戦によって抑制されていた宗教・民族の対立が一気に火を噴いたもので、特にソ連が解体して、大国の影響力を失った旧共産圏で顕著でした。旧ユーゴスラヴィアの民族紛争やチェチェン紛争はその典型例といえます。 一方、影響力を失っていないアメリカ中心の自由経済圏では、目立った大規模紛争は起きていません。 歴史的に見ると、大国が盟主としてその他の国々に対する影響力を行使する時代のほうが大きな紛争が少なく、大国が力を失うと、民族紛争や、それに取って代わろうとする勢力との大きな戦争が起こる傾向があります。 例としては、オーストリア・ハンガリー帝国の弱体化は国内での諸民族の反乱と普墺戦争を引き起こし、19世紀の世界帝国だった英国の弱体化は、20世紀においてナチスの勃興と第二次世界大戦を招きました。 フセイン元大統領は「大アラブ主義」を掲げ、アラブ諸国を統一しようという思想を持っていましたから、ポスト冷戦下では「取って代わる勢力」に分類されるかもしれません。 >アメリカがほしいのは結局石油の利権だろうが、これを手に入れるためにはアメリカはさらに強大な軍事力をもって侵攻するだろう。それに対しイラクももっと軍事力を増強する。するとアメリカはさらに…ボム!「イラクが強かったら?」という想定を前回挙げた時に「どんな事情があれ米軍はイラクに侵攻するに決まっている、とかいうような先入観なしで考えてほしい」 と言ったのですが、無視されてしまったようですね。残念です。 実際の冷戦が「ボム!」で終わらなかったように、仮にG.N.さんの言うように「米ソの冷戦と似たような構造」がアメリカとイラクの間に出来たとしても、その結末も米ソ冷戦と同様に「どちらかの国が軍拡競争に耐えかねて経済崩壊する」であると考える方が自然です。 イラク戦争は「軍事的にイラクを打倒するのは困難ではない」 という大前提があったからこそ始まったのであり、どんなに石油が欲しかったとしても、共倒れが予想される状況で戦端を開くほど、アメリカが理性の無い国とは思えません。もしそうだったら、人類の歴史は1962年の10月で終わっていたでしょうね。 今回は結局G.N.さんは先入観に囚われたままだと確認しただけで終わった気がします。とりあえず >この次の記事ではまた違ったIfを私たちが提起したい。 ということなので、それに期待しましょう。「面白いから軍備を続ける者はいない。恐ろしいから軍備を続けるのだ」(ウィンストン・チャーチル)
2006.07.09
コメント(0)
-
続・G.N.さんとの対話
G.N.さんから以前の日記に対する反論をいただきました。早速中を見て行きたいと思います。>…なんでやねん? たとえば消防隊員が常時訓練するのに、民間を脅かす会社が必要ですか? どうもG.N.さんは「災害救助」を「直接的な人命救助」という点でしか捉えていないように見受けられます。これはまぁ、自衛隊を災害救助専門部隊に、という説を唱える人にありがちな見方なのですが。 一見して一番「華々しい」ので、それだけが災害救助に見えるのも、わからないでもないですが、「災害救助」とは消防隊員がやっているような、倒壊した家に入り込んで行って、下敷きになっている人々を救出したり、負傷者を治療したり、と言ったこと「だけ」ではありません。それは人命救助・救急医療という災害救助の中の一つのステージではあっても、災害救助そのものではありません。 これは以前の日記や、Kimdongsungさんとのやりとりでも書きましたが、災害救助には人命救助だけでなく、被災者の生活支援という面も含まれます。自衛隊(軍隊)が威力を発揮するのは、どちらかという生活支援の面です。 人命救助・救急医療は災害発生から72~96時間(これを過ぎると生存率はほぼ0になる)で一段落付きますが、生活支援は月単位、時には年単位で続き、その重要性は人命救助に決して劣りません。 そして、被災地では道路やその他の交通が寸断され、普通の運送会社が使う一般車両はなかなか入っていけません。そこで、瓦礫が散乱していようと、道路が破壊されていようと、それを乗り越えて進んでいける装備と能力を持つ自衛隊の後方支援部隊の能力が重宝される訳です。 また、ヘリ輸送も国内では自衛隊が最大の能力を持っています。10トン級の運荷能力を持つヘリは民間にも自衛隊以外の公的機関にもほとんどありません。 しかし、これらの装備・能力はというと ・不整地も走れて頑丈だけど、重くて燃費が悪い(=輸送費の高騰に繋がる)トラック。・ラリー競技ドライバー並みの運転技術(でも一般道路を走る分には不要な能力)を持つ運転手。・10トントラックよりも経費が高い輸送ヘリと、その操縦有資格者。 といった、民間企業では不必要に「豪華」で、しかも訓練と維持費も高価なものです。 これらは軍隊である限りは、戦闘部隊の行動(実戦・訓練問わず)を支援すると言う形で維持され、災害時の生活支援にも貢献しますが、戦闘部隊がなくなると、支援対象が消えるため、能力を維持するためには民間に伍してひたすら土木工事や運送業をしなくてはならなくなります。しかも、経費が高くつく装備・人員で。 だから「災害救助専門部隊」は無駄が多いと申し上げたわけです。それは実質的に「非効率な土木業・運輸業」となんら変わりない存在に過ぎないのですから。>米軍が、イラクで民間人を多数虐殺していることは周知だと思いますが、このことひとつととってみても、軍隊の存在がいかに理不尽かを物語るものだと思います。 それでは、G.N.さんには次の問題について考えてみてください。「もし、イラク軍が米軍を領土に侵攻する前に撃退できていたら、あるいは米国にイラク侵攻を断念させるだけの戦力を有していたら、現在の米軍によるイラク人の犠牲はありえたか?」 IFの問題には答えられない、とか、どんな事情があれ米軍はイラクに侵攻するに決まっている、とかいうような先入観なしで考えてほしいと思います。そして、イラク人にとって「自分たちを守ってくれるイラク軍」が「理不尽な存在」なのかどうかも。 ちなみに、この問題は日中戦争時を想定して「イラク=中国」「米=日本」などと置き換える事も可能です。>軍隊は必要だ、とか抑止力で、などといっている人は、戦争を「ゲーム」のように捉えているのかもしれません。 G.N.さんにはかなりキツい言い方になるかもしれませんが、私はこのように言われるのは自分が「想像力の欠如した人間」と言われているようで、非常に不愉快です。 確かに私は戦争を題材にしたゲームをすることは良くあります。昨日は「ACE COMBAT ZERO THE BELKAN WAR」をプレイしていました。 このゲームはドラマ仕立てで、作中には「貧困ゆえに、戦争を選ばざるを得なかった小国の悲劇」「生還したら恋人に結婚を申し込む決意をして出撃し、戦死するパイロット」「敵の侵攻を食い止めるため、あえて自国領内に核兵器を使用する作戦」「戦争の無い世界を作るために、既存の国家全てに戦いを挑むという狂気に魅入られた兵士たち」 と言った、戦争の理不尽さ、悲惨さを語るエピソードが盛り込まれています。 ゲームのクリエーターであっても戦争に対する想像力は持っていますし、プレイヤーもそうです。もっとも、想像力の無い人間はゲームを楽しむことなどできないでしょうけどね。 軍隊の必要性を認識している人間を、何か欠陥のある人間のように言うのはやめていただきたい。 >「軍隊」の「武器」でこの世から消滅させられるのです。 直接的に消滅させているのは、軍隊であり武器でしょうね。 ですが、そうせよと命じたのは政治の側です。 私は日記で何度も書いているのですが、戦争が起きる時、その結果もたらされる悲惨な事態や理不尽な出来事の責任を「軍隊」や「武器」の存在に押し付ける人々は、「戦争は政治の結果として引き起こされる」という事を見ていないように思います。 戦争と政治の関わりについては、有名なクラウゼヴィッツの「戦争論」にある「戦争は武力を持ってする政治の延長である」 と言う言葉や、毛沢東の「政治が一定の段階にまで発展して、もうそれ以上従来どおりには前進できなくなると、政治の途上によこたわる障害を一掃するために戦争が勃発する。」 と言う言葉に語りつくされていると思いますが、要するに、戦争は政治上の問題を解決する最終手段として行われるものであって、軍隊が好き勝手に始めるようなものではありません(軍隊が政府の統制から外れていれば別ですが)。「政治問題解決の手段として戦争(武力闘争)が有効である」という認識が改められない限り、軍隊を無くそうが武器を無くそうが、戦争が無くなることはないでしょう。人間は国家の枠組みが無く、軍隊も存在しなかった部族社会の時代に、既に部族間戦争をしています。 よって、>国家の軍隊をなくす運動をすることは、実は全世界の人々の共通の課題 という言葉には明確に否定の意思を示します。「国家の軍隊」を無くしたら「民間の軍隊」によって政府が打倒され、秩序が崩壊して多数の死者を出した悲惨な例は、既にハイチの例を紹介しました。 私はもし戦争をなくしたいのであれば、軍隊をなくすのではなく、「政治的問題の軍事力解決が、常に平和的解決よりもハイリスク・ノーリターンである状況」 を作るしかないと考えます。しょせん戦争は損得勘定でやるものなのですから。例えば、軍事力を行使した国・組織に対し、他の全世界の国が一斉に報復/制裁を加える機構を作る、などです。 まぁ、この案は、全世界を敵に回して戦争ができそうなアメリカやロシアがいるので難しいですが。 ともあれ、今回G.N.さんは>そもそも、なぜ軍隊が必要か。「軍隊」とは、「武器」とは、ということをもう一度考えてみる必要があります。 と言っていて、それはその通りだと思うのですが、肝心の御本人が「軍隊は虐殺や殺戮を目的として存在する極悪非道の集団である」 と言う誤解に凝り固まってしまっていて、そこから何の前進もないようなので、まずは御本人に自分の言葉をもう一度実践し直してもらいたいものだと思います。「戦争においてさえ、戦争が最終目的ではない」(ウィリアム・シェイクスピア)
2006.07.04
コメント(3)
全5件 (5件中 1-5件目)
1