2009年10月の記事
全26件 (26件中 1-26件目)
1
-

『教室はまちがうところだ』~教室は何をするところ?
子どもたちが集団で暮らし、学ぶ教室。そもそも教室とはなんでしょうか。そこに教師の哲学が現れる!・・・ような気がします。たとえば、『教室はまちがうところだ』(蒔田晋治 /長谷川知子 、子どもの未来社 、絵本、2004、1500円)============================内容(「MARC」データベースより)教室はまちがうところだ みんなどしどし手をあげてまちがった意見を言おうじゃないかまちがった答えを言おうじゃないか-。蒔田晋治の詩が絵本に。まちがうことなんか、こわくない! そんな教室を作ろうやあ。============================▼参考リンク 絵本ナビ前任校で、この絵本に出てくる長文の詩を書いた横長の模造紙を必ず教室に掲示されていた先生がおられました。先生の、「こんな教室にしたい!」という痛烈なメッセージを感じたものです。失敗に対して寛容である教室は、いいですね。(^0^)森竹高裕先生は、この詩を使って「授業開き」をされる際の、実践記録を、インターネット上で公開されています。______________________「教室は○○するところだ」という詩があります。さて、教室は何をするところだと思いますか。______________________という発問は、僕もまねしてみたい、と思いました。▼教室はまちがうところだ ~子どもを勇気づける授業びらきを~(静岡教育サークル「シリウス」より) ☆以下のブログランキングに参加しています。応援していただける方のクリックをお願いしています。(^0^) ブログ王ランキング
2009.10.30
コメント(2)
-

ミクシィアプリで「三国志」~本格シミュレーションゲームが手軽にできる
今日は、ほとんど教育に関係ない話。ミクシイで、アプリというのができます。携帯アプリのように、ミニゲームみたいなのが多かったのですがなんか最近、きちんとしたシミュレーションゲームが出だしたような気がします。やるだけなら無料です。昨日から「ブラウザ三国志」というのをやりはじめました。自分の都市を少しずつ開発していって、数値が上がったり、施設の数が増えていくのが、シムシティー(市長になって街を作るゲーム)みたいでおもしろいです。たとえば「畑を作る」という命令を出すと、それができるまで何分何秒かかって、現実世界の何時何分には出来上がる、という表示がされます。時間がたつと、ちゃんと畑ができています。ちょこっとさわっては、別のことをして、またちょこっとさわるという遊び方がなかなかいいです。全く余談ですが、一応「教育」にからめると、シミュレーションゲームというのは疑似体験ができるので、学校の授業で子どもにさせているところもあるようです。有名なところでは和田中の「よのなか科」の中で、「市長になって住みよいまちを作ろう」という実践があります。(参考リンク) ▼全国[よのなか]科ネットワーク 一般教員向け授業ビデオ集現実にはなかなか体験できないことをシミュレーションするというのは、非常に有意義な学習になると思います。ま、「三国志」はあんまり学習っぽい題材ではないですけど。(^。^;)にほんブログ村▲「そうだね」と思われた方は、クリックください。(^^;)
2009.10.28
コメント(0)
-

『問題児はいなかった』より~”手製の「讃嘆日記」”
『問題児はいなかった』(木原源吉、日本教文社、絶版)より、ほかにもちらちらと引用したいと思います。この本にはいろんな事例が出てきます。その中から「呆れるほどの三日坊主」と親御さんが語った茂くんの例を。小学校1年生の茂くん。「外から帰ったら手を洗う」という約束をした母親。3日間はおぼえていたが、4日目は忘れていた。すかさず母親「あなた忘れたわね!!だめじゃない!! 手洗ってうがいしてらっしゃい!!」筆者談「わたしは、この場合の母親の叱りは妥当だったと考える。」 「母親はすぐさまブレーキを踏んだのだ。」この叱り方は、筆者から良いとされています。僕も、目ざとくすぐさまブレーキをかけるような、こういう叱り方ができたらと思います。(^^;)まあでも、この話には続きがあります。その後の話では、母親は不安になって、黙っていてもできるはずのときにも念押しをしてしまい、ほめる機会を失ったことが出てきます。========================『問題児はいなかった』部分的読書メモ(p177~179より)「言わないと、やらないかもしれない。」・わが子に対する疑いの精神波動・これがそもそも、ハンドルの切りそこない。・何も言わずに黙っていて、彼が自分から手を洗い、うがいをしたら、 大いに子どもをほめる材料があった。・わが子を、よい方向に前進させるのに必要なアクセルを踏む 絶好のチャンスを自ら逃している。※母親は、実行できた日のチェックは大変お粗末であった。 ブレーキはよく踏んでいるが、アクセルをちっとも踏んでいなかった。========================ここで、前回紹介した「アクセルとブレーキ」の話が具体的に生きてきます。僕もよくありますが、何か問題が発生すると、また起きないかと不安になります。問題にしか目がいかなくなって、「また問題を引き寄せてしまう」。問題自体は、「叱る」などの何らかの対処で対応しますが、対症療法的で、後でまた同じことが起こるので、それにかかずらわっているだけでは、かえって問題を誘発・増やしてしまうという悪循環に陥ってしまいます。これは、本当に覚えがあります。学級経営がうまくいかず、クラスの問題の対処に追われていた時、アドバイスとして先輩の先生から言われたのは「しっかりやっている、いい子たちを見ることを忘れない」ということでした。また、「問題」を起こす子どもたちについても、四六時中ずっと問題を起こしているわけではないので、「しっかりやっている時を逃さずに見るように」ということも、教育書に書いてあり、意識するようになりました。さて、そういう意識をすると、どうなるのでしょうか。引用した本の中では、筆者が参考になる本を貸し出し、母親の対応が変わりました。いよいよ、今日のタイトル、「讃嘆日記」が登場します。========================『問題児はいなかった』部分的読書メモ(p181より)・母親は、茂の美点をチェックすることに全力をあげるようになった。・母親はメモ帳を用意して、 わが子のよい点を1つでも見つけるとすぐに記録する。・手製の「讃嘆日記」である。========================これ、いいですね!よい点を1つでも見つけるとすぐに記録する「讃嘆日記」!こんなのをつけられた日にゃあ、子どもがよくならないわけがない、と思います。でも、なかなかつける時間がないのですが・・・と自分に言い訳。でもでも、本当に効果的だと思います。時間がないとか言わずに、プラス面を見る癖をつけるためにも、こういう習慣を形にすることを大事にしていかないといけないですね。夫婦関係の改善とか、人間関係の悩み全般に効果的かも!? ☆以下のブログランキングに参加しています。日記に共感していただけた方はどれか1つ、クリックください。ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^) ブログ王ランキング
2009.10.27
コメント(0)
-

ほめることと叱ることとETCの話(つながり全くナシ!)
今日は本当は『問題児はいなかった』という本のことをブログに書いていたのでした。「ほめるのはアクセル。しかるのはブレーキ」という説明がほめることと叱ることをよく言い表しているなと思ったからでした。ところが!だいぶ書いた後に、跡形もなく消えてしまったのです!ブログを書いていると、操作ミスやちょっとしたことで、こういうことがよくあります。そこで、もう一度同じことをするなという神のお告げと捉えて、そのことはもうやめるとします。同じことをもう一度するのがきらいなのです。(>。<)代わりに。今日、車で高速道路を通行した時のこと。ETCの入口が「閉鎖中」になっていたのです。そこで、久しぶりに、普通の入口を通って「通行券」をとりました。他の車は「閉鎖中」のところに列をなして並んでいました。ETCのところは「閉鎖中」なのだから、なぜこっちの、閉鎖していないところを通らないのだろう、と思っていました。最後に、最寄りのICで下りました。通行券を入れて、お金を払いました。お金を払う時に、分かりました。なんと、ETC利用時の倍の値段がしたのです。ETCは並んで待つだけの割引メリットがあるのですね。ちなみに、ETCなら600円のところを、通常料金では1200円でした。 ほめることと叱ることと、ETC。まったく、話がつながらないですね。そこを強引につなげて、今日のまとめとしたいと思います。ほめることがアクセルで、叱ることがブレーキならば、ETCは、教育で言うと、何か!? ・・・さっぱりわかりません。 たまにはこんな日もあるということで。 にほんブログ村
2009.10.25
コメント(0)
-
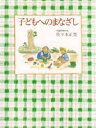
佐々木正美『子どもへのまなざし』6~しからない、ゆずらない
『子どもへのまなざし』の読書メモ、最終回です。僕のブログでは同じ本の内容を紹介し続ける最長記録となりました。(第1回はこちら。)良書と出合えたことに感謝いたします。『子どもへのまなざし』==========『子どもへのまなざし』読書メモ6 (p291~「お母さんへ、お父さんへ」の章以降、部分抜粋)・夫婦の相性がよければ、 子どもに自分の思いどおりになってもらおう、 というような関係の深入りをしないですみます。・夫との関係が深ければ、それだけ、 子どものありのままの姿を尊重しやすくなる。・夫を受け入れられなければ、 その満たされない部分を子どもに求めることになります。・子どもとのいまの時間をたいせつに・最善は、しからない、ゆずらないというのがいい。・とうとうゆずってしまった、こっちが根負けして負けてしまった、 けれどもしからないですんだ、これが中ぐらい。・子どもにたいして、 できるだけしからないけれども、ゆずらない、 だめなことはだめと負けないで根気強く、 止めるべきものは止めるという気持ちでいるのがいい。・泣いたら泣いたことをしずめてあげるだけで、 「泣かないの、泣かないの」なんていう必要はない。・泣きたければ泣きなさいと、それでいいのです。 ・相手を思いやらずして、自己実現などない。 「人間」という文字の形や意味が表わしている。・子どもをたいせつに育てることは、 大人自身がそのような意味で、 自分をたいせつにして生きていることなのだ。 ===========================昨日はこちらの都合で子どもを早く動かしたくて怒鳴ってしまいました。「しからない、ゆずらない」これをやるためには、こちらが余裕を持って、自分の都合で子どもを動かそうとしないことですね。僕の場合、時間ぎりぎりで行動することが多く、そもそも自分自身に余裕がないことが多いので、まず自分が余裕ある行動をすることを心がけていきたいです。いろいろな方々からアドバイスを受けたり、いろいろな本を自分で探して読んでいくうちに、ずいぶん「余裕」の大切さが分かってきたような気がします。余裕のない社会だからこそ、余裕を生み出す工夫が大切だと思います。「自分が満たされない部分を子どもに求める」のは、子どもがかわいそう。でも、自分が満たされないときは、子どもに「癒しや救い」を求めている自分がいます。それは全部が悪いことではないだろうけれども、自己中心的。「子どものため」という大義名分は、本当は「自分のため」。「自分の感受性くらい、 自分でまもれ、 ばかものよ」 (『自分の感受性くらい』茨木のりこ)これで、『子どもへのまなざし』の読書メモと、自分の感想・気づきを終わります。ここまで読んでくださって、ありがとうございました。ご感想・ご意見ございましたら、ぜひコメントをお寄せ下さい。『子どもへのまなざし』(佐々木正美、福音館書店、1998、1700円)最後に、『子どもへのまなざし』に書いてあったようなことを、あたたかいイラストとマンガで読みやすくふれてある本をみつけましたので、これも紹介します。『子育てハッピーアドバイス』(明橋大二 /太田知子 、1万年堂出版 、2005、980円)『子どもへのまなざし』には続編もあります。これも、貸して下さる方がいらっしゃいましたので、これから読もうと思います。『子どもへのまなざし(続)』(佐々木正美、福音館書店、2001、1800円)☆以下のブログランキングに参加しています。日記に共感していただけた方はどうかクリックください。ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^) ブログ王ランキング
2009.10.24
コメント(0)
-
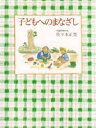
佐々木正美『子どもへのまなざし』5~子どもの「注意獲得行動」にどうするか
『子どもへのまなざし』の読書メモ、つづきです。(今回が第5回。 第1回はこちら。)『子どもへのまなざし』==========『子どもへのまなざし』読書メモ5 (p277~290「保母さん、幼稚園の先生へ」の章、部分抜粋)・子どもをしからないがまん。・保母さんに目を向けてもらうには、手段を選ばずどんなことでもする。 = 注意獲得行動 ・そういう子はしかればしかるほど、 そういうことがエスカレートしていきます。・子どもが人のいやがることを、わざとやるということは、 こんなことをしても、僕のことを愛してくれるかなということを 確かめているわけです。・育児のうまくいかないお母さんを支援しなければいけない。・そういうお母さんを愛せるか、思いやってあげられるか。・その親も子どものころに、ほぼ同じ運命にあってきたのですし、 いまも、もしかしたら周囲から思いやられていないのかもしれないのです。・その子どもをふびんに思うのとおなじ感情を、 親にも持ってあげられたらいいですね。・少なくとも子どもたちの親を敵にするということは、しないでいただきたい。・親の幸せをないがしろにして 子どもの幸せは考えられない。・親を幸せにするためにはどうするかという訓練を、 まず、うけなければなりません。 子どもの幸せを考えるということは、かならずそういうことになります。・はじめは、子どもには手をつけなくてもいいのです。 親の幸せだけを考えるところから入っていくのです。・子どもそっちのけで、親の幸せだけを考える。・人が好きだから教育にたずさわり、保育にたずさわり、 子どもが好きだから保育者になったのでしょう。・根は人が好きなのですね。 ですから、ちょっと心がければいいのです。(今回参照したのは「保母さん、幼稚園の先生へ」の章より、一部の表記だけです。 次回は「お母さんへ、お父さんへ」の章から。)===========================「注意獲得行動」は、「注目欲求」などの用語で、他の本でもふれられていたのをおぼえています。今、こういう子が非常に増えていると思います。僕が本を参考に心がけていたことは、注目を引きたいがためにわざと悪いことをする子への基本対処法は、「悪い行動に取り合わず、 よいことをしたときにすかさずほめる」こう書くと簡単ですが、これが簡単に行きません。具体的には「立ち歩いたとしてもほうっておく」というような対処になるのですが、僕がひとつ学びになったのは、「立ち歩いたから即止めなければいけない」という常識はない、ということです。「視界にとらえながら、あえて無視する」という教師の選択肢は、ありなんです。これをうまくされている先生は、非常に泰然とされておられます。子どもが、「ふさわしくない行動」で気を引こうとしても、根を深く張った大木の如く、歯牙にもかけないありさまで、そのかわり、そういう子がちょっと良いことをすると、目ざとく注目して、称賛を与えるのです。僕はとてもその域まで行きませんので、子どものペースにはまってドツボから脱出できないことも多いです。ただ、「愛されたいのだ」「注目を引きたいのだ」「かまってほしいのだ」という子どもの側の隠された意図に、いじらしさやかわいらしさを感じる教師ではありたいと思っています。でも、本当言うと、「やめてほしい」んですけどね。(^^;)これについて佐々木先生がおっしゃる「まず親の幸せを考える」は、新しい視点でした。子どもを変えようと思っても、親や教師が変わらなかったら、変わらんですよ。教師も変わろうとし、親も変わろうとする。すると子どもが変わる。親と教師のつながりはとても大事ですね。「連絡帳」「電話」「家庭訪問」「学級通信」は、そのためにも、大事なことだと思っています。こちらから動くことで、少しでも親とつながりが持てたらすてきだなあと考えています。『子どもへのまなざし』(佐々木正美、福音館書店、1998、1700円) ☆以下のブログランキングに参加しています。日記に共感していただけた方はどうかクリックください。ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^) ブログ王ランキング
2009.10.23
コメント(0)
-
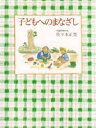
佐々木正美『子どもへのまなざし』4~幸福であればあるほど、がまんができる。
今日は、突発的なことがたくさん起きました。ただ、それに対処しているうちに、勢いがついてきて、大変充実感のある1日となりました。忙しいことは、いいことかな。と思った1日でした。それでは、『子どもへのまなざし』の読書メモを再開します。(今回が第4回。 第1回はこちら。)『子どもへのまなざし』==========『子どもへのまなざし』読書メモ4 (p249~276「豊かな社会がもたらしたもの」の章より、部分抜粋)・人は幸福であればあるほど、 そのとき必要な抑制がきく。がまんができる。・自分の欲求をおさえられない両親の子どもに、 思いやりがそだつはずがありません。・できるなら私たちは、 優越感と劣等感という感情はできるだけ小さく、 弱くもちたいものです。・すぐれた人の前にいっても劣等感を感じない、 すぐれていない人の前にいっても、優越感なんか感じないでいられるのがいい と思っているのです。(今回参照したのは「豊かな社会がもたらしたもの」の章より、一部の表記だけです。 次回は「保母さん、幼稚園の先生へ」の章から。)===========================本の中の文を引用しだしてからだいぶたちましたが、「やっぱりいいことを言っているな」と思います。自分の経験に照らして納得できる記述が多いです。みなさんはどうでしょうか?さて、しょうこりもなく、次回へ続きます。もう本の終わりごろを迎えるところですが、付箋を貼ったのは、ここから集中的にございます。「なんでこんなに貼っているのか」と思うぐらい。(^^;)▼子育てにかかわるすべての方に、おすすめです。 なにしろ本当に本気でおススメなので、今日、友人に買って送りました。『子どもへのまなざし』(佐々木正美、福音館書店、1998、1700円) ☆以下のブログランキングに参加しています。日記に共感していただけた方はどうかクリックください。ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^) ブログ王ランキング
2009.10.22
コメント(0)
-
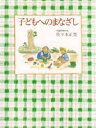
佐々木正美『子どもへのまなざし』3~自分でできない分だけ、口うるさくなっている。
『子どもへのまなざし』2日前から、この本の読書メモを連載のようにして公開しています。 平日は忙しい日が多く、今日もちょっとだけ進みます。まあ、ぼちぼちいきましょう。(^、^;)===========================『子どもへのまなざし』読書メモ3 (p192より)・子どもは親の言ったとおりにはしないで、 親のやっているとおりにやる。・基本的に教育というのは、たいていの場合、 相手の言うことを聞いていればいい。・口でやる教育は避けて、 心とかしぐさとか物腰、行動で教育をする。・自分でできない分だけ口うるさくなっている。 口うるさいとは、そういうこと。(参照したのはp192だけですが、一応p248までで付箋を貼ったところを チェックし終わりました。次回は「豊かな社会がもたらしたもの」の章から。)===========================「鏡の法則」というのがありますが、これと似たようなことを言っている気がします。「鏡の法則」的なことは、人間関係では非常によく起こりますね。子どもに望んでいる姿を、自分自身が実践してそれを見せられたらベストなのですが、なかなかそうはいかないところも。。。だからこそ、「自己成長」をめざすことが大事なのですが。僕は教師になって以来、「言葉が多すぎる」とよく言われてきました。(なる前からかな・・・。)どうしても説明したがる、言葉が長くなる傾向があります。このブログにしても、長くなる傾向が!(^^;)本当は、言葉は少なく、端的に。言葉よりもむしろ行動で示す。これが、いいんだろうな、と思います。端的な言葉で、無駄な言葉を言わない教育実践としては、向山洋一先生が思い浮かびます。近頃久しぶりに向山先生の著書を読み返していますが、子どもにどんな言葉で話をするのか、授業に限らず、朝会での話など多彩な分野で、事前によく吟味し、これ以上ないほど無駄な言葉を削った、効果的な言葉を使われているのが分かります。「どんな言葉を使うのか」これは教育方法の一つの大きな課題です。録音して自分の声を聞くのはとても恥ずかしいですが、授業中の教師の声をすべて録音して後で聴くと、いかに不用意で意味のないことを言っているかよく分かります。また、声の抑揚や、強調、強弱、聞きやすさなども、録音するとあからさまに分かってこわいぐらいです。自分と向き合うことは恥ずかしいですが、教師として、やっておきたいと思っている「修行法」の一つです。今回も反省を胸に・・・次回へ続きます。『子どもへのまなざし』(佐々木正美、福音館書店、1998、1700円) ☆以下のブログランキングに参加しています。日記に共感していただけた方はどうかクリックください。ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^) ブログ王ランキング
2009.10.20
コメント(0)
-
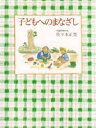
佐々木正美『子どもへのまなざし』2~「しつけ」とは何か
昨日の続きです。 個人的に非常に感銘を受けた部分だけ抜粋してメモった読書メモです。(^。^)今回は「しつけ」をテーマに。「しつけ」、苦手なんですよ、僕。漢字で書くと「躾」。「身を美しくする」と書くのですが、肝心の僕自身が美しくできていないので、「人のことは言えない」です。(>。<)反省します。とはいえ、子育てでは大変重要な部分です。そして、悩みの種です。「しつけ」をどうしようか、という悩みに、1つの指針になるのではないかと思います。===========================『子どもへのまなざし』読書メモ2 (p182まで)(#は僕の個人的なコメントです。)・しつけのはじまる時期は、 基本的信頼感による。・自分や相手を信じる力が育っている子には、 多少きびしいしつけをしても大丈夫。・私たちは、あなたにここでうんちをしてほしいんだと、 ここでおしっこをしてほしいんだということを、 くり返し伝えることがしつけ。・本当にあなたがここで上手にできるようになるのはいつか、 楽しみに待っていてあげるからという気持ち。・時期は自分で決めなさい、 自分で決めればいいのですよ と言ってあげることです。 そういう態度で接してあげることです。・しつけをされることは、子どもたちにとっては、ある意味では喜び。(p182まで)===========================「楽しみに待っていてあげるからという気持ち」という部分、これは大人側の余裕にも起因すると思います。小林正観さんの本、僕は好きなんですが、正観さんも同じようなことを言っておられたのを思い出しました。「絶対そうならないといけない」というのではなく、「ならなくてもいいけど、もしそうなったらうれしい、そうなったら楽しい」という気持ちについて、正観さんは講演CDや著書の中で言っておられました。前回の話の、「待つ」ことが大事、というのにも、つながると思います。 この本は大変、いい本なので、読書メモとして書き残したいことがいっぱいあります。そんなわけで、まだまだ次回に続きます。(^。^)送料無料でネットで買いたいという方はこちらから。『子どもへのまなざし』(佐々木正美、福音館書店、1998、1700円) ☆以下のブログランキングに参加しています。日記に共感していただけた方はどうかクリックください。ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^) ブログ王ランキング
2009.10.19
コメント(0)
-

佐々木正美『子どもへのまなざし』1~ゆっくりめでいいのです。
同じ学校の先生からお借りした本を、夏休みから今までにかけてずっと読んでいました。11月に僕たち夫婦に子どもが生まれるということで、貸していただきました。「子育て」についてのあたたかく確かなアドバイスが詰まっています。子育てを経験された、他の方からも「これがいいので読みなさい」と勧められている本です。読んでみて、私も同感です。すでに多くの方がご存じだと思いますが、例によって「読書メモ」としてブログ上に内容記録を残しておきたいと思います。子育てにかかわっておられる方は、ぜひぜひ、読まれることをお勧めします。おススメする度合いがとびきり高いので、普通の楽天画像リンクでは思いが伝わりません。特大画像で、貼り付けておきます。(笑)『子どもへのまなざし』 ~乳幼児期は、人間の基礎をつくるもっとも重要な時期です(佐々木正美、福音館書店、1998、1700円)===========================【目次】(「BOOK」データベースより)乳幼児期は人格の基礎をつくるとき/子どもをとりまく社会の変化/人と育ち合う育児/こんな気持ちで子育てを/生命との出会い/乳児期に人を信頼できると子どもは順調に育つ/子どもの望んだことを満たしてあげる/幼児期は自立へのステップの時期/しつけはくり返し教えること、そして待つこと/思いやりは身近な人とともに育つ/子ども同士の遊びのなかで生まれるもの/友達と学び合う時期/思春期は自分さがしの時期/豊かな社会がもたらしたもの/保母さん、幼稚園の先生へ/お母さんへ、お父さんへ ===========================以下、個人的に非常に感銘を受けた部分だけ抜粋してメモった読書メモです。(^。^)===========================『子どもへのまなざし』読書メモ1 (p86まで)(#は僕の個人的なコメントです。)・マニュアル通りに、育児をやろうとしても、うまくいかない。・なぜ育児が下手になったかというと、 それは人間関係が下手になったからだ。・親子関係だけを一生懸命やっても、親子の関係はうまくいかない。・多様な人間関係ができる人の方が、 それだけ子どもとの関係も柔軟にできる。・育児不安というのは、お母さんの自分の存在自体にたいする不安だ。・人間がみんな、自分の周囲の人と、おたがいに守り守られて生きている という気持ちになれば、存在への不安は小さくなる。・自分ひとりという気持ちになってしまうのがいけない。・教育とか育てるということは、待つことだ。・「ゆっくり待っていてあげるから、心配しなくていいよ」というメッセージを どう伝えてあげるか。・人間の体というのは、かならず治るほうにいく、 よくなるほうへいこうとするのです。 あるいは成長しようとする、発達しようとするのです。・ひそかに最善をつくして、じっと待っていればいいのです。・実際の育児は、育児書に書いてあるのよりは、ゆっくりめでいいのです。・昔の育児では、だれもあせらなかった。・「もう2度とこんなことするんじゃないぞ」なんていう必要はないのです。 それをいわないがまんというのも必要なのです。 「2度とするなよ」とか、「どうしてそんなばかなことをしたんだ」とか、 「どうして」なんて聞かれたって、子どもに答えられるものではないですよ。 #これ、僕はどうしても言ってしまっています。 #子どもが何か悪いことをした時、どんな言葉かけをするか。 #どうしても、「なんでそんなことするんや」「もうしないように」という #”指導”をしてしまいます。 #しかし、それでこどもは「よくなる」のか? #この場合、一番大切なことは何なのか? #結局、自分の「指導者」としての体裁を取り繕っているだけのような気がします。 #子どもを「包み込む」ような接し方ができるようになりたいです。 #「どうして」と聞かれて答えられるようなものではない、というのは、 #ある意味とてもよく分かります。 #「なぜ」と聞いてはいけない、というのは他の人間関係の本でも読んだような?・「おまえもあやまらなくちゃだめだ。頭をさげて」、なんてことは いわないでいてあげるのです。 親は自分のやすっぽいプライドなどはすっかり捨てて、 ただただあやまるのです。 #僕の好きな歌に「やきとりじいさん」という歌があります。 #その歌詞に「安いプライド 捨ててしまいましょう。何の役にも 立ちません。」 #というのが出てきます。 #僕の成長は、プライドをどれだけ捨てられるかにかかっていると #思うことがたびたびあります。 #子育てするうえで、大人のメンツとかプライドというのは、 #しばしば邪魔になるのでしょうね。 #「自分を客観視する」ということにも、つながると思います。 #大人が、我を通すと、子どもも、我を通します。 #大人が、調和を大事に考えると、子どもも、調和を大事に考えます。 #人間の芯には「大事なプライド」というものがありますが、 #「余計なプライド」というものもあります。 #「余計なプライド」は捨てる。 #僕はそのために、「考える前に動く」というのを心がけるようになりました。 #考えだすと、余計なプライドを守ろうとしてしまうような気がします。 #中村文昭さんが言う「返事は0.2秒」も、自分のプライドより #相手との信頼関係を優先するということだと思います。・子どもに伝えてやればいいのです。 お父さんもおまえのような年ごろのときには、 同じようなことをやって記憶があるということをね。・京都大学の霊長類研究所にいらっしゃった河合雅雄先生が、 現代はしばしば、人間である子どもをペットのように育ててしまって、 さあ適当な年齢になったから、野生のサルの群れのなかで、 生き生きと行動してらっしゃいと、解き放っているようなものだと おっしゃっています。・子どもたちから思いきり依存される保育者になってください、 そして思いきり反抗を受け止められる先生になってほしい。 ちょうど、ピッチャーのすばらしいスピードボールを、 しっかりとミットに受け取ったキャッチャーの喜びのようなものです。・子どもは親を信じているから反抗しているのだと、認識すればいい。・依存と反抗をくり返しながら、らせん階段をのぼるようにして 進展していく。(p86まで)===========================この本もまた、いい本なので、読書メモとして書き残したいことがいっぱいあります。そんなわけで、例によって次回に続きます。(^。^) ☆以下のブログランキングに参加しています。日記に共感していただけた方はどうかクリックください。ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^) ブログ王ランキング
2009.10.18
コメント(0)
-

植松努さんの”日本一感動する講演会”その4~可能性を信じて
4日連続。植松さんの講演ブックを部分的に紹介しながら自分の感想をさしはさむ第4弾。 初めて来られた方はまず3日前の日記からお読みください。(^。^)==========================『きみならできる!「夢」は僕らのロケットエンジン』 講演録 講演&読書メモ4(#は僕の個人的なコメントです。)・世界初は、すべて個人が自腹でやる。・坂本竜馬は何人いたっけ? 僕たちはインターネットもあります、 飛行機だって乗れます。 だから、せめて坂本竜馬くらいのことはできてもいいんでないの? ↑ ↓・楽をするための汚い言い訳・人を殺すことが罪なのは、もはや人類レベルで大切な 一人の人間の可能性を奪ってしまうからです。 #教師をしていると、「しね」と気軽に口にする子どもに会うことがあります。 #本人の苦しさ、理解されていないという心の叫びの裏返しであるかもしれませんが、 #それに対し、きちんと相対し、話をしていきたいと思っています。 #それは、自分が前任校で学んだ最も大切なことだと思っています。 #前任校は、震災で在籍児童8人をなくした学校でした。 #そのため、震災や防災についての学習、命の大切さを語り継ぐ取組が #継続してなされていました。 #今、「しね」と口にする子どもはどこの学校でも珍しくありません。 #それを見過ごし、笑って済ませるのか、 #本気でその子と向き合う契機とするのか。 #いつもは逃げてしまっている僕がいます。 #時間がない、他にやることがある、と逃げてしまう僕がいます。 #「いのち」のことからは、逃げてはいけないのではないか、 #と僕は思いはじめています。 #近年、学校では「あれも大事」、「これも大事」、と #教える内容がめちゃくちゃに増えてきています。 #でも、本当に大事なことを教えていかなくちゃいけない、と思います。 #「可能性」の話には深く共感します。 #教育の本質とダブる話だと思っています。 #前任校の6年生が卒業する時に書いた「可能性を信じて」という話は、 #そのとき僕が最も信じていた、大事だと思うことの話でした。 #大事なことを大事にしていこうと思います。(過去の日記にも書きました。)・学力とは、学ぶ力と書きます。 今よりどれほど変われるか、という未来の可能性の価値こそが、 本当の学力です。・「夢」はたくさんあっていい。・夢は大いに語り合うべきです。・くふうという生き方こそが、人間の本当の生き方です。・くふうの結果が社会の役に立てば、仕事になります。 #僕は「くふう」が大好きです。 #くふうした事実があってこそ、自分の成長を実感できると思っています。 #僕は「特別支援教育」に生きることを志しています。 #特別支援教育というのは、「くふうの教育」だと思っています。 #壁があって喜べるのは、くふうのしがいがあるからこそに、ほかなりません。 #くふうを忘れた時は、成長が止まった時だ、と思っています。・よりよくしたいというワクワクが、本当のビジネスを生みだします。・Dream can do ! Reality can do ! 「思い描くことができれば、それは現実にできる」 「思うは招く」・子どもは裏切らない、大人が裏切ったのです。・自信というものを失った人が他の人の自信を奪うから、 児童虐待が起きる。・出世払いです。・僕らが、彼らが出世するように助けなければいけないのです。・「僕にもできる」と思った子たちは優しくなります。 ・理想とは、北極星です。・「理想なんか、届かないから」と捨ててしまうと、 見える範囲でしか歩けなくなるのです。・理想は高く高く持つべきです。 届く届かないはどうでもいい話なのです。・明日のために、今日の屈辱に耐える。・人は、自分の愛する人の笑顔が見たくて生きています。・しっかり笑顔を間違わないようにしなければいけません。・「どうせ無理」禁止条例・現在と未来をつなぐ新しい学校「ARCプロジェクト」 ・虹です。 現在と未来をつなぐ虹をつくろうと思っています。・住むためのコストを10分の1にすること・食べるためのコストを半分にすること。・学ぶためのコストをゼロにすること。 ↑ ↓ 日本人だけが、自分の愛する家族の将来の不安を人質に取られて、 ただひたすらゴミをつくるために働かされています。 ・僕が必要とする先生は、自分のあきらめなかった経験を伝えてくれる人です。・よいこともねずみ算になります。 #「ペイ・フォワード」? #僕はこの映画見たいんです。 #映画を見ていない時点で確かなことは言えませんが、 #植松さんの「よいことをねずみ算に」を聞いて、 #「ペイ・フォワード」運動を思い出しました。・NPO法人読書普及協会 (「本との出逢い、人との出逢い、出来事との出逢い」を提供し、 成長しあう仲間の会。植松氏の講演会を各地で開催している。) #植松さんの講演会の実現は、この協会の努力によるところが大きいです。 #大変有意義なコンセプトを持っておられる会だと思います。 #理事長の清水さんは「読書のすすめ」という本屋をされていて、 #おもしろい語り口の本を何冊も書かれています。(以上。)==========================これで、全4回にわたっての内容のご紹介を終わります。この本・DVDとの出逢いに感謝します。『きみならできる!「夢」は僕らのロケットエンジン 植松努の特別講演会 北海道の小さな町工場が"知恵"と"くふう"で「宇宙開発」に挑む』(植松努、現代書林、 2009/9、4200円) ☆以下のブログランキングに参加しています。日記に共感していただけた方はどうかクリックください。ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^) ブログ王ランキング
2009.10.17
コメント(0)
-

植松努さんの”日本一感動する講演会”その3~失敗してこその「自信」だ
前日、前々日の続き。植松さんの講演ブックを部分的に紹介しながら自分の感想をさしはさむ第3弾。==========================『きみならできる!「夢」は僕らのロケットエンジン』 講演録 講演&読書メモ3(#は僕の個人的なコメントです。)・欲しいものと出合ったら、値段ではなく「仕組み」を考える ・値段をつける人に自由にやられちゃうからね。 #前日参照の「自分の人生の時間を取り戻す」に通じるところです。 #そうなんです、自分で作ればいいんです。 #「欲しいものは、買う」という思考から、 #「欲しいものは、自分で作る」という発想へ。 #これがほんとの自立型人間です。 #僕は、ゲームソフトが欲しくてゲームソフトを作る会社に就職した経験があるので、 #こういう発想をする傾向は強かったんです。 #でも、大人になってだんだん年がたつと、「お金で何とかすればいい」という #考えにシフトしていったのも事実です。 #「大事なところに集中するために瑣末なことに手間をかけずお金をかける」 #という考えでいるので、自分でやろうという気をなくしたわけではないですが、 #それにしても大事なことを思い出させてくれたと思います。・「こいつのせいかもしれない」というのは、 数字になったりグラフになったりしているけれど、 ただの憶測と偶然でしかないのです。・やったことがないことは、試しにやってみると必ず失敗する。・でも、失敗をデータにして、改良して再挑戦すれば、 どんなことも必ず成功する。・最初から失敗する覚悟を持って準備さえしていれば、 何も怖いものはない。・「信じる」とは、「自分自身の覚悟」である。・自分たちで繰り返し試して、自分たちで信じるしかない。・誰かが保証してくれる人生というものは存在しません。・自分たちで信じるしかない。 それが 自信というものです。・失敗をデータとして乗り越えていったから、自信がついたのです。・失敗するチャンスがないから、子どもたちは自信を持てません。・失敗を伴わない自信というものは、 うぬぼれと言われてもしょうがないのです。・とにかく失敗するチャンス、そして失敗を乗り越えるチャンス、 それが必要だと思います。・自分が何をするかという覚悟こそが、 本当の信頼を生みだします。 #p96,97の見開き2ページに、赤線を引きまくりました。 #本当にそうだなあとうなづける言葉の連続でした。 #元気が出てきました。覚悟が出てきました。 #方向性が定まり、失敗する勇気がわいてきました。 #植松さんの講演の中で、ここの部分が一番自分に響いたところかもしれません。 #「信じる」ことや「自信」「失敗」「覚悟」ということについて、 #これまでも壁にぶち当たる度に考えてきました。 #「信じる」という曲をちょうど1年前、練習し、公開しました。 #この曲の歌詞にふれて以来、「信じる」ということを余計に考えるようになりました。 #今の教育の課題は、「子どもたちに自信がない」ということに尽きると思います。 #それを乗り越えるために、「自信」を生む具体策を展開していかなければと思います。・能力は「してもらう」と失われ、「する」と得られる。・してもらったり、誰かにさせると、能力は失われる一方です。・「する」と能力が得られるのです。・無料でやっても損はしません。 #成功哲学の本によく「行動することが大事」と書かれていますが、 #同じことを言っていると思います。 #植松さんの言葉は、「なぜ行動することが大事か」を、 #端的に分かりやすくスパンと言いきっています。 #座右の銘として、時々思い出したい言葉です。(以上。講演録p106まで)==========================内容が濃すぎて・・・またまた、続きます。(^0^)完璧主義な性格なのか、一度ここまで細かく紹介しだすとなかなか終われなかったりして。少しでも皆さんのやる気につながる内容を紹介できたなら幸いです。そして、もし共感されたなら、ぜひDVDブックをお買いになって、講演をお聴きください。植松さんの姿と声で、この内容に触れるのが、一番衝撃的な体験になることと思います。 『きみならできる!「夢」は僕らのロケットエンジン 植松努の特別講演会 北海道の小さな町工場が"知恵"と"くふう"で「宇宙開発」に挑む』(植松努、現代書林、 2009/9、4200円)↑最近のイチオシです。 またまた続く! ☆以下のブログランキングに参加しています。日記に共感していただけた方はどうかクリックください。ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^) ブログ王ランキング
2009.10.16
コメント(0)
-

植松努さんの”日本一感動する講演会”その2~自分の人生の時間を取り戻す
前日の続きです。今日も、「楽をすると無能になる」という言葉が帰宅途上の頭に響いていました。最近この言葉がよく頭の中に響いています。苦手なことから逃げていると、無能になるばかりだなあと、今日1日を振り返り、反省しています。(>。<)==========================『きみならできる!「夢」は僕らのロケットエンジン』 講演録 講演&読書メモ2(#は僕の個人的なコメントです。)・稼働率を下げる。なるべく売らない。なるべくつくらない。 #これを聞いて、「地球村」の高木善之さんの言われていたことを思い出しました。 #大量生産・大量消費の時代は終わりを迎えています。 #この講演の趣旨とは違うと思いますが、 #植松さんも、非常に大きな目で「仕事」というのをとらえられているので、 #自分たちの子ども世代が幸せに暮らすための「会社」での働き方というのを #考えておられるのじゃないか、と思いました。・僕らは人間です。 知恵があるんです。 だから屁理屈上等なのです。 #僕は昔から、とても屁理屈を言う子どもでした。 #屁理屈上等と言われると、自分が肯定された気がして、ほっとします。(^^;)・何でもかんでも、全力を尽くしてやるべきです。 #「全力で」も、僕が好きな言葉です。 #全力でやるから、「やった!」という達成感があるのだと思います。 #僕の好きな曲は「全力少年」です。(『全力少年』/スキマスイッチ) #この曲で2年生と運動会ダンスをやったこともあります。 #一生の思い出に残るダンスでした。・最低限やらなければいけないことは、最低限の時間で終わらせてください。・自分の人生の時間を取り戻すのです。 #ああ、この人は、自分の「人生の時間」をコントロールされているのだな、 #と思います。 #生き生きと人生を生きるには、自分の人生くらい自分でコントロールしなくては、 #と思います。 #「自分の感受性くらい、自分で守れ、ばかものよ」 #という、茨木のり子さんの詩を思い出します。(出典:『自分の感受性くらい』) #たまに、自分にムチを入れるために、この詩を思い出します。(以上。講演録p74まで)==========================まだ、続きます。(^0^) ☆以下のブログランキングに参加しています。内容に共感していただける方はどうかクリックください。ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^) ブログ王ランキング
2009.10.15
コメント(0)
-

植松努さんの”日本一感動する講演会”その中身について 1
前日に予告したとおり、植松努さんの特別講演会DVDブックから、具体的な中身を紹介していきます。植松努さんの講演は、かなり評判になっています。最近では、日刊のメールマガジン「てっぺん大嶋啓介の【夢エール】」でも紹介されていました。僕が視聴した時の感想としては、「確かに、日本一の講演会かもしれない。」と思いました。話し方が熱かったり、うまかったりするわけではないです。淡々と話されますが、非常に整理された内容です。「〇〇です。そして、~~です。」と、接続詞でつなげて短文を展開していくその話し方は、非常に分かりやすく、引き込まれます。もっとも、一番感動するのは、話された中身についてですが。感動するかどうかは人それぞれですが、僕は日頃考えていたことや、これまでいろんな方に影響を受けて大事だと思ってきたことと、この方の「生き方」の足跡がリンクする部分が多く、この講演会DVDを見てよかった、と思いました。DVDはなかなか見る時間がとれないので、一度見た後は音声だけCD-Rに焼いて、車の中で聴けるようにしています。座右の銘として覚えておきたい言葉が、いろいろな話の中から飛び出してきます。実際に実践された、事実の裏付けのある話なので、納得します。そして、勇気を奮い起こされます。聴かれたことのない方は、ぜひ。▼『きみならできる!「夢」は僕らのロケットエンジン 植松努の特別講演会 北海道の小さな町工場が"知恵"と"くふう"で「宇宙開発」に挑む』(植松努、現代書林、 2009/9、4200円)==========================『きみならできる!「夢」は僕らのロケットエンジン』 講演録 講演&読書メモ(講演時間122分 DVDブックは、講演DVDと、講演録のセットです。 #は僕の個人的なコメントです。)・人の輝きを支える活動を続けている ・「どうせ無理」という言葉を世の中からなくしたい・ゼロから1を生みだすキーワード 「だったら、こうしてみたら?」・生まれた時は、本当はみんな前向きだったのです。・誰かがあきらめ方を教えている。・「いい子」=「都合のいい子」 #このあたり、教育関係者には耳が痛い話です。 #「都合のいい子を作る教育をしているのではないか」というのは、 #常に自問自答しておきたいところだと思っています。・僕たちは、宇宙開発を、 「どうせ無理」という言葉をこの世からなくすためにやっています。・誰もがどうせ無理だと思う宇宙開発を僕たちがやってみせることで、 「どうせ無理」という言葉が使えなくなることを祈っています。 #そのためにも、この話を、世の中の多くの人たちに知っていただきたいと #思っています。・ずっとやり続けるためには、 よその人のお金をあてにしない。 #これは、お金だけのことではないと思います。 #他人をあてにするということは、 #それをやるかやらないかが他人に左右されるということです。 #「自分がやる」と決めたなら、本当に「自分でやる」ことが大事だと強く思います。 #それとは反対に、他人任せにして他人に責任転嫁して、 #いいわけをしている自分がよくいます。(>。<)・そもそもなぜ、お金が必要になるのでしょうか。 #これも大事な視点だと思います。 #実は、お金がなくても社会は成り立つということを言われている方はいます。 # 「そもそも」論。 #大前提を疑う。 # 「そもそも」論については、道徳の実践家深澤久先生がよく言われています。 #深澤先生のそもそも論を読むたびに、姿勢や心構えが正される気がしています。 # 「そもそも」を考える癖をつけるのは、大事な習慣だと思っています。・常識って、普通って、ものすごく簡単に変わるのです。・お金というものは、知恵や経験と等価である。 #僕の母の教えは「若い時の苦労は買ってでもしろ」でした。 #お金を使って自分の知恵や経験に変える、ということは、 #ずいぶん前からやってきたような気がします。 #身銭を切って学ぶと、おもしろいです。 #人生のだいご味ですね。 #逆に、それができるのが、「お金」の価値だと思います。 #「モノ」を買えるのは、お金の価値のほんの一部分しか表していません。・学校の評価基準にないものは、「無駄なことだ」と言われてしまう。・小学生の時、プラモデルが作りたくなって、父に言った。 父:「男なら、鉄で作れ」 そんなわけで、小学生のうちから電気溶接とかができるようになっていました。 #これを聞くと、「おもしろい」と思うんだけど、 #「確かにありえる話だな」とも思います。 #小学生ぐらいの年齢で可能なことって、 #本当はむちゃくちゃすごい範囲に及んでいるんです。 #ただ、まわりがさせないだけ、ということがすごくあると思います。・「好き」だとイヤでも努力する・まだまだ発展途上・世界で一番のものは、誰も教えてくれません。・「あなたとは違うんです。」・2番煎じと前例踏襲では、 絶対に世界一になれません。・親がわが子の評価を他者にゆだねるからです。 だから、子どもがゆがんでしまいます。 どこかの誰かがつけた点数で、自分の子どものことを親が評価すると、 大変なことが起きます。 #僕はあと1か月で親になりますが、頭に叩き込んでおこうと思います。 #少し前のところでも「他者にゆだねる」ことへの批判がありましたが、 #ここはもっとも大事なところだと思っています。 #「夜回り先生」の水谷修先生が講演で話された言葉がずっと耳に残っています。 #「自分がやったことの始末は、自分でつけなさい。」 # 子どもには子どもの自己決定があり、 # 親には親の自己決定があり、 # それが責任ということなんだろうから、 # だから人におもねちゃダメなんだ。 # 人の評価を気にすると、自分が弱くなっちゃうんだ。 #というように、理解しています。(^。^)・なぜ、楽をしたいのでしょうか。・楽をすると、無能になるのです。・そして、無能になると自信が持てなくなります。・自信はく奪は連鎖します。・でも、連鎖は切れるのです。 「いやなことは俺のところで食い止めるぞ」という 鋼のハートさえあればいいのです。 #勇気づけられます。 #「嫌な連鎖」はしょっちゅう見ています。 #「嫌な連鎖」を切る能力は、「楽をしたい」という気持ちと反比例して #あらわれてくるのでしょうね。 (^0^)(以上。講演録p64まで)==========================長くなったので回数を分けます。ここまでのところで、どう思われたでしょうか?ではまた次回。 ☆以下のブログランキングに参加しています。内容に共感していただける方はクリックください。ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^) ブログ王ランキング
2009.10.14
コメント(0)
-

「楽をするということは、無能になること」~植松努さん講演より
昨日の日記で、「自分に甘い、いいかげんな子」を見ると、自分もいい加減だからなーと反省しています。ということを、書きました。いい加減というのは、一方では非常にいいことです。「いい加減は、よい加減」という言葉があったり、『いいかげんが いい』という本があったりします。僕も、「いい加減」は、非常に大事にしています。『いいかげんがいい』(鎌田實、1000円)そういうバランス感覚はいいと思うんですが、真剣さがないと、成長がない、と思います。このことで思い出したのが、先日購入した「日本一感動する講演会」のDVDブックで植松努さんが言っておられた言葉です。「楽をすると、無能になるのです。」(『「夢」は僕らのロケットエンジン』講演録p60)楽をしようとすることが悪いことだとは思いません。でも、成長しようとするなら、これは自制すべきことだと思います。実はこのへんは細かいことにこだわりすぎると、なかなか理解するのが難しいのです。植松さんは「何でもかんでも、全力を尽くしてやるべきです。」と言います。でも、植松さんの会社の経営方針は、「稼働率を下げる。なるべく売らない。なるべくつくらない」というものです。見据えているものがはっきりしないと、混乱するんです。「いい加減にやる」ということは、必ずしも「楽をしている」ということではないのです。そこで、「何のために」が重要になってきます。「何のために」がはっきりしている人は、「いい加減」にやっているようにみえて、その実、「全力で」やっています。自分が何になりたいか。チームをどんな状態に導きたいのか。迷いがある人は、1つの実践事例として、とびぬけた実践事例として、植松さんの講演DVDブックをご覧になることをおすすめします。僕はこれにかなり感銘を受けました。すごく刺激になりました。「こういうことか」と納得したことが、たくさんあります。今回は、わけのわからない引用の仕方になってしまいましたが、次回、少し整理した状態で、植松さんの講演会を取り上げたいと思います。DVDブックの無料動画の情報等、以前書いた日記がありますので、まずはこちらをお読みください↓▼植松努さんの動画での「可能性の話」に感動しました! ▼『きみならできる!「夢」は僕らのロケットエンジン 植松努の特別講演会 北海道の小さな町工場が"知恵"と"くふう"で「宇宙開発」に挑む』(植松努、現代書林、 2009/9、4200円)それでは、また明日!(^0^) ☆以下のブログランキングに参加しています。内容に共感していただける方はクリックください。ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^) ブログ王ランキング
2009.10.13
コメント(0)
-

子どもの成長は、自分の成長の鏡である
昨日のブログに、「人のことより自分のこと」と書きました。これ、一言ですが、すっごく重要だと思います。教育の現場では、「子どもをよくしよう」と思っている人が多いです。というか、そういう人ばっかりです。で、それは何によってもたらされるのか、といったときに、いろいろな言われ方で言われていますが、結局は、まず「自分をよくする」ということに尽きると思います。子どもの成長は、自分の成長の鏡でもあるのですね。だから、自分ができていないことを、口先だけ、言葉だけで子どもに指示する、ということは、あってはならないと思います。また、もしそうしたとしても、それで子どもが従わないからと言って怒るのは筋違いです。勉強を好きになる子に育てたいなら、まず自分が勉強を好きになること。やさしい子に育てたいなら、まず自分がやさしくなること。真剣に生きる子どもに育てたいなら、まず自分が真剣に生きること。学校現場ではいろんな子どもに出会います。僕の場合、「自分に甘い、いいかげんな子」を見ると、自分もいい加減だからなーと反省しています。学校では、日々自分と向き合っている気がしています。これを読まれている、学校の先生方や、保護者の方々、一緒に、「自分育て」をがんばりましょう。これは、とっても大事なことだと思ったので、その瞬間から、このブログのサブタイトルが変わりました。子どもの成長を目指すことは、自分の成長を目指すことと、イコールだな、としみじみと思ったからです。これがこのブログのコンセプトです。同意して下さる方が、今後もこのブログを見に来て下さることを、とても励みにしています。 ☆以下のブログランキングに参加しています。応援していただける方のクリックをお願いしています。ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^) ブログ王ランキング
2009.10.12
コメント(0)
-

現状のアセスメントと、目標の数値化~ブログの成長を目指す場合~
2日前の日記で、特別支援教育における「アセスメント」の話をちょっと書きました。アセスメント(正確な実態把握)は、現実的な目標や、目標達成のための具体的なやり方を考える上で、とても大切です。これを「子どもの成長のために」と考えるのが「教育」の世界。しかし、「人のことより自分のこと」。教師といえども、「人のアセスメントをするんだったら、まず自分のアセスメントをしろよ」ということは、言えると思います。そこで、自分のことに置き換えてみました。ただ、漠然と「自分のこと」というと、範囲が広すぎるので、絞り込みます。今回は、これ、このブログに絞り込みました。ここからは、ブログの現状を正確に数値で把握し、成長をしていくための目標を設定する、という話です。ブログをやっている方は、ぜひやってみてください。★ブログの人気度というのは、いろいろな数値で測れます。今回は、「被リンク数」を調べてみます。まず、検索エンジンGoogleに移動します。そして、自分のブログのアドレスを入れます。(「きょういく ユースフル!」だったら、 http://plaza.rakuten.co.jp/kyouikuuseful/ です。)これで検索をかけると、ネット上でこのアドレスにリンクが貼られている数(被リンク数)を調べることができます。その数は、昨日の時点で 423 でした。基本的に、ブログをどんどん人から見てもらおうと思ったら、この「被リンク数」を上げることが近道です。そこで、目標となる数値を「500」にしよう、と思ったわけです。★(目標) 10月中に 被リンク数を、500にする。これで、現状に即した、具体的な数値目標と、その期限が設定できました。そして、そのための具体策として、・ブログランキングにも、新たに2つ、加入しました。ブログを応援して下さる方、よかったらぜひクリックしてください。それも1つを1日1回ずつ。(笑) ブログ王ランキングさあ、これで・現状把握・目標設定・目標の達成期限・そのために何をするかが一通りできたわけです。これはかなり分かりやすい事例だと思います。 「教育」などで考えると、もっと複雑になってきますが、こういう数値化しやすい例を知っておくと、ちょっとはシンプルに考えやすいかもしれませんよ。(^。^)さあ、目標達成はなるかどうか?ぜひぜひ、応援よろしくお願いします。こうやって、数値で目標が設定できると、達成できるかな、とワクワクするので、けっこういいですよ!他のことにもどんどん応用していきたいと思います。☆以下のブログランキングに参加しています。応援していただける方の1日1クリックをお願いします!(^0^) ブログ王ランキング
2009.10.11
コメント(2)
-

烏骨鶏(うこっけい)の卵を買いました。(^^)
烏骨鶏(うこっけい)。この珍しい鶏の名前は、聞いたことはあれど、見たことはありませんでした。その卵を売る、田舎の道の駅があります。スーパーで買うと、1個500円らしいです。それを5個500円で買いました。安っ!!今まで行った時にはいつも売り切れだったのが、今日の15時ごろに行くと、なんとあったんです。 うれしー!珍しい物好きなので、とりあえず買っときました。さきほど、「卵かけごはん」にして食べました。黄身がすごくイエローな感じです。普通の卵とは明らかに違います。醤油をかけると醤油の味が勝ってしまったので今度は生のまま食してみようかと思います。 さて、その「烏骨鶏(うこっけい)の卵」の入手先、知りたいですか?(^。^)大きい道路沿いにあるのですぐ分かりますし、ちょっと遠くからでも足を延ばす価値はあると思いますよ。国道175号線。兵庫県丹波市氷上町稲継の交差点から、南の山南町に下るあたりです。ここに、知る人ぞ知る、地元産の野菜や花を格安で売っている「道の駅」があります。「朝香の里(あさかのさと)とれたて野菜市」ホームページはないです。地元の人がやっている「市」で、信じられない安い値段で、地元産のものを買うことができます。場所は、丹波篠山トイレマップというのに、地図が表示されますのでそれを参考に、行ってみてください。(^^)丹波に住んでいて思うのは、地元産の新鮮野菜がとてもおいしい!ということ。 都会の人でもぜひたまに足を運んでいただいて、田舎の新鮮食材にふれてもらいたいです。 そうは言ってもなかなか来れない人のために、例によって楽天で一応検索してみました。さすがネット社会。ネットでも烏骨鶏(うこっけい)の卵を格安で買えるようです。高級卵驚きの安さでびっくりしないで下さい 烏骨鶏の卵(有精卵)(ひろせ直売所、6個入り1200円)ここのお店に、烏骨鶏の卵のとても分かりやすい説明が載っていました。=======================烏骨鶏の卵は普通の卵より小さめでSサイズです。烏骨鶏の卵は良質の高タンパク質で栄養豊富な卵です。生卵でのお召し上がりをお勧めします。小ぶりの卵ですが卵黄の割合が大きく濃厚な味がします。卵黄の色は黄色味がかっていて箸でつまんでも、崩れずしっかりとしています。濃くのある栄養がぎっしりと詰った高級卵です。賞味期限生卵でお召し上がりの場合はお手元に届きましてから15日位です。加熱してお召し上がりの場合は25日位です。烏骨鶏はニワトリのように毎日卵を産んでくれませんので品切れになる場合がございます。========================丹波市の小学校では、烏骨鶏を育てていたところもあるそうです。今は、「鶏インフルエンザ」対策で、鶏の飼育がしにくくなっていて残念です。 ☆以下のブログランキングに参加しています。応援していただける方の1日1クリックをお願いします!(^0^)
2009.10.10
コメント(0)
-

落ち着いたクラス作りのための授業時間
今日は神戸に出張でした。特別支援教育の「アセスメント」(子どもの特性を正確に把握するための方法)についての実技研修です。LDI-R(学習障害の傾向を調べるもの)やKIDS乳幼児発達スケール、S-M社会生活能力検査といった質問紙法によるアセスメントと、WISC-IIIについて学びました。LDI-R、KIDS、S-M社会生活能力検査の検査用紙をそれぞれ購入できたので、よかったです。それぞれ1部ずつ買って、910円。公的な研修ではなかなか珍しい。で、その研修の最後に演習がありました。「支援の方法を具体的に話し合う」というもので、最初はペアで、最後にはグループで話し合いました。その中の最後のテーマに、「片付けが苦手な子への支援アイデアを出し合う」というものがありました。みなさんだったら、何を思い浮かべられますか?これについて話し合っていた時に、僕は「片付ける時間を、授業の最後にきっちりとる。できてから休み時間」という、「お片付けタイム」の提案をしました。これ、実は僕はやっていなかったのですが。他の先生がやっておられたのを見たことがあり、非常にバツグンの効果があると感じた手法です。つまり、「授業を早めに終わり、 今の授業で使ったものを机の中に片付け、 次の授業の用意を机の上に出してから、遊びに行く」ということの習慣化です。これを続けると、とにかく授業がきっちりできます。授業のスタートがさっとできます。けじめがつきにくいクラスを落ち着かせるとっておきの方法だと思います。そんなとっておきの方法ですが、僕の場合、1時間の授業でやりたいことが終わらず、早めに終わることがどうしてもできなくて実践を続けることができませんでした。長い目で見れば、「早めに終わる」ほうがあとあと無駄な時間が出ずに、勉強時間をきっちり確保することにつながるのに・・・。そのころはそれが見えていなかったです。(今もかな?)そのときの授業に一生懸命になりすぎていました。今は通常学級担任を持っていないので状況が違いますが前よりは、余裕を持って授業が行えているような気がします。(^^;)でも、あいかわらず、授業は終わる時間ぎりぎりか、ちょっとオーバーしている・・・。う~ん、このクセは、直したほうがいいですね。ともあれ、授業の終わりを余裕を持って迎えられる方で、子どもに「用意や片付け」の習慣をしっかりつけさせたい方は、これはなかなかおススメの方法です。ぜひお試しください。(^0^)早めに遊びに行けるとなると、子どももうれしいので、進んで片付けや用意をするようになります。学校だけでなく、家庭でも、応用できるかもしれませんね。言っている僕が実現できていないのでその分説得力がないですが。(>。<) あ~、もっと「時間の使い方」を大事に実践できるようになろう。自分ができていないことをたくさん発言して、かなり自己反省した1日でした。(>。<;)さてさて、以下のブログランキングに参加しています。こんなブログでも応援していただける方のクリックをお願いします!
2009.10.09
コメント(0)
-

「降水量●ミリ」って?/「降水確率」はイマ降っていても100%じゃないの?
台風18号関連でTVを見ることが多かったです。ところで、素朴な疑問。「降水量」と「降水確率」って、どうやって決めているか、知ってますか?僕は全然わからなかったです。「理科」の時間とかに習ったかなあ。100ミリとか200ミリとか言われても、全然ピンときません。「それって、どれくらい?」降水確率もナゾです。「今降っていたら、もう雨が降ってるんだから、100%じゃないの?」こういった天気予報用語についての子どもにも分かりやすい解説は、ネット上でもあんまり見つかりません。ただ、TBS お天気ガイド のQ&Aは、かなり分かりやすかったです。====================雪が降ったときのことを思い浮かべてください。10センチの雪だったら、その周辺はどこも10センチの深さだけ雪が降ったということですよね。雨も同じように考えてください。雨が雪と同じように流れないで、その場所に溜まっていたら・・・(略)(引用元:「森田さんのお天気ですかァ?:お天気Q&A:10ミリの雨って?」)http://www.tbs.co.jp/morita/qa_ame/faq_010821-26.html====================この説明は分かりやすいですね。なるほど、「雪」のように積もると思って「雨」を見るのか。その発想はなかったなあ。 なお、Yahoo!知恵袋の「降水確率ってどうやって決めてるの?」もかなり参考になりました。これによると、降水確率についての質問に答えてくれているだけでなく、1ミリの雨は小雨だがはっきりとした雨、2ミリでは傘をささなければならないくらい、5ミリでは、傘があっても困るくらいの強い雨といった説明がなされています。(かなり僕の言葉で言い換えてますが)ところで降水確率についてですが、「今実際に降っているかどうか」というのは、「今、自分」の視点でしか見ていないわけで、過去に同じ気象図でどうだったかとか、他の場所(たとえば風下とか山の上とか)でも降っているのかという視点が欠落しています。天気予報を見ている人はあちらこちらにいるので、「自分」中心に考えて、「当たった、外れた」というのもおかしなものだ、ということがあるようです。勉強になりました。(^。^) ☆以下のブログランキングに参加しています。応援していただける方の1日1クリックをお願いします!(^0^)
2009.10.08
コメント(0)
-

本を丸ごと電子書籍化!?~今どき、けっこう楽にできるらしい~
今日は台風のため、休校でした。警報が解除されたのが9:10。午前9時の時点で休校かどうか判断するのでぎりぎりアウト!残念、また明日!はい、それはともかくとして、全く違った話題です。(^。^)「まぐまぐニュース! 2009年(平成21年) 10月08日 木曜日」号によると、「アマゾン、電子ブックリーダー「Kindle」日本向け販売を開始」ということでした。http://news.mag2.com/archive/20091008100000 これだけだと「??」ですが、とりあえず、「外国では電子書籍が大流行りなので、日本もこれからだ!」みたいな勢いを感じます。実は、電子書籍化というのには、注目していた時期があります。 蔵書を「電子書籍化」してしまえば、・場所をとらない・検索をかけられる(検索にひっかかるようなデータにすれば)・PC上で管理でき、整理・整頓しやすいというメリットがあるからです。(でも、「本」の状態の方が読みやすいというデメリットもあります。) とにかく僕は本屋で本は買うし、古本屋で本は買うし、ネットでも本を買うので、本がたまりにたまりまくっています。本棚と倉庫と実家と学校に分散させて置いていますが、「本の整理」は個人的にはけっこうな課題です。 厄介なのは、「後で必要になるかもしれない」情報で、実際には何年も読み返さないのに「一応」置いてある本。なるべく古本屋に持っていくようにしていますが、判断に迷うものはとりあえず置いています。必然的に、場所を取って困っています。 で、広い世の中、実際に自分の本を「裁断して、スキャナで読んで、電子書籍化」している人がいるらしいです。 今どきの機器を使えば、スキャナには次々読み込むし、データ化もかなり速くできるようなので、1冊丸ごと電子書籍化する時間もそんなにかからない模様。 スキャナは、普通のスキャナじゃなくて、それ用の、「ドキュメントスキャナ」というものを使います。紙を次々読み込んでスキャンしていくハイテク機器です。 「本を1冊丸ごと電子書籍化」なんて、時間はかかるし手間はかかるし、個人ではとてもできないと思っていただけに ちょっとびっくり。 (具体的参考サイト)▼裁断機×ブックスキャナ新生活(やねうらお-よっちゃんイカを食べながら年収1億円稼げる(かも知れない)仕事術) ☆以下のブログランキングに参加しています。応援していただける方の1日1クリックをお願いします!(^0^)
2009.10.08
コメント(0)
-

けんかの仲裁
今日、ひさしぶりにけんかの仲裁をした。小学校2年生の、昼休み後のけんかである。苦労してつくった砂場の山を、踏まれてつぶされた、という訴えを聞いたのがきっかけ。双方を出会わせて、話を聞く。・・・うまくいかなかった。互いに相手の非を言い合うのみ。そういえば、こういう場面に出会うのは久しぶり。通常学級担任のころは、それこそしょっちゅうけんかが起こっていたので、どうすればいいか真剣に考え、対応策を練っていたものですが。そのころ考えたことが記録として残っていないか、マイハードディスクを探してみた。・・・すぐには見つからなかった。そんなわけで、「けんかの仲裁」という言葉で、ネットで検索。考え方と、具体例が載っていた。今は、ネットで「問題」を入れると、誰かの「解答」が簡単に出てくるので、便利な時代ですね。読んでみると、なるほどと思えることもあったので、紹介します。============================= 「けんか・トラブル」への対処の仕方 ・小林幸雄流「けんかの仲裁」で教師のリーダーシップを発揮する。 (1) 当事者を落ち着ける場所に連れて行く。(2) 教師が中立を宣言する。(3) 自分がとった態度を自己評価させる。(4) その点をつけた理由を聞く(5) 悪かった部分のみを謝らせる。※要点のみ引用=============================このサイトのやり方で、なるほどと思ったのは、以下の所です。=============================視点が自分に向いていない状態で、あれこれ事情をたずねても実りは少ない。なぜなら、視点は相手に向き、相手の非のみに向けられているからである。 口を開けば、悪口の言い合いになるのは、火を見るより明らかだ。 ところが、「自分の態度は何点だったのか?」と問われると、視点は、他者から自己へと変わる。=============================実際、「口を開けば、悪口の言い合いになる」のを見た後なだけに、この記述には非常に共感。僕が留意してたのは、この先生の(1)から(5)の中の(1)と(5)ぐらい。「自己評価させる」という視点は、「どうできたらいいな」ぐらいにあいまいに願っているだけで、そんなに意識していなかった。意識していないことは、いざというとき、できないですね。よいご意見にふれさせていただいたと思います。感謝します。 ☆以下のブログランキングに参加しています。応援していただける方の1日1クリックをお願いします!(^0^)
2009.10.07
コメント(0)
-

台風18号に警戒せよ!~伊勢湾台風規模なら甚大な被害?~
台風18号が接近中らしい。新型インフルエンザは来るし、台風は来るし、今週予定している「稲刈り」はどうなるんだ!?一説によると、この台風18号、歴史に残る被害を出した「伊勢湾台風」と檄似しているとか。TVをあんまり見ないので台風のについての情報を全然知りませんでした。そんなわけで調べてみました。▼台風情報 - ウェザーニュース ↑台風被害シミュレーションがあります。▼(動画ニュース)YouTube非常に強い台風18号、8日にも上陸か ところで、「伊勢湾台風」についてはご存じでしょうか?僕は全くご存じでなかったのでこれまた、調べてみました。(^^;)▼伊勢湾台風 - Wikipedia↑これによると、被害の数字がすごい。「死者4,697名、行方不明者401名、負傷者38,921名」「被災者数は全国で約153万人」台風でこれだけの死者が出るものですか!?なお、台風が何を引き起こしたための被害なのか、を具体的に見てみると「伊勢湾台風で最も顕著であったのは高潮の被害であった。」という記述があります。沿岸部は特に、津波・高潮に警戒が必要と思われます。 学校行事どころではないかもしれませんね。。。 ☆以下のブログランキングに参加しています。応援していただける方の1日1クリックをお願いします!(^0^)
2009.10.06
コメント(0)
-
中村文昭さん講演~みるみる元気がわいてくる!(^0^)
先日参加したトークライブから、中村文昭さんの話を。この人の語る「体験談」や「エピソード」はすさまじいです。仕事に対して、生きるということに対して、人と接することに対して、意気込みが変わります。意識が変わります。中村文昭さんのCDを持ってますが、車の中でよく聞いています。車内のHDに入れてます。CDのタイトルは"中村文昭のみるみる元気がわいてくる! PART1 パワーの源"その名の通り、「元気がわいてくる」CDです。==============================■内容 (上記リンクの出版元サイトより)●フミアキ流、朝をスッキリ始める法●落ち込むときは、とことん落ち込もう●犬に教えられた「ボクは人間なんだ!」●人間の悩みは「3つの箱」に分けられる●メッセージとなって現れる苦手なこと●ピンチこそチャンスの芽●成功の気づきがわかる「青虫の話」●たったの1秒で人間は変われる●魂に問いかける「何のために?」●お腹のネジが弛んでいるか、締まっているか●からだの中心に軸をもって仕事をする●DNAに誇りがもてる生き方●動けば変わる、止まれば太る!?●「99日目をもって半ばとせよ!」●師匠が母に問いかけた究極の質問●何でも「楽しみながら」やってみよう●人間は不自由だと努力する●人それぞれのなかに「スイッチ」はある●恩返しではなく「恩送り」をしよう!-ほか==============================フミちゃん節とも言えるその「話し方」にまず魅了されます。生で聴いた「フミちゃん節」は、それこそ最高でした。不特定多数に語りかえられた言葉と分かっていても、「自分に対して語りかけられた言葉」として自分のど真ん中にずしんと響きます。仕事する人、夢を追う人には圧倒的におススメのセミナーです。では、実際に聴いてきた生講演の内容を、メモでお送りします。==========================トークライブでの中村文昭 講演メモ~09年10月3日in京都~・年間300回以上行われる講演会 その3分の1から4分の1は学校での講演。・何のために ・何のために大学に行くのか? ・片腕をとばして教師になった、師匠の父の話 (どうしても教師になりたかったその人の葬儀には、 2000人の弔問客が訪れた。 元教え子たちの連絡網がすごい速さで回った。)・出口を間違わない生き方・素直に「ハイ」・謙虚に「やらせていただきます」<師匠の4つの教え> 1) 返事は0.2秒 ・損得を考えるな。 ・これをやりだすと気持ちいい。 ・「あなたとの間柄にNoはない」 ・自分を捨てる練習 2) 頼まれごとは試されごと ・喜ばせるチャンス! 3) できない理由を言うな 4) 今できることを探して動け☆感動させてはじめて仕事★仕事は心がすべて・どんな世界のものも受け入れろ ・周波数を合わす★経営者はかがやくことや! 「夢」をもつことや!・壁にぶつかったら映像を撮って将来のネタに使おうと思っている。 「ネタ作り ネタ作り」==========================この人の考え方はかなりうなづけるもので、僕が小さい頃や、若いころに考えていたこととも共通します。僕の場合、「考える」のは考えるんだけども、なかなか行動が伴わないんですよね。「ネタ作り」と割り切って、失敗してもいいと踏み出すことがなかなかできません。それが僕の課題です。さて、中村文昭さんの講演は、ネットからのダウンロードでも購入できます。すぐに聴きたい方はこちら。▼中村文昭の「人を活かす人になれ!」▼中村文昭特別セット!龍になれ! プレゼント付!(リンク先で試聴できます。)========================(内容の一部)■ 龍になれ! ・ 中村文昭が語る"坂本龍馬"・ 自分のルーツを知り、役割を考えろ・ 中村文昭が考える自分の一番いいところ・ 中村文昭が一番好きな坂本龍馬のエピソード・ 自分を持っていないということ・ 夢がない人がすべきこと・ 役割が与えられる、"おまえじゃないと"と言われる人生・ 人の心に火をつける・ "No"がない人 ■ 本気で生きる人になれ! ・ やる気と本気の差・ 本気の人 居酒屋てっぺん 大嶋啓介の話・ 本気の人 てんつくマンの話・ コップとおちょこ・ 人のために本気になる?・ 無力と微力■ 応援される人になれ! ・ 人を成長させる出会い・ 出会いがつながっていく、人を惹きつけていく人になるために・ 出会いを生かしたいあなたが今、やるべきこと■ 人を活かす人になれ! ・ 人生を変える「過去」の2通りの考え方・ なぜ、昔の日本は不安が少なかったか?・ 「どうせ僕は・・」という人へ・ 全ての過去に感謝できるようになるには・ 自信をなくす「せめてこれくらいなら」・ 中村流「人を活かす方法」・ 指導ではなく、スイッチを入れてあげる・ 1秒で人はスイッチを入れられる========================自分に元気を生みだすために、ぜひ、だまされたと思って一度聴いてみてください! ☆以下のブログランキングに参加しています。応援していただける方の1日1クリックをお願いします!(^0^)
2009.10.05
コメント(0)
-

斎藤一人『二千年たってもいい話』
ここ1週間くらいのうちに、5人の方の講演会にふれました。1) DVDで鑑賞した「日本一の講演会」:植松努さん2) 本についてきたCDで聴いた「日本一の大金持ち」:斎藤一人さん昨日10月3日、京都でのコラボトークライブで生でお聞きした3)居酒屋てっぺん創業者・居酒屋甲子園主宰:大嶋啓介さん4)映画「107+1~天国はつくるもの~」の企画・監督:てんつくマンさん5)「みるみる元気がわいてくる!」:中村文昭さんどれもよかったので、紹介したいと思います。まずは2番、斎藤一人さんから。一人さんの話、ブログではひさしぶり!ちょっと前に新刊が出ました。新刊が出たら買うと決めているので、買いました。毎回、講演会がそのまま書籍化され、講演CDとそれを文字に起こしたものがセットになっているのですが、今回の講演はすごい。一人さんの講演の中でも、今までで最高の講演だと思います。一人さんの盛り上がり方がすごい。(^^)中身も濃いです。「聞きたい話」がてんこもりです。今回は特に、僕に合った話がされていたと思います。聴けてよかったです。『二千年たってもいい話』~夢の持ちかた夢の叶えかた奇跡の起こしかた魅力のつけかた~(斎藤一人、イースト・プレス 、2009/9、CD付き、1500円、楽天ブックスは売り切れ)==========================【内容情報】(「BOOK」データベースより)人生の成功と、社会的成功、全部が手に入れられる、成功への近道。想像を絶するほど、明るく、楽しく、笑える話。特別付録に「講演終了後、一人さんから最後のお話」。 【目次】(「BOOK」データベースより)二千年たってもいい話(「みんなの顔、見たいな」ってひと言いったら、講演会になっちゃって.../「私は、変な人ですよ」といってるのに、こんなに聞きにくるのは変です(笑)/「斎藤さん、それ違うんじゃないかな」「いやぁ、オレも、そう思ってたんだよ」 ほか)/夢の話、奇跡の話(私の夢をお話しします 身内は「この話は止めて」というけれど、私は止めません/夢の話は、これからが肝心 これからが、いい話なんだよ.../うまくいったら、さらにその上を目指しちゃいけないんだよ 竹の子も、人間も、下から伸びてくるんだから ほか)/一人さん的あそび、の話(人の暗い話を聞いてるとね、いつも、なんか思いつくのね それで、この前、「ダメな男」っていう遊びを思いついたの/ダメな男に、もう一人の男がこういいます「こうやってごらん。元気が出るから...」/麻雀だって、配られた手に文句いってても、どうにもなんない そっから始めるんだよ、そっからいいほうにしてくんだよ ほか) ==========================(↓『二千年たってもいい話』 個人的な読書・講演メモ)==========================・自分で自信のあることは、 「私、少し変ですよ」って、言わないとダメです。 「私が正しい」って言ったら、「みんなが間違ってる」ってことになっちゃう。 それを言ったらケンカになります。・もめごとを起こさない。・ケンカするために勉強してるんじゃないからね。・逃げるときは、思いっきり後ろ向いて全速力で逃げる。・逃げられないときは、ちょっと転化する。・夢は小さく、努力を大きく。・「歩く」ってのは、「止まるが少ない」 止まんのが少なきゃ、いいんだよ。 人生ってね、早く行こうとしちゃダメだよ。 止まっちゃダメだよ。・「奇跡なんだ」と思う癖をつける。・一点に向かって、じぃわぁ~っといくんだよ。・一瞬、一点に集中しなきゃあ、ダメなんだよ。・人間って、魅力があればいいんだよ。・必ず「また」つけて考えな。・おもしろいことに変える。・受け身を覚えようよ、ってこと。・いい玉にして、投げ返そうよ。==========================メモだけ見てもなんだかよく分からないと思いますが、本当に面白い講演です。楽天ブックスでは売り切れのようですが、なんとか手に入れてぜひ読んでください、聴いてください。 ☆以下のブログランキングに参加しています。応援していただける方の1日1クリックをお願いします!(^0^)
2009.10.04
コメント(4)
-

飾るだけで夢が叶う『魔法の宝地図』
「宝地図」のムック本を読みました。付録の「夢カード」を使えば、カンタンに宝地図が作れる!というのが、売りです。「宝地図」関係のほかの本をすでに読んでいましたが、これはこれで、読んでよかったです。(もともと嫁さんの本です。 付録の夢カードはすでに嫁さんの宝地図作成に 使われていました。(^^))Makino mook『飾るだけで夢が叶う「魔法の宝地図」』(望月俊孝、マキノ出版、2007、780円)========================超幸運人生にガラリ一変!ツキを呼ぶ! お金が舞い込む! やせる! と大評判「引き寄せの法則」実践版!!「宝地図」がすぐに出来る3大特別付録付き!========================このブログを書くにあたり、関連情報をネットで調べました。そうすると、「宝地図ムービー」が雑誌の付録になっていた!という情報に行き当たりました。雑誌「ゆほびか」9月号 定価 630円がそれです。(画像:出版社サイトの『ゆほびか』2009年9月号)情報元は、みりあ♪さんによる楽天ブログ「ソライロノキモチ」07月12日の日記です。「宝地図ムービーが収録されたDVDが付録でついてくる!」ということで、「宝地図」に興味を持っている私からすれば非常に耳寄りな情報です。少し前の号になりますが、まだ手に入るかな?具体的な内容は、上のリンク先を見ていただくとして、僕が一番気になるのは・全身麻痺の絶望から立ち直り光へ向かって歩き始めた私の「命の授業」という項目です。教師ですので、よりよい授業とは何か、というのを常に考え続けていますので。そのヒントになるものなら、貪欲に吸収したいと思っています。今日紹介したムック本にしても、雑誌にしても、780円や630円と、ヒジョーに安い!のがいいですね。安いのに中身が濃くて、カラーで具体的に説明がされています。(ムック本の話ですが、たぶん雑誌のほうもそうです。)「付録」がついていて実際に「宝地図」をつくってみよう、という行動にすぐ結びつくのがすばらしいです。さらにネットで調べていると、「宝地図ムービー」の本物にも出会いました。今はネット動画ですぐに見れちゃうのですね。雑誌に収録されていたのもこれなのかな?非常によくできていて、自分用にして毎日見ようかと思ってしまう出来です。BGMがまた、よく合っています。YouTube - takaramapmovie's Channel ☆以下のブログランキングに参加しています。応援していただける方の1日1クリックをお願いします!(^0^)
2009.10.03
コメント(0)
全26件 (26件中 1-26件目)
1
-
-

- 0歳児のママ集まれ~
- ☆寝かしつけ ベビーキャップ☆
- (2025-11-16 21:36:26)
-
-
-

- 楽天アフィリエイト
- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…
- (2025-06-15 15:14:58)
-
-
-
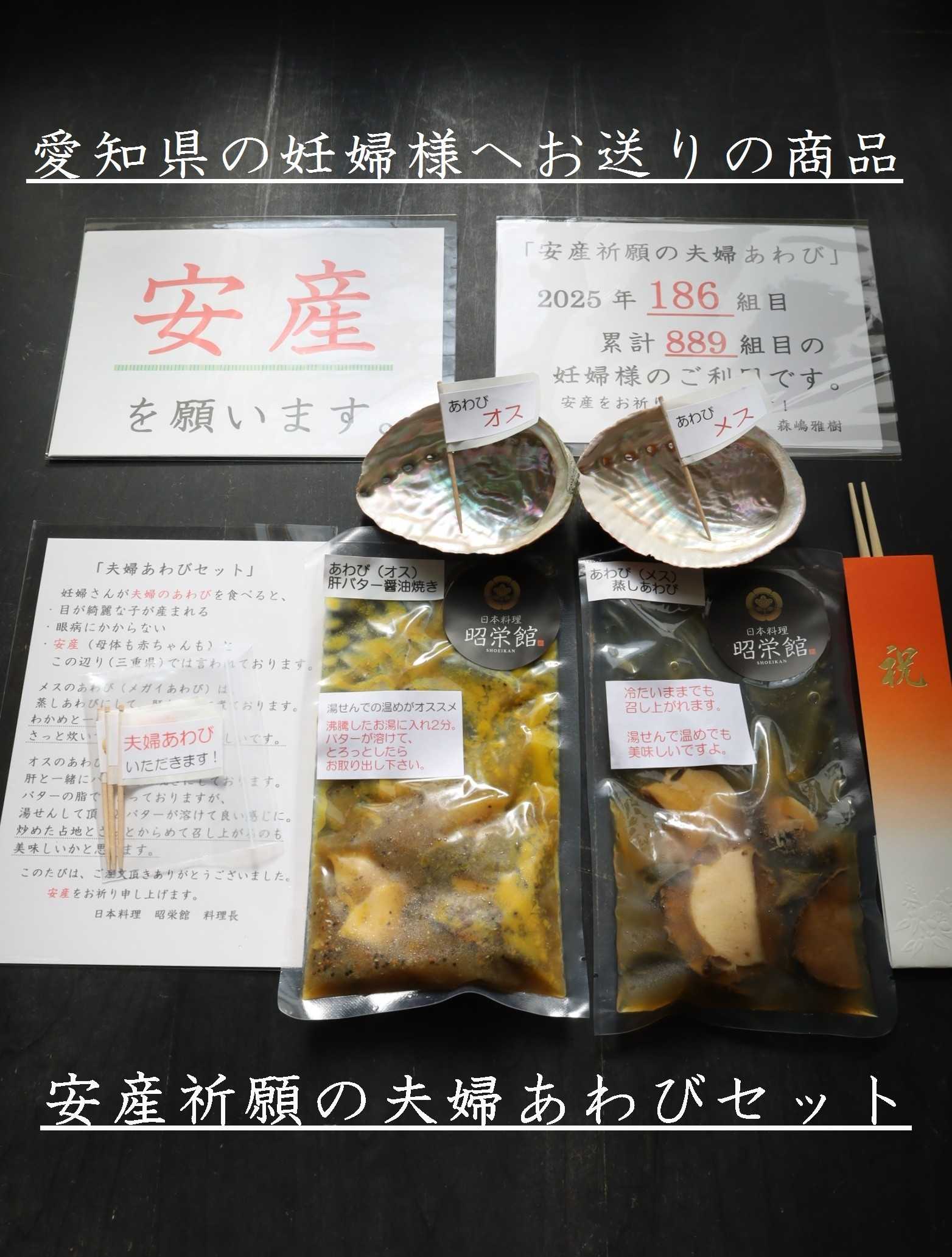
- 妊婦さん集まれ~!!
- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…
- (2025-11-22 06:19:53)
-


